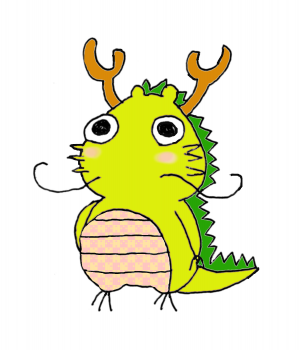大切な、花。
皆様お久しぶりです。
長編を書いて、少し趣味丸出しで妄想をしていたのですが、また形になりそうなものに出会えたので、ここにそっとおかさせていただきます。
ハヤブサさん×シュバルツさん。ハヤブサさん攻め、シュバルツさん受けの、BL小説となっております。
基本いちゃいちゃしている私の小説ですが、今回多少強姦紛いの場面が出てまいります。モブ×シュバルツさんです。これの意味が分からない方、不快に思われる方は、あんまり読まない方がいいかも……。多分ろくな事にはなりませんので。
それでも構わない。許せる、という方だけ、どうか今回もお楽しみください。
完全に、私の趣味の世界でごめんなさい。
そして、強姦は絶対だめだと思うよ本当に……。自分で書いていてそう思いました。
では、読める方だけ、続きからどうぞ~。
(菊の花言葉……か……。シュバルツを、思い出すな……)
古書店で、何気なく開いた本の中の『花言葉』を見つけて、ハヤブサはそう思った。
菊の花言葉は、『高貴』『高潔』『私を信じて』『貞操』――――どれも、ハヤブサにとっては、愛おしいヒトを連想させる言葉だ。
シュバルツほど、信じられるヒトはいないし、シュバルツほど、高貴な美しさを湛えたヒトもいない。ハヤブサがシュバルツを何度も犯し抜く様に抱いても――――その美しさが損なわれると言う事はなかった。それでいて、しっかりとした貞操観念も併せ持っている。きっと彼が『女性』であるならば、間違いなく『良妻』となる事だろう。
彼が、身体を開くのは俺だけ。
俺が、それを求めるのも彼だけ。
俺たちは今――――とても幸せな恋愛をしている様に思う。
自分の腕の中だけで花開くシュバルツが、とても愛おしかった。
しかしそれが、今まさに危機に立たされようとしていた。
『色街』と呼ばれる街の一角にある奥の部屋の大きなベッドの上で、一糸纏わぬ姿のシュバルツが、昏々と眠り続けている。その身体には、痛々しい緊縛の跡と、暴力の跡が刻まれていた。
そんなシュバルツの上にハヤブサが覆いかぶさりながら、涙ながらに彼を見つめていた。
(俺のせいだ……! 俺のせいで、シュバルツは……!)
ハヤブサの中で、激しい後悔と贖罪の気持ちが渦を巻く。
(どうすればいい……? 彼のために、俺はいったいどうすれば――――!)
震える手でシュバルツの頭を撫でれば、彼の黒髪が指の間からさらりと零れ落ちていた。
事の起こりはこうだ。
『龍の忍者』と言う肩書を背負っているが故に、ハヤブサの歩む道は、決して平坦な物ではない。その道行きには、当然敵も多かった。龍の忍者はその力量で、その多くを跳ねのけて来たのだが、今回の敵は違った。
恐ろしく腕が立つ忍者軍団だった。
完全に不意をつかれた格好になったハヤブサは、忍者団の連携の取れた攻撃の前に、重傷を負ってしまう。
「く…………!」
ふらつきながらも、何とか逃げようとするハヤブサ。だが、断崖絶壁に追い込まれてしまう。
(後少し……! 後少しで回復の『呪』が使えるのに………!)
ほんの、後一握りの『気力』が、自分の中に溜まらない。敵にやられないように、刀を上げ続けるのが精一杯だった。
「手こずらせおって……! だが、貴様の命運もここまでだ……!」
頭領格の男が、刀を構えてじりじりと距離を詰めてくる。
「…………!」
半ば死を覚悟しながら、ハヤブサが龍剣を構えている所に、一つの影がそこに飛び込んできた。
「ハヤブサ!!」
(シュバルツ――――!)
愛おしいヒトの顔を見た瞬間、ハヤブサの中で何かの糸が切れてしまう。
「――――――」
ぐらりと傾いだ龍の忍者の身体が、断崖絶壁から、川に向かって落ちて行きそうになる。
シュバルツは迷わなかった。
彼は躊躇うことなくハヤブサを追ってその身を宙へ踊らせて、ハヤブサの身体を腕の中へ捉えると――――そのまま川の中へと、姿を消して行ったのだった。
「おのれっ!! 後一歩のところまで追いつめておきながら――――!!」
忌々しそうに川を見つめる部下たちに、頭領の声が飛んだ。
「探せ!! あの重症の龍の忍者を抱えて、そう遠くには逃げられん!!」
「頭!!」
「草の根分けても探し出して――――必ず奴を、仕留めるのだ!!」
(追手はいない様だな……。どうやら、撒けたか?)
川から上がりながらシュバルツは、周りの気配を探る。人の気配はなく、静かな物だった。どうやらここは安全だと確認したシュバルツは、意識の無いハヤブサを抱きかかえて、そのまま近くの洞窟状になっている所に入り込む。そこでシュバルツは、ハヤブサの身体を手早く治療した。
(冷え切っているな……。しかし……)
何とか止血をし、傷口を塞いだが、冷たい川の水の中に落ちたハヤブサの身体は、冷え切ってしまっていた。何とか温めてやりたいと願うが、追手のかかっているこの状態で、火を焚くのは危険すぎた。
ならば、どうするか。
「…………」
シュバルツは無言で、自身の着ている服を脱ぎだした。
(私が『人間』であったなら……自分の体温で、ハヤブサを温めてやれるだろうにな……)
そう感じて苦笑する。DG細胞で作られているこの身体に、体温など宿っていないこと――――シュバルツはとっくに承知していた。
だけどハヤブサだけは、何としても助けたい。
例え、自分がどうなろうとも。
シュバルツは意識の無いハヤブサの身体に、己の肌を密着させると、中のモーターの回転数を上げ出した。そこから放出される『熱』で、ハヤブサを温める算段であった。
(38度から40度ぐらいか……。熱を上げ過ぎないように注意しなければ……)
モーターからもたらされる熱を感じながら、シュバルツは歯を食いしばっていた。熱を微調整する仕組みなど自分の中に備わっていないから、中々に骨が折れる。ハヤブサをちゃんと温めらているかどうか、酷く不安だった。
それでも――――
(ハヤブサ………)
シュバルツは祈る様に、彼の身体を抱きしめ続けていた――――。
(温かい……)
酷く心地のいい温かさを手放したくなくて、ハヤブサはそれを抱き寄せて頬ずりをする。
「う………」
ゆるゆると意識の覚醒を感じて、ハヤブサは目を開けた。
「……気が、ついたか……?」
目の前に、愛おしいヒトの優しい笑顔がある。
「シュバルツ……!」
ハヤブサはかなり驚いて、ガバッと跳ね起きようとして――――身体に激痛が走った。
「ぐッ!!」
低く呻いて、起きる仕種を中断せざるを得なくなる。
「……………ッ!」
懸命に痛みと格闘していると、シュバルツから声をかけられた。
「……無理を、するな、ハヤブサ……。お前は……怪我を……」
「――――!」
シュバルツのその言葉に、ハヤブサはこれまでの経緯を思い出す。
そうだった。
俺はいきなり『刺客』たちに襲われて――――
「……お前が、助けてくれたのか?」
問うハヤブサに、シュバルツは優しく微笑む。
「たまたま、通りかかった……ただ……それだけの、事だ……」
「シュバルツ?」
酷くしんどそうなシュバルツの様子に、ハヤブサは眉をひそめる。愛おしいヒトは上半身裸のまま自分の横にその身を横たえて、なかなかその身を起こそうとしなかった。
「どうした?」
怪訝に思ったハヤブサがシュバルツの身体に触れれば、彼の身体が酷く熱い。
「お前、熱が――――!」
そう叫んでから、ハヤブサははたと気がついた。
「熱?」
そう。アンドロイドであるシュバルツに『体温』など存在する筈もない事を、ハヤブサもよく承知していた。にも拘らず、今目の前で『高熱』を出して倒れているシュバルツ。そして、川に落ちて冷えた筈の自分の身体が温められている事実。そこから、導きだされる答えは一つだ。
「お前……! 俺のために、何か無茶を――――!」
「『無茶』とかじゃない……。ちょっと、自分の機能を……試してみたかった、だけだ……」
「…………!」
「お前が……意識が戻ったのなら……良かった……」
そう言って優しく微笑む愛おしいヒトに、ハヤブサはたまらなくなる。
「とにかく寝ていろ! 今、水を――――ぐッ!」
斬られた腹の辺りに激痛が走って、ハヤブサは己が身体を抱え込んでしまう。
「ハヤブサ……!」
それを見たシュバルツが、ふらふらと起き上がった。
「……寝ていろ……ハヤブサ……。水、くらい……私が……」
「―――――!」
そう言いながら弱々しく歩きだそうとするシュバルツの手を、ハヤブサは強引に取って引き倒した。
「あ………っ!?」
「いいから寝ていろ……。シュバルツ……!」
ハヤブサは、シュバルツが起きないように彼を抑え込むと、自身は胸の前で印を結びながら『呪』を唱えた。
「叭―――――ッ」
彼の放つ『気』と同時に、彼の周りに青白い光の玉が出現する。それは、ハヤブサの身体に吸収され、彼の身体の傷を癒した。
「……そんな事が、出来たのか……」
茫然としているシュバルツに、ハヤブサは少しぶっきらぼうに答える。
「隼流忍術の一種だ。戦いの間に『気』を溜めて使う事が出来るが、あまり頻回には使えない。本当に、いざという時のための、非常手段だ」
「そうか……」
ハヤブサの言葉に、少し安心したのか、シュバルツの面に笑みが浮かぶ。それを見たハヤブサも、とても優しい気持ちになれた。
「後少しの『気力』がたまらなくて困っていたのだが……お前がそれを分けてくれたんだな……。本当にありがとう」
ハヤブサの礼の言葉に、シュバルツは頭をふる。
「私は何もしていない……。それはお前自身の『気』の力で……あ……」
そこまで話したシュバルツの唇を、ハヤブサのそれが優しく塞ぐ。
「……ん…………」
優しく、甘い口付け――――至福のひと時だった。
(まだ、熱があるな……)
普段、冷たいぐらいのシュバルツの口腔が、温かさを伴っている。上半身裸で瞳を潤ませ、ぐったりと横たわっている愛おしいヒトのしどけない肢体。ハヤブサの強くない理性が酷く傾いだ。
(いやいや! 無いだろう!? 刺客がまだ近くにいるかもしれないし、こんなに具合の悪そうなシュバルツを襲うだなんて――――)
「水が要るだろう? 持って来てやる」
だからハヤブサは、そう言って立ち上がった。
愛おしいヒトの熱を、早く醒ましてあげたいと思ったから。
そして愛おしいヒトを独りにしてしまった事を――――ハヤブサは死ぬほど後悔する事になってしまったのだった。
(何だ……?)
ざわついた感覚に、シュバルツはそろり、と、身を起こす。
この気配はハヤブサの物ではない。明確な殺気だ。
(来る――――!)
シュバルツは、コートの中に忍ばせていた短刀を、咄嗟に手に取った。それと同時に、一斉に飛びかかって来る黒い影達。
「――――!」
いつものシュバルツであったならば、問題なく対処できたであろう。だが、オーバーヒートを起こしてふらついていた彼は、反応が一歩遅れた。そしてその一歩の遅れは――――この忍者団の前では致命傷となってしまった。
「ぐっ!!」
抵抗むなしく、あっという間に彼は忍者団によって取り押さえられてしまう。
「……リュウ・ハヤブサの姿はない様だな……」
縛りあげられるシュバルツを眼の端に捉えながら、頭領らしき男が辺りを見渡している。
(そうか……! こいつらがハヤブサを襲った――――!)
シュバルツはギリ、と、歯を食いしばっていた。
「おい、そこのお前――――」
頭領格の男がシュバルツの方につかつかと歩み寄って来て、顎を手に捉えてぐい、と、強引にこちらに向かせる。
「お前は、リュウ・ハヤブサの仲間か? 奴は何処にいる?」
「……………」
その問いに、シュバルツは沈黙を返す。それに対して頭領は、口の端を歪めただけの笑みを見せた。
「生意気な目つきだ!!」
そう言いながら頭領はシュバルツの顔を思いっきり殴りつけた。
「ぐっ!!」
縛られているうえに、部下たちに抑えつけられているシュバルツは、避ける事も抵抗する事も出来ない。そのまましばらく、頭領に嬲らるれるように殴られ続けた。
「……頭(かしら)、この男、どうします?」
シュバルツを抑えつけている男の1人が、少し下卑た声で頭領に問うてきた。実はこの男、シュバルツを縛り上げる時から、その身体を必要以上に触り続けていた。
部下の求める物を悟った頭領は、ふ、と、口の端を吊り上げた笑みを向ける。
「服をひんむいて慰み物にしろ。ただし、手短に済ませろよ。続きはアジトに帰ってから、たっぷりとさせてやる」
「やった!!」
「へへっ! さすが頭領だ!!」
頭領のその言葉に、シュバルツを押さえていた部下たちから歓喜の声が上がる。
「な―――――! あぐッ!!」
流石にシュバルツもこの言葉には顔色が変わった。しかし、抵抗する間もなく猿轡を噛まされてしまう。そのまま乱暴に押し倒され、数人の男たちによって、あっという間に服をはぎ取られてしまった。
「――――ッ!」
シュバルツの白い肌が、男たちの前に容赦なく曝されてしまう。
(上物だな………)
その身体を見て、頭領はにやりと笑った。この獲物は、後で自ら『味見』をしても良いかもしれないと思った。
「頭。本当に、我らが先に頂いてもよろしいので?」
部下たちも頭領の顔を見て何かを察したのか、シュバルツに手を出す前に、頭領に問いかけてくる。それに対して頭領は、ふ、と、その面に笑みを浮かべた。
「……わしは後でいい。それよりもお前たち、さっさと済ませろよ。あの龍の忍者が来ぬとも限らん」
最も、大怪我を負わせてあるから、それほど心配はいらぬだろうが、と、頭領は付け加えた。部下たちは歓声を上げながら、シュバルツに襲いかかって行った。
「こいつ!! 大人しくしろ!!」
無抵抗のシュバルツに、暴力と罵声と劣情の嵐が容赦なく降りかかっていく。
「――――ッ! ううっ!!」
部下たちの中でのたうつシュバルツの白い身体を見ながら、頭領はその面に残忍な笑みを浮かべていた。
(捕虜の自尊心をへし折り、自分の『立場』を分からせるのに――――『強姦』は非常に有効だ。見た目以上の『苦痛』を、味あわせてやることもできるしな……)
頭領は舌なめずりをしながら、目の前の光景を見つめていた。
「まだ殺すなよ? そいつはおそらく『龍の忍者』と繋がりがある。情報源のほかにも、人質として利用できる可能性が大だ。だから、我等に抵抗できぬよう、よおく『躾』をしておく事が肝要なのだからな」
「分かってますって! 頭!」
「こいつ、可愛らしいですよ。俺らの愛撫に、雌犬みたいに腰を振ってやがる!」
「大方好き者の、淫売なんだろうよ!」
その言葉に周りの男たちから一斉にげらげらと笑い声が上がる。
「う………! う……く……ッ!」
そんな中、シュバルツは独り、足掻き続けていた。
(嫌だ……! いや………だ………ッ!)
男たちに身体中をいい様に触られながら、それでもシュバルツは、必死の抵抗を試みていた。自分の身体の上を滑る男たちの手には嫌悪感しかないし、噎せかえる雄の匂いにも吐き気しか感じない。
そして何よりも、自分に触れてくる男たちから流れ込んでくる興奮と侮蔑と劣情の入り混じった感情が―――――たまらなく嫌だった。
「んうっ!」
それなのに時折、自分の意志とは裏腹に、触れられた場所に反応を返してしまう。
「おっ!? おまえ、ここか? ここがいいのか?」
シュバルツが反応した場所を、男の指が嬲る様に執拗に触って来る。
「ん………! ん………!」
これ以上反応を返したくないシュバルツは、必死にその感触に耐える。そんな彼の肌を、別の男がべちゃべちゃと音を立てて舐めまわしていた。
「本当にすべすべだな……。ヒヒ……こりゃ確かに上物だ……」
「く………!」
「おら!! 気持ち良くなりてぇんなら、さっさと股を開けよ!!」
別の男から罵声を浴びせられながら、背中を蹴り飛ばされる。
「うぐッ!!」
だがシュバルツは、これだけの目に遭わされても、男たちの言う事を聞くにはなれなかった。
(冗談ではない! ハヤブサ以外を受け入れてたまるか―――!)
その想い一つを抱えて、彼は懸命な抵抗を続けていた。
何度か身を捩り、抵抗を試みているうちに、片方の足が自由になる。
「――――!」
シュバルツは迷わず、自分に触れてくる男の1人を蹴り飛ばす。蹴り飛ばされた男は、物も言わずにふっとばされた。
「この……!」
「生意気な奴め!!」
ボキッ! と言う鈍い音と共に、シュバルツの足に激痛が走る。彼の足が、叩き折られていた。
「――――――――ッ!!」
これには流石のシュバルツもくぐもった悲鳴を上げてしまう。力の入らなくなった足は割開かれ、ついに、そこに指の侵入を許した。
「んっ! う……!」
ビクッ! と、涙を飛び散らせるシュバルツに、男たちの劣情はさらに煽られる。
「なまじ抵抗するから痛い目に遭うんだ」
「へへへ……。すぐによくしてやるからな……」
ズブ、と、音を立てて、さらに侵入してくる、指。
「…………ッ!」
(ハヤブサ……!)
祈る様に閉じられたシュバルツの瞳から、一筋の涙が零れ落ちた刹那――――それは起きた。
洞窟の一角で、ドンッ!! と言う音と共に、刎ねあげられる首。
「――――!?」
驚く頭領の目の前で、次から次へと部下たちが斬り捨てられていく。その間を駆け抜ける、黒い影が在った。
(龍の忍者――――!)
その正体を悟った頭領は、咄嗟にシュバルツの身体を鷲掴みにし、それを己の盾とした。
「龍の忍者!! 見ろ!!」
その呼び掛けに、それまで疾走していた黒い影が動きを止める。龍の忍者と視線の合った頭領は、シュバルツの喉元に刀を突きつけながら、叫んだ。
「そこから一歩でも動いてみろ……! こいつの命はないぞ……!」
「…………」
しかしハヤブサは答えない。何の感情も読み取れない眼差しで、黙って頭領を見つめ返している。
頭領は、この人質はハヤブサには非常に有効だと確信していた。故に彼は、部下たちに命じた。
「さあお前たち、この男を始末しろ!!」
「承知!!」
命を受けた男たちが、一斉に襲いかかる。
しかし。
ドカッ!!
次の瞬間、部下たちが返り討ちにあった光景を見て、頭領は己が目を疑った。
「な――――!!」
全く躊躇することなく剣を振るう龍の忍者に、頭領は動揺を禁じ得ない。龍の忍者の動きは鈍るどころか、更に加速して行くばかりだ。
「き、貴様!! この男の命がどうなっても良いと――――!?」
「――――斬れ!」
短く、低い声が龍の忍者から帰ってくる。
「――――!?」
何を言われたかが瞬間理解できず、目を白黒させる頭領に向かって、ハヤブサはさらにたたみかけて来た。
「聞こえなかったのか? 『斬れ』と、言ったんだ……!」
尋常ならざる殺気を漂わせながら、龍の忍者は歩を進めてくる。
「な………!」
「尤も――――そいつを斬っている間に、俺は貴様を斬るがな……!」
ハヤブサの周りで、バシバシッと黒い『気』の塊が爆ぜる。彼の身体から壮絶な龍の『燐気』が放たれていた。
「……………!」
(な、何て奴だ……! こいつは、仲間の命すら平気で見捨てると言うのか――――!?)
ふと頭領は、腕の中の人質の顔を見る。
シュバルツは、酷く穏やかな顔をしていた。まるで、自分がここで斬られるのが当然だと言わんばかりに。
(くそっ!!)
頭領は悟った。今自分が刀を突きつけているこの人間には、最早人質としての価値はない。自分がこの男を盾とした所で、目の前の龍の忍者は、この男の身体ごと、自分を斬りに来るだろうと。
そうなって来ると、今ここで抱え込んでいるこの男の身体は、今や自分にとっては荷物でしかない。下手をしたらこの男の動き一つが、自分にとっての獅子身中の虫になりかねなかった。
(おのれ……!)
そうこうしている間にも、龍の忍者は躊躇うことなく距離を詰めてくる。頭領は焦った。
この手の中の物。
『荷物』でしかないと言うのなら――――する事は一つだ。
荷物であるならば、『障害物』ぐらいにはなるだろう。
突如として頭領は、シュバルツの身体をハヤブサに向かって乱暴に蹴り飛ばす。
「――――!」
一瞬ハヤブサがそれに気を取られた隙に、頭領が動いた。
「死ねええええええい!!」
裂帛の気合と共に、頭領がハヤブサに向かって突っ込んでくる。
ドカッ!!
気と気が激しくぶつかり合い―――――そして、勝敗は決した。
頭領の剣は弾き飛ばされて地面に刺さり、ハヤブサの龍剣は、過たず頭領の身体を貫いて、いた。
「……一つ、教えておいてやろう……」
頭領に剣を突きさしたまま、ハヤブサの静かな声が響く。
「俺にとって『シュバルツ』と言う存在は………弱点になったり、足手まといになると言うことは、決してあり得ない」
(ハヤブサ……!)
彼の足元でその言葉を聞いたシュバルツは、思わず瞳を見開いて、ハヤブサを見上げていた。
「ただ――――俺にとっての『起爆剤』となるだけだ。龍の逆鱗に触れるが如くに……!」
ハヤブサのその言葉に、頭領からの答えはなかった。
そしてそのまま、彼は絶命して行った。
「……………」
ハヤブサは無言で頭領から龍剣を引き抜き、ブン、と、露払いをする。
「シュバルツ……!」
そして、愛おしいヒトへとハヤブサが向き直った瞬間。
「――――――」
シュバルツは物も言わずに昏倒してしまったのだった。
それからしばらくして、『色街』と呼ばれるこの一角に、シュバルツを抱きかかえたリュウ・ハヤブサの姿があった。
「湖月! 湖月はいるか!?」
「どうしたんだい? リュウさん」
ハヤブサの呼び掛けに応じて、豪奢な着物をいなせに着こなした、美しい女性が出てくる。彼女はこの『色街』を仕切る実力者であり、高級遊女であり――――その広い人脈と顔から、『情報屋』としての一面も併せ持っていた。ひょんな縁から湖月はハヤブサに助けられ――――それから彼女は何かと彼に便宜を図る様になっていた。
「金は払う。済まないが、一部屋貸してくれないか?」
「――――!」
ハヤブサが抱きかかえているロングコートに包まれたシュバルツの姿を見て、湖月もおおよその事情を察した。
「一番奥の部屋が空いてる。そこを使いな」
「感謝する」
ハヤブサは短く礼を言うと、シュバルツを抱きかかえたまま奥へと消えた。
(……あれが、リュウさんが夢中になっている『恋人』と言う訳だね……。なるほど……)
その後ろ姿を見送りながら湖月が煙管をくゆらせていると、控えていた侍女たちが声をかけて来た。
「姉様! 今の方誰ですの!? とても綺麗な方……!」
「腕の中にいらっしゃったのは、あの方の恋人でしょうか? 怪我をされていた様ですが……」
「今の方は私たちにとっても『特別』なんだ。だから、大切にしなくちゃいけないよ」
「……………!」
湖月の言葉に、侍女たちははっと襟を正す。
「それと……分かっていると思うけど、余計な事は詮索も口外も無用だよ。それが、この街のルールだから」
「はい」
「承知しております。姉様」
侍女たちの返事に、湖月もうんと頷く。
「さあさあ、あんたたちも仕事に戻りな。何かあったら、また私に報告しておくれ」
その言葉に頷いた侍女たちは、静々と湖月の前から退出して行った。
(やれやれ……今宵もまた、ざわめいた夜になりそうだね……)
湖月は煙管をくゆらせながら、霞む月を見上げていた。
そして――――現在に至る。
(シュバルツ……!)
部屋の中央に設えられた大きなベッドに、ハヤブサはシュバルツの身体をそっと横たえる。身体を覆っていたロングコートを取れば、その下にはシュバルツの、傷だらけの裸体があった。
(……………!)
ハヤブサはギリ、と、歯を食いしばりながら、その傷の一つに触れる。
猿轡を噛まされ、痛々しく縛られていた跡。殴られて、痣だらけになっている身体。折られてしまった足――――それだけでも、もう許し難いのに。
あの男たちに囲まれて
服を脱がされて
お前は――――何をされていたんだ。
あの男たちの中で
お前は――――!
(くそっ!!)
シュバルツがこんな目に遭ってしまったのは、間違いなく自分のせいだ。
彼が自分を助けてくれたから――――こんな目に。
悔やんでも悔やみきれない。
何故自分は、水を汲みに行く時、ろくに動く事も出来ない彼を独りにしてしまったのか。
自分を襲ってきた刺客たちが居ることぐらい、容易に想像できる状況であったのに――――!
悔み続けるハヤブサの目の前で、シュバルツの身体の傷が、静かに治っていく。折られてしまっていた足も、もう添え木を外しても大丈夫の様だった。
痛めつけられても、『無かった事』にしてしまえる、シュバルツの身体。後半刻もすれば、総ての傷跡も消えて――――すっかり元に戻ってしまっている事だろう。
(だがお前の心は……。心はそうじゃないだろう? シュバルツ……)
心も身体同様、相当ダメージを受けているはずだ。
あれだけの事を『無かった事』になど、簡単には出来ないだろう。
(どうすればいい……? 俺はお前のために、一体どうすれば――――)
ハヤブサはシュバルツの髪や肌を優しく撫でながら、彼が起きるのをひたすら待ち続けていた。
「う…………!」
身動きできない自分の身体に容赦なく男たちの『悪意』が降り注いでくる。
感じる所を執拗に嬲られ、それに少しでも自分が反応を返せば、嘲笑と侮蔑が返ってきた。
「見ろよ! こいつこんな所を触られて喜んでるぜ!!」
ち……違う……!
断じて……喜んでなど……ッ!
「おら! もっと女みたいに――――可愛らしく、啼けよ!!」
「んんっ!」
理不尽に打ちすえられ、殴られる身体。
……タスケテ……!
闇の中、虚空に向かってシュバルツは助けを求める。だけどその声を聞く者など――――当然誰もいる筈もなく。げらげらと笑い声が響き渡る中、ついに、シュバルツの内側に『指』が侵入してきた。
「ひっ!! あ………っ!」
イヤダ……!
イヤダ――――――!!
必死に指を拒もうとするのだが、身動きの取れない身体は指の侵入を許して行くばかりで。
嫌だ………!
この身体を好きにして良いのは1人だけだ!
それ以外の人間になど、私は――――!
………操(みさお)か………?
「――――!?」
不意に、闇から響いてきた声に、シュバルツの身体が固くこわばる。
………1人以外の人間に、赦したくない……。お前は、その人間に『操』を立てているのか……?
「あ……! 当たり前、だ……ッ!」
内部に蠢く指の感触を感じながらも、シュバルツは叫んだ。
「わ……! 私が……あっ! 身体を……許すのは……ッ! ハヤブサ、だけ……ッ!」
……滑稽だな……。その指を、お前は自ら咥え込んでいると言うのに……?
「―――――!?」
その声に、シュバルツは反論の余地を失う。
何故なら自分の腰が浮きあがり、自ら足を開いて――――進んでその指を、受け入れていたからだ。
「ち……違う……!」
シュバルツは必死に足を閉じようとするのだが、何故か足が動かない。指の侵入は、どんどん深まっていくばかりだ。
「ああっ!!」
ビクッ! と、その身をしならせるシュバルツに、闇から嘲笑の声が響き渡る。
……要するに、お前は誰でもいいんだ……。お前の『隙間』を満たしてくれるものならば、『ハヤブサ』ではなくとも、誰でも――――
「そ……! そんな……ッ! 違う……ッ!」
……違わないさ。現にお前は、喜んでいるのだろう? 随分淫らな身体だな……。
「嫌だ……ッ! 違………! あっ!! ああっ!!」
びくん! びくん! と、跳ねて乱れる身体に、闇からの声はそれ見た事かと嘲笑った。
……いい加減認めろ。お前は穢れた存在なんだ。そんな『モノ』が人間に『操』を立てた所で、立てられた方も迷惑するだけだろうよ……。
(ハヤブサ……!)
闇の中シュバルツは、ハヤブサの事を想う。
ハヤブサは、何時もまっすぐ私の事を想ってくれていた。
必死に、手を差し伸べてくれていた。
お前は『光』だと
かけがえのない存在なのだと
言ってくれた。
贅沢な願いなのだろうか。
その手を取りたいと願うのは。
過ぎた幸せなのだろうか。
彼の『想い』を、受け取り続けると言う事は――――
こんな、穢れた存在の私なんかが………!
「ハヤブサ……!」
いつしかシュバルツは、縋るようにその名を口にしていた。
「ハヤブサ……ッ!」
ここには居ないと
届かないと分かっていても
それに縋らずにはいられなかった。
不様だ。
滑稽だ。
何時から私は、こんなに弱くなってしまったのだろう。
それでも
それは『希望』だった。
シュバルツにとっては、唯一の――――
「ハヤブサ……!」
「シュバルツ!!」
「―――――!?」
闇を斬り裂く様に響く、ハヤブサの声。
光と共に、力強い彼の手が、シュバルツの腕を掴んで――――
「あ…………!」
シュバルツは、ようやく『悪夢』から、覚める事が出来たのだった。
目が覚めたシュバルツの視界に、心配そうにこちらを覗き込むハヤブサの顔が飛び込んでくる。
「シュバルツ……!」
「ハヤブサ……!」
茫然とこちらを見つめているシュバルツの瞳から、涙が零れ落ちて行く。その涙を掬い取ろうと、ハヤブサがシュバルツに向かって手を伸ばした、刹那。
「うわあああっ!! 嫌だああああああ!!」
シュバルツが突如大声を出して、ハヤブサの下で暴れ出した。
「シュバルツ!!」
ハヤブサは咄嗟に、シュバルツの両手を捉えて、ベッドに縫い付ける様に押さえ込んだ。だがシュバルツは、尚も足掻く事を止めない。四肢を突っ張らせながら体をのけぞらせ、必死にこちらの下から逃れようとしている。
「シュバルツ!! 落ちつけ!! 俺だ!!」
ハヤブサは必死に、シュバルツに向かって呼びかけた。だが、パニックに陥ってしまった愛おしいヒトは、なかなかこちらを見ようとしない。
「嫌っ!! 嫌だあああっ!!」
叫びながら暴れるシュバルツは、ハヤブサの手を振りほどく。それをハヤブサがもう一度掴んだ瞬間。
「離せっ!! 離せえッ!!」
ガキッ!!
シュバルツが思いっきりハヤブサを殴りつけた音が、部屋に響き渡った。
「痛………ッ」
加減なしのその拳に、流石にハヤブサも低く呻いてしまう。
「―――――!」
それを見たシュバルツが、ようやく動きを止める。ハヤブサを「ハヤブサ」として、認識したようだった。
「あ………! 私………は………!」
だが今度は、顔面蒼白になった愛おしいヒトが、カタカタと震えだしていた。
「シュバルツ……」
「ハヤブサ……! 私は……!」
「シュバルツ……大丈夫だ……」
ハヤブサは懸命に、その面に笑みを浮かべる。だが内心は、泣きたい気持ちでいっぱいだった。
完全に怯えきってしまっているシュバルツ。
彼が受けてしまった傷は―――――どれだけ深いのだろう。
「大丈夫、だから……」
そう言いながら、ハヤブサはシュバルツの髪にそっと触れる。
「―――――ッ!」
だが愛おしいヒトは、それを拒絶するかのように、己の顔を手で隠しながらその身体を強張らせた。いつものシュバルツであったなら、自分がこうすれば、必ず優しく抱きしめ返してくれていたのに。
たまらない。
悔しくて、堪らなかった。
あの優しくて柔らかいシュバルツを、今すぐ返して欲しいと思った。
「だからシュバルツ……! お願いだ……! 『俺』を拒絶しないでくれ……!」
ハヤブサは懇願しながら、腹の下のシュバルツの身体をそっと、抱きしめた。
「――――!!」
ビクビクッ!! と、過剰反応をして、腕の中で身体を強張らせ続ける愛おしいヒト。怯えたような小さな震えも消えない。
「シュバルツ……!」
ハヤブサの瞳から、涙が零れ落ちる。
悔しい。
あいつら――――もっと、苦しめてから殺してやればよかった。
「……ハヤブサ………」
自分を抱きしめてくれているのが『ハヤブサ』なのだと、シュバルツも頭では分かっている。自分は、ハヤブサになら何をされても良いと思っているし、殺されることすら厭わなかった。
だから、怯える事はない。
シュバルツは、必死に自分に言い聞かす。
愛すべき、愛おしむべき人が、自分を抱きしめながら、涙を流している。
慰めたい。
愛したい。
抱きしめ返すべきだと思った。
ピクリ、と、シュバルツの手が動く。
だが。
ペチャペチャと音を立てて、自分の身体を這いまわる男たちの舌。
「みろよ! こいつ感じているぜ!!」
「淫売だな! 液が垂れてるぞ!」
「抵抗するふりをして――――よがってんじゃねえのか?」
ゲラゲラと嘲笑され、無遠慮に撫でまわしてくる手と降り注ぐ悪意。何の脈絡もなく震われる暴力。足を開かされて、挿れられた指に、自分は――――
汚イ。
オ前ハ、汚イ。
ソンナオ前ニ、『人間』ヲ愛スル資格ナド――――
「…………!」
シュバルツは持ちあげかけていた手を、ぱたりと下ろしてしまった。
自分が触れたら、ハヤブサを穢してしまうと思った。
「ハヤブサ……」
代わりに、声をかけた。
ハヤブサが、自分のために涙を流し、抱きしめてくれている。
それでもう――――充分じゃないのか。
「ハヤブサ……ありがとう」
だからシュバルツはそう言った。自分のために泣いてくれたハヤブサに、感謝を込めて。
「―――――!?」
だが、その言葉を聞いたハヤブサは、逆にその身を強張らせた。
(何を……! 何を言っているんだ……!? こいつは――――!)
理解できなかった。
寝言を言っているんじゃないかと思った。
だってそうだろう?
こいつが『強姦』されたのは、俺を助けた所為なのに。
刺客に襲われ、大怪我した俺を助けて、川に飛び込んで
自身がオーバーヒートすることすら顧みずに、俺の手当てと介抱をしてくれて
ふらふらになっていたところを、俺を追ってきた刺客たちに――――襲われた。
この一連の流れで、シュバルツの一体どこに落ち度があると言うのだ。100%、全く以って俺の方が悪いじゃないか。俺が狙われて不覚をとってしまったから、こんな事になったのに。
だから、詰ってくれていいんだ。
責めてくれていいんだ。
恨まれこそすれ、『感謝』される筋合いなど――――全くないではないか。
それなのに、なぜ『ありがとう』なんて言葉が出てくる!?
頭悪いんじゃないのか!?
「……私は、『大丈夫』だから………」
続いて紡がれたシュバルツの言葉に、ハヤブサの中の堪忍袋の緒が、ついに切れた。
「………何を、言っているんだ? お前は……!」
「えっ?」
「本当に――――何を言っているんだ!? お前は!! 馬鹿か!?」
「ハ、ハヤブサ?」
腹の下で本気で戸惑っているシュバルツに、感情が抑えきれないハヤブサは、ついつい叩きつけるように怒鳴ってしまう。
「『大丈夫』な訳無いだろう!? そんな瞳をして、完全に怯えきってしまって――――『大丈夫』な訳がないんだ!!」
「…………!」
「それなのにお前は――――! こんな時ですら、自分の事を後回しにするのか!? 悲鳴を上げている自分を無視して、他人の『心配』をするのか!? そんな事をしている場合か!?」
「ハ……ハヤブサ………!」
自分に怒鳴られた愛おしいヒトが茫然と瞳を見開き、心底怯えたようにカタカタとその身を震わせている。
(くそ………ッ!)
今にも壊れそうな様相を湛えたシュバルツに、ハヤブサはギリ、と、歯を食いしばった。
分かっている。
本来ならば、深い傷を負ってしまったシュバルツを気遣って―――――優しく、ゆっくりとその傷を癒して行ってやるのが正解なのだろう。
彼の怯えが取れるまで、優しく傍にいて。
彼の負った傷に、そっと寄り添って。
彼が再び、その身を許してくれるまで、優しく包み込むように――――
(だがそれをしている間、シュバルツは何を思い出す?)
ハヤブサは自分に問いかける。
そうして自分がシュバルツに寄り添っている間にも――――シュバルツは思い出し続けてしまうのではないのか。自分を汚した男たちの事を。それは結局、男たちによるシュバルツに対する暴力や辱めが、継続して行われている事に他ならない
(誰がそんな事を許せるか……!)
ハヤブサは強く思った。
我慢できない。
シュバルツが、自分以外の男たちの事を、何時までも覚えているなんて。
そんな事を、許すくらいなら――――
「言え。シュバルツ」
「な、何を……?」
腹の下で怯える愛おしいヒトを強く押さえ込んで、ハヤブサは問いかけた。
「お前は一体、あいつらに何をされたんだ?」
「――――ッ!!」
息を飲み、身を強張らせるシュバルツに、ハヤブサは更に答えを要求した。
「言え。洗いざらい、総てを」
「い……嫌だ……! そんな事を聞いて……どうするんだ………!」
当然その問いに答えたくないシュバルツは、懸命に身を捩って、ハヤブサの下から逃れようとする。だがハヤブサがそれを許す筈もない。シュバルツを押さえ込む手に、さらに体重をかけた。
「あっ!」
強く押さえ込まれたシュバルツから、小さな悲鳴が上がる。だがそれで、シュバルツの抵抗が止む筈もない。ハヤブサはギリ、と、歯を食いしばった。
「言え! かくすな、シュバルツ……!」
ハヤブサの要求に、しかしシュバルツはフルフルとその首を横に振った。穢されたのは自分だ。これは自分の問題だった。故に、自分だけがその苦しみに耐えれば良いだけの話だと思った。
「い、嫌だ……! これは、私だけの問題だ……! お前には、関係な――――」
「関係ある!! お前は俺の『恋人』だッ!!」
「――――!」
はっと瞳を見開いてこちらを見つめてくるシュバルツを、ハヤブサも真正面から見つめ返した。
「お前は、俺だけのものだ!! 俺も、お前だけのものだ!!」
「ハ……ハヤブサ………!」
「そんなお前が……俺以外の奴らの事を覚えているなんて……耐えられるか……ッ!」
「……………!」
吐き捨てられるように紡がれたハヤブサの言葉に、シュバルツは息を飲んだ。
私は、ハヤブサだけのもの―――――確かに、そうで在りたかった。
だけど自分の身体は、ハヤブサ以外の者にも『反応』してしまった。これは、立派な裏切り行為ではないのかとシュバルツは思うのだ。
「そ………そうかもしれないが………。だけど、ハヤブサ……私は――――」
「『穢されたから俺の恋人としてはもう居られない』などと――――馬鹿な事を言い出すなよ、シュバルツ……!」
そう言いながらハヤブサが、殺気だった目でシュバルツを睨みつけてくる。
「―――――!」
「俺はお前を手放す気なんて……一欠けらもないのだからな!」
そう言うが否や、ハヤブサはシュバルツの手を取って、強引に後ろ手に絡め取る。壁にかけてあった絹の紐をもう片方の手で素早く手に取ると、そのままシュバルツを縛り始めた。
「あ……ッ!? 何を……!?」
「お前は確か――――こんな風に縛られていたな……」
ビクッ! と、身を硬直させるシュバルツには構わず、ハヤブサはその行為を続ける。シュルシュルと衣擦れの音を立てながら、シュバルツの身体は、まるで飾り付けられるかのように縛りあげられて行った。
「い……! 嫌だ……! 止めてくれ……ッ!」
「止めて欲しかったら言え。シュバルツ。自分が何をされたのかを――――」
「そ、そんな……! 言える訳無いだろう……!」
愛おしいヒトが、心底怯えたようにその身を震わせている。その間にシュバルツを縛り終えたハヤブサは、その背中にチュッ、と、音を立ててキスをした。
「――――!」
ビクッ! と、その身を震わせ、過剰反応するシュバルツ。そんな彼をハヤブサは後ろから優しく抱きしめると、シュバルツ自身にそっと手を伸ばした。
「あ………!」
懸命に身を捩り、シュバルツはそれから逃れようとする。しかし、ハヤブサがそれを許す筈もない。逃げるシュバルツを追いかけて、優しくそこへの愛撫を続けた。
「く………ッ!」
ビクビクッ! と、シュバルツは身体を震わせる。だが彼は、それ以上は拒否するかのように首を振った。
「ハヤブサ……! 本当に無理だ……! 止めてくれッ!」
「逃げるな、シュバルツ……。力を抜いて――――」
「無理……! 嫌だぁ………!」
シュバルツにとって縛られてそこを触られると言う行為は、そのままあの男たちとの行為の再現に他ならなかった。
―――見ろよ! こいつ勃ち上がってるぜ!
―――液まで垂らして……
―――淫売だな!
―――雌犬みたいに腰を―――
「う………! う………!」
シュバルツの脳裏に、男たちの罵詈雑言と、下卑た笑いと、おぞましい感触がどうしても甦って来てしまう。
違う……!
感じてなどいない……!
反応を、返したくない――――!
「違う……! 嫌だ………!」
シュバルツは弱々しく首を振り続けて、それに抗っていた。
(シュバルツ……!)
シュバルツへの愛撫を続けながら、ハヤブサは唇を噛みしめていた。
元々シュバルツは、複雑な出自を持つアンドロイドだ。それ故に彼は、己の『生』もなかなか肯定できなかったし、まして自身の性欲など、言わずもがなだった。それが、彼を禁欲的な性格へと仕立て上げ、そして、孤独の中へと追いやっていた。
独り、闇の中で歩み続けていたシュバルツ。その手を、ハヤブサが無理やり取った。
酷く惹かれた。
どうしても――――『彼と共に生きたい』と、自分が願ってしまったから。
その身体を無理やり開いて――――そして、教え込んだ。
愛し、愛される世界の素晴らしさを。それを実現する手段の一つとして、性欲があるのだと言う事を。
はじめは、それをなかなか肯定できず、戸惑っていたシュバルツ。
だが、回数を重ねるに連れ、ハヤブサに愛を教え込まれて行くうちに――――綺麗な感性と身体を持つこのヒトは、それを素直に受け入れて行った。ハヤブサの腕の中で、その愛を受け入れ――――妖艶にあでやかに、大輪の花を咲かせるようになっていた。
二人だけの幸せな愛の世界。
これがずっと続くものだと、ハヤブサは信じて疑っていなかった。
だけど、今のシュバルツは――――
「ん………! く………!」
は、は、と、短い息をしながら体を震わせ、ハヤブサの愛撫を全身で拒絶している。ハヤブサに愛され続けるそこは、なかなか勃ち上がる気配を見せなかった。
「シュバルツ……」
ハヤブサは、酷く淋しい気持ちに襲われていた。
手塩をかけて愛を育み、せっかく綺麗で艶やかな花を咲かせていたのに――――
突然やってきた男たちにいきなり鉢を叩き割られ、花弁をむしられて―――――茎や葉をズタズタに切り裂かれてしまった。そんな心持になってしまう。見るも無残に踏みにじられてしまったこの花を、一体自分は、どうすればいいと言うのだろう。
この花をあきらめて、新しい種を求めるか。
それとも、もう一度咲くと信じて、世話をし直すか――――
だけど、今から土を寄せ集めて、もう一度鉢に入れた所で、このボロボロになってしまった花は、もう二度と咲かないだろう。鉢の中から何かが生えて来たとしても、それはきっともう、別の種類の何かだ。
「……………」
それでもハヤブサは、地面に散らばってしまった土を、もう一度寄せ集める事を選択した。
自分は、この花が良いんだ。
どのようになろうとも、この花を、愛し抜きたいんだ。
割れてしまった鉢よりも、少し小ぶりの鉢に、土を入れ直す。そこにボロボロになった茎を、そっと挿し込んだ。
(大丈夫……。この花は強い……)
ハヤブサは自分で自分に言い聞かせる。
絶対に、茎の中や土の中にその根は残っているんだ。ならばどんな形であれ――――この花は、必ず芽を出す筈なんだ。
(しかし……酷く愚かな事をしているのかもしれない……)
歯を食いしばり、がたがたと震え――――今にも壊れそうなシュバルツを見つめながら、ハヤブサは思った。これ以上彼に愛の行為を強要したら、本当に、今度こそ彼はこのまま壊れてしまうかもしれない。
(それでもいい)
ハヤブサは思った。
このまま彼が壊れてしまっても、その彼をまた俺は愛そう。
あの艶やかな花が二度と見られなくても、この花をずっと愛して行こう。
だからシュバルツ、お願いだ。
このまま壊れてしまうのならば、他の奴らになど壊されないで。
せめて―――――俺の手で、壊れてくれ。
どうなろうとも、俺はお前を愛し続けるのだから。
「ん………!」
歯を食いしばり、震え続ける愛おしいヒトは、なかなかハヤブサの愛撫を受け入れようとしない。ハヤブサは小さくため息を吐くと、シュバルツの牡茎の根元に、カチリと音を立てて『リング』を取り付けた。
「――――!」
それを見た愛おしいヒトが、はっと息を飲む。
「覚えているか? これは、男性の射精を阻害する『拷問道具(リング)』だ。効果は……お前が一番よく知っているよな?」
「な…………!」
ハヤブサのその言葉に、愛おしいヒトの顔色が、さらに蒼白になった。
「や、止めてくれッ!! こんな事までされなかっ………!」
「じゃあ、お前は何をされたんだ?」
シュバルツの叫びが終わらぬうちに被さってきたハヤブサの言葉に、シュバルツは再びぐっと、押し黙ってしまう。
「教えてくれよ……シュバルツ。お前は一体、何をされたんだ?」
「そ、それは……!」
戸惑った表情を見せる愛おしいヒトに、ハヤブサはにこりと微笑みかけると、思わせぶりにリングに触れた。
「話してくれれば、外してやるよ。『これ』を」
「――――!」
リングと同時にするりと触れられた自身への刺激に、シュバルツの身体がビクン! と跳ねる。しかしやはり――――愛撫を受け入れるまでには至らなかった。
「無理………! 無理だ………!」
壊れそうな小さな声で、儚く反論してくるシュバルツに、胸が締め付けられる。
愛おしさが命じるままに、ハヤブサはもう一度、シュバルツを後ろから抱きしめた。
「ほら………シュバルツ………」
ちゅぷっと音を立てて、ハヤブサはシュバルツの耳を口に含む。
「――――!」
ビクン! と、跳ねて硬直する、愛おしいヒトの身体。
「遠慮なく、叫んでいいぞ」
「な…………!」
「ここは『色街』の一角だ。ここでお前がどんなに泣こうが喚こうが、決して邪魔は入らない。だから安心しろ。時間もたっぷりある……。お前が話してくれるまで――――俺はこれを続けるからな」
ハヤブサはそう言いながら、シュバルツの耳をペチャペチャと音を立てて愛し始めた。
「そ、そんな………! あっ!!」
ハヤブサの愛撫に、一瞬反応するシュバルツ。
しかしすぐに声を殺し、歯を食いしばり――――身体を硬直させて、ハヤブサの愛撫を拒絶しだした。
(シュバルツ……!)
ハヤブサは、得も言われぬ淋しさに襲われた。
シュバルツは今――――自分の愛撫を受けながら、自分の方を見ていない。恐らく、彼は自分を穢した男たちの方を、思い出してしまっているのだろう。
淋しい。
お前を抱きしめているのは、『俺』なのに。
お前を愛しているのは、『俺』なのに――――
どうすればいいのだろう。
このまま優しく愛撫を続けるべきなのか。
それとももっと強引にシュバルツの身体を割り開いて――――彼を犯せばいいのか。
(でも、暴力に訴えるのは、きっと違う)
ハヤブサはそう思って頭をふる。
今、壊れかかっているシュバルツを、力によって屈服させる事は、おそらく酷く簡単だろう。
だけどそれは違うのだ。
自分は、シュバルツを屈服させたいのではない。愛し合いたいのだ。
暴力による屈従など――――あの男たちと何ら変わらないではないか。
だからと言って、今シュバルツに対して自分がやっている行為も、あの男たちの物とそんなに変わらないように思える。
劣情と欲と熱を孕みながら、彼の身体を弄んでいる事に、大差はない。
(どうすればいい……? どうすれば、お前はもう一度、『俺』を見てくれるんだ……?)
もう一度、綺麗で艶やかなシュバルツを見たい。
それは、贅沢な望みなのだろうか。
(せめて、声が聞きたい……。お前の、甘やかな声が……)
そう願うハヤブサの手が、声を殺し続けるシュバルツの唇へと滑って行った――――。
(嫌だ……! 嫌だ―――――!)
今、自分の身体に触れて来ているのは『ハヤブサ』なのだと、シュバルツも頭では分かっている。
だが、耳元で響く、ペチャペチャと言う水音。荒い息づかい。自分を暴き立てようと肌の上を蠢く指が―――――
どうしても、思い出させてしまう。あの男たちの事を。
淫売!!
雌犬――――!
喜んで、腰を振って………!
侮蔑と嘲笑の声が、どうしても頭の中に甦って来てしまう。
(違う……! 私は喜んでなどいない……! 感じてなんか――――!)
「あっ!!」
なのに時折、肌の上を滑る指が、敏感な所に触れてくるから――――望まぬ反応を返してしまう。
「……………」
そのたびに、誰かから何かを言われ、またそこを優しく触られる。
「…………ッ! …………!」
シュバルツはそれを、唇を噛みしめながら懸命に耐えた。
聞きたくない。
侮蔑の言葉なんか。
触るな。
浸食しようとするな。
私を弄ばないでくれ――――!
「……………」
耳元で誰かが何かを囁きながら、肌の上を蠢いていた指が、胸元から首、そして顎から唇へと滑って来る。その指は、しばらく唇を優しくなぞり続けていたかと思うと、口の中に侵入しようとしてきた。
嫌だ……!
挿入(はい)って来るな――――!
触 る な ――――!!
少し開いたシュバルツの唇に、その指はするりと入り込んでくる。シュバルツはそれに向かって、思いっきり噛みついた。
「――――ウッ!」
「――――!」
耳慣れた声にシュバルツが驚いて振り向くと、自分を抱きしめていたハヤブサと視線があった。
「いいぞ。そのまま噛み千切っても……」
そう言いながら、瞳に少し哀しげな色を湛えたハヤブサが、優しく微笑む。
「…………!」
それでようやくシュバルツは、自分を抱きしめていたのはハヤブサなのだと、この指はハヤブサの物なのだと言う事を、思い出していた。
「あ…………!」
慌ててシュバルツは、噛んでいた指を口の中から解放する。ハヤブサの指には歯型が深く刻まれて、そこから血が滲んで来ていた。
(何故……? 何故だ……? 私に触れてくれていたのは、ハヤブサだと分かっていたのに――――!)
滲み出るハヤブサの血を見ながら、シュバルツは茫然とするしか無かった。
自分を抱きしめているのは確かにハヤブサなのだと、シュバルツは、頭では理解していたつもりだった。
なのに、いつの間にか、自分は分からなくなってしまっていた。肌の上を滑る指が、誰の物なのか。熱を持って触れてくるその唇が、誰の物なのか――――
何故なのだろう。
もう本当に、自分は壊れてしまっているのだろうか。
「……………」
血が滴り落ちているハヤブサの指。
治したい。
癒したい。
愛したいと願って、シュバルツはその指に向かって口を近づける。
だが。
好き者なんだろうよ!!
穢れた存在――――
お前の様なモノに、『操』を立てられても――――
「……………!」
次々と浮かぶ自分を責める言葉に、シュバルツの動きは阻まれてしまう。
(駄目だ………)
ハヤブサの指の前で震えていた唇は、再び固く引き結ばれ――――シュバルツは、その頭を垂れてしまった。
駄目だ。
私はハヤブサに触れられない。
愛する資格もない………!
最低だ。
ろくに彼に身体を許す事も出来ない自分。
このままではきっと――――自分は彼の『負担』にしかなれないだろう。
それならばいっそ、自分をこのまま突き放して欲しい。
ここで終わりにして欲しかった。
彼にはもっと――――ふさわしい『人間』のパートナーが、いる筈なのだから。
「シュバルツ……」
愛おしいヒトの頬に流れる哀しげな涙を拭いたくて――――ハヤブサは手を伸ばす。
だがその頬に触れる直前に、シュバルツから声をかけられた。
「ハヤブサ………」
「どうした? シュバルツ……」
「…………」
ハヤブサの問いに、一瞬唇を震わせる愛おしいヒト。それからしばらく何かに逡巡しているような仕種を見せたが、やがて、意を決したようにその口を開いた。
「………何をされたのか、話す……」
「―――――!」
「話すから………」
(話せば、これを終わりにしてくれるだろうか)
乾いた心で、シュバルツは思った。
こうして縛られる事も
求められる事も
好きだと言ってくれる事も――――
お願いだ。
もう止めてくれ。
きっと 私は モウ 壊レテ ル カ ラ
「お願いだ……。少し、私から離れてくれ………」
(……………!)
シュバルツのその言葉に、ハヤブサは胸をナイフで刺されたような衝撃を受ける。
本当は、数瞬たりとも離れたくはない。
ずっと愛おしいヒトを、この手の中に抱いていたい。
だけど、離れた方が、シュバルツが話しやすいと言うのなら――――
「分かった……」
ハヤブサは涙を飲んで、彼の言う事を聞いた。やっとの思いで彼から手を離し、少し後ろへと下がった。
するとシュバルツの方からも距離を取られてしまうから、ハヤブサは本当に突っ伏して泣きそうになってしまう。だけど、彼の望みは聞かねばならぬと、ハヤブサは、必死に自分に言い聞かせていた。
「……離れたぞ? それで? お前は何をされたんだ?」
泣きたい気持ちを押し隠して、ハヤブサはシュバルツに問いかける。
「――――――……………」
まだ、尚も逡巡している様なシュバルツであったが、やがて意を決したのか、震えるその唇を開いた。
「く………口以外の、総ての場所を……舐められたり、触られたり、した………」
「口以外?」
問うハヤブサに、シュバルツは少し無理やり作った笑顔を見せる。
「……猿轡を……噛まされていたから………口は、触れなかったのだろう………。そ……そして…………指……も、挿れられ………て………」
嫌で嫌で仕方がなかった。
なのに、自分の身体はその愛撫に『反応』してしまった。
勃ち上がらせて愛液を滴らせ――――声を上げてしまった。
それ故に――――『淫売』と『雌犬』と、罵られ、嘲笑された。
だけどシュバルツは、その言葉による暴力を、どうしても言う事が出来なかった。
この壊れかけたアンドロイドにも、僅かばかりの矜持が残っていたと言う事なのだろうか。
そう考えると、妙に可笑しかった。
「それで………終わりか?」
その面に自嘲的な笑みを浮かべながら押し黙ってしまったシュバルツに、ハヤブサはそう声をかける。シュバルツはこくりと頷いた。
「そうか………」
酷く穏やかな、ハヤブサの声。シュバルツはただ瞳を閉じて、その身を固くこわばらせている事しか出来なかった。
酷く惨めだった。
口にしてみれば、何て事無い事の様にも思う。だけど、自分には耐えがたかった。
全身を隅々まで触られ、汚された事が。
それに、あさましくも『反応』してしまった自分の身体が。
罵られてきた言葉が。降り注いできた『悪意』が―――――
たまらなく恐ろしかった。
こんな事では駄目だと自分を叱咤してみても。
折れてしまった心は、自分でもどうしようもない程、立ち上がってはくれなくて。
本当に駄目だ。
私は――――何時からこんなに弱くなってしまったのだろう。
このままでは自分は、ハヤブサを受け入れる事も出来ずに、ただ彼の負担になっていくしかないように思えた。
だから、早く彼から、最後通牒を突きつけられたいと、願った。
「じゃあ………シュバルツ………」
(これで、終わりにしよう)
ハヤブサから言われるのはこの言葉だと信じて、シュバルツは唇を噛みしめた。だが次の瞬間、伸びてきたハヤブサの手は、シュバルツの頬を優しく撫でた。
(―――――!?)
ビクッ! と、顔を上げ、瞳を開けるシュバルツ。するとそこには、酷く幸せそうに微笑む、ハヤブサの姿があった。
(え…………?)
ハヤブサの笑顔の意味が分からず、激しく戸惑うしかないシュバルツ。ただ茫然としていると、頬を撫でていたハヤブサの手が、そのまま唇へと滑ってきた。
「……本当に……この唇を知っているのは……世界に俺だけしかいないって、事だな………」
「―――――!」
シュバルツが驚いた様に、自分を見つめ返しているのがハヤブサには分かった。
(呆れられたかな)
そう思い、苦笑する。
だけど、自分は嬉しかった。
酷く些末で些細な事が―――――自分でも呆れるほどに、嬉しかった。
知らなかった。
自分しか知らないシュバルツがあると言うだけで
こんなにも――――幸せな心地になれるだなんて。
「シュバルツ………」
ハヤブサの手が、そっと彼を抱き寄せて――――
「あ………!」
想いを込めて、キスをする。
「…………!」
瞬間強張ったシュバルツの身体だが、何度か唇をついばむように押し当てているうちに、彼の身体から、徐々に力が抜けて行く。薄く開いた唇の隙間から、そっと舌を忍ばせた。
「ん…………」
ただただ優しいキスを受け入れて行くうちに、シュバルツの胸の奥に、ポッと熱が灯る。それは――――暗い闇に沈んで行きそうになっていた彼の心を、確かに優しく照らし始めていた。
「……………」
キスを終えたハヤブサは、そのままシュバルツの額に、唇を押し当てる。
「ハ、ハヤブサ?」
腕の中で戸惑うシュバルツに、ハヤブサは優しく声をかけた。
「そのまま……じっとしていてくれ……」
そう言ってハヤブサは、シュバルツの額の隅々まで、自身の唇で触れて行く。それが終われば、眉、瞳、鼻、頬――――余すことなく、唇を落とし始めた。
(……ハヤブサ……! まさかお前、そうやって私の全身を、くまなく触れて行くつもりか!?)
ハヤブサの意図を悟ったシュバルツは、訳の分からない焦燥感に囚われた。
確かに、あの男たちに全身を触られたと言った。だけど、ハヤブサがそんな事をする必要はないと思った。そんな事をしたら、ハヤブサの唇の方が穢れてしまう様な気がした。
「ハ……ハヤブサ……! 待て……!」
だからシュバルツは、ハヤブサの腕の中で足掻く。だけどハヤブサが、それを許す筈もなかった。
「いいから!! じっとしていろ!!」
「……………!」
ハヤブサに強く抱きしめられて、シュバルツは身動きとれなくなってしまう。シュバルツが大人しくなったのを確認してから、ハヤブサは再び唇をシュバルツの身体に押し当て始めた。
(シュバルツ……)
シュバルツの身体に唇を押しあてながらハヤブサは思う。全身をくまなく嬲られる様に触られながらの罵声と暴力。どれほど恐ろしかった事だろう。どれほど傷ついた事だろう。
知っていた。
シュバルツが理不尽に罵られていた事は。洞窟の中の異常に気が付いた時から、嫌でも自分の耳に入って来ていた。
罵られながら、嘲笑われながら、男たちの間で揺れていたシュバルツの折れた足を見た瞬間、自分の視界がかつてないほど真っ赤に染まった。助け出した直後のシュバルツのボロボロだった姿は、きっと一生忘れる事が出来ないだろう。
(……俺のせいだな……)
暴力の跡も辱めの跡も今は消えて、綺麗になっているシュバルツの肌を愛しながら、ハヤブサは思った。
自分の歩む道は修羅の道だ。当然敵も多い。平和な生活など――――望むべくもなかった。
自分と親しくなれば、そう言う修羅の業に巻き込まれる――――それを、自分は知っていた。だから、独りで歩んで行くつもりだった。そして、独りで死んでいくつもりだった。
なのに―――――お前と出会ってしまった。
願ってしまった。
その手を取りたいと。
共に生きたいと。
傍にいて欲しいと―――――
孤独の中で佇む光を、愛さずにはいられなかった。
幸せにするとは言えなかった。だが、大切にするつもりでいた。
それが――――
結局彼を、このような目に遭わせてしまった。
俺が不覚をとってしまったばかりに。彼は俺を、助けてくれたと言うのに。
自分の傍にいれば、自分の『業』に巻き込まれる。
場合によっては、彼を深く傷つけてしまう。
それが分かっていて―――――
それでも彼を手放したくないと、足掻いてしまう俺はいったい何なのだ。
なんて業の深い―――――『人を愛する資格がない』とは、まさしく、自分のためにある言葉なのかもしれない。
(シュバルツ……!)
シュバルツの肌を優しく愛しながら、ハヤブサはいつしか涙を落していた。
「う…………!」
ベッドに優しく押し倒され、そのまま肌をそっと愛してくるハヤブサの唇。
その酷く優しい刺激にどうしたらいいか分からず、シュバルツはただ戸惑うばかりだ。
こちらを浸食してくる訳でもなく、暴こうとする訳でもなく、ただ、ひたすらに優しく触れてくるその唇に、自分は、一体どうすればいいと言うのだろう。
ふと、シュバルツの肌の上に、ポトリ、と、水滴が落ちる。
「…………?」
怪訝に思ったシュバルツが瞳を開けると、静かに涙を落としているハヤブサの姿が視界に飛び込んできた。
(ハヤブサ……! 泣いている……?)
ハヤブサの涙の意味が分からずに、シュバルツは困惑する。
何故だ……?
あの忍者団の前で不覚を取ってしまったのは自分だ。その結果、乱暴されたとしても、それは自分の責任だ。
ハヤブサは、何も悪くないのに――――
「ハヤブサ……」
「…………」
シュバルツの呼び掛けには答えず、ただひたすら、涙を落としながら肌に優しく触れてくるハヤブサ。唇と共に、落ちてくる涙が――――シュバルツに、ある光景を見せ始めた。
シュバルツの身体を構成しているモノは、『DG細胞』――――それは、ヒトの『ココロ』に感応する能力を持つ。それが、ハヤブサの『ココロ』に感応して、ハヤブサの背後に、『影』を浮かび上がらせていた。
その影は、『ハヤブサ』の形をしていた。
ハヤブサの影は背後に背負っている龍剣を抜き放ったかと思うと。
「―――――!!」
いきなり、シュバルツに愛撫をしている本体に向かって、斬りつけ始めた。
「…………!」
はっと息を飲むシュバルツの目の前で、その影による攻撃は何度も続いた。
苛烈に。
容赦なく。
何度も何度も斬りつけられるその背中から、どす黒い『血』が辺りに飛び散った。
「ハ、ハヤブサ……!」
「……………」
影による攻撃で、ハヤブサの本体がどうこうなっている訳ではない。だが、シュバルツに見せられる心象風景の中のハヤブサは、既に血だらけだった。血の涙を流し、血反吐を吐きながら―――――それでも彼は、シュバルツへの愛撫を続けていた。そして、そんな彼を、影は容赦なく斬り続けていた。
(だ……! 駄目だ……! ハヤブサ……!)
シュバルツは、ハヤブサが自分を責め過ぎていると悟った。
このままでは死んでしまう。
ハヤブサの『ココロ』が死んでしまう。
そんな風に、自分を責めるな、ハヤブサ――――!
「ハ、ハヤブサ……ッ!」
斬り続ける『影』の攻撃を、何とか止めさせたいと願って、シュバルツは足掻く。だが、絹の紐によってきつく縛られているシュバルツの身体は、なかなか自由にならなかった。
「く………!」
(くそ……ッ! 相変わらず縛るのがうまい奴め……!)
足掻きながらシュバルツは舌打ちをする。自分は割と縄抜けは得意な方だが、ハヤブサが本気で縛った縄からは、未だに抜けられたためしがない。龍の忍者の技術の確かさに感心するほかないのだろうが、抜けられないのは、自分の腕の未熟もあると思った。
「ハヤブサ……ッ!」
縋るように叫ぶシュバルツの身体に、また、べシャッと音を立てて、ハヤブサのどす黒い血が飛び散っていた。
(シュバルツ……!)
シュバルツの肌に優しく唇を落としながら、彼が足掻いている姿をハヤブサは目の端に捉えていた。
(嫌なのだろうか)
シュバルツの足掻く姿を見て、ハヤブサはそう感じた。
だが自分は、たとえそうだとしてもシュバルツを手放す事は出来なかった。
こんなにも愛おしいのに、どうして彼を離す事が出来るだろう。
本当に――――何て、業の深い……!
自分を責め立てながら、それでもなおハヤブサは願う。
お願いだ。
逃げないでくれ。
足掻くシュバルツの身体を押さえようと、ハヤブサの手がシュバルツの身体の上を滑る。
それが、シュバルツの敏感な部分と意図せずに――――擦れ合った。
「は……! あ………ッ!」
予期せぬ刺激にシュバルツの身体は勝手に跳ね、知らず声が出てしまう。その声を聞いた刹那、ハヤブサと、ハヤブサを斬りつけていた影の動きが、止まった。
(止まった……?)
止まった影を確認するように、シュバルツはその影を見つめる。影の方もまた、シュバルツの方をじっと見ているように見えた。
「……………」
しばし、奇妙な沈黙が続く。しかし、シュバルツの方にこれ以上動きが無いと見て取った影は、再びハヤブサに向かって剣を振りあげ始めた。
(駄目だ!!)
その影の動きを止めたいシュバルツは、今度は意図的に『声』を上げてみた。
「ああっ! あ………っ!」
その声を聞いた影の動きが、また止まる。
(やはり……。私の『声』に、反応している………)
そう確信した彼は、震える唇をぎゅっと噛みしめた。
今は、手段を選んでいる場合ではない。
とにかく――――あの『影』の動きを、止めなければ……!
「ん……ッ! あ………ッ!」
ハヤブサの唇に触れられている部分の感度を、最大限にあげる。ハヤブサの唇の動きに合わせて声を上げ、喘ぎ、その身を少し大袈裟にしならせた。
――――淫売!!
(…………!)
心の中で、自分を責める言葉が響き渡る。だけど、それがどうしたとシュバルツは思った。
ハヤブサのあの『影』の動きを止める事が出来るのならば、自分は『淫売』でよかった。『雌犬』でよかった。それでハヤブサの『ココロ』を守ることができるのならば――――自分が『汚泥』を被る事など、容易い事ではないか。
だからハヤブサの『影』よ、お願いだ。
どうかその人の『ココロ』を、それ以上斬りつけないでくれ。
どうしても斬りつけたいと言うのであれば、私の方に来い。
はしたない声を上げ
娼婦の様によがり、喘いでいる私の方に。
こんな下卑た存在――――お前が天罰を与えるに、ふさわしいだろう?
「……………!」
シュバルツの、挑発的とも言える媚態に、ハヤブサの愛撫にも知らず熱が入ってしまう。
肌に優しく落とされていた唇は、いつしか跡が残るほどその肌に吸いつき、加えて指も、シュバルツを暴き立てるかのように、その肌の上を蠢き始めた。
「あっ!! ああっ!!」
シュバルツの嬌声もしなる身体の動きも、一段と大きなものになる。それに気付いたハヤブサは、はっと我に帰って動きを止めた。
(何をやっているんだ!? 俺は……! 傷ついたシュバルツの身体を、優しく愛そうと思っていたのに……!)
熱と欲を孕みながらこのヒトの身体を暴き立てる行為は、あの男たちがシュバルツにしていた事と何ら変わりがない。このヒトを踏みにじってしまっていないかと、ハヤブサは思わずシュバルツの顔を覗き込んでいた。
「……………」
愛おしいヒトはその瞳に涙をにじませながら、は、は、と、短い息をして、その身を小さく震わせている。だが、ハヤブサが見つめる視線から、その眼差しを逸らす事はなかった。
「シュバルツ……」
「どうした……。ハヤブサ……」
涙で潤んでいるのに、その瞳には酷く力強い意志が宿っていた。
ハヤブサが惹かれてやまない、あの強いシュバルツの意志が――――
「私は……大丈夫だから……」
「シュバルツ……!」
「続けて……」
「……………!」
その愛おしいヒトの様に、ハヤブサの胸が何故か締め付けられた。
暴力と凌辱に傷つけられたお前。
今も同じような状況でその身体を弄ばれようとしているのに。
恐怖を感じない訳が無いだろう。
身体が震えているじゃないか。
その瞳には、涙が滲んでいるじゃないか。
なのに――――お前は、俺の前に進んでその身を投げ出そうと言うのか?
どうして
何故――――
ああ………シュバルツ……!
何て、いじましい………!
そして、何て愛おしい――――
「シュバルツ……!」
自身の中の愛おしさが命じるままに、ハヤブサはシュバルツの肌の上に指を滑らせる。その指はシュバルツの胸の先端を捉えると、そこを優しく擦りだした。
「……はっ! あんっ!」
弱い所を撫でられて、ビクビクッ! と、愛おしいヒトの身体が跳ねる。その可愛らしい様にハヤブサはふわりと微笑むと、喘ぐその唇を優しく塞いだ。
「……ん……! ふ………! んぅ……!」
その間にも、胸への優しい刺激は続く。それ故にシュバルツは、ハヤブサの下で、その身を扇情的にしならせ続けなければならなかった。
「……………」
少し長めのキスを終え、涙をにじませてとろんとした眼差しの愛おしいヒトが、飲み切れなかった唾液を口から溢れさせながら、ぜいぜいと喘ぐ。そのヒトの様は、酷く妖艶だった。そして、素直に美しいと感じた。
(…………ッ!)
――――淫売!
――――淫売!
シュバルツの中で、自分を責める声が止む事はない。自分が裸で縛られている状況に、あの男たちに囲まれている映像が、自身の中で何度もフラッシュバックしてしまう。
(それでもいい……! それでも……!)
シュバルツは、ハヤブサの背後にいる影を見ながら、必死に己と戦っていた。ハヤブサの形をした『影』は、抜刀したまま二人の様子をじっと見ている。
あの血だらけのハヤブサの姿を見るぐらいなら、自分が苦しめられた方がよほどマシだとシュバルツは思った。
「シュバルツ……」
つい、と、ハヤブサの手が頬に滑って来る。シュバルツがそれにビクッ! と、身を固くすると、ハヤブサの唇が、そっと耳元に降りて来た。
「……綺麗だよ………」
「……………!」
はっと、息を飲むシュバルツにハヤブサはにこりと微笑みかけると、再びその肌の上に唇を滑らせ始めた。その唇は胸から腹、そして、腰へと彼の肌を愛して行く。そして――――
シュバルツの中心が、勃ち上がって来ているのを、ハヤブサは確かに見た。
「シュバルツ……!」
ハヤブサがそっと、そこを手で愛し始めると、シュバルツの腰が浮きあがり、乱れ始めた。
「あっ!! ああっ!! や……! あ………ッ!」
しどけないため息を吐きながら、涙を飛び散らせ、必死に身を捩るシュバルツ。ハヤブサの手に、そこから溢れだした愛液が絡みついてくる。
「く………! はあ……ッ!」
愛撫を『愛撫』として素直に受け入れてくれているシュバルツのその様子に、ハヤブサは、自身の瞳から、先ほどとは違う意味の涙が零れ落ちて来るのが分かった。
花が、咲こうとしている。
傷つけられ、踏みにじられた花が。
前と同じか
いや――――それ以上の艶やかさを伴って……!
ああ。やはり、この花は強い。
俺の、大切な、大切な、花。
(良かった……)
どうしようもない程の、愛おしさが溢れる。
己自身もまた、強くいきり立つのを感じた。
今すぐにでも、その最奥を貫き、ぐちゃぐちゃに掻き回したい衝動にかられる。
だが自分はまだ、彼の身体の総てに触れていない。
それが終わるまでは――――その最奥に触れてはならないと感じた。
だが愛おしさが抑えきれないハヤブサは、しどけなく喘ぐシュバルツの唇を優しく塞ぐ。
「ん………!」
次いで、愛液を溢れさせているその先端にも、唇で優しく触れた。
「ああっ!! ああんっ!!」
ビクビクッと身をのけ反らせるシュバルツに、ハヤブサは優しく微笑みかける。
「シュバルツ……愛している」
そう言うとハヤブサは、再びシュバルツの腰回りから太股にかけて、愛撫を再開しだした。
(ハヤブサ……!)
シュバルツは、は、は、と、短く息をしながら閉じていた瞳を開け、自分を愛撫するハヤブサの方を見た。ハヤブサはシュバルツの足を大事そうに抱え上げ、そこにそっと唇を落とし、舌を這わせている。ハヤブサの『影』の方は、もうその姿を見つける事は出来なかった。
(良かった……)
シュバルツは、ほっと安堵のため息を吐いた。
ハヤブサは、自分を責めるのを止めてくれたのだと悟る。
私は、大切な人の『ココロ』を守ることができたのだろうか。
そう思いながら何気なく視線を移して行くと、自分のすぐ目の前に怒張し切ったハヤブサ自身があるから、シュバルツはぎょっと、息を飲んでしまう。そこは欲を孕んで膨れ上がり、震えながら愛液を垂らしていた。なのに、ハヤブサの方は、今もシュバルツの足を抱え上げ、ゆっくりと大事そうに愛撫している。その様子に、彼をひどく我慢させてしまっているのではないか――――シュバルツはそう、思った。
「ハヤブサ……」
だからシュバルツは、ある願いを持ってハヤブサに呼びかけた。
この望みは、ある意味非常にはしたない物である事を、シュバルツは十分承知していた。だがシュバルツは、あえてそれを欲した。
彼を慰めたい。
癒したい。
愛したい。
自分の『総て』で、彼に触れたい――――
それ以上の、望みはなかった。
「どうした? シュバルツ……」
愛おしいヒトからの呼び掛けに、ハヤブサは愛撫を中断して振り返る。
「その………」
シュバルツは少し躊躇ってから、意を決して口を開いた。
「お、お前を、『口』で……受け入れたい、の、だが………」
「―――――!」
「駄目か……?」
少し驚いたようにこちらを見るハヤブサを、見つめながら、シュバルツは思い返していた。ハヤブサと身体を繋げるようになってから、自分は、まだ一度も彼を口では受け入れていなかったという事を。
あの男たちに乱暴をされた時、口は猿轡を噛まされていたから、幸いにして穢されなかった。後ろも、指を挿れられただけで済んだ。
だが――――あのままハヤブサの助けが間に合わず、アジトに連れて行かれていたらと思うとぞっとする。自分はもっと嬲られるように蹂躙され、非道い目に遭わされていた事だろう。今回はこうして助かったが、次また同じような事が起きないとは限らない。そうなって総てを穢されてしまう前に――――自分の総てで彼に触れておきたい。そう願った。
「シュバルツ……!」
思いもかけない愛おしいヒトからの願いに、ハヤブサは少なからず動揺する。
シュバルツにフェラをしてもらう事を、拒んでいた訳ではない。寧ろ、やってもらいたかった。あの口で、自分を愛してもらえたらと思うだけで、天にも昇る心地がする。しかし確かに、ハヤブサはそれをシュバルツに今まで求めた事はなかった。
それは何故か――――答えは簡単だ。
実はシュバルツは、フェラをされる事を嫌がる。
それは、シュバルツがDG細胞でその身体を構成されているアンドロイドであるが故だった。DG細胞でできている自分の身体から出される『精』も、当然DG細胞の塊だから、相手の身体には極力入れたくない――――と、言うのがシュバルツの言い分だった。
何度も身体を繋げている自分がDG細胞に感染などしていないのだから、大丈夫だ――――と、ハヤブサはシュバルツに言うのだが、愛おしいヒトは頑なに首を振る。
確かに、自分の主張には科学的根拠はないし、今は大丈夫でも、明日DG細胞に感染しないと言う保証もない。だからハヤブサもそれ以上強くは言えず、余程の事がない限り、シュバルツにそれをする事はなかった。愛おしいヒトが望んでいないのに、それを無理強いする事など出来なかった。
故にハヤブサも、シュバルツにそれをしてもらう事を求めなかった。シュバルツがその行為を望んでいないのに、自分だけそれをしてもらうのは、フェアじゃない気がしたからだ。
なのに今――――目の前の愛おしいヒトは、「フェラをしたい」と、言ってくれている。そして、涙でぬれた懇願するような眼差しが、自分から逸らされる事はない。
「いいのか……?」
念のため問うハヤブサに、シュバルツはこくりと頷いた。愛おしいヒトの決意は固く、変わらないのだと悟る。
「分かった……」
ハヤブサは少し夢見心地で頷くと、シュバルツの足を抱きかかえたまま、彼の顔の上に跨る。そしてその口の前に、己自身を差し出した。
「……………」
シュバルツはしばらく逡巡するようにそれを眺めていたが、やがて意を決したのか―――――おずおずと、その舌を伸ばしてきた。ペチャ……と、音を立てて、ハヤブサのそれにシュバルツの舌が触れる。
(…………!)
シュバルツの舌が、ぎこちない動きでハヤブサ自身を愛して行く。それが想像以上にもどかしくて、たまらなく気持ちがいい。ハヤブサは己の理性が飛ばないように、細心の注意を払わなければならなかった。
(……これで、いいのか……?)
ハヤブサに気持ち良くなってもらいたいと願うシュバルツは、懸命に舌を動かす。すると、ハヤブサから熱を含んだ声が降ってきた。
「いいぞ……シュバルツ……。そのまま咥えて……」
「く、咥える……? こう、か……?」
シュバルツは言われるままに、ハヤブサの先端を口の中に含む。
「――――ッ!」
その瞬間、ハヤブサの腰がビクッと動いた。彼の口の中は、蕩けそうになる程気持ちが良くて、本当に理性が飛びそうになる。だが、懸命に堪えて次の指示を出す。この愛おしいヒトに、口技を教える喜びに震えた。
「そのまま吸って……舌を動かして……」
「ん………」
ちゅくちゅくと音を立てて、愛おしいヒトがたどたどしくハヤブサを愛し始める。その刺激と甘やかな喜びに、どうにも辛抱が利かなくなったハヤブサは、自身もまた、シュバルツのそれを口に含み、愛し始めた。
「あっ!!」
それに驚いた愛おしいヒトが、ハヤブサから口を離してしまう。
「は、ハヤブサ!! 待てっ!! 私のはしなくても―――――んうっ!!」
反論しようとしたシュバルツの口に、ハヤブサは再び己自身を突っ込む。
「心配せずともシュバルツ。お前は『リング(拷問道具)』を嵌めているから――――簡単にイケやしないさ」
そう言いながらハヤブサは、それをするりと触ってにやりと笑いかける。
「んっ!!」
「だから安心して……続けて、シュバルツ……」
「…………」
ハヤブサにそう言われ、シュバルツはあきらめた様に、再びたどたどしい愛撫を再開する。
「ん……う………」
ちゅくちゅくと音を立てて口を動かし、懸命に舌を動かしていた。
(シュバルツ……!)
ハヤブサもまた、シュバルツ自身を愛撫する。
(ほら……こうすると、気持ちいいだろう……?)
教え込むようにシュバルツ自身を口で愛してやると、シュバルツも懸命にそれを習うように舌を動かしていた。本当に、このヒトは素直で飲みこみが早い、と、ハヤブサは喜びに震える。思わず、本能のままにその口腔を犯し抜きたくなって、それを必死に自制しなければならなくなった。
「ん…………」
シュバルツはハヤブサに教えられるままに、その舌を動かし、口を動かす。時折ハヤブサの腰が動き、しどけないため息かその口から漏れるのを聞いた。
(ハヤブサ……感じてくれているんだな……。良かった……)
口の中のハヤブサ自身も脈打ち、愛液を溢れさせ、硬度が増して来ているのが分かる。
(もしかして……このまま射精(だ)されるのかな………)
未知の経験に、シュバルツは少しの恐怖を覚え、その瞳から涙がこぼれた。そうしている間にも、ハヤブサ自身の容量が口の中で増え、息をするのも困難になって来る。だがシュバルツは、そのままハヤブサを愛し続けた。
「ん………んぅ………」
このまま口に出されるにしろ、顔にかけられるにしろ―――――彼に汚される事を、シュバルツは望んでいた。
(シュバルツ……! シュバルツ……!)
シュバルツの愛撫に、ハヤブサはどんどん追い込まれていく。愛おしさが溢れる。彼を愛したくて愛したくてたまらない。
「く………!」
もう本当に限界だった。
ハヤブサは一瞬迷う。このまま口の中に出すべきか。それとも、外に出すべきか。
それとも――――
「シュバルツ……!」
ハヤブサの目の前に曝されているシュバルツの秘所は、ひくひくと妖しく蠢き、もう充分にハヤブサを待ち望んでいるようだった。ためしに指を挿れてみると、そこは喜んでそれを飲み込んで行く。
「んうっ!!」
指に秘所を犯されながらも、懸命にハヤブサを愛し続ける愛おしいヒト。その腹の下の媚態を見た瞬間――――ハヤブサの決意は固まった。
口の中から、ズボッと音を立てて己自身を引き抜く。
「あ…………!」
淋しそうな声を出す愛おしいヒトを宥めるようにハヤブサは抱きしめると、ハヤブサは己自身で、迷わずシュバルツを貫いた。
「あっ!! ああああ――――ッ!!」
ろくにほぐされもせず、一気に貫かれた事に、愛おしいヒトは悲鳴を上げる。それを強く抱きしめながら、ハヤブサは突き動かされるように律動を始めた。
(済まない……! シュバルツ……!)
心の中で謝りながらも、ハヤブサはその身体を強くゆすり続ける。
口には出せない。
愛おしくて大切なお前を、まだそこまでは汚せない。
それよりも、お前の中で――――中で、果てたい。
一つになりたかった。
このヒトの身体は自分の物なのだと、強く主張したかった。
済まない。お前は、乱暴されて傷ついているのに。
優しくしてやらなければならないのに――――
その想いを軽く吹き飛ばしてしまう程、このヒトへの愛おしさが溢れた。
この凶悪な衝動を―――――何と呼べば、いいのだろう。
「シュバルツ……! シュバルツ……!」
熱を含んだ声で、うわ言のようにその名を呼び、ハヤブサはシュバルツの身体を抱きしめながらゆすり続ける。
「は……! あっ! あ………っ!」
縛られて身動きの取れないシュバルツは、唯されるがままに受け入れるほか道はなく。突き上げられる衝動のまま、喘ぐよりほかに道はなかった。酷く乱暴にゆすられる身体。なのに「大切にされている」――――そう感じられるのは何故だろう。
「シュバルツ……!」
熱を含んだ唇が、首筋を這う。その間にも、彼の指が、こちらを暴き立てるように肌の上を蠢いてくる。
「はあっ!! ああっ!!」
こちらがそれに反応を返すと、その熱も欲も、嬉しそうにシュバルツに侵食してこようとしてくる。
同じなのに。
その熱も欲も――――あの男たちの物と、同じなのに。
――――淫売!
――――雌犬!
その言葉と共に、落ちてくる嘲笑。降り注ぐ悪意。
「…………!」
無意識のうちに、身を固くしてしまうシュバルツ。するとそこに、ハヤブサの手がふわりと降りて来た。
「大丈夫だ……。シュバルツ……」
頬から唇をふわりと撫でられ、自分がいつの間にか唇を強く噛み締めていた事に気づく。
「力を抜いて……」
そう言われながら唇を指でなぞられる。シュバルツが言われるままに唇を緩めると、指がその中に侵入してきた。
「んっ!! あ………!」
「お前は、綺麗だ……」
その口腔を指で愛しながら、ハヤブサは囁く。
「ハ……ヤ………! んぅ……!」
「綺麗だよ……」
ハヤブサにとってシュバルツは、愛すべき『花』だった。
その花はただひたすら美しく、健気だった。
そして、どんなに犯しても、犯しきれない高貴さを湛えていた。
愛しても、愛したりない花――――。
その心の命じるままに、ハヤブサはただひたすらに、その花を愛す。
愛おしさに、歯止めなど――――かけてやらない。
愛している。
愛している。
その想いを込めて、ハヤブサは律動を繰り返していた。
「はあっ!! ああっ!! んあっ……!!」
繋がるそこから流れ込んでくるハヤブサの『想い』に、シュバルツはひたすら翻弄される。
(ああ、そうか)
シュバルツは不意に悟った。
あの男たちとハヤブサ――――一体、何が違うのか。
そう。
ココロ。
ココロが、違う。
あの男たちから流れ込んできたのは、悪意と侮蔑。どうしようもない暗い感情――――。
だけど、ハヤブサから流れ込んでくるココロは。
愛シテイル
愛シテイル
愛シテイル
「あ………! あ………!」
その熱は、甘やかさを伴って、シュバルツの内側に酷く響いた。
欲しがってしまう。
もっと
もっと
その熱を
その甘さを
もっと私に――――!
(でもきっと、駄目だ……。本当は……。こんな事を想っては……)
シュバルツはそう思って、唇を噛みしめる。
ハヤブサは、『人間』
私は、『アンドロイド』
ハヤブサの『生命』を、未来に繋いでいく事は出来ないのに――――
何時までもその『愛』を独り占めしている状態は、やはり、不自然だと思う。
なのに、願う。
傍に居たいと。
失いたくないと。
愛したいと。
愛して欲しいと――――
こんな事を願う私は
きっと、誰よりも罪深い。
分かっている。私は彼にとって『繋ぎ』の存在でいい。
彼が真に愛する人を得れば、自分は何時でも身を引かねばならぬ。
それだけは――――わきまえておこうと、シュバルツは自分に強く言い聞かせていた。
それでも、今は。今だけは――――
ハヤブサ
ハヤブサ
愛 シテ イ ル
「ハヤブサ……!」
ふと縋る様に零された言葉に、ハヤブサが反応した。
「シュバルツ……!」
顎を捉え、その唇を奪う。
自分を愛してくれた唇。
このヒトは、俺の物だ。
心も身体も、俺だけの物だ。
熱が膨らむ。
愛おしさが溢れる。
もう止まれない。
止まる事など出来ない。
愛シテイル
愛シテイル
愛シテイル――――
「――――――ッ!!」
深いキスを交わしながら、二人は同時に絶頂を迎えた。ハヤブサから放たれた熱い迸りが、シュバルツの内側にじわりと広がっていく。
(シュバルツ……)
熱の余韻に浸りながら、ハヤブサはシュバルツを幸せそうに抱きしめる。だが、シュバルツの方は、何故か小刻みにフルフルと震えていた。
「ハヤブサ……!」
はあっと、しどけないため息と共に、切羽詰まった声で名を呼ばれるから、収まりかけていたハヤブサの『雄』の部分が、再び反応しそうになる。それを面には出さず、何気ない風を装って、ハヤブサはシュバルツに声をかけた。
「どうした……? シュバルツ」
「ハ……ハヤブサ……」
切なそうに呼びかけてきたシュバルツは、もどかしげに腰を揺らめかせ始めた。
「り……『リング』を、外して、くれないか……?」
「―――――!」
その一言でハヤブサは総てを察した。
つまりシュバルツは、先程の絶頂の瞬間、リングのせいで望む解放が得られなかった。つまり――――『空イキ』をしてしまったのだ。
「く……苦しくて……お願い、だ………」
そう言って愛おしいヒトが妖しく腰を揺らめかせながら、可愛らしく懇願をしてくれるものだから―――――ハヤブサの中で、変なスイッチが入ってしまう。彼の面に今――――爽やかだがどこか邪悪な色を含んだ笑みが、浮かびあがっていた。
その指が、つい、と、シュバルツの、リングに締め上げられ、はちきれんばかりになっている牡茎の上を滑る。
「はあんっ!! あんっ!!」
案の定過剰に、そして可愛らしく反応してくる愛おしいヒトに気を良くしたハヤブサは、そのままそこを、優しく手で愛し始めた。
「ああっ!! 駄目……っ! 今、敏感になってるからぁ……ッ!!」
ビクビクッとシュバルツの身体が跳ね、腰が揺れる。それがシュバルツの中に繋がったままになっているハヤブサ自身を、とてもいい具合に刺激してくれた。
「シュバルツ……」
手で愛しながら、律動もゆっくり再開させる。
「やっ!! 駄目っ!! お願……! リングを……ッ!!」
シュバルツの腰が浮きあがり、大きく揺れる。その動きがハヤブサを更に誘ってしまっている事に、シュバルツは気付けない。
「もう一度俺がイク時……一緒にいこうな……」
囁きながらハヤブサは、シュバルツの身体を強く抱きしめる。
こんなに愛おしいヒトのこんなにも可愛らしい痴態を、ハヤブサが見逃すはずもなかった。
「そ、そんな……ッ! ああっ!!」
深い律動を始めたハヤブサの腕の中で、シュバルツは再び咲き乱れ始めた。
ハヤブサは再び、その花を深く堪能して行った。
(これからもこうして……俺の腕の中だけで、花開いてくれ……)
俺の
俺だけの
大切な、花。
色街の一角で、二人の愛し合う時間に、しばらく終わりは訪れそうになかったのだった。
大切な、花。
今回も、こうして無事に書き上げる事が出来ました。ひっそりと置いてある私の小説を読みに来てくださって、本当にありがとうございます。
ええ………ね………。艶のある場面は、書くの難しかったです。何と言うんですかその……『加減』がいまいちつかめなくて……。
自分の理性も吹っ飛びそうになるのが大変でした。皆さんはこういう場面、いったいどうやって自分を律しているのでしょうか。嫌そもそも、こういう阿呆な小説は、まず書かないかな。けしからん妄想ばかりでごめんなさい。
でも、強姦の場面よりも、愛ある場面の方が、書いていて楽しかったです。やはり人間、愛し合うのが一番だと思います。
ではまた、何か思いつきましたらば、こっそり作品を置きに来ます。
その時に忘れていなければ、また読んでくれると嬉しいです。