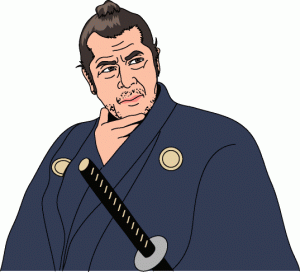竹の社 ――前篇――
1
大学生になって、初めて購入したものは、新しい音楽プレイヤーだった。
ノートパソコンは入学祝にと祖父母に買ってもらったため、入学したてのあの頃は、思い返せば、春休みの間に貯めた五万円という大金をどうしようが、すべてはおれの自由だったのである。
くだらない、ちっぽけなミスから多くの金をどぶに投げ込んできたおれではあるが、しかし今になってこうして思い返して見ると、あの買い物は素晴らしい選択だったと思う。
悉く飽き性なおれの傍らに常に寄り添い続けてはや三年。こんな風に一つのものを持ち続けた経験は、コイツを除けば、存在しない。
大学三年になって、初めてノートパソコンが、見慣れぬ症状に襲われた。
かくかくとマウスカーソルが画面の中を、宇宙旅行よろしくワープし、キーボードに打ち込んだ文字は意思とはそぐわない文字列を吐き出す。
一体どうしたというのか。
確かに、ノートパソコンを見ながらメシを食い、安いビールをやったときに、そいつを倒して引っかけてしまったことがつい三日前にあったばかりだ。
それに、「ノートパソコンはキーの下に基盤があるから、水気のものはご法度だぞ打緒。わかっているな」と、兄に注意を受けたこともある。
いけないことをしたという自覚はあったが、同時にコイツを信じてもいた。
「なに、水気のひとつやふたつ」と言わんばかりに、寄せ付けないと思っていたのだ。本当だ。機械にだって情がある――だなんてメルヘンをかまそうとは思わないけれど、情が沸くことだってあるんだから移ることだってあるだろうな。ならば移った情が返ってこず、そのままソイツのものになってしまうことだって、あるはずだった。
あるはずだったのだが、おれのパソコンに限っては、そうはならなかったようだ。
意地でも認めまいといたずらにキーを叩いても無駄なことは、いじり始めて早三分で気づいた。
それから修理にだし、一万以上の金をどぶに流し、返ってきたのは結局一週間後の月曜日。
その日は講義は昼まで入っていなく、下宿でゆったりと朝飯を食い、部屋に上がって、鉛を溶かしたかのような味の水道水を、ねちねちと文句を垂れつつコップ一杯やった。
さて一眠りしようかと考えていると、ドアをノックする無礼者がいる。鉛水を飲まされた恨みもついでに清算してやろうと思いドアを開けると、根性のない相棒の帰還であったというわけであった。
―― 一週間である。
一週間、おれは音楽を聴けなかったのである。
何かと気取りがちなのが大学生という生き物だ。おれもその例に漏れることはない。購入した音楽プレイヤーは最新式。シーデーだなんていう野蛮なカラス除け道具を持ち運んで、これまた野蛮なポータブルカラス除け再生機にひっかける必要なんてない。
今の音楽はデータなのだ。兄に言わせると、シーデーだってデータだったようだが、あのキリギリスメガネの言うことは小難しくて聞いていられん。
だがそんな小話ひとつ理解できなかったところで、コイツが最新機器だということは事実として揺らがない。
でんと構えて常におれの右ポケットにスマートに収まっている――はずだったのが、一週間、その存在を無くした。
最新音楽機器であるコイツは、その曲の出どころをパソコンにするものである。そして充電もまた、パソコンで行う。もちろんそれ以外の方法もある。電源に直接差して充電できるようにするアダプターやケーブルもあるし、電源接続をする機器に取り付けることさえできれば、あとは放置で構わない。
だが、おれはといえば、もっぱらパソコンでの充電のみであったのだ。コイツを差し込める機器なんて、ほかに持っていなければ、入学と同時にこの七畳一間に、お門違いなブルジョアジーを持ち込んだわけでもない。どぶさらいに金をやるのはソイツの母親だけでいい。
そんな話をすると、お前の思考はプチブルだ、などと兄に否定されてしまったことがあるが、あんな奴の言うことは聞く価値がない。「どうぞ」と言ってやりさえすれば、浜の砂に向かってでも永遠に話し続けているような男の話のどこに聞く価値があるのか。
しかし、この時ばかりは、自分が小市民にすらなり切れていなかったことが切なくなった。
「打緒よ。打緒ったら。初めについてくるケーブルはすぐに切れたり、切れずとも使えなくなってしまったりするものだから、早めに別のものを買っておくんだぞ。金ならあるだろう。そのダンボールの中身に、いったいどれだけお前の財布から出た金で買ったものがある。その財布だって、母さんが買ってくれたものじゃないか。そんなお前に、兄からアドバイスだぞ」
実家で荷造りをしていた時に、脇からこんなことを言われた日にはいくら大人なおれですら耳元でいくらかの血管の切れる音が聞こえたが、しかし間違ってはいなかった。傲慢ちきでプライドばかりがニューヨークのどの建物よりも高くなっているあの兄の言うことは、当たっていたのだ。
こればかりは怠慢だった。
そしてその怠慢のせいで、おれの最新音楽機器はあっけなく充電を使い切り、あっという間に騒音だけの世界が訪れたのである。
あふれるのは雑多な騒音、害音ばかり。やれ車の音だ、やれ昼に何を食うだ、やれ隣の住人の話し声だと、この世界には間抜けな音が多すぎる。
ニューマンが聞きたい。
スミスが聞きたい。
初めはこんな世界も新鮮で悪くないと思ったものの、すぐに飽き、やがて苦痛に変わっていった。
そうして一週間が経つ。
パソコンが届いて真っ先に行ったのは、充電だった。次に音楽再生のアプリケーションを起動させ、USB電源のスピーカーから、ニューマンのアルバムを轟かせたのである。
鳥肌が立った。
波に押されて砂がざあっと全身を駆け抜けて、涙を流しそうになった。
その時、おれは初めて気づいたのである。
何かを失えば死ぬ――という表現は、まんざらありえないものでもないのだ、と。
間違いない。
あと一週間、いや五日ほど、パソコンの修理に時間がかかっていたなら、おれはどこぞで野良猫の死体のようになっていたはずである。
コイツを失って初めて死にかけた。
そんな感覚は、おれにとってみれば、ある種の感動でもあったわけだが――さて。
「これがなくなってしまえば死んでしまう」というものは、おそらく千差万別だろう。
水だとか、塩だとか、そういうくだらない教師が出すようななぞかけをしたいわけではない。
「これがないなら、自分の人生は台無しだ」
そう感じるような、何か。
加えるなら、おれはパソコンでスポーツを見る男である。パソコンが修理から帰ってきて、ニューマンをバックに流しながらに行ったのは、ニューヨーク・ニックスのハイライトを見ることだった。
これもまた、なくてはならない何かだろう。
そして、三年の夏に出会った一人の、名も知らないおばあちゃん。彼女にとってのそれは、竹ぼうきだった。
竹ぼうき。
汚いものときれいなもの。
薄汚れたおばあちゃんのあの竹ぼうきは、間違いなく、きれいなものだったのである。
2
「夏休みが終わったら今度は冬休み。それが終わったら春休みね」
隣に座っている小さな少女が、威勢良さそうにポニーテールを揺らしながらそう言った。
脈絡はない。おれたちは、太陽のやつが張り切りすぎているこの真昼に、そんな話をしていたわけではなかった。
「いやなのか。休みがあることは、いいことだろう」
「いいことでもないわ。学校に行くのが当たり前だから、休みはありがたいものだもの」
「君が思っている以上に、世界っていうのは丈夫なんだぜ。簡単にひっくり返ったりするものか」
この齢の少年少女というのは、常日頃から足元がおぼつかないような感覚に襲われるものである。
おれもそうだった。
自分の住んでいる世界というものに、興味を示したころの話。
そういえばそんなこともあったな。
「私の世界は丈夫かもしれないけれど――」
「けれど、なんだ」
「私以外の人の世界はどうなの?」
「なんだって?」
「だって、先生が言っていたわ。世の中は自分一人で作られているのではないのですよーって。私もそう思うもの。でも、たとえば私が一人で、ここから駄菓子屋に向かったとして。それは私しかいないんじゃない? ううんと、私次第、ということなのだけど」
「わかるよ、わかるさ。大丈夫だ」
神社には木陰が多いのだ。
もはや常連となったおれやこの少女にとってすれば、今更「どの木陰が一番長く涼めるか」だなんてことは議論に上がらない。
ちょうどこの時期は、小汚いあの賽銭箱の右隣が、おれたちの居場所だったのである。
そんな定位置で、この少女は、アイスをなめるのをやめておれの方を見上げ、目をいつもより大きくしていた。
「君の言うことは、ううん、よくわかる。けどそれは、言葉にできない部分の話だよ。誰にも、できない部分の話だ。わかるかい? できないのさ」
「はぐらかすのは嫌い」
はぐらかしちゃいない。
はぐらかしちゃいないのだ。
ただちょっと、いい答えが浮かばなかった。
口さえ開いてしまえば、嘘か真か関わらず万の言葉が飛び出すようなうちの兄ならいざ知らず、おれにはそのような技術はない。
さしてうらやましいとも思わなかったが。
「さて、休憩は終わりじゃないか。いつまでも休んでいると、おばあちゃんが湯気を立てているぞ」
「私のおばあちゃんはやかんじゃないの。そんな風な言い方はよして」
「わかったから、ほら。『今日は私がやる』と言ったのは、おれじゃない。君なんだぜ」
「もう、わかったわ。ただこのアイスがちょっと――冷たかったものだから。そのうえ固くって、時間がかかったの」
なんという無様な言い訳だろう。
既に溶け始めていた薄いブルーのアイスをしゃくしゃくと一気に食い散らかし、立てかけてあった竹ぼうきを手に取って陰を飛び出していった。
「うん?」
少女が自分の座っていた場所においていった棒を見てみると、なんと当たっているではないか。
もう一本だ。
恥ずかしいことではない。
当たったことを吹きながら往来を歩きつつ、こいつを買った駄菓子屋に入っていきもう一本もらったところで、おれはみっともないだなんて思わない。
当たったのは運の強さだ。
強い奴は、往来で大声を出しても許されるのである。
「十雨よ。十雨ったら」
「なあに? 今忙しいって、わからないの」
「わかるさ。わかるけど、でももっと忙しくしてやるぞ」
不服そうにこちらに振り向いた少女に向かって、日陰から棒をひらひらと振って見せる。
「当たったの?」
小汚い竹ぼうきをずりずりと擦りながら、そんなことお構いなしで飛びついてくる。
これも強者の特権である。
また、どうやら世間には子供ならではの特権というのも存在しているらしく。そのどちらをも有しているコイツはおそらく世界中の誰よりも偉いのだ。
「当たったよ。当たったから、掃除を終えたらアイスもらいに行こう」
「お駄賃と合わせたら、二本もらえるわ」
「おなか壊すから駄目。その日のお駄賃は次の日に使い道を考えるって約束だぞ」
ううう、と短く唸って、それから「無くさないでね。絶対」と言い放ち、掃除に戻った。
腕に巻かれた安くて黒い、若干気取ったような腕時計は、三時になったことを示している。
この日はいつもより遅いペイスだ。
おれは腰を上げ、神社の周りの雑木林を見に、ビニール袋を抱えて歩き出したのであった。
この日は、特に暑い日であった。
3
三年生の夏。
この頃のおれはといえば、腐った果物のような人間であった。
今であっても決してろくな人間だとは言えないだろうけど、それでも今のおれは、あのころに比べればいくらかましだと信じている。その分だけ、きっと幸せなのだろう。こういうことを言うやつは決まって幸せなやつだと相場は決まっているのである。
本当にどん底のやつは、幸福か不幸かだなんてことにこだわりはしないものだ。
原因は何だったろう。
一年ほど昔、あの頃のおれには確かにわかっていたものが、今ではわからなくなってきている。
やはりおれというのは、幸せになっているらしかった。
「――掃除かい。偉いねえ」
そんな風に声をかけられたのは、あまりにも苦痛な帰省から逃げるように足を向けた神社でのこと。
昔からある神社である。
実家にいても、口うるさい兄と、無駄に鼻の頭が高い男と女がきいきいとやかましいだけ。
「夏休みだろう。お前の大学の行事予定を見たぞ。どうして帰らない。去年も帰らなかっただろうから、父さんと母さんが泣いていたぞ」と兄から電話がかかってきたときは何事かと思ったが、要するに、いくらかの試験(と言っても、おれの大学の試験なぞ笑い飛ばしていいようなものばかりだ)で単位不認定となったことに腹を立てた人間が、小言を言うために呼び戻した、というだけの話である。
そうして、その話も、帰省一日目に済んだ。
「すみませんでした。おれの不真面目さから起きたことで、ほかの何事にも非はございません。精進します」と頭を下げていれば、あとは情報量が皆無な言葉の羅列を聞き流しているだけでよい。
何が三年生だ。
何が就職か。
いまだおれが何者かも知ろうとしない貴様らに、おれの何がわかる。
説教を聞き流してすぐにトンボ返りをしてもよかったのだが、しかし長距離バスの運賃が往復で一万を超える(電車だと? ばかを言うな。あれらはもっと金をふんだくる)。北海道というのは広いのだ。コイツの懐の広さに何度むかっぱらが立ったことか。
このままではおれは帰れぬ。
そう思い立ち、夏休みは何もない自室でクーラーをフル稼働、一日三食しっかり食ってやることにしたのであった。
とはいえ、いつまでもあの声帯の権化どもとともにいると、いつかおれの脳が沸騰しかねない。
そう思い、帰省三日目には散歩に出かけるようになる。
散歩とはいっても、根本的に見せ場のない町である。町を一周といったところで、二時間もあれば事足りる。おれであれば、二時間もあれば二周できるやもしれない。
であるから、どこかに居場所を作る必要があったのである。
大きな自然公園を中心に、広場がある。しかしここは駄目だ。隣に学校がある。
頭のいくらかが抜け落ちて足りぬような子供たちが、自らたちの城のようにふるまっている。
おれがこの学校で、頭の足りない中学生をやっていたころ、一度聞いたことがある。「貴様、家でもそうなのか」と。すると小学生らを蟻の群れのように率いている一人の中学生が答えた。「どこであっても、おれはこうだ」と。
こんなばか共がわらわらいる場所に、おれの居場所はない。
実家の近くの坂を下ると、大きな湖と、それに面した休憩場所がある。
ここもいけない。
なにせ虫が多いのだ。おれは特に虫に好かれるたちなので、ここにはいけない。
ここは、物珍しさにつられた、これまた間抜けなツーリング客がキャンプを張ったりする場所なのである。おれの居場所には不適当だ。
そんなわけで、おれは、古臭い神社に寄ることにしたのである。
町のはずれにあるこの神社は、周りを林で囲まれていて、無駄に長い石段の上で、厳めしく構えている建物であり、例え正月であろうと参拝客はせいぜい物好きな老人とカラスくらいだろうという、そんな神社なわけであった。
おれは若い。
そのうえ時間もあった。
だから俺はたっぷり十分ほどかけて石段を登り、境内に入る。「しまった、ここも虫が多い」と思ったものの、その環境からは想定もできないほどの静寂さ。セミもどこか遠くで鳴いている様子で、この林には目もくれていない。蚊柱が立っていることもないし、野良猫が盛っているような様子も見受けられない。
賽銭箱のあたりまで向かい、小ぶりな屋根の下に入れば太陽の光は当たらないし、何より静かなのが気に入った。
気に入ったからこそ、敷き詰められている砂利がまばらになっていることに目が行ったし、賽銭箱の真ん前に落ちている、ビニールゴミが気になった。
どこに捨てるというあてもなかったが、とにかくまずは拾い上げること。そんな風に感じて行動に移したあの時のおれは確かにどうかしていたのだろうが、わざとらしい気取った善行を、あろうことか一人の老人に見られていたということの方が、問題なのだろう。
「掃除。ああ、これですか。いや、掃除ってわけじゃ、ないんです。ただ気になったもんですから」
ちょうどビニールを持ち上げた瞬間の姿勢のまま、おれは返す。
すると年老いた女性はけらけらと笑い、「それはじゃあ、どうするんだい」と答えた。
おれは、どうにも答えられなくなり、不細工な笑顔を一つ、そのおばあちゃんに送るのである。
「こんな暑い日にはね、誰もが動きたくないというけれど。それでも続けるから意味があるのよな」
水が張られたバケツに、枯れ木のような腕を突っ込みながら、彼女が言った。
おれはといえば、なぜだか知らないが、おばあちゃんの持っていた竹ぼうきを使って掃き掃除をしている。
掃除を始めたおばあちゃんを見ながら涼むわけにいくまい。かといって、気まずさから帰宅しようものなら、今の時間なら母がいる。これほど気まずいことはないのだから、そうするわけにもいかなかった。
「どうして、おれは掃除をしているんだろう」
「はえ?」
間抜けな返事だった。
年の功は馬鹿に出来ぬと思っていたが、意外とそんなことはないのかもしれない。
「おばあちゃん、知らないだろうけど、おれは本当に、掃除なんぞをしようと思ってここに来たわけじゃないんです。それはほんの、気の迷いなんですから。本当ですよ」
「だろうね」
「本当にわかっているんですか」
「わかっているよ。掃除をしに来たやつが、そんなしかめっつらをして箒を持つもんか。ちょっと貸してみなされ。違う違う。竹ぼうきの扱い方は、こう。箒は、腰で掃くんだ」
水にぬれた枯れ木がふれると、いやになるほど冷たかった。
彼女は今おれに、こうして物事を教えているが、この腕からは何も伝わってこない。
夏だからといって、冷たすぎるものが好まれるわけでもないのである。
「お前は、帰らないでこうして手伝っている。これまでがどうであれ、善人様だ。それだけでいいよ。老い先短いんだ。細かいことは気にしてないとも」
「ふうむ。そういうものかね」
「そういうものさ」
「おれがたとえば、ひどい親泣かせだとしても、かね」
「ひどい親泣かせ、だとしても、私を泣かせたわけじゃないだろう。私の知るところじゃない」
「ひどいばばあだ」
からからと笑って、おばあちゃんは賽銭箱を磨き始めた。
木でできているものに水雑巾がいいのかどうか――とも思ったが、口にはしなかった。
このおばあちゃんには、どうにも敵わないような気がしたのである。
「昼ごはんは食べたのかい」
「食べていないですよ。家に帰れば、たぶんあるんでしょうけど」
「ならもうちょっとの辛抱だね。それでも辛抱できないようなら、そら、あのビニールに、飯が入っている。好きに食うといい。握り飯なんだけど、ね」
「握り飯? あのビニールに? おばあちゃん。あのビニールは、集めたごみをいれるビニールでしょう」
「そういうのは、ごみを集めてからいうんだよ。食べなさいや」
「いいよ。あれはおばあちゃんのごはんでしょう。家に帰ればあるんです。本当なんですから」
「たぶんといった」
「はあ?」
「お前はさっき、『たぶん家にある』と言った。ないかもしれないんだろう。それともなんだろう。食べないかもしれないのかね」
何も、言い返せなかった。
言い返せなかったが、黙っているのもしゃくなので「ほんとに大丈夫ですから」と、絞り出した。
何が大丈夫なのかは、今でもわからない。
おれだって、おれの全てを知って生きているわけではないのだ。こうしておばあちゃんと知り合ったことが、そのいい例だろう。
掃除を一通り終えると、おばあちゃんはエプロンのポケットから何かを取り出した。
真っ黒になった雑巾がバケツの中をゆっくり泳いでいるが、彼女はこれを家に持って帰るのだろうか。
おれが集めたごみを、握り飯を食った後であのビニールに入れ、家で処分するのだろうか。
そう考えると、やけに彼女のあの枯れ木のような腕が思い返された。
「それ、なに?」
「五円玉。賽銭箱に入れるんだ」
するとおばあちゃんは、賽銭箱に背を向け、おれを見た。
ちょこちょこと、手招きをしている。
「神様が感謝してくださるから、お前もほら、賽銭入れるといいよ。ほら。その腰にささっている黒いの、財布だろう。うちの娘の旦那が、そんなのをさしていたよ」
この黒財布は、兄が進学祝いにと買ってくれたものだった。
今でもまだ使っている。
「感謝してくれるんでしょう。その上さらに賽銭までいれますか」
「賽銭は、神様の儲けじゃないんだよ。ほら、はやく」
おばあちゃんの隣に立つと、その存在の小ささがよくわかる。
そんな小さなおばあちゃんの後を追い、おれも銭を入れた。額は五円。
意味合いのようなものは――きっとあるんだろうけど――おれにはなく、ただの模倣だった。
汚い綱をもって鈴を鳴らしてみると、ぱらぱらと木葉のようなものが落ち、音もまた不恰好であったが、おばあちゃんは全く気にも留めていないというのだから、おれもいちいち反応はするまい。
じっと手を合わせ、何も願わず、強いて言うならば、何を願うべきかと考え続けた。
「何を伝えたんですか。ずいぶん、長く手を合わせていたけど」
「孫の健康を。前にうちに来た時も、外に出るのを嫌がっていたからね。おひさまが嫌いなんだろうねえ」
「わからなくもない。太陽がなくても、楽しいことはたくさんあるから」
「それはわかるんだけど。おひさまの下で駆け回っていた方が、人間っていうのは明るく育つものだから」
少しだけ悲しそうにうつむいて、おばあちゃんは賽銭箱の左隣の階段に腰を下ろした。
おれは何の気なしに右。
日陰が気持ちいい。
時々柔い風が吹いて、おれをやさしく撫でていた。
風はいい。
誰にでも優しいし、誰にでも厳しい。人を見ない。
醜い人間とは、まるで違う。高尚な存在というのは、間違いない、自然のもののことをいうのだ。
「お孫さん、いくつ?」
「先月に九つになった。誕生日だからと、バスで会いに来たんだ。危ないからいいって、言ったんだけど」
小さな小さな白い握り飯をアルミホイルから剥き出しながら、本当に彼女は楽しそうな顔をした。
孫どころか、おれには自分の嫁という人間の存在すら想像できない。
おれの家族のようなものを築き上げようとする存在ならば、まともなものではないんだろうが。
「一人で来るんですね。近いんだ」
「往復で三千円くらいかかってるみたいだよ」
三千円。
九つになるばかりの少女がしれっと財布から出すような額じゃない。
ならば親か。親が渡しているのか。
バスで。
バスで行け、と。
片道千五百円の道を、一人で、いけ――と。
「ろくなものじゃない」
「そうなんだ。ろくなものじゃない。孫娘をひとり、金だけ握らせてほっぽりだすようなやつらだ。私の娘も、その旦那も、孫の誕生日と正月には帰ってくるといっていたのに、今年はまだ一度も顔を見せていないじゃないか。去年にお父さんが逝っちまって、私はもう一人。寂しい老人になったね」
過程などどうでもいいことだと、おばあちゃんは言った。
今この瞬間の行いで、おれという人間の丈が決まるんだと、そう言っていたのだ。
おれは今でもその言葉を忘れてはいない。
そしてこの瞬間にもまた、おれはその言葉を思い出し、そうして夏休みの間中、おばあちゃんの掃除を手伝うことを決めたのだった。
おれにもいいところがある。
そんなことを思いたかっただけである。非常に浅く、愚かな人間である。
そんな人間であるが、しかし、ならばどうすればよかったのか。
浅く愚かなおれには、そのうえで行動を決めるほかに道はない。
――ばかめ打緒。お前の行いはみっともない――。
それでもいいのだと、思ってみたかったのである。
だから、この日から夏休み終了三日前まで、おれは一日の大半をこのおばあちゃんと過ごすことになる。
おれが竹ぼうきでごみを集めて、おばあちゃんが社を拭く。最後のお参りを忘れてはいけない。必ず入れる銭は、五円だ。なくなりそうならコンビニでくだらないものを買っては小銭を作って、買ったものは思慮の足りんばかどもにくれてやる。時には飯をごちそうになり、時には買い出しを手伝った。
最後の別れ際、彼女はその目に涙をため、おれに向かって手を差し伸べたが、やはり握ったその手はおそろしく冷たくて。
汚い七畳一間に戻るバスの中、じいっとおれは、音楽も聞かずに自分の手を眺めていたのだった。
おれは当時、そのおばあちゃんの名を知らぬ。
おばあちゃんも、おれの名を知らぬ。
冬休みに帰省したおれは、おばあちゃんが秋ごろに病で死んだことを聞いて、自分の名を明かさなかったことをひどく後悔したのであった。
前篇 おわり
竹の社 ――前篇――
眼蝋です。
いろいろな聖書を読むのが好きで、実に多くのものを浅く読み散らかした男であります。ろくな知識もないくせに一著前に偉そうに椅子なんぞに座り、読むのです。
かつて僕に、聖書の読み方を教えた男がおりまして。彼は常々、人とは何かと考えるためのツールとして聖書を用いる、いわゆる罪深い愚者でありましたが、その姿と僕の現在とが重なっていないかと言われれば、重なっております。確実に。
さて、自分という人間が一番信用ならないという話ですが。かつて宇宙飛行士を目指して坂道ダッシュなどという見当外れもいいところの努力を欠かさなかったクソガキであった頃の僕は、成人し、いくらか年月を重ね多自分が、偉そうに聖書なぞを読んでいると思うでしょうか。仮に今の僕を見たとして、あの頃の僕は、何を言うのでしょう。いえ、むしろ何を投げてくるのでしょう。
自分という人間が一番信用なりません。狂ったように悪事を働いたと思えば、気の迷いで偽善に走ってみる。しれっと募金なんかをして、ちょっとだけ胸を上げて自動ドアをくぐった僕は、そのままコンビニ袋を片手にスマートフォンで「仕事しています」などと、彼女からの現在地を問うメッセージに嘘をついたりするのでした。
そんなお話です。なんでこんなものを読んでしまったのかだなんて、後から考えてもいいと思いますよ。
眼蝋でした。