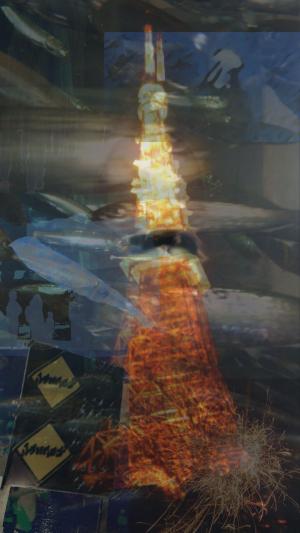不気味、歩く、話す
不気味、歩く、話す
怪文に 主張をのせて フツウフツウと 喚きたし
--私立徳実高校文芸部誌より抜粋 ある女性徒のエッセイ
生来このかた、私はどうも会話というのが上手くできない。声が出せなくなるわけではなく、「言葉」が出せなくなるのだ。たとえば中学の時分、部活動前に部室でひとり憩うとき、後からやってきた先輩に鉢合わせした際などは、実に息の詰まる思いをした。挨拶は定型だから良い。今この人と私が話すにふさわしいことは何だろうかと考え出すと、二の句が継げない。二の句を継げぬと間ができるから、いよいよ話せなくなる。ありがたいかな、相手が話しの口火を切ってくれようものなら、気の利かぬ返しで真っ先に消火活動に勤しむ始末である。(会話のコツは疑問詞にあるそうだけれど、すると回答には次の質問の余地を残さなければいけないということになる。至難。)だがどうしたものか、こんな私にも一丁前に何か話さなくてはという観念だけは根付いているらしい。あるいは、根っこには会話への欲求があるのかもしれない。だから無様に口を動かしてみるけれど、客観的には必死に口をパクパクさせる酸欠の金魚に見えているだろう。それで、儚い会話が終わった後は、却って私の心に失態への嫌悪ばかりが積もるのだ。他の同期たちが先輩方と上下の垣根なく流暢に語りあうさまは、もはや憧憬を超えて目を背けたい程だ。実際そんなとき、用もないのにそそくさと立ち去ってしまうことが私には多い。灰を食らうような惨めさから逃げるためである。
思うに私はモノローグ的な脳の持ち主なのだ。流行に則って言えば、コミュニケーション障害者。ひとり思案ばかりで、相手の返答を期待できない思考様式がすっかりこびりついている。こうやって独白的に言葉を紡ぐ分には、淡々とセンテンスを繋げ続けることができる。ただ、会話の場合は相手の返答が予測不可能であり、(「不可能」と言い切ってしまうあたりに私の欠陥があるような気はする。わかってはいるのだ。)さらにそこへ満足ゆく発言を即座に合わせる必要がある。会話がよくキャッチボールに喩えられるのは、私からすれば間違いで、正確にはバッティングに近いと思う。相手の予測不能な配球を上手くバットにミートさせなくてはいけない。しかもピッチャーのグローブめがけて打ち返せというわけだ。投げては打ち、投げては打ち。球数は一球限りという緊張感。
どうして私たちは小説に出てくる人々のような「スムーズな会話」ができないのだろう? 当たり前だ。小説のダイアログなんかは結局、作家の搾り出した、脂の乗った独り言なのだから。そこに見られる当意即妙の連続は「作品」であり、日常になどありはしない。絶対にホンモノの会話ではないのだ。だけれど、私の知っている「会話」のサンプルは幼いころから本の中、つまりフィクションの物語中にあった。作中では、かの主人公たちが冴えた言葉のやりとりをしていて、なんとも完成された感があり、素直に私もこれに習おうと思った。そういった、いわば虚構の対話集を教科書にして生きてきたのが私なのだと、最近ようやく気付いてしまったわけだ。
ところで、世には「不気味の谷」と呼ばれる現象があるそうだ。元はロボット工学の分野で生まれた言葉らしい。ロボットをヒトに似せて作ってゆく際、ヒトへの類似度を横軸に、それを見た人間の心理的好感度の高さを縦軸にとってグラフ化すると、ある程度の類似度まではロボットがヒトに近づけば近づくほど一般に受け入れられる傾向があり、グラフは上昇してゆく。しかし、かなりヒトへと近づいてきたある段階で、右肩上がりだった好感度は急下降をみせ、完全にヒトになったところで再び急上昇する。グラフ上に描かれたこの激しいV字谷こそが不気味の谷と呼ばれる由来だ。要するに、私たちは精巧な人体模型より、デフォルメされたゆるキャラの方が好きなはずで、シリコンで作られた肌色の皮膚を纏ったロボット(しかも動くし、喋る。)なんかは、「似すぎていて、でも絶対にホンモノじゃないし、なんだかとにかく気持ち悪い。」と一蹴されてしまうのである。
急にロボット云々の話をしたのは言うまでも無い、他者から見たときの私がまさにこの深く陰気な谷底をさまよう存在と化している気がするからである。不気味な奴だと思われていなかったか、これまでをふり返ると思い当たる節が多すぎる。私は周りの人と限りなく同じように努め、脳内での涙ぐましいお喋り訓練と風呂場での笑顔の練習を欠かさず、好感度を勝ち得ようとしているつもりだ。ただ、頭の回路がちょっと一方通行だったのと、勉強するにも教材が悪かったので、見てくればかりはヒトだがどこか出来損ないの「みょうちくりん」になってしまった。どうぞ読者のみなさま、私が健康で(これは問題ない。)文化的な(自分の中では私はすこぶる文化的だ。)最低限度の生活(ここが満たされていない。)を送れるように、応援していただきたいものである。谷底からの脱却!
二年 竹林 たえ
不気味、歩く、話す
女性徒のエッセイというのはもちろん設定に過ぎず、実際は著者の自身に対して思うところを書き付けただけのものです。
個人化の新時代に自己という意識をどう形成するか。コミュニケーション至上主義への不安。
アイデンティティの感覚はいい大人になっても掴みきれないところがありますね。
気恥ずかしさを誤魔化そうとして高校生の作文という形を借りてみましたが、思えばそんなことばかり。
竹を割ったような主張は我が立ちすぎるから、屈折した表現が必要だ。ところが普通は、そんな意思表示は不通なのです。