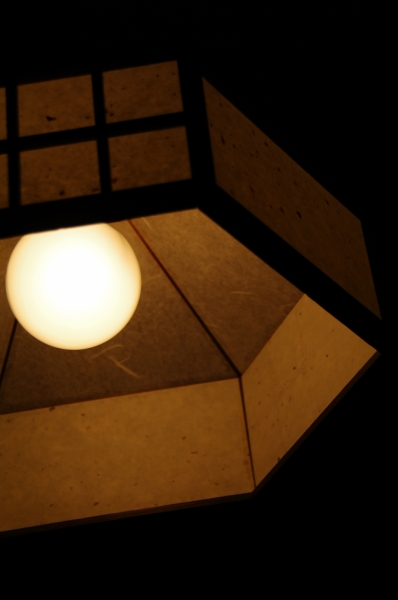
不条理語りの文月
◇◇
絆と呪いは何が違うか。
あるいはそれは似たようなものか。
俺と彼女は兄妹だ。
俺には彼女という妹がおり、彼女には俺という兄がいる。
彼女は俺を兄と呼び、俺もそれに応じて彼女を妹とする。
俺と彼女は兄妹ですか。俺は彼女の兄ですか。彼女は俺の妹ですか。
返ってくるのはイエスのみ。
誰に聞いても別の関係を見出される事はなく、俺と彼女は兄妹らしく。
何故だったか。
俺と彼女が二人連なって兄妹であるのはどうしてか。
他の立場ではいけなかったのか。俺が兄であるのはどうしてだったか。
問うてすぐ頭の内側から答えが飛ぶレベル、自問するにもつまらな過ぎるくらいに易しい話。
俺と彼女の二人がいて、俺が彼女より先に生まれた。
それを理由に兄妹をこじつけた、ただそれだけの話である。
事実、俺達は兄妹だ。
それが尊い事かはよく知らない。
◇◇
弱々しい明かりが一つだけ灯った薄暗いリビング。
パチパチと不規則な光を発しながらゾンビを映しているのが壊れかけのテレビで。
ソファーに腰掛けてその化石家電の方を向いているのが俺で。
その後ろから足音を立てないように近付いてくるのが俺の妹だ。
妹の名は文月(ふづき)と言った。
俺の名前は今はいい。妹は俺を名前で呼ばないからだ。
「兄様、映画を見ているのですか?」
文月が俺の肩に手を置いて顔を覗き込み、その長い黒髪がサラリと頬に触れた。俺が映画を見ているかどうかなんて、俺がこうして映画を見ているのを見れば一目瞭然だろうに、何を思ってそんな改まった質問を投げかけるのか。
文月は身長170cmの俺と比べても大して変わらない背の高い女子だが、その長身がこの距離まで足音の一つもさせずに近付いたのは、俺の意識がテレビの中に向いているのを知っていたからこその気まぐれではないのか。
「見ての通り、ホラー映画を見ているよ。君の感性だとチャップリンのコメディに見えたりするのか?」
気まぐれには気まぐれだとばかりにウィットに富んだジョークを飛ばしてみたが、言ってしまった後でなんだか外したような気もして汗が出そうになる。安っぽい三流洋物映画を見ながらのこの台詞、お前はどれだけ影響されやすい人間なのだと冷めた態度をくらっても仕方がないだろう。
しかし文月にとって相手の言い回しなどは些事であるらしく、俺が滑った言い訳をする前に、次の質問を重ねてきた。
「トイレはどうしました?」
年頃の男子高校生が妹にトイレ事情を尋ねられるというこの状況がよくわからず、何を言ったものかと言葉に詰まる。トイレはちょうど20分くらい前に済ませていたのだが、そんな事をクソ真面目に報告したいとも思えなかった。
「トイレの話の何がそんなに大事なんだ? 俺は別に今は行きたくないさ、文月が先に行けばいいよ。」
年功序列にでも気を遣ったのだろうと半ば決めつけて返事をしたが、文月はそれを聞いてトイレに向かう訳でもなく、ただ何事かを考えるように黙り込んだ。俺もそんな彼女に何を言えばいいのかが特に思い付かず、何か考える訳でも無いが同じように黙った。
時計の秒針がカチカチカチと三秒程進んだ所で、黙って見られているのに気付いたのか、文月はコホンと咳払いをする。そしてやけにゆっくりと顔を近づけ、吐息に混ざって溶けそうな囁き声を俺の耳元に浴びせてきた。
「何の話かというとですね……今夜は兄様と私の二人きりです。そうでしょう?」
耳にむずがゆい感触を覚えながら、だったら内緒話なんていう可愛げのあるコミュニケーション手段を選ぶ必要は無いじゃないかと心中でぼんやり考える。
そして文月の方はやはりそんなところに問題があるとは感じていないようで、ざわざわと広がる俺の鳥肌には気付く素振りも見せず、次の言葉を告げた。
「トイレに鍵が掛かっているのは何故ですか。」
言わんとする事を理解するまでの少しの静寂。
家に二人。
ここに二人。
トイレは使用中。
テレビの中で血にまみれた三流役者が叫び声を上げた。隠れ家に忍び込んでいたゾンビに首筋を噛まれ、彼の肌はみるみるとゾンビ色に変わっていく。
「誰がトイレの中にいるんだよ。」
知らず、口の中で消えてしまうほど小さな呟きとなった。
先程のチャップリンの時とは全く別の、嫌な焦燥感がじわじわと体に広がっていく。あらためて目を向けると、文月の表情も落ち着いているようでいて、強いてそれを装っているようなぎこちなさが伺えた。
遊びの空気ではない。
俺は静かに席を立ち、文月の横まで歩み寄った。
焦りはあれども、理解した瞬間にその驚きを大声に変えてしまうような愚行を犯さなかったのは正解らしい。こいつが自身の不安を抑え込みながら努めて緩やかに提供してくれたのは、俺の心の準備という事だ。それを無駄にするのは兄ではないだろう。
「鍵が掛かっているのに気付いたのはいつだ?」
妹に倣い、顔を寄せての耳打ちで聞き返す。トイレの中でじっと聞き耳を立てる何者かを想像すると、意識せずとも余計に声が小さくなるのだと知った。
「俺は20分前に一度トイレに行ったんだ。何者かが入ったのなら、その後になる。」
その20分の間に知らない人間が家に入り込んだ様を想像し、少し背筋が寒くなる。
すると文月は今度は俺の耳元に顔を寄せる事はせず、ただこちらと目を合わせて呟いた。
「兄様、これ、息がくすぐったいです……。」
「俺が一番最初にくすぐったかったよ!」
気の抜ける返事に反射的に強い調子で返してしまったが、まだ兄でいられるだろう範疇の小声ではあった。
◇◇
ゾンビがうるさいから耳打ちなんてしたくなるのだろう。雑念をシャットアウトするためにも、リモコンでテレビをオフにする。せっかく視聴していたのに結末を見ないままだが、悪友にネタバレされてオチを知っているから気にしない。
世界中がゾンビだらけになって人類が滅亡して終わるB級映画だ。バッドエンドを笑い飛ばすのが好きだから見ていた。あんな冗談みたいな破滅が、その通りただの物語でしかないなんて素敵な事だ。
安い世界が安い滅亡を迎えるのを思い浮かべながら、俺はゆっくりと呼吸をして気持ちを落ち着かせた。
「誰かが入り込んでるかもしれないって言うんだろう。」
「そう……ですね。そういう事です。」
耳打ちなんて小細工を使わずに小声で話す。
「空き巣だろうか? トイレに立て篭もる理由が謎だけど。」
「そうかもしれません。最近はこの辺りにも空き巣が出るらしいと回覧板で注意されていました。」
細かい事を言うなら、留守でない今の我が家に忍び込む行為は空き巣ではないが、その情報は現在トイレに封じ込められている不気味な空気を更に粘性の高いものに変えるのだった。
「俺が調べてくるよ。君は携帯を持って、110番をスムーズに押す準備をしてろ。」
「でも、それは兄様が危ないです。」
「そうは言っても、流石にこの段階で警察を呼ぶのは躊躇うからな。ノブが変な具合に引っ掛かって回らなくなった事、前にあっただろ? 今回もその程度の話なのかもしれない。まずは俺にも現場を改めさせてくれよ。」
そうやって安心させようと笑ったが、言い終わらない内に妹は俺の腕を掴んでいた。単なるポーズでない、真剣味のこもった力強い圧力が俺をトイレに行かせようとしない。こいつが希望的観測で納得するような性格じゃない事は知っていたが、こんな風にただ物理的に俺の行動を阻止するような態度に出たのは少し意外だ。
何か言いたげながらも口に出すべきかどうかを迷っている様子の文月。繋ぎとめる手に少し力が込められたかと感じた直後、彼女は意を決したように口を開いた。
「ドッペルゲンガーだったらどうするんです。」
「うん。」
中にいるのがドッペルゲンガーだったら。
それはご対面したら死ぬだろうな、だってドッペルゲンガーとはそういうものなのだから。
ならばもちろんトイレに近づくべきではないと答えるのが正解だったのかもしれないが、考えるべき疑点はそこではないような気がして、俺の喉からはただ生返事しか出てこなかった。
「ドッペルゲンガーだったらどうするんです。」
「ドッペルゲンガーだったら……大変だよな。」
「そうなんですよ!」
俺の変わらぬ生返事の何が燃料になったのか、急に勢い込んだ文月は語り出した。
「兄様、こんな日が来るのではないかと思っていたのです。
私たち一家は父様と母様と兄様と私、四人家族ですよね。ですが、私には時々それが信じられなくなる事があります……ただの四人にしては、家に漂う人の気配が少し賑やかすぎるのではないかと。具体的に言えば、どうも実際の人数よりも一人多いような気がするのです。
一家揃って食事をしている時に部屋の外から聞こえる物音は壁のきしみでは無い気がします。家族が階段を登り下りする足音なんて、長く暮らせば誰であるかの判別が付くものですが、目の前で本を読んでいる兄様が階段を登っているはずがありません。兄様の旅行中に私が夢うつつで聞いた兄様の声、あれは本当に夢だったのですか?
今のように兄様と家に二人でいると、そんな違和感が一層顕著に現れます。兄様、トイレの確認になんて行かないでください。あなたがそのドアを開けた途端に何処か取り返しの付かない所に連れていかれてしまうかもしれない、それを馬鹿馬鹿しいと思わずに、どうか信じてほしいのです。」
やや早口にまくし立てるその取り乱し様は、年頃の少女に失礼でない言葉で形容するのがちょっと難しい程だ。多くの知人が「君の妹は歳の割に落ち着いていて賢い」と言うし、俺も自分でそのように思っていたのだが、それを今日限りで気のせいにしてしまうべきなのだろうかと悩む。
しかしそうだ、そういえばそういう奴だ。ここ数年はそういう事が無かったから忘れてた。こいつは……そう、ちょっとそういう所があるのだ。
そう、あれなのだ、つまり、こいつは、そう、実は想像力が豊かなのだ。
こんなのどうすればいい、どう言ったものか。
文月の言うとおりに誰もいないはずのトイレに鍵が掛かっているのなら、それは要確認事項だ。
だが、その文月自身がどう考えても現実的とは思えないポイントを心配している、この絡まった状況。
先に手を掴まれた時の力強さからも実感できるが、こいつは恵まれた身長に相応しく身体能力抜群であり、青春期の女子高生の寝言だと突っぱねて強引に押し進む事は難しい。俺はこれから、この目の前の少女の夢見がちな頭の中身を最大限尊重しつつ、しかし一方でそれを覆すのを目的として、長い説得を始めなければいけないようだ。
それも、あのトイレの中に本当にいるとも限らない、そう、よくよく考えてみれば、まだ実在も確定していない強盗だか殺人鬼だかの脅威に万全を期する為だけに。
「兄様、そこのガラス戸を開けて庭に出ましょう、家から逃げましょう。家に不審者がいるようだと警察を呼べばいいのです、違ったら二人で一緒に怒られればいいじゃないですか。」
そうなんだ、これから俺は実在するかもわからない仮定段階の脅威に用心するためだけに、妹の仮定以前に架空でしかない脅威を「考え過ぎだよ」と棚上げチックに笑わなければいけないんだ、いつドアを開いて襲ってくるとも限らない仮定の脅威への仮定の緊張感にビクビクしながら。その先に待っている現実が結局はドアの不具合だろうとやらねばならない、仮定の殺人鬼が殺しに来るのだから。
いやしかし待てよ、本当に説得は大前提なのか。
そもそも俺と文月の利害は一致しているじゃないか、トイレの中に危険が潜んでいると考えているのは同じなんだ。だったら、文月の言うように外に逃げて警察を呼べばいいだけの話なのかもしれない。中に潜むのがなんであろうと、物騒な事態に対応するプロの彼らに任せれば全て安心じゃないか。
だが、いくら怖いからといって、仮空き巣や仮ドッペルゲンガーを理由に警察を呼ぶのはやはりどうなのだろう。仮とはいえ命の脅威にさらされているのかもしれないのだと考えれば、その判断が正解なのかもしれないが。
「何もなかったら、絶対警察に迷惑を掛けるな。後々で怒られるかもしれない、そうでなくても呆れられるかもしれないな。」
「兄様!危険が現実になってからでは遅いんです!」
なんだろうか、この、俺の見通しの甘さを責めるような正論じみた叱責は。生きるか死ぬかの土壇場、そんな見栄を気にしている俺の方が聞き分けが無いとでも言うのか。譲歩すべきなのは俺の方なのか。
違うだろう。
だって、ドッペルゲンガーだぞ。目の前のこの子が気にしているのはドッペルゲンガーなんだぞ。
もう、どうすればいいのかが本気でわからなくなってきた。ここで突然叫んでみよう、なんて意味不明で直情的なアイデアだけがやけに湧いてくる。
そうだな、いいじゃないかもう。面倒になってどうでもいい気分になって、それを全て叫びに変えてぶちまけてしまえよ、きっと心の底からスッキリできるに違いないぜ。
仮定の犯罪者も架空のドッペルゲンガーも知ったことかとばかりに叫べばいい、その叫び声をきっかけに全てがうやむやの内に解決される夢を見て叫べばいいじゃないか、年長者の余裕と無責任な咆哮が乗った天秤、後者に傾けて叫んでしまえよ。
一切合切荷物を投げ捨て、根の根の感情目指して走れ、先にあるのがすなわちハッピー、そうとも正しくハッピーエンドだろうさ。
「でも、君はそんな子供じみた逃避行動に走る俺を見たくはないだろうね。」
「兄様?」
何を格好付けた事を言っているのかはわからないが、妹の前で醜態を晒すのは好きでは無かった。駄々をこねても報われない、前を向いて頑張って初めて報われる、兄様というのは大体そんなものだと知っている。
「いいかい文月、よく聞いて。ドッペルゲンガーなんて、どうせ何処ぞのやぶ医者が考えた作り話さ。診断が難しかった時に『死因はドッペルゲンガーです』なんて言っておけば、楽で嬉しいだろう? そういうくだらない背景で作られたデタラメなんだよ、ちょっと考えればわかる事じゃないかハハハ。」
前を向いて頑張りだせたのは良いが、口から出たのは毒を持って毒を制すようなデタラメでしかなかった。
なんだか違うな。これで文月が納得してくれるようなイメージがまるで浮かばない。
「え、それは、そんな何の根拠も無い空想を語られても流石に困ります!」
確かに。
「なら、巷に蔓延るドッペルゲンガー伝説が今言った空想よりも真実か?」
「はい。」
「はいじゃないよ、あれだって結局は作り話でしか無い。それにドッペルゲンガー自体の実在が疑わしいのに加えて、君の言う事にはもう一つおかしな点があるな。仮に本当に変な妖怪が家にいるとしても、それがそのドッペルゲンガーだと決め付けるのはおかしいだろ? 君がドッペルだと思っているのがぬらりひょんでは無いと、どうして言い切れる?」
問う所がずれている気もするが、今のは割と大事なポイントかもしれない。本人がドッペルゲンガーだと思い込んでるからドッペルゲンガーになってしまう、話の本質はそういう事だろう。
「ぬらりひょんは兄様の気配を持ちません! 兄様、疑わしく思う気持ちはわかります。私もドッペルゲンガーなんて非現実的だとは思っているんです。こんな空想のような考えを真面目に話して、兄様に軽蔑されるの、本当は嫌です……。
でもお願いです、聞いてください。私の言ってる事は根本的におかしくて、一刻も早く目を覚まさせなければいけない類の妄言である、それは解ります。でも今は私の話を聞いてください、馬鹿な妹だと一笑に付す前に、私が体験した初めの不可解を。先月の出来事……今と同じ、休日に私と兄様が家に二人きりだった時の話をさせてください。」
恣意的ながらもこちらが理詰めで語っているというのに、自身の話に疑念の一つも生まれた様子は無い。
いつもこうだ。こいつは形の上では人並みに理屈を口にして他人を納得させようとしたりもするが、こいつ自身は理屈なんて少しも重視しちゃいない。自分がフィーリングでこうと思ったら、それを目の前の事実で覆されるまでは意見を絶対に変えようとしない。こちらの言う事はちゃんと全て聞いてその妥当性だって理解しているはずなのに、にも関わらず自分の直感の方こそを正しいと思えるのは何故なのか。無知無能ゆえの思考放棄ではなく、全て受け止めた上でそれでも歯牙にも掛けない、この強固な歪の所以は何処だ。
「その日の私は寂しく自室に一人きりでした。机でただただ小説を読んでいた事くらいしか説明するところもない、そんな何も無い休日の昼下がり。けれども、扉を何枚か隔てた先の兄様もまた自室で本を読んだり勉強をしているのだろうと想像すると、なんだか不思議と安心感が生まれてくるのです。昼を過ぎてから一言も口を開かず、ただ同じ空間にそっと存在する兄様に思いを馳せるだけ。ゆっくりと日が暮れるだけのその日の事を私は気に入りました。」
「そうか、良い話だな。」
「良い話ではありません兄様。だって今はドッペルゲンガーの話をしているのですから。」
話している内に汗ばんできたらしく、文月は俺の腕から手を放して一呼吸つく。
「ふう……あの、兄様、私が腕を放したからって隙を付いてトイレに行こうとなんてしないでくださいね。
それで、それから私は最後のページまで読み終えて本を閉じました。正直に言えばそこまで独創的でもないありふれた小説だったのですが、同じようにありふれた休日の穏やかなムードを演出するのには大きく貢献したようでした。
目を閉じて机に突っ伏すと、長い読書の姿勢で固まった身体がほぐれていきます。肌に感じる昼下がりの日常と、本を通じたフワフワとした空想の世界を身体の中で混ぜあわせ、しばし、内側に沈み込むようなまどろみを楽しんでいました。
そんな風に積極的な行動から離れてじっとしていると、色々な事を考えるものです。本を読んでいる間は忘れていたような事もふと気にかかります。『そういえば兄様は今日は模試に出ている、今頃ちゃんとできているだろうかな』と」
家で二人きりでは無かったのかい、なんて野暮なツッコミをしないのが兄様だ。手で握られていた場所の汗が冷えてきた。
「そうです。考えてみれば兄様は模試に行っていました。兄様は遠くでした。家に私は一人でした。扉数枚隔てた先に兄様はいないのでした。私は勘違いをしていたのです。」
「なのに、その兄様の不在という事実が全く実感できないのは何故でしょうか。そうです、扉数枚隔てた先に兄様はいないのです。いないのに、それがどうしても理屈でしか理解できないのは何故ですか。なんで私の感覚の中での兄様はまだこの家の中にじっと佇んでいるのでしょう。どうして壁の向こうから私の方をじっと見ているような気がするのでしょうか。
そもそも私はなんで兄様がこの家の中にいると思っていたのでしょう。ようく思い出してみると、確かに私は兄様が朝に家を出ていった姿を見ていました。なのに兄様と家に二人きりの幻想を垣間見る。ありえないと思いますか?
更にようく思い出してみるならどうでしょう。朝に玄関から出ていく兄様、それを見送る私。それが本当にその日の私と兄様との最後の邂逅だったでしょうか。出かけたはずの兄様と、何故かその後も数度顔を合わせていたとしたら。まさに模試を受けている最中のはずの兄様が何故かこの家にも同時に存在していて、その兄様に私は既に接していたのだとしたら。私が無防備に身体の内側まで浸かりきった素朴で温かい一日の根がそこにあるとしたら。
私はそこから先を考えるのが怖くなりました。怖い……そうです、私はとても怖かったのです兄様。ようくようく思い出した結果、いないはずの兄様と確かに顔を合わせていたのだとしたら。私が素敵だと思った静かな昼下がりの意味がぐるりと逆転し、得体の知れない異世界の瘴気を纏うのだとしたら。
考えるのをやめた所で震えが止まる訳ではありません。一人きりの心細さの話ではないのです、得体の知れない二人きりが耐えられないのです。
私は携帯電話を持って家を飛び出しました。靴を履くのに失敗したので、裸足で飛び出しました。もう駄目だったんです、早く兄様に会いたかったんです。兄様の姿を見ないと、兄様の声を聞かないと、私は安心できなかった。どこの誰がどう考えてもその場に正しく存在する本当の兄様に触れたかったんです。
兄様、あの時の事は本当にごめんなさい……。大事な全国模試を中断させるような駄々をこねて、悪い妹だと思ったでしょう。」
「それは……そんな事は気にしなくていい。不安になったら頼ればいいんだから。」
どんなあり得ない理由だろうと、その不安だけは確かに現実なのだから……と言うと皮肉みたいになってしまうが。
あの日の文月からの通話は酷く要領を得ないもので、とにかく向こう側の動揺だけが伝わってきたものだった。こちらが通話に応じて声を聞かせた途端に、やけに勢い込んで俺の様子を確認してくる。平穏無事を伝えるとほっとするが、どうしたのかと問えば言葉に詰まる。
しかし、とにかくあいつが今すぐ俺に会いたがっている事と、模試の事を考えてそれを言い出せない事だけは察しがついた。
「理由も聞けずじまいだったが、まさかドッペルゲンガーにおびえていたとは……。だけど、ファーストフード店で落ち合ってからの君は落ち着いたように見えたぞ。あの時『きっと勘違いだった』と言ったのは本心からだろう? だから俺も、その日の事はそれで済んだと思ったんだが。」
「ええ、本心でした。兄様に会えて安心すると、途端に今までの事が全て妄想だったように思えて……正直、少し恥ずかしくなりました。兄の不在が寂しくて泣くような年でもないのに。だから電話を掛けた理由も言いにくかったんです、だってこれじゃあ小さい子供と変わらないじゃないですか。」
「今起きてる事だって、きっと終わった後に勘違いと思うだろう?」
「思いません。その日初めて恐怖を抱いてから今日に至り、私の心には確信が生まれました。」
聞けば聞くほど、いやに根が深い。
なるほどその確信はさっきから俺にも見えているが、まさかこれからずっとそれを抱いて生き続けるつもりじゃないだろうな。俺が一々それに付き合って逃げて、こいつが一々それの不安で憔悴する。そんなのは流石に受け入れ難い。
だから、言葉の説得はこれまで。
このまま話を続けていても、お互いの舌が乾くだけだとわかった。ドッペルゲンガーとその不安、無理矢理にでも今日限りで忘れてもらうしかない。
どう変に思われようが俺を救おうとした文月には覚悟がある。対する俺には、それを無慈悲に踏み砕く覚悟が必要だろう。
俺はリビングの扉を開け、廊下に一歩踏み出た。真正面には件のトイレ。取るに足らない妄想は、それを覆す事実によって消える。
「兄様!?」
慌てて肩を掴もうとする文月の手は、その対象が更に二歩目三歩目と進んだ事で空振る。
俺はそのまま壁に立てかけてある床拭き用のモップを手に取り、その柄でトイレのドアを勢い良く叩いた。叩いた俺自身でさえ驚くような大音に威圧され、それを制止する素振りだった文月が固まる。
「なあドッペルゲンガー、トイレの中にいるならさっさと出てこればいいだろうが! 反応をよこせ! 実在するなら、その実在を示してみろ!」
「兄様、何を馬鹿な事を! やめてください!」
振り向き、文月と顔を合わせる。
馬鹿げた事をやっているのは事実なので、多少心に来る言葉ではあった。
「ど、ドッペルが! ドッペルゲンガーが出てくるじゃないですか! ドッペルゲンガーじゃないにしても、泥棒が入っているかもしれないとは思っていたんでしょう!? なんでこんな軽はずみな行動を……!」
確かにその辺の前提を考えれば賢い行動では無いだろう。だが、妄想に妄想を重ねて混乱している妹とは違い、俺の頭は一足先に冷えている。見えないドアの向こうに鬼を描くより、もっと観測が可能な部分に意識を向けるといい。
「トイレ用擬音装置が鳴ってない。だからトイレには誰もいるはずがないんだよ。」
「あっ……。」
我が家のトイレには、人が入ったら自動で流水音を流す装置が付いており、その音はトイレ前の廊下どころかリビングにいても微かに聞き取れる。リビングで文月の長い話を聞いている最中、俺はそれが聞こえない事に気付いたのだ。
「もっとも、あの機械でお化けを感知できるかどうかなんて知らないけどな。ドッペルゲンガーはセンサーに反応しない存在なのだ……なんて言うかい?」
「それは……その可能性だって否定はできないです。ドッペルゲンガーは実体の無い虚像のような存在なのかもしれないから……。」
そんな事を言いはするものの、文月の態度は先程と比べて明らかに歯切れが悪い。流石に、虚像が兄様の気配を持つなんてしっくり来ない話だからな。
今ここにある妄想を半分でも砕く事ができたのなら、あとはこのドアも開けやすくなるというものだ。
「兄様……それでも、本当に……」
さあこいつの鼻先に突き付ける、この中の無人の空間。
このドアを開けた時、俺でなくドッペルゲンガーが死ぬ。
◇◇
ノブに手を掛けて回してみた。ガチャガチャと引っ掛かるだけで回らない。
我が家のトイレのドアは、ノブの中心にあるボタンを押すと鍵が閉まるタイプであり、ノブが動かなくなる事で開閉を防ぐ。よって、ノブの不具合で引っ掛かっているのか、中から鍵が掛けられているのか、手応えだけでは判別し辛い。
「鍵が掛けられてるんじゃない、きっとノブの調子が悪いだけだ。前だってそうだったんだ、今回もそうさ。ドッペルゲンガーの出番なんて無いよ。」
「に、兄様……やめてください……。」
弱々しい制止が、逆に文月の揺れる心を知らせてくれる。ここでやめる理由は無い。
「文月、ここで開ければ全部解決するとは思わないか。一応、鍵を差し込んでみようか。故障のメカニズムなんて解らないからな、もしかしたらそれで開くかもしれない。」
ドア横に吊るされた絵を額縁ごと下ろして裏を向けると、セロハンテープで貼りつけられた鍵が見える。そうそう使われない鍵だから、無くして面倒な事にならないようにと分かりやすいところに置かれている訳だ。無用心過ぎて気持ち悪いとも思っていたが、なるほどこういう状況を体験してみると、確かに便利だな。
テープを引き剥がし、べたつく鍵に構いもせずに鍵穴に挿し込んだ。
そして手首をひねろうとした所で、後ろから俺の両脇の下を何かがすっと通りすぎる。
「兄様、やめて!」
「えっ」
そのまま文月に羽交い絞めにされ、両腕の自由を奪われた。
「痛い痛い! ちょっと待て! なんか変なふうに極まってる! 痛い、待って待って!」
「兄様こそ待ってください! 兄様が待ってくれたら待ちます!」
単なる拘束にとどまらず、余分な力をぐいぐい加えてくる文月。頑張れば頑張るほど抜けにくくなるという理屈だろうが、その努力の大半は単に俺の苦痛へと変わる。
「うぐあ、何でこんなに思い切り良く拘束できるんだよ! ちょっと勢いを削いだと思って油断した、ちくしょう! ていうか痛い、加減しろ! いたたたたた!!」
「加減したら抜けるじゃないですか! 男の人は力が強いですから!」
「加減を知らない女の子の方が怖いよ! わかった、待つから! 話せば分かる、ひとまず放せ!」
こちらが譲歩の姿勢を見せると、文月はそのままの体勢で力を緩めた。その隙をついて無理矢理腕を解こうかとも考えたが、その拍子に文月を突き飛ばしてしまうと危ないし、俺への誠意を踏みにじるような真似はやはり気が引けた。
「妹にガッチリ羽交い締めされてるなんて、他人に見られたくないな……。なあ文月、君が今までしてきた話、何の具体的な超常現象も起こってないって気付いてるか?」
「全部『勘違い』で済ませられると言うのでしょう? でも、そんなのは実際に超常現象が起こったとしても同じ事です。たとえ兄様を同時に二人見たと言っても、きっとあなたは夢でも見たのだろうと信じてくれないですから。」
「痛い所を付くな。」
確かにドッペルゲンガーなんて地味な怪物、露骨な痕跡は残してくれないだろう。建物を破壊する訳でも魔術を使う訳でもないのに、他人にその存在を信じさせるのは難しい。そいつが起こす唯一の超常現象は、俺自身は絶対に確認する事ができないものだしな。
「私としても歯痒いです……今日まで恐怖を感じた事ならいくらでもあったのに、それは結局私だけのものでしか無いなんて。」
途方に暮れた様子で俺の背中に額をくっつける。
考えてみれば、彼女は誰にも理解されないまま一人で超現象に立ち向かうしか無いのだな。俺の腕を軽く締め付ける似合わない実力行使から、心中の無力感が見えるような気がした。冷たい正論を投げるのも躊躇われ、そのまま黙ってしまう。
「そういえば……トイレといえば、全国模試より以前にこんな事もありました。兄様がやけにこそこそとトイレや部屋を往復しているのを見かけたのですが、後で兄様に聞いてみても『そんな事は無かった』と言われたのです。思えば、それをきっかけに私は異変を感じ始めたのかもしれません。」
「ん?」
何かに思い当たる。
まさかとは思うが、どうしてもそこに関してだけは嫌に身に覚えがある。
なんだそれは、単にそれだけの話だというのか。今からそれを妹に全部説明しなければならないのか。なんだか凄く気が進まないのだが。
「まあいいや、それがこの事態を招く一因になってるなら心苦しいから言おう。あんまりこんな事を馬鹿正直に告白したくはないが。」
「え?」
ちなみにここで面と向かって話そうとしないのは、単に拘束されて振り向けないからである。
「俺の自室には鍵が無いじゃないか、だからベッドの下に隠すような類の本をそこで広げるのははばかられるだろう。そうなると、安全な別の場所に持って行って読む訳で……。だから、そういう事について言及されてもそれは誤魔化すよ、な?」
「えっ! いや、それは……!」
動揺したのか、俺を羽交い締める腕に力がこもり、再度痛い。
「あの……。」
二の句を告げられない様子の文月。
先程自分で言った内容と俺の話を照らし合わせているのか、ぼそぼそと何事かを呟いている。
長く続いた不毛な夜の一幕にようやく終わりの兆しが見えた気がした。なんだか俺の心臓はやけにべたつき乾いているが、とにかくこれで全てが丸く収まるのだろう。
「いや、でも……。でも、そういうのとは違います! そういう時の兄様は結構態度でわかるものなんです! そういうのとは違うんです!」
「おい。」
気のせいだった。何の成果もあげない俺の恥ずかしい告白こそが不毛だった。
「いや、待て、ちょっと待て! どういう事だよ、態度で全部わかるとは! いくら君の勘が鋭いからって、それは流石に適当言ってるだろう!」
「兄様が待ってくださいよ! 今、そんな話はしてなかったでしょう! そうじゃなくて……!」
恥を偲んで正直に言ったのに、そんな簡単に突っぱねられてはどんな顔をすればいいのか。荒唐無稽な事を言っているのはあちらなのに、なんだか俺の方が場違いな事を言ってしまったような気まずさ。
拘束を解くとかのためではなく、ある意味照れ隠し、暴れるために暴れるように俺は両腕を無意味にバタバタさせる。
妹がそれをやけに乱暴に抑えようとする理由も、その気持ちと似たようなものかもしれなかった。
そこに、そんな茶番に近いノリとは一線を画する鋭い物音が響いた。
突如すぐ近くに発生した爆音に、俺と文月は身をすくめる。
衝撃の余韻による、場の硬直。何が音を立てたのか解らなかったのは、その数秒間だけだった。
先程、俺がトイレのドアを叩いた時の音と同じだ。
「兄様……。」
質問するように、あるいは確認するように俺に呼びかける文月。
「俺の腕も足も、はずみでドアに当たったりはしていない。」
自分で口に出した単なる無機質な事実が、そのまま心臓に引っ掛かって取れなくなった。首筋にあたる吐息をさっきより冷たく感じるのは気のせいか。
文月は俺に身を寄せるように腕の力を強めた。妙にハッキリとした鼓動が俺の背中を打つ。
「内側から……?」
この夜の初心を思い出してしまうような小声だった。
文月が今どんな顔で呟いたのか、どんな感情が胸の中に蓄積されていっているのか、背中に伝わる微妙な所作を通じて手に取るようにわかる。だが一方、今はそれが文月の感情なのか俺の感情なのか、その区別は曖昧だった。
震えているのは誰なのか。震えているのは俺なのか。中にいるのは誰なのか。
文月の意識は既に俺を拘束する事には向いてない。
俺は刺さったままの鍵に手を伸ばし、それを回していた。『ガチャ』と鍵が解除された音を聞いて妹が我に返る。「兄様!?」と声を上げた瞬間には、俺はもうノブに手を掛けている。
その瞬間、自分が何を考えていたのかはわからない。ドッペルゲンガーなんて信じていなかったのかどうかもよくわからなかった。向こうにいる何者かの魔力に引き寄せられて何も考えられなくなっていたのか。それとも、俺の脳みそが意外に怠惰で思考放棄をしていただけか。
ともかく俺はノブを回した。
妹の制止は間に合っていない。
ドアは押し開けられた。
赤い。
まず、開けて真っ先にトイレの赤い壁紙が目に飛び込む。視界が一気に赤く染まり、次元の壁を飛び越えたような錯覚に目がくらむ。壁が血の色と同じである事に不吉を感じたのは、これが初めてだった。
その次、家の床のタイルがそういえば青かった事を思い出す。青い正方形が隙間なくビッシリと足元を埋め尽くし、見つめていると気が遠くなり。今この瞬間はその鮮やかな青が、空でも海でもなく死人の顔色に思えた。
その上に、閉じた洋式便器が鎮座している。ぽつりと佇む白。赤に囲まれて生えた白。青の真ん中に咲いた白。
とにかく白いが、白いだけ。やはりそれを清浄な存在と感じるような事は無い。
それで終わり。ドアの向こうはただのトイレだった。
「……あれ?」
「兄様……これは……。」
いない。
いや、いないはずはない。ついさっき、内側からドアが叩かれたのだ。それが何よりの証拠で、中には確かに何かがいるはずなのに。
いや、違うのか。
それならば逆も言える。そもそもトイレ用擬音装置が反応しておらず、それが証拠で中に誰もいないと言ったのは俺自身だ。中に誰かがいたのなら、前に立つ人間を熱センサーで感知するあれがどうして動かないのか。
あるいは装置より姿勢を低くしていればセンサーには引っ掛からないのかもしれないが、いずれにせよ地べたに体を伏せた怪人物などは見当たらない。ちなみに装置が故障している訳ではない、今まさに俺を迎え入れて音を出している。
『いないはず』と『いるはず』が内包されたトイレを開けてみれば、『誰もいない』。こうして中が空っぽである事実を目の当たりにしても、その矛盾の理由がわからなかった。喉が痛い。
「ごほっ」
ねばつく唾液が絡んだ咳の音。
俺の咳だ。急に咳が出た。
「兄様?」
目に違和感を覚える。奥の方から角膜の表面をじわじわと這い上がってくるむず痒さ。思わず、空いている方の手で目をこする。
痒い。
こすってこすって、それでも痒い。
視界がぼやける。
こすってこすって、それが何にもならなくて、それなのに俺はこすらざるを得ないままで。
「兄様!」
体がおかしい。
体調がおかしい。
異変がある。
どんどんどんどん異変が生じる。
指が涙まみれ。
俺は泣いている。
咳は止まらない。
これは これは
「兄様、ドアを閉めて!」
文月は気付いた。とっくに羽交い締めは解いている。
間抜けな俺も遅れて気付いた。
ドアの裏、反対側からぐいぐいと押してくる何かがいる。
それの正体を俺は身体全体で理解した。
絶対にそれに触れてはいけない、触れてはいけなかったからこんな事になっている。
眼部の違和感は、既に違和感と呼ぶには明確に過ぎ、自分が喉から搾り出すべき叫びが「痒い」で正しいのかがわからない。痒みというのは、人の目玉を縦横に掘り進む線虫の名前だっただろうか。
両手でそのおぞましい痒み畜生共を残らずこすり潰したい衝動を抑え、俺は自身の全ての気力を込めてノブを掴んだ。一生、二度と、金輪際関わり合いになってはならない。断絶の意思を叩きつけるような勢いでドアを閉めるのだ。
俺はノブを力の限り握り締め、そのまま引っ張ろうとした。
引っ張ろうとして
「ごほっ、ごほっぉ」
咳で体が折れた。
その刹那
それはドアの裏から顔を出した。
目が合う。
じっとじっとこちらを覗き込むように見ている。
目が逸らせない。奴も逸らさない。
視線の交錯を通して流れ込んでくる何かが、俺の体をどんどん重くしていく。
文月が俺の代わりにドアを閉めようと手を伸ばした。
そして、その手をやすやすとすり抜け、そいつは扉が閉まるより先に俺に跳びかかる
以上、それで詰みだ。
妹の耳打ちからドアの中身に直面するまで、紆余曲折の思考と選択を経て、俺は結局はここに至ってしまったのだ。
「フニャアー!」
イラッとする鳴き声を上げて俺の胸にドンと飛び込んできた、その毛むくじゃら。
猫である。
空気中に盛大に拡散される細かい悪夢が見えた気がした。
そうなんだ。俺は重度の猫アレルギーなんだ。
そんな事、忘れて過ごしていたかったのに。絶望感と諦めが頭の中を隅々まで支配する。
俺の人生、この世で最も無慈悲な生き物が猫だった。
◇◇
「兄様! 気が付いたんですね、兄様! 大丈夫ですか!?」
目を開けてすぐ飛び込んできたのは、屈み込んで俺を見る文月の泣きそうな顔と、その向こうにある天井。普段あまり見ない表情をあまり体験した事の無いアングルからぼーっと眺めていると、なんだか夢うつつが加速されていくようだ。
「なんだ……? どうなった、これ?」
すぐに身体を起こそうとしたが、文月に手のひらで頭を押さえられた。
「無理をしないでください。兄様は気絶していたんです。」
「ああ。」
すぐに思い出せた。
トイレのドアを開けたら猫が胸に飛び込んできたんだ。
普通の人間はそんなもの叩き落してしまえばいいと考えるかもしれないが、俺は猫アレルギーな訳で。咳でふらふらしてるところにそんなものをくらったら、それは後ろに倒れる訳なのだよな。
「ごめんなさい、固い床に寝かせたままで。でも頭を動かしちゃいけないと言われたから……救急車が来るまで、できるだけ身体を動かさないでいてください。」
横目で確認するが、寝ているのはトイレの前だ。ずっと倒れたまんまの位置で寝てたのか。
「あの猫はどうした?」
「真っ直ぐリビングに入っていったので、そのまま閉じ込めました。」
「そうか……部屋の中を荒らしていなければいいけど。」
一分一秒を争って意識不明者を介抱しなければならない状況において、その判断はベストに近いだろうな。邪魔のとりあえずの排除、俺の容態の確認、119のプッシュ、全部で20秒も掛けずに手際よくこなしただろう様が想像できた。向いている方向が正しければ、文月は非常に頼れる。
「兄様、具合はどうですか?」
「頭が痛いな、頭痛って意味じゃなく。それ以外は……特に無い。」
「アレルギーは?」
「言われてみれば、目が痒い。でも少しだな。」
質問に答える度に、自分の身体が大事ない事を改めて確認できる。俺の無事にほっとしている様子の文月の顔を見て、今が単なる平日の日常の夜なのだという事を思い出した。結局のところは、俺も文月も無意味な部分に気を張っていただけらしい。力の抜ける気分だが、それに付随する安心感は悪くない。
「ドッペルゲンガー、いなかったな。」
「ただの猫でした。」
トイレの窓の網戸を破って入ったらしい、と妹は言う。それで、偶然にも猫がノブのボタンを押し込んで施錠してしまったのだろうと。
まったく、何も不思議なんてものはありはしない。空き巣と比べたって、まだありふれた事件じゃないか。
「何か言う事はないのか。」
「ごめんなさい……。」
真っ直ぐ目を見て問うと、素直に謝った。
うちの妹は素直に謝る。
「兄様の言うとおりでした。私は今、今日これまでの全部はただの勘違いだったのだと思っています。兄様があれほど言ってくれたのに……もう、恥ずかしい。あんまり見ないでください、逃げてしまいそう。」
「ふうん。倒れている身としては、ここで診ていてほしいんだけどな。」
「だから逃げられません。」
そう言う、妙な夢から目覚めたいつも通りの文月に、つい軽く声を出して笑ってしまう。文月は拗ねたように目を細めたが、すぐに笑顔になった。
今日の出来事は結果的にほどよい刺激として吸収されたのか、さっぱりとした気分だった。冷静に考えれば別に何も良い事は起こっていないのだが、妙に疲労が心地良い。結果論だが、ソファーに座って檻の中のゾンビを眺め続けるよりはハラハラドキドキできて楽しかっただろう。
さっきあれほど脅えていた文月も、今は落ち着いて笑っている。頭の方から微かに聞こえる猫の声だけがやけに不機嫌そうだったが、それもなんだか面白かった。
「でも良かったです。こんな事を言うと、また笑われるかもしれないけど……兄様が生きていてよかった。」
ドッペルゲンガーの事か頭を打った事か、どっちの命の心配だろうか。猫アレルギーだって甘く見たら深刻な事態を招きかねないものなので、おそらく、諸々を全て合わせた上での『よかった』なのだろう。
「俺が死ぬのは、君が婆さんになってからだよ。」
「それ、妹に言う台詞じゃないです。」
そう言いながらも、彼女は嬉しそうな顔をする。俺はその顔を見るのが結構好きだった。
「もう本当に大丈夫そうですね。そろそろ救急車が来ると思うので、そのまま少し寝ていてください。」
席でも外すのだろうか、先程も言ったような事をまた念を押すように言う。
「何処かに行くのか?」
「えっとですね。」
文月は強いて何でもない風を装ったような顔で、斜め前のただの壁を見ながら言う。
「トイレに。」
言う間にそそくさと立ち上がり、俺の頭とは反対の側へ歩いていった。
そっと扉の閉まる気配が地面を伝わる。ドアの向こうで流水音が流れ始めた。
薄目で天井を仰ぎ、電球の眩しさを片手で受け止める。視界を狭めると河原で寝ているような錯覚が生まれるが、目を完全に閉じてその河原を探検したりはしない。
起きてから文月と話す事で色々と急速に落ち着いていったが、その落ち着き加減もまた落ち着いたように思う。本当の冷静というのは、今この瞬間からなのだろう。
じっと仰向けに静止していたところで、床の冷たさが俺とお話をしてくれる訳もない。
考えてしまうのは先程の事だ。先程の侵入者騒動。回しても開かなかった、あのノブの手応えを思い出す。俺が目一杯の力を込めて叩いたのと同じくらい、トイレの内側から力強く返されたあの音の事を思い出す。
俺が目一杯の力を込めて叩いたのと同じくらい、トイレの内側から力強く叩き返す猫?
猫は一体、ドアに何をぶつけたのか。目一杯頭突きをしてみせたのか。
猫とはそういう生き物だったか。
猫がボロの網戸を破って、窓から入るのはあり得る話だ。
その猫がノブのボタンを偶然プッシュしてしまうのはあり得る話だろうか。
あり得ない、とは言い切れないだろうな。何が楽しいのかノブに精力的にジャンプパンチをしていた所、偶然にもボタンを押し込み施錠してしまう猫。少し強引だが、それでもいくらかの現実味は残す想像だ。
では、家の人間がその物音を一切聞いていないのは何の偶然だろう。そもそも俺が鍵を使って扉を開くまで、あの猫は鳴き声一つさえ漏らしていないのだが、それは、そんな事もあるさと済ませてしまえる話なのか。
リビングから聞こえてくる鳴き声に意識を傾ける。
先程不満気な鳴き声と形容したが、もちろん猫の感情なんて俺には測れない。ただ平常心ではなさそうな鳴き方だったから、勝手に不満気な事にしただけだ。本当はあいつが鳴き声に乗せている感情は怒りではなく、悲しみだったり、あるいは恐怖だったりしたのかもしれない。
恐怖。
恐怖で声も出ない、という状態は人間特有のものであろうか。
あの猫は何かに恐怖していただろうか。あの閉鎖された空間の中で何かに脅えていたのだろうか。そもそも、あの何もない空間で猫が何に恐怖できるというのか。
血の色をした壁紙に恐れおののいたのか。
それは無い。
では、無機質なタイルに幻の屍体を見たのか。
違うな。
いっそ、便器が襲ってくるとでも思ったのか。
馬鹿げている。
だとしたら
真正面のドアから堂々と入り込み、そのまま黙って鍵を閉めた『何か』が怖かったのか。
人とも獣とも知れぬ不自然な異様に脅え、身体が動かなくなってしまったのか。
なんて。
俺は今、何故そんな荒唐無稽を想像しているのだろうか。妹を少しも笑えない。これこそまさしく妄想じゃないか。
だったら、その妖怪は何処に消えたんだ。猫がそいつに脅えたように、そいつも猫に脅えて消えたとでも? 馬鹿馬鹿しいな、猫に倒される怪異なんて。重度の猫アレルギーだったとでも言うのか。
何気なく入ったトイレでぼーっと佇んでいたら、その場に偶然居合わせたアレルゲンからごりごりとダメージをもらってくたばったのか?
そんな間抜けを誰がする。
俺だったら、そんな自殺行為は絶対に避けるだろう。
俺だったら。
俺だったら、か。
俺だったらどうするだろうか。
ある日突然形を成した俺はドッペルゲンガー。顔を合わせる事で本体を死に至らしめる事ができるらしい、そんな立場でどう動くのか。戯れに近付いて殺してみるか?
そんな悪趣味は犯さない。
だったら……それを避ける。隠れるのだろうか。
とにかくひたすら本体の動向に気を配り、外出中は家に、在宅中は外に出るような生活を心掛ける……だろうな。
ドッペルゲンガーだからといって俺である事に違いは無く、家にも家族にも思い入れがあり、できればそこで暮らしたい……と思うだろうか。
たまに本体が長く出掛けるような時は、ハメを外してつい活発になったりもする……のだろうか。
そんな風にしている内に、きっと勘の良い妹には感付かれてしまう。
やはり自分の居場所はここには無いと痛感するようになる。
そんな中、猫に出会う。
消えてしまえばいいのかと思う。
サイレンの音が徐々に近付いてきた所で、俺は思考を中断した。まずは、これから自分が救急車に運ばれるのだという現実を考えなければならないはずだった。
あやふやな記憶を頼りに妄想にふけっていても仕方がないというのは正論だ。ドアを叩き返した音は本当はもっと大人しいものだったかもしれないし、猫の鳴き声だって、聞こえていたのに映画に夢中だっただけかもしれない。あのドアを開けた時の身体の違和感が全て猫アレルギーの症状と同じだったかどうかなんて、結局俺はそんな細かい事を覚えてはいないのだ。
ドアが静かに開く音に振り向くと、トイレから出てきた文月と目が合った。文月は少し落ち着かないような顔でその目を逸らし、足早に手洗い場の方に歩いて行った。
文月はごく稀に今日のような妄言を口にする。
そして後に、それが何も理の無い妄言でしかないと気付くと、しばらく少し反省したような態度を取る。
こういう事は、あいつが何かしら精神的にあるいは肉体的にプレッシャーを受けている時によく起こり、今まで、その全てが笑い話に終わっていた。
後々になって俺などに笑われるたび、本人は少しムキになって自己弁護を始める。笑うしかない、だって本当に何の理も無い不条理語りでしかなかったのだから。
さっきも実感したが、あいつはそもそも俺に何かを伝える時に、論を組み立てる事なんてあまり考えていない。ただただ自分が感じた何かしらの生々しさを伝える事こそを重要視し、終始そのスタンスを崩さないのだ。
こちらが理屈の方を向いているすぐ後ろで、あいつの言葉は刻々とその不安や恐怖やおぞましさを具体的なものにしていく。論理、常識、そんな類の固い鎧で身を守っているつもりの俺だが、気付けばいつも意味不明の説得力で取り囲まれ、文月が語る理屈の無い話をただ聞くままになっている。理屈で否定するつもりだったその話に、気付けば理屈を見出そうとまでしている。
文月は今まで繰り返してきた自分の妄想を、真にただの妄想として記憶しているに過ぎないだろう。果たして俺も同じだろうか。感覚で捉えた違和感は時と共に風化するが、理屈は別の理屈で解体しない限りはずっと残り続けるのではないか。
文月という入り口を通して、俺の中に細かい奇妙が溜まり続けている。俺が見ている世界はちゃんと昔と同じだろうか。
笑うしかない。
笑わなければ、笑い話にならないじゃないか。
程なくして家に上がりこんできた救急隊員達は、俺の容態を確認後、すぐに俺を運んでいった。意識がハッキリしているのがわかった時点で撤収してしまうんじゃないかとも予想していたが、念のために検査はするらしい。
文月は家の中からガラス戸越しに俺を見送った。その手にガッチリと捕えられた猫は、俺を鋭く睨みつけていた。
さっきも体当たりしてきたこの猫、よっぽど俺の事が嫌いなのだろうか。俺は何もしていないのに。
--------------------
「それにしても、結局ドッペルゲンガーというものの正体が何であるかは不明瞭ですよね。」
「不可解な現象にとりあえずの名前を付けただけだからな。
胡散臭い色を強調するなら、本体から抜け出た魂の一部だという説を採るといい。
その一部が意思を持ち、別個の存在になったという事だな。」
「その別個の存在が、何故本体を殺そうとするのでしょうか。」
「いや、対面の結果で本体が死んでしまうのはドッペルゲンガーの大きな特徴だが、
俺はドッペルゲンガー自身が意図的に本体を殺そうとしている訳では無いんじゃないかと思う。
なんとなくだけどな。」
「ではドッペルゲンガーは優しいとして、
それが本体と顔を合わせた時に何が起こるのでしょう。
何が原因で死に至るのでしょうか。」
「元々一つだったぐらいだから、引き合わされて一つに戻ってしまうのだろうな。
それでキャパシティを超えてしまうのさ。
元は何者でも無かった魂の一部が、別個の経験を経て別個の人格を肥大させていく、それがドッペルゲンガー。
一人の人間が二人分の人生を受け入れる事なんてできない、という事だよ。」
「なるほど。
では、それでもしキャパシティを越えずに死ななかった場合はどうなるのでしょうね。」
「二人分の過去を持つ人間になる。
ドッペルゲンガーが経験した知識や記憶が手に入るんだ。」
「なるほど。」
「仮にドッペルゲンガーが死にかけで崩壊寸前だったとしたら、
それを全て取り込む事もできるんだろう、なんてね。」
「面白いですね。」
「そうかな?
ドッペルゲンガーが味わってきた気持ち、本体にとって愉快なものだと良いのだがね。」
「いえ、そこも含めて面白い空想話だなと」
「そうだな。」
不条理語りの文月
続き物だと思っていましたが、そんな事もなかったです。


