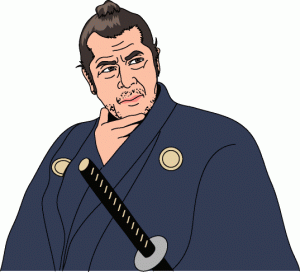冬の雨
1
昔から、除雪作業に楽しみを見出す少年だった。
自分のガレージや車、家庭菜園を持たない当時の僕(我が家としては、両親がそれぞれ車を所持してはいたが、それが少年の僕にとっての私物でないことは明らかだろう)にとっては、雪はただひたすらに僕に付き合ってくれる遊び相手でしかなかったし、「雪かきしておいで」という母の言葉は、だから嫌いではなかった。
高校生になり、次第に雪かきと疎遠になっていく。
雪にいちいち舞い上がること自体がなくなりはしたものの、それでも雪が降ったときのあの言いようのないうずきは消えず。雪かきという作業に悪い思い出もない僕としては、高校生だろうが母に言われたままに雪かきに汗を流してもよかったのだろうと思うのだ。
そこに、年齢なんて関係ないと、思うのである。
「だけど、僕が二年生の時だ。母さんが、仕事に向かう途中に事故を起こしたんだな。ふもと沿いに上がっていく道路があるだろう。あそこをいつも通り走っている途中で、落っこちたんだ。ガードレールを突き破って落ちてしまった」
「お母さんは、大丈夫だったの?」
「まあね。道路脇の木に支えられて、車はすぐ止まったんだ。父さんに聞いたんだけれど、車の中で、母さんはじっと固まっていたんだそうだよ」
「車を揺らしたら、落ちるかもしれないものね」
「そういうことじゃないと思うよ。けれど、まあ怖かったという意味では、同じなのかも」
以来、母は、雪の降る日に笑わなくなった。
灰色の空からそれがちらつくたび、母は人が変わったように口数が減り、そしてその少ない言葉には、怒声が混じり始める。
高校三年になるころには、母と父は、言葉を極力交わさないようになっていた。
「――雪、か」
僕のすぐ隣に腰を下ろしている少女が、おもむろに口を開く。
二人しかいないこの空間ではやけに声が響いたが、今更気に留める必要もないだろう。
僕らの腰を支える緑の長いベンチシートは、相変わらずいやに柔らかかった。
「嫌いかい」
「ううん、嫌いじゃない。でも好きっていうほど、雪に何かをされた覚えはないかも」
「そうか。外で遊ぶような子供じゃないんだな」
「そもそも子供じゃないもの」
「子供さ」
「違うわ」
「子供だと指摘されてそういう顔をする人のことを、子供だと言うらしいよ。受け売りだけれど」
「ふうん。じゃあさ、あなた、例えば三十……いや四十歳になったとするでしょう」
「うん」
「なった?」
「気分だけね」
「気分だけじゃないわ。外見もなったつもりで」
「結局気分の問題なんだな」
「もうっ、早く!」
「はいはい」
頭から突っ込んでくるのではないかというほどの勢いで憤怒する少女をあしらい、それでも、四十のおっさんになった気分だけは作ってみる。
将来のことは考えたくはないけれど、仕方がないだろう。
「なったよ」
「本当に?」
「本当さ」
「今一番怖いものはなあに?」
「自分の体臭」
「よし」
小さい頭を小さく一度だけ上下させる。
ベージュにホワイトのストライプが入った耳当てがやけにいじらしい。
「じゃあ次は『あなたは子供だわ』って言われた気分になってみて」
「想像力の世界ばかりだな」
「実際に言ってあげる?」
「いや結構」
見た目中学生の少女にそんなことを言われてしまえば、おそらく僕の自尊心がどうにかなってしまいそうだ。
「なった?」
「なったよ」
「で、どう?」
「どうって?」
「頭に来ない?」
「ううん、来そうではある」
「じゃあ来ないの?」
「たぶん」
「なんでよっ」
きいきい言い始めただけならよかったが、頭まで左右にシェイクするものだから、可愛らしい耳当てが落ちてしまったではないか。
全く。
そういうところが、子供だと言っているのだ。
「もう、あなたは想像力がなくていけないのだわ。昔はもうちょっと想像力があったに決まっているのに」
「想像力か。確かに、昔は想像次第でどんなことでも楽しかったな」
「お洗濯も?」
「お洗濯もさ。それこそ、雪かきだってそうだ。真っ白の世界の中で、自分一人がシャベルを持っていて、汗だくになっている。僕は、あの世界の中ではいつでも勇者だったんだ」
「へえ。ちなみに、それはいつごろのお話?」
「ちょっと待て。昔って言ったじゃないか。つい最近もそうだったみたいな認識で会話するんじゃない」
「勇者なんでしょ。細かいこと気にしないのよ」
「あのなあ……」
ふと、窓の外が気になる。
大きな窓からは『3番乗り場』と書かれた看板が街灯に照らされて見え、そしてその明かりの中にはちらほらと、雪が降っていた。
「雪だ」
「本当だ。最近多いわよね」
「そうだなあ。春も近いはずなのに、まだまだ降りそうだね」
沈黙がのしかかる。
彼女にも、もちろん僕にも、わかっているのだ。
今晩はこれまでだと。
もう、時間が来ているのだと。
壁に掛けられた時計の太い針が丑三つ時を過ぎ去ってから、またしばらく話し混んでしまった。
僕の責任だった。
いつも、切り出すのは僕の仕事であり、丑三つ時は、そんな僕の一つの目安であったはずだからである。
「寒くない?」
「ちょっとだけ」
「そうか。なら、そうだね。僕も君も、もう帰らなくちゃ」
そろそろ深夜の長距離ドライブを終えたバスが、この小さなターミナルに到着する。
そこが僕らの分水嶺だった。
「そうだね。帰るわ」
こうしてまたひとつ、彼女との時間が終わりを告げた。
これが一日の始まりなのか、それとも終わりなのか。そんなことがどうでもよくなるほどには、この空間に僕らが入り浸り始めてから、多くの時間が経過してしまっていたのであるが。しかしそんなことには全く気付かないふりをしながら、僕らはお互い、深夜の街並みをそれぞれ逆の方向に歩き始めていった――。
2
目が覚め、真っ先に部屋を出る。
時計は見ていないが、間違いなく正午は過ぎている。その証拠に、僕の下宿はやけに静かだった。
共用の洗面台まで足を運び、三度だけ水を顔に浴びせてから拭く。
階下では、何者かが何者かと話し混んでいる声が聞こえた。おそらく玄関近くでたむろっているのだろう。
学校に向かうのか、それとも帰ってきたのか。どのみち僕には関係のないことである。
鏡に映った自分の顔を一瞥して、それ自体には目もくれず足元のスリッパを履きなおした。コイツを買ってから、一体何か月が経っただろうか。いい加減に新調しなければいけないはずだったが、しかし新しいスリッパを履くのは気が引ける。
それというのも、新しいものはたいてい底が固く、やけに大きな足音が鳴ってしまうのである。
履きつぶしたこいつなら、たとえウチの急な階段を上がるときでさえ、無音でこなせるというのに。
「泥棒みたいだな……」
鏡の中の男が口を動かした。
少女といる瞬間とは明らかに違う、暗く、もそもそとしたおぼつかない口の動きだった。
そんな自分の姿に情けなさを感じなくなってから、もう何か月だろう。
その自問はつまり、僕が人として地に堕ちた瞬間から、いくら時が経ったかという問いに違いない。
既に日は上り、愚かしい男の一日が、始まっていた――。
カーテンを半分だけ開くと、鬱陶しいまでに痛々しい太陽の光が差し込んでいて、すぐに閉めなおした。
そのまま雑多にモノが散らかっているデスクの上に乗ったPCを立ち上げながら、ケータイで時刻をチェックする。おやつの時間はもうとっくに過ぎていた。
早ければそろそろ夕刻の講義を終えた学生がぞろぞろと下宿に戻ってくる頃である。
PCの起動音を聞くと同時に、そっとベッドの脇に転がっていたヘッドフォンを取出し、頭にかぶせ、ジャックをPCに差し込んだ。
手入れの行き届いたヘッドフォンやPCとは対照的に、デスクの下の段ボールに詰め込まれた大学の教材には埃がかぶっていることだろう。
講義テキスト、まとめ買いした大学ノート、詰め替え用にと溜めておいた修正テープや接着テープなど。
高校から大学に上がって真っ先に驚いたのは、必要だと言われたものをそろえるのにかかる金額の桁だったが、こうして無駄にしてみて思う。
入学時に勧められたままにそろえた自分はバカだったと。
「どうせこのように学校に行かなくなるのだ」というような意味合いではない。もちろん僕に限ればそれも否定できなかったが、そうではないのだ。
そうではなく、単純に、不必要なものが多すぎたのである。
例を出してみよう。
入学時に、購入必至だと説明されたノートPC。相場から見て、その値段は非常に高価なものだったが、カマキリのような女性の説明によれば、「大学での高度な研究に、このスペックと持ち運びの容易さは必要なものなのです」とのことだった。
しかし大学に入り、数多の教授の研究を目にし、そして知った。
こんなノートPCを現場に持ち出してくる教授はじめ研究生など、誰もいないということを。
その上大学四年間の間にPCを使う講義はおよそ八つ。そのすべてが文章作成ソフトとプレゼン作成ソフトの使用を求めてくるのみだった。
馬鹿らしい。なんとも馬鹿らしい。
この大学が、だろうか。
それとも意地汚いあのカマキリ女が、だろうか。
いいや、どちらも違う。
馬鹿で愚図で浅はかなのは、間違いなくこの僕だった。
妥協に妥協を重ねて、大した努力もせずにこの大学に入った自分に、一体どれだけの期待を寄せていたというのか。
一体自分は何者だと思ったのか。
一体自分は、何者になれると思っていたのか。
愚かなり。
――そんなことに気付いてしまった僕は、大学に行くことをやめた。
朝起きるのをやめた。
毎日三食食べるのをやめた。
本を読むことをやめた。
酒を始めた。
タバコを始めた。
初めてパチンコにも行った。
初めて女を買った――。
そうして、死ぬつもりだった。
が、そんな風に目覚ましく堕落していく自分にも、一つだけやめられない習慣があったのである。
二年通いつめ、成績は上位を収め、単位を一つも落とさなかった僕には友人もそこそこに、恋人だっていた。
しかしそんなものは三年生に上がると同時にですべて捨て去り、一人で夜な夜な遊びはじめ、仕送りを食いつぶし、極限まで自分を痛めつけた。
そう。遊ぶという行為は、僕にとっては自虐行為だった。
日付を気にせず遊び尽くし、いつのまにか学期は終わり、しかし覚悟したくせに死に踏み出すこともせず。
自虐行為を始めてから一か月後には部屋から出ないようになり、そうして朝から晩までベッドの中で天井を見つめるだけの日々を過ごしていた。
ただ、そんな僕でも! どうしても続けていた習慣があったのだ。
「――なんだ、負けてるじゃないか」
大学推奨PCを早々と売って、高校時代のバイト代と合わせて買ったデスクトップPCのモニターには、バスケットボールの試合が映っている。ヘッドフォンからはけたたましい歓声に紛れて外国語の実況、そして炸裂する笛の音が混じる。
アリーナにはホームチームを鼓舞するサウンドがあふれ、ゲームをより高密度なものにし、時折それに合わせて観客がチャンツを送る。
渡米したこともなければ外人の知り合いもいない僕が、このNBAという世界に憑りつかれたのは、大学二年の十一月ごろ、丁度シーズンが始まるころのことだった。
有料視聴サービスが、期間限定で無料トライアルを実施しているというニュースを偶然知った僕は、なんとはなしに手続きを進め、手元のPCとタブレットでNBAのゲームが見られるという環境を手に入れる。
そこからは雪崩式だった。
あれよあれよとチームの熱意にはまり、選手の個性に没入していった。
堕落し自虐していたところで決して観戦はやめない。
NBAは、まさになけなしの活力だった。
自分が贔屓にしているチームとは違うチームが優勝したのを目の当たりにした、夏直前のあの瞬間。金色に輝くトロフィーを掲げ、この世のものとは思えないような賞賛を体いっぱいに浴びるあの瞬間。
そこにいるのが自分の応援するチームであれば! と思わずにはいられなかったのである。
「来年こそは」と、自然に考えていた自分が怖くもあり、気恥ずかしくもあったが、しかし嬉しくもあった。
「死のうとしていたのではなかったのか、バカめ」と思うと、学校にも行かずに冷蔵庫に余っていた缶ビールを昼から煽りながら、どうしようもなく可笑しくなって、笑いが止まらなかった。
NBAとの付き合いは決して長くはなかったが、どうにもイマイチ死に踏み出せない僕を、さらに精一杯生へとすがりつかせているのがこのNBAであるという事実が明らかな以上、NBAに対する執着だけは、何人にも否定しきれないだろう。
そしてもう一つ。
もう一つだけ、生に執着する理由がある。
いや、正確に言えば、これもまたNBAという趣味によって生まれた執着であるので、先ほどのものと同様に括ってしまってもいいといえばいいのだが、そうするには些か特殊なもののような気がするので、分けることにする。
それは少女だった。
少女であり、人付き合いだった。
NBAを見始めるようになった僕は、三年生で深夜の徘徊を始める。国立大学が一つに私立大学が大小四つ程度。人口一万人にあとちょっと届かない程度の僕のこの街にある、寂れたバスターミナル。
酒に酔った勢いで思考力が低下していた当時の僕は、このままでは家に帰ることもままならないと考え、どこかで一休みしようと試みる。
大して酒に詳しくもないくせに勢いで入ったバーを出て真っ先に目についたのは、車の走らない道路の小脇に小さく構えるそれであり、迷うことなく、しかし足取りはおぼつかないままに、バスターミナルのドアを押し開いた。
そして出会う。
一人の少女に。
一人で何をするのではなく、ただぽつんと、一人で、緑のベンチシートの一番端に、座っていたのだ。
キャリーバッグどころか手荷物一つ持たない少女の風体を見れば、彼女が深夜バスに乗ろうとしているのではないことは明らかだったが、しかしまさか深夜に年端もいかない少女を目にして「善行に勤しんでいるのだ」と判断するほど、澄んだ瞳を持っているわけではなかった僕は、その少女が非行に走っている最中なのだと理解する。
一人で。
深夜のバスターミナルで。
なんともけなげなことだ。
そう思いはしたが、しかしみすみす「失礼しました」と退散するわけにもいかず、僕は一声かける。
「君、何しているんだ? こんな時間に。みたところ中学生くらいじゃないか。家に帰りなさい」
「あなたに言われたくないわ。酒に頬を赤くして、まっすぐ歩くこともできないみたいじゃないの。中学生だってまっすぐ歩けるのに」
ぐうの音も出ない、完璧なカウンターだった。
そうして少女を知り、僕は何の気なしに、その翌日も、バスターミナルに足を運ぶことになるのである。
理由なんてなかった。
ただ、生きた人間に――それがたとえ年端もいかない少女であろうが――「お前はダメだ」と頬を張られたような気がして。
無性に、気持ちがよかったのかもしれない。
「――負けたよ。また負けた。参ったなあ。ただでさえけが人多いのに、相手はスパーズだものなあ……」
また彼女の機嫌が悪くなる。
そう。
そうなのだ。
足しげくターミナルに通い詰めて知ったことだったが、彼女と僕は、NBAという趣味において同類であり、また同じチームを応援してもいたのである。
なぜ。
どうして。
どうやって。
そんなことは知らなかった。
何せ僕は、いまだ彼女の名前すら知らないのだ。見た目は中学生だが、本当にそうなのかも知らない。
ましてや彼女がなぜひとりでターミナルにいるのかどうかも知らないというのだから、実は幽霊なんじゃないかという気さえしてくるというものだった。
そんな彼女は、果たして、今夜も来るのだろうか。
勝利者インタビューに嬉々として答える黒人選手の顔を見ているとあまりにも精神に悪い気がしたので(どの口が言う)、即座にウィンドウを閉じ、新規ウィンドウにてブックマークから天気予報を開いた。
今日は冬の季節には珍しいことに陽気漂う夜となるらしく、時間ごとの天気図を見遣ると、夜からはなんと雨が降るとのことだった。
この地域における冬の雨とは、車通勤を行う社会人にとってはほとんど死刑宣告のようなものだが、車どころか社会人ですらなく、学生としての本分すらまっとうできていない僕は、ただひたすら、今夜は傘を二本持っていくことばかりを考えていたのだった。
あいつ、傘すらもってこないからな。
3
「今日はあったかいね」
「春が近いのかもしれない。嫌だわ」
「春が嫌い?」
「うん。でも春のせいじゃないの。彼らは動いているだけだから。私が、止まっているだけだから」
彼女がこういう哲学的な物言いをするのは、今に始まったことではない。
幼い容姿に収められたこれまた幼い双眸には、時折僕には感じることのできない何かが映っているらしいのである。
僕は、そんな彼女の声を聴くのが好きだった。
「そういえば、今日も負けたよね。ニックス」
「見てたのっ?」
「ううんと、最後だけ。うまく起きられなくて」
「私はうまく起きたのに見られなかったわ。でもそうなんだ。やっぱり負けたんだ」
「やっぱりって。ひどい物言いだ」
「だって、ホセもいないんだもの。彼がいないニックスなんて、だめだめ」
「メロもいないしな」
「あれはいいのよ。はしゃいでオールスター出た罰」
「ふふ。やっぱり手厳しいんだ」
ホセという選手を一番評価している少女の意見にすべて同意だ――とは思わないけれど、それでも僕が彼女の意見に異を唱えたことは一度もなかった。
やはり、好きなのだ。
彼女の流れるような言葉を聞くのが、好きなのだ。
それが聞いていられる間は、たとえこのベンチシートが石橋のように固かろうが、あまり問題ではない。
外にある待合所がそのまま見える大きなガラスには、とんとんと雨がぶつかり続けている、そんな夜だった。
「私としては、やっぱりホセの傍らにはティムがいてほしいの」
「ギャロウェイじゃダメ?」
「なんだっけ? なんちゃらトーナメントから成りあがってきただけでしょう? あれこそ、はしゃいでいるだけよ」
「デベロップメント・リーグな。NBAはそんな排他的じゃない」
NBAには下部リーグが存在する。
デベロップメントという名の通り、そこは現状NBAレベルではないが、将来的にそうなれるだけの可能性を持つだろうという選手がプレイするリーグなのだ。
NBAは有料視聴で観戦できる一方、こちらは無料で見れたりする。
もちろん、僕はデベロップメント・リーグまでチェックするようなコアなファンではないのだが、それでも活躍次第でNBAに上がってくる選手も多くいるということを考えれば、チェックしているファンもいて然るべきだろうというものだ。
「でもたとえホセとティムがスタメンで安定していても、ギャロウェイは控えで最も威力のある選手だぞ。ジェイ・アールだっていないんだし」
「ジェイ・アール……」
彼女はつい先日トレードされた、ジェイ・アール・スミスの熱狂的なファンだった。
数々のスキャンダルを持つ選手だが、彼女曰く「そこがいい」のだそうだ。
「そもそも、どうしてイマンとジェイ・アールを出したのかっていう話なの」
「だからそれは何度も話したじゃないか。ジャクソンの意向としては、来シーズンのフリーエージェント市場に――」
いつもこうしてNBAの話ばかりをしているわけではない。
わけではないのだが、しかし一度ジェイ・アールを経てスイッチの入ってしまった彼女はもう止まらない。
結局この日は、いつものように深夜営業に勤しむ自販機でココアを買うということもせず、いつもの時刻がくるまでNBAの話題で話し混んでしまった。
彼女がどうやってNBAを見ているのか。今更気にもならなかったが、話す内容を聞いていれば、大体どのメディアを利用しているのか、おおよそ推測がつく。
それがいけないのかもしれない。
変な推測ができてしまうから、それを手掛かりにもっと多くを推測しはじめる。
見ないようにしていたはずの本質を。
僕らのこの曖昧な世界の本質を、見ようとしはじめているような気がした。
それはいけないことだ。
いけないことだから、せめて、今夜も僕が切り出そう。
一度だけ時計を見る。
時刻なんてもうとっくにわかりきっているのに、それでも見てみる。
三時を少し過ぎたばかり。深夜バスの到着にはまだ時間があるが、それが余裕につながるほど、僕はこの世界を粗末にするつもりはない。
今夜も切り出さねば。
帰ろう、と。
「――もう、帰らなくちゃ」
「……え?」
しかし、今夜ばかりは違った。
世界の終焉は、いつもとは違う形で訪れる。
いやというほど聞き慣れた、澄んだ少女の声が、その言葉を発したのだった。
「もう、帰らなくちゃ」
「そう、か……」
やけに心臓を音がうるさい。
のどのあたりから目じりにかけて、ものすごい勢いで、皮膚の下を血が駆け巡っている。
ひねり出した声はあまりに脆弱で、少女に届いていたのかすらわからない。
膝の上で組んでいた両手に、異常なほど力が入った。
「お父さんが、ね」
「お父さん?」
「うん、お父さん。そのお父さんがね。彼女と別れたから」
「……彼女」
「だから、帰らなくちゃ。もう、帰らなくちゃ、ダメなの」
何も、言えなかった。
互いの名前すら知らない僕らは、しかし互いの趣味は知っていて、それでも互いの事情なんて一切知らなかった。
意図してか無意識か。僕らは聞かず、極力探らず、そうして知ろうとしなかった。
それは致命的なことだと、お互いに察していたからだろう。
僕らの世界には不必要で、そして持ち込めば滅ぶ、破滅的な毒として、理解していたのだろう。
そんな僕らの世界に、しんしんと雨が降る。
繊細で、今にも崩れそうなこの世界に、汚らわしい水が、一滴侵入してきたような、感覚だった。
僕の貸した傘を差して帰る少女の背中を、ひたすらじいっと眺めながら、僕は、泣いていた。
何が悲しくて涙したのかわからない。そして、わかるまい。一生、僕にはわからないのだ。
わかりたくないと望んでいる以上、わからないに決まっているのである。
ただ、僕らの世界に侵入した汚水。そいつが、自身の侵入したひびを、ゆっくりと、確実に押し広げていく様を、見ていることしかできなかったのだった――。
4
雨が続いていた。
長い雨だ。
今夜になって、丁度丸一日振り続けていることになる。
昼ごろには一度途絶えた雨脚は、しかしどうやら明日の早朝まで続くらしかった。
昔から、雨が好きな少年だった。
特に夜のお供に雨の音は最高である。まだ小さかった頃、ことあるごとに夜な夜な窓を開けては雨空を眺めては、そして母に叱られていた。
雨はまだか、雨はまだかと、そんな風に待ち望んでいた少年も今ではすっかり寂れた男にまで成長し、だのにこうして未だ、夜に窓を開けながら、雨の音を聞いていたのだった。
今夜はどうしようか――と考え始めたのは、夕方ごろ。一度やんだ雨がまた本降りになり始めたころだ。
ターミナルへ足を運ぶのが、急に億劫になったのである。
その理由を察するためには、まずこの気怠さを詳細に理解しなければならないと考え始め、はや数時間。
いつの間にか日は暮れ、夜の闇には気味が悪いほどの暖かさが漂ってしまっている。
思えば、こんな風な気持ちになるのは初めてかもしれない。
というのも、彼女と築き上げたあの世界は、必ず僕の傍らにあったと言ってもいいほどの、そんな代物であったはずであり、それはどうやら、彼女にとっても同じらしかったからだ。
もっと平たく言ってしまえば、だ。
「どうして少女に会いに行くのか――」
だなんて、考えたこともなかったのだ。
初めて出会い、二度目もそれとなく会いに行ってしまい、三度目にはもうそれ自体を目的にして、夜な夜な下宿を後にするようになっていた。
単純に誰かと声を交わしたいのか。
このような生活になって、僕は会話によって存在を認識にしてもらうという行為に飢えていたといってもいい。
モニターや天井に向かって放つ独り言が増えてから、ようやく実感しはじめた欲求だった。
だから、少女が僕と会話をしてくれるから――というのは、この僕にとっては、もっともらしいと言えばもっともらしい理由に違いないのである。
だけれど。
だけれど、それは、僕がわざわざ少女に会いに行く理由としては適切でないような感覚がする。不躾に言えば、しっくりこないのだ。
こんな生活のくせにプライドだけは一人前の僕は、それがたとえ苦痛であっても、誰に対してでもなく、他でもない自分自身に向けての体裁を整えるために、かつての友人に電話をすることだってできたのだ。
どころか、食事に誘われることだってある。たいてい断るが。
現時点で留年が確定的である僕には、愚かしくも前ばかりを見ていた当時には見えなかったものが多く見えるのである。それが良いだなんて決して言わないが、あまり良い傾向にはない部類の人付き合いも生まれたし、何より、連絡をたくさんもらうようになった。
「大丈夫?」だの「元気?」だの、その種類は幅広く、しかしワンパターンに、男女問わず連絡が来る。一方的に無視し続けていても未だにしつこく送られてくるというのだから、集団において上下をはっきりさせようとする人間の浅ましい本能というのが手に取るようだ。犬畜生のことをバカにできたものではない。
――しかし、だ。その浅ましい本能に乗っかってしまえば、庇護を受けることだってできるかもしれないだろう。少なくとも、半歩下がって食事についていくことくらい、できるに違いない。
だから、しっくりこないのである。
「寒い。なんだ、やっぱり冬は寒いんじゃないか」
気づけば、家を出ていた。
いつもより少しばかり遅めの外出になる。
ああだこうだ考えつつも、僕にも! 彼女にも! あのターミナルが必要なのだということは一目瞭然なのである。
世間一般的に、受け入れられてはいけない空間である。
世間一般的に、受け入れられてはいけない関係である。
――年端もいかない少女が、学校にもいかずに仕送りを食いつぶすだけの学生と、深夜バスを待つだけのバスターミナルで、目的もなくぶらぶらと話し混んでいる――。
自分でこうして振り返ってみれば、問題だらけ。むしろ問題点しかない。
僕や彼女という存在そのものをひっくるめて、僕らは、存在してはいけない世界なのだ。
だのに、僕はこうして傘を差し、雨だというのに少女のもとへ向かう。
少女も少女で、今夜も間違いなくあの場所にいるのだろう。
そうだ、今日はホセが負傷から復帰するだろうというニュースがあったのだった。
あいつ、きっと喜ぶ。
ジェイ・アールが移籍先のチームで必要戦力として認識されているという、某チームの監督のコメントも、一通り目を通して翻訳して理解済みだ。
あいつ、昨日貸した傘、持ってきているんだろうな。
深夜、明るさが極限まで落ちた片田舎の街で、ぼうっと光るバスターミナル。
そこで、一人の少女が緑のベンチシートに座り、脚をぶらぶらしながら何かを口ずさんでいるのが見えた。
今日もやってきた。
今日も、やってきてしまった。
そしてどちらかが、切り出さねばならないのだ。
「もう帰らなくちゃ」と。
望むべくは、僕の方から、彼女に、世界の終焉を――。
終わり
冬の雨
生きることとはなんと苦痛なのだろうと、思わず口にしてしまった瞬間、私の隣にいたのは母親でした。その時の彼女の心中を察するのは難く、それでもひどく後悔したものです。
誰にも、生きるためには必要だ、というものがいくつかあるんじゃなかろうかと思っていますが、それが自覚的なのかはたまた逆なのかは、私の察するところではないような気がして。だのに私には、このような短編を書くことをしかできないのでした。
二作目となる今回の作品。前作と合わせてごらんになった方々も、今作だけでも読了していただきました方々にも、感謝を述べさせていただきます。何がどうこうだなんて野暮ったいことは言いませんが、このような稚拙極まる物語から何かを感じていただけたなら、望外の喜びでございます。
2015年3月5日
眼蝋