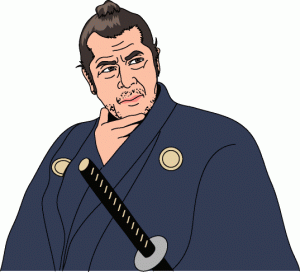財布のかえどき
1
「財布、変えて頂戴よ。いい加減」
季節が逆戻りしたかのような寒波に見舞われたと思えば、今度は季節を先取りしたかのような暖かな陽気が訪れた、そんな晩冬の日。早番を終えてシャワーを浴び、さて午後からどうしようかと、そんな呆けたことを考えていた僕の耳に、聞きなれた女の声が飛んできた。
呆れ。
それに少しばかりの――怒気。
もう八年ほどの付き合いになる同居人の機嫌くらい、声の調子でおおよそわかる。
「財布? まだ使えるよ、これ。ほら」
PCモニターの前に、これみよがしにでんと置いてある黒い椅子に腰かけた後、彼女に向かってさして高級感もない長財布を放ってみる。
「なんでとらないんだ」
「だってアキラ、何も言わないんだもの」
僕の放った財布はあろうことか彼女の足元に着地。大して音がならなかったのが余計に悲しい。
窓から暖かな日差しが入ってくる昼前にこんな気分になるとは。
「言わなくてもわかりそうなもんだ。――それで、どう? まだ使えるだろう」
「外見はね。でも中身が滅茶苦茶だわ」
「中身? そんなにひどいかね」
「ええ、とっても。見れたもんじゃないわ。だってほら――うっ、もういい加減にしてよ」
拾い上げた財布をまじまじと眺めた彼女は、財布を開いた瞬間に眉間にしわを寄せる。
そんなにボロボロだろうか。
それともいけないカードでもはいっていただろうか。
いや、そんなはずはない。キャバクラの類いにはいったことがないし、あの店でも、彼女からもらったピンクのカードはしっかり処分してきたはずだ。
そんな、試合後のジャージの臭いを嗅いだような顔をするようなものは、何もないはずじゃないか。
「ホントにわからないみたいね。嘘みたい。何度も言っているじゃないの」
「その都度忘れているのかも」
「病気ね、間違いなく。まだ若いのに」
開いた財布に彼女が指を入れる。心底嫌そうな顔をして、彼女の穿り出したものは――
「――よせよ、僕のカードだ!」
そう、やはりカードである。
しかしそのカードにはマネーが入っているわけでもなければ何らかのポイントを記憶しているようなものでもない、一枚のトレーディングカードだった。
「こんなカードを財布にいれないでって、私何回も言ったでしょ? ねえ、言ったわよね」
「返せ! そんな風につまんでいいものじゃないぞ」
人差し指と親指の爪で極力触れないようにするかのようにつまむ。
失礼極まりない。
それは汚いティッシュを持つ時の持ち方だ。
「僕の方こそ何度も言った。これには触れるなって。なあ、言ったよな」
「その都度忘れているんだわ。ごめんなさい」
「豚に真珠だ。さあ返せ」
「誰が豚なのよ、誰が」
物の価値はその持ち主が決めるモノであって、外部の人間が決めるものではない。
僕に限れば、財布にしまってあった、縁のはげたこのトレーディングカードは、真珠なんかよりも価値のあるモノなのだ。
彼女の正体が豚だろうとなんだろうと、カードの価値は揺るがない。
価値はわからずとも、それくらいは知っていてほしいものである。
いつかに僕が、ベッドサイドのあの綿菓子の妖怪みたいな人形に向かって「甘くてうまそうだな」と言った途端、君がひっかいてきたのと、全く同じことだというのに――。
2
NBAという言葉の意味するところは、つまりはリーグである。競技はバスケット。世界最高峰だなんて言ってしまうあたりがアメリカ臭いけれど、僕にはそれを肯定も否定もする術がない。なぜなら生まれてから今まで、バスケットのプロというものをこのNBAでしかみたことがないからだ。近年のNBAにおける外国人選手の多さを見れば、世界中に優秀な選手が多いことはすぐにわかるし、なるほど確かにNBAが世界最高峰かと言われればそれは難しい問いなのかもしれなかった。
ただ、知名度で言えば、やはり世界最高峰はNBAなのではないだろうか。そもそもバスケットととのなれ初めはいつだったかと言われれば、それは小学生の時、友人に勧められて少年団の体験入団に参加して、ドハまりしたのがそれであったはずだ。
NBAを始めて見たのは中学一年生のとき。バスケ部でありながら自分の中に手本を持たない、いわゆるただの「バスケ好き」に落ち着いてしまう程度の少年だった僕に、一人の友人が一本のビデオを渡してきた。白いユニフォームをまとった巨人たち。どちらが守備かすらわからないほど、圧倒的に攻撃的で、全ての意味でサイズが違った。
そう。僕が初めて見たNBAチームはデトロイト・ピストンズで、初めて知った選手はベン・ウォレスだったのである。
「――わかるかね。そんな思い出深いベンのカードなんだよ、これは」
「知ってるわよ。何度も聞いたもの」
「ならなぜあんな風に扱ったのか聞きたいな」
「だから、カードの収集は別にいいって、私はそう言っているじゃない。ただ財布に入れて持ち歩くのはやめて頂戴って、それだけよ」
「なぜ」
「『なぜ』? 冗談でしょ。わからないの」
「わからない。ベンになんの非があるのか」
「その黒人には非はないわよ。アキラにあるだけ。財布に入れて持ち歩かれたら、隣を歩く私が恥ずかしいって、それだけよ」
「むう」
わからなくはなかった。
彼女同様、僕だって、まさか本当に、小言の全てを、繰り返し言われるたびに忘れているわけではなかったのだから。
「でも、財布を変える理由にはならないだろう。ベンを抜けば、それでいいんじゃないかね」
「抜くの?」
「抜かない」
「でしょう。だから、一生その財布に入れておけばいいわよ。ただ外出用に、別の財布を持ってさえくれれば」
「二つの財布に入れるほどの金はないな」
「今の財布にはなにもいれなければいいじゃない」
「ベンだけ?」
「ベンだけ」
参った。
というか、それはもう財布ではない。ただのベン入れだ。
彼女はつまり、ベンを抜かないのであれば、今の財布ごとベンを家に置いておけ――と、こう言っているのである。
「仕方ないと言えば、仕方ないか……」
「ええ、素直でいいことだわ」
「なに、仕事終わりで寛容になっているだけさ。明日になればまた入れる」
「ふざけるな、この野郎」
財布から抜いたベンをデスクの上に置いたあたりで、彼女がようやくソファーに腰を下ろした。仕事前にテレビを見てくつろぐ暇があるなら、もっと遅くに準備を始めればいいのに。
「大体ね――」
「――待った。もうベンは抜いたよ。この話はこれで終わりじゃないのか」
「ベンの話はね。そうじゃなくて、それよ」
「それ?」
彼女が指を差したのは、壁にでかでかと貼られたポスターだった。これまたピストンズ時代の名選手、ビラップスである。
「NBAなんか見て、どうするの?」
「どうもしないよ。強いて言えば、興奮するんだ」
「興奮して、どうなるっていうの」
「生きる活力になる」
「はあ?」と一度訝しげな声を漏らし、彼女はゆっくり――本当にゆっくり、僕の方を見つめた。
「――NBAがなきゃ、死ぬの?」
「もちろんだ」と即答するには、少しばかり嫌な空気だった。
おかしい。今までもこのような問答は繰り返したはずだが、一体何が、今日の彼女をここまで本気にさせているのだろうか。
「死には、しないだろうね。でも間違いなく、違う人生にはなっている」
「違う人生? それは何? あなたの人生の展望には、私はいないっていうことなの? ねえ、そういうことかしら」
「……何を言っているんだ。本当に、今日の君は変だ」
「かもね。でも、今更だわ」
「お互いね」とつづけた後、立ち上がってテレビを主電源から落とした彼女は、そのまま玄関へと向かっていった。
生きているのが嫌になるほど、暖かな日だった。
3
高校の時、僕は彼女に出会った。
お互いにバスケットが好きで、彼女はマネージャーという形でバスケットに携わっていたものの、一方の僕は帰宅部を貫いていた。正確には、一度バスケットボール部には入部したのだ。したのだが、やめた。
楽しめればそれでよしという部の空気は、僕にはどうにも合わなかったのだと思う。あの頃はその空気を痛烈に批判したものだったけれど、今にして思う。仲間とバスケットに汗を流し、楽しむ。それの何がいけないのだろう、と。
NBAを知り、バスケットが一層好きになって、その世界に憧れもした。でも現実はそんな世界――少なくとも、夢に描いていた世界――とはあまりにも違って、とても冷ややかで。
僕の高校生活は、何とも噛みごたえのない、清流だったのである。
そんな清流でくすぶっているだけの僕のどこに、果たして何を、見出したのかはわからないけれど、彼女は僕を彼氏にしようと思い立ったらしく。僕も僕で、彼女の申し出を断るだけの理由がなく、どころか、クラスで一番仲のいい女子と言えば彼女しかいない、という程度には、申し出を受け入れる理由があった。
高校を卒業し、彼女は就職、僕は大学へと足を進めた。道は違うもののすぐ近くに住所を置いたということもあり、大学二年のころから同棲を始める。向こうの両親は大反対だったけれど、なんとかなった。いや、実際のところ、なんとかなったのかはわからない。
結婚するのではないのだ。僕だって、そこまで彼女の家の事情に深入りはしていないのである。
「でもアキラって、結構有名な大学出てるのな」
「一応、ですが」
「一応って。国立じゃないか」
「国立がすごいっていう認識も、大分ずれているような気がしますけれど」
「言うじゃないか」
盛大に笑いながら、生ビールを一飲み。そのままテーブルにあった呼び出しボタンへと指を伸ばす。
「そんなんで、なんでウチみたいなとこで働いてるわけ? つうか、なんでそもそもフリーターなんかになってんだよ」
「就活に失敗したんですよ。前にも言ったでしょうが。本当に、ありきたりな理由なんです。良い大学出たって、就職できなきゃクズですよ。そんなものです」
「おまけに、学歴にコンプレックスがあるウチのリーダーみたいな厄介者に、目を付けられるしな」
笑いながら店員に注文を告げ、また笑う。
バイト先で最も気の置ける人間と言えば、間違いなくこの人になるだろう。向こうがどう思っているのかは、わからないのだけれど。
「同棲中のあの彼女は、働いてるんだろ?」
「一応。彼女も彼女でフリーターですけれど」
「そうだったのか」
彼女は一年もたたずに職を離れた。俗に言う、人間関係でのトラブルというヤツだった。
当時未熟でまだ青々しい彼女は、職場で数人の女性社員からいじめにあっていたのである。
まさか高等学校よりも上のステージでそんな幼稚なことが――と思わずにはいられなかったが、彼女が退職したのちに、大学の学生掲示板で『いじめ撲滅』というタイトルの啓発ポスターを目にしたので、なるほど、僕が見ようとしていないだけだったらしい。
身近になって初めて目につくようになる。
自身の好いた女の身に振りかかるまで無縁を貫いていたという自分が、当時は途方もなく情けなくなったものだった。
「アキラ、ウチに就職すれば?」
「嫌ですよ、あんな真っ黒なところ。ウチはグループの中で一番たちが悪いって、ヤマモトさんが言ったんじゃないですか」
「それはほら、人がいないからさ。アキラが入れば、あるいは」
「バイト上がりに、何人分の力を期待しているんですか……」
「あたしみたいなクズが集まる職場には、何か問題があるってな。まあしょうがないんだけども。それでもたまに情けなくなるよ。お前みたいな若いヤツをみるとね」
「ヤマモトさん、二七でしょう。女は物言いから老けていくって、本当なんですね」
「うるせえ。今日だって調理のババアにまたいちゃもん付けられてさあ」
「またですか」
「もう最悪だ。予約のキャンセル二件、あたしが伝えてないから余計に作っちゃったって、もう大騒ぎ」
「連絡を各所に回すのはヤマモトさんの仕事じゃないでしょうに」
「そうなんだよ。あたしが言わなきゃわからねえのかあいつは。クソババア。連絡来てるだろうが。言わなくてもわかれ、バカヤローめ」
ふと、グラスから酒を流し込む作業に、一抹の間が空いた。
ヤマモトさんの言葉のどこかに、今日の彼女を見たのだ。
「――言わなくてもわかりますよね、やっぱり」
「うん? まあ、ものによるけどな」
「今日、彼女に向かって財布を投げたんですけれど。あいつ、受け取らないでそのまま足元に落下するのを見ていたんです。ありえないでしょう」
「ふふ。知った仲の、暗黙の呼吸ってあるからな。ただ、それを期待しすぎると、やっぱり痛い目見ると思うよ」
からからと笑いながら、焼き鳥の串を口に運び、新しく来たビールで追い打ちをかける。
本当に、おいしそうにお酒を飲む女性だ。
「まあ、さっきはあんな風に言ったけども。クソババアだって、ホントに知らなかったかもしれないよな。それに、あたしは調理場でクソババアと何度も顔合せてたわけだし。何とはなしにあの人の手元みてりゃあ、予約のコース料理作ってることくらい、わかりそうなもんなのに」
「はあ。結局、五分五分ですか」
「そうそう。五分五分よ、五分五分。アキラが聞いてくれるから、クソババアって言っちゃうっていう部分はあるな」
「僕のせいですか」
「うむ」
正直ヤマモトさんは人が良すぎるだろうと思う。確かに、ミスをカバーしあうのが集団ではあるけれど、目の前からダンプカーが走ってきていることすら、集団の誰かに注意されなければわからないような人は、少なくとも社会には向いていないだろう。
誰かをカバーできるから、誰かをカバーしていい。少年団のコーチが言っていたことだった。
「けれど――」
「おう」
けれど、それでも考えてしまうのだ。
言わずに嫌われるのなら、念のため言ったうえで嫌われた方が、幾分マシだ、と。
「それは、けれど結局、自己満足でしかないよなあ。責任逃れというか」
「なんだ? 何の話だよ。一人で頭抱えるなよアキラ」
何の肉も貫いていないむき身の串で僕の腕をいじくる。
やめろ、マジで。
痛い汚い。
「言わなくてもわかるって、ずるいですよね」
「ずるいな。本当はそんなわけ、ないのに」
「全くですか」
「全く。全て、な。言わなくてもわかるってのは、要するに、前言ったことを覚えているだろうってことじゃないか。結局以前同じこと言ってるわけだから、正確には『言葉なしで伝わっている』ってわけじゃないよな」
「そんなこともないと思うんですけれどね。だってほら、財布の件。僕、彼女の財布を投げたの、たぶんあれが初めてですよ」
「ホントか?」
「たぶん……」
「うむ。だとしても、財布以外のものを投げ渡したことは、あるんじゃないのか」
「それは、ありますね」
ケータイ、ボールペン、クッション、エトセトラ。思い出そうとすれば思い出そうとするほど、出てくる出てくる。
「大体な、アキラ」
「はい」
「たとえばバイトでウチに入ったばかりのアキラがいるだろ?」
「例えばですね。はい、わかります」
「うん。で、今、バイト初めてもう二年ほどたったアキラがいるわけだ」
ここに、いる。
それはちょっと認めたくなかったが、しょうがない。認めよう。
「先に出てきたアキラと、今出てきたアキラ。この二人は同一人物か?」
「同一人物でしょう。二年経って僕がアキラじゃなく、例えばレインビアあたりになっていたら怖いですよ。色々と」
「外見がレインビアになっていたら怖いよ。でも中身がレインビアのようになっていたとしても、あたしは驚かない自信がある。人って、そういうもんだろ」
そういうもの。
人間という存在を定義するのは難しそうだし、そういう哲学的な部分の話は著名な方に任せるとして。
それでも。確かに。
人間というのは――少なくとも、著名でない僕たちの感じるところによれば――そういうものなのかもしれない。
「第一、レインビアだって、現役時代からは想像もできないような、名指導者っぷりじゃないか。人間なんてどうなるかわからない。いくらか歳を重ねればなおさら、だ。その人間が前話した時の人間と同じかなんて、わかりっこないわけだ。あたしの言いたいこと、わかるか」
「なんとなく、ですけれど。バイトに入ったばかりの僕と、今の僕とが同一人物である確証はないってことですよね」
「ううん、ちょっと違うな」
新しく来た生ビールを半分ほど空にしたあたりで、彼女はタバコに火をつけた。
燻らせながら、それでいて彼女の目線はふらつかず、じっとりと腰を据えているようだった。
「同一人物なわけ、ないんだ。そもそもな」
「絶対変わっているはずだって、こと?」
「うん。あたしはそう思う」
変わらない人間はいない。
良くも悪くも、それこそが人間の本質なのだと言われてしまえば、やっぱり僕にはそれを肯定も否定もする術はないわけで。
言わずにいてもずるいけれど、口にしてみてもまたそれはそれでずるいなあ、なんて。
少しばかり渋い臭いを運ぶ煙を、すこしばかり嫌がりながら、考えてしまった。
「僕も、変わっていっているんですかね」
「そりゃそうだ。こうして話していても、ずいぶん変わったよ。お前があたしと同じようにNBAを見ると知った初めのころは、アキラの口からレインビアの名前なんて出なかった」
「それは、たまたまでしょう。ぱっと浮かんだのがレインビアだったのか、そうでなかったのかの違いです。ただそれだけですから」
「考えなしに誰が浮かぶのかってのも、変化の一つだと思わねえ?」
「ヤマモトさん、それはさすがに」
「ふふっ。阿漕か」
「阿漕です」
仕事終わりの彼女に呼び出されたのが夜の十時ごろだった。ふと、自分の彼女は家で何をしているのだろうと思いはせてみる。
彼女がちょうど仕事を終えて帰ってきたところを入れ替わりで出てきたのだが、僕の説明は彼女に聞こえていたのだろうか。なにせ、応答がなかったのだ。
ただ見様によっては頷いていたようにも見える。
了承したのか、していないけれど無視したのか。
それとも、そんな程度の了承だったのか。
なるほど、口にしなければ、わからない――か。
「ヤマモトさん」
「うん?」
「僕、今日彼女とケンカしたんです。ケンカというか、まあいざこざ。すれ違いって言った方がいいのかな」
「同棲してりゃ、そんなこともある」
「その通りです。だからそのたびに、僕が謝ってきました。そういう時、男が先に折れた方が、楽だっていう考えがあったから」
「間違いじゃない。一緒に居れば、女の方が強くなってくるもんだからなあ。男が持ち上げてやるってのは、重要さ」
「でも、それってずるいですよね」
「ずるいな。クズだ。謝れば許してもらえるってのは、アキラ。まともな男の思考じゃないぞ」
「そう思います」
知っている。
知っていて、諦めていた。
僕に言わせれば、「長年一緒に居ればケンカだってある」という妥協だって、ずるい。
「ヤマモトさん。僕、やっぱりちょっとだけ、変わっていっているのかもしれません」
「お? 自覚、出てきたか」
「昔は、もうちょっと柔軟だったかな、って」
「柔軟? お前、そいつは劣化してるって意味じゃねえか」
「いや、そうでもないのかもしれません」
うん、そうでないのかもしれない。
口に出す、出さない。
言葉にする、しない。
みんな、みいんな、なんて、ずるい生き方なんだろう。
「少なくとも今ほど、彼女の怒っている理由がはっきりわかったことなんて、一度もなかったんですから」
4
熱を帯びてきた――という表現を自粛せずに使える程度には、バスケットへの熱はあるつもりだ。
熱いバスケットボールプレイヤーではない自分に何があるのだろうかと考えれば考えるほど、暗くて狭い落とし穴に落ちたような感覚に襲われる。が、それでも寒くはなかった。
NBAを見て、世界最高峰を見て、選手を知って、スタッツの見方を知って、ネットを介して誰かと趣味を共有することの幸福感を知った。
あの頃の熱さはないけれど、僕は確かにほどほど絶望しながら、それでも未だ、バスケットに熱を上げているのである。
さて、そのことが、僕の同居人には果たして、伝わっていたのだろうか。
僕の人生の主軸はバスケットであり、すなわちNBAなのかもしれない。
しかし、僕という存在そのものがそうかと言われれば、そんなことはない。
ヤマモトさんに深夜呼び出されることもまた僕自身だし、彼女の様子に頭を抱えるのも僕という存在そのもの。主軸はあっても、外見が変遷していっているのだろう。ヤマモトさんは、きっとそういうことが言いたかったのかもしれない。
僕が僕でなかったとして、彼女は今夜、僕を居酒屋に誘ったのだろうか。
「ただいま」
「早かったのね。もっとゆっくりしてくるのかと思った」
ソファーでテレビを見ている彼女の隣には、綿菓子みたいなへんてこな人形が鎮座している。
昔からの、ある種のサインだった。君は気付いているのだろうか。いいや、気付いているまい。
本当に、変わらないのだ。
「それ、何?」
「帰りにコンビニに寄ったんだ。まだまだ飲み足りなかったし、君があそこのシュークリームは最高だって言っていたのを思い出してしまったから。それに――」
「何?」
「ちょっとだけ、話したいこともあったものだから」
最寄りのコンビニで購入した缶ビールは二本とも、すでに温くなってしまっていた。つまみにと買ったきゅうりの浅漬けも、どこかやる気がないようにすらみられる。
「漬物って、ちょっとセンスおかしいわ」
「揚げ物買ってきたら、食べないだろう」
「当たり前」
ぽりぽり。
ぐいっ。
なんだ、やっぱり食べるんじゃないか。
「また、ヤマモトさんでしょ」
「ああ、そう。帰るって言ったらしょげてたよ」
「元気そうで何よりだわ。本当に、あの人はいい人すぎるもの」
「そうなんだよなあ」
僕経由でヤマモトさんと仲を深めた彼女は、つい先月も、二人きりでワインを飲みに出かけて行った。
僕を共通して知っている女性が二人きりで呑んでいるとなると、不穏な気分にしかならないが、まあそれはそれだろう。
「それで? 話って何?」
「何って……しているじゃないか、今。話」
「はあ? 話って、雑談のこと?」
「それ以外何があるんだ。まさか僕がこのタイミングで別れ話を振ると思ったのか」
「まさか。でも重要なことなんだとは思ったわ」
「どうして」
「だってあなた、今お酒入っているんだもの」
嫌なことを言う。
が、もともと彼女はそういう女だった。察しがいいくせにすっきりとモノを言う。さばさばしているようで、勝負事にめっぽう熱くなる。負けず嫌いだけれどさびしがり屋。
そんな彼女に僕は――今の僕は――確かに似合わないのかもしれない。
そんなことを、もうずいぶん前から考えていた。
「高校の時さ。君、僕に告白したろ。『熱いところが好きです』って。顔真っ赤にしながら」
「うるさい」
「いや、冗談めかしているわけじゃないんだ。本当に雑談をしたかったんだけれど、でもメインといえば、この話がメインでもあるんだから」
溜息を吐きながら置かれた彼女のビール缶は、中身の入っていないマヌケな音がした。
「告白なんて初めてだったし、仕方ないじゃない。考えていたように口は動かないんだって、あのとき初めて知ったわ」
「そんなものかな」
「そんなものよ。ただの言葉なのにね。伝えようと思えば、簡単なはずなのに」
「今思えばさ、メールでもよかったわけだろ? なんであんな風に、直接言ってきたのかね」
「メールって」
一度だけ鼻を鳴らす。
彼女のそういう格好いいところは好きだ。
「それは言葉じゃないじゃない。思って、考えて、口に出すから言葉でしょう。恥ずかしいからって文章にしていたら、元も子もないわ」
「それはペンフレンドという存在が一般的だった時代をバカにしているのかな」
「茶化さないのよ。それこそ、伝えられる立場の人間が伝えないんだったら、言葉なんていらないじゃないって話だわ」
「詩的だ。君、たまにそういうところがあるよ」
「現実的なのよ。ただそれを誰も言葉にしないから、いざはっきり言われたときに詩的だなんて感じてしまうのだわ」
そんなこともないだろう、とは思うが、しかしなるほど詩人は現実的、か。
彼らには、僕らとは違う世界が見えているわけではないのだから、きっとそうなのだろう。僕の恋人が、間違えるはずはないのだ。
「でもさ。僕、高校の時帰宅部だったんだよな。君、何か勘違いしているんじゃないのかな。ずうっと聞きたかったことなんだけれど、さ」
「それこそ今更だわ。私はマネージャーよ? そんなこと、知っているわよ」
「だよなあ」
「そう、マネージャー。だから私は、ウチのバスケ部とあなたがもめていたことも、全部知っているんだわ」
「いやまあ、君にも話していたしな」
「全部? 違うでしょう」
「違うけれど」
自分なりの気遣いのつもりだった。
彼女の部活を否定することが、彼女自身の批判につながると思ってしまえばだれでも言葉は出なくなる。
それでも、あの頃の僕には、気心が知れていて、そして事情も分かっている。そんな彼女の存在が、必要だったのである。
「そういうの、熱いなって思ったのよ」
アルコールのせいか、少しだけ上気して赤くなった顔をそむけた彼女は、「それだけっ」と短く放った。
それだけ、なんだそうだ。
本当に、それだけ。
そうわかった途端、途方もなく力の抜ける感覚に襲われる。何を恐れていたのか。大学を出て、就職活動に失敗し、いい年していままでフリーターをやり、結婚の香りすら匂わせてやれない自分に、かつての熱さはもうなく。
彼女と共に生きるには、自分は錆びつきすぎたんだと、恐れていた。
でも、何もかも、実は、そんなに難しくはなかったのかもしれない。
ヤマモトさんと話して感じた確かなもの。彼女が憤っていた理由。いや、彼女が寂しがっていた、理由。
そんなことだったのか。
全く、僕も僕だが君も君だ。
「僕はもうバスケもしていないから、そういう意味では熱くはないかな」
「でしょうね」
「でもさ、知ってる? 僕、NBA見るのが途方もなく好きなんだ」
「知っているわ」
「いいや、知らないな。僕がどれだけ好きなのかって、君は知らないんだ。だって言ってないんだもの。全部全部、伝えていないんだから」
「どうして、言わなかったの」
「嫌いだって思ったんだ。かつての熱意を追い回すようにモニターにかじりついている姿なんて、君は嫌いだろうって思ったんだ」
自分の人生に対する自信の無さも、きっとあっただろう。
わかっているつもりだった。
言われなくても、わかっているつもりだった。
「でも、私はそんなこと言っていないわ」
「そうだね、言ってない。だって僕が聞いていないものな」
少しだけ。
いつでも触れられるはずの彼女の手に触れるのが、少しだけ、緊張した。
「ねえ。僕は、ことにバスケットに関しては熱いんだよ」
「知っているわ」
「知っていないよ。だって、言ってないもの」
テレビからは何が流れていただろうか。
僕の缶ビールはまだ残っていただろうか。
明日の仕事は何時からだったろうか。
何もかもがわからない。
わからなくとも大丈夫。
そんな気のする、柔らかくて暖かな、感触がした。
「ごめんな。全部全部、教えるから」
終わり
財布のかえどき
読了感謝でございます。やってみればこれほど楽しいこともなく、また時間もそこまでかからないということで、継続できればいいなあと思っておりますので、次回の短編も読んでいただけるならば、望外の喜びでございます。