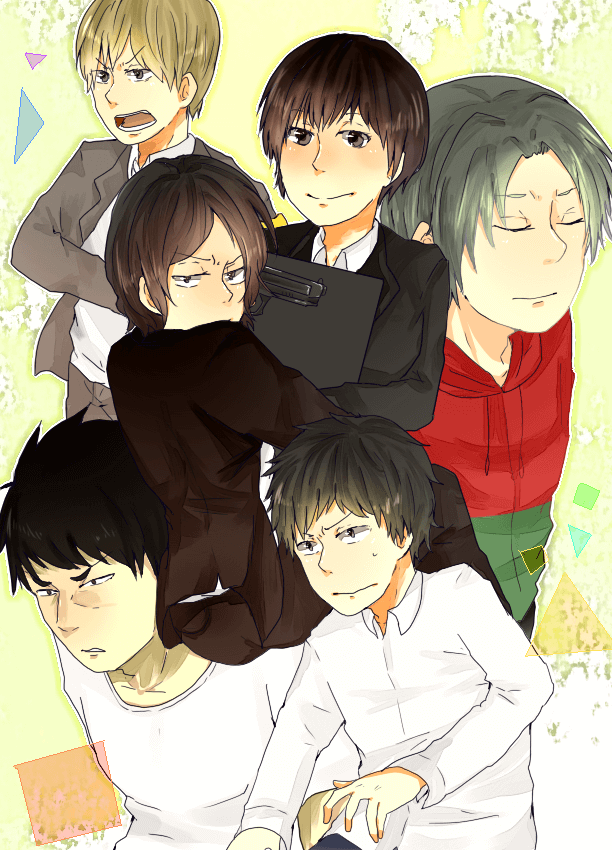
piscium capsa(後編)
神は残虐である。 人間の存在そのものが残虐である。
そして、人類が如何に残虐を愛したか。
-江戸川乱歩より-
〇
私たちは真実を見極めるすべを知らない。
真実が真実として認めるのは、それは一つの断片にしか過ぎない。
即ち理性である。
しかし、その理性こそが、人の本能を加速させ、いつしか。
いつしか、だれも気付いてくれないような姿に成れ果てて、朽ち果てて、
歪んだ偽物の世界は今日も真実として回り続ける。
一
「うぁーぁああ…やっちまったぁぁん…」
九重里留、元ニート、いや、元医者からの元ニートからの医者に復帰した九重里留は北東接骨院、に来ていた。
痛そうに首を右手で押さえている里留は、今となっては見慣れた白衣ではなくかつての白Yシャツを着て、コートを手に診療室から出てきた。
「デスクで寝るんじゃなかったわ…あーもーイダダダダダダダダダ」
うっかり首を逆方向に向けると電撃のようなものが走る。
せっかく明日から休暇に入るというのに思わぬアクシデントに里留の顔は疲れきっていた。
といっても自業自得なのだが。
フラフラと受け付けに行くと通路で見覚えのある人物を見つけた。
「あれっ、先輩!どうしたんですか?」
「ヴォーーーーーーーサンジローーーー」
相変わらずの大きさで、首が痛い今見上げることができない里留はあいている方の手をヒラヒラとふった。
北東三次郎。
心なしか二年前よりも身長が伸びてる気がした。
「なに?手伝い?」
「あ、はい。大学休みなんで、雑用ですけど」
三次郎は手に持っていたダンボールを床にドシンと置くと、首にかけていたタオルで汗を拭いた。
この真冬に相変わらず三次郎は半袖であった。
そんな場合ではない里留は、早々にその場を立ち去ろうとしたが、その瞬間、もうひとつの衝撃に思わずうめき声をあげた。
「?先輩どうかしましたか?」
「とっ……どこっ……!?」
「とっとこ?ハム太郎ですか?」
里留は「ちがう!」といった具合に手を振って自身の腹を押さえた。
「と…トイレどこっ……」
12月15日
ちょうど二年前もこれくらいの時期にあの事件が転がり込んだのを思い出す。。
あれからの毎日は真っ白い部屋にでも立たされ続けているような気分であった。
なにもない、朧気な毎日であった。
そして、二年の月日が経った。
「あっ!三好さぁーん!そっち!そっちです!そっちいきましアブッ」
夕暮れの光を浴びる冬の校舎には似合わない姿の二人が校庭に見えた。
渡り廊下に差し掛かったときに盛大にずっこけた日輪香は、痛そうにその額を擦った。
その様子を一人の男、三好咲良はタバコを吹かしながらぼんやりと見詰めていた。
「もぉー三好さんなんで捕まえてくれないんですか~…」
「俺はこんなペット探しの依頼なんて了承した覚えはない。勝手に引き受けたお前がやれ」
香が追いかけていた猫はヒュルリと香の横をすり抜けて三好の足元に寄ってきた。
やっと大人しくしている猫を香は抱き上げるとクリクリとしたその瞳と目があった。
「まったく…猫が二匹いるみたいですよ」
「なんだ」
「イエッなにもっ!」
焦った笑みを浮かべると香は猫をかごのなかにしまった。
「ヒマワリちゃんっていうんですってこの子ー可愛いなぁー」
「……そうか」
複雑な気持ちを割るように、電話の音が三好のポケットから鳴り響いた。
12月15日。
二年前の始まりと同じ日だった。
二
それはその日の日も落ちた頃のこと。
日中はいつもと同じように営んでいた北東接骨院の前には騒がしく光るパトカーの灯りと救急車が並んでいた。
黄色いテープを乗り越え、三好は香と共に三次郎たちがいるロビーへと歩いていった。
三好らがこの現場に来るに到るまでの経緯を語るには、また少し時間を遡ることになる。
その時、三次郎は里留に言われたトイレを案内しようとしていたところであった。
「先輩大丈夫ですか」
「夜勤明けで腹もユルッユルだわ寝違えるわもうやだ…マジヤミ…」
三次郎に言われて無事トイレに着くと里留は弱々しくヨタヨタとトイレの個室へと入っていった。
と、そこまではいいのだ。
問題はその後だった。
快適に用をたしてる里留の個室の隣に、何かがいるのだ。
いる、というか、異臭がするというか。
汚物という意味合いではなくてだ。
「……なんか…血液くさいんですが…これは…」
慌てて自分の便器の中を見るが、もちろん血便など出ていない。
と、なると、確実に隣から臭っているのだ。
ふと、下を見ると、案の定隣の部屋から漏れた赤い液体が里留の左の足元辺りに達していた。
「…あー、ハイハイハイ…これはーあれですね、ただの生理ですねー…ってここ男子便所っっ!!!!!!イダッ」
個室で下手くそな1人ノリツッコミをすると里留は自分の用も済ませ、個室の外に出た。
ノックをしてみるが返事はない。
ごくりと生唾を飲み込み、恐る恐るその個室の扉に手をかけた。
里留の悲鳴が聞こえたのはその後すぐのことであった。
「…で、その本人はどうしたんだ」
三次郎の話を聞いていた三好はメモを取りつつその見つけた本人について尋ねた。
が、まもなくその本人は疲れた表情を浮かべながら三人の前に姿を現した。
「もー最悪…じゃん?」
「あっ、先輩!もう大丈夫なんですか?」
すっかりげっそりとしている里留は右腕で自身の反対の腕を掴みながらよたよたとこちらに向かって歩いてきた。
そして三好の顔を見つけるとさらに声を荒げて「最悪!!」と叫んだ。
「先輩、気分というか事情聴取もう大丈夫なんですか?」
「え、いや大丈夫っつーかいや大丈夫なんだけど気分はもう最悪なんですけどなんでこいつ呼んだの?なんで三好なの?頼れる人ならもっといるでしょ?なんで三好なの?せめてもの東の名探偵じゃだめだったの?あーはん?」
三好はむっとして冷ややかな目を向けたが、香は興味津々にその様子を見ていた。
「この方三好さんの知り合いなんですか?」
「…まぁ」
里留が騒がしくしていると、その奥からまたもう1人。
見覚えのある人物がこちらにやって来るのが見えた。
「九重さぁーん…もう一度お伺いしてもよろしいですかねぇ…?」
「げぇ!まただよ!もう何回も言ってんだろぉ!デジャヴもいいとこだよ!ヤメテ!」
捜査一課と書かれた腕章に白い手袋、相変わらずの気難しそうな険しい顔をしてやって来たその人物はあの槻上であった。
またしっきりなしに第一発見者の里留を疑っているようで、三好に気が付くと、またさらに目を細めてこちらに強い視線をとばしてきた。
「探偵~まーたお前らかよ…いい加減にしろ!なんだこれは!」
「いい加減にしろと言われても俺はこいつらに呼び出されただけなんだが」
槻上はチラリと里留と三次郎を一瞥すると、なにやら腑に落ちないといったようにため息をついた。
「ほんとな…こーゆー変なオカルト事件は勘弁してくれよ…捜査のしようがねぇんだよ」
「それはお前ら警察が能無しだからだろ」
「んだとおい」
二人の会話を聞いてまたあの現場の光景を思い出したのか、里留は気分が悪そうに手を口にあてた。
どうやら状況を理解してないのは三好と香だけのようで、里留の反応を見て槻上と三次郎は険しい顔をしながらも目を伏せた。
「…ちょっとこっちこい…」
槻上に連れられ入った部屋は監視カメラを管理している所であった。
中には志貴もおり、三好を見つけると嬉しそうに眉を八の字にした。
さて、本題。
槻上が何やら部下に命令をしてるとまもなく巻き戻された監視カメラの映像が流れ始めた。
三好も香もじっとそれを見つめる。
「…?おい、なんだ今の」
その映像のほんの一瞬間に移った白い物影。
三好はそれを見逃さなかった。
すると今度は槻上がその映像を巻き戻し、その物影の映る一瞬にあわせて画面を停止した。
「おそらく…というか、こいつが犯人だ…いや、"人"ではないか…」
そこに映っていたのは、にゅるりとドアの隙間から出入りをしている体長150cmくらいの、口と二本の足のみの白い生き物であった。
「ヒッ…!な、なななななななんですかコレッ!?」
香の反応の通り、そう思うのが普通の容姿だ。
大きな口に餅のような白い体をしているその生き物はこの世の生き物とは到底思えなかった。
白い生物が映ったのはその一瞬のみで、瞬く間に画面からその姿を消してしまった。
どう考えてもこれは人間ではない。
ふと、その時に三好の頭にはあの二年前の出来事が頭中をよぎった。
「亡くなった人物は大きな口で腹部を食い千切られたような形跡があった、しかも一口でだ。…信じたくないが、犯人はこの化け物だろう」
「だから俺は無罪だっていったじゃないですかーンモーー」
この奇妙な感じは間違いない。
あの時と一緒だ。
しかし、奴が生きているはずがない。
あの日、間違いなく奴はその召喚とやらに失敗し、瀕死状態のアイツを、俺自身が、確かにこの手で脳を撃ち抜いたのだ。
その感覚は恐ろしく目が眩むほど覚えている。
「……」
三
「あのサイトが…?」
槻上の元を離れ、院の外で三次郎は一枚の紙切れを三好に手渡した。
紙にはとあるサイトのURLが綴られていた。
香と里留も一緒になってその紙を覗くが、当然心当たりや見覚えなどはなかった。
「はい。…実は気になって二年前に繋がることがないか調べてたんですよ…、そしたら、なんか前みたいなサイトがあるみたいで…でも、以前のサイトはあの時のまま止まってたんです」
早々に三好はそのページを開くと前と同じような黒背景で赤文字のサイトが現れた。
「たしかに似てるな…」
ただ、以前のサイトと違うのは気味の悪いマスコットキャラクターや説明文が、どうにも悪趣味に構成されていた。
コンテンツをクリックしていくと前と同じように外国語で綴られた文章のページを見つけた。
「…前のサイトは風見さんがやっていたのか分かりませんけど…、これがあるってことはもしかしたら風見さんは誰かに利用されてたんじゃないかって思ったんです」
「利用…」
今となっては、真相は全く分からないが、たしかにあの風見が1人でこんな芸当を出来るとは思えない。
世間への憎しみと、精神的ダメージが積み重なり壊れていった風見に甘い言葉を吹き込んで糸を引いていた人物がいた可能性は十分にある。
もしかしたら、これを調べれば二年前の真相が分かるのではないか。
「あ、あのぉ…」
香が申し訳なさそうに手をあげる。
むさくるしい男三人に注目され、なんとも言えなさそうにはにかんだ。
「あ、あの、みなさんはその…この事件について何か知ってるんですか?」
この中で香だけは置いてきぼりの状態であった。
真顔で黙っている三好と、言っていいものかと様子を伺う三次郎に香は少し戸惑いながら苦笑いをした。
「…まっ、その子の言う通り、知らない人は知らない、まぁどーーでもいいことなんだもんなぁ~、まぁさ、そこのロン毛さんは精々ガンバッテナー」
「えっ、先輩どこ行くんですか」
「えっ、だ、だって俺関係ないし…つか、こんなことしてる場合じゃねーの!今の俺はたとえ寝違えても絶好調なんだからよぉ~~!アイタッ」
それだけを述べ、里留はその場からさっさと姿を消してしまった。
ポカンとする三次郎と香に、黙ったままの三好だけが取り残された。
「二年前の真相、か…」
三好は鋭い目付きでその紙を見詰めていた。
四
真冬の7時ともなると道はすっかり暗くなっていて、12月らしいきらびやかなイルミネーションが街中を飾っていた。
その通りを走る里留の姿は、きらびやかな雰囲気にはいささか似合わない格好であった。
そうしてたどり着いた頃には、里留の息はすっかり切れていた。
目の前に立つ女性は驚いたように肩で呼吸をする里留を見詰めた。
「どうしたのさっくん…?」
「ご、ごめっ……おっほ……ちょっとあれがアレでふっへ…ふへ」
「ごめん、ちょっとなにいってるかわかんないんだけど」
とりあえず、と言って里留は目の前の扉を開けた。
途端、美味しそうな匂いがぷんと匂う。
「ハァ…えと、今日は、ほら、おごり、俺の奢りだから!さ、さ、たのんじゃってよハハッ」
「ファミレスなんだけど……まぁありがたく…」
デートとは言いがたいが、形はどうであれ桃子と食事をできることに里留は大層ご機嫌であった。
デレデレしている里留に呆れながら、桃子はメニューを眺めていた。
まぁよくよく考えてみれば里留がこうして無事医者に復帰し、仕事を再開するようになって初めての年末でもあるのだ。
多少は目を瞑って素直に喜んでもいいのかもしれない。
「で、どーなの、最近仕事は」
「んー?そりゃもーぜっこぜっこぜっこーちょーだよぉん、夜勤でラリる程度には」
「そうねー、湊先生が里留くん勤務中寝るほど疲れてるって言ってたものねー」
「んー?あれぇ?なんでばれてるのぉ?あれぇ?」
運ばれてきたグラタンを口に、桃子はすました顔で里留を見つめてきた。
それにあわせ、とぼけたように里留は口を尖らせて視線を外に向けた。
「もー…少しはあんたも湊先生見習いなさいよ…さっくんより歳上なのにさっくんよりずっと元気あるよ?」
「イケメンは死…」
「まず仕事してから言いなさいそれは」
おもしろくなさそうにハンバーグを頬張る里留。
桃子はふと、湊先生とやらを思い出したのかフフッと小さく笑った。
「でもまぁ湊先生かっこいいもんね~福山雅治似」
「どこがだよ!おっさんだろ!おっさん!ハーイケメン憎し!」
正直どこも勝てる要素がない里留はただひがみを言う他なかった。
やけくそと言わんばかりにさらに肉汁の滴るハンバーグを口一杯に頬張る。
「てか、今日なんであんな走ってきたの?さっくん仕事終わったのもうとっくの前じゃない?」
あー…と膨らんだ頬を飲み込んで戻すと、言い方を探しながらフォークでくるくると円を描いていた。
そしてしばらくの間を置くと、少々目を伏せながら口を開いた。
「いや…あのねぇ、大したことではないんだよ?いやホントに……」
「はぁ!?大したことないわけないでしょ…」
先ほどまでのことをさらりと話すと桃子は目を見開いて里留に強く言葉を吐いた。
桃子が驚くのも当然である。
誤解だと言わんばかりに里留今度はそのフォークを横に振った。
「あ、あのね?北東接骨院に行っただけなのよ俺はね、そもそも!そこでたまたま死体見つけちゃってさぁーえらいこっちゃーちょっと第一発見者のyouカムヒヤァーって変に疑われただけでね?ね?またあの三好のクソッタレが扱うような事件なだけだよ、ハーめんどくさかった、ほんとめんどくさかった!」
ズラズラと長い台詞をいい終えると里留は置いていたコップの水をグイッと一気に呑み込んだ。
桃子はしばらくポカンとしていたが、ふと、ある違和感に気づいたようで眉間にシワを寄せた。
「…つまり…最終的に三好さんたちほっぽってきたってわけ…?」
「まぁそうだね」
ケロリと言う里留は、桃子がうつむいているのを見て少し首を傾げた。
が、次の瞬間残っていた里留のハンバーグにザクリとフォークが突き刺さった。
一瞬の出来事過ぎて理解できない里留は恐る恐る桃子の顔に視線を向けた。
その時合った視線は、まるで養豚場の豚を見るかのような冷たい目であった。
「さっくんがそんなに薄情だとは思わなかったわ…」
「へっ…?え、い、いやだって三好のしごと…」
「友達なら手伝うくらいの良心見せなさいよこのドアホ!!!!!」
「エエエエ友達だと思ったことないんだけど!?」
望んでない展開に思わず里留は情けない叫び声をあげてしまった。
せっかくのデートのはずが、まさかたったひとつの話題で修羅場と化するとは思ってもいなかったし望んでなどもちろんなかった。
「いや、桃子ちょっと待って、今来たばっかだし、ね?帰るには」
「あれ、里留くんと桃子くんじゃないか、奇遇だね」
「だから望んでないてんかぁあああい!!!」
不運にも、里留達の後ろの席からひょっこりと顔を出したのは先程話題に出た湊と言う東方病院の医師であった。
まさかの偶然に桃子も少し驚いていたが、ふと思い付いたように桃子はにんまりと笑顔を里留に向けた。
「あら先生、丁度よかった、今席が一人分空いちゃうんですよー、湊先生ご一緒にどうですか?私湊先生と音楽の話ずっとしたかったんです」
「ファ!?」
「え、でも里留くんと食べてたんじゃ…?」
焦る里留の横で湊は爽やかな笑みを浮かべながら困ったように頬をかいていた。
「いえ?里留くんはちょっと用事ができちゃったみたいで、ね?」
「…ウィッス…」
反論しようにも、もはやそこに里留の居場所はなかった。
「…で、」
そして場所は変わって。
目の前には足をくんで気だるそうに座る三好と、その両サイドのソファーに礼儀正しく腰を下ろしている三次郎と香の姿があった。
そしてそれよりもさらに下、その床には、まるで切腹でもするかのように正座をしてうつむいている里留がただ静かにピクリとも動かずにいた。
三好は黙っているばかりで、香と三次郎はどうすればよいのかと顔を見合わせた。
「チョーテツダウ」
「帰れ」
「帰ったら桃子にももう人として見てもらえねぇんだよ!!クソガ!察しろ!」
一心不乱に床を叩く里留を三好は興味なさそうにフンと受け流していた。
沈黙。
香はポカンとその様子を見ており、また表情の変化が全くわからない三次郎が果たしてこの状況に同じくポカンとしているのか怒っているのか分からなくひとり慌てふためいていた。
「あ…えと…じゃ、じゃあ!お会いするの初めてですし、自己紹介しますね!えー今年から三好さんの助手、っていうかバイトをさせていただいてます、日輪香です!香って書いて"かおり"じゃなくて、"こう"です!」
右手を元気よく挙げ名刺を二人に渡す香は、この曖昧な空気を変えようとまるで少年のように張りのある声をあげた。
三好は相変わらずどうでも良さそうに資料を読みながらそっぽを向いていたが、三次郎はそれに対して丁寧に自己紹介を返した。
「ははっ…香ちゃんっていうのかー…いいねぇー元気がいい…すごくいい…よくこの湿気男の助手になろうと思ったね…ハハッ」
未だに桃子のことを引きずっているのか、里留の背後にはどんよりとした火の玉が見えたような気がした。
ここぞとばかりに嫌みを言う里留など気に留めず、三好は繁々と事件についての資料を眺めていた。
「えぇーっ…とぉ…あ、そ、それじゃあ!まず、事件の内容を把握しなきゃですよね…!三好さん!」
「…お前ら全員帰れ」
「ハイ!…ってはぇっ!?」
三好からようやく出た言葉はただその一言であった。
当然香は驚いて身をのりだし、三次郎も目を見開いた。
唯一嬉しそうにしている里留だが、あの桃子の恐ろしい顔を思い出したのか、すぐに表情は曖昧なものへと戻っていった。
「あの、三好さん、…お気持ちは察しますけど…けどもし僕らのこと気にしてるならそんなこと思わないでください。…1人でできることでもないですよ…」
「そんなんじゃない。…そもそも、今回は誰の依頼でもない、俺が勝手に始めようとしているだけだ。金にもならないことに首突っ込むんじゃねぇ…そこのニートもさっさと帰れ」
「いーまーはー医者ですぅーーバーカバーカ」
三好は軽く興味なさそうに里留を見るとそのまま奥の部屋へと入っていってしまった。
取り残された三人。
香と三次郎は多少困惑しながらその部屋のドアを見詰めた。
シン、と静まり返った部屋で、三人はしばらく黙り込んでしまった。
もっとも、気まずそうにしているのは二人だけで、里留は気にすることもなく気楽そうに口笛なんかを吹いているが。
「あの…」
香はどうすればよいのか、うつむきながらも上目使いでその様子をうかがっていた。
そして、何か決断したのか、今度はしっかりとした目で里留と三次郎に向き合った。
「お願いします」
「言われなくても手伝いますよ、ねぇ、先輩」
「えっ、アッハイ」
困ったように笑う香はペコリと二人に頭を下げた。
心配そうに視線をドアに向けるが、三好が出てくる気配はなかった。
五
「ったく…まぁーたお前かよ」
鬱陶しそうにこちら側を見ながら、いつものように不機嫌な表情を浮かべて歩いてくる男。
さながらイタチのような髪色は、遠くからでも奴が来たとよくわかった。
無機質に立ち構えていた三好は、ポケットに手をを入れたまま、槻上の方へと数歩、歩み寄った。
「昨日の事件のこと、怪物の詳しい大きさと前例がないか教えろ」
「だぁかぁらぁ、なんでテメーに教えなきゃなんねーんだよ!帰れ!」
ギチギチと歯を食い縛りながら威嚇する槻上と顔を目の前で見合わせる三好は、その槻上の顔の前にスッとお菓子の箱を差し出した。
「またトッポかよ………、チッ、なんだ、怪物の大きさと前例?」
三好の手から奪い取り、それをジャケットの中に隠すと槻上は真顔で三好に尋ねた。
三好は突っ込んでいた手をポケットから出し、ペンと手帳を取り出した。
「…あー、怪物の大きさは推定約150cm、かなり小さい大人か中学生くらいの大きさだ…つっても、まぁもう半分以上は足だけどな、それ」
前例は全くもってないらしく、槻上は相変わらず面白くなさそうに顔をしかめた。
「ったく…ふざけたことしやがって…どんなイタズラかは知らねぇがぜってー取っ捕まえてやる」
手帳を閉じた三好は、その無機質な表情でぼんやりと槻上を見詰めた。
「本当にいたずらだと思っているのか」
癇に障ったのか、少し槻上にきつく睨まれた。
「…当たり前だ、どんな奴だろうと捕まえてやる」
覚めたように見つめる三好に、眉間にしわを寄せ睨み付ける槻上は威嚇するかのように顔を近づけた。
「なんだ、今日のお前どうかしてるぞ」
心配をしているというよりは、不思議そうにそのしかめっ面をこちらに向けていた。
虚ろな目で、三好はしばらく宙を見つめて考えていた。
そういえば警察はあの時の結局のところを知らないのだな。
奴の遺体はサラサラと砂になって消えてしまった。
そこにいた自分を含めた三人しか知らない。
「…どうかしてない時だなんてあったか」
別段、早足ではないが、三好はそのまま淡々と自動ドアに向かって歩いていった。
「オイ」
目を細めて、槻上はひとつ叫んだ。
手帳をポケットにしまうと、三好は一度だけ槻上を見て、くるりと背を向けた。
「オイこれトッポじゃなくてトッポギだぞオイ!オイコラ探偵!」
署を出て三好は再びあの手帳を開いた。
前例はない。
いいや、二年前と同じものだというのは確実だ。……
白い魔物、とかいう奴が実際どの程度のものなのかはわからないが、今は分かるところをとにかくしらみつぶしに当たっていく他はない。
「…みーよしさんっ」
突然遠くから聞こえた聞き覚えのある声に振り向くと、黒いバックを肩に下げ、植木の陰から顔を出している香がこちらに向かって手を振っていた。
黙ってそのまま立ち去ろうとする三好を香は慌てて追いかけた。
「ちょっと無視しないでくださいよ!」
「だれがお前のこと呼んだ。帰れ、大学生は家で勉強してろ」
「そんなことよりすごいことわかったんですって!この間北東さんが教えてくれたサイトのことなんですけど…」
尚も足を止めない三好に一生懸命ついてゆきながら香はいつもの黒いバインダーを取り出して三好の前に突き出した。
「どーもこのサイト、ラテン語で書かれてるらしいんですよ、で、里留さんが調べてくれたんです、知り合いに聞いて」
三好は諦めたのか、顔をしかめてため息をつくと、そのバインダーを手に取った。
半ば仕方なさそうに目を向けていたが、段々に目を見開いてその文を読み始めた。
「…オイ、これ本当なのか」
次の瞬間、警察署から銃声が鳴り響いた。
六
「これラテン語だよな?多分」
それは昨日の夜の話。
今後どう捜査していくかを三人で話し合ってる際、里留がサイトの文を見て言ったことだ。
どうりで読めないわけか、と香は手にしていた英和辞典をそっと閉じた。
「…で、なんて書いてあるんですか?」
「ファ?読めないけど?」
一気にズッコケたその空気を気にとめることもなく里留はキョトンとしている。
「だ、だれか読める人はいないんですか…?知り合いとか…」
そうそうラテン語をマスターしている人なんて身近にいるわけがない。
ましてや知り合いでもない人物にこんなものを頼めるわけはないのだから。
「あ」
ふと、なにか思い出したのか、里留は軽く短い声をあげた。
が、その顔はたちまち臭いものでも見るかのような表情になり、見るからに嫌そうな顔つきをした。
「……ひとり、いたわ……」
「…で、ラテン語がとても、トテモタッシャナミナトセンセーニオタノミモウシアゲタインデスゥ、ウッ」
「は、はぁ…」
しばらくして、湊に電話をかけている里留は嫌々ながらも、ものすごい形相で受話器を握っていた。
そんな里留に反して、湊は快く引き受けてくれ、明日の朝に来てもらえば教えられるだろうと言ってくれた。
「それにしても、里留君非番の時まで忙しそうだけど大丈夫かい、ラテン語の解読だなんて」
「ハハッ、かわいい子に頼まれちゃったもんでーヘヘ…」
モテるねぇと湊は茶化すように笑ったが当然里留は面白くなさそうな顔を浮かべている。
サイトのページを印刷したコピー用紙をファックスで送ると、不本意ながらも貸しを作ってしまった里留は歯を食い縛りながらも礼を言ってその受話器を置いた。
と、思いきやもう一度受話器を手に取り、番号を押し始めた。
「あ、もしもし桃子?湊のおっさんの弱点知ってないかな?」
「有名医学部出身で料理とボクシングが趣味の湊先生のことかしら?」
「アッ、ハイッ、ありがとうございました」
七
銃声が署内から辺りへと鳴り響いた。
里留が今日もらってきた訳文は、三好の手に握られている。
まずい。三好は再び署へ走り出した。
案の定、思った通り中ではもうすでに撃ち合が始まっていた。
それが人同士ならまだどれだけよかったことか。
三好は慌てて走りながら入り口においてある消火器をつかむと、思い切りその対峙する敵に向かい投げつけた。
銃を構えていた槻上は、三好にかがつくとハッとして彼の方に振り返った。
「オイ探偵!これは一体どういうことだ!」
消火器を投げつけられた白い生き物、は、しばらく床で痛そうにもだもだしている。
その間に三好は槻上のもとに駆け寄った。
「知るわけないだろ…、ただ、これがここに出るってのは、決まってたことみたいだな…」
三好がジッと白い生き物を凝視すると、奴はムクリと起き上がってその大きな口を歪ませた。
朝、里留はその訳をもらったとき、当然その文章を見て驚いた。
湊自身もそれを気味悪そうにしていたが、何よりことを知っている里留はすぐさまそこを飛び出さずにはいられなかった。
『再び世界を滅ぼすための魔術を行う。来る23日、あのイケニエを力とし世界を滅亡させる呪文をとなえる』
そして何より、それらを実行するまでの内容が、こちらに宣戦布告するかのごとく、堂々と書いてあるのだ。
『そのため、前回使用した五つの魔方陣を利用する。そこから使い魔にエネルギーを吸収させよう』
嫌な予感だけはハッキリとしていた。
そして因果なことに、そのことは、今目の前で起こってしまった。
槻上は銃を構えているが、入っていたのはあの一発だったようで、ジリジリと生き物と向き合うばかりであった。
当然、三好も規制されているただの護身の空気銃を普段から持ち歩くわけもなく、ましてや仮に持っていたとしても警察署内で撃てるわけはない。
おそらく、今だれかしらが応援を呼びにいっているだろうが、まさかこの生き物相手に丸裸で来るわけはない。
装備することも考えて少しは時間がかかるとみる。
ジリジリと生き物と向かい合う三好と槻上。
正直に言ってこちらが不利なのは明白だ。
どう考えても、勝てるはずがない。
「やめとけ、今逃げた方が身のためだ」
「……」
槻上は視線を生き物から外すことくジッと黙っていた。
三好は呆れたように槻上を睨んだ。
「オイ」
「じゃーお前だけ逃げろ、腐っても一般市民だしなァ」
槻上はガチャリと銃をわざとならして威嚇した。
生き物は、ビクリと一瞬体を震わせると、警戒したようで強く地面を踏みしめた。
三好がハッとしたその瞬間。
白いバケモノは凄まじい速さでこちらに襲いかかってきたのだ。
避ける間など一片たりともなく、三好はただ目を見開いた。
だがしかし、その目の前でもうひとつの驚くべき光景を三好は目の当たりにした。
それは瞬きする間もないくらいの速さで、槻上は隣にあった観葉植物の苗木の幹をおもいきり掴むと、その植木を鉢ごと生き物の脳天に叩きつけたのだ。
獣のような叫びと共にぶつけられたその植木は、パラパラと鉢が割れ、白い生き物はフラフラとよろめくと、気絶したのか床にはバタリと倒れこんでしまった。
「オイ!なにしてる!捕獲班はやくしろ!」
が、まもなくその魔物であろう生き物は、ドロドロと消えてしまい、辺りにはバラバラになった植木鉢と土ばかりが飛び散っていた。
八
一方その頃。
里留たちはというと、あの文を見てから急いで以前魔方陣のあった所へ向かった。
…のだが
「あ、スイマセン、オムライスひとつ追加で」
なぜか二人は例のごとくファミレスで優雅に食事をしていた。
まぁもっとも、気楽にしているのは里留くらいなのだが。
「…先輩、大丈夫なんですか、こんなことしてて…」
相変わらず無表情ながらも礼儀正しい北東三次郎は、ポテトの皿が置かれた机の目の前で拳を膝の上においてぴっちりと座っていた。
モグモグとポテトを食べている里留は呑気にも手をヒラヒラと振って笑っている。
「大丈夫大丈夫、もーやることやったし、てーか何も手がかりないのに行ってもね?さっきみたいに魔方陣の跡の上で踊るくらいしかできないじゃん?…あとはあのロン」
「なにしてんだオイコラニート」
後ろからグリグリと頭に手帳の角を押し付けられハッとした里留は悲痛の声をあげた。
三好の後ろには香もおり、里留のやられる様を呆然と見つめていた。
「何ってなにさぁ!俺がなにしたのさ!ブッコロスゾオイヤァ!」
「それはこっちの台詞だ」
バンッと音をたてて机の上に叩きつけられた物を里留と三次郎はキョトンと見つめた。
「…えっ、な、なに?まじでなんなの?おこ?おこなの?」
「誰が手伝えって言った」
三好はいつにも増して殺気立っていた。
しばらくの沈黙の間で、コップの氷がカランと音をならした。
「誰って…香ちゃんだけど…、えっ、なに?自分が助けてもらってると思っちゃったの?そうなの?キモインデスケドー!!」
透かさず三好は手帳で里留の後頭部を撲ると、バタリとテーブルの上に里留の顔は倒れこんだ。
「すいません…で、でも、こんな案件、一人じゃ絶対無理ですって」
香が申し訳なさそうに、三好の前に出た。
もちろん、三好さんの能力が劣ってるって訳ではないですよ、と後付けた。
が、しかし、三好の眉間に走った癇癪が和らぐことはなかった。
「…もういい、勝手にしろ。俺は一切お前らの責任はとらないからな」
三好はさらに強く紙を机に押し付けるてと、そのまま爪先を入り口へと向けた。
「魔方陣を解除すれば事は逃れられる。訳読むかぎり、どっかに呪文でもアンダロー」
机に突っ伏したままの里留の言葉に、ピタリと一瞬足を止めた。
が、すぐにその足音は店の外へと消えていってしまった。
「…怒らせちゃいました…」
「ハァー気にすることないよー、つかもうほっときゃいいじゃん?あんなクソ野郎なんかのために一々怒られてらんないじゃんか」
香は静かに席に着いた。
ふと、目の前にある紙をぼぅっと見つめ、唇を噛みしめると鼻で大きくため息をついた。
「…私、以前三好さんのとこでバイトする前、客として頼んだ依頼でとてもお世話になったんです…まぁ、実際依頼は友達がしたんで、私は付き添いだったんですけど…」
香はしばらく黙って一点を見詰めていた。
「やっぱり私、三好さんのこと手伝ってきます」
急に決心すると、香はガタリと席から立ち上がり、慌てて店のドアを飛び出していった。
その走って行く様子を、里留と三次郎は窓から見届けた。
「三好のくせにムカツクワァ~めっちゃいい子ジャーン、クッソ死ねロン毛」
「しかし…このままでうまくいきますかね…」
里留はそれを聞き流してぼやぼやと紙を手にとって眺めていた。
口にくわえたポテトを揺らしながら、目を半月にしてその羅列された文字を瞳に映す。
「…風見、か…」
九
昼過ぎ。里留達と別れた三好は、街の少しはずれにあるとあるマンションの屋上に立っていた。
12月の冷たい風が通り抜け、肌にピリピリとした痛みが植え付けられる。
見晴らしのいい場所から数歩離れて背を向けると、彼はその屋上の中心に立ち尽くした。
「…血、だったのか…」
地面にはうっすらと円の痕が残っていた。
あれから二年も経ったものだから、あまりはっきりとは見えないが、赤黒い、人の血液で描かれたその円は、二年の歳月が経っても尚、彼の記憶同様、あの出来事を思い出すのには十分な色彩で残っていた。
三好の白い指がそのあとを頼りにゆっくりと円をなぞってゆく。
はたしてこれは風見自分自身の血で描いたのだろうか。とても大きな円だ。
スタート地点に指が戻ると、しばらく三好は地面を凝視していた。
あの日のその後、三好は彼の里親であった親戚の家へ行って地面に手をついて謝った。
謝っても謝っても、終わらぬくらいに謝り続けた。
しかし、誰ひとりとしてそれを信じてくれなかったのだ。
「あらやだ、あなた、ウチに優太くんなんて子はいませんでしたよ。いたのは沙綾ちゃん一人ですよ」
皆、誰もが風見優太を知らなかった。
自分が殺したのだ、どうかこのとおり。
いくら言っても、結局は気味悪がられるだけであった。
俺は、奴を本当にひとりぼっちにしてしまった。…。
階段を下りてゆくと見覚えのある顔がこちらに向かって走ってきた。
にっこりと笑うその人物を無視しようと構わず歩き出したが、執拗に後をつけてきた。
「だから無視しないでくださいってば!…怒らせちゃったのは私かもしれませんけど…」
わざと拗ねたような素振りを見せるが、チラチラと三好の様子をうかがっている。
「ついてくるなって言っただろ」
「勝手にしろって言ったのも三好さんじゃないですか!」
不満げに口を尖らせる彼女を三好はチラリと見た。
それを見て、得意気に笑うので、癪にさわったのか、わずかに眉間にシワがよった。
「すいませんねー、ありましたありました、はい鍵」
そんなことをしていると、管理室から管理人であろう、老人の男性が緑の札のついた鍵を持ってきた。
三好はそれを軽く頭を下げて受けとると、手のひらに乗ったその鍵を見詰めた。
「あんた、その部屋の奴の知り合いかい? なら荷物引き取ってくれないか。どうせもうじき処分するから」
…。
十
407と貼られた重いドアを開けると、中は以外と物静かな部屋であった。
カラーボックスが数個、テーブル、ベットにあとは段ボールが何個も重ねられているような感じだ。
シンクには洗われたであろうコップひとつだけが、中に水を貯めたまま置いてあった。
三好はしばし玄関で立ち止まりその部屋を見澄した。
靴を脱いで上がると、同じように香も靴を脱いで後ろからついてきた。
「あの、三好さん、ここは…?」
「…呪文の手がかりを探しにきただけだ」
ゆっくりとリビングへ足を進めるとひとつのカラーボックスに立て掛けてあった写真が目についた。
小さい男の子とひとりの女性が向日葵の前で笑っている。…。
「わぁー綺麗な写真ですね、あたしもこういう姉弟欲しがったなぁー…」
段ボールは三、四箱程度あった。
ほとんどは日用品ばかりで、今のところ変わったものは見当たらない。
三好は、果たして風見が本当に何を望んでいたのか、よくよく分からなくなっていた。
何を殺したかったのか、なぜ自分自身を殺したのか、そして自分は本当に風見にとって友人であったのか。
ふと、服に紛れて分厚い本が一冊入っていたのを見つけた。
奇妙に思った三好はその想いをかき消し、パラパラと本をめくりはじめた。
そのめくる風に乗って、一枚の紙がページの間からふわりと飛び出した。
ゆっくりと床に落ちたその紙を拾おうとすると、向かいで調べていた香が咄嗟にひょいと拾い上げてしまった。
「?落ちましたよ三好さん」
「わかってるから、ほら返せ」
受け取ろうと三好はその差し出された紙に手を伸ばした。
しかし。
いくら手を伸ばしても三好の手に紙はかすりもしない。
香の手の数センチまでゆく三好の手は終いにはなにか見えないようなものでバチんと弾かれてしまった。
まるで電気のような音と共に弾かれたその瞬間、二人とも目を丸くした。
「…おい、何したんだ」
「えぇっ!?わ、私なにもしてませんよ!!な、なんで…あれ?」
香が慌てて空いていた左手で三好の右腕に手をのばすとあっさりと触れることができた。
キョトンとして、香は紙をそっとテーブルの上に置くと、その空いた右手でもペタペタと三好の腕を触ってみせた。
「あれ…これ、紙のせいなんですかね…アイタッ!」
三好に弾かれた自身の手が鼻に直撃して香は間抜けな悲鳴をあげた。
髪をぐしゃぐしゃとしながらため息混じりに三好は髪を見詰めた。
「…最悪だ…」
十一
「キャーオカエリナサーイ、釜茹でにする?毒死にする?それとも し・け・い ?」
事務所のドアを開けた瞬間出てきたその禍々しい生物を三好は蹴り倒すとギロリと隣にいた香を睨んで訴えた。
「…なんでこいつに合鍵渡してんだよ…!」
乾いた笑いをしながら目を背けると、その威圧に震えながら肩を窄めていた。
ぷぅん、と油っこい匂いが部屋から匂うので奥に進むと例のごとく二メートル近い男が中華鍋を持って立っていた。
「あ、三好さんたちおかえりなさい、ごはんなら作っときましたよ」
そろそろと逃げようとする香の頭を三好はガシリと掴んだ。
まるで彼の背後には仁王でもいるかのような出で立ちだと、香は心の内で呟いた。
食事という名の会議は不機嫌な三好をはじめ、たんこぶをこしらえた香、礼儀正しく椅子に座る本日のシェフ三次郎、そして玄関に倒れた里留の四人で始まった。
さて、テーブルの上には料理の他に一枚の紙切れが置いてあった。
「さわれないと…」
三好は面白くなさそうに頷き、腕をくんで俯いている。
香はその紙をそっと手に取ると、皆に見えるように文字の書いてある側を向けた。
玄関ではなぜかひとり双眼鏡をもっている。
「…?これ、何て書いてあるんですか」
「…やっぱり、三次郎さん達も読めませんか…」
香は、ハァとため息をつくと、今度はその文字を自分の見える側に向けて、少し高くあげると小さく息を吸った。
「『魔方陣の解除方法① この呪文を唱えることにより魔方陣は解除される。ただし、一日に一回唱えるのが人間の限界だろう』…」
「え、香さん読めるんですか」
「こいつだけな」
ふてぶてしく言う三好の言葉に香は困ったように頷いた。
「…『そしてもう一つ、②この聖水を使うことも可能ではあるが、約三回分しかない。よって、呪文を唱えることは不可避であろう』…と」
どうやらこの紙に最初に触った者のみ触れることができて読むことができるらしい。
そんな馬鹿なことがあるかといって触ろうとしても、現にあの見つけた時三好は全くもって触れることはできなかった。
とりあえず香が読むかぎりには、これによって魔方陣を駆除することができるらしいということだ。
果たしてこれを書いたのが風見なのか。それはハッキリとは分からない。
だが、こうして三本のボトルに入れられた「聖水」とやらとこの紙があるならば、やらねばならないのだ。
これが彼の足跡ならば、慰めをもって何年か越しの後始末とやらをやらねばならない。
こうして、この奇妙な人間関係はさらに深みをましてゆくのであった。
…。
12月17日。
皆より早く起きていた三好は、事務所の綺麗なテレビでニュースをぼんやりと見ていた。
だが、とうとうあのニュースが流れることはなかった。
やはりこの事は現実世間では到底あり得ない、<あってはならない事>らしい。
実際、揉み消すだなんてそんなご都合主義が本当にこの社会に通用するのかときっとこうして生きてるやつらは皆そう思ってるだろう。
しかしそういったいやらしいものというものは鮮やかに大衆の目を誤魔化しながら根強く流通している、そういうものなのだ。
そうして、その本物か偽物か分からないリアルと、その偽物が産み出した現実の間がここ。
そこで自分達は戦おうとしている。
一体自分はどこに位置していて、自分すら実際本物なのかまがい物なのか、それすら分かってはいないというのにだ。…。
7時頃。朝のトレーニングから戻ってきた三次郎は湯気を出しながら、玄関で寝ている里留を起こすと、四人は事務所のリビングに集まった。
ソファーで寝ていた香はまだ夢うつつか、少々よたよたとしている。
それからテーブルを囲んで立つ三人は皆同じように三好に注目した。
「…なんも言うことはねぇぞ」
三好はそれだけ言うと財布とタバコをポケットに突っ込み玄関へと歩いていった。
香も、心なしか三次郎も嬉しそうに笑うと、同じように玄関へと駆けていった。
後ろからはのそのそと気だるそうに歩く里留が苦笑いしながら事務所を出た。
十二
行き先はいつも通り二手に別れることとなった。
魔方陣を解くのには聖水、もしくは呪文が必要である。
そのため、三好は香と呪文での解除を、里留と三次郎は聖水での解除をしようということにした。
「もー三好さん素直じゃないんですからぁ~、ちょーっとくらい爽やかにスマイル見せて"ありがとう…"とかいだだだだ」
「お前が勝手に紙触ったせいだろうが…!!」
香が必死に謝ると頭をつかんでいた手を離し、またスタスタと三好は目的地へと歩き出した。
「お前さ、俺の仕事なんか勘違いしてねぇか」
警察署に着くといつものように三好は入り口のロビーに槻上を呼び出した。
「実際いつもいるんだからどうせ暇なんだろう、ほらよ」
「ほらよって、もうこれチヂミじゃねぇか!完全に韓国料理だろ、オイ」
三好はその箱を押し付け、槻上の小言を聞き流しつつ例の生き物と対峙した位置へと足を進めた。
魔方陣の痕さえないが、あの白い餅のような生き物に生えていた鋭い足の爪痕がわずかながらも床や壁に残されていた。
槻上にここでよいのかと訊ねると、不満ながらも小さく顎でしゃくって返事をした。
香はそこに静かに一歩踏み出すとチラリと三好を見た。
「…じゃあ、やってみますね」
周りに物がないことを確認するとあの紙を出した。
何が起こるか、というか何をしているのか分からない槻上は、この急な怪しい行動に戸惑いの視線を向けた。
三好が槻上を左手で制しているうちに、香は胸一杯に息を吸い込んで、発音のできないその呪文を唱え出した。
わずかな風が床から舞い起こった。
次第に床には黄色い淡い光の円がじんわりと浮かび上がって、ミシリと音を立てた。
最後には透明になってゆき、ガラスが割れるようにヒビが円の中に駆け巡り、そして ぱきん と割れるとその破片はじゅわりと音をたて消えていった。
半信半疑ではあったが、こうも具体的に目の前で起こるとさすがに三好も目を丸くした。
そして、それ以上に理解をしていない槻上はなおさら混乱をしていた。
皆が驚く一方で、三好は一抹の不安がぼんやりと浮かび上がってきていた。
本当にこの呪文を唱えることはよかったことなのだろうか。
当然、魔法についてなんて知るわけはないが、とにもかくにも、三好は呪文によって身を滅ぼした人物を知っている。
果たしてこの方法が正解だったのか、それはなんとも答えがたい。
香の額にはわずかに汗がにじんでいる。
呼吸も少しではあるが通常よりは荒く、肩が上がったり下がったりしている。
「…じゃあ、帰るぞ」
「はぁ!?オイまてたんて」
「あぁそうだった、このリストの中に最近事件があった会社はないか、調べとけ。じゃ」
三好は一枚のメモを槻上の胸ポケットにねじ込むとさっさとその場を後にしていった。
そして、それを追うように、香は一つ会釈をすると三好の後を走っていった。
ひとりロビーに取り残された槻上。
どことなく、周囲の憐れみの目が痛かった。
「待ってくださいよぉ三好さーん!」
必死に追い付こうと、後方からトテトテと小走りする助手の日輪香。
声が聞こえると彼は長い足を渋々と止め、めんどくさそうに舌打ちをしてその場に立ち止まった。
やはり、呪文というのはかなり負担が大きいように見える。
もし、あの時紙を自分が一番最初に触れていたらどうなっていたのか。
今となってはもう遅い事ではあるが。
「休む」
「は、はい?」
三好はそれだけ言うと近くに見つけた冷たい石のベンチに腰を下ろした。
ポケットから出したタバコをくわえると、カチカチと音をたて、オイルのたくさん入ったライターで火をつけた。
急にそんなことを言い出した三好に少し驚いていた香だが、とりあえず流れのままにそのベンチに少しの距離を空けて座った。
しばらく二人とも黙っていたが、それに耐えられなくなった香は最初に唇を動かした。
「その…風見さん、って、一体誰なんですか…?」
三好はプカプカとタバコをふかしている。
無造作にタバコの箱をいじっていて、こちらに視線は向けてくれない。
「…知り合いだ」
三分の一ほど燃えたタバコを揺らしながら、大分間を空けた後に呟いた。
「…お亡くなり、なんですよね」
「あぁ」
三好はためらわずに言った。
「俺が殺した」
一三
一方その頃、里留たちは三本の聖水を手に、以前の魔方陣の場所を巡っていた。
「ほんとに効くのかね、こんなんが」
四角い透明なペットボトルに詰められた聖水は、どうみても紛うことなきなき水にしか見えなかった。
おまけにペットボトルには太い黒マジックででかでかと"聖水"と書いてある。
里留はこれを見てふと、よく詐欺師が売り付けるの泉の水、なんてのを思い出した。
二人は何事もなく一件目の北東接骨院を終え、次に向かうは月光大学であった。
二本のうちの一本をくるくるとひっくり返しながら里留は観察をしていたが、見れば見るほどただの水以外の何にもみえやしなかった。
先程病院でかけたとき、たしかに「じゅわり」という音を聞いたのだが、それ以外大した反応はなかった。
「商売でもしようとしてたんじゃねーのーコレー」
「さぁ…でも、一応音しましたし」
「んなテキトーな」
そうも話していると、二人は二つ目の場所、月光大学に着いた。
鳥塚教授を通じて、早速例の場所へと案内をしてもらうと、里留は早々にペットボトルのキャップをあけた。
「コレ仮にホールのど真ん中とかでやったらほんと気違いだよな」
「まぁ…」
接骨院でやったのと同じように円を描きながらまんべんなく水を掛けてゆく。
こんなものが本当に効いているのか、そえ思っていたが、1回目より大きく「じゅわり」という音がした。
不覚にもその音に少しだけ目を見開いてしまったが、まぁ効いているならばそれでいいだろうと、里留その500ml程度のペットボトルの水を掛け続けた。
ふと、里留はその時足元に目を向けた。
何やらまた違う音がするのだ。
気になって一旦ペットボトルの口を上に向けると三次郎を手招きした。
その時であった。
地面で小さく鳴っていた「ポポポ」というその違う音が急激に早さと音量を増し、次第にブクブクグツグツと沸き立つ音を出し始めた。
粘土が沸き出てきたのだ。
驚き退く二人の前にはみるみるうちに粘土が蓄積され、そうしてあの白い餅のような、二本足の大きな口をもった生物に変貌した。
マズイ、と思った里留は背後を見たが、ここは一方通行の廊下だ。
そう慌てている間にも、白い生き物は完全な状態へと固まってゆき、そしてとうとう太い足のバネをきかせて里留に牙を向けて襲いかかってきた。
ぎゃふん! と情けない声をあげ、間一髪で避けたが、左のワイシャツの袖が鋭い牙でわずかに破かれた。
床に転げた彼を見て、再度生き物は強く地面を蹴ってこちらに向かって跳び上がってきた。
やられる、と里留は口を大きく開けて悟った。
しかし、その生き物のガラ空きになった体に、一つと物理的衝撃が走った。
「先輩!大丈夫ですか!!」
高く振りかぶった三次郎の拳は、その生き物を強く壁に叩きつけた。
もはやどちらが化け物なのかがわからないその光景に、里留は思わず泡を吹いて白目をむきそうになった。
だが、当然それで闘いが終わるはずはなかった。
「お、オイ!!三次郎うしろだ!!」
壁にいたはずの生き物はすでにいなく、二人の頭上に高く跳ね上がっていたのだ。
これには三次郎も間に合わない。
どうにかできないかっ焦った里留は咄嗟に手元にあった物を掴むと思い切りその生き物めがけて投げつけた。
もう一つの水が満タンに入ったペットボトルが生き物めがけてクルクルと回転をしながら飛んでいった。
やってしまった、と里留は青ざめたた。
勿論ペットボトルは生き物の口によってそのまま粉々に噛み砕かれてしまった。
万事休す、水が一斉に飛び散る中、もうだめだと思ったその瞬間であった。
「……え?あ、ん?えっ」
叫び声をあげたのは生き物の方であった。
金切り声のような叫びをあげる生き物は里留が目を開けると床で這いつくばっており、体は痙攣をおこしてビクビクと震えながらその大きな口一杯に泡を吹き出した。
そして、あの魔方陣と同じように「じゅわり」という音を出すとドロドロと粘土のように溶けてゆき、終いには跡形もなく消えてしまった。
廊下には、生き物がめり込んだ壁の跡だけが残され、しばらく無の空間と化していた。
しりもちをついてひっくり返っていた里留は、空になったペットボトルを震えながら手に取った。
「こ、これ……」
「里留てめぇどういうことだ」
事務所のテーブルの上には空っぽのペットボトルが二本置かれ、三好は里留の両目尻あたりを右手で強く掴みながらきつく目を光らせていた。
「いやね…ホントマジヤバかったんだって…いやほんとだってぇ…ほら、でも今日二つも終わらせたしあがががががががががががが」
頭蓋骨が陥没するかのような圧力で押さえつけられ、里留は叫び声をあげた。
香がまぁまぁと三好を後ろから宥めに入ると、ようやく里留は地に足をつけることができた。
「お前な…一本無駄にしてんだぞ、怒らないわけないだろ!」
「いっつも怒ってんじゃん!!俺には!!」
頑張って二本の中から残っている水滴をかき集めても、小指程度あるかないかという程の量であった。
これでは、到底あの魔方陣の解除ができるとは思えない。
大丈夫と言ってその場を納めようとする香に対して、三好は再びあのきつい視線を彼女に向けた。その苛立ちの中、三好はふとそのペットボトルを見詰めた。
「…本当にこの水がバケモノに効いたんだよな」
二本を手に取ると、三好は何を思ったか、徐にそれをポリ袋に放り投げ、事務所から出ていってしまった。
香はポカンとその閉まるドアを見つめて首をかしげた。
三好が出ていくと重りが外れたように、里留は大きなため息をついてソファーに大きくもたれ掛かった。
「もーほんと何アイツーーー、こちとら死にそうだったってのに!!死ね!!」
「しかし…香さん、あと二回…いや、二回では済まないかもしれない…本当に大丈夫ですか」
三次郎を見上げ、目をぱちくりさせると、苦笑いしながら彼女は頷いた。
時刻はもう既に夕方の5時を回っていた。
一四
午後8時。
三好が外から戻ってくると事務所は真っ暗であった。
靴がないのを見ると、おそらく出掛けたのであろう。
黒い艶のよいその靴を脱ぐと電気もつけぬまま、三好は自分の机に歩いてゆき、その隣に置いてある厚い金庫を開いた。
冷たい箱の中に入っていた一丁の銃を手に取ると、そのカラダをじっと見詰めた。
その瞬間、手から脳へと様々な情景が彼の中に襲いかかってきた。
一瞬息を、ヒュ、と呑み込んだ。
険しい表情で銃を恐る恐る握りしめると、今度はぼんやりとあの時の記憶が蘇り始めた。
冬の夜空。
切ないくらいに夜景の光も、空も、美しい。
冬の夜空。
都会にピストルの音が鳴り響いた。
床はおそらく黒だ。そこに奴は立っている。
真っ黒に成り果てた屍を前に、探偵は、立っている。
ゴトリ、と銃が落ちた音で三好はハッとした。
我に返って、ようやくするべき事を思い出した彼はバックからある弾を取りだしその銃に詰め込んだ。
ここでようやく三好はこの部屋が真っ暗であることに気がついた。
銃をもう一度しっかりと金庫にしまうと、スイッチの方へ振り返った。
「うぁああああああんやめろ!!やだ!!さわらないで!!やめてよしてさわらないで!!…お?」
三好も驚いたが、振り返った先にいた人物は尚も驚いて叫び声をあげていた。
が、こちらに気がつくと疑いながらも後ろ手でそっと電気のスイッチを入れた。
「…何してんだよ」
「お前かよ!!クッソ!!泥棒かと思ったわ!!電気つけろよ!!」
なぜかしゃもじを振り上げて立っていた里留は、相手が三好だと気がつくと安心してそのしゃもじを振り下ろしてきた。
なんの興味もなく三好はそれを振り払うと、さっさと机に歩いてゆき、持っていた鞄をドサリと机の上に置いた。
「あれ、三好さん帰ってたんですか」
ドアに目を向けると、香と三次郎がスーパーの袋を両手にもって立っていた。
まるで漫画のようにネギやら大根やらが飛び出しているその袋を見る限り夕飯の買い物でも行ったのだろうか。
「あ、ほんとだ三好さん、何しに行ってたんですか」
香は重い袋をテーブルにおいて買ったものをもそもそ弄っている。
三好はバックから小さな箱を取り出すとふたを開けてみせた。
「……どんぐり…?」
「んなわけねーだろ黙ってろニート」
こちらに来て中身を見るなり、香も眉を潜めてそれを見た。
両脇からも三次郎と里留が身を乗り出して同じように箱の中を凝視した。
銃の弾だ。
香は驚いて目を見張らせ唾を飲み込んだ。
少しだけ見せると三好はサッとフタを閉めてあの金庫にそれをしまってしまった。
「あの水が弾に入っている」
かりかりっとダイヤルを回しながら三好は言った。
「少なからず、あのバケモノに効果はあるだろう…」
「おいおい、まさか一般市民の前でやらかすってか?やだコワーイ」
「だからどうした」
へらへら笑っていた里留も顔をひきつらせた。
そのあまりにも冷淡で、冷徹な、狂気にも近い返答に彼ですら少し戸惑ってしまった。
「明日、俺らで神社を済ませてくる…お前らは道場の下見にでも行ってくれ」
それだけ吐き捨てると、机においていた手帳だけをもって、奥の部屋へと姿を消した。
一五
「あらあら、もうご用は済みましたか」
12月18日
三好らは昨日話したように各々が行くべき場所へと向かった。
二人は昨日と同じように魔方陣に向かい、昨日と同じように呪文を唱え、何事もなく事を終えてしまった。
無事に終わったことを神主に伝えるとニコニコと笑って、よかったよかったと言っていた。
果たしてこの人は意味がわかっているのか。
後ろであくびをしている香の靴を軽く踏んで指摘すると、香は慌てて姿勢をいつもより大袈裟に正した。
「ところで、探偵さんは何をなさってたのですか?」
思った通りの質問が神主から飛んできて、三好は顔をひきつらせないように出来る限りの精一杯の微笑みを作って口を開いた。
「…いえ、少し変な事件があるので調べていたんですよ。大したことはありません」
「まぁそうなんですか。いやですねぇ、最近ここら辺も物騒で…あぁ、お守りいかがですか?恋愛成就ですけど」
結構ですと目をそらしながら三好はそのピンクの布地のお守りを拒否した。
ここの神社では二年前、里留が変な男達に遭遇したという場所でもあった。
三好が引っ掛かっていたのはそのことであった。
「さぁ……二年も前ですし…」
風見を見る限り、決して多くの仲間を控えているようには見えなかった。
しかし三好達は探索中に不審な男二人に出会った。
この神社で里留達が出会った男達と三好らが出会った男達。
いずれも謎の変死を遂げた彼らだが、二年前の風見の死をもってしても奴等の死や目的の謎は一切明らかになることはなかった。
「あぁ、でも」
神主はふと何かを思い出したのか、少し首をかしげながらスッと三好たちの背後の向こう側を指差した。
「なんというか、先日あちらにある幼稚園の隣の公園で何だか物騒な事があったそうですよ…まぁ、よくわかりませんがお気を付けてくださいね」
そう言って再び差し出されたピンクのお守りを、三好は再び拒否した。
「というわけで桃子、俺死ぬかもしれんね」
「はぁ、全然意味がわからないわ」
昼時、里留らは東方病院を訪れていた。
院内の食堂で、ほどほどに目の前にいる男の子話を聞き流しながら、桃子は黙々と食を進めていた。
一方で里留は、今までの話を身ぶり手振り大袈裟に話していた。
「ちょっとー、桃子きいてるぅー?ねぇー、桃子ぉーねぇねぇねぇねぇ」
「あーもーうるっさいなぁ!はいはい、白いバケモノでしょ、牙のある」
「なんだよ、今回は随分すんなりと信じてくれんの」
うっとおしそうにしながらも内容をちゃんと理解していた桃子に対して、里留は少々驚きながら目をぱちくりさせた。
「そりゃぁ……」
桃子はしばし分が悪そうに口をモゴモゴさせていた。
が、小さくあたりを見回すと、箸を置いて里留に顔を近づけて小声で話を続けた。
あまり表立っては言えないけど、と前置きをする桃子に里留は再び瞬きをした。
「…最近、変な患者が多いのよ…どうもみんな怪物怪物って。…それこそ、さっくんの有休中に外科なんかんは肉を食いちぎられた人とか運ばれてきたらしいし」
その言葉で当然思い出されたのは、あの白い生き物であった。
あの大きな顎が、容赦なく人の身体の一部を食いちぎったのだと思うと、ゾッとする。
それによって、昔のあの手術の光景が一瞬過り、里留は微苦笑した。
…なんだか居心地も悪くなったので、里留は三次郎を連れ、東方病院を後にした。
道場の下見は午前のうちに終わってしまった。
と、言っても、テープが張られていて外からしか見れなかったというか。
二人は街をどことなくぶらついていた。
「先輩」
ワゴン車で売っていたハンバーガーを片手に食べていると、少し感慨深そうに三次郎が訊ねてきた。
桃子はあの後、ただひとつ「本当に今、何が起こってるのか、さっくんは知ってるの」と、言葉を突きつけられた。
「桃子さんの言った通り…、実際僕らが生きているのは今であって、…こういった非現実的なことに夢中になってるのって…どうなんでしょうね」
「なんだよ急に」
ハンバーガーからソースが地面に滴る。
里留は気がついて慌ててハンバーガーにかぶりつくと口でしっかり噛みしめながら目を細めた。
「そうだな。…俺はおそらく医者として知らなきゃいけないことを今の今まで知ってなかった」
里留は至って平常であった。
だがそう言って自分自身に微苦笑しているようにも見えた。
「臭いことを言っちゃえばさ、まぁそれでも誰だってそんなもんだろって。…医者は所詮訪れる人しか助けられない」
「…えぇ、僕の兄も、そう言っていました」
「そ。そうなんだよ。だから俺は人生行き当たりばったりで十分なんだわ」
特に里留は感慨深くしているようには見えなかった。
ただ、ハンバーガーを食べる動作と同じように坦々と、時を見据えて話していた。
「どうせね。知ってようが知ってまいが最後にはどこかしら、行着きゃするんだから、…それで人でなしって言われんなら、仕方ない。俺は別に人でなしでも構わないさ」
里留は、そうして最後の一口を放り込んだ。
「やっぱり真実は俺に重すぎる」
一六
神矢が言っていた場所は神社からおよそ2、3キロほど離れたところにある「よつば幼稚園」のことであった。
ちょうど昼に訪れたということもあり、園児達は食後の歯磨きをみんな揃って水道を前にしているところであった。
三好らは入り口から職員らと目が合うと、ぺこりと一つ礼をした。
「えぇ…結局なにがなんだかは分からなかったんですが…」
園児達には聞こえないよう、みんなが遊び時間になってから三好はそこの園長に話を聞いた。
香は園児たちの相手をしている。
「実際近くで起こっただけでここは何も関係はないんですよ…でも真隣の公園でそんなのが見つかっただなんて聞くと…」
おそらく、いやきっとそれはあの生き物の仕業であろう。
警察は隠していたらしいが、第一発見者の通行人が「人が噛みきられていた」と言っていたのを、確かに聞いたと園長は青い顔をしながら話した。
「おい!探偵!」
突然、甲高い声が背後から聞こえ、三好は後ろにチラリと顔を向けた。
そのまま視線を落とすと、金髪のおさげをした1人の幼稚園児がキラキラとした眼差しを向けて立っていた。
「三好さん、この子探偵が大好きなんですって。ね?」
後ろから追ってきた香はその金髪の少女の頭を撫でて微笑むと少女もまた元気よく大きな返事をした。
ハーフなのだろうか、黒髪ばかりの園児の中でその髪と緑がかった瞳は、異国の空気を漂わせていた。
日本語がどこか拙いためか、少々乱暴な口調でこちらに迫ってくる少女に、三好は少し引き気味だったが、なんとか平然を装って視線を返した。
「それでは、お時間失礼しました」
三好は足早に園長に会釈をすると室内を後にした。
外では園児達が元気よく遊んでいる。
この煌めいた空間に自分が土足でふみ入れていることに三好は違和感と、名状しがたい罪悪感を感じていた。
数人の園児達にバイバイと手を振られもたついている香を待ちながら、三好は待ちの向こう側を眺めた。
この地から一歩出ようと自分の生きづらさは変わらない。
それを彼はよく知っていた。
「…ん?」
ふと、三好は向こう側にモヤモヤとした白い影を見つけた。
いくつかあるその影はこちらに向かってきている。
ぐっと目を凝らして、三好はその影を凝視した。
ヤツだ。
三好は、ヤツ、をカメラ越しでしか見たことはなかった。
しかし、それがヤツであると彼は確かに確信できた。
大きな口、二本の足で動き回るその白い影。
咄嗟に大声で香の名を呼ぶと彼女は驚いたようにこちらを見た。
早く園児達を連れて逃げろ、と叫ぶが誰しもが首をかしげている。
「『ヤツ』だ!!」
香はその言葉で今何が迫ってきているのかようやく理解した。
だが、それに気づかない園児達は間抜けに辺りをキョロキョロしているだけであった。
ヤツらはビルをつたってやはりこちらに向かってきている。
三好が苦い顔をして腰の銃に手を添える中、香はあたふたとどうすべきか煩悶していた。
三好がもう一度叫ぼうとした時、香はやけくそと言わんばかりに目をつむり右手を天高く掲げ一言叫んだ。
「お、鬼ごっこするよみんな!!」
香の大きな叫び声が辺りに広がった。
「ほら、早くしないとお姉さんが捕まえちゃうよ!!街全部使っての鬼ごっこ!よーい、ドンッ!!」
その言葉に押されるよう、園児達は皆一斉に外に向かって走り出した。
「先生方も早く!」
香の必死な表情に職員も危険を感じたのか、バタバタとその園児の後を追っていった。
三好は素早く銃を引き抜くと透かさずあの白い生き物目掛けてそれを撃ち放った。
あの水の入った弾が生き物の中心部を貫いた。
生き物はぷくぷくと膨れ上がると風船のように白い皮膚を撒き散らして破裂した。
先生達はさらにそれを見ると顔を真っ青にして走り出した。
足の遅い園児らを香や先生たちで抱え、皆が園から姿を消した。
空っぽになった幼稚園で、三好はしっかりと足を踏ん張ると、残る生き物にどんどん弾を撃ち込んでいった。
一発、二発、三発、四発。
三好は驚くほど的確に命中させていった。
最後の一匹はもうほぼ目と鼻の先にまで近づいてきていた。
狙いを定め、三好が集中していたその時であった。
目の前にある一つの教室の扉がガラガラと開き、あの金髪の少女が出てきたのだ。
大方、トイレにでも行っていたのであろう。
小首を傾げる少女は今どのような状況下にいるのか全く理解していなかった。
「三好さん!」
それに気づいて戻ってきたのだろうか、香の焦った声が背後から聞こえてきた。
が、白い生き物はもう既に教室の屋根にいた。
三好の頬に嫌な汗がつたう。
地を蹴り、彼は思い切り少女の元へ飛び込んだ。
抱きしめたまま三好と少女は地面に転がる。
もう、目の前には鋭い歯をむき出しにして口を開いている生き物がいた。
だが、その口の前には、彼の銃口が煙を立てて凛として立ちはだかっていた。
三好はその時確かに見た。
白い皮膚が飛び散るその時に。
幽かな人としての面影が、彼の瞳の奥に写り込んだ。
一七
警察を呼んだが、実際に来たのは交番勤務の者が二人程度であった。
その二人も特に詳しく調べることはなく、軽く辺りを見回すだけでさっさと帰っていってしまった。
三好はそのまま警察署に向かい槻上を呼び出した。
「なんだ、警察も随分当てにならないもんだな」
皮肉を込めて三好が呟いたのを、槻上は答えられずに、悔しそうに眉を寄せながら一枚の紙を突き出してきた。
「…この間言ってたリストのヤツ…特に事件はなかった」
三好が先日槻上に押し付けたとある会社が載っているリスト。
四、五件載せられていた会社名の周りには赤いペンでラインやらメモやらが施されていた。
殆んどの会社には横線が引かれている中で、ある一件だけ波線が引かれているのに三好は目をやった。
「そこのお菓子会社な…別段何か事件があったわけじゃねーんだが」
槻上はそう前置きすると一枚の女性の写真を見せてきた。
「そこの女社長、…こう言ったらあれだが、なんでも妙な趣味をもってるとかで有名なんだ。…人の趣味どうこう言うのもなんだがな」
槻上から差し出された写真を手に取って、三好はその瞳をじっと見つめてみた。
槻上は曇った表情を浮かべていたが、それ以上、何も言うことはなかった。
……。
外に出ると、今日三好が助けた例のハーフの少女が母親と並んで立っていた。
二人とも三好達に気づくと、少女が母親の手を引いてこちらに近寄ってきて嬉しそうに微笑んでいた。
「探偵はスゲーのナ!探偵はスゲー!」
三好が気に入ったのか、少女は目を輝かせて興奮気味にそう繰り返していた。
母親の礼の言葉に受け答えする香のやり取りをぼぅと見ながら、自分になつく少女に視線を下ろし、軽く彼女の頭に手を乗せ言い聞かせるように呟いた。
「探偵はひどい人だよ」
三好は香と二人で事務所に帰る中、ひとり心の内で今日の感触を思い出していた。
銃。
二年前より取り出したことのなかったあの銃を久々に撃った感触。
捕まらなかったのは幸い、といっても三好にとってそんなことはもはやどうでもよかった。
風見が死んでからの三好は実に見苦しいものであった。
元より孤独心の高かった彼の心は風見の死によってより一層深いものとなった。
あの屋上で親友を撃った時、そしてそれが塵となったとき、三好はまだそれが現実であると受け入れられていなかった。
いや、視覚としては確実に捉えていた。
ただ、彼に腹を刺されたあの時からぽっかり空いてしまった理性の穴は、その事実を受け入れようとはしなかったのだった。
あぁ、彼は紛れもなく死んだのだ。そうはじめて知ったのは、三好が彼の親戚に頭を下げ、誰も風見を知らないと知った日のことだ。
そして、殺したのは自分だった。そう理解した。
それからやっと死のうと思えた。
飛び降りはダメ。身投げもだめ。
我が親友と同じように誰にも知られずに死なねばと思ったのだ。
だが、それも無意味であった。
風呂に顔を埋め死のうとする時も、刃物を持って腹をかっ切ろうとする時も、水に、刃物に、風見が写りこちらを観ているのだ。
何も言わず、ただこちらを恐ろしい形相で見つめている。
それに思わずヒッとなって怯んでしまう。
彼が私に生きて地獄を見ろと言っている気がしてならないのだ。
最早まともに寝れぬ日ばかりが続いた。
薬を飲んで寝る、薬を飲んで寝る。
といとう自分すらも考えなくなった三好にとって、それは死んでいるも同然なものであった。
そうこうしているうちに助手ができた。
日輪香。
元々女性嫌いである三好が彼女のような助手を受け入れるのはおかしなことであった。
ましてや、助手など彼にとって邪魔なだけなのだ。
そう、だからこそ彼は彼女を助手として迎え入れたのかもしれない。
三好はもはや分離した自分自身に悪意をもってこうしたのだ。
女嫌いが、人嫌いが助手を置けばこの上ない生き地獄だ。
そうだ、これはアイツ、三好咲良への戒めなのだ!
彼は一種の死体に成り果てていた。
「あの子供は、探偵になりたいのか」
夕方六時を回った帰路、三好から珍しく口を開いた。
「え、あ、はい。そう言ってましたよ」
きっと三好さんのことみてますますそうなったんじゃないですかねぇ、と香ははにかんで白い息を漏らした。
そうか、と三好も少しの間を空けてからわずかな白い息を漏らした。
あの時、少女を助けたのはそこが屋上に見えたからだ。
「探偵と高利貸ほど下等な職はないと、どこかの小説家は言っていた」
三好にはどこまでも屋上しか広がっていなかった。
一八
事務所に帰り、また玄関でふざけている里留を見かけたが三好は特に気に留めずその横をあっさりと通り過ぎていった。
ソファーにカバンを投げつけ黙っている三好を気味悪そうに見ている里留と心配そうに見ている三次郎に構うことなく、三好はそのまましばらく息を荒げていた。
「…そういやあ、道場、どうしたんだ」
ふと思い出したのか、そう言って振り返った三好の顔は案外平常であった。
しばし動揺しながらも三次郎は手に持っていた中華鍋を置いてデジカメを取り出した。
「…随分廃れてるな」
写真に写っている道場は二年前よりも遥かに劣化していた。
「見ての通り立ち入り禁止で大して見ることはできなかったんですが…」
道場の正門は黄色いテープで塞がれ、周囲の溝からは時間の経過が見られる草が大量に生えていた。
外壁にはヒビが入っているように見え、かつてよりかなり風化していた。
「やー、でもなぁ、特になにもなさそうだったよなぁ」
外壁の隙間から覗いてみたのだと里留は手と手の間から目を覗かせて表してみせた。
「…で」
「え?東方病院行ってた感じかな???」
「おい中華鍋貸せ、ぶったたいてやる」
まてまてまてと、怒りを震わせる三好を里留は手で制しながら慌てて声を張り上げた。
「留置場の茂庭に会ってきたの!!その代わり!!」
三好の手がピタリと止まり里留はホッと胸を撫で下ろした。
「…なんで今更。今回そいつは関係ないだろう」
チッチッチと舌を鳴らし顔の前で人差し指を揺らすと里留は続けた。
「いや確かにね、今回は関係ないわけよ。…まぁだから無収穫だったわけだけど」
そっと中華鍋を手に取る三好を慌てて三次郎と香が宥めた。
一九
逃げるようにして東方病院から退散してきた里留たちはその後道場に向かい、何も残っていない荒れた敷地を隙間からこそこそと覗いていた。
そして、ふとあの一人の女性を思い出したのだ。
茂庭弥生はあの後当然逮捕されたわけだが、具体的な証拠がないため未だに牢屋の中に置かれていた。
一先ずは詐偽の罪のして咎められているのだが、実際がそれで済まないことがあったというのは皆当たり前だが知っていた。
しかし、彼女の証言はあまりにも奇妙であり、それでいて現実性がないために精神異常と診断されていた。
里留らは二年前の真相を聞きに茂庭に面会を頼んだ。
「ヤァもにもに教祖先輩ー」
実際に会いに行ってみると茂庭は至って冷静であった。
むしろ冷めきっているようにも見え、虚ろな目で茂庭はこちらをジロリと睨んできた。
里留はお約束の言葉をかけながら、恐る恐る目の前にある丸いすに腰をおろした。
三次郎も警戒しつつ里留に続いて腰をおろした。
黙ったままの茂庭を前に一つ咳払いをすると里留は話を続けた。
「や、ね、もにもに教祖先輩の先輩、サンフラワー先輩の先輩についての話なんですけどね」
お互い探り合うように視線を交わす。
食い入るようにこちらを見る妖美な顔をしている茂庭に里留は思わず冷や汗をかいた。
「…あんた誰」
「あ、覚えてないのね、純粋に、ちょっと待って超ハズカシイアー」
一気にずっこけた空気の中、ようやく思い出したようで茂庭は人差し指をヒョコヒョコ動かしながら一人納得したように頷いていた。
そして、そうとわかったからか、里留らを今度は嘲るかのような目で見ると小さくほくそ笑んだ。
「なぁに、まだ頭のおかしなことやってるのあんたら、まったくバカだねぇ」
それは果たして風見に言っているのかそれとも里留らに向けて言っているのか。
その矛先は分からないが、茂庭はただバカにしたように頬杖をついてへらへらと笑っていた。
「頭のおかしいって…もにもにには言われたくねーんだけど…」
ボソリと呟くとキツく睨まれたため里留は思わず背筋を伸ばした。
茂庭はセミロングの髪を指でクルクルと絡めながら大きくため息をついた。
「で、なぁに?今回だかなんだか知らないけど私は見ての通り囚われの身なんだから」
今回の一件に彼女が関わっていないことはどことなく分かっていた。
分かっていたと言うべきか、そう感じていたというべきだろう。
里留が聞きたかったのは、あくまでも二年前のことだった。
「純粋に腑に落ちないわけよ、あんたはどうせ金儲けのために頭おかしいふりしてたわけだろうし」
「ま、もうこの際関係ないことだしね、言っちゃえばそうよ。世界征服だか滅亡だかしらないけど金さえもらえりゃなんでもよかったのよ」
開き直ったように言う茂庭に思わず里留は恐怖を覚えた。
女性という生き物がもしかしたら化け物なのではないだろうか。
分かりきっていた事ではあったがやはりそれを生で見ると恐ろしいものであった。
「サンフラワー先輩ね、あの後死んじゃったのよ」
やはり茂庭はそれを知らなかったのか、少々目を見開いて驚いた視線をこちらに向けた。
が、すぐに冷めきった目つきに戻り、俯いて笑いの息を漏らした。
「知ってたのかどうかね、聞きたかったんだけど」
「知るわけないでしょう、第一あの魔法とか言ったのも私は何一つやってないんだから」
あの男、つまり風見が全てやったということを茂庭はつらつらと喋りだした。
狂言と言われた彼女が実際に見た奇怪現象の話も時折混じってそれらは語られた。
「あの男はね、魔術師でも奇術師でもなんでもないわよ。―――あたしと同じで、強欲で、ただ何かにすがっていなきゃいられないただの人間、人間だったわよ」
彼女の話は嘘か真か、それは定かではない。
しかしそれも一つの真実なのだと、里留は知っていた。
「俺はそういう非現実的悪意があると思うけど」
真実と現実は別物なのである。
「そして、おそらく風見は真実すら伝えられないまま死んだ」
里留は三好らに、風見の裏にも確かに誰かがいたと言うことを伝えた。
「先輩、言わなくていいんですか」
三好が部屋に入った後に三次郎はこっそりと里留に問いかけた。
「別に。…俺が気になって聞きにいっただけのことだからな」
風見がはじめから三好を利用していたことも、また真実なのである。
二十
三好は一つ気がかりなことがあった。
あの白い化け物は一体どうやって、いやどこから出てきているのか。
はじめは北東接骨院。
あの時は知る限り一体のみであった。
その後の警察署や大学でも一体。
しかし、幼稚園ではなぜか遠方から複数の化け物がこちらに向かってやってきた。
「今までは魔方陣を解くと一体出てきていた…となると妙なのは北東接骨院で見かけた一体と神社で現れなかった何体かの化け物だ」
三好の推理からして、おそらく出現した数とは、"あの時"実際に生け贄になった人と同じなのではないかというものであった。
そうなると、北東接骨院、神矢神社、そしてあの警察署付近で三好らが対峙した男二人となる。
なので、三好が幼稚園で出会った化け物はこれらのものであると考えられるのだが。
問題はそんなことではなかった。
「え…じゃあつまり…道場で解除したら…」
里留はかつて潜入時にいた人数を思い返した。
大広間に集まった人数で考えればおよそ80人近く。
「は、80体以上の化け物が…」
さすがの三次郎もその言葉に息を飲んだ。
香もあの白い生き物を思い出したのか、ブルッと身を震わせた。
「じゃ、じゃあ、解除しちゃだめじゃないですか!!」
「解除しなかったらしなかったで23日を待つだけだ」
三好がそう言うと香は困ったように眉を下げた。
手段は一つに二つ。
どの道、何もしなければ皆死んでしまうのだ。
「……」
到底、80体全てを倒せるわけはない。
本来ならば倒すということ自体が安全な策ではないのだ。
「俺に考えがある」
三好は、一本のライターを取り出した。
…。
翌日。
四人は例の道場に魔方陣を解くため向かった。
写真で見た通り外壁にはヒビが入っており、雨風によって人のいない住居はすっかり風化していた。
人に見られないよう、こっそりと裏門から忍び込むと中は草木が生え放題で、より荒れていた。
「うわぁ…なんかクサッ、ぜってートイレからなんか溢れてる臭いだよこれぇ…もうやだぁ…」
「先輩もうすぐですから、頑張りましょうよ」
三好と香は二人に案内され、例の魔方陣が現れた場所に向かった。
あの"御告げ"と言われたのが行われた場所はまだ生々しい状態で残っていた。
隙間に残っている粘土を見つけると里留は気持ち悪そうに青ざめ手を口にやった。
「オイコラロン毛、やるならとっととやってぱっぱとちゃっちゃとホイホイっと帰ろうぜ、俺吐いちゃう」
三好はまじまじとその大広間を観察していた。
隙間にある粘土を指でなぞりとり、じっと目に近づけた。
「三好さん、それは……」
香もわきからその粘土を覗いて眉をひそめた。
青緑色の粘土は至って普通の粘土にしか見えなかった。
「もしこれが人間の肉だって知ったら」
「えっ」
三好が呟いた言葉に驚いた香はピクリと動き三好の顔を見た。
「…冗談だ」
「ちょっと…脅かさないでくださいよ三好さん…」
後ろで騒いでいる里留に急かされ香はあの紙を取り出し、魔方陣があった場所の前に立った。
「…」
これからすることによって多くの怪物がここから放たれる。
香は当然躊躇して踏みとどまった。
「…うまく、いきますかね」
「…さぁな」
素っ気ない三好の言葉を聞くと香は安心したように息を漏らした。
僅かな静寂。
淡い光と共にガラスが割れるような音が辺りに鳴り響いた。
「燃やすんだ」
昨夜三好はライターを片手にそう話した。
「え、も、燃やすって…」
「言葉通り、あの道場ごと燃やす」
当然皆が驚いた表情をした。
だが、方法がないのも確かであった。
80という数が街に飛び出すほうが危険なのである。
四人は香の呪文が終わると同時にその場から駆け足で逃げ出した。
大広間を出て大きな廊下を、四人は二手に分かれて走り進んだ。
三好と里留、香と三次郎。
魔方陣の跡から漏れだした白い生き物たちは四人と同じように大広間を飛び出した。
「香さん、急ぎましょう!」
出口に向かって走り出す香は三次郎と共に灯油を撒きつつ腕を精一杯振りながら走り続けた。
反対方向から逃げた三好達も同じように灯油を撒きながら裏口を目指し広い二階から下りるため階段に向かっていた。
この建物は外見とは裏腹に非常に内部構造が複雑になっていた。
おそらく信者がそう簡単に逃げられないようにだろうが、事前に内部を把握していない三好にとっては非常に不利であったし、里留も全てを理解しているわけではなかった。
「どけ!!ロン毛!!できれば死ね!!頼むから!」
「いいから黙って走れ!!」
脇の通路から次々と現れる生き物を避けながら二人はようやくこの敷地の庭に出ることができた。
そして二人とも入り口に向かって思い切りライターを投げつけた。
瞬間、火が一気に廊下を走り始めた。
「三好さん!」
二人が頭上から聞こえた声に顔をあげると二つの部屋から三次郎と香が別々に顔を出していた。
おそらく逃げる段階で追い込まれてしまったのだろう、ドンドンと壁を殴る音が聞こえる。
「早くしないと怪物が」
二階から地上への距離は凡そ2.5メートル。
三次郎ならそこから飛び降りることも可能であろうが。
「えっ、ちょっ、香ちゃん!!ムチャ!ヤムチャだって!!」
窓枠に迷いなく足をかける香にギョッとし、必死にそれを止めた。
「だってどっち道死んじゃいますもん!!えーいままよ!!」
「ああああ勇ましいけど香ちゃん!!」
そうこうしている間にも火の手はどんどん二階へと上ってゆく。
刹那、三好は咄嗟に香の下に走り出した。
三次郎が降り立つ音が鳴り響くのと共に、三好はしっかりと香を腕でとらえた。
やがて、道場は火にのまれてしまった。
…。
二十一
「三好さん、その、ありがとうございました」
逃げるようにして事務所に帰ると香は深々と礼をしてきた。
「…」
だが、三好はあまり浮かない顔をしていた。
どうもあの生き物は元来"化け物"ではなかったのではないか。
言ってしまえば三好はあれが人間のようにも見えてきたのだ。
三好はそれを警察署で見たときから薄々と感じていた。
しかし、この発見は決して喜ばしいものではなくむしろ絶望にも近かった。
少なくとも三好はそう見つめていた。
お前は人殺しなのだと誰かが自分を責め立てているとしか思えないのだ。
襲われる時に目に写る化け物は、殺そうと銃を向けた時、途端に人のなりに化けるのだ。
常に目の前のものを疑い、自分をも不確かなものとして見つめる彼は過去の自分と一対一。
身を震わせながらあの疑わない自分を睨み続けてきた。
同じ視覚的事実は、二人のなかでは全く別の真実を写し出していたのだ。
「あぁ」
三好はそれだけ答えるとまた自室に戻っていった。
…。
翌日、12月20日
朝早く三好はパソコンの前に座りマウスをゆっくり動かしていた。
「K」という者を覚えているだろうか。
三好は今回の一件が始まってから再びその人物と連絡を取っていた。
いや、正しくはあの北東接骨院に行った日、「K」側からメールが送られてきたのだ。
『風見さんは、生きています』
ただそれだけが綴られた文章だったが、三好には十分衝撃的だった。
『あなたは、一体誰なのですか』
それから間もなくして、来たもう一通のメールには、いつものように短い文でこう綴られた。
『あなたは、もう知っていはずです、三好さん』
あなたはもう知っているはずです。
あなたたちは、………。
二十二
「潜入!?」
朝食時に言い渡した今日の予定に当然ながら里留は身を乗り出して聞き返した。
魔方陣は一応全てを解除することができた。
だがしかし、これで全てが解決したわけではなかった。
「『5つの魔方陣の解除はあくまで23日の召喚を弱体化させるためのものである。当日の魔方陣を解除をする呪文は、別に記した』…だそうです…」
実質あと2日。その当日の魔方陣とやらを解除するための呪文はまだ見つかってはいない。
こうとなると大分危機的なものになってきた。
香は、先程からうとうととしている。やはり"疲れ"がでてきたのだろう。
いや、香だけではない。四人とも疲労は相当なものになっていた。
そのなかでまた新たな呪文を探さなければならないという事実はかなりのショックでもあった。
だが、三好には心当たりがあった。
例のお菓子会社である。
先日槻上からもらった紙と写真を取り出し机に広げた。
この会社リストは元々風見の部屋に張り付けてあったもので、おそらく彼が連絡を取り合っていたのでは、と三好は推測した。
となると怪しいのはこの中にいるはずなのである。
〈妙な趣味を持っている〉
そんな槻上の言葉を頼りに、三好はあれからずっとあの一社について調べていた。
おそらく、その中にいるであろう黒幕がなにかしら手がかりを持っているのだろう。
そう三好は考えた。
里留なにやらあまり腑に落ちない顔つきをしていたが、その写真を見ると「ははぁ」と苦笑いして三次郎に手渡した。
「どうかしましたか先輩」
「んん、いや、いつもの俺の勘だよ、勘」
美しすぎる女には必ず裏がある。そういって鼻で笑った。
二十三
この会社は地下を含め、9階になっており、社長室は最上階、つまりは8階にある。
近年、この会社はどうも赤字が続いている。
それを逆手に、うまい具合に社長に合うためにはそれ相応のうまい話が必要だ。
「ここに鳥塚教授に借りてきた"香り"がある」
「香りってー…お菓子とかに使うやつの」
「あぁ…、上手く事を運べるかといったら五分五分だが」
月光大学は研究したものを他社に提供していることもあった。
そのため、出始めに疑われる可能性は低い。
「…三好さぁ、仮にここの奴が黒幕だったらどうするんだ」
ふと、準備をする三好に向かい、里留はよそ見をしながら何気なく問いかけた。
三好はそんな里留を静かに見つめた。
里留も、黙っている三好に向かって冷めた目線を向けた。
「殺してやる」
月光大学の研究会名義でアポをとってもらい、三好らはそのまま応接室に案内された。
「なんだかお花が多い会社ですね」
案内される中、あちらこちらに色とりどりの花が飾られてあった。
香は少々疑問に思いながらも、きれいな花たちにしばし目を奪われていた。
「にしても多すぎて臭くね?ぶひぃくっさ…」
「そうですね…でも僕、花は大好きですよ」
三次郎の言葉のあとには静かな沈黙が走った。
さて、部屋に案内された四人は分厚い扉を開いてもらいあの長い金髪の美女の顔を初めて生で拝むことができた。
いかにも妖美に微笑むその顔に、三好も里留も内心顔をひきつらせた。
「あらぁわざわざありがとうございます、私が社長の山西と申します」
先程まで案内してくれた人物はいつの間にかフラフラと消え去り、その場には山西とその秘書の女性、スーツを着たもう一人の男性社員に三好ら四人だけとなった。
秘書の女性の方は山西とうってかわって非常に大人しめな、悪く言えば地味な雰囲気を漂わせていた。
丸眼鏡で俯いたままのその黒髪の秘書は黒いファイルを持ったまま山西の座るソファーの後ろにひっそりと立っていた。
「まぁお掛けになってくださいよ、どうせ暇ですのでごゆっくりお話ししましょう」
言われるがまま四人は座る。
香はまた大量に飾られた花を見つけたのかパッと目を一瞬張らせると不思議そうに見つめた。
「お花、お好きなんですね」
「えぇ、社内は華やかなほうが」
成る程、と香が微笑むと山西も赤い艶やかな唇を上げて微笑み返した。
だが、やはり里留はなにやら腑に落ちない表情をしていた。
「菓子会社なら、こういった粉が飛ぶようなものは置かない方がいいのでは」
「きれいに見えた方が、何かと評判もよいのです」
三好は落ち着いたように話してはいるものの、ムッとした様子は変わらなかった。
なにやら里留も含め、二人は腑に落ちてないようだったが、仕方なくその話はやめ、例の香りとやらを手渡した。
「あら、いい香りね」
借りてきた香りとやらを開いて手渡すとまず上品にその臭いの染み付いた紙ね臭いを山西が嗅いだ。
そのまま隣の社員に同意を求めるように渡すと、その社員もにこやかに笑って一つ、頷いた。
が、三好はその表情をみてさらに目を細めた。
男性社員がこちらに返すのを受け取ろうとした三好の手がピタリと止まった。
「?どうかなさいました?」
「本当にいい香りに臭うんですか」
匂いの染み付いたその紙を受けとると三好はそのまま紙を香に渡して匂いを嗅がせた。
「え、なん…くさっ!くさっ、なんですかこれ!?あ」
香はしまったといった顔をしたが三好は構わず話を続けた。
「たしかにこれはほどほどなら良い匂いなんですがね。…普段から嗅いでたら良い臭いかもしれませんけど」
里留も大分臭そうに鼻をつまみながら怪訝そうな顔をした。
ドンと構えている三次郎もわずかに方眉をあげている。
「なんですかやぶからぼうに」
「この臭いは嗅ぎすぎると幻覚症状やら感情操作ができる、そういうやつなんですよ。…あなたがた社員にとっては嗅ぎ馴れているみたいですが」
三好も少々臭そうに鼻を手で覆った。
山西はしらばっくれるように微笑みを崩さない。
「嗅ぎなれてると言われてましても、一体」
「あの花ですよ」
三好が指差す先には例の、たくさんの花が飾られた花瓶があった。
「ただの花ですよ、カモミールにカーネーション、みんな見慣れた花なのは見てわかりますでしょう」
「いいや、臭いのはそれじゃないです」
里留は鼻をつまんだまま目を細めて同じように花瓶を指差して話始めた。
「その中に紛れているあのベルみたいな形の花、あれはエンジェルトランペットっていう花で、匂いは良いけど一輪あたりの匂いが凄まじいんですよ」
里留が指差す先をよくみるとたしかに花瓶の中にひっそりとそのベルのような形の白い花が蕾を開かせていた。
見た目自体は百合科とも見間違ってもおかしくない出で立ちをしている。
「エンジェルトランペットは普通の花ですよ」
「アトロピン、ヒヨスチアシン、コポラミン…、たしかに少量なら日本でも鑑賞用として売ってますけど、基本的に成分はいずれも神経傷害を引き起こす強い毒性ばかりですよ…換気しましょ換気!」
里留はそれだけいい終えるとたまらなくなり近くにあった窓を全開にさせてわざとらしく大きな深呼吸をした。
「…この紙の臭いも、それと同じです。…何に使いたいのかはなんとなくわかりますけど」
山西は相変わらず微笑んだまま黙っている。
里留のわざとらしい呼吸の音のみが沈黙に響き渡っていた。
二十四
「…ま、お話ししましょうよ」
ようやく口を開いた山西は、ぼそぼそと秘書に耳打ちをさせると男と秘書を外に出るように指示した。
「…そちらの長身の方とお嬢さんも外に出ていただいて構わないですかね、なに、変なことはいたしませんよ」
三好も同じように二人を外に行くよう指示をした。
部屋には山西と三好と里留の三人になった。
「…いらっしゃると思ってましたよ」
今度の山西はいやらしい微笑みを浮かべていた。
陳腐なその言葉に三好は多少の苛立ちを感じたが、黙ってその様子を伺っていた。
「まぁ茶番はここまでにしまして。…私が黒幕とやらに思われているようですが、それは大きな間違いですよ。私はただの信者に過ぎません」
コツコツ、とヒールの音を立てながら背後の本棚に行くと一冊の赤黒い本を取り出した。
上品だが少し古くさい、その辞書のように分厚い本はずるりという音をたてて棚から引き抜かれた。
「12月23日に世界が滅亡する、これは私がたくらんだことでもなんでもなく全て決まっていたことなのですよ」
山西が開いて見せたその白黒のページには、黒いペンで描かれたひどくおぞましい、巨大な生き物が月に照らされて立たずんでいた。
二人はそれを遠目にしかみなかったが、一瞬寒気のような、恐ろしく神経が揺れ動かされる感覚を覚えた。
「私にはね、この神が乗り遷っているんですよ」
ずしりという音をたててその本は閉じられた。
山西は信じて疑わない表情で話を続ける。
「神がね、やれと言われるんですから私は一介の信者としてやるしかないじゃないですか、えぇ死ねと言えば死にますよ」
彼女は金色の上品なクルクルとした髪を揺らしながら、微笑みではなく腹のそこでふつふつと唸るような笑いを漏らした。
二人は何を各々に思っているか、ただそれを黙って聞いていた。
「逆に私は尊敬いたしますよ、世界をたった一瞬で狂気に変えるあの神を、私はその絶対的な権力や恐怖を信仰し続けて、そして認められた」
山西が狂ったように話す中、彼女の背後からムクムクと例の白い生き物が沸き上がっていた。
里留はぎょっとし、三好は息を飲んだ。
「ミヨシさん、」
急にその名を呼ばれ、キツイ眼差しを返した。
「あなただって、人を信じられないのでしょう、ならもう、人間なんてやめてしまいなさい」
三好はその言葉の裏に風見を感じた。
あの瞬間、あの時間が、自分の神経や心臓の鼓動を辿ってありありと甦る。
山西は光のない目でじっとこちらを見つめている。
「ココノエさんも、あなただって理解してるはずです、生き方はわからないまま、真実の重さも…でもミヨシさんとあなたは違う」
まるでその眼差しは妖しい世界へ招くかのようなものを感じた。
たくさん白い生き物がまるでたくさんの人間に見える、二人を怨めしそうに見つめている。
「あなた方ふたりはわかるはずです、たった四人で動いたってどうにもならないと」
三好の手は今にも銃を引き抜きそうに強く拳を握りしめていた。
その隣で、里留は不服そうな表情を浮かべていた。
「あの男、風見は今だってあんたらを信じてない、ずっとあいつが信じているのは復讐、大きなこの得体の知れない恐怖だ」
白い生き物がじわりと迫り、三好はとうとう銃をぬいた。
里留はそれを制するのに立ち上がった彼の肩を掴んだが、彼の、今までにない形相で奴を睨み付けるその瞳にただ怪訝な表情を浮かべながら黙っていることしかできなかった。
「すがってるだけのあいつにはこの神は大きすぎたんだ、ハハ、殺せるものなら殺してごらんよ、どうせ数日後にはみんな死ぬのだから!」
ガタガタと床が揺れるのを感じた。
白い生き物が二人を睨んで、あたりは山西の狂人のような静かな笑いに包まれている。
「くそ…くそ!」
その時、ガチャリと部屋の扉が開いた。
あの気弱そうな助手が、拳銃を向けてこちらに入ってきたのだ。
俯いてその表情は見えないが、彼女はただ静かに銃の引き金に指をかけた。
「お、オイ!!やめろ!!」
咄嗟に里留は止めようと声を張り上げた。
三好は握った銃をおろさない。
三好には、目の前のあの忌々しい死神のような女しか見えていなかった。
「ハハ!!いいぞ!!撃ち殺せ!!どうせみんな死ぬのだから!!私が最期をみとど」
バン。
弾が真っ直ぐ風をきって山西の額を貫いた。
再生停止ボタンを押したように彼女の笑い声と台詞がブツンと途絶えた。
「…調子ニ、ノルナ…魚ゴトキガ」
秘書の声はあの弱々しい先程までの声とうって代わり、まるで虎のごとく低い、化け物のような声でボソリと呟いた。
三好もハッとして、里留と同じように目を見開いて秘書を見つめた。
「…呪文ナラ本棚ニアルハズダ…勝手ニスルガイイ」
獣のような低い声でそう呟くと、秘書はそのままそこにバタリと倒れこんでしまった。
気がつくと、白い生き物もいなくなっていた。
二十五
あの後、なぜか山西の遺体は見つからなかった。
いや、遺体どころか、その存在さえも抹消されていた。
あの秘書や、男性社員も、駆けつけた警察さえも山西を知らなかった。
三好はこの現象に覚えがあった。
だが、それを証明できるものはどこにもない。
何だか煮え切らない、妙な感触で戻ってきた四人は、一先ず禍々しいあの本をそっと開いてみることにした。
「これは…一体…」
気味の悪い挿し絵と、大量の文字が犇めくその本は、怪しげな気味の悪い色を放っていた。
香の言葉どうり、得体の知れないその形のとりとめてない生物に、四人は思わず悪寒を走らせた。
怪訝そうにする三人をよそに、三好はパラパラとめくり続け、あの山西が開いていたページにたどり着いた。
相変わらず文字は訳のわからない異国の言葉であった。
だが、三好はある一行を見つけると、ぼそりぼそりと言葉を紡ぎ始めた。
「三好さん、読めるんですか」
驚いたように顔をあげる香に対して、三好は「いや、」と一つ否定をした。
「…ただ、知っている一文があったから、そこが読めただけだ」
あなた達はもう知っているはずです。
そんな言葉が頭に問いかけてくる。
「ピスキウムキャプサ。はこの中の魚。俺たちは魚だ。救いようのない」
「魚…?」
香の視線は三好と本を行ったり来たりしている。
三好は深怨のこもった虚ろな目で本をじっと見つめていた。
「皮肉か、…まぁそうだろうなぁ」
里留は横目で本を視界にいれながら嘲笑した。
その本は、今にも文字を震わせてうじゃうじゃと動き出しそうにも見えた。
「風見は、正しかったのかもしれない」
「バカ言え、俺は人殺ししてまで生きてたくないわ」
「あぁ、だから死んだ」
里留は呆れたように鼻から息を漏らした。
「なら風見はとんだ詩人だな、俺にはまったく理解できねぇよ」
香と三次郎は静かに、ただ哀れむようにその本を見つめていた。
三好は、ただただ虚しかった。
虚しいがゆえに、もはや彼を認める他、気持ちを押さえる方法が見つからなかったのだ。
「煙草吸ってくる」
無に近い感情ながらも、やり場のない虚しさだけはこうしてたまに顔を出してきて嘲け笑って、そして彼の心を蝕んでいった。
涙でも出れば楽なのだろうが、息が詰まり苦しいだけだった。
「…三好さん」
「ほっとけよ三次郎、またどうせ青くなって戻ってくんだろう」
「…しかし、先輩それはあまりにもひどすぎやしませんか」
三好が出ていった部屋で、またいつもの夜と同じく三人だけが残った。
三次郎はとりわけ怒っているわけではなさそうだが、三好が可哀想だといった言い方であった。
「…香ちゃんはどうなのさ」
急な里留の問いかけに、香は思わず「へぇ?」と声をあげた。
「ど、どうというと?」
「三好のヤローだよ、はっきりいってあいつは香ちゃんのことも俺ら二人のことだって信じちゃいない、どうしてそこまでしてやれるんだ、正直俺は香ちゃんがいなきゃもう帰りたい」
香は里留の言葉に少し戸惑ったのか視線をうつむかせてしばし黙っていた。
そして微苦笑の顔をあげると冗談のような口調で話はじめた。
「…前に、私は昔友達の付き添いでここに来たって言いましたけど、あれ嘘なんです」
二人はわずかに眉を動かした。
香は続ける。
「私がお願いしたんです。…私の父を探して欲しいって。私の家、母子家庭なんですよ」
「それで、三好さんは」
「正直嫌そうでした、まぁたしかに、こんな依頼大したお金にもなりませんし、ただの大学生のお願いですし…で結局その日は帰ったんですけどね」
へらりと照れ臭く頭をかきながら香は笑った。
「数日後、電話がかかってきて」
「ファッ!?みつけたの!?」
「私もびっくりしましたけどね、でもその代わり働け、ここで働けって言われたんです」
意外な展開に里留は今度は思わず目を見開いて声をあげた。
三好の女嫌いは里留も三次郎もどことなく察していた。
それゆえに、女性である香を雇うということはかなりの驚きだった。
「…なんで私が雇われたのかわかりませんけど、でも、三好さんは本当は優しいんです、きっと。私は知ってます」
まぁたしかにケチ臭いですけどね、と付け足す。
里留はしばし動揺していたがなぜか三次郎は目頭を押さえて震えていた。
「三好さんにも、父親がいないっていうのを後から知って、きっと哀れんでくれたのかなって。…でもとにかく、私は三好さんのせめてもの支えになりたいんです」
里留には、少々理解しかねる答えだった。
だが、理解できない理由も分かっていた。
「…とにかく、呪文探しましょ!!きっとここに載っているはずです!」
里留にも、香の姿は眩しすぎた。
「ところで、香ちゃんのお父さんってどんな人なの?イケメンなんだろうなぁ」
「えへへ、まぁたしかにそうですね。この町で医者をやってるんですけど、結構有名みたいです、湊っていう…」
「…え?」
二十六
「あーさぶ!!ちょうさぶい!!しぬぅ!!」
夜の公園でやかましい声をあげながら歩いてくる里留に三好はチラリと一瞬だけ視線を向けた。
「ムシスンジャネーヨ、おい、こら、呪文解読してるからハヨこい、ハヨ!」
「うるせぇよ、聞こえてる」
くわえた煙草を吐き捨て、靴で踏むと三好はベンチから立ち上がった。
ワイシャツ一枚にマフラーだけの里留は寒そうに足をじたばたさせて跳び跳ねている。
ふと、三好は足で踏みつけた煙草をもう一度見つめた。
「…やっぱり風見は正しかった」
「あ、まだんなことほざいてんのかよ、お前やっぱり頭おかしくなったんじゃねぇの」
里留は少々不機嫌そうに言い放った。
三好はまだじっと煙草を見つめ、足でほじくりかえしている。
「…そうかもしれないな」
「呆れた、香ちゃんが可哀想なこった」
「…だな」
煙草の葉が外側に飛び出す。
三好はそれを思い切り踏みつけて大きく息を吐き出した。
「あいつは、たしかに可哀想だ、俺はどうしても信じてやれない」
三好の声は自嘲するようだった。
その声に反応するように里留の表情は眉をひくつかせた。
「お前が雇ったんだろ」
「…あぁ、でも無理だ」
スッと、三好は顔をあげる。
「今でもあの朽ち果てていく風見の目が、ずっとずっと俺を見ている」
三好の息は浅かった。
とにかくなにかに怯えていて、そして戸惑っていた。
「どうしていいかわからない、完全に生き方を見失った」
里留と三好の間に風が通り抜ける。
真冬の音だけが響くその空間で、三好の瞳と里留の瞳が交差した。
「…もういいだろそんなこと。…どうせ、23日にはどうにかなっちまうんだから」
「…そうだな」
そうひとつ呟くと三好はスタスタと里留を通りすぎて事務所に戻っていった。
里留も戻ろうと、爪先の向きを変える。
「目、…」
ふと、里留は振り返って公園を見渡した。
目は、たしかにこちらを見ていた。
三好さん、といつもの明るくて眩しい声が背後から聞こえた。
話し合いを終えた三好はまたいつものように自室に隠ってしまっていた。
里留と三次郎は、明日のために早々と寝てしまった。
時計の針が刻々と明日に向かっていく音が三好の部屋には鳴り響いていた。
「すいません、まだ、起きてますか」
ドア越しに聞こえる香の声を、三好はぼんやりと見つめた。
短い言葉でわずかに返事をすると、香はそのまま続けた。
「…この間は、助けてくれてありがとうございました、道場で」
三好には、到底香の表情がわからない。
ただ、ドア越しに聞こえる声だけをぼんやりと聞いているだけだ。
香もあえて入ってくるようにはみえなかった。
ただ、素直な気持ちをいつも通りに述べているだけだった。
優しい声だ。
カランコロンとゆったりと揺れるような心地が僅かにした。
「ねぇ三好さん、明日はきっと晴れですよ、空が澄んでます、探索日和ですよ」
明日なんてもうすぐなくなる。
三好はそればかりしか頭に浮かばなかった。
「いらない情報だ」
「んーん、そんなことありませんよ、晴れてれば少しは探索だって気持ち良くできますよ」
果たして彼女は泣きながら話してるのか、それとも仕方なしに呆れたような顔をして話してるのか。はたまた…。
「三好さん、私は助手ですよ」
カタン、と扉に触れる音がした。
「私は、確かに過去のあなたを知りません、…けど今はだれよりも知ってます」
香はにこりと笑った。
「いつでも困ったら、私の手、つかんでください」
三好の手元にあった煙草の箱はいつの間にかぐしゃぐしゃになっていた。
「おやすみなさい」
と、一言。
声と共にゆっくり歩いて行く音が聞こえた。
「風見……」
詰まる呼吸を断ち切るように、その身をベットに埋めた。
二十七
二日後。
12月22日。
召喚の場所は、町の外れにある無人の屋敷とわかった。
「ねぇ桃子~今度ばっかしは俺もお釈迦だって~告白するなら今のうちだから、ほら、カモンベイベ」
鬱陶しく出勤の桃子の後ろを着いていく里留に飽き飽きしながらも、桃子は適当に聞き流していた。
「そんなこれから死にますみたいな人に告白したって意味ないじゃないの」
「んもぉー全部三好、三好のせいだわ…くっそ」
桃子は立ち止まると里留に顔を突き詰めた。
「さっくん、結局いつまでも本音言わないじゃないの、だったら私だって同じよ」
少々強い口調であった。
里留はキョトンとして自身の頭の後ろをさすった。
「桃子に言われたら、直さなきゃなぁ」
少し困ったように、里留は頷いた。
里留が戻ってくると、ようやく四人は例の召喚場所とやらに向かおうと足を踏み出した。
「…しかし、香さん、行く前にご両親に会わなくてよかったんですか」
三次郎に問われると香はまたいつものように目を丸くした。
「本来、香さんが行くのは危険なことなんでしょうけど…、僕らが全力でサポートしたとしても、もしもってことはあり得ますし」
その様子を、三好と里留も黙って横目に入れていた。
三次郎の言うことはもっともなのだ。
「…大丈夫ですよ、三次郎の力と、里留さんの医療技術、三好さんのハイパー推理と射撃があれば、もーどーんとこーいです!」
香のこの妙な自信は実際にその強大な怪物とやらを目にしたことがないからか、それとも、それは純粋なる信頼なのか。
だがこの四人の中で香は誰よりも揺るぎなかった。
「私が学んだ法学も、こんな大事件にはまったく役にたたないんです、せめて私にしかできないこと、やらせてください」
香は三人よりズンッと一歩大きく足を踏み入れてくるりと振り向くと指を天高く突き上げた。
「ほら!!今日は快晴です!きっと明日も明後日も!きっときっと空は続いてます!」
冬のうっすらとした雲が緩やかに青空を流れている。
明日があることが当たり前。
私のいる明日が当たり前。
そんなことはあり得ないのだ。
「甘ったれたこと言うな」
三好が少し離れた香に口を開いた。
「そのままずっと存在してくれるものなんてこれっぽっちも有りはしない、だから俺は一切の運命も信じたりしない」
コツコツと靴をならし、立ち止まった場所から彼女に近づいて行く。
「運命はその神様とやらが決めることだ。…俺ら人間は、人間らしく懸命に働けば、それで十分だ」
再度、今度は静かな口調で発した。
一瞬立ち止まった三好の瞳に、キラリ光る自分自身を香はたしかに感じた。
また、目をぱちくりさせた香だが、すぐににんまりと笑い、自身を通りすぎて歩いて行く三好を小走りで追いかけた。
「なんだか生意気だなあのロン毛、何様だぁ」
フン、と里留は鼻で笑って返した。
二十八
廃墟と化した屋敷周辺は、昼間にも関わらず妙な薄暗さを感じた。
周囲には木が茂っており、カラスが何羽もひゅうひゅう飛び交っていた。
日付は22日。
三好達は慎重に屋敷の中に入っていった。
「うっほぉなんじゃこりゃ!埃クサッ…くもねーわ…汚いだけだわ…」
里留のいう通り、廃墟としての風化のみで、あたりは人のいない屋敷としては少しきれいな気もした。
例をあげるならば、まさに埃を拭き取ったようなあとや、室内に残された家具を動かしたような跡がある。
果たしてこれが山西がやったものか、それとも別の誰かが潜んでいるのかは、分からない。
入ってすぐには大きな階段が真っ直ぐあり、それがさらに左右に別れている。
二階建ての屋敷で、その二階の廊下もギャラリーのようになっているので、部屋の数が一階からでも一望できた。
「…1、2…、上と下合わせて部屋は6つか…」
一階には二部屋、二階には四部屋存在する。
だが、一階の二部屋は風化したせいで壁が崩れ、入れなくなっている。
となると、必然的に二階を探索することになった。
軋む階段を注意しながら(特に三次郎は)上り、まず右側の二部屋を覗いた。
一部屋目、なにもなし。
二部屋目、古びた机と本棚のみで、これといったものはなかった。
左側の二部屋を覗こうとした時、一階から妙な音が聞こえた。
「…化け物だ…」
例の白い生き物の歯を軋ませる音が一階の一室からキリキリと鳴り響いている。
足早に四人は目の前の部屋に入ると、あの生き物にまだバレていないことを確認し、ホッと胸を撫で下ろした。
しかし、そんな安堵もままならないまま、四人はその入った部屋の様子に目を見開いた。
何もかもが真っ白なのだ。
先程まであった廃墟の汚れも一切なく、ただただ一面が白い。
「なぁにこれぇ…目に逆に悪っ…あれ、てか奥になんか」
里留が奥に一枚の紙切れを見つけそれをヒョイと拾い上げた。
『出たくない出たくない出たくない出たくない出たくない出たくない出たくない出たくない出たくない…』
「なぁにこれぇ!!」
ひたすら"出たくない"と書きなぐられたその紙切れに驚き、里留は思わずそれを放り投げた。
三好が再び拾い上げるとじっとその狂気のメモを見つめ考えはじめた。
ここにつれてこられた人間でもいたのか、いやしかしそれならば出たくないというのは妙だ。
三好がふと、ドアに触れようとすると、あろうことかドアがヒョイと彼の手から逃げたのだ。
「…!?ドアにたどり着かない…?」
それどころか、ドアはますます遠くなって行く。
三好だけでなく他の三人もだ。
「この部屋トラップかよぉ!!おいロン毛、どうにかしろ!!俺までおかしくなりそうだわ!!」
「お前はもとからおかしいだろう…、しかし…」
煽られるようにして三好はメモをもう一度見た。
"出たくない"
「出たくない、か…」
三好はひとつ息をつくと、ゆっくりとドアに向かって歩き出した。
一歩、二歩、三歩…。
いつの間にか三好はドアノブに手を掛けていた。
「出たくない、いや、なにもしたいと思うな、とにかくそうしろ!」
「えぇっ、ど、どういう…」
「いいから何も考えるな!」
三好に言われるまま、同じように深呼吸をし、ゆっくりと足を踏み入れはじめた。
ただ、一人を除いては。
「なんで俺だけ着けねぇんだよぉ!!!」
里留はひとり取り残され、床に手を着いていた。
「先輩煩悩が多すぎるから…」
「無になるってどういうことだよぉ!!俺始めっからすっからかんだっつーの!!あ、言ってて悲しくなってきた…」
とうとう里留は床に大の字になって寝転び始めた。
無になるという概念に囚われすぎるあまり、頭が混沌とする。
桃子に会いたいし桃子に会いたいし、あと桃子に会いたい。
「あぁあー働きたくないでござるー!」
ふとある憂鬱を思い出したのか、里留はそのままごろごろと転がり始めた。
すると、背中にゴンッという衝撃を感じた。
「あ、あれ…無に、なれた感じ…?」
「…」
いつも通り、ゴロゴロと転がったところ、里留はドアの目の前に到着していた。
二十九
三好には本来、信頼というものがないに等しかった。
家庭を裏切った、顔も知らない父の存在と貧乏な家庭生活が三好咲良という人間の内部を蝕んでいったのだ。
そこに、風見という出会いは実に偉大なものであった。
友人のいる彼と、根暗な三好とでは、まるで接点のないもののように思えたが、彼の家庭を知って、少年三好は僅に心の拠り所を見つけた気がしたのだ。
風見は可哀想な子で自分は不潔な中から生まれてきた子、そういう現実を知っていたが、それでも、厳しい境遇で生き抜く風見を三好はいつしか唯一無二の親友だと確信し、それを誓った。
例え裏切られたとしても、三好のなかで風見はいつまでも風見だったのだ。
そうして会いに来た。
三好は最後のドアを開けた。
「普通の、応接室みたいですね…」
辺りには手入れされているのか、古いながらも埃ひとつない本棚やソファーなどが置いてあった。
「これは、随分と骨が折れますね…」
本棚にはぎっしりと本がつまっている。
何かの手がかりがあるかもしれない、少々時間はかかるが調べようと、三次郎は手を伸ばした。
「はぁー、この量を…」
里留があんぐりと口を開けている間に三好も香も、本に手を伸ばし始めた。
あまり気がすすまないのか、里留はソファーの取っ手の縁に軽く腰をおろした。
ガチャリ。
変なスイッチ音と共に里留の尻の下のがめこりとヘコみ、ソファーとソファーの間が床を震わせながらごごごと開き始めたのだ。
「!?隠し部屋…!?」
里留は目をぱちくりさせ、自身の座ったところを見た。
「あコレスイッチ…まじか…ま、まじか…」
「先輩…!流石です!」
「いや、偶然つか…うん!!それな!!」
三好はパタンと本を閉じた。
「…行くか…」
偶然の産物にせよ、おそらく召喚の場所はこの地下なのだろう。
先は暗い。
持っていたライターをつけ、三好は地下へと続く階段に足を踏み入れた。
…。
暗い階段を手探りで下りてゆくことに、三好はどことなく彼との繋がりを手繰り寄せているような心地になった。
だが、あまりにも冷たいこの地下へと続く階段に虚しさと後悔も覚えた。
爪先にコツンと壁にぶつかる音がした。
ずるりとこけそうになる里留。
「扉」
ドアノブはひどく凍りきっていた。
ドライアイスでも触ったかのように三好の手にはビリビリと手を裂くような痛みが走った。
それでも構わず、多少顔を歪ませて一気にそのドアノブをひねり押し抜けた。
瞬間、生暖かい風が四人に向かい吹き込んできた。
「ファッ!?なんだここ…地下だろ…?」
青空が頭上一杯に広がっている。
人工ではない、紛れもなくそれは青空だった。
燦々と降り注ぐ太陽の光の下には広い草原がどこまでも敷き詰められている。
何よりも目についたのは奥に広がる金色の花畑だ。
「あれは…」
香が目を凝らすとピトリと一枚の花弁が額に当たる。
向日葵だ。
向日葵の花弁がヒラヒラと踊るように風に流され辺りに飛び舞っている。
ふと、後ろを見るとドアがない。
「三好さん…これ」
三好は足を踏み出した。
いつもより大きな歩幅が、彼の今の懸命さを表していた。
三好には向日葵の視線が痛かった。
三人も不気味そうにその花畑を見渡しながら後に続いて奥へと歩き始めた。
「…また奥になにか…木、ですかね…」
三次郎が目を細めて見つめた先には確かに一本の木が見えた。
そこに近づくたびに、三好には心臓を掴み取られるような、脳が揺さぶられるような囁きが、彼の身体中をぐるぐると駆け巡り始めた。
なぜ来た、なぜ来た、と。
三好の本能はそれへの恐怖をしっかりと感じ取っていた。
段々と足がふらつく。
すると、急に右腕を香に掴まれた。
「いきましょう、」
三好は、苦し紛れにか、その右腕で香の肩をポンと叩き返した。
そうして、ついに大木の根元に四人は足を止めた。
目の前の大木の葉は青々とした、夏の姿の木であった。
白い幹に、顔のようなものが。
いいや、人間の半身が一体化して貼り付いていた。
「おい、こいつ…」
まじまじと見なくとも、三好はそれが誰だかよく分かっていた。
「…どうするんだよ、…三好」
「…」
攻撃してくる様子はなかった。
だが、それは紛れもなく化け物だった。
もう、人間ではない、
きっと、23日になるとこの化け物は世界を食う本当の化け物になるのだろう。
息が詰まりそうな感覚で、香の手にある本を見つめた。
もう、声は聞こえない。
「香、本開け」
開かれた本は心なしか呼吸をしているようだった。
「…三好さん」
香はその文字を口ずさむ前に真剣な、そして少し怯えたように、三好を見つめた。
「三好さん、三好さんは、ずっと三好さんです…私の、先輩です」
香は、本を開いてスッと木に向き合った。
「これを唱えると、時空が少し歪む、らしいです…だから、その間、私は暫く動けません」
「任せてください、僕らがしっかり守りますから」
「ま、やんなかったとしても死ぬんだろうし、ちゃっちゃとやっちゃおうぜ、…三好いいのか」
最後に、三好はその化け物を見つめた。
目は伏せっている。
「…あぁ」
香の口から、聞きとれないような文字が飛び出した。
瞬間、青空が曇り始め、ごうごうと風がうなり出した。
化け物が、苦しみ動き始めた。
化け物は青々とした葉を揺らしながらもがくようにしてその枝を四人に向かって振り回し始めた。
3メートル近くある木がうなり声をあげる。
香はその間必死に呪文を唱え続けた。
彼女に向かって振るわれる大きな枝を三人は必死に払いのけて守った。
時々それが彼女をかすり、血がわずかに滲んだ。
呪文はなかなか終わらない。
素手や鞄で払うのには限界があった。
「こっれ…、もつかわかんねぇぞ…くっそ…」
三好も里留も三次郎も精一杯であった。
三次郎に至っては二人の倍はその枝を防いでいる。
そのせいで、三次郎の体にはあちこち血が滲んでいた。
三好は必死にその枝を止めながら、次第に今までのたくさんの人間的感情が沸き上がってきた。
今押さえるこの無機質な化け物の手を頬に寄せて泣いて微笑みたい。謝りたい。
君が、たしかに生きていたということを伝えてやりたい。
思えばずっと先を歩かれていた。
彼がやったことは、三好自身にもありえたことだったのかもしれない。
学生時代に助けられて以来、彼は少なくとも化け物なんかではなかった。
神様だった。
そして、唯一無二であった。
三好の目が次第に熱くなり始めた。
「風見…」
瞬間、わずかに枝の力が和らいだ。
丁度、香の口がピタリと止まった瞬間でもあった。
…。
三十
「あ……?」
里留の目の前には真っ白い見覚えのある天井が広がっていた。
「さっくん!?」
急に聞こえた声に目を右にやると桃子が目を丸くしてこちらを見つめていた。
「え!?桃子!?あ、ん!?ここ病院!?東方病院!?」
桃子が安堵のため息をつくと、今度はいつものようにキッと目を尖らせた。
心なしか、その眼は赤く潤んでいた。
「まったく!!心配させないでよ!!あんなとこで何してたのよ!!」
まだ記憶が曖昧な里留はあたふたしながら辺りを見回した。
ふと、枕元の電子時計に目をやると、日付は12月24日を示していた。
「明日が…きてる…」
「はぁ?…もう、よく分からないけど階段でずっこけただなんてやめてよね…お酒でも飲んで」
「おい!あれ、あれは!?三次郎とかロン毛とか香ちゃん…あいや、女の子!大学生の!」
訳もわからず焦っていると、里留の隣のベットのカーテンがシャッと開いた。
「……よう」
頬に湿布のようなものを貼り、頭には包帯が巻かれている、三好であった。
三好も、大分困惑したようにも見えたが、里留と同様立っては動けるようで、里留の隣のベットで眠っているのは香であった。
「…どういうことだよこれ…」
「……」
しばらくすると、頭に包帯を巻かれた三次郎が病室に険しそうな表情をして入ってきた。
「先輩、ちょっと…」
ただならぬ表情の三次郎に呼ばれ、里留は病室を出た。
「時空が、歪んだ…」
人一倍傷を負っている香は、わずかに顔だけを三好に向けながらうなずいた。
「あの本に、書いてあったんです…、呪文を唱えれば必ずどこかの時空が歪むって…」
香は申し訳なさそうに目を天井に移した。
三好はかける言葉が見当たらず、黙ったままであった。
そうして、しばらくすると携帯をとってくれと香に言われたので、三好は隣の引き出しにしまわれていた香の荷物の中から白いスマートフォンを取り手渡してやった。
疲労と怪我で香の言葉は少し拙かった。
ゆっくりと携帯を確認していると、三好のポケットからバイブ音が鳴り出した。
『もしもし』
「…なにやってんだよ」
仕方なく電話に出てやると香は嬉しそうに笑った。
「アハハ、病院で携帯はだめですよね」
「当たり前だ」
「アハハ」
香は携帯を切るとそっと枕元に置いた。
そしてまた天井を見つめながら口を開き始めた。
「三好さん、わたし、ひとつだけウソついてました、」
三好が黙って視線をこちらに向けると安心したように続けた。
「あの本には、まだ書いてあって」
香の視線が入り口から見える廊下に移る。
廊下には何人かの医師が行き来していた。
「あの本に、術者は呪文を唱えると、大切なものが消えるって」
「……」
「書いてあったのに、それがなんなのか、気づかなくて」
香は視線を天井に戻すと、次第に目を腕で覆いながらアァ、アァ、と声を漏らした。
「せっかく見つけてもらった家族だって、気づかなくて」
腕と顔面の間からとうとう水がこぼれだした。
「看護師さんに聞いたら、父は、ここにはいないそうです…私もどこのだれなのか、わからないそうです…そうです…」
口を大きく開けて香は懸命に話続けた。
それが三好には痛く辛くてならなかった。
「…お前は、よく今まで泣かなかったよ、おかしなやつだ」
三好は、香の顔を覆う腕をそっと撫でてやった。
一人の仲間も、家族も、自分さえも分からなくなった香は、ただ泣くしかなかった。
三好も、ただ泣くしかなかった。
三十一
あれから一週間がたち、香が退院する日になった。
香はしばらく三好のもとにいることになった。
あれから、彼女の両親も、奇妙な怪物も、もう見ることはなくなった。
そして風見優太も。
だが、せめて彼らを覚えている私たちが生きなければいけない。
でなければ本当に彼らを殺してしまう。
ある外科医はそう言っていた。
とにかくみんなわからないことだらけであった。
なぜ、彼女からなんとか存在している家族を奪ったのか。
愛すべき家族も親友も、全てはなくなってから尊いものとなった。
神はたしかにいるのか。
こうやって私たちから取り上げて、気づかせたいのか。
余りにも横暴だ。
しかし、気づいたならばそれをもう二度と忘れてはいけない。
里留も香も、皆が同じようにそう思い、そして各々に想いを馳せた。
冬晴れの空が余りにも皮肉だった。
だが、これが自分等が必死に掴みとった必然的、いや奇跡的明日なのだ。
なぜ、人は明日を信じるようになったのだろう。
必ずしも明日が訪れるだなんて、そんな保証はどこにもないというのに、地球は回り、日が昇っては沈むという流れを当たり前だと信じきっている。
もし、あなたが突然死んでしまったとして、明日が来なかったとしたら、人々はそれを"偶然"と呼ぶのだ。
しかし。
僕らが見た明日というものは、少なからず偶然なんかではなかった。
そう、伝えたい。
-----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
エピローグ
三好は花屋に来た。
この花屋にあった、季節外れの黄色い太陽が目に留まったのだ。
香の退院祝いに持っていこうか。
三好は店の主人を呼び、向日葵とあと数本取り繕ってもらうことにした。
「はい、ただいま」
短い緑がかった髪を中央から掻き分けた髪型をした主人。
年齢は、自分と同じくらいのように思えた。
「あはは、季節外れの向日葵もいいでしょう、うちはそれが売りなんです、店名通りに」
奥でモタモタしているバイトの男をどやしながら燦々と輝く向日葵と温かい色をした花々をクリーム色の包装用紙で包んでくれた。
サンフラワーという店名シールが貼られた花束。
三好は、最初は驚いていたが、すぐにホッとしたように、頬を緩めた。
「向日葵が、お好きなんですか」
主人はキョトンとしたが、いつものように無邪気に笑って「えぇ、大好きです」と返した。
「探偵さん」
店を出ようとガラス扉に手をかけた時、後ろから主人の優しく無邪気な声が聞こえた。
「ありがとうございました」
「…いえ」
懐かしい匂いを漂わせて、花束は街へと飛び出していった。
END
piscium capsa(後編)

