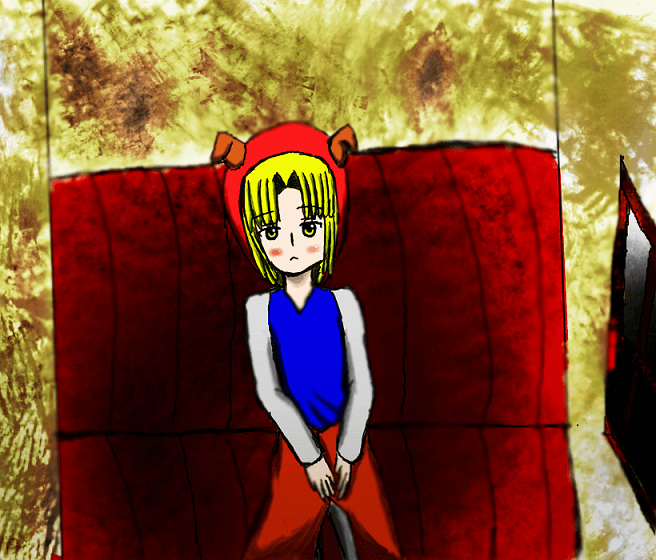
渡り蒸気機関車と猫の少女
オジン&オヴァン物語でギャグを書くつもりなので、こちらではシリアスを書いてみました(どこがだ)
不思議な雰囲気を感じたい人はちょっと覗いて見てください。
そんな方に気に入ってもらえるようなものを書くつもりです。(努力しますが…)
ちなみに、私は蒸気機関車について知識は殆どありません。描写も殆どありません。タイトルでここまでこられた方、本当にすみません。
盆に帰らない涙
ゴトン、ゴトン。
重量ある箱は、中に乗る住人を割れ物注意のように優しく気を使いながら夜道を駆ける。室内に漂うは哀愁か、歓喜の喜びか。
乗車車両の3車両目。
ゐリアは今日もこの蒸気機関車のこの車両にいた。
来るとも限らない、そんな人を待って。
…プシューッ
どうやら、次の駅に到着したらしい。
ゐリアはピクリと動いた。酷く湿気のある匂いだ。雨に打たれてそのまま来たような匂い。すうっと上を向くと中学生くらいの男の子が立っていた。
彼はゐリアに眺められている事に気が付くとそっぽを向いてしまった。
「あら、随分と早かったじゃない」
男の子はそれが自分に言っているのだと気付くのに1分ほどの時間を必要とした。キョロキョロした後、人差し指を自分の方に向けて首を傾げた。
ゐリアはクスッと笑い、頷いた。
「…仕方がないじゃないか。どうしようもない事だってあるよ」
彼は座席に腰を下ろして言った。ごもっともだ。
「ふふふ、そうね。その気になれば何だって出来るっていう言葉があるけど私はそう思わないわ」
うつむいた彼は、自分の意見に反論してきたり自分の考えを押し付けて来ないのだと安心すると、リラックスするようにイスに深く座った。
「俺だって、どうにかしたかったよ。でも動いても一種の解決は一種の問題を生んだ。それを繰り返すうち、嫌になったんだよ。…そうして選ばない事も選択であって、時と共にまた問題を生むんだって気付いた時、俺はこの道を選んだんだよ」
彼は深くため息をついた。
返事がないので彼は頭を上げた。ゐリアは話しに関心がないのか窓を見つめている。少し傷ついた。
「…その選択が他の問題を生むことは考えなかったのね」
さらに傷ついた。そう。この選択がまた大きな問題を生んだ事も分かっている。
解決の為に選んだ選択だった。
だけど、現実はそうじゃない。結局自分のために選んだ選択であって何の解決にもなっていないし、ただ苦しくて逃げただけだ。
結果、他の人にまた迷惑をかけただろうな。
「分かってるよ。…分かってる、と思ってたよ」
何だかかっこ悪い気がして目を瞑った。今度は関心を持たれないどころか無視されても良かった。この話はもうしたくない事だから。
だけど、ゐリアは今度は彼の目の前で車両の床に座って下から彼を見上げている。
「後悔してるの?」
「無責任だけど、ね」
彼はそう言うとそのままゐリアを見つめていた。
彼女も彼女で目を背けようともしないので、何だか気恥ずかしくなってこちらから目を背けた。
「大丈夫。あなたは選択した。それが正しいかは分からないけど、もうあなたはそれを考える必要はなくなる。だから、考えられる今のうちに後悔しておくといいんじゃない?」
ゐリアは向かいの席からそう言った。
「それって、どういう意味なの?」
彼女はイジワルそうにニンマリと笑った。
後悔なんて、したくないし考えたくも無い。それをわざわざ自分から考えろっていうのはどういう意味なんだろう。
考えている彼をゐリアは楽しそうに見ていた。何だか不愉快だ。そう感じた彼は横になった。視線は感じても寝れば反応もしなくて済むし視界にも映らない。
だがゐリアはわざわざヒョッコリと視界に入った。
「ねえ、イイモノあげるよ」
それはただの小さな鈴だった。少し小汚く、使い古されている。でも鈴についている紐のデザインは可愛らしいし、鳴らせば音もする。
これが一体何だって言うんだろう。
「お守り。私が苦しい時、大切な人からもらったモノよ」
「何で俺なんかに?大事なんだろ?」
ゐリアは少し悲しそうな顔をした。どうやら図星らしい。
なお更どうして俺に渡すのか分からない。
「これはね、大切な人がかけたおまじないがあるの。どんな苦境でもこれを握り締めて願えば超えられるってさ。…今度は、私が誰かを救う番だから」
それからも何とか返そうとしたが、彼女は最後まで断り続けた。最後は拗ねたりして、結局は彼が妥協することにした。
…静けさが戻ってきた頃に「ありがとう」と短く伝えると、向こうの席から「大切にしなきゃ殴りに行くから」と聞こえた。恐ろしい。
それからどのくらい経っただろう。
ゐリアはまた彼の前に戻ってきていた。
「…そろそろ、駅に着くわね。あなたはそこで降りればいいと思うよ」
「ああ。ありがとう」
彼はもう一度鈴を見た。
次は、本当にやり直せるのだろうか。
鈴を置いている手にゐリアは両手を置いた。
「大丈夫だよ。私のおまじない、強力なんだからね」
そう彼女が言い終えたあたりで、ブレーキがかかった。
彼の行く先の駅に到着したらしい。ゐリアとはここでお別れである。
「さよなら」
彼はそう言って出て行った。乗ったままのゐリアも同じ言葉で別れを告げると、手を振った。
…この駅で、入れ替わりに年配の男性が乗車した。
未来と過去のあべこべ物語
ゐリアは、外を見ている。
その老人は、しばらくするとため息をついた。
ゐリアは一瞥をくれたが、また窓の方を向き直った。
「何とか間に合ったな。全く、疲れちゃうな~」
彼は大きな独り言を言った。それが彼女の耳に届いたかは分からない。…しばらくすると、彼は再び口を開いた。
「お嬢ちゃん、随分と襲い時間帯に乗っているんだね」
ゐリアは少し眉をひそめたが、彼と向き合って座った。
でもうつむいたままだ。…さすがに気まずくなったのか、ゐリアも口を開いた。
「私はいいの。あなたも随分と遅い帰りなのね」
「ああ。ちょっと残業をね。私がいないと会社も上手く回らないんだよ」
彼はそう言ってハンカチで汗を拭いた。持っているバックには資料らしき物がずっしりとつまっている。返ってからも処理する資料だろうか。
「大変だったのね」
「ん?ああ、これか。うん。大変だよ。今日も、これからも」
彼はそう言って鞄の中をゴソゴソしだした。ゐリアはちょっと近くでそれを見ている。
やがて彼はごっつい財布を取り出した。その中から1万円を出し、ゐリアに渡した。
「お嬢ちゃんも大変だろうし、これで何か買いなよ。君もお年頃の女の子なら、多少の足しにはなるんじゃない?」
ゐリアはムスッとした顔でそっぽを向いた。彼は思ってもみなかった反応に驚いた。真面目な子なんだろうか。そして彼は…
「全く、人の善意が分からない子供だな!!俺が受け取れって言ってんだから黙って受け取ればいいんだよ!」
そう言放ってしまった。ゐリアはビクッとすると、怯えて端っこに逃げてしまった。
彼は頭を横に振った。…またやってしまった。
そう彼が思うのは言い終えたあとだ。仕事場でもそうしてしまう様に怒鳴ってしまった。
彼も本当は分かっている。こんな風なやり方では私生活も仕事も上手くいかないと。…だが、彼の人生はこうでなくては今の地位も家庭も築けなかったのだ。
それがあまり必要なくなった今でさえも、そのクセは治らなかった。
いつもそこで反省しては同じ事を繰り返している。この後も、いつもは本当は後悔しているのにここでもムスッとして周りを引きつけない様な雰囲気を出している。
そして次の日にはややリセットされたように出勤する。その繰り返しだ。
…妻にも、子供にも
今日の彼は違った。何がきっかけか、自分にも分からないのだがそんな自分が情けなくってうつむいた。両手で顔を覆い隠し、沈黙する。
遠くで隠れて見ていたゐリアが戻ってきた。
うずくまる彼の背中をさすった。
「大丈夫だよ。怖くない、怖くない」
ゐリアは何を言っているか分からなかった。自分が一体何を怖がっているというのだろう。それは分からなかったが、彼女は今の自分を許しているのだと思うと少し気が楽になった。
同時に、こんな子供に慰められている自分が情けなく思えた。
「ごめんな。怒鳴るつもりはなかったんだ。けど、お嬢ちゃんがそんな態度を取るのも悪いんだよ?」
またやってしまった。いつもの悪いクセだ。
こんな言い方だとまるで自分の非を認めずに相手だけを悪く言うように聞こえてしまう。
…特に最悪な事に、これは自分にも非があると思った時に言ってしまう自己弁解だった。今度こそは完全に嫌われて、帰りまでは誰とも話せないで孤独でいることだろうと思った。
「おじちゃんも大変だったんだね」
ゐリアは悲しげに言った。本当にこの子が何を言っているのか分からない。大変だったのは確かだが、あの返事からどうしたらこんな返事が返ってくるのか…
どちらかというと、心で思った言葉に返事が直接来たかのようだった。
思えば、大金を稼いでから家族を養った気でいた。
実質、十分に養っていたと思う。だけど、今はどうしてかそこにどこかほころびを感じずにはいられなかった。
そういえば、最近家族の笑顔を見てないな…
まだ出世もしてない頃。お金がなくても頑張って笑顔で俺の背中を押してくれた妻と息子。息子はまだ年が一桁の小さい小さい息子だったが、どんなに出勤が早くても「言ってらっしゃい」を言ってくれた。
どんなに帰りが遅いときも、妻に叱られても帰ったときは「おかえりなさい」を言っていた。
気が付けば、隣でゐリアは泣いていた。嗚咽をもらして泣いている訳ではなかったが、目からはボロボロと雫が滴り、頬を伝って落ちて行っていた。
自分では気付かなかったが、自分もすでに。彼女以上に涙を流していたのだ。嗚咽ももらしていた。
「うう、ううう。すまないね、お嬢ちゃん。見苦しいよね、すまないね…」
そして、彼はようやく思い出した。
最後に見た光景を。
地下駅に行く最中、どうしても時間が間に合わなくて横断歩道を走って飛び出した時の事を。急いでいて、見えなかった車の前照灯が自分の体を照らした事も。
「…そうか、俺は既に」
「…おじさん」
「次の駅かな。俺が降りるのは」
「…うん」
彼は体に入れていた力が一気に脱力するのを感じた。
行き先は、楽園か地の果てか…
どちらにしても、既に受け入れる覚悟はできているつもりだった。
やがて駅についた。ここでお互いにお別れだ。
だが、彼はいつもの仕事にでも出かけるようにして機関車から降車した。そのまま振り返り、ゐリアに言った。
「いってきます」
ゐリアは涙を拭き、今出来る最高の笑みを浮かべて言った。
「いってらっしゃい」
…やがて扉が閉まった。
今度も、変わりに誰かが入ってきたようである。
若い女性のようだ。とても元気がよさげで、電話が通じない事になにやらぶつぶつと文句を言っている様だ。
ゐリアも一度深呼吸して、彼女の席の向かいに座った。
遠くて近い何か
「ん?この車両、アンタしかいないの?」
その女性はごく普通そうにゐリアに話しかけた。
「そうよ。そんなにいっぺんに沢山の人は乗車しないわね。このあたりじゃ」
ゐリアはそう言った。給湯室からお茶を持ってきて女性に渡した。玄米茶は彼女の口に合うのだろうか。少なくとも出した本人は気にしてないようだが。
「やばくない?それってここの運営が上手く行ってないって事じゃないだよね?まああたしにはどうでもいいけど」
「あなたに心配されるようなモノでもないわよ」
…はたから見ると見た目年齢と中身が逆になっているように見える。ゐリアはかなり落ち着いた感じで接している。
彼女はしばらく携帯がいじれないので仕方なしに周りをうろついたり、車窓からの風景を見ていたりしていた。
確かこの子は友達に包丁で刺されて死んだんだったわね。
このタイプの子だと、何も教えないで降ろしてあげた方がいいのかしら?
「で、どうして私はここにいるのかな」
「あなたの帰り道で乗るんでしょ?」
「そうなの?あたしは確か友達に包丁でぶっ刺されて死んだと思ったんだけどね」
ゐリアは驚いた。自分が死んでいる事を、こう曖昧であっても気付く人は中々いないからだ。…こちら側の世界の質問されても答えてあげられる事も少ないし、話をそらす事にした。
「夢でもみたんじゃないの?その話が本当なら少なくとも病院にいるんじゃない?」
「はは、それはどうかな。意識がなくなるところから何まで覚えてるし」
…参った。ここまで覚えられていると話もそらしようがない。
「はあ。…そうよ。あなたの言う通りあなたは死んだわ」
女性はしばらくゐリアを見つめていた。それからしばらく考えるしぐさを見せると、何か閃いた様な顔をした。
「あ、ってことはあなた死神?私を迎えに来たの?」
自分が死んだのに軽いリアクションだ。意外でもあったが、騒がれないのは助かる。わりとゐリアは耳がいいからだ。
「迎えにあがったのは別の死神ね。死に方によっては部署も違うわ。運搬は私達がやってるけど」
女性は驚いて、それからゐリアをまじまじと見た。見世物ではないのだが。…それから彼女は近くに座った。
「現代の死神って布を被ってたり大鎌は持っていないのね」
「私たちの担当はそんなんじゃないわね。わりと地味な配役よ」
へぇ~、と話を頷きながら聞く女性。ゐリアは自分の分の玄米茶をすすった。
「死神ってどうやって生まれるの?」
「知らないわ。私は死後に志願して死神になったわ」
「え?どうして?」
ゐリアはその質問に対して、しばらく考え込んでいた。
言えない事だったり、言葉に出来無いと言うよりは自分でもあまり分かってない様子だった。
「変な死神さんね」
「あなたも十分に変わり者だけどね」
ゐリアはそこには即答した。女性は思わずどっと笑った。つられて何だか可笑しく思えたゐリアもクスクスと笑った。
「今度は私から質問させてよ。あなたは殺されたわ。しかも友達に。…普通は悔しかったり、うらんだり。悲しかったりするものだと思うわ。あなたはどうしてそう明るくいられるの?」
彼女は腕を組んで考え始めた。まあ、即答できるような答えではないだろう。
「う~ん。確かに悔しかったりはしたし悲しかったよ。痛かったしね。でも、そこまで殺意を持たれる程の事をしたんだな~って思うと何だか一方的に恨めないんだよね」
その言い方は、まるで昨日のテレビの内容を話すっていう感じだった。出来事自体にあまりこだわらない。
「でも、家族とか彼氏とか、友達と会えないのはとても残念だね…」
女性は力なく俯いた。実感が湧いてきたのか、その事だけが本当の気がかりだったのか、体が少し震えていた。
ゐリアは女性の背中をさすった。
「でも、それは死んでしまった私にはどうもしようがない事だしね。そうでしょ、死神さん」
ゐリアは頷いた。どんな未練であっても、死んでからではゐリアだってどうしてもあげられないのだ。だから、それは仕方のない事だと割り切るしかない。
ゐリアは死神を勤めながら自分の無力さを感じている所の一つだった。
「ねえ、死神さん。あたしはこの後どうすればいいの?」
まだ震えていたが、とりあえず話題を変える事にしたらしい。ゐリアもそれに気づいてすぐに返事を返す。
「次の駅で降りればいいわ。その後の事はそこで分かるし、私には分からないわ」
女性は頷いて「そっか」と言った。
それからはしばらく沈黙が続いた。お互いに何か話そうと思っていたが、話題にする程の事が思い浮かばなかった。
そうこうしている間に、駅についてしまった。
「ありがとう、死神さん。玄米茶、美味しかったよ」
「うん。あなたも達者でね」
二人は手を振っていたが、やがて蒸気機関車は走り出してしまった。…ゐリアには、女性の中にある何かが自分と似ている様な気がして、放っておけない気がした。
もしも彼女が転生したのであれば、何らかの方法で見守ってあげたい。そんな事を思っていた。
その時、ゐリアはすっかりと忘れていたがあの駅で乗客がいた。
ゐリアがその客を見た。
客も、ゐリアを見ていた。90代の、老婆だった。
希望のかかり火
ゐリアの全身に電撃が走った。
もう気が長くなるほどこの職務を全うしてきた理由が今そこにあったからだ。…この老婆は、ゐリアにとって、ゐリアにとって…
「ん?この車両はお嬢ちゃん1人かえ?」
ゐリアは目を吊り上げて老婆の前に座った。その顔つきから何まで、誰がどうみても拗ねている。
「私1人よ」
「ほっほ、そうかえ、そうかえ。で、お嬢ちゃんお名前はなんだい?」
ゐリアはますます機嫌が悪くなったようにそっぽを向いた。
しばらくするとポツリと「ゐリア」と言った。
「え?イクラ?」
ゐリアは顔を耳まで真っ赤にした。どんな感情が彼女の頭にめぐっての反応かは分からない…
「ええ、ええイクラよ!何とでも呼べばいいじゃないっ!」
ゐリアは席を移動して端に座った。きっと老婆は動揺しているだろう。
「ほっほっほ、相変わらずだねお前も。ミケなんだろう?」
ゐリアは目を皿のように開かせた。
そして老婆を真っ直ぐに見据えた。その眼は、真っ黒くてとても落ち着いていた。
「最初から、そうじゃないんだろうかって思ってたよ。人の姿をしてたって分かるよ。お前は家で飼っていた猫のミケだろう?」
ゐリアは目をキュッときつく閉じた。そして老婆からは目を背け、窓側を向いていた。
老婆からゐリアに近づき、ゐリアの背中をさすった。
「ごめんねえ、まだ現世でやる事があったんだよ。随分と待たせちまったねえ」
ゐリアは涙をこらえた顔で振り向いた。一生懸命に目を吊り上げているが、感情がこらえきれずにすっかり情けない泣き顔になっている。
その老婆の目からも涙が落ちた。
それが、ゐリアがこらえていた全てが決壊する最後のトリガーだった。
「おばあちゃんの馬鹿、馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿バカバカバカばかばかばか、うわぁぁぁああああぁぁぁぁああん!!」
ゐリアは力なく老婆を叩いた。老婆はゐリアを抱きしめながら、背中を撫でていた…。
自分の息子や娘が自立して家を去った。介護の必要はなかったため、彼女は家で過ごしていた。夫はすでに他界していて一人でいつまでも孤独だった。
息子や娘にはいつも変わらない様子で接していたから気付かれなかったようだ。
そんなある日、夫がなくなった日である。お供え物を一匹の猫が食べてしまった。
老婆は怒ってほうきで威嚇して猫を追い払ったのだが、その次の日も次の日も猫はやってきた。その猫がやせきっていて、日に日に弱っていっているのに気付いたのは3日後の事だった。
それからは自分の食べたものの残りの魚をあげたりしていた。自分の食べる分も段々と少なくなってはいたが。
それからは、猫と接するうちに彼女の中の孤独も薄れて行った。毎日が幸せだったわけじゃないが、共に過ごす日々はそれなりに楽しかった。
出て行った息子から同居を誘われたくらいの時だった。もとからもう年を取っていた猫は死んでしまった。
自分たちの墓の近くに埋葬し、老婆は息子と一緒に暮らした。
それからというものの、息子や息子の嫁。子供に囲まれて彼女はくらした。
この時は子供の世話もあってとても大変だった。
それも、孫の長男が中学にあがった夏の頃までだったが。
彼女が猫のミケを忘れた日はそれでも一日もなかった。
そうして、再び再開したわけだ。
ミケも、死んでからはこうして同じように死神と会話をした。どうにかして再開する方法を相談したところ、死神になれば可能かもしれないという話を聞き、彼女は何とかして死神になった。
それは容易な事ではなかったが、ただ彼女を待つためだけなら、何十年も待つつもりでいた。
その長い月日が、ようやく報われた…。
目的が果たされたからと言って、ミケが死神を止める事は出来ない。それは、本人も知っている。このためだけに転生の輪から抜け、このためだけに魂をあの世へ送り続けたのだ。
だから、ミケはきっと死神としての生涯の全ての分を、今という時の中で老婆に甘えた。泣いた。もう後悔することのないように。
彼女は転生してしまう。そうすれば、記憶は引き継がれない。
「ほほ、お前もバカな子だねえ、私なんかに会うためにあんなに長い時間を待ち続けたなんて。バカだねえ、バカだねえ」
老婆も涙を流しながら彼女に応えた。
やがて、機関車は駅に止まった。早くもお別れの時間である。二人は名残惜しそうに、機関車が動き出してからお互いに見えなくなるまでいつまでもお互いに見送っていた。
満願成就の夜。
再開した二人は、再び離れ離れになった。
ゐリアは、その後も機関車に乗りながら魂をあの世に送りながら、空を見上げることが多々あった。
…転生した老婆が、きっと同じ星空を眺めている事を思って。
渡り蒸気機関車と猫の少女
ここまで読んでくださった方、本当に有難う御座いました!
渡り蒸気機関車と猫の少女はいかがでしょうか。「蒸気機関車関係ないじゃないかっ」って言う方もいらっしゃるかもしれません。この場を借りてお詫び申し上げます。
m(_ _;)m
ちなみに、死神については完全に脳内設定です。私の頭の中ではただ魂をあの世に受け渡しに行く職業なんだと思ってます。なので、目的地まで移動するまでにちょっとお話をするタクシー運転手みたいな感覚ですね。
…与太話ですが、場所移動がなくて少し難しかったですね。
(・ω・;)
それでは、あとがきまで読んでくださった方、本当に最後までお付き合いいただき、有難う御座いました!
PS
またいつかゐリアは出てくるかもしれませんが、他の作品ではデレません。名前はゐリアかミケで登場しますが、どちらも本人です。


