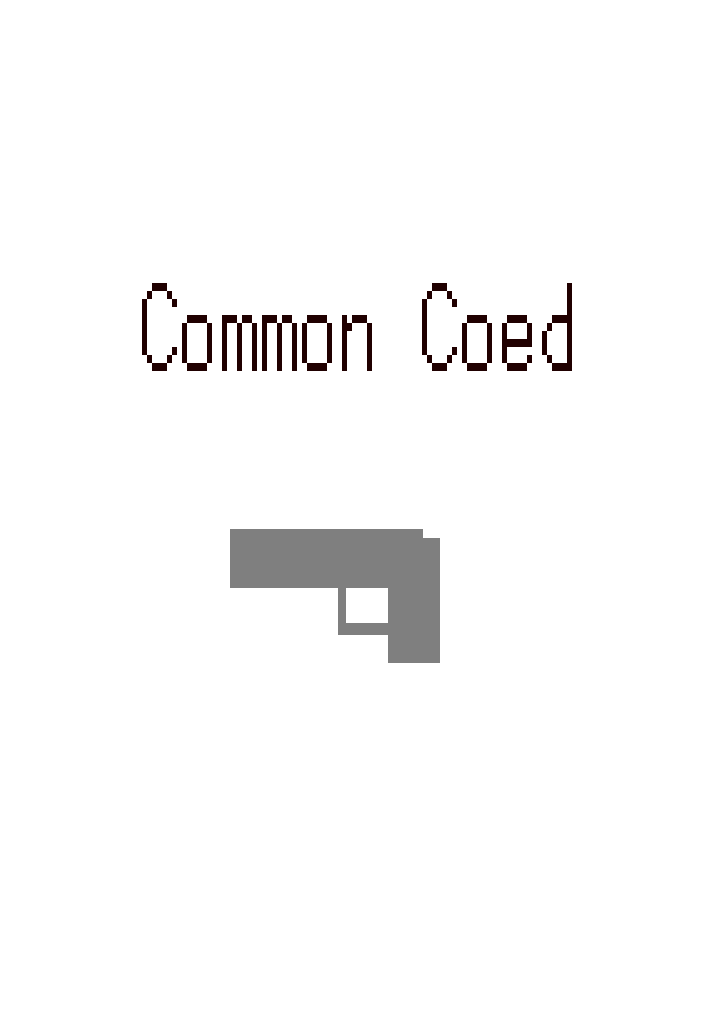
Common Coed
Common Coed
東欧の山中にリービッヒという国がある。
山と深い森と湖に囲まれた、静かな立憲君主国だった。
その小王国の、湖のほとりに建った王城の一角に、一人の少女が立っていた。
少女の名はシャリー・アグレル。十五歳。
シャリーは、消し炭だけとなった焦げ臭い空間を、呆然と眺めていた。
昨晩までは、自分の部屋だった空間である。
就寝中のシャリーの部屋に、何者かが火を放ったのだ。
「おやおや、これはひどいザマだね」
シャリーは声のする方向を振り返った。
痩せぎすの一人の男が立っている。
アンジー・アグレル。
この国の王弟であり、シャリーの叔父だった。
「リービッヒの姫君にして未来の女王陛下のお部屋に火を放つなどとは……大胆な人間もいたものだよ。怪我はないかね?」
「幸いにして、軽いやけどぐらいですみました」
「そうか、それは結構だ。しかし、不思議なものだね。我が国は革命が起きるほど政治経済的に困窮しているわけでもなければ、テロリズムの標的になりうるような大国家でもないはずだが……」
シャリーはくるりと向きを変え、歩き出した。
「部屋を眺めるのはもう終わりかね、シャリー?」
「ええ。叔父さま一人でごゆっくりどうぞ。……昨夜の火事は、叔父さまにとっても『残念』なことでらっしゃったでしょうから」
「……ははは」
アンジーは笑った。
シャリーは、足早に歩く。
歩きながら考えていた。
――以前から、両親と練っていた計画を実行に移そう。
この国には、もういるべきじゃない。
※
琺瑯大学文学部二年生、一条恵は、自室で寝転がっている。
四畳半一間の畳の上である。
季節は夏。
時刻は昼の二時。
蝉がけたたましく鳴いている。
蝉の音に混じって、玄関チャイムの音がした。
恵はゆっくりと立ち上がり、玄関口へと向かった。
ドアを開けると、一人の金髪の少女が立っている。
目は青い。
白人である。
年齢は十四歳ぐらいに見えた。
「はじめまして」
少女はお辞儀をし、のし袋に包まれたタオルを差し出した。
「隣の部屋に引っ越してきたものです。シャリー・アグレル」
「どうも……」
恵はタオルを受け取った。
「よろしくお願いいたします」
少女はまたお辞儀をして、去って行った。
恵はタオルを手の中で弄びながら玄関ドアを閉めた。
タオルを無造作に畳の上に放り投げた。
元の場所に戻り、また寝っ転がる。
蝉はじいじいと言い続けていた。
※
一条恵は畳の上で目を覚ました。
いつのまにか眠ってしまっていたようだった。
身を起こし、窓の外を見た。
既に空は暗い。
恵は腕に巻いている時計をちらりと見た。
七時半を指している。
彼女は立ち上がった。
夕飯を食べなければならない。
商店街へ出た。
行きつけのラーメン屋に入り、半チャンラーメンを頼んだ。
五分後に半チャンラーメンが来たので、三分でたいらげた。
五百八十円だった。
ラーメン屋を出た恵は、駅前の本屋へと入った。
本屋で雑誌を立ち読みしようと思ったのだ。
雑誌コーナーに行くと、一人の金髪の少女が、パチンコ雑誌を立ち読みしているのに気がついた。
昼間、挨拶に来た、シャリー・アグレルである。
シャリーは恵に気がついたようで、
「こんばんは」
と言ってきた。
「こんばんは。……パチンコとかやるの?」
「十五なので年齢的に無理です。ただ、私の国にはないので」
「ああ、そう。……そういや、『私の国』って、どこ?」
「リービッヒ王国です。ヨーロッパの山奥にあります」
「……ごめん、聞いたことないわ。私、地理に弱いの」
「大抵の日本人の方は、そうおっしゃいます。お気になさらなくていいですよ」
「そう?」
「ええ」
シャリーはパチンコ雑誌を閉じた。
「では、失礼します」
シャリーはお辞儀をして、その場を去って行った。
恵は、十五分ばかり立ち読みした後、本屋を出た。
自宅に向かって歩いた。
が、自宅にたどりつく前に、見過ごしがたい光景を目にした。
先ほど本屋で別れたばかりのシャリー・アグレルが、道端で、人相の悪い白人の男三人に囲まれていた。
「ふむ」
恵は、男たちとシャリーを眺めながら、その会話に耳をそばだてた。
「だから、一緒に来てくれりゃあいいんですよ。それだけで厄介ごとは全部かたづくんだから」
「でも、お断りします。私には、あなた方と一緒に行く理由がありませんから。……おじさまの思い通りになりたくもないですし」
「なら、仕方ねえや。無理にでもついてきてもらう。……おい、お連れしな」
シャリーと話していた男が、残りの二人に命令を下す。
二人の男は、シャリーの右腕と左腕をぎゅうとつかんだ。
「痛っ!」
シャリーは苦痛の声を上げた。
傍から眺めていた恵が、そこで男たちに声をかけた。
「そこのオッサン方。そういうことはやめなさい」
男たちは恵の存在に気がついたようで、ちらと彼女を一瞥する。
やがて、リーダー格の男が言った。
「どういうつもりだ、姉ちゃん?」
「もっかい聞きたいの? さっさとやめろって言ってんのよ」
「……おい、黙らせろ」
リーダー格の男は、シャリーの左腕をつかんでいた方の男に言った。
左腕の男は、シャリーの腕から手を離すと、手をぼきぼきと鳴らしながら、恵の方へと歩いて来る。
が、恵の目前まで到達した瞬間、彼は、
「うっ」
と呻いて、倒れた。
恵の金蹴りが、目にも止まらぬ速さで股間を強襲したのだ。
目の前の男が倒れると同時に、恵は、シャリーと、彼女の右腕をつかんでいる男の方へと走り寄った。
そして、右腕の男の顔面めがけて拳の一撃を見舞う。
男の体は吹っ飛ぶ。
恵は、シャリーの手を取った。
「逃げましょうよ」
シャリーはうなずく。
恵は、シャリーの手を引いて走りだした。
※
恵とシャリーは三十分ばかりの間、街中をやみくもに走った。
曲がれる角は全て曲がり、人ごみをくぐりぬけ、自分たちですらどちらに向かっているのかが分からなくなるほどにムチャクチャな道を走った。
やがて、人通りのない、恵ですら見たことのないような公園にたどり着いた。
人気のない、小さい公園である。
遊具は古びたすべり台とブランコがあるのみだった。
恵は、手をつないでいるシャリーが息を切らしていることに気がついた。
「あそこのベンチで休もうか」
シャリーは頷いた。
二人は、公園内にあった自動販売機で買ったオレンジジュースを飲みながら、ベンチに腰を下ろした。
無言の時が流れた。
恵は、シャリーに聞くべきことがあるのは分かっている。
あの男たちはなんなのか、とか。
そもそも、あんたはなにものなのか、とか。
とはいえ、シャリーに一息つかせてからでもよい、とも思った。
数分経って、シャリーはようやく呼吸を落ち着かせた。
それを確認し、恵は言った。
「ええと。私、あそこであんたを助けてもよかったのよね。多分」
「少なくとも、私にとっては大変に結構です」
「じゃ、次の質問。あの男たちって何者なわけ?」
「私のとある知り合いの部下です。彼は私を狙って……」
シャリーは最後まで言葉を言えなかった。
一人のむくつけき黒人の大男が、ぬっと二人の目の前に姿を現したからである。
身長は二メートルを軽く超えている。
「……こんばんは」
恵は大男に向かって手を振った。
そして、傍らのシャリーに聞いた。
「あの人も、あんたを狙ってるなにか?」
「多分」
「私が彼とケンカしたらどうなるかしら?」
「腕の一本を折られるぐらいですめば御の字でしょう」
「私が? あっちが?」
「恵さんが」
「……私もそう思う」
恵はそう言って、走りだした。
かなわぬ相手からは逃げるしかない。
シャリーもそれに続く。
恵たちが逃げた後。
公園に残された大男は、懐から携帶電話を取り出した。
「お嬢様を捕捉しました。……はい。ほどなくお渡しできるかと」
※
一条恵とシャリー・アグレルは、また数十分ほど街中を歩き回った末に、一軒の安食堂へと飛び込んだ。
「こういう場所の方が、案外とばれないもんよ」
恵は、席につきながら言った。
「それに、ここだったら、あいつらもむやみに襲いかかるってわけにはいかないでしょう、多分。……カレー二つください」
「確かに、下手に人気のない場所に行くよりはいいかもしれませんけれど」
「ね。……でさ、いい加減、聞いておきたいことがあるんだけど」
「どうぞ」
「あいつらは何者なわけ?」
「私の叔父の部下たちです。私の身柄を拘束したいんでしょう」
「……あんたの叔父って何者なのよ」
「リービッヒ王国の第二位王位継承者、アンジー・アグレルです。現国王の弟に当たります」
「そんで、その現国王ってのが、あんたのパパ」
「まあ、そうなります」
「で、あんたが第一位の王位継承者って感じかな? 話の流れ的に考えると」
「その通りですね」
「ふむ」
どすんと音がした。
女店員が、カレー二皿を、無造作にテーブルの上に置いたのだった。
「その叔父さんは、あんたを殺したいのかしら?」
恵はカレーをひとすくい、スプーンで自らの口に運んだ。
「ええ。母国にいる頃に、何度か暗殺されそうになりました、私」
「そりゃ、若いのに苦労するわね。……にしても、変だわ」
「なにがです?」
「そいつの仕業って分かってるなら、ばっさりやっちゃえばいいのに」
恵はそう言って、自らの首を切るようなジェスチャーをした。
そんな叔父は国王である親父の力で死刑にしてしまえばいいだろう、ということである。
「叔父の暗殺計画を立証するのも、逆に暗殺するのもなかなか簡単ではありませんよ。だから、父は苦肉の策として、私を秘密裏にこの国に『留学』させることにしたんです。当面の間」
「それで私のアパートに越してきたってわけだ」
「ええ。……ですから、これで平穏な日々が私にも訪れるかな、と、淡い期待をしてたんですが」
「その願いは虚しく散ったって感じね」
「ですね。叔父さんには露見していたみたいです」
シャリーはため息をついた後、カレーをすくった。
十数分後、二人はカレーを腹に詰め終わった。
店内には二人と女店員と店主兼料理人の他には誰もおらず、ただ、つけっぱなしにされている小型テレビの発する音が流れているだけである。
地方局にチャンネルがあわされたテレビは、お決まりのたわいのないローカルニュース番組を流し続けている。
そのうち、テレビは、一人の西洋人男性を映しだした。
やせた面長の男である。
レポーターの声が流れる。
「こちらは、東欧のリービッヒ王国の王弟でいらっしゃる、アンジー・アグレル氏でらっしゃいます。アンジー氏は、とある用件のために、日本にいらっしゃったということでらっしゃいますが……」
アンジーと呼ばれた、面長の男が答えた。
「ええ。私はですね、愛する姪の行方を追って、はるばるこの国へとやって来たのですよ」
「姪ごさん、でらっしゃいますか?」
「ええ。私の姪にして、リービッヒ王国の次期国王であるシャリー・アグレルは、数ヶ月ほど前から、この日本に留学にやってきていたのですよ。見聞を広めるためにね。しかし、ここ一週間ばかり、その行方が分からなくなってしまっておりまして……多忙を極める兄の代わりに、この私が、姪の行方を探しに参ったという次第で……」
そこで、テレビにパッと、シャリー・アグレルの写真が映された。
「……写りのいい写真使ったのねえ。本物より五割増しで美少女に見えるわよ」
テレビを見ながら、恵はシャリーに小声で言った。
「私は元々あれぐらい美少女ですよ」
シャリーは真顔で答える。
「あんた、結構いい性格してるわよ」
恵はそう言いながら立ち上がって、店員に叫んだ。
「お勘定!」
カレーライスの会計が終わったところで、店員が、
「あの……お連れの方は、先ほどテレビの……」
と言った。
恵は平然とした顔で、
「私の家にホームステイで来てる子なんです。外国人って、芸能人と友達以外はみんな同じ顔に見えたりしますよね」
と、答えた。
店員は首をかしげたが、それ以上は追求をしなかった。
※
「で、どうしよう」
食堂の外に出るなり、恵はシャリーに言った。
「私としては、さっさと近場の交番にでも駆け込んで終わりにしようと思ってたんだけど、あんたの叔父さんがテレビに出ちゃったせいで、それも難しくなった感じだし?」
「……確かに。おまわりさんのところに行っても、あまりいい結果が待っていなさそうですね」
「そう。『交番に行く、おまわりさんが叔父さんに電話、あんたが捕まる』ってパターンが待ってるだけな気がするわ」
「……ですよねえ。打つ手なしでしょうか」
シャリーはため息をついた。
しかし、それに答えるかのように、恵は手を打ち、
「でも、ないわよ」
「いい手があります?」
「テレビ局に行けばいいのよ」
「あのインタビューをしていた場所に行くってことですか?」
「そう。それで、あのオッサンをとっちめてやりましょう」
「……すごく難しくありません、それ?」
恵はうなずいた。
が、うなずいた後に続ける。
「でも、私の頭じゃそれぐらいし考えつかないし。あんたは?」
「……右に同じです」
「じゃあ、そうしよう」
※
恵は、レンタカーショップで借りた赤いマーチで、国道を南下していた。
助手席にはシャリーが座っている。
「免許、持ってらしたんですね」
走りだしてから十分ばかり経ったところで、シャリーが言った。
「大学一年の時に、合宿でね。就職してからじゃ取りにくいし」
「免許取るのって、大変でした?」
「とりあえず、教習所の教官の悪口を言えって頼まれれば、二時間はそれで潰せるわ。私が一番嫌いだったのは、嫌味なメガネのおっさんで、教習日誌に女生徒と撮ったプリクラ写真をべたべたと貼ってて――」
恵はそこまで言ったところで、急激にハンドルを切った。
目の前を走っていたクラウンが、急ブレーキを踏んだからである。
あまりにも突然だったのでブレーキを踏んでも衝突を免れえず、恵はあわててハンドルを回転させ、横の車線に逃げなければならなかったのだった。
「ドヘタクソ!」
恵はクラウンに向かって悪態をついた。
それに対し、
「下手だからああなったわけじゃないと思いますよ」
と、シャリーが言った。
「あんた、あの車のバカドライバーをかばいたい理由でもあるの?」
「かばいたい理由はないですけど、ほら……」
シャリーはクラウンを指した。
人相の悪い男が一人、頭を出していた。
恵の見覚えのある顔だった。
例の、シャリーを取り囲んでいた三人組の男たちの内の一人である。
「ああ……急ブレーキはわざとだろって言いたいわけ」
「だと思いますけど」
「あいつら、これからどうしたいのかしら」
恵の問いへの回答は、窓から顔を出した男の行動によって示された。
まきびしのようなものを、恵たちの走っている車線にばらまいたのだ。
シャリーが叫んだ。
「恵さん、避けて!」
「無理言うなって!」
恵はハンドルを切ったが、まきびしを避けることは能わない。
ぱん、という音がし、軽自動車のタイヤはパンクした。
軽自動車は、しばらく惰性で走った後に、その移動を停止する。
「降りよう!」
恵はシャリーに言った。
シャリーはうなずき、二人は同時にドアを開け、車の外へと飛び出した。
幸いにして、恵たちの走っていた国道のすぐ横は森になっていた。
恵はシャリーの手を引いて、木々の中へと飛び込み、ひたすらに走る。
背後から、男たちの怒号が聞こえた。
※
恵たちは、森の中をがむしゃらに走った。
が、やがて、シャリーの疲労が限界に達したので、暗い木陰で休憩を取ることにした。
二人は木の根元に座り込む。
シャリーは、ぜい、ぜいと肩で息をし、ぐったりとする。
「大丈夫?」
恵が聞いた。
「生きてはいます」
「そりゃそうだ。しかし、まずったわ」
「まきびしを避けられなかったことですか?」
「あれは最初から避けるの無理でしょ。私が言ってるのは、車を借りたことの方よ。電車で行くよりは、見つかりにくいと思ったんだけどな」
「計算違いでしたね」
「まったくね。あいつら、多分、まだ私たちのこと探してるんだろうなあ」
「なら、同じ場所に長居しない方がいいですね」
「……立てる?」
「なんとか」
シャリーはそう言って、よろよろと立ち上がろうとする。
とはいえ、その足元はおぼつかない。
「やれやれ」
恵は、シャリーの体を抱きかかえた。
※
シャリーを抱いた恵は、辺りに気を配りながら、暗い森の中を進んだ。
なにしろ追っ手に気を配りながらなので、その進みは遅い。
物音がするたびに、木陰に身を隠しながらの牛歩である。
森の中を二時間ばかりさまよったところで、恵たちは、二人の人間の話し声に出くわした。
男の声だった。
恵は、シャリーを地面に降ろす。
そして、共に近場の木陰に身を隠し、声の方を窺った。
二人の男が、懐中電灯で辺りを照らしつつ、森の中を進んでいた。
「で? お嬢様とあの女は、本当に森の中にまだいると思うかい?」
「どっか遠くに行っちまった可能性があるって言いたいわけか」
「あっちの運がよければな。今頃、森を抜け出てどこかのドライブ・インで休憩中、なんてこともありえるぜ」
「だからって俺たちもそうするってわけにはいくめえ。まだ、もう少し探そう」
男たちの会話は、明らかに、『恵たちを探している』者たちのそれである。
つまり、彼らは追っ手であった。
懐中電灯の光の反射が照らし出した顔は、例の三人の男たちのものである。
ただしリーダー格の一人だけはいない。
「どうしましょう?」
シャリーが小声で恵に聞いた。
「二人か」
恵は少し、考えた。考えたあと、
「シャリー、音を立てないでね」
とだけつぶやいた。
男たちは、懐中電灯を振り回しながら、少しずつ進んでいく。
やがて、恵たちの隠れている木陰を通り過ぎた。
恵は、男たちが通り過ぎると同時に、木陰からそっと出た。
二人のうち、後ろを歩いていた男の背後に近づき、その首筋に手刀を見舞う。
男は、「うっ」と叫んでその場に崩れ落ちた。
「なんだ?」
前を歩いていた方の男は、驚いて振り向き、恵の姿を認めると、
「てめえ!」
と叫んだ。
が、それとほぼ同時に、恵の飛び蹴りが、彼の顔面を襲っていた。
男は、地を舐めて気絶した。
恵は、男の持っている懐中電灯を奪って、男の姿を照らし、懐を探った。
持っていたのは、携帯電話、ナイフ、そして、拳銃である。
型式までは恵には分からない。
「撃たれてたらやばかったなあ」
恵はそう言いつつも、拳銃を奪い、ズボンのポケットにしまった。
木陰に懐中電灯を向け、シャリーに声をかける。
「シャリー、もう平気よ」
シャリーはおずおずと木陰から出てくる。
恵は、シャリーを自らの手元まで引き寄せると、言った。
「とりあえず、懐中電灯は使わないで進みましょう。こいつら以外にも、私たちを探してる連中がいるはずだし。……また、抱っこする?」
シャリーは首を振った。
※
恵とシャリーは、更に二時間ばかり森の中をさまよった後、やっとの思いで元の国道へと戻った。
「で、どうしましょう?」
舗装されたアスファルトの道を踏みしめながら、シャリーは恵に聞く。
「南に向かう」
「そこで、アンジー叔父さんに会う」
「そう」
疲れのためだろうか、二人とも言葉が少なくなっていた。
二十分ほど、国道をとぼとぼと南下すると、コンビニが見えた。
おあつらえ向きに、フードコートが併設されているタイプの店である。
恵とシャリーは、なにも言わずに店の中へと入った。
無言のままに、恵は入り口に設置された買い物カゴをひっつかみ、店を歩き回りながら食べ物をぶちこむ。
シャリーもそれについて歩き、手近な食べ物を投げ込んだ。
おにぎりや菓子パンやスナック菓子やピスタチオを。
レジでの支払いをすませた後、フードコートに座り込んだ。
ジャンクフードを貪り食べた。
大半の食事をたいらげたところで、コンビニの自動ドアがうぃんという音を立てて開いた。
恵は、なんとはなしにドアの方を見る。
入ってきたのは、見覚えのある人間だった。
シャリーを最初に襲った三人組の男のうち、リーダー格であった一人である。
不機嫌なままに店内をのしのしと歩きまわり、棚の食物を物色している。
その様を観察している恵に、シャリーが言った。
「あの人がここに来たのは、私たちと同じ目的でしょうか?」
彼女もまた、男が誰であるかに気がついたようである。
恵は答えた。
「多分ね」
「どうしましょう」
「さっさと外に出ましょう」
恵は立ち上がった。
シャリーもそれに続く。
※
ジェマシー・ガンダンは、イライラしながらコンビニの中を歩いていた。
ガキと女は見つからない。
手下の二人は、森の中での捜索中に連絡を絶った。
腹が減った。
舌打ちを漏らさざるをえない。
ボスであるアンジー・アグレルは、この分では間違いなく機嫌を壊す。
少なくとも減給は間違いない。
怒りと不安のないまぜになった感情に包まれながら、アンジーは、パンと牛乳を買って、コンビニの外に出た。
フードコートは使う気にならなかった。
パンのビニールを破り、ほおばる。
咀嚼しながら歩き、歩きながら今後の方策を考える。
とにかくガキと女だ。
あいつらを見つけなければ話にならない。
しかし、再び森に戻ってしらみつぶしにするべきか、森を抜けた可能性を考えるべきか、はジェマシーには判断しかねた。
車に戻って、直属の上司であるレントンに電話で相談すべきかもしれない。
あの黒人の大男に。
ジェマシーはそんなことを考えながら、コンビニの駐車場に止めてある、自分の車まで歩き、ドアの鍵穴に鍵を挿した。
挿した瞬間、背後から首根っこをひっつかまれた。
体が地面へと押し倒される――。
※
「また会えて嬉しいわ、おじさん」
恵は、首根っこを掴んで組み敷いた男に向かってそう言った。
男は呆然としたまま、倒れている。
自分の置かれている状況を、いまひとつ把握できていないようだった。
「私たちに会いたかったんじゃないの? もうちょっと喜んでよ」
「……お前、なにをした」
組み敷かれた男は、しぼりだすような声で言った。
恵はそれに答えて、
「私とシャリーは、コンビニでのお食事中にあんたを見つけた。で、先に外に出て待ち伏せ。あんたが自分の車までてくてくと歩いてきて、鍵を挿した瞬間に――」
「俺に飛びかかったってわけか」
「そういうこと。そして、今のこのザマ」
「ちくしょう」
「……ま、命が惜しかったら、言うことを聞いてもらうわよ。ええと――」
「ジェマシーだ。ジェマシー・ガンダン」
「じゃあ、ジェマシーさん、この状態を他の人に見られるのは、お互いにあんまりみっともよくないわ。車に乗りましょう。……シャリー、ドア開けて」
三人は、ジェマシーの車である、黒いクラウンへと乗り込んだ。
「右ハンドル車は、外人のあんたには運転しにくいんじゃないの」
後部座席にジェマシーの体を押しつけて、ドアを閉めながら、恵は言った。
「素人じゃねえんだ、別にどうってことはねえ」
「プロって割には、私の方が腕っ節はマシなようだけど」
「ふん」
「ま、いいや。とりあえずは、出すもの出してもらおうかな。シャリー、ポケットとか、適当に漁ってくんない?」
「あんまり気が進みませんけど」
シャリーはそう言いながらも、後部座席に体を動かし、ジェマシーの持ち物をあらいざらいさらった。発見されたのは、拳銃、ナイフ、携帯電話、それにグラビア女優のピンナップ写真が入った黒い財布と言ったところである。
「手下が持ってたのと変わり映えしないわね」
「なにか特別なもんでも期待してたってのかよ」
「別に。……さてと。単刀直入に核心的な質問からさせてもらうわ。あんたらのボスが、どこにいるのかを教えてもらおうかしら?」
恵にそう言われると、ジェマシーは素直に話しだした。
「9チャンネル……だったか? ローカルテレビ局の隣に建ったホテルの最上階だ。ボスのアンジーはそこから指示を出してる」
「警備は?」
「屋上は貸しきって、廊下に警備の連中を配置してる。まあ、一国のVIPクラスへの警護としちゃ、そんなでもないな。自分が襲われる可能性なんて、大して考えるような状況でもあるまいし」
「叔父さんは、私と鬼ごっこをしに来ただけですもんね」
と、シャリーが言った。
「その通りですよ、お嬢さん。さっさとあんたを確保したあと、事故かなにかに見せかけて殺す。ボスは、それだけですむつもりしかなかったんだ」
「なるほどね。そういうつもりだった奴が相手だっていうなら、多少はこっちの勝利する確率が上がってきたってもんだ」
恵はそう言って、ポケットから拳銃を取り出した。
※
アンジー・アグレルは、ホテルの最上階にいた。
ソファに身を沈め、眼前に手を組み、いらただしくその指を動かしていた。
その背後に、黒人の巨漢――腹心のレントンが、微動だにせずに立っていた。
アンジーは、吐き捨てるようにレントンに言った。
「ほどなく確保できると言ったね、君は」
「……左様で」
「女と小娘だ。女と小娘だぞ。それを今もって確保できんとは、君の指揮にはあまりにも問題があるということだ」
「お言葉ですが」
レントンは低い声を発す。
「この国では、我々は思うようには動けませんからな。街中で銃を撃つのすら冒険です。人数もそれほどを動員できるわけではない」
「だからと言って……」
アンジーは反論しようとした。
が、レントンのゆっくりとした言葉によって遮られる。
「落ち着いて下さい、閣下。確かに『ほどなく』と申し上げた私の言葉は訂正の必要があるでしょう。しかし、別に閣下に危険が迫っているわけではない。大体、彼女たちが永久にかくれんぼを続けられるとお思いですか?」
「うむ……」
アンジーは言葉に窮す。
「娘二人がどれだけ逃げ回ったところで、閣下が日本でおくつろぎ遊ばす時間が多少長くなるだけのことではありませんか。どう転んでも同じことです」
※
恵はシャリーを後部座席に乗せ、ジェマシーをトランクに放りこんで、クラウンを走らせた。
国道を南下する。
今度こそアンジーの宿泊するホテルへたどり着こうという腹だ。
既に深夜といってもよい時間帯なため、走る車も少ない。
広い国道を、一台のクラウンがぽつねんと走行している。
「今だったら、同じことをされても大丈夫かもしれませんね」
シャリーが言った。
「それはつまり、こんだけ空いてれば、さっきみたいにまきびしをまかれても平気だろってことかしら?」
「そういうことです」
「避けるスペースだけあってもねえ。私、ルパン三世やハリウッド映画の主人公みたいなスーパードライバーじゃないんだから……おっと」
恵は、ガソリンランプが点滅していることに気がついた。
クラウンのガソリンが切れかけていた。
「なによ、あのジェマシーってヤツ。プロだって割には、仕事用の車をガス欠寸前まで放っておくなんて」
「コンビニエンス・ストアでご飯を食べた後に、ガソリンスタンドに入るつもりだったのかもしれませんよ」
シャリーも、ガソリンが尽きたことに気づいたようだった。
「ちぇっ……参ったなあ。どっかでガソリンを補充しないと、とてもじゃないけどあんたの叔父さんのホテルになんて行けないわよ」
「お金ないんですか?」
「さっき食事した時にありったけ使っちゃったのよ」
「無計画ですね」
「やかましい。……とりあえず止めましょう」
恵は車を、道路の左端に停車させた。
「シャリー、あんたはお金持ってないの?」
「散歩していただけなので、ほとんど……。カードも家です」
シャリーは首を振る。
恵はため息をついた。
「ここまで来てガソリン代が問題になるとは思わなかったわ」
「……恵さん、貯金かなにかないんですか? それをコンビニで引き落とせば、ガソリン代くらいは……」
「宵越しの金は持たない主義で。両親からの仕送りはもう底を尽きてる。深夜引き落としの手数料分もない」
「もう少し、もしもの時を考えて生きた方がいいですよ」
「ガキに人生の送り方について説教されたくないっつーの。……いいわ、もう」
恵はエンジンをかけ、アクセルを踏み込んだ。
クラウンが発車する。
「出ちゃうんですか?」
「国道に停めっぱなしじゃ迷惑でしょうが。とりあえず行けそうなところまでは走って、後は……」
「後は?」
「乗り捨てましょう」
※
しばらく走ったところで、国道を降りて、恵はクラウンを止めた。
車を降りて、夜の町を歩き出す。
シャリーもそれに続く。
「ジェマシーさんはどうしましょう?」
「まだぶちこんどくわ。ことが終わったら、トランクから出してあげましょう」
「私たちが殺されたら?」
「あのおっさんも運がなかったってことよ。一蓮托生ね」
恵は肩をすくめた。
二人は歩く。
既に国道を抜けて市街地に入っている。
辺りに大小のビルが立ち並んでいた。
「徒歩でどれくらいかかるんでしょうか」
歩きながらシャリーが聞いた。
「ここまで来れば、あと二十分もかからずに着くわよ」
十分ばかり歩いたところで、恵は、自分のすぐ後ろを歩いているはずのシャリーに対して「ほら」と言い、前方にそびえるビルを指した。
「あれがテレビ局。ホテルはそのすぐ近くに建ってるはずだけど――まあ、そばまで行けば分かんでしょ」
シャリーからは返事がない。
恵はシャリーのいるはずの場所、すなわち自分の背後を振り向き、見た。
一人の黒人の大男が、シャリーをはがいじめにして、彼女の口を塞いでいる。
シャリーは抵抗しようとじたばたともがいているが、腕力の圧倒的な差ゆえに無意味であるようだった。
黒人の大男を、恵は見たことがあった。
公園で出会い、かなわぬと見て逃げ出した相手である。
「お久しぶりね」
恵はそう言いながら、ポケットから拳銃を取り出し、男に向かって構えた。
「よせ」
男は低い声を出した。
「安全装置だったかは外してあるわよ。引き金を引けば弾が飛ぶ」
恵と男の間の距離は、わずか二メートル足らず。
「シャリーお嬢様に当てずに、俺だけに当てられるか?」
男は淡々と言う。
確かに、男がシャリーをはがいじめにしていることで、シャリーが男の防弾チョッキ代わりのような状況になっている。
「頭でも狙うわよ。あんたの頭、でっかいし」
「素人が思うほど簡単には当たらんぞ。それればお嬢様が死ぬ」
「じゃあ、私にどうしろってのよ」
「ガンを投げ捨てて逃げ出せ。家に帰れ。全てを忘れろ」
「そんで、あんたたちはシャリーをぶっ殺すんでしょ? で、アンジーとかいうおっさんが、なんとかいう国の次期国王になる」
「お前の人生には関係のないことだ」
「ここまで来たら、あるに決まってんでしょ。一生、そのことを思い出して寝覚めが悪くなるじゃない」
「一生がなくなるよりはマシだろう」
「爽やかな目覚めのない一生なんて欲しくもないわ。大体、私がここで逃げ出して、あんたたちが私をずっと見逃してくれるとも思えないわね。――少なくとも私の主観じゃ、この状況での私の行動は一択」
恵は銃口を男の頭に向けた。
「あんたにぶっぱなすことよ」
男は表情を変えない。
「その行動はお互いにとってリスクが大きい」
「死ぬ可能性が一番高いのはあんたよ」
「シャリーお嬢様かもしれんぞ」
「ん……」
恵は多少、たじろいだ。
元々、道端でシャリーに起こした義侠心がことの始まりなのだから、シャリーを自分の手で撃つような結末はごめんである。
といって、ここで銃口を下げるのが利口な手とは思えない。
男は言った。
「お前は度胸のいい女だ。拳銃を持っていた点も予想外だ。……ここは、お互いに会わなかったことにしよう。俺はお嬢様を放す。お前は撃たない」
「――シャリーを放しなさい」
「よかろう」
男は、シャリーへのはがいじめを解いた。
解放されたシャリーは恵の方へと走る。
男もまた、くるりと向きを変え、その巨体を揺らして走り去った。
恵は男の足元めがけて二発撃ったが、アスファルトをえぐったのみだった。
シャリーが言った。
「今のを撃つのは卑怯じゃないですか?」
「私があんたを放せって言ったら、あいつが勝手に放しただけよ? あいつの出してきた条件に応じるなんて、一言も言ってないじゃない」
恵は平然と答えた。
※
テレビ局の隣に建ったホテルが、恵たちの眼前にある。
豪奢な作りの入り口の看板には、『セントラル・ホテル』と書かれていた。
「ここが悪党の本拠地ってわけね」
恵は、堂々と正面玄関に向かって歩いた。
自動ドアが開く。
大理石の敷かれたホテルの中を悠々と歩き、フロントにたどり着いた。
「すいません。最上階の部屋、空いてますか?」
恵がフロントマンにそう聞くと、
「あいにくと満室になっておりまして」
「へえ。この不景気に結構ですね」
恵がそう言うと、フロントマンは案外と口が軽い男のようで、
「……外国のお客様が、貸切になさってるんですよ。とある国の王族の方がね」
と、『ここだけの話ですよ』とでも言いたげにささやいた。
「ふうん……一番いい景色を見たかったんだけどなあ」
「最上階のすぐ下でしたら、お二人様部屋はいくつか空いてございますよ」
「じゃあ、そん中のどれか……いや、非常階段に一番近いとこをお願いします」
「はは、非常階段を使うようなことなんて起きませんよ」
「そりゃそうだけど、近い部屋をお願いしても悪いことはないでしょう?」
「……ええ、ええ。もちろんです」
恵たちは、ボーイの案内で、最上階の一つ下の階の、端の部屋へと通された。
「ふう!」
恵はベッドに身を投げ出した。
「のんびりしてていいんですか?」
くつろぐ恵にシャリーが言う。
「まあ、確かに落ち着いてる場合じゃないかもね。明日チェックアウトするまでに、お金を用意しなきゃなんないし」
「そうですよ。私たち、お金なんてほとんど持ってないんですから……いえ、そうじゃなくて」
「敵の本拠地の真下まで来て、だらけてんのが気に食わないってんでしょ」
「そういうことです」
と、シャリーは膨れた。
「落ち着きなさい、お姫様。こういう時は頭を冷やして動いた奴の勝ちよ。……とはいえ、あんましゆっくりしてもいらんないか」
恵は立ち上がる。
窓際まで歩き、カーテンを勢いよく引っ張り、取り外した。
外れたカーテンを、びりびりと破り出す。
十数分後、恵は、縦に破ったカーテンを繋ぎあわせて作り上げたロープを持って、ベランダに立っていた。
夏場とはいえ、高層ビルの最上階付近となると、夜風が冷たい。
「今が冬じゃなかったことを感謝しなきゃね」
そう言いながら恵は、ベランダの東の端へと歩いた。
東の端に立つと、非常階段の踊り場が見える。
「――案の定ね」
踊り場には、はげあがった頭の、一人の男が立っている。
「見張りの人がいるんですか?」
シャリーが言った。
「うん。普通に登ったら撃たれてたわ」
恵は、カーテン製ロープの先に、拳銃をゆわいつけた。
その拳銃を重り代わりにしてぐるぐるとロープを回して、拳銃を男の頭にめがけて投げつける。
ロープの先の拳銃は男の後頭部に命中し、男はばたんと倒れた。
「撃った方が早いんじゃないですか?」
シャリーが言った。
「撃ち殺せばよかったっていいたいわけ?」
「……まあ、割とそういうことになりますけど」
「あんた、結構怖い子ね」
「叔父さんに何度も殺されそうになってるせいでしょう」
「なるほど。穏やかならざる年少期を過ごしたせいで、人命非尊重のおっかない子供が育ってしまったというわけね」
「かもしれません」
「……ま、それはいいわ。でも、今の状況で銃をぶっぱなすのは、二つの理由で得策じゃないわ。人命度外視でもね」
「なにかあります?」
「私は射撃なんか慣れてない。さっき黒人のおっさんに撃ったのが生まれて初めて。それに、下手に撃って音を立てたくない」
「なるほど」
「納得していただけたようね。さて」
恵は、踊り場に投げたカーテンロープをぐいぐいと引いた。
先端にゆわいつけられた拳銃が、踊り場を囲う鉄格子に引っかかり、ロープはなんとか固定された格好になる。
「切れないでくれりゃいいけど」
恵はロープに飛び移り、登り始めた。
彼女の体重で、ロープはぐらぐらと揺れる。
「下を見ないでくださいね」
シャリーが言った。
「え、なに?」
恵は、シャリーがいる方向――すなわち『下』を見てしまう。
遥か遠くの地面が見えた。
落下すれば、よほどの幸運に見舞われない限り死を免れえない高さだった。
流石に目がくらむ思いがした。
「……恨むわよ」
恵はまた上を見て、ロープを登った。
やがて、踊り場にたどり着く。
恵は踊り場の柵に身をよせ、下にいるシャリーに言った。
「よし。強度はOK。シャリー、あんたも登ってきて」
「……ここにいちゃダメですか?」
「私がいない間に、あんたの叔父さんの手下が、そこにあんたを殺しに行っても平気なら」
「…………その可能性、あります?」
「私たちがここに泊まりに来たことぐらいは、察知しててもおかしくないんじゃない?」
「………………登ります」
「下を見ちゃダメよ」
「……………………分かってます」
シャリーはカーテン製のロープをたぐりよせ、つかんだ。
数秒の逡巡の後、登り始める。
恵よりも遥かにゆっくりとした危なっかしい登り方ではあったが、しばらくの後に、シャリーも踊り場へとたどりついた。
「よし、よくやった、よくやった」
恵はシャリーの頭をなでた。
「やめてください、そういうの」
シャリーは恵の手を振り払った。
「怖かった?」
「当たり前です。死ぬかもしれなかったんですから」
「そりゃそうか。でも、『かもしれない』方が、確実にブッ殺されるよりはマシでしょ」
「ええ、まあ。……恵さん」
「なによ」
「恵さんって、なにか特殊な訓練でも受けてらっしゃるんですか? なんというか、あまりにも……」
「ああ、そういうこと」
恵はこほんと咳をした。
そして、シャリーに反問する。
「虎はなぜ強いと思う?」
「はあ。ええと……」
「元から強いからよ」
「なるほど。恵さんは虎ですか」
「そうそう」
「上手なたとえを思いつかれますね」
「パパの持ってた漫画のセリフよ」
と、恵は舌を出した。
立ち上がり、シャリーの手を引く。
「じゃあ、そろそろこの件は終わりにしましょうか」
アンジー・アグレルはいらつきと高揚の混合した気分でソファに座っている。
十分前から、足を揺らしながら黙りこくっていた。
が、それにも耐えかね、
「始末できるかな?」
と、傍らにいる黒人――レントンに声をかけた。
部屋には今、彼らしかいなかった。
レントンは、
「おそらくは大丈夫でしょう。姫様方が泊まった部屋に向かわせた私の部下五人は、それなりの腕利きです」
と、歯切れ悪く答える。
「おそらく? でしょう? 断定できないのかね」
「断定はできませんな。あの一条恵という日本人、何者かは分かりかねますが、なかなかやる」
「ふん。君の失態は目に余るぞ。部下は女二人にきりきりまい、君自身が出向いての先ほどの捜索も不首尾――雇うのではなかったよ」
「もうしわけございません」
レントンは無表情に頭を下げた。
アンジーは、淡々とした謝り方に余計に腹を立て、勢いよく立ち上がると、部屋の隅にある冷蔵庫まで歩き、開けた。
中からウィスキーを取り出し、レントンに向かって、
「割ってくれんか。指二本分だ」
と言った。
レントンは、
「私はバーテンとして雇われたつもりはありませんが」
と答える。あくまでも声に表情はない。
「いいから、作れっ。雇い主の命令だ」
「私にそれをやらせるのは、あまり上策ではありませんな」
「なぜかね」
「たとえば、私がウィスキーに氷を入れている間に、一条恵の襲撃があったとすれば、あなたの身を守る者は誰も……」
そこで、銃声が何度か鳴った。
部屋の外から銃弾が飛来する。
銃弾は部屋のドアを貫き、室内の調度品を破壊した。
「身を隠せ!」
懐の拳銃を取り出しながら、レントンが叫んだ。
アンジーは既に、ソファからずれ落ち、その裏へと隠れていた。
ドアが部屋の外から強烈に蹴られ、がたりと外れた。
一人の日本人の女と、金髪の少女が現れる。
一条恵とシャリー・アグレルだった。
「こんばんは」
一条恵が、拳銃を構えたまま部屋の中に踏み込み、言った。
そして、レントンの姿を認める。
「またお会いしたわね」
レントンもまた、油断なく拳銃を構えている。
お互いがお互いに銃口を向けていた。
恵が室内を見渡した。
「あれ? この部屋にも、叔父貴はいないのかしら?」
「いえ。叔父さんはここにいます」
シャリーが言った。
「ソファの裏に隠れてます。……ちょっと、ソファからはみだしてます」
アンジーは、その言葉に体を震わせた。
「そう。二部屋めで見つかってラッキーだったわ。……それにしても、貸切になってるはずなのに、親玉の部屋に二人しかいないってのはどういうわけ?」
「俺の部下どもは今頃、貴様らの部屋だ」
レントンが言った。
「ありゃま。そりゃ結構」
「どうやってここに来たかは聞くまい。今度こそ、俺とお前のどちらかが銃弾を喰らうことになる。……アグレル家の方々は、どちらもなんの役にも立たん」
レントンはソファの影で震えるアンジーを一瞥した。
が、すぐにまた、注意を恵に集中する。
今、部屋にいる中でレントンを傷つけうるのは、あの拳銃を構えた女、一条恵しかいない。
あとは、レントンと一条恵のどちらが先に、相手の体に銃弾を当てるか、という問題でしかなかった。
レントンは引き金を引いた。
引き金を引きつつ、近場にあった大きなテーブルの下へ転がり込んだ。
一条恵もまた、似たような行為を行っていた。
レントンに向かって撃ちながらも、横に転がり、銃撃をかわしていた。
――結果として、互いの銃弾は当たっていない。
しかしながら、レントンは勝利を確信した。
一応は遮蔽物の影である『テーブルの下』へともぐりこんだレントンと違い、一条恵は、ただ銃弾をかわしたに留まり、その身全てをレントンの前にさらしていた。
レントンは、一条恵に銃を向けた。
銃声が鳴った。
レントンの右手から血が流れ、拳銃が床に落ちた。
撃ったのは一条恵ではなかった。
シャリー・アグレルが、レントンに向かって拳銃を構えていた。
彼女が発射したことは疑いようもない。
「ジェマシーさんを捕まえた時に、拳銃をいただいておいたんです。撃ってみたら当たっちゃいました」
シャリーは言った。
射的場で的を仕留めたことを自慢するかのような呑気な言い方だった。
※
「さて、この二人を一体どうしようかしら?」
床に座りこんで震えているアンジー・アグレルと、その隣に座って右手の流血を抑えている巨漢の黒人レントン(と、彼は降伏した時に恵たちに名乗った)に拳銃を向けながら、恵は言った。
「この国のおまわりさんに言っても、逮捕はしてくれませんよね」
「上手く本当のことを説明できればいいんだけど、難しそうね」
「……なら、撃っちゃってくれます?」
「あんたにとってはベストかもしれないけど、私、無抵抗な相手を撃ちたくないなあ」
アンジーが突然叫んだ。
「頼むから命は助けてくれ、シャリー! これまでのことは全て謝る! 二度とお前のことを狙わせたりはしないから!」
「そんなの、信じられないです」
シャリーは首を振った。
「同感だ。金と身分を与えたまま放逐するなら、この男はまた、必ず同じことをするぞ」
こう言ったのは、レントンである。
「レントン、貴様! 主人に向かってなにを言うか!」
アンジーはわめいた。
「あんたからの報酬の支払いは、もう見込めそうにないからな。ならば主人ではないさ」
「くそっ……」
「だが、当面の命は助けてやろう、アンジー。一条恵、敗者からの提案がある」
「なによ」
「お前はこの男を連れて、成田空港まで行くがいい。この部屋の鏡台の引き出しに置いてある鍵が、ホテルの駐車場に停めてある、アンジーの車の鍵だ。そいつを使え」
「空港まで連れてってどうすんのよ」
「適当な国――できるだけヨーロッパと縁遠そうな国がいい――までの航空券を買わせろ。その後はパスポートと最低限の小銭以外は身ぐるみはいで、飛行機に乗せてしまえ」
「それでこいつとはグッバイってわけ?」
「その通りだ。言葉も通じない異国に放り出してやれば、こんな男は帰ってこれん。大使館のない国なら、小国のリービッヒなど誰も知らん。パスポートだけがあっても大した意味もなく、アンジーはただの男に落ちぶれるというわけだ」
「……で、私とシャリーがこのおっさんを連れて空港まで行っている間に、あんたはどっかに逃げるわけね」
「当然だ」
「あんたが得してばかりじゃないの」
「気に食わないなら俺とアンジーを撃ち殺せばいい。ただ、いい加減、俺の部下が戻ってくるだろうな」
「あー……私たちの部屋に行かせた奴ら?」
「お前のような女ならば、追加で五人を殺すのも簡単かもしれん。が、その後の始末は面倒だろうな? 俺の案を飲むのならば、互いに無事にすむわけだ。部下どもは『俺の』部下だ。俺を助けるなら攻撃はさせんと約束する」
「……よし、乗った」
恵は、アンジーに立つように促した。
アンジーは観念したように立ち上がる。
※
一条恵とシャリー・アグレルは、成田空港のラウンジから、一機の飛行機が飛んでいくのを見送った。
「あれが叔父さんの飛行機ですか?」
「の、はずよ。南米の、ええと……まあ、とにかくどっかの国に行くやつよ」
「考えてみたんですけど、叔父さん、本当に行ってくれてるでしょうか? 素直に飛行機に乗らないかも。なにかの言い訳を係員さんに言って空港を脱出して、自分の名前と顔が通じる日本のどこかに駈け込んだりとか……」
「頭がまともに働いてるなら、そうするでしょうね」
恵はあっさりと言った。
「じゃあ、まずいじゃないですか」
「まともに働いてるならって言ったわ」
「…………ああ、なるほど」
シャリーは、空港にいる間の、叔父の半死人のような姿を思い出した。
※
飛行機の中で、アンジー・アグレルは、呆然と雲を眺めていた。
シャリーが危惧したような行為は、空港にいる間、この小心者の頭の隅にも出てこなかった。
ただ、言われるままに航空券を買い、言われるままに飛行機に乗る。そうしなければ殺される。そうなるに決まっている。
――そういう考えに頭を支配され、それに従って体を動かすことしかできなかった。
アンジーは、今後の南米での、自分の人生へと思いを馳せた。
それが『人生』と言えるものになるかどうかを考え、アンジーの目の前は暗くなった。
Common Coed

