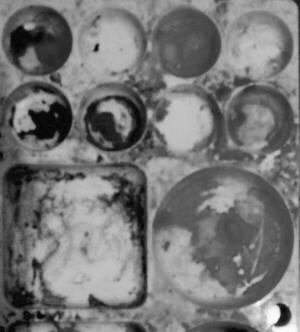青年と雪
コンクリートの道を歩き、帰路をいそいだ。あまりに寒かったのだ。
マンションへ向かう路地には人気がない。
まだ夕方にも関わらず、空は灰色だった。
頬に冷たさを感じ、空中を見た。この街には珍しく雪が降り始めていた。
フローリングにホットカーペットを用意した。いくぶん、エアコンだけで過ごすよりは暖かくなったように思う。
コンビニで買ってきたおにぎりを食べて、風呂に入って、テレビを見て、寝る。味気ないなと思う。僕は、この寒い季節を一人で越さなければならないことを身を持って実感していた。
朝食を食べ、働いて寄り道して帰って、夕食を食べて、風呂に入って、テレビを見て、寝た。朝食、労働、寄り道、夕食。
朝、ゴミ出しのために昨日食べたコンビニのおにぎりのビニールと紙パックなどを仕分けしていると、なんとなく妙な感じがした。
そのとき理由はわからなかったので仕事に行った。
仕事帰りにどこか寄ろうとするが、あまりの寒さにまっすぐ帰ることにした。ここ数日に渡って降り続いた雪は、すでに積もっており、足元を悪くした。この気候に慣れない都会育ちの僕は、とにかく滑って転ぶようなことがないよう、雪を踏みしめて歩いた。
帰ってひとりで夕食にありつくとき、僕はまた妙な感じを憶えた。僕は自分でコンビニで八つもおにぎりを購入していたようだ。いくら男とはいえ僕はこんなに食べきれない。さきほどまでそう思っていたはずなのだけれど、腹が膨れたころには全部食べ終わっていた。僕はいまじぶんで食べたのだろうか。不思議なことに自信を持って断言できなかった。記憶にないのである。
他のことを考えながら行動していると、実際にじぶんがそれをやったかどうか自信を持てないときがある。たとえば駅の乗換えなんかがそうだ。今日やらねばならないことなどの方に意識が集中していると、いざ現実に引き戻されたとき、あれ、今いるのはどのあたりだろうか、なんてことが、ままある。
今回のこともそういったものであろうと納得して、深くは考えず、風呂に入って、寝た。
朝起きて出勤、夕食、風呂、就寝。
僕は夜中に目が覚めた。明るいなと思った。電気を点けたまま寝てしまったようだ。
部屋を暗くしてから寝なおそうと立ち上がると、その先に白い生き物を発見した。色は真っ白で、背丈は僕の腰あたりまでで、目鼻口も何処にあるのかわからなかった。ユーレイを疑ってみたりしたが、実際にそれは生物であることがはっきりとわかった。たしかにそこに存在し、その質量は僕という存在に影響を与えていた。僕にとって、昔飼っていた猫が部屋にいるような安心と、感謝と、愛情に似たものを感じていた。
それは、ぼくの手前までくると、ベッドにのぼり、白くふわふわした形状は、こんどはアメーバのように変容し、くるりと丸まって、そのまま動かなくなった。僕はそれに触った。やはりそれは、確かに生きていて、丸くなったからだは静かに上下していた。
無機質な部屋にとつぜんあらわれた生命は、僕の寂しさに住みついた。
けれど、ほんとうにとつぜんあらわれたのだろうか。僕はむしろ、この生物がいなかった頃の部屋の様子が思い出せないくらいで、よく考えてみるとずっと前から夕食のごみは二人分出ていたし、僕はこの生物が部屋にいたことを忘れていただけなのだろうと思い始めた。
* * *
僕はその生物と、毎日を共にした。
起きて、朝食をとりながら、今日のニュースについて、話す。
といっても、僕が一方的に話しているばかりではない。その生物は、日本語を話せなかったが声は出た。言葉はまったくのでたらめのように思えたが、動物の鳴き声というよりは異国の人間が話しているのに近い印象も覚えた。
その言葉が何語にあたるのか、試しにその生物に直接聞いてみた。しかし、言葉がわからないから結局答えはわからなかった。
その生物の声は、決してコンピュータの音声のように乾いた声ではなかった。そこに存在する生物が発している、温度を持った声だった。
外は銀世界だった。真っ白な雪が積もり、更にあとからあとから降ってきた。路上に駐車してある車、マンションの塀、コンビニに停められている自転車のサドル、街路樹の枝、――さまざまな場所に雪は溶けることなく留まっていた。
僕は寄り道をせずに帰るようになり、夕食も二人分買って、テーブルで広げて食べた。
その生物は、コンビニで買ってきたおにぎりをちゃんとビニールをむいて自分のからだに取り込むみたいに消化にしていた。皮膚の表面が波打ったかと思えば、おにぎりは消えていた。その皮膚はアメーバのようでもあったが、同時にワニのような爬虫類を連想させるものでもあった。
夕食を食べながらテレビはあまり見なくなった。代わりに僕はその日あったことをその生物に語って聞かせた。
風呂にも一緒に入った。生物と一緒に入ると湯船の温度はちょうど良かった。
朝食、仕事、夕食、風呂、就寝。いままでと同じことをしているだけなのに、なにもかもが暖かかった。生物は、僕の生活には欠かせない存在となった。部屋にいるときがいちばん心地よい場所だった。
働くのにも、恋をするのにも、言葉というのは相手が本心で言っているのではないと気付いたときから、僕はできるだけ周りに合わせていたけれど、ずっと、疲れていた。こんなふうに感じるということは、僕も昔は、この生物のようなものだったのだろうかと考えたりした。
あるとき、この生物にも、死ぬときがくるのだろうか、と考えた。生物なのだから、死はきっと訪れるのだろう。僕はそのときを考えると怖くなった。
その白い生物に「きみは死ぬのか?」と問いかけてみたけれど、何を言っているのかわからなかった。イエス・ノーで解答できる内容ではなかったのだろう。ずっと何かを僕に話しかけていた。けれど僕にはわからなかった。僕は白い皮膚を撫でながら眠った。
* * *
朝食、仕事、夕食、風呂、就寝。ずいぶんと長い間これを繰り返した。
夕食どき、僕は奇妙な感じを覚えたのだけど、眠かったしそのまま眠った。
僕は朝食をとり、仕事へ行き、帰り道にコンビニで二人分の食事を買おうとしていることに気付いた。僕は、なぜ二人分買おうとしたのだろう。僕は一人暮らしだ。
けれど、僕はずっと一人暮らしだっただろうか。昨晩奇妙な感じを覚えたのも、誰かがいないことに変な感じを覚えたのではなかったか。
僕は思い出そうとした。けれどやっぱり僕は一人暮らしのはずだった。きっと長く一人身だから、寂しくて、感覚がおかしくなったのだろうと思う。
コンビニを出ると、もう雪はほとんど溶けてなくなっていることに改めて気付いた。そういえば数日前から少し暖かくなった。
僕はめずらしく、遠くにある白い雲を、子供のころのように、しばらくぼんやりと眺めていた。
青年と雪
2014.1月執筆。
2014.4月改稿