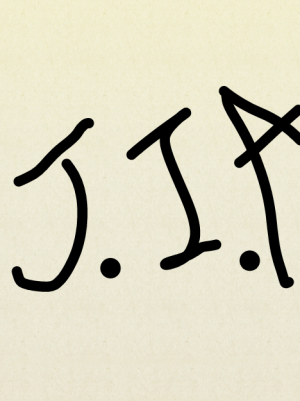アンシェ=アンシール=アルシカのラジオ
あの頃、私の住んでいる工場町で密かなブームを呼んでいるラジオ番組があった。
昼食の時間になると、地域住民は誰もが決まってこの局にチャンネルをあわせた。お椀形の湾岸一帯が巨大スピーカーと化して、地中海を飛行中の飛空艇にまで彼の声は聞こえていたという。
「みなさんこんにちはリビング・イン・セオフィールドのお時間がやってまいりました、今日は記録的な大雪の中からお届けしております。
こちらの窓の外は雪景色、旅行者のみなさん、今日は写真を撮っても地中海には見えませんのでご容赦を、越冬に来たシュピールたちも水の冷たさに凍えています。
全国推定一万人のバーリオ(バーリャ人)のみなさん、防寒対策はお済みですか?
鱗の生えている方は道端でうっかり冬眠しないように。
毛の生えている方は道端でうっかりはしゃぎすぎないように。
また、どちらも生えていない方はうっかり風邪を引かないようにご注意ください。
本日も楽しい音楽と昼食のひと時を、DJコバタとお過ごしください、では後ほど」
DJコバタさんの声が流れはじめると、セオフィールドの犬たちが尻尾を振ってはしゃぎだす。バーリオの彼は動物達に好かれる特別な声を持っていた。
そう、これはバーリオ、獣人による獣人のためのラジオ番組だ。ちっぽけな工場町で個人的に始められたのが、色んな局が放送しはじめ、今では全国にまで流れていた。ちょっぴり普通じゃないのがウケたのか、人間の中にもコアなファンがあらわれ始めているそうだ。
このラジオが収録されているのはジペンゼ州、セオフィールド市のとある歯車製造工場の奥だった。もともと人間の土地だった東部アーディナル大陸のど真ん中にありながら、工員の全員が西部の獣人たちで構成されているという不思議な工場だ。
私、アンシェ・アンシール=アルシカはそんな工場に住み込みをしていた女の子だった。身長一四七センチ、趣味は機械いじり。獣人たちの間を駆け回って仕事のお手伝いをしたり、社員食堂でDJコバタさんの昼食を包んで、放送局に持って行くのが日課だった。
そこの社員食堂はとにかく倉庫のように広くて、いつも動物くさくて賑やかで、さしずめ動物園だった。彼らの食事のマナーは至ってシンプルで覚えやすい、『人の食物は横取りしないこと!』たったの一行だ。獣人の中にはこのたった一行の命令も覚えられない、という種族も中にはいるので、壁にでかでかと張り紙がしてあった。
チョコ・ペーストを毛むくじゃらの手ですくい舐め、ナイフのような牙をかちゃかちゃならし、いつも机の下には食べかすと動物の毛が固まったものが散らばっていた。
私はそんな場所をくぐり抜けてゆかなければならない。本日のお弁当を包んでもらったら、誰かに横取りされないうちにすばやく社員食堂を出なくてはならなかった。裏手のドアを開けてすぐ正面、山際の広場に設置されたLIS放送局が目に入る。
鉄骨が組み合わさった塔に錆びの浮いた「LIS放送局」の看板があって、その天辺に、「隙間風? 防音? なにそれ、おいしいの?」と言った風情のボロ小屋があって、その上に台風が来たらあっけなく飛んでいきそうで、これがなかなか飛んでいかないしぶといアンテナが乗っかっている。これがブースだと聞いたら人間のDJはみんなぶっ飛ぶだろう。
終戦から十五年目、アーディナル復興期真っ只中の九二三年。獣人がこの地に移民として流れてきて間もない頃、この工場を経営していたスクルフ族の兄弟が独力で建てた《魔力通信塔》だった。その頃、遠い地からやってきた獣人が人間の社会になじむには相当な時間がかかり、多くの社会問題を抱えていた。そこで地域に住む獣人が悩みを相談できる専用ラジオ番組を制作しよう、という着想からすべては始まったらしい。
出来栄えはともかく、その心意気が私は好きだった。恥ずかしくてなかなか友達には見せられないけれど、ぶっちゃけ世界一の建物だと思っていた。
食堂から持ってきたお弁当箱を頭の上に乗っけて、異様に高い段差(一段がおへそぐらいまである)をよいしょよいしょの掛け声を出して昇っていった。
水蒸気で曇ったガラスの表面にぺたっと額を貼り付けると、ひんやりと気持ちのいいガラスの向こうに、音楽にあわせて右に左に腰を振る人影が見える。
人間専用のヘッドホンを頭上に掲げていて、その脇から白い狼の耳がぴょこんと生えている。体の構造は比較的に人間とよく似ているけれど、ヘッドホンは両手で押さえていなければならないのでいつも使いづらそうだ。それでも本人は至って陽気に白い尻尾をふりふり振っていた。
窓を叩くと、DJコバタさんの狼の顔が振り返る。
雪のように白くてふかふかの毛、まっすぐ私を見つめ返す紺碧の両目。私はこの狼顔のDJの為にとびっきりの笑顔を見せた。誰にでも見せる訳じゃない。
DJコバタさんは軽く手を挙げて挨拶すると、操作盤のつまみを下ろして曲のボリュームを下げ、机の上のマイクにピンク色の鼻面を近づけた。
「ただいまのリクエストをくださった防具の町ウッドロックのRN(ラジオ・ネーム)『強化武装Ⅱ』さんからのメッセージを頂いております。
『こんにちはDJコバタさん、最近はよく冷えますね。(冷えますねぇ)
私たちマッシュ族(トカゲの獣人です)は寒くなると動きが鈍くなるので、朝起きるのがとても辛いです。先週は急に気温が氷点下になったせいもあって、家に帰り着くまでに道端で冬眠をしはじめてしまった仲間が多いと聞きます。
冬期休暇まであとほんの少し。寒い日は家で一日中布団に包まって、ネコと遊んで暖まるぐうたらな毎日を送っています。DJコバタさんはこの冬をどのように過ごす予定でしょうか? よかったらぜひ聞かせてください!』
そうなんですよねー、爬虫類系の方は特に冬の寒さが問題なんですよねー。働く場所によっては冬期休暇をずらす事も出来ない場合が多いですし。ウチでは特に冷える日は早引きしもらったりしてますけど、それでも心配なので夜更けに道端で倒れていないかパトロールしたりしていますね。
ラジオではお見せで来ませんが、強化武装Ⅱさんからは可愛いネコさんの写真まで送って頂きました。なんとまぁ、お腹がでっぷりとしていかにも美味そ……いやいや、歯ごたえというか、喉ごし、とにかく、飼い主の愛情がいっぱい詰まってそうな可愛いネコさんですねぇ……じゅるり」
最後に彼がよだれを拭ったのは、太ったネコのせいではなかった。たぶん私のせいだ。
コバタさんは放送を続けながらも、窓の外で私が見せびらかしている本日のお弁当をじいっと見ていた。ズボンから突き出した尻尾をいまにも飛んでいきそうな勢いで振っていた。
「そう言えば、ウチは兄がうるさいからペットは飼ってはいないんですが、《ジトーノ》の女の子が一人いるんですね。これがやんちゃな子でしてねー。構って欲しい盛りなんでしょうかね。いま、窓の外にその子が見えていますけど。工員達に付きまとって、いつもイタズラばかりしてるんですよー」
「イタズラじゃない、お手伝いをしてるの!」
私が突っ込みを入れても、トークを続けているコバタさんの目は、もはや私が差し出したお弁当箱のカラフルな色彩しか映していないみたいだった。
調子に乗った私はミニトマトを摘み上げて、顔上からゆっくりと口の中に落とし込む素振りをしてみせた。
「ジトーノは少数民族なのでご存じない方も多いと思います。私もあまり知り合いが居ないんですけど、基本的にアーディナル人によく似ていますね。
目立った体毛は、髪ぐらいしかありません。ゴールドで額の髪が長くて、いつも両目が隠れています。寒い地方にあんな感じの毛むくじゃらな犬がいますね。そいつの背中に羽が生えた感じだと思ってください。
今も私のお弁当箱を見せびらかして、何か不穏な動きをしていますね。……ちょっと脱線していいですか。私の本日のおかずを中継いたしますと、野菜炒めに先ほどまで三つ子だった一つ子のミニトマト、うーん可哀想に。近海で採れたクルマエビが丸のまま五匹、今にも襲われそうな恐怖に震えながら入っています。
ベーコンエッグは六枚のサラミを惜しげもなく使った最高の出来栄え、黒胡椒がふりかけられていて、見てるだけで鼻腔をつんっと刺激されそうです。うーん、刺激されたい。
それを、うちのアンシェちゃんは? どうするの? ……あー、食べるの。へー、食べちゃうんだ。そんなにがっつり? いっちゃうの。好き嫌いしちゃダメよ。白身だけ綺麗に残すとかダメよ。
クルマエビはおいといてね。そうそう、それ。おじさん大好物だから。あ……あ……あ……あー、でもやっぱり食べちゃうんだ。へぇー。困ったなあ、困った食いしんぼさんだなぁ、ウチのアンシェちゃんは。……まー、ウチで暖を取る方法と言えば、やっぱりこれでしょうな」
DJコバタさんはマイクを引っ掴んでぶわっと毛を膨らませ、打って変わって獰猛な怒鳴り声をあげた。
「全工員に告ぐ! アンシェを捕まえた奴には賞金四十エルシャルンだ! 手段は問わない! 多少泣いていても気にするな! かかれーっ!」
彼が仲間を呼ぶ瞬間、私はより一層目を輝かせて喜んでいたそうだ。……そんなに意地が悪かった覚えはないんだけどな?
私は怒ったDJコバタさんも格好よくて好きだった。彼が遠吠えをすると、ディーグ湾一帯の犬達が遠吠えをはじめ、羊や馬は本能的な恐怖を覚えて震え上がった。空を見上げるとカモメたちがどこからともなく群れ集い、万華鏡を覗いたような鮮やかな編隊飛行を行っていた。
欄干から塔の下を見下ろすと、食堂の両開きの扉が開き、うおーという唸り声をあげて大小さまざまな獣人たちが溢れてくる。みんな顔なじみの工員たちだった。小柄な体を生かして早くも階段を駆け上ってくるネズミやイタチの工員たちもいて、私はすぐに逃げ場を失った。
けれども慌てる必要はなかった。なぜなら、私は飛べるのだ。手すりに両足をかけて、バランスを保ちながら立つと、ちょうど雪の降る広場を埋め尽くす工員たちが、毛むくじゃらの手を挙げて、B級映画のゾンビの群れさながらに私を待ち構えていた。
工員たちの平均身長は二メートル、向こうの屋根までおよそ五十メートル、《ジトーノ(有翼人)》の私にはなんと言うことの無い距離だ。背中に生えた短めの翼をめいいっぱい広げて、私は一気に電波塔から飛び立った。
*
鬼ごっこの終わりはとてもカッコ悪くて、びしょ濡れで、惨めなものだった。
調子に乗っていた私は工員達の頭上すれすれを飛んで、食堂の屋根にある風見鶏にしがみついた。風見鶏ごと三六〇度ぐーるんと一回転して、今度は屋根の端から下を覗き込んだ瞬間、とつぜん足場の雪が雪崩を起こして、私はまっさかさまに落っこちたのだった。
工員達の騒ぎ声は一瞬で笑い声に変わった。誰か笑う暇があったら私を助けてくれてもよかったのに、と苦々しく思うけれど、そのとき食堂の近くに居たのは寒くて出遅れていたトカゲやカエルの獣人たちばかりで、誰も雪の中に手を突っ込めなかったのだ。
数分後、雪の中から私を引っ張り出してくれたのは、結局コバタさんだった。
DJコバタさんの背中に負われながら、私は何度も「ごめんなさい」と繰り返し呟いていた。
呆れているのか怒っているのか分からないため息をついて、コバタさんは私を事務所まで連れて行ってくれた。
「帰るぞ。風邪を引いたら大変だ」
多分ひかないと思うのだけれど、コバタさんは私を気遣って家まで送ってくれた。こんな風にして、LISはしばしば中断した。
大切な番組が中断しても、コバタさんは何も言わなかった。「もう謝らなくていい」とも、「二度とするな」とも。
忠告されたところでそれに懲りる自信はなかったのだけれど、いつものコバタさんと少し様子が違った風に思えて、私は素直に謝るしかなかった。
「……ごめん」
心の中で何かを決意しているような、そんな気がしたのだ。
「お前がここに現れたのも、こんな雪の降る珍しい日だったな」
DJコバタさんはそう言った。私は急に不安になって、コバタさんの背中の毛を握り締めていた。
十三年前、今日みたいな雪の日に、セオフィールドの建物と建物の間に落っこちていたのが私だ。パトロール中のDJコバタさんが私の匂いをかぎつけて、発見してくれた。正確な誕生日はわからないけど、以来その冬の日が私の誕生日という事になっている。
私の羽はDJコバタさんに拾われた時点で半分ほど無くなっていた。肩甲骨あたりからにゅっと突き出した白い羽は、どうにかこうにか羽ばたけるといった程度にちびていた。
当然ながら、飛ぶのはかなりへたっぴだった。ジトーノは北部の高山地帯に住まう少数民族で、私はそれまで他のジトーノの飛行を見た事がなかったから容易には気づかなかったのだけど、実際の彼らは本当に優雅に空を舞っていた。
成人のジトーノの翼は一枚で体を覆い隠せるほど大きなものだ。二の腕ほどの長さしかない翼では、うまく飛ぶことはできない。たとえばさっき落下した時のように、空中でくるっと身を翻して着地することができない。私は工場内で何度も大きな飛行事故を起こしては、工員の人たちに迷惑をかけまくっていた。
私が引き起こした今回の騒動は一瞬で収まった。けれど、その話は工場のもう一人の経営者の耳にも入ってしまっていた。ラジオで大々的に騒いでいたのだから当然だろう。
私が事務所のソファでうとうとしている頃、マルハトさんが帰ってきて、その晩、DJコバタさんとちょっとした諍いを起こしていた。
マルハトさんは同じ狼の頭を持っているけれど、コバタさんとは対照的に全身の毛が真っ黒で、目つきも鋭い。しっかり者の印象を受ける人だった。事務所のドアを開けた途端に彼は怒鳴った。
「また飛んだのか?」マルハトさんは体をぶるるっと震わせて、コートの肩に積もった雪を落とした。「コバタ、お前がしっかり監督しておかないからいけないんだ」
外回りを受け持っているマルハトさんは、最近は滅多に工場に帰っていなかった。私に関する事は現場監督のDJコバタさんにすべて押し付けていた。それでも私が飛行事故を起こしたと聞くたびに出張から戻ってきては、コバタさんを叱り付けるのだった。
「兄さん、仕方ないんだよ。やっぱりあいつはジトーノなんだ。飛ぶのが本能みたいなものだよ、無理に押さえつけてはいけない」
「またお前はそうやって責任逃れをする気か。本能は押さえつけて当然のものだろうが。いいか、これ以上アンシェに無茶な飛行をさせるな。これは業務命令だ」
「たまにはあいつを好きなように飛ばしてやった方がいい。ディーグ湾にでも連れて行ってやろう」
「たまには? ディーグ湾だと?」
マルハトさんは、バーリオ特有の四本しかない指を彼に向け、きつく言いつけた。
「絶対に飛ばすな! 工場内の事故ならまだ目をつぶっていられるが、ディーグ湾ではアーディナル中の会社の飛空艇テスト飛行も行われているんだぞ。もし万が一、そいつらとの衝突事故などあってみろ」
マルハトさんは帽子とコートを事務所の片隅にかけて、いつものようにふんと鼻を鳴らしてデスクに着く。
「その時は、我々も苦情を聞かされるだけではすまんぞ」
そして、この話はこれで終わりとばかりに、メガネをかけて書類を広げ始めた。この人はいつもこんな感じなのだ。強引で、正論が好きで。
羽ペンでさらさらと書面を書きしたためるマルハトさんの前に立ち尽くして、あきらめ切れない様子のDJコバタさんは、肩をすくめて呼びかけた。
「兄さん、けどこのままじゃ何も変わらないって。考えたんだが、あいつにも同じ種族の友達が必要なんじゃないか? ジトーノにはジトーノの、同じ種族の連中にしか分からないルールがあるはずだ」
話を聞かずに席を立とうとするマルハトさんの前に、DJコバタさんは立ちふさがった。
「今後は私たちよりも、彼らから色んな物を学ばせないと。そのためには、アンシェが普通のジトーノと同じように、空を飛べるようになる必要があると思うんだ」
「飛ぶだって……?」マルハトさんは鼻の頭にぎゅっとしわを寄せた。「馬鹿馬鹿しい、これ以上危険を増やしてどうする?」
DJコバタさんは、信じられない事を聞いたといった風に目を丸くしていた。
「……飛ぶのが、危険だって?」
マルハトさんの目は、しばらくの間紙面から離れて弟の鼻っ面に注がれていた。
失言だと思ったのか、マルハトさんは渋い顔をして、すぐに視線を逸らしてどこかに移動してしまう。DJコバタさんはしつこく彼の後を追いかけた。
「おい何を言っているんだ、兄さん、昔の兄さんはそんなことを言わなかったはずだ」
「もういい、勝手にしろ、あいつを拾ったのはお前だ、最後までお前が責任を取ればいい」
そう言って、マルハトさんは事務所から出て行ってしまった。
「待ってくれ、兄さんはまだあの事故を引きずっているのか?」
ドアの向こうに去ってしまったマルハトさんを追いかけて、DJコバタさんは声を張り上げた。
「私だって飛ぶのは恐い、失敗したときの事を考えない訳ではないさ。けれど兄さん、一度でいいからあの子が飛ぶ姿を見てみろよ。アンシェは空を飛ぶとき、一番綺麗な目をしている。彼女は飛ぶ瞬間、何も恐れてはいないんだ。あの子にとって空を飛ぶ事は、鳥が空を飛ぶのと同じくらい自然な事なんだよ。兄さん、それが自然なんだ。私たちが昔の技術を取り戻せば、あの子を自由に飛べる体にしてやれるんじゃないのか!」
暗闇に溶けてしまったマルハトさんから返事はなかったけれど、DJコバタさんはずっと声を張り上げていた。犬の遠吠えがその声に何重にもかさなっていった。
「兄さん、もう一度空に挑戦しよう! 昔、飛空艇を作ってた頃のように! これは他の誰にもできない、私たちがするべき仕事だ!」
*
私がここに来る直前まで、つまりは十三年前まで、この工場は飛空艇の造船工場だったのだと聞いた。
まだ飛空艇開発が最盛期を迎えていた時代だ。造船工場があぶくのように生まれては消え、有能な技師は競うように積載量や速さの限界を追求し、時代の最先端を行く飛行技術が次々と開発されてきた。
しかし、それもたった一度の悲劇でひっくり返り、今はすっかり変わってしまったのだ。
獣人の工員たちの間で、今も語り草になっている技術者が居る。《ドックⅠ世》という、獣人としてアーディナル大陸で大きな成功を収めた最初の人物だ。
新聞や雑誌に彼の開発した新技術が公開されるたびに、幼かった頃のスクルフ兄弟は目を輝かせて喜んでいたという。私に当時の記憶はないけれど、古株の工員たちはみんな懐かしそうに教えてくれた。
けれども、飛空艇の最盛期を終わらせたのもそのドックⅠ世だった。着想に十年、開発に二年をかけ、満を持して空に浮かばせた巨大飛空艇、それが都市上空を飛行する途中、突然の強風に煽られて地上二百メートルの《霞の塔》に衝突し、乗船していた開発者ドックⅠ世を含め、千人近くの乗客が命を落とす大事故になったのだ。
DJコバタさんとマルハトさんはそこに居た。視察の為に現場を訪れていて、有名な飛空艇事故の瞬間を目の当たりにしてしまったという。
この事故の後、マルハトさんは突然飛空艇の開発をやめて下請け業に専念してしまった。その時もDJコバタさんとはさんざん口論があったみたいだけど、結局はコバタさんの方が折れたそうだ。それは決して感情的なものではなくて、誰よりも客観的に現状を見極めたがゆえの結論だったのだ。
ドックⅠ世の失敗で、飛空艇そのものに対する世間の信頼が大きく揺らぎ始めていた。
受注が急激に少なくなっていったのは当然、さらにその後、飛空艇の開発には政府から厳重な規制が敷かれるようになって、一隻の開発にかかるコストが倍以上に膨んでしまったのだ。
小規模な造船会社ではとても立ち行くことができず、ディーグ湾に無数にあった飛空艇開発工場は次々と閉鎖を余儀なくされていったのだ。
マルハトさんはこの経営危機の到来をすぐさま察知した経営者の一人で、工場を部品製造業に切り替えることでなんとか生きながらえてきた。
マルハトさんはいつだって理性的だった。だからこそ、今もこうしてこの工場が存続しているのだと言えた。
「けれども、やっぱりあの事故を見た時のショックがないわけじゃなかったんだな……」
DJコバタさんは受話器をぶら下げ、うな垂れてそう呟いた。
片っ端から営業先に電話をしてみたけれど、あの雪の日以来、マルハトさんが知り合いの営業先に向かった形跡はなかった。自宅にも工場にも帰ってきておらず、まったく連絡が取れなくなっていた。
兄弟は二人で一人だった。どんな時も理性的なマルハトさんが隣に居たから、DJコバタさんは後ろを任せて頑張れたはずだ。それがこんな形で兄弟が分かれてしまって、この先工場はどうなっていくのだろうか。
なんて感傷に浸ることはなかった。スクルフ族は結構ドライなのだった。
「でもまあ、兄さんが居なくなるのはいつもの事だから」
これからの自分の事を心配すればいいのに、コバタさんは心配そうに彼を見上げている私を慰めていた。
「さ、なんとか飛ぶ方法を考えようか」
DJコバタさんはいつだって自分の事を後回しに考えているような人だった。それが短所でもあり、長所でもある。
朝方近くまで航空魔法学の本を読んで勉強しなおし、現場監督とラジオDJはいつも通りこなしながら、工員達が帰った後も工場に残り、製図用の巨大な机を前にして図面を引いていた。
油圧式アームで定規を動かす、けっこう大掛かりな机だった。キャンバスも縦三メートル、横八メートルはある。元々は飛空艇の図面を引くためのものだ。この工場でそこまで規模の大きな製品はもう扱っていないのだけれど、ずっと大切に取ってあったのだ。
そんなあれこれがあって一週間、ラジオに変な手紙が届いた。
「では、次のお便りに参りましょう。おっ、わが町、工場町セオフィールド在住の、RN『飛行アビリティ』さんからのお便りです。
『こらコバタ、お前の作っている設計図ではダメだ、全然ダメだ。
これはわざとか? わざと飛行事故を引き起こしたいのか?
いいか、ジトーノは空を飛ぶための魔法を生まれつき身につけているんだ。何もかもを魔石でサポートしてやる必要はない。
そもそもお前、風魔法が何なのかわかって装置に組み込んでいるのか? 風魔法は要するにベクトルの向きを捻じ曲げる魔法だぞ。邪魔な方向に働く力を分散させるだけでも十分に事足りるのに、なんでわざわざ下向きのベクトルを上に向けるために五つも六つも石を並べる必要がある? いくらブランクが長いからと言ってジョークもほどほどにしろ。
いいか、鳥じゃない、魚のヒレをイメージしろ。ジトーノにとっての翼とは、魚のヒレに近い。これがないと、潮の流れに身を任せて漂う事は出来ても、自由に泳ぐことが出来ないんだ――』
……えー、飛行アビリティさん、開発チームに入りたいんだったら素直にそう言ってください。連絡待ってます」
謎の技師『飛行アビリティ』さんの助言がラジオで公開されると、リスナーから沢山の意見や問い合わせが寄せられた。
なぜスクルフ兄弟が義翼を開発しているのか、とか、無理せず政府の障害児養護施設に預けるべきだ、とか、アンシェについての事がもっとよく知りたい、だとか。ジペンゼ州の住民たちは、基本的に世話焼きが多くて、私のことはあっという間に話題になってしまったのだ。
この放送があってからというもの、私達の身の回りがにわかに変化しはじめた。話題を聞きつけて、報道局が工場に押しかけてきた事もある。
工場の敷地内に泥のついたバンで乗り付けて、マイクやら撮影機材やらを担いだクルー達がわらわらとたむろしていた。私の庭に勝手にやってきて、という感じがしてちょっとむっとしていたけれど、人間が結構多かったので恐くて近寄れなかった。
そのとき投影結晶で全国に放送された映像は、工員の一人が録画して今も大事にとってある。
ツナギを着た白い狼頭のおじさんが、のんびりと立っている。その太ももに、顔をうずめるようにして立っている身長一四七センチぐらいの女の子が映っている。前髪で顔を隠しているのは恥ずかしいからだ。
真っ直ぐ立っていられない感じでもじもじして、無意識のうちに自分のワンピースの裾をぎゅっと掴んでいる。
「この子がアンシェです」コバタさんはカメラに向かって足元の私を紹介した。「私たちはこの子の為に義翼の開発を行っています」
「義翼が完成したら、将来商品化などはできるのでしょうか?」
工場の敷地内にやってきたテレビクルーの質問に、コバタさんは単純な受け答えをしていた。
どういう経緯で私がこの工場に住んでいるのか、私はいったい何者なのかは、事前に話し合っていたため質問されなかった。
「一刻も早くこの子の翼を取り戻して、そして、同じジトーノと暮らしていけるようにしてあげる事が我々の目標です。そして」
今でも私の記憶に残っているのは、私の頭を優しく撫でているDJコバタさんの一言だった。
「一刻も早く、この子を本当の両親の元に帰してあげたいと願っています」
生放送の直後から、報道局には電話が殺到したそうだ。
アーディナル全土からひっきりなしにかかってきて、回線が一時パンク状態に陥ったほどだった。
後日、工場にやってきた局員に、工員たちが総出で対応していた。
「そんなにですかい?」
「里親になりたい、あの子は私の子だ、という件数だけで八百件近くある。中には『グレート・マザー』も居る」
「グレート・マザーって?」
「有名人がテレビに出演するたびに『自分の生き別れの子供だ』と騒いでいるおばさんだよ。この間は自分はリゲル=シーライトの母親だと言っていた」
「リゲル=シーライト?」
「憲兵団大佐だよ。ほら、やたら派手好きで最近よくマスコミを騒がせているあの人だよ」
「憲兵団大佐って?」
工員たちは工場の外の事にはあんまし詳しくなかったけれど、丁寧にメモを取って応対してくれていた。
本来ならDJコバタさんが応対していなくちゃならなかったのだけれど、そのときコバタさんはお腹に重たい駄々っ子を抱えていたせいで、それどころではなかったのだ。
取材があったその日から、私はDJコバタさんに子猿のようにしがみついて離れなかった。
今まで不安に思っていた事が形を成して、はっきりと目の前に迫ってきたせいで、私の感情は砕けてしまったのだ。
本当は私の事を重荷に思っているんでしょ。
いつか私を見放すんでしょ。
実際、私と兄弟との間に血のつながりはこれっぽっちもなかった。他所からの借り物だった。言ってみれば、他の工員たちと同じなのだ。お互いにいつも微妙な線引きがあって、私はただ同じ家に住んでいるだけの女の子でしかなかった。スクルフ兄弟みたいな絆が欲しかった。家に居なくなっても「まあいつもの事だから」で済ませてしまうぐらいの厚い信頼が欲しかった。
「コバタさん、私を捨てないで……」
「大丈夫、捨てたりしないよ」
私の頭上から降ってくるDJコバタさんの声は、いつもラジオから聞こえてくるのと同じ、強くて優しい声だった。
「私はジトーノなんかじゃないの……私は、コバタさんと同じスクルフなの……毛むくじゃらの犬で、背中に羽が生えただけの犬なの……十六になったら、コバタさんと結婚するの、だからお願い、私を捨てないで……」
「ああ、その頃になって、まだ私の事が好きだったらね」
コバタさんは髪の毛を舐めて落ち着かせてくれた。
この日を境に、コバタさんは一生私の親で居る決意をしたのだそうだ。
その後、いくつかあった里親の申し出を彼はみんな拒否してしまい、義翼の開発をつづけた。
ジペンゼ州に義翼の開発をしているスクルフ兄弟がいる、という噂は、こうしてたちどころに世間に知れ渡った。
マルハトさんも営業先でその事ばかり質問ぜめにあって困ったらしい。どこから様子を伺っていたのかは分からないけれど、いままで謎のリスナー『飛行アビリティ』さんとして影ながら助言を送っていたのが、途中から直接開発チームに加わるようになった。世に言うツンデレというやつらしかった。
開発チームは八名ほどの工員の有志によって構成されていた。仕事が終わった後の二時間から三時間ほどを使って開発にいそしんで、彼らが帰ったあとも、二人の兄弟は夜遅くまで工場で粘って、缶コーヒーを飲みながら問題だらけのタイムラインや設計図を睨んであーだこーだと話し合っていた。
私は隅っこの方で毛布に包まって、二人を見ながらずっとにこにこしていた。これが私の好きなスクルフ兄弟の姿だった。まだ造船業を撤退して間もなく、会社を軌道に乗せるために徹夜で試行錯誤していた、あの頃の彼らだった。私の記憶の中にある彼らは、本当はこういう兄弟だった。
「……航空法が昔とはまるで別物になっている事は考えてあるのか」
「ああ、その辺は知り合いに詳しい奴がいるからチェックを全部まかせてある」
「それはいいとして、特にまったく進展が見られていないのは機関部の小型化だな。こんな大きさじゃ、あの小さな背中に背負わせるのは無理じゃないか?」
「大丈夫、要はこれから負荷が小さくなるようにすればいいんだ」
「可能な限り魔法は使うなよ」
「無茶言わないでくれ、材質的にこれ以上の軽量化は難しいところだよ。フレームだってもう強度より軽さ重視の魔鋼を使ってるし、後は魔法を使ってごりごり負荷を削っていくしか……」
「それをなんとかするのが設計技師の仕事じゃないか……」
そんな風に開発が難航していたとき、冬眠休暇から目覚めたばかりのマッシュ族の工員が飛び込んできて、状況を激変させる一報をもたらした。
「おい、やばいぞ! まじでやばい! トラスト社が乗り込んできた!」
二人とも聞き耳をぴんと張り詰めて、顔をこわばらせていた。
「トラスト社が?」
《ジペンゼ・エア・トラスト社》はジペンゼ州の飛空艇製造会社だった。かのドックⅠ世が創始者という、東部でも指折りの超一流企業である。
飛空挺ではすでにアーディナル大陸全土でトップシェアを誇るメーカーで、大規模な需要の見込めない義翼みたいなニッチ産業に手を出すような事は今までなかったことだ。
「ははぁ、要するに企業のイメージアップ戦略ってとこだな」と、マルハトさんは睨んだ。
「イメージアップって?」マッシュ族の工員が不思議そうに尋ねた。
「つまり、俺たちの義翼の開発はラジオやテレビで全国的に広く知られている。ということは、今後ラジオ放送でスポンサーの紹介にトラスト社の名前が入れば、連中はそれだけで労せずして大きな宣伝効果が図れるってことだ」
「こっすいなぁ……けど、開発援助はほしいよなぁ……」
今回は、そのエア・トラスト社が義翼の開発援助を申し出てきたらしい。
コバタさんは頭をかいたけれど、マルハトさんはふんと鼻を鳴らした。
「馬鹿を言え、こういうのを許すと、そのうち向こうが開発に口を挟むようになってくるぞ」
「チーフ、それって一体どういう事なんですか?」
「ああ、向こうの都合でもっと早く完成させるように要求されるってこと。こっちのペースでは作れなくなる」
「それだけじゃ済まないぞ。工房も設備が整っている向こうにそっくり移されて、開発チームも向こうの技術者とウチの工員が全員入れ替えられても文句は言えないって事だ。あり得ない話じゃないぞ。お前がアンシェだったら、そんな風に色んな物を取りこぼしながら作られた義翼を貰って素直に喜べるか? 俺達工員が一から作っているからこそ意味があるんだろうが」
DJコバタさんもマッシュ工員もはたと動きを止めて、マルハトさんがマルハトさんでないみたいな目で彼を見ていた。
「なんだその目は……」
「いや、別に……いっそその方が効率いいとか言わないんだなぁ、と思って」
「ふん、言いそびれただけだ」
マルハトさんが牙をむいてガルルと唸った声に、しゃがれた陽気な声が重なった。
「がっはっは、邪魔するぜぇ!」
見ると、見覚えのないスクルフ族が一人、挨拶もなく設計室に踏み込んできた。
マルハトさんと同じネイビーブルーの体毛だけど、手入れを怠っているのか、似ても似つかないくらいボサボサだ。色ガラスのゴーグルをかけた顔つきは狂犬そのもので、唇がめくれ上がってぎらりと並んだ牙をむいている口元は、狼というよりワニに近い。背が低くてずんぐりむっくりした体型のスクルフが、ツナギのポケットに両手を突っ込んで、ぼっさぼさのホウキのような尻尾をあちこちにこすりつけながら、ぶらぶら歩いてくる。
DJコバタさんは初対面だったようで、「誰?」という顔だったけれど、外回りのマルハトさんは顔を見た事があるらしく、声を詰まらせた。
「ドック……Ⅲ世!」
そう、彼こそが伝説のドックⅠ世の孫、人呼んでドックⅢ世だ。
そのフランクな風貌や立ち振る舞いには偉人の血の影も見当たらないけれど、彼は間違いなく天才の遺伝子を受け継いでいた。
『魔石航空学界きっての異端児』。『ジペンゼが生んだ奇才』。様々な呼び名を持つが、彼の二つ名は必ず『異/奇/変/狂/電』のいずれかを含んでいると言われている。この世界でその名を知らぬものは居ない逸材だった。
後々になって、私はその凄さを身をもって知ることになるのだが、このときの私は鼻をつまんで、「なんだかオイル臭い犬がきたなぁ」ぐらいにしか思っていなかった。
じっさい彼はついさっき機械いじりをしていたみたいに薄汚れた身なりをして、尻尾にべっとりついた黒い液体を、その辺の柱に擦り付けていた。とても大企業の重役が交渉をしにきた風には見えなかったのだ。
「お前が開発援助を申し出るとは、一体どういう風の吹き回しだ、トラスト社でも鼻つまみ者だと聞いたが?」マルハトさんは鼻の頭にしわを寄せて、この胡散臭い変人の来訪を本心から警戒していた。どうやら元ライバル企業同士、私怨があるらしい。
「ぐっふっふ、まあ、テレビを観てあんたらのやってる事にちぃと興味が沸いたんでな。心配しなくとも、トラスト社の名前を出してもらうつもりはねぇよ、これは俺個人の開発援助だ。素直に面白いと思ったから手を貸しに来たのさ」
などと言いつつ、ドックⅢ世は隅っこの私をじろじろと観察していた。私ははっとして毛布を引き寄せ、首をすぼめた。ゴーグル越しだったけど、なんだか居心地の悪い目線を感じたのだ。
私の体をじっと見て、いったい何を考えているのだろう。
どうやらこの男は私にひどく興味を示しているらしかった。それがどういう興味なのかはまだ良く分かっていなかったけれど、マッド・サイエンティストという人種が一体どんな連中なのかということを、このときの私はきっと本能的に予感していたのだと思う。
ドックⅢ世はにやにや笑いを始終引っ込める事なく、人差し指を立てて交渉に入った。
「ただし、条件がある」
「待った」
DJコバタさんがすばやく制した。
「まさかお前まで彼女の父親だ、とか言い出すんじゃないだろうな?」
「がっはっは。おいおい、何言ってやがる? 機械を生涯の恋人と誓ったこの俺様だぞ」
豪快に笑うドックⅢ世を、DJコバタさんは不審そうににらみつけていた。
「いいか、どんな条件を提示するつもりだろうと、あの子に指一本触れるような事は私が許さん、それだけは先に理解しておけ」
DJコバタさんが念を押すと、ドックⅢ世は言いたい事を完全に封じられたのか、ただにやにや笑っていた。
「ぐっふっふっふっふ……」
どうやら私に触れないといけない条件しか考えていなかったらしい。危ないところだった。ドックⅢ世は耳をぶんぶん振ってオイルを飛ばしながら言った。
「がーっ。わーったよ。そう来ると思ってたぜ。じゃあ魔力機関の製作は全面的に俺様にやらせてくれよ。それと素材はここの工房のもんを好きに使わせてくれ、それで手を打とうじゃねぇか」
交渉が下手なのか、あるいはこの場合は男気があるというべきなのか。あっという間に下手に出て格安の条件を出してきた。彼の事を怪しんでいたマルハトさんも、かえって驚いたような顔をしていた。
「そんな疑り深い顔すんじゃねぇよ、どうせあんたらも利益度外視でやってんだろ? それに俺様はエコノミストじゃねぇ、アーティストだぜ。タダで環境借りて自分の作りたい物を作られたらそれで……ああ、じゃあ、そのラジオをちょこっといじらせてくれ」
と、私の抱えている携帯型ラジオを指して言った。
私たちはみんな心配そうに顔を見合わせていた。何か裏がありそうだ。本当に信用して大丈夫なのだろうか。ねぇこのくさい犬だれ? そんな不安に満ちた声ばかりがあがった。
けれどもドックⅢ世はそんな空気など意に介さず、ゴーグルをぎらりと光らせて凶悪な笑みを浮かべたのだった。
「ぐっふっふ、まあ見てなって。魔法に不可能はないって事を証明してやんぜ」
*
ドックⅢ世はそれから工場内をぶらぶらと歩き回って、その辺に落ちていた鉄くずを幾つかと、壁に立てかけてあった大きな歯車と、あと既に作っていた試作品の義翼を持ってこさせ、工房を借りるといって三日ほどこもりっぱなしになった。
「いいか、誰も覗くんじゃねぇ。決して覗くなよ。覗いちゃダメだぞ、わかったな、覗いたら何が起こっても保証しかねるからな、いいな、の、ぞ、く、な、約束だぞ」
まるで覗いて欲しいと言わんばかりの口ぶりで念を押しつつ、鉄の扉を閉じてしまった。
誰も覗くつもりはなかったけれど、朝から晩までズバババババというなにげに凄い音が鳴り響いていて、さすがに何をやっているのか気になって仕方なかった。
工員たちも気が散ったせいなのか、ケアレスミスや事故が多くなった。溶鉱炉で指を火傷する事故が一件、落下してきた鉄板で頭を打つ事故が一件、プレス機で尻尾を挟む事故が二件もあった。ちなみにバーリャ人たちの回復能力は半端ではないので、いずれも翌日には完全に回復していたが。
問題なのは私達が寝るときだった。夜通しその音が鳴り響いていたため、普段から事務所の二階で眠っている私達には、建物を通してその振動が直に伝わってきて、その頃は毎晩変な時間に目が覚めた。
ちなみにスクルフ族は基本的に地べたで丸まって眠るので、その習慣を受け継いだ私もたいてい床で丸まって眠っていた。
目がさえてしまって身を起こすと、事務所の床で眠っている白い毛の塊が、呼吸にあわせてゆっくり上下していた。
DJコバタさんである。たぶん私の目は十ルクスくらい輝きを増していた。DJコバタさんと一緒に寝るのは久しぶりだった。走り寄っていって、毛の塊に頭からぼふんと突っ込んだ。コバタさんの体毛は石鹸のにおいがして、どこに頭を置いてもふかふかで気持ちよかった。コバタさんはぐるると唸って仰向けになり、太い尻尾で私を包んでくれた。
「ねぇ、コバタさん。義翼を作ってもお金にならないって本当?」
疲れていた筈のコバタさんは、私の質問にも律儀に答えてくれた。
「まぁ、必要な人はあまりいないだろうからね。スクルフ用のヘッドホンと一緒で」
「じゃあ、どうしてみんなが作ってくれるの? どうして一生懸命になってるの?」
「アンシェは飛びたくないの?」
「………」
飛びたいかどうかと聞かれて、私は一瞬戸惑った。一瞬恐怖さえ感じた。
けれども、それは一瞬だけだ。本能が私にこう言えと命じていた。
「飛びたい」
背中の寸足らずの羽根がぱたぱたと羽ばたいて、飛びたいと叫んでいた。翼を得ることは未知の世界に足を踏み入れる事だった。青空に住むようになってしまえば、今までのように工場でぬくぬくとした生活を続ける事はできなくなってしまうかもしれない。けれども、それでも、やっぱり私は飛びたい。
コバタさんは人の気持ちを感じ取る不思議な嗅覚を持っていた。私の頭に顎を乗せて言った。
「そう、私たちも飛びたいんだよ。それで十分なんだ」
そう言って、コバタさんは私の頭を押さえつけたまま眠りについた。ずばばばばという音はいつしか止んでいた。
そんな夜を幾つか過ごして、三日目にとんでもないものが完成していた。
コバタさんが工房の引き戸を開けると、銀色のヘルメットのようなものが空中にぷっかり浮かんでいるのを見つけた。
薄い歯車がそれをぐるりと取り囲んでいて、それが定期的に緑色の魔法のわっかを、シャボン玉みたいにふわっ、ふわっ、と上下に放っていた。歯車は一部だけ欠けていて、魔法陣もやはり一部だけ欠けている。
「こ、これは一体なんだ、ドック!」
お風呂にも入っていなかったらしいドックⅢ世は、三日前よりもますます汚らしい犬になって、にやにや笑いを浮かべていた。
「がっはっはぁ! こいつは風の魔力を増幅させる魔法陣を空中に描写する《魔法陣描写機関》だ! 余ったエネルギーで補助ブースターを起動させて立体角の自由な方向に移動させるようにしてやったぜ! 総重量は一キロ未満! 三シスルの石で三トンの荷物まで持ち運び可能だぜぇ!」
「すげぇぇぇぇ! なにげに凄い事言ってるぞそれぇぇ!」
新型エンジンの恐るべきスペックに、DJコバタさんはおもいっきり興奮していた。
にやにや笑いのドックⅢ世が手元のコントローラーをいじると、それはぐるぐると天井付近を自在に動き回った。歯車の歯のひとつひとつが、がちっ、がちっ、と音を立てて回転し、緑色の光の形を変えながら、ズバババババという例の音をひっきりなしに上げていた。
それは今までの魔石工学機器の概念を覆す発明だった。従来のように魔力機関の中に必要な魔法陣をすべて組み込んでいたのを、必要なときにだけ空中に描写させる事によって、その分本体の容積をコンパクトにしたのだ。本当に溢れる才能だけはドックⅠ世を髣髴とさせる犬だった。DJコバタさんは宙に浮かぶ高性能エンジンに目をきらきらさせていた。マルハトさんも営業から帰ってくれば、きっと同じ風に興奮するに違いなかった。
「ドック、やっぱりお前は天才だ!」
「なんだってぇえ!?」
「お前は天才だっ!」
「ワンモアセッ!!」
「アオオオオオオオオォォオオン!!」
「ワオオオオオオオオオォォォン!!」
「あおおおおん!」
私も彼らと一緒になって、高らかに吼えた。
こうして私の翼は、スクルフ兄弟と開発チームのみんなの情熱と、あと変人ドックと、ラジオが結んでくれた多くの人の手によって完成した。この場を借りて、みんなに感謝を伝えさせて。
ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとーーーーっ!
2
あっという間に月日が流れて、私は十五になった。
身長は変わらず一四七センチ。前髪は変わらずくしゃくしゃと顔を覆っている。唯一変わったのは、もう『空飛ぶ女の子』になってしまったという事だ。
完成した義翼は肩帯がついた、リュックサックのように背中に背負うタイプだ。動力機関にはドックⅢ世の開発した最新の魔力機関を搭載している。
操縦機関は工場の皆ががんばって作ってくれた。私の短い背中の羽をすっぽりと包み込んで、羽の微細な動きを感知して舵を切る設計になっていた。
製作の途中で私が背負ってみると「パプシ(てんとう虫)みたいだな」とマルハトさんに茶化された(あの人は真面目に言ったのだろうけど)ので、そのまま通称となった。
総重量は二キロに達してしまったけれど、電波塔に並ぶ私のお気に入りだった。
三年、文字で書くと短いけれど、けっこう色んな事があった。
町に出かけて買った可愛い白のチュニックを着るようになった。下にはいているスパッツは空を飛ぶ女の子の味方だ。異論は認めない。
友達も何人か出来たけれど、ジトーノよりもダウンタウンの獣人の方が気の会う子が多かった。たまーに外泊もする。あんまりコバタさんに聞かれたくないこともする。ふらっと家を飛び出して、地中海の終わりパンゼペルカまで一人で遊びに行ったりもする。
それでもラジオだけは肌身離さず、どこにでも持っていった。DJコバタさんの声を聞くのはセオフィールド住民のお昼の習慣みたいなものだ。風のいい日は日当たりのいい海岸に腰掛けて、羽の手入れをする海鳥の群れに囲まれながら、お気に入りの白のヘッドホンでラジオを聴いていた。
「さて、続きましてはお悩み相談室のコーナーです。魔導師の園テン=ディルコンタル州にお住まいのRN『わんだるふ』さんからお便りいただきました。
『はじめましてDJコバタさん、私はスクルフ族の主婦です。今回は私の娘について相談したい事があります。
今年十五歳になる娘がいるのですが、その子の素行が最近おかしいのです。
派手な化粧や香水をつけるようになって、ブランド物のバッグや高価な指輪を身につけていたり、最近は夜遅くまで家に帰ってこない事もあります。
せめてちゃんと門限には家に帰ってくるように言っているのですが、娘に注意しても放っておいてと言われてしまいます。夫に相談しても返事は放っておけの一言です。
色んな事件が起きる世の中なので、娘の事を思うとどうしても心配でたまりません。DJコバタさん、私はこれからどうしたらいいのでしょう? 私は心配性なのでしょうか?』
うーん、親にとってはいつまで経っても子供は子供ですからね。いつまでも子供の身を心配するのは、親として当然の事だと思います。その気持ちは大切でしょう。
ただ、スクルフ族で十五歳と言ったらもういい大人ですからね。結婚適齢期もそろそろ後半ですし。娘さんのその辺の事情も理解してあげてはどうでしょうか?」
私はラジオを睨んで、むうと唸った。
ちなみに獣人は種族によって体の成熟する速度がまちまちで、スクルフ族はだいたい人間の二倍の早さで大人になると言われている。では私は三十歳か。コバタさんに結婚適齢期の後半と言われてしまった。
私はまだまだ子供のままでいいはずだけど、心はDJコバタさんと同じスクルフでありたかった。しょっちゅう家を出て行くのも、もうとっくに独立してもいい年頃だと信じているからだ。そうか、そろそろ結婚適齢期の後半なのか。
私がどんなに遠くに離れても、DJコバタさんの優しい声は変わらず優しかった。それはいつかマルハトさんが居なくなった時と同様に、私の事も心配しなくなった証拠だった。
そうなのだ、それが私の欲しかったスクルフ族の絆だった。
少し寂しくもあったけれど、それは私を一人前と認めてくれた証なのだと思う。
カッコいい言い方をすると、それが私の誇りでもあった。今のつかず離れずの距離感も私のお気に入りなのだ。
「では、リクエスト曲のコーナーに参りましょう。曲目は……」
ぐわしゃっ、と音がして、私のヘッドホンが頭から引き剥がされた。
耳をもぎ取られた人みたいに硬直していると、私の頭上を真っ白い一対の翼が横切っていった。
プラチナブロンドの髪の毛から両肩が覗いていた。翼はその肩甲骨から下に向かって八の字に伸び、腰の辺りでぐぐっと上向きに大きく曲がり、細い腕を目一杯伸ばせるくらい離れた辺りで、下向きの扇のように羽毛を広げている。左右あわせれば、身長の倍ほどもある綺麗な翼だった。
「ゼラちゃん! 待って、返して!」
私は慌ててそれを追いかけていった。
ゼラは崖から少し離れた辺りで、いつの間にか空に浮かんでいたジトーノのグループと合流した。
振り返ったのもやはりジトーノの女の子だった。なんだかイライラしているみたいだけど可愛いので憎めない。フリルの沢山付いたピンクのワンピース、足には可愛いアンクレットを巻いていた。
「へぇー、あんた今どきラジオなんか聞いてるんだ」
両端の取り巻きがおなかを抱えてけらけらと笑っていた。見た目に反して中身は本当に意地悪な子たちだった。私はふくれっ面で抗議した。
「もぉーっ、返してよぉーっ! それ大切なラジオなのぉーっ!」
地中海の終わりパン=ゼペルカは暖流と還流の合流点で、岬に吹きつける上昇気流を求めてジトーノの若者がよく集まるスポットだった。他の子達は端から見ているだけなのだけど、みんな翼を持たない私がからかわれても見てみぬ振りをしていた。
大人になって分かったことだけど、ジトーノは翼のないジトーノを仲間はずれにする傾向にあるらしい。同じ能力を持った種族にしか分からない違いというものがあるらしくて、私は彼らのグループに入るのに難儀していた。
「なに聞いてんの? うわー、LISじゃん、なつかしー」
「返してよぉー、勝手に聞いちゃだめぇー!」
離れた岬で寝そべっていた男子グループから、笑い声が起こった。
お調子者のエジリンがキャップの顎ひもをぶんぶん振って、横じまのシャツをよじってくねくね変なダンスを踊っていた。
「もぉーっ、ゼラったらぁーっ。いつまで経ってもデレ期が来ないんだからぁー」
デレ期ってなんだ。
エジリンは男子グループの笑いを誘いつつ、女子グループから汚い物を見るような目線を集めるのが得意な男の子だった。どんなグループにも一人はいるタイプだ。
ゼラの表情が石を飲み込んだみたいに、かちん、と固まった。この手のからかわれ方をすると、ゼラは決まって極端に機嫌を悪くするのだった。
今は大事なラジオを持っているのでとってもまずい。冷や冷やしながら見守っていると、ゼラは肩をわなわなと震わせ、唇の間からぷすぷすと、何か声にならない声を呟きはじめた。
ちなみに、彼女と私の仲が険悪になったのは今にはじまった事ではない。この義翼ができた最初の夏だった。LISを知っている事からも分かるとおり、彼女はセオフィールドの近くに住んでいて、ディーグ湾周辺を一人でよく飛んでいた。
その頃のゼラは一人ぼっちで、海軍の人に育てられたらしい。冷たいけど本当はとっても優しい子だった。まだ飛ぶのが下手な私の手を取って、地中海をぐるぐる飛び回ってくれたりした。
岬や島の名前をひとつひとつ教えてくれて、帆船のマストに腰掛けて沿岸警備隊の訓練を見学したり、おしゃれな女の子達を見ては羨望の眼差しを送っていた私に、マイクロミニなんて地上の女が履くものよ、と言って笑ってみせたりしていた。
私にとってゼラは女神様だった。彼女が居なければ、私はこれほどまで早く空の世界になじむ事は出来なかっただろう。
けれども、そんな関係も些細な行き違いで不意になってしまうものだ。
思い出すのも恥ずかしい黒歴史だ。岩の上に並んで休んでいるとき、思い切って「友達になってくれる?」と聞いてみた。
まだどちらにも同い年の友達がいなかった頃、つまりどちらにとっても初めての友達だった。ゼラは確か「別にー」とか「いいけどー」とか気のない返事をしたはずだったけれど、私は初めて出来た同種族の友達を思わず抱きしめたのだった。
そこまでは良かった。ゼラもくすぐったがっていたけど笑っていたし、そこまでで止めておけば良かった。その時、私はスクルフ族がよくやる《親愛の挨拶》をしてしまった。
犬や狼が人の口を舐めようとする事はよく知っていると思う。あれは彼らが人に敬意を示すための挨拶行為なのだそうだ。もう大体察しは付くだろうと思うが、スクルフ族のこの挨拶も、それと非常によく似た形式の挨拶だった。というかまんまそれだったのだ。
ゼラの唇はバニラと炭酸ジュースを足したような味がした。しばらく魂が抜けたみたいにぽかーんとして、握った手は岩と同化したみたいに硬くなっていた。
私にとっては単なる挨拶程度でも、ゼラにとって、それはものすごく大切な事だったのだ。人が実際に目の前で爆発するのを、私ははじめて見た。爆発するってああいうのを言うんだと知った。
同じ獣人でも挨拶の仕方を間違えるととんでもない事になる、そう教えてくれたのはコバタさんだった。そういうハプニングに関する投稿がLISでも一番多かったので、私もじゅうぶん分かっているつもりだった。けれども、身の回りに居た工員はみんな大人だから、私の粗相を笑って許してくれていたのだ。私はその意味の重大性を、この時になるまで漠然としか理解していなかった。
ボロボロの泥まみれ、土まみれ、泣きじゃくって帰ってきた私に、DJコバタさんは情けなさそうに耳をぺたりと伏せながら言った。
「相手の機嫌を損ねたときは、自分の何が悪かったのかよく考えてごらん。それからその事を謝って、何がいけなかったのかをちゃんと話し合ってごらん」
正論が好きなのはやっぱり兄弟だ。
話そうにも、ゼラは超不機嫌で私と目を合わせてもくれなかった。私は何がいけなかったのか分からないまま二年を過ごし、去年の冬、このままではいけないと思い立ち、とにかく謝ろうと誠心誠意を尽くした。
友達とたむろしている所に押しかけていって、ごめんねごめんねと何度も謝った。ゼラは相変わらずむっつりして私の話を聞こうとはしてくれなかった。何がいけなかったのか私が理解していなかったのだから当然だ。ちなみにファーストなんとかだったらしい。謝るときもまた口を舐める習性があって、セカンドなんとかもつい私がいただいてしまって、私が真相を知ったときにはもう修復不可能な関係になってしまった、そしてそのまま現在に至る。
男子グループに茶化されたゼラはあの時みたいに激昂しており、空中で地団駄を踏んだ。
「デレ期なんか永遠に来るかーっ! ちくしょーっ! お前なんか、羽をもいで地べたに這いつくばっても許さないっ! 返して欲しかったら、ここまで飛んでみなさいっ!」
大きな翼をはためかせて、海の彼方へとまっしぐらに飛んでいってしまうのだった。やれやれ。
「うわぁーん、もう許してよぉーっ!」
私は泣きべそをかきながら、とにかく崖の上に置いてあった義翼の元へと走った。他のジトーノからは歓声やブーイングが投げかけられる。義翼そのものは完全なアウェーってわけでもなさそうだ。
義翼を背負いなおし、羽を軽く振って起動させ、もうとっくに消えてしまったゼラの姿を追って、崖を全速力で駆け下りていった。
「きゅううううううううううううううううううううううううううううううぅ……!」
背中の方で段階的にギアが、がちっ、がちっ、がちっと入り、私の背後に魔法の輪が生まれるたびに、前から押し付けてくる風圧が分散されて弱まってゆく。
地面を一度蹴るたびに足元にも緑色の魔法陣がふわっ、ふわっ、と生まれ、私の体はもう自分では止められないくらい、どんどん加速していった。
風魔法が私に圧し掛かるあらゆる抵抗のベクトルを捻じ曲げている。重圧がないはずなのに肌がびりびりと痺れて、心臓が早鐘を打った。
空を飛ぶ者の本能が呼び覚まされて、パプシの中の翼が反射的に風をうけようとめいいっぱい広がった。その挙動を受けて、パプシがいつでも離陸可能な態勢に入る。
足の裏の草の感触が消え、やがてゴムボールを踏んでいるような反発力を感じるようになる。
私は振り絞るように声を上げて、崖から飛んだ。
「ううううううううううううううううううううううううううううううぅんわふっ!」
ほんの一瞬だけ現れた巨大な魔法陣が、シャンパンのコルクをぽんっと弾くように私を勢いよく弾き飛ばした。《ワルゼルベタの紋章》はエルフが使っていた直径十メートルの大きな魔法陣だ。陶磁のような鮮やかな蔓模様が生まれて、いつ見ても美しかった。
ちなみに、そのときの私のパプシはいつの間にかドックⅢ世による余計なチューンナップが施されていて、補助ブースターから赤い火を噴いてマッハ三まで出せるようになっていた。
今までそんな速度を出した事はなかったけれど、ラジオに必死だった私はそんな事を気にしている場合ではなかった。崖の先端から真っ青な海上に身を躍らせた私は、すでに音速にまで達していた。
一面に広がる雲海が飛ぶように足元を過ぎ去っていった。崖はとっくに遠ざかって霞みの向こうに消えていた。
正面の風圧を分散するのを怠れば、空気の壁と衝突事故を起こしてしまう速度だ。そもそも呼吸が満足に出来ない。私はかなり無茶をして叫んだ。
「ゼラぁぁぁっ! 待ってえええええええぇえっ!」
あっという間にゼラのプラチナブロンドの髪を視野に捕らえて、彼女が振り返ったその一瞬の表情を確認した。
「きゃあああああああああっ! 来ないでええええぇぇぇっ!」
ゼラは夜道で恐ろしいものに追いかけられたような顔をして逃げ出した。大きく右に左に旋回しながら追跡を振り切ろうとするゼラを、パプシのブースターが火を噴いて角度を調整しながらぐんぐん追い上げていく。
「待ってよおおっ!」
「た、助けてえええぇぇぇぇっ! 誰か、助けてえええぇぇぇっ!」
助けを求められてしまった。やばい、意外とショックだ。けれども仲間たちは既に遥か遠くに消えていたので、彼女の声は仲間の誰にも届かなかっただろう。
じたばたもがくゼラの姿がどんどん大きくなって、もうすぐその羽に手が届くというとき、彼女は向かい風をめいいっぱい受け止めるように翼を垂直に立てて、ぶわっと浮かび上がった。
進行方向からほぼ直角に上に舞い上がるのは、けっこう高難易度の飛行技術だった。それはパプシにとっても同じことで、一旦補助ブースターをすべて停止させなくてはならない。肩甲骨同士をくっつけるように羽を縮めると、背中の歯車が互い違いに回転してぴたりと重なり、歯がぼっぼっと最後の火を噴いて直進を止めた。次に進行方向を定めなくてはならない。私は慣性に従って真っ直ぐ飛びながら、両足を蹴り上げて真上を向いた。空を昇ってゆくゼラに向かって仰ぐような姿勢に切り替わった直後、私の頭上を何か細いコードにつながれたものがかすめていった。長年見慣れてきたそれの形状は、一瞬見ただけですぐに分かってしまった。
「……ラジオ!」
ラジオはヘッドホンと一緒にくるくる円を描き、雲の隙間で一瞬きらりと光って、高度千メートルから海に落ちていった。ラジオもドッグⅢ世がなにやら魔改造していたけれど、ここから落ちて無事なほど耐久性を高めてくれたかまでは知らなかった。
私の目標はすぐさまラジオに切り替わった。勢いに任せてぐるっと一回転し、真下に顔の向きを変え、ぼんっ、という音を立ててもうひとつ特大の魔法陣を発生させながら急降下した。
周囲の雲が円形に吹き飛ばされ、風圧で一瞬のけぞって、首がぐきっと鳴った。……ちょっと慌てすぎた。意識を集中させて、どうにか空気抵抗を微風に感じるぐらいにぎゅっと絞り込んだ。
ラジオはカモメの群れの中をすり通り抜けて、紺碧の海に向かって落ちていった。まだ間に合う距離だった。前方右下に見えた白いヘッドホンに向かって急降下し、なんとか手を伸ばして掴み取ってみると――ヘッドホンだけだった。
「うそっ、やだ!」
コードの先にラジオ本体がついていなかった。
必死になって目を凝らしても、海上には紺碧の波間しか見えなかった。仰向けに飛びながら先ほどのカモメの群れに目を凝らしても、それらしきものは見えない。焦って前方不注意のまま海上を突っ走っていた私は、その時ぐうぜん海上を通過していた大型船の甲板に盛大に突っ込んだ。
ずぼーん
分厚い甲板を私が景気よく突き破った音だ。
真下の室内をごろごろと転がって、何か硬い金属のようなものに踵をぶつけ、ごきんっ、という音と共に止まった。あまりの痛さに数秒のあいだ手足を捻じ曲げて悶え、そして仰向けにばったりと倒れた。
もういやだ。十五になってもこういう飛行事故はたまに起こした。その度にスクルフ兄弟に迷惑をかけっぱなしだったけれど、今回事故った相手は、私が今まで事故った相手の中で、まさに人生史上、最悪の相手だった。
甲板に突っ込む直前、黒塗りのごつい船体が一瞬見えたので、ヤクザの車ではないがそれによく似た嫌な気配はしていた。ああ、これはまずい相手だな、という予感はあった。
しばらくその格好でへばっていると、私の足が何か冷たい金属質の物を蹴っているのに気がついた。
ばんざいをした格好で首をごろりと曲げてみると、それは砲台だった。先ほど踵を打ちつけたものの正体がこれだ。どうやらここは戦艦の、砲甲板と呼ばれる場所のようだ。湾曲した壁には大砲の先端を突き出すのにちょうどいい窓があって、船と併走しているカモメが一羽見えた。
恐る恐る首をめぐらすと、放甲板の中央には、兵士と思しき鎧を身にまとった人々が沢山集っていた。
兵士、である。分厚い全身鎧に身を包んで、肌が一箇所も見えない。顔も無表情な鉄仮面に覆われていて、十字型のスリットの隙間からこっちを見ている。どうやら私は、どこかの軍艦に突っ込んでしまったらしいのだった。
それだけならまだ良かった。もし、彼らが連合軍の海軍だったら、むろん事故ったらまずい相手には変わりないんだけど、今の状態ほど恐くは無かった。ジトーノの不良グループは海軍に結構補導されていたりするし、疲れた時には船に乗せてもらったりするので、知り合いが居る可能性もあったのだ。
けれども、彼らに共通しているある要素が、この船に私の知り合いが一人もいない事を物語っていた。
なぜか、彼らは全員、帝国兵の格好をしていたのだ。
帝国兵。言わずと知れた敵国の兵士たちである。
耳を澄ませばぶるるるるというスクリューの回転音がして、煙突からは煙がもくもくと昇っていた。一世紀以上も昔に廃れた蒸気機関をいまだに使っている国は、世界広しと言えどそうそうないはずだ。
要するに、ここは敵の船の中だった。
「……あの、これって……帝国の船?」
「……」
「……」
「ヤップ(そうだ)」
言葉が、通じなかった。
「はは、はは……」
私は、力なく笑った。この場をなんとか笑って切り抜けようと、無駄な努力をした訳ではない、笑っていられるうちに笑っておけ、と、そう開き直ったのだ。
3
帝国兵たちを見ていると、たまに鎧の中身は空っぽなんじゃないかと思う事があった。何を言っても文句の一つも言われないし、叩いても蹴ってもびくともしない。
本当は鎧の中に生身の体なんか無くて、甲冑が意思を宿して歩いているのではないか。そんな不気味な雰囲気すら漂わせていた。
千人も乗船できそうな広い装甲船の狭い一室に、私は見張りの兵士と一緒に閉じ込められてしまった。
兵士は私にはまるで興味がなさそうで、つまらない役を押し付けられた事を不満に思いつつ、本棚から適当に本を選んで読んでいた。
「ねぇ、なんで貴方たちって、いつもそんな格好をしてるの?」
見張りの兵士は私のいちばん嫌いなタイプだった。無口で、そのくせ態度が尊大だった。鎧の上からマントをつけているので、階級は他の兵士より高そうだ。この船の千人隊長にはウラジミールという名前で呼ばれていたけれど、例の如く鎧の中身は全く見えない。
「海に落ちたら溺れちゃわない? それ以前にあっちぃよねぇ今日、脱いじゃわない?」
もとより返事がもらえるとは思っていない。話し相手が欲しくてしつこく話しかけていたら、その見張りは椅子と本を持って外に移動してしまった。
後を追うように窓から顔をのぞかせても、船楼の窓からはただっぴろい甲板と、黒煙を吹く太い煙突が一本見えるだけだった。
見上げると、マストの上の見張りが強烈な太陽光を反射していた。――とてつもなく暇だった。
「アンシェ、なにやってんのこのドジ! バカ! 変態! 天然飛行犬!」
海に面した丸い窓の向こうから、ゼラがここぞとばかりに言いたい事をぶちまけながら顔をのぞかせた。心細さの極地に追い込まれていた私は、思わぬ知り合いの出現に涙目になって駆け寄った。
「ゼラぁぁ~っ。びぁあああっ」
心強い味方は私の舐め癖をとことん警戒していて、両手で私の肩を押しのけてしゃちほこばった。
「まって、落ち着け、あんたはその気でも私そんな趣味ないんだからっ」
「何を言ってるのか分かんないよぉ、それよりもお願いラジオかえして、あれがないと死んじゃうよぉぉ~」
「うーるさい、わかったわよ、ほれほれ」
ゼラは白いラジオのストラップをつまんで、ビーフジャーキーみたいに私の頭上にぶらぶらゆらして見せた。不覚にも私がビーフジャーキーをぶら下げられた犬のようにラジオを追っている隙に、ゼラは甲板室の内部に身を滑り込ませ、絨毯の弾力を踏んで確かめ、すかさず内装を値踏みした。
壁には重苦しい装丁の本ばかりの本棚があり、狩りの獲物を自慢するかのように熊の毛皮や、サメの顎の骨などが飾られていた。滑らかな黒壇の机があって、角には目立つように三つ四つぐらいの勲章が飾られていた。船長クラスの人が使う部屋のようである。壁に飾られている海図には私たちの住むアーディナル大陸の近海と、周辺の島がいくつか描かれている。地名が少し古い。
「なによこれ……優遇されてんじゃん。……てっきり物陰にフナムシとか密航者が潜んでいそうな薄暗い船倉にでも閉じ込められてるのかと思ったわ」
「それ私も思ったけど……なんか水夫さんたちが縁起が悪いとか言って騒いでたから、途中で部屋が変わったの」
「ああ、それ聞いたことある。たしか帝国が信仰している勝利の女神様は、黄金の翼を持った女の人、つまりジトーノだったらしいのよ。空を飛ぶ鳥が好きなのね」
「へぇー、ゼラちゃん、物知りぃ~」
「向こうの世界には有翼人がいないのかしらね。なんでも戦時中に山岳地方に生息していたジトーノを発見した帝国兵が、村をまるごと向こうの世界に連れて帰っちゃったとか」
「うへぇぇ~、私、向こうの世界に連れてかれちゃうのおぉ~」
ちょっと家出をしてパンゼペルカの岬でラジオを聞いていただけの私には、当然、異世界に連れて行かれるほどの心構えは出来ていなかった。
帝国兵が信心深いなどと聞いた事がないけれど、この船が停戦から今日までなかった尋常でない作戦の最中なのは明らかだった。重要な任務で緊張していた兵士たちの目に、偶然船に飛び込んできた私の姿はどのように映っただろう。なんせ勝利をもたらす女神様なのである。
ショックを受けている私にゼラは「あんたは大丈夫よ、翼の生えた犬でしょ」とか気休めとも言えない冗談を言ってにやりと笑い、手ぐしで髪を整え、おいしい獲物を狙う狐の目つきになった。
「いいじゃん、この船のセレブになれて。で、どう?」
「どうって何のこと?」
「ここだけの話、いい男いる?」
「みんな仮面かぶってて顔わかんないし、ご飯は非常食みたいなパンとライムだけだよ」
「あっそ、じゃあこんな所にいるだけ時間の無駄ね。さっさと逃げましょ、ほら」
「う~ん、そ、それが……」
私はパプシの肩帯をぎゅっと掴んで、円形の窓をじとっと睨んだ。私の義翼は、ゼラのような折りたたみ自在の翼とは違って、硬い歯車を背負っている。どんな角度に傾けても、歯車がつっかえて窓を潜れそうになかったのだ。
「うわあぁ~ん、なんで余計な機能は沢山あるくせにこんな時に役立つ機能はないのよぉ~。十六段階ギアだとかヘルスメーターだとかGPSだとか私全然要らないってのにぃ~。こんなんだからⅢ世ってバカにされるのよぉ~あの犬ぅぅ~」
「あ、アンシェ、落ち着け。物に当たるな、本をばら撒くな、熊を殴るな。GPSって何?」
「詳しい事は分んないけど、なんか、月との距離を測ってどこに居るかがわかる機能だって言ってた。あと魔法の地図と情報のやり取りをしてて、それでパプシの居る場所が地図にうつるらしくって、小さい頃迷子になった時によくそれで探してもらってたんだけど、今はもう面倒だし倉庫でほこり被って……あ」
はっと閃いた。今もその魔法の地図でパプシの居場所が分かるのなら、コバタさんたちに迎えに来てもらえばいいのではないか。
「何、そのニンマリ顔。ひょっとして帝国軍の船に単身乗り込んで娘を助けに来るスーパーヒーローに心当たりがあるわけ?」
「こ、コバタさんならそのくらいやってくれるもん!」
「殺すつもりか、どんだけ信頼が厚いんだ……えー、つうか、あんたひょっとしてDJコバタの知り合いなんだ?」
「うん、私のお父さんなの」
えへんと胸を張って言うと、ゼラは諸手を打って、何か素敵なドッキリを仕掛けられたような顔をして頬を赤く染めた。ジペンゼ州にはDJコバタさんのファンが結構多かったのだけれど、その種族が何であるのか、ファンの間でも様々な議論が飛び交って謎とされてきたのだ。
「スクルフ族なんだけどね」
「おいおい、私の夢をピンポイントで破壊するなよ……。わかった、困ったときの沿岸警備隊にでも連絡してみよっか。ヒゲ親父の知り合いがいるのよ、何かあったら電話よこせって名刺くれたんだー」
さすが、だてに悪い子をしていないゼラである。ポケットから携帯を取り出して目にも留まらぬ高速連打で操作し、しばらく耳にあてがった。けれども繋がらないらしくて、すぐに、ちっと舌打ちする。
「圏外かよ……そういやパンゼペルカってM波塔が少ないんだよなぁ。じゃあ、ちょっくら陸地まで戻ってきます。がんばって生きろよ」
「ゼラぁぁ~、ごめん置いてかないで私をひとりぼっちにしないでぇ~」
「おいおい、泣くなよタリぃな。……よし、分かった、一回だけデレてやる。一生に一度のサービスだ。だから勘違いするなよ、本当に私はそんな趣味はないんだからな?」
船室から外に出たゼラは窓枠に両手を乗せて、呼吸を整えること数度、きりっと眉を尖らせた。
「あ、アンシェ、お前、空を飛ぶときだけ綺麗な碧眼がむきだしになるんだけどさ、その、意外と可愛くて、び、びっくりしたぞっ」
言い切ったゼラは、頬にちゅっとキスをした。なぜか照れたように顔を赤くして、ばっさばっさと飛んでいった。
いまのは何だったのか。何がサービスだったのか。展開がよく飲み込めなくてぼんやりしていた私の手に、ラジオの硬い感触だけが残されていた。
一般の通信機に使われている魔力・七五〇系統は、他の魔力の抵抗を受けにくいため理論上はどんな遠くへも飛んでゆくものだったが、通信機として使うために、特定の魔石の配置に反応して音を出すようにしているため、自然界の魔力が偶然似たような配置を持っていると抵抗を受けてしまい、遠くに行けば行くほど磨り減って徐々に聞こえづらくなってしまう。
それを克服したのがマールターク式波性魔力信号(通称M波)で、石の配置を自然界にほとんど存在しない虚数配置というものにして、さらに同じ虚数配置でも同じ波長のものにしか反応しないようにしてあるため、理論上はどんなに遠くでも抵抗を受けずに通信ができるものらしい。
けれども便利すぎるM波の通信網は国が管理していて、通信台の設置にかなりの手間と費用がかかる。使っているのは主に国営放送のラジオやテレビや電話局くらいで、私たちがよく使う携帯は製造コストを抑えるために信号をあらかじめ弱いものにしてあった。アーディナルのあちこちにあるM波塔を仲介してM波通信をする仕組みになっているため、ダンジョンに入ったり強烈な魔力のミストが立ち込めたり、あるいはM波塔から五キロ以上離れただけでたちまち使い物にならなくなってしまうのだった。
スクルフ兄弟が作ったアマチュア・ラジオ塔は、一体どのくらい遠くまで信号を飛ばしているのだろう? はたと気になった。全国放送しているとは聴いたけれど。急に不安になって、その辺にしゃがんでラジオを耳にあてがった。
さっきの岬でも十分に音が聞こえたので、ここからでもまだ大丈夫なはずだった。じっと耳を澄ましていると、やがていつも通り、DJコバタさんの優しい声が鮮明に聞こえはじめた。
「さーて、続いてのお便りは、錬金術師の聖地グランコルーフにお住まいのRN『九十九児の母』さんから。
『はじめましてDJコバタさん。今回は混み入った事情の話があってお手紙を出します。
私はアナトー族(カエルの獣人です)の主婦です。優しい夫とも仲がよく、先月、おなかを痛めて生んだ九十九個の卵も無事に孵化し、一〇一人の大家族でこの冬を乗り切り、春から理想の家庭を築いていこうとしておりました。
けれどもそんな矢先に、夫婦仲がとつぜん危機に陥る事件がおきたのです……。
病院で遺伝子を調べてみた結果、九十九匹の子供のうち五十八匹が夫の遺伝子を受け継いでいない、赤の他人の子供であることが判明しました。つまり、私が結婚する以前に関係を持った男との間に生まれた子だったのです。
さらに詳しく調べてみると、なんと! 私の遺伝子も受け継いでいない、母親の異なる子供が四十四匹も紛れていたのです!
どうやら二十匹は出産のときに病院の手違いで卵を取り違えてしまったらしいとの事。残り二十四匹は夫の遺伝子しか受け継いでいない子供だと分かったのです!
どうして「夫の遺伝子しか受け継いでいない子供」が紛れているのか不思議に思い、夫に問い詰めてみると、どうやら夫が以前雌だった時(アマトー族は環境に応じて性転換するそうです)に私と同じような経緯で身ごもった子供だったらしく、「自分がお腹を痛めて生んだ子供なので、どうにかして育てたかった、悪気は無かった」と言って、私の卵にこっそり自分の卵を紛れ込ませた事を素直に白状しました。
計算上、私の遺伝子のみを受け継いだ子供は九十九匹中たったの三十八匹という事になります。私と今の夫との間に生まれた子供はわずか十七匹でした……。
現在、取り違えられた二十匹の子供はうち二匹に親が見つかって今は十八匹。代わりに私と夫の本当の子が五匹もどってきて二十二匹。父親のわからない私の子が計算上は三十八匹。父親のわからない夫の子が新たに二十三匹見つかって四十七匹。計一二四匹の子供が我が家にいて、以前より増えてこんがらがり、もう誰が誰の子やらさっぱりという状態です。
……DJコバタさん、私たち夫婦はこれから一体どうしたらよいのでしょう?』
結論、もうみんなまとめて愛しちゃいなYOー!」
私は笑った。とにかく笑って、やがて泣き笑いになって、抑えきれなくなってぐじぐじ泣いた。
「コバタさん、帰りたいよぅ……ひぐっ」
時に責任という言葉は可哀想な子犬や異国の船の姿をして十五歳の女の子を途方にくれさせるものだった。自分から家出をしておいて無責任な、と自分でも思うのだけれど、世の中には自分ひとりの責任で背負いきれない物なんていくらでもあるのだった。
ぐじぐじ泣いていると、見張りのウラジミールがやってきた。脇に抱えていた毛布を、投げる位置も考えずにぞんざいに投げてよこした。
「くれるの?」
甲冑に身を包んだウラジミールは何も言わなかった。鎧を構成している部品のひとつひとつにボリュームがあって、ふんわりとした花弁のように重なって陰影を生んでいる。ところどころ隙間から黒い肌着が見えていたけれど、肌はどこからも見えなかった。
毛布の端を持って細かく眺めていると、ウラジミールはさっさと部屋からひっこんでいった。
「あ、ありがとう」
人見知りをせずにちゃんとお礼を言った。えらい。私にしてはとても珍しい事だった。ウラジミールはしばらく戸口に立ち止まって、何か言いたげに振り返った。
「女の立ち話は本人が思っている以上に周囲に聞こえているぞ、覚えておけ」
うぐ、と喉が詰まった。どうやらさっきのゼラとの会話は部屋の外まで聞こえていたようだ。
十字のスリットが刻まれた仮面越しに脅すような、けれども半分からかうような声が聞こえた。
「言っておくが、俺はげん担ぎに拘るような腑抜けではないのだ。お前が我々に勝利をもたらしてくれる女神だなどとは微塵も思ってはいない。だが俺の部下達はその限りではないのでな……」
ウラジミールはどうしても言っておきたかったらしいその点を嫌みったらしく付け加えて、さらに戸口を指で指して言った。
「命が惜しければ早々に立ち去る事だ、たとえ逃げても撃ち落すような真似はしないだろう。俺もこんなお守り役からとっとと開放されたい気分なんだ。逃げたいだろう、ん?」
ウラジミールの隣で、戸口はぽっかりと青空をのぞかせて完全に開いていた。
けれどもこいつに促されてそこからこそこそ出て行くのは途轍もなく癪な気がした。なんというか、虫唾が走る。私は「ちょっとそこどいてくれる?」と言う代わりにちょっときつい目線を送ってやっていた。ウラジミールは私の毛布を指差して、感情のこもっていない声で続けた。
「泣きたいならその毛布に包まっていろ……声を漏らすな、耳障りだ」
頭がかああっと熱くなった。何なんだこいつは。無口かと思っていたら、喋りだしたら一言も二言も多い奴だった。なんだかむかむかしてきて、私はウラジミールの背中に毛布を投げつけてやった。ドアのところまでは届かず、足元にばふっと広がっただけだった。
ぷーっと膨らんで、耳を洗うつもりでラジオに耳を傾けた。けれどもラジオは国営の緊急ニュースに切り替わっていて、DJコバタさんの声は聞こえなかった。M波はたまにこういうのがあるから困る。
うあーと唸って、その辺に大の字に寝転がった。照明用の小さなシャンデリアはこのまま顔面に落ちてくるのが恐いくらいゆらゆら揺れていて、木の床板がやけに大きく、ぎしぎしと傾いていた。
手にしっかりと握ったラジオが、平坦な声で台風情報を伝えていた。
「……南海で発生した大型台風はヨビ諸島南西沖を北上し、現在アディンゴ州、クルスルーブ州の一部で発達した雨雲による集中豪雨が観測されています。台風はこのまま進路を東に変えて沖合いを通過していくものと見られています。沿岸地域ではその後も大型の波が押し寄せてくるものと思われ、引き続き避難勧告が……」
この台風の事を、あの冷血漢ウラジミールではなく、千人隊長にでも伝えてさえいれば、あるいはあの恐るべき事件を未然に防ぐことができたかもしれない。
きっと伝えたところで、私の意見など聞く耳もたなかったかもしれないけれども、私の存在の重要性をこの後、連中に嫌というほど思い知らせてやることは出来たはずだった。
*
その晩、大型台風は見事に船の進路と重なり、私は床の上をごろごろと転がっていた。
ぐわーっと口を開けたサメの頭の前に行ったり、がおーっと襲い掛かってきそうな熊の毛皮の前に行ったり、わああああと叫ぶ私の手の中で、ラジオの国営放送が延々と緊急ニュースを告げていた。
船はあさっての方向に流されないように碇を降ろしていた。船全体がぎりぎり、みしみしみし、という嫌な軋みをあげて私の神経を逆なでした。
窓の外は食器洗浄器みたいな土砂降りで、甲板にいたウラジミールはさすがに室内に戻ってきたけれど、この状況で信じられない事に、室内で椅子に座って平然と本を読みはじめた。絶対酔う。適度に開かれた膝をわっしわっしと掴んで、本の上に身をぐいっと乗り出した。
「ウラジミール! 大変、朝食を戻しそう!」
「夕食と昼食はもう吐いたのか?」
「あんなカロリーの低いおやつ、食事のうちにも入んないもん! てかなんで私の言うこと聞いてくれないのよっ! 台風くるかもってあれほど言ったじゃない!」
「軍隊で通用する言語は『かも』ではない、『いる』のみだ」
「はぁ? 意味わかんないっ! ひょっとして私の事バカにしてる?!」
「あの時点で確認できたのは、『羽の生えたチビが台風がくるかもしれないと騒いでいる』という事実だけだ、そんなもののためにわざわざ腰を上げるととんだ笑いものになる」
「あれ? 今、ひょっとして私の事チビって言った? チビって言ったの? むっかあああああーっ! 私の身長は一四八(!)センチよぉーっ! それを言っていいのは二五八センチのコバタさんだけなのぉーっ!」
私は猟犬のごとくウラジミールに殴りかかったけれど、分厚い鎧はびっくりするぐらい頑丈な素材で出来ていて、裸足で蹴っても素手で殴ってもびくともしない。フライパンなんかを想定していた私は反対に手足を痛めてしまった。
基本的に行動原理が犬な私は次に歯をたててみたけれど、ウラジミールは横に向いて私のよだれが本に付くのをかわしただけだった。そんな一方的な攻防を繰り広げている内に、嵐の中でも辛うじて聞き分けられる鐘の音が響いた。部屋の外で、嵐の中を誰かがあわただしく動き回っているらしかった。
「何の音?」
「警鐘だ、どうせ魔物か何かが出たのだろう」
ウラジミールはなんだか他人事のような言い草だった。実際この男にとっては海の魔物など、他の兵士が処置するべき他人事でしかないのだろう。
驚いて声の出なかった私は、この男の全身をもう一度じっくり観察した。つま先から頭の天辺まで嫌いなタイプだった。なんて嫌な奴だ。嫌味の塊だ。けれど、彼の大仰な態度は、通信管から聞こえてきた次の一声で掻き消えた。
「海賊が出現したっ! 戦闘員は直ちに戦闘態勢に入れ!」
帝国船の通信管は、金属製のパイプが壁づたいに船室同士を繋いでいるだけの原始的なものだった。
わんわんと聞こえづらいその声を聞いた瞬間、ウラジミールは本をばんと閉じた。
「……海賊って何?」
窓の外が雷光で一瞬明るくなり、そこに奇妙な光景が見えた。
空を覆い尽くす雲の中央に、空を走る人影がうつりこんでいたのだ。
ウラジミールが突然立ち上がって、彼の腕にしがみついていた私は部屋の反対側まで弾き飛ばされた。
「いったぁ~!」
私はごろごろと床を転がって、黒檀の机に背中をぶつけていた。腹立ち紛れに勲章を手当たり次第につかんで投げつけてやった。
しかし、ウラジミールは私の事など眼中に無いらしい。ウラジミールが本棚に向かって乱暴に本を投げつけると、何かの魔法を使ったのか、本はページも開かず綺麗な形を保ったまま、真っ直ぐ他の本と本の隙間に収まった。
船が恐ろしいくらいの急角度に傾いて行ったけれど、そのまま彼は甲板側を見渡せる窓の脇にへばりついていた。手足を突っ張ってトカゲのように窓の外をうかがっている。彼の隣に立っていた椅子があまりの角度に耐え切れずにぱたりと倒れても、本棚の本が数冊落ちても、まだ様子を伺っていた。
甲板が見えるのはあそこの窓だけだ、私は四つん這いになって床をよじ登っていったけど、またごろごろと転がっていった。仕方ないので途中からパプシで軽く飛んでいった。適当な掴まる物がなかったのでウラジミールの腕にしがみついたのだけれど、私が恐がっているみたいで途轍もなく不本意だった。
丸い窓からは荒波に洗われる甲板が見渡せた。その中央部に左右に分かれた人垣が出来ていて、人垣も波を被ってイモ洗い状態で並んでいた。
片方は五十人あまりの鎧を着た帝国兵たち、もう片方は僅か十三名の鎧を着ていない、恐らくは海賊と呼ばれる者たちだった。
「《船幽霊》どもだ……」
彼の仮面のスリットの奥に、不安げに揺れる瞳が浮かんでいた。
私は何をそんなに恐れているのか不思議だった。
たった十数名。装備も貧弱、数の上でも圧倒的に不利な海賊たち。みな上半身が裸で、シダの葉を編んだ腰みのを身に付けているといった風情だった。
暗闇に溶け込みそうな暗褐色の肌をむきだしにしていて、目を凝らせば一人一人の身体の特徴がはっきりと見て取れるようだ。全員がひょろひょろとして細い。全員が正方形の巨大なお面を顔につけていて、顔だけは分からないようにしてある。
四角いお面の目玉のような図形をぎょろりと真正面に向け、海賊たちは横一線にならんで帝国兵たちとにらみ合っていた。帝国兵たちがきっちりと統制された、隙の無い隊列を組んでいるのとは対照的に、だらだらと、その辺で自由にたむろしている様子だった。
あるとき突然、ヒヒのような雄たけびをあげてぴょんぴょん跳びはねた。
はっはっはっ、はっはっはっ、はっはっはっはっはっはっはっ!
体をぐいっとひねって剣を掲げて、ぴたりと同じ角度で腕を引き絞り、片足でぴょんぴょん飛び跳ねながら甲板をぐるぐる横に移動しはじめた。
掛け声もアップテンポだ。なんだか分からないけど妙にドキドキした。
帝国兵と海賊の戦い方は完全に静と動で、ぴしりと整列した帝国兵は、彼らの戦いの踊りを前にして微動だにしなかった。列を成して踊っていた海賊たちは、とつぜん端の方から蜂の羽音みたいな音をたてて掻き消えた。
ぶううんと言う音がした。消えたという表現がぴったりくる、何の前触れもなく、すごい速さで帝国兵たちに飛び掛っていったのだ。
私には見えなかった短剣による攻撃を、けれども兵士は両手剣でがっちりと受け止めていた。端のほうから順に火花がずぱぱぱっ、と散った。
海賊たちの速さがすごければ、それに瞬間的に反応してのけた帝国兵たちの動きもすごかった。
対応の遅れた約一名が、甲板から海賊に鷹のようにさらわれていったのを見た。私の目は丸窓に限界までくっついて、その行く先を見送った。窓から消えたので、次々と隣の窓に飛び移って姿を探すと、海に面した窓で二人を見つけた。上空でぴょんと跳んだ海賊が、捕まえた兵士の背中に両足でどすんと蹴りをいれ、そのまま真下に蹴落としているのを目撃した。
兵士が落ちていった先は荒れ狂う海だ。あっというまに甲冑は波にもまれて見えなくなった。やっぱりあの装備では泳ぎにくいだろう。海賊の方は長い足を蹴って翼もないのに空を飛んで、甲板の方へ再び舞い戻っていた。翼の代わりに強靭な脚力を使い、空気をぽんぽんと蹴ってジグザグに空を進んでいるのだ。
風魔法だ――。
見た目は全く別物だけれど、彼らが使っているのは根本的にジトーノと同じ原理の魔法だった。
体をひねり、足で空を蹴り、風魔法を放って、立体的な空間移動をしているのだ。
戦闘に目を凝らしてみると、海賊たちは力で勝る帝国兵たちを速さで翻弄していた。直角移動や一八〇度ターンを多用して、これは当たったと思われるようなタイミングの反撃でさえすり抜けて、かすりもしない。
これは本来ジトーノにとってタブーとされている風魔法の使い方だった。せっかく前方に突進する推力を魔法で得たのに、それを完全に打ち消すために余計に膨大な魔力を消費してしまう。非常に効率が悪く、長時間飛行するには全く適さない技術なのだ。
「ウラジミールさん、こちらからは攻撃しないで!」
その弱点に気づいた私は、気づくとウラジミールの方に飛んでいた。ただ熱心に窓の外を見続けているウラジミールの腕を揺すって呼びかけていた。
「お願い、なるべく時間を稼いで! 風魔法はあんな使い方をしちゃダメなの、彼らは長時間空を飛ぶ事が出来ない、そのうちすぐにバテてしまうわ!」
どうして帝国兵に助言を与えようとしているのか、こうなったら乗りかかった船だとか、そんな後ろ向きな思いはこれっぽっちも含まれていなかった。たぶん私の思考回路はもっと単純に働いていて、船が襲われているのなら、それを黙って見過ごすわけにはいかなかったのだと思う。
けれども、ウラジミールは強引に腕を振り解いて、凄まじい気迫で言い募った。
「戦争に口を挟むな、小娘が」彼は厳しい口調で切って捨てた。「我々の作戦に口を挟んでいいのは上官か、さもなくばその作戦が失敗したときに腹を切る覚悟のある奴だけだ。そのどちらにも属さない者は黙って見ていろ」
普段から怒られた事のなかった私は、その気迫を目の当たりにして、胃が縮こまる思いをした。ちょっぴり涙がにじんだ。
彼らはコバタさんとは違う、本物の兵士だった。私なんかに言われなくとも、すでにそうするつもりだったのだ。帝国兵たちは短い戦いの中で敵の性質を確実に把握し、徐々に戦い方を変えてゆき、やがて反撃のコツを完全に掴もうとしていた。
「最大防御を取れ! 攻撃は中止! 敵の動きが鈍くなるのを待て!」
巨大な両手剣を片手で振り回しながら、嵐の中で千人隊長が檄を飛ばしていた。
「敵の攻撃力はさほどない、陣形を死守しろ! 背後を庇いあえ!」
この悪天候の中で、抜きん出た状況把握能力だ。
こうなると後は早い、凍った世界からやってきた兵士たち、耐え忍ぶのは得意中の得意だった。
ウラジミールは船室の壁に取り付けられたパイプにすがりつくと、蓋を開けた。その通信管からも壮絶な金属音が漏れてきた。戦火が広がっているのは甲板だけではなかった。どうやら船内でも繰り広げられているらしい。
「こちらウラジミール、機関部、そちらの戦況を報告しろ!」
「こちら機関部、外の廊下で数名と応戦している!」
「応援が必要か!」
「いいえ必要ありません、嵐が過ぎるまで持ちこたえてみせます!」
「……いえ、そいつは無理な相談です!」
横から誰かの焦ったような声が聞こえた。はっと息を呑む声が聞こえた。肌に冷たい気配を感じて、見ると、船の進行方向には、先ほどは無かった黒い影が二つ、壁のように無言で立ちはだかっていた。
「碇が断たれている!」
この海域は彼らの縄張りだ。岩礁のある場所も、潮の流れもすべて把握済みだったのだ。
「くそっ、甲板の海賊達はただのおとりだ!」
「まずい、岩礁に吸い寄せられているぞ!」
かんかんかんという警鐘が船員達を急かし、通信管から悲鳴に近い声が振り絞られた。「面舵一杯!」とか、「全速後進!」とかの指示が聞こえたけれど、巨大帆船は怠惰なゾウみたいにのろのろと前進し続け、その指示通りに動いてくれそうな気配はなかった。
「くそっ、アーディナルの悪夢か……!」
迫り来る岩陰がベッラ・キニヤのジェラートのお化けに見えたことは覚えているのだが、それ以降は何も覚えていない。船底ががりがりっと削れるような鈍い音がして、船が持ち上げられたような衝撃があった。本棚から大量の本が降って来て、直後に世界が暗転した。
*
気づくと背中を湿った森の風が撫でていて、私は無人島の真ん中で目を覚ました。どうやってこんな所にたどり着いたのか分からない、岩の上の、スポンジみたいな苔のベッドにうつぶせになっていた。周りはもこもこふわふわした緑色の鞠に囲まれている。頭のてっぺんに小さな花の咲いたそいつらが、四方八方からもそもそと私の体をついばんでいた。
髪の毛をもしゃもしゃ齧って、わきの下やふくらはぎや足の裏の硬いところをぺちゃぺちゃ舐めていた。他のやつに踏まれた一匹がころころころと秋虫のような声で騒いていた。
よく見ると人懐っこい細い目と、猫みたいな小さな口があって、至る方向から私を味見している最中であるらしかった。なんか食べられているなぁ、と感じてのっそり体を起こすと、生きているとは思わなかったのか、きゅーきゅー鳴いて森の奥へ逃げていった。
教会にピンク色のがいるが、こいつらはその亜種なのか。はたまた無人島生活を送るうちに全身苔むしてワイルドになっただけなのか。もし後者だとしても、せいぜい経験値一から二になった程度だろう。こいつらも教会のと同様に、全く害はなさそうだった。
私の翼、パプシは壊れていた。泥の付いた胴体からウィィーンと変なモーター音が聞こえていて、へし折れた歯車が意味もなくぐるぐる回っている。ぷんすか、ぷんすか、と排煙のように魔法陣を生み出し続けているのを見て、魔力系統がやられているらしい事が分かった。きっと私が森の奥までふっ飛ばされたのもこいつが暴走したせいだ。
これまでも事故った時に何度か自力で修理した事があるが、ここまで壊れるとちゃんとした工房でなければ修復は難しいだろう。密林をさ迷い歩いて、とにかく海岸に出てみようと思った。サバイバルの知識なんて何一つ持ち合わせていなかった、上手くすれば人のいる場所を見つけられるかもしれないと思ったのだ。
台風一過の森はひどい有様だった。湿った木の枝を踏み砕いて、じゅくじゅくした苔の絨毯に足を取られながらなおも進むと、あの帝国兵達が車座を組んでいるのに出くわした。
べそをかいて歩いていた私は、はっとして涙を払い、その辺の木陰に隠れた。
ちょうど彼らの向こうに小さな入り江が見え、そこに帆船らしき物の姿も見えた。砂浜に船のへさきだけが立っていて、鷲の像が真っ直ぐに空を向いて、ますます勇ましく見える。この様子によると、岩礁にぶつかった拍子に船は大破してしまったようだ。
「狩人スキルを持ったものは?」
仮面をしているといったい誰の発言かよく分からない。十名近くいた兵士達の中で、ほぼ全員が手を挙げて、ますます分からなくなった。
帝国軍には何千通りものスキルがあって、兵士達は正確にその型通りに動く技術が要求されるらしい。
「工船スキルを持ったものは?」
こちらはマイナーな能力なのか、手を挙げたのは一名きりだ。それでも誰が発言したのかはやっぱり分からなかった。
遭難者となった帝国兵たちは、どうやらこの島からの脱出方法を探っている最中のようだった。
「地図によれば、この周辺にはここと同じような小島が大小あわせて二十ほどあり、その間を入り組んだ海流が流れているようだ。……連合の目から隠れるのに十分な広さを持っていると見ていい。先ほどのスキルの者がいれば、食糧の確保もさほど難しくはないだろう」
「最大の問題は」角つき兜の兵士が、のっそりとした動きで腕を組み替えた。「どのようにして連合に見つからずに元の世界まで戻るか、だ」
全員が仮面で頭部をすっぽりと覆っていて、誰の表情も読み取ることは出来なかった。彼らの話し合いはまるでパントマイムのように見える。誰が喋っているかは身振りで判断するしかない。
兵士達の中に見覚えのあるマントがあった。ウラジミールだ。巨木を背にした連中の中でも、真ん中の一番偉そうな位置にいる彼は、聞き覚えのある嫌に強気な声を発した。
「我々の船の残骸が連合に発見される可能性も含めて考慮しなくてはなるまい。連合は警戒を強めて海上の警備を強化するはずだ。もしそれらに海上で遭遇した場合、現在の我々の戦力では到底太刀打ちできない。無力化され、敵国の捕虜にされるのは目に見えている」
意外と冷静な判断である。仮面越しにも、兵士達の浮かない表情が見て取れた。私は木陰からちょこっと身を乗り出して、沈んでいる兵士たちの様子を伺うことにした。
「もしこのまま連合の捕虜になるような事態が起これば、祖国では敵に情報を漏らした売国奴として我々だけではない、我が部隊そのものが非難される事になるだろう。
――もしここで脱出を諦め、この場で自決したい者がいるならば、私は何も見なかったことにする。手を上げろ」
何を言っているのだろう。自決など、そんな事をするのはウラジミール一人で十分だ。
いったい誰が手を挙げるものか、と思ったけれど、驚いた事に多少のとまどいのあと、全員手をあげてしまった。他の人の目を気にしているとでも言うのだろうか。帝国の兵士たちは、時に命よりも個人としての面目を保つ事を何よりも大事にする生き物だという。
ウラジミールが脇に提げていた美しい小刀を、左脇の兵士に差し出した。ごくりと唾を飲む音が聞こえた。
「曹長、お前からだ」
「だ、ダメーっ! やめてーっ!」
隠れていなければと思ったけれど、こんな時になりふり構っていられない。というか、ここはウラジミールの横暴をとにかく止めなければと思ったのだった。
私が叫んで飛び出しても、兵士たちは大して驚いた様子は見せなかった。どうやら索敵スキルというものがあったらしく、木陰から覗いていた私の存在は、先ほどから彼らにずっと知れ渡っていたらしい。経験値二の魔物よろしく無視されていただけだった。
小刀を首筋にあてがって躊躇している曹長にしがみついて、わめき散らしたり叩いたりしながら色々阻止していると、ウラジミールが怒りを押し殺したような声で言った。
「我々の戦争に口出しするなと言ったはずだぞ、チビ」
「チビって呼ぶなって言ったはずよ! この冷血漢! なによあなたたち、辛さに耐えて生きているより、死んだ方がカッコいいとでも思ってるんだ!?」
「覚悟を決めた男を非難するな、名誉を取り戻すにはこうするしかない」
「バッカじゃないの!? ちょっと失敗したぐらいで死ぬなんて、そんなのが名誉だなんて絶対おかしいわ、あんまりよ!」
「ちょっとの失敗だと? 我々の失敗の責務は、お前が想像している失敗とは比較にならないほど重いものだ」
「私の想像を勝手に決めつけないでよ、あんたに何が分かるっていうの?!」
「いいか、この任務を達成する為だけに既に大勢が命を落としている。彼らの命によって繋げられた任務を受け継いだ我々が、己の命を惜しむ為に任務を放棄することを選択しようとしている。それで名誉が今までどおり保てると思うのはよほどの厚顔だ」
「何よ任務、任務って! コバタさんが言ってたよ、あなたたちはどんなに辛くても生きなきゃダメだって! それが生き物の任務じゃない! しっかりしてよ、もうちょっとの辛抱よ、あと少しぐらい頑張れないの? もうじきここに助けが来るんだから!」
言い争いをしているうちに、黙ってうつむいていた兵士達が、次第に私の方に顔を向けはじめた。私は背中のパプシを自慢げに彼らに見せてやった。
「ほら見て、私のこのパプシ、GPS機能がついてるの! これで世界中のどこに居ても私の位置が分かるのよ! ゼラちゃんが沿岸警備隊の人に連絡して、私を迎えに寄越してくれるって言ってたから、もうすぐこの島までお迎えがやってくるはずよ! もうすぐここに連合軍がやってくるんだから! 安心して、みんなもう少しの辛抱なんだから!」
――その連合軍に捕まりたくないからこうしているのだ、という彼らの根本的な悩みをまるで理解していない私なのだった。
ともあれ、連合軍が接近しているという情報を聞いた兵士たちは、全員弾かれたように顔を上げていた。
私はまるでそれが自分の手柄であるかのように得意になっていた。本当はぜんぶ他力本願で、私は偶然パプシを背負っていただけなのだけれど。
木の根元からウラジミールが腰を上げて、私の肩をがっちりと掴んだ。ちょっと痛くて身をよじった。彼は驚きと感動の混じった、気後れしたような声で言った。
「素晴らしい……こいつは本当に、我々の勝利の女神なのかもしれんぞ……!」
*
数時間後、私は沿岸警備隊の巡視船『ウォーター・クラフト号』に乗せられ、無事に群島の森を脱出していた。
はじめて入った巡視船の操舵室は、ゴーグルの中みたいに横に平べったく、塵一つ落ちていない清潔ぶりだった。きっと厳しい上官に鍛えられた船員たちが、毎日丁寧に掃除しているのだろう。前方のガラス窓からの眺めは爽快で、視界もじゅうぶん広く保たれている。
ゼラの言っていたヒゲのおじさん、三等准尉が自ら舵を取っていた。白いベレー帽の奥に緊迫した瞳を隠し、ぱりっとした白い軍服を着た、五十過ぎの口ひげの特徴的なおじさんだ。
操舵室にはこの船長の他に、私と、あと数名の帝国兵もいた。と言っても、今は誰が誰だかわからない。帝国兵たちは今は全身鎧を着ておらず、代わりに飴色の強化金属の鎧を身にまとって、連合軍の小銃を構えて、出入り口の付近にずらりと並んでいた。
連合軍がやってくると聞いた後の兵士たちの行動は実に迅速だった。群島の奥の大型船が容易に通れない島にパプシごと私を移動させ、そこにのこのこやってきた海兵たちから装備を強奪したのだ。
その隙にウラジミールが海を潜ってウォーター・クラフト号に単独で侵入し、この船長を人質にして船を占領し、残りの兵士たちを乗せて無人島を脱出した。シージャックだ。本当に、どうしてこうなった?
黒髪から海水を滴らせたウラジミールは色白で、まるでロウを塗ったお化けのようだった。海水に濡れたプギオというナイフを、無線機を握る船長の首筋に押し当てていた。
「こちらウォーター・クラフト号、少女の身柄を確認した。命に別状はなさそうだ」
『了解、速やかに本土へ帰還せよ』
群島の周辺を哨戒していた海軍の船は、引き続き帝国船の捜索を続けていた。
群島を取り囲むように並んだ大型軍艦の、ウォーター・クラフト号の為だけに空けられた隙間を通って、船は難なく海へとすべり出ていった。
准尉によると、ふつうは女の子が帝国の船に連れて行かれたというゼラの通報だけで、海軍がここまで大騒ぎすることは珍しいらしい。
軍はそんな曖昧な証言だけで動くほど単純ではないし、なにより予算も潤沢ではない。不審船の取締りや通報の内容確認など、そういった些事は本来沿岸警備隊が受け持つ仕事である。
捜査に乗り出した沿岸警備隊は、ゼラが通報してくれた昨夜、GPS情報でパプシが嵐の海上に長時間留まっていた事などから、『未確認の船が海上に居て、少女はそれに乗っている可能性が高い』というはっきりとした証拠を掴んだ。
なので准尉も上官にそのように通達し、調査に向かう事を報告したところ、なぜか上からは海軍との合同作戦を行うように指示されたのだそうだ。
どうやら連合軍は他にも帝国船の目撃情報を受けていたらしく、可能性のある全ての海域で警戒を強めていた最中らしかった。
このとき、ゼラの帝国船の目撃情報もあわせて報告していれば、まず間違いない。海軍もこの船だけで私の救助に向かわせるような油断は決してしなかったかもしれない。けれども准尉はあえてそれをしなかった。
「歳は取りたくないものだな」
准尉は五十いくばくの壮年の顔に、疲れた表情を浮かべていた。
「ウォーター・クラフト号も生半可な海賊に負けないぐらいの武装もしているし、それに海難救助は迅速さが命だ。君はゼラの大切な友達みたいだからね。何とか早く助けてあげたかったのだけれど……」
「余計なことしないでよ。ゼラちゃんに嫌われてるよ、私」
「喧嘩するほど仲がいい、と言うね。古い言葉しか知らなくて申し訳ないけど。ゼラは仲間がらみの事で私の所に来ることは何度もあったけれど、今回みたいに必死になるのを見たのははじめてだったよ」
准尉はしわしわの手で私の頭を撫でた。ちびっ子扱いしないで欲しい。
「昨晩、嵐で船が出せなかった間、もの凄い剣幕で罵られてね。本当は彼女に追い立てられるように出て来てしまったんだ。それでも自信はあったんだがね。やれやれ、しかしこうもあっさり船を奪われてしまうとは。――すっかり平和ボケしてしまったようだ」
と、反省の色を浮かべた准尉は、帽子を目深に被りなおした。
シー・ジャックされた船は、そのまま軍艦に怪しまれる事もなく群島から脱出し、海軍の警戒水域からも抜け出した。
ウラジミールは操舵室の片隅に座り込んでいる私と船長の所にやってきて、老人の方を底冷えのするような目で見下ろしながら言った。
「軍用通信機を出せ」
彼の注文に、准尉はベレー帽の下の眉根を寄せた。軍用通信機は連合軍の主要機関にしか通じない、特殊なM波を使っているものだ。
「……何をする気だ?」
「大戦を多少なり知っている海兵ならば、もう少し利口な対応をするべきだと思うがな」
私はウラジミールの冷酷な顔を下から睨み返した。いちいち腹を立てるだけ無駄だと分かっているのだけど、こいつはどうも許せなかった。
訝しそうにしながら、准尉はよろよろと立ち上がった。
計器パネルの脇に上下の二箇所に鍵がかけられた透明な箱があった。准尉はポケットの鍵を使って蓋を開き、厳重に保管された大型無線機を取り出した。
「連れて行け」
用済みになった准尉は、ウラジミールの指示ひとつで部屋から連れ出された。
「船倉に閉じ込めるだけだ」准尉の後を追っていた私の頭を、ウラジミールは大きな手でがっちり掴んだ。「勝利の女神、向こうの世界に着いたらお前にはもうひと働きしてもらうからな?」
ウラジミールは薄気味悪く笑った。その発言に込められた意味に、何かぞっとするものを感じた。なんでこんな陰険な男の言いなりにならなければならないのだろうか。パプシは奪われるし、嫌な笑い方をするし、呼び方はころころ変わるし、口は臭いし、何もかも、腹が立って仕方がなかった。
こうして船員たちは全員船倉に閉じ込められ、操舵室には計器パネルの上にどっかりとブーツの足を組んでいるウラジミールと、すでに特殊部隊の装備を解いて帝国兵の姿に戻っていた兵士たちだけになった。
無線機をしげしげと眺めていたウラジミールは、なぜか使い方を知っているらしく、迷わず番号を押して携帯のように耳にあてがった。
「こちら《大鴉(レイヴン)》、三ニ五‐○六一、《偉大なる狩人(グレート・ハンター)》の応答願う」
『……用件を言え』
「我々は現在、連合軍沿岸警備隊の保有する海上巡視船ウォーター・クラフト号に乗船し、ヨビ諸島北部をパン=ゼペルカに向けて北上している。船の位置はそちらで確認できるか」
『……確認している』
「霧の向こうの世界に帰還するために、足の付かない船が必要だ。定員は約十名、女の子が一人、指定する海上に至急寄越してほしい」
『……了解した、一時間以内に調達する。……健闘を祈る』
ウラジミールは無線を切って、にやけ顔を海上に向けた。
上手くいきそうだ、という会心の笑みだった。
4
三等准尉はその日の午後、スクルフ兄弟の元に訪れていたそうだ。
沿岸警備隊は魔法の地図を受け取る為に一度ここに訪れていたのだけれど、准尉が直接訪問するのは今回がはじめてとなった。
すなわち彼は私を救助する任務を失敗した責任者として、家族への慰問に訪れたのだ。
准尉は事実をありのまま報告した。沿岸警備隊が帝国兵たちと接触し、私が帝国兵に連れられているのを確認した事。けれども彼らをあえなく逃してしまい、私が霧の向こうの世界に連れ去られてしまった可能性があること、などである。
工場の一角にソファと机を置いただけの応接間で、准尉とスクルフ兄弟は話し合っていた。工員たちにも作業を中止させているため、巨大な工機に囲まれたその一角はやけに静まり返っている。机の上の魔法の地図には、「MISSING(探知不能)」という赤い警告文字が点滅していた。
「恐らく海上のこの地点で、帝国兵の乗り継いだ船が霧の向こうの世界に没入してしまった可能性があります」
その気になればどこまでも通じるM波通信だったけれども、霧の向こうの世界にはこちらの世界と同じ月が存在しないので、送られてくるデータはめちゃくちゃな座標を示してしまうのだった。
「……なんとかならないんですか」
DJコバタさんはすがるような目で言ったけれど、准将は静かに首を振った。
「なんとかしたいのは山々なのですが……」
「おいおい、そりゃねぇだろ? もう打つ手なしってのかよ?」
話し合いを立ち見していたドックが、呆れたように言った。准尉は口惜しそうに首を横に振るばかりだった。
「心中お察しいたします。ですがこれ以上、この事件に沿岸警備隊が関与する事はできません。連合軍本部が本件を国際紛争事件として取り扱い始めています。申し訳ございませんが、我々には出る幕がありません」
「まだパプシは信号を発しているんだ。そいつをたどっていけば、どこにパプシがあるか、方角くらいなら分かるはずだ。今から向こうの世界に乗り込んでいって、その船を追いかければ、まだとっ捕まえる事もできるんじゃないか?」
「し、しかしですな……霧の向こうの世界に立ち入る事は、法律でも禁止されているところでして……」
「おいおっさぁーーんっ!」
言い終わるか終わらないかの内に、どこからともなく応接間にゼラが飛び込んできた。彼女は三等准尉の詰め襟を掴んでがくがく揺すぶった。
「おいおっさん、アンシェを助けてくれるんじゃなかったのかよ! 何だこのざまは、任せておけっていったのはあんただろ! ああっ!?」
「い、いや、すまない」ゼラの剣幕に、准尉はただただ謝っていた。「すまない、友達の事で取り乱す気持ちは分かる……」
「と、と、と、友達なんかじゃねぇよ! ばかっ! 友達なんかじゃねぇ! 勘違いすんじゃねぇぞ!」
ばさささっと羽を羽ばたかせて、天井近くに設けられた窓に飛び移った。ゼラは顔を真っ赤にして叫んだ。
「なんだよ、見てんじゃねぇよ! うぜぇ、何も出来ないんだったらもうこっち来るんじゃねぇ! バカァ! もう知らない!」
白い羽をニ、三枚散らして、来たときと同じくらい突然去ってしまったゼラだった。
――もちろんこれは私が人から聞いた話なので、ゼラの印象が実物とは多少違っている可能性があるのは否めない。
彼女が去ってから、暫く場の空気が沈んでしまった。マルハトさんは姿勢を正して、三等准尉に詰め寄った。
「連合軍が国際紛争として取り扱うこととなったわけですね……では、具体的にはあの子の救出はどうなるんです。連合軍が代わりに救出してくれるという事ですか」
「……可能性が無いことは、無いのです」
曖昧な返事をする准尉に、三人のスクルフは不安げな顔を向けていた。准尉は帽子の下をかいて困った顔をした。
「正直に申しましょう。これは、本来ならば私が言ってはならない事かもしれませんが。……帝国と連合の関係はいままさに微妙な緊張状態に置かれています。……政府でもまとまった対応策を決めかねていて、主に戦争推進派と反対派、いわゆるタカ派とハト派に分かれて激しい争いが繰り広げられている状態なのです。そんな中で、この事件の存在は決して無価値ではないと思われます。これはごく普通の女の子が誘拐されるのとは違います。娘さんの名は、なんといいますか」
「世間に広く知られているから?」
「そう、この事件は両国の緊張状態に対して大きなブレイクスルーとなる可能性を秘めています。私の知り得る範囲では、海軍将軍などは典型的なタカ派でして。……大戦時に大佐だった彼の大雑把な性根はよく覚えていますが。……この事件を利用し、事件そのものを論拠にして、帝国に対する威圧行動にでる可能性があります」
「ダメじゃん」
「もちろん。それではダメなのです。なので、ハト派はこの事件が手に負えなくなってしまう前に、戦争を回避するための何らかの策を講じるはずです。ひょっとすると、先ほどあなた方が言われたように、霧の向こうの世界に救助隊を派遣する、という策も取るかもしれない。……ひょっとすると、前の世界大戦を終わらせたときと同様に、両国の政府高官同士で《秘密の会談》がもたらされるかもしれない。
……既に軍部が動いている状態で、たった一人の少女が救出されるという可能性は、実を言うとそういった危ない裏の駆け引きに頼るしかありません。最悪の場合は――ハト派でさえ、動かないという事態も考えられます」
スクルフ兄弟もドックも、あまりの大きな話にぽかんと口を開いていた。どうやら私が救出されるかどうかは、政治的な駆け引きの結果によって左右されるという。
「連合軍が、我々を助けてくれない? 見捨てる? そんな事があるのか?」
三等准尉が現実的なため息をついた。万策尽きたといった面持ちである。
現実が大嫌いなドックが、大げさな身振りで天井を仰いだ。
「ああーっ、くそっ、もう駆け引きだろうとなんだろうとどうでもいい、こんな時に誰か助けてくれるような奴はいねぇのかよ……」
誰もが絶望に打ちひしがれていた、その時だった。
どこからともなくスネアドラムを叩くような音がぱらぱらと鳴り響き、その場の沈痛な空気を打ち破る甲高い声が響いた。
「僕の名前が呼ばれた気がしたーっ!」
スクルフ族は三人とも聞き耳をぴんと立て、辺りをきょろきょろと見回していた。
「あ、あそこだ!」
見ると、先ほどゼラが出て行った天井付近の窓枠に、スーツ姿の何者かが後光を浴びて立っていたのだった。
この秋出たばかりの新作スーツを着て、青シャツに紺色のネクタイをかっちり締めた背の低い男である。靴は五センチもある上げ底で、実際の身長は私よりも低いと思われる。どこからともなく流れてくる陽気な音楽にあわせてつま先をあげたりさげたりしていた。
「はっ!」
謎の男は短く息を吐くと、おもむろに窓際の工機に飛びついた。彼がクレーンの鎖にぶら下がると、ごうんごうんと工機が動き始め、室内灯が昼の室内をさらに明るく照らした。
管楽器のBGMがさらに華やかになり、何かのきっかけで、工場全体に魔力がみなぎっているようだった。ダイヤモンドのように輝く明かりに照らされ、男はゆっくり降下しながら短い足を振り上げ、音楽にあわせてテノールの声で歌った。――らしい。私は又聞きなので、これはスクルフ達のジョークなのかもしれないが。
「国際事件が起きたなら♪ 俺にお任せ♪
どんな無理難題だって♪ ズバっと解決しちゃう♪
国家警察捜査局、特殊捜査官の名にかけて♪
世界の美少女をぎゅっぎゅしたいな♪
ご安心ください、お宅のお嬢さんは、我々が安全確実、五体満足、無事にお助けいたします! まずはフリーダイヤル、54D54D(ごよーだ、ごよーだ)へ、今すぐご連絡を!」
背広のポケットから取り出した私の写真にキスをしたその下劣な男は、松の種のようにくるくる回転しながら応接間の床に着地した。むずむずと足を震わせて、精一杯ぐーんと伸び上がると、ネクタイをきゅいっと締めなおしながら大声で宣言した。
「僕は東部アーディナル中央政府(EACG)、国家警察捜査局、特殊捜査官『アア=アア』! 安心したまえ、この誘拐事件は我々が預かり受ける事になった!」
椅子に座っていた者は、スクルフ兄弟も三等准尉も、そろって飛び上がった。
「『ああああ』だって!?」
「なんて適当な名前だ!」
「バカな、国家警察が事件解決に乗り出したというのか!?」
『国家警察』とは――EACG行政機関の中枢である賢者の塔が設置した巨大な警察機構の名称である。
その捜査員はいずれも秀でた魔法使いや異能力者によって構成されており、総戦力は軍部が組織した旧警察機構、『ミッドスフィア憲兵団』と比肩するとさえ言われている。賢者の塔の指令によって、決して表ざたには出ない、国境の垣根を越えた工作活動や独自の捜査を行っている。――とかなんとか言われている。
そのとき、地面や壁からキノコのように透明な人影がにょきにょきと生えてきた。いずれも何故か体が半透明で、向こうの風景が透き通って見える。
地面でのたうち回っていた泥人形じみた体が徐々に固まってくると、それらは全員美少女の姿になって、両手を挙げてアア捜査官に殺到した。きゃーきゃー嬌声を上げる美少女たちにもみくちゃにされながら、やがて工場内に溢れるほどの数に増えた彼女たちの手の上を、アア捜査官は背泳ぎで渡っていった。
「浮いた!」どうやら海兵たちにはその透明な美少女たちが一人も見えないらしくて、一様にびっくりして後ずさっていた。
「うろたえるなっ、これは彼の異能力だ」
経歴の長い三等准尉はただ一人、眼光を鋭くしてそれを睨んでいた。
「彼は我々の眼に見えない魔物、レイスたちを操る異能力者だ」
アア捜査官は空中をフローしながら、星の数を数えるように花を一輪天井にかざし、指をぱちんと鳴らした。
「ああそうさ♪ 《死霊使い(レイス・マスター)》それが僕の異能力☆
僕の捜査を手助けするのは♪ 総勢七十二人の個人秘書♪(しかも全員美少女!)」
壁際でぽかんと棒立ちになっていた海兵たちのベレー帽が、次々に飛び跳ねた。
もちろん背後に居た透明な美人秘書たちの悪戯なのだったが、海兵たちはくるくる飛びまわる帽子に蜂の巣をつついたような騒ぎまわっていた。
コバタさんたちは自分の毛を撫でようとしてくるレイスたちの手をうるさがって牙をむいていた。スクルフ族は犬っぽい特性のひとつとして、普通の人には見えないものが見えやすかったりするらしい。
アア捜査官はレイスたちと息の合った動きでフロア中を歌い踊り、あちこちで軽快なステップを踏み鳴らした。
「油断大敵♪ 死人に口あり♪ 壁に耳あり♪ 後ろにメアリー♪
万が一の時にもご安心を♪ 僕のコレクションにくわえちゃう!
難事件なら僕におまかせ、迷宮入りする前に――アア捜査!」
「アア捜査!」部屋を埋め尽くすレイスたちがぴょこんと一斉に飛び跳ねた。
「アアァァ~~♪ 捜おぉぉ~~♪ 査ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁあ~~~~!」
ノリノリで歌を締めくくったアア捜査官だった。
死霊から話を聞き出せたところで、異世界における捜査でそれがどのようにして役立つのかは不明だった。いや、ともすると彼は私を秘書レイスの一員に加えようと企んでいたのかもしれない。とんでもない奴である。アア捜査官の歌がクライマックスに達した所で、唸るような低い声が空気をふるわせた。
「引っ込んでな、このロリコン捜査官が!」
どかんと大砲が打ち込まれたような衝撃だった。それほど大きくない声なのに全員がたじろいで、レイスたちは蝋燭の火のように半分消えかかっていた。
サーコートを羽織った巨躯の男が、正面玄関に影を落としていた。黒髪に碧眼、無精ひげをのさばらせているけれど整った顔立ちをしている。だらしのないその風貌は、口元にたたえた不敵と言っていい笑みと不思議なほどにマッチしていた。
踊りを中断していたレイス達は、彼の姿を目で追いながらうっとりするようなため息を漏らした。どうやら、なかなかいい男のようだ。
その異様な迫力をたたえた男が背後にぞろぞろと引き連れているのは、緑色の軍服をまとった憲兵たちだ。三等准尉は目を膨らませてのけぞった。
「ば、ばかな、《ミッドスフィア憲兵団》だと!? ま、まさかあの男は……!」
アア捜査官は、まるで親の仇を見つけたように血相を変えて猛ダッシュした。男に見蕩れて立ち尽くしているレイスを脇にどかし、猛然と抗議をし始めた。
「いい加減にしてくれよ、リゲル大佐! こんな所まで僕の仕事を邪魔しに来たのか!? もうでしゃばらないでくれ、君の管轄はミッドスフィア近郊のはずじゃないか!」
リゲル大佐は、常人ばなれした肺活量の全てを使って大きく息を吸い込むと、驚くほどの美声を放った。
「はあああぁぁああぁぁ~~~~アアアァ~~~~~~♪」
凄まじい美声に圧倒されて、何人かのレイスたちが卒倒した。訳が分からなかった。先ほどからずっと流れっぱなしだったBGMがリゲルの声にあわせてテンポアップし、短調を多用するブルース風の曲に切り替わり、ワイルドなリゲル大佐のパートがはじまった。
「はっ、最近はやたらと退屈な事件ばかりが起きるもんでね♪
管轄、階級、身分、権限? よく分からねぇ専門用語だな、俺は元賞金稼ぎだぜ!
全てのダークサイドが俺の領域♪ 全ての事件現場が俺の仕事場♪ 全ての犯罪者のいるところがおれの狩場さ♪
不幸な美少女を救い出し、この手で抱きしめて、連れ帰ってやるヒーローに権限なんかはいらねぇだろう?
この事件は俺の《ミッドスフィア第五憲兵旅団》が受け継いだ! 邪魔する奴は消してやるから前に出な!」
大佐の左手がぐいんと伸びて、つんとすました長身のレイスの顎をくいっと持ち上げた。
「ところで、お前たちの方はどんな調子だ? こっちは就任してから半年で八五二件の凶悪犯罪を解決してやったぜ、ふふん、どうだい、惚れただろ?」
どうやら彼にもレイスの存在が分かるらしい、あんがい誰にでも見えるんじゃないのか、この死霊たち。
挑発されたとびきり美人のレイスは顔をしかめて、フレームレス眼鏡を筋肉の動きでくいっと持ち上げ、煙のように輪郭を崩しながら彼の手から逃れた。
くるくると身を翻しながら、同じく不快そうな顔をしていたアア捜査官の体にぶつかると、煙になって吸い込まれてしまった。
「ふん、数こなせばいいってもんじゃないのよ!」
アア捜査官は、突然真っ赤になってリゲルのサーコートに掴みかかった。
「アンタのせいで私たち国家警察のおとり捜査が幾つも不意になったじゃない!」
「ん? ああ、そういや何件か間違えてお仲間をしょっぴいた事があったかな。ちょっと邪魔だったもんでついな」
「賢者の塔からクレーム殺到してんのよ、どうしてくれんのよ、そのうちあんたも軍部からお叱りを受けるわよ!」
「それにしたって国家警察は凶悪犯を街中にうようよ泳がせすぎじゃないか? ああ、なるほどこれが必要悪って奴か? 悪いんだけど今回の俺の不法捜査も必要悪ってことで見逃しといてくれないかな?」
「きぃぃ~~~っ! このDQN憲兵、四十八歳にもなってまだ独身のくせにぃぃ~~~!」
アア捜査官は手の甲を噛んで目に涙を浮かべていた。だみゅ、だみゅ、と上げ底の靴が地面を踏みつけるたびに情けない音を立てた。
突然オカマ口調になったアア捜査官に、周りの海兵は奇異な物を見るような顔をしていたけれど、DJコバタさんたちは自分たちが見た一部始終を彼らに伝える必要性は感じなかった。
そのとき、先ほどまでただ沈黙を守ってばかりいた三等准尉がついに立ち上がった。
「ええいっ、黙れお前らっ! わしからも一言いわせてもらう!」
――繰り返し言うが、これはスクルフたちからの又聞きである。――
曲調はやや速度を落として穏やかなバラード風になり、三等准尉のパリッとした白い軍服がスポットライトに照らし出された。どうやらこの国の警察機構は、歌って踊れなければ話し合いができないらしい。
「おお、かわいそうにアンシェ♪ 今もこの寒空のどこかで震えているだろうのに♪
彼女の救出の為に募った勇者たちは、色ボケ警察にDQN憲兵♪
彼女の心の苦しみを♪ いったい誰が知っているだろう♪
白い翼をはためかせるジトーノの心は、我ら沿岸警備隊だけが――救えるというのに――!」
三等准尉はその場にがっくりと膝をついて、どこか痛むように胸を押さえていた。
が、やがて何かを決心したようにかっと目を見開いて、猛然と駆け出した。
「……ええい、お前たちにはもう任せておけん!」
国家警察と国家憲兵の間に割って入り、うるさい言い争いをさらに過熱させた。
「こうなったらわしが、彼女を助け出す!」
「おいじいさん、年寄りの冷や水って言うぜ?」
「黙れひよっこ、こう見えてもわしは帝国軍から霧の塔と魔弦の塔を奪還した、元海兵隊だ!」
「どうでもいいけどさ、三十年前の装備で向こうに殴りこみに行くつもりか? あぶねぇって」
「わしの武器はこの腕一本、女房の心を射止めたこの腕っ節を見るがいい!」
「だったらこの三人で勝負するかい? その方が手っ取り早いぜ」
「ふん、望むところだ、後でほえ面かくなよ?」
「アアァァ~~♪ 捜おぉぉ~~♪ 査ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁあ~~~~!」
国家警察と憲兵団と沿岸警備隊の果てしない言い争いをバックに、マルハトさんは他のスクルフたちと向き合い、鼻面をつき合わせてこっそり打ち合わせていた。
「……七ページも費やしてしまったが、この国の警察機構がもうあてにならないという事はよく分かった。こうなったら、我々の手でアンシェを救おう。それしかない」
全員一致で頷いて、彼らは盛大なフィナーレを背後に聞きながら、応接室から退出して行ったのだった。
*
「続いてのお便りは、大発明家スーベイの生まれ故郷ニューガーデンにお住まいのRN『ああああ』さんから。
『はじめまして、DJコバタさん。頭脳明晰で地位も名誉もお金もある僕の唯一の悩みは、異様に背が低いことです。
とっても嫌な仕事上のライバルが居るのですが、そいつが嫌らしいくらいの巨漢で、同じ種族なのに身長が五十センチ近く違うという、存在自体が嫌がらせのような奴なのです。
僕は誰かに見下ろされていると感じるのが大嫌いなので、自分と同じ背丈の女の子ばかりが気になってしまうのですが、その男はさらに許せない事に僕の事をロリコンなどと言ってけなすのです。
傍から見ると確かにそう思われるのかもしれません。実際、個人秘書に雇っている女の子の大半がローティーンなのは認めます。けれど違うんですっ、背丈を基準にして選んでいると自然そうなるのであって、決して僕に少女嗜好があるなどという理由からじゃないんですっ!
DJコバタさん、みんなの誤解を解くにはどうしたらいいのでしょうか?』
……そうですね、私たちバーリャ人は色んな種族と混じって暮らしていますからよく分かりますが、やっぱり自分と近しい種族に自然と惹かれるものですよね。
身体的特徴や自分の嗜好について、私たちも他の種族にからかわれる事はしばしばあります。色々不満はあると思いますが、まあ、一番の対症療法は気にしない事ですね。
良識的な人間なら、相手を傷つける事を言ってしまったら少なからず後悔しているものです。口には出さなくともね。そこで気にせずに優しく接してあげる事で、この人はいい人だという印象を相手に与える事ができる、逆にチャンスとなります。
何回も言い続ける場合は、やめて欲しいという意思さえはっきり示せば、普通の人なら時間はかかってもやめようとする努力はしてくれます。ここで怒って関係を悪化させる事の方がよっぽど損をするので、これも気にしないであげた方があなたの為です。
残念なことに、世の中思い通りにならないのは、それでもからかい続けるというコミュニケーションの悪癖を持っている人も少なからずいるという事ですね。付き合いもありますし、なかなかすぐに関係をなくすという訳にはいきません。色々手を打ってダメな場合は、もうあなたが気にしないでいる事しかできません。
要するに我々が一番になすべきことは、そういった場面に遭遇しても気にしないで居られる環境を作ることです。どんどん交流を増やしてどんどん人の輪を作っていきましょう。いい人との繋がりを増やして嫌な人のことを紛らわしましょう。
私の個人的な意見ですが、ああああさん、少しでも参考になりましたらと思います。
……えーと、この文章を書きしたためてくださったのは、個人秘書の方でしょうかね。こんな追伸があります。
『追伸、個人秘書の私から見ても、この人は十分にロリコンです』」
私はヘッドホンから聞こえてくるDJコバタさんの声に耳を傾けながら、しばらくロリコンの意味について頭を悩ませていた。
「ねぇ、ロリコンって何?」
「………」
戸口の外に見張りが居る事は分かっているのだけど、話しかけても相変わらず黙り込んだまま、無視を決め込んでいた。
私を誘拐した帝国兵たちが巡視船から乗り換えた中型船は、十名が乗ることの出来る必要最小限の大きさしか備えていなかった。
私にあてがわれた船室は殺風景、家具の一つも置いてなくて、床は切り出したばかりの材木の香りが漂っていた。修理のためにパプシを床に置いている間、背中の短い羽が寒さに時おりふるふる震えた。
修理キットが収まっているキャビネットを開くと、工具の脇の隙間に小さなランチボックスがあった。中にはエビチリのサンドウィッチが入っていて、DJコバタさんの気の利いた優しさにお腹が鳴った。
修理に夢中になっているうちに、窓の外はいつしか濃い霧に包まれていた。気温はぐんぐん下がって、どこをどう走っているのかさえ分からない。中型船はアーディナルの東の海上に定期的に現れる巨大な霧の層、《大白斑》の中に入っていた。
ゼラと一緒に東の海を飛び回っていた頃の、懐かしい記憶が蘇った。彼女に最初に忠告されたのは、「この霧の中に入ると二度と外に出てこられなくなる」という怪談めいた話だった。実際に霧の中に入って出てきた事がある、という人は見たことが無い。
ひとまず修理を中断して、口の中でぼそぼそしたパンとトマトの酸味を味わっていると、サンドウィッチの脇にメッセージカードが添えてあって、「困ったときのラジオの裏機能:五五五→七七七→九九九」と書かれてあった。
ラジオの裏機能、という文字を睨んでいると、私の中の歯車がかちりとはまる音がした。これをいじったドックが、なにか新しい変てこ機能をつけていったのだ。
帝国兵に見つからないよう慎重に、わくわくしながらチューナーを捻って、数字の順番に局をあわせてゆくと、ラジオがほのかな光に包まれて、ふわっと宙に浮かんだ。
宙に浮かんだラジオ。とつぜん七色のまばゆい光を放ち、スネアドラムがどかどかどかどか、ラッパが音階練習のようなぱぱぱぱぱぱぱぱ~ぱぱぱぱぱぱぱぱ~、そんな感じの騒々しい音を部屋中に撒き散らしはじめ、私は必死にラジオを押さえ込んだ。
「Ⅲ世ぇぇ~~~~~~~~~~~~~~~~っ!!」
騒がしい事この上ないラジオの裏機能としばし格闘しているうちに、窓の外の霧は薄れ、しっとりとした夜空が辺りを覆った。
「間もなく公国領に到着します」
戸の外から声がして、誰かが小さな声で返事をしていた。窓に張り付いて見ると、そこは一面真っ白い世界だった。
はじめて見る《凍った土地》は静かで、短調で、とても幻想的な風景の世界だった。見渡す限り何もない。ただ、海岸線に沿って煙突がずらっと並んでいて、神殿に灯されたトーチのように赤い炎を吹き上げていた。
冷気が窓からじわりとにじみ出てきて、痛くなった手を脇に挟んだ。そこは地中海で生まれ育った私が経験した事のない極寒の世界だった。後で知ったことだが、あの白い大地はすべてが氷で出来ているものだそうだ。
船は完全に凍結した大地を横切りながら進み続け、やがてうっかりすると見落としてしまいそうなほど小さな一軒の建物に横付けた。
岸壁から広い橋げたが突き出して、そのまま建物の入り口まで私達を導いていた。全体的に丸くて、膨らんだパンのように思われた。丸みを帯びた構造が雪に埋もれるのを防いでいるらしい。レンガを積み重ねたような石の継ぎ目が所々にあったけれど、ぱっと見ただけでは氷で出来ているように見える。
丸い窓からぼんやり見ていると、やがて部屋にウラジミールがやってきた。彼は私に毛皮のマントを投げ渡すと、簡潔に用件を告げた。
「降りるぞ」
「ねぇ、ここどこ? 私もうそろそろお風呂に入りたいんだけど」私が不満顔で訴えると、ウラジミールは自分も大きなマントを羽織りながら、また簡潔に答えを返した。
「ここは港町ジーリだ。風呂はもうしばらく我慢しろ」
港町ジーリを見て、殺風景で寒い場所だな、ひょっとすると帝国では、こんな辺鄙な場所でも人が多い方なのだろうか、と思っていたのは、身を切るような横風にさらされながら橋げたを渡って、ぽつんと建った例の建物に入るまでの間だった。
屋内には地下に降りる階段が真ん中にあって、他になにも無い。外よりかは温かかったけれど、入り口から侵入する冷たい風のせいで、毛皮のマントは手放せなった。
けれども、何はともあれ階段である。地下にこもった熱気と喧騒がこちらまで伝わってきて、この先に何かがある、と感じずにはいられなかった。
階段を五十段も降りると、地下に巨大なすり鉢状の空間に出た。そこがジーリの港だった。左右に船の胸骨みたいな棚が並んでいて、照明に照らされて、何艘もの船が納まっているのが見えた。
うぃーんという音を立てて、天井の一部がゆっくりとせり出して来た。どこかに乾ドックのような場所があるのか、磐木に載せられた船がそこに乗っかっていて、隙間から氷の匂いのする外気が侵入してきた。
ジーリの竜骨の一番底の層では、ちょうど荷下ろしが始まっているらしく、荷物を担いだ大男たちが忙しそうに出入りしている。上半身はタンクトップしか着ていないけれど、顔を他人に見せてはいけないルールでもあるのか、バンダナとスカーフで目以外の顔を隠していた。
驚いたのは彼らの怪力だった。自分の身長の三倍もある木箱ですら軽々と担いでいた。獣人にも匹敵するのではないかと思われた。
私とウラジミールは、スチールで出来た階段を降りて、地上から五十メートルくらいの高さの陸橋を渡っていった。
その奥の通路には左右に屋台が並んでいた。眼球が曇りそうなほどの濃密な人いきれと油っこい匂いが立ち込めていた。辛うじて判別できたのはオニオンスープの匂いぐらいだ。巨大な獣肉の丸焼きが店の前にでんと吊るされていて、それをナイフで切り裂いて売っている。天井からぶらさがった照明がけばけばしい光を放って、隣を歩くウラジミールの鎧を黄色く照らしていた。
天井にかけられたアーチにはこの世界で主要らしい十ヶ国語くらいの文字が書かれていたけれど、どれ一つとして私に読めるものはなかった。
「ベイゼル横丁と書いてある」と、ウラジミールが先に説明してくれた。
「ウラジミール、どうしてここの魔力灯、黄色っぽいの?」
「魔力灯ではない、これは《電灯》と言う。いいから私から離れるな」
もう一度警告されて、私はもっと屋台を見て回りたいという不満はあったが、ウラジミールにしっかりとしがみついた。なんだか癪なので思いっきり力を込めて、離せと言われても離さないことにした。
ベイゼル横丁はその先のモーナ・ナハト通りと垂直に交わっていた。横丁の地面より階段二十段ぶんくらい低くなっていて、チューブ状の天井は等間隔に綺麗な《電灯》が輝いていた。壁には四角い穴が等間隔に開いていて、アリ塚みたいな印象を受けたけれど、ちゃんと人が出入りしているみたいだった。
どうやら壁の向こうに建物があるらしかった。この世界では建物まで仮面で覆われて平均化しているようだ。読めない十ヶ国語で書かれた看板だけがずらりと並んでいたけれど、これも形や大きさが画一されているみたいで、ほとんど無個性だ。
港町ジーリは迷子になりそうなくらい広くて、どこへ行ってもとにかくすごい人の数だった。「離れるな」という忠告をもう何度聞いたか分からない。
鎧を着た兵士が鉄仮面を被っていたり、高貴な女性は綺麗な顔の描かれた白磁の面を被っていたり、抱っこされている赤ちゃんはお母さんとおそろいの布で顔を隠している。
中部の祭りにも仮面行列というものがあった。春を迎える為に行なわれる冬の行事で、そこでは身分の違いを超えて、みな仮面を被って祭りを楽しむのだそうだ。
けれどこの国では、仮面にすら私には分からない身分の違いが刻まれている。全員に共通する事は、とにかく顔を隠しているという事だった。
「なんでこんなに沢山の人がいるの!?」
「輸入品が目当てで公国中から人が訪れている。この世界では《グリーン・ベルト》と呼ばれる南北の緯度差が約三十度の限られた土地でしか農作物が育たない。ここで生き残りたかったら生肉に耐性をつけておくんだな。クジラ肉は食べられるか?」
「ていうか、人が多くて息がつまりそうなんだけど! もうちょっと目立たない入り口とかないわけ?」
「軍事用の入り口はあるが、私が今それを使う訳には行かない」途端に、ウラジミールの声は喧騒に消え入りそうになった。「私たちは今、任務を途中放棄してこの国に滞在しているからだ。もし帝国騎士団に見つかれば直ちに処刑されるだろう」
私は驚嘆して思わず叫んだ。おもわず逃げようとすると手を強引に引っ張られた。
「帝国騎士団に見つかればの話だ、町を守っているのは公国騎士団だから心配するな」
「やめて離して! おまわりさん助けてぇ! 変な人が私を連れ去ろうとしているの!」
「騒いでもムダだ。お前は仮面をしていない以上、人間として認められない」
「えっ、うそっ!」
やけに落ち着いたウラジミールの言うとおり、公国騎士団の兵士たちは私たちのやり取りを見てみぬふりしていた。
「人種、容姿、仕事に収入、公の場ではみな仮面が定める階級の下に平等とみなされる……翻って、仮面をつけていない者は、仮面をつけられない『獣』や『物』と等価とされる。いくら騒いだところで保護を受けられる対象ですらないんだ。だからとにかく俺からは離れるな、今のお前は、俺の付属品だ。剣と盾だ」
「……私、あなたたちが凄いのかバカなのか、よく分からないんだけど!」
「ははは、違いない」
ウラジミールは鼻で笑った。
笑い事じゃない、人として扱われない身分があるなんて初めて知ったのはショックだった。
塀や鉄格子が並ぶ通りに入ると、急に人通りが少なくなった。布で顔を隠している人はいなくなり、代わりに白磁の仮面をつけた人ばかりになった。派手な羽飾りをつけたり、装飾品や服装からリッチさが分かる人々が、空気の入った風船みたいにゆっくりと歩いていた。どうやら貴族街であるらしい。
奥に進めば進むほど塀の規模が大きくなっていって、黒い穴の開いた壁しか見えない路地側からでも、その奥の家の規模がうかがい知れるようになった。中にはカジノみたいな娯楽施設と思しき騒がしい家もあった。
そのうち、やたらと幅を利かせた巨大な塀に差し掛かった。相当な分厚さと高さだった。どこまで歩いていっても延々と塀が続いている。
永遠に続いている気がした。もう歩き疲れるくらい歩いていった先に、ようやく見つけた鉄格子の前で、ウラジミールはぴたりと立ち止まった。
バケツをさかさまに被ったような、表情のまったく読み取れない見張り番が近づいてきて、私は思わずウラジミールの影に隠れた。顔が全く見えないのに、私のほうにちらりと目をやった動きが感じられたような気がした。
「いかがなさいましたか。帝国騎士団隊長どの」
ウラジミールの仮面で、どの兵団のどの階級の兵士かぐらいは即座に分かるらしい。見張り番は慇懃な言葉遣いでたずねてきたけれど、その口調から私たちを訝しんでいるのは明らかだった。
「私は帝国騎士団の百人隊長ウラジミールだ。我が軍は任務上の都合により、貴国に寄航せざるを得ない状況に置かれた。……ゆえに公爵殿下に、我々の船の入港を認可してもらいに来た」
見張り番は、互いに顔を見合わせる素振りをした。
「恐れ入りますが、公爵殿下と帝国の不仲はご存知かと……」
「我々の一存では、帝国騎士団のお方を中に入れるわけには参りませんので……」
見張り番も困ってしまった様子で、おずおずと口を挟んだ。どうやら「ここに来るのはお門違いです」を慇懃に言い換えた言葉のようだった。けれども、ウラジミールは私の手をぎゅっと握り締め、はっきりとこう言った。
「魔法世界から公爵のお目に適う珍しい物を持ち帰ってきた、その事も併せて、ぜひお伺いを立てていただきたい」
「……」
見張り番はしばらく目線をかわしあっていた。魔法世界? 珍しい物?
私はその言葉の意味が分からなくて、暫くぼんやりしていた。
このとき、私はまだ、この世界では自分自身が『物』と等価であるという正しい認識を理解していなかった。魔法世界から持ってきた、羽根の生えた珍しい犬。それが今の私なのだった。
「し、しばし、お待ちを」一人の兵士がそう言って、慌てて中に入っていった。
「お伺いを立てて参りますので」
*
こうして私はテルマ公爵の所有物となった。
私がテルマ公爵の部屋に通されたのは、それから二時間半もあとの事だった。
普通なら数日ほど待たされるところだったそうだが、そんな事はどうでもよかった。
とにかく、私は珍しい物として公爵の部屋に連れてこられた。公爵の部屋は妖精の繭のような印象があった。薄いレースのカーテンの向こうはガラス張りで、ちらほらと雪の降り始めた氷の大地が広がっていた。今は纏め上げられている分厚いカーテンがぐるりと天井付近を取り囲んでいて、丸くくぼんだ天井には色とりどりの織物が吊るされていて、半透明の絵巻物のように私の足元まで垂れ下がっていた。
ふわふわ揺れる織物の間を歩いてゆくと、この世界にあるあらゆる種類の布に護られるようにして、ぼんやりと明るい箱型の繭のようなものがあった。天蓋から垂れ下がった紗のカーテンの向こうに人影が透けて見えて、私より先に部屋に通されたウラジミールがその前にひざまずいていた。
「有翼人とは、随分古風なみやげ物を持ってきたものね」
声を発したのは、天蓋の隣に立っている女の人だった。
確かに喋ってはいるけど、やけにうつむき加減で、ただ声を出しているだけと言った感じだった。金箔で飾られた切れ長の目は伏せられていて、誰の方も向いてはいない。彼女はお面を被っていない、ということは、この人も身分のない『物』なのだろうか。化粧をしているから、本当はそれに近い身分なのか。さしずめ通訳機みたいだ。
「有翼人が最初に発見されたのは四十八年前、魔法世界を探検してきた帝国兵の一団だと言われています。数十名の有翼人を生け捕りにして帝国に連れ返った彼らは、勝利の女神の姿をしたそれらを嬉々として皇帝アウクスⅡ世に献上した。……けれどもその軽薄な行いが逆に皇帝の怒りを買ってしまい――その場で兵士達は惨殺されたと聞きます」
意図せずあの伝承の知られざる続きを知ってしまって、背筋が震えた。ウラジミールはさらに頭を低くした。ますます低くなったその背中から、ごくりと唾を飲む音さえ聞こえた。
「そのとき皇帝は『この世界に余計な物を持ち込むな』と仰せになったそうね。これは帝王学の基本だわ。完全な統治を実現するためには例外を許したり、あるいは結果の予測がつかない新しい物をなるべく持ち込んではならない。私もそれを正しいと理解しています……けれども《テルマ公爵》はそんな考えは古臭いものだと信じている」
まるで他人の事の様にテルマ公爵と言ったその口ぶりに、私は眉をひそめた。
「そして何より異国の珍しい物が好きだから、任務に失敗して帝国に帰還したくとも出来ない遁走兵でも、有翼人を手土産にすればうまく公国領に匿ってもらえるのではと、つまりはそういう魂胆で私の有用な時間をつぶしにやってきた訳ね?」
今まで感じた事のない、不思議な気配があった。なんだろう、この人は。通訳機の人が感情を一切交えずに淡々と呟いているだけだったけれど、それでも一言一言に痺れるような威圧感があった。
公爵の姿は影しか見えないけれど、すごい人がそこに居ると思った。まるで全てを見透かしている感じがした。ウラジミールは何か反論しようと体を浮かしていたけれど、なかなか声を出すきっかけがつかめずにいた。
「公、私は……」
「いけません! 公、よくお考え直しください!」
ウラジミールの発言を遮るように、いきなり怒鳴り声が聞こえた。ビックリして振り返ると、誰かが正面の入り口から入ってきたらしい。
大きなお尻に極端に細い足で、どたどたとぎこちなく走ってくる。派手な襟巻きをしていて、アコーディオンを首に巻いているのかと思った。マントをはためかせながら部屋の真ん中を突き進んでくる大男は、左頬から口元にかけて大きく欠けた木製の仮面をつけていて、唇とでっぷりとした頬肉をはみ出させていた。
さしずめこの国のブレーンと言ったところだろうか。いかにも重鎮と言った感じだ。大勢の兵士たちを背後に引き連れて、やはり兵士たちも全員顔にはつるりとした公国兵士の面をかぶっている。けれど、どうしてこの大臣の仮面だけ不完全なのだろうか。
大臣は主との適切な距離というものを心得ているらしい、だいたい私から十歩くらい後ろの方にずさっと跪くと、大声で申し立てた。
「帝国の兵士を匿うなど、言語道断、もっての他でございます! このハルミネ大臣の仮面にかけて申し上げます、どうか考えを改められますよう……!」
「ハルミネ、今は貴方の小言を聞いてなどおりません」
ぜーはー息をする大臣を一言でやっつけて、公爵は話題をいきなり変えた。
「では、有翼人にお尋ねします」
急に呼びかけられて、私はびくっと震えた。何かの不思議な力が漂っているのか、天幕と私の間に垂れ下がっている織物がふわふわと揺れていた。
「名乗りなさい」
「……アンシェ・アンシール=アルシカ」
「《天使はかく答へき》、素敵な名前です」
公爵はアーディナルの古語にまで堪能だった。どこまで凄いんだこの人は。
「……叔母さまから貰った名前なの」
「では良い名を受け継ぎました。誇りに思うべきです」
褒められたところでちっとも嬉しくない。むしろますますプレッシャーが強まってゆく気がした。
「ところで、有翼人として献上されるあなた。あなたは本当に有翼人なのですか?」
ぎくり。
私はきゅっと胃が縮こまる思いをした。確かに私は背中に翼を持っている。今はパプシを背負っていないし、ゆっくり開いたり閉じたりしている羽根が十分に見えるはずだけれども、なんで公爵はこんな事を聞くのだろう。羽があったら有翼人ではいけないのだろうか? ウラジミールは横から口を挟もうとしたけど、結局何も言えなかった。彼が何か言ったところで、無駄な相手なのだ。
「服を脱ぎなさい」
うそ、やだ。なにこの人、変態?
その声を放ったのは通訳の人だったけれど、表情らしい表情を浮かべず、無言でただ側にかしずいているだけだった。目じりの金箔をきらりと光らせて、ただの通訳機に徹していた。
ハルミネ大臣の方をちらりと見やった。大臣は私の視線にはっと気づいて、くるりと背中を向けた。見ないようにしてくれている。ひょっとして案外いい人なのかもしれない。
「アンシェ、頼む」
沈黙に耐え切れなくて声を出したのは、平伏しているウラジミールの方だった。お前にだけは頼まれる筋合いはなかった。
うそでしょ、なにこの展開。どうして私がこんな目にあわなければならないの。どうして私は帝国兵たちが生き残る為に、顔も知らないような公爵の前で裸にならなければならないの。
それ以前に人身売買は立派な犯罪ですよ。ここは犯罪現場です。犯罪成立です。けれどもこの世界では、ジトーノは人間としては数えられないらしい。私はあくまで人以外の珍しい物でしかないのだ。
けれども、私にはそういう賢い区分けができなかった。人とそれ以外の人を区別する事は間違っていると思う。だからこそ、ウラジミールや帝国兵たちだって同じ人として命を軽く考える事が出来なかった。帝国兵だから、酷い事をした人達だから見捨てるというのは、賢い生き方なのかもしれないけれど、私にはやっぱり無理なのだった。
ちくしょう。何もかもが気に入らない、全ての重圧が私にのしかかってくる様な、ムカつく事ばかりだったけれど、私はぐっと我慢した。どの道、私がここで逆らってみたところでどうにもならない場所だった。どんなに辛くても、今はとにかく生きるしかない。
私はチュニックの裾を掴んでいた手を上げたり下げたりしていた。そのままするりと肩まで持ち上げて、頭の上をくぐらせた。胸を押さえると、心臓が自分の心臓じゃないみたいに鳴っていた。上着を脇に置くと、次の指示が発せられた。
「背中を見せなさい」
私は精一杯体を隠しながら、ゆっくり振り返った。背中の羽が緊張でぱたぱたと震えていた。
この傷は誰にも見られたくないなぁ、と思っていたのに。私の背中には、肩甲骨の間に誰にも見られたくない、深い傷があった。
肉がえぐられて、ちょうど羽の基部があらわになって、羽が動くたびに機関部分がきしゅきしゅと音を立てていた。震える羽の下に、人工皮膚が裂けて、金属でできた硬質な私の本当の体がある。兵士の鎧みたいに黒光りして、金属の裏側でハチドリみたいな心臓が拍動しているのが透けて見える。
「ほら、思った通り」
天蓋の向こうから、くすくす笑う声が聞こえた。
誰かが息を飲む声が聞こえた。見るとウラジミールがこっちを見て腰を抜かしていた。
「そんな、まさか……こんな事が!」
こ、こ、こっち見んな。男子禁制だ。ハルミネ大臣を見習え。唇を尖らせて睨みつけていると、視界いっぱいに黒い影が立ちはだかった。
背中の傷を上から下に爪がなぞって、全身が痙攣した。
「ぎゅううっ……!」
痛くはない、痛くはないけれど翼が痙攣して、あちこちあらぬ方向にびんと張っている。モーターが焦げ付くくらいに熱い。
けれども我慢した。私はそんなに我慢強い子じゃなかったけれど、とにかく、背後に立っている気配が異様過ぎて、圧倒的過ぎて、抵抗する事さえ忘れてしまったのだ。
「有翼の機械人(エカデナ)ね……素晴らしい、帝国大辞海にも、載っていないわ……」
どす黒い、と言った形容詞がしっくりくるか細い声で、背後の女性は言った。
《エカデナ》と呼ばれて、私は目をむいた。この人は私ですらその名を知らなかった、《機械人》の存在を知っている。
振り返ると、真っ黒いノースリーブのドレスから二の腕の付け根が見えた。
黒いシェードの袖ごしに異様に長い手が透けて見える。手だけで淫卑なものを思わせるあでやかな長い手だ。私の頭より高い位置に大きな胸があって、クモの巣を思わせるレースのデザインがかかっていた。
見上げると、テルマ公爵はやんわりと微笑んでいた。
これがとんでもない美人だったわけよ。私見たことないよこんな人。
「私もはじめて見ます……はじめまして、エカデナ……」
髪の毛は黒と赤の混色だった。生まれてこのかた一度も切った事がないような容量の髪を頭の上で束ねていて、ほつれた前髪が一見穢れを知らないような優しげな顔にちらほらとかかっている。顔のもう半分はツギハギだらけの巻貝みたいな仮面で覆われていて、まるでこの世界の美女が兼ね備えているべき条件みたいな人相だった。
私がぼんやり見蕩れているうちに、彼女はドレスの長い裾を引きずって、天蓋まで歩いて引き返した。
その腰がやたらと細い。足は見えなかったけれど、きっと手と同様に長くて艶かしいに違いなかった。
彼女の動きにあわせて壁際を黒いネコがとてとてっと歩いていったけど、それは彼女の影だった。平伏しているウラジミールの体の上を影のようにするりと通過していった。公爵は影までおしゃれだった。
テルマ公爵はたっぷり時間を置くようにベッドの方を向いて、やはり笑みを浮かべてくるりとこちらに振り返って、ベッドが壊れないように気を使ってたおやかに腰を置いた。紗のカーテンは開いたまま、今度は本人が声を出した。
「ウラジミール……貴方のお申し出は、却下します……」
ウラジミールは悲壮な表情でがばっと身を起こした。背が高いので疲れるのか、テルマ公爵は頬杖をついて、私のほうをじいっと見ていた。
「確かに彼女は珍しい……興味深い……そして美しい……けど、それだけ……その美しさは、けっして私を殺してはくれませんもの……」
ただ見られているだけなのに、とつぜん極寒の大地に放り出されたような絶望的な予感が過ぎった。
あの時、彼女の目がたたえていた感情は一体なんだったのだろう。羨望とか、哀しみとか、諦念とか、今でもわからない。微笑をたたえた優しい表情なのは変わらない、けれども根本的な何かが違っていた。凍てついた大地を見詰め続けて、芯まで冷え切ったような、そんな目をしていた。
「帝国騎士団が、他に良い受け入れ先を見つけられますよう……せめてお祈りしておりますわ……」
「公、お許しください、どうか寛大なご処置を……!」
他に受け入れてくれる場所など思いつかないのだろう、ウラジミールは這うように追いすがって、さらに頭を下げた。
「恐れながら、恥を忍んで申し上げます! 帝国の脅威を恐れずに我々どもに手をお貸しくださる国など、貴国を置いて他にはございません……!」
「そろそろ会食のお時間ですわ……ハルミネ、参りましょう……」
公爵が立ち上がると、着付けの女性が二人がかりで外行きのコートをはおらせた。
ハルミネ大臣も立ち上がり、周囲の兵士達もそれに倣った。もうお開きといった様子である。ウラジミールはその場に平伏して俯いたままだった。
このままでは私も放り出されてしまう。私はどうしたらいいか分からずきょどきょどして、上着のポケットに入っていたラジオの事を急に思い出した。
これしかない、と思った。チュニックを拾い上げると、ポケットに手を突っ込んだ。
「な、な、悩み事はありませんかっ!」
公爵はぴたりと立ち止まって、何この子という平然とした目で私を見てきた。氷の針が心臓に真っ直ぐすっと入ってくるみたいだった。痛いなんてもんじゃなかったけれど、私は恐怖にめげずに言った。
「悩み事があったら、解決します、どんな事でも! 私が聞いてあげます、だから、ウラジミールさんたちを、助けてあげて……!」
「チビ……お前……」
ウラジミールは顔を上げて私の方を見ていた。
「私の国に、すごいDJさんが居るの! ジペンゼで知らない人はいないくらい有名なのよ! みんなの悩みを聞いてくれて、すっごいかっこ好くて、ここには無いけど私の義翼だって作ってくれたんだから! そう、DJコバタさんなら、きっとなんとかしてくれるもん!」
「チビ……お前……」
ウラジミールさんはもう一度同じ事を言ったけれど、心なしか声のトーンが情けなさそうに尻すぼみだった。
「他力本願かよ……」
凍ったように動かない公爵は、どうやら私の到着を待ってくれているらしかった。私は上着のポケットをごそごそと探ってラジオを取り出し、勇んで公爵に差し出そうとした。
「止まれ! チビ! それ以上近づくな!」
ウラジミールの声が響いた途端、緩やかな風に前髪がふわっと持ち上がった。
気づくと布で顔を隠した侍女が二人、私を左右から挟んで立っていた。
着付けの侍女と同じ桃色の服を身に着けていて、腰に巻きつけた帯に短刀を差している。ゆったりとした袖から覗く手が、その柄を掴んでいた。
「あら……そう……」
二人の袖に阻まれてよく見えないけれど、公爵が先ほどと同じ姿勢で、ほんの少し口角を持ち上げていた。
「いらっしゃい……どうぞ、こちらへ……」
どうやら彼女の許可なく近づいてはいけないみたいだった。危うく切られるところだったとわかって、鳥肌が立った。公爵は再びベッドに戻って、両手を横に広げ、着付けの女性たちに上着を脱がせた。どうやら会食の件はそれほど急ぎではなかったようだ。カチコチになって侍女たちの間を通って、ほとんど無害そうな着付けの侍女にもびくびく怯えながらラジオを差し出すと、公爵はラジオを受け取った。
「耳に、耳に」
ラジオを手にするのもはじめてといった様子だったので、あれこれとレクチャーした。公爵は不釣合いなヘッドホンを優雅に耳にあてがいながら、じっと息を潜めていた。何をしても様になるのは美女の特権だった。
耳にあてがって間もなく、公爵はくすっと笑った。
やった。異世界でもバッチリ聞こえるなんて、さすがはDJコバタさんのラジオだ。
このラジオをいじっていたドックⅢ世が常識外れの魔改造していたという可能性について、このときの私には思いもよらなかったけれど、とにかく私の中でDJコバタさんの株だけが上がりまくっていた。
「ウラジミール……」
呼びかけられるまで息を止めていたらしいウラジミールは、はっと息を吹き返して姿勢を正した。
「この子に感謝なさい……本当に珍しい……興味深い……そして、美しい……」
気がつくと、公爵の長い指が私の頬を撫でていた。見た目以上に硬くてざらざらしていて、気を抜くと頚動脈をさっと撫で切られるような気がした。
「いいでしょう、ラジオと引き換えに、《大鴉》に公国の仮面を授けましょう……一人分でよろしいわね……」
「身に余る光栄にございます……!」
ウラジミールは鎧ががしゃんと音を立てるほど平伏した。公爵はそれに目もくれず、ラジオを通訳の侍女に預けて、さっと立ち上がった。
「伯爵の身分がよろしいですわね……どこか人目につかない辺境の……ハルミネに探させましょう……」
どうやら取り引きは終了したようだった。彼が伯爵になれば、伯爵の権限で仲間を屋敷に雇い入れる事ができる。
無事に交渉役を果たし、ようやく肩の荷が下りたと思っていると、ハルミネ大臣がしゃしゃり出て、大声で異議を申し立てた。
「お待ちください、公……!」
「ハルミネ……お前のお小言は飽きましたわ……」
「いいえ、我慢してお聞きください、これは国家の一大事に関わる事にございます!」
「まあ、いつも同じ事ばかり……」
公爵は、侍女の持っていた大きな黒い剣を手に取り、それを片手に提げて、ゆらりゆらりと大臣の前まで歩いていった。
剣ではない、先端がすぱっとVの字に分かれたそれは、巨大な黒いハサミだ。大臣は何か大変な事のように訴えかけ続けている。研ぎ澄まされたハサミの刃を、ぼたぼたと汗が落ちて行く方を向いている大臣の前に突き立て、公爵はぴりぴりするぐらい冷たい声で言った。
「たまには新しい事を言いなさい……眠ってしまいそうですわ……」
「こ、公、これはお遊びではございません……!」
大臣はとにかく必死に言い募っていた。
「昨今の帝国が、なにやら得体の知れぬ動きをしているのはご存知のものと存じあげます!
各国諸侯はこれを魔法世界への再戦の兆しと受け止め、水面下では互いに相手を牽制する算段をめぐらせ、機あらば、いの一番に帝国に取り入ろうとする動きを見せております!
今、この公国が帝国に背く真似をすればまさに格好の標的……! 列強が大挙して我が公国を敵に回すのは明らかでございます! 一時の感情に流されて、状況判断を誤ってはなりませんっ! どうか、いま一度お考え直しください! その兵士をかくまう事だけは、どうか! 三百年間、歴代公爵家に仕えてきた、この老いぼれの首にかけて!」
大臣は汗をびっしょりとかいた顎を揺らし続けていた。三百年間? 彼は今、三百年間と言ったか?
常識はずれの発言に、私は目を見張っていたけれど、強張ってぴくりとも動かない彼の顔の表面は、だらだらと汗だけが流れ続けているだけだった。
対する公爵の目には、何の感情もこもっていなかった。ただ一言、黒いハサミを持ち上げてこう言った。
「……それで何か新しい事を言ったつもり?」
ずやぶっんん!
布を切り裂く音がした。大臣の仮面が空高く飛んで、丸々とふとった両手を広げた大臣が、ぱったりと仰向けに倒れた。
室内は不思議なくらい静かだった。どうして誰も悲鳴を上げなかったのだろう。
公爵は長い手でハサミを一振りすると、二枚の刃をぱたりと閉じ、濃紺の面と白い面を交互に見せながら落ちてくるハルミネの仮面をまっすぐ突いた。仮面の細い目の隙間に刃を通す鮮やかな一突き。ハサミの先端を中心に、藍色の面がらんらんと回転していた。
「ハルミネの魂は……この仮面にこもります……明日の式典までに……《ハルミネの仮面》を受け継ぐ者は……申し出なさい……」
兵士たちも侍女たちも気を飲まれて、ただじっとその様子を見守っていた。仮面の向こうの表情は見えないけれど、きっと自分の首がはねられたように青ざめていたに違いなかった。
と、ここでウラジミールが疾風のように飛び出していった。
「テルマ公! どうか、今ここで私にその仮面をお譲りください!」
さすが百人隊長、すばらしい行動力だ。彼はたまに信じられない行動に出て私を驚かせてくれる。
私にはこの国のルールは分からないけれど、それがとても勇気のいる事だというのは、他の兵士たちの様子を見れば一目瞭然だった。だって、この時点になってもウラジミール以外、誰も仮面を継ぎたいと申し出たものはいなかったのだから。
面白い事が大好きという公爵は、にやっと口元を吊り上げ、彼の方に向きを直した。
彼女は仮面を突き刺したまま、黒いハサミをそっと彼の肩に乗せたのだ。神聖な儀式を執り行う聖職者のように頭を下げ、厳かに宣言したのだった。
「第七五九代目テルマ公爵の名に……あなたを第一〇九代目ハルミネ侯爵大臣に任命します……これよりあなたは……仮面と共に……ハルミネの魂を受け継ぎます……さあ、仮面を、受け取りなさい……」
諸々の正式な手続きを踏まない、もちろん勝手なことには違いない。けれど彼女に諌言する太った大臣はもうここには居なかった。
なんだろう、この国は。何かがおかしかった。太った大臣がすぐそこで血を流して呻いているというのに、誰も気にしていないのだ。
この国で仮面を剥がれた人は、もう人ではなくて、人だった物に過ぎないのだろうか。そんな認識で彼らは簡単に納得できるのだろうか。それとも、彼らは仮面に宿る魂こそが本体で、人間はまさに仮面を運ぶ機械にすぎないと信じているのだろうか。
ウラジミールが顔の前に突き出された仮面を両手で挟むと、左目に刺さっていたハサミはささやかな響きを残して抜かれた。
こうして簡潔な儀式はあっという間に終わり、ウラジミールはハルミネ大臣となってしまった。私の見ている目の前で、人が生まれ変わったのだ。
「では、ハルミネ……早速あなたに、最初の指示を与えます……」
テルマ公爵は、すぐに脇に跪いた侍女にハサミを預け、正面玄関に向かって布の間をゆらゆらと歩き始めた。
「会食に……参りましょう……ああ、そう……私、硬いものは……食べられませんことよ……」
5
数時間ぶりに屋敷から出ることができた私は、猛然と走っていった。
ウラジミールが公爵の会食に同行している間、私は船に居るほかの仲間たちとの連絡を取りに向かわされたのだ。
本当はこれ以上あんな奴に使われるのは嫌だったけれど、あの屋敷の異様な空気にすっかり気圧されていた私は、ここから出られるならば、とうんうん頷いて承諾した。いま思えば使者くらい公爵が用意してくれそうなものだったけれど、帝国の仮面をいつまでも公国の屋敷に預けるのは色々と問題があったのだろう。
ウラジミールは公爵の側から離れられないので、私が彼の代わりにウラジミールの仮面をかぶった。私は『帝国騎士団百人隊長ウラジミール』というなんとも偉そうな肩書きを一瞬だけ手に入れ、護送する兵士を引き連れて船に戻る事になった。ややこしい。
ウラジミールの仮面は視界が十字に狭められて前がよく見えず、大きくてぐらぐらした。すれ違う人たちがみんな私の方を見ていたけれど、どんな顔をしているのかさえ分からない。町の全員が仮面をつけている利点が一つあった、たとえ周りの人に笑われていても、それと気づかない事だ。
「ウラジミールが……ウラジミールが、戻ってきたぞっ!」
帝国兵士たちは、狭い船室で総立ちになって私を待っていた。緊迫した面持ちでウラジミール隊長を出迎えた。なにせ、隊長がすぐに戻ってくると言って出ていってから、実に半日が過ぎていたのだ。
船室にウラジミールの仮面をかぶった私がひょっこり登場すると、彼らは一瞬のあいだ固まっていたけれど、次の瞬間、身をよじって大爆笑した。
腹を抱えて壁や床をどんどん叩き、呼吸するのも苦しそうだった。普段無表情な彼らの笑い声は一分ちかく鳴り止まなかった。私はふるふる肩を震わせて、百人隊長ウラジミールの権限をフルに行使した。
「笑うなーっ! 全員、腕立て千回っ!」
ためしに言ってみたら本当に全員がその場で腕立てをはじめたので驚いた。この国では仮面の身分が物を言う。その力は絶大だ。
私も鬼ではないので五十回ぐらいで許してあげたけれど、仮面の奥の私の顔は相当にやけていたはずだ。このとき、兵士達はまだ知らなかったのだ。私にこういうオモチャを与えると碌な事がないと言う事を。
私はウラジミールの置かれた現状をなるべく忠実に伝えた。背中の傷に関する事は黙っていた。私が仮面をつけているとどうしても笑いを誘ってしまうので、隊長命令を発動してこの場だけ全員仮面を外すことにした。
「……つまり、前ウラジミールはテルマ公爵つきの大臣の役を得た、というわけか」
兵士達はウラジミールを心配しているはずなのに、既に『前ウラジミール』などという言い方をしていた。この国にはこの国のルールがあるのだろうけれど、少し悲しいと思うのは、異邦人の勝手な思い込みなのだろうか。
「こうすれば大臣の権限で、皆にもう少し高い身分をあげられるかもしれないんだって、ウラジミールが言ってたよ。全員ちゃんと騎士の身分に戻られるし、うまくすれば伯爵にだって出来るかもしれないって」
爵位を与えられるかもしれないと聞いて、みんなどよめいていた。私はまた自分の手柄でもないのに胸を張っていたけれど、よく見ると皆どことなく浮かない顔をしていた。
「……隊長はそこまで我々の身を案じてくださっていたのか」
「ねぇ、私、この国で何が起こっているのかまだよく分からないんだけど。なんで誰も大臣になりたがらなかったの? なんでウラジミールが大臣になっちゃったの? 隊長命令でわかりやすい説明を求めます」
私一人かやの外だったので膨れて言うと、髭の濃い兵士が説明してくれた。
「それにはまず、この国の仕組みを知らなければなりませんな」
最初は誰だか分からなかったけれど、脇に抱えている兜に上向きの牙がにょっきり生えているのを見て、二等兵より少し上の地位だと判断がついた。たしかベン軍曹だ。
「この国は言ってみれば巨大な演劇舞台なのです。現在は全部で五百十三種の仮面が主体となって、それぞれが自分の受け継いだ魂、すなわち役割を演じることによって国家が成立しています」
「要するに、この国ではみんな仮面の役になりきっているわけね?」
「そういう事です。……その中でも、テルマ公爵はある特別な役を与えられています。それが《反逆者》と呼ばれる役割なのです」
「《反逆者》の役割?」
思わぬ単語が出てきて、きょとんとしてしまう。なんでそんな役割が定められているんだろうか。
「珍しい物を収集し、快楽のみを追い求め、時には宗主国の帝国の意向にさえ逆らう。そういう役割を担っています。その際、時にこうして帝国からの遁走兵を受け入れることもあったようです。だからこそ前隊長は、今回もそれが起こることに賭けたのです」
「む~、ちょっと待って、逆に色々突っ込みたいところが増えちゃったんだけど……反逆者の役割が法律で決められているって、それってどう言うこと? テルマちゃん好き勝手しちゃっていいの?」
「て、テルマちゃん……も、もちろん度が過ぎれば帝国が制圧のために動きますとも。好き勝手できるというよりも、帝国がこの社会の仕組みを維持してゆく為の、必要悪としての側面が強い役です。いわゆる影の仕事を担ったり、戦の時には帝国の為に力を貸したりもします。――が」
「が」
「ひとつだけ、これだけは言って置かねばならないでしょう。……これはこの法ができた当初は予定されていなかったことですが………。初代が十六歳で死んだため、それにならって、すべてのテルマ公爵は十六歳までに殺される事になっています」
それほど難しい事をいわれた訳ではなかったのに、頭の中がパニックになった。
計算ができない。えっ、だって、それだとテルマ公爵が、十六歳以下という事にならないか。だって、あのテルマ公爵が、私と同い年。
私は思わず自分のぺたんこな胸を見下ろして、呟いていた。「うそ……でしょ」
曹長は私の驚きを違う意味に捉えた様子で、苦々しげに話を続けた。
「さらにある特別な仮面を割り当てられる為には、テルマ公爵を殺害して名乗りを上げなくてはなくてはならいといった補則まであります。
誰もそんな役割を買って出ようなどと思わないでしょう。和平などともったいつけて、物心つかない子供を養子に迎えて犠牲にするなど、じつに奇妙な伝統になってきています。貴族間で根付いた、忌まわしき習慣です。こういった物は本当に潰えた試しがない。
現在のテルマ公爵は第七五九代目に数えられていますが、これは他の仮面に比べても異様に大きな数字です。それはこの法が成立してから七五八回、実に七五八人ものテルマ公爵が、同じ風に特別な仮面を受け継ぐために殺されてきたという事に他ならない。
ウラジミールが仕えようとしているのは――そういうお方の側なのです」
*
兵士たちの言いたい事はなんとなく分かった。今もなんとなくだけど。
要するに、テルマ公爵の側に仕えるという事は、帝国兵が生き残ることのできる唯一の可能性であり、また同時に危険な賭けだったのだ。
テルマ公爵の仮面は半分が欠けていて、ツギハギだらけだった。半仮面より食事もしやすいし、いつも綺麗な笑顔が見えるけれど、本当はおしゃれでつけているんじゃない。七百回も繰り返し乱暴に殺されたせいで、修復が追いつかないぐらい破損してしまっただけなのだ。
彼女の側に仕えているハルミネ大臣の仮面も、似たような理由から左頬が欠けているのだろう。私には身分の大切さはよく分からなかった。どうしてウラジミールは自分の命を危険にさらしてまで、兵士たちに高い身分をあげようとするのだろうか。
地位やプライドを重んじる感覚は、私にはやっぱり理解できない。
会食は、港に程近いジェフトバルドのお城で行なわれていた。見渡す限り公爵のお家らしいけど、とにかく広かった。
食卓にはパンに挟んだパストゥルミ(香辛料をふんだんに使った塩漬けのお肉だ)が大量に盛られていた。野菜はほんの気持ち程度だ。外の貴族街でも見られなかった半仮面を身につけた人々がわいわい話し合っていたけれど、これは元から下半分が無いつくりの仮面みたいだった。壊れたわけじゃない。
ところで、一介の騎士だった男に大臣の役割は上手く務まるのだろうか。戦闘がある前に、なにかやらかして即刻首になりそうな気がする。公爵の命令でおっかなびっくりグラスにワインを注いでいるウラジミールをぼんやり見ていると、不意にウラジミールが私の視線に気づいた。
「どうした、チビ」
なんでここに居る? みたいな顔をされて、正直イラっとした。
誘拐したのはそっちのくせに。ついさっきまで私の事を売って生き延びようとしていたくせに。用が済んだらまるで私に興味がないとは。
本当に鳥みたいに、放って置いたらそのうち帰るだろうと思っていたのだろうか。実際、帝国船に幽閉されていたときも彼はそんな感じだったし、今でも半分はそのつもりなのだろう。本当に、こっちの都合などまるで知らないで。
私はパプシがないと飛べないんですよ。飛んで帰ろうにもそのパプシは壊れたままなんですよ。それにほら、なんというかラジオが無いと飛ぶとき耳が寂しいんですよ。というか、私はウラジミールみたいに見知らぬ世界に飛び込んで、知恵とほんのちょっとの運を使って大白斑の向こう側に脱出生還するような、そんなアクションヒーローとは違うのだ。
なんだかむしゃくしゃして憮然としていると、ウラジミールがやってきて目の前に屈みこんだ。
「仮面をつけていないと誰かに踏んづけられるぞ」
「……カッコ悪いからやだ」
「か、カッコ悪いだと? バカを言え、俺があれを手に入れるのにどれくらい苦労したと思っているんだ!」
「だってカッコ悪いんだもん。センスない、ダサすぎ」
「身分証明書にカッコ悪いも何もあるか。いいからつけておけ、ここはお前の居た世界とは違うんだぞ」
「世界が違ってもカッコ悪いものはカッコ悪いもんっ」
遠まわしにウラジミールのカッコ悪さを指弾しつつ、私はだだをこねていた。兵士達に笑われたのがショックだったのもある。
場所が場所なせいか、あるいは仮面が変わると性格も変わるというのか、ウラジミールは左半分に困り顔を浮かべて見えた。いや、本当はこいつ無愛想だと思っていたけど、仮面の向こうではいつもこんな困り顔をしていたのかもしれない。
ああ、なんでこの人は本当はいい人みたいな顔をするのだろう。根っから無愛想な極悪人であってもムカついていたのには違いないのだろうけど、要するに私は彼の事が心底嫌いなのだ。
困り顔のウラジミールを見ながら、長い指をグラスに絡めた公爵は、にこにこと微笑んでいた。
「ハルミネ……お嬢ちゃんとあまり仲良くしないで……妬いてしまいますわよ………」
もちろん冗談だったのだろうけれど、ウラジミールは即座に立ち上がって彼女の隣に行ってしまった。その後姿を見て私は鼻を鳴らした。
テルマ公爵が立ち上がると、社交場の空気が一変した。ぬきんでて背の高い公爵は、嫌でも人目を引き付けてしまう。
公爵の後ろに影のネコが続き、通訳の人がすぐにその後ろをついてゆく。ハルミネことウラジミールが慌ててその後に付き従った。置いてきぼりにされそうだった私はその横を追い抜いて、影のネコさんを踏まないように一緒に階段を上っていった。
パーティ会場は吹き抜けになっていて、その先の二階のテラスから会場全体を見渡せる構造になっていた。
公爵は手すりに両手をついて、じっと大衆を眺めていた。下階から響いていた話し声は、ひとつ、またひとつと聞こえなくなって、いつしか人々は黙って彼女を見上げていた。
「みなさん……ご機嫌麗しゅう……私は間もなく……十六になります……」
脇に居た通訳の人が、よどみなく、きびきびと同じ言葉を繰り返した。
やっぱり彼女は私と同い年だったみたいだ。これだけでも重大発表だったけど、何かとんでもない事をはじめそうな予感がする。まさか飛び降りはしないだろう。どきどきしながら見守っていると、テルマ公爵は人々を見渡しながら、本当に重大な発表を行った。
「この中に……ディートリヒが居ます……」
通訳の人が同じ言葉を繰り返すと、大衆は動揺して口々にざわめきあった。それが何か切羽詰ったような、尋常ではない騒ぎだった。
「ディートリヒって誰?」
ウラジミールの袖を引っ張って尋ねた瞬間、人ごみの中から絹を裂くような悲鳴が沸き起こった。
食器の割れる音がして、その周辺で人の動きが活発になる。細剣の輝きがひゅんひゅんと舞って見えた。どうやら、何者かが人ごみの中で剣を振り回して暴れているらしかった。
悲鳴は会場のあちこちで上がり、下階の衛兵たちが抜剣し、人ごみの中に分け入っていった。出入り口は我先に逃げ出そうとする人々でごったがえし、現場に駆けつけようとする追加の兵士たちの行く手を阻んでいた。
公爵の方を見ると、侍女たちが彼女を中心にして、左右対称の扇形の配置に並んでいた。侍女達の体のラインは床に垂れている裾までぴしりと揃っていて、金のイヤリングだけがゆれている。どうやら既にこちらは臨戦態勢のようだ。
遅れて、黒い仮面を身につけた公爵お抱えの衛兵達も、左右の階段からがしゃがしゃとテラスに駆けつけてきていた。
「アンシェ、ここから離れていろ」
ウラジミールが私を押しのけたけれど、私はいう事を聞かずに彼を振り切り、欄干に身を乗り出した。
混乱する会場の只中で、ひと際良い動きをする男が居た。白銀の半仮面を被ったその男はスノーボードのトリックみたいな跳躍でテーブルの上に登ると、テーブルの上を飛び移って兵士達の頭上を移動し、さらに普通では考えられないような跳躍で階段の手すりにまで飛び移った。
半仮面の男は素早い突き技で兵士たちの流れのただ中に潜り込んだ。階段は十歩ほどの幅がある。男一人に対して六名以上が上下から押し寄せる形になったけれど、男の剣さばきはそれらを物ともしない鮮やかなものだった。
かわす、受け止める、潜る。風のような足さばきで剣をかいくぐり、背後の攻撃は背中に目があるのかと思うぐらい的確に弾く。階段の上にいる兵士たちの足を薙ぎ払うと、次の瞬間兵士たちは宙に放り投げられ、下にいる兵士たちを巻き込んで転がり落ちてしまった。
何者だろう、この男は。並み居る兵士達がまるで相手になっていない。さらに男は階段の手すりを踏み台にし、白いマントをはためかせて再び跳んだ。今度は二階テラスの欄干に飛び移り、先ほどから口に咥えていた黒バラをぴっと顔の横に揃えた。
「やあ、愛しいテルマ、こんばんは。僕がディートリヒだ。今夜は僕と一緒に踊らないか?」
ディートリヒはちょっぴり引くぐらいキザな男だった。できればその目と黒バラを公爵に向けないで欲しい。
それを遮るようにすかさず侍女たちが立ちはだかり、短刀を握り締めて攻撃態勢に入った。
ディートリヒはひゅーうと口笛を吹くと、欄干の上でくるりと身を翻した。侍女達は瞬きをするような短い時間で移動し、短刀を男のいたところで交差させていた。
うまく逃れた男は上空でぐるりと回転して、遠く離れた欄干の上に着地した。まるで踊るような戦いだ。
目と鼻の先で展開されている剣舞をぽかんとして見ていると、ウラジミールの罵声が飛んできた。
「バカ、何を見ている、伏せろ!」
私はウラジミールに欄干から引き剥がされ、地面に押し付けられた。とつぜん目の前で爆発が起こって、ディートリヒの居た辺りと、テラスの中央が吹き飛んだ。
「ホワッッツ!?」
どうやら下の階から砲撃があったようだ。ウラジミールが私を引き離してくれたお陰で事なきを得た。彼の腕の下からテラスの様子に目を見張ると、なんとも卑下た声が耳朶をうった。
「ぐぇっへっへぇ! ディートリヒになるのはオデだぁ!」
下の階には、テーブルに乗っかって煙を吹く大砲を担いだ大男が居た。驚く事に彼もディートリヒを名乗っている。大砲の筒の裏側には魔法の紋章が描かれていて、中央にはめ込まれた石が赤い火を噴いている。《小火砲》と呼ばれる、私たちの世界では既に使われなくなった古い魔石兵器だった。
でっぷりとした太鼓腹を揺らし、身につけたお面は真っ赤で、大きな白い牙がいかにも得意そうに上を向いていた。こんなのがディートリヒ?
「ディートリヒになったらオデの部族を全員貴族にするだぁ! 凍える思いをして獲ってきた魚を横取りされた恨み、全部取り返してやるだぁ! 誰にも邪魔させねぇ! もう今日のオデは止まらねぇ! 死ぬ思いで沈没船から引き上げてきた小火砲、おうら、もう一本おまけだぁ!」
二本目の大砲を肩に担いで、ぴたりとテラスに向ける大男。また砲撃が来そうな予感に、ぎゅっと体を強張らせた。そのとき、天井付近から変な声が聞こえてきた。
「ちっ、邪魔だあのバカめ」
横目でちらりと見たけれど、テルマ公爵は同じ場所からぴくりとも動いていない。その代わり細身の兵士が一人、彼女の真上のシャンデリアを蹴って、大男に向かって飛び出していった。
布で顔を隠していて、皮製の黒いジャケットはいかにも隠密行動に向いていそうだ。向かい風を調節するように両足を前に突っ張り、黒いマントを翼のように軌道上にはためかせながら、大砲と公爵を結ぶ直線上を突き進んでいった。
名乗らなくても分かった、こいつもディートリヒだ。
左右の大砲からどどんという音が響くのと同時に極細の剣を振り、地面に着地すると同時に前転し、大男の足元を通過していった。
筒から飛び出した丸い弾は、テラスにまで届かずに真っ二つにぶち切れて落ちていった。驚くべき剣の腕だった。けれどももっと驚いたのは、この争いのさなか、テーブルからお皿を下げていた給仕たちだった。降ってくる砲弾の破片を真っ黒焦げのハンバーグみたいにお皿の上にぱしんと受け取って、何食わぬ顔をしてテラス下の給仕室にひっこんで行ったのだった。どうやら並みの給仕ではこの仕事は勤まらないみたいだ。
「悪いな、俺がディートリヒだ」大男の背後に潜んだ黒衣の兵士は、やはりそう呟いた。
ディートリヒ、ディートリヒ、またディートリヒ。みんなディートリヒになりたがっている。どうやらテルマ公爵はモテモテみたいだった。
大男の理解が今の状況に追いつくには少々早すぎる展開だ。背後に回りこんだ小柄な兵士が、隙だらけの相手に慈悲を与えるはずもなかった。
肩で相手の背中を押し上げるような格好で急接近し、ひじ打ちを食らわすようにその極細の剣を斜めに突き立て――ようとした瞬間、なぜかそうはせずに、曲芸師みたいにくるりと宙返りして脇に飛びのいた。
その直後、燃え盛る炎の柱が攻城杭のように扉を突き破って飛び込んできた。雷が落ちたような音と共に光が現れて、会場が一直線に焼き払われた。
「ぬがぁーっ!」
一瞬助かったと思った大男は全身をその炎に包まれ、断末魔の悲鳴を上げて焼け焦げてしまった。
似たような魔法は海兵隊の魔術師団がデモンストレーションで行っているのを見た事があるけれど、ここまで大規模な魔法を見たのは初めてだった。
火柱はパーティ会場のど真ん中を突っ走り、先ほどの大砲で損傷を負ったテラスをさらに破壊し、ほぼ真っ二つに分断した。テラスが激しく揺れて少し頭を打ちつけた。痛い。普段見えない給事室が焼け焦げている様子まで上から見下ろす事ができた。
「なに今の魔法、帝国にも魔術師がいるの?」
「違う、これはただの魔法剣スキル、《火炎斬り》だ……」
ウラジミールは分断されたテラスの壁際まで私を引きずって、喉を鳴らした。
「ここまで強力な《火炎斬り》を使いこなすとは……将官クラスがいるな」
私はウラジミールの声をろくに聞かず、下の階の方を見ていた。辛うじて炎の剣から逃れた小柄な兵士は、這いつくばったまま扉の方向に目を向けていた。
「ぐっ、何者……!」
けれども、彼が二つの砲弾を切ってしまうぐらい反応速度が早かろうと、敵の姿を見ることは敵わなかった。その敵は既に小柄な兵士の真後ろに回りこんでいて、大振りな剣をぐさりと背中に突き刺し、兵士の薄い胸板を地面に押しとめていたのだった。
命のやり取りなんて映画やゲームでしか見た事がなかった。嫌なリアリティに私は思わず悲鳴を上げた。血を吐いた兵士は地面にがくりと崩れ落ちた。
「ご、ご、ゴドホック騎士団長……!」
最初に現れたキザなディートリヒは、驚嘆して階段に座り込んでいた。白服はかなりすす汚れていたけど、どうやらまだ生きているらしい。
「そんな、公国騎士団の長が……ディートリヒだと!」
よく見ると、驚嘆しているのは彼だけではなかった。公国兵もそうだ。他の候補者たちは先ほど放たれた火炎の破壊力に竦みあがって、立ち上がることさえ出来ない様子だった。脇を素通りして行く獅子のような団長のオーラを浴びてぶるぶる震えているしかなかった。
一歩ごとに触角のように襟がゆれるコート、鬣のように捻じ曲がった群青色の髪、顔を覆っているまん丸いお面は、目の高さに真っ直ぐなスリットが一本あるだけで、後は蔓を象った美しい彫刻がまんべんなく施されている。
「私がディートリヒだ、異論はあるか?」
もう他にディートリヒが出てきそうな気配はなかった。居てもこれだけ迫力のある候補者が現れたら、しり込みして出てこないだろう。刃を向ける気力すら持てず、階段を昇ってゆく団長を、ただただ見守っているしか出来なかった。
けれども衛兵や侍女たちは公爵の周りで旋回し、彼女を護り続けていた。テラスに団長が足を踏み入れた途端、捨て鉢のように切りかかった。
しかし、まるで歯が立たない。
ゴドホック団長の長剣は兵士たちの攻撃を次々といなし、時おり紅蓮の炎の塊を吐き出した。その炎が軽く撫でるだけで相手を天井近くまで吹き飛ばした。見えない竜巻がそこにあるかのようだった。鎧を着ている兵士にも容易に立ち上がれないほどの強烈なダメージを与えていた。
誰が死んで誰が生きているかはすぐに分かる。死んだ兵士は鎧の中に仕込まれた魔法が発動し、肉体が消滅するのだ。いくつもの鎧がねじれて、ばらばらと足元に散らばった。肉体を失った仮面が量産されていく。
「きゃーっ、なにあのライオン! ウラジミール、はやく助けにいってよ! テルマちゃんが危ないっ!」
私は判官びいきで、ついつい公爵の守衛側になっていた。なぜなら騎士団長の力があまりに圧倒的すぎるのだ。
さっきから私に覆いかぶさっているウラジミールは、私が飛び出さないようにさらに強く押し付けていた。
「いや、私が出てゆく必要はない」
「何言ってるのあんた、本当は弱いの!?」
そう言えば、私は彼が実際に戦った姿を見た事がないので、実力のほどをまだ知らなかった。それ以前に一介の百人隊長が騎士団長に敵うものだろうか。
さきほどまで敵に囲まれていたはずの団長の周囲は綺麗に片付いており、半径五メートルほど離れたあたりに近衛兵たちや侍女たちが惨々たる状況で散らばっていた。
「どうして……」
公爵はその円の反対側に愕然と立ち尽くしていた。むき出しになっている片方の顔に、青ざめ、戦意を失ったような表情を貼り付けていた。
「どうしてなの……」
「……久しぶりだな、テルマ」
団長は悠々と公爵の前に歩み出ると、無礼にも長剣を彼女の鼻先に突きつけた。ゴドホック隊長の仮面の奥から、なんのてらいもない声が漏れてきた。
「今宵、私がディートリヒになる」
公爵はただ、ひどく驚いていた。青ざめていた。けれど、それは決して恐怖に打ちひしがれているわけではなかった。多くの護衛を失った怒りに我を忘れているわけでもなかった。ただ、目の前に現れた男を評して、素直にこう驚いていただけだった。
「どうして……お前は……そんなに弱いの……騎士団長?」
向かい合っていた団長の目線が、少し泳いだ。と思ったら、彼はお腹の辺りから火を吹いたように、背後に十メートルも弾き飛ばされた。
「ぐふうっ!」
同時に、テルマ公爵の腰の辺りから、ちぃんっ、という鍔鳴りの音がした。よく見ると彼女は脇に長い曲刀を一本ぶら下げていた。
一体何が起こったのか、息を潜めて目を見張っていたのに、何も見えなかった。
さっきの一瞬で鞘から抜いて、切りつけ、鞘に収めた。いや、それよりもその少し前に、背後の壁に飾られていたあの曲刀を取ってきて、また元の場所に戻ってくる必要があるのではないか。
徴剣から抜刀まで。すべてが一瞬の早業だった。
重たい一撃を食らった団長の勢いは止まらず、そのままゴロゴロと床を転がり、壁にぶつかってうな垂れた。むせ返り、仮面の縁から血を吹きこぼしていた。
テルマ公爵は、背後に仕えていた通訳の侍女に剣を持たせると、凄まじい声で命じた。
「立ちなさい……」
公爵が命じると、団長の背後の影から真っ黒い腕が無数に伸びてきて彼の手足に絡みついた。頭の影から伸びた腕が髪を引っ掴んで、両手両足を背後からゴムのように引っ張って、前に倒れないように足がお腹を蹴って支えていた。
何か良くないものが居る。団長の背後で、影がまるで悪魔のように動いていた。
公爵は彼の前で椅子にすとんと腰掛け、また命じた。
「座りなさい……」
足元の影が盛り上がって、ヘルメットをかぶった歩兵の影に姿を変えて、影の小銃を構えてばんっと片足を撃ちぬいた。
火薬の音と共に団長はがくんとその場に跪き、敬礼をする格好になると、少しもいたわられる事なく銃台で殴り飛ばされた。
うわっ、うわっ、もうやめて欲しい。けれども怒りが込められているのか、影の悪魔は止まらない。団長はそのまま影の大蛇にぐるぐると巻きつかれ、背後にいつの間にか出現したもう一脚の椅子に押し込められ、がちがちに縛り付けられてしまった。
今まで出てきた男たちの中で最も強いと思われた団長が、まるで手も足も出ない。仮面の下から弱々しい声が漏れた。
「や、やはり、あの噂は本当だったか……第七五九代目は《影魔使いシェイド・マスター》の異能力者だと……! ま、まさか、この私が手も足も出ないとは……!」
所在なさげな公爵の手にはワイングラスがあって、いつの間にかそこにいた給仕がワインをどぷどぷと注いでいた。
「わたくし失望……致しましたわ……」
テルマ公爵は《影魔使い》と呼ばれていた。あの速度を生み出しているのは《影渡り》と呼ばれる特殊スキル。影と影の間を悪魔的な速さで移動できる技だ。
給仕の姿はふっと消えた。一瞬しか見えないけれど、公爵の影のなかに潜り込むように消えていった。これも彼女の特殊な力だった。
そういえば彼女の影はネコの姿をしていたけれど、あれも彼女の力の一端だったのだ。もし流行のお洒落とかだったらどうにか教えてもらおうと思っていたのに。がっかりしたと同時に、憧れそうになった。
並み居るディートリヒの襲撃を切り抜けた公爵は、周囲の凄惨な状況に目もくれず、荒廃した会場でひとり椅子に腰掛け、ぶつぶつ独り言を言っていた。
「どういうこと……ディートリヒが……テルマを、殺せない……? なぜ……この国の演劇は、一体どうなるの……この先……このままでは、次期皇帝は……永久に生まれない……」
テルマ公爵自身も、自分が殺害されなかった事に相当動揺しているみたいだった。その心情は私にはとても理解できない事だったけれど、どうやら彼女が生き残っているのは、よっぽど想定外の事態だったみたいだ。
公爵は、彼女には珍しい苛立った唸り声を上げて立ち上がった。私はいつしかびくびくして彼女を見ていた。肩を怒らせ、いつものように周りに聞き取ってくれる人が居ないのにも関わらず、小さな声で呟いた。
「よろしい……よろしいでしょう……ならば、これからテルマは毎晩会食を開きましょう……十六の誕生日まで……もう日がありませんものね……」
などと言いながら、じりじりと壁際のゴドホック団長に近づいていく。
私は今度はゴドホック団長を助けて欲しいとさえ願っていた。
ゴドホック団長は体を揺すって、縛り付けてくる影からなんとか顎を抜き出すと、公爵に向かって言い募った。
「や、やめろ……もう止せ! そんなものの為に命を落とすんじゃない……! 分かっているはずだ、全ての元凶である黒竜が滅ぼされた今、この演劇を続ける事に、もはや何の価値もないのだと……!」
公爵は聞き入れようとせず、団長につかつかと歩み寄った。その表情はいつにも増して険しいものだった。彼女がいつの間にか手に持っていた一本の黒い剣は、先が割れて、二つの尖った刃物になった。鬼気迫る表情の彼女の手には、影でできた巨大なハサミが提げられていた。
「テルマ、お願いだ、その仮面を捨ててくれ。私に全てをゆだねるのだ……! この狂った国を変えるために、私はテルマ公爵を征伐し、ディートリヒにならなければならないのだ……! テルマ、君を無駄死にさせたくはない……私はお前を助けたい、なぜなら、私は……!」
公爵は傲然と巨大なハサミを掲げ、じゃきんと刃を鳴らし、斜め上から団長の首にあてがった。仮面からこぼれた血が、血管の浮き出た首筋を伝っていた。垂れる血を、公爵は感情の伴わない目でじっと見詰めていた。
「分かるか、なぜなら、私は、君がまだテルマではなかった頃を知っているからだ……! 私だ、覚えているか……!」
影に縛られている団長は、力を込めて切々と訴えていた。
「君は私にとって唯一、素顔を知り合えた友だった……君がテルマ公爵となった日、私は自分にこう誓ったのだ。いつか私が皇帝になり、君をここから救い出してみせると……○○○、我々はこんな仮面の呪縛など捨てて、新しい世界を歩むのだ……仮面の魂がなんだというのだ。そんなものはこの国に必要ないのだと、誰もが知る日が来るだろう。全てをなくして、いつか素顔で話し合おう……そして……そして……」
公爵の目は冷たく、しかし、団長を見詰めて動かなかった。
「……それで何か新しい事を言ったつもり?」
ずぶしゅんんっ
鈍い音がして、声が絶えた。
公爵はドレスの裾を翻し、通訳の女性を連れて去った。影のハサミはするりと消え、影の縛めが解けて、空っぽになった鎧ががらがらと床の上に散らばった。
「私は自分の宿命から逃げるつもりなどありません……七五八人の気持ちを代弁出来るのは……七五九代目だけだと……信じておりますのよ……」
嘘だ。きっと嘘だ。そう思った。
さっきのは、団長の口からでまかせ……公爵にそんな友達は一人もいなかった……はず。
ぽかんと口を開けていた私に覆いかぶさって、様子を見ていたウラジミールはひとりごちた。
「なるほど、噂には聞いていたが……今回の公爵は強すぎる」
6
東部アーディナルにも中世の頃に作られたお城がいくつか点在していて、ジペンゼ州にもその一つがあった。
カステラみたいな四角い形をしていた。筒を縦に二つ積み重ねたような監視塔に四方を囲まれていて、日に焼けたレンガでできた胸壁からは地中海が見えた。渡航する船を見張る歩哨の真似をするには最適だった。落書きをしたらさぞ書きごたえがありそうだった広い壁には、両脇に塔が配置された西向きの門が一つはめ込まれている。世界的にも有名な白鳥城と比べるとそれほど大きくは無いけれど、緑がとても綺麗で大好きなお城だった。
ジェフトバルドの公爵のお城は……まあまあかな、と言った所だ。少なくとも、ジペンゼのよりかは背が高くて、石碑みたいに薄く、すらっとしている。おしゃれだった。吹雪の中でも見事にそそり立っていた。
正直に言うと、悔しいけど、雪の中のお城ほど様になるものは無いな、と思った。もちろん隣の芝生はおいしそうに見えるとかいう奴かもしれないけれど、基本構造からして地中海のお城とは違う気がするのだ。
おまけにこのお城、地下には温泉もあるらしい。温泉である。地上のただっぴろい雪原に墓標みたいに突き出している煙突からは、白い湯気が絶え間なく噴き出ていた。
聞きかじった所だとセントラル・ヒーティングとかいう仕組みで、地熱を利用して温かい水蒸気を城中に巡らせ、自然の暖房にしているのだそうだ。
そんな事よりも温泉、温泉である。私の行動原理は基本的に犬なので、温泉も大好きなのだった。ごめん、犬はあんまり関係なかった。とにかく侍女の立ち話からそんな情報を手に入れた私は、早速お風呂を借りることにした。
地下に行けば行くほど濡れて黒っぽくなる階段を最後まで降りると、水蒸気を閉じ込めた洞窟のような一室に突き当たる。
部屋のさらに奥のほうに明るい小部屋があって、視界をさえぎる蒸気に悪戦苦闘しながらたどり着くと、誰かの付き人が慌てて私を呼び止めた。袖のゆったりとした小姓の格好をしている。のっぺりした仮面で顔は見えないけれど、声は少年のようだった。
「いま使ってるよ」
「誰が入ってるの?」
「ハルミネ様」
「ウラジミール? ふーん。じゃ、構わないか」
もともと裸を見られることにさほど抵抗の無かった私はその場で服を脱いで、小姓を慌てて俯かせた。引き戸をがらがらと開けると、その先にはウラジミールが居た。中央の台に裸で寝そべって、女の人に垢すりをされているところだった。
ウラジミールもここでは仮面を外していて、私の登場を気味悪がっている表情がありありと伺えた。
「なんだチビ」
「なんだとは何よ。あのね、私お風呂入りたいって言ってたでしょ。聞いてなかった?」
「だからって、俺が入っている時に入ってくるなよ」
「お互い様よ」
「お互い様っていわねぇよ」
「ねぇ、このお風呂の水、異様に冷たいんだけどどうしたの?」
「それは水風呂だ、サウナだここは。公衆浴場なら降りるところが別だ」
「うーん? よくわかんないけど、ここでいいや」
「なんでお前が決めるんだ。おいこら、だからそこに入るな水風呂だぞ。やめろ、犬みたいに髪をぶんぶん降るな、冷たいだろうが」
ウラジミールがあんまりうるさいので、壁際の段差に腰掛けて温かい水蒸気を浴びた。じりじりと肌が熱かったけれど、私のこの機械の体は汗をかかない。ジェネレーターがうんうん唸って、冷却水を耳の後ろから指先までぐるぐる巡らせていた。
「ねぇ、私のこと変だと思う?」
「……色々ありすぎるが、たとえばどの点が変だと思うんだ?」
「たとえば、機械で出来ている事とか。羽とか、体とかが」
「変だな、すべてが変だ」
ウラジミールはあっさりと言い切った。もうちょっと言い方というものがあるだろうのに、と私はぐぬぬと堪え、羽をぱたぱたさせていた。
「気にするな、魔法世界の物事はたいてい俺たちにとって変なものばかりだ。空を飛ぶ船に、巨人族に小人族、そんなもの、俺たちの居る現実世界では常識の埒外の存在だ」
「そういう意味じゃなくて……うーん。そう言うのを言って欲しいんじゃなくてさ」
ウラジミールはさほど気にしてない、という意味で言ったのだろうけれど、私が求めていたのはそういう言葉ではなかった。
機械人、エカデナ。何故か体が機械で出来ている人間。
ひょっとすると、彼らなら私が何者であるのか知っているのかもしれない、そう思ったのだ。私の世界では誰も教えてくれなかった、コバタさんもマルハトさんも、誰にも知られないように気を使っていた。自分自身を表す言葉を、この世界の公爵が知っていたのだから。
「ねぇ、ウラジミール」
「ハルミネだ」
「ウラジミールが本当の名前でしょ?」
「本当もなにも、ウラジミールも他人から受け継いだ名前だよ。その前はシオン軍曹だった。その前はエド士官候補生、その前は……」
「もう慣れちゃったからウラジミールって呼ぶわ。ねぇ、この国ってなんでこんな変なルールがまかり通っているわけ?」
「そんなに変か?」
「ていうか、人の仮面を受け継ぐのって、正直ちょっと嫌じゃない? あ、ひょっとして仮面が本体で、みんなは仮面の魂とかに操られちゃったりしているわけ?」
「……やれやれ、お前の発想はいかにも魔法世界的だな」
ウラジミールは深く息を吐いた。
「質問が多すぎていちいち答え切れんが、一言で言えば、実際の生身の体の存在価値など、どんな社会体系でも似たり寄ったりじゃないか? そうだな、元々ここは極寒の土地だから、みな冷風から肌を守ろうとするだろう。だからみんな仮面を身につけるようになったのさ、そういうことだ」
「嘘だ。なんか超適当な事言ってるでしょ……」顔がにやけているのですぐにばれた。私が苛立っていると、彼は顔を背けてさらに苦笑した。「じゃあ、だれがこの法律を決めてるの?」
「皇帝だ。正確には、アウクスⅡ世と呼ばれる《皇帝の仮面》を受け継ぐ者だ。この法律はもともと三百年前、黒竜に家族を殺され、復讐を誓ったアウクスⅡ世が、黒竜を退治するために国を巻き込んではじめたとされている」
ドラゴンとの壮大な戦いを繰り広げるために、始まったこの演劇。またもや不思議な話で、私は首を傾げた。
「……仮面で竜が倒せるわけ?」
「恐らく無理だろう。それよりも防御の意味合いの方が強い。途方もなく寿命の長いドラゴンが、人間の国と戦うときに最も有効な戦術は何だと思う? 国力が衰退するまでただひたすら待つ事さ。アウクスⅡ世が始めたのは、何百年、何代に渡って続くとも分からない戦いだ。その間、ドラゴンはこの国を滅ぼす隙を虎視眈々と狙っているのだからな。もし国内で有力な戦士が相次いで死ぬような年があれば、そこが狙い目だ。ドラゴンがそれに勘付いた途端、気に攻め込まれる。それを防ぐための作戦、そういう事だ。……つまり、三十年前にお前たちの世界で黒竜が退治されてしまった時に、この演劇の本来の役割はもう果たされているのだがな」
「もう終わっちゃったのに、それでもみんな続けてるんだ?」
「本来の役割以外にも沢山の役割が結びついてしまった。特に政治と深く絡んでしまっていて、すぐに廃止するという訳にもいかなくなった。さらにアウクスⅡ世の仮面に関しては、三百年の戦いの間に仮面を受け継ぐ資格を持った王族の血脈が途絶えてしまっている。それで今では……」
「ディートリヒだけがその仮面を受け継ぐ事になっているのね」
「そうだ。現アウクスⅡ世が法を変えようとしない以上、誰かが次のアウクスⅡ世にならなければならない。演劇が終わるとすれば、次のアウクスⅡ世が決定した時だろう。……なにか、納得いかないという顔だな」
ウラジミールは私の方を見ずに言った。半分半分だ。それなりに理解できてきた私は、やはりそれなりに頬を膨らませていた。
「竜を退治するなら、最初っから皆で協力しあえばいいじゃない。なんでテルマちゃん一人が除け者にされなくちゃならないの? あんなに強いんだからさ」
一つの敵と戦う為に国民が一致団結するというのは、現実的にはとても難しい事なのだ。それは言われなくても分かっていた。特にここは、いくらでも奇跡を起こせる魔法がある世界ではない。必ずどこかに不満の捌け口が必要となる。
けれども、ウラジミールはそんな事は言わなかった。一瞬黙って、私の顔を見詰めていた。
「さあな。そればかりは、私にも分からないな」
彼は考え事をするようにうつ伏せになった。彼の頑丈な背中には、鎧に締め付けられた跡がくっきりと残っていた。鋭利な刃物で裂かれたような傷跡も幾つかあった。
人生と演劇、役者と役割。この世界に終焉が来るとすれば、それは一体どのような終わりかただろう。
現実の肉体に存在価値がないのならば、では、彼が負ったこの傷は一体なんの為に存在するのだろう。
「簡単よ……黒竜の正体が……初代テルマ伯爵だったからです……」
がらっと引き戸が開いて、テルマ公爵が入ってきた。全裸だった。
「ディートリヒは二百年前に帝国に再来した彼女を撃退し……王族に名を連ねた英雄なの……だから今のような法ができたのです……」
ウラジミールは、私が入ってきたときとは全く違う反応速度を見せた。軽快に台から降りて素早くその横に跪き、汗をびしっと飛ばして頭を垂れていた。ゆっくり歩いてきた公爵が代わりにその台に腰掛けて、うつぶせに寝そべった。どうやら場所を譲ったらしい。
「私の時は場所を譲ろうともしなかったくせに……」
文句をたれたところで反応は無かった。ウラジミールはだらだら汗をかいて、顔もあげられない様子だった。いや、だって、今の状況では上げられないだろう。彼の顔の横でうつぶせになったテルマ公爵は、とにかく胸がすごいことになっていた。お肉ばっかり食べているからなのか。都合のいいときだけ語彙が貧弱になって誠に申し訳ないが、そのとき私の目の前には、見たことの無い生き物が寝そべっていたのだった。
「テルマちゃんって凄いね」
「チビ、お前は少し黙っていろ」
「なに食べたらあんなに大きくなるんだろう?」
「チビ、どうせお前は成長しないから、黙っていろ」
ウラジミールが見せた精一杯の反応だった。私は彼の背中に水滴をびゅっと投げつけてやった。公爵は踵まで届くような長い髪を侍女に梳いてもらいながら、私の顔を見てにやにや笑っていた。
「何を見てるの?」私は首をかしげた。
「気にしないで……あなたの向こうの天使さんを、誘惑してるだけだから……」
不思議な返し方だった。これもこの世界独特の風習とか言い回しだろうか。というか、この人の話し方そのものが独特だ。いったい誰を誘惑しているつもりなのだろう。
うーんと唸って首をかしげていると、ウラジミールは消え入りそうな声で言った。
「で、では、私はこれにて失礼致します」
「許可しません……そこに居なさい……」
立ち上がろうとしたウラジミールが、また元の跪く姿勢に戻った。大臣のお勤めは大変である。
きっと言おうとした用があったから呼び止めたのだろうけれど、それに気づかなかった私は横から話を遮ってしまった。
「ねぇねぇ、天使さんって、誰のこと?」
「私たちの世界では……背中に羽の生えた神様のメッセンジャーの事をそう呼ぶの……」
「えっ、羽の生えた人? ひょっとして、私の事? う~ん……悪いけど、私はパス。だって、私は他に好きな人がいるのよ」
「違うわ……ラジオの向こうに居る人の事よ……」
「それって、DJコバタさんの事? ええぇっ、て、テルマちゃん。ひょっとして、コバタさんが、す、す、好きになっちゃったのぉ? ダメダメ、ダメだよぉ、それはダメ」
「いけないかしら?……顔も知らない人と恋に落ちるのが……この国では普通なのよ……」
「あ、あのね……私はコバタさんの顔、知ってるけどさぁ……テルマちゃんとは、ちょーっとつり合わないというか、かなーりつり合わないというか、行き場がないというか、なんというか」
「あら……貴女も彼の事が好きなのね?……」
「ぎゃーっ!! えーっ、ちょっと待って私そんなんじゃないそんなんじゃないからやめてーっ!!」
私と公爵はウラジミールの事などすっかり忘れて、延々と女の子の会話を繰り広げていた。ウラジミールは可哀想なくらい茹で上がっていた。さすが帝国兵、彼らの忍耐強さは賞賛に値する。
「ああ、忘れるところでしたわ……ハルミネ……」
テルマ公爵はようやく用事を思い出して、ウラジミールに声をかけた。
「明日も会食を開きます……仕立て屋の手配を、お願いね……」
「……御意に」
短くそう答えると、ウラジミールはようやくサウナからの退出を許可された。立ち上がった瞬間、ちょっとふらついた。鼻血が出ていた気がする。
ウラジミールが退出して、テルマ公爵と私は二人きりになった。
「テルマちゃん、機械人ってなに?」
公爵は、面白い事を聞いたように微笑んでいた。
「あら……アーディナルの神話よ……エカデナ……かつて機械の体を持つ神エカ神になぞらえて……そう呼ばれる種族があったの……この現実世界にもいたそうよ……」
「どんな種族なの? 誰が作ったかわかる?」
「さあ……ある日突然、空から降ってきたそうよ……誰が作ったのかわからない……どうして動いているのかも分からない……ひょっとすると、魔法世界でも現実世界でもない『第三世界』からやってきたのかもね」
「『第三世界』……三つ目の世界? そんな世界があるの?」
「わかりませんわよ……空に……上下逆さまの世界がある……昔の人は、そう夢想していたこともあるのよ……」
暫く公爵と談笑していたけれど、髪の手入れに数時間かかりそうなので、とうとう私もギブアップした。
サウナからよろよろと這い出てすぐの所で、着付けの女性が替えの着物を胸の前に抱えていて、私に向かってにっこり微笑んでいた。どうやら私にくれるらしかった。
木綿を使った生地はこの世界では非常に高価な一品だ。どうやって作るのかは知らないが、普段は石油から作っているらしい。柔らかい生地の衣に袖を通していると、相変わらずつんと澄ました表情の通訳の人がやってきて、思いがけずお礼を言われた。
「ありがとうございます、公に代わってお礼申し上げます」
彼女の仕事は、公爵の発言を正確に伝えるだけだった。彼女は公爵の内なる気持ちも代弁してくれたのだろうか。
たぶん、いやきっと、公爵と女の子の話ができるような相手は、今の今まで居なかったのだ。
仮面と役割に支配された国でも、私たちが普段知っている力は、変わらず存在しているんじゃないかと思う。
自分に課せられた役割以上のもの、役者の気持ちや、生身の体の価値もそれなりに価値があって、みな黙ってはいるけどその価値を少なからず知っているのだ。
テルマ公爵が一体どんな気持ちで今の役割を担っているのか、私があれこれ考えてみたところで意味のない事だろう。けれども、彼女と過ごした日々を思い返すたびに、私は考えてしまう。彼女は不幸だったのだろうか?
交渉役を果たした時点で私の用事はとっくに済んでいたのだけれど、パプシが壊れている間、空を飛べない私は城に逗留し続けていた。
公爵はすっかり私のラジオの虜になっていた。使い方がよく分かっていないのか、時々ラジオに向かって話しかけている。ええそうね、とか、それはこうしたらどうかしら、などと。ちょっと恐かったけれど、やっぱり何をしても絵になる美少女だった。
公務中でも食事中でも決まってラジオを聴いていて、私はその間ずっと側にいるように申し付けられた。特に何をするでもない、片隅でネコの影とじゃれあっていたり、絨毯をごろごろ転がっていたり、ふわふわ浮かんでガラス窓にへばりついたりしていた。
DJコバタさんのLISが始まる頃になると、居ても立ってもいられなくなる。文机に顎を載せて、うーと目で訴えかけたり、横からヘッドホンに頭を押し付けて、むりやり音を聞き取ろうとした。
本当は邪魔だったろうに、公爵は文句も言わなかった。懸命のアプローチが功を奏したのか、ヘッドホンを外して、私と一緒に耳を押し付けた。
「次のお便りは、クレープ発祥の地メージュにお住まいのRN『骨ホリック』さんから。
『はじめまして、DJコバタさん。ブリック大学病院所属の『骨ホリック』と申します。(はじめまして)
早速ですが、私の信じられない体験談を聞いてください!(おお)
先日、同じ大学出身の友人とベッラ・キニヤでクレープを食べていたとき、私は世にも不思議な現象を目の当たりにしたのです。
その友人は私と途中まで楽しくお喋りしていたのですが、店内にLISのラジオ放送が流れると、とたんに口数が少なくなってしまったのです。
彼だけではありませんでした、周囲の人たちもぴたりと会話を止めていました。ぼんやりと空ろな目をして、どうやらLISに集中しているらしいのです。友人は私がどのように話しかけても反応は薄く、私の声が耳に届いているのかさえ疑わしいほどでした。
しかし、それも一時のこと。LISが終わったとたんに彼らはまた元のように話し始めたのです。
さっきはどうしたの? と聞いても、なにが? と返事をするだけで、どうやら友人にはまったく自覚症状がなかったようなのです。
それだけではありませんでした。勤め先の病院でも、LISが流れる時間帯になると無意識の内に活動が遅くなってしまう患者が何人か見受けられたのです。
このような症例は、私も今まで聞いた事がありませんでした。ですが彼らに共通する事は、全員が東地中海の出身だったということです。
この症状に興味を持った私は、東地中海についてさらに詳しく調べてみました。するとLISの町、セオフィールドに関する、ある驚くべき噂が耳に飛び込んできたのです。
セオフィールドではLISが流れている時間帯はみんな家にひきこもり、道路に人通りがまったくなくなってしまうのだそうです。
さらにLISが流れている間はどんな重要な会議でも中断されて、マフィアでさえLISが流れている間は発砲してはならないという不文律があって、動物たちはみんな静かに木陰で休んでいるのだとか。LISが終わったとたんに町がいつもどおり活発に動き始めるとの事。
この噂が本当だとすれば、これは大変な事実です。まさしくLISが時間の流れを止めているとしか思えません。私はこの症状を《セオフィールド症候群》と名づけて、近々学会で発表しようと思っています』
……それってみんなお昼だから休んでいるだけじゃないんでしょうか?」
「ベッラ・キニヤ(大手甘味店の店名。店長のベッラ・キンから)って、何かしら?」とか「キュープ(生クリームを大量に包んだちょい硬めのクレープ、ジャム入りがおすすめ)って、美味しいのかしら?」とか、向こうの世界の分からない単語が出てくるたびに尋ねてくるので、私も公爵の質問にひとつひとつ答えていた。
いま思うと、公爵はラジオを通じて敵国の情報を収集していた事になるのだろう。けれど、その時のテルマ公爵が何を考えてそんなことをしていたのか、本当にラジオの向こうの世界を敵国だと考えていたのか、私には想像もつかなかった。
あの時の私の位置づけは今でも謎のままである。捕虜? 辞書? ペット? 居候? たぶん、どれでもなかった。あの頃の私の存在が捕虜の仮面、辞書の仮面、ペットの仮面と置き換えが可能なわけではないし、人知れず公爵の中に芽吹いていた新しい気持ちに名前をつけることはきっと難しいだろう。
私の役割は帝国大辞海にも載っていないはずだ。それに名前をつけるにはまったく新しい言語が必要だった。お喋りと、くすくす笑いと、ラジオの音楽を組みあわせた、まったく新しい言語が。
「みんな誰かに……自分を知ってもらいたがっているのね………不幸を……共感できる誰かと……分かち合うことが…………不幸………」
ある日、いつもの通りラジオのコラムを聴きながら、『不幸』という言葉に詰まったテルマ公爵は眉をひそめて、ひとしきりむーんと唸って、いつものように私に微笑みながら尋ねた。
「『不幸』って、甘いのかしら?」
もっとも不幸な者は、不幸な人生の中で一時だけ幸福を知ってしまった者だと言った者が居る。
その人はきっと他人の身に起こることのなにが幸福でなにが不幸か、自分ならきちんと言い分ける事ができると考えている人なのだろう。
生まれたときから巨大な演劇に巻き込まれ、振り回されている彼女の人生を、彼ならばそれは不幸だときっぱり言い切れるのだと思う。けれど私にそれはできなかった。
自分を不幸にした演劇を成立させるために、人生を終わらせてくれる相手を探し続ける、その人生をやはり大いなる不幸と言うのだろう。それは私にはとても背負ってゆくことはできない途轍もなく巨大な責任だった。
けれども、それでも、やっぱり私は考えてしまうのだ。彼女は果たして不幸だったのだろうか?
テルマ公爵はそれからの一週間、毎晩貴族たちと豪華絢爛な会食を開き、あるいは呼ばれもしない会食に自ら乗り込んでゆき、そしてこう宣言した。
「皆さん……ご機嫌麗しゅう……この中に……ディートリヒが居ます……」
そして乱闘が始まる。いつもウラジミールと共に屋敷に舞い戻ってくる。傷ひとつ負わずに興ざめした顔で戻ってきた日もあれば、傷を負って青ざめた顔をして戻ってきて、腕から真っ赤な血が滴っていたときもあった。その日は召使いたちが手当てのために城中を駆けずり回って大騒ぎしていた。
常に死と隣り合わせの彼女の人生に比べれば、私の生き方は真っ直ぐではなかったけれど、間違いなく幸福だった。たぶん。翼は半分しかなかったし、同じ種族の仲間にはいじめられるし、誘拐されたりウラジミールみたいなのに出会ってしまったのは別問題として、私の人生は決して自分の手を血に染めなくてはならない事はなかったし、いつも側にはスクルフたちや、獣の工員たちがいてくれたのだ。
DJコバタさんの声は今も私の胸の中に息づいて居て、私はそこから思いがけないほど多くの力を得る事が出来た。夜に暖炉の前で丸まって眠るとき、幾つもの思い出を引っ張り出すとき、私はいつも幸福を噛みしめていた。
だから、あのラジオを彼女にプレゼントしてあげようと思った。気に入っているのならそうした方がいいと思った。けっして彼女に同情したわけではなかった。
彼女は強い、私なんか居なくても、たった一人でも生きていける。なんだかよく分からない役割の私は、なんだかよく分からないまま、こっそり元の世界に消えてしまおうと思っていた。
*
月の綺麗なある夜に、私のパプシは完全に回復した。珍しく雪は止んでいて、風も微風、飛ぶにはこれ以上ないという天候だった。
お城の人もすっかり私の事を認知してくれたみたいで、公爵の留守中に廊下を歩いていても、すれ違いざまにお辞儀をされただけで済んだ。
それでも私はびくんと飛び跳ねて慌ててお辞儀を返した。服の中に食糧を詰め込んでいたので、立ち振る舞いはかなりぎくしゃくしていた。怪しまれなかっただろうかとか、兵士に通報されないだろうかとか、食糧庫から食べ物が盗まれている事に誰か気づかないだろうかとか、もうドキドキしていた。
公爵の部屋の隣にある倉庫を見つけても、忍び込むのは結構命がけだった。ほんの少しだけ開けたドアの隙間に身を滑り込ませ、ドアを勢いよく閉じた拍子に、足の指を挟んで悶絶した。
なみだ目になって見渡すと、その倉庫には珍しいものの収集が大好きな歴代のテルマ公爵が、三百年をかけて集めた収集品が置いてあった。
公国は大白斑に近いせいか、私たちの世界の物もたまに海岸に漂流してくるみたいだった。三十年前の飛行機事故の記事が載った雑誌、古びた魔法道具、見覚えのある正方形の海賊の面なんかも飾ってあった。
美術館が開けそうな量の絵画や彫刻が、棚に何層にもなってぎっしり収まっている。そんな棚と棚の隙間に、季節外れのテントウムシみたいに私のパプシがうずくまっていた。
ウラジミールの船から運び込んで、修理キットを使って少しずつ修理を試みていたのだ。
私に修理できるのかって? 伊達に機械工場で育ったわけではない。少しずつではあるけれども、元の機能を取り戻して、一ヶ月も経った頃にはほとんど直りかけていた。
ちかっちかっと緑色に光ると、以前のように緑色の魔法陣をふわっと吹き上げて、私の目の前にテントウムシのように浮かび上がった。
お帰り私の翼。私はテントウムシを力強く抱きしめた。そうだ、私だってやればできるのだ。一人だってきっと大丈夫だ。
どれくらいの旅になるかは分からないし、何日分の食糧が必要かもわからない。キャビネットに食糧をぎゅうぎゅう詰め込んだ。さすがに重くなったかもしれないと考え、試しに背負おうとして、振り返った時だった。倉庫の入り口にテルマ公爵が佇んでいて、私を見ているのに気づいた。
全力で叫びそうになった。全身の力が抜けて、その場にへなへなと座り込んだ。声も出せなかった。涼しげな微笑をたたえていた公爵は、ゆるりゆるりと、真っ黒な裾を引きずって、危なっかしい足取りで近寄ってきた。
この数週間の出来事が一気に頭の中を過ぎった。主にクビを刎ねられた家臣たちの事が。なにか新しい事を言わなくちゃ。新しい事、新しい事。と必死に考えをめぐらせていたけれど、私の思考は空回りするばかりだった。このままだと間違いなく私もクビだ。鳥肌の立った首を手で抑え、目の前に迫ってくるテルマ公爵に目を見張っていた。
テルマ公爵は、長い体を折りたたんで私の前にしゃがみ込んだ。身につけていた白いヘッドホンを外して、それをそっと私の耳にかけた。低音が一定のリズムを刻んでいる。DJコバタさんの声はない。今の時間帯は、リクエストのあった音楽がランダムに流れているのだった。
テルマ公爵は、友達と内緒話をするような、ひそひそ声で尋ねてきた。
「これは……何という曲?……」
とても激しい曲だった。ドラムセットと、乾いた音を響かせる弦楽器、社会体制への反抗心を叫ぶ歌。恐らく、この帝国には決して存在しないであろう音楽形式だった。
「……『ロック』……です……たぶん……」
私もひそひそ声で返答した。がくがくと震えて、まるでいけない事をしているみたいだった。屋根裏で秘密を共有する姉妹みたいに、テルマ公爵も小声になって、いけない事のように、私に言った。
「そう……『ロック』……いい歌です……」
公爵は私の頭からヘッドホンを取ると、自分の耳に押し当てた。ゆっくりと立ち上がると、くすくす笑いながら、ゆらゆらと去っていった。
汗がどっと出る代わりにラジエーターがうんうん唸っていた。彼女があんなに笑ったところなんて今まで見たことない、どうやら、相当ラジオの事を気に入ってくれたようだった。
「テルマちゃん」
言うなら、今しかないと思った。あのラジオと引き換えに、私は元の世界に戻るのだ。
「私、お家に帰ろうと思うの」
公爵は立ち止まって、ゆっくりと私の方に振り返った。その目は出合った時に感じた、凍った大地の印象を彷彿とさせた。空虚で、壮大で、寒々しい。雪が降ってくる直前の灰色の空の色をした目だった。
恐くなかった訳が無い。何も悪い事はしていない筈なのに、とてつもなく恐かった。けれども、心の中では震えながらも、私は最後まで言い切った。
「だからもう、バイバイ……ラジオは、大切にして。ちょっと早いけど、お誕生日プレゼントよ。……私、お家に帰るね。ラジオをずっと聞いててね。いつか、私もラジオに出演するかもしれないから。そしたら……そしたらね、私、好きな人に告白しようかと思ってるの。ラジオで告白するなんて、コバタさんもたぶんビックリすると思うの。……そ、それで……」
かたーん、という甲高い音が鳴って、私は身をすくめた。
テルマ公爵の手から、ラジオがすべり落ちたのだった。公爵はその手を真っ直ぐ私のほうに伸ばして、裾をずりずり引きずりながら、少しずつ私のほうに近づいてきた。正直恐かった。今にも逃げ出したかったけれど、逃げ道などどこにもなかった。それ以前に足が動かなかった。
泣いている? 泣いているの?
はじめて二本の足で歩く赤ん坊みたいに顔をくしゃっとゆがめて、一歩一歩、ぎこちなく歩いてきた。
公爵は長い腕で私をぎゅっと抱きしめると、一言こう言った。
「行かないで……」
うそ――――――っ、可愛い――――――――っ!?
結局、私は逃げられなかった。
彼女が私に言ったのは本当にただその一言だけだった。すすり泣くことも、同じ言葉を繰り返す事もせず、倉庫の奥で横になって、私をただぎゅっと抱きしめていた。
時計がなかったので、二人がどれくらいそうしていたかは分からない。遠くから兵士達の呼び声が聞こえた。
すると公爵はスイッチが入ったように体をこわばらせた。仮面を手に取って、ゆっくりと立ち上がると、倉庫から出て行った。どうやら会食の時間が訪れたらしかった。
私はぼんやりとそれを見送った。パーティに赴く時の彼女の後姿は、いつも堂々としていて、それでいて危うげだった。
光の残滓を反射する仮面を身につけながら、彼女は少しの間だけ私の方を振り返っていた。
「行きなさい……」
そうなのだ、私は彼女のことを不幸だなどと、上から目線では決して語れなかった。テルマ公爵はこれまで私が知り合った中で、最強の女の子だったからだ。
その夜のうちに、私はジェフトバルド城から出て行った。雲のない空の方が寒く感じられた。
空には輪っかのない月が浮かんでいた。この世界の月には輪っかがなかった事を始めて知った。
7
「続いてのお便りは、なんと国外から頂きました! ジェフトバルドにお住まいのRN『テルマ』さんから。
『コバタさんのお話をいつも楽しく拝聴させて頂いております。
私はあまり歳を取るのが嬉しくありません。非常に限られた人生を歩んでいると、特にそれを感じます。ひとつ歳を取るごとに、毎年死に近づいている気がするのです。
けれど先日、間もなく誕生日を迎えようという日に、私のお屋敷に可愛い小鳥がやってきました。
その鳥は人に捕まえられて酷い事をされているというのに、いつまでも人の手に懐いて、いっこうに離れようとしないのです。
お陰で私は毎日たくさん小鳥とお話をすることが出来ました。
私は命の短さと引き換えに、これまでなに不自由なく育てられてきました。十六の誕生日を迎えてもまだ死に至らない、今の境遇にはとても感謝しています。
ひとつ残念な事は、その小鳥の本当の気持ちが私に分かればよかったのに、という事です。
その小鳥は故郷に帰ってしまいました。とても悲しかったです。
私は不幸がどういう物かよく知りませんが、恐らく幸福がどんなものかを理解していたと思います』
……うーん、こうして遠い国の人とお手紙のやりとりをすると、本当に平和のありがたさを感じますねぇ。
私も離れ離れになって心配している家族がいますが、例えどんなに遠くに行ってしまっても、みんなこのラジオを聞いて元気にしてくれている、そんな風に前向きに思えて、私も毎日希望をもらっています。
ジェフトバルドは雪深い所なんでしょうかね、お手紙から雪の匂いがします。あれ、目から汗が……。
いつもラジオを聞いてくださっているそうで、ありがとうございます。冬のシーズンはこれから長いですが、お体に気をつけて、どうか末永くお付き合いくださいね。
さて、テルマさんから曲のリクエストを頂いております。先月ファーストシングル『ザ・ロスタイム~止めないでチンパン』で鮮烈なメジャーデビューを果たしたロックバンド『酷薄☆重病☆魔猿』のファーストアルバム『ゴリ夢中』からの一曲です。では、どうぞ」
ドラム缶やサイレンを使った、まるで騒音そのものといった音楽がラジオから流れ始めると、ウラジミールはちらりと眉を上げて、隣の公爵を見やった。彼女が肌身離さず身に着けている白いヘッドホン越しからも、その凄まじい重低音が響き渡っていた。
テルマ公爵は激しいビートにあわせて体を上下させ、「うーいえー」とか「もえろもえろ」とか、かすれるような声で歌詞を口ずさんでいた。
右足を大きく前に出して、体を揺する。次に左足。ずりずりと裾を引きずりながら、雪の降り積もった路上を少しずつ前進してゆく。
目の前には、とうとう十六歳になってしまった彼女の命を狙う帝国兵が、ずらりと居並んでいても、まるで眼中にないといった風情だった。
この中で最上級の兵士と見受けられる牛角の仮面を被った一人は、無表情に右手をさっとあげる。並み居る帝国兵たちはそれにあわせ、身をかがめて道の両脇に下がった。
王宮に、ざんっと足音が響き渡る。左右には、寒空に突き刺さるように五柱が立ち並んでいる。そこは本来ドラゴンを迎え撃つために設けられた、王宮スザリース・パレスの中央にある閲兵場だった。
雪道の遥か先には玉座があって、そこにはフェン・ルードを統べる帝国の主、皇帝アウクスⅡ世の姿が見えた。
テルマ公爵は玉座の前に続く長い階段を、ゆっくりゆっくり上り終えると、仮面の王が座る玉座にぴょこんと飛び乗って、皇帝の面を撫でた。
「お久しぶりです……殿下……私、十六になりましたの……」
演劇のスケジュールにはまったく無い、十六歳の後のテルマ公爵が演じられる。皇帝の仮面はぴくりとも動かない。この寒さに凍てついてしまったかのようだった。
武器を手にした衛兵たちが遠巻きに見守る中。テルマ公爵はゆっくりとヘッドホンを外し、それを皇帝に差し出した。
「今日はぜひとも殿下に……お話して貰いたい方がおりますの……殿下……悩み事は……ございませんか……?」
*
テルマ公爵がとうとう十六歳の誕生日を迎えた日、彼女は王宮スザリース・パレスに押し入り、謀反を働いた。そのニュースを聞いたのは、私が彼女のお城を旅立ってから三日目の事だった。
ちょうど昼時、氷に閉ざされた古代都市が一望できるバルフーツ湖の真っ只中にぽつんと建っているカフェで、店番をするでもなくせいぜいお客さんの邪魔にならないように店先でぶらぶらしていた時だった。
店主はマシモフとかいう元気のいいおじさんだった。肩にかけている猟銃はドラゴンの鼻の穴みたいに大きくて、防寒具でがちがちに身を固めているせいで、大きな体がよけい横に広く見えた。三日前に上空から背中を見かけたとき、キャンピングカーに頭を突っ込んで食糧をあさっている熊かと思った。
熊なんか見た事もなかったけれど、二足歩行で歩く毛むくじゃらの生き物としてこの上ない親近感を覚えていた私は、ひょっとしたら友達になれるかもしれないと思って近づいてみた。実際はシチューを作ろうとしているただの太った人であることが判明して、命拾いしたとも知らずにがっかりしたものだ。
それから成り行きで私はマシモフのキャンピングカーにお世話になっていた。
列車並みに大きなキャンピングカーは、ガソリンエンジンで後部のキャタピラを駆動させて氷上を移動する仕組みだ。軌道の制御は前方ににゅっと突っ張った、イノシシの牙みたいな板切れで行っていて、運転席のハンドルで舵を切って進む。魔石機関は一切使っていない、完全な非魔法仕様の車だった。
氷の上をごりごり削るように移動して、等間隔に開いた穴から昨晩漬けておいた長い糸を引きずり出して、釣り針に食いついてぴちぴちしている小さな魚を摘まんで水槽に入れた。キャンピングカーの後部には養鶏場みたいな車両があって、この世界の気候に適応したのか、ものすごく毛のふかふかな美しいニワトリが寒さに身を縮めていた。毎朝卵を産んで、毛は衣類になって、骨は鶏がらスープになって、肉は美味しくいただける、完全家禽だ。使えない所がない。実は糞からも小魚の餌となる虫が取れるのはここだけの秘密だ。一箇所につき十本近い仕掛けをぜんぶ付け直して、キャンピングカーはまた次の場所へとごりごり移動する。たっぷり半日かけてごりごり湖を一周し、元の場所に戻ってくる頃には百匹前後の小魚が手に入っていた。
マシモフは仮面を身につけておらず、真っ赤なスカーフを顔に巻いて平民の格好をしていた。彼も昔はどんな身分の人だったのか分からない。十カ国語に堪能で、私たちの世界の言葉も流暢に喋った。
「うまいスープを作るのに仮面の魂なんて必要ないね。必要なものはここに全部揃っている」
ふんふん鼻歌まじりでジャガイモを切り刻んでいくマシモフ。シャベルみたいに大きな手でその辺の雪をすくって、鍋の中に豪快に投げ込んでみせた。いつも酔っ払ったような赤ら顔で、私に向かってウィンクなんかしてみせて、下らないギャクを口走ってたまに私を寒がらせた。
こんな場所でお客がくるのだろうかと思ったけれど、このおじさんの作った小さな魚入りのスープを求めて、カフェには毎日お客が訪れた。
主なお客は公国領の西に広がる雪原でアザラシ猟を行っている狩猟民族で、みんな短い牙の生えた真っ赤なお面を身につけていた。
「ヤン、ゴナ・カンジ(おっさん、いつもの頼む)」
「ヤー、ポートイ(ああ、しばし待っていろ)」
彼らはみなキャンピングカーと同じ仕組みで動く《スノーモービル》と呼ばれる乗り物でやってきて、マシモフお手製の温めのスープをもくもくと頬張っていた。彼らは基本的に猫舌だった。小魚が特に美味しいみたいだけれど、餌の秘密を知っている私は頑なに手をつけなかった。
手の空いたマシモフが棚の上に目をやって、ラジオでも聞くか、と言って、スピーカー付きの古びた箱ににゅっと手を伸ばした。
「ラジオがあるの?」
「ああ、珍しいかい?」
驚いた事に、この世界にもラジオはあった。電波を使った非魔法系の通信技術があるらしく、十六種類の番組が視聴できるのだそうだ。
《電波》と言うのが何なのか、私には皆目見当がつかなかったけれど、外界からの物理的な干渉を受けやすいものらしい。音がひどく割れていて、ざらざらとした耳にこそばゆい雑音が混じっていた。チューナーを捻り、ばん、ばん、とラジオを叩きながら、苦笑まじりにマシモフは言った。
「この世界のマシンはちとうるさいだろう?」
私はふるふると首を振った。静かな世界にうるさい機械、味があると思う。
ようやくラジオの音が鮮明になって、件のニュースが流れ始めたのだった。
――ニュースキャスターが喋っている帝国の言葉はさっぱり聞き取れなかったけれど、客の二人が顔を上げて真剣に聞き入っていた。マシモフが内容を要約してくれた。
「テルマ公爵が王宮に押し入って逮捕されたそうだ」
マシモフは眉をきりっとしかめて、ラジオを睨みつけていた。
「ハルミネ大臣と共に、今日の夕方頃、公開処刑される事が決まった」
それを聞いたとき、私はきゅっと心臓を押さえつけられたような心地になった。
私はもう元の世界に帰るのに。もう私とは関係のない世界のはずなのに。気にしてもきりが無いというのに。
それでも私は罪悪感に苛まれていた。これは私の罪ではないという逃げ道を、私は認められなかった。
私は逃げた、逃げちゃいけなかったの? 公爵と沢山おしゃべりをした、しちゃいけなかったの? ただ演劇に紛れ込んだだけの私の罪って、私の役割って、いったいなんなのだろう?
「ヤーァ!」
ニュースが終わった途端に、カウンター席の狩人たちは歓声をあげて立ち上がり、両手をぱしんと叩き合わせた。
ずいぶん大げさな喜びようだった。たぶん彼らの民族は公国からひどい抑圧を受けていたのだろう。ディートリヒになろうとしていた彼らの仲間も、確かそんな事を言っていた。
テルマが居なくなっても、また新しいテルマが立てられる、それは彼らも知っている筈だった。それでも彼らは一時の喜びに湧いていた。
「ヤン、ブナ・パッフェ(オヤジ、ごっそうさん)」
「ブナ・パッフェ・ムソ(ごっそうさん)」
猟銃を背負ったり、仮面の上からゴーグルを身に着けたり、私の頭をくしゃくしゃ撫でたりしながらカウンターから去ってゆくと、スノーモービルに跨って古代都市の上を爆音を轟かせながら滑っていった。
爆音が過ぎ去ると、辺りの静けさがより際立った。凍った世界は吹雪の日以外はほとんど音のない静かな場所なのだった。
ラジオは淡々とニュースを流し続け、マシモフは代金にも手をつけず、カウンターの上で硬く握り締めた手をじっと見下ろしていた。私は乱れた髪の毛を手櫛で整えていた。
「ぐ……」
突然マシモフは呻いた、胸元がうずくと言わんばかりに、ぎゅっと服を掴んでいた。そこには刃物で切りつけられた大きな傷があった。
私はその太った顔に、僅かな既見感を覚えた。私は立ち上がってカウンターに身を乗り上げ、その顔をじっとよく見た。その正体は、手で顔の辺りを隠さないと分からなかった。
「………ハルミネさん?」
マシモフはいつもの様に笑おうとしていたけれど、ただ顔がゆがんだだけだった。
「その名前はもう、私のものではないよ」
少し痩せてしまっているけれど、彼は最初に出合ったハルミネ大臣の空気を身にまとっていた。
「けど、あなたはハルミネさんだったじゃない。命をかけてまで大臣の役割を演じてたでしょ?」
「仮面を失った今の私はただの観客に過ぎない。もう私にハルミネを名乗る資格はないんだよ。
そうだな、私は先代テルマ公爵の代から大臣の役割を担ってきた。先代が彼女を産んでご病気で亡くなられるまで、私は幼い頃から彼女を見てきたし、彼女が先代の仮面を継いだ後は、大臣としてずっと彼女の傍らにいた。
彼女が死に直面する姿を何度も見てきたし、そのたびに生還する姿も見てきた。その記憶は紛れもない私のものだ。けれども、仮面はもう別の者の手に渡ってしまったからな」
なるべく未練を残さないよう、遠まわしに彼は何かを訴えようとしている気がした。私は犬の特性として、人の感情の変化には人一倍敏感だった。
「なんか、それって寂しくない?」
「そりゃあ、寂しいさ。寂しい事だよ」
マシモフは返事をする力を失ったようだった。私は黙って椅子に座りなおすと、しょうが湯に口をつけた。
この国では仮面を持たない人が泣いても笑っても、舞台上で進行する劇の内容に口出しする事はできない。偶然巻き込まれただけの私も、マシモフも、今はただ演劇を見ている側の観客に過ぎないのだ。けれども仮面を被って舞台に立つ人たちは、本当の自分の感情を表す事ができないでいる。それは私たちの世界にも横たわっている、ひとつの大きなジレンマなのだった。
「あまり愚痴は言いたくないからね、ひとつだけ思い出話を語っておこう。彼女の演じるテルマ公爵は完璧だった」
「今まで見た中で一番?」
「もちろん。強欲で、わがままで、そして残忍で。時には帝国にさえ平気で牙を剥く、誰も忌避してやりたがらない悪役だ。
けれども、彼女は決してその役から逃げようとはしなかった。先代も先々代も自然死してしまったから、いまこの国にディートリヒは一人も居ない。彼女は生まれながらにして、ディートリヒをこの国に誕生させる使命を背負い込んでいたんだ。この演劇を終わらせるディートリヒを生み出すために、彼女は逃げられなかったんだ。
けれども、本当に使命のためなのかと疑うときもある。時々、本当に初代テルマ伯爵が目の前にいるのかとさえ錯覚するほどに。あの子はまさに――まさに仮面そのものだった」
マシモフは大きく息をついて、「だから、本当はあの子の本心が私を生かそうとしてくれたのかもしれないなどと思うのは、単なる思い上がりかもしれないね」と言った。
もしここに、こんがらがった全ての問題をずばっと解決してくれる大男が居れば、どれほどスカッとする事だろうと思う。
きっと気持ちいい事だろう。仮面がなんだ、演劇がなんだと喚きながら舞台のど真ん中に乱入していって、全ての役割と仮面をひっぺがえしてしまうのだ。けれどそれだと社会が成り立たなくて苦労するので、その大男は目が眩んでおろおろする人々に向かって、お前はこの役割、お前はこの役割と、もう一度あたらしい仮面を采配するのだ。
つまるところ、そんな大男が居たところでこの国が抱えている根本的な問題は何も変えられないのではないか。そいつはただ演劇が自分の好みに合わないから怒っているだけの、アルコールが入った観客ではないのか。この世界の最も重大な問題は、本当はそれぞれの仮面などではないのではないか。
「さあ、早くしないと大白斑がもうすぐ消えてしまう。元の世界に帰るんだろう。それとも、春までここにいるつもりかい?」
私は唇をひんまげて、この引退した元大臣を見詰めていた。
笑おうとしている。支配に慣れきった者の卑屈な表情を浮かべてようとしている。
いやだ。確かに、私たちが騒いだところでどうにもならない相手だろう、けれども本当の敵は仮面なんかじゃない。この世界にだって、仮面なんかよりもっと大事な物があるはずだった。
私はピアノを叩くつもりでカウンターをばーんと叩いた。最高の不協和音を起こしたつもりだったけれど、マシモフは私には目もくれずに小魚を湯ではじめた。
「マシモフさん、テルマちゃんにお手紙書いて、急いで!」
あんまり勢い込んで言ったので、マシモフは目をぱちぱちさせていた。
「……お手紙かい? しかし、私はもう彼女に手紙を出せるような身分ではないし……」
「そんなのは関係ないの、ウラジミールじゃ絶対にダメ、あいつには荷が重過ぎる、だから急いで! ――あーっ、出来たら、私達の世界の言葉で!」
いぶかるマシモフを急かして、その辺のメモ用紙に手紙を書いてもらった。急いで書いたのにも関わらず、マシモフの字はかなり達筆だった。
カフェから飛び出して、天候を視認した。日はまだ高く、正中線を少し過ぎた辺りだった。風は良好、雲量ゼロ。手紙を胸元に押し込んで、大白斑のある西の方角に向けて走り出した。
がちっ、……がちっ、……がちっ、……がちっ、……がちっ、……
氷の上に踏み出した途端、足がしゅるしゅる滑った。パプシのギアがいつもよりゆっくり押し込まれて、私は氷上を一気に駆け抜けた。
「きゅううううううううううううううううううううううううううううううううん!」
最高速度に達した瞬間、緑色の魔法陣が波紋のように現れて私を空の彼方へと押し上げた。
視界クリア。青一色だ。可能な限り高度を高く取って正面の氷山を飛び越えた。連綿と続く湖底の古代遺跡が小さくかすむぐらい高く飛ぶと、雪山の向こうに狩人達が住処にする朽ち果てた寺院がちらほらと見えて、その向こうに巨大な流氷の漂う海が見えた。
西の空に横たわる大白斑は、まるで白い大蛇のように力強くうねっていた。こちら側の世界から見ても凍えるほど不気味だった。
あの霧の渦を抜ければ、そこは元の世界だった。消えるにはまだ時間がある。
ここから急いで大白斑を越えて、ジペンゼに戻ってコバタさんに出会って、その時、まだ彼女が私のラジオを持っていたら。そうしたら、彼の声だけでも届けられるかもしれないと思ったのだ。
胸に入れた手紙が熱かった。ストーヴの上で書いていたのかと思うくらいに熱かった。
私にできるのは手紙を持って、ただひたすら飛び続けることだけだった。可能な限り早く、一直線に。処刑の時間が迫っているのなら、太陽が沈んでしまわないうちに。熱を持っているのなら、この手紙が熱を失ってしまわないうちに。
これが私に出来る精一杯の事だった。
そう、これで私の役割はおしまい。
明日からはただのジトーノの女の子に戻って、思いっきり羽を伸ばす。
雲間を飛びながら、この国のことをたまに思い出すのだ。
ふいにある日の帝国兵たちの顔が脳裏を過ぎった。
仮面越しにも感情が分かるようになっていた、彼らはみな力強い目をしていた。
連日のパーティ開催のおかげで、公爵の身を守る護衛は日を経るごとにどんどん数が少なくなっていた。ウラジミールは戦闘不能になった護衛たちの仮面を集めて、仮面を引き継ぐ人材を募る大規模なお触れを出していた。彼が受け持った、最初の大臣っぽい仕事だ。
公爵の護衛の身分は高級騎士、けっして低くは無い。膨大な報酬も提示していたにも拘らず、なかなかこれといった人材は集まってくれなかった。金のためなら命も惜しまないという傭兵たちも、次から次へと無尽蔵に湧いてくるものではなかった。
補佐官たちと一緒に頭を悩ませていた折、ウラジミールの元部下だった元帝国兵士たちが、ぞろぞろとお城にやってきた。
今は爵位を貰っている元帝国兵氏たちは、みなそろって昔の兵士の鎧を身につけていた。きらびやかな貴族の服などまとわず、傷だらけの鎧を着こなして、彼らは口々に言った。
「隊長ひとりを危険にさらして、自分ひとり安穏としている訳には行きません!」
「自分は無人島でかつて死んだ身であります、今さらなにを恐れる事がございましょう!」
「隊長に長らえさせてもらった残りの命、隊長のために捧げるつもりであります!」
「誠に勝手ながら、頂いた爵位は返上させて貰いました! 我々はもう後には引け!」
「ませ!」
「ん!」
それで何か感動的な事を言ったつもりだろうか。ウラジミールはその場にがっくり項垂れて、恨み言を言っていた。
「お、お前たち……俺の決死の行動は一体なんだったんだ……! このままこっそり逃げるつもりでいたのに……! 俺はいったい何のためにこんな仮面を引き受けたと……!」
ウラジミールの行動が完全な裏目に出たのは残念だったけれど、内心では彼は相当嬉しかったに違いない。だって、窮地に心強い仲間が駆けつけてくれたのだから。
けれど、例え帝国兵たちの護衛なんて居なくても、たった一人でパーティに出かけていったとしても、きっとテルマ公爵は死ななかっただろうと思う。
それが不幸なのか幸福なのかは別として、彼女は文字通り、最強の女の子だったからだ。
後から後からわいてくる邪魔な雑念を振り切るために、私はこれから帰る向こうの世界の事を思い返していた。
ジペンゼの熱い太陽が恋しかった。海岸警備隊のいる海岸線や、海兵隊の訓練する声や、地中海のお城や、騒々しい食堂や、出来立てのパンや、獣人の友達やゼラの声が聞きたかった。工場のみんなや、中でも一番、いまはコバタさんの声が聞きたかった。
私は無駄に血を流す必要はないし、自分を殺す相手を探す事に、執念を燃やす必要もない。翼を持った使者としての、これが私の果たすべき役目だった。
あとは地中海料理を食べて、ラジオを聞きながらカウチでぼんやり寝そべって、たまに友達とつるんで悪さをして生きるだけだ。
けれど、もしこんな物が本当に私の役目だったのなら、寄り道もせずまっすぐに帰るべきだったのだ。
三日間も私は何をしていたのだろう。何かやり残した事があったのだろうか。この演劇を納得のいくところまで見届けたかったのだろうか。どうして帰らなかった。なぜ私はずっとあそこに居たんだ。お家に帰ったときの挨拶の仕方さえ考えて居なかったのだ。今から考えても間に合わないかもしれない。色んな思いが溢れてまともに考えられない。助けて、助けてコバタさん。私はいま何か大変な間違いを犯しているような気がする。
気づくと私はどんどん加速していた。風圧で涙がぼろぼろと後方に飛んでいった。頭の中はもう真っ白になっていた。日はどんどん傾いていった。
霧の世界に突入して、ひょろ長い蛇のような気流が脇を通り過ぎていった。声を上げたけれど、大きな風の唸りに圧されて何も聞こえなかった。
風の唸りだけではなかった、甲高い風切り音が私の耳を聾していた。
空を見上げた私は、はるか上空をゆっくりと横切ってゆく白い影を見て、ぴたりと泣き止んだ。
音も無く空を飛ぶ魔法の船、飛空艇。霧の隙間に陽が射して、そこを通過しようとしている一機があった。
魔法世界ではもはや一般的となりつつある乗り物だったけれども、その形状は私が今まで見たものとはずいぶん異なっていた。鳥のように広げている翼は三角形に近い。高速飛行で安定しやすいデルタ翼だ。船尾は大きく二つに割れていて、こちらもV字形のデルタ翼だった。
その謎の飛空艇が、大白斑から今まさに飛び出してきて、白い雲を引きながら私とすれ違った。そのまま、まっすぐ公国のある方角に飛んで行ったのだった。
――連合軍の船だ。
私は両足を縮めて空中に静止し、本来ならばしてはならない一八〇度ターンを行った。
胸騒ぎがした。何かすごく嫌な予感がした。
真下からその飛空艇の影を追ったけれど、どうやら相手は音速を越えているらしい、引き離されないようにするだけでも精一杯だった。
私は覚悟を決める必要があった、数ある機能の中で、この機能を使うのだけは嫌だった。なぜならあのドックが「使うな、絶対に使うな」と念を押すほどの機能だったのだ。パプシのトップギア。私はパプシの中の翼をはためかせ、ギアをさらにもう一段階上げた。
背中の歯車がぎゅんぎゅんと高速回転し、血のように赤い魔法陣を背後にひとつ、ぷかりと吐き出した。
振り向くと、五つの赤い小魔法陣を組み合わせた巨大な魔法陣だった。それぞれが時計の部品みたいにぎりぎりと耳障りな歯軋りを立てながら回転して、赤紫色の電光が木の根のように放射されていた。その異様さに私はごくりと唾を飲んだ。
五つの小魔方陣が赤い光線をパプシの一点に照射した瞬間、私はその光の圧力に押されて、上空をすっとんでいった。
上空に七色の魔法陣を一列に連ねながら、光線に押しやられたみたいにすっ飛ばされて、あっという間に機影の背後まで接近していた。もう音速とか目じゃなかった。光速だ。どうやって風圧を制御できたのか、自分でもよく分からない。
機体なんか後ろから追い抜きそうになったので、慌てて機体前方に飛びつき、両手を広げて鼻っ面にしがみついた。進行方向が変わったせいで、制御し切れなかった風圧がもろに背中に当たった。飛行艇がべこっとつぶれた。機械の体じゃなかったら多分死んでいたと思う。うーと唸って、噛り付くように歯を食いしばって耐えていると、コックピットの操縦者とばっちり目があってしまった。
操縦者はマスクとヘルメットをつけていて、表情は全く見えなかった。流線型のガラスで前面が覆われている、一人乗り用の小さなコックピットに座っていた。
目があった直後、操縦者は中で火事が起こったように慌てていた。中の音はさっぱり聞こえなかったけれど、身をよじって足をばたつかせている。騒いでる内容はたぶんこんな感じだろう。
「か、管制室っ! 応答願う、こちらイーグルワンっ!」
「こちら管制室、イーグルワン、聞こえている、どうぞ」
「外に! 機体の外に女の子がいるっ! どうぞっ!」
「女の子? ひょっとしてそれは有翼人か何かではないのか? どうぞ」
「わからない、羽は目視できない! 背中には変わったリュックサック、服装は白のチュニック! 機体との距離、およそゼロメートル! 五十センチ、四十センチ、機体を這うように、少しずつコックピットににじりよって来る……うわあああっ!」
「落ち着くんだ、イーグルワン、それはただの幻覚だ。たとえ訓練された兵士であっても、高速飛行時には気圧の急速な変化によって意識低下や呼吸困難などに見舞われ、時に幻覚症状に陥る事が……」
「ぎゃあああっ! キャノピーに、顔をへばりつけてっ、こ、こっちを、じっと睨んでいるーっ!」
「落ち着くんだ、イーグルワン、繰り返す、それはただの幻覚にすぎない。そういった場合には手足の指先に意識を集中させ、しかるのちに……」
「も、もうだめだ、脱出するーっ!」
たぶん、こんな感じ(?)のやり取りがあったものと思われる。ともかくパイロットが錯乱してしまった飛空艇はコントロールを失い、空中できりもみ状態になって、まっさかさまに凍った世界へと墜落していったのだった。
この最新の戦闘機は、衝撃緩和システムもばっちり整っていた。
着地の瞬間に防御魔法が発動し、機体がばらばらになるのを防いだ。茨を丸めたような青い光に包まれて、氷の地表をがりがりと削ってライディングしていった。
浜に打ち上げられた深海魚みたいに横向きに止まった戦闘機は、コックピットを包む防風ガラスをぱかんと開き、マスクを外してぐでんとしなだれている運転手を白日の下にさらした。
計器のある辺りに立って見下ろしていると、運転手はゴーグルを外して空ろな目で私を見た。見たところ私と同い年ぐらいの男の子だった。口をぽかんと開けて、頭の中でひとしきり何か考え事をしている様子だった。
「お前は……アンシェ・アンシール=アルシカか?」
私は頷いた。
「叔母さまから貰った名前なの」
どうやら私が誘拐された事件は向こうの世界でニュースになっていたらしい。少年はようやく体を起こすと、思いがけない外気の冷たさに顔をしかめながら言った。
「頼む、すぐに元の世界に戻ってくれ」
「どうしたの?」
「二つの世界の間で、もう一度戦争が始まろうとしているんだ」
話によると、どうやらこの船は偵察機だったようだ。私の誘拐事件を口実に、帝国の情勢次第では、アーディナル東軍は議会の承認を待たずに先制攻撃に踏み切るつもりだ。
しばらく口をぱくぱくさせていると、パイロットは私の肩をぐっと掴んで、まじめに語りかけた。
「俺は今までいろんな国を旅してきたが、その旅で見えてきたのは今の連合諸国が様々な問題を抱えているという事実だ。とても戦争を始めるべき時期じゃないし、戦争でうやむやにしてしまっていいような問題なんかひとつもない。お前が無事に帰還すれば、アーディナル東軍は帝国に潜入する理由を失う。とにかく、戦争を止める事が出来るかもしれないんだ」
私には実感の沸かない、とても大きな話だった。
無言でパイロットを見詰めていると、もうじき戦争が始まろうとしている事実が遠い国の出来事のように思われてくる。
彼の真剣な眼差しから逃れるように、私は小さなコックピットを指差した。
「……この飛行機、二人くらい乗れる?」
パイロットは機体を見下ろして、あーと唸った。
「もちろん、乗れるようにはする。ちょっと窮屈かもしれないけど」
私はぽかんと口を開いて、大きく息を吸って、吐いて、それからきゅっとまぶたを閉じた。
私はこのとき、自分の中から無謀なアイデアが溢れてきそうになるのを感じていた。
大きな賭けだった。せっかく掴んだチップを捨てて、失敗すれば取り返しがつかない賭けをしようとしている。
確かに愚かな行為には違いなかった。それでも、自分ひとり遠く離れた地に逃げ延びて、安全地点からせいぜいラジオを流すだけで自分は精一杯やったと言い張るなんて、そんな相手にとって何の実利にもならない身の案じ方だってじゅうぶんに愚かな行為には違いなかった。
ひょっとしたら私は、この演劇のなにかが気に食わないと心の中で理解していたはずだったのだ。誰かが何かの拍子で酔っ払った大男になってくれないかと、無関心を気取りながら心のなかで願っていたのだ。だって、私にはこの演劇を覆す力はなかったから。けれど、私には翼があった。そして翼が私に勇気をくれた。
「待ってて、すぐに戻ってくる!」
「えっ、どこ行くの?」
既に前方に駆け出していた私を、パイロットは呼び止めた。私は振り向きざまに答えた。
「連合に、友達を連れていきたいの!」
「げっ、マジで!?」
「お願い、なるべく早く戻ってくるから!」
私は返答も聞かず、魔法の輪を潜って、再び青空の彼方へと舞い上がった。
8
カフェを飛び立ってから丸四時間が経過していた。地表との温度差でいつも薄ぼんやりとしていた太陽は、早くも西の空に沈み始めていた。
ジェフトバルドの広大な平地を南下している最中は、目標にできる山も川もなにも無かった。ただ太陽と地磁気を頼りに進むしかない。上空の気流にさらわれて多少横にずれるのも、気にしている場合ではない、ようやく前方に海が見えたときは、すぐさま頭の中にインプットしていた地図を呼び出して、何度も海岸線の形と照らし合わせた。
大丈夫、私は一人でも戦える。
*
先刻、公爵のお城に戻ってこの地図を貰ったとき、通訳機の仕事をしていたお付きの女性は厳しい目をして私に言った。
「この世界の地図は、重要機密です、決して他人の耳目に触れぬよう、厳重に扱われています……」
「だ、ダメ?」
「ですが今回は特別です、用が済み次第、記憶からも消しなさい。分かりましたね?」
「う、うん、わかった」
私があまりにもあっさりと首肯したので、彼女はかえって心配そうな顔つきになってしまった。
あいにく彼女の目に私はただの子供にしか映っていなかったらしい。私にもっと身長と信用があれば良かったのだけれど。
「心配しなくても、私の人工知能は記憶の出し入れが得意なのよ」
けれど口頭で説明したところで分かってもらえるような物でもなかった。さらに目つきが険しくなっただけだ。
「いいですか、帝国における戒律では、たとえどんな些細な事であろうと国家に関する情報は門外不出なのです。これは規則ではなく原則です。軽々しく他人に渡しては首が飛んでしまいます。分かりますね」
「うん、わかったよ」
「けれども私はあなたにこの地図を授けようとしています、いったい何故だか分かりますか?」
わざともったいぶった、私には分からないだろうと思っている問い掛けだった。
実際、分からないのが悔しい。私はむーんと首を捻った。なんで?
「なぜなら私が次期テルマ公爵だからです。帝国の戒律を破って何が悪いの? という事です」
「あー………え、えー? 本当に」
彼女は涼しい眼をしてこくりと頷いた。
「私、嘘は申しません事よ。でございます」
「あー……じゃ、じゃあ『……それで何か新しい事を言ったつもり?』って言ってみて」
彼女は目を細めて斜に構え、まるでテルマ公爵が乗り移ったみたいな不敵な流し目をした。
「『……それで何か新しい事を言ったつもり』でございますか?」
「あー……あー……惜しい」
やっぱり今のテルマ公爵の方が数倍かっこいい、と思ったのはここだけの話だ。
*
海岸線を伝って国境を目指すと、間もなく地平線の雪景色が山吹色に染まり始めた。
その先に見えるのは、もうもうと蒸気を吹き上げる煙突の群れである。レンガ造りの建物の一つ一つが夕日を浴びて、チョコレートみたいに延々と横に連なっていた。
国境の町グートモルゲン。このラインから先が本当の帝国領だ。処刑場があるのはさらにその先、第六都市フラノの中央広場にあるはずだった。
この世界の建物の基本構造は、公国で知ったばかりだ。地上に一部分がつき出ている建物は、実は地下にはその数倍の規模がある巨大なものだ。
だったら、あの偵察機は全くの無駄足だ。そもそも、いくら飛空艇技術が発達していようともこの国に対しては無駄なのだ。そもそも上空から飛来してくるドラゴンとの戦いの歴史が産んだ国家なのだ。空から見ただけでは、この国の何ひとつ計り知る事はできないように作られている。
すでに私の真下にも、公国と同じような巨大都市が広がっているのだろうか。見えている限りでは、公国とも比較にならない、桁外れの規模の国だった。
太陽は見ている間にもじりじりと高度を下げてゆき、間もなく稜線の向こうに没しようとしていた。
長距離飛行で魔力を保てる限界を無視して、私は速度を上げた。何日かかっても戻ってやるつもりだった、今はとにかく日没に間に合わなければならなかった。
まもなくグートモルゲン上空にさしかかろうとしたとき、前方の風景に違和感がある事に気づいた。
このとき、私は帝国の恐ろしさを初めて知った。彼らの狡猾さを、もっと警戒しているべきだったのだ。
さっき墜落した偵察機の存在がすでに帝国に知られていて、国境付近は臨戦態勢に入った軍隊が対空兵器を持って待ち構えているなどという事態は、思いもよらなかったのだ。
その対空兵器は、遠目には煙突の群れのように見えていたものだった。建物の二倍の高さを持つ、直立した円筒形の煙突が、グートモルゲンと雪原の境目にびっしりと並んでいた。
その煙突が、よく見ると雪原に向かって歩いてきていたのだ。
もはや正気の沙汰ではなかった。煙突の根元には革帯が取り付けられていて、一本につき一人の兵士がそれを肩に担いで、雪を踏みしめながら行進していたのだ。
背後の建物の二倍の高さはあろうかという煙突を担いでいるのに背筋はぴんと伸ばされ、煙突の角度も足をあげる角度もびしっと揃っていた。
分厚い甲冑に身を包んだそんな小隊が十個ほど、一糸乱れぬ行進で国境付近のあちこちに展開していたのである。
《大火砲隊》……!
世界大戦の神話として語り継がれる、侵略戦争における帝国軍の三つの恐怖。その一つ騎士団が抱える砲兵集団だった。
千人近くの兵士が銃のように肩に担いでいるのは、普通は馬数十頭で車に乗せて運ぶような長さ十五メートルにも及ぶ超巨大機関砲だった。魔法世界にも類を見ない異様な腕力で、それを軽々と肩に担いで行進する。
こんな狂気的な兵団がアーディナルの街中を闊歩していた時代がかつてあったのだ。アーディナル諸国は彼らの行進を見ただけで抵抗する気力さえ失せてしまったはずだ。
戦場においてもっとも有効なのは、実際の兵力ではなく、それが与える恐怖だと言った中部の軍師が居た。彼ら帝国兵はそれを論理的にではなく、感覚的に体現している節があった。
各小隊の前一列が雪原に膝を付き、煙突の角度が微妙に調節されはじめた。私はただ震えていた。完全にすくみあがっていた。私が目の当たりにしたのは、まさに恐怖そのものだった。
上空に向けられた筒の先端から、銃身の半分ほどもある火柱が吹かれた。遅れて、獣の咆哮のような音でギーンと耳鳴りがした。
網の目のように砲弾が飛んできた。飛んでくる様子は見えていたのに、直径が大きすぎて回避しきれなかった。砲弾の一つがパプシの歯車を掠めた。
歯車がくるくる回転しながら本体から外れていった。私はそれに手を伸ばす事しかできなかった。立て続けに砲弾が背中のパプシ本体にも直撃して、あまりの衝撃に意識がとんだ。分厚い雲にぼこぼこと穴が開いていて、星のない夜空が見えた。そこに手を伸ばすような格好で硬直したまま、私は雪原にまっさかさまに落ちていった。
私はしばらく人形のような状態になって硬直していた。非常動力モードに切り替わるのに数秒を要し、むくりと体を起こすと、焼け焦げた服の上をぱらぱらと雪がこぼれていった。滴が背中に入っていって、うひゃっと身をすくめた。
背中にパプシがなかった。慌てて探すと、数歩先の雪の中に、それらしき落下物のうがった穴が開いていた。
立とうとしたけれど、何故か立てない。すとんとその場に座り込んでしまう。体の状態をスキャンしたけれど、下半身がうまく診察できない。どうやら脊椎にあたる中枢神経がやられているらしかった。
足ががくがく震えていた。事故には慣れているけれど、これはもはや生命維持に関わる事態だ。早急なメンテナンスが必要だった。少しずつ足を動かして雪の上を這いながら、とにかくパプシににじり寄っていると、なにか異様なものの気配を察知して、ぞわっと鳥肌が立った。
鳥類は上から襲われる事を極端に嫌う。ジトーノもそれは同じで、エカデナである私の機械の体もその本能を忠実に再現していた。
空を見上げると、サイコロのような形をした檻が数個、くるくると回転しながら飛んできていた。
あまりに巨大で重力を感じさせない。檻の間から明らかに人のものではない、無数の腕が伸ばされていた。喚き声やがんがんと格子を叩く音が、ずっと遠くの物のように聞こえてくる。どうやら悪魔を閉じ込めた牢屋が三つほど飛んでくるようだった。
これも侵略時代の三つの恐怖の一つ、《悪魔の箱》だ。
帝国騎士団の特殊部隊が持ち運ぶこの鋼鉄の檻の枠には、歩兵が投げやすいように取っ手がついている。すなわち投擲用のオリだ。ヤリではない。
雪原に墜落すると同時にばらばらに分解され、あるいは扉が開放され、中から影がうぞうぞと溢れ出した。黒い魔獣が鼻を鳴らしながら、辺りをかけずりまわった。
獣の群れは真っ先に私に襲い掛かった。悪臭のする牙で服が引き裂かれ、足や腹の肉を食いちぎられ、首を噛まれたまま何メートルも引きずりまわされた。
その時の恐怖はとても口では言い表せられない。辛くても死んではいけないなどと言っていた私だったけれど、戦争の恐怖はそこで想定される辛さとはまるで別次元のものだった。強制的に死をイメージさせられて、なぜ死なないのか不思議だという概念が浮かんでくるほどに圧倒的だった。
攻撃の嵐はまもなくぴたりと止んだ。首に刺さっていた悪魔の牙が、私の体からずるずると抜けていった。オイルがのどに詰まって咳き込んだ。黒い恐怖は四つん這いになったままじりじりと後ずさりし、飼い主に見つかった猛犬のように、鋼鉄の檻の中に自ら後ろ向きに入っていった。口には私の金髪を一束咥えていた。
私は泣いたり叫んだりしなかった、被ダメージが大きすぎて意識が朦朧としていた。何者かが訪れた気配がしたけれど、周りの状況がよく把握できなかった。視界は時おり砂嵐でぶれ、目の前の情景を鮮明に映そうと、もどかしい努力を続けていた。
ようやく相手の姿を目で捉えたけれど、そこに現れたのは、どう見たところで私を助けるために訪れたものではなかった。
月光の中にゾウのような大きさの馬がいて、私に鼻面を向けていた。
全身に銀色の縞模様が描かれ、額からは一本の角がすらりと伸びていた。私の肌に吹き付ける鼻息は何故か異様に冷たかった。
その背中に巨躯の帝国兵が跨っていて、公国の最高級兵が被るような角つき兜の中から私を見下ろしていた。腰に提げている剣がぼんやりと光を放って、月光の強さに比例して強くなったり弱くなったりしているようだった。
その騎士の左右から、するり、するり、と、空間に溶けていた幽霊のように、同じ馬と騎士が二組ずつ現れた。
帝国軍にまつわる最後の恐怖、《幽霊軍馬》を抱える騎士団の騎兵隊だった。
魔法世界に知れ渡っているのは、侵攻開始時に魔法世界に現れたこの三つの騎士団だけだったという。
けれども私達の世界を統治するには、それで十分だったのだろう。これだけで一切の希望をくじくには十分すぎるほどの力を持っていた。
逃げようとして地面に手をついたけれど、腕が片方どこかに行っていた。食われたのか。思わず檻を睨んでみたけれど無駄だった。ようやくふと気づくと、幽霊軍馬は次々に現れて、あちらこちらに佇んでいた。
騎士の数はいつの間にか百人以上に膨れ上がっていて、私の周囲はすでに馬軍によって埋め尽くされていた。
「……飛空艇ではなかったか」
「……ともすると誤報かもしれぬ」
「……そう決めるのはまだ早計に過ぎよう」
「……小康状態が長引いて哨兵も気が立っているのだろう」
「……我が隊はもう半日近くも兵を待機させているのだぞ」
「……我々は一旦自国領に帰還せねばならぬ」
「……今は暫く様子を見るべきだ」
帝国騎士は傷だらけの私を取り囲んで、ぼんやりと佇んだまま口々に議論していた。恐るべき不遜さだった。
帝国の戦力は、最新の兵器の保有量では決して量れない。
戦争が始まればどちらに勝ち目があったかは分からない。
この大国は伝説の黒竜との戦いを何百年にも渡って続けてきた、超人たちによる超人たちの国家だったのだ。
*
ちょうど十六年前の雪の振る日、私はDJコバタさんに拾われた。
工場の建物と建物のすき間。どうしてあんな所に落ちていたのかは分からない。地中海に雪が降った日だったから、天使ぐらい降ってきてもおかしくは無いとDJコバタさんは言っていた。
その時も私は体中傷だらけで、あちこちからスパークが漏れていた。背中の両翼は中間からへし折れていて、私の身長は一四七センチだった。
誰かが雪をぎゅっぎゅっと踏みしめる音がしても、そちらに顔を向けるのも億劫だった。相手が見えたところで、体を引きずって物陰に身を隠すことすらできなかった。
なかなか去ってゆかないので見上げてみると、私を見下ろしているDJコバタさんと目があった。
こうもり傘の下には狼の顔があった。強くて優しい目だ。けれど私は上から見下ろされる事に恐怖を覚える。
私が不意に想像したのは、食べられるかもしれないという事だった。けれども不思議と落ち着いていた。
「……私を食べる?」
「がおー」狼はやる気無さげに牙もむかずに吼えて、それから肩をすくめてみせた。「食べたら怒る?」
「……食べてみたら?」
「食べないよ、なんかお腹壊しそうだ」
狼はため息をついて、何も言わずに私を負ぶって、それから雪道を歩き始めた。
ふかふかで暖かい背中だった。私は彼の背中の毛にぎゅっと体を押し付けていた。
私の人工知能は覚えるのも得意で、忘れるのも得意だった。けど、大きな怪我をするたびに、忘れていた記憶が時折ふっと蘇った。
私は大きな翼を持って、夜空を自由に飛んでいた。
見下ろすと塔があって、千人乗りの大きな飛空挺がゆっくり墜落するところだった。真っ赤に燃えていて、とても綺麗だった。
他の記憶はずいぶん曖昧で、覚えているのはそのくらいだった。きっとどこかの時点で、何かの理由で消去したのだろう。
とにかく、彼に拾われた頃から私は生まれ変わって、年齢もその日をゼロ歳にしてカウントしはじめた。体を修復する機能は忘れずに残っていて、お陰で私の正体は今までスクルフ兄弟以外にはばれずに済んでいた。けれど、どうしても両翼とその間の傷だけは自力で治すことはできなかった。単純に手が届かなかったのだ。たぶん前の私もおっちょこちょいだったのだろう。
コバタさんの手を借りる事もできただろうけれど、彼に私の傷を修復させるのはちょっと恐かった。彼は私が機械だという事実をもう知っているはずなのに、私が機械だという認識が強まると思うと、とても不安な気持ちになったのだ。なぜかは分からない。認識に濃度があるというのもちょっと不思議な話だった。
*
最悪の目覚めだった。風邪を引いたように頭ががんがんして、鼻の奥がずきんと痛んだ。口の中がオイルの味でごわごわしていた。
私は筒状の牢屋の底にいた。錆びきった鎖が壁から垂れ下がっていて、空気も冷え冷えとしていた。まるで井戸の底のようだった。
私は自分で自分を抱きしめるように縮こまった。アーディナルでは牢屋と言えば大まかに二種類の用途があった。
東部では罪人にも一定の権利が保障されているため、牢屋でもそこそこ不自由のない生活が送られるように設計されている。
中部では拘留刑そのものがなくて、罪状が確定するまでの一時的な拘留所としてしか使われていないそうだ。
けれど、この牢屋の使用目的はそのどちらとも違っていた。
誰かが生きていた臭いがしない、かといって、何の臭いもしない訳ではなかった。そこにはむせ返るような死のにおいが漂っていた。
禍々しい染み、以前ここに居た誰かの強い念が焼き付けられた壁、苦悶の声を吸い込むのに慣れた錆びた鎖、見詰められるのに慣れた頑丈な木の扉。目には見えないけれど、一つ一つが誰かがここに居たわずかな気配を宿していた。私はそのひとつひとつの気配から逃れるように壁から離れ、肩を抱いて震えていた。
壁に吊るされた鎖がカチカチと鳴っていた。たぶん何かの拍子でゆれたのだろう。
壁の向こうから乾いた足音が響いてきた。どうやら誰かが階段を降りてくる様子だった。
たとえ何を感じても何ひとつ対処できなかった。身を守るものは圧倒的に何も無かったのだ。とにかく扉からなるべく離れて、藁にもすがる思いで錆びた鎖に腕を絡めて、涙を見られないように顔を伏せていた。
がちゃがちゃと鍵を弄る音がして、光が牢屋の中に差し込んだ。顔を上げてみると、ドアが開かれていて、そこに黒服を身にまとった貴婦人が立っていた。
「テルマ……ちゃん……」
私の見間違えでなければ、それは明らかにテルマ公爵だった。
顎が震えて、言葉にならなかった。自分の声が酷く掠れている事にようやく気づいた。上手く声の出せない、穴の開いた喉を震わせた。
「どう……して……」
彼女がこんな所に現れるはずがなかった。日没と共に処刑されているはずだった。けれども確かに、彼女は凛として私の目の前に現れたのだった。
彼女はただにっこりと微笑んで、私にゆるりゆるりと近づいてくる。逃げる気力ももう持ち合わせていなかった。私の目の前に屈みこむと、公爵の長い腕が前に伸びて、白いヘッドホンを差し出し、私の耳にそっと押し当てた。
そのヘッドホンから、とつぜん聞き覚えのある声が聞こえてきた。
「アンシェーーーーーーーーーーーーーーーっ!! 大丈夫かーーーーーーーーっ!!」
背後に同じ声が重なって聞こえる。アオオオンと犬達の遠吠えも聞こえていた。私は意味が分からず、ぽかんと口を開けていた。ただにっこり微笑んでいる目の前のテルマ公爵を見詰めていた。
「……なん、で……」
「まったく無茶な事はするな! もう許可無く飛ぶんじゃないぞ! 約束だ!」
「なん、で? マルハト、さん……番組は……これ……だって、これラジオじゃ……」
そこまで言って、ようやくこのラジオの正体が何なのか掴めてきた。にっこり微笑んでいるテルマ公爵に向かって、尋ねてみた。
「これは、つまり……これは、ラジオ、じゃないの?」
テルマ公爵は唇だけ動かして、「そうよ」と言った。
ラジオではない。けれども仕組み自体はラジオによく似たものだった。
ドックⅢ世が私のラジオに施した仕掛けは、ちょっと特殊な魔力信号を傍受する機能だった。
それがなんと、私の神経回路を流れている信号だった。
私の聞いているものや見ているもの、あらゆる感覚情報を盗み出して、弱い信号でそれをパプシに送りつけ、国のチェックを逃れるためにパプシのGPS機能を経由して魔法の地図まで飛ばし、さらにその情報をドックの手元で高度に解析して、音声や映像を復元する……という壮大な試みを行なっていたらしい。
かいつまんで言えば、私を介してこちらの世界の音声や映像を知る事が出来る、超高性能スパイウェアになっていたというのだ。二年にわたるチューンナップを繰り返してようやく完成したそうだ。
ともかくスクルフたちは私が捕らえられてから、ラジオの通信機能を使ってずっと救難信号を送り続け、それを聞いていたテルマ公爵が動いて、ここに閉じ込められている私を探し出したと言う事だった。
話はうまく曲がったがなぜ、なんでそんな機能をドックⅢ世は取り付けたのか。
「あー、言いにくいんだが、ドックがお前の機械の体にえらく興味を示していただろう。機械の仕組みがどうなっているのか調べようとしていたらしいんだ。それで指一本触れるなと言ったら、指一本触れずに外から情報を盗み出そうとしたらしくてな。……あの野郎、天才か、さもなきゃ途轍もない大馬鹿者だ!」
胸がきゅんと痛くなった。ぶわっと涙が溢れてきて、堪える事ができなかった。お城から去ったときとは逆に、今度は私がテルマ公爵の胸にしがみついてわんわん泣いた。
ごん、がすっ、ばこっ、な、なんだよ指は触れてねぇだろ――!
ラジオからは物騒な音が鳴り響いていたけれど、私はみんなとの再会に感極まって、心の底から安堵していたのだった。
*
日没に予定されていたテルマ公爵の処刑は、連合の飛空艇がやってくるという騒ぎのせいで延期されていたらしく、翌日早朝に執り行われた。
凍えるような朝だというのに、処刑場の周囲には沢山の人だかりが出来ていた。公開処刑はこの国ではそれほど稀な行事だったのだ。
もともとドラゴンに人の死を見破られないように仮面と役割を引き継いでいたのだから、わざわざ大々的に公開処刑するということは、すなわち「公的に役割を廃止させる」のと同義なのだった。
ボロボロになった自分の体のメンテナンスもそこそこに、私は第六都市フランの中央広場に訪れていた。
「ありがとう……あ、えっと……」
私の隣にいる女の子に、今は名前はない。白い陶器の仮面を斜めにかけていて、染み付いた癖のように顔の左半分を隠している。右半分の顔は朝日に照らされてどことなく柔らかく見えた。
「気にしないで……天使さんとの約束だから……」
「そう……でも、ありがとう」
私が船の中でラジオの裏機能を覚醒させたあと、最初にその通信機能を使ったのはテルマ公爵だった。
私の差し出したラジオ(実際にはドックが魔改造を施した超高性能スパイウェア)に耳をあてがったテルマ公爵の耳に、最初に飛び込んできた第一声は、「おい、娘を危険な目にあわせたらただじゃすまんからな」というDJコバタさんの脅し文句だったらしい。
それを聞いた私はちょっとびっくりした。だって、私の記憶が確かなら、耳を当てた直後、テルマ公爵はくすりと笑ったような気がするんだけど。
「面白かったから……」と、テルマ公爵はすました顔で言った。「だからあの後すぐに貴女を助けて差し上げたのよ……それからあの方は貴女の目と耳を通じて、公国の事情を知ったらしくて……私に何度も話しかけてくださって……とても親切で素敵な方でしたわ……」
なんだかうっとりするような顔になっていた。私は喉元まで出掛かっている一言をなんとか堪えようとした。だから、公爵とはちょっとつりあわないというか、なんというか。
「別の生き方など考えてもいませんでしたのに……ついには説得されてしまったわ……貴女を助けたお礼に、帝国軍との交渉役になって……今回の公開処刑を、取り計らってくださったの……」
さすがスクルフ兄弟、帝国兵にも引けをとらない、もの凄い行動力だった。
「けど、帝国軍がそんなことタダでしてくれたの?」
「あの方は、魔法世界の情報を……少し与えたそうよ……」
驚いて目を見張った。いくら私を助けるためとは言え、連合の情報を引き渡すなんて、そんなスパイみたいな真似をしてもいいのだろうか。
「魔石機器の製造技術や……そういったものでも、帝国にはとても重要だったから……」
「ああ、なるほどね……そういえばみんな技師だし、それにドックⅢ世もいるから……あ」
はた、と恐ろしい考えに行き当たった。いや、まて。あのドックⅢ世なら、あるいは連合軍のどんな機密情報を盗んでいてもおかしくないのでは? いや、あいつが普通じゃないからと言って、まさかさすがにそんな情報を帝国に売り渡すような事まではしていないだろうけど。いや、けど、本当に魔石機器の情報なんかで帝国は首を縦に振ったのだろうか? 実際の所はどうなんだろう?
「後は……貴女が帰られなければ、連合は最新兵器で戦争を仕掛けるつもりだ……そう言えば、簡単に事は運んだでしょうね……なぜなら……帝国は今、戦争をしたくても出来ない状態だから……」
「戦争ができないの? どう言うこと?」私は眉をひそめた。
私は帝国の三つの恐怖に遭遇した。国境で飛空艇を待ち伏せしていた兵士たちは、私には十分すぎるほどの戦力を兼ね備えているように見えた。あんなものが故郷に足を踏み入れたと想像するだけで身の毛がよだつ。けれど、それでも戦争が出来ないとは、一体どう言うことだろうか。
「皇帝が、不在だったの……今の政治の実権を握っているのは騎士団よ……アウクスⅡ世の仮面の中身は……空っぽだったわ……」
テルマ公爵にとっては、それが唯一の心残りだったそうだ。
舞台上に並べられた椅子の上には、二つの仮面が置かれていた。
一つはテルマ公爵の仮面、そしてもう一つは、ハルミネ大臣の仮面だった。
紫色のマントを羽織り、同色の帽子を被った裁判官は一礼をすると、槌を大きく振り上げて二つの仮面を叩き割った。
これで二つの役割はこの世から消えた。皇帝の世継ぎとなるディートリヒも生まれなくなった訳だ。けれど、いまは戦争を行なったり法を変えたりする権限を持つ皇帝が存在しない。
「……テルマちゃん、この国は一体、どうなるの?」
処刑の様子をじっと見守っていたテルマ公爵は、私と秘密を共有するように呟いた。
「さあ……私、存じません事よ……」
*
その後、私は名もない騎士の位を手に入れたウラジミールに連れられて、偵察機の墜落したカバナール雪原に戻ってきた。
この国では素性が分からないようにあえて素顔を晒して挑むらしい、ウラジミールは身分を明かさないためにあえて仮面をつけていなかった。
メンテナンスはなんとか終わったけれど、パプシが壊れているし、マルハトさんには飛行禁止命令をくらっている。なにより遠すぎるので、私はウラジミールのスノーモービルに相乗りして雪原を北上していった。
雪原のほぼ中央に見える機影から、十分に離れた位置でスノーモービルを止め、そこから手を繋いでてくてく歩いていった。
パイロットは例の飛空艇の中で丸一日過ごしていたらしい、コックピットから足を投げ出して、どこから持ち込んだのかサングラス越しにこっちをじっと見ていた。
よっという声と共に機体の外に出て、けん制するように先に声をかけた。
「ねぇ、ひょっとして彼が君のお友達?」
ウラジミールを見たパイロットは不審そうに眉を上げ、私に同意を求めた。
「思ったよりでかいな」
互いに憎みあっている帝国兵と連合兵の間に、ただならぬ緊張が漂っていたのは傍目にも明らかだった。
私はなるべく雰囲気を悪化させないよう、無邪気を装ってにっこり頷いた。少し大人になった気がする。
ちらりとコックピットを見やったウラジミールは、小さく呟いた。
「これが連合の船か。思ったより狭いな」
「なに、寝そべってりゃ大丈夫、なんとかなる」
機体の背後には救難用の積荷や、予備の機関銃などが捨てられていて、運転席の脇に大人一人が入る事の出来る隙間が出来ていた。
それでも難色を示すよううに、じろりとパイロットに目を向けたウラジミール。パイロットは少し怯んでいた。
「変な真似はするなよ」
ウラジミールはそれだけ忠告した。パイロットはきゅっと眉を寄せて、変な物を見るようにウラジミールを見ていた。
「……そんな趣味はないから安心しろ」
なにやら含みのある言い方だった。私とウラジミールはしばらく顔を見合わせていた。どうやらお互いの意図が通じていなかったようだ。
「予定が変わった。彼女は羽を失って、自力で帰還できないんだ、乗せてやって欲しい」
「なんだ、チビたんが乗るのか」ふーん、と彼は鼻息を漏らした。「じゃ、お友達は?」
「彼女はもう来ない」
それ以上は何も詮索をする必要はない。そんな時間も無い。パイロットはしきりに頷いて、足元の影に目を落とした。
「じゃ、行くか。速攻で飛び立つから、お別れの挨拶をするなら今の内にしておいてくれ」
別れの挨拶、と言われても。何もない雪原のど真ん中で、一体なにに挨拶をすればよいのか。私はきょろきょろと周りを見た。隣に居るのはウラジミールだけだ。ふいに彼と一瞬目があった。
私はウラジミールの襟をぎゅっと握り締めて、背伸びをして親愛の挨拶を行った。スクルフ式の、口をぺろっと舐めるいつもの挨拶だ。なんだか余計に寂しかったので、もう二、三回した。とうとうウラジミールは怒ったらしい、私の肩を押しのけて引き剥がした。
「……許されぬ恋か、切ないねぇ」
パイロットは魔力機関が唸りを上げる機体に腰を下ろして、口笛を吹いていた。
「なっ……」ウラジミールは顔色を目まぐるしく変えた。「なんだ、とっ……」
「わかったわかった、もう何も言うな。愛しのチビたんは、この俺が責任を持って送り届けてやるから」
「どういう意味だ。いや違う、そうじゃない、今のはこいつが勝手にやったことだ!」
口をごしごし拭うウラジミールの足元を通って、私はコックピットに乗り込んだ。機体は防風窓を降ろして、ゆっくりと前進しはじめた。
ウラジミールは機体を追いかけてきて、どんどんと窓を叩いていた。手を振る私の向こうで、涼しい顔をしているパイロットに罵声を飛ばしていた。
「おい待て、こらお前っ! 止めろ、この船を止めろっ!」
「悪いけどもうマジで時間がねぇんだって、名残惜しいかもしれねぇけど諦めてくれ」
「違うっ! やめろっ! やめてくれ、勘違いしたまま向こうの世界に行くな!」
「安心しなって誰にも言わないさ、俺達の世界じゃ恋愛は自由なんだぜ?」
「そうか、では連合は男だろうが幼女だろうが恋愛対象として見る、見境の無い連中だと軍に報告をせねばなるまいな!」
パイロットは焦った様子で振り返った。
「な、なんだとっ! お前、せっかく黙っておいてやろうと言っているのにっ! もう止めた、さっきのは酒場でネタにしてやる! アーディナル中の酔っ払いたちが夜な夜なお前のネタ話を口ずさんでいるぜ!」
「貴様ァ! 戦場で会ったら覚えていろ! その細長い飛空艇を片っ端から海に沈めてやる!」
「上から機雷を落としてやる!」
九三八年、冬の前期。再び戦争の危機に陥った連合と帝国の間で、互いの国の兵士が誘拐された少女の身柄を密かに受け渡して衝突の危機を回避する出来事があった。
アーディナルの歴史のなかで小さいけれどとても重要だったこの事件の存在を、このときはまだ誰も知る由はなかったのだ。国家的なレベルでの戦争を阻止し、個人的なレベルでの宿敵を生み出して、飛空艇は氷の世界から軽やかに旅立っていった。
終わりに
テルマ公爵はその後、南国の僻地で伯爵として新たな生活を送るようになった。
気候の涼しいグリーンベルトの農耕地で、屋敷からはジャガイモやパセリの畑が見渡せるそうだ。この間貰った手紙では、テラスから緑を眺めるのが好きだと言っていた。
湖でカフェをしていたハルミネ大臣もそこに招かれ、身分は持っていないけれど、再び彼女に仕える事になった。
給仕をするには不向きな大柄な体で、ひいひい言いながらテラスにお茶を持ってくるのが彼の日課だそうだ。
日当たりのいいテラスに置かれたラジオのスピーカーからは、今もなおDJコバタさんの明朗な声が聞こえていた。
「みなさんこんにちは、リビング・イン・セオフィールドのお時間がやってまいりました。さて、本日は素敵なゲストとお電話が繋がっています。皆さんのご厚意によって、無事に戻って来る事ができました。私の娘、アンシェ・アンシール=アルシカです! 聞こえますかー?」
「……あ、コバタさん。う、うん、聞こえますよー」
「はっはっは。こいつめネコ被っちゃってー。えー、今回くださったお手紙では、誰か特別な人に特別な思いを伝えたいのだそうですね?」
「ネタ先にばらさないでよ……うん、あの、あのね……私ね……」
ラジオから聞こえる私の声はどんどん小さくなっていって、隣でゼラが頑張れ、言っちゃえと囁く声が入っていた。
テーブルの側にやってきたハルミネ大臣が、「またラジオを聞いておいでですか?」と苦笑する。
公爵は人差し指を唇にあてがって、口うるさい大臣に向かっていつものように微笑んでいた。
「私ね、もう、十六歳になったのね。そ、それでね、私、まだコバタさんとしたあの約束覚えてるの……十六歳になって、まだコバタさんの事が好きだったら、結婚、してもいいって……」
ラジオの向こうで、一瞬空気が凍り付いてしまった。場の空気を取り持つのがうまいコバタさんにしては珍しい事である。
眉を思いっきりひそめていたハルミネ大臣の注ぐお茶は、ティーカップから溢れてテーブルクロスを浸していた。彼は押し殺した声であつっ、と言って飛び跳ねた。
「……えっ、えーっ。そ、そんな昔の約束を覚えていたんだ、はっはぁー、なんだか嬉しいなぁ! さて、次のお便りだけど……」
昔の事だと水に流し、なんとか和やかな雰囲気を保とうと必死のコバタさんに対して、私は電話越しに畳み掛けるような早口を喋った。
「わ、わたしわたしわたしっ、今まで家出したときは、どんなに家から離れていても平気だった。だって、ずっとコバタさんのラジオを聞いてたから。だから、どんなに苦しくても平気だった。
けどラジオが側からなくなった時、胸の奥が急に痛くなったの。私、どうしてもコバタさんの声が聞きたくなって、耐え切れなくなったの。自分でも何が起こったのかわからなかった、人工知能のバグか何かかと思ってた。どうしたんだろうと思ってて、けど、ようやく原因に気づいたの。
雪の日に、コバタさんが私を拾ってくれたときから、何かは思い出せないけど、ずっと心の中に何か温かいプログラムが書き込まれていたの。ラジオを聞いている間はそれを思い出さなかったんだけど、コバタさんの事を思い出そうとすると、そのたびにプログラムが開いて、なんだか胸が苦しくなるの。
私、このプログラムの名前はよく知らないけど、もう止まらないの。閉じないの、これ。コバタさんにぎゅっとして貰わないと落ち着かないの。ごめんなさい、コバタさん、こんな事言われても、迷惑かもしれないけど。
こ、こ、こ、コバタさん、私、十六になりました。結婚してくださいっ! 私、メカだけど、羽が生えているけど、毛むくじゃらの犬だけど、貴方の事が――好きっ!」
テルマ公爵は白い手袋をはめた手で口元をおさえ、品の良い笑い声を上げていた。
その隣で、ハルミネ大臣は石のように硬直して、机に身を乗り出すようにラジオを凝視していた。
「………えー……では、ここで、一旦CMに入りまーす………」
このラジオ番組にCMはない。長年のDJとしての勘がなせる、鮮やかな逃げだった。リクエスト曲の紹介と同じように軽快な音楽が流れ、ハルミネ大臣は眉をひそめてテルマ公爵を見やった。
「ど、どうなるのでしょう?」
「さあ……私、存じません事よ……」
我関せずと言った様子でくすくす笑っていると、中途半端なところで曲がぶつっと途切れた。代わりに、野太いマルハトさんの大声が響いた。
「えー、突然ですがコバタの兄のマルハトです。ラジオ番組の途中に申し訳ございません、緊急事態です! DJコバタが逃げました!」
ハルミネ大臣はええーっと目を剥いて、テルマ公爵はいっそう笑っていた。
「当番組ではDJコバタの目撃情報を募集します、逮捕に繋がる有力情報には賞金七百五十エルシャルンを贈呈します! 手段は問わず! 多少手荒な真似をしても構いません! 生死? ……もちろん問うものか! セオフィールドの獣人ども、かかれーっ!」
なにか奇怪な唸り声がラジオをびりびりと震わせた。セオフィールド中の獣たちの咆哮だった。
DJの不在で番組が途絶えてしまい、しばらくあわただしい騒音がラジオから流れていた。不意に椅子から立ち上がったテルマ公爵に、ハルミネ大臣は声をかけた。
「どちらへ?」
「ウラジミールに頼んで……ちょっと向こうの世界まで……」
テルマ公爵は日傘をさすと、にっと微笑んだ。
「お話の続きがどうしても……気になりますの……」
まさかまさか、ラジオの向こうでそんなやり取りがあったとは、その頃の私達は露ほども思っていなかった。
ラジオからは騒々しいセオフィールドの音声が流れ続けていた。マルハトさんは気遣わしげに言った。
「アンシェ、聞こえるか? 大丈夫だ、そこで待っていろ、見つかったらすぐに連絡するからな!」
ラジオ局とまだ電話で繋がっていた私は、とつぜんキレて、大声で唸り声を上げた。
「きゅうううううううううううううううううううううううううううううううううううん!」
ぶぶぶぶぶ、と電話越しに翼のはためく振動音が響いていた。私は怒っていた。体の芯から怒っていた。なんてデリカシーのなさだろう。ひどいっしょ。最悪っしょ。最後の最後で乙女心を踏みにじられたよ。
「飛んでもいい?! ねぇ、ごめん事後承諾だけど! マルハトさん、私、このまま飛んで探しちゃっても、構わないかなァ?!」
私の怒声は羽音よりも、もっとくっきりと、はっきりと、ラジオから世界中に向かって放送されていたのだった。
アンシェ=アンシール=アルシカのラジオ