
つぶれたかえる
もうすぐ中学生の娘と、先日誕生日を迎えた嫁が俺の買ったワンピースを着て襖からこんな俺を見つめていた。
じとじとと、じめじめという
どす黒くて厭らしい音が聞こえてきそうだった。
それできっとよかった。
あ
目の前の四人掛けの優先席に太ったクソババアが二匹。
【がたんごとん がたんごとん】
そんなクソババアを通り越して宙を見つめながら私が考えているのは彼のことと、以外はただの空想にしか過ぎない。高校生の途中から訳あって一人暮らし。2LDK。一人で暮らすには無駄に一部屋多くて寂しさも感じるがいつだって話しかける水槽が一つ。寂しさなんてこんな簡単に紛れてしまう。紛れ込んでしまう。そんな質素な部屋に帰ってきて早々、口の中のトイレットペーパーをトイレに吐き出す。水に溶けるトイレットペーパーを口の中で飼育する企画を自分たった一人で遂行。そして電車の中だってどこだって大勢の人間という生物に埋もれて誰にも聞かれてなくても言ってやるんだ。「私が噛んでいるのは間違えなくガムです」と。真剣な顔つきで貴方を見つめて。
彼とした遊びを紹介します。
私の質素な家の台所にある、着物を着た太ったおじさんが大きな虎と大喧嘩している柄のどんぶり。綺麗な色のついたガラスのおしゃれな器、ワイングラスを用意してそれらに梅干しの種を投下。食べ終わった種の山。電気を消して、ろうそくをつけた。どっかの国の危ない儀式にも見える、見たこともないグロテスクキュート。口の中はすっぱいすっぱい大惨事。趣味はひらめき。私は彼を尊敬しているし彼も私を。とは言え、私達は至って普通のカップル。セックスもする。女の、子は、セックスがしたいだなんて自分から口にしたものなら「女の子でしょ」とか言われがちなご時世だが、セックスがしたいだなんて素晴らしく普通の話だ。こんなに楽しいスポーツないでしょう。こんなにワクワクする遊びないでしょう。こんなに幸せな儀式、他にないでしょ?ていうか、あんた達はしないとでも言うのか。女の子は便も屁もしなければ交尾もしないだなんて、ちゃんちゃらおかしいわ。これは空想かしら。彼のことかしら。
彼は私の頭を包み込んだ。ふんわりいつもの柔軟剤の匂いがして目を瞑る。この世の全ての星の生物を全員集めて恋愛ごっこをしたって彼ほど好きな人は居ない。このぬくもりに包み込まれるたび、そう心の中で何度も再確認した。いや、そうじゃなくて彼以外はとても興味がない。つまらない。つまらない。なにがいいのか、どこがいいのか、一緒にいて何がプラスになるのか。プラス。プラス。プラス。そうよ。そうだわ。プラス。プラス。プラス。つまり私は彼だ。私は彼だ。彼も私しかいなくて彼も。彼が。彼は・・・きっと。
全国民に言いたいわ。あなたのいいところはどこでしょう。わかりやすくプレゼンテーションして下さい。パワーポイントも使って良いので。つまんなかったら、貴方のノートパソコンをパカッと割って遠くからあんたの股間に投げつけて致命傷かのいきおいで心の傷を負わせて外に放り投げてやる。
また関係のないこと。
ビリっ
い
頭の中でいろんな足のいろんなストッキングをびりびりびり。びりっ。
みんなより早めの生理がきた頃あたりから、他人なんて全員どうでもよかった。中学校のクラスメイトなんてバカとクソガキとザコの集まりだったので仲良くなろうなんてこれっぽっちも思わなかった。わめく前の席のブス。その前、ぶりっこ。その前、泣き虫あまのじゃく。そのななめ後ろの男子、変な臭い。その後ろ、ムードメーカー(自称)。そのななめ後ろ、私。私は世界一くだらなくない。そんなどっからともない自信があった。理由なんてない。私はその頃から、ガムみたいなものをくちゃくちゃ、くちゃくちゃと、噛んでいた。「空ちゃん」と名前を呼ばれて顔を上げると、目の前に色んな色の爪した金色の爆発頭のギャルが飛び込んできた。彼女は盛りすぎくらい髪の毛を盛っていたのでシルエットがもはや巨大だった。バサバサの付けまつ毛によって、もう性別すら私にはよくわからない。このモンスターを「女の子」と呼ぶ男は全員顔にある二つの切れ目の中身はピンポン玉なんだわ。
「友だちになろう」
ともだちに?
「ずっと友だちになりたいって思って。ほら、空ぽん可愛いじゃん。男子からもチョー人気だよ」
空ぽんです。
人にどう思われてるか気にしたことなんて一度も無かった。周りと違って私は、そこまで濃い化粧をしなくたってある程度の顔になっていたので目の周りを流行の真っ黒に塗りつぶすわけでもなく、こいつみたいに豹柄ばかりを身にまとい存在するはずの無いピンクのネコちゃんのストラップをつけて「まさか自分が動物(ネコちゃんを筆頭とした)と同じ類と思ってるのか」ってほど獣柄を好むわけでもなく自分を飾ることが出来た。地味な訳では無かったが、派手でもなかった。流行も、全くよくわからない。モンスターの中に紛れた人間というイメージで逆に目立っていたのかもしれない。自分でいうのもなんだが顔も普通。美人でもなければ、笑えるほどブスでもない。このクソ女よりはマシなのかな。つまりは、私のすべてが何のへんてつもない。種も仕掛けも。私の通っていた学校は見た目が派手で街を歩けば目立つような子が多かったが、中身はクズ人間大集合で毎日うんざりしていた。目立つな。目立つな!!全員に勝てる自信が、どこからか湧いてくる。喧嘩するわけでもなく、人間として、勝てる自信。男子からもチョー人気だと?とっさに男子を睨みつける。私の視線に気づいて、わざとらしく口笛を吹くやつ、照れながらどつき合うやつ。
昭和?
ここは、どこの村?どこの星?それから毎日避けても避けても、どうしてもその金髪の化け物はつきまとってきた。お弁当を食べるときも、移動教室も…トイレも!人数も、増えていった。同じような化け物ばかりで香水臭くて死にたかった。そのうち、風の噂でここにいる人間に嫌われる条件を聞いた。
「あいつ、してるらしいよ、オナニー!」
「うわー!」
「てかあいつ痴女らしいよ。いろんなやつと、ヤッてんだって。」
「まじきもー、ヤリマンじゃん。ただの!」
性に関する内容。くだらない。好奇心。それを横目で見ながら、紙パックのバナナミルクを飲んでいた。その噂をおかずに、たわいもないバナナミルクを。
私は、可愛くも面白くもなんともない合成顔面野郎(名前も忘れた)と喋るのが兎に角、面倒臭かった。くちゃくちゃと何か噛みながら、変な顔だなぁだとか、いきなりこいつのスカートを無理矢理引きちぎったらこいつ史上、一番面白い事になるだろうだとか。そんなことを考えていた。むしろ頭の中で、こいつのスカート引きちぎりまくっていた。一人にしてくれ。特に意味なんてないわ。
「私してるよ」
突然ぶっこんでみる。
「オナニー、してるよ」
「…」
こいつの顔が、どんどん余計ブスになっていく。目を見開いて、首を傾げた。
「オナニー大好きオナニー大好きオナニー大好きオナニー大好きオナニー大好きオナニー大好きオナニー大好きオナニー大好きオナニー大好きオナニー」
化け物を見る目?
作戦は成功。たったそれだけのことで、私は一人になれた。化け物を見る目って、あんな目なのね。そしたら私は貴方のことをまだギリギリ化け物じゃないとでも思ってたのか。まぁ、嬉しい。おめでとうございます!自ら一人になったのだから、何も文句はないだろう。何も寂しい事なんてない。少しだけ。少しだけ考えていた。こんな私を笑い飛ばしてくれたら、一緒に居てやったのに。むしろ、一緒に居たかったのに。そうゆうことなら。「友達」っていうのは「同類」ってことだってお父さんが言っていた。だから、そうでしょ?そう言えば、私はみんなより早い生理がきたくらいの時期、家族が大好きだった。優しいお父さん。愛情がいつだって伝わってくる情の深いお父さん。可愛いお母さん。私なんかと違って人と話すのが大好きで明るくて。私の不器用なところはお父さん似だな。って思ってた。家族、大好き。どっからともなく、今の彼は私のお父さんに似ていた気がした。私がどんな変な事を言っても笑ってくれる。というか、動じないというか。お母さんは少し嫌な顔をする時もあるけどお父さんはいつだって笑ってくれた。「好き」ってことも、「同類」なんだ。きっと。まあ、そんなことですが。同類、を探している訳でも、「好き」を探してる訳でもないが、私はどこでも変に人間観察をするのが癖になっていた。どういう人か気になってるわけじゃなくて、どういう性質の人間かって話。生物の授業の要領ね。電車の吊革を掴む後ろ姿の、ポケットにパンダのワッペン貼ったおっさん。目の前のウトウトしながらヨダレたらしてる女の子。透明の唾液の糸が、ロングスカートにシミを作る。ありゃ起きたらきっと恥ずかしい。どうしても服装がダサい小学生の大群。「俺あいつ好きになっちゃったよーだっておっぱい見ちゃったんだもん」学ランを着た、中二病どころか、小二病くらいのレベルの会話をする高校生。うらやましい。そんなものばかり見ていた。この頃はまだこう思ってた。どうしたって世の中はこんなに笑いが止まらない物で溢れているんだろう。
うらやましい。
私が高校に入学する頃、お父さんが死んだ。
ガタンゴトン ガタンゴトン がたんごとん
よく見る額縁でにこにこ笑うお父さん。額縁の中だけまるで3D。私の目の前まで飛び出てきてて、目を擦っても擦っても存在してるかのようで、触れようとしても触れない。そんな下手な例えで、悲しいのを誤魔化した。「どうでもいい」心の中では声を出して泣いてたが、私の涙の流し方は震えもしなかった。眉間にしわもよらず、表情も変わらない。ただただ、涙は頬をつたっていった。よく「滝のように」だとか「こぼれ落ちる」だとか言うけど全然違った。なんだろう、もずくだとかそうめんだとか。目から出るって創造しただけで痛くてものすごく怖いものがもともと私の目の奥に詰まってて、すごい音を立てて目の淵から脱走する感じ。痛いの、痛いんだ。悲しい時の涙って。我慢しようとでも思ってたのか、よく覚えてないけれど、とにかく意味不明な位に悲しかった。帰ってきてほしかった。外国より、遠いところってどこよ。宇宙よりも。どこよ、そこ。誰か説明して。お母さんは壊れそうだった。目をぎゅっとしてわんわん言っていた。子供のようだった。まるで風船が木にひっかかった子供。そう考えたら、風船が木に引っかかったくらいであんなに泣きわめいてんじゃねえよガキ共。こういう時に、こうやって泣くんだ。私は、額縁の中で嬉しそうなお父さんを見て、ふいに私が小さい頃に珍しくて飼っていた真っ赤なカエルをお父さんが生足で潰したのを思い出した。
【ぐしゃっげこっ】
見た目はもはやトラウマだった。はずなのに、そのみじめなカエルの姿、かたちを思い出す事は一度も無かった。思い出そうとしても可愛らしいイラストのカエルがぺったんこになっている様しか思い浮かばない。トラウマ?これが。いいえ。でも、何故あの時。カエルを。素足で。カエルを。かえるって、あんなにぐっちゃぐちゃになるのね。お父さんは、病死だった。つまりは、死ぬ過程を私は見た。苦しむ姿。無理に笑う顔。かすれた声。しわしわの小さな手。よぼよぼの顔、痩せた体。小さなお父さん。小さくなったんだ。こんなに人は小さくなるのね。ふいに一人になった時、これからお父さんがいつか私の前から消えてしまうのが切なくて切なくて、わんわん泣いたこともあった。助けてお父さん。涙が止まらない。お父さんは、私よりももっともっと辛くて痛くて苦しいのに笑っていた。誤魔化していた。一日一日、ずっとずっと夢だと思っていた。日に日に瞼が重くなった、お父さんもそうだと思う。だから、寝ちゃったんでしょう?疲れて。お父さんの死んだ日、私は足元につぶれたカエルが見えた。それは、いつか電車に乗ってた知らないおじさんのお尻についた可愛くもなんともないワッペンにそっくりだった。少し早めの生理が来たときあたりからずっと、目が回ると、目眩がするとあのカエルが見える。お父さんが死んでからもずっとだ。どうしても思い出せない、あのカエルがポップになってフラッシュバックする。私は、それを見たことによって混乱の渦に迷い込んでしまう気がして目を逸らす癖があった。どうしたって嫌な事だとわかっていることを考えるときはすっごくすっごく楽しかった思い出に浸るのだ。そんな秘密の幸せを、昔お父さんに教わった。お父さんは、あの時つぶれたカエルの可哀想な形を覚えてるだろうか。お父さん、覚えてる?お父さんが死んでからは、クラスで私に寄ってくる女の子がたくさん出てきた。「相談乗る」だとか、「大丈夫?」だとか。「話し聞く」だとか「無理しないでね」だとか教師ですらそんな馬鹿げた事をぬかした。テンプレートがあるのですか?と思った。思ってもいない癖に。人間それ以外かける言葉が思いつかないんでしょうね。みんながみんな、人間はいい人になりたいのね。何故だろう。ものすごく迷惑だわ。何故?私はその吐き気がする綺麗事全部に、完璧な愛想笑いで返した。
話を聞くだなんて安易でバカなこと言うヤツには100点満点の笑顔で最初から最後まで話して「ほらなんかいいこと言ってくれるんでしょ?」と追い詰め逆に泣かすという嫌がらせを遂行した。慰められた時に「無理して笑ってますけど顔」をする女子高生っていうのはそこらじゅうたくさんいるが、私はそんな回りくどい演技をするほど弱くない。完璧な愛想笑いだった。
葬式から帰ってもお母さんは泣き続けた。「人間、中身ほとんど水なんだから」と言ってやりたかった。萎む。間違えなく。そう思った。夕方を過ぎると、泣き声がうるさく感じた。壊れてしまうんじゃないかと、本気でそう感じさせた。お母さんが私を産んだ時、私こんなんだったのかな。赤ちゃんがいる母親っていうのはこうゆう気持ちなのだろうか。お母さんも、家すらも壊れてしまうんじゃないかというくらい大声で泣く日もあった。お母さんはそのうち、泣き疲れて寝てしまった。すると今度は、起きなくなった。狭いリビングに質素に引いてある布団で丸くなっていた。一週間も寝たきりで、私は話しかけなかったけれど「ただいま」だけは言い続けた。正式には、多分母は起きていたが、生きるのに疲れて、考えるのにも疲れて動くのも嫌になって、つまりは悲しくてどうしようもないんだと思った。なんだかわかる気がした。私もしばらくはそんな気持ちで学校に行っていた。家にいることでお父さんを思い出して泣いてしまうのが私は嫌だった。もし天国からこちらの様子が見えるとしたら、「そら、弱っちいな」とお父さんに思われて、おまけに心配しすぎてお父さんも泣いちゃったら嫌じゃないか。お父さんは、強いのに。最強なのに。お母さんもまさか、息をするのに疲れて死んでしまったのではないかという心配はしなかった。そんなこと、この世にあり得ない。起こり得ない。だって、お母さんだって本当は最強だと思っていたんだ。私は。
「ただいま」
お母さんが、布団の中に居ない。冷静に家の中を探した。キッチン、押入れの中、クローゼット。これで本当にクローゼットの中に入ってたら大笑いしてやろうと思った。何をみっともない、本当に子供かあんたは。お母さんは見つからない。うちはアパートだったから、探すところなんて限られていた。私は心の中でバカバカしいと思いつつ小さな紺色の冷蔵庫を開けてみた。ぎっしりと、中身はトマトだった。
からだが、かちんこちん。
こ。
「ただいま」
お母さんが帰ってきた。私は急いで冷蔵庫を閉じ、お母さんの方を見た。
お母さんは、真っ赤なリボンに真っ赤なワンピース、真っ赤な口紅をしていた。
う
そんな真っ赤なワンピース、どこで買ったの?
「ただいま」
考えるな。
考えるな、感じろ!
きっと少し触れただけで何かが壊れてしまう。私の、お母さんはどこに行ってしまったのかしら。いいえ。私の、お母さんは、ここよ。
「おかえり」
ちぎれそうな母の目をじっと見た。買い物袋からたくさんのトマトを取り出しあまりにも無理矢理冷蔵庫に入れた。入りきらないトマトは、ぐちゃっという音をさせながら無理矢理突っ込み、オレンジの気味悪い汁が笑顔の母の顔に飛んだ。それでも、母は笑顔だった。しばらくすると、当たり前のように冷蔵庫の中身は真っ赤になった。
「お母さん」
「赤が好きーーーーーーーーーーーーー!!!!」
意味の分からないイントネーションで母が絶叫した。言葉が出ない。母の喉はきっとキリキリ痛んで、ぶち破れそう。母は呼吸を整えると母親のように優しく私に微笑んだ。
「赤が好きだって気づいたの」
母は冷蔵庫を閉めて早歩きで自分の寝ていた布団をめくる。大量のカセットテープ。そこから一つ取り出し埃をかぶったラジカセに「ブーッ」と息を吹きかけてから突っ込んだ。踊る。不器用に。そしてラジカセからささやくように小さく流れたのは「リンゴの唄」 口ずさむ、母の赤い口元。オレンジ色の、ゆらゆらキッチンの間接照明。中身の赤い冷蔵庫。赤、赤、赤。
『赤が好きだって、気づいたの…』
がたんごとん。がたんごとん。
どこか全くわからない真っ白なお部屋。真っ白な服を着て赤ちゃんの頃にしていた前掛けをしていた。目の前には、小さなカエルのカラフルなおもちゃの山があった。私はその前に座り込んでぼーっとしていた。すごく広くて、すごく静かで誰も居なかった。私は小さな頃から何かを口の中にいれるのが好きだ。好きなの。理由は無い。そのカエル達を、ひとつひとつ口の中に入れてみる。見ないで口の中にいれたのに、赤が口の中に入ると吐き出した。吹き矢のように飛ばした。おもちゃの山を掻き分けると、本物の緑のカエルがひっくり返っていたので、私はそれを握りつぶ
握りしめ
だってびっくりしたから
足元にはつぶれたカエルのワッペンが少しだけ可愛くなくなって地面に張り付いていた。
『次は高円寺、高円寺。』
はっとして目が覚め、慌てて電車を降りた。かいたことのないような汗をかいていた。妄想の中に迷い込んでいた。癖だ。
家に帰ると、母が台所で何やら切っていた。料理をするくらいまで前向きになったと私は信じたかったが、母の頭に真っ赤なリボンが乗ってるのを見たとき、そう簡単にはいかないと察した。
「ただいま」
私は普通にした。
「おかえり、遅かったわね」
いつもの母だったが、大きな銀のボールに切ったトマトが山積みになっているのを見てぞっとした。切っているのも、全てトマト。ボールの中身も、全部。
オレンジ色のライトに照らされて、地獄絵図。私の体は、 金縛りにあったみたいに動かなくなった。母が怖い訳では無く、今まで生きててこんなに意味が分からないことがこの世に無かったからだ。意味が、わからない。考えても考えても
よりによってうちの母がそんな訳ない。
そんな訳?
ただただ、頭の中で何度も、首から上がきっと鉄になった。そんな夢。ダンベルだ。重くて鉄のような自分の頭をなんの疑いも無く触った。触った。触った。触った。血が音もせず吹き出した。気づいた時には私の手が千本の針で出来ていた。千本。そんな夢だった。夢を、ちゃんと起きている時にはっきりと。足元に気配を感じて、目を逸らす。都合が、悪くなると。そうだ。私は今、
都合が悪いのよ。
深呼吸。
何も考えず次の日私はクラスメイトの男の子の家に行った。だって来いって言ったんだもんっ。
名前はカズキと言った。ガリガリだが、ひ弱では無く、やんちゃそうな八重歯がチャームポイント。茶髪の短い髪が今風(よくわからない)にいつもセットされていて、顔もそこまで悪くない。身長もそこそこ。授業中、妙にアイコンタクトをしてくる。ニヤニヤする訳でもなく、「わかってるだろ?」みたいな顔をしてこっちを見てくる。
たいしてわかりません。
最初はたいした人間じゃないのが見え見えな癖して図に乗るなと思い睨みつけてたが、そのうち興味本意に可愛い笑顔で返してみた。
あからさまに「うわっやべぇ。」って顔をされたら面白かったものの、そいつは「よしよし、それでいいんだ。強がってたんだろ?」みたいな顔をしてきやがったもんだから心の中でめった刺しにしてやったわ。
何故そんなやつの家に来たかと言うと、私は正直こいつが私に気があるってことにいい気になっていて、そのうえ家に帰りたくない病。病んでたんだもんっ。悲劇のヒロインぶってる訳じゃ無いけど、家では母が意味不明な行動を繰り返している。エンターテイメントとして見ていれば家に居て退屈なことなんて一つもないだろう。でも母のその行動は何故か、私にとっちゃ面白いと思えなかった。つまりは、つまらなかった。笑えない。エンターテイメントではない。すべっている。ただただ、意味がわからなくて考えたく無い。まぁそんなことは、どうでもいいのよ。
「お茶、飲む?」
「大丈夫。ありがと」
妙に優しくしてみる。目をぱっちりと開いて微笑んだ。コップの中の溶けていく氷を意味もなく眺めたりしていた。
「一人暮らしって楽しい?」
いつもみたいにガムみたいな何かを噛むのも、今日はやめていた。
こんなに、たいした顔面じゃないたいした考えもないたいしたお金もないのに何故、悲観的にならずに女の子を誘えるのだろうか。今思えば、みんなに言える事かもしれないけど。まあ、いろいろな理由があるとか無いとかは置いといて、適当に愛されたくて寂しかった。そんな気分だった。ムラムラした。ティッシュなんか噛んでるのがバレて嫌われたくなかった。
DQN
「ねぇ、空さぁ、クラスで誰と仲良いの?」
いきなり下の名前で呼んできやがったなと思いながらコップを揺らした。氷のぶつかる音を聞いてから、極力目を見開いてそちらを見つめた。
「わかんない。ねぇ、仲良い人って居なきゃだめかなぁ」
そして詰め寄る。
「友達って必ず必要?」
カズキはしばらく私と見つめあって唖然としてから、吹き出すように笑った。口から吹き出たお茶が口元についてるのを見て、心の中でオロロロロロロロロロロロ
なのに、私にキスをしてきた。
「ほんっと面白い奴だよな、空は」
私は究極に可愛く微笑んで喜んだ。
心の中で高層ビルの屋上から何度もこいつを放り投げた。
え
いらないと言ったのにお茶が出てきました。
私はそれをゆっくり飲みながら、目の前にあるお菓子たちを見下ろす。センスのかけらもないお皿に、ビスケットと煎餅。お母さんの仕送りかなぁ。とぼんやり考えた。バイトしろよクズ。お母さん、息子はもうすぐ私に自分の息子を見せびらかすでしょう。私はもうすぐ貴方の息子の息子とご対面するのでしょうか?お菓子を見てぼんやりとしているフリをした。具合が悪くなった。
カズキは何の迷いもなくお菓子に手を伸ばし、少しこぼしながらボリボリと食べて私の視線に気がついた。
「なぁに、食べたいの?」
甘えた声。微笑む顔が私にとっちゃ究極に気持ち悪かった。
「別に大丈夫」
私は精一杯可愛い顔で、そちらの目を見つめそう言った。こいつは、なんてバカで勘違いでつまらなくてしょうもない。そう思いながら見つめる先の彼の瞳に写り込む私は、月の中で餅をつくうさぎのように嘘臭かった。あいつは餅なんかついちゃいない。ただのぐちゃぐちゃのシミだわ。そうやって全部の物事に対してひねくれた感情を私は抱いていた。
そういや、今思えば思春期の時なんてのは
エロいことで寂しさ埋まればそれで完璧よ。
女も。
「ただいま」
薄暗いオレンジのライトに照らされた母の姿、いやそれよりも母の頭の上の大きなリボン。もう違和感はなかった。
ただ赤いワンピースを着ていた母だが、そのワンピースがお父さんに昔買ってもらったものだと気づいた時「なるほどね」と言ってしまった。
「遅かったわね」
「ま、ちょっと」
私は何事もなくソファに腰掛けた。母は相変わらずトマトを切っていて、ボールはもう溢れている。山盛りで、業務用の何かに使うトマト達みたい。というか、トマト地獄。そんな単語あるのかどうかは、知らないけど。トマトを切り続ける音が、テンポよく響く。
「…空、今日はねぇ、」
母が口を開く。私は母の背中を見つめる。一瞬時が止まったようだった。
あまり間隔も開けず「うん」と自然に返事をした。母の背中から目が離せなかった。
「…トマト料理なんて、どうかしら」
包丁の音がストンと綺麗に途切れた。母の動きが止まった。重たくて、すべての音に濁点がついたような空気が私に襲いかかったが、平然を装った。
「お腹あんまりすいてない」
母がいつか振り向くのが怖かった。私は今、ちゃんと余裕な顔をしているのか。余裕な顔とは、こんな感じだっただろうか。ちょうどそんなことを考えている時、母が振り向く。
ライトに照らされててらてらと光る赤い口紅に鳥肌が立った。本当に自分の母親か疑うほど怖い。ご機嫌な母はまだ切ってない形のいいトマトを片手に、それをうっとりと眺めた。まるで、そのトマトに恋でもしてるかのように誘う目をしていた。
「トマト」
そう言って私に微笑み、正直気味が悪かった。
「そうね、トマトね、はいはい」
私はどんな顔をすればいいのか分からず、携帯に目をやり、聞き流してるふりをした。いつも通りって、こんな感じであってただろうか。沈黙が怖くてテレビをつけようと、リモコンに手を伸ばすと
「トマト」ともう一度母が言った。
見るつもりは無かったが、反射的にそちらを向いてしまい目がそらせなくなってしまった。母は私に甘えるような目をしてきた。見つめあって、両方そらしそうになかった。母は、ゆっくりと私のほうに近づいてきた。
鼓動が早いのが自分でもわかった。母の顔は、楽しそうでまるで子供だった。そういえば、父も少し子供っぽいところがあった。遊園地に行ったり海に行ったりすると、普段そんなことしないのに、私達と一緒になって気づいたら遊ん
「食べる?」
母の声でまた、はっとなった。私はまた都合が悪かった。
突然息を吸ってしまい、「ヒッ」と変な音が出た。咳き込んだ。母は私から目を離さない。
私はしばらくの沈黙のあと、何も迷わずに答えた。声が、震えてたかなんて、覚えてない。私は、冷静を装って「食べない」と言った。
母の顔から急に笑顔が消え、すぐに鬼のような顔になった。奇妙だった。私の腕に鳥肌がトゲトゲに逆立って、瞬きも忘れそうだった。私は余計に目が離せなくなり、今誰と話しているのかも忘れるように、また頭の中で必死に関係ないことを思い浮かべた。頭の中ではメリーゴーランドに乗った体が銀色の80歳くらいの全く知りもしない裸のおじいちゃんが頭を振り乱して踊り狂っている。指には全部にジャイアントコーン。
グチャ!!!
母は床に向かって手に持っていたトマトを思いっきり叩きつけた。汁が私にまで飛んできた。 目は私を見たままで、どんどん息が荒くなった。母の喉の奥から、ヒューヒューと音がした。歯を食いしばって、人間じゃないような顔つきだった。こんな母、知らなかった。何かが、取り憑いている。きっとそうだ。いや、母だ。いや…
「きいいぃぃいいぃ!!!!」
意味不明な奇声を上げて母は足をバタバタさせ始めた。突然また台所に走り、なにやらレジ袋からケチャップを出しで荒々しく開封し、「アレンジ」と連呼しながらトマトの山にぶっかけた。
冷静な顔をするも、足が震えて飛び跳ねてしまいそうだった。
必死に頭の中のメリーゴーランドを高速回転させていた。
もっと、もっと、もっと早く。もっと。もっと。
おい、おい早くしろ!!はやく!!!もっともっともっと!!!もっと・・・
そのうち、母はゆっくりと振り向き私に微笑み直した。昔の笑顔だった。いつもの笑顔だ。メリーゴーランドの夢は消え、窓の外の音や、自分の呼吸する音が何かの蓋を開けたように耳にどっと入り込んできた。時計さえ今まで止まっていて動き出したかのように感じた。ほっとしてしまった。母はまた、私に背中を向けトマトを切り始めた。ストンストン音がするたび安心したつもりだった。が、
「トマト。食べるでしょ?」
振り出しに戻った。私は絶対に食べるとは答えず、あとはその繰り返しだった。床で潰れるトマト達と終わりの見えない連鎖に対して何故か「食べると言ったらどうなるのだろう」までも頭が回らなかった。ピリピリとした。キリキリとした。なんて重たい空気。私らしくない。頭の中のおじいちゃんが、笑っている。大笑いしている。私を指差して、ああ、なんて屈辱でなんて恐ろしい。笑い出してしまいそうだった。
床がべちゃべちゃのぐちゃぐちゃになったところで、やっと私はまともな口が聞けるようになった。
「トマトは朝がいいって言ってたよ」
「…朝?」
「うん。」
母の表情がどんどん、泣きそうになっていく。私は微笑んだ。
「ダイエットの先生が、言ってた」
どこの先生だよ。
カンカンカンカーン!!!!と、ゴングが鳴りまして。
母がようやく寝て、私はカズキにメールを送った。
『淋しい』だとか、そんな内容だ。誰かとコミニュケーションをとりたい気分だった。要するに寝れなかった。
指先が震える。頭の中を整理する気にもなれないが、冷静なつもりでいた。誰でもいいのよ。好きなんていうのはただの、寂しがり屋の集まりで嘘っぱち。刺激しあい求め合い飽きたらおしまい後は情。
カズキからすぐに着信がきたが、とても出る気になれず。なんてコイツは間が悪いんだ、メールにしろよ。なんて八つ当たりの言葉しか思い浮かばなかった。生理が一日目。とってもデリケートなんです。
『悲しくて電話が出れない。明日、昼間ランチに行こう』そんなようなメールをもう一度カズキに送った瞬間、笑い転げてしまった。母が起きるから、声を押し殺した。悲しくて電話が出れないなんてシチュエーションこの世に存在するのだろうか。この世にというか、私の人生に。
すぐに『わかったよ。無理すんなよ?』と返信がきた。なんてバカなんだろう。こいつの脳みそ、リアルにただの味噌かも。メールを見た瞬間、何かのテンプレートかと思った。お父さんが死んだときのみんなとそっくりだ。私はシナリオがあるならば読まなくても、その台詞にそっていたと思う。
『ごめんね、ありがとう。』
かん~わいぃ。
指先の震えは、止まることを知らない。
お
真っ白い空間。真っ白な服。子供の頃にしていた前掛けは、もうしていなかった。目の前に小さなカエルのオモチャが山積みで、カラフルではなかった。白黒で、そのほとんどは白だった。私はそれを慣れた手つきで口の中に入れた。一つ一つ入れて、一つ一つ飲み込んでいった。何も味がしなかった。噛むこともなかった。カエルの形を舌で感じながら、舐めたらもう丸呑みした。喉をボコボコつたっていく感触がした。
味なんていらなかった。ティッシュにだって味はないでしょ?見ないでどんどん食べていたのに、突然私の口の中に、赤が入ったのがわかった。
硬直した。恐くなった。赤が口の中に入っただけなのに、何が起こるのかわからないと焦った。汗が脇から滲み出るのがわかった。私は小さな短い奇声をあげて、まっすぐ前を向き、広くて白い部屋に大量の赤い毒を吐き出し、動けなくなった。
目が覚めると私は、ベッドも無視して床で寝ていた。丸くなって横向きに、赤ちゃんみたいに、寝ていた。リビングから、りんごの唄が聞こえる。母が起きている。頭がガンガンして、首が痛い。今日は土曜日だ。
起き上がり部屋のドアを開けると、母が絵の具片手に今度はりんごを眺めていた。相変わらず、うっとりとした表情だった。一口かじると、赤の絵の具をりんごのかじった部分に塗っていた。りんごは、中身が黄色だからか。
「おはよ」と、私に気づいて笑った母は、懐かしい昔の笑顔だ。母親のようだ。風呂に入ったばかりのようで、リボンもしていなければ化粧もせずだがワンピースは着ていた。少しだけ泣きそうになったのを堪えて、私も「おはよう」と笑う。私は要するに、みんなより早めの生理がきたくらいから家族が一番好きだった。
そういえば来週は、私の誕生日だ。
私は化粧をして、髪の毛を巻いて精一杯オシャレをしていた。そんなとき、メールがきた。
『ランチ、どこ行くか決めた?』
え?探してないの?
『おはよう。私が探すの?』
『だってランチに行きたいって言ったのは空でしょ?w w 』
いらっ
未成年の私は、男の子とはそういうものだと思うようにした。本当はそちらが引っ張って行って欲しかったが、期待もしていない。いらいらいらいらと、音になって耳
元で、ああ、うるさい。
『じゃあ表参道の、パスタ屋さん!』と無邪気に言ってみた。
『駅から近い?』
調べろや。
『行ったことがないからわからない。調べよーよ』そっちに受け流そうと必死だったが、予想以上に彼は天然だった。
『よろしくw ありがと w 』
いらラララララララララ
世の中そうゆうもんよね。
耳鳴りがする。
駅まで行く道のりで、私は本物のガムを噛んでいた。なんだかつまらない人間に格下げになったような気分だった。
遠回りして、空気が綺麗な公園を通った。ぽかぽか良いお天気。深呼吸をした。クルクルに巻いたポニーテールを、わざと揺らして歩いた。可愛いでしょ?
歩きながら幾千もの屁をこいた。
ポカポカ陽気にご機嫌でオシャレをした女の子が、屁をこき歩いてるなんて誰も思わないだろう。そう考えるともっとご機嫌になった。私はティッシュを噛んでみたりだとか、誰も予想だにしないけど本当はあり得ることをいつでも実現したいんだっ。いつか突然誰かに口の中見せてやるんだ。貴方私がガム噛んでると思ったでしょ?って。
お父さんに昔、「女の子はオナラをしない生き物」と教えられた。それからはオナラをするたび思いっきり引っ叩かれた。何も悪いと思わなかった。私はオナラをしない生き物の中の珍しくオナラをするやつ。絶滅危惧種的なイメージだった。遠くで小さい音でこいても走ってくるの、お父さんは。そして手加減なしに頭を思いっきり、、
そんなことを考えていると向こうからヒールを履いた女の人が早歩きで歩いてきた。顔のバランスが、ものすごかった。顔が異常にでかい。トリッ○アート美術館。笑いたくて仕方が無い。何をしてもこの人の見た目のインパクトにはきっと敵わないと考えた。すれ違う瞬間、彼女の鼻のしたの薄くて長い毛に気づいた。汗で少し潤っていて、前髪はデコの広さが目立つセンター分け。ケツのでかさが目立つタイトスカート。すれ違って後ろ姿を見送ると、ヒールの部分がすごく短く見えた。錯覚でしょうか。全てに置いて間違えの方を選択している。この人を私は一生の先輩としよう。
そんなことを考えてるうちに、デートは終わった。
帰りの電車は、早く家に着けと思いながら寝ていた。耳元で喧嘩するのは「がたん」と「ごとん」では無かった。
「ストン」
それをかき消すようにイヤホンで狂気のヘビメタルと天使のクラシックをyoutubeで交互に聞いている。頭の中で朝出会った「妖怪顔でかヒール先輩」が、ひたすら私に「大丈夫」と言った。つまりは、吐きそうだ。
足元には、つぶれたカエル。電車よ止まれ。
「ただいま」
母の声がしません。寝てるのかな。靴を脱ぎ、カバンを乱暴にぶん投げた。一日のほとんどなのに、私は今日カズキと何をしたか何を話したかっていうのが全く頭から消えていた。最近自分が起きている時間帯、何をしてたか忘れてしまう。すぐに。そんなことをぼんやり考えながら、居間に行くと、母が鉄腕アトムだった。鉄腕アトムの格好をしてオヤスミになられていた。布団をめくる。鉄腕アトムだった。もう一度めくる。空を超えた。
まつ毛の長さまで完璧。うちの母親たまに鉄腕アトムなんです。と錯覚するほど思考停止。きらきらしちゃう。きらきらしちゃう。
私は静かに携帯で写真を撮る。そのうち、動けなくなった。なんて面白くないのだろう。こんなにも摩訶不思議なこと、他にないのに。絶好のシチュエーションなのに。なんて笑えない。なんでだろう。全身にワイヤーが入った人形みたいに、体が強張って
笑え!笑え!
私は色んな方向、角度から連写。つまり連写連射連写だ。
もっと
もっと、もっと、もっと、
もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっともっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと
ぱしゃ ぱしゃ ぱしゃ ぱしゃ
笑えない。笑え。笑え。下半身が震えて動かなくなって、股のところに力が入らない。それからは足が震え、ひやっと太ももを冷たい液体が通り過ぎた。「あ…」と声が出た。
おもらし。
一瞬信じられず固まっていたが、これを機に台所のトマトをばれないように綺麗にしようと冷静に考え、おもらしぱんつを脱いだ。そうだ、私は冷静を装うのが得意だった。ああ、誰か買ってくれますかね。私のおもらしぱんつ。おもらしすることなんて人生で無かったもんだからさ。
私はパンツも穿かず偉く冷静に皿を洗っていた。床を拭いていた。叩きつけられたトマト達を回収していた。何を考えてたかなんて、覚えてません。むしろ、何も考えてないのは都合が悪いからだ。
食べるものが無いので、一人でラーメンを食べに行こうと思った。商店街を、スウェットで歩いた。マスクもした。なんならポケットに果物ナイフも入れた。特に意味なんてなかった。危ないやつだと思われたかった。なんか、ヤンキーの気の小さな奴みたいになりたい気分で、それだけ。近くにあった。それだけ。
ラーメンが美味しいことで、今日の自分のいいことになる。きっと。見た目で、美味しそうな店を決めて入ってその店おすすめの「炙り味噌」を注文した。携帯を開くと、メッセージ。カズキだ。
『なにしてる?』
うるせえなぁ。
何も無かったように私はメッセージを開封して、ゲームを開いた。集中してるうちに、ラーメンがきた。今日という日がいい日に変わる瞬間だ。私は店員さんに可愛く笑顔を振りまいて「いただきます」といった。店員さんは、まあまあイケメンだった。
何か気に食わないことがあるとすれば、ただの味噌だった。炙り要素ゼロ。あと、旨味ってゆうものがまるで無かったというか。美味しくないからクレームつけたいところだけど、まずくもない。
えぇっ!?
今日という日が、いい日に終わらない。私は接客に期待をして、店員さんに笑いかけた。
「あの、」
イケメンの店員。
「はい」
「美味しいです」
嘘です。
「…はい」
ありがとうだろう?
私はお金を卓上に置き、「レシートいいです」と言った。すると「あの」と店員が呼び止め、舌打ちをしそうになる。
「足りません」
早く今日という日をリベンジさせてあげたかった。これを史上最悪と呼ぶ。私は早歩きでその場を去った。イケメンの店員は「ありがとうございます」の声だけ無駄に大きかった。私は急いでいた。別に用はない。ついてない今日から逃げたかった。
そして、発見したのだ。向こうから歩いてくる
「妖怪、顔でかヒール」
そう呟くと、人に肩がぶつかった。
「すいません」
厄介そうなおばさんだって覚えてる。おばさんは私の顔を見た途端あからさまに不機嫌な顔をした。それも覚えてる。私は頭を下げた。それも覚えてる。後は、私の顔を見てから、視線をさげたおばさんの目が飛び出るんじゃないかってくらい全開で開いたの。それも覚えて
「キャーーーーーーッッ!!」
奇声。おばさんの視線を追うと、
果物ナイフ。
「違うんです」
とっさに叫ぶ。紛れも無く私のポケットから落ちた果物ナイフだ。身に覚えしかない。でも、でも、
「ごめんなさい!ごめんなさい!誰かァァー!!」
違う違う違うのよ。危ないヤツだとは思われたかったけどこのままじゃ、母が。
とっさに思ったのはそれだった。母が病院にぶち込まれてしまう。治るものも治らなくなってしまう。治す?
え?何を?
「誤解。誤解です」
私は冷静を装うのが得意だった。果物ナイフを拾って再びポケットにしまい、両手を上げて出来るだけ淡々と喋った。
なんてついてない。
お父さん、お父さん。私が見えてるなら、おばけっぽいアイテム使って今日という日をいい日にしてくれないか。もう、夜だけど。
それなら、明日が今日の損した分いい日のほうが嬉しいかしら。兎に角ピンチなんです。
私は言い訳を考えたが、そのうち何故かお父さんの名言集しか思い浮かばなくなり思考停止。完全に真っ白になった。
パトカーの音がして、周りで写メを撮る人や、私に怯える人がでてきた。今日の自分を客観視してみる。危ないヤツだ。ばばあてめーがうっせえからだ。
私は意味のない行動をよくして楽しんだ。それを、説明できる自信が全くなかった。証明する人も居ない。
「なんとなく危ないやつだとか思われたかっただけなんだけど」
そう呟くと、周りは私を余計怯えるような目で見た。
「おりゃああああー!!」
英雄ぶったじじいが、私に突進してきた。私は地面に強く頭を打ち「いてえな畜生」ととっさにキレてしまった。終わりだと思った。だって痛いのよ痛いじゃない。こんなばかな英雄じじいよりばかだと思われるのね。なんて死にたいのよ。それより痛いのよ、頭が。もう、どうだっていいさ。はい、終了。
そんなところで、目が覚めた。
私は気がつくと、ラーメン屋で突っ伏して寝ていた。
心の中で、終了と叫んだと同時に気絶したらしい。「大丈夫ですか?」と能無しなイケメンが私に囁く。しばらくの沈黙。頭よ、回れ。私は、黙ってお金を卓上に置き、その場を去ろうとする。
「あの」
「知ってます」
私は足りない分を財布から出して、なんとなく走って帰った。
走りながら考えていたのは、私は今日、おもらしをしたのかという事。あんな感覚初めてだった。
『ご飯食べてた』カズキに適当に返信をして、家についた。
ドアが全開だ。
「ただいま」
家の中に、母の姿は無かった。私は
【 トマトを綺麗に片付けてしまった 】
ふと、どろどろした赤い部屋を幸せな家族の住む部屋に戻してしまった自分を思い出して息がつまりそうになり、外に走り出した。まだ床は、綺麗なままだった。
握りしめた携帯にはカズキからのメールと、知らない番号からの着信音が表示されていた。
うちのアトムはどこ?
ああ
ああ
嗚呼
歌声が聞こえる。私は、違うことを考えようとしている。
ああ
ああ~~~
ああ
目が回る。汗をかく。吐きそうだ。
またもや着信音が鳴った。また、知らない番号からだ。私は一瞬立ち止まり、息を軽く整えてから電話に出た。
嫌な予感がする。手にびっしょりとかいた原因不明の汗を拭いて、
「もしもし」
相手は、スーパーマーケットでした。
か
「「「 おかあさんは
スーパーマーケットのトマトを りょうていっぱいに
いえにもちかえろうと おもったみたい 」」」
家の近くのすざきマーケットというスーパーに着くと店の人に案内され、裏の小さくて埃まみれの部屋に連れてかれた。
すざきマーケットは、地方の田舎にあるような少しぼろぼろのスーパーで、何より東京にしては野菜が新鮮で安く買えるとこの辺じゃ有名だった。
裏の小さな部屋は、ドアが閉まっていて、ドアを開けるとうちのアトムがアトムバージョンそこにいたので私は寒気が止まらなかった。トラウマでおもらしをしそうだ。母と店長みたいなおじさんの間にあるテーブルにはトマトとりんごが大量に積んである。とっさに目をそらす。ハエが飛んでいる。壁際に積まれた段ボールや、書類の山。ゴミ箱からはみ出たお弁当のゴミには、米粒がいくつも目に見えた。吐きそうだ。目が回る。
母はというと、機嫌がものすごく悪そうだ。
「ごめんなさい」
私は、遠慮がちに店長に頭を下げる。
「娘さん?」
「はい」
「…可哀想だと思わないのかね」
店長さんが、母に視線を移して問いかける。その、ため息交じりの台詞に私は更に深く下げた頭をあげられずにいた。
別に私は可哀想なんて自分でも思わなければ、他人が可哀想だとかなんだとか思おうと、さほど何にも影響しなかった。
「財布でも出せば」
私がやっと頭を上げて母にそう言うと、母は怒りの目で私を見た。唇の震えと目の充血によって、母が化け物に見える。
「だってね、家がね、せっかく楽しい毎日だったのに。すっごく綺麗な赤色で、素敵だったのに」
「それとこれとは、別よ」
頭の中の真っ白な空間でわたしはひたすら、狂ったようにゴボウを折っていた。大量のゴボウ。白い服が泥だらけ。ゴボウなんてそんなに好きでもないのに、真っ白な空間には、必死でゴボウを次々折って、ひきちぎって、時には歯で噛んで、砂だらけの口で、
「娘さぁん」
店長さんが、私を影に呼んだ。
「あのねえ」
優しい口調で、白髪混じりの剥げたおじさんが言う。この人は息が臭くて、私はこっそり息を止めた。
「お母さんじゃ、話にならないしきみもきっと言わないのだろう。でも、大変かもしれないけど、おせっかいだが、」
頭をぽりぽりかく店長さん。
「お母さん、病院につれてきなよ」
「なんででしょう」
「お父さんは、居るの?」
「なんですか?」
「ここに娘さんが来るってことは、母子家庭?しかも長女?病院の電話の仕方がわからないなら、代わりにしてあげる。あれじゃあ、あまりにもだもの。ほら、目の黒い部分が開いてるでしょ。昔、強盗が入った時の強盗犯と同じ目だわ。しかも、なに?あの格好。気持ちの悪い」
気がついていた。瞳孔がたまに全開なことくらい。さあ、どう言い訳しようか。私が考えてるのはそんなことだった。腹が立つ訳でもなく、仕方ない。これは、仕方ないこと。だって
うちのかあちゃん気持ち悪いの?
じりじりじりじり
じりじりじりじり
台詞を、台詞を考えた。
「母の何が悪いっていうのよ!」
「母はいたって普通です」
これは私ごと病院にぶち込まれる可能性がある。
「人の母をよくそんな風に言えますね。」
喧嘩になって警察を呼ばれたらたまったものじゃない。
冷静に頭をフル回転させた。店長らしきやつが、私の顔を見つめる。あまりにも口が臭いため、だいたい息を止めた。顔をこっちにむけるなと怒鳴ってやりたかった。店長の目の中の兎が、こっちを
「母は今、治療中なんですよ。」
慎重に言った。
「今日は本当にすみませんでした。」
しばらく笑顔で誤魔化したが、店長はせっかくの心配を無視したのをとても怒ってる様で顔がまっかっかになりそうだった。空気が重い。じりじり。じりじり聞こえる。何の音?何の。沈黙の時間を、破壊した。
心配してなんて頼んだかよ。へんなおとな。
私は土下座をした。屈辱だとは思わなかった。私がお金を払った。
家に着くと、23:45だった。まだ、15分ある。
鼻歌を歌いながら母が冷蔵庫を真っ赤にして行く。「今日はカレーね」と言ってはいるが、その材料でどうやって作るのよ。
なぜか分からないが今日という日に意味もなくこだわってた私は目をつぶって妄想でサーカスでも見ることにした。ピエロたちが全裸でゾウの上に逆立ちしてる。なんだこりゃ。
こんなサーカス見たことない。
さっきゴボウで口が真っ黒になってしまった私が無邪気に拍手をする。
「空」
母の声で目を開けた。ストン、ストン、と音がする。
「トマト、食べる?」
母が振り向いた。目が真っ黒だ。
カズキの名前を呼んだ。誰か抱いてください。どなたか私とセックスしたい方はいませんか。頭の中は著名活動中。選挙カーにでも飛び乗っちゃう。てーかもはや飛び乗ってる。面舵いっぱい!
しばらく何故か朦朧としていると、目の前に真っ赤なカレーが置かれた。これはどうゆうレシピで作ったのでしょうか。
見上げると、真っ黒な目をした母が、「お食べ」と言った。もう一度おもらしをしてしまいそうだ。
食べなきゃだめでしょうか。これ。
つまりは寂しかった。もう23:59だ。
その日から私は、「俺昔とんがってたからさー」と、ダサい台詞を吐くおっさんのセリフにそったようなとんがり方をしていた。
私はそんな過去にとらわれたダサい言い方はしない。
私は今、とんがっています。
バイトを始めた。薄暗いところでお酒を飲んで、おじさんの隣でドレスを着て笑っていた。グラスのフチにふやけたスナック菓子がついてるのを見たとき、吐き気がして目が回った。自分の笑い声にめまいがして、もう聞きたくないと思うようになった。
この世には、勘違い男がとても多かった。
客を待機する小さな部屋はいつもタバコくさくて、女の子はといえば、全員大嫌いだった。
きがつくとクラブのど真ん中で一人で突っ立っていた。店の女の子達の媚びた目が頭を高速で行き来した。私は人に媚びるということが元はと言えば嫌いで、そんなやつを見るのはもっと嫌いで、人を騙すような嘘をついたことも生まれてこの方少ない方だった。だから、長くここにいるやつらや、こんなところで上に上がってるようなやつはくだらないと自分のことを棚にあげて思っていた。棚にあげて。自分が一番、しょうもなくない。
世の中金。
「私ここ長いから、なんでも言いなね。私、みんなの相談役なの。でもね、私みたいなスタンスは、お手本にしない方がいいよ。」
小さくて臭い部屋で嘘くさい女がそう自信満々に私に微笑みかけた。私はなぜか、みんなに慕われてるこの人に一番違和感を感じた。
くさいっ
「ただいま」
ストンストンと音がしない。母は何をしてるのでしょう。部屋に入ると母は、鏡を見て何かご機嫌だった。
「おかえり」
母は私に気がつくと、立ち上がり近づいてきた。後ずさりはしなかった。そして母の頭の上についた大きなリボンの全く同じ物を私に渡してきた。
「見つけたの」
「そりゃよかった」
「つけてみて」
「後でね」
「つけてみなさいよ」
母は私の頭にそのリボンをつけて鏡に誘導した。鏡には、キチガイが二人写っていた。
「かわいい。やっぱり、似合う」
母は嬉しそうだ。
母が女王様で、私がお姫様みたい。そう一瞬でも思ってしまった。なんて気品があるのだろうと。なぜそう思ってしまったのだろう。
それはきっと私が少しだけこのリボンが似合ってしまったからだ。そうに違いない。私はまともなのだからと、ぼんやり自分に言い聞かせながらぼーっとしていた。
私は母の方も見ずに、鏡の中の自分の目の中の兎を見つめていた。
「私はね、」母が私の肩に手をやり、顔の横に顔をつけた。
「毎日、このリボンをつけてようと思ってるのよ。内緒だよ。ばれてると思うけどね、ふふっ!」
昨日会った鉄腕アトムはどこの「私」なんだろうか。
「そうなんだ」
「空も、そうする?可愛いし。」
「いや、私は別にいいや」
「エッ!!!!!」
急に母の声が急に壊れた。
「するする、つける」
私は鏡から目を離さなかった。鏡の中の私の目ん玉も黒くなる夢をみて、その夢を自分で見逃した。
き
それから家ではリボンをつけた。
外ではさすがに付けられない。だが私はこれを機に、家に帰りたくない病が治りつつあった。リボンをつけているいつもと違う自分にまんざらでもない気持ちでいた。
学校ではよくお母さんのことを聞かれた。「すごく元気で部屋中飛び回ってますよ。嘘ですけど。」と常に明るい声で答えるばかりだった。
たまに
理由も無しに人をぶん殴りたいという気持ちの波が押し寄せて来る。
だいたいのとんがってるやつは弱そうなやつをいじめる傾向にあるが、私は衝動に身を任せて生きていたので目の前にいる誰彼かまわず引っ叩いていた。どんな状況でもそんな気持ちの波が私を煽ると衝動に身を任せてしまう。スリッパでも持ち歩いてしまおうかと思った。エスカレーターの前に立ってるお姉さん。すれ違う自転車に乗った子供。前の席のブスのクズ。たまに激怒されると、喧嘩になるのはめんどくさいのですぐに土下座していた。土下座の体制になるまで1秒もかからなかった。
土下座するたび、すざきマーケットに居たアトムが脳みそを高速で通過した。
耳元で鳴る「がたんごとん」に「ストン」が混じって、いつでも高速で耳鳴りのようだった。白い空間にあるカエルの山積みのおもちゃが全部赤だが、何も怖くなかった。
私は、怖いのと疲れるのと辛いのと痛いのと出来ないということが嫌いだった。
つまりは普通の人間のお話です。なんて素直でしょう。
カズキという彼氏が存在するにも関わらず、クラブのど真ん中で一人で突っ立っている時に話しかけてきた清潔感があるやつとはキスをした。
もちろん、そんな気分じゃない時はしなかった。
夜、仕事中は常に引っ叩きたい気分だったので我慢した。
だって私はお金が欲しかった。人間だもの。
なんて素直でしょう。
兎にも角にもね、衝動!!衝動!!
「あのさ」
女の子が待機する狭くて狭くて狭い部屋で、あの嘘くさい女が話しかけてきた。
「はい」
「最近、仕事中ぼーっとしてる?」
ヤンキー口調がとてもわざとらしくて喉がイガイガした。
「お前のためを思って言ってるんだよ。こんな言い方しかできねーけどさぁ。」
「周りの空気を読んで生活するなんてこと生きててあんまなかったでしょう。わかるよ?難しいよな。はぁ」
ため息をついた後、こっちを見た。
「あたしと一緒だよ。」
一緒かーい。
「私でいいなら頼ってよ。私なんて間違って長く続いちゃったようなものなのに、今となっては、お客様が入ってきた瞬間声のトーンが勝手に変わっちゃう。自分でもびっくりだわ。わざとじゃないんだけどプロになっちゃったんだなーって。ここだけの話、昔とんがってたからさ。いろんな経験してんのよ」
違和感というのはきっと「自称」から生まれる。「私はこうだ」と自分で説明をされるとよくわからない違和感が生まれる。昔からそうだ。私は自分のことが一番わからない。これから一生わかるはずもない。普通、そうではないのか?「自称」と「願望」は口に出すことによって紙一重になり、麻痺するものなんだろう。それは理想のモノマネだ。私はそんな薄っぺらい仮面を被るのはごめんだし、そういう人は理解できなかった。
「ルミさんは本当苦労してきてしっかりしてるよ、生き方を尊敬するの」
もう一人の女が、マスカラをしながらそう優しい声で言った。ルミさんとは、この嘘くさい女の名前だと思う。名前も初めて知った。
「かっこいいのよ、ルミさんは。ずっと。いう事も全部」
「やめろって。苦労なんかしてないよ」
茶番とはまさにこのことでした。将来子供に「茶番ってどうゆう意味?」と聞かれたら私は今の会話を黒板に書いて「はい!!これです!!今日の授業終わり!!」
「そう思わない?」
女が、私の方を見る。眉間にシワがよった。
「…特に」
しばらく言い訳を考えたが、めんどくさくなった。嘘はつけない。気味が悪い、嫌いだ。少しだけ、鼻で笑ってしまったのが癇に障ったらしく。しばらく時が止まったあと、「ばかにしてんだろ」と始まった。
あーめんどくさい。もう土下座をするのもめんどくさかった。1秒で出来るのにちくしょう。
世の中は、面白いものでなんか溢れちゃいなかった。
「してないです」
「てかてめールミさんなめてんだろ」
「なめてないです」
そいつは、まるで不良高校ドラマでも見たかのように壁を殴った。飽き飽きとした。
「なめてんだろ。もっとあげろよ、先輩だろ。」
「あげる?どこに?」
「は?ルミさんだぞ?」
彼女がルミさんを指差した。
「へんなの。きちがい」
「おまえ、それはちげーだろ」
すごくかっこつけたキレ方だった。私はけなしてもいいけど後輩をけなされるのは~の後に続く台詞を考えるのも飽き飽きとする。とにかく、吐きそうにぐるぐるとした。
なんてめんどくさい。今までの嫌なことが写真になって頭の中を走る新幹線の窓に次々と張り付いてる。なんだこりゃ。ルミさんという女は、私の胸ぐらを掴んだ。掴み返すことは、疲れたからしなかった。
ポケットに果物ナイフあれば警察に捕まることだって出来るのに。てえかぶっ刺すまでもねえよお前なんか。
ふと一瞬目をつぶると、サーカスのステージだ。
全裸の太ったお姉さんがキリンの首にしがみついて離れない。口が真っ黒な私がはしゃいでいる。小さい頃だ。赤いカエルをキリンにむかってたくさん投げた。
目を開けた。
足元には、つぶれたカエル。かわいいやつ。
「何が違うの」
「ああ?」
弱いくせに、くだらない。私はルミさんの顔にブーッと、子供の頃したようにツバをかけた。ルミさんは顔を真っ赤にして何言ってるかわからないくらい大声で私に怒鳴った。
見た目がヤクザみたいな店長が止めにきて、何故か私だけ外に引っ張り出された。ルミさんは私を見て嬉しそうにしていた。
外に出ると、雨が降っていた。ドレスがすごく寒かった。謝れ。どいつもこいつも。被害者は私だ。こんなに必死で嫌な事を我慢してきたのにどいつもこいつもわかってくれやしなければ邪魔ばっかりしやがって。
頬を一発殴られた後、何言ってるか分からないくらいデカイ声でデコをピッタリくっつけて怒鳴られた。何が起きたのかも何を言われてるのかも全然わからなかった。何故だか、すごく納得がいかなくてすごくムカついた。全員叩きのめしてやりたかった。てめえら、ザコのくせに。私はとんがっているんだ。
頬がじんじん痛かったので、何喋ってるかわからないうちに顔面を殴り返した。私が強いという根拠はどこにもないが完全にキレてしまいそうだった。いつもなら面倒臭い事は避けるが、うんざりというモードだった。とんがっていた。とんがっている若者というのはつまり、何も怖いものなんてないと思い込んでるのが強みで最強で無敵だ。イライラして止まらなかった。生理なのもあります。アイアム生理が二日目です。生理中のとんがってる若者は、最強にとんがっているんだ。
もう一発殴ると、殴り合いになった。私はちっとも折れず、手加減も無しに殴った。しばらくすると思いのほか頬を押さえて何もしゃべらず、店長は静かになった。歯がどうにかなったらしい。このテカテカの髪の毛を後ろに追いやったオールバックのやくざが見た目倒しなこともなんとなくみんな察していた。
なぜ人は人を怖がらせるための言葉や格好をするのかね。
店長を外に放置して小部屋に戻り着替え終えた後、席につく女とルミさんを引っ張り出してドレスをまくって頭にかぶせた。パンツも何もかも丸見え。ドレスの中から泣き声や悲鳴が聞こえた。傷を負わせるなどどうでもいい。傷がいい場所についてしまって逆にカッコつけられても困るので、辱めてやりたかった。
外にいたやくざ店長が走ってきて、涙目でまた私を引きずり回した。テーブルの赤ワインボトルで股間を思いっきり殴った。苦しむ店長の白いズボンに、赤ワインを注いだ。店長の股間は真っ赤に染まり店長にも生理が来ました。
周りから見た私はきっと、キチガイ最上級。
ルミさん指名のお客様たちが怒鳴りまくっていた。なんにも聞こえません。こんな場所に来るってことは許すが、こんな女に引っかかるてめーらは、ザコなんです。お客様達が、私の頭を思いっきり引っ叩いた。髪の毛も引っ張った。一人、精一杯怖そうなお客様に髪の毛を鷲掴みされておでこをピッタリとくっつけられ、ニヤリと笑われる。人生恐怖映像ベスト10には完全に入るほど鳥肌が立ったが、むかつくので私も負けじと微笑んだ。頭の中はおむつパーティー。足がガクガクした。
「…」
逃走。必死で取り押さえられて色々引きちぎれてほぼおっぱいが見えそうです。
早朝だが外は雨で、誰も追いかけて来ないのが逆に恐ろしかった。
家の前で周りに誰も居ないか何度も何度も確認した。べちゃ濡れでやっと家にはいると、すっごく寒く感じた。テレビで首から上がパンでできた奴が「顔が濡れて〜」みたいなことをぬかしてた。液晶にむかってボックスティッシュを思いっきり投げた。
ふざけんじゃねーよ。お前はびしょびしょのビリビリでおっぱい見えそうな格好で走ったことあんのか。そのくらいの経験してからヒーロー名乗れ。愛でも勇気でもどっちでもいいから私に君の友達を紹介してください。
母は寝ていた。
なぜか今日もアトムだった。
部屋の扉を閉める。少しだけ安心した私はバイト先の連絡先を全消ししてから、とにかく疲れたので昼間まで寝ている気だった。もう、十分稼いだでしょ。お疲れ様、自分。自分自身が最大の味方よ。バイトハチャメチャばっくれ記念日おめでとう自分。腰も頭も顔も痛い。鏡に写る私の口から血が出てる。鞄に入っていたお茶でうがいをして、母のところに戻るのもなんだか起きたら面倒なので窓から水を吐いた。もうどうでもいい、なるようになるだろうと思ってた…時にカズキから電話がきた。早朝だぞコラ。
舌打ちとともに、機嫌悪いのを隠し出る。
『おはよ。今日ひま?』
「おはよう、土曜日じゃんか」
『ランチに行こう、この前のとこ』
「具合が悪くて。昼過ぎから会うのじゃだめかな」
寝たい。
『大丈夫?お見舞いいくよ』
なんて面倒くさい。
「大丈夫、ありがと」
『ほんとに大丈夫?なんか食べたいものでも買っていくよ』
「食欲ないの。ありがとう、今日はお母さんもいるから。一回寝る。ごめんね」
夜働いてたことは、カズキに言ってなかった。あーもう、会いたくないのよ。ムラムラしてる訳でもないわ。
『わかった、本当に大丈夫?むりするなよ。強がってない?』
うっせーな。大丈夫じゃないとしたらあんたのせいでイライラしてることぐらいです。と性格の悪さが全開だったが、それも現在とんがってることにより許されてる気になっていた。
「うん、おやすみ」
電話を切った。ため息をつく。やっぱり寝る前に風呂に入ろう。そう一息してそーっと部屋の扉を開くと、すぐ目の前に母が立っていて驚いた。硬直したまま二人、朝から見つめあった。
「おはよ」
「キャーーー!!」
悲鳴をあげられる。黄色い声だ。
「あんた、あん・・・あんたぁっ!!」
母が奇声をあげた。そこからは母は頭を抱え、黄色い音を出しまくっていた。暴れていた。アトムのカツラを自分の頭からむしり取ってぶん投げていた。網むき出しの頭で暴れていた。それ、放送していいんですか?私は急いでリボンを探した。もし見つけて装着したらこの目覚まし時計が止まると思った。
「なんでーぇえ?せっかくあげたのにぃいー!!!!」
そうゆうあんたも今日はアトム。
「ちょっとまちなよ」
言葉は落ち着いてるが、手は焦っていた。落ち着け。落ち着け。
「ひゃああああー!!」
黄色い声。見つけた!私の視界にりぼんが、見えた瞬間、拾い上げてすぐさま装着し母の方に振り返った。
母が真顔になり、黄色い声の目覚まし時計が止まる。
私は息を飲んだ。
しばらくの沈黙のあと、母が微笑んだ。
「似合う」
母は振り返って、私の部屋のドアを閉めどうやら着替えてるようだった。その日は風呂に入り、目を瞑ると母の目覚まし声の夢にうなされた。黄色い声が止まらず地獄だった。耳がキンキンと壊れそうだ。ああ、私が何をしたって、言うの。
私がさ、何をしたの。
「体調大丈夫か?」
カズキが頭を撫でてきた。癇に障ったが、私は微笑んだ。お父さん以外の男に体調を心配されるのはとても腹が立った。心配したところで医者でもあるまいし何もできない癖にふざけんじゃねえよ。
※父も医者じゃありません。
「どこいくの?」
「空が寝てるからーいつものカフェはやめようと思ってー。」
「ごめんなさいね」
「ステーキ屋さん。予約したんだけどどう?なんか食べたいもんある?」
ステーキかよ。重。予約したのに聞くんじゃないわよ。
「私、パスタがよかったな」
「こら。わがまま言わない」
カズキが私の頭を叩く。私は「えへ」と、照れて微笑む。
頭の中で何度もこいつをマシンガンで乱射した。
く
結局のところ夢にうなされ今日は一睡も出来ていない気持ちでいた。
昨日雨にあんだけ打たれたので、本当に体調が良くなかった。つまり、ステーキなんてもの本当は助けて欲しかった。そもそも、体調が悪いのを伝えたのになんでステーキという選択肢になったのよこのバカは。まあまあの値段でおまけに割り勘。味は、覚えていない。
不愉快で不愉快で、本気で別れを考えてぼーっとしていた。帰り道、私があまり喋らずにいると、カズキは
「おいしかったーあそこのステーキ屋いってみたかったんだよ!俺」
私の心には「あっそ」の泉が広がった。
「体調は?」
「だいぶ良くなった」
悪化傾向にあります。
するとカズキは嬉しそうにカバンから何か取り出す。
「はい」
「え」
「誕生日おめでとう」
ピンクの包み紙に、大きなリボン。そうか、今日は私の誕生日か。そう思った瞬間、感動と共に先ほど割り勘だった件とディナーがステーキだった件に無性に苛立ちを覚えた。
とは言え、私は喜んで包み紙を開けた。中身は無駄に高そうなくまのぬいぐるみだった。地面に叩きつける夢を見たが、私は「ありがとう」と微笑んだ。
小学校の時、私が「好きで好きでたまらない」と言って毎日モノマネしてたキャラクターのグッツを、飽きた頃にお父さんが「ちょっと目瞑ってて、まだだよ、まだ、いいよ」とか言って無邪気に全種類買い揃えてきたのを思い出した。
グッツを全種類。つまりぬいぐるみから絆創膏からハウスキットみたいな大きなやつまで。私の学習机に綺麗に並べて「そら、これで毎日どれで遊んでもいいんだよ。楽しいね」って。もう飽きたっつーのなんて全く思わなかった。嬉しくて嬉しくて、お父さん大好き!って思った。
それが私の人生で至上最強に極上の誕生日よ。
第一、誕生日にお金払うなんて初めてだこのフニャチン小僧。
お父さんの優しさを思い返し泣きそうになったのをぐっと堪え、帰りに自分にケーキを買うと決意した。
誕生日に「こんなものしかお金なくて買えないけど」と言って「気持ちだけで十分だよ」と言う人が居てその会話の意味もすごくわかるし素晴らしいと思うが、今回に関しては気持ちだけで十分とか言っちゃいられなかった。
欲しいもん買ってくれ。
とんがってる時期ってーのは常に「なめんなよ」って思ってるものよね。
何を期待してか私は、あのラーメン屋さんに行った。お腹もすいちゃいないし体調も悪いのに何をしていらっしゃるのかよくわからない。ぼーっとしていた。「いらっしゃい」と言われたので割と大きめの声で「こんにちは」と言ってみたが、笑顔も無くスルーでした。はい。ありがとうございます。
帰りに、ケーキを一瞬買った。食べたくもないのに。明日の朝食べようかな。いや、冷蔵庫はトマト地獄だった。完全に胃がもたれている。即座にケーキを返品。何をやっているのでしょう。
お父さんの極上の誕生日によって私は小さい頃から自分の誕生日を粗末にされるのが一番嫌いだった。それで泣いたことだってある。
「ただいま」
「ヒャーーーーー!!!!!」
帰った瞬間大号泣されてしまった。この大きな赤ちゃんに。クソババア赤ちゃん。ネーミングセンス30点。ステーキにラーメンに胃の中がすごいのよ、自殺なんですけど。
「なんで。なんで。なんで。」
「なんで。なんで。なんで。なんで。なんで。なんで。なんで。なんで。なんで。なんで。なんで。なんで。なんで。なんで。なんで。なんで。なんで。なんで。なんで。なんで。」私の目をじっとり見つめる母の声。途中から一緒に私も「なんで」と口ずさんでいた。
のっとられたみたい。だね。
頭に何者かに穴を開けられて、空気が抜けた気分だ。リボンをした。わかったってば。お母さんは泣き止んで、何か楽しそうにはしゃいでいた。たまに母が床に叩きつけるトマトが、片付けてないから最近部屋が臭い。もう常識がどこにあるのかわかんなくなって、目が回った。くさいのだって少し前から気づいていた。それが、普通の人間の私。
トマトが床に散らかって腐りかけた室内で大きなリボンをつけた二匹のキチガイが暮らしている。ハエが飛んでいる。あのすざきマーケットの汚い小部屋よりうちの方がずっと汚い。そんなの、気がつかない。普通の人間同士しか。
目なんてそらしてない。見えている。視力も自慢。聴覚だって嗅覚だってそうだ。
「そらちゃん」
ニコニコした母が、何か持ってきた。
「お誕生日おめでとう」
誕生日ケーキだ。真っ赤で、トマトとケチャップで出来ていた。イチゴの部分は、カリカリ梅だった。ケーキかどうかもロウソクが刺さっていないと認識出来なかった。お皿に乗った赤いカタマリが私の目の前にスライディングしてきた瞬間、頭の中で半裸の妖怪顔でかヒールが行進してた。先頭が鍵盤ハーモニカを吹いている。最後尾は旗をふり、旗には「極上バースデー」の文字。その映像を頭の中で何度も、
早送り 巻き戻し 早送り 巻き戻し
キリキリなるビデオテープが、真っ白な部屋で爆発して、また私は真っ白な空間であのまずい赤い毒を吐き出した。やだ。、やだやだ。
足元にはつぶれたカエル。まだ可愛いやつ。
つまりはもうよくわかんなくなっていて、それから外でもリボンをつけた。
私はキチガイの母によってそれが普通になった。私の中ではそれが普通の人間だ。文句があるやつはかかってこい。
洗脳されているという噂が立った。つけ睫毛の金髪爆発頭の化け物が私を恐怖の目で見つめた。お前みたいなクズは、みんなと違うやつをいじめなきゃだめでしょうが。いじめなさいよ。かかってきなさいよ。笑いなさいよ。何怯えてんだよ。クズにさえ、なれないの?
洗脳?
現にされていたのかもしれない。母がおかしい事はよーくわかっているはずなのに。はずだったのに。はずなのに。母の機嫌が良かった。
カズキをカフェに呼び出した。
「最近どうしたのそのリボン」少し笑われたくらいで、カズキはこのリボンをファッションだとでも思っていそうないきおいだった。「そういう気分なのよ」と言った。私も私ですね。偏見がないところは、好きなところだった。バカなところは、嫌い。
「あのね」
「失礼します」
ブラックコーヒーが私の目の前に置かれ、女子力満点ホイップの乗った甘いキャラメルラテはカズキの目の前に置かれた。いらっ。うん。そういうことだ。そう思った。深刻な気持ちが少しだけ楽になった。
「別れたいのよね」
「えぇ?!」
ニコニコ笑顔から一変、カズキがキャラメルラテを私に向かってこぼした。「あぁ、ごめん!」と慌てて挙手して「すいません」とお洒落なカフェでバカみたいに大きな声で店員を呼ぶ。誰も反応せず。
「おしぼりを」
私が手を挙げて冷静にいうと、やっと店員が焦ってたくさんおしぼりを持ってきた。
「…冗談?」
「ちがうよ、ごめんね」
「おかあさんのこと?」
まあそういうことにしておこうか。
「そうね、そうなの。しばらくカズキのことを考える余裕がないわ」
「…すみません、ホイップのキャラメルラテ、無料でもうひとつ」
無料でって。
世間で言えば、私の母はキチガイに値するかもしれないが私にはこいつの方がキチガイに見える。
「俺」
カズキは私の目をじっくりみた。
「空のこと、大好きなのに」
何故か目頭が熱くなり、気が狂いそうだった。なんの妄想も出てこないままカズキの目を見つめて何かと錯覚した。
「なんで。」
なんで。
何かと、錯覚した。
連呼すればするほど、カズキは怯えた。
け
気がついたら、バイト帰りによく行ってたクラブに突っ立っていた。
いろんな色のライトに照らされ埃が浮いているのをなんとなく見つめる。踊りもせず爆音の中宙を見つめていた。外国人が話しかけてくる。近い、吐息がかかって気持ちが悪くなったので睨みつけてお酒を瓶で横取りし、走って逃げた。爆音のはずの音が、何も聞こえない気持ちでいた。
外はむしむしとしていた。不愉快でたまらなかった。横取りしたお酒を瓶ごと一気飲みして瓶は壁にぶん投げて大きな音を立てて割った。
次の日ティッシュを口の中に入るだけたくさん突っ込んで、赤い口紅を口にぐちゃぐちゃに塗ったくって学校に行った。謝ろうとでも考えたのか朝、家にカズキが来たが母が出た。ドアを開けた赤を身にまとうの母の姿とぐちゃぐちゃの部屋の中を見て失禁でもするんじゃないかってくらい怯えた顔でカズキくんは逃げた。もうどうでもよかった。帰りにまたクラブに行った。今度は踊ってみた。踊るというよりも、自分と格闘していた。自分とは自分だが、自分とは誰でしょう。私は結局キチガイにはなれず、そこで自分がまともじゃないのに気がつくことが出来てしまった。本物のキチガイとはそれに気づかず誇りを持っているものだが、私はその瞬間なんだか少し楽しい気分になった。やっとキチガイになれる。って思ったのに。
帰りに公園で、お祭りがやっていた。
屋台臭い雰囲気の中、イカ焼き売り場のでっかい文字を見つめて立ち止まる。「いかやき」と懐かしいひらがな四文字。ああ、イカ焼きが食べたくて食べたくて仕方がない。小さい頃お父さんと食べたのを思い出した。ドライブと称して、お父さんの助手席であてもなく走った。自然いっぱいの森みたいな場所に車を止めて、車のトランクを開けてそこに座った。後から何故かそこにお墓がたくさんあるのに気づいたのよね。お墓でイカ焼きを食べるという複雑な心境。思い出す。
嗚呼。
今度は自分がまともだということに気付いてしまいそうだ。
「すいません、一つください…あー、ふたつくらい適当にください」
財布をゴソゴソとあさる。キチガイの定理に気づいてしまいそうだった。足元に、つぶれたカエルはもういない。心の中の暴風がおさまった。なぜか、頭の中に「赤い屋根の家」という童謡が流れた。
「あ…」
後ろから声がして、振り返った。若い男で、全く見覚えがなかった。リボンを指差す彼。どの記憶を辿っても、どうしても知らない顔だった。
「どちら様?」
私が多少とんがると、彼はリボンから私の顔に目線を下げた。
「…なんでもありません」
間違えたような顔をしていたが、しばらく私の目から目を離さなかった。怯えてもいないようだ。なんて腹が立つ。そらすのが負けな気がして私はじっと睨みつけていた。時が止まったかのようだった。
「どちら様?」
声を張ってみた。イライラした。きっと憎しみに満ちた顔をしていた。別にこの人に何をされた訳でもないが私は人に長時間見られるのが嫌いだった。やっぱり私はお父さんに似ている。お金を払って、イカ焼きを受け取る。見てんじゃねえよ。てーか誰だよ。
「見てんじゃねぇよ」
声に出した。自分でも驚くほどドス黒い声だった。無視して家に帰った。帰り道、とてつもなくイライラしたが、これまた早いとこ冷静になった。深呼吸をして、空を見上げてから袋の中のイカ焼きの匂いを嗅ぐ。お父さんの匂いがした。忘れてるかもしれないが、私は中学校、高校くらいまで家族が大好きだった。
今でも変わらなかった。しいて言うなら、世界中の家族以外のやつを馬鹿にしていた。
「ただいま」
家の中には、りんごの唄が響き渡る。私は、わかっていた。
薄暗い部屋でご機嫌な母が、窓際にペタンと座りトマトを眺めていた。「おかえり」とこちらも見ずに腐りかけの熟れたトマトに夢中だった。窓から涼しげな風が入ってきていた。夏の虫たちの声も聞こえてきた。もう、夏も終わってしまうのだろうか。私はしばらく母を眺めた。母は、私と同じ「人間」という種類の「キチガイじゃない科」だと信じたかった。いや、信じたかったよりも、そうなのだ。
「見て、イカ焼き買ってきた」
「わっ」
母の声が極端に高く裏返る。私の方をやっと見た。私は母の近くに座り、袋をあさる。
私が袋からイカ焼きを出すと、それを母は黙って見ていた。そのうち、母の手からトマトが落下してべちゃっと音がした。私がイカ焼きを差し出すと母はしばらくそれを見つめてから、お父さんを思い出したのか昔の優しい顔に戻った気がした。
「お腹すいたでしょ?すいてない?」
「…」
「まあそんなことはどうでもいいのよ」
母は私の差し出すイカ焼きを不思議そうに目で追っていた。母は、しばらくぼーっとそれを見つめる。なかなか受け取らないのでそれを床に置き、入れ物から自分の分を取り出して食べ始める。「いただきます」と手を合わせると、母は私に視線を移した。少しだけ驚いた様子だった。
久しぶりに食べたイカ焼きは美味しくて、母と食べる久々のトマト以外の食べ物も新鮮だった。母は、家でトマトしか食べてないというのにガリガリに痩せてるわけじゃなかった。つまり母は、狂っちゃいない。どっかで、戻ってる。生きようと。
そのうち、母はイカ焼きを開けて食べ始めた。二人で、窓の外の星を見ながらイカ焼きを食べていた。
「…美味しい」
母が言った。私は、泣きそうになるのをぐっと堪えて「そうだね」と言った。いつも聞いているはずなのに母の声を久しぶりに聞いたような気になった。自分の感情を誤魔化すように、自分の頭のリボンを外した。唾をごくんと飲む音が響いてしまったが母は何も言わなかった。
母はキチガイになりたかったんじゃないかな、と思った。キチガイや病気じゃなくて思春期の中学生にもよくある「現実逃避」ってやつなんだ、きっと。私が、都合が悪くなったら見る夢とそっくりの話だ。部屋でかかっているりんごの唄だって、趣味で音楽を聴く人の異色バージョンよ。きっとそうだわ。
「ありがとう」と母が食べ終わって入れ物をゴミ箱に捨てる。つまりは
母は、普通の人間。
私も。
今夜はぐっすり寝れそうだ。
こ
朝起きると、母は寝ていた。
何も変装せず昔のままだった。長いまつ毛を見て、そういえばこうゆう顔をしてたなあと思った。「おはよう、お母さん」と昔みたいにおデコを叩いてみる。
年の割に赤ちゃんのようなツルツルの肌をしている。母はびっくりして目を見開く。私は面白くなって笑った。
「学校、行くの」
眠そうに母は目をこする。昨日はあれからちゃんと、風呂に入ったらしい。化粧が完全に落ちきっていた。
「いってきます。」
「早起きね、空は。いってらっしゃい」
あくびをしながら母が、また布団に包まる。このクソ暑いのに、と思い母を布団の上から叩く。いつも通り急いで髪の毛を束ねて、玄関を出た。
空が真っ青で気持ちよかった。スキップしたくなった。なんだかニヤニヤした。今日家に帰ったら、床や台所のトマトを全部綺麗にしよう。母と一緒に。そんなことを考えていた。久しぶりに、とんがってる自分と離れていた。
めずらしくご機嫌な私に、前の席のブスなギャルが笑っていた。それに気付いて私が真顔になると「めずらしいですね」とおどおど言った。「別に」と、私はカズキを見るような目で可愛く微笑んだ。カズキの視線にも気づいていた。あれからあいつは常に私を気にしていた。思春期によくあるお話です。
そ、ん、な、こ、と、は。
どうでもいいのよ。
機嫌が良すぎるのだ。私は当たり前という言葉が何より好きだった。電車では我慢出来ず歌い出していたし、帰り道は、我慢出来ずスキップしていた。
世界中のみんな、大好きよ。
夕焼けが綺麗だ。
いつものラーメン屋も、もう行く気にはならなかった。美味しくないから。それも、当たり前の話よ。
家の前のゴミ置き場の前で立ち止まる。ぐちゃぐちゃのトマトが詰まった大きなゴミ袋が何個かあった。夕焼けに照らされて、きっとご近所さんからすれば衝撃的な光景だが、私は最上級に嬉しくなった。空っぽの冷蔵庫と、幸せな家庭の部屋の床を創造した。
「ただいま」
私は大きな声で言った。台所のトマトがもう片付いていた。お父さんが生きてた時の、家に戻っていた。懐かしいにおいがした。母が、片づけてくれたのね。
お母さん。
お母さん!
「おかえり」が聞こえず、もう一度言った。
「ただいまぁ」
冷蔵庫を開ける。新品のトマトが、ひとつだけになっている。私は笑い転げた。お母さん、おかえり。
母の声がしない。寝ているのか。居ないのか。それとも前向きに買い物でも行っているのか。またもやクローゼットを開けた。居ない。いろいろなところを覗き込む。なんだか、鼻歌を歌ってしまいそうだ。何気なく私は、トイレの個室のドアを開け、何気なく便座のふたを開けた。
大量のカセットテープが、水浸しになっていた。
じり
じりじりじりじり
体が固まった。脳みそが一瞬にしてコンクリート詰めになった気分。鼻の横あたりの筋肉がピクピク動いて気持ちが悪い。カセットテープの中身は、きっと、
りんごの唄だ。
「~♪」
お風呂場から聞き覚えのある鼻歌が聞こえ、ぞっとした。見なかったことにしたかっ
た。無かったことにしたかった。何も起こってません。何も。これで、終わり。終わりでしょ。頭の中のモンスターたちに助けを求めた。顔でかヒールに80歳のおじいちゃん。ああ、こんなにも私には仲間がいるはずなのに。誰も出てこない。今や、頭の中の仲間が光に包まれ横並びで整列して私を見守っている。その中に、お父さんも居た。
なんで助けてくれないんだと文句を言ってやりたかった。皆様の背景から、白い光が漏れていた。お父さんが、「そら、下。下。」と私の足元を優しい笑顔で指さす。
落ち着け、落ち着け。恐る恐る、足元を見た。
つぶれたカエル。
助けて、助けて、お母さん。
私はいきおいよくお風呂の扉を開けた。
鼻歌が止まる。真っ白の壁に、赤い水がたくさんはねていた。
視線を落とすと、母はこちらを見た。リボンをしていた。ワンピースも着ていた。楽しそうに、片手にはあの時の果物ナイフが握られていた。両足を洗面器にいれて座っていた。洗面器には赤い水がはってあり周りにも飛び散っていた。
「あら、おかえりなさい」
私は言葉を発せなかった。口を開いてもいないのに顎が外れそうだ。母の目は充血していて、化粧もまるでぐちゃぐちゃだった。震えが、震えが止まらない。
「見て」
嬉しそうに、母は洗面器から足を上げる。赤い水から上がった母の足は深い傷がたくさんついていて、見覚えのあるような刻まれ方をしていた。
「…いかやき」
なるほど
心臓の音が聞こえる。私の、心臓の音だ。
お母さんから生まれた私の、心臓の音だ。まぎれもない。
笑顔の母は、奇妙なくらい黒い目をしていて鳥肌が立った。目を見開いたままそらせず、動けず、息もできなかった。水の中にいるみたいだった。苦しかった。私、エラ呼吸じゃないんですけど。地上に、出してよ。出してくれ。
お父さんの笑顔が一瞬だけぼやけて見えた気がした。「そら、下。下。」って聞こえた気がした。
ゆっくりと、足元を見た。
みっともないほど可哀想な、あの時の、つぶれたカエルが。
ぐ っ ち ゃ ぐ ち ゃ !!
「なんで?なんで?なんで?なんでなんでなんでよ!!!お母さん!目を覚まして!お母さん!お母さん!お母さぁん!!戻ってきたじゃない、昨日、戻ってきたもん。お母さん!なんでよ、戻ってきて!戻ってきてよ!!帰ってきて!おかあさぁん!」
感情が爆発して、母の胸ぐらを両手で掴んだ。冷静な私が居なくなった。、よくわからなくなった。母にしがみついた。必死だった。怖かった。どうしたらいいのか、わからない。冷静な私が、戻ってこない。誰も冷静な私を呼んできてくれない。
お父さんも、空から私のことなんてきっと遠くて見えない。小さくて見えやしない。夜空の星も、きっとお父さんじゃない。あんなの所詮、大きめの石のカタマリだって知っている。なぜだろう、突然愛と勇気だけが友達の、あの方の頭が高速回転している夢を見た。怖い。来ないで。戻ってきて。おかあさん。みんな。なんで
なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんで
「…嫌よ」
今度は、母が冷静に言い放った。こちらを見ずに、ぼーっと正面を見つめていた。
時が止まって、私ももがくのをやめた。とても冷静に戻れそうではなかった。冷静とはなんでしょう。冷たくて、静か。それって、正義なのかしら。
静寂。
カラスの鳴き声が、小さく響いて。恐ろしく感じる。母にしがみついた両手に、かすかに力を込めた。洗面器の赤い水に、蛇口の透明なしずくが
ぴちょん。
「嫌よ」
真正面を向いたまま母が突然、か細い声で静かに笑い出した。私はそれを、じっと見つめていた。小さな笑い声が、風呂場に響いた。水が滴り落ちたって、ぴちょん、という音は、私にはまったく聞こえなかった。
そのうち、母は真っ黒な目でこっちを見た。なにか違う生き物と目を合わせたみたいだったが、そのうち、母がいつもの優しい顔に戻っていった。少し潤んだ目で切ない表情をしたので、お父さんが入院してた時を思い出した。
しばらくして、母はまた静かに笑い出した。
両手で、私のほっぺたを触り鼻歌を歌っていた。私の顔は、母の手によって優しく包みこまれていた。されるがままに、母の目を見つめていた。母の瞳が黒いのに、恐怖は無かった。悲しくて、悲しくてどうしようもなかった。次第に母の目がうつろになっていった。鼻歌は、異常なくらいどんどん大きな音になった。母は、歌を叫んでいた。
突然母は笑うのをやめ、歌うのもやめた。片手で私の髪の毛を掴んだ。すごい力だった。もう片方の手で、ほっぺたをちぎれるんじゃないかって位鷲掴みされた。憎しみの顔に変わっていく母を見て、腹をくくった。やっと、冷静な私が戻ってきたのか。冷たくて、静かで。
怖いよ。
私は、だるい、重たい、面倒くさい、怒られる、つまんない、痛い、ということが嫌いだった。つまりは、普通の人間のお話です。なんて素直でしょう。
それから母は、なぜか私の顔を平手で殴り続けた。開いた手に、優しさはなかった。私を見る目にも、悲しさと憎しみしかなかった。私の頬は痛み、私の瞳はきっと、うさんくさいうさぎのいる月で出来ていた。ぴしゃん。ぴしゃんと
何度も。
ぴしゃん ぴしゃん
震えもしなかった。私からしたら母のすべてが、普通の人間のお話でした。そうゆうことに、してあげたかった。もう、戻ってこなくてもいいよ無理して。だって、仕方ないんだもの。戻ってきてなんて言った私は、ばかだ。世の中に、本当に仕方のないことなんかたくさんあるわ。とにかく頬が、痛い。全部全部、痛くて痛くて死んでしまいそう。ただ、それだけ。それだけの話よ。
赤いりんごに唇よせて
私を殴ってる途中で眠くなったのか、母は寝てしまった。
私は母の足を手当てして、布団まで運んだ。腫れた自分の顔を鏡で見て、何事もなかったように冷凍庫の保冷剤で冷やした。外はまだ真っ暗で、時刻は23:40。今日が、終わっていく。
あまり、覚えていない。
窓を開けて、外の空気を吸った。何も考えてなかった。空っぽだった。深呼吸をする。ぼーっとしていた。
えらくぼーっとしていたので、いつ寝たのか、いつ布団に入ったのかなんて覚えちゃいなかった。
朝が来ていた。早朝は、すがすがしい涼しさで静かだった。漫画みたいに小鳥が鳴いていた。
寝ている母を見た。化粧がぼろぼろだ。髪もぐちゃぐちゃ。格好だって、ひどいや。睫毛が、やっぱり長かった。笑いもせず、母の顔を見てしゃがみこんだ。母の頭から、リボンをこっそりはずしてポケットに入れた。片方の目頭に、一瞬だけ燃えるような、ひんやりした感覚がした。よくわからなかった。下唇を、ちぎれるんじゃないかって位に一瞬噛んで何かを飲み込んだ。軽く深呼吸。深呼吸だ。
ティッシュを口の中に入れ外に出た。まだ少し薄暗かった。あてもなく少しだけ、ゆっくりと散歩した。水色の薄暗い空に、澄んだ空気。朝だ。
朝だ。
私は、冷静。
私は、ポケットから携帯を取り出し電話を掛ける。プルルル、と5回鳴ってようやく、出た。
番号は、110番。
さ
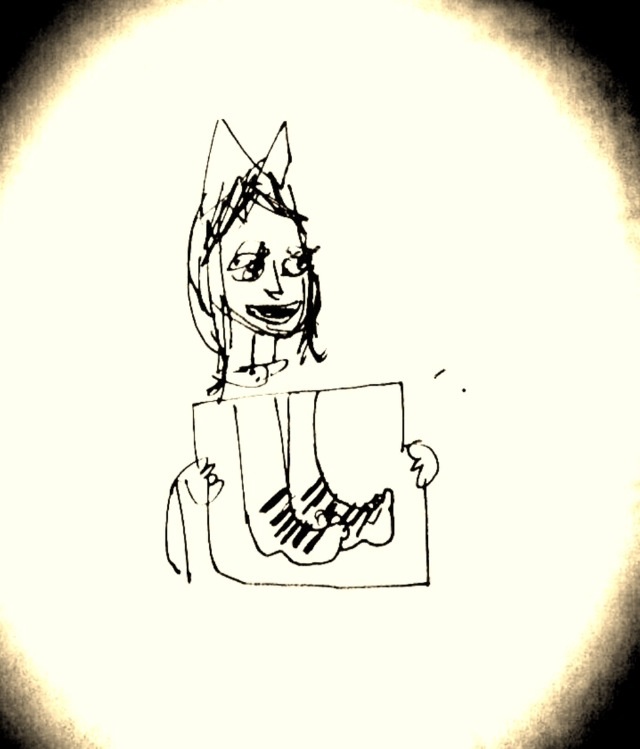
すごく簡単に言うと、母は自らどろどろした赤い部屋を幸せな家族の住む部屋に戻してしまい、また赤が好きになったらしかった。
解離性同一障害という病気だった。私は、そんな話どうだってよかったので、すぐに話も聞かず病院を出た。腫れた頬がまだじんじん痛かった。ていうか思ったの。きっと、私も別の病気だと。
コミュニケーション 障害ね。
なんちゃって。
何も考えてないとはこのことだ。疲れていた。コンビニでガムを買って、くちゃくちゃ食べた。財布の中の、命にしか変えられない三千四百五十円。少し家から歩いたところにある公園のブランコに座り足をぶらぶらさせていた。片方の鎖にもたれかかり、風船ガムを作った。とにかくダラダラしていた。風船ガムが、割れたと同時に叫んでしまいそうになった。
母が居なくなった。いや、かぞくが居なくなった。
居なくなるってわかっていても、寂しいものでした。急に電車に乗って、飽きるまで降りないということを無性にしたくなった。私は駅のホームに立ち、ただただ電車を待ってぼーっとしていた。寂しいけれどしばらく母のことを考えるのは、やめにしたかった。お父さんが居なくなったときは、たくさんお父さんのことを考えたかったのに。寂しいから。
悪循環。
「つまんない。つまんない。」
ボソボソと一人で喋るのが癖になっていた。電車に乗りっぱなしで、席が空いても座らなかった。人間観察をする余裕も妄想をする余裕も無かった。ツマンナイ。ツマンナイ。耳がぼわぼわした。「がたん」の「が」の字すら聞こえない。だが私はまともだ。
『次は高円寺』家の最寄駅でちゃんと降りるということが出来た。
空を見て歩いていた。もう夕方だった。
「つまんない。つまんない。」
上の空とはこのこと。
ふと視線を目の前に戻すと、見覚えのある顔があった。いかやき売り場に居た男だった。頭がボサボサでこんな時間に寝起きのようだった。まあ、私も変わらないか。男は、私を見るなり頭の上に視線を移した。リボンの、確認のつもりか。
「シーッ」と威嚇する猫のような音が出た。私は男に威嚇をした。爪が長ければ引搔いてやりたかったし牙があれば食いちぎってやりたかった。カメムシだったら臭いの出してぶっかけ。
むかつく。無視して家に帰り、窓際にぺたんと座った。
お腹が鳴ったので、舌打ちをして自分の腹を殴った。何度も、何度も。
この野郎。この野郎。いたい。この野朗。
冷蔵庫からトマトをひとつ取って、丸かじりした。冷蔵庫は真っ赤では無く、トマトはひとつしか入っていなかった。口の周りが汁マミレになるが、なんの味もしなかった。狂ったように、むしゃぶりつくす。だんだん、笑いが止まらなくなってきた。口の周りが、かゆかった。ティッシュをたくさん乱暴に取り、口の周りを拭く。そのティッシュをそのまま無理矢理口に押し込み、トイレに走った。
吐いた。暗かった。トイレは暗かった。叫びたくなった。吐くのは、苦しいから嫌いだった。涙が出るから嫌いだった。
しばらく自分の吐いた便器の中のオーロラを見つめていた。オーロラに見えた。幻だなんて思わなかった。オーロラよ。これは間違いなく、オーロラ。便器を思いっきりぶん殴る。割れたような音がしたが、割れない。天を仰ぐ。何も見えない。天井にも、オーロラが…
「この世の…」
ぽつん、と呟く。天井にカエルがうじゃうじゃ張り付いているのが見える。ああ、あぁ。嗚呼、もぉ、。私は自分の髪の毛を両手で鷲掴みした。
「この世の、全てに腹が立つっ!!!」
そう大きく叫んで下着のタンスをこじ開け、ブラジャーを窓から全部外にぶん投げた。耐えかねて外に飛び出した。冷たくて、静かな私は出張に行っていた。ドアに鍵も欠けず全力で走った。住宅地から商店街に抜ける途中で、歩道橋の下に整列する自転車たちを思いっきり蹴っ飛ばしてドミノしてから、助走をつけてジャンプしておもいっきり踏んづけた。端によせてあった一番ボロそうな、鍵の無いママチャリにとっさにまたがり、全力でこいだ。
「どいつもこいつも邪魔くせぇぇええ!!どけー!!ブスども!!ザコども!!ゴミが!!なめやがって!!ふざけやがって!!」
あてもなく怒鳴りながら全力で人混みを掻き分けた。お母さんもキチガイなんかじゃない。お父さんだって。ほら、見てみ。私がきっと、キチガイだ。
唖然としている人。私を見て恐怖に怯える人。そんな人ごみの中に、いかやきの男が居た。いかやき男は私を見て、からかうわけでもなく心の底から大爆笑して息ができなくなっていた。彼の笑顔がキツネみたいに見えて気味が悪い。キツネのお面のようだ。声も出さずこちらを見つめて笑っている。手を叩くわけでも無く、立ったままびくとも動かない。声を上げるわけでもない。腹が立つがそれより、気味が悪い。
「前を歩くのが、のろいやつ!息や体がくさい奴!なぜかべたべたするやつ!声が
癇に障るやつ!」
世の中でむかつくやつの名前を叫んだ。
「目の上かぴかぴ野郎、綺麗事もらい泣き女!ブサイクいちゃいちゃカップル!よわいものいじめ!」
心も体も大激走していた。全力だった。ああ、見てますかね、あの日おもらしパンツを脱いで台所を片付けた鉄腕アトムの娘よ。あなたは鉄腕アトムの娘なのです。いいえ、鉄腕アトムじゃない頃から。
愛と、勇気と私は絶交中。なんだか泣けてきた。なんだか泣けてきたわ。
少しだけ私の視界にまた、きつねのような気味の悪い顔をした男が見切れて、とっさに「しね!」と叫んだと同時に私は自転車のまま壁に激突した。
横転した私は、真っ暗闇の中で「ストン」という音を聴きながらただ横たわっていた。自転車で私が突っ込んだのは汚い商店街の、古臭くて汚くて狭い道だった。野良猫の鳴き声が一瞬だけ聞こえてそこからは、また懐かしい白い空間でカラフルなカエルのおもちゃを足でつぶして遊んでいた。
シ
「…さむ」
寒さで目が覚めた。夜中だった。暗い路地だというのに、レイプすらされていない。なんて薄汚いんだ私は。自転車は無くなっていて、上にコートがかけられてた。黄土色の少しよれたコートで、柔軟剤のにおいがした。きっと心優しい誰かがかけてくれたのね。少しだけ心が温かくなった。狭くて汚い路地には猫のほかにも、変な虫やらトカゲやらきっとたくさん居た。体が痛かった。ヒザから精一杯血が流れて乾いてかさぶたになっていた。両膝だ。しばらくスカートは履けない。
はっとなってポケットの中を探した。定期入れがお尻のポケットにいつも通り狭そうに入っていた。私は眉間にしわをよせて他のポケットを探した。財布が…無い。さんぜんよんひゃく、ごじゅうえん。
「クソ!!!」
私は腹を立てとっさにコートを地面に投げつけた。
気がついたらお金も全く無いのにあのラーメン屋さんのカウンターに座っていた。「いらっしゃいませ」いつものイケメンの店員さんが私の目の前に水を置く。私は、まっすぐと店員さんの目を見た。ずーっと、ずーっと見てそのうち、水くらいいただいておこうとコップを持った。
コップのふちに何故か、胡麻がついていた。私は一口も飲んでいないどころか客もガラガラで、どっかから胡麻が飛んでくる気配も無かった。胡麻をじっと見つめて胸の奥から「イライラ」と聞こえた。そんな声が急ピッチで追っかけてくる。
「ご注文は…」
遠慮がちに、無愛想に店員が私に話しかけるのでそちらを見た。
「ありません」
はっきりと言った。
「…」
「…」
しばらく見つめあう。
「…困りま「胡麻がついてます」
これまた、はっきりと言うと店員はやっとコップに目を向けた。しばらくの沈黙の後、また店員は私を見る。
「…あの「胡、麻」
私は負けない。目をそらさなかった。タダになるだろうなんて思っちゃいないしお金をくれることも無いことだってわかっている。ていうより、タダになったとしても胡麻が怖くて怖くて食えやしないわよ。
「お皿を、ちゃんと、洗いま、しょう!!!!」
私は立ち上がる。
「以上!」
なんか言えよ。
なんか言えよ、てめえ。これじゃただのクレーマーよ。
喉がカラッカラじゃボケ。
家に帰って死んだように寝た。夢の中で、お母さんとコロッケを作っていた。台所に立つ私は、まだ小さくて背伸びがちだった。小麦粉、タマゴ、パン粉。順番につけて、お母さんに渡す。お母さんは、グロスでつやつやした綺麗な唇を歪ませる。私の顔を見て微笑んでから、しゃがんで目線を合わせた。パーマがかったふわふわの髪の毛からお母さんの匂いがした。シャンプーの匂いだ。お母さんはいつもシャンプーの匂いがするのよ。お母さんは、私の頭をなでると、寂しそうな顔をして突然、私の髪の毛とほっぺたを握りつぶ
目覚めた。
早朝だった。薄暗くて、涼しかった。外に出たくなった。口の中にティッシュを入れて、くちゃくちゃと噛んだ。何も持たず、鍵もかけず外に出た。いつも通る公園のフェンスにタックルしたい衝動にかわれたが、やめておいた。ぼーっとしていた。
ベンチに座った。特に何もせずボーっとしていた。ぼーっと。ぼーーーーっと。ぼーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
はあ、ねむい。
「何してんの」
声にビックリして目覚めた。気がついたら、座ったまま寝ていたらしい。ふと声のほうを見ると、あきらかに「走りに来ました」という格好のいか焼き男が現れた。そう。
【 いか焼き男が、現れた!】
「…なんなの」
「…なんなの?」
「視界に入んな」
吐き捨てるように、目も見ずに言った。
「うぜえ。まじ。うぜえ」
目を見てはっきりと言ってやった。真顔だった。彼も真顔だった。私はあらためて立ち上がり、彼の目の前に立つ。
「うぜえ。まじ。うぜえ」
もう一回。はっきりと言った。すると彼も表情を変えず、しばらく見つめあった。すぐに飽きて、また私はベンチにだらりと座った。なんとなく、自分の足の先を見た。もちろん、何にも無かった。何にも起きなかった。
無愛想に、彼が「あっそ」と言ったのが小さく聞こえた。しばらくの沈黙のあと、どこかで見たことのあるように彼が私の目線に合わせてしゃがんだ。私の顔を見たが、私は目も合わせず遠くを見ていた。早くどけろよと思うまでも無く、イライラも何故かしていなかった。無心とは、こうゆうことなんだって今思えば、そうだ。
「うぜえ・まじ・うぜえ」
彼がボソッと私の目を見て言い返したので、私はガムのようなものを噛むのをやめ、ふいにそちらを見た。
「…」
「…」
「…あぁ?」
どす黒くて大きな声が出た。と、同時に
お腹が鳴る。私は彼の目を見ながら、とっさに
「お腹すきました」
あの頃のように。突然1秒で土下座をした。
彼が連れてってくれたのはとある24時間の、定食も出しているようなマニアックなチェーン店だった。メニューを見ただけで、よだれが吹き出そうだった。ていうか、吹き出た。迷いに迷って、コロッケ定食。正直、この男は気に入らないとさえ思わないほどどうでもいいので、私は素直にワクワクしていた。もうはしゃいでいた。
出てきたコロッケ定食は、バカなのかと叫んでしまいそうなほど美味しかった。美味とはこうゆうことね。彼が何を頼んだとかそんな事はどうでも
「うっっっま!!!」
一口食べた瞬間彼が大声を出したので、びくっとした。コロッケと二人きりの世界に入り込んでいた私は、夢から覚めた気分だった。
彼は私の存在も無視してゆっくりと口に運び、そのたび衝撃的な顔で首をかしげながら「えっ?」「えぇ…」と言った。私はそれを気がついたらじっと見つめていた。彼が食べてたのは、さほど興味が無い焼き魚だったが私は彼のオーバーリアクションによって焼き魚の熱狂的ファンになりそうだった。こんなに素敵なコロッケ定食が目の前にあって、奢りなのに。私はおあずけを食らった気分だった。
ていうか、誰。
「…あのさ」
「あ、なに」
彼が突然普通のトーンでこちらを見ながら返事する。
「ひとくち」
「…は?」
「おなかすいた」
「…あんじゃん、それ」
「…たべたい」
「図々しいな、死ねよ」
「…」
「…」
「ケチぃ!!!」
「食えよしたら!うっとうしい」
私は嬉しくなり、蔓延の笑みで箸をそちらに伸ばして焼き魚を取った。ひとくち、口に運ぶ。いらっしゃいませ、私の口の中へようこそ。焼き魚。異常に普通の味で機嫌が悪くなりそうだったのでそこからはコロッケと仲良くした。皆様、知ってた?
リアクションとは、エンターテイメントなのです。
特に語り合うわけでもなくただご飯を、奢ってもらった。
外はさっきまで早朝とはいえ空が水色だったのに、それがまんまと灰色に変わって雨が降っていた。彼がレジでお金を払っている間、何故か錆びている曇りガラスの外を見つめた。ドアを開けると、「ザー」というより「ぴちょん」の大集合が爆音で聞こえた。
ああ、つい最近まで必死に違うことを考えようと妄想の中で生きていたというのに。今は現実に必死だった。何故かカズキの『空のこと、大好きなのに』というセリフが、顔が、頭の中でずっと完全再現されていた。
不愉快だとは思わなかった。つまりは、好きでも嫌いでもなければいい思い出でも悪い思い出でもない。腹も立たない。図に乗るなと頭の中で暴言も吐いたりしない。
『オナニー大好き』と真顔で連呼する私と、それを見てポカンとドン引きする顔面爆発女…あ。顔面合成大失敗ギャルも今はたくさん頭の中に生息してた。本当は、笑ってほしかったのか。どうでも良くなんか無かったのか。そんなこと、わかりゃーせん。
つまりは、とんがり終わったのだ。私は。
「邪魔なんだけど」
後ろから彼がどついた。こいつだってそうだ。名前すら知らなければ一緒に飯を食ってる理由さえわからない。不愉快でも愉快でもない。
これならとんがっていた方が色々と便利だった気がした。
店の前の少しだけ古びた道は、もう早朝と呼ばれる時間は少しばかり過ぎたのに天気の悪さにより薄暗かった。人通りはほとんど無くて、もう一回店の中を見ても朝帰りの水商売の姉ちゃんか、おっさんしか居なかった。
私はぼーっと彼を見つめていて、気がついたら雨に濡れていた。
「何」
「え?」
「ぼーっとしてんの」
「してない」
意外とはきはきと声が出る自分に少し驚いた。少し前の私なら、こいつを家にでも連れ込んでセックスでもしてたんだろうな。
その辺の路地裏でも。そうゆう雰囲気になるようにわざと振舞ってたかもしれない…あ、わかった!思春期だったん
「傘は」
彼が言ったと同時に雷が鳴った。柄にも無く少し一瞬震えた。わざとでは無い。
「傘」
聞こえてるって言うのに大きな声で彼が言った。
「あるよ」
「どこに」
「…家!!」
「…」
自信満々に言った私を見て、聞こえないけど彼は舌打ちをしたようだった。
「ごちそうさま、あばよ」
そうアホっぽい台詞を笑顔もなしで叫ぶ。私は何も気にせずべちゃ濡れのまま家まで歩いたが彼が追っかけてくる様子は無かった。正解。正解です。
というより、彼もランニング中のためきっと傘が無かった。
空を見上げて雨を飲んでしまおうと思ったが、想像しただけで吐きそうになったのでやめました。
すんっ。
家に着くと私によって私の家の中がびしょびしょになって、フローリングの床がとても滑る。
お母さんが居た頃は、狭いと思ってたこの家も今じゃ広い。怖くなるほど広いのだ。私は床が濡れるのも気にせずタオルを引き出しから取り出し、風呂に入った。
風呂はもう赤い水の跡ひとつ無かった。私はあの後ちゃんと冷静に掃除したのだ。腫れた頬で、掃除したのだ。得意の、冷静が無意識に出たらしく私は自分で風呂をあの後掃除した記憶なんて無かった。
風呂の鏡に全裸の私が水浸しでうつっていた。頬の腫れはだいぶひいていた。
全裸の私の股間の毛を見て、可哀相だと思った。何故か泣きそうなくらい可哀相な毛並みをしているように見えた。例えば小学校低学年に弄ばれた習字の授業の墨汁だらけの筆の先でも、こんなみじめな姿無いだろうなって位に思えた。
そんなこと、女の子は考えないの!ってカズキに怒られたような気になった。「うっせーな」と呟いた。
うっさいわ。
私はとんがり終えてないのかもしれない。
髪の毛を無心で乾かしてから、雨の音を聴きつつぼーっとしていた。お腹もいっぱい。なんだか世界がこの部屋の中しか無いんじゃないかと思い始めた。妄想だけど、妄想が前よりも思い浮かばなくて突如お父さんとお母さんの喧嘩を思い出した。
私の頭や、体の中のすっごく遠いところにしまっておいてあった記憶だった。
私は家族の完璧な部分しか、信じてなかったのかもしれない。お別れになる直前だけだ。そうだ。
眠りたい。眠ってしまいたい。金も無い、考えたくも無い。何も。
心病んでいたよりはきっと、私はだらけてるんだ。きっとそうよ。
自分の息をする音が、爆音で聞こえた。嗚呼、
突然、涙が目から脱走し始めた。
連想するのはクラゲ。異常にやわらかいクラゲ。目の中から、異常にやわらかいクラゲが脱走。脱走した後は、水になる。
すごい量の、水だ。きっとあの時の、ぺちゃんこのカエルも、頭の中の小さなカエルのおもちゃも、私の目から出て行く水で泳いでる。
滝みたいでしょ。
ウォータースライダーだぜ、喜べ。
「えぇぇぇええぇっぇっぇぇん!!」
声を上げて泣いていた。父が死んだときの母みたいに。誰か、誰か、助けてください。
悲しくて、悲しくて、寂しくて、寂しくて、助けてください。溺れさせて下さい。私を黙らせてください。
「うぁあぁぁああぁぁん!!」
声が枯れそうだったので、とっさの本能か、水分補給に外に出た。
叫んだ。死ぬほど叫んだ。自分でも訳がわからないほど。遠くに。
のどから血が出そうで余計悲しくなった。もう、腹が立つという感情はゼロだった。悲しかった。綺麗事を言うと、誰か私とセックスしてじゃなくて、誰か私を愛してくれじゃなくて。仲良くしてくれでも、構ってくれでも、無くて。
父さんと母さんの、笑った顔が、見たぁぁああああぁぁい。
見たい、見たい、見たいよう。三人で、居るときじゃなきゃ、だめだよ。ていうか、昔みたいじゃなきゃ、だめだよ。
だめ、だめ、全然だめよ。私、一人じゃ全然だめよ。だめ。やだ。やだ。とにかく、いや!!
唇が震えた。
何故か、誰ともすれ違わなかった。雨が、ぴちょんぴちょん私を叩くじゃないか。
やめて。
暗い。明るいのに。
どれだけ、歩いたんだろう。どれだけ、泣いたんだろう。疲れてふらふらと歩く頃には、昼なんてとっくに過ぎていて。
立ちくらみがして、私はよくわからない場所のよくわからない河川敷に向かって転がり落ちてしまった。
このまま、顔とか虫に食われてメンドクサイことになって人前に出れなくなってまたきっと怖い悲しい言って泣くんだわ。もう、どうでもいい。
もう。
キラキラと、安っぽい宇宙にアトムが飛び交う夢を見た。何も喋らず、音も無い。
そこからは、テレビみたいな画面が出てきて、お父さんとお母さんがビデオレターみたいに私に手を振っていた。
「元気~?」
母が無邪気に手を振る。
「そらちゃん、元気か」
父がニヤニヤとしている。
「今、宇宙でーす。どう?最近、楽しい~?」
「そらちゃん元気ないのか」
父がまじめな顔に戻る。するとそれにつられて、母も悲しそうな顔をした。
「ドッキリだってば。」
「違うだろ」
「あんまり怖がらせないであげなさいよ、ね~?そら」
「そらちゃん、懐かしいだろ。俺の元気な顔」
「やーだー♪ちょっとそれ面白い」
「そらー」
「呼びすぎー!!今しゃべれないんだから。(笑)最近面白~い♪あなた最近面白いよ~~」
「そらちゃん、げんきげんき」
「まあ、、
起きて」
バシャアアアアッ!!!!!!!!!
冷たい顔面に水が突然大量に降ってきて、のどにつまった。ゴホゴホむせて、涙が出た。大量に水を飲んで、具合が悪い。苦しくて立ち上がるが、ふらついてまた倒れた。鼻からも水を飲んでしまい激痛が走った。
「ゴッホ!ゴホゴホ!!おえっ!」
しばらく咳と戦い、誰かが大笑いする声に気づいた。
はっとなると、今が夕方だということに気づいた。雨も、降っていない。もうやんだらしく、もう外は暗かった。
息を整えながら、笑い声のほうを見る。
バケツを持ったいかやき野郎が立っていた。仁王立ちしながら、大笑い。バケツは家から持ってきたらしく大きめで、水をかけられたんだとわかった。
とにかく鼻が痛くて、ずっとむせていた。彼は笑うのをやめた。しばらくして
私の息が整うと、彼が言った。
「ごち」
私の財布を、私に投げた。何故か腹も立たなかった。あぁ、私の金だったのね。コロッケ定食。そのくらい。なんてみじめなんだろう。なんて、屈辱なんだろう。黄土色の上着も、あんたのか。彼の目をずっと見つめていたが、濁ってはいなかった。だんだんといろんな感情がこみ上げてきそうで、無心のうちに黙って帰ろうと思い、財布の中身を確認した。
さ
さんまんよんひゃくごじゅうえん。
「…」
さ
さん
さんまん「ん」
彼がビニール袋を差し出した。中身はコンビニオニギリだったが、食欲をそそった。ぼーっと彼を見つめていると、彼は噴出すように笑った。
「顔が!」
また大爆笑された。虫に食われていた。パンッパンだった。そんなこと、気にせず私は叫んだ。
発狂した。世界に。
絶望した。
自分に絶望。
そこからは、またのどから血が出るくらい泣いて、彼は黙ってその近くでオニギリを食べていた。ずっと「寂しい」だとか「悲しい」だとか叫んでいた。冷静な私が~…だとかどうでもよかった。
笑って欲しかった。
私、笑って欲しかった。
どんな時も。
私は視界にチラッと入った財布をあらためて見てから絶叫と呼べるほど叫んだ。
「図々しいなぁ、死ねよ!!!!!」
のどから血が出ました。
じれったい劇場 開幕
懐かしい。においがする。においがするぜ。夏です。皆さん。
蝉が鳴く。空が青くて、白いティーシャツばっかり干しちゃう。そんな夏です。スイカです。皆さん。今年の夏は、初めて経験したみたいに青い夏だ。いつも私はきっと、ドス黒い夏を経験していたんだ。
自転車にまたがりアイスの袋を開けた。棒アイスは、溶けて手がベタベタになるから本当は嫌いだった。でも、だって、夏よね。
アイスを食べながら駅までチャリをぶっ飛ばして、息がしにくい。緑に囲まれた公園に時々あるベンチに一人だけハーモニカを吹いたオッサンがこっちを見て座っていた。あいつはよくそこに居る。きっと、ホームレスか何かだ。
駅に着くと、駅の近くにあるコンビニにアイスの棒と袋を捨てて、証拠隠滅。近くにある住んだことも無いアパートの駐輪場に、いつも通り勝手に自転車を停めた。駅のトイレに走って手を洗って、いい香りのするコロンを少しつけた。
全部、全部、証拠隠滅。電車の中は効きすぎている冷房が寒かった。渋谷にあるレストランに向かった。おしゃれなレストランだとわかっていたのである程度お洒落をしてきた。これは正解なのでしょうか?
走って息をきらして汗をかきながらも、店の扉を開けた。
「ごめん待ったでしょ、ごめんごめん」
中に彼を発見。
「そんな待ってないよ」
きっと嘘だった。彼のコーヒーが入ったコップは空になっていた。汗をかいたので、顔から髪型から心配だ。店の中はいい具合に涼しかった。
「おはよ」
「あちーなぁ」
「ちょっと、お手洗い」
「はいはい」
彼はメニューに夢中だった。お腹がすいているのかしら。ポーチを持ってトイレの鏡で軽く整え、彼の迎え側に座った。
「何食べるか決まったの」
「お前がおせーからとっくのとーに決めてんだよ」
「ごめんって」
「うそだよ」
彼が何故か大きな声で言った。
「ドリアがいい」
私も負けずに大きな声で言ってみると「うるさい」と食い気味で突っ込まれた。私は笑顔で店員さんを呼びつけ、食べ物を注文した。彼は肩の骨をだるそうにポキポキ鳴らした。
なんだかんだ気づいたら一緒に居て三年もたっていた。
食べ物が運ばれてきて、彼の口に運ばれるオムライスの卵ちゃんをなんだかじっとりと見つめていた。卵ちゃんはとろけすぎて少し彼の口からはみでそうだった。私はそれを横目で見た。何も考えちゃいなかった。別にいやらしいことを考えてた訳でも、ニヤニヤ口元が緩んだわけでも無い。ただただ、それをじっとり、見ていただけ。
久しぶりに遠出することにしたのだ。電車に乗って何もないとわかっていながらも川原を目指した。なんてったっていい天気だから。電車に一歩乗り込むと、冷房が異常なくらいきいていて肌寒かった。それが今は心地よかった、汗もかいていたからすごく寒かったんだけれど。がたんごとんという音なんてまったく聞こえなかった。長くだらだら電車に乗っているこの時間が好きで、窓には色んな緑色の色んな景色や、色んな名前の駅が映りこんでゆく。電車の中が美術館になったみたいだった。窓が一枚一枚絵に見えた。
普通のデートなんて久しぶりだ。たまには、こうゆうのもいいなぁとウトウトしながら考えていた。なんとなく起きていたかった私だが、彼は途中でウトウト期間を通り越して爆睡モードだった。別に電車の中は何を話すわけでも無かったけれど。だから寂しさもなく自分だけの絵画たちをだらだら眺めていた。
電車を降りると、冷房マジックが溶けて空気が固まってしまったようだった。さらさらした空気に水溶き片栗粉をちょっと足したみたいな…それはちょっとブリッコしたわ。
無人駅に近いような寂しい駅に到着した。少し歩いて古臭いコンビニに立ち寄り、缶ビールとお菓子を買った。私は大好物のチーカマも買った。それを見て、彼は不機嫌そうな顔をしたが、私はにっこり笑った。そこからまたしばらく歩いて、川が見えた瞬間全力で走った。川原の水が、きらきらと
「光ってる!!」
「はいはい」
「夏っぽい!焼肉したい!」
「はいはい」
「おい」
「なに」
「はいはいばっかり」
「…ビール飲むか!飲むか、ビール」
「飲みます!!!!!!」
「うるさ」
二人でビールを開けて、ただただきらきら見てた。私は水でだいぶ遊んでた。だいぶ。彼は無事だが、私はべちゃ濡れ。やれやれといった感じだった。彼は突然私を追い掛け回したり、びしょびしょにしたりしようとしたけど、すぐ疲れてきらきら見てた。彼への仕返しに私はチーカマをちぎって投げたり、石を投げたり調子に乗ったので彼は意味不明な傷やアザがたくさん出来ていた。
はしゃぎ疲れて、帰りの電車は寝ていた。彼は夜の絵画たちを見ていたんだろうか。彼の肩で勝手にスヤスヤ寝てた私はどんだけアホな寝顔だったんでしょうか。
人は皆動物だ。甘えたくて、甘えてほしくて当たり前。
帰りは、彼がうちに来た。だらだら、テレビを見ていた。ただ、だらだらしてた。たまに私が何かの衝動で立ち上がって歌いだすぐらいで、それ以外はなんとなくイチャこいていた。ただ、たまに私が何かの衝動で立ち上がって歌いだすくら
「お誕生日おめでとーーーーー!」
どこかで見たことあるように、部屋のどこかに隠していたプレゼントを彼の目の前に滑り込ませた。スライディングシュート。
「…」
彼は、何も言わずプレゼントを見つめてから嬉しそうに少しニヤっとした。
「覚えてんの」
「当たり前じゃないか」
「…」
「…あれ?」
「嬉しいんだけど」
彼はプレゼントを開けて、ときめいた顔を見せた。中身は彼の好きなものばっかりだったはずだ。何気なく「コレがほしい」と言えば私は覚えていた。陰湿な意味じゃなくて。私はサンタさんになりたかった。サンタポジションを完全に狙っていた。なんで?いつのまにボクの欲しい物知ってるの?っていう風に思われたかった。単純に、自分がそれをされたら嬉しいからだ。
彼は珍しくワクワクが全開に表情に出ていてなんだか私は面白かった。笑い出しそうになった。嬉しくて、愉快で、大成功で、照れくさくて。
「ありがとう」
彼の欲しいものと言えば変わった物ばっかりだった。普通の男の人みたいに時計だとかベルトだとか服だとか、まれにある香水だとか買っても喜びそうに無かった。箱の中身は、望遠鏡、虫の置物、生魚のぬいぐるみ、地球の本。
彼の欲しがる物は子供みたいな物ばっかりだった。子供と言ったって、普通の子供じゃなくて、きっとちょっとだけ変わった子供だ。
私だって人のことは言えたもんじゃないけど。
本当は寝てる間に枕元に置いておきたかったんだけどごめんね、我慢出来なかったのよ。
どうもこんにちは、サンタさんです。
「ねえ今日さ」
二人で布団もかけずに天井を見つめた。
「川でさ、くるぶしから血でたの」
「ふーん」
「岩でも蹴ったらしい」
「俺はヒザとヒジから血が出て太ももにアザができたよ」
「ふーん」
「岩が飛んできたらしい」
「面白いねぇ、君って」
「面白くねぇよ」
「…」
「…」
「てかさ」
「あぁ」
「おめでとう」
「しつこいね」
「…私たち」
「うん」
「…付き合って、どんくらいだ」
「…」
「…」
真っ暗な部屋に、開いた窓から風の音が響いた。
何気ない一言だったのに、しばらくなんの音もせず二人とも天井を見つめていた。飾ってないのに、風鈴の音がしそうな夜だった。扇風機の音が、ちょっとだけうるさい。
「俺」
「…」
「…付き合おうとか、言ってない」
「…」
「好きとかも」
「…」
「言ってません」
ちりん
ちりんちりん
サー
サーーーーーー
ちりんちりんちりん
だから飾ってないって。
ちり
ん
「…」
「…」
「…は?」
極端に大きな声が出た。体制はそのままで、イライラという音と共に焦りと変な汗が私の体を襲った。風の音が、小さく聞こえた。自分の心臓の音が変に耳元で聞こえて、私は鼻で笑ってもう一回
「は?」と言った。
彼は、返事をしなかった。
2
風鈴の音、爆音で聴いたことある?
私は今、ある程度安定した日常を送っている。もうホームレスみたいな時期も乗り越えてちゃんと働いていた。昼は、とあるレストランの正社員で、コミュ障も解決。友達みたいなのもある程度居た。みたいなの?
とんがってもいなかった。人には皆欠点があり、私だってそうだということを悟った。つまり前よりだいぶ大人になったのだ。
まあ、そんな事は今のこの状況と全く関係が無い話である。
朝。どこかの古臭いアニメみたいにわかりやすく小鳥のさえずりが聞こえた。
ゆっくり体を起こした。夢だと思いたかった。実際のところよくわからなかった。そういえば、コーンフレークがあまってたから目玉焼きとか簡単に作って朝ご飯にしようかなとか、関係ないことも考え始めた。彼が寝返りをうつ。それを、睨むわけでもなくじっとり見つめた。少し寝ぼけていた。彼の寝顔は普段の彼からしたらすごくブサイクだったがそれも可愛く思えた。窓から差し込む光が丁度良くてカーテンは開けなかった。原因不明の頭痛が何回も不定期に襲ってきた。わたしはじっとりと彼を見たまま、話しかけてみる。
「…起きれば」
「…」
寝起きのため声が少しかすれる。返事は無かったが、彼が目を開けた。
「…おはよ」
「…」
私は少しだけ試してみようと思った。
もう一度彼の隣に寝転んだ。
「好き」
小さい声で自信なさげにそう言うと、彼は
「・・・」
SHIKATO
頭の中でごみごみと、何かがいっぱいになってくのがわかって、とんがってた頃の自分が「やっちゃえよ、やっちゃえよ」って煽ってきた。何をだよ。心臓が無駄にバクバクと、あぁ、生きているってことね。
目をそらす様に、目を閉じた。まぁいっか。って思ってるつもりだったが
そのうち気がついたら職場の男の人の家に居た。だって来いって言ったんだもんっ。行くまでに色んなことを考えたが全て無駄なことに間違いなかった。「私はもしかしたらロボットなのかもしれない」だとか「もし明日地球が終わったらどうしよう」だとか「この先生きてて死ぬまで何人の人に何回怒られることがあるんだろう。やだな」だとかだった。気がついたらカズキにも連絡していた。自分を試したい気持ちでいっぱいだった。カズキからはすぐに返事が来た。あぁ、なんてくだらないんだろう。今の彼も例えば何かのはずみでお別れして、久しぶりに連絡をとることになったらちゃんと愛想良く接してくれるのだろうか。
「汚いでしょ」
職場の男の人は、アキと言った。アキさんは先輩で、背が高くてルックスも完璧でなんで彼女が居ないのか全くわからなかった。私のことをよく可愛がってくれていた。ので、家に来てみた。
「掃除してあげましょうか」
「や、いいよ。自分で生活できなくなる、人にしてもらうと」
「その気持ち、わかります」
「そっか。空ちゃんみたいなお子様にもわかるか。そんな気持ちが。」
「言い方悪い」
アキさんは、無邪気に笑って私のほうを見た。彼に対しての罪悪感は、なんだか無かった。アキさんに対してはそこまで猫を被ろうだとか、上目遣いをしようだとかいう気持ちにはならなかった。セックスをしようだなんてことも思ってなかった。ただ、彼に「他の男の人の家に行った」ということを何故かアピールするわけでもなく、そんな嘘をついていたかった。
とは言え、いつも職場が一緒で慣れ親しんだ仲なので、だらだらとしていても話は絶えなかった。職場の上司の悪口で、げらげら大爆笑していた。気がついたらまっ昼間だったのが、夕方になっていた。するとアキさんは時計をチラっと見て
「空ちゃんさ、夜ご飯作ってよ」
と言った。
「冷蔵庫の中身、なんかあるんですか?」
わざと間隔をあけずに返事をした。意識してるだとか思われたくなかった。現に、意識なんて全くしていなかった。
「勝手に見ていいよ。あ、そうゆうので作れるタイプ?」
「物による」
「やるぅ」
「なにそれ」
照れて笑った。なんだこれ。付き合いたてかよ。冷蔵庫を開けると、ほとんど何も入ってなくて噴出すように笑ってしまった。
「何もないじゃないか!」
「え?そう?」
「何食べてるんだよって、思っちゃった」
「俺の生きる源は、まかないかな。」
「ちっとも格好良くないですけど」
「買い物でも行く?」
そこから一緒に近くのスーパーに買い物に行き、お金はアキさんが出してくれた。彼と買い物に行くときはだいたいが当たり前のように割り勘だったので、やっぱり大人に見えた。遠まわしに、自然な流れでアキさんの家に泊まることになっていた。冷やし中華を作って、食べて、私の嫌いな23:45だった。まだ、終電には間に合う。
「終電が」
私がわざと時計を気にして言ってみた。アキさんは
「泊まってけばいいじゃん。面倒くさい」
と下心もあんまり無い様子で、眠たそうにアクビをしながらテレビを見ていた。その様子を見て安心した訳では全く無いが、家に帰ってしまうと『俺付き合ってとか言ったっけの件』についてひどく思い悩んで寂しくなってしまいそうだから泊まることにした。
アキさんは私に普通にシャワーを貸してくれて普通にベットに寝かせてくれた。おまけに私に気を使ってアキさんはソファに寝ていた。イビキが聞こえた頃、カズキとメールをした。
近いうちに呑みに行く約束をした。ちょっとだけ、面倒くさいと思ってしまったくらいでなんのときめきも無かった。
なんとなく私は色んな男と遊ぶことで、彼だけが悪くないようにしたかったのかもしれない。アキさんの家のベットの中で、彼の夢を見た。びしゃ濡れのブサイクな私に雑に財布をほうり投げる彼の夢。財布の中身は打ち出の小槌を使ったかのようにお金が増えていて、私の頭は世界のどんな出来事よりきっとパニックになっていた。
夜中に目が覚めた。ふいに、叫んでしまいたくなった。いつかの、心の状態とまるでそっくりな気がしたが昔の私とは違う。
ぼーっと昼間の暑苦しい公園を歩いた。アキさんとは、結局何事も無くだったがなんだか気持ちが楽になった。今とっても嫌な事があって甘えてしまうとすればきっとそれはアキさんだ。
カズキから着信が来た。携帯の画面をじっと見つめてしばらくぼーっとしていた。私は『拒否』のボタンをとっさに押してしまい、携帯を地面にぶん投げそうになった。気持ちが楽になったと口では言っているが、無性にイライラしていた。生理でも来るのかしら。
部屋を掃除してたら夕方になって、街を探索することにした。無駄に電車に乗って、新宿歌舞伎町まで行った。昔、とんがってるときはよく六本木のクラブに突っ立っていたが、新宿を探索したことは無かった。
ナンパされでもしたらついて行こうと思っていたが、何故か話しかけてくるのは外人ばかりで何を言われても全て「ゴールデンボール」と答えた。
ふらふらとネオンがぼやけて見えてきそうだった。落ち着きそうな居酒屋を発見しても、何か違う。ふと、お父さんのことを思い出した。お母さんが私の目を見つめて泣いていた。
小さい頃のお父さん像は立派そのもので、愛情もたっぷり貰っていたうえに、お父さんって最強で無敵なんだって思っていた。子供にそう思われる父親って言うのはつまりは、極上の父親なのだ。お母さんについて考えるのが嫌なときはお父さんの極上の部分を何回も思い出しては思い出に浸っていた。忘れてたわけではない。お母さんは私が中学校に入ったくらいからたくさんお父さんに泣かされていた。
お父さんは最低なわけではない。お父さんは、弱いのだ。私みたいに、きっとコミュ障で、きっと私より少しだけ人間からずれてしまっているだけ。悪いことじゃないんだ。お母さんは、きっと普通の人間だった。子供に涙をたくさん見せていても、きっと強くてたくさん我慢していた。それが出来てしまっていたから甘えるところが、私しか無かったんだ。
目の黒いお母さんの優しくて切ない笑顔が浮かんだ。
ふいにたどり着いた。
ローマ字で、『TARUTO』とだけ書いてある古びた看板の前で立ち止まる。メニューの提示も無く、階段だけが地下に繋がっていた。明らかに怪しくて、明らかに暗がりだった。下を覗き込むと、少しだけ賑わってそうな声が聞こえたので、私は気がついたら階段を降りていた。少し重たいドアを開けると耳がキーンとなるほど爆音の意味のわからない歌が耳の中を占領した。小さなライブハウスのようなショーパブのようだった。奥にいる黒人のオカマのような派手なピアスの大きな人が、壁にもたれながら私を舐めまわすように見つめていた。
何故か居心地がよかった。私は、しばらくぼーっと彷徨ってから近くにあるワインの瓶を勝手に一気に口に含んだ。そして、我慢できずその黒人にぶっかけてしまった。
気がついたら、ステージで歌を歌っていた。
赤いドレスに、赤いリボン。どこか見たことのある服装で、赤い口紅に、トマト片手にいやらしい照明。それで気がついたら、お金を貰っていた。体のストレスを取っ払うように大きな声で歌った。トマトを壁や地面やそのへんの客に向かって投げてしまいたくなったが、我慢した。
そっか
おとうさんは、おちこぼれだったのか。
3
彼と本屋さんに来ていた。
一番厚い『広辞苑』とかいう本を顔面にぶん投げてやりたくてそればっかり考えていた。彼は何事も無く何故か小学校で読むようないろんな図鑑を買っていた。帰り道、すごく重くてクレームたれてやりたかった。
「ねぇ」
「あ?」
「なにするの」
「ひみつ」
「あっそう!」
彼の家に帰った。大きな紙を何枚もつなげて、図鑑のなかから好きなどうぶつや生き物だけピックアップして描いた。
「わかった」
「なにが」
「これ、アートでしょ!」
「…そ!」
私はジャマをするわけではないが、その大きな紙に自分の好きなどうぶつも描いた。おまけに人体模型の絵を超下手糞に描いて、彼に引っ叩かれた。一人でそのことについて大爆笑していた。人体模型には、×が描かれた。可哀相。なんて可哀相。人体模型。
なんだかワクワクした。大きな紙も、すぐに埋まってしまった。彼が描いた方には変な虫やら魚やらものすごかったが、私の描いた方はゾウやら恐竜やら強くてごっついものばかりだった。
人体模型、大きく描き過ぎたわね。
描き終わって夕方になると、彼は突然「疲れた」とか言って後ろから私を抱きしめてきた。ドキッとした。そうだね、これがそうゆうことだよね。と思った。カズキと呑みに行くの、やめようかなあとか必死に考えた。だって絶対につまらないから。100パーセントだ。
私がバカなのか、それとも考えすぎなのか。そのラインはえげつないほどハッキリしなかった。
「セフレ?」
突然顔を見てそう言ってみた。少しだけ、怖かった。
「あ?なにが?」
「…」
「…は?」
「わたしとあなた」
冷静を装ったが、さすがに少しだけ目をそらした。彼は、表情も変えず淡々と言った。
「お前、俺の名前知ってんの?」
「…」
知らない。
「じゃー山田太郎で」
彼は少し機嫌悪そうに私を馬鹿にしたように微笑んだ。ほんのりと憎しみが一気に私の頭まで登ってきて、一気に急降下したので何も言う気にはなれなかった。名前を聞く気も起きず、彼もそのまま「腹減った」だとか言って教えてくれそうに無かった。こいつはきっと
悪者のボスか何かでしょうね。
こんなにも一緒に居て、居心地だけよければよかったなんて。名前も知らなかったなんて。言葉がこんなに大切だったなんて聞いてない。頭の中で、いかやきの看板がスローモーションで近づいてきてうっとうしかった。
聞いてないわよ!!!
なんだか泣き叫んでしまいそうになった。
誰か私に、広辞苑を下さい。
4
カズキに会うのは、二年ぶりくらいだった。
昔みたいにすごくお洒落をして家を出た。ピンクのワンピースに、最近買った大き目のネックレス。香水も忘れなかった、つけすぎず、ほのかに香るように。カズキとは言え、久しぶりに人に会うというのはドキドキした。いつもみたいに自転車をぶっ飛ばすわけでもなく駅までゆっくりと歩いていった。どっちにしろメイクを直しても直しても、夕方とはいえ真夏の気温なので汗ばっかりかいてしまう。少しまだ空は明るくて蝉の音がかすかに聞こえた。
何故かカズキのもとに向かう電車に揺られてると思い出す。お父さんが借金をして、私の目をまったく見ずに毎日ひ汗で顔を曇らせてたあの頃を。すっごく悲しい思い出だった。見逃してあげるから、こっちを見ておくれ。あなたの可愛がっていた、空だよ。見える?どんなに幸せな家族だって、そんな一面はあってしょうがないんだ。むしむしと、電車を降りた瞬間の蒸し暑さがなんとなく懐かしい気になった。
カズキに電話をかけた。コールの音を聞いても、緊張はそこまでなかった。
『もしもし』
懐かしい声。
「もしもし、ついた、久しぶり」
わざと少しだけ高い声で話した。改札を出ると、ロータリーの近くできょろきょろ周りを見渡すカズキが居た。髪の毛が真っ黒で、短くなっていた。あんなにガリガリだったのに少しだけ太って人並みの体系になっていた。なんだか、懐かしい匂いがするような。カズキは、たくさんきょろきょろしてる割には私を見つけられてないようだった。相変わらずバカだな。
「おいっ」
トンっと肩を押すと、びっくりした顔をしてこちらを見た。私は微笑んだ。カズキは照れて目をいったんそらしてから
「久しぶり」
となんだか気まずそうだった。私は、照れることもなくずっとニコニコ微笑んでいた。一瞬だけあの頃の『空のこと、大好きなのに』と言う素朴に切ない表情のカズキがフラッシュバックしたが、気のせいだと自分に言い聞かせた。
来たときよりだいぶ外は暗くなっていた。安いチェーン店の居酒屋に入り、どうせ割り勘なんだろうよ、とか考えていじけたような気持ちになった。そうよ。本当のバカは私です。
しばらくお酒を飲んで昔のことや、今のことを話した。私はビールだったが、彼はカシスソーダばっかり飲んでいた。つまりは、変わってねえなってやつね。
カズキは、今美容師の勉強をしているらしかった。何故美容師の勉強をしていて太るのか全く理解不能だったが、学生ということで飲みすぎたんだな、と思った。なんだか、楽しそうで羨ましかった。学校の話をしているカズキの目は、きらきらしていた。前までの私なら、微笑みながらも「なんでお前ばっか楽しいんだよ、むかつく」とか思ってたかもしれないが、夢を見つけたカズキになんだか嬉しくなった。素敵だな、と素直に思ってしまった。
しばらくたって私はほろ酔いだったが、カズキは何故かベロベロに酔っ払っていた。しだいに「めんどくさい、どう言って家に帰ろうか」と考えながらカズキの話を全く聞いていない時間が訪れた。その中の選択肢に、今この男をぶん殴って気絶させるか、ベロベロにぶっ潰して寝かせるのもありだな、とやっぱり私は欠落していた。
「先輩がちょーむかつくんだぁ、そら、どうする、そら。」
うっせーなぁ。
「頑張ってるのね」
「そらーーーっ!どうする!」
「こら静かにしなさい」
「そらさぁ
…なんで俺を振るんだよ」
なんでと聞かれても、わかりませんか?
「俺は今日、決めてきたんだ」
うつろな目で、カズキがこっちの目を見つめた。
「何を?」
「俺、」
「うん」
「もう、終電無いぜ」
「…」
「…」
「すいませーん。タクシー呼べますか?」
カズキが、うちに来ました。
私はといえば昔ほどカズキを面倒臭がる訳でもなく、先輩に囲まれて常に気を張って疲れてるのかもなぁと本当に親みたいな気持ちで居た。よーく考えてみると、もしこれが彼にバレて別れを切り出されるのもバカバカしい話だが。
「お母さん居ないんだ」
明らかにラッキーという顔をするカズキに若干イラッとはしたが、それも一瞬だった。二年くらいもの時を経て、他のいい女が居ないもんなのか、こいつは。お母さんやお父さんの悲しい話を打ち明けるのもなんだかすごく面倒なので、とにかくさっさとコイツを寝かせよう。
「風呂入ってくるね。寝てていいよ」
しばらく考えた末、私がそう言うと何故か寂しそうにカズキは私を見つめた。人と長く見つめ合うのはあまり好きでは無いので、目をそらしそうになるとカズキはこっちに歩いて来て私を抱きしめた。
「一緒に入ってもいい?」
面倒くっっっさ!!!!!!!!!!
「寝てなよ」
「…お願「寝ようか」
極端に大きな声が出た。悪い癖だ。私はさっさと風呂に入ったが、落ち着かずに居た。あのバカが突然入ってきたらたまったもんじゃないと考えていた。あぁ、なんて落ち着かない。ていうか、なんて疲れるんだ。とっさに彼の顔を思い浮かべた。彼に一緒に入ろうと言われたら、即効入るのに。というより彼はそんな面倒なこと絶対に言わない。
脱衣所で体を拭いて、髪の毛を乾かした。恐る恐る部屋に戻るとカズキは寝ていた。私のベッドで、大の字で。
思い出した。彼が一番最初にうちに来たときは、気を使って彼はソファに座って小さくなって寝てた。私は、ベッドも無視して隣に寝たけれど。
そんなことを考えていると、カズキの目が開いた。「げ」と思ってしまった。
「寝なさいよ」
そっちの気を反らそうと、髪の毛を整えるように鏡の前に座った。髪の毛にくしを通した。私の部屋の赤いオレンジのライトが私の頬を照らす。彼にいつだか買ってもらった、メリーゴーランドみたいな置物が私の頭の中で高速で回っていった。ぶらぶら何故かぶら下がる気味の悪いピエロ崩れみたいな小さな人形にライトが当たって余計不気味だ。
いつかみたいに一生懸命全く違うことを考え始めた。なんだか懐かしくて笑い出しそうだった。鏡越しに、カズキが近づいてくるのが見えた。違うって。違うってば。来ないで。来ないで~~~~~~~~~~~
「そら」
仕方なく、セックスをしたわ。
何度も彼の顔が浮かんでめまいがした。あんたが悪いのよ。あんたが。彼にも同じことを言われてる気になった。メリーゴーランドの、置物に体が銀色の80歳くらいのオッサンが座っていた。まわれ!まわれよ!って叫びながらなんだか楽しそうに笑っていた。オッサンは、しばらくピエロ崩れたちを眺めていたけどそのうち振り返ってカズキに抱かれる私を見た。
彼にそっくりな顔をしていた。
気がついたら、タルトという馬鹿馬鹿しい名前のショーパブでいつも通り歌っていた。ささやくように、騒ぐことも無く。冷たくて、静かな空気が私の目の前を行き来する。ああ、なんて居心地の悪い。この世のどこもかしこも、360度居心地が悪かった。イライラしていたが、私の居場所は彼の隣だけだったのかもしれない。
ガッチャーン!!
「…あっ…すいません。失礼しました」
割れたお皿を眺める暇もなかった。
近くに居たアキさんが笑っていた。いや、笑ってくれていた。他の従業員は睨むようにしてこっちを見ていたが、近くに居たお年寄りのお客さんは微笑んで「大丈夫かい」と言った。困った顔をして頭を下げた。きっと私は無意識にぼーっとしながら深刻な考え事でもしてたに違いない。接客と言う名のポーカーフェイスで誤魔化していたのだ。指からトロリと出た血を見て、母のいかやきみたいな足を一瞬だけ思い出した。落ち着こう。落ち着け落ち着け。深呼吸。
「大丈夫か?そらちゃん」
キッチンに入って指を見つめた。お皿も指も割れた。アキさんが、私を心配そうに見る。
「全然、どうってことないです。ごめんなさい」
指をとっさに隠しながら淡々と言った。
「ぼーっとしてるの?」
「いや、別に、それほどでも。ええ。」
「そう」
深く何も聞いてこないのが、アキさんのいいところだった。アキさんは私の指をちらっとみて大げさに心配もせずに絆創膏を探しているようだったが、それもあまり気にとめず私は忙しい店の中を早歩きで動き回っていた。
なんだか、歌でも歌いたい。今日は帰りに、彼が迎えにきてくれる約束だ。そこで聞いてみたいもんだわ。
お兄さん、罪悪感ってなんでしょう。
5
がたんごとん。
彼が居る。気が狂ってしまいそうだった。ピアノの音がする。それも、すごく上手な演奏で、何の曲かわからない。
「何」
「なにが?」
「疲れてんじゃん」
彼がタバコに火をつけた。彼がタバコを吸うようになったのは最近だ。
「疲れてないよ」
「連勤続きだったっけ」
「いや」
携帯が鳴った。メッセージで、カズキから『やり直さない?』という文が軽々しく来ていた。一瞬見てすぐに閉じた。彼は、何も聞かなかった。むしろこっちも見ずに、何も気にして無いようだった。こっちも、こそこそ隠す気はまるで無かった。
静かな私の家に向かうまでの公園で、ベンチには誰一人座ってないどころか人一人見当たらなかった。夜の公園は少し涼しく感じた。
彼の横顔に街灯が当たってつやつやと、光っていた。私の顔は今、彼の顔の影で暗い色に染まっているかもしれない。彼の黒いティーシャツに気持ちの悪い熊の絵が描いてあって、首をかしげた。ちょっとだけにやけた。
「歌いたいわ」
私が言うと
「…歌うか。あーーーーーー」
「うっさいなぁ」
「あぁ」
「涼しいね」
「確かに」
「座る?」
気がついたらベンチの近くまで来ていたので、ベンチを指差した。彼はこっちの目を見て、なにかたくらんでるみたいな笑顔を見せた。
ベンチに座り、さっきより近くで彼の顔を見ると、カズキの顔が何故か思い浮かんで本気で吐き気がした。携帯をもう一度見た。のどに何かが詰まってる感覚がした。
「眠たい」
「涼しいからじゃない」
「うん、ねむい」
私は彼の肩にもたれかかった。彼は無表情のまま正面を見つめていた。
「なんか歌ってもいいよ」
「今は歌いたくない」
「あっそ」
「疲れたの」
「疲れてないって言ってたじゃん」
「あのさ」
「…」
「太郎さ」
「…」
「…」
「いいけど」
「やっぱやめた」
それから彼は無言で何も喋らなかったので、少し疲れたフリをして「帰りましょう!」と言った。聞けばいいのに。「お名前は?」のその一言が聞けないのは不安すぎるからだった。昔同じ場所で、私は野生動物みたいに彼を威嚇してたっけ。そんなようなことを、ふと思い出した。帰って寝る前に彼とセックスをしたがこの前のカズキとの夜と全然違った。何故か幸せで嬉しい気分になった。だが、罪悪感は無かった。
次の日の朝、なんだか具合悪くなりそうになるのを堪えて、カズキに「ごめん」と返事をした。『また会ってくれる?』とすぐに返事が来たので私は「もちろん」と返した。ああぁ。何がしたいのかしら。私、どうしたいのかしら。
その夜はタルトの更衣室の鏡で、自分の顔をじっくりと見つめていた。赤い口紅を塗った。ここのオーナーの私物だった。安っぽいビーズで出来たのれんをくぐって、真っ黒なオカマが入ってきた。そんなことも気にせず、私は自分の顔を見つめて何重にも重ねて口紅を塗っていた。
「やけにでもなっているの。マリンちゃん」
この方は、タルトというこの店のオーナーだった。名前はもちろん、タルトさん。店で、私の名前はマリンと言った。一番最初にココに迷い込んだ夜。イライラした私はこの方に赤ワインを口から思いっきりぶっかけた。
黒い顔が赤黒く染まって、何もリアクションは無かった。吸ってた煙草の火も消えたようで、大きなピアスから赤い不気味な雫がたれていた。暗い店内で、ピアスだけが濡れてテラテラと光っていたのを思い出す。私はタルトさんから目を離さなかった。タンクトップの端からちらちらと刺青なのか、タトゥーなのか見たことも無い動物がうごめいてた。そんなこと、どうでもよかった。ワインをぶっかけたことだって特に、意味なんて無かったが
タルトさんはあの夜、色っぽく口角を片方上げた。
「やぁねぇ」と言いながら私の頬を思いっきり殴った。すごい力だった。私は壁までぶっ飛んだ。しばらくして、笑いが止まらなくなった。久しぶりにたまらなく面白いと思ったのだ。
タルトさんに裏に無理矢理引きずられてるときに、スポットライトが当たったステージの上を見た。綺麗な女の人が、変な格好をして歌を歌っていて。私はそこから目が離せなくなった。何故か赤いワンピース姿のお母さんが連想されたが、私にはステージの上が輝いて見えた。
裏の更衣室に連れてかれたはいいものの、ずっと笑いが止まらなくて困ったものだった。タルトさんは、そんな私に怒鳴るわけでも殴るわけでもなく。不思議そうな顔もしないでじっとりと見ていた。
しばらくして急に笑いが止まると、私はタルトさんに話しかけた。
「きらきらしてたわ」
「?」
「ステージの女の人」
「そうゆう場所なの」
「こんな部屋に連れてどうするつもりよ」
「ぶん殴ってぐちゃぐちゃにしようと思ったの」
タルトさんはなんの迷いも無くそう指の骨を鳴らしながら、私の目を見つめていったので私は噴出すように笑った。
「まさか、タルトってあなたの名前ですか?」
「そうよぅ。可愛いでしょ」
「うん!可愛い!」
心からそう頷くと、タルトさんは妖艶な笑みを見せた。
「お子様にもわかるのねぇ。やだわぁ。嬉しい」
「なんでぶん殴って、ぐちゃぐちゃにしないの?後でするの?」
「しないわよ」
「なんで?」
タルトさんは真剣な顔で、私の目を見た。
「もうぐちゃぐちゃよアンタ」
失礼な。
またもや笑いが止まらない。タルトさんはオカマなのに、どの行動も色っぽくて魅力的だった。肩から、カタツムリと虎とトカゲが混じったような意味不明なタトゥーがちらちらと見えた。こうなってみたい。と思った。私も、きらきらしたい。始めてそんな事を思ったので、私はとっさに
「手下になる」
と言った。
「手下?」
「子分にしてよ」
それから、なんとなく私がうんざりしてることをタルトさんに話しまくってみた。初めて、こんなに人に心を開いて話をした。タルトさんは、リアクションがいちいち大きかったが、最後には静かに微笑んで私を子分にしてくれた。マリンと言うのは、タルトさんがつけてくれた名前だった。
6
彼の仕事は、デザイン関係だった。
これまた、私の職種とは全然違ったが彼はいつも、仕事するのが楽しそうだった。私も私なりに、だんだんステージで歌うのが生きがいになってきていた。いつもと違う自分になるために名前を変えて演技をして、自分には誰も知らない顔がある。というだけでなんだか楽しい気分になった。
「マリンさーん」
夜、帰るときに高校生くらいにも見える男の子から突然手紙を渡された。いつもステージを見に来てくれているようだった。私は少し嬉しくなって頭を下げた。レストランの仕事なんかよりずっとやりがいを感じるようになっていた。
手紙の内容は、『いつも憧れてステージを見ていました。これからもマリンさんらしく、頑張ってください。応援しています。』という内容で下の方に『よかったらご飯に行きましょう』と電話番号が載っていた。
見た目は少し幼いが、昔のカズキみたいに痩せていて長身で顔は目が細めの童顔だった。タルトさんに相談したが、「行って来なさいよ、出会いよ、出会い!楽しいじゃない。そうゆうの。」とウキウキして背中を押されてしまった。
どうしたものか、気がついたら私は懲りずにカズキとランチをしていた。
カズキは、ようく見ると前より格好良くなっていたが、そんなことはまるでどうっっっでも良かった。もう一回会ってしまった事で調子に乗ったのか、テンションが無駄に高くてしまいには
「なあ、今日空の家行ってもいい?」
と真昼間からこっそりと聞いてきたので、私はそれを真顔で見つめながら
「ダメよ!!」
と急に果てしなく大きな声で叫んだ。カズキは焦ったように周りを見て口に人差し指を当てた。なんの前触れも無く突然、カズキの昔からのウザさに耐えられなくなり秘めてたものが小さく爆発した。
「泊めてだなんて!!そんな、付き合っても無いのに!!泊めてだなんて!!」
大きく、爆発した。
「しっ、しっ。」
「チャラーーーーーーい!!!!!」
ひたすら大声でそう叫んで、まわりでコソコソ噂をするお客様方の反応を見てしまいには笑いが止まらなくなった。けらけらと子供みたいに足をばたつかせて笑った。この店のハンバーグは、うまくて美味しくて、うまかった。なので、今度タルトさんでも連れてこようと思った。今日も割り勘か。と財布を出すと、珍しくカズキが私の手を止めた。
「払う」
しばらく見つめあってしまい、私はまたもや笑いが止まらなくなり大爆笑した。何が払うだよ。ここまで一緒に居て、誕生日もクリスマスも割り勘だったのに、払うですって。無邪気に笑う私を見て、カズキは何故か嬉しそうだった。店員さんにこっそり「また来ます」とささやいて、私たちは店を出た。
「そらさ」
外は相変わらず蒸し暑くて、もう可愛い子ぶるのがめんどくさくなっちゃった私はカバンを振り回していた。
「うん」
「変わったね」
「え?」
「昔はもっと冷静で、まぁ昔も可愛かったけどなんていうか。子供みたいになったね」
「変わってないよ別に」
「変わったよ。今のほうがいいよ」
言い終わる前に、振り回していた鞄でカズキの頭を思いっきりぶん殴った。本質が見えてないだけで何を自分を棚に上げて言ってんだよ。本質を見せたくないような偏見という壁を持って、なんで上からそんなことを。
「変わってないよ」
「・・・痛いよ」
「だって昔から私はカズキのことぶっ殺したいだとか死ねばいいのにだとか思ってたよ。」
「痛い」
「聞けよ」
少しだけ腹が立って、低い声が出た。私は、カズキの目の前に回りこんで、にっこりと笑った。
「今度会うときはディナーね」
カズキは頭を抑えながら呆然と私を見つめていたが、私は早歩きでその場を去った。別にイライラはしなかったし、本当に暇があればまた会ってやろうとか上から思っていた。しばらく歩いてから駅につく前に、あの手紙を鞄から出した。よーく見ると、下のほうに【相田 元気】と名前が書いてあった。やつの名前は、元気というのね。
人生ではじめてのファン。少し緊張しながら電話をかけた。
長めにコールが鳴って、『もしもし』と寝起きの声が聞こえた。
こんな時間に、寝起きかよ。
「もしもし、マリンです。急にごめんなさい」
『あぁ!!』
飛び起きたようだった。
「寝てました?」
タルトで私は、卑猥な唄ばっかり感情こめて歌っているので何故か元気くんには気を使うことも猫を被ることもせず話すことが出来た。第一、服装も化粧も母親の生き写しで、それを知らずにファンになってくれるだなんて都合が良かった。
『どうも。まさか電話来るなんて!うわぁ!!』
「私なんかにそんなに緊張しなくていいよ」
『いや、もういっぱいいっぱいっすわ!』
「今日、夜ステージ出るんだけど早く終わりそうだからご飯でもと思って」
『えっ?!いいんすか!!』
若いなぁ~。
「いや、私友達少ないからさ。楽しくいこうよ。」
『いきますっ!ステージも、見に行きます』
「連絡する!」
私にしては珍しく、いい子だなあと心から思っていた。私は、男の子とたくさん遊びたかった訳でも、遅れてきた発情期な訳でも無い。ただ寂しくて一人の時間を少しでも減らしたかった。つまりは普通の人間のお話です。電車に乗って蒸し暑い部屋に帰り、窓を開けた。携帯を見た。『熱中症で死んでない?』と彼からメッセージが入っていて、気の抜けた気分になった。私が寂しいのはあんたのせいよ。そう思いながらも、誰と会っても一番彼に会いたい気持ちで居た。お前等馬鹿にすんなよ。私には本命が居るんだぞ。と思っていたが、本命には馬鹿にすんなよ、男はお前だけじゃねえ、優しくしないとどっかに行っちゃうよ。って思っていた。これは
普通の人間の、お話なのでしょうか。
そういえば、うちのお父さんと、お母さんの恋愛事情はきっと他の家の親と比べると果てしなく良かった。私が生まれて、お父さんがヘマをするまではバカップルを永遠と見ているかのようにラブラブだった。愛情とは、目に見えないものだとよく言うけど私にはよーく見えていた。父から、子へ。母から、子へ。父から母へ。母から父へ。全部見えていた。子から両親への愛情も、目に見えてただろうか。
きっと今の彼と私が長く一緒に居ようと心に両方誓ったとしてもああなるのは難しいことである。つまりは、綺麗事は嫌いだが運命っていうのはいい意味でも悪い意味でもあるのかもしれない。例えば私とカズキは出会うことで私のイライラが止まらなくなるというそれはそれで運命と呼んでもいいのよ。
相変わらずじっくりと更衣室で鏡を見つめていると、タルトさんがまた心配そうに言った。
「最近生き生きしてるから、変に。マリンちゃん。」
「そう?」
「変になったらだめよ」
「ありがとう」
タルトさんを除いても、ここの店の女の子や、オッサンも居るけれどいい人たちばかりだ。タルトさんが私を心配すると、みんながみんな流れに乗って心配そうに私を見た。お互い、何も聞かないけれど。こんなに目立たない場所でオーナーがオカマでなんの店かもわからないのに働いているのはきっとみんな訳アリに違いない。そんな事はなんとなく察していた。全員がドレスな訳でもなく、セーラー服でステージに立ってるのも居ればオッサンなんて黒い仮面をかぶってアコースティックギターを弾いているのだ。不思議な空間だが、悪い人は一人も居ない。
今日は、最初にタルトさんが歌う日だ。私はいつもこの日を楽しみにしていた。
「そういえば、私ってなんでマリンちゃんなの?」
私がそう言うと、タルトさんが、ウイスキーのロックグラス片手に話し始めた。
「アタシね」
「…」
「栗がすきなのよ、栗のことを考えていたのあの時。アンタにワインぶっかけられたあのとき。だから頭の中で、とげとげの栗を何回もあんたに思いっきりぶつけて血だらけにしてやりたいだとか考えてたら。話してるうちにこの子、絶対に、マロンって名前にしたいって。したら、」
「…」
「噛んだのよ。マリンって言っちゃった。仕方ないわよね、まぁいっかって。やっだもう」
途中で、聞くのをやめて口紅を塗っていた。
真っ暗な少し狭い空間がたくさんのキチガイで埋め尽くされてた。この中にだったら、もしかしたらティッシュを噛んでる人が一人か二人いるかもしれないとまじめに考えていた。ガムを噛んでそうな一人一人に、「あーんして口の中見ーせーて。」って言いたかった。私は生まれてから出会った中で一番のキチガイの格好をして隅っこのカウンターで色んなお酒を楽しんでいた。バーテンダーは爆発頭の陽気なおじさんだったが、この人はきっと普通の人だ。楽しく会話をしていると、『ヴーーーー』と古臭いブザーが鳴って、みんなステージに目を向けた。スポットライトに埃が浮いているのを私はぼーっと目で追っかけていた。そのうち、スポットライトの中にいかつい黒人が入ってきた。耳には大きめのピアスがいつも通りじゃらじゃらと光っていた。背が高くて、顔立ちがはっきりしていて陰影が目立つ。私はお酒を一口飲んで、うっとりとステージを見つめていた。なんて色っぽくて、なんて格好いいのだろう。タルトさんは、流し目で遠くから私を見下すと、ニヤリと口角を上げてみんなにお辞儀をした。
いつもの陽気なタルトさんは、居なかった。
ワクワクする。私は唾を飲んだ。のどが熱くなって、度数の高いお酒の香りがほんのり鼻から抜けていく。タルトさんは、マイクも持たずに歌い始めた。そこからは、聴き入って、魅入って、もう虜そのものだった。誰一人身動きをとらなかった。タルトさんは私みたいに感情にまかせて歌うことはしない。静かな歌声だが感情がすぅっと入ってくる。伝わってくる。タルトさんの人生は、一体どんな物語だったのだろうか。どんな辛く悲しく打ちひしがれるような想いをしたのだろうか。きっと、誰もがそう思うほど切ない歌声で涙が出そうだった。
タルトさんのステージが終わって、みんなワイワイと騒ぎ始めた。次のステージまでは、まだ時間がある。しばらくカウンターでまた、お酒を飲んでいた。何故か目の前にあった顔が溶けそうなピエロの蝋人形と目が合って、背の高い椅子に座りそれがライトに少しだけ照らされてるのを見つめていた。目のところが剥げてて、ホラー。少しだけ酔っ払っていた。静かに、首を傾けると「うそでしょ」と後ろから声がした。
「空ちゃん?」
振り向くと何か見覚えがあるような無いような、同じくらいの年の女の人が居た。茶色くて長い髪の毛を巻いて、団子鼻でどこかダサいような派手な色のワンピースを着ていた。何か見たことあるようでないような。私がキョトンとしていると、彼女は笑った。
「うっわ、マジ?大丈夫?」
「…」
馬鹿っぽい喋り方で、少しずつ私の記憶が蘇ってきた。それはまだ私が若くてとんがっていた頃の、顔面合成を見事に成功させ頭を何かで毎日二時間くらいかけてわざわざ大爆発させていたような…
『友達になろう』
「…ああ」
極端に低くて大きな声が出たので向こうもびっくりしたようだった。彼女は、見た目はすっかり落ち着いていて小さくなったようにも見えた。どこの毛で作られてるのかわからないようなバサバサの付け睫毛も卒業していて頭も爆発していなかった。当時、人の名前なんてそもそも聞いてたとしても全く興味が無かったので覚えてるか覚えてないかという以前の問題で名前はわかりませんが
「綺麗になったね」
素直にそう言うと
「えっ?!…変わりましたね?なんか。」
「…」
「でも、本当に大丈夫?」
「なにが?」
「あれ、これ、言っていいのかな?・・・洗脳されてたじゃん?」
「…」
「その様子じゃ…」
デリカシーの【デ】の字が落ちてないか必死に彼女の周りを探す夢を見た。遠慮がちに、どこか退いていて馬鹿にしてるかのように苦笑いするその顔は昔と変わっていなかった。私は表情も変えずとっさに頭で自分の姿を客観視してみた。母親の、生き写し。自分で精神病院にぶちこんだ母親の、生き写し。
こんなに面白いこと他にないでしょう。
また発作のように笑いが止まらなくなりそうなのをぐっと堪えて、つばを飲んだ。
「なんでここに?」
「えー、タルトって書いてあったからスイーツ系かと思ったのよね。違うんだもん。でも、お酒飲めるし、楽しいからいいかーって」
初めて来た様だった。発言の馬鹿っぽさも昔から変わらなかった。明るいトーンで話してニコニコはしているが時折私の頭の先からつま先まで何か意味深に舐めまわすように物色するところも変わらなかった。気味が悪いとでも思っているのだろうか。
彼女はブサイクの癖に偏見の塊で、きっとこの世で最も人間としてどうってことなかった。とんがり終わったというのに、それ前提で話してしまっていた。今更憎しみも哀れみも無いが彼女が着ているワンピースに墨汁でもなんでも洗濯しても落ちないヤツをぶっかける妄想を繰り返しながら目を見ていた。
「まだオナニー大好きなの?」
これまた、馬鹿にしたように笑う彼女に
「うん」
と適当に返事をした。彼女は鼻の横をぴくっとさせ「相変わらず変わってるね」と言った。私は「そうそう参っちゃう」と適当に言いその場を離れた。出番の時間だ。ロックグラスを片手に持ったまま、ステージに上がるといつも通りお辞儀をした。ステージの隅にあらかじめ置いてあった双子のカエルの蝋人形をもう片方の手に持ってニコッとすると小さな歓声が上がった。元気くんが手前側に立っているのがわかった。私を見て、瞳を子供みたいに輝かせていた。私は目であいさつした。
「今日は、ついてる方が三人。三人も居るわ。この子達、一匹ずつあげちゃう。三人目は、お楽しみ。ひみつ。私、ラッキーだよって思う人。一番可愛い顔して手を挙げてくれたら、一匹ずつ、あげちゃう。三人目は、乞うご期待。はい、せーの」
私が舞台口調でそう言うと、たくさんの人が手を挙げた。その中に元気くんも居た。ピンと腕を上に一生懸命伸ばしていたので、笑いそうになった。「ひとりめ」と片方のカエルにキスをして元気くんに渡した。きらきらと、すごく嬉しそうだった。
もうひとつは、目が合ったタルトさんに微笑み「今日のトップバッターね」といって「ふたりめ、私の師匠」ともう一匹のカエルを投げた。タルトさんは「やだっ」と言って焦って床に落としたので、会場に笑いが漏れた。
「サイゴに」
と私は観客を見下ろす。にやにやしながら、キョロキョロと周りを見た。手を挙げる客の中に埋もれて、苦笑いをする元顔面合成女を発見した。ひいたような、哀れんだような顔で私を見ていたので私は深呼吸をしてロックグラスのお酒を飲み干した。グラスの中の大きな丸い氷がいやらしい音を立てて、私は彼女の方を無表情で目を見開いて見つめていた。彼女はそれに気づいて、恐る恐る目をそらしたので、私は笑顔を見せた。
「さんにんめ」
三人目は決まっていた。とっさに氷を彼女めがけて投げた。彼女は「キャー」と言って涙目で尻餅をついていた。周りのお客様は、悲鳴もあげなければ何も言わなかった。元気くんはと言えば、そんな私に喜んでるようにも見えた。私は大笑いして、今夜も気持ちよく歌い始めた。
7
「それで?」
私は両手で頬杖をついて上目遣いでそちらを見つめた。元気くんはキラキラした目で私のことを私の目の前で嬉しそうに話した。早めのステージ終わりに焼き鳥屋さんに来ていた。どこか懐かしい雰囲気の小汚い場所で、狭い店内に唯一あるテーブル席に座ってお酒を飲んでいた。デートに来るような場所では決して無いが、どこか二人とも落ち着いてしまったようだった。
「マリンさんはすごいっす、人間が丸出しで。全開で。」
「私のことそんな風に言う物好きな人、きみぐらいだよ」
「そんなこと絶対にない!」
「あるんだなーそれが」
元気くんのきらきらした目で褒め称えられると、自分が黒くて心が汚いのを隠してしまいたくなった。それかこの場ですっごく悪いことをしてやろうか。元気くんはどんな顔をするんだろうか。とは言え、私は珍しくベロベロに酔っ払っていた。必死に隠そうと得意の冷静を装っていたが、お会計の際立ち上がった瞬間ものすごい立ちくらみに襲われて元気くんに支えられた。外に出てからはぐわんぐわんと辺り一面揺れていた。急に走り回ったり、具合が悪いとうつむいたり落ち着かないのを元気くんが介抱してくれていた。真夜中で、私の嫌いな0時だった。今日が、終わって始まった。しばらく立ち止って腕時計を見つめていると、なんだか陽気な気分になってきた。元気くんは少し戸惑い疲れていた。駅まで歩けばギリギリ終電はあるが、なんとなく、近くのホテルに泊まることにした。なんとなく。18歳の子にホテル代を出させるのもなんとなく酷なので、私が出した。私が居るので冷静を装ってはいるがなんだかんだ元気くんも酔っ払っていた。
ホテルに着くと、意外にも元気くんは心の中の何かが爆発したように、すぐにそういう雰囲気になった。部屋に入って鞄を置くと、急にベッドに押し倒してきた。箱型のベッドがやわらかく弾んだ。まるでスローモーション。
「俺、マリンさんになりたいよ。マリンさんみたいになりたい」
そう言いながら、私の胸に顔をうずめた。子供みたいだった。シャンプーの匂いがして、お母さんに買ってもらったのかな、と考えてしまった。私は丁寧に、おでこや顔にキスだけして眠りにつこうと思った。酔っ払ってるフリをして、寝てしまおうと思った。子供過ぎる元気くんには、抱かれたくなかった。私はベッドで元気くんを抱きしめたまま、目をつぶった。懐かしく感じる、彼の顔が思い浮かんで泣いてしまいそうになった。二人で、西部劇ごっこをして歌を歌っていた。
朝起きると、かわいらしい寝顔が隣にあった。可愛らしすぎて笑ってしまいそうになった。小動物を見つけたときのような感覚のときめきがした。シャワーに入り、化粧をして元気くんを起こした。寝ぼけた様子で、ぴょんぴょん飛んだ髪の毛を片手でわしゃわしゃとして、でっかい口を開けてアクビをしていた。私はそれを見て、にっこりと笑った。部屋の中は冷房が効いていたが、ホテルから出た瞬間蒸し暑さがどっと体にまとわりついた。元気くんは寝ぼけて昨日より口数が減っていた。朝、風呂に入ったからか髪の毛がぺたんこだ。朝ごはんを買いに、コンビニに立ち寄り私はトイレへと向かった。用を足して、鏡で笑顔の練習をした。トイレから出ると、すぐに元気くんが居たのでびっくりして後退りしそうになった。
「なにか買ったの?」
「いや、俺、やっぱりいいやと思って。」
「あ、そう。ほんと?」
「二日酔いで」
少し目が泳いでるのは、私を一瞬でも押し倒したことへの罪悪感なのだろうか。その理由はわからなかった。私だけコーヒーを買って、元気くんと別れた。外は蒸し蒸しとしていた。レストランの仕事が入っていたが二日酔いで気分は最悪だった。なんで昨日、あんなに飲んでしまったのだろうか。色んな男の人とデートすることで正直自分が最高にいい女だと勘違いしていた。みんながみんな私のことが好きなんだよって彼に自慢してやりたかった。そして、目の前で笑ってやりたかった。大声で。指差して笑ってやる。そして彼も焦って私を欲しがるでしょう。取られたくない、とようやく自分のものにしてくれるでしょう。頭の中のいつもよりもっともっと派手なステージで、私は大熱唱してきらきらと輝いていた。観客は、カズキ、アキさん、元気くん、真ん中に、彼。さぁ、名前を言いなさい。言え。
私は私史上、最強にうぬぼれていた。頭がぐるぐるぐるぐるして、変な汗が出た。彼から、メールが来てた。
『あつくて頭いてぇ』
『ほんと、頭痛い』
『なに、死んでんの。暑さごときで』
『うるさい、あんたもでしょ』
『俺は暑さとの戦い方心得てるから』
『いや、そこ負けない』
『アイス買って』
『いや』
そのまま、仕事に行った。
「おはよ」
アキさんが居た。私は真っ青な顔で「おはようございます」と言った。
「どうしたの?」
「いえ、二日酔いです」
「あぁ。そうなの。ばかだね」
優しく、アキさんは笑った。その日は、自分の運ぶ全ての料理がまずそうに見え。こんなことってあるのね。夕方も過ぎると体調も回復してきていた。キッチンに入るたびにいちいち深呼吸をしていたので、たまにアキさんに笑われた。営業終わりに、アキさんとまかないを食べていた。二日酔いの最後のほうと言うのは食欲が増量してカロリーのオバケを愛して愛して欲して仕方なかった。もう外は夜だった。彼とそのうち、花火をしようとメールを送り、ご飯も食べて用もないはずなのにアキさんの家に泊まりに行った。つまりは、寂しくなった。ずっと人といたのに今更一人なんてムリよ。そう思っていた。アキさんは冷蔵庫から発泡酒の缶を取り出し私に手渡した。暑い部屋には背の低い扇風機が上向きに回っていた。
8
「発泡酒ってこんなに美味しかったっけ」
冷え冷えの仕事終わりの一杯は、きっと何を飲んでも美味しかった。私たちは喉が渇いていたのか、がぶがぶと一気に冷蔵庫の全部のお酒を飲み干してしまった。テレビからはバラエティの観客の笑い声が小さくぼわぼわと耳に近づいてきていた。アキさんは疲れたのかソファに座りそのまま寝てしまったので、ささやかなテレビの音と私のお酒を飲み干す音が部屋に響いていた。部屋と言うか、私の耳に。お部屋を少し片付けて、扇風機を消して電気を消した。テレビの明かりだけが室内を照らしていた。アキさんは小さくイビキをかいていた。鼻奥のほうから何故かピーピー鳴っていた。窓を開けた。外の匂いがする。何故かふと、彼を思い出した。罪悪感なんて何一つ無くて、ただただ自分が孤独になっただけだった。吸ったこともない煙草を吸ってみたくなった。彼の匂いが私の中で今は、外の匂いと、煙草の匂い。やっぱり、彼が一番好きだ。人の家なのに、アキさんをソファに寝かせて私はベッドで寝ていいのだろうか。そう何度か迷ってからなんとなくアキさんにタオルケットをかけて、私はベッドで寝た。彼から『おやすみ』とメールが来てたのに気づいて、なんだか涙が出そうだった。『おやすみ』と私も送った。ひどいよひどい。愛してるなら愛してると、どうでもいいならどうでもいいと言っておくれ。言葉にしなきゃ伝わらないことなんてこの世にたくさんあるんだ。
壁際を見て携帯をいじっていると、アキさんが起き上がった音がした。別に何もやましい事は無いが、液晶の画面を消して寝たふりをした。何の声も出さず、しばらくするとこちらに近づいてくるような足音がした。体が強張ったが、ひたすら寝たフリをするとアキさんは私の隣に寝転がった。心臓がバクバクしてるのを隠したかった。ぐっすり眠っている訳じゃないのを静かな部屋が全部種明かししてしまった。発泡酒のにおいがする、アキさんは私の体を掴んで自分のほうに裏返した。時間は23:45。今日が、終わってゆく…
「起きてたでしょ」
アキさんのそんな所、見たくなかったような気がした。素直にドキドキした。いつもなら「まぁこんなのもたまにはいいかな」と思っているところだがなんだか今日はいつもと違った。アキさんは、ねっとりとしていた。セックスというスポーツを楽しんでいた。最中に、色んなことを言ったり、たまに私を引っ叩いたりした。ベッドの下から、変な形の秘密道具も出してきた。秘密道具を使って、私で実験をしてるかのように弄んだ。体とか心とか無理矢理、切り裂かれたような気持ちだ。ねっとりと、違う生き物と接してるみたいに色っぽかった。なんだか怖くなって、楽しめなかった。次第に、吐きそうなくらい具合が悪くなった。
気色悪い。
あり得ないような、私の体の色んなところを口に含んで美味しそうにヨダレを溜めていた。そのうち、見たら入りもしないことくらいわかる拳を私の口に突っ込んで息ができなくなりそうだった。追い打ちをかけるように首を絞め、目から涙が伝う私をアキさんが見下ろす。嬉しそう。楽しそう。狂っている。身動き取れない。言葉も発せない。水の中に居るみたいに息苦しかった。吐き気がした。痛かった。それを鏡で見せられて、鏡には肌色のキチガイが二人写っていた。アキさんはそのうち、暴言に近い台詞を何度も私に浴びせた。まるで、人が違う。誰?これは、誰?
アキさんは楽しそうだったが、私は必死に平気な演技をして死にたくなっていた。悪い癖で、また必死に違うことを考え始めた。拳をリズムに乗って振りかざして、どこのかわからない応援ソングを歌う私が居た。蔓延の笑みで、学ランを着てはちまきを巻いていた。その光景が、どんどん近づいてくる。
助けて、彼。そう思った。
自分でこの家に迷い込んできたのにずうずうしくそう思った。間違えて怖い場所にきてしまった。誰も味方もヒーローも居ないと思った。
お父さん。
目覚ましの小さな音で目が覚めた。私は裸でベッドに横たわっていて、隣にはアキさんがすやすやと大きなイビキをかいて寝ていた。なんだかその顔を踏みつけて、潰れたみかんみたいにぐちゃぐちゃにしてやりたかった。優しくてお兄ちゃんで、そんなアキさんに対して初めてそんな事を思った。何故か思い出した。お父さんが昔、赤いカエルを間違えてつぶして、色んなことでやけになって更に何度も何度も足で踏みつけてぐちゃぐちゃにしたの。自分の弱さで、やけになってしまったの。うまくいかなくて、泣きたくなってしまったんだ。
私は服を着て、少し明るくなった外をチラッと見てから鞄を持った。アキさんが
「またね、気をつけて」と言った。起きてたのね。
早朝だった。まただ。深呼吸をした。珍しく晴れていたが、死ぬほど泣きたくなって鼻の奥が痛かった。誰のせいかも、もはやよくわからない。全部が全部間違ってる気がした。彼に『おはよう』とメールをした。余計に鼻の奥が痛かった。無駄に水色の薄暗い空を見上げて「はぁ」と言った。落ち着こう。今日は誰とも遊ばず、頭の中をクールダウンするんだ。
しばらく家の中でぼーっとしていたが、気がつくと寝てしまっていた。地獄のような夢を見て目が覚めたが、内容は覚えていなかった。私は昔から、何か思い悩むと悪夢にうなされ目が覚めていた。胃が痛くなることや、食欲が無くなる様なことはめったに無かった。カズキからまた『やり直そう』としつこくメールが入っていてストーカーのようだった。ぶちキレてやりたい気分になった。私はうぬぼれていて、おまけにとんがり直してしまったのでしょうか。彼が『今ヒマ?』とメールしてきたので会うことになった。誰とも遊ばないとは言えども、彼は別だった。
逢いたい。こんな私だけど、逢いたすぎる。
会う前に何度も鏡を見て髪型を直した。数日しかあいていないのに本当にしばらく会ってない気分になった。寂しい気持ちと一緒に楽しみが押し寄せてきた。男と会うのが、こんな楽しみって思うなんて奇跡だ。昼間の混雑する駅のホームで、彼を見つけた。にやにやが止まらず、こっそり近寄って「おはよ」と言うと、彼も口角を片方上げて「おー」と言った。
「あついねぇ」
「おー」
「おーばっかり」
「…何して遊ぶ?」
彼がこちらに目も向けずに言った。私は素直に微笑んだ。
「何して遊ぼう?」
9
夜、電気を消して彼の隣に寝転がった。天井を見つめて、外から入る風で涼しんでいた。彼も天井を見つめて、二人でいやらしい雰囲気になることもなくぼーっとしていた。彼の手をそちらも見ずに握ってみた。小さな力で握り返してきたので「はは」と突然笑ってみた。窓の外を見ると、半分くらいしか無い月が私たちを見ていた。なんだかおとぎ話のようで、ミュージカル風の音楽が聞こえてきそうだ。歌詞が英語の、よくわからないやつ。
コンコン
と扉を叩く音がした。インターフォンがあるのに、どちら様だろうか。もう深夜の1時を回っていた。一度気のせいかと思い無視すると、今度は少し遠慮がちに『コンコン』と音がした。眉間にしわを寄せ、起き上がり彼から手を離すと彼は私の腕を掴んだ。
「こんな時間に変じゃない」
小声でこっそりと彼が言った。
「…でもなんか」
言い終わる前に、またコンコンと鳴った。彼は私の代わりに玄関に歩いて、のぞき穴を覗いた。首をかしげて、こっちに戻ってくる。
「誰も居ない」
「いたずらかな」
「おばけじゃない」
「真顔で言うのやめてよ」
「え?」
彼は突然キスをしてきた。「なんだぁ、おい」と私が笑うと、窓の外から何か歩き回ってるような音がしたので私はとっさにカーテンをめくった。一瞬だけ、人影が見えた。見覚えのある、顔だった。その人影は間違いなくカズキで、鳥肌が立った。
「なんか居た?」
しばらく動かない私に、少し心配そうに彼は言った。
「なにも」
カズキは、奇妙なほど真っ黒な目でずぅっと何かぶつぶつ言いながらこちらを見ていた。
次の日は、レストランだった。頭の中は、アキさんだった。トラウマになるくらいのあの夜を、何度も思い出した。彼が寝ぼけた顔で「いってらっしゃい」と言った。カズキが何をするかわからないので、一人で彼を家に置くのは嫌だったが仕方なく「いってきます」と言った。色々とやる気が出なかった。というより、身の回りに危険がいっぱいに思えた。
なんでこうなってしまうんだろう。
「おはようございます」
アキさんと目があった。優しくいつも通り微笑んで「おはよう」と言ってくれたが、今はそれもなぜか怖いように感じた。案外、いつも通りの空気で時間は過ぎていくように思えた。アキさんも、態度を変えることなく私を見て笑ったり、普通に話しかけてきていた。考えすぎなのかもしれないが、逆に私のほうが調子が狂ってしまうようで気疲れしていた。好きなわけでは無く、こんなに一人の人を意識して見てしまうなんて今まで無かった。警戒とも違う、常に距離を測っている空気。休憩室で、首を振る扇風機を見つめながらぼーっとしていた。上の空と言うよりは、考えることが山ほどあったのだ。どうして私の浮気相手は性癖異常者とストーカーなのだろう。そんな、他人が聞いたらくだらないと思うような内容だった。コンビニで買ったどこのブランドかもわからない安いコーヒーを中途半端に残して、読んでもいないのにひたすらラベルを眺めていた。やっぱり、キチガイの周りにはキチガイが集まってしまうのか。突然ドアが開いた。
とっさに振り向くと、優しい顔で疲れたアキさんが隣に座った。
「おつかれい」
少し固まってしまったが、いつも通りの口調で、表情で安心してしまった。それと同時に一瞬にも満たない時間だが、悪魔のアキさんが頭をよぎった。
「お疲れ様です」
「元気ないの?」
「いえ。ちょっと、もー暑くて」
「はは、夏バテ?」
「違いますよ~」
アキさんは、さほどこの前のことを気にしてないようだった。と言うより、覚えてないのだろうか。そんなことは、絶対にあり得ないはずだ。アキさんはコンビニの袋から質素なパンを取り出し、頬張った。私はそのパンを見つめて、この前の私はこのパンみたいに…と史上最強にくだらないことを考えていた。その表情を見て、アキさんは普通のトーンで言った。
「次いつ遊ぼっか」
「…」
言葉が出なかった。
「また会うでしょ?」
パンを頬張りながら、何事も無いことかのように言った。
「あの」
「わかった。清純ぶってんでしょ?」
「…」
「普通のセックスしかできないと思って拒否?いや、現に出来てたから大丈夫だよ」
もぐもぐと口の中にあるパンたちを噛み砕きながら、普通のトーンで、いつもの表情で言うので不思議な感じがした。これはアフレコでしょうか。この人は、誰でしょう。
「私やっぱり…」
「本命が居るから?」
「…」
「そんなの関係ないでしょ。元からそうじゃない」
アキさんはパンのゴミをくるくると綺麗に巻いて袋に入れ、口をしばってゴミ箱に投げた。それはふたが開いてるゴミ箱に、外すことなく入った。全身鏡で、エプロンを直してからアキさんは私の目を見つめた。怖くて、私は少しで逸らした。すると、アキさんは私の耳元で「よかったくせに」と少し低い声でささやいてまた微笑み、休憩室を出た。しばらく体が動かなかった。叫んでしまいそうだった。もしここで叫んでしまうとしたら、私はなんて叫ぶのだろうか。そこから、私は普通に働けていただろうか。記憶が全然無いまま、夜になって気がつくとタルトに居た。タルトさんが、私を心配そうに見つめていた。いつだって何も話さなくても、タルトさんにはわかってしまうのだ。何も聞かずにいてくれたが、私は鏡を見て上の空で、鏡の中の自分に話しかけてしまいそうな気持ちでいた。タルトさんが、美しく鏡の端っこに写っていた。
「タルトさん」
鏡の自分から目を離さず、話しかけた。
「なあに」
誰よりも優しい声で、タルトさんは返事をする。
「キチガイの周りには、キチガイが集まるのよ」
「そりゃぁそうねえ、一緒にいれるってことは、どこかが同類なのよ」
お父さんみたいなことを言う、タルトさん。
「でも私、性欲異常者と、ストーカーは嫌いだわ」
「そりゃわたしだってそうよ!何言ってるの」
タルトさんが高らかに笑う。
「でも、わたしもそうかもしれないわ」
彼の顔が浮かんだ。鏡の中の自分の片目から、水が一筋流れた気がした。鼻の奥で、クラゲの大群が暴れだしそうなのを必死になだめた。私は、何がしたくて何を知りたくて何にビビッているんだろう。私という生物は、キチガイ科に属しているのかしら。ささいなことが、寂しくて仕方ない。頭の中で、色んな人々が歌って踊って暴れている。頭が痛い。ずっしりと、首から上が重く感じた。
10
ステージから観客を見渡すと、今日は元気くんが来ていないことに気づいた。こんな私への罰かしら。たった一回のステージに来てないだけでこんなにも寂しい。虚しい気持ちになるなんて。一人、カウンターに座り何も考えず誰とも喋らず一人でお酒を飲んでいた。私のファンは居ないわけではないし、私のステージの時間になったら来てくれるお客さんもいるが元気くん以外は私に話しかけることは無かった。顔面合成糞野朗もあれから二度と、タルトで見かけることは無かった。怖気ついたのでしょうか。なんだかとってもやさぐれていた。アキさんの言葉が耳の中で大暴れしてるのを必死に無視した。うるせえ。うるせえんだよ。うるせえ。どいつもこいつも。自分の声でかき消すように、心の中で怒鳴っていた。そのうち、気がついたら河川敷でべちゃべちゃのぐちゃぐちゃで立っている私が居た。少し離れて、見上げると彼が私に向かって財布を投げてきた。大笑いしてる彼を見て、顔が腫れすぎてどうにもならなかった。お母さんに平手で殴られたときも、こんなに腫れてないのに。虫ってすごいわねぇ、怖いわねぇ…彼が私に向かって、叫んだ。
「俺の名前は、山田太郎だーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!」
…
ピンポンピンポンピンポン
入店です。
酔っ払ってタルトで突っ伏して寝ていた私だが、気づいたら早朝のコンビニで履歴書をずっと手にとって眺めていた。一番前にある、見本の名前のところに『山田太郎』の文字。そのうえにはもちろん『やまだ たろう』。なんて馬鹿馬鹿しい。
それにしても具合が悪かった。遠くにあるコンビニトイレの鏡に写る私服の自分を見て、なんて普通なんだと叫んでしまいたかった。もしかして私は、とっても小さくて細かいことでやけになってるんじゃないかと思ってきた。三年も一緒に居て命の恩人で初めて本気で好きになった彼と付き合ってると勘違いしてた私は気がついたらおまけに名前も知らなかったなんてよくある話なんだろうか。笑って終わらせることなんて簡単なんだ。私は彼の何も知らない。なんで言ってくれなかったのじゃなくて、なんで聞かないのだろう。アキさんの思い出したくも無い言葉達が耳の中を這いずり回って、私はもう一度履歴書に目をやる。それからぐわんぐわんする脳みそとお友達。ぼーっと何気なく横を見た。元気くんだ。
「あ」
話しかけようと思い、小さな声が出たが元気くんは私に気づく前に近くの商品のガムを鞄に入れた。私は言葉も出ず、動けずに居た。元気くんは躊躇無くガムや駄菓子を袖にしまってこちらに向かって歩いてきて、すれ違いそうになって私に気がついた。
「あ」
鞄の中はさっきのガムと、おまけに大量のコンドーム。箱から出してどうやって。どこで盗んできたんだ。それと、大量のAV。私は、冷静を装うのがとっても得意なはずなのに、ふいにその鞄の中身をガン見してしまい目が離せなくなった。ぐるぐるぐるぐると、二日酔いの気持ち悪さと自称山田太郎の『付き合ってとか言ってない』がマーブル色になって私を襲う。アキさんの言葉なんかは、もう私の頭の中では沸騰して歌になってしまっていた。
【清純ぶってんでしょ~♪
普通のセックスしかできないと思って拒否?
現に出来てたから、大丈夫だよ~
本命が居るから?
そんなの関係ないでしょ~元からそうじゃない】
歌にあわせて、マーブル色の顔した山田太郎が空中ブランコに乗って「あはは、あはは」と棒読みで笑っていた。元気くんは、鞄の中を見つめる私のおっぱいを突然わし掴み、何故かウインクした。
は?
は?どうゆう意味ですか?
【現に出来てたから、大丈夫だよ】
類は友を呼ぶ?私は、こいつらの類なの?
なんてろくでもねえ!!
今度は元気くんの目から、目が離せなくなり私は何も言わずに店を出た。ピンポンピンポンと音が鳴り、早歩きで歩いた。元気くんだけは普通だと思ってたのに、元気くんだけは。助けて。誰か私をこの世から引っ張り出してください。しばらく早歩きしてから、気配を感じて後ろに突然振り返った。
「わぁ」
とカズキがアニメみたいな声を出し、馬鹿みたいに口を押さえていた。ストーカー。クズ。ゴミ。私と言う人間はなんて見る目がなくてどうしようもない馬鹿女でおまけにこいつはなんでこんなにどうしようもないくらい女心がわからなくて間が悪くて女の気持ちを見下してなんていうか…もう…もうっ!!!!イライラする!!!胸倉を掴んで意味不明なことを叫んだ後、私はカズキを突き放した。落ち着け、落ち着け、落ち着け。
「だって、聞いてよ。俺の話を聞いてよ、そら。そらってば、好きなんだ。俺、わかんないけどそらのこと好きなんだ。空が本気じゃ無くったってなんでもいい。俺は…そらを愛しているんだよおお!!!!!」
気味が悪い。目が、絵で書いたみたいに真っ黒だ。
「消えろよ!!!!!」
怒鳴った。のどから血が出そうよ。助けて、誰でもいいから。ゆらゆらと、彼の顔を思い出した。目が回る。私は何をやってるんだろう。夏祭り、私にりんご飴を差し出す、自称やまだたろう。そんな夢だった。人って、起きている時にもきっと夢を見るんだ。お母さんだって、そうよ。てか、りんご飴、でけえよ…。でかすぎだろ…。私は息を切らし肩の震えが止まらなかった。興奮状態のカズキは、私を通り越して背後を奇妙に見つめて突然首をかしげた。時間は平凡で、朝の6:45。ふくろうみたいに見えた。カズキは、ふくろうみたいに私の背後を見つめた。恐れもせずに振り返る。
彼が。
反対車線に彼が違う女と歩いていた。
こんな時間に、何してるのよ。
最近の私と居る時みたいに、冷めた目はしてなかった。きらきらと、まるで恋をしていた。隣に居る女の人は、私なんかよりずっと背が高くて綺麗で細くて。じゃれるみたいに彼のことをばしばし叩いてた。
触んないで。
触んないで。私のよ。
がたんごとん
がたんごとん
がたんごとんがたんごとんがたんごとん
がたんごとんがたんごとんがたんごとんがたんごとん
ストン。
カズキが私の顔を無理矢理掴んでキスをしてきた。時が止まっていた。爆音のヘビメタな音楽とバイオリンのクラシックを交互に頭の中で再生した。何かの歯車がキリキリと音を立てて暴れまくっていた。きっと、もう少しで爆発。爆発するんだわ。カズキの舌が、私の口の中で踊っている。べたべたと、ぬるぬると。ああ、涙も出ない。吐き気もしない。乾いている。こんなにべとべとぬるぬるとねっとりしているのにのどが渇いてカラカラだ。
からっから!!!
「お疲れ、もう上がり?」
気がついたら私は、レストランの休憩室でただぼーっと正面を見つめていた。アキさんが、私の間の前に手をパタパタさせて「お~い」と言った。私は、何も返事をしなかった。アキさんの整った顔がすごく癇に障る今日だった。横目で、それを見ていた。頭の中で何度も、赤いドレスに赤いリボンのいつもの衣装で首吊りを繰り返した。アキさんは隣に座って野菜ジュースを飲みながら私を見つめているようだった。うざかった。
「ねえ」
甘えるようにアキさんが言った。
「今夜おいでよ」
「…」
にやにやしながら、アキさんは私の頭を触った。
「こいよ、今夜」
おい。そこの腐れナルシスト。
私はあんたにこれっぽっちも依存してないしこれっぽっちも好きじゃねえ 第一タイプじゃねえ そんなに格好よくもねえ 頭触られるのも 好きじゃねえ 転がされてる つもりもねえ 調子に乗るな とっとと消えろ 消えうせろ 見つめてくるな 可愛くねえ 甘えてくるな うざったい ただ憎たらしいだけの性癖にキュンとするギャップなんてねえ 虜にもなってねえ さっさと消えろ 勘違い男 てめえにときめかされたことなんて一度もねえよ
と
思ってたことを私は気がついたら全部口に出して居た。
そして、
ゲップが出た。
大爆笑が止まらなかった。これっぽっちも男としてなんて見ちゃいないわ。笑いが止まらなくなって、私は鞄を肩に背負い、元気な声で「お疲れ様でした」と言って頭を下げた。アキさんは、化け物を見る目でこちらを見ていた。懐かしい目だった。カズキがついて来てるのがわかったが、私はタルトに向かった。
「なんだか久しぶりね」
タルトさんが笑って私を見た。私も、微笑んだ。
「いえ」
鏡の前のカラフルな化粧道具たち。古臭くて派手な更衣室。赤いドレスがかかったハンガーラックがなんだか懐かしく思えた。そんなに久しぶりでもないはずなのに。
キラキラして見えた。私の機嫌はすぐに良くなった。
「ねえタルトさん」
「ん?どうしたの?」
「一番の勘違い女は私よ。キチガイは私よ」
「…」
「だってね、ゲップが出たのよ。セックスした男の目の前の目の前で、ゲップが出たの。おっかしい!!」
私が笑うと、タルトさんは少し間を置いて私よりはるかに大きな声で大爆笑したのでそちらを見つめてしまった。男みたいな声で、机を激しく叩いて手を負傷していた。タルトさんらしかったので、私は途中から無視して口紅を塗っていた。ステージの上に立つ私は相変わらずスポットライトを浴びていた。光の中に浮く埃が、私を高揚させた。何もかも忘れて、きっと私の本当の名前はマリンだわ。彼の顔が何回も頭をよぎって苦しいが、それすら私の歌に繋がった。
「はじめましてぇええ!!」
私は叫んだ。叫び声は響き渡る。全然はじめましてじゃないのに誰も指摘しない。タルトさんもどこかわかっていて、私を色っぽく見つめて煙草の煙を吐いていた。好き。タルトさんが好き。人間として、生物として。涙が出そうだ。遠くに、ちらっとカズキが口をパクパクさせ私を見ていた。カズキは、母の姿を知っていたから私を恐怖の目で見た。完全に洗脳された姿だとでも思ったのか。それとも、私の瞳も貴方みたいに不気味に真っ黒だったのか。歌い終わると、カズキが尿をもらして騒ぎが起きた。よかったね、私と一緒じゃない。おもらし。あんたのおもらしパンツ。誰か買ってくれるといいわね。ふと携帯を見ると、彼から電話が入っていた。私は騒ぎも無視して、ステージの上で電話に出た。
「はい」
さぁ、言い訳しなさい。
11
カズキのストーカー騒動は終わった。久しぶりに早起きの日曜日。朝起きて歯を磨いて、口の中にトイレットペーパーを突っ込んだ。
こんにちは。私。
こんにちは、私です。
自転車をぶっ飛ばしていた。久しぶりに自転車に乗った気がした。駅の近くにある住んだこともないアパートの駐車場に自転車をいつも通り停めた。珍しく外は晴れていて、珍しく過ごしやすいくらいに涼しかった。雲がゆっくりと動いている。まだ午前中だ。
久しぶりのデートの約束だった。
窮屈な電車の中で、どうしても生理的に受け付けない顔面の奴がちらちらとこっちを見ている。私は吊革を掴み、正面をただ無表情で見つめている。彼は私の目の前の席に座り何かもぞもぞと動いている。私は久しぶりに性癖異常者や万引き常習犯やおもらしストーカーのことも考えずにこの人間の顔面によりほんのりとイライラしていた。そのうち目の前の男はポケットから携帯を取り出し、ニヤニヤと画面を見た。あまり見ないような、異常に画面の大きなスマートフォンだった。無駄に肌の綺麗すぎる大きな顔、目は無駄なほどくっきり二重まぶた。兎に角好きになれない鼻の形で、髪はピョンピョンはね放題。そのうえスーツで、出来る男気取り。体型、普通。ただ不愉快だ。決してブサイクな訳ではないが、私は今目の前にある光景がとても不愉快でならない。ほんのり香るナルシストな香水の匂いが癇に障る。仕草も髪型も。全て嫌い。こんなに癇に障る顔の人に今まで出会った事が無かった。快挙だ。私の耳もとで、こもった音の「がたん」と「ごとん」。あと何分だろう。げ、あと10分もある。てめえ、早く降りろ。今とても真剣な顔で電車に乗っている私だが、頭の中はこいつで汚染されてゲロの洪水で大惨事。なんてめでたいのよ。こいつは普段、気持ち悪い女でも連れて歩いてるに違いない。そしてその彼女を世界一可愛いと勘違いしているんだ。『次は中野、中野』
視線を、電光掲示板に移した。
「ヴォうえぇええええええええ!!」
「…あ」
私には、きっと癖があった。
とんでもない状況とクズのような人間に囲まれると、愛しているのにクズな人のクズな部分を全く忘れていい思い出を並べて見せるの。
お父さんのことだってそうだ。
心が寂しく凍りつくと冷静な私を呼び起こすために夢を見る。全然平気な顔をしたくなる。お母さんが心の病気になった瞬間私は、お父さんのゴミの部分を忘れて完璧に良いお父さんだったことにしたくなった。ゴミ箱にしまった。透明のゴミ箱に。
透明
【 まるみえ ! 】
この日なんてまさにそうだった。彼とのいい思い出だけをくり抜いて心の映画館でリピート再生。なんて幸せで心地いいんだろう。踊りだしそうよ。大好きで自慢で何も不満が無い。まさにそんな催眠術を自分に、ハッピーな催眠術を自分に。幸せ。これが幸せ。私は幸せ。彼と居ることで、頭の中がが毎日お祭りのようだった。私達は、いたって普通のカップルだ。セックスもする。したいからする。セックスが楽しいなんて言うのは、ごく一般的で普通の話だ。こんなに楽しいスポーツないでしょう。こんなにワクワクする遊びないでしょう。こんなに幸せな儀式、他にないでしょ?ていうか、あんた達はしないとでも言うのか。女の子は便も屁もしなければ交尾もしないだなんて、ちゃんちゃらおかしいわ。
私は、セックスが好きなわけじゃなくて彼とのセックスが好きなんだ。そう地を這い蹲るような経験をしてきっと気づいた。
どんな経験だったかは、とっくに忘れた。
私は彼を裏切らないし、彼も私を。
簡単なことを言えば私は彼が大好きで、二人と居ない存在で、居て当たり前で、つまり、愛すってこうゆうことよ。
そんなことを、何回も言い聞かせた。
「ポッキー食べる?」
ポッキーを彼が一本だけくわえながら私の目の前に差し出す。カーテンの隙間から日が入る。私はポッキーと彼を二度見してから
「食べるわ、たかがポッキー」
と満開の笑み。
「…たかが?」彼が不満そうに眉間にしわを寄せる。元から切れ長の細い目を、もっと細くしてこちらを見るので何故か私は嬉しくなった。
「たかがポッキーばんざい!!痛い痛い」
彼が私の髪の毛を引っ張る。そのまま彼は私の頭を包み込んだ。ふんわりいつもの柔軟剤の匂いがして、目を瞑った。この世の全ての星の生物を全員集めて恋愛ごっこをしたって彼ほど好きな人は居ない。このぬくもりに包み込まれるたび、そう心の中で何度も再確認した。いや、そうじゃなくて彼以外はとても興味がない。つまらない。なにがいいのか、どこがいいのか、自分が一緒にいて何がプラスになるのかわからなかった。全国民に言いたいわ。あなたのいいところはどこでしょう。あなたのいいところを、わかりやすくプレゼンテーションして下さいな。
逆に
私のいいところは、どこでしょう。
包み込まれた空間がいきなりぎゅっと狭く暗くなった気がした。どんどん闇へと落ちてゆく。音もせず、今日の私のスカートの上を思い出した。スカートの上は私に忘れろというように小花だらけだった。目を瞑ると私たちをあの女の人が見ていた。
『俺の名前は、山田太郎だーーー!!!!』
私は彼を突き飛ばした。
彼はソファから落ちて地面に頭を打つ。呼吸が荒くなる。頭の中が、パニックだ。あの時と同じ。瞬きをする度、ぐっちゃぐちゃのつぶれたカエルがお父さんの足に絡み付いて、犬が遠くに吠えるように泣くお父さんが居た。足をいかやきにしてしまおうとした血だらけの風呂場で私を何度もビンタするお母さんも居た。綺麗な女の人と歩く彼も居た。おもらしをするカズキも、耳元でささやくアキさんも、コンドームだらけの鞄を持ってウィンクする元気くんも。
現実から逃げて逃げて、一気に追いつかれて襲ってきた。
食べられる。現実に食べられる。
「見たの」
私は震えた声で言った。頭が痛い。自分の髪の毛をぐしゃぐしゃにして頭痛を誤魔化して、震えた声で彼の目を見て冷静に話した。
「きのうのきのう、あさ、見たの」
「…」
「お前が、ちがうおんなのひとと、見たの」
「…」
「悲しかったの」
「…」
「なんか言えよ」
「別に」
「…え?」
「付き合ってないって言ったじゃない」
耳鳴りがした。
「だって」
彼の顔を見ると、子供に戻ってしまいそうだった。たくさん、彼との思い出を思い出して涙が零れ落ちた。溢れ出た。もうみちみち。もう、満ち満ち。
私を拾ってくれたのに。
ささいなことだ。
名前を知らないのも、付き合ってないという事実も一緒に居られてたんだから。
他の女と歩いてたのだって、勘違いかもしれない。
全てが、ささいなことだ。
大げさではないことだ。
なんてこともないことだ。
なんでこんなに好きなんだろう。
※これは少女マンガではありません
「私だって、うわきしてるから」
「…」
「おまえに、隠し事もいっぱいあるんだから。おとこと、あんなことやこんなことだってしたし、しかも、一人じゃないから。いっぱいだから。たのしかったんだから」
「知ってるけど」
彼が、興味無さそうに煙草に火をつけた。
「悔しくないの」
「別に」
「はらたたないの」
「たつよ」
「このまえの、あれは?」
「仕事のヤツだよ。一緒に居たくらいでなんだよ」
「え?」
「お前なんて、キスとかしてたじゃん。しかも路上で。べろっべろされてなんにもリアクションしないの見てんだよこっちは」
少し声を上げて、彼が言った。
「だって付き合ってないんでしょ?」
「またそれか」
「そんな私に何も言わずなぜ」
「さあ」
「へんだよ!きちがい!」
私は叫んだ。
彼は一度目を伏せて、灰皿に煙草の灰を捨てた。
「しらねえよ、…気持ち悪い」
初めて彼が、私を軽蔑した目で見た。
頭が真っ白だ。
「気持ち悪い」
もう一度にやにやして彼が言った。涙は、垂れ流し状態だった。私は近くにあるクッションを投げた。
「好きなら好き嫌いなら嫌いと、言え!!」
「うぜえ、まじ、うぜえ」
「言え!!!!」
私は彼の胸倉を掴んだ。すると彼は私の髪の毛を掴んで私を突き放した。私は彼の腕をかじる。そこからは、大乱闘だった。まるで、スマッシュブラザーズ。
いえいえ。
お互いアザだらけの私は涙で顔もぐしゃぐしゃだ。兄妹喧嘩みたいに二人とも折れず、「ばか」だとか「ぶす」だとか言い合いながらずっと二人で痛いところを叩き合った。痛くて心が折れそうだった。が、憎しみが勝った。なんで私が、こんなに辛い想いをしなければならないんだ。こんなに泣かなければならないんだ。なんでこんなに辛いんだ。誰か、一緒に居て。誰かと言うか、誰かと言うか…
ゴンッ
ごつっ
一瞬だった。
二発だけ。
すろーもーしょん
二発だけ
ごんっ
って。
ゴツッ
って。
「…ねえ」
「ねえ」
「ねえ」
「ねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえ」
灰皿で、彼を
彼の頭により床は赤く染まり、彼は何も喋らず動かなくなったので彼の色んなパーツに耳を当ててみた。「もしもし」何も聞こえない。もちろん、股間からも。どこも動かない。
私は、
すっからかんの脳みそで、彼の隣に血だらけになっても気にせず、寝転んだ。
ささいなことだった。
名前を知らないのも、付き合ってないという事実も一緒に居られてたんだから。
他の女と歩いてたのだって、勘違いかもしれない。
全てが、ささいなことだ。
大げさではないことだ。
なんてこともないことだ。
馬鹿になるくらい好きなんでしょう。
ピンクだ。
彼の居ない世界を、私が作ってしまいました。
12
お父さんは最強なんだ。お母さんだって、そうよ…。
目を開けながら寝ていた。思い出すのは、小花だらけのおひざの上。
彼の永遠の寝顔を見て、柔軟剤の匂いを感じた。仰向けになって、怖かったけど目を瞑った。
宇宙だ。
どんでもなくリアルな宇宙に、昭和なブラウン管テレビが置いてある。ここは月かしら。なんじゃこりゃ。
ザーと大きな音を立てて、テレビがついた。
「久しぶり」
何故か学ランを着た母と、セーラー服を着た父がビデオレターみたいに手を振っていた。
「頭血だらけじゃーーん!!気持ちわるぅーい!!(笑)」
「そらちゃん、元気かい」
「はじめて見る~そんな人~!!頭だけ血だらけの人~!しーかーもっ!無傷~~あなた面白い~~(笑)」
「そらちゃん、元気ないのか」
「あなたの格好が気持ち悪いんだよって言ってやんな~そら!あははは♪」
「ドッキリだよ」
「あんま期待させちゃダメよ」
母が急にまじめなトーンになり、父を見た。
「そらちゃん、また明日ね」
急に目が覚めた。
息が切れていた。本当に宇宙に居たみたいだ。部屋の中は真っ暗で、もう夜中だった。私は起き上がり、立ち上がる。髪の毛から、血が垂れた。べたべたとした。彼の顔を見た。起きない。彼は。
彼のほっぺたを触った。まだ、暖かい。
台所で水をくんで一気に飲み干した。台所にある照明だけがオレンジに部屋を照らしてなんだか懐かしかった。何故か私ののどはカラカラで、からだ全体に水が染み渡る。私はもう一度、彼の体に耳をあてた。何も聞こえない。私は息を止めているのに。頭が、まだ熱い。なんだか怖くなった。おもいっきり殴ったり、パンツを脱いでかぶせたり、顔に落書きしたり、髪の毛を七三わけにしたりしてみた。彼は何も言わない。また、彼の隣にぴったりとくっついて寝転ぶ。涙が押し寄せてきた。止まらないや。
宇宙より、遠いところ?
眠くも無いのに、目を瞑る。おなかもすかない。生きてるのかもよくわからない。私、生きてる?
これは彼の心臓の音じゃなくて?
「ストン」
お母さん。
部屋には時計の音が中途半端に鳴り響く。
ふいに私は彼の鞄を勝手にあさってみた。
財布を見ると、免許証らしきものを発見して息を飲んだ。私は、勇気を出して涙だらけの顔で免許書の名前のところを出して
「キャーーーーーーーーー!!!」
本気で悲鳴を上げた。
そこには
【山田太郎】
と書いてあった。
頭が、真っ白だ。
私たちは、何も起きちゃいなかった。
呼吸が荒くて息が苦しかった。私は焦ったように彼の鞄を漁り狂った。何か、何かあるかも。一通の手紙が出てきた。急いでその手紙を開けて、中身を見た。中には、グラフィカルなデザインの絵はがきと、それのもっと大きなヤツと、長めの手紙と、指輪。彼は、私に、プロポー・・・
「キャーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!」
気がついたら、病院でした。
「久しぶり~」
どこかで見たことがあるような光景。シチュエーションは違えど、燃え尽きた私の死んだ魚のような目に写ったのは紛れも無く、昔より健康な肌の色をした母だった。母は、夢で見るくらいに明るく、回復しているようだった。なんだか脳みそがぐちゃぐちゃになって、家族に会いたくなってしまった。私は、何も喋らずにいた。病院のパジャマを着た母はなんだか眠そうで、私たちは病院にあるカフェみたいな空間に迎え合わせで座っていた。なんとなく朝は早かった。私は泣いたうえに寝ていなかったので顔がパンパンでまるで母に平手打ちされ続けたあの日にそっくりだった。
母は化粧はしておらず、スッピンで髪の毛も根元は黒かった。黒い根元をぼんやり見つめていると、恥ずかしそうに「行く暇無いのよ」と言った。
「元気そうで」
私は不機嫌そうに言うと
「まあーねえ。もうすこしよ。きっと」
「よかった」
「帰ったら一緒に飲みに行っちゃいましょうよ。もう成人したでしょ」
「…そうね」
なんとなく視線をはずして足元を見ると、母の足にイカ焼き風のあの傷跡が見えた。
「よかったーこうやってまたお話が出来て」
「…私も。顔見に来ただけ」
「…」
「じゃあ、元気で」
少しの間のあと、立ち上がると母は私の腕を掴んだ。
「忙しいのね」
「…」
私がそこから、母の目を見ることは無かった。
「迷惑かけたわね。ごめんね…反省しているわ…ごめんね、ごめんね」
母が、泣いているようだった。私は「別にいいよ」とそちらも振り返らずに言った。「どうってことないよ」とわざと、優しい声でそっちを見ずに言ってその場を離れた。そんなことが聞きたいんじゃなかった。ただ、演技をして欲しかった。母という人間の演技をして安心させて欲しかっただけだった。ごめんねも、ありがとうもいらなかった。涙なんて、もっといらなかった。私は自分でもびっくりするくらい頭が空っぽだった。レストランから大量の着信が入っていたので携帯をゴミ箱に捨てた。
宇宙より遠いところ。どこよりも厚い壁。
がたんごとん
ごとーん
ごつっ
ごんっ
すとん
ぐちゃっげこっ
タルトに顔を出した。昼間で鍵も開いていた。ゆっくりと重いドアを開けると、タルトさんがメガネをかけて鼻歌を歌いながらお金の計算をしていた。
外より薄暗い店内で、私に気づいて表情も変えなかった。さすがタルトさんだ。
私は初めて、彼をぶっ殺してから笑った。にっこりと、自然に笑った。タルトさんは私に冷たいココアを出してくれた。私がそれを飲むことは無かったが、それもわかっていたらしかった。誰も居ない店内は、逆に狭くも感じた。何も聞かずカウンターでお金の計算をするタルトさんは本当に優しくて涙が出そうだった。何も言わず寂しくスポットライトすらあたらないステージを見つめた。タルトさんと居るときだけ私は、人間に戻れた気になった。
「タルトさん」
しばらくしてようやく私は口を開いた。
「宇宙より遠いとこってどこよ」
何故かそういった途端、頭の中に鉄腕アトムの歌が流れた。陽気なメロディが、少しずつ私を追い詰めた。
「宇宙に居るより、会いたくても会える確率が低いだなんて、どこよ。そこ」
すると、タルトさんは私のほうを見た。
「体内よ」
タルトさん。
「なんにも」
「うん」
「なんにも音がしなかったよ」
目が
「なんにもしないんだよ」
目の奥が、焼ける。
「無重力どころじゃないんだからそうよぅ」
タルトさん、こっちを見ないで。
「タルトさん」
「ん?」
「さよならを、言いに来たんだよ」
タルトさんと話すと、子供の頃に戻ってしまいそうだ。まっすぐ目を見たが、涙が、滝どころでは済まなかった。
ウォータースライダーだぜ、喜べ。
タルトさんはしばらく心配そうに私を見てから、いつものように世界一、宇宙一色っぽく笑った。
「いってらっしゃい」
だ っ て さ
ぶ っ 殺 し ち ゃ っ た の ☆
ザーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
雨が降っていた。私は雨を浴びながら、歩いていた。よたよたと、足に力も入らなかった。
私の家には、彼が居る。居ないけど居る。
だって、彼からは
なんの音も。
また、涙が止まらない。
気がついたら、踏み切りに居た。
カンカンと、聞き覚えのあるがたんごとんの音がした。
色んな男の顔がぐるぐると、私の頭のなかの竜巻に巻き込まれてた。そのなかに、お父さんも居た。好きよ、お父さん。好きよ、山田太郎。好きよ、お母さん。タルトさん、大好きよ。アトムも。大好き。赤いリボンにドレスのあの女の人も。マリンちゃん。大好き。愛してる。
やまだたろう。ねえ、おきてよやまだたろう。
だんだん音が近づいてくる。頭の中が履歴書だらけだ。
カンカンカンカンカンカンカン
電車が
来る。
しろい
しろいせかいにつれてって
わたしを
わたしのからだのなかの おとうさんと やまだたろうごと
カンカンカンカン
私の体の周りを舞う履歴書は、私の顔に小さな傷を作りそうなほど踊っていた。
私の体を引きちぎって引き裂いてぐっちゃぐちゃのずっさずさに
こころとからだが伴ってないの
カエルになりたい、あんときの
「危ない!」
ザーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
雨の音が、耳に響く。
電車が、
線路を踏み潰す化け物のように通り過ぎた。踏み潰されたかった。あのときのカエルみたいに原型すら失いたかった。救われてしまった。
べしゃべしゃの私に傘をさす、女の人の顔を見た。
顔でかヒール先輩。
私を殺してください。
閉幕
ぞうさん
ぞうさん
おはながながいのね
べしゃべしゃのブサイクな顔の私を見ても、雨は止みそうに無かった。頭の中で、タルトに居た。いつもより派手なステージで踊っていた。歌っていた。真っ赤な衣装を着て、真っ赤なリボンを付けてトマト片手にいつかのキチガイみたいに。タルトさんが、優しく見ていた。天使のクラシックが聞こえてきそうだった。元気くんも、可愛いままでこっちを見て。真ん中には、彼が居た。大笑いして嬉しそうだった。私がここに居るのが。私が歌を歌っているのが。私が、キチガイなのが。嬉しそうだった。楽しそうだった。笑っていた。笑って。彼の鞄から出てきた手紙の内容を思い出した。ついに、胸がいっぱいになりすぎて声を出してしまった。どうして良いのか、全くわからず大声を出しながら全力で走っていた。どんな声を出しているのか自分にだってわからなければきっと誰にも届くことはなかった。時々すれ違う人が私を軽蔑した目で見つめた。どろどろのぐちゃぐちゃになって、疲れた私は公園の暗い洞穴で死んだ。私は死んだ。自称死んだ。自称。「つまんないつまんない」とあの日のようにブツブツと呟いた。彼の顔が浮かんだ。彼の、柔軟剤の匂いを思い出した。きっと一番最初に柔軟剤の香りを嗅いだのは人気も無い虫だらけの路地裏だ。独りぼっちで突っ走って、孤独の歌も歌えなかったあの頃だ。こころが、すっからかんよ。また歩き出す。知らないアパートの一階の物干し竿に一個だけあった針金ハンガーを盗んだ。それを力づくで紐解いて、両手にぐるぐる巻きにした。
捕まえた。
がたんごとん。がたんごとん。
人生で起きた様々な名場面が、すっからかんの頭に流れてった。
目の前の席のブス。
彼が差し出すポッキー。妖怪顔でかヒール。メリーゴーランドの銀色のオッサン。閉じ込められた白い空間。オナニー大好き連発。顔面合成女。いかやきの屋台。あまりおいしくない定食の魚。ラーメン屋のイケメンザコ。何故かポケットに入れたナイフ。カズキにアイコンタクトされた教室。アトムによる万引き。トマトだらけの冷蔵庫。カセットだらけの便器。裸の私を馬鹿みたいに叩くアキさん。元気くんのウィンク。べろチューのカズキ。耳元でささやくアキさん。おもらしカズキ。おもらし私。財布を投げる彼。喧嘩。最後の殴り合いの喧嘩。元気くんの鞄の中。履歴書。鏡に写るキチガイ親子。優しいお父さん。クズっぽいお父さん。泣く母の声。月の上のブラウン管。アトム。指輪。
つぶれたカエル。
おまわりさんは、どこですか。
りんごの唄。
みんな、宇宙より遠いところ?
みんな、
私の体内にいるの?
なみだは、垂れ流し。
でんしゃよ、止まれ。
がたんごとん
がたんごとん
おまわりさん
雨が止んだ。薄暗い夕暮れ。
彼の私を見て笑う顔がリピートされた。掴んでも掴みきれない。3D映画かよ。またかよ…。
「うぅ」
立ち止まった。
「うぅぅ…」
何も見えなかった。
おまわりさん。
【でんしゃのまどから
みえるあかいやねは
ちいさいころぼくが
すんでたあのいえ】
夕日が綺麗。私の顔を照らす。精一杯汚くてみじめな、私の顔を照らす。なんだか、眩しかった。23:59でもないのに、こう思った。
今日が、
【にわにうめた
かきのたね おおきくなったかな
くれよんの らくがきは
まだかべにあるかな】
終わっていく。
オレンジ色の光に照らされて、なんだか少し寂しさと、恐怖が和らいだ。人が、罪を犯したら罰を受けるのは当たり前。普通。私は、キチガイ。今から普通の道を…。きっと歩めない。でも、歩もうとする。するの?私は、キチガイ。
やまだたろうは、私の山田太郎。
私と類。
唯一の類。
一緒のところに行きたかった。
私の体内に。私も行きたかった。
逃げたかった。あなたと一緒に、現実に食べられる前に、もっと前に、宇宙よりこっから遠いところに行きたかった。
私は…
ふと自分で作った手錠に巻かれる泥だらけの手首を見る。あの日家を出て、110番に電話をかけたときのコール音を思い出した。
プルルルルル
プルルルルル
プルルル
そっか。
私は
ベシャアァァァァッ!!!
一瞬で前が見えなくなり息が出来なくなった。頭の上からあり得ない量の水が降ってきた。溺れる。手の塞がった私は、その場に崩れ落ちた。それじゃ終わらず、永遠と穴の無いじょうろで水をかけられた。前が見えない。
「うえっ、おえ、うぷっ…ゴッホゴッホ!!」
鼻の奥に激痛が走り、水を大量に飲んだ。
死ぬ。
私は手の針金を無理矢理必死に解いて、また転んだ。ヒザがきっと血だらけだ。顔に張り付く髪の毛を、懸命にどけてそちらを見る。
そこには、
血だらけの真っ赤な顔した彼が居た。
「…」
「…」
言葉が出ない。
父と母が、ちゃっちいロケットの窓から手を振っている。父の手にはポリ袋に入ったつぶれたカエル。母はいかやきを食べて、そして遠くに飛んでいった。
目を見開く私に、じょうろを持って立ちつくす彼。まっかっか。
「…何で居るの?」
「…なんか」
「…」
「…」
「めっちゃ水飲んだわ」
「うん」
「うんって」
「うん」
「…」
「…」
そのうち彼は、馬鹿にしたように鼻で笑った。
「お前なんかにやられねえよ」
腹を抱えて笑う彼を私はぼーっと何も考えられずに目を見開いて見つめていた。そして気がついたら高揚して、世界一のキチガイのように絶叫した。
「▼※◎kぁ×○!!!!!!!!!!!!!!!」
のどから、血が出ました。
河川敷だ。
周りも見ずに、気がついたら私はあの河川敷に居たんだ。口の中は、血の味。ゆっくりと沈む夕日を無視して、私たちは何故か大笑いしていた。一緒にいるって事は、同類。のどを切らして大笑いしながら、私は大泣きしていた。涙が止まらない。また顔がパンパンになってしばらく外に出られないのかな。
頭の中では、タルトという店でマリンという女の子が派手な衣装を着て笑顔で一生懸命歌っている。
がたんごとん、がたんごとん
がたん
がたんごとん。
すとん
ぐちゃっげこっ飛び散るのは、バーベキューに使う生肉のようで、焼けたホルモンのようで、あのイライラとムラムラと近づいてくる私が女である保証日の二日目に音を立てて逃げ出すカタマリにも似ていて、そこから頭の中で何度も、何度も何度も笑った。何度も、何度もあの時の果物ナイフで彼をめった刺しにした。
なにこれ、楽しい。
なに?これ、楽しいわ。
花吹雪のように白い羽のように。刺せばさすほど楽しいわ。舞い上がる。綺麗。綺麗。舞い上がる履歴書と肉の塊。私は今、白い世界に帰ってきた。
ぐちゃっげこっ
何度も何度も父に踏み潰される私が見えた。
そうよね。あれは私だったのね。
そうよね。そうよ。
ささいなことだ。
どうってことないことだ。
そうよね、そうよ。
どうってことないことだ。
遅くない。
まだ
遅くない
目覚め
俺はびっしょりと汗をかいて、ぎゅっとこらえてゆっくりと地に足を降ろした。息が切れている。今時珍しいので長く育てていた赤色のカエルは、何事も無く遠くに呑気に逃げた。
ぴょんっ
娘が見ていた。
つぶれたかえる

