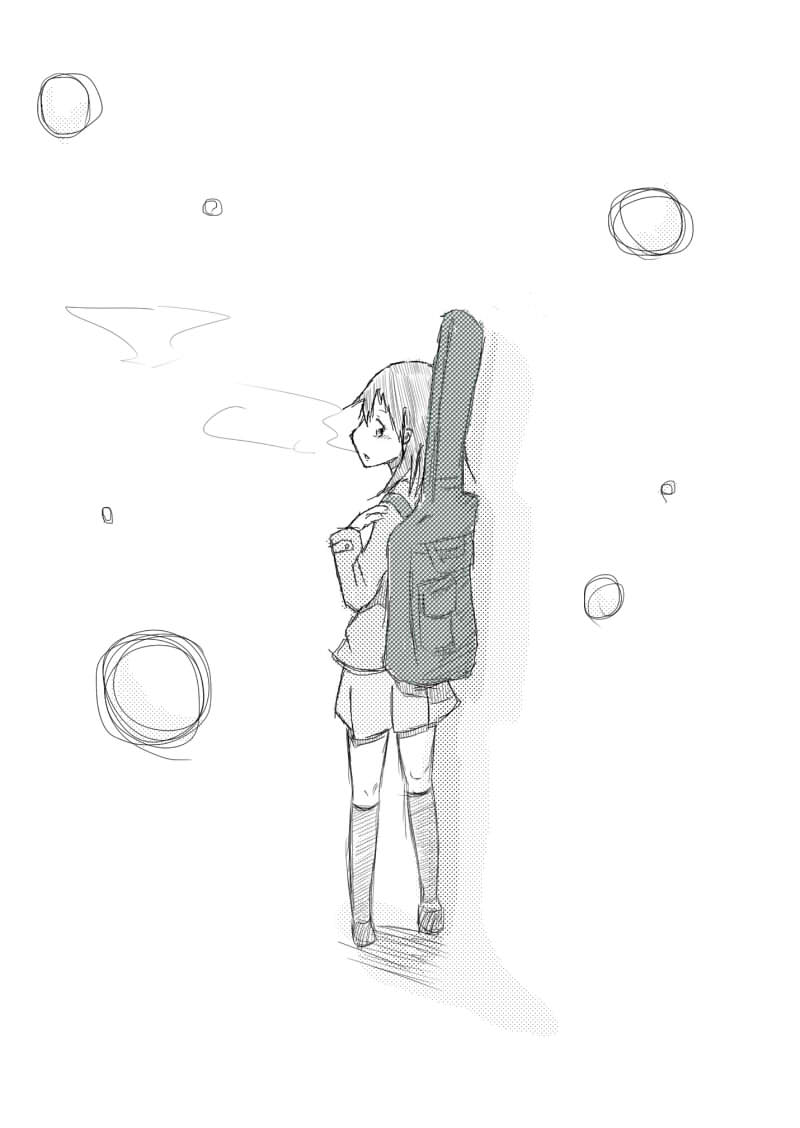
人殺したちの歌―prologue
prologue
***
もしもし、と電話口に問いかけると、よう、元気か、と男は的はずれなことを聞いてくる。もちろん、元気です、と答える訳もなく。
今から乗るところ。順調よ。
そうかい、警備は?
ざるなんてものじゃないわ。今のところなんの苦労もない。
男は電話の向こう側で小さく微笑む。
まあ、今のご時世、誰も自分が殺されるなんて思ってもいないからな。戦争は海の向こう側の出来事で、殺人事件は液晶画面の向こう側の出来事だ。死なんてものは、小説の中のもんだとでも思ってんじゃねえの、きっと。
あとはゲームの中よ、きっと。
そうかい。今の若い奴の考えてることはわっかんねえからな、全く。
何言ってんのよ、と私は呆れる。相手はおじいちゃんじゃない。
あー、そういえばそうでした、と男が言う。ねえ、大丈夫、仕事を持ってきたのはあなたじゃない。そう聞くと、男は、大丈夫、大丈夫と心もとない返事をよこした。
おじいちゃん、なんて優しそうなもんじゃねえよな、あれは。笑顔の裏っ側は真っ黒だ。それよりも、ほら、なんだ。どちらかというと、あれだ。もっといい二文字の熟語があるんだが。
老害。
そう、それ。
***
街中に明かりが点っている。街灯の光は、吐息のようにゆらゆらと揺れて、生命らしさを感じさせる。街のどこかで明かりが消え、またどこかで明かりが灯る。心臓の拍動のように、リズミカルに街というものが形を変えていく。
港には大きな光が集まっていた。不規則に波に揺られて、大きな船が一船停泊している。その周りではまるで真昼のようにライトがさんさんと照らされ、口にしたアルコールと相まって時間の感覚を鈍らせる。女は思わず船内の時計を眺めた。いつの間にか朝になってしまっているのではないか、そんな錯覚を抱いていたが、時計の短針はちょうど円の四分の三を回ろうかという頃であった。
頃合かもしれないな、と女は一人頷く。
くるりと周囲を見渡す。船上にはタキシードに身を包んだ優男、胸元の大きく空いたドレスを着た若い女、スーツを着た老人、給仕姿の少女。カジュアルな格好の若者までいる。人、人、人、人。どこを見渡しても人だかりだった。その人影の中で点々とするテーブルの上には、大きな皿の上に高そうな食物が食い散らかされている。着飾った人間の中身が、テーブルの上に展開されているような気がして、女は小さく笑った。そして黒い艶やかなドレスを羽織った自分のことを省みて、ふと我に返る。
さて、と女は息をつく。余計なことを考えているのは、そろそろおしまいだ。
仕事をしなければ。
人は、女のことを様々に呼ぶ。だが、固有の名称はなく、呼び名も一つに定まらない。
ここでは便宜上、蠍(さそり)、と呼ばせてもらう。
蠍、だ。黒くて、毒々しい、あの蠍。毒の針を持つ、砂漠の王者。
蠍は、この呼び名を気に入っていた。自分にピッタリじゃないか、とよく思う。毒の針でもって、相手に気づかせないままに命を奪う。まるで、というか、自分そのものではないか、と。
固有の呼び名がない、というのには理由がある。必然的で道理にかなった理由が。
蠍は―――殺し屋だ。
殺し屋、というと多くの人間は嘲笑するだろう。何をおかしなことを言っているのですか、と。
そして、蠍はそういう人たちを見て嘲笑する。自分の知っている世界をすべてだと思っている人間は、滑稽で仕方がない。自分の視界の外に世界があることを知らない、盲目な人間は、経済の原理というものを知らないのだろうか。
需要があるから、供給は発生する。逆はない。
需要があるそこに、必ず供給は発生する。
誰かが死んでくれればいいと願う人間は、山ほどいるのだろう。そうして少しばかりの対価を払うような人間も山ほどいる。需要がまずあり、そしてあとを追うように供給が発生する。
フィクションめいたこの仕事は、経済の循環の上に成り立っている。
蠍は金のために人を殺し、作為的に命を奪っては生活している。人の命を奪うことに何ら抵抗はなく、罪悪感もない。かと言って快感もやり甲斐もなく、単に存在するのは金が手に入るという事実だけだった。
仕事として、人を殺す。蠍は、一度だけ経験のあるスーパーでのバイトを思い出した。商品のバーコードを読み込み、レジを打つ。あれと、本質的には何も変わらない。淡々とレジを打つように、淡々と、ごくごく自然に死をもたらす。
需要へ対する、ひとつの供給として。
だれかの殺意の代弁者として。
誰かの殺意を叶えるために。
蠍は、一番人が集まっている、ステージ前のテーブルへ目をやる。
その人だかりの中心に、今回のターゲットがいる。
富田重五郎(とんだじゅうごろう)。経済界の重鎮、と呼ばれてる男だ。
富田がどんな男なのか、蠍はほとんど情報を持たない。知っていることはといえば、仲介業者から聞いた“経済界の重鎮”という称号と、写真を見て記憶した彼の見てくれだけだ。あとは、誰かに恨まれる程度には悪事に手を染めているのだろうなという事。たったそれぐらいだが、蠍は不足に感じない。これから殺す相手など興味の対象ですらない。
蠍は遠目に富田のことを眺め、記憶に眠る彼の写真と比較する。恰幅のいい腹回りに、ほりの深い鼻筋。シワの多く刻まれた顔にわざとらしく乗せられたひげが、いかにも威厳らしさを醸し出している。間違いなく、富田本人だった。後ろにはボディガードと思しき男がひとりいるが、そのほかにそれらしい人物は見当たらない。富田に群がっている人の塊がいささか邪魔だが、逆に言えばその群衆に紛れて彼に近付くこともできる、と蠍は踏んだ。何点か気になることはあったが仕事の遂行に問題はないだろうと、高をくくった。
それにしても、と蠍は思う。
富田に近づいていく人間は皆、確認をしに行くようだった。私はあなたの敵ではありませんよ、もしくは、あなたの同胞ですよ、という確認作業が延々と続けられている。それほど、富田は恐ろしいのだろう。いやそれとも、富田の甘い蜜を啜れるとでも思っているのだろうか。富田に近づくことが自分の利益になる、と。めまぐるしく入れ替わる小さな人間たちを、富田はいちいち覚えてはいないのだろうなと想像して苦笑する。自分が思っているほど、相手は自分のことを気にかけていないものだ。それならばいっそ、私はあなたに敵意があります、と言ったほうが名前ぐらいは覚えてもらえるのではないか、と思う。まあ、そのあとのことは知ったことではないが。
蠍はそのまま、富田という人間をしばらく観察する。
外見上は威厳があるものの、おおらかな人間ではありそうだった。顔にベッタリと張り付いた作り物の笑みは、きっと長年の人生経験で作り上げてきたものだろう。不意に背後から話しかけられても、くるりと笑顔で対応する。おおよその人間はきっとあの笑顔で騙し通せる。たったさっき給仕姿の女とぶつかったが、紳士的に「大丈夫かい」と声をかける姿など、理想的な好々爺であった。
まあ、暗殺の依頼が来ている時点で、それが本当の姿かどうかも怪しいものだが。きっとあの笑顔の裏には何かがあって、それを隠すために一生懸命に仮面をかぶっているのではないかと、蠍はどうしても疑ってしまう。善人の皮をかぶった悪人。
蠍は不意に、仲介業者の言葉を思い出した。今回の依頼を投げてきた業者は、教訓めいてこういった。
―――本当の悪人は、笑顔でやってくるのだ、と。
***
ちょっと気になることがあるんだけど、と言うと、電話口で男は、金髪美女だ、と答える。
何が。
俺の好みのタイプだ。参考になったか。
今すぐそっちに向かって、こしらえる死体を変更してもいいのよ。
それは、やめていただけるとありがたいな。俺はまだ死にたくはない。
そう、と私は小さく呟いた。今回はとりあえず、見逃すこととする。
で、と男は言う。なんだよ、気になることって。
富田に一人、ぴったり張り付いてる奴がいる。
ファンかもな。
だといいけど。
私はそこで言葉に迷うが、脳内で生じたかすかな直感を口にする。
―――同業者かもしれない。
電話の向こう側の空気が変わるのがわかった。何、と男は低くつぶやいた。
直感、だけど。
いいや、直感は案外当たるもんだ。
どうすればいい?
うーん、と男が小さく唸っているのが聞こえた。重複依頼は勘弁してくれよ、ほんと、と愚痴を言ったのも確かに聞こえた。
仕事には? と男は聞く。
ちょっと邪魔かも、と私は正直に答える。
もし遂行に支障が出そうなら、排除してくれて構わない。
了解。
少々手間が増えるだけだ、そう思いながら電話を切る。こってり絞ってやらないとな、と男がつぶやいたのが聞こえた。
***
電話を切って、蠍は再びデッキへ戻った。何食わぬ顔でもとのテーブルまで戻り、再び富田の周辺に目をやる。富田の周辺には、相変わらずの人だかりがあった。蠍はうんざりする。人が多い分、想定外が起こりやすくなるのは事実である。あの雑多に紛れて近づくことは可能かもしれないが、そもそも仕事が遂行できないことも考えられる。失敗した時のことを考えると、蠍の表情はどうしても苦々しくなる。今回の報酬が手に入らないだけなら、まだ百歩譲って許せるが、それよりも信頼を失ってしまうのが怖かった。
信頼されなければ仕事は回ってこない。仕事が回ってこなければ、自分で探しに行くしかない。そうすると、誰も手を出さないような仕事にまで手を出さなければいけない。誰も手を出さない、というのはすなわち誰もやりたくない仕事であり、概して気分のいいものではない。一度だけ、一般人の家庭に乗り込み押し込み強盗まがいのことをしたことがあったが、ああいったことは、できればゴメンだ。あの時泣きついてきた少女の顔は、今でもたまに枕元に出てくる。
あれから、いくつもの仕事を成功させてきた。お金を得て生きていくために仕事をこなしていったというのももちろんあるが、むしろあのような仕事を二度とやりたくないという気持ちもあった。おかげさまで、今では汚れ仕事に手を染めずに済んでいる。
そういった意味では、信頼というものは創造の難しい一種の情報なのかもしれない。と蠍は蠍なりに社会を考察する。信頼の失墜は仕事の減少を招く。
そのあたりは、一般の企業と一緒なのだ。
所詮、殺し屋という職業だって経済の輪からは逃れられない。
蠍は軽く目を閉じて、自分の動きを立体的にシミュレートする。富田に近づき、靴に仕込んだ針を刺すだけの簡単な仕事だが、周囲に人間がいるというだけで不測因子が指数関数的に増大する。その一つ一つを、蠍は頭の中で潰していく。成功する確率をより高め、仕事へ臨む。
今回の問題点は、いかにして周りの人間の意識を外へ向けるか、だ。殺し自体は非常に簡単に、しかも手短に済む。針を刺し終え、私が船をあとにする頃には富田は地に伏しているだろう。こんな簡単な仕事、中学生だってできる。まあ、あくまで不測因子の存在しないコントロール下での話だが。
だが、実行に移せる人間は少ないだろう。
人を殺すことに抵抗のない人間など、なかなかいるものではない。
人は人を殺すことを嫌う。それは生物として間違ってはいない。我々はあくまで動物なのだ。種の繁栄という、原則的かつ根本的な原理を埋め込まれた哺乳類だ。同族殺しなど、その本能が許しはしない。
この世界には、“どうして人を殺してはいけないのか”という、ふざけた質問がある。幸いにも蠍はその質問に出会ったことはないが、全く考えたことがないわけではない。
そんなことを聞く子供には、ナイフを握らせてやればいい。そして「ほら、殺してごらん」というだけでいい。大抵の人間はそっとナイフを置く。
それでいいではないか。
わかっているのだ、本能は。命を奪うことがどれだけのことか、人は本能的に理解している。それをあえて言語化する必要はない。
人を殺すことがどういうことか、蠍は経験的に理解している。―――たがが外れるのだ。全てにおいて。
本能を押さえ込むまでに肥大化した理性によって、すべてのたがが外れる。物事の加減がわからなくなり、喜怒哀楽すらも希薄化する。善悪の概念は消失し、生きていくためにどんなことでもするようになる。そしてそれらの全てに罪悪感を覚えず―――やりがいすらも感じない、無味乾燥な生になる。
一言で言い換えよう。
人間ではなくなる。
人間としての何かを失う。
そして、ドラッグと同じように、一度きりなのだ。
一度“殺し”を覚えてしまえば、もう戻れはしない。
蠍はゆっくりと目を開ける。シミュレーションのつもりが、いつの間にか脳内が雑念であふれかえってしまった。集中できていない、と感じる。最近仕事が続いて疲れているのだろうか。
これが終わったら、どこかにゆっくりと旅へ行くのもいいな、と蠍は思う。それに十分な資金はきっと手に入るはずだ。そうだ。そうしたら、しばらくは肩の荷をおろしてどこかでゆっくりしよう。世間から離れて、ひっそりと。それがいい。
さて、と息をつく。そしてそのまま、電話をしても気にされないような位置まで移動する。
まずは、この仕事を片付けなくては。
***
やるよ。私がそう言うと、男はポカンとする。もちろん、電話の向こう側で、だが。
そんなことでわざわざ報告しなくていいよ。
と男は言った。
私は電話を切る。
そっとテーブルの上に手を伸ばした。
***
電話をかけていた腕を下ろし、蠍は海を眺めながら一息をつく。何度コールしても仲介業者が出ないので、蠍は首をかしげたくなるが、まあ電話をかけるのは仕事のあとでもいいかと思い返す。不安要素は忘れ去ってしまおう。仕事へ向かう前に、精神を落ち着ける。一番怖いのは不測因子でもなく己の単純ミスであると、蠍は経験的に知っていた。大事な局面で一番頭が働くようにしておかなければなるまい。
その時だ。
急に頭が重くなる。少し遅れて、首筋がじわっと熱くなる。
何が、と言おうとして、全く声になっていないのに気がつく。そこで初めて、喉が貫かれているのに気がついた。視界の下には、赤く染まったテーブルナイフが見える。
ああ、刺されたのだ、と蠍の頭はいたって正常に機能した。どこか他人事めいた現実感に襲われる。
激痛が体の内側でのたうちまわる。声を出そうにも喉は潰され、傷口から笛のように空気が漏れる。視界の淵がわずかに黒ずむ。
「あんた、邪魔なのよ」
耳元で少女の声がした。なんの悪い冗談だ、と思う。皆殺しにした一家の、あの泣き顔の忘れられない少女の声にそっくりだった。いや彼女は確かに殺したはずだと、蠍は自問自答する。きっと、似ているだけだ。あるいは、似たように聞こえているだけだ。
続いて、どん、と背中が押されると、視界が反転する。落ちているのだ、と気がつく。水面へ向かって落とされているのだ、と。
唐突に死を直感する。不思議なことに走馬灯のようなものは見えず、ただただゆっくりと自由落下していくだけだった。
耳元で、少女の声がする。
―――ようこそ。
今度こそは、正真正銘彼女のものだ。彼女が地獄の入口で待っている。
蠍の視界は徐々に狭くなる。狭くなった視界の中心に、少女が佇む。
そこにいたのは、給仕の格好をした小さな女だった。
***
少女は階段を小走りで駆け上がる。屋上につき、少し重い扉を開くと、ギイイ、とさびた音とともに人工の明かりがきらめく。港に近いこの繁華街はそれなりに賑わっていた。種々の音が混ざり合った雑踏が、街という個体を生み出している。この街は確かに、有機的編制を持っていた。
ここからは港の船がよく見える。それにしてもまあ明るいものだ、少女は感心をした。あの富田という男がどれだけの金を持っているのかは知らないが、富田は強い光なのだろうと思った。そして彼に群がっていくのは、光に吸い寄せられた蛾だ。
ポケットで携帯が小さく振動する。肩にかけたギターケースを床におろし、少女は携帯の通話ボタンを押す。
『よう、元気か』
もちろん、元気です、と答える訳もなく。代わりに少女は悪態をつく。
「電話をかけるときは、必ず相手の安否を確認しなければいけない決まりでもあるのかしら」
『もちろんだ』
「聞いたことないわ」
『電話じゃあ相手の顔が見えないからな。相手を気遣うってことは大事なことだ。元気じゃなかったら電話している場合じゃないしな』
はあ、と小さくため息を履きながら、船がよく見える端の方まで移動する。意味のないコミュニケーションを続けながら、少女は着々と仕事の準備を進める。
「で、なんの用よ」
『同業者はどうした』
何だ、そのことか、と少女は得心した。
「殺したわ。今頃きっと海のもずくよ」
『もくず、な』
少女はハッとするが、知っていたわよ、と精一杯強がってみせた。電話口で男がフッと笑うので、少々頭にきた。
『どんな輩だったか、覚えてるか』
「女だったわ。黒いドレスを着て、スタイルのいい女。動きやすそうな格好じゃなかったけど、どうやって殺すつもりだったのかしら」
少女は携帯電話を肩と耳で挟み込み、あいた両手でギターケースを開ける。分解して詰め込んである銃のパーツを、淡々と組み上げていく。何千、何万回と繰り返してきた作業はすっかり両手に染み込んでいて、意識をせずとも勝手に手が動いていく。耳元からは、電話の向こうで男が何やら考え込んでいるのが聞こえる。
『・・・蠍かもな』
「蠍?」
『毒針を使って殺す業者だよ。見たことはないが、聞いた感じだと特徴は一致する』
ああ、と少女は合点がいった。毒を持った蠍、か。確かに毒々しい容姿だったかもしれないなと、皮肉めいて笑った。艶容なあの姿はある意味で蠍のグロテスクさと通ずるものがあったかもしれない。
まあ、それは追々こちらで調べるとして、と男は続ける。
『仕事の話をしようじゃないか』
もう仕事の真っ最中なのだ、と少女は悪態をつきたくなる。
『順調か、とりあえずは』
「無論よ」
『メイド服はどうした』
少女は質問の意図をつかみあぐねて、内心で首を傾ける。「もちろん捨てたわ」
すると男は心底残念そうな声を漏らす。少女は電話口でそれを聞いて、ますます首を傾げる。男が小さく『勿体無い』とつぶやくので、少女は「何が」と小さく答えた。
『お前のメイド服姿を見られるのは、そうなかなか無いからな』
ああそうですか、と少女は呆れてため息をついた。誰があんな、証拠にまみれた服を着たまま移動するのだろうか。肩に塗った蛍光塗料が見つかれば一発でおしまいなのに。そんなことを考えながら、いつの間にか少女の両手は弾倉に弾薬を詰めていた。
弾倉を装填し、レバーを引く。ガシャン、という小気味いい音と共に、すべての準備が整う。
『あ、お前俺の話聞いてなかったろ。今ガシャンって言ったぞ、ガシャン、て。相棒との会話は銃の組立の片手間、ってか』
「どちらかというと、相棒はこっちなのだけれど」
少女はそう言いながら、両手で抱えた黒く光る塊をなでる。外気に熱を奪われて、すっかり冷たくなった銃の表面が、今度は少女から熱量を奪っていく。少女は両目をつぶって、その感覚を両手で確かめた。
『辛いな、それは』
男があまりにも泣きそうな声を漏らすので、少女は思わず微笑んだ。仕事を前に時間の余裕もでき、少しだけ緊張がほぐれる。『あ、今笑った?』と今度は男が嬉しそうな声を出すので、少女は固く口を結んだ。
「さあ、そろそろふざけてないで仕事をするわ」
『はいはい』
少女は銃の先端を、屋上外周を囲むコンクリートの低い段差に固定する。照準がぶれないように何度か安定性を確かめ、しっくりと来る位置に今度は体を落ち着けた。ちょうど、少女は地面に腰を下ろして、段差に軽く足をかけ、背中を後ろに傾けるような格好になる。
少女は携帯電話を右肩で挟み、そのままスコープを覗き込む。小さな円の中には、貨客船上の雑踏が映りこんでいて、少女はその中央にある男を据える。
「あとどれくらいかしら」
『予定だと、あと一分もしないで富田大先生の演説が始まる』
了解、そう小さく答えたあと、少女は両目を閉じて深呼吸をする。精神を研ぎ澄ませるのだ。体内の酸素をすべて吐き出し、新たな空気を取り入れる。そしてそのまま両手に神経を集中する。両手がじんわりと熱くなると、その熱は銃に移行する。やがて銃と少女の間に温度差はなくなる。両手から神経や血管が銃の中に入り込むイメージを頭の中で克明に描き出す。やがて、銃と少女は一体になる。
最初からだ、少女はそう思う。最初に銃を握ったあの時からこうだった。黒い鉄の塊に自分の魂が移っていくような感覚があった。何年前になるだろうか―――少女の記憶は定かではない。ただ、自分の海馬の奥で何かが燻るような感覚だけが残る。
―――よく狙って撃てよ。
頭の奥で声がする。あの時の、声。
『そろそろだな』
電話口で男は言う。それを合図に少女は回想を打ち切って、ゆっくりと目を開ける。スコープの外は意識から除外され、小さな円形の世界に潜り込む。
『ご武運を、由那(ゆな)』
「まかせて、春市(はるいち)」
バツン、という音と共に船上の電気が落ちる。停電などではない―――富田が暗がりの中、ゆっくりと船尾にある壇上に移動する。サプライズ仕様にしたかったのだろう。まったく、偉い人間の考えることはわからない。
だがそれが仇になってしまうとは、今この瞬間も本人は気がついていないに違いない。
真っ暗になった船の上に、輪郭の曖昧な小さな光がぼうっと浮かぶ。
富田の背中―――ちょうど心臓の真裏が光る。
そこは先ほど、少女―――由那がぶつかったところだ。給仕の格好をして富田に近づき、ハプニングのふりをして富田にぶつかった。背骨と肩甲骨の間をめがけて。
給仕服の肩の部分には蛍光塗料がたっぷりと塗ってあったのだ。ぶつかった拍子に、当然塗料は富田の服に移った。しかしあんなに燦々とライトが照らされていては、誰も塗料に気がつかない。由那はそのまま船をあとにし、海上に服を投げ捨て、そのままこのビルの上まで移動してきた。近くから殺すのは―――あの蠍とかいう女は、きっとそうしようとしていたのだろうが―――あまりにもリスクが大きい。
由那は標準をゆっくりと定める。富田の背中にある白い光を追いかけていく。ステージの手前で一瞬動きが止まる。
風もない。
円の中心には白い光がある。
さあ、と頭の中で誰かが背中を押す。
―――さようなら
由那はそう小さく呟いて、右の人差し指に力を入れた。
***
「お前、今日が何月何日か知ってるか」
パトカーを降りた笹木(ささき)は不機嫌さをあらわにしながら、助手席から降りてきた後輩の円谷(つぶらや)に話し出す。
「12月25日です」
「そうだ。クリスマスだよ、クリスマス」
笹木がそうぼやきながら足をすすめるので、円谷は遅れじと後に続く。きらびやかなイルミネーションが流れるように視界をすり抜けていき、二人は浮き足立った世間を早足で駆け抜ける。
「なんで世間様がこうも浮ついている時に殺しなんか起きるかね。しかも銃殺だ、銃殺。きっとろくな事件じゃない。もう、クリスマスに人を銃で殺してはいけません、って法律作ればいいんじゃないの」
「クリスマスじゃなくてもダメですけどね」
あーあ、と笹木は小さくぼやく。そのままの足並みで繁華街を抜け、路地へ入っていく。ギラギラとうるさいほどの光から抜け出し、人気のない暗がりに足を踏み入れる。
その時、ドン、と何かにぶつかる感覚があって笹木は思わず足を止めた。目線を下にやると、制服を着た高校生くらいの少女が尻餅を付いていた。
「っと、すまねえお嬢ちゃん。おじさん急いでたもんでな。怪我はないか」
笹木がそう言って手を差し伸べると、少女は笹木の手を掴んで立ち上がる。大丈夫ですよ、と少女は小さく笑った。
「そうだ、今日は早く帰ったほうがいいぞ。最近はこの辺も何かと物騒だからな」
笹木は少女に忠告めいて伝える。何かと物騒とは曖昧な表現だなと、円谷は苦笑した。今まさに現在進行形でその“物騒”なことに遭遇しているというのに。
少女はそんなこともつゆ知らず、軽く礼をしてそそくさと立ち去った。
「しかしまあ」と笹木が感慨深そうに話し始めるので、なんだろうかと円谷は思わず耳を傾ける。
「ああいう純朴な女の子が、こういう事件の被害者にならなくてよかった、と思うわな」
「純朴ですかね、あの子」
そう言うと笹木が首をかしげるので、円谷は背中のあたりを指差した。
「ギターケース背負ってましたよ。しかもこんな時間に、繁華街の外れにいて。不良少女かなんかじゃないですかね」
「馬鹿野郎」と笹木は顔をしかめる。
「不良少女ぐらいなら、まだ可愛いもんじゃねえか」
そう言いながら、笹木は少女の背中をずっと目で追っていった。
しばらく歩くと視界が開けて港が見え、野次馬の殺到する船舶を見つける。笹木は鬱陶しい気分になりおながらも、人の塊をかき分け、規制線の所轄の警官に一礼して船に乗り込む。円谷は例にならってあとに続いた。船尾に近づくと、磯の臭いに混じって鉄臭い血の匂いが鼻をついた。笹木と円谷はポケットから取り出した手袋を両手にはめる。
小さなステージの上に転がっている骸に、二人は両手を合わせた。
「心臓を一撃か、えげつない事をするもんだ」
笹木は死体の胸のあたりをまじまじと見つめ、貫通した穴の大きさから銃口を推定する。しばらく考え込んで、おそらくはライフルのようなものだと結論づける。もちろん弾丸を見つけないことには確信できないが、船の上となると既に海の中という可能性の方が高い。目撃者がいないのが不思議だが、逆に言えば遠方からの狙撃である可能性が高いということでもある。
「笹木先輩」
円谷に呼び止められ体を翻すと、円谷はステージの隅の方で何やら地面を覗き込んでいた。
「ありました、弾痕です」
「でかした」
笹木は駆け寄って弾痕を確認し、銃弾を持っていたピンセットでかき出した。地面にはライフル弾が潜り込んでいた。遠方からの狙撃、という線で間違いはなさそうだ。
笹木は振り返り、想像力を働かせる。死体の立っていたであろう位置、その心臓の位置、弾痕―――線でつなげば、おのずと犯人のいた場所が見えてくるはずである。
そして―――見えてきたその場所に、笹木は言葉を失う。
「笹木先輩?」
円谷の問いかけに、笹木は指をさした。
「あそこだろうな」
その指を目で追って、円谷は思わず息を飲む。
その指の示す先には廃ビルと思しき古い建物があった。外観は煤けていて、屋上にも廃棄されたと思われる荷物が並んでいる。あそこなら簡単に隠れることができるのは想像に容易い。
だが、と笹木は心の中で否定する。
無理なのだ。
あの位置からでは。狙撃は不可能だ。
―――遠すぎる。
目算でゆうに300mはある。その距離で被害者の心臓に正確な一撃を食らわせるなど、対物ライフルでも使わない限り不可能だ。まったくもって常識の範囲を逸脱している。
異常だ。
笹木はいつの間にか頬を汗が伝っていることに気がつく。指先は軽く震えている。目を横にやると、円谷も神妙な面持ちで立ち尽くしていた。触れたことのない狂気にさらされて、いつの間にか恐怖を感じているのだと遅れて気がつく。
人殺しの現場を、仕事柄笹木はよく見ている。だがそれらのいずれにもこの現場は当てはまらない。えも言われない狂気を感じる。残虐性に、ではない。むしろ一切の残虐性を感じないことに、恐怖を感じる。あんな遠距離から、淡々と、確実に心臓を食い破る。純粋な目的のもとに生み出されるものは美しいという。単純で明快、どこか美しさまで感じてしまいそうな簡便さ―――そんな思考が頭をよぎり、笹木は思わず首を横に振った。だが思わずそう考えてしまうほど、この現場からは何も読み取れない。
殺意が存在しないのだ。単純に殺人という目的に特化しているはずなのに、一切の悪意が存在していないように思える。
まるで―――そう、仕事、をするかのような。
「いったい誰がこんなこと」答えがでないことを知っていて、それでも笹木は口に出さずにはいられない。頭の中をめぐる黒く霞んだ思考を吐き出してしまいたい衝動に襲われる。
―――悪魔だ。
笹木の中の何かがつぶやく。これは悪魔の仕業だ、と。あんなにも遠くから悪魔がこの男の心臓を食い破りに来たのだ。
そうであってほしい。
そうでなくてはならない。
こんなことができる人間が存在しているとは、信じたくもない。
不意に額に冷たい感覚があり、笹木は思わず飛び上がってしまいそうになる。見上げると、明く照らされた夜空から雪が舞っていた。
ポツリポツリと、雪の粒が地面に触れては溶けていく。ゆっくりと自由落下する雪は、やがて一粒の染みへと姿を変える。笹木はそこに自分の心情を重ね合わせる。染みはやがて大きくなり、やがて心を覆い尽くす。
佐々木は再び空に目をやり小さく舌打ちをした。
雪はまだ、止みそうにない。
人殺したちの歌―prologue
お読みいただきありがとうございました。

