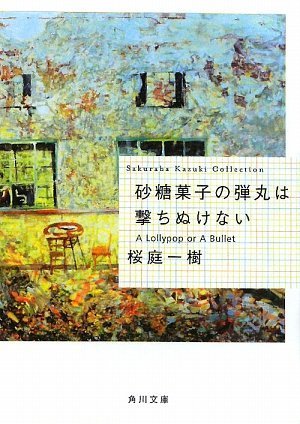夢幻の騎士と有限の夢
この小説は私が学生時代の最後に書いたものです。
それまで割と台詞が多い物を書いていたのですが、この小説は全編に渡り手記や独白などで構成されており、台詞は少なめとなっています。
分かる方には分かると思いますが、この小説の形式は東野圭吾の『悪意』を意識しています。
この小説の中にも多少の”悪意”が含まれているかもしれないので、その辺を感じていただければ幸いです。
タイトル通りこの小説には剣を持つ騎士が出てきますが、決してライトな内容ではありません。
あくまで文学を意識したつもりですので、敬遠せずに読んでいただきたいと思っています。
或る日の君と僕
「牧村くんの小説って、いつも主人公の男の子を、かっこいい女の子が助けに来るよね。私、こういう話って好きじゃないんだ。どんなに辛くてもいつかは誰かが助けてくれるって考え、私は本当に大嫌い。ねえ牧村くん、現実では、こんな子が助けに来てくれることなんて、絶対にないんだって分かってる? 自分から変わる努力をしない人間には、どんな良いことも起きはしないんだって、あなたは分かってる? あなたが、どんなに辛かろうと、どんなに助けを求めようと、誰も助けてはくれないのよ。昔の私がそうだったようにね……」
三田村さんは自身の胸に手を置いて目を瞑っている。
「これまで言わないようにしていたけど、この際だから言わせてもらうわ。私は、あなたのそういった他力本願なところが嫌いだった。あなたはいつも、自分が不幸なのは他の誰かのせいのように言うけど、本当は違う。あなたが変わろうと思えばいつだって変われた。なのにあなたは、その努力を怠ってきた。それに、もし変わることが出来ていれば、人はあなたを決して嫌いになったりしなかった。あなたが殻に閉じこもり続けるから、みんなあなたのことを好きになることが出来なかったのよ」
三田村さんはそう言うと、今度は僕に背を向けた。僕はその背中をどうしたらよいか分からず黙って見続ける。
「牧村くんが小説に逃げちゃう気持ち、私にも分かるから、そういうことを決して否定したりはしない。だけど、そうやっていつもいもしない女の子を妄想して、それで人生満足してしまっている様なら、あなたは間違っているわ。そんな小説では、誰も感動しないし、あなただって虚しいだけだわ……」
洟をすする音が聞こえる。声も僅かに震えているのが分かる。最後に彼女は、少し声のトーンを下げて言った。
「散々酷いことを言ってしまってごめんなさい。でも、これだけは覚えておいて。私だって変われたんだから、あなただってきっと、変われるんだってことをね……」
三田村さんはそのまま僕と目を合わせることなく文芸部室を出ていった。後には、呆然とする僕だけが残された。
そんなこと、言われるまでもなく知っていたさ。
漫画や小説の様な、愉快なボーイミ―ツガールなんてあり得ない。少年は誰とも出会わない。少女は彼の横を素通りしていく。ただつったているだけの、情けない子供を残して、一人で成長していく。僕は取り残される。永遠に大人になれずに、河原で一人誰かを待っている。
分かっていた。全部僕は知っていたんだ。自分の考えていることが、いかに無謀な妄想であるか、僕は良く知っていたんだ。
僕の前に現れる少女などいない。僕を好きになってくれる少女などいない。僕を好きな所へ連れて行ってくれる少女なんていない。僕が放課後の教室で抱きしめてあげられる少女なんていない。僕と唇を重ねてくれる少女なんていない。僕と身体を重ねてくれる少女なんていない。いやしない。
ぐらっと身体が揺れる。僕は力なく教室の壁に寄りかかる。そしてそのまま地面に腰を下ろす。僕は片手で顔を覆いながら、意味もなく笑っていた。涙を両目から溢れさせて、心は悲しさと惨めさで溢れているのに、僕は笑い続けていた。
変わる努力を怠っていた訳じゃない。僕だって頑張ったんだ。だが結果が出なかった。僕の決意は打ち砕かれ、俯いていることしか出来なくなったんだ。そんな僕に残されていたのは、やはり小説しかなかった。小説だけが、僕を癒やす唯一の手段だったのだ。
自分が変われたからって、人もそう簡単に変われると思わないで欲しかった。三田村さんは何も分かってない。彼女の様な不理解な人間が、僕の様な弱い人間を追い詰めるのだ。
気付くと僕はいつも小説を書いていた。僕の大好きな少女を、僕は夢中になって描いていた。そんな彼女がいないなんてこと、僕だって知っている。だけど、それでも、僕はまだ、素敵なボーイミールガールを信じていたかったのだ。だって、それが僕の心を唯一守る方法だったのだから。それを失ってしまったら、僕は足元から溶けてなくなってしまうと思ったから。
何を言われようと構わなかった。妄想だって構わなかった。妄想であっても、彼女がいてくれるならそれでよかった。僕の少女は僕が妄想した通り現れると信じるより他に、僕には方法がなかったのだ。
僕は立ち上がり、服に埃を付けたまま、ふら付いた足取りで教室のドアに手を掛けた。鉄扉の様に重いそれを、僕は静かに開いた。廊下にはもう、誰もいなかった。
「微かなことにすがったっていいじゃないか。大好きな女の子を妄想したっていいじゃないか。僕の狭くて苦しい世界を変える様な存在が、いたっていいじゃないか……。三田村さん、君には分からないよ。君には、一生、理解なんて出来ないよ……」
僕の声は、誰もいない教室に、虚しく響いていた。
牧村光士郎の手記
1
彼女があの様な状態になっている今、僕がこんなことをしている場合ではないのは重々承知している。だが、僕はどうしてもこれまでのことを文章として残しておかなければならないと思ったのだ。
僕がこの手記を残す理由は、ひとえに僕が今のこの状況を整理したいという思いがあるからだ。
これまでの十七年間、僕にも色々な事態が降りかかってきた。時には氷の様に冷たく、時には春の木漏れ日の様に温かく。だけども、これほどまでに不思議で、理解出来ないことは、僕には全く経験のないことだった。
僕が経験している事柄にはどんな意味があるのだろうか。僕はそれを知りたい。僕はこれを解き明かすことで、彼女の気持ちを知ることが出来るのではないかと考えている。だからこそ僕は、この数日で体験したことをまとめる必要があるのだ。
この文章を記す理由として、小説書きの血が騒いだのだろう? と問われれば、僕は決して否定はしない。恐らくそれもまた一つの事実だ。まるで自分自身が物語の主人公にでもなったかの様なこの体験を、記さないというのはあまりにももったいないことだ。不謹慎であることは分かっている。だけど、僕は生まれ持っての生粋の物書きとして、この衝動に駆られることはやむを得ないことなのだと思う。これは恐らく、彼女とて理解してくれるはずだ。
だがそういった心があったとしても、僕が彼女の為にこの文章を記していることだけは絶対に揺るがない真実だ。誰かに嘘だと言われる筋合いはないし、もしそんな人がいるなら、僕はその人に対して何時間だって違うと言い続けるだろう。
前口上が長くなってしまったが、これから僕が体験したことを書き記していこうと思う。そしてそこから何かしらの仮説を立てることが出来ればいいと、僕は思っている。
2
五月八日水曜日、僕は学校を出ると、いつも通り最寄りの駅まで一人で向かった。左右に小さな雑居ビルが立ち並ぶ大きな通りを抜けると、大きなロータリーが眼前に広がってくる。そしてその一番奥には、ガラス張りの三階建ての幾分か古びた駅舎が佇んでいる。駅舎の前の道路にはバス停がいくつかあり、この駅と付近の駅などをバスが結んでいる。僕は辺りでせっせとチラシを配っている青いポロシャツと青い帽子のコンタクトレンズ屋の店員と思われる男からチラシを受け取りながら、左回りで駅舎の正面までやって来る。そこまで来ると、今度は視線を元来た方へと向ける。そして目の前にあるバス停にまで歩みを進めた。
時刻は十五時二十分。バスが来るのは三十分だからあと十分ほどだ。僕はバス停の前で列を作っている学生たちの後ろに並ぶと、そそくさと肩に下げていたバッグから文庫本を取りだす。それはお気に入りの作家の小説で、この前ブックオフで三冊ほどまとめ買いした中の一冊であった。
僕は栞が刺してあるページを開くと、黙々と文字を目で追い始めた。その途端、ロータリーの喧騒は、僕の耳から全てシャットアウトされた。車のエンジン音も、学生たちの話声も聞こえない。僕の耳にはただ、物語の登場人物たちの話す言葉だけが届いてきていた。
不意に背中に衝撃が走った。僕は転びそうになりながらも、なんとか右足だけで身体を支え、本から顔を上げた。すると僕の前方には、先程並んでいた学生の姿の代わりに、一台の見慣れたバスが停まっていた。後方の人物が何やら僕に文句を言っている。どうやら僕がなかなかバスに乗り込まないことに対して怒っている様だ。僕は後ろの人物に対して軽く頭を下げ、「すみません」とだけ言ってバスに乗り込んだ。
バスの座席は空席が目立っていた。それもそうだろう。だってこのバスは住宅街の方には向かわないのだから。このバスの最終目的地は中心地から外れた所にあるとある病院。僕は毎日そこに通っている。その他の乗客はその病院に向かう途中にある寂れた旧市街地に住んでいるのだろう。
僕は入口のすぐ近くの一人用の座席に腰を下ろすと、手に持ったままだった文庫本の指を挟んでいたページを開く。そしてまた自分の世界に浸りこむのだった。
バスのアナウンスが終点を告げる。僕は慌てて栞を挟み、バスの先頭に向かう。定期をタッチし、バスの運転手に軽く会釈してからバスを降りた。僕の後ろに乗客はいない。どうやら僕が最後の乗客だったようだ。
バスを降りて二分ほど歩くと、前方に住宅と住宅の間から赤茶色の建物が現れる。以前はもっと古びた外装だったが、数年前の大改修で外は随分と綺麗になり、看板のデザインも一新された。ただ、中は昔とたいして変わってはいないのだが。
古びた住宅街を抜けると、病院の全体像が明らかになる。僕は足早に病院の正面玄関に向かう。建物の中に入ると、僕は靴箱から群青色のスリッパを取りだし、床に無造作に放り投げる。そして自分の靴を靴箱に入れると、床のスリッパを履いた。
自動ドアをくぐり、受付には向かわずにそのまま左折する。パタパタと廊下を歩いていると、頭の上の方で機械音が鳴り、箱の様なものが僕の上方を通り過ぎて行った。僕は音のする方に視線を向けた。天井に張り巡らされたレールの上を機械の箱が走っていた。それは僕から離れていくと、受付の近くで左折し、僕の視界から完全に消えた。実はあれにはカルテが入っている。前に診てもらった時に医師が僕に関するカルテをその箱の中に入れてレールに流しているのを見たのだ。内装が古ぼけている割に、使っている機械は近未来的なのがこの病院の不思議なところだ。
廊下を抜けると左手に売店がある。僕は売店に寄ることにした。店は駅の売店ほどの大きさしかなく、商品はあまり充実していない。僕はいつもの様に明治のミルクチョコレートを手に取りレジまで持っていく。店員がチラリと僕の顔を見る。僕は気にせず百円と五十円玉を出す。店員は黙って十円玉を三枚僕に手渡した。
売店を出ると僕はエレベーターに乗り込んだ。四階のボタンを押す。途中二階で別の人が乗り込んできた。その人はパジャマ姿で点滴をぶら下げている。見たところ七十過ぎのおじいさんの様だった。四階に着くと、おじいさんはフラフラっとした危うい足取りでエレベーターから出て行く。僕は『開』ボタンを押したままおじいさんの姿を見送り、その後でエレベーターから出た。
廊下は僕の眼前と、左手に伸びている。僕は正面の方に真っすぐ進み、途中でおじいさんを追い抜いた。彼女の部屋は四○七号室だ。エレベーターのすぐ近くが四○一号室だから、そこから少し距離がある。と言っても僕の足ではほんの二十秒ほどの距離だが。
部屋の前に辿り着く。プレートには、四○七号室と書いてある下に、『真辺梓』と名前が書かれている。僕は二回だけノックする。返答はない。だが僕は気にせず扉を開けた。
部屋の奥の窓が開け放たれているお陰で、気持ちの良い風が部屋の中に吹き込んでいた。僕はベッドの方へ歩みを進めた。そこには、目を閉じて眠り込んでいる女の子の姿があった。黒くて長い髪はほどかれて無造作に枕に投げ出されている。彼女からはかすかに寝息が聞こえるだけで、それ以外には何の物音も聞こえない。僕が入ってきても、起き上がって迎え入れてくれることはなかった。
僕は彼女を見下ろした。可愛らしい寝顔がそこにはあった。目を閉じていても分かる、意思の強さを反映している様なつり眼、日本人離れした高い鼻、そして吸い寄せられる様に魅惑的な厚い唇。そのどれもが僕にとっては愛おしくて、そして同時に堪らなく僕を辛い気持ちにさせた。僕は風で乱れた彼女の髪の毛に触れる。そして優しく整えてやった。
僕はベッドの横に置いてある椅子に腰を降ろした。そしてベッドに備え付けてあるテーブルの上にさっき買ってきたチョコを置いた。
僕は少しの間彼女の寝顔に語りかけた。今日学校であったことや、彼女の友達がこんなことを君に言っていた、といったことだった。
風の音が痛く耳に届いた。僕はそっと彼女の手をとった。温かかった。鼓動が聞こえた。生きていると、僕は強く実感した。
静寂が辛かった。
いつしか僕は、彼女の手をとったままウトウトし始めていた。そしていつしか、僕の意識はまどろみの中に消えていった。
3
ふと目を覚ます。風が突き刺す様に冷たい。思わず身体が震えた。僕は身体を起こした。どうやら僕はベンチで眠りこけていた様だった。ベンチに手を触れると、そこは僕の体温ですっかり温かくなっていた。
僕は呆けた頭のまま辺りを見渡した。辺りは真っ暗だった。太陽は既になく、いくつもの星たちが空を埋め尽くしていた。やけに澄んだ星空。まるで、冬の空の様だった。辺りにはいくつか街灯があり、また建物にも電気が灯っている箇所があった。
僕はどこで眠っていたのか? 寝る前の記憶がなくて、僕はここがどこなのかを確認するために、付近の建物に目を凝らした。
「さむっ……」
意識がはっきりしてきて、改めて寒さに驚いた。春の陽気じゃなかった。手がすっかりかじかみ、身体が小刻みに震えていた。
まるっきり冬だった。
何かがおかしい。そう思って僕は勢いよく立ち上がった。すると、僕の視界にあるものが飛び込んできた。僕はそれをはっきり見るために、その正面に回った。一瞬、僕は自分の目を疑った。だってそれを僕が今見ているはずがないのだから。僕は先刻まで病院にいたんだ。その僕が、あの時あの子と一緒に見たあれを、見ているはずがないのだから。
僕は怖くなった。だから僕は誰かを呼ぼうと声を出した。
「だ、誰か、誰かいませんか……?」
お腹から声を出したつもりだった。だけどその声は情けないほど脆弱な音を響かせただけだった。だがこれだけの静寂なら、この程度の声でも誰かには届くだろうと僕は思った。しかし、いくら待っても人っ子一人やって来る様子はなかった。だから僕は堪らず走りだした。適当にそこら中の建物の中に入り、部屋をノックしたりした。だが、やはり誰一人いない様だった。
僕はもう一度さっきの場所に戻ってきた。やはりそれはそこにあった。それは、有名な政治家の銅像だった。彼はここ、W大学創始者としても知られている。その人物の銅像が、僕の眼前にあったのだ。そうだ、ここはあの全国的に良く知られているW大学の本キャンだったのだ。
創始者の像は、一度あの子とここを訪れた時に見た。あの時僕たちは、二人で再びここに来ることを誓った。だが、見たのはそれ一度きり。それから二人で訪れたことはないし、当然一人で来たこともない。だいたい、ここに来るには電車を乗り継いで来なければならない。僕はさっきまで病院にいたんだ。こんな所に来られる訳がなかった。
「牧村くん」
不意に女性の高い声が僕の名を呼んだ。僕は驚いて心臓が止まりかけたが、なんとか心を落ちつけ、声の主の方へ振り返った。そこにはクラスメートの赤間千鶴さんの姿があった。茶色のロングヘアーにアイドルの様に可愛らしい顔、そしてうちの学校の制服であるこげ茶色のブレザーにチェックのスカートの姿で、彼女はそこにいた。彼女は笑顔のまま僕のことを見ていた。それは普段学校で見る時と全く同じだった。その可愛らしさで学校中の男子の注目を集める彼女は、チアリーディング部に所属している。そんな彼女はなぜかこんな僕とよく話をする。とは言っても、その内容は大抵他愛のないことなのだけれど。
「牧村くん、こんな所で何してるの?」
彼女は笑顔で尋ねる。だが聞かれたところで僕には分からなかった。そもそも、ただでさえおかしな状況なのに、そこに赤間さんまで出てきてしまったら、奇妙な状況に拍車がかかってしまうと、僕は思った。
僕が何も答えられないでいると、先に彼女の方から口を開いた。
「じゃあさ、あたしが何をしているかをまず教えてあげようか?」
それは是非聞きたいと思った。彼女の答が何かしらの道しるべになるなら、聞いておいて損はないだろうからだ。だから僕は「教えて」と彼女に言った。
僕の言葉に赤間さんがほほ笑んだ。そして満面の笑みのまま、
「あたしは、あなたを手に入れるためにここに来たのよ」
と、はっきりと言った。意味が分からなかった。学校一のアイドルである彼女が発した突拍子もない言葉に、僕は耳を疑ってしまった。『僕を手に入れる』だって? それはあまりに馬鹿げた発言だった。僕は、もしかしたら僕の頭がおかしくなってしまったんじゃないだろうかと思った。そうじゃなかったらこんなことあり得ない。彼女の言葉は、それくらい理解に苦しむものだったのだ。
「ねえ、牧村くん」
気付くと赤間さんの顔が僕の眼前まで迫ってきていた。いくら考えこんでいたとはいっても、一瞬でここまで接近されるなんて全く思ってもみなかった。赤間さんの吐息が僕の顔にかかり、ミントの様な爽やかな匂いが鼻の中に広がった。それは頭に靄がかかった様な感覚だった。彼女の言うままになりたい。そんな思考が頭を埋め尽くしかける。だが、僅かに残っていた僕の理性がそれに歯止めを掛けた。そして今度はあの子の顔で僕の頭の中を埋め尽くしていった。
「駄目だ」と、僕は大声で言った。そして僕は彼女の元から一目散に走り出した。銅像から離れると、右前方に古ぼけた黄土色の建物がある。そして左には工事中を示す大きな囲いがあり、そこにはこの大学の歴史を表す建物の写真などが貼られていた。僕は立ち止まらず、そこから更に走った。工事中の敷地を過ぎると、今度はこれまた古い四階か五階建ての建物が現れた。パッと見でも昭和初期頃に造られた歴史の詰まった建物である様だった。
しかし、そこで僕は気付いてしまった。聞こえて来る足音が、実は一つだけではなかったということに。一つは僕が懸命に走る足音なのは間違いなかった。だがもう一つは、人間とは思えない様な速さで僕を追いかける、ハンターの足音だったのだ。僕は恐怖した。あまりの速さに、背筋に悪寒が走った。
その時僕の視線の先に、有名なこれまた創始者の名を冠した講堂が姿を現した。そして講堂がある石造りの敷地の前方には、左右に伸びる二車線の道路があった。右手を見ると、そこから大きな道路に繋がっていることが分かった。近くにはバス停も見えた。僕はここしかないと思った。ここを辿れば、バスや地下鉄の駅などがあるはずだと、混乱する頭でも考えることが出来た。だから僕は少ない力を振り絞って、そちらの方面を目指そうと思った。
だが、残念ながらその時にはもう手遅れだった。僕が必死に走る横から、彼女が顔を出したのだ。僕は情けなくも思わず叫び声を上げてしまった。赤間さんが、またしても顔を僕に近づけながら、「ねえ、どうして逃げるの?」と尋ねた。
その顔からは、先刻の笑顔などとうに失せていた。僕は彼女の瞳のあまりの冷酷な色に再び身体が震えあがるのを感じた。何かがおかしい。こんな恐ろしい瞳を、赤間さんがする訳がないと、ぐちゃぐちゃの頭で僕は思った。僕は決死の覚悟で走るスピードを速めた。そしてなんとか道路を右折しようとした時だった。
背中に強烈な衝撃が走り、僕は自分の身体が浮遊した感覚を覚えた。そしてそのまま数メートル前方へと飛ばされ、無様にも地面に転がり落ちた。僕の目にはコンクリートとは違う、石の地面が見えていた。僕は倒れた状態のまま背中に手をやった。それは時折感じたことのある痛みだった。そう、それはあいつらに蹴られた時と全く同じものの様に思われた。僕はその時ようやく理解した。僕は、赤間さんに蹴り飛ばされたのだということに。
道路の方から足音が聞こえた。僕はその体勢のまま音の主を見た。
「牧村くんが逃げるからいけないんだよ」
と、愉快そうに彼女はそう言った。その顔は、まるで楽しいことをしている時の様な屈託のない笑顔だった。その笑顔がもし、いつもの教室で見られたのなら何も怖いことはない。だがそこは夜の大学で、しかも彼女は容赦なく僕を蹴り飛ばした後なのだ。そんな天使の様な笑顔が、その時の僕には角の生えた悪魔にしか見えなかった。
そう言えば、僕はさっき赤間さんの蹴りがあいつらの蹴りと同じ様と書いたが、それは大きな間違いだった。それはそんなやわな痛みじゃなかった。あまりの痛みに僕は立ちあがることが出来ないほどだったのだ。だがずっとそこにいれば、また彼女にあの強烈な蹴りをお見舞いされてしまう。だから僕は一刻も早くあの女から逃げなければならなかった。
しかし、その時僕は痛みのせいでどうしても立ち上がれずにいた。だから僕は、惨めにも虫の様に這いつくばってその場から逃げるしかなかった。
「逃がさないよ」
冷酷な彼女の声が響き、その手が僕をあっさり捕えた。僕は「放して」と必死に懇願するも、彼女は僕の言葉など全く聞き入れず、僕の襟首を掴み、僕の身体を石の地面に思いきり叩き付けた。
再び背中に衝撃が走った。息が出来ないほどの痛みが身体を走り抜けた。僕は絶え絶えになった息のまま、なんとか赤間さんを見上げた。瞬間、僕は恐怖した。彼女は唇をつり上げ、醜く笑みを浮かべていたのだ。
僕は動くことが出来ず、ただ地面に情けなく寝そべっていることしか出来なかった。赤間さんはしゃがみ込むと、膝と掌を地面につけた。そして上体を起こしながらも相変わらず寝そべったままの僕の方に近づいた。そして荒い息遣いで僕の足を赤間さん自身の膝で挟む様な状態になるまで僕に接近した。
赤間さんの顔は暗がりでもよく分かるくらい紅潮していた。息が絶え絶えの僕とは違った意味で呼吸を乱している。すると不意に、彼女の両手が僕の両肩を掴んだ。そして僕の身体を引っ張り上げ、そのまま、
――僕の唇を奪った。
彼女の息が直接体内へ流れ込んでいく。身体が麻痺する様な、毒気にやられる様な感覚に襲われた。一方僕は何が起こったのか分からず、そのまま茫然として動くことが出来なかった。更に彼女は僕の頭を両手でがっちり掴んだ。そして今度は自身の舌を僕の舌に絡めてきた。彼女の淫猥な声と舌が擦れ合う官能的な音が僕の頭に響いた。
しばらくして彼女は僕の唇から自分の唇を離した。彼女は口の脇に残っている唾液を拭くこともせず、僕の足を挟んだまま膝立ちの状態でいる。尚も僕が朦朧とした意識で、茫然と彼女を見ていると、彼女は驚くべき行動に出た。
彼女は着ていたブレザーのボタンに手を掛けたのだ。彼女はブレザーのボタンを上から全て外すと、サッとそれを脱ぎ、後方へ投げ捨てた。すると今度は自身の胸元のリボンにまで手を伸ばした。
僕は慌ててそれを止めにかかるが、彼女に思いきり顔面を叩かれてまた地面に落ちてしまった。その隙に彼女はリボンを外し、ブラウス姿でその紅潮した顔を僕に向けた。
これ以上は本当にまずいと思った。もしこんな所を人に見られたらどんな誤解をされるか分かったものじゃない。その時人の影は見えなかったが、本来ならば大学の生徒や教授などがそこを通っても全くおかしくないはずだった。警備員が近くにいる可能性だってあった。それに僕には、あの子がいるのだ。そんな僕が、ここでそんなことをする訳にいかなかった。
あれこれと考えている内に、ついに彼女はブラウスのボタンにまで手を伸ばしていた。抵抗する僕を彼女は左手一本で抑えつけながら、自身のボタンを右手だけで器用に外していった。
上から一つずつボタンが外れ、その下の桃色の下着が露わになっていく。着痩せするタイプなのか、彼女の胸は思ったよりも大きかった。僕はもうそれ以上彼女のあられもない姿を見ていることが出来ず、目をつぶって抵抗を試みるしかなかった。
しかし、その時だった。
「赤間、千鶴!」
怒声が闇夜に響き渡った。すると、僕の身体に覆いかぶさっていた重みが消えた。僕が目を開けると、もうそこに赤間さんの姿はなかった。だが、眼前にはさっきの赤間さんよりも信じられない光景が広がっていた。僕は何度も目を凝らした。だが、それは全く消える気配がなかった。頬をつねっても、頭を叩いてみても、ただ痛みがするだけで、世界は全く変動する気配がなかった。
僕の目がようやく眼前の状況を正確に捉える。そこには二つの人影があった。一つはブラウスの前を開けて下着を露出させたままの赤間千鶴の姿だった。だが、もう一つを僕はすぐに理解することが出来なかった。
全身から放たれる銀色のオーラ。右手に握られているのは、まるで中世を彷彿とさせるような銀色の剣。そして腕や足、更に上半身全体を守る銀色の鎧。まるで百合の花を思わせる白色のドレスの様なスカート。それは戦士の物なのか、それともお姫様の物なのか分からないが、剣を持っているその人は、紛れもなく騎士であった。
だが驚いたのはそれだけではない。その騎士の顔には見覚えがあったのだ。いや、見覚えなんてチャチなものじゃない。それは確信だった。僕は彼女を知っている。どんな格好をしていようとも、一目見た瞬間に確信した。黒の長い髪の毛を銀色に変化させ、その髪を黒のリボンで結んでいる。瞳の色はブラウンではなく幾分か青くなっているが、それでも僕は見間違えなかった。意思の強さを反映している様なつり眼、日本人離れした高い鼻、そして吸い寄せられる様に魅惑的な厚い唇……。間違いない、彼女は、僕の大切な人である、真辺梓その人であった。
それが僕と、白銀の騎士との、冬の夜の邂逅であった。
4
「梓なのか……?」
僕の問いかけに白銀の騎士は答えない。言葉を発しないどころか、眼前の赤間さんを睨みつけたまま微動だにしていなかった。一方胸をはだけさせたままの赤間さんも同様に騎士を睨んでいた。睨み合う二人は、真夜中の大学のキャンパスには全く似つかわしくないと僕は思った。
すると、黙ったままだった赤間さんがようやく言葉を発した。
「あたしと牧村くんとの時間を邪魔するなんて、あなた、一体どういうつもり?」
随分と勝手な言い草だと僕は思った。僕は彼女と時間を共にするつもりなんて最初からない。そう思った時、白銀の騎士は言った。
「勝手なことを言わないで。彼はあなたなどと身体を重ねたりしない。同意もなしに身体を奪おうだなんて、身勝手すぎると思わない?」
その声はやはり、真辺梓そのものだった。敵に対してはとことん冷淡な口調なあの子そのものだった。
「そんなこと、やってみなければ分からないじゃない? 男はみんな野獣なのよ。彼らはみんな、女の裸を見れば本性を現してくれるわ。それは、彼とて例外ではないわ」
赤間さんは勝ち誇った様にそんなことを言った。だが、騎士は全く動じた様子は見せず、逆に吐き捨てる様に言った。
「くだらないわ。あなたでは彼を手に入れることは出来ない」
そう言って騎士は、その剣を赤間さんに向け、
「二度と彼に近づけない様に、今ここであなたを殺してあげる」
と、残酷な言葉を浴びせた。
彼女は剣を構えた。それと同時に、赤間さんも何やら体勢を整える。だがこれではどう考えたって赤間さんが不利だ。武器を持っている相手に丸腰で挑むなど、自殺行為に等しい。戦いの結果など、火を見るよりも明らかな様に思われた。僕はこのままでは、本当にあの子が赤間さんを殺してしまうと思った。確かに赤間さんは僕を誘惑したが、それで殺してしまうというのはいくらなんでもやり過ぎだろう。僕は、あの子を殺人者にする訳にはいかないし、クラスメートが目の前で殺されるのを黙って見過ごす訳にもいかなかった。僕は痛む背中をおさえながら、ヨロヨロと立ち上がった。しかし、結果としてそれが恐らく合図になってしまったのだろう。僕が立ちあがると同時に、二人が互いに飛びかかってしまったのだ。互いの怒声が響いた。
人間同士の戦いなど、これまで僕はテレビの格闘技などでしか見たことがなかった。あれだって所詮はスポーツだ。本気で命まで取ろうとはしていない。それは剣道やフェンシングの様に剣を使った競技も同じだ。目的はあくまでポイントを稼ぐこと。殺し合いをするためのものではない。
目の前で繰り広げられている光景は、まさにその殺し合いであった。剣を振るう騎士に向かって、人間であるはずの少女が真っ向から立ち向かい、その騎士の息の根を止めようとしている。騎士は騎士で、少女の人外の動きに対応しつつ、生命を奪うために首に狙いを定めている。それはまるでハリウッドのアクション映画の様だった。だが目の前の光景はフィクションではない。それは本当の、本物の人間であるはずの二人の殺し合いだったのだ。
そんな戦いの前で、僕なんかに一体何が出来ただろうか? 何も出来る訳がなかった。それは止めよう、止められると考えていた自分が馬鹿らしくなるほどの戦いだった。手を出せば僕の命が危ない。そう感じさせるほど鬼気迫るものだったのだ。
戦いは、僕には随分と長い時間続いていた気がしていたのだが、今考えると、それは恐らくほんの数分のものだったはずだ。それだけ二人の動きが速すぎて、僕には捕えらことが出来ないほどだったのだ。僕に分かったのは、戦いの最中、赤間さんの身体が徐々に傷つき、血を流し始めていたということだけだ。
不意に静寂が訪れ、しばしの睨み合いの時間が訪れる。だがそんなものも一瞬だ。勝負の原因が、二人の力の差なのか、それとも彼女の油断なのかは分からない。どちらにせよ、その一撃で勝負は決まったかに思われた。踏み出したことすら分からなかった騎士が、一跳躍で赤間さんの元まで飛んでいき、防御態勢を取ろうとした彼女をあざ笑うかの如く、鋭い剣撃で彼女をなぎ払ったのだ。
赤間さんの腹部から血が噴き出した。騎士の銀の剣も、真っ赤な血で染まった。
僕は自分の身体が震えていることに気付いた。騎士の剣から、血が滴り落ちる度に、心臓が爆発するかの様に脈打った。
血だらけの赤間さんは、騎士の足もとで呻いていた。だが騎士はそんな様子を気にも留めず、両手で柄を持ち、刃を彼女の脳天へ向ける。僕はこのままでは、あの子が、梓が赤間さんを殺してしまうと思った。そんなことは絶対に許せなかった。許しちゃいけなかった。あの子が殺人者になることを、僕は決して許す訳にいかなかった。だから僕は必死で走った。どこが痛かろうと関係ない。その時の僕にはもう何も関係なかった。
「駄目だ! 梓、やめて!」
僕が叫ぶ。彼女の目が僕を捉えた。僕は彼女のその瞳に、初めて人間らしい感情が宿っていることに気がついた。彼女の口が動いた。だが声は聞こえなかった。あまりに切羽詰まっていて、彼女の言葉を聞き取ることが出来なかった。
瞬間、あの子の短い叫びと共に、あの子の身体が十メートル後方に吹き飛ばされていくのが僕の眼に入った。彼女は辛うじて両足でバランスを取り、転倒を防いだ。だが、彼女の左腕の甲冑は壊れ、細い白い腕が露わになっていた。その白い腕も、流れ出した血ですぐに真っ赤に染まった。そして彼女が纏っていた銀色のオーラも霧散してしまっていた。
僕は急いで赤間さんを見た。彼女はブラウスを血に染めながらも、どっしりと地面に仁王立ちしていた。ブラウスの間から見える生傷はとにかく生々しく、血が溢れだしていた。なのに、彼女は倒れなかった。あんな状態になりながらも、無傷の騎士をその拳で殴りつけたのだ。赤間さんの形相は、まるで鬼のお面の様になっていた。あの可愛らしかった彼女や、先刻見せた様な淫猥な雰囲気は、もうそこにはなかった。ただ騎士の命を奪うだけの悪魔になってしまったのだと、僕はその時感じた。
騎士は左腕を押さえながら苦悶の表情を浮かべていた。その様子を見て、完全に人外となり果てた赤間千鶴が、血に染まった白銀の騎士へと突進していった。どちらも手負いには違いなかったが、赤間千鶴と白銀の騎士では、傷によるダメージに大きな違いがある様に思えた。だから僕は、騎士にはもう勝ち目がないと思った。しかしその時、霧散してしまっていたあの銀色のオーラが、また彼女の元へ集まっていくのが見えた。そしてそれは、彼女全体ではなく、彼女の傷ついた腕だけを包んだのだ。すると騎士の表情が痛みを訴えるものから、戦いのみに集中するものへと変わった。
そんな騎士に向かって、悪魔が飛びかかった。だが騎士はその場から動かなかった。ジッと目をつむり、剣を構えていた。その時僕は、騎士の勝利を確信した。どんな格闘漫画や映画でも、無駄な動きをした方が、戦いには負けるものなのだ。
騎士がほとんど見えない位の速さで剣を振った。瞬間、悪魔と化した赤間千鶴の首が跳ね跳んだ。生々しい鮮血が、首のない死体から溢れ出した。まさに一瞬の早業だった。
騎士は目を開けると、一度大きく息を吐いた。そして血に濡れた剣を、持っていた布でふき取り、それを鞘に収めた。
僕が何も言わずに佇んでいると、騎士がこちらの方に顔を向けた。彼女は僕を視界に捉えると、無言のまま僕の方へ歩みを進めた。白銀の騎士が僕へと近づく。僕が口を開きかけると、先に彼女が言った。
「光士郎が無事で良かった」
それは温かみのある、彼女本来の言葉だった。
途端、さっきまで何事もなかった世界が揺らぎ始める。強烈な地震が起き、僕の足元をグラグラにしていった。そしていつしか、僕の視界すらも波を打った様に揺らめき、やがて、何もかもが、見えなくなった。
5
目を開ける。ぼやけた僕の目には、学ランの袖と机が映り込んだ。僕は顔を上げ、呆けたまま教室内を見回した。教室では生徒たちが思い思いに昼食を食べていた。僕の座席は一番左奥の席だ。ここからなら教室中の全ての生徒の動向を把握することが出来た。
僕は隣の席に目をやる。空席だった。それはそうだ。この席は四月の初め頃からずっと空席なのだから。僕は眠気眼をこすりながら、自分の鞄に手を伸ばした。当然、昼食をとるためだ。
「牧村くん」
その時誰かに声を掛けられた。僕に声を掛ける様な人間は限られている。クラス委員の長谷川さん、数少ない友達である早坂君、顔見知りの杉山暁、そして、赤間千鶴くらいだろう。
赤間さんはアイドルの様に笑顔全開で僕の方に近づいてきた。学校中の憧れの存在である彼女は、なぜかいつも僕の席にやって来る。話す内容は本当に大したことはない。僕と彼女では趣味が違い過ぎるからだ。それでも彼女は飽きずに僕に話しかけてくる。
「あれ、牧村くんお昼まだなの?」と彼女は僕に尋ねた。見ての通りでございますと、僕は母親が作ってくれた弁当を彼女の前で広げてみせた。僕は一度教室の前方にある時計を見た。時刻は十二時四十分だった。昼休みは十二時十分からだから、もう既に三十分は経過していた。
「あ、もしかして牧村くん寝てた? ほら、頬っぺた! 痕がついてるよ」
彼女は笑いながら僕の頬を指さした。僕は思わず顔を触った。彼女は楽しそうにそんな僕の様子を眺めていた。
「そっかー、ご飯まだだって分かってたら、一緒に食べたのに」
彼女は僕の前の席に腰掛けながら、そう残念そうに言った。
「え、一緒に?」
「そう、一緒に。……なに? あたし何か変なこと言った?」
「いや、別に……」
僕はしどろもどろしながら再びご飯に視線を移した。ご飯を掴む箸がほんの僅かだけ震えていた。女の子の前では基本僕はこんな感じだ。オドオドしているせいで、よく気持ち悪がられてしまう。平常心でいられるのは、世界でたった一人の前だけだ。
ふと、遠くで彼女の名前を呼ぶ声が聞こえた。恐らくチアリーディング部のメンバーだろう。彼女は大きな声で返答を寄越すと、サッと立ち上がった。そして僕に対して「じゃあね」と言うと、小走りでその人の元に向かった。
僕の周りに平静が訪れた。彼女が過ぎ去った所にはいつも誰もいない。彼女はまるで台風の様な人だと僕は思った。僕はまた黙ってご飯をつつき出した。するとそのすぐ後に、また聞き覚えのある声が響いた。
「また赤間と喋ってたのか。相変わらずモテますな、牧村よ」
僕は何も言わずに鮭の塩焼きを箸でほぐし、それを口に持っていく。
「なあ聞いてるのか? 牧村」
無視していると、その男は僕の顔を覗き込むようにして話し掛けてきた。
「そんなんじゃないよ。赤間さんは僕みたいな人種が珍しいだけだと思うよ」
僕の前の席に座ったのは杉山暁だった。彼とは友達未満知り合い以上の関係だ。彼は僕よりも、梓の友人だった。梓が女子バレー部で、杉山は男子バレー部に所属している。梓が彼と仲が良かった縁で僕も少しばかり話すようになったというだけだ。まあ、それももう昔の話だが。
「そうかねえ。俺はそんなことないと思うぜ。あいつは絶対にお前に気がある。俺も色々と経験してるけど、あれは間違いないだろうな」
杉山は長い前髪をクルクル回しながらそう言った。そしていつも通りに携帯電話を取りだし、LINEやらtwitterをいじり出した。彼は画面を見ながらニヤケ面をする。そして小さな声で「マジかよ、あいつバカだな」と言った。僕が気にせず残ったきんぴらごぼうに手をつけていると、彼は携帯をいじりながら言った。
「どうせなら付き合っちまえば? 赤間と付き合えれば、お前にも箔がつくと思うぜ」
彼は凄いスピードで画面に指を這わせていた。まるで今言った自分の言葉すら、自分は責任を取らないとでも言うかのようだった。
「杉山くん、それ、冗談で言ってるんだよね……?」
僕の質問に彼は答えなかった。面倒なのか、それとも本当に聞いていないのか分からないが、彼は結局何も答えずに立ち去ってしまった。僕は残ったきんぴらとご飯を一気に口にかき込むと、力を込めて蓋を閉じた。そしてまた、僕は机に突っ伏した。
放課後、僕は教室を出ると、フラフラっと体育館の方へ向かった。僕は文芸部に一応所属しているけど、現在はほとんど幽霊部員状態だ。つまり帰宅部も同然ということだ。そんな僕にとって放課後の学校など居づらいだけだ。だというのに、その日の僕はなぜか体育館に足が向いていた。
体育館は教室から直接繋がっておらず、一度外に出てからでないと入れない。そして面倒なことに、体育館に入るには体育館用のシューズが必要なのだ。僕は運動部には入っていないが、体育の授業は当然受けていた。よって僕も体育館用のシューズを持っていた。だけど、その日はそれを持って行かなかった。ちょっと立ち寄るだけだし、中に入ろうとまでは思っていなかったからだ。
僕は体育館の入口までやって来た。ただ入るのには勇気が必要で、僕は途端に尻込みしてしまった。僕は止むなく体育館の別の開け放たれている扉から中の様子を窺うことにした。丁度体育館の左側の扉が開いていた。僕がそこから中の様子を窺っていると、不意に誰かに声を掛けられた。
「やあ、久方ぶりだね。君も覗き見かい?」
話し掛けてきたのは、やたらと爽やかな人物だった。彼はまるで、お金持ちばかりが集まる高校でホスト部でもやっているかの様に端正な顔をしている。彼の名前は鳳元(おおとりげん)。この学校の生徒会長だ。面倒見がよく、誰に対しても優しいと評判の人物だ。かくいう僕も一度お世話になったことがある。彼の人柄は評判通りのものだった。
「あ、いや、別にそういう訳じゃ……」
「いいさいいさ、男なら覗きぐらいして当然だ」
彼は笑ってそう言いながら僕の背中を軽く叩いた。僕は鳳さんにここに来た理由を聞くと、彼は「当然覗きだよ」としれっと言ってのけた。
しばらく僕らは近況を話し合った。彼はあの事件から僕のことをずっと心配していてくれていたらしく、結構しつこく僕の現状を聞きたがった。
「大丈夫そうなら良かった。あんなことがあったら、不登校になってしまう生徒だっている。君の心が強くて良かった」
彼はそう言ったが、実際は僕の心が強かったからという訳じゃない。それは、彼女が、梓がいてくれたからだ。あの子がいなかったら、僕は鳳さんが言うように不登校になっていただろう。
そう言えば、彼は他にこんなことも言っていた。
「あの事件に関しては、僕はまだ調査を続行している。実は最近になって有力な情報を得てね。しつこく通い詰めたら、若干ばかり口を割ってくれたんだ……。うん、そうそう、中根雄二ね。完全に話してくれるのも時間の問題だと思うよ。裏で糸を引いているやつがいたなら、そいつも処分を受けなければ平等じゃない。君がどう思っているのか分からないけど、少なくとも僕はそう考えている。君がどうしてもやめろと言うのなら、やめないことはないけどね」
生徒会長は案外粘着質だという話も、どうやら嘘ではないらしかった。
彼は一通り話し終わると、体育館で活動中のチアリーディング部の方に視線を移した。チア部ではやはり赤間さんがダントツに目立っていた。他にも可愛い子はいるが、あそこまで可愛い人の前では霞んでしまう。体育館で活動中の他の部員たちも、恐らく赤間さんのことばかり見ているに違いなかった。
僕は鳳さんの方へ視線を移す。彼はどうやらジッと赤間さんを見ているらしかった。珍しく僕がふざけた調子で言った。
「鳳さんは赤間さんにご執心みたいですね」
「そんなんじゃないよ、どちらかと言えば……」
彼はそこで一度言葉を切る。そして体育館から視線を逸らし、そこから歩き去ろうとする。その去り際、彼はこう言った。
「僕は彼女が嫌いなんだ」
彼はそう言い残すと、もうこちらには振り返らずにその場から立ち去ってしまった。僕は彼の言葉の意味を計りかねて、ただただそこに立ちつくしていた。
6
その日も僕はいつも通り病院に向かった。いつも通り病院行きのバスに乗り、いつも通り病院の売店で明治のミルクチョコレートを買った。そして、いつも通りそのチョコレートを彼女のベッドの脇に置いた。
僕自身あまり甘い物は好きではない。だから普段からチョコやビスケットといったものを好んで食べたりはしない。僕がチョコを買うのは、あの子の大好物が甘い物だからだ。決して食べてくれないと分かっていても、僕はどうしてもそれをお見舞いの品として持ってきてしまうのだ。
彼女のベッドの脇には、前日買ってきたチョコがそのままの状態で残されていた。うっかりしていた。どうやら前日持って帰るのを忘れていたらしい。彼女のお母さんに処分させるのも忍びないので、自身で処理してしまうことにした。
売店でコーヒーを買って再び病室に戻る。そして久しぶりにミルクチョコの袋を開けた。中からはカカオの甘いにおいが込み上げてきた。僕はチョコを歯で割る。すると思いのほか一口分が大きくなってしまった。僕は仕方なくその大きな欠片を頬張ると、カリカリ音を立てながら咀嚼し、缶コーヒーでそれを喉の奥に流し込んだ。そしてそれを何回か繰り返した。
チョコを食べ終わると、僕はウトウトとしてきてしまった。そう言えばその前日もそこで寝てしまった様な気がするが、なぜだかその時の記憶がやけにぼやけていた。その時の僕は、正直に言うと、何時にここを出たのかも覚えていなかった。
彼女の手を握りながらも、僕の視界は段々とぼやけていった。もし眠るとしたら一時間程度にしておこうと僕は思い、目を閉じた。
身体が震えた。あまりの寒さに目を覚ました。辺りはすっかり真っ暗だった。灯りは見えるも、人の話声はなかった。
僕はまだぼんやりとした頭で歩き出した。すると、足元に何かぶつかった。僕は、目を擦りながらそれを見やった。
首のない死体だった。
あまりの恐怖に気が動転し、柄にもなく叫び声を上げてしまった。急いでその場から逃げようとするが、地面に転がっている死体に足を取られてしまった。転んだ先には、鬼の形相をした人の顔があった。今度は声も上げられなかった。完全に腰を抜かしてしまったのだ。僕は地面に尻もちをついたまま情けなく後ずさりした。僕は動転しながらもその死体を観察した。それは、赤間千鶴の死体だった。その時僕は思い出した。彼女は、昨日あの白銀の騎士に殺されたのだということを。
しかし、それはおかしいと瞬時に気付いた。だって僕は先刻、教室で赤間さんと言葉を交わしたのだから。いつもの様に、いつも通りのあの笑顔で、彼女は僕の所にやって来たのだ。それに、鳳さんと一緒に、放課後チア部で活動する彼女を覗いたりもした。「僕は彼女が嫌いなんだ」という鳳さんの言葉だって、僕はしっかりと覚えていた。だからあれが全て嘘だった訳がなかった。だが、そこに転がっている死体と、赤間さんが死体になる瞬間も僕は確かに見た。生々しく飛び散る鮮血が嘘だった訳もなかった。
僕の頭はすっかり混乱していた。鮮明なのに、相反する二つの記憶。これを説明することが出来なくて、僕の頭はパニックを起こしたのだ。
「派手にやられたもんだな」
突然背後で声がした。僕は瞬間的に振り返った。そこには、気だるそうな顔をした杉山暁の姿があった。教室で見る様に、彼は髪を無造作にはねさせ、学ランの前を開けワイシャツの第二ボタンまで外していた。首には銀のクロスのペンダントがついたネックレスが下げられ、腰にはチェーンがついている。それは確かに、僕の友達未満知り合い以上の関係の人物であった。
彼は物珍しそうに赤間さんの死体を眺めている。すると彼はポケットから携帯を取り出した。そしてなんと、あろうことか、赤間さんの死体をカメラで撮影し始めたのだ。僕は言葉を失った。彼は楽しそうに「すげー、キモー」とか言って撮影会を楽しんでいる。常軌を逸していると思った。死体を見るだけでも恐ろしいのに、写真を撮れる神経が僕には理解出来なかった。ましてやそこで死んでいるのは、クラスメートだというのに、どうして彼はそこまで無神経でいられるのだろうか。
「ほら牧村、やっべえぞこれ。マジキモイ、きゃははは。これtwitterに上げようかな。やっぱ駄目か、いくらなんでもヤバすぎるか」
僕はその時、ふとあの子の言葉を思い出していた。
――あいつは異常だよ。私は、あいつとの縁を切ることにした……。
それはある時僕の部屋で彼女が言っていた言葉だ。何があったのか彼女に問うと、彼女は苦々しそうな顔で答えた。「ストーカーをされている」と。それを聞いた時は、いくらなんでもそこまで彼がするかなと思った。彼は顔は悪いが、見た目には結構気を使っているためか、彼女がいつもいた。少なくとも僕が聞いた範囲ではだが。そんな彼が、クラスメートをストーキングすることが信じられなかったのだ。
だけど、その時僕は理解した。毎夜家の近くまで女の子を追いまわす杉山、死体を見てキャーキャー騒いでいる杉山。その二つがその時はっきりと重なったのだ。彼ならやりかねない。彼は危険だ。頭が恐怖で埋め尽くされた。だが、そのすぐ後だった。
彼の笑い声が消えた。水を打った様に、辺りは静まり返る。僕は恐る恐る、横の彼を見た。
彼の胸から、何やら棒の様な物が生えていた。棒の先端からは、赤い液体が滴り落ちていた。そしてその水滴が、徐々に大きな水たまりを作っていった。彼の顔は、笑顔のまま固まっていた。よく見ると、彼の口元からは、水たまりと同じ様な赤い液体が滴っていた。
棒が引き抜かれる。彼の身体が、ゆっくりと、まるでスローモーションの様に前のめりに倒れていき、バシャと、気色の悪い音を響かせて、彼の身体は地面に落ちた。少しの間ヒクヒクと動いていた彼の身体も、少し経つともう全く動かなくなった。
僕は首だけで棒の様な物が消えた方を見た。そこには、無表情で剣と杉山の死体を見比べている白銀の騎士の姿があった。彼女は刃についた血を振り払うと、それを素早い手つきで鞘に戻した。すると彼女は表情を変えずに死体に方に歩み寄る。
「この人でなしが」
彼女は血だまりの死体に対しそう吐き捨てた。僕はその様子をずっと固まったまま見つめていた。言葉など何も言えるはずがない。目の前で人が絶命していく様を見て、普段通りに振る舞える人などいる訳がない。例え、それをやったのが、自分の恋人だったとしても。
僕が固まったまま彼女を見ていると、彼女は僕の方に視線を向けた。まるで氷の様に冷徹な表情。それは時折彼女が見せる表情。憎むべき相手に対して、彼女は怒りを剥き出しにしたりはしない。いつも信じられないほど冷酷な表情をして相対する。それはまさにその時の表情だった。
「光士郎……」
彼女の表情が少し憂いを帯びたそれへと変わる。何でもいい。とにかく声を掛けてあげたかった。でも、口を開きかけた僕を彼女が遮った。
「何も、言わないで」
彼女は寂しそうに僕にそう言った。そんな彼女の様子が痛々しくて、僕はどうしても彼女を抱きしめてあげたかった。僕は苦しみから彼女を解き放ってあげたかった。でも、僕は彼女に触れることが出来なかった。目の前にいるのに、こうやって言葉を交わせるのに、僕は何も出来なかった。自分の無力さを、ただただ痛感するしかなかった。
彼女は儚げな顔のまま、何も言わずに僕の目から視線を逸らす。彼女との距離が僅かに離れる。僕はせめて彼女から離れまいと足を踏み出す。その時、白銀の騎士を月明かりが照らし出した。彼女の銀の鎧は、月の光を受けてより一層輝きを増した。彼女はまるで、夜空の一等星の様であり、闇夜に咲く一輪の花の様でもあった。
彼女はふと棒立ちの僕を見た。その表情は、まるで今にも泣き出しそうな、そんな雰囲気すらあった。彼女は一度唇を噛みしめ、寂しそうな顔で言った。
「光士郎、彼らには近付かないで……」
僕は学校での彼女を思い出す。僕が赤間さんと言葉を交わすと、彼女はいつも機嫌を損ねた。理由を尋ねてもいつも答えてくれなかった。でも、その時は、その理由も分かる気がしていた。梓が杉山とは関わらなくなった後も、杉山は僕に絡んできた。梓はきっとそれを不愉快に思っていただろう。自分をストーキングした男と言葉を交わすこと自体、汚らわしいことだったに違いない。でも大丈夫だよ。僕は二人に心を許していた訳じゃない。僕には君しかいない。君が僕の全てだ。だから、そんな顔をしないでほしい。そう伝えたかった。
だけど、僕の意識は、僕の意思とは裏腹に急速に薄れていった。言葉を、想いを伝えなければならないのに。たった一人で戦っている彼女に、伝えなければならないのに、僕の視界は真っ黒になっていった。
7
ここまで書いたことが、ここ数日で僕が体験したことだ。ちなみに僕が翌日学校に行くと、やはり赤間千鶴も杉山暁もピンピンした様子だった。あの凄惨な殺人は、現実で起こったことではなかったのだ。では一体、あれは何だったのか?
僕の仮説はこうだ。あれは、あの子の、真辺梓が見せていた夢だったのではないかということだ。僕は彼女の病室でこの夢を見た。それも決まって、彼女の身体に触れている時だったのだ。そして夢の中には決まって、彼女が現れた。それも決まって騎士の恰好でだ。
夢とはその人の精神世界が反映されるという。確かに彼女の性格から考えても騎士はピッタリの恰好だが、僕は彼女のそんな姿を想像したことはないし、僕が考え知れないこともあの夢には出てきた。よって、あれは僕自身が創り上げた夢ではないと考える。まあそもそも人に夢を見せるという発想も、かなり無理があることなのかもしれないが。それでも僕は彼女が夢を見せているという説を採用したい。僕はあの夢を二日続けて見たのだ。これに何も意味がないはずがない。
では、、あれには一体どんな意味があるのだろうか。僕はこう考える。あの夢は、彼女の願いそのものなのだと。梓は赤間千鶴を僕に近づけたくないと思っていたのは間違いない。でもその時は、彼女が僕を赤間さんの元から引き離すことは容易だった。だって僕たちは同じクラスだったんだから。でも今、彼女にそれは出来ない。僕から赤間千鶴を引き離す手段がないことに、彼女は苛立っていたはずだ。いくら僕を信じていると言っても、男という生き物は完全には信用出来ないのが世の常だ。それは夢の中の赤間さんも言っていた。
夢の中で、梓は赤間さんを殺した。それはつまり、彼女を僕に近づけたくないのに何も出来ない現状への不満を暗示しているのだと、僕は思った。彼女が本当に赤間さんを殺したいと考えているとは思わない。だが、あれほどまでに赤間さんを攻撃するほど苛立った強い想いがあったと考えることは出来る。梓にしては理性的ではなかったし、少し残酷すぎる気もしたが。
次に杉山に関してだが、彼に関しては言わずもがなだ。彼は梓をストーキングしたのだ。梓が彼を憎むのは当然だし、僕と口を利いてほしい訳がないだろう。夢の中で彼女は、杉山に毒を吐いていた。恐らくあれは彼女の本心だろう。問答無用で後ろから一突きしたところを見ると、憎しみも一塩と思われる。
以上のことからも、梓が赤間千鶴や杉山暁を僕から引き離したいのに、現状それが叶わないことをへの鬱憤から、先の夢を創り出したと言えると思う。このことは僕自身が撒いた種でもある。彼女に入らぬ心配をさせた僕の責任は重い。僕は彼女に誓わなければならない。僕は絶対に君を裏切りはしないと。
それを伝えるためには、現状僕には手段が一つしかない。それは、もう一度あの夢の中に行くことだ。夜の大学のキャンパスで待つ、白銀の騎士の元に行かなければならない。そして早く彼女を安心させなければならない。
とにかく、僕の仮説はこんな感じだ。本当に僕が彼女の本意を捉えきれているのか分からないし、そもそも夢はただ僕が見ているだけという可能性も否定出来ないから、詳しいことが分かり次第、また記していこうと思う。
僕は早く彼女の本意を明らかにしなければならない。彼女の笑顔を、もう一度見るためにも、早くなんとかしなくてはならない。
とある少年の日記
七月七日(木)
文芸部に入ってから二カ月以上たち、多少はみんなとも話が出来るようになった。話をしてみて気付いたのだが、ここには文学の才能を持つ人たちが実に沢山いると思った。その中でも、三田村さんは図抜けている。
文芸部一同で彼女の小説を読んでみたのだが、読み終わるや否や方々から称賛の嵐が起こった。そして僕もごたぶんにもれず、彼女の小説に感動を覚えた。彼女の描く物語は、頑張り屋の女の子が努力に努力を重ね、最終的に報われるという、ある意味では実にオーソドックスなものだ。だが物語に出てくる少女の健気さに読者は心を打たれ、その優しさに人々は引きこまれてしまうのである。優しく人の心を包んでくれる彼女の小説は、あまり感受性が豊かではない僕には描くことが出来ない繊細な文章によって形作られている。三田村さんは、いつも部室でお菓子を食べて友達を話しているばかりだと思っていたけど、本当は多分沢山の人生経験を重ねてきたはずだ。だからこそ、あれだけ良い文章が書けるのだと僕は思う。僕ももっと他人と関わり、感性を磨いて、彼女の様な文章を書いてみたいと思った。
ところで、彼女はかつてとある文芸賞で大賞を受賞したことがあるらしい。確かにあれだけの実力があればそれも頷けるというものだ。僕はこれまで数年文章を書いてきて少し有頂天になっていた気がする。人より文章が書けると自負していた部分があったのだ。だが、三田村さんの様な他の小説家の卵に触れあうことで、僕は自身の未熟さを痛感することになった。だが、僕はそれで自信を喪失し、書く意欲を失ってしまったかと言えば、もちろんそんなことはなく、前述したようにむしろ俄然やる気が出てきたほどだ。僕はこれまで以上に魅力的な文章表現を意識して書いていくことにしようと思った。
そう言えば、部活中誰かが三田村さんに賞状を見せてほしいと言っているのを聞いた。あれは確か、中根くんだっただろうか。彼はこの部活に入りたての頃僕に初めて話しかけてきてくれた人だ。彼は非常に熱心に人とコミュニケーションを取る。小説を書くのははっきり言ってこの部活の誰よりも下手だが、そういった他人と積極的に話すことは、僕はもっと真似をした方がいいと思った。そしてそれが感受性を磨く第一歩であるはずだ。
賞状に関しては僕も少し興味がある。僕はこれまで何かの賞を取るということとは縁遠かったから、何かに秀でている証をこの目で見ることは決して無駄じゃないと思う。恐らく小説を書く意欲もより向上するだろう。実に楽しみである。
それにしても、今日は珍しくこの日記を明るく書けた気がする。高校に入って三カ月経ってもまだ、僕には決まった友達が出来ていない。快適な学生生活を送り、もっと日記を楽しくする為にも、数日以内に是非とも友達を作りたいところだ。
今日は気分が良かったが、あの小説を少しばかり書いた。嫌なことがあった日と比べると、彼女の性格に多少の差が生まれている様な気がした。今日の彼女はただ優しいだけでなく、少し情熱的だった。僕の背中を押そうとしてくれた。僕は彼女の言う通り、もっと積極的に生きていこうと思う。そしてこれが一過性にならないように気をつけようとも思う。
変に思い悩んで、折角の良い日を台無しにしてしまってはもったいない。今日は少し早いがもう寝ることにする。今日はコーヒーも飲んでいないし、恐らくすぐに寝ることが出来るだろう。
では、また明日。
鳳元の独白
僕があのカップルのことを知ったのは、今から半年ほど前、ちょうど文化祭のシーズンだったと思う。丁度僕は生徒会長になったばかりで、色々な仕事に四苦八苦している時だったからよく覚えている。
事件が起こったのは十月四日の木曜日。文化祭の準備で慌ただしくなり始めた頃のことだった。事件の一報が入ったのが、放課後の十六時二十分頃だ。
現場である文芸部室に僕が駆け付けた時には、教室は色々な物が散らかり放題だった。机がいくつも倒れていて、部員のものと思われる鞄の中身が散乱していた。何があったのか僕は先生に尋ねた。するとどうやら、生徒が数名で一人の生徒を暴行したということのようだった。これが事実なら一大事だと僕は思った。と言うのも、この学校は進学校で、これまで大きな傷害事件が起きたことはなかったからだ。僕はそれから付近の生徒や、事件には関わっていない文芸部員に話を聞いた。事件のあらましはこんなところだ。
事件の被害者の名前は、牧村光士郎、十六歳、二年B組だ。クラスではどちらかと言えば目立たない引っ込み思案の生徒ということだ。事件当日彼がいつも通りに文芸部室に赴いたところ、突然数名の文芸部員に難癖をつけられたため反論。その際ヒートアップした部員が彼の両手足を拘束し、彼に殴る蹴るの暴行を加えた。そしてバランスを崩した彼が転んで倒れていた机に頭をぶつけ、気絶してしまった。被害者は若干だが出血していたため、驚いた部員数名が助けを呼びに行ったことで、事件が明らかになった、ということのようだ。ちなみにこの牧村という少年、人に対して悪口を言ったり暴力を振るったりということは皆無だったらしく、これまで部員たちと問題を起こしたこともなかったそうだ。
次に加害者について。事件の加害者は全部で四人。その全員がその後停学処分を受けている。名前は、秋山豊、中根雄二、西野弘毅、渡会正平。その中でも首謀者は中根雄二だったと多くの人が証言している。突然難癖をつけたのも彼だったらしい。その難癖というのは、今度の文化祭で発表する小説の案を、牧村くんが盗んだのではないか? ということだったそうだ。どうやらその数日前に、部活内で作品集を製作するために各部員が小説を書いて持ちよっていたらしく、牧村くんの作品が自分の考えたのにそっくりだったため、中根雄二は牧村くんが彼のアイデアを盗んだのだと考えたようだ。
事件の概要はこんなところだ。被害者の牧村くんはその後病院で意識を取り戻し、翌週には無事退院した。だが、仲間に暴行されたことへの精神的ショックから、学校に行くのを拒んでいるらしかった。気が弱い生徒だった様だし、彼の精神的ケアは大変そうだと、その時僕は思った。
ただ、僕は事件の全てを解明するべきだと思っていた。暴行をした生徒が処分されるのは当然だが、もし盗作があったのだとしたら、牧村くん自身も彼らに謝罪する必要があるのではと、その時僕は思っていた。だから僕は、彼が精神的ショックを受けているとは知りつつも、事件の詳細を尋ねるため、彼の自宅を訪れることにした。
彼の自宅を訪れると、出てきたのは彼の両親ではなく、うちの学校の生徒であった。彼女の名前は、真辺梓。年齢は十七、所属は牧村くんと同じく二年B組だ。僕がそこを訪ねた理由を話すと、彼女は怒って僕に言った。
「光士郎が人の作品を盗むなんてあり得ません。彼は心から小説を書くことを愛しています。小説書きにとって作品は命です。他人の命を奪うことなど、彼がするはずありません!」
僕は彼女のエネルギーに圧倒されてしまった。それと同時に、彼女が彼を思う気持ちが物凄く伝わってきたのだ。
彼女と話した後、今度は牧村くん本人に話を聞くことが出来た。彼は多少話しづらそうにしていたが、隣に座っていた真辺さんに励まされて、ようやくあの事件に関して口を開いてくれた。彼は一貫して中根雄二たちが言っていたことを否定した。僕は盗作なんてしていない。彼らが突然訳のわからないことを言いだしただけだと。彼の目は真剣そのものだった。彼はその盗作されたという作品についても語ってくれた。どうやらその作品は、真辺さんをモデルにしたヒロインが登場する物語らしかった。彼が今まで知った彼女のイメージを小説にした作品であり、心から好きな作品であると彼は教えてくれた。それを盗作だなんて言った中根雄二たちのことが許せないとも彼は言った。僕は彼が嘘を言っているとは思わなかった。彼の眼の奥に、小説を書くことへの熱い想いを感じ取ることが出来たからだ。それは、中根雄二には感じなかったものだった。
僕は彼らの話を元に、中根雄二たちを問い詰めた。すると驚くことに、全員口を揃えて盗作した牧村くんが悪いと言っていた彼らが、事件に関してこれ以上一切の証言をしないと言いだしたのだ。自分たちは停学の処分を受けたのだからもういいではないかと言うのだ。もし最初からそのことを言わなければそれでもいいだろう。だが彼らは、牧村くんの名誉を傷つけかねない証言をしたのだ。そのことに関して責任を取らないその態度は許しがたいものだった。
結局、彼らの証言は嘘であったということが教師や生徒には認識された。一応は牧村くんの名誉が守られ僕は安堵した。しかし、そうするとあることが疑問として残る。それは、もし盗作が嘘なら、彼らはなぜ牧村くんに難癖をつけたのかということだ。彼らの間にはこれまで目立ったいざこざはなかった。むしろ同じ小説好きとして活発な意見交換があったほどだ。そんな彼らの対立に何の理由もないはずがない。だから僕は決意した。この件に関しては、僕が納得出来るまで徹底的に調べてやると。
そして先日、このことに関する重大な証言を入手した。それは、僕がしつこく通い詰めていた中心人物の中根雄二がふと漏らしたことだった。彼は言った。
「しょうがなかったんだよ。あの時はああするより他になかったんだから……」
それは含みのある言葉だった。まるでやりたくないのにやらざるを得なかったとでも言いたげな言葉。僕はピンときた。この事件、裏で糸を引いている人間がいる。
ある時生徒がこんなことを言っているのを聞いた。
「生徒会長って、優しくて面倒見が良くて、凄く良い人だよな――」
おっと、自慢じゃないよ。彼は最後にこんなことも言っていたんだ。
「会長ってあれで実は、…………かなり粘着質らしいよ……」
そう。まさに彼の言う通り。僕は粘着質だ。一度くっついたら嫌でも離れない。恋愛もさることながら、こういったなぞ解きに関してはそれが如何なく発揮される。そしてようやく僕は、尻尾を掴んだ。もう逃がさない。彼にはしかるべき処分を受けてもらう。そして、謝罪してもらう。牧村くんと、彼を心から信じ続けた、あの、眠り続けている少女にね。
そうだ、ちょうどいいから、ここで少しばかり個人的な話をさせてもらうことにしよう。
僕には妹がいる。とても可愛く、活発な女の子だった。“だった”ということは、すなわち今は違うということだ。彼女を壊したのは、とある事件だった。
それは僕が中学三年生の時の話だ。僕の妹、美紀は当時中学二年生だった。僕の家族は、両親と僕たち兄妹の四人家族だった。だがある日、父との不仲から母が家を出ていった。我が家はそこから急速に活気を失っていった。そしてそれは唐突に起こった。
妹がある夜突然、僕の部屋にやって来た。僕は美紀に、どうしたのかと問うた。だが彼女は答えなかった。彼女は無言のまま僕のベッドに潜りこみ、そしてそのまま寝息を立て始めた。僕は少し心配だったが、母がいなくなってショックを受けているのだろうと解釈し、そのまま寝ることにした。
しかしそれから、妹は日に日に生気を失っていった。理由を尋ねても、彼女は答えなかった。僕は思い切って妹を問い詰めることにした。取り返しがつかなくなる訳にはいかなかったからだ。僕が彼女に尋ねても、初めは、理由を全く言いたがらなかった。だが僕はそこで譲ったりはしなかった。僕は粘着質だ。絶対に引かないと分かると、美紀はようやく諦め、僕に何があったのかを話してくれた。
「お父さんが部屋に来て、わたしの服を無理やり脱がして、それで、それで……」
耳を疑った。彼女は大粒の涙を流し、僕に告白した。父親が娘を犯すなど、あっていい訳がないことだった。僕は許せなかった。あいつを殺してやろうとさえ思った。その日僕は、妹を父に渡さない様に、一緒のベッドで寝た。そしてそれは、その時のことだった。僕は、牧村くんと同じ様な体験をしたのだ。そしてもうその時には、悲劇は始まっていたのだった。
牧村光士郎の手記 其の二
1
これから記録は一日ごとにつけていこうと思う。まとめて書いていると、その時の僕の行動や誰かの言葉などが曖昧になってしまうことがあるので、出来るだけ正確な記録を残したいと思う。
本日は五月十三日の月曜日。土日は僕の家の都合があったせいで病院には行けなかった。よってあの夢の世界にも金曜日以来行っていない。だが、僕がこの手記を書いているということは、つまりはそういうことだ。僕は今日あの世界に行った。あの真っ暗で冷たい、白銀の世界に。その時の様子を述べていこうと思う。
いつもの様に僕は彼女の病室に行った。彼女はいつも通り窓際のベッドで横になって目をつむっていた。ベッドの脇のミルクチョコレートはなくなっていた。恐らく、看護師さんが処分してくれたのだろう。
僕は自身の仮説に絶対の自信を持っていた訳じゃなかった。ああは書いたが、彼女の想いを取り違えている可能性が高いと考えていたのだ。だから僕は、それを確かめるためにも、今日も彼女のあの夢に連れて行ってほしいと思っていた。そして夢の中の彼女に、僕が直接問いかけたいと思っていた。
僕は彼女の手を取った。温かくて、柔らかいその手を。
不思議なことに僕は彼女の病室に行く時間帯になると急に眠気が襲ってくる。それはだいたい四時から五時までの間だ。その日病室に行ったのが四時三分だった。だから彼女の手を取る頃には程良い眠気が押し寄せていたのだ。僕はすぐに眠りにつくことが出来た。
あの世界での目覚めはいつも最悪だ。だっていつも物凄い寒さによって強制的に起こされるのだから。あの寒さはやはり冬の寒さなのか。僕と彼女があの大学を訪れたのが十二月の冬の日だったから、もしかしたらそのイメージがこの世界に反映されているのかもしれない。もっとも、僕らがキャンパスを訪れたのは昼間だったのだが。しかし、今日に関しては、僕はその寒さで起こされた訳ではなかった。僕はぬくぬくとした温かさの中で、腕のしびれを感じて目を覚ましたのだから。
僕は辺りに目を凝らした。どうやらここはこの前とは場所が違うようだと思った。赤間千鶴の惨殺死体も、杉山暁の血みどろの死体も辺りには見当たらなかった。そこは図書館だった。柔らかな灯りに、沢山の本の数。周りには長机が何台も置かれていて、その一つ一つに椅子が六個ずつ用意されている。右側には大きな窓ガラスがあり、そこからキャンパスの夜の灯りが見える。見たところこの図書館はキャンパスからは僅かにだが離れているようだ。といっても大きな門と、一本の道路を隔てている程度だが。
ちなみに腕が痺れていたのは、僕が自分の腕を枕にして眠り込んでしまっていたからだ。僕はよく小説を書きながら眠ってしまった時にこうやって寝てしまう。夢の中の僕もご多分に漏れずそういった性質がある様だった。
しかしそれにしてもなぜ今回は図書館なのか。確かに僕は前にここを訪れた時、尋常じゃないこの図書館の蔵書量に思わずテンションが上がってしまったものだが、この夢においてここが重要だとはあまり思えなかった。というのも、あの白銀の騎士と本とはあまり関係がなさそうだからだ。僕は彼女が近くにいないか確認する。いつも通りで人の気配が全くしなかった。いつも突然人が現れるからもうあまり驚かないが、やはり人は誰もいない様子だった。僕はやることもないので、とりあえず本の山をチェックすることにした。
ただ少し残念なのだが、この図書館の蔵書量は半端でないのだが、いかんせん小説の量が少なすぎるということだ。むしろ皆無と言ってもいいほどだ。と言うのも実は、この蔵書の大半は学術書であり、大学生が日々の研究に利用するのが専らなのである。噂によるとここではなく戸山キャンパスの方が小説が充実しているということだ。どうせなら向こうの図書館に行っておくんだったと僕は思った。しかしそうそう文句ばかり考えていても始まらない。僕はとりあえず適当に一冊の本を手に取ることにした。
手に取った本を見て、僕は思わず声を上げてしまった。なんとその本の作者の名前が、
「真辺、梓……」
あの子の名前だったのだ。小説のタイトルは、『幸せの法則』。中身は知っている。この本は、あの子が前に僕に読ませてくれたものだったのだ。
小説の主人公は引っ込み思案な女子中学生。その子がある日、意中の男の子に手紙で告白するのだが、男の子はその女の子のことを振ってしまう。実はその男の子には好きな女の子がいたのだ。女の子はそのことで落ち込んでしまうのだが、そこから男の子を振り向かせるために、数々の努力を重ねていく。彼の趣味や、行きたい所を調べたり、彼の好みに近づける様に洋服を作ったり、料理の練習をしたりする。また彼女の友人たちも彼女をサポートし、彼女は徐々に彼が気になる存在にまで成長していく。一方その男の子が元々好きだった女の子は、そんな地道な努力を繰り返す主人公の女の子をバカにする。実はその女の子、魔女から魔法の力を借りて彼の理想の女の子に変身していたのだ。しかし男の子は女の子が本当は心の醜い人間だったということを知ると、その子とは距離を置くようになる。そしていつも一生懸命な主人公の女の子のことを好きになる。そして最後は二人がめでたく結ばれる。物語はこんな感じだ。
実にありがちな物語だが、この小説の良い所は、主人公の女の子がとても可愛く、そして活き活きと描かれているところにある。意中の男の子を振り向かせるため、ずるは絶対にせずひたすら健気に頑張るその姿には、男子高校生である僕も非常に心打たれたものだ。あと登場する主人公の親友が実に良いキャラをしている。本当はその親友も例の男の子のことが好きなのだが、親友の為に自身の心は押し殺して、様々なアドバイスをくれるのだ。僕もこんな親友がいたらどんなにいいだろうと思ったものだ。
ところで、この小説の主人公である引っ込み思案な女の子というのは、実は梓自身をモデルにしているらしかった。梓は表面的には勝気で明朗快活な女の子だが、本当はとてもか弱いところがある。彼女はそれを後から身につけた見栄や虚勢で誤魔化しているだけなのだ。彼女は僕の前では時折そういった本当の部分を見せてくれる。その時の彼女は、触れば折れてしまうんじゃないかというくらい脆い女の子なのだ。
彼女は中学の時、見栄も虚勢もはれない女の子だった。いつも教室の隅の方で本を読んでいる様な子だったのだ。そんな彼女の趣味は、僕と同じく小説を書くこと。実は彼女は中学時代小説ジュニア大賞で優秀賞を獲るほどの素晴らしい小説家だったのだ。彼女は小説の中に自分の求める世界を描いたのだ。今は駄目でも、努力をすれば必ず報われる様な世界を。
だがそんな純朴な少女にも魔の手が伸びた。クラスメートによるいじめだ。当時彼女は原稿用紙に小説を書いていたのだが、それがクラスメートに見つかってしまい、原稿は無残にもビリビリに破かれてしまった。そういったことが繰り返され、いつしか彼女の精神はすっかり疲弊してしまった。それは彼女の心に暗い影を落とした。唯一人生が楽しいと感じられるものであった小説ですら、彼女は書けなくなってしまったのだ。
しかし、彼女はそこでめげなかった。待っていも幸せになれないのなら、小説の登場人物の様に、自分から幸せを掴みにいかなければならないと考えたのだ。彼女は変わる為の努力を始めた。心身共に鍛えるために彼女が始めたのが剣道だ。それまで彼女は運動らしい運動を何もしてこなかった。だから初めはついていくのがやっとだった。だが彼女は決して諦めなかった。剣道を始めたことで体力がつき、精神的にもタフさというものを身につけ始めた。
彼女は高校入学を期に、これまで住んでいた所から離れた所に越して来た。昔の自分を知らない場所で、もう一度新しい自分で勝負するために。
高校に入学すると彼女は市内の剣道場に通い始めた。学校では文芸部に入っていたため剣道部には入らなかったが、大会が近い時は部活にはほとんど顔を出さずに剣道に集中する程の熱の入れようだった。こうして剣道で鍛えられた彼女の心身は瞬く間にたくましくなっていった。
彼女の交友関係も高校入学を期に大きく変化した。いつも教室の隅で本を読んでいた様な子が、一気にクラスの中心人物になったのだ。その明るい性格で、彼女はたちまち人気者になった。
僕が彼女の距離が一気に近づいたのは二年生の春だ。彼女は僕と同じ文芸部だったから、それまでも多少は話をしたことがあった。だが僕は誰に対しても自分を出すことが出来なかったから、特に彼女とは親しいということはなかった。そんな感じだから、僕は小学校、中学校とよくクラスではいじめの対象になった。そしてそれは、高校でも同じだった。もしあのままいじめが続いていたら、世間一般のいじめ被害者の様に、不登校になっていたり、場合によっては自殺してしまったりしていたかもしれない。
それは去年の五月のことだった。僕をいじめていたのは、岩崎陸也を初めとした男数名だった。彼らは僕の鞄を隠したり、僕にバケツの水を引っかけたりした。その日は、僕がたまたま持ってきていた、小説をプリントアウトした紙がやつらに見つかってしまったのだ。彼らは原稿を見つけると、辺りにばら撒き、足で散々に踏みつけた。そして彼らはそれを拾いもせずどこかに行ってしまった。僕はそんなやつらの背中を恨めしそうに見ながら、その原稿を拾おうとした。その時だった。
「手伝うわ」
彼女が僕の原稿を拾うのを手伝ってくれたのだ。別に仲良くもなく、助けたところで何の得にもならない、こんな僕を助けてくれたのだ。でも僕は、小説をあまり人に見られたくなくて、「一人で出来るからいい」と彼女に言った。でも彼女は気にせず原稿を拾うのを手伝ってくれた。拾いながら彼女が「これって小説?」と尋ねた。僕はバカにされるのが嫌で、素っ気なくそうだと答えた。でも、彼女はバカにしなかった。むしろ逆だ。僕の小説を読ませてほしいと言ってきたのだ。
正直その申し出には抵抗があった。だけど、僕は彼女の勢いに負けた。僕は夜、彼女の催促メールに、僕が一番自信のある小説のデータを添付して返信した。
数日後、彼女から物凄い長文メールが返ってきた。それは小説の評論だったのだ。僕は驚いてそれを読んだ。あまりに深く読みこんであって、逆に僕が恥ずかしくなるほどだった。
それが僕と彼女が付き合うきっかけだった。小説が僕たちを巡り合わせてくれたのだった。
僕は『幸せの法則』を本棚に戻した。よく見ると、その横にも彼女の作品があった。その横にも、更にその横にも、彼女の作品が並んでいた。中には僕が読んだこともない作品があった。もしかしたら、これは彼女の頭の中だけにある作品なのかもしれないと僕は思った。ここが彼女のイメージした世界なら、それも決してあり得ないことではないからだ。
ふと僕は足元を見た。名前のない本が落ちていた。更に近くには別の本も落ちている。まるで目印の様に、列の様に本が落ちていた。そしてそれは、とある階段へと続いていた。
僕は急に不安になった。名前のない本が指示している先には何があるのか確かに気になった。でも、名前がないということは、彼女にとって残したくないものという意味なのではないかとも思えた。僕は息を飲んだ。僕はあの子のことを何でも知っている気でいた。だが人間、一つや二つ隠し事があって当然だ。僕にだって人には言えない隠し事はある。でも、今あそこに行けば、僕は彼女の全てを知ることが出来るのではないかと思った。彼女が眠り続けている理由を、彼女が夢を通して何を伝えようとしているのか、分かるのではないかと思った。だから僕は踏み出していた。まるでその不気味に光る闇に吸い込まれるかのように。
僕は一段一段を慎重に降りていく。闇が深くなっていく。ここが彼女の暗部だと分かった。でも僕は止まれない。
階下は沼の底の様に真っ暗であった。それでも、一番奥にほのかに光る灯りがあった。僕はそこを目指して歩く。広い広い部屋を突っ切り、僕はその灯りの前にやって来た。そこには、一つの本棚があった。僕は僅かな灯りの中目を凝らした。どの本にも、タイトルがなかった。僕は息を飲み、その中の一冊に手を伸ばす。そしてその本をしっかりと掴んだ。信じられないくらいその本は冷たかった。冷凍庫に入れたみたいに、その本には温かみが感じられなかった。
心臓が暴れ馬の如く激しく脈打った。喉元まで吐き気が込み上げてくる。まるでそれに触れるなと警告されているかのようだった。それでも僕は本を戻さなかった。決死の覚悟で僕は本を本棚から引き抜いた。
真っ黒なカバーの本を開く。すると奇妙なことが起こった。文字を読んでいないのに、内容が勝手に頭の中を流れたのだ。この物語の初めから終わりが、まるで走馬灯のように頭の中を流れた。一瞬だったのに、僕は内容を理解していた。それは僕が感じたことがない、真辺梓の心だった。
不意に気配がした。僕は闇から闇に向かって振り返った。すると真っ暗だった部屋が、一瞬にして銀色に染め上げられた。その時改めて分かったことだが、その部屋はこの本棚以外全く何も物がなかった。広大な空間に、たった一つだけの本棚。これだけ見れば分かる。これらの本が、彼女にとってどういった位置づけなのか、どれほど人に見られたくはないものなのかということを。
白銀の騎士は、苦悶の表情を浮かべながらこちらに歩み寄る。僕は黒い本を持ったまま立ちすくむ。見てしまった。あの子が見られたくないと思っていた部分を見てしまった。
彼女は僕から本を引っ手繰ると、それを本棚に戻した。僕はその横顔を見た。まるで、何かを諦めたかの様な顔だった。僕はその時思った。彼女は、わざと僕にこれらの本を見せたのではないかと。
彼女は本棚に手を置いたまま尋ねた。
「私のこと、幻滅したでしょ?」
確かに見た。でも、あれが何だって言うんだ。あの程度のこと、僕にだってある。自分より不幸な誰かを描いて、その人を自分の不幸のはけ口をしてしまうことなんて、よくあることだ。
「あんなの、僕は気にしないよ」
声は震えていなかった。だって、これは偽らざる真実なんだから。あの程度で僕が君を幻滅すると思ったら大間違いだ。
「私は、あなたと違って、身勝手で、矮小な人間なのよ……」
彼女は尚も自身を卑下する言葉を吐く。何があなたと違ってだ。まるで僕が偉い人間みたいに言わないでくれ。僕はただ小説の世界に逃げていただけなのに。
「『絶望を希望に変える』僕の生き方が好きだ」と、彼女はある時言った。自分と同じ様な境遇にありながら、希望に満ちた小説を描けることが凄いと彼女は言ったのだ。何が凄いものか。僕は現実から目を逸らして、好きな世界を創り上げていただけだ。現実と向き合って心身を鍛えた君の方が何倍も偉い。完璧な人間なんていない。身勝手で矮小な方がリアルだ。
なぜ君はそうやって僕に嫌われようとする? どうしてそんな辛いことを僕にさせようとする? 僕が君を嫌いになれる訳ないと分からないのか?
僕は踵を返す。彼女に完全に背を向けた恰好だ。僕は彼女の元から歩き出す。彼女の視線が背中に突き刺さった。だが僕は歩みを止めない。見つめる先にあるのは、さっき降りてきた階段だけだ。
僕は僕を見ている彼女に向かって、最後にこう言った。
「僕は君を幻滅したりしない。身勝手で矮小な人間は、僕の方さ……。僕ほど酷い人間はいないと、僕自身自負しているからね」
僕は苦笑交じりにそう言った。後ろで彼女が息を飲んだのが分かる。きっと僕の言葉に対して何か反論を言おうとしてくれたのだろう。だが彼女は何も言わなかった。恐らく彼女は、唇を噛んでいたんだと思う。
僕はもう一度も振り返らなかった。薄暗くなった図書館を出て、寒空の下に躍り出た。夢は、そこで途切れた。
僕は彼女の気持ちを取り違えていたのだろうか? ただの憂さ晴らしだと、安直な結論に逃げようとしていただけだったのか? でも、彼女が何をしようとも僕の気持ちは変わらない。絶対に見捨てたりしない。僕は君がどんな状態になろうとも受け入れる。僕は君を手放す方が何倍も辛いのだから。
梓にはどうかそれを分かってほしい。どうか僕の気持ちを理解してほしいと願っている。
2
五月十四日火曜日、今日はあの夢を見なかった。だから病室でのことは取り立てて記すことはない。ただ別のことで非常に衝撃的なことがあった。今日はそのことについて記すことにする。
病院からの帰り道、僕はバスの途中で、男の人と歩いている赤間さんを見つけた。僕はなんとなく気になって、彼女の後を追うため途中下車したのだ。
僕がなぜこんなことをしたのかと言えば、一つはやはりあの夢で赤間さんが出てきて、僕を誘惑してきた印象が非常に強かったからだ。学校では赤間さんは夢の様に僕を誘ったりはしない。でも、彼女が積極的なアプローチを仕掛けてきていたのは間違いないと思う。にも関わらず、彼女は今親しそうに男の人と歩いている。別に彼女にとっては大きなお世話かもしれないが、相手がどういった関係なのか調べておいて損はないだろうと思ったのだ。
もう一つの理由は、夢の中で彼女は無残にも梓に切り殺されたからだ。梓が彼女を嫌っていたのは知っているが、あそこまでやったのには何か理由があると僕は睨んでいる。以上の理由から、途中下車してでも彼女のことを調べる価値があると僕は思ったのだ。
バス停付近には小さいながらも商店街があった。そこには昔ながらの八百屋や魚屋、更には呉服屋などが軒を連ねていた。僕が赤間さんの後を追っていると、赤間さんはその商店街に入って行った。商店街には六十代と思われる女性が数名買い物に来ているくらいで、全体的にはひっそりとした雰囲気だった。よって高校生のカップルである二人は、この空間においてひどく浮いた存在であったと思う。当然、その後をつけている僕も異様だったとは思うが。
二人は商店街の中ほどに差し掛かったところで左手に曲がった。それは所謂裏路地と言うやつだ。人の通りはほぼ皆無だった。僕はまるで探偵みたいにこっそり二人の方へ近づくと、曲がり角にあった自動販売機の影に隠れ、そこから二人の会話を聞くことにした。
二人は狭い路地で抱き合いながら、お互いのことを見つめ合っていた。二人の間では、一般的なカップル、特にラブラブなカップル同士なら日常交わされていそうな、歯が浮きそうになるくらいの臭い台詞が展開されていた。付き合いたての高校生ならこういうこともあるかと僕は思っていたのだが、どうにもその相手の男の台詞が何とも言えない性質のものだったので、僕はバレないように自販機の影から相手の男を覗き見ることにした。
相手の男子高校生は、お世辞にもカッコイイとは言えない容姿をしていた。失礼を承知で言うならば、不細工であった。さらに驚くべきことに、その男は学ランではなくブレザーを着ていた。つまり、彼は他校の生徒ということになる。どうして赤間さんともあろう人がそんな男と付き合っているんだと僕が思案していると、二人の会話が次回のデートのことに及んでいた。
男が次はどこがいいかと切り出す。赤間さんはそれに対し、たまには原宿辺りにでも行きたいと言った。一般的なカップルのデートと言えば、やはり定番は原宿の竹下通りとか、渋谷といったところだろう。僕はどうやら普通にデートに行くみたいだなと思っていると、男は「次は何が欲しい?」といったことを尋ねた。赤間さんは少しの間うーんと唸っていたが、すぐに「昭がくれるのならなんでもいいにゃん」と、僕がこれまで学校では聞いたことがない言葉遣いで返答した。すると男は、「ちーこが可愛いから何でも買ってあげる、よしよし」と、恐らく頭を撫でながら返したのだと思う。闇が深くなってきたというのもあるが、僕はそんな二人の様子を直視出来なかったのだ。
二人が裏路地から出てきた。赤間さんは相変わらず「にゃんにゃん」言いながら、昭と呼ばれた男にじゃれついていた。僕はさっと自販機の影に隠れると、それ以上二人の様子を確認することなく、その商店街を離れた。
バス停でバスを待っていると、十分ほどしてバスがやって来た。僕はフラフラっとした足取りでバスに乗り込んだ。
バスが駅前に辿り着く。すると僕は、思わぬ人と会った。鳳さんだった。彼は生徒会の帰りだったらしく、左手になにやら資料の入った袋をぶら下げていた。なぜかその袋から猫耳が見えていたせいで、僕は一瞬立ちくらみを起こしそうになった。
「どうしたんだい牧村くん? 何やら体調が悪そうだけど」
彼が心配そうに尋ねたので、僕は「なんでもないです」と一言言った後、袋からはみ出ている例の物について質問した。
「ああこれかい。実は今度僕たち生徒会が、障害を持つ児童たちの前で劇をすることになってね。これはその衣装だよ」
と、明るい笑顔で言った。
僕は一瞬でもさっきの赤間さんとあの男の様子を考えてしまった自分を恥じた。すると彼が、突然おどけた口調で、驚くべきことを口にした。
「牧村くんに、元気を分けてあげるにゃん」
僕は噴き出していた。あまりに驚きすぎて鼻水が出てしまった。僕はいきなりなんてことをこの人は言うんだと思い、彼の顔を見た。だが予想に反して、彼は真顔だった。右手に猫耳を持ってはいたが。
彼の顔が、真顔から不敵な笑みに変わる。そして彼はこう言った。
「赤間千鶴には気を付けた方がいい」
前回彼が、彼女のことが嫌いだと言った理由が、その時ようやく分かった。彼は知っていたのだ。赤間千鶴がどんな女なのかを。そしてその時僕は思った。きっと、梓も、そのことを知っていたんだ、と……。
彼は教えてくれた。赤間千鶴は、金を持っていそうで、なおかつ女の子と縁のなさそうな男を見つけては、その男を手なずけている。そしてその男に散々貢がせた挙句、ゴミの様に捨てていく。基本的に彼女は、男を他校や、全く関係のないコミュニティで見つける。しかもみんな気の弱そうな人ばかりをだ。彼らは気が弱くて友達もいない。だから、捨てられたと分かっても誰にも話をすることが出来ない。よって、赤間千鶴の悪い評判は広がらない。それが彼女の手口なのだ。僕もきっと、その中の一人でしかなかったのだ。彼女は梓があんなことになって、寂しい思いをしている僕を狙ったのだ。
僕は絶対に梓を裏切ったりしない。でも、赤間千鶴を全く意識していなかったかと言われれば、決してそんなことはなかっただろう。僕はなんと迂闊だったのか。僕は思わず奥歯をギリッと噛みしめた。
「しかし、彼女は今回ばかりは相手を間違えたな」
不意に鳳さんが言った。
「何が、ですか……?」
僕は彼の目を見ずに尋ねた。
「彼女はいつも全く友達のいなさそうな人を対象にする。だが、牧村くんには友達がいる。君がそう思ってくれているか分からないけど、僕も君の友達のつもりだ。そして君には、最強の騎士がいる……」
「え?」
僕は瞬間的に彼の顔を見た。なぜ、彼がそれを知っているのか。僕しか知らないはずの、あの白銀の騎士を、彼も知っていると言うのか? しかし、彼は慌てた様子も見せずにこう言った。
「傍で君を守るという意味じゃ、彼女は立派な騎士だ。あの時の事件で、まるでこの子は君を守る騎士の様だと思ったのさ。正直羨ましかったよ。あそこまで絆の深いカップルを僕は見たことがなかったからね」
彼はそう言うと、手に持っていた猫耳を近くにあったゴミ箱に投げ込んだ。劇に使わないんですかと僕が尋ねると、
「あんな気色の悪い物、僕は願い下げだ」
と、晴々した顔で言った。
同意だった。あの二人のさっきの様子ほど、僕の身体に悪寒が走るものはないと思う。
結局僕らは駅の前で別れた。僕は別のバスに、鳳さんは徒歩で帰宅の途に就いた。
自宅の前で僕は、一匹の黒い猫を見た。よく辺りを走りまわっている野良猫だ。その猫は僕を見つけると、敵意をむき出しにしてシャーシャー鳴いた。あの気味の悪い猫よりも、こっちの方が百倍良いと、僕はこっそり思った。
この前の仮説だが、僕はもう捨てることにした。
図書館での一件、そして赤間千鶴の本性を鑑みれば、僕の仮説が実に浅はかであったかが分かる。
お互いにまだ分からないことが沢山ある。だからこそ、その人のことをもっと知りたいと思う。人が人と一緒にいる理由とはそういうものなのかもしれない。僕は彼女について知らないことが沢山ある。僕はそれを認める。認めたうえで、もっと彼女を理解するように努力する。
僕はまた明日病院へ行く。彼女がもう来るなと言おうとも行く。行って確かめる。それだけが、今の僕に出来ることだと、信じている。
真辺梓の記憶
「俺じゃないって言ってるだろ」
杉山が気だるそうに頭を掻きながら言った。
決して証拠がある訳じゃない。彼が怪しい素振りを見せている訳でもない。でも私は、彼が諸悪の根源であると理解していた。
文芸部員が光士郎に暴力を振るったという知らせを受けた時、私は耳を疑ってしまった。彼にとって、文芸部員は同じ趣味を共有する仲間であり、普段から多くの時間を共にする友人であったはずだった。実際、私が道場に行っている時、彼は決まって文芸部室に行き、彼らと小説について議論を交わしたり、面白い小説を紹介し合ったりしていた。
彼らは本当に酷かった。ありもしない盗作話を先生たちに吹き込もうとしたんだ。彼らが持っていたノートには、光士郎が書いた小説と同じ様な内容が書かれていた。そしてそのノートはいつも文芸部室に置かれていた。彼らは、光士郎がそのノートを見て、アイデアを盗んで小説を書いたと言いだしたのである。私はこんな酷い話はないと思った。彼らが一方的に悪いくせに、光士郎の名誉まで傷つけようとしたのだから。
先生たちは初め、この話を真に受けそうになった。ノートの存在は割と文芸部員みんなが知っていたらしく、光士郎自身もその存在を認知していた。文化祭には任意で一人が一作品を出すことになっていた。光士郎があの頃なかなか作品が書けなくて焦っていたのは事実だ。だからと言って、文化祭程度で盗作をするメリットがどこにあるのかと私は思った。
それにそもそも、小説家にとって作品は命と同じだ。光士郎は人の作品を盗むことは、人の命をとることと同義であると理解していた。だからそんなことは絶対にするはずがない。彼の性格を考えても、そんなことが出来るはずがなかった。
でも、私がいくらそう主張しても、証拠の様な物が存在していることは非常にまずかった。光士郎がそれを盗み見た証拠なんて全くないのに、本当に盗作があったのではと思う教師が何人か出てきてしまった。
そんな中で、私たちを助けてくれたのは、うちの学校の生徒会長の鳳元だった。前から評判の良い人だったけど、初め私は彼を信用していなかった。彼が家にやって来た時、彼が文芸部員の話を鵜呑みにしているんじゃないかと思った。でも、それは私の思い違いだった。彼はしっかりと私たちの話を聞き、私たちが本当のことを言っていると信じてくれた。そして彼は、光士郎の名誉を守るべく行動してくれた。
彼は光士郎の行動を洗い出し、彼が放課後一人で文芸部室にいたことがないことを証明した。というのも、二人で文芸部に行く時は決まって二人で下校するし、私がいない時であれば、光士郎はいつもどの文芸部員よりも早く下校して、私のいる道場の近くのカフェで私を待っていてくれるのだ。もちろん、そのカフェの店主は光士郎がいつも来ていることを証言してくれた。そして文芸部員が全員帰宅した後に関しては、私の母親が平日は家にいないため私はいつも牧村家でご飯を御馳走になっていて、その席には必ず光士郎も同席していた。だからアリバイは完璧だった。更に二人で近くのコンビニまで買い物に行っていた様子も何度か目撃されており、光士郎に疑う余地はないことが証明されたのである。
この結果を元に、鳳君は加害者たちを問い詰めた。すると驚くべきことに、彼らは自らの主張をあっさり翻したのだ。このことは先生たちが全員、彼らが嘘を言っていたと確信するのに充分のことだった。これでようやく、光士郎の無実が証明された。
光士郎はその後、周りの人のサポートもあり、しばらくして学校に復帰することが出来た。一方加害者たちは、暴行だけでなく嘘までついたことが分かり、一時は退学処分が出るのではないかと言われていた。しかし、その処分に光士郎が待ったをかけた。彼はあんな酷い目に遭わされたというのに、彼らの処分を軽くするように先生方にお願いしたのだ。というのも、処分が下される直前、光士郎を暴行した四人が私たちの元に謝罪に来たのだ。私は正直言うと許すつもりはなかった。でも、彼は許した。反省しているならもうそれでいいと言ったのだ。光士郎がそう決めたのなら、その決定に異議を唱える必要はない。だから私はもう彼らに関しては何も言わなかった。どちらにしろ重い処分であることは間違いない訳だから。
彼らは処分された。しかし、私はそれで全てが解決したとは思えなかった。私はあることに違和感を覚えたのだ。それは、光士郎が何もしていないなら、彼らはどうして光士郎に暴力を振るったのかということだ。彼らは、ただイライラしてやったと言った。だけどそんなことであそこまで用意周到なことをするだろうか。私の疑問はつのった。
ある時私はこんな噂を聞いた。女子水泳部の更衣室に、カメラが仕組まれていたという話だ。初めはそれがどこから出てきた話なのかはよく分からなかった。実際調べてみても、更衣室にはカメラはなかったらしい。でも、火のない所に煙は立たないと言う。こんな話が出るには何かしらのことがあったはずだ。だから私は調べた。
出てきたのは、驚くべき事実だった。ある男子生徒が、放課後の視聴覚室から聞こえてくる話声を聞いていたのだ。ちなみに視聴覚室は放課後に利用されることはない。鍵も職員室においてあるはずだった。彼が聞いたのは、男数人の話声だった。小さな声だったが、彼らが歓喜していたのはよく分かったらしい。話し声から、彼は誰がそこにいるかほとんど把握出来たそうだ。もちろんその中には、今回の事件の加害者が含まれていた。その中で彼らは実に卑猥な話をしていた。思い出すのは正直嫌だ。助平なのは仕方ないが、女の子の大事な部分を見るために、そこまで卑劣なことをする彼らの神経が私には理解出来ない。とにかく、彼はその話を聞いて、盗撮があったのではないかと疑った。そしてそれを何人かの生徒に話したらしい。
噂の正体はこんな感じだった。噂は噂を呼ぶ。その話がどこまで広がっていたのかは、私は知らない。私は当然彼らにそのことを問い詰めた。だが、彼らはそんなことは知らないと白を切る一方だった。でも私は、絶対にこのことは今回の一件と関連があると思った。これを偶然と言って済ませてしまうのは、いくらなんでも都合が良過ぎる。
そこで私はある仮説を立ててみた。盗撮が実は誰かに露見していたという説だ。そこから導き出されることは、それを盾にしたゆすりだ。このことを黙っていてやる代わりに、金を出せ。ゆすりの手段としてはこれが一番一般的だと思う。でも私は、今回に関してはそれは違うと思った。お金を奪われることと、暴行の件に関連性を持たせるなら、もっと違う答が導き出されるからだ。
杉山暁という人物と私は、かつて友達だった。つまり今は違うということだ。彼が私に好意を抱いていると感じたのは、二年になってからのことだった。でも、その時にはもう私は光士郎と付き合い始めていた。だから彼の好意を受けることは出来なかった。いや、もし付き合っていなくても私は彼とは付き合ったりしないが。彼の顔がタイプではないということも、まああると言えばある。でもそれだけではない。彼は非常に自尊心が強い。それも、実績の伴わない自尊心だ。これは実に性質が悪い。何も彼を支えるものがないのにプライドだけは高いというのは、人間として最も嫌なタイプだ。そういうタイプは、失敗から反省することもほとんどないから余計に始末が悪い。彼は誰に対しても横柄だ。女子と付き合っても、一週間後には振られる。それは恐らく彼の態度が原因だろう。バレー部員に彼のことをどう思うか聞けば、七割以上は嫌いと答えるだろう。騙されるのは彼を知らない新入生程度だ。
そんな彼に好意を向けられるのは、正直言って迷惑な話だ。それだけならまだしも、彼氏がいると分かっていながらもストーキングをされたのにはほとほと困り果てた。
私はその日を境に、彼から完全に距離を置くようになった。彼もそれに気付き私に近づいてこなくなった。でも私には分かる。彼はまだ、私を諦めてはいないということを。時折感じる気色の悪い視線は、紛れもなく彼のものだ。彼が下劣な感情を私に抱き続けていることは、実はこの事件と大いに関わってくるのだ。好意の反対は憎しみだ。私に向けられている好意は、いつしか、とある人物に対する憎しみへと変わっていった。
もう、言わなくても分かるだろう。暴行を働いた文芸部員たちが、盗撮を露見させないことと引き換えにしたのは、光士郎の心身への攻撃だった。そう、杉山暁は、私の恋人である光士郎へ憎しみをぶつけようとしたのだ。
彼はそれを認めない。当然証拠もない。
だけど、もうそれしか考えられない。彼が文芸部員をけしかける以外に、一連の事件は起こりようがない。
杉山暁を、光士郎に近づけてはならない。私のせいで彼が傷つくことは絶対に許さない。何があっても、私が彼を守る。その時私は、そう心に誓った。
牧村光士郎の手記 其の三
1
目が覚めた。今回は、凍える様な寒さによってでもなく、腕の痺れによってでもなく、僕は明確な意思を持ってこの世界に目覚めた。今までとは違うと、僕ははっきり認識していた。
僕は現在位置を確認する。目の前の窓からは少し古びた建物とその入口が見えた。入口の横には看板が立ててあり、その建物が六号館であることを示していた。そして僕がいる建物とその建物の間には、コンクリートの道といくつかのベンチが並んでいる。これだけでは残念ながら現在位置は把握出来そうもなかった。
左手には下り用の階段、右手には登り用の階段がある。振り向いてみると、四メートルほど奥に掲示物が貼られている壁がある。見たところ、僕がいた空間自体はあまり広くないようだった。恐らく、入口によって入れる部分が違うのだろうと僕は思った。
僕は壁の方に進んでから右手を見る。どこかの教室への入口があった。なんとなくだが、僕はそこに誰かがいるような気がした。僕はそちらに向かって歩き出した。
ドアノブを握り、手前に引く。教室の中は廊下よりも幾分か明るい。僕はその中に入った。
そこは縦長の教室だった。三列に並んでいる沢山の長机に椅子が五つずつ備え付けられている。教室の端から端までざっと二十メートル弱といったところか。
教室の一番後ろの席、そこに彼がいた。僕が最も嫌いと言ってもいい人間である、彼が。髪の毛をオールバックにし、異様に目つき悪く僕を見ているその人は、岩崎陸也だった。こんなに外は寒いと言うのに、ワイシャツ一枚で、胸元をざっくり開け、金色の髑髏の派手なペンダントがついたネックレスをしている。いかにもと言った感じの典型的ヤンキーを気取る彼は、いつも仲間という名の下僕数名を引きつれてターゲットを探している。自分の、ありもしないストレスを発散するためのはけ口となる人間を。彼の見た目は、かなり頭の悪い学校にありがちな悪逆の限りを尽くすヤンキーといった感じだが、実際彼はそこまで大層なことはしない。やるとしたら、集団による冷やかし、集団による軽めの暴力、集団による喫煙くらいなものだ。もちろん、対象となっている僕としてみればそんなもの堪ったものじゃないのだけれど。
彼は本物のヤンキーではない。要は、彼は悪に憧れているだけなのだ。だが僕達の学校は進学校だ。よって彼も頭はそれなりにいい。それはつまり、どこまでが人間としてやってはいけないことなのかが分かってしまっているということだ。彼の実家はかなりのお金持らしく、彼がもし大きな犯罪をしてしまった場合、実家に多大なる迷惑がかかることを知ってしまっているのだ。だから彼はあまり派手に悪いことは出来ない。やるとしたら、ちょっとしたいじめ程度なのである。悪に憧れていながら、律儀にも色々なことを守ろうとしてしまっていることが、もしかしたら彼にとってのストレスと言えるのかもしれない。
そんな彼が、いつもの様に嫌な視線を僕にぶつけていた。夢の中でも変わらず彼は僕を不愉快にさせた。
「よう牧村、お前、ちょっとこっちに来な」
大きくてしゃがれた声で彼が僕を呼んだ。わざわざ向こうに行ってやる義理はない。だけど、ここは彼女の夢だ。夢にあの男がいるのなら、それに全く意味がないということはないはずだ。それに、僕がピンチになれば、彼女が出てきてくれるのではないかとも僕は思った。だから僕は、彼の方に足を踏み出した。
彼はニヤリと笑った。だが勘違いしないでほしい。僕は決して、君が来いと言ったからそちらに向かった訳ではないのだと。
岩崎との距離が近づく。息苦しさが増してくる。普段の嫌な記憶が身体を抉っているのが分かる。ほとんどアレルギーに近い。僕の日常をつまらなくしている一員である彼に、僕は心の底から嫌悪感を覚えているのだ。僕を助けてくれたのは梓だった。いつもやられ放題だった僕を、岩崎の魔の手から救ってくれたのは梓なのだ。だが、その梓が今はいない。僕は無防備も同然だった。
距離が三メートルになる。彼の顔のニキビを一つ一つ数えることが出来るほどの距離だ。僕はそこで立ち止まった。彼の表情が僅かに歪む。岩崎が言った。
「ちゃんと俺の隣まで来いよ牧村。来ないとぶっ殺すぞ」
“ぶっ殺す”が彼の口癖だ。もしかしたら、そのためにこの世界にいるのかもしれない。普段なら出来ない、その“ぶっ殺す”とやらを実践するために、彼はここにいるのかもしれない。赤間さんがいきなり服を脱ぎ出した様に、杉山が死体を見てヘラヘラ笑っていた様に、この世界はその人の異常性のリミッターを解除する役割があるのかもしれない。だとしたら彼が僕を“ぶっ殺す”ことも可能かもしれない。本当にそんなことをされるのは堪ったものじゃない。だが、あの騎士を呼び出すためには、ここで彼を挑発した方が良い気がした。だから僕は、普段なら絶対に言わない様なことを、彼に向かって言ってのけたのだ。
「やれるものならやってみなよ。今日は友達はいないみたいだけど、僕を痛めつけるくらい一人で出来るでしょ?」
僕は彼から三メートルの距離でそう言った。彼の顔がピクリと動く。イラついているのがよく分かる。自分より下だと思っている僕に、生意気な口を聞かれてさぞ怒っていることだろう。
「なんだと牧村。てめえ、今すぐ訂正しないとマジでぶっ殺すぞ」
「絶対に訂正はしない。僕は君の言いなりにはならないよ」
彼の言葉に被せる様に僕は言った。彼が殺気立つ。正直少し怖かった。心臓が激しく脈打つ。でも僕は、決して表情には表さなかった。岩崎が立ち上がった。そしてポケットに手を突っ込んで、こちらを思いきり睨みながら歩み寄って来る。挑発はもう充分にした。あとは逃げるだけだと、僕は思った。これだけ机や椅子があるなら簡単には追って来れまい。夢の中だろうが、わざわざ殴られに行ってやる筋合いはないのだから。だから僕は足を一歩引いた。だが、気付くと僕は胸倉を掴まれていた。いつの間に触られていたのか、全く気がつかなかった。これだけ殺気立っているのに気付かないなんて、明らかにおかしいと思った。だが、そんなことを言っていられる状況ではとっくになくなっていた。
「マジでぶっ殺す」
彼が唾を飛ばしながらそう言った。拳を振りかぶった。殴られるのに一秒も掛かりはしまいと僕は思った。だと言うのに、なぜか僕は落ち着いていた。むしろ先刻よりもずっと。そしてそれは唐突に訪れた。
「その汚い手を放しなさい」
氷の様に冷え切った声が聞こえた。そして次の瞬間には、岩崎が教室の端まで吹き飛ばされていく様子を、この目が捉えていた。白銀の騎士がそこにはいた。彼女は岩崎が飛んでいった方を睨んでいた。彼女に倣って僕も視線をそちらに向けた。岩崎は窓際まで飛ばされていたが、こちらの視線に気付くとすぐに立ち上がった。思いきり身体をぶつけていたはずだが、どうやら彼は無事の様だった。
騎士が彼の方へ足を踏み出した。彼はそんな彼女の様子を先程以上の殺気で睨みつけた。彼女が僅かな距離を開けて立ち止まった。そして腰の剣に手を掛けた。
「てめえ、もしかして真辺か? 変な恰好しやがって、調子こいてんじゃねえぞ。こんなことしてタダで済むと思うなよ」
また“ぶっ殺す”が出るかと思ったが、珍しく彼はそう言わなかった。
岩崎と梓は所謂犬猿の仲だ。きっかけは、僕が彼に殴られているところを梓が止めてくれたことだった。
梓自身にも辛い過去があったことはここに記した。それ故、彼女は暴力やいじめの類は絶対に許せないと思っている。しかもそれが、恋人である僕を大いに苦しめるものであるなら尚のこと。彼女は僕と関わりを持つようになってからというもの、僕が彼らに狙われた際は、必ず僕の元に駆けつけ、彼らを追い払ってくれた。男としては情けない限りだが、気弱な僕にとってそれは本当に助かることだった。
岩崎は相手が女だろうとも容赦しない。彼らを止めに来た梓に、岩崎の配下の男子生徒は手を上げようとした。だが、所詮は単なる取り巻き。彼ら程度に剣道で心身を鍛えた梓が相手になるはずがなかった。素早い身のこなしで仲間たちを倒すと、怒りに震える岩崎と相対した。岩崎は漫画で見たヤンキーの様に拳を振り回すが、軽やかな足さばきでかわす梓には全く命中することがなかった。逆に隙だらけになった頭を思いきり引っ叩かれる始末だ。これには岩崎はキレた。教室にあった椅子を掴むと、それを頭の上で思いきり振り回したのだ。教室はパニックになり、机や椅子はグチャグチャになった。これでは梓が怪我をしてしまうと思った僕は、構えたままの彼女を引かせた。するとタイミングの良いことに、担任の教師が騒ぎを聞きつけてやって来た。どっちが悪いかなど火を見るよりも明らかだった。岩崎はそれにより厳重注意の処分を受けた。怪我人が出ていたら停学は軽かっただろう。岩崎が梓を一方的にライバル視するようになったのはそれからのことだ。岩崎の配下は梓のいないところで僕に嫌がらせをすることがあったが、岩崎自身は僕よりも梓を狙うようになった。
岩崎は会うたびに梓に因縁をつけたが、彼女はあの一件以来ほとんど彼を無視した。本気の喧嘩になったら自分自身処分を受ける恐れがあったし、そもそも僕に危害が加わらないのならそれでいいとも思ったのだ。それでも岩崎は梓にちょっかいを出し続けた。そのしつこさや、逆に梓のことが好きなんじゃないかと思えるほどであった。
とにかく、そんなことが二年生の間中続いた。結局岩崎は一度も諦めなかった。それは夢の中だって同じはずだ。
「今日こそはマジでてめを殺すぜ。いつも無視ばかりしやがってたてめえが、今日はやる気と見た。本気でやりあえば、俺は絶対に負けない。今日、それをここで証明してやる」
彼はそう言って不敵に笑うと、ワイシャツの前ボタンを全て弾き飛ばし、それを豪快に脱ぎ捨てた。見たところ、岩崎の上半身は思ったよりも引き締まっていた。
梓が剣を抜く。そして銀色の刃に殺気を込める。このままいけば、岩崎も赤間千鶴や杉山暁と同じく身体を切り裂かれて絶命するはずだ。剣を持つ相手に、赤間千鶴は素手で善戦した。しかし結局は彼女の刀のさびになった。それは岩崎とて同じはず。だからきっと、勝負は余裕のはずだと僕は思ったのだ。だと言うのに、梓自身の顔から余裕の色は微塵も窺えなかった。むしろ相手を恐れているかのような、そんな雰囲気すらあったのだ。
先に動いたのは梓の方だった。気合の一声の後、彼女は足を踏み出し、一直線に岩崎に切りかかる。岩崎はそれを素手で掴んだ。騎士は驚愕の色を浮かべた。岩崎はニヤリと笑い、右手で剣を掴んだまま騎士の身体ごと投げ飛ばした。彼女の身体は数メートルほど飛び、備え付けてあった机と椅子を吹き飛ばした。しかしすぐに体勢を立て直し、再び岩崎に飛びかかった。
今度は横に刃が振り出される。僕は目を疑った。なんと岩崎は、振られる刃を殴りつけたのだ。その衝撃で騎士の身体が揺さぶられる。岩崎はその瞬間を見逃さなかった。素早く梓の懐に入り込み、梓の顔面を殴りつけた。そして間髪容れずに彼女の身体を蹴り上げた。
物凄い衝撃音と共に、天井に大穴が開く。彼女は上階に突き上げられたのだ。岩崎はその穴を見ながらニヤリと笑う。そして人間とは思えない跳躍力で上の階に飛び上がった。
これはまずいと思った。僕ではジャンプであそこに行くことは不可能だ。だから僕は、ボロボロの教室を全速力で駆け抜けて扉を開け、上に続く階段へと走った。僕は二段飛ばしで階段を昇った。四階に上がると扉がすぐに現れた。僕はその中の一つに走り寄り、思いきり扉を開いた。
大きな教室だった。端から端までは五十メートルはあるだろうか。木製の長机が七列、椅子はそれぞれ五つずつある。部屋は灯りがついていて、そのほぼ真ん中辺りに彼らはいた。
剣を構える梓の左の頬が腫れ上がっていた。唇の端が切れてそこから血が流れている。僕は唇を噛んだ。彼女は僕のせいで傷ついたも同然だ。僕はこの時ほど、助けてもらうばかりで何もしない自分自身を殴りたいと思ったことはなかった。
岩崎は余裕しゃくしゃくだった。机の上に乗り、騎士を見下ろしていた。一方梓は慎重になっている様だった。先に攻撃することは危険だとさっきの岩崎の動きで理解したのだろう。
先に仕掛けてこないと分かると、岩崎は大きく跳躍した。彼は梓の頭の上を飛び越えると、ちょうど反対側の机の上に着地した。そして机に備え付けてある椅子に手を伸ばした。またしても僕は目を疑った。彼は椅子を机から千切り取ったのだ。それも一気に二つだ。彼は両手に椅子を持ち、机の上に立ちあがると、思いきりそれらを騎士に投げつけた。騎士はそれを剣でなぎ払った。衝撃の強さからか、彼女は椅子を受ける度に僅かだが後退した。だが彼の攻撃はそれで終わらなかった。
岩崎はすぐに他の机に飛び移ると、またしても椅子を外した。そして次から次へと投げつけた。梓はそれになんとか応戦しているが、徐々に息が上がっていくのが僕からも分かった。額からは汗が滲み、表情も厳しくなっていった。
恐ろしい腕力だった。この夢では異常性や欲望が解放される傾向にあるようだが、ここまで彼女を苦しめた人はいなかった。赤間千鶴も途中から化け物じみた力を帯びていたが、彼はそれ以上だった。しかしここでふと思った。今の梓には、最初の時見せた銀色のオーラが見えなかったのだ。図書館の時も、部屋は一気に銀色に染まった。あの時だって、彼女が自身のオーラで真っ暗だった部屋に色をつけたはずだ。だったら今、彼女がオーラを纏っていないのはおかしい。もしかして発動条件があるのだろうか? あるとしたらそれは何か。彼女にオーラを纏わせるには、何が必要なのだろうかと、僕は思案を巡らせた。
岩崎の連続椅子投げが終わる。しかしそれと同時に彼自身が梓に飛びかかった。岩崎の素手の拳を剣で受け止める。彼女の身体が僅かに沈んだ。あまりの衝撃に床が壊れそうになっていたのだ。また穴が開くのも時間の問題のように思われた。
僕はまた思案を巡らせた。あのオーラは彼女の腕の傷を治した。そして襲いかかる赤間千鶴を一蹴した。そこから、あの銀色のオーラに何かしらの効果があることは僕にも理解出来た。ちなみに今のこの部屋は、蛍光灯の光が覆っていたが、その光は銀色とは言い難く、若干黄色が混ざった様な、ほの暗い光だった。
そんなことを考えている内に、梓の戦況は更に悪化してしまっていた。動きが衰えてきた梓の隙を付き、岩崎は腹のあたりを甲冑ごと殴り飛ばした。彼女の身体が宙に浮く。岩崎は彼女に向かって飛びあがり、彼女の身体を蹴り飛ばした。
彼女の身体がまっすぐこちらに飛んでくる。もし彼女の身体が地面に叩きつけられるようなことがあれば、もう彼女は立ち上がれないかもしれない。そうしたらもう僕らに勝ち目はなかった。そしてそもそも、僕は彼女がこれ以上傷つく姿など見たくなかった。
僕は両手を前に突き出した。そして彼女が落ちてくる軌道上に入り、彼女の身体をしっかりとキャッチした。だが残念ながら僕の能力は夢でも変わっていない様だった。僕は岩崎から送られてきた勢いを止めることが出来ず、彼女を抱きかかえたまま後ろの壁に思いきり激突してしまった。背中に激痛が走った。瞬間的に息が出来なくなる。だがそれでも僕は梓を放さなかった。
二人で地面に倒れ込んだ。すると弱弱しい声で彼女が言った。
「光士郎、あなたは、大丈夫……?」
「これくらい、大丈夫だよ。そんなことよりも君の怪我の方が酷いよ。あいつからは離れた方がいい。ここが夢なら、夢が覚めてしまえばいいはずなんだから」
そう言って僕は地面に伏している彼女の身体に触れた。久しぶりのことだった。これが夢だとしても、彼女にこうして触れたのは本当に久しぶりのことだったと思う。
彼女が輝きを纏ったのはまさにその時のことだった。
2
仕組みなんて分からない。初めからこの世界は僕の理解の範疇を越えている。何かが起こり、彼女の力が蘇った。僕にはそうとしか言えない。彼女は全身に銀色のオーラを纏っていた。見ると、彼女の腫れていた頬や、切れてしまっていた唇が徐々に癒えていくのが分かった。恐らく全身に受けたダメージもどんどん軽減していっているのだろう。
彼女が立ち上がる。そしてそのまま前方の岩崎陸也を睨みつけた。そして僕も、ヨロヨロしながらもなんとか立ち上がった。
岩崎はあからさまに不愉快そうな顔をしていた。あと一歩のところで振り出しに戻されてしまった訳だから、彼の心中は実に容易に推し量ることが出来た。
梓が精悍な顔立ちで剣を構える。剣からも当然銀色のオーラが発せられる。
岩崎の表情から先程までの余裕しゃくしゃくな雰囲気は消えていた。彼は体勢を低くして、今にも飛びかからんばかりにこちらに狙いを定めた。そして彼は右足で思いきり机を蹴った。備え付けの机がぐしゃりと音を立て破壊され、彼の身体が弾丸の様なスピードを帯びた。そして一直線にこちらに突っ込んできた。突っ込む瞬間、彼は右の拳を振り上げ、そのまま振り下ろした。白銀の騎士はそれを剣で受け止める。物凄い衝撃に再び地面が崩れかけた。だが、彼女は体勢を崩さなかった。完全に自身を防御しその場から微動だにしていない。それが恐らくあのオーラによるものなのだろうと、僕は考えた。
力技では崩せないことが分かると、彼は飛び跳ねて梓から一定の距離を取った。僕はもしかしたらまた飛び道具を使ってくるのかと思った。しかしその前に梓が仕掛けた。
彼女は目をつむり、両手で掴んでいる剣を前方に突き出す。刃の光が徐々にその輝きを増していく。そして彼女がカッと目を見開くと、気合の一声と一緒に斜めにかけてその剣を振り下ろした。
彼女の光り輝く剣から映画で見るCGの様な衝撃波が発生した。それは十メートルほどの幅を持ち、途中にあった机などを粉々に砕きながら高速で前進していった。
岩崎の顔がその時初めて恐怖の色を浮かべた。これまで感じたこともない様な打撃の嵐の接近に、彼は一瞬腰が引けた。しかし彼は意地になっているのか、そこから逃げようともせず両手を前に突き出した。恐らく防御のつもりなのだろう。だがそんなものは無駄だ。いくら常識外れの力を岩崎が持っていようとも、その更に上位の常識外の攻撃をされてしまっては一たまりもない。
銀色の波動が岩崎を襲う。文章で書いているからかなり遅い攻撃なのかと思えるが、実際は彼女が剣を振るってから、岩崎に攻撃が届くまでほんの二秒足らずのことだった。そんな一瞬では正直逃げることは厳しかっただろう。彼には元より選択肢などなかったと言った方が正しいかもしれない。光が岩崎を包み、岩崎は情けなく叫び声を上げた。それがどれほどの衝撃だったか、言うに及ばないだろう。
光の衝撃が消える。銀色の光は教室の照明すら吹き飛ばしてしまった。だから攻撃の後教室は真っ暗になってしまった。明りと言えば、割れた窓の外から差し込む月明かりくらいだっただろう。繰り出した梓は僅かに息を切らしていた。原理は分からないが、あれだけの攻撃を繰り出せば体力を奪われるのも納得出来る。
果たして岩崎はどうなったのだろうか。僕はそれを確かめようと、ボロボロになった教室の中心まで行こうとした。その時だった。人影が瓦礫から飛び出し、僕の身体を捕えたのだ。目が徐々に闇に慣れる。何が起こったのか、それで僕はようやく理解した。
血だらけになった誰かの腕が僕の首に巻かれていた。そして後ろからは血が絡む様な呼吸をしている人物がいることが分かった。結論から言えばそれは岩崎陸也その人だった。岩崎はまだ死んでいなかったのだ。全身が血だらけだったが、それでも彼には立ち上がる力が残されていたのだ。
要はそういうことだ。僕は、岩崎の人質になってしまったのだ。岩崎は恐らく、テレビドラマで犯人が言うような典型的な台詞を言っていたと思う。ここに書くにはあまりにチープな発言のため割愛するが。
岩崎が何かを叫んだ。だがもうほとんど言葉になっていなかった。梓の攻撃は既に岩崎の大事な何かを破壊していたのかもしれない。正直、僕の首を絞めるその腕の力も、僕はほとんど感じることが出来なかった。厳しい表情で梓が近づく。岩崎は怖気づいて後ずさりした。怯えきった岩崎に、僕はもう恐怖を感じなかった。彼の底を知ってしまった。人質を取るような低俗な人間に、僕はもう屈したりはしなかった。
僕は自由な右足を上げる。そして、勢いよく岩崎の右足めがけて突き降ろした。彼が情けない叫び声を漏らした。そして僕を捕えていた力がゼロに等しくなる。僕はそこから難なく抜け出すことが出来た。
人質を失って彼が慌てた。梓は彼にジリジリと接近した。恐怖した彼は敵前にも関わらず、背中を向けてその場から走りだした。ヨロヨロとした足取りで破壊された机を乗り越えていく。その度に彼は転びそうになった。そして彼は、やっとの思いで破壊された窓の付近にまでやって来た。窓の外は吹き抜けで、下には中庭がある。つまり、そこは安全地帯でも、出口でも何でもない。そこに来て安心出来ることなど何もない。彼はもうそれすらも理解出来なかったのだろう。
梓が窓際の男を目指して駆けだす。岩崎からすれば、それはさぞ恐ろしい光景だっただろう。恐らく、残り少ない理性を完全に失わせるのに十分だったはずだ。彼は梓の攻撃から逃れようと割れた窓から外に出ようとしていた。この教室の外にベランダはない。よって彼がここから逃れるためには僅かにある窓枠をつたわなくてはならない。彼は鬼気迫る顔で窓枠を掴みながら外に踏み出す。梓はスピードを緩めることなく窓まで走り、そして彼が摑まる窓枠を一撃のもとに破壊した。岩崎はバランスを崩し、体重が後ろにかかる。それでも彼は死にたくない一心で腕を伸ばし、窓枠に手を掛けようとした。
彼に窓枠にずっと摑まっていられるほどの握力が残されていたとは思わない。だが、一瞬くらいなら手を掛けることは出来たかもしれない。だが残念ながらその時の彼にはそれすら不可能であった。なぜなら彼は全身血だらけだったからだ。窓枠を摑みかけた彼の手は、自身の血で滑ってしまった。その時の彼の顔は、まさに絶望といったところだった。そして彼の姿は完全に僕の視界から消えた。
生々しく肉が弾ける音が中庭で鳴り響いた。彼の最期を確認する必要はもうなさそうだった。
騎士は剣を収めた。そして一度大きく息を吐いた。僕は彼女を見た。彼女も僕を見た。梓は、とても悲しそうに僕を見ていた。
僕は梓の方へ歩み寄ろうとした。だけど梓は、僕から視線を逸らし、後ろの窓枠に飛び乗った。そして大きく跳躍すると、そのまま真冬の夜空に消えていった。
僕は身震いした。気付くと、窓がなくなった部屋は随分と気温が低くなっている様だった。
僕はシンと静まりかえった教室を後にした。廊下に出ると、下へ続く階段を下っていった。
建物の外に出る。ここはどうやら七号館らしかった。僕はそこから右手に曲がった。左右のベンチを通過し、十字路を再び右に曲がる。工事中の建物を左手に見ながら僕は前に進んだ。そこを抜けた先には、例の銅像があった。そこは、僕が初めてあの騎士と出会った場所だった。そしてあの日、二人でここに来ることを誓い合った場所だった。
僕の頬を涙が伝った。
長い夢だった。
僕はそこに佇んでいることしか出来なかった。
あの子のいる世界、いない世界 作者:牧村光士郎
A
牧瀬小太郎は空っぽだった。信頼すべき友達も、心を寄せられる恋人もいない、空っぽの存在だった。
彼はいつも窓の外を眺めていた。そんな彼を人は、気持ち悪いとか、不気味と蔑んだ。クラスのいじめっ子は、しょっちゅう彼をいじめた。
彼は何も抵抗しなかった。もう何もかも、諦めているかのように。
彼はそうして、死んだように学校生活を送り続けた。
彼の楽しみは、小説を書くことだけだった。彼はそんな妄想の世界に入り込むことで自分を保ち続けた。
彼はいつしかとあることを夢見るようになった。詰まらない日常に、突如として現れ、彼を夢の様な世界に連れて行ってくれる少女。彼はそんな少女が現れてくれることを夢見た。
そんな少女が本当にいると考えると、彼は空っぽのままでも生きていける気がしていた。
しかしある時、彼のそんな妄想は現実のものとなった。まるで彼の小説の中から抜け出したかの様に、その少女は彼の理想通りの人だった。
「行こう! 小太郎!」
楓は彼の手を引き、彼を連れだしてくれた。こんなロクでもない世界から、夢の様な広い世界へ連れて行ってくれた。小太郎は、彼女が連れて行ってくれる世界のどれもが新鮮に思えた。学生がよく行くゲームセンターも、色々な店があるショッピングモールも、風が気持ち良い学校の屋上も、何もかもが新鮮で、刺激的で、輝かしい世界だった。
まるで干上がった大地に雨が降るように、彼の心は生きる喜びで溢れていった。
放課後の教室で、彼は楓と二人きりになった。紅くて幻想的な空間で、彼は生まれて初めて女の子と唇を重ね合わせた。いつもいじめられ、虐げられていただけのこの教室で、まるで見せつけるかのように、彼は幸せを手に入れたのだった。
いつも一人きりだった学校からの帰り道を、二人並んで歩いた。一人で何の希望も見出せずに机に向かっているだけだった勉強も、お互いに目標を語り合いながら励めるようになった。そして、いつも涙を堪えて意識が落ちるのを待つだけだったベッドの中も、もう一人ではなくなっていた。
楓の体温に触れることで、心が安らぐのを感じた。楓に頭を撫でられることで、心の傷が徐々に塞がっていくのを感じた。楓と何度も口づけを交わすことで、生きていく喜びを感じることが出来た。
楓が彼の全てとなった。
彼はずっと待っていた。自分を救いだしてくれる人を。
彼は想った。僕は楓と出会うために生まれてきたのだと。
彼の心は、そうして満たされていった。
彼の小説も、徐々にその内容を変化させていった。理想を追い求めるだけだった主人公も、今ある幸せを噛みしめられるようになっていった。彼は好んで、楓に似た女の子を描いた。楓が彼を幸せにしたように、楓に似た少女は皆を幸せにした。それは楓さえいれば、僕に怖いものなんて何もないという、彼の心の表れであった。小説を書くことで現実から逃避していた彼は、小説を書くことで幸せを噛みしめるようになった。小説は希望から、幸せの象徴へと変わったのだった。
そして更に、彼は自分と同じ様な不幸な状況に置かれている人たちへ、小説を通してエールを送るようになった。願いはきっと叶う。だから希望を捨てないで。人生に絶望せずに、希望を抱き続けてほしい。彼はそう願った。
彼の元には、小説で心を救われたという人たちからメッセージが届いた。自分の幸せで他の人までも幸せにすることが出来た。彼は嬉しかった。そうやって、みんなが幸せになって欲しいと思った。
世界が幸せでありますように。それが彼の心からの願いだった。そう、あの日を迎えるまでは……。
○
ある日楓が倒れた。ただの風邪だと思っていた彼女の容体は、瞬く間に悪化していった。
数日後、彼は医者にあまりにも残酷なことを告げられる。楓の両足はもう動かない。そう言われた。
信じられなかった。つい最近まで一緒に商店街を歩いて、休日は二人で遠出をした。彼女は元気いっぱいに歩いていた。なのに、もう歩けないだなんて信じられる訳がなかった。
だが、悲劇はそれだけでは終わらなかった。
「手術をしても、治る可能性は半々といったところです……」
医者は申し訳なさそうに言った。彼は医者が何を言っているのか分からなかった。
二分の一。二分の一で、医者は楓が死ぬと言ったのだ。そんな現実を、受け入れろと言ったのだ。受け入れられる訳がなかった。足が動かなくなることだけでもあんまりなのに、命すらその病気は奪いかねないと言うのだ。
彼は思った。どうしてそんな酷いことをあの子に強いるんだ。あんなに良い子にどうしてそんな過酷な運命を強いるんだ。世の中にはクズみたいな人間が山のようにいるのに、どうして楓だけがそんな目に遭わなければならないんだ、と。
病室で楓は彼に何も文句を言わなかった。彼女は笑い、逆に彼を励ました。彼にとってそれは逆に辛いことであった。彼は彼女に吐き出してほしかった。ありとあらゆる鬱憤を、この理不尽さに対する憎しみを、彼にぶつけてほしかったのだ。
そんな時、彼の元に一通のメールが来た。そのメールにはこう書いてあった。
“小太郎さんの小説のお陰で心が救われ、死ぬことを思いとどまりました。そして信じて頑張り続けていたら、僕のことを心から理解してくれる人と巡り合うことが出来ました。彼女と出会えたのはあなたのお陰です。本当に、ありがとうございました! そしてこれからも、素敵な小説を書き続けてください!”
彼は近くに置いてあった時計を手に持ち、そして力いっぱい壁に投げつけた。時計はバラバラに壊れ、もう二度と彼に時刻を告げることはなかった。
彼はメールを削除した。そして、全ての小説を消去した。
病室では、彼は努めて平静を装った。だが、彼の心の動揺が楓に悟られないはずがなかった。
ある日楓は彼を病室に呼び出した。そして、初めて見せる様な真面目な顔でこう言ったのだ。
「私たち、別れましょう」
彼は動揺しきった声で、「どうして?」と尋ねた。彼女は答えた。
「これ以上、あなたに辛い想いはさせたくないから」
そうして彼女は精一杯笑った。それはまるで、今にも泣き出しそうな、そんな笑顔だった。
彼は力なく病室を出た。そしてヨロヨロとした足取りで、病院の階段を昇り始めた。
彼の心には、ある一つの感情だけが渦巻いていた。それは、後悔だった。あの時僕が、楓と出会っていなかったら、今頃どうなっていただろうかと、彼は思った。
一人で孤独に学校生活を送り、何の感動もなく日常を送っていただろうと彼は思う。だがそれは、決して不幸なことではないのかもしれない。だって、その世界の彼は、小説に逃げ込むことが出来るのだから。辛いことから目を逸らしても、誰も文句を言わないのだから。自分以外の誰の不幸も背負っていないのだから。だから彼は幸せだと思った。
彼は風を感じた。出来ることなら、この世界を全て吹き飛ばしてほしいと思った。
彼は金網に足を掛けた。そして力を込めて上まで昇る。
そこから見える光景は、泣きたいほど綺麗だった。世界はこんなに綺麗なのに、幸せでない自分がいることが辛くてしょうがなかった。
彼は金網の向こうに降り立ち、下を見た。
そして最後に彼は、誰にでもなくこう言った。
「あの時、楓と出会わなければ良かった。出会わなければ、こんなに辛い想いをしないですんだのに。ずっと一人でいれば良かった。幸せになんてならなければよかった……」
風が吹いている。そこにはもう、誰もいなかった。
B
牧瀬小太郎は空っぽだった。信頼すべき友達も、心を寄せられる恋人もいない、空っぽの存在だった。
彼はいつも窓の外を眺めていた。そんな彼を人は、気持ち悪いとか、不気味と蔑んだ。クラスのいじめっ子は、しょっちゅう彼をいじめた。
彼は何も抵抗しなかった。もう何もかも、諦めているかのように。
彼はそうして、死んだように学校生活を送り続けた。
彼の楽しみは、小説を書くことだけだった。彼はそんな妄想の世界に入り込むことで自分を保ち続けた。
彼はいつしかとあることを夢見るようになった。詰まらない日常に、突如として現れ、彼を夢の様な世界に連れて行ってくれる少女。彼はそんな少女が現れてくれることを夢見た。
そんな少女が本当にいると考えると、彼は空っぽのままでも生きていける気がしていた。
彼は少女に、ありとあらゆる願望をつぎ込んだ。容姿や性格はもちろんのこと、自分が言って欲しい台詞や、やって欲しいことを全て小説の中の少女にやらせた。時には卑猥なことを考えもした。故に、彼の妄想は時に度が過ぎるものだった。
彼には何もなかった。だけども彼は、その妄想だけで充分満足だった。そんな少女がいてくれたらと思うだけで、彼の心は満たされたのだ。
彼が三年生になる頃、ピタッと彼に対するいじめが止んだ。彼の学校は進学校だ。恐らく彼に構っている時間があるなら、勉強をしていた方がましだといじめっ子も考えたのだろうと、彼は思った。
月日があっという間に走り去っていった。彼は普通に受験し、それなりの大学に進学した。
大学は高校までとは違い、好きな人とだけ関わりを持つことが出来るコミュニティだ。だからもういじめは存在していなかった。学生は、嫌いな人をいじめるのではなく無視すればいいだけの話だからだ。
彼は大学では文芸サークルに入った。そこには、自分と同じ様に小説が好きなのだが、内気なせいでいじめを受けていた人が何人もいた。彼はその人たちと仲良くなった。彼らは誰かを仲間はずれにはしなかったから、彼はとても居心地が良いと感じた。
彼は大学で、小説以外ではサブカルチャーにも興味を持つようになった。深夜にやっているアニメを見あさり、オタク友達とアニメ談議を楽しんだ。そして年に二度あるコミケに参加し、自分の小説を販売したり、同人誌を買いあさったりした。
それでもやはり、彼の楽しみは憧れの女性を妄想することだった。いつか必ず夢に見た少女が現れてくれるはずと信じ続けた。彼が妄想したのは、そんな女性とのデート、そして時には夜の生活を思い浮かべたりもした。その度彼は、あられもない少女の姿を夢想して自慰行為に励んだ。彼はそんな自堕落な大学生活を謳歌した。彼の人生は非常に充実したものになった。
四年生の夏ごろ、彼はとある中堅の出版社の内定を獲得し、大学卒業と同時に一人暮らしを始めた。
就職と同時に彼の生活は大きく変わった。忙しくて息を付く暇もなかった。だが彼の妄想だけは変わらなかった。彼の頭の中には、あの時と変わらずあの少女がいた。
彼が忙しなく働いていた時だった。頑張り屋の彼に好意を持つ女性が現れたのだ。そして彼も、その女性の好意に気付いていた。彼は、周りが言うままに彼女を食事に誘い、休日には映画に誘ったりもした。そして二十六歳の時、彼は生まれて初めて本物のセックスをした。だが、それは思っていたよりも気持ちの良いものではなかった。
彼は女性と交際をスタートした。
彼の妄想は、まだ続いていた。
○
女性との交際は長くは続かなかった。
女性は度々彼に対して怒った。彼は何が不満なのか分からなかった。
最後の日、彼女は彼に尋ねた。
――本当に私のこと好きなの? と。
彼は好きだと言った。でも、好きじゃないと分かっていた。
彼は未だに信じていたのだ。あの少女が、自分の前に現れることを。
結局それ以降も、女性との関係はなかなか上手くいかなかった。
次第に女性から敬遠されるようになった。何かがおかしいと、遠巻きに噂されるようになった。不憫に思った会社の上司は、彼にお見合いの話を持ちかけた。
彼は最終的にその女性と結婚した。理由は早く身を固めた方が良いと、両親に口酸っぱく言われたからだった。
その女性との生活はそれなりに上手くいった。彼は三十を過ぎた頃、自分の元にはもう理想の女性は現れないのだろうと思った。その女性で妥協したとまでは言わないが、もう潮時なのかもしれないと、彼は思ったのだ。
彼には子供が二人できた。子供は可愛かった。妻も大事だと思った。だが、彼は自分の生活に心から満足出来ていなかった。
無理だ、妄想だ、あり得ないと思いながらも、彼はまだ信じてみたいと心のどこかで思っていた。あの少女が、ある日ひょっこり自分の前に現れるとことを、彼は望んでいたのだ。
ある日彼は、大学時代の友人と飲んだ。その中の一人は、未だにサブカルチャーに傾倒しているらしく、同人誌を描いて生計を立てていた。彼は、この歳で未だに女性と交際したこともない学友が、エッチなシーンばかりの同人誌を描いていることがおかしくてならなかった。そんな彼が不意に言った。
「俺はあの時妄想し続けた、ゆきちゃんを今でも描いているんだ。同人誌の中では、ゆきちゃんといくらでもエッチが出来る。彼女は歳を取らないから、ずっと美しいままなんだ」
別の学友が、その言葉に対して「お前相変わらずバカなままだな」と言って笑った。だが、彼は笑わなかった。くだらないことかもしれないが、彼にとっては凄いことだった。彼は本気で、その学友を羨ましく思ったのだ。
そして彼は帰りに、その友人に頼んだ。
「俺の嫁の同人誌って、描けないかな……?」
友人はバカ笑いしながら、その提案を受けてくれた。五千円でだが。
妻も子供もいて、仕事もそれなりに順調。それでも彼は、未だに満ち足りていなかった。あの時、あの子が現れてくれさえすればと、彼は思わずにいられなかった。あの子が今いてくれれば、自分は心から幸せであったに違いない。仕事が上手くいかなくても、子供が出来なかったとしても、彼は満ち足りていたはずだ。休日に楓を主人公にした同人誌を読みながらマスターベーションをしている自分もいなかったはずだった。
ある日の夜、彼は近所の川辺で無線機を拾った。トランシーバーみたいで、彼はカッコイイと思った。彼は通信をするみたいに、それに向かって語りかけた。
「もしもし、ぶーぶー、もしもし?」
くだらないと思いながらも、彼はいつしか本気になっていた。彼は、心の中に思い描くとある人物と交信をすることにした。
「ぶーぶー。えーと、おっほん。もしもし、小太郎さん、聞こえていますかー? あっちの世界の小太郎さん、聞こえていたら返事をお願いします」
「はいこちら小太郎。おやおや、あなたはそちらの世界の小太郎さんじゃないですか。今日はどうされたんですか?」
「今日連絡したのは他でもありません。実はあっちの世界の小太郎さんは、今どんな生活を送っているのか知りたくなってしまったんですよ」
闇夜に響く中年男性の声。だけど彼は気にせず寸劇を続けた。
「生活はとても楽しいですよ。楓が作るご飯はとても美味しいですし、身の回りの世話は完璧にこなしてくれます。それにそもそも僕は、彼女を眺めているだけで幸せなんです。楓がいるだけで、僕は世界一の幸せ者でいられるんです」
「そうですか。それは羨ましい。やはり僕は、僕は……」
言葉に詰まる。言ってしまっていいものか。誰も聞いてやしないのに、彼は躊躇ってしまっていた。
「えーと、あ、あれ、おかしいな。別にこんなこと、悲しくなんて、ないはずなのに……」
彼は口に手を当てる。なぜか無性に泣けてきてしまった。彼は必死に涙を堪えた。
唐突に、壊れて捨てられていたはずの無線機が大きな音を発した。その音を聞いて、彼の心臓は危うく破裂しそうになるほど脈打った。それはまるで、お化け屋敷に入ってすぐに驚かされた時の様な慌て方だった。彼は恥ずかしさで耳まで真っ赤にしながら、無線機に向かって叫んだ。
「す、すみません、今のなしです! 楓なんて子、僕は知らない! あの時楓と出会ってればなんて思ってません!」
彼は情けない声で言い訳を言い続ける。しかし無線機からは何の音も聞こえてこない。彼はもしや聞き間違いかと思った。彼はそれをコンコン叩いた。やはり反応がない。彼はその様子を見て、一度大きく溜息をつくと、それをもう捨ててしまうおうかと考えた。
しかし、その時だった。
「楓と……」
聞き間違いだと思っていた無線機から、今度は本当に声が聞こえたのだ。彼は急いでそれを耳に近付けた。声ははっきりと彼の耳に届いた。
「あの時、楓と出会わなければ良かった。出会わなければ、こんなに辛い想いをしないですんだのに。ずっと一人でいれば良かった。幸せになんてならなければよかった……」
一体どこから、そしてなぜこんな捨てられた無線機に連絡をしてきたのかは分からないが、彼はその人の言葉に耳を傾けた。
向こう側の人物は酷く落ち込んでいる様だった。それもかなり切羽詰まっている。彼は焦った。このままでは無線機の向こうの人物が自殺でもしかねないと思った。
彼は、その人を落ちつけるために話を聞くことにした。彼はその人に何があったのか詳しく話してほしいと頼んだ。
その人は答えた。恐らく、もう自分の中だけに留めておくことは出来なかったのだろう。
その人の話によれば、その人は自分が理想としていた女の子と巡り合い、仲を深めることができ最近までは本当に幸せであったのだが、つい最近その子が大きな病を患い、自分は彼女に別れを告げられ、思いつめて今まさに命を断とうとしていたということだった。
彼は驚いた。その人の元々の境遇から理想まで、自分のものと完全に一致していたからだ。彼はその人がその女の子と巡り合えたことを羨ましいと思った。だがそれだけに、彼が今どれほど悩んでいるのかが痛いほど分かった。
“楓と出会わなければ良かった”。その言葉は、彼の心に深く突き刺さった。自分は今、こんな歳になっても追い求めているほど楓という少女に憧れているのに、無線機の向こうの人物は、彼女と出会わなければ良かったと言っている。その人にどれほど辛い試練が降りかかっているのか、それは想像に難くないことだった。
だけれども、だ。
「こう言うのもなんですが、それは随分と贅沢な悩みだと思いますよ」
無線の主は少なくとも自らの理想と巡り合い、これまで素晴らしい時を過ごして来たのだ。どんなに今辛かろうとも、その事実だけは決して揺らぐことはない。
「それに比べて僕は、この歳になっても未だに理想のあの子のことを追い求め続けているんです。もう妻も子もいるのに、未だに理想のあの子のことを妄想して、夜毎に自慰行為に励んでいるようなどうしようもない人間になってしまったんです。もう現れる訳ないと分かっているつもりでも、未だに諦められない、情けない人間にね」
無線の主がどう思おうがもう知ったことではなかった。彼はたまりにたまったものを吐き出すかのように、はたまた全然関係ない人に八つ当たりでもするかのように喋り続けた。
「一回フラれたくらいでなんだ。まだその子のことが好きならそれ位で諦めるな。諦めるくらいなら、出会わなければ良かったと思うくらいなら……、最初から僕と代われ! 僕が代わりに楓と出会ってやる! そして僕が彼女と幸せになってやる!」
どんなに彼女の病気が重くても、どんなに彼女が別れたいと言っても、彼は彼女から離れるつもりはなかった。十年以上、彼女を妄想し続けていきた彼には、それが出来る絶対の自信があった。
「こんな気持ちの悪いおっさんに取られたくないなら自分でちゃんと彼女を守れ。それに、もし彼女と上手くいかなかったとしても、絶対に死んだりするんじゃない。確かに心残りはある。だが、彼女が、楓がいない人生だって、決して捨てたものじゃないから」
彼は家で待つ妻と子を思い浮かべた。そう言ってから思ったことだが、彼は思ったよりも家族のことが好きだということを、今この場で理解していた。彼は自分の顔がほころんでいるのを感じていた。
彼はそれだけ言うと、静かに無線機を持つ右腕を下ろした。
彼は川の向こう側を睨み、そして、右腕を思いきり振った。無線機は弧を描き、ポチャリと音を立てて水底に沈んでいった。
そして川に向かってこう叫んだ。
「僕は一生、楓を想い続けてやるからなああああああ!!」
家族は好きだが、アイドルは別物。そんな四十、五十代の主婦が韓流スターを大好きな様に、彼も楓のことがいつまでも好きだった。
河原の夜道を、何人かの会社帰りの人が歩いていた。散歩で通りかかった学生もいた。だがそんなものは関係ない。彼は満足すると、サッと踵を返し、そのまま全速力で河原の土手を駆けあがっていった。
A
風が吹いている。そこにはもう、誰もいない。
そこには、ただ古ぼけた無線機だけが残されていた。
病室にて
杉山が恐喝の事実を認めたよ。彼は中根雄二たちが女子更衣室に隠し撮りのカメラを仕掛けていたのを知り、それをバラさない代わりに言うことを聞くよう脅したのだ。
その内容はこうだ。彼は君に並々ならぬ感情を抱いていた。彼は君に様々なアプローチを試みたが芳しい効果は得られなかった。だが彼は諦めなかった。君が彼を避けていると知りながらも、君に対する感情は変わらなかった。そんな時、君に彼氏が出来た。僕もよく知っている牧村光士郎くんだ。好きな人に彼氏が出来た場合の男の気持ちを想像してごらん? それはもう辛いんだ。大抵の男はその彼氏を羨むか、早く別れろと思うものさ。
彼の場合は少し違った。いや決して普通の人と大きく異なっている訳じゃない。つまりは、少し過激だったというだけだ。彼は羨むを通り越して、光士郎くんを恨んだ。そして酷いことに、彼の信頼を失墜させようとした。
実に身勝手な行為だ。自分は君に全く相手にされていないというのに、一方的に光士郎くんを恨んだのだから。
彼は光士郎くんの信頼を失墜させるために色々な策を考えたが、そんな時盗撮の噂話を聞いた。彼はそれを聞くとすぐにゆすりを考えたそうだ。まさに根っからの悪党と言ったところだね。その策が上手くいけば彼は光士郎くんに肉体的ダメージと精神的ダメージの両方を与えることが出来る。しかも、もしバレたとしても中根たちが彼の関与をほのめかさない限り彼のやったことが露見することはない。彼は恐らくそう考えたはずだ。
だがこの策は些か強引過ぎた。上手くいけば効果はあるが、そんな良く調べれば分かるトリックを仕掛けたのは慎重さに欠けていた。もしかしたら、彼らは光士郎くんにはさしたる味方などいないと考えていたのかもしれないが、光士郎くんには当然君がいるし、生徒会長として僕も捜査に関わるということを失念していたのは彼らにとって大きな痛手となった。
彼は中根雄二たちを利用することで外から事件を傍観するつもりだったのだろうが、理由もなく中根たちが光士郎くんを陥れようとするはずもない。すぐに君や僕にそれを気付かれるということを彼は考えなかったのだろうか? いや、もしかしたらバレるかもしれないとは思っていたのかもしれない。彼は恐らく、盗撮の件はそれだけ大きなカードだと考えていたのだろう。中根雄二たちが証言をしない限り、彼が脅してやらせたという証拠は全くない訳だから、そう考えるのも確かにおかしくはない。だがここでも彼は失念していた。この僕が、実に執着心の強い性格だということをね。
とは言っても、この事件を最初に解いたのは恐らく僕ではないのだろうね。
君の洞察力には参った。こんなことなら、初めから君に情報をもらっておくべきだった。杉山が、君にしつこくこの件に関して聞かれたと言ったのを聞いた時、僕は思わず感心してしまった。それほど君にとってこの事件は大きな意味があり、君が光士郎くんをいかに大事にしているのかを改めて実感したよ。
そんな君が眠ったまま目覚めないという知らせを受けたのは、五月の初めのことだ。僕は君の状態に思い当たる節があった。というのも、僕の妹も、君と似た様な状態になっていたことがあるんだ。
僕が中学三年、妹の美紀が二年の時だった。僕の家は両親が離婚していて、父親だけしかいなかった。父は表向き生真面目なサラリーマンだった。だがその本性は全く異なっていたんだ。
父は妹を犯した。父親なのに、相手は娘なのに、やつは見境もなく彼女を犯した。僕ももう少し早く気付いてあげられればよかった。あんな状態になるまで気付けなかった僕も罪は重い。
美紀から父の話を聞いた時、僕は本気で父を殺しそうになった。だが美紀はそれを止めた。僕を人殺しにする訳にはいかないと思ったからだ。だから僕は、せめて彼女を守ろうと思った。翌日になったら、児童相談所に行こうと思っていた。
その夜のことだった。僕は家の居間のソファーで目を覚ました。自分の部屋で、美紀と一緒に眠ったはずなのにだ。その日、父親は出張で家を開けていた。でも僕は心配で、すぐに自分の部屋に戻ろうと思った。そんな時、和室の方から何やら声が聞こえてきた。それは聞き覚えのある、二人の人間の声だった。
少し朦朧としていた意識が、その瞬間一気に覚醒した。声は、妹の泣き叫ぶ声と、父のゲスな欲望にまみれた笑い声だったのだ。僕は走った。途中テーブルにぶつかり、上からコップが落ち、粉々に割れた。だが僕は気にせず走った。
和室に駆け込んだ。そこには、服を裂かれ、あられもない姿にされた美紀と、醜い笑い顔で腰を振る、あの男の姿があった。妹は涙を溢れさせて、必死にやめてと懇願していた。だがあいつは、全くそれを意に介することなく娘を犯し続けた。
そんな光景を見せられて僕が平常心でいられる訳がない。僕はやつに殴りかかった。だが、あいつの腕力は思ったよりも強く、僕はあっさり壁の方に突き飛ばされてしまった。やつは美紀を放すと、憎しみの籠った顔で僕を見下ろした。そして僕の腹に蹴りを入れた。痛かった。胃液が逆流し、口から溢れた。やつはそんな僕に尚も攻撃を加えた。僕は殺されると思った。妹も守れずに死んでしまうと思った。だが次の瞬間、やつの身体が僕の横に倒れてきた。そして少しピクピクと身体を痙攣させた後、完全に動きが停止した。良く見ると、やつの後頭部が血だらけになっていた。そしてそこから流れ落ちた血が集まり、畳の上に血だまりを作った。
僕は、恐る恐る視線を上げた。気配のする方に、視線を持っていく。そこには血だらけの裸の少女が立っていた。両手には、血ぬられた金属バット。顔や未発達の乳房に、べっとりと血が付いていた。その顔は、笑顔だった。
僕は目を覚ました。自分の部屋のベッドの上で汗だくになっていた。隣には昨夜と変わらない様子の美紀の姿があった。僕はそれが夢だったのだと悟った。まだ美紀を助けられる、そう思った。だが状況は完全に変わってしまっていた。美紀は目を覚まさなかった。息はあるのに、目覚めることだけがない。僕はどうしていいか分からず、ただただ混乱するだけだった。その夜も僕はあの夢を見た。父親はやはり殺された。そして美紀は、笑っていた。
翌日出張から父が帰って来た。僕は美紀を犯したことをやつに問い詰めた。すると、逆上したやつに殴られ、情けないことに僕は気を失ってしまった。その甘さこそ全てだ。僕はどうしようもなく無力だった。
目が覚めたのはすっかり暗くなってからのことだった。僕は玄関で目を覚ました。身体の節々が痛んだが、僕は気にせず走った。
美紀の部屋に、やつはいた。やつは意識のない美紀の服を脱がし、その汚らわしいものを、美紀の綺麗な身体に突き立てていた。やつは何か言っていたと思う。恐らく美紀が何も反応を示さないことに腹を立てていたのだと思う。
僕は、置いてあった金属バットでやつに襲いかかった。だが、やつは僕の攻撃を掻い潜り、僕の身体を掴んだ。そして思いきり投げ飛ばそうとした。しかし今度は僕が食らいついた。やつの身体をがっちりつかみ、一緒に転倒させたのだ。その時僕らは、美紀の裸の身体の近くに倒れ込んだ。恐らく二人とも彼女の身体に触れたんだと思う。意識が飛んだのはそのすぐ後だった。
目覚めるとそこは、やはり家の居間だった。すぐ近くにやつが倒れていた。僕はやつを殺そうと思い、台所に向かおうとした。
すると、美紀が裸のまま父の前に立っているのが目に入った。何もその身に纏わず、しかもそんな自分を恥ずかしがる素振りも見せずに、彼女はその手で金属バットを握りしめていた。やつは動揺していた。まるで戦場で銃口を向けられている一兵卒の様に、恐怖で顔を引きつらせて、美紀を見つめていた。
やめてくれ。許してくれ。お父さんが悪かった。謝るから、どうかそのバットを下げてくれ。そんなことをあいつは言っていたんだと思う。
美紀は、無表情で金属バットを振り上げ、そして、やつの頭めがけて振り下ろした。
ぐしゃりと音がし、べちゃりと何かが飛び散った。美紀はまたバットを振り下ろす。さらに鈍い音が響いた。どれくらい殴っただろうか。恐らく十回ほどだったと思う。
ぐちゃぐちゃになった人間だった者の身体が、居間の地面に横たわる。身体に返り血を一杯に浴びた美紀は、狂ったように笑い始めた。
僕は恐怖で凍りつき、その様子を無言で見つめていた。
目が覚めると、そこには裸のまま笑顔で眠る美紀と、息をしていない父親の姿があった。父は、外傷もなく、死んでいた。妹は気が狂った。そのまま精神病院に入り、今も回復の見込みはない……。
この話を他人にしたのは初めてだ。僕がこの話をした理由は分かるはずだ。美紀の状態と、君の状態は、恐らく同じなのではないかと僕は思ったのだ。
君がどんな夢を見ているのかは知らない。でも僕は今とても怖い。君がこれからとんでもないことをしようとしているのではないかと思えてならないからだ。
光士郎くんは今闘っている。ここ数日彼は学校に来ていない。風邪ということになっているが恐らく違う。彼は今自分に問いかけているのだ。そして答を見つけ出そうとしている。
僕はそんな彼を助けたい。そして君が取り返しのつかない結論を下す前に、君を止めたい。僕は美紀を止められなかった。だがせめて、君だけは取り返しがつく前に止めたい。
だから、僕は先に行かせてもらう。光士郎くんは、恐らくもう少しでここにやって来る。夢の中で僕は彼を待つ。
絶対にあんな結末は見たくない。絶対に、助けてみせる。
牧村光士郎の手記 其の四
1
この手記が書かれているということは、もう全てが終わったということだ。僕らの数日間の物語がいかなる結末を迎えたのか、今日僕はここに書き記そうと思う。
冒頭部分で詳しいことを書くつもりはない。今ここでまとめられる様なことを僕は体験していない。全てを記すことが、僕に与えられた責務だと思う。
長ったらしい前置きはもういいだろう。僕はこれまであったことを全て書き記していく。あまり強烈過ぎて忘れられそうにもないが、出来るだけ記憶が新鮮な内に書きあげようと思う。
僕が梓の入院する病院に着いたのが、午後二時ごろだ。本当はもっと早く来ることも出来たのだけれど、なかなか覚悟が決まらずこの時間までかかってしまったのである。しかし、病院に着いた僕はもうしっかりと腹を決めていた。何もかも終わらせるという強い気持ちを持って来たのである。
受付を通りすぎ、エレベーターの方へ向かう。いつもなら寄る売店も今回ばかりはスルーした。ミルクチョコレートを買うのは、全てが終わった後でいいと思ったからだ。
四階へと昇る。廊下は日差しが差し込んでとても温かった。僕は吹き抜けに差し込む日差しを存分に浴びながら病室を目指した。
僕は病室の前にたどり着く。ノックはしない。ノックをしたところで彼女は答えてはくれないし、そもそも僕は今日彼女の意見を聞くつもりはない。だから僕は無言で病室の扉を開けた。
いつものように、彼女は窓際のベッドで眠っていた。僕はベッドの横の椅子に腰を下ろした。気持ちのいい風が窓から吹き込む。その度にレースのカーテンがゆらゆらと揺らめいた。僕は彼女の顔を覗き込んだ。
穏やかな顔。だが、今彼女が悩んでいることを僕は知っていた。
僕は彼女の手を取った。そして僕も目をつむった。
僕はパソコンの前に座っていた。辺りを見回すと、僕のすぐ左隣には教卓があり、この教室が僕の座っている所から右側に向かって三十メートルほどの長さがあることが分かった。そして横が長いのに比べ、縦の長さは五メートルほどしかなく、そこが非常に横長の教室であることが分かった。各席にパソコンがあることから、どうやらそこはパソコン室である様だった。
僕はその部屋に見覚えがあった。そこは前に二人で訪れたことのある部屋だった。そこは大学の政治経済学部の建物にあるため、政治経済学部を希望する彼女がこの建物に入りたいと言ったのだった。ちなみに僕は文学部が第一志望で、政治経済学部は第二志望だ。正直言うとこっちに入る方がよっぽど難しいのだけれどね。
教室には電気がついていたし、暖房もちゃんとついていたため非常に暖かかった。パソコンは起動していなかった。僕はスイッチを押してみたが、残念ながらそのパソコンはうんともすんとも反応してくれなかった。横のパソコンも、その横のパソコンも同じだった。僕は諦めて席を立った。
すると不意にパソコン室の扉が開いた。入ってきたのは、真辺梓その人だった。彼女はこの夢に出てくるとき必ず着用している甲冑を着ていなかった。それに加えて剣も持っていなかった。彼女の恰好は僕と同じように学校の制服だった。それはまさにあの時と一緒だった。二人でキャンパス内を見て回ったあの時と。だがその時とは絶望的に状況が違っていた。なんと彼女は、車椅子に乗っていたのだ。
あの時は、自身の足で校内を見て回っていたはずなのに、彼女の足は今の現実の彼女と全く同じ状態になっていたのである。
彼女は僕を見て特に驚いている様子はなかった。驚いてはいないのだが、なぜだが少し怒っている様に見えた。僕は車椅子の前に立った。すると彼女が言った。
「どこ行ってたの光士郎? 探したんだよ! ほら、もうかなり遅くなっちゃったし、早く帰ろうよ!」
そう言うと、彼女は僕の腕を掴んだ。僕は何がなにやら分からず狼狽するが、彼女は気にせず「早く行こう!」と言った。
彼女の口ぶりを聞いていると、どうやら僕がキャンパス内で一人で勝手にいなくなってしまい、彼女がずっと探していたということになっているらしかった。実際僕は大学を訪れた時一人になったことはなかった。だからこれは恐らくこの夢の中の設定なのだろう。だがなぜ急に制服姿で、しかも車椅子に乗って彼女が現れたのか僕には理解出来なかった。
制服姿の彼女がここにいるということは、騎士の恰好をした彼女はいないのだろうか。もしいないのだとしたら、この夢の目的は何なのだろうか? これまで、夢の中で彼女が騎士の恰好をしていたのには目的があったはずだ。僕はそれを理解してここに来た。だから僕は騎士姿の梓に会わなければならなかった。
彼女は相変わらず僕の腕を掴み、教室から出ようとする。僕はそんな梓に向って尋ねた。
「鎧は……あの甲冑はどうしたの?」
僕が尋ねると、彼女は顔全体に疑問の色を浮かべた。まるで何を言っているのとでも言いたげな顔だった。
「甲冑って、一体何のこと? どうして私がそんなもの着ないといけないの?」
どうやら彼女はしらばくれている訳ではなさそうだった。彼女は本当にあの騎士姿のことを知らなかったのだ。僕はますます分からなくなった。騎士姿の梓と、制服姿の梓が別人だとは思えない。どっちも彼女であることは間違いなかった。だが何かが違っている。騎士姿の彼女は銀髪に青い眼だから雰囲気が違うのは当然だが、そういうことではなく、何か根本的な、大元が違う様な気がしたのだ。
眼の前にいる少女は、梓ではあるが、あの梓ではないのではと僕は思った。でもだとしたら彼女は誰なのか? 車椅子に乗っているのだから、現実世界の梓なのか。しかし彼女は眠ったまま目を覚ましていないはずだ。僕は結局彼女が何者なのか分からないまま、彼女と一緒に建物から出た。
外はやはり寒かった。彼女は自らの手に息を吹きかけている。その仕草は、あの騎士とは違う可愛らしさがあると思った。騎士は騎士で勇ましいが、彼女にはこういった一面もあったことを僕は思い出していた。
僕は梓の車椅子を押しながら歩いた。そして徐々にあの銅像に僕たちは近づこうとしていた。僕は段々と心がざわめき立つのを感じていた。それと同時に足も震えだしていた。僕の身体はまるで、これ以上先に行かせたくないかの様に僕の動きを止めようとした。だが僕は止まれない。まるで吸い寄せられる様に、この足は歩みを止めようとはしなかった。そして僕らはついに銅像前にやって来た。
建物の灯りとは違う、人工的ではない不思議な光をその身にまとい、騎士は佇んでいた。やはり彼女はいた。制服姿の梓とは別に騎士姿の梓がいる。この空間には二人の梓が存在していたのだ。
車椅子上の梓は明らかに狼狽していた。自分とそっくりの人間が突然現れれば驚くに決まっている。しかもその人が甲冑を着ていたとしたら、その驚きは何倍にも膨れ上がるに違いない。
正直言って、狼狽していたのは彼女だけではなかった。僕も混乱していた。あまりに予想外だった。僕は確かに騎士姿の梓に会いに来た。だがそこにもう一人の梓が現れることなど想定すらしていなかった。
この夢の意味は何だ? 彼女が見せる夢にはいつも意味があった。二人の梓が存在する世界にどんな意味があるのか? 僕は急いで頭を回転させる。だが、答えは導き出せない。分からない。その時の僕には彼女の気持ちが全く分からなかったのだ。
騎士は驚いている僕らを見た。彼女の表情から感情は読み取れなかった。騎士は僕らを見ながら言った。
「光士郎、あなたに対する私の気持ちは、もうとっくに理解しているはずだよね……?」
僕は無言で頷く。表情はかなり強張っていたと思う。騎士の顔は変わらない。
「ちょ、ちょっと光士郎、これ一体どういうこと……? どうして、私がもう一人いるの? それにあの恰好は……? 私の気持ちって、何のことよ……?」
彼女が矢継ぎ早に質問をぶつける。これほどまでに動揺している梓は見たことがなかった。僕は答えない。無言のまま騎士を見つめる。戸惑うばかりだった梓も、僕のただならぬ様子を見て黙った。そして同じように騎士を見つめた。
彼女が僕に何をしてほしいのかは知っていた。だが僕はそれを絶対に認めない。そのために僕はここに来たのだ。僕はやはり梓が二人いるという意味が分からずにいた。僕が尚も何も言わずにいると、彼女は口を開いた。
「光士郎、分かっているなら、ここには来てほしくなかった。素直に身を引いて欲しかった……。でも、もう仕方がない。私はもうこうするしか、あなたに想いを伝えられない……。だから……」
彼女は右手を腰に挿してある剣へと伸ばす。そしてしっかりと柄を握り締めた。
僕はその時やっと理解した。そして恐怖した。彼女の意志の強さは、僕の想像を超えていた。
彼女が剣を鞘から引き抜く。そしてこう言った。
「私は、私自身を殺します。それで全て終わらせます」
僕は車椅子から彼女を抱きあげ、戸惑う彼女を無視して背負い込んだ。そして、騎士に背中を向けて走り出した。
2
「ちょ、ちょっと、一体、どういう、ことなの?」
「いいから! いいから今は黙っていて! 絶対に僕は彼女に追いつかれちゃ駄目なんだ! 追いつかれたら……もし、追いつかれたら……」
それ以上は言えず、僕は梓を背負ったまま走り続けた。
彼女はとんでもないことを考えていた。この夢に来た時点で一悶着あるとは思っていたが、まさか自分自身を殺そうとするとは思いもよらなかった。
この夢の仕組みは相変わらずよく分からない。今まで赤間千鶴や杉山暁、岩崎陸也が夢の中で死んだところで現実世界には何の変化ももたらさなかった。だからもし、今回彼女が自分自身をこの世界で殺したとしても、現実世界の彼女には何ら変化はないのではないだろうかと僕は思った。すると、
「牧村くん! こっちだ!」
鳳さんが僕を呼んでいた。彼は大きなオフィスビルの様な綺麗な建物の下にいた。僕は全力でそちらの方へ走った。彼の元へ辿り着くと、彼は手を伸ばしながら「真辺さんは僕が」と言った。だが僕はそれを断った。彼女は、自分自身で守りたいと思ったからだ。
建物に入る直前、彼は僕に言った。
「細かいことを言っている時間はない。とにかく、僕らは彼女を守らなければならない。もし、ここで真辺さんが殺されてしまったら、現実世界の彼女も死ぬことになる。それは絶対に避けなければならない。絶対に守りぬかなければならない! 正確なことまでは分からないが、この夢が終わるとしたら、それは恐らくこの大学を飛び出した瞬間だと思う。なんとか彼女を撒き、この大学の敷地内から出ることが出来れば、この夢はきっと終わるはずだ」
彼はだいたいそんなことを言っていた。細かいことを端折っているせいで、なぜそんなことが分かるのか疑問を感じたが、なぜか彼がそう言うのならそうなのだろうという気になった。とにかく僕は、彼女を撒き、この敷地を出るまで彼女を守らなければならないということだ。僕がこの夢ですべきことは実に単純明快だった。
だが、何をやるかが分かっていても、実際にそれをやり遂げるのは至難の業だ。白銀の騎士が走るスピードと僕らが走るスピードを比べたら、その速さの差など一目瞭然だ。単純な競争ではすぐに追いつかれてしまう。しかも僕は梓を背負って走っている。障害物を味方につけないことには、とても逃げることは出来そうもなかった。
入った建物は非常に新しい建物であった。広いエントランスに、目の前には階段とエスカレーターがあり、二階がそこからもう見えている。あまり障害物はなかったが入ってしまったのだから仕方がない。僕らは一目散にエスカレーターまで走ると、それを一気に駆け上がった。
二階に上がると、すぐ左手にはラウンジがあった。その空間は非常に広く、五十メートル×二十メートルほどありそうだった。だが残念ながらそこにもあまり障害物がなかった。長机や椅子はあるが、彼女だったらまとめて吹き飛ばしてしまえるほどのものしかなさそうだった。だから僕らはラウンジには向かわず、今昇って来たエスカレーターの横にある、上階へ向かうエスカレーターに乗ったのである。
騎士の姿はまだ確認出来なかった。だが彼女が僕らを追ってこない訳がない。僕らを追うくらい、本気を出すまでもないと思っているのだろうか。もしそうだとしたら、それはある意味ではラッキーなことだった。この建物内で彼女と鉢合わせせず脱出することが出来れば、敷地を抜けることは不可能ではないはずだからだ。
僕らは三階に到着すると、更なるエスカレーターを昇りにかかる。僕はその瞬間、思わず息をするのを忘れてしまっていた。エスカレーターが辿り着く場所に、彼女の姿があったのだ。
どうやったのか、いつの間にそこに辿り着いたのかすら分からなかった。ただとにかく、騎士が僕たちを待ちかまえていたのである。
僕らはそのエスカレーターに乗りかけていたのだが、彼女を見つけるやいなや、急いで引き返した。昇りかけていたエスカレーターを降りたことで、僕は危うく躓きそうになったが、鳳さんがなんとか僕の身体を支えてくれた。体勢を立て直すと、僕らは後ろには目もくれずに、元来た道を引き返していった。
二階に辿り着くと、前方にガラスの扉を見つけた。僕らはほとんどぶつかる位の勢いで、その扉を押し開いた。その瞬間、夜の寒さが僕らを襲った。強烈な北風が僕らの身体を吹き抜けた。興奮してすっかり熱くなっている身体ですらそれは冷たいと感じた。それほどにここは冷たい世界だった。
僕らは急いで、前方の階段へと向かう。そこからは先日激闘を繰り広げた七号館と、そこから見ることが出来た六号館が見えた。右手には今いた高層ビルの様な十一号館、そして左手にはこれまた大きな建物が二棟見える。後ろはこの敷地内から出られる門があったが、この距離では彼女を撒けないと考え、僕らは大人しく階段を駆け降りることを選んだ。
二十段ほどある階段を素早く降りる。僕はすっかり息が上がっていた。正直、彼女を背負ったまま階段を降りるのは辛かった。だが文句を言っていられる状況ではなかった。僕は鳳さんに支えられ、その階段を出来るだけ急いで駆け降りた。
僕はそこで振りかえる。階段の真上に彼女がいた。いつかの時の様に月明かりを全身に浴び光り輝いていた。一瞬僕はそれを美しいと思ったが、彼女の瞳は信じられないくらい淀んだ色をしていたのを僕は見逃さなかった。感情が麻痺したかのようなその表情に、僕は恐怖すら覚えた。
騎士はゆっくりと階段を下りる。僕らは全速力で左手に曲がり、大き目の建物の中を目指した。扉を押し、僕らは中に入った。そこにはまたしてもエスカレーターがあった。先程の恐怖が蘇る。彼女はどんなルートを通ってやって来るか分からない。だが考えている余裕はない。僕らは飛び込むようにエスカレーターに乗った。
息を切らしながら三階まで向かう。彼女がこの建物に入った気配がした。まさか一跳躍で三階まで来ることはあるまいが、彼女の身体能力は現実世界の人間を軽く凌駕しているのは間違いなかった。
三階は、右手と左手どちらにも廊下が伸びていた。恐らくこの階は、ぐるりと一周回る仕組みになっているのだろう。だから恐らくどっちから入っても辿りつく先は一緒のはずだ。もし彼女を撒くとしたら、その途中にある教室を使うしかあるまい。
僕らは左手から廊下に入った。見たところ廊下の左右に教室がある様だった。右手の教室を窓から覗いてみた。部屋はかなりの広さがあった。大きなホワイボードに扇型に並べられた長机が七列ほどある。そして向こうの出口からも廊下が見えた。どうやらどちらの廊下からもこの教室には入れるらしい。
廊下の右手の教室は全部で三つ。騎士の気配はすぐそこまで迫っていた。僕らは二番目の教室へと駆け込んだ。僕らが三階に行ったことは彼女も分かっているはずだ。だから彼女が教室内を探すのは分かっていた。僕らはジッと耳を澄ました。彼女が来る方からは見えない位置に隠れようと思ったのだ。だが待てども待てども彼女が廊下を歩いてくる気配がなかった。もしかしたら一番奥の廊下にいる可能性も捨てきれていないのかとも思ったが、それにしたって全く確認にも来ないというのはおかしな話だ。僕は鳳さんと顔を見合す。彼も緊張した面持ちの中に疑問の色を浮かべていた。
だがそんな僕らの疑問は二秒後には吹き飛ぶことになった。僕は失念していた。赤間千鶴が腹を裂かれながら騎士と相対した様に、岩崎陸也が天井を破壊するほど化け物じみたパワーを発揮した様に、そして、あの白銀の騎士が、たったの一振りで教室を破壊しつくした様に、この世界では、常識など存在しないということに。
強烈な衝撃音と共に、教室内が銀色の光に包まれた。僕らは吹き飛ばされ、教室の壁に叩きつけられた。僕は痛みに耐えながら目と耳を凝らした。梓の苦しそうな声が聞こえた。僕は急いで彼女を抱き寄せた。鳳さんの声は聞こえなかった。
僕は苦悶の表情を浮かべる梓の身体を支えながら何が起こったのかを確認しようとした。教室は僅かに埃などで視界が悪かったが、なんとか中の様子は確認出来た。机が端の方を残してほとんど吹き飛ばされていた。見るとホワイトボードが壁ごとなくなっていた。教室の後方にも大穴が開いていた。大きく開けられたそれぞれの穴からは、隣の教室を見ることが出来た。どうやら隣の教室も似た様な惨状の様だった。
常識外なのは分かっていた。だが、こんなことを彼女がするとは普通考えないのではないだろうか。誰だって、廊下を歩いて確認しにくると思うんじゃないだろうか。
煙の中に光が浮かび上がった。そして、僕の眼でもその姿をはっきりと確認することが出来た。花の様なドレスに、銀色の甲冑、そして精悍な顔つき。それは紛れもなく、騎士となった真辺梓その人であった。
彼女は剣を僕らに向けた。僕の背に隠れた梓が僕の服を掴んだ。恐怖のせいか、僕の服を掴む彼女の手は震えていた。僕は彼女の身体を庇い、必死に騎士の瞳を見上げた。
「そこをどいて。私が用があるのは、そっち……」
彼女は僕を睨みつける。それは獲物を射殺さんとする目だった。僕はその時、気の抜けた様に息をもらした。僕は、自身の学ランの懐に手を伸ばしながら、その場で立ち上がった。僕はそこから、サバイバルナイフを取り出した。
僕の足元の梓も、騎士姿の梓も同時に息を飲んだのが分かった。僕にはあまりに似つかわしくない得物に驚いたとしても、それは当然だろう。
僕がナイフを取り出すと、彼女の目が鋭くなった。剣を握る彼女の手も、先程よりもきつく握られたことが僕からでも分かった。彼女は決して僕を殺すつもりはなかったはずだ。だが彼女なら僕を戦闘不能にすることは容易だろう。もし僕が彼女にサバイバルナイフを振り下そうとすれば、彼女は一瞬にして剣を抜き、僕のナイフを叩き落としたはずだ。
それはつまり、僕に勝機はないということだ。僕は戦うことなど無駄だと、ちゃんと理解していたのだ。もう僕の後ろの梓を守りきれないと、僕はしっかり理解していたのだ。どうにもならないと、ここにいる全員が理解していたのだ。
僕はニヤリと笑った。そしてその不敵な笑顔のまま、騎士の顔を見た。
彼女の顔に動揺が走ったのが分かった。それはそうだ。守っている人が殺されようとしている状態で笑える人など普通はいない。もしかしたら、僕の頭がおかしくなってしまったのだと思ったのかもしれない。だが安心して欲しい。僕は頭がおかしくなった訳でも、あまりに手詰まりな状態につい笑ってしまったという訳でもない。
僕は決心しただけだった。こうすると、決めただけだったのだ。
僕は、右手に持っていたサバイバルナイフを逆手に持ちかえた。そしてそこに左手を添え、勢いよくそれを、自分の腹に突き刺した。
口から込み上げてくるものがあった。僕はそれを吐き出した。
すると、僕の身体がふわりと浮かんだかと思うと、足の力が抜け、そのまま背中から倒れ込んだ。地面に身体が落ちる。それなりに衝撃があるだろうが、その時の僕にはもうどうでもいいことだった。
僕は倒れるその瞬間見た。騎士の恰好をした梓が、今にも泣き出しそうになっているその顔を、僕ははっきりと見た。
「光士郎!!」
騎士の絶叫が、このボロボロの教室に響き渡っていた。
とある少年の日記
四月二六日(木)
いつものことだが、クラスが変わって一月が経とうとしているのに未だにクラスに馴染めていない。誰かと話をしようと思っても、どうしても口ごもってしまう。女の子などもっての外だが、男でもそんな調子なのだから手の打ちようがない。
僕に友達が出来ない原因ははっきりしている。僕が暗いからだ。僕が暗くて、内気だから誰も僕と仲良くしようなんて思わないのだ。いつも教室の隅で下を向いている僕に話しかけてくれる人なんている訳がないのだ。でもそれが分かっていても、僕にはどうすることも出来ない。今さらこの性格を直そうにもどうやって直したらいいのか全く分からない。
今日も岩崎陸也に悪口を言われた。あと他の三人にはバケツの水をひっかけられた。クラスのみんなはバカにした様な目で僕のことを見ていた。
僕がこんな目に遭うのは、やっぱり僕が暗いからだろうか。
明るくすれば友達も出来るし、いじめもなくなるだろうか? だがそうだとしても、毎日こんな酷い目に遭わされているのに、明るくするなんて無理に決まっている。学校に行くだけでも吐き気を催すと言うのに、笑顔でいろなんて無茶も大概にしてほしい。
学校で人生のことを考えていると暗くなる一方だから、僕はいつも通り小説のアイデアを考えることにした。
丁度岩崎たちに酷い目に遭わされた後だったから、僕は僕を助けてくれる強くてカッコイイヒロインを想像した。彼女はとても優しいが、強くて気高く、悪には決して屈しない。女の子が大きな声で怒鳴り散らしたりするのは少しイメージと合わないから、僕が想像する彼女は、凍りつくほど冷徹な顔を敵に向けて闘う。そんな冷徹な顔と、僕に向けられる笑顔とのギャップがまた堪らなかったりもするのだが。
僕が想像する女の子は基本的にはいつもそんな感じだ。僕を守ってくれる強くて優しい人、僕を求めてくれる愛らしい人、そして僕の小説を決してバカにしない人だ。
小説を書いていると人に言えば、だいたいの人は僕をバカにするはずだ。実際先日、僕はあの人に小説を酷評された。いや、決して小説のできを批判されたのではない。彼女が批判したのは、僕の考え方そのものだった。正直彼女にあそこまで言われる筋合いはない。彼女の過去に何があろうと、あの子と僕は違う。変われる素質が、彼女にはあっただけの話だ。三田村さんには、僕のことは絶対に分からない。
僕がいてほしいと思う少女は、三田村さんと違って決して僕の小説をバカにしない。いや、むしろ僕の小説を好きでいてくれる。それこそが僕の理想だ。彼女を想像する上でそれだけは外せない。
もちろん見た目も大切だ。さっきも書いたが、僕はどちらかと言えば可愛いよりカッコイイ女の子の方が好みだ。そして身長は僕よりも少し高いくらいの方が良い。そして肝心の顔の特徴は、彼女自身の意思の強さを反映しているかの様なつり眼、スラッと通った高い鼻、そして吸い寄せられる様に魅惑的な厚い唇。それが僕の憧れである。しかし実はそのイメージに一番符合するのは、あろうことかあの三田村さんだったのだ。何たる皮肉か。僕のことなど決して受けいれてくれるはずのない彼女が僕の理想の女の子の容姿だなんて。しかしいくら容姿が理想的だろうとも、中身が伴っていないなら全くもってそれは無意味だ。見た目は大事だが、僕はそれだけで人を判断する様な薄っぺらい人間ではないつもりだ。だから僕は決して三田村さんを好きになったりはしないだろう。
ちなみに僕のイメージする少女の好きな食べ物はチョコレートだ。僕はチョコが嫌いだが、女の子はスイーツが好きだがら、チョコが好きなのは女の子らしいと思う。そして更に嫌いなものは苦い物にした。これは僕がコーヒー好きだから、コーヒーを飲んでいる僕に対して「大人だね」と言ってもらうためだ。
そんな女の子が、ある日僕の目の前にひょっこり現れる。そんなシチュエーションを僕はいつも夢想している。そしてそれを小説として形にして、実体験しているかの様な錯覚を僕は楽しんでいるのだ。
三田村さんの様に、くだらないことだと多くの人は言うのかもしれない。だが僕にとってはこれが全てなのだ。みんなは本当の世界で、本当の友情や愛情を手に入れられるのかもしれない。だけど、僕には何もない。それらを手に入れることが出来ないのだから、妄想の世界に浸ることが悪いことであるはずがない。
と、こんなことを勢いに任せて書いてしまったが、最近少しこの妄想をするのがきつくなってくることがある。僕は小さい時から、そんな女の子が実際に僕の目の前に現れることを望んできた。だけれど、僕がいくら願ってもそんな女の子は今まで一度も現れなかった。いつか来るかもしれない、いつか僕を助けてくれるに違いない、そう信じられたからこそ、僕はこの妄想で心を支えてくることが出来た。だけど、そんな子は僕の周りにはいなかった。今だってそうだ。クラス中を見回してみても、誰一人僕を助けてくれそうな人はいない。
赤間さん、石橋さん、井上さん、遠藤さん、小田島さん、加賀美さん、小谷さん、佐藤綾香さん、佐藤恵美さん、鈴村さん、瀬古さん、田所さん、十和田さん、中島さん、西野さん、野呂さん、長谷川さん、帆足さん、三田村さん、山口さん、渡貫さん……。二年B組にいる二一人の女の子は、ほとんど僕の理想とは異なっているし、そもそも僕は彼女らとほぼ全く言葉を交わしたことがない。
文芸部の知り合いと言えば、よりにもよって三田村さんしかいない。何度も書いているが、残念ながら彼女とは友達になれそうもない。それも僕にとっては非常に痛いことだ。
僕はこんな生活をいつまで続ければいいのだろうか。日常で溜まっていく鬱憤を、妄想で晴らす日々を、いつまで続ければいいのだろうか。絶対に現れない人を待ち続け駄目になっていく人生を、いつまで続ければいいのだろうか。
このままでは駄目だと思った時期もあった。運動をして、自分を鍛え直さなければと思った時期もあった。だが結局うまくいかなかった。剣道など、僕には到底不可能なことだったんだ。三田村さんの様な華麗な成功体験を参考にしたのがバカだったんだ。
妄想は僕の心を支えている。でも同時に、僕を駄目にもしていく。
変わりたい。変わらなければいけない。だからみんなは僕を待ってほしい。みんな僕をいじめずに、気長に待ってほしい。それが今の僕の一番の願いだ。
今日はもう遅くなってしまった。小説の続きはまた明日書くことにしよう。
四月二七日(金)
ゴールデンウィーク前の最後の日だと言うのに、今日は本当に最低な日だった。
もう我慢の限界だ。誰も僕を待ってくれない。僕は変わろうと頑張っているのに、みんなが僕を追い詰めていく。
また岩崎たちにいじめられた。あいつらは絶対に許せない。殺したくらい憎い。そして何もしてくれないクラスメートも同じくらい憎い。絶対に許せない。
本当にもういい加減にしてほしい。あいつらは僕の小説を奪ってクラス中の見せものにした。そして全部足で踏みつぶした。いくらプリントアウトした紙だからって、あれは僕にとって到底許せることではない。クラスメートが口々に気持ち悪いとか囁き合っていた。僕は耐えられなかった。涙が出そうだった。
みんな助けてくれない。その時僕は現実に何かを求めることはもう無駄だと悟ったのだ。
今はもう死んでもいいかと思っている。でも一人で死ぬのはあまりにも悔しい。僕は何も悪いことをしていないのに、寂しく死んでいく事だけは嫌だ。だから僕は考えた。僕が死ぬ前に、僕を苦しめた連中にも死んでもらうことにしたのだ。
我ながら恐ろしいことを書いていると思う。だがもう我慢の限界だ。人の痛みを分からない人間など、死んで当然だ。そして僕も死ぬのだから、何も怖いことなどありはしない。
僕は連休明けの学校で、放課後クラスメートを殺すつもりだ。当日、小説を今度はわざと岩崎たちに見せて、それをばら撒かせる。岩崎たちや他のクラスメートがそれに気を取られている内に、僕は彼らをナイフで一人ずつ刺し殺す。
多分何人かは逃げてしまうと思う。でもせめて、岩崎陸也と僕の小説を気持ち悪いと言った赤間千鶴と、岩崎と一緒に僕を一番酷い目に遭わせた杉山暁だけは殺してやりたい。あいつらさえ殺せれば、僕の願いは叶ったも同然だ。あ、あと三田村さんにも何かしらの仕返しをしてやりたい。だが彼女は小説を愛する人間だ。出来れば、やつらとは違ったことをしてやりたいところだ。そしてそれが済んだ後は、学校の屋上から飛び降りて死んでやるつもりだ。
決行に向けて、僕はナイフを用意する必要がある。ちゃんと命を奪えるように、刃が長くてごついサバイバルナイフがいいと思う。僕が苦しんだ分、あいつらにも苦しみを与えるつもりだ。
今この時でも、僕は両親に対して特に感慨はない。彼らは僕に無関心だ。一緒に住んでいるだけのただの他人だ。僕が人を殺して自殺した所で興味などあるまい。
ただ僕が残念に思うのは、やはりあの子に対してだ。まだ僕の前に現れていないだけで、いずれ僕の前に現れようとしているのではないかと、僕はまだ思えてならないのだ。ここで僕が死んでしまっては永久に僕があの子と会う機会はなくなってしまう。それだけが僕の心残りだ。
会いたい。あの子に会いたい。どうしても会って抱きしめたい。あの子を自分のものにしたい。僕を助けてほしい。この世の全ての困難から僕を守って欲しい。
夜の七時を回った。あまり遅いと店が閉まってしまう。この機会を逃せば、僕はもう動きだせないかもしれない。だから僕は、これから、ナイフを買って来ることにする。
五月七日(月)
おかしなことが起こった。一体何が起こったのか訳が分からない。
あの子がこれまで、あんな風に僕に話しかけてきてくれたことなどなかった。僕には、彼女は今までの彼女ではなかったような気がした。
“From: m-azusa2B19@kitakou.co.jp
title: 真辺です
本文:こんばんは、真辺梓です。と言っても呼びづらいかな。つい先週まで違う苗字だったしね。でもこれからは“真辺”が私の苗字なので、牧村くんも私のことは、真辺梓と呼んでくださいね。
ということで、牧村くんの小説を読ませて欲しいので送ってください。待ってます。”
言われるがままにアドレスを教えてしまった。絶対また僕をバカにするのだと思ったのに、また僕を叱責するのだと思ったのに、彼女はそんなことはしなかった。
一体どうなっているんだ? 真辺梓に、いや、“三田村梓”に何が起こったと言うのか?
分からない。僕はただただ混乱するしかない。
少し悩んだ後、とにかく僕は、彼女に小説を送ってみることに決めた。どうするかは、彼女の反応を見て決めることにする。彼女が僕を騙しているなら、あの作戦を決行するまでだ。だが、もしそうじゃなかったら……。
ナイフは机の奥にしまった。これを使うかどうかは、彼女にかかっている。
メールを送った。もう後戻り出来ない。あとはリプライを待つのみだ。
もう寝ることにする。
五月九日(水)
日記を書くのはひとまずやめることにする。
もう決めたから、決心を揺るがせないためにも日記は書かないし、読まない。
ただ、もし何かある時は、またこれを見ると思う。
その時まで、サヨナラ。
牧村光士郎の告白
1
梓、心配掛けてごめん。もう僕にはこうするより他に方法がなかったんだ。
僕の死は恐らくもう確定している。まだ死なないのは、僕にまだ伝えたいことがあるからだと思う。僕が死ぬ前に、君にどうしても聞いてほしいことがある。血が喉に絡んでくるせいで聞き苦しいと思うけど、どうか最後まで聞いてほしい。
君は、僕がなぜこんなことをしたのか、全く理解出来ていないと思う。もしかしたら、君を守る為に僕が犠牲になったと思っているかもしれない。しかしそれは正しくもあり、間違ってもいるんだ。確かに僕は君を守りたかった。だが、僕が自らの死を選んだのにはそれ以外の重大な理由がある。
はっきり言おう。僕はずるをしたんだ。だからこれは報いなんだ。因果応報だったんだよ。
落ち付いて聞いてほしい。これは君にとって極めて重要なことだ。
僕がこれまでどんな人生を歩んできたかは知っているね? 僕は君と出会うまで死んだように生きてきた。誰も僕を認めてくれず、死人の様な毎日だった。僕はいつも願っていた。僕を認め、愛してくれる人を。そんなことを、僕は十六年間も願い続けていたんだ。
僕は高校二年生では、クラスはB組になった。そこは僕にとって最悪の場所だった。徒党を組んで弱い者いじめをする人、僕を遠巻きにバカにしている人。クラスにはそんな人しかいなかった。僕の味方は一人もいなかった。
君がいただって? いや、僕の味方は一人もいなかったよ。クラスには僕以外で四一人の人がいたけど、僕はそのほとんど全員が嫌いだった。混乱させる様なことを言ってごめん。だけど、これは真実なんだ。僕のクラスには、僕を好きになってくれそうな人なんていなかったんだ。
それは五月のことだった。ゴールデンウィークが明け、僕は学校へ行った。もう気分は最悪だった。岩崎たちがいつも僕のものを隠したり、僕の悪口を言ったりするから、本当に学校には行きたくなかった。
放課後、僕は自分の小説をわざと見える位置に置いておいた。彼らは案の定それを見つけ、僕から取り上げた。バカにした様に四人が笑った。彼らは僕の小説を辺り一面にばら撒いた。僕はその状況を待っていた。だが、その時だった。誰かが僕に手を差し伸べてくれたんだ。みなまで言う必要はないだろう。そうだ。それは、君だった。僕のことを嫌っていたはずの君が、僕を助けてくれたんだ。
何をバカなことをと思うかい? 君が僕を嫌いだなんて、嘘だと思うかい?
残念ながらそれは嘘じゃない。君はある日僕にこう言った。「牧村くんの小説や考え方は、私は本当に大嫌い」ってね。
そんなこと言うはずがないって? いや、これは本当のことだ。君は確かにあの時僕にそう言ったんだ。夕焼けに染まるあの部屋で、僕の小説を読んでいた君、三田村梓は僕にはっきりそう言ったんだ。
君の苗字が変わったと聞いたのは、あの出来事があった日の朝だった。教室に行くと、君がクラスの他の女子と話しているのを小耳にはさんだんだ。三田村から真辺に変わっても、出席番号は十九のままだから何も変わらないよと、君は笑顔で言っていた。両親が離婚をしたのだろうと、僕にはその時察しがついていた。だが僕はその頃君に良い印象を持っていなかった。だからそんな話を聞いたところで何も感じることはなかった。
君が豹変したのは、恐らくその日からだったと思う。僕を嫌っていたはずの君が、突然僕を助けてくれたんだ。僕は驚いた。目の前の光景が嘘にしか思えなかった。君が笑顔で僕に小説を読ませて欲しいと言ってきた時は、頭がどうにかなるんじゃないかと思ったほどだ。
君は過去に僕の小説を読んだことがあった。なのに君は、まるで初めてのように読みたいと言ってきた。僕はすぐにおかしいと思った。それだけじゃない。君の発する言葉はなぜかことごとく僕の記憶と異なっていた。僕が尋ねても君は「冗談よしてよ」といった感じで、全く取り合ってくれなかった。
その日家に帰って僕はあれこれと思案した。すると僕の中で、あるとんでもない仮説が思い浮かんだ。それは、
――僕の妄想が、君の人格を書き換えてしまったのではないかということだ。
無茶な話だとは思う。だが現にその時信じられないことが起こったのだ。君は見た目こそ僕の理想だったが、中身はそうじゃなかった。だと言うのに、その日から君は完全に僕の理想通りとなったのだ。
こんな都合のよいことが現実に起こるだろうか? 当然、そんなこと起こりようもないはずだ。それが妄想でなかったらなんなのだと、僕は思ったんだ。
僕の妄想が君の人格や記憶を捻じ曲げたというある意味では荒唐無稽な仮説を信じろというのは難しいことかもしれない。だがそれを否定する充分な材料も、僕の前には全く存在していなかったのだ。
君は両親が離婚し、小さなアパートに引っ越した。君のお母さんが仕事に行く都合上、君は家の家事を手伝うことになった。そのせいで文芸部に君が来る頻度は随分減った。部員たちが残念がっていたのを僕はよく覚えているよ。
混乱する僕をよそに、君は急激に僕に接近してきた。例の仮定を立ててすぐは、僕はなんてことをしてしまったのだと思っていた。だが、僕自身妄想の少女を待ち焦がれていたのは事実だ。そんな中現れた君は、暗闇だった僕の世界に突如として射しこんできた一筋の日の光の様なものだったんだ。だからいつしか僕は、罪の意識よりも、梓という僕が夢に描いていた少女の登場を喜ぶようになってしまっていたのだった。
君が僕を嫌っていた証拠でもあるのかだって? 残念ながらあるよ。君が、今の君なら絶対にしないことをした記録が残っているんだ。
これを見て欲しい。これは、僕の昔の小説の原稿だ。その時僕は原稿用紙に小説を書くことに凝っていた。これはその当時のものだ。これを読んでみて欲しい。見事な赤字ばかりだ。文章表現を訂正するものもあれば、内容を批判する文言も載っている。僕はあの時、小説大賞を受賞したことがある君に勇気を出して文章の校正を頼んだんだ。少しは褒めてもらえると思ったんだろう。しかし君は僕の予想とは全く正反対の反応を寄越した。あの日、君が自ら赤ペンを入れた僕の原稿用紙を手で持ちながら怒ったように僕を見ていたのを、僕ははっきりと覚えている。
この字は紛れもなく君のものだ。自信に満ち溢れた真っすぐで、力強い特徴的なこの文字を書くのは、僕の知っている中では君しかいない。そして更に、ここにサインもある。苗字は違うがそれは間違いなく君のものだろう。
この赤字の文章だけでは、君が僕を嫌いだったかは分からない。だが少なくとも、僕は君に考え方が嫌いと言われたんだ。それはつまり、君が僕自身のことが嫌いと言ったも同然だったのではないだろうか。少なくとも僕はそう捉えている。
あの日以降の君は僕の小説を好きだと言ってくれた。登場人物たちがまるで自分たちみたいで親近感が湧くとすら言ってくれた。そんな君が、その少し前に同じ様な文章をここまでことごとく否定するだろうか? 答は否だ。人間の感情が短期間でそこまで動くことなどありはしないからだ。
しかしそうだとしても、実際僕がどうやって君の精神を書き換えてしまったのか、その方法は全く分からない。もしかしたら、僕らがいた世界は君が見せている世界の様に、僕の見ていた夢だったのかもしれない。もし全ては僕が見ている夢ならば、君の意思を捻じ曲げ、君を僕の妄想通りの人間に仕立ててしまうことも可能だろう。まあ、もしそうだったとしても、今の僕らにそれを確かめる術はない訳だが。
ただはっきりしているのは、元来僕を嫌っていた、いや、嫌いとまではいかなくても好意を抱いていた可能性はほとんどゼロだったはずの君が、ある日突然僕に好意を寄せてくれたという事実があるということだけだ。そんなことが起こる理由は、僕が君という人間を書き換えたこと以外には考えられないんだ。それが超常的な事象によって行われたのか、それとも僕の夢のせいで行われたのかは分からないが、その事実だけは決して揺らぐことはない。君の意思を捻じ曲げることは、君という人間を殺す事と同義だ。つまり僕は、君を殺した様なものだったんだ。
本来の君を殺した僕は、君の恋人には値しない。
僕は本当に、最低の男だったんだ。
2
これだけ衝撃なことを伝えておいてなんだが、僕がこの事実を伝えたのは、決して君を動揺させるためじゃなかったということを知ってほしい。僕がこのことを伝えたのは、君に謝りたかったからなんだ。君の気持を弄んだことを謝りたかったからなんだ。
君が僕のことを気にしてくれたのは、残念ながら君の意思じゃない。僕だ。僕が君に僕を気にするように仕向けたんだ。僕を好きになるように強制したんだ。僕を一生想い続けるように縛り付けたんだ。君は違うと否定するかもしれない。だが、これこそが事実なんだ。僕が君を変えてしまった時点で確定していた事実なんだ。君と僕は恋人同士になる。僕がそう願ったから、君はその通り動いてくれた。君の気持を一切無視して、僕は君を手に入れたんだ。
クラスの誰もが、僕を相手にしなかったのに、君だけは僕を助けてくれた。君は僕の小説に興味を持ったことがきっかけだと言っていた。だがそんなきっかけは都合が良過ぎた。百歩譲って、もしそれがご都合主義じゃなかったとしても、その後の展開はやはり僕にとって都合が良過ぎた。僕の理想・妄想の体現である女の子が、僕の望み通りに動くことなんてあり得ない。所詮それは、僕が望んだ物語でしかなかったんだ。あまりにも僕たちの関係は、小説的過ぎたんだ。
僕の小説に興味を持った程度で、女の子はそこまでしてくれないだろう。僕たちが恋人同士になれた理由は、さっきから言っている様に実に単純だ。それは君が僕に興味を持ち、最終的に好きになる様に僕が願ったからだ。僕がそうなってほしいと妄想したから、君はその通りになったんだ。君には選択の余地がなかった。全て僕の身勝手さに振り回されていただけだったんだ。
……そうだね。確かに、きっかけがどうあれ、今ここにおいてお互いがお互いを好きであるという事実は変わらない。確かにそれは事実だ。だが、それが事実だからこそ、僕の罪は重い。
梓、今この現実をもう一度見てくれ。君は自らの夢の中で剣を持つ騎士となった。僕は何も出来ずただ逃げるだけだった。そして君は、自らを殺そうとした。
梓、君は僕たちがこんな状況になってしまったのに、お互い好きでいられるならそれで良いと言えるのか? 良い訳がないよ。君が難病にかかったこと自体は不幸な偶然だった。だが病気を患い、フィジカル的にもメンタル的にも不安定な君には、僕という存在は重荷でしかなかった。僕が重荷だったからこそ、こんな事態になってしまったのだ。これらのことは全て僕が悪い。君を縛ったから君を苦しめ、自殺にまで追い込もうとしてしまった。君の心を、僕は傷つけただけだったんだ。
だから僕は謝らねばならない。そして、お願いをしなければならない。そのお願いというのは、
――僕のことを忘れてほしい、ということだ。
その理由は単純だ。君が僕を忘れれば、君を縛る悪夢は終わる。僕がこのまま死ねば、君は僕から解放される。一人の人間として、僕とは縁のない人生を送れる。そう思ったからなんだ。
人は夢に無限の憧れを抱く。だが、夢にも限りがある。人の見られる夢には限界がある。僕は君を理想通りにした。しかし君はそのせいで苦しむことになった。夢とはそんな不完全なものだ。夢は必ずしも全員を幸福にはしてくれないんだ。だから君は、そんな夢から解放されなければならない。この有限で息苦しい夢から、旅立たなくてはならないんだ。
身勝手なことを言っているのは分かっている。でも、僕にはもう他に君に何もしてあげられない。本当にごめん……。本当に、なんと、謝ったらいいのか……。
また喉から込み上げてくるものがある。すまないが、鳳さん、彼女を、頼みます。
どうやら、もう本当に時間がないみたいだ。目も霞んできたし、意識も薄れてきている。梓の顔も、鳳さんの顔も、今はもうあまり認識出来ない。
鳳さん、混乱させてしまってごめんなさい。あなたには数えきれないほど優しくしてもらったのに、こんな結末を導いてしまって、本当に、ごめんなさい。
梓、どうか泣かないでほしい。梓が僕に涙してくれるのは、やはり僕の意思が反映してしまっているからだと思う。だから僕がいなくなれば、恐らく君から僕の影響力が取り払われると思うんだ。確証はない。だが、僕の意思で君を捻じ曲げたのなら、その元凶がいなくなれば事態は好転するはずだ。君を苦しめるのはもうこれで終いだ。今の僕はもうそれだけで満足だ。僕は君が無事なら、それ以上何もいらないと思っているのだから。
ところで梓、死ぬ前に一つだけ頼み事をしてもいいだろうか? これまで散々な目に遭わせておいて、今さら何をと思うかもしれないが、これだけはどうしても頼みたいんだ。
それは、僕の手記を仕上げてほしいということだ。僕はここ数日の出来事を手記に残してきた。そこに書かれていることは、決して全てが真実という訳ではないが、それが僕の心情を記した最期の記録なのは間違いない。僕はもう今日のことを書き記すことは出来ない。だがそれでは、僕の最期の作品は完成しない。死ぬのは怖くない。だが死ぬ前に僕を形として遺したい。
つくづく自分勝手だと思う。だが、どうかこれだけは頼みたい。そしてそれを書いたら、それは全て処分してほしい。矛盾していると思うかもしれない。でも僕は、一瞬でも、僕の心が形になったなら、もうその事実だけで充分なんだ。だからそれが灰と化してしまうことを悲しいとは思わない。
そしてそれを処分したら、君は、もう僕のことを忘れてほしい。それで全てが終わるから。君を縛る全てがこの世からなくなるから。だから、よろしく頼むよ。
そろそろ時間だ。僕は旅立つよ。
では、どうかお元気で。親愛なる、真辺梓さん……。
真辺梓の後日談
灰の臭いが、私の鼻をひくひくさせる。煙は真っ青な空へと昇っていく。まるで、彼の想いごと空に届ける様に。
私の得意なことは小説を書くことだ。正直、彼よりも実力は上だと思う。私はあの日のことを、彼の文体や表現を参考にして記した。文章を書くのは随分と久しぶりだったが、それなりに上手く書けたと思う。
ところで、実に不思議なことなのだけれど、あれから数日経つに連れ私の中から彼と過ごした記憶や、彼を好きだったはずの心が徐々に薄れてきている様なのだ。あれほどまでに彼のことで私の頭は一杯だったのに、あまりにもあっさりと私は彼を忘れてしまいそうなのだ。
だけど、彼を忘れたところで何かが解決される訳ではない。私の中には今喪失感しかない。心にぽっかりと穴が開いてしまったかの様なこの感覚は、恐らく当分の間癒えることはないだろう。
いくら抗おうとも、彼に関する記憶は刻一刻と薄れていっている。まるで夢から覚めるとその夢の内容はほとんど思い出せなくなってしまう様に、目覚めは、楽しかった記憶も想いも、全てを消し去ってしまうのだと私は思った。彼が私に与えたものが、全て夢の彼方に消えていくのだと思った。
私は先日手術をした。その結果、私の病は完治した。足は相変わらず動かない。だけど、私は死ななかった。生きながらえることが出来た。
鳳君は光士郎の葬儀の時私に言った。
「君を助けられたことは良かったが、彼を死なせてしまった。出来ることなら、僕はみんなを助けたかった。彼がしたことは、僕はまだ深く理解出来ていない。まだまだ、僕には心を整理する時間が必要なようだ」と。
心の整理が必要なのは私も同じだった。身体は治った。だけど、さっきから言っている様に私はちっとも晴れやかな気分にはなれなかった。私の心の穴は塞がる気配が全くなかった。そしてそれが今後埋まるのかも、今の私には分からなかった。
光士郎は私に、牧村光士郎という人間から、真辺梓という人間が解放されるべきだと言った。でも、その必要が本当にあったのか、今の私にはまだ分からない。
そもそも解放とは何だったのか。私自身は、今まで決して彼に束縛されていたつもりはない。だから私は何からも解放されたりしない。確かに私は彼とのことを深く考え過ぎるあまり、あまりに極端な答を選択してしまった。だがそれは私が悩みぬいて出した結論だ。その答に問題があったとしても、その選択に後悔など含まれてはいない。彼がいなくなったのは、私にとって解放などではなく喪失でしかなかったのだ。私という人間のアイデンティティーを、私は喪失したのだ。
今の私は、ぐらぐらの今にも崩れそうな吊り橋の上に立っている様なものだ。一歩間違えれば壊れて、バラバラと崩壊していくだろう。
それくらい今の私は不安定な存在だ。それは恐らくこれからしばらく続くと思う。
死の縁で光士郎は私に、この世界はもしかしたら彼が見ていた夢なのかもしれないと言った。私の夢が、私の悲しみを表した凍える様な寒い世界だったのに比べ、彼の夢は実に温かかった。想いは捻じ曲げられたのかもしれない。だけど、そんな温かな世界なら、それに浸るのも悪くないと、私は思うのではないだろうか。彼は、夢は有限だと言った。だけども私は、決して夢に限りがあるとは思わない。彼の夢はどこまでも深く、私のことを愛してくれたのだから。
色々と思う所はある。辛くて、泣きそうになることもある。だけども、今の私は決して後ろ向きな訳じゃない。なんとか前向きになろうと努力しているのだ。
少なくとも、今の私はまた夢の中に引き籠ったりはしない。いくら温かくとも夢は夢だ。現実で生きて欲しいと彼が言ったのなら、私は現実と向き合わなければならない。
覚悟は出来ている。私はもう彼との夢の日々を懐かしんだりなどしない。
鎧は夢幻の彼方に置いてきた。構えた剣は、十字架に供えた。
騎士はもう現れない。夢の中に置き去りにしてきた。もう騎士の力は借りない。
私は、裸のまま歩き出す。
いつか、未だ見ぬ幸せのありかを探して、私は一人で歩き続ける。
もう決して、振り返りはしない。それだけは、約束する。
夢幻の騎士と有限の夢
この小説には実に沢山の謎が残されています。
実にずるい逃げ方に見えるかもしれませんが、それらの謎に何を感じるかは読者の方次第だと思います。
果たして光士郎の決断は正しかったのか、遺された梓は、またしても助けることが出来なかった鳳は今度どうなるのか。
自由に想像していただけたら幸いです。
もし少しでも面白と感じていただけたら、是非とも感想をお願いします。