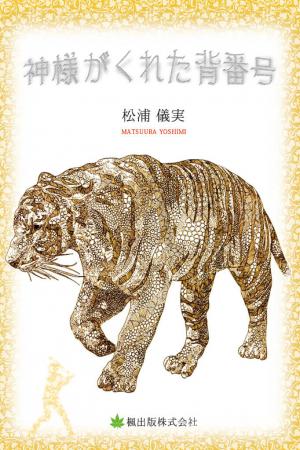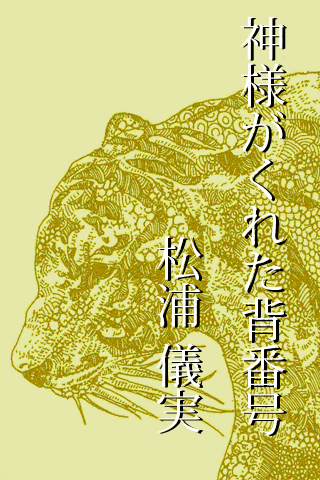
神様がくれた背番号(前半部掲載)
本作は、小説投稿サイト『作家でごはん!鍛錬場』に掲載されたのが縁で、2010年楓出版から刊行した作品です。著者のブログ「寒い人生で悪かったな」で連載がスタートし阪神タイガースファンの間で評判となって、人気ブログランキング2位を獲得しました。このたび、星空文庫にて掲載させていただけることとなりました。作品の前半部分を掲載しましたので、よろしければお読みください。(楓出版)
二〇XX年一〇月 人間の及ぶことと及ばないこと、そして奇跡
真面目にコツコツ生きている人がいる。
嘘をつかず、身の丈にあった暮らしをし、贅沢を望まず、人を羨むこともない。朝に目を覚まし、夕暮れとともに住処に戻り、布団に潜って目を閉じる。晴れの日は仕事に精を出し、雨の日は一人静かに時間を過ごす。そのような生き方が必ずしも幸せと言えないのが人間という生き物の難しいところだ。
上手く嘘をついて如才なく立ち振る舞い、時には人を傷つけながら大金を手にし、豪邸に住んで高級車を乗り回している人の方が、いわゆる一般的な幸せというものを享受していると言え、多くの人から羨望の眼差しで見られるのである。
片や、真面目にコツコツ生きている人たちが恵まれない暮らしをしていると、これはたちまち、羨望ではなく同情を浴びることとなる。
「神さんも仏さんも、あったもんじゃない」
同情とともに語られるのが、この言葉。仏様は仏教に限られた存在だからさておくとして、問題は神様である。地球上のほとんどの地域で、形こそ違えど神様と呼ばれる存在があり、民族、言語、宗教を超えて普遍的である。
「天網恢々疎にして漏らさず」という言葉があるが、本当に神様というものが存在するのであれば、何故、前述のような真面目に生きている人間に幸福を享受させないのであろう。
実は神様とて辛いのだ。
影があって初めて光が生まれる。世界中が燦燦たる光に溢れていれば、誰もその有り難味を感じないであろうし、第一、眩しくってしょうがない。
雨の日があるからこそ、晴れの日を人は歓ぶ。晴天だけで全てのものが恵まれてしまうなら誰一人、空を見上げたりしないだろうし、その青さに気づくこともない。若い女性は日焼け対策に追われて太陽を恨むことだろう。
幸福とはつまり、そのようなものなのである。報われないことがあるからこそ、報われた時の喜びは大きいし、報われようと真面目に生きる人が多くなればなるほど、この世はとかく上手く行くことの方が多い。
神様は正しく生きることの意味を問う。人の心が不条理に流されてしまわないように、正しく生きることの価値を見せる。正しく生きるとも報われなかった人間に、時に信じられない幸福を与え、それを目にした人々に勇気を与える。
人はそれを「奇跡」と呼ぶ。
大阪に天王寺という町がある。JRや私鉄の路線が集約し、百貨店が軒を連ねている。近代的な駅ビルの間を路面電車が通り、大阪のシンボル「通天閣」にも近い。また街としての歴史も深く、林立するビル群の一本裏通りでは昔ながらの街並みが広がっていて、更には隣接する四天王寺やその塔頂をはじめとする古刹が点在しているといった、最高のロケーションでありながら、キタやミナミほどの人気はなく、どこか垢抜けない。
天王寺駅から大阪市立天王寺公園へと向かう歩行者専用の通路。かつて青空カラオケ通りと呼ばれていたその通りには、九十年代から有料カラオケのテントが軒を連ねていて、朝から晩まで周囲に響き渡る大音量で誰かの歌う演歌が休むことなく流れていた。その後、二〇〇三年に環境整備の御旗のもと、大阪市による強制撤去が行われ、現在では当時の喧騒は見る影もないが、それでも街のあちらこちらには路上生活者、いわゆるホームレスの姿が見える。
ホームレスといいながら、彼らの住居はトタンやコンパネを利用した立派なもので、中には表札を掲げている物まである。表には何とも年季を感じさせる色合いの自転車やリヤカーが停められており、普通の家で言う玄関にあたる場所には靴が揃えて並べられていたりして、そこには立派に生活臭が漂っている。
大阪市は強制撤去が済んだ場所にはオレンジ色の工事現場用フェンスを設置したりして、新たなホームレスが居付く事を防ごうとしているが、所詮はいたちごっこであった。
そんな天王寺界隈のホームレスの中に「ケンちゃん」と呼ばれる男がいる。彼の通り名は「噛みケン」
狂犬を連想させる、通り名の由来は彼の強烈な吃音にあった。
かつてタクシー運転手をしていた頃、ケンちゃんは難波で乗せた客に「川西能勢口までなら阪神高速使いますか?」という質問を聞き取ってもらえなかった。
「かかかばにすぃのんせせせぐぐぐっちいいまままなら、はんしんここここそっくついまつか?」
幸か不幸か親切なその客が何度もわかるまで聞きなおしてくれたおかげで、ようやく話が通じて阪神高速に乗ったのは、すでに道のりの半ばを過ぎた豊中南ランプだった。
検問で職務質問を受けたりすれば、あまりの呂律の回らなさに、よからぬ薬物を摂取していると疑われ、署に連行された挙句、尿検査を受けさせられた。かといって黙っていれば黙っていたで、挙動不審と判断され、やはり連行である。七回目に連行された時など、終に会社の係長は迎えに来なかった。
そんなケンちゃんはやがて、不運な交通事故を起こしてしまい、タクシー運転手の職を奪われた。人とまともな会話が出来ないケンちゃんに新しい仕事など見つかるはずもなく、あらかじめそれが決められていたかのように、自然な流れで天王寺に住み着くホームレスとなった。
ケンちゃんの仕事は空き缶集めである。毎日自転車に乗って、天王寺界隈を中心に空き缶を集めて回り、スクラップ屋に持ち込むのが彼の生業であった。ケンちゃんは空き缶を拾い上げただけで、それがスチール缶なのかアルミ缶であるかを見分けることが出来、自転車の荷台の左右に取り付けられたビニール袋に、スチール缶は左、アルミ缶は右という風に器用に分別し、拾い集めていく。
彼が仕事する時の正装は、常に阪神タイガースの法被である。「ビクトリー1985 Fresh Fight For The Team」と書かれたそのタテジマの白い法被は、すでに薄汚れてビジター用ユニフォームの灰色に近かった。またケンちゃんの数少ない、噛まずに言える単語の中には「ハンシン」そして「タイガース」という言葉があった。
そう、ケンちゃんは正真正銘、筋金入りの阪神タイガースファンだったのである。
シーズン中は自転車の前カゴにAMラジオを載せて、そこから流れてくる実況に自分なりの解説を加えながら、夜の阿倍野あたりを走り回る。もちろん、彼の解説を聞き取れる人間など誰もいなかったので、周りから見ると、ホームレスが何か呪いの呪文をかけながら、野球中継を聞いているようにしか見えなかった。
その日もケンちゃんは、いつものように前カゴに積んだラジオに耳を傾けながら、天王寺アポロビル近くの路地を走っていた。
ラジオから流れていたのは愛すべき阪神タイガースの試合ではない。阪神タイガースは猛追及ばず、今シーズンを四位で終了しており、ケンちゃんが聞いていたのは読売ジャイアンツ対北海道日本ハムの日本シリーズであった。
「っやややぱぱぱっりよよよよみみみりうりうりうわ、っつつつよあやいやあああ」
読売はやっぱり強いという意味らしき言葉を吐いて、ケンちゃんは静かにラジオのスイッチを切った。
空き缶を集め終わった自動販売機の横を見ると、ペットボトルのコーラが三分の一ほど飲み残したまま捨てられていた。街灯の光にペットボトルをかざし、不純物が浮いていないことを確かめると、ケンちゃんはキャップを空けて一気に飲み干した。炭酸が抜けて甘みの増したコーラが、口の中の粘膜を溶かしていくようだった。ふと空を見上げると、ビルの向こうに暗い夜空が広がっていた。表の喧騒が嘘のように路地裏は静まり返っている。目を細めて見つめてみても、夜空には星ひとつ見つけることは出来ず、ビルの屋上から舞い上がるボイラーの水蒸気がゆらゆらゆらゆらと流れているだけだった。
そんな夜が、ケンちゃんの奇跡の始まりだった。
神様がやってきた、ヤア、ヤア、ヤア
天王寺動物園の上を横切る公園道路の中ほど、コンパネに囲まれた住処に帰ると、入口横にぶら下げてある30センチ×40センチぐらいの黒板に、
――ケンちゃんの言うとおりやっぱヨミウリ強いわ 来年はリベンジやな!
と見慣れた字で書かれていた。
メッセージの主はケンちゃんがいつも空き缶を引き取ってもらっている中島鉄工所の一人息子、「タケ坊」ことタケシであった。
小学二年生のタケ坊とケンちゃんは同じ阪神ファン同士で、親子ほど年齢が離れているにもかかわらず不思議とウマがあった。ケンちゃんの吃音をタケ坊は一度も馬鹿にしたことがなくそして普通の人が聞けば、ジャングル奥地に住むシャーマンが唱える祈祷の言葉にしか聞こえないケンちゃんの言葉を、タケ坊はかなり正確に聞き取ることが出来た。タケ坊はしばしばケンちゃんの住処を訪れては阪神について二人で語り合い、ケンちゃんが仕事に出て不在の時は、黒板にメッセージを残して帰っていくのが常だった。
阪神タイガース、そして野球が大好きなタケ坊だったが、彼は生まれつき心臓が弱く、スポーツなどの運動を医者から強く止められているために、実際の野球はキャッチボールひとつすることが出来なかった。そんなタケ坊にとって同世代の友達を作ることはなかなか難しく、ケンちゃんと過ごす時間は、タケ坊にとってもかけがえのない大切な時間だったのである。
入口にかけられている「六甲おろし」の歌詞がプリントされた暖簾をくぐって部屋の中に入ると、ケンちゃんは拾い集めた毛布を重ねて作ったベッドに身体を横たえた。
いつものように、天井代わりに取り付けられたトタン板の波の数を数えていると、やがてケンちゃんはゆっくりとまどろみの中へ落ちて行った。
「………ケンちゃん」
「………起きんかい」
「おい、ケンちゃん………」
誰かの呼ぶ声に眠りを妨げられてケンちゃんが目を開くと、くたびれたスーツに身を固め、銀縁の眼鏡をかけた、リストラ直前のサラリーマンのような男が毛布の横に座っていた。
「うわ!」
驚いて跳ね起きたケンちゃんを銀縁眼鏡の奥から見つめながら、その男はゆっくりと煙草をふかしている。
「あ、あんた誰?」
そう尋ねてはみたものの、パニックになっているケンちゃんの吃音はいつもより二割増だったので相手に聞き取れないはずだった。
「知りたい?」
ところが、その男は不思議なことに、アマゾン奥地に住む原住民のようなケンちゃんの言葉をしっかりと聞き取っていた。驚きながらもケンちゃんは黙って、素早くふたつ頷いた。
「ハッピーバースデイ、ケンちゃん。わしゃ神様だよ」
ケンちゃんは黄色に変色した隙間だらけの歯を見せて、口をあんぐりと開けた。
「あ、今、『こんな格好の神様おるはずない』って思たやろ? ちゃうねん、大体、神様のイメージなんか人間が勝手に決めた物で、実際はこんなもんやねんて」
神様と名乗るその男は、眼鏡の奥の涼しげな目をわずかにほころばせると、驚きのあまり涎を流しているケンちゃんを無視して、更に続けた。
「なんでその天地を司る神様が、突然お前のところに現れたかと言うとやな、コングラチュレーション! お前さんは今年の人間大賞に選ばれました。はい拍手パチパチパチ」
そう言って神様を名乗る男は両手で拍手をすると、その後くわえていた煙草を手のひらで握り締めた。次に手を開いた時、その煙草は跡形もなく消え去っていて、その手のひらには火傷の痕ひとつ付いていなかった。
神様というより、手品師のようだとケンちゃんは思ったが、それを口にはしなかった。
「ににに人間大賞? それってなんですか?」
「人間大賞ってのはやなあ、全世界にいる一〇八人で運営している世界神様協同組合が選定する名誉ある賞なんだよ。この賞に選ばれた人間の元には誕生日になると、それぞれ担当の神様が訪れて、何でも願いを一個叶えてあげるねん。あのIT社長も、あのノーベル賞受賞者も、みーんな人間大賞受賞者やで」
ケンちゃんはようやく、今日が自分の誕生日であることを思い出した。ケンちゃんは不惑の四十歳を迎えていたのだった。ケンちゃんは何か馬鹿馬鹿しく感じて来たが、とりあえず、
「そのににに人間大賞とやらに、ななななんで俺が選ばれたんですか?」
と聞いてみた。
「うむ、そこよ、ケンちゃん。ええこと聞くなあ。選考理由はただひとつ、ケンちゃん生まれてから今まで一回も嘘ついたこと無いやろ? そこが神様の間で高く評価されたのだよ。何しろ調査部の報告によると、五歳以上の人間では世界でケンちゃん一人しかいなかったからなあ」
ケンちゃんは自分が今まで嘘をついたことが無かったかどうかを思い出してみたが、本当に嘘を付いたことが無いのか、嘘を付いたのに相手に聞き取ってもらえなかったのかは、はっきりしなかった。
「さあ、ケンちゃん何でも望みを言いたまえ」
神様と名乗るその男はワイシャツのネクタイを緩めながら、仕事終りに立ち飲み屋で一杯ひっかけている係長のような風情でそう言った。ケンちゃんはもちろん、神様と名乗る男のことも、その男が言うことも、信じることは出来なかったが、とりあえず前から憧れていたことを言ってみた。
「こここのドモリ癖をなおしてほしいでですす」
神様を名乗る男は、右手を顔の前でひらひらさせた。
「うーん、なんかショボイなあ。治るか治らないかは別にして、あちこちに『ドモリ治します』みたいな広告いっぱいあるやんなあ。神様でないと出来へん、ってことじゃないと、賞の価値が下がるやん。それにケンちゃん、ドモリ治したいかあ? 治してしもたらケンちゃんらしくなくなるやん。どうせやからケンちゃん、パーっと景気のええ願い事頼むわ。キーワードは『奇跡』これよ、ケンちゃん」
ケンちゃんは、だんだんと腹が立って来たが、どうせ夢だと思い直し、他に願い事を考えてみた。顎を掻いている神様を名乗る男の向こうに、阪神タイガースのカレンダーがかかっている。
「せせせ世界で一番、ややや野球の上手い四十歳になって阪神タイガースで活躍してみたいです」
神様と名乗るその男はにっこりと笑う。
「そんなんでええのん? お安い御用。じゃあ頑張りやあ」
今度はことさらあっさりと、そう言い終えるやいなや、あっという間に目の前から神様を名乗る男は姿を消した。
黒ずんだコンパネに囲まれた空間は、いつものケンちゃんの部屋に戻っていた。
夢か現実か、始まりの始まり
「こら、ケンちゃん。起きんかい」
翌朝、ケンちゃんは誰かに揺り起こされて目を覚ました。やはり昨夜の出来事が夢であったと気付いて、安堵と失望で複雑な気分だった。
「いつまで寝てんねん、もう十時やで」
毛布の横にはタケ坊が座っている。
「早よ起きて野球盤やろうや。今三勝三敗の五分やん。今日こそ決着やで」
既に床の上には野球盤が置かれていて、プラスチック製の選手人形も、マウンド上の銀球もセッティングが完了されていた。
「ううううん」
ケンちゃんはのっそりと起き出して、野球盤のバックスクリーン側に座り、第一球を投ずるべく真ん中のレバーを手前に引き寄せた。スプリングから放たれたボールは真っ直ぐにホームベースに向かい、やがてボールと同じ色のタケ坊が振った銀バットに当たって野球盤を転がっていく。
「よっしゃ! 赤星スリーベース!」
銀球は水色に囲まれた左中間のスペースに転がり落ちた。ケンちゃんは「3BH」とそこに書かれた文字をじっと見つめていたが、やがて何かを思いついたように、おもむろに立ち上がりトタンの屋根に頭をぶつけた。
「どうしたん、ケンちゃん」
「そそそそ総理の所へ行って来る」
飛び出したケンちゃんの背中に、
「汚ねえええ! 打たれたからって逃げるんかあ」
というタケ坊の叫び声が突き刺さった。
ホームレス仲間から「総理」と呼ばれているその男は、集団のリーダー的存在であり、豊富な知識と、常に冷静なその佇まいから、多くの信頼を一身に集めている男である。
彼の性格を表すように整然と片付けられている総理の住処は、公園外周道路から僅かに外れた小径の、楡の木陰にあった。
「そそそそそーり」
「そそそそそーり」
珍獣が求愛するような声でケンちゃんが総理を呼ぶ。
「何事だよ?」
グレーの作業服上下を身に付け、黄色い手ぬぐいを首に巻いた総理が、被災地を視察に訪れた内閣総理大臣のようにゆったりと現れた。買っているのか拾っているのかわからないポマードで、総理は髪を常に七三に分けている。
「どうした? ケンちゃん。っとその前に忠告しておく。とにかくゆっくりゆっくり喋るんだ。わかったか?」
ケンちゃんは素早く四回頷いて、恐ろしくゆっくりと話し始めた。
「きぃゃぁ?っちぃ?ぃ?い ぼぅをぉぉるぅ ぅをぉ しぃぃぃたぁぁいねぇぇぇんぅ」
「なんだって? キャッチセールスにひっかかった? てめえみたいな見るからに金を持ってねえ人間に声をかける間抜けなキャッチがいるのかい?」
ケンちゃんは、今度は横方向に四回、素早く首を振った。
「キャッチボールしたいって言うてるみたいやで」
彼らの後ろから声が聞こえ、二人が声の方向を振り返ると、ケンちゃんを追いかけて、タケ坊が向こうから歩いて来ていた。
「おう、タケ坊。助かったよ。しかしおめえ、本当によく聞き取れるよなあ」
タケ坊は総理ににっこり笑い、次にケンちゃんの方へ向き直った。
「なんやねん、ケンちゃん。こっちはノーアウト三塁の大チャンスやったのに、なんでいきなりキャッチボールやねん」
「ごごごごめん」
「ちゃんと説明してえや。ケンちゃん」
ケンちゃんは例によって呪文のように話し始めた。総理には全く聞き取れなかったが、タケ坊は時々、聞き返しながらも、ふんふんと頷いたり、驚いたりしながら聞いている。
「ケンちゃんはなんて言ってんだ? タケ坊」
「うーん、ようわからへんねんけど。なんか昨日な、夢に神様が出てきてな、ケンちゃんを世界で一番野球が上手い四十歳にさせてくれたから、それが本当かどうか試してみたいんやって」
タケ坊は訝しがるような表情でケンちゃんの方を見やりながら、総理に答えた。
「何を言ってんだケンちゃんは? いよいよ頭がクルクルパピーか?」
不思議そうに見つめる二人の前でケンちゃんの表情はひたすら真剣であった。総理は推し量るように、ケンちゃんのしょぼくれた二つの小さな瞳を見つめた。
「タケ坊、グローブ持ってるかい?」
「いや、俺野球出来へんから……」
寂しそうに答えたタケ坊の頭を、総理は黙って撫でた。
「たしかバルやんがグローブとボール持ってたな。行ってみるか」
バルやんと言うのは、顔がバルタン星人にそっくりな元料理人のホームレスである。いつも屁理屈をこねて一言多いので、どこの店に行っても人間関係がこじれて勤めが続かず、ついにはホームレスになったのだった。実はホームレス仲間の間でも煙たがられているのだが、当の本人は全く気付いていなかった。
バルやんは阪神高速の高架下に、段ボールハウスを作って住んでいる。ケンちゃんたちがやって来ると、彼はまだ寝袋に入っていびきをかいていた。総理は眠っているバルやんの横にしゃがみこみ、耳元に口を持っていくと、
「炊き出しじゃああ!」
と大声で叫んだ。塩をかけられたナメクジのようにバルやんの寝袋がくねくねとうごめいてやがて大笑いしている総理たちに気付いた。
「なんやねんな。睡眠はその深さが波のように変化しているんやから、無理矢理起こしたりしたら、精神障害を引き起こす原因にもなりかねんのやで」
寝袋に入ったままエビフライのような姿で訴えるバルやんの言葉を、完全に無視して総理は尋ねた。
「起きろ、バルやん。お前さんグローブとボール持ってたよな?」
「持ってるで、グローブはゼットの投手用。ボールはケンコーの軟式A球や」
総理はひとつ頷いて、バルやんの寝袋のチャックを引き下ろしながら言った。
「お前、ちょっとケンちゃんの球受けてみい」
ケンちゃんとタケ坊、そして総理とバルやんの4人は天王寺動物園を横切る陸橋の上、ケンちゃんの住処前に集まった。
「ケンちゃん野球できるんかいな? 素人と野球経験者ではボールの回転にその差が一番現れるんやで。だいたい……」
「ぶつぶつ言ってねえで早く構えな、バルやん」
総理がバルやんの言葉を遮った。そしてキャッチボールの距離に離れていくバルやんの背中に向かって、
「喜べ、バルやん。世界一の野球選手になる男の球を初めて受けるのが、おまえさんってことになるかも知れないぜ」
と言った。バルやんは聞えたのか、聞えなかったのか、その言葉を無視して、適当な距離の場所に着くと準備運動を始めた。平日の午前中ということで、陸橋の上には殆ど人がいなかったが、わずかに行き交う人は、バルやんの不思議な柔軟体操に不審な視線を送った。
「早よしいな。バルやん」
タケ坊が口に両手を添えて言う。
「たかが準備運動と馬鹿にするなかれ。全てのスポーツに通じる大事な儀式なんやで、かつて鹿島のデッドボールで引退に追い込まれた掛布雅之も準備運動を……」
「バルやん、グローブ貸せ。俺が受ける」
と総理が言って、バルヤンの方に近づこうとした時、
「大変長らくお待たせ致しました。さあ、来おおい! ケンちゃん!」
と、ようやくバルやんがアキレス腱伸ばしを途中で止めて言った。総理が手の平で弄っていた黒ずんだ軟式ボールを、ケンちゃんの手にトンと置く。
「さ、投げてみな」
ケンちゃんはコクンとうなずいて、バルやんの正面に向かった。
「ケンちゃん、もうちょっと後ろだなあ、ピッチャーマウンドからホームベースまでの距離は60.6フィート。メートルに換算すると約18.44メートル。うん、それぐらいだ」
しかし、バルやんが止まれと言ったその位置は、明らかに20メートル以上離れていた。
「ケンちゃんがんばれよ!」
タケ坊が声を出す。総理は腕を組んでじっとケンちゃんを見つめている。バルやんが右手の握りこぶしでポンポンとグラブをふたつ叩いてから、キャッチャーのようにしゃがみ、そして構えた。
ケンちゃんは投球モーションに入る前に大きく息を吸い込んだ。やがてグローブを持たない両手が、胸の前からゆっくりと頭の後ろへ引っ張り上げられる。大きなワインドアップに合わせて、ケンちゃんはほんの少し左足を後に引いた。ほんの一瞬だけ静止した身体は、やがてゆっくりと再始動を始め、引いた左足が身体に巻きつくように上がって行くと、両手が足の動きにリンクしながらベルトのバックルの辺りまで下がっていく。まるで空から糸で引っ張られているかのように、まっすぐ上に伸びたケンちゃんの身体は、刹那、スイッチが切り替わったかのように動きの速度を変え、持ち上げた左足を大きく前に踏み出した。そしてその動きに引っ張られるかのようにケンちゃんの胸が前にせり出すと、次に肩、そして肘、最後に手首が鞭のようにしなりながら頭の上を通過していった。ケンちゃんのしわだらけの右手から「投げた」というよりは、「発射された」という言葉がふさわしいかのように放たれた軟式ボールは、まるでガラガラヘビが敵を威嚇するような風切り音を立てながら空中に糸を引くような軌跡を描き、両手で構えたミットの上をすり抜けて、バルやんの鼻骨を粉々に粉砕した
二〇XX年一一月 動き始めた夢、仲間たちは本気だ
総理を中心とするグループは、総理にケンちゃんとバルやん、その他にアンちゃん、ゴリさんと呼ばれる二人を加えた五人である。五人にタケ坊を加えた六人は、天王寺公園を外周する歩行者専用通路から少し奥まった場所に入った総理の住処に集まっていた。
アンちゃんは身長一メートル九八センチ、体重一二〇キロの大男で、元々はとある相撲部屋に所属していたのだが、気弱な性格が災いして序の口止まり。相撲を引退した後は居酒屋の店員や、建設作業員をしていたのだが、その体躯と性格のギャップから、どこに行っても同僚や上司のいじめに遭う羽目になった。ある日のこと、あまりにひどい虐めに耐えかねて、勤め先の寮を飛び出し、街をふらふら歩いているところを総理に拾われてホームレスとなったのだった 気は優しくて力持ちというのは、まさしく彼のためにある言葉で、彼が激したところを見た者はいなかった。彼は毎朝、きっちり同じ時間に起き出して、あいりんへ土木作業の仕事を探しに行く。ちなみにアンちゃんという渾名はアンドレ・ザ・ジャイアントにあやかって総理が付けた物である。
ゴリさんと呼ばれるもう一人の男は、もともと京都でピアノ教室を開いていた。一時は百人を超える生徒を抱えていたゴリさんは、さらに自分の教室を拡大する為に大阪へと進出。しかし、京都と大阪では、たかがピアノ教室といえど競争の激しさが桁違いで、ゴリさんの教室には閑古鳥が鳴いた。更に、大阪の教室を軌道に乗せるため、奔走していたゴリさんの留守中に、奥さんと雇っていた音大生の講師が、絵に書いたような不倫関係に陥ってしまい、ゴリさんは離婚する羽目となり、本当は自分がもらえる筈の慰謝料を請求され、京都と大阪のピアノ
教室も取り上げられてしまった。すっかり世の中に悲観したゴリさんは、あちこちをさまよった挙句、天王寺へ流れ着いてホームレスとなった。ゴリさんの名の由来は、有名な刑事ドラマの登場人物に顔が似ていたからである。そして、その風貌のせいで、未だに誰からもピアノ教師だった過去を信じて貰えなかった。
総理のグループでは、彼の指導の元、数々のルールが決められている。
例えばそのひとつは仕事を持つこと。総理自身は段ボール集めを仕事としていたし、ケンちゃんの空き缶集め、アンちゃんの土木作業、バルやんは飲食街のゴミ捨て場を掃除して、残った食材や料理をもらっていたし、ゴリさんは古雑誌を拾っては古本屋に持ち込んだり、時には自ら路上で販売したりした。
その他にも、当番制で路上を清掃すること、大通りや公園でたむろしないこと、週に一度は全員分の服をまとめて洗濯をすること、知った顔にはきちんと挨拶をすることなど、こと細かく、暮らしていく上での決め事がなされていた。
総理は常に、
「俺達は社会の邪魔者なんだよ。絶対に他所様に迷惑かけちゃいけねえ。皆様の往来を間借りして住まわせてもらってんだから、決して驕ったり、出しゃばったことをしてはいけねえんだよ」
と話していた。おかげで、数々のホームレスの中でも彼らのグループは地元の人からも、比較的クレームが少なく、中には好意的な目を向ける人さえいた。
誰かが困った時には親身に相談に乗ってくれ、他のホームレスグループとテリトリー争いになった時は、先頭に立って暴力以外の方法で戦い、そして何より、自分に対して最も厳しい総理を、グループの全員が心から信頼していた。
また、厳しく管理するばかりではなく、総理はメンバーの収入の一部を預かっては、ひとまとめに貯めていて、誰かの誕生日や正月には一杯飲み屋で美味い酒を飲んだ。メンバーにとってそれは何よりも楽しみなことであった。
あの日、総理はケンちゃんのストレートに吹っ飛ばされたバルやんを病院へ連れて行った。治療費は飲み会の為の貯金を取り崩した。病院へ着いて、ガーゼで血をふき取られたバルやんの鼻は潰れ、顔全体が一回り大きく腫れ上がっており、今はノーズガードと包帯で見えないが総理が治療中に見た時には、バルタン星人というよりも、むしろザラブ星人のようになってしまっていた。
ボールを顔面で受けて、鼻血をだらだら流しながら白目を剥いて倒れているバルやんに、ケンちゃんは泣き叫びながら謝り続けた。次に治療の為に貯金を使うという総理の言葉を聞いて、今度はその場にいなかったアンちゃんとゴリさんに対して謝り続けた。しかしなんと言って謝っているのかはタケ坊以外の誰にもわからなかった。
こうしてグループ全員が顔を揃えるのは久しぶりのことであった。というのも、キャッチボールをしたあの日以来、ケンちゃんがすっかり自分の住処に閉じこもってしまったためである。タケ坊と総理の必死の説得にケンちゃんがようやく応じたこの日まで、既に三週間近い日が経っていたのであった。
「ケンちゃん気にすんなって、鼻が折れたぐらいどうってことないわ。どっちかって言うと、俺のキャッチングに問題があったのかもわからんし。やはりストレートには、もう少しその伸びを計算してミットを合わせるべきだったなあ」
ノーズガードを着けている為に、アヒルのような声になっているバルやんが言うと、ケンちゃんは笑い声にも、呪いのようにも聞える、奇妙な嗚咽を漏らしながら、両の目から涙をぽろぽろとこぼした。そんなケンちゃんの肩を、アンちゃんの熊手のような大きな手の平が優しく抱いている。
「今日、集まってもらったのは他でも無い、今後のケンちゃんのことをみんなで相談したかったからだ」
総理が全員の目を見回すように言った。それを聞いてケンちゃんが何事か呟いた。
「タケ坊」
総理がタケ坊に通訳を促す。
「なんかな、もう二度と野球なんかせえへんとかなんとか」
「あら、そんなこと言ってもさあ、阪神で活躍するって神様に言っちゃったんだから、もうほっといてもケンちゃんは阪神に入ることになるんじゃないの?」
そう言ったのはゴリさんだった。ゴリさんはその風貌に似合わない、お姐言葉を使うオカマだった。本人曰く前の奥さんに裏切られた時、あまりのショックと女性不信から、気がつくとオカマになっていたらしい。相撲部屋出身のアンちゃんはケンちゃんの肩を抱きながら頷いてそんなゴリさんの言葉に同意した。
「確かにそうだろうな。もし、神さんの力が働いているのなら、ケンちゃんが望むと望まざるとにかかわらず、恐らくケンちゃんは阪神で活躍する選手になるだろう」
ケンちゃんの泣き声が鳴き声になった。
「けど、お前らそれを見てるだけでいいのか? 俺は嫌だね。ケンちゃんを夢の世界へ送り出す物語の中で、何かの役割を俺は果たしたい」
「どういうこと?」
今度はガチョウのような声でバルやんが聞いた。
「俺達が阪神にケンちゃんを売り込むんだよ。きっかけを作るんだ。それすらもひょっとすると、神さんのシナリオに組み込まれているのかも知れねえ。けどな、俺は何もせずにケンちゃん
が阪神に連れ去られていくのを見届ける気はないぜ。俺たちもケンちゃんと一緒に夢に乗っかるんだ」
総理の言葉にみんな黙り込んだ。ホームレスの自分達に何が出来るのか、全く想像することが出来なかったが、それでも総理の言葉は、彼らの心を揺さぶる力を持っていた。
「ぶひぃぃぃっぃ!」
突然ケンちゃんが、火傷した豚のような声を上げて立ち上がった。
逃げ出そうとするケンちゃんを捕まえようとしたアンちゃんの両手は空を切り、アンちゃんの巨体はバルやんの上に倒れこんだ。バルやんは一二〇キロのボディプレスを受けて、アヒルとガチョウを混ぜたような声を上げて気を失った。
「待て、ケンちゃん」
総理の制止を振り切って走り出したケンちゃんは、歩行者用通路を自分の住処へと向かって走り出した。何よりも人を傷つけることが嫌いなケンちゃんの脳裏には、顔を鮮血で染めたバルやんの姿が今も鮮やかにこびりついていた。いくら神様がどうだろうと、いくら阪神タイガースが好きだろうと、あんな思いをするぐらいなら絶対に野球のボールを握りたくなかった。
あふれ出る涙を汚れた袖で拭いながら走っていると、背後から総理たちの声が聞えた。ケンちゃんは絶対に振り返るつもりはなかったが、ケンちゃんの名を呼んでいた総理の声が突然、その調子を変えた。
「あああああ! タケ坊!」
ケンちゃんが振り返ると、苦しそうに胸を押さえてしゃがみ込んでいるタケ坊を、総理とゴリさんがのぞきこんでいる。タケ坊は医者から運動を禁じられているにもかかわらず、逃げ出したケンちゃんを見て、思わず後を追って走り出してしまっていたのである。
「たたたたタケ坊!」
ケンちゃんは不可解な動きで回れ右をすると、慌ててタケ坊のところに駆け寄った。そしてそのゴボウのように痩せてささくれだった腕にタケ坊を抱きかかえた。
「ケンちゃんのアホウ」
タケ坊は苦しさに顔を歪めたまま、ケンちゃんの顔をしっかり見つめて言った。
「わいを見てみいや。こんなな、情け無い身体なんやで。ケンちゃんなんやねん。自分で神さんにお願いしといて、すっげーチャンスもらっといて逃げ出すんかいやあ」
タケ坊の背中をさすっていた総理が、
「タケ坊、しゃべるな」
とたしなめたが、タケ坊は目に涙をいっぱいに溜めてケンちゃんに叫び続けた。
「わいなあ、バルやんには悪いけど、ケンちゃんのストレート見て、ごっつワクワクしたんやで。俺、野球大好きやのに、キャッチボールも出来へん身体やんか。なんぼ友達と野球したくても、我慢せなアカン身体や。けどな、あの日ケンちゃんのストレート見てな、『俺の分までケンちゃんがやってくれるわ! 阪神タイガースを優勝させてくれるわ!』って思ったんや。せやのに…… せやのに…… ケンちゃんのアホウ! 弱虫! ケンちゃん、わいの親友ちゃうんかいや? もう、そんなケンちゃん絶交や! うわああああん」
と小さな声で言って泣きながらうずくまっていた。ケンちゃんはただ、ひたすらタケ坊の小さな身体を抱きしめていた。
総理の住処の、あちこちからスプリングをのぞかせているマットレスの上で、タケ坊は目を覚ました。
「どうだい? タケ坊、ちょっとは落ち着いたかい?」
総理が、横になっているタケ坊に尋ねた。
「うん、もう大丈夫や。ありがとう総理。みんな」
バルやんとケンちゃん以外のみんながにっこりと笑った。バルやんはタケ坊の向こう側でまだ気を失ったまま、鼾をかいて眠っていた。ケンちゃんはしょんぼりと、みんなの輪から離れたところでぽつねんと体育座りをしていた。
「もう、アンタいつまでショゲてんのよ、ほらケンちゃん、しっかりしなさいよ。タケ坊もう大丈夫よ」
叱咤するように声をかけたのはゴリさんだった。
「ねえ、ケンちゃん。タケ坊のためにも頑張ってあげなさいよ」
ゴリさんの声にケンちゃんがさらに深くうな垂れた。
「ゴリさんの言うとおりだぞ、ケンちゃん」
総理が立ち上がり、ケンちゃんの方へ歩きながら言った。
「それにタケ坊のためだけじゃない。お前がもし、あの甲子園で巨人や中日のバッターを三振に取ってみろよ。そのシーンを俺たちがラジオで聞いてるところを想像してみな。俺達はどれだけそれが誇らしく、嬉しいと思うか考えてみなよ。なあ、ケンちゃん」
総理の言葉にアンちゃんもゴリさんも頷いた。バルやんは寝返りを打った。総理はケンちゃんの側まで行くと、ゆっくりとしゃがみこんだ。
「タケ坊を見てみなよ。あの子、あんな身体でもいつも明るいだろう? 本当はタケ坊だってみんなと野球したり、あちこち走り回りたいはずなんだよ。けどタケ坊は偉いぞ、そのことでくよくよしたり絶対しねえじゃないか。それに引き換えお前はなんだよ。たかがキャッチボール一回で怖気付きやがって。てめえ、くそったれのホームレスのくせしやがって、何を一人前に悩んでんだよ。こんなてめえのことを親友だなんて呼んでくれるタケ坊のために『よーしやってやる』って気にならねえのかよ、ここで逃げ出したらホームレス以下だよ。なあ、ケンちゃん頑張ってみろよ。タケ坊のために、俺達のために」
ケンちゃんは顔を上げて、総理を見、そしてタケ坊を見た。タケ坊は、まだ流した涙の跡の残る顔で、じっとケンちゃんの方を見つめていた。綺麗に整頓された部屋の壁の向こうから、表通りを走る救急車の音が聞え、やがて去っていった。
「おらあああるよ」
ケンちゃんが消え入りそうな声で言った。
「ほんまか? ケンちゃん!」
タケ坊が叫んだ。
「何よ、タケ坊。ケンちゃんなんて言ったのよ」
ゴリさんがタケ坊に聞いた。アンちゃんも焦ったような表情でタケ坊を見た。総理はケンちゃんの言葉がわかったのか、あるいは表情から何かを感じ取ったのか、唇の端に微笑を浮かべた。バルやんは絶妙のタイミングで寝屁をした。
「おおお俺、やるよ」
もう一度、先ほどよりゆっくりと喋ったケンちゃんの言葉は、今度はゴリさんの耳にも、アンちゃんの耳にもはっきりと届いた。
「そうよ! それでこそケンちゃんよぉ」
両の手の平を唇の前で合わせて、ゴリさんが言うと、アンちゃんが歓声を上げて立ち上がった天井の梁代わりに渡してある角材に頭をぶつけて、角材が折れ、総理の部屋が一瞬部屋ごと持ち上がって、その後、大きく揺れた。
総理はケンちゃんの肩をぽんぽんと二つ叩いて、その後、右手を差し出した。ケンちゃんがそれに応えて二人は握手を交わした。
「よし、こうしちゃいられねえ。おい、タケ坊、もう歩けるかい?」
立ち上がった総理がタケ坊に向かって言った。
「うん、もう大丈夫や」
タケ坊も立ち上がって、ケンちゃんのところへ行き、そして抱きついた。
「タケ坊、家からおとっつぁん呼んで来るんだ」
総理の言葉に、タケ坊がケンちゃんから身体を離して不思議そうな顔をする。
「パパを連れてくるの?」
「パパって顔かよ、あのオヤジが」
総理の言葉に、アンちゃんとゴリさんも声を上げて笑った。
「まあ、いい。そのパパと一緒に、この間バルやんが怪我したところまで来るんだ」
「ええけど……、どうして?」
「連れて来ればわかるさ、タケ坊」
そう言って総理は何かを企んでいるようにニヤリと笑った。
「ふうん、ようわからんけど、とりあえず、ほな連れて来るわ」
そう言って、ベニヤでしつらえた部屋のドアノブを回して、タケ坊が出て行こうとした時、総理が思い出したように言った。
「パパにキャッチャーミット忘れんなよと言うんだぜ」
総理以外のみんなは呆気に取られ、そしてバルやんが二発目の寝屁を放った。
総理の目論見、そしてパパの正体!
タケ坊の父親、中島作蔵は工場の二階にある事務所で電話に出ていた。
「あほんだら、何が再開発や。俺が奈良に引っ込んだら、空き缶拾って持ってくる奴等はどうなんねん。お前ら、建前ばっかりのホームレス対策しやがって、あいつらが酒盛り禁止の宿泊所に入るはず無いやろが。あいつらが自分で暮らしていける仕事を作ったるのがおまえらの仕事やろが」
傍らではもう一本の電話が鳴り出した。作蔵は一瞬、取引先からかも知れないと考えたが、火の付いた心は既にブレーキを失っていた。
「こぎれいなマンション並べて、ホームレス追い出すことが再開発かい。たとえ築二百年でも、家賃が安いところを選ぶ人間がおるんや。お前、いっぺん天王寺来て、あいつらがどんな思いで、どんないきさつでホームレスやってるんか全員に聞き取り調査してみやがれ。わかったか」
作蔵は呼び出し音が鳴り響く中、そう言って電話を叩き切り、慌ててもう一本の電話に出た。
「大変お待たせしました。中島鉄……」
手にした電話は既に切れていた。作蔵は舌打ちをして受話器を置き、事務机の椅子にため息を付きながら身体を沈めた。
父親の経営していた中島鉄工所を受け継いで既に二十五年。空き缶や屑鉄などのスクラップをその材質毎に分別後、直方体にプレスし、堺にある製鋼会社に納めるのが中島鉄工所の仕事である。バブル崩壊後の冗談のような鉄鋼不況で、中島鉄工所も例に漏れず、その経営にはすき間風が吹いたが、バブル時にここぞとばかりに設備投資に励む同業他社を横目に見ながら、無借金経営を続けたおかげで、拡大もしなかった代わりに、倒産の憂いを受けることなく今日までやって来た。
二十八歳で結婚した作蔵はずっと子宝に恵まれなかったが、厄が明けた四十二歳の春に妻が突然妊娠した。妻は四歳下とは言え、当時三十八歳で押しも押されぬ高齢出産だったが、夫婦は躍り上がって喜び合った。三十八週で産気づいた妻が帝王切開の上出産した未熟児は、作蔵の父の名前から一字を取って「武司」と名付けられた。タケシは生まれつき心臓に疾患を持っていた。
身長一八八センチ、体重一○○キロの父親に似ず、タケシは小柄で痩せぎすの貧弱な身体だったが、作蔵と妻の濃やかな愛情を受けて、素直で明るい子供に育っていった。作蔵は先ほどの電話を思い出し、タケシの将来を考えると、環境の良い奈良へ工場を移した方がよいのかも知れないと考えた。
作蔵は天王寺にたむろするホームレス達に積極的に仕事を与えた。ホームレスの男達が持ってくる空き缶を決して断ることは無かったし、集めた空き缶を洗う作業もホームレスを臨時で雇って、日払いで給料を与えた。
無論、最初はごみを散らかし、近隣の迷惑となるホームレスを嫌っていたが、町内会長をやっていた時期に、彼等と一対一で話す機会が多くなり、毛嫌いをして排除するよりも共存の道を探ることが、彼等のためにも、そして自分の愛するこの天王寺を守るためにも良いことなのだと考えるようになった。
そのようにホームレスに対し、協力的である一方、他人に危害を加えたり、ルールを守らないホームレスに対しては、それこそ決して許さない厳しさも併せて持っていた。ホームレスの存在を認めている訳ではない。どこかの政党やNPOに参加して声を上げるわけでもない。けれど行政の行う代執行は絶対に間違っているという確信が作蔵にはあった。作蔵はあくまで作蔵個人として、自分の信じるところに従ってホームレスと向き合っていた。ただ、大切な息子がホームレス連中と仲良く付き合っていることには閉口し、頭を痛めてはいたが。
「パパ! ケンちゃん野球やるって!」
タケ坊が事務所のドアを開き、そう叫んだ時、作蔵は思わず両手で頭を抱えた。
「タケシなあ、まだそんなこと言うてんのか。あいつらはあいつらで忙しいんやから、ちょろちょろ邪魔すんな。宿題やったんか」
そう言うと、作蔵は机の上に広げていた得意先元帳に目を落とした。
「宿題は後でちゃんとするから。なあ、パパ。ケンちゃん阪神行くって言うてん」
作蔵はその大きな身体を丸めながら、得意先元帳に請求書の金額を書き写しながら言った。
「空き缶袋ふたつでふらふらするケンちゃんが阪神に入れるはずないやろ? ケンちゃんが阪神に入団出来るんやったら、桜井なんか今頃ヤンキースの四番打っとるわい」
「せやから、こないだ言うたやんか。ケンちゃん神様と会うて世界一の野球選手に……」
「もう、わかった、わかった。ケンちゃんも何思ってそんなこと言い出したんやろなあ。それか、タケシが何か聞き違えてんのかなあ」
タケ坊は不満気に頬をふくらませたが、作蔵はデスクの上に目を落としたままだ。
「とにかく、一回見に来てえな。総理がパパ呼んで来てって言うてんねん」
作蔵は椅子を回転させて、タケ坊の方に振り返り、
「パパは仕事中。ケンちゃんや総理の遊びに付き合ってる暇はあらへんの。タケシもあいつらとばっかり遊んどったら、いつまで経っても学校の友達出来へんぞ」
タケ坊は唇を噛んで下を向いた。
「なあ、タケシ。あいつらと付き合うなとは言わん。けどな、たまには勇気出して学校の友達とも遊んでみいや」
「もう、ええわい」
「タケシ……」
「わいかて、野球出来るんやったら、アキスケやコウジと遊ぶわ。こんな身体で……こんな身体とちゃうかったら……」
そこまで言ってシャツの袖で瞼を拭うと、タケ坊は立ち上がり、事務所を出て行こうとした。作蔵は言わずもがなのことを言ってしまった自分を嫌悪し、なんとも言えない苦味が喉元を上がって来るのを飲み下ろしていた。
「あ、そうや」
タケ坊が立ち止まって言った。
「パパ来えへんのやったら、キャッチャーミットだけ貸してえや」
「なんやと?」
「総理がパパにキャッチャーミット持って来てもらえって。パパは絶対持ってるはずやからって」
作蔵は何かを思いつめるように、遠くを見るような目をした。タケ坊は父の戸惑った表情に少しだけ不安を覚えた。やがて、大きなため息をついた作蔵は電話の内線ボタンを押した。
「おう、ママ。ちょっと出かけるから電話番頼むわ」
受話器を置くと、立ち上がってタケ坊に言った。
「そんで、あいつらどこにおんねん」
総理達はいまだ目を覚まさないバルやんを置いて、四人でケンちゃんの住処である、天王寺動物園上の陸橋に向かった。
陸橋の上では、四人が思い思いにタケ坊の到着を待った。総理はベージュ色の欄干に身体を預けて胡坐をかき、ハイライトに火を点けて、雲ひとつ無い秋の空へと煙を吐き出した。灰皿はワンカップの空き瓶である。
アンちゃんは欄干の銀色の手摺に両手を預け、フェンスの向こうにある動物園に目をやっていた。
ゴリさんは石とコンクリートで作られた陸橋の端を、伏し目がちに歩いていて、吸殻やゴミが目につくと、それを手に持ったダイエーの買い物袋に拾い入れた。
主役のケンちゃんはというと、住処の前に停めた自転車のサドルに腰掛け、退屈を紛らわすように時々ペダルを漕いだ。ペダルを踏み込む足を止めると、後輪だけが空回りして、
――しゅうううううん
という乾いた音が鳴った。ケンちゃんはひとしきりその音を聞いた後、おもむろにブレーキを握って後輪を止め、そしてまた最初からその動作を繰り返した。
――しゅううううううん、キッ
――しゅううううううん、キッ
――しゅううううううん、キッ
――しゅううううううん、キッ
何度目かのブレーキをケンちゃんが握り締めた時、
「来たわよ!」
というゴリさんの声が聞えて、ケンちゃんは自転車を降りた。
陸橋の新世界側から、見慣れた巨体を揺らしながら作蔵がタケ坊の手を引いて歩いてくるのが見えた。ケンちゃんにとっては、いつも空き缶を引き取ってくれる厳しく優しい大将であった遠目ではあるが、その表情はいつも空き缶を持ち込む時のそれより、少し険しいようにケンちゃんの目には映った。
誰かに肩を抱かれたケンちゃんが振り向くと総理だった。総理は近付いてくる作蔵に目を遣りながら静かに頷いた。アンちゃんは何故か拍手している。ゴリさんが内股で駆け寄っていきタケ坊の頭を撫でた。
「悪いね、仕事中」
総理が顔の横に右手を上げて挨拶するように言った。作蔵の右手にはマンシングウェアのロゴが描かれた紙袋が提げられている。
「なんで、わしがキャッチャーミット持ってること知ってんねん?」
「あら、本当に入ってるわ」
ゴリさんが紙袋をのぞきこんで言うと、総理が作蔵の方を見てにやりと笑い、そして言った。
「新日鉄堺のノンプロナンバーワン捕手、中島作蔵と言やあ、そりゃ有名よ。ドラフトにかかるって噂だったが、怪我かい? それともやっぱり家業を継ぐ為かい?」
「えええええ!」
総理以外の全員が大声を上げた。特にタケ坊はびっくりして顎が外れてしまったかのように大口を開けている。
「ふん、結局、それだけの力が無かったっちゅうことよ」
言葉少なに言った作蔵を全員が呆気に取られて見つめていた。総理だけはニヤニヤと口の端に笑いを浮かべている。
強肩強打で鳴らした中島作蔵だったが、ドラフト対象となる社会人三年目の春に父親が脳梗塞で倒れた。母親を早くに亡くし、男手一人で作蔵を育ててくれた父親が守り続けた工場を、作蔵はどうしても捨てることが出来なかった。父親の治療費とまだ高校在学中だった妹の学費を捻出する為に、いくら契約金が貰えるとは言え、先の保障がないプロ野球の世界に飛び込むことは出来なかった。作蔵に選択の余地は無かったのである。右半身に麻痺の残った父親を作蔵は献身的に介護したが、その父親もタケ坊が生まれて半月後、まるでタケ坊に自らの命の灯を分け与えるようにこの世を去った。
「作蔵さんよ、阪神のスカウトやってる栗田さん。あれ、作蔵さんの同期だよな。ひとつどうだい。ケンちゃんの口を利いてやってくれないかい?」
総理と作蔵以外の四人はもう訳がわからなくなっている。タケ坊はすっかり呆気にとられてもはや泣きそうな顔になっている。作蔵は参ったなというような表情をして、小さくため息をついた。
「何もかもお見通しかいな」
そう言ってケンちゃんの方を見て微笑んだ。
「まあ、見てやってくれよ。あっと言う間に神さんの存在信じるからさ」
言い終えると総理は黒ずんだ軟球をケンちゃんの手に握らせた。
「待て、ケンちゃん。これ放ってみろ」
作蔵が紙袋に手を入れてごそごそと取り出したのは、朽葉色に色褪せた皮に、赤い糸が二本縫いこまれた硬球だった。
「なるほど」
総理がケンちゃんの手から軟球を取り戻し、ズボンのポケットに押し込むと右ポケットがドーム型に膨らんだ。
作蔵は紙袋を持って、ゆっくりと陸橋を新世界方向へと歩いて行った。やがて立ち止まり振り向くと、距離を測るように二、三歩下がり、そして紙袋から小豆色に染まったキャッチャーミットを取り出して、しゃがみこみ、そして言った。
「おい、ええど」
作蔵が言うと、総理がケンちゃんの方を見て頷いた。タケ坊はドキドキして心臓の発作が出ないか心配だった。ゴリさんは、
「私、まだケンちゃんが野球しているとこ見てないのよお。がんばれえ!」
と手を叩きながら、その場で小さくジャンプした。アンちゃんは大きな顔に似合わぬ小さな瞳を、自分の限界まで見開いた。
ケンちゃんは振りかぶって、作蔵に向けてボールを投げた。しかしバルやんの鼻を砕いたあの日とは比べ物にならないほど、そのフォームは小さく、放たれたボールも作蔵の遥か手前でワンバウンドして、力なくころころと作蔵の足元に転がった。ケンちゃんの脳裏に白目を剥いたバルやんが現れて、すっかりケンちゃんは萎縮してしまっていたのだった。
総理は作蔵が怒って帰ってしまうのではないかと心配になり、作蔵の方を注意深く見たが、何かを感じたらしい作蔵は手にしたボールをじっと見つめると、やがてグローブを持たないケンちゃんのために、ボーリングのようにゴロでボールを返した。それを見てほっと息をついた総理は、続けてケンちゃんに言った。
「ケンちゃん、タケ坊を見ろ」
ケンちゃんがタケ坊を見ると、心配とも怒りともつかない真剣な表情で、じっと自分を見つめるタケ坊の視線が、突き刺さった。
脳裏によぎるバルやんの鼻を忘れようと、ケンちゃんは大きく深呼吸をして、晴れ渡る秋深い青空を見上げた。ユトリロでも描けないような大きな青空に一筋、消えかかる飛行機雲の轍が見えた。やがて何かを決意したケンちゃんは、もう一度振りかぶった。今度はあの日の録画を見直すかのようだった。
空気が分子の集合体であることを見ている者に実感させるケンちゃんの直球は、大気を切り裂く音を周囲に共鳴させて、やがて大きな破裂音と共に作蔵のミットに収まった。
「いやあああん。ケンちゃんすごおおおい」
「うおおおおおお」
ゴリさんが興奮して腰をくねらせ、アンちゃんが吠えた。総理とタケ坊は見つめ合って微笑みお互いに小さく頷いた。
作蔵は再びゴロの球をケンちゃんに返し、
「さ、もっちょ来い」
と再び腰を深く沈めた。
パアアアア―――ン
パアアアア―――ン
パアアアア―――ン
パアアアア―――ン……
都合十七球、ケンちゃんの放つボールは機械のように正確に作蔵のミットに収まり続けた。
「作蔵さん、どうだい?」
作蔵は息を少し荒げながら、興奮を抑えきれない面持ちで、
「わしも久しぶりやから、はっきりしたことは言われへんのやけど、百四十キロどころの騒ぎやないぞ、これは。それにこのコントロール……」
作蔵を囲んだ全員が息を呑んだ。ケンちゃんは上気した顔を見せて、肩で息をしている。
「タケシ、ケンちゃん神さんになんてお願いしたんや?」
作蔵の問いに、タケ坊が答えた。
「あんな、世界一野球の上手い四十歳になって、阪神で活躍したいって言うたらしい」
タケ坊の言葉を聞いて、何か閃いたらしい作蔵は、
「みんなちょっと待っといてくれ」
そう言って巨体を揺らしながら新世界の方へと陸橋を駆け出した。
残されたみんなが、ケンちゃんの周りでわいわい騒いでいると、やがて先ほど去っていった場所から、作蔵が再び巨体を揺らして戻ってきた。その手には年季の入った金属バットが握られている。
「ケンちゃん、これちょっと振ってみい」
はあはあ、ぜえぜえ肩で息をしながら、作蔵がバットをケンちゃんに手渡そうとすると、ケンちゃんはそれを受け取る前に、自分の住処に入って行き、あちこち凹みまくった魔法瓶を取ってきて、コップ代わりのキャップに水を注ぎ、作蔵に渡した。ただの水のはずだが旨そうだった
「おおきに」
少し照れくさそうにはにかんだケンちゃんの顔を見て、作蔵はにっこり笑い、そして一気に水を飲み干した。
作蔵が飲み終えるのを見ると、ケンちゃんは皆の輪から少し離れ、やや戸惑うような顔つきでバットを構えた。
腰を絞り、高くグリップを掲げた構えから、地面に短いラインを引くように左足の爪先が右足に近付いて行き、それに合わせてゴボウのように細いケンちゃんの腰にさらなる捻りが加えられた。左腕が顎の下で真っ直ぐに、それでいて柔らかく後方へと伸び、右腕が弓を引き絞るような形になった刹那、限界まで巻かれたゼンマイがその力を解放するように、バットがスイングを開始した。それを見つめる全員はケンちゃんのスイングアークの軌跡によって、美しい円を描かれるのをはっきりと目に焼きつけ、ピッチングのそれよりも、僅かに周波数の低い風切り音を耳に刻みこんだ。
「信じられん……」
そう言ったのは作蔵だった。
「なるほど、打撃も世界一ってわけか……」
得心したように総理が呟いた。
「いやん、おしっこちびっちゃいそう」
「うおおおおお」
ゴリさんとアンちゃんである。
タケ坊は胸がいっぱいになって、何も言葉が出て来なかった。言いようのない感動で、胸の奥が少しだけ酸っぱくなるのを感じた。
「ケンちゃん、わしが投げるから、ちょっと打ってみい。アンちゃん、ケンちゃんの家からコンパネ一枚持って来て、そこに立ってくれるか」
アンちゃんは「アイ」と返事をして、ケンちゃんの家の前に立てかけられていたコンパネを一枚持つと、陸橋のちょうど真ん中で大阪市立美術館の方を向いて立った。
「よし、もしケンちゃんが空振りしたら、キャッチャー代わりの壁になってくれよ」
「アイ」
アンちゃんが返事をした。
作蔵は右腕をぐるぐると回しながら歩いていくと、やがて、アンちゃんの掲げるコンパネの方を向いて振り返った。
「さ、ケンちゃん」
ケンちゃんは頷くと、コンパネの前に立ち、軽く素振りを二回してから一歩前に踏み出した。
作蔵がマサカリ投法を思わせるフォームで振りかぶり、ボールを投げ込んだ。ケンちゃんは力強くスイングを行ったが、スイングスピードよりも球速が遅すぎたため、ケンちゃんの身体は大きく泳いで、引っ掛けたボールは三塁側方向に高く舞い上がった。
ケンちゃんの打ち上げたファウルボールは、甲子園で言うとオレンジシートの中段に当たる位置に落下したが、陸橋のフェンスを越えた左側のその場所には、鮮やかなピンク色のチリーフラミンゴとベニイロフラミンゴの群れがいた。優雅に水を飲んでいたフラミンゴは突然空から落ちてきた硬球に、断末魔の叫び声を挙げた。
「ケンちゃん、もっとボールが自分の手元に近づくまでボールを見てみ。ギリギリまで引きつけてから振ったらええから。タケシ、紙袋の中にまだボールあるはずやから取ってくれ」
「うん」
タケ坊はマンシングウェアの紙袋から、硬球を取り出すと、二、三歩助走してから作蔵に投げた。タケ坊の投げたボールは作蔵の四メートルぐらい手前に弱々しく落ちて、ツーバウンドした後、作蔵の大きな両手に収まった。
それを見届けたケンちゃんは、作蔵の言葉に頷いて、首をぐるんと一回転させてから、もう一度構えを作った。作蔵がモーションを開始する。先ほどより僅かに球速が増したように見えた作蔵の直球は、ケンちゃんの手元で甲高い金属音と共に弾かれた。目にも止まらぬスピードで、作蔵の頭上の、手が届きそうなぐらいの高さを通過した薄汚れた硬球は、ジャンボ尾崎のドライバーショットのようにそこから更に軌道を上に向け、さっきまでより少し橙色を濃くした秋空へと伸びて行った。
総理も、タケ坊も、ゴリさんも、コンパネの横から顔を覗かせるアンちゃんも、そして振り
返った作蔵も、甲子園の夜空へと駆け上がる白球の軌跡をその頭に思い描いた。カクテルライトの届かぬ闇で一瞬静止したその白球は、やがて濃緑色のバックスクリーンへと静かに落下していく。「三菱電機」と描かれたネオンサインの「菱」と「電」の字の間を直撃しようとする、その瞬間、
「あ、バルやん」
タケ坊がぼそりと言った。
ケンちゃんの打球はバックスクリーンではなく、やっと目を覚まして、ふらふらとこっちに向かって歩いていたバルやんの頭頂部に着弾した。
思い立ったが吉日、いざ甲子園
総理をはじめとする全員は、ケンちゃんの住処の前で車座になり、作蔵がごちそうしてくれた缶ジュースを飲んでいた。
「世界一の野球選手になろうかとする人間のだね、生涯初の投球を顔面に、そして更には、生涯初の打球を脳天で受け止めた俺って、やっぱり何か持ってるんだよ。だいたい、あのタイミングで俺が陸橋に現れて、ケンちゃんの打球の真下に入る確率を計算したら、恐らく天文学的数字になるやろなあ、やっぱり」
誰にともなく語っているバルやんは、不自然に頭頂部がふくれあがり、トレードマークのおかっぱ頭と相俟って、高松塚古墳の壁画に描かれた、飛鳥時代の人々にそっくりだった。
「で、どうだい作蔵さん。栗田スカウトに紹介してやってくれるかい?」
作蔵はケンちゃんの打球を見届けた後、ゴリさんとアンちゃんに千円札を渡して飲み物を買いに行かせると、それからは、バルやんの頭を冷やしてやりながら、ずっと何かを考え込んでいる様子だった。
ケンちゃんはタケ坊を膝の上に抱いて、じっと作蔵の表情を見つめている。タケ坊は、父親が野球選手だったという、自分が知らされていなかった過去を知って、子供なりに何か複雑な思いを胸に抱いているようだった。
「なあ、ケンちゃん。いくらすごい技術を持ってたって、プロになるってのは簡単ちゃうぞ。ほんまにええんか?」
作蔵は腕組みをしたまま、ぎょろりと瞳だけを向けてケンちゃんに聞いた。
「たたたタケ坊と約束したから。おおおお俺がんばるよ」
タケ坊からの通訳を聞いた作蔵は、何度もうなずいた。
「ありがとうな、ケンちゃん」
そういうと作蔵はズボンのポケットから銀色の携帯電話を取り出した。矢野と赤星と桧山と能見のマスコットストラップがぶらさがっている、ともすると女子高生に似合いそうなその携帯電話を太い指でぎこちなく操作すると、作蔵は静かにそれを耳に当てた。
「ああ、クリか。久しぶりやな。何、同期会? ああ、行けると思う。それよりクリよ。お前に見せたい選手がおるんや」
タケ坊は目の前の父親を、未だ信じられない思いで見ている。作蔵はひとつ、ふたつ無言で頷くと、ゆっくりと目を閉じて言った。
「そうやドラフト対象や」
全員が作蔵の会話に耳を澄ましている。
「もう既に指名選手は決まってるって? そんなことわかっとるわ。それを承知で電話しとるんや。ああ、並の選手ちゃうで、お前も見たらわかる。え、明日から出張? じゃあ、今から見に来いや」
「今から……すごいな、やはりこの決断力の速さと行動力。これはノンプロ時代に培われた……」
ぶつぶつ解説を加えるバルやんの頭を総理が叩いた。高松塚古墳のような頭頂部を叩かれてバルやんはあまりの痛さに虫のようにのたうち回った。
「鳴尾浜? アカン。人がおるやろが。そうや、人目に付かん方がええ。甲子園の室内練習場?わかった。関係者駐車場に停めたらええんやな。そっから階段昇って……うんうん、わかったじゃあ今から向かうわ」
電話を切った作蔵はため息をひとつついてから、全員の顔を見回した。それぞれがそれぞれの緊張を覆い隠して作蔵を見つめている。どこか遠くで車のバックファイアの音が聞こえた。
「お前らも、行くか?」
全員が力強く頷いた。いや、全員ではない、ケンちゃんは一人、蝋人形のように固まっていた
ケンちゃんと作蔵を初めとする七人は、作蔵の運転するハイエースで阪神高速を西へと走った車中には異様な緊張が流れていて、誰も口を聞く者はおらず、ラジオから流れている、どこかのアナウンサーが汚職をした政治家に怒っている関西弁だけが、車内に流れていた。
車は阿波座から神戸線へと入り、やがて、国道四十三号線へと降りた。甲子園球場と書かれた標識にしたがって作蔵のハイエースは側道へと入り、大きな交差点の信号が青に変わると直進し、すぐにウィンカーを左に出して二階建ての駐車場へと車を滑らせた。
車がまばらに停まっている駐車場に七人が降りると、蛍光グリーンのジャンバーを着た若者が彼等に近付いてきて、
「栗田とお約束の方ですか? こちらへどうぞ」
と、駐車場内の階段からトンネルのような渡り廊下へと、ケンちゃん達を案内した。柔らかな物腰ではあったが、その額にははっきりと、
「なんじゃこいつら」
という、あからさまな疑惑が浮かんでいた。
渡り廊下を抜けると、明らかに関係者専用という雰囲気を漂わせている、甲子園球場の内部へと入った。本来ならワクワクして、はしゃぎたくなるはずのシチュエーションにも、作蔵以外の全員は、緊張のあまり前だけをしっかりと見つめて、まるで軍隊の歩行訓練のようにその廊下を歩いた。
やがて、再び遊歩道のようになっている渡り廊下を過ぎ、階段を降りていくと、案内してくれた若者が鈍色の重そうな扉を向こう側に押し開けて、
「栗田が参るまで、こちらでお待ちください」
と言って、去った。
開かれた扉の向こう側は、土と人工芝に染め分けられ、あちこちがライトグリーンのネットで仕切られた、甲子園球場隣接の室内練習場だった。
作蔵以外の六人は室内練習場の壁に沿って、まるで銃殺刑を待つ死刑囚かのような真っ青な顔をして、直立不動の姿勢で並んだ。
入団テスト、そして、あの男もやって来た!
栗田和則はクラウンのハンドルを握り、梅田の電鉄本社から、すでに夕闇迫る阪神高速を西へと走らせていた。後部座席には佐野西日本統括スカウトと、新人獲得やチーム編成に関わる球団の責任者である黒田編成部長が座っている。
栗田は新日鉄堺からドラフト5位で阪神に投手として入団した。入団した翌年に肘を痛め、打者に転向したが結局芽が出ず、一軍出場僅か三十八試合で引退した。引退後は高い野球理論が認められてスコアラーとして球団に残り、五年後にスカウトとなってからは既に十年以上が経過していた。彼の発掘した選手で、現在チームの主力となっている選手は少なく無い。
そんな彼の元へ、新日鉄堺の同期で親友のサクやんこと、中島作蔵から電話があったのは、ドラフト当日のスケジューリングと担当配置について行われたミーティングが終わったばかりの時だった。彼がスカウトに就任して以来、これまで作蔵が選手の紹介などしてきたことはなくむしろ野球からは、すっかり離れているように感じていた作蔵の尋常ならざる語り口に、栗田はつい、電話の内容を自ら吟味することもなく、そのまま責任者の黒田に伝えてしまったのだった。
ドラフトの指名予定選手は、既に大筋で決まっていた。一位指名は、春夏の甲子園を湧かせた、みちのくの大物ルーキーだ。予想される抽選に外れた場合の外れ一位も、二巡目以降の指名選手もすでに候補者、指名順ともに決定している。そんな中かかってきた、作蔵からの突然の電話。しかも選手の名前も、よくよく考えてみると、投手か野手かもわからない電話の内容を栗田から聞いた黒田は、
「まあ、見るだけ見ておけばええやろ。ちょうど球団事務所には帰らにゃあならん」
と、日本一の人気球団の編成部長とは思えない腰の軽さで、
「おーい、佐野ちゃんも付き合えやあ」
とコーヒーを飲んでいた佐野スカウトも無理矢理引っ張り出して、栗田に甲子園までの運転を命じたのだった。
やがて栗田の運転するクラウンも作蔵がハイエースを停めたのと同じ駐車場に入り、三人は球団事務所へと向かった。
球団事務所に入るとスタッフが、
「お客様は既にお着きで、室内練習場へご案内しておきました」
と、栗田に伝えた。
「どんな奴だ?」
と尋ねた栗田の問いには、
「どんな奴と言われましても、それがなんとも……」
とニヤケているのか、困っているのか分からない表情で、どうにも要領を得なかった。
「ええやん、栗やん。とりあえず行ってみようや」
と黒田は上部に大きな水色のポリタンクが付いているミネラルウォータのサーバーから、紙コップで水を一杯飲み干すと、ドアを開けて室内練習場へと自ら先頭を切って歩き出した。栗田と佐野が、追う様にしてその後に続き、渡り廊下から階段を下りたところで、栗田が先を行く黒田を追い越して、室内練習場のドアを押し開けた。
室内練習場に入った三人の目に飛び込んで来たのは、現役時代の身体が見る影もなく肥った作蔵と、その横に直立不動の体制で並んでいる七三分けの作業服と、アンドレ・ザ・ジャイアントに似た巨人、ゴリラ刑事に似たオカマと、鼻を怪我したバルタン星人に、阪神の帽子をかぶった色白の小学生、そしてタテジマのハッピを着たゴボウのようなオッサンの姿だった。
「さ、サクやん……これは何の冗談や」
「冗談とちゃう、阪神の未来を変える選手を連れて来た」
栗田が焦って、黒田と佐野の方を振り返ると、二人とも鳩が豆鉄砲どころか、散弾を喰らったような顔をして呆気に取られていた。
「おい、あれ佐野やで。川崎球場でフェンスに激突して頭蓋骨骨折したにもかかわらず、不死鳥の如く蘇り、八十五年の優勝を決めたヤクルト戦では……」
アンちゃんがバルやんを後から羽交い絞めにして、その口を塞いだ。
「部長、申し訳ございませんでした。帰りましょう。こんな冗談を言う奴じゃなかったんですが
栗田が未だ口をぽかんと開けたままの黒田と佐野を促して、室内練習場を出ようとした瞬間総理の声が練習場内にこだました。
「見もしねえで、何がわかるってんだよ。人を外見で判断したらいけねえって、小学校で習わなかったのかい」
「わい習たで!」
タケ坊が続けた。その声を聞いて、黒田が立ち止まり、やっとの思いで咳払いをひとつしてから振り向いた。
「まあ、せっかくやないか、栗やん見てみよう。確かに立派な体つきをしている」
黒田の視線はアンちゃんを見ていた。
「部長がそうおっしゃるならかまいませんが…… サクやん、それじゃあ、投げるにしろ、打つにしろとっとと見せてくれ」
作蔵はにやりと笑って、傍らのコンテナに積み上げられていたボールをひとつ手に取り、傍らに置いてあったグラブと一緒にケンちゃんに投げた。
栗田と黒田と佐野の三人は、マウンドに向かったのが予想していた大男ではなく、ゴボウのタテジマハッピであったのを見て、再度呆気に取られ、黒田に至っては内ポケットから救心を取り出して、一気に飲み下した。
「総理、ケンちゃんおかしいわよ」
ケンちゃんの異変に気付いたゴリさんが、総理に耳打ちした。確かにケンちゃんの歩き方は下手糞なブレイクダンスのようにガチガチであった。
実はケンちゃんは佐野スカウトの姿を見て、血圧が倍になったかと思うぐらい、緊張しま
くっていた。ケンちゃんの脳裏には八十五年の優勝を決めた神宮での九回表、同点となる大きな犠牲フライを左中間に打ち上げた佐野の姿が、さっきから何度もリプレイ映像で流れていたのだった。
「ケンちゃん、落ち着け」
「ケンちゃん、緊張をほぐすには、手の平に三回、人という字を書いて飲めば良いと言われとるけど、科学的根拠は……」
「ケンちゃんしっかりしなさいよ」
「うおおおお!」
みんな、それぞれにケンちゃんを励ましたが、ケンちゃんの目は宙を彷徨っていた。
――ボスッ
突然、室内練習場に響いた場違いな音は、タケ坊がケンちゃんの太股に回し蹴りを食らわせた音だった。
「しっかりせえやあ、ケンちゃん。ここでビビっとったら、甲子園球場四万七千人の前で投げられへんど」
タケ坊の声に、栗田らは苦笑し、総理たちは頷き、作蔵はキャッチングの構えを取り、そしてケンちゃんは、その目に光を取り戻した。
ゆっくりと振りかぶったケンちゃんの右手から放たれたボールは、天王寺公園陸橋でのそれと同じく、糸を引くような軌道を描いて、作蔵のミットに吸い込まれ、室内練習場に乾いた音をこだまさせた。
総理達が歓声を上げ、栗田ら三人は、驚きの声を上げた。
「栗やん、スピードガンや! 仙ちゃん、ビデオ用意してくれ」
目を覚ましたかのように黒田が叫び、自ら上着を脱いで作蔵に走りより、アンパイアの位置に立った。佐野がドアを跳ね開けて飛び出して行き、栗田は練習場の隅に置いてあったロッカーから、小さなメガホンのような機械を取り出して、中腰に構えた。
「ケンちゃん、と呼べばええんか? もう一球投げてくれ」
黒田は栗田が用意を終えるのを待って、ケンちゃんに声をかけた。ケンちゃんはしっかりと頷き、再び作蔵のミット目掛けて直球を投げ込んだ。
「栗やん、どうや」
黒田が叫んだ。
「ひゃ、ひゃ、ひゃくごじゅうななです。部長」
「ケンちゃん、もういっちょ」
「百五十六」
「百五十七」
「百五十八……」
壁際に立つ総理達は既にお祭り騒ぎであった。
「ケンちゃん、ちょっとまだ固いぞ。深呼吸せえ」
作蔵がケンちゃんにボールを返しながら言った。ケンちゃんは頷いて、作蔵からのボールを受け取ると、グラブとボールを足元に置き、Fresh Fight For the Teamと書かれたハッピを脱いだ。
そして、大きく両手を広げて深呼吸した後、もう一度振りかぶった。先ほどより室内の温度が上昇したように感じられる空気の中、モーションに入ったケンちゃんの、作業ズボンの擦れる音がかすかに聞え、そして一瞬の後、あの風切り音がやってきた。
「く、栗やん……」
「部長……百六十一です……」
室内練習場には歓声が巻き起こり、黒田と栗田はなぜか、顔を見合わせて、大声で笑い出した
「クリよ、驚くんはまだ早いで」
そう言って作蔵はケンちゃんの手を引くと、ネットに囲まれたバッティングケージにケンちゃんを連れて行き、そして自分はピッチングマシンの横に立って、スイッチを入れた。
――ぶうううううん
と低く唸る音が聞え、ケンちゃんは静かにケージに立てかけられていたマスコットバットを手にした。
「行くど」
作蔵は右手にボールを掲げて、ケンちゃんに見せると、静かに回転する二つのローラーの間へとボールを転がした。
しっかりと振りぬいたケンちゃんの打球は、室内練習場を二つに大きく仕切っているグリーンのネットに、今にも突き破らんかという勢いで突き刺さった。作蔵が続けてピッチングマシンからボールを放つ度にネットが大きく揺れて、そこにいた全員が、まるで室内練習場自体が揺れているかのような錯覚に陥った。
「信じられん……何が起こっとるんや……」
黒田が呟いた時、室内練習場の扉が開いて、佐野が三脚とビデオを持って入ってきた。そして入口の方を振り返って誰かを手招きしている。
開いた扉の向こうから明るい光が差して来て、まるで後光の中を歩んで来たような、その男の姿がはっきり映し出されると、ケンちゃんは感激のあまり気を失って、その場に倒れ込んだ。
阪神タイガース監督岡田彰布は、マスコットバットを抱えたまま、泡を吹いているゴボウのような男を見て、一言だけ言った。
「そらそうよ」
監督さんも、偉いさんも、とにかくドラフト会議
阪神タイガース球団事務所の会議室は異様な緊張感に包まれていた。長い球団の歴史の中でも、ドラフト会議の一週間前になって新たな選手を獲得検討することなどありえなかったし、そして、その選手がなんといってもホームレスなのである。
ケンちゃんは気を失ったまま、アンちゃんに担がれて球場内の救護所に運ばれた。傍にはゴリさんが付き添った。
総理を始めとする面々は応接室で待つように言われたが、豪華なソファーを汚してしまうのが怖くて、総理も、アンちゃんも、バルやんも、タケ坊までもが床に腰を下ろした。
一方、会議室にいるのは岡田監督、黒田編成部長、佐野西日本統括スカウト、栗田投手スカウト、そして中島作蔵の五名である。オフホワイトの長机を囲むように座った男達のそれぞれの表情を、蛍光灯の人工的な光が青白く浮かび上がらせていた。
「神様って言われて、そうそう信じるわけにはいかないが、それでもあのボールを見ると信じないわけには……」
既に山積みになった吸殻の隙間を探すように、栗田は煙草を灰皿に突き刺した。佐野はドラフト指名予定選手のプロフィールが書かれた紙の綴りをせわしなくめくっている。黒田と岡田監督は二人とも全く同じポーズで腕組みをし、両目を閉じていた。寝ているのか、考えを巡らせているのかはわからない。
会議室に重くのしかかる空気は、そんな彼らの姿を凝固させるかのように、部屋中に淀んでいる。
「ちょっとしゃべらせてもうてもええですか」
作蔵の言葉に、黒田の瞼がぴくりと動き、岡田監督の腕組みしていた左手の小指が少し立った「私事で申し訳ないんですが、少し聞いてやって下さい。栗田君はご存知と思いますが、私の息子は生まれつき、心臓の畸形による障害を持っておるんです。命にかかわるもんでは無いんですが、他の子供たちのように、野ッ原駆け回ったり、野球をしたりってことは出来ません」
作蔵はその大きな肩を丸めて、訥々と話した。
「そんな息子に私は『夢を持て』って言葉をかけてやることが、今まで出来ませんでした。ところが、あのしょぼくれたホームレスは、今、息子に夢を見せてくれてるんですわ。神さんがどーのこーの、私には関係ありません。ただあのケンちゃんの姿に、私の息子や、他のホームレスの連中がキラキラ目を輝かしとるんですわ」
そこまで言って、作蔵は出されたお茶に初めて口をつけた。
「無茶なこと、常識外れやってこと、十分承知しております。ただ、一人のアホな父親として、息子の夢を叶えてやりたいと思っとります。よろしくお願いします」
作蔵は、その大きな身体を折り曲げて、額を会議室のテーブルに押し付けた。
永遠に続くかのような沈黙が流れていた。壁に掛けられている楕円形の電波時計が、秒針を刻んでいる音すら聞えてきそうだった。窓の無い会議室では、表の宵闇も風の鳴き声も感じることは出来なかった。
腕組みを解かず、目も開かず、やがてゆっくりと黒田編成部長がその沈黙を破った。
「プロ野球のチームとして、年齢がどうの、生い立ちがどうの、そんな事は関係なく、そこにプロとして十分な力を持った選手がいれば、獲得に動くのは当然のことや。なあ、監督」
岡田監督も微動だにせず、言った。
「そらそうよ」
「プロ野球選手は夢を与える仕事。その選手の姿が見る者に夢を与えることが出来るんなら、その選手はプロになるべき、プロ野球選手の道を『道一筋』に生きるべきですわな」
「そらそうよ」
岡田監督がそう発すると、会議室は信じられないほどの幸福な空気に満たされた。
「事情が事情ですから、今から社長とオーナーに電話を入れます。よろしいですね、監督」
「そらそうよ」
黒田は頷いて、会議室を出た。岡田も立ち上がり、作蔵の肩をぽんぽんと二つ叩いて、その後を追った。佐野が作蔵に微笑みかけてから後に続き、会議室には作蔵と栗田の二人が残った
お互い積もる話が山ほどあるはずの二人は、結局一言も発せず、会議室の中には紫煙が途切れなく漂い続けるだけだった。
一時間ほど経過した頃、黒田が佐野と共に戻って来た。
「中島さん、あなたケンちゃんの身元保証人になれますか」
作蔵は頷いた。
「さすがにホームレスはまずい。彼をあなたの会社の社員にすることは出来ますか」
作蔵が頷いた。栗田も頷いた。黒田は椅子に座ると、背筋を伸ばし、まっすぐに作蔵の目を見て言った。
「私共阪神タイガースは、御社のケンちゃんを来るドラフト会議で獲得希望選手とさせて頂きたいと考えております。つきましてはご満足頂ける条件を検討しておりますので、指名の暁にはぜひとも、入団へ向けてご協力頂けますよう、お願い申し上げます」
作蔵も背筋を伸ばし、身体を前に傾けて粛々と諳んじた。
「過分な評価を頂き、ありがたく存じます。つつがなくご指名の時が迎えられることを、心よりお待ち申し上げます」
それはかつて彼方の昔、作蔵の父が元気だった頃、酔っぱらって口にした言葉だった。作蔵がプロ野球選手になることを心から望んでいた彼の父は、指名挨拶に来た球団関係者への返答を既に考えていたのだった。少しだけ運命が違えば、作蔵の青春を締めくくるはずだった言葉二十五年の時を経て、今度は息子の夢を叶える為に蘇ったその言葉。そして、作蔵にとってもケンちゃんは夢の続きであるのかも知れなかった。
黒田が立ち上がり、作蔵が立ち上がった。お互いの右手を会議室の机の上でしっかりと握り合い、傍らの栗田と佐野が小さな拍手をした時、医務室のベッドでケンちゃんが大きなくしゃみをした。
◇
次の日、大阪梅田の阪神電鉄本社、役員室が居並ぶフロアのカーペットが敷かれた廊下を、黒田編成部長と栗田スカウトの二人が緊張の面持ちで歩いていた。昨日、電話で内容は説明し内諾を得ていたとは言え、翌日に来参しての事情説明を命じられていた黒田は、
「クリやん、お前も道連れや」
と言って、恐ろしく緊張を強いられるであろう、御前報告に栗田を同行させていたのだった「球団の黒田です。よろしくお願いいたします」
かつて世間を騒がせたファンドによる阪神電鉄の買収工作。手塚前オーナーが一連の責任を取って電鉄会長職を辞した後、代わって会長に就任した坂井信也は、慣例に従えば球団のオーナー職にも就くはずであった。しかしながら買収対抗策としての阪急との合併に纏わる諸事情によって、生粋の阪神ファンであったにもかかわらず、坂井はオーナー職に就くことが出来なかった。やがて騒動も終結し、合併後の人事も落ち着いて、坂井が晴れてオーナー職に就任することが出来たのは、騒動から更に二年が経過した後のことだった。阪神タイガースの球団史上、最もオーナー職に就任することを渇望していたオーナーと言える人物こそが、彼ら二人が今から会おうとしている、阪急阪神ホールディングス代表取締役、坂井信也その人であった
「しばらくお待ち下さい」
取次ぎの為に執務室へと立ち去った秘書は、非人道的にスタイルが良かった。空中に浮き上がっているかのような、その丸い尻を見ていると、栗田は持病の不整脈が出た。
「どうぞ、中でお待ちです」
わざわざ彼らに正対するところまで歩み寄ってきて、深々と頭を下げた秘書の、二つ外されたブラウスのボタンの隙間に目が釘付けになった栗田は、黒田が携帯しているであろう、救心を二粒貰おうかと思った。
「失礼致します」
二人声を揃えて入った執務室の中央に置かれた黒革のソファーには、坂井ではなく、南信男球団社長が座っていた。
贅沢に切り取られた大きな窓からは大阪湾を囲むように広がる大阪の町並みが一望でき、部屋の中には蛍光灯の明りを凌駕する太陽の暖かい日差しが降り注いでいた。
直立不動で立ち尽くす二人に、南社長が口の端に笑みを浮かべて、ソファーに座るように促した。小さく頭を下げて、黒田がソファーに座り、彼が座り終えるのを待って栗田が続いた 触れると切れそうな緊張感の張り詰める室内に、突然朗々と張りのある声が響いた。
「わしなあ、タイガース子供の会に入っとったんや」
窓の方に背を向ける形で座っていた黒田と栗田は、声のした方向に振り返らなければならなかった。そこには、背中の腰の部分に両手を置いて軽く握り、凛とした姿勢で佇む坂井オーナーが、白く輝く窓の向こうに視線を送っていた。
「池田の落球も、江夏と田淵の放出も、純金ノムさん人形も、全部わしにとっては、阪神タイガースの思い出や」
オーナーの肩の向こうには、浪花の摩天楼が聳え立ち、さらに彼方では臨海工業地帯の煙突から立ち上る白い煙が、渺々と広がる空にアクセントを付けているのが見えた。
「こうしてこの窓から見とったらな、汗水垂らして働いてるお父ちゃんや、晩御飯の支度しとるお母ちゃん、塾の帰りにハンバーガーにかぶりついとる子供ら、そう、この街に住んでる人みんながみんな、阪神を愛してくれてる言うんを、ひしひしとこの身体に感じるんや。そういう人達に愛される選手やないとアカンで」
黒田は胸が一杯になった。栗田の脳裏から秘書の丸い尻が完全に消えた。
「ホームレス出身ってことで、マスコミも色々うるさくなるやろう。
黒さん、クリやん、そのケンちゃんとやらを、ファンの人たちの夢を、しっかり守ってあげなさい」
窓の外を見つめ続けながら、そう言った坂井オーナーの背中に、二人は深々と頭を下げた。しばらくそうした後、頭を上げた黒田と栗田に、南社長が菩薩のような優しい笑顔で微笑みかけ、そして頷いた。
◇
池田奈津子は新高輪プリンスホテルで行われるドラフト会議会場に用意された記者席で、一見するとスポーツ新聞の記者には見えない映画女優のような横顔に真剣な眼差しを湛えながら、本社に送信する記事をノートパソコンのキーボードに打ち込んでいた。デイリースポーツに入社し、芸能面の担当を四年勤めた後に、念願の虎番記者となってから、更に三年が経過していた。ドラフト会議を担当するのは今回が初めてである。先輩の名物ヤンキー記者、松下からは、
「今年は、一巡目の抽選が終わったら、そんな劇的な展開はねえよ」
と言われていたが、それでも初めて吸い込んだドラフトの空気に圧倒されそうになる自分を池田は何度も叱咤奮励させなくてはならなかった。
自分の担当する阪神タイガースは三巡目まで予定していた選手をことごとく抽選で外していて四巡目が終わった後の休憩時間に行われた囲み取材の時、明らかに岡田監督の表情には不満が見て取れた。
自らの取材によると、球団の本指名は今告げられた五巡目の選手で終了の予定になっておりあとは育成選手を残すのみの筈だった。
ところが、五巡目最後の日本ハムが指名を終えても、阪神タイガースの丸テーブルからは誰も席を立とうとしなかった。池田は他社の記者に目を巡らせたが、他には誰も異変を感じている様子はない。六巡目に名前が挙がるのを他社は掴んでいるのか、それともただ単に誰も気付いていないだけなのか、池田はじっとりと手に汗がにじんで来るのを感じ、右手の薬指に嵌めていた指輪をそっと外した。
オリックスが大卒の無名内野手を指名し、かすかに会場がどよめいた後、いよいよ阪神の番がやってきた。
「選択希望選手、阪神」
この声を聞いた記者席が僅かにざわついた。そのざわつきを感じて、池田の緊張はほんの少しだけ弛緩した。
記者席のざわつきが伝播したかのように、本部席も慌しさを見せた。司会者が焦ったように周囲に向けて、手にした書類の確認を求めている。通常のドラフト会議ではありえない沈黙が訪れた。やがて、正面に向き直った司会者が咳払いをひとつした。
「失礼致しました。ええ、阪神、選択希望選手」
ここでもまた少し間が空いた。会場に言い様の無い緊張感が広がった。
「飛田謙吉 四十歳 投手 中島鉄工所」
どよめきという言葉の見本といえるような声と空気が会場に発生し、やがて記者席から怒号が飛んだ。何人かの記者が会場の外に走り出して行き、あちこちで慌しくキーボードを叩く音が響いた。騒然とする会場の中でただ一人、池田だけがお互いに握手を交わす、岡田監督と南社長と黒田編成部長の姿を見つめていた。
会議を進行する司会者の、福岡ソフトバンクの指名選手を告げる声を聞いて、ようやく我に返った池田は、USBスロットにモデムを差込み、猛然とキーボードを叩いた。しかし、自社のデータベースからは何一つ情報を得ることは出来ず、「飛田」「謙吉」「中島鉄工所」どの検索ワードを打ち込んでもヒットすることはなかった。
あきらめた池田は立ち上がり、囲み取材を行う会場外のロビーに向かった。
「なっちゃん、何か知ってんのか?」
会場の出口で他社の顔見知りの記者が話しかけてきたが、池田は小さくかぶりを振ることしか出来なかった。
ほどなくして南社長がロビーに登場し、大勢の記者が雲霞のように群がったが、南は足を止めずに、
「詳しいことは黒田に聞いて下さい」
とだけ、笑顔で言い残して立ち去った。
続けて出てきた岡田監督も囲み取材には応じず、ようやく池田の放った、
「指名したということは、四十歳という年齢を考慮しても、戦力として期待されていると言うことですか」
という問いに、
「そらそうよ」
と答えただけだった。
岡田監督が立ち去ってから約五分後、象牙色のキャンバスが張られた両開きの扉を押し開けて黒田編成部長が姿を見せた時、最後の取材対象を逃がすまいとする記者達が、我先にと出口へ殺到した。他球団の番記者の姿も数多く見えた。
「ええ、飛田選手に関しては、今日のところはあまりお話出来ることはありません。おいおい皆さんのご存知となるところだと考えております。そうです、もちろん戦力としての指名ですそれには色々事情がございまして。申し訳ございません。お話出来る時が来ましたらお話しします。中島鉄工所の場所? それは勘弁してください。はい、ではこの辺で」
立ち去ろうとする黒田の進路を塞ぎながら、矢継ぎ早に記者の質問が飛んだが、結局黒田は貝になり、誰一人として情報らしき情報を得ることは出来なかった。
その日からマスコミ各社の中島鉄工所探しが始まったが、全国に同名の鉄工所は山ほどありまた阿倍野区にある、野球チームすら持たない従業員二名の作蔵の会社は、どのマスコミからも電話一本入ることがなかった。
(後半へつづく)
神様がくれた背番号(前半部掲載)
タイガースに入団するこのあとケンちゃんはどうなっていくのか?
笑いあり、涙あり、阪神タイガースの面々と愉快なホームレスの仲間達と繰り広げられる仰天の数々のエピソードと、そして大感動のラストがあなたをお待ちしています。
続きはお手数ですが書籍版のご購入をお願いいたします。
なお、8月1日よりiPhone,iPad等で閲覧いただける電子書籍アプリ『神様がくれた背番号|松浦儀実』通常料金¥1100(キャンペーン期間中の10月末迄は500)をリリースいたしますので、是非こちらの方もお立ち寄りください。
■目次
「人間の及ぶことと及ばないこと、そして奇跡」*
「神様がやってきた、ヤア、ヤア、ヤア」*
「夢か現実か、始まりの始まり」*
「動き始めた夢、仲間たちは本気だ」*
「総理の目論見、そしてパパの正体!」*
「思い立ったが吉日、いざ甲子園」*
「入団テスト、そして、あの男もやって来た!」*
「監督さんも、偉いさんも、とにかくドラフト会議」*
「神様がくれた背番号は何番? 憧れの選手もやって来た」
「別れの夜、それは旅立ちの夜。だから泣くな」
「いよいよ、年が明けた。ケンちゃんは阪神の選手」
「鉄腕強打、鍛えるここは鳴尾浜」
「仲間が集まって、はじまりの足音が聞こえてきた」
「奇跡の始まり、ケンちゃんお立ち台に立つ!」
「久々の天王寺、まさかのタイガース御一行様」
「ケンちゃんを守れ!」
「守るべきものと、守られるべきもの」
「最高の夏休み? 最悪の夏休み?」
「作蔵の勇気、タケ坊の戦い」
「旅立ちの日に」
「神様がくれた背番号」
こちらのサイトでは*部分の章をお読みいただくことができます。
■著者紹介
昭和41年生まれ。兵庫県三田市出身、淡路島育ち。大阪教育大学教育学部中退。阪神タイガースファン。2006年から2007年にかけて、著者ブログにて連載された本作が阪神ファンのハートを見事つかみ、堂々のデビュー作となった。
※星空文庫運営掲載承認済