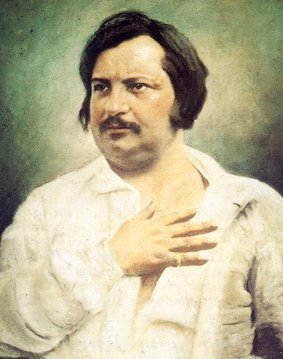支え合いの国
支え合いの国
我らが輝かしい自助と相互扶助の伝統を誇る「支え合いの国」が、確実に文明史を刷新するに違いない画期的で革命的な新薬を発表したのは、ほんの一年前のことだった。新薬「アンブロシア」には錠剤と飲み薬とスナック菓子型があり、そのどの形態でもいいので摂取すれば人間に必要な栄養は万遍なく過不足なく得ることができるのであった。カロリーを控えたい場合には錠剤タイプを二三錠水とともに飲み込めばよく、喉が渇いている場合には飲み薬タイプを飲めばよく、また腹が減ったときにはスナック菓子タイプを食べればよかった。とはいえ、空腹そのものに対しては胃の中で膨らんで胃酸が胃を傷つけないようにするための「まんぷく」という空腹薬が存在しており、日中不意に空腹症状に襲われたら、この粉末状の「まんぷく」一包を水で飲めば良かった。「アンブロシア」と「まんぷく」という二大発明のお陰で、人類は飢餓と肥満という両極端な食にまつわる宿痾からいよいよ解放されたのであった。もはや人類は食事を必要としないのである。食事、という行為を敢えて行うのは、いつの時代にも必ずいるあの鼻持ちならない洒落た文化人気取りか、あるいは食事を未だにカッコいいと思っている田中康介のような社会の底辺を生きるチンピラ同然の人間達だけであった。
田中康介は熊本県の田舎で生まれてからなんとか中学を卒業をできるまでずっとろくでもない不良として生きてきて、高校時代からもタバコ所持や飲料用アルコール所持のかどで何度も少年刑務所に出たり入ったりを繰り返しており、最後にカフェイン入り飲料使用罪で捕まってから刑務所から出てきたときにはもう30歳になってしまっていた。ところが出てきたばかりだというのに出所祝いの席で密輸入の低アルコールビールをあけて、チンピラ仲間とドンチャン騒ぎするのだから呆れたものである。田中康介の辞書には反省の二文字は無かった。これについては親も悪く、両親ともに健在であるくせに康介がどこからか持って帰ってくる東南アジア製の栄養ドリンク「リボンビダンD」(これには微量だがアルコールもカフェインも含まれている)を摂取してキメキメの状態で、昼間から「元気が出る!」などと言って野良稼ぎに精を出すのだから手がつけられない。その息子が、タバコ、酒、カフェインと一通り味を占めてしまうのは無理からぬことであった。もっとも、タバコに関しては、タバコの密売で儲ける多国籍犯罪組織を撲滅しようという運動が国際的に広まっているため、海外のヤクザにでもツテがない限り手に入らない状態だった。それゆえ最近はあの愛おしい紫煙とはすっかりご無沙汰で、もっぱら低アルコールビールと自家栽培の茶葉が康介達のパーティーのお供であった。
ニュースで「アンブロシア」開発成功の知らせを聞いた時、康介の父は、
「これは不味いことになるぞ」
と言ってニヤリとした。この言葉には二重の意味があるのである。つまり、自分たちの日々のささやかな楽しみである食事の機会が、食事の必要性を抹殺せしめる新薬の開発とともに段々と無駄な行為として批判され始め、ついには法律で禁止されてしまうであろう、という予感。それと、食事ができなくなるということは「美味い」と思うことがなくなるわけであり、結局「不味い」ことしかなくなってしまう、というわけだ。康介の父母は歳とってから康介を生んでいて、彼らが子供の頃は、大人達は徐々に弾圧されはじめてはいたけれど、まだタバコを吸っている人も珍しくなかったのだと言う。それより強烈なクスリ、それも幻覚が見えてくるほど強烈なクスリも、昔は色々とあったような気がするのだが、父親はついにそのクスリがどういうものだったかを思い出せないままである。もっとも康介は、そんな夢みたいな「クスリ」などあるはずがなく、おおかた父親が「リボD」のやり過ぎでボケを早めてしまったのだろう、と推測している。ともあれ、康介の親たちは、タバコや酒やカフェインが次々と違法化していったときのことを憶えているわけである。
「なら食いもんだけは禁止にならんように、反対運動しろや」
と康介は親達に言ったが、
「いやぁ、今は「まんぷく」もあるし、食べもん食べよったらなんか悪いことしとるみたいでね。食べなかったら、鳥も豚も牛も死なないし、良いことだらけやしねぇ。申し訳ない気持ちになるんよ」
などと母親は言う。全く、バカそのものだ。テレビや世間に簡単に流されてしまっていて、主体性というものがない。康介はいつも親の姿をみて、こういう人間にだけはなりたくない、と誓いながら生きてきたのだ。
「ババァ、てめぇ、そんなこと言ったらウチの畑だって一応米とか作ってんだから食いもん関係だろが。商売できなくなってもいいってのか?」
康介が怒鳴ると、
「実はねえ、もう畑も潮時かなって」
今度は康介が目を白黒させる番だった。
「畑で仕事してるのなんて、こんな田舎でももうウチくらいのもんだし。みんなどんどん公務員になっちゃって」
「そら、今の時代申請すりゃあ誰だって公務員にゃなれるけどよう、ババァてめえ「リボD」もう飲めなくなんだぞ」
「公務員になると、家にも巡回調査入るからねえ。でもそれも仕方ないかな、って。ねえお父さん?」
「うむ。収入は三倍以上んなるしな」
「クソジジイ&クソババアが……」
康介は拳を握って打ち震えた、しかしこんな老いぼれどもに拳を「食らわせて」やるのも勿体なかった。何しろ食うのが申し訳ないなどといっているのだから。
康介の家は農家であり、一応国から諸々の補助金が出ているとはいえ、「まんぷく」登場以後国民が食事への関心を失っていくスピードと言ったら凄まじく、どんどん作物の売れ行きは落ちていった。しかしながら、康介一家が既に述べたような違法な薬物にまみれて暮らしていられるのは、農家をやっているお陰でもあるのだ。一応田中家の農家は国営の範疇に含まれないので、田中家には公務員や行政受託企業が必ず受けさせられる抜き打ちの巡回調査がやってこないのである。つまり、違法薬物の所持や使用がバレる確率がかなり低く、やりたい放題なのだ。最近は警察官の事業も多国籍企業へと民間委託で行われていて、効率化が進んでいる。圧倒的に犯罪件数の多い都市部に警察は密集していて、田舎は地域全体で二、三人の警官が交代で見回る程度であった。警官たちは、一件手柄を立てる度にいくら、という厳格な成果主義で組織されていたので、それももっともなことであった(そんな田舎の手薄な警官たちに何で康介が何度も逮捕されたのかというと、誰かに薬物所持を通報されたからである。康介には人望が全くなかった)。ちなみにわれらが「支え合いの国」は、警察官や看護師や介護師などの仕事は同じ多国籍企業グループの子会社が請け負っていて、その道のプロの外国人達によるきめ細やかなサービスを実現している一方で、国民の90パーセント以上が公務員であった。公務員は志願すれば誰でもなることができ、国も国民がどんどん公務員になるのを推奨していた。現政権のマニフェストは、一億総公務員化社会、であった。民間に留まろうとしているのは、そのほとんどが一人だけ抜け駆けして外資系企業で働いて高級を得ようとしたり、あるいはベンチャー企業でギャンブル的に設けようなどと考えるような輩ばかりであり、「支え合いの国」の理念に照らせば当然のことだが、そういう者たちは性根のさもしさから倫理的に批判されているのだ。先ほども言ったとおり、康介たちの家も農家とは言え一応民間の範疇に含まれるがゆえに、両親たちが世間の冷たい目を恐れて公務員になりたがるのも無理からぬことであった。
それから十年の間、康介は家を出て放浪の旅をすることにした。彼は日に日に「反食事」の波が吹き荒れる世論を各県のテレビ情報で聞きながらも、全国津々浦々の名産品を食べ歩く日々を送った。康介はなるべく田舎の土地を回ることにしていた。なぜなら、田舎には食文化で身を立ててきた者たちが多く、「反・反食事」の姿勢を全く隠そうとしない康介に対して存外に親切にしてくれるものが沢山いたからだ。その内、誰が呼び出したのか知らないが、「最後の食通」とまで呼ばれるようになったのであるから人生どうなるかわからないものである。十年の旅を終えて、康介は口腔の中に今もよみがえる色とりどりの味覚をうっとりしながら思い出していた。真っ先に思い出すのは全国各地で食べ比べした牡蠣の味である。四国に行ったときなど、海女が獲ってきた牡蠣を生で食したこともある。康介は、この世で一番うまい食べ物は牡蠣であると断言してはばからなかった。もちろん地鶏を飼育しているオヤジ連中からは嘲笑まじりに反論されたし、京都で茄子を栽培している青年からは茄子の漬物が乗った茶漬けを振舞われたほどであったが、しかし従来ならそこで修復しようもない論争状態に陥るはずの彼らが、食の排斥運動に対する危機意識、あるいはこういってよければレジスタンスとしての一体感からか、各地の名産品自慢をして論争をすればするほど、何か不思議な連帯感をむしろ強固にしてゆくのであった。
康介が旅して回っていた十年のうちに、かろうじて法律までは成立しなかったものの、世論は食事撲滅一色と言っていいくらいだった。「アンブロシア」と「まんぷく」のコンビはそれほどまでに強烈だったのだ。しかしながら、依然として食事の大切さを訴えかける人たちは存在した。好事家たちである。今日この日、いよいよオールナイト放送の討論番組で、食事撲滅派と食事擁護派が最終論争を行うことになっていたのである。
康介は、じっとモニターを見つめていた。時刻は深夜丁度零時である。
「さあ今月もこの時間がやってまいりました」
有名なテレビジャーナリストが司会進行をしている。パネリストがテンポ良く紹介されていく様は、さすがにベテランという感じだ。この司会者は、実はもう百歳を超えている。時代の先端医療や栄養学の成果のおかげで、今は百二十歳の老人も珍しくはない。百歳などはまだまだ現役の境なのだ。
老人の隣に座る女子アナウンサーが導入を述べる。
「昨今、食の問題をめぐって世論が大きく転換しようとしています。食は、古来より人類になくてはならないものでした。しかし、新薬「アンブロシア」の開発や、「まんぷく」の定着によって、いよいよ人類は空腹や食べ過ぎから自由になろうとしています。私たちは今後、食やその文化に対してどのように向きあって行けばいいのでしょうか。ご覧ください、当番組のアンケート調査によりますと、食事は生活に必要だと思いますか? との質問に対して、「必要ない」と答えた人が78%、「必要だ」または「わからない」と答えた人が22%で、大半の人がもはや食事は必要ないと考えていることがわかります」
一ヶ月位まえから新聞でも似たような調査が行われていて、似たような結果が出ていたことは康介も知っていた。
続いて、街頭インタビューの様子がモニターに映し出された。
「いやあ、飯食うのって、めんどくさいですよね。時間かかるし」二十台のフリーター男性。
「食事のたびに仕事を中断させられるのは、結構効率が悪いんです」四十台のサラリーマン男性。
「新薬? いいんじゃないですか。毎日料理する手間も省けるし(笑)」五十台主婦の女性。
「まぁ……自分的には美味しい御飯は食べたいですけど、食べる必要ないって人にとってはいいんじゃないですかね。美味しいレストランだけ残ってくれればいいんじゃないでしょうか」二十台女性。スーツを着ている。
「仕事の付き合いで食事会とかに呼ばれてたじゃないですか、今までは。そういうのが全然なくなって、私は食事なくなったの、すごくいいことだと思います」三十台女性。夫と思しき男性と連れ立っている。
「食事はねえ、服や体に匂いがつくし、今は「アンブロシア」と「まんぷく」を飲んでたほうが健康だし長生きできるんでしょ。全くメリットがないですよね。食事に誘ってくる人は本当に迷惑。一人で食べてろ、って言いたい。あとね、料理は火使うでしょ? 火事が心配なんですよ、ウチなんかマンションだから。ほんとね、法律できちっと制限してほしいですよね」これは四十歳前後の女性。まだ小さな子どもを二人連れている。
画面は再び収録スタジオへと戻る。
「御覧頂きましたように、現在多くの方々が、食事というものが本当に必要なのかどうかを見直され始めています。こちらの別の調査では」と言って女性アナウンサーは新しいフリップを取り出す。「どれくらいの頻度で食事をしていますか? という質問に対して、現在、すでに食事をしていない、という人が54%、週に一回以上食べる、という人が27%、毎日食べている、という人はなんと10%にまで減っています。また、食事を何らかの法律で規制するべきだと思いますか? という質問に対しては、完全に禁止するべきだ、が12%、部分的に規制すべきだ、が40%、規制はしなくてよいがマナーを守るべきだ、が31%、今まで通りでよいと思う、は8%となっております」
各調査結果のうち、読み上げられなかったのこりの割合の人々は「その他」の人である。
「皆さんのご意見をまとめたのが、こちらになります」
いつのまにか、司会者と女性アナウンサーの後ろに大き目のフリップが運ばれてきていた。
「食事を禁止または規制すべきだ、と答えたかたの理由は、まず、1、食事には時間がかかる。2、食事は不健康である。3、食事に誘われて拘束されるのが迷惑である。4、食事は服や体に匂いがついてしまう、また、食べ物の匂いは他人の胃を刺激して胃痛をもたらすので迷惑である。5、食事のための料理は火を使うので危険である。以上の五つが、主要な理由となっています。この五つの論点を中心にして、最初は皆さんにお話しを伺っていければと思うのですが……」
「あたしはね、食事はもう時代遅れだと思いますよ」よっぽど言いたいことがたまっていたのか、恐らくは彼も百歳を超えているであろう老人が言下に口角泡を飛ばし始めた。「そこのボードにも書いてあることもですね、やっぱり食事がダメなことの証拠だと思いますしですね、あたしは何よりも思うのはね、食事は汚い! なんと言っても汚いですよ。あたしらなんかはね、子供の頃から飯を食って生きてきましたけどね、料理のために買い物にスーパーマーケット、スーパーマーケットっていうのが昔はあってですね、これは今で言うドラッグストアに、まあ野菜やら肉やらの食料品が一緒に売ってあるような、そういう店なんですけどね、コンビニの食品の棚が大きくなった店だと思ってもらえばよろしい。そこに親に手を引っ張られて買い物にいくとですね、魚の死体の山ですよ。これが本当に気味が悪いし、こんなものをまかりまちがって子どもがそのまま口に入れようもんならね、これは大問題ですよ。こんな社会は、やっぱり野蛮だったですね。しかもですね、食べ物が汚いっちゅうだけならまだいい。まだいいとする。しかしね、食べ物は排泄物になるんですよ。これが本当に汚い。汚いだけじゃない。これはね、色々な悪い菌の温床になりましてね、排泄物が手についたまま、その手でまた別の食べ物を食べたりするとですね、消化器が病気になったりですね、熱を出したり、嘔吐したり、もう大変だったですね。これはね、食べ物が人間の体を通って排泄されるとね、毒になる、ちゅうことなんでね、これを昔は食中毒、って言ってたもんです。つまりね、食べ物っていうのはね、毒なんですよ。そーんなねぇ、悪いものをねえ、文化だ伝統だなんていって子どもに食わせるのはね、こりゃ野蛮だしね、犯罪です。犯罪ですよこれは」
「何を言ってんですか。テレビの前でウソをつくのはおやめなさい」今度は対面の側に座っている、こちらは六十歳くらいのまだ背筋の伸びた中年の紳士が、顔を赤くして反論をし始めた。「あんたねえ、食べ物を汚い汚い言いますけどね、この地球で食べ物を食べない生き物は人間くらいのもんですよ。あんたねえ、食べ物を食べる、という行為はですね、極めて自然な行為であって、何にも間違ってはいないんです。あんたは知らないだろうけど、排泄物だってね、昔の人の農法の本を見るとわかるけど、作物をまた育てるために使われてたんですよ。排泄物が毒だなんて、これほど無知蒙昧きわまる考え方はない! もう笑っちゃいますよ。あんたね、排泄物は栄養なんです。命をはぐくむんです。そういう循環の中で、人類は歴史を作ってきたんです。それをですね、急に自然に逆らって突然やめたりしたら、必ずしっぺ返しが来るよ。間違いないよ」
「しかしですね、科学的にはあらゆる研究の結果がしっぺ返しの可能性をほぼゼロだと結論付けているのです」今度は百歳の老人の隣に座った、四十台くらいの、わざわざ白衣を着せられて登壇した科学者が微笑さえ浮かべながら言った。「米国では、「まんぷく」にも用いられているFILという薬品が発明された時に、不食――文字通り何も食べない生活スタイルのことを指しますが――の研究はいち早くスタートしまして、過去三十年間で、食べ物を一切食べない生活をした人と、従来どおり一日三食食べ続けた人の健康を比較調査しています。結果、三十年間の間に病気で亡くなった人の割合は、不食の人に比べて、食事を続けた人たちはなんと三倍にも上ります。また、これらの調査結果を精査した結果、昔の人たちのような一日二から三食を食べる生活を続けていると、長くても平均寿命が九十歳で留まるのに対し、生まれてからずっと不食で続けた人の平均寿命は百四十歳を超えるだろうと目されています」
スタジオが少なからずざわついた。百四十という数字はそれほどまでに大きな意味を持っているのである。なぜなら、近代的な官僚制度以降の人類史における長寿の最長記録が百四十歳だったからである。科学者の説によれば、平均寿命がそれを超えるというのだ。ということは、当然のことながら百五十歳、百六十歳まで生きる人間が出てきたとしても不思議ではない。否、二百歳を超える、もはや超人といっても良い者も現れるかもしれないのだ。彼の言葉は、人類が間違いなく新しいステージに到達したことを「支え合いの国」中に知らしめていた。
「そんな夢みたいな話があるか! デマですよデマ! 科学だ何だと言ったって、俺は認めないぞ! 皆さん、こんな口先だけの人間にだまされちゃあいけません」
先ほどの食事擁護派の紳士が言った。
「あんたの言い分は何の反論にもなってない。人格攻撃じゃないか」
百歳の撲滅派が呆れつつ言った。科学者はめがねの位置を直して微笑している。
「今度は別の方面から食事を廃止する理由を述べましょうか」また科学者が話し始めた。「食事を擁護したい人たちの論理に、味覚の楽しさ、というものがあります。味覚は娯楽だ、芸術だ、と言う訳ですね。確かに、美味しい食べ物を食べている人たちの脳を検査してみると、快感を司る部位が活発化していることが科学的に検証できます。しかし、だからといって味覚はやっぱり良い物なのかというと、決してそうではありません。なぜなら、人間は味覚の快感に溺れて依存するからです。昔の食品企業の資料を調べていますと、昔の人間たちも食事にある種の制限を試みたことがあるようで、たとえば肉は美味しいけれど食べすぎはよくなく、むしろ野菜を沢山食べることを推奨すべし、という流行があったようです。しかし、肉食を好む人たちは簡単には食生活を変えませんでした。昼も夜も肉を食い、野菜は肉に少量添えてあるものを食べるくらい。頭では、肉食は体に悪く、野菜を食べるべきなのだ、とわかっていながら、肉食をやめられないのです。これは、肉を食べるときに感じる味覚が、ある種の依存症を生み出しているからだと考えられるのです」
今度は先ほどの明るい調査結果が発表されたときとは真逆のざわめきが、周囲で起こった。
「依存症!?」「やっぱり食事は危ない!」「ウソだ! 依存症なんてでたらめだ!」
この国では、依存症という言葉は最も忌み嫌われていた。「支え合いの国」の相互扶助の精神は自助あってのものである。自助なくして相互扶助もない。依存は決して相互扶助とは違うとして、区別されていたのである。そのため、「支え合いの国」では、依存症を引き起こすと国から認定された嗜好品や娯楽に対しては厳しく規制をせねばならない、と憲法で定められていた。タバコ、酒、カフェインが規制の対象になったのはもちろんのこと、パチンコ、競馬、競輪、競艇などの各種ギャンブルも禁止されたほか、宝くじやサッカーくじも禁止された。オンラインゲームも禁止されたし、携帯電話に娯楽用の機能を付けることも一切禁じられた。携帯電話でゲームをする者が絶えなかったからである。逆にテレビは一切禁止されなかった。テレビには全く危険性はないと国が判断したのだ。意外なところでは、服飾ブランドは規制の対象になった。ある種の若者が見境なくクレジットカードで買い物するからである。服を売る業者は、国の厳格な審査を通過せねばならず、審査をパスするために各服飾企業はどこも似たような服をしか売らなくなった。
「仮に依存症があったとしたら」食事擁護派の六十歳がまたも吼えた。「あんたらの大好きな「アンブロシア」だの「まんぷく」だのという薬が一番の依存のもとじゃないか! あんたたちね、食事の習慣がなくなったらだね、もうこの二つの薬なくしては生きられんのじゃないかね! それを依存と言わずしてなんと言うんだ! え! たかだか製薬会社に自分の人生、命を人質にとられて、それでどの口が自助だなんだと喋喋するんだ!」
この批判には一定の理があった。しかし、白衣の四十歳が冷静沈着に反駁した。
「いま製薬会社の話題が出ましたけれども、「アンブロシア」を出しているネクタールという会社と、「まんぷく」を出しているまんぷく製薬――この製薬会社は昔星野製薬という名前でしたが――は、近々「アンブロシア」と「まんぷく」の効能を同時に持つ薬を作り出すための合同企業を立ち上げることになっていて、その合同企業にはわが国の行政も参画し全面的にバックアップします。このことは一見、いま擁護派の方がおっしゃったように我々市民が製薬会社への依存を高めることを意味するかのように思えるかもしれませんが、しかしながら我々は、近い未来に提供されるであろう最先端の薬によって、愛すべき国家、この「支え合いの国」と一体化するわけです。今まで政治的無関心や、酷い場合には反国家の姿勢を隠そうとしなかったような若者たちも、こうなると国の行く末についてしっかりと目を見据えることが必要になってきます。国と国民が相互に離れることができなくなるが故に、ますます市民の意識は高まり、結果として犯罪も減り、政治に対する議論は活発になり、祖先にも恥じない国になるのではないでしょうか。そして、祖国への依存というものが、そこの人が仰るようにありうるとしても、私はそれを依存とは思いません。なぜなら、我々市民の一人ひとりは、国民の一人ひとりは、祖国の力によって立っているからです。そうであれば、我々が祖国の大きな力に頼るのはこれは当たり前のことであって、何ら恥じるべきことでもない。むしろ新しい医学、新しい科学の力によって、国家が国民の誰一人をも見捨てることのない、歴史上類を見ないほどに懐の深い誇るべき共同体が生まれつつあると言うべきなのではないでしょうか」
さすがにこの論理には無理があったのだが、もとより食事撲滅派が多数をしめる現在において、論理的な説得力の有無などは問題にはならず、スタジオも、そして恐らくは日本全国でテレビを前に熱中して議論を聞きこんでいる全国民たちのお茶の間も、激しい賛同の言葉と拍手で埋め尽くされたのであった。
「なんだ!」
突然、画面の脇のほうから悲鳴が聞こえてきた。ダークスーツを着た背の高い白人と黒人が、銃を持って闖入してきたのである。それを取り押さえようとした番組スタッフは、生まれて初めて生で聴く銃声に慄き、その場で尻餅をついてしまった。このような椿事を前にして番組スタッフは生放送を止めればいいのに、依然全国に映像が流れ続けているということは本当に奇妙なことであり、視聴者たちのうち知性の鋭い者の何人かは、ここに作為的なものを感じ取ったかもしれない。
「みなさん、落ち着いてください。私は食事について自分の意見を言いたいがためにやってきた者です。手荒な登場となってしまったことをお許しください」
両手を少しひろげて、どうどう、と動物たちをなだめるかのような身振りをしながらやってきたのは、なんと他ならぬ田中康介であった。珍しくスーツを着ているが、チンピラらしく派手なストライプの入った柄をしていた。用意周到なことに、彼のネクタイにはピンマイクが留めてあった。
「ここ、ここ。ここにテーブル頼むわ」
田中康介の指示に従ってダークスーツの外国人がさらに数人やってきたが、彼らは銃の変わりにロココ調の優美な椅子とテーブルを運んできた。田中康介は、大儀そうに椅子に座った。
「先ほど私は、自分の意見を言いたい、と申しましたが、正確には少し違います。私も先ほどまでの皆さんの議論を聞かせていただきましたが、食事のことが話題となっているはずなのに、そもそも皆さんは全く食事というものがどういうことなのかお分かりでない、という感想を抱いたのです。そこで私は、議論の大前提となる食事について、それが具体的にどういうものなのかをデモンストレーションして理解していただくために、登場したのであります」
田中康介にしてはきちんとした言葉遣いをしているものであるが、人生の半分近くを刑務所で過ごしていた彼は、元々の頭が不出来であったにしろ、潤沢な時間を利用して通俗小説などを差し入れしてもらい読みふけっていたので、言語が不自由なわけでは決してなかった。
「食事には色々な方法がありますし、色々な食べ物があるのですが、基本は一つ。自分が好きな方法で、好きなように好きなものを食べる、ということに尽きます。ところが、勝手気ままにやっていてもなかなかうまい食べ方を実践することはできない。その点昔の人はよく考えたもので、色々と食事の作法が発達しまして、その作法に従っていれば大体おいしく食べられる。ですが、私の考える食事は、なんというか、作法なき作法とでもいいますか、食事とはある種純粋なものでありまして、基本的には良い食材、それにあった調味料、水、そしてお皿があれば足りるのであります。たとえばここにですね――」
そう田中康介が言いかけて後ろに控えるダークスーツに目配せすると、何かを察した外国人は一つの皿を持ってきた。皿の上には赤い球体が乗っている。
「たとえばここにトマトがあります。御覧いただけますか? 皆さんはもはやご存知ない方も多いかもしれません。これはトマトというものです。野菜です。「アンブロシア」の発明によってもはや栄養としては存在価値を失ってしまったあの野菜というやつです。私は無学なので、ここでトマトについて歴史的に、あるいは文化的に含蓄のある解説を述べることはできませんが、トマトをおいしく食べることならできます。このトマトは私の実家のある熊本県で採れたものです。トマトといったら思い出すのは、祖母から伝え聞いた昔の話で、わが国も百年以上前の戦争の頃は食べ物が少なく、国民はみんな貧しい暮らしをしていたそうですね。そのころ、やはり貧しい家に生まれた少年たちが、農家の畑からトマトを盗んでひもじさを凌いでいたのだそうで、百姓たちの怒号を浴びながら逃げ延びた草っぱらでトマトを丸かじりすると、大変に甘く、涙が出たそうです。しかし、実際に私がトマトを食べて感じる味わいは、そんな甘さとは別のもので、生で丸かじりなどしたら口の中が酸っぱさと青臭さでいっぱいになり、とても涙が出るどころではありません。ところが、私が食ということについて探求するようになってから、昔の少年たちの味わったトマトの甘みを再現する方法を発見したのであります。先ほど私は、食事には食材にあった調味料があると良い、と述べましたが、調味料といっても大抵の場合塩だけで済みます。塩は万能で、どんな食材にも用いることが可能です。トマトだってそうです。まず、綺麗な水でトマトを洗います」
そういって田中康介が指を鳴らすと、外国人がたらいとペットボトルを持ってきた。ペットボトルには水が入っているようで、田中康介はそれをたらいの中にどぼどぼと入れ、トマトを洗い始めた。じゃぶじゃぶと威勢よく洗ううちに水はそのままスタジオの床に垂れ流されて、水溜りを作ってしまった。
「なんて非常識なんだ!」
そう叫んだのは食事撲滅派の列に並ぶ一人の男性だったが、
「いや、面白い、これ、面白い!」という司会者の老人がそれを抑えつけた。
「水は食事に関しては最も重要で、どんな料理であっても水を使います。だから、水が悪ければどんなに良い食材もダメになります。トマトを洗い終わったら、塩をこのようにつまんで、まぶします」
塩は皿の端に小さく盛ってあった。
「そして思い切りこれにかぶりつくのです」
いい終わったその口で、田中康介は歯茎を見せびらかしながらトマトを齧った。口の端から透明な汁が溢れ、顎から滴り落ち、自慢げな縦ストライプに染みを作ってしまったが、意に介している様子は全くない。ただ黙って咀嚼し、もぐもぐやったあと、ついには飲み込んだ。
「こうすると、トマトの甘さが口の中いっぱいに広がって幸福な気持ちになるのです。塩は辛い味を付与するものですが、そうすることによって食材の持つ甘さが引き立つのです。これは非常に基本的な塩の使い方で、甘みを持つ料理をするにあたっては、昔の人は最も気を使って塩を用いました」
一通り述べると、田中康介は食いかけのトマトを床に投げ捨てた。ピンク色の液体がびちゃりと音を立ててスタジオを汚してしまった。あまりの傍若無人ぶりに、その場にいた文化人達はもはやあきれてものも言えない様子だった。
「このように、自然そのものを収奪して食するだけでも、我々は食というものを楽しむことができます。この体験は他の何物にも換えがたい。確かに栄養価としては「アンブロシア」に比べて不完全でしょう。確かに、あの最高のサプリメントが与えてくれる健康は、このトマトにはない長寿をも与えてくれるかもしれません。ですが、その長寿が何ほどのものでしょうか? あなたがたはその伸びた命で何をするおつもりですか? サッカーの試合のロスタイムが異常に伸びたからといって、それがどうしたというのでしょう? 各ハーフを目一杯全力で戦ってこそ試合というものではないですかな? つまり、「アンブロシア」によって得られた時間などというものは、無時間的な時間なのですよ。それはあっという間に過ぎてしまうでしょう。あまりに平板すぎて、寿命が伸びたという実感がまるでないことでしょう。それは家畜の生命です。少なくとも私にとっては、生きるに値せず、ですよ」
とても快活な調子で笑顔たっぷりに田中康介が語るものだから、正に痛烈に批判されている当の食事不要論者達もつられて思わず笑みをこぼしてしまう有様だった。
「さて次はカキフライを食べてみましょう。カキフライは私がこの世で最も旨い食べ物だと思っている物です。もちろん、牡蠣愛好家達からは散々邪道だと批判されるのですがね。しかし、好きなものは好きなのだからしょうがない。ご存知かどうかわかりませんが、フライというのは食材を油で揚げたものです。ですから当然火を使います。火を使う、ということ自体が食事に対する批判の一論拠となっていたようですが、火の力は偉大ですよ。火は食べ物を消毒しますし、何より食べ物に生気を与えます。熱々の食べ物を食べる我々の体を暖めてくれます。我々は、燃えるような熱さのカキフライを口の中で転がしながら、汗すらかいて必死に食べるのです。サクっとした衣をやっとの思いで歯で割ると、中から濃厚な天然の牡蠣のスープが溢れ出てきます。これが旨い!」
絶叫するかのように大声を出して、唐突に田中康介は押し黙ってしまった。いつの間にか、黒服たちの手によってテレビ文化人達の卓上にもカキフライが運ばれていた。もちろん田中康介のテーブルにも湯気のたったカキフライが箸とともに置いてある。
「さあ、皆さん、食べてみてください。さあ。何? 食べたくない? 参ったな。もう食事をとるという行為のやり方までわすれてしまったのですか? では私がお手本をお見せしましょう。こうするのです」
そこに箸が置いてあるというのに、田中康介は手づかみでカキフライをとりあげ、口の中に放り込んだ。しばらくの間、顔を紅潮させてホクホクと舌を転がしていたようだったが、やがて咀嚼し始め、眦を垂らし、天国に上らんばかりの幸福のオーラを撒き散らしながら、ついに牡蠣を飲み込んでしまった。田中康介が食べ終わらないうちに、我慢できないといった様子で文化人達も見よう見まねでカキフライを食べ始めた。十年以上も全く食事をやめてしまっていた人間もいるので、食べ終わるのには時間がかかるようだった。みな、おおむね、子供のようにこの魅惑の揚げ物と格闘している。時には牡蠣の熱さに眉をしかめ、しかし牡蠣の旨みにまたすぐ顔をほころばせた。
「どうですか、皆さん? 旨いでしょう? そして思い出したでしょう? これが、時間、というものなのです」
時間。この言葉はカキフライを食べた者には今や特別の重みを持って受け止められた。確かにカキフライを食べて、止まっていた時間が動き出したかのように皆感じてしまったのだった。あの白衣の科学者でさえそうなのである。
「食事がひと段落ついたら、昔の人間達は一服しておりました」
「一服?」
周囲の人々には、一服の意味がわからないようだった。
「これです」
田中康介は小さな紙の箱を取り出した。箱には穴が開いていて、そこからさらに紙で巻かれた小さな筒が出てきた。
「煙草だ!」
まるで悪魔を見たかのように叫ぶ者がいた。然り、煙草であった。
「こうやって、火を点けます。この高等な人間的な文化の産物にも、やはり火が使われているのです」
田中康介はマッチをすった。趣にあふれる火薬の臭いが仄かに漂い、咥えた煙草の周囲を片手で覆うと、そこへマッチの火があてがわれた。先端に火が点くと、まだ燃えているマッチを田中康介は床へ投げ捨てた。そして、革靴の裏でゴシゴシともみ消したのであった。
彼は肺一杯に煙を吸い込んだようだった。とても満足そうなリラックスした顔をしていた。全身の緊張がほどけたようで、まるで彼の霊魂が身体の檻を解き放たれたかのようであった。
「この瞬間、私は一日の中で最も幸福を感じるのです。私は、煙草は一日に一本と決めております。それは普段夕食のあとに楽しみます。食事のあとの煙草は、まるで世界そのものを作り変えてくれるのです」
田中康介は、本当に美味しそうに煙草をのんだ。根元ギリギリまで吸うと、これを靴の裏に手で押し当てて火を消し、やはり床に投げ捨てた。もはや床はゴミだらけの様相を呈していた。しかしその場にいた誰もが、カキフライの快楽を味わったあと、既に煙草もまた時間を作り出す何か奇跡的な産物なのではないかと甘い疑いを抱き始めていた。
「これ、一本もらってもいいかな……?」
食事擁護派の論客がそう言いながら手を伸ばそうとした瞬間、田中康介の肉体が爆発した。論客の全身には血が降りかかった。床に撒き散らされたトマトやマッチや煙草に混じって、田中康介の臓物が散らばった。どれも血の色をしているので、トマトとなかなか区別がつきにくかった。文化人たちはそのうち数人が失神したし、そのうち数人は不用意に動いてしまい黒服たちに射撃されて死亡した。
結局、その一日の椿事はアメリカの食品業界の陰謀なのであった。食事という習慣は、分厚い利害関係者に守られて、今日もまた繰り返し人々の時間と金を奪っていくのだった。もちろん「アンブロシア」と「まんぷく」も、製造工場と研究所がもれなく爆破され、メトセラへの夢は夢に終わった。支え合いの国における体脂肪率30%以上の肥満者の割合は、先日6割を超えたばかりである。
支え合いの国