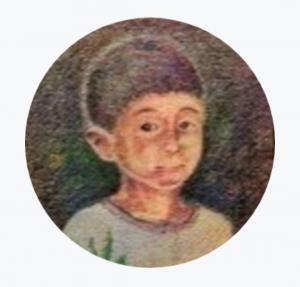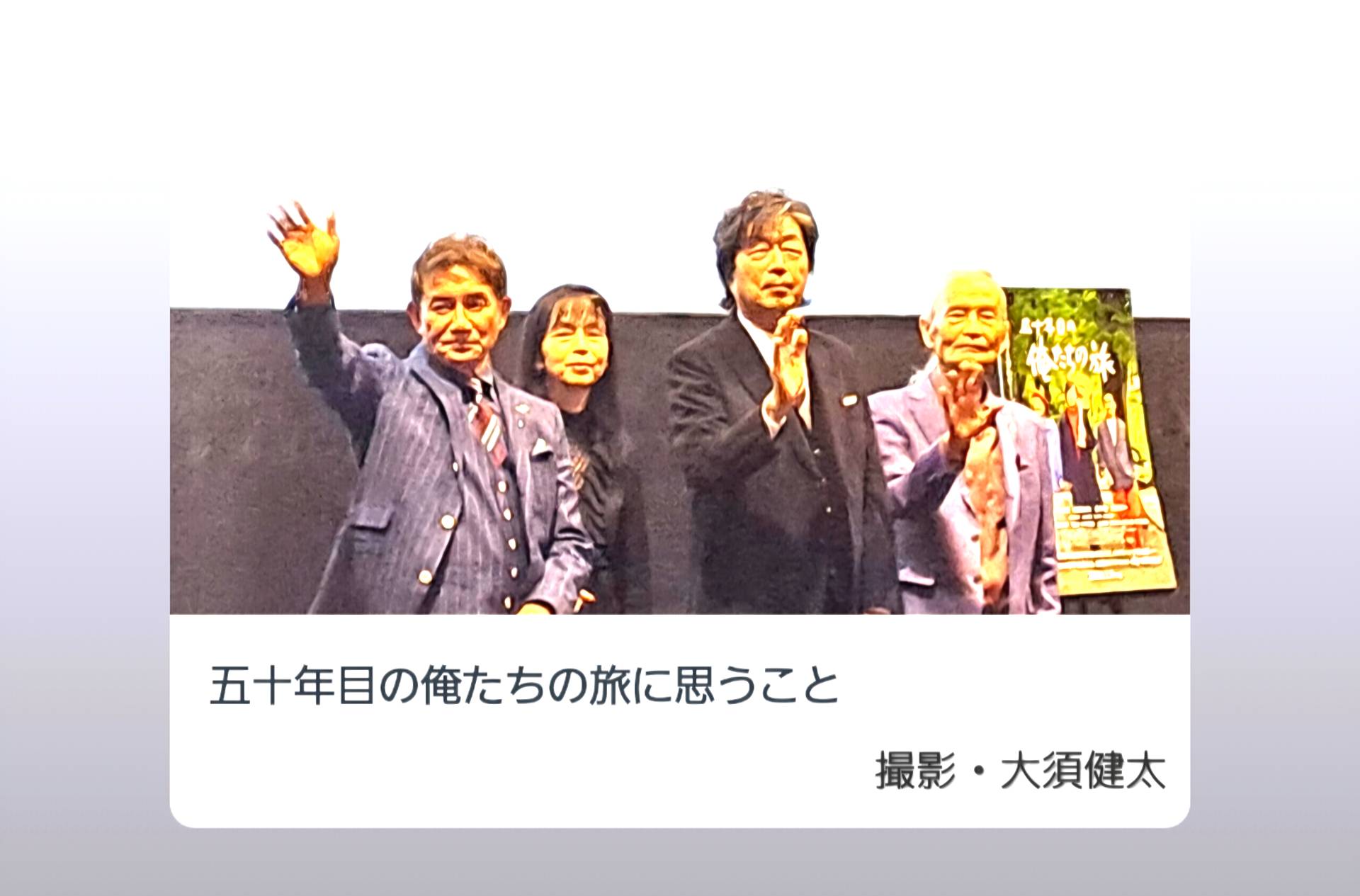
五十年目の俺たちの旅に思うこと
いつの時代にも、自分の人生に多大な影響を与える物事との出会いがある。それは、現代においてはインターネットの類であろうが、それがまだ登場する前や登場して間もない頃となると、それは本であったりテレビであったり、その媒体は既存のものであり限られたものであった。 今から20年くらい前、私の人生にも人生とは何かを深く考えさせられずにはいられない、一つのドラマとの出会いがあった。
1975年に放送された青春ドラマの金字塔「俺たちの旅」である。
何年か前、「下駄の音」というタイトルのエッセイにほんのちょっとだけこのドラマのことを書いたが、初放送から50年を迎えた。 メインキャストの中村雅俊、田中健、秋野太作(旧名・津坂まさあき)、それに田中健の妹役を演じた岡田奈々が集結し、「五十年目の俺たちの旅」と題して初の映画化が話題となっている。
あの時代をリアルタイムで生きていた同世代の人たちは、きっとドラマを見ればあの頃の自分に戻って、画面の中に映る井の頭公園をはじめとする懐かしい町の景色に、気がつくと自分も溶け込んでいるのではないかと思う。 当時まだ生まれていなかった私のような人間が見てもどこか懐かしく思うのは、画面に映る当時のファッションや演者の若さという目に見える視覚的なものも去ることながら、そこには誰の人生においても普遍的な「生きることの意味」という問いかけが、随所にちりばめられているからなのだろう。
初回放送された50年前、日本は高度経済成長期から安定成長期へと移行した時期だったが、学歴社会であり、就職難であり、一度人生のレールから脱線すると、やり直すのは難しいということがドラマを観ると分かる。そんな時代に青春を送りながら大人になっていく大学生を中村雅俊と田中健が演じ、そこから一歩先に抜け出た社会や組織という中で不器用に生きる社会人を秋野太作が演じている。鎌田敏夫をはじめとする脚本家たちの描き出すストーリーや台詞が素晴らしいことは言うまでもないが、この年齢設定とそのキャスティングは今見ても秀逸である。脚本と役者がピタリとはまるとドラマは半世紀の時を超えても、色褪せることがないことを証明した作品と言える。
毎回、ゲスト俳優には桃井かおりや檀ふみ、柴俊夫といった当時の旬な役者や、親世代には映画界からキャリアをスタートさせた津島恵子、岡田英次らを起用し、脇で出演する役者も確かな演技力を持つ新劇出身の野村昭子や下條正己をはじめ、芸達者な素晴らしい役者を起用し、ドラマに真実味現実味を持たせ完成度を高くした。
昨年、映画化を記念してBS日テレの再放送を観て、個人的に最も胸を打たれたのは、今更リアルタイムで観ていない私のような者が言うまでもないが、山下洋子と彼女を演じた金沢碧の存在である。そのどこか妖しい美貌も去ることながら、2歳年上の中村雅俊よりも大人びていて、どんと落ち着いた雰囲気を醸し出し、母性のようなものを感じさせる反面、凄みすらを観る者に感じさせていた。
カースケと洋子然り、世の中、人生は、殊に恋愛においては思い通りにいかないと相場は決まっているが、そんな中でもカースケを心から愛し、10年20年経っても死ぬまで惚れた男のことを心の片隅で、そっとずっと思い続けていた洋子の一途な健気は、うつろいやすい人の世において立場や性別を超えて尊い存在だったと言える。
10年後のスペシャル版、「俺たちの旅 十年目の再会」で洋子が幸せではないことを知った私は、ドラマとはいえカースケに怒りしか湧いてこなかった。どうしてこんなに自分を思い、ずっと見守り続けてくれた洋子と結婚しなかったのか。洋子の気持ちを分かっていたくせに、洋子と幸せになる人生を選ばなかったカースケに、どうしようもなく腹が立って仕方がなかった。
この一途な洋子の姿を見ていて、私はふと阿部定を思い出した。洋子を語るのに阿部定を引き合いに出すのは妙な奴だと思われそうだが、洋子のカースケへの一途な愛は阿部定のそれにも通じるものがあるように思えてならなかった。なぜなら、阿部定はドキュメンタリー映画の中で、人を好きになることは何度もあるかもしれないが、それでも長い人生の中で本当に惚れるのはたった一人きりではないかと語っていたことを思い出したからだった。
そのたった一人きりの男であるカースケに洋子は惚れたのである。その惚れた男を結婚した後も誰にも立ち入られることのない心の中で、洋子は生涯愛したのである。 後に青春の日々を振り返り、洋子はカースケを好きになって良かったとドラマの中で言い切った。成就することはなかったが、青春時代の手垢のついていない純な恋愛が、その後を生きる自分の支えになっているのだから、誰の人生からも若き日の恋は消えることはないのだろう。
金沢碧さんを最後に見たのは、市原悦子主演のドラマ「家政婦は見た」のファイナルだったように記憶しているから、相当前である。その後、彼女が演じている姿を久しく見ていなかった。そんな折、一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構が彼女の連絡先を求めているという一文を彼女のウィキペディアで目にした。彼女は今、どうしているのだろうと気を揉んでいたが、現在はガラス作家に転身し作品を製作しているという。お元気なのだと知り、ホッと胸を撫で下ろしたところである。
30年目のスペシャル版、「俺たちの旅 三十年目の運命」で人生をまっとうした洋子が、50年目の今作に笑顔でスクリーンに登場することは作品の設定上不可能だが、そうと分かっていても胸が痛み、悔しいのは私だけではないだろう。 脚本を書いた鎌田敏夫は、なぜ30年目にドラマの主要なポジションにあった洋子をこの世から抹殺してしまったのか。憤りを隠せない人も多いかもしれないが、人の世とはそういうものである。一途で真面目で、人のことばかりを心配し、自分のことは後回しにしてでも他人の幸せを願わずにはいられないような人は、長くは生きられないのである。山下洋子とはそういう人だったと思う。
カースケみたいなバカな男は「死ななきゃ」直らないのではない。カースケみたいなバカな男は洋子という大切な人に「死なれなきゃ」、本当に大切な人の存在は分からなかったのである。それが、自分らしく必死に生きてきたとはいえ、大切な人を傷つけて生きてきたカースケが、死ぬまで背負って生きていかなければならない、人生最大の悲しみというものなのかもしれない。
大切な人は、何があっても絶対に放してはならないのである。一度放したその手を、二度と掴むことは出来ない。50年とは、それくらい途方もない年月なのである。
五十年目の俺たちの旅に思うこと
2026年1月3日 書き下ろし
2026年1月7日 「note」掲載