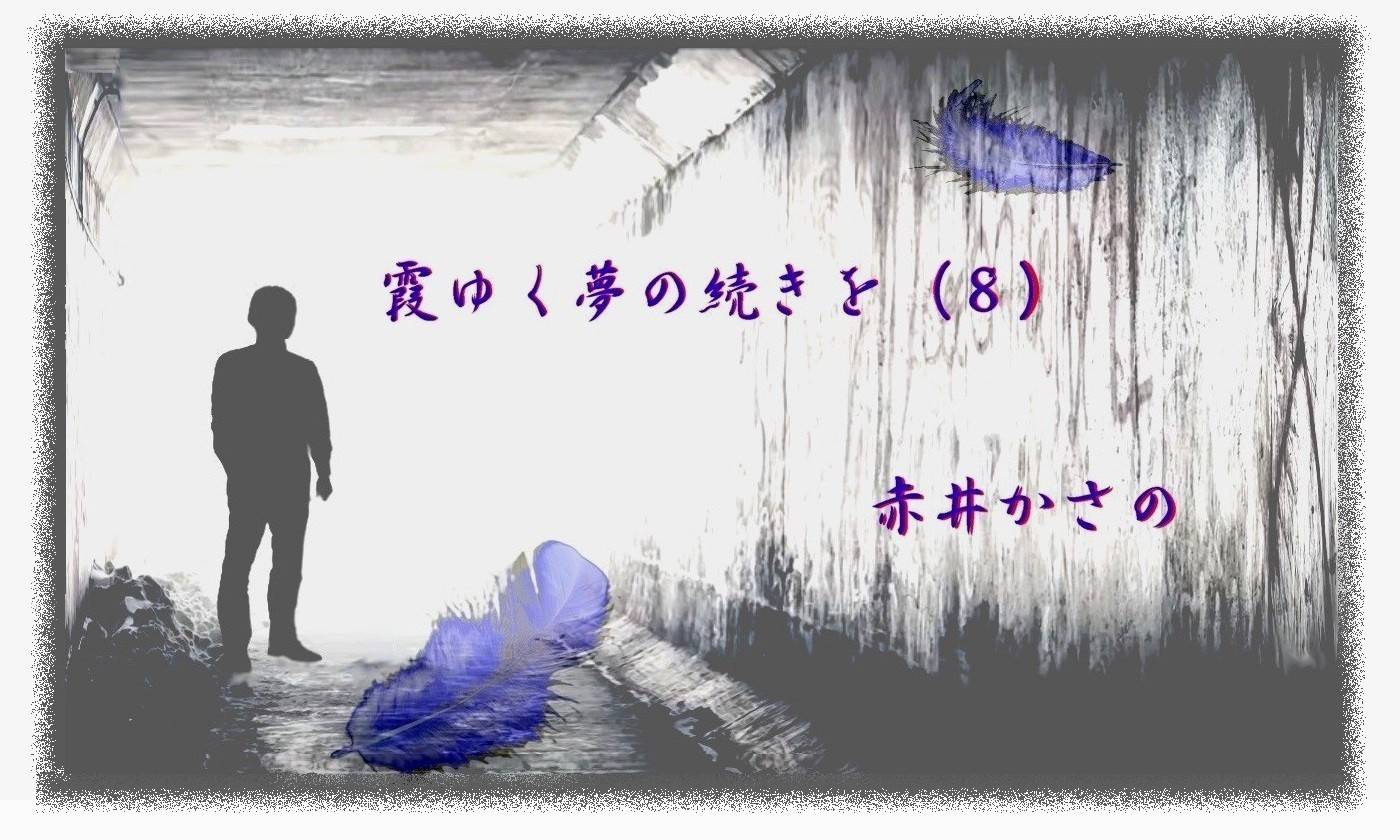
霞ゆく夢の続きを(8)
(51)
モノクロームの街をぬけ
月光に顔をうずめるとき
風は
いつもそんなところに吹いていて
手のひらを離れた青いカナリアの羽根は
くるくると空へ舞い上がる
死んでしまった私は
もうこの街にいないのに
閉鎖病棟の一室、男はベッドの上で浅い夢を見る。今日も夜がデスマスクを被ってやって来た。男の夢はあらゆる情景と時間と経験が混濁している。そこには何人もの人格が溶け合っている。それに解釈を加えたり話の筋道を辿ろうとしても無駄だ。もともと無意味なものに意味を求めても意味はない。狂っている? 狂っていない? それすらも分からない。
男は風に舞う青いカナリアの羽根を追い求めて、都会の森に迷い込んだ。今、小倉の中心部、繁華街を歩いている。男は生きていくことに倦んでいた。いつのことだろう、ずっと昔からだ。ずっと昔から生きていくことに倦んで、老木のように不安と恐怖の河を漂い続けている。
男は色彩を失っていた。水溜りに映る風船。その風船にも色がない。モノクロ映画の中の街。いま握りしめるカナリアの羽根だけ指の間から青い色彩をのぞかせている。夜の闇をワインに溶かし込んだような青。白と黒のモノトーンの光景に時折、このように部分的に色がつくことがある。
目に見えぬ暗い霧が街をつつんだ。夢の骨格が闇に沈んでいる。私はいま夢をみているのだろう。だが同じことだ。目覚めている時も心の風景には色がない。いつも半覚醒状態で夢と現実の中間に漂っている。仕方ない、それが私なのだから。
狂気の影がしのび寄る。静かだ。街は死の影ばかり漂っている。死人の国にいるのかもしれない。夜をさまよう青ざめたシルエット、ネオンに炙られた空、夜空には星も見えない。
───これは本当に私の人生なのだろうか。別人の脚本を演じているだけなのではないのか。魔界から舞い落ちてきた地図をたよりに彷徨う私。観察するつもりで、実は何物かに観察されているだけなのではないのか。
駅。天井に向かって続くエスカレーターに乗って、黒いコートをはおった男が降りて来た。フィルムが流れるように男を目で追う。視線がステージを走り抜ける。足音が近づいてくる。あの足音は私の足音なのだろうか。あの男が私なのだろうか。男に近づいていく、古い記憶を確かめるために。そして本当の私の姿を確かめるために。
ショーウインドウがモノクロの万華鏡に変わる。陳列台のマネキンには髪の毛がなく、乳首かなく、性器がない。その冷たい肩からはサテンのスカーフがすべり落ちる。目玉の貝殻は緑。ヘルメットの首がすぐ前方の道路を横にスライドする。
少女が二人近づいてくる。指の曲がった眼の細い方の少女が‥‥‥‥もはや笑うことのできないであろう少女が、私にギターの弦をくれた。きっとこの少女は死んでいる。指先が冷たかった。月光に透ける氷の体。ずっと、ずっと昔に私はギターを弾いていたことがある。どうしてそれを知っていたのだろうか。遠ざかる少女たちがつなぐ手が、今は蛇になっている。彼女たちは冷たい指で私の若さを奪っていった。
道路はヘッドライトの洪水だ。あそこには象の脚が服を着ているような寸胴女がいる。顔にほどこされた石灰の厚化粧。道端にはセルロイド人形が立ち、手招きしている。埃まみれで汚れてしまった笑顔。破れかかったドレス。彼女たちは娼婦なのだろうか。
聖徳太子が印刷されたストリップ劇場のビラが、地下道の隅にまるめて捨ててある。聖徳太子のビラとは? お札を模したものか? であればいったい今はいつの時代なのだろうか。
痺れた指からコーヒーカップが滑り落ち、砕け散った。水たまりに割れたコーヒーカップの破片が浮いている。すぐさま転んで脚を切る少女の姿がそこに現れる。さっきの少女だ。血が流れている。少女の肩がまるい。撫であげる猫の背中の湾曲。振り向いて私を見る顔が青い。何とかしなければ。私の背中がやけに熱い。脚を切る少女‥‥‥切る、切る、切る‥‥‥‥何とかしてやらなければ。何もできない。何もしないくせに。私にあるのは言葉だけ。
自動販売機の缶の転がり落ちる音が、私の耳朶を切る‥‥‥切る、切る、切る‥‥‥‥。空腹を訴える女は白いウエディングドレスを着た。乾いた音を残して鏡の中の私が割れる。露店には魚の手首を斬り落とす大きな鉞がぶら下っていた。魚の手首? それはどういうものなのだ。まさか人魚か。それともあの女か。別れた女。

鉄橋が空を割き、頭にのしかかってくる。男女のカップルが月の青い顔に触れようとしている。月の下で二人は影を並べて唇を合せる。それに比べて、街灯に照らし出される私の影はなんと不安定で、なんと淡いことだろう。嫉妬と憎悪から、抱きしめ重なり合っている二人をそのまま銛で串刺しにしてやりたい衝動にかられる。
噴水が照明され、闇にシャンデリアが灯った。空に濃淡ができて斑になる。赤井君、君がベンチに横たわり、ずっと眺めていた噴水だよ。そう、砂漠の心を青い水に変えた、あの公園の噴水だ。きっと覚えているはずだ。君はあのとき、霞ゆく夢の続きを見ていた。
ネオンが濡れた長い睫毛に落ちて瞬く。転がるダイヤモンドに街のネオンが反射して、無数の光の矢が目に飛び入ってくる。
紫川に出ると灯火はますます明るく、河面は微笑を浮かべる鏡になった。灯火はスタンド傘が覆う端正な寝顔のように、その河面に反映している。水影がゆらぐ。水面は悪魔の笑い声を映す。
私は歩き続ける。道は奥深く、底無しの闇に向かってのびている。七色のネオンが夜に溶けていく。コッペパンのバスは黄色い鼻飾りをつけ、眼鏡をかけていた。シティホテルの窓ガラスのずっと奥では、裸の平べったい顔をした女が浴槽のなかで髪を解いている。地べたに耳をつけてみた。いろいろな音が聞こえてくる。頭のなかを靴音や、自動車や、列車が走りぬけていく。
そのとき私は狭くて、長くて、暗いトンネルの中に立っていた。トンネルの先には車の途切れた、雨に濡れた車道に信号の明かりが長く尾をひいて映っている。体に鉄の杭が打ち込まれ身動きできない。地面に私の影が凍りつき、剥がせなくなってしまった。悪魔が死の淵に固定するために鉛の靴をはかせようとしているのだろうか。
脳組織が粘液状に溶ける。いま夢のなかに入ろうとしているのだろう。このトンネルが終わりに近づき、誰かの指の音が鳴ると完全に夢の底に落ちてしまうのだろうか。ずっと眠ったまま時計の振り子は止まってしまうのだろうか。私は未来が軋む音を聞き、永遠の扉が閉ざされてしまうのだろうか。
頭痛がする。言葉が‥‥‥‥言葉が湧き出てくる。何のつながりもない言葉が自在に動き出す。闇の中にさらに漆黒の扉が開く。私はそこに入っていく。
ああ、頭痛がする。言葉が息つく間もなく溢れ出す‥‥‥言葉があてどもなく想像の荒野をさまよう‥‥‥。
時間の停止。天秤の腕が折れた。永遠の細長い振り子の糸が、神の小指に絡みつく。今朝見た夢の外側で、宇宙の呼吸が途絶え、大時計は真空の中に凍りつく。宇宙の小箱の底に私の後ろ姿が沈んでいく。
大理石に巨大な神の影が映り、大時計の針がその影と重なる。そのとき絞首台に吊られた死体が振り子となり、魔の時間を刻むと、どこからかこの世の終わりを告げるきれぎれのチャイムが、しなったハイヒールのような曲線を描きながら街全体に流れる。
ベッドの周囲に無数の腐乱死体が転がっている。悪魔が交差したカミソリの溝にそれらの死体を押し込んでいく。幾重にもかさなる影。わきたつ泡。私はその泡で喉を潤す。自分の鮮血を舐めながら、不毛な愛情で渇ききった喉を潤す。
切り取られた悪魔の舌が幻の城に火をつけた。心の扉の閂は鮮血のうちに溶ける。壁のなかの叫び、縛られた影法師。フーガに合わせて踊る女の足首が、沼にゆっくり沈んでいく。双面鏡の無限の空間、そこに吊るされる迷妄の頭。風に漂う種子のように、私の頭が虚空に飛ばされていく。
*
ある女のことを思い出し、悲しくなった。別れた女。
「──さんは神についてはどう思われるのですか?」
「でも苦しい時の神頼みって言うでしょう、そんなバカ丁寧な言い方しないで」
満員電車の中で女は私の向かいに座り、私は女のためにブラインドを下した。女は信じられないぐらい小さくて、信じられないぐらい優しく見えた。
半年ぶりに会った女は髪を短く切っていて、頬にニキビが一つできていた。別れた後、私は目に焼き付いたその像を愛欲の舌で舐め、幸せになってくれるよう心から願った。
さらに五年後、かなり離れたある大都市のデパート屋上の古本売り場で、偶然レジ打ちする女の姿を見かけた。女は眼の下に濃い隈をつくり、悪魔に支配されているかに見えた。ふいにダリオ・アルジェントの「シャドー」という映画の、殺人鬼が女の手首を切り落とすシーンが脳裏に浮かんだ。気分を悪くした私は欝々とした気分のまま埴谷雄高の「死霊」のハードカバーとヘミングウェイの「老人と海」の文庫本を買った。レジ打ちするとき、女は声をかけずに知らんぷりしていた私に気づいたのだろうか。あのとき声掛けが躊躇われたのはなぜだ。私のせいか、女のせいか。
それからは記憶がない。独りでソフトクリームを舐めながらベンチに座り、呆然とゴミ箱に捨ててあるタコ焼きの食べ残しを見つめて数時間過ごしたことだけ、辛うじて憶えている。その後、女とは一度も遇ってはいない。
*
「でも苦しい時の神頼みって言うでしょう、そんなバカ丁寧な言い方しないで」
「知ってますか? 神様からチャンスは一度しかもらえないんですよ」
女の姿が次第に薄く、透明になっていく。
「行っちゃうんですか?」
「仕方ないわ。私、死んでるんですもの。もう忘れたのね。あなたに頼んで殺してもらったのよ」
「え?」
「私はもういない。あなたには私の影は見えない。今、幻覚と話しているの」
*
「生きていることと死んでいることの間にどんな違いがあるの? あなたは私がどこにいるか知らない。私もあなたがどこにいるか知らない。ただそれだけのことよ」
「でもいま君が見えているということは‥‥‥そうか、実はこれは見えていないことと同じなのか」
「あなたも私もどこにも行かなかった。行かないところに行くことはできないのよ」
「存在していない者の物語。二人とも存在していない。だとすれば、どこからもやって来ないので、どこへも行けないということか。ところで君の名前、まだ聞いてなかったね」
「私の名前はね、箱村温子」
「え?」
「そう、ハ‥‥コ‥‥ム‥‥ラ‥‥ア‥‥ツ‥‥コ」
(52)
花菱がマウスを滑らせる。脂肪でぽってりとした指がディスプレイのアイコンをクリックすると、室内に雫のたれる音が流れ出した。ボックス内で聞いたあの雫音だ。数十秒後、それに重なって箱村の声が聞こえだす。これもあの時の声だ(霞ゆく夢の続きを〈4〉─29)。
───豊穣たる大地の向こうに赤い屋根の家が見える。俺はその家に帰らねばならない。俺は青い果実を頬ばると、感覚と動悸の渦の中に溺れるカタツムリとなって、眼窩の窪地から虚空に眼玉を飛ばす───。
音が前面の大型モニターにリアルタイムで文字起こしされていく。今は音声がこんなにも正確に自動テキスト化できるのか。最近のA Iの進歩はめざましい。誤変換がきわめて少ないのもそのせいか。これ、何と言うソフトウエアかな? たぶんクラウドサーバーかなんかに繋がっているんだろうな。
「これってクラウドのデーターベースですかね」
箱村に小声で耳打ちする。
「ああ、そんな気もするが、よくは知んねえ。その手の知識は持ち合わせてねぇ。空っけつだ。なにを隠そう、チャットGPTの使用法をチャットGPTに尋ねるほどのIT音痴だ」
「なにもそんなに誇らしげに言わなくても」
「お前がそれ、言うかぁ? 少なくともお前にゃあ勝ってるぞ」
「もしかして情報、ぬけちゃってません? 最近、サイバー攻撃をくらう有名企業が次々と出てきてるでしょう」
「うちが有名企業か、笑わせる。いくら抜け作といっても、抜かれるようなドジは踏まねぇだろうよ。さすがに金庫にキーを差しっぱなしにして誰でも盗めるようにはしてねぇわな。な〜に、抜かれたって構わないよ。どうせ雇われの身だから痛くも痒くもない。だいたいこんなの誰が欲しがるのか。なんの使い道もないガラクタじゃねぇか」
味も素っ気のない答えだ。
「はあ、そうですか」
「けど、欲しがる物好きもたまにゃあ、いるかな?」
箱村はそう付け足すと、離れたところでパソコン操作に熱中する花菱の禿げかかった頭頂部をチラ見しながら、ほくそ笑んだ。あのポテッとした指でよくキーボードが叩けるもんだ。
痩せツボにハリの届かない、はり師泣かせの丸い後ろ姿。分厚い皮下脂肪のプヨプヨ背中が細かく揺れ動いている。なにやら作業をしていることだけは間違いない。タイピング音にあわせて両肩が小刻みに上下しているので、どうやらちゃんと両手でキータッチしているらしい。少なくとも指一本の、ヨボヨボ爺さん叩きではない。手慣れている。「アレ? どうしてこんな画面になちゃたんだろう」的なことはなさそうだ。
「社長の話じゃ、Web3だから皆で監視して大丈夫なんだと。ド素人のくせに知った口ききやがって。ブロックなんたらかんたら、だとよ。最近よく聞くバズワードだが、何のことだかサッパリわかんねえ」
「え? ウエッブ何? そんな言葉、生まれて初めて耳にしたなあ。やっぱり駄目なんだ、IT音痴のまんまでいちゃあ。でも皆で監視するってことは、皆に見られてることじゃないですか。こんな恥ずかしいもの、皆に見られてるんですか」
「だから言ってるだろう、俺も何のことだか分からないって。ほんなことあるんか〜い、って感じだ」
「けど花菱社長は分かってるんですね」
「なあに、社長も何にも分かってないよ。知ったかぶりしてるだけだ。自分は生き仏だなんぞとほざいているが、“仏陀ならぬ、知ったか豚”ってとこだ。胡散臭い業者の受け売りだよ、丸め込まれちまって。グルッとマルッと騙されキャラとくらぁ。さすが丸っこい体形だけのことはある」
「それってカモかもね」
「お、懐かしい昭和ギャグいれてきたな」
「まさか僕たち、悪事に加担してるんじゃないでしょうね。気づかず詐欺の片棒をかついでいるとか。それだけが心配で」
「オレオレ詐欺の受け子とか掛け子みたいなことか? なるほど中には自分が悪いことをしている自覚がない呑気な奴らも一定数いるだろうな」
「そうそう」
「警察に追い回されてにっちもさっちも行かなくなったら、いっそ有名人気取りでドバイにでも逃亡するか」
「そのまえに僕、パスポートもってないんですよぉ‥‥‥てか、これって真に受けていい話?」
「んなわけねぇだろう。冗談だよ。俺らにそんな金あるかぁ」
「そうですよねぇ、びっくりした」
「あのデブは変人だが、痩せても枯れても犯罪に手を染める人間じゃねぇ。痩せてねぇ、太ってるってかぁ?」
「ああ、確かに。悪い事する人じゃないですよね。けど社長も気づかず悪事に加担させられてる側かもしれないし」
「ああ、いくらでも拡大推測はできるわな。いずれにせよ花菱がどんな青写真を描いてるかハッキリしないんじゃどうしようもないよ。もうちっとは子分にガラス張りにしてくんないとな。未だ仕事の全体像が見えていない子分が、自分が悪事に加担させられてるかどうかなんて知りようがねぇもんな」
「社員が二人しかいないんだから安心していいんじゃないっすか? 少なくとも多角経営の枝葉のどこか目立たぬ部署で良からぬことをしているってのは無いですよね。何かそんなの、大企業でよく聞くじゃないっすか。いわゆる表に出ず水面下で便所掃除的なことをする人たち。こんな小さい会社じゃ、そんな大仕掛けな話はあり得ない」
「そりゃ言いきれねぇぞ。俺らが知らないだけで他の場所にも別の社員がいたらどうだ。アイツよくズル休みすんだろう。ズル休みじゃなくて別の社員のとこへ行ってたとしたらどうなんだ? この会社にはほぼ寝に戻るだけってな感じでな」
「まさかぁ」
「分かんねぇぞ。他にもピンク産業に手を出してるのかもな。だからお前が風俗に毎夜かよっていのもダダ漏れなんだ。だから知ってるんだよ。そんなの、生き仏の神通力でもなんでもない」
「え、まるはだかってこと?」
「文字通りな。お前もやるときゃ丸裸だろう」
「うぇ〜~」
「いずれにせよ、もう走りだしちまってる。今さら後戻りはできないわな。シュッシュッポッポと汽車はいく、なんだ坂、こんな坂‥‥‥真っ暗なトンネルだよ。深入りしようにも、どう入っていったらいいかも分かんねぇ」
「ところでブロックなんとかって、ブロックチェーンのことじゃないんですか?」
「おうおう、それそれ」
「それそれって、うわぁ、僕よりIT音痴がいた。そうかぁ、俗に言う分散型のインターネットなんだな。ネットを運営する企業のサーバーの代わりに、作業は全部ブロックチェーン上で実行されるんだ。社長はたぶんDAOに属して商売してるんでしょう」
「なんじゃい、それは」
「日本語では分散型自律組織と訳されてます」
「やけに詳しいじゃねぇか。ああ、そういえばYouTubeのその手の番組で、なんか見たことあるぞ。Dappsとかなんとかいうアプリを使うやつだな」
「よく知ってるじゃないですか」
「お前こそ、パソコンで文書保存のやり方も知らないローテク人間のくせによく分かるな」
「ただ想像で話してるだけですよ。役に立たないボヤーッとした雑学として知ってるだけです。なま分かりって言うか、一知半解って言うか」
「お、俺の大好き四字熟語じゃん、サービスしてくれるじゃんか。まあ、ダップスだかウップスだか何だか知らんが、そんなの一時の流行だ。昔話ばかりする野球解説者になるつもりはねぇが、昭和や平成に一太郎とか、ロータスとかいうのがあったろう。今もあるかもしんないが、最近はあんまり聞かないよな。その前はマルチプランか。その前は‥‥とにかく、あん頃は雨後の筍で、色々なのが出てきたよ。お前が知ってるわけないけどな。あんなのみたいにそのうち消えちまうよ。おっと、消えちまったら困るよな。俺らの飯の種だからよ」
「ド素人だからよく分かんないけど、ブロックチェーンといえば思い浮かぶのは仮想通貨でしょう。仮想通貨って用途は金融分野に限ったわけじゃないんですよね」
「社長がカチカチとキーボードを打つのをこれまでチラ見してきた限りでは、著作権かなんかのフィルターを通してるんじゃないかと思うぜ。そんな感じの画面が出てた。あるいは既存の著作物データベースに照合してるとか。俺の想像だけどな」
「なるほどそれもあるかもしれないな。だけど今んとこ、そこ、メジャーじゃない。でもNFTアートなんかもブロックチェーン技術を活用してるでしょう」
「なんだ、それ。また横文字を並べやがって」
「非代替性トークンとか言って、ブロックチェーン上に記録される鑑定書つきの部数限定のアートっていうのかな、うまく言えないけど。絵や音楽や、確か電子書籍でもそういうのがあったんじゃないのかな」
「ああ、そうなの。これって作品を銭にするって話だったの。そういやあ、シンガポールの仮想通貨ファンドが、その何やらアートってやつを史上最高額で落札したとニュースでやってたな」
「どこのニュースで?」
「BBCだったかな、CNNだったかな。忘れたけど有名な放送局だ。まだ花菱とボケ比べはしたくないんで、脳トレのつもりでBSやCSの海外ニュースは副音声で聴くことにしてんだが、なんかいつもボンヤリとしか理解できんのよ。少しは英語の勉強になるんじゃないかと思ってんだが、昭和カタカナ英語世代にゃ砂漠に水撒きだよな。こんな積み重ねぐらいじゃ若い奴らについていけない。もう手遅れなんかもな」
「箱村さんみたいに語学の目的が脳トレだったらいいんですけど、今はAIの時代でしょう。街ゆく人みんなが、ポケットAIやメガネ型のスマートグラスで同時通訳、同時翻訳しだすのは目の前ですよ。そのうち誰でも日本語を操るように外国語を操れるようになっちゃうんじゃないっすか? こんな時代に外国語を学ぶメリットなんてあんのかなぁ。なんで僕、外国語学部なんかに入ったんだろうか。英語と日本語は脳ミソの別々の場所にしまわれるんでしょう。箱村さんの場合、なかなか上達しないのは日本語の語彙が多すぎて英語の空きスペースがもうないからなんじゃないっすか?」
出まかせで、つまらんヨイショをする赤井君。どうやら花菱といっしょにいる時間が多いせいでヨイショ癖がついているらしい。
「そうなのかなぁ、エヘヘへ」( *´꒳`*)੭⁾⁾ポリポリ
適当につくった話を真に受けて、照れる箱村も箱村だ。
「なんかシンガポールや中国なんかでは、その何とかアートがフィーバーし始めてるとか言ってたような気がする。これ、正しく聞き取れてるかどうかは知らんぞ」と箱村。
「それ、それ。それを言いたかったんですよ。もしそうだったら、サトシ・ナカモトも僕らのあの恥ずかしいのを読んでたりして‥‥‥てなわけないか」
「もしかしたらアイツ、ビットコイン創始者のサトシ・ナカモトになりてぇんじゃないの。なんせビットコインの保有額が推定20兆円で、ビル・ゲイツの総資産を抜いて世界第10位に迫ってるとかいうからな。けど、なんて馬鹿なんだ、あのデブ。サトシ・ナカモトってホントの名前じゃないだろう。なら、どこの誰だか分かんねぇじゃんか。そんなもんにどうやってなるんだ、なりようがないじゃないか。あほくさ、ダブル高木ブーで、事故で死んじゃった仲本工事の穴埋めでもしとけっちゅーの。サトシ・ナカモトの銅像はハンガリーのブタペストに建っているって話だ。けどその像には顔がないってんだ。顔がなけりゃ、益々どこのどいつか分かんねぇじゃないか。ドイツじゃなくてハンガリーなんだけどよ」
話をまた変なところへ持っていこうとする。“ドイツじゃなくてハンガリーなんだけどよ”もちっとも面白くないし。
「なりたいもなにも、開けてびっくり玉手箱、実際に社長がサトシ・ナカモト本人だったりして‥‥‥てな訳ないですか。いくら人は見かけによらないと言ったって」
「人は見かけによらないか‥‥言えてるよな。ん? 待てよ。もしかしてそう言うお前がサトシ・ナカモトなんじゃねぇの? 全世界を驚かせたあんな論文を書くぐらいだから、きっとサトシ・ナカモトは超賢い奴なんだろう。だからあえて身を隠す。本当はアインシュタイン並の理系脳でも、ド文系のヘッポコ兄ちゃんのフリしてそこいらを今もブラついているに違いねぇ。天才は自分が天才であることをめったに悟らせないもんなんだ。悟らせても不利益になるだけだからな。そこが天才が天才たる所以だ」
「僕がサトシ・ナカモトなんすか? そんなの、突飛すぎて笑えませんよ。そんなこと言い出したら、箱村さんだって宇宙人に見えてきます。いつUFOに乗って地球に来たんですか」
「なんで宇宙人なんだよ」
「だって浮世離れしてるから。きっとノッポ星人なんでしょう」
ギャグを飛ばしたつもりなのだが、箱村は聞く耳を持たない。反応ゼロのまま、しつこくサトシ・ナカモトにこだわり続ける。
「そうかぁ、お前だったのかぁ、サトシ・ナカモトって。彼は自分の資産をまったく動かさない。だからまったく追跡できないんだそうな。お前が実は超ビンボーなふりして実際は巨万も富をどこかに隠し持っていたとしても、まったく資産を動かさなかったとしたら、それ、誰にも分かんないよな。薄ら馬鹿の赤井カサノは、なんと世を忍ぶ仮の姿だったんだ。うわっ、衝撃。これって、びっくり、ぎっくり、坊主めくりじゃんか。たいていこの手の人物は本名を並び替えてアナグラムにしている。アカイ・カサノ‥‥サトシ・ナカモト‥‥う~~ん“カ”と“サ”しか同じゃないな。文字を入れ替えてもどうにもならんわ。え~~い、白状しろ。花菱は騙せても俺の目はごまかせんぞ!」
「アホらし、僕のはずないじゃないですか。ちょっと前までパソコンで打った文章を保存できることも知らなかったIT音痴なんですよ」
「すっとぼけても、そうは問屋が卸さんぞ。お前だろう」
「おろして下さいよ。大根にでも何でもなりますから」
「はん?」
「いや、いや、いや‥‥‥でも意外と女だったりしてね」
「オナゴでもいいんじゃねえ? お前、オカマだろ? 女々しいし」
「またそっちに持って行く」
「サトシ・ナカモトは顔だけでなく身長も体型も全くわかっていない。だからお前みたいにチビでヤセで、そのうえアホっぽい奴だったとしても少しもおかしくないってことだ」
「“アホっぽい”はないでしょう」
「“アホっぽい”でいいじゃんか。アホとは言ってない。要は微妙にアホというニュアンスだ」
「どこがどう違うんですか、そんなの同じようなもんじゃないっすか」
「そうかぁ、そうだったのかぁ。下手人はお前だったのか。ついに謎は解けた。稀にみるストーリ展開、まさにドンデン返しだ。けどよ、そんな大金をつかんだままでどうすんだ。寝かせたまま使わなけりゃ死に金じゃん。そうかぁ、だったら自腹で出版社をつくったらいいじゃねえか。そんでもって優秀な編集者を別の出版社から金にまかして引っこ抜く。それがダメならフリーの編集者を紹介してもらってもいい。そんなの、大判小判がざっくざくのお前だったら訳ねぇ。彼らにお前の作品、あの天才バカ本を売りこんでもらうんだ。装幀もプロに頼んでやり直してもらってさ。どうせ売れないってか? 売れるよ。なぜってお前が自分の金で自分の本を買うからさ。ビットコイン資産で大量購入だ。ベストセラーよ。劣等感、ぶっ飛ぶぜ。買った本の置き場がないってか? ならブックオフにタダ同然で買い取ってもらやぁいいじゃないか。どのブックオフにもお前の本が山積みだ。大笑いだな。アホはアホでも、そこまでアホタレとは知らなんだ。大々的に宣伝もしなきゃね。それも雇った編集者がしてくれるよ。重版出来とか何万部突破とか、派手に広告を出してもらってさ。そうすりゃ、たまにはお前の駄作を買う物好きもでてくるかもしれん。もちろん騙されて買うわけだけどな」
なにが「謎は解けた」だ。ふざけているのか半分本気なのか。箱村の書く小説もこんな荒唐無稽で俗っぽいんだろうか。そりゃ何度だしても落ちるだろうな。そんなことするアホがどこにいる。いや、人は名誉欲の化け物だ。金がたんまりある人なら案外チラホラいたりしてね。
「しかしアベノミクス以降、ゼロ金利政策でタンス預金が増えたらしいけど、お前はどうなってんだ。どこにコインを隠しもってんだ。超どデカい貯金箱がいるよな。重くて床がぬけるんじゃねぇか? タンス預金は利息ゼロだろう。馬鹿々々しいじゃねぇか、資金運用しなきゃ。あれ? ちょっくら待ってくれよ、ビットコインって利子つくの?」
「‥‥‥?」
なにを言っているんだ。この人、なんも分かってない。
「でもよ、何でビット紙幣にしなかったんだろな。募金箱みたいに小銭ばっかじゃ扱いに困るだろう。そんなことにも気づかなかったんだろうか。なんだぁ、サトシ・ナカモトはアホやないか。やっぱお前がサトシ・ナカモトだ。アホという共通項がある」
ありゃま、コインが法定通貨のように現物としてどこかに存在していると思ってるのか? コインはネット上のデジタルデータにすぎず、実物が存在しないことを知らないらしい。ビットコインが別名、仮想通貨と呼ばれていることに思いが至らないのだろうか。子供みたいだ。いや子供だってそんなことは知ってる。
「タンス預金といやぁ脱税とくるよな。待てよ、ビットコインの収益にも税金はかかるんかぁ? よくは知んないが」
「そりゃ、取引で利益が出たらかかるでしょう。たぶん雑所得かなんかで」
「ほう、さすが公務員試験の問題集を読んでることはある」
「あんまり関係ないと思うんですけど。これって常識でしょ?」
「おい、おい、おい、呑気な顔してる場合じゃないぞ。もしかかるとすりゃ、お前は日本史上、最悪の脱税王だよな。ウルトラ虚偽申告じゃねぇか。てか、お前、確定申告自体をしてないんじゃないの? こりゃ大変だ。悪いことは言わない、今からでも税務署に行って土下座しろ。ほんでもって追徴課税を払え。相手も鬼じゃないから、それで許してくれるかもしれん」
「本気でそれ、言ってます?(w)」
「しかしなあ、払う税金だけでも何兆円にもなるんじゃね? どうやって金を数えるんだ。数えるだけで何年もかかるんじゃね? その前にビッドコインをどうやって税務署に納付すんだ。まさか銀行振込ってなわけにはいかないだろう。軽トラで国税庁に運ぶのか。それとも受けを狙ってリヤカーで運ぶか。ちょっと、どうするよぉ。芸能レポーターが来るかもしんねぇぞ。一躍、話題の人じゃねぇか」
「さてねぇ~、税額控除をねらって、ふるさと納税でもしますかね。ダメかぁ、控除額に上限がある」
「細けぇな、お前。やっぱ小説家より公務員が向いてるよ」
「それともどっかに寄付するかだな」
「寄付するなら俺にしろ」
このままだと話がズレたまま何処にいくかわからない。付き合いきれないので、箱村の戯言は素っ飛ばして、話を暗号資産にもどすことにした。
「その件はちょっと置いといて、あのね、暗号資産ってのは絵でも音楽でもデジタル作品であればいいんでしょ? アメリカじゃデジタル通貨で不動産事業を扱う業者も出てきているそうだし。だったら僕らが録音した、あの変なやつもきっと‥‥‥」
「その前に、さっき話していたブロックチェーン上の鑑定書ってなんじゃい。何をもっての鑑定書か」
「ほら、データの作成者とか所有者とか、盗用とか改ざんとかをさせないためにですよ。なんせブロックチェーン上の遺言書まであるぐらいですから」
「データの作成者って誰なんだ。俺らじゃないよな」
「そりゃあ、僕らじゃない。あの‥‥‥」
「あの高木ブーかあ!」
二人は声をそろえて、顔を見合わせた。
「そりゃ高木ブーだろうよ。実権を掌握してるのは奴だ。社長のアイツが指揮者で、タクトをふってんだからな。一度チラッと盗み見したことがあるけど、会社の通帳の名義人も当然アイツになってる。独り占めだよ。俺たちゃただの勤め人、発言力のない操り人形にすぎないもんな。家来はお殿様に盾突けないよ。このおふざけドラマの主役はアイツだ。どうした、トンビに油揚げをさらわれた気分か?」
「別に‥‥」
「おっとぉ、沢尻エリカなんか~い」
「え?」
「これ、古いのか? そんなに古かないから分かんだろう」
「いえ、分かったんですけど面白くなかったもんで」
「お前もズケズケと言うようになったな(w)。そうよな、俺も“別に”だ。黒子で結構。売らんかなの商魂が透け透けのアイツが、従業員のつくり出した不用品をどうリユースしようが知ったこっちゃない。俺らみたいな役に立たない枯れ木や流木を拾って、好きなだけキャンプファイヤーやりゃあいい。だが問題はそれより何より、これが銭の話だってことだ。困ったな。なんであのデブ、後先考えず暗号資産なんかに飛びついたのかな。何で頭がシーラカンスのくせに、あんな先端的でおニューなものに興味をもったんだ」
「もうそんなに先端的でもないっすよ。トランプが今、デジタル通貨の普及に意地になってるでしょう。アレ見て感化されたんとちゃいまっか?」
「どうせトランプなんかビットコインで自分や身内の私腹を肥やしたいだけだろう。なんで花菱が真似すんだ。ミニ・トランプか。ミニでもないな、あれだけ太ってりゃ。あのジジイ、新しもの好きなんだからよぉ。年寄りのくせに移り気で、握った途端にまた別のモノを追いかけたがる質なんだから。ひと儲けしたいんだよ。欲の皮が突っ張ってんだ。“万馬券、当たるとデカい”ってかぁ? 当たるもんか。これ、お前の小説と同じだよ。絶対に当たんねぇ。よぉよぉ、きな臭くなってきやがったな。言語イメージは物じゃない、物じゃないから仕入れなしで売れる。幼稚なアイツが考えそうなことだ。そんなふざけたビジネスモデルが通用するほどこの世の中、甘くないわな。幼児化現象か。俺らが半分眠ってる時に見た夢を売ろうとしてんのかぁ? 誰がそんなもの買う。買うのはバクぐらいのもんだぜ」
「でも優秀な経営者というのは、リスクをとる勇気のある人なんじゃないっすか?」
「コラコラ、なにを分かったふうなことを言ってるんだ。アイツのは勇気なんかじゃないよ」
「じゃ何ですか?」
「欲だよ。金欲と名誉欲ってとこだな。欲得ずくの商売人だ。商売人なら馬鹿げたお遊戯に金をつぎこむなっつ~の。目先の利益に飛びつきやがって。だいたいアイツの派手な金の使い方といったら見てられねぇ。財布のヒモがゆるゆるだ。いつも大盤振る舞い、無茶苦茶だぜぇ。こっちとら口癖になるぐらい、これまで何度“金がねぇ”と言ったか分かんねぇのによ。あのデブ、今は金を持ってるが、そのうち身ぐるみ剥がされるんじゃねえか。バブリーにしてられるのも今だけだ。アイツの財テク術もとうとう錆びついたか。策士策に溺れるってか? 誰だ、胡麻すりでアイツを策士ともちあげた奴は!」
箱村がこっちの顔をのぞき込み、いきり立つ。
「え、え~ぇ!? 僕じゃないですよ」
目線を泳がす赤井君である。
「そこまでアイツに胡麻すって、備蓄米でも放出してもらいたいのか。このお調子者がぁ。すりこ木でお前を胡麻ペースト状にしちゃろか」
「え、なんの話? 意味わかんないですけど」
「あれ? 貧乏人のお前ならこの備蓄米ギャグ、響くと思ったんだけどなぁ」
「僕はお米券でいいです。金券をタダでくれると言われたら、そりゃ欲しいでしょう。備蓄米を放出してもらっても、金が無ければどっちみち買えない」
「くわ~っ、そこまで行くか。貧乏根性まる出しだな。えらく農林族寄りじゃないか。昔、お前んとこ、農家だったのか?」
「違いますよ」
「農家じゃない‥‥ウ~ン、なんでだろう。ま、いいや。てか、なんで俺たち、お米の話をしてんだ。もともと花菱の暗号資産の話だったじゃないか」
「ずれていったの、箱村さんのほうですよ」
「だいたいだな、アメリカの世界有数の暗号資産取引会社FTXも結局破綻しちゃったじゃないか。CEOは金融詐欺で逮捕されてるしな。他にもマネーロンダリングとか何とか怪しい話がてんこ盛りだ。最近もCSの海外ニュースで見たんだが、香港なんかじゃ今、暗号資産をかたる投資詐欺が横行してるそうだぜ。被害額が一週間で17億円だとよ。目ん玉とび出るぜぇ。いくらトランプ大統領が推してるからって、肥満体どうしで暗号資産に憑りつかれてんじゃねぇよ。ブロックチェーンに関しては法律や規則が未整備だろう。ということは何でもありの世界ちゅーこった。あの古狸が目をつけそうな金儲けだ。なあ、暗号資産ってよぉ、“狸が化かして木の葉を小判に見せてるだけだ”ってよく喩えられるだろう。お前みてぇにすぐ狐や狸に化かされる奴なんて完全にカモだ。アイツもよく見てみると豚じゃなくて狸に似てないかぁ。自分では化かしてるつもりでも、最後には大狸に化かされる小狸にされるんじゃねぇ? 海老で鯛を釣ろうとしたら、逆に釣られてたりしてな。おめでタイやつだ。アイツなんて歳で暗証番号も憶わらないじゃないか。どっかに書いとくのか? どこに書いたかも忘れちまわぁ。セキュリティー甘々じゃんか。半ボケのアイツが考え出すことなんて、いずれ絵に描いた餅だ。どうせ計画倒れに決まっている。ん? ちょっと待て。おいおい、ひょっとしてアイツ、もう全財産をビットコインに両替しちゃってんじゃないだろな。激ヤバだぜ。ビットコインなんざ価値が日々大きく乱高下するやんけ。スローモーなアイツがついていけるもんか。黄金虫野郎の末路も赤信号だぜ。いくら蔵を建てようが、中に入れるものがないとクラぁ。ボロ儲けしようと思って、くたびれ儲け。ビットコインかビックリコインか知らねぇが、宝クジの当てが外れて宝クズになりましたとさ、ぽてちん。終了で~~す。あっという間にスッテンテン、空っぽ金庫ときたもんだ。まあ、アイツの金だから、ドラを打つのは勝手だけどよぉ。銭が尽きたらアイツは陸に上がった河童も同然。こりゃもう愛想が尽きた。屋台骨がゆるむ前にそろそろ遁ズラしなきゃなあ」
(‘⚇’)ぶひぃぃ、豚ズラ!
驚いた、このオッチャンは何を言い出すんだ。のけぞってリンボーダンスを踊りだしてしまいそうだ。
「え? 辞めちゃうんですか。な、な、な、なんで?」
箱村の思いがけぬ言葉に、感情メーターの針が激しく揺れる赤井君である。
「あたりきしゃりきよ。マヨネーズの容器は中身を使い切ったら捨てるだろうが。捨てずに取っとくのか、あらまあ変わったコレクターだこと」
「マヨネーズの容器はなくなりかけたら逆さに立てて、最後には鋏で切って中身を舐めます。もったいないでしょう」
「ウェッ、きたね。それってエコかぁ? どケチを暴露してるだけじゃねぇのか。ただのしみったれ根性だろう」
「なんで? みんなやってるんじゃないの?」
「やってねぇよ、そんなこと‥‥‥お前って足湯場で強引に肩までつかろうとするタイプだろう。ついでに頭まで洗ったりしてな‥‥‥おい、なんで俺らマヨネーズのこと、話してんだ。話はあのデブのことだったじゃん」
「そうだったですね。箱村さん、見捨てちゃうんです?」
「戦線離脱の脱走兵でござんすよ。アイツのエゴに振り回されるのはもう御免だ。世間じゃ“金の切れ目が縁の切れ目”と言うだろに。三十六計逃げるに如かず、スタコラサッサでありんす」
「むしろ“金の切れ目で縁が問われる”と言い換えたいぐらいです。ほんとに花菱社長を見捨てるんですか? そんな薄情な。社長をポイ捨てしちゃうなんて、ひどい」
「いつポイ捨てすると言った。ポイ捨てしていいのはマラソン選手だけだ」
「ん?‥‥‥あぁ、給水ボトルをね。なんだか上手いような上手くないようなギャグですね」
「素人がいちいち評論家ぶってギャグを評価すんな。あんな重たい粗大ゴミをどこに捨てるってんだ。アイツはアイツでここに残って好きなようにやりゃいい。のさばらせとけ。どうせ後は老醜をさらして晩節を汚すだけのことだからな。お前、残るの?」
「残りますよ。取りあえず安全装置を、ってとこですかね。最低限、食いぶちは稼がないといけないんで。起きてるのか眠ってるのか分かんない状態でも仕事は務まる。アレですよ、子供が絵日記をつけてるみたいな仕事でしょう。しかも毎日、描く絵はグチャグチャでも通る。のんびりと、ただバカ言ってりゃいいだけ。しゃべるのがメインで仕事が片手間って感じじゃないすか。被災もしていないのに義援金をもらってるのと同じですよ。おまけに『今日もバッチ、グーだな。金を持ってくの忘れるなよ』とまで言ってもらえる。定時出社に定時退社、ほとんど残業なし。手ぶらで来て手ぶらで帰るだけ。遅刻しちゃっても『エヘヘ』で済む。油だって売り放題でしょう。ほんとにダラダラして余白だらけの仕事だ。そのうえ3人しかいないから、人間関係の緊張もほとんどゼロ。こんな楽してお金をもらえる仕事って他にあります? 世の中には織田信長ばりのパワハラ経営者があふれているのに」
「そりゃ現場監督自ら率先してサボり放題、ズル休みし放題、喋り放題、あんな社長じゃ社員に示しはつかんわな」
「とりあえず、これからもずっと厄介になるつもりです。テコでも動きません。でも箱村さんがいなくなると思うと‥‥。箱村さん、“和して同ぜず”でいいじゃないっすか。このまま適当に合わせて働き続ければ」
「♪猫はコタツで丸くなるゥ~~。お前、思い切ってコタツからぬけ出せないだけだろう。ぬるいな」
「なんで歌い出すんですか」
「これ、お前もだろう」
「あ、確かに」
「ちょっと現状維持バイアスに囚われすぎてねぇ? 小沢一郎のたまわく“どこまでも付いて行きます、下駄の雪”ってか? そのうち溶けちまわなけりゃいいけどな。思い切って連立離脱した公明党を見習え。晴れたらお前が歩いてきた下駄底の跡なんぞ消えちまわぁ。損失回避ばかりして安全策ばかりとってたら、ジリ貧で人生を渡っていけねぇぞ」
「それってどういう意味ですか?」
「分かんねぇなら、分かっているフリだけしとけ。お前はそれでいい。要するに結論は、生活できなかったらどないしょうと、奴がばら撒く小銭に集るなってことだ。お前は蟻んこサンか。いまだにあんな少額な子供手当をもらってハッピールンルンとはねぇ。大の男がお金頂戴、お金頂戴と手を出すな。大仏さんかよ、みっともない。お前の腹はだいたい分かる。塵も積もれば山となると考えてるんだろう。キリギリスがサボってる間に、少しずつでも餌をせっせと巣に運ぶってか? お前、ダメだろう。貯めようと思っても風俗に通ってスッカラカンじゃねぇか。お前は俺と同じ、生涯その日暮らしで生きてゆくタイプだ。まとまった金とは縁がないんだよ」
「まあ、今はそうですが、そのうち‥‥‥」
「三つ子の魂百まで。今がダメなら一生ダメだ。爪に火をともす最底辺の生活でも、ちゃんと生きてるじゃないか。お前なら霞を食うだけでも生きてけんじゃね? 仙人かよ。貧困にあえいで、生活の三要件、衣食住も十分満たしてないじゃんか。それでもちゃんと生きている。なんだ、あの倹しい倉庫暮らしは。どこの避難民だ。感染防止で隔離されてんのかよぉ」
「引っ込み思案だから倉庫に引っ込んでるんですよ」
「内気ならちゃんとした家に住め」
「ウチキとウチ‥‥‥駄洒落のつもりなんすか?」
「えへっ、誰も気づかない? 気づかないよな。ちょっと今のは流せ」
「勝手気ままで、いいじゃないっすか。倉庫で十分ですよ。一時期、勝山公園のベンチで夜通し眠る日々が続いていたぐらいですから(『女と』)。どこにいるのか住所不定、“あんたの住民票、どうなってんの?”的な人間だったんですよぉ。それに比べたら‥‥」
「え? それ、夢ん中の出来事じゃね? それかぁ〜、そっちが現実で、こっちが夢だったりしてな。ま、いいけどさ」
「え? それって‥‥‥」
「“それって”って何だ。アドリブで作り話してるんじゃないだろな。嘘ついたら鼻がピューッと伸びるぞ」
「僕はピノキオなんですかぁ」
「いやね、勝山公園に大の男が横になれるようなサイズのベンチなんてあったかなって思ってよ。ベンチは図書館奥の煉瓦道の脇に並んでるのだけだった気がするけど、ありゃ小さすぎる、とても寝転がれねぇ。浮浪者に定住されちゃ困るから、お上があえて小っちゃくしたのかもしんねぇな。よぉ、お前もちょっくら頭ん中に公園のイラストマップを描いてみな」
「え?」
「なんて顔してるんだ。これ、記憶違いかなぁ。公衆トイレがあるぐらいだから、そんなベンチもどこかにあるのかもしんねぇけどよ」
「あれ? じゃデジャブを見てたのかな」
「どっちがデジャブだ。どっちが本来お前のいる場所なんだ」
「分かんない」
「分かんないなら、そりゃ、いい、いい。どっちが現実で、どっちが夢かなんてどうでもいいことだ。“栄耀栄華を極めても、目覚めてみればただの夢”ときたもんだ。取るに足らない、同じだよ」
はて? 軽薄な箱村にしては意味深なことを言う。
「ベンチで寝てたっていうの、送っても送っても出版社に一次ではねられ続けた時期だよな」
「ええ」
「ほんでもって、切羽詰まって駅でお手製本を配ったと(霞ゆく夢の続きを〈1〉プロローグ)」
「でも駅員さんに怒られちゃって。許可なしに配るなって」
「変じゃないのか、それって」
「なんで?」
「新聞の号外なんかが、よく駅前で配布されるだろう。アイツらはいいのか」
「許可とってるんじゃないですか。そんなぁ、人を疑っちゃぁダメですよ」
「そうなのかあ? 規則を楯に取って許可しないというのは、大きな組織の常套手段だ。情実で目こぼしなんて一杯あるくせによぉ。許可って事前にとる事務的手続きのことだよな。役所みたいに順番待って、書類を不備なく作成しなきゃなんないんだろ?」
「そうでしょうね、ふつうに考えれば」
「号外なんて、各社が競って一秒でも早く皆に配るもんだろ? そんな余裕なんてあんのかなぁ」
「あ~~~~なるほどなるほど、他社に先がけて配りたいですよね」
「だろ? 申し込んだら、ロクに審査、確認もしないで一瞬で許可が出るのか。なんのために申請させるんだ。審査せず全部フリーパスなら申請させる意味ないじゃんか。好き放題やらせりゃいい。好き放題やらせたら問題が生ずるから、じっくりと審査すんだろう。人の命をあずかるJR九州が、そこまでヌルいのか。あげな優良企業がよぉ」
と、さらに追い打ちをかける箱村。
「あれ、そうですよね。もし彼らだけ許可がいらないんだったら、差別じゃないっすか」
「そりゃ差別されるだろうよ、お前なら」
わざとらしく箱村は仄めかす。
「そんな奥歯に物が挟まった言い方じゃなくて、単刀直入に言ってもらったほうが‥‥」
「いいのかぁ? なら言うが、要するに“負け組は目障りだから消えろ”ってことだ」
「え?」
「だから言いたくなかったんだ。物も言いようで角が立つだろう」
「それって僕が舐められてるってこと?」😟ミジメ~
「“当たり”と言いたいところだが、その前に、おい、そんなしょぼくれた表情すんな」
「そうですよね、僕じゃ舐められてもしょうがないか」
赤井君は蚊の鳴くような声でつぶやく。気持ちのやり場がない。
「気弱なことを言うんじゃねぇ。意気消沈してどうにかなるもんでもないだろう。お前はこの広い世の中にたった一人しかおらんのだぞ。日本人のほとんどが負け組だよ。勝ち組はほんの一握りしかおらん。自信を持て。自分を信じるから自信というんだ」
出た。テープレコーダー箱村の例のセリフ。このセリフ、もう口癖になっている。耳タコだが、なぜが聞く度に元気が出る。
「人の心ん中のことだから舐めてるかどうか実際のところは分かんねぇ。けどよ、もしそうだとしても、そんなもん、人の表面だけ見て舐めてくる方が悪いんだ。いくら弱肉強食の世の中で、脆さを衝いてくる輩ばかりだとしてもな。ほんと奴ら分かってないよ。みんなで衝きあったら本体ごと崩れちゃうじゃないか。ほらほら、しょぼんとした顔すんな」

箱村の無駄話は続く。
「勘違いしてもらいたくないんだが、多少辻褄が合わないからってお前の話がぜんぶ夢で、たんなる幻想みたいなもんだと決めつけてるわけじゃない。ちゃんと現実にあったことだと信じているよ。夢だったら俺も消えちゃうもんな。お前が作ったお手製の小説も一揃い、家にある。駅で女房がお前からもらってきたやつだ」
「そうですよね、箱村さんは現にここにいるし、頬をつねったら痛いし、憶えていないけど僕、駅で奥さんに本を手渡したんですよね」
「おい、ホントにつねる奴があるか。つまり、お前のお手製本が実際にこの世に一冊でも存在している限り、少なくとも今の俺たちも夢でなくて実際に存在しているってこった。お前が勝山公園のベンチで夜通し寝てたっていう、もう一つの話はともかくとしてな」
「そんなこと分かりませんよ。箱村さんの家にある僕の小説も含めて、夢の中の架空の産物なのかもしれませんよ」
「ああ、ややこしいこと言わんでくれ、こんがらがる。そんなこと言いはじめたら、きりがないじゃんか。あ~~やめだ、やめだ、もうこの話はやめだ。そんなことよりもな、さっきから言いたかったのはこっちの方だ。お前って社長からあんな雀の涙を毎日めぐんでもらって感謝してるったぁ、ほんとに殊勝なおぼっちゃまだな。貧乏根性もそこまでくるか。お前、物を買う度いちいちポイントを気にするタイプだろう」
話が本線に戻ってきた。JRだけに支線に迷い込んでいたようだ───てか、あそこまでいくと脱線だな。
「僕、その手のカード持ってないんで。いつもレジで『ポイントカードお持ちですか?』って聞かれるんですけど、いつも持ってない。作らないから。ポイントをつけるより、品物そのものを値下げして欲しいです」
「そっか。お前ぐらいの超貧乏人になっちまうと、そうなっちゃうんだ。そうだな、お前、セルフレジにもお辞儀しそうなタイプだもんね」
「そうですよ、一般的なZ世代とは違います。Z世代でも最下層の人間は、あの、たとえば今どき飛行機や電車に乗るのもチケットレスになってますよね、アレだってアタフタ戸惑っちゃうんですよね。もうお爺ちゃん、お婆ちゃんと一緒なんです」
「そう言やぁ、お前、スマホも持ってないもんな。いいや、この前ソレらしき物、持ってたんじゃなかったっけ。知らんけど」
冷やっとする赤井君。スマホの件はなるべく避けないと‥‥。
「もうどうでもいいっていうか、食べる分だけ稼げればいいですから。ポイントカードなんて関係ないっす。人生、お金が全てじゃないですから」
「お金が全てじゃない? それ、超貧乏のお前が言っても説得力ないよな」
箱村が笑い出した。茄子のヘタみたいな人だ、煮ても焼いても食えない。ここまで他人を虚仮にして何が面白いんだろう。
「虚仮にしてるんですか?」
「プリプリすんな。虚仮になんかしてない。励ましジョークだよ。弱気になってシケたこと言ってるからさ。お互い、生きるためだけに生きるのはよそうぜ。“どうして人は生きなければならないのか”というお前の命題は何処にいっちゃうんだ」
「それ、忘れてないっす。今度部屋を掃除した時にもう一度探しておきます」
「ちぇっ、ボケで逃げたか」
「社長さんには感謝してますよ。だってそうじゃないですか。ふつう働くってことは我慢することでしょう。我慢と引き換えにお金をもらう。だけどこの仕事、半分遊びでお金が稼げるんだもん。機嫌のいい時はお給金の上乗せまである。ぜんぶ社長さんのお陰じゃないっすか」
「アイツが気前がいいのはアレだ、アレ。北風は太陽と争って負けただろう。人を動かすのはムチじゃない、飴なんだ。アイツにもそれぐらいのノーハウはあるってこった」
「ちょっと飴をもらい過ぎって気もするでしょう、しません?」
「分かってないなぁ。小僧が駄賃もらって大喜びしてどーすんだ。この人手不足の世の中に、あげなトンチンカンな仕事をやってくれる奴なんて滅多にいねぇぜ。だから飴をくれるんだよ。日本語カタコトの外国人労働者にアレをやらせようってのか。日本語知らなきゃ、できねぇよな。あんな仕事はハムスターの車輪だ。訳が分からず頭をぐるぐる回して作業を続けるが、いつまでたっても進歩なし。それどころか何が進歩で何が退歩かも分かんねぇ。だいいち目的すらも不明。それってイカれたサイクルでしかないだろう。芥川龍之介いうところの『狂人の主催するオリンピック』じゃねぇか。どこまでいってもゴールがなくて、目的なくトラックをぐるぐる走り続けるだけ。そんな人生は嫌だろう」
「それって何ですか?」
「『侏儒の言葉』ん中にあるだろう、こんな有名なのを知らねぇのか。それでも脱ゆとり世代なんかぁ?」
「でも‥‥」
「“でも”もストライキもあるか。お前のシュプレヒコールなんざ怖かねぇ。餌もらって飼われるのがそんなに嬉しいのか。やっぱお前って、尻尾フリフリのポチだな。なるほど毎晩、犬小屋に寝に帰るのも無理はねぇ。この花菱の腰巾着がぁ。そんなに長いものに巻かれたいの? そのうち大蛇か巨大象の鼻にしめ殺されんといいけどな。俺は辛くても長いものに巻かれぬ孤高の人を選ぶぞ」
「大丈夫、もともと箱村さんを巻こうとする人なんていませんから」
「何でだ」
「デカすぎて誰も巻きたがらないですよ。包帯がどれだけいると思うんですか」
「くわぁ、俺をミイラ男にするつもりか。お前が長いものには巻かれたがっている人間だというのはな、隙あらばまた小説を投稿しようと企んでるのがその証拠だ。隠してても分かるぞ。いじましい奴だ。そういうとこ、情けねぇんだよな。いまだに大出版社におもねっているとはねぇ。もういい加減イチかバチかの賭けはやめな、向いてないんだよね。たとえ下読みや選考委員がAIになったとしても、お前は落とされ続けるよ。AIになりゃ公正になるってか? そんなもん、なんねぇよ。よしんば公正になったとしても、なったらなったでますますお前は落とされる。なぜかってか? お前が落とされるということ自体が、選考が公正におこなわれているということだがらだ」
「何でそこに飛んじゃうんですか。結びつけないで下さいよ。これとそれとはまったく別次元の話でしょう」
「次元もクソもあるもんか。長いものに巻かれようとしてるの、花菱の御機嫌取りにしても大手出版社への小説投稿にしても、どっちもおんなじじゃないか。言うならば日和見主義だ。男一匹、情けねぇぞ。そもそも長いもの巻かれるたぁ、懸賞小説に即して解説すればこういうことだ」
「ほう、どういうことなんです?」
「出版社の連中は、みんな金目当てで賞に原稿を送ってくると思っている。小説は以前ほど金のなる樹でなくなったとはいえ、実際にそうだからだ。金以外の何か崇高な目的をもって送るヤツなんてどれぐらいいる? かつての俺はそうだったけどな。けど何回も落とされていくうち、尻に火がついて金目当てになっていかざるを得ない。武士は食わねど高楊枝とはいかねぇんだ。お前だって今は違うかもしんないが、いずれそうなる。時間の問題だ。いつか辿った路だよ。結局そんな崇高な志なんてもんは元々なかったんだと嫌でも気づかされる時がくるってわけだ。そういうのが長いものに巻かれようとする人間の正体なんだ。最初から金目当てと見透かしてんだから、巻く方は巻きやすいよな。一流の商売人は人の強欲さを餌にできる。またそのノウハウの蓄積もある。さあて、巻きごたえのあるのはどれかなぁ───てな具合に都合のいい奴に目星を付ける。“ゴッツアンです”は決まって巻く側だよ。要するに標的にするつもりで標的にされてるってこった。もろ、お馬鹿さんだよ。結局な、リフトで雪山の頂上にのぼってから“あれ? 俺って今までスキーをしたことなかったんだ”と気づくわけさ。はい、巻いて巻いてぇ、巻かれて巻かれてぇ、お前は海苔巻きにでもなりてぇのか」
「ふう、なんともかんとも。それが解説なんですか」
「“ふう、なんともかんとも”って何だ。俺の明快な解説が理解できないなんて、お前はアホか。頭ん中を煤払いせい! いくらネジを巻いても脳ミソが動いてくれないってか? オツムの歯車に潤滑油を差しちゃろか。いいかげん、花菱を見てて気づかないの? あると思って無いのが人望、無いと思ってあるのが借金だ。アイツそのものじゃないか。だってそうだろう。かなり前の話だけど、ビットコインを法定通貨にした中米のエルサルバドルがどうなった? ビットコインの価格が大暴落するわ、国の格付けは引き下げられるわで、テンヤワンヤになっただろう。それなのに大統領のブケレはチボというアプリを国民に配って、消費者に仮想通貨を使わせようと躍起になってた。今どうなってんだろう。結局試みは失敗に終わったと聞くけど、きっと悲惨な状態はまだ続いているんだろうな。エルサルバドルがギャングメンバー約300人を9億円でアメリカから一年間受け入れるって記事を最近新聞で読んだが、それもきっと金に困っているからだろう。一国家でさえそうなんだ。あんな棺桶に片足を突っ込んだ老いぼれジジイが、仮想通貨でうまくいくわけねぇじゃねぇか。金の工面がつかなくなるのは目に見えてる。暗号資産を貯めこんでるアイツは、そのまんまブケレだよ。いよいよ破産が現実味を帯びてきたな。仮想通貨で儲けるまえに火葬にされちまわあ。カモにされるだけだ。いつまでもあると思うな親と金。分け前にあずかれるのは今だけさ。それどころか火葬にされたアイツの借金の火の粉が俺らにまで降りかかってきたらどうする? 俺らの慌てぶりを冥途の土産にされたらかなわん。とんだとばっちりだろう。激ヤバやんけ」
「花菱社長だって飼い犬に手を噛まれたら痛いでしょう。箱村さんも少しは社長の身になってみたら? 僕らはただの飼い犬、従業員にすぎないでしょう。火の粉なんて飛んできますか?」
「社員だからといってアイツのツケを回されないとも限らないぞ。泥はかぶりたくないわな。借金の肩代わりさせられたら、かなわねぇ。お前サンよぉ、飼い犬、飼い犬とほざくけどな、お散歩犬の糞の始末は飼い主の責任だが、飼い犬は飼い主が野糞を垂れたって何の責任もねぇ。どうしてアイツの尻拭いを俺らがすんだ。一人で好き勝手にブリブリひり出しとけ。ホントに最後までアイツと付き合うつもりなの?」
「ええ、首にならなければそのつもりです。だいいち文無しが借金の肩代わりなんてできないでしょう。」
「ああ、それは言えてる。確かに文無しのお前に限ってはよぉ。いつも貧乏神に憑かれているもんな。じゃ、お散歩で迷子になったボケ爺さんを自宅に連れてかえる、飼い犬のままでいな。やっぱり最後の最後までお前はポチだ。それも忠犬ハチ公気どりのな」
「花菱社長、ああ見えて百戦錬磨の強者でしょう。長い人生、風雨にさらされつつも小金を貯めちゃってる。今度もうまくやってのけますよ、きっと。あまりにも現実離れしたプランなんで、競合相手がいなくてそのうち上場企業に大化けしたりして‥‥‥なんてワケないか。けど、よしんばこのプランが頓挫しても、七転び八起きでまた何か別の変わったことをやりはじめますって。いわゆる“転んでもただでは起きぬ”ってやつ。社長は強欲だから、失敗しても必ず何か他のことで利益を得ようとしますよ。箱村さん、考え過ぎです。取り越し苦労で白髪が増えますよ」
「花菱は起き上がり小法師か。甘いな。七転びすれども、あれだけ歳くっちまたら八起きはねえ。転んだまんまだ。百戦錬磨の強者だって? CEO面してるが、ただのお遊び自営業の糞オヤジじゃんか。あんな爺さん、リフォームしようのないボロ家だ、苔が生えてらぁ。そりゃアイツにも河面に揺れて広がる大輪の花火を映した時期もあったろう、それは認める。けど既に花火は散った。河面の水も切れそうなほど冷たい。もうすぐ棺桶だよ。あの時代遅れがいつまでこの超絶弱小、零細企業を切り盛りしていけると思うんだ。それを百戦錬磨の強者だって? アホぬかせ。そのうち閉店ガラガラだよ。おっと、お笑いコンビ『ますだおかだ』の持ちネタを勝手に拝借しちまった。ま、いいか。あれだけ売れてるんなら」
「花菱社長を棺桶に容れちゃう話なんてよして下さいよ。長生きしてもらわないと。今のところ僕にとっちゃ金のなる木なんですから。枯らさないで下さい。朽ち果ててもらったら困ります。きっとこの度もうまくやりますって。お札の雨が降ってくるかもしれない」
「しょせん儲けたって泡銭だ。小銭がチョロチョロ降ってくるだけのこった。だって神様の手元にあるのは小銭ばっかだろう。この不景気じゃ賽銭箱は小銭だらけだかんな」
「小銭が降ってきたら嫌だな。身体に当たって、さぞや痛いでしょう」
「これからの時代、降ってくるのはビットコインなのかもしんねぇぞ」
「大丈夫ですよ。政治家が裏金づくりをする限り、現ナマはなくなんないですよ。キャッシュレスだと足が付いちゃいますから。あそこ界隈だけ世間から取り残されているんですもん」
「それでウイットをきかしたつもりか。トロくさ~~ぁ、トロ~ントロ~ンのドロ~ンギャグ、墜落だな。しょせん俺たちは樋みたいに、どれだけ金の雨が降ってきても、ただ受けるだけでどんどん地上に流れ落とす定めだ」
「社長さんは今までもうまいこと、大怪我せずに事業を回して小金ふやしてきたんでしょう。だったら‥‥」
「アイツは禿げて毛がないからケガなしってかぁ! また手垢のついた駄洒落を言いやがって。今まで何人のオヤジがそのギャグ、言ったと思ってんのか」
「僕、そんな駄洒落、言ったつもりはありませんよ」
「言わなくても顔にウケ狙いのスケベ心が出てんだよ。心ん中はまるっと、するっと全部お見通しだぁ。いっぱしの企業家気取りだが、アイツは根っからのギャンブラーだ。人生をなめてるよ。付き合いが長いからよく分かるんだが、奴はいつも場当たり的で出たとこ勝負だ。いつも思いつきだけで行動する。これまで破産しなかったのは、ただ運がよかっただけだよ。仕事内容の全貌も見えてないお前に何が分かる。それは俺もおんなじだけどよ。まあアイツの商売自体がギャンブルだから、引いた手札を見せたがらない気持ちも分からんこともないけどね。それにしても、あの成金野郎がぁ。いつまでもお前のやり方が通用する時代だと思うなよ。少しは“歩”だった頃を思い出して心を入れ替えろってんだ」
しばし笑みをうかべて黙っている箱村。どうしたのだろう。ややあって、ここが笑うとこだと気づいたが、おあいそ笑いのタイミングがずれてしまった。
「なあ、今の分かった?」と、箱村はあくまでしつこい。
「分かりましたよ、将棋にかこつけたんでしょう。成金と歩ですよね、よくあるネタじゃないっすか。フ~~ッ」
「おっ、そのフ~っての歩と掛けたんだよな。進歩したな、教え甲斐がある」
───なにを言っているんだ、このオッチャンは。二人でスカタン比べしあってどうする。
「さぁ〜てと、赤井、今日も滑って滑って滑りたおそうぜ。それにしてもアイツがおっ死んだら、腰が曲がっちゃうかもしんねぇな」
「え、なんで?」
「そりゃ、デブだから背後霊になったら重いだろう、ハッハッハ」
───また笑いものにしている。この二人、どこまでいっても歩み寄りはないな。
「楽しみだねぇ、独りモンのアイツが死んだら、アイツの家を大掃除だ。タンス預金がいっぱい出てくるんとちゃうか。ほんなら二人で山分けして、ウハウハだな。山分けしたら後は野となれ山となれだ。裏金ハゲちゃびんがぁ、たぶん脱税しとるでぇ。あれだけの好き者なんだから、サービスでダッチワイフとティシュペーパーぐらい棺桶に一緒に入れちゃろか。ヘヘッ、それにしてもアイツがくたばったら式場で噴き出しちゃうかもしれんな。“おい、ドリフの葬式コントかよ”ってな。なあ、高木ブーが葬式コントで、お棺の中によく寝かせられてただろう。ご遺体役でよ。死人のくせに最後にブーがお棺のフタあけてさ、ヌッと顔出してキョロキョロするの、あれ、ブチおもろかったやろ」
箱村の突っ込みは続く。相も変わらず口数が多い。口にガムテープを貼って欲しい。

(53)
土曜、18時、勝山公園。
赤井君はベンチに座り、彼女を待っている。別にどんよりと曇った空に合わせたわけではないだろうが、生気がなく能面を想わせる表情だ。人というのは極端に緊張するとこういう顔になるらしい。
昨日は緊張でほとんど眠れなかった。よく眠れなかったとはいえ、今日は朝から落ち着かない。そわそわしっぱなしだ。彼女との約束とあっては、それも仕方なかろう。
眉間のあたりに疲労が集中していて、両手で瞼を軽く押さえれば、目の奥の黒い壁が近づいたり遠のいたりと、ゆっくりと動きだした。アンバランスな脳の痺れが支配している。ズンと重たい痺れは大脳の粘膜に深くめり込んでくる。頭がコールタールにつかっているかのようだ。頭の中を血液の代わりに何かドロリとした液体が流れている。
疲れを丸めて指でもてあそぶイメージに興じているうちに、それが頭の芯へむかってコロコロと転がりだし、雪ダルマよろしく大きくなりはじめた。はじめは心地よいとすら思えた意識の痺れが、やがて脳天に錐で穴をあけられているような鋭角的な痛みに変わっていく。脳ミソが過冷却されて小さな鉄の箱のなかをカラカラ転がっている。
頭痛の波が海鳴りとなって、押し寄せてきた。折れ曲がる女の舌のような波。閉じた目の奥に水平線が見える。夜の底の、漆黒の空と海との間に水平線が白チョークのラインを引く。
眉間とこめかみを親指の腹で強く圧してみた。痛みは収まらない。眼球が鉛玉をはめこんだように重い。顔を覆う指と指との隙間から何やら動くものが見える。目を凝らせば、なんと眉間に落ち込む竪穴の底で、血を吐くピエロが踊り狂っているではないか。
米粒大のとても小さなピエロたち。そのまま見続けていると、次の瞬間そのピエロが這い上がってきた。わっ、やめてくれ、上がってくんな、上がってくんなって。
眉間のうえで小人のピエロたちが跳ねまわりだしている。一人のピエロが踊るのをやめ、僕を見つめて笑い出した。何かに急き立てられるような笑い方だ。なにが可笑しい、馬鹿にしてるのか。
やっとピエロが髑髏の顎を外すように笑うのをやめた。ピエロが話しかけてくる。
「お前、なんでここにいるの? お前はもうここにはいないんだぞ。お前の過去はもうお前自身のものではない。そんなものは誰かに全部くれてやれ!」
おっといけない、いけない。ベンチの上でゆったりしていたら、ここにきて疲労が眠りを誘ったらしい。夢の入り口に差し掛かろうとしていた。かなり寝汗はかいているものの、さいわい頭痛は消えている。
不覚にもふいに眠くなってしまった、これはまずい。いま目を閉じると瞼が貼りついて、もう二度と目を開くことができないのでは。そんな気すらしてくるほどだ。
ここにこうやって座っていると、なぜだか分からないが長い時間の経過を感じてしまう。たかだか二十年そこそ生きてきたぐらいで、どうしちゃったんだろう。遠い過去から夢が細長く延びてきて、後ろから僕の首に絡みついてきたのだろうか。
日はかなり傾いている。雲を通して薄日が差しはじめた。尖ったナイフさながら、陽光の先端が地面の白肌に長く影を刻み込んでいる。路傍の人々も同様で、シルエットが街を行きかっているかに見える。都会のただ中にある公園にしてはあたりは物静かで、あらゆるものが耳を澄まして大自然の囁きを聴き取ろうとしている。
今日の彼の出で立ちはいつもと違う。糊のきいた白ワイシャツと折り目の入ったスラックスだ。ネクタイも締めようと考えたが、ながらく締めたことがなかったので締め方を忘れていた。彼女のスマホでやり方を検索しかけたが、さて検索方法が分からない。結局ノーネクタイだ。
とはいえ常日頃のだらしない恰好に比べれば、かなりおめかし風である。これでも精一杯よそ行きモードにしたつもりだ。当初は例の一張羅のスーツを着込んで出向こうと意気込むものの、あまりに「いかにも感」が強すぎて逆にみっともないのではないかと思い留まった。服装は相手にたいする敬意の表れ───そう解釈する社会人は少なくない。要するに彼にとっては「アナタは大切な人で、決して軽く見てはいませんよ」というサインが出せればそれでよかったのである。
雲の切れ目に晴れ間が出ている。太陽に見捨てられた空ではなかった。雲間から水のようにこぼれ落ちる光が鋏となり、その赤みがかった輪郭を人影ごとに切り抜いていく。
───いやまぁ、この木製ベンチはかなり老朽化していること。何十年前からここにあるのだろうか。年代物だ。これがワインであれば価値もでようが、ベンチとあっては都合が悪い。ペンキは剥げ落ち、色あせている。言い過ぎかもしれないが、いつ朽ち果ててもおかしくない有り様である。
見ればベンチの端っこに小さな蜥蜴が這っている。束の間、頭上を仰げばそこは空。割れ目に青インクを注ぎ込んだように薄雲の間から向こうがのぞいていた。目線を下にもどせば蜥蜴はもういない。瞬く間の出来事。神や仏の目から見れば、人間の一生も同じく刹那にすぎないのだろうな。
人生はシャボン玉。屋根まで飛んで壊れて消えた‥‥‥か。
あるいは僕がいるこの場所自体も、本当は架空で実体がないのかもしれない。ここはシャボン玉の地球の上、本当はぜんぶ透きとおっていて何もない。やっぱり僕は透明人間なんだ。
紡いで紡いで雨の糸
糸を小指にからませて
知らぬ間に時が過ぎ
そしていつしか雨も人も
思い出の中に消えていく
少し前まで雨が降っていて、胸を圧迫する息苦しい曇り空だった。だが今はかろうじて所どころ、晴れ間がのぞいている。重々しい灰色の雲のむこうに青空が滲み出ているのも見える。ストッキングに染み込ませた青インク。雨に濡れた女のストッキングが脚の体温で乾いていくように、アスファルトが陽光の手のひらに愛撫されている。草の上に落ちた雨粒も、今はその水玉に陽光が反射して光っている。
ようよう晴れてはきているが、どことなくカラッとしない。空のどこかに雨上がりの虹でも掛かってくれれば少しはカラッとするものを。音もなく走る風。猫の舌に触れるような生温かく湿った空気が頬をなぞっていく。七色の架け橋をさがす赤井君もまた目を舌に変えていた。真珠貝の殻の、虹色の内側を空に舐めまわす。
いま雨が降っていないからといって、気はぬけない。どうせ降っても天気雨、狐の嫁入りだろうと高は括れない。この空が黒ぐろと波立ち、いつ暗雲が逆巻くとも限らない。
過日、福岡天神で彼女にスマホで電話したときのように、都市部ではいつ何時ゲリラ豪雨が襲ってくるか知れたものではないのだ(霞ゆく夢の続きを〈7〉─46)。灰色の空が吊り天井のごとく下りてきて、蜘蛛の巣も流れ落とさんばかりの雨が降りだせば、薄雲に濾されたこの淡い陽光もたちまちにして消え去ってしまうことだろう。
夏の草花は慈雨で生き返るが、幸か不幸か僕は草花ではない。雨のトレモロはたくさんだ。それでもトレモロのうちならまだいいが、雨のシャワーを浴びることになったらたまらない。
大量の雨がアスファルトに降り注ぎ、路面に一気に透明の芝生を広げる。そのうえ突風でも吹きだしたら始末に負えない。いつも折り畳み傘を持ち歩くわけにもいかんだろう。
やがて透明な芝生がうねり、はじけ跳び、ぬかるむ。あたかも空から硫酸の雨が降り、大地が透明な無数の蛇の塊となってその体をくねらせているかのようだ。はては雷鳴が乱暴された女の衣服さながら、空をつんざく。
雨具が無ければ、たちまちにして濡れ鼠だ。風呂上がりの湿った肌に上から直接ニスで塗り固められたかのごとき、あの皮膚感覚。全身の不快さ。ドバーッとこられるのはあの時でもう懲りた。
異常気象である。いつから日本は亜熱帯気候にすっぽり入ってしまったんだろうね。これも地球温暖化のせいか。体感的に福岡はモロ沖縄じゃないか。そのうちここら辺も亜熱帯植物だらけになっちゃったりしてね。
手に持っているのはその時のスマホだ。このスマホにもてあそばれるのにも、ほとほと疲れた。天神から彼女の会社に電話した例のスマホ。彼女がわざと置き忘れていった例のスマホ。このスマホ中心にすべてが回っている気がする。赤井君は回想する。
「あたしのビビビはあなたなの」(霞ゆく夢の続きを〈5〉─39)───それって本心からなのかぁ? ただ感電してるだけじゃないんか〜~い。脳が電気ショックでイカれただけちゃうんか〜~い。
緊張し過ぎているからだろう、電気に触れたように突発的にギャグが浮かんで、思い出し笑いしてしまった。
待ち受け画面には時刻が表示されている。見れば時刻は18時5分とある。もしや待ち合わせの時間を聞き間違えたか。そうなら入れ違いというのも十分あり得る。うっかり者の僕にはよくあることだ。では、時間じゃなくて日にちを間違えていたとすればどうだ? まさかね、いくら抜けているといってもそこまでアホではないつもりだ。そんなことはあるまい。
そもそもこんなだだっ広い公園のどこで待ち合わせするのか、具体的にその詳細を詰めていない。仕事中だったからだろうが、彼女がそうする前に早々と電話を切ってしまったからである。こっちから探して回るべきだろうか。いやいや、双方が探していたらどうするんだ。どちらか一方が居場所を固定していなければ永遠に巡りあえない可能性もゼロではないだろう。
胸騒ぎがする。あるいは───ドタキャン!? 女心と秋の空、ありうることだ。あまり考えたくないんだが、これが空手形だとしたら───いやいや、実際に彼女とこのスマホで話しているんだからそんなことはないさ。
いろいろ考えるほどに頭に不安の蔦が巻きついてくる。僕の予感はたいてい外れるが、たまに当たる時もある。そんなことを言いだせば、それを聞いた天の声は「誰だってそうだ」と笑うのだろうが、なんとなく怖い。余裕をもって出てきてよかった。これだけ余裕を持たせれば、少なくとも行き違いというのは考えにくい。こっちが悪くなければそれでいいんだ。な〜にドタキャンだったら焼けのやんぱち、諦めるだけのことだ。
───はめてない. けど見てしまう. 腕時計
ローテク人間の赤井君に似つかわしいのは、どう贔屓目に見てもスマホでなくて文字盤付き腕時計である。今日は彼女のスマホがあるから、たまたま身に着けていないだけのことだ。若さとは無関係に、あるいはファッションとも無関係に、間違いなくアナログ腕時計派である。彼は時間をひとまとまりの物として把握するのが苦手だ。時間とは一秒一秒が積み重なっていく過程だと信じきっている。針の動きにいつも囚われているのはこのためだ。
彼にとって時間とは、数量でもなく、スパンでもなく、継続でもない。つまるところ観念なのである。だから、きっと今の彼には一秒が数分に感じられることであろう。
短針が彼女で長針が僕? それとも短針が僕で長針が彼女? ついつい空想してしまうのだ、たったいま時間が止まれば二人の心の針は重なりあえるのだろうかと。まるでメルヘンにひたる少女だ。こんなところに秒針の刻む時間の中に迷い込んでいく男の悲劇がある。
しかしいつからだろうか、スマホを持たず街を歩く自分がどこか仲間外れにされていると感じるようになったのは。スマホがないということは、言うなれば昭和に生きているということだ。一人だけ時代にとり残されているというか何というか、そんなモヤッとした不安が残る。
他方、誰からも束縛されず自由でいられるという意識もある。赤井君にとってスマホは電波の糸にぐるぐる巻きにされるというイメージがともなう。スマホを携帯し電波で不特定多数といつも繋がっているということは、いつ誰からお呼びがかかるか分からないということだ。最悪の場合、スマホを持っていたばかりに悪意ある相手からから損害をこうむる事態にも至りかねない。
多くの人は「そんな大袈裟な」と思うに違いない。しかし過去イジメを経験した赤井君には、決してそれが大袈裟なことに思えないのである。「油断は禁物。世間は悪意に満ちている、そういうことは常にありうる」と考えている。「地雷は至る所に埋まっている、気を抜くな」は彼の教訓である。確かにそれを教訓とするのは必ずしも悪いことではない。だがその発端がイジメだと知れば、なんとも悲しい話ではあるまいか。
眼前には例の噴水がある。妙なかたちをした、球体の噴水だ。そんなに昔のことに思えないのだが、なぜか懐かしい。学生アパートが潰れて行き場を失っていた頃だ。このベンチの上で寝袋にもぐりこみ、目の前の噴水の音を聞きながら眠ったっけ。噴水の音は、夜海辺の宿に寝転がり、遠くの海鳴りに耳を澄ます気分にさせてくれた。(『女と』)
改めて繰り返すが、このベンチはラワン材風の質感と肌触りで表面がザラザラしている。座り心地がすこぶる悪い。しかも、ここまでペンキが剥げ落ちているとあっては無様このうえないではないか。
いったい何色だったんだろうか。気になるが判別しようがない。う~ん、緑色かな? 木彫りの偶像がかもしだす厳かな沈黙。辺りは静かだ。緑色の沈黙のなかに僕はいるのだろうか。
カメラが蛇の目線でベンチの表面を這う。───それにしても年月を感じさせるベンチだ。直射日光に当たりすぎたせいだろうか、注意して見ればほんの僅かだが反り返っている。緊張にこわばった女の体のようだ。そもそも木製だということだけでも時代がかっており、今どきあまり見かけない。
はて、ベンチはどうしてこんなに古ぼけているだろうか。もっと新しかったんじゃなかろうか。気のせいかな。どうだったっけ、何度もここで寝たから分かりそうなものだが。
あの噴水もそうだ。噴水はベンチと逆で、間違いなくもっと古くて、茶褐色に錆びついていたはずだが。今は銀ピカで景色が映り込みそうである。長期使用によって見栄えが悪くなったので改装したのもかもしれない。
そういえばさっきから気になっていたんだが、周りの風景が襖絵さながら、平面的に見える。しかも水彩画のように淡く今にも流れ落ちそうだ。ずっと、ずーっと長い年月を挟んで、記憶の薄れとともに風化していく光景。なんとも不思議だ。
♪名も知らぬ遠き島より流れ寄る椰子の実ひとつ~
ふと自分が海辺に流れ着いた孤独な椰子の実にに思えてきた。どうしてかなぁ。そんなに彼の小説を読んだわけでもないのに最近、意味もなく島崎藤村づいている。こんなに待たされるのなら文庫本でも持ってこればよかった。赤井君はしばらく新札のホログラムを見ながら時間を潰す。
「もういいかい?」
「まぁだだよ」
いつまで経っても、まぁだだよ。かくれんぼの鬼がそうそう待っているわけにもいかない。公園で長時間ベンチを占有していちゃぁ、いつ挙動不審な人物と見なさるとも限らない。ついにしびれを切らして立ち上がり、そこら辺をうろついてみることにした。どこかで彼女に出くわすかもしれないしね。
肩を落とし、夏の余韻を女の長髪のように引きずってトボトボと歩きだす。その後ろ影はまさしくホラー映画『リング』の貞子だ。───「ちぇっ、どうにでもなれってんだ。どうせ僕なんざ、こんなもんさ。女なんていなくたって少しも困らねぇ」
───振られたら 振ってやったと 負け惜しみ
すると、そこに心のドアをノックする声が。
「ごめん、待った?」
「あっ」
その声に赤井君の背中がぴくりと動く。さながら雷に驚く猫の耳だ。そう言えばさっきから彼女を待っていた君の気持ちも、猫の目のようにコロコロ変わりっぱなしだったよね。
♪か〜ごめかごめ‥‥‥‥後ろの正面だあれ。
迂闊だった。まさか後ろからくるとは思わなかった。これは虚を衝かれたな。どうやら雨上がりの虹は背後に見えていたらしい。まさか虹空を背負って歩いていたとは。幸運の虹は手鏡がなければ映せなかったのだ。でもゴルゴ13だったら、後ろから来られたら撃ち殺しちゃうところだろうけどねぇ(w)。
待望の人が現れた。ビックリ箱よろしくドキンと心臓で受けとめる。彼女だ。姿を蛍光ペンで縁取ったかのように確かにそこにいる。探していた虹が目の前に掛かった。水彩画の淡い風景の中に、ただ彼女だけが輪郭を強調され、ビビットにその存在感を示す。
彼女の温かい声の響きに胸の奥、凍った心が溶けていく。雨のかわりに花ビラが降ってきた。喜びのあまりファンファーレが鳴る。うれしすぎて随喜の涙がこぼれ落ちてしまいそうだ。そのうち幸せな気持ちがポケットから溢れ出すのではなかろうか。
周りにはいなかったはずだが。どこにいたんだろう。神出鬼没。木陰の薄暗がりにでも身を隠していたのか。窓の外に浮かぶ月が、忍び足で部屋の隅に光を届かせたかのようだ。
気配を消すのが上手すぎる。くノ一だな。くノ一ならカモフラージュはお手の物だ。くしくも今日の御召し物も薄手の黒だし。葉隠れの術か。忍術とあっては、さすがに鳥になって辺りを滑空するぐらいでなきゃ何処にいたか分からないよね。
かりに隠れていたのが彼女でなくビットコイン花菱だったら、すぐ分かったであろうに。彼なら樹に身を隠すには横幅がありすぎ、おまけに間抜けで尻尾をポロンと出していそうだからである。さしずめ狸隠れといったところか。化かしたつもりで化かされて、木の葉を小判と見間違えている。
冗談はさておき、彼女の服装は小粋で実に洗練されていた。見事な着こなしである。ファッション音痴の僕でもそれぐらいは分かる。しっとりと濡れた闇に忽然と咲く妖艶な花。さもコサージュが似合いそうなシックな装いだ。
赤井君は想像をふくらませる。ひょっとして彼女は僕の来るずっと前から周囲のどこかに身を隠していたのではないかと。そして僕を認めた後、しばらくしてからさりげなく姿を現す。そういうのがいわゆる“大人の恋の駆け引き”というものなのではないか、などと。
───恋のカモフラージュ。ちょっと考えすぎかな。自惚れが過ぎるか。彼女を風俗嬢になぞらえてしてしまうのは申し訳ないが、わざと待たせる風俗嬢も結構いた。ひどいときは一時間、時計の針が一回りだ。あれは一体どういう企みなんだろう。ただ相手を惑わせるためだけのフェイントなのだろうか。いまだもって理解に苦しむ。何はともあれ一時間、待たせた方も待たせた方なら待っていた僕も僕だ。
たとえかりに彼女が何らかの意図を持って隠れて僕を見ていたとしても、その女は彼女ではなく別の女のような気がしてしまうのは何故だろう。どんな周到な計画を立てたとしても、この広い公園で彼女に僕のいる場所がそう簡単に予測できるとは思えないからか。だから別の女のような気がしてしまうのか。自分の気持ちなのに自分で分からない。なんとも不可解だ。
「待たしちゃったかしら。勝山公園って大きいわね。きっと図書館のあたりにいると思ったのね」
───はたしてそれってウソかホントか。

「‥‥‥‥‥」
赤井君は息を凝らす。喉の奥が乾ききって声が出ない。彼の表情には硬さが見て取れる。歌を忘れたカナリアになってしまった。舌がちぎれて、喉に詰まってしまったかのようだ。待ち望んでいた人が現れたというのに何故か膝が震える。
黙り込んでしまったのは、きっと嬉し過ぎるからだろう。けっして緊張や重圧が石の錘となって声を塞いだわけではない。カチカチに固まった心など、彼女の声を聞けば瞬時に解凍してしまう。「感動で言葉を失う」とよくいうが、たぶんこんな有り様のことを指すに違いない。
しばらくぶりだ。至近距離で見るのは、あの展望レストランの会食以来二度目である。こうやって面と向かってみると、やはり綺麗で嫋やかだ。整った顔立ちの女。というか僕は生来、母親に似たこういう容貌の女が好きなのだ。だから特別、整った面差しに見えるのかもしれない。何はともあれ、ど真ん中、ストライクの女であることは間違いない。
「こんなに公園が広くて、しかも人も一杯いるのに、よく僕の居場所が分かりましたね。イルカみたいに超音波を出して位置を特定したんですか? お得意のビビビで」
やっと言葉が出た。声が上ずっている。言葉が出たのはいいが、出鼻から小ボケをかましてしまった。どうしていつもこうなっちゃうんだろう、情けない。きっと箱村と花菱のせいだ。朱に交わりすぎて赤くなってしまったらしい。昔はもっと暗い性格だった。とりあえず明るい色に染まったんだから良しとするか。
「陽気な人ね。それがスマホの位置情報だったどうする?」
「え?」
もしかして冗談返しだろうか。スマホ音痴の赤井君には何のことだか分からない。
「あなたこそ待ち合わせ場所の詳細を言いそびれちゃったのに、ここに私がやって来ることがよく分かったわね。それも、時間もかなり過ぎてるのに。ずっと待っててくれて」
微笑みながら、物腰やわらかく受け流してくれた。「冗談返し」でなく「微笑みがえし」だった。夫婦でも、ムキになって小ボケに大ボケで対抗する旦那とは大違いだ。
「誰か女の人に僕がこのベンチに座っているところを隠れて見られているような気がして動けなかったんですよ」
「その女の人って私のことよね」
「分かんない。もしかして別の女の人かもしれません、ずっと過去からやってきた」
〈アンタが忘れていても、過去はアンタを忘れないのよ〉
「え? 今なんて言ったんですか? ちょっと遠くて聞こえなくて」
「なにも言ってないわよ」
「おかしいな、なにか女の人の声がしたよな気がして」
女は男をアンタと呼び、男も女をアンタと呼んだ。男が女にアンタなんておかしいが、そうだったんだからしょうがない(『女と』)。
「どうしちゃったのかな、変な人」
───そうだな、ほんとにどうしちゃったんだろう。
冷却されたナイフのように一条の光が雲を切り、雲間から日差しのスポットライトが筒状に公園の芝生に当たっている。俗に言う天使の梯子だ。その梯子から今しがた下りてきたといわんばかりに、スポットライトの光芒に照らしだされる彼女が目映い。
脈拍の速まりを感じる、ドクドクドク‥‥‥。ハートが早鐘を打ち鳴らす。動悸が時を刻む。今にも指の間から零れ落ちてしまいそうなほど貴重なこの瞬間。鼓動が彼女の方から聞こえてくる。僕のうちに流れるこの時間に、彼女の時間がそっと寄り添ってくれそうな気がする。
なぜ君はここにいる。そして、どうしてお母さんに似ている───今さらながら、これが偶然の巡り合いとはとても思えない。このまま君といることさえできれば、いつかは思慕の情が天に届いて、亡き母のいる家路に就けるのではあるまいか。
依然として光は白っぽく淡い。もし光に色があるとすれば、たぶんその色が周囲に溶けだしているためだろう。あたりの風景が水彩画に見える。しかもその風景画が、何故か手の届かない遥か彼方にあるような気がする。
にもかかわらず、彼女の姿だけがレリーフとなって背景から立体的に浮き出たかような鮮明な印象を与える。まるで3D映画だ。黒い服を着ているからだろうか。黒が彼女のくっきりした輪郭を描き、水彩画のなかに生き生きと映えている。
「驚いちゃった、まさかこんなだだっ広い芝生広場の隅っこにボーッと突っ立ってるなんて」
「ボーッと突っ立ってたですって? あぁ、あそこの‥‥木立の陰んとこの‥‥ベンチに座って噴水を眺めてた後のことですね」
今にも舞い上がりそうな気持をつとめて抑えながら、赤井君はそう言う。喉が渇ききり、それでも声をしぼり出すと声帯が枯れ枝のようにこすれた。
「噴水って何かしら。ベンチって何処にあるの?」
艶のある声。歌の調べが聞こえる。玉を転がすその響きが耳に心地よい。彼女の声は乾いた喉を潤すなめらかな水だ。僕のなかに水を満たす。
「あの球体のおかしな噴水を‥‥ですよ」
「え? この場所に噴水もベンチもないわよ。なるほどずっと昔、それらしきものはあったらしいけど、アナタ、そのとき生まれてないでしょう? 今は影も形もないわ」
今は噴水もベンチもない。うん? 今でもあふれ出る泉の旋律は耳に残っているのに。あの水彩画にも似た白っぽい風景の陰影や色合いの変化は、長い時間の経過を映しだしていたのだろうか。よもや色あせたのは風景ではなく、実は僕の記憶なのではあるまいな。記憶の額縁に入っている噴水とベンチをずっと見続けていたのではあるまいな。「昔それらしきものがあった」と言うならば、僕は遠く離れている過去を、魂の望遠鏡で覗いていただけなのか。それとも過去から伸びる蔦にからまっていただけなのか。
じゃあ、今しがたベンチの縁に這っていた蜥蜴はどうなる。ずっと昔から今まで生き続けてきたとでも言うのか。あの蜥蜴は古いアルバムのスナップショットにすぎなかったのか。おいおい、どうしちゃったんだ。そんな瑣末で、どうでもいいことは考えるな。そんなことを考えていると、そのうち生えるの見たさに蜥蜴の尻尾を切り落とす悪ガキになるぞ。馬鹿な真似はよせ。どうかしてる。蜥蜴に遇ったのはいいけども、このぶんだと夜中、恐竜に追い回される夢にうなされるな。
「どうしたの? 見ればわかるでしょう」
そんな馬鹿なことがあるか。周りを見渡す‥‥‥ありゃ? 確かにそうだ。ここは芝生広場だ。ベンチもなければ噴水もない。もしこの場所があそこだったとすれば、ほんのわずかの昔の面影も残していないことになる。
それなら僕はいままで何を見ていたんだ。蜃気楼でも見ていたのか。それとも夢をか。ずっと、ずーっと長い年月を挟んで、記憶の薄れとともに風化していく夢。霞ゆく夢を見ていたのか。もしあれが夢だとすれば、夢の欠片を拾い集め、どこかに閉じ込めておかなければ。なぜって、後から思い出の欠片を繋ぎ合わせないといけないからね。
夢はたいてい起きればすぐ忘れてしまう。とはいえよくよく考えてみれば、ベンチに座ってあの噴水を眺めているシーンを今まで繰り返し夢の中に見たような気がする。もう何度目になることだろう。ベンチと噴水は僕の生まれる前にしかなかった。だとすれば夢の材料はどこから持ってきたんだろう。僕は存在していないのだから過去からではない。もしかすると材料を未来から持ってきたのか。それも同様にあり得ないではないか。
現に今この目に像を結んでいる世界と、まったく異質な世界を見ていたというのはどういうことなんだろう。二重写しの画面を見ていて、過去と現在と、そしてあるいは未来とが無作為に入れ替わったというのか。僕は空から降ろされた縄梯子を必死で掴もうとしている盲人なのか。盲目であるがゆえに、現実でなく空想を見ていたというのか。
それとも僕の頭に小部屋が幾つもあって、それぞれ違った現実とそれぞれ違った自分が入っているとでもいうのか。そこから取り出す現実と自分は、時と場合によって異なってくるとでもいうのか。そこまで記憶が細かく仕切られているとしたら、人生のどのページに栞を挟んだらいいか、まるっきり分からなくなるではないか。
よもや一時的に前世に舞い戻っていたんじゃあるまいな。前世の僕が短命だったとすれば、それもありうることだ。時系列的には整合する。夢の記憶といっしょで、前世の記憶も生まれ変わればあっという間に消えてしまう。だが何かの偶然で記憶の断片が甦り、それが前世の自分と今世の自分をシンクロナイズさせた。あたかもデジャブのように───そんなふうには考えられないものだろうか。
時間というゴムチューブにグルグル巻きにされ、坂道を転がり落とされた気分だ。過去が回転しながら急に遠ざかり、現実が一気に近づいてきた。まるで自分はゴム毬だ。ぱっくりと口を開いた断崖にむかって転がっていくゴム毬。これからバンジージャンプでもさせられるのか。いや~~これは笑えないでしょう。僕の魂の歴史が、崖の奥の水底に眠っているとでもいうのか。そんなものわざわざ崖の下まで確かめに行きたくないぞ。崖の上のポニョにバンジージャンプさせる気なんか〜~い。
ま、いっか。考えても絶対分からないことを考えても仕方ない。凡人が考え過ぎれば迷いだす、これは道理だ。浮かぶのは雑念ばかり、肝心なことは浮かんできてはくれない。時間とエネルギーの無駄。頭の中で時間をどう逆転させようが、それでどうなるわけでもない。非生産的だ。時計の針が回るように、僕は生まれてからずっと時間を刻み続けてきた───確かなのはそれだけだ。仮説をいくら並べ立てても意味をなさない。宛名のない手紙は永久に届くことはないのだ。
僕は自他ともに認める幻覚体質である。花菱や箱村もそう言っていた。だったら、ちょっぴりイタズラ好きな邪鬼が死の淵から浮かび上がってきて、たまたま誤って魂の糸をぷつりと断ち切ってしまった───そんな童話風に軽~くとらえておいても一向構わないではないか。いま魂の糸はちゃんと繋がっているので何ら問題はないんだ。
ネット接続と同じだ。なにかの障害で一時的に回線が遮断されることはよくある。いま回線が復旧していれば、ことさら原因を詮索するには及ばないのである。もう毛糸玉をほどこうとはすまい。
テレビを点けたり、パソコンを開いたりすれば、真偽はともかくこの世は神秘的な出来事で溢れていることが知れる。その中の一つがたまたま僕に起こったとて何を騒ぎ立てることがあろうか。何事もこんなふうに軽い感じで、劇画調に突っぱねてしまえば、どうってことはない。
「あの、僕ってここでどうしてました?」
「どうしたって自分のことなのに分からないの? あの隅っこにぼんやりと突っ立ってたわよ」
「どんな感じで?」
「そうねぇ、白っぽい服きてるから、砂浜から突き出た動物の骨って感じ───いいえ、砂浜じゃなくてもっと広い。砂漠ね、砂漠から突き出た骨の先端かな。360度まわりには砂以外なにもないの」
晴れゆく空模様とあべこべに、赤井君の心に暗雲が垂れこめはじめた。突っ立っていた? その記憶がスコーンと抜け落ちている。
「で、それってどんなふうに突っ立ってたってことなんです?」
「どんなふうにって、そんなふうによ。石灯籠のように動かずじっとしてた」
「そうか、そうなんだ」
「そうなのよ。あなた、写真のなかにいた。じっと動かず」
水彩画の風景がさらに色あせ、もやっとして輪郭のはっきりしない妙な素描画に変じていく。闇のなかに突然目を覚ましたような不安が襲った。ドーンと重みのある恐怖が、液化して僕の胸にじわじわと滲みこんでくる。再び邪鬼の魔手が死の淵から抜け出て、溺れかけの僕の足をつかみ引きずり込もうとしているとでもいうのか。劇画タッチでもこれは笑えない、いったいどうなってるんだろう。
「あらぁ〜ボクちゃん、どうしちゃったのかな?」と、子供をあやすような口調の彼女。
「えへっ、一時的に浦島太郎になっちゃったみたいで」
「それって素敵じゃないの。短い間でもタイムマシンに乗れたってことでしょ?」
「あ、言われてみればそっかぁ。ずっと昔には噴水もベンチもここにあったんですもんね。なんだか遠方の旅先から絵葉書が送られてきた感じがする」
「誰が送ったの?」
「誰だろう、過去の僕かな? それとも過去いっしょにいた知り合い」
「なによ、それ。ボクちゃんって変な子ね。もしかしてタイムマシンには車窓の景色を案内するガイドさんも乗ってたりして。そして彼女に促されるまま、ボクちゃんはずっと昔の光景を見た」
彼女は穏やかに、だがそれでいてどこか訝しげな、何とも複雑な表情をしながらそう言った。
「ん? ボクちゃん? 変な子?」
「あ、違う、違う。変な人。あなた、私の子供じゃないものね」
変なことを言う人だ。変なのは君のほうじゃないのか。
「今日は砂漠の骨になったり庭の石灯籠になったり、とうとう最後には写真なっちゃった。結構いそがしいなぁ」
かろうじて自然体を装い、赤井君は冗談めかす。
「あら、変な子が憎まれ口きいてる。今は石灯籠じゃなくて回り灯籠ね。軽口の影絵が灯りに照らされてクルクル回ってる」
また“変な子”と言った。
「おかしいな、立ったまま眠ってたのかなぁ」
「まだ気にしてる、結構しつこい性格なのね。私にしつこくしてくれればいいのに。動かずじっと立ってたのは、その時たまたま地球が気絶したんじゃないかしら。それで時間が止まって動かなくなった。きっと神様が砂時計を横に倒したのね。でも今、動いてるから別にいいじゃないの。この異常気象だもの。さっき雨が降ってたと思ったらもう晴れてきてる。最近、地球って狂いはじめてるでしょう。そういうことがあっても、おかしくないと思うの(w)」
彼女は無垢な眼差しで空を見上げながら言う。そう、子供が舞い上がる色とりどりの風船を見上げる時のあの眼差しで。
「結構やさしいんですね、そんなこと言ってくれるなんて」
「何を?」
「“私にしつこくしてくれればいいのに”だなんて。甘えてるかもしれないけど、そういう優しい言葉の海で泳ぎたくなります」
彼女はこぼれ出る笑みを抑えようともせず、こう言った。
「溺れるかも知れなくてよ」
幸せな時間は速く過ぎる。絵筆溶く空模様。夕焼けが暗雲を裂き、赤インクの血液を西の空に流しはじめた。血管がひしゃげたように筋雲が薄っすらと走っている。街の色が徐々に朱に染まっていく。うん、明日は晴れだ。彼女の優しさに赤井君の心も晴れ渡る。もう心の傘はたたんでもよさそうだ。
「血は立ったまま眠っている」
「突然、何なんですか?」
「寺山修司の詩よ。あなた、今さっき“立ったまま眠ってたのかな”って言ったでしょ?」
「変な詩ですね」
「変な詩よね。若いころ読んだの。チンプンカンプンだった。後に戯曲にもなったそうだけど、きっとそれも変な演劇だったに違いないわ」
「若いころ読んだって、今も若いじゃないですか」
「そう? うれしい。まだ夢見る少女だった頃のことを言ったのよ」
「その詩っていつごろの詩なのかなぁ。ずいぶんと昔のことみたいな気がするんですけど」
「女に自分の歳を語らせたいの?」
「いえいえ、そんなつもりでは」
「まだかろうじて恋に恋してる頃よ。惚れていない男にも惚れることができた」
「え、それってどういうこと?」
「男の人にはそういうことないの? たとえば同情や共感から好意を持って、それが恋愛感情に発展しちゃうとか。そういうのって女より男のほうが多いと思う」
ん? 同情? もしかしてこの人、箱村さんのことを話してるんじゃないのか。仮にそうだとすれば───
「なるほどガッテン承知の助。そういうことかぁ。それで今は?」
「今は違う。夢は見ないことにしてるの」
───仮にそうだとすれば、今の彼女の気持ちやこれまでの行動の意味が、うっすらと浮かび上がってくる気がする。よもや僕は彼女の駆け込み寺ではあるまいな。
広い芝生広場には子供連れの母親が目立つ。いつもこうなんだろうか。広場の真ん中で、黒っぽい猫が「の」の字に丸まって眠っていた。遠目からはタイヤみたいに見える。捨て猫だろうか、飼い猫だろうか。都会では最近、野良猫はあまり見かけなくなった。たぶん誰かの飼い猫だろう。
雨上がりの芝生の地面が甘い息を吐いている。生ぬるい空気が足許に流れる。いずれにしても日本は平和で長閑だ。僕たちも平和で長閑、野に咲く花も欠伸するに違いない。
「僕たち変な子どうしですね」
彼女の顔に涼しげな微笑みの花が咲いた。あのスカイレストランで対面したときと同じだ(霞ゆく夢の続きを〈5〉─36)。彼女の微笑みは草原の匂いがする。またそこはかと母性も感じる。
「歩かない? 変な子どうしで」
言うがはやいか彼女は歩きだしている。ノコノコついていく赤井君。最初から後手に回っている。今の彼には自分がない。木の葉の舟となって潮にゆられていく。まるで母親に手をひかれる幼児だ。“変な子”と呼ばれるのも無理はない。
童謡よろしく靴が鳴る。二人の靴音はカスタネットの響き。淡い恋のメトロノームを刻む。青春が甦り、フォークダンスのリズムにのる二人。彼女の履くフラットヒールのパンプスが虹の弧を描く。サーカスで綱渡りする少女のように彼女の足首が細い。走る風に乗り、心を弾ませる赤井君。
だがなぜか気がかりも。来し方に後戻りして今にも意識の果ての断崖にストンと墜ちてしまうのではないかといった、一抹の不安にかられるのである。それというのも、落ち着いてきたとはいえ、まだ噴水とベンチが消えたことが心の隅に残っているからだ。いまだ迷夢が覚めやらぬ赤井君である。
前方に足を踏み出し体を平行移動させる度、その移動が何だか膨大な歴史の流れと逆方向で、前進するほどに何かの吸引力でより後方に引き戻されていく。滑稽だがそんなふうに思えてくるのだ。
───どうして噴水やベンチは消えちゃったんだろう。彼女の話だと、ずっと昔にそれらしきものはあったという。あの記憶のベンチに小石を置き忘れたら後から取りにいけるのだろうか。遠い過去が狂ったように追いかけてきて、現在の僕に重なったとしたら、もう取りにいけないな。
こんなこと考えてみても仕方ないが、未来行きの列車に乗ったとしてもその進行方向が過去に向かっていて、いやいや、むしろ過去と未来が融合してしまって、結果的にまた現在に戻ってしまうことだってありうるのではないか。首都圏には様々な環状線が走っているだろう。あれと同じだと思えばいいんだ。
アインシュタインもびっくりの奇妙奇天烈な屁理屈をこねて、なんとか自分を納得させようとする赤井君である。
〈赤井君、思い悩んだところで意味はない。君が遠くの過去を見ていたのだとしても、それがどうしたと言うのか。人は誰しも気球に乗り、もう決して後戻りできない過去の思い出に、いずれ手を振ることになるのだから。そら、彼女も言ってるだろう〉
「あのね、ボクちゃん。人って経験している以上のものを脳に記録していくものなのよ。だから考え過ぎないこと。そんなこと誰にだってある。気にしないことよ」
ゆっくり歩を進める彼女の手足の緩やかな振幅。ぬける白さがいよいよ目映い。その動作は生フィルムのように艶やかで未成熟に見える。感光する素肌が舌のさきに触れたかのようだ。肌のなめらかさを燐光が醸す。
「あれって冗談かイタズラの類ですか? おふざけ? それとも悪乗り?」
「置きスマホのことね。いろいろ並べたてたわね」
コバルトブルーの風がリフレインを残して吹き抜けていく。風が彼女の黒髪とじゃれ合う。風に靡くスカートの曲線。スローモーションで時間が流れる。ふり向いた彼女の、香水の淡い匂い。漂う芳香が気持ちをくすぐる。
風の内に君の吐息を嗅ぐ。風になってしまいたい気持ちだ。風になれば、君が母のいる場所に僕を運んでくれるのかもしれない。
風───なぜか思った。宇宙にも風があるのだろうか、と。
「風はないわよ、だって空気がないでしょう」と彼女。
え? どうして君は僕の心のなかが見えたんだ。
「僕いま、風のこと訊きました?」
「さあ、どうかしら」
彼女が微笑む。
「え?」
「訊いたわよ。急にぜんぜん脈略のないこと言い出すんだもん。言ったそばから忘れちゃうの? 変な子。からかってるんでしょう。顔を水に浸けて、息を止める練習でもしたら?」
「どういうこと?」
「だって風があるかどうか宇宙に確かめに行くんでしょう」
からかわれているのは僕の方だ。
「二人はまだ逢っていないんだと思った」と彼女。
「え?」
「脈絡のないこと訊かれたから、脈略のない言葉で返したの」
「というと?」
「いじわるね。私の存在があなたの中であまりにも小さすぎて、目に入ってなかったのかなと思ったのよ。電話してくれなかったから。それかぁ、目の届かない遠くの場所に行っちゃったのかも、って」
「いえ、いくら野暮でもそういったニュアンスぐらいは分かるんですけれども‥‥‥でも実際にはそんなことないんで」
口ごもってしまった。気恥ずかしさがこみ上げたのかもしれない。言いたいことが言葉にならない。舌が冷たくこわばっている。雪女が息を吹きかけ、舌を凍らせてしまったとでも言うのか(w)。
───僕は今、彼女と並んで二人きりで歩いているんだ。
そう思うと、嬉しくて自分が女の白肌を撫で上げる風になったような心地がする。得も言われぬ昂揚感がある。ネットスラング風に言えばテンションあげあげ、だ。彼女から元気をもらい、公園広場はすでにパワースポットになっている。
「カサノちゃん、いいから自首しなさい」
は? 藪から棒に何を言い出すんだ。“カサノちゃん”という呼び方も何か子供扱いされている感じだし。赤井君は開いた口が塞がらない。
「そんなに間の抜けた口をあけていると、中に虫が入ってくるわよ。さっきの続き、脈略のない話の倍返しよ。あなた、私の大切なもの、盗んだでしょう」
「え、アレってわざと置き忘れたんでしょう。そんなぁ〜、人聞きの悪い」
「アレって何よ」
「スマホでしょ?」
「違うわ」
「じゃ、なんですか?」
「私のハートを盗んだ」
彼女のその言葉にこの身が震えた。周囲の淡い風景が豊かに色づく。塗り絵のようだ。人間、生きてさえいればいいことがあるもんだ。この幸福感はなんだろう。その幸福感にまぎれて、ほんの少しだけ甘酸っぱい切なさもある。中学や高校時代に脳ミソが戻ってしまったのだろうか。
青春が帰ってきた。別れたあと長いあいだ捜していた恋人に、やっと夢の中で遇えた気分だ。歓喜が雄大な時の流れの中を人魚のように泳ぎ回った、水のさわやかな感触に優越感だに覚えながら。
「ハートのエースが出てこない♪、こりゃこりゃ、ハートのエースが出てこない♪───なぁんちゃって」エヘ(〃´∪`〃)ヾ
悦びまくり、照れまくったあげく、ついキャンディーズを歌い出しそうになってしまう赤井君なのであった。おい、歌うならカラオケ喫茶にしろよ。
「あれは驚いちゃいましたよ。物は試しってことですか? でも僕って試してみるほどの価値、あんのかなぁ」
有頂天の赤井君、素直でない。言いたいのはそんなことではないはずなのに。無理に平静さを装っている。へんに格好つけたら、かえって格好悪いことを知らないのだ。大根役者はすぐバレる。
「見方は人それぞれね。たぶん来てくれないと思った。どうして来たの?」
「こっちが訊きたいぐらいですよ。このスマホ、返さなきゃいけないし‥‥‥どうやら僕、スマートフォンをスマートに扱えないもんですからねぇ」
「まあ」
再び彼女の顔に涼しげな微笑みの花が開く。シャレのかけらもないこんな文句にもちゃんと微笑んでくれる。素敵な人だ。お高くとまった女のように白い目で見たりしない。
「でしょ? 完全アナログ人間の僕にスマホは馴染まないっしょ。どんどんIT化が進んでいくこの世の中、でも僕にとっちゃ便利になるというより不便にどんどんなってく気がすんですよ。そんな男がスマホなんてねぇ───変でしょう、笑っちゃいますよね」
少しはしゃぎ過ぎだ。赤井君は再び彼女に会えたことの嬉しさのあまり、ハイテンションで余計なことをチャラチャラ喋りだす。すでに心のなかは晴れ渡っている。
だが彼女はそれには答えず、
「火遊びじゃないのよ、真剣なの」
いきなりそう言った。笑みを絶やさない。だがその笑みの内に、どことなく恥じらいが見える。笑みを強ばらせたわずかな表情の変化は、よくよく注意して見なければ分からない。
微笑に雨を滲ませたような翳りがある。砂丘に落ちた人影が風紋の動きとともに揺れるのにも似て、きわめて微妙で繊細な余情をたたえる。
辿りついた意識の果ての断崖。その深い底から赤いマニュキュアの彼女の、ほっそりとした指が手招きしているかのような気がする。
───何だって。どうしてこんな風采の上がらぬチビに真剣なんだ。やはり花菱いわく、魂の色が似ているからか(霞ゆく夢の続きを〈7〉─50)。馬鹿な、そんなこと誰が信じる。
「え、本気なの? やめてくださいよ、あなたにはカッコいい旦那さんがいるじゃないですか」
「造花の愛よ、偽物。つくってるだけ。昔はそうじゃなかったけど。夫婦なんて舌先に残る蜂蜜の一匙。甘さは続かない。情熱と興奮はすぐに単調な生活に取って代わられるものよ。ガラスの家庭にいったんヒビが入ってしまうと、いつ割れてしまってもおかしくない。今の私の心は窓明かりの一つもない夜なの」
波間に浮かべた玩具の小舟のように、一抹の不安が彼と彼女の狭間を揺れ動いた。黙に波が光る。女はひび割れる真珠。男は生贄の水鳥。
「よりによって何で僕なんです?」
「何でかな? 分からない、人を好きになるって理屈じゃないもの。こんな気持ちになったの初めて。あなたの気持ちに火をつけたい。もう少しおそく生まれてこればよかった。でも後の祭りには絶対にしない。今日はその覚悟で来たの」
綿菓子を水に浸すかのように彼女の声が固形化し、わずかな震えを呈する。無理して笑みをつくる、こわばったその表情。青白い顔の動きが一瞬、雪崩に見えた。これはうつ伏せになって見る、残夢のなかの白い廃墟か。あるいは記憶のほぞに絡みあう四肢のよじれか。
───覚悟って、それってどういうこと? まさかアレってこと? いくらなんでも早すぎでしょう。未熟な読者が冒頭からクライマックスを見せつけられても、物語に入っていけないじゃないか。
思い切って彼女の手を握ってみた。真意が指先から点字のように読み取れるかもしれないと思ったからだ。彼女は拒まない。それどころか強く握り返してきた。
その感触に欲情の水位がダダ上がりである。そのうち氾濫するんじゃあるまいね。あそこが早くも自動的に臨戦態勢を整えはじめた。心臓がバクつく、ゴトンゴトンと水車小屋だ。いかん、いかん、これはいかん。訳も分からぬまま体も火照ってきた。意思に逆らい、全身が血を放出するがごとく勃起しだす。なにしてるんだ、せっかくの哀切でロマンチックな恋愛ムードがぶち壊しではないか。
───おい、まだ早い、大人しくしてろ。落ち着け、鼻息あらいぞ。時と場合をわきまえろ。どう、どう。勇み立つな。なんでこんなことになってしまうんだ、コイツは。
ああ情けなきかな、これも男の性である。女の肌を這う獣の息づかいのように、欲望がゆっくりと中空に直立していく。好色な虫どもが床から這い出た白い手のように、異様な指先の蠕動を露わにする。
それにしても美形の彼女がこうまで積極的になるのが解せない。赤井君は彼女のオーラの色を必死で探ろうとする。彼女も箱村と同じで透明に近い色のはずだ。う~ん、やっぱりそんなものは見えない。でも待って。そうなんだよね、もともと透明に近い色なら見えないのも当然じゃないの。
「覚悟って‥‥‥」
「今日は捨て身で来たの」
そのとき微笑みが湖面にできた波紋のように消え去る。真顔だ。
捨て身だって? 何を言い出すんだ。驚きに赤井君の思考は茹で玉子よろしく沸騰する。
「捨て身?」
「体当たりということよ、分かってほしいの」
彼女は葉が枯れ落ちるような、か弱い声でつぶやいた。女心と秋の空──秋かぁ。季節の移り変わりと時の流れははやいものだ。
男ならまだしも、女が軽々にこんなセリフを言えるものではない。完全にガチである。
───え? 告られちゃったの? なんで彼女が告白する。立場が逆じゃないのか。ふつう告白してふられるのは三枚目の役まわりだろう。これって奇跡かぁ? それとも生涯一度あるかどうかのハイライトなのかぁ? 自分史上、最高の瞬間ではないか。
赤井君は鈍い脳味噌を高速回転させて、この事態を理解しようと必死になる。
───魂の色が似ているから相手を好きになるという話もロマンチックでいいが、どことなくメルヘンの世界にのみ通用する解釈に思える。他にもっと本当らしい、科学的な仮説があってもいいんじゃないのか。
例えば遺伝子コードの配列がたまたま相互に補完しあうものであったとかいうふうに。いわば凹と凸の関係だ。もちろんそれは、より多様な環境に対応しうる子孫を将来にのこすためである。仮にそう考えるとするならば、たとえ“美女と野獣”ならぬ“美女とチビ”の組み合わせが成立しても少しもおかしくないことになる。
もう花菱のあの夢物語に付き合うのはよそう。混乱するだけだ。どうせド文系の自分に真実は分からない。たとい優秀な理系脳をもってしても恋愛のメカニズムを完璧に解き明かせる人はごく少数だろう。
赤井君はこの奇跡とも呼べそうな出来事を無理矢理そう自分に納得させることにした。
「若いのにどうしてスマホ、持たないの?」と彼女。
困惑しているのを慮ったのか、彼女が話題を逸らしてくれた。
「え~と、高いし、それに僕には必要ないから。電話する相手もいないし」
「これから私に電話すればいいじゃない。買ってあげる」
赤井君はさら固まる。頭の中は欲望と理性がせめぎ合っている。
ノーとは言えない。「買ってもらわなくてもいい」と言えば誘いを断ったことになりそうで───。それは嫌だ。そんな他愛ないことでこの人と切れてしまうのはどうしても嫌だ。
「私ももう一つ、新しいのを買おうかな。仕事用とプライベート用を分けるの。旦那のまったく知らないやつ」
う~ん、外堀を埋められ、何となく逃げ場を失った感がある。どうやら僕のかなう相手ではなさそうだ。心理を操られている。悪女は美人であるほど怖さが増す。「綺麗な薔薇には棘がある」とか。この人、もしかして危ない人ではあるまいか。何か魂胆があるとしたら───いいや、そんなの、歯茎に刺さった魚の小骨だ。元来、美というのは認知を歪ませるものだ。その程度の懸念など全く取るに足らない。考え過ぎにもほどがあるだろう。
さりげなく手に持つスマホを彼女に手渡す赤井君。
「とりあえずこのスマホ、お返ししますね。二人が再会するための忘れ物」
どうやら今の彼にはそう言うのが一杯いっぱいのようだ。これ以上気障なセリフは浮かぶべくもない。
「わざと忘れた忘れ物ね、憶えててくれてよかった」
しんみりと彼女はそう答える。とても優しいセリフだ。忘れるわけないじゃないか。
夕焼け雲の切れ目から太陽が赤々とのぞいている。陽光はすっかり斜め色。胸に空洞があいて、その奥をのぞき込めば行きつく果てに夕焼けが見えた。そんな気分になる。草葉にのった雨粒が夕陽に照らされ怪しく光る。日差しがビロードの幕となって二人を頭から包む。
色どりを朱に染めた街が、赤い光の糸を二人のハートに縫い付ける。いとをかし(清少納言なんか~~い)。エモい情景描写が官能を刺激してふつふつと欲望がたぎる。そのうち良からぬ悪魔の声まで聞こえたるは、わろし。
───ほらほら、彼女がくれたのは義理チョコじゃないぞ。ちゃんとホワイトデーにお返しの品を返せ。毒を食らわば皿までだ。いっそ破れかぶれで、欲望の赴くまま夢の中にドロドロにとろけ込んじゃいな。乙女チックに恋文を瓶に入れて海に浮かべたって彼女のところには永久に届かないぞ。
即実行あるのみだ。欲しいものを手に入れたくば危ない橋も渡れ。犯罪ぎりぎりを狙うんだ。千載一遇のチャンスじゃないか。こんな出来事は未来永劫やって来ないぞ。君の長い将来、これほど脈のありそうな女は、彼女以外あらわれてくれないんじゃないのか。こりゃもう愛欲地獄だな。決まり! いいじゃないの、愛欲地獄で。地獄へでも何処でも行っちまおうぜ。
黄昏に追い立てられるまま、悪魔のが囁きに頷く彼。たまたま入り込んだ道は一方通行だった。もうバックで引き返えすことはできない。そこには階段を踏み外し、無限の底へ落ちていく若者の姿がある。いま天国にいるからといって、天国で落とし穴におちてそのまま地獄へ真っ逆さま‥‥てなことにならないといいけどね。
───そうだ、落ちるとこまで落ちちまえ! なんなら今、どっかの木陰で押し倒したっていいんだ。
「そりゃ、いくらなんでもダメでしょう。そういうのが好きな女ならともかく。強姦でしょう。それに誰か見てるかも知んないっしょ」
悪魔の激励にナンヤカヤと、かろうじて抵抗する赤井君である。まだ魔界からたらされたロープを掴みあぐねているようだ。からっきし意気地がない。
♪トンボのメガネは水色メガネ‥‥♪
これは何なんだ、乾燥したトンボの複眼がくずれ落ちていくようなこの理性の崩壊感は。不倫は御法度と自分を抑制するほど、カリギュラ効果で欲求はますます高まっていく。
「えい、ままよ、あとは野となれ山となれ」───最後にはそう独り言つ赤井君、ついに覚悟を決めたのか。
その刹那、雲の切れ目からのぞく落日が巨大な悪魔の目玉に見えた。まさか僕はこのまま魔の滑車に巻き上げられていくんじゃあるまいな。光芒が生糸のような水の流れとなって、彼の手首に絡みつく。太陽という名の赤く大きな心臓が光の鼓動をつむぎだす。光の鼓動と渦のなかで銀のドレスを着た少女が二人のために踊っている。
(54)
L L装置もどきのボックスで聞いた声は続いている。表情を忘れた能面の平板さ。こうやって改めて声を聴いてみると、伸びっぱなしで戻らなくなったバネやゴム紐が浮かんでくる。再生速度をぎりぎりまで落としてYouTube動画を視聴しているかのようだ。こうまで間延びした肉声を聞かされると、機器がいかれてるんじゃないかと疑りたくなる。おまけに話し終わってから、また話し始めるまでの間隔が不自然なほど長い。
───豊穣たる大地の向こうに赤い屋根の家が見える。俺はその家に帰らねばならない。俺は青い果実を頬ばると、感覚と動悸の渦の中に溺れるカタツムリとなって、眼窩の窪地から虚空に眼玉を飛ばす。見ているのか。意識のはらわたが脈打つ心臓に糸のように絡みついてくるこの情景を。爪と肉のあいだに流れ込んでくる葡萄酒の夢の向こうに、赤い屋根の家が見える。その家に帰らねばならない。裸体の丘を下ると、その家の白く干からびた扉が見えた。家の庭には人がいないのに夕暮れに揺れ続けるブランコがある。俺は静かに骸骨のノブをまわす(霞ゆく夢の続きを〈4〉─29)。
‥‥‥‥あれ? 「豊穣たる大地」だったかな。もっともの寂しいイメージの風景が見えたはずなんだが‥‥‥‥記憶が今いちだ。
しばらく間があって、今度は僕が話し始めた。声のテンポは箱村同様、異常に遅い。間隔の取り方も似ていて、まともでない。ただ声の質が違う。僕の声はややくぐもって聞こえるものの、やけに高い。何者かが背後にいて、腹話術人形の僕を通じて声を発しているかのようだ。とても自分の意思で言葉を語っているとは思えない。そのうえ息も荒い。どうしてこんなに荒いのだ。全力疾走した直後の息遣いとでも表現したらよいのか、男というより、むしろ情交中の女の嬌声に近い。自分の声ながら背筋に寒気が走る。なんと薄気味悪い声だろう。
───扉の内側には顔があった。顔は口からも、目からも、鼻からも血を噴き出している。それはもう一人の僕の姿‥‥‥‥過去の姿か、未来の姿か。それとも、もしかして今この時の僕自身か。海辺の静寂の果てに笑っているあの人がいる。彼はベッドの上に横たわっている。誰だ? 僕か? 僕は本当に僕なのか。僕は本当に僕でいいのか。ブランコはまだ揺れている。この家で僕は、赤い手毬をかかえた少女の帰りを待つ。猫の目をした少女、かつてこの家で暮らしていたはず‥‥‥‥。
少女が胸に抱いていたのは手毬ではなかった。毛糸玉だった。毛糸玉が地面に落ちて、こちらに転がって来る。少女から僕の足許に一本の毛糸の赤い線が引かれた。僕は毛糸の端を小指に巻きつけた。庭のブランコの揺れはまだ止まらない。
ふと気づくと、小部屋にいた。小部屋で安楽椅子が揺れている。ブランコの揺れが、安楽椅子の揺れと重なって見える。毛糸のもう一方の端が安楽椅子の足に結ばれていた。音はしていない。無音の世界にしばらく佇んだあと、安楽椅子に向かって歩いていく。
すると三角頭巾の男がどこからともなく現れ、前をふさいだ。男は目をむき何やら口をパクパクさせている。必死で何かを伝えようとしてるようだ。だが何も聞こえない。制止してるのか、何か別のことなのか。分からない、さっぱりだ。
いや待て、男は何かを指してるぞ。左方向‥‥‥何だ? 扉だ。部屋の左側にある扉、ちょっと開いてるぞ。闇がのぞいている。何だ? 扉の先になにがあるというのかな。そっと扉を開き、なかに入ると‥‥‥
とつぜん意識が飛んだ。いま僕は足の指の間に血をにじませて、透明なフロアーの上に立っている。小指にはまだ赤い毛糸が巻きついていて、その先はフロアーのずっと奥までのびている。透明なフロアーを通して真下には、筋骨たくましい外国人らしき男が、上半身裸で僕を見上げていた。男は笑みを浮かべながらアイ・ラブ・ユーと言った。
前を向く。壁だ。壁には鏡がかかっている。鏡に自分を映してみると、そこには女の顔があった。濃いメイクアップがほどこされた白い顔。僕はポケットから化粧品を取り出し、眼の周囲に真っ赤なアイラインをひき、唇に緑色のリップスティックを塗った。
鏡の中、僕の背後に螺旋階段が見える。それはドリルの先のように闇に落ち込んでいる。深く深く底に続いていて、下方の果てから何やらランプの灯りのようなものが上ってくるのが微かに見える。急に自分から何か丸い物が落ちた。落ちたのはあの少女の手毬か? 転がり落ちていく、転がり落ちていく。ランプの灯りにむかって転がり落ちていく‥‥‥‥目を凝らすと手毬ではなかった。それは僕の首だった。僕はここで自分の首が転がり落ちていくのを見下ろしている。
あの少女が再び現れた。少女はやはり手毬をかかえている。よく見ると手毬は切った髪の毛の束でできている。少女の長い髪が水中にあるかのように、風になびいて宙にゆっくりと流れる。はるか彼方から遠く時間をさかのぼり、その情景がここにありありと見える。神の予定さるべき回転軸が、赤い手毬の糸を巻きとる。今、手毬が少女の指先から転がり落ち、フロアーに崩れた。それは青白く柔らかい僕の脳味噌。
花菱はそこで音声を止めた。
「そこから先は録音されてないんですか? その後に何か怪しげなもう一人の男が出てきたような‥‥‥詳しくは憶えてないんですけど、周りに誰もいないのに何故か誰かに見られていた記憶が残っているんですが」
そう赤井君が尋ねる。
「なにアホ言うてまんねん。君だって先祖の墓参りぐらいは行くじゃろうが。誰だって墓地に行けば、周りに人がいなくても何かの視線は感じるぞ。霊かなんか、よう知らんが。そんなのありふれたことじゃわい」
「あ、そっか。言われてみれば」
「寝入り際、脳波がアルファからシーターに移行するあたりはワシらの収穫期なんじゃが、寝坊助の君ことだ、ここでストンと眠りに落ちたんじゃないのかね。目を開いたまま見る夢もある。ここからも霞ゆく夢の続きがあるのなら、目を開けたまま夢を見ていたんだ。ホンマモンの夢じゃあ。君は現実だと思っとるらしいが、夢だと気づかなかっただけのことじゃ。とうの昔に賢明な読者はそのことに気づいておるぞ。ま、それはともかくその夢、おもろいヤツやったか。だったらしっかり思い出して記録しといてくれ。以前ICレコーダー持って歩いて、いいのが浮かんだら録音しろと言ってなかったか? まだ言ってなかったら、これからそうしてくれ」
たしか箱村も同じことを言っていたな。いつでもどこでもその都度浮かんだことの記録をとれと言われてもなあ。浮かんだイメージのポイ捨て罷りならぬって、僕は歩く携帯式灰皿なのか。
「まあ眠りに落ちても、死なずに目覚めたからいいじゃないか。目覚めて心がそのまま仏になっていたら、なおいいんじゃろうがな。人生、そんなウマい具合にはいかんわい、そうじゃろう」と花菱。
「は? ああ、そのことなら勿論大丈夫です。目覚めた時ちゃんと肉体はありましたから」
トンチンカンな受け答えをしてしまった。なんせ彼の話自体が元々とらえどころがないので仕方ない。だが花菱はそんなことは気にもとめず、
「うん、圧巻だ。なかなかいい。屈指の仕上がりだ。旨みたっぷりの、こってり濃厚スープじゃな。上出来だぞ。君もこの仕事が板についてきたようじゃ。狂気と隣り合わせじゃな。そこが強みだ。君はオミクロン株もビビりあがるウイルスの変異種だ。もう完全に気違いアートの域じゃな。シュールここに極まれり、こんな狂いに狂った才能はなかなか掘りだせない。君は値千金の希少金属、レアアースじゃ。ちなみにレアアースといえば中国だな。最後の方に出てくる首チョンパのイメージはアレか。いまXで炎上している、イカれ中国総領事の汚い首斬ったろか発言の影響か? こいつ、アホちゃうの。お勉強のできる外交官のくせに、そんなことXに書き込んだらいずれ我が身もクビにされちゃうことぐらい分からんのやろうか。それともコレかなぁ、ビートたけしの映画『首』。ちょっくら前の話だけど、君もアレ見て潜在脳が触発されたんとちゃうんか」
「さあ、分かりません。この頃にはもう喋っているのは僕じゃありませんから。得体のしれない他人が喋ってるというか、そんな感じ」
花菱のマシュマロ顔がほころぶ。褒めているのか貶しているのかよく分からない。笑っているところをみると褒めているんだろう。
ワッ、この丸顔、ふわふわ御菓子じゃないの? 何だかうまそうだ。プヨプヨ感がたまらない、思わず食べたくなっちまう。
「うん、秀逸だ。赤井君、君自身の感想が聞きたい」
「なんか聞いてると薄気味悪いですね、ドン引きしちゃう。胸糞悪くなりません?」
「アホぬかせ。そんなことあるもんか。恐怖のあまり、少女の手毬となって自分が夜の谷間に落ちていく幻覚に襲われる‥‥‥‥何か知らん、鬼気迫る情景じゃないか。背中がゾッとするじゃろう。きっと限りなく長い、永遠の夜のなかに転がり落ちていくんじゃろうな。強烈な落下の恐怖だ。運命に突き落とされた男。落伍者の君にピッタリだ。そこには滅びゆく者の悲劇が切々と詠われている。バッチグーじゃよ。グロテスクなものほど美的処理をほどこした後の芸術性は高いんじゃよ。真の芸術家たるもの、崩れゆくものにこそ美を見出すべきなんだ。廃墟の美学だよ。君は芥川龍之介の『地獄変』を読んだことはないのか。猟奇的シチュエーションがNGなら横溝正史文学の立つ瀬がなかろうが。心にもない謙遜はするな」
はて? 心にあるもないも、別に謙遜などしてないが。
「なにが薄気味悪いだ。人生という劇が終われば誰しも、死の緞帳がその光る刃を自らの首に落すんだ。みんな平等だ。誰一人逃れることはできん。そのとき、君も、ワシも、誰もかれも、自身の影を寸断されることになるんだ。そして永遠に再び影となりえない影として、虚空をさまよわなければならんのだ。そのことを踏まえたうえでの“薄気味悪い”なのか。違うじゃろう」
あくまで首にこだわり、シリアスに語る花菱。何でそんな気色の悪いものにそこまでこだわるんだろうか。ただし本人はシリアスなつもりなのだろうが、外見がボテーッとした豚なので深刻ぶればぶるほどコミカルに見える。思わず噴き出してしまいそうになる。
「君の才能の話に戻ろう。たとえば君が道路を転がる紙屑を見たとする。夢茶に酩酊した君はそれを見て、直ちに女体を急速度で滑り落ちる金平糖を想起するんじゃ。うん、正気じゃない。もう特殊能力だな」
自信満々の花菱である。なに訳の分からないことを言っているんだ、付き合いきれない。
「なんというか、アンバランスと意外性の妙じゃな。普段アホまるだしの男が突如狂人に豹変するんじゃ」と花菱は嬉しそうに言葉を継ぐ。
「アンバランスと意外性とはどういうことですか、具体的に僕はどういう男なんでしょうか」
「つまり、だ。つまりクリスマスの長靴から出てきた生首みたいに醜悪で、女の尻の茂みから生え出たチューリップみたいに滑稽な男ということじゃ」
あん? また“首”が出てきたぞ。導火線に火をつけてしまったようだ。僕がボックスで見た幻覚の煽りを受け、ゲテモノ好きの花菱の官能が刺激されてしまったらしい。こりゃ、相当いっちゃてるな。アバンギャルドもここまで突き抜ければ大したもんだ。そもそも“具体的に”と訊いてるのにどうして比喩で説明するんだ。それも一方はオカルト的、もう一方は何とも御下劣でな比喩だ。どっちに向かっている。
だいいちクリスマスプレゼントの長靴に生首のような大きなものが何で入るのか? 長靴から出てくると言うが、生首にぴょこっと脚がはえて出てくるんだろうか。そんなの、猟奇というよりお笑いでっしゃろ。せっかく長靴に入れたのに、勝手に出てこられちゃサンタクロースも困るじゃないか。そもそもサンタのプレゼントの配達場所は長靴なのか。入れるのは確か靴下じゃなかったっけ?
赤井君はこんなふうに、細かなことに妙にこだわってしまう質である。裏返った手袋や下着が目の前に散乱しているのを見るかのように、微妙に神経がささくれ立つことがある。どうでもいいことなのだが、なぜか気になる。きちんと整理したい。粗雑な性格で服装はこんなにだらしないのに、言葉には変に偏執的になる事しばしば。些細なことが気になりだすと、とことん気にする。痒ければ傷になるまで掻いてしまうのだ。どういうわけだろうか、最近ますますその傾向が顕著だ。
そんな下らないことなど神経質にならず軽く受け流してしまえばすむものを、どうしても流せない。詰まった便所だ。同じ人でも理性と感性は違うので、こういうことは誰にでもあるに違いない。だが、堪えきれずそれを口にしてしまえば周囲は迷惑なだけだ。少なくとも彼は口に出さないので幾らかマシか。口に出せば本格的にアホまる出しになってしまうのだが、口にしないので何とか頭隠して尻隠さずにとどまっている。
そんな赤井君の思いもよそに、花菱は一人でヒートアップする。彼は開けっぴろげの言いたい放題。頭も尻も隠さない。完全にストリップだ。毎回毎回、太っちょのヌードを見せつけられる身にもなってほしい。
「見込んだとおりじゃ。実際、夢茶の力なんぞ微々たるものだ。君の場合、心の嘔吐が生活の片鱗を研ぎ澄ましておるんだ。じゃから常人とは異なり、イカれた才能が花開くんだわさ」
わっ、ますます意味不明。これって事故レベルじゃね? イカれてるのはアンタのほうだろう。
「アンドレ・ブルトンばりの、いやそれ以上の自動記述じゃよ。もともと現実と非現実は表裏一体だ。じゃが、残念なことにこの二つの世界の間には覗き穴がない。ところが君は、あのボックスのなかで表裏のない曲面、すなわちメビウスの帯となり現実と非現実を連続させたというわけじゃ。それが証拠にシナリオのない世界で潜在意識のおもむくままに語っておるじゃないか。まったく技巧を凝らしてないとこがいい。しかも、だ───しかもその言葉の混沌の中から、ある種の秩序さえ生み出されつつある。いうならば昇華だ」
「は、はあ(?)」
もうアカン、ついていけん。正面衝突、即死だ。褒めてくれるのはもちろんうれしい。けどこの録音って、夢茶に酔ってクダ巻いているのを記録したにすぎないんでしょ? ただ僕の酒癖ならぬ夢茶癖が、超絶悪いのを証明しているだけだと思うんだけど。
「マラソンじゃないんだぞ。“はあ、はあ”言ってないで、何か思うところはないのか」
また意見を求めてきたぞ。やれ困った。何をくっちゃべったらいいんだろうか。まあ適当に褒めとくか。
「さすがぁ、社長のおっしゃることは深いですね」
「うん。バカだと思っとったが、ワシの分析についてこれるとは案外、利発な男じゃな。ちなみにどういう点が深いんだ。興味がわく。言ってみんしゃい」
え? そうくるの? そりゃダメでしょう。困った、困った。
「あの~、その~、つまり~、結局ぅ~、少なくとも浅くはないですね」
「君は何を言っとるんじゃ」
「“深い”という表現がふさわしくないなら、これはどうですか? いやぁ〜花菱社長のおっしゃることは渋い! 考え方に落ち着いた味わいがある。“渋い”ならいいでしょう。どうです?」
「ワシャ、柿か」
「おっと、と、と、と‥‥‥あの~それはそれとして、混沌の中から秩序が生み出されるってどういうことですか?」
「いいポイントじゃ。サソリの毒が化粧品の原料になることは知っとるな」
「ええ、他にも医薬品の原料にもなったりするそうで」
「そうじゃ、よく知っとるじゃないか。君は頭がカラだから、赤ん坊が言葉を覚えるみたいに、何でもかんでも自然にどんどん入ってくんのかいな。こりゃ屑入れじゃわい」
「いえ、たまたまどこかで聞き齧っただけです。たんなる豆知識ですよ。それはそうと僕って空っぽの屑入れなんですか?」
「いや、いくら何でもそこまではいかん。卑下すんな。ワシも無闇やたらにゴミを投げ入れようとは思っちゃおらん」
え、なんでそうなるの? 卑下なんてしてないけど。てか、いままでずっとゴミを投げ入れられてたんかい。
「何や分からん得体のしれない毒液が、女の肌にのれば妖艶な美貌に変わる。真の美というのはドロドロと汚れたものの中にこそ花ひらくものなんじゃ。濁った泥水の中にこそ美しく睡蓮は咲く。薔薇も肥料をやるから美しく育つ。社会に認められず抑圧された君の性的エネルギー、いわばイドが混沌とした君の無意識のなかで芸術性に置換されたわけじゃ。すなわちこれ、精神分析用語で言うところの昇華だ。君の紡ぐ言葉は、さながらボードレールの悪の華じゃわい。たとえば君が眼の周囲に真っ赤なアイラインをひき、唇に緑色のリップスティックを塗るシーンがあるな。ありゃゲテモノ描写だ。そこがいい。あのゲテモノ趣味の何がいいかというと、普段意識している表面上の君と意識できていない真実の君との乖離を、図らずも暗示しているからじゃ。それは偽善と言ってもいい、虚飾と言ってもいい、無自覚と言ってもいい。まあ、大概そのどれかじゃろな」
空理空論をもてあそぶ花菱。付き合ってられない。この人の脳ミソはぐちゃぐちゃに入り組んだ迷路だ。そこを歩かされる身にもなってほしい。
「はあ? 何をおっしゃってるんです?」
「何をおっしゃる兎さん、ってか? つまりじゃ、この時点で君はもはや君ではなくゼロにもどったんだ。真っ白な無地に新たな模様を描きだそうとしておるじゃないか」
「何のこっちゃ」
「分からんのか。外国旅行に行く金もないくせに、なんで朝っぱらから時差ボケなんかい。世話が焼けるヤツじゃ。よく自我に目覚めるというだろう。その反対じゃ。簡単なことじゃないか。変な言い方じゃが、“自我に眠る”ちゅうかな」
「ちゅうか、ちゅうかの、本中華」
「おい、変な言葉遊びはすんな、そんなの、少しもウケんばい。笑いの本場、大阪でそんなアホっぽい茶々を入れようものなら、刻まれてタコ焼きにされるぞ。みじん切りばい」
よく言うよ。アンタだって高木ブーがブヒブヒ鳴くだけだから、豚肉入りお好み焼きでんがな。鉄板の上でパンパン叩かれて平べったくなるのがせいぜいっしょ。う~ん、なんだかお腹がすいてきちゃったな。まったく、僕という男はどこまで食い意地が張っているんだ。
一方花菱は困り入った様子で、
「アホにどう解説すりゃいいのかなぁ、なかなか針に糸が通らんわい。君レベルまで下りていくのは大変じゃ。まあ平たく言っちゃえば、君は口ぱくアイドルになったんだ。歌っているように見えて実際は歌っていない、口だけパクパク、そういうこっちゃ」
完全に「テキトーにあしらっとけ」モードだ。苦しまぎれに口から出任せを言っている。子供じゃあるまいし、そんな説明で煙に巻けると思ってるんだろうか。
「はあ? もっと分かんなくなりました。それ、ヒントにもなってないですよ。もっと僕にも分かるように‥‥もう少しで痒い所に手が届くんですが」
「痒い所に手が届くって、一般的にそんな使い方はせんじゃろう、まんまじゃないか。今の若者はそんな使い方をするのか」
「いいじゃないっすか、ハチャメチャな日本語で。そういう感じが好きなんでしょう。なにごとも既成の枠組みにとらわれない、自由奔放な着想の方が」
「そりゃそうじゃが‥‥‥うん、そうじゃな。型にはめられてたまるか」
「やっぱり箱村さんが推測する通りこのお方、B型でありまする」
「なんじゃ?」
「いえいえいえ、こっちの話。もう少しで届きますんで、レクチャーを」
「痒いってどこが痒いんだ、背中か。どっかに孫の手が仕舞ってなかったか。そこまで言うならワシがかいちゃるぞ」
「かくって何を? マスですか? ア~そこ、そこ。逝く~ゥ」
(*~ρ~ ) エロ~い、ちんぽっぽ♪
───静寂。
笑いをとれると思ったら、コテッとこけてしまった。ジョークがお気に召さなかったらしい。うまくいかないものだ。仕方ないかぁ、しょせん僕にはトランプ大統領やラトニック商務長官の懐にうまく取り入る、赤沢大臣ほどの人間力はない。
「老人をおちょくって、そんなに面白いのか。こしゃくな奴だ。このマスかき小僧が。そこで一人でシコっとけ。おかず無しじゃ」
「失礼しゃあした。でも理解できないんですよねぇ」
「やれ、困ったな」
どうやら詰みらしい。太った王様の逃げ道はもうない。といっても論戦らしき論戦をした結果ではない。赤井君は相手が根負けするまで「分からない」を繰り返しただけのことだ。バカが利口に勝つ唯一の戦術───「まだピンとこないんですよ」論法である。バカは豪速球を投げようとしてはいけない。ぬる~~いサブマリン投法でいくべきなのだ。
「まあ結論を急ぐな、物事には順序がある。結婚式にも、葬式にも、入学式にも、卒業式にもちゃんと式次第があるじゃないか」
「は、はあ」
「曲がるときには前もってウインカーを出さなきゃな。突然曲がっちゃいかん。そんなのルール破りのトランプ関税といっしょじゃろう」
一生懸命、取り繕っている。赤井君のしつこさに、とうとう音をあげてしまった花菱である。
「赤井君、想像してみろ。もし鏡の像が君が笑う前に笑ったとしたら恐ろしいだろう」
「そりゃ、恐ろしいですね。ホラー映画です。ぞっとして身が縮んじゃいますよ」
「身が縮むだろう。君はもっと小っちゃくなっちまうんだぞ、それでいいのか。物事には順序が大切なんだ。そういうことだ。いいか、必ずしもいま理解するには及ばん。人生の荒波に処したくば、速く泳ぐより長く泳ぐことを考えることじゃ。赤信号は止まらにゃいかん。焦るな、プランクトンみたいにプカプカ浮かんどけ。人並みの暮らしが長く続くことが一番じゃろ。大急ぎで上りつめようとしちゃいかん。いつか君にもワシの含意が読み取れる時がくる。成長するのを待て。ところで解説するまでもないが、いま“波”と“並”をさりげなく掛けたんじゃぞ」
アホらし。誰がそんな細かなことに気づく。たまたま同音異義語だっただけじゃないか。もう語呂を無理に合わせようとするはよしましょうや。お腹がゴロゴロしてきそうだ(😬オモロナ~)。だいたい負け惜しみがしつこくて大袈裟。プランクトンって、僕は浮遊生物なんかい。
「赤井君、歌にもあるだろう、月が青くて綺麗なら遠廻りして帰るもんじゃ。そうじゃろう。そうは思わんか」
まだ負け惜しみが続いている。往生際が悪いですよ。根負けしたのに、みっともない。誤魔化して懐柔しようとするのはよしましょうや。もみ消そうとするんじゃなくて、男らしく負けを認めなさい。
「それ、歌じゃなくて夏目漱石じゃないっすか? I love youを“月が綺麗ですね”って訳したっていう」
「なにピント外れを言うとるんじゃ、菅原都々子の名曲じゃろうが」
「菅原都々子? 誰っすか? その人、有名な人なんですか?」
「これじゃから知識のない若者は困る」
「でも‥‥‥」
「“でも”もストライキもあるか! 民主主義国家でも君のシュプレヒコールなんか怖くないぞ。馬鹿のくせに口答えするな!」
「は、はあ」
と、渋々ながら上辺では一応うなずく赤井君。“でも”もストライキもナンタラというのは、どうやら花菱と箱村の定番表現らしい。
「たとえば君は偽善とはどういうことだと思うか?」
案の定、変化球を投げてきた。しれ~っと話題を前にさかのぼるとは、論点ずらしでっか。
「あの、見せかけだけ善人ぶるとか‥‥‥」
「いやいや、聞いてるのは辞書にのってる意味じゃない」
「え?」
誰がどう考えても辞書に載っていない意味など分かるワケないよな。正答のないパズルを解かされたんじゃたまらないよ。
「偽善───それは鏡のなかの厚化粧のことじゃよ。君の経験した幻覚そのままじゃないか、ただ君の場合は偽善とはちと違うんだけれどもな、偽善というよりは‥‥‥」
「あの、まだ意味がちょっと‥‥‥」
性懲りもなく「まだピンとこないんですよ」論法を続ける赤井君である。
「‥‥分からないってか? お天道さまは真上にあるぞ。いつまで寝ぼけてるんだ。君的にはまだ夜が明けていないのか。島崎藤村か」
「え、なんです?」
「やっぱり寝ぼけておるな。『夜明け前』じゃろうが。そう、かの有名な『木曽路はすべて山の中である』から始まる長編小説だ。こんなの誰でも知っとるぞ。シャレの通じん奴だのぉ」
「島崎藤村というよりは志賀直哉です。暗い夜道でよく見えてこないんですよ~ぉ」
「それ、『暗夜行路』じゃろうが。見え見えじゃわい。ワシのギャグパターンをパクるなら、もっと上手にパクりんしゃい」
「はあ」
当てつけがましく言ってくる花菱。ぺしゃんこにされてしまった。僕はパンクしたタイヤなのか。
赤井君はしょぼんとする。確かに下手クソすぎてバレバレだ。あまりの下手さに赤面してしまいそうだ。
「言いたいことはだな、君の場合は複数の顔があるということじゃよ。目の前にしたその鏡には幾つもの君の顔が映っている。観るところ最低三つの顔があるな。一つは仮面で、もう一つは素顔。そして素顔の奥に君の気づいていないもう一つの顔がある。真実の君の顔じゃよ」
「はぁ? ねえ、箱村さん。この意味、分かります?」
と助けをもとめれば、隣に立っているはずの箱村がいつの間にか消えている。援護射撃してもらおうと思ったら、するりと敵前逃亡だ。どこに鳴りを潜めているのやら。お喋り箱村が押し黙ってウンともスンとも言わないのはおかしいと思っていたらこうだ。やけに大人しかったのは遁ズラのせいだったとは。
このように箱村は花菱が話し出すとプイッと何処かへ行ってしまうことが多い。逆もまたしかり。どうにも食い合わせが悪い。ウナギと梅干、スイカと天ぷらだ。
僕がいなくて二人きりだった頃はどんな状態だったんだろうか。聞き役や仕切り役がいないせいで、かつての「朝ナマ」や「そこまで言って委員会」みたいなカオス状態になっていたんだろうか。いざ闘いの火ぶたが切られるや、にらみ合いのすえ口論がいつの間にやら取っ組み合いの大喧嘩に。そこでは言いたい放題のボクシングバトルが繰り広げられていた───なんて感じだったのかなぁ。
箱村は以前、「そんなことはない。こっちが正論を吐けば花菱は反論できないので、怒り狂うだけで即終了だ」などと大口たたいていた記憶があるが、はなはだ疑わしい(霞ゆく夢の続きを〈3〉─22)。
お喋りイカサマ師どうしの一騎打ち。なんだかそこ、知りたい。国会本会議のヤジの応酬合戦は白ける一方で、つい面白くて見続けてしまう。いわゆる怖いもの見たさの興味である。
実際、ふたりとも大人げないったりゃありゃしない。こんな少人数の零細企業で互いに張り合ったところで、せいぜい掛け合いの漫才でんがな。とてもドラマ仕立て内部抗争とはいかないっしょ。たった三人しかいないんじゃ、どんなお家騒動もコップの中の嵐。てか、お猪口の中の泡でっしゃろ。
「あれ? 箱村さんどこに行っちゃたんだろう」
「瞬間移動でもしたんじゃろう、どアホが」と花菱。
「え?」
「アイツまるごと遺失物か。どうせあっちの部屋で、草花とかをいろいろと調合して遊んどるんじゃわ。アイツはあの部屋にリンクが貼ってある。自分が喋れないと途端に機嫌が悪くなって、ワンクリックであっちに飛んでっちまうんだ。そこで勝手に沼っとけ。アレじゃよ、あれ、マズくなったら机を叩き、怒ったふりして席を立つ、アレじゃ、北朝鮮の外交交渉だ。なにをムクれてんだ。まったくアイツときたら獅子身中の虫じゃわい。木彫りの鯛みたいに煮ても焼いても食えん野郎だ。アイツとは結構長い付き合いなんだが、ずっーと悩みの種じゃ。この弱虫め、ワシの実力に恐れをなして敬遠のフォアボールときやがった。いつも落ち着きがない。風の吹くまま気の向くまま、あの歳で自分探しの旅とはな。お前はフワフワと飛んでいくタンポポの綿毛か。それとも浮草か。クサを研究しよる自分がクサじゃないか。薄っぺらい奴じゃ。今日からアイツをペラ男と呼ぶことにしよう。あれで研究者気取りとは厚かましい。図体がデカいだけで草食恐竜なみの脳ミソしかないくせにのぉ。あん、背高ノッポがぁ。なに食ったらあんなにデカくなるんだ。そう言やあ、恐竜をはじめとして草を主食にしてる動物の方が形はデカいな。アイツは草食ってあんなにデカくなったんばい。そんなに草が食いたけりゃ、あの部屋にかいば桶でも置いといちゃろか。ああいうのをホンマもんの無芸大食ノッポって言うんだ」
無芸大食ノッポ? なんだ、それ。“ホンマもん”っていうけど、こんなの初めて聞く言葉だ。勝手に言葉を作んなよ。新語流行語大賞にでもノミネートされたいのかな。
「形ばかり大きいが、中身はただのガキ。頭スッカラカン、あんこの入ってない饅頭じゃ。デカくたって少しも偉くないぞ。そのうち茂みからヌッとひょろ長い首が出てくるわい。ほっとけ、毎度のことじゃい。そこで草でも食っとけ。これぞ文字通り道草を食うだ、ワッハッハッハ~」
よくもまあ、それだけズラズラと悪口が出てくるもんだ。おまけに最後には笑い出したりして。いったいぜんたい、自分が言ったギャグに自分がそこまで笑えるものなのだろうか。それってそんなに面白い? やたらめったら昭和ギャグを繰り出すな、つーの。
いつも花菱はつまらないネタで急に笑い出す。そう言えば、どうでもいい事で突然ヘソを曲げたり、小言幸兵衛になって怒りだすこともよくある。笑ったり怒ったりと、気候変動の激しい人だ。こんな起伏のある山に登らされる身にもなってくれ。高くなったり低くなったり高低差がありすぎる。
どこを刺したら黒ひげ人形は樽から飛び出るのか。ハラハラドキドキ、そのたびごとに気をもむ小心者の赤井君である。ドナルド・トランプなみに御機嫌取りに神経をつかう。
「道端に生えてる草を食べたらマズいですよ。せめて夢茶みたいに煎じてもらわないと」
「うわっ、赤井君、そ、そこまで言うのかぁ。おもろすぎじゃ、ワッハッハッハ~、こりゃ腹が痛い、誰かなんとかしてくれ〜ぃ。悶絶する~ぅ。殺す気かぁ」😆…ギャハッハッハ~
花菱の笑い声が響き渡る。手足をばたつかせながら、ますます大声で笑っている。とどまることを知らない。なんでこんなのが面白いのか。
「箱村さん、夢茶の新バージョンでも作ってるのかなぁ。あの、夢茶ってホントに合法なんですか? 実は前からずっと、ちょっぴり心配なんですが。とつぜん僕の住んでるとこにマトリがやってきて、お縄を掛けられるなんてことにはならないでしょうね」
「なるもんか、酒は百薬の長と言うじゃないか。酒がそうなら草も薬クサ。草で病気や怪我が治るから“薬草”という言葉があるんじゃろうが。たとえばゲンノショウコは下痢止めに効く薬草だと広く知られとるじゃろうが」
「ゲンノショウコ? 何ですか、それ」
「おやおや、ゲンノショウコも知らんのか。君は小学校の理科の時間、何しよったんだ。どうせ授業中ボケーッとして給食のことばかり考えとったんじゃろう。そんなに食いしん坊なら、薬膳料理を食べたことぐらいはあるな、ないんか。だったらかの有名な養命酒は知っとるな。昔はテレビコマーシャルでよう宣伝しよった。あれはどうなるんじゃ。ありゃ薬用酒じゃろう。ラベルにもちゃんとそう書いてある。言ってみりゃ万能薬だ。あれが万能薬なら夢茶も万能薬ばい」
なんでここに養命酒が出てくるんだ。養命酒そのものよりも、養命酒を引き合いに出すアンタの思考回路がどうなってるかの方が気になる。はては万能薬などと開き直られてしまうと、ますます夢茶が眉唾物臭く思えてくる。
「まさかフェンタニルとかが混ざってないでしょうね」
「アホじゃな。医者でもないワシらが、どうやって合成オピオイドを入手するんじゃ。フェンタニルが混ざっとたら、今ごろ君は死んどるよ。いい若い者がなにをビクビクしとる。少しはリスクをとらんかい。裸足で歩いても土踏まずは汚れんぞ」
「でも少なくとも健康的じゃないっすよね」
「だからさっき万能薬と言ったじゃないか。君のお頭は吹き抜けか。何を聞いとるんだ。万能薬だったら健康的じゃろうが。飲んだ後、性欲モリモリになったろう。あれは老化防止にも効く。老け込んでしまわないようワシらも愛飲しとるんじゃぞ」
「あ、そうか。そういえばそうだったですね。それ、思い当たるフシがあります」
「そうじゃろが。いくぶん頭が変になるが、あれは毒をもって毒を制しとるんばい。アナフィラキシーショックや多臓器不全を引き起こすハチ毒や、ハブの猛毒が医薬品の開発・製造に役立っとることを知らんのか。ハチ毒やハブ毒がアルツハイマー病の原因物質の分解をうながすことも、もうラットを使った研究で実証されとるんじゃぞ。そんなことも知らんくせに分かったふうな口をきくな。毒があるからってフグを食べたら捕まるのか?🐡 ハブ酒は違法なのか?🐍 何の問題もなかろう。健康にいいから沖縄じゃ居酒屋でみんな飲んどるじゃないか」
「え? 僕って毒なんですか?」
花菱がドッと噴き出した。これも受けた。文脈を取り違え、あまりにおバカな質問をしたせいらしい。いいぞ赤井君、抜群の理解力だ。
「ガハッハッハ~~、君はなにを言っとるんじゃ、年寄りを笑い漬けにするつもりか。この人殺し~ぃ」
「だって“毒をもって毒を制す”とおっしゃったじゃないですか」
不服顔の赤井君に対して、
「そうじゃ、そうじゃ。見るからに毒じゃ。毒の塊じゃ。糞ころがしが、鼻糞をころがして糞ダルマを作っとるんじゃがぁ。君をデトックスしたら後にはな〜んも残らんばい」
と、さらに笑い物にする花菱。下品このうえない。
「でも、ホントに夢茶って大丈夫なんでしょうか。心配で」
「まだ言うか、夢茶、夢茶とくどいな。オツムはどうなっとんじゃ。赤ちゃんにもどってオムツでもつけるかぁ? そこまで夢茶、夢茶と言うなら、君、芥川賞じゃなくて茶川賞を目指したらどないや」
芥川賞と茶川賞? 最悪だ、花菱ギャグもここまで落ちてしまうとは。思わず失笑してしまった。見事にバットが空を切っている。おお寒い。寒冷前線でも通ったか。開いた口が塞がらない。
「どうした、口をポカンと開けて。嗽でもするつもりか。そうか、ワシの爆笑ギャグの出来栄えに感心して言葉を失ったんだな」
「へぇ、そうなんですかぁ」
ギャグの不発に気づいていない。失笑されたのに受けたものと早とちりしている。自信家というか鋼のメンタルというか。花菱は顎を撫で撫でさらに力説し続ける。
「“へぇ、そうなんですかぁ”とワシに尋ねてどうするんだ。どうもさっきから君は夢茶を信用せんようだ。じゃがな、今ここで石を見せられて、これは“中国月面探査機が月の裏から持ちかえった石だ”と言われたら信じるしかなかろう。何故って、それを確かめる手段がないんだから、嘘を立証できんじゃろう。それが嘘だという根拠は? また、その根拠を裏付ける実証データは? 何もないじゃろう。それともアレか、君にはロボットアームで月面上のサンプルを採取する技術と金があるとでもいうのかね。夢茶もそれと同じじゃと思っとけ。だいたいド文系の君は夢茶の化学式すら書くことができんじゃろうが。ついでに言っとけば死後の世界や因果の法も夢茶と同じじゃ。どんなに頭がよくても信用しない者はとことん信用せん。いくらIQが高かろうと、そういったことが分からない者のことを馬鹿というんだ。たとえば“神が人をつくったのか人が神をつくったのか”───そういった根源的な問いに論理的な答えを出そうとしたって不可能じゃろう。結局は感じるしかないんだよ。むろん彼らだって、死んだら夢から目覚めて、忘れていたその真理を思い出す。人の心や魂はそんな単純なものじゃない。死んでみて初めて知るんじゃ。肉体と違って死んだら撮影終了、クランクアップとはいかんことをな。これが“馬鹿は死ななきゃ直らない”の本当の意味だ」
なんという屁理屈だ。因果応報は僕も信じてはいるが、なんせ話があっちこっちに飛んで、何を力説したいのか理解不能。理屈の道筋に混乱して迷路にはまってしまう。こりゃ、吹き替えがいりそうだな。
「逆に死後の世界も因果応報も知らないほうがいい気もするんですけど」
「どうしてじゃ」
「人生なんて大仕掛けのトリックじゃないですか。タネを知ったら価値がなくなっちゃうでしょう」
「こりゃ、痛撃をくらったな。運動オンチの君にしては鮮やかなリターンじゃないか。なかなか味のある反論だぞ。じゃが、その見方は正しくない。小泉構文ならぬ、赤井クン構文でワシの頭脳崩壊を企てたところで無駄なあがきじゃ。君の知能指数でこれほどの根源的な命題を解こうするとはド厚かましい。危なっかしいんだよ。マッチ棒パズルでも解いとけ。そんな軽いもんじゃないんだよね」
───確かにアンタは重いよね。だって体形がまんまるガスタンクなんだもん。
「はい、重く受け止めさせていただきます」
とりあえずシャレでそう言っておいた。
「だいたいワシャ、高学歴・高IQの学匠的知識人は気に食わんのじゃ。アイツら似非博学面して“死後の世界など存在せん、いわんや因果の道理をや”とぬかすが、なんも分かっちゃおらん。象牙の塔という巨大な果実の中に潜りこんだ蛆虫じゃ。亡霊といっしょで、もう自身が白骨化してることすら気づかないんだ。自然科学の凝固剤にカリカリに固められて、もはや体を切り裂かれても血もでまい!」
完全に詩人になりきっている。自分に酔って口角泡を飛ばすのはいいが、芸術家っぽく抽象的な言葉を並べるだけで、具体的な中身がないので、まるで説得力がない。
「監督の“はい、カット”という一声で、切られ役も息を吹き返す。死んで生まれて、また死んで生まれて。ぜんぶ脚本どおり───これが生死循環のメカニズムじゃ! 流転輪廻じゃよ。肉体なんぞ魂にとっちゃ舞台装置と同じで、劇が終われば用済みだ。万物は流転する。仮面ライダーもショッカーも死ねばいっしょの楽屋で弁当を食べることになるんだ。ところで赤井君、『キューブ』っていう外国映画を見たことがあるか」
「ああ、あります、あります。あれ、怖い脱出劇ですよね。立方体の各部屋に仕掛けられたいろいろなトラップが特に」
「人の生涯というのも、一見あの『キューブ』と似たり寄ったりだと思わんか。もちろん実際の人の生涯には、あの映画みたいなエグい死のトラップはそうそう仕掛けられてはおらんがな。要するに人生なんてワシらが今いるこの部屋といっしょなんじゃ。いつとは知らずワシはドアを開けて入ってきた。つまりこの世に生まれたんだ。たまたま君とここにいる。だがいずれドアを開けて出ていく。死んであの世に出ていくことになるんだ。そしたらまた別の誰かが入ってくる。入れ替わり立ち替わり。このように色々な部屋を出たり入ったりと、人は輪廻転生のループをクルグル回り続ける。君もそうなんだぞ。真理を見ぬけぬ者は、人の生涯は『キューブ』みたいな閉じた迷宮にすぎず、その中で永久にさまよい続けるのだと絶望する。現に人生には『キューブ』と同じ様々なトラップが仕掛けられているではないか、などと生きることの虚無感に支配される。そんなふうに考えるから生き地獄になっちまうんだ。人生は一見、『キューブ』と似たり寄ったりだが、実は似て非なるものなんだぞ。本来自分がいるべき魂の故郷が、迷宮の外側に無窮に広がっていることに気づけさえすればな。ここに気づきさえすれば、死はもはや恐怖ではなくて非常脱出口だ。火事で煙に巻かれそうになったら、そこから逃げりゃいいんだ。大事なのは逃げ方を知っていることだな。正しいやり方で逃げることができれば、また気が向いたらこっちに戻ってこりゃいい」
花菱が声高らかにブチあげている。興奮はとどまることを知らない。熱っぽく語るのはいいのが、かたや赤井君はといえば“ようやるわい”と欠伸を噛み殺している。
「どうした、心ここにあらずか。いつから頭が空っぽの部屋になっとる。『キューブ』の話を気にするあまり非常脱出口が見つからんのか。大丈夫だ。君がつぼみを咲かせる頃までには必ず夢遮断法を試させてやる。指切りげんまん、約束しただろう」
しばらくボーッとしていたら、花菱に不意打ちをくらってしまった。オナってる最中に、とつぜん非常ベルが鳴った気分だ。確かに上の空で別のことを考えていた。だってその嘘つき話、いままでに何回きいたか分からないんだもん。おまけに夢遮断法などという与太のおまけまでついてきて。
「すいましぇん、話があまりにも高度すぎて圧倒されていました」
おべっかで矛先をかわす赤井君。花菱は不満そうだ。
「一つ質問があるんですが」
「なんだ」
「迷宮の外側にある魂の故郷がそんなに素晴らしいところなら、なぜわざわざ再びこの世に生まれ変わってくるのですか?」
「そこだ、ポイントは。迷いの輪から解き放れる修行はこの世でしかできんからだよ」
「はあ?」
何を言っているんだ。まあホラ・虚言の類なら、いかようにも言えるな。そんなの確かめようがないもんね。
「意味が解らんのか。知的グレーゾーンにいる君ならそれも仕方ないか。おいおい懇切丁寧にレクチャーしてやるから待っとれ。で、ワシが力説しておる間、ボーッとしてどんな別事を考えちょった?」
「あのぉ〜、草をこねくり回して夢茶をつくるんじゃじゃなくて、どうせなら草餅でも作ってくれると嬉しいなと思って」
付き合いきれない赤井君は、冗談かましてクールダウン、すたこら逃げることにした。
だが、これがまた大受けしてしまった。見れば不満そうだったはずの花菱がソファを叩いて笑い転げだしている。その笑い上戸は何とかならんもんだろうか。笑ってばかりのこのお爺ちゃん、結構長生きするに違いない。笑えばメンタル的にもフィジカル的にも健康になるって言うしね。
「おお、それいい、それいい。大ばか者にしてはグッドアイデアじゃ。赤井君、どっかでヨモギでも取ってこい。どうせ暇じゃろう。昔はそこらへんに生えとったが、今じゃ山奥にでも行かんと生え取らん。こりゃ大仕事じゃわ。いっそ山へ秘湯巡りでもしにいくか」
あん? 今の本気にしたの? 冗談なのに。
「え~と、僕は桃太郎のお爺さんになるんでしょうか」
「なんじゃ、それ」
「山へ芝刈りに‥‥‥」
声が先細っていく赤井君。しまった、これ、言うんじゃなかった。
「は? ひょっとしてそれ、ギャグのつもりなん?」
あら、もしかして僕、赤っ恥をかいてる? うわぁ、穴があったら入りたい。完全に自爆だ。
「てへっ、芝刈りでなくて秘湯巡り‥‥んじゃなかった。ヨモギ刈りでした」
今さら釈明しようとしても遅いよね。
「おいおい、そういうことを言うちょるんじゃない。やれ困った、こりゃ重症じゃわい(www)」
「あら? 草を生やしちゃいました? まあまあ、そんなに突っ込まずに。つい条件反射で。ただの日本昔話でおま。はあ~~~クサを刈ったら臭かった、てな感じ?」
「およっ? なんじゃて? 今なんて言うた?」
「いえ、いえ、いえ、そこは気にせずに。せっかくご厚意ですが、山奥に行くのは遠慮します」
「なんでじゃ、旅費はワシのポケットマネーから出しちゃるぞ」
「熊と出くわして、あの世行きってのは嫌ですから」
「そりゃ心配ない。君の人生の台本は若くして死ぬことにはなっとらん」
人生の台本? この爺さん、箱村と同じことを言う。そんなこと分かるわけないじゃん。
「若くして死ぬことになってないんですか?」
「そうだ。じゃから山奥で出くわしたら、マサカリかついだ金太郎になって熊にまたがりお馬の稽古でもしたらいい。それでも死なん、生きてるよ。自分で強制終了せん限りはな。♪そりゃ、ハイシィドウドウ、ハイドウドウ。ハイシィドウドウ、ハイドウドウ。🐻」
「へっ?」
「自分のことなのに分からんのか。そりゃそうじゃろな。まだ仏の悟りをひらいとらんから仕方ない。クマったもんじゃ」
「クマわんで下さい。余計なお世話です」
「何でワシら、こんな下らんシャレが口から衝いて出てくるんじゃろうか。もう二人とも病気じゃな。箱村を笑えんばい」
「人の人生がどうなるかなんて分かるんですか?」
「もちろんじゃ、ワシは生き仏じゃぞ。人生は長嶋茂雄のメークドラマじゃないんだ。一見筋書きのないドラマのようでいて、実は誰しも筋書きがある。これは決まり事だから、非科学的だとか何やかやと、そこに異論を唱えてみたところで始まらん。いくら屁理屈をこねようが真実は一つだ。ワシには君の顔と君の人生の台本が重なって見えるんだよ。この前、半分ぐらいサラサラと飛ばし読みしてみたら、子供の頃ちょっと危ない時期もあったものの、図々しく生き続けちょる。そこそこ無難な筋立てじゃて。揺れの少ない遊覧船の人生だ。これまでずっと一人ぼっちだったからといって、過酷なヨット単独太平洋大横断じゃない。君は将来を憂うるに及ばん。卑屈になるな。♪明日という字は明るい日と書くのね~~」
「でも僕、ヨモギってどんなのか知らないんで」
「ありゃまあ、ゲンノショウコも知らんのかと思っていたら、ヨモギまで知らんとは。こりゃ、おっ魂消じゃ。テレビのお馬鹿クイズ大会に出演できるぞ。馬鹿の無限大かぁ、これぞ本バカじゃい。ヨモギ取りじゃなくて、いっそ石器時代にもどってマンモスと闘ってくるか」
花菱は笑いが止まらない。底のぬけたドラム缶になっている。僕の馬鹿さかげんに馬鹿笑いの垂れ流しだ。馬鹿が馬鹿を肴に馬鹿笑い───ああ、馬鹿馬鹿しい。ていうか、嘆かわしい。
馬鹿であることは間違いないが、よりによって“本バカ”とは。そこまで言わなくてもいいだろう。
「なんや、“本バカ”を気にしとるんかい。これは褒め言葉じゃ。褒めたんじゃよ。バカだから一服の清涼剤になれるんだ。お馬鹿タレントが本当は知能指数150だったとしたら、安心して笑えんじゃないか。“なんだコイツ、緻密に計算したうえで馬鹿を演技してやがる”になっちゃうだろう。そんなの興醒めじゃ。本バカだけが君の持ち味なんだぞ。近頃のカメラは精巧過ぎてピンボケがないだろう。君は昔はやったフジカラー“写ルンです”だ。お脳がピンボケだからこそ味があるんだ。それと〜ぉ、ちっこいから場所をとらないことも取り柄だな。刑事ドラマの他殺死体役でトランクにもすっぽり入る」
おいおい、しまいには殺されちゃったぞ。これで褒めたことになるんだろうか、疑問。
「なんだ浮かん顔して。ワシ、君を沈んだ気持ちにさせるようなこと、言ったか?」
「沈んでいるのに浮かぬ顔とは、これいかに」
「なんだ、それ。“ウマい!”と一声ほしいのか。でもマズいぞ、それ」
「これでも一流シェフのつもりですが」
「ちょ、ちょい勘弁。もうこれ以上、君のすっとぼけギャグの練習台にせんでくれや、後生だから」
「社長さんは、僕を褒めてるんですか、それともからかってるんですか?」
赤井君は追及の手をゆるめない。
「もちろん褒めとるんじゃ、何度も言わせるな。ワシャ重宝しとるぞ、君を。パッとしない奴ほど、いざというとき心のオアシスになってくれるんだ。いっしょにいて気楽でいられるだろう。地味でそのうえアホだからこそ、人に安心感を与えることができるんじゃろうが。ビールには枝豆じゃろう。君は枝豆だ。ワシらとすこぶる相性のいい、おつまみだ。君は使い捨てカイロだ。ちっさいから懐に手軽に入れることができて、冷え切ったハートを温めてくれるんだ。もちろん使い捨てたりなんかはせんぞ。君はミミズだ。ちっちゃい体でくねくね這いずり回り、土地を肥やしてくれるんだ。君は鯉だ。手を叩けば餌が欲しくて水面から顔を出す。可愛いやっちゃ、箱村とは違う。餌なんぞいくらでもくれてやるぞ。君は癒しだ。わがチームのマスコットじゃよ」
枝豆になったり、カイロになったり、ミミズになったり、鯉になったりと───これで褒めたことになるんだろうか、疑問。
「重宝してくれてるんですよね」
「もちろんじゃ、何度も言わせるな。大事なワシの秘蔵っ子たい。いわば君は自販機じゃな。コインを入れるだけで、ちゃんと仕事は忠実にしてくれる。便利じゃろうが。感謝しとるばい」
こんどは自動販売機にされてしまった。そのコインというのはまさかビットコインじゃないでしょね。ともあれ感謝しているとまで言われて気分のよくない人はいない。赤井君も単純に喜ぶ。憐れ、実際は馬鹿にされていることに気づいていない。
「僕って他人の目からどんなふうに見えるんですか、そこまでお馬鹿風なんでしょうか?」
「こらこら、外見なんか気にするな。ゴシック文字みたいにもっと太っとく生きんかい。うん、といってもそんなガリガリじゃ無理かな? まぁ、ともかく君は君じゃないか。君は君であるからして意義があるんじゃ。スポットライト効果にもろハマりだぞ」
「何すか、それ」
「スポットライト効果も知らんのか。このイカレポンチの、オタンコナスの、オタンチン! 簡単に言っちゃえば、自分が実質以上に注目されていると勘違いしてしまうこっちゃ。大学の一般教養で心理学をとってなかったのか? 君にとって大学は何のためにあるんだ」
「さあ。貧乏な親が苦労して、やっとこさ行かしてくれたから行ってるだけなのかな。そのせいで今、僕が金に窮して苦労してるんですけど」
「自分の価値を他人に預けるな。他人に馬鹿と思われたら君の価値が下がるのか。そんなことはなかろう。人生の手綱は自分で握れ、他人に握らせちゃいかん。君とは無関係の外部条件に振り回されてどうする」
「え、何の話? それ大学の話じゃないですよね」
「君は馬鹿か。自分は他人の目からどう見えるかなんて下らんことを聞いてくるから、人の生き方を諭してやってるんじゃないか。君が中卒だろうが高卒だろうが大卒だろうが大学院卒だろうが、そんなの枝葉末節じゃ!」
トホホ、この人は話があっちこっちに飛ぶんで付いて行くのに大変だ。
「確かにおっしゃることが正論なんでしょうけど、自分がどう見えるかぐらいは知っておいても悪くないと思うので。知っても執着さえしなければいいんでしょう」
「君もしつこいなぁ。つまらん事にこだわってガチ詰めしてくるつもりなんかぁ? こん、分からず屋がぁ。お手上げじゃわい。そうさなぁ、あえて例えるならアレだ、吹き流しだ」
「鯉のぼりなんかのアレですか」🎏スイスイ~
「さっき君は鯉だと言ったばかりだろう、忘れたのか。そう、アレだ。♪屋根より高~い、だ。」
「え、アレ?」
「アレだ。中身からっぽ、脳ミソからっぽ、風が通り抜けていくだけちゅうこっちゃ。軽いこと、軽いこと」
「え?」
「脳ミソだけでなく、お腹もからっぽ。だからどんな辛辣な非難の暴風も、腹蔵なく飄々と受け流すことができる。サッパリとしてて、なかなかよろしい」
「そうかなぁ、結構ドロドロした性格だと思うんですけど。閻魔大王が地獄の扉を開いて待っていそうな人間です」
「そりゃ内側じゃろう。外側はボーッとして何も考えていない馬鹿ニイチャンだ。内側は生き仏じゃないと見えん。じゃから、そんなことは誰も気にせんから心配すんな。それより外側だけでも少しはピリッとせい。いくらボーッとしてても大物っぽくは見えんぞ。君は何処から見ても体重の軽い、小物の馬鹿チビじゃて」
「とほほ、そうなんっすね」
「じゃが、気を落とすな。チワワはちっこいから人気があるんじゃ。高身長でイケメンの出川哲朗が“ヤバいよ、ヤバいよ”とリアクション芸しても、ちっともおもろないだろう。出川哲朗は不細工だったおかげで、あれだけみんなにウケて、テレビ番組なんかに引っ張りだこなんだ。いいか、サーカスの主役は何といってもピエロじゃ」
「へっ?」
不細工なチビはアンタもじゃないか。けどここで、お亀とひょっとこが背比べしても仕方ないな。
「ただしじゃ、ただし鯉のぼりの君は風がない日は悲惨じゃ。急に元気がなくなる。ダラリとぶら下がり、精彩を欠く。フニャフニャに萎えた鱈子ペニスだ。こんなんじゃモチベーションもダダ下がりじゃわい」
赤井君は不満げに口を尖らせる。
───やれやれ、イジりたおしてくれるよ。結局また下ネタに落ち着くのか。油断も隙もあったもんじゃない。まったく下ネタが服を着て歩いているような人である。本人は生き字引然とふるまうが、口を開けば下ネタばかり。アンタは生き下ネタだ。
もしや下ネタ大王、福山雅治の向こうを張っているんじゃなかろうな。あんな超イケメンに何でアンタが対抗するんだ。その歳でまだ女の娘にキャーッとかワァーッとか言ってもらいたいのか。

「で、話を元に戻しますが、ほんとにヨモギって知らないんですよ。それって変ですかね」
と、表面上はあくまで従順さを取り繕う赤井君である。
「ほっ、やっと話が戻ったか。別に変じゃない。だが残念じゃ。毎日狭いボックスに入り、夢茶に酔った脳ミソの海の中で、ペニスを腐ったバナナのように振りまくる狂った仕事ばかりじゃ嫌んなるだろう。たまには出で湯の里にでも旅行して、パッと開放感を味わうのもいいと思ってな。今の君はまた邪気が増えてきとる。自分でも、ちょっぴり精神を病んどる気がするじゃろう。恋煩い、ならぬド助平わずらいかぁ? 大自然の下で骨休めすることが必要じゃ。猿なみの脳しかない君は、お猿さんと一緒に露天風呂に入るのが一番効くんだ。憂さ晴らしに風俗街をうろつき、振り珍バナナの叩き売りをするよりはずっとマシじゃろう。じゃが、ヨモギを知らんなら仕方ない。まあよかろう。小汚い小僧が粗珍をご開帳して秘湯巡りしてもグロテスクなだけじゃからな。秘湯巡りは美女でなけりゃサマにならん。箱村に取りにいかせるか。君はクサ、草について無知すぎるぞ。よし、草ついでにクサ、不見識な赤井君にクサ、耳寄りな草話をしちゃるばい」
「くさくさ」
つられて赤井君までクサを口に出す始末。わぁ、クサばかりで草中毒になりそうクサ。
「ウガンダとオックスフォード大学の共同研究でクサ‥‥‥もうクサはいい加減にしとくか、田舎っぺ丸出しじゃ。クサを食べすぎたら牛や馬になっちゃうもんな」
「“草”って“笑える”って意味のネットスラングですよ。使えば若返るんじゃないっすか?」
「そんなこた知らん。クサは九州の方言じゃわい。九州に住んどってそんなことも分からんのか。“とっぱちからクサ、やんつきラーメン”じゃろうが! 立派な正統博多弁たい。なんば言うとっと?」
え? なにラーメン? 大昔、そんなラーメンがあったのかな? あったのかもしれないけど、ノスタルジックに過去をふりかえって得意顔すんなって。博多弁? 見栄をはるな。それって福岡の、どっかの片田舎でしか通じない方言だろう。
「さすが社長はインターナショナルピーポーで、あちらこちらの方言に詳しくあられる」
「はぁ? インターナショナルピーポーとは何ぞや、説明せい」
「箱村さんの定義によれば、いろいろな方言を自分なりにアレンジして話す人達のことだそうです」
「アイツの定義じゃ話にならん。たとえばワシの話す雅な言語は、主として関西弁と福岡弁のチャンポンじゃろう。標準語は変わりつつあるんだ。もっと純客観的に人を観察せんか。そな、ピーポーピーポー言わんで。君は救急車か。しっかり分析せい。定義するのはそれからだ」
なんでこんな下らないことを分析せにゃいかんのでっか? 花菱も箱村も(ひっとしたら僕も?)、あっちこっちのお国訛りの詰め合わせセットである。箱村に至っては、それがインターナショナルピーポーの証だとまで言い張る始末だ(霞ゆく夢の続きを〈4〉─28)。どこがインターナショナルなのだろうか、笑ってしまう。
とはいえ通信技術の発達等で日本はますます狭くなっている。そのうち地方という概念も薄れていくだろう。花菱が言うように、方言のごった煮が徐々に日本語を塗り替え、新たな標準語を形成していく日も近いかもしれない。
「で、レクチャーの続きを」
「何の続きだ」
えっ、忘れちゃったの? またかいな。道具を出したら、出しっぱなしじゃ駄目でしょう。出したなら、ちゃんと使おうよ。どれだけ茗荷を食べたらそんなふうになるんだろうか。
「ウガンダとオックスフォード大学の共同研究で、って話ですよ」
「ああ、そうじゃった、そうじゃった。言われればちゃんと思い出すから、まだワシの認知機能は大丈夫だな。あのな、その共同研究では、チンパンジーは病気や怪我をしたとき抗菌作用や消炎作用のある草花や葉っぱを集中的に摂取することが観察されている。奴らはエテ公の分際で仲間同士、学び合うんだな。そして試行錯誤の結果、薬用効果のある草花がどれか識別できるよう進化したわけだ。敵もサルもの引っ掻くもの、だ。草花には人がまだ解明していない無限の可能性がある。猿でさえ草花のもつ薬用資源を活用できるんだ。猿なみの知能しかない箱村のアホだって試行錯誤を繰り返せば、たまさか夢茶もどきの発見をする珍事も起こりうるんじゃ。婆さんの発明を横取りして自分の手柄にするんじゃなくてな。こぼれ話は以上でござる」🐵
え? “ござる”が落ちってこと? 唖然───。落ちというより落馬じゃね?
「どうじゃ赤井君、ワシの蘊蓄は。知識がありすぎて才能がこぼれ落ちるばい。これぞまさしく、こぼれ話だ。ワッハッハッハ~〜おもろて、おもろて腹がよじれるわい。こりゃ愉快、愉快、ワッハッハッハ~」
だからぁ〜何でそんなに笑い出すの? それってそんなに面白い? 完全に昭和のノリだ。
「箱村なんかほっとけ、モンキーマジック、モンキーマジック♪。どうだ、こういう学識ある話は面白いだろう。ワシの知見は池上彰レベルじゃな。ヘイ! 君はファンキーモンキー、ベイビ~~♪」(^(◎◎)^)ブヒブヒ
なんという言い草だ(くさくさ)。いつもそうだが、なんでこんな話になるんだろうか。ぶひぶひと鼻高だかなのは分かるが、道草を食っているのはアンタ自身じゃないか。知識欲のない僕にはそんな話、さっぱり興味なしクサ。
てか、なんでそんな陽気に歌いだすんだ。おまけにかなり適当な節をつけて歌っている。ここは喉自慢大会の会場なのか。しかも昭和の古い持ち唄を。鼻歌とはいえ格別音痴ときてるから始末が悪い。おっといけね、急に歌い出すのは僕もそうだったっけ。このさい目糞鼻糞を笑うで、ジョイントコンサートでも開きまひょか。
しかし常々思うことなんだが、毎度毎度でてくる花菱の蘊蓄は全部つくり話なんじゃないのだろうか。どうも疑わしい。思いつくまま架空の創作をくっちゃべってるだけちゃうんか? 僕が無知なのをいいことに、やれナンタラ効果とか、やれナンタラの定理とか、やれナンタラ理論とか訳の分からぬ話で威張りちらすが、実際はそんなものなくて、馬鹿をからかって面白がっているだけ。そんな気がしてくる。社長、いいかげんにしてよ。閻魔サンに舌を抜かれちゃうぞ。
ただ、よしんばそうだとしても、嘘から出た実も一つや二つはあるかもしれない。それに、好意的に考えれば僕の素直さを試しているとも考えられないこともない‥‥‥いや、いや、いや、まさかね。そんな計算をする人にはとても見えないな。やっぱ、からかってるんだ。
「さすが草博士だけありまする。僕など到底およびません」
情けない。本心とは裏腹、また心にもないオベンチャラを口にしてしまった。なんという芯のない男か。
「お、ワシ教養の深さを理解できるなんぞ、こりゃ、お利口さんじゃわい。ワシャ、草のことを知悉しておるからな。そうクサ、そうクサ、草博士クサ」
🌷🌸🌻🌹クサクサハナハナハナハナ
博士と呼ばれて花菱が照れている。何もそこまで満面の笑みをたたえなくてもなぁ。別に「はいチーズ」とは言ってないだろう。
「君は若いのに生意気でなくて腰が低いな。いい心掛けじゃ。チビだと腰が低いんかな?」
チビはアンタもだろう。アンタは腰が低いんかぁ? 笑わせる。
「う~ん、ばってん、そうでもなか。猪瀬直樹のことを考えればのぉ。人間、器が小さいほど一杯注ぎたくなるもんじゃからの」
アンタもそうじゃんか。どっちもどっちでんがな。自分はそっちのけか。性格と身長は関係ないクサ。
「腰が低い位置にあるのは、それ、脚が短いからですよ、チャンチャン」
ポカンとする花菱。投げたギャグのボールがうまく当たらない、空振りだ。タイミングがマズかったのかなぁ。
「あ~ん、その自虐ボケはいまいちだ。そのまんまを言っただけだろう。君もワシを見習って少しはヒネリを入れんと‥‥」
違った、どうやらボケをかまされたことは認識できているらしい。見逃がし三振じゃなかった、少しはバットにかすったようだ。
「はい、見習って修練させていただきます。ともかく花菱社長はすごい。虫博士でもありますし」🐜🐛🐝🐞‥‥‥‥ムシムシムシムシ
こうなりゃオベンチャラの連打だ。食レポだってベタ褒めコメントできなきゃ務まらないじゃないか。パンチをかわすにゃクリンチに限る。とことん媚びへつらってやれ。しかし何を修練するというのだろう、ボケをか。我ながらアホかいな、やっぱ本バカだ。
「そうクサ、そうクサ、虫博士ばい。そうよなぁ、赤井君」
手拍子を催促する花菱。エンターテイナーになったつもりらしい。もっと空世辞を並べないと。よし、ヨイショ話のスーパーてんこ盛りだぁ。
「そのうち“昆虫こども大図鑑”でも編纂してみたらいかがでしょうか」
「ん?」
あら? これって手拍子になっていなかったかな。ちょっと調子が外れちゃったみたい。デッドボールじゃないか。ギガ盛りし過ぎた。お追従のオンパレードも考えものだ。
すると、「ほんでもってワシら、この前に何を話しよったんかな?」とまたまた花菱。
よっ、極め付きの名人芸! 待ってました。お約束どおり、これこそ花菱流小ボケの王道だ。もはや芸の域。そうそう、さっきみたいなフェイントじゃなくて、ちゃんと本流をいってくれなきゃ。
「“この前に”とおっしゃいますと?」
「虫と草の話の前じゃよ」
「アレですよ、え~と、アレのアレのアレ‥‥」
「アレだけじゃ分からん、アレの三乗根か、理系脳でもないくせに」
「あれ? 思い出せない」
「ほら、またアレって言った。若さに胡坐かいとるからじゃ。政界じゃ“四十、五十は鼻たれ小僧”と言うじゃろうが。若くて能力値が高いからと言って、それだけじゃ世の中に通用せん。もっと謙虚になりんさい」
は? ここって政界なの? この人はいつからキングメーカー麻生太郎になったんだ。あっ、だいたい同じ世代かぁ。そういやぁ親分風を吹かすのもどこか似てる。
「ここって政界なんですか?」
「こら、また幼稚園児のような質問をする。政界だろうがなかろうが世間は同じじゃ、魑魅魍魎がウヨウヨしとる」
「はあ、そういうもんですか」
「もっとも君が思い出せんのも当然かもしれんのぉ。最近じゃ若者だって忘れてしまうほど時代の流れがはやい。新語・流行語大賞のフレーズなんざ、知らぬ間に素通りで意味もなんもチンプンカンプンじゃろう。赤井君は今年の幾つ覚えとる」
「あ、思い出しました」
「今年の流行語大賞のフレーズをか」
「そっちでなく、こっち」
「こっちって、どっちじゃ」
「分からないんですか?」
「なんじゃい、その上から目線は。分からんはずがない。ただあっちかこっちか選ぶだけのことじゃろう。二者択一じゃないか。とはいえ人生は甘くない、選択の連続じゃ。ホイ、あっち向いてホイ。ホイホイホイの“あっちこっち丁稚”!」
「???」
何でそんな話になるんだ。ふざけてるのか。
「なんじゃ、あっちこっち丁稚も知らんのか。伝説のお笑い番組じゃろうが、昭和の」
「昭和の話もいいですけど、それより僕が何を思い出せなかったか分かりましたか?」
「なんじゃったかのぉ、言ってみんしゃい」
やっぱりだ。話をあっちこっちに飛ばすから忘れちゃうんだ。この、あっちこっち爺さんがぁ。同じことを何度も聞き返すのは、オレオレ詐欺対策なんかい。
「僕、花菱先生のレクチャーをうかがっていたんでしょう。たしか僕に三つの顔があるという‥‥‥」
「ああ、そうじゃった、そうじゃった。“三つの顔”───それが君と言う人物を解き明かすキーワードだ。実はワシもホントは忘れちゃおらん。君がちゃんと草博士の話に付いてこれてるか確認してみたまでじゃ」
「またまたぁ、それってホントとなんですかぁ?」
「嘘に決まっとるじゃろうが(w)。やれ、気は若いつもりじゃが歳には勝てんわい。老けたら顔にシワがよっても、脳ミソにはなかなか記憶のシワがよってくれんようじゃ。“記憶にございません”と国会で答弁する老いぼれ大臣は、意外と正直者だっだりしてな。ぜんぶ忘れちゃったら、ワシにもこんな時代があったんだなと昔を懐かしむこともできんくなるじゃないか。いやま〜あ、歳はとりたくないもんじゃ。とうとう生命線の長さを気にせにゃならん歳になったか。最近じゃ老人臭で蚊も寄りつかんわ。やれ脱臭剤がいるわい」
───ついでに養毛剤もどうでっしゃろ(!?)
赤井君は心の中でそう語りかける。心の中でどう語ろうと黙ってりゃ分かんないもんね。
「なに、思い出せなくたっていいんだ。すべては移ろいゆく、諸行無常じゃ」
あら、珍しく弱音を吐いている。花菱から自虐ネタを聞くのは珍しい。同情心から、つい弾みで言い放ってしまった。
「社長はまだまだ若いですよ。肌なんかもツヤツヤしてて」
「ほう、そうかぁ?」
「そうですよ、特に頭のてっぺんの辺りなんかテカテカですよ」
「あん?」
おいおい赤井君、口に出したら分かっちゃうだろう。それって何の慰めにもなってないぞ。
「この際、カツラでもかぶってみれば。イメチェンで気持ちだけでも若返るんじゃないっすか」
「ん、なんだ?」
「それとも後頭部にちょろっと残っている毛を結ってチョンマゲにしてみたら。ちょっとした時代劇ヒーローじゃないっすかぁ」
「はあ?」
「う~ん、でもその分量じゃマゲは無理かぁ。少なすぎて、もうツムジの渦巻きもほとんど分からない。残念ですけど、それじゃ断髪式もできないでしょう」
「ワシャ、相撲取りか」
「そう、堂々たる力士です、アンコ型の。どう見てもソップ型じゃないでしょう」
「ワシがお相撲さんなら、君は何だ」
「僕も堂々たる褌かつぎです、マイクロソップ型の」
「なんか臭ってきそうじゃな」
おっと。しまった、しまった、勇み足だ。虎の尾‥‥‥ならぬ豚の尾を踏んじまったかな? つい養毛剤からの連想で、やってしまった。普段から思っているから、口からツルリと滑らしちまうんだ。ハゲだけにツルリってか? おい、ふざけてる場合じゃないぞ。きっと気に障ったにちがいない。取れた葡萄の粒はもう房には戻らない、いったん口から出した言葉ももう戻らない、トホホ。(🙏ゴメンナサイ)
「どうした。覆水盆に返らず、ってか?」
え? なんで分かっちゃうの? どうしてだろう、ときどきこういうことがある。そうかそうか、たぶん表情に出たんだな。一つ、僕は理知的な人間ではない。二つ、したがって感情にすぐ流される。三つ、感情は顔に出やすい。立派な三段論法じゃないか。
「調子に乗りすぎました。反省します」
顔色をうかがいながら、恐る恐るそう言えば、
「ワッハハハ、安心せい。仮面ライダーじゃないから変身はせんよ。しかし何だな、髭はちゃんとまだ生えるんだ。髭を頭のてっぺんにまで持ってこれんもんかのぉ。赤井君考えてもみろ、ワシがカツラをかぶったら、それこそ高木ブーのそっくりサンになっちまうだろう。コメディアンにはなりたくないわな。イケメン俳優にならなってやってもいいけどな。それにあんな言葉数の少ない人間には到底なれんよ。あんなんじゃ窒息死しちまう。は~あ、ババンバ・バンバンバン、歯みがいてるかぁ〜♬」
意外にも上機嫌のままだ。赤井君は安堵の胸をなでおろす。たいして気に障っていなかったらしい。
このカンタービレ爺さん、歌いだすところみると相当機嫌がいいんだな。他人の外見に頓着するわりには、自分の外見に頓着する人ではなさそうだ。なるほどその歳じゃ、見てくれを気にするもしないもないな。ジジハラにならなくて、よかった。な〜んだ、本人も高木ブーに似てることは自覚しているんだ。とりあえず腹を立てなかったので助かった。
「髪の毛が多くて若い奴らはいいよな。髪ふさふさの赤井君、いっそパーマで縮らせてアフロヘアにしてみるか」と花菱。
「ただでさえ大きな頭がますます膨らむじゃないっすか、嫌ですよ。😠ウンモォ~」
「じゃ、茶髪に染めて、リーゼントスタイルにカチカチに固めて、金の鯱にしてみっか。こりゃ爆笑もんばい」
「ふざけないで下さいよ。そんなに僕、しゃちほこばっていますか?」
「ほら、またシャレを入れた。でもそれ、シャレになっとらんだろう、そのまんまじゃないか」
「そんな頭にしちゃ、みんなから笑われちゃいます」
「もうすでにさんざん笑われてるじゃないか。笑いをとれたなら悦べ。似合うと思うけどなぁ。女の子がキャッキャッと喜ぶぞ、“なんなの? あの人”ってな。注目されること請け合いだ。あ、そうか。そんなのより髪の毛を全部剃っちまってツルッパゲになりゃいいんだ。そうすりゃ一休さんみたいに少しはトンチが働くかもしれんばい。普段の君はボーッとしていて頭がまったく動いとらんからな。いつもパッとせん君がピカピカに輝いて見えるぞ」
「スキンヘッドでっか?」
「そうじゃ、脚の短いブルース・ウィルスだ。多少彼より脚が短ろうが、君なら十分かっちょいいぞ」
「あの人、もともとツルッパゲなんじゃないんっすか? 剃ったんじゃなくて」
「何を言っとる。そりゃユル・ブリンナーじゃろう。ブルース・ウィルスは人気テレビシリーズ『こちらブルームーン探偵社』の頃はフサフサじゃったぞ。いや待てよ、あの頃もカツラを被っとっただけなんかな? 彼の床屋さんじゃないからよう分からん」
やれやれ他人の髪型で遊んでくれるよ。だけどこっちも、さんざん社長の禿げ頭を玩具にしたからな。彼はハゲ攻撃から身を守るために応戦したまでのことだ。おかげで僕のハゲちょろけミサイルは、あえなく迎撃されちまった。でもそれって正当防衛じゃないっすか。「じゃんけんポン、相子でしょ」でありまする。😠ハゲハゲぃぅナ!
「ところで君は夜な夜なピンク街をうろついているだろう」
「え? 急にそこに行っちゃうんですか。勘弁してくださいよぉ。本当にバレちゃってるんですね、お恥ずかしい。でも、それとこれとどういう関係があるんっすか?」
「大ありだ。つまりじゃな、君に三つの顔があると言うのはだな‥‥‥ひとつが仮面で、一つは素顔。おっと、その素顔の奥にもう一つ顔があったわい。グラスの底に顔があってもいいじゃないか、岡本太郎‥‥‥ありゃ? なんだか訳わかんなくなったぞ。な〜に、ただの言い損じだ。つまりだな‥‥‥‥つまり‥‥あれ? ワシ、なに話そうとしとったのかのぉ」
「僕に尋ねても分かるわけないじゃないですか」
わっ、またまた出てきた岡本太郎か〜~い。十五夜お月様のアンタの丸顔もグラスの底に負けてないぞ。さて、この爺さんはなに戯言いっているのだろう。どういう精神状態だ。話しているのに、何を話しているか忘れるなんて、バカというか、抜けているというか。
「くそ! なんだ、なんだ、なんだ。もういっぺん言い直しの井伊直弼じゃ!」
花菱はそう言い放つと、「どっこらしょ」とばかり例の専用ソファーに寝そべってしまった。角のない丸い体がゴロリ。太ったボールがバウンドする。一日中パソコンとソファーの往復だけじゃ、太るのも必定ですな。勝手に変な話をしだして勝手にキレてりゃ世話ない。
寝転がる緩慢な動作は牛のふくよかな乳房のように重くて弾力がある。丸餅だな。噛んで味わえそうだ。搾れば何か出てくるかもしれないが、彼を搾ったところで、脂肪とか涎とか鼻水とか、そんな汚らしいしいものが出てくるだけのことだ。
牧場の牛小屋で悪魔の乳搾りでっか? ゾッとするな。げに恐ろしきオカルトかな。おっと、アンタは牡牛だから乳は出ないじゃないか。それにこの部屋は別に牛小屋じゃないっしょ。
さてさて、特等席に転がるいつものマグロ。だらけきったそのお姿。お定まりの見慣れた絵だ。最近では最も目に触れる光景の一つになってしまった。さながら待ち受け画面である。
「一つ、歓楽街をうろつき、女を買ってエッチをしたがるのは、君の仮面をかぶった顔。人に知られたら恥ずかしいので仮面をかぶって隠す。二つ、今ここにいる普段の君は素顔。そして三つ、幻覚の中でどぎつい化粧をする顔は、君の知らない真実の顔だ。ついに心の奥に眠っている何者かが目覚めたんじゃ。なんたるかな、この三つめに至っては、君は歪な時空にとり残され、ただの入れ物と化しておるわい。トランス状態で自我がまったく消失しておる。もうすでに誰かが君に乗り移ってきているのかもしれんな。なんか色っぽいフェミニンな魂がのぉ、ウッシッシ──」
と、寝っ転がって奇笑を発する花菱。布袋様の太鼓腹が揺れている。人を食うのもいい加減にしてくれ。
「腹にストンと落ちてきません、さっぱり」
「鏡に三つも自分の顔が映ってたんじゃ、そりゃ自画像は描けんじゃろな。気持ちは分かる」
「はあ」
「気持ちは分からんこともないが、一人の人間に意識が一つとは限らんじゃろ。巨匠、岡本太郎いわく“グラスの底に顔があってもいいじゃないか”。一人の人間にいくつもの心があったって構わんじゃないか」
「はてな?」
ひょっとしてこの人、手話知らずに手話を読み取らせようとしてるんじゃなかろうか。そんなぁ無理スジでんがな。
「君は自分の心は自分が一番知っていると思うかもしれんが、自分の知らない心の領域はそれよりずっと広いんだぞ。しかも深いところにあるんだ。ユングをかじったことはないのか」
「それって、かじったら美味しいんですか?」
「ん? そら、また下らんボケを入れる。少しもそんなの、おもろなかばい」
「すいましぇん、つい条件反射で」
「話が飛躍しちまうがな。かりに君の体のどこかにガン細胞ができたとする、そのガン細胞は誰のものじゃね」
「僕のものかな。いや、どこかエイリアン的なもののような気もするし‥‥」
「そうじゃろう。君のものでもありそうで、それでいて君のものじゃなさそうじゃろう。つまりガンは君であって君でないんじゃ。たとえば君がアルツハイマー型認知症になった。じゃあ、その原因とされる脳内にできたアミロイドベータたんぱく質は、君のものかね、それとも君以外のものかね」
「そりゃ僕のもの‥‥‥あれ、違うかな。僕がどんどん別人になっていくことを考えれば‥‥‥これは迷いますよね。本来の自分が少しずつ違う自分に変わっていくんですから」
「そうじゃろう。最新の研究では、宇宙空間に行けばガン細胞は重力の関係で地上にいるよりはるかに速く増殖するそうじゃ。君だって何かの環境の変化で、別人が君の中で増殖し、そのうち君を支配し、乗っ取っちゃうこともありうるんじゃないのか。ゾンビみたいに」
「う~ん、そんなことあるんでしょうか。一個人に幾つもの人格があったりすると、ホントの自分の心がどれか分かんなくなっちゃいますよね。それって奇妙奇天烈だと思いません?」
「たとえば、どんなふうにじゃ」
「たとえば朝起きて自分が赤の他人になっていたとしたら驚くでしょう」
「そりゃ何の問題もなかろう。驚きゃせん。起きた時、君は自分が別の人間になっていることに気づくか? 気づきようがないじゃろう。こう考えてみろ。寝る前の君は前世にいた、寝ている間はあの世、起きた後の君は現世にいる。現世の君は前世の自分が誰だったか分かるか? それと同じじゃよ」
「あれ? 言われてみればそうですね」
「それに寝る前の君は赤の他人なんかじゃないぞ。赤の他人に思えても別人格のもう一人の君じゃ」
う~わっ、なんなんだろう、この丸め込まれちゃってる感は。
「なるほど。じゃこれはどうですか? たとえば『君らしく生きろ』と言われても、どの自分で生きたらいいか迷っちゃうでしょう。自分のなかに、僕という存在が何人もいるんじゃあ」
「迷ってもどれかに決めなきゃいかん。君の人生だ。ワシが代わって決めるわけにはいかんのじゃ。前も言ったじゃろう。忘れちゃったのか? 他人が自分の人生に責任を取ってくれると思うのかね。というか、そもそも取れないだろう」
たしかに言われた。いつだったっけなあ。そうだ、いつか魂の色がどうのこうのという荒唐無稽な話を聞かされたときだったな(霞ゆく夢の続きを〈7〉─50)。
「ワシが決めたら君が選べなくなっちゃうだろう。数限りない人間がこの世に生まれてくるよな。その誰しもが神様の決めた通りにしなきゃならないとしたら、わざわざ生まれてくる意味がなくなっちゃうじゃないか。神様の決めた通りにすりゃ、戦争もなく、飢餓も、イジメも、汚職も、レイプも、自殺もなくなるってか? それじゃいかんのだ。そりゃただの操り人形じゃろう。人として生きていることにはならん。だから君がどれかにきめなきゃいかんのだ。ちなみにワシは生き神様じゃなくて仏様、すなわち生き仏だ。神様とは違う。細かい点だが、そこんとこ間違えんようにな」
な〜んだ、巷によくある自由意志論じゃないっすかぁ。それって、何が起ころうと沈黙している神を擁護する人たちが言ってる理屈でしょ? たとえば「世界の至る所で戦争が起こり無辜の民がたくさん殺されてるのに、神は何で知らんぷりしてるんだ」と詰め寄られとしたら、たいていこんな調子で反駁する。僕もいろんなとこで何度聞いたか分からない。見え見えの、いかにも付け焼き刃っぽい仕込みでんがな。やっぱりこの人は底の浅い、知ったか豚‥‥‥おっと失礼。知ったか仏陀だ。なるほどそういう意味ではアンタは生きボケ、じゃなかった、生き仏ですな。
あの時もそうだったな。実は自分は生き仏で、それゆえ他人の魂の色が見えると言い張ってたっけ。彼に言わせれば、箱村と僕の魂の色は限りなく透明に近い色だそうな。箱村に関しては、最近ますます色が薄くなり行く末みじかいだろうとまで言っていた。人が聞いたら「そんなアホな」と思わず溜息をつきたくなるような、とんでもない与太話である。
だが与太話にしてはどこか真に迫るものがあり、自分の魂の色が透明に近いと聞いた瞬間、頭の回路の一部が閉ざされ、なぜか爪の先まで凍りついていくように感じた。それは海のように僕の心を呑みこんだ。
もしかして小説家になろうとしているから僕の魂の色はどんどん薄まっていくのではないかと。そしてまかり間違って現実に小説家になれたとしたら、それこそ箱村が以前から予言しているとおり、透明な死へまっしぐらなのではないかと。
そんなことをつらつら考えていくと断崖絶壁を見下しているような、ぞっとした気持ちになってくる。この知ったか仏陀爺さんの言うことは、話半分で聞いておいた方がいい。本人にまったく悪気がないのは分かっているが、真に受けすぎれば精神が擦り減る。

最後までお読み下さり有難うございました。
赤井かさの(ペンネーム、挿絵も)
霞ゆく夢の続きを(8)

