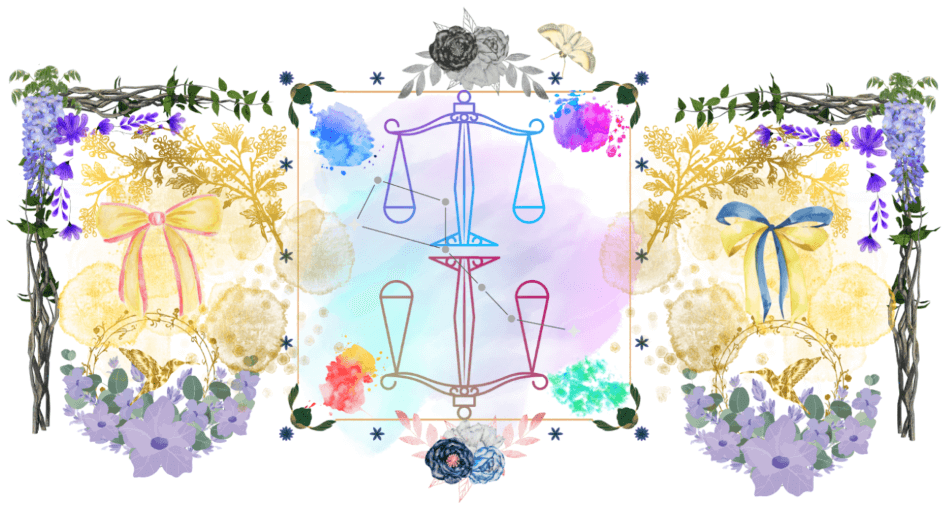
「水仙」
境界線に、佇め。
毎朝、夢を見るの。
鉱石の輝きを極光のように搖らめかせて
泉の下から手招きをする懐かしい水辺
微笑みかけて 微笑んで
涙を零せば同じ様
水が心をいためれば
波紋は一切消えてしまう。
凪いだ姿は哀しみに
じッと耐えているさまである
同じ痛みを分かち合う
それは、遙かに昔の誰かの手記
あなたの苦しみは今でも誰かが継いでいるのだとうっかり口を滑らせたらと
それが怖くて今日もカーテンを閉めるのです
私が何も示してしまわないうちに
私は夢から醒めるのです
第一章 一
墓の隣には、坂がある。何の不思議も無い。よくある話である。ラムネ売りと郵便局を兼ねた店主の媼が言う事に、坂は境界線の役目を持つ、だから坂を歩く時は気を付けろ、此方側と幽世の狭間に閉じ込められて迷ってしまう、その間に寿命は削られる、だから坂と名が付く場所では転んでしまうのは禁忌なのだと今世迄戒められているのじゃぞと。
そのような言い伝えは幼少期より聴き教えられてきて承知している。姫烏頭は店の軒先で叱言がましく小児等に話す臭い息を一瞥して苦笑した。
姫烏頭と言うが、花としての名ではない、この若き一人の人間、男としての名である。花の名を、しかも姫と語の付く名を借りたにしてはおっとりさとはかけ離れた若者で、唇こそ丹花の如き笑みを浮べてはいるものの、眦は鋭く二重に刃を研ぎ、白銀の鋭利な残月を滴らせる両眼、満月欠けゆく痕跡をありありと刻印したる夜空は一点の染みをも小虫をも見逃すまじき威と冷徹が濡々と輝く瞳は何人たりとも気軽に寄りつくことを拒んでいる。鼻筋清く眉は秀でて輪郭骨格ともに引き緊まった丈夫の相を湛えており、到底姫君とは縁遠い。
「おい、其処の子供達。」
姫烏頭は店前で婆の話を一心に聴く子等に声を掛けた。小児等は不意に話を遮った相手をぽかんと見上げ、婆さんも腰を伸ばして彼を見た。
「此の町は坂が多いからね、遊ぶ時や走る時は充分に注意をしなさい。君等の大切な人達を悲しませない為にもね。さあ、お行き。くれぐれも境内ではしゃいではいけないよ。」
怖い話を夢中で聴いていた直後だからであろう、子供達は姫烏頭に一礼をしてぱらぱらと走り去って行った。その姿を二人見送ると婆が大きな溜息を吐いた。
「折角これから面白くなろうと言う所でしたのに、お前さまはまた儂の邪魔をなさってからに。」
吐いた息に険は無く、軽く睨む視線にも気の置けなさが含んである。姫烏頭は折目正しい袴を汚さぬように気を付けて店棚の横にある椅子に腰を降ろす。着物の袂から扇を取り出し開くと己を涼ませ始めた。柄は朝日の山に白雀が雲を目掛けて飛ぶ絵であった。
「話ではなく子供の怯えた顔が愉快なのだろう。全く性悪婆さんだ。」
軽口を叩いてちらり見上げれば婆は破顔一笑ケタケタと。
「当り前よ。そのような褒美も無いのに土地のタブーを真面目に教えられますかい。どうせ学校では習わぬこと、どうせ親御達も斯様な知識には疎かろう。アイスクリンを買うた次手に一つ頭に叩き込んでやるのよ、その方が話甲斐がありますによって。」
「違いない。」
婆が笑って姫烏頭も笑う。暫く往来にはしゃがれ声と凛々しき声が小さく愉快に混ざり合っていた。蟬の鳴く音も聞えない。
二
姫烏頭にとっては土地のタブーは幼少期より耳に吹き込められたものだとは前述したとおりであるが、何故そのような境遇に在ったのかを説明しなければなるまい。だがこれと言って複雑な事情に因る訳でもなし、姫烏頭の父親が神職だったからである。
神職を預かる身、即ち神主と言うのがより分り易かろうが、神主だからと言って姫烏頭の実家が神社であったのではない。父親は昔高校を卒業して後神主の養成所に入り、修行を重ねたうえでその専門職を名乗ることを許された。本来、と言うか大多数の卒業生の進路は何處か一つの神社に常駐する形を取るものなのだが、姫烏頭の父親は一ツ所に収まることを良しとせず、自分の力が求められるのであればその都度現場に赴き祈祷をする、そのような姿勢の人間であったので、極
く極く少数派の彼は神職者が加入する組織との相性が良好ではなかったらしい。尤も組織との不和について息子に語ることは全く無かったので、あくまでも子供の目から見た印象、なのではあるが。
其処迄熱心な身でありながらも、父親は姫烏頭に後を継げとは決して言わなかった。後世の育成をする気はとんと無く、神主の仕事は自分の代で終わりにすると深く決めていたそうだ。その代り生きて行く上で知識・教養として備えておくと良い伝承や言い伝えについてはよく話してくれたので、姫烏頭少年は毎夜眠る前の寝物語を楽しみに、きらきらした目で聴いていたのだった。
老いた父親は天寿を全うして此の世を去り、次いで母親も深く愛する子との暫しの別れに涙を一筋零して幽世へと歩いて行った。年を経てから授かった子である一人息子は、成年前に両親を亡くすことにはなったが、その頃にはもう都会の会社への就職が決まっていたので、金銭で苦労はしなかった。祈祷や神事、祝詞とは無縁の一般企業であったが姫烏頭は満たされていた。
生れ育った町へ戻って来たのは、夏期休暇の為とよくある理由からだった。よく御参りへ行った神社へ参詣し、馴染みの婆と少し喋ると、彼は里帰り中泊まっているホテルへと向かった。実家は両親の遺言に従い、売却してもう更地になっていた。取り壊して土地として売れ、と念を押して書かれていたのだ。
部屋のベッドへ寝転がり、両親の意図を考えてみた。
恵まれていた、とは思う。両親との仲も良かったし、大学まで出させてもらえた。それに生活も困窮を極めていた訳でも無く、望むものを与え与えられる環境にはあったのだろう、と思う。家族に不自由も不満も抱いたことは無い。無いが、疑問は抱かずには居られない。
「何故実家を取り壊さなくてはいけなかったんだろうな。」
理由に関する明記は一切無く、只管に取り壊す事を念押ししたいた。温和乍らも威のある生前の面影を残す両親の言葉に子供は素直に応じ、実際更地になる日もその光景を見つめていた。懐かしい家が、と惜しむ気持ちとこれで良いと納得する意、寂寞と肯定が混ざり合った妙ちきりんな心境だったのを今でも憶えている。
「きっと隠し通したいものがあったのじゃろう。」
性悪婆はそう揶揄った。死体や出所不明な金が出て来るなぞと姫烏頭にほざいたが、土建屋達の悲鳴も驚嘆も鳴らなかった。お前の邪推は外れたぞ、と更地の前で一人クスクス笑ったっけ。
「此の土地が嫌いだったのかな。」
そもそも父も母も地域の出自ではない。父方は雪国の家系で、母方は南方の育ちである。何の縁故があって此処で居を構えるに到ったのだろう。理由理由と求むれど、頼りがあの婆一人では諦めざるを得ない、まゝならぬ世かな、なんて溜息をほうと吹いた時。
ちゅっ、ちぃ、ちい
部屋の窓越しに一羽のエナガが留まっていた。窓の棧を足場にでもしているのだろう、見掛けた次手にちらと空を見やると灰色の雲が兎のお尻のようにむくむくと湧いてきている。
「もうじき雨になるよ、此処ではなくって雨宿り出来る場所にお行き。」
瞬く間に降り出した。雲は最早可愛い兎の姿を潜め梟の如き眼を呈し容赦無く水を叩きつける。
ちゅっ、ちぃ、ちい
「早くお行き、もう濡れてしまっているではないか、ねえ。ほら早く。」
ちゅっ、ちぃ、ちい
声が少しか細くなった。
「あゝ、もう。」
錠を降ろし硝子を引く。エナガは拒んだが多少強引に掌で追うと部屋にぽとりと着地した。窓を閉めて錠も戻す。雨の間だけならばホテルの者にも悟られまい。
「見た目によらず頑固だね。」
さぞ濡れそぼって寒かろうと手巾で拭い包もうとすると、鳥のか弱い脚でなく、金字紺泥の背皮のぶ厚い表紙が横たわって此方を見ているではないか。本、と青年が声を出す間も置かず背表紙はスックと立って横向きになり、ようやく正面の顔を姫烏頭に示した。
表題の文字は刻まれず、その代りとある清廉たりし泉の水面下に沈む一個の金時計が銀鎖に繋がれている滲みの手法で描かれた絵画が一つ。
「画集?」
声を出すと書物は起用に宙返りをして流星一閃の内にエナガの姿に戻っていた。
ちい、ちゅりり、ちゅりっ
本と鳥は似ていると、父に教えてもらったな。言葉にも羽が植わっているから、気ままに目的のままに飛んでゆく。言葉は距離を保ってこそ本領を発揮する場合もあるのだと。遠くには聞こえる、近くには以心伝心。それが理想の言葉の伝え方だと昔テレビで言ってた時さ、父さんは時々肯いていたよね。
「その時俺どんな顔してたかな。」
エナガが机の上でまるまって眠ったのに吊られて、姫烏頭もベッドに倒れ込んだ。
それは、見たことの無いであろう記憶。なれど心には確と刻まれている記憶。勿忘草が莟を解いて花弁を外へ垂らす時、記憶は一つ一つ泉に雫され水面の下には搖らぎが戻る。
夢を見なくなったのは何歳の時からだったろう。幼い頃は怖い夢を見ては泣いて起きて、父と母に何度慰められたか分らない。物心ついた時には毎夜悪夢を見ていた気がする。しかもそれらの内容を目覚めても克明に憶えているのだから生活を送っていても何かにつけて怖い怖いと怯えていたっけか。端から見ればたかだか十数年程度の昔の話だけれど、自分にとっては遙かに遠い微かな名残である。
「なあ、君。」
朝日のシャワーを満遍無く浴びて輝くエナガはもう先に起きていて、机の上で首を右左に傾げながらまるっこい目で見つめている。
「名前、何て言うんだい。」
ちゅりり、ちゅっ、ちりり
「本に化けて教えてくれても良いだろう。」
ちゅっ、ちゅっ、ちゅっ
「うーん、何が良いだろう。可愛らしい名前の方が良いのかな、それとも洒落た単語を付けた方が喜ぶのか?」
エナガ、エナガ、可愛いエナガ。やっぱり愛々しい見目に似合う名前の方が相応しいだろうか。
「プリンの上に乗っかったさくらんぼは、ちょこんとしていて可愛いもんな。」
桜桃と名付けられたエナガは、首を傾げるのを止めて、また一声鳴いた。
「じゃあ桜桃、俺は今から実家の跡地に行って来るから、おまえのご飯もその帰りに買って来るから、今は悪いが水を飲んでな。」
サニタリーの歯磨き用コップに一杯水を入れて机に置いた。桜桃はグラスの縁にひょいと乗ると嘴を水面に触れて上手に水を飲み始めた。
ちゅっ、ちゅっ、ぴちゅっ
「じゃあ行って来るよ。」
ドアの向う、姫烏頭は微笑んだのを桜桃は感づいていたのだろうか。それは、擦れ違いざまギョッとしたホテルマンの内心には到底察し得ないことだったろう。
三
故郷。と言いたくなるほど此の土地に懐かしみも執着も抱えてはいないので、町並みが幼少期と比べて変ろうとも特に何の感慨も無い。両親の墓も此処には建てず、今自分が住んでいる部屋に遺骨と写真を置き、毎日の花と相似を欠かしていない。実家の在った地域、もはや姫烏頭にとっては直接的な繋がりはそのくらいなもので、いくら夏季休暇だからと言って戻る必要も無い、むしろ今の家に居た方が盆らしいのだが。最初は毎年そうしているように、戻る予定など無かったのである。しかし、一通の手紙が青年を再び此の場所に呼び寄せた。それは、差出人の無い女性からの葉書であった。
――貴方の伯母にあたる者です。決して邪な念を抱いて貴方へ手紙を出したのではございません。信じてくださるのであれば、〇月□日、ご実家の近くにあります神社の境内でお待ちしています。――
内容はそれだけであった。
会いたいと指定された日は丁度休暇の真ン中にあたっていた為、そんなら一層のこと数日泊まってしまおうと思い立ち、今に到る訳である。そして明日が約束の日なのだ。待ち合せ場所の神社の宮司に見慣れぬ女性は来なかったかと訊いたが、来るのは地域の人間だけで知己の者しか来なかったと言われた。差別をする訳ではないのだが、あの筆跡は此の土地の者とは少し、否だいぶと離れた美しく寂しい手であった。今でも相手を確かめる為に革鞄には入れてはきたが。
「姉妹がいたとは聞いていないな。」
母には姉弟が多くいたが、父から身内の話は出なかったので、てっきり一人っ子だと考えていたが、どうやら違っているらしい。
「会わせたくない理由でもあったのかな。」
誰にだって明かしたくない事実はあるもの。また神社に来て、境内にある木の椅子に腰掛ける。
「おや坊ッちゃん。」
朝の掃除をしている宮司に呼び止められた。両手で握る竹箒は幾度もあちこち修理されてきたのだろう、色が所々変わっていて、何も知らない者が見れば小洒落たパッチワークデザインの其かと見ゆるかもしれない。
「宮司さん。」
「また、例の女性をお探しに来たので?」
「貴方の方がずっと年上なのに、僕みたいな若輩に敬語を使わなくッても良いですよ。」
「いゝえ何を申します。神主が人への礼儀を欠いて神々に仕えられる道理はありません。この権六、例えお相手がお子様でもお偉方でも取る態度は同じ、まして貴方のお父上には随分お世話になり申しましたから、敬語を使うのを止められはしませぬよ。」
権六爺さんは氏子からも慕われている人格者だ。だからこそ姫烏頭は自分のような者に敬語を心から使われることがむず痒いのだが、温和なようで存外頑固、特に道理に関しては正しきを曲げようとはしないお人、此の爺さんは旧友にもこのような姿勢で話すのだ。
「貴方が此の地域に居てくれているから僕は心強くもあるのですよ、何て言っても思い入れの深い土地とは言い難いので、誰か縁故の頼りが無いと今回も戻る決心は付かなかったと思います。」
「そのようなお言葉を頂けまして、私は幸せ者ですな。有難い言葉でございます、このような枝切れの如き身でも誰かを支え得る杖になれますとは。」
「相変らず謙遜な方でおいでなさる。時に、宮司さん。私の父の話なのですがね、姉か妹が居たと言うのは御存知でありましたでしょうか。」
「お父上は貴方と奥様の話はようされましたが、ご自分の出自については多くを語りませんでした。ただ…一度だけ、尤も些細な内容ではありますが、ごきょうだいについて言及されたことがありました。」
姫烏頭が身を乗り出したのは言うまでも無い。
「何、何を言ったのですか、父は。」
「修業時代のことでありました。一日行を続けている若者にとって週に一度、学校周りの散策は待ちに待った娯楽でしてな。私はあまり乗り気ではなかった引込思案でしたが、お父上に手を引かれて近くの植物園に参りましたよ。その時擦れ違ったお客の中に双子の姉妹がいらっしゃいましてな、微笑ましう手を取り合って若草、花々の中を歩いておられる姿は異国の妖精のようでございました。お父上もてっきりそう思われてお二人を見送ったのかと思いましたが、違いました。一言、呟きになられたのです。
(きょうだいの手は、離したくないものな。)
聞いた時は双子のことを仰有っているのかと思いましたが、今思えばご自身のお身内に関する言葉であったのかもしれませぬ。それ以来きょうだいに関する話は一言もなさりませんでしたが。」
「やはり、本当に伯母上がおられるのかもしれない。明日が待ち合せの日なのです、事前に姿を現わすことももしやあろうかと思い数日参詣の後にこうしてぼんやりしている訳なのです。」
「明日の何時頃ですか。」
「時間の指定は何も…ですから一日待つ心算です。」
四
「桜桃。」
小鳥は本の姿になっていた。折角鳥用の餌を買って来たのだが、と少しだけねぢける。
「表紙に何の文字も刻まれていないのは何でだろうな。」
背中には金色の文字がしたためられてはいるが見たことのなさそうな文字だった。もしかしたら文字ではなく模様なのかもしれぬ。
「おまえの正体も分らないし、伯母上がいつ来られるのかも分らない。いるような気はするが実在しているかも定かではない。ないないづくしで呆れちまう。」
苦笑して昼ご飯を袋から取り出し弁当を食べ始めた。まずは清涼剤として腹を膨らまさなくては。考えられることも考えられず、とッちたことばかりしてかすだろうから。姫烏頭が食事をしている間、本は居眠りするかのように日向にぽかぽかと当たっていた。
昼食から一時間半は過ぎたろう、自分の家から持って来ていた文庫本を読み進めていたが、うつらうつらと瞼が垂れてきてしまう。夏の暑気にやられたか、と外を歩いて疲れた身体をベッドに横たえ、瞳を閉じた花の顔は眠りに就く。
「どうしたの。」
再び開いた冷泉の瞳は花畑の真ン中に居て数度驚きにしばたいた。桔梗、萩、女郎花、曼珠沙華に芒の穂、正しく秋を代表する花々方を囲うように縁取るのは青々と繁茂し天へと頤を迷わず伸ばす樟の大樹達であった。夏と秋が迷子になったような場所で、姫烏頭は再び目を覚ました。夢であろうか、いいやそれより今は。
「どうしたの。」
二度声がした。同じ台詞、同じ声。辺りをぐるりと眺むれど人影らしき姿も見えず。それでも声は彼を気遣う。
「驚いているの。」
「君は誰なんです?」
「貴方は姫烏頭。知っている。」
「いや、俺のことじゃあなくて。」
「知っている、知っている。貴方のことを知っているのよ。」
「…如何して俺のこと知っているの?」
「だって雨の日、部屋に入れてくれたから。」
ちゅっ、ちゅり、ちゅりりと口真似る声、よく似ているのも当然だ、人の声真似と言うレベルではない、実際に小鳥が囀る声。
「では君は桜桃なのかい?」
「そう。桜桃、貴方が呉れた呼び名。」
質問をすると小鳥は歌から忽ち変じてまた元通り人語を操る。
「桜桃。姿を見せてくれないのは何故?」
「貴方は夢の中に入ったことが無いの。」
「いや、そんな特殊能力は持っていない…」
「特殊じゃない。ただ傍で眠るそれだけ。そうすれば生物は相手の夢へ訪ねることが出来る。」
「俺達人間には真似出来ない自然の摂理だな。」
「人間は、出来ない。夢に踏み込めない。」
「桜桃に目で逢えないのも、人間の知らない君等の常識?」
「ふふ、ふふふ、おもしろいのね姫烏頭。先刻から質問ばかり、知らないことだらけ、可愛いね。」
他人が自分の顔を見ると目を避けられてばかりなのだ。到底可愛いと評される顔立ちではなかろうに、無邪気な声は御機嫌だ。
「可愛い子だから教えてあげる。それに知らないまゝは不安でしょう。あのね、夢の中に入って来た時、入った方はお客様、夢の中に招いたのは家主。本来なら家主は来客をもてなすものなのだけれど、夢の中江は活動時の習慣は意味が無くなってしまう。家主の夢に居る間、お客様は家主の声しか聴こえないの。目視することが一切叶わない。」
「成程。起きている時みたいに振舞おうとしても、夢の内ではそれは出来ないってことか。こうして君と話せるようになったのは正直助かったが、相手の顔を見て話をしてみたかったな。」
お互いに言葉が途絶えた。互いに喋りっ放しで些少は疲れが見えたのか、三分間ほど姫烏頭も桜桃も黙りこくっていた。
「夢なの。」
息を整えた桜桃から話し始めた。
「貴方に夢をね、旅してほしいの。」
それはどうしてと問う間も無く桜桃の声は続ける。
「私の夢は、過去の記憶。けれど私自身は自らの夢を旅することが出来ないの。本は自分で頁を捲られない。だから貴方に。」
「君の過去に潜って、俺は何をすれば良い?」
「早くしないと明日の旭が出てしまう。月夜には戻って来られるように、気を付けて。」
「一寸、」
制止の言葉も発しきれぬまゝ、姫烏頭はポンと空へ仰向けにされ、背中を地面に預けた状態でバラバラと雨粒をもろに浴びる。先程迄晴れていた碧の空模様はすっかり漆の雨粒へと刺繍われていた。身体を起こすと手元足元に咲いていた秋草達は影も見えず、代りに焦げた土に黒い影のような塊が点々と染みており、樟ではなく鉄塔が四方八方に頭の向きも定まらず転がっている。人の声も、物音も、何もしない。しかし掌を数度地面に擦り付けると砂利の動く轢音がした、その震動も感じ取られる。
「誰かを待て、と言う指令でもなさそうだ。」
何せ旅をしろと求められた。じッとしていることを望まれてはいないのだろう。夢の中だと言うのなら何が起きようと不思議ではない、姫烏頭はこのような経緯に至った理由を深く考えるのは一旦置いておいた。
「若しかしたら父さんに関する何かを見つけられるかもしれない。」
現実ではまだ正午を少し過ぎたくらいであろう。晩ご飯までには戻らなくてはならないそうだ。
何方が北かも分らないが、北だと思う方角へ足を動かす。姫烏頭青年は長い午睡の旅を開始した。
五
灰色は、好きな色であった。昔に可愛がっていた近所のお婆さんの飼っていた兎の色。お婆さんは昔社長令嬢で、いつも動物達と暮らす生活をしていたのだとラムネ店の性悪婆から聞いたことがある。ああいう類の人間は貧乏人を人と思わぬ節があると性悪の方は言っていたが、兎のお婆さんは誰にでもおっとりと優しかったので、或日父親に訊いてみると、姫烏頭の父は笑い乍ら教えてくれた。ランドセルを背負ってきょとんとした顔の坊主頭を撫でて言うことには、心の貧しい者を貧乏人と呼ぶのだと。
(だから性悪婆さんは兎のお婆さんから優しくしてもらえないんだ。)
兎のお婆さんが愛兎と一緒に息を引き取った後、お葬式に入られないのはラムネの性悪婆さんだけだった。
灰色が好きだからと言って、黒なんかはどうなのさ、と追及されても全く困るもので、自身の好きなものと密接に結わえられていなければ関心興味は湧かないのである。だからこそ姫烏頭は黒い景色が続く眺めにはそろそろ気が滅入りそうになってきていた。
「昔話で例えたら、そろそろ一ツ家の明りくらい見えて来ても良さげな頃だろう。それとも全く知らない土地なんだろうか。」
夢なれば、の常識は今適用されず、夢だが触感の生きている世界の内をただ歩き続けていれば、お腹は空き脚もくたびれる。いくら体力のある身とは言え二時間ばかり只管に当て無く歩き続けていれば彼とて疲れてしまう。
「実際どれくらい歩いたろう。感覚では二時間は過ぎたような手触りだが、此処と現実世界では時の流れ方は同じなのかな。」
喉の渇きを覚え、近くに小川か湖はあるまいかと周囲を見渡す。すると、足先にひたりと沁みる気配があった。水かと期待し指で掬い口元に近づけると、苔蒸した深川鉄の匂いがした。
途端に灯が点いた。姫烏頭の遙か頭上、星の一つから煌々と光を留めた一本の縫糸が垂らされると、彼の近辺は急に光の反射を思い出し、不要な類の色を捨て去って眼前に鮮やかに現れた。地面に点々と染みの如く認められたのは、何れも残らず人であった。人間が、確かに其処に居て、その直後焼かれた痕。痕跡の上に雨水が溜まり水を欲して歯朶類が根を張ったので、青臭さと生臭さの入り混じった匂いと化したのだろう、この恐るべき人型の苔は地面のあちらこちらに倒れている。
「これは…」
姫烏頭が絶句していると声がした。
「それは、戦争の記憶。私を育ててくれていたお家が、街が土台から焼かれた時の記憶。」
桜桃の声の調子は、言うまでも無いであろうか。
「街は頭から爪先まで焼き尽された。この出来事を大いなる破壊と讃える者達が澤山居ることも、知っている。産みの苦しみと捉える者達が多いことも、私、知っているの。」
神話では多い展開であるのは否めない。前時代の神の骸を苗床に現代に繋がる人間の祖が育っていく姿は。確かに生命は生きている、けれど、これは。
「大量虐殺の痕に何が生まれるって言うのだ。」
こんなの…と言いかけてその場にしゃがみこみ、痛む頭を片手で押さえ、もう一方の手は我身を抱きしめるような形で震えている。彼の状態を見兼ねたか、声は前向きな言葉を紡いだ。
「私は大きな傷を負った。けれど今では時折、痛むだけ。その程度にまで回復したの。多くの人が殺された街を諦めなかった。……皮肉ね。戦争の後に団結して平和を望み築き上げていくなんて。」
ポソリと呟いた最後の方の言葉は低すぎて、人の耳には風の唸り声にしか認識出来なかった。
「姫烏頭、次、次を見てほしい。一番最初に歩いてほしかった所ではあるけれど、次はきっと、馴染みのある光景だから。」
声で物理的に背中は押せない。動かすかどうかは結局本人が決めるのである。声援を受けて己を奮い起こすのか、耳を塞いでジッとしているかを選ぶのは。姫烏頭は耳は覆わなかったけれど、奮い立つことはしなかった。桜桃の声を聞き乍らも膝を付き、大いなる破壊の引き摺っていった尾の跡をぼんやり眺めている。
「姫烏頭!」
手が伸ばせられたのなら懸命に伸ばしていたことだろう。だが苔の地面に膝から下半身から胴体から沈み始めた青年を引き止めようとする手は此処には存在しない。
とぷり
最後頭の先が沈んで見えなくなると、星の糸はするすると元いた場所まで格納され、最後の一巻きを終えた直後、また大地は暗くなった。
六
これが何處の、何時の戦争か判然とは分らない。だが復興が、新たな文明が彼處から誕生し育まれたとしても、土台は死である。バランスの悪いおもちゃをどんどん積んでいくのと同じだ。いつまでも死臭は背後霊となって纏わり付く、発展など、とんだ偽善・独善ではないか。
とぷり
これまでの生活が虚ろに思えて来た時、彼は空中に放り投げられていた。
「え?」
沈んだ先が、空?
天地と書いてあめつちと読むとおり、天と地は別々に分けて考えられるものでは本来無い。空からもたらされた雨が大地に沁みて循環を繰り返してまた空に戻る。大地を潤す川・泉なども水滴達も天に昇り雨と化しまた大地に戻って来る。即ち天地は水糸を通せば表裏一体背中合せの別側面と言えるのである。なればこそ、何處かの空は何處かの大地と繋がっており、土に溺れる者は空から降る、斯様な珍妙且つ当然の摂理が働く訳で。
空から落ちる、と言うのは初めての経験であった。しかし今のんびりとその感覚を味わっている場合ではない。夢の中、虚空に居る者が取る動きは当然、両腕を羽のように動かすこと。姫烏頭は逆しまに落下しながらも腕を地面と平行に伸ばし、颼々と両液に流るゝ冷たい風の剝き身の刀身を感じつつも、その目に先刻のような迷いの銀色は一片とて無かった。
死んでたまるか
その懸命だけを央に据え両腕を力一杯振り上げる。すると下向きになっていた身体は腕を動かした一煽りの勢いで体制を整え頭を上に、さながら空に立っているように直立の懐かしい姿勢となる。一度起き上がった身を前方に傾け今度は全身が大地と平行になる形を保ち、両腕を二回三回、羽ばたかせた。すると身体は落下を止め、飛翔の姿勢を姫烏頭に与えた。成功だ。姫烏頭は夢の中で鳥達のように羽ばたき飛んでいるのである。
「飛べている。」
「姫烏頭!」
彼が驚きと歓喜を凝縮した声で呟いたのと、桜桃の声が彼を呼んだのはほゞ同時であった。
「姫烏頭良かった、動けている。」
「桜桃、かい?」
「あのまゝ動かないで落ちてしまうかと思った。でも飛べているから安心した。」
「済まないね、心配させてしまって。」
飛び方のコツを覚えたか腕を左右真直ぐに伸ばして上昇気流を掴み推進力とする。その瞳は初めて会った時と変らなかった。それまで曇っていた眼下の視界が霧払いされたかのように輪郭を描き直し、色彩を以てして姫烏頭に呼び掛けた。
「あれは、町?俺の住んでいた地域よりも大きいものだな。」
「彼處は、楽しい町。毎日お祭りが日替わりで開催されている祈りの町。」
「祈りの町とは?」
「降りてみたら分る。」
徐々に徐々に高度を下げ、地面に緩やかに着地する。土は明るい焦茶色、南瓜やカブのようなお面を被っていない人間は姫烏頭のみ、皆ドレスにタキシードを白く纏ってくるりくるりと手を取り合い踊っている。町の建物のレンガ造りに静かな笑い声と息づかいが吸い込まれて、サイレント映画を眺めているような、そんな光景であった。
「年中祭りをしているから賑やかなのかと思ったけれど、正反対の様子じゃないか。今日のこの祭りだけがこんななのかい?」
自然と声量も抑えがちとなる。しかし思い返せば此処は夢。他人に話し掛けたところで気付かれなさそうではあるけれど。ましてや桜桃の記憶である、辻褄が合わなくなる空間でもなさそうで。案の定、夢の主は笑っていた。
「周りに合わせようとしなくて良いわ。貴方が居るのは私の過去の記憶。感じ取ることが出来るけれど干渉することは叶わない。」
「その割に結構干渉している気がするが。」
「沈んだのも飛べたのも場面の転換に必要なだけ。でも、そうね、意思ある舞台装置とでも言うべきかしら?」
「機械に例えられたのは初めてだよ。」
苦笑していると、祭りの参加者達の装いがパッと藍色に一変した。
「今度は祈りを捧げる色が藍色へと変わったんだ。」
先に桜桃に答えられた質問を放り乍ら踊る人々の仮面を見る。ちらりと除く口元は寸分違わぬ微笑を歪ませること無く、静かに静かに祈り続ける。何となく、心地が良い。尤も、先刻迄居た空間に比ぶれば、かもしれないが、それを勘定しても、此処は今姫烏頭にとって安心出来る場所であった。
「もう少し、此処で見ていたい。」
地面に三角座りをして休む。翻る町民達の服の裾が、手巾を振っているように見えた。
七
祭りは朝日の出、正午、月の入りの計三度、色調が翻る時が来る。色の変化自体に決まりは無さそうだが、色を変える時には全員が漏れ無く色を同時に変えるのは決まり事らしく、町民達は秩序を乱すこと無く踊り続けていた。今度は半色。
「此処は色に祈りを捧げているように見えるが、色彩を讃える為の祭りなのかな。」
「よく休まったみたいね。そう、色への感謝、此の町の人達は、色そのものを神々として捉えていた。」
「なら、最も位の高い色はやはりあるものなのかね。」
「そういうのは、無い。あらゆる色があらゆる神様。何かを司る神様が全色にそれぞれ含まれているのだと考えるから、唯一神・絶対神の概念は無い。」
「よく知っているね桜桃は。」
少しずつ饒舌になってくる桜桃が嬉しい。褒められて彼女の声も嬉しそうに感じる。此処は一番見てほしい所だと言ってくれていた気がするし、桜桃の記憶の中でも最も楽しく痛みの無いものなのかもしれない。
「此処の人達は、君に良くしてくれたのかい。」
「居心地はとても良かった。私が空腹を囀れば上等な豆を呉れたし、喉が渇けば綺麗でおいしい水を呉れた。歌を奏でれば褒めてくれたし、争いが起こった例も無い。」
まさに楽土、と称するに相応しい町であったろう。けれど理想郷と彼女は言わなかった。言う直前で口を噤んだ。この感想は、姫烏頭には分らないと思ったからである。でも、自分の過去を旅してもらっている以上、隠し事は露見し白日に晒されるであろう、善悪の問題ならず、意味の有無の問題なので。
「…黙っていても何ればれてしまうから教えるけれど、私は此処を楽園と呼べなかった。」
「君にとって良い町で、平和がずっと続いている、綺麗で優しい町なのだろう?理想郷と言えない気掛かりなんて一見無いように見受けられるが。」
姫烏頭は丁度此時一人の女性の踊る姿を正面から見ており、桜桃に話した内容は正直な気持ちだった。本当に、理想郷と呼んで良いであろう。空もこんなに澄んで、と月昇る夜空を仰いで見た時。
黒の染み、生きたまゝ焼かれた人間の痕、
「あッ!」
魂消る青年の心には、一番最初の土地の記憶が呻いている。
楽園では無い、此処は後悔の町なんだ。絶えず移り変るものに祈りを捧げ、自分達の身体に刻み込む為に踊り続けている。他者を慈しみ愛しく思うことは、過去の償いの為。あゝ此の町は、絶えず移ろう世であることを忘れたがゆえに戦争と言う手段を講じてしまった歴史を忘れない為に踊り祈り後悔し続けている。移ろいの世に在り乍ら絶対的なものを求めた行為を悔んで悔んで、二度と誰もが忘れること無きようにと修行をし続けているのだ。
「桜桃、此の町は楽園では無かったね。楽園とは現実に赴くことの出来ない場所のことを指すのだろうから。」
「……気づいたの?」
「戦争後にさも復興したように目では見えても、心は同じじゃない、当然さ、器官が別々らしいんだから。心は永遠に息をつけない、戦争をしたことへの後悔がずっと拭えないから、戦争をした事実は消すことが出来ないから。…此処の人達は、戦争が起り得ない状態を全身に刻むのに必死なんだ、それで、そんな我身を恥じて仮面を被る。そうしないと怖くなってしまいそうなんだろう、罪業が総身に彫られた己の姿を見せるのなんて。…怯えている、怯えているんだ人々は。戦争を許した自分達に、ずっと。」
「だから一生踊り続けていた。踊りは祈りの手段の一つだもの。」
「理想郷とは程遠い、まるで現実だ。」
祈りも空虚にしてしまう。最早色の移り変りにだけ目を向けて、その色にはどの神が宿っていたのかなど町民達は憶えていないだろう。何色でも良いから変遷を想起させるような動きをしていれば、と。
「俺は、始めの土地から動いていないようだ。これは、夢をあちこち旅するものと聴いていたが、桜桃、君は俺に何を望みたいんだ?」
「私は故郷を救いたいの。」
「えっ、故郷ッて…?」
まさか、否変身出来るエナガなぞ自分達の文化圏には見られない生物だ。迷い無く答えられて動搖したのは姫烏頭の方。
「私の故郷は夢の中。戦争を起こした場所も、怯えて暮らしている場所も私の故郷。桜桃と言う愛らしい名前を付けてくれて、有難う。そう言う所は兄さんにそっくりね。」
「兄さんとは…え?まさか。」
町の踊りはピタリと止まり、絵画となった。まだ身動きの出来る姫烏頭の目前に、一人の少女が現れた。
極光の輝きを背中に搖らめかせ黒のレエスワンピイス品良く着こなす身を包むように胸の前で光を羽のように交差させた恰好は、蛾の女神であろうかとくらくらさせる。落ち着いた顔立ちに少しふっくらした丸い顔、その輪郭には既視感がある。それに、黒に菫が咲く穏やかな瞳にも。
「父さんも、同じ瞳をしていた。」
「兄妹だから、似たのでしょうね。」
にこりと唇辺に笑みを湛える。とても少女のものとは思えない優しい威があった。
「では、貴女が、伯母上…」
「えゝそうよ姫烏頭。大きくなったのね。」
八
姫烏頭の父、竹一には三歳下の妹が一人居た。霧舟と名付けられたその少女には、生れた時から使命があったと言う。それは、夢の番人となること。夢の番人と名だけ聞けば随分とファンシーなように感じるが、その実過酷な運命を負うものである。
そもそも夢とは何ものであろう。眠る時に見るもの、それは夢である。過去の記憶、これも夢である。心に思い浮ぶるものは凡そ夢と称されるのに、馴染みにくさは薄い筈。しかし竹一・霧舟両人の生家では、分り易い意味ともう一つ、聞き覚えの無い意味も含めて夢を定義していたのだった。それは、夢とは色を指すと言う内容だ。今度は竹一家での色の意味を説明しなくてはならぬ。
竹一の生れ育った家は代々神職を務めとしてきた系図である。竹一の世代になってこそ世間は神主を認知していたが、彼等が幼いころには神職は一般に知られておらず、その為受容の土台も無かった。戦前、神社はまがいものを重要視する狂気の場所だと、信仰心の捨てられていた時代の露を正面に浴びた場所であった。人の力が過剰に信じられ託されていた時代であったので、祈りは人を信じない輩の愚行だと考えられていた。世間から袋叩きに遭わされても、竹一の一族は神主で在り続ける姿勢を崩しはしなかった。竹一少年と霧舟少女にとっては、両親の信仰心ゆえと信じていたのだが、実際彼等の両親は其処まで強い人物ではなかった。両親は神々ではなく自分達の復讐心を強く信じていたのである。
いつか我々を虚仮にした者共への罰が下されるように、いつか我々一族が日の目を見、侮辱し貶してきた奴等を見下せるようにと、両親の呪詛の言葉を聞き乍ら二人は育ったのであった。堅固で歪んだ信仰心は、子供二人をそれぞれの任から外すことなど認め得なかった。一人は現実世界で、もう一人は幽世の世界での使命を与えたのだ。
竹一の家で、夢とは幽世の世界、彼岸側での力のことを指し、現実世界、此岸側に光を与える力だと考えられてきた。そして、彼岸側の住民になることは誰しも平等に与えられた権利ではあるが、其処を守る者は女でなければならないとも考えられてきた。男は神々に談判することは出来るが、神々の助力をすることは出来ないとされているからだ。特に、死を司る神は女神であり、大の男嫌いだと記された神話に忠実な所為もあり、夢の番人は女性でなければならないと両親は折れなかった。だから一人娘をトリカブトで毒殺することに躊躇いは無かった。竹一が小学校から帰って来た夏の日のことであった。
九
「その日から少し前、風邪をひいてしまって。だから外の人からしたら私は風邪をこじらせて死んだの。でも、本当は違う、殺されたんだと知っていたのは兄さんだけだと思う。」
表情に一切のぶれも示さず穏やかに話す少女の言葉に姫烏頭は愕然とした。親が子を殺す、そんなことが。
「物心つく前から教えられてきたことだから、善悪も恐怖も感じなかった、考えることは無かった。兄さんも私も「あゝそうなんだ」って思っていた。でも、お別れを言えなかったのは正直心残り。此処から見えてはいたけれど、手を取り合えない寒さはこたえるもの。」
「ずっと見ていたから、俺のことも知っているの?一度も面識は無いのに。」
「兄さんが私のことを一度たりとも忘れたことが無いから、私は貴方達を彼岸側から見守り続けることが出来たの。」
霧舟の長い髪の毛は星纏う黒雲のようにふわりと微風にたなびく。
「風が出て来た。もう此の町とはお別れしなくては。さようなら、祈りの町。姫烏頭、行きましょう、次の場所へ。落ち着いた場所で、或程度の質問には答えてあげられるから。」
成人した甥ッ子の手を取る少女の伯母に引かれて、姫烏頭は足を動かした。
「次は、どの夢に?」
「今度は境界線に向かう。旅は一旦ストップだ。」
地面のマンホールの蓋をからりと取り払うと、手を繋いだまゝ霧舟は一直線に落下した。姫烏頭の叫び声は大きくやがて少しずつ細くなり、後には何も聞えなくなった。重い蓋は辻褄を合わすかのようにひとりでに閉められた。
現実世界よりも、夢の世界での方が長く生きている。だから此処を故郷だと言った。けれど、やはり気掛かりなのは兄のあの時の表情。冷えきった私の亡骸を見て、一筋零した涙の顔。取り乱しも叫びもしないでじっと黙って私を見つめていた顔は傍目には無表情に映ったろうけれども、私には寂しさをいっぱい湛えた顔に見えた。
天と地の間は、水面であった。樹木も草花も見当らない、かと言って砂漠みたいに荒涼の空間ではない、似ている例を挙げるなら、硝子瓶の内側の光景だろうか。風も吹かず細波も起こらない澄んだ水面に、二人は半身を浸していた。
「此処は…?」
隣に居る霧舟に声を掛けた心算が、音は予想以上に反響して、自分でも何を話したか単語を聞き取れない。
(此処での話し方は、声を出さないこと。心に言葉を思い浮べるだけで相手に伝わる。)
霧舟の声が耳の奥で谺した。清涼剤の清流に濁流していた意識は洗い流され、戸惑いは軽くなり深く息が出来るまで落ち着いた。
(先ず、貴女が何者なのか、改めて確認しておきたい。貴女は父の妹、なのですよね。)
彼女は頷く。
(では、桜桃は?自分が可愛がっていたエナガも、貴女が姿を変えていたものですか。)
もう一度。
(お名前は。)
(好きに呼んで構わないよ。桜桃のまゝでも良いし、伯母さんと呼んでくれたって、本名の霧舟でも。貴方が呼び易い名で呼びなさいな。)
(その見た目で伯母さんと呼ぶのは少し抵抗があるや。)
(子供扱いしないの。私の方が貴女より年上なのよ。)
(成長は亡くなった時の姿で止まっているんじゃあないの?)
(幽世ではその人の一番幸せだった時間の見た目が固定されるの。まあ、子供時代の記憶しかないから死んだときのまゝに見られても文句は言えないけれど。)
(自分で姿を選べる訳ではないの?)
(見た目はどうしようもないみたい。私が彼岸側で目を覚ますと、もうこの恰好だったから。)
(ふうん…)
(他には?何が知りたい?)
(いっぱいあって何から訊こうか迷うんだ。)
(それなら一つ、物語を聞かせましょうか。)
(貴女の、物語?)
(いゝえ、夢の世界についての御話。断片的には教えたけれど、その表情の様子だと或程度の全体を把握しきれていなさそうだから。)
言い返せなかった。無理もなかろう、昼寝をしたら旅をしろと言われて夢の世界を救いたいだの伯母であるだのけれど見目は定められているだのと告げられて、直ぐにはいそうですかと飲み込める人間は稀であろう。これまで平静を装って来た姫烏頭の顔には疲労の色が濃く見える。脳内で情報が整理しきれていないせいだ。
(此処は休憩場所のようなものだと捉えてくれたら良い。少し旅のくたびれを癒しましょう。)
そう微笑んで、霧舟は歌い始めた。
昔々渦があった 渦は飛沫を立てて動いていた
海がそうであるように、大陸がそうであるように、
渦もまた一ツ所には留まること能わずして
白き朝露は彼方此方に散らばって沈み込み
深き閨で種の訪れを待つ
やがて種は風で運ばれ
絡繰の絹糸で生命は編み出され
世界は背中合せの二つの顔を持った
一つは生命の歩く表側
一つは生命の安らぐ裏側
歩く世界は生と呼ばれ
安らぐ場所は死と呼ばれた
生は生き物から歓待されたが
死は生き物から忌避された
死は哀しみの涙を零し泉を成して身を沈めた
泉の水面には小舟が一叟
月下に佇む花が楫を取る笹の舟
風になってしまわぬようにと
繰る日も繰る日も泉を漕ぐ
烏瓜の花のはつ恋は
一夜だけの寿命を永らえて
泉に接吻する死にかけの螢よ
ついに目を閉じ愛しき君へ
寂しい手を求めて沈みゆく
放たれた最期の涙は灯となって空へ昇り
生の世界を花火で彩った
夢のはじまり、色のはじまり
水底で他を想ふ哀れさなる臍の緒
背中合せの身体と身体、顔を合わすことは許されざりしが
手と手をとって固く指先を繋いでいる
そして今も繋いでいる
(どう?)
(どうって…でも、面白い歌ですよ。)
(此の歌は番人は必ず憶えなくちゃならないの。苦手だった暗記を彼岸側でもしなきゃならないなんて思わなかったわ。)
如何にもプン、とむくれた表情が子供ッぽく見えて姫烏頭は思わずアハハと笑う。笑い声は静かに響いただけだった。笑える余裕が出て来たのなら、一先ず落ち着いた証拠だろう、安心して霧舟も笑った。
(聴いたところ、生者の世界と冥界の誕生が最初に歌われていましたね、それから、冥界での夢が生者の世界に色彩を与えている、とも。色彩を光と捉えるならば、やはり冥界は光を与える場所、と考えられますかね。)
(そうそう、その通り。夢とは現実世界に光を与える力のことさ。)
(つまり、彼岸側が存在しないと、此岸側も存在出来ない関係…だから背中合せなのか。)
(理解が早いわ姫烏頭。兄さんに教えてもらったの?)
(いや、あまり宗教的に詳しい話はしてもらえなかった。あ、でも、境界線の話とかは教えてもらったかな。)
(境界線?)
(坂道の話。家の建っていた近所には神社もあったけれど、寺もあったからさ、墓も身近だった。其の隣の道は坂道になっていて。)
(…坂道は、彼岸と此岸の境目。だから転んではいけない。転べば寿命が縮まるから。)
(伯母さんも御存知でしたか。)
(私の家には古くから言われてきた言葉だから。私も兄さんも、よく知っている。死が身近だった所為もあるかもね。)
(ごめんなさい。嫌な事を。)
苦い記憶を思い出させてしまったと詫びる姫烏頭に霧舟は頭を振る。
(私は此処へ送られたこと、後悔も、恨みもしていないの。それより、此処を助けたいって言ったこと憶えている?)
(えゝ。困り事なんて無さそうな世界なのに気掛かりな点でもあるのですか。)
彼女は頷き、躊躇わずに発した。
(彼岸の世界が失われようとしている。)
十
生と死は表裏一体。生命が在れば其処には必ず死が佇んでいる。これはよく耳にする論だが、その逆はどうであろう。死が在るから生が在るとは最近の道徳では主張してくれているのであろうかな。いずれにせよ、もう少し霧舟の話を聴かなければならないようだ。
(彼岸が失われようとしているとは、死の世界が消えてしむと言うことですか?)
(そう。でも勘違いさせないように先に言っておく。現実での科学の進歩に因る影響では無い。永遠に生き続ける技術が編み出されようとしているからでもない。仮に不死の人間しか居なくなった世界でも、彼岸側は失われない。)
(生きものも所為じゃないとすれば…)
(理由は一つ。死者達の所為だよ。)
二人が身を半分浸す水面が搖らぎか細く波を立てた。この現象は姫烏頭の動搖による結果ではない。霧舟は薄い唇を緊張させて一文字に瞬間黙る。
(風が出て来た。)
この台詞を先刻も聴いた気がする。
(伯母さん、その、風が出て来たとはどういう意味です?町に、踊りの町を立ち去る時にもそう仰有っていたような。)
(彼岸の世界での風は、呻き声とか叫び声に近しい。傷を負った時に漏れ出る声、と言ったところかしら。)
現実での定義と大いに異なる意味をさらりと言われて驚く間も無く次の驚きがやって来る。
(では、誰かが怪我をしていると…)
(正確には誰かの記憶が、ね。夢が傷を負うとこうやって風が起きる。でも此の場所は私の夢ではない中立点だから襲われる事は無いけれど…風が出たってころは、他の夢の悲鳴が耳に届くほど弱まりきっているのかも。)
急に話が物騒になっている。だが思考を止めてはならない。姫烏頭は受けた情報を整理して今度は質問ではなく確認をした。
(霧舟さん、僕を呼んだのは彼岸側を脅かす存在をどうにかして止めたいから、なのですね。脅威は死者達に関係しており、そして今貴女の夢が被害に遭っている。それを止めさせる為の手段を具体的に教えて下さい。)
覚悟は固めたようだ。姫烏頭の耳と耳の間には意思がある。霧舟は彼の顔を見て大きく頷き、水面下のもっと奥に腕を突込み何かを探すように動かしていたが、やがてビタリと動きを止めて勢い良く二人の目線へと引き上げた。
色に染まらぬ雫が滴る中其は零れる露を身体に受け留め、漏れることの無いよう穏やかに抱きしめ続けている。霧舟は手にしているのは、木造の櫓であった。
(これを持て。舟を漕ぐんだ。)
(舟は、何方に。)
(私の名前を見くびるな。)
ニヤリと笑み深いまゝ両の掌を天へと向けた。すると二人の眼前に淡い色彩の笹舟が一叟、人が三人乗っても余裕のある広さのものが忽ちに現れた。
(姫烏頭、乗りなさい。)
慣れた動作で流れるようにヒラリと飛び乗る霧舟に遅れまじと姫烏頭も小舟の縁を掴むと水面を一気に飛び出し木製のオールと共に舟へ転がり込む。笹で編まれた割に随分しっかりと固い床に背中は多少痛んだが櫓握る力は決して緩めなかった。直ちに起き上がって足を踏みしめ背筋を凜と伸ばして行手を尋ねる。
(前に漕げば良いですか。)
(えゝ。前に漕げば此の中立地点から外に出られる。その時一瞬視界が真ッ黒になるのが出た合図。次に視界に映るのは、先程迄とはまた違う夢。)
笹舟はゆっくり確実に前へと進み、何も見えなくなった。
十一
「一つ訊いても良い?」
「どうしたの姫烏頭?」
「死者達は何故夢を襲うようになったの?」
紅茶を淹れた後の薫りと温かさが夜のカフェテラスに座る二人に沁みる。笹舟は霧舟の片耳に輝くオパールのイヤリングに、櫓は姫烏頭の腕に巻く銀の時計となっていた。場所の雰囲気に合わせてどちらも小洒落た様相の格好をしている。霧舟曰く。脅威について調べるのに都合が良いから身なりを整えただけであって、旅の楽しみとして術を行使した訳ではないそうで。先程の祈りの町と違い、今度は彼女等は夢の風景に溶け込んでいた。席に着いて紅茶セットを早々に頼んだのは霧舟の方である。運ばれて来たケーキとポット・ティーカップ達を見た時の彼女の華やいだ顔と言ったら!折角のひと時を真剣な話で終わらせるのも気が引けたので、紅茶好きだった母親の話を始めた。すると伯母は甥の近況を知りたがり、会社ではどうか、夏バテしていないか、ちゃんとご飯を食べているか寝ているか、実の母よりも細かい質問をケーキ片手にどんどんされたが、姫烏頭はちっとも嫌に感じなかった。訊ねたかったことを一通り聴けたかして、霧舟は紅茶を飲み、残っている分のケーキを食べ始めた。このタイミングで、姫烏頭は冒頭の質問をしたのである。
霧舟はティーポッドの紅茶を全て飲み干してから答えた。
「死者が全員、自分の死に納得しているとは限らない。全ての死者が死を受け入れられる訳じゃない。未練を残した嘗ての生命は私達の言葉で迷子と呼ばれている。」
「迷子。」
「其方側では迷子に一生分の手を焼かされる事は無いでしょう、一時だけ辿り着く先を見失ってしまっているだけで、案内や助言があれば迷子ではなくなる。」
「霧舟さん達の世界では厄介なものなのか。」
察した言葉に頷く。すると霧舟は左腕の長袖を捲り、二の腕の少し下辺りで手を止めた。同時に姫烏頭も息を呑む、彼の視線の先には皮膚を刃物で横ざまに裂いた痕が幾条もあったから。
「まさか、」
自傷行為、の単語を飲み込んだ。代りに拳を固く握る。どの、口が。
「私が自分で傷付けたのではないよ。」
寂しい微笑みを何も言えなくなった甥に掛けて。
「これは、迷子となった者達の付けた傷。彼等彼女等は自身に与えた傷を相手にそのまま付けることが出来るのさ。だから実際自らの腕を切り付けたのは迷子達本人なの。……姫烏頭、話、続けるの辛くない?」
避けては通られない話題。迷子に光を知らせたいのであれば、己の迷いを直視しなくては。だからこそ、兄さんは私に託したのだろう。一人息子が自分を正しく見つめられるように。
「乗り越えるべき波を起こす。姫烏頭、私はこうする方法しか知らない訳じゃないけれど、此の手段が一等よく利くと考えたから、そうさせてもらう。貴方の傷を、貴方の手で抉り出させる。」
固く目を閉じ、息を吸うのは此方も同じ。
「ねえ、お寺と神社は何が違うの?」
小学校の時にクラスメイトは繰り返し尋ねた。お墓があるのがお寺で、神様がいらっしゃるのが神社だよ。
「どうしてお墓を神社の中に造らないの?」
まだ質問をし足りない子はそう続けていた。確か、神仏分離令が施行されたからだったような気が。法律で決められているからじゃないかな。
「ふーん。」
少し小学生には馴染みが無い話題になってきたからか、同級生は去って行く。ごめんね、僕には分けられている事が当り前の認識なんだ。当り前の理由を深く考えたことは無い。小学生は当り前に疑問を抱かない。
「ねえ、将来は神主になるの?」
中学校を卒業したら進学ではなく実家の家業を継いで働く人が多い地域だったから、自分も父親の仕事を継ぐのだと思われていた。いいや、僕は神主にはならないよ、卒業したら高校に通うから。
「ふーん。姫烏頭のお父さんって、家でもあんな格好してんの?」
装束は神前で祈祷やお作法をする時だけに着るものだから、家ではパジャマやジャージも着るよ。
「でもこの間、和服で迎えに来てたじゃん。具合が悪くなって早退した時。」
まさか階段に躓いて十段程転がり落ちるなんて。頭痛が酷かったから、ちゃんと足元を確認出来ていなかったんだろうね。先生が父さんに連絡した時、父さんは丁度仕事先だったから、神事を少し延期させてもらうと直ぐに学校へ来てくれたよ。着替える間も惜しかったのかな。
「ものすごい人来たって、クラスで一寸話題だったよ。姫烏頭の父ちゃんってすげえって。」
あの顔であの雰囲気で装束着てたら初見の人は大概驚くよ。でも見てもらえて正直一寸嬉しくもあったんだよね。うちの父さん凄いだろうって、風邪ッ引きのガンガンする頭で誇らしさを感じていたのはよく憶えているから。
「やっぱり神主になると、色々な神社に行かれることもあるのですか?」
古典の先生に質問された。先生は確か無神論的なお考えをお持ちの方でしたよね。それに此の学校はカトリックスクール、けれど仏教徒の先生も居れば古典の先生みたいな偏屈者も居る、宗派の門が広く寛容な変わった学校でしたね。小・中の同級生が一人も居ない都会の私立、先生、勝手に暴露しないで下さいよ。
「姫烏頭君神社の子なんだ。」
神社の子ではなくて、神主の家の子です。神社に住んでいる訳ではありませんから。
「神主になるの?」
父さんが継がせようとしていないから神主にはなりませんよ。
「父親の職業が神主、と言うのは初めて聞きました。英語では………ですよ。神社に住んでおられるの?」
大学で友人は出来たけれど、もう社会人に近い者同士家庭の内情を探る質問はしなかった。だからこそ、英語のクラス、コミュニケーション練習の為のテーマが父親の職業、と言うのには驚いた。嘘を吐いて適当でっち上げるか、でも相手は友人だ。説明したら理解してくれる優しい気心の男だから、後から事情を話せば嘘で課題を進めて行ったことを許してくれるだろう、そもそも嘘を吐かれていても彼は怒らない。
でも。そんな大切でかけがえの無い友人だから、正直に話さなくてはいけないと気が咎める。先生に神主を英語で何と言うのか尋ねたら、友人は驚いていた。
「おまえ、すごい家に生まれたんだな。」
姫烏頭がカフェテラスのテーブルに俯伏せに倒れる。落としたグラスは店員が箒とちりとりで処理する。
一般的な家庭と内情は然程変らない筈なのに、親の仕事が神主だからと、珍しいからと接し続けられる。結局大学の友人とは疎遠になり、卒業後就職した。
「父さんは誇りだったよ。でも俺は神主の息子として見られることが苦痛だった。地域の人は皆俺が神職の家の子だって知っている。私立では親の経済状況を把握しておく為に情報を学校側が集めている。大学になって、自分からは言わないようにしていれば、知り合いの一人も居ない大きな四年制大学でなら教員から暴露される危険性も無い、油断していた。その友人、もう友人ではないから知己程度か、此処でも自傷行為は誘惑して来た。」
「それは、小学校の頃からか。」
「親にはバレない、見つからない箇所を日々切り付けた。」
「丁度一人でお風呂入りたがるのは小学生からだものな。」
「服で隠せる部分はどうしてもシャワーが腕とかに比べて沁みるんだ。それでも止められなかった。」
物心ついた時からの悪夢は自傷行為が原因だった。
「でも最近では悪夢を見ないんだ。自傷を、止めたからかな。」
「何で自傷を止められたんだ?」
「する必要が無くなったんだ。今の仕事の上司に、自分は神主の息子なんですって休憩時間中に言ってみたんだ、どうせいるか思い掛けない形で知られることになるのなら、もう先に伝えてしまおうって。そしたら上司はコーヒーを飲んで笑って、
(おまえのずば抜けたコミュニケーション能力は、親父さん譲りなのかもな。)
って、言ったんだ。」
「兄さん譲りの才能?」
「ほら、神主は祈祷や御参りに来た人達とお話、説法のような話をする機会があるんだ。自分で文章を考えて、参拝者に分り易く話をするんだよ。質問に答えることだって多かった。それに、父さんは一つの神社に常駐する形じゃなかったから、企業に赴いて地鎮祭を執り行ったり、また別の企業では業績を上げ続けていけるようにと御祈祷をしたり。色々な、本当に色々な所で仕事をしてきたから、澤山の人とお話する機会があったんだよ。上司の人は取引先で営業担当責任者として地鎮祭や御祈祷に参列したことがあったんだって、しかもそれが、父さんの仕事先だったんだ。」
「え、じゃあ兄さんのことを上司の人は知っていたってこと?」
「実際に話した訳じゃないから、名刺の交換もしなかったけれど、父さんの働きぶりを遠目から見てくれていたんだって。
(神主さんがあんなに話をしなければならない職業だとは知らなかった。正直営業部門に欲しい人材だと思ったよ。)
でもまあ、まさかその息子が営業事務として円滑に社内のコミュニケーション取れている姿を見たら、或意味スカウト成功かもなッて笑ってくれたんだ。」
「すてきな御縁に恵まれたのね。」
「会社では生い立ちよりも今持っている実力の方が大事だからね。僕自身の力を見てくれていたことがとても嬉しかったんだ。」
「その日から、怖い夢を克服出来たのね。」
「うん、それから、父さんと母さんに深い感謝と…尊敬を。」
「そう……」
ほーッと深い息を吐く。
「よく、話してくれたね、姫烏頭。辛い記憶を抉り出して晒すのはとても苦しかったろう、疲れたろう。」
「疲れたけれど、自傷のことは父さんと母さんにも言えずじまいだったんだ。だから…今日、伯母さんが聴いてくれてよかった。ありがとう。」
先にお礼を言われたら、もう辛いことさせてごめんねを言えなくなる。察しの良さは兄さんにも似たが、義姉さんにも似ているかもね。
「この、話す工程が必要だったの。死者達を止める為には、攻撃から身を守るには。」
「これから、どうするの?」
「此処で悪夢達を待つ。向こうはあらゆる夢を否定したがる。から此の夢にも遅かれ早かれやって来るだろう。」
「分かった。…ところで、カフェテラスも伯母さんの記憶なの?」
「彼岸側には全ての生命の記憶が息づく。だから此れは他の生物か人間の記憶。でも、最初と二番目の場所は、私がエナガとして世界のあちらこちらを旅した時の記憶。」
「色々な生命の記憶があるんだね、境界線の世界では。」
毎日居ても退屈しなさそうだなと感じた途端、コーヒーの匂いがした。
十二
迷子はどのような姿で現れるのか、と問えば普通の人間の姿で現れる。迷子と化してしまう確率的には人間が九点九割を占めており、人間以外の生物でも極く極く稀になってしまうのがあるとのこと。
「迷子は最初、一人で夢を訪れる。其処で数人の住民に接触して、何気無い話始めるの。最初の振舞いでは迷子かどうかは判断出来ない。」
「ではどうやって迷子を識別したら良いのです。」
「迷子は自分に慣れて来たと相手を判断したら、相手の腕に噛みつく。当然相手は悲鳴を上げる、その悲鳴が迷子軍団の行進の合図。奴等は風に乗って夢の景色を壊し始め、人を襲う。」
「死者の世界で人を襲う、彼岸なのに危ない目に遭うなンざうんざりするな。」
「そう、そう住民達に思わせることが相手の狙いなんだ。死者の世界を拒み始めたものは地上で彷徨う霊になって、人間に大なり小なりいたずらをする。生者の世界を守護する役割を捨ててしまうんだ。」
「怖い会社に怯えて働くより、気楽な場所に行って好き勝手する方がいいもんな、住民にとっては。」
「私が抵抗を続けているからまだ死者の世界は失われてはいない、ぎりぎりのところで保っているけれど、この姿じゃあずっと一人では闘いきれない。」
いくら番人とは言え見目は小学生の女の子だ。体力の限界なんぞ直ぐに何度も来るだろうに。
「そうか。なら俺も協力しなきゃあいけませんね。具体的な策は?」
霧舟はカフェテラスのもっと向こうにある暗い海辺を指差した。
「今腕時計として巻いている舟は、乗る人数に合わせて大きくなる。だから拾える者は全て乗せて、あの海辺に向かえ。迷子は水を極端に怖がるから、水の上に浮ぶ舟に手出し叶わない。此の町に来た迷子は私の術で打ち払う。」
「俺は眺めていろと言わないですよね。」
「当然。姫烏頭、君には舟で助けた人達の説得をしてもらう。奴等を払えても此の町は大きな被害を受けるだろう。だが、誰も居なくなってしまえばいずれ此の町は、夢は、失われる。傷心の彼等・彼女等に此の夢を諦めさせない心を抱かせろ。」
「迷子への一番の策は、住民達の心を彼岸の世界から離れさせないようにすることか。」
「察しが良い子供は助かる。」
貴方達の息子さんはもう大丈夫。だからもう心配しないで、泣かないで。あの子が頑張る姿を見てあげて。今はまだ人の姿として彼岸に在れない修行中の身だから、生前の姿で再会はさせてあげられないけれど、彼岸の国の一部となって、必ず何處からか見ているのでしょう?愛しい貴方達の一人息子の今の姿を。
十三
他人の悲鳴は否応無く身を竦ませる。それは、悲鳴を上げた者の心情がありありと分るから、自分が悲鳴を上げていた時の心を思い出すから。
戦時中は地獄だった。新聞や号外で知らせられる戦況、何千人の死者と連日書かれていても実感出来ないあの感覚が怖かった。そして近所の人達も。戦時中石を投げつけて無力だと罵られる、道を歩けば襲われそうになる、何度兄の手に守られて家迄曳かれたことだったろう。それも戦後、怖いものはパタリと止まった。
私がトリカブトを飲まされたのは、戦争が終結する一日前だった。終戦の日を彼岸で迎え、此岸の様子はどうであろうと実家を覗き込んだ。正直、見なきゃ良かったと後悔した。
実家だけでなく、敗戦国の国民全員が等しく壊れていた。戦死した兵士達は神に祭り上げられ、荒神として扱われ整美されていった。古来の神々は遺物として捨てられて、国には生れながらの神々ではなく元人間の神々があちこちで信仰されていた。
兵士が神になれるかよ。
古い神々を祀っていた実家は国民の手によって取り壊され、更地となった。父母は耐えられなかったのだろう、兄が配給色を貰いに行っている間に御神木に血が掛からない距離で喉を突いて死んでいた。兄は二人の遺体をなけなしの水や塩で清めた後、火を免れた桐タンスにしまってあった母の白無垢で二人を包んで
「今度は良い音に囲まれて生まれて来られますように。幽世の大神様、憐れみ給え。」
そう唱えると両親に別れを告げ、古来の神々に仕える神職者を育てる為の場所、神主養成所へと向かった。私は昇る旭に向かい歩き去って行く彼の背中を見つめていたが、視界はずっと滲んでいた。頬を伝う玉は温かかった。
何かに縋りたいが何に縋って良いのか分らない、そんな迷いは生きていても死んでいても生命を脅かす。容赦はしない、彼岸の番人に逆らえばどうなるか、一度殴って正気にさせてやろう。
「慈悲だ。」
霧舟は雪の槍を迷子一人一人の眉間に発射させる。人差し指一本で幾らでも繰り出される精密射撃に迷子は次々と仰向けに倒れていく。
「前まではこんなに手こずらなかったのにって、悔しそうだな迷子ども。」
先鋒隊を全員倒れさせた霧舟は、今度は左手を天に向け、そのまゝ握り拳を作る。
悲鳴、悲鳴、迷子の悲鳴。身体中の中央部から石英の水晶柱が飛び出して来て厚みのあった第二陣も残らず倒される。第二陣には屈強でガタイの良さそうなパワー系が列を成していたので、次に控える三陣は町を襲う暇も無く霧舟の前に立たされる運びとなってしまっていた。
「突ッ走って来た彼等のように倒れさせるのに十秒も掛からない。例え残りの総力で一斉に襲って来たとしても。負ける闘いに身体を貫かれるか、それとも大人しく話を聴くか。私は何方でも一向構わん。」
迷子は互いに顔を見合わせて、倒れた仲間の介抱をし始めた。其の背中には先刻までの殺気は無く、しょぼくれたただの人間の背中だった。
「あの…話って、誰の話を?」
迷子の一人におそるおそる尋ねられ、霧舟は軽やかにニッと笑む。
「私の甥だ。今避難民の説得を海上でしている。」
さあ、話をしろよ。まだ吐けていないことも含めてな。
十四
「助けてくれて有難う。」
「番人様の甥御なんだってねえ。」
「もう駄目かと覚悟したよ。」
様々な年代の人からお礼を言われる。ないがしろにしては本題に耳を傾けてもらい難くなると予想し、一人一人のお礼の言葉に正面から向き合う。
「あの、皆さん、お訊きしたいことが。また、あの町に戻って暮らしたいですか?」
腕を噛まれた青年が真先に呟く。
「もう彼岸の世界は怖い。こんなんじゃあ、役目を果たす以前の問題だ。住めないよ。それより地上でフラフラする方が気楽で良いよ。」
「そうね、番人様はとても頑張ってくれているけれど、お一人では限界があるでしょうし…」
「でもだからと言って僕等は迷子と闘うのは怖い。」
「闘う必要なんて、無いんです。」
不安な本音の積み重ねに、姫烏頭はきっぱり言った。
「迷子達は今実際に番人様が抑えてくださっています。ですが抑え続けたところで迷子の数は増えていくでしょう。」
「そうだ。だから我々にはどうしようも…」
「増えるのを止めたいのであれば、減らすのです。そもそも迷子を発生させない土台を構築すれば良い。」
「理屈は分る。だが、そんな強い力私達には無いよ。」
「いゝえ、必要なのは強い力ではありません。彼岸の国に、死者の国に留まろうとする意志があれば良いのです。」
一同は声援の提案にぽかんとした。意志だけであんなおッかない怪物達をどうこう出来るのだ果して。それでも青年は言葉を紡ぐ。
「迷子達も、嘗ては此の場所の住民だったのです。生前不条理に遭い未練を抱えて此処に来てしまった。未練を果たせない悔しさと悲憤は運命に向けられ、死を恨みます。だから迷子は死者の国を壊そうとしているのです。」
少しずつ住民達は頷き始めた。それでも不安の声はある。
「で、ですが、死者の国をありありと示せばそのぶん迷子の反発は強くなるのでは?悪あがき、のように大暴れしてしまわないでしょうか。」
姫烏頭は拳を握りなおす。もう少し、もう少し。
「意志が集まれば国の幹は安定する、そしたら番人様は力を根から借りられる。仮に迷子が暴走しても、必ず番人様が守ってくださる。」
「要は、彼岸側を信じ抜けるかどうかの問題か。」
一度死んだ身は理解が速い。うんうんと納得する一同は、一つだけ姫烏頭に問いを投げた。
「それにしても、君は如何して彼岸の国に助力してくれるんだい?見たところ、まだ死んでいないように見受けられるが。」
「それは…」
死者の国の住民達は皆生きていた頃より色んなものが見えるし、感じられるし、分るようになる。故に、彼等彼女等は生者を試す。此の人物がどのような本性なのかは見えてはいるが、敢て試練を与えるのだ。ずっと霧舟と居た影響か、質問された瞬間、姫烏頭は直覚的に試されていると分った。そして、直感で答えた。
「まだ生きたいからです。」
大義とか、使命とか、そんなじゃあない。
「まだ僕は、自分自身を消化出来ていない。人とは違う家に生れたこと、誇りに思うことが多かったけれど、それだけじゃない。嫌だと感じ続けたことも、逃げ出したいと考えた時も澤山あった。でも僕はまだそれを自分の中で認めきれていない。自分の感情を全て受けとめたいのです。でないと僕は、僕を好きになれないまゝだ。」
何處に行っても褒められた。褒められるような存在でなければいけなかった。親に強制されていなかったからこそ余計にそう考えた。都会に出たのは、窒息しそうになるのを避けたかった、或種の生存本能に因るものかもしれなくて。
「彼岸と此岸は鏡合せの世界だから、彼岸が失われたら此方側も生きていけない。きっと地上は、不死の存在が闊歩する虚ろな世界になる。」
「死の世界が無くなれば生命は死ななくて済むようになるなあ。坊主、君だって死から解放されるんだぞ?見たところまだまだ若い、ずっと元気で生き続けられることに何を嫌がる?」
正直――、まだ弱い。まだもう一押しが欲しいところだ。
住民の問いに品良い白歯を喰いしばり、少し顔を俯向ける。清らかな鼻筋にみしみしと皴を寄せたのは涼しい身権威濃い影の刻みを彫った共鳴の為で、眦固く堪えた瞳を月が弾くが如き勢いで見開き大きな声でとうとう叫んだ。
「いつまでも俺が死ねなかったら、親父とお袋に永遠に会えなくなるだろうが!」
おぉ…と一同は目を丸く。
「言いたかったこと全部を言いきれてなんざいないんだよ、二人の嫌だった所も二人といて苦しかったことも全部隠し通したまゝ二人とも見送っちまったんだ俺は!だからこそ生きている間に俺の正負の感情全部俺自身が飲み込んで理解して、言葉にして二人に伝えなきゃならねえんだ!」
最後の方は酷く掠れた声になって、恰も血を吐くような鬼迫があった。人生で、初めてであろう。シャウトのようにあるがまま叫びつくすと言うのは。反動でその場にへたりと座り込んだ。立つ余力も無い程全霊で叫んだ結果である。意識もやや薄れ気味になった荒く息吐く姫烏頭の目は、疲れにぐったりと閉じていた。
一人が言う。
「あらあら、反動が強すぎたようねえ。恐らく初めてだったんじゃあない?本心を叫ぶなんて行為。」
続けて
「若いねェ、でもその若い時に成したかったことは、きっと此の子の未来でも役に立つさ。清濁併せて己とするのは難儀なことなのに、とんだチャレンジャーだ。」
最後に
「死在るからこそ生は在り得る。生を求める者が一人でも居るのであれば、彼岸の国は失くなっちゃあならないもんな。」
その発言に居合わせた住民は全員応と頷いた。すると、目に見えて迷子の圧力が弱まった。
「番人様!聞こえますか!」
住民の一人が舟の上から霧舟の居る方向へ呼び掛ける。
「随分相手がしおらしくなってきた。君等は彼岸に居ることを選んだんだな?」
霧舟は今や片手間となった抵抗を軽くいなしながら返事した。
「はい。我々は今から舟で他の住民の夢に向います。其処で住民達に彼岸の国を去ってしまわぬように説得して参ります!」
「此の迷子の力が完全に抜け切ったら私も後を追う。説得の間は私が応戦しよう。」
「お願いいたします!」
「ところで、私の甥はどうなった?」
「眠っています!疲れが一気に来たものかと。」
「分った。悪いがそのまゝ休ませてあげておくれ。」
「承知しました!」
舟はえっちらおっちらと漕いで次の夢に進んで行った。それを見送る霧舟の後ろには、もうただの人間に戻った元迷子達が震える声で一言呟いた。
「なんで…?」
迷子の力が全て霧散すれば、彼等彼女等は死んだことを認められない、受け容れられない不条理の弱い犠牲者である。膝をついて涙を落し、頭をぐちゃぐちゃに掻き回す者達のうち一人の手に霧舟は自分の手を置いて止めさせた。
「番人様…」
「君達自身を責めはしない。それに、未練ある者に救済の措置を設けなかった番人として、君達に謝らせてほしい。まこと、申し訳無かった。」
深々と頭を下げる霧舟に、元迷子達はおろおろ。
「あ、頭をお上げください番人様…謝るのは、我々の方なのですから。」
懇願を受け霧舟は相手の意に沿った。顔には寂しい微笑みが湛えられていて。
「実はまだ、全ての迷子を正気づかせられた訳じゃない。他の夢では侵略が進んでいる。国民の説得は国民に任せれる。迷子の力も或程度まで私が壊せる。迷子の力が弱まったら、君達に迷子を説得してもらいたい。同じ苦しみを味わった者同士、通じるものは在る筈だ。」
返答は、
十五
凪の湖面は麗しいと、旅行先で両親が話していたことがある。ぼんやり眺めていた湖面には、本当にさゞ波一つ無くて、魚の影も認められなかった。鳥が訪ねる音も、木の葉の搖らぎも無い。
苦しいのかな
何かに耐えているようだ、水面下では何がもだえているのだろう。手近にあった小石を投げ入れて反応してもらおうと思ったら、両親に行為を止められた。
(驚かせてはいけないよ、水の中の生物達を。)
でもずっと黙っていたら苦しいだろうに。
(姫烏頭どうしたの。そんな乱暴な事しようなんて。)
乱暴じゃないよ声を上げさせたいだけだもの
(いけませんよ、魚さんが怪我するかもしれないでしょう。)
(穏やかなものはそのまゝにしておくのが良い。ほらおいで。)
違うよ母さん、怪我させたいんじゃないよ。父さんも聴いておくれよ、このまんまじゃあ可哀想だよ。
「離して。」
掠れた一言と共に目が覚めた。あんな記憶は、初めてだ。実際湖を見に行ったことはあるし、小石も投げようとしていた。けれどもその行為は父に優しく止められ直ぐに小石を地面に戻したのに。あんな駄々を、抵抗をするなんて今までありはしなった。息を長めに吐いて身を起す。姫烏頭はまだ舟の中に居た。舟の後ろの方で誰かの上着を掛布団に寝ていたようだ。彼の動く気配を察して、住民の一人が声を掛けた。
「おや、もう動いて平気なのかい?」
「え、えゝ。」
意識も半ばあやふやに頷く青年に寝起きの無防備を見て声の主も他の住民達もふふと頬を緩める。夢は過去の記憶の姿だと考えていたが、どうやらそうではない…?」
否、否、今は均衡の窮地。
「迷子達は?」
意識を飛ばしそうになるのを急いで打ち止め、現状況を確認する。慌てる姫烏頭と対照的に住民達は落ち着き払っていた。
「此の場所に、見覚えは無いかい。」
問われてようやく舟の外の景色に焦点を当てる。其処は、一面の雪野原であった。新雪が蜉蝣の翼のように重なり合う地面は踏むのも躊躇われる玻璃の鏡かと紛う中に、点々と花の項が見てとれる。
「雪野原でしょうか。こんな白い光景を見た覚えはありません。訪れたことも。」
「姫烏頭。」
よく馴染んだ声がして、振り向くと霧舟が立っていた。初めて逢った時と同じ冥界の番人たる姿で。服装も微笑みも、最初の様相と寸分違わぬ風格のまゝ雪の上に。
「霧舟様。」
「…名前を呼んでもらえるのはやはり嬉しいけれど、此処ではまだエナガの名前で呼んでもらっていた。」
「え、では、此処は、彼岸側に来たばかりの時に訪ねた中のどれかなのです?」
「驚くのも無理ないかな。初めの頃とは随分様子が変っているから。」
姫烏頭は考えた。まさか、と思う回答は一つあるが、余りに別の眺めになっているから流石に違うだろうと。生者の隠し事は死者には丸見えであるのに。
「その答えで合っているよ。」
霧舟は住民達と顔を見合わせ静かに笑った。信じられるだろうか。こんなに穏やかな景色が一番最初の戦争の記憶と同じものであるなどと。
「雪など積もっていなかった。それに、花など息づく隙も無く、人体の残骸が染みとなって土にこびりついていた筈だ。何故、このような。」
「君の言った通り、雪が降ったからさ。過去は切り取って保管し続けていられるほど大人しくは無い。常に絶えず動いている、蠢いていると呼ぶ方が似つかわしいかな。例えるなら、うむ、そうさな…自己修復の機能が生き物には備わっているだろう?あれと同じ類さ。時間やら時代にもその機能がちゃんとあるのよ。」
「えゝと…いきなり何の話です?」
「何故何故と問いを投げられるのは生者特有のものだな。今の君なら必ず自分で理由を求められる筈さ。」
舟の中に座っていた姫烏頭の手を取り雪の大地に連れ出して立たせると、彼女は寂しい微笑みと共に甥の額にキスをした。
「現実世界に戻る前に、一人でもう少し潜って行くと良い。」
僕の質問に何一つ答えていませんが、と文句を思う暇も無く、姫烏頭の身体は四方から青水晶の柱に囲まれ、そのまゝ荒ぶるエレベーターより気性激しい勢いで地面の下に落とされた。
第二章 十六
「もし、もし、聞えますか、もし?」
若い女性の声と、頬を遠慮がちに数回打つ搖れ。姫烏頭は路地裏で大の字になって気絶していた。彼女が傍で声を掛けないまゝだったら姫烏頭は今頃身包みひッぺがされて情け無い恰好となっていただろう。恥を避けられたのは幸いであった。目を薄ら開けた先にビルのような煉瓦の高い建物があり、その隙間から青空が覗く、そして、飛行機よりも鋭い音を立てて空を切りながら飛ぶ機体も。
「戦闘機だ。」
ではもうすぐ此の場所は焼野原になるのか、と考えた際には隣で気遣わしげな女性の手を握り迷わず発言していた。
「逃げよう。直に此処が酷い焦土となるんだ。人はそのまゝ地面の染みにさせられる。少しでも、水の深い所か、山奥の洞窟へ。」
姫烏頭の差し迫る提案を娘は軽く手離した。
「今日は戦勝記念パレードが挙行されているのです。あの戦闘機の音はパレードのプログラム、空中演技を見せていただけですよ。」
「あ、あゝ、そう、なのか。」
「此の近辺では見ないお方ですね。あゝ、若しかして国外の方かしら、移住希望の方?」
今すぐ黒い地面と化す恐れは無いと女性から聴いた時、表通りに出て行こうとしたが女性は姫烏頭を気に掛け歩く後ろを付いて来る。
「移住希望の方の手続き場所は確か役所だったわ。でも此の方お一人で行かせるのは不安だわ。やっぱり、案内さしあげるのが良いわよね。」
独り言は声を抑えないと意味が無いのに、彼女は話すのと同じ音量ですらすらと。これでは姫烏頭一旦付き合わなくてはなるまいと観念し、先ず他所者の風を装って女性に話し掛ける。大通りはもう後十数歩のところだったのに。慰めか、ネズミのチュウと壁這う声。
「貴方、とても堪能にお話なさるのね。勉強なさったのですか?」
「えゝ、まあ。…ですがそのぶん、時世の方はとんとしていなくって、新聞も読まずに没頭していたものですから、その、此方の事情を碌に知らずに来てしまいました。宜しければ、今何が行われているのか教えていただけないでしょうか。」
女性に付いて行き乍ら姫烏頭は会話を続けることにした。言葉少なにあしらうよりも現状を把握した方が良いと考えたから。情報はいざと言う時矛にも盾にもなり得る。一人で潜れと背中を押された以上、夢が覚めるをじっと待つ訳にもいくまい、まだ覚めてはならない理由がある。それに辿り着く為にも此の夢がどの時代辺りなのか、何處の夢なのかを知っておくのは必然。
「まあ、そんなに熱心に言葉を学んでくれたのですか、国民として礼を申し上げます。」
女性は足を止め姫烏頭に振り向き正面から目を見つめた後、深々と礼を施した。
「我国をそこまえ愛してくださって、有難うございます。」
何と、彼女のみならず、路地裏に居た人々は皆素性の知らない男にこぞって深々と頭を下げているではないか、これはそも如何に。
大通りでは路地裏に背を向けて賑やかなパレードが続いている。彼等彼女等はパレードに参加しに行くこともせず、じっと姫烏頭に礼し続けている。大通りと路地裏、よくある光と影の対照ではあるが、それだけではない気がする。
「あの…顔を上げて下さい。お話…伺っても?」
「えゝ、では、此方へ。路地の突当りに私の家がありますから、詳しい話は其方で。」
若い女性が自分を見る目が変った。それまでは国外の者として糸目でおっとり接していたが、今では恰も同士を見る強い眦、聡明で鋭利な石英宿す瞳で姫烏頭を見つめている。
十七
「先ずは貴殿の名前を教えてもらおう。」
店を兼ねたような造りの家の中は、普通の家の様相をしていた。部屋が然程広くなくとも必要な機能を備えた家具達が動線を殺さないレイアウトは住み心地が良さそうだと正直に感じる。家に集った人数は自分と例の女性を含めて合計五人。各々ソファや床や椅子と好きな所に座り、此方を見る。案内されたテーブルダイニングの椅子に座ると、同じく反対側に座った例の女性が質問した。
なんと答えた者か。本名を言うべきか外国の者を装ったまゝにするべきか。押し黙ったまゝいると、女性はふうと息を吐き、呆れた声で
「薄情な奴め。性悪婆さんの顔をもう見忘れたのかえ。」
正体を明かされた姫烏頭が卒倒したのも無理はない。
「本当に、性悪婆さんですか?」
布団に寝かされ頭痛膏まで貼ってもらった姫烏頭は目覚めて起き上がるより先に尋ねていた。
「そうだよ。尤も昔の、若い姿だがなか、二十歳前後と言った辺りかね。声まで若々しくなったろう?」
ケタケタ声の破顔一笑。まさかが納得して理解した。
「じゃあ、もう僕が倒れている時分から正体分かっていたのですね。」
「竹一さんとこの一人息子だとは直ぐに分かった。まさか私の夢にお前が来るとはなあ。」
「貴女のことだ、与えた情報は全て嘘?」
「いや、それは断じて嘘ではない。」
「はい?」
「教えてやろう。嘗て戦時中私達が何をしていたのか。」
戦続きだが連戦連勝、勝者は敗者を従えさせられる、だから国中は戦争に好意的だった。故に戦争を憎む土台は、乏しかった。そして国益に直結している事象でもあったから、流行に飽きる感覚も適用されなかった。
「それは、人の目が眩んでいた結果だ。」
目が眩んだ状態だと、人は普段通り生活している時の思考をしなくなる。考えるよりも目先の光の正体を見ようとばかり焦るから。しかしそんな状態で前進するのは非常に危険であるのだと若い婆さんは言う。
「普段歩いていると、足元に気を付ける。だが目が眩んでいると気を付けなきゃならないことにまで意識が回らない。だから躓きこける。歩みを邪魔した対象を強く憎み必要以上に叩きのめす。そうならない為には、いつも通りの何気無い思考を忘れないことが肝要だと私は考えた。」
「戦時中に、その姿勢は貫けたものですか?」
非国民、と言う語が頭をよぎる。
「私は私の親しい者達が戦死しなけりゃそれで良かった。だから逃げたのは私を含めて数名さ。」
「でも、軍が許しましたか?」
「姫烏頭。」
布団で上半身を起こす書生姿の青年に若い婆は片手を突きつけてピシリと言葉を止めた。遠くパレットのトランペットが高らかに雄叫ぶ声。固唾を呑んで突き出された制止の手を見つめる。冷たい汗が皮膚の内側を流れ、動脈をどんどん冷やしていく。
「いいかい、これから私が貴方に教えるのは教科書には載りきらなかった事実。歴史の復習は今は置いておきなさい。と言っても、もう一度勉強する為に此処に連れて来られた訳でもなさそうだけどね。」
国民総動員法の裏で澤山の無念や悲しみが渦巻いたことを授業では教えられた。戦争の一番の被害者は罪の無い国民だと、如何に無茶な戦争であったか、軍部が力を付けすぎる事の警告も文章にはそれとなくだが確実に織り込まれていたが。
それらは、一旦置いておくのだ。
「貴方達が何を見、何を経験してきたのか、教えて下さい。きっと其処、僕が此処に来なくてはならなかった理由があると思うから。」
若婆さんはハッと勇ましく笑った。
「若宮。私の本名だよ。此の姿で性悪婆さんと呼ばれるのは些と癪だからね。」
「若宮さん。」
「じゃあ早速準備だ。荷物をまとめて分担して持つんだよ。」
仲間がてきぱきと動くのに遅れまいと姫烏頭も布団から出てくるくると丸め、背負えるくらいの大きさに紐で縛った。
「手が空いたらあの子のぶんも手伝ってあげて。」
指示された先には兎を一羽連れた妙齢の女性がお世話用品の荷作り中のところだった。
「手伝います。」
「あゝ有難う。若宮ちゃんはやっぱりすごいわねぇ、もう荷作り終わってるもの。私は要領が悪くって、えゝと、干し草は何處に置いたかしら。」
「此の袋ですか?」
「そうそう、助かるわ坊や。何に入れたら良いかしら、道中も直ぐに食べさせてあげたいから背負うのは止した方が良いわよね。」
「では僕がお持ちします。兎さんを籠に入れて抱えるのに手では持ちにくいでしょう。僕兎にご飯をあげたり部屋の掃除を手伝ったりした経験があるので、役に立ちますよ。」
「まあ本当に有難う。私との思い出、忘れないで憶えていてくれているの嬉しいわ。」
ん?彼女の発言に違和を覚え改めてお顔を見る。うふゝと微笑んだ穏やかな目元の泣きぼくろ…
「兎のお婆さん!?」
「当たりよー!姫ちゃん久し振りねぇ、お葬式以来かしら?まあ大きくなって、すてきな坊やじゃないの、ねえ?」
「い、いや坊やと呼べる齢では…もう二十を超えているのに。」
「私達からしたらまだまだ坊やよ~ねえ若宮ちゃん。」
「坊主の驚いた顔は最高だな。」
グル…だったのか……?
「お二人、仲良かったんですか?てっきり悪いものとばかり。」
「私が彼女の葬式に呼ばれなかったからか?」
「父は、そのように…」
「まあまあ、竹一ちゃんも女の友情には詳しくなかったみたいねぇ。私と若宮ちゃんのことはまた落ち着いたら教えましょうね。先ずは引越し先に行かないと。」
「何處まで?」
「山奥だ。」
若宮が地図を広げて示した印の場所は、菫山と記されていた。
十八
菫山は、元寺の建っている場所でもあり、一番多い時で百名を超える墓の数があったらしいが、時代が忙しなくなって墓参は廃れ、墓は荒れ放題になる一歩手前で何とか老僧が保っていたのだが年寄る波には誰も叶わず跡継ぐ者もいないまゝ美しい枯葉は土に埋もれ嘗ての寂しさすらも樹々に覆われ深山の腹の中に納まった。自然が濃く手付かずの場所を人は畏れ敬遠し、菫山は今ではすっかり魔所として見なされるようになっていた。故に街行く途中、大荷物を抱えて何處へ行くと軍の者に問われ素直に返答すれば、屈強の男児達も無事を祈る数語を掛けて不問とした。尤も、戦争の勝利に沸き立つ中、都ではなく山へ旅する好き者など警戒するにも及ばなかった所為もあろう。
山の麓に人は住まず、獣道すら残らぬ茂み。なれど緑の影濃く咽せ返るからと言って、足元を怠ってはいけない。来る者を拒む大樹の山門を潜り抜け半町ほど歩を進めれば、点、点と白い菫が列をなして案内するように項を見せ始める。次いで水晶の羽持つ姫蛾がふわふわと水に戯れる如く舞を披露目れば、螢袋の花輪に一燈一燈火が宿る。この歓迎のもてなしが為に若宮一行は方位磁石も使わず一里先の一つ家に無事辿り着くことが出来たのである。
「普段山にも登らないような坊ッちゃんの割に。弱音を一度も吐かなかったじゃあないか、つまらない男だね。」
「弱音を吐いたところで休憩なぞさせてはくださらないでしょう貴女なら。」
「まあ、そうさね。」
清らかな汗を玉のように落とす姫烏頭に対し、若宮達は汗粒一つ息切れ一つ浮ばせていない。このように人の踏み入らない場所を歩き慣れてでもいるのだろうか。兎のお婆さん、名前は鈴と言う令嬢でさえにこやかに飼い兎の世話をしている。
「此処は鈴の隠れ家だったんだ。」
「隠れ家とはどういうことです?」
「家出用の家。」
「家出用の家?」
家を出たのに家が用意されているとは、親の過保護の語が浮ぶ。姫烏頭達は家の中に入ると、扉を閉め、鍵を閉めた。
「暫く此処で過ごしたんだ。戦争が続いて続いて、いつか負ける時まで山の中で私達は過ごした。」
「え、終戦迄ずット此処に居たのです?」
敗戦となった戦争の渦中では軍を志願した国民でさえ強制的に徴兵されたのに、女子供は怯えて暮らしていた筈なのに、此処では世間の嵐を受けていなかったのだろうか。
「それに、山は軍の基地と次々になっていったではありませんか。やがて家にも軍人が踏み入って来たのではありませんか。」
「否、誰一人人間は来なかった。」
「な、何故?」
「此処が見捨てられた土地だからさ。先刻も話したろう菫山は人が畏れて踏み込めない場所。其処を無理に開拓すれば死者達の怒りを買うかもしれない、怨念は隊の士気を大きく下げる、軍の中に怯えをもたらす、そして怯えの感情はやがて相手国にも向けられるだろう。そうなればもう兵士達は人を殺すフリをしてわざと銃の狙いを外す、臆病風に襲われた兵士は役立たず、一人でも役立たずが現れてしまえば伝播する、隊全体が機能しなくなる、だから魔所は無理に開拓しなかったのさ。」
姫烏頭は若宮の流れるような言葉に口を噤んだ。国中が勝利に酔いしれているものだとばかり思っていたが、実際はそうではなく、極く少数ではあるがいつか負けることを想定して備え隠れ戦火を避けた人達も確かに居たのだ。
だがその事実は決して記されることも語り継がれることもない。しかし伝えられない小さな事実があることで、過去は再び鼓動を始める。鼓動は水に波紋を生み、湖面は凪を捨てさり震えを取り戻した命の水脈は連綿と命を繋ぎ続ける。雫に込められた過去の搖らぎは生物の体内で命となり生き続ける。
ザアと風が吹く。草木は波打ち虫と花達は名残を惜しむが如く風を身に受けていた。
「到着したばかりなのに、もう別のとこ行かされるのか。」
「あらぁ、もっと坊やとお話したかったけれど、今回は此処迄みたいね。でも大丈夫。きっとまたいつか会えるから、その時はいっぱいお話しましょうね。」
「若宮さん、鈴さん。」
そう言って瞬きをしたら、焼けた街中に倒れていた。
十九
見憶えがある。あの石燈籠、実家近くの神社の物だ、ばらばらになってしまっているけれど間違い無い。
「今度は、俺の実家の在った地域の…夢?」
しかも戦争直後。思わず足元を見るが、地面は土の色で、人間の染みは付いていない。あれは故郷の姿では無かったようだ。一先ず溜息が出ると、今の自分の格好に目が行った。
ひどいぼろの着物だ。青空淡き色は褪せ模様格子は掠れてかろうじて痕跡を留めている、縫い目も所々ほつれて微風をひゅうひゅうと肌に感じる。
「風?」
これまで夢巡りしてきた景色の中で風が最初から吹いていた例は無い。確か夢の世界では風は目覚めの前兆だとか。
「また直ぐに移るのかな。」
それとも覚めようとして覚められないでいるのか、何にせよ此処で過ごす他手立てはるまいと観念する。いつになれば自分も目を覚まさせてもらえるのであろう。
「今度は誰の夢の中なのだろう。若宮の婆さまのように知っている人のものかもしれない。何せ実家の地域の光景だもの。」
ん?
何だか変じゃないか?
「夢の主人は声だけの筈だったよな。なのに、何で先刻は若宮婆さまを見ることが出来たんだ?」
あの夢の主は婆さまじゃなかった?他の人、例えば婆さま達の仲間のものだったとすれば説明は付く。実際若宮・鈴両人以外にも避難者は居たもの。
「何も変じゃないか、当然だもの。」
一人では答えは出ない。それに、霧舟様はまだ自分を起こす心算は無いらしい。取り敢えず風景を歩かないと手掛かりも何も掴めない。終戦直後の眺めを動き回るのは正直心苦しいが。
神社の境内の隅に、手づくりの小さな墓が並んであった。戦時中亡くなった人をそのまゝにしておくのは忍びなくて火葬はしたが骨を埋める場所を探す余裕まで持てなかったのだろう。道端に咲いていた青い菫の花を少し積、名前も知らぬ誰かに供えた。
「知り合いか?」
幼い声に振り向く。頭を剃った少年が手に花を二、三輪抱えている。彼の衣服も大概ぼろぼろだった。しかしその眼光は見た目の年齢に似合わず刺すような容赦無さがある。
「いや、知らない人だよ。若しかして、君の知っている人達だったかな。」
「いや、俺も知らない人達だと思う。俺つい最近なんだ、此の地域にやって来たの。戦争が終わってから引越して来たから。」
少年は持っていた花々を丁寧に盛り土の上に載せると、両手を合わし瞳を閉じて頭を垂れた。姿勢を元に戻して立ち上がり、姫烏頭の目を正面に見る。
「あんたも引越して来た、流れ者?」
「まあ…そういったところかな。」
「ふーん。嘘ついても無駄だぞ、いつかはバレちゃうからな。あんた見た目の格好は流れ者ッぽいけど、その眼、死んでいないし敵意も無い。夢から醒めた奴の瞳じゃあないよ。」
初対面にしては鋭い指摘だ。若しかしたら夢の世界の守り手側の人間かもしれないと半分期待を抱き質問する。
「君は、夢の世界の番人なのかい。」
「番人は番人様がいらっしゃるだろう既に。俺は住民だよ。」
「でも、君はたゞの住民ではないのだろう。」
「何言ってんだ只の住民だよ。此処では番人様以外は皆誰かの夢に住んでいる住民。おまえやっぱり流れ者なんかじゃなかったんだな嘘吐きやがって。」
少年は腹帯に忍ばせていたナイフを利き手で抜き取り構えた。
「待ってくれ、確かに俺は流れ者ではない。俺はまだ死者になってはいない。」
「ほざけ、何故死者でない者が彼岸側の住民と同じ位置にいる。」
「連れて来られたんだ、霧舟様に、番人様に。彼女は俺の父親の妹で、俺の伯母なんだよ。だから、連れて来たんだと思う。」
ナイフを下ろし元の通り鞘に納め帯に隠す。
「噓吐きの眼だったが、先刻の言葉は嘘じゃなさそうだ。目の様子が変ったからな。…何で俺を只の住民じゃないないなんて言ったんだ?」
未だ距離を縮めない相手。警戒心は置かずに持ち続けている。
「その洞察力だよ。その、死者は誰しも洞察力に長けていることは実感している、彼岸側で会った人達は皆そうだったから、死後に開かれる目ッて言うのは生きている頃よりうんと多くを見透かせるようになるんだろう。でも君は、未だ幼い、それに、霧舟様も同じ齢くらいの見た目であられた。だから、只の一住民とはどうにも思えなくッて…」
本当は少しそうであってくれと願望も混じっていたけれど
「……」
少年は大きく息を吐くと地面に胡坐をかき数秒目を閉じまた開けると、姫烏頭を手招き座れと言いたげに指を動かした。
「…当たり?」
座って小声で問うと少年は素直に頷いた。
「正確には番人様の助手だ。お手伝い係ッて訳だよ。番人様からのご指示でおまえを監視してた。」
「監視とは一寸気掛かりだな。何故霧舟様は俺を見張ろうと?」
甥が心配ならば見張りではなく連れの役を用意するのではないだろうか。
「俺にバレてはいけなかった理由があるんだろう、教えておくれ少年。」
「実家を取り壊した理由を追うな。」
隠しても無駄かと観念したか、少年は直ぐ答えた、姫烏頭の胸に痛みを一瞬閃かせる程に。
二十
家主の顔を見られないのは、招かれた側だから。夢の主人を予め知っていなければ家主の姿を視覚で知ることは叶わない。
妙な感覚はしていた。最初は完全にお客さんで、殺戮の景色に絶望し、後悔の町を憐れむ姿は幼い子供のようだった。だからつい可愛くなって可哀相になって姿を見せた。その時の反応も、自分の親や兄との記憶を話した時も、甥として捉えられるような子の其であった筈。番人様、と呼んだのは恐らく住民に合わせたから。
「やはり避難民の説得を終えた後からか。」
(離して)
ひどく疲れ掠れた声ではあったが、確かにあの子はそう言って同時に目を覚ました。恐らく何かの夢を見ていたのだろうが、私には何も見えなかった。夢の番人が故郷に於いて他者の夢を知ることが出来ないなど、初めての経験だった。
「夢ではない…?」
じゃああの子は何を見た。何故あの子が目覚めてから雪が積もって景色が進んだ?
知人の夢に送り込んだ時も最初は違っていた。何故若宮の、あの夢の主人の姿を見ることが出来た?若宮のお蔭で抱いた疑惑を確信に固められたが、今度はその理由が分らない。
「今度の夢で理由を突きとめられれば良いのだけれど。」
今のまゝではあの子の隣に立ってあげられない。傍に居て無理に答えを引き出すことも可能なのだろうけれど、それだけは決してしてはいけないと本能が全身で怯えていた。
二十一
「何故、実家を取り壊したことを知っているんだい?」
「本当に質問ばかりする奴だな。番人様の仰有っていた通りだ。」
少年の言うのも当然だった。現に姫烏頭は少年に名前から好物から死んだ理由に到る迄尋ねていたのだから。少年は、名前だけ教えて後は無視した。倉吉、と言う少年だった。
「おまえ変だと思わないのか?何故そんなに知りたがる?」
「知りたいことを知るのは悪いことなのか?」
「好奇心を非難しているんじゃない。いいか、此処は夢の集う彼岸の国、もっと単純に言ってしまえば境界線でもあるんだぞ。現実世界と死の世界の交差する中に在るあやふやな立ち位置、迷えばどうなってしまうかくらい、想像つくだろう。だから大人しくいた方が良いんだよ、うろうろして取り返しの付かないことになったらどうする。そうならない為にもあれこれ知ろうなんてしないことだ。」
「でも、そうしていたとして、僕は目が覚められるのかな。」
「番人様は鬼ではない。おまえが為す術も無くじっとしていれば返してくれるさ。おまえが迷子にでもなったら大変だ。」
「………」
諦めたか?
「倉吉君は、俺の住んでいた地域に疎開して来たの?」
黙っていれば生娘も恥じらい逃げてゆく見目の癖に中身は頑固爺並みである。一直線に此方を見つめるのも気に食わない。番人様と彼の父親は兄妹だから黒に菫咲くおっとりした瞳を持っているが、此奴の目は花が息づくなんて類のものではない、母親似かとも予測したが、彼岸から見た限り母親も夫と似て穏やかな光の持ち主だったから推測は打ち消した。そもそも外見で身内か否かを判断しても良いのだろうか?倉吉が次の言葉をあれこれ考えていると、姫烏頭の眦がすうと三日月に伏せられた。
「知りたいことを知らないまゝ死ぬ後悔と、知りたくなかったことを知る後悔、どちらの方が苦しかった?」
少年の顔色が即座に変る。浅黒く日焼けした活発そうな肌は生臙脂の怒り、恐れ、惑いが忽ちに影濃く差し、幼い唇を小さな白歯でぎりゝと噛むが、一筋零れたのは体温滴る血ではなく背中を逃げた冷汗で。
「何で知っている。」
「あゝ、やっぱり当たりだった。」
立場は逆転し、今度は倉吉が質問を投げ掛ける側になる。
倉吉は戦時中に生れた子供であった。夜鷹と客の間に出来た子で彼は父親の名は知らなかったが母の優しさと温もりは澤山知っていたので、特段不自由とは感じなかったし、あの時代は倉吉みたいな出自を持つ子供はごまんと溢れていた。
「お父さんは、今戦争に行ってらっしゃるのよ。」
母は幼い我が子の手を取り撫でて言うのが癖だった。父の面影を残す自分を見ると寂しさが胸に湧き上がる所為であろうと子供心に母を不憫に想い母と父が逢引した場所を母の話から割り出した。其処が将来姫烏頭達の住む地域となった場所だったのである。父は此の辺りに住んでいた一般人男性だったのであろう。今回の出兵には国民総出で向かっているから、一般男性でも要項を満たせば赤紙が来る。
「お父さんとは望んだ初対面にならないかもしれないけれど、倉吉はそれでも良いのかい?」
気遣う母。戦争に行った以上死は完全に絶ち切られない、日常生活よりも死の影が濃くなる場所に行ったんだ。
「お父さんの戦士報告書が届いたって、覚悟は出来ている。」
爆弾を落とされただけあって更地に近い焼野原には崩れた建物や壊れた建物の瓦礫の量がひどかった。
「戦争は後始末がとても面倒なんだな。片付けの手伝いに来ないくらいなら戦争なんざ起こすなよ軍人ども。」
思わず朝刊に載っているA級戦犯とされた軍人達の写真の列に唾を吐く。
「母さん新聞。此処に広げとくから見たかったら見てよね。」
作業の休憩は終り。また瓦礫を運びに行こうと小屋を出たら、
「倉吉!お父さんが映っているわ!」
その時の母の顔を、煌めく情熱を、今でも忘れられない。彼女の震えて指さす先にはA級戦犯者達、戦時中の軍の上層部にいた者達の内一人であった。
(母さんは使い捨ての商品としてしか見てもらえなかったんだ。)
その日から倉吉は母の傍を離れなかった。
「とんだ偽善だな。」
姫烏頭の声で夢から目が醒める。いつの間に、夢を見ていた?俺は姫烏頭と睨めあっていた筈だ。
「強制的に夢を見せたんじゃない。君の夢を見させてもらったんだ。」
さらりと言ってのけるが此奴が今俺にしたのはとんでもないことだ。
「番人様でもないのにそんなこと出来る筈が無い。たゞの生者がしていい技じゃない。」
否、番人様でも夢の主を特定するなんて真似は…
「出来ないよ。番人には其処迄権限が無いからね。でも俺には出来るんだ。」
微笑み、笑う。楽しそうに、乙女のように頬を染めて。
「ひ、姫烏頭…じゃないのか?」
「姫烏頭だよ。でもそれだけじゃないってこと。」
「何がおまえに含まれている?」
「…お母さん、病気になっちゃったんだってねえ。」
探るな、と声にした言葉は別のものと置き換っていた。
「母さん、今日は雛芥子が咲いていたよ。」
立派な墓など建ててあげられなかった。第一世間の物資に其処迄の余裕が無い。此の辺りも空爆の被害を受けた。焼死と圧死、両方の遺体は日毎に馬鹿みたいに数が増え続けていく、道端に急拵えのせめてもの墓が増えていく、母さんも小さく土を盛った列の一部となった、最期迄胸に抱き続けた新聞と共に。
「母さん、そっちで軍人さんとは会えたかい?」
人々の不安が雲と化し、ようやく大粒の雨を流し始める。自分の周りは誰かの死を悼む人達だらけ。
「俺は父親が誰でも良いよ。母さんの子供だもの。」
毎日夫の帰りを恍惚と待ちわびる母の姿は英雄に焦がるゝ非力な乙女のようであり、終ぞその言葉を掛けることは出来なかった、自分が父親に期待していない事実を。
「言えていたら、病気にならなかった?もっと生き続けていられた?」
儚さを取り払えられた?
「それとも後を追っていた?軍人さんが絞首刑になった翌日に。」
この方は立派なお人だからきっと情けを掛けていただいたわ、この記事は形式的なものなのよ。そんな事、真剣に言っていたのだもの、俺は否定出来なくって、あんまり瞳がいぢらしいほど澄んでいたから、肯いてしまったけれど、上手に笑えていたか自信無いや。
「母さんごめんよ、俺、嘘つきな息子だよ。母さんは毎日父親似の立派な良い子だって褒めてくれたけどそんなこと無いよ。正直になる勇気が無かったんだ。」
配給食は全て俺に回して、自分は平気だって言って食べなかった。
「もう覚悟を決めていたの?」
強く断りきれず与えられる通りにしていた。
「死にたかったの?」
分かっていたの?事実を全て。俺が嘘ついて話を合わせていることもばれていた?
「君はどうすれば良かったのだろうなあ。」
その場に倒れ込んでしまった倉吉少年を見下ろして呟く。夢とは何もかも明らかにさせたがるものなのか。
「次は何處に行こうかな。」
空はだんだん夜に近付く。
二十二
倉吉の意識が途切れる音が頭で鳴り、急いで彼のもとへと移動する。霧舟は夢の壊れる姿を目の当りにした。
色は本来塗られていた用途を忘れて黒が赤に、白が黄色に、青は赤に土は紫と混乱を生じ、此処が小さな町の一隅であったことなど見た者が予測出来る道理は捨てられている。物の形も所々歪み神社の燈籠の土台は小川の下流の石粒の如く丸くなり境内の砂利は三角形の棘を持ち手水零れる水滴は四角形に成り損なったひしゃげた輪郭となっていた。
見た者を黙らせる眺めの真ん中に、倉吉がぱたりと横たわっている。
「倉吉!」
駈け寄り脈を確かめると、鼓動は確かに反応があり額には苦しい汗が大粒で浮んでいる。二、三度頬を軽く叩くと涙の膜濃い少年の瞳がぼんやり霧舟の顔を見た。
「番人様…」
震える声で謝罪しようとする倉吉を制止する。まさかこうもされるなどあの時点では誰も分らなかった。死者達の神経を以てしても分らなかったからこそ様子見に徹したのだもの。
「ごめんなさい。私が居ながら貴方に全く任せるようにしていたから…あの子は貴方には荷が重過ぎたのね。」
「申し訳…ありません…」
「謝らなくて良い。貴方の所為じゃないのだから、どうか負い目と感じないで。」
この調子では他の夢も壊されているかもしれない。まだ意識の途切れる音は倉吉のぶんだけしかないけれど、それも時間の問題、一先ず住民を避難させなくてはならない。
私が案内した場所は何處も危険かもしれない。
指でトネリコの大樹を模した幾何学模様を地面に施し、ふッと息を吹き掛けると、玻璃の湖面が空へと化した桔梗の泉の場所へと繋がる穴がぽこりと開いた。霧舟は丸い扉に倉吉を抱え入り込む。泉に倉吉の背を浸し浮べた状態にすると、彼の意識は少しずつ癒えて、数分の内に再び立ち上がれるくらいにまで回復した。
「倉吉、説明を。」
住民が見守る中、少年の声がはっきりと響く。
「今頃対策でもしているのかね。住民はすっかり移動させられちまったようだ。」
気に食わない。だが同時に面白いと感じる、曝したいと感じる。もっと知り尽くしてしまいたいと楽しくなってくる。
「存外簡単に案内してくれたよな、やっぱり親族と言うのは信頼せざるを得ないのかな。」
自分の声が響きすぎて混乱したのが十年以上前のように懐かしい。そうかもしれないと考えてはいたがやはり休憩所に霧舟の姿は無かった。
「俺を連れて回った場所は避けたか。」
これまでは霧舟が次の行先を指定していただけあって、自分に彼岸側を自在に移動する力は与えられていなかった。住民は自由に行き来することを許されているのだろうか、まだ”お客さん”にはそこまでの権限を付与してはもらえないようだ。
「お客と住民では扱いが違う、か。それなら区別している存在が居る筈。霧舟はあくまでも番人であって、彼岸側の主ではないようだ。主が居るのかな?其が此の世界を構築して、運営している?でも唯一神のような類ではないだろうま。此処は一つの絶対とその他大勢で成り立っている空間じゃあなさそうだった。」
思い出すのは、祈りの町。
「それぞれにそれぞれの神が宿る…八百万、の概念の方に近しいのかもな。」
なあんだそれなら得意分野、古巣じゃあないか。
「居心地の良さは懐かしさの所為か。」
大きく息を吐いて吸って、水面の下に身体を沈める。
古代、否もっと昔、神代の頃から悪しき存在と見なされていた性分ではあった。神々の内一柱を死なすに至った存在、他者を苦しめ貶めることに喜びを抱くとされた存在。それゆえ昔話や物語では常に嫌な奴と設定されてしまった。
「天邪鬼なんて、品の無い呼び名。」
天探女。元々はちゃんとした名前があったのに、後世では洒落の無い名前にされてしまった。神殺しのきっかけを作った悪しきもの、否定は出来ないが事実は随分とひん曲げられて捉えられているのが愉快なようで腹立たしい。
「名前の通り、使命を果たしただけなのに。」
殺された神には反逆の意思があった。それを文字通り白日に晒しただけである。謀反の隙が無ければ返し矢で死ぬことも無かっただろうに。だが世は神ではなく精霊を標的にした。例え反逆を企てていたとしても神は神であることは失われない、悪く描くのは躊躇われるのは生命ならば当然だ。それよりかはポッと出のよく分らないキャラクターの方が好きに扱い易い。神々でもなく人間でもなく動植物の形を持たない生命の宿命と言ったところであろうか。
霧舟は俺をどうするのだろう。此の世界では探る行為は近畿に等しいことかもしれぬ。探ることが息をすることの自分を、素直に追放させる心算か?だが素直に受け容れる性分でもないのは自負している、現に住民達への抵抗の術は先刻倉吉君の例で成功したじゃあないか。霧舟が相手でも同じ事をするだけさ。
「きっと私が相手でも、彼は倉吉の時と同様探ってくるに違いない。」
世界樹の麓に集う住民達は霧舟の言葉にどよめきを止めた。口を噤んだ群集は自分達の足元を見つめる習慣があるらしい。誰も、何も言えなくなった。あの破壊者は我々の世界を壊しに来たのだ、そして探られる事に抵抗する手段は無い。生者の夢の中でしか生きられない者と、自分の夢の中で生きる者、両方同じ苦しみを味わうのであろうか、それともどちらかはより苦しむのだろうか…恐怖は予測を冗長させ、まだ起きていない筈の出来事への恐怖を新たに産む、良くない鎖が住民達を等しく雁字搦めにしていた。
言葉を失った群集に霧舟は黙っていた。今、状況を動かす為の一手を頭の中で練りに練ってもう最終段階にまでシミュレーションしているから、黙っていたのである。そして、沈黙は破られた。
「彼のしたいようにさせてみよう。」
流石の倉吉も絶句した。番人様が諦めると仰有るなんて。国民も皆同じである。絶望の雫が心に染みを成し最後の一縷を水の重さで千切ろうとしていた。
「きっと今、我々の住む世界は変ろうとしているのだと思う。現に倉吉、君はどうだった?夢を探られてあばかれて、どう感じている?」
「ええと……番人様に泉に浸していただく迄は、心臓を抉り出すような痛みと苦しみがありました、息をしても肺から抜けていくようで空気を溜める感覚も失われて……けれど、今は、正気に戻って振り返ると、あゝ、でも、良かったなと、良かったのかも、しれないと…思い始めています。」
どよめきは想定内。倉吉はボロの着物の裾をくしゃりと握り言葉を続けた。
「夢は、綺麗なものじゃないんだ。一つの夢の中にも目を背けたいことや見てはいけないことだって在ったんだ。なのに俺は母さんが病気になるまでの、引越前後の夢しか描かなかった。逸らしていたんだ、自分が苦しんで悩んで泣いた過去を見ないフリして、綺麗な所だけをずっと繰り返し夢見ていたんだ。でもそれは…俺の本当の夢じゃない、俺自身が切り捨ててしまったら誰にも光を当てられることの無い夢の欠片達は…ずっと寂しいままじゃないか。その最後の呼び声が、俺のこのボロの着物になっているんだと思う。ずっと幸せな夢を見ているのなら、もっと綺麗な着物の姿で表される筈だろう。」
綺麗どころだけに光が当てられている世界。その指摘は国民全員に言えるものだ。苦しんだ過去や悲しい過去は描かないことで、楽園としていた。死後の世界は楽園なのだと現実世界に色を塗っていた。その色を信じて命を絶った者達も多く居た。そして増々彼岸側はステキな過去で埋め尽くされ、美しい場所へと進み続けてしまったのだ。
誰の所為でも無い。命が光に顔を向けるのは自然の摂理であり、抗える代物ではないのだから。
「死んでも自分と向き合い続けなきゃいけない。それこそ彼岸が此岸に示す色よ。楽園の本当の意味を、今構築しないといけない。だから、」
「番人様のご提案に賛成。」
一条の線は次第次第に波紋を描き水面を搖らし広がって行く。凪はすっかり取り払われて、世界樹の麓は柔らかなせゝらぎが幾つも幾つも生まれていく。
他者を探るのも大切だが、自身を探れているであろうか。
「いや、結構探ってきた心算だけどな。」
神主の子として生れた子として扱われるあの疼痛。
「それだけかな?」
だって家族の記憶で探りたい歪みなんざ無い。平々凡々、絵に描いた温和平和の家だった。
「ん?」
(女の友情は竹一君には分らなかったみたいねぇ。)
「父さん、若宮さん達の関係、勘違いしていたよな。」
でも父さんの言葉を僕は信じきっていた。いつでも父や母が正しく、従順に応じてきた。
「いやいや、それで良かったんじゃないか、だから何も問題無く家族で在り続けられたんだろう?」
言い訳する背中は、静かに迫る霧舟に気付かない。次の弁明を呟く前に、姫烏頭は霧舟に背中を押され、同時にぽっかり開いた丸い穴に落ちて行った。
二十三
恨んでなどいないと確かにそう言ったのだ。夢の世界の番人は女しか歓迎されないから一人娘を選んだ事実を。恨みも怒りも悲しみもまだ芽生え始める少し前の頃だから、送られた直後特に何も湧き上がらなかった、あゝ送ったのだな、と微かに思っただけだった。兄の一筋の涙を見て心はつきりと痛んだものゝ、でももう顔を拭うこと出来ないんだものな、と感じるくらいで、淡々と死を受け容れていた。彼岸側に送られたのならもう逆流は出来ない、あがいても叫んでも泣いても喚いても意味が無い。意味の無い行為で暇を潰すより、やるべき事にいそしんで時間を過ごそう。番人として彼岸側を管理しながらも此岸の兄達を見守っていた。
(兄さんが私を忘れなかったから、私は兄さんとその家族を見守ることが出来た。)
姫烏頭にはそう言ったけれど、兄さんの他にも私を生涯忘れなかった人達が居た。
父さんと母さんは、私が冷たくなったのを確認すると、躯に覆い被さり声をなりたけ抑えて泣いていた。大声で泣きそうなものなのに。だって風邪で死んだのをよりアピール出来るじゃない、慟哭した方が。如何して人が集まらないようにしているの?
分らなかった。てっきり喜ぶものとばかり思っていたのに。演技するならオーバーにした方が伝わりやすいのに、と首を傾げた瞬間、死にゆく蛾の声より細くほどけそうな声で、
「霧舟、可愛い私達の娘……」
その言葉はその夜、兄さんが眠った後二人が眠る前に内緒に内緒にまた呟かれた。日中の狂った祝詞や歪な祈りの言葉とは裏腹な、虫の息よりも弱々しい調子で。
終戦を迎えて神社は生き残った人間の手により壊されてしまった。更地にされた実家を一番に見たのは両親だった。兄さんは三人が居た避難所で配給食を三人分貰う為の列に並んでいたから。古い神社を壊してしまえと壊れた者達の狼藉の痕を二人は暫く黙って見つめていたが、やがて御神木の方へと歩き出した。
「夢の世界は、本当に在ったのかしら。」
え?
「若し無かったら、あの子、一人で泣いていないかしら。」
母さんが神木の幹に縋りついてさめざめと泣いている。
「あの子は神職の親を持つ娘、そんな子が敗戦直後の世界で生きることが蒸す香椎。戦前以前から信仰されていた神々は悉く貶され、以前から貶されていた神職はより一層凌辱されるだろう。竹一は神主の養成学校に入れるが、霧舟は女の子だから入ることは許されない。此の国は敗戦し、霧舟は暴力の格好の餌となる社会になると踏んでいたが、まさか実際その通りになるとはな。…死なせて正解だったんだよ。」
父さんは血を吐き乍ら母さんを諭していた。目を零れる涙は一滴も無いのに、口から赤い雫を途切れさすこと無く流していた。
「それでも子供を殺したんだ、きっと霧舟とは同じ場所には行けないが、」
「えゝ、でもあの子が彼岸側で生きていてくれていたら、」
「楽しく笑えているのなら――」
二人は同時に喉を突いて、御神木に血が行かないように数歩ヨロヨロと離れた後、力尽きた。最期の二人の一言は、どちらも兄さんと私の名前であった。
恨みは無い、殺されたことを責め立てる激情は無い。でも、でも、伝えたかった、二人の頬を平手で打って、
「父さんと母さんは馬鹿よ」
そう泣きながら、抱きつきたかった。
背中を押されて理解した。霧舟はもうとっくに自分で探れていたのだと。何度か隙を窺ったが入り込む余地が無かったのはその為か。
「何處に連れて行かれる?」
点と遠かった光の輪がみるみる大きく近くなっていき、地面に放り出される。どうやら到着したようだ。
「知らない土地だな。」
家族で出掛けた記憶も無い場所。電信柱が風車のように立ち並び、淡い空には月白の花欠零れる冷たい虚空、なんの花であったのだろうと目で追いゆけば遠くに一つの小屋が見えた。小屋はぐるりと石の柱で囲われて、どうやら茨が小屋の壁から屋根までぴしりと守護しているようである。他に建物も生物もいない、黄昏が終りかけの場所で姫烏頭は佇む。
「円形に配置された石柱と茨か…極めて神聖なシンボルが同時に揃ってやがる、あの小屋は禁足地であるに違いない。下手してもしなくても、連れて行かれっぱなしになる危ない場所だ。」
確か、ケルトの妖精の伝説、言い伝え。故郷古来のものでもない話の筈なのに、何故倒産は教えてくれたのだろう。
(異国の文化は必ず何處かで思い掛けなく繋がっているものさ。)
「あゝそうだった。そう言えば父さんは古代文明にも詳しかったものね。」
父である竹一は息子に妖精文化の残る地域に伝わっている物語をも教えていた。姫烏頭の住む国とは思想が似ていないのではないかと彼が父に問うた時、父は右の通り息子に説いたのだった。
「無理に繋げようとしていただけだろう?まあ面白い内容だったから必死で聴いていたけれど。」
呟き、呟き、小屋と一定の距離を保つ。警戒を緩めてはいけない状況なのに頭の中は思い出が五月蝿い。
(妖精は、昔の神々が零落した姿だと考える人も居るんだよ。)
(昔の神様?神様にも古いとか新しいとかってあるの?)
(父さん達の住む国ではあまり聞かない話だけれどね。でも信仰とは時代によって大きく動くから、若しかしたら神様の中にも古い新しいがあったのかもしれないね。)
(妖精達の話と、此の国の神様達がどう繋がるの?)
(此の国の神代の物語にもね、神様でも人間でもない存在が登場するんだよ。お使いの鳥や虫、他の獣もいるけれどね、精霊のような者もいる。)
(精霊?)
(精霊達は妖精と似ているんだ。一番有名なのは、天探女…)
「うッ!」
身体が一、二歩勝手に小屋へと近付いた。まるで誰かに首に巻いた紐を引ッ張られているかのように両足は前に前に進み出す。茨がどんどん近くなる。
「止まれ!」
身体の意志は止まらない。歩いていては物足りなくなったかしてなんと駈け出した。耳を切る風の音が冷汗を更に冷やしていく。抗いきれない現実に姫烏頭は恐怖を感じた。歩むレールを定められ歩かされ変える術の無いことに怯えた。
「離して。」
茨の扉を押した時の声は扉の閉まった音に覆われた。
入ってしまった、入ってしまった、焦りと恐怖で目が四方八方を観察する。小屋の中は暖色のランプが木の天井から吊り下げられ、その下には丸い木造のテーブルが置かれている。その上に何やら手紙が一通置かれていて、姫烏頭は思わず白い便箋を手に取った。
”姫烏頭君、君は期待通り育ってくれた。遠く昔虐げられた我々の希望の星として見事育ってくれた。これからはもう人間の世界で動いてもらわずとも我々の世界で暮らすと良い。現実世界への干渉を我等の世界に居ながらできるほどの力を君はもう備えているのだから、戻る必要は無いよ。”
「現実の世界に…戻らなくても良い?」
コーヒーの匂い
手紙はまだ続いていた。
”此の自宅は今日から君の家となる場所だ。此処から現実世界に力を以て干渉しなさい。夢を見る人達の中に入り込み、古来の神々に関する認識を改めさせるのだ。今の信仰対象は元より神だった者と人間を神とした者に大別される。戦争で信仰はぐちゃぐちゃにされてしまった。ゆえに戦争が起るずっと以前の信仰の在り方に戻すのだ。君の父君が信仰し仕えてくれていた我々への信仰だけを再び日の目に映し出す役割は、天探女の器を与えた君にしか託せられない。”
「これは、大神様達からの文…?」
自身の仕える存在からの手紙を読んだ姫烏頭の横がほは、いたずらッぽく微笑湛える天探女の其になっていた。強い言霊は書き言葉であっても人の性を変え得る。姫烏頭青年の心はすっかり天探女の心に覆われ、コーヒーの匂いを勿忘草の花びらに溶かした。
「此処に居たら、霧舟も追って来られないのかな?でも此処に突落したのは彼女だもの、若しかしたら此の場所自体罠かもしれない。」
「その通りだ。」
また、後ろから声がする。
「いつも背後をとるのね。」
「君と二人ッきりで話をする為にはこうするのが一番早かったから、君を此の空間に落下させた。」
「話をしに来たのなら、お互いに向かい合って座りましょうか。丁度テーブルがあるし、あら、気付かなかった、椅子も二人分あるじゃない。ほら、座って座って。」
雪の野原で別れて以降、それほどまで時間は経っていないが、目の前でにこやかに笑む花の顔は最早其の性質を大きく変えている。あの子の微笑みだが、あの子の微笑みじゃない。姫烏頭なのに、まるで別人、否、別のもの…
「伯母様怖がらないで。俺は俺。でも今は姫烏頭より天探女としての俺が強く表に出ているだけ。俺が乗っ取られている訳じゃないからさ。」
「天探女…そのものが君の中に居ると?」
相手はうんと言って頷いた。
「俺が生れた時、は姫烏頭としての姫烏頭しか居なかったよ。天探女の要素が入って来たのは小学生になる前だった。あの日は家の近くの神社に、茅の輪を潜りに行った。御参りしていると、何だか水の音がやけに響いてきた。でも父さんと母さんは分らないみたいで、俺が此方って案内したら、神社の裏手にある知さな瀧だった。数百年前に水枯れしてもう流れないだろうとされていた瀧が、さらさらと雫を流すのを見て二人は大層驚いていた。その間に俺は岩を飛び飛び、導かれるように軽やかに水に触れた。」
「其の時か。」
普段のお行儀の良さが嘘のように時々他人を害しかねない言動をする。それも、いたずら好きの男の子のようなものではなく大人が人の古傷を抉って満足するような、齢に似合わぬ恐ろしさ。
「それで、兄さんは如何したの。」
「伯母様はずっと俺達を見ていたのではないの?」
「丁度其頃から途中途中霧が掛かるようになった。正面に見られるようになったのは兄さんと義姉さんが亡くなってから。それまでは姿を追うことも叶わなかった。」
「じゃあ、あの時から天探女時からは貴女を拒んでいたんだ。」
霧舟は今更乍ら凍とした。自分は夢の番人を任されている身とは言え、所詮雇われの人の身、人間である。しかし今甥の身体を借りてにこにことたをやかに組んだ両手に細い顎をソッと乗せて可憐に気高く座るのは神々に並ぶ存在、精霊である。
(場所によれば天探女は神として祀られることもある。)
純粋な人ならざる者、人を越える力を易々と当然の如く有する者、それが、どうやって、この子の内側に。
「父さんは神主の組織とあまり仲良くしていなかったから、自分で調べたよ。そして分かった。息子の中に何が在るのかを。それからが一寸可笑しくてね、父さんは天探女とケルトの妖精を同じ存在として結び付けたんだ。」
「ケルト…義姉さんの影響もあったのかしら。」
「母さんは紅茶好きだったからね、英国文化を知る内に大昔のヨーロッパ文明も知ったらしい。普段母さんと世界の古代文明について父さんは談笑し合うくらいだから、相応の知識はあったのだろうと思う。それで、ある研究者のとある言葉を用いたのさ。…妖精は前時代の神々の落ちぶれた姿である、とね。」
滑稽だ。天探女は良い事悪い事を与える妖精とは大いに違う。
「彼女は人の大事にしまっている傷を探るのが楽しみなだけさ、肚の内を明かすのが好きなだけ、そう振舞い在る事が天探女の使命なんだから。」
だから大神様達を再び信仰される国に立て直す為に、選ばれたもの。適任だって、君に任せてみようって。
頬を染める彼の表情が何を物語っているか、其の方面に疎い霧舟でも暗く輝く眦の影を一目見れば察し得た。何てうつくしい表情で焦がれるのだろう。
天探女は、神々に深く恋をしているのだ。
二十四
地を照らす御姿は美しかった。生命の眠りに寄添う御姿も美しかった。武を司る御姿も、知を司る御姿も、森羅万象一つ一つをそれぞれに司る御姿はどれもこれも美しかった。
最初は湖の中に居たと思う。ちらちら雪の粉が結晶になる前の姿で水の仲を波に搖れてあっちへこっちへ大勢静かに移動していた。穏やかな波だと思って、自分の此の波の世話になり運ばれてゆくのだろうかと考えた。するとみるみる上へ引ッ張られて水面下から出て来た、と感じた時にはもう肉体は完成していて、顔があり身体があり頭髪もあり器官も備わっていた。素裸でおろおろしていれば、幾種類もの花が細かく頭から爪先まで降り掛けられた。花の水流を浴びたら衣服が皮膚を覆っており、服を着た身に今度は王冠をか細く解いて糸に紡ぎ直したかのような無垢でひんやりとした銀糸を緩く二巻きされると、自分が何を背負う存在なのかを悟り、正座して、あらゆる神々に礼を施した。顔を上げた後に見た清く苛烈に輝く御姿は、涙を零すほどに美しかった。此の方々の為に在れたのならば、何手恵まれた幸せだろうと心が震えた。
心を探り、神々へ仇成す存在を浮き彫りにした。だが働いた結果死んだのもまた神であったから、人の世に降りるようにと下界へ送られた。神々よ、追放、と呼ぶには優しすぎます、だって神社の裏手にある瀧に送られるなんて、私にとっては神々の傍に侍ることと同じこと。天地も雲も風も木々も、言葉や挨拶の愛撫を常に恵んでくださったから私は人間の世界でも貴女様方に守っていただけたのです。
水枯れしたのも、その為。教えられた伝言は、「神々は古い遺物とされ、人間が神となる時代が来る。一時の気の迷い、傷心から生れた幼い駄々のようなものだから、長くは続かない。それまで身を潜めておきなさい、瀧を止めてもう枯れたと思わせるのです。」
大神様方も心配だったけれど、私は追放されて此処に在るからお許し無しには動かれない。どうか御無事でと涙に祈り、私は目をつむった。
「ちょうど神々への迫害が止まって、世間が勝機を取り戻した時、天探女の目は開いた。其は同時に瀧の水が再び流れ始める時でもあった。俺は天探女の瀧に指を触れた時、彼女と言葉を交わしたんだ。あの娘、悲しみ乍ら怒っていた。」
姫烏頭は机ととんとん指で軽く叩くと紅茶セットが丁度二人分花咲いた。
「姫烏頭、君…術が使えたのか?」
「いえ、天探女が起きないと使えません。ただの姫烏頭として在る時は何も使えやしませんよ。」
「兄さんや義姉さんの前では使わなかったの?」
「天探女が起きたのは、迷子退治に行って騒動を収めた直後みたいです。なので、つい先刻迄俺は本当にただの姫烏頭だったのです。彼女、ずっと眠ってたんですよ。植物は咲く時にならないと目を覚まさない、それと似たようなものです。
おや。
「君の話の通りなら…天探女は瀧を通じて君の精神に居候し、暫く眠っていた、そして先程目を覚まして影響し始めた…となるわけか。彼女が眠っていた理由は?」
甥は口を暫くムグムグと噤んでいたが、苦笑してこう言った。
「多分…湖での、あの出来事…かな?」
家族で湖に行った時、両親と三人で水面を眺めて綺麗だと言った。けれど、綺麗な穏やかなのは苦しんでいる声を上げられないから、我慢しているからではないかと思い、息子は近くにあった小石を拾って湖面に投げようとしたが、父に腕を握られた。振りほどこくと文句を言おうと顔を彼の方に向けると、何も言えなくなった。
(姫烏頭、小石を投げてはいけないよ。)
瞳に艶も光もあるけれど、黒い菫は涙に震えているように見えた。一見息子の悪戯を注意する優しい穏やかな父親の表情。微笑みの柔らかさも普段通りで涙など一滴も零していない程遠い顔なのに。
(ごめんよ、父さん。ごめんなさい。)
息子がそう素直に言ったので、私はまた目をつむることにした。
あの父親は、私が息子の中に居ることを分っているのだ。普通の人なら悪霊憑きとか騒ぐのでしょう、大人しかった子供が急にとんでもないいたずらをしれッとするようにいなったら。或いは自分達の教育が悪かったと自分を責めるか。でも父親は双方にも属さない。流石は神主と言ったところかな。人間の世界では私の在り方は意味を成さない、意味を成さない場所で起きている必要も無い。それまでただの姫烏頭として生きてあげたら良い。そしたら父親も母親も息子も悲しまなくて良いでしょう。
二十五
「父さんがとても悲しそうに見えて、直ぐ心から謝った。その時から天探女の側面は出てこなくなって、あんなに初対面の時は怒って泣いてたのにあっさり黙っちゃったと思って。」
紅茶を淹れ始めた姫烏頭。ミルクティーにでもする予定なのかセイロンエクストラの茶葉を硝子のポットのお湯の中で踊らせている。クリオネを初めて見る少年の頬のように楽しそうなのは、初めて術を使った高揚感の為であろうか。
本当に、たゞの男の子に
「天探女と、初めて逢った時何を話したの?言葉を交わしたって言っていたよわよね。」
しゅんと睫毛が伏せがちとなる。
「泣いてたんだ。悔しい、許せないって。戦前も戦時中も神々を敬っていたのに、戦争に敗けそうだと感じたら掌を返して唾を吐いて、結局敗けたら神々の所為だと憎み罵り自分達に都合の良い存在を神として褒めそやす。馬鹿馬鹿しいッたらない。人の業は神々の力に因るものではない。何もかもを神々の所為だと押し付けて挙句の果てに神などいないと宣って、自らの悪行を顧みもしないなんて。あの御方達が戦時中どれほど心を痛め悲しんでいたのか想像もしないで偉そうに。神々は争いを止めなかったと嘆く輩も大勢いたさ、悪者め、干渉出来る訳が無い、人間が勝手に始めた事態に神々は関わることが出来ないのだと如何して如何して分らない!…そう泣いてたんだ。だから水を両手で掬んだ。」
其時の様子を思い返したのか、青年は両腕を前に差し出して指をお椀形にそッと丸めた。霧舟の瞼の裏には今にも細い清流が白砂滴る如く迷い無しに注がれている姿ありありと浮び、互いの意の堅さを察し得た。今の世では過ぎた事と言い表せるけれど、当時一瞬の内に深く深く切り付けられた神々の痛みは人が想像するに余り有る、同情などと軽い言葉では済まないけれど、霧舟も天探女の言い分には頷かざるを得なかった。そして乙女の悲痛且つやりきれぬ胸の内を、物心付く以前の直感に従い受けとめ抱えた甥にも、一人で負わせた申し訳無さと不甲斐無さが込み上げる。差し出した手は興味本位からであったとしても繋ぐ指先は断じて遊びの延長戦でなかったと、先迄彼を被害者扱いしていた自分を恥と思う。
それでも、己は彼岸と此岸の間を守る番人である。
「君達を此の家に入れたのには理由がある。此の世界を、正しい在り方に変える為の手助けをしてほしい。」
姫烏頭は笑った。笑い乍らポットに宙からミルクを注いで、霧舟の真剣な眼差しをお菓子に、砂糖の含まれないミルクティーをにこにこと飲み始めた。
「断るよ、悪いとは思わないけれど。」
ハミングの節でくすくす笑う。
「雪野原を憶えている伯母様?如何して一番最初の土地に雪が降ったか分りますか?」
「過去の心臓が再び動いたから。君が此の世界の崩壊を防いでくれた御蔭で、また夢達を呼吸を始めたから…」
「ふゝ、違うよ伯母様。貴女は僕にそう言いましたけれど、違うのです。確かに僕は夢の世界の住民達に思いの丈を叫びました。そして住民の皆さんは此方に留まる決心をしてくれました、それは僕の声が住民に届いたから。でもね伯母様、俺の心は何も住民だけに聞えた訳ではないのですよ。」
「他に、誰に届いたと……まさか。」
「えゝ、そう、先程からお話していたでしょう?神々のお話を。神々はだからこそ天探女を起こしたのです。伯母様には見えていなかったかもしれませんね、彼女が起きた時の光景を…僕、離してッて寝言で言いませんでしたか?」
あの言葉は
「天探女が起きた光景は現在のものだから夢にはなりませんでした。僕も此処に来てようやくあの景色の意味が分ったのです。そして、あの雪が、僕達に向けて神々がしたためてくださった文であることもね。」
神々は仰有っていましたもの、夢の中に入り込んで人間達の考えを改めさせないと。それって、夢を正しく在らせることとは真反対の行為でしょう?
二十六
甥の中のケルトの妖精譚の記憶を元に家を用意したのは霧舟である。しかし其の中に手紙を送ったのが大神様と姫烏頭と天探女が畏れ敬愛する古来の神々であった。神々は霧舟の意図を知り、即座に姫烏頭達の有利となるよう形勢を整えたのである。此処が人間の世界であれば上手くいかなったであろう、此の空間、夢の世界が神々と繋がりの強い彼岸側に片脚置いている境目の場所だからこそ神々の力は強まっているのである。
「あの雪が、手紙?」
「そう。」
「夢の国を滅茶苦茶にしろと指示書きでもされていたの。」
「そんな無粋な真似なさらないわ。恋文のように澄み冴えて思いきりの良い、すてきな文。水底の真珠を連ねた言葉。口先で人をたぶらかす悪い奴とは雲泥の差、真心と真心は玉響の楽を奏でるもの。…伯母様には難しいかしら。」
敵意と敵意が首を擡げて睨み合う。
「人の世界は人が動かし考えていけば良い。神と呼ばれる存在が移り変ろうと放っておくべきなのではないの。」
「愛する者に触れられない寂しさと苦しさを御存知無い訳ないでしょう?」
「姫烏頭の姿を私に碌に見せなかったくせに何を言うか。」
「だって知ったら貴女、天探女を取り払おうとしたでしょう?僕を取り憑かれた被害者だってそう考えて。僕が説明したところで聴き入れて下さるのかしら?今の様子を見る限りそうは思えないけれど。」
「被害者であろうとなかろうと天探女は引き剝す。姫烏頭、君は人の世界で生きなきゃいけない。」
「大神様は此処で暮らせば良いと仰有るわ。」
「ずっと境界線に居てはいけない!生きた人間が佇み続けて良い場所じゃないのよ。」
「じゃあ如何して僕を呼んだの伯母様。貴女から便りが来なかったら、俺は実家の建っていた土地に帰って来なくても済んだのに。ずっとエナガの姿で居れば良かったじゃあないの。手紙を出したのは其方でしょう?」
「それは…!」
夢の国を助けてほしかったから。迷子を迷子をなくさせられるのは生きている者でないと果たせないから。だから貴方を呼んで
「分らないの伯母様。貴女が此方側に僕を呼んだ時点で、神々の計画は始まっていたのよ。」
細い喉をこくりと上下させて飲み干した。ミルクティーの空となったカップを五本の指で撫ぜれば食器は星の粉雪となり細かな蝶々になって家の天井へ飛び飛びパチッと溶け消えた。
「迷子が急に増えたのなんて、本当に偶然だと信じていたの?」
霧舟の顔から血の気が引く。まさか、迷子を発生させたのも伏線だと?迷子は死を受け容れられない者達のもがいた成れの果て、もっと生きたかった、死にたくなかった、希望を不条理に圧し潰された人間の絶叫の成れの果て。では、まさか、現実の不条理も、理不尽も、神々が仕組んだ事だと言うのか?
「恨むなら人の愚かさを恨んでね、きっかけを作ったのは人間の方だったのだから。」
霧舟は次の瞬間、黒い地面に叩きつけられた。其処は、雪が降る前のあの焼野原であった。
二十七
何を言えば良いのか分らない。何を叫べば良いのか分らない。昔生れた神々の怒りが、哀しみが、今世の人間達に牙を剝いて命を奪っている。もう人間への情け容赦を一旦置いて、溜まった感情を奮っているのだ。
「その一旦の間に、何人が死ななくてはならないの。」
気にはなっていた。戦争は終り国は復興を遂げたのに、戦時中と変らず人間の世界には不条理が溢れている、善人が酷い目に遭い悪人が涎を垂らして歓楽に耽っている。ひたむきに生きている者が憂き目を見る、そんなの、幼少期の自分とまるで同じではないか。
「此の土地であったことと、何も変っていない…」
焼け染みた土を指でなぞる。案の定指と爪の間に煤けた土がこびり付き、嫌でも思い出す、町の記憶。エナガとなって故郷に帰った、哀しい思い出。爆弾で人も建物も根こそぎ焼かれ、生前兄と共に手を取り歩いた景色は死灰の中に奪われていた。いつも丘の上で夕日を眺めて、慰めてもらった優しい記憶は、もう二度と同じように立ち上がれない。
「兄さん。」
堰を切って流れる涙。前も向けず、立ち上がれず、霧舟はたゞの少女に戻って咽び泣く。どうすれば良いのか分らない。そもそも夢の番人なんて必要なのだろうか、両親の言葉を真に受けて自分でそのように振舞っているだけで、本当は自分は番人ですらない死に損ないの無知な女の子なのではないか。
「姫烏頭。」
見守らねばならなかった子の本音を一つも察してあげられなかった。私が彼を此方に招かねば、成長した姿で会いたいなどと浮つかなければ、きっとあの子は平穏な日々を、天探女を眠らせたまゝの状態で生きられたかもしれないのに。
「ごめんなさい、ごめんなさい、私の所為で、兄さんの大切な子供を日常の世界に返せなくなってしまった。姫烏頭ごめんなさい、貴方に平穏を捨てさせる決意を固めさせてしまって。住民達にも申し訳が立たない、皆が生前くらった理不尽な死も不条理な殺害も止められなかった。」
あゝ、あゝと髪をぐしゃりぐしゃりと握りしめ膝を付く。頭を地面にガツンガツンと叩きつけて額は裂け生温い血がだらりと瞼を垂直にずるりずるり這い下りて行く。顎先から赤い涙が滴る勢いはますます上がり、寸分の内に血は四方にビチャビチャ散らばりひしゃげる程になってしまった。
「役立たず、役立たず!番人のくせに、何も守れていないじゃないか!神々の牙も止められない、無力な、たゞの女の子、お前なんか、お前なんか、最初から地獄に墮ちてりゃ良かったんだ!」
ギャアアと喚き自傷を止めぬ霧舟に、裸足で歩み寄る者があった。
「お嬢さん、霧舟さん、自分を傷付けるのはおやめなさい。」
息も絶え絶えな少女の両肩を掴み、強引に顔を正面に上げさせる。
「…?誰…?」
彼女の眼前には人間ならば幼年児ほどの身の丈であろうか、霧舟よりももう一回り小さい生き物が立っていた。肌は位の高い氷のように白く滑らかで、びっしりともこもこの白毛に覆われている。一見すると鹿に似た顔立ちをしているがその両眼は深い叡智の翠玉を湛えた賢者の瞳、梟のように賢いが翡翠の慎み深きと狼の謙虚を玉に混ぜた輝きを静かに控えめに放っている。そして頭の上には緑が茂り、其処から枝が八方向に伸び緑を支える働きをしている。まるで樹木の王冠を載せている恰好である。しかも二足歩行でちゃんと服を着ている、菫であつらえた絹で拵えた子供の制服に似た洋服上下を。
人間?動物?ぬいぐるみ?
「どれでもないぞよ。」
声は可愛い。
「霧舟さん、少しは落ち着きましたかな。」
彼女の頭を撫でる手はテディベアのようだった。いきなり現れた珍客に霧舟は恐る恐る問い掛ける。
「あなたは…天探女の仲間なの?」
相手は穏やかに首を横に振る。首に下げた小さな角を連ねたネックレスがしゃらしゃらと美しく鳴った。
「余はケルヌンノスである。お困りのようだから少し出張して参ったのであるぞ。」
夢の筈なのに夢を見ている。
二十八
「ケルヌンノスとは、会うのは初めてですかね、お嬢さん。」
ぬいぐるみの延長線上の姿をした冥府と豊穣を司る異国の神はおっちんとっちん三角座りをして霧舟に話し掛けたので、吊られて此方も同じように座る。
「会うも何も、神の一柱と直に顔を合わす機会など人間にはまず与えられませんよ。しかも貴方様はケルトの神話の主神ではないですか。何故、このような場所に?」
ケルヌンノスは頭の緑にふかふかの丸い手を差し込むと、数秒もぞもぞ探るように動かした後一輪の花を取り出した。それは、何處にでも生えていそうな、パンジーの花。
「此処にパンジーがある。霧舟さんはパンジーを特別な花だと思うかな?」
「…特別な思い入れのある人もいるかもしれないけれど、私にはごくありふれた植物だと感じます。」
「うん。あのね、神と呼ばれる存在も実は同じなのだよ。」
焼け焦げた地面を手で少し掘ると、パンジーの灯火を穴に入れて根元を土で覆った。こんな事をして、ケルヌンノス神は何を言いたいのかまだ霧舟には分らない。
「人が生きている限り、神は生れ続けるものでね、人の心と言う土があれば神は自然と芽吹くものなのだよ。中には此の神は自分にとって特別だと強く思う者も現れるだろう、それが所謂信仰と言うものさ、どうも今の世の中は信仰ばかりが重視されていて、神がどこにでも息づいている根本が見失われているような気がする。だからこそ、お嬢さんの国の神々も影響を受けて混乱してしまったのだろうね。」
「人が、神々に影響を及ぼす…?」
「うん。先刻神の土壌は人だと伝えたろう?土の性質が変れば生える植物の種類も変るのは当然なこと。ほら、植物にだっておっかない種類はいるだろう?でもね、おっかない植物達も誰かを攻撃したくてしているのではない、臆病だからこそ攻撃せざるを得ないのさ。攻撃させない植物を育てたいのなら、土が植物を安心させてあげなくちゃいけない。その手伝いを余はしに来たのだよ。」
「土、土壌…人の心を穏やかにする為に、此処に?」
「うん。」
草食動物の王のように円らな瞳で見つめられる。
「でも、貴方は」
異国の神でしょうと言いかけてハッと止まった。植物に国境が関係無いように、神にも国境は関係無い。異国がどうかなど気に掛けることではなく、信じる人が居るから来ただけなのか。そう考え至って相手の顔を見ると、ふわふわにこにこと嬉しそうで、此方の心を見透す瞳は玲瓏なれど温かい。
「余はとても嬉しくもある。余のいる文化は新たな国々の文明の土台になったとは言え、既に失われて忘れられてしまったのではないかともじもじしていたのだが、いやまさかヨーロッパから遠く離れた土地で余を知り信じてくれる者がおろうとはよもや想像もしなかった。憶えていてくれる、忘れないでいてくれることは神々にとっては何より嬉しいことなのじゃもん。」
ぱあ…ッと音が聞えそうなくらいにぱっと喜色満面なケルヌンノス。心が旭を思い出す。
「貴方が嬉しいのならば、良かったです。私も何だか嬉しいです。」
「そうかそうか、人が喜んでくれると神も幸せを感じる。さて霧舟お嬢さん、お互いがぽやぽわ嬉しいうちに、作戦会議をしよう。未来の為のアイデアは楽しい気分で考えないとの。」
ケルヌンノスは焦土に小さな木の椅子を二つ、まぁるいテーブルを間に一つ、その上には真珠で作った紅茶のせっとをぽんぽんと並べて勿体ぶった可笑しな動作で茶葉をポットにさッさと入れて湯を注ぐ。ソーサ―とティースプーンの間にはマーマレード・ブルーベリー・フランボワーズのジャムがそれぞれ盛られ、甘い匂いと紅茶の落ち着いた薫りが余韻を持って来る。
「紅茶には何を入れても美味であるぞな。」
ほくほく温もる表情はケルヌンノスが紅茶好きであると語っているようなものだ。
「紅茶が好きなのですか?人の作った産物なのに?」
「うむうむ。人の道具や加工品や料理などの人が産み出す物は神の世界では手に入らない。人の叡智の結晶が神には何より嬉しいプレゼントなのである。だから余は紅茶も好きじゃ。」
人の作った物が好き?
「ケルヌンノス神、若しかしたらそれが突破口になるかもしれません。」
「ぬ?」
兎みたいなもひもひ土で返事した相手に可愛さのあまり思わず吹き出しそうになるのを堪えて霧舟は言った。
「弁論の決闘なのです。天探女と姫烏頭達に夢の世界が正しく在る手伝いをしてもらう為には、神々が牙をしまう流れになる理由を用意する必要があったの。その鍵となるのが、神々は人が叡智を集めて産み出した物が好き、と言う性質。人間の心を変えるのではない別の方法が、此の鍵から思いつくかもしれない。」
「ふぉん、みょん、ふぉん、にょにょー。」
喜んだ時に出す声なのか、ケルヌンノスは両手で持っていたカップをきちんとソーサ―に置いて霧舟に拍手を送ってそう言った。若しかして此の神様、可愛い仕草や言葉遣いを相当意識しているのではないだろうかと、存外呑気なことを考えていた。
二十九
一番最初に魅せられたあの場所、妙に天探女が嫌っていた場所なんだよな。たゞの人の町が殺された景色だのに、目を逸らしたがっている。何だろ、あそこに行けば希望なんて考えられなくなるだろうと思って伯母様を落ッことして来たのに、左手がまだ震えている。
「そんなにあの場所が嫌だった?でも人間の町だろう?何を其処まで怯えるのだか。」
違う。姫烏頭は首を振っていた。
「違うのか?人の染みがある以上誰の住んでいる」
(姫烏頭、神様の世界ではね、)
「また昔の記憶か。今度は何だよ。」
(神様の世界では、神様はどなたも人の姿に戻られるのだよ。)
(人間になるの?)
(いいや神様達は人間にはなられない。けれど見た目は人とそっくりな御姿なんだよ。人間の姿は、神様の姿を模したものなのだ。)
(如何して神様達はご自分の形を人間に投影させたのかしら。)
記憶は途切れ幼い自分に対する父の返答は分らなかった。だが、思い出せたことがある。神々の姿は人間の見た目と同じ。
「まさか、あの焦土は神々の世界だと?」
それなら天探女があの焼野原を嫌い怖れるのも説明が付く。愛する神々の死体など、見たくもないだろうに。でもそれなら妙ではないか、あの場所は霧舟がエナガの姿で訪れた彼女の故郷の町だった筈、霧舟は人間である、神々の世界を訪れたことに、彼女自身は気付いているのか気付いていないのか。
「不安要素は解消しておかないと、不測の事態が起きてしまっては人間の心を上書きする計画が駄目になってしまうかもしれない、それはいけないこと。」
人々が再び神々を敬うようにするには少しの失敗も認められない。
「完璧でなくちゃ。」
拳を握りしめ、歯をグッと噛む。彼の眉間には清い鼻筋を無理矢理堰き止める深い皺が刺さっていた。
「ですから、花の冠を編むのですよ。」
「霧舟ちゃん、何だかそれは妙案ではないと余の神様センサーが困っているぞよ。」
「何故です、貴方の咲かすお花と私の花冠を編む技術、神々の与えられたものを人の技術で新しいものへと生れ変らせる、まさに人が作ったものの理想的な在り方の品じゃあないですか。」
ケルヌンノス神はぐるぐると悩み顔。
「理屈は分るぞよ、でも、うぅん、花冠かあ、素直で素朴で良いのだがなあ、むぅん、むぅん。」
「花冠のような庶民的な物だと神々のお眼鏡には適わないと仰有りたいのでございますか?」
霧舟も今では中々に胴が座り、古代の一神にも容赦が無くなってきていた。
「そうではない。贅沢品を求めている訳ではないのだぞよ。贈り物は贈り主の贈り物への深みが深いほど良い、傍目には路地の石ころでもその深みがあれば貰い手には金剛石にも勝るオパールとなるのであるが。」
「深み?思いの深さってことですか、愛情とか、真心とか?」
「むぅ、ちょっと違うかな。贈り物への理解の度合い、と言ったところかなぁ。」
霧舟には今一つ分らない。首を傾げていると、ケルヌンノスはぽふんと手を打ち何か閃いたようだ。
「お賽銭、の例えで話そうか。一円と百万円、どちらを貰ったら君は嬉しい?」
「金額が、多い方?」
「それは人間の感覚じゃもん、人間は生きる為にはお金を必要とするものじゃから、霧舟お嬢ちゃんの感覚は間違っていない。でも神々はお金を必要としないから、多くても少なくても加護は同じもん。我々が重要視するのは、そのお金がどのようにして生じたものか、経緯を見ることだ。これを物の道と呼ぶじゃあもん、覚えておくと一寸は役立つもんぬ。」
「物の道。お賽銭の場合なら、その人がお金をどのように得たのか、と言うことを辿る訳ですか。」
「ふぉん、みょん、ふぉん、にょにょー」
拍手。ケルヌンノス神は褒めて育てるタイプの性格なのだろうか。ぬいぐるみがきゃっきゃうふふする花の光景に胸を押さえて悶えそうになる衝動も最初よりかは抑えられるようになってきた。
「そのお金がの、人を騙して得た百万円なら、其奴を神々は守らない。だが一生懸命働いて心血注ぎ貯めた百万円なら喜ばしい、その人間を見守り善き道へ導こうとする。」
「…では、心血注いだ百万円と一円、どちらが嬉しいです?物の道は同じですよね?」
「物の道は一つではないぞよ。そのお金がどのような心持ちで捧げられたのかも物の道だよ。」
「心を込めて投げられた一円か、とりあえずで捧げられた百万円か。またはその逆もありますが……人間の浅間しさから物申せば、一円で加護を受けられるのなら、百万円入れて損したと感じる人もいるでしょうが、そのような人達はどうなるのです?贈り物をした時は確かに真心がありましたが、その時の感情が錆び付いたり風化したら?」
「相応にその者は苦しむじゃろうもん、畏れと感謝の気持ちを忘れてしもうたらもん。」
素朴な可愛さだけでない大神たる毅然とした思想にドキリとする。
「……贈り物とは存外難しいのですね、神々相手の類は。」
「だから信仰する者は敬虔であれ、感謝の心を失うなとよく警句を残すじゃろう。」
「成程、そういう道理でしたか。…物の道、私の花冠には道の深みが足りていないと?」
「足りてはいるが、浅瀬じゃないかな、湖はもっと深くなければ。」
「では、私を導いてくださ、ケルヌンノス神。」
視線清らかな黒の菫、より良き道を望む心は自ずと眦に表れる、ケルヌンノスは大きく縦に頷いた。
「では霧舟さん、此の焼け焦げた場所のことから話をしよう。」
「私の、故郷についてえすか。戦争でこのような有り様に…」
「君は誤解している。確かに此処は戦争が終ったばかりの君の故郷の町に似ているが、そうではない。此処は神々の夢の中、神々の住む世界の景色だよ。」
三十
神話を読んでみると、人の時代が訪れる直前には、神代の世界は滅亡しているケースが多い。神の死体が人間の住む国土になったりする場合もある。神が死んで人が育つ、そのような描写が物語の中には多いのだ。
「神達はね、自分達の住む世界では人間の姿をしているのだよ。だから此の土に染みを成している者は皆残らず神なのだ。」
「そんな、如何してこのような!」
「人間の世界から切り離されてしまったkら。神々は物理的なダメージは受けないけれどその分精神的なダメージにはとても弱いのだよ。人間が生れて一緒に生きて行けると期待したが、人間は自分達の世界に神々が同じ立場で在ることを拒絶した。その宣告は一種の神殺し。置いてきぼりの寂しさの結果が此処さ。神々は人の世界に実体を持ち現れることが出来なくなり、運上の存在へと変質したのだ。」
「拒絶されて、その涙で神々の世界は焼けてしまったのですね。」
思わず黙りこくってしまう。何と言えば良いのか全く分らない。
「霧舟ちゃん、そう悲しいお顔をしたら悲しいぞよ。大丈夫、神々はしぶといのじゃもん見て御覧。染みの後には雨水が沁み込み草木が生え植物の芽は増えていく。神々も新しい世界の在り方に馴染もうとしているのじゃもん。」
やがて染みは麗しい花々が息づく為の土台を全うし、土の奥へと溶けて行った。あちこちで開き始めた花達はやがて虫達を呼び生物を呼び空の黒雲が晴れて陽光が綺羅と輝く。
「焼野原が、立ち上がっていく。」
「人間達と同じ立場ではもうあられずとも、それでも人を、命を愛する心は放棄しない、見守り導き照らし続けるのが神々の使命。此の場所で咲いた花は、神々の本来の人思ふ千尋の心の心象なのである。」
「ケルヌンノス神が頭部の緑から取り出した花では、確かに物の道は浅いですね。此の場所に咲いた花々でないと、神々の御心でないと、意味が薄い。」
「そういうことじゃもん。早く摘んでしまわないと、雪が降るぞよ。神々から天探女への手紙なのじゃろう?」
「え、でももう雪は焼野原に降っていましたよ。」
「夢の世界で焼野原なのは此処だけと霧舟ちゃんの故郷の二つだけじゃもん。全部見て来たから間違い無いもん。霧舟ちゃんの夢には雪は積もらずあのまゝだったよ。」
「意味が……じゃあ…雪が降っていた神々の世界は、巻戻しと再生を繰り返しているとでも?」
「そうじゃもんッ、雪が降って天探女達を飛ばした後君等は住民と一緒にその場を去ったから気付かなかったのよ。余は眺めていたから知っているもん、雪野原は積もり終ると動きを止めて焼野原の姿に戻り、雨が降り花が咲き陽光が射して雪が降る、そしてまた積もれば動きを止め焼野原から始める。ずぅっとそのサイクルを繰り返しておるのだよ。」
「繰り返す理由。…若しかして、迷っている?」
「そうじゃろうなあ、人間の心の上書きをすることを命じておきながらも、本当にそれで良いのか逡巡しているようだ。」
「ケルヌンノス神。」
「うむうむそうじゃなあ霧舟さん。」
「考えていたより、上手く事が運べるかもしれませんね。」
その為には先ず、
「霧舟に会いに行かなくちゃいけない、でないと完璧にすることが出来なくなっちゃう。」
姫烏頭が霧舟の居場所に戻ろうと移動の穴を焼野原に開けた時、眼前に人の手がグアッと迫り彼の顔面をむンずと掴み思いッきり強くぐいと引ッ張り出された。落下し仰向けに倒れた衝撃で目をつぶるが、開き馴染んだ声に呼ばれて目を開けて声の主をちらりと見上ぐる。
「伯母様、数刻ぶり。」
「姫烏頭。」
「俺に何か用でしょうか?」
「まあ、それもそうだが、おまえの方こそ私に用事があったから来ようとしたのではないかな。」
苛つくほどに落ち着き払っている伯母に姫烏頭は内心首を傾ぐ、焦土に突き落いた際は狼狽ひどく見ていて可笑しいと思ったのに、数刻離れている間にすッかり平静を取り戻しているなど、彼女に何が起きたのだろう。
(焦土に突き落したのは悪手だったかな。)
心が舌打ちをするが噯にもそれは出さないでニコリと笑う。
「姫烏頭が此の場所に連れて来てくれた御蔭で、貴方達の慕ってやまない神々の御心が分ったの。」
パアと心から顔が晴れる。
「じゃあ、伯母様も僕達の計画に力を貸してくれるってこと?」
乙女の喜びに水を差して済まない。身体をガバと起こし自らの片手を両手で握り込んだ甥の手にもう片方の手を掛ける。
「違うわ姫烏頭。貴方が気付いているかどうかは察し得ないけれど、神々は迷っておられるの。このまゝ人間の心を上書きしても良いのかどうか、踏ん切りが付かずにいらっしゃる。」
表情が冷めてゆく。光の灯らぬ瞳は今にも零れ落ちそうに艶々と震えている。
「姫烏頭、此処は彼岸と此岸の間の世界、彼岸でもあり此岸でもあるきょうかいせんだって言ったわよね。あのね、生きている人間は境界線に佇み続けてはいけないの、どちらかを選ばなくてはいけない、でも私は貴方をこのまゝ死なせる心算はさらさら無い、姫烏頭、貴方にはまだまだ生きていてほしいの、私のように幼くして彼岸に来てほしくないの。」
「もう、子供じゃないもん、僕は…」
「子供よ。兄さんと義姉さんからしたら貴方はずっと子供だし、私の目からもまだまだ幼く見える。憶えていない?貴方のことをたゞの姫烏頭として見てくれた上司の人の話、喜んで私に教えてくれたじゃない、思い出して御覧、貴方が人間世界で生きていて、一緒に笑い合った人はいない?」
一人の男の子の顔に空から雨粒がぽとりと落ちた。一つ、二つ、雫は一つずつ増えて、絶え間無く降って来て、やがて幾条もの白糸、宝玉の露の筋となり、頭髪を濡らし肌に沁み、瞳に注ぎ溢れた水に、下がる瞼が自然と止められない。
瞬きをする直前、彼は温もりに包まれた。あゝ、抱きしめられているのだな、と感じた直後、姫烏頭はホテルのベッドで目を覚ました。
第三章 三十一
丁度日が暮れて月が昇り始めた薄花桜の空の色は窓を通して姫烏頭に注ぎ、柔らかに彼の身体を温めている。細胞が起きたのだろう、体温を取り戻し始めた身体は起き上がりたいと脳に伝え、青年はぼんやりと身を起こした。
何を言えば良いのだろう。呟く言葉も見当たらずたゞぼんやりと目の前のアイボリーの壁を見つめる。天探女の干渉は、感じ取れない。長い長い夢を見ていた筈なのに、それこそ一生分の夢となる期待をしていたのに、醒めて見れば半日も経っていなかった。まだ何處となくふわつく感覚を捨て切れぬまゝ姫烏頭は扉を開けて外に出た。部屋の中には彼一人だけだった。
「行ってらっしゃいませ。」
ドアボーイが頭を下げる。一階の広いエントランスホールに来る迄に何人ものホテルスタッフとすれ違い会釈をされた。その都度此方もぎこちなく片言の会釈を返す、眠る前の滑らかな所作を一気に忘れてしまったかのように滑稽だったが誰も彼に怪訝な眉一つもせず丁寧に過ぎ去って行った。
目的は果されないまゝ、夢から醒めてしまったこと。
「君と一緒に愛すると決めたのに。」
また、果たせないまゝ君は眠り黙ってしまったこと。横断歩道でまだぼんやりと戻りたがらない心を重荷に赤信号に佇み続ける。青になっても立ち止まったまゝでいる姫烏頭に一人の少年が首を傾げたが、母親がこの視線を覆ったので親子は向う側の歩道にスタスタと歩き去ってしまった。小さくなりゆく少年の足元に菫の花がアスファルト越しに咲いている。
「菫。」
今更神社に立ち入る資格は無い。実家が更地になったことも、今となってはどうでも良い。けれど、菫の単語は何故か降り切れられないでまだ片隅にしがみついていた。
「菫、菫山。」
天探女は何も触れて来ない。神々に合わす顔の無い自分に愛想を尽かしてしまったのだろうか。今の己は神々への愛を全う出来なかった半端者、もう後は現実の世界で日がな一日を過ごして過ごして死んでゆくだけの空蟬だが、完全な脱殻になる為には此の一点の染みを雪がねばならない。
「まだ夏休みは半分残っている。」
再び変わった青信号に背を向けて、姫烏頭はホテルへの道を戻り始めた。
エントランスに入るなり受付の男性に質問した。
「菫山は、何處にあります。」
この年代の者なら検索して自分で勝手に行きそうなものを、男性は美しいアーチ状の眉を描いたまゝ客の質問に応じてくれた。
「菫山は、昔の呼び方ですね、今では冠山と名称が変っています。当ホテルからですと、最寄り駅から三〇分程急行に乗っていただきましたら麓近くの駅に到着いたしますよ。」
「近くの駅。駅があるんですか。」
「えゝ。冠山は戦時中の急速な発展を受けなかった土地とされていますので、それを目当てに訪れる方も多いのです。お客様も、観光しに行かれるのですか?」
「いえ、自分は…」
死に場所、にしたくなるかは分らないが、少なくとも明るい気分で向かう訳ではないので此の質問には窮してしまった。それでもホテルマンはにこやかに話をしてくれる。
「行かれるのでしたら、防寒対策はしていかれますように。夏でも軽装で向かわれた方が低体温症で動けなくなる事故は頻繁に起きていますので、どうぞお気をつけて行かれますように。」
「雪。雪ですか、真夏なのに…そりゃ危険だ。」
見捨てられた腹いせをするだけの業は持っているのだろう。魔所は今でも魔所らしい。
「寒さも勿論なのですが、山中にある湖にもお気を付け下さいませ。」
「湖…なんてありましたっけ?」
「はい。最近にあの山を研究対象にしている学者が発見したと一時話題になりました。ですが其処は冠山の数多い難所の中でもとりわけ道の難しく迷いやすい所にありましたので、今では幻の湖と呼ばれています。」
「実在するのに幻、ですか…」
「大きさは池ほどのものだそうですが、深さは尋常でないらしいと言われています。其処は山の奥深くにあり樹木が自ずから盾や鎧となる為かしてそよりとも風が吹くことは無いだとか。」
「……あゝ、そうですか。どうも有難うございました。」
姫烏頭はスタッフに深く一礼すると、踵を返して自室へと急いだ。後ろから「お気を付けて行ってらっしゃいませ」とチェロの弓が呼ぶような声に見送られて。
三十二
部屋の中には姫烏頭の持ち物が待っており、エナガはやはり居なかったし初見の文様が施された本も待ってはいなかった。
「ねえ、君は凪に反応する習性でもあるのかい。」
部屋に聞える声は青年のものだが、
(久し振りの対話が出来るようになったのに、開口一番が野暮な質問だなんて残念ね。)
彼に聞えている声はもう一つあった。
「天探女、そう呼んだら良いのかい?」
(それじゃ初めて逢った時から変っていないわ、お洒落じゃない。いつまで経っても坊やの感覚で呼ばれるのは何となく嫌。)
「では、どう呼んでほしい?」
(今、姿を見せるから貴方が相応しい名前を付けて。大丈夫、人間の姿では出ないわよ。此処は神々でなく人間の世界だもの、それくらいの分別は付いていますもの。)
心臓の少し斜め上辺りが神経痛のようにつきりと疼くと、衣服の下で何かがもぞもぞ蠢く気配に皮膚がぞわと泡立つ。
(もう少し我慢しなさい。)
ごそごそ、もぞもぞ。
「上着を脱いで覗いたら失礼かい。」
(見たらきっと気絶すると思うわ。…目を閉じて。)
言われるまゝに目を閉じる。もだえそうなるのを堪えて暫くじっとしていると、声が内側からでなく前から聞えた。
「ご苦労様。お待たせしてごめんなさいね。目を開けて見て。」
低いテーブルの上には、彼の薬指の長さ程度の髪留めが置いてあった。妖精の番える小弓のような可憐な鋭利は月清らかに泉に沈む古代の苛烈な祈りの気を帯びつゝも胸を押さえて自制しようと試みるいじらしい冷たさがある。そして矛盾の向かう果てには一羽の蛾。白雪の精かと溜息零るゝ遠き真珠の蛾が先端に細工されていた。
「俺男なんだけれど…シャルロット。」
「あら可愛いお洒落な名前をどうもね。それはそれとして、何よ、銀の髪飾り付けても可笑しくなんかならないわよ。利き手側の耳の上に留めておくように。安心すると良い、壊れたり外れたりしないから。」
「…風呂はどうすれば?」
「貴方の裸なんて興味無いわよ。」
蝶よ花よと育てられ扱われて来た姫烏頭にとっては人生で最も散々な旅立ちの始まりであった。
三十三
夜の急行列車は空いており、乗客は姫烏頭以外居なかった。音楽も流れない車内にアナウンスの声は寂しい。外の光景は一つ一つ灯りが減って今ではすっかり真ッ暗で窓を眺めても影の映らない鏡にしかならない。
「今周りに人間が居ないのでしょう。」
「居ないよ。」
「そんなら喋っても平気ね。」
「君の声、今は僕以外にも聞えてしまうのかい。」
「心配してくれているの?」
「人間の世界では人語を操るヘアアクセなんて存在しないもの。」
「まあ、優しい。」
くすくすと愉快に弾む密かな声。それも車輪搖れる働きに混ざってほのかに灯る。
「私の声は貴方にしか聴えないわ。だから人の多い場所ではご自分の心配をすることね、一人で話をしている変な子になっちゃうから!」
大人しさは我慢出来ずふふふ、あはゝと笑い出した。けれど姫烏頭だって言われ放しは良しとしない。
「歩いている時は電源を切った携帯電話に耳を押し付けてやるから良い、でも、電車の中は参ったね。今みたいに僕等以外誰も居ない状況で声を掛けて話をしておかないと菫山に行くまでの状況整理が出来ないからね。
あゝ、本当に機を見計らって声掛けしてくれたんだねシャルロット。其処迄俺を思って気にしてくれていただなんて嬉しいよ。」
一揶揄えば百の言葉でつらつらねちねり返される。
「…あんまり相手を揶揄わない方が、」
「お互いの為には良いのかもね。」
二人はふうと一緒に溜息軽くつき、これからの予定を確認し始めた。
「菫山迄は後どれくらい掛かるの?」
「まだ出発したばかりだよ。二十五分は駅まで掛かる。もう向うに着いたら店は何處も閉まっているだろうか、森の中で寝るのは正直キツいな。」
「そもそも宿泊施設なんかあるのかしら?菫山は魔所として人から捨てられた場所、人間に仕返ししているのでは?」
「山に着いては浅薄だが着いてから動きを考えよう。君が最初に質問して来たから、今度は僕が質問を挙げるよ。」
ピリと二人互いに緊張感が走る。
「シャルロット、君、夢の世界での記憶、忘れているのかい?」
「忘れられたら、きっと幸福なんでしょうね。」
短い言葉だったが、それだけで語るに及ばず、二人は互いに口を閉ざした。
急行列車は最初は各停、目的地に近付くに連れてどんどん停車駅が少なくなっていくのが多く、姫烏頭達の乗る電車もこのパターンの道行であった。車両はまだ速度を出し切れていない状態で二回、三回と停車を繰り返す。アナウンスが次の駅を告げる、其処は停まった駅から距離のある場所で十分は搖れ続けなくてはならない。
「楽しかったの。」
話し始める相手をそっと指先で撫ぜた。
「私は本心を暴く願いから生み出された存在だから、他者の隠すものを白日の下に出させることに何の疑問も悩みも抱かない。自分の使命が神々に必要なものだと分かっていたし、畏れ敬愛してやまない御方達の為になるのは嬉しかった、とても幸せだった。だから夢の世界で住民の、えっと…」
「倉吉君。」
「そう、倉吉少年の過去を、深く押し込めていた記憶を引き出した時は、楽しかったの。」
「伯母さんは、他の住民全員にもそれをしてほしかったみたいだね。」
「お目出たいお人。夢の世界を楽園でなく正しい在り方に戻そうなんて。何も考えずに能天気な楽園のまゝいれば良いのよ。」
「その方が、上書きしやすいものね。」
「私は罪悪感なんて無いわ。計画を中止したのは、神々が迷っていらしたから。私は従うだけよ。若し今直ぐにでも計画が再開されるのならば今度こそ夢の世界から上書きを始めに向かうわ。」
「そう…」
寂しい微笑みの姫烏頭に、シャルロットはむきになって返した。彼はそうかと頷くことしか出来なかった。
「貴方は如何なの姫烏頭。楽しかった?」
「君にはどう見えた?」
「何その質問。自分のことでしょう?自分で分るものなんじゃなくて?」
「人は…他者から見られることで初めて気付くこともあるんだよ。」
「自分自身のことなのに?」
「自分自身であればこそさ。人は他人を見る方が上手なんだよ。」
「そう言うものなの。神々や私のような精霊とは違うのね。私達は自分が生れた瞬間から使命が分かっている、何を司る存在かを弁えているから、第三者の視点だとか客観視の必要性とか無用の長物、迷う余地なんて最初から有り得ないのに、人は迷い悩んで答えを出すのに時間が掛かるものなのね。でもそれって人だけに与えられた特権かしら。」
「特権、ねえ。その特権の為に何人が死んだり悲しんだりしているのだか。」
「神々を手離す世界を選んだ時点で間違っているのよ。」
「間違っている世界が現実、か…」
「でも生れて来た以上は精々悩み苦しみ生き抜いてもらわないよ。変に神々の所為にされたら腹立たしいもの。」
「ふゝ…」
シャルロットと話していると自然穏やかな笑いが込み上げ吐息を零す。それは先程の寂しい微笑とは違う、ごくごくありふれた静かな笑顔であった。
「馬鹿にした。」
「してないよ、シャルロット。振り返る元気が出て来ただけさ。夢の世界での、僕の行動をね。」
がたんごとん がたんごとん
電車は一定の速度を保っている。
「水仙」


