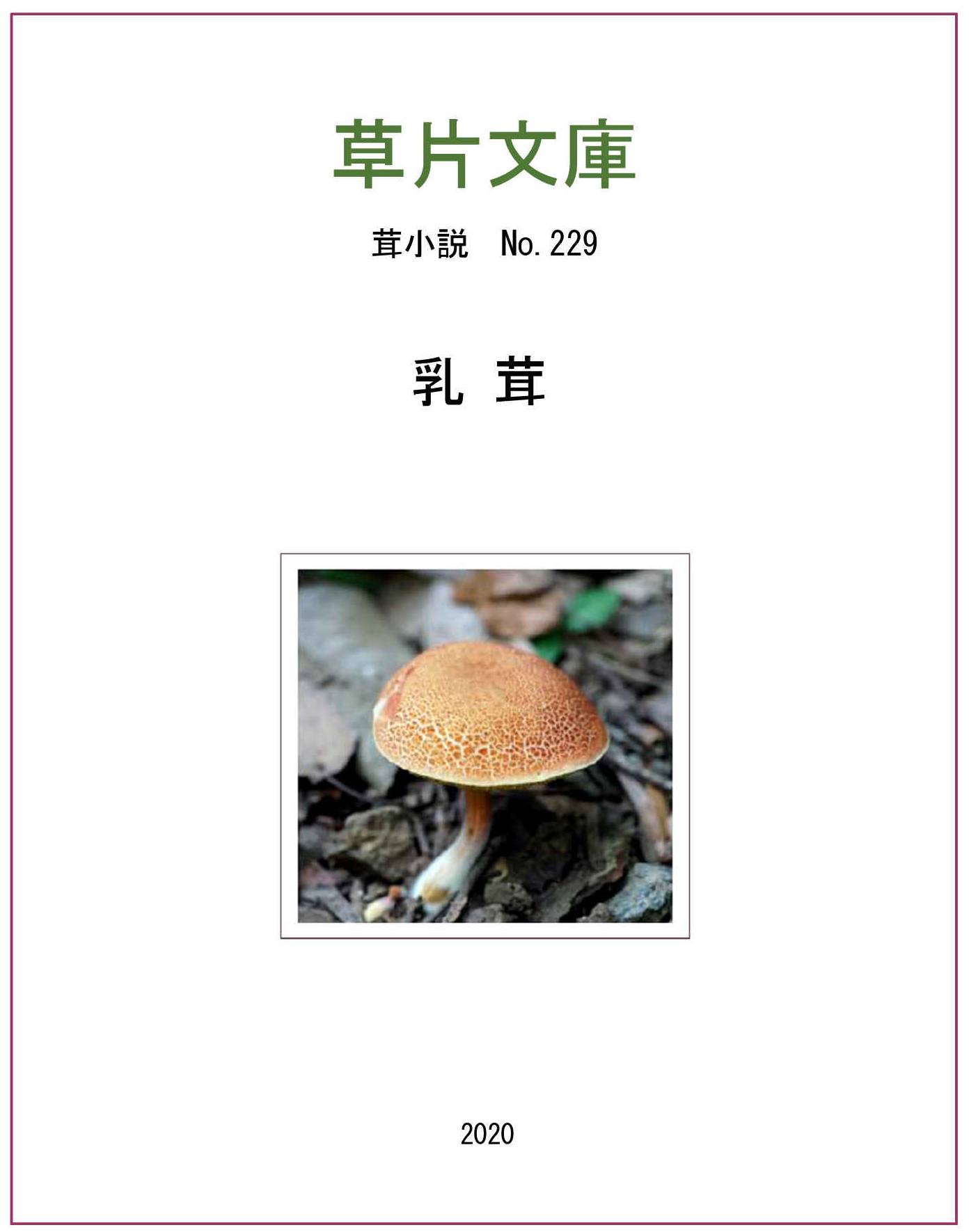
乳茸
日曜日の朝。
夢をみていることが自分でもわかっている。
乳がでないとわめいている家内に、
「大丈夫だ、だしてやる」と言って裏山に行った。
夢の中ではいつも行っているようだ、裏山のその場所には赤黄色い茸が生えているのを知っていた。赤黄色いというのは赤と黄色のまだらではなく、真っ赤な柄に黄色い傘がついている、大きな松茸ほどの茸だ。
二本採って手に持った。家に戻ると、「これでいい」と手渡した。
かみさんは、「なにこれ、どうしたらいいの」と受け取って、柄のところを握ったら、茸の傘の先から白い液がプピュとでた。白いネバ液が床に落ちた。
「なにさ、これ乳茸じゃない、私のが出ないのよ」
かみさんはこちらをちらっと見ると、馬鹿にするようにいった。
「傘をとって、胸につけるといいよ」
そう言ったらかみさんが怒った。
「あんたがつければいい」と
大むくれでキッチンにいってしまった。
しょうがないので、乳茸を自分の胸のところにもっていこうとすると、猫の玉がやってきて、吸い付いてちゅうちゅう吸った。
キッチンからそれを見ていたかみさんは、私が玉にやると、ブラウスの前を広げた。二つの乳茸がはえている。玉は眼を大きくして、かみさんの乳茸に吸い付いた。
「ほら、玉、おいしいでしょ」
かみさんが言ったところで目が覚めた。五時だ。
おとといの夜、大学時代の同級生、神山から茸をおくると電話があった。神山は大学卒業後、茨城の家業を継いだ。産物の卸問屋だ。よく茨城の名産を送ってくれる。彼はクラス会の幹事長だ。東京の僕もやらされているが、役割は店の予約である。
「チタケを送る準備してんだ、生と乾燥した奴、それに佃煮、乾燥した奴はそばやうどんに入れるといい出汁がとれてうめえんだ」
電話ではなんだか酔っぱらっているような感じだ。
「いつも悪いね、クラス会は今年も大学の近くのレストランを予約するけど、それでいいね」
「いいよお」
やけにハイテンションだ。
「飲んでんのか」
「うーん、いや、昼間っから茸食った」
「何の茸、チタケとやらを食うとそうなるんじゃないだろうな」
「なんねいよ、ちょっと、紅天狗を試したんだ」
それは僕も知っている茸だ。真っ赤で白い点々のある毒々しいやつ。
「そいつ毒茸じゃないの」
「だいじょうーぶ、うまいんだよこの茸は、ともかく明日黒猫にたのむからよ」
「チタケは生でも食えるんかい」
「食えるよ、でもこっちでは、チタケを生で食うと、母犬になっちまうという、変な言い伝えがあっからな」
「どういうことだい」
「いわれはしらんけど、あんまりうまいんで料理する前にくわれちまわないように、そういったんじゃないかな」
「でもさ、何で母犬だ」
「食いすぎて太っちまうということじゃないかとおもうのだ、俺の想像だけどな」
そう言って電話が切れた。言っていることがよくわからん。土曜日だから好きなことしているんだろう。それにしても毒茸を試すとはどういうことなんだろう。
朝食の前に、我家のぐうたら犬、虎をつれて散歩にでた。天気も良かったし、ちょっと遠出して浅川に行った。といっても歩いてたった十五分ほどだが、家のある丘の下をはしる北野街道をわたって、駅の脇をすぎるとすぐ浅川になる。
太った柴犬の綱を引っ張って、ちんたら歩き、やっとこ土手にでた。川の中州に白い鳥が数羽集まっているのが見える。サギの仲間だ。それを見た虎はいきたそうな顔をして、サギに向かって、ワンでなく、ヤンと小さくほえた。そういえば、虎が声を出すのを久しぶりに聞いた。
土手を降りたがったので、引っ張られるように階段を下り、河原の石ころの上に立った。岸辺まで行くのかと思ったら虎のやつ草原の中で立ち止まった。
嬉しそうに尾っぽを振っている。
草の中を見ると、秋になってもタンポポにつぼみがついている。その脇に橙色の茸が生えていた。先生茸と呼んでいる茸だ。虎はこの茸が大好きで、さっき声を出したのはサギに向かってじゃなくて、草むらにこの茸を認めたからのようだ。
なぜ先生茸なのかというと、なくなった僕の大学のときの恩師は物事の道理をまっすぐに見ることのできる人で、何事でも相談すると将来を見据えた正しい意見を下さる。それはとても頼りになる先生だった。
その先生は茸がとても好きで、茸の名前をよく知っていた。先生はときどきゼミの学生と、茸探しのため大学の裏山を歩いた。そこでこの橙色の茸が生えていて、
「こいつは好きな形の茸で、きっと食えると思うけど、名前を知らないんだ、それで、専門家に送って調べてもらっている」そう言っていた。
この茸の名前がどうなったか聞くこともなく、自分は卒業をしてしまい、その年、先生は心筋梗塞でなくなってしまった。虎の散歩のとき、この茸が生えていて、先生を懐かしく思い出し、先生茸と呼ぶことにしたのである。しかも虎ががぶりと食ってしまった。虎にはうまい茸のようである。
今日も虎がかぶりついてしまった。
「うまかったか」
虎は尾っぽを千切れんばかりに振っている。この茸を食べると元気になる。覚醒剤のような成分があるのかもしれない。
河原にでて、川べりまで行くと、中州にいた白鷺たちがそろってこちらを見た。虎は川に口を突っ込んで水を飲んだ。べちゃべちゃと大きな音を立てたものだから、サギたちがびっくりして飛び立ってしまった。
「さて帰ろうか」
虎をひっぱって土手にもどった。
そこに、散歩のときに時々会うおじいさんが、やはり犬を連れて歩いてきた。もうすぐ卒寿の内田さんである。柴犬をつれている。何度か話をしたが、ハンガリーの物品を輸入する会社の社長をしていて、今は息子さんに譲り、会長となっている人だ。この人も茸が好きな人で、犬の名前をゴンバとつけている。ゴンバはハンガリー語で茸の意味だ。虎とゴンバはおたがいの鼻先で挨拶をしている。なかがいい。
「おはようございます」
「おはようございます、虎君も元気そうでいいですな」
「ゴンバちゃんも元気ですね」
「もう、二十をこしましてね、だいぶ与太ってますよ、わしとおなじだ」
そういうのだが、内山さんもゴンバもとても元気だ。この人は茸のことをよく知っていて、聞くと親切に教えてくれる。
「茨城の友達がチタケを送ってくれるんですが、チタケってどんな茸ですか」
「おお、いいですね、チタケは食べ方によってはうまいですぞ」
「友達もそういっていました」
「チタケは茨城の方言で、乳茸が本名ですよ」
今日見た夢では、すでにチタケがチチタケになってでてきた。たいしたものだ。
「乳茸ですか」
「そうです、ちちたけです、タンポポの花をちょんぎると、白い汁がでますでしょう、同じようにな、チチタケを傷つけると、白い汁がでるんです、だから乳茸という名が付けられたんだと思います」
乳茸の夢を見たのは、まともなことだったようだ。
「チチタケには白い汁がたくさんはいってましてね、2・5から4%もあるそうです、だから切ったりすると白い汁がすぐにでてきますよ」
「飲めるんですか」
「いや、飲むことはできんでしょうけど、うまみにはなるようですよ」
「ミルクの味がするんですか」
「少し甘いような感じもするが、渋いこともあるそうですね」
「チタケもそういう味ですか」
「あまりうまいものじゃないが、煮るとこくがでてね、出汁を取るには最高だそうですよ、茨城のチタケそばは有名です」
「ええ、送ってくれる友人も茨城です」
「チチタケのことよくご存知ですね」
「たまたま、ハンガリーの茸を調べたことがあるんです、チタケの仲間もありましてね、向こうじゃ食べませんけどね」
「チタケの佃煮も送ってくれるそうです」
「チチタケの身はぼそぼそしていて、格別うまいとは思えないが、佃煮にすると、サクサクした感じにもなるし、飯によくあうということです」
「そりゃあ楽しみです、でも白い汁ってなんでしょうか」
「ポリイソプレンの仲間ということでな、要するにゴムの木の成分です」
「ゴムの木ですか、タンポポの白い汁もそうなのでしょうか」
「そうなんです、同じようなもので、ポリイソプレンという物質です」
「植物や茸はどうしてそのようなものをもっているのでしょうね」
「それも調べたことがあります、白い汁の役割はわかっていないのですけど、生体の防御と書いてありましたな、人によってはタンポポの乳液がつくと、かゆっぽくなったり、かぶれたりするのはそのせいでしょう」
内山さんはやけに詳しい。
「3・11の地震は大変でしたね、津波もそうだが、原発が壊れた放射能、なかなかおさまらない、茸や野菜は放射能を吸って、農家が大変です、チチタケは放射能を吸収する傾向にあるのでこわいですけど、もう時間がたち食べることができるようになっていますね、おいしく食べてください」
「詳しく教えていただいて、ありがとうございました」
そこで、内山さんとゴンバと別れた。
家に戻ると虎を庭に放し、キッチンにいった。
かみさんが朝食の紅茶の準備をしていた。目玉焼きとハム、ヨーグルト、これからトーストを作ってくれる。
「チタケは本当はチチタケっていうんだって、白い汁が出るので乳茸、内山さんがおしえてくれた、散歩で会ったんだ」
「そう」
「チチタケはいい出汁がでるんだって、それでソバにするとうまいそうだよ、チチタケが届いたらソバ食おう」
「いいわよ」
いつもの朝食を食べ終え、二階に上がると猫の玉もついてきた。いつも俺の部屋のデスクの下でごろんと横になる。もう十八歳のおばあちゃん猫だ。
読みかけの本を開いた。加田伶太郎全集。福永武彦の探偵小説集だ。
しばらくすると下からかみさんが叫んだ。
「神山さんから、チタケ届いたよ」
黒猫がきたようだ。
降りていくと、居間で大きなダンボールを抱えて、テープをはずしている。
「ずいぶんたくさんおくってくれたのね」
中からは干したチタケが一袋、チタケの佃煮、さらにかなり大きなボール箱が二つはいっていた。取り出して開けると、保冷用の箱で中には保冷剤とともに、生の乳茸がたくさんはいっていた。
すぐ彼に電話をかけた。
「いまとどいたよ、ありがとう、生のものがずいぶんたくさんあるじゃないか、乳茸って言うから、白いかと思ったら、柄のところまで赤いじゃないの」
「うん、きれいな赤だろ、だけど食えるよ、切ってみなよ、白い汁が出るから、おちちみたいだよ、洋食にしてもいいよ、オムレツでもなんでも」
「そうなんだ、でもこんなにたくさん食いきれるかな、なまで食べると母犬になっちまうんだろ」
「そんなことはないだろうけど、凍らしておくといいよ、かなりもつよ」
「そうだな、そうするよ、ともかく珍しいものだから、おいしくいただく」
「それじゃ、クラス会であおう」
今日の彼はまともに話をした。
かみさんに洋食にもあうことと、凍らせておけばずっと使えることを伝えた。
かみさんが、生の乳茸の傘を少しちぎった。白い汁がじわっと切り口にたまってきた。指の上にとって舐めた。
「おいしいわけじゃないわね、少しあまっぽい、しぶみもあるかな」
そんな感想を言った。
「どうする、やっぱりおそばにする」
「昼は干したやつをそばつゆに入れて煮て、ざるぞばにしよう」
「それじゃ、夜は、シチュウとオムレツにでもしようか」
「それがいいな」
「あら、お手紙が入っているわ」
箱の底からかみさんが封筒をとりだして僕に渡してくれた。
封筒をあけると、彼にしては珍しくかなり長い文章だ。だけど一行が右に曲がったり左に曲がったり、よれよれである。紅天狗を食べてラリッて書いたんだろう。
『クラス会の会場予約頼む、予算はいつもの程度でいいからよろしく。
チチタケの食べ方はやはり汁ものに使うのがいいよ、茸の味は人によって評価が違うが、ぼそぼその歯触りをいいという人と、食えんという人がいる。天ぷらなど俺は好きだが、なんともわからん。
実はチチタケは俺に忘れられない子供の頃の思い出があるんだ。小学校の2年の頃だったな、近くの家の女の子とよく遊んでいたんだ。幼なじみだな、高校まで一緒だった。その子と近くの雑木林に茸採りに行ったんだ。といっても、食べられる茸はわからない、茸を見に行ったといったらいいのかな。手をつないでな、そのころは異性っていう意識はないから、恥ずかしくないんだよな。ぽちゃっとしたかわいい子でな』
あいつの奥さんとは結婚式で一度あったが、やっぱりぽっちゃり系だった。
『大きな林じゃないから、迷子になるようなところではないんだ。切り株なんかもあって、腰掛けられる。君はお医者さんごっこってやったことがあるだろう』
なんだあいつの手紙は、かなりいつもと違う。
なにを書いているんだ。それでなんだ、と次を読もうとしたら、『思い出話はここまで、そのうち電話するよ』で終りである。
なんて手紙だ。手紙になっていない。
「神山さんなんていってきたの」
「クラス会のことだよ」
手紙を持って二階の自分の部屋にいった。
彼に電話をした。
「手紙が入っているのに気づいたんだ」
「あ、読んだか」
「ああ、それで電話したんだ」
「奥さんに見せてないよな」
「ああ、なんだいあれ」
「いや、紅天狗は頭が浮いちまうな、変なこと書いていることはわかっていたんだ、だけど、なんつうか、とまらなくて書いちまった、すまん、忘れてくれ」
「そうはいかんさ、幼なじみと茸畑で、お医者さんごっこか、その続きをきかせろ」
「うーん、いや、あの娘の服を脱がせてな、チタケを二つちぎって、お乳のところにあてがうと、取ったところから白い液がでてな、それで、さあ、赤ちゃんに乳をやれよ、なんていってな、遊んだんだ」
「何で、そんなこと書いたんだ」
「紅天狗食ったら、急に幼なじみのその子のことを思い出してな、ついつい書いちまった」
「奥さんにみられなかったのか」
「うん、でも、書いている途中で、なんだかいけないような気がして、そのまま、封筒にいれて、箱の中に入れておいた、次の日遅くに目が覚めたら、かみさんが気を利かせて、黒猫に出しちまったってわけなんだ」
「幼なじみは、近くにいるんかい」
「ああ、いまでも町にいる、飲み屋をやっててな、たまにいくよ、それがまたいい女になってな」
「なに言ってんの、奥さんに言っちまうぞ」
「いや、そんな関係じゃないよ」
「まあいいや、この年になって、離婚されたなんて言ってクラス会にでるなよ」
「いや、ご忠告ありがとう」
「ともかく、おかげさまでこれから、しばらくチチタケ料理だよ」
「楽しんでくれたまえ」
電話が切れた。対応はまっとうだったので少し安心した。
昼はチチタケの入ったそばつゆでそばを食った。なかなかおいしかった。
夕食は生の乳茸をつかったシチュウとオムレツ。チチタケというのはなかなか利用範囲が広いうまい茸であることを知った。
夕方、かみさんがオムレツに入れるために、チチタケをゆでているところに、猫の玉がやってきた。玉は箱に首を突っ込むと、チチタケをくわえだした。玉はくちゃくちゃとあっという間に一つ食べてしまった。顔を洗っている。
芝犬の虎もキッチンに入ってきた。玉がチチタケを食べているのを見て、虎も箱に首を突っ込んだ。やっぱり一口で食っちまった。先生茸を食べる犬である、茸がすきなのであろう。虎は一つではがまんできず、二本食べてしまった。
あいつもなまで食えないことはないだろうといっていた。食べてみるか。そう思って、僕も一本箱から取り出した。赤というか朱色のチチタケはとても食べられそうに思えない。少しばかり勇気が言ったが、赤い傘をくちにいれた。なかなかうまい。
「生でもうまいよ」
それをきいた、かみさんも一つとった。
「本当、おいしいわね、このまま食べちゃおうかしら」
もう一つしょうゆに漬けて食べた。
「なかなかいける」
ゆでたチチタケができあがった。すでにできているシチューの中にいれた。シロいシッチュウに赤い乳茸は目立つ。
だが、とてもおいしかった。オムレツは作らなかった。生で食べたせいもあるが、かみさんが面倒になったようだ。
その晩、ベッドの上に横になったら、彼の手紙をのことが思い出された。それにしてもあいつは懐かしい言葉を思い出させてくれた。自分はしたことがないが、お医者さんごっこはただのおままごとではない、親に隠れてする遊びだった。理由はわからなかったが、いけないことなのだと言うことを子供心に知っていたものである。今の小さい子供たちはそんなことをして遊ぶ機会も場所もないであろう。いや、もっと過激な場面をいろいろな形で目にしてしまっているかもしれない。日本の変わりようはすごい。テレビや漫画にはとても信じられない男女の場面があらわれる。
あいつが懐かしいと思ったところに、ちょっとばかり理解ができる気がした。
隣のベッドから、家内が言った。
「ねえ、乳茸のお乳は、赤ちゃんの役に立たないのかしら」
「チチタケの汁はミルクじゃないんだよ、ポリイソプレン」
「なにそれ」
「内山さんがおしえてくれたんだけど、ゴムの材料だって」
「食べ物じゃないのね」
「うん、でも、チチタケはネットなどに書いてあるより、旨い茸だということがわかったな」
「そうね、意外と生がおいしいわね」
かみさんは料理がかなりうまいほうだ。結婚して五十年たつが、食事はいつも満足していた。
それから三日間、家内が腕を振るって、乳茸のいろいろな料理がテーブルの上にならんだ。そればかりか、生のままで犬猫も一緒に食べたので、三日目には空になってしまった。冷凍してとっとこうと思ってたのに、うますぎて山盛りあったチチタケが三日でなくなってしまったのである。
その翌日、朝起きると、朝食を用意していたかみさんが、「今日、国立病院にいってくる」といった。
月に一度ほど、高齢者の健康診断に行くので、それだろうと思った。
彼女が帰ってきたとき、健康診断の結果はどうだったと聞いた。
ところが、かみさんは、
「健康診断じゃなかったのよ
「なんだい、風邪ぎみかい」ときいたのだが、首を横に振って、少しばかりはにかんだ表情で、こんなことをいった。
「胸が張ってきて、癌にでもなっているといやだから、みてもらったの」
「痛かったのかい」
「ちがうのよ、この年になって、お乳がでたのよ」
何がおきたというのだ。なかなか飲み込めない顔をしていたのだろう。
「昨日の夜からぽたぽた出て、下着を汚すのよ、それで医者にいったの」
「それで、なんだって」
「ちょっとした体の異変だからすぐ直るだろうって言ってた」
「お前いくつになったんだ」
「七十一よ」
そこに玉がやってきた。テーブルに飛び上がると、ごろんと横になった。腹に白い汁がついている。
「玉がおかしいぞ」
かみさんが玉のお腹をさすると、前足の付け根の三対の乳から白い汁が出てきている。後ろ足の脇の三対からも同様にでている。
玉が両手をのばしてにゃあとないた。
「玉は十九歳になったんだよな、お前と一緒で、年なのに乳が出てきた」
「そうなの、医者にどうしてか聞いたら、お乳は、女性ホルモンなどで乳腺が発達して、下垂体というホルモンを出す臓器からでるプロラクチンによってでるんだって」
「もしかして、あいつが送ってきた茸がそうさせたんだろうか」
「そうかもしれない、でもとても体に悪いこととは限らないって、それにね、男も女もないって」
「どういうことだい」
「あなただって、お乳がふくらむかもしれないのよ」
自分の胸をみた。どうにもなっていない。
「俺はもう七十三歳だぞ、そんなことはないだろう」
ところが、その二日後、僕の胸が膨らんできた。そして、乳首からたらりと白いミルクがたれた。
同級生の神山に電話をした。
「やっぱり、そうなったか、生の乳茸がうまくて食っていたら、実は俺の乳も膨らんで、ミルクがでてきた。なおんないんだ、でも毒にならんよ、今じゃ、自分の胸触ってあそんでいる」
「なにいってんだ、膨らんだのか、元に戻すにゃどうしたらいい、乳茸ってそう言う茸なのか」
「うーーん、もしかすると、原発が壊れて放射線がもれて、変化した乳茸かもしれない、でもな、乳牛にこの茸を食べさせると、もっとたくさんミルクが出るようになるかもしれないからためしている」
「俺の胸膨らんだらどうしたらいい」
「わかんない、わかったら、しらせるよ」
彼はそう言うと電話をきってしまった。
なんだか、つい先ごろ見た夢が正夢になりそうだ。
そこに犬の虎がやってきた。
おなかからぽたぽたと白い汁をたらしている。
アー、とうとう雄犬の虎もお乳を出している。
かみさんが言った。
「もういいじゃない、天からの授かりものよ、お乳を楽しみましょう」
女性のかみさんは受け入れやすいだろうが、男と育った僕には、いくら七十三歳になったといえ難しい気持ちで一杯だ。
自分の膨らんだ乳から搾った乳をグラスにためて一口飲んでみた。
「確かにうまいじゃないか」
なぜかほっとした。まあいいか、俺もさわって遊ぶか。
ちょっと揉んでみた。手触りがいい。お、意外と気持ちのいいものである。
乳茸
私家版第二十二茸小説集「桃皮茸、2026予定 一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2023-9-17


