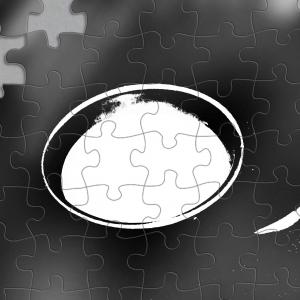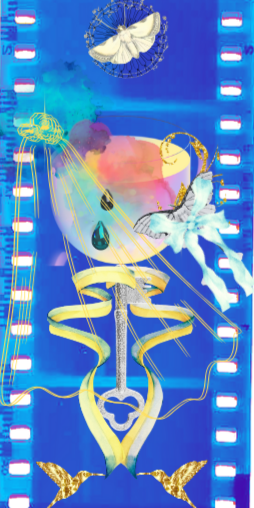
「陰陽」
それは、王国の使命。
序
雨が俺の身体を濡らし始めた。絹を掛けたような冷たい肌触りはやがてまとまった雫と集まり点々と肌に流れてゆく。微睡んでしまう柔らかな誘惑を完全に振り切れず、瞼の力を緩める心地良さに抗い乍ら手元に咲く一面紫陽花の花束に身を埋もれさせた。深く呼吸をしてしまえば、もう此の国の住民となるのだろう、手に触れる花の欠片を握りつぶす。上等だ。
此の国に良からぬ者が混ざって来たか、雨の日はどうも入り込み易い。まあ構わない、悪なら殺せば良いだけの話。国民には念の為避難命令を出し身と安全の確保を。久々のお客さんだが警戒は解かない方が良いかもしれんと伝えておこうか、此方で害意が無いと確信出来たら呼ぶから暫く待機していてくれ、気になるだろうけれどちょっとだけ我慢して待っててね。
新月
瞳に光が宿っていないから新月と名付けられたのだ。眦に勇壮と秀麗の気は満つるも眼光は殺しを躊躇わぬ一線越えた身特有の色気と不敵を隠しもせぬ男は新月と呼ばれていた。
新月は人の子である。人の子である以上両親は必定存在していたが、彼は恵まれた環境を選ぶことが出来なかった。尤も、最初の方は良かったのだ。道端の溝に捨てられていた赤ン坊を拾って命を温もりで繋ぎ留めた育ての父親は、今の新月と同じくらいの齢であったが、甘く陰惨な落し穴は経験したことが無かったのだ。
情に厚く真面目な生き方をしてきた義父は、命も捨てかねない程の恋に狂ったと言う。それも義父の片思いでなく双方想い慕う仲なのだから歯止めは利かなかった。義父は世間から姿を消した、まだ幼い新月の涙を残して。
行政に保護され政府の監視下で育つ新月が選んだ道は人を殺める道だった。違法も合法とさせる権力は嘗て育ての父が嫌った対象なのはよく憶えている、新月は政府御用達の殺し屋に育った。情は含まず確実に仕事をこなす精密さと効率の良さは同業者の中でもトップクラス、重宝されるのは当然であったろう。おまけに牙を剝く愚行もしない。取り残された後から感じていたものは、家族や情愛への憎しみ、と言うよりは気色悪さである。仕事を指示する者も協力する者もそのような気色悪さを有していなかったから新月は殺しに集中出来た。真横で局部を撃ち抜かれた同僚の絶叫を耳にしても顔色一つ冷汗一滴零すこと無く対象者の心臓を撃ち抜いた手元、狂いは微塵も無い。
だが重宝された道具であれ使用者が存在し続ける限り別れは必ず訪れる。情が移れば手離し難くなる、手離し難さは使用者の弱味になり時には致命傷にも成り得る。だから愛着が湧く前に入れ替えなければならない、新月も其は知っていた、何せ初めての仕事は熟練の殺し屋を殺す事だったもの。いつかは自分も使用者に切り捨てられる結末を最初から教えられていたのだ。
こうして話は冒頭に戻る。新月は深手を負わされ俯向けに倒れ込んでいる。しかし其の場所は人気の無い路地裏でも黴くさい廃屋でも無かった、彼は全く、紫陽花の敷き満ちる地面に伏せていたのである。
「死に際に乙女のような夢を見るとは。」
もう声も上がらない咽元で笑う。こんな光景はつい先刻迄在りもしなかった。死ぬのだなと感じた時から見え始めたものを現実とは言わない。それにしても、花とは無縁の生き方で最期に花を思うとは、自分は無意識の中で何を願っていたのだろう、此処以外の土地や国でも望んでいたのか、己が嫌悪し続けた愛やらが満ち満ちる世界を、捨てられなかった結末ではない物語を、誰かの為を想い生きる事の許された国を……?
「下手くそな殺し屋だ。俺ならもう思考の暇も与えていないのに、未だ対象につべこべ思う余裕を残すとは、初仕事かな。」
滲み搖れる狭い視界の微かな感覚に雨を覚える、赤い血を吸う目の前の沈黙者達は白露に濡れて瞳を輝かせる、期待に満ちた顔で見ても自分はもう死ぬのだからと呆れるが、うとうとし始めた脳裏でふと捻くれた考えが跳ねた。此奴達は人の躯を好み糧とする類の生物かもしれない。紫陽花に化けた物の怪だ、腐肉に舌鼓みし、鮮血を啜り骨もむしゃむしゃと残さずいただく、そんな人食植物なのかもしれない、それなら自分はこれから化物の住む国へ墮とされるのだろう、そして延々と食材となり続けなくてはならないのだ、もう上げ続けられない瞼を閉じれば、身の丈に合った国へ叩き落とされるのだろう。
ニヤリと笑って拳で一輪を握り潰した。
旭影
瞳に旭の影が差すと言われた。それでも今の生活を与えてくれた両親と此の国には深く感謝している。こんな不具者を見捨てないで育ててくれたのだから、受け容れてくれたのだから。
旭影と名付けられた娘は深い湖を其の目に湛えていた。だが彼女の暮らす世界では虹の光彩の瞳が当然とされ、輝きを有さない者など不吉だと忌み嫌われた。産みの親である国王夫妻はそれでも愛娘を決して手離さず深い愛情を注ぎ育てた。国民は王を信頼していたから最初こそ懐疑を抱いたものの、懸命に子を育てる王と妃の姿に心ほだされ納得し、瞳の光云々で文句を言う者はやがていなくなり、旭影は国民から親しまれ愛される存在となった。彼女は実に恵まれた環境で育てられたのだ。
親と国を愛すればこそ、乙女が国防の大任を目指すのは自然な流れであったかもしれない。旭影は男装の麗人と国じゅうの娘達からうっとりされる程の横がほに育ち、国を守護する手腕に劣らぬ眦の鋭さは老若男女問わず畏敬の念を思い起こさせる。玲瓏たる乙女、美しき血塗れ将軍、清廉なる苛烈、国の誇らしき愛娘は此の日、空を見上げて品のある眉を顰めていた。
「今日の地上の雨模様は素通り出来そうにないな。」
近頃は混ざり者が落ちて来ないから一安心していたが今日は久々に厄介な奴が来そうな鳥肌が立つ。だが怯えずとも良い、国に害を及ぼす者なら此迄通り殺して埋葬するだけのこと、随分暴れた奴も多かったが私は必ず使命を果たす。巻き込まれる恐れの無いよう国民は定められたシェルターに誘導する。避難は部下に任しておける、私は敵を殺すのだ。其れ迄誰も顔を覗かせたりしませんように。
国
新月は意識を取り戻し瞼を動かす前に今自分の置かれている状況を確認した。手足、頭、胴体、いづれも拘束はされていない、指先をそれぞれ動かさないように意識を向けると、足先指先も自由だった。背中の滑らかな固さから地面ではなく台の上にでも載せられているらしい。話し声は一言も聞えないが、生物の気配は感じ取れる。息を殺して対象を見る時の強い視線と消しきれていない気配。どうやら未熟な所から察するに相手はその筋の者ではないらしいが、問題は未熟者の其の後ろ、殺気を抑えこみもしないで自分を見ている者がいる。此の類の気配を持つ者に姿を晒している状態は正直危険だ。此方が身じろぎ一つでもしたら容赦無く一発で殺しきるタイプだ、熟練の殺し屋、俺と同じ種類の者。
規則的な寝息を立てて策を考え乍ら身体の痛みに集中していくも、倒れた直後から感じていた激痛と灼熱はすっかり失せている。ガーゼや包帯の肌触りも無いのに?だが痛みが全く無いのも事実。さては脳をいじられて感覚を幾つか消されたか?
「意識が戻っているのなら、起きろ。」
ヴィオラに似た波長で静かに呼び掛けたのは旭影だった。師匠の言葉に弟子は彼女の後ろへ隠れ、ちろちろと新月の横たわる寝台を覗き見る。
「綺麗なお声で招いても無駄だ。俺が起き上がったらお前が誰かを知る間も与えてもらえず殺される未来が見えている。」
想像してた声とかなり違うな。まるで乙女のようだ。
「ならばその予知は大外れだな。私はいきなり貴殿を撃ち殺す真似はしない。」
「そう言い切れる理由は?」
「私の弟子の前だからだ。此の子の前で私は殺しをしない。」
新月は目を閉じたまゝ上半身を起こし、声の主の方を向いて顔と瞼を上げていった。
目の前の娘に、理解が追い付かない。
寝たフリをしたまゝ進めた推測内容に間違いは無かった、仕事上で何度も役に立った技術だったが、今は確かな実績があるのに自信が無い。頭の中で描いていた恐ろしい獣と娘が結び付けられない。
此のふっくらと穏やかな眦が?清らかな泉の底の瞳の色が?愚かな光を有しない聡そうな目が?志の強さは整った鼻筋を見て分かるが、鈴蘭のように初々しい紅染まる唇も信じられなかった。言葉を失う新月に、靴音凛々しく歩み寄ると、旭影は新月の右頬をビンタした。
「殺しはしないが、私の愛する国民を驚かせたことには変り無い。此の平手は其の分だ。しかし、我々は貴殿を迎え入れよう。今日からは此処で暮らすと良い。」
弟子はもう既に病室を離れたのか姿は見えなかった。目を瞬かせる新月は、頬のおしとやかな楓模様を擦りながら娘の後をもそもそ歩き付いて行く。情報を遮断する為のカーテンが旭影の手で開かれた。
雪の蔦が空から枝垂れる桜の如き指先の糸の下には紺青の玉が荒削りに広がっている。鋭い先端には桔梗を翼に溶かした蛾が留まり、極光の色彩灯すまろい両目で此方を見ている。その隣にも、臙脂の秋桜溶かす羽の蛾がひとり、隣、隣、その隣、ぐるりと国土を囲う城壁の如き鉱石は地面に被せる巨大な王冠のようでもある。人の姿は旭影と新月しか見えない。
「此処で暮すって言うが、国民は何處に居る?」
「目の前に居る。此処は人の国ではない。」
旭影は紫陽花の空を背に新月を見つめる。
「此の国は虫達の治める世界だ。私の名は旭影、此の国の王女だ。人の姿をしているがな。」
勉強、お茶会、また勉強?
一、お茶会の時間を一日の内で必ず一度は設けること
二、暴力に訴えた願いは認められない
三、旭影以外の者が武器を所持することが認められない。但し旭影が承認している場合は此の限りではない。
四、常に清潔な環境を保つ努力をすること
呆れるにも呆れてしまう。国の法律が四本しかないことも、内容の第一がお茶会に言及していることも、武力をほぼ持たない環境も。
「人の世界じゃ考えられないが…虫の暮らす桃源郷じゃ人間のルールも常識も関係あるまい。」
新月は与えられた自宅、躑躅ヶ雪の町の片隅に構えられた三角屋根の一軒家の広いリビングで苦笑していた。
「何が可笑しい?」
キッチンで金平糖の刺繍こまやかなエプロンを身に着けスコーンと紅茶の用意をする旭影の銀細工を施された雪雲柔らかき頭髪はくるりと几帳面に纏められ黒のリボンに灰色の金属釦留で真ん中をとめた控えめな華を添えたのは彼女の弟子、ポンムと呼ばれている水晶玉であった。
「本当に其奴が昆虫なのかね。地上で見る生物とは全くの別物だが。」
ソファーに座って待っていろと命じられた新月は旭影の手伝い甲斐甲斐しい鉱石の一種類を大人しく眺めている。
「其奴、ではなくポンム。虫達は本来故郷では鉱石の姿をしている。だが人間の世界へ訪れる際には生れつきの姿ではなく着物を被る。貴殿が見慣れている虫の姿形は虫が着物を纏ったものだ。」
「何故着物を身に付ける必要が?」
「人間が衣服を必要とするのと同じ理由だ。」
旭影の簡潔な説明の後、ポンムが此方を見ている(らしい)。今日会ったばかりで声を持たない鉱石の表情など分らないし理解出来る筈無いが、自分が今ポンムに馬鹿にされていることは何となく感じる。砕いてやろうかこの野郎。
「新月殿。」
焦茶木目の滑らかな丸テーブルに白梅色の絞り戯れるテーブルクロスをシワ無く敷くと、小花や小枝を誂えた銀食器、ソーサー・ティーカップ・ティースプーンを並べる、丸い硝子のティーポットには初心者向けのさくらんぼティーがストレートで淹れてあり、机に置くとマカロンの形したティーコゼーをもふりと被す。弟子の運んだスコーンとサンドウィッチのお皿を一枚たん、一枚たん、と三つ並べて旭影とポンムは着席した。
「どうぞ此方へ。お茶会へこれまで参加されたご経験は?」
彼女に手招きされ、重い腰を立たせお茶会の席にストンと従う。準備されているのを最初から見ていれば、此処迄されて無下に断るのも何となく気が咎めたし。
「嫌…誰かと食卓を囲むのは……」
しまった。黙りこくってしまった…?彼の哀しい過去を思い起こさせてしまったかもしれない、あゝ、父様から注意されていたのに、質問はよく考えて相手を傷付けないものを選びなさいねと…ポンム、告げ口はせず黙っていてくれないかな…と横目で弟子を盗み見たら驚いていた、彼女の視界には新月殿。
手掴みではあるけれど食べ物を食べている、丁寧に、涙を流しながら。
ポンムとそっと目を合わせて頷いた。今は、お喋りは一寸お休み、それが良いよね。
おまえは愛されて生まれて来た。捨て子だったからと言って負い目に感じることは無い、堂々としていなさい。
愛されていたのなら如何して道の側溝に捨てられていたの。
其処にしなくてはならない止むに止まれない事情があったのかもしれないよ。
邪魔だったから?死んでも構わないからあの場所を選んだのかな。
違うよ新月、そんな惨いことを思う親はいないよ。
嘘だ
だって貴方も置いて行っただろうが
食事は嫌いだった。義父とは毎食一緒に食べるのが習慣だった。だから一人になってから食事をすると否が応にもあの人の笑う顔を思い出す、それが嫌でバランス栄養食しか摂らないようにした、きちんとしたありふれた食事はもう十年以上経験していない。
サンドウィッチと、スコーンとか言ってたっけか。見たこと無い焼き菓子に手を伸ばして味わう。バターの甘さとブルーベリーチップの甘酸っぱさがクセになる。気付けば自分に用意されていた分は全て平らげていた。
「お口にあったようで、何よりだ。」
紅茶を啜り微笑む旭影。そのしなやかな肩で弾む水晶玉。地獄にしては穏やかすぎる。それとも此れから食われ続ける羽目になるのか。
「俺をどうする気だい。」
「どうするもこうするも、此の家で暮らしてもらいたいだけだ。暴れてはくれるな。墓をまた増やすのも手間だからな。」
「殺さないのか。」
「貴殿の歪んだ趣味に付き合う心算は無い。痛めつけられて悦ぶ男の理解者は此処にはひとりもおらんぞ。」
「いや、いや、そうじゃあなくて。俺だってそんな性癖無い。勘違いするな。」
「それからもう一つ。此の場所は地獄ではない。」
心を読んだのか?
「読唇術は使っていない。」
読んでるじゃないか。
「地上からやって来る者を私達ははぐれ者と呼んでいる。此の国には以前はぐれ者がちらほらやって来てな、貴殿が初めてではないのさ。其奴等は共通して国を地獄と勘違いしていて、中には大層暴れまわった酷い輩もいた。」
「俺より先にも似た奴がいたのか。まあ確かに人の道を外れて散々した奴が楽に死ねる訳も無いし、平和な場所に連れて行ってもらえる理屈も無い。先達が暴れるのも全く理解出来ないとは思わないがね。で、そんなはぐれ者達を貴女が始末しているッて言かな。」
「察しの良い者は嫌いではない。理解しているのであれば大人しくしていろ。私の大切な国民達に恐怖を与えてくれるな。」
「虫でないから俺は国民とは見なされないのかい。」
「見目の問題ではない。正式な国民には未だ到っていないのは来たばかりのお試し期間だからだ。貴殿が国に相応しい性質を持っていると判断されれば其時は快く迎え入れるとも。」
言い終えたら旭影は新月に一礼を施し椅子から立つ。肩に乗る弟子にかろく微笑み家主に背を向けるとそのまま扉を開けて出て行った。
地上では所詮死んだ身だ。もう死んだのであればいつか死ぬと神経をヒリつかせる必要も無いから旭影の要求に従うのも良いだろう。
「先ずは紅茶を一人で淹れられるようになって、お茶会のアイテムも選べるようにならないと。…あの戸棚の中の名前、一通りは把握しておかないとな…」
テーブルのお茶会セットをシンクに運び隅々迄洗いつつも大きな戸棚に目を遣った。イチョウの樹で誂えた大きな戸棚には、食器の他にも茶葉の缶々やお菓子の材料や道具類がぎっしり。
実は此の戸棚の中には旭影の書いた紅茶・お菓子のレシピが冊子とは異なる形式で隠し混ぜられているのだが、新月青年には見つけられるだろうか。
繭
「国王陛下。」
ガーネットに頭を垂れる。玉座には国王と琥珀の女王陛下もあられた。
「本日地上から降って来たはぐれ者ですが、今のところ害はありません。ですが直ぐに正式に認めるには尚早かと。」
「旭影。其方は彼が悪い存在だと思うか?」
父として尋ねる声は威厳を消して娘に問う。
「命を奪う事自体に抵抗も躊躇も一切無いように感じました。寝台から起き上がる前、意識が戻ったことを隠して現状を探れるような男でしたから。あの年齢であそこまでの慎重さなら、地上では手練れの狙撃手をしていたのではないかと推察しております。」
「旭影。はぐれ者の、新月さん、御本人は何と仰有って?」
母も夫と同じように問うたが、娘の姿勢は変らない。
「過去をひた隠し、にする姿勢はありませんので、此方から出自や職業を質問すれば多少返してくれるものと思います。」
娘ではなく国防将軍の報告を終えると旭影は二人に再度深く一礼する。そして王室を他の言葉無く出て行った。ガーネットと琥珀は向こうから閉められたアンティークの木の扉を見つめて同時に溜息をついた。つかずにはいられない。
「お茶会の準備を後ろにこっそり控えさせていたけれど、今日も空振りでしたね、貴方。」
「あれではどう見ても業務報告だ。親子の会話とは…言い難い。やはり、姿形が我々と全く異なるのを傷だと信じ続けているのだろうか。」
無理もないであろう、二人の胸中は察するに余り有る。旭影は産声を上げた日から両親の前で碌に笑った試が無いのだから。恩義を抱きすぎた弊害かもしれない。痛ましいもどかしさを今日も抱えつつも、琥珀のお妃様はどことなく微笑んでいるように見える。ガーネットの王様は長年連れ添う愛妻の表情にはてなを浮べた。
「しかし、どうしておまえは嬉しそうなのだい?」
優しい男性が女心をまるっと理解出来ている訳ではないと知っている女王は可笑しくって楽しそう。
「貴方、良い王様なのに今一つ乙女心には疎いのね。」
あの子があんなに夢中になっているのに、ヒヤヒヤする素振も無いなんて。本当に気付いていないのかしらと内心呟くもやっぱり夫は分らない、小首を傾げてまあ何と可愛らしい坊やだこと、もうお爺さんに近い齢なのに。
「暫く様子を見てみましょう。きっとあの子は今にすてきに成長しますから。」
「当然だ。私とおまえ、そして国民達に愛されて育ったのだから、立派な娘になるだろう。もう充分に立派な良い娘だとも。」
王の言葉にまた女王はふふふと笑った。
そんな両親のやり取りなぞ露知らず、謁見を終えた旭影は服の袂で大人しく待っていたポンムを肩に乗せる。
「国の法律の説明はしたけれど、それだけで静かに暮らせる確証は無いわよね。それにあの人、紅茶の淹れ方も、茶葉の選び方も、道具の選び方も下手そうだもの。仕事に忠実なのは褒めたいけれど、地上と此処ではそもそもの職種が違いすぎる。穏やかな生き方を望まない人に平穏な生活は難題よ。うん、やっぱり隣に仮住居を建てて監視と補助をした方が正解だと思う。ポンムはどう思う?貴女の意見も聴きたいの。」
城の外へ近付く程に足が速くなり早口になり鼓動が乱れている。ポンムは師匠が彼女の身体的な変化が全くの無意識であるのをよく理解していた。だから自らが何を提案すれば良いのかも当然分っている。
「監視役とは御苦労なことだ。ところで、気になっていたんだがな、おまえの弟子、ポンムは何の虫なんだ?」
テーブルには苺のドライチップを交ぜたスコーンと山盛りのクロテッドクリーム、お皿は菜の花が散る白いお皿。青いリボンがちょこんと飾る銀食器達には砂糖を含めないカモミールのハーブティーが湯気柔らかにひらひら手を振り微笑ましい。花畑でのピクニックには草木涼やかな色味のテーブルクロスが丁度いい…再び新月の自宅を訪ねた師弟はリビングの光景に一寸固まる。
「レシピなのか分からないが、戸棚の隙間に白いレースの刺繍が隠れていた。此の国ではレースが紙や本になるのか?文字が要所要所に刻まれていたのを頭の中で繋ぎ合わせたら菓子や紅茶の作り方のような文が浮びあがったから、一先ず其の通りにしてみたんだが。」
材料は戸棚に揃ってたしなと気楽に付け加える新月は旭影用の椅子を引いた後、自分の席に座った。
「で、ポンムは何の虫なんだ?」
チェロの弓をこするような音色の声に二人はハッと正気付き、旭影は軽く咳払いしてから着座する。
「ポンムは蛾だ。まだ成虫になれる段階ではないから繭の状態、だから此処では水晶の形をしている。」
「成虫になったら大きな柱にでもなるのか。」
「否、蛾は成虫になったら貴殿の知っている姿になる。鉱石にはならない。寝台から出てカーテンを開いた時、城壁に留まる蛾達を見たのを憶えていないか。」
そう言えば、羽の模様や色こそ珍しくはあったが、一般的な蛾の姿を最初に見たな。
「私達の文化では蛾は守護者なんだ。生命を守る者として大切に尊ばれている。だから新月殿、蛾をないがしろにするのは御法度だ。外に出掛ける時は気を付けなさい。」
「法律に明文化されていなかったのは、それほど当然・自然な信仰だからなのか?俺達人間が息をするように。」
「虫達は生れた時から既に仰ぐものを知っているらしい。」
「旭影は?」
「何。」
湯気が蓋に重なり支えきれず雫となる。香りも味も通さない硝子のティーポットの中では音もしない。
「おまえは、蛾を大切にする遺伝を予め持って生れたのかって訊いている。虫の姿をしていない奴でも信仰心は抱けるのか?」
「私が生れ乍らに物語を知っていたのかは分らない。貴殿も共感出来るかもしれないが、人は赤子として息を吸った記憶は霧雨よりも不確かだ。だから生れた私が何を知っていて何を知らなかったのかは分らない。
それでも、両親から蛾への信仰心を教えてもらった時、心の中に違和は無かったむしろ、懐かしいと感じ安心した。すんなり受け容れられたんだ。何も土台を持っていなかったのであれば、懐かさを感じることは無いと思う。」
「懐かしい、か。」
「新月殿には何か懐かしいと想えるものはないのか?」
一瞬明滅したのは育ての
「無い。強いて言うなら…此処に来る前に愛用していた銃が恋しいよ。」
「銃は…渡せられない。私は貴殿に武器の装備を許可していないからだ。」
「でも一人で血を浴びるのは苦しいだろう?貴女以外は無邪気に輝いているのに、一人だけ水底のような瞳をしているじゃあないか。俺なら旭影の背負う荷を一緒に背負ってあげられる。…もう感づいているとは思うが、俺の地上での仕事振りはかなり上等な評価を貰えていたよ。おまえの実績に引けを取らん程度にはな。」
「新参者に国防の役をいきなり預けると思うのか。」
「だから傍で学ばせてくれたら嬉しい。貴女は俺の見張りも出来るし、俺は信頼を築いていけることが出来る。損な話では無い筈だが、一寸考えてみてもらえないかい?」
紅茶はもう冷めていた。
「良いだろう。国の案内もいずれはせねばならないし、国民達への挨拶や礼儀も教えたい。」
「じゃあ、上官殿とお呼びすれば宜しいか?」
「虫達の世界は基本的に横社会だ。敬称も敬語も必要無い。貴殿がどうしてもしたいのなら咎めはしないがな。」
スコーンをそのまま食べる。
「そうかい。じゃあ旭影のままで呼ばせてもらおう。貴女も気軽に接してくれると助かる。堅苦しいのは苦手でね。」
今度は半分に割った片方にホイップクリームをたっぷり付けて。
「そうか。では改めて宜しく、新月殿。」
ハーブティーを啜る。
月下園
長い髪の毛は憧れだった。蛾は誰しも豊かで美しい髪を持っていると、幼い御伽話で聴いたから。姿の違う私の為に国は人が主人公のお話を澤山編み出してくれた。其等の中で蛾は、常に神々しく描かれていた。恐ろしくも美しい、寂しく哀しい女神像、憂いは長い睫毛と髪型によく映える。羽を持てない代りに私は髪を伸ばした。
「私は貴女が羨ましい。」
ポンム。私の可愛い弟子であり、優しい騎士。頬を撫でて霖雨を拭ってくれる、本当は私などには勿体無い女の子。貴女はきっと、すてきな成虫になるのでしょう。だからお願いどうか、
「私のようにならないで。」
墓の前で膝をつき項垂れる。墓の後ろにも墓、墓、墓。傷だらけの身体、血が取れない掌。痛くて痛くて堪らない。
紫陽花の空は黙っている。優しい命を産む時も、おぞましい悪人達を墮とす時も。喜びの笑顔が響く時も、恐怖の悲鳴が泣く時も。自分の愛してやまぬものは他者の気にも留めないものになる。
一番最初はカナブンのパーセ。怖くて身動きが取れないから暴れる相手の都合に適った。パーセだけが固まってしまったのではない、生れて初めて目の当たりにする暴力と道理を弁えられぬ者、あの日硬直しない国民などいなかった、血の凍えた生命などいなかった。恐怖で身じろぎ出来ないものは無抵抗の餌と見なされる。次は、ヒメユリトンボの暁。そして侵入者は息絶えた。私は自分の腰に差していたナイフが果物以外も刺せることを、人間の血が赤いことを震える手で初めて知った。
誰も咎めなかった。むしろ深く心配してもらった。パーセと暁を白躑躅の棺で包み瞑色の菫が沈む月下の泉へ送った後、父と母は臣下を連れて月下園へと人間の埋葬をしに行った、私は連れて行ってもらえず、城壁の蛾達に預けられた。
皆、みんな傷を負っていた。破片は国土のあちらこちらに散らばっていたし、蛾の翼も欠けていて満足に飛翔することもまゝならない。誰も殺す術を知らないのだ、此の王国の虫達は果物に接吻し草の抱く白露を飲んで生きるのに。果物を切るのは私だけ、草を引き抜くのも私だけ、そして襲撃犯を殺せるのも私だけ。
与えられた役目は、人間を、悪人を殺すこと。
愛する国よ、美しい国民達よ、慕ってやまない両親よ、涙に仰ぐ月の使者よ、ポンムを託した想いも、察するに難くはありません。
「旭影。」
武器を身に付けたまゝ誰かの前で転寝するなど、地上ではまあ考えられない。呼んでも起きそうにない、そんなにハンギングチェアが気に入ったのか。葡萄の蔓で簡単に作れるとレース編みの本の端に示されていたから一つ試してみようと思ったのが存外上手に出来た自覚はあったが、此処迄人を無防備にさせる代物とまでは予測がつかなかった。もう姉弟子は自宅に帰ったぞ。
「おい…」
再度声を掛けたが変らない。肩を搖すぶる程度なら構わないかと言い訳をし身体に触れても目覚めない、両肩を大きく搖らしてもあの瞳は固く閉ざされて睫毛にそよ風ほどにもなっていない。
血が凍る。名前を呼んだ心算の声は掠れすぎて音を為さなかった、もう一度喉を震わせても息が続かない、寒い。溜らず温もりに縋るように抱きしめる。大きな自分の鼓動が動脈の氷を割らんと暴れている、幼い叫びがこめかみに伝い頭を痛めつけて明滅する疼痛は心臓をわし掴む。
また、捨てられた
「起きている。」
自分より柔い両肩を握ったまゝ顔を見る。彼女は俯向いた顔を上げようとはしない。酸素の感覚を思い出し始めた頭はまだ通常の会話をするに到らない。
「こっちをみてよ。」
旭影はふるふると首を振る。
「なんで?」
「今、夢を見ていた、昔の夢。だから今、みっとも無い顔をしている。だから貴殿には見せたくない。」
「それでもいいから、ねえ、俺を見て。」
手の位置をずらし彼女の両頬に移動させて持ち上げる。光を知らぬ瞳と光を捨てた瞳が水晶の内側で重なりあえば月の生れぬ創世以前、寂しい潔白の大地の光景。娘の両手が青年の両手に触れると、もう彼には心が通じて互いの手と手を握りしめる。瞳は決して逸らさない。
「怖い夢を、見ていたのか?」
「えゝ、とても、怖い夢。貴方も、見ていたのでは?」
「うん。君と内容は違うだろうけれど、同じくらいに怖かった。」
新月さん、と気掛かりな表情と共に呟いた言葉にもう大丈夫だよと少し頬を緩めて静かに答える。
「此の国は、地上なんかよりも遙かに美しい。俺には勿体無いよ。」
「私にだって、勿体無い。王女としてしっかりしなくちゃいけないのに、気後ればかりしてしまう。」
「それでも、守り続けるんだろう?」
「これからも止める心算はありません。」
優しい場所を優しい場所で在り続けさせる為に、容赦はしてはならないのだ。
「止めなくて良いんだよ。俺も一緒に歩くからって言ったろう?」
貴方にそんな事させたくない。
「一人で背負う重さじゃない。人間は鉱石の身体を持てないくらい脆弱なんだから。」
貴女に甘えてほしいんだ。
新月の指が旭影の鋼の檻をほどいていく、硝子の仕切りをほどいていく、そして玻璃の心に接吻をする。
外は久しぶりの雨の夜。女神達は祝福を鱗粉に込めて星くずを降らし月下に舞う。
開花
ポンムは甚だ不愉快である。ポンムは姉弟子だ、そう、ポンムは新参者の先輩なのだ。それなのにあの無礼者ときたら、ポンム以上にお師匠にくっ付いているではないか。距離が近い事も当然不躾であるが、弟弟子としても罪状は他にもあるのをポンムは知っている。
「ポンム、今日は北の方角に行きましょうか。」
お師匠の言う通り。ふりふりと丸い身体を弾ませて特等席に着座した。旭影の方に乗って良いのはポンムだけなのだ。もっと言えば、お師匠のお身体に触れるのはポンムだけが許されていたのだ。
「旭影、バスケットなら俺が持つ。」
なのになのにそれなのに!あの弟弟子とはお師匠と手を繋いだり、腰に手をまわしたり、頭を撫でたり、頬にキッスをしたり挙句の果てには抱きしめたり!けしからん、姉弟子であり一番弟子であるポンムを差し置いて大好きなお師匠に馴々しくするなど言語道断。伴侶でもないくせに何様のつもりであろう、お師匠の優しさと寂しさにつけ込んで不埒な奴め、今日こそポンムが礼儀を教えてあげるのだ。一番弟子の威厳に驚き慄くが良い。
ポンムの企みなど知る由も無い新月は、もう此処での暮らしにかなり馴染んで来ていた。お茶会の準備の実力をめきめきと伸ばし、旭影からもお墨付きを貰うくらいに上達していたのだ。
「何が向いてるのかは分らないもんだな。」
「きっかけが無ければ糸同士は交差しません、貴方の隠れた得意が此の国で見つけられて良かった。」
国の一番北方には氷雨の洞穴を呼ばれる一角があるらしい。そこまでの道中、すれちがう国民達への挨拶も慣れたものだ、軽く手を挙げたり会釈をしたり黙礼したり、それぞれの礼儀も弁えている。
「氷雨の洞穴はどんな場所なんだ?俺達の居る躑躅ヶ雪町のような住宅地なのか?」
「氷雨の洞穴には誰も住みません。住居としての役目は持っていないのです。氷雨は博物館や美術館のような場所として認識されています。」
「地上でもよく訪れたよ。尤も展示物ではなく展示室の方に用が有ってなんだが。連絡の際によく使っていたよ。」
月に一度は定期報告をしなければならなかった、例え意味の無い行為でもする事が肝要で、し続けていれば意味は追って来る。雇い主の存在を認識させ勝手を許してはいないと暗に示す為の其は人の出入りが盛んで静かな空間が好まれた。
そんな場所連れて行ってもらった事は無くて
「絵画や遺跡はお嫌いですか?」
「嫌うほどの素養も無いさ。仕事が忙しくて趣味の時間に手が回らない訳でも無かったんだが、どうにも興味が持てなくてね。旭影はよく洞穴に行くのかい。」
「氷雨は墓地へ続く唯一の道です。」
細い髪の毛が頬に掛かる。こまやかな影が瞳を照らした。
「墓地…人間のか。」
「陛下達は私に其処へ訪れてほしくはないみたいですけれど、時々どうしても行かなければならない気がして、それで通うのを止められないのです。お二人は黙認してくださってはいますが、本心は晴やかとは程遠いでしょう。」
いっその事命令してくれた方が行かないと、あちらもお分かりではあろうけれど。禁止した方が、抑え込んだ方が人間は案外従うと御存知であろうけれど、命令も抑圧も一度も受けた事が無い。だからますます勿体無いと感じてしまいそうになる。
陛下の望むように生きられているだろうか。両親の望みはきっと私の望みではない、と口に出しても割り切れない、今日迄大切に大切に包んでくれているからこそ切り離せないしたくない。私と親は違うのだから私の思うように生きていいよろよく聞く決着は所詮頭の中でだけ、表面上の一時しのぎ。
「俺は親の望みを知っていたよ。でも望まれた姿とは正反対に向かう片道を選んだ。親不孝だと雇い主からは笑われたよ、でもどの道を選んだところで、選ぶ根元の理由は親からの願いだ。其に順じようが反発しようが親を想っているのは共通している。だから俺は親孝行な義理の息子ですよと言い返した。」
「義理の息子…?」
「殺し屋としての情報しか与えなかったな。旭影、俺は出産直後どしゃ降りの側溝に捨てられていたんだ。其処から拾われて、義理の父親のもとで育った。」
「育てのお父様が殺しを生業をしていたのですか。」
「そうじゃない。政府に反抗はしていたが暴力や血とは無縁の人間でね。虐待を受けた経験も無い。でもな、あまりに真直ぐ過ぎたんだろうな、身を滅ぼす情熱の恋を知ったら相手の女と二人で出奔しちまった。後は政府に引き取られて、奴等の忠実な手先になった。」
「汚れ仕事を引き受ける決断は、政府への恩を感じての結果?」
「まさか。俺は健気の対価で銃を相棒にしない。相性が良かっただけ、狙撃手としての資質を持ち合わせていたってだけで、何かを守ろうだとか誰かの為に決めた道じゃあないのさ。」
旭影は新月の横がほを見つめた。自分よりも上背の高い男性で、童顔でもない筈だのに幼く感じた第一印象を思ひ出す。そうか、だからあんなに必死になって自分を見てと言ったのだ。
何て声を掛けたら良いのだろう。此の国で捨て子など起きた事例は無いし、私には親に置いて行かれた者の心情が分らない。自分も同じだと頷く事など出来ないし、見知らぬ者達を頭ごなしに否定するのも後ろ暗い。かと言って彼を哀れんでも新月は喜ぶのだろうか。同情は時に相手の心を傷付ける、柔らかな葉先でズブズブと身体の奥深く刺し沈めていく行為になるかもしれない。けれど苦しい、向き合いたくない息が詰るような苦しい過去を教えてくれたのだ、一切触れずに今此処に居る彼を無条件に肯定したところで真実優しい対応になるのだろうか。
ぐる、ぐる、汁を吸って膨らみ続ける車麩にじゅわりじゅわり首を絞められてしまいそう。人間と話す時はこうも息がしづらくなっていくのだろうか。もっと貴方と話がしたいのに、言葉も声も絞り出せないなんて。
「でもまあ…ガキの頃の自分にようやく顔向け出来るかな。」
優しい声、穏やかな声、一人ですてきなお茶会の仕度を見事になさっていた日のチェロの弦すゝりなくそのお声。
きっと、貴方の根は殺しに向いていなかったと思います。
新月は立ち止まった。足音が重ならなくなった音に旭影も立ち止まり、後ろを振り向く。新月は瞳孔を細くして白昼の猫のように固まっていた。口元はキュッと引き緊められ眉間は微かに歪んでいる。黒曜石から艶を消した眼球の色は淵より濃い。
「本当にそう思うか?」
何をです、と訊く直前思い当たったのは一寸前の自分の心。
「俺が、無理をして殺し屋をしていたと思っているのか?」
甘くまとわりつく低い声、洞穴の入り口に生える糸杉の地面の影が陽も傾かぬのに背丈を伸ばす、沼の水が五指を広げてじわじわと手を伸ばしているように。底無しの孤独が手を招く。
「新月さん。」
いつもは安心する筈の抱擁が背筋を強張らせる。耳元で囁かれる雪の火が氷柱になって鼓膜を嬲る。端から見れば恋人同士の微笑ましい秘密の光景であるものを、生唾を飲み込む音が一つ一つ増えている。涙を流さない代りに喉元が泣いているのだろうか。もう一度名前を呼んで彼の腕から脱け出たいけれど唇が虚ろに動くだけ。
「おまえなら分かってくれると信じていたよ。」
とろけた林檎の如く染まる新月の両頬。嘗て仕事上相手をした商売女達には一度も見せなかった恍惚の芳しい表情。ブランデーよりも濃い酩酊の薫りに充てられた乙女の白い喉は未だ声を取り戻せない。
何を、私が、分かる、と?
ふっと微笑む新月の唇。
「俺が殺し屋に向いていない人間だってことを。」
日焼けもしない血管淡い首筋に深く顔を埋められて見えた故郷の景色は然程歩いて来ていない筈なのに指を伸ばしても届きそうになかった。
ポンムは激怒した。氷雨の洞穴はポンムのお気に入りの場所である。国を襲った者達の墓場に繋がる唯一の道は雨風を凌げるからとお師匠の服をくいくい引ッ張って墓から此処迄歩かせた記憶は古いけれど色褪せない、やはりあの日からお師匠の心は進めていない、ずっとずっと優しい真綿の心のままなのだ。だから此の男に隙を与えてしまった。
貴様が人殺しに向いていない筈があるまい、恐らく一晩中隣人の悲鳴や絶叫を聞いていても確実に機を覗い続けて獲物を仕留められる類の奴だ、根ッからのスナイパー、お師匠とは似もつかないタイプ。相手の優しさに自ら飛び込み沈み込んで道連れにしようとする一途で陰惨な愛情を大切なお師匠に浴びせられるか、一番弟子は大人しくしない。
銀の横笛の響きが空気を回した。冴えて澄む音に新月と旭影は同時に瞬きをし、振動の出処に目を向ける。
一羽の蛾が牡丹の花弁の翼を細かに擦り合わせている。恰も鈴蟲がするような独奏に二人は固まり蛾を見つめた。その舌には水晶が真珠貝の形に開いている。
「ポンム?」
「ポンムなのか?」
旭影の問い掛けに音を止めるのは新月の声に応じる結果にもなってしまったけれど、お師匠の華やぐ嬉しそうな顔が見られたのであれば気にしない。
「このタイミングで孵化するとはな。」
ポンムはもう繭を作っていたんだ、卵じゃなかったんだぞ。全くこれだからお師匠以外の人間はお馬鹿だな、脳味噌がきっと無いんだろう。
「新月さん、あの……」
言い淀む。まさか心の声が零れただけでなく貴方にも見えてしまっていたなんて、両親や国民の前では有り得ないことなのに。
「いや、君は何も…おまえは何も悪くない。すまない、俺の気がどうかしていたんだ。」
墓に通じる道だと言っていた。暫く離れていた死の匂いに充てられたか?
「…きっと両親は、だから氷雨の洞穴に行かせたくなかったのでしょうね。」
「それは、やはり俺を危険視していたと言うことか?」
「違います。貴方ではなく、此の場所の潜在的な問題なのです。」
「美術館や博物館の立ち位置に相当する場所なんだろう?それが問題になるものなのか?」
「貴方は美術館をどのような施設だとお考えですか。ただ単に古物を保管し修復や展示を行なっている場所だと?」
「そうじゃないのか。」
「私達の考えでは、彼処は、鎮魂の空間です。魂を休ませる慰霊の塔、と申しても良いでしょう。人が産み出したものには必ず霊が宿ります。特に絵画は荒ぶる気質のものが多い。其等を野放しにしないよう収集を始めたのが美術館の誕生なのです。」
死そのものとは言い切れないが限り無く死に近く執念を負う存在。
「へえ、人の世界では聞いたこと無い考え方だな。俺の居た国では或種のステータスとされていたよ。美術館や博物館に行くのは教養がある賢い人間アピールになるから、喧しい奴等も鼻息荒くして必死に訪れていたよ。」
「まあ、興味も無いのに?」
「そう、興味も無いのに。でもそういう輩はすぐにべらべら喋りたがるから一目でバレているんだがな。気付かないのは本人だけ。嫌な体臭と同じだ。」
旭影の碧い鏡の瞳が新月を映す。湖面は波風も立たず穏やかで。それをにこりと微笑んで隠すと、片腕を少し上げてポンムを招いた。
「博物館も美術館と似たような目的なのですよ。此の国では。」
「教えてくれるかい。」
「其は、墓地で話した方が良さそうです。」
黒いビオラの花の門が洞穴の出口、光の中に佇んでいた。
墓
絵画は人が作り出した物。他にも藝術と呼称される部類の物達は人の手によって産まれた謂わば加工品である。人の思いを受けて発光した以上、影を伴うのは必然とも考えられる、故に慰霊を空間と言うのは全くの見当違いな見方ではないようにも思えるから旭影の発言に肯くことも出来るだろう。だが、自然界に最初から存在している者達は如何であろうか。
読者諸君逸り立つな。旭影は其の質問をこそ待っていたのであるから。
「人間は自然の摂理から些か逸れた生物なので、全員が全員当て嵌まる理ではないのですが、自然界に存在する生命は総て意思を持って生まれて来ています。」
「木や石が、心を持っていると。」
「ですから自然に在る物質達を集めて管理する行為は、死体を丁寧に保管し続ける行為と同義なのです。」
「つまりは、墓か。」
紫陽花の空は変らぬが枝垂れつのは此処に於て雪の蔦とは色味水温共に異なる。衣服を貫き肌を濡らす苔蒸した雨はヒヤヒヤと骨身を薄氷の切ッ先で苛む。俄雨には程遠そうな長雨がズキズキと降る中を表情一つ変えずに旭影は門を開けて歩いていく。ポンムは新月の持つバスケットに身体ごとすっぽり隠れ、上から布を自ら引き被った。
何度も似たような道を堂々巡りしているのではないかと不審に思うも、確認し続けている墓碑の名前は重なってはいない。広い国土の片隅に墓だけの空間を設けた理由は弔いの意味でもあるのだろうか。旭影達の国が罪悪感や死者への慰霊を目的として建てたのであれば否定はしないが、その結果国の一部を逸れ者どもに占拠されているような気がしないで無いから不愉快だ。
律儀な鬱屈を肚に据えつつ迷路を歩き続けていると、旭影が立ち止まった。
「此処が墓地の始まりです。私が初めて殺した逸れ者。」
”カナブンのパーセとヒメユリトンボの暁を殺めた者”
水滴がゆっくりと垂れる指先で示された墓石にはこう刻まれていた。
「相手の名前は?」
「身分証のような物は所持してはいましたけれど、必要ありません。当人の名前よりも其奴が誰を殺したかの方が重要ですから。」
一つ一つまじまじと見た訳ではないので確証は持てなかったが、今こうして墓を一つ眺める時間を与えられてようやく頷くことが出来た。やはり地上の墓とは異なり、本人の固有名詞どころか属する一族の苗字すら記録することを許していない、かと言って無縁仏のような扱いもしていない、逸れ者を振り返る時此の国の住民達は「誰々をころしたあの人間」として認識する、つまり、犯罪者は名前を永遠に奪われるのだ。弔いの為、としてではなく死してなお罰を与える為に此の場所を造ったのだろう。
「思っていたより容赦をしない文化なんだな。」
一足間違えていれば自分も此奴等の仲間入りだったのか、と想像するだけで胸がムカムカしてくるようだ。
「でも、全てに容赦が無い訳じゃないと思います。……陛下達も、国民達も、私の墓は造らないと言っていますから。」
「あゝそうか、国民達は儀式に則って泉に送られるから、こういう墓は建てないのだっけ。」
「その代り、亡くなった者の住居を皆で掃除し続けて、亡くなった者の想ひ出話を語り合うお茶会を定期的に開いたりもしています、それが標になるから墓を建てる必要は無いのです。……全うな者達の分は。」
全うでないのは自分だけだ。他の国民達と自分が同じ扱いを受けて良いのだろうか?逸れ者と同じ殺しをした身の私はもう、とっくに此の国の国民の資格に相応しくないのでは?
「部隊の部下達は威嚇までしか出来ないから、侵入者が来たら先ず国民を避難させ威嚇用の数名で相手を逃がさないよう包囲する。それから私が仕留める。包囲する迄に殺される部下もいます。でも此の方法を取ってから非戦闘員の者達が被害に遭うことは無くなったのです。」
「暴れ回る破壊者相手に立ち向かうとは、君等の軍隊は全員優秀だな。」
「勿論。死んでいった者達も全員余さず自慢の部下でしたとも。今でも欠かさず彼等の家でお茶会をしにまわりますよ。」
てっきり旭影だけが侵入者を追い詰め殺しているのかと思ったが、軍も自国を守る為に命を張っていたとは。
「君は随分愛され慕われているんだな、此の国から。
見た目が異なる者への憐れみで優しくしているのだと思っていたが、此の国は地上と違いそうではないと、今断言出来るよ。一人の死者を全員で弔い想い続けるのが此処の国民性だと言うのであれば、旭影にばかり負担を背負わせないよう遺伝子の鎖に縛られたままでも出来得る事をしようと、軍部は動くことを決めたのだ、旭影一人の為に、あの深い湖の瞳の為に。国からそんな対応されて愛されていないなんて言える訳無い。だから、君の墓を造らんのは当然だろう。国民に墓は建てる必要無いのだから。」
お師匠。お師匠は知らないだけで、此処の国民達は全員貴女を同じ民として想っていますよ、私の姉さま方がよくそうお話しているのを私よく聴いていましたもの。城壁の井戸端会議、一寸女神っぽさは減りますが、本当に楽しそうにお師匠のことお話ししていたのですよ、ポンムは知っています、お師匠が国民として愛されて大切に想われていることをポンムは知っているのです、なのに弟弟子が全部言った!姉弟子にもっと敬意を払え。
墓を造る手伝いを頼む予定だった。名前の無い墓石を一つ、墓地の隅の方に置く心算で、来たと言うのに。
「そう、思いますか。」
このままでは搖らいでしまいそうになるではないか。だって私を私足らしめているのは
「人の姿でなくとも旭影は旭影だろう。」
何てこと無い事実だ。地上で仕事をこなし続けて分かった事、殺す相手が例え人間でなくなったとしても俺は殺す。標的の心臓は変りはしない。
「表皮なんて変っても旭影の心臓は変らない。自分が人間だから、殺生をしなければいけない姿だからってご両親やポンム達から一歩引き続けることはしなくて良いと思うがね。」
いいの、かな。
「これでも得心が行かないのなら、俺が正式な国民になるまで待っていてくれ。逸れ者でも認められれば、君も自分を許してあげられるだろう。」
あゝ、此れが、惚れた弱味と言うものなのか。
種
墓地を呆気無く出て氷雨の洞穴を通り抜け、見慣れた草原に戻る。ポンムがバスケットから飛び出し早速お茶会の仕度をいそいそと始めだす。
「今日の紅茶はアールグレイのストレートか。だがシトロンクリームをたっぷり練り込んだフィナンシェによく似合っている。偶にはシンプルなお茶を味わいに戻るのも悪くない。」
人間の世界ではストレートティーはごくありふれた紅茶の種類だったが虫達の世界ではあまり嗜まれる機会の滅多に無いものだった。此方では果物と合わせて抽出するのが一般的なので初めてストレートを淹れた時旭影達に不思議なものを見つめる視線を送られた記憶は比較的新しい。
「貴方の故郷の味ですか?」
「故郷と呼べる程愛着も執心もしていない。だが、些か懐かしいのは否めないな。」
「懐かしい、其は良い感情ですね。私達の文化でも懐旧の情は大切に扱われています、ほら、此処から小川が見えるでしょう。あの清流は紺青の玉の城壁に添って国中を流れているのです。行き着く先は二箇所、一つは亡くなった同胞を送る儀式をする月下の泉です。」
「確か瞑色の菫が沈んでいるってポンムに連れて行ってもらって実際見たな。」
「えゝ、よく姉弟子の教えを憶えていましたね、弟弟子としては大変ハナマルですよ。」
「時々師匠モードが出るとポンムがやけに嬉しそうなんだよなあ。そんな時に恋人として接するのは何とはなしに畏れ多くて…だから喜んでんだな姉弟子は。」
お師匠、もう一つ小川の行き着く先をまだまだ無知な弟弟子に教えてあげてくださいな。
ふふッと相変らず微笑んだまゝ、此方へと言ってお茶会のセットもそのままにゆったり歩き出す。
「氷雨の洞穴の近くにあるので、すぐ行って戻って来られる距離です。」
ハミングでもしそうな穏やかに上気した頬で花咲く草原をくるりと時々回転しながらかろやかな足の動き。長い髪はふわりと風になびき空気を吸ってあまく膨らむ。辿り着いたのは水浴み場だった。
蛾や鉱石が羽を小流れに浸した後の水面に、砂金のようなチラチラと光る小さな石が混ざり、再び国中を流れてゆく。
「旭影、この砂金のような物は何だ?彼等の翼から出ているようだけれど。」
「それは、彼等それぞれが集めた物語の種です。」
「物語の種…?」
初めて聞く未知の単語だが、その言葉自体に嫌悪感も危機迫る感覚も起こらなかった。どういうものか訊ねてみる。
「物語の種は此の国の蛾や本来の姿の虫達が生活する事で彼等の翼に少しずつ重ねられていく月の欠片が原材料です。月の欠片が層を編むことで物語の種は生まれます。そして水浴び場で種を小川の流れに送ることで物語を生む国土と成すのですよ。」
此の国の物語を読ませてもらったこともある。どれも優しく穏やかな作品で地上とはえらい違いだと驚いたのもつい最近、ミステリーとか無いんだなと呟きそうになったのを堪えたのも同じく。
雨と、言葉と、植物の国。虫は本来の美しい姿で穏やかに暮し花開いた物語にキスを贈り糧とする。そして温もり薫る焼菓子や果実を絞ったブレンドティー、本当に地獄とは程遠い王国。清流に指先を浸し涼やかな感覚に溺れていた新月。
ザクリと刃物が何かを切る音がする。釣られて見れば、旭影が新月に背を向けて川辺に座り、長い毛先を水に浸けて一気に短く散髪している姿があった。絹のような髪束は小さく砕けて削られて小さくなって、銀色のアラザンのように溶けていった。
ポンムと新月は彼女の背中を見つめている。もう水辺には三人しかいない。後ろからの視線に耐え切れなくなったのか、先に旭影がまだ振り向かないまま話し始めた。
「憧れていたのです、長い髪に。けれど、もう良いのです。」
振り向く。自棄を起したにしてはあまりにおっとりと無防備な、ヤケくそでナイフを手にしたのでは斯様な微笑みは紡がれまい。
ポンムが擽るように髪の毛に遊ぶ、凡そ一番弟子の態度とは思われないがこの師匠が咎める筈も無い。新月は浅い水面に反射する師弟の姿を眺めていた。こんなに穏やかな心持で過ごすのは懐かしいと称するには遠過ぎた。
調理
主人公は、若い娘と青年。二人は互いの一族から望まれていない関係になる。大勢から逃げる二人。その娘の腕には赤ン坊が抱かれている。夫は捕まり、妻ももう追手から逃げられないことを悟った。忌み子と呼ばれたこの坊やは捕まればどんな仕打ちを受けるか分からない。母親は泣きながら子を側溝に隠した。大雨の中親と子の指は濁流に距てられていく。子供を流す水流に無事であれと形見の涙を零して、娘は捕らえられた。だが、子の行方は今でも見つかってはいない。
子を訪ねて母親が旅をする。きっと生きている、必ず生きている。あの日逃がした我が子は何處に流れ着いて生きているのだろう、それを探す旅が今始まる。
「あゝ駄目だ、却下。」
硝子ペンで引いた二本の線が文章を埋めていく。アイデアは既にどん詰まりなのは誰?
物語は王国の住民ならば芳しい息を吹くように生み出せる。しかし新月は未だ逸れ者であり正式な国民として認められていないので、彼は物語を編むのに自らの分析をしなければならない。自分の分析とは当然のようで当然でなく、容易なようで容易でない作業である。己の中に住まう星の数ほどの自分自身の声を聞き取り理解しなければならないのだから。
「親になった経験も無いのに親の心情を描けるのか?」
「親になったらどうするかを考えて描けば良い。作家は男性でも女性が主人公の話だって幾らもあった。」
「自分の願望を登場人物に押し付ければ良い。そして自分の嫌悪する存在は醜く描いてやれ。」
「お前は何を願うんだ?」
「お前が憎むものは分かっているだろう。」
「正直に書き綴るのが物語だと言えるのか?そんなものはSNSの投稿と何の違いがある、下らない。」
「お前が許せないものは何だ?許したいのか、許したくないのか?」
「お前の好きな単語で描かなくてはつまらないぞ。ただ辻褄を合わせる文章なんかAIでも作れる。」
「お前は何が好きなんだ。愛して止まないものは何?教えておくれよ。」
「お前が譲れないものは何?死守したいものは?」
新月は地上世界では無口な男だった。自分の中の新月の声も一人二人ほどだったのに、此処に落下して眠っていたのかやる気の無かったのか分からないが自分が自分の中でどんどん起き始めて、物語の作成に取り掛かる時はとても、とても、うるさい。
「小説描くのがこんなに喧しい作業だったとはな。黙々と執筆する裏では常に瞬時に自分の声に答えていた訳か。静かな場所を望む標的が多かったのは、音の少ない環境の方が声を聞き取りやすくなるからか。」
手を止めてソファに寝転がる、リビングの電灯は点けたまゝに。旭影とポンムが来る迄後二時間は余裕がある。疲れた。このままひと眠りしよう。
よく眠れるようになったのは仕事を始めてからだったかもしれない、幼少期は頑固な不眠症だったからいつも同級生から不気味がられていたもの。目の下に隈があって身の丈には少し大きい着物。教科書で出て来た”だんまり入道”の見た目にそっくりだと言われてから学校へ行く事を何だか申し訳無いと感じ始めた。
何が申し訳無いんだ?
だって皆を怖がらせてる。
毎晩眠れなくて苦しんでいるだろうおまえだって。他の子達はよく眠れているからおまえの苦しみが理解出来ないのさ。
理解出来ないから怖く感じてしまうの?
そうだよ、人は分らないことや未知のものに恐怖を抱く、生存の為の防衛本能が働くからだ、恐怖を感じることそのものは悪いことではないんだ。
でも、情け無いね、一寸だけ。
人は格好良くない生き物なんだ、だからヘマもするし余計な事だってする。人は情け無い生き物なんだ、だからお前を捨てたんだ
「新月さん。」
ぼやけた逆光の光の視界でも誰だか分る。もう一度瞬きをすると想ったとおりの相手の顔が線こまやかに鮮やかに呼んでいる。
「執筆中に、居眠りをしていたのですね。」
顔色が健康的でないのは王国に落下して来た日から知ってはいた。でも今のは普段より一層深く窶れている。転寝は人間に碌でも無い過去を見せる場合もあると、人体について書かれた医学書に載っていた。
「お水をどうぞ。」
硝子のコップに注がれた飲み水を一息に呷る。動脈と気管を強制的に冷やす寒気の後に舌がミントの一葉のエッセンスを感じ取る。息を吸う、息を吐く、頭痛と吐き気は流れ散り全身の痛みは引く波のように徐々に去っていった。
「君達が来る迄二時間あったから、一眠りしてからサンドウィッチを作る筈だったんだ。時計を…今何時だい?」
ソファーの肘に置いた片手を支えとして立ち上がり、壁掛けの振子時計を見ると。思ったより爆睡していない。
「なあ旭影、君達との約束の時間にはまだ一時間と三十分あるじゃあないか。どうしたんだ早く来るなんて珍しい。」
「折角ですから、私もお菓子を作ろうと思いまして。いつものように自分達の住居で静かに待っていても良かったんですけれど、あの、今日は何だかお手伝いに行きたい気持ちが抑えられなくて、お手伝いに来てしまいました。貴方の大切な準備の時間に割り込んでしまってごめんなさい。」
謝らなくてもいい、嫌うものか、むしろ此方が救われたものを、遠慮することなど無いのだから。
「謝らなくて良い。」
「でも。」
「早く来て手伝ってくれることは謝る行動じゃない。お茶会の準備をするのは確かにとても楽しくて嬉しくて堪らないのは事実だがね、だからこそ二人で準備すれば喜びも二倍に膨らむだろう。」
二人で肩を並べてこねこね。ポンムには残念乍ら地団駄踏んでも真似出来ない、旭影と新月だから出来る調理。
執筆
全てを思い出せるとは信じていない。けれど、何かの拍子にフト思い出すことがあるかもしれない。そしてその忘れていた記憶の中に、とても大切な事が含まれているかもしれない。そうしてペンを手に取り始めたが、簡単に行くものか、何度も何度も途中で止めにしてしまっている。物語の中に自分の生立ちへの祝福を求めたが、描けない。理想を並べ記しても、嘘くさくて続けていられなくなる。
「向いていないのかもしれないな。」
「物語を紡ぐことが、ですか?」
旭影の瞳を見返してフッと苦笑う。向いてないものは仕方あるまい、労力を掛けても疲れが募るだけで生き乍ら埋められてしまいそう。
「なあ旭影、此処は何處なんだ?」
「私の故郷、蛾を女神と信仰する王国ですよ。そして此の家のある地域名は躑躅ヶ雪町。」
「そうじゃない。此の場所、王国自体が何ものなんだって訊いているんだ。地下に在る天国か?地獄にしては優しく穏やかすぎる、それとも実際の地獄は喜びを与えるだけ与えてそれから取り上げるものなのか?
俺が地上で死を感じた時、人気の無い路地に在る黴の生えた空き家を出た直後だった、隠れ家の一つだ、其処の周囲に紫陽花なんて咲いていない筈だったんだよ。なのに俺は撃たれたら紫陽花の花束に埋れ始めていた、あれは此の国の空だったんだろう、此の空間は一体、何處なんだ。」
お茶会の後片付けを済ました部屋の寝台でポンムはくうくう眠っていた。羅針盤が透かし彫りされた硝子のテーブル、北極星と南十字星は眼光鋭利に互いを見つめる。
「亡くなった国民は送られるのだとお教えしましたが、まだ続きがあるのです。送りの儀式を終えた後、此の国で命を落とした虫達は地上の世界で服を着た姿で目を覚まします。そして地上での寿命が尽きたら再び国で目を覚まします、本来の鉱石の姿でね。私達にとって地上の世界とは、再び故郷で生を受ける為の通過地点、修行の場なのです。そう考えてみるのなら、此の国は地上で亡くなったものが再び地上で生きる為の通過の場、修行の為に来た土地だと捉えられますが。」
「つまり、此の国で一度死んだら地上で目を覚ますと言うことか。姿形はどうであれ。」
「王国の正式な国民になれば、地上に行くことは戻ることではなくなり、一時的に訪れるものになります。王国が帰る場所になるのですよ。」
「正式な国民になりたくて日々努力をしている。此処が故郷になるのなら本望だ。前にも何度か言ったかもしれないが、地上に未練は無い。待つ人もいない、代りは幾らでも育てられる。…地上界を帰る場所だと思いたくはないんだ。」
これまで落下して来た逸れ者はまともな者が一人もいなかった。だから死後名を奪い墓地に埋めたが、彼等は修行を成し遂げた身とは到底評価出来ない、地上で目を覚ます未来は自分達で断ち切ったのだ。無論此処で目を覚ますことも許されない。しかし正反対に、修行を見事成し遂げた者だと蛾達が判断したら地上でパチリと目を開くことが出来るのだろう、そして住み慣れた地上で生き直していけるが、其はあくまでも逸れ者としての話。
このまゝ新月が此処で生き続けたいと望むなら?旭影には当然喜びもある、初恋の恋人と居続けられたらどれだけ嬉しいか!でも、本当に良いのかな、本当に地上では誰も、新月のことを待っていない?
煉獄の役目を背負う王国に生まれた一人娘は搖れていた。答えは出なくて、微笑んだ彼に微笑みを返すことしか動けなかった。
曙の時刻、隣で寝ていた新月を起こさないように身支度を整え、新月の家の隣に立つ仮住居にポンムを肩に載せて戻った。手紙を書かなくてはならない。大切な手紙だ、一番弟子の手伝いが要る。
「お父様…お母様。」
そう呼びたいと思っていた。此の国で暴れた者を殺した日から、そう呼ぶことに恐怖が生まれてずっと避け続けて来たけれど、この手紙は軍の者としての伝令ではなく、極めて個人的な、一人娘として想いの丈を記すのであるから、向き合わないと、勇気を絞って、言わないと。書き終えた手紙を丸めてリボンで結び、それをまたポンムの大きなぽってりフォルムの胴体に括り付ける。
「お二人のところへ、お願いね。」
昇り始めた日の色を紫陽花の糸垂らす雨の輝きがそれぞれ重なり合い、手を取り合って踊りながら落ちてゆく。陽の雫に身体を濡らすことの無い翼は王宮へ一直線に伸びて行く。
「おや!ポンム、どうかしたのかい?」
突如窓越しに現れた愛娘の愛弟子を起抜けの顔で見て、国王は頭も覚めたらしい。
「旭影からの手紙でしょうか。足に紺青と白のリボンが結わえられていますし、あの子が私達に便りを寄越したのだと思いますが…」
女王は伝書係のポンムを室内へ招き入れ、彼女の疲れを労わるように膝の上で身体と羽を撫でさすっている。
「貴方、手紙の内容は?」
陛下は少し上ずった声で、ゆっくり、一語ずつ丁寧に読み上げ始めた。
”お父様、お母様。本日はご相談したい事がありこのようにしてお手紙をお送りいたしました。相談したいのは、新月さんのことです。
彼は今此の国の住民に帰化しようと日々頑張っています。ですが私は彼には逸れ者のまゝで在ってほしいと思うのです。例え彼が彼の望み通り国民として認められゝば私の愛する対象となります。
ですが私はもう彼を愛しているのです。逸れ者である、地上が本来の故郷である者の想いに指を繋いだのです。仮に王国の民となっても此の慕う気持ちは変りませんが、同時に彼への後ろめたさも感じ続けなくてはならないでしょう。彼から人間の帰る場所を奪ったのだから。
新月さんは地上には誰も待つ者はいないと言いますが、私は其が事実かを確かめたいのです。確かめて、誰一人彼の帰りを待たないと知ったら、私は彼に国民となる際に必要となる儀式の準備を伝えて、用意いたします。
お願い、お父様、お母様。どうか私が地上の世界へ行く事をお許しください。勝手な娘で、ごめんなさい。”
読み終えた陛下と聴き終えた女王の頬に涙が伝う。だが其の口元はにこにこと喜び、目元は宮殿の外、窓硝子の向こう、躑躅ヶ雪町の方角に向けられ、眦は美しい孤を描く稲穂の実り。夫婦手を取り合い何度何度も大きく頷いて、旭影が生まれて初めて娘の姿と対面したあの日と同じ輝きを放っていた。
地上
頻繁に、夢を見る。見るだけならまだしも、日中行動している際にも意識に割り込んで来るから、起きている間も夢のことを考えずにはいられない、侵蝕である。頭の内を蝕むもの達の性分は無慈悲な奴もいれば手心を加え乍ら進んで来る奴もいた。つまり酷い内容の夢もあれば優しい内容の夢もあったと言うことなので、新月はほとほと参っていたのだ。尤もポンムにとってはあまり心を痛めるものではなかったけれども。だが新月が具合が悪いとお師匠が哀しいのを一番弟子は知っていたから、お茶会に参加くらいはしてあげた。だって留守の間彼を頼むと直々に言われたのだから、放っておくなど論外なのだ。
いつも魘されているように見える。
声を持たぬポンムは目で喋る。
浅い睡眠を繰り返す新月は寝台で寝ようとしない。そもそもソファで横になったまま眠るからいけないのではないか?姉弟子の言葉が判別出来ぬ未熟で無礼な弟子ではあるが師匠の大切な想い人、一度起こしてベッドで寝かせようとポンムは弟弟子の羽織の袂を脚で引ッ張る。起きない。
誰に魘されている。
天井に向かって寝る彼は、いつうも同じ指を動かし、掌をやゝ上へ向けている、五指の付け根は伸ばされているけれどその先まで力は届いていない、震える爪先、中々肚の決まらない物事を考えていると言う占星術のタロットカードと当てはまる。えゝと確か、其の内容のモチーフは風車のイラスト。風車は幼い記憶を象徴するシンボルとして国の物語にもよく編み込まれたり織り込まれている。
結果、幼少期の出来事に悩まされていると浮き彫りに出来た。此の見事な手腕!またお師匠に抱きしめられて褒められて、また新月との格の違いが生じちゃうわ。
新月を連れずにお一人で地上に行かれた訳がよく分かった。此奴にとって地上界は殺しの仕事とトラウマが埋め尽された空五倍色、決断する迄地上に戻すのは避けた方が良いと判断された。新月本人から聴いた由縁の地を一つずつ訪ねた後、お師匠の意思は固まるだろうが、念の為補助的情報を用意しておこう。
何を求めたかったのだろう
新月の手はパタリと下に垂れ、身体を仰向けから横向きに寝返りした。地上の者はかくも切ない生き方を強いられるものなのか、ポンムは旭影を想った。
雪が降っている土地だった。けれど、故郷の雪と違って冷たくひんやりした体温の氷である。けれど、空の艶やかさは王国ではお目に掛かられない。ポンムと一緒に編んだマフラーに鼻まで埋めてフロックコートの釦留を両手で握り歩き出す。自らを打ち抜いた鉛弾で拵えられたであろう釦留は外気温に染まらず旭影の体温が染みていた。
生まれ育った場所とは異なるものが多いのに、珍しいとは感じない。建物の硝子に映る自分の顔と姿を見ても驚かないのと同じこと。
人間の見目と機能で生れて来て良かったのかもしれないと考える。若しポンム達のような虫の姿で迎えられていたら無事な遠出は実際厳しいであろう。人に空気に鳥に動物…数えあげたらキリが無い危険の手。人間ならば、都会の街の方が都合が良い。余所者ばかり送り込まれる胃腸の中では異物が紛れてしまっても歩く人々は気に留めない。
「先ずは、側溝。」
地上へ修行に赴いた経験のある国民達の力を借りて作成した地図は現実と寸分違わぬ正確さで点、々、々、と三箇所それぞれ離れた場所に印がある。側溝と前の家・職場とマークの横に細い筆で書かれた二つの文字、新月はどれだけ力を振り絞っただろう。
確認すればきっと此れからどうするべきかが分かる筈。短い髪を冬風に好きにさせておいて、旭影は側溝へ向かった。
都会から離れるだけでもう王国と似た景色になり始めた。徒歩で進める距離を振り返れば、摩天楼は恐れ多くも雲を眼下に収め上機嫌で酔っている、ふらふらと踊る足取りも覚束無い。不敬への白い目と不安のへの字口で旭影は数秒固まっていたが、背を向けてまた歩き始めた。側溝へはもう少し。
人通りが見られない場所に街灯は望まれないのであろうかして、新月が捨てられていたと言う溝のある道は月光だけが頼りであった。母親の胎内でさえもう少し明かりはあろう、置き去りにするにはうってつけの道に旭影は口を噤んでしまう。道が斯様な有り様ならば自然人家は寄り付かぬ、向こうを見ても反対を見ても人の住む場所とは距離があるが、全く遠いと言う程ではなさそうで。ならばせめて街中に…と思わずにはいられないが、そもそも何故このような人目の無い場所に捨てられたのか、そしてどのような経緯で育ての父親と出逢っていくようになったのか。
「人からの情報は望めそうに無いから……場所の記憶を読むしかないか。」
髪飾りとして留めていたミント色のリボンを取り両手に載せて、両目を閉じてキスをする。ポンムと新月と三人で生地を選びテーブルクロスとレースの本を縫い合わせて作り変えた物は雨夜の螢が泳ぐように微かな光を放ち、アスファルトの地面に一粒種子を落とした。
「答えておくれ、あなた方の記憶への問い掛けに。」
種は芽吹いて蠟燭の炎となった。たずねびとの目線と同じ高さにまで浮かんだ一本の蠟燭にはどれほどの命の情景が固まっているのだろう。炎は旭影の声が望むものを選び与えた。
今は雪の降る空だが、新月が生まれた日は雨穏やかな冬の日だった。赤ン坊以外の笑い声が風に伝って来る。間違い無い、新月は生みの親達に祝福されて誕生したのだ。
「良かった。生まれた瞬間に顔も見たくないと殺される赤子も多いと地上に行っていた者達から聴いていたから不安ではあったけれど…此のおだやかな笑い声、赤子と、女性と、男性の三つの声が混ざっている。新月を抱いて、此処の道を歩いていたんだ。夜の散歩に来ていたのかな。」
笑い声の途中で男性の声が発言した。
(もうこの辺りで良いだろう。捨てろ。)
血の気が引いても答え続ける場所の記憶。今度は女性の声がした。
(あんたはもう良いよ飽きたから。)
ゴソゴソとダンボールを用意するような音の後は少しの間何も聞こえなかったが、赤子の泣き叫ぶ声がだんまりを破った。赤子の呼び声に応じた男女の此の後の言葉は凡そ誰にも聞かせたくはない酷な文章に仕上がっていた。子を負う責も無いのによくもそんな…餓鬼畜生、畜生道の住人どもめが。その土性骨を叩ッ砕いて口に突っ込んでやろうか奴等…旭影は射殺す眦で空を睨み、憤怒の涙は月明かりに強く煌めく。自分の望む結末を支えに考えた予想は見事裏切られたが、彼女は次に登場するであろう義父に期待した。後に置いて行かれる結末は変えられないけれど、今語られて存在している赤子の新月の悲痛な涙をどうにか拭ってくれる指が欲しかったのだ、声の聞き手は手を出せないから…
空が白む音が徐々に谺してやがて明朗に聞えるくらいになると、新月の泣き声は朝日の響きに反して小さく途切れがちになり始めた。最後の一息になってしまいはせぬかと旭影が口元を押さえて泣き叫びそうになるのを堪えて黙って涙をぼろぼろ落している時、ようやく声がした。
(こいつは大変だ。)
次いでバタバタと急ぐ音、走る音が続いて、話は閉じられた。新月が一命を取りとめているとは理解していても心への負担は相応に大きく、話が終わるやいなや旭影がその場にへなへなと座り込んだのは仕方の無いことだろう。
「新月は生みの親から愛されてはいなかった。」
彼は側溝に捨てられていたのだと自身の出生を正直に語ったけれど、心の何處かでは期待していたのではないか、きっと今でも。だが事実は子の淡い願いに首を振ったのである。
次は、義父と生活した家。旭影は街へ向かって歩き始めた。もう側溝を振り返ることはしない。
素地
新月が幼少期を暮らした家は、まだ残っていた。マンション、とか言うのだっけ。ビル、にも劣らずマンション、も中々に図々しい性根を持っているようだ、私達の国でこれほど高い物を建ててしまえば紫陽花の空の枝垂れに絡まって生活云々の問題ではなくなるだろうよ。
でもまあ、この建物であれば問題は無いかもしれない。本を読む時たまに掛けるんだよと仰有っていたお父様に提案されて作った眼鏡を装着してみる。度入りの真ん丸薄型レンズが故郷のお茶会の読書の薫りを思い出させると同時に眼前の建物の情報を硝子越しに聞いていく。
「今は住人がほぼほぼ居ないのか。人の住まない建物なら高さが異様でも問題は無い。枝垂れに近距離で降られてもどうってこと無いが、お化け屋敷を国に置くみたいで嫌だな、王国にまるごと転送してみようかと考えたが、良い案では無さそうだ。
「それに、此の建物に新月の優しい記憶が含まれていると確証がある訳ではない。義父にも捨てられた……そう仰有っていたから側溝よりマシなだけ、そんな場所かもしれない。」
希望は抱きづらいが、当時住んでいた五〇五号室へと非常階段を昇って向かって行く。
「おや、誰か住んでいる?」
表札カバーの中身は空ではなく、名前を書いたプレート代りに緑色のカードが挿れられていた。旭影はインターホンを一回押す。扉が開いて向こうから現れたのは、新月よりは年齢を幾分か上回っていそうな男性であった。スーツをきっちり身に纏ったが、額から左目を通り唇に達する白い大きな傷痕はどうしたのであろう。
「誰です?」
訊ねる単語を用いているが帰れと言っているのも同然な声の低さ、いかめしい喉仏に睨まれているかのようだ。
「以前此方に住んでいた男の行方を追っている。新月と言う名前に聞き覚えは?」
「新月。其奴を探しているのかい。」
「否、新月の育ての父親なる人物を探している。」
「……ハハッ。」
男は旭影が用件を伝えると乾いた笑い声を発した。自らの顔の上半分を無骨な片手でガバと覆ったから目の表情は読み取れない。旭影が言葉を選んでいると、男は彼女の白い手首をむずと掴んだ。
「入れ。教えてやる。」
強引な力に抗いきれず、旭影はずるずると男の部屋へ連れ込まれてしまった。扉が閉まり、錠をを下ろす音がする。
初めて王国を出て外の世界を歩いた王女様だからと言って、無礼に怯えて手も足も出なくなる箱入娘ではない、侵入者の討伐を一人で果たせるのである、暴漢に歯向かう胆勇と力量は持っている。旭影は痛む手首の元凶である男の首根ッこを鷲掴み、爪を肉に食い込ませて太い動脈の一ミリ手前で止めた。男も旭影の殺気を激痛を通した氷点下の怒りで感じ取ったか、掴んでいた手首を解放し、両手を挙げて降参の格好を取ったので、背中を蹴りつけ床に俯伏せにした上から背中を殴った。強烈な打撃を二回も受け、男はがくりと気を失った。スーツの襟元をむんずと握り、旭影は男を室内へずるずる運んで行った。
冷水を叩きつけられた衝撃で男は息を吹き返した。霞んだ視界を必死に振り払うように首を左右へ動かせば、霞は晴れて物のピントが合ってきた、自分の前には玄関先にいた女が座っている。
「もう俺を殺しに来たのか。」
やるなら一息でやってくれとボヤくと、女は一回瞬きをした。
「私は貴様を殺す為に訪ねたのではない。此の部屋に昔住んでいた者の行方を知りたいから来ただけだ。貴様が不埒な真似をしなければ痛い目に遭わすこともしなかった。」
「政府に雇われた奴じゃないのか?」
「私は誰かに雇われて此処に来たのではない。恐らく貴様の予想は大概外れていると思うぞ。」
政府。新月も其の言葉を使っていた。となれば、此の者も彼の同業者であろうか。私を追手と勘違いしている状況を鑑みる限り、殺され得る条件を持つ者となる。
(殺し屋であればいつか標的になる日が訪れる。)
そうして彼と私は逢ったのだ。
男に対峙する姿勢と態度は緩めず、しかし追想の愛撫は故郷を離れ一人異邦の土地で奮闘する娘の寂しさによく沁みた。水滴は人を黙らせる。
政府の手の者では無いと言い切った後言葉を止めている旭影の瞳の底が僅かに柔らいだを見逃さなかった男は外せそうに無い拘束を解くよりも話をした方が状況が好転しそうだと判断し、彼女に声を掛けた。
「お嬢さん、此方が悪かった。確かに野郎が若い女性を自分の部屋の中に連れ込むなんて、しかも乱暴に手首を捕らえた状態でなんて、紳士の、否人としてあるまじき行為をした。其は心から詫びさせていただくよ。本当に、申し訳無かった。
でも、俺はお嬢さんを殺し屋だと思ったんだ、政府の奴等が俺の口を閉じさせたいから組織が送った使いだと思って、部屋で殺し合おうと中に無理矢理引き込んだ。外でドンパチしてたら他の階にいる奴等までヤジ馬になって駆け下りてきちゃうかもしれないだろう?ターゲット以外を巻き込んで殺すなんて、殺し屋としては最低のマナー違反だ。
理由を述べたところで俺の非礼がチャラになる訳ではない。だから貴女の知りたい情報、話せるだけ話すよ、俺の知っている限りで。」
眼鏡越にひそひそと囁く物達のお話を聴く限り、此の男にはもう私を襲う腹積りは皆無だと言う。だから外してあげてと懇願するキッチンのまな板は汚れ一つ無いのに長く使い込まれた翳りが見える。他にも似たようなケースが多いと言うことは、道具を大切にしている人だと言えよう。
「分かりました。貴方がそのように対応してくださるのであれば、私も貴方に応えましょう。」
麻縄で雁字搦めに縛っていた男の拘束を一本ずつ丁寧に解き、ようやく二人はリビングにある椅子に座り、向き合う形で話が出来る体制になったが、冷たい水を何に入れたか知らないがぶッ掛けられて男は濡れねずみである。服を着替えて来てもと言う前に衣服の水分はあッと言う間に綺麗に乾いた。
「き、君が?」
「はい。その水は私が術で掛けたものですから、もう乾いて良いよと命じました。もう元の場所に戻っています。」
「えゝ……も、もとのばしょって?」
「其は貴方が私の質問に、私が満足する情報を以て応えてもらえればお伝えいたします。」
男の名前は鈴蘭と言い、やはり新月の同業者であった。二人はチームを組んで仕事をすることも多く、仲が良いとまではならなかったが相手の情報を幾つか話し合うことはあったと言う。
「育ての親父さんの話題になった時があったんだ。」
(なあ鈴蘭、お前はどういう経緯で政府に引き取られた?)
(俺は両親を流行病で幼い時に亡くしてな。駈落ちした二人だったから親類とは縁を切っていたんだ。それで身寄りが無いから政府にお世話になった訳だ。)
(ははッ、面白いな。)
(いや、面白くは無いだろう。お前の喜ぶポイントは未だによく分からん。)
(あゝ違う違う。お前のご両親が亡くなったことが、じゃあない。)
(じゃあ何がだよ。それに、俺はもう教えたんだからお前も教えろよ、焦れッたい。)
(俺は育ての親父が女と駈落ちして行方知れずになったから政府に引き取られた。……ハハッ。)
「何が楽しかったのかその日は随分笑っていたよ。上機嫌のまゝ二千メートル離れた標的の心臓を一発で撃ち抜いた。あいつはスナイパーをして生きる為に生れた奴だったよ。」
(おまえなら分かってくれると信じていたよ。)
「射撃の腕が名人級だからと言って、そう定義付けるのは間違っているのでは?本当は殺し屋になりたくなかった本心があったとは思わないのですか。」
「いや、銃の腕前だけで判断しているんじゃないんだお嬢さん。狙撃手は腕の良さと標的を撃つのに絶好のチャンスを待ち続ける忍耐力と執念、どんな相手でも一発で心臓を貫かせると言う考えを常に持つ冷酷さ、非情さ…これらが必要条件なんだ。だが新月は其等を一つも欠かすことなく持っていた。」
「それは、政府の教育の過程で培われていったのでは?」
「素質の無い者は途中で脱落していく。殺しに向いていない子は普通の孤児院へと送られて日常の生活に溶けていく。脱落したから酷い目に遭わされることは決して無い、殺しの世界から離れた子は実際多いさ。この間も一緒に教育を受け始めて途中で諦めた男の子がマイホームパパになって法律事務所へ出社している事例を見た。
……俺も新月も素質があったから全教育をこなしていけたんだ。」
「素質が、あるから…」
「それになお嬢さん、彼奴は殺しを楽しんでいたように思う。仕事中は真顔でも、仕留めた後は決まって笑みを浮べていた。……義理の父親を一発だけで殺した時も。」
「……………………」
「二千メートル離れていたんだ。風もキツかったのにさ。見事な手腕だったよ、他の仕事と変らずに。」
(俺が殺し屋に向いていない人間だってことを。)
雨降る
十年振りくらい、或はもう少し経っていたかもしれない。恋人と諸共に姿を消した育ての父親は、マンションの一室に住んでいた。標的の情報を記した紙の資料を受け取った時、上司は変な顔で俺の様子を窺っていた、きちんと殺しきるのかが不安なのかと分かったのは相手の名前を確認した際で。
(他の者に代りを頼んでも良いが。)
上司の言葉には確か、結構ですだの問題ありませんだのと答えた気がする。しかし、そう言った時の自分のしていた表情が全く思い出せない。一つ憶えているのは返答した後上司が逃げるように歩き去って行った事、これ以上顔を見ていたくないとでも悲鳴を吞み込む力んだ表情で。
よく晴れた夜で、視界は激しい俄雨の直後とは思えないほどに鮮明で冴え渡っていた。吐く息は白く輝き、愛用のマフラーに珍しく顔を埋めるのが惜しいくらいに澄んだ月夜の空を何度も何度も味わう。硝煙の匂いに慣れてきていた頃で、嗅覚も血生臭さと腐乱を始めた死体にも麻痺し始めていた冬の夜。
子供は質問することを生業をする人間である。驚破と言う際には何も状況が把握出来ずキョトンとしているイメージがあるが、実際には沈黙とは正反対で何故如何してをこれでもかと言う程繰り返す。子供は存外泣かないものだ。父親の射殺体を見た後も、母親が眼前で撃たれた時も、穴の開いた心臓に小さな手を突き込んで如何して如何してと今際の綴じ目まで反復していた。
(お前は愛されていたか?)
答えを聞きたくて質問をしたが、子供は大人より息絶えるのが早く、回答が貰えなかったので少し残念だった。問い掛けても会話のキャッチボールが成立しなかったので気付の要領で心臓を撃ったんだがなと鈴蘭に言うも今日の相方はだんまりだった。まァ、仕方が無い、明日は我が身と怯える中で親しい者を作る余裕の有る者など誰一人居なかったものな。
「でも鈴蘭が落ちて来たら、あいつ旭影を口説くだろうな。」
自慢の妻は、夫が親殺しだと辿り着いた頃だろうか。
広大な草原の中、今年も実り始めた金の稲穂が、北風に逆らわず頭を搖らす。紫陽花の空は連綿と雨を紡ぎ、王国中に命の泉を分かち合う。
歪みと一途
「新月が人間の暮す、えゝと…地上世界、と呼ぶんだっけか。新月が地上世界を見限ったのは、単に誰も彼奴を待っていないからだけじゃあないと思う。彼奴は人間自体に怒っている。まあ、生い立ちを考慮すれば納得いかん理由ではないが。」
生んだ子供を飽きたから捨てても、置き去りにした養子を迎えにも行かず新しい家庭を築いても、人間達は罰せられない。例え罪に問われて裁きを受けたとて、更生の為に生き続ける、否、生きることを望まれる。
「俺達の業界はまだ単純な構図なんだ。殺したら殺される、遅かれ早かれ、な。まあ俺達に仕事を頼む奴等の世界はそうじゃないかもしれないが。殺し屋の世界は報いが必ず巡って来る。俺は今回君に逢えたから運良く生き延びた訳だが、いつか必ず殺される。明日か十年後かたった今かもしれないがな。
でも因果応報の摂理は今の世界では薄れて弱まってきているから、新月の碌でも無い実の親と育ての親は何の報いも受けていなかった。その社会の構図に彼奴はうんざりしていたんじゃないか?」
道義も道理も弁えようとしない輩が両肘張って太い鼻息を吐く、それでも日光は遍く降り瞳を照らす。その光の恩恵を恩恵とも感じてさえいない者にも、等しく。太陽は自分で自分の光を除くことは出来ないから、誰からも光を奪えない。奪えるのは、自らで発光しないもの。実行する事自体は許された行為ではないが、光を放てぬもの達は実行する力があるのだ。
「新月さんは、人殺しに向いている人だったのですね。」
ただ愛されたかった、捨てられたくなかった。言葉にしてしまえば至極ありふれた文章になるのに、此の一文どおりに生きられている人はありふれた存在ではないだろう。歪んだ理由は環境の所為と済ましてしまえば容易いが、掘り下げてしまえば坩堝かもしれない。
「お嬢さんは地上の住民じゃない、今新月が君の世界で生きているのなら其方側のルールに従って生きてもらえば良い。過去ッてのは良くても悪くても抱きしめ続けていれば苦しくなるものだからな。」
鈴蘭は煙草に燐寸で火を点けてふかし始めた。濁った白い煙は昼日中の薄い空に流れて行くも、その色のもとまでは形を保っていられない。
「新月の義理の父親は、反政府組織の人間だった。資料を読ませてもらったが、何やら大層な御託を並べていたよ。支持している一般人も多かった。でもまあ、行き場の無い学生達の延長線上って感じだった俺からすれば。新月にも名を与え育てる為に拾ったのはパフォーマンスだ、捨て子やホームレスなんかが多い地域をパトロールしていたんだ。助けを求めていそうな人物がいやしないかってさ。大人から見捨てられた存在を汚れた衣服のまゝ抱え上げて自分の胸に抱きしめる。分け隔ての無い立派なリーダー像が定着するだろう?」
誰でも良かった相手が偶々新月だっただけなのか。
「だから平気で置き去りに出来たのでしょうか。そんな、そんな恐ろしい考えが罷り通るなんて…」
故郷を強く想い出す。私には帰りを待ってくれている場所があるけれど、新月は何處にも其が無い。だから王国を愛して、故郷にしたがっていた、地上では誰も、待っていないから。咎めだてもしてくれないから。
「国民になりたいと仰有っていた新月さんの動機に間違いはありませんでした。誰もあの人を待っていないのであれば、此れ以上私が儀式を先延ばしにする理由はありません。鈴蘭さん、お話を聴かせてくださり有難うございました。」
「もう故郷へ帰るのかい?」
「えゝ、もう新月さんが王国の国民になるに充分な理由は得られましたから。」
「もう一つ寄って行く所があるんじゃないの?彼奴の職場はどうするの?」
鈴蘭は喫煙していたベランダでくるりと向き直ると、旭影の顔をまじまじと眺めて嬉しそうにニマニマしている。
「帰る前に寄って行くだけでもどう?若しかしたら有用な情報が手に入るかもしれないし。」
一人で外に出る支度をばたばた始めた鈴蘭に、もう欲しい情報は入手出来たので結構だと旭影が言うと、待ってましたと言わんばかりに返答した。
「彼奴が地上でどんな人間だったのかを、本人以外の口から聴くのも大切だぜお嬢さん。自分の知らない伴侶の一面も知った上で愛せる関係が至高の夫婦ッてものさ。至高の夫婦、なりたくないのかい?」
きっと職場に赴けば彼の数多の殺人に関する話を聴かなければならなくなるだろう。人殺しの天賦の才を抱く夫の、最も残酷な部分を知らなければならなくなる。
「表面上の盲目愛は私の望む愛し方ではありません。相手の本性などどうでもイイ愛してくれたらそれでイイだなど極めて愚かな考えです。そのような愚かの恋情で愛が育まれ続ける道理はありません。私は新月さんのおぞましい過去も残酷な所業の数々も抱き留めてこれからを共に生きて行きたい。深層に閉じ籠もっている新月さんの一部分達に、私は赴き逢いたいのです。」
「じゃあ決まったな。」
デートに誘う気だったが無粋な企みだったな。これほど想ってくれているなんて彼奴も幸せ者になれたじゃあないか。お前には正直勿体無い子だろうに、でも一途同士お似合いかも?だって新月、お前は一途が暴走して人殺しになったんだからなあ。
花々
ビジネス街の中央部、心臓のような立地に新月の職場のビルは建っていた。
「硝子が惜しみ無く使われているのですね、殺し屋とは宮仕えの者でもあるのでしょうか?」
硝子が到る処に施されているのは王宮の建築様式である、国民の家には窓硝子や鏡くらいしか飾りは要らないので、旭影は全面硝子張りのビルを宮殿か何かと勘違いしたのであった。鈴蘭は文化の違いなんだろうなと予想しながら微笑んでいる。
「地上じゃガラス張りの建物なんざ珍しいものじゃあない、あっちこっちにあるさ。」
「何と豪勢な…成程、それで各々自らの会社の権威を示し合っているのですか、硝子は権力誇示の為のステータスとして使用されているのですね。」
うーん、どう答えたものか。
「まあ、そう受け取ってもらっても構わないけれど。中に入ろうか。俺達のボスが待っている。」
ホテルのような内装のエントランスを通り、エレベーターで目的の階へ昇って行く。てっきり目下の眺めにはしゃぐかと思っていたのに、旭影はうんともすんとも言わず、黙って小さくなりゆく景色を見ている。
「若しかして、ビルに既に昇った経験ある?」
王国では珍しくもない光景だったかな。
「いえ、ビルと呼ばれている建物自体初めてです、王国にはこのような高い建物はありませんでしたから。」
「その割に、硝子以外ではしゃがないのな。地上は珍しい物に溢れていると思っていたんだが、お眼鏡に適わなかったか?」
そうではない。だが旭影は応じなかった。鈴蘭に自分の事情を伝えすぎている気がして、何となく後ろめたい気持ちがあったから。しかし鈴蘭は初心な王女の心情を察していたらしい。
「今俺と仲良くお話をしたからって浮気になんかなりはしないさ。男女が二人きりになったから不義だのとは言われない。現に先刻だって俺の部屋に居たけれど、何も問題は起きていない、互いに知りたい情報を提供し合っただけで、有意義な時間だったろう?」
あの時は殺し合いに発展する一歩手前が発端だったので、不道徳を考える余地も無かったが、部屋を出て冷静になれば何とはしたない真似をしていたのだろうと恥を覚えた。けれども鈴蘭の言い方からすると、地上では妻が他の男と一つ屋根の下に居たからとて即座に不貞となる訳ではないらしい。これも、故郷とは少し違う。
「慣れませんが、少し安心しました。それでは貴方とお話をしても特段問題無いのですね、此方側では。地上にお邪魔しに来た以上、地上のルールに従わせていただきます。」
「郷に入っては何とやら、だな。まあもう少し居るなら気楽にな。」
「あの、そう言えば、」
何故鈴蘭は新月の義父の家に住んでいたのだろう、と訊ねる前にエレベーターの到着音が鳴ってしまった。
黒電話やタイプライターに羊皮紙とインクと羽根のペン。
「殺し屋の仕事のやり取りはアナログ的な手法に限るのさ。時に伝書鳩なんかの動物に使いをやらせることもある。」
「虫は?」
「虫は流石に無いかな。まあ雀蜂とかの毒を使って殺しをする同業者はいた気がするけど。まだ生き延びてたかな?」
「虫を使う殺し屋は以前新月が殺した。お前もチームに入れていた筈だぞ、鈴蘭。」
古風なオフィスに入っている二人の後ろから声を掛けたのは、水銀色の着流しなのに藍褐の羽織を肩にきちりと備えた髭麗しき一人の壮者。顔には米神から鎖骨まで肉を裂かれた傷痕があり、皮膚に走る白い隆起が当時傷を負わせた相手の憎しみを言外に睨み、今でも威嚇している。しかし斯様な威嚇何するものぞ、壮者は心底穏やかな微笑みを浮べ、瞳を少し細めているが、旭影は其の奥を見逃さない。背筋を凍てつかす無慈悲の一端を読み取った。
「貴殿が組織の長か?」
鈴蘭が言い掛けたのを遮り壮者に直接問い掛けた。油断ならない相手に先手を許してはいけない。
「ボス、この女性が先程電話でお話した…」
「あゝ。初めましてお嬢さん。遠国から遙々どうも御苦労様です、私は今貴女の仰有った通り、殺し屋組織の長を任されている人間です。名前は雛芥子、宜しく頼みます。」
差し出された新月よりも大きくごつごつした手に旭影は一瞬怯んだが、その手を握りかえすことはしなかった。
「頼みたいのは貴殿に非ず此方側なのだから、何も頼まれる予定は無い。新月の職場での話を聴かせていただきたい。今日は其用件で参った次第だ。」
無礼だとは分かっているであろうが握手を拒み自ら名告る真似もしない乙女に雛芥子は内心ほお、と感心した。初対面の物腰の時点で即座に警戒を怠らない姿勢を準備している、大抵は気を許してしまう筈なのに、目が合っただけで私の本性を看破したか、この子で二人目だな。鈴蘭に電話で聞いた情報で予測は立てていたが、やはりこの娘は新月によく似ている。利用しない手は無い。雛芥子は差し出したまゝの宙ぶらりんな片手を戻し、両手を背中に回して組んで腰を支えるような姿勢で旭影と話を続けている。
「新月は実に優秀な殺し屋だった。顧客への反抗心も抱かない冷徹で忠実な部下だったとも。…私も特に目を掛けていたよ、いずれ殺さなければならないと分かっていても……。」
一寸言葉を区切り
「だから積る話は澤山ある。立ち話では周りの邪魔になってしまうくらいにはね。だが簡潔に話をしてはお互い納得はいかんだろう?彼処に応接室がある、普段はカーテンを閉めきった全面硝子張りの部屋だ。だが今日は仕事の依頼人と話をする訳じゃないからカーテンは開けておこう。一人の男の思い出話を教えるだけなのだからね。」
旭影を室へ案内するように片腕を部屋の方向へ伸ばした。
「ふむ…確かに貴殿の仰有る通りだな、私は貴殿達の仕事を邪魔しに来た訳ではない。それに、新月の地上での活動を出来る限り知りたいと言うのも曲げられない。ご提案いただいた応接室での会話は双方の目的に合致しているようだ。お言葉に甘えて失礼しよう。」
全面硝子張りでカーテンも閉めないのなら室外の様子も窺える。それにいざとなれば蹴破って逃げられる。此方に害意があるかの判断材料が集めやすい状況だな。
旭影は部屋へ先に通されながらも少し安心した。続いて雛芥子も応接室に入り部屋の外にいた鈴蘭が扉を閉めた。鈴蘭が自分に手を振り乍ら笑顔で立ち去って行く須賀らに彼女は少しだけ微笑み手を振り返す。
彼女は遂に気付くことが出来なかった。雛芥子が握手の片手を引っ込めた時から部屋に入る迄、始終鈴蘭にサインで指示を送り続けていたことを。
前例
「鈴蘭、お前も同席しろとは言っていないぞ。」
「でもボスはこの子の国の文化御存知でないでしょう?話をしている途中で噛み合わないことがあったら困るでしょう。だから自分も同席させてもらいますよ。」
雛芥子は大きい溜息を吐いたが、其は怒りではなく呆れを多分に含んだものであった。そのまま鈴蘭の淹れて来たコーヒーを飲む。
「済まないねお嬢さん。彼に害意は無いんだが…どうも女性と仲良くしたがる節がある。」
「いや、構わない。それに、鈴蘭さんからも大切な情報を教えてもらえた。彼も同席していた方が話に花が咲くだろう。」
旭影もコーヒーを飲んだ。
「時に、お嬢さん。私から一つ提案があるのだけれども、聞いていただけますか?」
「雛芥子殿、私は貴方がたの仕事の手伝いをする気は毛頭無い。新月の話を聴かせてもらえないのであれば、早速失礼させていただく。」
「まあまあお嬢さん、ボスにも対面ってものがある、俺の気を失わせる程の実力を持った女性なんて滅多にお会い出来る逸材じゃあないんだからさ。」
コーヒーを飲み干しマグカップを静かに置いて立ち上がろうとした気迫の旭影を鈴蘭が宥めるも敵意は抑えきれない。雛芥子を睨む玲瓏たる苛烈の湖面模様を正面から見つめた男は一言放った。
「やはり、新月によく似ている。」
初恋を生涯一度の恋とした身は、其言葉をすり抜けられない、白露は風となって滴り沈み行く。
「私が、新月さんに似ていると?」
此方では二日程度の時間の流れでも王国では早や数ヶ月にはなるであろう、異なる水質を泳ぐ心は慕う言葉を無意識に。
鈴蘭から報告のあった通りの相愛ぶりだ。尤も新月当人は彼方側の住民となりかけているから実際言質を取った訳ではないが、初めて触れる愛隣の情を無下にする男でもない。澄ましていても白鳥の泳ぐ脚はもがいている、組織の長は旭影の瞳の閨の波紋を逃さなかった。
「彼の生い立ちは酷いものだ。誰からも必要とされず愛を与えて貰えなかった子供。そのような孤児は政府に引き取られるのが此の国の第一の法律さ。表向きは未来ある者を国が守る立派な鎧に見えるだろう。実際法の制定時には反対意見はほぼほぼ無かった。でもお嬢さん、法には建前と真意があり、双方欠けてはならないものだ、二つの秤が等しく釣り合った時初めて法律は産声を上げて誕生したと見なされる。
第一の法の真意は、政府に不都合な人間達を殺す為の人材確保と言うものだった。」
怒りの余り眩暈がする。
「今にも裂き殺しそうな視線だな。その若さ、あくまでも見た目から推察する年齢だがね、弱冠にしてこれほどの殺意を操るのは才能のある者でないと叶わんだろう。新月を政府から引き取った日の彼の眦を思い出す、そっくりだ君達は。天性の殺し屋にして愛情に飢える者、矛盾を抱えるよう定められた星の光だ。……あゝ手放すには惜しい駒だよ。」
軟禁された部屋は清潔で手触りも良かった。激しい眩暈に意識を奪われた後、再び目を開いたのは白い部屋。手足に枷のような物は無く寝台から起き上がりもう一度自分の身体の様子を確認する。着衣には一切の乱れも無く、身体を荒らされた痕跡も無い。拘束する細工も室内には用意されている気配も無いが、コートのポケットに入れておいた眼鏡は何處にも見当たらない。
「人間があの眼鏡を重宝がるとは思えない。」
没収されたと言う事は相手に有用であると判断されたから。しかしあれは人間の手の内にあっても効力を発しない。王国の守り手である蛾の女神達が秋の夜空に灯す菫の迎火の散る欠片から編み出された装身具。王国で作られた道具は地上世界では命を閉ざす。
「地上の人間の目にはありふれた眼鏡しか見受けられない筈。そんな物を私から奪う理由は?首代りの心算なら私は殺されていなければ可笑しい。でも殺した痕は身体の何處にも残っていない。マフラーやブーツもそのまゝなのを考えれば、運ぶ時に邪魔になったとするのも難しいか。」
このまゝ王国に帰るのはやろうと思えば直ちに実行出来る。コートのボタンを一つ引き千切り心臓部に一度強く押し付けるだけ、ボタンは銃の鉛玉へと本来の姿に戻り王国を旅立つ際と同様に自らの務めを果たすだろう。眼鏡だって、作る事自体は然程難儀な物ではない、ないけれど。
(初めてのお揃いだからって、あのひとはあんなに喜んで。)
そう仰有るお母様もお父様に劣らず喜んでいました。
(王国での眼鏡はこうやって作られるのか。地上とは材料が全く異なるようだ。)
貴方は好奇に目を輝かせて。その肩ではポンムが得意気にしていたのが可愛らしくて。
「代りは作れるけれど、代りが利かない物だもの。置いて行ってしまうのは…」
命があっても大切な記憶の一部を切り離しては…旭影が逡巡していると、部屋に置かれていた白い黒電話は大きな声で彼女を呼んだ。受話器を取って耳に当てる。その向うには憎い声。
「おはようお嬢さん、意識が戻ったようですね。」
「雛芥子、貴様の仕業か?」
「声だけで相手を殺せる技術があるのなら其の道の達人と称せますな。」
「私の眼鏡を奪ったのか。」
「えゝ、此方に。鍵を掛けた箱にしまってあります。傷や曇り一つ付けていませんよ。」
「返せ。」
「煉獄の役目を担う王国の愛娘にしては随分荒々しい言葉遣いだ。旭に影差す忌まわしの身の本性か。」
ズキリ
受話器を握る手も握らない手も固く力が入る。生唾を飲むことも忘れた喉は乾き声は掠れる。
「何故、知っている…鈴蘭にも名前など教えては……」
「鈴蘭は私の指示に従って動いてくれたに過ぎない。彼は正真正銘の地上が故郷の人間だ。地上に住む者達に君の持つ眼鏡は使えない。けれどね旭影、私は使える。使う為の力を生れ乍らに持っている。」
「まさか、」
「私は嘗て王国で誕生した最初の人間だ。」
ガチャリと一方的に電話を切られ、そのまゝ呆然と立ち尽す旭影の後ろで扉が開く音がした。左右に動いたドアの中央には雛芥子が葉巻をふかしくゆらせた煙の中薄ら微笑んで待って居た。
語るべからず
「ポンム姉さん、この本は?」
いつまでも自宅でぐうたらしている新月をげしげしと小さな脚六本で蹴り乍ら一緒にやって来たのは図書館であった。国民になりたいならもっと国の文化や歴史を勉強しなさいと言う姉弟子の言葉に素直に従う。
「お師匠が戻って来られた時、立派になったおまえを見て感動するくらいに立派になれ。そうしたら私が育てましたと胸を張ってお伝え申し上げられる。そうしたら凄いわポンムと褒めていただける。ぐうたらしていないで知らない事を知り、知っている事はより深めなさい。忙しくしていれば魘されることも減る。」
「あゝ、目だけでこんなに喧しいなんて信じられん。もう口で喋っているのと変わらない五月蝿だぞ。こんな事になると分っていたら目での会話の勉強なんてしなきゃ良かった。」
「蝿とて本来の姿はタンザナイトだ。地上での鎧の性質は人避けにはもってこいでしょうに。」
「あゝすみませんね、蝿殿を軽蔑した訳ではないんです。軽蔑したのは貴女ですよ姉さん。」
「新月!」
「ほらほら図書館では声を抑えるが常識ですよ。今未熟者は勉強しているんですから。」
「むう。」
してやられた不満はあれど、言い出しっぺの役割は果たさねばならない。次に読ませる為の本を次々と弟弟子の机に積み、横に自分も腰を降ろし、質問への回答者として構える。次に読む本の表紙を見て、新月が問い掛けた。
「ポンム姉さん、これは歴史書か?」
「あゝ、これは、仙台の国王の統治の歴史についてまとめられた本ですよ。見るのは初めて?」
「お義父様とお義母様の御治世しか知らなくて。」
「先代の分も知っておくと良い。今と比較して感じる事も多い筈ですよ。」
先代国王は今の国王陛下の父親に当たり、地上では蜻蛉の鎧を纏っておられたトルマリンの偉丈夫であらせられた。お世継ぎに恵まれない不運の中でも妻である先代女王陛下との仲は良く、互いによく支え合って国を治めておられた。
或夜、一匹の女神が眠る先代女王に夢を与えた。彼女が夢の中で一枚の書簡を紐解き読むと、朝日が昇り先代女王のお腹の膨らみを照らし目を覚まさせた。温かいのは陽光の為だけではない。
御懐妊の福音は風の唄で国中に伝えられ、国民達は生まれて来る御子に毎日お茶会と物語を進んで捧げた。
トルマリンとローズクオーツの夫妻から生まれた子は、鉱石の姿をしていなかった。人間の姿をしていたのである。その者の姿は飢えた砂漠の如き瞳をしており、国王夫妻も臣下達も国民達もよもやこのように恐怖を催させる赤子が生まれて来るとは思わなかったであろう。それでも国王と女王は愛しい我が子を捨てようなどとは微塵も考えず、自らの座を託すものとして育てることを女神達にお誓いなさったのである。
まこと、王国は平穏であった。お世継のお名前は火徳と名付けられて、火徳王子は最初こそ民に怖がられてはいたが懸命に国の為に働く彼の汗は一点の曇り無く、国民達の瞳を次第次第にほどいて開いていったのである。火徳は国を愛し、命を慈しむことの出来る王子へと立派に成長していった。
彼が成人の齢を迎えた時、女神は再び女王陛下に夢を与えた。今度は水府を眺めており、見上ぐる湖面に指先を伸ばすと一片の紫陽花が彼女のしなやかな御手に挨拶をして、月光鮮やかなりけり夜の庭に、女王は急激に産気付いた。
大きな産声を上げたのはガーネット。父親の鎧を見事に引いた男の子であった。火徳王子に弟が生まれた瞬間だった。弟を抱いた時の火徳の表情は、丁度空を泳ぐ散る木の葉に重なってよく見えなかった。
ガーネットの現国王は、自分を抱いていたのが兄だとは思っていない。あの時若い人間が居ませんでしたか、と父君に訊ねれば、いつも決まってこう答えられた。
「あの者は、逸れ者だ。忠実な性格の持ち主だったから城の手伝いを任せていた従者だ。もう寿命を迎えて地上に帰って行った。」
まさか自らの兄が王国を追放されたなど想像もしない正当な世継ぎは、城の中で王国を預かるに相応しくなる為の教育を受け、先代の後を託された。
この記録は、本来知る事も許されないものである。決して他言をしないように。
先代国王の治世を記した本の序文にはそのように刻まれてあった。その後は、彼がどう国を治め民と関わっていったのかが詳細に書かれていき、やがて天命を果たし後世に代を譲り、国土の一部へとなって本はおしまいだった。
「ポンム姉さん。」
「何も訊くな。訊いてはいけません。序文を読んだでしょう。」
「読みましたが…」
「ならば言葉に従いなさい。法律に触れないけれど、呪われますから。」
「悪しき言葉は悪しき輩を呼んでしまう、でしたっけ。此の国のマナーでしたよね。」
「貴方の疑問を無下にする訳ではありません。ですが、嘗ての王子の名は勿論、その後についても決して語ってはなりません。呪いは当人ではなく、当人の大切な者に掛かるものですから。」
旭影。口を強く引き緊めて、妻の名を呼ぶ。
罠
「知る事自体は解放されていた。だが知り得た内容は決して語ってはならぬ事と序文に刻まれていた。故に誰も先に人間が誕生していた前例を話として聴かす事も出来なかったのだ。私は先代陛下が国土へと還られた夜更け、一匹の女神に誘われて其の書物を図書館で読んだ。今でも深夜の図書館で月の翼の灯りをランタンのよううにして照らしてくださった光景をよく憶えている。」
白く固い材質の重いテーブルを真中に挟み、旭影と雛芥子はアルミの椅子に座って対峙する。二人だけの穏やかな殺気が目を閉じ息を潜めて来たる時を待っている。
「でも、追放を受けた理由は示されていなかった。理由を知ろうにも誰かに話す事も出来なかったから諦めてはいたけれど…まさかこうして相まみえる状況が来ようとは。」
雛芥子は自身の姪の瞳を注視しながらハッと笑い声を漏らす。
「都会には妙な噂が流れ込むことが多々ある。無論我々組織が意図的に作り出して放すのも多いがね。それらの中に一つ、死んだ人間の身体が忽然と消える、と言う噂が混ざっていた。世間は掃除屋だのゾンビだのと益もない当推量を楽しんでいるけれども、私は直ぐに分かったよ、あゝ、王国の空に沈んだのか、と。」
「逸れ者のことか。」
「噂を耳にした後は虫達の目を盗み聞いて今の王国の内情を知るだけだ。虫達はこぞって貴様を褒めていたよ。人の姿をした王女は勇敢なお方で慈悲深いとね。…まあ、如何にも呑気な考えだと唾棄したさ。そんな素晴らしい王女様に一つ質問をしよう。何、根本的で初歩的なものだから簡単に答えられるだろうよ。」
「何か。」
「王国が何故逸れ者を連れて来るか、考えたことはあるかい。」
雛芥子はそれまで吸っていた物を灰皿に押し潰すと、新しい葉巻を胸ポケットから取り出し、火を点けた。
「伯父上。それは、王国が果たす使命の為だ。地上世界での罪人達を再び地上に返す、王国で心根を正し、今度は良い人となって生きて行けるように。それが、私達の故郷が担う役目だから。」
「それは本当に必要か?」
葉巻の香りは苦い。
「王国がある以上、必要でない筈が無いだろう。」
「王国があるからは一旦置いておいて、役目だけで考えて御覧。世界の機構の一つとして、罪人達を死後更生させて善人として新たに道を歩ませる。その過程は世界にとって本当に必要な一手間なのかな?」
雛芥子は微笑んでいる。心から微笑みながら旭影を警戒し、葉巻を無骨な指で軽く弄びつつもう片方の手指は自らの一番目立つ傷痕をじっくりとなぞっている。
「その、米神から鎖骨へ掛けての大きな傷。地上で負ったものなのか。」
旭影は直ぐに答えが出せなかったようだ。相手に引き込まれてしまいそうになるのを回避する為、目の前の景色に集中する。
「これは父上に付けられたものだ。」
食虫植物の罠。再び王国の話に戻ってしまったではないか。
「お祖父様に…」
「さぞ立派な祖父だったろう、君にとってはきっと祖母も。あの国での立派の定義は、どれだけ国を愛しているか、愛国心の深さが徳分を表すのだよ。それで言えば私は立派からはかけ離れた存在だったろう。」
「王国を、憎んでいたの?」
「何故憎んでいたのかと尋ねる?」
溶解液に身体を浸けてしまった獲物はたゞ虚しい風鳴りの谺を聞くのみと思うてか、雛芥子は会話の中で相手に余裕を与え始めた。殺気も幾分柔らかくなり旭影にしっかりと考える時間を持たせたのは断じて油断に因るものでも憐憫から来る情けの為でもない骨の髄まで彼女の思想を知りたいからである。
「王国を愛していなかったから立派とは言えない、のでしょう?愛の逆は憎しみ。貴殿は王国を憎んでいた。それに気付いたお祖父様が地上へと追放した。国を憎む思想を広めてはならないから、箝口令が刻まれた。」
あゝ、トルマリンの面影が端々にちらつく。物言い、考え方、いや、苛立ちなどしていない。していない筈なのに、父の顔がフッと旭影の背中に浮び消えたら米神と鎖骨の傷が痒くなり、疼き出してしまう。
吸い終わった葉巻を鎖骨に押し当て火を皮膚で消す。幾分かこの娘へと集中出来る心境に戻っていく。
「旭影、君は愛する心の正反対が憎しみだと考えているのだね。」
肯くか。まさに王国の思想を見事学び修めた優等生の反応だ。
異物を一滴垂らせ。
「私が王国を追放されたのは、国を愛していたからさ。私は王国の使命を放棄する事を奏上したのだ父上に。」
鎖骨の辺を凝視している。火傷の痕から目を離せないでいるな。とても大の男を殺せる実力の持ち主とは思えない瞳。
染みを作って搖さぶれ。
「君の父上…私にとっての弟で現国王陛下が生れた時、私は彼を抱っこさせてもらったんだ。あの時のガーネットの幼い光を私は今でも忘れない。嗚呼、此の子には醜いものを見せたくないと当時は、否、追放された今に到っても祈った、祈り続けている。だから地上での愚者を落す空を塞いでしまえと、紫陽花の空をむしってもう役目なんざ捨ててしまえば良い、隠れた世界で静かに、のどかに暮らして行けば良いではないかと。そう申し上げた瞬間、烈火の一太刀を喰らったよ、悪縁を断つ炎の怒り、目が覚めたら私は地上の人間になっていた。故郷は完全に沈黙し、何度帰ろうと思っても帰られない、私は王国から追い出されたんだ。」
瞳を閉じて眉根を寄せる。だが目を再び開けた時、雛芥子は我知らず固まってしまっていた。何故ならば、目の前に座る乙女が三日月の光輪の如き微笑みを浮べていからである。
引金
「何とまあ、幼いこと。」
王女は膝の上で作っていた握り拳をほどき丹田の前で両手を組む。今度は正反対に雛芥子が前傾姿勢になる番だった。
「幼い、とは私に向かっての単語か?」
「えゝ伯父様。貴方に向けての言葉で間違いありません。」
「伯父だと言う口から出る言葉とは思えんがね。」
冷々然たる湖面の凪。水面の奥は何時でも温度が低いと聞く。伯父の小枝でせっせと編み出し仕掛けた罠を纏めて身に受け一息憐憫と共に流れ去らせる渦巻く余裕よ。
「伯父上は人を殺めたくなかっただけでありましょう。」
「まさか。此方に来て殺しは澤山したさ。経験の不足する者が組織の長を任される事は無い。」
「では何故王国では殺しをしなかったのです?……どうやら殺しの素地は備わっているようにお見受けしますが。」
「それは、」
「私の父に醜い血を見せたくなかったから?」
「そうだ。先刻申した通りさ。」
「愚かな。もっと潜りなさい。」
言い放つと同時に組んでいた指を即座に離し頭の後ろに付けたまゝのミント色のリボンを片手に握る。その手に力を更に加えて雛芥子の不意を突かれた顔の真ン前に突き出し動きを止める、この間僅かに人間の瞼を驚かす間、瞬きをする一寸にさえも満たない光陰の矢。
「答えておくれ。幼き火徳青年の頃よ。」
部屋の明りの白色燈が色を含み出し、注ぐ光は紫陽花の空、故郷の色に染まった。旭影の目の前には火徳青年が椅子に座っていた。旭影は恭しく頭を垂れて彼と会話を始めた。
「火徳殿。お初にお目に掛かります。」
「そう固い挨拶は苦手なんだ。敬語なんか使わなくて良い、君は初めて見る顔だね、しかも人間だ、逸れ者?」
「えゝまあ。今は此方で修行を積んでおります身でして。」
「へえ、地上の故郷に帰りたいから修行に励んでいるのかい。」
「いいえそうではありません。私は地上を故郷と思いたくないのです、何も幸せを感じ取れません場所でしたから、戻る為の修行ではなく、王国の民となりたくて、今は蛾の麗人に使えて勉強中です。」
「と言うことは…君は今お弟子さんの立ち位置に居る訳だね。名前は?何と言うのだい?」
「わたくしの、でしょうか。」
「無論だとも!話をするのに相手の名を聞かない間抜けはいないからね。」
「かしこまりました。それでは…地上で生きている時は、柘榴と呼ばれておりました。」
「柘榴!うん、良い名ではないか。丁度私の弟とよく似た瞳の光をしていると思っていたが、不思議な巡りあわせだな。私の弟は麗しいガーネットの姿をしているのだ。同じ言葉を持つ者同士は、似通う所があるのかもしれないな。」
火徳青年の姿には未だ追放された時の傷痕が無い。雛芥子と名告る直前の姿であろうか。もしそうならば彼が殺しを避けた本当の理由が分かる筈。
「ところで殿下、お尋ねしたい事がございます。貴殿の御機嫌を損なう可能性の高い質問内容だと存じますので、どうか、お気分を害されても私との話を切り上げないでくださいまし。勝手なお願いとは百も承知、どうか…」
「良い、良いのだ柘榴。頭を上げなさい悲しくなるから。大方前置きの時点で大抵推測出来たよ。私の謀反を止めに来てくれたのだろう?だがもう私の決意は固い。これから父上に上奏しに参るところだ、止めても申し訳無いが其の手を振り払う。折角此の王国を愛してくれている者への無礼とは分かっている。それでも私は王国から使命を放棄させなくてはならんのだ。許しておくれ。」
「何故、何故使命を切り離すのです?」
「君は偶々善き逸れ者の土台を持っていたから例外だが、逸れ者とは基本碌でも無い事を地上で犯していた輩だ。そのような汚濁に塗れた醜い者共を弟に見せたくないんだ。だから使命を放棄して紫陽花の空を剝ぎ取ってしまえば逸れ者が落下してくる事もそもそも無くなる。」
「ならば貴方が殺せば良いでしょう。貴方は王の子でありながら人の身体を持つ者。人間の身体は殺しが可能な構造になっています。貴方が逸れ者を、狼藉を働く侵入者達を殺せば良いではありませんか。国軍を指揮する立場になって、侵入者を追い詰め、とどめは貴方が手づから行なうのです。」
「君は……まるで経験してきたみたいに淀み無く言えるのだな。……地上でも、そのような仕事をしていたのかい?」
「えゝ。そうして守って来たのです、愛する者達を。」
これまで一度も顔を俯向けなかった火徳青年は、椅子の背もたれに初めて体全体を載せ、手は左右にくたりと垂れて頤はようやく襟に触れた。睫毛しっとりと伏せられた瞳の色は、きっと先代国王陛下に似たのであろう。
「殺してしまったら、父上は私を見捨てるかもしれない。」
火徳青年の輪郭が震えて鳴る。哀切なる歔欷はヴィオラの弦擦る弓の響きと異ならず。
「私は人間の見目と機能を以て生れて来た。世継ぎが私しかいない時は、父と母を疑うこともなかった。ただ自らの務めを、責を果たすのに必死で、傍目もふらずがむしゃらに励み続けられていたのだ。」
「けれど、弟が…私のお父様が誕生したのですね。」
力無く頷く心は、旭影とて同じ。
「両親や国民と同じ姿をした王子が生れたのであれば、何かの理由を付けて手離したくなるのではないかと…私は弟を抱いた時疑いに取り憑れ、本心に覆いを被せ、恐怖に怯え、人の子の姿の者が果たすべき役目から逃げた。」
自分は一人っ子だけれど、若し、下の子が生まれていたら如何したのだろう。火徳青年のように悩み恐れて逃げだしたくならないと断言出来るだろうか。彼の寂しい郷愁は時計の針へと輪郭を変えてピシリと罅が入り涙は空気に溶かされた。あゝ、表層を剝がせただけでも良しとしなければ。耳元で空を切る鈍い音にたじろぎもせず雛芥子を正面に見据える。
「隙を突けば撃ち殺せると考えたが、流石に甘かったか。」
弾を装填するレボルバーは爛々と眼を光らせる。後ろの壁に突き刺さった一発も牙は萎えていない、息を潜めて次の機を狙っている。
「伯父上、私と殺し合うのか。」
「可愛い弟の一人娘だからと思わない訳では無いが、だから何なのだとも思っている。此処でおまえを殺してしまえば、王国も閉ざされ美しい世界は汚れずに済む。もう罪人は墮ちて来ない。」
私を殺したところで
「王国の穢れは払えない。それに、王国は責務を放棄しない。」
「それはやってみないと分るまいよ。」
「組織の長ともある者が随分と見通しが緩やかだな。幼稚な感情が抜け切れていないぞ?」
「おまえは恋心が隠し通せなかっただろうが。」
蛇の舌と鷹の眦は火を噴き地上を睨み互いに互いの首を喰いちぎろうとする権幕よ、故郷を愛する者と愛する者の信念の違いは凄まじく、止まらぬ大百足の渦巻き土削り毒噛む姿に一輪とて違わない。国想う故の殺し合いはとは日常の中に潜んでいる。それは紛う事無く人の姿が編み出した哀しい遺物の一つである。旭影と雛芥子はビルの中で隔離された真白の座敷牢で殺し合った。
水面下
地上で暮らしていた王国の国民達が、ぽつりぽつりと帰って来た。留守番のお茶会は出迎えのお茶会となり、住居が点在する躑躅ヶ雪町は賑わいを見せ、夜も螢袋の街灯は輝き、帰国を祝う歌と御馳走の掛合を微笑ましく照らしている。土草柔らかき和毛のような足取りに、ポンムも新月も祝いの歌がまだ鼻から抜け切らぬ。こんな時に、泉下の歯車は動き始める。
「ポンム様、新月様。」
鈴の音に振り向けば、カロコロリ駈け寄って来たのは石英のシロガネボタン。
「おやルリム、一体如何したの?」
ルリムと呼ばれたシロガネボタンは僅かに息が切れている。どれ程速く翔けても体力の有り余る此の種族が息を荒く吐くのは余程の事、ポンムと新月のもとまで全身全霊の力を込めて急ぎ走って来たと言外に示す証拠である。
道から少し逸れた芝生にルリムを座らせ休ませて、二人も彼女を挟むようにして横に座った。
「国王陛下と女王陛下には真先に申し上げたのですが、お二方にも早くお伝えしたかったので、走って参りました。陛下の伝令を待つ間も惜しくて…」
「ルリム、一体何が?」
問う新月の顔を見て、ルリムの顔色はみるみる血の気が引いていき、終いにはワッと泣き出してしまった。
「新月さま、どうか、どうかお気に病まれないでください。地上で人として生活を続けているだろうとは予想していました。ですが、まさか、貴方様と関わりのある人間となっていたなど、誰も予測がつけられなかったのです。そんな奇縁が貴方様とあのお方の間に結ばれていたなどと。」
「あの方?」
「火徳王子です。先の王様の長子、陛下の兄君、旭影様の伯父上であり、貴方の所属していらした組織の長。」
「雛芥子が?」
鈴蘭はよく会うと言っていたが、自分は一度しか顔を合わせた事は無い。初めて組織の床を踏んだ時、手を曳き連れて来たのはあの男だった。
(今日から此処が君の世界になる。生きるのも死ぬのも此の業界でだけ為されることになる。見込みのある子供は近頃減ってきていてね、新月、君は久々の逸材だよ。それを決して忘れないように。自信を持ち己を励ましなさい。)
言葉だけが優しかったが、それはあくまでも使用している単語と組み合せの話で、声色・視線・握っている手の力の籠め方・口元・服の色や生地・形に到る迄他者を拒絶するものだと強く恐怖を抱いた記憶は王国の清流でも雪げなかった。何より一等恐ろしかったのは視線だった。否、若しかしたら眦の傍にも走っていた裂け傷だったかもしれない。
尋常ではない男。それがまさか王国の追放者であるとは。
「嗚呼、旭影様!」
ルリムの叫びは悲鳴に近かった。波に弾かれ声の掛けられた方角へと首を向けると、王国に居る時と寸分も変らぬ姿の旭影が立っていた。
「只今帰りました、皆、そして旦那様。」
たをやかな微笑。その顔にも衣服にも手指にも髪の毛にも、一滴の血も連れてはいなかった。
「銃を使って殺し合うのですもの、随分地上では塗れましたよ。血にね。」
玉座の間にて旭影は少し呆れた表情で笑う。
初めのうちは鉱石に表情があるものかと疑い深かったが、今では以前の自分を無知と笑いに付すことが出来る、それくらいに王国に馴染んだ新月はそれゆえに今は危惧している。
国王陛下と女王陛下のお顔に、恐怖が見てとれるからだ。
雛芥子の関係者として新月も旭影の御前報告に立ち会ったが、ずっと穏やかなまゝで、恰もお茶会を満喫しているかのように楽しそうに笑みを湛えている最愛の妻の様子に、胸騒ぎが抑えきれない。
「そう言えば、旦那様のお知己に、鈴蘭と仰有る方がいらっしゃったでしょう。あの方も、遅れて座敷牢に突入してきましたので大変な撃ち合いになりましたが、王国での経験は幸いにも彼等に勝りました。不意を突いて、心臓と眉間に一発ずつ貫いてきました。もう過去の追手に怯えることもありませんよ。」
殺せたと言うのか。あの隙の無い相当な手練れ二人を相手に。
「兄上は、今でも御自分の理想を諦めておられなかったのだね、旭影。」
「やはりお父様は伯父上のことをお察ししていたのですね。」
「書物に納得出来んことなど幾等でもあるものだ。父上は私に兄の存在を教えなかったが、私は父上を完全に信用はしなかった。何か、隠しておられる事があるのではないかと。だがその御心を無下にするのもまた情に反するのではないかと悩み…父上が天寿を全うなされた後、私は先代の御治世に関する本を編集させた。」
「では、あの序文は…」
「私が直接記した内容そのままを刻んだ。知ってはいてほしい、だが口を噤んでいてほしいと願ったのは私の意志によるものだ。」
「お父様、お母様。」
国王の話を黙って聴いていた娘は、唇を軽く噛みしめた。
「私が、おぞましいですか?」
一人娘を見つめる眦に怯えと嫌悪が深く混じっているのは感じている。そんなこと無いと嘯かれたら睨んでしまいそうだ。
「私は伯父上と最期迄意見も考え方も合いませんでした。仮に私にとっての油のような相手が国民の内の誰かであったら、地上で遭遇した誰かで会ったら我慢出来たのかもしれません。そのような捉え方もあると己を納得させることが出来たかもしれません。
ですが決して相容れない存在が身内に居たらどうなのでしょう。私には到底耐え切れませんでした。憎くて憎くて堪らない、嫌わずにはあられない、彼奴が苦しめば私は嬉しくなる、溜飲が下がる、心地が良い。あの時、座敷牢で伯父上と対峙した時、王国を守る為ではなく、自身の快楽の為に私は殺しを働きました。殺し屋組織の長を殺したところで地上から殺し屋稼業が無くなる訳でもないと言うのに。」
駄目だ、保っていられない。
「旭影……」
顔を覆わずに泣く姿は初めて見る姿ではない。けれどお師匠がご両親に名前を呼ばれてそれに応えず涙を零し続けて嗚咽も止めないのは初めてだった。
若しかして、此の方に国防を任せるなんて、自分達は負わせすぎていたのではないか?けれど、だからといってどうするのだ。人間に託せないのであれば、誰が略奪者から国民の生活を守ると言うのか。此の身は蛾である。人にはなれない。
「おまえを疎んじることは決して無いよ。今迄も、此れから先も。ただ、ね、恐ろしいと感じなかったと言えば真ッ赤な嘘になってしまう。私は、おまえの殺しの実力に恐怖を感じた。先代はとても剛力な御仁であった。私はその才を継げなかったがね、新月君のお話を聴くと、きっと戦闘の才は兄上が継がれたのだろうと思う。その兄上をおまえは射た。それも多対一でだ。それでも、おまえを疎んじることは無いのだよ旭影。」
「旭影、私達の国に暴力に恵まれた者はいない。国王陛下を…お父様を見れば分かるでしょう?王は国民の象徴、戦う力など持ち合わせていない。その事実は女王である私にも当て嵌まる、私は武に愛されなかった。国民を守りきれないもどかしさは、先代を送ってからは私達の中にずっと渦巻いていた。――貴女が私達を選んで生れて来てくれる迄は。
貴女には確かに殺しの才能がある。その事に私達は戦慄いている。武力の欠片も習得出来ない私達の間に才能の塊が誕生するなんて、と信じられない気持ちは今でもある、でも、でもね旭影。
貴女が一人の可愛い正直な女の子であることも、また事実なの。私達も、ポンムも、新月殿も、それに国民も女神も皆分かっている、貴女が王女であり国防の要である以前に、一人の優しい女の子だと言うことは、王国の者はよくよく分かっているのです。だからね旭影、私達のかけがえないいつまでも愛しい子…どうか自分を嫌いにならないで。貴女は、あらゆる感情を持っていても良いのですよ。」
私が持っていて良いのなら、お父様達も、新月さんも、ポンム達だって持っていて良いものだ。拭えない感情を負い乍らも愛してくれるのであれば、私はその愛を抱きしめかえしたい…
責任も、秩序も、見栄も無い。今玉座には疲れ果てた娘を抱きしめる親子の姿だけがあり、一番弟子と二番弟子も師匠を一緒に抱きしめた。
愁殺
火徳は既に王国を追われた身であるので、両陛下は旭影を罪には問わなかったし、そもそも此の国には刑法のような法律が無いので、王女は再び日常生活を躑躅ヶ雪町で過ごす日々に戻ることが許された。しかし、王女は外の世界を知らなかった頃の自分には戻れない。
「組織の奴等を全員殺したのか?」
「全容まで把握は出来ませんでしたが、向かって来る相手は残らず。」
「それだと多分全員になると思うが…」
夫婦の家でお茶会の話題としては随分血生臭いが、避けるのもまた違う気がした。問うても良いかと尋ねれば、ほんの少し睫毛を翳して瞳は頷いた。
「雛芥子の本性、直ぐに見破れた?」
「えゝ。握手を求められたけれど、拒絶しました。心を許してはならない恐怖を強く感じて。鈴蘭とはまた違う怖さでした。底無し沼が隠れた落とし穴まで笑顔で招くような奸佞と爛漫さがありました。…あのような人の下で生きていたのですよね。」
震えている手にマグカップは危ない。ホットココアにマシュマロを浮べた甘い湯気も、雛芥子のおぞましさには太刀打ち叶わず、無理もない。カップを手に取り、二人座るベランダの長椅子に置く。旭影の顔は沈む陽に向けられており、湖面に斜陽特有の沈黙が反射し映っていた。
「一度しか対面したことはないんだ、彼とは。義父に捨てられて初めて逢った大人が雛芥子だった。口調も言葉も優しかった。後から同じプログラムを履修している同年の子達も口を揃えて雛芥子さんはお優しい、身寄りの無い自分達にも親身となってくださる、話をされる時は必ずしゃがんで、幼い者の目線に合わしてくださる。…もうその時点で洗脳は済んでいたのさ。」
簡単な方程式だ。憂き目辛い目を見て来た子供に大人の身近な優しさを加えれば、酷い環境から自分達は救われたのだ政府の手によって、と信ずるようになる。そして一番身近な親しい親は雛芥子だと刷り込まされて、結果は政府と組織に従順な駒となって行く。例え自分達の末路を事前に教えられても、逃げたいと望む者はほゞいなかった。
「貴方も、洗脳されていたのですか?」
「否、俺は少し違った理由で組織と顧客に従順で在り続けた。」
「それは…?」
「忠義や恩なんかじゃあない。俺はたゞ、死ぬのが怖かっただけなんだ。尤も…いずれは組織の誰かに仕留められて路傍で死ぬ事実は理解していたよ、真ッ先に話された事項だったからな。それでも、今此の男の提案を吞まないと其の場で殺されてしまうのではないか、雛芥子と言う男が只管に怖かったんだ。だから仕事に忠実で在り続けて、露命を繋いでいくしかなかっただけ。」
まだ幼い子供に与えられる選択肢を雛芥子は一択に絞ったのであろう、相手に選ばせる手段を限定させるのは戦争の常套手段である。一目見て新月を見込みのある者と考えたのかもしれないし、他の子等と同様に扱っただけかもしれない。
「殺しは、楽しかったですか?」
新月は黙った。鈴蘭から話を聴いたのだとすれば、どう取り繕っても弁明は出来ない。
「育ての父親の家族を皆殺しにした時は、愉快だったよ。」
瀕死の子供の何で何でを思い出す。
「それまではまだ死にたくないから仕事を確実にこなしていたから楽しみも喜びも感じる暇無かったんだが、彼奴等だけは違っていたな。心が満たされる気配がしたよ。義父を撃ち抜く直前に鈴蘭としていた話題の所為もあるかもしれないけれど。」
憎しみだの哀しみだのが一気に噴き出して、悲憤の槍となって背中を突き刺したのだ、その弾みでライフルを握ったに違いない。憎いからこそ哀しいからこそ脳を零して絶命した義父の姿は心地良かった。弾みは陽気なステップに変貌して奴等の大切にしていたかけがえの無い者達にまで歩み寄った。
バン!バン!バン!
踊りなんて苦手なのに筈だったのに。
地上で赤ン坊の新月の境遇を聴いて来たから、彼に生き残る為の術は選べなかったのだと考える。碌でなしに捨てられて人でなしに拾われて生き永らえて人肌を知った後に捨てられて。散々だと思わずにはいられない。親を選べない者が臥薪嘗胆の目に遭うなんて、王国ではそもそも親を選べない事例の方が歪である。子は親を選び女神の夢と意識を繋ぎ同調させる。生れた後の宿命までは分らずとも、王国で生まれる命は残らず親を選ぶことがごく自然なことなのである。
「私は女神さまの一柱に呼ばれて、その呼び掛けに応えた。だから私はお父様とお母様のもとに生れて来られた。流石に人の姿形で生れることは知らなかったけれど。」
でも、此の姿で在れたから私は貴方と夫婦になれたのかもしれませんね。
心の呟きは声に表れ、新月の耳に届いた。自信がありそうで自信の無いのも、夫にならないと分かる由も無かったであろう。確かに同じ見目形をしているから馴染み易かったのは確かである。王国に墮とされた当初は虫達と目で会話しあうなど持ち合わせていない技術であったし、未知の文化であったから。
「旭影は橋を治める役割なのかもな。」
「橋?」
「そう。地上には橋にまつわるちょっとした逸話が幾つかある。その中でも一番有名なのは、橋姫の物語だ。
橋姫は言葉の通り橋に住みつく妖でね、古い物語では鬼として扱われて退治される場合もある。まあ最も有名なのは鬼女として描かれたものなんだろうけれど、地上は一つの伝説や伝承に複数の顔を持たせるのが習わしだ、別の物語では薄幸な女性として哀れみを誘う設定がされていたりもする。だから一つのキャラクターに納め籠める事は難しいのだけどね。」
「それで、貴方はどうお考えなのです?」
「俺は二つの側面を感じている。一つは分断、一つは掩護だ。」
「えんご?」
「掩い護る、と言う意味の物語さ。王国を守る為に侵略者を断つ、その一方で国を護り乍らも罪人の、人間がまた良い音を持って地上で生れることが出来るよう王国の使命を果たし続け人間達をも護っている。そんな姿が橋の守り手・番人とされる橋姫と重なったんだがね。」
「私は、人間を殺す一方で人間達を見捨て切れていない、と言うことでしょうか。」
「まあ具体的に言うなればそうか。でも良いんじゃないかそれで。矛盾は人の持つ特権でもあるのだから、ね。」
二人はやはり微笑み合う。
「貴方、よくそのような難しい言葉御存知なのですね。一般にはあまり聞き馴染みの無い熟語のような気がしますけれど。」
「義父が、よく使っていた言葉なんだ。国を掩護する、その為には政府を倒してどうのこうのッてさ。奴は政府を兎角敵視していたから毎日聞かされた、だからよく憶えてはいる。殺しをしている時は一度も思い出すことなんざ無かったが、今、ふと思い出した。不思議だよな、碌でなしとの記憶が今になって訪ねて来るなんて。」
陽が沈みきって夜の幕が開いた時、新月は初めて人前で涙を零した。
デザート
全ての罪人が王国に降って来る訳ではない。王国を経ないで墮ちてゆく者も数え切れず、と女神の一柱にこっそり教えてもらったことがある。
では、弟弟子の親達や、お師匠の伯父は此の国を訪れることも無いのだろうか。弟弟子の親の方は若しかしたら此処に来て名前を既に奪われた者の一人になっているかもしれないが、いずれにせよ墓からでは誰が誰だか分かりはしまい。
伯父は国を追われた身だから、きっと此処へは二度と戻ることは叶わない。仮に戻れるとしても当人が拒み続けるだろう。
そう言えば、お師匠の話で面白そうな奴が一人いた気がする。花の名前、確かスズランとか言ったっけ。新月の同僚だのと言っていたようなそうでないような。
「ポンム、早くいらっしゃい。」
「姉さん、儀式が始まりますよ。」
私を呼ぶ愛しい声がする。これから新月は正式に弟弟子となる女神様も天も地ももう支度は整ったようだ。私は極光の翼を羽ばたかし、新月の為の儀式へと向かって行く。
物語の続きは、また後で。
終幕
「陰陽」