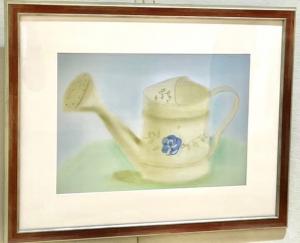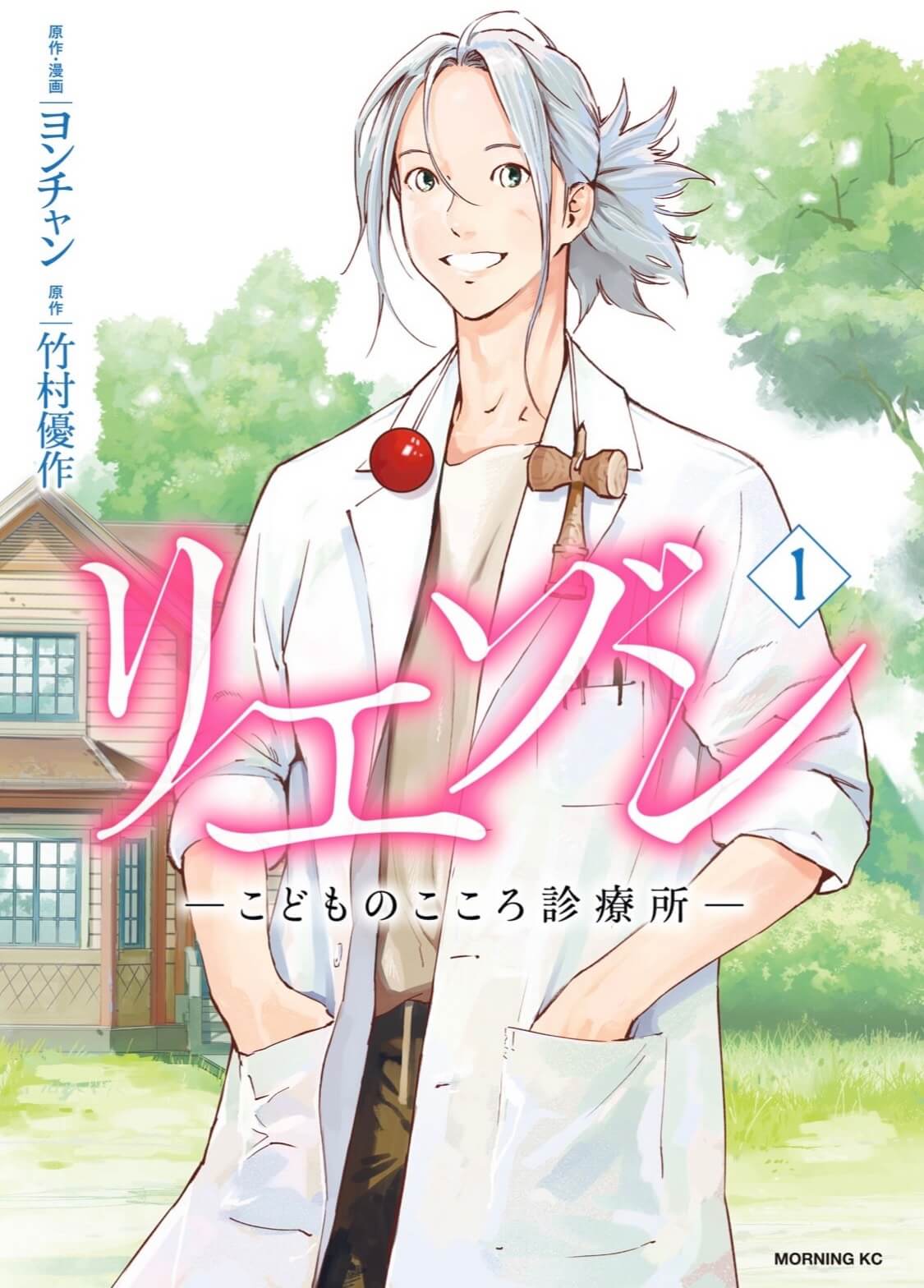
漫画『リエゾンこどものこころ診療所①』個人的な感想
《ジャンル》漫画/児童精神科
※あくまで私個人が感じた感想に過ぎません。
ご参考までによろしくお願いします。
第1巻では、
①発達障がい(ADHD / ASD / LD)
②強迫性障がい
③うつ病
④双極性障がい
についてのエピソードが漫画で描かれております。
大切なのは、
障がいの有無に関わらず、自分の特性にあった安心出来る環境を知り、「自分にとって丁度良く、心地良い」と本心からそう思えること。
そして、「得意なこと」や「好きなこと」を活かして伸ばして行くことが大切なんだと私は感じます。
「子どもと向き合うということは、自分と向き合うこと」ー本文の言葉よりー
この言葉は、
「人と向き合うことは自分と向き合うこと」
「自分と向き合うことは人と向き合うこと」
そのことを思い起こさせてくれる言葉。
【所感:大切なことを思い出させてくれる】
「どうしてそんなことをするのか」と、本人の行動を「問題」として捉えないこと。
「困り事の背景は何だろう」
「どうしたら本人にとって安心できるかな」
「楽しんでもらえるために、自分には何が出来るかな」
「本人にとって、どういう時に安心や不安を感じるのかな」
「周囲の人だけでなく、本人が1番苦しくて抱えているのかもしれない。そのことを忘れずに、見たままの表面だけで判断せず、粘り強く向き合い続けて理解することが大事」と、前向きに当人の気持ちを理解することの大切さを教えてくれます。
「本人が心地良いと感じる環境はどんなことだろう」と、自分の考えは入れずに、本人の目線になって考えることも大切。
自分の我を忘れて、相手の気持ちや感情にフォーカス・尊重して、
お話を遮らずに最後でじっくりと待って、聴くことも大切。
周りからすると問題に感じてしまうその行動には、子どもたちからの「助けて!」というメッセージでもあるということ。
人と人との衝突は、「助けて欲しい!」という魂の叫びのぶつかり合い。
何事も1人で抱え込まないことが大切。
「話し合うこと」は、困り事に対してみんなの気持ちを確かめ合いながら理解を進めるためにも必要なこと。
「この人はどんなメッセージを伝えようとしてくれているのか」
という、自分だけでなく、
相手の気持ちを理解する姿勢の大切さを教えてくれる優しい物語でした。
最後までお読みいただきありがとうございました。
漫画『リエゾンこどものこころ診療所①』個人的な感想