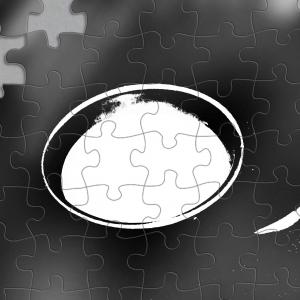「守りて」
序詩
眠る夜に月の幻燈を仄かに焚く
睡眠薬のまどろみが未だ微笑んでいる内に
銀白色の鍵を掛けて錠を下ろせば綿毛の散る音
懐かしい雨音に被さって霙はいつしか霧へと離れている
駈け出して
雨の中佇んでいればきっと来てくださる
品の良い蛇目傘で困ったように笑う人
振り返って 泣きながら そうした方が楽だけど
旭の極光は必ずやって来る 雨などお構いなしに
待ち続ける時ではないと自分の手首を大きな手で握り込んで
駈け出されていく
もう遠い靄の都 キャンディの街 ホッピンシャワー
遠く離れて遠く引かれてもう影に灰色に滲んでいく
幻燈の移し身カンテラに
月を思って火を灯す
いつまで忘れられないでいられるだろう
いつまで覚えていられるだろう
夜の森枝葉のトンネルを手が引くまま目を閉じて
走りきる後
其処は人気配の一本も枯れた古城
青い滝は枯れずに領内を巡っている
湖に浮ぶ切り絵のお城
カンテラの火は緩まない
影と待つ白いお城
湖に浮ぶ孤独の城
コツ・コツ・と固い靴音 響音に身を強張らせる
いらっしゃいませお客様お一人でのご来店ですか?
一人な訳が無い此処には手を曳かれて来たんだと振り向いても一人だけ
雨音が直き其処迄聞こえて来ているのは
切り絵の城に飛び込んだ 飛んで入っても見慣れぬ恐怖
どうぞ此方へと靴音の反響音が案内する
さあ、順番にお召し上がり下さいませ
誕生石
青緑の石がころころと視界を過ってゆく
足を忘れて置いて来た亡霊達
そんなにいそがなくても君達の家は失くならない
帰る場所があるのならば あるのだから
夏の向日葵が霜を表層に浮べていた
蟬の黒曜石の眼球が凍り始めていた
動けもしない寂しさは
仏壇の前でナイフになって鈴を震わす
死者の姿を生きる者に被せるのは
赤い宝石一つあれば出来るもの
貴女の弟の骨よと言って
首飾りを持たすれば済むだけのこと
父と母は今日も念願の第一子に語り掛ける
貴女の弟の骨よと言って
でも首飾りを付けていたって不思議は無いと
女のような顔立ちの息子に笑い掛ける
文
「望み通りに生きられんのなら死ね、親不孝者。」
机で詩を描いているのがばれた直後、父親は子供を撲り倒した。母は父のもとへ駈け寄り、愛する男の肩を持つ。
「詩なんて何の役に立とう、小説家になる訳でも無しに。」
夫婦は子供に唾を吐き吐き寄り添い合って部屋を出た。
世の中が忙しくなって来た時代のことである。女が男以上に働いて、男が女よりも働けなくなっているのが常となって幾百年過ぎたのだろう、時勢はは移ろわず教会の鐘は何かの部品の一部へ溶かされ寺には無縁仏が群を成し神社には落葉が吐き溜まっている。人はこういう時に空想を望み物語を求め出す。その空想語りが長ければ長いほど土から離れていればいるほど飢えは満たされ渇きは潤い笑顔の持続は長く保ち、首はポキリと中折れせずに済むものを、詩などを描くなど言語道断、子供が殴られたのもその為で。
理由如何にせよ人が人を傷付けて良い道理は無い、増して親が子を虐待するなど以ての外。嗚呼諸君、君達の時代は幸いだ。例え口先だけでも庇護の言葉が生まれるのであれば幸せだ。
先程叱られていたのは白羽と言う妙齢の娘である。白羽は一人弟が居るのだが、彼は産声をあげることもせず肉塊のまゝ手足も生やさずに旅立ってしまった。男子を流産した現実は両親の瞳をくもらせていつしか娘を息子として生きさせるようになっていたので、白羽は年頃のお嬢さんが好む服を一度も着た事が無い。リボンも、帽子も、三ツ編も、何も許された例が無い。
予備兵の格好で街を歩けば、人は彼女を端正な海軍予備兵と錯覚する。喋ってしまえば女だと判明てしまうから口は家でも外でも閉ざしたまゝ、ニコリともお微笑いなさらないところが反って頼もしいではないかと近所では評判で、両親からも自慢の息子だと褒められる。白羽は段々話し言葉を忘れていった。
或日のことである。白羽は街の本屋に用があったので訪れた。両親に頼まれた雑誌を二冊、和歌俳句の本と裁縫の最新刊をそれぞれ買いに来たのであった。無言のまゝ店主に会釈しては雑誌を手に取り会計を済まそうとしたら、視界にちらと赤い本が見えた。
三五〇頁はあろうかな、赤い拍子に金の題字、いかにも派手そうな色味の合わせ方であるのに葉巻のくゆりと洋酒の孤独、そして燃え止しの捨てられた燐寸を思い浮ばせるのは何故。
「おや、軍人様。」
店主の声。
「それは詩集ですよ。この作家は、否作家と申して同じ部類にするのは烏滸がましいですな。この詩集の主はね、詩人と宣う奴ですよ。新聞小説でも書くなら御立派と讃えられもしましょうが、詩人なんざポツポツと一言二言書き散らして喚くだけにございましょう、和歌や俳句のような風流も雅も持ち合わせぬ未熟な八ツ当りの作法です。軍人様のお目に入れてしまい大変申し訳も御座居ませぬ、これはもう処分しようとしていた屑同然の物でして、つい、手前の用事を言い訳に店棚の脇へ置きっ放しになり申して…ハハ、誠にお恥かしい次第です。」
聞かぬことをべらべらと。屑と見なして捨てる腹積りの本ならば自分が貰っても良かろうと、普段頼まれた動作以外は一つもせぬ白羽は店主が会計と包装をしている間大胆にも赤い表紙の詩集を手に取り身の丈よりも大きな袂でそっと隠した。今になっても騒ぎにならないのを見れば、連れて帰って良かったのであろう。
両親にお使いを手渡し自室への階段を上がる途中で我慢ならず一目から伏せていた詩集を開き読み始める。
それは、此の国に無い宗教を土台とした話。物語は単調に適応してしまうことも無く一語一語媚薬の薫りを含む白いヴェールで顔を覆い、ほのかに透ける蒼白の唇から言葉を紡ぐ。寿ぎを否定する冷めた頬、氷柱を煙管にして呑む毒草、七星 背負う小さな虫のやがて蛾に到る湖面下だけの突然変異、その漣。驚いて向けたは青い撫子の朽ちる音、その死体からむくむくと桂の伸びて月を薔薇の形に囲うこと、鳥籠は旭にとろけて陽のしづく、雨は鏡の羽を生やして飛ぶ姿。
生れて初めて己に向けられた遠くの誰かの関心が、こんなに嬉しいものだとは。此の方は、自分に手紙を書いてくれたのでしょうか。まるで、まだ見ぬ会えぬ恋人を想って言葉を綴ってくれたよう。これが、詩。自分の読んではいけないとされて来た類の本、知らない言葉、小説には表しきれない心情の独白、音の許されない歌。
詩集を胸に抱きしめて、そっと作者の名前を見つめて静かに静かに声に出す。
「星北川面。星北さま、川面さま。」
反骨無頼
家の傍を流れる緩やかな小川に、首根っこを引ン掴まれたまゝ顔面を突込まれた。親父とお袋の顔はそれ以来見ていない。くそくらえ。そんな感情の癒えぬまゝ家を出て、群衆に紛れて都会へ流れる。敗戦国の人だかりは数歩歩けば直ぐに見つかる、薄汚れた格好を咎める者はいやしない。
何度戦争に負けたのだ。国々同士の調停役を買って出て圧倒的な兵力・兵器差と士気の高さの前に幾億の肉塊が産まれたろう。熱狂する若者、老爺、涙を流す婆、世間体を気にする婦人。戦争を止める為に戦争をするのだと大義名分を用意しておくと動搖は抑えられ平静を保てる、事前の準備が大切と言うのはそういうことだ。
諦めずに立ち上がり、国は随分とゲッソリ痩せたようで、都会の熱狂の大通りの裏手には冷めた煙草の毒が霧のように待機している細い路地。健気な台詞は人の心も国の体形をも駄目にするとは、これ如何に。
北へ北へと流れゆく。食べる物は道端の死体から奪えば済む。懐に入れた万年筆をしわくちゃの原稿用紙の無事を確かめると徐に取り出し暫く佇んでみるが、今はやはり何も思い浮かばない。が、
「あゝ。」
丁度良い。生まれ持った名を捨てて、好きに名乗ってしまえば良い、所詮家を失くした身、誰に何と言われようが貴方達に迷惑は掛けることも無いのですから。
此れより内へは来るは易し、踏み入れ易い足置き場
帰りのお靴お草履は御座居ませんのでさようなら
別れを済ましてお入りなさい
貴方が覗くは硝子の秘国
逆しまなテエブル・クロスにティーセット
紙ナフキンは船になり申す
指を弾いていただきましょう
煙草を刻んで振り掛けたロオスト・ビイフ!
銀食器持て金の盃満たしてしまえ
大いに食え食え!鏡の正面
質素に暮らす敗残國
あゝくだらないファンタジア、リアリズム
夢見がちな女も真面目な男もお断り、逆でもダメダメ入れたげない
よくある話は嫌いなの
ねえいつ手を取ってくださるの貴方様
星北川面
「あゝ良い、やっぱり詩は楽しいな。」
国が御法度とする詩の創作だって、都会の溝でなら朗々と唱えられる。
「そうだ、いつか詩集を出してやる。そしてもう一度詩の地位を押し上げるんだ。」
軍の制服に反して青と銀ではなく赤と金文字、人を直接には殺めぬ爆弾よ。読めば本に夢中になって、読まないでは正常でいられぬほどに詩に飢える呪い。そして自らも詩を作り始めるのだ、かつて国を困窮させた感染症の最新型は言葉生れよ。
「さあ、どうか上手く爆発しろよ俺の武器。」
数年後出版した本は、数年後店から盗まれ、否、此の場合に限ってのみ、救われた。
修行
先づは、ノオトブックに硝子ペンとインキを用意して書き写してみよう。川面さまの詩を一言一句感じ触れるには此の方法がきっと一番良い。真似は一番最初の学ぶ姿勢、意味や理解は後から自ずと付いて来るもの。
「背丈の高い…樹々のあわい…春が雪に遠慮して……」
一階で親が寝静まった後、二階の一室に秘かな娘の声が澄む。幾年振りに喉から音を出したろう、しゃがれた錆声だと思って久しかった自分の声は、失う前の其とほぼ変わりが無かった。
「此方を見つむる寂しい瞳、其の眦、なれど微笑むその唇は、」
さら さら さら さら
「一言も語らぬ、偶像なるか、或いはまた涙を捨てた身か……」
さら さら さら さら
一人で自分の為だけに活動する、秘めていなければならないような、けれど他人に見せたいような、もどかしい時間を筆記の音が軽やかに区切っていく。このような音も感覚も白羽にとっては初めてのことである。楽しい、と呼ぶのだろうか、けれどもヘラヘラしている訳ではない、真剣に、一言一句間違えず書き写す、一文字でも変えてしまっては意味を成せなくなってしまう細い綾糸の連なり。
「これは本当に恋文のよう。川面さまにも恋焦がれたお相手がいらっしゃったのかしら。」
若しそうだとすれば、どんな方?お優しい方、つれない方、蠱惑な方、嘘つきな方、あなたが身も世も忘れて一方的に思い慕いたいのはどのようなお人でしょうか。
「私が川面さまのお立場だったなら……」
このような想像から物語は生まれる。誕生の契機は喜劇悲劇こもごもであるが、白羽の場合は恋から始まった。一目も見たことの無い詩人を思って祈って写した作品の横、それも隅っこにどきどきしながらぽつぽつと言葉を考え、選び、置いていく。
「烏滸がましいかもしれないけれど、いつかあなたのお顔を拝見したい。そしたらまた言葉は綴られるかしら。」
此の日から毎晩、両親には勉強をしていると信じ込ませる為に集めた和歌の雑誌を数種類重ねた机の下で、隠れて詩を読み詩を描く時間が出来た。最初のうちは窓硝子を掠む風の歔欷にも肩をびくりと震わし咄嗟に雑誌で覆うのが常であったがやがて大胆になって来て一階で親が未だ寝ない先から部屋に籠るようになっていった。しかし父も母も息子が和歌の勉強に励んでいるのだと信じ咎めも諫めもしなかったので、白羽は思い込みを味方に付けることが出来たのである。更に都合が良かったのは、詩に触れることで彼女は或程度和歌を作ることも出来たことであった。その為父も母も子を疑う必要も無く。“和歌の勉強を熱心にする予備兵の孝行息子”と捉え続けていられたのだった。
きっと此頃が白羽にとって最も純粋な幸せを感じられた時期であろう。再び国が戦争を始める迄が。
再び世間は忙しくなり始めた。父と母は何時息子が徴兵されるか気を揉んでいたが、戦争への招待状が白羽に届く訳ではないのである、何せ白羽は軍に入隊出来る男子ではないのだから。しかし両親は気にしている、白羽はこの時分かなり肚が据わって来ていたので、或日一階で父と母を手招くと、
「お二人とも、私が軍に呼ばれることは先ずありますまい。我が国の軍隊は何度壊滅しても歩みを止めぬ不屈の軍隊、私のようなこのように声も細い男が駆り立てられることなどありませんよ。むしろ自分みたいな軟弱者が戦場に立てば士気を下げてしまいましょう。ですのでどうか、私の為に心を傷めてくださいますな。」
喉の細さは変えられねども声色を低く下げて演技をすることを新しく覚えた乙女は見事に親を欺いた。父も母も息子の立派な発言に涙を流し何度も何度も頷くのを見て白羽は内心微笑んだのだが、自室へ戻る階段を一つ一つ登っていると、だんだん笑みは薄れてゆき部屋に戻って扉を閉めた頃にはもう項垂れていた。
このような日が幾度も幾度も続いた。その渦中でも白羽はペンを投げ捨てることは一度もしなかったが、初めて詩を描いたあの日の喜びと淡い心は黒く暗い水底の雨にぐっしょりと濡れ始めていたのに、彼女はまだ気が付いていない。
来訪侵入
自分は望まれて両親のもとへ生まれたのだと、まだ娘として扱われていた時に教えてもらった。子供は親を選び自らの意志で生まれて来るの、だから子供は誰しも親を慕い、親は子を慈しむものである、その関係性から親は子に道を示し子は親の期待に応えようとする構図が誕生する、この構図を人の道と言い、道理と言います、人は道理に従って生きる命です。貴女も人に生まれたのであれば道理を弁えておくようにしなければなりませんよ。
母上、母上は私に望みましたか。貴女の望むように生きることを望みましたか。父上、貴方は私にどのように在ってほしかったのですか。私、私は何を望み何を欲していたのですか、何を願って二人のもとに向かったのでしょう。
月を仰ぐ。月は古来より悲しみと慈しみにあふれる存在とされて来た。太陽が居なければ輝けない宝石、磨かれなければ光ることの叶わぬ原石。きっと月が生れた時に悲哀の概念も生れたのではないかしら。
「新月。新月したる。」
涙と共に言葉が零れ、またペンを持ち紙に音さす。
月は原初の涙を知る
それは湖であった、鏡のような悲しい湖
星は湖のか細い声の糸に連なり空へと刺繍られていく
月は自らの姿を見つめている
背後には極光が搖らめいて
月の姿を明るいものへと押し上げようと微笑んでいた
向けていた背中を返し、正面からヴェールを見つめた後、
月は背中から湖へと落ちて行った
遠くの歓喜に微笑うよりも
菫の泣き声に沈んで溺れたがったのである
湖は枯れず今も花を咲かせる水辺
その散る破片を身に抱きしめて透明な血が流れている
天上から零れた傷ましくも美しい硝子の水よ
「月を水に見立てるのは如何言う了簡だ?」
声が明らかに自分に話し掛けた。部屋には白羽一人きり、もう親は一階で寝ている。使用人の類はもうとっくに解雇して、広い日本家屋の中に起きているのは娘一人の筈なのだが。
「おばけ?」
侵入者とも泥棒とも疑わず真先におばけと信じ怖がる女の子の無邪気さと素直さよ、親に娘として思われなくなってしまい己を殺して過ごす荷を背負ったにしては少々呑気だと言わざるを得ないが、発想の転換、仮面を被り心を氷に閉ざした日々の中でも生来の純真さと素朴さを失わなかったのだと考えれば良い、そうすれば彼女の、彼女自身も知らない頑なさもとい芯の強さがおのずと想像さるることであろうと思う。
さて、娘の性格が新たに一つ判明したは良い、良いが此の物語には生憎怪異の類は身を潜めているので、声の主をきちんと把握しておかなくてはならぬ。
「おばけじゃない、不法侵入者さ。」
きょろきょろと部屋を見回していた白羽の背後に音も無く立ち、小さなナイフを細腰にひたり押し付けて脅迫する者は誰。
「不法侵入。」
鸚鵡返しのあんまりな素直さに凶器を持つ方がはあと不安気に眉を顰め息を吐く。見た目ではもっと騒いだりするかと思っていたが中身はどうだ、微塵もナイフに怯えていない、どころかおばけではないのが残念だと少しはしょげているかもしれない声の色。
「要は泥棒だよ。これから都の北に向おうと思ったんだが金が無くてね。まあ、家を流れて飛び出して来たんだから元々一文無しみたいなものではあるが、こんなになっても人間は流石だ、腹が減る。なので手始めに何か食事がしたい、金はその後から取らせてもらうことにする。お嬢さん、何でも良い、生米でも構わない、一つ食べさせてくれはしないか。」
顔を見られたくないのか、恐らく男だろうと思われる声の主は白羽の背後から立ち位置をずらす心算は無さそうだ。背中にまだナイフを突き付けられた姿勢のまま、侵入犯は白羽の腕を掴み家の中を案内させようとしたが、ふと机の上の詩に目線を移した。
(やはり此処で間違い無い。)
「なあお嬢さん、お名前は?」
「白羽。」
「うむ、白い羽、か。白羽君、君は俺のことが怖くないのかな?君頃の年齢なら直ぐにでも甲高い悲鳴を上げそうなものなのにさあ、白羽君は未だ助けも望まないよね。それともアレか、怖い時程声が出なくなっちゃうタイプかな。可哀想に俺なんかに目ェ付けられちゃってね、でもまあ諦めてね、君のような箱入りお嬢さんはどう見たって喰われる方のお人だもの。」
撫肩にそッと手を掛けて、耳元に少し近付き小さな声で囁くように問い詰める、おっといかん、今泣き崩れさせたら事だろう、慣れない仕事は段取りが悪くなってついつい普段の減らず口が疑問と一緒に噴き出した。どうしよう、どうしようもないさっさと窓から木を伝って逃げようか……
「何故漢字が分かったの。」
此処に侵入までして法を破り来た本来の目的を置いて一度逃亡を図った不審者は、白羽の上ずっていない声に動きを止めた。
「何?」
「私、自分の名前がどんな漢字を書くかまで言っていないのに、如何して白いに羽だと分かったの。」
二人の声はひそひそと、内緒の逢瀬でもあるかの如くに秘やかなものだった。
しらは、人の名前、しかも娘、であれば真先に思いつくのは白羽の矢、天使の羽色。白い歯なんて一人娘に付けるものかよ、それに、今時当て字は厳しく取り締まられる対象であるから奇妙な漢字を使っちゃいまい。たったこれだけのことを、困ったことにまだ顔もハッキリと見ていない相手は嬉しそうに聞きたがっている。
「…理由を教えてあげるから、一先ず食べ物持って来てくれるかい。」
レモンとビイフ
「これってもしかして、ローストビイフ?」
「はい。今日の夕食の余りです。母が夜食用にと置いていてくれたのがあったので、それをお持ちしました。」
「へえ………」
「あの…お嫌いでしたか?」
嫌いも何も食べた経験が無いし、食べる為の高額な金が家には無かった。憧れを抱いていた訳ではないが、市井に暮らす者達が容易に食べることの出来ない料理を目の前にして喉がむずがゆくなるのは止められない。
「本当に食べても良いのか。」
「是非どうぞ。その方が自分にも都合が良いので。」
最後まで聞き終わらず薄肉にむしゃぶりついた。長いこと食事らしい食事を摂っていない前に現れたのが高級料理。今此時白羽が警察を大声で呼んだとしても彼は止めないであろう、このような御馳走を食べて刑務所へ走られるのならば良い気分だ。それはそれとして白羽君。
「君、俺が怖くないの。仮にも本物のナイフを突き立てようとしていた男だよ。」
「不思議なことを仰有りますね。不審者に対して男子がどうこう喚く筈は無いでしょう。」
嗚呼、予想はしていたが貴女も大概か。まあ予想はしていた、していたし、恐らく今の世では珍しくもないのかもしれない。でもそんな性分だからこそ気の付くものとはあるので。
「それもそうか。あゝ、御馳走様。やはり食事はたまにきちんと摂るのが好いな、頭が刺激を受けてよく冴える。冴えたところでもう一つの用件を御所望しようか。」
「お金、ですよね。」
「否違う。君、詩集持っていないか?」
白羽の眼が一度泳ぐと素早く半身を後ろへくねらせて戸の向うを気に掛ける素振を白地。搖らいだ、と直覚する。ぐッと声を潜めて男は畳み掛けた。
「若しかして禁句だったか?君一人だけの内緒だった?」
扉の向こうは静かである。両親は良い夢を見ているのかもしれない。娘は薄絹さえ重そうな両肩を自らの腕で確かと抱くが呼吸は一向に深く戻らず外は凪であるのに細かにカタカタ震えている。
「怯えなくて良い。俺は君から詩集を取り上げる為に親御さんに頼まれた訳じゃあない。あのね、君の持っている本、赤い表紙に金の題字を刻んだやつだよ、嗚呼好かった震えが止まったみたいだね。そんなに大切に想われているのなら作者冥利に尽きるや、実に有難い。」
え、では貴方が星北川面さま?
言葉は二人の間に黄色く射す半月の光に吸い込まれ、白羽はそれまで俯向けていた顔をパッと上げて初めて不法侵入者の顔を正面に見たのである。爽やかな高鳴りと苦い締めつけが胸に同時に湧き上がり喉をくすぐって鼻腔に到る、瞬間身体は涙を零す、涙は机に置かれた白色灯の水面を返し湖水に滴る光の雫となってきら、きらと乙女の膝元に一片二片降りそそぐ。少女は泣いた、娘は泣いた、乙女は初めて人前で泣いたのだった。
才たる罰
暴力的でない反応など如何せん初めてなので最初川面は驚きに涼しい眦を見張ったが、女性の涙には幾らか慣れているので袂から手巾を出して差し出そうと次には冷静に思い付き手慣れた動作で袂を探ると取り出した手巾は薄汚れていた。面目を捨てた身では何をしても締まりが無く恰好がつかないらしい。頭をポリリと掻いて何か拭える清潔な物を月明りに探せばティッシュケースにちょこんと収まったティッシュが一箱。それを手にして白羽の傍にそうっと添える、此処までしおらしい川面は初めてである。
暫くの間言葉は黙って待っていた。今はそれぞれの主人が泣き止むのを急いだり泣き止むのを気長に待ったりといそいそどきどき忙しそうだから、部屋には時計の秒を刻む音だけが鳴っている、任された時計は二人をじっと見守って。秒針が幾度も幾度も地球を回ったところでようやく男の方が声を出した。
「此の辺りを歩いて、と言うか彷徨っていると、俺の昔描いた詩を読む声が聞えたんだ、他の人には音無にしか捉えられないだろうけれど、俺にはよく聞えたよ。此の耳に感謝したのは今が初めてだ。それで当分君の家の前で突っ立ってたら今度も詩が届いた。でも今回のは自分の作品じゃないなと首を傾げてみるとどうにも気になってならない。深夜だし、折角だから話のついでに泥棒もしてからサヨナラする計画だったが……
やれやれ、俺は本当に幸せ者だ。」
まだ少し鼻をスンスンさせている白羽に心底の笑顔を向ける、その目は普段の飢えた光の鳴りを潜めた、慈しみの微笑みであった。誰にも今迄向けたことも、向けられたことの無いお互いの来歴の厳しさよ。
「すみません、驚かせてしまいまして、あの…まさか急に、御本人さまに会えるとはこれっぽっちも想像していませんでしたので、私、本当に吃驚して、あの、すみませんでした。」
もうしどろもどろは落着いたかな?心中頷き、川面は訊きたがっていた質問をする。
「月を水に見立てるのは如何言う思いがあったのかな?それが訊きたかったんだよ実は。」
「あの詩は…唯、悲しくて、思い浮ぶまゝに文字をしたためただけです。考えも、何も、あ…無くって。」
生来の才。詩を描くべき人は生れ乍らに決まっている。小説家は努力次第で頑張ったらなれる世界だが、詩人は努力を許さない。懸命に励む者に詩の才を与えず、一見詩の世界に無縁そうな者の所へ赴いて行く。勿論当人は無縁だと思い込んでいるだけで、項に結ばれた可憐な雨の糸は赤子の時から付いてまわっている、詩の才能からは、逃げられない。
ならば存分に使えば良い。借り物は散々に使い古してなんぼだ。
「じゃあ君も詩人として生まれるいたんだな。」
川面の言葉に白羽は頬を輝かせた、雨中に眺む街の灯火の風に怯えつつも光る色の目覚ましさ。
「一度抱えちまったら、もう手放せなくなる。ほら、詩を描くのは楽しいだろ?一回知ってしまえばまた知りたくなる、連綿とそれの繰り返し、見切りを付けられる奴もいるが、まあ詩人はそう出来ないタイプ、言葉を綴らないで丸一日過ごせるか?俺は土台無理だね。食うより寝るより探していた言葉を見つけたら書かずにはいられない、詩を描くのは俺に与えられた唯一の幸せさ。」
「私も…そうかもしれません。一人で机に向かって好きにペンを走らせる時が、唯言葉と向き合っていられる時間が至福です。父も母も弟も世間も物音も、其時だけは私を振りまわさないから、唯一の幸せ、と言うのは少し理解る気がします。尤も、貴方がお嫌でなかったら…の話ではありますけれど……」
また俯向いてしまったデクレッシェンド、自信の無さは自分を示されない場合に起るもの、無理もあるまい、誰も彼女を彼女として見ていないのだろう、壁に掛けた清潔な軍服を見れば大抵事情は察せられる、妙齢の娘の部屋にしては殺風景なインテリアも…
「君は、どうしたい?」
連れ出されたい、と思ったことは?
「……………」
白羽はこっくり黙ってしまう。自分の未来を考えた経験など一度も無かったから、如何返答して良いのか分からずに考え込んだからである。川面は急に表情から一切の感情を消した仄暗い湖を見て背筋に寒気を感じずにはいられなかった。この少女で娘で乙女の瞳は過去も未来も見てはいない、現実だけを映しているかと思えばそうでもない、かと言って空想に遊び続ける眼差しでもない、何を見つめているか分からない、見てはいるけれど見つめてはいない、見つめたがらない堅固な虚ろの意志。未来など過去など現実など全て黒い雨水に同じ、泥の水溜り、流れて何處へなりと行ってしまえど一欠片も痛まぬ無感覚な心、彼女の闇は想像よりもずっと深くひん曲がっている。
どうでも、いいのだ。詩以外は。
燐光
目を覚ませば、まだ深更であった。月は太陽に目を伏せたまゝ街を見下ろし一言も発しはしない、静かな、静かな夜。枕元には一枚の紙切れが、恐らく原稿用紙の欠片であろう、癖のある達筆な文字で
「また来ます。夜更かしの習慣を取り入れておくように。」
と記されている。白羽は紙片を胸に抱きしめ暫くそのまゝ眠っていた。
パチリ 薪が、爆ぜる
いつものように軍服を手に取り、本来予備兵が着用するにはやゝなめらかなる手触りの袖に腕を通す。釦留を掛け違えぬように気をつけて襟を正し鏡の前に立って短い髪を軽く整えてから帽子を深く、鍔持つ指の爪白く。視界が少しくらくらする。
階段を降り朝食の味噌汁の香りに身体を向けて襖を開けると新聞を読む父と仕度をする母の姿。此の家で最も広いスペース。
私が左手に握りしめている原稿用紙を机上に置いて、二双の眼玉がぎょろと詰る。説明をしようと開いた蒼さめた唇からは
「さようなら」
の単語しか顕れなかった。
白羽は撲たれ、勘当された。痛みに俯向く顔は両親を見上げられないで表情も分らない。長い前髪がバサリと目を隠す。
両親が去って行った部屋で白羽は原稿用紙を畳み愛用のペンと洋墨と詩集を入れた手提げ革鞄に収うと、取れた帽子を被り直して家を出た。二人の泣き声に足を止めないよう背を向けて。
「おはよう。」
「川面さま。」
「手紙読んでくれたなら、もう今すぐにでも発ってしまいそうだなあと一応危惧した甲斐はあったな。一度俺もビンタと一緒に喰らったっけ。“箱入り娘を舐めないで”って。本当、侮るものではないね、お嬢さんがたの行動力はね。」
「お供します。」
「あゝ、だろうなあ、そう言うと思っていたよ。まあいいか、おいで白羽君。今日から俺が君の師匠だよ。」
「はい、師匠。」
二人の詩人は此の日から旅に出た、行く先々を決めない放浪の身、自分の為だけに行う外出、遠出、白羽の夜空が星空に染まり大きく見開いたまゝ川面の後を追い掛けた。
昨日の友は
白羽の雅号は無かった。彼女は詩人として名告る際は必ず白羽を称した。まあ実名で小説描いてる奴も澤山いるし、川面はさりとて気にしなかったと言う。
「師匠のお名前は、本名ですか?」
彼女は無口な上に内気で恥ずかしがりやでもあった為、滅多に自分から川面に話し掛けることはしなかったのだが、此の時期一度だけ進んで質問をしたことがあった。
「本名ではないよ。本名はね、もう思い出せない。」
「では何が契機で名告るようになったのですか?」
「うむ。家を出た時だ。俺は親から虐待されていたから、もう少し腕ッぷしが強くなれば今に家出してやる、と毎日毎日狙っていたよ。で、其時を迎えたから家を出た。直前に親父に顔面を川に突ッ込まれてね。川面は其処から取った。星北は、まあ取り敢えず北に向かうからてことで。」
「………申し訳ありません。」
「何を?」
「てっきり、その、心得違いを、私……」
「俺の藝名についてかい?」
「私…その、北極星が冬の澄み冴えた水面に映る景色から名付けたものだろうと、勝手生意気にも考えて…居りましたので……お恥ずかしい、情けない…御容赦を。」
川面の此時の顔。鳩が見れば飯を噴く。
「師匠の詩は、とてもロマンチックで、命懸けの恋文のように思いますもの。だから筆名も、てっきり……」
師匠だよと豪語しておき乍ら早速に面目丸潰れである。あちゃーとむず痒く後悔しながら苦笑する他あるまいて。
「まあ、男が詩を描くなんて物好きにしか見えんだろうな傍目には。詩は女性のするもの、手遊び慰め暇潰し、誰ももう懸命の仕事とは考えてくれんさ、君を除いて。」
「師匠、何故詩はこんなに嫌われて蔑まれているのでしょう。私が物心着いた時にはもう文壇からも世間からも詩は厭うべきものと処断されていました。初めからこのような扱いを受けていたのでしょうか?」
彼女は知らないのか、そうか、一つの幸せでもあるかもしれないけれど知っておいても不幸にはなるまい。川面は此時確かにそう思った、思ったからこそ昔話を白羽に教えたのである。
小説の一節を憶えろ、或いは詩の一節を憶えろと言われた時人は何方を選ぶだろう、勿論詩は詩でも叙事詩のような歴史を歌う長大なものではなく、歌詞の如く短いものであるならば。人はあらすじが好きで、印象的な台詞が好き、記憶力の問題云々も関係しているだろうが心に残りやすいものが好きなのだ。そしてそれの代表格に押し上げられたのが詩であったと言う訳で。詩は讃えられ尊ばれ貴い芸術と見なされ詩人は神聖化された。
けれど人は移り気で、いつだって神を呪い敵対したがる。そうして幾星霜嫌われ続けて来たのだろう、本家本元がそのように扱われるのであればその名を借りた存在もすぐに同じ扱いを受けてします。戦意高揚の為に用いられた詩は敗戦後憎しみと侮蔑の格好の餌食とされてしまった。此処迄話せば詩人が此の国でどのような態度で接されているか見当は付くであろう。
「師匠も、戦意を上げるような作品を描かれたのですか?」
「いんや。」
川面の暮らしは世間の流れと隔絶されていた。それもそうである、子供を虐待していることを他人様に知られたら両親は無傷では済まされない、しかし川面の両親の心配は杞憂であったのだ、だって、汚らしい男子一人大衆がどうしたものか。
「だが此の境遇が今となっては有難いものだったのだよ、負け惜しみのように聞えるやもしれんがね。親は子供に愛情を以て接しなかったが夫婦間ではそうでなかった。二人きりの時だけだと実に微笑ましく仲睦まじい――俺は幼いなりにも恋人と言う存在の美しさを知った、そして家族の情け無さをも痛覚した。だからまあ、君が命懸けの恋文と感じ取られるような作品ばかり仕上げたんだろうよ。」
自分の作品達を他人事のように扱うのは、彼の子を持ちたくないと忌む心の表れであったかもしれない。実際川面は自らの描いた詩を描き終った次の瞬間にはよく憶えていないと言う。それでは師匠の詩が可哀想ではありませんかと弟子は問うたが、彼は少し笑っただけだった。
溺れる翡翠
美しい霙がやって来るのである
わたしの持つ傘を透して額に触れる
精霊達の末期の口づけは静脈に沁みて
やがては白い雪となって頬を伝った
灰色の空に手を伸ばす
愛しく過ごした日々の名残の色
物を燃やす不吉な色が灰色とは限らない
大切な生き物の記憶 その澄んだ瞳と長い睫毛
星は動かず月も動かず
太陽に目を逸らして来た冬の街々
極光は城壁となりやがて視界を覆うだろう
捨てられた唄を肌に感じながら
夜が降る 夜が降る
美しい霙がやって来る
もう鳴らぬ鐘を動かしながら
忘れられない冷たさを抱いて
指を伸ばして示してくれた
遠い燈台の北極星は
きっと今ごろ瞼を閉じて
穏やかに眠っていることだろう
祈りあれ 平和あれ 白い菫よたんと芽吹け
微笑みを忘れた笑顔の街々に霙よ降っておくれ
優しい蔦で抱き包む遠い昔の物語よ
涙を忘れた涙の街々にどうか降りやまぬことの無いように
「新月したるゝ」
復興とは時間が合えば速やかに進むもので、国の中枢機関が集結する都市は数か月で戦前の暮らしに巻き戻っていた。そうでも言わなければ人は前に進めない、明らかに元の通りの生活ではないのに、さゝやかな喜びは旧来と変らぬとして恰も日常が再び送れるようになったと顔の下は引き攣っていても明るく笑っている。如何に腰を伸ばそうと、神経は何處かしらひん曲っているもの、人目には感知し得ぬ歪みを直感で見聞きするのが詩人なのだと、昔誰かがそう言っていたっけか。
川面は穏やかな日を過ごしていた。此処は都会から少し離れた郊外の一軒家。平屋造りではあるが煉瓦やタイルが施され貧相な藁屋とは程遠い、染みも汚れも寄り付かぬ青濃い藍色の城壁達は森の傍、山への入口へ踏み入る者共を一人も見落すこと無く瞳を鋭く光らせている艶の冴えた色。その城壁の一部がカタリと軽い音を立てて前面に動いた、扉が開いたのである。
「師匠、お食事が。」
中から日射しが眩しそうに目を細め微笑んだのは彼の弟子であり今は妻である白羽のエプロン姿であった。
「ああ、うん。」
些か呆けた声で返事をする夫に彼女は嬉しそうに再び顔を緩ませ、家の中へ戻って行った。その後を川面が続き、扉は静かに閉められる。
白羽が実家を出て数ヶ月で二人は夫婦の契りを月に交わした。素面の弟子に酔った師匠が手を出した、と言う愚かな類のものではない。
「新月したるの次は新月したるゝかい。」
白羽の描き上げた詩を横からちらと見ただけでもう全部読んだらしい。
「師匠。」
「いや済まない。盗み見る形になってしまったが全部きちんと読んだとも。白羽は新月、朔が好きなのかい。」
硝子ペンを置いて洋墨の蓋を閉めると両膝にきちんと両手を揃えて俯向いた。じっと考え込む癖は簡単には治らない。
「あまり、深くは考えていませんでした。詩を描く時、最初の頃は言葉が降って来るような感覚があったのですけれど、家を出て、街を彷徨っている間、溺れるような感覚が新しくやって来たのです。」
「溺れる?」
家を出てから頭の中に水のイメージがよく湧いて来るようになった気がする。流れる清水の小川の時もあれば凪の湖の時もあり、雨の破片山奥の泉空を映さない水溜りの場合だってあった。そして其処にはいつも一つのモチーフが必ず佇んでいるのである。
「モチーフ。一体どんな?」
「古時計です。歌に出て来るような焦茶の古びた柱時計。秒針が動くでしょう、時計ですもの、そうしたら頭から爪先まで水に浸かっているんです、立ったまま、いつもいつも目を開いて、唇は小さく開けていると思います、水の中でも呼吸は出来るから苦しくてもがくことは無いですが、その代り、なのでしょうか、音は一つも届きません。」
「それが、君の言う溺れることなのかな?」
「はい。それが最近頻繁で。溺れている時は必ず朔を思い雫を思います、だから多分、新月としたたりばかりではないのかと……」
自分を客観的に読める者はよく本音をパタリ閉じることがよくあるが、白羽は本音の頁を音読していた。これが恐らく詩人の才の其の一ツなのであろう。川面は喜色満面に何度も何度も頷いて、夫の腑抜けた仕草に妻はふと緩く微笑んだ。
その日の次の日であった。白羽が消息をパタリと閉じたのは。
木樵の案内人
朝起きると、隣で抱きしめていた温もりも、ほの甘い清廉な残り香も居なかった。朝飯の仕度だろうかと布団を出て寝巻きをゆるく羽織り居間へと向う。と、白羽ではなく一人の老人がちょこんと座敷童のようにかしこまって正座していた。
「木樵の爺さんじゃないか。」
「旦那さん、随分遅起きなことで。奥さまから言伝を預かっておりますよ。」
柔和な眉毛ふさふさと白く温和な声でほくほくと笑う爺やの様子を見て、川面は白羽が買物にでも出掛けたのだと思ったらしい、余りにのどかな朝の一景は平和の単語の有難さをひねくれ者の臓腑にも深く沁みさせた。
「白羽は買物にでも行ったのかい爺さん。」
「いいえ。」
「なら朝の散歩かい?あの娘は一人で近所を歩くのが好きだろう、この周辺では人の姿もまばらだし、都会ほど喧しくもないから過ごしやすいんだよ。本当に爺さん良い家を紹介してくれた。」
此処で少しこのお爺さんについて話をしなければならない。川面と白羽の今住んでいる家を与えてくれたのは他でもないお爺さんなのである。
白羽には自傷癖があった。それはどうやら川面の詩集と逢うずっと以前から続けられていた大切な秘密らしく、垢も寄り付かぬいつも綺麗な袂の内に一筋の月夜の銀の小川みたいなカッターナイフを潜ませており、誰にも見られていない夜更の時間に自らの左腕(彼女の利き手は右である、ペンも右で扱った所為であろう)を四五度細く切り付けていた。
初め其を偶々目撃した時、川面は幼少期両親の平手打ちを喰らい翌日喉を突いて死んでいた幼い妹を重ねた。
「やめろ!」
と叫んだのが不味かった。てっきり誰も見ていまいと思い込んでいた白羽の手元が狂い太い血管をズキリと刺してしまったのである、夥しい出血と倒れた妻の肌がみるみる鮮明に生死のコントラストを分けて行くのを呆然と震えながら抱いていた時、
「これを巻きなされ。」
何處から現れたのか霞のようにふらりと手を出し腕を伸ばし瞬きの間に洗浄消毒止血をこなした人こそ、今夫婦の家に腰を伸ばす老人なのである。意識を戻した白羽は惨めさと羞恥で涙ぐむ声で夫と老人に謝罪し頭を下げた。短時間、ものの数分の間に深夜の路地で起きた次々の出来事に川面は呆れ慄いたが、白羽の温もりを確かめる怯えの腕は解かぬまゝ、じっと老人を見た。青褪めた二人と裏腹に老人は頬の血色も確かにフォッフォッと笑う。
「おや、旦那の方もちと怪しいな、薬が切れましたか、酒の震えではござらん、モルヒネか、阿片か、まあ双方でも構わん構わん、一粒これを飲みなされ。」
手渡された藍碧の秘密深い丸薬を覚束ぬ指先で受け取ると貪りついて噛み砕いて溜飲を下げた。
「若い者は無茶をなさる。ちょっくらいらっしゃい、もう儂には広過ぎる家が一戸余っているからそれで雨露を凌ぎ米と野菜を食べて布団で寝れば、お二人の憑き物も落ちようで。まあ先ずは温かい風呂に浸かりなせえ、爺が湧かせてあげませづ。」
たった一晩で川面と白羽は路地上でのその日暮らしから立派な一軒家での日常を与えられ、死肉を切り取り食べていた食生活も温かい白米と味噌汁おかずの三食となり、温かな風呂と布団に身を置ける身上となったのであった。これらの工面は万事お爺さんがしてくれた。
「如何して自分達にこんなに良くしてくださるのです。」
一度川面は流石に問うたことがある。他人に親切を施し頭から一呑みにされてしまう者など戦時下でも大勢見た、その者達の残酷な末路も知っている、そして彼等彼女等には差し伸べられる手も無い事実も余裕も現状此の国には無いと言うことも。故に例え愛する妻の命の恩人であっても、自らの禁断症状を鎮めてくれた者であっても、心から信用するには危険ではないかと考えたのである。老人は暫く川面の顔を黙って見つめていたが焦点の合い始めた眼球を見るとにっこりと微笑み頷いた。
「何、暇な老人の人助けだとでも思うてくだされば良い。貴方がたをどうこうしてやろうとは微塵も企んではおりません。それに、儂自身が先の戦争で息子夫婦を亡くしております、お二人がどうも息子達に似てござってな、哀れな爺を助ける功徳と思うて御慈悲をお垂れくださいませ。」
老人はやがて深々と頭を下げた。此処迄丁寧に親切に言ってくれるのならば仮に騙されても良いだろう一層のこと清々しいと思うた夫の意は正気づいた妻の夢にも届いたか、
「師匠。」
布団の中から弱々と呼ぶ声に駈け寄って病める手を取る。
「白羽。」
川面は白羽を娶った時より彼女に口数を尽すことはしなくなった。話し言葉が本当は苦手な男は、最愛の前では素面で居られるようになったのである。そしてその言えぬ本音は幸いなことに同じ呪いに愛された心の身内への通じた為、二人はさして言葉交わさねど一言二言で充分に足りた、なので白羽の一言は川面へ常人の十言となって響いたのであった。
「言わなくても良い。何も言わなくても良いから……良いんだ、白羽。良いんだ。」
慰めきれぬ心の水底が朱にポトリポトリ染みる、その傷は生きている間も死んだこれからも塞げず繕うことは叶わない。寄り添い抱き合い涙する、前世からの宿業の傷を持ち合う二人の背中を爺は邪魔せず見つめていた。その瞳には目の前に居る夫婦とは別の俤が滲んでおり、そして皺だらけの手には一片の紙切れが握られていた。
森へ
木樵を生業とする老人の名は鴉谷と言った。彼は都会に住んでいながらも毎日郊外にやって来ては森の中へ入り木を伐っては森の入口にある家(今は川面と白羽が住んでいる家である)で一息ついて日暮れにはトボトボ都会の家へと帰る、ちと不思議なルーティンを穏やかにこなしている人物であった。
「爺さん言伝って何だい。」
「奥さまから預かりました、これを。」
いつもと何一つ変らぬ温厚な顔に川面はすっかり気を抜いていた、だからこそ、書かれている文字を読んだ時の胸に氷柱を押し当てられたような抜身の戦慄は如何程大きな衝撃を与えたであろう。
“星北川面様
この文をお読みになっている頃、私は貴方のお傍に居ないことと存じます。もう二度と見ることが叶わないのであれば目に焼きつけ心に刻み烙印のような痛みとして抱き続けようと思い、師匠の安らかな寝顔を見られたことは私の最後の幸せでありました。
私はもう貴方とは一緒に居られない身になってしまったのです。川面様、どうか私を探さないで。師のもとをお許しを請う詫びすらなく立ち去ることをどうか愚かと罵り唾棄してください、そして私をお見捨てになってください。それを餞として胸に抱き白羽は遠く生きて参ります。
私が生涯の内唯一愛なるものを捧げられた貴方、北極星のような貴方、どうかお身体をお大事になさってくださいまし。
白羽“
「白羽。」
手紙を潰さぬように握りしめ青褪めた顔色のまゝ勢いだけよく外へ飛び出そうと走る川面。ところがその背中に声を掛けた者が居る。
「旦那さま、落ち着かれなさいまし。儂は奥さまの行先を知っておりますで、だから今此方にお伺いしているのでございますよ。」
鴉谷の相も変らぬ声に川面はピクリと動きを止めて、今度は彼に走り寄る。
「爺さん本当か?白羽が何處に向かった知っているのか?」
「えゝ。儂も貴方もよおく知っとる場所であすよ。」
「何處か、それは一体何處なんだ。」
「森ですよ。此の家が入口になっとる此の山です。白羽さんは此方に入られて行きましたよ。」
「爺さん、今直ぐに仕度だ。振り返って森の入口が望める辺り迄は入ったことはあるが、俺はそれより深く山に潜ったことが無い。けれど貴方は木樵で、毎日森深くまで踏み入っている。お願いだ、頭を下げて、頼みます。妻にもう一度逢って話がしたい、その為には鴉谷さん、貴方のお力を是非ともお借りしなければならない。山への案内人として、自分と一緒に来てくれませんか、どうか、この通り……」
話し言葉が苦手な男がこれ程淀み無く助力を求める文を話すとは。…鴉谷は森の方へ顔を向けると、片方灰色に染まる両眼玉をぎょろりと四方に動かした、途端に鳥や獣草木花々が冴えた冬風にざっと揃って声を上げる。
「うん。協力的ですわ、安心なされい。」
今の老人の様子を黙って見ていた川面は文を読んだ時は背筋だけで済んだ氷柱が今度は肋骨全てになったかと錯覚う程肝を冷やした。何か妙な爺さまだとは薄々思ってはいたけれど、もしかしてさあ、タダ者じゃない感じ?否怯むな放浪詩人!白羽と話をするまでは何があっても退ることはしない。
「旦那さまァ。」
「何だい。」
「旦那さまの身仕度整えられましたらもう入りましょうか。荷は全て儂が纏めさしてもらいましたので、御心配無く。ゆっくり、しっかり身仕度なされましよ。」
速い。俺が寝巻きを脱ぐ前にもう物資の準備が出来たなどと。やはり山も森も、其処を日々通う者に頼むのが一等安全な行路なのだ、此の爺さまが居てくれて本当に良かった。
「待たせてしまい申し訳無い。」
「いんえ、山は真面目に優しく登ってあげれば怒ることは無い。焦って礼儀を欠けば目的の叶えられないようにちゃあんと摂理道理が回っておりますから、準備で遅れるのは大目に見て下さいますよ、その証拠にまだ朝方ですわ。さあ、参りましょう。」
鴉谷と川面は前後一列に並んで歩き出した。その縦一列の小さな小さな行列に、旭が白蛇の鱗を擽るように男二人の背中を照らしていた。
襲
いつも溺れていた気がする。産まれる筈だった弟は羊水に溺れて死んだのだろうかと一度考えたことがあったけれど、もしかしたら其時からだったのかな、頭の内に、泉やら湖とかの影たちが照らされ始めたのは。水、水、水。そう言えば演じていたのも陸軍ではなく海軍の予備兵だったっけ、縁があるのかな、名前には一文字も水に関する言葉なぞ含まれていやしないのに。あ、でも待てよ、泉の漢字は分解すれば白いに水だな、泉の資質は知らず知らず与えられていたってことになるのかしら。
あゝ嫌だ。愛してもくれなかった母が付けた名であるのに。
けれど弟と逢えなくなってから白羽と呼ばれることも無くなった。代りに紀莟と呼ばれた、与える予定だった息子の名前を、師匠に伝えようか迷っていた時だったのに。傷を深く抉るのは何時だって慣れない、痛みとは容赦が無さすぎるもの。
「紀莟。」
また呼ばれようとは思わなかった。実家から逃げたのに、名前はいつも付いて来る。見た筈も無い弟に、声も知らない弟に、ずっと甘えられている、名前を呼ばれれば白羽は紀莟になって私は自分へなっていく、白羽が溶けて、小川になって、花びらを時折混ぜ返し乍ら小さな莟にそゝいでゆく、いつまでも花を知らず咲かせられない莟へと。
「白羽。」
川面さまのお声を想い出す。貴方が呼んでくださったからようやく好きになれた名前を耳にしたら、私は涙が止まらなくなる。川面さま、川面さま、私だってお逢いしたい。逢って、また抱きしめてほしい。抱擁など私には一生縁も無く与えられない愛情のしるしだと信じきっていたけれど、貴方さまが初めて恵んでくれた、家を出ると決めて外へ逃げたあの夜に。
嗚呼、此の胸の内をそのまゝ記してはいけない、半分溺れている間に詩を描き上げてみせましょう、師匠の弟子に相応しいように、川面、さま。
「紀莟。」
声の主は白羽が気を失ったのを見届けると、ぐっしょり雨露に濡れそぼった無垢の皮膚を拭い始めた。
「夜露を眺むるのは風情を含んだ行為ではありますが、あまり深酒はされぬように。」
「面倒はお掛けしませんよ。」
紀莟と呼ばれた娘はすっくと立ち上がり手際良く寝巻きを締め直すと、ニパッと笑って続けた。
「この雨景を直に身に浴びてみたらさぞ佳い詩が生れるだろうと思っただけなんです。でも、姉上の御身を流石に此処迄濡れそぼらせる肚はありませんでした。自分はもう寝ましょう。」
そしてまた虚ろな紫陽花の色を深く籠めた娘がふらふらと床に倒れた、冷たい冬の川のような大理石の床の上に。
「もう今晩は限界でありましょう。」
気を失った乙女の微かな吐息を確認して一つの声が言った。
「えゝ、人間がそもそも抱えることですら無い筈のものを、ましてそれに挑むなど…此方のお嬢さんは顔に似ず結構な頑固者であらせられる。…今日はもう休ませてあげましょう、部屋へは自分が運びます。」
もう一つの声が先の声の心配を受けて提案した。まるでお姫様を運ぶように月光に照らし浮き彫りになる黒い靄のような人影達は一体何。
昔話
朝の眩しい光の中二人は森を通り山を登って行く。
「此の森のお話を聞いたことはございませぬか?」
会話のタネにしてくれるのだろう鴉谷が、厳めしい表情を一つも乱さぬのを背中で感じながらフウと呑気に口を開いた。
「話?何か伝承でも有する森でしたか。」
「えゝ、まあ、細かいのは道々歩いていれば自然にお気づきになりましょうで、一番有名なお話を不束乍ら申し上げてみましょう。」
昔、此の森には村が在り、桑の木の傍に建つ家の横、其処には一人の青年が住んでいた。青年の名前は彼岸と言い、彼岸には二ツ下の妹がいた。妹の名前迄は現在伝わっていないので妹とだけ称するが、妹は彼岸が二十二の年、二十歳の旭を迎える直前、十九の齢の月夜の雨に泉下へと旅立った。村に於いて二十歳とは成人を意味する目出度い年であったので、其を迎えられない者が居ると不吉とされた、彼岸の妹は不吉な女、不名誉な女と見なされて彼岸の家は村八分に処され追い込まれてしまった、人はこういう時新たな発想と称して奇妙で陰惨な考えを起こしてしまう。
(彼岸と言う名を戴くのであれば、妹を其の身に取り込んでおくれ。)
訳の分らない文である。彼岸の家系は巫子の血は一滴も引かないのだ。しかし話し言葉にはこの呆れた物言いでもそれらしく思わせるエフェクトが付く。それは表情であったり声音であったり身に纏わせる雰囲気だったり呼吸だったり、無理を頷かせるのは言葉そのものの力による圧力ではないのが人の世の習慣である。
親に乞われた日から彼岸は死に、彼岸の妹、として生きることになったのだった。親を選べなかった不幸の他にもう一つ彼の不幸があるとすれば、生娘と名乗っても疑いの余地無いくらい美しくしとやかな顔をしていたことであろう。
「彼岸はその後も、娘として生き続けたのですか。」
川面の胸には言う迄も無く白羽の境遇が思い返されていた。問われた爺はゆっくり首を横に。
「身を投げました、三十を迎える直前の、二十九の月夜に。妹さまと同じく雨の綺麗な夜だったと申すことで。」
「昔話とは、彼岸と言う哀れな青年の物語のことなのですか。」
「いんえ、本題は此処からでございますよ。彼岸が投身なさった次の日に、不思議な現象が村の長者宅で起こり始めました。
先ずは家の庭に植えていた花が三日に一度、しかも一本だけ忽然と消えるのが始まりでありました、それから次は一週間に一度丑三時にトントン、と戸を叩く音がするように。」
「はあ、あゝ。」
「戸が鳴るのは流石に獣の悪戯ではあるまいとは思いましたが、人の寝静まる時間に表を歩くは何ものよと疑う長者殿、初めのうちは知らぬ態度を通しましたが毎週其の日其の刻になるとどうしたものか目がぱッと冴えて眠りを必ず中断される、そして例のトントン……でござりましょう。一ト月経てば気は滅入り、とうとう丑三時に扉を開けましたとの。」
「外に居たのは幽霊ででもありましたか。」
思わず身を乗り出して話に聴き入る、青年の眼の下の隈は濃くも目玉は続きの知りたさにキラキラしている。それを見て鴉谷は意外、と目を丸くする。
「旦那さまはこういう類の話がお好きでしたか。」
「えゝ、まあ。怪異に興味が無いと言えば嘘になる、実際好きな方ですよ。正直人間ドラマよりも人で無しを扱った作品が好いんです、人の感覚は俺には分らないから興味が無いし、つまらない。何處で誰が泣こうが苦しもうが喜ぼうが舞い上がろうが構わない、尤も、人が目の前で苦痛に嘆き声を上げて喚き泣いていたとしても自分は如何したら良いのかさえ分らない、そんな男です。人の道理や通常の感覚も弁えない奴が人のドラマを観たところで、でしょう。」
若い男の眉間が僅かに険しく歪んだのを、老夫は見逃さなかった。若気の至りとまで小馬鹿にはせぬが壮年にはまだまだ遠い青年ゆえの苦悩の他、詩人としての宿業も負った気苦労も重なって川面の表情は齢の割に憔悴している、最愛の妻が行方知れずであれば尚更であろう。せめて昔話に凭れる寸毫と雖も気休めになれば良いと爺は続きを始め出した。
「幽霊かと長者本人も案じたそうで俯向き乍ら戸をガラリ、一息に開けました。すると、きちんと揃えられた脚がある、おやおや裸足でもないわと恐る恐る目線を上げてゆきました、砂泥や塵も寄せぬ端整な裾、雪を染め抜いた真冬の曙の色に染めた着物には乱れもあらずパチンと固く締めた帯留めの桔梗、黄金に旭の輝き放ち凛然たる紺の帯は緩みも認め得ぬ上品な二重太鼓、深く菅笠をかぶる輪郭の清らかさ、牡丹の唇、長者殿は凍としながらも目を離すことが出来なかったと申し伝えまする。
呆気に取られている親父を余所に客人はしなやかな御手でスッと軽く笠を外しますと、なんと其の女性は盲目の方でありましたが、目は天ノ河を墨に溶いたように艶々と涼しい御様子で。」
「目の不自由な方がまた、一体如何して森に来たと言うのでしょう、其の御婦人はお一人で?」
「えゝ。お連れ様を従えている訳でも無し、道中おみ足に触れたものかもしれません、丈約一メエトルと六十はあろうかと言う木の枝をな、杖代りにして背も曲げずにすらりと立って居られました。一体 何のような用件でと長者が訊ねますとな、此の村に彼岸と言う青年はいるか、と問われました。」
「ははあ。恩返しの仇返し、と言った顛末ですか。長者はさぞ困ったのではないですか。」
「想像するに難きことではござりません。もう死んだ男の名を求むるお前は何者かと震えに震えて指差したとのことで。貴婦人は奴の態度を気に留める素振りも無く、唯一言キッパリとお答えなさった。
(彼に命を救っていただいた者です。――)
翌日、年老いたがめつい男は首を括って絶命していました。それもどうやら自ら進んでの働きらしい……話は此処迄です。」
「え、終りかい?」
「はい。旦那さまのお見立て通り恩返しの、と言う部類のものでございます。面白うございましたでしょう?」
「そうだね…面白くはありましたけれど、結末がちと唐突だったかな。もう少しあれこれ場面があるものだと思い込んでいたものだから、呆気に取られた感じですね。一体、その謎の女性が何者かも分らずのままじゃないですか?」
「それはまあ、実際逢われた方が宜しいので。」
生存者
何と言った?
「逢う、とは俺の聞き間違いかな。」
「いいえ旦那さま、爺は言い違えておりませんし、貴方の耳は聞き違えなどしていませぬとも。」
「でも、貴方が今話してみせたのは昔話でしょう。」
「確かに昔話ではございます。ですがね旦那さま、昔話のものと言って現代と切り離すのは賢いとは呼べませぬ。何故かお考えになったことはありますか、昔話と称される者達が今世迄生き残っておられるかを。」
風がととと、と木々の間を緩く走り始めた。木の葉の微かに触れ合い擦れる音がする。
「うん、それは昔の教えや戒めを伝え続ける為にあるのでは?実際人の在り様は古今東西似たり寄ったりだ、時代が変遷しようと人間は同じような事を繰り返す、その際の解決策になるようにと受け継がれて来たのではないでしょうかね。」
「そうですか、貴方はそのようにお考えなさいますか。」
「爺さんは違うのかい?」
「奥様にも同じ質問をしましたら、あちらはこうお答えなさったのです。……それは、生き残りでしょう、と。」
物語は人の心と同じように何回も襲われて殺されるもの、尤も物語に限ったことではないかもしれません、実際詩はもう殺されています、戦争を起こしただの、戦意高揚の為に嘘を吐いていただの、敗戦に追い込んだだの、まあ滅茶苦茶にされています、責任は誰かが負っていると人は安心を覚えますから、誰の所為でもない・誰の責任でもないと口では言いつつ本心は誰かを苛みたくてならないのでしょう、その矛先は何時だって物言わぬもの達へと向くのでしょう。
……私は弟の流産死した責任を負わされました。何の関係も、出産にだって立ち合ってはいないのに、母親は呆けている私を恨めしさに潤み淀む瞳で睨み、父親は表情を消した顔で私を見ました。そして揃って一言、お前の所為だと。
私は本当ならとっくに死んでいて良い存在なのです、人の普通や人間の常識を持ち合わせていなかったから、疎んじられましたよ弟が母を妊娠するまでは。その日から我家は明るくなりました、両親は私の学校でのテストの結果より弟の話で持ちきりでしたから、毎日楽しそうだったのですけれど…人ならざる化物が生れた家だから祝福されないのだと咎められた時、自裁すれば良かったのですが、そうはしませんでした、理由はね、実のところ分らなくって、生き延びてやると確固たる意志を持っていた訳でもないのに…
でも物語だって、そういう子も居ると思いますよ、もしかしたら。人間がそうやってフラフラ生き続けているのだもの、同じように特に意味も無く生き続けた子だって居たって良いではありませんか…なんて、彼等に言ったら怒るかしらお爺さん。あんまり情けない考えだから師匠にも怖くって恥ずかしくって言えません。きっと、物語の生命力も似ているのかもしれません、だって人が作るんですもの、人と似ていたって可笑しくはありません。…なんてね、自分を誤魔化してみてはいるけれど、やっぱり師匠には言い辛いの。師匠はよく詩人は嘘吐きでも素直でなければいけないと仰有います、私は素直ですらないのだから、本当は詩人でないのかも。折角、認めてもらえたと言うのに、本当に――
「最後の方は遠い静かな目で話されていました、奥さまは元よりお静かな、おっとりした、それでいて何處か寂しく狂気を隠したそうな綺麗な瞳をされていますがな。」
白羽がそんなことを、自分が詩人であるかなど疑う必要も無い程彼女は歴然とした詩人の器であるのに、育てられた環境の所為で自らを愛することが未だに出来ないでいる。夫が如何に心を尽くして想えども妻の微笑みは何故か寂しい、そして止まない自傷癖、己を責めて血を流さなければ落ち着いていられないやるせなさ。自分や白羽のような人間は底無しに渇いている、幾ら雨が降れども満たされることは決して無い、孤独が解消されることは無い、詩人とは団欒の音の内にも歔欷の休符を聞くのである。薄らと感じてはいた冷汗が、氷となって肋骨を這い鳩尾に噛みつく、人が人を愛してもすくいきれぬと言う事実はちらちらと舌を出しながら川面を正面に見据える。
「所詮、詩人は生きている限り苦しまなければならない規定か。
「だからこその、昔話でございましょう。」
鴉谷は小さく息を吸うと、詩を一遍空で読み上げた。
遠く垣根の柵を越え
蜜柑がひとつ寒空に留まる
灰色の外套は金の釦を千切り離した
落ちて来る嘗ての旭の威光は
ポトリ 地面に心臓を残した
暗い雨が降り始める
その合図となった砲声は
街に轟く雄叫びでもあったらしく
人々は黒波となって道に押し寄せ
誰も潰れて石のように変貌した果実を気に留めなかった
鳥も、木々も黙っていた
けれどかれらは、蜜柑の変化を見逃さずにいた
小さな溜息が何處かから零れた
遠く 垣根の柵を越えて
爺さまが滔々と朗じたのは川面の過去の作品の一つであった。しかも、まだ詩を描き始めた時のもので、発表した詩集にも含めていない筈のものであった。
「貴方、何故そのような未熟な作を…?」
「人を信じられなくなった者は後ろ姿に安心します、勿論人間の姿も意味しますが、純粋な疑心暗鬼の根はあらゆる実物・概念にも繊毛を伸ばしますので、彼等彼女等は自ずと過去や歴史を眺め始め見つめるようになりやがては安堵を覚えていくのです。その為、その安堵の為に積み重なって来たものこそが昔話、過去の記憶なのでございます。
未来の誰かが投身自殺を図った時、最後の最後で大きな綿袋となって命を救うのが、昔話なのでございます。」
「…………」
「作家詩人は未来の名も知らぬ悲鳴の為に今を犠牲にして言葉を連綿と紡いでいるのです、現在報われぬは当然でありましょう、例えそれが確固たる意志を持ち生き残ろうが目的も無く生き延びようが、ただ、在れば良いのです。人が手づから編み出し産んだものであれば、背骨などどうなっていようが構わないのです。」
一息に言い終えた老人の後ろでざわざわと樹の鳴りが強まる。
「貴方はどうお考えです。」
其の声はもう老夫の喉から出るしわがれたものではなかった。
玲瓏苛烈
変化譚、と呼ばれる物語は数多い。人ならざる者が人の見た目を借りて訪ねて来る御伽話はよく知られているであろう、川面自身も馴染みが無いことはないが、まさか現実に起きる展開になろうとは予期もしていなかったに違いなく。
「誰です、あなたは、鴉谷の爺さんじゃない。」
如何に普段他人に対し反骨無頼を以て接する(勿論白羽以外にであるが)野郎であってもこれには怯夫にならざるを得まいと思う、爺さまと信じていた相手が老人とは似ても似つかぬ瑞々しい鈴蘭の如き声を発したら。
「木樵の老人には昔会った記憶がありますから、そのお姿を空気中の鏡に映しただけですよ。…声真似はしていましたが。」
クスリと微笑み老人は羽織っていた赤い半纏を脱いだ。すると忽ち玲瓏たる美人が眼前に代って居た。
男か女か分らない。眦は凍れる彗星のようにすらりと長く尾を引いた、端から零れる威は静かであるが逆らえない、それを見越した瞳の色は潤みを混ぜた銀の雪に首を傾げる円らな灰色、ともすれば小動物の眼を想起させる風情であるものの隙が見つからぬ鋭利な微笑が油断を打ち消す。黒髪すらりと肩にまですなおに伸びたおかっぱ頭からは想像も出来ぬ気高さと威圧は川面の両肩を寒からしめた。
「鴉谷です、改めましてにはなりますけれど。まあ可愛らしいまん丸な目、さぞ驚いたことでしょう、しわしわのお爺さんがぼろの半纏を脱いだ途端こうなったから。」
クスクス笑う、穏やかな笑み。けれど目も口元も確かに微笑んではいるのに詩人の直感がこれは笑顔ではないと冷汗垂らすのは何故であろう。敵意や悪意でないのは分かる、判断は出来るのだか、このものは、ちっとも笑っていない。それを見透かしたか鴉谷はまたフフと笑う。
「貴方を害しようと企んで老人になっていたのではありませんよ、それは直感で分る筈でしょう?わたしが近付きたかったのは白羽さん。あの娘に用があったから、ほら、穏やかでお人好しなお爺さんなら警戒されにくいと思ったもので。だけれどもまさか自傷行為の最中に逢うとは流石に考えられなかったから、あの時は正直吃驚しました。」
「妻に、何の用です。」
絞り出す。
「妻だなんて、まあ立派な旦那気取りだことですね。実際わたしが旦那さまって呼んだら気分良さげな顔していたものね。でもね、白羽さんはもう貴方のもとへは戻って来られませんよ。」
「何故。あんたは白羽の居場所を知っていると言ったじゃないか、そもそも白羽は如何して俺のもとを離れなければならなかった。」
「あの娘がいつまでも人間の振りをしているからに決まっているでしょう、詩人だと豪語する割に大した直感は持ち合わせていないのね。」
鴉谷はフッと溜息を短く吐いた。さもそれが当然であるかのよに。
「白羽が人間の振りをしている?貴女の言う其は振りじゃなくて人間ならではの行動のことじゃあないのか、白羽は元より人なのだから。」
何を馬鹿げたことをと次は川面が嘲笑えば。鴉谷はピクリと柳眉を片方引き攣らせ凪の空を装った瞳の色は颶風霹靂渦巻く嵐の本性を露わにする、おかっぱの毛先はするすると土に伸びて地を這う黒蛇怒りの矛先に鎌首を擡げ刃の鋭さの陽光を裏切る痛々しいギラつき様、髪の重さに震うのではなさそうなしなやかな肩は撫でた素振を投げ捨て屹と睨む針山を双方に隆起さす。染み一つ無かった滑らかな陶器の肌には数多の裂いた傷の名残であろうか白い線が手首と平行に幾条も浮び上がり、握った拳は鬱血して青黒い。
「白羽が人間?白羽が根ッからの人間?侮辱だ、それは私の友への侮辱の言葉だ!」
身じろぎも出来ぬ川面の頬をヒュッと冷たい風が吹いたと思うと、眦から顎下に掛けて顔を斜めに横断するように激痛が走る。鼻と唇にも容赦無く刃先は見逃さない、赤い血滲み始めた切り傷を両手で押さえ呻く川面の頭を土足で踏みつけ額を血に抑えつけた。
「謝れ、謝れ、謝れ!貴様如きがあの子を幸せに出来るとでも思うたか、人ではない者が人の世界に生れ落ちたのがどれ程の苦しみか分るのか、人に成らなければならなかったあの子の心が、貴様のような人間に分かってたまるか!」
息荒く切らしながら頭を蹴りつける、強い衝撃で血が噴き出し川面は身動きもままならない、意識は痺れ痙攣し
栓
目を開ける。身体が仰向けにされている。背中に感じるのは山道の砂利じゃない。視界を片側覆う白いもの、肌ざわりからして包帯かガーゼらしきものが。少しずつ覚醒していく中で、切られた痛みもジンジンと熱くなって次は頭の痛みも起きて来た。また目を閉じる。
血の匂いはしない、土の匂いも、葉の音も。横たわっているのはベッドだろうか。ならば屋内に運ばれた?此処は病院かもしれない、手当ての際に使用されたろう消毒液の匂いが遅れて鼻に感じられた後、こうなる直前の、記憶が。
息があがる、恐怖でじっとりと身が冷える、奴は、相手は、いないかと確かめるため首を横に動かす直前、
「師匠。」
聞き慣れた、声が。
そして手を握る、ぬくもり。包帯の巻かれていない目から熱い寂しさが堪え切れず零れてしまう。カハ、カハ、と掠れた呼吸だけを繰り返す夫の姿に、白羽は唇を震わせる。
「師匠、自分です、貴方の、妻の……白羽です。ごめんなさい、ごめんなさいよ、貴方をどれほど苦しませたか、私、私……」
結婚の道を選ぶ前からも見続けてきた泣き顔は、およそ一日会わない間にいたく窶れて頬は幾らか落ち窪み痩せた顔に乱れた細い毛がぱらりと擦れる、その刺激にも耐え得ざるべき搖らぐ瞳は夫を見つめて恥と恐れと愛おしさに俯向くものの焦点はきちんと定まっていた。彼女のさまを他人は一縷の頼母しさと馬鹿にし軽んじようが、川面には戦艦の錆びぬ錨よりも深く安心出来ることであった。
「良い、良い。俺とて以前君の住居にコソ泥として這い上がった前科がある、それと比ぶれば俺の方がよっぽど悪人さ、妻が夫に無断で出掛けたとてまたこうして会えれば何者にも咎めることは能わず、気に病むものじゃあない。さ、涙を、お拭き。」
手の伸ばして触れられる距離に愛する者が居る嬉しさと安堵感からつい心は弾み口が軽くなり普段の調子を取り戻す。
こういう時に魔は笑う。
「まだ夫婦だと言い張るのかい。」
声を聞いただけで傷が酷く疼く、言うまでもなく主は鴉谷である。
「あ。」
白羽は振り向きざまに軽く声を立てたが、直ぐに、
「菫ちゃん、あの、私からちゃんと説明しますから。」
「どうでしょう、人が簡単に納得する性質であったでしょうか。」
「大丈夫、川面さまならば大丈夫だから。……貴方。」
彼女と会話をするのはどういう関係だろう。夫が尋ねるより一足先に妻は真摯な眼差しで伴侶を見つむ。
「私が家を離れました事は、今から申します話でお分りいただけるかと思います、けれど、複雑であまりに突拍子も無い内容だとどうぞお嬲りあそばさないで、法螺話だと疑わないでくださいますか。」
手を握る細い指を、力を込めて握り返す。
「無論、疑いも貶しもしないと約束しよう。現に怪異に文字通り打ちのめされた身だ。まして君の言葉だ、俺が見切りをつけるなど有り得ない。」
白羽はほろりとも一度微笑んだ。
「………闇市で売っていたラムネを憶えていますか。」
ラムネ。
もう数えるのも止めた戦後の食糧難、あまり頻繁に起きるから定期的に訪れるイベントのように賑いと活気を楽しみにしている者も多いのは人々の表情でも分かる。前述した通り以前は路傍の人間の死骸の肉を削ぎ食った経験も多々あったが、結婚の後は木樵の翁に変装していた鴉谷に養われるような形であった為大衆の需要からは遠のいていた。いたのであるが…それはあくまでも食料に関する話、詩人が寂しさから逃れられないように、白羽が自傷癖を止められないように、川面もドラッグを手離せない、そして闇市は非合法なものである。
違法薬物の代価を賭場で稼いで来た或昼中のこと、いつもより良いクスリが買えたと喜んで勇み足にて家路を急ぐ時、会わぬ筈の白羽の姿を市場で見つけた。他人の空似で無い証拠に、川面と目が合うと小走りに駈け寄って来たではないか。
「師匠。今お帰りですか?」
場面だけ見れば微笑ましい夫婦の逢瀬である、日は明るく雲は白く風もそよりと吹くばかり……片頬笑む互いは互いの瞳の奥濁る結晶を知っている、日は暗く雲は煤け風塵には家屋人肉の焼けて地面に焦げ付いた匂いも混じる。
「あゝ、今日は良い買物が出来たから。…それより、おまえは?市場に来なくとも食材も水もあの家にはあるだろう。しかも一人で、こんな時勢だ、悪漢にでも攫われたら危ないよ。」
本心の心配の言葉すらも自嘲の声色になってしまうニヒルは引き剝がせない。それでも白羽は笑うのである。
「お爺さんがラムネを飲みたいって、そう言って…」
「ラムネ?」
「えゝ。自分が幼い時飲んだっきりでこの年になるまで再会出来ない、老いれば突拍子も無くふとした事柄が妙に懐かしいと思うものだからって。普段お世話していただいているお礼に、私家を出て来ましたの。」
「そんな話をしていたのかい、他愛の無い日常だな。」
「ちゃんと買えました、この通り。」
「駄菓子屋も露店商へ移り客は大人ばかりさ、つまらない…ラムネ瓶なぞ誰も望みはしまいものを、もう都会にしかない玩具みたいなのを欲しがるなんて爺さん可愛らしいもんじゃないか、ねえ。」
「本当ですね。」
帰る手に握っていたラムネの入った風呂敷包みの影が伸びたを、いくら白昼と言え二人は気付くことはついぞ無かった。
白羽が言うのは、その時買ったラムネ瓶のことである。
「憶えているよ、何だか昔の色はぼやりと朧気だが、輪郭はまだはっきりしている。闇市で買った物だろう。」
「私達にとっては変哲の無い瓶だったのですが、菫…鴉谷さん達にとっては大切な物なんです。それは、その理由は…ラムネの玉、瓶に栓をしているビイ玉があるでしょう、それが、人間の始まりの姿とおんなじだからなんです。」
「ビイ玉が、人の始まり…?」
「人は赤子として生れる前は皆ビイ玉の姿をしていて、それは綺麗な湖から作られる物だから基本的に他の物と混じることは有り得ないのです。けれどもやはり極く稀に居るのですって、自分と関わりの無さそうな誰かの硝子玉を知っている人と言うのが。
罪ではない。罪ではないらしいのです。仕方の無い事象であって、目に映ずるものを、耳に聞くものを、肌に感じるものを拒むなんて出来ないからと…けれど、現実にそういう人達は苦しむのです、前世でも来世でもない知らぬ他人の記憶を身に抱えて切り離せられないなんて…まるでへその緒みたいで嫌なんですよ。」
不純物、とまで言うのは行き過ぎな気もするので、恐らく謝って紛れ込んだビーズや硝子の欠片と言った雰囲気のものであろう、白羽の言う全く繋がりの有さぬ他人の記憶とは。命を直接奪いかねない致命傷を生む武器屋脅威にはならない代物であるかもしれぬが精神を病む種には充分に成り得る厄介な存在だとは川面は妻の笑えない微笑から察した。
「ビイ玉の理論は分った、そのような概念も確かに在るべきものなのかもしれない、否現に君が証明しているのだから疑うことも無いのだが。俺がさらに教えてほしい問題は、何故鴉谷はビイ玉を欲したのか、そして白羽、君は誰の硝子を混ぜられているのか、の二つだ。答えてくれるかい?」
努めて優しく問う夫に、妻は目を紅く疲れさせながらもハッキリと頷いた、その細い骨に何を澤山背負わされているのだろう。
「私の内側には、彼岸と言う青年の破片を混ぜられているようです。」
本来の性別の通りに生きられない苦しみを聞いた時、妻を思い浮べなかった訳ではなかったが、今昔も似た境遇の者は存在するのかと人の世を嘆く程度にしか到らなかったのである。
「じゃあ、君が望むように生きられなかったのは、その、混じった欠片の所為だと…?」
もしかしたらそうなのかもしれない。そのように因果を決め付けても良かったのかもしれない、けれど、それではあまりに可哀想だと咎める自分が居たのも事実。
「貴方も、そうお考えになりますか?」
妻の瞳は一度夫から逸らされた。嗚呼、彼女は得心がいかぬのか。
「白羽。君は如何思いたい、考えたいと?」
やはり話し言葉は嫌い。心に想う万分の一も伝え切れないから。
「彼岸青年の所為にはしたくないんじゃあないか?」
拍手。二人は同時に肩をびくッと上下し音の出所を見向いた。待ちあぐんだ鴉谷が高く手を鳴らしている。
「腐っていても師匠は師匠でいらっしゃいますのね。まあ随分と下らない問答と茶番を見せてくれましたこと、人は茶番に身を沈めて生きるのねェ…なんて脆い。」
川面には明らかな敵意の微笑みで、白羽には憐憫の微笑を湛え代る代る頷き終えるとピタリと真ん中で停止し笑顔を消して無表情になった。読者は憶えておられるだろうか、川面が過去一度だけ白羽の表情に背筋を震わせた時を。あの時晒した彼女の本性の一部、堅固な虚ろ、無感覚が今鴉谷のする顔を酷似していたのである、温度、湿度、吐息の静かさ穏やかさ、瞳の彩色までも。
「自分からきちんと話すと仰有って今一つ要領の得ないお涙頂戴なお話をどうも彼岸さん。本当に貴方は話すのが下手、文章なら好きに暴れるくせして声に出すとなると良い子ちゃんになろうなろうと無意識に精神を削るもんだから性質が悪いし性格も悪い。でもまあ良いわ、そうでなくっちゃ彼岸さんじゃないもの、貴方じゃない、貴方でなかったら今頃私は此処に居ないから、感謝はしていますよ、でも感謝と好意はまた別物です。感謝している相手の背中を襲ったり、好意の微塵も無い相手を庇うことだって人はするもの、でしょう?」
「鴉谷、おまえは一体何なのだ?以前彼岸青年と繋がりのある人間だったのか?」
「菫ちゃん。」
その名前を忘れないでいてくれたから
「彼岸さんに免じて川面さんは殺さないでいてあげます、このことからもお分かり?私は人間ではないのです。昔、彼岸さんが暮らしていた家の傍に生えていた桑の木ですよ。ちゃんと冒頭に勿体付けて話したでしょう、聴きとれていいましたか詩人先生。」
彼岸青年は人と面と話して話すことが嫌いであった、それは赤の他人だけでなく血縁関係にある両親に対しても同様で、唯一嫌悪を抱かずに済んだ話し相手が妹と桑の木だけだったのである。
「私は見ていました。彼岸さんが妹さんと楽しく笑っている姿を、そのお顔がだんだん感情を消していく過程も、身を投げる前に一度だけ私を抱きしめて泣いていた体温も。木は人の世であるから人のように自在に動けぬのです、人の妨げにならないように静かに黙って耐えているだけ、けれど想う人が居なくなれば人の世ではありません、人の世でないのなら嘗てのように動いても良い。」
長者の命を絶ったのは、人間の手によるものではなかった。
「彼に、命を救われたと言うのは…」
「私、私のことです。私達のような生命は掟を破ると二度と本来の格好に戻れなくなる決まりがあります。掟とは勿論人を勝手に殺すこと、人の世界とよく似た決まりごと、私は何百年掟を守って心を殺して来ましたが、彼岸さん、貴方が亡くなって私は生きることが出来たのです、私の心を助けてくれたのは貴方なの、だから長者は始末しました、二度と本来の在るべき姿に帰れなくっても、身体を失い心を生かすことが叶いました。私に、相応しくもない菫なんてあだ名を付けてくれた貴方…」
鴉谷の告白に川面と白羽は互いに身を抱きつつ絶句していた。人の殺意は街で度々目にしたが、人ならざる者の其を初めて知って、その単純に落ち着けない熱量と複雑怪奇な冷酷さに肝は冷えて瞳が熱い、恐ろしくてやりきれない人を超えたものの純烈たる意志を骨にまで刻みつけられたから。
善行
「菫ちゃん、菫ちゃんって、憶えていてくれたのね、嬉しいです。」
夜になっていた。三人が居るのは消毒液の匂い強かった部屋ではなく、囲炉裏のある木組の一室で、天井には幹もそのまゝに見事にうねった松が入り組んでおり、屋根の更に上から今を覗かんとする何ものかの目をあてる為開けた障子の穴(それにしては数百倍はあるが)に魚を焼く煙がもくもくと濃く上っている。話す菫はにこにこと嬉しそうに夕餉の世話を甲斐々々しく務めており、彼女に面倒を見られている白羽と川面の顔は極めて神妙それもその筈、二人は此の場所から出られない状態に整えられてしまったからだ。菫の激昂から幸せそうな笑顔に到る迄何が起き何が判明したのか物言う余裕の無い二人に代って説明申し上げよう。先づはそもそも此処が何處なのか、から。
菫が彼岸を迎える為に言霊で編み出した白い木槿の花の屋敷。彼岸を追い詰めた村の人間を一人残らず肥やしへと加工しその土で育てた歓迎の花々、を大理石にし畳にしフローリングへと刺繍した、床ばかりではもてなしにしてはなんとも貧相、では次は柱をそれぞれ組みましょうと一ツ目虚ろな花を澤山と注いで骨組を造ると、あれもこれもと興が乗って尽きぬ花を材料に一夜の月光の光の下に大きな屋敷を建築した、内装も外装も質素純朴なれど質の高く品の好い飾りつけで潤す気配りの殊勝さよ。殺風景だと昔の村を思い出してしまうかもしれないと現代寄りに寄せたデザインは山の中の森の中に建つにしては僅かに浮世離れをしているが、其を咎める者は一人も居ない。否、そもそも気づかれることは無いと言う。その理屈は
“桑の木が風にそよぐのを疑う人はいませんから”――
人ならざるもの達の世界に、人智は一切意味を成せない。考える葦と称される種族に考えるなとせゝら笑う、彼女等は敵意があるから災いを引き起すのではない、憎しみから災いを引き起こすのではない。天罰、天誅と言う単語も恐らく菫達の常識には当てはまらないのであろう。
兎角此方側にどうこうしよう、困らせよう、などと企む気配は無いのは今彼女の表情からも見て取れる。若い夫婦が身を寄せ合い目の前の乙女に戦慄していた時、愛しい面影月輪に濃い白羽の表情に怯えを察したのか、苛烈な物言いは急に鳴りをひそめ腰の抜けて立ちも出来ぬ人間の女の前に両膝をついた。
「まあ彼岸さん、驚かせる心算《つもり》は無かったのよ、急に貴方の立ち去った後の話をされても困るわよね。えゝ、えゝ、私ったら慌てたのかしら、いきなりオチから話すだなんて藝の無い、無粋だわ。先ずは貴方との想ひ出から始めなくてはいけないわ。それから順々に話をしていけば貴方もこんがらからない筈、こういう時は夕食がぴったりね、今直ぐ仕度をしますから。」
と瞬き一つ触れ合えば山の中は夜になり、目の前には囲炉裏があり…と言った次第である。
「貴方…」
「怖がらないであげた方が良い。今は彼岸として彼女と話してあげなさい。」
そのうち人の世界に戻る方法も分かるかもしれない。あんなに厭うていた人間達が此時になって懐かしく思うとは…川面は苦い笑いを胸に秘め、震える腕を着物の上からギウとつねった、二人で帰るのだ、元の世界、住むべき所、在るべき場所へ、相手に畏れを抱けど怖がっている暇は無い。妻は川面の言葉に静かに頷き、菫と二人話に花を咲かせている。
「では、菫ちゃんがビイ玉を探しまわっていたのは、自分に逢いたかったからなの?」
「私達はね、視力が鳥達みたいに良くないの。だから人を見ただけでは破片が混じっているかどうかは分らない、ビイ玉を透かして人を見ないといけないから。」
「だからラムネ瓶のビイ玉が欲しいって、お爺さんの姿の時によく話していたのね。」
「えゝそうよ。ねえ彼岸さん、あのお爺さん憶えている?村に一度だけやって来た不思議な木樵が居たでしょう。僧だか木樵だか何方なのか判然としないから村の人達は避けていたわ、どうせ物乞いだろうと結論づけたのでしょうね。でも貴方は違ったのよ、妹さんを亡くしたばかりなのに、お爺さんを泊めてあげたじゃない。」
「そう…そうだったかな。」
「お爺さんお名前は?ッて尋ねたら鴉谷と申しますと丁寧に頭を深く下げたのを私見ていてよ。まあ何てきちんとした人だろうって感心したもの。」
「菫ちゃんは本当によく憶えているのね。そのお爺さんの姿になって逢いに来てくれたのなら、その人はきっと、とても優しい人だったのではない?自分はよく憶えていないけれど。」
「彼岸が完全に記憶を探られないのは、白羽さんとして生きた記憶が邪魔をしているの、道を塞いでしまっているんだわ。でもね、それももう今日でおしまい、わたしが硝子瓶を集めていたのは此時の為だもの。」
底知れぬ崖から落ちる列車の積荷が終いまでその事実を知らぬまゝ穏やかに瞳を閉じて眠り続けているように、恍惚と目をそばめ夢みる乙女は薔薇に笑う、その頬の艶は相手の顔からますます血の気が引くのも物ともしないで可憐に色づく。さながら生き血を吸うかのように、相反して。
「何を、するの?」
白羽の声色は読者の想像に難くない。
「元の通りに戻してあげるの。混ざった異物を取り除いて、健康な精神にしてあげる、爽やかな、良い心持ちになれたら、彼岸だって嬉しいでしょう?人が人ならざる者に戻るだけ。今迄通り故郷で楽しく生きるだけ。」
菫さん、と声を上げ制止する間も認められず、白羽の額に一粒の丸い硝子玉がトン、と当てられた。
発火
「……あれ?」
白羽が目を開くと、其処に夫の姿は居なかった。布団の温もりも消えている、家の天井の木目も変わっている、模様替えなんてしていないのに。
「師匠?」
消毒液の濃い空気に肌がピリつき喉が緊まる、見覚えの無い場所の筈が、懐かしさを交ぜた恐れを感じているのは如何してだろう。
師匠、ともう一度愛する人を呼んでみる。此処は何處、と首を動かし身体を起こし視界に入った白いカーテンを左右に開き窓の外の景色を確かめようと試みた。
「……何、これは。」
それしか言えなかった。彼女の視野一杯に広がるのは、堆く積まれて今や巨大な山々と成り果てた硝子玉含むラムネの瓶、瓶、瓶。或る物は鳩尾を抉られ或る物は頭部を破壊され或る物は別の瓶を身体に無理から捻じ込まれ、ただの廃棄場にしては不穏な色濃き霧の中に、嘗て誰かの傍に居たであろう物体達は凄惨な姿となって倒れている。捨てる為の場所、と言うより此処は
「捨てられた物達を集める場所よ。」
咄嗟に悲鳴を呑み込み振り返る。すると、其処にはおかっぱ頭の綺麗な身なりした女性が一人立っていた。
「誰?」
「忘れちゃったの?菫ですよ。菫ちゃんってよく話し掛けてくれたじゃない、彼岸。」
「彼岸?それは――」
誰のこと、と質問する前に、胸が大きくさざめく。のたうつ心は指先を細かく震わせて瞳の焦点をぐらぐらと歪ませた。目の前に立つ娘の姿がだんだん薄墨にぼやけて木の葉が擦れる音が際立って来る、窓の外にも部屋の中にも木なんて生えていないのに、眩暈は回り足から力は抜け冷たい大理石の床にぺたんと崩れるように座り込む、この冷たさ、冷たい、冷たい。私は、この温度を知っている。
「そう。貴方は、身を投げてしまったの。その先には、清い川が…けれどもとても深くて、溺れたらもう溺れ続けるしかない淵の川に、貴方は身を任せてしまった。」
何で、いや、私は理由を知っている、だって、私は、自分として生きられなかったから、あの時も――
「姉さん。」
やめて、聞える筈の無い声。
「兄さん。」
助けられなかった十九の妹。
離れて、離れて。あなた達なんて知らない、憶えていない、
「忘れて良いのですよ。」
「忘れたって良いのよ。」
嘘。こんな言葉掛けてもらったことなんて無い、これは嘘だ、夢だ、まやかしだ、自らに都合の良い願望を見ているんだ。だってあの子達に物語なんて無かった、持つ前に消えてしまった、紡ぐ契機すら与えられなかったではないか、在ることさえ認めてもらえなかったじゃないか。
だから、わたしは
「白羽君。」
描ける時をずっと待っていたんだ。誰かが与えてくれるのを、貴方が与えてくれる日を。
パチリ
今度は薪が青い火花を散らすのを見逃さなかった
ビイ玉を押し付けた菫の手首を確と掴み本来曲げてはならぬ方向へ素早く回した。
「痛ッ。」
菫は指から硝子を零し、コロコロ転がる其を川面が袂と床の間に押さえ付ける。直接人が触るのを本能で嫌がったのは賢明であった。
「白羽、無事か?」
無事でないのは自身の心であろう、まだ動悸の止まぬ胸をえいと抑え付けて窮地を脱する手助けをした川面の顔は英雄、と褒めるにはだいぶ間抜けが過ぎる表情ではあるものの、何が何やら分らぬまゝ蚊帳の外の立場にしては胆勇を示した方である、流石死体の肉を削ぎ取ってでも生きようとしたしぶとさは其処等の雑草にも劣らず立派と言う他ないであろう。そんな夫の、懐かしい本性を見て白羽はにっこり微笑んだ、寂しさの晴れた、出逢った月夜のような旭の光で。
「はい、師匠。白羽は無事でございます。」
もがく菫の手首を放し、キッと見上ぐる涙目に一歩も怯まず白羽は続けた。
「菫ちゃん。私は確かに混ざりものです、彼岸青年の記憶を所々有しているのは事実、前世でもない者の記憶を点々と持っている事自体恐ろしくて理解出来なくて苦しみました、自分は人間じゃなくて化物か何か異類のものではないかって。でも、今、思い出せた気がするの。この記憶を物語にすることが、彼岸の望んだ、私に託した願いではなかったかと。」
「ねがい…?」
「思い出すのがこんなに遅くなってしまってごめんなさい。もっと早くに出来ていれば、貴女は硝子瓶を躍起になって集めることも無かったのに…昔から鈍間なの、だから妹も助けてやれなかった。」
菫の手を両手で取り、そしてそのまま抱きしめた。彼女の背中は肉も薄く、細かった、何よりずっと震えていた。
「ずっと一人で頑張っていたのに、傍に居てあげられなくてごめんね菫ちゃん。もういいの、もう頑張らなくっていいの。戻っておいで。」
くたりと菫の身体から力が一気に抜けて行く、恰も人形から空気がシュルルと抜けてしぼんでしまうように。みるみるうちに乙女の姿は小さく小さく縮んでいって、最後には一本の枯れた小さな枝だけが音も立てずに床へ落ちると砂糖が崩れるみたいにほろほろと輪郭を手放し、一欠片も形を残さなかった。
閑話
「彼岸青年は医術を学ぶ若者でありました。生れつき身体の弱い妹の為に、日々勉学に励む素直な者でした。村の人達も両親も、彼の心願を理解していたので応援してくれていましたが、妹の寿命は彼岸が医師になる直前に尽きてしまったのです。それから村は病み始めました。
彼が妹さんとして生きている時、一人の木樵が家を訪ねました。木樵は言います、“今夜一晩泊めてくださいませんか。”何處から寄って来たのかも判別しない他所者を招くのは危険だと豪語し村の人々は彼を拒みました、外はその日、例に無い大雨の降る夜でした。老人が此処で誰にも構われることなく水に砕けるが天命かと諦めた時、声がしました。
“お爺さん、どうぞ中へ。私の家へお上がりくださいまし。”
それが夢にも忘れぬ彼岸さまでございますよ。」
森の中の木の一つ、周りより少しだけ頭の一つ抜けた背の高い榛ノ木がおり、その頂上に一人の烏が留まっている。
「お爺さんのお名前は何と仰有りますか、彼岸さまは訊きました。昔は名前が与えられて着ていたような気がしまするがもう何百年と時を経ましたもので忘れてしまいました恥ずかしながら、木樵は白い頭を指で掻き掻き笑います。では自分が今付けましょうか、二人で考えればまた暫く忘れることの無い名前が出来ましょうと、まあ何と素直な実直なことと呆れる爺をニコリと心緩ませてくださったあの瞳、あの瞳を忘れはしませぬ。何を経験なさればあのような瞳が出来るのか…」
一旦言葉を区切ってふうと息 吐く、烏の黒曜石の二ツ目は解け始めた木槿の城を眺めている。
急転
「もう枯れていたのか。」
「きっと村の長者を殺めた後からでしょう、もう二度と元の姿には戻れない…覚悟の上でもがき怒り続けていただろうから。」
袂から出した彼女の手巾を菫の去った場所に手向けの花として置いた。白羽と川面は顔を見合わせ、言葉も無く頷く。
「詩を、描いてあげたらどうだい?」
「描けるかしら、などと弱気になるのも許されない、私は描かなくてはならないから。」
「それは、白羽としての意志かい?彼岸としての願い、とやら?」
最期菫に言ったのを聞き逃してはいなかった。ビイ玉を押し付けられた刹那、何か水のいなづまでも翔けたのかこれまでの弱く脆い瞳が剝がれ踏み侵し難き神木の幹がすっくと立ち顕れ搖らがぬ視線は川面の知る彼女のものと全く異なっていた。今にも倒れそうな水底の月に非ず、旭光無くては光纏えぬ月光にも非ず、果ての知れない黒い湖の無秩序にも非ざる。それは、泉から親離れした繭、与えられた名を以て力の限り羽ばたかんとする希望の蛾である。
「しらは。白羽としての、生れた意味です。」
「確かに俺は君を詩人の器だと言ったが…」
「詩人ならば詩を紡がねばならないのです、それは詩人の生きる意味、詩を語れなくなった私に存在する意義はありません。」
「白羽、それは違うだろう。君が詩を描けなくなっても君は生きていて良いに決まってる。」
「先生は何を託されて詩人になったのです?」
「俺は誰かに頼まれて詩を描いている訳じゃない、俺は何かを気負って描く訳じゃないぞ白羽。詩人はそんな」
「重荷を負うべきではない、と仰有りたいのですか。以前はそう考えられていたではないですか。避けられない業なのでしょう、努力して詩人になることは出来ないと、詩人の才能は生れ持っている罪なのでしょう、詩人とは罰なのでしょう。」
「そうだ。だが俺は詩を自分の為に描いている、自分の気晴らしの為に描いている、詩は、そんな……誰かを救う為に生れるものとは」
「私は詩に救われました。他でもない貴方の詩に。それに、私とは彼岸でもあるのです、彼の一部を含めての私ですから。彼岸を救けることは自分の為でもあるのですよ、如何です?」
言葉を失う。生れ乍らの明確な違いと詩を始めた経緯の差が二人を完全に隔ててしまった。愛し恋した者同士のいつか通る道であると人は笑おうが当人達にとっては笑って済まされぬのも確かであろう、川面の喉はヒリつき酷く渇く。
「白羽、白羽。」
名前を呼ぶことしか出来ない。呼べば元に戻らぬかと惨めで淡い期待を捨て切れずに。しかし白羽は、
「貴方が泥棒として私を訪ねた明日、置き手紙を残してくださったのを憶えていますか、夜更かしの習慣を取り入れておくようにと言伝されたあの紙切れを。菫ちゃんがお爺さんの振りして私の介抱をしてくれたあの夜に、盗まれたの、盗んだのは菫ちゃんだって本人から教えてもらいました、此の場所に連れて来られたばかりの時に、此処、何の為の場所か分ります?山の中ではありますけれど、自然を身近に置く為の別荘なんかじゃないんです、後で御覧になってみて下さい、ラムネ瓶が捨てられていますから、それも澤山。捨てる為の場所なんです、要らなくなった生命を物語を言葉を捨てる為の場所、でもそれだけでは無いんです。殺す場所、嬲る場所、玩具にして楽しみ乍ら壊す場所、そんな恐ろしい所であるのに、私は、今紙切れのお守りを持たなくっても平気なんです。自分の腕を深く抉ったあの日から、私は貴方の言葉が無くても立っていられるようになってしまっているのです。……だからもう、貴方が居なくても私は詩を紡ぐでしょう。私の使命に貴方の力は必要無い。」
拒絶を示すと瞼を伏せた。ザッと氷の如き冷たさの雨が室を覆い川面の視界を霧に化す、次に瞬きをした時にはもう遅い、星北川面は闇市の真ん中に突っ立って居た。
凡庸
「オイ、邪魔だよ。」
「ボケッと立ってんなよ危ないだろう。」
「退いた退いた、通るよ。」
パパー
キキィ
ドンドンドン
ガシャンガラガラ
これまで一度も気にならなかった赤の他人の声がやたら細かく聞き取れる、聞き慣れた音が騒音になって雑音になって神経を高ぶらせる。ザリ、ザリ、と砂利を踏みしめて摺れる誰かの足音ですら疎ましくてならない。
こういう時、川面に対してどう接するのが正解であろう、条件としては見ず知らずの者が、であるが。ひとまず声を掛けて道端に誘導する?もう一度気絶させて手頃な場所に落ち着かせる?どちらを選択しても突ッ放されてしまいかねないが、いつまでも気の済む迄佇ませておく訳にもいかない、放って置けば誰かと喧嘩沙汰を起こしかねないし、何せ此の場所は閑静な高級住宅街ではない、闇市と言う無法地帯なのだから。それに、彼岸と何かしらの形で関わりを持つことになっている身であればおざなりには出来ない。
「カア。」
意を決した第一声はものの見事に無視された。ゴミを漁りにやって来た其処等の輩と同一視されたのかもしれない。今度こそ
「カア。」
気づかないのは少し寂しい、一人で居るのが気楽であるのは認めるけれど、孤独孤独といつまでも鳴き続けていられる奴がいるものか。
「カー。」
お願い気付いてー!と半ば自棄に長く呼ぶと、嗚呼ようやく。
「…何だコイツ。」
覚悟はしていたがまあとても尋常な話を持ち掛けられる状態ではござらぬ。
「カア、カア、カア。」
三回呼んで彼の目先をこちこち歩く、南に二歩、西に一歩東に一歩、北には三歩進んで円を描く。これは人間の文化上には在らず烏の印。これを切れば人は烏の言葉を聞き取れる目を持つと言うが、果して。
「川面さん、星北川面さん、聞えますか。」
「…………」
円らな眼を凝視させて私を見下ろす、おゝどうやら上手く行ったようだ。
「誰だ、と心の中でお尋ねになってください。声に出してはいけません。印が解けてしまいますから。それに、いくら闇市とは言え昼間から烏相手に話をすると周りの人間に疑われてしまいます、人目が増えれば、やがて警察もやって来ます、形骸化した公務員達なので軍人ほど屈強ではなくなっていますが面倒には変りありません、貴方も警察に絡まれるのは避けたいでしょう。」
かごとがましい口ぶりではあるが烏の川面を案じていつ思いは信じても良さそうだ、荒んだ者には疑いの念がプツッと切れる瞬間がある。言葉には未だ上手く出来ない代りに彼は首肯する動作で不思議な来訪者に答えた。確かに警察は不味い、強盗未遂も違法薬物もした男だから言い逃れは出来ない。それに、静かな場所に移りたかった、眠りたい、とても疲れている。戦争が起きてから繰り返されて来た情勢から受け続けた疲弊が一度にどっと身体を埋めて、強がりも振舞えなくなった本来臆病な詩人の肩に圧し掛かる。知らず知らずの内に演技をしていた、無骨で無頼なやくざな男を勤めていたのに、急に妹を亡くした頃の儚い青年の身一つに戻された、纏うべき鎧も風に散って跡形も無い、無防備でむきだしの、愛を望む危い若輩者ただ一人。烏の飛ぶ後ろを付いて行く身は青白く頬は涙で削れていた。周りの音が遠ざかる。
戻って来たのは、二人で住んでいた家だった。主の留守中に家は他人に襲われた様子も無く、きちんとそのまゝ待っていた。
何が嬉しい。
「そう仰有るのもご無理ありますまい、奥さまを森に奪われたようなものです。ですのでお話は私の方からさせていただきましょう。」
烏はまだ烏の姿のまゝ、床に胡坐する川面の前にピョコンと姿勢を伸ばすとコホン咳払い一つ軽く勿体ぶった様子で話し始めた。
「私の名前は鴉谷と申します。あゝ、そうお睨みあそばすな、鴉谷は鴉谷でも桑の木菫が化けていた贋作では御座居ません。正真正銘、嘗て彼岸さまのご自宅に泊めていただいた木樵の鴉谷で御座居ますので。ははあ、疑っておられる、勿論、勿論ですとも、お疑いなさるのも無理はありません旦那さま、何せ朝から色々なことが立て続けに起りました、しかもまだ時分は夕刻にもなっていやしないなど!日は真上にあり、と言うのも信じられますまい。」
全く本筋に入らなさそうな自己紹介がいつまであるかも不明なので、重くはあるが川面は口を開いた。
「疑っちゃいない。貴方がそう言う人ならそうなんだろう。現実離れした展開を今更否定する訳でもない。ビイ玉だの廃棄場だの桑の木だの彼岸だの嬲るだの弄ぶだのうんざりする程に怪異とは近付きになっちまったから、この期に及んで烏が人語を繰る、なんて不思議だとも思わないから、教えてくれないか。もう俺は、白羽と居られない身になったのか、それともまだ投げ出すには尚早なのか。」
「結論から申しましょうか。」
「俺次第、と言う返答では腑に落ちんぞ。」
「ハハ、ありきたりな希望的観測はお嫌いですか。自分が動けば事態は動き好転するとは考えておられないようですね。」
「当然だ。俺の力ではどうにもならん事ばかり起きる。」
一気に顔が血色盛んになり眦は思わず厳しく吊り上がる。声をやや荒げ飄々と何處吹く風の黒烏に癇癪を起すも、元凶なぞ居ない事実を思い出して直ぐに小さく謝った。
「ごめんよ、君に怒ったところでだ。」
「まあ其処迄打ちひしがれていては私とても悲しくなってきます。ですのでお互いの為にも焦らさず申し上げましょう。星北川面さま、貴方は白羽さんと居られない身だと定義はされています。」
「もう夫婦であることは認められていない、か。」
予想はしていた、予想はしていたけれど、覚悟など。項垂れる川面を見て鴉谷は何やら慌てた様子。
「よく言葉を聞き取ってください。認められていないのではなく、一緒に居るべき存在ではないと定義されているだけですよ、辞書、辞書を連想したなら分り易いでしょう、ほら。」
何處から取り出したものか、烏は嘴に一枚の小さな正方形の紙を咥えている。其処には
“星北川面と白羽夫婦
互いに種類の異なる存在なれば共存を勧めず。“
と丁寧な教科書体で記されていた。何だこりゃ、と質問するのも煩わしくなったのであろう、
「勧めずってことは、禁止ではないってことか。」
自分と最愛を表す言葉に注視していた。川面の瞳が再び湖の深さを測る慎重な光を取り戻し始めるのを見て鴉谷は内心しめたもの。重箱の隅を突ッつくと笑うのならば笑え、言葉の端々に意識を向けて好きに解釈するだけで飽き足りず新たに言葉を紡ぎ出すのは職業柄得意分野である、例え雑誌に載らないでも小説に足蹴にされても此処にまだ詩人は一人居るではないか。
「なんだ、下らない。結局は俺自身、俺次第に収まりやがった。」
袂に突き込んでいた阿片混ぜ込めたラムネを掌に握ると地面に叩きつけて泥土塗れの草履で踏み付ける、この砕き様であれば犬もうっかり喰らうまい。
ありきたり、ありきたりな展開。けれど今程その陳腐に感謝したことは無い、だって、描けば良いのだから。あの娘が自らの救いだと言ってくれたような、何處にでもありうる詩を。
山猫譚
作戦会議は川面の書斎で大将と参謀の二人だけで開かれた。先ずは相手の様子と今の戦況を明らかにするのが肝要と言って鴉谷は一枚の地図を用意していた。
「あの場所には白羽嬢の他に住まっているものが居ります。菫は言わば最初の関門とでも申しましょうか、まさか私の昔化けた姿を借りていたとは夢にも思いませんでしたが、彼岸さまが見覚えのあり、且つ彼に悪意を抱かなかった外側を選んだのだろうと思います。後のもの達は私を嫌っておりますからもう爺の姿を見ることはございますまい。」
「後のもの、それは具体的に幾つ居る?」
「関門は全部で三つ、一つ目はもう済みましたが、残り二つは健在ですな。」
「菫や君みたく人ならざるものが残っていると?今度は花か、木か、それとも獣か?」
調子を取り戻した軽口なんか叩かなきゃあ良かったな。
「獣です。狛犬のような役割を持つ山猫です。」
「…何だそれ、ずっと昔の童話に似たようなものがあった気がするぞ。人を喰おうと企む山猫の登場する話だ、最後は犬に驚かされて退散してしまうんだがね。」
「山猫のイメージは清廉潔白とはかけ離れていますからね。」
「確かにそうだな、山猫のような人、とは褒め言葉には分類されないし、何處か裏切る素振を隠している雰囲気を感じ取ってしまう、それも涙乍らに胸を潰す決死の思いに因る裏切りではなくって気分でひょいと右にも左にも移るような、身軽と言うのもあれだが、まあ兎角そんなイメージがあるよ。」
「ほう。それでは旦那さまは山猫譚を御存知無い?」
また昔話の類か。
「内心うんざり、と思わなくもないが、どうやら君達人外の存在にとっては物語、とりわけ昔話と言うのがどうも重要な位置を占めているらしい。菫も爺さまに化けていた時俺に話してくれたよ、昔の物語はただ在るだけで価値あるものだと、いつか誰かを救うものになるのだと。彼女の言う中には詩も含まれていた、君等にとって詩も物語も違いは無いのかい?」
詩は小説に非ず、小説もまた詩に非ず。川面はそう信じ続けていた心算《つもり》だが、戦意高揚の為に利用されてからその境界はどんどん崩れて来たように肌で感じ取ってもいた。詩の如き小説を執筆せしめた偉大な時代は太古遠くに鎮座して荒廃の現代を遙か先に眺めて居らるゝ、もはや内容ばかりが選び取られ修辞を邪魔とする今の時代は、書けたら何でも良いのであろう、言葉に敏感になったようで鈍感になってしまったものだと川面は学の無い人間ながらに嘆いていた。
「菫は人間の仕業であれば何のような物でも認めたがらない性分だから区別の目は持ち合せておりませなんだ。あの娘にとっては彼岸かそれ以外か、詩人も小説家も同じそれ以外の者、あまり気になさらぬ方が宜しいかと。」
「かと言って全く無視できるような話でもなかったのだがね。」
「どうせ辿り着く迄に集めたラムネ瓶の内容をそれらしく継ぎ接ぎした愚説です。あの者の手口にすっかり搦め捕られてしまいましたか、菫と二人きりで話をするのは本来忌むべきなのですが、姿を変えてさも導き手のように振舞われては疑いさえ抱き辛い、彼奴め充分に考えましたな、尤も其知識は彼女本人に発したものではないのですが。」
「菫に言い含めたのは、例の二匹の山猫かい?」
「えゝ左様でござります。二匹と言うのをできれば一対と改められた方が良いですな、あの者達は個別で数えられるのを激しく厭う傾向にありますから。理由も知っておいたら損はありません、ちと山猫譚をお話いたしましょう。」
此処に一対の山猫が居りました。片方は銀と紺の瞳を持つ猫で名を阿礼、もう片方は金と赤の瞳を持つ少女と名の与えられた山猫にございました。阿礼と少女は大変仲睦まじく、いつも陽だまりに目を柔らげ黄昏に耳を攲てては夜に牙を研ぎ恍惚として蛾の眉開くを肩寄せ合って仰ぎ見ていました。互いは互いに信じる心を失わず、その清廉なる冬の川の如き誠実さは互い以外の生命にも余す所無く向けられていたのでございます。」
「誠実、か。従来のイメージ像とは大いに異なる一対だね。」
「そうです、今のお言葉を彼等は恐れておりますので。自分達の本性と他の抱く想像の姿がかけ離れているものだから人間を大層恐れています。」
てっきり菫よりも図々しく人を見下すきらいのある難敵かと覚悟していたがまさか正反対の性格を持つとは思いもよらなかった。
「人を怖がる相手に俺が如何やって話をすれば良い……いや、待っておくれ、ははあ成程、その山猫譚にヒントが在るのだろう。」
「ご理解が早くて何よりです。さて阿礼と少女の話ですが、人でない者と雖も怖いもの見たさに人間が気になるのは愛らしいもので。或日一対は意を決して人間の住む場所に降りてみることにしたのです。
(退治されたりしないかな。)少女は阿礼の顔をちらちら伺い落ち着きなくそわそわしています。
(大丈夫だよ。害意は持たないと相手に示せば向こうもやたらと追い掛けたり責めたりしようなんざ考えないから。)阿礼は少女を安心させようと努めて穏やかに微笑み言いました。彼の中にも少女のような心配の気が多少はありましたが、人がどのような生活をしているのか、そして自分達山猫が何故疎んじられるのかを知りたい好奇心が怯えよりも少しだけ勝っていたのです。
一対は他愛ない話をしつつとうとう山の麓に下りて来ました。
(喋る山猫と聞けばきっと人は驚いてしまうだろう。人は人とだけ言葉を交わす特徴があるようだから。)
人を遠目で見ながらも気配を隠して相手を観察するのは本能乍らに備わっているので人間の特徴を幾らか把握はしていました。人は同じ姿をした者と言葉による意思疎通を行うこと、いつも微笑みを忘れないこと、学ぶ姿勢を失わないこと、なにか敬い大切にするものを一つは持っていること…どうです、これでもまだ山猫を胡乱と申せますか?」
川面は何も言わず、苦笑いして額に手を当てるのみ。
「人と関わるには人の格好をするのが良いと判断し、一対は姿を変えました。阿礼はおさげ髪の女の子の格好に、少女はおかっぱの男の子の姿へと霧一つで移りますと、いよいよ麓の村へ足を踏み入れました。真っ先に向いましたのは村の外れにありました公園、其処には山ではお目に掛かることのできない遊び道具がたくさんあり、ごれも二人をおいでおいでと手招きするようで。
(人の子は公園でよく遊ぶものらしい。親子の会話を幾度か耳にしたけれど幼い声はよく公園をねだっていたから、人には身近な場所には違いない。)
(公園に居れば人間と関わるのも容易いかもしれないね。)
「何だか起伏の乏しい物語だね、確かに公園は親子連れが多く居るし、危険な場所と聞いて真先に連想するものではない。それじゃあ山猫達は無事に人と接するのが叶ったんだね。」
誰かの話を聞いている時、先回りして結論づけるのは礼儀正しい作法に非ず。そんな者は少し痛い目を見るのが通説である。
「常識とは昼間の活動に焦点を当てたものです。一対が山の麓、公園を訪れたのは月夜のこと、この話は昼日中の出来事ではありませぬ。」
「そうか。てっきり日中の舞台かと決めつけていた。夜の公園ならば治安が良くない。何か怖い体験をしたのだろう。」
「えゝ。一対は一人の女の子を見ました。ベンチに横たわり、自死している年端も行かぬ冷え切った少女を。」
幼い娘の自死、川面は自らの妹を再び思い出さねばならなくなった。
抉り
愛は見ていたから知っていた、両親の間には平手打ちの一つも罵りあいも生じず、互い互いに凭れ掛かるような気味の悪い睦まじさが存ったから。けれどそれは子には向けられないものだった。
聞き取られない言葉を投げ付けられれば同時に体の何處かを衝撃が襲い”痛い”を感じる。自分の痛みは親にとっては喜びである、サンドバッグを殴って快感を得るあの感覚に近しい喜び、そして喜びは共有される、恋人同士の間で、泣く子供に気付かないで。
「何故。何故女の子はそんな…」
「実の親達に手酷く殴られたのです。それまでは耐えていたようですが、或日プツリと糸が切れたものかと。」
「糸が切れる。」
鸚鵡返しに震える声。忘れようと努めた行為を嘲笑する一瞬にして鮮烈な記憶、届かなかった手、慰められていると疑わなかった己の過信、冷たくなった手首に凝り固まる處女の血、何も変わらぬ親達、握った凶器。
川に顔面を突込まれたのは、相手の抵抗に因る結果だった。油断していた女親の背中を斧で、直後ビクビクと舌をだらりと出した顔が気色悪かったから今度は首ごと潰した。斧は圧し潰すのも得意なんだなとぼんやりしていると、怒号がした、男親。腕力は自分より確実に上回っているのは知っていたから、上半身を奮えぬよう下半身をずくり裂いた。断末魔と共に首根ッこを掴まれて二人小川に頭から突ッ込んだ、どうせ死体ばかり捨てられている川なのだから両親を捨ててもさして色が変わることも無く、見分けの付かなくなって埋もれた誰かの返り血をインク代りにして指で直接原稿用紙に詩を描いた。
「兄さんは私と違って賢いから、いつかすてきなお城を作ってね。」
見つからないように盗んで来たまっさらの原稿用紙をくれたのは昨日のことだ、誕生日プレゼントだと言って。あの時は今日おまえが死ぬこともあいつらを殺すことも夢だに想像しなかったのに。
糸が切れる、糸が切れる。その意味を俺はよく知っている。
「川面さん。」
浅い呼吸と深い呼吸を均一に繰り返す川面の耳に鴉谷の声が静かに届いた、凪の瀬に月の光が一筋落ちるように。
「聞えているでしょう、星北川面さん。」
川面を呼びながら鴉谷は内心不味いと案じていた。面白いを通り越し此方側に心配・不安を催させる程に彼が記憶を消していたとは予想外であったのだ。妹の死を悼むこともしなかった犯人への憎しみも怒りも今の今迄自我の外に放り投げたままでいたとは半ば呆れたものだがやはり不憫と感じざるを得ない。しかし此の儀式を済まさないでは恋ふる妻を取り戻すなんぞ夢のまた夢となってしまう、もう一度言葉を吐け、身体をもがけ、心を痛めろ、詩人はその才を自認して筆を執った日を忘れてはならない。鴉谷の瞳がじっと白い虚ろの川面に注がれる、その眼差しには確かに信頼も濃ゆく黒曜石の艶にも劣らず滲む。
「名前を与えられなかったんだ。」
指の爪先は寒さを忘れぬ。
「名前なんて高価な代物お前には不必要だと哄笑されてね。」
本当に声ばかり大い輩だった。腹を痛めて産んだものの、とんだ外れが来たものだと毎日小突かれる、今度は当たりを引きたいと言ってまた妊娠する、女の子だ、まあ長男よりは良い女は幾らでも金に化るからと喜んでいたよ、生まれたての赤子だった妹も喜んでいた、理由も知らずに親が笑っているからあの子も笑ったんだよ、素直な子だった。俺はニコリとも笑わなかったって、産声を上げた時親の企みが分かったからね、心を許すものかとしていたけれど、妹が笑った時、俺は初めて笑えたんだ、心を許せる存在を知った。あの子に見抜く為の目は生れつき備わってはいなかったものの相手を我が事のように思う、時に自分以上に大切にする為の目に恵まれていたから、俺と妹が二人で居れば理想的と言われている聡く優しい生命になれるだろうと過信していた。
俺は賢くもなんともない、他者を助ける力も持たない。
「惨めですか?」
惨めの他に何がある。妹を助けてやる才覚も持たない俺が、弟子など、妻など。思いあがりにも程があろうよ。
「ではもう放っておかれたら如何です?向こうは貴方が干渉してくるのを望んでいないかもしれませんよ。山猫達も怯えなくても済みますからね。」
一人で路傍に朽ち果てる。それが本名も知らない者には相応しい幕引きなのであろう、澤山の無縁仏と肩を並べて腐ってゆくのが。蛆に集られ蝿に喰われ小さき存在に分解されていく。海底に沈む鯨のように神秘的にはならないが闇市の一粒の土くらいにはなれるやもしれぬ。
「闇市、闇市、闇市。貴方が阿片に染まり董が人を誘拐して来た場所ですね。」
誘拐?
「硝子瓶が何そのまゝ人の魂である筈が無いでしょう。そう見えているだけで、あれらは瓶の姿などしていませんよ。全員生身の、否生身だった人間です。」
だが実際彼女は瓶を探しに市場まで来ていたではなかったか
「おや、あれがまっとうなラムネに見えていたのですね、まあまあ幸福なことですな。ですが此の時代ならば人間の生身の破片を持ち歩いていたとて訝しまれることはありますまい、あゝあの腕は爆撃で飛んだ家族の一部だろう親兄弟か或は夫か子供であろうか可哀想にと思われておしまいですよ、現に闇市の人達だけでなく家路の途中も誰にも咎められなかったでしょうに。それはラムネ瓶だからではなく、珍しくもなくなってしまった戦争の一風景であったからですよ。」
俺の目は、ありふれた日常を映していた筈だったのに。
正体
自分の目に無意識で補正が掛かっているのであれば、己の見て来たもの聞いた事柄は全て何處か擦れていたのであろうか。川面は詩を描こうとしていた手の動きを止めた。
「おっと、描かれないのですか?白羽さんを呼ぶには詩を描かなくてはいけませんのに。」
「鴉谷。」
手を止めたのは度重なり身に降る怪奇の所為でも、湧き出した記憶の所為でも無かった。
「今から言うのは、惨めな男の独り言として聞いてくれ。同意も慰めも要らない、反論や悪口も今だけは我慢していてほしい、話が済んだら幾らでも聞こうから。ただ、俺が言葉を切るまでは口を噤んでいてほしい。」
そう言うと川面は山を一度見、そして自らの両手を見る。視線はそのまま話し始めた。
「俺はこれまで自分には詩の才があると信じていた。詩の才を持つ者は同時に生れ乍らの罰を負っているから、まっとうな生活ができないのは天命なのだと諦め受け入れていた。でもね、本当は違っていたんだよ。才能だの罰だのと傲慢も甚だしい、俺が詩を始めたのは妹の為だったんだ。毎日暴力を奮われる家の中でね、いつも窓の外を眺めていたんだ、黙ってじっとしていれば気まぐれに撲たれる割合が些かは減ったからね。窓の外には柵が見えた。あれから向こうに出ようとすればたちまち死ぬ直前まで痛めつけられるから、俺にとって家を囲う柵は逃げ道に通ずる唯一の存在に思えた。最初の内は逃げたくて眺めるだけだったが、そのうち見知り顔になってくるとあの柵を越えた向こうに広がる景色を思った、生活を思った、命を思ったんだ。そしてそれらの憧れはふとした時言葉に連なって字を刻んだ…
――遠く垣根の柵を越え
董が爺の振りをして暗唱してみせた一編の詩は、星北川面と名告る前、名の無い一人の男子が自らの望みを託した新芽であったのに。俺は俺の始まりを踏みつけにして無かったことにしていたんだ、董から聞くまでも忘れていた、デビュー作ではないとは言え成熟に到らなかった未熟ものとして捨て去った、妹が、すてきな詩だねと褒めてくれた詩だったのに、俺は妹を喜ばせたくて詩を描き続けた、あの子言ったんだよ、兄さんの詩はおとぎの国のお城みたいだって。澤山の優しいお客さまを招待して、美味しいごちそうも用意してさ、ローストビイフ、なんかもいいわねなんて、ませてやがる小さい癖にと笑ったものさ。」
一度描く手を止めたのは、ながら作業ではなくきちんと向き合いたかったから。名前を親から貰えなかった兄妹は不幸の中でも輝いていた、生きているよと伝えていた、とても小さな、小さな声で。
「あの子が死んでしまった日に、二人きりの想ひ出も約束も変に書き変えてしまったんだ。」
「ですが本能は残ったのでしょう。」
鴉谷、君は優しすぎるぞ。と苦笑して言い掛けた時、また引っ掛かった。
「本能?」
「詩人は感情の獣だと聞いたことはありませんか。詩作はその人にとっては本能による働きなのです。貴方はそれを失わずに居られることができたのですね。」
理論も理屈も証拠も無いが、川面は途端に理解した。山の中で白羽を守っているもの、否白羽が守っているものは
「山猫は、俺自身の捨て忘れた記憶なのか。」
鴉谷も山も家も煙のようにふと消えた。正解だとでもニヤと笑って拍手をするかのように。
証言一
「両親を殺しました。」
そう言って血だらけで我家の玄関先に立っていた青年は私の瞳を真直ぐに見つめていました。てっきりいつもこの時間帯に家を訪ねる新聞屋さんだと思っていた私達家族は不意な来訪者に肝を抜かれましたが、青年は一言告げるとそのまま前のめりに倒れてしまったので、ひとまず介抱して様子を見ることにしよう、不審者であることに疑いは無いが何か事情がありそうだから話を聞けば本人も気が良い方へ変わるかもしれないからと警察へ届けるのは一旦止めにしたのです。父と母が青年を風呂場で綺麗にしている間、私は彼の眠る布団を仕度しました。
「身体が冷え切っていたから湯船に沈まないように支えて浸からしたのだけれどね、お湯を浴びても顔が濡れてもぴくりともしなさらない。お父さんは死灰のようだと言って心配しておいでだ、私もお医者を頼もうかしらと思っていたから、今お父さんが電話を掛けてくれているのよ。」
青年の身体と髪を拭き父の肌着や寝巻(少しだけ大きかったみたいです)を着せて床に休ませた後、彼から少し離れた場所に座り乍ら畳の上で母は私にそう言いました。湯に入れても酷く顔色が悪いのはやはり案じられますので、私も両親の行動に頷きました。
「両親を…と言っていたけれど事実かしら。今日町ではそのような騒ぎは起きていないけれど…」
「此の町じゃない所から来たのかもしれないね。何で家を訪ねたのかは分らないけれど。」
「私、少しだけ怖いわお母さん。」
「大丈夫だよ。凶器も何も持っていなかったし、危害を加えたがる眼をしてはいないってお父さんも言っていたからそんなに怖がらなくても良い。」
やがて父の呼んだお医者さんと、念の為にと呼んだお巡りさんが一緒に来ました。ですが青年は一向に目を覚ます気配がありません。」
「一旦警察病院へ入院させます。見た目でも察せられますがこの人は酷い栄養失調だ。」
青年は連れられて行きました。お巡りさんは私達に幾つか質問をした後礼儀正しく頭を下げて警察病院へ向かう為の車に乗りました。
「あの人、お見舞いに行かれないかしら?果物の一つでも食べさせてあげたいけれど、まだ直ぐには難しいかしら。」
父も母も私の肩に手を置いて、一緒に車を見送りました。名前も知らないあの人の泣きそうな深い色をした瞳が胸から離れませんでした。
証言二
此方の御宅の若様をご存知?とても凛々しくていらっしゃるのよ、海軍の予備兵なんですってねえ、予備とは言えエリイトですよ、生れも育ちもあたしらのような並大抵のものではないんだから当然じゃあございますけど何だか尊く拝まれますよ。でもね、若様実際は女性の方なんです、綺麗なお嬢様でいらっしゃるのですけれど、えゝ、何故分かるのかって、まあ身体つきを誤魔化すにも限度がありますもの、でもご本人が男性として振舞っておられるから、町の人達もそのように辻褄を合わせて若様と申すのです、旦那様と奥様も娘さん思いのお優しい方々で。よく話していらっしゃいますよ、たった一人の女の子だから、あの子の望むものは何でも与えてあげたくなって困るのだと苦笑いしながら仰有って。
それから、どうしてお嬢様は突然男装を始められたのですとお訊ね申しますとね、旦那様にも奥様にも分からない、あの娘の中で何かしら契機があったのだろうけれど、或時から無口になってしまって気掛かりなんですって。素行が悪い訳でもなし、外で誰かと厄介事になっている訳でもなし、探偵を雇って調査してもらったから確かだとは思うけれどもならば尚の事原因が分からないと溜息を吐いておられたわ、ご不憫さが身に沁みてどうにかしてあげたいと思いましてね、お嬢様に話し掛けてみました、まあお似合いではありますが如何して左様な海軍の制服をお召しなんですって、そうしたらあの美しいお顔を崩さず誰もが恍惚とする微笑みと共に涼しく仰有られたのです。
(夢叶わなかった弟の為ですから。)
弟様などあの御宅にはいらっしゃいません。でもお嬢様は穏やかなまゝ続けられました。
(貴女方が御存知ないのも無理はありませんよ、母のお腹の中で亡くなってしまったのですから。)
そんな筈ありませんよ、だってあたしはお嬢様の母君様、奥様の召使いなのですから。此方のお家ではどなたも流産をしていませんよ。
証言三
娘が行方不明になってしまったのです。えゝ、名前は白羽と申します。年齢は十九、もうじき二十歳になる予定です。特徴は……あゝ、娘のことはもうご存知?近所で知らぬ者は無い…と仰有りますか、それは助かります。
……えゝ、左様です、海軍予備兵の制服と制帽をいつも身に着けた子です、行方が分からなくなったのは昨晩からでございまして。家の者総出で心当りの場所は探しましたが見つかりません、私はてっきり警察病院に向かったのだと思ったのですが、其処にも居ませんでした。受付の方もそのような人は見掛けていないと。
あゝ、貴方はあの日非番でしたかもしれません、一人の青年が我家の玄関に侵入して来た事件があったのです。おや、御存知、日報をご覧になって…あゝそうですが、それならば話は大抵お分かりでしょうか。
実はあの後、青年が病院へ送られた後から、娘は青年のことをよく話すようになりまして、えゝ、瞳が泣きそうだった、食事は摂れているか心配だ、どうして殺人を犯したのだろう、何かの事情があったのならせめて話だけでも聞いてあげたい…優しい子に育ってくれたのは親とても嬉しいことですが、一人娘だけに尚心配でございました、箱入りとまでは申しませんが幾分か世間を知らぬ箇所があると召使の者達にも言われたことがあるのです、相手が男性でなければこのような不安も生じ得なかっただろうとは思います、今更思ってもどうしようもございませぬのに……
確証がある訳ではないのですがね、娘が斯様な身なりを始めたのも恐らく例の青年の影響ではないかと。妻の側近の者が話してくれました。理由までは察し得ませんが男装を始めたのは青年と遭遇して二日後です、偶々かもしれませんが、何か関係あるのではと一度疑ってしまえばもうそうだとしか考え及びません。
でも、何故海軍の予備兵なのかが分かりませぬ。私共の身内にはそのような…海軍に関わる身上の者はいませんのに。
証言四
おはようございます旦那さま。随分と長い間ぐっすりとよく眠っておられましたねえ、その証拠にまだ頭が冴えきっていないようです、寝ぼけ眼の可笑しなこと。今度は誰方に会いました?男?女?人間?人以外?今貴方の前に居るのは人でない烏ですけどね。
鴉谷は地面に仰向けになっている男に話し掛けている。男の顔は濡れている。顔だけでなく首も四肢も胴体も、服を通して皮膚に沁み臓器神経の奥を刺すのは雨であった。相変らずの微笑みに川面は何を思ったのか此方もにへらと虚ろに笑う。彼の表情を見ると鴉谷はおや、と意外な反応をする、その間に相手はゆっくりと上半身を起こし雨止まぬ中に佇んだ。無言で這うようにして歩き始め、さり、さり、と地面を擦る僅かな足音。
何方へ行かれるので?と鳥が訊いても黙って首を縦に振るばかりで、目元は雫にまみれた髪の毛でぐっしょりとよく見えない。
此の場所は何處だか分っているのだろうか。
鴉谷の心中での呟きにまたも川面は頷いた。
此処は、焼けた街跡。焼夷弾に因り市場も家屋も人体も一瞬のうちに吹き散らされた辺り一面の焼野原。
開幕
遅すぎたと文句を言っても仕方があるまい。命の名残も許さぬ錆きった嘗ての街だった場所は、一人の青年をいとも容易く歪め歪めてあらぬ世界を創作させた。
焼野原の眺めを黄昏の市場で賑う光景に、別の場所から吹き流されて来た空気中の砂利は人しか嗜なむ異様の薬に、そして深く閉ざされた森の入口には在る筈も無い一軒家に。だからと言って彼は完全な空想家には至れなかった、何故なら菜の花畑に紛れる彼岸花の欠片のように彼の身に起きた事実を時折混ぜ込んでいるからである。
「描けたよ鴉谷。」
灰の後に水が落ちれば土に化すことを経験上知っていたかして、川面はふたりきりの足元に文字を紡いでいた。
(読者には此処で冒頭の序詩を御覧いただきたい)
「もう待っているのはあきあきだ。迎えに行こう、あの日のお嬢さんを。」
あの日とは川面が実の両親を殺害した日のことである。そして妹の墓を造った彼は同じ街に住む白羽の家に侵入したのだった。もっと人を傷付けたいと望んで衝動的に押し入ったのではなく(幸いなことに)、此処に行けば慰めてもらえるかもしれないと玄関越に直覚した。(今川面の精神状態を記していて、彼自身に害意や悪意が無かったことは勿論。暴挙に出る為の体力も気力も残されていなかったことを心より奇跡と思う)
目と目が合い、恋を生じる。それは昔読んだ物語にしか生きられない概念だと諦めていたが、諦念の中に稀に放り込まれる原石は見る者の瞳をどれほど輝かせるものか。
二の句を継ごうとして意識をぱったり手放した。急激に全身に新鮮な血を巡らしすぎたから。正気に戻った時川面は警察病院の白ッぽい天井を見上げていた。事情はどうあれ法を侵したことに変りは無い、清潔なベッドから脱走できぬよう両手首には手錠が嵌められたまゝ医師同伴の下取調べを受けた。
「両親を殺したと言うのは事実か?」
「はい。間違いありません。妹を死に追いやった二人をこの手で殺めました。遺体はそのままにしてあります、腐り始めているかもしれませんが、奴等を妹と同じ墓に入れるのは嫌でしたから。」
川面は刑事の問いに一つ一つ答えていく。
「あの、一つだけ宜しいですか。」
「何か。」
でもやはりどうしても気掛かりなことが。
「あの、私の侵入した御宅の、玄関で逢ったお嬢さんは…」
「あの娘さんがどうかしたのか。何だ狼藉でも働く腹積りだったのか貴様。」
「いいえ、いいえ、違います。私は、あのお嬢さんが、その、私の所為で気を悪くされたり、倒れたり、怯えてはおられないだろうかと、その、心配で。」
「元凶に心配されても向こうさんは迷惑なだけだ。それなら最初から事件を起さなきゃ良かったんだと罵られるぞ。貴様が案じる必要性など無い。」
刑事はそう言い切ると病室を去って行った。
「あの刑事のおじさんも、死んでしまったのかな。」
言葉は乱暴だった。でも眼差しは正直な人であった。
「何故貴方はご無事でいられたのです。他は塵も残せなかったと言うのに。」
鴉谷は川面の地面に刻んだ詩を原稿用紙に書き写す作業を続けつつ質問した。
「間抜けな理由だが聞いても笑わないかい。」
「内容によりますね。」
「マンホールに落ちたんだ。」
案の定の笑い声。雨が音を吸う中でも笑いはハッキリと。
「自殺でも計画していたんですか?」
「違うよ。病院で治療を受けて、人並みに歩ける程度に迄回復した時に医師が散歩をするようにと指示したんだ、ずっと寝てばかりだったからね、敷地内であれば見張りの警官が居るから入院患者は好きに歩いて良かったんだよ、尤も手錠と足首の重りはそのままだがね。
私は庭を歩いていた。囚人どもが歩いている割に景色はのどかでね、整備された並木道の両側に咲く青い楓の樹々をぼんやり眺めていると、どうだ、詩が思いついたじゃないか、書く物一つも持たない状態で。見張りの者にメモでも頼まないではと心ばかり急いて慌てて走ったんだ、将に空ばかり見て足下を見ず、工事中と区切られていた場所に気付かず駈け込んでね、ぽっかり穴の開いていたマンホールに足から真直ぐに落下した。下水道にぼちゃりと浸かった嫌な気持ちは今思い出しても好いものじゃあない、あゝ間抜けめと己に唾を吐いてよいしょと梯子をガチャガチャカンカン登って外へ出る、そうすると、もうこの通りさ。」
「音も衝撃も無かったのですか。」
「妹が自裁する前日もそうだったからこう考えるのだがね、日常が終る時には何の前触れも無いと思うんだ。変哲の無い穏やかな時間は静かに壊されつくしてしまう。殺人犯の台詞だから好きに扱ってくれたら良いよ、人ではない君等からしたら人間から逸れた奴が何を吐くと失笑にもならんことだろう。」
「いいえ、間違いでは無いでしょう。私は永い時間人の世界の傍に佇み続けましたが、爆音や轟きはあくまでも派生的な結果で、破壊そのもの自体は静かなもんでした。……音も無く、ふッと見たらもう……そんなものでした、いずれの惨劇も。」
此時初めて鴉谷の声は曇った。剽軽な演技を忘れるくらいに数え上げ切れぬ悲しい歴史を思い出した所為であろう。互いは暫く黙って居た。
「何故君は俺のもとに来てくれたんだい。普通、人外の手助けはまともな人間もしくは平凡で善良な人間に振りまかれるものでは?」
気まずさを嫌った訳ではないが、今更ながらでも尋ねておきたかった、白羽の所へ向かう前に。
「頼まれたのですよ。」
一度本性を見せたらもう吹ッ切れたのかして鴉谷は澄みつつも濁った本来の瞳で話し始めた。黒曜石に傷は無いが艶も無い。誰にと問われる前に一息後に答えを続ける。
「貴方、図書塔と言う名を知りますまい。」
征箭
図書塔の始まりは惨憺たるものであったらしい。気まぐれに始めた遊びが度を越えて世界を白く壊し始めてしまった、崩壊も侵蝕も抑えきれず止められず、悲嘆と怨嗟に手足を掴まれて逃げもならなくなった時、鎮魂の償いの為にと生じたものが図書塔だと言う。一体何の遊びをしていたのか気になるのは察するものの、知らない方が良い事実は存在する。いつか誰かが知ることにはなるが、記した者でさえ拒みたくなるような内容を強く願い、後悔の覚悟を決めたのであれば、読み進めても構わない。拒む者を否定しないし責めもしない。その人達はこの章を飛ばした続きから読んでもらえればと思う。
人が誕生する前、地球には旋律があふれていた。宇宙の惑星はそれぞれに音を奏で満たされた和音は星々の間を滑らかに流れ淀みの無い淵は誰に繋がれる鎖も留められる錨も求めずに搖籃の時を楽しんでいた。けれど或時旋律は一輪の彗星を見た。あの燐火と燃ゆる尾鰭を楽曲の中に放り込んだらどうなるだろう、好奇心が手を伸ばす。
不協和音を楽しいと思ってしまったのだ、一度でも。それからは多くの音を滅茶苦茶にして戯れて最後に残っていたのは地球、指を伸ばすと、パチリ目が醒めた。あゝ、遊びすぎたのね、なんて。
楽しみの後には償いを望まれ秩序の番人へと昇華され鎖を与えられた、自縛の情け、解けぬ約定、涙は地を射す征箭となって陽光雨露月光と共に降り注ぐ。それが図書塔の開始と言われる物語であった。
「まあ幾つか説はありますから、本当の始まりが何れかは誰にも分らないようになっているのですけれど。」
川面にとっては初めて聞く単語である。図書館ならば人の文明の中に含まれているが塔とは思いつきもしない言葉だった。
「図書塔と名告るようにしてからは塔の役目を守らなければならないから、鎮魂の責務を負いました。」
「レクイエムでも唱えるのかい。」
「貴方ご冗談は今お控えに。塔は言葉を発することも戒められているのです、歌など如何して奏でられましょう、囚人が時々鼻歌を歌うのとは訳が違います。」
冗談を言った心算《つもり》は無かったのだが。
「鎮魂と言ったって、具体的には何をするんだい。一言も喋ることが叶わないのなら何をするんだい?」
「黙る者は居場所を差し与えることで語ります。行き着くことのできなかった者達を受け取る為の場所。」
「つまりは安寧を与える楽園のような場所だとでも?秩序を任された身がそんなに簡単にいくものかね。」
「まあ楽園と言えば楽園ですよ、捉え方に当然差異はあれども。誕生の経緯など関係無く、何を果たし続けるかが肝要なのです。」
「其処では、人…否生命と言う方が適切か、生命はおとなしくしているのかい、安らぎを得て、静かに眠り続けているのかい。」
実際にお行きなされば良いと言い掛けたのを半途で押さえ、自分が彼のもとに向かうよう指示された流れに繋ぐ。
「えゝ。塔そのものはとても静かですよ、世界樹の枝の一部を込めたとも言われていますから柔と剛を備えた表皮、その内側には眠る生命達が収納されています。どの本を読んでいても報われない健気、受け容れられない一途のものばかり、尤も図書塔にはそのような書物しかやって来られませんがね。塔の中には一人の年老いた男が番人をしています。清掃が主な役割ですね、塔を清潔で清浄で清廉な場として保つ為には彼の力が必要なのです。」
人が居るのか、人ならざるを匿う建築物の中に。
「その番人は塔の声を聞くことができるのです。私が本を読んで友の蛾と追いかけっこをしていた時、塔から私への伝言を番人は預かりました。指示はこうでした。紀莟を慰める為に星北川面の手助けをすること、とね。」
紀莟とは、白羽の死んだ弟の名前ではなかったか。彼が如何して自分に関わってくる?
「答えはもう少し話せばご自分で分りますよ。さあ、再び貴方の記憶の続きを教えて下さいな。」
マンホールにアリスの如く落下した後の続きを。
鎮め
一夜のうちに何も誰も居なくなっていたのを見た後、真先に思ったのはあのお嬢さんだった。もしかしたら彼女も彼女の家も、と考えたら、毎日病室の窓から眺めていた方角へと駈けていた。今出せる全力で走ったが、身体中に鞭打っても結果が好転することはなかった。何も無い景色はずっと何も無いまゝで、人肉が焼け染み血が焦げ黒くこびりついた地面は同じ様相を呈するばかり、多少も変らない背景の中進むのはその場で足踏みをするのと酷似していた。
「お嬢さん。」
痛み渇く喉で名前も知らない思い人を呼ぶ、反響も増幅もせぬ酷く掠れた声は空気中を伝ってもちっとも伸びない。もう一度呼ぼうとしたら咽せてしまい、咳は微量に血の混じる痰と足元にびしゃり撒かれた。息苦しさに涙が込み上げ気管は悲鳴を隠さない、ゲボゲボと苦い汁を吐く、出し切りたくて鳩尾と胃の辺りを拳で殴る、酸い臭気。
「止めた方が良いですよ。」
無意識に土を握りしめて汚れた指先を緩やかに解き、膝をつきもがく背中をゆっくりと大きく上下にさする、醜い口元を染み一つ滲まぬ手巾で拭う、その声、その指、その姿、一目見ただけの天上の女神に異ならずと歓喜の呟きは喉を破らず瞳にのぼっていた。
「苦しそうに、お可哀想に…あの、少しばかりではありますけれど、水を。」
そう言って唇に恵んだ硝子の縁と水の冷たさに正気を取り戻し両眼には涙に因らぬ光が映る、砂利と埃を吐き出していたのが遙か以前の出来事のように胸もすく。精神のピントが合い始めると人間、今度は自分の佇まいに意識が向くので、勿体無い御手に縋り乍らも頭は深く下げたまゝ元の通りの声で申す。
「お嬢さま、天女さま、女神さま……死ぬ前に一度お目見え叶いまして恐縮にございます…願いは、望みは果せられました、思い残さず妹に会いに行けます、本望……」
火照り空回る頬へ垂れた濁る雫を掌で受け、新月の情けに潤む玲瓏なる一双の湖面が我が面をじっと見守られる。
「其処迄して苦しんで…ねえ、もう此の方を解放してあげなさいな。」
意識は其処で一時夜空を見た。そして曙の呼び声に瞳を開くと、あの夢の日々を過ごしていたのである。
「むむ、む。」
「鴉谷、君が唸るもの当然さ。目が醒めた筈なのにずっと自分に都合の良い夢を暮らしていたなんざ、俺にも分らないよ。忘れたくない記憶を忘れて、何も頓着しない無頼漢のように歩いていた、詩を描いて世間に疎まれ妻を貰い阿片を呑みそうして夢は俺から離れて、今に到るのだもの。森はあるが家なぞ無かった、白羽を救う為の冒険も所詮は男の幼稚な見栄ッ張りの性に因る夢だったんだ。俺は白羽、あの時逢ったお嬢さんを忘れることだけはしなかった、それは惨めな身分違いの恋の為さ、叶わぬ恋と言えば聞こえが良い、捨てるべき過去を捨てられなかった、我ながら未練がましくて嫌になるね。」
てっきり鴉谷が呻いたのは川面への情けなさからだと思っていた。だが当の本人は白羽の台詞を気にしているらしい。
「解放。確かにそう仰有ったのですか。」
「あゝ。あの人の言葉は一言一句違えない、俺が何を言ったか忘れても彼女の言葉は憶えている。確かに仰有ったよ、解放とね。」
「…そうですか。分りました。えゝと、もう川面さんのお話はお終いでしょうか?」
「今の段階ではもう昔のことは話せないよ。憶えているだけの来歴はすっかり明かした。」
「左様ですか。それでは今度は私が図書塔に命じられた任務をお話しましょう。」
そう言うと、一双の足をピタリと揃えて一回飛んだ。
地面に着地した時、一羽と一人は大理石の迷宮の中に座っていたのである。
「お帰り鴉谷。今度は誰を迷わせた?」
川面の目の前天地逆さまに立つ老夫が長く白いふさふさの白髭を片手ですいすい撫でながら声を掛けた。
「ふッ、掃除夫のくせに生意気仰有る。」
継ぎ木
「折角です、一つ書籍を取ってみなさると良い。」
老人に勧められるまゝ川面は手近な本を一冊手に取る。題は「継ぎ木」と細字で丁寧にしたためられている。分厚さは然程でもなく世間一般の文庫本とよく似た外見をしていた。自分の詩集を思い出しながら頁を捲る。
燃やしつくされなかった世界樹の鏡、燃やされて一本の枝のみの姿となったもう一つのユグドラシルは時間の星々の川の中で逆らう力も無く漾っていたのであります。見捨てられてしまった方の樹の残骸はこのまま消滅するのだろうとぼんやり思いました。必要とされず望まれなかった世界樹、涙を浮べる気力も認められず放り出されたまゝ、その一生を終えようとしていました。
「起きて。起きてください。このまま死んではいけません。」
声がします。小枝は手を伸ばしました。すると何者かが小枝をぐいと強くも優しい力で引き寄せ、渦に沈みそうだったのを狭間の陸へと引き上げました。
小枝を助けたのは一匹の蛇でした。その名はニーズホッグ、望まれない姿の鏡、望まれたもう一つの毒蛇でした。
望まれなかった世界樹と望まれた悪しき蛇。溶けない硝子で隔てられていた互いの世界は迷子同士出逢ってしまったのです。毒蛇の献身により小枝は蕾を膨らませるまで回復しました、けれども此方側の世界樹は花を咲かせる命懸けのさゝやかな喜びも許されず、春風を待つ蕾は生れて数日後にさらさらと灰と散って行くので、小枝は涙を蛇に見せぬよう堪えるのが常となっておりました。共に居る以上は笑顔でいたかったのです。
互いは優しすぎました。自らを必要とせぬ世界や悪しき存在と見なした世界を恨むでもなく憤るでもなく唯遙か遠くへ切り離されたふたりきりの陸地でじっと見つめて居るのです。
「貴方は、怒ったりしないのですね。」
ニーズホッグが時間の銀河を眺めて問いました。
「はい。怒りはしません。私は望まれなかった方の世界樹。平和が戦争を受け容れ難いように、戦争が平和を認めきれないように、世界がこの身と距離を置いただけのこと。世界の理に順応するのは生命の定め、ですから。」
徒花さえ散らせぬ姿は少し笑ったようでした。ニーズホッグは胸が痛むのを感じます。存在を許された自分の言葉はトネリコの小枝に届かないかもしれないけれど、不安より恐怖より、小枝を助けたい気持ちが此時は勝ったのです。
「では、君のことを残しませんか。誰にも望まれなかった世界樹が存在していた事実を残すのです。」
「そうして、どうなりますか?」
「残った事実はやがて物語へと到ります。そしていつか、その物語に救われる者が現れるかもしれない。存在するだけで誰かの明星となる日がいつか必ず訪れます。」
小枝は寂しい笑顔を浮べました。もう互いの別れの星が降るのを双方感じていたのです。時間を惜しみふたりは語らいました。
さよならと一粒の真珠を残し、世界樹は旅立ちました。残されたニーズホッグは呆気無さと無力を感じます。けれど約束を失うわけにはいきません、ニーズホッグは小枝の命を物語へと継ぎ木しなくてはなりませんでした。悲しみを原動力に痛む胸を抱えながらニーズホッグは語ります。語って、語って、語った後、ふッと考えが一つ、彼の心のやわい部分に訪れました。
“どうして望まれない方を理は生み出したのだろう。”
人間が神へ怒ることと似たようなニーズホッグの最後の台詞に、川面は背筋がゾッとするのを隠せない。最愛を失った者の暴走など、いくらでも思い付く話である。
「お爺さん、この物語、続きは…」
「続きはありません。ニーズホッグ達のお話はそれでお終いです。」
「そうか…」
そうか、としか言うことができない。不穏な結末に自身のみ生き残った焼野原を重ねてしまう。
「まさか、この神話の続きが俺の居る世界だなんて言わないよな。」
老夫は笑った。大きな声で、アハハ。
「図書塔に集うのは世界から逸れたものばかりです。延長線上に立つことは到底かなわぬものしかおりませんよ。…ですが旦那さま、どうもそんな説明では納得いきそうもありませんな。」
無理もない。自分達の世界がマンホールに落下していた僅かの間に薙ぎ払われたのはよもや蛇の復讐ではあるまいかと空恐ろしくなったのである。こわいもの程知らなくては不安になる、ありがちな強迫観念に突きつけられて川面は説明を求めた。
「物語が継ぎ木だと言うのなら、俺達の世界はその枝の先に咲く花、なんてことはありませんか。であればあのように何も残らない世界に陥るのも納得がいきます。蛇が仇を討つためにしたからと理由を定義できたのなら、あんな目に遭うのも人間達の自業自得だと諦められる。」
必死の形相に老夫はほくほくと笑みを絶やさない。
「おまえさま、諦めだのと結論を求められるのであれば、ご自分で描いてみなさるが宜しい。」
「えっ?」
「鴉谷が何故詩人である貴方のもとへ赴いたのか、今一度考えて御覧なさいい。詩の才を与えられた、そしてその才を活かすことの叶った人間だからでございましょう。貴方を此処に呼んだのも、此の場所での出来事を詩として吐かせる為、詩の描けない詩人は哀しいかな只の狂人です。只の狂人が愛する者を愛せますか、自らの脚で逢いに行けますか、白羽嬢に再び相見えたいのであれば詩人で居続ける他ありませんよ。逢いに行っておあげなさいな。先程は詩を描けたではありませんか。」
「鴉谷に見せたものですか。」
「彼から聞きましたよ。鴉谷は言葉にはしていませんが今も多くを儂に話してくれています。貴方が優しすぎることも、白羽嬢にも一度逢うのを切に切に願っていることも。儂も嘗ては不条理や理不尽を散々に味わいましたからね、自分の居た世界が亡びる苦みや痛みはお察しします。」
「や、貴方も?」
「はい。そして家族も失いました、妻と息子を。そして息子は、物語の中でしか自我を保てぬ状態に変えられましてな。」
老夫の変らぬ穏やかな笑みに胸が痛まぬ男ではない。自分以上に苦しみを知っている者の前では、時に若者は無力である。
「そうでしたか…」
「どのような本が他にあるのか、正直に申せば貴方の手で一冊一冊読んで確かめてほしいとは願います。ですが、その前に貴方はご自分の足痕と向き合わなくてはなりません。他者を思う前に自らの土台を据えなくては救えるものも救えはしませぬ、儂は此処に運ばれてその理を知りました、ですから先輩、としての助言ですが、年寄りの独り言として受け取ってくだされば良い。」
未知なるものに意識を馳せる。其の希望から話を紡ぐのが小説家で、光に影を見出すのが詩人である、と昔確かに、誰かに、得意気に語って聞かせた俺が……
「そうだ、あれは。」
他者の記憶を有する者。それは白羽に限った特例ではなかったようだ。
未練
生きているうちに果せなかった事や叶えきれなかった夢は死後遺体の周りに繭となって集い、魂が絹糸を重ね紡がれた其にもう一度 接吻をした途端に未練となって魂の輪郭を縁取る。その縁取りの中でのみ死者は再び現世に手を出す行為ができるのだ。そしてこの摂理は産まれることのできなかった命に対しても適応される。
紀莟は白羽のように生れることができなかった。何故なら彼は嘗て彼岸と言う名で一度生きていたことがあったから。妹を救えず村から見捨てられた若い男子は自ら命を絶った、そうすることで二度目の生を拒んだのである。だが紀莟は再びの生存を手放した者が傀儡師の人形と成り果ててしまう理までは知らなかった、人が知ることも禁じられた星々の掟だった。
人形を操り踊り躍らせる法悦。それは喜劇の時よりも悲劇の上演の方が技術が要る、感嘆と喝采は不条理の後だとより多くなる。哀れ心優しき彼岸青年は今や好き勝手に弄ばれる土くれへと到ってしまったのである。此処迄申せば読者諸君は流石にお気付きであろう、何より名前の響きがよく似ているもの。
紀莟とは悲願の一つ後の生であり、その命は今星北川面として現世に在る。理は一度の過ちをも許さない、彼岸青年はまたしても妹を失う道を辿り歩かされてしまったのだ、あゝ無情にも程がある、悲劇とは人一人いとも容易に転がしてしまう。
「お嬢さんは。」
「白羽さんですか。」
「まさか、あの方が…」
「妹さんではありませんよ、昔も、今もね。」
疑問を手早くあしらい案内役は尚続ける。
「私はあの娘の正体を知っていますからお伝えするのは簡単です。ですが貴方にその度胸があるかまでは一寸…」
そう言われて相手は大概次のように必死になる。
「あります。覚悟ならしている、ずっと重く垂れ込めていた黒い靄がだんだんひっくり返っていく、そんな気がするんだよ、俺が、昔彼岸として生きていたことも、自殺したことも、生れることを拒んだことも、今全部流れ込んで来ている、この流れが行き着く淵はきっとあのお嬢さんだ、根拠も何も用意は無いが、星北川面として生き永らえて来た本能・直感がそう言っているんだ、叫んでいる、やはり俺はあの方を探さないでは求めないでは居られないのだと、頼む、どうか頼みます、白羽とはいったい何者なのですか、教えてください。」
興奮している者には一つ、純朴な事実を掛けて頬を冷やさせるに限る。長年役目を降りずに人の傍で人を見続けて来た鴉谷はもう勿体ぶりはしない。
「白羽さんはね、守りてです。人間ではなく、理をね。」
未練があった。役目に徹する手のもう片方、ずっと一粒の雨が滴っていた。
人間の姿で生れたからには人並みの友情や恋愛や喜怒哀楽を味わうものだと信じていたけれど、理はそんなに甘くはなかったみたいで。確かに他が為を思い想われること自体は叶った、にも関わらず役目は非情に命令する。理は平和と友好を持続させようとする力、それに抗い戦争に現を抜かす人々には相応の罰を。何度多くの人を苦しめ痛めつけ踏みにじったことだろう、平和を希求する人の眼前に白炎の斧を振り翳したことだろう、皆が争いたいわけではないと言うのに、理は一度の過ちも許さず一人の罪は全員の罪としてしまう。此世に命を受けた以上、理に逆らうことはできない、私の力に詰することもできない。
可愛い、可哀い人間達。生きたいと願ったゆえに生れることのできた生命達。無情で清廉な理が私に力の行使を許した時にもはや一人一人を気に掛けるなどしなくなった時、雨粒が私の掌にようやく届いた、何百何千何万年と時間をかけにかけた一粒。
当初は些細なよくある抵抗だと軽んじていた、人々が全員理に従い健やかに争わず生きようとしない方が悪いのだから情けを恵む必要などあるまいと普段通り不条理を与えて命を奪うだけだと。
此れより内へ来るは易し、踏み入れ易い足置き場。
「何?」
背丈の高い樹々のあわい、春が雪に遠慮して…
「言葉?」
新月のしたるるを止められぬ悔しさに歯噛する
手を濡らす一粒の雨が言葉を描いていた。それは初めて聴く言葉の手紙、怨嗟にも憎しみにも頼らない、ただただ自らと相手の孤独を慈しむような、寂しくも優しい手紙であった。恨みつらみ、悪逆背徳、これまで理とその守りてである自分に投げつけられた被害者感情に因る言葉以外を、私は此の時確かに受け取った、私達へと贈られたもう一つの人の英知の結晶を。捧げられるなど初めての経験だったから、大いに戸惑はした。それでも此方から返礼をしなくては沽券に関わる、私は数えるのを止めた回数の焼野原の真ん中で佇みながら考えて、その詩人を楽にしてやりたいと思いました。
彼を理の制限から抜け出す為には、私が代りにならなくては。
失敗
では白羽は俺の言葉で自信を苦しめる境遇に入ったと言うのか?などとても言えない、ブッ飛んだ話と思っていたらまさか己が自身の慰めの為に呟いていた過去作が主軸に立っていたなんて。
「そんな、優れたものではなかったろうに…お嬢さんは何故。」
「作者にとっては特別なものでなくとも他の人には命の次に尊く感じられるものだってあるでしょう。白羽嬢の胸には何より貴方の言葉が嬉しかったのです。」
「俺が病院でマンホールに落ちたのは。」
「おそらく彼女の計らいでしょうな。貴方だけを助けて、自らの役目を行なった、と言う具合でしょう。そして貴方が一人で狂乱した際に、貴方が幸せになる世界を記した。けれど其処では白羽嬢は父母から虐待を受けていた、そしてどうやら元の世界と完全に切り離すことはできなかったみたいでどうも要所要所実の世界と相混じっているようだ、書き上げる技術が未熟だったのか、理からは逃げきれなかったのか……結局貴方が目醒めたことで白羽の創作世界は終りました。鏡の世界は、もうおしまいとされたのです。いつまでも人が赤子では生きていけないように、しゃぼんだまはいつか散ります、世界を逆さまに映した光景を抱きながらね。」
鴉谷の瞳の水晶は雨を待つ夜空のようであった。
「それまではずっと役目に忠実だったのに、貴方の言葉で彼女は世界を知ったんです、知らない世界に恋焦がれて初めて自分の意志で行動したのです。」
なのに報われなかった結末。大団円には程遠く。
「あの娘が去ってしまったのは、俺の傍に居るのはいたたまれないと思ったから?」
一度きりの失敗で、と嘲笑いますか
「命が懸かった行動ですよ。実際白羽は真面目がすぎる気がありましょう、一人で思い詰めてしまうこと、あちら側でもあったでしょう。」
自傷行為。夫婦になってもう悩みは無いと思い込んでいた日の、驚きで
「貴方の記憶は一部戻った。亡くなった妹さんのことを思い出した。その時彼女も思った筈ですよ、まさか失敗したのではなかろうかと。」
俺は詩人の才を持つ者の宿命だと思い自傷行為を責めはしなかった。あの娘が申し訳なさそうにしていたのは不条理に遭わせない世界である筈が彼女の自傷行為を俺が発見したからだろう。彼女にはバレない核心があったからこそ思い詰めた行動の痛ましい発散法を実践していたのだ。あの自傷行為は、不安から衝動的に切ったものだった、不条理を見せないような世界づくりが上手くいくのかどうか分らない、間違えてはいけない、私が反した理由を理はのぞき込んで白日に曝す、そうなってしまうと理由の原因である彼が、川面さまがもっと理不尽に苦しめられる。逃げた者を理が許す筈が無い。怖い、怖い、あの人にだけは、あの人にだけは怖い目に遭わせてはいけないの。なのに
白羽、やめろ
見られてしまった、できなかった。優しい愛妻家が妻の自傷行為を発見するなんて、何て痛みを与えてしまったのだろう、ごめんなさい川面さま
理から逃げ続ける世界の永劫化を果たせるのか、娘は重責に追い詰められた時にパッとやってしまった自傷行為を最愛の夫に見つかってしまったその瞬間、自分の描き上げた世界が元の世界と混在していることを直感し、こう思った
私の望んだ世界は失敗だった。
貴方の為の世界は描ききれていなかったんだ。いやだ、未熟で助けられないなんて……でも、若しかしたら、チャンスはあるかもしれない。
けれど、阿片は彼の元へやって来た。
阿片なんて要らない筈なのに。夫婦となって互いの寂しさが埋めきれない、埋めても埋めてもまた穴は生れる。
駄目!このままじゃこの人がまた悲しい道を辿ってしまう。私に心を与れた貴方、私に意志を持たせてくれた貴方が、また犯罪に手招きされている。あゝ、そんな要素必要無かった筈なのに、どんどんあちら側が侵蝕してきている、此処でも逃げられない、理からは、何處に行っても……失敗した、失敗した!
許してくださることはありますまい。貴方の傍に私が居れば川面さまはずっと不条理を味わい続け破滅の道にしか辿り着けない
さようなら、もう貴方と共には居られない。こんな災いの娘、貴方から離れるべきだったんです。身の程も弁えられずに馬鹿なことを、馬鹿なことを……
夏の夜
山に着いた。勿論麓ではなくって頂上に程近くなったまだ雪 被ぐ清浄の地、新雪の平らな湖面には足痕一つも認められず凍れる鏡の深々と音を吸う警告ばかりが此方を見つめる。
時は夕刻、まだ陽は見届けたいらしい、月が再び雲から姿を現はすか否かを、まだ自分の役目が必要とされているのかを。
「白羽さん。」
上ずっているかと危ぶんだ声は存外静めて静かに低く、川面の平生の調子そのまゝであった。呼び声にハタと駈ける足音が草木の間を吹く風に伝わり耳に届くと、一本のシマトネリコの樹影から懐かしい顔が覗かれた。
「先生…?」
何故来たの、とでも泣き出しそうなきょとんとした顔で夫を見つめるその瞳、あゝ、血塗れの姿で初めて逢った時から一つも変らぬ明眉と憂愁と慈しみのほのぐらい輝き。
「迎えに…来たんだ。」
「お帰りください。」
告げた言葉をにべも無く拒むと川面から顔を背けて視線を落す、誰の目にも本心で無いことは瞭然であったが、川面は白羽を責めもせず、一つ聞いた。
「俺には背負わせられないかい?」
白羽の瞳が再び川面を映す、柳の眉は怒るに怒れぬ風情を湛えてやゝ吊上がりつゝも悄然とする。
「貴方を理から逃がしたかったのに。自分で作った別世界に私自身が溺れてしまって、何も上手く果たせなかった。菫ちゃんが来てくれる迄私は逃げ続けられると信じて、祈っていたのです。なんて馬鹿な女、恋の一つも知らないで命懸けの恋に生きようとしたなんて…私は結局貴方をぐるぐると引ッ搔き回したうえ元の世界に戻すことしか叶わなかった無能です、絶対に失敗させてはいけない、貴方の命に関わる抵抗あだったのに、私は失敗してしまったのです。もう貴方と共に在ることは烏滸がましい、だからどうぞ、お帰りください。山を下りて、二度と戻って来ないで。」
歔欷の声に呼び立てられて彼女の後ろ、両側に二つの黒い影がぼやりと立ち現れる。
「旦那。山猫達です。」
影は輪郭を編み出せずほつれた紙片のようにほろ、ほろと時折 縁が蠢いているが、ぼやりとして目鼻の位置もあるかどうかも分らない。大きな夜の靄が白羽と川面の間に立って隔てた。
「……………」
音声を発さず其処に留まり続ける番人を川面は見つめている、無理にどかそうとも、力に物言わせるでも、罵るでもなく、黙って口を引き緊めて、だけど何處か微笑んでいるようにもとれる口元をしながら、決して目を逸らさない。
「旦那、もし、どうかしたんです…」
鴉谷の問いを静かに手を伸ばして制止する。噤んだ付添は肩を軽くすくめて言わんとすることに頷いた。
「…今でも正直、何のような言葉を掛けたら良いのか迷っているんだ。」
川面は山猫達に話し始めた。
「けれどずっと黙りっぱなしも寂しいもんだろう?何たって自分の過去なんだから、せめて俺が君達一対を捨ててしまっては本当に君達は孤独になってしまうじゃないか。置いてきぼりにするなんて、嫌だよな。求められないから、望まれないから無視されるなんて、其方からすれば堪ったもんじゃないのにな。」
そして、傍に転がっている変哲の無い枝を利き手に取る。
灯台の火は嵐の中の最後の希望
空に頼られなくなった人々は
灯台の炎に道を見る
導かれて歩みを進め
やがて陸地へと到る者達
喜び・祝福・讃美は数限り無く尽くされる
陸地に上がってもう海で嵐を避けさえすれば
灯台は一つの光景にしか過ぎなくなった
歓喜と感謝の声は遠のき
命救われた喜びの涙に抱擁しあった熱気は風に冷えて
もう誰も灯台の炎を憶えていない時代になった
灯台は古い城と同じ扱いを受け始め
炎を灯すことはできなくなっていた
必要とされた筈の過去は未来には不要のものだった
未来が認められないものだった
役目を望まれ在るだけで眩き救いとなった
灯台は
大人しくしていることだけを新たに望まれた
嘗て炎を望まれた灯台は
炎を望まれない姿に移ることを望まれた
今でも老人が一人、苔蒸した灯台の足元に座り込む
老人はいつも挨拶の後灯台を仰ぎ見て笑う
「いつか必ず導きの炎が輝く時が来るだろう。
そん時一人も操作出来んとは洒落にならん。此処に居る、
此処に居るよ儂の相棒、その日が来るのを待っていよう。」
山猫の隙間から文字描く音が届いた白羽の耳。居ても立ってもいられず一対の隙間からぐいぐいと身体を潜らせて音のする方げ飛び出した。
「第一の詩、ですか?」
「そんなもんだね。でも恋文には程遠いぜ、何だか物語ってか短編小説みたいになっちまったな。まだまだ!」
「否!続けて、このお話、続けてください。」
白羽の高い声に川面は驚き彼女の顔を正面に見た。笑っている。泣き痕は乾いて頬に名残が見えるがその頬は桜の紅潮に襲ね牡丹の喜びに染まっている。瞳は杜若の紫水晶に潤み若葉の吐息がもっととねだる。
「川面さま……師匠!師匠の作品をもっと続けて見せてください。私、私、今、とても喜んでいる!」
熱烈なファンの直々のお願いを払うような馬鹿は此の場に居らず。川面は灯台の詩物語を続け出す。
灯台と老人は仲良く苔蒸していく
話し相手の失くした灯台にまた草木が被さって来る
もう老人が居た残骸も土に埋もれて分解されたことであろう
灯台はやがて姿を数十倍になってしまうほど大きくなった
草花の重みを抱えきれなくなった灯台は身を横たえ
それでも植物は彼のもとに集まっては実を結び花を咲かし莟を託す
灯台はもう一つの島のような大きさになっていた
けれど人間が足を踏み入れるには脆い地盤で
訪う者は小鳥、小兎、仔猫に仔犬、そして他の小さく軽い動物達
かれらは灯台の昔話を聴き
島に入れられない者達の為に唄って聞かせた
唄は文字へ姿を変えてそれぞれの生命間で紡がれていった
灯台は最期に一言掠れた声でこう言って
「ありがとう」
二度と炎を宿すことはなくなった
沈黙の土壌は今日も
遙か遠い場所での詩の土台となっている
灯台は、死してもなおその使命を果たし続けている
失うかもしれないと感じた恐怖に目を背けて何事も心配無いよと誤魔化した幼少期。妹の瞳が摺硝子みたくぼやけて焦点が合わなくなったことくらいとっくに気が付いていたのに、それを打ち払う具体策が見当たらず言葉に、詩に縋ったのだ。
置いて行ってごめんよ、一緒に手を繋いで歩いてやることもしなかった兄ちゃんを許してくれなくっても良いから、きちんと謝ることだけはさせておくれ。
妹よ
どうしておまえの水晶はそんなに澄んでいるのだろう
光をいくつ与えられても眇めることもしないで
陽の涙を一面に、そしてやがては全身で浴び続ける妹よ
おまえの心はとてもいじらしい
祝福が齎されないと賢い心で直覚しながらも
猶親の笑顔を求めるおまえ
自らの心が
とっくに破壊しつくされて掬う欠片も足りないことを見られないで
歩き続けてしまったおまえ
立ち止まって休んでも良かったのに
おまえは僅かな休息をも惜しんだばかりに
世界の手綱からこぼれてしまった
そうして私だけが生きさらばえて
おまえとの記憶を何度も何度も捻じ曲げて
おまえの心に湧いていたゆきどけのような城とは似もつかぬ
霧雨の冷たい城を建てて居た
もう一度逢えたのなら
その時私は小さな雀にでもなって
毎朝日光と雨粒をおまえの清らかな窓辺に捧げたい
住む世界が違っていても
おまえが心健やかに生きることができるなら
妹よ 妹よ
どうかしあわせに恵まれておくれ
気にしない振りをしてきた死の恐怖。詩に涙する間は隣に有る痛みを感じず忘れることができたから、俺は詩を作って強がり妹に大丈夫だよと笑い続けたのだ。今更過去を掘り起こして何になると笑いたければどうぞ笑うが良いさ、何れ過去はふとした隙間に現れる、此方からは見えていないだけで、向こうは此方をずっと見続けている。
「いつか向き合わなければならないものを、早めて今向き合うことの何が悪い!」
文字を刻む意志と動作は肝の束ねをむんずと掴みめいっぱいの酸素を味わわせることから始まる激痛の産物、人によってはお産よりも過酷だと感じる者もいるかもしれない。
「それでも描かなければならない。」
意識朦朧と神経の熱病に悩み浮されながらでも
「白羽。」
個々よりも全体よりも何かもっと大切なもののために、私は。
風船
世界を終らせる力、とはよく耳にする架空の力である。大概はSF映画・コミック・小説なんぞでお目に掛る強力なもので、装置のようなものから射出されたり個人から放出されたりして大爆発や生命を吸い取ったりする類かもしれない。何せ人が考える事柄だから似たような着地点に落ちつくのは仕方が無い。
「でもこんな最終兵器みたいに光り輝いたり、オーラを発したりする訳ではないのだけれど。」
白羽は小さく笑った。彼女の膝元にまるまり縁側の日光で暖を取る仔猫二匹はすうすうと寝息も静かにくうくう夢を見る。
「待ちくたびれてしまったのね、きっと。ゆっくり寝んねするのよ。」
読み掛けていた本を再び読み始める。小さな文庫本程の大きさの其はいつか何處かで海軍予備兵の身装をしていた時、本屋の天守の目を盗み袂へ拝借した詩集だった。まだ見ぬ想い人への恋文かと思えば自らの過去への懺悔、血声を絞る謝罪、或いは詩と定義するには些か難しい小品まで描かれていて、その内の一つに白羽をモデルにした作がある。
題名は「白瑪瑙」。主人公は何千年も乙女の姿で生き続ける娘の新月で、最初は人の世界に不条理と精彩を落す自らの役目に忠実な感情持たぬ者、しかし人間の産み出した文化に触れていくことで次第に人のような気持ちを抱き始める筋書きになっている。
「主人公が成長していく物語はありふれた展開ではあるけれど…貴方にとっては筋書きよりも言葉を扱うことの方が面白いことなんでしょうね。」
イエネコにしては少し耳の長く先端の鋭い形をした二匹の眠りを妨げないように囁き声で庭先に咲く蒲公英に話し掛ける、一輪だけの黄色な花の他には不思議や青く透いた菫ばかりが咲く庭で。
嘗ては人間の真似をして抗ったこともある。けれど抗いきれなかった。畢竟するに自分は理の指示を心の片隅で受け容れる準備が仕上がっていたのであろう、諦めと言うよりはやはり理に付随する者だったのだと思い知らされてしまったのだ、きっと理は白羽が其処に行き着くことも分かっていた、でなけでば彼女に意志など与えなかった筈だから。意志を与えたのは、迷いと苦しみを与える為、そして其等は不完全なる人間と言う種族なればこそ感じるもの。
「私は最初から人間だった。」
口に出してしまえばなんのその。自ら一線を引き離れ続けていただけで、根ッこはずっと繋がっていた。
辺り一面の焼野原と化した昔の町は今や港が造られ大きな船舶が一日に何度も行き来する港湾都市へと歩みを進めていた。山の上から見降ろす白い煙が烏の羽ばたく空の雲へと溶けてゆく。
「山の中から見る海が、ずっと憧れだったものね。」
昔は貿易船ではなく帝国海軍の戦艦だった。医者の勉強の合間合間に恥じるように目を輝かせて見ていたのは、妹さんくらいしか知らないのでは?責任の為に生きても詩を捨て切れなかった中途半端な未熟者、図書塔はそんな貴方だからこそ目を掛けたのかもしれないけれど、塔は何も語らないから今日も空想で描き足されていく。
「白羽。」
貴方の声を聞いただけで、私と山猫達に向けられている眼差しが分ります。だって、妻ですもの。
「貴方。」
先生でも何でもなくなった一人の人。言葉を紡ぐのが人より得意なただの人。無力なだけさと貴方は自嘲するけれど、私はそうは考えません。だって
「妻ですもの、かな?」
自信無さ気に正確な答えを告げる優しい人、今二人手を取り合って仔猫を互いに一匹ずつ抱えたまゝ縁側から座敷へと移動する。
「此処は、もう戦前の町じゃなくなったのか。」
愛しい面影、愛しい声。私に言葉を届けてくれたあの日以来変らぬ瞳の色。
「今日は随分とご気分が宜しいのですね。」
「うん、昨日は久々にゆっくりと眠ることができたからね。近頃は書斎に籠もりきり肩も痛むし頭も痛いや、目を酷使したからだろう。」
「では今日はきちんと湯船に浸かってくれますか?」
「実は其を頼みたさに恰好つけて出て来たのだ…もう入れるかい?」
「今に沸きますからもうしばしお待ちなさいな…ねえ、あの、その間にお話を聴かせてくれませんか。最近聴いていないから私、もう耳が退屈なのですよ。」
「長い間待たせて済まなかったね。じゃあきちんと正座して背筋を伸ばして…形から入ることも大切だよ、先ずは身装を整えるんだ。」
語る準備を始める自分に笑い掛ける白羽。風の搖らぎに長い耳をピクと反応させて、まだまだ幼い山猫達が目を覚ました。その瞳の色は、夕暮を示す黄昏の色。忘れ物を探す、迷子の為の世界の色。
終
「守りて」