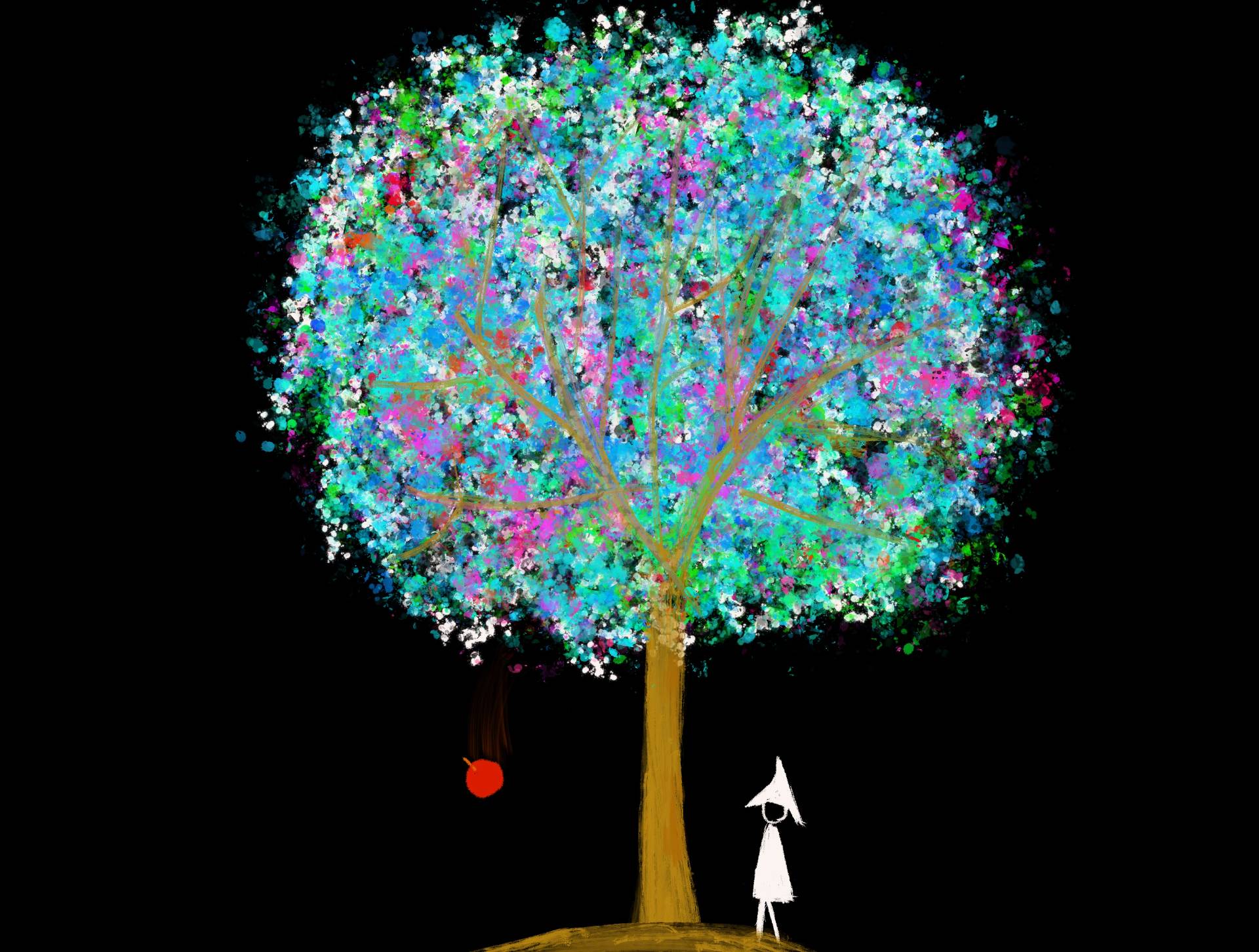
木曜日の虹
木曜日の虹
精神病院から出てきた僕は、その美しい虹に涙した。高校の友だちとみんな縁を切って、連絡も返さず、退院するときにはもう、ひとりぼっちになっていたから。
死にたくてたまらない日が幾度となく過ぎた。それは海の底に沈んでいくのに似ていた。たゆたう光が目の前にあるのに、僕の手は届かない。突き刺すような冷たさが身を包み、息ができないほど苦しい。僕は海の底の死の淵に落ちていく。誰も助けてくれやしない。自分を救えるのは自分だけなんだと思い知る。だけど、それでも僕は誰かにすがることしかできなかった。
訪問看護の緒方さんは、僕の出会った人のなかで、最も純粋で優しい人だった。ちょっとおっちょこちょいで、机に手をぶつけたり、午後二時を知らせる時計の音に体を上下させたり、くすりと笑える変なことを言い出したり、思い出せば微笑ましい出来事をいっぱい生み出してくれる人だけれど、その根底にはどこまでも透き通った湖が広がっている。それは夜の月を携えて、薄明かりのなかにまどろみ浮かぶ。僕の言葉は石のようなものだ。緒方さんの心に投げ込まれた僕の言葉の石は、湖に波紋を浮かばせてしまう。だからどうしても本当のことを言うことができなかった。僕は彼女の純粋で透き通った湖を壊したくはなかった。
「明日、死のう」僕は隣に座る彼にそう言った。彼は「そうだね。明日死のう」と言った。解離性同一性障害だった。もはや、僕の心は二重になっていて、本当の僕はどこにもいなかった。病状が悪化しているのは確かだった。でもこのまま終わりゆくのもいいなとさえ思っていた。その日は木曜日で、これから緒方さんが来る予定だった。僕は緒方さんと話を終えたら、ロープを買いに行こうとしていた。
緒方さんがやってくる。僕は自然な笑顔を保つ。死にたいという欲求を隠す。感情をどこまでも平坦にする。なにも感じない。なにも感じない。僕はそう唱え続ける。
緒方さんが一週間の様子を尋ねる。僕は「変わりありません」と答える。緒方さんは顔をほころばせてうなずく。
「あ、そうだ。國枝さん」
「なんですか?」僕は感情をおさえた声でそう言った。
「見てほしいものがあるんです」
「え?」緒方さんはポケットから携帯を取り出し、僕に見せてきた。その画面上には住宅街の上空に橋をかける美しく大きな虹が映っていた。僕はじっとその虹を見つめていた。
「綺麗だね」もうひとりの僕がそう言った。
「ああ、綺麗だ」僕も頷いた。
時が止まったような感覚がしていた。なぜか緒方さんの見せてくれた虹が、僕の心を奪っていた。緒方さんは笑っている。ただの笑顔じゃない。純粋な子どもみたいな笑顔だ。
僕は気がつくと泣いていた。涙が一滴二滴とこぼれ落ちてきた。虹が浮かんでいる。あの大空に、浮かんでいる。死にたかった。誰にも言えなかった。さびしかった。本当は普通に大学に行きたかった。みんなと同じ道を行きたかった。そんな思いが虹に運ばれて、僕の口から出てきた。たぶん僕は、緒方さんが虹を見せてくれたことで、愛を感じたのだ。僕はやっぱり死にたくないって思った。
看護師は、見守る人という意味なのかもしれない。緒方さんはずっとひとりぼっちの僕を見守ってくれていたんだ。僕が死んだら、緒方さんはなんて思うだろう。この純粋で美しい虹はどうなってしまうのだろう。僕は彼にこう告げた。
「僕は死にたくない」
「裏切るのかい?」彼は僕の首をしめた。
「僕は、生きるんだ。虹はただそこにあるだけでいいんだ。僕もそこにいるだけでいいんだ。生きるんだ。生きて、生きて、生きて、そして……虹を見るんだ」
彼は「そうかい」と言って首から手を離すと、そのまま消えていった。それが僕と彼の別れだった。彼は僕のなかで僕となり、混ざり合っていった。
気がつくと、緒方さんは携帯を閉じて、僕にこう囁いてくれた。
「今度は一緒に見れるといいですね」
僕は「そうですね」と呟いた。「でもその前に、聞いてほしい話があるんです」
「え! どんな話ですか?」
「僕のこれからの話です。緒方さん」僕は歩み始める。まずはこの話をしようと思った。
*了*
木曜日の虹


