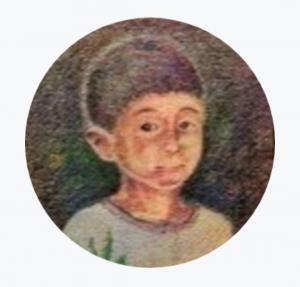ピアニスト・田中希代子の哲学
病は人を選ばず、突然その体に忍び込み、蝕んで行く。完治する期間限定のものであるならば、何とかしてその期間を有意義に、苦痛に堪えて治療に専念しようと努力することもできるが、その後、その病が癒えず共存していく道を取らなければならないと分かった時、果たして人は、その病と冷静に向き合うことができるのだろうか。
絶望の淵に浸っている間はまだいいかもしれないが、そこから一旦這い上がると決めた後、本当の地獄が待っているのかもしれない。
突然の病により、その生き方を変えざるを得なくなることは、不本意な話だが誰の身にも起きることである。しかし、それが専門分野において、己の才能ひとつで世界を魅力した人だったらば、本人のみならず、その人から生きる喜びや希望を見出していた人たちにとっても、大きな衝撃であり痛手である。
36歳という若さで不治の病である膠原病に倒れた悲運のピアニスト、田中希代子は1970年、38歳でそのピアニストとしての、輝かしい半生に、才能の開花途中で惜しくも終止符を打った。
一寸先は闇とはよく言ったものだが、田中希代子のピアニストとしての人生が、こんなにも突然に断ち切られることを分かっていたら、当の希代子も希代子のファンも関係者も、その演奏を後世に保存しようと、早い段階から動いていたかもしれない。そうすれば、私たちは希代子の優れた演奏を、限られた時期のみであるが、その殆どを聴くことができた筈である。
希代子が活躍した1960年代は、ようやく生放送から録音というスタイルが浸透してきた過渡期であり、まだまだ音源や映像をきちんとした形で保存するというところまでには程遠い時代であった。ちょうど高度経済成長期と重なり、東京オリンピックも開催されたことで、消費することにすべてが注がれていたような時代であった。
そんな時代の転換期に、ピアニストとしての道を断たれた希代子が、悲嘆に暮れたまま1970年代を迎えたわけではなかった。何があっても命ある限り人の暮らしは続いていく。希代子の人生もまた、波乱に満ちたものになったが、決して終わったわけではなかった。希代子の肉体は病によって自由を奪われたが、幸か不幸かピアニストにとってもう一つ、大切な聴力までは奪われていなかったのである。
国立音楽大学で教鞭をとる傍ら、自宅で後進のレッスンにも当たった。自ら模範演奏を聴かせることのできない、世界でも稀なピアノ教師となった希代子は、そこで世界に通用するピアニストを育てることで、苦しい人生の中にも生きる糧を見いだす日々となったのかもしれない。
一流のピアニストだった希代子が、まだ海のものとも山のものとも分からない、原石の状態である子供にピアノを教えることは正直、苦痛以外何物でもなかったかもしれない。どうして自分には容易くできることが生徒はできないのかと、時には怒りを爆発させたくなったこともあっただろう。しかし、言い換えれば現在の希代子は、その練習すらできない状態であり、酷な言い方だが、弟子の子供以上に上手く弾くことは二度とできないのである。
だが、希代子が根気強く見守っていれば、才能のある子供なら、時間はかかっても希代子を納得させられるくらい、素晴らしい演奏をする日が来ることは間違いなかった。なぜなら指導に当たっているピアノ教師は紛れもなく、一流ピアニストとして世界を魅了した田中希代子だからである。 聴衆に演奏を聴かせる側だったピアニストから、生徒に演奏を聴かせられるピアノ教師へと、ある意味、生徒に育てられたと言ってもいい、ピアノ教師・田中希代子が誕生した1970年代は幕を閉じた。
迎えた1980年、膠原病の治療薬の副作用により、希代子は脳梗塞を発症し、右半身不随の身となった。自由の利かなくなった体を引きずるように、後進の育成に励み続けるそんなある日、希代子は1989年2月19日、TBSラジオ制作『「夜明けのショパン」~よみがえる天才ピアニスト田中希代子~』に出演する。そこで希代子は、自らの人生で失い、そして再び得た哲学とでも言うのだろうか、そこに思い至った胸中のひとつである「自己表現」について、希代子らしい謙虚な思いを次のように語った。
もし、神様がお前から様々な能力を奪い取ってしまったが、そのうちの一つである皿を洗う能力を返してやろうと言ったら、私は喜んで皿を洗う。
かつて、世界中を魅了し激賞されたピアニスト・田中希代子が、もし、もう一度ピアノを弾くことができたらというものではなく、皿を洗うという誰もができる日常の動作を例えに出したところに、希代子の様々な心の葛藤と、昇華しきれない積年の思いを垣間見たような気がした。
病を得てから20年の月日を経て、ようやく辿り着いた希代子の人生観であり、究極の哲学であった。 人はどうしても自分にないものをねだったり、手のうちにあるものに満足せず、もっと欲しがったりするものだが、本当に何もすることができなくなった時にしか、見えて来ないものがあるのかもしれない。
膠原病にならなかったら、という仮の話をすること程、無意味なことはないが、田中希代子はピアニストであり続けただろうかと問われたら、こればかりは希代子にも、もしかしたら分からないことだったかもしれない。しかし、この膠原病という病を得た後も、ピアノを弾き続けることが可能であったなら、希代子の演奏はどのようなものになっていただろうか。それはきっと、もっと人間臭く、そして、温かみ溢れる懐の深い、喜びも哀しみも超越した、唯一無二の演奏になっていたのではないだろうか。考えるだけ虚しい、ピアニストとしては辿り着くことのできなかった、希代子の未開の境地であった。
そんな人生の最後に、希代子が見出だした究極の自己表現があった。それは、膠原病治療の役に立てるよう、自らの体を「献体」することであった。 ピアニストとしてではなく、田中希代子という人として辿り着いた、それは尊い境地であった。
ピアニスト・田中希代子の哲学
2025年3月9日 書き下ろし
2025年3月12日「note」掲載