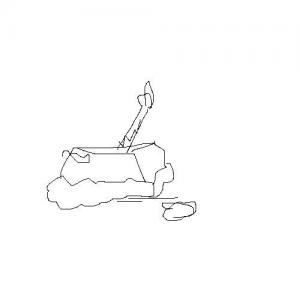なにもいわないでいいよ
静かな朝だった。
カーテンの隙間から溢れんばかりに漏れ出る控えめだけど眩しい光、ベッドの傍らに脱ぎ捨てられた自分の足の形を記憶したままのスリッパ、半分だけ微かに膨らんだ、消失の惑星。
全部いつも通りの朝だった。だけど今日で終わるとわかっていた。
ひなちゃんのお家で消しゴムを盗ってしまった日から多分ずっと間違ってきたんだろう。
お腹が減っていた。
飲みかけの紙パックのりんごジュースと少ししけたバゲットを頬張る。ペットボトルが捨てられなくなって、洋服が畳めなくなって、それらが部屋に溜まっていくのを私は受け入れていた。ただ、受け入れるしかなかった。ガムシロップが溢れて、コーヒーを苦くしてしまってから糸が切れたのか。そもそも糸すらなかったのか。数ヶ月閉まったままのカーテン。の真横でうずくまって波打ち際の想像ばかりしている。波の音を脳内再生して、ひなちゃんとした約束を思い出す。けど、やっぱり思い出せなくて、ふわふわなパンケーキのバターの匂いと、ぼんやりとした指切りした日のひなちゃんみたいなひかりの輪郭だけをなぞってみた。ぐちゃぐちゃに散乱したカップ麺と服と郵便物の間(或いは下)に挟まっていた、ケーキを運んできたいつしかのリボンを引っ張り出した。昔はリボンひとつであやとりも、髪結いも、儀式も、祈りも、誓いもできたのに、今は蜘蛛の糸ですらなくなった。これじゃ今はなんにもできない。透明な肋骨に手を透かしてみる、透けないけど、透けるものだとしか思えなかったの、くらげを見てから。多分憧れていたんだと思う。揺蕩う姿とすてきなフリル、毒を持つ自衛の意識すらも。喫茶店に入ってみて、でも、お金がないから、お金がないという事実だけがわたしを生かしていたから、いちばん安い温かいミルクを頼んだ。机の上に鎮座する、恒常的に、人工的に、無機質に光っていた、ブルースクリーン。面を滑っても指で弾いても熱をもたなくなった。私みたいだと思った。からん、ころん、と転がるような心臓音のパッチワークのくまのぬいぐるみ。いつかの魔法だね。爪先まで魔法をかけて、ふりふりのレースで踊るように街を歩きたかったの。…
心臓の音がよく聞こえる夜だった。
全開になったカーテンと窓、からちいさな三日月が覗いていたように思う。
わたしは、郵便物も手紙もひなちゃんも全部すてた。リボンもすてた。
それでいいとおもった、おもえるようになりたかったから。
なにもいわないでいいよ