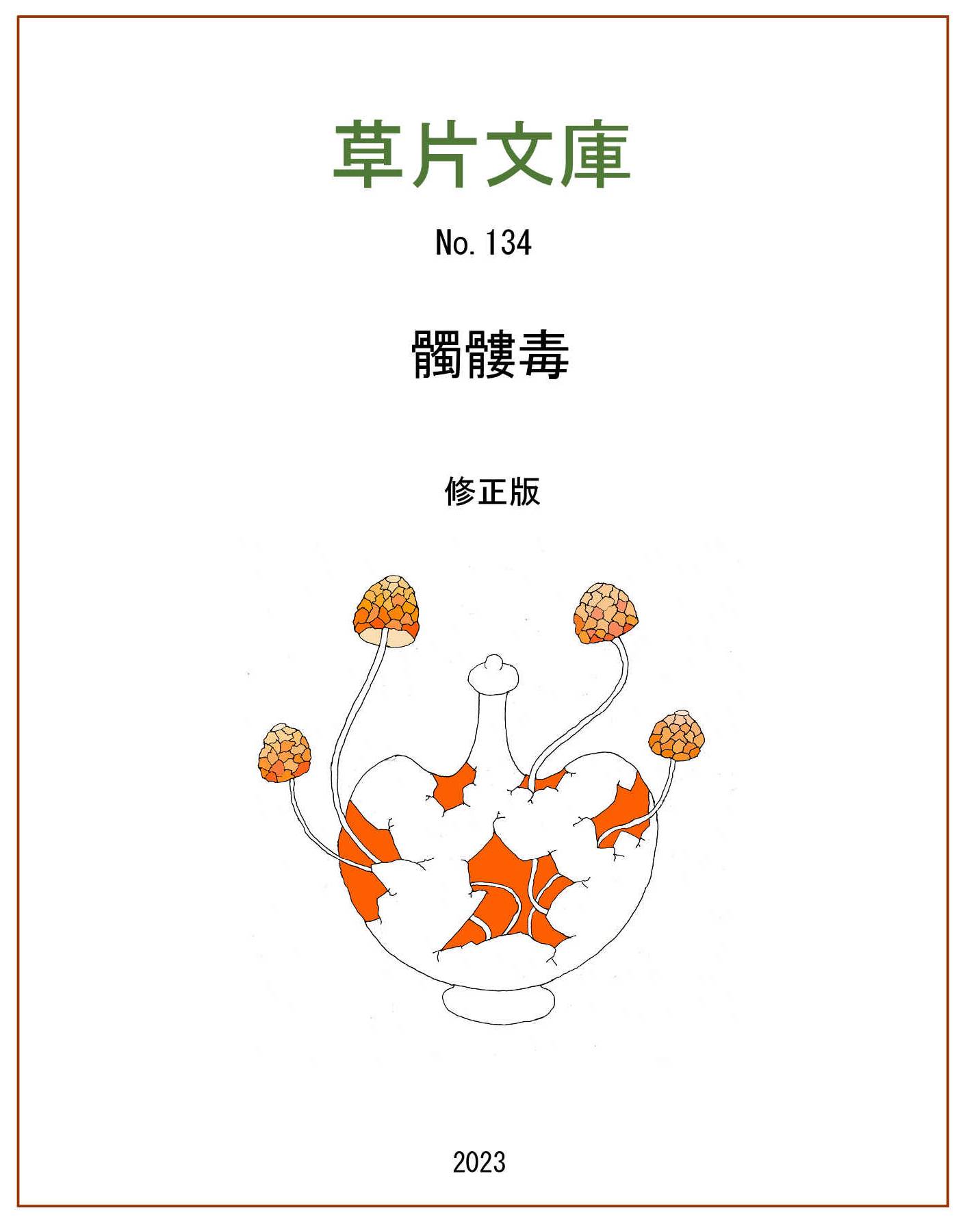
髑髏毒
探偵小説です
警視庁刑事課捜査支援分析センター分室、第八研究室の古書(ふるほん)羊貴は古文書解読のベテランである。第八研究室には奇妙な事件のデータがそろえてあるばかりではなく、読本、昔の小説であるが、など、おかしな事件の記述のあるものが、電子化されてしまってある。国会図書館で電子化された古文書から古本が怪奇な事件を切り取ってファイルしているのだ。事実ではないにしろ、似たような事件が下敷きになっていることもあり、参考になることがある。
古本はそういう作業をいとわない。漢文ばかりではなく、古い文字も読むことができる。古書は「古文書をほじくる」と題された本を最近出版した。古い書物やかきつけに、奇妙なできごとをみつけることができる。その楽しさを書き綴ったものだ。帯には庚申塚探偵事務所所長の奥さんで、作家の詐貸(さがし)野霧の推薦文がのっている。古書という苗字の彼の趣味は、そのまま古本屋めぐりである。
その日は珍しく仕事を早く終え、神田の行きつけの古書店、巌生堂によった。
この店は古書が学生時代にとある古文書を探しにきた店で、若い人がこんな本を探すのはめずらしいね、と店のおやじに気に入られ、通うようになった。話してみると同じ大学の同じ学部を卒業したことがわかり、それ以来、古文書のことはこの店主に相談している。
「おお、古書さん、久ぶりだね、変な本が手に入ったよ」
間口が狭く、奥行きの長い店の奥のデスクに、主人はいつも腰掛けて、仕入れた本の値踏みなどをしている。
差し出された本は和綴じの本で「江戸変態事象」というタイトルの本だ。
古書は手に取ると「確かに古いものだけど、あまり文を書いたことのない人物が書き残したものですね」と店主に言った。
「そうなんだよ、どうも、江戸詰めになった旗本の家来の一人が、物好きに江戸での出来事を書き留めたものらしい、鍋島藩の警護の役割の侍だったようだ。古書さんのような立場かな」
店の主人は、古書が警視庁の刑事課で、捜査支援の立場にいることを知っている。
「面白そうですね」
「もってっていいよ」
「いくらです」
「いいよ、ゴミ収集会社の奴が、どこかの家の前に出されていた雑誌類の中から見つけてうちにもってきたんだ、ときどき面白い本が手にはいることもあるが、こいつはよくわからんから千円わたしてやった」
「二千円で」
「そんな気を使わなくていいよ」
「それじゃ、いただいときます」
古書は店内を見て回ると、一冊の本を主人に「これもらいます」
と、差し出した。
「これね、確かに資料としていい本だけど、あまり売れないんだ」
河出書房の「書物の宇宙誌ー澁澤龍彦蔵書目録」である。サドの翻訳者である澁澤龍彦は古今東西の珍しい本から、不思議な出来事などをたくさん紹介している。したがって、澁澤の蔵書から西洋の珍書奇書のたぐいのことを知ることができる。
「前々からほしかったけど、ここまで値下がりしているんで驚きました」
「今、古書値は最低だね、だから逆にお買い得さ、澁澤の本は1980年代から90年代にはすごい値が付いていたもんね、その当時から比べたら半値だね、それでも澁澤の本はいい値がついているけどね、戦後の文豪の初版本だって、ずいぶん安くなってる」
「そうですね」
「古書さん、澁澤の本も買ってるの、澁澤は西洋物じゃないの」
「小説本もよんだけど、基本的には、面白いことを集めてある本が中心かな、そう言う意味では種村季弘は博学で本のことも幅が広いし、面白い本が多い」
「そうだね、古書さんは北原北明や宮武外骨の初版を集めてたものね、もうだいぶそろったんじゃない」
「ここでずいぶんいただいた、酒井潔なんかも」
「仕事とは関係ないんだろ」
「いや、結構昔のおかしな出来事は、今の事件のヒントとなることも多いんです、人間の本質はかわってないから」
「たしかにね」
古書は二冊の本をザックに入れて店をあとにした。
古書は自分のマンションに帰ると、簡単な夕食をすませ、巌生堂がくれた江戸変態事象を開いた。そんなに厚くない和綴じの本である。
あまり上手とはいえない字がならんでいる。目次にはタイトルと一緒に、場所と日時がかいてある。
本自体には安政一年とあるから、1854年まで、およそ三年間見聞きしたことが書いてあるようだ。
最初の記述は円裸草地と題された、寺町にある天撹寺墓場の近くの草地にいくつかみられた、全く草が生えていない場所の話である。その草地はかなりの坪数になる荒れ地だった。ずいぶん昔、そのときから250年ほど前になるだろう、江戸が定まる前になるが、二つの豪族の争いがあった場所だそうだ。多くの戦死者たちが、鎧甲は持ち去られ、裸同然で転がっていたところという。時間がたち遺体も土にうずもれ、飛び出ていた骨なども見えなくなった。この草の茂った荒地は、この寺として、いずれ墓地にしようと考えていたようである。寺の者たちは、その草地の中に、草が生えておらず、土が盛られているようになっている場所がいくつかあることに気付いていたとある。
これを書き留めた江戸詰めの鍋島藩警護係の武士は、寺男の話を聞いて、見に行ったとある。生き物の仕業なら食われた草などが残っているはずだが、まったくの裸地で、何らかの理由で草が生えることができないのだろう。草木のからだに悪いものが埋まっているのかもしれない。そう思った武士が寺男に掘ってみるといいと進言した。言われるとおりに、寺のものが丸くはげた裸地を掘り、中から頭蓋骨がでてきたと知らせてきた。戦死した者の骨のようで、頭蓋骨に矢が当たったとおぼしき穴があいていた。
他の草の生えないところからも頭蓋骨がでてきた。しかし、草の生えているところからも、足の骨や肋骨などが埋まっていたことから、骨と草の生えないこととは関係ないと結論づけている。
江戸と言うところはほこりっぽいところで好きではない、などと感想が書かれていたりする。だがそれだけ読むと、頭蓋骨の埋まっていたところだけが裸地になっているこには気づいていないようだ。頭蓋骨が草の生育に毒となったのだろうか。
寺に関わる話はいくつか書いてあった。天撹寺と同様に大きな寺の一つだが、勝生寺の墓での出来事である。
新しい墓の脇に掘った跡があり、そのわきで一頭の犬が死んでいた。寺ではその犬も一緒にその墓に埋めてやったということである。
それには理由があった。墓にねむる大店の旦那がかわいがっていた犬で、旦那が病死したその日に姿をくらまし、家族がさがしていたということだった。家族は犬が主人をしたって、遺体を掘り出そうとしたのだろうと哀れみ、是非、主人と一緒に葬ってほしいと申し出たそうだ。寺でもそれに応えたわけである。
これを書いた侍は寺の住職に会いに行ったようだ。犬がどうして死んだか知りたかったのだ。犬が自死するなど聴いたことがないから、これは不思議だと思ったという。
寺では発見した墓守にも話を聞いている。
「朝早く、墓を見回りに言ったときに、若い赤犬が墓のわきで死んでおりやした」
「どのような姿でしたかな」
「へえ、舌をだらりと口の脇から垂らし、泡をふいておりやした」
毒でも食べたようだと侍はその様子を聞いて思った。しかし、どこで毒などを口にしたのだろう。この段階で、侍は寺の誰かが墓には入り込んだ犬に毒餌でも与えたのではないかと疑った。
「犬はいつからいたのですかな」
「いえ、いきなり死体がありました」
「とすると、死んだ犬のことを知っているだれかが、犬の死体を墓の脇に運んでやったということも考えられるな」
「そうかもしれません、夜中の見回りはしないですし」
「ご主人の墓を掘り返して、一緒に埋めてやったわけだな」
「いえ、墓はほじくられ、埋めた遺体が棺桶から引っ張り出され、頭がかじられておりました」
これを聴いた武士はあぜんとした。穴があったとしか聞いていなかったのだが、まさか死体をひきずり出していたとは思わなかった。その上、犬が主人の遺体の頭をかじったとは。そこまで主人を慕っていたのか。それとも単に腹がへっていたのか。
寺男は申しなさそうに、
「ご家族さんには、そこまで言うと、気味悪がるだろうとおもいやして、和尚様とも相談し、ただ墓の脇に穴があったとしか申しませんでした」
「それで、だいぶ食われたのかな」
「へえ、頭蓋骨を半分ほどかじり、脳髄がとび出ていましたが、そこまではかじっていませんでした、気味が悪い景色で、へどがでそうでした」
そういったことが書かれていたが、大事に育てられていた犬が死んだ理由はなかった。頭の骨をかじって死んでしまったのはどうしてか。古書は頭の骨がこの犬を殺したのだろうかと想像した。
こんな話ものっていた。
その昔は河原に死体の一つもよくころがっていたものだというが、江戸時代になると、江戸のはずれはともかく、町中を流れる川に死体があれば、八丁堀のお出ましという事件となる。事件でなくとも、ときどき昔埋もれていた死体の骨が、大風のあとにあふれた水により流れ出し、日照りで乾いて転がっていたりすることはよくあったことだという。
落語にそんな頭蓋骨を川原で見つけた釣り人が、供養にとつるしていた五合徳利から、酒を少しばかり振りかけると、その夜、侍や美女の幽霊が現れるという話がある。野ざらし、というタイトルだった。
江戸変態事象に記されていたのは、新宿の宿の主人だった老人の話である。宿に泊まった若い侍が、物好きにも近くの小川のふちで拾ったという、乾いて半分に割れた頭蓋骨を拾ってきた。侍は女中に部屋に酒を熱くしてもってくるように言いつけたのだが、女中が気味悪がって宿の主人にうったえた。主人はしかたなく温めた酒を自ら部屋まで運んだ。障子をあけると、若侍は頭蓋骨を手に布で磨いていた。
「すまんな、こんなものを拾ったので、供養のため、この骨で酒を一杯飲んでやろうと思う」
それをきいて、主人は安堵したという。変なお侍だと面倒なことになる。情けのある人のようだ。
「はあ、それは功徳になりますです、酒はここにおきます、つまみはなにか」
「そうよな、なにがある」
「すぐご用意できるものは、土筆の煮たものなどしかありませんが」
「おお、それがよい」
主人は女中に侍のことを話した。心配いらぬから、土筆の煮たものなど、ちょっとつまみを取りそろえて、これは宿から骨の主様への供養のもの、差し上げますので、どうぞお召し上がりください、と言うように言った。
部屋に行った女中の話では、侍は髑髏の中に酒をいれ、なにやら唱えながら飲んでいたという。
夕食時になると、若侍は、飯の前に何本か熱燗をはこばせた。
酒に強いお侍だと思いながら女中は酒を運んだ。
ところが、その侍は次の朝、布団の中で動かなくなっていた。脇には頭蓋骨がころがっていたという。
すぐに番屋に連絡がいき、医師の見立てでは、心の臓が急に止まる病によるものとわかった。
用事をいいつかって江戸に出てきた侍で、江戸のみやげをたくさんたずさえていたという。棺に入れられ信州松本まで、早馬で運ばれていった。
宿の主人は侍が頭蓋骨で酒を飲んだことが気になった。侍の拾ってきた頭蓋骨を捜したが、部屋からなくなっていた。あとで女中にきくと、河原にもどして参りましたということだった。
これを書いた鍋島藩の侍は、頭蓋骨にしみこんだ毒物が酒に溶け、若侍の心の臓を止めたのではないかと自分なりの解釈を書き添えていた。
この古文書をよんでいて、古書は古代ミステリーの話が中心の雑誌に載っていた最近の記事を思い出した。円形脱草と名づけられた奇妙なサークルである。草地の一角に丸く草が生えず、土が露出しているところである。
古書は次の日、警視庁に出勤してから、コンピューターを開き、古代ミステリーの雑誌にのった円形脱草のデータを探り出した。円形脱草とはつまらない名を付けたものだ。円形脱毛から命名したのだろう。
円形脱草は甲斐の山奥で発見されたようだ。誰が書いたのか文末をみると岩井祝とある。古文書にあった円形裸地には死体が埋もれていた。円形脱草の下にも髑髏や骨が埋もれているかもしれないと、古本は想像した。
比較的最近、奄美の海底の砂に、きれいな放射状のもようのあるサークル構造がみつかった。貝殻なども規則正しく集められており、海底のミステリーサークルとして、テレビで紹介された。かなり大きなものである。潮の流れが作った模様だとか、宇宙人の仕業だというものもあったが、生物学者が、犯人は新種の小型のフグであることを発見した。配偶者をよびよせるため雄が砂の模様をつくりだす。雌はその中心で産卵するという。
雑誌の文章の続きは、そのフグの話をヒントにしたようなことが書かれていた。草地に見られる裸地サークルには模様らしきものはなく、ほとんどまん丸である。筆者はこのサークルも昆虫か、は虫類などの生物が作ったのではないかと、カメラを設置して二十四時間観察を行っていたが、犯人はあらわれなかったとある。
当然、その裸地もほじくり返してみているはずだが、なにもでてこなかったのか、進展がないようで、それ以降、その雑誌には、甲斐の山奥の円形脱草に関しての記事はのっていない。
羊貴はそれからたびたび、第八研究室の電子事件簿に頭蓋骨と毒というキーワードで変わった事件がないか、検索をかけて調べていた。だが頭蓋骨と毒と両方のキーワードに一致するものはなかった。
頭蓋骨の検索では、打撲、陥没、首切りと言った事件が目白押しだ。そのようななかで、事件と言うより報告の一つが、彼の目に留まった。
一週間ほど前、脳神経外科医が頭蓋骨を開ける手術中に倒れたという、薬新聞の記事である。東京のある病院のできごとである。医者の働きすぎ、と題されたコラム欄に書かれていた。このような小さなことは、大きな新聞に載ったり、テレビで報道されるものではない。警視庁の第八研究室にはこういうものも集められている。
古書は頭蓋骨を開いているときにというところが気になった。過労ではなく、何かが起きたのではないかと、胸騒ぎがしたのである。これが古書羊貴の勘というものかもしれない。
もやもやとした古書は同僚の高胎蓉子にきいた。高胎は文学部卒業後、看護大学に入り直して、助産婦の資格までもっている。
「脳梗塞になった人にはどんな手術をするの」
「血を抜くだけなら頭に穴をあけて吸い出すのだけど、奥の方にできている動脈瘤が破裂したら、頭を開いて、血管の破れを止めなければならないわね」
「そのときは頭をどうするの」
「場合によれば骨の一部を大きく切り取って、開けて手術するわね」
「終わったあとはどうするの」
「とっておいた骨で蓋をするのよ」
「大変な手術でしょう」
「そりゃあ大変よ、急がなければいけないし、全身麻酔だから、大手術よ」
「みてくれる、この場合はどうだろう」
PC上の記載を高胎にみてもらった。
「大変な手術でしょうね、この病院ずいぶん大きな病院で、脳神経外科は有名よ、なんか気になるの、古書さん鼻がいいから、事件の匂いがするわけね、気になるなら行ってみたらいいじゃない」
「事件というわけじゃないから、いきなり話を聞きたいと連絡すると、向こうが驚いちゃう、病院の様子を知ってからかな」
「そうね、その病院なら看護師さん紹介してもらえるかもしれないから、知り合いにきいてみるわよ」
高胎は卒業した看護学校に電話を入れた。すぐに様子が分かったようで、古書に、その病院の脳神経外科で働いている看護師の名前を言った。
「もし話をするのなら、私がアポとってあげる」
まだ頭の中が整理されていない古書は、ちょっと躊躇したがうなずいた。
「おねがいします、僕の方はいつでもかまわないです」
第八研究室では、室長の薩摩警視正に一言言えばいつでも外出できる。
高胎が電話で話をしながら、「明日、3時でひけるそうだけど、どう」
「僕はいいですよ、病院の方に出向きます」
「1時に病院の受付よ」
高胎が受話器をおいた。
「四井病院の飛鳥碧さんという看護師さん、年は三十半ば、もうベテランにはいるかしら、私と同じ大学の卒業生」
ずいぶん急なことなのだが、こうもトントンと、ことが運ぶということは、なにかあるかもしれない。古書は本気で調べてみる気になった。
四井病院は赤羽駅から歩けるところにある。古書はその日、少し早く行って、外来の様子を見て回った。十階建てで五階まで各科の外来がある。どのフロアーもかなりの患者がいて、薬の待合室にいたっては、かなりの広さがあるのにもかかわらず、椅子はほとんどうまっていた。働いている人たちは誰もが患者に気配りしながら歩いている様子がよくわかる。人気のある病院はこういった感じだ。
時間になり、受付に現れたのは、紺色の地味なスーツに身を包んだ中肉中背、物腰の柔らかな女性だった。ほとんど化粧のあとがみえない、色の白い顔に笑みを浮かべている。看護婦さんはいつも柔らかな顔をしているが、きっと長い間に身につくものなのだろう。看護婦や医者の顔や仕草はそれだけで薬になる。
「飛鳥さんですか、お疲れのところすみません、古書です、ちょっとお話をきかせてください」
彼は警察手帳ではなく、自分の名刺をだした。古文書研究家となっている。
「あ、警察の方ではないのですか」
「そうですけど、古文書からみつけたことを調べていたら、ここの病院の脳神経外科の先生が頭の手術中に倒れたことが検索されたので、脳の手術のことを教えていただこうかと思ってきました、事件とかそういったことではありません」
「そうでしたか、どうして警察の人から電話がかかってきたのかちょっと心配しました、ただ、同じ看護大学を卒業した方からの電話でしたので、お受けしましたが」
「地下に食堂がありますね、そこで聞かせていただきますか」
古書は彼女と地下の食堂に行った。
「驚かれたのはわかります、たまたま、薬の新聞で頭の手術中に倒れたお医者さんのことを読んだものですから、頭蓋骨と毒のことを調べています」
古書の頭の中でも、頭蓋骨に毒という疑問がはっきりと抽出されてきていた。
「頭蓋骨と毒ってどういうことでしょう」
「あ、気にしないでください、戦国時代末の文献にそのようなことがあっただけです、事実だとかそういうことではありません」
「そうですか、倒れた飯山先生は脳手術で有名な先生です、難しい手術もこなされていて、日本でも五本指にはいると思います、おそらくお疲れになっていたのではないかと思っています、今も大活躍されています」
倒れたのは飯山と言う医師のようだ。
「飛鳥さんもその場にいらしたのですか」
「はい、私も補助でおりました」
「そのときの手術は何時間くらいかかったのですか」
「麻酔の準備やらを含め5時間くらいでしたか、飯山先生は、他の先生と違って、準備の段階から手術室にはいられます」
「先生が倒れたのは、いつごろのことでしょう」
「開頭をして、すぐですから、比較的はやいじきでした、病気一つしたことのない丈夫な飯山先生が急に床にばったり倒れたので驚きました」
「手術はその後どうなったのですか」
「補助の先生が手術を進めました」
「患者さんは元気になったのですか」
「はい手術は問題なくおわり、もう普通に働いていらっしゃると思います」
「飯山先生はどうしましたか」
「他の部屋に移されて、一時間後に気がつかれたと聞いています、数日入院されました」
「原因はなんだったのでしょうか」
「わからないんです、からだや脳の検査では異常はなかったようです」
これは奇妙だ。
「もう少し手術のことを教えてください」
飛鳥看護師は患者の頭を坊主にする事から、頭の皮膚の切開、頭蓋骨の切り開き、拡大鏡をもちいての患部の露呈、出血の取りのぞきと、原因の血管への処理を順序だってはなしてくれた。骨を切り開いたところで倒れたということだ。かなり早いときだ。
「切り出した骨はどうするのですか」
「手術後、その骨で蓋をするので、とっておきます」
「先生が倒れたのは骨を取り出す前ですか、あとですか」
「そういえば、取り出した骨をトレイにおいたときでした」
「倒れたとき何かおっしゃいましたか」
「おかしい、変わってくれ、といって床にどさっと」
「患者さんはなんとおっしゃる方ですか」
「あの、患者さんに関しては外部の方に、話してはいけないことになっていますが」
古書はうかつな質問だったと思った。警察の取調べにしても、簡単には当事者の名前は明かさない。
「そうでしたね、すみません、飯山先生にはお会いすることができるでしょうか」
「いい先生で、気さくな方です、だけど、私が取り次ぐわけにはいきません、警察の方から直接依頼されればいいのではないでしょうか」
飛鳥碧はどこまでもしっかりした看護師である。古書は自分の著書を彼女にさしだし、お礼を言って病院をあとにした。
古書は警視庁に戻ると、室長と相談した。
室長の薩摩冬児は、「羊貴君はほじくり出すのが得意だからな、今度はなにがほじくりだされるんだい」と笑いながら、飯山医師と連絡をとってくれた。
「頭蓋骨をほじくります」
古書はまじめに答えた。
飯山医師は医者というより、ヨットを操るスポーツマンといった雰囲気だ。病院の接客室に大またで入ってきた医師は、ソファから立ち上がった古書の前で、直立不動になり、頭を下げた。
「飯山です」
古書もあわててあいさつをした。
「理事長から、警視庁から刑事さんがみえるとうかがって、スピード違反のことかと思ったら、脳の手術のことだそうで、驚きました」
車も相当好きなようだ。古書はこの人には隠さずにすべて話したほうがいいと判断し、古文書の件から、頭骨について調べていることを話した。
「としますと、草が生えなかったり、犬が忌んだりしたのは、骨に毒があったとお考えですか」
飯山の推理力もたいしたものだ。
「素人の勘ですが、頭の骨に毒がはいるなどということがあるでしょうか」
「毒は体じゅう血液の行くところには必ず行きます。ですから骨にも入るわけです。原理的には骨に蓄積されるものもある可能性はあります」
「そう言った毒は、他人に危害をくわえますか」
「刑事さんは僕が手術中に倒れたのは、骨から何か毒がでたと考えたわけですか、それはなかなか考えにくいですね、最もまだ原因はわかっていませんが」
彼は笑った。
「僕は確かに患者さんの頭骨を扱いましたが、かじった訳じゃない、たとえば、サリンのような毒は、気体ですが、そういったものが骨に蓄積されることは考えにくいですね」
「確かにそうですね」
古書もそこまでは考えていなかったので、逆にいいヒントをもらった気がしていた。
「実は黒子に毒がたまっていたり、息に毒が混じっていたりなんていうケースがありました、それで、そんな考えに至ったのです」
「そんなことがあるのですか、特殊なケースでしょうね」
「ええ、それで、もしかすると、その患者さんは特殊なケースかと思ったわけです、飛鳥看護師さんに患者さんの名前などを聞いたのですが、守秘義務からお答えできないので、先生にきいてみてほしいといわれました」
「飛鳥さんはしっかりした人でたよりになります、ご存知でしょうけど、守秘義務は医者にもあるんですが、事件の調査でないとすると、お教えするのは難しいと思います。その患者さんは、巣鴨で昔ながらの八百屋さんをしている人で、とても明るい人です、八百長といって、産地直送の山菜や天然の茸などもあつかっています、結構おなじみさんが買いにいくみたいですよ」
飯山先生は守秘義務を守りながらヒントをくれた。名前は言っていない。
「ありがとうございました、お時間とらせてしまってすみませんでした」
古書が礼を言って、席をたとうとすると、飯山先生が、
「刑事さん、肩や首がこっているようにみえます、コンピューターのやりすぎや、本の読みすぎに注意されてください、脳が疲れてめまいなどを起こしますよ、脳は体の中の働きを整えます、それは脳自身を健康に生かしていくためです。目眩などは純粋に耳の奥の平衡感覚装置の故障の場合もありますが、脳の疲れのシグナルにもなります」
「はい、注意します、ありがとうございます」
逆に診察されてしまった。飯山先生は根っからの医者である。
自分の著書をわたして部屋からでた。
古書はその週の土曜日に巣鴨に行った。ネットに八百長がのっていたので、店への道はだいたいわかる。主人の名前は三井真三という。巣鴨には庚申塚探偵事務所があり、探偵たちと飲みに行く酒処もあるのでなじみがある。
八百長はすぐみつかった。昔ながらの構えの店である。木箱の上に並べられているキュウリやほうれん草、トマトなどはどれも形がいびつだが、採りたての色だ。驚いたことに一本、一個売りだ。
「ひん曲がってるが、うまいよ、新鮮だしな」
古書が野菜類に見とれていると、奥にいた親父さんが出てきて声をかけてきた。背が高くちょっとヨーロッパ系の顔で、八百屋のおじさんの容貌ではない。
きっとこの男が手術を受けた人だろう。
「トマト二つと、キュウリ一本、ほうれん草一束ください」
「あいよ」
容貌はともかく、八百屋のおやじの声をはりあげ、八百屋のおやじの動きで、ぽいぽいと紙の袋に買ったものを放り込むと、二百五十円と言って、古書の顔をみた。
「もしかしたら、そこの大学の先生かね」
近くに大学がある。
古書は首を横に振って
「いえ、ネットで見てきてみたんです、天然の茸や山菜を扱っていると書いてあったので」
「ああ、ネットは会社員の息子がつくってくれてね、俺にゃわからんが、確かにお客さんのような人が増えたね」
「きのこがいいって言うコメントがのってました」
「今は時期じゃないが、秋には、近くのものがたくさんでるよ」
「どこのきのこなんですか」
「八ヶ岳の麓の小原村っちゅうところでね、山梨だ。おやじがそこの生まれ、その村の人ったら、みんな親戚さ、みんな茸採りがうまくてね、朝とったのをその日のうちに届けてくれて、夕方には店にならぶんさ」
お、小原村だ。円形脱草とつながったじゃないか。
「きのこだけですか」
「山菜なんどもあるけどね、やっぱり春と秋かな、信州のリンゴもならべるよ」
「そのころきてみます」
今は春の終わりである。
「ありがとね」
主人は店の奥に入っていった。
家に帰りネットで調べると、甲斐の山間の村のようだ。山梨県の人口をしらべると、小原村は五十八人である。落人部落だったのかもしれない。村長は三井喜三郎とある。
この件はやはり円形脱草となにか関わりがありそうである。
古代ミステリー雑誌の円形脱草の筆者に会うべきだろう。
古書は古代ミステリー雑誌の編集部に電話を入れた。円形脱草を書いた人と話をするつもりだ。
警察のものだが、興味を持ったので、筆者に会いたい旨をはっきり言った。
編集長の話では、その話題を執筆した人は、岩井祝(しゅく)という素人の民俗学好きで、奇妙なできごとなどを追いかけ、雑誌に投稿するのが趣味だという。円形脱草の正体について第二報を書いてもらうことになっているそうだ。
「いや、なかなか原稿がこないので、目白の自宅に電話を入れたのですけどね、誰もでなくて、携帯に電話してもでません、彼は小原村に円形脱草の調査に行っていると思いますが、調査が長引いているのならそれなりに電話をくれているはずですけど」
編集長も気にしていたようだ。
古書は直接、その雑誌社に出向いた。
警察手帳を見せ、話を直接聞いた。
「私のほうで、目白警察から警察官をいかせます」
そう言って、岩井祝の住所をきいた。
古書は目白の警察に岩井のマンションにいってもらうように連絡した。
目白の警察からはすぐに返事が来た。
「岩井祝、本名鈴木次郎は一人暮らしで、新聞が1週間もたまっています、新聞をとめなかったというのは長く家をあける予定ではなかったのだと思います、ただ、事件性はこれだけでは感じられません」
「隣近所には聞き込んだのですか」
「はい、隣の奥さんがいうには、鈴木はよく出かける人で、旅先のみやげをよくもらうそうです」
「そうですか、ありがとうございました、ご苦労様です」
古書はやはり小原村に行く必要があると思った。
次の日、そのことを室長に話すと、
「とうとう事件をほじくりだしたのか」と言われた。
「いえ、まだ事件かどうかわかりませんけど」
「中三日くらいかな、行っといで」
室長の許可をもらった古書はすぐに小原村に向かう準備をととのえた。
小原村は主要駅からバスで一時間かかるところである。バスは一日に八便しかない不便なところだ。村役場にあらかじめ連絡をいれておいた古書は、自分の車ででかけることにした。不得手な運転のくせに、車だけは自分の気に入った外車をもっている。1960年代の車、タウナス17MP3だ。フォードだがドイツフォードでヨーロッパスタイル、そのなかでも丸いフォルムでやわらかみがある。前から見るとカニのようだ。古書には大きすぎる車だが、なかなか手放すことができず、車検を通すために大変なお金を使っている。そのうち日産のフィガロに買い換えようと考えてもいる。それもとっくの昔に終売でヴィンテージ車になってしまった。
タウナスは1500cc弱で時速はそんなにでない。今の感覚だと、のたのた走っているかんじだ。そのあたりは古書的でもある。
其の日、東京からかなりの時間をかけて小原村に到着した。役場につくと、もう八十になろうとしている村長、三井喜三郎が出迎えてくれた。背が高く腰も曲がっておらず、農村のおじいさんの感じがしない。
「警視庁の方がこんな遠いところになんのご用でしょうかな」
村長の三井はしゃんとした声で古書を役場の会議室に案内した。鈴木次郎のことは伝えていない。
「鈴木次郎というミステリーハンターのようなことをしている人はごぞんじですか」
「岩井さんですな、岩井さんなら何度かきて、草の生えていないところを見つけて、円形脱草と名づけて、雑誌にこの村のことを書いてくれました、村のためにもなると思って協力しましたよ、いい人ですよ、鈴木さんなにかしたんですか」
「鈴木さんが家に帰っていないので、雑誌社の人が心配して、相談されたのです」
「ほうそうですか、わしはしばらく会ってないが、ちょっとまってください、さよちゃあーん、最近、鈴木さんきたあー」
奥に声をかけた。
「一週間ほど前にきましたよ、それから会ってないでーす」
役場の事務をすべてやってくれている若い女性が返事をした。あとで聞いたところによると、市役所の職員で、人手のない村役場に出向してきてくれている人だそうで、毎日バスでかよってきているということだった。
「どこにいったのかな」
「新しい禿さがすって、言ってました」
「鈴木さんは車で来ているのですか」
「そうですな、いつも小型の四輪駆動車を運転してました」
「村からはもうでていったのでしょうか」
奥から出てきた事務の女の子が、
「どうでしょう、帰るときはいつもいいにくるのですけど、みえてません」
「そうですか、とすると、どこかでまだ調査しているのですね」
「だけど一週間は長いね、鈴木さんいつもは町のホテルに泊まって、かよってましたな、さよちゃん、ホテルに電話してみて」
さよちゃんはすぐに電話をかけた。
「鈴木さん三日の予約で泊まったのだけど、最初の日に泊まったきりで、戻らなかったと言っています、あのホテル先払いなので、気にしていなかったようです、荷物は何も残っていないそうです」
さよちゃんの説明をきくと、鈴木はまだ山のなかにいる可能性がある。明日から捜索しよう。今日は三井村長に村の様子をきくことにした。
三井村長は「鈴木さん、何か見つけて夢中になっとるんじゃないでしょうかな」と心配した様子はない。
「円形脱草のことを詳しく知りたいので、村の歴史から教えていただけますか」
古書は村長に著書をわたした。三井村長は本をひらいて、「ホー、刑事さんなのに古文書の専門家なのですな」と出迎えてくれたときとは違う表情になった
「この村の祖先はとある大名のおかかえ薬師だったんですわ」
「落人の部落と推測してきたのですが、違いましたか」
「落人といってもいいでしょうな、というのも大名が戦に負けましてな、大名の薬師だった男が、生まれ故郷のここにもどってきたんですわ」
「ということは、この村の方は昔からここで薬をつくっていたのですか」
「そうですな、ここの村民たちは薬草、茸のことをよく知っておって、薬をつくってましたんで」
「それは毒薬ですね」
「そうです、さすが刑事さん、お見通しですな、そんじょそこらのものと違って、即効性の強いもので、その大名は裏の者にそれを使わせ、敵を弱めておったんですわ」
「忍者ですか、九の一も」
「男の忍者も女の忍者もいたそうですな、そいつ等もここの村出身が多かったとききます」
「実は江戸時代の人が書いたものにも、江戸のとあるところの草地にまるく草の生えないところがあって、それは円裸草地と呼ばれていることが書かれていました」
「ほう、似たものが江戸にあったんですか、この村の祖先は、草の生えないところを、恵塚と呼んでましたな。そんなにあったわけではないようで、今はもうほとんどなくなりました、みんなつかっちまった」
使ってしまうということはどういうことだろうか。
「鈴木さんは、恵塚とせずに、どうして円形脱草などと書いたのでしょうか」
「この村でも、恵塚を知っている者はほとんどおらんです、昔のことですからな、だが、ほんのたまですがな、今でも草地が丸く禿げているところがみつかることは村人たちも知っています、それで、ミステリーサークルのようなものを探しに村に来た鈴木さんに、案内した村のもんが、草地がまるく禿てると言ったことから、鈴木さんが円形脱毛を連想して、円形脱草と洒落たつもりで、雑誌に書いたのだと思いますな」
古書はあたまにひっかかったことを尋ねた。
「使ったというのは、そこに何かあったわけですか」
「祖先の頭蓋骨が埋まってます、怖いものでしてな、毒になる骨ですわ」
「それがこの村で作っていた毒のもとですか」
「薬草づくりもしておったけどそれは薬として売ってましてな、祖先の頭蓋骨はとても毒が強くて、大名が使う毒として売ってたようです、よく売れて儲かったようで、恵塚がみつかると、そこを柵でかこって、三日三晩周りで、酒を飲み踊って祝ったということです」
「そのことを鈴木さんは知らないのですか」
「あの雑誌がでてから、鈴木さんには詳しく話しました、だから、あしげくここにかようになったんですな、もう掘り尽くされているんで、他の恵塚を探して、毒の頭蓋骨が埋まっていることを証明してから書くと言ってました」
「なぜ髑髏に毒があったのでしょう」
「わからんですな、昔の村人は骨が土に埋まって、毒草の根から染み出たものを吸収して、それがつよい毒に変わり、そのため、周りの草が枯れてしまったと考えておったようですな」
古書は違うと思った。
「そんな大事なものなのに、先ほど、恵塚は危険とおっしゃった、どうしてですか」
「掘り出すときに毒にやられて、何日も寝込むものがいたときいています、そういうものが入っていることを知らない頃は、きっと死人がでたでしょう」
「触るだけで毒になるのですか」
「いや、掘り出したときの漂う臭いにやられたとありますからな、空中に飛散したものが毒だったんです、もちろん骨そのものに毒があって、とびっ散ったのでしょうな、ともかく、昔の村の誰かが、恵塚の骨に毒が含まれることに気がついて毒薬にしたてたのでしょう、しかも空気に触れると飛散して、それを吸い込むと死ぬわけです」
「サリンみたいだ」
「そうですな、だが、わし等より何代も前に、そのような毒薬づくりはしておりませんで、やめちまったわけですな」
「毒のことはなぜ世間に知られていないのでしょうか」
「当時としては秘密なことだったでしょうな、恵塚があったということは私の父親の時代には外に話さなかった、そんな怖いところに人は住もうとしませんからな、だが、もう今の時代、気にせんでしょう、歴史の一つとして残すべきだと思って、わしは鈴木さんに話したのです」
「鈴木さんは吸うだけで毒になることを知っていましたか」
「話ましたよ、だけど、嗅いだだけで死ぬなんてことないでしょ、って笑っていましたな」
「三井さんがおっしゃったことは、何かに書き残されてあったわけですね」
「言い伝えだけですな、その当時は書いたものもあったのでしょうが、危ないので、毒づくりをやめた時点で焼いちまったんだと想像しているのですがね、今話したことは、親父からきいたことです、親父も親父、祖父から聞いたと言ってましたな、伝承になっています、わしのところが庄屋だったのでね」
「昔はどのようなものを食べて暮らしていたのですか」
「ごらんのような場所ですから、森の恵みに頼っていたんですよ、今も変わらんところがある、特に茸です、今でも村人たちはどんな茸でも食べる、ちょっとした毒茸でも平気で食べますからな」
この村の人は毒にも強いようだ。そのへんに鍵がありそうだ。
「実は、西巣鴨の八百屋さんが、ここの出身だとうかがいました」
「三井真三ですな、おやじの兄弟の孫になりますな、採れた山菜や茸などを売ってくれてます、助かっとります」
あの八百屋さん庄屋さんの家系だった。
「村から出て行った人は多いのですか」
「そりゃ、みてごらんの通り、山のもんしかないでしょう、簡単には暮らしていけません、皆ここが好きですんでいるだけで、いずれは廃村になるでしょうな、観光資源なんてものもない、毒じゃ観光資源にならんでしょう」
鈴木次男が新しい円形脱草をみつけ、掘り返して、髑髏を見つけたらどうなるだろう、三井村長の伝承話が本当とすると、毒の臭いにやられていないだろうか。心配なになってくる。
その日、古書は町に戻って、鈴木が泊まっていたというホテルに宿をとった。
次の日、村の中で一番若いという六十代の人が、彼の車で山に連れて行ってくれることになった。三井良三さんといった。この人が最初に鈴木さんを案内したという。古書は自分の車は村役場の駐車場にとめ、良三さんのハイエースに乗った。
「なんもねえとこですけど、気持ちのいいとこで、離れられなくてね、うちの両親は結局、町のケアハウスで生涯を終えました。わたしらももう少したったらそうなんべえ」
良三さんはすでに掘り終わった一つの恵塚に連れていってくれた。山を少し登った森の脇に車を止めた。
「だいたい、恵塚は森からはいってすぐのところにあるもんですわ」
そう言う良三さんについていくと、森の中の一角に木が生えておらず丸く草原になっている所があった。その一部に草の生えていない2メートルほどの円形の場所があった。
杭に恵塚1と書かれた板がうちつけてある。
「ここが最初にみつかった恵塚で、掘ったがなにもでなくて、掘ったじいさんの一人が貧血で倒れましたんで、それからはそのままにしてあります、鈴木さんが偉く興味を持ちましてね、三ヶ所連れて行きました」
「鈴木さんは掘ったりはしなかったのですか」
「ちょっと掘ってみたようだよ、だけどなにもでないといっていたな」
「新しい恵塚はまだあるのですか」
「あると思うけどね、森に茸採りに入ったもんが、偶然見つけることがあるが、いざ探すとなるとなかなかなくてね、それじゃ、観光資源にもならんですわ」
「鈴木さんはどのあたりにいったのでしょう」
「最近は、一人できて、自分で探していなさったから、わしらもどこまでいったのかわからんです、ともかく、鈴木さんは自分の車できてるんで、車が見つかればそこにいるってことでしょう」
良三さんは車をゆっくり走らせて山道をのぼっていった。途中からいくつかの道に分かれた。
「こっちは山を越えると、小さな湖の方にいきますな、湖の畔には恵塚はみつかったことがありません」
「なぜでしょう」
「わしゃわからんが、村長さんは知ってなさるかもしれんな」
「鈴木さんがどちらに行ったか全くわからんけど、ともかく走ってみましょう」
良三さんが湖に行く道とは違う方向に車を進め、しばらくいったところで古書が車に気がついた。
「とめてください、あっちに車が見えました」
車からおりた古書が森の方を指さした。森の脇のぼうぼうと伸びた草の間に白い車があるのがわかった。降りてきた良三さんもうなずいた。
「四輪駆動しゃだからすずきさんはここにいるにちげえねえね」
草を掻き分けて進むと、明らかに鈴木さんの車だ。鍵がかかっていない。キーもさしこんだままである。調べてすぐ戻るつもりだったのだろう。何かあったのではないか、気になるところである。
前の座席には小原村の大きな地図が広げてあり、所々赤い丸がつけてある。今みてきた恵塚1号のところにも赤丸がある。彼が調査している円形脱草の位置を示しているに違いない。後部座席下には穴掘りの道具がいくつかある。大きなシャベルなどはないので鈴木さんがもっていったのだろう。
「この林の中に違いありませんね、急いだ方がいいでしょう」
古書が先に立って森にはいると、良三さんが、
「あっちの方向のようだね」と指を指した。
「何回か人が通ったあとがある」
確かに踏みつけられた草がある。なれた人だとすぐわかるようだ。
古書は急いだ。
踏み込むとすぐに木々のない場所にでた。かなり草は覆い茂っている。草をかき分けると、円形脱草があった。穴が掘られ、脇に人がたおれている。
「鈴木さんだ」
良三さんがかけよった。鈴木さんはうつ伏せで、頭の脇には掘り出されたとみられる土の付いた髑髏がころがっている。
良三さんが鈴木さんの前にかがもうとしたので、「ちょっとまって」とあわてて古書が頭骨を足で遠ざけた。
「足をひっぱります」
古書が鈴木さんの足をもって、掘った穴からひきはなすと、鈴木さんがぴくっと動いた。
「生きている」
体をひっくり返すと、かすかに息をしている。古書が鈴木さんを担ぎ上げた。
「もどりましょう、あそこに落ちているカメラをもっていってくれませんか」
良三さんをうながして、車に戻ると、鈴木さんを荷台の上にのせた。
「警察に電話をします、村役場のところまで急いでもらえますか」
古書は携帯で村役場に電話をいれ、電話に出たさよちゃんに様子を話した。救急車を役場によんでもらった。
良三さんがたたんだブルーシートを荷台に広げ鈴木さんをその上に移動させた。古本は鈴木の手首をつかみ脈をみた。しっかりしている、大丈夫だ。
良三さんは「鈴木さんになんかせんでいいか」と心配そうに運転席に入り、エンジンをかけた。古本は、
「いつ倒れたのかわからないけど、大丈夫だと思います、救急車が役場に来るので、病院に入れば回復します。すぐ役場に行ってください、あの髑髏にはさわらないようにしないと、柵を作って人が入らないようにしたほうがいい」
頭蓋骨のことを知らない良三さんは不思議そうな顔をした。
「あの髑髏は毒なんです」
それを聞いた良三さんは目を丸くして驚いた。
古書は荷台に上がり、鈴木さんによりそった。
「ついたら、わしが村長に言って、何人か連れて、さっきのところにもどります」
良三さんは思いっきりハイエースを飛ばした。
車が役場につくと、さよちゃんが出迎えてくれて、役場の人たちが鈴木さんを集会場の畳の間に運び入れた。
さよちゃんが「救急車は町からだからだから、あと二十分もすると来ると思うから」
といいながら、「こうしろといわれています」
鈴木さんの顔を蒸しタオルでふいた。かすかだが息をしている。そのあとで、お湯を湿した布を唇に当てがった。
なかなか落ち着いていて手際がいい。
「よく知ってますね」
「村に医者が往診にきたときに、人手がないと手伝わされるんです、救急救命士のトレーニングも受けました」
救急車はすぐにきた。
鈴木さんは無事救急車にはこびこまれた。古書もつきそって乗った。
良三さんは村長をのせて、鈴木さんのみつけた恵塚に再度むかっている。
市の大きな病院に運ばれた鈴木さんは、検査の結果、重篤状態ではなく、次の日には話ができるようになった。
古書は室長の薩摩警視に電話を入れ、戻るのが三日遅れることを報告し、やっぱり事件になったことを話した。
鈴木さんは頭骨を発掘したときのことを話したがった。古書は要点を聞き取り、髑髏に毒のあることを改めて確認した。
「まさか、本当に臭いだけで倒れてしまうとはおもいませんでした、村長さんから話は聞いていました、うかつです、ミステリーハンターとしては失格です」
そう言って笑うまで鈴木さんも回復した。
今後、歴史的なものも含め、恵塚に関してしっかりしたものを書き残したいと彼は言っていた。
頭骨は危険物として警察があずかり、東京の科学捜査室に送ってある。やがて毒の成分なども明らかになるだろう。
こうして、円形脱草、恵塚の事件は終わりになった。警視庁にもどった古書に、薩摩警視が「ほんとうにほじくりだしたな、ともかく人の命が救えたのは表彰もんだよ」と声をかけた。
書斎推理派の古書が外に出かけて解決しためずらしい事件だった。
小原村のことを飯山医師に伝えた。そんなことがあるのだとびっくりしていた。そして、こんなことを言っていた。
「なぜ頭蓋骨だけなんでしょうね、考えられるのは頭蓋骨は他の骨と出来方が違うんからかな、他の骨は軟骨ができて、そこに骨が作られる。ところが、頭蓋骨は軟骨はできずに、膜ができてそこから直接骨になる。そういえば鎖骨も頭蓋骨と同じで気方をしますよ、鎖骨も調べる必要がありますね」
さすがに医者である。古書はそのことを科学捜査室に伝えた。
だが、なぜ頭蓋骨に毒があるのか。そのところは全くわからない。ただいえるのは、八百屋の信三さんを含め、小原村の人たちの頭骨には毒があるようである。毒茸を食べているためかどうかわかっていない。このような頭蓋骨をもっていることが知られると、この村の人はどのようなめに会うかわからない。外には知られないように、極秘扱いの調査がはいることになるだろう。
古書は人間の体の中には謎がいっぱいあるんだと言うことを知った。古文書の収集は歴史物ばかりでなく、解剖図譜など生命科学の分野にまで広げることにした。
このことを巌生堂の主人に話すと、捨てられちまう運命の古本が、人の命を救ったのか、これも古書さんが読んだからだな、またそんな本が出たらとっとくから寄ってよね、と嬉しそうに笑った。
髑髏毒


