
千族宝界録AR✛blue murder.
✛Cry/シリーズC2 A版①
1作が大体文庫本1冊の3部作①です。本作ARはC2前日譚となり、比較的まったりな出会い編になります。
update:2023.9.1-8 Cry/シリーズB・Atlas'版① AR
※直観探偵シリーズの過去で異世界の話になりますが単独で読めます
プロローグ「雑種化け物譚」の本編→https://www.novelabo.com/books/6333/chapters
直接関連作:雑種化け物譚R→https://www.novelabo.com/books/6334/chapters
†謡.雑種化け物譚 R
崩れ落ちていく昏い地の底で。何より死に近い場所でやっと、願いを得たバカな少年がいた。
「シヴァは、生きろよ」
大切な形見を預けた黒い鳥を逃がし、一人取り残された死地。銀色の髪の少年はただ、失った妹の名を叫ぶ。
「俺……エルを、助けたい……」
その苛烈さを選んだのは、少女達自身。
天性の死神と、赤き鎧の処刑人、気ままな死の天使。殺し殺される生き筋を選んだ罰だと、彼らは知っていた。
「エルを死なせたのは……俺と、アンタだ」
あどけない少女を誰かの暗闇へ巻き込んだこと。たった一人、少年が断罪すべき者へと告げる。
彼もすぐ理解したようだった。彼が少年に裁かれることも、少年が暗い青の目で希んでいることも。
「お前は……ならば、私の同類か」
彼はたった一人、愛した人間を得られず、守ることすら叶わず失った。
それでも決して、国王たる務めから逃げなかった。使命のためだけに生き続けてきた。
その生に何の希みも持てなかった彼の姿は、少年の行く末だと憐れむ。
それは赤き鎧の少女にとって、いつかと同じ場面だった。
突然、命の危機に晒された少女は、倒れた少年の横でぺたんと座り込んだ。
「兄さんを……巻き込んじゃった……」
そもそも、以前から少女は、育ての家族以外には疎まれていた。だからあの森に住むしか安息はなかった。
俯せに倒れていた少年を、取り返した菱盾の上に仰向けに乗せて、暗い青の目はぽろぽろ泣き出していた。
時間を止めてしまった少年。自分を守って傷付けられた兄。
幼いあの時より成長した少女はぐっと涙を拭い、唇を引き結んだ。
「……大丈夫。……母さんが、守ってくれる」
母の竜の眼を填める、この宝の盾の傍にある限り、少年の命はもう幾分だけ――最悪の状態であっても、その灯は留められる。
空を駆ける菱盾をふわりと機動させ、ぐるぐると蔓を巻いて少年を固定する。
「……ディレステアに、行かないと」
この状態となった少年を助けられるのは、ただ一人だけ。
その道の果てを思い、少女はふっと、顔を曇らせた。
「……――」
ほとんど消えかかった命で、少年は菱盾の上に眠る。これまでで一番穏やかな顔のように見えた。
それに少女は、ただ、ごめんね、と小さく呟く。
それから、赤い少女が降り立った場所は――
石造りの建造物が多いディレステアの中で、王都に白くそびえ立つ、荘厳な城に少女はまっすぐに向かった。
そこに降り立ち、赤い少女はほっとする。間に合った、少年はまだ生きている、と。
これで自身の果たす部分は終わった。母の形見の「鈴」を菱盾から取り出し、細い鎖のペンダントに戻した。
「……もう大丈夫だよ、兄さん」
菱盾から下ろした少年を、石垣の下の広場に横たえる。その首に「鈴」のペンダントをかけて穏やかに笑う。
――そして。
「――――」
見知った気配に、振り返った少女の胸を、正面から一瞬で――凝縮された水の槍が、容赦なく貫いていった。
あ――……と。声にならない声が、込み上げてきた血と共にこぼれた。
どんな化け物の力も、通すはずのない宝の赤き鎧。珠玉の殻を貫いた黒い力。
鎧以外も赤く染まり、ふわり、と黒い横髪が舞い、少女は仰向けに倒れ込んだ。
「……愚かな……ゾレンの刺客よ……」
この地に来ると決めた時に、わかっていた展開。
「たとえキラ君を助けるためでも……アヴィス様に消えない傷を負わせた君を……僕が、見逃すとでも思ったのか」
「……――」
かつて少女は、命を奪うべき標的ではなく、優しい人間を傷付けてしまった。その過ちを裁くべく、場に現れた化け物の姿。
じわりと石の床に血が広がり、少女が事切れていく様を、人間を守る化け物は黙って見守る。
「……うん。わたし……わかってた、よ」
最後に残った力で、少女は青の目を開けて呟く。純粋な化け物の青年に、感謝をのせた顔で笑った。
「ありがと……兄さん、を、助けて、くれて」
それができるのはこの相手だけ。それだけ伝え、満足したように目を閉じる。
そうしてその短い生を、赤い少女は終えていた。
もしもその少女に――兄である少年に憐れみを持てていなければ。国王はそこから何も言わなかった。
闘いが終わり、虫の息の彼に背を向けた少年に、ある真実を伝えることはしなかっただろう。
「……聞け、ライザの息子」
「……――?」
ぼろぼろの体で振り返った少年に、国王は倒れたまま石の空を眺め、重い声を振り絞った。
「かの赤き鎧には未だに、あの娘が宿っている」
「……え?」
「あの秘宝に適合する者は、死後の魂を秘宝に囚われる。代わりの適合者が現れるまで、安らぎを得ることはない」
「……え……?」
彼は本当に久しぶりに、誰かへ心から憐れみを持った。
使命の鎖。愛した人間にも感じた心。失って以後に初めて、ヒトの感情を取り戻していた。
「……あの娘のことも、私は救いたい」
「……――」
けれど最早、彼にはそれは叶わない。その思いだけで彼は少年を見上げる。
「方途はわからぬ――が。その竜の眼を持つお前に……それをどうか頼みたい」
「……それは――……」
――救うことは、できはしないと。
少年がその返事を彼に伝える前に。
一際大きく崩れ落ちてきた瓦礫が、力尽きた物憂げな国王を包み、全てを呑み込んでいった。
そうして、崩れ落ちていく昏い地の底で。何より死に近い場所でやっと、願いを得たバカな少年がいた。
「俺……死にたく、ない……」
取り残された地底で、蹲って膝を抱えて、暗い青の目で少年は妹の名を叫ぶ。
「俺……エルを助けたい……!」
少年と共に地底に残り、思わず心を打たれてしまった蛇も、その思いを叫ぶ。
「キラのことはオイラが何とかするにょろ!」
元々心など無かったその蛇は、ある迂闊な「神」の青年を呑み込み、甘く適当な部分をまるごと受け取っていた。
これでは最早、蛇が頑張るしかあるまい、と奮起する。
「キラ、よく聞くにょろ!」
「……!?」
「オマエを地上に、すぐに帰すのは無理にょろ! しかしオイラにはできることがあるにょろ!」
「神」と一つになった後に。「抜け殻」として「意味」を持った蛇は、呑み込んだもの達を長く中身にしていると、意味を一つにしてしまう特性を持った。
その特性でもって、少年を助けるためにある決断を行う。
「オイラの中身はもうないから、そうすれば今のオイラは消えるがにょろ!」
しかしそれは決して、別れではない。
元々生きていない抜け殻蛇の「意味」が変わるだけだ、と笑って言う。
「ちょっと時間は、かかるにょろが! 必ずオマエを――死者の一族にしてやるにょろ!」
そうして蛇は、おりゃあにょろ! と一発、気合を入れて叫ぶ。
「え――!!?」
その昏い地底が真に崩れ落ちる直前に。
有り得ない大口を開けた蛇に驚き、思わず剣を握り締めた銀色の髪の少年を、抜け殻蛇は剣と共に呑み込む。
そんな蛇を無情に、崩れる町は呑み込み、流れ込む深い海の懐へと包んでいった。
長い長い、永過ぎた長い時を経て。
その抜け殻がようやく、海底の遺跡から、古代の遺物として発掘されるその日までは。
+++++
✛開幕✛ Atlas' -Cry- 前日譚

金色の髪の少年は、気付けば広がっていた赤い光景に息を呑んだ。
「……え?」
目前には、赤まみれで転がる女と一つの人形。
手元には青銀の刃を赤く染めた、黒い柄の宝剣。
まず間違いなく。吐き気を堪えながら事実を直視する。
その平穏な建物の一角を、真っ赤に汚したのは少年。今も握り締める柄に填まる鈴玉へ、手を染めた赤がつるりと伝う。
「何で、オレ……殺してない――……?」
少年にとって、ただ不思議だったのは。
足元の女には確実に息があること。それだけだった。
胸を貫かれた女の痛みが、こうして伝わり続ける限りは。
忍装束という姿に隠れながら、天の使いの形に作られた人形。
そのカラクリの目が確かに、銀色の髪の少年の姿を捉えた。
ただ斬るだけでは殺せない人形。二つとない宝の剣から放たれた白い光。「力」のカラクリを無力化させた少年に、古い殺戮の天使が暗い青の目を開ける。
「……?」
自身が司る人形の一つが、白い光で壊された時。人形使いの幼子は強く、鋭い碧の目を歪めた。
礼拝堂に一人で座り、灰色の猫のぬいぐるみを抱く黒髪の幼子に、教会の主が静かに声をかける。
「どうしました? ソール」
自分をそう呼ぶ、この神父の魂になる。
それが仕事、と受け入れた幼子。天井につられた数多の人形を眺めながら、ただ呟いていた。
「……『ピアス』を、起こさなきゃ」
首を傾げる神父は、聖い魂を穢され魔とされた者。白銀の髪で蒼い目の神父の虚心は、幼子が知るある伝説の、赤い鎧の天使の兄に似ていた。
「誰か、面白い死者でも見つけましたか?」
「うん……翼槞以上の、死神がいたよ」
「……?」
幼子は悪魔や死者に取り入り、化け物が宿る人形を動かす稀有な才能を持つ。人形使い――本質的には悪魔使いであると、魔性の周囲からも認められていた。
「オマエ達もアイツも……ピアスも彼らも」
だから幼子はわかっている。この渦中の者は皆、同じ闇に囚われていることを。
「みんな……死者の一族……」
幼子が抱く猫に隠された黒い珠玉。少年が持つ透明な玉を填める剣。
二つの秘宝が青銀の死神の導きで出会う、忘却の時は近い。
+++++
C2新約前日譚
Cry per B/AR. -Atlas’ regurgitation-
+++++
†寂.AR
ある小さな島国が、今では世界地図の中心だった。
島国の名前はジパングと言い、世界で三本指に入る、独特の文化が発達した歴史の濃い国だ。
特に支配階級者の集まる「京都」は、静かな街並みも地味に洗練されている。その管理中心地たる「花の御所」では、公家という分類のジパング文化を代表する管理者が、京の街で起きた荒事に頭を悩ませていた。
獄舎という、日頃は全く訪れる機会のない拘置所へ、いつもの直衣で公家が訪れる。数回目の訪問相手であるのが、金色の髪を持つ異国の少年だ。最近の悩みの種が蹲る簡易牢の前で溜息をつくと、少年は顔も上げずに、すぐさま同じ反応を見せた。
「――嫌だ。ここから出ない、何処にも行かない」
「……そうか。おぬしはまだ、そのようなことを言うておるのか」
身元不明で、紫の目に尖った耳など、明らかに人間ではない特徴を持つ少年。着ているものも西の大陸でよく見る「洋服」で、ほぼ黒一色の縦襟の装い。袖の無い黒衣が秋の気候では肌寒そうだが、大きな厚い外套で全身をくるみ、不審者そのものの恰好で少年は膝を抱え続けている。
それでもこの少年はつい先日に、荒事に巻き込まれた公家の息子達を助けてくれた。
公家は昔から、人間でない化け物との関わりを沢山持っている。公家自身、人間の中で暮らしているが、本当は人外生物の血をひく混血だ。
だから、怖がらなくて良い。その思いを最大限に黒の瞳にたたえ、少年を見つめると、公家を見上げていた少年が動揺を見せた。ぴったりとした下衣の膝を、外套の上からぎゅっと掴むのが見えた。
敵ではない。その思いは確かに伝わっている。公家も敏い方なので、少年が揺れていることがわかる。なのに何故、少年はここに留まり続けるのだろう。
鉄格子を開けると、びくっと少年が震えて、改めて公家の方を見上げてきた。
中に入り、少年の前で膝をついて目線を合わせる。土の床で着物が汚れるが、気にせずそっと、袂を押えながら公家は細い手を少年に差し出した。
「ほら、何も恐れることはない。おぬしは恩人なのじゃから、わしが身元を引き受けて当然であろう?」
「…………」
少年は口を引き結び、逡巡するように、公家の顔と手を交互に見る。
そして数分。思い悩んだらしい挙句、少年は恐る恐る公家の手の方へ、自身の汚れた手を小さく差し伸べ……。
「大きなお世話だ。知らない奴なのに」
「――」
ぱん、と。派手な音が簡易牢中に響くほど、少年は思い切って公家の手を叩き、あからさまに振り払っていた。
「…………」
笑顔のまま固まった公家の前で、少年がすぐに目を伏せる。この公家でない貴族なら、無礼者、と激昂してもおかしくない非礼だ。
これは確実に、悪いとわかっていてやったのだろう。わざとは良くない、そんなことを、公家はまず思った。
そして……。
「フウ……力ずくで解決というのは、良くないことなのじゃよ?」
少年を諭すように、これまでで一番の笑顔で言い切った後、公家はぱちんと指を鳴らした。そしてその数分後……。
「いやだあああ! 放せこのっ、筋肉ダルマっ、ヒト攫いっ、脳まで筋肉、人でなしっ、何でも剣で解決する力バカの筋肉バケモノー!!」
「てめえ、凄く失礼なことを、全部わかって言ってやがるな……頼也の頼みじゃなきゃ、ぶちのめしてやるところだぞ」
雅やかなはずの京の街で、ガタイの良い侍に担がれた少年が、無理やり何処かに連れられていく。その後を歩く公家が、力ずくは良くないと力ずくで示して頭を抱えていたことを、ばたばた抵抗する少年以外は知る由もない。
少年は当初、不本意だった。
近場だが慣れない京都に一人で来て、顔見知りの占い師を探したまでは良かった。しかし行き道で謎の人形来襲事件に巻き込まれ、結局占い師には会えなかった。
更にはそこで、烏丸蒼潤という剣士見習いに加勢したばかりに、蒼潤の父である頼也のいる「花の御所」に身柄を引き取られてしまった。
早く帰りたい。そう思いつつも、気絶している間に獄舎に運ばれたせいで方角も現在地もわからない。転々と商売地を変える占い師が、あの日いたはずの場所も説明できない。迷子状態なのは「花の御所」にいても変わらず、門の内側で座り込んだまま、長居する気はないと行動で示すことしかできなかった。
少年を無理やり運んだ侍、山科幻次には一人娘がいた。同年代の娘はそんな少年を何とか御所内へ迎え入れようと、今日も説得しにやってきていた。
「ねぇ、ちょっと。いい加減、ずっとそこにいられると迷惑なんだけど」
「……」
凛とした声のきつい口調。侍譲りのさらさらの赤い髪は、ジパングの娘には珍しい短かさで、座り込む少年の前で小袖の裾を押えてしゃがんでいる。少年の異国語が通じる不思議な公家、叔父だという者と同じ黒の目で覗き込んでくる。
「アンタ、ここに来てから何も食べてないでしょ? この御所で客人にそんな扱いをするわけにはいかないの。記憶が無くて、帰る場所がわからないなら、ここにいてもらうしかないんだから。いい加減諦めて言うことをきいてくれない?」
少年は、自身が何者かが元々思い出せない。半年前に化け物の養父母に拾われ、ジパングの一角に先日まで暮らしていた。
しかしジパング語は全然わからず、養父からもらった翻訳機を左耳につけている。それで言葉だけ聴けば、少年をこのまま放置すれば自分達の沽券に関わる、娘がそう言っていることはわかった。
「ちょっと、ねえ。聴いてるの? そもそもまず、名前くらいは名乗りなさいよ」
「…………」
言葉はきついが、娘の感情は全く苛立っていない。むしろ、少年が何者であるのか、何としても聞き出して力になろうとしている。それはすぐに、この正体不明の少年には伝わっていた。
少年は目前にいるもの、もしくは周囲にあるものの感じていることを、共に感じる謎の感覚がある。養父はそれが「直観」という特殊感覚だと教えてくれたが、その直観は少年に、娘に対して、一つの返答しか必要とさせなかった。
「……別に、ツグミが心配することじゃない」
「――って……え?」
膝の間に埋めていた顔を上げ、まっすぐにそれだけ言う。
少年を覗き込んでいた黒い目が、ぱっと見開かれた。突然の正視に驚いたらしい。加えて娘は、反感を買うことを承知で強気に接しており、穏やかでも全て見透かすように返した少年に、顔中を一瞬で赤らめてしまった。
山科幻次の娘の「鶫」。一応御所では最上位の侍の姫で、本来なら様付けされるべきその名を、身内以外で最初から呼び捨てにする無礼者もそうそういないようだった。
――あ……そういうこと、なのか。
赤面したこと自体も恥ずかしいように、娘は顔を押えてばっと立ち上がり、走り去ってしまった。
どうしてわざわざ、お節介な内面とは裏腹に怒ったような言い方をするのかと思っていたが、そもそも異国の異性と話したことがほとんどないと見えた。緊張で虚勢を張っていたのだ。
少年を力ずくで連れてきた公家もそうだが、どうやらここの人々は、少年のような埒外者を放っておけないらしい。それは治安の維持のためでもあるが、おそらく多分、度が過ぎたお人好しの集団なのだ。
ふーん。と少年が、感慨にふける暇もなかった。
「――おい、てめえ。うちの可愛い娘の忠告を無視するからには、それ相応の覚悟があるんだろうな?」
目の前には、両手をぽきぽきと鳴らす山科幻次と、硬派な無表情ながら熱い目をして竹刀を握る烏丸蒼潤がいた。
そしてこの後、御所筆頭の剣士達にぼこぼこにされた少年は、山科幻次の二番目の弟子となった。帯剣も認められ、黒衣の上から剣を下げる紫の袴を履いた姿で、束の間の居場所を与えられることになる。
+++++
一度目の問題は、少年が山科家の近くに自室をもらってすぐに起こった。
山科一家は御所の衛兵達の総元締めだ。だから出処のわからない荷物が届いた時など、宛先の貴族に渡される前に山科幻次――今では剣の師がまず検分する。
そんな中、弟子である少年が師匠の居室に近い廊下で雑巾がけをしていた時に、間が悪くその兇事は届いてしまったのだ。
「もう! どうしてアンタが、人の家の荷物を勝手に開けるのよ! それでこんな怪我をされちゃ、父上の面目が立たないでしょう!」
ぎゅっ。と厳しく少年の左腕に包帯を巻きながら、師の娘が相変わらずのきつい口調で少年を糾弾する。
「蒼達からきいてはいたけど、本当にアンタ、髪の色が急に変わるのね。だからって御所の中で剣なんて振り回されたら困るの、それくらいわかるでしょ!?」
「……」
金色の髪の少年は時に、その髪が銀色に、同時に紫の目が青へと変わる。
それは養父母も心配していたことで、そうなると少年は、周囲のことなどかまわずに動いてしまう。
しかし師の娘が怒っているのは、あくまで少年の怪我にだった。慣れない袴で立ち回ったせいか、贈り物に模した突然の外敵に苦戦してしまった。
それらの狼藉自体は半ば仕方ない、と本当は娘も理解している。少年は思わず、何度目かの弱音を吐いてしまった。
「だから、オレ……ここには、いたくない」
少年はずっと、養父母の家で引きこもって暮らしていたかった。自身が異端者であり、容易に外の世界のルールを犯すことは想像がついていた。
しかしあの家には常時の結界が施されているためか、術師である公家の占いでも探し当てることができないのだという。そして公家達からもらった袴は帯剣には存外に便利で、異邦者の少年を御所に馴染ませてもいた。
夕暮れ時の縁側に向かい合って座り、少年の手当てをしていた娘は、ふう、と息をつきながら、空の端に現れ始めた夕焼けを横目で見上げていた。
「頼也さんだって、帰せるものなら帰してるわよ。アンタ、自分が京都では不審者な上に監察期間中なこと、まだ理解できてないの?」
「…………」
だからこの滞在は花の御所側の都合で、少年自身の咎とは言えない。娘が言外に込める不器用な想いを、少年の直観は易々と受け取る。
なので、ありがとう。と静かに言うと、また娘は顔を赤くし、夕陽から目をそらしてまでそっぽを向いてしまった。
「そこ、お礼言うところ? 意味わからないし……」
「? だって、手当てもしてくれて、ツグミはいい奴だし」
少年はどうせ、長くはここにいない。娘はそう思いつつ、何だかんだで異国者に興味があるようで、度々話しかけてきた。
いつも怒っているような、それでいて声は落ち着き、仕草一つにも品のある鋭い雰囲気。それはまるで、高潔な戦友のような不思議な気安さだった。
少し暮らしてみて、少年にはすぐ、この御所の実態の一端がわかってきた。
ここは貴族階級が集まって暮らしているせいか、その身を狙われている者が多い。それを剣で守るのが師匠達の役目で、管理者である公家の烏丸頼也は、人間ならぬ「力」で御所全体を守っているようだった。
「でなきゃ、魔物が入った荷物なんて、多分送られてこないよな……」
御所の内には、その管理上、立ち入ってはいけない区域が多々存在する。少年はそんな区域の近くに行くと、「怒られる」と肌で感じ、いてはいけない場所が何となくわかった。
少年の保護監察期間は一応二カ月とされており、それもじきに終わるので、これ以上無用なトラブルを起こすことはない。居心地は少しずつ良くなっていたが、そんな感傷で自宅を放置するのは駄目だ、少年はそう判断している。
けれど、それはあくまで、金色の髪の少年の理性でしかなく……。
その事件は、少年が日中にたまたま掃き掃除をしていた時のこと。公家の下に訪れたある客人を、間近で「観て」しまったのが禍の元だった。
「それでは、陽炎殿と言ったか。しばらくはこの御所に滞在されると良い」
「ありがとうございます。どうかよろしくお願い致します――烏丸頼也殿」
東の大陸でよく見られる、覆面をした護衛の忍を連れる着物姿の女。公家が迎え入れた二人を観て、少年の目は一瞬で青く染まり、髪もすぐさま銀色へと変質を始めた。
突然の衝動に、少年自身、吐き出しそうな怖れを覚えた。
無視すればいい。それが禍であるかなんて、激しく鼓動を始めた少年の胸以外、誰も保証はしない。
少年自身、何故その客達をそんなに脅威に感じるか、理由の全てはわからなかった。
それでも止まらない。この胸騒ぎを捨て置けば、いったい誰に被害があるだろうか。
帚を取り落とし、肌身離さぬ剣に手をかけた時、いつかの公家の笑顔が浮かび上がった。
――おぬしは恩人なのじゃから、わしが身元を引き受けて当然であろう。
そうなのだ。あの公家は温かく、こんな得体の知れない少年を共に住まわせるお人好しだ。剣を決して手放せない少年を理解し、だからこそ御所の一員として袴まで与えてくれた。
ここで剣を収めても、少年が保身できるだけだろう。公家達に近付く禍を、それと知りながら見逃してしまえば、どの道少年は自分を赦せなくなる。
それが答だった。同時に、髪の色が完全に、金から銀へと移り変わった。
――だからって剣なんて振り回されたら困るの、それくらいわかるでしょ!?
居心地が良い、と感じ始めてしまったのが、おそらくは一番の間違いだった。
温もりを知れば、失いたくなくなってしまう。たとえどんな手段を使ってでも。
そうしてそのヒト殺しは、袴と同じ紫の目を閉じ、長く眠り続けた青の眼光を確実に覚まし……。
数分後。少年は、気付けば広がっていた赤い光景に息を呑んだ。
「……え?」
目前には、赤まみれで転がる女と一つの人形。
手元には青銀の刃を赤く染めた、黒い柄の剣。
「……オレ……なんで――?」
自分以外は誰もいない見知らぬ部屋で、茫然と呟くしかできなかった。
力無く下がる片手に、凶器と思しき剣を携えながら。
空いた手で胸を強く掴み、金色の髪の少年は両膝をつく。
「――……いた、い……」
まず間違いなく。吐き気を堪えながら、少年が置かれた事実を冷静に直視する。
その平穏な建物の一角を、真っ赤に汚したのは少年なのだ。今もまだ握り締める剣の柄の鈴玉へ、手を染めた赤がするりと伝う。
それでも少年にとって、ただ不思議だったのは、足元の女には確実に息があること。それだけだった。
「何でオレ……殺して、ない――……?」
胸を貫かれた女の痛みが、こうして直観で伝わる限り、女はまだ死なずに痛みを感じている。少年はきっと、女を殺すつもりでここに現れたはずだったのに。
しばらく忘れていた赤い夢が、ふっと、倒れ込む少年の脳裏をよぎった。
――あいつだけは――絶対に殺す。
そうだった。この女は確か、少年の獲物ではなかったはずで……――
赤い部屋に崩れ落ち、赤まみれになった袴のように、そのまま血塗られた夢が少年を満たしていった。
_起:記憶喪失の少年
「まいったのう。まさかこのようなことになるとは」
「それでさ。その下手人の『ユーオン』君は、まだ眠ったまんまなワケ?」
その御所の一室に眠る、少年の様子を窺いながら、知らない相手が公家と立ち話をしていた。
部屋を仕切る襖の外で、薄青いシルエットの軽装の青年と、重い声色の公家が何やら相談をしている。
「それが困るのじゃ。予想以上に体力の消耗が激しいようでな」
「ええー? それ、困るとこ違うんじゃないの、頼也兄ちゃん?」
白い浴衣で夢現の少年も、それは同感だった。
二か月前より公家――烏丸頼也がこの御所に引受け、保護監察中だった正体不明の記憶喪失の少年。
ようやく監察期間が明けようとした矢先に、少年は突然、客人を斬る前代未聞の問題を起こした。
それで頼也は、今話している青年を呼び出していたのだ。
「いくら『悪魔憑き』とはいえ、初対面の、しかも女のヒトを斬り捨て御免かあ。兄ちゃん達の拾い者にしてはイイ度胸だよねー」
「言葉には気をつけぬか。そもそも誰も死んでおらぬぞ」
「それも妙な話だよねェ。オレに来る『悪魔払い』の依頼なら大体、誰か一人は死ぬんだけどさ」
頼也には蒼潤という十四歳の長男がいるので、見た目ほどには若くないはずだ。それでも中性的で端整な顔立ちの頼也は、この京都では有名な陰陽師の家系といい、実際は呪術を専門としている。その頼也を、被害者の客人は悪魔祓いという依頼を手に訪ねていた。
「そもそも何で、『悪魔憑き』が呪術使いの兄ちゃんを訪ねてきたのかとか、色々ツッコミどころはありそうだけど」
青年の言う通り、頼也には悪魔など専門外だ。だから頼也は、悪魔と契約を交した人間への介入を仕事とする青年――通称「死神」である旧知の仲間に、意見を聞くつもりだったのだ。
「さすがに、いくら悪魔相手でもこんな人間の御所内でバッサリ殺っちゃうのは、オレでも躊躇するけどね?」
管理者として相当困んないの? と。死神でも何でもなく、一傍観者として青年は不思議そうにする。
「それはもう、各方面から、不審の声は上がっておるがのう……」
少年に斬られた客人は生きていた。それでもこの風雅な花の御所が、血で汚される事態はそうそうあることではない。
「そちらも追々対処が必要じゃが、こちらは差し迫っておる。お主でも回復はできそうにないか? あの少年は」
「残念だけど、ケガも毒もないんじゃ、こっちの方はお手上げ」
そうか、と項垂れる頼也の一番の悩みは、目を覚まさない少年の消耗だった。
「お主も不調の所、呼び立てして悪かったのう。アラス殿」
そうして、死神でありながら「精霊魔法」による回復の業を得意とする青年を、礼を言って見送ったのだった。
これで、金色の髪の少年が銀色の髪となり、御所で問題を起こすのは二度目となった。
銀色の髪の少年は、金色の髪の少年の心に関わらず、必要とあらば容赦なき殺戮者となる。御所中にそれが示されてしまった手前、頼也は最早、何の処分もなしに済ませるわけにはいかなくなっていた。
「最初は確か、御所に魔物が郵送されてきた時じゃったのう」
「……」
ようやく目を覚まし、布団の上に起き上がった少年の横で、頼也が鎮座していた。紫の目を伏せて俯く少年に、淡々と静かに話しかける。
「お主が初めて現れた時の、不審な依童人形の襲撃からこちら……何やら京都に、不穏な風が吹いておることは否めぬ」
この少年を頼也が引き受けるキッカケとなった出来事。蒼潤と悠夜という頼也の子供達を謎の人形が多数で襲った時、通りがかった少年は変貌して蒼潤に加勢していた。その事件を含めれば、少年が銀色の髪となるのは三度目でもあった。
「お主の行動は、一貫しておるように思うが。お主は本当に、『銀色』の時のことを覚えておらぬのか?」
「…………」
頼也の目には、少年の変貌は魔物や悪魔などを前にした時――苛烈ではあるが、何かを守るために少年が剣を取ることが映っていた。
銀色の髪である時の意志を、少年はほとんど覚えていない。わかるのは体の負担が大きいことだ。だから動ける時間が少なく、単身で魔を制す「銀色」に比べて、金色の髪の少年は自身の弱小さに悩んでいる。
そして頼也は、頼也自身が少年を罰したい理由はないのに、立場上甘い顔はできないことを苦悩している。それが伝わってくる少年は、ひたすら俯いたまま、口を閉ざすしかできなかった。
――だから……何処にも、行きたくないって……。
どうせ家がわからないなら、あのまま拘置所にいれば、こんな迷惑はかけなかった。
客人が奇蹟的に生きていたとはいえ、少年のしたことはヒト殺しだ。少年は自身がそうした疫病神だととっくに知っていた。
今もなお、あの時殺し損ねた相手への、殺意の鼓動をこの胸は覚えているのだから。
「……――……」
少年を真摯に見透すような頼也の、青みがかった黒い目には、怯えすらも感じてしまう。
目を覚ましたものの、少年の体調はまだ万全でないとわかる頼也は追求をやめ、困ったように笑って結論を告げた。
「とはいえ、事が事じゃから、罰は受けてもらうがのう?」
「――当たり前だ」
はっと顔を上げる。どうして当たり前のことを、頼也はわざわざ、優しい笑顔で告げるのだろう。
まるで、その罰を与えるのは不本意と言わんばかりだ。それではますます、頼也の立場が悪くなってしまう。
「お主の保護監察期間は延長じゃ。当面は期限の無いままに、御所で引き続き衛兵見習いをしてもらう」
「……」
それでは駄目だ。ヒト殺しの少年を放置すれば、頼也と山科の一家以外、他に御所に住まう誰もが納得いかないだろう。
――オレ、ここにはいたくない。
御所に最初に来た頃と同じに、自分を追い出すべきだと目線で訴える。
どんな事情があったとしても、頼也にいか程迷惑をかけたか、少年は自分でわかっている。
おそらくは、それをも感じ取っている頼也は、だから躊躇うことなく、ある厳罰を少年に伝えた。
「それと今後、おぬしには一切、自由に行動してもらうわけにはいかぬ――」
本当は人間でないものの血をひく、頼也達の家に伝わる深い業。
それを全て、少年は受け入れると決めた。
受け入れたところで、少年の咎がなんら変わるわけでもないが、この呪いが後々のヒト殺しの運命を決めることを少年はまだ知らない。
+++++
「いいか? 今度からこんな当たり前のこと、説教させんな!」
数日後。
金色の髪の少年がいつも、剣の鍛錬を受ける離れの道場に、師匠が赤い髪をふるわせるほど思い切りの良い怒声が響いた。
「一方的な刃傷は禁止! そもそも御所内での戦闘も不可だ! 何かあったらまず報告して、それから行動の判断を仰げ!」
袖なしの黒衣に紫の袴。いつもの姿で正座させられた少年の後ろで、袖を破った長袴スタイルの兄弟子の蒼潤が首を傾げた。夕焼け色の鳥頭をひねり、不思議そうに師を振り返っている。
「幻次さん。それだと、問答無用に襲われた時はどうするんですか?」
「自衛は戦闘に入らない。自分から喧嘩を売るなってことだ、蒼潤もな」
先日の場合、完全に金色の髪の少年から、刃傷相手の居室まで押し入った形だった。
「……うん。ごめんなさい」
どう考えても、説教程度の処分では済まないはずの、危険人物であるヒト殺しは、
「今度から――御所の外でするように気を付ける」
「全然わかってねぇ! 先に相談しろっつってんだ!」
そのように心温まらない遣り取りをかわしながらも、何だかんだでこれまで通りの生活に戻れた状態だった。
陽炎の姫。少年が剣を向けた相手は、東の大陸出身という忍らしき侍従を一人連れた、うら若き乙女だ。
自分にとりついた悪魔を祓ってほしい、とその姫は珍しい依頼と共に、この御所を訪れていた。
「蒼潤と悠夜両方から確認がとれた。あのお姫さんが連れてた人形の侍従は、アイツらを襲った人形と同じ系統だってよ」
姫と侍従を、偶然見かけてしまった金色の髪の少年は、その場で銀色に変貌していた。恐ろしいことに真昼間から、凶行に及んだわけだった。
「やっぱり、ユオンは敵を倒しただけなんですね」
硬派な蒼潤は、勘の良い少年にはそれがわかったのだ、と信じていた。それも侍従の正体が判明する前からだった。
「いつもユオンは、敵も味方も、攻撃される手筋もほとんど観えている。でもわかっていても、さばけないだけですしね」
褒められているのか、貶されているのか。鍛錬の度にぼこぼこにされる弱小な少年が、「本当はわかっている」と察知している兄弟子こそ、その剣気がわかる達人の域にあった。
師――幻次はそうした弟子達を知りながらも、遠慮なく苦言を呈する。
「相手が敵かどうかなんて、いくら勘が良くても、一瞬で全てわかる奴はいない。さらにはたとえ敵でも、問答無用で喧嘩を売るな」
先にその人形である侍従を斬り捨て、姫には普通の人間なら確実に死ぬ胸への一太刀のみで、銀色の髪に変貌した少年は事を終えた。
そこで少年も力尽き、赤く染まる部屋で倒れたのだった。
「大体ユーオンも死にそうだったみたいじゃねぇか。そこまで無理して一人で戦ってんじゃねぇ」
「いてっ」
ごつん、と。幻次は一度だけ、きつい拳骨を弟子に見舞う。
「お姫さんは順調に回復してるとよ。自分に憑いた悪魔だけを殺してくれた相手に、会ってみたいとさ」
そして心の底から嫌そうにする少年に、にやりと笑ったのだった。
本日の鍛錬が終わった後で。道場の掃除をしながら、蒼潤が真面目な顔で尋ねる。
「なあユオン。悪魔だけ殺すってどうやるんだ?」
「さぁ? 完全にまぐれなんじゃないかな」
「銀色」の時のことを少年はあまり覚えていない。さも、他人事のように答える。
「オレにわかるのは、弱そうなとことか、雰囲気だけだし」
少年は剣技で全く蒼潤に敵わない。しかし蒼潤が言っていた通り、攻撃がどう来るかなどは、避けられないだけでわかっている。そんな周囲の現状を感覚で看破する勘の良さ――直観という珍しい特技があることを、蒼潤も幻次も剣士の嗅覚で気が付いていた。
「それですぐ、あの忍者が人形だってわかったのか?」
「多分。ジュンが言うほど、はっきりわかったわけじゃないけど」
侍従の方が人形であることは、一目でわかった。しかし以前に彼らを襲った者と同系統とまで、その場でわかったわけではない。
それでもその時、これは敵だと。それもなるべく、この御所に住まう者達に近付けてはいけない――
激しい思いが根拠なく湧き出し、気が付けば赤い部屋にいた少年は、バツが悪い心で再び目を伏せた。
「……ヨリヤに迷惑、かけるのにな」
わかり切った行動の結果。何故それを無視して、「銀色」がそこまで強行に出たのか……。
その過程については、少年自身も重い気持ちを抱えていた。
人形の侍従を連れていた姫は、侍従がいなくなってみれば、何故自分がその侍従を連れていたかわからない、と当惑しつつ語ったとのことだった。
「人形の出所は結局不明だと、父上は仰ってた」
「……あの女の関係者じゃないのか?」
それは真っ先に疑われて然るべきだが、忍という類の恰好をしていた侍従は、東の大陸伝統のフリーの護衛集団だ。誰でも護衛に雇える上に、正体は明かさない不文律にある。だから身上も追跡できない。
「それなら姫も、侍従の正体を知らなかったことは有り得るだろうって」
「それって……ジュンはどう思う?」
蒼潤の名を、少年からはジュンと呼ばれる兄弟子は、首を傾げる。
「何か変な気はするな。自分に憑いた悪魔を祓ってくれなんて、本当に悪魔が憑いた奴が言うのか?」
だからその姫が何がしか、怪しい相手であることには変わりがない。蒼潤は難しい顔をしながら雑巾をしぼっている。
「……」
それなら何故、「銀色」は相手を生かしたのか。少年は暗い面持ちになる。
余程無害とみなさない限りは有り得ない。斬るほど有害なら殺し切らなければいけない。それでも少年は、蒼潤の言も大きく頷けた。
だからその根本的な問いを、無意識に口にしていたのだった。
「……『悪魔』って、何なのかな……」
そんな少年の元へ、ひょっこりと、
「『魔』というのは、ヒトから奪わないと生きられないもの達、全般のことみたいだよ」
幼いながら、聡明で落ち着いた声が響く。発信源に少年が振り返ると、にこにこと、黒く短い髪に袴姿の和服の子供が穏やかに微笑んでいた。
「――ユウヤ」
少年をこの御所に引受けた公家の、ミニチュアとも言えそうな公家の次男、悠夜。それが兄の蒼潤と少年の元まで来ていた。
「『悪』がつくと、どう変わるのかはよくわからないけど。あまり良い連想は、どうしても湧かないよね」
「……なるほど。ユウヤは本当、頭いいな」
名だたる術師の公家の血をひき、この幼さで既に大人顔負けの天才術師である悠夜は、公家というより武家の子供のような恰好だ。立ち居振る舞いも少年達より洗練されていた。
「兄様達。泉の広場に、各地で評判の旅芸人一座が来ていると聞いたんですが、みんなで観に行きませんか?」
「旅芸人一座? 珍しそうだな」
「――オレは遠慮する」
条件反射のように即答した引きこもりの少年は、御所に引き受けられる前から基本、住む場所の外にあまり出たがらなかった。
「そんなこと言わずに。『同行』、『要請』」
「――!」
びくっと、念を込められた悠夜の声に、少年は静電気が走ったように体を震わせる。
「一緒に行こうよ。きっと楽しいよ」
楽しそうに笑う悠夜に、呼吸が止まる。これは断ることが不可能な事態、と悟る。胸を掴みつつ、ぎぎぎと頷かされる。
その後は何も言わずに、ただ怪訝な思いで黙り込む。
「ちゃんと効いてるみたいですね、父様の術は」
「――?」
それをついでに確かめたかった風の弟に、兄弟子がふむ、と頷く。
「悠夜と鶫と父上、すみれさんには絶対服従。っていうアレか?」
事も無げに言われた、その厳罰――「言霊」を使って告げられた命令には、逆らえない呪い。いつ何時「銀色」となり、何をするかわからない少年への首輪について、その実態を納得したらしい蒼潤だった。
「……何か……息が、苦しい」
しかし少年は、段々と青ざめてきた顔でそんなことを呟く。
「あれ。そこまで抵抗すると、命に関わっちゃうよ」
この命令だけは聞きたくなかった。呪いを受け入れたのは自己責任なので、難しい顔で黙る少年に、天使のような顔で悠夜が笑う。
「『抵抗』、『不可』。悪あがきは良くないよ」
びくっとそこで、完全に少年は、抵抗の気力の根すら断たれたのだった。
「それにしても……本当に、呪いと親和性が強いみたいだね」
罰としての呪いを、少年は公家から二つ返事で受け入れた。そのバカ正直さに、術師の悠夜はただ苦く笑ったのだった。
旅芸人一座。それはこの、身元が不明で記憶喪失の少年には、決して近付きたくなかった鬼門。
自らについてあまり口にしない少年の周囲は、知る由もない。
+++++
花の御所でよく関わる三人の子供と、旅する一座「レスト」を見に行った金色の髪の少年は、始終黙り、辺りを窺い、まさに挙動不審の引きこもりだった。
少年には、これまでの自分の記憶が無い。気が付けば今、この体を動かしていた。
そしてそれは、同行の彼らを襲った謎の人形と、本当は大差ない存在であることを知っていた。
精・妖刃。発音がしにくく、一座の者からイーレンと呼ばれていた名前を、偶然出くわした幼げな花形に言われてしまった。花形からやっと離れた所で、少年はたどたどしく説明を始めた。
「オレの知ってるソイツが、あいつらの護衛をしてたんだけど。ソイツ、死んだから……だからあいつらには、会いたくないんだ」
一座の者には、知らせたくない。それだけ伝えて、紫の目を伏せる。
「じゃあ、ユーオン君の、知り合いの知り合いってこと?」
「そうなるかな。妖精らしいことは、改めて知ったけど」
「それじゃ……ユーオンは結局……その知り合いの妖精と同じ、妖精。って類になるの?」
「――え?」
この少年のことも元々、姿形から養父母はおそらく妖精――精霊にしては強い自我を持つ、「妖」と言える千族と検討をつけていた。しかし今までは確信がなかったことでもあった。
「多分……わかりやすく言えば、オレも妖精なのかな」
記憶を辿って言う少年に、師の娘、鶫が不思議そうに首を傾げる。
そこで聡明な悠夜も同じように首を傾げた。
「妖精なら羽があるはずなんだけど……」
有名なその妖の特徴を思い浮かべ、まじまじと少年を見る悠夜に、ただ少年はキョトンとする。
彼らがそんな話を、まさにしている時――
「――イーレン!? イーレンじゃない!?」
あからさまに、うわ……と困った顔をする少年の後ろで。二人、先程の幼げな花形とは違う人影が来ていた。
「ルンから聴いたの……! お願い、その剣を私に見せて!」
一人は一座のもう一人の花形。「咲姫」としての名は霖という、黒髪を首元で丸く結わえるジパング風の美女だった。ただジパングの女性は、ここまで露出の多い踊り子の姿はしないだろう。
「……霖。迂闊に近付かないで下さい」
対してもう一人の、護衛らしき女は、ジパング風の羽織物と、その内に下衣を身に着け、がちりと全身を覆う珍しい服装だった。どちらかと言えば、ジパングの名が「ヤマト」や「和の国」であった旧い時代の、「漢服」に似た装いだと後で少年は聞く。
「……――」
珍しい白青の長い髪をまっすぐ垂らす護衛が、薄青い目を少年にじっと向ける。
少年はその薄青い目に、声を呑んで唐突に固まる。
「――」
この動き難そうな恰好の護衛は、恐ろしく強い。その威光を感じ取った。
少年の髪が一瞬で銀色に変貌した。
戸惑いの紫の目を忘れたように、迷いなき青の目で少年は、待ったなしにギラリと、袴に下げた剣を抜き――
「ちょっと――『銀色』、『自重』! ユーオン、待って!」
咄嗟に声をかけてくれた鶫に、びくっと息を飲む。すぐに金色に戻った髪で、あれ、とばかりに胸元を掴んでいた。
きょとん、と、少年と鶫を黒髪の花形が交互に見つめる。
花形に付き添う護衛は、当初から厳しげな顔で佇んでいた。
「……一瞬、強い殺意を感じましたが」
端整に整っている切れ長の目。しかし声には柔らかさもあり、事も無げに、剣を抜き放った少年に対して余裕の様相だった。
「今は特に――大きな脅威では無いようですね」
少年は、ジパングで最強レベルの侍に剣を習うも、なかなか上達してくれない。他には勘の良さ以外、命を削るくらいしか特技がない。なのであっさり、弱小者だと護衛は見切ったようだった。
そしてそんな護衛について、一番先にそれに気が付いたのは、観察力も高い悠夜だった。
「……あれ? ……アラス君?」
「――?」
瞬時に子供の方を見る護衛に、護衛が無表情のまま振り返る。
蒼潤も不思議そうに弟を見る。
「どうしたんだ? 悠夜」
「髪の色はアラス君より薄いし……しかも長いけど。まるで、アラス君が女の人になったみたいな姿の、護衛さんだなって……」
「……私の現在の主を、知っているのですか」
護衛はあっさり、悠夜が出した名と、自らの関連を口にする。
時間がもったいない、と護衛はあっさり本題を切り出していた。
「もしもその剣が精妖刃の物と同じなら。何故貴方がその剣を持っているか、霖は気になるそうです」
黙って成り行きを見守りつつ、御所の子供陣も顔を見合わせる。
その妖精は死んだ。そのことを隠したい様子だった少年が、何故そうするのか、どう対応するつもりか……周囲の方がハラハラしている。
「霖の目には、似た剣であることしかわからないようです。座の目利きの者に鑑定を願いたいと言うので、同行してもらうか、剣を貸してもらうことはできませんか?」
「――貸すのは、絶対に無理」
少年は即答する。露骨に困る、不服な顔を作り護衛を見返す。
そして、今度はまっすぐ表情を消して、花形を見る。
「……剣がもし同じだったら……それで何になるんだ?」
「……――」
それもそうか、と。御所の子供陣も、その違和感に気が付いていた。
「そうよね。ユーオンがどうしてその剣を手に入れたのか……それを真っ先に訊けば早いのに」
護衛はそうしたのに、何故花形はそうしないのか。そして、慣れない袴を着用してまで常に剣を手放さない少年の警戒も、そこで納得のいった子供陣だった。
「ユオンの剣が欲しいのか? あんた」
「……」
「妖精さんが何処に行ったかは、あまり興味は無いんですか?」
それが気になるのならば、同一の剣と確信してから、持ち主はどうしたのかと尋ねるのも回りくどい。剣に拘っていた花形に、揃って不審の目を子供陣が向けた。
「そうですね。霖の目的は、それであるように私も感じます」
駄目押しの護衛の一言に、黒髪の花形は、困ったように笑った。
「……そうね。イーレンは、帰ってくる気はないと思うから」
そうして花形が知っていることについて、簡単に話し、嘆息したのだった。
「こんな話をするのは、恥ずかしいけど。もう一人の咲姫……ルンは、イーレンと付き合ってたの」
え。と何故か、少年をちらりと子供陣が見る。
「でもイーレンがいなくなる前、ちょっと色々揉めてたみたい。ルンは淡々としたものだけど、イーレンは落ち込んでたし」
だからもう、その妖精は帰らないだろう、とさっぱりした顔で花形は語った。
「イーレンは剣マニアだったから、何回も剣を買い替えてたわ。いい剣ばかりだから、いつかどれか、私にくれるって……そう約束してたの」
「……」
「だからもし、それがイーレンの剣なら、譲ってくれないか、お願いしちゃおうって思ってた」
てへへ。とばかりに、軽く舌を出す花形に、少年は淡々と、その答を返していた。
「……誰の剣でも……これは、譲れない」
そっか、と花形は、あっさり諦めたように爽やかに笑った。
とりあえず――と。
帰路についた一行の中で、不服気に口を開いたのは鶫だった。
「ユーオンは、これで良かったの?」
「え?」
「そうだな。何か今一つ、何が何だかでスッキリしないな」
結局あまり、少年の事情がわからなかった彼らには、色々不消化らしい。
「ユーオン君の記憶の手がかり、あのヒト達はなりそうにないの?」
そこにほとんど、少年が興味を見せなかったことを含めて、全員が訝しがっている。
不透明なままの妖精の行方や、一瞬でも「銀色」が出てまで対峙した護衛。それについて、何も語らずにいる少年が気になるようだった。
「――ごめん。ツグミ達には時間とらせて、迷惑かけた」
「そういうことじゃないでしょ? 別に……ユーオンが話す気がないなら、無理にはきかないけど」
「……」
「御所に来る前、何処で何をしてたのか。本当にユオンは、何も言わないよな」
記憶を失ったという春から、少なくとも半年、何処かではそれなりの生活があったはずの少年。
身寄りはない、知り合いは全て行方不明、それしか少年は語っていない。そのために今も、保護監察が続く身上でもある。
そして子供陣は、彼らにとっても関係がなくはない事項に、うーんと顔を悩ませている。
「アラス君も、大丈夫なのかな……最近調子が悪いって父様に言ってたのに、あんなに大きな『力』を単独行動させて」
「そうなのか? この間も来たけど、いつも通りに見えたけど」
人形に憑依する「力」である護衛。その主君について子供陣は心配らしい。
子供陣の知るところには自称死神は、何やら最近、東の大陸で大怪我をしたという。基本的に謎めいた青年で、彼らの父曰く「悪くない吸血鬼」らしいが――「レスト」を含め、昔馴染の知らない様々な所で活動しているようだった。
「それにしても、何で人形なのかしらね」
さすがにタイミングが悪いわよ、と。早速「絶対服従」を少年に強いることになった鶫――頼也の姪で、同じく「言霊」を紡げる呪術師が呟く。
そうした強制は本来好まないのだろう。不服気に少年を見つつ、口にしている。
「そっか。そう言えばさっきはありがとう、ツグミ」
対照的に、素直な心で笑い、少年は赤い髪の娘に振り返った。
「……呪われた後にありがとうって言うバカ、信じられない」
鶫には無害な笑顔に見えたらしい。頭痛を抑えるように息をついている。
「何か、胸がドキドキして、温かかった。何でかな?」
「バカ。そのまま心臓止まるわよ、下手したら」
厳罰としての「言霊」は甘く見てはいけない。逆らえば待つのは死だ。
それでも少年は、こうしてとても気楽に笑える。それが彼らの住む御所の一角を血で染めたなど、現場を見たわけではない鶫は、初めはその厳罰に反対していた。
全く、と溜息をつく鶫が何を葛藤しているのかよくわからず、少年は不思議な気持ちで見つめる。
絶対服従。御所の管理者たる頼也と、その周囲の術師達には逆らえない呪い。そうした罰をあっさり受け入れた少年は、主人の一人となった赤い髪の娘に、後に所感を語った。
「オレは多分、ろくでもないから。そうじゃない奴の言うことを聞いてた方がいいと思う」
「はぁ? 何よ、それ?」
うん、と。首を傾げて自ら考え込みつつ、素直な気持ちを伝える。
「ヨリヤもユウヤも、ツグミもいい奴だから」
こくこく頷きながら、頼也の采配に、少年自身はとても納得がいっていた。
その少年の納得が、鶫はあまり理解できないのだ。
「全く。悪いのは銀で、銀に負けるユーオンは弱々なだけよね」
「……なんで? それ、逆だと思うけど」
首を傾げる少年に、鶫は更にイラっとする様子を見せた。
「だって、銀の暴走を、ユーオンが止められたら一番早いんじゃない」
「…………」
なるほど、と……鶫の複雑な思惑がわかった少年は、しばし声を呑み込んでいた。
しかしそうなると、一つの誤解を解かねばならなかった。
「……オレは別に、止める気はないんだと思う」
そうしてそんな、反省のカケラもない返答をする。
「――何、それ?」
怪訝そのものの目で見る鶫に、少年も少し怯む。
「いつも、何をしたのか覚えてない……わけじゃないんだ」
「銀色」である時のことを、全く覚えていないというのは誤りであると。珍しく自ら実情を口にした。
「それって――ユーオン」
「オレは別に、違う誰かになってるわけじゃない」
周囲は「銀色」と少年を、いつも分けて扱ってくれる。その方が物事が円滑にいくので、これまであえて口にしていなかったことだ。
「やったこと自体は、覚えてる。ただ単に、どうしてその時は、そうしようと思ったのか……その時に何を考えたのかが、どうしても思い出せない」
「…………」
厳しい真っ黒な目線で、鶫が少年を見た。
「つまり……何を考えたかを思い出せば、ユーオンは銀と同じことをする。そう言ってる?」
「……うん。多分」
あのねぇ――と。頭痛を抑えるように片手で額を触りながら、鶫はやっと理解できた、とばかりに、大きく頷いて言った。
「確かに必要みたいね。ユーオンには、その呪い」
だろ? と首を傾げる少年に、開き直るな! と頭をはたいてきた。叔父である頼也の判断は妥当だった、とようやく納得したようだった。
「弱いのは多分……銀の方なんだ」
ぽつりと。自身の暗闇を見つめるように、少年は呟く。
それでも、その力に頼る自身の咎に、悪いのは自分だと――当たり前のように現実を口にした。
+++++
その日はとても、少年にとっては疲れが大きかった。
傍目からは始終、淡々としたように見えた少年であっても、一番避けたかった旅芸人一座との再会。しかもそこにいた護衛の人形……どう観ても、これまでで一番強そうだった難物に、色々と複雑な思いを抱える。
「……あいつ。大人しくしてるかな……」
それでなくても問題を背負う少年への、天罰なのだろうか。
御所に帰り着いた少年を待ち受けていた、ある者の存在があった。
「――え?」
「お邪魔しております。アナタがユーオン殿でしょうか?」
貸し与えられた御所の一室。寝具と灯り以外は一切物が無い、飾り気や彩りとは無縁な少年の居場所に、その異物は居座っていた。
「……――」
「陽炎と申します。先日は非常にお世話になりました」
異物はただ、毒も薬も無い目付きで少年を見つめる。
土色の、肩までの癖の強い髪は、あまり着物には合っていない。
陽炎という儚い響きとは裏腹に、意志の強そうな雰囲気で、その姫は自分を殺そうとした少年を出迎えていた。
「……あんた……」
これは何の悪い冗談か、と少年は顔を歪めるしかできない。
その、特にこれといった特徴の無い、一見は無力そうな様子の姫君。
ジパングの風土に合わない「悪魔憑き」を、最初に少年が観た時だった。
――あいつだけは――
数か月前に観ていた光景。
養父母の里帰りに同伴した時、少年を襲った赤く昏い夢が瞬時に顔を出した。
――あいつだけは――絶対に殺す。
それが根本。そのためだけに、赤い夢の誰かはここまで来ていた。
けれどその夢は少年も、「銀色」も特に気にしたことはなかった。
広くはない少年の居所で、一角に居座っている侵入者。少年は特に感情は無く、金色の髪と紫の目のまま――
しかし警戒と嫌悪を隠さない声で、大事な問題を尋ねた。
「あんた……ここに、何をしに来たんだ?」
「それは――アナタに会いに来たに、決まっておりますが」
姫君というほど、気品や艶を伴うわけでもない一般的な女。
無難としか言いようのない微笑みを浮かべ、座ったまま、黙り込む少年をしばらく見上げていたのだった。
自身の居室でありながら、立ち尽くしたままの少年に、陽炎はようやく、訪室の目的を語る。
「不躾で申し訳ありません。わたくしはただ、アナタにお礼と、お願いがあって参ったのです」
「……?」
怪訝な顔を崩さない少年にめげず、陽炎も微笑み続ける。
「アナタのおかげで、わたくしに長い間巣食っていた悪魔は、影も形も無くなりました。この二百年――誰にも不可能だった悪魔祓いを、アナタは成し遂げてくださったのです」
「……二百年?」
正座した体勢で両手をつき、陽炎が深々と頭を下げる。
「長い時でした。こうして、自らのことをお話しできる機会も、わたくしには長く許されませんでした」
「……」
陽炎はおそらく、何一つ嘘はついていない。それは少年にはわかったが。
「わたくしの話を、アナタはきいてくださいますか?」
「――……話、だって?」
それでも少年の内を占めるのは、至って単純な葛藤だけだった。
その葛藤が何処からくるのか、それがわからないことだけが、普段は平和に笑う金色の髪の少年の顔を険しくさせていた。
――……殺さなきゃ、いけないのに。
今この感情は、「銀色」でなくても明らかに少年自身のものだ。その必要を確実に感じておきながら、「銀色」がこの相手を見逃した理由。
――でも……殺しちゃ、いけない。
湧き上がる思いの根拠が、金色の髪の少年にはわからなかった。
殺したいほど警戒すべき相手であるのに、殺してはいけない鎖が自身を縛る。
戦う者としての強さも、現状を見極める直観も。金色の髪の少年よりも、「銀色」の方がいつも上回っている。しかし「銀色」が外に出る時、少年の体には必ず強い消耗が起こる。
「オレにはあんたと――話す理由はない」
だから外に出るタイミングも「銀色」は滅多に間違えない。どうしても必要であれば、最低限だけ手助けをする。
「でも……あんたが……」
だから今、「銀色」が全く姿を見せない理由。戦うべき時でないことだけは、少年にもわかる。
「……何か話をしたいなら。……勝手にすればいい」
厳しい顔でも、それだけ何とか口にした。
陽炎はずっと同じ無難な微笑みで、有難う、と口にしたのだった。
縁側に近いその居室内で。客人から可能な限り距離をとって座った少年を、塀の上から障子ごしに確認する人影があった。
「……これは……厄介、ですね」
薄青いシルエットの持ち主は、ただそれだけ、静かに呟いていた。
+++++
何故か、元悪魔憑きの姫君から今後の護衛を依頼された。まずもって軟弱な少年は、即座に断っていた。
その後の姫君は、新たな護衛と目的、行先が見つかるまで、頼也の厚意で花の御所に滞在するらしい。
「そうか。やはりお主には気が進まぬか」
それはわかり切っていたが、と、正座して文を書いている頼也が穏やかに笑う。
それでも陽炎のたっての希望で、少年の居室を教えていた頼也の元を、少年はその後に訪ねていた。
「ヨリヤ……あいつ。しばらく御所にいるって本当か?」
少年は別に、陽炎の訪室に文句があるわけではない。ただ陽炎が、このまま滞在することだけが、気になって仕方なかった。
「ここで追い出したりすれば、ますますわしも、お主の立場も、おそらくただでは済まぬよ?」
「…………」
「わしも後味が悪いしのう。やはり、悪魔祓いの件だけでなく、あふたーけあ。は大事だと思うのじゃよ」
ともすれば、陽炎を殺しかねない事態だった。平穏な花の御所が血で汚された暴挙の後で、行く当てのない姫を見捨てるような行動を、人のよい頼也がとれるわけもない。
ぐう。と俯いて座る少年も、それはわかっていた。
「……あいつ絶対……天女とかじゃないぞ」
陽炎は、自分はかつて天にいて、仕えた主が天を裏切ったという話を切々とした。しかし一通り聞いた後で、少年が得た結論はそれだ。一応伝えるために、頼也の元まで来た少年だった。
「ほほう。天女とはまた、言い得て妙じゃな」
あの客人を姫君と呼ぶことが、同じくしっくりこなかったらしい頼也は笑う。
「お主はどうして、そう思うのじゃ?」
「あいつ、ヨリヤやゲンジと全然似てない。梅が言ってた……ヨリヤかゲンジは、元々は天にいたヒトの家系だって」
ほう。と頼也は、少年が出した占い師の名と言葉に、面白そうな目をして少年を見返してきた。
「しかし、陽炎殿の話には、嘘は感じられなかったがのう?」
「……嘘は確かに……ついてないと思う」
それは少年も感じていた。それなら何故そう思うのか、自分でも不可解ではあった。
「確かにわしも、胸を斬られて生きていられるとは思えぬのう」
少年の前で頼也も、腕を組んで笑いつつ、不思議そうにする。
「と言っても、初めから心臓は外されていた。お主には何か意図があって、陽炎殿を生かしたようにしか思えないがのう」
「……へ?」
「お主が深追いをしなかったから、陽炎殿は生き延びたのではない。『銀色』には何か、陽炎殿を生かすべく考えがあったはずじゃよ」
「……何だ、そりゃ」
少年はてっきり、予想外に丈夫だった相手に、それ以上体力を消耗してまでとどめを刺すことを躊躇ったのかと思っていた。
しかし、最初から殺す気がなかったなら、それは――
「それじゃ、ヨリヤに迷惑かけるだけじゃないか」
思わず腹立たしげに呟く。頼也はまたも、おやおや。という顔で、穏やかに少年を見つめて笑った。
「殺すか生かすか。どちらかにしろと、お主は怒っておるのか?」
「……だって。生かすんだったら、傷付けることもないし」
逆に言えば、剣を振るうなら、殺す覚悟で臨むことが当たり前だ。
たとえ弱小の身でも、それが剣を持つ者の覚悟であると。
そんな少年に、頼也は困ったような顔で笑う。
「まるで――戦国を生きた兵のような覚悟じゃのう」
「……?」
「もう少し、肩の力を抜いても良いのじゃよ? 少なくとも、お主がここにおる限りはのう」
御所の管理者としての頼也は、書類仕事らしき文をしたためながら、少年に笑いかける。少年はキョトン、としながら頼也を見つめる。
「わしもこれまで、多くの敵を持って生きてきたが……敵でも協力し合えることもあれば、味方でも傷つけ合うこともあった」
それはヒトが生きる限り、不変の定めであると。頼也は少しだけ難しい顔で俯く。
「しかしお主のように、敵は全て斬り、味方には何事も負担をかけまいとするなら。お主はいつまでも、何処でも独りじゃよ?」
「――……」
その少年を最初に見た時から、頼也は何かを哀れんでいた。この世界では異端者である少年を、知っていたわけではないとしても。
元来、術師として感受性が強く、「淋しさ」に敏感だった頼也は、少年の根本的な欠損に無意識に気付いていたのかもしれない。
「お主は常に、ヒトより早く気が付き、また多くを感じておる」
「……?」
「だから何事も、自ら動き、すぐ対処しなければ気が済まないようじゃが……本当はそこまで、お主に余裕はないはずじゃよ」
頼也がこの少年を、引き受けると決めた大きな契機。
最初に頼也の子供に加勢し、「銀色」に変貌した後、少年は長く意識を失っていた。原因を調べるように依頼された頼也が来るまで、目を覚ますことはできなかった。それで頼也は少年に、袴の着用を勧めたのだ――少年の意識を保ち、命である剣を決して手放さないように。
戦う以前に、ただ生きることすら、本当は精一杯であるはずの旧い剣。その危うい孤高に自ら気が付いたのは、おそらく頼也だけだった。
だからその少年を、放っておいてはいけないのだと。
「誰が滞在しておるか、御所のことをお主が気にする必要はない。それでもあの姫君が気になるのなら、わしも注意しておこう」
「…………」
頼也の言葉は、ごく妥当であると納得している。
それでも何故か、しゅん……と、少年は気が塞いでいた。
「お主はそれ以上に、何が気にかかっておるのじゃ?」
楽しげに笑いかけた頼也に、少年はただ、ぼやくように言った。
「……オレも何か……ヨリヤやゲンジの、役に立ちたい」
少しだけでも、せめて、気が付いた範囲においてくらいは。そんな少年に、
「そんなこと、別に考えなくていいのじゃよ」
心から穏やかに、頼也は即答で微笑んでいたのだった。
_承:旅芸人一座「レスト」
寝不足が続いた少年の躰が、ようやく本調子となってきた頃だった。
「ねぇ、ユーオン。ちょっと相談していい……?」
想定外過ぎる妙な事態は、ある日突然少年を襲っていた。
「ツグミ? どうしたんだ?」
赤い髪の娘は日頃から凛として、若年ながら公卿の家の気品を窺わせる鋭さを持つ。しかしその日は、ひたすら何処か当惑気だった。
「『レスト』って実際……どんなところか、知ってる?」
「――へ?」
あくまで引きこもる少年を置いて、結局馴染みのメンバーで、鶫達はその旅芸人一座を再び観に行ったという。
そこで鶫達の顔を覚えていた花形の女から、公演の後でしっかり声をかけられ、何やら全員で茶店に連れ込まれたと語った。
帰って来たその足で、鶫は真っ先に少年の居室を訪れていた。
「いきなりうちの『咲姫』にならないかって誘われたんだけど……そんなのって、有り得ることなの?」
「――な」
驚愕の顔のまま、絶句した少年の正面で。僅かに伏し目がちに、肩に届くか届かないかの赤い髪をくるくるといじる鶫だった。
あまりに驚き過ぎて、声も出せなくなった少年は、そのまま鶫をくいくいと道場へ引っ張っていった。
「――絶対に駄目だ。有り得ない論外だ話にもならない」
剣の師――鶫の実父幻次は少年以上に動揺し、必死にそれを隠す硬い顔で、すぐそう却下していた。
「……」
鶫は困ったような顔付きで、うーんと俯きつつ、少しだけ恨めしげにしている。それが肝だとわかってはいたが、問答無用に鶫を父の前に連れていった少年を横目で見つめる。
「旅芸人一座なんてろくな奴らじゃない。いつ何処にいて何をするか、いつ帰るかもわからない奴らに大事な一人娘を託せるわけがない」
「……それは、父上の偏見だと思うわ」
むーと口を引き結びながら、冷静に懐から名刺を一枚取り出していた。実際に話されたスカウト内容について、改めてそこで説明する。
「今日はあくまで、ちょっと話を聞いただけで。少しでも私が興味があるなら、きちんと一座の活動について、ご両親を含めいつでも何処でも説明に来ますって、そう言ってたけど」
「――何だとぉ?」
幻次が受け取った名刺には、マネージャーらしき者の名前と、裏には花形の女からのメッセージが書かれていた。幻次は警戒に満ちた目を少しだけ丸くする。
――お嬢様に惚れちゃいました! 下さいなんて申しませんから、ジパング滞在の間だけでもお付き合いしたいです! 霖
筆致の整う直球なメッセージに、鶫自身、戸惑いの表情で呟く。
「私なんかよりもっと綺麗で上手いヒト、きっと一杯いると思うんだけど……」
「いや、この一座見る目だけは確かだ間違いない」
びしっと、まっとうな謙虚さを持った娘に、素早過ぎる親バカ反応をする父。
「ツグミは……レストに少しでも、興味あるのか?」
ようやく衝撃を消化してきた少年が口を開く。少年としては近づきたくない一座に、困惑の思いがとにかく強かった。
「……楽しそうだな、とは、ちょっと思うけど」
まっすぐ見つめる少年から目を逸らし、おそらく照れ隠しで不服気な赤い髪の娘だった。
強く動揺している幻次が、仕切り直しに咳払いをして、げほっと本気で咳込んでいた。
「この一座のこと、ユーオンは知ってるのか……?」
「……知り合いの知り合い、くらいには」
「そうか……ユーオンから見たらどうなんだ、こいつらは、実際」
硬過ぎる目つきと、目から上が暗黒に染まった顔。怯えを隠さず、座ったまま少年は後ずさる。
「いい奴らだけど……危ないと思う。ツグミにはぴったりだと思うけど、オレもどうかと思う……」
そんな矛盾した台詞だけ、辛うじて口にして返した。
勘の良さや、現状把握の力は極めて優れると、少年の特性を幻次は知っている。うんうん、と納得したように、実際はごごごと仏像のように硬く頷いていた。
逆に、少し緊張の緩んだ表情で鶫は少年の方を向く。
「合ってると思う? 私に、こういうのって」
「うん。それはもう、まず間違いないと思う」
全く正直な気持ちを、飾ることなく口にする。そっか、と僅かに微笑んだ鶫を前に、
「ユーオンてめえ。どっちの味方だこのヤロウ」
幻次はその首根っこをあっさりと掴み、そのまま立ち上がった。
「その一座の所まで案内しやがれ。ヒトの大事な娘を誑かすふてぇヤロウは――俺が直接引導を渡してやる」
「ちょっと――父上……」
まるで猫のように軽々と少年を持ち上げた幻次は、最早鶫の声は聞こえていないかのように前だけを見ていた。
「……えっと。……行ってきます、ツグミ」
「バカ、私も行くわよ!」
少年を肩に担ぎ直し、無言で先に進む幻次の背で、困ったように少年は笑うしかない。ごくまっとうな感覚を持った娘は、父の暴走を止めるべく後に続くのだった。
基本的に。この一座とは、関わりたくなかったのに……と暗い面持ちの少年の前で、少年達を出迎えた一座の花形は、心からまず嬉しげに笑った。
「うわぁ、来てくれたんだ、イーレンちゃんのそっくりさんと、ジパングらぶりーな小鳥ちゃん!」
花形が二人存在しているこの芸人一座は、外回りと内回りと称する、二つの見世物を中心にしている。軽業を中心とした青空下の舞台と、きちんとした場を借りる本格的な芝居舞台を主に手掛けるらしい。
現在、赤い髪の娘に声をかけたもう一人の花形は外回り中であると、内回りが中心らしい幼げな花形が言い、妙な呼称に戸惑う鶫に抱き着いていた。
「って――……この名刺の奴も、今はいないのか?」
幼げな花形のあまりの毒気無さに、幻次は勢いを削がれたらしい。少年を下ろし、頭を抱えながら尋ねる。
「マネージャーのスカイちゃんはもうすぐ帰ってくると思うよぅ。霖は夜まで予定があるけど、良かったら入って、入ってぇ♪」
一座が滞在している川辺のテントに、幼げな花形は躊躇なく、そこで待つようにと一行を誘う。
突然現れた、不穏さしかない顔付きのガタイのいい侍に、あくまで歓迎の眼差しを向ける花形の笑顔。少年と幻次は、互いに目を丸くしながら顔を見合わせるのだった。
「……」
じろりと川辺で、少年を見ていた護衛の人形が、幻次の仲間たる吸血鬼に瓜二つなことに気付く余裕もなく、そこで誘いを受けた剣の師だった。
花形二人の専用楽屋であるという、舞台衣装と装身具が沢山置かれたテント内で。鶫に声をかけた外回りの花形と、この一座のマネージャーを待つ間、落ち着かない体で少年と幻次は地面の敷物に座っていた。
「小鳥ちゃんはどんなお洋服が好きぃ? 何か着てみない?」
「ううん……あまり着物以外、着たことがなくて」
「えぇー。何でも似合いそうなのに、もったいなぁい♪」
内回り中心という幼げな花形は、ひたすら赤い髪の娘が気になるようだった。
そんな一方的に賑やかな少女陣を横目に、幻次は少年に、こそこそと現状の確認をする。
「……あの子は何なんだ、ユーオン」
「えっと……この一座の花形の一人ってことしか、オレは……」
困ったような顔で、それだけ少年が返した――その時だった。
「ルンは、我がレストのロリっこ担当。広い範囲のお兄さんの客寄せに、一役買ってもらっているのです」
すっ、と。テントの覆いを開けて、中に入ってきた黒い人影。
「老若男女、いずれの世代にも受け入れてもらうことを目指した我がレストでは、小鳥のお嬢様のような正統派かつ不滅の、ツンデレ素材を必要としているのです」
にこにこと、その二十代前半にしか見えない黒っぽい女が、流暢に口上を述べながら近付いてくる。長い黒髪を高い位置で一つに括り、黒の上衣と手袋を着けて、腰元に長剣を下げて場に現れていた。
「……は?」
「???」
一見大人しげな黒い女が、見た目によらない軽い声色で言った業界用語の数々。まずあまり理解できなかった幻次と少年は、ただ呆気にとられる。
「どうも、お初にお目にかかります。レスト千族マネージャー、スカイ・S・レーテと申します」
へ。と更に言葉を失う少年達の横で、現れたマネージャーへと幼げな花形が振り返った。
「千族で専属! スカイちゃん、相変わらずうまいねぇ♪」
ともすればただの親父ギャグに、本気で喜んでいる風の幼げな花形を、黒い女――スカイはよしよしと撫で回している。
「うちのレストは、私のような行き場なき千族保護も兼ねた、旅芸人一座なのですよ。お宅のお嬢様には当然ながら、保護は必要ないので、純粋にスカウトのお話をしたいわけですが」
「……は?」
マネージャーというイメージからは大きく離れた、清楚風なまっすぐの黒髪のスカイ。黒い衣の上に着ける、膝までのつなぎ服が揺れて、口調と身振りは営業そのものの軽妙な女に幻次が呆気にとられている。
横で少年は、何故か唐突に激しい悪寒に襲われた。その黒い女の全身像に、強い吐き気と眩暈を覚え、思わず胸をぐっと掴んだ。
そのため幻次と同じように、黒い女に咄嗟に反応できなかった。
黙り込んでしまった少年と幻次の前で、スカイは視線が合うように改めて正座し、幻次にまずぺこりと頭を下げていた。
「ま、千族と言ってもあまりに遠縁の私は弱小そのものでして。どうぞご警戒なきよう、お願い致します」
「……あぁ?」
そこでやっと、呆れたような声を幻次が絞り出す。
「ヒトの大事な一人娘に、突然妙な話を持ちかけておいて――警戒するなと言う方がおかしいだろ」
ふむふむ、とスカイは、両腕を組んで何度も頷く。
「ご尤もです。私が言うのも何ですが、信用しろという方が、無理のある話だと重々思います」
あくまでにこやかに、幻次にまっすぐ対座するスカイに、隣で少年はただひたすら胸を掴む。
スカイと話している幻次も、幼げな花形に未だ付き纏われる鶫も、息を詰まらせる少年の異変にすぐには気付かなかった。
「――え?」
ただ、パタ――と。座っていた体勢から、そのまま横向きに倒れた少年に、場にいた全員がそこで同時に振り返った。
「ユーオン!?」
全身に冷や汗が溢れ、苦しい息遣いで横たわる少年の髪は、何故か自然に、そのまま銀色へと変貌していたのだった。
突然倒れた少年を心配し、呼びかける者の声も全く届かなかった。
ただその強い痛みが、銀色の髪の少年にこだまし続けていた。
――あなたのせいよ……。
これまで何度も、少年を襲うことのあった赤い光景。
とっくに慣れていたはずの夢。それでも銀色の髪の少年だけが、その全容を把握していた――誰かの強い痛みと怨念の嘆き。
何故その黒い女が、少年にそれを突き付けるのか。今まで一目も見たことがない、それだけは確信を持てる相手なのに。
しかし確かに黒い女は、金色の髪の少年には対抗できない、確かな脅威を以ってそこに在った。
黒い女が言う通り、どれだけ弱小な存在であったとしても。
正直な話。それは、おそらく。
銀色の髪の少年にも、歯が立たない相手だった。
「それなら……忘れてしまえば、いいと思うよ?」
何故か最後に、ある誰かに似た声が、少年は聞こえた気がした。
+++++
眠ったままで金色の髪に戻った少年が、ようやくその目を開けた時には、しばらくの時間がたっていたようだった。
「あぁー! 起きたよ小鳥ちゃん、小鳥ちゃんのおじさーん!」
心配げに少年の様子を窺っていた幼げな花形が、少年の意識が戻ったことを、円形に座る者達に慌てて伝えていた。
「ユーオン、大丈夫!?」
真っ先に駆けつけた赤い髪の娘を、少年は不思議そうに見る。
「……あれ? ……ツグミ……?」
まだ頭がぼやけたような少年が、それでもただ一つ。すぐに大きく気になったことがあった。
「何で――……そんなに、怒ってるの?」
「バカ! 何時間眠ってたと思ってるのよ!」
そして鶫は、珍しく申し訳なさそうな顔で、その後すぐに目を伏せていた。
「多分、この間に使った呪いがまだ、続いたままだったんだわ……『自重』させてた『銀色』が無理に出ようとして、大きな負担になっちゃったんだと思う」
その解除を忘れていた、と辛そうな目で俯いた鶫。何とか上半身をゆっくり起こした少年は、何で? と、困った気分で穏やかに笑った。
「そっか。最近銀が出なかったのは、そのおかげだったんだ」
それはむしろ、有り難かった。相変わらず平和な声色で口にする。
「そこまでして、無理に出ようとする銀が悪いだろ。ごめん、ツグミに気を遣わせて」
まだ少しだけ痛みの残る胸をさすりながら、心からの思いで、淡々と少年は口にしていた。
「――ったく。ようやく起きたか、ちゃんと金色で」
少年が倒れていた間、幻次は長々と、一座のマネージャーに加えて帰って来た外回りの花形と話していたらしい。一度話を切り上げ、目を覚ました少年の方へやってきていた。
「そこまでさっき、銀が出る必要あったのか?」
「……全然。何でそうなったのか、オレにもさっぱり」
不可解気な幻次に、少年も全く同意で頷く。
「大丈夫? 今、ルンとスカイがお水を取りにいってくれたわ」
師の後ろで、外回りの黒髪の花形が心配そうな目でしゃがみこんでいた。しゅん、と親身に心配している姿に、複雑な心情になった少年は思わず目をそらしていた。
「えっと……話はついたのか? ゲンジ」
そもそも彼らがここへ来た理由を思い出した。難しい顔の幻次を見つめて当惑気に尋ねた少年に、
「いや。今から十五歳以上限定で、飲みにいくことになった」
「――は?」
至ってあっさり、幻次はそんな返答をする。一応十五歳というふれこみだった少年も数に入れられている。
呆れるように溜息をつく鶫は、十四歳だから帰るように、と言われたらしい。そのようなわけのわからない展開が少年を待ち受けていたのだった。
「えっと……何で、こんなことに?」
元々食がかなり拙い少年は、当然飲酒など全く未経験だった。
そもそも成人前に飲み屋に連れていかれること自体、否定されるべき事柄だったが。
「君も大変だねぇ。倒れて目が覚めたばっかりだって言うのに、まさか飲みに連れていかれるなんて」
にこにこと、少年の対面に座るスカイが楽しげに笑う。
「女とだけ飲みに行くなんて、下手したら誤解されるだろう」
そこに少年を連れてきた理由を、既婚者である幻次は事も無く明かす。
そうして、少年、幻次、黒髪の花形、スカイと。丸い机を四人で囲む謎の事態に、ひたすら呆気にとられる少年だった。
「ゴメンね。もうちょっとだけ、今夜は付き合ってね」
「…………」
明るく苦笑しながら、一番まっとうな声をかけてくれる黒髪の花形――霖。しかしそれこそが一番複雑な相手で、何も返せず、少年はただ黙り込む。
少年が倒れている傍らで、赤い髪の娘のスカウトについて、ひたすら師らは話していたという。
究極は座の一員として旅に加わってほしいが、そうでなくても、現地座員のようなメンバーもその座には多々存在し、ジパング来演時だけでも良いので参加しないか、ということだった。
「気が向いた時にひょっこりやって来て、臨時花形をしていく『咲姫』すらいるのよ。うちは最大五人の『咲姫』を置く形式だから、今は本当に可愛い女のコが足りてないの」
霖は戸惑う鶫の手を愛しげに握り、そう力説したという。
「お嬢様はどうやら、並ならぬ身のこなしと旅への適性。また、芸の素養も持たれたご身分とお見受けします」
「そうなのよ。スカイの目はいつも確かだし、何より貴女……とてもいいコそうなんだもの」
にこにこと爽やかな笑顔の霖は、それがまさに本意とばかり、鶫を見つめるのだった。
少なくとも霖は、赤い髪の娘を本気で気に入ったらしいことは、鶫にもその父にも嫌でも伝わっていた。
結局の所、一座を信頼する根拠が無い、と頑なに娘から手を引けと言い張る幻次に対し、
「まーまー。ここはお酒でも飲んで、腹を割って話し合いましょー」
そんなことを言い出したスカイが、本当に熱燗を用意させた。一度飲んでしまうと、それだけでは物足りなくなったといい、勢いで決まった現在の状況だった。
「……で……」
そして少年はその後、スカウトの話の続きなど全く出ない、わけのわからない現状に首を傾げる。
「あんたら……何しにここに来たんだ?」
既に場は、酔った幻次の娘語りと、霖の愚痴に占められていた。
「大体ねぇ、内回りがある時くらいは外回りを少なくしたらいいのに。こんな夜まで働いた後で、内回りの練習もしろって、鬼でしょう、鬼! 私は癒しが欲しいの、可愛い癒しが!」
「違ぇねぇ。そりゃー花形さんも大変だな。うちの娘は確実に癒しになるけど、あのもう一人の花形さんじゃ駄目なのか?」
「あのコは完全、男性向けなの! 可愛いから許される的な、そんなお姫様はお呼びじゃないの! せめてもう少しだけでも、営業や調整を手伝ってくれたらいいのに……」
どうやら花形の女同士は、少なくとも霖の方からは、複雑な思いがあるようだった。
「まぁまぁ。霖は芸事だけでなく、仕事もできる女性ですから」
「そんなこと言っても、私だってまだ十八歳だし……色々してたら、肝心の芸はルンには全然敵わないし。そもそも私、スカイはお色気担当なんて言うけど、絶対そんなキャラじゃないし……」
つまり確実に、未成年でかぱかぱと酒瓶をあけている霖は、ケープの下の常に露出の多い恰好は本意ではないらしい。
「かと言って、小鳥ちゃんみたいに凛とした良さがあるわけじゃないし……わかってるのよ、私みたいに地味な女は、カラダを売りにするしかないってことは……」
段々と霖の周囲の空気が重苦しくなる。そして更に、スカイが面白げに場を煽る。
「霖。貴女から地味をとったら何が残るとゆーのです」
「うう――もういっそ、咲姫も降板させてくれたらいいのに。私がナナハ様直属だからって、みんな気を使ってるだけなのよ」
「霖は一番、レストの古株なんですから。当然でしょ?」
「そうよ、実力じゃなくて単に年功序列なのよ。みんな本当はルンや小鳥ちゃんみたく、若くて可愛いコを求めているのよ」
おーい……と置いてけぼりの幻次に、そこでようやく霖は、きっと涙混じりの視線を向けた。
「可愛い娘さんがいていいわね。何この赤い髪、キレイ過ぎ? 小鳥ちゃんてば貴男と奥様のいいとこどり? 反則じゃない?」
「あんた……若いのに、苦労してんな……」
「よしてよ、同情はいらないわ。男なんてみんな、可愛い若いコが好きなんでしょう」
「いや。俺の連れも、黒髪で大人しめだけど……充分過ぎるほど可愛いし、あんたもあんたの良さがあると思うけどな」
「慰めはよして! 妻帯者のくせに何よ、卑怯よそんなの!」
気が付けば飲み屋の外の天気は、霖の心情を表すように、突然の豪雨によって真っ暗に変貌していたのだった。
「…………」
ちみちみと、幻次から渡された盃を少しずつあけながら、少年は黙って成り行きを見守っていた。
「酒って……効率は、いいのかな?」
食物とは違う純粋なエネルギー源。その本来の効用も知らず、段々と顔を赤くし、ふらふらしつつ、何故か気分は悪くなかった
「イーレン君。アレ、放ってていいの?」
そしてスカイの声も聞こえず、気付けば再び意識を失ったのだった。
+++++
にわか豪雨が過ぎ去った後で、唐突な飲み会はお開きとなっていた。
行きの道とは違い、幻次に背負われていた形で、ぶるっと寒気を感じた少年は目を覚ますことになった。
「……あれ? 今――……どこ?」
「ばかヤロウ。知らない間に、熱燗三本あけてんじゃねぇよ、未成年のくせに」
それを同伴した張本人は、肩に頭を乗せた少年に悪びれもせずに笑いかけた。
「……話……どうなった……?」
まだ頭がぽけーっとし、急に心細くなって首にしがみついた。
昔に、昼間は眠ることが多かった吸血鬼の少年を、幻次はよく同じように背負って歩かされたらしい。懐かしげに笑う心が伝わってきた。
「あの花形さんの勢いに押し切られたよ。ジパングにいる間、一公演だけでもって、承諾させられちまった」
「あいつ……よっぽどツグミのこと、気にいったのか……?」
なんで……? と背中で首を傾げると、幻次は言う。
「ユーオンを手の平の上で転がしながら、全く出しゃばらずに慎ましい鶫が、初対面から気になってたらしいぞ」
――は? と少年はまさに固まる。その旅する花形の真意を慮るように、幻次も難しい顔をする。
「多分、ある程度強い者じゃなきゃ、一座には誘えないってことじゃないか? あの花形さんも、単なる人間じゃなさそうだ」
「それは……知ってた、けど……」
少年はまだ、くらくらふわふわとまとまらない頭で、急な雨で濡れた町並みを見回してみた。
「ツグミなら負けないと思うけど……でも、心配だな……」
不穏事に近づく赤い髪の娘への強い懸念。小さくも真剣な声色で呟いていた。
「ばか野郎。ユーオンが二十四時間体制で、専属で護衛するに決まってんじゃねぇか」
「……へ?」
「それが最低条件だ。鶫に悪い虫、つかせたら承知しねーぞ」
既に一座のジパング滞在は始まっている。今回は外回りの活動だけでなく、きちんとした舞台も行うために、連日公演先の建物で目下稽古中ということだった。飛び入りの鶫には特に、泊まり込みで急ピッチで演目を覚えてほしい、その間は自分が責任を持って娘を預かる、と霖は硬く誓ったという。
「少なくとも三日に一度は、家に帰すと約束するっつー話だったが。いきなりそんな、娘を一人で下宿させろと言われたってな」
「ってことは……ゲンジ……」
「ユーオンも鶫と、花形さんの所に泊まり込みだ。花形さんも二つ返事で、それがいいって了承してたぞ」
「……――……」
それでなくても関わりを避けていた一座との、思ってもみない試練。動揺を超えて少年は、何故か全身が熱くなった。
「了解……にょろ……」
そこで謎の語尾を口にした自分にも気付かず、深く頷いたのだった。
+++++
「花の御所」は、四季を通して風流な庭木が評判故の名前の御所だ。
最初に招かれた紅葉の季節とは違い、常緑樹以外はすっかり葉を落とす季節となったことに、少年はふと気が付いていた。
「そう言えば……もう、三カ月くらいになるのか」
発端を思い起こせば、ある秋の朝、目を覚ますと周囲には誰もいなかった。
しばらく出かけてきます。留守をよろしくね。その二言だけ残された状態で、少なくともその後一週間、何の音沙汰もなかった。
それなら良し、と少年はある目的を一つ思い立った。
記憶の無い少年の名を引き出した占い師を、一人で訪ねてみようとその家を後にしたわけだった。
旧知の占い師の元へ、養父母が最初に少年を連れていった時のことだ。
――お主……非常に変わった様相をしておるな?
占い師はともすれば、翠に光る妖しげな目線で、あまりにあっさり尋ねてきていた。
――名は?
身元不明の少年の、素性を占ってもらうためにそこに行ったというのに、少年はそこで、自ら簡単にその答を拾っていた。
「ゆ……おん?」
「そうじゃろ。お主、ゆ・おんじゃろ」
詐欺じゃないか。とそこでは思ったのだが、そうして催眠のように、少年自身から古い名前を引き出した占い師だった。
「……知りたかった名前とは、違う気がするけど」
それでもその名で、確かに間違いはない。それだけはわかった少年は、あっさり自らの名を受け入れていた。
ただしそこで、自身をユオンと思った少年とは違い、周囲はユーオンと少年を呼ぶようになる。
「――ユオン! しばらく留守にするって本当か?」
「あ――……ジュン」
今や、少年をユオンと呼ぶのは、道場の方から駆けてきたこの兄弟子くらいだった。
それもひとえに、蒼潤という名を少年が略すので、蒼潤も少年の名を微妙に略しただけの話だ。基本的にユーオンと、現在の少年は周囲から認められていた。
「でも、三日に一度は帰ってくるんだよね?」
蒼潤について現れた弟の悠夜も、おずおずと尋ねてくる。冷静ではあるものの、少年がこの御所にいる――「帰る」ことを当然と考えているらしき二人に、少年は知らず顔を綻ばせる。
「ツグミのお供だから、今までと似たようなものだと思うけど。元々オレ、ツグミの所の居候だし」
「幻次さんも随分心配してるんだな。でも少なくとも、京都かその近くでやってるんだろ?」
その距離での下宿に、二十四時間体制のお供。護衛としては弱小過ぎる少年は、それはお供だ、と自分で言い張っていたのだった。
「早いよね。もうユーオン君に会ってから季節が一つ過ぎて、年も明けたんだよね」
「寒くなったけど、ユオンのあの羽織物じゃ目立つと思うぞ。すみれさんが後で、出る前に自分の所に来いと言われていた」
「そうなのか? 何の用だろ?」
すっかり袴姿に慣れたが、袖がない黒衣を基本着とする少年は、暑さや寒さには鈍い方だ。それでも稀に外出する時や、冷え込んだ時は、少年達が初めて出会った時――少年が占い師を探して単独で遠出した時に羽織った、厚手のケープを身に着けていた。
今ではもう、養父母が帰るまでは御所にいてもいいか。そう思えて、家に帰る時までは、と襖の奥にしまってあった。
「あれからは特に、変な人形が襲ってくることもなかったしな。本当、何だったんだろうな? あの人形達は」
その時に複数の人形に弟を集中して狙われ、苦戦することになった蒼潤は、今でもリベンジを目論んでいる様子だった。
「人形師が操ってるにしては、個々の動きが細か過ぎたし……それぞれの意志で、僕達を襲ったようにも見えましたよね」
「でも、死霊とかそういうのが憑いた人形でもないんだろ?」
それなら術師たる弟にはわかるはずだ、と蒼潤は両腕を組んで悩んでいる。
「兄様の言われる通り、死んだ人間という感じではなくて。依童――普通なら、霊を降ろすための人形ではあったけど」
「……」
その出会いの時は「銀色」が関わった時間が多い。今の金色の髪の少年は何も言えず、黙って成り行きを眺めていた。
「ねぇ。ユーオン君がこの間壊した、侍従の人形は……あれは何だったのかとかはわからないの?」
それも「銀色」の仕事ではあった。それでも、最初よりはもう少し状況を把握していた部分を、少年は素直に答えた。
「あれも、人間って感じじゃ、なかったと思う。多分何かの千族……それこそ『悪魔』が、動かしてたんじゃないかな」
「――え?」
そこで逆に、術師の悠夜は意外そうな顔をした。まるで少年が、そこまで把握していたことが想定外と言わんばかりに。
「もし最初の人形と、ユウヤ達から見て同じだったなら。最初の奴らも、もしかしたら『悪魔憑き』だったのかもしれない」
「魔」に堕ちた何かという、悪魔の定義を教えてくれたのは悠夜だ。それを把握したことにより、少年は、観えていたものが何かを伝えられただけだが、それで逆に悠夜の所感もまとまったらしい。
「じゃあ……死霊というよりは、一つ一つ全てが、何か目的を持った悪魔に動かされてたのかもしれないね……」
身近な現状把握に特化した少年と、心霊という存在に鋭い霊感を持つ悠夜。その力を合わせれば、そうして容易く真実の一端に辿り着いていた。
「動かされてるというより、ほんとに憑いてる感じだった――多分、自分の身体は持ってない悪魔なんじゃないかな」
それは没した人間を指す「死霊」よりも、ただ「魔」であると。身体を失った程度では、「力」も意志も明確に残し得るしつこい存在に、顔を顰めながら呟いた少年だった。
それなら……と。悠夜はその父によく似た黒の、日頃はあえて封じた鋭い感性を持つ目に痛みを浮かべる。
「何が欲しかったんだろう……その悪魔達は」
特に契約のために召喚されない限り、生半可なことでは、「悪魔」は人間に関わることはない。そうした相手の不穏さを、しっかり感じたようだった。
「死んでも何かに乗り移ってまで。悪魔であろうと、確かに相当の執念だよな、それは」
うんうん、と頷く蒼潤の前で、少年も青みを帯びた紫の目を軽く澱ませる。
「…………」
今ここに在る少年にも、確かに理由があったはずだった。
この躰で目を覚ました時から少年にはわかっていた。その理由に出会うことがあれば、少なくとも「銀色」は見逃さないと。
それでも後数か月で、少年が養父母に拾われて一年になる。その間何一つ、自分がここにいる理由に出会えなかった。
他にも大切なものは増えた。けれどどうしても、現状はこれでよいのか、自身の存在の理由をないがしろにしている気がしてならなかった。
「なぁ――ユウヤ」
難解な問いになるとは承知しつつ、珍しく少年は自ら口に出した。
「何がほしいのか、自分でもわからない時……それを見つける方法って、何かあるのかな?」
それは常に――たとえ記憶があったとしても、この少年には元々わかり辛いものだ。周囲と己の境が曖昧な直観の副作用、それを自身で知るわけではなくても。
「ユーオン君……」
神妙に聞いた少年に、敏い悠夜は少し躊躇いを見せていた。
「……そういう漠然としたのは……目的ある占いでもなくて。ただ、霊感を持ったようなヒト――その方が、何となくわかると思うよ」
この少年に小手先の返答は通用しない。それを知る悠夜が考え込む。
「ユーオン君みたいな直観でもなくて。誰かの存在や願い、心霊……無意識を見てしまえるのは、霊感くらいだと思う」
だから、と、困った風な、それでも安堵した顔で悠夜は微笑んでいた。
「根拠は全然ないことだけど。僕は――ユーオン君はそう遠くない内に、待ってるヒトに会えると思うよ」
「……――」
「ヒトかどうかも、本当はわからないけど。でも……向こうも、ユーオン君を探してる気がする。だから――」
心配はないよ、と。そう断言する、幼いながら神童と言われた悠夜だった。
そうして、その父の頼也とよく似た優しい目で微笑む。
「…………ありがとう」
何故かごく僅かに、胸をちくりと刺された気がした。頼也に会った時と同じ懼れを抱えながら、少年は礼を口にした。
この優し過ぎる場所に迷い込んだ異端者。それを責める涼やかな声が、いつまでも少年の脳裏に響き渡っていた。
+++++
蒼潤に言われていた通り、自分を呼んだという師の奥方の所へ顔を出した後で。
「あれ――……ユーオン?」
これまでとは違う風貌で玄関へ出て来た少年を、赤い髪の娘が面白そうに出迎えていた。
「どうしたの? 袴だけじゃなくて、今度は着物まで袖を通すなんて」
「……寒いだろうからって。スミレさんが、着付けてくれた」
当初はスミレ、と不遜にも人妻を呼び捨てにした少年には、すみれをすみれと呼んでいいのは俺だけだ! と幻次からきつい拳骨がお見舞いされた。その後少年が唯一「さん」付けで呼ぶ女性は、少年を御所に引き取った頼也の実姉でもあった。
「似合ってるわよ。さすが母上、シンプルだけど質のいい生地ね」
「ツグミの隣で歩くなら、変な恰好するなって怒られた」
黒衣の上に重ねて着せられた、裾の短い白の街着。蒼潤が千切ってしまう気持ちがわかる、ゆったりの袖が少年は不服だった。
「これじゃ動きにくいって言ったら、オレは下手に動くなって言われた。スミレさんってどうして、ヨリヤよりあんなに厳しいんだ?」
それはばっさり、少年の目下最大の難問を、絶対服従の強制力たり得る念の強さで言う女性の声だった。
――お主のような、動くだけで命を削る外法はもっての他じゃ。もう少し違う戦い方を身につけられよ。
実の娘はそれに対して、身も蓋もない感想を続ける。
「仕方ないわよ。剣もダメ、体術もダメのユーオンの唯一の特技と言ったら、あの変な白い光くらいじゃない。あれはそうそう、使っちゃ駄目だと思うわ」
「変とかヒドイな。オレには命がけなのに」
その光とは、「銀色」が出る時には特に強まる異端の「力」だ。少年の持つ剣を青銀に染め、「悪魔憑き」人形を一太刀で崩壊させた、何かの攻撃に纏わせるタイプの謎の「力」だった。
「だって、物には全然通じないのに、『力』ならほぼどんな相手でも浸食しちゃうなんて、反則じゃない?」
「力」と一口にいっても、その種類は本当に多様だ。原材料たる魔力や霊力、気や理を始めとし、「力」を紡ぐ術は陰陽術や呪術などの魔道、または体質による特技など、この世界では様々な生成法と結果が存在している。
その相性や様式に縛られず、ともすれば全ての「力」を無効にできる可能性を持つのが、少年の謎の白い光らしかった。
「あれを使う度にユーオン、死にそうになるんだから。母上の言う通りよ、何か違う方法を探さないと」
「……」
そのため先日の刃傷沙汰の後、少年は一週間以上眠り続けた。あまりに弱小な自身の唯一の切り札は、簡単に使えないのも確かだった。
何かとそうして、一般的な感覚からずれたお供を横に、沢山のテントが張られた川辺へ、赤い髪の娘は辿り着いていた。
「きゃぁぁ! 小鳥ちゃんてば、本当に来てくれたの……!?」
ここまで話を運んでおいて、それでも半信半疑だったらしい霖が、鶫の姿に気付いて歓喜の声をあげる。僅かに緊張の顔をする少年には目もくれずに、鶫の方へと駆けつけてきた。
「あ、えっと……すみません、よろしくお願いします」
「いいの、いいの! 他人行儀は一切なしで! 何かあったら、いつでも私に遠慮なく言って! もしくはスカイをこき使う!」
霖は余程嬉しいのか、呆気にとられる鶫の手を強く握る。胸元で大きく揺れる蝶型のペンダントも気にせず、ぶんぶんとその手を振り回していた。
「えっと……」
そして少年は他にも、おかしな存在に気が付く。
「……何でいるの? クヌギ」
「――あれ? ユーオン君だ」
堤防に座り、この一座の護衛とマネージャーと、にこにこと当たり前のように気軽に話をしている人影。
鶫の友人で、蒼潤には従弟にあたる槶。西の大陸で見られる洋服を着て、帽子のよく似合う友人は、隣に座る人形の護衛と傍らに立つスカイの間で楽しげにこちらを見たのだった。
「凄いんだよ! リタンさんはアラス君と本当そっくりだし、スカイさんは知り合いが僕の友達かもしれないって言うんだ!」
「……はぇ」
「僕も何か、スカイさんと初めて会った気がしないんだけど! ――って全然、見たことも喋ったこともない人だけど!」
楽しげな槶を前に、少年は難しい顔で護衛とマネージャーを見つめる。
同じように難しい顔の人形の護衛と、楽しげなマネージャーの黒い女も少年に視線を返す。
「槶君はいいコだねぇ、騙しやすそうだねぇ。丁度いいから、君もレストで働かないかい?」
「ええっ? でも僕、大したことはできないけど?」
「そんなことはない。作家から演出家、下働きから介護士まで、ありとあらゆる職種を求めているんだよ、我がレストでは」
「……何か最後らへん、変なの混じってなかった? スカイさん」
妙に楽しげな槶とスカイとは裏腹に、少年と護衛はただ、黙ってしばらく睨み合っていた。
「……」
しかしそれも、護衛が最初に口を開くまでの短い間だった。
「……海底らしいです」
「――は?」
「精妖刃が買ったその古い剣は、東の大陸の海底遺跡からの発掘品だと、スカイが言っていました」
何故か淡々と、護衛は唐突に、無表情にそんなことを口にした。
「……私の主が、その仲間の、アナタが滞在する御所の公家と、話したところによりますと」
「――?」
「その剣に宿る何かの力が、アナタを動かし――今のアナタの、意識を保っている源のようですね」
「…………」
それは……と。少年は、困ったように首を傾げた。
「知ってたけど――……あんたやあんたの主は、そんなことを聞いてどうするんだ?」
簡単に言われてしまったものの、それはこの、呪われた生を受けた少年に関わる深い真実。
少年は最早、その剣がなければ生きることができない。袴に下げる黒い柄を知らず、ぎゅっと握りしめた。
「……」
人形の護衛は黙り込むが、何故か互いに警戒は緩んだ状態でもあった。
「……リンじゃないんだな。あんたの言っている『主』は」
「彼女は雇い主です。私の宿主になれるような力の持ち主は、ここ数百年は、黒の守護者くらいでしょうね」
その宿主。「水」の力を司る「守護者」の色が黒だと、少年は後に知る。
「でも――リンがいれば、あんたは強くなれるんじゃないか?」
同じ「水」の力を冠する黒い柄の剣。それを持つ少年は淡々と尋ねる。
「それでアナタは、私を警戒しているのですね」
「……」
「アナタの思う通り、霖はアナタの剣を、今でも確かに欲しいようですよ」
少年が護衛を警戒する理由。もしもその黒髪の花形が、この護衛に命じて力ずくで少年の剣を奪おうとすれば、それは少年の終わりを意味する事態だった。
「それでも……」
少しだけ呆れたように、護衛は横目で少年を見つめる。
「私と霖以上に、アナタには警戒すべき相手がいますけどね」
記憶の無い少年のルーツを、わざわざ情報を与えた護衛の意図の一端。
人形の主が巻き込まれていた事態を、話すことはできなくても、少年はいずれそれに深く関わるはずだった。その僅かな因縁に、憐れみと共に口にしていた。
気が付けば槶とスカイは、賑やかになり出した花形達のいる方向へ戻っていた。二人だけで堤防に座っていた少年と護衛の人形だった。
「警戒って……?」
少年にとっては、この人形は一座の護衛でしかない。
だからここで警戒すべき者は、謎のマネージャーと花形だけ。
「ここでの話ではありません。二百年以上前の、黒の守護者を殺した者の側近が、今、アナタの近くにはいるはずなのです」
「――え」
「この身は現在の黒の守護者と前代の黒の守護者の、両方の魂に仕えた経緯があります。そして――その宿主達の記憶も、多少なりと把握しています」
二代に渡り、黒の守護者の運命に関わることになった古き「力」。
無愛想な見た目によらず、「力」は本来畑違いだった宿主達に深い思い入れを有していた。そして今また動き出した宿主の運命に、自らの意思で関わると決め、久々に人形という実体に宿ってまで、現世に介入する気になった強大な「力」だった。
一方で、人が集まっている中心地が賑やかになっていた。
ひとまず何か、現在できる芸があれば、と赤い髪の娘が求められていた。公卿の家の娘として、適当に嗜んでいた舞の一つを軽く披露している。
「やばい! 小鳥ちゃん超やばい! 激かわいい!!」
それを見て霖のテンションが上がる一方だった。騒ぎの頭上で、もくもくとどす黒い雲が誰の目にも明らかに広がっていた。
「霖―、ごめぇん、ちょっと抑えてぇ。このままじゃ大雨降っちゃうよ、げりら豪雨来ちゃうよぉ、それは困るよぉー」
「それもまた一興かと。しかしこれなら、明日からでも鶫さん、外回りもお願いできそうですね?」
「ええっ!? 鶫ちゃん凄い、頑張れー!」
こちらも暗くなってきた空の下で、氾濫すれば洒落にならないだろう川を前に、少年は怪訝な顔で護衛を見つめる。
「守護者を殺した奴の……側近?」
「彼女が何と名乗っているかは知りませんが。あれは確かに、前代の黒の守護者の顔見知りであり、更に前代の守護者を殺した悪魔のそばにいた女です」
そこで少年の脳裏で、ようやくこの人形と、少年の現在の大切な居場所が繋がっていた。
――わたくしの主は、共に育った自らの従兄と妹を手にかけるほどの、悪しき『魔』へ変貌してしまったのです。
天女を名乗る陽炎はそう話していた。その時殺された者が、前々代の黒の守護者。護衛はそれを言いたいのだと伝わる。
「って……」
それでも少年は、それを言い出した人形の意図が全くわからなかった。
「オレに……何の、関係があるのさ?」
少年はあくまで、天の民や守護者など、この京都に来るまでは全く関わりを持った覚えがない。目前の人形と同じように、畑違いの存在であるはずだったが……しかし人形の護衛は言う。
「彼女はアナタが、欲しいのではないですか?」
アナタは、わたくしの主と何処となく似ています。だからこそ護衛を依頼してきた陽炎の言を思い出した。
「彼女にはほぼ力はありませんが、意思の強さに関しては、どうやらアナタの比ではなさそうです」
「……――」
自らが曖昧である少年にとって、脅威となり得るはずのその可能性。それを本当の意味で人形の護衛が知っていたわけではなかった。
「アナタを連れていけるまで、彼女は留まる気かもしれません」
主が落ちた渦中から一歩、あえて離され、人形の護衛は事情を深くは知っていない。ただ憂い気に少年を見て、それ以上は何も口にしなかった。
「…………」
少年はただ、大切な場所に居座る、二つの異物に顔を歪める。
――あんた……ここに、何をしに来たんだ?
その異物の滞在がもしも、自らの責であったとしたら。
思わず口元を塞ぐほどの、強い吐き気を必死に抑える。
ボツボツと。黒く染まり切った空から、大粒の雨が、やがて降り落ちて来ていた。
「あっちゃー。本当に降ってきちゃいましたかー。皆様撤収ー、テントが流されないよう、注意してくださーい」
「ほらぁ、だから言ったじゃない、スカイちゃんてばー」
うわーん、ごめーんなどと、何故か霖の声が響いている。
しかしもう一人の幼げな花形は、鶫に何故か突然抱き着いていた。
「!?」
「でも嬉しいー。霖がこんなに元気なのって、イーレンちゃんがいなくなってからは久しぶりだぁ。ほんとにありがとぉ、小鳥ちゃん」
半分涙目で強く抱き着く幼げな花形は、どうやら本気で、黒髪の花形のことを心配している様子だった。
「ユーオン君ー! 濡れちゃうよ、テントに入れてもらおーよ!」
遠目から自分を呼ぶ声に、少年はようやく、ハッと我に返る。
「……行きましょう。お互い、雨と相性は良さそうですが――」
すっと立ち上がった護衛は、最早ほとんど少年に対して、警戒心は無くなった様子だった。
「ずぶ濡れになれば、中身はともかく器は傷みそうです。せいぜい大切に使うとしましょう――貴重な相性の合う器は」
「…………」
少年もただ、憮然と黙ったまま、後に続くしかできなかった。
_転:赤い小鳥
三日に一度は帰るとはいえ、世話になっていた御所をしばらく後にすることになった時、少年は何処か、肩の荷が降りた気がしていた。
――正直少し、安心したし。
当面の行先は、それはそれで問題だらけの居場所だ。それでもここ最近の少年は、御所にいる時は常に、客人の陽炎を目にすると浮かぶ葛藤を呑み込むことに必死だった。それでずっと、落ち着かない日々でもあった。
――……殺さなきゃ、いけない。
その確固たる思いは日に日に、強くなりつつあったことと、
――でも……殺しちゃいけない。
根拠のわからない躊躇いに戸惑い、それでもよくよく考えれば、それが妥当なことのはずだった。
頼也にこれ以上迷惑をかけないためにも。しかしそう思うそばから、それなら尚のこと、殺さなければいけない、とまさにループする思いを持て余していた。
「……何でなのか、せめてわかればな……」
どちらの思いにも、結局はっきりわかる理由はないのだ。その直観だけを頼りとする少年の欠損は、じわりと足場を侵し続けていた。
街では今日も、一座の外回り活動が花開いていた。
「うわぁ、鶫ちゃん、可愛いよ! 今日は花山吹の襲だね! 季節ちょっと早い気するけど、鶫ちゃんにピッタリの色目だよね!」
「……何で毎日来るのよ、槶?」
浅紅と黄の色合いの、舞い用の着物を羽織った赤い髪の娘。その姿を槶はパシパシと、撮像という機能があるらしきPHSを片手に、あらゆる方向から撮り回っていた。
「写真送ってほしいって頼まれてるんだ! 学校さえなければ絶対、観に来たかったって言ってたよー」
早速外回りで舞をすることになった鶫も知る友、槶のPHS仲間から頼まれたのだ、と主語を出さずとも通じている二人だった。
そんな娘達を見守る少年。一時要員として一座に加わった鶫の、更に一時のお供に対しては、また別の反響があった。
「オイ。イーレン帰ってきたなら、金返せよ、金」
「……ごめんなさい。ヒト違いだ」
以前いた妖精に似るという少年に対して、一座の者に度々、そうした声をかけられることになってしまった。
「ああ? 整形した程度で俺の目はごまかせんぞ! お前とはいつか決着をつけると言ったじゃないか!」
「ごめん。もうソイツ、というかオレの負けでいいと思うよ」
鶫の仕事は内回りの演目と、練習予定についての説明が終わった後で、その日の外回りが始まった。
「鶫」という名をそのまま芸名に、何故か内輪では小鳥と呼ばれる、赤い髪の娘だった。
「ルンと私も、セットみたいな名前だしね。うちには後一人、鴉もいるから、鳥同士でちょうどいいわ♪」
平坦な広場や、良い時には能楽堂があるような場所を回り、各地のワープゲートまで駆使して、京都の周辺地域一円に一座は得意先を持っていた。
「外回りで内回りの宣伝をして、各地からお客を集めるのです。てなわけで、君達はチラシ配りをお願いしますねぇ」
どうせついてくるなら、と、少年と槶は分厚い紙の束を渡されてしまった。そうしてスカイに体よく使われていたのだった。
「何かスカイさん、誰かに似てる気がするなー。でも誰かなぁ」
「にしても……何でクヌギまで手伝うんだ?」
「ええ? だってこういう、色んな所に行くのって珍しいし、楽しいよ♪」
一座の中で、すぐに行方不明の妖精扱いされる少年にとって、知り合いの話し相手がいるのは正直有り難い。外回りの舞や芸が披露される傍ら、隙あらば広告を配りつつ、どうでもいい様々なことを沢山槶と喋り合う日々となっていた。
ちょうど、年が明けてまだ半月程度だった。ユーオン君は初夢見た? という話題が、少年には印象に残るものだった。
「僕はねぇ、初夢、みんなで何処かに冒険に行く楽しいやつだったよ。可愛いもふもふや、知らないけど知ってる小さな女の子もいたり、よく考えたら色々ヘンだったけどね」
「ふーん……それ、縁起がどうとかは、よくわからないな」
初夢に関しては縁起が大切であるらしい。それで御所でも話題になっていた。
「オレもその日に、ヨリヤ達に訊かれたけどさ。よく見る夢を、そのまま見ただけだったから、あまり意味はないんだってさ」
「えぇー。何かしんどそーな顔だけど、嫌な夢なの?」
「そうかな? ……何かいっつも、妙に吐き気はするんだけど」
それ、明らかにしんどいんじゃん! と槶がツッコむ。夢をあまり覚えていないこともあり、アハハ、と少年は言葉を濁す。
「それより、暮れに見た夢の方が、何かハッキリ覚えてて……夢は沢山見るけど、こんなに覚えてるのは珍しいんだ」
「そうなんだぁ。どんな夢だったの?」
ハイ。とまた、通りすがりにしっかり広告を渡しつつ、槶は楽しげに、珍しくよく話す金色の髪の少年を見てくる。
「それが……クヌギもいて、ジュンもツグミもユウヤもいて。みんなで何でか、草原みたいな所にいたんだけど」
「へぇー。ユーオン君が外にいるの、珍しいね?」
「オレもそう思ってさ。でもその夢では、それが当たり前で……何か色々、おかしいんだ、その夢」
? と首を傾げる槶を前に、少年はふっと苦く笑った。
そして少年は――その、有り得なかった世界の夢を改めて思い出す。
「オレさ。今はいないけど、妹みたいな奴がいるんだけど」
「ええ!? そーだったの、ほんとに!?」
身元不明の少年の意外な事実に、槶が目を丸くする。
「なのにその夢は、そいつがいないことになってる有り得ない世界なんだ。でも途中でオレは、そいつを思い出して……いないのはヘンだって、そいつを探して、気が付けばずっと一人で走ってたんだ」
「――」
そうしてやっと、見つけた相手。何故かそこで、「シーをよろしく頼む」と、少年は告げられる。
「シーちゃん? って愛称だよね? 多分」
うん、と少年は頷き、夢の終わりをそこでまとめた。
「いつでも笑ってる奴なのに、助けてって一人で泣いてるから。オレの知ってるそいつの名前を呼んだら……そこで全部消えて、目が覚めたんだ」
「うわぁ。なかなか意味深な夢だね、確かにそれって」
ごくり、と槶が息を飲んだ。
そして少年自身気になっていた、同じ疑問を口にした。
「そこで、違う名前の方……シーちゃんって呼んでたら、どうなってたんだろ?」
「…………」
その有り得ない世界の夢の、実情は何か。この少年に、わかることはない。
夢の理由より大切な意味。泣いていた者に助けが必要であることだけは、既に知っていた願いだった――少なくとも「銀色」にとっては。
――あなたのせいよ……。
慣れ切った昏く赤い夢。それがただ、違う形で現れただけだと。
ひょいっと。そこで不意に、第三者の感想が述べられていた。
「――夢が覚めずに、シーちゃんも帰ってこれなかったかも?」
「――!」
「あれ、スカイさん?」
にこにこと、自身も近くでチラシを配っていたマネージャーの黒い女が、いつの間にか近くに来ていた。少年達の背後から間に顔を出していた。
「イーレン君、鈍そうだしねえ。よっぽど強いSOSじゃないと、そんな夢はみないんじゃないかい?」
なら気を付けてあげなよ、と、スカイが何故か口を挟む。普段の営業とは微妙に違った、何処か親しげな口調だった。
「…………」
違う、と言っても、あくまで行方不明の妖精の名でそのマネージャーは少年を呼ぶ。軽く睨む少年を、近くにいる槶がハラハラして見守る。
「それにしても――鶫さんは、逸材ですねぇ」
スカイはあっさり話題を変えると、元通りの営業口調になった。
今まさに、花山吹の重ね姿で、淡い表情で気品に満ちた舞――地を渡る鳥のように躍る鶫が、視線の先にあった。
「……――」
周囲と同じように、赤い髪の娘を視界に捉える。
天の鳥でも地の鳥でもない、ただ地に足の着いた聖なる娘。
天の青光がよく映えながら、地上で慎ましく生きている小さな赤い鳥。
少年は不意をつかれたように、瞬きをすることも忘れて、揺れる赤い髪をただ見つめていた。
「あの若さで、安定感が半端ないですね。羨ましい限りです」
「鶫ちゃんは何でもできるんだよ。凄いんだよー」
天と地、青と赤の併存など、その娘は事も無しにこなす。少年のそばにいる者達は、それを当たり前に最大限に称える。
青空の下を黄色い飾りで舞う赤い小鳥が、長い睫毛で黒い瞳を憂いげに伏せる。
まだあどけない姿に大人びた黒が、よりいっそうの深みを、青と赤の混じる目の少年まで確かに届けていた。
「……――……」
それは本来、守られることを必要としない強い鳥で。
それでも守り守られることを尊び、仲間を大切にする小さな赤い鳥。
何をも犠牲に何かを守る剣が、取り落としたものをこそ守る――何をも大切にできる強さ、それ故の弱味を持つ赤い小鳥だった。
花山吹の小鳥が舞う傍ら、空の色は段々深みを増しつつあった。
その暗い雲が何処から来るか、この一座は誰もが知り尽くしていた。
「…………」
一しきり鶫の姿を見つめた後で、少年は一度、周囲の者をざっと眺めた。
可憐な小鳥にわきたつ賑やかな面々の中に、本来在るべき者の姿が見当たらない。それにすぐ気が付いていた。
「……あいつ……」
広告も配り終え、娘の出番もちょうど終わった。
スカイとずっと話題の尽きない槶を後に、誰も気付かないほど自然に、少年は静かに場から離れていた。
ぽつぽつと。細くか弱い雨粒が、涙のように降り落ちてきていた。
「……――あれ? 君……」
一座が陣取っていた外回り先の広場から、少しだけ離れた場所についた。ひと気のない小さな川の流れる林だった。
「どうしたの? 小鳥ちゃん、まだ向こうにいるでしょ?」
無表情にここまで来た少年に、独りで休んでいた霖が気付く。腰かけた短い橋の縁の上で、不思議そうに振り返っていた。
思えば少年は、この相手に自ら話しかけるのは、これが最初だった。
「あんたこそ……ここにいていいのか?」
仕事中ではないのか。と一応、少年も返答する。
「大丈夫。小鳥ちゃんがいるから、私なんていなくても今日のノルマは十分達成できるわ」
「……そういう問題じゃないと思うけど」
「だって、向こうにいったら私、また雨を降らせちゃうもの」
それは返って、一座の外回りの足を引っ張る。黒髪の花形は数々の気に入りの場所の一つで、あえて羽を伸ばしていたようだった。
「小鳥ちゃんを見てると、何だか嬉し過ぎて、コントロールが全然効かなくなってるの。困ったものよねー……化け物失格だわ」
「…………」
千族混じりのこの一座で、花形など大きな役回りをする者は、何らかの「力」を持った者であることが必要条件となる。目立つ者は外敵から狙われやすいからだ。
「私なんてただ単に、感情の強弱で、雨を降らせるだけの力なのにね。そんな簡単なことすらできないから……だからダメなんだわ、私」
少年の方を見ずに、苦笑しながら眼下の小川を見つめる黒髪の花形は、霖――長雨というその名の通り、雨女という「力」を受け継いでいる。かなり純粋な血統の妖の末裔だった。
「いいなぁ。私、きっと、小鳥ちゃんみたいになりたかったのよ」
「……」
「雪女さんとかと違って、雨女なんて雅さも無いし、名前も知れてないし。とにかく弱小だから……人間のフリした方が得だったし、誰かと関わり過ぎて正体がばれないよう、一人で何でもできなきゃいけなかった。本当に、せこせこ生きてきたのよ……レストをやる前までは」
そんな雨女の正体を見抜き、ディアルスという国に招き、女王に協力する自らの直属としたのがある妖精の魔女だった。
「ナナハ様は、私ができることをすればいいと言ってくれたけど。私の役割なんてせいぜい、隙間産業、何かあれば穴埋めくらいよ。小鳥ちゃんくらい慎ましく堂々とできてたら、あんな風になれたのかしら?」
「……あんたは」
まるで霖は、少年に何も言わせまいとばかりに、何かを話し続けている。少年は苦い顔のまま、淡々とそこで割り込む。
「そいつがあんたに期待したのは――穴埋めじゃないだろ」
「……君は……ナナハ様を知ってるの?」
「……知り合いの知り合い。ちらりとだけなら、会ったこともある」
「そっか。……イーレンは、同じ妖精でも、ナナハ様と会ったことはないって言ってたけど」
ふう、と。ようやく霖は少年の方を向いて、大人びた顔付きで笑顔を見せた。
「スカイはね。君がイーレンだって、そう言って譲らないの」
「……」
「ああ見えて強い霊感持ちらしいけど。本当に、他のみんなもどうかしてるわよね。君は全然、イーレンには似てないのにね?」
少年を行方不明の妖精扱いする、同じ一座の者達。
その大半はただの勘違いと知る黒髪の花形は、ふふ、と危うげに笑う。
「…………」
彼女がそうして笑う理由を、少年はとっくに知っていた。
「あんたは……」
彼女の目を正面からは観ずに。ただ胸元の蝶型のペンダントに紫の目を合わせて、少年ははっきりと口にした。
「あんたは何で、イーレンを――殺したんだ?」
「…………」
彼女はその妖精が帰らないと知っていた。だから剣だけを欲しがっていた。
少年のことも敵視している。口封じのために殺さんとする可能性すら、その笑顔の内にはずっと観えていた。だから少年も警戒を絶やさなかった。
「やっぱり……知ってたんだね、君は」
空の暗雲は明らかにその黒さを増し、雨女の淡々とした表情とは対照的に、重苦しい色合いを少年に見せつけていた。
「なのに、誰にも何も言わないで、イーレン扱いされるのを黙って我慢してるなんて……」
人間のようにしていた雨女が、それでも明らかに化け物であると示す空色。あくまで表情だけは、悪びれもなく少年をまっすぐに見つめる、純粋な妖の雨女だった。
「それじゃ、あの時……その剣を渡すまいとしたのも、君?」
妖精のような背格好の少年は、殺された妖精の仲間なのかと。そうした風に、雨女は現状を捉えているようだった。
「剣も持って行きたかったのに。変な光で、邪魔したでしょ」
「……ああ。それなら多分、オレのことだ」
殺した妖精の大切な剣を、霖はその時持ち去ろうとした。しかし手にした時に剣から発した白い光が霖を遮り、その剣は霖の手に渡ることを拒否したかのようだった。
「変なの。それだけ近くにいたなら、イーレンのこと……助けてくれれば良かったのに」
「あれだけ串刺しなら即死だ。止める暇なんて無かった」
霖は本来、雨を降らせるだけの化生で、特に強い妖ではない。
しかしその感情の高ぶりをコントロールできず、刃と化された雨を、全て目前の妖精に向けてしまったのだ。
「雨を刃にする力も、分けたのはイーレンだし。それなら、自業自得だろ」
「…………」
冷静な少年が、霖は意外だったらしい。
ヒト殺しである雨女の事実を、全く動揺せずに見据える少年。人間の感覚であれば、それは信じられない不秩序だろう。
「妖精さんは……妖なんてわりと本当、淡白なのね」
仲間が殺されても、平然としているように見える少年に苦く笑う。自らはヒト殺しの咎に苛まれ続け、霖はそうとしか言えないようだった。
霖は、あくまで冷静な少年から、再び目を逸らして呟いていた。
「……私が、悪かったのよ」
「……」
「三つも年下の気まぐれなコに、本気になっちゃったのも……みんなには隠してって言ったのも、私からだったし」
座内で三角関係を作り、一座から去ったと噂されている妖精。そこには更に、ややこしい関係が隠れていたらしい。
「ルンや鴉に浮気されちゃったのも、私がつまらなかったからだろうし。逆恨みなのは、わかってたんだけど……」
それでも妖精の、その宝の剣に拘った霖。それはただ、形見が欲しいだけの切なる想いだった。
自ら殺してしまった相手。その理由すらも、抑え切れない慕情だったのだから。
「でも、そう思えば思うほど、抑えられなくなって……私もう、何処か、壊れちゃったのかもしれないわ」
「…………」
「前はこのくらいなら、雨もコントロールできたはずなのに、今は何をやっても駄目になっちゃったの……可愛い小鳥ちゃんを見てると、久しぶりに何だか、幸せな気持ちが思い出せて……私、駄目な奴だから、どうしても抑えがきいてくれないの」
重過ぎる色の空からは、小さな雨粒が申し訳程度に降りて来ている。
霖が今、どれだけ必死に自らを抑えているか、少年には嫌というほど伝わってきていた。
少年にとっては、この雨が本当に雨女の害意ではないと確認できたこと。
赤い髪の娘を歓迎する気持ちだとわかった時点で、妖精殺しの方を追求する気はなかった。
「……なぁ」
ただ一つ。ここまで話を聞いた以上は、ある事柄だけ――
見過ごすことはできない問題を、最後に口にする。
「あんたがもし、アイツを殺したことを、後悔してるなら……」
「……?」
そしてその後。少年が口にしたことをそのまま認めて、霖は少年の言うことに素直に従っていた。
「あんたはオレより――まだ全然、帰ってこれるよ」
少年はただ、苦く笑う。
そうやって不戦協定を結んだ雨女に、今まで通り頑張るように背中を押したのだった。
そうして。
一人の妖精が命を落とした瞬間から、その「剣の精霊」は世に顕現することとなった。
その直前に妖精が最後に買っていた剣が、海底から掘り出された古い時代の「力」だった。
この一座に加わる前に、少年は改めて占い師に会いに行った。
やっと会うことができた占い師は、様々な真実を率直に教えてくれた。
――いまやお主は……その自我を剣に依存した、『剣の精霊』。
宝の剣の中にあった古の「力」。それがぼろぼろだった妖精の体を辛うじて蘇生させ、顔などを僅かに造り替えた。
そうして妖精の躰を使い、少年は少年として、その目を覚ましたのだ。
少年も尋ねる。果たしてそれは、最早変えられない定めであるのだろうかと。
――この身体で、コイツが目を覚ますこと、できるのかな?
体は蘇生しても、妖精自身の意識は戻らなかった。そのためそのまま剣の内の「力」が、呪われた生を受けることになった。
「本当に……ろくでもないよな」
無表情に、青白い剣を掲げて見つめながら、少年は口にする。
「生きてるのはオレじゃなくて、こっちなんだから」
本体は今も、剣のままである少年。だからその剣が傍になければ、最早意識を保つことすらもできない身の上だった。
――妖精なら羽があるはずなんだけど……。
周囲から何度か聴かされた言葉を、少年は忘れなかった。だから霖の胸元に、探していたものの一つを真っ先に見つけた。
霖から譲り受けた蝶型のペンダントを、少年は剣に纏わせる。この先決して無くさないように、しっかりと巻き付けていた。
「……くっつくかどーかは、わかんないけど」
霖にも同様に言ったことを呟く。けれどこれがあれば、妖精はまだ、目を覚ませるかもしれない。
それを思い、蝶型のペンダントを見つめながら、一人で苦く笑い続けていた。
+++++
レストの巡業。午前中は、京都もしくは近隣で外回りを。
午後からは内回り、京都で上演する舞台の練習と、なかなか突然、赤い髪の娘は多忙な生活を送ることになっていた。
「今月の中旬二週間、週二回公演なので計四回ですね。もしもご家族を呼ばれるなら、初日と千秋楽の二回をお勧めしますよ」
練習は本当に根を詰めて行っているのに、上演回数がそれだけというのは勿体無い、という声も身近で上がる。
「さすがに無理だから。いきなりそんなに沢山するの」
「えー。期間長くなれば観に行けるのにって、ぼやいてたよー」
「幻次さんがまず許さないよね? 何で帰ってこないーって、昨日も泣きながらヤケ酒呑んでたよ、鶫ちゃん」
その多忙さの中で、御所まで頻繁に戻るのも返って疲れる。三日という約束の間隔は開き、御所の子供達の方から、今日は朝から川辺にやって来ていた。
「特に鶫の身辺に変わりはないのか? ユオン」
「うん、今の所。危険なことも、最初に思ったよりは無さそうだった」
一番の不安材料だったのは霖の動向だ。それが少年にとって解決していたため、ここ数日は至って気楽に過ごせた。川辺のテントで花形達や鶫と共に、毎夜がわいわいとお祭り騒ぎだった。
霖の方も、あれから随分と物腰が落ち着いていた。鶫がなるべく快適に過ごせるよう、最大限に気を使ってくれていた。
むしろ気になるのは、花の御所の近況だった。
「御所の方はどうなんだ? あの客の女……大人しくしてるのか?」
「ああ。でも何か、もうすぐお暇すると言ってたらしい」
「……?」
暮れ前からずっと滞在していた客人について、蒼潤が思わぬ展開を口にする。少年は怪訝な顔付きになる。
「新たな護衛、それも女の手練れが雇えるかもしれないんだと。ほとんど御所にいたのに、どうやって探してるんだろうな?」
「……いなくなるなら、何でもいいけど」
しかしどうしてか、その陽炎が去っていく時こそ、何か――花の御所にいる者達にとって、良くないことがあるのではないか。不意に少年は、御所に帰りたい気持ちに唐突に襲われていた。
午前中は、娘は外回りの仕事があるため、子供達はそれに同行していった。それなら、と少年は、蒼潤に今日一日の供を変わってもらうことを頼んだ。
「ユオンは御所に帰るのか?」
「そうする。夕方には練習先に行くから、ジュンはそこまで、悪いけどお願いできるか?」
「わかった。にしても、ユオンも律儀だよな」
槶も今日は用事があるらしく、御所の子供達だけで、その日は一座に混じることになった次第だった。
それを何故か――ちらりと一瞬。意味ありげな目線で、その一座のマネージャーは見つめていた。
最近足が遠のいていたが、不意に帰った花の御所では、特に何も、これといった変哲はなかった。
しかし頼也は、少年が帰ればきいてみたいと思ったことがあったらしい。会いに行くと笑って居室に入れてくれた。
「回復魔法が効かない状態とは、どういうことなのかお主にはわかるかのう?」
「――へ?」
急に押しかけた少年に、首を傾げつつそんなことを尋ねてきた。
最近、その同じ質問を持ち、仲間の死神が訪ねてきたとのことだった。
「お主も似た状態の時があったじゃろう。陽炎殿との一件で、お主が昏睡状態だった時に、治療ができないか頼んだ者があったのじゃよ」
「そうなんだ……」
「精霊魔法の使い手で、大怪我や外毒など、急を要する回復の業に長ける者でな。しかしお主のように、寝たきりというのは専門外らしくてのう。何故回復魔法が効かぬのか、それを今でも気にしておったのじゃよ」
回復魔法とは、それが外傷であれば、命の灯さえ消えていなければ通じる奇跡だ。特に精霊魔法ほどになると、どれだけ瀕死者でも救える確率が高い。
ところがある娘のごく簡単な怪我に、何故か回復魔法が効かなかったらしい。その使い手は頼也に、半ばボヤキに来たらしかった。
「わしにも結局、答はわからなくてな。アラス殿の不調が、まだ続いておるせいかとも思うがのう」
「…………」
レストの護衛の、まだ見ぬ主の名に、少年は知らず声を呑んだ。
剣の師の元にも顔を出した少年は、鶫の近況を報告し、一しきり久々の鍛錬でぼこぼこにされた。
その後にレスト公演先の、京都では賑やかな地域にある建物へと向かった。
「……全然、見咎められないな」
まだ保護観察が続いている少年が、そうして一人で出歩くことは、基本的にはよろしくない。しかし少し前から袖を通した着物は、何とか少年を京都にも馴染ませているようだった。
「いざとなったら、言霊もあるけど……」
刃傷沙汰を起こした代償として、少年は言霊による命令に絶対服従の呪いを受け入れていた。こうして一人でいる時も、万一まずいと思う状況があった時は、と鶫はあるアイテムを少年に持たせてくれていた。
――私達が誰もいない時に、銀が出て困りそうになったら。これ、使うといいわ。
鶫についてまわるために、少年の外出が増えたことを考え、言霊を封じ込めたというお札を娘は書いてくれた。
「力をこんな紙に、小さくまとめて使えるなんて。便利だな」
でも――と少年は、複雑そうに、娘がくれたお札を眺める。
「これ、顔に貼れって……それも何か、やだな……」
それでなくとも、片耳に常備する同時翻訳機たる装身具も少し不格好だ。それが不服だった少年は、身なりには人並みに気を使う性質でもあるのだった。
動き難さにさえ慣れれば、白の小袖と紫の袴はとても気に入っていた。これを黒衣の上から身に着けている限りは、呪われた身上の少年であっても、御所で暮らしていて良い気がした。
公演先の建物についた時には、ちょうど日が暮れてしまった。楽屋では蒼潤と悠夜が、裏方達と話しながら少年を待っていた。
「凄いなユオン。レストでいったい、何人の女に声かけたんだ?」
「違う、それ絶対ガセ情報だから……妖精違いだから……」
「似てるヒトが色々悪いことしてると、大変だね、ユーオン君」
すっかり妙な裏話を掴まされた彼らを、早く帰るように出口で見送る。日も完全に暮れ、一座の練習も休憩に入る頃合いだった。
「……え?」
「あれぇ? 小鳥ちゃん、楽屋に帰ってないのぉ?」
舞台の方に顔を出した少年に、花形達が不思議そうな顔を見せた。
「ついさっき、休憩になってからは、こっちにはいないわよ。……ユーオン君は会ってないの?」
霖は一座で唯一、少年を名前で呼んでくれるようになった。隣に控える人形の護衛と顔を見合わせる。護衛は今回、護衛役として出演するので一緒に練習しているらしい。
「私が探しに行ってきましょうか?」
「――いいよ。多分オレ、ちょっと探せばすぐにわかるから」
これだけ限定した建物の内であれば、探し物はむしろ、得意な部類だ。身近な現状の把握にとても長ける直観によって。
そうしてあっさり少年は、身軽な街着を稽古着にしていた赤い髪の娘を、長い廊下の先に見つけた。
「――……え? ツグ……ミ?」
しかしその目の前には――あってはいけない光景が広がっていた。
時間は少しだけ戻る。
休憩に入った鶫が、いつも差し入れが置いてある楽屋に、軽くお菓子でもとろうと足を向けていた時のことだった。
「……――あれ?」
一座が借りた古い劇場。京都では珍しい造りの公演向きの建物で。
日も暮れた薄暗い廊下の先を、ス――と横切っていった暗い人影に、霊感の強い術師の家系の娘は否応なく気が付いてしまった。
「こういう所だと……やっぱりいるわね」
歴史が古いその建物に、あまり性質の良くないものがいる。
気が付いた以上、見て見ぬふりはできないと人影を追って、強い霊感を持つ娘がその長い廊下に踏み出していた。
そこにいたのは、有り得ない誰かの姿――今この場所にいるはずのない者。
ここに来れないことを嘆いていたという友達によく似た人影。鶫はすぐ絶句した。
「――何、で?」
茫然とする鶫に、人影はこんばんは、と上品に笑う。
長い髪をまっすぐおろし、鶫よりも高い背で大人びた体つき。その顔が何故か鶫の友達にそっくりなために、混乱に陥る。
「あなた……まさか――……」
確実に死んだ霊だとわかった。それでもその相手を祓って良いか、鶫は咄嗟に判断できなかった。
黒い人影もそれをわかっていた。優しい娘は必ず、それを躊躇うだろうと。
忘我の手綱はそこで握られた。優しく甘い娘に付け込むのは簡単だった。
「……ねぇ、鶫ちゃん。お願いが、あるんだけど――」
今この時間は、鶫の記憶には残らない。人影はそれを知って笑う。
「鶫ちゃんのカギを――……私に、くれない?」
それが誰かの大切な願い。鶫の大事な友達によく似た黒い人影が望む。
それは大切なことだと、鶫の霊感はわかってしまう。その優しさと鋭さ――大切なことは何事も疎かにできない、娘の隙間に人影は付け入る。
「――のこと――……忘れてほしいの……」
今はまだ、それはあまりに唐突な願いだった。しかし強過ぎる昏い願いに、鶫は身動きができなかった。
決してソレは、娘達を傷付けることはない。それでも確かな侵蝕を伴い、黒い人影はあっさりと、鶫の意識を奪ってしまった。
「――!」
ちょうどその場に、少年は出食わしていた。
起こってはいけない禍事。娘に近付く禍は何であれ、少年に許せるわけがなかった。
専属護衛たる少年が銀色の髪に変貌し、瞬時に剣を抜いて場に飛び込んでいた。
「……やぁ、キラ君」
ソレが誰か、少年にもわからない黒い人影。
しかし何故か、銀色の髪の少年をあっさりそう呼ぶ。少年が本来、己のものとして取り戻したかった古い名前を。
そのまま黒い人影は、剣を剣で軽く受け止め、昏く笑っていた。
「銀色」の出現は、本当に必要な時に最低限しか動けないほど、大きな消耗を少年にもたらす。
どうして今、迷いなく現れたか、銀色の髪の少年自身も自覚できなかった。それでも強い想いがそこにはあった。
けれどその鋭過ぎる直観を以ってすら、黒い人影が誰であるのか判別できない。見知らぬ、というより、「覚えられない」という不審な敵がそこには在った。
「――……何の、つもりだ」
その相手は娘達を傷付けない。初めて会った時からそれはわかっていた少年は、ただ自らの剣だけを相手に向ける。
「別に何も、害なんてないよ? ホントにちょっとだけ、心の隙間に入る道を教えてもらっただけだから」
少年の特技、白い光を抑えたその剣は、普通の剣と脅威に大差はない。
倒れていた鶫を大切に壁にもたれさせた少年の前で、相手も剣を抜いた黒い人影が無邪気に笑った。
「私の目的のために、この子達は邪魔だから――……何とか、邪魔にならなくなってほしいんだ」
「――この子、達?」
寒気が走った。間髪入れずに人影に斬りかかると、相手は巧みな剣技だけで応じる。
力を使わずに戦わなければ、「銀色」は敵と長く対峙できない。そんな制限のある今の少年を、軽々と払っていく剣の達人は、その剣と感覚でしか戦う術を持たない弱小な相手だった。
「キラ君も知っているでしょう? この子達がいるからあの子は、いつまでも迷ってるんだよ」
「――……」
黒い人影が、いったい誰のことを言っているのか。その相手と人影が、どうした繋がりを持っているのか。それをどうしても思い出せない少年は、ひたすら歯噛みする。
「無理だよ。君より私の方が、剣も願いも強いからね」
「――」
「知ってるよ。君には私は――……殺せないでしょ?」
それだからこそ少年は、この相手を覚えていることができない。そう言って黒い人影は、娘達と似た隙間を持つ少年に入り込んで笑う。
ソレは少年にとって、最も致命的な深い傷を、躊躇いなくそこで晒していた。
「君はもう……殺したくないと、思ってるからね」
青白い剣の夢。少年の終着を招く逆光。絶え間ない吐き気を運び来る毎夜の苦悶。
その痛みを知っている、と。誰かもわからない人影が昏く微笑む。
耳障りな声を封じようとして、何度斬りかかっても同じだった。
「どうせ君には、何もできないままであるなら」
少年のことも傷付けまいと、願う相手の剣はただ強かった。
「それなら……忘れてしまえば、いいと思うよ?」
ならばそれだけが救いであると、人影の勝利をここで宣言する。
少年がそこで、意識を失った赤い髪の娘の姿を目にしなければ、少年はすぐにも敗北を認めたはずだった。
初めにこの相手を観た時もそうだった。「銀色」に変わろうとはしたものの、敵わない相手であるとわかった。だからその後に倒れてしまった。
「っ――……!」
激しい動悸と嘔吐きを抑え込んだ。雑念を捨てて、銀色の髪の少年はその剣に白い光を纏わせ始める。
「鶫達に――……何かするなら……――」
最早何も、躊躇うことはない。命を削る光を最大に消費することを決める。
「あんたが誰だって……俺には関係ない……!」
同じ青い目を持った相手に、少年はその呪われた剣を向ける。
自身の命と引き換えにしてでも、躊躇なくその刃を振り下ろしていた。
ふ、と人影は、黒い微笑みを宿す。迫り来る剣を青い目で見返す。
バカだね、と。
その生来の霊的な感覚と、夢を覗き見る旧い目を以って、人影がとっくに知っていたこと。その「銀色」を止める方法をけろりと見定める。
「何もしたくないから――……私はここに来たんだよ?」
少年を含めて、娘達を決して傷付けまいとする意思がそこに在った。
だからソレは、その命をかける少年以上の、強い願いであると――白い光を纏う剣を、類稀な剣技で事も無く受け流していく。
「残念だけど。生きてない上、力も無い私にはそれも通じないから」
それだけが強みだった人影は、少年の懐を着物だけ切り裂き、言霊の札を己の剣の切っ先に引っ掛けて奪った。
「ほら。自重してね――キラ君?」
「――!!」
そのままスっと、剣を振るって少年の額に札を貼り付ける。
瞬時に強く胸を掴んだ少年が崩れ落ちた。
札はすぐに、その後に燃えて消えてしまった。
「銀色」を封じる言霊の「力」で、激しい動悸に襲われた少年が次に目を開けた時には、思い出せない人影の姿は何処にも無くなっていたのだった。
「……っ――あ……!」
力無く両膝をついたままで、少年は胸元を強く掴む。札の影響か、それとも命を削る力の反動か、痛みの灼熱が全身を襲った。
額を地に打ちつけて身悶えを堪える。銀とも金ともとれない髪が床に擦り付けられる。
傍らに落ちた剣から離れないよう、身動きだけは必死に自制していた。
「――……ぇっ……」
何一つ。時間の止まったその体に、吐き出すものなどないのに、込み上げる憎悪が一気に少年を襲った。
この躰で目を覚ましてから初めて彼は、命そのものをぶちまけるように、真っ赤な何かを吐き戻していた。
少し離れた場所で、今も眠る鶫の姿を見れないままで――
守り切れなかったとも言える現実に、ただ彼は嘔吐くしかない。
――君はもう……殺したくないと思ってるからね。
その人影に敗れた原因は、たとえそこには無かったとしても。
もしも相手が、彼らの敵であったならば、赤い髪の娘はここで失われていたかもしれない。
「もう――……それだけは、イヤ、だ――……」
どんなことをしてでも、その結末は受け入れられない。それなのに自身は、とても弱小な生き物へと堕ちてしまった。これでは何も守れない、と現実を突き付けられる。
気が付けば金色に戻っていた髪と紫の目は、失い続けた古い痛みを、その時だけは思い出していた。
銀色の髪の少年が幾度も刻まれてきた痛み。その度に自らを鬩ぎたてていたのが同じ呪い。
それでも少年は最後まで気が付けなかった。それはただ、失うことへの怖れという激痛であると。
周りと溶け込んでしまうほど、直観の鋭い「銀色」とは違い、金色の髪の少年が「銀色」より優れるところ。
それはその弱小さ故に、「銀色」より少しだけ曖昧でない想い。大切なものを失くしたくない怖れを自覚できる、あまりに不安な自分自身だった。
本当にただ、意識を失っていただけの鶫は、程無くしてから気が付いていた。
束の間の午睡から覚めるように、娘が穏やかに目を開けた時には、金色の髪の少年もぎりぎり体を立て直し、鶫を大切に抱えて座り込んでいた。
「……――え?」
「……――……」
鶫は咄嗟に、状況がわからなかったらしい。少年の腕の中で覚めた目には、うるうると、子供のように涙ぐんでいる金色の髪の少年が映った。
「ツグミ……目、覚めた……?」
隣に正座した状態で、少年は壁際の鶫の上半身を横向きに抱えていた。そのままぎゅっと安堵のあまり、鶫を力の限りに抱き竦めていた。
「ちょ、ちょっと――……!」
鶫が焦る。それで全身に血が通ったのか、一瞬で身体が赤く熱くなっていた。それも感じて少年はやっと一息をつく。
どちらかと言えば、少年はヒトに触れるのを避ける方だった。鶫は驚きのあまりに抵抗もできず、腕の中で硬直してしまった。
「良かった……全然、目、覚まさないから……」
少年にとっては、ごく一瞬の抱擁だった。鶫が今まで通りで、何も変わりなく温かいこと。それだけで世界が安らぎに包まれていた。
がっちり固まる鶫を離すと、正座の体勢のまま、鶫の体から手を離した。
鶫は横向きに座り直し、とりあえず埃を払っている。わけがわからず盛大に赤まった顔を少年から必死にそむけていた。
「何があったのよ、これ……?」
「わからないけど。気が付いたら、ツグミが倒れてたから」
少年はまだ心配が治まり切らない。涙ぐんで両膝を掴みながら、それ以上の事情を考える余裕もなかった。
「……何でそれだけで、アンタはそんなに、ぐしぐしとしてるのよ」
その直向きさは、鶫からは子供っぽくみえたらしい。けれどおそらく、これが金色の髪の少年には本来の姿だった。
ただひたすらに、鶫の無事だけを案じる少年がそこにいること。鶫は半分納得いかなげに少年を見つめた。
「って、まだ、大して時間もたってないじゃない」
休憩時間は残っている。鶫はそこまで長く気を失っていたわけではないはずだった。
何故意識が無かったのか、それは気にかかるが、珍しい生活での疲れも多少は自覚していた。
「それより……どっちかっていうと――」
「…………」
鶫がそれを、座り込んでいる少年に口にするよりも早かった。
完全に気を取り直していた鶫を観て、ふっと少年は、そこでぱたりと倒れ込んでいた。
「……」
どちらかと言えば、少年の方が余程、鶫より真っ青な顔色で死にそうに見えた。
完全に意識を失い、か細く拙い気配の少年に、ふーっと頭を抱えながら溜息をついた。
「何て言うか……わけ、わからないんだけど」
これはとても、自らの手に負える状態ではない。一目で少年の窮状を看破した鶫は、自宅へと術の力による連絡を行い、瀕死の少年の迎えを要請したのだった。
_結:逆流
それからしばらく、ひたすら少年はまた眠り続けた。
傍らで様子を見守る頼也や幻次は、頭を悩ませているようだった。
「特に何か、戦闘があった気配や痕跡はないってさ」
「気になるのは、ユーオン殿の着物が切れていたことじゃな。鶫の札が一枚だけ使われていたというのも、消耗の原因だけは、裏付けはするが……」
何かで「銀色」が外に出て体力を消耗し、それを少年が、呪符の力を借りてまで自ら止めようとした。
その場で起こり得たことを考えると、それくらいしかなかった。
「本人が目を覚まさなきゃ、どーしようもねぇな。しっかし今度は、どれくらい眠れば良くなるんだ、コイツ?」
幻次が妙に不服気なのは、下宿中の娘のお供を少年が果たせなくなったからだけではなかった。
「鶫の晴れ舞台、もうすぐ始まっちまうじゃねーか。全公演応援に行って、その後で呑もうって約束してたっつーのに」
少年は非常に食が細いが、酒はわりと大丈夫なのだ。それでこっそり、共に呑む楽しみができた師でもあった。
「期間は二週間というし、確かに下手をすれば、眠ってる間に全て終わってしまう可能性はあるのう」
少年がせっかく守っていた娘の舞台を観られないこと。それは不憫であると頼也も悩む。
そうして少年を親身に心配してくれる温かな者達の声は、ほとんど身動きせずに横たわる少年に、うっすらと届いていた。
しかしその温かさ以上に、傍らの剣の冷たさが少年の温度を奪っていた。
青白い光を仄かに放つ剣は、今も確かに、不滅の問いを少年に突き付け続ける。
剣がなければ少年は生きられない。しかしこの剣こそが、少年の命を奪ってもいる。
それでなくても拙い命を使い続け、決して消えない責苦を、金色の髪の少年へと送り続けていた。
うなされている。そうとしか言えない顔付きで、時に苦しげに眠る少年を知っていたのは、頼也だけではなかった。
「……おや、まあ……」
自称天の民の姫君は、新たな護衛を得る手筈がそろそろ整いつつあった。この御所に滞在する目的も果たせたと言って良かった。
「本当に……わたくし達と共に来られた方が、アナタにとって、幸せでしょうに……」
在り方の無難さと思いの強さ。ヒトのために動くことが信条と信じている身。
いつもあまりに無力だったために、無害な存在としてここまで時を過ごして来れた陽炎は、少年の苦しみにフっと微笑む。
「少しだけ。無理をしてでも、お誘いしてみましょうか――?」
真新しい傷痕を押さえながら、それだけ楽しげに呟いた陽炎だった。
そして少年は、青白い剣の夢に今日も襲われる。
銀色の髪で青い目の少年。
年端もいかず、人気のない山奥で暮らしていたその少年は、元々何処か世間離れしていたところがあった。
一言で言えば、きっと彼は……彼とそれ以外のモノの区別が、何処か曖昧だったのだ。
――……エルがいたくないなら、いたくないよ。
彼の五感は彼以外のことも、彼のことのように感じる故障品だった。
虫を踏めば、その存在に気付かずとも虫の痛みが彼を襲った。
誰かが悲しめばそれは彼の悲しみと、当たり前に共に傷んでいた。
――……もう、やめて……キラ……。
だから彼は、ただ在るだけで感じられることが多過ぎて、痛みや悲しみといった強い思いを受けると、容易く自らを見失った。
自身のちっぽけな悲鳴には気付かず、他者の都合ばかりを重視していた。
――だから、――は……優しいんだよ。
そのため、誰かの強い願いを我が事として動く彼を、ヒトは優しいと言った。たとえ彼が、多くの者の命を奪った死神であっても。
「でも…………」
剣が語る死神の夢が、弱小な少年を追い立てていく。
ある身勝手な歎きに、少年はいつも吐き気を堪える。
「もう――……それだけは、イヤ、だ――……」
失いたくない、と望む少年。それがどうして、今更己の役目を迷うのか、青白い剣は責め立て続ける。
虫の痛みすら、自らのモノとして感じたその少年は、本当はずっと解っていた。
その手にかけた多くの命や、失われた命の全ての痛みを、一つ一つ共に味わっていた。
それは本当に必要な痛みなのか。そう、望みと相反する迷い。青い逆光の芽は確かに拾えてしまうほど育ちつつあった。
だからこそ剣は、弱小な少年への警鐘を発したのだ。
――何で……殺さないの?
たった一つの望み以外、青白い剣はそんな隙間を全て排した存在だった。
それが必要な仕事であれば、迷いごと殺せばいいだけだった。
それこそが今の少年を責め立てる、かつての死神の誓い。何故ならあくまで、少年の迷いは、誰のためでもないことだからだ。
「なんて……かってなヤツ……」
その赤まみれの誓いも、それを厭いつつある今の青さも。
どちらも自身の都合でしかない身勝手に――彼は、嘔吐くしかなかった。
その夢を見る時の少年の髪は、銀と金を往き来していると、赤い髪の娘は知ることになる。
「……何がしたいんだか……本当」
三日に一度、当初通り帰ってくるようになった鶫は、その度に必ず少年の様子を見に来ていた。白い浴衣で横たわる少年はまるで、死者の仲間にすらも見えていた。
「銀色にも金色にも戻れないの? ……どっちがいいのか、わかるまで眠り続ける、なんてつもり?」
常に誰かを映すような、自らが曖昧であるこの少年。その事情は、鋭い感性を持つ鶫達のような術師をしても、深くはわからないままだった。
正確には、わからないことが本質である少年を、鶫達は的確に把握していた。
鶫達のその感性は、そうした漠然としたもので。
「それがわかり過ぎたら、悠夜やユーオンみたいになっちゃうのかしら」
強過ぎる感性で、幼くして大人びてしまった従弟の悠夜や、悠夜とは違った鋭さを持つ少年は、鶫にすればいずれも危うかった。そうした感性の持ち主は、本来ならば自らを閉ざすことで、己を守るしかないのだから。
「アンタはソレ、悠夜みたいに封じておくどころか……ソレだけが基準で、自分なんてどうでも良かったみたいよね」
ぺしっと。沢山の大切なものを大切にしないために、苦しげに眠る少年の銀色の頭を、思わずはたいた赤い髪の娘だった。
それでも確かに少年は、何かの願いを持ってここに在った。その願いが現れた時には、きっとこの御所からも去っていくのだろう。
願い以外のことは全て捨てかねないような少年にとって、それが良いことなのかどうか、鶫は今もわからなかった。
――オレは多分、ろくでもないから。
居候先の居宅を、突然血で染める少年が真っ当でないのは明らかだった。
それでも鶫は、「絶対服従」の呪いには反対だった。
――そうじゃない奴の言うことを、聞いてた方がいいと思う。
本当は鶫以外の者もそうだった。術師でない従兄すら、真っ当でないほどまっすぐな少年を、短い付き合いで知っていたのだから。
「何か理由があることくらい……みんな、わかるのに」
しかし今は、その呪いは当分、この少年には必要だった。
――オレは別に、止める気はないんだと思う。
あくまで少年はこの先も、自らを守らないことを言い切っていた。
それを周囲が無理に止めた所で、限界がある。それでもせめて少年が、この場所に留まる間だけは――
少年の願いはもうすぐ現れる、と断言した悠夜とは違った。
無意識にそれだけ――少年がこの御所を去る日が近いと感じていた鶫は、眠る少年をただ、不服気に見守るのだった。
+++++
数日後に。世界を旅する千族一座の現地座員として、赤い髪の娘の初舞台の、まさに初日が訪れていた。
「ったく。やっぱりまだ起きやがらねぇな、コイツ」
千秋楽まで一週間以上の猶予はあるので、幻次はそこまで焦る風でもない。ただ純粋に、残念そうにしている。
「寝たきりになるってとこも、そういや誰かさんを思い出すな。今日はアラスも、観に来るって言ってたっけな?」
師の古い仲間。過去に一度、命に近い「宝珠」を失いかけて長く眠りについた者を思い出して、幻次は苦笑したようだった。
「ま、あまり無理はすんな。すみれも頼也も、今日は行けないみたいだしな」
幻次は頼也から子供二人を任され、後一人、槶を連れて、鶫の舞台を保護者として観に行くことになっていた。
「よりによって、今日がご出立とは……ついてねーなぁ」
せっかくの初日に、公家と連れ合いが同伴できなくなった理由をブツクサと口にする。そのまま眠る少年を後にしたのだった。
花の御所の管理者の一人である頼也は、三カ月近く留まった客の出立に、京都を出るまで付き添うことになった。
そうした時は、御所を預かる役目は姉に任せる必要があった。それで姪の舞台の初日を観れなかったことや、何より実母の姉に観せてやれなかったことは大きな痛手だっただろう。
頼也も幻次も不在となった花の御所では、ようやくとばかりに、ある異変の発現があった。
「……ねぇ。……私と一緒に、アナタも此方に来るのよ」
眠る少年に囁きかける声。少年と大きく年の変わらなそうな、謎の乙女の姿があった。
「私を捕まえたのはアナタだしね。私もアナタにも用があったの」
乙女は少年の剣の傍らに坐し、土色の短い髪を小さく揺らす。
「私の依り代を、壊したのはアナタだから。今度はアナタが、私の依り代になるのよ」
無力で無難な姫君の、有害だった侍従だけではない。その侍従を使役する根本、霊核たる媒介を姫君の胸に宿らせていた乙女は、その媒介だけを破壊した剣に、逆に憑いた状態と言えた。
だからこうして、人手の薄くなった御所で初めて現れ、少年にひっそり誘いをかける。
「酷いことをするわよね。私は何も、悪いことはしていないのに」
その乙女も何一つ、力は持ち合わせない、無力な偵察者だった。
「弱い者でも遠慮なく害するアナタは、まさに死神ね」
ただ一点。無力であり、曇りなき強い善意の持ち主だった。それは力ある者にほど、無意識に見逃され、受け入れられやすい特性とも言える。そうして偵察者としての乙女の適性は測り知れなかった。
それなのに一目で、少年は乙女を敵と見切った。そんな少年とよく似た知り合いのために、乙女は少年のことも偵察にここまで来ていた。
「起きてね、死神さん。出発の時間よ」
乙女の思いの強さは、言霊に匹敵するほどの執念と言える。絶対服従という呪いに縛られる少年は、それを借用した相手の前で、ふっと、色の無い目をようやく開けていた。
そうして少年は夢遊病のように、浴衣の上から慣れた紫の袴を着ける。足取りは確実に、人目にふれないように御所を抜け出していく。
どれだけ長く歩いたのだろう。京都の南端、そこに広がる草原との境に無言で辿り着いた。その先で待ち受けていた者が、今もあまり似合わない着物を身に着けたまま、にこりと少年に微笑みかけていた。
「よくぞいらして下さいました。わたくしの痛みもどうやら、無駄ではなかったようですね」
「…………」
その絶対服従たる呪いは、この姫君を害した少年への罰だ。だからその呪いの力でここまで来たのは、少年の意志――自業自得だと言える。強い心で土色の髪の陽炎は微笑む。
「紹介しましょう。わたくしの新たな護衛の、吸血姫です」
誰かの傍らには、ケープで身を隠す若い女らしき人影があった。
「アナタと同じ死者とも言えます。最も彼女は、相当新しい、つい最近の死者ですけどね」
ふふふ、と、そのケープの中身を思い、陽炎は実に楽しそうだった。
おそらくは、この少年が異端者であること。死者と呼ばれてもよいほど、本来ここにいるはずのない何者かだと陽炎は知っていた。
むしろそれを知るために、御所に現れていたとも言えた。
「わたくし達は皆、本来終わった生を繋ぐ『死者の一族』……自らの身体を使っているのは、どうやらわたくしだけですけど」
死者の一族。それは本来、相性良き媒介に遷した魂の力で、死した自らの身体を動かす異端の化け物の総称だった。
「わたくしの命は、返していただきますね」
その媒介を突然、初対面の少年に姫君は破壊されてしまった。胸元に潜めたペンダントを完膚なきまでに斬られてしまった。
それまではずっと身体活動を全て封じ、死者と同様にすることで長く保っていた身体を、そこで急遽解凍するしかなかった。そうして己を生き物に戻すことで、存在の連続性を辛うじて繋いでいた。
「…………」
無言で剣を差し出す少年から、陽炎はそのまま受け取る。
いともあっさり、その剣で自らの頸動脈を切る。
噴き出す血に横髪を赤く染めながら、次の瞬間――まるであどけない乙女のような顔で笑った。
「ああ痛い。致命傷って本当に痛いわ、厄介なことね」
無力な身には、「命の遣り取り」はそれ以外ではできないからだ。ペンダントから剣に奪われていた命を、そうして受け取った土色の髪の乙女だった。
血はあっさりと、乙女の傍らの外套の人影が、首筋を軽く押えるだけで止まっていた。
「さすが吸血姫ね。血の扱いには長けているのね」
よしよし、と乙女から、それまでの控えめな面影が消えた。出血を止めて身の内に戻してくれた護衛の頭を、にこやかな顔でさらりと撫でる。
「それじゃ、みんなで……私達の行くべき所へ、帰りましょ?」
すっかり口調が若返った乙女に、水を差す大人びた声が響いた。
「悪いが――そういうわけにはいかぬよ、陽炎殿」
その乙女の命が、少年の剣から離れたことを確認できた時点で、彼は現れた。
見送った客人の前に戻ってきた、黒い髪と目の公家がそこにいる。
「その少年は死者ではない。だからお主達には渡せぬよ」
少年を引き受けるのは自らの役目、と。頼也は改めて、厳しい目で土色の髪の乙女を見据えていた。
「これはこれは、青の守護者さん。まだ帰ってなかったの?」
見送り有難う、と今までと違う口調の乙女がにこやかに笑う。
「ユーオン殿を解放せよ。さすればお主が何者であろうと、わしには特に咎める気はない」
「そうなの? 私が陽炎に憑いた悪魔かって、訊かないの?」
全く興味は無い、と頼也は断言する。ただ少年の身だけを案じてそこに立っていた。
「お主の事情は、既に伺った。何が真の目的かはわからぬが、わしらに害を成す気でもあるまい?」
「ええ、そうね。貴男達の中には、私が求める器はなかった。貴男達が生粋の青の家系だと、近くで確認できただけでもう十分だったから」
でも、と乙女は、少年の肩を後ろから抱くように両手をまわした。
「私の媒介と、私達の人形を壊してくれたこのコはね――ひょっとしたら、うちの人形使いの知り合いかもしれなかったの」
「……何?」
「凄い偶然だけど、それも確かめたくて、私はここに来たから。でもよくわからないから、結局連れて帰るしかないわね」
あくまで目的は偵察で、嘘はつかなかったと乙女は自負している。それ以上は特に語らず、親しげな翠の目で頼也に微笑み続けていた。
「……ということらしいが? ユーオン殿」
頼也は半ば、呆れたような声で呟く。ずっと身動きしなかった少年に、突然そうして声をかけていた。
「そろそろ良かろう? その程度の縛呪は、自力で解除されよ」
「――え?」
キョトンとする乙女の前で。少年は、す――と、尖った耳元に素早い動作で軽く手を当てる。
「あらイヤだ。随分甘い処罰をするのね、こんな悪いコに」
ずっと尖り耳につけていた同時翻訳機を、少年が自分で外した瞬間、その目には紫の色が戻っていた。乙女からすぐに剣を取り返し、その切っ先を瞬時に向けていた。
「その器械が『絶対服従』の術の媒介だったのね。言霊を確実に届ける呪い、なるほど、巧いわね」
「……動くな、裏切り者」
翻訳機を外したことで、乙女が何を言っているのか少年は理解できなくなった。ただ冷たい青の目に変わり、見知らぬ乙女を観通す。
「『銀色』殿。お主が手を汚す必要はない。誘いだけお断りし、早いところ、御所に戻るのじゃ」
「…………」
「まだ体調は戻っておるまい? それにお主は――初めから、陽炎殿を殺す気はなかったはずじゃ」
少年はちらりと、少年を案じている頼也を肩越しに振り返る。その厳しい目に無機質なだけの目線を向ける。
「……そうだな。こいつは――」
殺さなければいけない。既に定まった結論を実行しない理由は一つだ。
「俺の獲物じゃ――ないからな」
その因である、青白い剣を侵す昏く赤い夢を思う。何の感情も無い声で、それだけを頼也に伝えていた。
「でも――」
そこで少年は、再び乙女の方に向き直った。
「アイツの相手は、俺の役目だ」
新たな護衛と言われながら、剣を向けられている乙女を特にかばうこともない外套の相手。しかしそれも越えて、少年が観ている者は他にあった。
「――……!?」
少年が言う者の気配に、気付いた頼也が愕然とした。
その場に突然、少年と乙女の間に割り込むように、ソレが降り立っていた。
このタイミングで必ず現れる、と銀色の髪の少年が気が付いていたその敵。
驚く頼也に構わず、少年は一跳び分の距離だけ後退すると、長物の武器を持つ敵に改めて剣を向けていた。
「――やぁ。君が、頼也兄ちゃんの言ってた『剣の精霊』?」
にこにこと、敵は一見、優しげでも不敵な笑みを浮かべた。そうして青銀のシルエットを持つ何かが、銀色の髪の少年を見据える。
「もしくは『刃の妖精』かな。どっちでもいいけど、あんまり兄ちゃん達の近くで、不穏なことはしないでほしいな」
「……アラス殿――」
ぎり、と頼也が、敵の存在をはっきり認知する。
乙女を守るように間に降り立った者。「つばさ」に関係する名前を二つ持ち、淡い青銀で硬質の髪と、鋭く蒼い目を持つ旧い仲間。上半身を黒く首まで覆う上衣と、長く軽装な上着を着こなす敵を厳しい眼差しで見つめる。
その、男とも女とも知れない人影。レスト護衛の人形とそっくりで端整な容姿の持ち主である青年は、いつも通りの笑顔で頼也を見ていた。
「やっほ、頼也兄ちゃん」
そうして青年はあまりに唐突に――その裏切りを宣言していた。
「悪いけどオレ、こっちのお手伝いをしないといけなくなってさ。邪魔しないなら、兄ちゃん達には何もしないけど、こいつらのお願いを聞かなきゃいけないんだよね」
だから、とばかりに、笑って銀色の髪の少年を見る。後ろにいる乙女が望む通り、その青年は、少年を連れていくと言わんばかりだった。
「……クラル殿から、連絡が来ている」
頼也の仲間、他の守護者の名前を口にする。同じ守護者たる青年は、フ――と笑う。
「南の地でお主が何をしたか――クラル殿も、直接に目にしたわけではないと言うが、お主は……――」
「まぁね。頼也兄ちゃん達の所は大丈夫だったけど……残念ながらオレと、後ろの吸血姫の姉ちゃんと、後一人。クラル兄ちゃんにとっては、そーだな……多分、姪っ娘ちゃんと言える奴が、こっちのヒト達が求める『資格者』らしいんだよね?」
乙女の傍らに佇む外套の者を、青年は「吸血姫」と呼んだ。それも南で、青年が刃を向けた者の一人であるらしい。
その時には、姪という少女には手を出さなかったというが、今後はそれも標的として既に定めていた青年だった。
「でも、悠夜君くらい強いと、それも欲しいって言ってたけどさ。さすがに諦めるよーに交渉しといたから、安心してよ♪」
「……アラス殿……――」
さらりと青年が口にしたこと。それが頼也達に対する、この青年の変わらぬ信頼と、同時に窮状を表していた。頼也の子供達を守るためにも、青年は敵側に渡ったのだ。
その意味を悟った頼也は、心から厳しく……痛ましげな顔で、青年をまっすぐに見返していた。
「お主はそれで、良いのか――……アラス殿」
今も頼也達、旧知の仲間への揺らがない思いを青年は持っている。それでも彼ら全てに背を向けると宣言する青年に、ただ尋ねる。
「イイわけないけど? 頼也兄ちゃん」
青年はそこで、とても不思議そうな顔で笑った。
「今は翼槞だって、とっくにわかってるのに。まだオレのこと、その名前で呼んでくれるんだね、兄ちゃんは」
「…………」
銀色の髪の少年と同じく、少なくとも二つの名前――己を持った青年。それ以上は何も口にしなかった頼也に、一瞬だけ悲しげに笑いかけた。
その後、頼也の動向を窺っていた少年の方へと楽しげに振り返った。
「驚いたな。オレ一応、死神って仕事をしてるんだけどさ?」
「……」
「オマエは仕事とかじゃなく、天性の死神だね。オレなんて可愛く見えるくらい、血の匂いが漂ってるや」
少年ほどではないが、青年も勘が良いらしい。そうしてあっさり赤まみれの少年を看破する。
そうして青年は、降り立った時は構えていた武器を、何処ぞへ消失させてしまった。
「オマエを今連れてくと、頼也兄ちゃん怒りそうだし。それに――鶫ちゃんにしてやられたな。当分あいつ、動けなさそう」
「――!?」
少年が聞き逃せない名前を青年が口にする。
青年は軽く水平に掲げた手から、視界を閉ざす強く濃い霧を唐突に発生させると、後ろの乙女と外套の人影を全てぼやかしてしまった。
「それじゃーね。またどっかで会おーか、『剣の精霊』」
「っ――……!」
体力が消耗し、立っていることも精一杯の銀色の髪の少年と、大き過ぎる力の差を見せつけられるようだった。
少年との敵対を宣言し、三人もの生き物を易々と転位させた強大な化け物は、その場から完全に去っていった。そうして頼也にも背中を向けた、今代の黒の守護者だった。
「…………」
ぺたん、と、金色の髪に戻った少年が、胸を掴みながら膝をついた。
「大丈夫か、ユーオン殿」
「……ヨリヤ……」
敵がいなくなったので、話をするために翻訳機を再度装着する。少年を心配そうに見下ろす頼也に、少年の方こそ、痛ましさが堪えなかった。
「……お主がそのような顔を、することはないのじゃよ?」
少年がどうしてそんな顔をするのか。自ら以外の苦しい何かを、自らのことと感じてしまう少年に、頼也は困ったように笑う。
敵側についた仲間を、引き戻すことができなかった頼也。その胸中には、自らの家族達の安泰への思いと、仲間を案じる葛藤が余りあった。
「幻次以外には――アラス殿のことは、黙っておいてくれ」
「…………」
青年が度々連れ回したという子供達を思い浮かべて、頼也はそう力無く告げる。少年は黙って、コクリと頷いていた。
「アラス殿は決して――わしらのことは害さないであろうが」
「……」
「お主と、クラル殿の姪とやらに関しては別のようじゃ。あえて標的を告げていったのも、実にあやつらしい」
何を求めて敵対したか、の宣言。無用な戦いを避ける青年の信条と覚悟、頼也はその思いも悟るように沈痛を浮かべる。
「お主が御所にいる間は、アラス殿も手出しはせぬじゃろう。しかし……そこから先は、アラス殿が本気なら、わしらにも止められるかどうか――」
「いい。ヨリヤ達には関係ないだろ」
「…………」
即答した少年に、守るべきものの多過ぎる頼也が苦悶の顔となった。
「ジュンもユウヤも、ツグミも誰も巻き込まない。ヨリヤが認めてくれるなら、すぐにでも出て行く」
「ばか者。お主の観察期間は、無期限じゃよ」
頼也も即答する。しかしどれだけ少年を引き止めたところで、今の状況が長く続かないことはわかっていた。そのために黒い目の奥に大きな痛みと憂いを宿しているのだ。
「お主の行くべき場所が見つかった時には、止めはしない。そうでなければ、そう簡単に御所を出ることは許さぬよ? お主はわしのいる所で――ヒトを傷付けたのじゃからな」
「……――」
これまでは誰も口にしなかった咎め。しかし本来、在るべき糾弾。
ともすれば生まれて初めて、少年はそれを耳にすることになった。
「ユーオン殿。ヒトを殺すのは、いけないことじゃよ」
「…………」
「たとえどんな理由があっても、そのことには変わりは無い。お主が何者であっても――今この時世に生きる以上は、それを肝に銘じられよ」
「……――……」
それは少年が、どの地で生きていようと必要である枷。
誰かが伝えなければいけなかった。たとえそれでも、少年は剣を取ってしまうとしても。
「同じように……お主が自らを殺して生きる必要もないのじゃ」
本来、少年は、そうした運命を望んだわけでは決して無かった。
どれだけ痛みしかなかった道でも、そう生きることしか役割を見出せなかった。その天性の死神を、知るわけではない頼也の言葉に、少年はただ、目を伏せることしかできなかった。
何故ならそれは、頼也自身が欺瞞とわかっていた。それでも祈るような心で、少年の身をただ案じるがため、あえて口にした綺麗事だった。
この少年は決して、その必要の無い流血など起こしたことはないだろう。周囲の誰もが無意識に感じ取るほど、いつも穏やかな顔で、少年は優しげに笑っていたのだから。
「さぁ。御所に帰ろう、ユーオン殿」
こくりと、黙って頷く少年の手を、ただ哀しげに微笑んだままとった頼也だった。
その手は最初と同じように、小さく温かった。
+++++
赤い髪の娘の初舞台の日、頼也と少年の周囲であったそうした出来事を、最終的には当事者と、頼也の姉夫婦だけが知ることとなった。
「こっちも大変だったぜ。何があったのか、蒼潤と槶は何故か覚えてないらしいんだがな」
公家に背を向けた仲間の青年と、生き写しの護衛人形に、幻次は娘の公演先で出会っていた。その人形の護衛の謎も含めて難しい顔付きで、彼らが巻き込まれた騒動の顛末を頼也と少年に語るのだった。
「力を貸して下さい。山科幻次」
「――はぁ?」
とても初心者とは思えない娘の晴れ舞台の幕間に、楽屋に押しかけた子供達を、扉の外で幻次は待っていた。
突然そうして、がっしり師の腕を掴んだ人形の護衛。つい先程までは娘の相手役をしていた、半分覆面の男装の麗人がいた。
「ってお前――何で、アラスそっくりなんだ?」
「その我が主との契約に反し、貴男方の子女の様子を窺う不届き者がいます。護衛として見過ごせませんが、私はこれでは、表立って動けません」
既に次章の幕開けも迫って来ていた。最初は鶫の単独シーンから始まるとは言え、護衛にもその出番が迫っていた。
「私は『渦』。遠い昔、貴男達の乗る船を沈めた海の竜です」
あっさりと爆弾発言を師に投げかけ、その舞台の高い天井側の梁の上へ、師を引きずっていった人形の護衛だった。
「海の……竜じゃと!?」
「ああ。アラスが最近は面倒見てたらしーが、今アイツ、それどころじゃなくなったんだ、とそいつも言ってたぜ」
幻次が梁の上に着いてすぐ、遥か下方、袖にスタンバイしていた鶫が、頭上の父に気が付いて顔を引きつらせる。
そこに幻次が連れていかれた理由は単純だった。
「って――……人、形、だと――!?」
そこにはたった一体、大きな鎌を携える、一見小柄な赤いシルエットが潜んでいた。
スポットライトより高い位置、姿もよくわからない暗い梁の上で、確かに舞台の様子を窺っていたのだった。
「あの人形には、現在の制限ある私の力は通用しません。私が本来の姿をとればこの劇場ごと崩壊します」
人形の護衛はそうして、淡々と爆弾発言を続ける。
「貴男ほどの手練れでないとあれは対峙できません。貴男の剣も通用するとは思えませんが、とりあえず牽制して下さい」
「何だそりゃ!?」
「実力の問題ではありません。そうした防具を、あの特別な人形は身につけているのです」
そこで一瞬、黙って話を聞いていた少年に、束の間でも強い頭痛が鋭く走っていた。
どうすれば謎の不審な人形に、騒ぎを起こさず対応できるか、幻次が悩む傍から後半の幕は上がった。
眼下では、膝上までの礼装と長い靴という衣装に身を包んだ鶫が、突然の見せ場から二幕を開始していた。
「何者です!? 私をディレス王女と知っての狼藉ですか!?」
幻次よりもう少し下で、梁から吊るされたワイヤーで動かされる風船がつられている。そのいくつもの中型サイズのセットに舞台上の鶫が叫ぶ。
鶫にとってはまさに、視線の先に、真の不審な人影と父の姿があった。
舞台としては、敵対者の罠で護衛から引き離された王女が、窮地に陥るシーンだった。
「って――!」
ゆらりと、梁の上の人形が、そこでついに身動きを始めた。護衛はそれを見て改めて、幻次にその場を託した。
「私はこの後、舞台に飛び降りて登場しなければいけません。後はよろしく頼みました、山科幻次」
「ってちょっと待て、無茶ぶりにもほどがないか、アラスのそっくりヤロウ――!!」
そのまま本気で、護衛はその高さから、事も無げに下方へと降り立ってしまった。暗い梁の上という足場も心許ない場所で、相手の姿もろくに見えない中で、幻次に向かって大きな鎌と飛行能力を持った人形が闇から襲いかかってきたのだった。
一方で。楽屋の外にいたはずが、何故か姿を消した保護者に、蒼潤、悠夜、槶の三人は迷子になっていた。仕方ないので子供達だけで、元の観客席に帰ろうとしたところで――
楽屋のある側から、一般の通路へと繋がる長い廊下で、蒼潤曰く、何故か思い出せない不審な剣士に出喰わしたと言う。
「――いや。久しぶりに、何か凄く充実した時間だったはずの気はするんだけどな」
「ジュン……何でそんなに、何かいい顔してるのさ?」
後の子供会で、少年は蒼潤と悠夜から、その不審者の話もしっかり聴き回っていた。
不審な剣士と蒼潤は戦い、そこで撃退したというが、相手の詳細は一切わからないとのことだった。
「ユウヤはさすがに、何があったか覚えてるんじゃないのか? クヌギとジュンは、どっちもあんな感じだけど……」
「…………」
じーっと。珍しく膝を抱えて座る術師の悠夜は、何処か心許なげに、何故か黙って少年を見つめる。
そんな悠夜の憂い気な姿から、誰かのことを我が事と観る少年の脳裏に、僅かに状況が伝わってきた。
謎の不審者。黒い邪気を持つ者だと蒼潤が食ってかかり、激しい剣戟を狭い廊下で交わした二つの人影。
悠夜と共に後ろに下がりながら、戦う二人の優れた剣技に、我を忘れたように見惚れる槶の姿が浮かぶ。
一しきり不審者は、蒼潤と剣技を交えた後で、一度距離をとって離れると悠夜の方を見て言った。
――……ダメだよ? そこの、とっても鋭い術師君。
その時の悪寒はたとえようがない。悠夜を言い知れない不安が襲う。
――視て見ぬふりは良くないな。私が誰かわかってるなら……。
と言っても、と。黒い不審者はくすくす、と強い霊的な感覚を持つ己以上に鋭い悠夜に笑いかける。
――それを言い出すと……君が何人いても足りないだろうけどね。
視えていること全てに、その子供に手を出せと言うのであれば。視え過ぎてしまう相手には酷なことと知りながら、そのカギをあえて不審者は回す。
「ユウヤ……何か、嫌なこと、あったんじゃないのか――?」
「…………」
口を引き結んで黙る悠夜の前で、少年は視線を合わせてかがみ込む。
ヒトを映す特性を持つ少年の憂い顔に、悠夜は更に黙り込む。
――残念だな。隙間はあるけど、君には介入できないみたい。
入り込めても、悠夜とは力の差が大き過ぎた。
心から憐れむように、その黒が最後にごめんね、とだけ、申し訳なさそうに笑いかけていた。
その実態を少年に悟られないこと。そのために悠夜は、必死に己を閉ざしていると少年は知らない。
その黒い何かの昏い願い。
――あの子のこと――……忘れてほしいの……。
いつかいなくなる、とわかっている誰か。
その時何も禍根を残すことのないように、誰かに関わった者達から、それは忘我のカギを集めてまわっていた。その昏い願いに悠夜だけが気が付いていた。
その別離は誰にも、変えられることではなかった。
だから誰かもそれを望んだ。ただ彼らを傷付けないため――そのためだけに、彼らにほんの少しだけ関わった何かだった。
そしてその実態を、この少年が知ってしまえば、少年は命を削ってでも看過できない。それをわかっていた悠夜は、最後まで一人で口を噤むことにした顛末だった。
「結局、ゲンジもジュン達も、ツグミの舞台……まだ最後まで、しっかり観れてないんだな」
何度となく少年は、その通し稽古は目にしていた。本番を一緒に観に行く師との約束も当然覚えていた。
「あのなあ。とりあえず舞台を守った俺を褒めろって」
足場も視界も悪い中、不審な人形の攻撃に幻次は応じた。真下の舞台に影響を出さないように見事に戦い切った幻次は、その結末が不服で、未だに不機嫌さを隠せない様子だった。
後半の幕が上がると、赤い髪の娘には最大の見せ場で、また問題シーンから舞台は始まっていた。
「何者です!? 私をディレス王女と知っての狼藉ですか!?」
凛と叫ぶ鶫の頭上に、ワイヤーを介して怪鳥型の風船が舞台の空を駆け回る。
「ああ!? 何なのでしょう、あの化け物の群れは!?」
「王女様、これは罠です、お下がりください! 護衛長がいない以上、私達を囮に逃げ延びて下さい!」
ばっと鶫は、無力な二人の侍従を、逆にかばうように前へと進み出る。
「何を言うのですか! これしきで怯む私ではありません!」
そこにすかさず、演出としてスポットライトの色が赤く変わる。
あらかじめ決まった位置に、怪鳥からの攻撃として、炎のような小道具も降り注いでいく。
「あのような卑劣な化け物に、明るい未来などありません!」
その時まさに、梁の上では幻次が、ぎりぎりと謎の人形と鎌と刀の鍔迫り合い中だった。
「――撃ち落とします! 貴方達は下がっていなさい!」
梁の上から父の姿は、今にも落ちそうに見えたという。
このシーンにあたり、悩んだ末にせっかく偽物でと頼み、与えられていた小道具を鶫は瞬時に袖に投げ入れた。
そうして舞台を続けながら、父を襲う敵のために、ばさりと舞わせた衣装の外套の内で、鶫の切札――本命の黒い武器を取り出していた。
そのシーンでは、怪鳥風船に対して、空砲を撃って対処する予定のはずだった。
銃声の後、怪鳥がワイヤーから落ちる手筈になっていたのだが……。
「な――!!?」
梁の上で幻次に大きな鎌を振りかぶろうとした人形は、怪鳥風船ごしにその凶行を阻まれていた。
舞台という有り得ない場所からの、突然の遠隔援護。精度の非常に高い本物の銃撃。怪鳥風船を破った銃弾が、人形の躯体の関節までを、見事に数か所貫いていた。
「――何者だ!? 我が君に手を出す輩には容赦しないぞ!」
梁の上からいくつかの箇所を経由し、出番ぴったりに舞台に人形の護衛が降り立ち、鶫はすぐに拳銃をしまった。そこから先は、父一人でも不審者を撃退できる、と踏んで舞台に集中する。
「まさか……ツグミ……」
関節が破損したため、攻撃能力が露骨に低下し、そこで不審な人形は去ったと言う。
「小道具が暴発したんだと。そんな危ない物をヒトの娘に持たせやがって、全く……」
鶫はそう誤魔化したらしい。ひたすら不服気な幻次に、少年はハハハ……と苦く笑う。
「えっと。小鳥、ちゃん……?」
後に、無事に初日が終了した後に。袖に控えていた霖は、茫然とした様子で問うたと言う。
「もしかして……本物、持ってるの?」
袖に投げ入れられた本来の小道具を片手に、霖は尋ねた。
いいえ? と鶫は、目を逸らして小さく答えたらしかった。
+++++
そうして始まった、旅芸人一座の珍しい大きな舞台公演。
赤い髪の娘の公演が無い日は、他の花形がメインの舞台が内回りで、鶫は外回りに出るローテーションが、その後の千秋楽まで続いた。
内回りの日は、幻次と共に鶫の舞台の応援を。外回りの日は鶫の供を、まだ本調子でないながらもついてまわった金色の髪の少年だった。
「あぁもぉー。小鳥ちゃんってば、もう十年前からうちにいてくれたんじゃないかってくらい、はまり過ぎ可愛い過ぎー」
「……うん。ツグミは本当に、キレイだと思う」
雨女である霖の近くにいると、少年の回復は妙に早かった。千秋楽の頃にはむしろ好調なくらいだった。
「本当に残念だわ。しばらくジパングには来れないと思うし、かと言ってあんなに可愛い御嬢さん、今下さいなんて、とても山科さんには言えないなぁ」
「…………」
そして霖は、何故か困ったような顔で少年を見て微笑む。
「君も無理しないでね。何かあったら、いつでも相談に来て」
「……相談って、何を。……何処にさ」
「ディアルスまで来てくれたら、何だかんだで私達の情報は、何処かで入るし。少し待ってくれたら、ちょくちょく帰るから」
一応本籍は人間の大国ディアルスで、自宅もそこにあるらしい霖は、連絡先を書いたメモを少年に渡してくれていた。
「――さぁ! 今日はぱーっと、打ち上げに呑むわよ!」
「……」
その予定はわりと早くから、幻次と霖の間で千秋楽の夜に約束されていた。今度は十四歳以上限定という、また微妙なラインの祝宴なのだった。
霖、人形の護衛、マネージャーの黒い女。
幻次、鶫、蒼潤、少年、そして槶。何故かその八人で小ぢんまりした座敷を借りて、千秋楽までしっかり、飛び入り座員を演り切った鶫に賛辞を贈る。
「うわぁぁん……小鳥ちゃんがもういなくなっちゃうなんてぇ……山科さん、明日から私、何を癒しに生きていけばいいの?」
「すまねぇ。けれどこればっかりは、我慢してくれ」
すっかり霖の聞き役になっている幻次の横で、蒼潤と護衛の謎の会話も交わされている。
「何だ。アラスの奴、当分ジパングには来そうにないのか?」
「主がこの先、貴方達に何か仕出かすなら、私にご連絡下さい。その時は遠慮なく、主をぶち殺して止めるように命じられています」
事情を知らない蒼潤は、よくわからないまま、適当におう、と頷く。至って本気らしい「力」の人形は、そのために宿主から独立させられたのだと、無表情に杯を含むのだった。
「槶君、色々お手伝い助かりました。槶君はなかなか、意外にできるオトコですね?」
「えー、こんなくらいで良ければ、いつでも言ってよ♪」
マネージャーと槶は、何故か期間中から何かと話している姿が多く、お人好しの槶を体よくこき使っただろうスカイだった。
「それにしても、やっぱりスカイさん、誰かに似てるなぁ?」
「そうですね。ちょっとヒントをあげてしまうなら、私のSは、シーちゃんのSなのですよ?」
スカイ・S・レーテと名乗る黒い女。それは槶と話すことが楽しいらしく、あっさりそんな本質を口にする。
「え? シーちゃんって何だっけ?」
至って真っ当な感覚の持ち主の槶は、既にそうした、他愛ない話を覚えているわけもなかった。
周囲でそんな会話が交わされながら、少年は目の前の者しか見えておらず、隣のそんな話を全く聞いていなかったのだった。
「……あのさ、ツグミ」
「――?」
ぐいっと。普段から食が細いわりには、お酒は妙に進む金色の髪の未成年が、赤い髪の娘の目に映る。
片手で杯を含む少年は、真面目そのものの、苦い目付きと硬い声色で――
「……はしたないのは、良くないと思うにょろ」
「――はい?」
全く唐突な謎の語尾に、聞き違いか、と鶫が目を丸くする。
「ツグミは今のままでいいと思うにょろ。特別変わったことをしなくても、ツグミは十分凄い奴だにょろ」
「ユーオン……アンタ、お酒入るとそんな喋り方になるの?」
顔色もテンションも、普段と変わらない少年であるのに。何故か語尾だけ変調を来した金色。わけのわからない鶫はとりあえず、杯に続きを注いでくるのだった。
王女と護衛の温泉物語。
鶫が今日まで演じていた役柄は、鳥の名を持つ若い王女だった。
その金色の髪で赤い目の王女は、辛い経緯の後に得た豪脚以外は、特にこれといった取り柄があるわけではなかった。
ただ、その王女はとにかく努力家で、バランスが良かった。
「ツグミは全部を大切にするから、何でもできる奴だから……それはツグミ自身が、もっと褒めていいことだと思うにょろ」
「何で今日は、そんなやたらに褒めるのよ? ユーオン」
「……だって……」
その王女が生涯大切にしたもの。王女たる羽をくれた黒い鳥は、様々な特技を持ち、それでも優しい鳥だったはずだ。
自らに厳しく、危うげな黒い鳥と、王女が両方鶫に重なる。旧い約束を思い出せなくても、少年は赤い髪の娘を見つめていた。
鶫は今回、どうして「レスト」に興味を持ったのだろう。その根本を、少年は漠然と感じ取っていた。
貴族と侍の娘であるからかもしれない。銃を隠し持ち、才ある呪術師でもある鶫は、何をさせてもソツなくこなす。それだけ器用なのに、鶫自身は驚くほどに不器用だった。「強く在らねばならない」思いが侍の娘として根付き、同時にヒトの業を知る呪術師の感性を持つ。優しいのに、素直に優しく在れない。何でもできるのは特技がないとも言える。
武技では蒼潤に、呪術では悠夜に敵わない。槶ほどの生活力もない。頑固な強気さでしっかり生きているが、それでも鶫は「自分以外の誰か」になってみたかったのだ。常に自他の境界が曖昧で、何にでもなる少年のように。
野山に潜む木の実のような、優しい色の、小さな赤い鳥。
しかし何処か、赤にして赤らしからぬ、鮮やかでありながら慎ましい娘。
赤は本来、温かい色だ。
自らのことを覚えていない少年は、赤い色味を持つ者には、理由なく安心してしまう所がある。遠い昔、今は思い出せない何時かに赤い呪いを受けた時にも、その呪いの存続を願った。
そうして今も、呪いへの大きな親和性を持つ少年は――
「……俺と違って。鶫のは、キレイな赤だから……」
「――?」
元は透明度の高い青に生まれた少年は、後から赤にまみれることになった。今では自身が何色かわからなくなった。
「そのまま――……キレイでいてほしいんだにょろー……」
「……かなり酔い、まわってない? ユーオン」
ぺしっと。座敷の上で丸まって寝付いてしまい、そんな寝言を口にする金色の髪の少年を、困惑の赤い顔ではたく鶫だった。
✛終幕✛
子供が多かったので、そう遅くない時間に会合はお開きとなった。
そうして御所に帰り着いた時には、金色の髪の少年は父の背で眠っていたはずだった。
「――あれ?」
赤い髪の娘が様子を見に、居室を訪れた時には、何も無い淋しい和室が広がっていた。
「……何してるんだか。こんな時間に」
そして真上の屋根の方で、鶫は不思議な気配をすぐに感じる。
幼い頃からよく登った屋根へ、鶫が瓦の上に降り立った時。
青白い月明かりの下で、滅多にない光景が広がっていた。
銀色の髪の少年が屋根に立っている。その周囲には、少年を取り巻くように月光を受ける呪符がひらひらと飛んでいた。
「……言霊の、お札?」
それは鶫が、以前に少年に渡していた幾枚もの呪符だ。しかし今は一つ一つ、元々込めた言霊ではなく、違った「力」で少年の周囲を舞っていた。
「あの白い光の、お札もあるみたいだけど……」
宙を舞う大半は、刃物のように鋭くなった、紫の光を帯びた呪符だった。夜空の月を見上げる少年を守るように、ハラハラと上に下に舞っている。
夜に溶け込み、暗く青い影に象られる少年。それが持つ剣は、本来雨滴の似合う透明な刃で、浴び続けた赤の洗礼にいつしか濁ってしまったようで……けれどそこには、哀しく鋭い少年を映す紫の光沢があった。
護符に、己の「力」を載せる。その使い方があると教えたのは鶫だ。戦いに生きる銀色の髪の少年は、新たな力を体調が良い時に試してみたらしい。
触れば指が切れてしまいそうな、「刃」の「力」を載せられた呪符。
舞い散る紫の鋭いお札が一通り落ち着くまで、幻想的な光景を鶫は黙って見続けていた。
その後に、こんばんは、と――自ら少年に声をかけたのだった。
月の光の下で、赤い髪の娘は後ろ手を組んで穏やかに尋ねた。
「アナタ……名前はあるの?」
「……」
振り返った銀色の髪の少年は、僅かに目を丸くして鶫を見つめた。
名前をきくこと。少年から言わせんとする問いかけの意味。
屋根に両手をつき、膝を立てて少年は座った。
佇むままの鶫をしばらく見上げ、声を呑んで黙っている。
そうして少年は、いつしか思い出していた、大切な名前を口にした。
「……キラ」
何だ、と。鶫が無表情な少年をまっすぐに見る。
「やっぱり、一応、別人なんじゃない」
「……」
二つの色の髪と目を持つ少年。それは少年自身には同じであっても、違う名前――心を持った者なのだ、と諭すように。
二つ以上の色を持ち、どちらも本当である少年のあやふやな在り方。鶫は目前の『銀色』も柔らかな無表情で受け入れていた。
「どうしてアナタは、ユーオンに自由にさせないの?」
「……」
「キラが独り占めしてるんじゃない? 力も体も……アナタ達二人の記憶も、本当はずっと」
その「剣の精霊」の手綱をとる者。体の自由も能力もあえて制限された「力」が、剣の制御下で動かされていることを鶫は知らない。
それでも少年の本性はこちら。銀色の髪の少年をこうして間近で視て、鶫の霊感はそう感じ取っていた。
「それじゃユーオンが、『銀色』の制御なんて、できる日は一生来ないでしょ?」
「……」
少年は、気が付けばそうなっていただけ。鶫もむしろ、「銀色」が自然に普段の少年に近付いてほしいとみえた。鶫はもっと、この少年と話したがっていた。
銀色の髪の少年は俯く。もしもこの娘達の前で、娘が言うように自らの「力」を解放してしまったら――
「……俺は……」
「……?」
ようやく何かを応えようとした彼に、鶫が軽く息を飲む。
頼也と話すまでは声を出せなかった「銀色」。理由もわからず人を避けていた自身。
「俺は、あんた達の前で……」
少年はただ、困ったように微笑む。そのまま自然に、その心を口にしていた。
「あんた達の前では……俺は、殺したくない」
「……――」
その時の少年は、哀しいほどに棘のない声で。問いと答が噛み合っていないが、鶫と話をしたい、と同じように願っていた。
人よりとても強い感性を以っても、鶫はそれ以上、少年の混濁を汲み取ることができない。向けられるまっすぐな思慕だけが、気が付けば胸に刺さる。それは月のように確かで静かな心で、何も言えずに言葉を呑むしかなかった。
そして少年も、そんなことはどうでもいい、とあっさり己の救難を捨て去る。
「でも――殺さなくちゃいけない奴がいるんだ」
「――え?」
「そいつを殺さないと、あいつはきっと……連れていかれる」
彼らの共通の敵とも言える相手。少し前の黒い人影を思い描く。無機質な目で全ての表情を消して、少年の最大の悩みを口にしていた。
「でも俺は……そいつを殺せないんだ」
「…………」
「それがどうしてなのか、わからなくて」
それはただ、彼らの両方が知る者のために、少年は問いかけていた。
「鶫なら――わかる?」
「…………」
ある赤い夢を呑み込み、欠け過ぎている声色。鶫は当然、少年が何を訊いたか、わかるはずはなかった。
それでも鶫は鶫なりの、確かな答を口にする。
「何を言ってるのか、私にはさっぱりわからないわ」
「……」
「どうしてキラは……誰かを殺せないことを、悪いことだと思うの?」
それが万一、どれだけ必要なことであったとしても、と。
「殺したくないって。どうしてそう思っちゃダメなの?」
少年自身が気付いていない、本当に答のほしかった葛藤。
それだけはわかった鶫は、痛ましげにその心を返した。
「…………」
いつかそれを――その答を何処かでも、同じように伝えられた。
思い出せなくても少年は、表情を隠す鶫をまっすぐ見上げる。
「……そう思っても……良かったのかな……」
それがたとえ、この少年の終着を教える答であっても、
「……キラは最初から、そうだったんじゃないの?」
そう言ってくれた鶫に、ただ苦しげな微笑みを返した。
それでも銀色の髪の少年は、無情に彼らの現実を伝える。
「……俺は『キラ』だから。きっとこれからも、ヒトを殺す」
「…………」
それが自らの役目であると。この娘を前にするからこそ、少年は望む。
「ありがと――鶫」
「――え?」
「鶫のおかげで、殺さずに済んだ」
その時だけは、金色の髪の少年と同じように平和に笑い。
最後にそれだけ、銀色の髪の少年は残して去っていった。
「…………」
後には、金色の髪に戻って小さく眠る少年だけがいて。
屋根に散らばった呪符に囲まれ、紫の袴で丸まっている姿は、そのまま夜に融けて消えてしまいそうだった。
その少年を襲う、青白い剣の夢を知らなくても。
鶫はただ、バカ、とだけ。遠い「銀色」に向かって呟いていた。
+++++
Cry per B/AR. -Atlas’ regurgitation-
C2前日譚 了
初稿:2015.4.26
†序幕:「空」
その黒い人影。空ろという側面の名前を持った何かは、己が「忘我」であると自覚していた。
ある固定した「意味」に、人影は遠い何時かに取り込まれた。
その「意味」に長くふれていたことで、それと似たことができる。ヒトの記憶を奪う性質を、後天的に持った不死の骸だった。
「――うん。蒼潤君、鶫ちゃんの、忘我は上々」
何かに熱中する。何かに茫然とする。相手のそうしたカギを、元々持っていた霊的な感覚で、骸は手探りで掴み続ける。
「槶君はやっぱり、意外に苦戦したな。チャンスは一番、沢山あったのに――蒼潤君の時にやっと、一緒にだものね」
求めるものは、最もそれが必要な相手にこそ苦労する。そんな風に、不死の骸はただ明るく笑う。
「悠夜君のは。まぁ、無理って、最初からわかってたけど」
カギを得て、中に入り込めても、動かせないものもやはりあった。
世の中は甘くない。だからこれで、その願いは及第点だろう。自らに言い聞かせるようにそれを呟く。
「これでいつでも――この子達なら介入できるよ、シーちゃん」
その三人の子供と同じ年齢の、ある娘の名――
娘にとって、最も自らの闇を知られたくない相手のカギを、探し求めた忘我の骸。その望みはただ、彼らに何もしないことだった。
「これで一歩、リードって所か。さて、どう出るかな? 白夜ちゃん」
その相手に彼らのカギを渡さずに済んだこと。その功績だけに微笑む。
そうして身近な昏く赤い夢を、しばらくただ、黒い不死人は待ち続ける。
+++++
†予告編:Atlas' ver.2
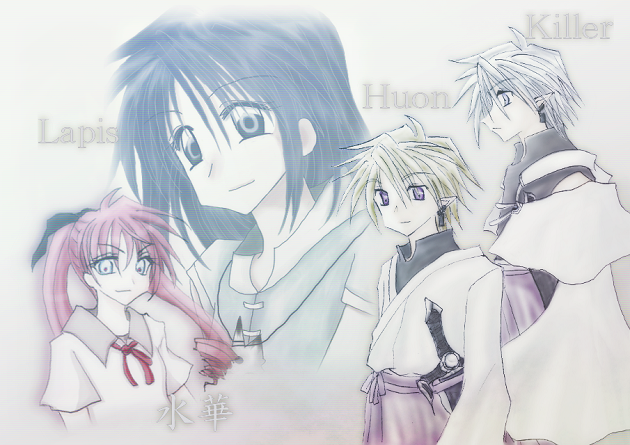
遠い昔は灼熱地獄。現在は開発途上の南の島の一城で。
朝一番から、水華にここ数カ月同伴する相方のPHSが、目覚まし代わりに鳴り響いた。
「もしもし? おはよーくーちゃん、元気してた?」
その幸せげな着信音は、相方ラピのPHSの、待ち受け画像の帽子の少年とすぐにわかる。
「今? 大丈夫だよ~。お寝坊さんなヒトが近くにいるから、叩き起こすくらい派手にお喋りしたいなぁ♪」
まだまだ起きる気のない水華は、意地でも惰眠を決め込む。
伝話相手は唐突な質問をしたようで、ラピが首を傾げていた。
「うん? うんうん、いるよー。去年くらいから私と同じで、拾われたお兄さんなんだけど」
その質問はもう一人から、とPHSの話し手が変わったようだった。
「おはよー鶫ちゃん、久しぶりー♪ みんな元気―?」
あくまで我関せずと、布団を被り直す水華なのだが……。
「っええええっ!?」
その声はあまりに、無視できないほど大きかった。
「ユーオン、そっちにいるのぉぉ!?」
数少ない義理の親戚。彼女らと年代の近い誰かの名前。
何も関係ないはずの水華は、ようやく目を開ける――
+++++
竜牙水華は生まれつき、反省という思考とは縁が無かった。
なのでこの、しきりに現状を省みている、瑠璃色の髪の相方を鬱陶しそうにする。
「ねぇ水華。ほんとにこれで良かったのー?」
水華の義理の姉の養女で、一つ年上でも義理の姪にあたるラピス・シルファリー。通称ラピのにこやかな追及が今日も煩い。
「ジパングに帰るの、私だけだろーなって思ってたのになー。水華が自分から私についてくるなんて、信じられない~」
これまで少女達がいた「南の島」から、世界地図の中央「ジパング」という島国に向かう船で、海を見ながら二人は話す。
「るさいなぁ。あたしがジパングに用があっちゃいけないわけ?」
おっとりとした速さで進む中規模の客船。水華の短いスカートと、髪を纏める黒いリボンが風にはためく。長い茜色の髪を巻き、毛先を二つに分けたポニーテールが解けないか、色素の薄い水色と紅の瞳で水華は追いかける。
「だって水華、あれだけ南の島のこと、気に入ってたしさ」
無愛想な水華とは対照的に、ラピは常に適度な笑顔だ。肩までの直毛と、首の後ろだけを長く伸ばす髪を揺らし、深い青の目で水華を見つめる。
「私達を置いてくれたザイさんも、城の他のヒト達も、水華がいなくなるの残念そーだったし。クアン君もサエル君もエルルちゃんも、いきなりでビックリしてたよ?」
「そりゃ、あんたが、ユーオン迎えに行くので帰ります! って、いきなり言い出すからじゃない」
「私は元々、そろそろお暇しなきゃって思ってたんだよ。でも水華は、南にずっといたいかな、と思ってた」
水華を見下ろす体勢で、ラピは柵の外側から足をかけて立っている。無袖の功夫服のような身軽な服装で、水華も水夫服と、二人して活動的な恰好が好きだ。
「別に、ジパングと南程度の距離なら、いつだって行けるし」
「あはは。すっかり水華も、おとーさん達と一緒で放浪人だねぇ」
旅する二人の少女は、南の地――十五年前までには鬱蒼と森が茂り、一つの城しか無かった島で、城主の厚意で滞在させてもらっていた。
「それじゃやっぱり、水華もザイさんとクアン君のこと、気に入ったでファイナルアンサー?」
「誰がよ! アイツらいつかまとめて見返してやるから、その日まで首を洗って待ってろってだけよ」
かつて四天王などと呼ばれ、強い「炎」を持った城主と、城主の甥である美少年。同じ「炎」を持ちながら歯が立たなかった水華は、ラピを睨むしかない。
この小さな世界――「宝界」には、数々の神秘「力」が存在している。そんな力をほとんど使えない人間に対して、人間の姿をしながら人間ならぬ力を持つ化け物をまとめて「千族」と呼ぶ。二人が出会ったのは、その中でも特に強い力を持つ者達だった。
「ムリムリ~。だってザイさんは『四天王』で、クアン君は次の『守護者』なんでしょ? ものすっごく強い魔族さんと天のヒトだって、水華が自分で言ってたんじゃんー」
「それならあたしは、魔族であり天のヒトなんだから。どっちも対抗できるなんてあたしくらいじゃない」
さらりと言う水華は、二つの有名な血統を幼少時から鍛えられている。類稀な聖魔両刀の魔法使いとして、一人立ちを果たした後だった。
「それって要するに、水華はどっちも中途半端なんじゃないの?」
「何でよ! アイツらだって半分人間とか、中途半端そのもんじゃないのよ!」
化け物の中でも、血統が旧く純度の高い者が「魔族」や「天界人」だ。それらと人間の混血は、数は少ないが、混血の方が強力なことはままあるらしい。
「そーだよねぇ。あまり人間の血が増え過ぎたらダメダメになるけど、その揺らぎが振り幅になるって、おとーさん達は言ってたよ」
「知ってるし! だからズルイってーのよアイツら!」
神秘の王道、魔道を叩き込まれた水華は当然知る知識。それを知りつつ口にするラピには苛立ちしかない。
「あれー。偉いねェ水華、さすが賢い賢いー」
こうして、水華をからかうことを至上とするラピを、もう乗せられまい、と不服気に睨む。
「クアン君って本当、優しいを絵に描いたみたいな美少年さんだったよねぇ。それなのに芯も強そうで、何か尊敬しちゃうなあ」
「別に生まれは関係ないでしょ。大体アイツ、ザイの甥だし」
「そーかなぁ? 確かにザイさんも物静かで優しかったけど、怖い所も持ってるヒトだと思うな、やっぱり」
「魔族」はヒトから奪う悪魔。それはよくある認識だ。しかし「天界人」は、存在をあまり知られておらず、代わりに近いイメージで知られる「天使」を思えば善なるもの、とラピは考えているらしい。
「あれだけザイに懐いておいて、よく言うわよ」
「え? 私そんなに、ザイさんに懐いてた?」
そこで本気で不思議そうにするラピに、こいつ……と、水華は両目を怪訝そうに細める。
「むしろ逆だけどなぁ。ザイさんには甘えちゃ駄目だなーって、ずっと思ってたんだけどな」
「それは知ってる。つか南のヒト全員にそうだったし、あんた」
あはは、といつも通り笑うラピは、何の屈託も無かった。
「だってザイさん、死んだお父さんにそっくりなんだもん」
そうしてあえてブレーキをかけていた理由を、あっさり口に出した。
「でもだからこそ、お父さんじゃないってわかってないとだし。大体、ザイさんは水華の獲物だもんね、狙っちゃダメだよね」
「意味わかんないし。ヒトのせいにするなっつーの」
ラピが何を言いたいかは薄々感じつつも、ぴしゃりと否定する水華だった。
一しきり水華をからかい満足したのか、ラピは最初のように、これで良かったの? とまた口にする。
「ユーオン迎えに行くくらい、私一人で大丈夫だよ? 元々、私の家だってジパングだから、後は帰るだけだし」
「知ってるし。あんな危ないの野放しにしたら、あんた一人で止められるわけないでしょーが」
だから付いてってやってんの。と恩着せがましく言う水華に、ラピは一瞬、キョトンとした後……柵から降りてまで、お腹を抱えて笑い出した。
「有り得なーい、水華が心配とか有り得なーい! ていうか絶対、ユーオンより水華の方が危険度上だしー!」
昨春にラピの養父母に拾われた少年。十四歳のラピには一つ年上で、兄貴分にあたるユーオンは、基本的には穏やかで平和な笑顔の似合う、金色の髪の少年だった。
「そもそもユーオン、水華とは比べ物にならないくらい弱々なのにー」
「何言ってんだか。アイツ弱いのは普段だけで、銀が起きたらあっさり人死にが出るわよ」
少年は時により、その髪が銀色に変わり、無表情で物言わぬ死神になる。それは数度しか会っていない水華にもわかるほど、ラピに危機感を持たせていた。
「うんうん。鶫ちゃん曰く『花の御所』でも何回か銀色さんになって暴れちゃったみたいで、ホントに頭が痛いよー」
ただしそれは、ユーオンが危険だからというわけではなく……。
「ああもぉー、鶫ちゃんと蒼潤君のご両親に、どれだけ謝ればいいんだろう、私。五ヵ月近く御所に居候なんて信じられない、ユーオンてば」
「何でそんな、あんたが謝る必要があんのよ」
およそ半年前に、ラピは養父母の急な出張と同時期に、水華と共に唐突な旅に出た。何も知らずに一人で家に残されたユーオンが、事もあろうにジパング有数の管理階級の居所、「花の御所」に転がり込むとは。
「私が紹介するって言った時は見向きもしなかったくせにぃ。何処で鶫ちゃん達と知り合ったのよー、ユーオンのバカぁ」
唸るラピは先程と違い、今度は最上段を足場にしゃがみこんでいる。
「つか、柵降りなさい、柵」
「私だって御所にお泊りすらしたことないのにぃー。羨ましい、じゃなかった不届き者めぇ」
怒ったように言いつつ顔は笑い、頭が痛い、と眉をひそめながら、ラピが全身ではしゃいでいることが水華にはわかった。
それなので、呆れた顔は崩さないまま、淡々とラピに尋ねる。
「『花の御所』の奴らって、元々あんたの知り合いなんだっけ?」
「うん、そーだよー。鶫ちゃんと蒼潤君と、後は蒼潤君の弟の悠夜君が、仲良くしてくれるんだよー」
にこにこと答えるラピは、不思議なものだよねぇ、と続けた。
「鶫ちゃんと蒼潤君とね、二人の友達のくーちゃんが、みんな私と同じ十四歳なんだ。クアン君達も三つ子で、水華と同じ十三歳でしょ?」
「偶然同年代が揃っただけじゃない」
「それだけじゃなくてね……何か、同じ匂いがするんだよね? 鶫ちゃん達と、クアン君達」
そこで不意に、ラピは柵の上にしゃがんだまま、何処か遠い目で海を見つめた。
「水華はクアン君達と、仲良くなれて良かったね」
「……」
別にラピは、先日まで共に学校にまで通った彼らと、打ち解けていないわけではない。それでもそういう性分なのだ。
「私はやっぱり、住む世界が違うのかなぁ。南のお城もそうだけど、花の御所にもしもお世話になっても、結局落ち着かないんだろーな」
この人間の娘は常に、人間ならぬ血を持つ者と一線をひいている。南の者との付き合いを通して、水華は改めて感じていた。
「ってことは、花の御所の奴らにも猫被ってるわけ? あんた」
「あははは。水華の前にいる私がホンモノとすれば、それより少しは多分マトモかな」
「逆だし! クアン達相手のがあんたチャラけてたし!」
常に笑顔で、時に濃い毒を吐いていたラピ。マトモの定義など興味ない水華すら、反論したくなることをラピは度々口にする。
ラピと水華は、ラピが水華の義姉に拾われた六年前から、里帰り時に度々顔を合わせる間柄だった。
「あんたが笑いながら、美形以外生きる価値ナシ。とか言う度、ラピってどーいうコ? って、何度きかれたことか……」
「本当~、感謝してよね。私がそうしていれば、水華すら真っ当に見えたんだねー」
船にあまり揺れがないとはいえ、柵上で器用にバランスをとるラピは、家系に伝わる人間向きの護身術を幼少から体得している。同年代と比較して稀なのはそのくらいで、家系に関する事柄以外では普通の人間、というのが水華の認識だ。
「真っ当でない猫を被るなんて、図々しいっつーの」
「うわぁ。水華に褒められちゃった。これから嵐になるよね」
「褒めてないし! クアン達の前のあんたの方が上等なのは、あたしも同意するわ」
「失礼なー。アレは私の、ノーモア真っ当モードなのにぃ」
「……はっちゃけてただけでしょーが、単に」
「ジパングではポッシブリー真っ当モードですよーだ。私にはそっちの私の方が、上等なんだもん~」
いずれにせよ、明るく危うげな部分をラピが見せる相手は限られている。水華の他には、同年代ではユーオンくらいだった。
いつまでも柵から降りようとしないラピを、苦々しい思いで水華は見続ける。
「クアン君達も鶫ちゃん達も、何か自然にいいヒト過ぎてさぁ。一度甘えちゃうと私、骨抜きになっちゃいそーだし、向こうは甘えさせてくれちゃいそーだし。そーいうのって、お互いのために良くないよね? うん」
「……ジパングの奴らも、あんな感じなわけ?」
水華の方は、自らの欲望に忠実であることを良しとし、思う存分気ままに生きている。ラピが言うように、自然体で普通に優しく在る同年代は釈然としない。
しかしそれが、彼らには自然な状態とわかる、複雑な相手でもあった。聖と魔を併せ持つ水華は、案外人間に近いリアリストなのだろう。
「あんたがよくPHSで話す奴は、確かにそれっぽいけど」
「……くーちゃんはわかんない。いいヒトなのは、確かだけど」
ふっと、珍しく少しラピの笑顔が蔭る。
「御所のみんなは、クアン君達みたいにそのままいいヒトだよ。でもくーちゃんは……それだけじゃない感じ」
その正体が未だ掴めない、とラピは当惑顔だ。対人観察が趣味のラピには珍しい姿でもあった。
「意味わかんない。あたしはどいつも、話しか聞いたことないし」
これまで何度も、ラピはジパングの友達についてニコニコと語った。今日も改めて水華に熱く口にする。
「みんなホントに、優しい化け物の子供さん達って感じだよ」
人間であるラピの周囲には、何故か人間がいないという。水華のみならず、水華の義兄姉である養父母も、ジパングに住んでから出会った友人達も。
「みんな、御所の管理者の烏丸さん一族だけど、蒼潤君は剣士だから、着物の袖が邪魔って破いちゃってるんだ。髪の毛が珍しい夕陽色でね、顔はいつもブアイソで、男は無言でみんなを守る! みたいな雰囲気がかっこいーの。お父さんより師匠の幻次さん似なんだって」
「へー」
「剣も凄いよ、剣の修行が命って感じで、道場破りとか余裕だよ。水華といっぺん、いつか闘ってみてくれないかなぁ♪」
「へー」
誠意のない返事の水華は、幼少から剣を仕込まれている。しかし現在は専ら魔法使いなので、興味がなかった。
「幻次さんの娘で、蒼潤君の従妹が鶫ちゃんで、着物なのに身のこなしが軽くて、でも凛とした落ち着いた貴族さんなんだぁ。ジパングでは珍しく髪も短いし赤色だし、目が鋭いからきつく見えることもあるけど、可愛いし凄く優しいし、理想的な女の子なんだよ♪」
「ふーん?」
「その上武術もいけるし、呪術って魔法も使えるし。内緒だけど、実は銃の使い手で、私にも教えてくれるけど全然敵わないよ。大体何でもできるんだよね、鶫ちゃんって」
「……へー」
ちらりと今度は、ラピを見返す水華だった。
「それだけ聞くと、そいつら化け物って確信できないんだけど。剣も銃も、呪術も人間だって使うし」
人間のラピに、何故彼らが化け物であるとわかるのか、ときくと、それは至って単純な理由だった。
「御所のみんなもくーちゃんも、西の大陸出身の私とは言葉が全然違うのに、会ったその日から話せちゃったんだ。それって化け物さん特有の能力らしいね?」
強い化け物――あえて呼称を探せば「聖魔」という水華や、霊獣やら何やらの義兄姉はともかく、島国ジパングの中心の京都は、本来は人間の国だ。それなのにそうした者達が紛れ込んでいるらしい。
「それに、蒼潤君の弟の悠夜君なんて凄いんだ。見た目は可愛い感じの、袴が似合う小さな子なんだけど、喋ると一番しっかりしてるの。天才って言われるくらい博識で、霊感もすっごい強いんだって」
「……ふーん」
「何でか私、たまに避けられてる気がしなくもないんだけど。ホントは凄く繊細な子みたいだから、何か私、邪悪なオーラが出てるのかも~」
「……へぇ? 自覚あったんだ、ソレ」
無愛想なまま感心したように言う水華に、ラピは笑って首を傾げる。
「悠夜君にはそんな、ヘンに接したつもりはないんだけどなぁ。鶫ちゃん達と会った頃は、まあ私、荒れてたんだけどねー」
あはは、と微笑むラピは、実の父を突然亡くした後、父を追って母が自殺した悲愴な過去がある。その後も二年近く養家を転々とさせられ、荒れる理由はあった後での友人達との出会いだった。
「…………」
友人達をひとまとめに呼ぶ時は、主に紅一点の鶫の名を出すラピに、水華は少しだけ眉をひそめる。
「んーで……後一人は?」
「え?」
「PHSの奴のこと。ソイツが一番、最初に会ったんでしょ?」
「そうだけど……くーちゃんはまず御所の人じゃないしなぁ。着物も着てないし、ジパングのヒトなのかも実はわからないよ」
ラピは、友人達を語る際には必ず、そこでトーンダウンしていた。
その相手こそが大きい存在だろうに。最初に声をかけてくれて、友人など作る気のなかったラピを御所の者達に紹介し、仲良し組に混ぜ込んだ張本人で……今も度々、PHSで連絡をとる間柄なのだから。
ラピのPHSの待ち受け画面は、深型の帽子がよく似合う、明るく優しげな笑顔のその少年だ。特別な存在であることはわかりきっている。
「くーちゃんのことは、若い薬師さんってくらいしか知らないなぁ」
無邪気に見えてしっかりしてるんだよ、と、これまでより落ち着いた様子でラピは口にした。
「あ、でもたまに、想像力が暴走しちゃうと凄く面白いんだよ。風が吹けば桶屋――とかでも、お風呂に穴が開くと大変だよ!? 気付かずに追い炊きして火事になっちゃったらどうしよう!? ご近所さんに何て謝ろう!? みたいな、お人好しさんなの」
「……」
ラピがPHSでその少年と話す時は大概、そうした話題で更に相手を煽るらしい。
――ダメだよ、くーちゃん! お風呂ってことは大体夜だよね、黒焦げ姿でご近所訪問なんて、お隣さんショック死するよ!
――えええっ!? つまり風が吹いたら僕、殺人犯決定!?
そんな無害なやり取りを好み、相手に深入りしようとはしない。
「……要するに、あんたがたまに突拍子のないこと言い出すのは、ソイツのせいなわけね」
「えー? それどういう意味、水華?」
珍しくキョトン、とラピが水華を見下ろす。いつも絶えない笑顔は、まるでPHSの少年を写したようだと、以前から水華は感じていた。
そこで話題を変えるように、京都はいい所だよ! とラピは、何度目かの口上と共に笑った。
「私も色んな所に行ったけど、ジパングのまったり感は凄いよぉ」
世界の内でヒトが住むのは、東西二つの大陸に、中央のジパングとその南にある島だ。最も文明が進む西の大陸が、護身用の銃を持ち、近代的な恰好のラピの出身地だった。
「水華と最初に行った東の大陸は、おとーさん達ともそんなに行ったことなくて、港町付近のことしかわからないけど……何処の土地も大概、港は一番栄えるって言うから、そうなると東の大陸はホントに未開っぽいね」
「つまり……港町すらしょぼかったと言いたいのね、あんた」
あはは、とラピは、悪びれもなく笑う。
「だから水華が言ってたみたいに、吸血鬼伝説とか怖がったり、村人総出で吸血鬼狩りしたり、凄い教会があったりするのかな」
「……巻き込まれた方はたまったもんじゃないけどね」
「電気も港町周囲くらいしかなさそうだったしね。南の島はその点、最近発展してきた所だから、開発途中なのに西の大陸なみの賑やかさがあるのが凄いね」
人口が最も多く、ほとんどが人間である西の大陸は、東半分に商業都市やディアルスなどの大国が集中している。
未開の東の大陸、先進の西の大陸の間の島ジパングは独特の文化を持ち、服装や建物、言葉が明らかに他とは違った。
「でも西の大陸も少し奥地に行けば、私の村みたいな古い所があるし。その点、南はもうかなり開発されてて、ジパングに至ってはほとんどの土地が人間の居住地として整備されてるんだよねー」
水華は何度か、ジパングにも行ったことがあるものの、ラピの家以外には京都に行ったことがある程度だった。
両親、義理の兄姉とラピとユーオン以外、水華には全然知り合いがいない。
――実はねぇ。あんたは私達の娘じゃないのよ、水華。
――……は?
育ての母――半年前までは実の親と思っていた相手が、突然正体を明かした後から、水華は親を探す名目の旅に出ることにした。実際の目的は家事や修行三昧の日々からの解放だが、それまではお金の単位も知らない箱入り娘でもあった。
――よ……よくも今まで育ててくれやがったわね!?
修行しか教育方法を知らないらしい親の下、育ての母には剣、父には魔道を教え込まれた。父はともかく、母の方針は恐怖政治に近く、こうしてジパングに向かう船にいる今も、実家にだけは帰るまい、と心に誓う水華だった。
ジパングからしか行けない土地に、水華の実家はある。何処にあるとも知れぬ孤高な無人の大陸で、唯一存在する有人の小さな城だった。
――水華もたまには、おば様達に遊びに連れてってもらえば? ずっとここに引きこもってるよりさぁ。
――つーたって、オフクロ達も滅多にこっから出ないし。
ラピと旅に出る半年前までは、水華はほとんど遠出したことはなかった。
――ここなら京都のゲートに近いのになぁ。おば様達だってお出かけしないわけじゃないんだし、その時にもっとついていかないの?
――その度に家事一週間独占の刑とか、いちいち執行されるからイヤ。
この世界には至る所に、空間を超え土地を繋ぐワープゲートという短絡経路がある。出口が固定したもの、固定していないものを合わせて無数に存在している。
固定していると確認された安全なゲートは、誰でも自由に使える。様々なゲートが存在する中、水華の実家近くに繋がるゲートは、特定者が複雑な力を行使しないと使えないものだった。
――ほんとに、世界地図に無いような場所だもんね、ここって。
――海に出たって絶対大嵐で、岸に打ち上げられるし……。
そのため水華は、出入りしたい場合は周囲に頼るしかない。養父母に連れられて世界中を旅するラピとは対照的に、真性の世間知らずとして育ったのだが……。
――大丈夫。あんたは頭は悪くないから、すぐに旅慣れるわ。
魔道など、知識の吸収が良く、魔法と剣を既に達人レベルに操る水華。順応性も高い養女を旅に出すことに、育ての両親は不安を全く見せなかった。
水華が実家を出て、早くも半年以上になる。
ジパングから船に乗り、東の大陸、南の島、北の島、そしてまた南の島と、実に密度の濃い旅を二人はしてきていた。
「いっぱい色んなヒトに会ったねー。また会えるといいね」
「……会わない方がいいって、言われた奴もいるでしょーが」
柵の上に立ち上がったラピが、バランスを取りつつ歩き出すのを、嫌な気分で水華は見上げる。
「……何でだったっけ」
先程からずっと、不安定な体勢のラピが気になる。何でだっけ、と水華はふと、腕を組んで考え込んだ。
「水華? どーしたの?」
ラピがそこで足を止め、水華の方を振り返った時。
ちょうどそうして、バランスのとりにくい体勢をラピがとった時だ。
今まで静かそのものだった船が、突然大きく揺れた。
「――げ」
その瞬間に水華は、嫌な予感の正体を思い出す。
「――あ」
全く想定外に揺れた船に、足場をあっさり失ったラピは――背後に広がる海へふわりと浮き上がるように、景気の良い水しぶきの音をたて、一瞬で呑み込まれていった。
その姿は、水華には強く、見覚えのあるものだった。
何でだったの? と。
それがその時、同じ光景が訪れる直前に、水華が口にした問いかけだった。
「ちょっとラピ……!」
一瞬であっさり海中に消えた相方に、ただ水華は茫然とする。
「あんた……二度までも――!」
これと全く同じことが、半年前にもあったのを否応なく思い出して。
帰らない、と決めた旅に水華が出る時のことだ。育ての母は何故か、彼女からは義理の孫を同伴するよう、水華に申し付けた。
――あんたはラピスちゃんを守りなさい、水華。
この海のように深い青の目を持つ義理の孫。空のような青の目の養母は、ただ痛ましげに見つめていた。
――あのコはとても……危うい子だから。
基本はただの人間であるラピと、化け物の血をひくらしき友人達。
初の船出で、単調な海の景色に飽きた水華は、深い意味もなく尋ねただけだった。
「何で、そいつらと知り合ったの?」
「――え?」
ラピは柵の上に、海に背を向けて腰掛けながら笑って答える。
「何でなんだろうね。私もずっと、不思議だったんだ」
「?」
「私ね、初めてジパングに来た頃、アクマって呼ばれてたんだ」
元々首を傾げていた水華は、唐突な話に、怪訝にラピを見つめる。
「アクマって何なのかは、よくわからなかったけど」
ラピの髪は、人間であるのに瑠璃色をしている。
友人達やユーオンのような赤毛や金髪は、人間にも有り得る色だが、人間の髪と目に深い青の色は存在しない。化け物扱いされるのも無理はないことだった。
「要は、余所者の私が目に障ったんじゃないかなぁ」
近隣の子供達と幼いラピは反りが合わず、周囲の子供は、言葉も通じないラピをアクマツキ、と言って罵ったという。
「でも、私は誰相手にも同じように荒れてたのに、くーちゃんも、くーちゃんが会わせてくれたみんなも、いつの間にか仲良くなってくれた。それがどうしてなのかは、わからないよ」
近隣の子供達と友人達の違いとして、ラピと言葉が通じることは確かに大きかった。しかし逆に、ラピはそれで、誰とも打ち解ける気などなかった内面を、態度だけでなく言葉でも伝えていた。
ジパングを後にする船の上で、寂しげに見える顔でラピは、水華に笑いかけながら思い出の一つを話した。
――ラピちゃん、遊ぼー! 今日は習い事、いつまでなの?
京都にジパング語を学びに通ったラピに、よく街を歩いている槶は、度々声をかけてきたという。
――……知らない。きっと終わったら、もう暗くなってるよ。
それに対して、色よく答えたことなどなかった。それでも槶は、すれ違えば必ず声をかけてくるのだ。
――何で……いつも、笑ってるの?
槶とはたまに、同年代の鶫と蒼潤が一緒に街を歩いていた。子供にしては気難しげな彼らは、ラピを見ると何故かいつも、楽しげになったという。
――このヒト達は……私のこと、何もきかない。
自分が嫌われたのは、自分に問題があったからなのに。
それだけは知っていた、とラピは水華に笑って伝える。
「鶫ちゃんや蒼潤君はね。あ、何となく気が合いそうって、そう思えるものはずっとあったよ」
「へぇ?」
「でもくーちゃんのことは、未だにわかんないよ。よく伝話するし伝話してくれるけど、用もイミもない話も多いし、何でその時伝話きたんだろ、ってこともよくあるし」
「あー。そんな感じね、確かに」
ラピが持つPHSは、遠出の仕事に出がちの養父母と、有事の際に連絡をとるため渡されたものだ。用事や理由がない時に話すことを、最初の内にはラピは戸惑ったらしい。
「でもそれ、わかんないって首傾げるほどのこと?」
珍しく常なる笑顔を薄れさせ、深く考え込むラピにその違和感を伝えた……次の場面のことだった。
「……くーちゃんはどうして、私に笑ってくれるのかなって。私は……ホントはみんなと、一緒にいられる資格はないのに」
「――は?」
困ったようにラピが笑った瞬間、前触れもなく、穏やかだった船が大きく揺れた。
あれれ、と呟くと同時に、ラピは背中から海に落ちていった。
そんな光景を、まじまじと思い起こす。
半年前と同じように海に消えた相方について、水華はぐう、と悩ましげに考え込んだ。
「さすがに……有り得なくない?」
前回は嫌々、助けるために水華も海に飛び込んだ。
しかし思いの外手間取ったため、船は遠くに行ってしまった。ジパング近海の孤島に何とかラピを連れて辿り着いたが、その後が色々と悲惨だったのだ。
「……あれをもう一度、あたしにやれっつーの?」
そして水華は、意識のないラピを孤島に置いて旅立つ。
それでも東の大陸でラピに見つかってしまい、諦めて同伴しているわけだが……。
水華は元々、決断は早い方だ。
考えるより先に動くこともままあり、それなのに今は呑気に、甲板に立ったままだ。
「悪いけど――……付き合い切れないわよ、さすがに」
あまりにあっさり、通常は考え難い、非人道的な決断を下す。
「あたしの邪魔をするならついてくるなって、前にも言ったよね」
ラピを守れ、と、育ての母の言葉も当然覚えている。
それとこれとは話が別と、くるりと踵を返し……なかったことかのようにして、場を後にした水華だった。
船室に戻る扉を開けた直後、何かが水華の顔へ飛びついた。
「みぎゃああ! ぎゃあああどいて離れて、あっち行ってー!」
「――ポピ? ダメだよー、戻っておいでー」
まるで、猫の頭だけの生き物。頭から長い尻尾と、短い手足の生える珍獣が、器用に水華の顔に張り付いている。奇跡の幻を呼ぶという珍獣の飼い主が、あはは、と笑った。
「早く取ってこれー!! あたしにこいつ近付けるなー!!」
「はいはい、こっちこっち。ホントに水華は、ポピが怖いんだねぇ」
普段は冷静な水華が、その珍獣にだけは慌てふためく。実家の近くの森に同じ珍獣が大量に住み、小さい頃から水華に何度も幻で恐怖体験をさせたからだ。
その様子に微笑ましげに……珍獣を模した小さなペンダントを身につける飼い主が、べりっと珍獣を引き剥がした。
「どーしたの、水華? 今まで一人で甲板にいたの?」
その飼い主とは、紛れもなく……――
先程水華の目前で、海に落ちていったラピに他ならず。
「また私のこと置いて、途中で船から降りちゃったのかと思った。船長さんとか心配するから、今度はそんなのダメだからね!」
「……また?」
そこでラピが、おかしなことを口にする。
「去年、一緒に旅に出た時。私だけ東の大陸行きの船に置いて、忽然と消えちゃったじゃない、水華」
いつもの笑顔ではなく、心配と不服の混じる顔で水華を見る。そのラピの肩で、水華の嫌いな珍獣が偉そうに鎮座していた。
一人で東の大陸についたラピは、港町より北東の村にいた水華を執念で探し出したという。
その珍獣の存在と、胸元の笛のペンダントに、ようやく水華はある真相を確信していた。
「じゃ……あの時も、ニセモノ?」
「? あの時、ニセモノって何?」
確かにあの時、彼女の身近に珍獣と笛はなかった。思い至るのが遅過ぎたくらいだ。
「みんなと別れて、もう半年って早いね。早いのに、長い旅だった気がするね」
にこり、と笑うラピは、これまでと何も変わるところはなかった。
水華はただ、違和感を確かめるために、同じ問いかけをした。
「何で、そいつらと知り合ったの?」
「――え? どーしたの、急に?」
ラピからすれば唐突だろう質問。しかしラピは、嬉しげに笑った。
「きっとみんな優しい化け物さんだから、弱っちい人間の私も、気にしないで面白がってくれてるんじゃないかな。クアン君やザイさんが、水華は危なっかしいって助けてくれてたみたいに」
「……あんたと一緒にするなっつーの」
不服な水華と対照的に、穏やかにラピが微笑む。
しかしすぐにラピの顔は、苦笑いに変わる。気弱にも聞こえる声でラピは、ねぇ……と水華を見た。
「水華は南にいたかったら、無理してついてこなくていーよ? おば様達の言い付けは知ってるけど……ユーオンやくーちゃん達がいれば、危ないことはないと思うよ、私」
「……別にあたし、あんたのためにジパングに行くわけじゃないし」
現在はある目的のために、水華はラピの同伴を決めた。南の城で色々と新しく知ったことがあり、南の強者達を見返すためにも全くの本心だったが。
「……らしくないね、水華。私やユーオンのこと、心配してるなんて」
覇気なく笑いつつ、ニセモノと同じ心情を口にするラピだった。
だから水華は、先程までのニセモノが口にしたことも真実だと悟る。
たとえそれが、ホンモノには口にできないことでも。
「水華もくーちゃんも……偉いよね」
「――は?」
船室に戻りながら笑うラピが、水華はただ鬱陶しかった。
「二人も私と一緒で、ホントの血縁はいないのに。私みたいに拗ねたりひねくれたりしないもんね」
「あんたねえ。スネオやヒネクレの何が悪いっつーのよ」
水華は生まれつき、反省という思考とは縁を切られていた。
在るがままを認め、使えるものは使い、自身に合わないものは切る。そして欲しいものができたから旅に出る、それだけだった。
前だけを見る揺るがなさは、時が止まったようなもので――
「私も二人みたいに……強かったら良かったな」
振り返るしかできない、同じく時の止まった相方が、ただ笑った。
了
-at that time-
――は……? と。水華は一瞬、きつく目をつむった。
海に落ちたカナヅチの相方を孤島の洞窟に運び、やっと意識を取り戻した時だ。突如冷たい石床に叩き付けられて、水華の全身に強い痛みが走った。
「……何……あんた、誰?」
馬乗りになり、細い首に手をかけてくる相方。深い青のはずの目に、きらり、と殺意が金色に光った。
この相手には、相方の名前を呼びたくない。何故か一瞬でそう思わせる輝きだった。
彼女は、くすり、と――
瑠璃色の髪の娘が抑え続けた、最も深い闇を口にした。
「ねぇ、水華……水華なら、助けてくれるよね?」
「……はい?」
「ラピスを助けるために……水華を全部、私にちょうだい?」
その痛みはいったい、誰のものであるのか。
非力な娘が化け物の水華を圧倒する、理不尽な胸の痛みがあった。
「私と……一緒、に――……」
同じ赤い夢の下、時を止めた二人の少女。その夜は今もなお、続いている。
夕闇の中、不思議と明るい洞窟の岩肌が少女達を白く囲む。
絞め上げられて視界の翳む水華には、まるで真っ白な夜の悪夢だった。
それでも水華は、閉ざし続けていた目を開ける。
「悪いけど――……付き合い切れないわ」
いつかは夢の先に進むために。前だけを見る少女を、赤い夢は縛り続ける。
+++++
To be continued Atlas' -Cry- ver.2
千族宝界録AR✛blue murder.
ここまで読んで下さりありがとうございました。9/8に終幕と予告編を掲載しました。以後はC2新約本筋に入っていきます。
同シリーズ②DRは9/15に、③RAは9/29に別個でUPしました。お気が向けば良ければ。
新約版は様々な箇所をカットしているので、もし物語がわからない場合は下記をご覧下さると幸いです。
ノーカット版:https://estar.jp/novels/23591077
初稿:2014.7-11 再編:2020.2.29


