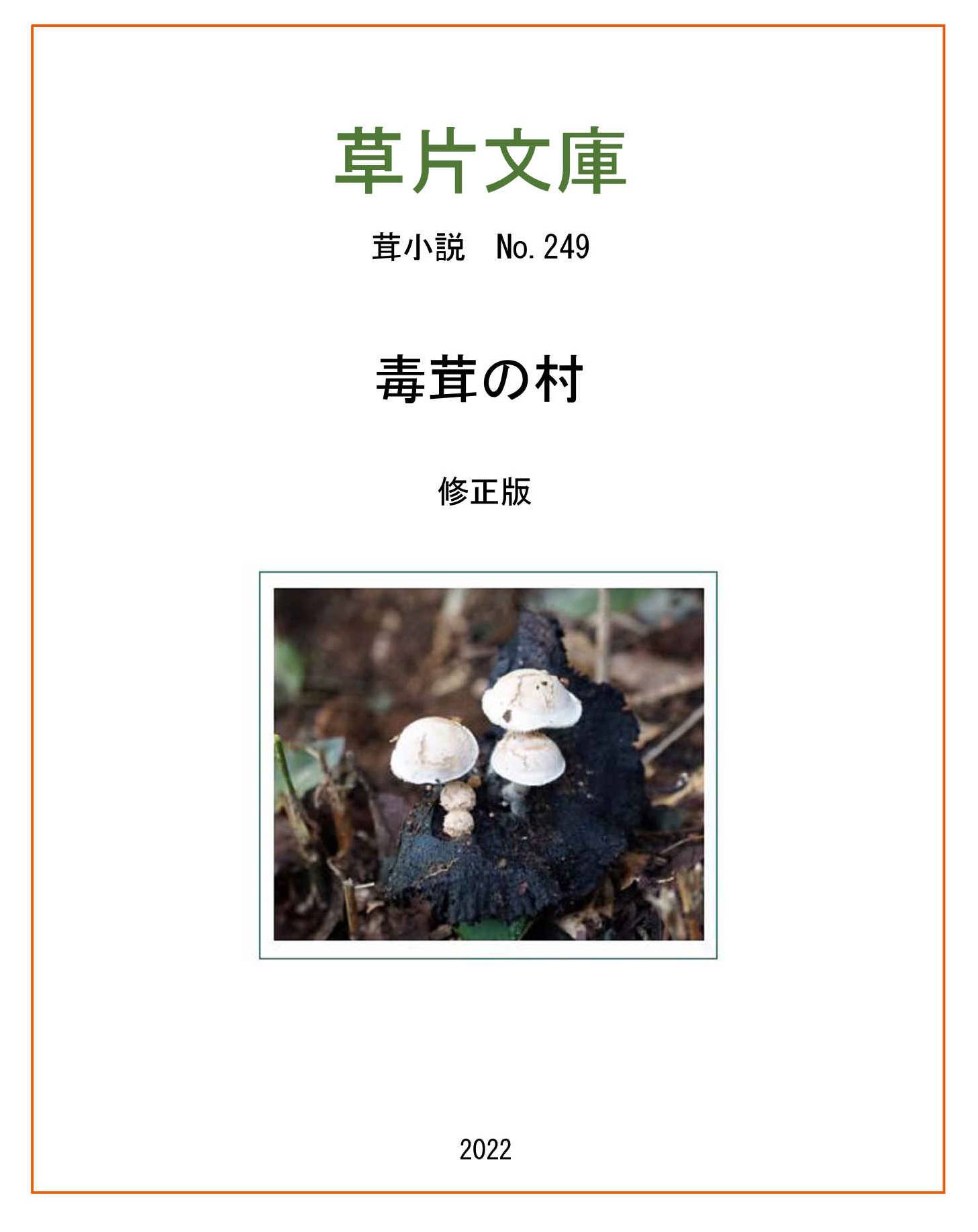
毒茸の村
茸村の歴史です。縦書きでお読みください。
日狩村はその昔ずいぶん繁栄したところだった。今では寒村の仲間入りである。信州山奥のこの村には、畑くらいはつくれるが、平地はほとんどなく、自分たちが食べる米をとるのに必要な田さえ狭いものだった。ただ水だけは豊富で、山の林のなかにいくつもの泉が湧き出し、村人の命と健康の源となっていた。山間を流れるきれいな水には大事なタンパク元である魚たちがたくさん泳いでいた。現在、日狩村は市の一区域として併合され、日狩地区と呼ばれている。数十軒の家があり、狭い田畑で自給自足のための稲と野菜を育て、天然の茸や山菜の販売、イノシシやシカの猟で生計をたてている。市の人口台帳には122名の名が登録されている。
もちろん四季を通じて、山の中には木の実、茸、山菜が豊富で、そういう場所にはウサギや鹿がすんでおり、村人たちは罠を仕掛け、食料にし、毛皮をとった。田畑はすくないが、昔から村人はさほど食べ物に苦労しなかったようだ。
そういう場所は日本の各地にあるだろう。その中でも日狩村は、独自の産物があり、全国から採取の依頼が舞い込んで賑わいを見せたこともある。
それは茸である。それはどこにでもあるという茸ではなかった。信州見渡せば、どこにいっても茸がたくさんとれる。だがその茸はこの村でしか見ることができなかった。
その昔、一人の老人がたくさんとってきた茸を食って、二日間死の淵をさまよった。医師などいないこの村で、周りの家族はただ見守るしかなかった。もうそろそろいけないかと家族が回りに集まったとき、老人がいきなり目を開け、立ち上がり、ノラ仕事の支度を始めたのには誰もが驚いた。息子は、おっとうだいじょうぶか、と声をかけたのだが、老人は、なにがだ、と逆に問い返したという。二日にもわたり、息絶え絶えで寝ていた様子など微塵も見せず、外にでていくと、そのまま畑にでて、土をたがやしはじめたという。
息子があとで聞いた話では、老人は毒茸を食べて死にそうな状態の間、泉に浸かり、からだの筋がもりもり盛り上がっていく夢を見ていたそうだ。どうしても体を動かしたくてしょうがなくなり、目を覚ましてすぐノラしごとにでかけのだそうだ。
息子が老人の食べた残した数本の毒茸を捨てようとしたのだが、老人は捨てるなといった。もう萎びてきていると息子が言っても、いやだめだと老人は毒茸をかかえこんだ。そして、毎日一本食べた。老人はみるみるうちに筋肉の張った若いからだになり、自分の息子の倍も働くようになったという。
その茸は名前がなかったのだが、老人の名である正太茸(しょうたたけ)と呼ばれ、若返りの毒茸として、その村の特産茸となったわけである。全国から干した正太郎茸を買いにきたという。
この茸は諸大名たちもほしがった。そのわけは、健康だけのためというわけではなかった。武将につく薬師たちは、その毒茸から毒の成分をとりだし、毒薬による暗殺に役立てていたのである。日狩村の住人は知る由もなかったが、武士の間では毒茸の村として知られていたということである。
今の日狩地区にそのような茸は採れない。ただの伝承話だったのか、今採れる茸のどれかが誇張して伝わったのかわからない。
これは、村の形成に興味をもっていた若い社会人類学者が、老人から昔の村について聞き取った話の中の一つである。
その社会人類学者は、村の老人から聞き取って多くの話を、研究雑誌や大学の紀要にたくさん報告している。それによると、日狩村には、正太郎茸が有名になるより以前から、毒茸の伝承話があったそうである。その学者によると、神代の時代から伝わる、村の成り立ちにかかわる話しで、いつごろその話ができたのかわからないという。
日狩村の数十件ある家々の誰もが、その話を祖父母、両親から聞かされ、よく知っていた。社会人類学者がそれぞれの家から聞き取った話は、出てくる人物の名前が少し違ったり、些末の部分に違いはあるにしても、おおよその話は同じである。
まだ日狩村という名前もついていないその村には八十八人の村人が住んでいたという。隣の村まではかなり離れているし、余所から訪れる人もほとんどいない。いつからそこに人が住み始めたのかわからないが、アダムとイブの話ではないが、森から男と女が現れて、林の中の日当たりのいいところに家をつくり住み始めたのが初めだそうだ。
森から出てきた男はエン、女はスイといった。その名前に関しては、家々で異なって伝えられていた。男の名前はヒ、女の名前はミであったり、ショウとリュウだったり、さまざまであるが、聞き取りをした社会人類学者は、男の名前は「火または日」に関係し、女は「水、流」に関係があるだろうと推測している。
林の中には茸がたくさん生え、木の実や山菜も豊富で食べるにはこまることがなかったが、エンとスイは畑を作るようになり、八人の子供を育てた。子供たちが大きくなると、林の中から現れた男や女と一緒になり、家を増やしていった。エンとスイは子供の伴侶となる人間が森から現れるのを当たり前と思っていた。というより自分たちがどこから現れたのかも知らないし、知ろうともしなかったようだ。子供たちは森から現れた男や女と番い、家を造り、移り住んだ。
エンとスイは六十近くまで生き老衰でなくなった。二人が死んだとき、林の中から一組の男女が現れ、家を作り住むようになった。その二人にも子ができた。エンとスイとの子供たちも大きくなり、森から現れた人と夫婦とになり、家を造った。
そうやって部落ができあがった。部落民は八十八人だった。
それからが不思議なことだが、村には八十八人の人間がいつも暮らしていた。誰かが死ぬと、林の中から男か女が現れ、子供が産まれると、老人が一人死んだ。子供が大きくなると、必ず森から人間が現れ、その子供と夫婦になる。するとやはり老人が一人死んだ。こうして、いつも八十八人だった。
伝承にはそのような人たちの生活を支えていた森の中の地下では壮絶な戦いが繰り広げられていたことが述べられていた。
森からエンとスイが現れた頃、森の中では様々な茸が陣取り合戦をしていた。一番勢力が強いのはエグチたちである。日の光が適度に当たる一番いいところにはエグチたちがじんどっていた。エグチたちは長い足を何本ももち、力強く土の中に足をのばしてふんばっていた。茸は植物のように根を土の中に延ばして立って、日の光をあび、風を吸って生きていると考えられていたようだ。茸の場合、根ではなく足と考えられ、夜歩くとも考えていたようだ。茸は植物のように種はつくらないが、風に粉を巻き、その粉が水とともにこね合わされ、朝日で茸の形ができる。
エグチはほかの茸たちが朝日により作られる前に、月の光りで生まれる。それでほかの茸より早く育ち、いい場所をとることができた。
テングタケの仲間は朝日により茸になることから、森の中程に集まることになった。星の光で生まれる茸はあまり大きくならず、そこいらに点々と育っていた。
森の中は茸だらけ、風にふかれていた茸の粉、胞子たちは集まって茸の形になる場所がなかなか見つからなかった。茸になれない胞子たちはお互いに空いている場所を伝えあい、そこに集まって茸になった。
そのころの茸は生えると生えっぱなし、大木と同じように、何千年も生きていたという。大きな嵐で倒壊したり、動物に食われるようなことでもない限り、すなわち物理的なアクシデントがない限り、そこに立ち続けていた。
そのころの茸は森の中にしか住めなかった。木々の間に足を延ばすことができなかったのである。
しかし、いくら広い林であろうと、限度がある。何千年もたつと、茸のいる場所がなくなった。
すると茸に変化が現れた。森の中の木の上に足を踏ん張る茸がでてきた。腰掛けや木耳の仲間である。しかし、それは木がいやがった。すると枯れて倒れた木に足を延ばすものも出てきた。ナメコなどはその代表である。
日の光が強い森の外にでる茸もあった。しかし、森の外にでた茸は太陽に照らされて七日もすると死んでしまった。それでも森の外で新たな茸が生まれるようになった。それも森の中は新たな茸が育つための隙間がなかったからである。
一方で、森の中ではまだいくつかの茸たちは育つ場所を探していた。死んだ動物たちに足を延ばすものも出てきた。死んだ動物の骨に足を延ばす骨茸である。この骨茸は自分たちの映える場所を確保するために、動物を殺す毒をもっていた。毒骨茸である
毒骨茸の胞子たちが茸になる場所を探していると、森の中に一本骨が突き出ているのを見つけ、そこに付着し、星の光で茸になった。骨が土の中に広がっていることを知った骨茸は、行き場所がなく風に舞っている胞子に土の中にまだ骨があることを伝えた。風の中の毒骨茸の胞子たちは土の中の骨の上で、土にしみこむ星の光をもらって茸に育った。
その骨は大昔の人間の骨だった。それは縄文人の骨である。
毒骨茸の足がとりついた骨はしだいに土の上にせせりでてきた。縄文人の骨にはどんどん茸が育ち、毒骨茸の上に育つ茸、いまでいう櫓茸の仲間がとりついた。
森の中には縄文人の骨がたくさんあった。
毒骨茸は縄文人の骨で育ち、櫓茸もその上に育っていった。
皆既月食のある夜、一番最初に茸の生えた縄文人の骨が立ち上がった。二番目の縄文人の骨も立ち上がった。
光りが縄文人の骨は茸が肉となり動き出し、森の外に出てきた。朝日を浴びた二体の骨は人になった。エンとスイはこうやって森から出てきたのである。
日狩村の村人の祖先は毒茸だった。正太郎茸で有名になった村のだれかが、作り出した比較的新しい伝承話かもしれないと、社会人類学者は推測しているが、それはわからない。
この話を大学院生の時に採取した社会人類学者研究者は、今では90になろうとする老人である。それでも足腰はしゃんとして、名誉教授となった彼は今でも年に数回は、若い研究者と一緒に日本にある山奥の集落を歩いて伝承話の収集や歴史の調査に加わっていた。
ある日、テレビの番組で、信州の山奥の地区で、数十軒あったすべての家から、いきなり住人がいなくなったという話が流れた。テロップには日狩の怪とあった。おもしろおかしく事件をほじくり返す番組だ。
三年前、日狩地区の中の二つの家族が、仕事をみつけたことからそこから移転することを市役所にとどけでていった。その後、市役所の担当者がその地区にいったところ、残りの数十軒の住人がいなくなっていたことがわかったということである。移転届けをだしてほかの県にうつった二つの家族の話では、家族がその地区をでるとき、お別れ会を開いてくれたということだった。そのときは特に変わったこともなく、いつものように楽しくすごして、自分たちは引越したということである。
その番組を見た大方の人は誇張され作られた話だろうと聞き流していたに違いない。ただ偶然そのテレビ番組を目にした社会人類学者の老人は、自分が昔調査した場所でもあることだし、何かが起こっていると気になった。そこで若い二人の大学院生とともに日狩地区に行ってみることにした。
老教授は、大学院生の運転する車で日狩村だった地区にむかった。彼らはまず市役所に寄り、市の職員と話をした。確かに民放の番組で言っているように、二組の家族が三年前に転出した。それ以後、転入転出者が全くなかったが、特に変わった様子もなく、市のほうでも気にすることはなかった。ところが、今年になって、台風が直撃しそうだという予報が出されたので、市の防災担当者がその地区長宅に電話をいれたがでなかった。いくつかの家にも電話を入れたが誰もでなかった。みな老人でネットを使っている人がいない。担当者が心配になりその村にいったところ、地区長の家を始めどの家にも人は居なかった。小さな神社があるが、神主もいなかった。家々を窓からのぞくと、電気は消され、きれいに片付けられていた。もちろん地区長を始め、何人かの携帯に電話を掛けたがでなかった。台風情報を聞いて、一時どこかに避難ししているのかもしれない。そう思った担当者はそれならば問題ないだろうと思い、そういった状況を市に報告しただけにとどめた。
台風は大したことがなく、通り去ってから一日後、市の担当者が日狩地区に確認しに行ったところ、住人はみな戻っていた。やはり台風の避難のためにみな離れていたようだということだった。
それをかぎつけた民放のディレクターが番組にしたいと、市に相談があったことから、日狩地区の人さえよければかまわないと返事をしたそうだ。どうも転出した二組の家族だけに話を聞いて、でっち上げたようだと、市の人は困ったような顔をした。
「それじゃ、もう日狩地区の人たちはいるわけですね」
老教授が聞くと、
「ええ、昨日も行きました。地区長をはじめみなさん畑を耕したり働いていました」と言った。
老教授は首をかしげた。
「今、日狩地区の人口は何人だかわかりますか」
市の担当者は台帳をもってきて、「八十五人ですね、みな年寄りばかりですよ」と笑った。
「転出した人は何人ですか」
「二家族ですが、三人でした」
彼らはお礼を言って市役所をでた。
「先生、なんでもなかったのですね」
「うん、だけど、おかしい、いくら台風といっても、地区の八十五人全員が家を空けることがあるだろうか、何かがあったに違いない、それを聞くだけでも面白い、行ってみよう」
老教授はたちは日狩地区にむかった。市役所のあるところから、車で一時間もかかる山奥である。彼が若いころ調査したときは電気もきておらず、ディーゼル発電器がそれぞれの家に備え付けてあった。電力会社の電気がいくようになったのはそれから数年後のことだ。
六十年以上も前のことだが、その学者はおおよそのことを覚えていた。村の寄り合いに使われていた家はなくなっていたし、確かに家の数は少なくなっている。そこで不思議な光景を見た。誰もいない。いくつかの家の前で車を止めた。
家の周りの畑には、草がはえておらず、野菜が青青と葉っぱをしげらせ、キュウリとトマトがなっていた。丁寧に栽培していることがわかる。
どの家も人がいないようだ。
「この時間どこにいっているのでしょう」
「うーん、お祭りの準備があるのかな、まだ早いと思うのだが」
大学院生がガラス戸から中をのぞき込んだ。
「部屋はきれいにかたずいていますね、あ、あれはなんだろう」
一人がガラス戸越しに畳の上にある赤い物を指さした。
老研究者がのぞいてみると、畳の上から赤い茸がいくつか生えていた。
「茸のようだが、畳に水でもこぼれていて腐ったのかもしれんね」
ほかの二つの家の中にも、白と黄色の茸が畳の上にまばらに生えていた。
老研究者は
「日狩村は、一時、正太郎茸という薬になる毒茸がとれて有名だったんだよ」
と若い二人に言った。
「茸が生えやすい気候なんですね」
「神社に行ってみよう、祭りの準備をしているかもしれない」
三人は神社に向かった。
境内にはだれもおらず、小さな社殿もがらんとしている。社殿に戸がなく、地区の人たちが勝手にはいり、拝むことができるようになっている神社だ。賽銭箱はない。
「神社が開いてますよ」
「ああ、昔から、天候の悪いときは閉めるが、一日中あけてあった、村の人が夜中でもおまいりできるようにな、ちょっと変わっていると言えば変わっているね、その当時の宮司さんと話をしたが、昔は村民すべてが檀家で、自分の家には神棚をおかず、神社にきて祈念するという習慣が昔からあったのだそうだよ、だからだろう」
神社の中に入った三人は目を見張った。
床の上ばかりではなく、柱や壁にまでにょきにょきと大きな黄色い茸が生えている。
正面の鏡がおいてある前に白と赤の茸が、黄色い茸に囲まれて生えている。
「なんですか、これ」
老教授もなんと答えようかことばにつまった。
この日狩村の住人は茸だったんじゃないか、今でも。そう言いたくなって、やめたのだ。代わりにこう答えた。
「この村には、森から出てきた茸が人に変わったという伝承があるんだよ、ここの神社の裏の森の中には林に泉がわいていたんだ」
「今では泉はあるのでしょうか」
「どうだろう、私が調べた頃に一度行ったが、きれいな泉だったよ」
「遠いのですか」
「いや、一番近いのは神社の裏山をのぼってすぐのところにあった、道があるよ」
「いってみますか」
「私はもう山の方にはいるのはちょっと大変だからよすよ」
三人は神社の裏に回った。山の中に入る細い道がある。
「ここを行けば、道の脇にあるよ、十分も歩くかな、社殿で待ってる」
老教授は大学院生たちを見送った。
道の脇には神社の中にも生えていた黄色い茸が点々とある。老教授は殿社に戻り中に入った。
「あっ」と彼は声を上げた。社殿に生えていた黄色い茸が全くなくなっていた。
茸が消えた。
老教授はいくつか置いてあった椅子に腰掛けた。
二人が戻るのを待った。なかなか帰ってこない。何かを見つけたのだろうか。もしかすると、地区の人たちが泉の周りに集まって何かしているのかもしれない。私も行ったほうがよかったのかもしれない。
老教授はそう思いながら時計を見た。もうすぐ一時間にもなる。
ふっと、境内のほうを見ると。二つの人影が歩いてくる。帰ってきたようだ。
椅子から立ち上がって「おそかったね」と声をかけた。
そのとたん人影は消えていた。
足元を見ると、黄色い茸が二つ、床の上から生えてきた。動いている。にょきにょきと生えてきた。
社殿の中に目をやると、壁や鏡の周りにも黄色い茸が伸びてきて蠢いている。
足元の黄色い二つの黄色い茸が、老研究者を見上げるように、黄色い傘を広げ始めた。社殿の中を覆うように伸びてきた茸のどれもが傘を広げ始めた。
シューと音を立てて、茸たちが一斉に黄色い胞子を飛ばした。黄色い煙が社殿の中をおおったとたん、年老いた社会人類学者はその場に崩れ落ちた。
黄色い胞子がしずかに、ゆっくりとその上に降り積もった。彼の姿はその中に埋もれていった。三人は日狩地区の人口を八十八に保つために、新たな茸として生えてくることになる。
このように日狩村は毒茸たちが仕組みを新たにしながら、八十八人の村を維持しているのである。
毒茸の村


