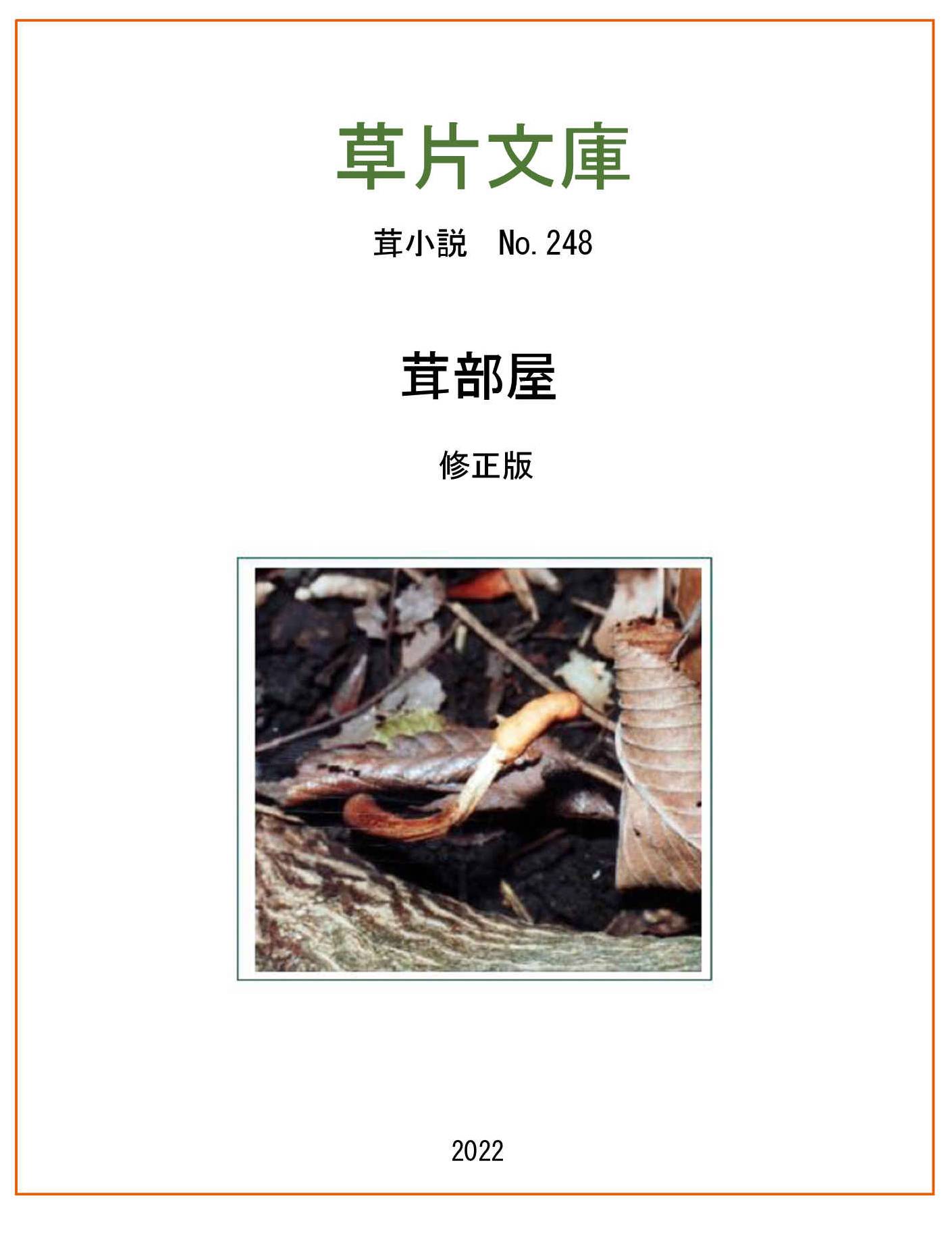
茸部屋
SFファンタジーです。
都の臨海部には多くの高層ビルが建てられ、数億もするような部屋がすぐに売り切れるという。
66階建てのタワーマンション、夢タワーには一つのフロアに十家族、全部で600家族が住んでいるマンモスビルだ。山奥の過疎地の人口よりも多い。村のようなものだ。
夢タワーの最上階、66の2号室に一人の老人が、タワーができたときから住んでいる。年はよくわからないがかなりの年のようだ。ヘルパーがくるわけでもなく、老人は一人で生活を楽しんでいる。ヘルパーが来るわけでもなく、すこぶる健康だ。
髭を生やし放題にして、一見野放図に見えるが、時々パリっと背広を着こなして朝出かける。その後ろ姿は五十代の大手の会社社長といったところか。タワーマンションの広い廊下にでてもあまり人とは会わない。そのフロアにすんでいる人たちは、どこの家も若い家族で、IT関係が多いのだろう、朝になっても旦那は滅多に仕事に出かけない。夕方になると、夫婦や家族で夕食を撮りにいくのか、少しばかり出入りが多くなる。
老人の家はフロアのー番奥の角部屋で、見晴らしの良い特等席とである。廊下の部屋の入り口脇には台が置かれ大きな鉢が三つほど並んでいる。それぞれの家でも、廊下に観葉植物などの鉢を置いて楽しんでいるが、老人の鉢から生えているものは植物ではない。
一つの鉢から大きな茶色のものがにょっきりとでている。真ん中の鉢には赤い人差し指ほどのものがいくつか生えている。その隣の鉢からは白いつぶつぶがでている。
どれもが傘をもち柄がある。茸だ。
茸が生えているのである。
どのようにはやしたのだろうか。そもそも茸は勝手に生えて困るもので、逆に生えてほしいと植えてもでてこない。温度湿度光にデリケートな生き物である。
じいさんの部屋のベランダにも素焼きの鉢が並べておいてある。土が入っているがなにも生えていない。
広い居間の壁際の棚の上にはやはり鉢がならんでいる。
高級そうなステレオ装置が一つの壁側にセットされ、再生装置がならんでいる。レコードプレーヤ、カセットデッキ、CDプレーヤー、レーザーディスクプレーヤと音の再生装置の歴史の展示のようだ。
今、ペルーの音楽が大きなスピーカーから、だが小さな音で流されている。
そこに、じいさんはいない。音だけが部屋の中に静かに満ち溢れている。
居間の隣は小さな部屋である。六畳ほどだろうか。居間から入れるが、分厚い戸を押し開けないと入れない。小部屋の一方の壁側に棚があり、ここにも小さな植木鉢が並んでいる。一見すると温室のような感じを受ける。部屋の真ん中には樫の木でできたがっちりしたテーブルがあり、無造作に大きなルーペが放り出してある。
じいさんはその部屋を茸部屋と呼んでいる。
茸部屋の隅にはトイレの部屋の戸がある。そのトイレにはその部屋からしか入れない。戸を開けてみよう。男性用のトイレだ。藍色の茸が描かれている古陶器の朝顔だ。朝顔は昭和初め頃まで屋敷に設置されていた男の小用のための器だ。
茸部屋にはベランダがある。隣の居間のベランダとはコンクリートの壁で仕切られていて、独立したベランダだ。ガラス戸を開けて外にでると、すぐ左側に階段がある。最上階のベランダから上に行くことができるとすると、まさか天国ではあるまいから、単純に屋上だろう。
上ってみよう。やっぱり屋上である。しかし不思議なことに、大きなビルの屋上にあがっても、じいさんの茸部屋のベランダからあがれる屋上に行くことができない。茸部屋の上の屋上は独立しているのである。じいさんはそこを世界の茸遊園地と言っている。その場所は夢タワーの隅に作られた見晴らし台のような場所だ。そんなに広い場所ではないが、ビルの一番見晴らしのいいところだ。
世界の茸遊園地には、木でできた縁台がぽつんと真ん中におかれている。
そこに腰掛けると全方向が見渡せる。
今日は天気がよい。富士山がきれいだ。
作務衣を着たじいさんがあがってきた。
富士山の方に目を向けた。年寄りにしては目尻にしわがない。ずいぶん大きな目だ。
白い山羊髭が風に揺れている。
今日の風は富士山の方向から吹いてきている。
立ったままじーっと富士山の方を見ている。
十分も見ていただろうか。
「ないのう」
そういいもらして縁台にすわった。
まだ富士山の方角を見ている。
ちょっと風が強くなった。
じいさんは大きな目玉をつきだして富士山の方を見た。いや違う。じいさんの目は遠くを見る目ではない。目の前の空間をじーっと見つめている。
あった
そう言ったじいさんの右手の人差し指が目の直前に突き出された。
じいさんは人差し指の腹の上をぎょ視した。
うむとれた。
じいさんは右の人差し指を突きだした、そのままのかっこうで階段をソロリソロリとおり、茸部屋にもどった。
茸部屋の真ん中にあるテーブルの前に腰掛けると、ルーペを左手で取り上げ、右人差し指の先を眺めた。
「いるいる、テオナナカトルじゃな」
とつぶやいた。
じいさんは棚から小さな鉢の一つをとると、右指を土の中に差し込んだ。
そのままトイレに行くと、左手でズボンのチャックをおろし、しなびた一物を取り出すと、自分の右手の上から鉢におしっこをかけた。手がしょんべんだらけだ。
左手で鉢をもち、右指を引き抜くと、その指で丁寧に指のくぼみを土でうずめた。
尿の匂いがぷーんと鼻をさす。
鉢をトイレの中の洗面台に置くと、手を石鹸でよく洗った。
茸部屋に戻ると、棚にその小鉢をもどし、テーブルの上の小箱からラベルを取り出して、サインペンで、テオナナカトルと書き、今日の日付をいれた。
「一月後だな」といいながら、その部屋を出て居間にもどった。
居間ではステレオのスイッチをオフにして、棚の上の鉢を見て回った。
小さな物から大きく育ったものまで、様々な形をした茸が鉢から生えている。
よく育った真っ青の茸が生えている鉢をとると、反対側の部屋にもって行った。そこには専門家が使う複雑そうな写真機がセットされている。カメラの前の台の上のものを撮影するように整えられていた撮影部屋だ。
老人は鉢をいくつかのカメラがセットされている前の台に置いた。コンピューターの画面を開くと、照明とカメラの電源もオンになり、青い茸が画面に現れた。
老人の指がEnterを押すと、茸が撮影され、茸鉢の置いてある台が回転していくと、周りのカメラが自動的にシャッターを切り、それが終わると、傘の襞の部分が大写しになった。次に画面が茸の傘の上にかわり、茸の姿があらゆる角度から撮影された。
老人は青い茸を鉢から引き抜くと、ト面相筆をつかって、傘の襞から胞子をガラス瓶におとした。きのこそのものも別のガラス瓶にいれ、研究用の大きな冷蔵庫の中にしまった。
ラベルにイッポンシメジの仲間と書いた。
老人は撮影した茸の写真を科学博物館の研究室を含めいくつかのところに、同時送信した。
一人の茸の研究者からすぐに返事があった。それには「私がボルネオでみつけた茸によく似ています。比較検討したいので、請求書とともにいつものように送ってください」とあった。
老人は冷蔵庫にしまった茸を包装し、すぐに宅配業者にメイルをして、要求してきた研究者に送った。
老人は世界中の珍しい茸を栽培していたのである。出版社をはじめ、世界中の研究者から、茸の採取を依頼される。新しい茸をいくつも見つけている。そういった茸を研究者に送ることもする。ともかく彼は世界中の珍しい茸を栽培することができる。それは菌学の進歩に多大な貢献をしていた。
一度、テレビにでたことがある。茸の科学番組である。
「どこで、茸を手に入れるのですか」
司会者の質問に、
「今、ここにも世界中の茸の胞子が飛んでましてな、私はそれが見えますので、捕まえて、育てますんですよ」
正直に答えたのだが、司会者は「どうやら企業秘密のようです、これからも珍しい茸をさがして、人類の健康に寄与してください」と結んだ。
茸と健康という番組だった。
じいさんは、ビルの屋上で、富士山の方を向いて、吹いてくる風の中をじーっと見ている。ふっと右手の人差し指を差し出して、その中から人の目には見えないはずの、胞子を捕まえる。胞子の大きさは種類によってまちまちだが、10ミクロンだとか20ミクロンだとか、ごく小さいものである。ミクロンは千分の一ミリメートル。だから1センチの百分の一ほどだが、じいさんの目には見える。しかも種類までわかる。
じいさんに会った人で、その能力に気がついた人はいない。
じいさんの瞳を観察してみよう。茶色の瞳のまん中である瞳孔から光が目の中に入り、ものを見ている。そこは何ら他の人と変わるところはない。ところが、老人の瞳孔の周りをよく見ると、透き通った茶色の無数の粒々からできていることがわかる。一つ一つがレンズである。じいさんが周りを見ようと意識すると、その無数の茶色の粒粒により、空気中の百分の一ミリの物でも大きく拡大されてもう一つの視覚野にはいる。じいさんは脳も他の人と違うようだ。瞳の茶色の粒粒に対応した第二の視覚野があり、通常の視覚野を通して、画像を形成しているようだ。
昆虫の複眼がなぜかほ乳類の目の中で進化し、人の目にそのような構造をつくってしまった。複眼になる遺伝子が老人の瞳の表面に発言してしまったのである。老人は特異体質の人間ということだ。それに気がついたのは、大きな不動産会社の社長を退き、趣味の写真機をもって山歩きをはじめたときだった。そのころ植物や茸の写真を撮って楽しんでいた。とある山の頂上で、遠くの山の頂にいる木の上の鳥は何だろうと思ったとき、急に目の前に枝に止まった鷲が現れたのだ。
驚いた老人は目をつむり、もう一度遠くの山をみた。ただの遠い山でしかなかった。あの鳥は何だったのだろうと思って見た。すると目の前に鷲がまた現れた。
今度は自分の手を見た。老眼なので、生命線をおいかけたがはっきりわからなかった。もっとみたいと思ったとたん。手の平の細胞が目の前に現れ、細胞の中の核まで見えた。腕を見た。目では見えない毛がロープのような太さで目の前に現れた。
見ようと思うと、空気の中のゴミがたくさん見えた。その中に花粉もあれば、そのころは知らなかった茸の胞子や羊歯の胞子が見えた。
その帰り道、生えていた茸の写真を撮った。もっとよく見てみたいと、自分の目で傘の裏を見たら、胞子がたくさんついているのが見えた。空中にそれが飛んでいるのも見えた。
空中の茸の胞子がわかるようになったのはその時からである、しかも形や色や場合によっては匂いによって、種類もわかるようになってきた。人類の知らない茸、珍しいものがたくさん混じっているのにも気がついた。それが世界中の茸の胞子たちだった。
世界の茸は数え切れないほどの胞子を空に放出する。上に上に上がった胞子は上空の気流で世界中にいきわたる。日本のここにいて、世界中の茸が見えるのである。
胞子のじいさんの茸部屋にはじいさんが発見した珍しい茸が育っている。それだけではなく、鉢に植えていない胞子が入っているシャーレもたくさんあった。その胞子は冬虫夏草の仲間であった。それは土の植木鉢では育たない。生きた宿主をあたえなければならない。
最近やっと冬虫夏草の培養もできるようになってきた。まだ完成したわけではない。
冬虫夏草はゼラチンからはやす。動物性の培地だ。ガラスの容器にゼラチンを基本として、その中に最近盛んになってきた昆虫食を買ってきてすりつぶしたものと、豚と鳥の肉汁をまぜてある。それだけではなく、なぜか、じいさんの小水も少しいれてある。
それで、やっと最も一般的な冬虫夏草であるさなぎ茸の菌糸が伸びてきた。糸実体、すなわち茸になる芽らしきものもできはじめた。
これがうまくいったら、今までためておいた冬虫夏草の栽培を始めるつもりだ。薬にするといい茸だ。そして、一つとてもきになっている胞子があった。今まで見つかっていないほ乳類にとりつく可能性のある奴だ。赤いマークのあるシャーレにいくつかたまっている。といっても普通の人の目には見えない。
冬虫夏草の周りに放出された胞子は、動物にくっついたりして運ばれることもあるが、森の中を漂ってどこかで虫と出会いもぐりこむ。森の中から空高くまで吹き上がるのは多くはないだろうが、希ではあるがあるようだ。こいつは、富士山の方角から飛んできたのではない。東北のほうから吹く風にのってきた。空中をただよっているうちに、太陽光線の何らかの成分か、自然の放射線かもしれないがそいったものによって変わった、すなわち突然変異を起こしたものかもしれない。もしやもすると、原発事故による放射能をあびて、遺伝子が変異した冬虫夏草の胞子の可能性も否定できない。ともかくじいさんの目にはその冬虫夏草の胞子が、他の冬虫夏草のものとはずいぶん違って見えた。赤いのである。血の色だ。哺乳類につく可能性がある。
冬虫夏草はついた動物の臓器の働きを止めて突序の死をもたらす。いうなれば毒キノコである。天狗茸などがもつ毒の物質をもつというのとはちょっと意味が違う。この冬虫夏草の胞子が知らない間のからだにとりつき、増えたら、人間がどうなるか。ちょっと怖い。
このじいさん、自分の目の性質を知ったときから、自分の役割は、人と菌類を結びつけ、お互いが生きやすいようにする事だと自覚していた。
ほ乳類につく冬虫夏草があってもいい。ただ、死をもたらすものではなく、ほ乳類の体に役に立つように共存してほしい。爺さんの願いである。
たとえば、人間の体にとりついた冬虫夏草が、ガン細胞だけを栄養源として育てば、人間にとってガンは怖いものではなくなり、大事な共同生活者になる。
この赤マークのシャーレに入っている胞子がほ乳類で生育するものであるならば、ガン細胞や、体の中のいらないものにとりつく冬虫夏草に改良したいと考えていた。
じいさんは会社の経営に関しては超一流の目をもっていた。しかし、生命科学者ではない。この冬虫夏草の胞子のことはどこにも話していない。培養系が確立したら、幅広い考えを持った細胞生理学者を探し出して、研究してもらおうと考えていた。
一方で、ビルの上で、風に含まれる世界中の茸の胞子をとらえ、茸学者とともに、空中の茸図鑑を作りたいという希望を持っていた。
今でも新しい茸の発見は研究者よりも素人によるものが多い。
そして、今、茸部屋で様々な冬虫夏草の茸体が頭をだしはじめていた。培養がうまく行き始めたのである。しかし、冬虫夏草はすべてが虫につくものばかりである。
赤いマークのシャーレの胞子も、培養瓶の中で大きくなり始めている。
今じいさんはこれまでに一人の菌学者に着目していた。世界の奇妙な茸の本を書いた研究者だ。目が世界に向かっているし、本を読むと説得力のある人のようだ。
すでに、コンタクトをとり、培養瓶に生えてきたほ乳類につく可能性のある冬虫夏草をわたしてある。
その研究者は大いに驚き、じいさんの言うことを理解し、研究体制を整えてくれた。
その冬虫夏草の培養が完璧なものになったら、実験用のラットに胞子を食べさせて、どのような発育をするか調べた後に、ガン細胞など特定なものにのみとりつかないような遺伝子改変を行うのである。
そこまでくると、爺さんの手が届かないところである。
この件はもう爺さんの手から離れていくところだ。
爺さんは今でも自分の特異的な進化した目をつかい、風の中の胞子をとらえている。
この特異的な目は胞子だけでなく、空中のあらゆるものを見分けることができる。
計測装置がなくても、空気の汚れ具合などはすぐわかる。
アメリカにいる娘が子どもをつれてはじめて里帰りしてきた。主人はアメリカ人で、カリフォルニアで不動産業をいとなんでいる。一時じいさんの会社で働いていたことがあり、母国に帰って独立したのだ。じいさんも出資者になっている。娘がその男の妻となったのだ。
ビルの上に老人と子供が空中を見ている。
七歳になる孫の男の子がじいさんの隣で、同じように富士山の方を向いて目をこらしているのだ。
「じいちゃん、小さいものがたくさん飛んでいるね」
じいさんが驚きの目で孫を見た。
「なにが見える」
「ちいちゃいつぶつぶがいっぱい」
じいさんは孫の瞳を見た。みようと思って見た。瞳に半透明のガラスのような粒が無数に寄り集まっているのが見えた。
じいさんはほほえんだ。
「いつも見えるのかい」
孫は首を横に振った。
「ううん、はじめて、じいちゃんのように富士山の方を向いて、じーっとみたいと思ったら、周りに粒が見えるようになった」
孫が大きくなったら、胞子やら、花粉やら、空気の中を飛んでいる生き物の子供たちを知ることになるだろう。できれば科学者になってほしいと思った。経済、軍備だけでは人間を守れない。
じいさんが孫の頭をなでた。
茸部屋


