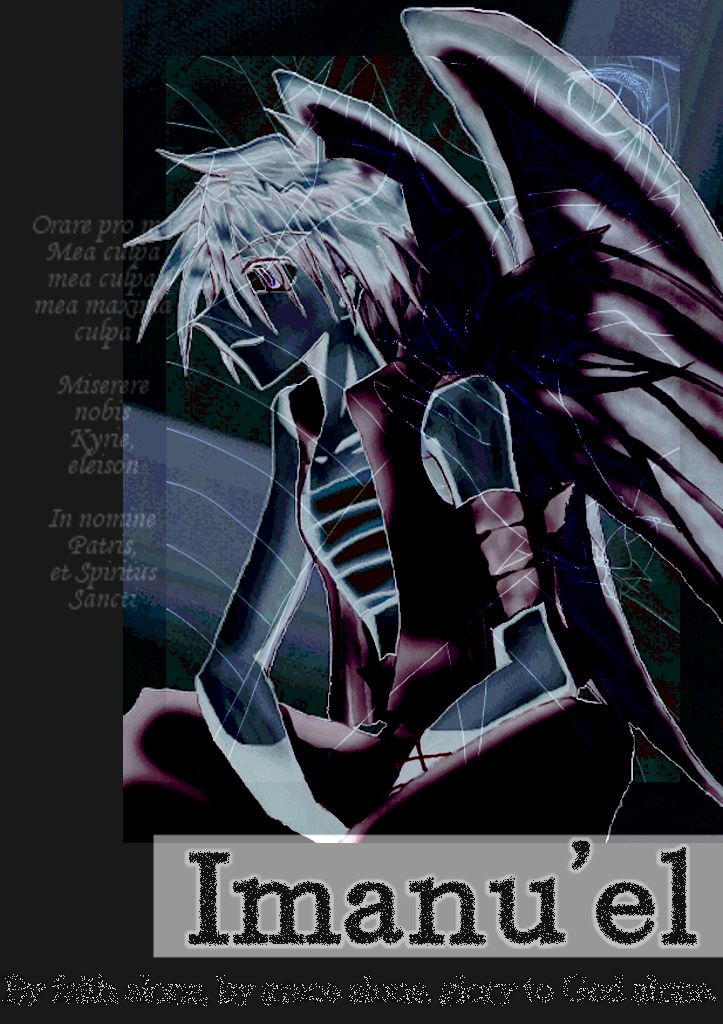
-青炎-
「神」の「力」をヒトが使う拙作の、世界観を凝縮して込めた短編集です。
星空文庫限定作「空の光」付き。
本作単独ではどの章も説明不足なので、雰囲気を何となくご鑑賞下さい。
update:2023.4.29
※「黒い水雷」で聖書の創世記を引用しています
追走曲
その黒い翼は、翼を引き受けた者を暗闇に誘う、悪しき神意の永い黒闇。
悪魔のささやきに近いかもしれない。ささやくだけの悪魔の方が、まだ可愛げがあった。
黒い翼は外から彼の体を破り、心の奥底までを侵す。彼の意思などまるで無視して、それなのに彼の望みとばかりに、彼のふりをし彼を動かす。
そんな彼を憐れむように、死神が大きく溜め息をついて両腕を組んでいた。
「それでもお前は……そいつのことを、助けたかったの?」
彼は吐き出しきれない激情のまま、背後の死神の服を掴んで引きずり倒した。
「アンタが、いるから……!」
ずっと無防備で、隙だらけだった死神は、あっさり彼に乗りかかられた。
動揺の欠片も浮かべず、無表情に見上げる蒼い鳥の目。彼は青白い月を背に、黒い怨嗟を吐き戻す。
「俺は……アンタを、殺したい……」
黒い襟に覆われた死神の首を、強張る両手が勝手に絞めにいった。
この憎悪は何処から来るのかわからないほど、悪心で震える手に力が入った。
窒息よりも前に、細い首の骨が折れそうなほど、彼の全霊が込められた穢れた指先。
黒く歪む彼を前に、死神はふっと、白く微笑んでいた――
†空の光

青い空は、何もかもを呑み込む冷たい光だと、いつか彼女は誰かに言った。自ら光を放つのでなく、巡る命を映す空ろな炎なのだと。
命を終えた体は土に還る。眠れる心は夜空の星と散る。想いを刻む魂は風に舞う灰となる。
スカイ・レーテ。古い「忘却」の「神」につながる彼女にとって、夢という天窓から見えるものは、彼女の周囲の人々が紡ぐ「命」だった。
スカイ・ライト。その名が奪われてから、どれくらいがたったのだろう。「神」はヒトに降りる時に、ヒトをまるごと「神」に書き換える。彼女が彼女の心を残せたのは、命のつながる双子に「力」を預け、新たな時代に逃がせたからだ。
何かの「神」の「力」を得ると、ヒトの「意味」は変わってしまう。移り変わる本質を記憶するのは、いつもそこにある空だけかもしれない。
彼女はいくつもヒトの世を知っている。そもそも生まれた神の宝箱、数多の化け物のヒトが生きる「宝界」。
天の主に赦され、力無き人間が咎人のまま生きていける地球。俗に言う「人間界」。
天の主の代行者、天使達が集う「天界」。その反逆者が溺れる魔の海、「魔界」。
姿の違ういずれの世界にも、一つだけ共通点がある。それは「神」という、八百万の「力」が存在すること。人間界では特に隠れているが、それでも「神」に隠される――意識や心を変えられてしまう者が、どの世界にも後を絶たない。
古い名を「神」に奪われてから、彼女はいくつかの世界を渡った。彼女の「力」を預かり続ける、誰ともわからぬ双子を無意識に探し続けた。
夢という万人の窓を通し、多くの命の因果を視てしまう「力」が、双子を魔の道へ駆り立てる未来も知らずに。
彼女は夢を忘れてしまう。双子は彼女の夢を視続けていく。
小さな星の光。そんな名前になった双子の片割れを、彼女がやっと見つけた時には遅かった。
激しい空の光である彼女は、双子の小さな光を隠してしまう。やがて小さな光は「天気雨」として、空の光を抱いて魔の海に降る。
彼女は呟く。最早己のルーツも忘れ、白い夜から解き放たれた「忘我」の後に。
「それはほんとに……愛と認めちゃってもいいのかな?」
双子は彼女を守ってくれた。けれど彼女は望んでいなかった。
彼女の悲しみは気付かぬ内に、古の「悪神」を起こす。「悪神」が奪う天の龍が飛ぶ前、騒乱の陰にいたのは彼女だ。
それでも彼女は、その「剣の精霊」――「悪神」に魅入られた少年を、かつて引き止めようとした。
――『鴉夜』を『悪夜』にしたくなければ、私にその剣を預けてもらう方がいいと思いますよ?
それが最大の一手だった。ここで彼女が剣の精霊を得れば、彼に黒い翼が生えることはなかっただろう。
思い返しても仕方がない。彼女は双子も、双子が「力」を分けた剣の精霊も助けられない。本当はとっくに、何度も見た夢で知っていたこと。
だからせめて、彼女の悲しみである青い炎を今日も夢に見る。「悪神」に利用される黒い水雷。「悪神」を引き受け、常世に迷い込む剣の精霊。失われてしまう青い霧氷、蛇の悪魔、鬼火のカラス――……いずれも皆、愛する者を守ろうとして、すれ違っていく空ろな光だ。
彼らはぬくもりを求め続ける。彼女は何もできることなく、黒い翼がどう羽ばたくか、やがて見届ける運命を待つ。
もしもこの空の果てに、「天国」があるのならば。空ろな青い炎は「神」から逃れて、己の光を得られるだろうか。たとえば剣の精霊をつなぎ留めた、十三夜の死神の血潮のように。
罪も涙も、意味も希望も。全ての痛みから解き放たれて。
青炎

ヒト喰いカラスは闇に還る。死神が与えた翼の「鍵」を棄てる。
ヒト喰いカラスのない世界では、あだ花の楔が浮かび上がる。黒い鳥と蛇の悪魔は、ヒト喰いカラスが手折った星と引き換えに生をつなぐ。
そのためヒト喰いカラス――黒い「神」の使徒には、灯火となる少女が必要となる。水底に伏すあだ花を探し出すには、時の谷底から混沌の沼に潜らなければならない。
夜水に光を溢す狼、「tor. Fenrisúlfr」。黒い水沼に棲む少女を照らし出したのは、命の赤火を呑み込む青い炎。
†黒い水雷
昼と夜との違いは、光の有無でしかない。余所から光を持ってこなければ、あるがままの世は常に夜なのだから、常世を常夜とも言うのだろうか。
人間界では常世とは、神域であると同時に幽世、死後の世界と思われている。確かに軸たる夜に還る「力」もあるが、大体の卑小な命は世を満たす混沌に還り、それが何処かは誰にも定められない。
何処にでもある混沌は、全てを内包する黒でドロドロの水だと言う。それに比べて人間界には光がある、と外から来た少年は「光の娘」に教えた。
「だから外には、空があるんだ。ここは混沌と夜で満たされた沼地だけど、人間の世界ではもっとはっきり、水とその他が分かたれてる」
常世で生まれた娘にとって、浮き上がる物質以外の空間が、真っ暗なのは当たり前だった。玄い水でない明るい空など想像もできない。常世の常識とは『地は混沌』、『闇は深淵の面にあり』『神の霊が水の面を動く』くらいで、実際に在るのは「意識あるものと波が川辺の街に集う」程度だ。
夜とは水で、昼とは光。少年はそう言うが、「雨」を名乗る少年そのものが娘にはよくわからない。呼吸というものが不要で、流れる混沌の軸たる常世の内では、「雨」がどんなものであるのか想像もつかない。
昼を知らない娘を「光」と呼ぶ謎の少年と、出会ったのは定例会の帰り道だった。
「あんたが、『tor.Fenrisúlfr / chaos』……『tao.Fenrir / fuchsia』?」
何の変哲もない住宅街で、塀にもたれて立っていた無造作な銀髪の少年。袖が無く襟を立てる黒衣で、外界の少年が来られた一画は、「日本」にそっくりだと言う。勿論「日本」が何かを娘は知らない。
優しい顔で笑う少年の空ろな金色の目だけが、常世では見慣れた有り触れたものだった。
「オレは『時雨』。あんたの次の新参者だから、良かったら仲良くしてよ」
この一帯の川長から、娘は便宜上、タオ・フェンリルと名付けられた。常世で新たな者が生まれるのは、外界で大きな「力」の変動があった時らしく、ある程度正体がわかるまで当初は「水雷」と呼ばれていた。
それというのも、娘が久方ぶりに現れた「混沌接続者」だからだという。
「時雨は、わたしのこと、何か知ってるの?」
常世の新人には身寄りのないことが多い。もっと原初の世ならともかく、全ての「力」――概念は既にほとんど体系化され、増えるとすれば単独の突然変異ばかりだ。それも少年のように、外界から来るものがほとんどで、娘ほど純度の高い新生者は少ない。
「フェンリル」とは、外界によっては「沼地に棲む狼」をさす名らしい。「タオ」は「道」やら「桃」やら意味が広いようで、混沌の黒い沼地に、光の花道を咲かせる桃花――水雷の紅火と言われている。この息苦しい常世が沼地というのは言い得て妙だ、と少年の方は納得していた。
先達の許可を得て娘の社に自由に出入りするようになった少年は、「日本」で言えば小さな家らしい一室で、よく娘と話をしてくれた。
そうしてほとんど毎日訪れるほど、娘を気に入ったらしい少年なのに、娘が何者であるかは穏やかに笑って知らない、と言う。
「さぁね? オレは確かに、あんたに光を届けろと言われたんだけど……それがどういうことで、誰に言われたのかも、正直思い出せなくってさ」
娘よりもよほど常世の者らしい少年の、光彩の乏しい金色の眼。まっすぐで艶のない黒髪の、常世の住人らしからぬ黒い目の娘が映っている。「水雷」と呼ばれた理由もわからず、ただ毎日を、先達の監視の中で過ごしている薄手の白いパーカー姿。
外界から来た少年も、徐々に生前の自らの記憶があやふやになっていると言う。常世とはそういう場所だと言うしかない。
おそらく娘も少年も、共に監視されているのだろう。一か所にいれば周囲の手間が省けるために、少年の来訪は許されている。
「時雨はどうしてここに来たの? 人間界には戻りたくないの?」
「いずれ戻されるらしいけど、今はその時じゃないんだってさ。オレは今後の仕事も決まってるみたいで、ここでは何も考えるなって言われてる」
二人はいつも、娘のベッドに並んで座って話す。娘もたまに定例会に呼ばれては、近況を報告するだけの毎日なので、少年と話せる時間は自然と大事なものになった。
それでもいつか、少年は常世から出て行ってしまう。そのことを思い出す度、今までにない不可解な衝動が娘の内に込み上げてくる。これまでずっと、常世の在り方には疑問を持たずに過ごしていたのに、少年がたまに酷く哀しげな顔をするのが気になってしまう。
どうして常世には、少年が好きだという赤い空がないのだろう。涼やかで透明な水の匂いも、頬を撫でる碧空の風も、何一つもない。ここには物と暗闇しかない。
ただ、娘の所にいる時だけは、少年も心が晴れると口にする。
そばにいたい、そればかりを想うようになった。娘の社から少年が帰ってしまう時は、いつも胸が締め付けられるように痛くなる。
「欲も無く変化も無く、毎日ただ、ここに在るだけ。タオはよくそんな生活、今まで耐えられてきたな」
少年は少年で、軟禁状態の娘に思うところがあったようで、ある日突然、一緒に外に出よう。そう言い出してきた。
「街を歩こう。オレがいつも通る場所くらい、何かあっても何とかなるよ」
常世では役目がない限り、己の社にいることが原則――不秩序の禁がある。
迷い出た者は何処でいつ、どんな目にあっても文句は言えない。まだ少年は住処が固定していないから、動き回っても許されているだけで。
夜の世の住人として、不秩序の禁をわかっていながらも、娘は平和な笑顔の少年の誘いに抗えなかった。
いつも座るベッドから手を引いて娘を連れ出してくれた時、少年はあまりに楽しそうだった。
「たまにはオレの所にタオが来てよ。タオの家、いつも誰かに見られてるから落ち着かないんだ」
そこから少年が辿り始めた広い道は、娘は初めて見る所ばかりだった。
小ぢんまりとした家々ではなく、背の高い建物が密集して立ち並ぶ都。物以外が暗闇にしか見えない常世で、これだけ何かが沢山あると、娘の住処付近より遥かに明るい。
「ねぇ、時雨――本当にこっちが、時雨の社なの?」
いつもこんなに歩く所から、少年は訪ねてきたのだろうか。娘の社から既にかなり離れてしまい、禁を侵していることも含めて不安が溢れて来た。
「大丈夫だよ。戻る時はちゃんと、出る前のさっきに戻すから」
手を引きながら軽く振り返った少年が、いつになく遠い笑顔で理解不能なことを言う。これで咎められないのは有り得ないと娘は思ったが、一通り歩き回った後に娘の社に戻ると、その後は本当に何も起きなかった。
川長もその取り巻きも、何か言ってくる気配は全くない。定例会では毎回、おかしなことをするな、と強く言い含められるのに。
それからは少年と街に出ることが飛躍的に増えた。誰にも出会わず二人で歩く。娘の社に、別の先達が訪ねて来るタイミングと重なることも全然ない。
監視はどうなっているのだろうと、それもわけがわからない。それが少年――「時雨」の持つ「時」の名の作用であるとは、娘は何も知らなかった。
川ばかりの暗い街を何度も歩くだけで、少年が住む所には着くことがない。
まるで何かを探しているよう。出る度に娘はそう感じた。
†剣の精霊
己がわざわざ、闇の常世――「神」の軸に来た目的を、少年は毎日忘れては思い出す。
これまで渡り歩いてきた時の闇と、「軸」はさすがに強度が違った。まだこの軸の絶対時間では「時雨」になり切っていない己が、「時雨」としての記憶を保つのは困難を極めた。
だから先住者の眼もごまかせているが、少年は本来、光になる娘に会うために少し先の未来からやってきた反則者だ。
「わたしは『水雷』って呼ばれてたよ。でもわたし、何もできることがないのに、どうしてなんだろう……」
その娘は未来では、爆発的な「光」の適合者だ。「光」を渡される前は水に親和性の高い夜の少女で、夜を溢す源の黒い狼が混沌の一部で娘の本体。少年の縁者が探す黒狼であるのを、娘は憶えていない。
渡される「光」の前任者はとっくに己が「力」を手放し、化け物として現世に出て行った。不秩序に放置されていた「力」を運ぶのは、秩序の管理者としての少年には合法と言える。
しかし今、娘と他意なく話す「昔の少年」は、まだ秩序の管理者ではない。この常世に不意に訪れた「剣の精霊」で、だから娘を訪ねる目的の記憶を保てない。
それでも一応目算はあって過去に来た。娘が「光」を継ぐ機会が早まったところで、変わり得るのは「剣の精霊」の僅かな未来だけだ。どの道、時を渡る「時雨」になることが定まっている世なら、この逆行すら運命通りで合法のはずだ。
そのため誤算と言うと、この頃の少年も娘も、予想を遥かに超えて無害であることだった。
「時雨、見て。これ、花だよね? 時雨が言うシゼンだよね?」
「あ、ほんとだ。まるごと花のまま咲いてるって、ここでは珍しいな」
常世では実に自然物が少ない。あまりに密度の濃い「力」の闇では、大体の意志なき概念は元素や要素レベルに戻ってしまう。
おそらく強い木霊と観られる野花を前に、並んでかがむ二人の姿は、心温まる友人達としか言いようがない。
「力」を視て介入できる心眼持ちでない限り、神性を持つ化け物達の、「力」の受け渡し法は限られる。「力」の媒介である「命」や「心」をやり取りするなら、それらを巡らせる血に触れる殺し合いが手早いが、娘は少年が無意識に憶えている妹に似ており、傷つけたくなかった。
「力」に翼などの入れ物があれば、渡したい相手に植え込むだけでいいが、少年が運んできた「光」は適性の問題上、一時的に身中の喉元に収まらせている。だから娘に少年の血を浴びてもらうか、娘との仲がもし進展すれば、口付けなどで体液を介して渡すのが一番早い。
しかしどうにもここの二人は、互いに煩悩がない。
「そろそろ帰ろう、タオ。あんまり知らない所へ行くと、さすがに何かに襲われかねない」
「うん。無理に遠くに行かなくても、時雨といられたらわたしはいい」
娘を危険な街に連れ出していくのも、少年が荒事に巻き込まれ、流血によって娘に「力」を渡したい本意が反映された行動だろう。それでも娘を危険に合わせまいと、少年が慎重に動いているために何事も起こらない。
妹に似ているとは言え、そこまで過去の己が光の娘を大切に扱うのが計算外だった。
荒事なり何なり、過去で娘に会いさえすれば、いつか何かが起こるだろう。その目算でやってきたが、これではいつ目的が果たされるかわかったものではない。
せめて時を渡る少年の根城、「天龍」に娘を連れ込めればいいのだが、外に出る度に意識下でこっそり探してもいつまでも辿りつけなかった。
「時雨の社は、いつか連れてってくれるの?」
「そうしたいんだけど、もう思い出せなくてさ」
結局ただ単に、娘と暗い街をうろついて時間が過ぎる。
娘もいずれ、色香の「桃花」を名乗るほど恋愛体質者のはずなのに、元はこうも純情だとは、想定外にもほどがあった。
「剣の精霊」に、そもそも妹似の娘へ恋愛感情が芽生えないことはわかっていた。少年の本命はずっと人間界にいて、永遠に手は届かずとも、忘れられることもない。
だから娘も時に顔を曇らせている。少年には踏み込め切れない壁があることを、出会った当初から感じ取っている。
「時雨は結局、いつ、外に戻されるの……?」
その時になればどの道、目的は果たされるだろう。少年が「時雨」になる――己が目的の記憶を取り戻すのは、この先に外界で動く秩序の管理者と成った時だ。
それなら今この時間は、秩序の管理者とされる前にしばらく眠っていた少年が観た、最後の安穏の夢かもしれない。
自然な運命通りでも、光の娘はいずれ「光」の力を受け取る。その後に娘が、黒狼を探す「青い霧氷」――ある死に損ないの男を愛することが、少年の気に食わない未来だった。
娘は結局「光」を失う。少年は成り行き上、死に損ないの男の力を受け継ぎ、そして光を失くした夜の少女と出会うのが本来の流れだ。その先には少女が、愛する男の影を少年に求め続ける未来が待っている。
「タオはずっと……オレと一緒にいたい?」
じわっと赤くなりながらも、はにかむように頷く娘。そこに迷いは見られなかった。このままいけばこれから娘は、違う男を愛するようになるのに。
男の力と共に、未練を受け継ぐ少年は、夜の少女と長い時を往くことになる。自身の本命に触れられずに、夜の少女を本気で愛することもできずに。
もしも娘が、男より先に少年と出会い、その「光」を受け渡せるような関係になれば何かは変わるのだろうか。
数多の時空を渡っては運命に干渉し、いくらか違う未来を作ってきた「時雨」には、この邂逅もそうした試行錯誤の一つだった。
結果から言えば、どの時点で娘に「光」が渡されようと、娘がその「光」を失うことこそが「時雨」への想いの鎮火に繋がる。光の娘でいない限り、娘は少年を想わない。ややこしい経過の後に少年が「月光」を調達し、少年を想う人形の少女を得るのは別の話だ。
「時雨」の一方的な思惑を悟っていながら、「天龍」を過去に向けてくれた夜の少女が、後に根城の管制台で言ったものだった。
「本当に最低ね、時雨は。烙人より先に出会って、わたしをたらしこもうなんて」
「どっちが。タオの頃はあんなにしおらしくて可愛かったのに、何で今はドロドロのあんたになっちまうの?」
無表情な夜の少女は、少年の前で少女の姿である時はなりを潜めているが、空ろな女の形をとれば簡単に乱れた生活を送る。
根は一途なのだが、「混沌」に繋がり目前のものの情報を見透かす視力のせいか、基本的に身も蓋もない。求められれば誰にでも応える、夜の泥水の性質を持っている。
だから少年も何も隠し立てせず、身勝手な目的での時渡りを決行できるわけだが。
少年の妹――人間界での「混沌」の接続者を、長年陰で守ってくれている少女に、秩序の管理者は何度目かの苦言を伝える。
「頼むから猫羽に、その魔性を伝染すなよ。猫羽は本来、水の性でもないんだから」
「……無理じゃないかしら。下手したらわたしより上手だと思う、あのコ」
妹は山猫、夜の少女は狼と、揃いも揃ってろくでもない牙を持っている。
妹の方は特に、あくまで純粋な理知で、悪魔でも受け入れる寂光の土の如きでタチが悪い。その水沼こそ「混沌」の接続者の資質なのだろう。
常夜はいつでもそこにあるが、恒久の光はおそらく浄土にしかない。それは「軸」に在るものすら届かない最果ての天。
得難いからこそ、闇に訪れた短い春は眩かった。少年が自ら、闇という安寧を脅かす「光」を壊すことになるその日まで。
†青い霧氷
正史 -Side.R-
靑には四つある、と、「力」を色で視る古い仲間がかつて言った。
青、蒼、碧、神。はて? と彼は首をひねり、最後の「神」は何だ、ときくと、自然界の不思議の総称であり、「あお」とも読むのだという。
「特に『天の神』とくれば、稲光を主にさすらしい。漢字は不思議だな。でもそれなら蒼天の『神竜』が雷使いなのは、やっと納得がいく」
外面は和風、内実は近代的な家で、家主である心配そうな「心眼」の仲間が言ったこと。彼を現在拘留する「神竜」について、以前教えてくれた話を反芻する。
少し前まで居候していた彼、竜牙烙人は、十五年以上前に負った古傷の呪い――仲間曰く「赤の鼓動」で、今にも死にかけている。それなのに「神竜」とやらに、大事な相手を二人もかっさらわれた。
だから今、彼は大空の中で、彼の双子がかつて設計した「天龍」という飛空艇にいる。古代の遺物を再現されたその船は、「神竜」一派の根城なのだが、古の禁忌に触れる「不秩序」な建造物の上、彼の戸籍がある国のクーデターにも絡み、事態は悲愴なほどに複雑化していた。
「ああ、もう……何処を向いても味方がいない上に、シグレまで攫われてきた、だと……」
船尾の甲板で冷やかな風にふかれ、雲の傍らで独りごちる。人質をとられているとはいえ、彼はこれまでの仲間を全て裏切る形になってしまった。
今の彼は、「神竜」の言いなりの身だ。心眼の仲間の養子が連れて来られても、助け船を出すこともできない。そもそも死に損ないの彼の存在自体も「神竜」には人質で、彼がどちらの陣営についたところで何一つ戦力になりはしない。
彼自身について、「力」を視る仲間は、本来青の本質の持ち主だと言っていた。青は「正しさ」の意を持ち、自然界を広くさす漠然とした気色だと。それなのに彼は後から蒼やら紫やらを模し、それは彼が持つ「赤の鼓動」の侵蝕のためらしく、その呪いこそ彼を殺す古傷でもある。
赤は本来、聖なる色だろ? 心眼の仲間にそう尋ねた時は、良きにつけ悪しきにつけ苛烈なのだ、という答が返ってきた。
「それでもって、極端な動の赤と静の青を混ぜたら蒼か紫、堕ちた紅の魔物が誕生するワケか……となるとそこに白を混ぜたピンクな奴らは、さしずめ魔性に光まで併せ持った破綻者か?」
冷え込む甲板にいると体調が悪化する。硬い床に座り込んでも生気が削られていく。
神竜が囲う「ピンク」の娘を縛り付けるため、目を付けられたのが彼だ。この根城にいさえすれば何をしてもいいと言うので自由にふらついているが、適当に与えられた自室にはあまり帰りたくなかった。
「サキと直接話させろよ、クソ……トウカをあてがっときゃ文句言わないだろって、魂胆が見え見えなんだよ、お前……」
自称神竜は心眼の仲間曰く、彼の源流たる存在から抜け出し、勝手に行動している「力」らしい。そのため彼と異性の好みが同じで、大事だからこそ遠ざけた若い仲間……桜色の髪の娘を一派に引き入れてしまった。
娘も昔から彼を大事に思っているので、彼がこの船にいることが娘を縛る鎖になる。彼も娘と、その霊獣がここにいるので来るしかなかったように。
桜色の娘は霊獣族という、「力」を投影した獣を己の分身とする化け物の最後の一人だ。普通霊獣族は一体の霊獣しか持たないが、娘は本命の白黒猫の他にもう一体の霊獣を持っており、それが今彼の部屋に置かれているので彼は帰りたくない。
何故ならその霊獣は、霊獣のくせにヒトの形をしている。それも彼が長年探し続けた、黒いヨメにそっくりな少女の姿で。
「そりゃーサキだけだろうさ、トウカを具現させられるのは……でも何とか見つけてみれば、その世界ではシグレにぞっこんって、何の禍根だよそれ」
あの狼少女め、と。彼の寝台で紅いストールにくるまり、眠りこけている長い黒髪の姿を想う。
心眼の仲間の養子、シグレが連れて来られたのは狼少女のためだろう。本来は黒い狼の霊獣である少女が、現在ヒトの形をとれているのは、シグレが呼び覚ました心というのだから。
かつて一度、彼と取引をしておきながら消えたヨメは、何でも屋を名乗る黒ずくめの同年代だった。それが「空の光」の陰でもあったと彼は知らない。
初めは体だけの関係に近かったが、段々と情の移ってしまった彼が、何でも屋ならうちに永久就職しろ。そう取引を更新せんとした時、日頃は感情を見せなかったくせに、とても痛ましげな顔で彼女は消えてしまった。
――その願いは、叶えられない。
己が誰であるか知らず、ヒト型で自律して動いていた霊獣。当時に彼の体を心配して同居していた桜色の娘も、それが自身の霊獣であると知らなかった。
赤の鼓動という呪いに蝕まれ、先の無かった彼にとって、桜色の娘は決して手を出さないと決めていた聖域だ。その捌け口に黒い狼女を利用したのは確かだが、桜色の娘もその後、彼の源流という存在に出会えたので、結果オーライのはず。そう思っていた矢先の自称神竜の出現だった。
「何で……サキにはダメでも、サクラはトウカを具現させられるんだ?」
神竜一派は、桜色の娘が己に封じ続けていた悪魔を目覚めさせた。そして悪魔の娘が狼少女をヒト型で世に戻し、彼のそばにつけさせた。それで彼は、ヨメが結局桜色の娘の霊獣だと確信する羽目になった。
これまでそれは否定したい推測だった。霊獣とその主は本来五感を共有するものであり、桜色の娘と狼女にそれはなかった。あれば彼は桜色の娘に手を出したのと大差ないので消えたい。
狼女が狼少女になったのがシグレとの関わりと言うが、その詳細は悪魔にもわからないらしい。それでも少女の姿は明らかに、シグレと釣り合いをとった形と思われた。
「それをオレの近くに置きますか、嫌味か……今、トウカに触れたらサクラに届くのか? 届いたらどーするつもりなんだ、あいつ……」
悪魔はその狼少女を、自分の妹だと言った。しかし狼少女は彼との取引も記憶があると言い、出会った頃の何でも屋より随分しおらしくなり、彼が狼女に見ていた本質が現れたようだった。
外に出たまま帰らない彼をそろそろ心配したらしい。船尾の扉の壁にもたれて座る彼の横で、がちゃりとドアの開く音がした。
近付く気配は感じていたので驚かない。現れたのは水色のパーカーに紅いストールを羽織る狼少女で、哀しげな全身で静かに彼を見つめて言った。
「……触れられないよ。今のわたしには、もう実体は持てないから」
物理的にドアノブに触れ、開けることもできているのに、狼少女は実体ではない。桜色の娘が悪魔になったキッカケなのだが、彼女達は先日命を失いかけ、自らの光を失うなど、「力」に大幅なダメージを受けた。それでこうして、実体に近い密度を持つことはできるが、真の体を持てるのは桜色の娘だけになったらしい。
「さいですか。ま、今のあんたに触れたらオレ、さすがにロリコンだしな」
実際問題、そんな体力もない。それでも隣に寝られていると落ち着かず、逃げ出す彼に狼少女はいつも憂い気な顔をする。
彼が知った何でも屋とは大分口調が違う。しかしヒトを視通すような目つきは同じで、その悲しげな黒い瞳は、彼の間近に死が迫っていることを示して余りあった。
狼少女が黙って彼の隣に座る。鎖骨くらいの長さで下ろした髪は艶のない漆黒で、これでもかというほどまっすぐだ。この「天龍」を不秩序として排除しようとしている、「悪神」憑きの秩序の管理者を思い出させた。
彼のそんなどうでもいい連想すら察し、勘の良い狼少女はまた喋り出す。
「鴉夜とは似てて当たり前。今の鴉夜の翼は元々、わたしの一部……鴉夜本来の翼を取り戻さない限り、鴉夜は『悪神』には勝てない」
彼を見ずに、悲しそうに言う。彼とは直接関係のない話題を、どうしてかわざわざ続けて言い始めた。
「シグレが攫われたのは鴉夜のため。今のシグレとわたしは、何も関係がない……わたしのためじゃないよ、烙人」
ぽかん。と彼は、思わず隣をゆっくりと見る。
膝を抱えて顔を伏せている狼少女は、いつになく拗ねた顔付きだった。
「わたしは橘桃花の影だから。咲杳が具現するわたしはそれしかいない。シグレと関わるのは、咲姫が守る方の光の娘」
「……さっぱりわかんねーけど、あんたはオレが好きって言ってるって。そう思っていいわけ?」
そこでじっと顔を上げて、無表情のまま狼少女が彼を見つめる。否定の色は清々しいほどに皆無で、純粋に彼の誤解を解きにここに来たとわかった。
ちょうど「天龍」が雲海に入った。濃霧のような真っ白な世界の中では目立つ、黒い狼少女は僅かに肩を震わせていた。
「今、シグレのふりをしてる炯に咲杳は気付いてる。シグレと鴉夜を会わせないで……烙人」
「……?」
「お願い。シグレに……炯に関わらないで。『悪神』は炯を利用して、鴉夜を壊す。神竜の後ろにも『悪神』がいる……咲杳を駆り立ててるのは鴉夜」
流暢だった以前と違い、舌足らずに紡がれる言葉は、どれも彼には意味がわからないものだ。それでも彼は、狼少女が彼の身を案じている気配だけは強く感じ取っていた。
「変えられないって、わかってるけど……でも、いなくならないで……」
彼だけを映して澱む真っ黒な目。下ろされた髪も悲しげな表情も、素直な口調も以前の狼女とは似ても似つかない。それなのにますます惹き込まれていく。
心臓は苦しく締め付けられているのに、赤の鼓動は大人しくしている。彼が何かに心を動かす度に、この身を脅かしてきた憎悪なのに。
そうか――と、彼は、真っ白な空の中で悟る。
この少女をこそ、彼も探していたのかもしれない。際限のない赤に侵され、蒼や紫に染まる前の、青だった頃の静かな彼が。
だからこそ、かの「悪神」のささやきに、彼も抗うことはできなかった。
「悪神」に動かされていると知らない黒い鳥――秩序の管理者、橘鴉夜。その訪れは確かに彼に、運命の分岐をもたらすことになる。
「サクラが消えれば、トウカも消える。あたしはサキを起こすためにも、それをしなければいけないの、竜牙烙人」
不秩序な「天龍」を沈める布石で、鴉夜は彼に誘いをかけた。
それが鴉夜を巧妙に駆り立てる、「悪神」の罠だと知ることはなく。
「桃花が消えるって……オレに言う必要あったのかよ、それ」
「悪神」の翼を持つ黒い鳥は、何も嘘を話したわけではない。ただ、黒い鳥と「悪神」の狙いが真逆にあっただけだ。黒い鳥が去ってすぐに、彼はその罠に気が付いていた。
桜色の娘を神竜から離したい彼を、黒い鳥は味方につけられると踏んだはずだ。しかしそれでは狼少女が消えるなら、彼は桜色の娘にも背を向けなければいけない。まさに彼の全てを裏切ることになる。
まず間違いなく、「悪神」は悪魔を存続させるつもりだろう。そうしなければ彼の大事なものがまた消える、と釘を刺しに来た。
おそらく黒い鳥の弱点となるのがシグレの存在。彼がどう動けば悪魔を消さずに、桜色の娘側である黒い鳥も保つことができるのだろう。
ひとまずシグレ――を名乗る、炯に接触してみるしかなかった。
それこそ狼少女が止めた、彼の滅びの道であると知りながらも。
「ふうん、そんでさ。オレの話に乗る気はあるん? お前さんは」
「何度も言わせるな、炯。そうでもしなきゃ、その躰……シグレを解放しないだろ、アンタ」
袖の無い黒衣に丈の短い上着を羽織る金髪の少年は、心眼の仲間の養子の体を勝手に使う蛇の悪魔で、黒い鳥の探し人だ。その事情自体は少し前から知っており、名前が炯ということだけが初耳だった。
「アンタの宿る逆鱗はシグレの短刀に遷して、オレのとどめはアンタが殺せ、炯。オレはこのまま悪神の言いなりになるしか、桃花を守れないんだから」
そうすれば蛇の悪魔は遠からずシグレから出て行く。その約束を条件に、悪魔が望んだものは彼の命。最早消えかけている彼の最後の「力」を、シグレに遷すことで黒い鳥を守る賭けをしたいと言う。
「……悪いな。お前さんの『力』が、時雨と妹以外に渡ると最悪だからな」
「アンタこそ、鴉夜を助ける算段はあるのか。このままじゃ誰もが犬死にするぞ」
彼の「力」の大半は、既にシグレの妹に行き先が決まっている。彼に紫の気を与えた神泉の精霊と、それに同化した彼の双子について、仲間と同じ「心眼」を持つ桜色の娘に遷移を頼んであった。そもそもシグレの妹を起こした張本人だからだ。
しかし呪われた赤の鼓動の行き先はない。彼と共に滅んでもらう所存だったが、蛇の悪魔が考える最悪の場合、それはシグレと黒い鳥を守る最後の砦になると言う。
「お前さんも鴉夜も、紛れもない『青炎』。氷と熱、形は違うが、お前さんの源流は見事な氷、そして鴉夜は熱の使い手。時雨は鴉夜の青炎の翼を持つ精霊崩れだから、お前さんに合う赤火なら適合する――それが悪神への対抗馬になる」
青炎というのは、青の字に月が入っているように、「月属性」の別名だという。月は太陽の光がなければ輝かないように、他者の力を己のものとして使う地獄の鬼火と言われている。
彼の本質は青だとかつて言われた。それは深淵の黄泉から生じる霧で、常に誰かの影となり、確かにそこに在りながら、単独では姿を見せることのない有り得ない存在。
だからこそ、何かに心を燃やし続ける赤の鼓動があっての彼だった。
自称神竜と敵対し、桜色の娘を取り戻そうとしている源流の彼は、彼がかつて失ったらしき蒼の魂――氷を扱う力を持っている。たとえ魔性の紅を帯びた蒼でも、それがなければ源流の方も己を保てない白い存在だ。力の通り、氷のように心は凍てついている。蒼の魂に桜色の娘を求める未練があるから、生き物として動けているとも言える。
桜色の娘に関しては、その蒼の源に任せるしかない。彼と違って寿命も近くない悪魔なので、おそらく何とかしてくれるだろう。
蛇の悪魔と取引した後に自室に戻ると、寝台の上で狼少女が膝を抱えて黒い頭を埋めていた。彼が何を決意してきたのか、リアルタイムで現状を悟れてしまう彼女の不思議な目敏さは、出会った頃から相変わらずだった。
「……泣いてるのか、あんた」
「…………」
シグレと――炯と関わるな、と彼女は言った。それでも彼を変えられないことを、わかっているとも。
彼の決意は、他ならぬ彼女を想ってのことだからだ。シグレだけでも残すためには、消えゆく彼の鼓動を受け継いでもらうしかない。そしてこの先、狼少女にはシグレが必要なのだと、彼も感じていた現実を蛇の悪魔は口にした。
ほぼ初対面の蛇の悪魔を、取引する程度に信頼したのには理由があった。
アレは彼と同じく、女のために運命を狂わされる性質だ。そして同じ悪魔の性を持つ桜色の娘と、狼少女を知っていると言った。狼少女も、桜色の娘もその内の悪魔も、消えない未来は存在するのだと。
――お前さんがサクラを残したいなら、それは正解だと思うぜ。
彼も思っていた。何故今この時に、狼少女が戻って来たのかを。
「……なあ。あんたがオレの前から消えたのは、サキのためだったんだろ」
「……」
寝台の中心で蹲っている狼少女を背に、彼も端に座る。
「サクラがサキになったのがあの時だった。それでサクラの霊獣のあんたは消えた。オレは今のサクラの方が、本当はよく知ってる気配だ。オレと一緒にいた頃のサキは、サクラだったんだろ」
桜色の娘は、彼が黒い狼女と知り合った頃には、今と同じ薄紅の眼をしていた。伴う霊獣も濃い灰色で、白黒猫を扱う青空の眼で桜色の髪になったのは、狼女が消える時のことなのだ。
「あんたも炯も、サキやシグレを守ろうとしてる。でもオレは、あんたとサクラを守りたい」
「……」
「多分シグレは苦しむから、助けてやってくれ。……勝手は承知してる」
ぴたり、と空気が止まったようだった。音も出さずに、震える狼少女が背中にしがみついた。
「わたしは、もう一度……アナタに、触れたい」
これを置いていくのかと思うと、決意があっさり挫けかけた。
未練だらけなのは悪くなかった。しかし遥か後に彼の願いが、狼少女と旅をする時雨によって覆されることを、この時には知る由もない。
†蛇の悪魔
正史 -Side.Kei-
「デザイナー……チャイルド?」
怪訝そうにぽかんとしている橘鴉夜が、久しぶりに戻った診療所では、院長の灰と患者の間で謎の単語が飛び交っていた。
話題の当事者である患者の刃は、いかにも人外生物の尖った耳をかきながら、困惑顔の鴉夜に素早く説明してやる。
「オレみたいな人造の生き物のことっすよ、鴉夜さん。『刃の精霊』なんて、普通いないっすからね、自然界には」
刃を名乗る金髪の少年は、何でも鋭く刃物にしてしまう「力」を持っている。その事は刃と以前、同じ劇団でバイトをしていた鴉夜なら知っているはずだ。
人外生物御用達な、橘診療所院長の養女である鴉夜は、人外生物を取り締まる神職に就いている。鋭く端整な顔立ちに、鴉の濡れ羽色の髪が映える、文句ない美少女の鴉夜に討伐されたら刃は本望だが、バイト仲間時代には見逃されていた。刃がそうした不自然な存在だと、その時には気付かれていなかったのだ。
外来で刃を前にし、やれやれと院長が頬杖をつく。白衣以外は鴉夜と同じように黒ずくめの院長は、見た目は完全に似た者親子だった。
「やるなと言うのに、コイツのようなアホを産む魔学者が未だに後を絶たない。もっと酷い、人間の都合で造られた吸血鬼も知ってるが、用途を決めてヒトを創っていいのは神だけだと、何で誰もわからないんだかな」
アナザーワールドワイド、つまり異世界中に広がる人外生物診療所の異端な院長が言うわりには、常識的な内容だと刃は思う。
けれどそれは、娘のはずの鴉夜には全く通じなかったらしい。
「能力や種族をあらかじめ選んで、新しい子供を作ることなの? それって何が、そんなに悪いことなの?」
「おまえが言うか、アヤ。おまえもそれで被害を受けたクチだろ」
養女になる前、鴉夜は計画的に生を受けさせられた人間だという。古い風習である「神」への貢物にするため、生贄であることを隠して育てられたのに、鴉夜本人にその疑問が浮かばないのが刃には憐れだった。
「オレは精霊崩れの妖魔だから知ったこっちゃないっすけど、人間の鴉夜さんには、それはどーかと思うっすよ。だって、人間だけじゃないっすか、神様に赦された存在って」
「……?」
「化け物と違って『神意』に縛られない『人間』なのに、何でわざわざ可能性を閉ざすんすか。オレみたいな化け物には理解できないっすね。せっかくの人間のぬくもりが勿体ない」
伝わってほしいが、難しいことは以前からわかっている。
鴉夜は刃のような、理の外に出かかった化け物を狩る神の使徒だ。人間の鴉夜がそうなってしまったのは生贄にされたからで、橘院長に拾われなければ「神隠し」で闇に消えていた少女なのだ。
人間は弱いが、代わりに化け物より行動が自由という利点がある。例えば世界を滅ぼせる「力」を持つ化け物がいたら、その機能は必ず制限される。人間世界のゲームのラスボスのように、存在の仕方までおそらく限定される。
「神意」――理というのはそういうものだ。でなければ世界は成立も存続もしていない。
外来の丸椅子にちょこんと座る刃の口上を、埒外者の命乞いと受け取ったらしい。両腕を組んで立ち尽くす鴉夜は、難しそうな顔付きで刃を見下ろしてきた。
「……まだアナタを、討伐する気はないから。下手な甘言で誑かそうとするのはやめて」
一見はとてつもなく不機嫌に見えるが、刃は内心でほっこりとしてしまう。
鴉夜は不器用だが、鈍い人間ではない。上手く解釈はできていないものの、刃の好意には気が付いている。先程の喋りが「甘言」と聴こえているくらいには。
幸薄い育ちの鴉夜に、僅かな心遣いだけでも受け取ってほしかった刃は、務めて能天気な笑顔を浮かべた。
「大丈夫っすよ! 鴉夜さんにちゃんと旦那がいるのは、オレ、知ってるっす!」
鴉夜の目付きが一瞬で過剰に険しくなった。オイ、と院長が思わず退いている中、場の空気が急激に凍結を始める。
「誰があんな――五年以上も人にペットの世話を押し付けていく奴……!」
その言い草にも、刃は笑いを堪えられない。問題はそこか、とつっこみたくなるのを、抑えるだけで必死だった。
橘診療所の外来室には、院長室と受付に続くドア以外に、四方の壁に一つずつドアがある。それぞれが数多な異世界に繋がるという稀少な中継地点を、鴉夜が暴発して吹っ飛ばす前に、院長は義理の娘をさっさと追い払っていた。
元々鴉夜は、様々な場所に行くためにここを通過するだけで、滅多に留まることはない。診察場とドアの間もカーテンで仕切っており、院長と顔を合わせることもあまりないという。
「ああいうところが、あいつの弱味だな。全然変わっていない」
溜め息をついて煙草をふかす院長に、丸椅子上であぐらをかきながら刃は笑いかけた。
「えー。神の温情など知らぬ、人間もまた求道者って感じで、いいじゃないっすか、クールビューティー」
「元凶のオマエが言うな。いつまでそこの妖魔の皮を被ってる、アホ炯が」
鴉夜がいなくなったので、遠慮なく口に出されたある真名。
その名の主を探す養女を知っていながら、院長は秘密裏に匿っている。灯台下暗しとあえてここで面倒を見る苦労性に、刃を名乗る金髪の少年は、たははと苦笑うしかない。
院長の縁戚である橘炯は、わけあって、この少年――「刃の妖魔」に、少し前から寄生している。勿論妖魔からは非難轟々だが、妖魔と共通する目的があるため、辛うじて体を使わせてもらっている。
「オマエをずっと探すアヤに、いつまで無駄骨をさせる気なんだ。この人でなしの蛇の悪魔が」
「それは言わないでぇ。オレも苦肉の策なんよ、刃くんにも無理言ってるのはわかってるんよー」
悪魔である炯が体を使う影響で、刃の精霊はほぼ完全に妖魔となってしまった。それでも刃が炯に従うのは、ただ一点、刃もバイト仲間時代に惚れていた鴉夜を守るためだ。
しかしこの憑依体質の体には他にも一つ問題があり、そちらについては、炯と刃は完全に敵対している。
刃にとってこの体は、本来「剣の精霊」――師匠と呼ぶ少年のものであり、それを炯が使うのは許せないようなのだが、肝心の「師匠」が体を使わない。同じ体の内にいるはずの時雨という存在は、欠片も顔を出そうとしない。
そんな奇妙な関係の三者は、誰もがおそらく、鴉夜という不遇な少女を守りたいと思っていた。
「神」への供物となった過去のある鴉夜は、残念ながらもう人間とは言えない。それでも人間である頃に悪魔の炯が契約を結び、「神」に隠される末路から既のところで逃れさせた。
そのために炯は、後に自らの体を失った。早い話、死んでしまったわけだった。
蛇を象徴とする悪魔の炯は、分身と言える小蛇を鴉夜に預けたままだ。それが生きているから、鴉夜は炯が生存していると信じて、年を取らなくなった少女の姿で探し続けている。
「アヤの一途さに感謝するんだな。今オマエをこの世に繋ぎ止めるのは、あいつとの『契約』だけだろうからな」
「仰る通りで。でもオレ、別に生き返ろうと思ってるわけじゃないんよ」
「……ん?」
仮にも悪魔である炯は、肉体の消滅が必ずしも死になるわけではない。こうして他者に憑依して、体を奪うこともできなくはない。
それでも今や、炯の望みは一つだった。
「オレは……ただ――……」
†鬼火のカラス
正史 -Side.Aya-
近頃よく顔を見かける妖魔に、その都度小さな説教をされる橘鴉夜は、己に不可解なストレスが溜まりつつあるのを自覚していた。
橘診療所以外に家のない鴉夜は、度々泊めてもらう知人の玖堂咲姫の下宿で、寝床の黒いソファに膝を抱えて座り込んでいた。
脳裏に何度も、他愛のないやり取りがしつこく再生される。
――せっかくの人間のぬくもりが勿体ない。
女好きでお気楽な妖魔に、もっと色々、何か言い返したかった。
悪意ではない、むしろお節介の言葉とはわかるのだが、鴉夜の心中はざわざわと騒いで鎮まってくれない。
本当に、「ぬくもり」が良いものであるなどと、いったい誰が決めたのだろう?
立て襟の服を愛用する鴉夜は、幅が広くゆったりとした襟ぐりに潜ませている小蛇に、文句を言うように話しかける。
「……あたしはそんなに、物欲しそうに見えているわけ?」
そもそも、神の使徒に罰されないことを「ぬくもり」と言い替える意味もわからない。
それは人間が、世界というシステムそのものに影響力のない弱小存在だからであって、罰則が緩いことを温かいというのはおかしい。
世界とは「理」で成り立っている。化け物が扱う神の神秘――「力」とは、この理そのものを揺がす奇跡だ。聖書に載る秘蹟などは、ごく一部の「力」に過ぎないだろう。
「力」に縁のない人間だけの世界には、そもそも「本物の神」もほとんどいない。橘診療所の大きな得意先、鴉夜が今いる日本は特に、妖怪や鬼など、何でもかんでも神認定する国だと養父が教えてくれた。
「カイみたいな神眼持ちが、隠居して引っ込んでるせいでしょ……でなければ……――」
もしも養父のような「神」の一端が、故郷のような僻地に目を光らせてくれていれば。
そう思いかけた瞬間、ぼやいた声の出所より深い体の奥で、身の内から背中を破るような激痛が突然走った。
「っ――……!」
いけない、こんな弱音を吐いてはいけない。
思ってすらいけないのだと、生贄の少女は両膝をきつく抱きかかえ、頭を埋めながら必死に呼吸を殺した。
鴉夜の故郷は、こことは違う、化け物の多い異世界の辺境にあった。先刻の妖魔と同じ世界の生まれだ。
多いと言っても化け物の絶対数は人間より圧倒的に少ない。何処の世界でも人間は多数を占めるらしく、神に赦された存在というのは伊達ではないのだろう。
ひっそりとした森の奥の集落、建前上は人間だけの原始的な村で、鴉夜の家は「金烏」という神を祀る神子の家系だった。会ったこともない兄が後を継いでいるが、一子相伝の家で第二子の鴉夜が随分遅くに儲けられたのは、村の災いとされた森の魔女、「黒鳥様」を討伐できる巫女が生まれると、金烏のお告げがあったからだという。
「黒鳥様を倒す、それだけがあたしの役目……別にあたしは、それで良かったのに……」
人間であるはずの鴉夜は、人間ならぬ「鬼火」の「力」を持って生を受けた。それで村を困らせる魔女を排除するのだと信じて、自らを鍛える生活に明け暮れていた。
鬼火というのは、地獄の青い炎と言われ、通常の火とは逆の性質を持つ。虚熱と言われる鬼火は「周囲環境の熱を吸収する力」であり、奪った熱を以って炎と成す。
つまり鴉夜にとって、熱――ぬくもりとは搾取するものだ。悪い魔女を殺すために、日夜集め続けた凶器なのだ。
「だから……別に、温かさ、なんて……」
その「熱」が鴉夜にとって、全く違う意味を持った日。
魔女の討伐に使うまではと、人間の弱い体にひたすら溜め込み、激しい苦しみしかもたらさなかった熱。それを、突然現れた陽気な蛇の悪魔は、自分が引き受けると言い出したのだ。
「あんなの……温かくなんて、なかった……」
黒鳥様を調査しにきたという、同年代に見える旅人の少年は炯と名乗った。珍しい鬱金の髪と、笑顔のわりに鋭い青白の目には怪しさしかなかったが、黒鳥様の元まで案内してほしいと言うので、いよいよ討伐に向かう鴉夜に炯は同道することになった。
――オレは、あんたに消えてほしくないんよ。わかる?
一目惚れしたと言って憚らない炯は、しきりに鴉夜を止めた。この村は何かおかしいと、可能な限り鴉夜の道中を引き延ばしにかかったのだ。
鴉夜はその当時、身の内に溜める熱のせいで常に体調不良で、道を急ぐこともできなかった。険しい森の丘は方角を定めることもままならず、炯と何度も暗い夜を明かした。
あまりに苦しそうな鴉夜を見かねたらしい炯は、自分が悪魔であることを明かし、鴉夜の熱を炯が代わりに溜める契約を持ちかけてきた。このままでは討伐もままならないと、鴉夜はそれを受け入れた。代償は炯の番になることだった。
――ダメ元でも言ってみるもんだなあ。っていうかあんた、相当ヤケだな?
鴉夜は役目を果たす以外の人生など考えたこともなかった。炯の好意が本気であるのは薄々感じていたが、ひたすら落ち着かなかったとしか言えない。
けれど、魔女を殺した後、自分はどうなるのだろう。鬼火以外に能のない人間は、無用の長物になるかもしれない。その不安は押し隠していただけで、他に自分が必要とされる道があるとは思えなかった。
だから炯の話に乗ってしまったのかもしれない。何か一つでも、未来を照らす灯りが欲しかったのだ。
「それなのに……嘘吐き……――」
思い出を手繰っている内に、肌寒い空気が居間に立ち込め、すっかり外も暗くなった。
もう少しすれば、この家の主も帰ってくるだろう。炯の姉のようなもの、と自称する咲姫には、無責任な弟の文句を言わねばならない。
「一緒に逃げようって……言ったくせに……」
鴉夜の熱を根こそぎ奪っておいて、魔女の社に辿り着く直前に、炯は突然、魔女を殺すなと言い出した。契約不履行で炯の番にはならなくていい、だから熱は渡さない――鴉夜に鬼火は使わせないと。
その時、自らの激震と共に感じたことを、鴉夜は今でも上手く言葉にできない。
とても追い詰められたのは確かだ。魔女を殺すためだけに育てられたのに、これではどの面を下げて村に帰れば良いのだろう。
しかし、社から出てきた魔女――鴉夜を待ち受けていた女の顔を見て、鴉夜は全ての嘘を知った。森の最奥の社にいた魔女は、他ならぬ鴉夜の母だったのだ。
正確には、それは母ではなかった。母に巣食い、母を魔女へと変貌させた「悪神」という神意――
いつの時代も、世の陰に隠れてヒトを唆し、太古から人々を悪行に導く黒い翼の神。今の養父が縁戚の炯を調査に派遣するほど警戒していた、古代の本物の「神」の一人だった。
初めから鴉夜は、金烏の家系に目を付けた悪神が、己の新たな器にするために作った第二子であるとそこでわかった。「悪神」を宿す母と金烏の父の間の子なら、天賦の神性を持ち、悪神にふさわしい何かの「力」を持つと見込まれていたのだ。
その結果が「鬼火」の存在なのだと、近い線まで途中で炯は気付いていたらしい。鴉夜が鬼火で溜める熱をよこせと言い出したのは、鴉夜に悪神以外との繋がりを作るためだった。
それで鴉夜は、悪神と一体化する――神隠しによって、鴉夜という存在が消えることを何とか免れた。
しかし、母と同じように悪神に巣食われた体は、隙を見せれば鴉夜の背に黒い翼を生やそうとする。先程の激痛はよくあることで、悪神と闘う発作と言っていい。
炯は負けるな、と言ってくれた。悪神から解放される術を、共に探そうと約束してくれたのに……。
こんなことになるなら、きっとあの時、鴉夜は消えていれば良かったのだ。
母がいつから、完全に悪神だったのかはわからない。兄は悪神の子ではないし、幼い頃の記憶にいる母は、あんな妖艶な微笑みを見せなかったと思う。
母の目論み通り、魔女を――母を殺す役目を終えて、後は悪神にこの身を渡せば良かった。炯がいたせいで、抵抗すると決めてしまったから、今も鴉夜は独りで闘い続けている。
たった一つの、契約という嘘。陽気な悪魔の少年がくれたぬくもりのために。
――だからここは、一緒に逃げよーぜ? オレの嫁になってもならなくても、鴉夜にはヒトを殺させたくないんだよ。
そんなことを言っておきながら、いなくなってしまった無責任な悪魔。そうした相手に、役目を果たすためだけに生きた鴉夜の気持ちがわかるわけはない。
なのにどうして、鴉夜はその手を取ってしまったのだろう。この時の炯を思い出すと、胸が熱くて肩の震えが止まらなくなる。
襟の内で鴉夜の首にじっと張りつく、悪魔の小蛇が温かい限り。
加えて、鴉夜の内に熱がこもらず鬼火が使えている間は、炯との契約は生きているはず。それが今の鴉夜を導く灯火で、呪いとすら感じる虚ろな青い炎なのだ。
悪神に祟られた後、鴉夜は橘診療所に連れていかれた。そこで使徒の仕事を引き受けることを条件に、一命を取り留めたと言える。
その後、悪神を祓う旅の途中で炯がいなくなる前に、炯は珍しく真面目な顔で鴉夜に言い含めたことがあった。
――鴉夜。ヒトが『悪』に負けるのは、何でだと思うよ?
ヒトの心に付け入ることを得意とするはずの、「悪魔」の名を冠する少年。その目に映る鴉夜の姿は、ひどく危なげだと言うように、いつもの陽気さが炯の声から抜け落ちていた。
――『悪』を扱うのなら、『ぬくもり』は必修事項だぜ。今すぐじゃなくていいけど、いつかは向き合えよ……自分自身でな。
いつの間にか、知らない内に知人宅のソファで横たわり、鴉夜は眠りこけていた。懐かしい夢の続きを思い出す前に目を覚ましてしまったことに、大きく溜め息をついたのだった。
結句

その黒い鳥の青い炎……悪魔と繋がるためのぬくもりは、まるで「呪い」のようだと、少女が本能的に怖れていたことは正しかった。
少女を縛り、旅から旅へ駆り立てるもの。
悪魔の少年も警鐘を鳴らしていた。思えば少年が妖魔に憑依して以後、少女から身を隠し続けたのは、実に懸命な判断だった。
ヒトが罪を犯す時は、どんな状態であるか。それを考えれば答は簡単だろう。「悪」への誘いは何処にでもある。それが悪魔からであれ、悪の意を持つ神からであれ。
彼らはその時、どうした餌を使うか。この少女を闇に堕とすことなど、「悪神」には些細な問題だった。
あえて少女を泳がせ続けたのは、退屈しのぎのつもりなのだが――もしかしたら、少女の母であった心の名残かもしれない。
そうだとすれば、これも一つのぬくもりがもたらした呪い、空しい嘘だったのだろう。
この先少女が少年に出会い、現実の冷たさを知る日までは、黒い翼は真の主を待ち続ける……。
-青炎-
ここまでご覧下さりありがとうございました。
5月中にUP予定の『インマヌエル -神-』でこのシリーズは一段落となります。
4/9にUP済の『インマヌエル -天-』が本作の続きとなります。よければご覧ください。
初稿:青炎
2020.9.29<R>
2018.12.13<Kei.Aya>
2023.3<Sky>


