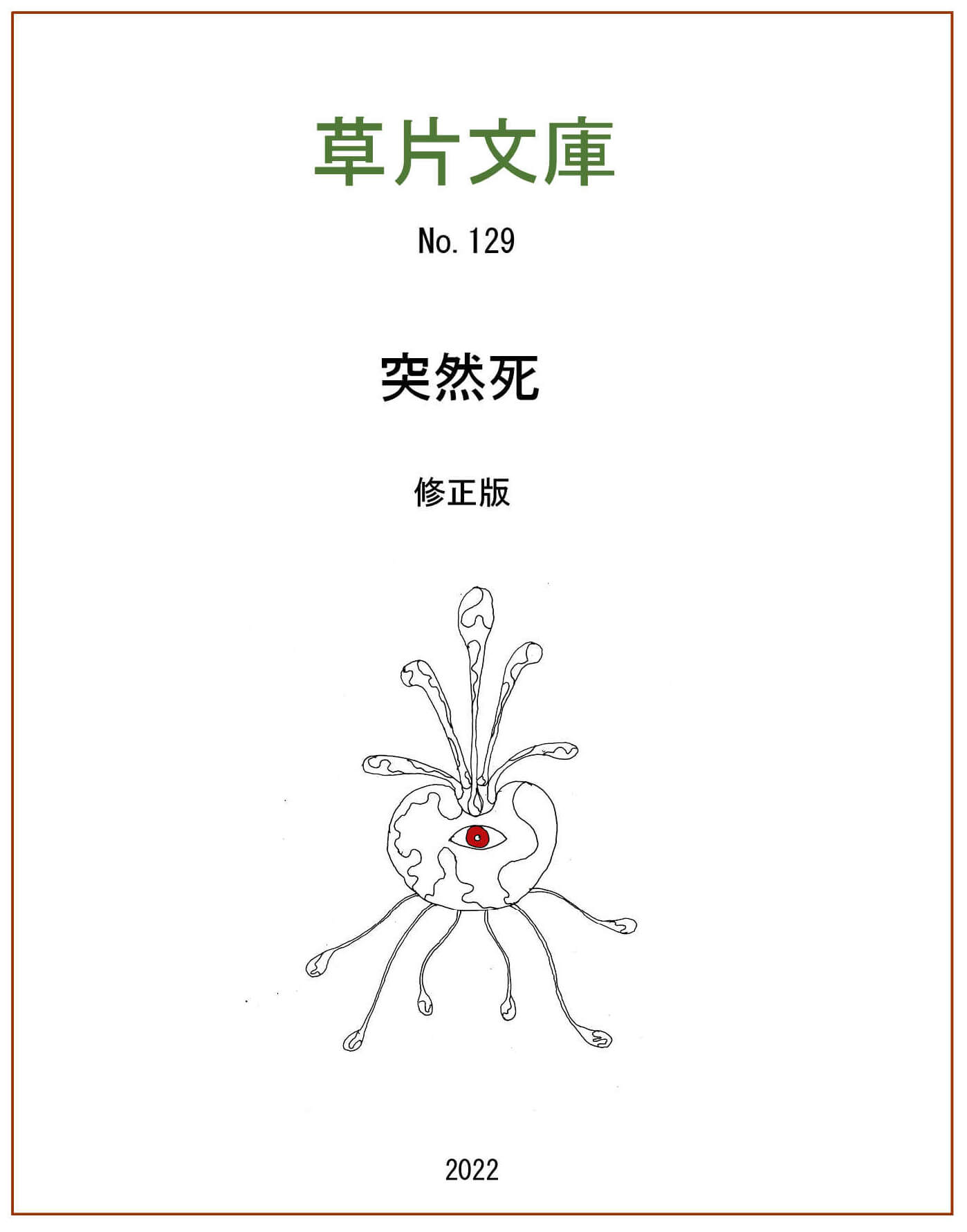
突然死
未来の話です。
2000年代の新聞をにぎわした科学記事がある。突然死を招く遺伝子が明らかになったのである。
突然死の原因は様々である。脳梗塞もあれば心臓の血管の梗塞もある、血液が脳に行かなければ脳の機能がすぐに停止し、心臓そのものに血液がいかなくても死にいたる。脳の血管がつまって、心臓を動かしている働きと意識の働きをもつ脳の部位の神経細胞が死ねば、痛みも感じないうちに死をむかえる。
その昔、ぽっくりさんという、ぽっくり死にたいという願望をかなえてほしいという、信仰に近い集まりがあった。
たしかに先に書いたように、意識の部分が停止してくれれば痛みも感ぜずにあの世にいけるわけである。いうなれば意識の停止をともなう突然死である。
しかし、医者は突然死がおこらないようにするのが仕事である。脳の血管や心臓の血管に血液が固まって、流れをふさいでしまわないような薬を開発したり、そうなりやすい体質の遺伝子の改良などを考え研究を進めるものである。
ある循環器の医師が基礎研究を続け、血管の細胞を作り出すことに関係のある遺伝子を発見した。その遺伝子は血管を作る細胞の表面を化学的になめらかにする遺伝子で、それにより梗塞が起こりにくくなるのである。その遺伝子の発現を強めることにより、脳にしろ心臓にしろ、梗塞の起こる確率は低くなる。ある意味で画期的な発見であった。
もちろん、世界中の研究者が、その遺伝子操作により梗塞をなくすような方法の開発に着手したのである。
そう言った涙ぐましい努力と、新たな発見の中で、今度は突然死そのものに直接かかわる遺伝子がみつかった。見つけたのは獣医師である。この遺伝子は、脳の主要な機能を司る遺伝子と連絡網をもち、通常は脳の遺伝子同士の強調に欠かせない働きをしている。ところがその遺伝子は、動物が思春期をむかえ性的な成熟をして数年または数十年たつと停止することがおき、脳の働きがあっという間に止まってしまうことによりぽっくり死ぬことがある。しかし通常は寿命以上に正常に働き続けるので、動物が生きている間にその遺伝子の停止で死ぬことはほとんどない。
人間以外のほ乳類は、生殖年齢が終わり、しばらくすると寿命が終わる。人間だけは、生殖年齢終了後も人生の3分の1以上寿命があり、社会の発展に貢献できる仕組みになっている。どちらにしろぽっくりと死ぬわけではない。見つかった遺伝子は、脳機能の司令塔であり、脳の寿命をつかさどるもので、それが何らかの異常を起こすとあっという間に死ぬわけである。
ほとんど問題にならない遺伝子であるが、遺伝子の働きである脳の機能の協調作用をより強くすれば、脳の寿命をのばすことができる。そういったことで、当時のトップニュースになったわけである。
逆に考えると、その遺伝子を薬か何かで停止させれば、ぽっくり死ねて、安楽死をもたらす遺伝子ということになる。痛みを感じることなく脳の機能が停止して死に至る。
ノーベル賞の候補になるとかならないとかいった、そのような程度の発見ではない。そのようなものを通り越して、人間生まれてから最もすごい発見と言っても言い過ぎではない。
その発見に至る経緯をみてみよう。
血管の内面を滑らかにする遺伝子の発見に考えを新たにした獣医師がいた。昔は寄生したフィラリアが心臓にはいって、犬が突然死んでしまうことがよくあった。衛生環境がよくなった今はあまり見られるようではない。だから、犬で突然死について研究している人はいなかったが、ペットブームになり、飼い主はできるだけ健康に長くペットと一緒にいたいとねがい、ペットの健康と寿命は獣医の世界でも大事なテーマとなっていた。もともと、家畜の管理が主だったが、犬猫を始め兎、モルモット、今では針鼠まで、寿命と健康管理が獣医に課せられたことになっていた。
その獣医師は昔から脳梗塞、心臓梗塞の基礎研究をしていた。だから血管表面の遺伝子の構造に着目していたのだが、先を越されてしまった感があった。心臓と血管をコントロールしている自律神経系にも関心があった獣医師は、拮抗する二つの自律神経、交感神経と副交感神経の協調に、どのような神経回路が発達しているのか、調べることにした。
自律神経は人であれば、大脳新皮質の精神作用まで影響する。ストレスで胃が痛くなるというのはそういうことだ。ということはとてつもなく複雑な神経回路が働いているに違いがなく、中心的働きをどこがしているのか突き止めて見ようと思った。まずは基本的な実験動物であるラットを使って始めた。鼠といって馬鹿にするなかれ、哺乳類の進化樹のかなり根元にいる動物で、人間の機能を調べるには適している。
血管の内側をスムースにする遺伝子の発見から十年、獣医師は神経細胞におかしな遺伝子をいくつかみつた。しぼっていくと、通常では着目しないようなよくわかっていない遺伝子だった。名前はない。とりあえずおかしな8つの遺伝子の中の八番目だったので、8番の遺伝子と呼んだ。8番遺伝子はネコ、大型のほ乳類、猿、どの動物にもあった。
研究者仲間の遺伝子研究の医師にも調べてもらったら人間にもあった。
その獣医師はネズミを用いてその遺伝子に一部を壊してみた。すると、ネズミの脳の機能が停止して死んだ。自律神経機能が働かなくなったのである。人間では実験なの度できない。医学部の知人は自律神経が極度におかしい患者の遺伝子を調べたところ、その8番の遺伝子の構成が正常のものと比較しておかしいところが多かった。
獣医師は遺伝子操作でネズミの8番遺伝子を調べていくと、脳の生きるための機能にかかわる遺伝子と相互作用をもつものだということがわかり、突然死んだ犬の遺伝子の詳細な解析をおこなった結果、8番遺伝子の構成部分に異常があった。その領域をA領域と呼ぼう。
ネズミで、8番遺伝子のA領域を、突然死した犬と同じものに変えたところ、大人になったら、ぽっくり死んだのである。ただし、その時点で寿命との関係はまだわからなかった。獣医師は医学部の研究者を巻き込んで研究を進め、8番遺伝子が脳全体神経細胞の維持統制にかかわる重要なものであることが、まずネズミで明らかになり、人でも確認されたのである。働きからすると、8番遺伝子は哺乳類の寿命にかかわることになる。8番遺伝子の寿命が脳機能の寿命、その動物の寿命ということになる。ということはその遺伝子を操作し、異変を起こさせればぽっくりと死ぬようになるし、逆に寿命もながくすることができる。
こうして、ぽっくり死ぬ遺伝子が明らかになったわけである。
付け加える話がある。
獣医師は動物愛護団体に入っていた。動物の蛋白は人間にとって重要である。人間の発育を考えたとき、植物の蛋白だけでは脳の機能が弱くなる。もちろん、筋そのものものにも動物タンパクは必要である。
昔の人間が動物を家畜にしたことはしかたがないことである。それが生活を豊かにし、安定な動物タンパクを供給する道を開いたわけである。しかし、家畜に死を与える役割の人たちがそこにいる。
動物福祉に関心が強くなってきたころ、人間は動物の細胞を培養して、筋肉を培養液の中で作り出してもいた。それでも、やっぱり草を食べいろいろな飼料を食べた牛の肉と比べると、栄養価はすべて同じというわけではないようだ。ただ、長時間の宇宙旅行などには培養食物は重要なものであり、研究は進められていた。
獣医師は動物愛護団体から要請され、神経細胞8番遺伝子の変異を生じさせることで、突然死のおきる牛をつくりだした。成長し生殖年齢を迎えたのちに8番遺伝子が変化し、突然死を引き起こす。死んだらすぐに肉処理会社に移送される。そうすれば、殺すという、行為はなくなる。さらに研究を進め、その動物の肉が最も美味しい年齢で死ぬような遺伝子操作もできるようになった。こうして食料問題にも、脳神経細胞8番遺伝子の発見は偉大な解決策を見出したのである。
もし、人間にそれを施したらどうなるのだろう。寿命がわかっている人間はどういきるかということなど、倫理問題に発展し、人への遺伝子操作は禁止された。
脳の中の突然死に関わる遺伝子と、時計遺伝子が関係している寿命の遺伝子との関係を明らかにすることで、一定に生きたのちぽっくり死ぬ動物を作ることができるようになるはずである。
しかし、ネコやイヌなどペットに関しては議論が巻き起こった。苦しまずに死ぬならいいじゃないかという人もいれば、最初からいつ死ぬのかわかっている犬猫を飼うのはつらいという人もいる。自分と同じ時に死ぬのならいいという人もいる。ただ共通していえるのは、苦痛なくぽっくりと死ぬのなら、動物にとってもいいのではないかという意見が大半をしめたのである。条件付の容認の方向に傾いた。
そこで出てきたのは、脳とからだの機能が著しく低下し、生きるのがつらそうになる前にぽっくり死ぬような遺伝子改良がなされるなら許可するということになった。
しかし、人間の寿命を決める遺伝子操作の研究は許可がおりることはなかった。
今では、肉は、培養より栄養価の高い突然死の畜産動物より取り出されるようになった。人間は、子どものころは突然死した家畜の肉を食べさせるほうがからだにいいということもわかり、十二歳までは自然の動物の肉の購入の補助が国よりでて、割安で買えるようになった。大人も高級食材店で購入できるが、かなり値の張るものである。収入の少ない家庭では、親が子供の食べなかった突然死豚や牛の肉を食べているという話もあった。
西暦で言うと3000年、人間も生まれて一年経ったときに、死ぬときには突然死をおこすような遺伝子操作を受けることが義務化されている。死ぬときにはぽくっと死ねるし苦しくもない。しかし、いつ死ぬか分からない。まだ寿命を決めるような遺伝子操作にはいたっていなかった。
西暦3000年の終わりころ、寿命の遺伝子も操作できるようになったが、これは本人の希望で、いつでも受けられる。その当時人間の寿命は130年である。今でも病にはかかる。特にウイルスによるものは彼らの遺伝子変異能力が人間に勝り、どうしても人間はウイルスによる病になり、苦しむ。一番怖い病気は肺炎である。昔ながらの病である。もちろん投薬でそれはおさまる。しかし、毎週新たなウイルスがでてきて、病にかかる人がいる。そういうときに、本人の希望があれば、遺伝子改良により、半年後にぽくっと死ぬような設定をすることもできる。それを取り消すこともできる。もちろん有料である。
大昔の、自殺のようなものだが、人間の考え方が変わったのである。生き物は死ぬ、そう言うことをやっと人間は自分のこととして、とらえることができるようになったのである。
「ずいぶん古いもの読んでいるのね」
万能情報機の画面をよんでいたムカショに、のぞきこんでいたニョイラが言った。
「うん、俺たちの寿命がどうしてこうなったか知りたくてさ」
「決まっているものを知ってどうするの」
「もっと長く生きられないものかと思ってね」
「長く生きたって、おもしろいことがこれ以上なければ、つまんないでしょ」
ニョイラの言っていることはムカショにもわかっている。寿命管理局の研究者たちは、楽しいうちに寿命のつきる日時がきてぽっくり死ぬように、突然死遺伝子システムが作動する仕組みを産まれてきた子供たちにうえつける。それは万人が150歳調度でぽっくり死ぬような仕組みだ。
生まれて15年で成熟して、社会での活動がはじまる。ムカショは今99歳、100歳になると社会から引退して、50年ぽっくり死ぬまで、自分のしたいことをする。15になったとき、社会統制局から、自分の能力を伸ばすことができるのは、宇宙空間航行艇の開発であることを言われ、宇宙局で新たな船の設計と建造に力を注いだ。タイムマシーンとか、異次元の航行などの技術は小説としてはあったが存在しない。現実には今ある宇宙を理解する事で人間は精一杯、エーテルの中をいかに早く他の恒星に行くことができる船をつくるかということであった。
今一番早いものは、光の1万倍の速度で真空中を進むことができる。百光年さきにある恒星に旅行に行くのに、三日か四日でいける。観光としてはとても面白いが、今まで人が住めるような星はみつかっていないし、ましてや、人間並みの生き物らしきものとも遭遇していない。ただ変わった生き物がいるので、そういった生き物を見に行くツアーはおもしろい。多くの人は101歳から150までの間は、星の探険に向かうのが普通だ。ムカショが開発にかかわってきた新しい船は、次世代の高速艇で今の10倍の早さ、光の十万倍の早さで進むことのできるものだったが、完成まではまだ100年はかかる。若い人に受け継いだところだ。二年後にはリタイアだが、五年前に一緒に住むようになったニョイラは寿命研究局につとめていて、やはり同時にリタイアだ。一生の間一人でいきる人、カップルでいきる人、複数の人と住む人、さまざまだが、ムカショは16になったときから、カップルでくらしてきた。ニョイラは18人目の相手だ。
子供は人口局が遺伝子操作で生み出していく。生殖の目的だった性行為は、いまは人間の脳の刺激のために必須のものの一つで、様々な刺激方法をもちいて、脳の活性かをおこなっている。脳の一部に電気刺激を与えてもいいのだが、寿命管理局としては、自然の形の刺激の方がより脳の機能維持にはよいと奨励している。ムカショは昔ながらのカップル形式が好みで、そういう逢手がいると数年カップルになる。ニョイラは寿命管理局の研究部門にいたときに、休暇で近場の宇宙空間遊泳旅行にいった。そこで、ムカショとであった。
「ムカショはリタイアしたら私と別れる?」
「ニョイラはリタイアしたあとは星の旅行かい」
「私は寿命管理局で研究してきたから、遠い宇宙に行ってみたい」
「そうだろうな、僕は新しい船の建造で、何度も試験運転で宇宙をとびまわったから、どちらかというと、人間社会の歴史なんか興味あるな」
「そうでしょうね」
「だけど、退職したら、一度一緒に宇宙の旅をしようか、そのあとに分かれようよ」
「そうね」
「ぼくはそのあとに、大昔の本というものを書いてみたい」
「紙の本の会にはいるの?」
その昔、人の伝達手段として、文字を植物の繊維で作った紙というものに印刷して、束ね本というものにした。それが歴史を伝えたり、自分の考えを伝えたりする手段だった。本には絵も入れ、一つのアート作品として、人たちの脳の刺激をする役割もあった。今は博物館で展示されている。
そのような本を自分たちの手でつくって楽しむ会がある。
「ぼくは会にははいらないかもしれないけど、そういうのもいいかもしれないな、まだ、なにをするか決めていないんだ、でも本を一冊ぐらいは作りたいな」
楮や三椏と言った木をそだて、その繊維から紙を作り、博物館で使わせてもらえる印刷機で、自分の描いた絵や文章を印刷して、自分で製本する。
そういった個人で作り出されたものは、国の文化局で、月の人間ミュージアムに展示される。
「ニョイラはなにを残すんだい」
「私は寿命研究で論文を書いたから、それだけでいいわ」
地球に生きていた人たちのその一生は、人口局で情報を管理していて、誰でもそれを見ることができる。
「今、寿命の研究はどうなってるの、これ以上のびないの」
「私がやっていたのは、寿命遺伝子の化学的寿命よ」
地球上に生まれてきたこどもたちは、知識教育と情操教育をうける。知識教育は学校のヘッドホンを当てると、さまざまな知識が自然と脳の中に入っていく。遺伝子の知識はだれでももっている。学校に行くのは情操教育のためである。社会性、芸術性などを、遊びを通して知る。
「寿命遺伝子の化学的寿命ってなに」
「物質は放っておけば分解していく、しかし物質同士が連絡しあって分解がくい止められる。遺伝子の化学物質同士、分子同士の連絡網が遺伝子の強さになるわけ、寿命遺伝子が強くなって、もっと長い寿命が設定できれば、人間は200歳まで生きられるわ」
「いつ、200歳で突然死になるようになるのかな」
「そうね、脳ばかりじゃなくて体の細胞の遺伝子も強くならなきゃだめだから、そっちの研究をしている人もいるわ」
とうとうニョイラとともに101歳のリタイアになった。
われわれは、百日間の宇宙旅行に出かけて、多くの星で、まだ未発達の生き物をみた。地球にいる昆虫類、鳥類、は虫類、ほ乳類に似た生物たちを見た。
旅から帰り、ニョイラと分かれた。ニョイラはもっと遠くの星へいく船に乗った。
ムカショは自分で本を作る前に、紙に印刷された古い古いものをみるため、地球と火星、それに月にあるミュージアムをたずねた。何年もかけてじっくりと見て廻った。
その中で火星にはもっとも古い文献や、生活に使われていた道具のミュージアムがいくつもあった。
ある意味では、古いものの倉庫のようになっている。身分証明書を出せば誰でもみることができる。管理しているのは機械類、昔はロボットと言ったが、ロボットがやっていて、大きなミュージアムでも専任の人間は数人だった。
火星の古代遺伝子ミュウージアムにいったときである。万能情報機で読んだ、突然死の大元の文献と、その研究者が書いた本があった。ムカショはそれを借りて、火星の宿泊施設にもっていった。
2100年の一人の獣医師がまとめたものである。
昔の人はずいぶんやっかいな操作を自分でおこなって、遺伝子を明らかにしていったものだ、とムカショは読みながら感じていた。ただ、自分の発見に体ごとの喜びを感じていることが文章からわかった。自分でたどり着いた想像を、自分の手で科学的に証明していくことは楽しかったに違いない。
それを文章に残して本にする。この科学者は寿命か病気か交通事故か、どのように死んだか分からないが、この本を残したことは、死ぬときには満足感に満たされていたのだろう。
読んでいくと、最後の20ページほどが、のり付けされて読めないようになっている。
なんだろうと、ムカショは借りてきた古代遺伝子ミュージアムにいって、本を見せ、理由を聞いた。
ロボットは「昔のことでわかりません」と答えた。
そのあと、「きっと封印でしょうといった」
「どうして封印されたんだろう、このミュージアムがやったの」
「今、過去のことを調べたところ、封印はこの本を所蔵していた。2100年代後期の国の機関がおこなったことです。この本自体はそのときにすでに禁書とされ処分されています。問題ない部分をのりで閉じて一冊保管したとあります。それを、この古代遺伝子ミュージアムが管理することになりました」
「今でも読んではいけないのだろうか」
「所長にうかがいます」
ロボットが言って、二分も経たないうちに、ロボットが、所長室に本を持ってどうぞ言ってください」と所長室の場所を提示してくれた。
部屋では所長がまっていた。
「ムカショさん、今禁止されていることはほとんどありません、自由です、その本の糊づけされているところ、きっとその当時は問題だったのだと思いますが、今は問題ないでしょう、はがす薬はいくらでも手には入りますから、ご自分で購入されて自由に読んでください」
所長はあいそがよかった。古代遺伝子ミュージアムに興味を持ってくれる人間などあまりいないから喜んだのだろう。
ムカショは糊をはがす薬品を購入し、閉じられている本にしみこませた。糊というものは今ないが、こんな簡単な成分なら、分解させる薬品はいくらでもある。
ページはすぐにひらけるようになった。
ムカショは人間生活の遺伝子工学転換期の、禁じられた遺伝子の改変について、興味はあったが、強い期待はしていなかった。脳機能の遺伝子解析はその当時としては先端だったと思われるが、今の技術から比べると小学校レベルだろう。
開くとタイトルは、進化遺伝子の発見とあった。人間が科学を手にしてから大きな進化がなかったのは、脳の複雑な機能遺伝子の進化に時間がかかることと、突然変異を押さえる機能が遺伝子間にあることである。と出だしに描かれている。
糊付けされた部分は、数十頁の短いものであり、まだ概念的なもので、理論はただしいものであった。
読み終わったムカショは、驚きの気持ちをかくせなかった。遺伝子開発局をリタイアしたニョイラに、局長を紹介してもらおう。これは大変な発見になる。
端的に言うと、からだはいらない、というものである。体が栄養や酸素を供給し、脳の機能を維持し、脳は体の機能を調整して、一番良いようにする。脳は体から酸素や栄養を得ている。さらに動くことも体がしている。
脳の機能に体の機能を備えるように遺伝改変をすることが、人間の次への進化であるということだ。
脳が直接、空中や水中から酸素や栄養を吸収し、脳波の発達によりコミュニケーションがとれ、空中に浮遊して動くことができればいいわけである。
閉じられていたところには、簡単ではあるが、そのためにはどのような遺伝子を操作したらいいか考察をしたものである。
脳の硬膜が強靱なものになり浮遊する道具になる。言うなれば風船のような膨らみが頭頂にできて、そこにヘリウムガスがたまり、脳は空中に浮き、脳の底面の硬膜から空気が放出され空中を進む。
人間は脳だけになる。
それが進化だ。
それを読んだ、当時の科学者や政治家たちはそうさせてはいけないと、梵書をおこない、この本をほとんど焼いてしまったのである。
ムカショは本のコピーをとり地球にもどり、遠い星星への宇宙旅行にいったニョイラのもどるのをまった。
もどってきたニョイラははつらつとしていた。
また二人で住むことにしたムカショは、その間に見つけた本の話をした。
ニョイラも興味を持ち、遺伝子開発局長と話をすることになった。
所長はムカショの話を聞き終わり、
「人は脳だけになるとは、体を進化させることばかり考えていました、考えをあらためねばなりません」
とため息をついた。
「新たな研究プロジェクトをつくります、お二人には名誉研究員におねがいしたい」
所長はそう約束した。
こうして、ムカショとニョイラは突然死になる残りの40年ばかりを、人の進化の研究に従事することになった。もちろん、その過程をムカショはニョイラとともに、「本」という形のものにするつもりである。
耳と目玉をもった脳を同時に想像して、ムカショとニョイラは眼を合わせ、ちょっとほほえんだ。
突然死


