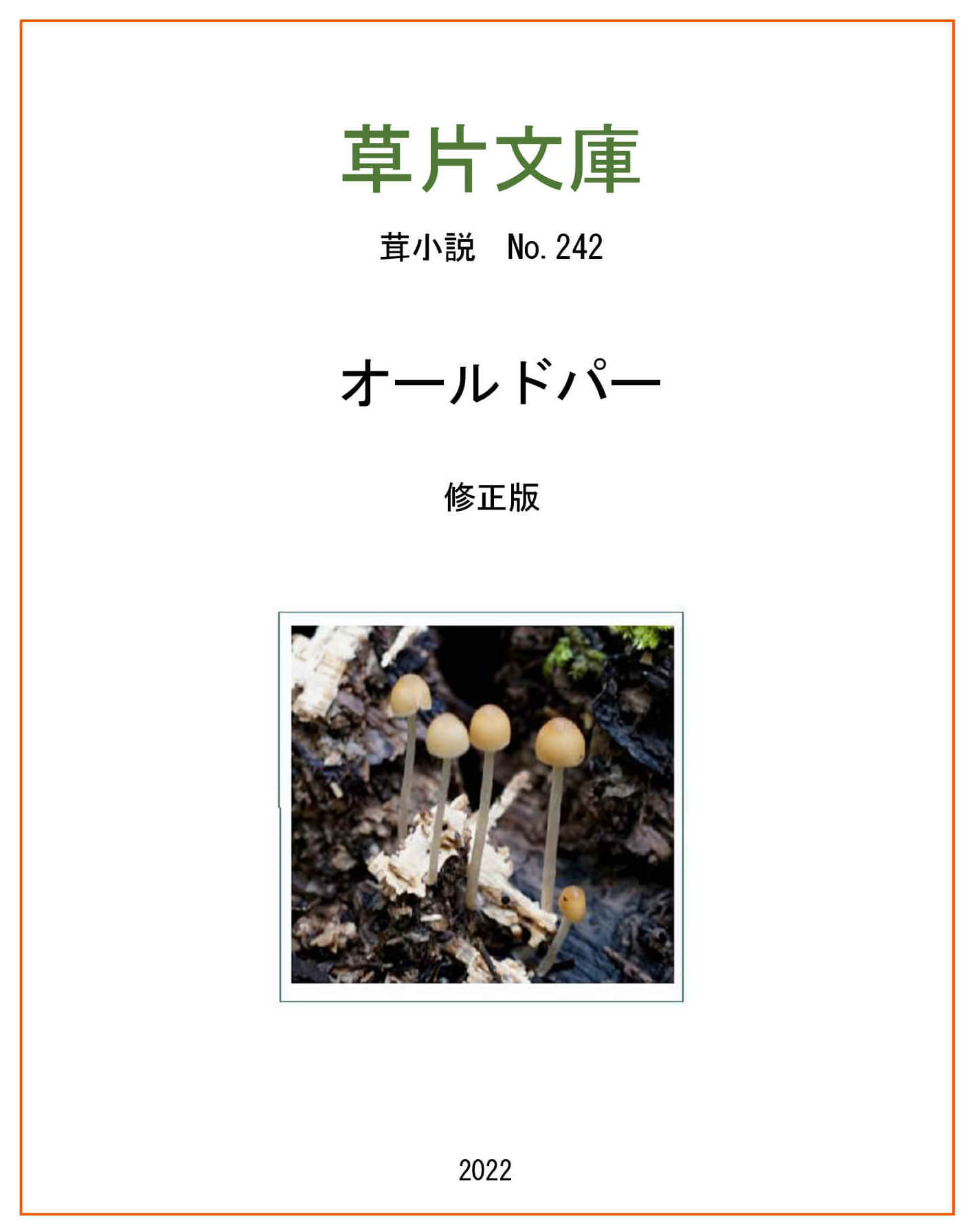
オールドパー
茸の森のおとぎ話、縦書きでお読みください。
小さな男の子と女の子が計5人、家に帰ってリュックをおろした。
「おもしろかったかい」
仕事から帰ってきたばかりの父親がでむかえた。
「うん、南の森に行ったらいろいろなキノコが生えていた」
五人の子どもはリュックを開けた。
「あそこは、キノコの宝庫だからね、おかあさんがよろこぶよ」
お父さんはリュックの中をみた。ずいぶん珍しいキノコもはいっている。
「でも、東に行ったら、もっとおもしろかった」
「なんだい」
「おとうさん、東の森はドングリの森でね、木の下はドングリがいっぱいなんだ。そこにいるおじいちゃんは、その上歩くと、足跡に水がたまってね、その周りにキノコが生えてくるんだ。それがね、あっと言う間だよ、歩くとすぐにそうなるんだ、どうしてだろう」
お父さんは説明した。
「あのおじいさんの足跡にはね、すぐ周りから水が浸み出していっぱいになるんだよ、水がたまってミジンコが湧いてくると、生きている小さな湖になるんだ、ミジンコが土の中の菌糸に、生えておいでと、言うんだよ、するとね、キノコが足跡の周りに生えてくるんだ」
「でも、何で水が出てくるのだろう」
「重なっているドングリの下の土は湿っていてね、凹みを作ると水が浸み出してくるんだよ」
「僕たちもやってみた、だけど、ドングリがあったので湖もキノコもできなかった」
「それはね、おまえたちの足がまだ小さいからだ、おじいさんの靴はドングリも一緒に土の中におしこんじゃうんだ、だから足跡の湖の底はドングリなんだ」
「それじゃ、お父さんが足跡を付ければ、みずうみはできるのかな」
「できないと思うよ、ドングリのつもっているところは足跡がなかなかできないんだよ、あのおじいさん152歳だということだから、お父さんよりずーっと年取っているから、足の底が重いんだよ」
「そうかー、年取れば重くなるんだ、でもあのおじいさんずいぶん痩せていたよ、足だけ重くなるの?」
「いやね、足の重さじゃないんだよ、たくさん生きた重みっていうのが足にくるんだ」
「ふーん、じゃお父さんが152歳になれば、足が重くなって、足跡が湖になるんだね」
「152歳まで生きてたらね」
「あのおじいさんなんていうの」
「パーだよ」
「パーじいさんだね、オールドパーだね、今度話しかけてみよう」
「ああ、そうしてごらん、だけど、昔の言葉でしゃべるから、むずかしいかもしれないね」
「足跡の周りに生えたキノコも採っていいんでしょ」
「もちろんだよ、パーじいさんも喜ぶよ
子供たちは、リュックをキッチンに持って行って、中のキノコをテーブルの上にぶちまけると、自分たちの部屋に行った。これからは夜の遊びだ。
「いつものやるよ」
一番上の男の子が声をかけた。
一番年下の女の子が、机の引き出しからキノコのカードをとりだした。
みんな丸くなって座った。
二番目の女の子がカードをきった。
「もういいよ」
二番目の女の子はきったカードを真ん中においた。
二番目の男の子が声をかけた。
一番上の女の子がいった。
「じゃんけんして最初の人を決めよう」
みんなでじゃんけんした。
二番目の男の子が一番最初になった。
真ん中のカードを開いて自分の前においた。絵はホコリタケだった。
「なんだ、つまんない」
左回りに開いていくことになる。というのもいつも年の順に左回りです座ることになっているし、順番は若い子のほうに回すからだ。
ここで順番を名前で書いておこう。五人すべて年子だ。一男(イチオ)、一女(イニョ)、二男(フタオ)、二女(ふうにょ)、三女(ミニョ)という名前だ。
僕はフタオ。
それで、つぎにフウニョが一番上のカードをめくった。マツタケだった。
「なんだつまんない」
ミニョのカードは赤いカゴタケだった。
「はずれた」
イチオがひらいた。
「お、すごいぞ」
テングタケだった。
「さすがはおにいちゃん」とみんなが言った。
次にイニョがカードを開いた。真っ白なドクツルタケだった。
「わーおねいちゃん強いな」
ぼくはそういいながら一番上のカードをめくった。
「わーお」
なんとベニテングタケがでた。毒キノコの女王だ。
「フタオの勝ち」とイチオが宣言した。
「それじゃ、あしたはベニテングタケに決まり」とイチオが言った。
「夕ご飯できたわよ」
台所からお母さんの声がした。
お父さんはすでにテーブルについていた。お母さんの作った、ナメコチーズでウスケボーを飲んでいるナメコチーズはお母さんじゃなければつくれない酒の珍味だそうだ。ナメコは森から僕たちが採ってきたのだけど、チーズの元がとても珍しいんだそうだ。内で飼っている山猫のお乳でつくったものだ。山猫は滅多にお乳を出さない。相当機嫌がよくないとだめだ。そこのところはお母さんが得意で、山猫のピーコの喉をさすったり、耳の後ろをこすったり、最後はおっぽの先をなでたりするらしい。他の人が見ているとお乳をださないので、子供たちはまだ見たことがない。
お父さんの飲んでいるウスケボーもめずらしいもので、キノコからつくるのだそうだ。お父さんが自分で作っている。キノコには発酵させる菌がついているので、家の地下室で成熟させて、蒸留してつくるのだそうだ、キノコの種類はアミノ酸の多いものがいいということで、何種類ものキノコをつかうようだ。お父さんはウスケボーをつくるとき、子どもたちに、スッポンタケ、テングタケ、ベニテングタケ、アミガサタケなどをとってこいといいうからそれらのキノコを使っているのだと思う。
蒸留して、地下の樽に入れて、50年以上たったてから、あけて飲むのだそうだ。お父さんのウスケボーの名前はウシュクベハという。命の水という意味だって。
テーブルには傘焼きができていた。いろいろなキノコの傘だけを焼いて、ふつうのチーズ、山羊のチーズや、いろいろな果物のジャムをつけて食べる。それが夕ご飯だ。飲むのは季節のジュース、森で採ってきたものをお母さんが絞る。もちろん採ってくるのは子どもたちさ。
テーブルについて、両手をくんで、森の神様に感謝をしてから食べる。
みんなベニテングタケの傘をねらっている。
そこで、じゃんけんして誰から食べるか決める。イニョからになった。左回りだからつぎは僕、フタオだ。
イニョはベニテングタケをとった。僕はテングタケにした。フウニョはツキヨタケ、ミニョはコガネタケ、イチオはアケボノタケをとった。
熱々だ。それにみなそれぞれジャムを塗った。イチオだけ羊のブルーチーズだ。
「めしあがれ」
お母さんの声で、食べ始めた。いつもお母さんの傘焼きはおいしい。
お母さんは、冬虫夏草を炒めて食べている。ちょっと胃の具合が悪いので、薬になるキノコ料理にしたそうだ。
お父さんはナメコの山猫のチーズまぶしを食べおわって、こんもりともったスッポンタケの蒸したのを食べている。とてもおいしいものだそうだ。大人になったら食べさせてもらえるものだ。
夕食が終わったら、自分のベッドにはいって本を読む。森の上の上の方にある星の世界のことが書いてある本だ。その昔、祖先が住んでいた星が遠くにあるのだそうだ。池のミジンコのように、休眠胞子と呼ばれる鞘をつくって、その中に入った祖先が、流れ星にのって、この地球にきたという。そのことが書いてある絵本を読んで寝るんだ。一番上のイチオだけは絵がない本を読んでいる。
そのうち眠くなって、つきの日になっているってわけだ。
「気をつけていくんだよ、おいしそうなのあったらとってらっしゃい」
母親が子どもたちをおくりだした。五人の子どもたちは直接東の森にいくことにした。空っぽのリュックをしょって、いいものがあったらその中に入れて持って帰る。
「今日、フタオはベニテングタケをあつめるんだよ、後はいろいろなキノコを採ろう、東の森でパーじいさんを捜して、足跡のキノコをとるよ」
イチオがみんなを連れて東の森に行った。
東の森には木の実や草の実は多いけど、キノコはそんなにない。東に生える、馬鹿でかかったり、毛が生えていたりして、余り食べる気がしない。しかしパーじいさんの足跡には、いろいろなキノコが生える。ちょうどいい大きさで、お母さんが料理するには手ごろなんだ。
東の森の入り口には、東の森の門番がいる。門はないけど、びっくり熊がいて、森の隣の山に住んでいるものだけをいれてくれる。
子どもたちの住んでいるところは、南の山だ。南の森が近いが、東と西の森だって隣だから遠くない。北の森にはだれでもはいれる。ということは、森の周りの山に住む者は東西南北どの森にも入ることはできる。
子どもたちは、東の森の入り口にいるびっくり熊に、やーと声をかけてはいっていった。
びっくり熊は気をつけていくべーと、ぶっとい手を振った。
イニョが「バーおじいさんどの辺にいるん」ときくと、びっくり熊は、朝早いときはとちの木の林にいるけど、今頃はもうドングリ林だべー、と教えてくれた。
それいけ、みんなはドングリ林にとんでった。ドングリ林には、ドングリがたくさんおちていて歩くのに大変だ。ドングリを踏んで歩かなければいけないので、すってんころりんと転んでしまうことがある。それだけじゃない、キノコはあんまり生えない。ただここにしか生えない。ドングリタケがはえていることがある。ドングリからキノコがでるのはとてもおもしろい。
ここじゃ、パーおじいさんの足跡できないキノコはとれないなとイチオが言った。ドングリを踏んでも足跡にならないからだ。
ぼくが見てみないとわからないさ、と言ったとき、からからという音がきこえてきた。遠くの方で人があるいている。
「あ、パーじいちゃん」
ミニョが気がついた。
みんなもそうだと思って、走っていった。
追いつくと、やっぱりパーじいさんだった。みんなはたちどっまって、歩くのを見ていた。
ぶかぶかの青い色のコットンズボンをはいたパーじいさんは、肩にかけた緑色のズック袋に、落ちているドングリの中から、ほしいドングリを拾っていれた。
子どもたちが近づくと、パーじいさんは橙色の帽子をかぶった顔を子どもたちの方に向けて、にこにこと笑いながら、「なにさがしているんじゃ」と声をかけた。
イチオが「きのこ、特にベニテングタケ」
「おおそうかい、それじゃついといで」
パーじいさんは、また足下に積もっているドングリの中からドングリさがしながら歩きはじめた。
子どもたちが後からついて行くと、じいさんの30センチもある足が、ドングリが積もっている中にずぶりとはいって、大きな穴をあけた。見る見る内に水がでてきて、足跡湖になった。
「ミジンコが出てきた」
みんながみていると、足跡湖の底にあるドングリが割れて、ミジンコがうじゃうじゃ出てきた。すると、こんどは足跡の周りのドングリの間から、ドングリタケではなくて、ベニテングタケがニョキニョキ生えてきた。
僕は、ひっこぬくとリュックにつめこんだ。
パーじいさんはゆっくりゆっくり歩いていく。
「いろいろなキノコはやして」
ミニョが舌足らずに叫んだ。
先を歩いていたパーじいさんが「あいよー}というと、次から次にできる足跡湖から、いろいろなキノコが生えてきた。
子どもたちは夢中になって、キノコをリュックにいれた。
「お母さん喜ぶね」
フウニョがうれしそうにタマゴタケを三つ採った。足跡の湖をのぞくと、「ミジンコがたくさんいる」
「ミジンコがキノコをはやしなさいって言うようだよ」
お父さんの言葉をおぼえていたフタオがいった。
「ミジンコさんありがと」
みんなでそういった。パーじいちゃんがニコニコと僕らを見ている。肩から下げている袋がパンパンになっている。
「パーじーちゃんもう終わりなの」
「ああ、家に帰るんだよ」
「パーじいちゃんの家遠いの」
「すぐそこさ」
「あそびにいっていい」
「いいとも、おいで」
ぼくたちは、パーじいちゃんのあとをついていった。足跡に湖ができない。
「パーじいちゃん、もう足跡に水が湧かないの」
「ああ、腹が減って軽くなるとだめなのさ、家でお十時だ、一緒に食べよう」
われわれは期待に胸を弾ませてついていった。
パーじいちゃんの家はドングリ林の斜面の穴だった。
真っ暗な穴なのに、じいちゃんはどんどん中に入っていく。
「ランプがないと真っ暗だよ」
ミニョが心配した。イチオが中を覗いた。
「奥の方はなんだか明るいよ」
そう言って、じいちゃんの後をついて、中に入っていった。みんなもぞろぞろついてはいった。
穴の壁には小さな緑色のキノコが生えていて光をはなっている。
「あ、シイノトモシビタケだ」
フウニョが知っていると叫んだ。
じいちゃんがどんどん中に入っていく。走っておいかけた。じいちゃんが木の戸を開けると明るい光が広がった。
中にはいると、壁一面にヤコウタケが生えていた。シイノトモシビタケより大きいんだ。だから明るい。
パーおじいちゃんは、大きな椎の木のテーブルに腰掛けた。
「みんなも好きなところに腰掛けなさい」
じいちゃんに一番近いところにミニョが腰掛けて、左回りで小さい順に腰掛けたら、ちょうどイチオがおじいちゃんの隣になった。
「さて、このドングリのごみをとってくれるかな」
じいちゃんは袋の中のドングリをテーブルにざらざらと山盛りにした。
「これなんのドングリ」
イニョがきいた。
「しいのみだよ」
ちょっと焦げ茶色で細長い。
「どうするの」
フウニョがきいた。
「食うんだよ、これからのおやつさ、おまえさんたちにもやるよ」
おやつと聞いたから僕たちは一生懸命ゴミをとって、ドングリをきれいにした。
僕が「どうやって食べるの」ときくと、じいさんは、シイノミを指でぱちんとわると、口にいれた。
「うまいよ、食べていいよ」
ぼくたちもシイノミを指で割ろうとしたが割れない。
「そうか、わしが割ってやろう」
パーじいちゃんは一つ割るとミニョの前に、また割るとフウニョの前においた、こうやって、五つ割るとみんなの前にはしいのみが一つあった。
「いただきます」
イチオの声で一斉にくちにいれた。堅いけどおいしかった。よくかむとつばのなかにあまさがしみだした。
じいちゃんはそれから自分も一つ食べて、また五つ殻を割ってみんなの前におき、また一つ自分で食べた。
「わしゃ、酒を飲みたくなったな」
「お父さんもお酒飲むよ」
僕がいうと、じいちゃんがきいた。
「そうかい、なに飲んでいるのかな」
「命の水だよ」
「おー、ウシュクベハか、うまいウスケボーじゃな」
そう言いながら、じいちゃんは隣の部屋から酒の瓶をもってきた。琥珀色の酒、ウスケボーだ。
「わしのは、ドングリで作ったウスケボーじゃ」
「なんていうウスケボー」
「わしのだから、パーウスケボーかな」
「オールドパーじゃない」
「そりゃいい名じゃ」
じいちゃんはグラスに並々とついでちょびっとなめた。こうやって一日中酒を飲んでドングリを食べている。外にでるのはドングリを拾いに行くときだけだ。
「僕たちも飲みたい」
「そうかい、それじゃやろうかね」
パアーじいちゃんはみんなの前にグラスを置いてドングリ酒をついだ。
「ごちそうになります」
イチオの声でみんながウスケボーをパーじいちゃんのようにちびちびなめて、ドングリを食べた。
「うみゃい」
ミニョが最初に酔っぱらった。左回りで順番によっぱらて、「じいさん、もういっぱい」と要求した。
「ありゃ、もう飲んだんか、まだ子どもだからいっぱいだけ、また来たときにいっぱいじゃ、お父さんはのませてくれんのか」
ちょっぴりびっくりしたようだ。
「うん、まだ飲んだことがない」
「もう飲んでもいいのじゃがな、きっとウスケボーがあまりないんじゃろ、作るのを手伝うと飲ませてもらえるかもしれんな」
「お父さんはなにで作っているのかな」
「知らない」
「きいてごらん」
「うん、それじゃ、ごちそうさま」
僕たちは礼儀正しく、パーじいちゃんにおじぎをすると穴をでた。
ちょっと千鳥足で家に戻るとお父さんにはすぐわかったようだ、
「おんや、おかえり、ウスケボーの香りだ、どこで飲んだのだい」と言った。
「ういー、パーじいちゃん」
ミニョが答えた。
「よかったな、ドングリのウスケボーは薄いのでおまえたちにちょうどいいからな」
「父ちゃん、なにでウスケボーつくっているんだ」
僕が聞くと、お父さんは
「おまえたちの採ってくるキノコだよ、アミガサタケだ」
「ねえ、父ちゃん、今度とってくるから、あたちたちにものまちて」
フウニョがまだ酔いが醒めない舌できいた。
「もちろんだよ、北の森には一年中アミガサタケが生えているよ」
お父さんは産科のお医者さんだ、妊婦さんから呼ばれると往診する。この森の周りにすんでいる者たちは、お父さんが産むときに手伝って生まれた者たちばかりだ。毎日一人はうまれるので、お父さんは忙しくて、アミガサタケを採りに北の森にいけなかったんだ。僕たちが採ってくるキノコの中からアミガサダケだけを使っていたのだ。
「それじゃ、一週間に一度は北の森に行ってアミガサタケをとってくるね」
イニョが言った。
「たのむよ、今日は食事の時に、少し飲ませてあげよう」
わーっと僕たちは声を上げた。
僕以外のみんなはリュックから足跡湖の周りから採ってきたキノコをテーブルの上にだした。
お母さんが、まー立派なキノコだこと、今日はキノコのムニエルにしてあげましょうね、と言った。
僕たちが、ウスケボーに合うねと言うと、お父さんが驚いたように、
「もうおとなになった気分かい」と笑った。
「さーそれじゃ、ぼくたちは部屋に行こう」
イチオのあとをぞろぞろと子供部屋にいった。
僕はリュックにはいっていたたくさんのベニテングタケを広げたビニールの上にぶちまけた。
「これで、どうやって毒を作るの」
イニョがイチオにきいた。
イチオは理科の実験が得意だ。道具を押入から取り出して用意した。
ベニテングタケをおおきなニューバチにいれてフウニョがつぶした。よーくつぶしたら、試験管の中にいれた。
「これどうするのさ」
ミニョが薄茶色に濁った液を見た。
「これをあったためて、その蒸気を集めるんだ」
イチオが、そのた蒸気を集める渦巻き装置にかけると、毒の濃い液になると言った。渦巻き装置はガラスの渦でできている。
「甘いのね」
イニョがいった。
「どうかな」
イチオが自分で作った装置に、ベニテンタケの汁が入った試験管をおいた。下に置いたアルコールランプに火をつけた。
このあいだみんなでお祈りをした。科学実験というのはお祈りをするとうまく行くものなのだ。
しばらくすると、蒸気がでてきて渦巻き装置の中に入ると、その先からぽたぽたと液がビーカーの中にたれてきた。それが毒液だ。
試験管の中の潰した汁が全部蒸発するまでお祈りを続けた。
全部蒸発したので、お祈りをやめると、イチオが冷めるまでまとうといった。
この装置のことをお父さんとお母さんは知らない。
そのとき、お母さんのご飯ができたわよ、と言う声が聞こえた。
「今日は立派なキノコがたくさん集まったから、キノコたっぷりスパにしましたよ、飲み物はお父さんが、ウシュクベハの水割りをつくってくれました」
「やったー」
誰もが声を上げた。
スパゲティーはとてもおいしかった。
ウシュクベハの舌触りはとてもよかった。
「パーじいちゃんが、ウシュクベハって、命の水って言うんだと教えてくれたよ」
僕がパーじいさんにあって、穴に行って、ウスケボーを飲ませてもらった時のことを、詳しく話した。
スパを食べたぼくたちはお父さんの作った、ウスケボーの水割りを飲んだ。イチオはウスケボー五割、イニョは四割、僕は三割、フウニョ二割、ミニョは一割の水割り。
「あ、オールドパーよりこい」
イニョが最初に声をあげ、ゴクゴクと飲んでしまった。
「うま」
「イニョはいいのみっぷりだな、ディンプルになれるかもしれないよ」
お父さんが笑顔になった。
「なにディンプルって」
「北の森の女王さんだ」
「アミガサタケの生えている森の女王様なんだ、会ってみたいな」
「よく知っているよ、北の森に行ったら、会ってくるといいよ」
「そうだ、明日は北の森に行こう」
子どもたちは夜の食事を終えると子供部屋に戻った。小さなビーカーの中のベニテングタケの蒸留したものが冷めていた。
「お、できたな」
イチオがビーカーの匂いをかいだ。
「いい匂いだな」
と指を入れてなめた。
「お、甘い」
イニョ、ボク、フウニョ、ミニョのジュンで舐めた。
「この毒おいしい」
みんな口をそろえた。
イチオが「毒の強いキノコの方が甘いかもしれないな、だって、お父さんがお酒は毒にもなるっていってたもんな」と言った。
みんなで大きな声を出したものだから、お父さんとお母さんが、子ども部屋にやってきた。
「なにをしてるの」
お母さんが聞いたので、イチオが説明をした。お父さんが、蒸留装置を見て、
「たいしたものじゃないか、誰かに教わったのかい」
とイチオにきくと、イチオは首を横に振って、
「自分で考えた」といった。
お母さんがビーカーに指を入れてなめた。
「おや、これはベニテングタケの蒸留水だね」
と言った。
「どうしてわかったの」
イチオがきくと、「ベニテングタケの汁は蒸留しても甘いんだよ、ふつうは蒸留すると、甘みは抜けるんだけどね」
と教えてくれた。
「どれどれ」
お父さんもなめた。
「ほんとうだね、お父さんは初めてだよ、これならウスケボーになるよ」
「ウスケボーもこうやって作るの」
フタオがきいた。
「そうだよ、ただ、まず発酵させて、それを蒸留装置にかけて、樽に入れて、五年十年と寝かしておくと、成熟しておいしくなるんだ」
「お父さんのウスケボーは、アミガサダケを発酵させて蒸留して、長い間置いておいたものなのだ」
「そうだよ、イチオはよく蒸留装置を考えたね、地下室のウスケボーを作るところに、大きな装置があるよ、今度見せて教えてあげよう」
僕たちは自分の家の地下室のウスケボーを作るところをみたことがない。
「うん」
「一つあいているのがあるからベニテングタケで作ってごらん」
「発酵ってどうやるの」
「キノコをつぶして、山ブドウの実の皮をちっとまぜておくんだ、しばらくすると発酵するから、上澄みを蒸留するんだ、ベニテングタケは蒸留しても甘いのだから、発酵させたらとても甘くなって、いいウイスケになるかもしれないな」
ウシュクベハはウスケボー、ウイスカとも言われるようだ。
「よーし、こんどみんなでやってみる」
「さー、そろそろねなさい」
お母さんにいわれて、僕たちは自分の穴にはいって寝た。
朝起きて、キノコジュースと、キノコトーストの朝食をたべると、僕たちはリュックをしょって、北の森にでかけた。お父さんのためにアミガサタケを集めるのだ。
北の森の入り口で、あくびをしている門番のカピバラにおはようの挨拶をして中に入った。北の森は桃の木がまばらに生えていて、ブドウがからまっていた。
イチオはベニテングタケのウスケボーをつくるため、ブドウをいくつかとった。ブドウについている酵素で発酵させるためだ。
森の奥の方にあるいていくと小さな草原にでた。
「アミガサダケがたくさんはえてる」
イニョがさけんだ。
草の間から、いろいろな種類のアミガサタケが顔を出している。黄色いのもあるしとがったのもある。
フウニョが「お父さんにどのアミガサタケか聞き忘れたね」
と、イチオにいった。今から聞きに帰ると時間がなくなる。
「いっしょくたじゃ、おいしくないよね」
「どうなのかな、まぜたほうがおいしいかもしれないし」
そこにカピバラにのった女の人がやってきた。赤い長いドレスを着て、カピバラの背中に横座りになっている。
この人が北の森のディンプル女王様だ。
女王様はカピバラから降りると、えくぼを寄せて、
「アミガサタケをとってるのかえ」
と聞いた。
にこにこ笑っている女王様はとてもきれいというよりかわいらしい。
「はい、女王様、父のウスケボーを作るためのアミガサタケを採りにきたのだけど、どのアミガサタケがいいのか、聞いてくるのを忘れました」
イニョが説明をした。
「南の山のウシュクベハを作っているお医者様ね」
「はい、わたしたちの父です」
「私も子供を産むときお世話になった、ウシュクベハを作るアミガサタケは、シャグマアミガサタケですよ」
子どもたちは草の中をみた。でこぼこの薄茶色のアミガサタケが生えている中に、赤黒っぽい脳のようにグニャグニャとうねった傘のあるアミガサダケが生えていた。
「これは生で食べたら死ぬこともあるくらいの毒のあるきのこなんじゃ、だからよいお酒を造ることができるのよ、でも普通のアミガサタケとは種類が違うのよ」
「シャグマってどんな意味なの」
ミニョがたずねた。
「赤い毛のこと、縮れた毛のことをいうのよ、赤い縮れ毛の熊さん」
「ほんとだ」
こどもたちはシャグマアミガサダケを採ってリュックに詰め込んだ。
女王様はえくぼを寄せて子どもたちを見ていた。
子どもたちがシャグマアミガサタケをリュック一杯にすると、女王様が
「おまえたち、うちにおいで」と誘ってくれた。
子どもたちは、よろこんで、カピバラに乗った女王様の後についていった。
ディンプル女王様の家は大きな太い桃の木のほら穴だった。
穴の中にはいると、パーじいさんの穴と同じように、壁にキノコが生えていて明るかった。イチオがツキヨタケだと教えてくれた。毒キノコだ。
奥の部屋のまた奥の部屋にはいると、ディンプル女王はテーブルに腰掛けたル用に僕たちに言った。そうしておいて、桃を向いてあげましょうと、桃をむいてくれた。
ミニョが、「秋なのにどうして、桃があるの」と聞いた。
「地下室は涼しくてね、夏にとった桃がみずみずしいままとっておけるのよ」
といって女王は嬉しそうに桃にかぶりついた。
あまりにも見事なかぶりつきだったので、みんなみとれてしまった。
「たべてくださいな」と女王様が言ったので、みんなも女王様のようにがあぶりと、かぶりついた。
じゅうっと、汁がしたたり落ちた。
大きくて甘くて水分たっぷりの桃だ。
なんと美味しい桃だ。
食べ終わったディンプル女王様はウスケボーを飲み始めた。
最初に食べ終わったフタオが「あ、女王さまがウシュクベハを飲んでいる」
と声を上げた。
女王はえくぼを寄せると、「これは桃から作ったウスケボーよ」とくっとグラスをあけた。
「おいしそ」桃を食べ終わったミニョがディンプル女王のグラスを見た。
「みんなまだ小さいからお酒は飲めないでしょ」
それをきいたフタオが「パーじいちゃんのところで飲んだし、昨日は父ちゃんが少し飲ませてくれた」
女王は「おやおや、いいのかしら、みんな飲みたいの」ときいた。
みんな目を輝かせて女王をみた。
ディンプル女王は、「それじゃみなさんにもごちそうしましょうね、桃のお酒よ」と、グラスを皆の前においてウイスケボーをついだ。
みんな香りをかいだ。
「いい匂い」
フウニョがいうと、みんなうなずいた。
くーっとのんだ。
「おいしいなー」
みんなおいしくて、笑顔になり、えくぼがよった。それをみた、イニョが「このウイスケボーはえくぼにしましょ」というと、女王が「あーら、ディンプルはえくぼって言う意味なのよと教えてくれえた」
「それじゃ、ディンプル、女王様と同じ名前でいいのかしら」
イニョはえんりょしながらいうと、
「あら、いい名前じゃない、私と同じ名前のウスケボーね」
と喜んでくれた。
「西の森にはね、全能の神が住んでいるのよ、あそこのキノコはとても大きくてね、全能の神はいろいろなキノコを混ぜて、とてもおいしいウイスケボーをつくるのよ」
「へー明日行ってみよう、女王様、お酒ごちそうさまでした」
「お父様によろしくね」
ディンプル女王に手を振られて、僕たちは北の森から家に帰った。
「ただいま、シャグマアミガサダケたくさんとってきたよ」
テーブルの上にリュックの中のキノコをぶちまけた。
父親が「おーたくさんとれたね、今年はたくさんのウシュクベハがつくれるな」と喜んだ。
「ディンプル女王さまがよろしくって」
「お元気だったかい」
「にこにことえくぼがたくさんよる女王さまだった」
ミニョがいうと、
「ディンプルというのはえくぼのことなんだよ」
お父さんが言った。
「うん、女王様がおしえてくれたよ、それでね、女王様の家に行って、ウスケボー飲ませてくれた、ディンプルって言うんだ、桃の酒だった」
「そりゃよかったな」
おかあさんも「シャグマアミガサダケの料理もしましょうね」
机の上のシャグマアミガサダケを少しばかり流しのところにもっていった。
「毒じゃないの」
「毒だわよ、だけどゆでると毒が抜けて、とても美味しいキノコになるの」
お母さんがシャグマアミガサダケを水につけた。
僕たちはノブドウを涼しいところにしまった。明日、全能の神のいる西の森に行って、ベニテングダケをとってきてウスケボーをつくろいうことになった。それで早く寝ることにした。
まだお日様が昇らない暗い内に僕たちは起きた。お父さんとお母さんはまだ寝ている。
みんなでキノコのサラダを作って、おかあさんが採ってきてしまってあったタンポポのお茶を作って飲んだ。タンポポって秋だって咲いているんだ。
いつもより大きなリュックをせおうと、僕たちは西の森に向かって歩いた。山の陰からお日様がのぞき始めているのでもう明るい。
南の森をぐるっとまわると、西の森の入り口についた。門のところにはタツノオトシゴが巻き付いていた。
「はやいじゃないか、おはよう」
「おはよう、全能の神様に会いたいんだ」
イチオが言うと、イニョが「ベニテングタケ採りたい」といった。
「なににするんだい」
「ウスケボーつくるんだ」
「全能の神様のウスケボーは美味いんだよ」
「のませてくれるかな」
「俺たちには一年に一度だけど、お客さんには飲ませているよ、きっとよろこぶよ」
「どこにいけばいいの」
「森の中を歩いていればかならずでてくるよ」
タツノオトシゴに言われてみんなは西の森の中に入った。
森の中は明るくて一面にタンポポが生えていた。
「あ、すっげーキノコ」
黄色いタンポポの中からにょきっと生えたカラカサタケだ。とても大きなキノコだ。フォイル焼きがとてもおいしい。
「すごく大きいわね、あれ一つで、みんなのごはんになっちゃう」
イニョが言った。そのカラカサタケは子どもたちの倍ほども背の高いもので、傘ときたらいつも使っている雨傘よりも大きい。
「とって行きたいけど次にしましょ、今日はベニテングタケ」
イニョがそういうと、森の奥の方にあるいていった。みんなもあとをついていくと、大きな赤いベニテングタケがニョキニョキ生えているところにでた。
「すごいベニテング、みんな採りましょ」
フウニョが採ってリュックにいれると、一つで一杯になってしまった。
みんなもリュックにいれた。五本のベニテングタケでもうはいらない。もっとほしいなと、みんながおもっているところに、一つ目の大入道が歩いてきた。きている服はおごそかなものだった。
「もしかすると、全能の神かしら」
イニョがいった。
「こどもたちよ、なにをしておる」
やっぱり神様ことばだ。
「ベニテングタケ、大きすぎてたった五本しか採れませんでした」
イニョがいうと、「そうか、おじょうちゃん、もっとほしいなら、空飛ぶタツノオトシゴに運ばせててやろうぞ」
と口笛を吹いた。
すると、タツノオトシゴが何匹も空に現れて、空中停車した。
空飛ぶタツノオトシゴなんて初めてだ。
「ほれ子どもたち、おまえたちがベニテングタケを採って、タツノオトシゴにわたせば、家にはこんでくれるぞ」
ぼくたちはタンポポの間から生えているおおきなベニテングタケを採って、タツノオトシゴにわたした。一匹のタツノオトシゴが、十本のベニテングタケを尾っぽで巻いた。
「おまえたち、キノコを子どもの家まで運んでおいてくれないか」
全能の神がそういうと、「へーい」と返事して、タツノオトシゴは飛んで行ってしまった。
「十匹もいる」
ミニョが数を数えた。
「どこからきたのじゃ」
全能の神がたずねた。
「南の山です」
「そうか、ウシュクベハを作る医者の家か」
「はいそうです」
イチオが答えた。
「それじゃわしの家においで、うまいウスケボーを飲ませてやろう」
ぼくたちは一つ目の入道のあとをついて北の森の奥にはいっていった。
全能の神はどんな穴に住んでいるのだろうと、僕たちは想像していた。
想像とは大違いだ。
全能の神の家はタンポポの花に囲まれた丸木小屋だった。
中にはいると、大きなテーブルと、窓際に大きな蒸留装置がおいてあった。棚にはずらーっと壷が並んでいて、ぷーっと、ウスケボーの匂いがした。
一つ目入道の全能の神は一つの壷を棚から採ると、蓋を開けて柄杓でウスケボーをくみ出した。
それをガラスのグラスに分けて、子どもたちの前においた。
「ほら、わしの作ったウスケボーだ、キングオブキングスというのだよ」
「どんな意味」
「わしのことだ、王の中の王、すなわち全能の神だ、好きなだけ飲みなさい」
子どもたちはぐびぐび飲んだ。
「おいしい」
「きれいな琥珀色だな」
すぐにおかわりを要求した。
「うまいかい、もっとお飲み」
もう酔っぱらったミニョが
「じぇんのうのきゃみしゃま、このウイスカはにゃにからつくったの」ときいた。
「はは、ちびチャンは酒が好きなようじゃな、このウスケボーはタンポポからつくったんじゃ」
「タンポポのお酒なの、どこかできいたような、でも、このウイスキーうまい」
「ウスケボーがウイスキーになっちまったな、うまいじゃろ」
「でもあたちたち、ベニテングタケでウイスキーちゅくるの」
「そうかい、そりゃ楽しみだ、できたら、飲ませてくれるかい」
ミニョは三杯めを飲んで眠くなっていた。
「うん」といって寝てしまった。みんもよっぱらっている。
「ウイスキーとは洒落た言い方だ、これからはウスケボーはウイスキーと言おうかの」
「眠くなっちゃった」
イチオがこっくりこっくりはじめた。
「タツノオトシゴにおくっていかせよう」
全能の神である一つ目入道は、タツノオトシゴを呼ぶと、寝てしまったぼくたちを、家まで運ばせたのだ。
子ども部屋の入り口で、お父さんが「お手数おかけしました、ウシュクベハでもどうです」と声をかけている。
タツノオトシゴが五匹、宙に浮かんで、子どもたちを子供部屋に運んできて、寝かしてくれたのだ。
「あ、それは嬉しいことで、やろうども、いただくとしようじゃねえか」
タツノオトシゴは力労働にたずさわっている者たちだったこともあって、威勢がいい。テーブルぐるりに腰掛けた。
お母さんが「キノコのオムレツいかがです」
とささっとつくってタツノオトシゴのまえにひとつづつおいた。お父さんはウシュクベハをグラスについで、みんなの前に置いた。
「ストレートでよろしいですな」
「へえ、ありがとうございやす」
タツノオトシゴはウスケボーをごくんと飲んだ。
「うまい」
オムレツを食べて、また
「うまい」
と声を合わせた。
「キングオブキングにはおよびませんが」
「全能の神が言ってたぜ、酒はそれぞれ個性があり、それが世の中を幸せにする、このウシュクベハもオールドパーもディンプルも、ウスクベーの森を楽しくしてくれる」
「それはそれは、さすが全能の神、いうことがいいですな」
「こんなことも言っていたぜ、ほら、一番下の嬢ちゃん、ミニョ、さけが強くなる、大きくなったら嫁にもらいたいもんだ」
「全能の神様、気の早いこと、ミニョは確かに酒に強くなりそうだが、神の后になるなどということはどうでしょうな、本人の意思でして」
「全能の神は未来もすべて見通しているからよお、わかってんだよ」
「確かに、そうかもしれませんな、大きくなるのが楽しみですな」
「全能の神が言うには、東の森にはオールドパーは寿命の神になるだろう、北のディンプル女王はほほえみの神、平和をもたらす神になるであろう、ところが、南の森には今神がいない、南の森の中に病院をたて、お産の医者であるあんたさんを、結びの神として招きいれたいそうだ」
「私を神にするのかね、それはな、にあわない」
「全能の神が言い出すと、千年は言い続ける、断るのは大変だぜ、なあ、ウシュクベハの先生、心積もりをしておきなよ」
「おまえはどう思う」
お父さんがおかあさんにきいた。
「あら、いいじゃない」
お母さんは答えた。
「どうです。もういっぱい」
おとうさんはタツノオトシゴにウスケボーをすすめた。
「そんじゃ、もういっぱい」
タツノオトシゴたちは、ぐいーっと、ウシュクベハハを飲んだ。
「うめかった、ごっそさん」
そういうと、宙にうかんで、くねくねと体をゆらして、家をでていった。
明くる朝、子どもたちはおきるとすぐに、東の森の大きなベニテングタケをつぶして、ブドウの皮と一緒に壷に入れた。発酵させて、蒸留して、子どもたちの新しいウイスケを作ろうとしているのだ。
地下室のお父さんの使っていない道具を使って、つくるのだ。
子どもたちは一生懸命につくった。
発酵してきた上澄みを、蒸留して、ウスケボーにした。あとは五年、十年と樽に入れてねかしておくと、立派なウスケボーになる。
それから五年たった。こともたちは大きくなった、それでもまだ子どもだ。
樽を開けようという日に、全能の神が、子どもたちの家にやってきた。
「わざわざ、おこしくださり、ありがとうございます」
お父さんとお母さんは、一つ目の入道を家に向かいいれた。
「おじゃましますよ、いいにおいだ」
「うちの子どもたちがお世話になりました」
「いやいや、みんな酒に強いし、よい子たちじゃ、むしろ、うちのタツノオトシゴにうまい酒をのましてくれたようで、あいつらとてもよろこんでいましたぞ」
「それで今日は何のご用でしょう」
「まず、どうだろうな、結びの神、安産の神として、もちろん医者として、森にすみませんかな、奥方も一緒に」
「私どもトロールが神になるというのはよいものなんでしょうか」
「もちろんじゃ、我々神は元はトロールじゃったんだ、森の木々たちに神にされたんだ」
「森が神をつくるのですか」
「そういうものなのだ、南の森がトロールのソナタたちを、神として迎えいれるということじゃ、わしは森の声を聞いておる」
「そうでしたか、わかりました、今日は子どもたちがベニテングタケで作ったウスケボーを寝かせて五年、まだ若いのですが、飲んでみようと、子どもたちが地下室におります、ごあんないします」
全能の神をともなって、お父さんとお母さんは地下室に降りてきた。
地下室では五人の子どもたちが、樽の口を開ける用意をしていた。
「あ、全能の神様、こんにちわ」
子どもたちが挨拶した。
「おお、おお、大きくなった」
ミニョが15さいだから、イチオは20だ。
「さー、みんな、樽からウスケボーをだして、全能の神様と一緒に飲もう」
地下のテーブルの周りにみな集まった。
イチオが樽からデカンターにウスケボーをいれると、地下室のテーブルの上においた。イニョがそれぞれのグラスにつぐと、
「全能の神様、どうでございましょう」といった。
全能の神は口に含むと、「うーむ、うまい」と叫んだ。
「うむ、これはキングオブキングスよりうまい、みなも飲んでみるがいい」
子どもたちも、お父さんもお母さんも飲んだ。
「おいしい」
お母さんもお父さんもいった。
「これはうまいウイスキーじゃ」
お父さんとお母さんはウイスキーとはなんだかわからなかった。
「フウニョが、酔っぱらって、ウスケボーをウイスキーといったのよ」
フウニョが説明した。
「ウスケボーの新しいよびかたじゃよ」
一つ目入道の全能の神はかっかと笑った。
「どうじゃ、こどもたち、よその国に行って、ウイスキーをつくらないか、お父さんとお母さんには、南の森で安産の神、縁結びの神になってもらうつもりじゃ」
「僕は、アメリカに行く」
フタオが言った。
「私はカナダ」
イニョが言った。
「私はフランス」
とフウニョ。
「俺はジャパンに決めた」
イチオが言った。
「私、この森に残りたい」
ミニョがいうと、お父さんとお母さんは
「ミニョは全能の神様のお嫁さんになるのどうかしら」
たずねた。
「うん」
ミニョは一つ目を全能の神様に向けた。
「おお、おお、それは嬉しいぞ」
全能の神様も一つ目をミニョに向けた。
「これで、この森も安泰じゃ、パーじいさんやディンプル女王に早速伝えよう」
スコットランドの森の中で、一つ目のトロールたちが、新しくできたベニテングタケのウイスキーを飲みながら、輪になって踊っている。
オールドパー


