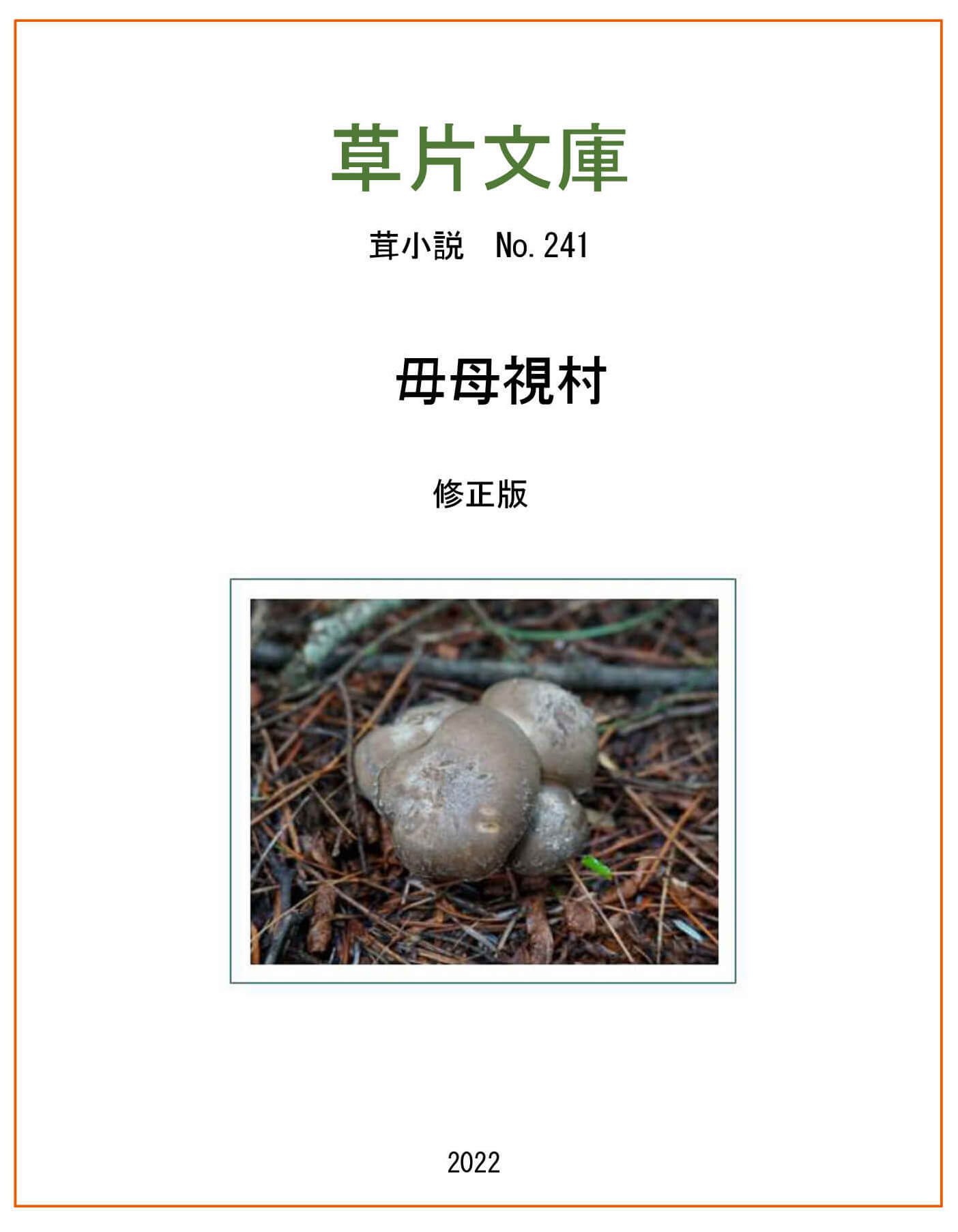
毋母視(なばみ)村
茸歴史ミステリー
信濃の国と越後の国にまたがる、山々に囲まれた村、毋母視(なばみ)村は古くからの小さな村だが、過疎の村になることなく、今でも人々が元気に生活をしている。やはり観光が村の人々の生活を支える主力産業であることは、日本のほかの村と同じである。
山菜茸、ジビエ料理、それにいい温泉がでることから、老人ばかりでなく若い人たちも噂を聞いて、一年を通してて遊びに来る。この村には毋母湖という小さいながら、深い湖があることも若い人達の人気の理由である。岸すれすれまで水がなみなみとたたえられ、水深二十メートルもあるのに、底で魚の泳ぐ様子が手に取るように見える。湖からでた毋母川(なばがわ)は毋母視村の中を通り、小さいながらも村に大きな恵みをほどこしていた。
ところが毋母視村のまわりにあった村々は、その大昔、何度も起きた火山の噴火によって、消滅してしまったということだ。多くの村民が降り注ぐ火山弾や火砕流、溶岩流によって命を落とし、村人は離散したという。
毋母視村だけは、火山の噴火にる火山灰や噴礫によって破壊され、埋まってしまっても、避難していた人々は状況が落ち着くと、埋まった家々を掘り出し、村を再建して今の発展の基礎を築いてきた。それには、噴火の予知に長けている者がいたからだという話である。
民俗学者の卵である、大学院生の伊能忠好は、高校生の頃から、火山の噴火が起こるたびに、なぜあんなに危険なところに人々は住んでいるのだろうと不思議に思っていた。どこに住もうと自然の災害はいつ起きるか分からないことはわかる、しかし、噴火が起こったら村ごとなくなるような事態になるにもかかわらず、人々が住む。調べていくと、火山のあるところは、人が住むのにいろいろな利点があることを知った。寒くて高い山間でも、地熱が高く、湯も沸き、山が火を噴かない限りは、まだ身にまとうものもない古代の人間にとっても、自然から暖がとれる住みよいところでもあったということがわかってきた。地の熱は植物や動物にも大事であることを高校生ながら理解をした。
自然を神としてあがめる頃は、赤く火を噴く山は、恐れもあるが、なだめることで身を守ってくれる偉大な存在で、信仰の対象となっていった。生活の中で火の山のことを絶えず考え、それにより精神的な支えをえるという、人間の脳の働きの安定を得るという恩恵を被っていたのだ。今となれば人間の歴史の当たり前のことであるが、図書館に通い詰め、そのような考えにいたった伊能は、人類学の道を歩み始めたわけである。大学に入り、村について調べるうちに、毋母視村のことを知り、その村を研究のフィールドとして選んだわけである。
伊能は三年生なり、人類学の先生のゼミに入ってから、二度ほど毋母視村に行った。村の役場や図書館を訪れ、地元の人と話をした中で、驚くほどほかの村にはない独特のものを感じ取った。それだけではなき、日本中の山間の村を探してもないようなものが作られている。それはシェルターである。火山の噴火が起きたときに住民が逃げ込めるようになっていた。
周りの山の噴火は、少なくとも記録がはっきりしている室町あたりからは起きていない。今はみな休火山で、たしかにいつまた火を噴くかわからないが、もし、噴火しても、地誌的にどの山もかなり離れていて、噴火が起きてもマグマが流れこむようなことはないだろう。しかし火山弾が火山灰は家を破壊し覆い尽くすほど降るだろう。
村の人たちは、そのことがわかっていて、コンクリート制のシェルターを小学校や中学校の地下に作った。この村に中学高ができたのは昭和のはじめであるから、かなり早い時期につくっている。そのころの地下室といっても、雑なもので、石を積み上げ手それにコンクリートをかぶせたようなものだったという。戦時中は防空壕の役目をしたというが、こんな寒村に焼夷弾を落とすアメリカの飛行機などおらんじゃったよと、村の一人の老人はいっていた。
その後、学校の立替と同時に、立派なシェルターをつくった。いつもは倉庫や、体育館として利用されているが、なにかあると、その学校に通う生徒の家族すべてが泊まれるるようになっている。村役場や図書館にもシェルターがあり、さらに、村に新たにきた人や、観光客のためのシェルターもあり、普段は会議室や、遊戯室としてりようされている。
こんな小さな村で、地震もほとんど起きないようなところで、シェルターをつくったのは、村の人たちが昔の人からの言い伝えを守った結果のようである。
まだ学部学生だった伊能は、そのときは興味半分に村のシェルターを見てまわるくらいのことしかしなかった。最初に泊まった村の宿は、朝日屋といったが、宿の主人にシェルターの由来を聞いた程度である。
若主人はこんなことを言った。
「大昔このあたりは、火山が火を噴くと、村がやられてしまって、そのあと住めなくなった村がたくさんあったようだけど、この村だけは生き残ったんだ、周りの村があったところは火山灰や岩で埋もれていて、今でも掘れば人骨がでてきたりする、逃げることができなかったんだね、だけど、この村ではそういう話しがなくてね、この村の人たちは、いつも噴火に注意していたというんだ、それが今に続いているんだよ、きっと、そういうことに得意な指導者がいたんだろうな。
山が火を噴くまえに遠くに逃げていて、また帰ってきたようだ。ともかく備えがよかった、それをまもって、この村では、シェルターを作ったんだ」
村の人があらかじめ火山が火を噴くことを予見し、村を離れ、また寄り集まったということである。火山を予知する科学をもっていた。いや、占い師でもいたのかもしれない。伊能はそう思った。
さらに、若旦那は
「シェルターをつくったのは比較的最近でね、前前の村長のときだったかな、小学校や中学校を立て替える機会にね、だけど普通じゃシェルターなどつくらんよね、村長を始め、村の議会の連中が火山を怖がっていたな、村人には昔からのものがしみついているのかもしれんな、俺も何となく山を恐れているからな」
と笑った。
学部生のときには、毋母視村のシェルターについて卒業研究を行い、村落形成を専門とする社会人類学の先生から修士課程に進むことを進められ、火山と社会生活について、毋母視村に焦点をあて、文献調査と村落の実地調査をはじめた。
こんなことがわかってきた。
それは縄文時代の後期からのことだ。3000年ほど前のことだろう。村はずいぶん山奥にあり、どのような縄文人が集落を作っていたのかわからないが、毋母湖と呼ばれる湖の周りに人々が集まり生活をしていたと考えられた。
その湖には幻のカエルがすんでいたといわれる。毋母視村から、カエルの化石が何種類か発見されている。その化石カエルは、縄文時代にもその村で見られたのではないかと考えられている。尾があるカエルで、進化の過程で、魚類から両生類が生じた頃の移行期の、古いものではないかと言われている。
縄文時代の毋母湖には、肺魚のように、その古いタイプのカエルが生きるのに、必要ななにかがあったのではないかといわれた。それをさぐるために、海外からも研究者がやってくる。縄文時代の遺跡に、鳥や魚の骨、それに湖にいたと思われる巻き貝の殻は見つかっている。食べていたものである。カエルの骨もまじっていたが、尾のあるカエルの骨はみつかっていない。ということは、食べルことができなかった可能性がある。
外国には猛毒のカエルがたくさんいるが、現在の日本にはそのようなカエルはいない。しかし、日本で普通にみかけるニホンヒキガエルの皮膚からでる白い液体も、神経毒で、口にはいれば麻痺をするし、食べたりすれば、けいれんや呼吸困難になる。これはカエルにとって自分の防御のためであるから、人がなにもしなければ問題ない。
毋母視村の昔のカエルに毒があったかどうかまだはっきりとはわかっていなし。もし毒があれば、鏃の先に獲物を捕るための毒薬として用いただろう。歯が痛いときには麻痺させ痛み止めにするなど、利用価値が高かったのではないかと考えられている。そういったことに役立てていたカエルではなかったか。ある研究者は、そのカエルが目的で、縄文人が集落を作ったと言う説をだした。火山があるにも関わらず、そこに集落を作ったということは、生きていくのに、よい条件が整っていたからであることは確かだが、このカエルだけが目的とは考えにくい。伊能はそう考えた。
毋母視村の水も一つの理由かもしれない。毋母湖は水が豊富で、そこから流れ出る毋母川の利用価値は高い。それに野天湯がいたるところに湧き出している。昔はもっと豊かだったろう。動物たちもこの暖かい湯を利用していたに違いないが、縄文人は特に喜んだのではないだろうか。湯を好む日本人のルーツかもしれない。
この村には南の暖かいところに見られる樹木が生えていた。特にハゼの木がめだつ。が地熱が高いためだろうか。ハゼは木蝋といわれる蝋がとれ、蝋燭の原料になるが、それは琉球からもたらされ、室町時代あたりから作られるようになったらしい。関西以西に生える木で、関東地方にはあまりみられな。毋母視村の森には当たり前に生えている。縄文後期には蝋燭とまでいかずともこの実を利用し、火を灯す技術をもっていた可能性がある。そういったことも、集落ができた理由の一つかもしれない。
特記すべきは、秋に茸類が特に多い。この地方は茸の多いところだが、その中でも群を抜いて、種類も多く、室の高い茸がとれる。茸は精神作用のある物質をふくむこともあり、食料としてでなく、薬や気持ちの高揚のために、大昔には様々な利用の仕方をしていたようである。
このように、毋母視村には周りと違った、人には住むための好条件がそろっていたことは確かである。人間は長い時間がかかるが、生活によい物が見つかると、集まり、より楽な生き方を得ようとするものである。毋母視村もこうしてできあがったのだろう。
カエル、ハゼの木、それに茸、特に茸に関しては、今でも村人たちは、言い伝えられてきた茸の効用について語り継がれている。文献は戦国時代からの物が一番古いが、その話の元は、古代からの言い伝えだろう。しかし、この村の不思議なところ、なぜ、多くの火山の噴火にも村人たちは生き延びたのか、村を再建できたのかと言うことと、どのようなつながりがあるのかまだ霧中である。
そういう修士論文をまとめ、最後の疑問を解くべく、博士課程にはいった伊能は、実地調査を研究の中心とした。そのためたびたび毋母視村に出向くようになった。
村の図書館には、小さな地方の村にしては珍しく、明治のはじめ頃に書かれた古文書がかなり残されており、修士の学生のときに気がついていたことだが、毋母視神社のことが多くでてきた。この村にとって、村を取り巻く自然が生活に不可欠な大事な要素であることは詳しくしらべてきたが、火山とシェルターのことを知るには、村を引っ張っていく力について追求する必要があると、伊能は毋母視神社に焦点をあてていた。
その大昔、火を山の気持ちを察することのできる人間がいて集落を引っ張っていた。今の村につながるのも、そういった人間がいたからだと考えたわけである。村人は何かに頼っていたはずである。それが毋母視神社の神主か巫女か、文献には神社のもようしについての記載はあるものの、神社の中のことが書かれているものはなかった。きっとそこに鍵があるに違いない。伊能は村の人たちの話をまとめたり、文献に当たったりしながら、多くの研究報告をおこなった。
そんなある日、毋母視村のことらしきことが書かれたものが、遠く離れた京都でみつかった。
六月に京都で開かれた学会で、伊能の学会発表を聞いた一人の男が、毋母視の意味を教えてほしいと話にきた。
彼は安部悟という京都の大学の博士課程の院生で、伊能と同じ年だった。茸の民族的な役割を研究しており、最近、鞍馬の黒皮神社の茸についてに調べ始めたところだそうだ。年も近いこともあって、話は弾んだ。安部が調べている黒皮神社は地元の人からは茸神社と呼ばれており、五穀豊穣の神をまつっているという。
その神社の境内に毎年秋になると黒皮が至る所に生えるという。黒皮は苦みが強い茸だが、好む人はただ焼いて醤油をつけ食す。鞍馬あたりは松茸のとれる地としてもよく知られているが、黒皮は松茸と同じように赤松林や、針葉樹林に生える。ただ不思議なことに、黒皮神社の境内には、数本の木があることはあるが、梅と椿で、松や杉はない。草の生えているところに、ぽこぽこと黒皮が生えるのを見て、地元の人たちは、黒皮が神をまもる者たちの化身として、とって食べるようなことはしないという。
黒皮神社の黒皮は「こくひ」とよんで、生えてきた茸の前に小石をおいて、その上に猪口に入れた酒をおいてもてなす風習があったという。今その風習はないが、年寄りはこくひ様にご挨拶をと黒皮に向かって手をあわせるという。
黒皮神社の歴史は長いそうだが、何代目かの神主は越後なばみ村の出で、江戸の中頃、京の都に働きにでてきた男だったという。いきさつはわからないが、鞍馬の神社の娘婿となり、修行の末、神社をついだということである。そのとき古くなった社屋を建て直したという。今の建物は、昭和になり立て替えられたということだが、全く同じ形に建てられたということだった。なばみ村の男が神主になる前は、黒皮神社ではなく、美鞍馬神社といっていたそうだ。
その男の母親がなばみ村の占い術師で、それに使う干した黒皮を、京都にでる息子にお守りとしてもたしたということである。男が住職になると、神社を守ってくれるようにと、境内に母親からもらった乾燥した黒皮を砕いてまいた。そういったことが黒皮神社の歴史を記した古文書に書かれているという。
安部は伊能の学会発表で、毋母視村の歴史を聞き、黒皮神社の男が育ったなばみ村は、そこではないかと思い、伊能に声をかけたそうである。
その話を聞いた伊能は、その神社に毋母視村のことが書き残されて者がないか、安部に尋ねたが、安部は、調査を始めたばかりで、これから宮司とともに、神社の中を調べるつもりだという。
新たな文献などがみつかったら教えてほしいと、二人はメイルアドレスを交換した。
東京に戻った伊能はただちに毋母視村に行き、占い師の存在を調べることにした。何度か調査に行ったったが、占い師や茸に関しての話は聞いていない。毋母視神社がかかわっている可能性が頭の中をよぎっていった。
いつも泊まる朝日旅館に荷物をおくと、村の図書館いった。一年まえより図書館には新しい司書さんがいた。由井亜衣という短大を出て、司書の資格を取り、村役場にもどってきた人だ。毋母視村の酒屋の娘である。毋母視村の歴史には興味があるようで、いくといろいろ便宜を図ってくれる
「由井さん、この村に伝わっている、占い師ってしってる」
「知らないけど、お父ちゃんに聞けば何かわかるかもしれないわね、聞いておいてあげる」
由井酒店は、村でも古い代々続く酒屋である。昔は酒も造っていたようだが、今は販売だけの店としてつづいている。敷地はかなり広く、酒蔵だったものがいくつか残っていて、古いものがおしこまれているという。一度町を歩いたときに、由井酒店で彼女の兄と話したことがあった。いつか古いものをみせてもらうことにもしてあったのだが、はやくそうするべきだったかもしれない。
「それはありがとう、お兄さんとは一度話したことがあるんだ、しまわれているものを見せてもらう話をしたんだけど、それっきりになってしまった、お兄さんにもよろしく言ってください、古い地図があったりすると助かるね」
図書館に明治になってからの村の地図はあるが、それより古い地図がみたい。
「どうかわからないけど、蔵があるから、何か出てくるかもしれない、お父ちゃんにいって、蔵の中を見ておくわ、私も興味あるから」
「それはお願い」
村にも寺や神社があり、特に毋母視神社は山を背にした、村の中心であり、その神社が持っているむかしからの古文書を調べたが、やはり明治になってからのものしかなく、江戸時代より古いものはなかった。現在毋母視神社がおこなっている、様々なもようしのしきたりなどはそこにかかれていたが、他の神社のものと特に注目するような違いはなかった。ただ、檀家の名簿などから、明治、昭和にどのような仕事をしていたのかはわかったが、ほとんどが農家か商店をやっていいるところで、医師の家があったが、その家系はたえていて、村にある医院は、昭和、特に戦後になってから外から来た人がつくったもので、一応話は聞いたが、毋母視村の歴史はしらなかった。
「伊能さん、直接見に来るほうがいいかな」
「そうできるかな」
「うん、朝日旅館にとまっているんでしょ、うちから遠くないから、うちにきてお父ちゃんかお兄ちゃんと話してみたら」
前に酒屋によったときには、主人は旅行に行っていて、兄だけだったのだ。
「話が聞ければ助かるけど」
「携帯に電話するわね」
「お願いします」
「それから、この村で、茸の詳しい人、誰だろう」
「この村の若い人は、詳しい人が多いのよ、若い人が観光にくるでしょ、茸狩りの案内なんかもやっているから、みなよく知っているわよ、それこそ朝日旅館の若旦那なんかいいんじゃないかな、あそこ茸料理も得意だし」
「あ、それはいいことをきいた、今日話をしてみよう」
「茸にも興味があるんだ」
「いや、ちょっと、おもしろいことを聞いてね、その昔、毋母視村から京都に行った人が、鞍馬の神社の神主さんになったらしくて、その人が黒皮の干したのをもっていて、それをまいたら、黒皮が境内に生えて、黒皮神社と名前を変えたということなんだ、京都の研究者から聞いてね、その神主の故郷で、母親が黒皮を薬にしていたということだったので、茸のことも知りたいとおもったわけ、ただ、ひらがなで、なばみむらなので、ここの毋母視むらかどうかわからないけどね、その神主の母親は黒皮を使った占い師だったようなんだ」
「それで、占い術か、おもしろそう、黒皮って、このあたりじゃ、うしびたえ、っていうんだよ」
「なに、それ」
「牛の額みたいだから、まだ食べたことないの」
「うん」
「渋いから、旅館じゃ出さないかな、このへんじゃよくとれるのよ、食べたいというと、秋ならばとってきてくれるわよ」
「わかだんなにきいてみいよう、それじゃおねがいしますね」
伊能は図書館をでた。
旅館の若旦那には学部学生時代にシェルターのことを調べる手助けしてもらったこともあり、友達のように話しができる。だが今まで茸の話しをしたことはない。朝日旅館そのものは昭和になってはじめたものだから、それ以前の古い資料などはもっていないということだった。
旅館に帰って若旦那をつかまえた。
「ウシビタエっていう茸が採れるそうですね」
「うん、特産というわけじゃないけど、どういうわけかこの村にはよく生えるね、苦みのある茸だから、宿ではしている人しかだんさんけど」
「どこに行ったら見ることができます」
「そうだな、松茸と同じようなところらしいけど、この村ではいろんなところに生えるよ、内の庭なんかにもでることがある、内の働いている連中で、好きな奴らが採っちまって、焼酎飲みながら焼いて食っている」
「そうですか、秋にきたときに食べてみたいですね」
「もちろん、ごちそうするよ、あれなばただでいいよ、飽きるほど食くわしてあげよう、もしかすると、冷凍庫にいくつかはいっているかもしれないな」
若旦那は丸い顔にしわを寄せて笑った。
「司書の亜衣の家の由井酒店は古いので、言い伝えなんかが残っているかもしれないっていってましたよ」
「このあたりじゃ最も古い家にはいるんじゃないかな、もちろん神社も古いけど、途中で宮司さんがかわってしまっているから、代々続いているのは亜衣ちゃんのところがいちばんかな」
「土蔵に昔の資料があるかどうか見てもらうことになっているんです」
「なにかあるとおもうよ、昔から神社に御神酒を納めていたから、亜衣チャンは女房の高校の同級生なんだ、内のは高校出てすぐに料理学校にいったんだけど、亜衣チャンは勉強できて、短大で司書の資格取ってもどってきてね、亜衣チャンの兄貴は俺と同級生なんだよ、酒を届けにきてくれるんでたまに話しをするけど、あいつもやり手でいつも忙しそうだ」
「そうだったんですか、お兄さんとも話をしたことがありますよ、感じのいい人だったな」
「商工会議所の青年部を引っ張っているからね」
その日の夕食に、凍らせてあった黒皮をもどしてだしてくれた。かなり苦みがあるが、以外とさっぱりとしていて歯ごたえがあり旨いものである、日本酒と合う茸だろう。
由井亜衣から電話が入った。次の日の午後、由井酒店の蔵を見せてもらうことになった。
次の日、午前中は毋母視神社の境内を見ることにした。神社の中は宮司さんに何度もみせていただいたが、境内の方は素通りだった。毋母視神社は全国の神社からすると、平均的な大きさである。だが境内はかなり広く、他の神社と同じように、社の裏は裏山に続いている。毋母視山である。毋母視山を越えれば、さらに高い山々があり、どれもが休火山で、いずれは活動が高くなるときもあるだろう。
この社殿は昭和になってから建て替えられたものだが、間取りは一切合財昔のままで、建材は違うところもあるが、江戸時代から続いていたたてものと同じだという。
広い境内は杉の木が取り囲んでいる。社殿の前は草原になっていて、盆踊りができるほどの広さを持つ。年に何回もの祭りがあって、数々の屋台もでるところから、観光客にも郷愁を誘うと人気になっているという。それにもまして、おもしろい試みがなされている。江戸時代の社殿の脇にはその昔、本殿の回廊につながった小さな建物があったという。それは伊能もすでに知っていた。しかし、その部分は今はない。何らかの目的で使われていたようだが、神社に残されている古文書には、茶室に使われたり住職の趣味の部屋として使われていたことが書かれている。明治になるかなり前に朽ちてしまったということである。そこは草原になっていたのだが、今ボウリングをしている。温泉を掘り当てようという魂胆である。村の青年会のきもいりで、もし湯がでたら露天風呂をつくり、はいったあとに、本殿の広い回廊で一休みできるようにするという計画だ。毋母視ビールを造ろうという動きもあるようで、神社の回廊で風呂上りにいっぱいという、商工会議所青年部の考えそうなことである。
露天風呂を持った神社となると、シェルターとおなじように、日本で唯一のものとなるだろう。若い神主も乗り気である。
伊能が境内にはいると本殿の脇にほろに囲まれ他場所が眼に入る。そこが大昔、小屋があったところで、温泉を掘り出しているところである。何人かでボーリングをしているようだ。
境内の草原には名もわからない小さな茸が顔を出している。秋になればそれなりの茸たちが生えるのだろう。黒皮も生えそうだ。となると、安部が調査している京都の黒皮神社と似ていることになる。
神社の周りを回ってみると、裏の毋母視山の斜面に穴があった。防空壕か何かなのだろうか。
神社を見て町に戻ると、由井酒店のならびの食堂で昼を食べた。茸そばをたのむと、茸がたっぷり入った蕎麦がでてきた。
「この茸はこのあたりでとれたものですか」
店のおじいさんに聞くと、うなずいた。
「ああ、そうだよ、こりゃヒラタケ、山からとってきたのを水にして、かんずめにしておいたやつだからうまいよ」
確かに歯ごたえがあってうまい。
「蕎麦も地元のですか」
「蕎麦は毋母視じゃないけど、信州蕎麦だからね、直接粉を買って内で打ったものだから」
「いや、うまいです」
名のある蕎麦屋じゃない定食屋で、これほどの蕎麦が出てくるとは思わなかった。これならば、遊びにきた若い人もこのような飾らない町の食堂をたのしめるだろう。SNSを介してこの村が知られてくるのもこういうところからだ。ヘルメットをてーぶるにおいて、男女が定食を食べていた。二人でバイクでツーリングのようだ。
食堂をでて由井酒店にいくと、主人が出迎えてくれた。丸顔の人の良さそうな、いい体格をした人だ。長男とよく似ている。
名刺を差し出すと、
「亜衣から聞いています。お世話になって、ありがとうごいます、酒屋の名刺しかないけど」といって、酒店の名刺を差し出した。由井秀吉とある。すごい名前だ。
「僕の方がお世話になっています」
と頭を下げた。伊能は大学院生だが、いろいろなところを訪ねることが多いので、身分を明らかにするために名刺をつくっている。
主人は「名前がはずかしいんですよ、親がとっくりにひょうたんを使っていたものだから、息子にこんな名前をつけたんですよ」と笑った。
伊能が名刺をみつめていたからだろう。
「蔵は物置代わりになっちまっています、入り口の前の方につっこんであるのは、家で使わないやつです、奥の方と二階に古いものがおいてありますので、自由にゆっくりみとってください。役に立ちそうなものがあったら、どうぞもってってください、私は店にいますので、何かあったら呼んででください」
主人のはからいだろう、伊能は一人でじっくりと調べることができる。
一階には酒に関係する道具類がつみあげてあった。二階に上がると、棚に埃をかぶった古文書がかなりたくさん積んである。昔の勘定書きが大方だが、このあたりのことを書いたものもあった。そういったものを抜き出すと六冊になった。
本の積んであった棚の奥に、押しつけられるようにして和紙の袋があった。開いてみると、干からびた茸である。しなびていて形はわからないが、もしやもするとと思い、それもとりだした。古文書と茸の袋を持って、蔵を出ると店番をしていた主人のところに持って行った。
「何か珍しいものがありましたかね」
「ざっとみただけですけど、この六冊には村のことなどが書かれているし、絵も入っています。江戸時代のもののようです。ちょっとかしてください。コピーをとってお返しします」
「どうぞどうぞ、お持ちいただいてかまいません、そのうち、村の図書館にでも寄付しますから」
伊能は借りていくことにした。
「こんなものも出てきました、写真を撮ったらお返しします」
「なんですか」
由井秀吉は袋をのぞいた。
「茸ですな、かなり古い、ウシビタエのようだ、なぜこんなもんがとってあったのでしょうかね、ウシビタエは珍しいもんじゃないんだけど」
「ウシビタエは薬になりますか」
「あまり聞いたことはないですな」
「他に使い道はありますか」
「私はしりませんな」
「これ茸の専門家に調べてもらっていいでしょうか」
伊能は京都の安部に送るつもりだった。
「どうぞお持ちください」
「茸の意味がわかったらおかえしします」
「研究のお役に立つといいですね」
「この村で、占い師がいたという話しはありますか」
「占いというと」
「占星術だとか、天地異変を占ったり、雨を降らしたり、日を照らしたりすることを取り仕切る、人がいたのでしょうか」
「豊作を祈願し、占うようなこと今でも神主がやってますが、今はそういう人は折らんですね、昔のことはわからんですけどね」
伊能は京都の黒皮神社の話しをした。
「ホー、そんなことがわかったんですか、おもしろいですね」
主人もおどろいていた。
「この資料にもなにか書いてあるかもしれません、わかったらお知らせします」
伊能はすぐにでも旅館に戻って読んでみたかった。
由井秀吉は「そうだ」、といって、棚にあった酒をとった。
「この酒、これから発売ですけど、この村で作り始めたものですから、まだ朝日屋でもだしてはいないないんです、朝日旅館の若旦那にもっていって、一緒に飲んでみてください」
一升びんの「毋母視の流れ」を手提げ袋にいれてくれた。
「すみません、なにからなにまで」
「いえいえ、亜衣も毋母視村のこと興味を持ち始めているようでね、あいつは四年制の大学に行きたかったのだと思いますけど、家に早く戻らなきゃいけないと思って、短大にしたんですよ」
伊能が怪訝な顔をしていたからだろう、
「母親が早くに死んだものだから」
と由井秀吉はつづけた。
「そうでしたか、いろいろありがとうございました、お酒は宿で飲みます」
御礼をいうと、朝日酒店をあとにした。
宿で若主人に酒をわたした。
「ホー、これから出す酒ね、夜にだししますね、冷がいいのかな、由井さんにきいてみようかな」
若旦那は一升瓶を台所に持って行った。
伊能はすぐに部屋にこもって、古文書を開いた。大学で詳細に読むつもりだが、ともかく目を通しておきたい。
どれも江戸中頃のもので、一つは毋母湖で穫れる魚の種類について詳しく書いてあった。おもしろいのは真水クラゲが夏になると発生することが記されていた。一寸ほどの傘を持ったクラゲで、海ではないところにも、このようなクラゲがいるのは毋母湖だけだと、あった。絵も描かれている。
すぐに、知人の生物学者にスマホで、真水にいるクラゲが、毋母視村の湖にはいたらしいと書いたら、すぐに返事が来て、真水クラゲはめずらしいものではないがが、直径は一センチほどの小さなものだと返事がきた。
毋母視胡のカエルに関する記載もあった。毋母視カエルとあり、絵を見るとガマのようだが尾のような突起がおしりにつきだしていた。
このことも、メイルしてきいてみた。
「そりゃおもしろいね、絵が書いてあるなら、スマホで写真撮って送ってよ、水クラゲもね」
そういわれたのですぐに送った。
「水クラゲは条件がよければ大きく育つかもしれないな、新種ではないだろうと思う、カエルはおもしろいね、カエルの専門家に見せてみるよ、興味を持つかもしれない。変態しても尾の部分が突起になって残っているようだ」
と返事が来た。やっぱり毋母視村にはなにかありそうだ。
江戸時代の地図がでてきた。
毋母視村の地図は毋母視神社を中心にして書かれていた。山の麓に地蔵が描かれている。毋母視村を歩くと、地蔵が多いのにはきがついていたが、地方の村にはよくあることなのであまりきにとめていなかった。地図に印がついているのは今までみたことがないし、それにしても多い。神社の裏にもあった。地蔵に何か意味があるのだろうか。毋母村の道沿いに置かれている地蔵について誰かに聞いてみるひつようがある。シェルターのあたりには必ず地蔵がおいてある。この地図を今と比較する必要があるだろう。
古い神社の図面も出てきた。境内、社殿の簡単図があり、本殿の脇に小さな四角い家が書かれている。宮づくりの建物ではなく、絵からすると茅葺きのようだ。今、温泉のボーリングをしている場所だ。文を読むと、本殿の隣の茅葺きの小屋は、毋母視小屋と呼ばれ、秋に毋母視がそこにこもるところという記述があった。そこで、村の名前でもある、毋母視がでてくる。毋母視とはどいうものだろう。毋母視がこもるということは、毋母視という人のことだ。何かをする人だ。占いか。この村が存続繁栄してきたわけがわかるかもしれない。
村全体は明治以降も大きな違いがない。もちろん道の整備、新たな家、そういったものもあるが、都会が明治の文明開化で大きな変革があったのに比べ、山奥の村にはそんなに目立った変化はない。さらに昭和の戦争と敗戦で都会にはさらに大きな変化が見られたが、やはり村には影響がなかった。ただ、敗戦後の復興、バブル期になると、毋母視村にも、廃村にならないように若い人たちの活躍があり、観光化による変化があり、シェルターが作られたという変化はある。
江戸の地図では毋母視村の一番大きな道沿いに家が点在している。家は増えたが今と代わりがない。地図に酒とある家がのっている。位置からすると、由井酒店のようだ。いつの世にも酒は食料と同じほど人々に必要なものだったのだろう。
その古文書は大変役に立った。伊能の毋母視村の成り立ちの研究が一歩前に進んだような気がした。
いつの間にやら、夕ご飯の時間になっていた。女中さんが時間になっても降りてこない伊能の部屋につげにきたのだ。伊能はあわてて食堂に行った。部屋の名前のおいてあるテーブルにつくと、料理が並べられている脇にガラスの容器に酒がはいっていた。毋母視の流れと書かれている。由井酒店でもらったものを冷やしておいてくれたのだ。
給仕の人が、ご飯は飲まれた後にしますかときいた。伊能は酒飲みではない。
「食事の用意もお願いします」
とご飯と味噌汁もいっしょにたのんでしまった。
日本酒は飲み慣れていない。用意されたグラスに酒をついで口をつけた。辛口というのだろう、口の中が甘ったるくない。確かにせせらぎのようだ。飲み込むと、ひんやりと胃の中におちていく。
料理に箸をつけた。茸と山菜の煮物だ。
ご飯と味噌汁が運ばれてきた。女中さんと一緒に若主人がきた。
「なかなかさっぱりと仕上がっていて、若い人が好みそうな酒にしあがってますよ、どうです」
ときいてきた。
「あ、ええ、うまいですね、酒はあまり飲めるほうじゃないんですけど」と答えると、彼は「ネーミングがいまいちだね、毋母視の流れ、じゃなくて、毋母視湖の水とか、毋母視湖清水とかにしたほうがいいね」
伊能は「確かにそうかもしれませんね」と相槌をうった。
「そうだ、聞きたいことがあったんですけど、この村にはお地蔵さんがずいぶんありますね」
「昔からたくさんあったね、爺さんたちは大事にしていたよ、この村を守ってくれてんだといってね、新しい家を建てるにしても地蔵はそのままにしておいたね」
「今新しい地蔵を作ったりしないのですか」
「そんなこともないんだ、商工会議所の若手がたのんで、石屋が新しいの作ってるよ、だけど、観光のためだけだね」
「江戸の地図に地蔵の位置がかいてあったものですから」
「へー、それは知らなかった」
「そのうちコピーでも送ります」
「うん、商工会議所の連中も知らないと思うよ、それじゃ、ごゆっくり」
若旦那はそういってもどっていった。
明日大学に戻ろう。あの文献をしっかり読み解かなければ。
大学に戻ると、安部にメイルで毋母視村の酒屋で乾燥した茸が見つかったことを書いた。みてみたい、なんなら、生物学の知り合いに調べてもらうという返事が来た。そこで、干からびた茸を安部に送った。
伊能は由井酒店の蔵から出た古文書を丁寧に読み解析した。今までに集めた資料と照らし合わせ、明治より前の毋母視村の様子をより明らかなものにした。印象としては、とてもよくまとまった村であることが感じられた。村人たちは皆で村を守り、生活がしやすいように改良して行った様子がわかる。共同に使う小屋がいろいろなところに建てられ、村民が自由に使えるようになっていたようだ。たとえば、田畑の脇には、大きな小屋が建てられ、皆が自分の家の農作業の道具をおいておけるようになっていた。住居地と田端が離れていたこともあり、道具の持ち運びは大変だったに違いない。その労力をを楽にする仕組みである。毋母湖脇には釣り小屋があった。それぞれの漁師の釣り道具がおいてあったようだ。
そういった共同小屋と、地蔵のマークの位置がかなり重なっているようである。ただ、山の裾の地蔵のマークと小屋とは重ならなかった。いずれにせよ村民のための施設には地蔵がおかれていたようだ。
酒屋の古文書の中の一冊は、特別の酒を神社の毋母視衆のために届けるということがかいてあった。届ける日付をみると、秋の祭りの頃のようである。毋母衆とはどういう人間か。神社の神主に電話をかけ聞いたが、まったく知らないということだった。もちろん毋母視村の亜衣にもメイルで聞いてみた。調べてくれたのだが、村に残されているもののなかにはでてこないそうで、酒屋の父親もしらないということだった。
秋になり、京都の安部悟が、茸の結果をメイルで知らせてきた。由井酒屋の蔵にあった袋の乾燥機のこはすべて黒皮であるということだった。遺伝子調査の結果では、京都の黒皮神社に生えるものとほぼ同じだと言うことである。ところが、毋母視村の由井酒店の黒皮も京都の黒皮も、一般の黒皮と遺伝子配列の違うところがあるということだった。何でも色素の遺伝子だそうである。
伊能には生物学的なことはよくわからなかった。安部は由井酒店の茸を返しがてら、毋母視村の神社を調べてみたいといってきた。京都の黒皮神社の境内にはすでに黒皮がではじめたので、毋母村の様子をみたいという。亜衣に電話できいたところ、茸類は8月の終わり頃からたくさんでているという返事をもらった。安部と相談して、5日ほど朝日旅館に予約を入れた。
安部とは現地で落ち合うことにして、毋母視村に向かった。
「久しぶり」
安部は朝日旅館に先についていた。
静岡で降りて、飯田線できたという。電車の時間をあわせてきたので、新宿周りより早いという。
「チェックインの時間より早くついたので、毋母神社視てきましたよ。驚ろいたな」
もう毋母視村を歩いたようだ。地図などは渡してある。
なにを驚いたというのだろう。伊能がなにをと聞く前に、彼は鞄から写真をとりだした。
伊能はそれを見てやはり驚いた。
「黒皮神社は毋母視神社とほとんど同じ形だった。黒皮神社はなばみ村からきた神主が持ってきた神社の図面をもとに作ったということです。黒皮神社を建てた宮司はあきらかに毋母視村の出身ですね、毋母視村で黒皮はどのように使われていたのか興味があります、毋母視神社にも黒皮がたくさんはえていましたよ、酒店に干した黒河が残されていたほどですから、ここの村でも黒皮が大事なものだったんじゃないですか」
「そうかもしれない、おもしろいな、本殿の左側でボーリングをやっていたでしょう」
「ええ、何のボーリングですか」
「温泉なんです、温泉にはいって、本堂の外の回廊で休みながら、ビールをのみ、お払いをうけるという、青年部と宮司さんの共同作業の試みなんだそうです」
「ずいぶん大胆な試みですね」
「あそこには小さな茅葺き小屋があったようなんですけど、なにをするところかわからない」
「京都の神社にはまだありますよ、茅葺きではないけど、今は物置のようですが、なばみ村から婿入りした宮司さんが占いに使っていたという話しです」
「宮司さんが占っていたのですか」
「ええ、おそらく、山のめぐみのでき具合ですね」
「というと」
「茸やアケビや、秋の味覚の出来具合を占ったんじゃないかな、よくお米の出来を占ったりするでしょうでしょう」
「それはおもしろい、この村の神社でもそのような占いをしていたかもしれないな、ただ今神社の人や村人はそのようなことを知っていない、やはり江戸時代のことなんでしょうね」
伊能がはチェックインし終わると、帳場に若旦那が顔を出した。
「伊能さん、いらっしゃい」
「あ、若旦那、こちら、京都の阿部さん、僕と同じように人類学をやってます、ただ茸の人類学」
「いらっしゃい、どうぞ毋母視村を楽しんでください、茸も豊富です」
「よろしくお願いします」安部がお辞儀をした。
「阿部さんが調べている鞍馬の黒皮神社をつくったのは、毋母視村出身の神主さんで、神社そのものが毋母視神社とそっくりなんです、それに、黒皮を占いに使っていたようです」
「そりゃ面白い、青年部の連中が知ったら、きっと鞍馬とこの村の姉妹都市を計画しますよ」
安部はそれをきいて苦笑いをしている。そういったことは苦手のようだ。
「それじゃ、われわれ、村を歩いて、地蔵のことなどを確認します」
「新しい発見を期待してますよ」
若旦那はおくにはいっていった。
伊能は安部を神社に誘った。
「かまわなければ、これからもう一度神社行きましょうか、宮司さんとも話しましょう、ただその宮司さんはよそからきた人で歴史はあまりご存知ありませんけど、前の亡くなった宮司さんに子供がいなかったということです」
「ええ、そうしましょう」
安部がうなずいた。そこにまた若旦那が帳場にでてきた。
「伊能さんいい忘れちまった、由井が、蔵の隅から神社に関わる書き物がみつかったといってた。亜衣ちゃんがみつけたらしい、亜衣ちゃんがもっているということだから、帰りに図書館によってみたらいいですよ」
「あ、ありがとうございました、安部さんが油井さんの茸を由井酒店にかえしたいので、もっていきます」
まだ古文書はでてくる。由井酒店ばかりじゃなく、他にもあるかもしれない。
この地方は8月の終わりになるともう秋風である。石段を登り境内にはいるとひんやりと冷たい空気がからだを包む。
「ほら、これが黒皮です」
安部が草の間にもっこりと固まっている、黒と言うより薄黒い、どちらかというと、きれいではない茸を指さした。
「ここでも、黒皮神社と同じように、こんなところに生えているんですね」
伊能は始めてみるし、茸はよくわからない。針葉樹に生える茸だと、前に安部に聞かされているが、たしかに境内の周りには大きく育った杉もあるが、梅や椿など広葉樹がたっくさん植えられている。
「一度旅館で食べさせてもらったけど、細く切ってあったので丸ごと見るのははじめてだな」
「そうですか、目立たない茸ですけど、好きな人は好きですね」
安部は写真を撮った。
宮司さんには旅館をでる前に電話をいれてある。社殿の脇の事務室の入り口で宮司さんがまっていた。
「伊能さん、いらっしゃい、温泉がでそうなんですよ」
30代の宮司さんはそちらの方が楽しみのようだ。
「こちら、安部さん、京都の大学の博士課程です、京都に黒皮神社というのがあって、それが、毋母視神社とそっくりだそうです、しかも境内には黒皮がはえている」
伊能はいままでのことをはなして聞かせた。
「それは不思議ですね、江戸の頃の書き物はのこっていないのですが、代々宮司をやった人の名簿はあります、それには江戸の中頃からの名前が書いてあります、ということは、この神社は江戸中ごろからあるようですね」
歴代の宮司の名簿を見せてもらわなかったというのはうかつだった。
「是非見せてください」
「どうぞどうぞ、書院にあります」
二人は書院に案内された。
宮司は古びた巻物をひろげた。
「これはかなり古いもので、時代と宮司の名前しか書いていない粗末なものです。ところどころに、年号が書いてあります。
最初年号がなくて、何人かの名前の後に、享和と書いてあります。その前の宮司の人数からすると、1700年代後半にこの神社はできたのではないでしょうか」
宮司の名字はみな安積(あさか)となっている。昭和になると、名前が変わるところもあるが、またもとの安積になる。
安部が巻物をみていて指差した。
「この、文久と書かれているところの、宮司さんの名前が気になります」
そこには安積(あさか)一之進とあった。
「どうしたんです」
「黒皮神社をつくった宮司の、婿入りの前の名前がわかったんです、安積次之進というなまえだったそうです、なんだか、この弟のような気がしたものですから」
「確かに、弟だから外に出されたということですね、そういうことはよくありますよ」
と宮司さんが言った。
「僕はこれです」
令和2年、安積光男とある。
「もとは、足立光男です、山梨の神社の家に次男として生まれたので、大きくなってからここに養子にきました」
「そうなんですね、でもおかげさまで、話しが進展しました、ここにきてよかったです」
安部はうれしそうだ。
「ということは、安積一之進の親、この家系図からいくと、安積史郎の子供であり、史郎の奥さんが占いをしていたということになる」
伊能が指摘すると、安部がうなずいた。
「占いのことはきいたことがありますか」
安部が訪ねたが、安積光男は「きいていませんね、毎年秋の収穫のお祝いの時に、来年の収穫祈念と同時に、村の運勢を占いますよ」
「どのようにですか」
「占星術です、夜空をみて、行います、方法は書いたものがあります、これはおそらく昭和になってからのものでしょう、私にはできないので、数年前から村に移住した、若い占星術師にたのんでいます」
「茸は使わないのですね」
「茸を占いに使うということは聞いたこともないし、書き物もありません、どの湯に浸かったんでしょうね、黒皮神社では使って占いをしていたのですか」
「いえ、黒皮神社を建てた神主の母親がそうだったというだけで、黒皮神社ではそういうことはしていなかったようです」
「そういえば、ボーリングをしているところにあったという小さな建物は毋母視小屋といって、毋母視が使うところだったと、由井酒店から出てきた江戸時代の古文書にああった、毋母視は村の名前だよね」
「え、それは知らなかった」
安部が驚いた顔をした。
「あれ、メイルに書いたつもりだったけど、地蔵のことは書いたよね」
「うん、江戸時代の地図はスキャンしたのを送ってくれた」
「毋母視神社の古い地図は送らなかったっけ」
「うん、おくってもらってないない」
「そりゃ、ごめん、後でコピーを渡すよ」
「うん、それはいいけど、前から気になっていた毋母視の意味だけど、「ナバ」って茸のことだよね、ただし西日本、特に九州で使われている方言なんだ、毋母視は茸を見るということだろ、茸を見て何かするのじゃないかと想像できるよね、ただ信州じゃ、茸のことをナバとは言わないだろうな」
「あー、そうか、大事なことだな、もっと早く教えてあげればよかったな」
「いや、まだはっきりしない、これから調べなきゃ」
聞いていた宮司さんは興味がないようだ。
「温泉のボーリング現場をごらんになってください、家の跡は何もなくなってますが」
宮司さんはわれわれをひっぱるように、温泉調査の現場に案内した。
本堂を横切って、外回廊にでると、石段にサンダルが用意されていて下におりた。目の前に幌で囲まれた試掘の現場があった。入り口の幌をあげると、二人の作業員がボーリングの機械を操っていた。
「ご苦労様です」
宮司が声をかけると、一人が、「もうすぐ湯がでるような雰囲気ですね」と言った。
「湯がでたら、この後ろの山の斜面に、露天風呂を作る予定なんです、毋母村のもう一つの目玉になりますよ、私は山梨出身だけど、毋母村の住人ですからね、神社が役に立角は嬉しいですね」
宮司の期待はかなり大きいようだ。
安部が足下を見て、おやという顔をした。カメラをそちらの方に向けた。その先には赤っぽい茸があった。ピンクに近い薄い赤である。よく見ると、形は黒皮である。
「桃色の黒皮だ」
安部はシャッターを押すと、その茸を採取した。
「そうなんです、ここのところ、白っぽかったり、ピンクだったりする黒皮が生えるんです」
機械をあやつっている一人が言った。
「ここにもある」
伊能も気がついた。
「珍しいですね」
「境内にもでていますよ、この近くに」
安部は茸に集中している。
「安積さん、あの宮司さんの系図、コピーをとらしていただけませんか」
伊能が頼み込むと、安積宮司は「こちらでコピーをとっておきます、まだいらっしゃるんでしょ」
「はい、三泊ほどします、そうだ、江戸時代の古文書に、地蔵さんが本殿の裏に描かれていました。地蔵さんは古くからあるみたいですね」
「地蔵さんは町中にたくさんあります、毋母視地蔵とよんでいます、だけど、神社にはありませんよ、裏の山には大きな穴があるだけです。あの穴はいつ頃からあるのかわかりませんが、かび臭くて使ってはいません。奥はかなり広いようです。防空壕のようにも見えますが、もしここに湯がでたら、あの穴も何とかしようと思います。」
伊能たちは本堂を通って、外にでた。本殿の裏にまわると、穴が確かにあった。中を覗くと、ふーっとかび臭いにおいが鼻をくすぐった。伊能がはいってみると、かなり広く、奥もどこまであるのかみない。壁の所々に小さなへこみが作られていて、ちびた蝋燭がおかれていた。宮司の言うように防空壕のような感じもある。
「ずいぶん大きな穴ですね、奥まで入ったことはないのですか」
「いや、一度ありますよ、まっすぐな穴で10メートルもありましたかね、一番奥が広がっていて、もしかすると、そこに地蔵でもあったのではないでしょうか」
温泉のボーリングをしているところにもどると、本殿の前にもどった。ボーリング工事を囲んでいる幌の近裾のあたりにもピンクの黒皮が生えていた。
「ここにもある」
安部は取って袋に入れた。
「どうしてでしょうね、渋みが消えたのかな、食べてみますよ」
安積宮司がいった。
「実は京都の黒皮神社のものは真っ黒ですが、遺伝子がちょっとおかしくて、ここの由井酒店の蔵から見つかった江戸時代の茸と同じだったんです、今採った茸も調べてみます」
「茸の遺伝子とは想像もつきませんが、きっと研究する方にはおもしろいことなんでしょうね」
宮司には理解ができないようだ。三人は社務所に向かい、伊能と安部は靴を履き替えて神社を出た。
「帰りに図書館によって、由井酒店で見つかった古文書をもいましょう」
「酒店に行くのではないのですか」
「図書館の司書が由井酒店のお嬢さんで、いろいろ便宜を図ってくれるんです、蔵でみつかった茸も彼女に渡せばいいと思います」
「ああ、そうなんですね」
「いい子ですよ」
伊能は前もって亜衣に電話をした。
「伊能さん、こんにちは、神社の温泉でそうですよ」
「そうだってね、今行って来たところ、亜衣さんも元気そうだ」
「ええ、私も内の倉庫をひっかき回したり、家の古い金庫をこじ開けたりしてみたの、そうしたら、金庫から、古い、おそらく江戸時代の5ページほどの古書がでてきたんです」
「お兄さんが朝日屋の若旦那に言っておいてくれたんで、よったんだ」
「そうなんだ、これ茸の絵が入っているし、おもしろそうだけど、漢文で読めない」
亜衣が伊能にわたした。
「ありがとう、こちら、京都の大学の安部君、同じ年なんだ。神社と茸のことを調べている」
「よろしくおねがいします、この茸とても役に立ちました、ありがとうございました」
安部が亜衣に乾いた茸の入った袋を渡した。
「はい、父親に渡しておきます、京都、いいな、まだ一度しか行っていない」
「どうぞいらしてください、案内しますよ」
「安部君は鞍馬にある黒皮神社のことを調べていて、毋母視村の人が住職になってから、毋母視神社とそっくりの社に建て変えたんだって、しかもその神社に黒皮がでるんだ」
「ふしぎね、縁があるところなのね」
「由井さんのところでみつけた干からびた茸と鞍馬の神社に生える黒皮の遺伝子が同じだそうだ」
「親戚ね」
亜衣が笑った。
伊能は受け取った古文書を開いた。
漢文で書かれている。タイトルは聞異老茸とある。
これは年をとった異なる茸から聞きおよぶ、ということなのだろうかと伊能が考えていると、安部がのぞき込んで、「老茸」はろうじといって、黒皮のことですけど、もしかして黒皮のことが書いてあるのかもしれませんね」といった。
「あ、そうか、黒皮に聞くということか」と伊能は頭をかいた。
ページをめくると、茸の並んだ絵があった。黒皮のようでもあり、違うようにも見える。茸の傘の色が濃い墨からだんだん薄くなっている。その上に数字の番号がふってある。
「説明の漢文も一から五までに分かれているから、それの説明でしょう」
「僕は漢文弱いな、文学の先生にみてもらうよ、安部君にもコピーをわたしていいかな」
亜衣に言うと、コピーを二部すっと差し出した。
「当然必要になると思って、たくさんコピーしといたんだ」
よく気がつく子である。
「ありがたいな」
「内容がわかったら、おしえるよ、お兄さんとお父さんによろしく、こちらにいる間に一度うかがいますといっておいて」
「はーい」
二人は朝日旅館に帰った。
「この漢文を写真にとって、知っている国文学者に送っておくよ」
伊能がいうと、「ええ、お願いします、僕もトライしてみます」
安部は漢文が読めるようだ。社会の成り立ちを研究の軸においている伊能とは、研究方法が違うようだ。
安部は帳場にいた朝日旅館の若主人に、亜衣がみつけた文献のコピーを見せて、「これ傘の色が濃いのから薄いほうにならべた黒皮だとおもうですけど、このあたりではこういった色の濃さの違う黒皮がみられるのですか」
とたずねた。
「宿の周りにでるのは濃い奴だけど、もう少しネズミっぽいのはよくみかけるよ、山の方に生えるのはどっちかというと鼠色っぽいかな、毋母視湖の近くの林のものは黒っぽいかな」
「神社の境内にはピンクぽいのがあったんです」
安部はボーリングしているところの茸をみせた。
「こんな色のは見たことないな、本当に黒皮なのかな」
「専門家に調べてはもらいます」
「黒皮を採りに行った時に見てみるよ」
そういって、若旦那は到着した客の対応をはじめた。前もそういっていたような気がする。
部屋に戻った二人は明日の相談をした。。
「僕は明日、江戸の地図にのっていた地蔵のところを歩いてみるつもりなんだ、まだあるかどうか調べてみる。君はどうする」
「村には寺もあるでしょう、その寺の茸も見てみようと思うんですけど」
「あれ、そういえば、この村に寺って聞かないな、どこかにあるのかな」
伊能はこの村のシェルターばかりきにとられていて、そういった基本的なことに目を向けていない自分にまだ研究者としては未熟だと思った。その点、阿倍の考えの広さがうらやましく思った。
「村に墓はあるけど寺はみないな」
「また、若主人にきいてみよう」
伊能と安部が帳場にいくと、客を部屋に案内した若主人がもどってくるところだった。
「たびたびすみませんけど、この村にお寺ってあるでしょうか」
「ああ、いいとこ気がつきましたね、ないんです、地蔵さんはあるけどね」
「葬式は毋母視神社がやるんですか」
「昔からの村のもんは、全部毋母視神社の氏子ですよ、毋母視神社が中心だな、むかしから、坊さんも村にきていたようだけど、居つかなかったということだな」
「神社の氏神さまはなにでしょう」
「後ろの毋母視山だな」
「いや、ありがとうございます」
「今日の夕飯には、村山で採れたマイタケのてんぷらがでるよ、うまいよ」
若主人は笑顔で言った
「村の人たちのまとまりの良さはそこからきているんだな」
伊能はなるほどと思ったが、阿部は不思議そうな顔をしている。
「地蔵は誰が管理しているのだろう、あれ地蔵と言っているけど、道祖神の可能性がありますね」
確かにその通りである。地蔵は仏教の地蔵菩薩だが、道にある地蔵は、疫病、悪魔を払う道祖神の役割ももつ。よその村には地蔵がおかれていたことから、この村でも毋母視地蔵と呼んだのかもしれない。
「それか、神仏混淆の時代の影響が残っているて、神社が仏教信仰の地蔵の部分をとりいれてしまったのかもしれない」
「確かにそうだな、気がつかなかった。明日はそういったことも村を歩いて調べるよ」
食事の時間になり、二人は食事処で、茸料理をたっぷり食べた。
次の日、朝食後、安部は山の裾の地蔵と黒皮を調べに行った。伊能は村の街中の地蔵を調べるということで、二手に分かれ、後で知ったことをあわせようということになった。
江戸時代に造られた村の中の道はほぼ今ものこっている。歩いていくと、地蔵はだいたい江戸時代の図に描かれたところにあった。すべてではないが、想像したとおり農作業の小屋や漁師小屋など、共同で使われた小屋のあったところに地蔵はあった。今そういうところにはコンクリート制の地上一階、地下二階のシェルターがつくられている。もう数十年立っていると思われるので、シェルター自身もだいぶ汚れている。屋上はちょっとした遊園地のようになっているところや、駐車場になっているところがある。
そういった公共施設のところ以外は、水田や畑に接した広い道の交差点などにおかれている。誰かが面倒を見ているのだろう、必ずお供えものがあった。
畑にでていた人に聞くと、やりたい人がやっているけど、ほぼ毎日誰かがお供えしているという。
あぜ道を歩いていると、いきなりサイレンが鳴った。急襲警報の音だ。驚いていると、遠くから消防車の鐘の音、救急車のサイレンが聞こえてきた。火事だろうか。街の方も山の方にも煙は見えない。
街に引き返し、由井酒店に行った。由井秀吉も亜衣の兄も店の前にでていた。
「伊能です、いろいろお世話になりました」
と声をかけると、二人とも振り返り、「伊能さん久しぶりです」と笑顔で声をかけてきた。
「火事でしょうか」
「わからんですね、どうも毋母視神社の方向だな」
「また後で、ご挨拶にうかがいます、ちょっと行ってみます」
「おれもちょっと行ってくる」
「ああ、たのむな」
伊能は由井酒店の若旦那と毋母神社に向かった。
神社の下には消防車と救急車がとまっているが、消防車からホースがのびていない。
人が集まりかけている。伊能たちは石段をあがると、消防署の人が温泉のボーリングをしているところに集まっている。現場を取り囲んでいる幌の下から水がでている。
宮司さんがいた。
「どうしたんだ」
由井酒店の若旦那が声をかけると、安積宮司は「湯が噴出したんですよ、工事をしていた人にかかって、火傷しちまって、今、救急車に搬送するところです」
「よほど熱い湯だったんだ」
「百度近くらしい、まだゴボゴボでているんです」
そこに安部も駆け寄ってきた。
「湯がでたようですね」
「やっていた人が火傷したらしい」
「この神社の鳥居近くの黒皮がピンクになっていて、境内のは赤に近い色になっているんですよ」
足下の草の中の黒皮をみると、確かに赤に近かった。
「この茸、熱いと赤くなるようです、だから、ボーリング現場の茸がピンクぽかったんです、温度で色が変わるんです」
伊能はぴんときた。
「亜衣ちゃんが探し出した古文書は土の温度で色を変える黒皮の説明だったんだ」
「そうだと思います、それを見て、作物の出来具合などを占っていたのかもしれませんね」
「たしかに、そうですね」
伊能は安部が言ったことから、火山の噴火をこの村にいた人が察知できた理由がわかったと思った。
「毋母師の役割、毋母視小屋の役割がみえてきましたね」
伊能が言うと、安部もこっくりうなずいた。
怪我人が担架に乗せられて運ばれていく。
安積宮司が「容体はどうです」と救急車の人に聞いた。
「宮司さん、よかったよ、二人とも顔はやられていない、服が熱い湯にかかったから、切り取るのに時間がかかった、足や顔をかばった手がちょっと大変だが、命には別状はないようだ」
救急隊の話が二人の耳にも入った。
安部と伊能は反対側から社殿の裏にいってみた。ボーリングをしていたあたりの草原に生えてる黒皮は真っ赤だった。
「茸の本体は土の中ですからね、土の中の情報を茸は表に出すのですね、養分条件が十分なら茸も大きくなるし、きっと土の状態で形などを変えていると思いますけどね、茸の専門家に研究してもらいましょう」
「茸のそういう面を読むことができると、環境を知ることができるね」
「この村の毋母視は黒皮の色の変化で作物の状態を占った訳でしょうね」
「大昔は火山の噴火も予知できた、黒皮が赤くなったら人々は避難をした。だから、火山の噴火が盛んな時期にも、この村は生き残ったのだろうな」
「あの神社の裏の穴なんだけど、あそこに黒皮が生えていたんじゃないのかな、ご神体である毋母視山の温度を一番感じやすいところだろう、あそこの黒皮の色が、占い師である毋母視たち判断になったんじゃないかな」
安部が言った。
その後、伊能によって毋母視村にシェルターがもうけられるにいたった、歴史的背景を解析され、まとめられて学会誌に掲載され、神社の毋母視による黒皮の色の変化による占いと、それが黒皮神社にもたらされた経緯の研究がやはり学会誌にまとめられた。二人の博士論文である。
さらに、茸の学者による、茸そのものの研究で、新たな茸の性質が明らかにされつつある。
毋母視村は、京都の黒皮神社の地域と姉妹としになり新たな発展をとげている。
まだ毋母視村の名前に関しては、その由来があきらかにされていない。
奥沢親子による「きのこの語原店方言辞典(山と渓谷社、1998)」によるとナバは茸の古語でもあり、方言でもあるのだが、その語原はあきらかではないという。一説には南方の茸の呼び名からきたものというが、確かに方言としてナバが使われているのは九州など暖かい地方である。平安時代の「なばる=かくれる」が変化したという説もあるようだが、信州の山奥の村にどのようにつたわったのかわからない。
さらに「毋母」という字である。毋は、ないの「な」である。母は乳母では「ば」と読む。読み方はともかく、母は「はは」、毋は「禁止」ととらえ、黒皮を土の母とし、赤くなった母は、この地があつくなっていることを村人に告げた。それを判定しているのがいつも黒皮を見ている毋母視の役割だったのだろう。これはあくまでも想像である。伊能と安部は二人して調べを進めているところである。
どのような結論になるのか、いずれ二人から発表されるであろう。
毋母視村は研究とは関係なく、どんどん発展している。二人の結論がでると、それも毋母視村の宣伝に取り入れられていくであろう。村も生き物である、役に立つものはみな食べて大きくなっていくのである。
毋母視(なばみ)村


