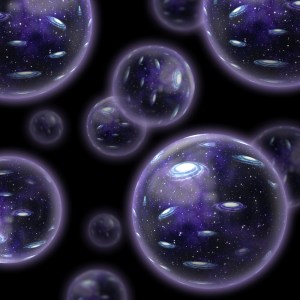第20話
1
ジェフ・アーガーの夢をみたメシア・クライストは、浮遊するベッドの上で目覚め、ここが巨大な都市であることを、窓の外、朝日に照らされる町並みを見て実感した。
これが夢ではないのか、本当はまだファン・ロッペンに追われているのではないのか。その疑念は拭いきれなかった。
ベッドから起き上がり、リビングへ向かうと、イラート・ガハノフは既に起床していた。
まだ大人になった、自分よりも年上になったイラートの姿に、なれなかった。
メシアがリビングに入ると、突然、彼の顔の周りに複数のホロスクリーンが現れ、膨大な情報と、聞いたことのない言語が耳に入ってきた。
何が起こったのか戸惑うメシアが顔を左右に振っても、ホロスクリーンは、顔を追いかけてくる。
「あ〜、すまない。ニュース設定が反応したようだ」
そう言うと、イラートは空中に向かって指を振った。
するとメシアの顔の前のホロスクリーンと、耳に入ってくる複数の言語が消えた。なにが起こったのか、未だに分からないメシアは、ただ呆然とするばかりである。
「星系のニュースを把握しとかないと、なにかと不便でな」
そう言うと、空中に浮かんだテーブルに紫色の塊を、透明な皿のような器に乗せて、出した。メシアはまさかと思いながら、身体に吸い付くソファに座り、
「まさか朝食か」
と、聞いてみた。この時間にテーブルに皿のようなものに乗っているということは、そういうことなのだろうと、メシアは推測した。
「この惑星の卵焼きだ。色は気味悪いが、味はタマゴだから心配するな」
というと次に見たことのない野菜のサラダや肉らしいものが乗った器を、腰ぐらいの高さの台から、取り出していた。冷蔵庫というわけでもないらしく、調理器具のようなものらしい。メシアにはそう見えた。
まずは朝食だ。
そう言いたげにイラートもソファに座った。
色の濃い卵を口に入れると、それは確かに卵の味がした。
その一口で、メシアは普通の食事を久しぶりにしているような気がしていた。あの終末の地球では、物を口にすると言うことはなかった。
時間の感覚はないものの、数日ぶりなのは確かなことである。あの酔ってマックス・ディンガー神父に水を求めたのが、随分昔のように思えて仕方がなかった。
イラートは普通通りに、肉を喰らい、卵を食べ、メシアの見慣れない野菜のサラダを口にしてから、青みがかった白い液体を、例のゴムのような入れ物から吸引した。
1人、食事をするイラートは、メシアの様子を口を動かしながら見た。手に持った、白銀のスプーンが進まないのは、理解できるから、あえて無理に食事を進めることはなかった。
ただ飲み物、青みがかった白い液体だけは、飲むように勧めた。
メシアは得体のしれない液体を口に入れると、牛乳に近い、それでいて牛乳よりも甘みの強い飲み物を、ゆっくり飲んだ。
それには栄養素が豊富に含まれており、まずそれだけでも飲んでおけば、1日のエネルギーはまかなえるので、イラートは勧めたのである。
食事のあと、汚れた食器類を、壁の金属に触れ口を開いた壁面へ、汚れたまま入れてしまった。もう一度壁を触れると、食器を飲み込むように、壁は閉じた。
食器を片付けると、イラートはテーブルを触れると、ホログラムがテーブルの真ん中に現れた。
それはこの惑星の地図であった。
第20話−2へ続く
2
まずはこの宇宙ついて知ってもらう必要がある。
イラート・ガハノフはそう考え、惑星から知ってもらうことにした。
「今、俺達がいる惑星はギントル。元は岩石や鉱石の採掘が盛んだった、銀河の中心部にある惑星だ。採掘時代に多くの人企業、人が流入してきたことで、またたく間に近代化が進み、ここ100年の内に、地面は金属で覆われ建物が建ち、その上にまた都市を建造して、また建物が建ち、と繰り返した結果、140万階層にもなる鋼鉄の都市が惑星を覆い、土は消えてしまった。交易が盛んになり、生産力がこの惑星の生命線となり、銀河の交易の中心ともなっている。
だが全てが順調ってわけじゃない。下方の階層には無法者が隠れ住み、治安が悪い。この惑星には180以上の国家、自治政府が存在するが、下のことはほとんど野放し状態にある。国境線があるのは上層階だけで、下方階層は自治も法律も国境もない。
お前が最初に落下したのは、無法地帯の本の数回に過ぎない。汚染物質が垂れ流しにされてるから、あのまま落下したら、身体が溶けて無くなってるところだでたぜ」
口早に説明するイラートに、なんとか頭はついていこうとするのだが、現実離れした惑星の構造と、壮大さに、呆然となるばかりだった。
説明に合わさてホログラムが回転するも、地理感覚がないので、どこがどうなっているのかも分からなかった。
「メシアに関係があるのはここからだ」
と、1つ呼吸を置いて、イラートはホログラムをチェンジした。テーブルの真ん中には惑星の代わりに、マークみたいなの細長い物が現れた。
「この印をけして忘れるな」
強い口調でイラートはメシアに言い放った。逆さまになった十字架の両サイドにさらにラインが入ったようなこの印。
メシアは何がこの印に意味があるのか、不思議に思った。
「メシア、お前は救世主だ。それは変えられないこどだし、どこの時間、空間に行っても、それだけは変わらない。ただ生きている生命体が皆、メシアを救世主と認めているわけじゃない。ファンのようにな」
ファンの最後の姿をメシアは脳裏に浮かべた。血みどろになりながら、自分を憎んでいた、かつての親友の顔を。
「この世界ではある宗教が宇宙規模で流行している。崇拝するのは『アリッタ』という闇の神。この世を闇から救うとされている。闇の神が闇から救う。おかしな話だが、宇宙のほとんどの生命体は信じている。厄介なのは、教団の教えに、【偽りの救世主現るとき、災い来る】ってあることだ。意味はわかるだろ」
メシアは納得した。つまりこの宇宙のほぼすべての生命体が、自分の命を狙ってく。
なんと言えばいいのか言葉に窮する事柄に、メシアは頭を抱えるしかなかった。
「アリッタ教団の信者数は数え切れない。国家が公用宗教として認めている国も多い。私設軍隊、政治団体、経済連合、金融市場にもおおきな影響を持っている。この宇宙を統一している教団って言ってもいい」
冷静に話すイラートは、教団のマークを変更して、今度はいくつものマークを表示した。
「もちろん体制に反発する連中もいる。真実、アリッタが闇の神としている、体制側からすると、反逆的思想だが、そういう思想を持っている連中も少数だがいる。ここに並べてあるのは、各教会の連合だ。教会連合、この宇宙でもっとも教団に反発している大きな存在だが、1つの組織というわけではない。あくまで、教会の集まりだ。
その支援を受けているのが反乱軍。武装組織を持たない教会連合が軍隊と共闘をしているってことだ。反乱軍は教団の私設軍隊から教団を信じない少数の連中を守ったり、軍隊が武力占領した地域を開放したりしている。だが規模では圧倒的に劣勢だ」
まるでSF映画の中の出来事のようで、メシアはため息を漏らすしかなかった。
「ここからが肝心なところだ」
といいホログラムをまた変更するイラートは、ある星系のホログラムを提示したのだが、メシアの知っている星星とは、妙に形が違っていた。なにかが星系を覆っているのだ。
黒い脈動する何かが奉仕のようなものを撒き散らしていた。
第20話ー3へ続く
3
何か生きているような、巨大な生命体に覆われているような姿がメシアには見えていた。
ため息混じりにイラートが説明する。
「これが惑星ゲートが属する【曇りの星系】だ。常に星系に存在するが惑星、衛生、恒星、合わせて278個が晴れることはない。誕生しておそらく40億年の恒星は、腐敗した膜に覆われ、恒星のエネルギーを吸収し、腐敗したこの黒い粘液のような物体が生存し、各惑星、衛生に触手を伸ばし、土壌を汚染し、植物も動物も生存できなくなっている。生存してるのはデヴィルズチルドレンだけ」
1つ息をして、イラートは続けた。
「預言者オルトはリーダーとなるニノラに何か詳しいことを授けていたみたいだから、俺も肝心なことはなにもしらないんだ。知っているのは惑星ゲートにメシア、お前を連れていかなくちゃならないってことだけだ」
メシアの胸が不安で高鳴り始めた。昨日までのあの光景が今も蘇ってくる。それに隕石から現れたあの化け物の群れ。マリアの手の感触。
そうだ、マリアを探さないと。
大切なことを思い出し、メシアは立ち上がった。
急なメシアの態度に、イラートは驚いてメシアの顔を、異様な恒星系のホログラム越しに見上げる。
「ソロモン、母さんと父さんに会わないと。ソロモンだ、イラート。ソロモンに連れて行ってくれ」
何を思い、メシアが立ち上がったのか、イラートはその言葉で察しがついた。
「残念だがこの世界にソロモンはない。そもそもソロモンがどこの宇宙からやってきたのかすら分からない。もし分かったとしても、次元を行き来する技術はこの宇宙じゃまだ発明されていない。恒星間移動は自由なんだけどな」
勢いよく立ち上がっただけに、座ることもせず、白い衣服で部屋の中を歩き回るメシア。
「なんにせよ、わざわざソロモンが連れていく、あれだけの科学技術がある組織が連れて行ったんだ、マリアは無事なはずだ。きっとなにかまた運命の何かがあるのさ」
気休めにしかならない。そう分かっていながら、イラートはメシアをとりあえず落ち着けようとした。
イラート自身、そもそもソロモンについて知っていることはあまりなく、メシアに与えられる情報も少なかった。彼がわかっているのは、科学技術でデヴィルに対抗している、どこかの宇宙の未来時間に存在している組織で、メシアを子供の頃、捨てた母親と父親が何らかの関わりを持っている、ということだけなのだ。
落ち着かないメシアを横目に、星系のホログラムを見たイラートは、マリアどころではない。メシアをどうやってここへ連れていくか、それを考えることで、頭がいっぱいだった。
この7年間、メシアを迎える準備はしてきたつもりだった。資金を貯めるために、様々な仕事をした、人脈も作った。この時代の、この宇宙の最先端技術は常に頭に入れ把握し、少しでもメシアが現れた時、役に立つように、運命を背負った【繭の盾】最後の1人として、メシアを守護するつもりでいた。
だが目的地がデヴィルズチルドレンの巣となると、どうした良いものか、準備をしてきたイラートも、腕組みして考え込むことしか今はできなかった。
「オルトなら、預言者なら、ソロモンのことを、マリアのことを、母さんのことを知ってるんじゃないか?」
考え込んでいたイラートへ、勢いよく、メシアが質問を幾つも投げつける。
オルトと話をしたというより、予言を与えやれた、宿命を背負わされたと言ったほうが正しく、やり取りをしたといえば、その通りなのだが、オルトからの一方的なものであった。
だからイラートには、この質問になんと答えて良いものか、頭を掻くしかできなかった。
「オルトのところへ行くしかない、ここへ向かうしかない」
答えを急いだメシアは即決して、この宇宙で最も危険な場所へ行くことを決めてしまった。
と、その時に室内を赤い照明が照らす。壁自体が赤く光っていた。
第20話-4へ続く
4
赤い光を見るなり、素早く立ち上がったイラートは、のっぺりとした壁に近づくと、掌で壁をなでた。
すると壁が口を開き、武器らしきものがぎっしり詰まった棚が現れた。
メシアは武器に詳しい方ではないものの、ゲーム、映画で見てきた物とは、明らかに形状が違っていた。しかしそれが何らかの武器であることは、イラートが手に持って、トリガーらしきところへ指をかけたことでわかった。
「俺がお前を見つけたってことは、奴らもおまえがこの時代、この宇宙に来たことを認識してるとは思っていたが、案外、早く見つかったみたいだ」
奴ら? 見つかった? メシアの脳裏に浮かんだのは黒い引き裂かれたローブとプロテクターの、グルズであった。
その予感はイメージというよりも、直感に近く、メシアの能力が覚醒しつつある証でもあった。
メシアの脳裏に写ったのは、建物の周囲を囲んだ黒いローブの集団で、近所に住んでいる人たちの、無残な姿までも、目の裏に写っていた。
必死に頭を降って、そのイメージを払いのけようとするが、建物を囲む連中が次第に獣のように姿を変えていくのが見ているかのように、メシアにはわかった。
イラートは、こんな時のための準備だ、とばかりに武器の詰まった棚に設置してある、青いスイッチを、拳で叩くように押した。
すると家が一瞬揺れ、外で無数の爆発音が聞こえた。
それと同時に、持てるだけの武器を持ち、ガンベルトをしたイラートは、入り口に手のひらを当てて開いた。
ライフルのような、流線型の武器の銃口で周囲を確認すると、グルズが家の周りから衝撃波で吹き飛ばされていた。
家自体が武器になっていたのだ。
「走るぞ」
イラートは周囲を警戒しながら、まだ室内にいるメシアに告げた。
「安全を確保するから、待ってろ」
そう言うと、ライフルの銃口を、弾きとまされた、獣に変化したグルズに近づき、頭にくっつけ、トリガー迷いなく引いた。
牙がむき出しになり、シワがより、石のような皮膚をしたグルズの皮膚を、陽電子が貫き、黒い血液ごと頭が蒸発した。
黒い血液が毒なのは知っている。ニノラ・ペンダースのあの苦しんでいる姿を思い浮かべながら、一匹ずつ、頭を消していく。
グルズを片付けたと、息を1つのついた時、隣合わせの金属の四角い家の裏から、隠れていたクルズが飛び出してきた。
銃を構える暇がなく、獣の巨大な爪がイラートへ突き出された。
その刹那、イラートは掌をを突き出し、稲妻を掌から放射した。
青白い閃光が空気を焼くと、グルズは地面にドサッと落ちた。しかしまだ生きていた。
それに向かい、銃口を向け、頭を消した。
「出てきていいぞ」
グロテスクな獣たちの死体と、犠牲になった近隣の人たちの遺体が、散らばる中に出たメシア。
また自分のせいで、関係ない人たちが犠牲になったことに、メシアは苦悶の顔を浮かべた。
「とにかくここを離れるぞ。お前を守るために、それなりに準備してるんだ」
というと、イラートは武器を片手に、足早にグルズの死体の間を抜けていく。
メシアも遅れないよう、必死に後を追った。
第20話-5へ続く
5
街は日が昇り、動き出していた。人々が働き出したというわけではない。ビル群自体が動き始めたのである。都市は住民が住む住居、四角いブロックを全面につけた、アーチや、複雑に絡み合ったビルなどがあり、それらにすべて、住居スペースがくっついた。
それが朝日に反応して音を立てながら動き始めている。それはまるで都市が呼吸するような光景だ。
数え切れない階層で、地面が見えない惑星の、一層下へ降りるには、様々な方法があるが、イラートはあえて階段を選んだ。
酔っぱらいやジャンキーが鋼鉄の地面に突っ伏した朝方の貧民街の路地を、イラートは慣れた様子で抜けていく。
途中、丸く、肉の塊としか形容できない、女性の異星人に、誘われた。客引きらしいが、地球の言葉ではないのにメシアは、理解できていた。
イラートは誘い文句を軽くあしらい、小型のホログラム広告が並ぶ、日の当たらない路地を行け、ようやく目的地に到着した。
そこは向かい側の住居がびっしりとくっつく鋼鉄の壁と、こちら側の壁が平行に並ぶ、巨大な人工の谷であった。
メシアが横を見ると、先が見えないほど、他には続き、空飛ぶバイクや、車が時折、谷をすり抜けていった。
イラートが促すように唖然とするメシアを連れて行くと、頑丈な鋼鉄の門でどぞされた場所に到着した。
門の大きさは3メートルほどで、横幅が5メートルと地の規模からしたらそこまで驚く大きさではない。
門に近づいたイラート。するとホログラムの端末が現れ、番号を打ち込まないと門の、鋼鉄の筒は動かず、開かないらしい。
するとイラートは、銀色の指が出るグローブを左手にはめて、端末にグローブをかざした。と、ホログラム端末はノイズが入ると自然と番号の色が変わり、ロックが解除され、門を横に貫き扉を締めていた筒が、左右に別れ、門が自動で開いた。
グローブを外しながら、イラートは軽く微笑んだ。
「緊急事態だ。違法行為も仕方ないさ」
やはりハッキングしたのか、とメシアはイラートの微笑みを見た。
その視線が開いた門の奥に移されると、白銀の階段が、空中に浮かんでいた。
ここを降りるのか。メシアはそう言いいイラートを見つめた。
「急ごう」
ライフルを担ぎ、先になんの躊躇もなくイラートは階段を降りていく。眼下はそこが見えない高さであった。
第20話-6へ続く
6
高いところが苦手なわけではないが、流石に下の見えない、壁面にへばりついた階段を降りるメシアの脚は、震えていた。
イラートは軽々と階段を降りていくが、メシアの額には嫌な汗が滲んでいた。
そんな彼に関係なく、空飛ぶトラックが列をなして横を通り過ぎていった。
そのまま階段が抜けるかと思いながら、何度かそんな経験を繰り返し、ようやくさっきの階層より、1つ下の階層にたどり着いた。
ホログラムネオンがひときわ目立つ、光の届かない下の階層は、柱のように、住居区画がくっついている、ビルが宮殿のように、どこまでも続いていた。
その足元には、貧民民街らしく、労働車たちが仕事に出かけるところがであった。
まるでロボットのように、空飛ぶトラックの前に並び、ロボットが列を整理していた。並ぶ労働者の人種は様々で、ヒューマン型の種族、肌の色が鮮やかな人種も居れば、昆虫のような人種、軟体動物のような人種、機械の雲のような足で運ばれるガラス管に詰まったスライムのような種族まで、多彩だった。
それを横目に、イラートが進むのに遅れまいと、メシアは小走りになる。この区画では、武器を所持していても、誰も注意するようすもなく、変な眼で見る様子もない。
ホログラムの、何語なのか分からない広告や、性別不明の異星人の広告、空飛車やバイクの広告が、そこら中でにぎやかに光っていた。
陽光が入らない海藻だけあって、上の階層の床、そのにも住居がびっしりとくっついていたが、その間に、巨大な照明器具があり、街を照らしていた。
行き交う人々の中を歩いていると、メシアは様々な声を耳にした。きっと他の人には聞こえない小さな音ですらも、彼の耳は拾い上げていた。
身体的にも何かが変わりつつあるのをメシアは感じつつ、イラートにこの異変を知らせたくても、知らせる暇もなく、イラートは先を急いでいた。
大通りから路地に入ってすぐ、ジャンキーの異星人たちが地面でぐったりしている中に、ネオン管でわからない文字が書かれた店があり、その鋼鉄の、半分錆びたドアが、イラートに反応してスライドした。
頭に入ってくる音を遮断したいメシアは、両耳を抑えて、店へ駆け込んだ。
第20話-7へ続く
7
そこは酒場だった。
アルコールの匂いと、異星人たちの陽気な様子、中央に浮遊するカウンター。ひと目見ただけで、メシアにもわかるほど、見た目が普通の酒場と変わりなかった。
慣れた様子でイラートは人混みをかき分けて進む。もちろん銃器を持っていようと、客たちは気にしない。
メシアが異星人の夜会に唖然としていると、背中に柔ない何がかあたった。振り向くと、そこにはブヨブヨに贅肉なのかあるいはそういう種族なのかわからないが、まんまるに近い4足歩行の異星人が、入れない様子で、明らかにメシアに怒りの言葉らしきものをぶつけてきた。
言葉はわからなかったが、その威圧感に圧倒されました、酒場の入り口の階段を急ぎ降りて、独特の強いアルコール臭と、タバコなのか、ヤニっぽい臭いのする中を、イラートの背中を追い、進んでいく。
カウンターの前まで、ようやくたどり着いたメシアは、イラートが、だれかと話しているのを眼に止めた。誰なのかイラートの身体で見えないくらい、小柄らしい。
彼の肩越しに、話している相手を除き込み、メシアは眼を見開いた。そこには浮遊するカウンターの椅子に座る、小さい二足歩行の猫のような生物がいた。だが猫と違い毛がなく、灰色の皮膚がむき出しになっている。
一応、ヒューマン型の生物らしく、猫のような口を開き、メシアの知らない言葉を、流暢に喋っていた。
喋るたびに、頭の上にある4つの耳はがピクピク動くのだった。
イラートは言葉がわかるらしく、彼は普通にメシアの理解できる言葉で話していた。
「時間が惜しい。予定通りに出発する」
これに猫のような口をたくみに動かし、エイリアンは否定的なことを行っているように、メシアには見えた。
その見え方は正しかったらしく、イラートは少し憤慨した様子でカウンターに拳を叩きつけた。
「いつでも出発できるようにしてろって言っただろ。前金で支払ってるんだ、仕事はしてもらわないと困る」
猫ような大きな眼を瞬かせ、エイリアンは一瞬だまり感だが、また何かを口にした。
それを聞いたイラートはため息混じりに立ち上がる。
「お前が来るときの為に、用心棒を雇っておいたんだが、どうやら酔っ払ってるらしい」
そうメシアの肩に手を置いて言ったイラートは、そのままもう片方の手を上げて、バーの奥を指差した。
そこには1人の女性が浮遊する大きめのソファに腰掛け、両脚をテーブルに投げ出し、周囲からアルコールらしき液体を飲んでいた。
しかしそうした粗暴な態度よりも、メシアが驚いたのは、両腕が金属製の機械の腕だったことであった。
第20話-8へ続く
8
女に近づいていったイラートは、ため息混じりに、さっきエイリアンに言ったことと同じことを口にした。
「いつでも出発できるようにしてろって言ったよな」
ベリーショートの髪の毛の女性は、40代くらいにみえる、人間だった。鉄板のついたタンクトップを着て、そこから出る両腕は、金属の骨の周りに金属の部品がついた、向こう側が透けている腕をしている。
腕を動かす度に勤続の音がして、丸い球体からアルコールをすするその、軽くシワの入った顔には、よって入るものの、鋭い眼光があった。
「あたしが何をしてようが、あたしの勝手だろ」
自分を正当化する素振りを見せる女性は、そう言うと緑色のまんまるな異星人のバーテンに、さらにあるコールを、メシアのわからないことばで注文した。
「前金は払ってるんだ、仕事をしてもらわないと困る」
これがイラートの準備であった。とこほが予定通りには行かないものである。
イラートが頭をかき苛立ちを顕にしたその時、バーの入り口の方で、騒ぎが起きた。
酔っている客たちが3人倒れ込み、入り口に、店獣の視線が集まる。そこには黒いプロテクターで全身を覆い、胸に逆さ十字に似た紋をつけ、真紅のマントを翻しながら、顔には紫色のゴーグルをつけ、手にイラートが持っているのと似た形のライフルを構えた、男女が殺到してきていた。
バーの連中が口々に、教団だ、教団の兵士だ、と言って
後ろに下がっていく。
不思議とメシアは聞いたことのない言葉なのに、理解できていた。
「教団の兵士が、こんなとこまで来るとは、よほどのことだね」
酔っ払った女が口にすると、イラートはライフルのトリガーに指をかけた。
それを見た女は、イラートたちが追われているのだと察し、渋い顔をした。教団と関わりたいと思うのは、教団に加入している連中だけで、それは決まって富裕層である。こんな陽光も届かない階層にいる人間たちが、教団に入信しているはずもなく、教団ともめるのは、誰も望まないところである。
彼女は特に教団とは関わりたくなく、依頼人が教団から追われているとなると、関わるしかなく、そのことを怪訝に思っていた。
教団の兵士たちが、酔っぱらいたちをかき分けて、押し飛ばしバーの中には入ってこようとする。
するとイラートは振り向きざまにライフルを乱射、先頭を来る兵士を撃ち抜いた。
それと同時に足元から稲妻を発し、バーノ電源をショートさせ、室内を暗くした。
イラートは装備の中から暗視メガネを取り出し、素早くかけると、混乱する酔っぱらいたちに、行く手を遮られる兵士たちの混乱ぶりをみた。
同時に横のメシアも、混乱しているのを落ち着かれる様子もなく、腕ん掴み、強引に引張り、バーの裏口へかけて向かう。
自動ドアが電源のショートで動かないのを、触ってドアノブ電源だけをオンにして、イラートはバーの外へ出た。
異星人たちの行き交う人混みに出た2人。
「教団とやり合うなんて、聞いてないぜ」
メシアが何が起こったのか分からないでいると、後ろから腕が機械の例の女性の声が聞こえてきた。
振り返ると、女性の後ろには猫のようなあの異星人の姿もある。
バーの裏には浮浪者やジャンキー、酔っぱらいの異星人が、ぐったりして細い路地の壁に背なかをもたげていた。
左右を確認すると、薄暗い路地を右にイラートは方向を決め、メシアを先に行かせ、バーから殺到してくる教団の兵士に銃口を向け、光を何℃も撃ち放った。
すると騒ぎを聞きつけたのか、バーの入り口で待機していた兵士が、路地へと殺到してきた。しかし路地は人が1人通れるくらいの幅しかなく、先頭を来る兵士は、ライフルを構えて、乱射してきた。
と、両腕が奇怪な女性が素早くバーから出てきて、迫るビームを腕で素早く払いのけた。
これに間髪を入れず、猫のような異星人がハンドガンのレーザー銃をガンベルトから抜き、兵士の額を一撃で撃ち抜いた。
第20話-9へ続く
9
後で銃撃の音がする中、イラートの逃げろ、という叫びに背中を押され、必死に前へ進むメシア。
配管から垂れた水滴が乾くこともなく、水たまりになった場所を踏みつけ、左右で手や触手を伸ばすエイリアンのジャンキーたちには目もくれず、路地の先が見え、大通りに出た。
そこは飲食店、露天が並び、エイリアンたちがなにかもわからない、ゼリー状のもの、巨大な虫のような物、触手がうねる小動物を丸呑みしたりしていた。
そんなことも知らず、メシアはどこに逃げるべきなのか、脚を止めた。知らない街、ましてやエイリアンが文化を築く世界で、彼が頼る相手もおらず、どうやって逃げればいいのか、分からず、周囲を見回した。
すると知らないエイリアンの言葉なのに、耳に入ってくる言葉たちは、なぜなのか理解できていた。何故、言葉が理解できるのか、言葉が分かるのか、自分に何が起こっているのかわからないまま、困惑するばかりのメシアの耳に、
「居たぞ」
と、声が強調されて入ってきた。声の方を見ると、教団の兵士にたちが銃を構えて向かってきていた。今にもトリガーを絞ろうとしている。
とその時、メシアの右の顔の横を、なにか高速で物体が複数飛んでいき、3人いた兵士たちの額を貫いた。
膝から倒れた兵士たちの1人の額に、そのエイリアンの分厚い脂肪のせいか貫くことができなかった、鋼鉄の串が突き立っていた。
メシアが後ろを振り向くと、タンクトップの女が立っており、鋼鉄の右腕を前に突き出し、手首の左右から銃口らしき物語出て、煙が銃口から揺らめいて上がってい。
鋼鉄の串を発射したのは女であった。
役目を終えた銃口は腕に収納され、女はメシアに近づいてきた。
「あんたに死なれちゃ困るんだよ。前金で依頼を受けてるからね」
女は通りに出て、猥雑な通りを見回し、警戒心の糸を張り巡らせなが、
「あたしはコールド。あんたの用心棒さ」
第20話-10へ続く
10
猫のようなエイリアンは、コールドの長い付き合いで、トクタリアンの相棒ジントだと、合流してから説明を受けたメシア。
この世界では名字はない、とポツリとイラートが銃口の充電パックを回してトリガー、円盤状の別の充電パックを、ライフルの側面へ装着しながら言った。
「プランは?」
ジントがトクタリアンの言葉で、イラートに尋ねる。
メシアには完全に分からないはずの言葉を聞き取れていた。これも変化の兆しなのか、と自問するメシア。
その戸惑いもよそにイラートは周囲を見回した。
「シャトルベイに向かいたいが、どうやら反対側に出ちまったみたいだな」
苦い顔をしてイラートは、今来た路地を一瞥する。戻ったところで教団の連中が待っているのは明白だった。
「迂回するしかないね」
コールドは機械の指で頬をかきながら言った。しかしそれがどれだけ大変なことなのか、コールドも理解しての発言だ。
エイリアンの人混みを見ながら、イラートは少し考えていた。なにが最善か。彼の計画はもうすでに破綻しかけている。オルトにメシアが現れる日時を聞いてて、準備してきたことが、無駄になりそうになっているのだ。焦りは、凄まじいものがあった。
「とりあえず移動だ。ここにいると危ない」
そういうと、イラートは率先してエイリアンの行き交う通りに入っていった。
「よそ見してると食われるからな」
冗談のつもりなのか、本気なのかジントはそういうと、先にイラートの後ろを追った。
「絶対に離れるんじゃない」
そういうと、コールドはメシアの胸を軽く金属の指で叩き、先に行く。
異世界に迷い込んだ、アリスのごとく、メシアはうさぎについていくように、コールドの後を追った。
第20話-11へ続く
11
そこは人がいられるような場所ではなかった。
紫色の炎があちこちで燃え上がり、巨大な大聖堂の中のようなのに、柱も壁も黒い粘度の高い黒い液体が常に流動し、牙をむき出した口や目玉が無数にその液体の中で現れては消えていくを繰り返している、異様な空間だった。
広い空間の、柱が並ぶ異様な世界の真ん中に、黒い液体でてきた、流動する椅子が玉座のようあった。大きさは500メートルは超えている。人が座ると言うには、あまりに大きすぎた。
そこには2つの影があった。黒い粘液の椅子に、座っているというよりも、この空間のすべての粘液、口、目玉、怪物のような爪がその座っていると人物から溢れ出ているようだった。
黒い2つの影、椅子に似合う巨体は、背中がつながった、骨ばったミイラのような、異様さ出てくるわけで、人間の姿に見えるが、干からびた腕は12本あり、同じく黒く干からびた足は16本ある。頭は2つしかないが、ほぼ頭蓋骨に近かった。
その化け物の住処に、浮遊する円盤に乗り、2人の人物が聖堂の中央へ近づいていった。
2人とも胸のところに逆さ十字に似た、教団のシンボルの入ったローブを着ている。
1人は触手に眼がついたような、緑色の軟体生物で、ローブの下からいくつもの触手、上からはいくつもの眼が先端についた触手が出ていた。
もう1人はペンキで塗ったかのように、不自然に白く、スキンヘッドに機械のゴーグルをつけた人型種族である。
触手だらけのテファリアンがまず最初に頭を、うやうやしく下げる。と言っても、触手だらけなので頭がどこかは分からない。
次にペンキで塗ったような白いサイダリン人が、スキンヘッドの頭を下げた。
この2人こそが教団の全権を掌握する2人の枢機卿であり、彼らの意見こそが、この5700億光年もある大宇宙に広がる、アリッタ教団の方針を決め、私設軍隊を動かし、教団を支持すら国家をも動かすのであった。
しかしこの2人ですら、権力も力も及ばない存在、教団の本当の主の前では、頭を避けることしかできなかった。
「救世主は予言どおり現れましてございます」
サイダリン人の言葉で、目の前の異形の黒い巨大な生命体へ告げた。
すると2つある黒い頭が、同時に、耳まで裂けた口を広げたい。
「預言は正しい。疑うことなく従うのだ。偽りの救世主は、災を宇宙へ振りまく。阻止せよ、阻止せよ」
二重になった、粘液と、目玉と口が流動する聖堂内に、異形の声は響いた。
「アリッタ様の仰せのままに」
今度は触手だらけのテファリアンが、テファリアン語で答えた。
そう彼ら枢機卿の目の前にいる、禍々しい異形の化け物こそが、闇の神、アリッタ教団の信仰の対象、アリッタ神そのものであった。
2人の枢機卿は報告だけすると、またうやうやしく頭を下げ、乗った浮遊円盤が移動して、聖堂のヌメヌメとした巨大な出入り口から出ていくのだった。
第20話-12へ続く
12
人、生命体が唯一、足をおける、星系内の別の聖堂は、石組みで建設されていた。
だがその下には黒い粘液と流動する目玉、口、怪物じみた生命体が現れては消えていた。
「まったくいつまで経っても、なれることがないな」
枢機卿の1人、白いペンキを塗ったような皮膚の、ヤーグが機械のゴーグルを外しながら言った。それを手にしながら、触手だらけの相棒へさらに言い放つ。
「このゴーグルがなければ、アリッタ神を直視すらできぬのだからな。神とは恐ろしいものよ」
しみじみというヤーグヘ、触手の中から声が走った。
「我らは神に救われたのだ。信仰心を捨ててはならない。例え、直視してその眼が焼けて溶け落ちようとも、信じる心をなくしてはならぬのだ」
そういう触手の生命体は、神を直視できる眼を持っているので、平気だった。
ヤーグ、触手の種族エッカに向かい、広い石造りのホールの中に並ぶ、石造りの長椅子の1つに腰掛け、緑色の瞳で逆さ従事のような、ホールの一番奥にある、崇拝の対象にして、教団の象徴でもある、シンボルを見つめながら言う。
「偽りの救世主を早急に始末する、目下の目的」
「エリスからの報告では、アリッタ様のお言葉通り、発見したそうだが、保護するものがいたらしく、取り逃がしたとの報告が上がってきている」
私設軍隊の通称、アリッタ教団の守護者という意味をもつエリスの名前で軍隊を示しながら、触手の中から、声が響いた。
「あの惑星は表層なら見つけやすいが、140万も都市階層があるからな、下に潜られれば、エリスでも探すのは難しくなる」
外したゴーグルを金属の、装飾された箱の中の、赤いビロードに包まれたクッションにはめ込み、箱の蓋を閉じながら白いスキンヘッドが言う。
「その為の信徒だろ? どんな職業、種族であろうと、我らは拒まない。神はすぐそばに居られる。信徒へ向けて、手配情報を流す。あの惑星の奥底にも届くようにない」
触手の中からそう言い、早速、ホロスクリーンを現出させ、情報を調べた。そこにはメシアの、惑星逃げている画像が大きく映し出されていた。
第20話-13へ続く
13
日雇いのエイリアンたちがシャトルに乗る列を作る横を、イラート・ガハノフを先頭に、一行は広い人工照明が照らし出す地下都市を、その湿度の高い空気を吸いながら、前へ進んでいた。
広大な室内にも見えるが、しかしビルで支えられた天井を行き交う、浮遊する車の列は、外へつながる、吹き抜けの惑星の割れ目から上空へ飛び出していた。
エイリアンの人混みを進む一行は、更に人の多い広大な空間に出。
陸橋が入り組み、下の階層まで抜けている、丸い縦穴のような都市構造をしていた。穴を縦に登ってかる車や逆に陸上から、縦穴に入っていく車が、大量に行き交っていた。
車道4車線ほどの幅がある陸橋を、たくさんの種族が行き交っていた。
圧倒されるメシアに、後ろから来た4足歩行で、紫色の体毛だらけのエイリアンがぶつかり、何やってんだ、と言い捨てて目の前の広い階段を降りていった。
言葉は耳では何を行っているのかわからないが、頭では言葉を理解する、不思議な感覚にメシアは包まれていた。
「止まってると見つかっちまう。早く開くぞ」
コールドがメシアの腰を軽く押して、階段を降りるように促した。
陸橋につながる広い階段は、エイリアンが行き交っている。イラートは後ろを気遣う余裕もないのか、階段の左右、広大な空間に警戒の視線を走らせ、どこにでもいる教団の信徒が、いつ向かってきてもおかしくない状況を、想定していた。
メシアは促されるまま、鋼鉄の階段を降りていく。
階段は整備が行き届いていないのか、ところどころサビが浮いていた。地下世界が地上世界と違うのが、そういうところを見ると、メシアにも貧困の差があるのだと理解できた。
階段を駆け下り、陸橋に降りると、鋼鉄の長い陸橋がメシアの前へ広がった。
と、妙な感覚にメシアは包まれた。前からくる複数のエイリアン、身体が螺旋状になった、浮遊するエイリアン、蜘蛛のような虫のエイリアン、背中にうずまきのある甲羅を背負った、ヌメヌメとした蛇のようなエイリアン、腕がやたらと巨大な機械の腕をつけた人間の集団が、周りと変わらないように普通に歩いているのに、メシアにはなにか眼が離せなかった。それに黒いモヤのようなものが彼らから吹き上がっていた。
それが自分にしか見えないのは、なんとなくわかっていた。
メシアが足を止めると、またコールドが嫌気が差したように、
「前へ進むんだよ」
そう言うがメシアはこれ以上、前へ進むと危険なのが本能的に分かっていた。
その時、螺旋状の皮膚が茶色で、どこに眼や口があるのか分からないエイリアンが回転を始めた。
周囲を歩くエイリアンたちも、何事か、とその場を足早に離れ、メシアたちの後ろから来る人混みは、足を止めて状況を見ていた。
するとメシアの脳裏に血しぶきが見えた。
「全員、伏せろ」
とっさにメシアは叫んでいた。自分も叫ぶと同時に鋼鉄の、立証に伏せた。
何がなんだか分からないコールドと相棒の猫のようなエイリアンも、耳をたたみその場に伏せた。
前を歩くイラートもメシアの声に疑いもなくその場に伏せる。
刹那、空中に浮いている螺旋状のエイリアンは、回転を早め、光線をその身体から360度、全方位に向けて放射した。犠牲など考えてもいなかった。
光に触れた通行人のエイリアンは、身体が痺れたようになりその場に倒れ、痙攣したあとは絶命したのだった。
これにはパニックが起こり、大勢の聞き慣れない言葉の悲鳴が上がり、陸橋から人が逃げ出していく。
第20話-14へ続く
14
悲鳴の中、螺旋のエイリアンは回転を続けた。
伏せていたイラートがライフルを向け、乱射する。
イラートの光線は螺旋の回転を少し弱めたが、まだ回転が続いていた。
するといつ光線の放射が起こるのか分からない中、コールドが立ち上がりその勢いのまま走り出すと、右腕が肘のところから開き、ビームサーベルが現れ、走る勢いままサーベルを回転するエイリアンに突き立てた。
エイリアンは自転で突き刺さったカーベルで、自らの身体が斬れて、ようやく回転が収まり、その場に鮮やかな黄色い蛍光色の血しぶきを流して倒れた。
大きく息を吐くコールドは、サーベルを腕から消し、開いた腕をもとに戻した。
その時、メシアの脳裏にまた危険なビジョンが見えた。
「避けろ」
メシアが叫んだ瞬間、蜘蛛ようなエイリアンが体毛を逆立て針のようになり、その状態でコールドに突進してきた。
毛針を機械の腕で抑え込むが、蜘蛛のようなエイリアンは、凄まじい力で、コールドを押していく。
すると巨大な機械の腕をつけた、ゴーグルで眼を覆う男が空中に飛び上がると、その腕を振りかぶり、コールドめがけ振り下ろした。
両手がふさがったコールドが押しつぶされそうになった刹那、光線が空中の男を撃つ。
円形のエネルギーパックを交換して、ライフルを構えるイラート。
しかしイラートの銃撃で皮膚がめくれ上がった男の身体の下には、金属の骨格が見えていた。巨大な腕を金属の陸橋に叩きつけ、男は立ち上がり、今度はイラートめがけ、殴りかかってきた。
するとイラートは掌をゴリラのような男にかざし、青白い稲妻を放った。
金属の強化骨格をつけている男は、稲妻に身体の身動きを奪われ、ロボットのように停止してしまった。
くそったれ、と動かないことに人間の言葉で叫んだ男。
その口にイラートは素早く銃口をねじ込み、トリガーを引き、頭を吹き飛ばした。
そのままネジ巻きの甲羅を背負ったナメクジのような、巨大なエイリアンに銃口を向けて、トリガーを引こうとした。
「撃ったらいけない」
慌ててメシアが叫んだ。
また哀れみか、とイラートが心中で舌打ちした時、それがメシアに聞こえたように、答えた。
「その種族は甲羅の中に大量の毒物が詰まってる。撃ったら皮膚から毒素が漏れる」
見たこともない。生体を知るはずもない生物の特徴を、メシアははっきりと言い当てていた。
銃口を離すと、静かにその生物から離れた。
するとネズミのようなコールドの相棒が、その豊富な知識からメシアの言葉を補足した。
「ダントライサ銀河の辺境にある湿地帯の惑星に住む種族だ。毒素が血液として流れているのは間違いない」
この会話の間も、毛針となった蜘蛛のような種族に迫られるコールドは、機械の腕に力を入れ、なんと自分の倍はある蜘蛛を持ち上げると、陸橋の外へ投げ飛ばして、そこの見えない縦穴へ落としてやった。
「殺さない代わりに、苦しませることはできるさ」
そう汗をかいた40代の女性は、タイトな黒いズボンのベルトから、金属製の箱を外し、中から吸盤のような透明なものを取り出し、ヌメヌメとした種族の顔と思われるところへくっつけ、箱のスイッチを押した。
すると甲羅まて硬直したように生物はしびれているのが、メシアにもわかった。
鋼鉄の指をスイッチから離し、電流を弱めると、イラートが代表して聞いた。
「俺達をなんで狙った」
そう言いつつも自分たちを狙う者の見当はついていた。
カタツムリのようなヌメヌメとした、四肢と呼べるかどうかわからない物をバタつかせ、口のような穴から、声が漏れてきた。
「教団のために」
そういうと背中の甲羅の色が緑色に変色し、水分のあったエイリアンの身体が、急激に乾燥して、縮んだ。
それが何を意味するのか理解したコールドは、吸盤を取り外し、装置に戻すと、腰のベルトへ装着した。
イラートも銃口をエイリアンから反らし、エイリアンの死を理解した。
おそらく体内に何らかの毒物を仕込んでいたのだろう、教団らしいやり口だ、とイラートは心中で呟いた。
「こいつらも教団の兵士」
唖然とするメシアが呟くと、イラートが無残な死骸を一つずつ一瞥して、首を横に振った。
「いや、ただの信徒だ。盲信者ってやつだな。末端の信者まで襲撃してくるとなると、ますます急がないと、命が星の数あっても足りなくなる」
そう言い、イラートは先を急ぐようメシアを軽く急かした。
信徒の遺体をそのままに、何事かと集まるエイリアンの野次馬の中を抜け、さらに一行は下の階層を目指す。
第20話-15へ続く
15
ジャンキーや異形のエイリアンたちの姿が顕著になってきていた。
入り組んだ鋼鉄の陸橋を渡り、階段を降りていくと、空気が違うのをメシアは肌で感じた。さっきまでいたエイリアンたちとは、明らかに雰囲気が違う、刹那的な快楽に溺れている連中が、陸橋の壁に持たれかかり、ぐったりとしている人数が増えていた。
エイリアンだから正常な状態がどういうものかメシアにはわからないが、なぜだか負の感情、枯渇する欲望、快楽への欲求が見えるように、感じられた。
イラートはそうした連中のことなど気にせず、先を急ぐ。
すれ違う人々もここまで降りてくると、武装している人々が多く、危険なのがすぐにわかった。
陸橋を抜けたところに、大きなゲートがあり、イラートはそこへ入っていく。
きっと検問所の役割を果たすものなのだろうが、故障しているのか、武器を持ったイラートが光の膜を抜けても反応しなかった。
ゲートを抜けると、そこは大きな街になっていた。もちろん上の階の天井があり、巨大な照明器具が天井から街を照らしていた。
エイリアンたちは生活しているらしい。しかしその生活水準は、明らかに地上とは異なっていた。華やかなビル群の違い、建物に無理やり居住区をくっつけたような、いびつな建物が並び、それが柱として、天井を支えていた。そこにいるエイリアンたちには覇気がなく、怯えているものまでいる。
目立つのは肉体に改造を施した連中が多いことである。メシアはこういった世界を見るのは初めてだが、明らかに身体のサイズとあっていない腕をつけていたり、頭が半分、メッキだったりと、正規ルートで改造したとは思えない連中に、眼を自然とそらしていた。
街の環状線と思われる広い鋼鉄の道路を進む一行だが、車が走る気配すらなく、ゴミで荒れ果て、武装した連中が、自らの縄張りだと言いたげに、そこら中でたむろっていた。
イラートの武器のおかげもあるのか、近づいては来なかったが、針のような視線は、よそ者である一行に突き刺さっていた。
メシアにも嫌な雰囲気なのはわかる。なるべく眼を合わせないように、イラートの背中だけを見て進んでいった。
すると環状線をある程度、進んだところに分かれ道があり、巨大なエレベーターにつながる道が現れた。何十台と車が乗れる巨大なエレベーターである。それが複数、並んでいた。
見たこともない巨大なエレベーターに、メシアが唖然としていると、コールドがベーター横のホログラムに手をスライドさせた。
すると錆びついた機械の音がかな切り声をを上げ、巨大な鋼鉄の扉が開いた。
するとイラートが銃を乱射した。
何事かとメシアが眼を見開いた時、エレベーターにはぎっしりとロボットが詰め込まれていた。しかもその胸には、教団のシンボルがデカデカと刻印されていた。
第20話-16へ続く
16
イラートの攻撃で一体は破壊できた。しかし数が尋常ではない。広大なエレベーターいっぱいに、出荷される荷物のように、整列して敷き詰められていた。
唖然とするメシアの真横を、何かが凄まじい速度で通り、整列したロボットの中央に落ちた。すると爆発が起こりロボットの部品が、四散した。
メシアが振り向くと肘から下が折れ曲がり、二の腕に装着された筒から、煙が上がっていた。それを見てメシアは何かの爆発物が発射されたのだと理解した。
ぶら下がった腕をもう片方の金属の腕で持ち上げ、コールドは外れた腕をはめ込み、掌を開閉し、装着感を確かめると、走り出し、爆発でよろめいたロボットの頭部を、金属の拳で殴りつけた。
イラートは銃のエネルギーパックを交換し、ビームを乱射し続けていた。
しかし数が多すぎた。細い金属製の四肢を動かし、前進してくるロボットの群れは、腕に火炎放射器を装着しており、炎の一斉掃射を開始した。
イラートが炎に呑み込まれると思ったメシアは、炎の津波を防ぐ透明な壁が現れたのに気づいた。
イラートの装備とも、炎の津波の外でロボットを殴り飛ばすコールドの腕のギミックでもないのを見て、次に猫のようなコールドの相棒を見ると、彼が両手を上げ、力を入れ入れているのを見た。
このトクタリアンは超能力者だった。トクタリアンにそういった能力があるわけではない。人よりも身体能力は、3倍ほどはある。だがシールドを展開する能力などはなく、ジント特有のものだった。
「あたしがただのトクタリアンを相棒にするわけ無いだろ」
ロボットの頭を金属の拳で砕きながら、得意げにコールドは言った。
ジントは見えない壁で炎を押し返して、ロボットの群れを逆に燃焼させ、耐久温度を超えたロボットは、次々に自滅していく。
だがそれも一部のロボットだけであり、前進を止めることはできず、感情もないため、同類のロボットが破壊されようとも、振り返りもせず、腕の銃口をメシアへ向けて、乱射してくる。
ジントのシールドが防いでいるとはいえ、広範囲をカバーできているわけではなく、メシアのところへいくつもの光が飛んでくる。
幸い、メシアへの直撃はなかったが、いつ直撃しても不思議ではない。
隠れようにも、周囲には何もなく、開けたエレベーターフロアで、メシアは立ち尽くしていた。
イラートは銀色の筒状になったプラズマグレネードを、ロボットの群れへ投げつけ、爆発する中でメシアへ逃げろと叫ぶ。
しかしメシアはなにか不思議な感覚になっていた。周りがゆっくり動いていて、自分だけが時間の違う場所に立っているような感覚。それになぜだか自分ならばロボットを停止させられるような気がして、ロボットの群れへ向けて手をかざした。
手に力を込めた瞬間、掌から何かが放射された気がした。
するとロボットな群れが動きを一切止め、炎も、ビームも、格闘戦も停止し、鉄の塊になってしまった。
イラート、コールド、ジントが何が起こったのか、それぞれロボットとの戦闘を停止し、呆然とした。
何もできないと思っていた、人間の男がロボットの群れを停止させたのだから、状況がわからないのは、当然である。
これも覚醒への前兆か、とイラートがメシアに近づこうとした時、メシアはその場に崩れるように倒れてしまった。
第21話-1へ続く
第20話