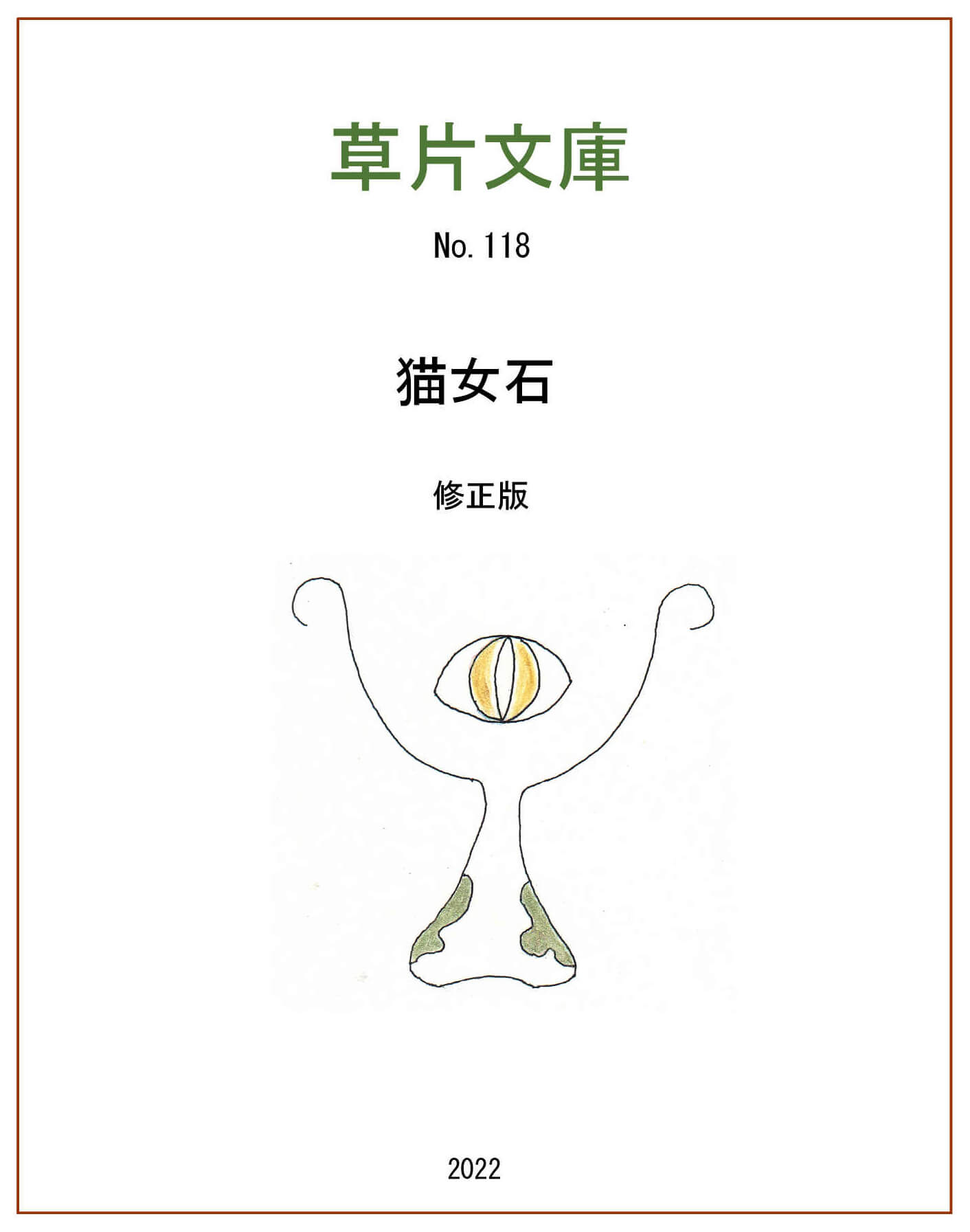
猫女石(ねこめいし)-第四探偵小説(最終)
殺人のない、長編探偵小説です。縦書きでお読みください。
猫女石 目次
猫女石プロローグ
猫の骨
猫の交通事故
猫の輸入
キャッツアイ
宙夜の報告
国際宝石展
山梨の宝石職人
野霧の本
キャッツアイの正体
猫女石の正体
猫女石エピローグ
おわりに
猫女石 プロローグ
動物は生きるために餌を探し、種を残すために相手をさがす。動物は遺伝子により脳にそのような機能を発達させる。ところが生きる、子供を残す本能だけでは、人間の発達した脳は満足しないように進化した。絵を見、音楽を聴き、または自分でそれらを作り、エネルギーが大量に消費するスポーツをする。そうすることで気分をよくし、脳のストレスを減らして、脳の機能を正常に保つようになったのである。それは人の寿命をのばし、地球の頂点に立たせることになった。
そのような新たな本能はどのように形成されたのだろう。まだ、自分たちがなぜここにいるかということを考えない頃、すなわち神が生まれていないとき、空に上る太陽は暖かいばかりではなく、自分のいる周りを明るく照らし、遠い山や海も目に見えるようにしてくれる、光る宝だった。
太陽が沈み夜が来て、真っ暗になると、今度は月が煌々と輝く、その周りには星々が煌めく。天に輝く月と星も宝である。
火を噴く山は怖いが、きれいだ。雲の間を縫って大きな音を鳴らしながら走る稲光はやっぱり怖いが、きれいだ。彼らは、なにがそれを起こしているのか考えることはなく、光るものに怖さも美しさも感じていたことであろう。
それにしても、輝くものはきれいだ。山の青葉が淡く輝く早春、濃い緑に輝く夏。海はきらきらと輝き、神のいなかった時代の人々の心を刺激したに違いない。闇との比較で明かりや光は人の脳に希望の刺激を与えたのに違いない。
そのころから、人の脳には光るものに感激する機能が芽生え、より大切にしようという気持ちが植え付けられていったのだ。
ものを作ることを覚えた人間は、火を、明かりを作り出し、ただ黒い石も磨くと光ることを知り、いろいろな色の石を磨き、首にかけ、満足を味わうと同時に、他人との比較もするようになったに違いない。
やがて赤や青や緑石の中から、透明に輝く部分を見つけ、光らせて、星のような輝きを身につけることをおぼえた。それは天の太陽、月、星の輝きを閉じこめた宝となり、やがて宝の石と呼ばれ、人の新たな本能である美への欲求をみたすものとなった。
それは物々交換の大事なものであったのと同時に、よりみなが欲しがるものを自分のものにしようと、悪の心が芽生えた。
いくら月や星にロケットをとばすようになった現代でもかわらず、きれいな宝石をもちたいばかりに、ふつうの生活から道をはみ出す人間がたくさんいる。
この話は、きれいな宝石を安くほしいという欲望から起きた、人間以外の動物を犠牲にした犯罪をあばくのに、探偵が多大な貢献をした物語である。四冊目になるこの探偵物語にも、やはり殺人はでてこない。しかも、結末は宝石より大事なものを手に入れることになるのである。
主要登場人物
庚申塚探偵事務所
詐貸美漬(さがしみつけ) :探偵 探偵事務所所長
逢手野霧(あいてのむ) :探偵助手
吉都可也(きっとかなり) :探偵助手
夢久愛子(むくあいこ) :詐貸の大学時代の彼女
警視庁刑事課 捜査支援分析センター分室(第八研究室)(通称ハチ公)
薩摩冬児(さつまとうじ) :警視、室長 詐貸の大学時代のサークル仲間
世久希紅子(よくきくこ) :分析官 化学博士
宙夜央(ちゅうやおう) :分析官
高胎蓉子(たかはらようこ):分析官
古書羊貴(ふるほんようき):分析官
津軽夏也 羽田の警備会社主任、元刑事、薩摩の先輩
猫の商売人
池波婦人 猫のブリーダー 所沢在住
池波寛 池波婦人の長男 貿易会社社長
池波光子 池波寛の妻 宝石鑑定士
鈴木静夫 鈴木動物病院院長
鈴木美和 鈴木の妻、猫美容室、「キャッツアイ」店長
サーマート リー 獣医大学留学生
バチェラ リー タイの猫ブリーダー
猫の骨
捜し物を必ず見つけだすと評判の、庚申塚探偵事務所が巣鴨にある。お岩さんの墓のある妙行寺の近くである。
今年はもうすぐ四月というのに、きびしい寒さが続いており、桜の開花もずいぶん遅れている。
事務所の二人の助手は、買ってきたお昼を食べおわり、それぞれ好きなことをしている。助手の一人、吉都可也(きっとかなり)は机の上のPCを開いて、かわいい動物の動画を見て、ひゃあ、かわいいとか、ありゃ、とか言っている。彼は生物学の大学院を卒業した男で、演劇をやっていたこともあり、演技をするのにも慣れている。だからか変装して尾行をするのが得意だ。
反対側の机に座っている、白くてぽっちゃり顔の女性、逢手野霧(あいてのむ)は図書館に勤めていたのだが、吉都と同時にこの事務所に雇われた。本の知識もあるが、いろいろなことをよく知っている。英語、中国語が話せ、他の国の言語もかなり読める。今、素甘を食べながら猫マンガを読んでいる。ミステリーが好きで、探偵事務所に入ったようだ。
「この猫絵十兵衛、おもしろいよ、長尾まるが描いたの」
「この猫の動画もかわいいですよ、野霧さん、漫画なんか読んでいていいんですか、本を書かなくていいんですか」
野霧は去年解決した事件を、ミステリーとして書き上げることになっている。
「本を書くのは夜中よ」
「そうですか、最近は猫ブームですね、猫の動画が多くて見切れない」
「そうね、でも昔は道を歩けば猫が横切ったものだけど、このごろ外にでている猫は少ないわね」
「飼い方が変わってしまいましたからね、昔は飼い猫でも、自由に外にでていましたけど」
「マンションじゃそういかないものね、岩合さんの番組に出てくる海外の猫は、自由に町中を歩いていて幸せそう」
そこに所長の詐貸美漬(さがしみつけ)が入ってきた。
「や、ただいま」
詐貸は北海道から帰ってきたところだ。三日ほど事務所を休んでいた。個人の用事だったようだが、なにをしにいったのか助手の二人は聞いていなかった。
それにしても珍しく紺の背広を着ている。二人とも詐貸の背広姿をみたのは二度目くらいだ。事務所が関わった事件の依頼人、テディじいさんのお別れの時以来かもしれない。
「お帰りなさい、北海道はまだ寒かったのじゃないですか」
「うん、かなり寒いね、留守中なにかあった」
「いいえ、なーんにも」
「退屈でした」
「いつもだろ」
詐貸がそういうと、二人とも笑った。
「カニを買ってきたよ、おみやげ、家にもって帰ってよ、一匹ずつしかないけど」
「カニはそろそろ終わりでしょ」
「そうだな」
そういって紙袋の中から、保冷袋を三つだし、ふたりに一つずつわたした。
ずいぶん重い。
「なにガニかしら」
野霧が袋の中を見ると、大きな毛ガニが入っている。
「こんなに大きいの、高いわよ」
吉都もあけてみて、
「ほんとだ、すごい」
「それじゃ、おれ、これを夢久さんに届けに行ってくる、早くした方がいいから」
「そうですね、愛子さんは今日本にいるんですね」
「うん」
夢久愛子は詐貸の大学のサークル仲間で、ある事件を依頼されたとき、十何年ぶりで再会した。大学時代の詐貸の彼女でもある。今、詐貸は夢久の祖父が始めた富山の薬の会社「北京骨商」の顧問弁護士を引き受けている。
詐貸は大学時代に法律試験に合格した天才だが、いろいろあって挫折し、大学も中退している。一時はバーテンなどもやっていた。
「愛子さんによろしく言ってください」
二人の助手は夢久愛子と親しい。愛子はノールウェーの幻想推理作家の作品を翻訳している。特に野夢はミステリーのことをよく知っているので話があう。
「それじゃ、いってくるよ、今日は適当に引けていいよ、家でみなさんとカニを食べたらいいよ」
「はーい」
二人とも詐貸がでるのを見送った。
「所長は愛子さんのうちでカニを食べるのかな」
吉都が三角の顔をとがらせた。
「私は食べないと思う、愛子さんだけならわからないけど、お母さんがいるでしょ、きっとおいて帰るだけよ」
野霧は丸い顔をちょっと小さくした。複雑な気持ちの時の表情だ。
探偵事務所は次の日からいつもの業務に戻った
といっても、ここのところ、もの探しの依頼はあまりない。
吉都はPCにへばりついて、相変わらず、動物のおもしろい映像を見ている。
吉都がちょっと目を留めた画像があった。
「シャムネコ、雌二歳、健康、2.5キロ、二万円、訳あり、猫輸入ーキャッツアイ」という宣伝である。投稿映像を見ていると、宣伝の画像がくっついてくるが、その中の一つである。
猫の動画に猫の宣伝はついてくるもので、シャム猫だと子猫で十から二十万ほどの値がつけてある。それをおぼえていたので、やけに安いなと思った。二歳に育っていると少し値が下がるとは思うが、それにしても安い。
しかし猫は拾うものと思っている可也には興味のないことではあった。
固定電話が鳴った。野霧が受話器をとった。
「あら、警視さん、おはようございます、ご無沙汰してます、ちょっとお待ちください」受話器を押さえると、、
「所長、ハチ公の薩摩警視から、電話です」と声を上げた。
「うん」
詐貸がデスクの電話のボタンを押して受話器を取った。
ハチ公とは警視庁刑事課、捜査支援分析センター分室、第八研究室のことで、四人の分析官と、室長である警視がいる。警視の薩摩冬児(とうじ)は詐貸や夢久愛子と大学のサークルメートで、仕事の手助けを頼んでくることがある。第八研究室には、変わった事件の情報が集まり、分析結果を、現場に知らせる役割をしている。四人の分析官はそれぞれ自分の得意分野があり、情報解析のエキスパートである。直接捜査のグループに加わって手助けすることもある。
昨年、ハチ公が担当した事件が、探偵事務所の依頼事件と思わぬ関係ができて、一緒に追いかけたことから、庚申塚探偵事務所とは友達づき合いになった。
「なに、そんなことまで、ハチ公のところにもちこまれるの」
詐貸が電話先の薩摩に言っている。
「うちは確かに猫を見つけるのがうまいけど、あまり関係ないんじゃないか、うん、調査費がでるわけか、下請けのようなものだな、わかった、契約してもいいよ、ちょうど今、捜索依頼がないから、詳しいことはメイルで、暗号メイルでたのむ」
そう言って、詐貸は電話を切った。
「なにか事件ですか」
吉都が聞くと、詐貸がうなずいて、
「また墓あばきだ」と声を上げた。
ここのところ墓に関わる事件が続いた。
「またですか、近くの染井霊園じゃないですよね」
その霊園には有名人の墓がたくさんあり、その中の一つの墓が掘り返されたりした事件があった。
「違うんだ、猫の骨がたくさん埋まっているところがみつかって、その土地を買った人が気味悪がって、警察に相談したそうだ、四十年前に団地ができてから空き地のままだったらしい。今ではなかなかいい団地になって、空き地の周りには住宅が建っている。猫の骨が埋まっていた空き地は、土地の持ち主が、家を建てずに外国に行ってしまったところらしい」
「どこですか」
「埼玉の小手指」
「西武池袋線ですね、所沢の次の次、西武線の電車基地があるところ」
「野霧君行ったことあるの」
「あそこにある大学のミステリーサークルのもようしに行ってみたことがありますけど、周りにはにもないところでした」
「現場は小手指の駅からバスで行ったところにある団地、その土地を持ち主が最近手放して、新しく購入した人が家を建てはじめたそうだ。地ならしのときに、シャベルカーが堀上げた土の中に、たくさんの骨がかたまってでてきて、気持ちが悪いので警察に届けた。警察がその骨を調べたら、十八匹の猫の骨で、死んで一年ほどのものだそうだ、ちょっと多いので、動物愛護の面でも問題がないか、ハチ公に捨てた人間を見つけるように指示が下ったみたいだ。もうすぐ薩摩からデータが送られてくる」
「それでどうするんです」
「警察は人の事件でなかなか猫まで手がまわらんようだ、といってほうっておくと、動物愛護団体から圧力がかかる、それでハチ公におはちがまわり、うちに下請けとして依頼がきたわけだ。誰が捨てたのか、調べてほしいということだ」
「近所への聞き込みですね」
「そいういうことになるね、警察だと周りの住人が驚くから、探偵事務所のほうがいいのかもしれないよ」
吉都が事務所宛にハチ公からメイルがきていることに気づいた。
「パスワードも二通目に来ています」
めいめい、自分のデスクの上のPCをみた。事務所にきたものは、助手たちのPCでも開ける。
ダウンロードしたファイルを開いた。
「椿山猫集団自殺」とタイトルがある。
「なに、これ、変なタイトルね、きっと、世久さんじゃないの、こういうタイトルをつけるのは」
野霧がいうとみんながうなずいた。世久希紅子(きくこ)はハチ公のスタッフの一人で化学の博士号をもっている、元気な分析官である。
「きっとそうですね、あとできいてみます」
吉都がまじめに返事をしている。
「十八匹の猫の骨をみな調べたようですね、すごい猫ばっかり、アビシニアン、コラット、シャム、シャルトリュウ、スコチシュホールド、バーミーズ、ヒマラヤン、ペルシャ、マンクス、マンチカン、メイクーン、ラグドール、ロシアンブルー、スフインクス、ベンガル、ノルウェジャンフォレストキャット、サイベリアン、ラガマフィン」
「なにこれ、知らない猫ちゃんがたくさんいる」
「みんな高い奴ばっかり、日本猫いない」
「日本猫は自殺する奴なんかいないよ」
詐貸が、なにを思ったか、その場にあわない冗談を言った。それがおかしくて、二人が笑った。
「猫の歳は二歳から三歳くらい、とありますね」
「大人になりたての猫ってところだね」
「そうね、売っている猫は、子猫が多いでしょ、おとなであるということは、ブリーダーが何らかの理由で放棄したのかしら」
「だけど、これだけの種類の猫をただで放棄するでしょうか、貰い手だってあるでしょう」
「ちょっと変ね」
「管理していた不動産屋は、草取りをしていなかったのかな、気付きそうなものだけど」
「周りの住人は、だれかが埋めているのに気がつかなかったのかしら」
「そういうことを我々に調べてもらいたいらしいよ」
「それじゃ、椿山の現場に行って、周りや不動産屋に聞き込めばいいのでしょうね、家を建てようとしている人にきいてもしょうがないわね」
「そうですね」
「都合のいいとき、行ってきてよ、地図が添付されている」
数日後、現場に向かった二人は小手指の駅に着いた。吉都が大きな紙袋をつるしている。中には野霧が買った、地蔵最中がたくさんはいっている。巣鴨の銘菓の一つだ。
小手指は池袋から急行で三十五分。まず駅の近くにある不動産屋に寄った。
警視庁から正式に調査の下請け依頼がきているので話しやすい。
不動産屋のおやじは、
「変なもんがでちまって、こっちも困ったんですよ、うちが管理するようになったのは実は一年前からなんでね、確かに造成したときに販売したものです、前の持ち主さんに私どもから土地を売りました。もう四十年も前ですよ、持ち主さんは結局、家を建てずにアメリカに行っちまって、向こうで暮らすことになっちまったようなんです、昨年、売ってってほしいと管理の委託を受けたんです。去年はうちで草かりしましたんですけどね、まさかあんなもんが埋まってるとは思っていませんでしたな」と言って、ファイルをだした。
「警察から、家を建てるのは問題ないって言われたので、もう基礎ずくりにかかってますよ」
ファイルから土地を売りだした四十年前の、黄ばんだパンフレットをだした。
ほぼ正方形に近い角地で、四十坪ほどである。
「なんか事件に関係してきましたか」
不動産屋はちょっと気がかりなようだ。
「いえ、何もないようです、ただ、動物愛護団体が問題にするでしょう、だれが埋めたのか調べておかなければなりません、それで警視庁からうちに依頼がありました、猫探しが得意なもんで」
「ああ、そういうことですね」
「土地の周りの人たちに、協力してもらおうと思ってますが」
「あそこの人たちはみないい人たちですよ、団地の一期の人たちですよ、隣の家も子供が大きくなって、夫婦で住んでますな」
「ありがとうございました、これから現場にいくつもりです」
「同じ通りに、その地区の班長さんがいるから、最初にそこに挨拶に行った方がいいね」
「あ、そうですね、それと今工事をしている会社の人から話が聞きたいのですけど」
工事会社の名前や住所は薩摩の送ってくれたメイルにあった。
「所沢駅から、そんなに遠くないよ、行くなら電話を入れとくよ」
「お願いします、現場を見てから伺います」
不動産屋は親切にも、売り出した当時の地図をコピーしてくれた。
地区班長の家を教わり、巣鴨の地蔵饅頭をお礼においてタクシーで現場に向かった。
椿山団地は丘陵に広がる大きな住宅地で、猫の骨のでた土地にはすでにコンクリートの基礎ができていた。まだ固めている最中で作業員はいなかった。
教えてもらった地区班長の家を尋ねると、六十後半の老人が説明してくれた。
「あの土地ね、たくさんの猫の骨がでたっていうんで驚きましたね、土地の前の持ち主がアメリカに行ったきりでね、買ったのはいいが、結局、向こうに住むことになって、売ったのですよ」
不動産屋と同じことを言った。
「持ち主とは何度か話をしたけど、当時としてはまだはしりのコンピューター会社に勤めていて、アメリカ支店勤務になったんですな、ところがその日本の会社は、アメリカの大きなIT会社に買収され、持ち主の人はその会社で技術者としていい地位になったようで、向こうに大きな家をもったようです。あの土地をそのままにしてあったのは、退職でもしたら日本に帰るつもりだったのかもしれませんね、いい人で、自治会費を納めてくれていまして、ずーっとですよ、その上、草取りの費用も送ってくれていましてね、その費用で所沢のシルバー会にこちらから依頼していました、一昨年までですけどね、そうそう池波さんのところにきていた学生が車を止めさせてくれっていうことで、時々車が止まってましたな、一昨年ほど前ですな、半年間ほどということだったので、土地の持ち主には連絡しませんでした」
「池波さんというのはどなたでしょう」
「ああ、この団地のはずれの大きな家にいる人ですよ、ご主人が亡くなられて、今は奥さんが猫と一人で住んでいらっしゃいますよ」
「シルバー会というのは、よくあるご老人たちの仕事の会ですか」
「そうです、いろいろありますよ、庭木の剪定やら、掃除やら」
「すると、シルバー会の人がなにか知っているかもしれませんね」
「そうね、シルバー会の電話教えてあげましょう、所沢市役所に行けばわかりますけどね」
「ありがとうございます、それと、あの土地の周りの人に話を聞きたいのですが、いきなり行ってかまわないでしょうか」
「ええ大丈夫ですよ、猫の骨のことは、私も聞いてみたけど、知らないようでしたよ」
自治会長にも地蔵饅頭をおいて現場に戻った。
土地に隣接する二軒の家の夫婦は、誰かが何かを埋めるようなところは見ていないということだった。もし、夜中におこなったとしても、家の窓から空き地はよく見えるそうで、そういった気配を感じたことはないということだ。ただ、一時期、池波さんのところにいた留学生の車が出入りしていたということだ。それに、シルバー会のひとによる草取りが毎年朝早く行われてきたことは知っているということだった。
とても閑寂な住宅街である。
野霧と吉都は地蔵饅頭をわたして、そうそうに小手指駅に戻った。
「シルバーの人に聞いてみる必要がありますね」
「そうね、市役所に行ってみよう」
「その前に、シルバー会に電話を入れてみます」
吉都が電話を入れこれから行くことを伝えた。
結局、シルバー会事務所は所沢市役所内にあった。十八匹の猫の死体がでたことや、その捨てた人を警察からの依頼で調べていることを告げると、係りの女性が応対してくれた。係りの人は帳簿を見ながら、
「あの団地の草取りは、畑山さんが担当してますね、毎年夏に一度行っています、七月の終わり頃です」と教えてくれた。
「畑山さんが草取りをしているのですか」
「いえ、とりまとめですね、畑山さん自身は監督です」
「お話を聞きたいのですが、会えるでしょうか」
「ああ、椿山団地に住んでらっしゃいますよ」
「あれ、今、椿山団地に行ってきたばかりです」
「あら、それは残念でしたね」
「でも、もう一度行きます、教えていただけませんでしょうか」
「警察からの依頼でしたよね、電話を入れておきます」
「その前に、今その土地で工事をしている工務店が所沢にあるということで、そこによってから行きますので、三時頃ということでお願いできますでしょうか」
係りの人はすぐに電話をかけてくれた。
「今日は家にいるそうです、三時なら大丈夫と言っていました。猫の死体がでたことを知っていましたよ」
「ありがとうございました」
野霧と吉都はタクシーで工務店に行った。家族経営の小規模な工務店で、社長が話をしてくれた。
「ああ、警察にも話しましたが、ショベルカーが掘った土を脇に積んだときに、バラバラと骨が出てきたのには驚きましたな、あまりにも多いので、すぐに警察に電話をしたら、刑事がすっとんできて、こりゃ、動物の骨だ、それにしても多いから、なにかあるといけないから、掘った土を警察の方にもってきてくれと言われましてね、まあ、シャベル二かきほどで、そんなにたくさんの土じゃなかったが、警察の裏に運んでおろしましたよ、手間がかかっちまった。そのときは仕事を一時中断したけど、猫の骨なので、後なにもでないようなら工事を続けていいと言うことでした」
「猫の骨はまとまってあったのですか」
「そうね、写真を撮ってありますよ」
机の引き出しから写真を出して見せてくれた。骨が折り重なっている。土より骨の方が多いので、いっぺんに穴の中に捨てたという感じである。
「ひでえことをする奴がいるもんだね、殺しちゃったんじゃないかね、皆同じ程度のものだったからね、病気で死んだのなら一匹、二匹だろう」
「確かにそうですね」
吉都が不動産屋の地図を取り出して、「土地のどのあたりからでたのですか」と聞いた。
「角のあたりだったかな」
吉都が社長が指さしたところにボールペンで丸をつけた。両隣の家から離れたところだ。
「草が生えていたのでしょうか」
「工事が始まったのが、二月終わりだから、そんなに生えてはいなかったな」
「ありがとうございました」
みやげを渡すと再び小手指に向かった。
タクシーで椿山団地の畑山さんの家に行った。現場からはずいぶん離れたところである。
「そうですな、一昨年は団地のはずれにいる池波さんがやりましたな」
「いつもやる人ですか」
「いえ、池波さんはシルバー会には登録していないんですけどね、当時、私が自治会長をしておりまして、池波さんはその地区の班長で、会合の時にシルバー会がこの界隈の草取りや庭木の剪定などをしている話をしました。そのとき、池波さんの家に一年来ていたタイの学生さんが、草取りというのを経験してみたいというので、お願いしました。何でも一時その学生が車を置かしてもらっているということでしたな。私がやったということで、私が手間賃をもらって、その学生に渡しました。草取りをした後を見たら、ずいぶんきれいにむしってありましたよ、その人の車がとまってましたな」
「そうですか、池波さんの家は遠いのですか」
「まあ団地内だから歩けないことはないけど、ちょっとありますよ」
「池波さんは猫と一人暮らしだと、あの土地の地区班長さんが言ってましたけど、留学生を泊めるような人なんですね」
「大きな家だからね、猫のブリーダーもしているとか言っていたな、海外旅行によく行っていたようだから、海外に知り合いがいるんだろうね、そういえば亡くなったご主人は貿易関係のしごとだったな」
「そうですか、いろいろ教えていただいて、ありがとうございました」
池波さんの家の場所を聞いて、地蔵のお菓子をおいてでた。
「行ってみますか」
「まあ、行くだけ行ってみましょうか、猫のブリーダーというのは気になるわね、その人のことは調べてから、必要なら直接話をしたほうがいいかもね」
野霧と吉都は池波さんの家のほうにむかった。団地の家は大体同じようなつくりで、その当時は新しい感覚のしゃれた家々だったのだろう。数十年たった庭の木々が大きく育って、落ち着いた雰囲気がある。
教わった通り地図にそって二十分も歩くと、団地の際のちょっと大きめの家の並んだ通りにでた。丘の上の椿山団地の縁になる。眺めがかなりいいところだ。
池波さんの家は、他の家と違って薄青色の西欧風の作りで、庭もかなり広そうだ。他の家の倍もあるかもしれない。二軒分だろう。
庭で女性が猫を抱いて、池をのぞいている。
「外にいますよ、どうします、声をかけますか」
吉都が聞くと、野霧はうなずいた。
「うん、ちょっとだけね、だけど名のらないからね、まかしておいて」
鉄柵の外から声をかけた。
「すみません」
猫を抱いた女性が振り向いた。体格のいい、ちょっと野霧に似た感じの女性だ。
「はーい」
野霧とは違って、かなり高音の声を張り上げた。
「すみません、道に迷ってしまって」
「あーら、どちらに行らしたいの」
「ちょっと用事があって、畑山さんのとこにいったのですが、バス停がわからなくなってしまって」
「あら、ここまで歩いてしまったの、遠かったでしょ、小手指に行かれるの」
「はい」
「向こうの角を右に曲がって、突き当たると大きな通りにでるから、そこを左にいくと停留所がありますよ」
「ありがとうございます」
「珍しい猫ちゃんですね」
「ええ、コラットよ」
「どこの猫なんですか」
「タイの猫ちゃん」
吉都が手を伸ばすと、首を伸ばして、ふすふすとかいだ」
「猫が好きな人はすぐわかるのよ」
「ええ、猫好きです」
「私、ブリーダーなのよ、まっててね」
彼女は家にはいると、今度は違う猫を抱いてでてきた。シャム猫だ。
「これお名刺、もし、猫ちゃんが欲しくなったら、連絡してくださいな、写真を送りますよ」
「ありがとうございます、どちらもタイの猫ちゃんですね」
吉都が名刺を見ると、「猫目石」とあった。おや、と吉都は思った。見たことがある。
「そうなの、タイにブリーダーの知人がいて、その人の助言で始めたのよ、一度行ったけど、すごい家を持っていて、タイの純粋な猫ちゃんがたくさんいるのよ、息子さんが一年間、このうちにいたのだけど、タイの貴族っていう感じの子なのに、草取りや、家の掃除も手伝ってくれる、とてもやさしい子だったわ」
自治会長が言っていた学生だ。
「遊びに来ていたのですか」
「一年間都内の大学に交換留学生できていたのよ、まじめな子でした」
「へー、タイの豪族の息子さんとはすごいですね、どこの大学にきていたのですか」
彼女は中央線沿線のある獣医科大学の名前を挙げた。吉都の高校の同級生が卒業した大学だ。渋谷に動物病院を開業している。
「僕の友人もその大学をでて、獣医さんになってます。いい大学ですね」
「あら、そうなの」
「その方のお名前を聞いていいですか」
池波夫人はちょっと困ったような顔になったが、すぐに笑顔になって、
「いいわよ、彼は向こうでいずれ獣医になって、お父さんの手助けをするって言ってたわ、私のところでも猫ちゃんを増やしてますけど、直接タイから取り寄せることもできますよ、そのような人がいたら、紹介してちょうだいな、彼のお父さんのやってる、ブリーダーの会社の名刺はたくさんもらっているわ、今もってきますから」
彼女はまた家にはいると、名刺をもってきた。
「会社の名前はメーオサマン、息子さんはサーマート・リーと言うんだけど、お父さんはパチェラ・リーよ」
「ありがとうございました」
「気をつけてね」
「あ、そうだ、失礼かもしれませんけど、用事があってこちらにきたのですけど、用事先の人数がわからなかったので、地元のお菓子をたくさんもってきたのです。一つ余ったのですけど、持って帰るのも何ですので、よろしかったら、いかがでしょうか巣鴨のお菓子ですけど、親切にしていただいたお礼です」
野霧が地蔵最中をだした。コネをつけておくつもりだろう。
「あら、巣鴨からいらっしゃった、いいのかしら、それじゃ遠慮なくいただくわ、猫ちゃんが必要なときには安くしてあげますね」
「そのうち、猫ちゃん見せていただきにきます」
「ぜひいらしてね」
池波夫人はにこにこしながら、地蔵最中をもって猫とともに家に入っていった。
吉都はスマホで、家の写真を撮った。
「猫に関係のある人でしたね」
「うーん、そうね、明日事務所で考えよう、なんだか腑に落ちないの」
「そうですね、ぼくも佐々木に聞いてみます」
野霧と吉都は停留所につくと、小手指行きのバスがすぐきた。
次の日、野霧は猫のブリーダーについて調べていた。吉都は高校の同級生がやっている佐々木動物病院に電話をしている。
「久しぶり、今大丈夫かな、実はちょっと知りたいことがあって、時間のあるとき行きたいんだけど、そう、じゃあ、明日の朝いくよ」
吉都は電話を切った。
「佐々木犬猫病院は明日定休日で、大学の方に研修に行くそうです、研究日といって、大学の卒業した研究室で、教授のセミナーに参加して、新しい技術のことや薬のことを知るんだそうです」
「獣医さんもお医者さんも大変ね、母親がいっていたわ、入れ歯が昔と段違いによくなったんだって、長い間かよっていた歯医者さんがやめることになったので、新しくできた評判のいい歯医者にいったら、入れ歯を作り替えることを勧められつくったら、もう昔のものとは段違い、軽いし、小さいし、やっぱり若いお医者さんはいいと言ってたわ、新しい技術を知ってるからって」
「そういうもんですね」
「見せてもらったけど、本当に小さいの、前の入れ歯も一年前に作ってもらったんだけど、ずいぶん大きいの、年取ったお医者さんは話がうまいけど、技術はだめねっていっていた」
「そうなんでしょうね、犬猫病院でも方法や道具がどんどん新しくなるようですよ、動物用のレントゲンどころか、CTスキャン装置もあるみたいだし」
「今ね、ネットで猫のブリーダー調べていたのだけど、キャッツアイという、猫の安い店が出てきたわよ、池波さんは猫目石よね、似ているけど違うのね」
「あ、思い出した。動物の映像見てたら、そのキャッツアイの宣伝みましたよ」
吉都は野霧のところに行くとPCをのぞいた。
「あ、これだ、僕もみた奴だ、池袋の近くだ」
「池波夫人とは関係ないでしょうね」
「そうですね、機会があったら聞いてみたらいいかもしれないですね」
そこに詐貸が入ってきた。朝、警視庁の薩摩警視のところによってきたのだ。
「やあ、昨日はどうだった」
「ええ、聞いた限りでは手がかりらしきものはでてきませんでした、誰もあの土地にものを埋めるのを見ていませんでした。関係ないかもしれませんけど、タイからの留学生がそこに車を一年間とめていました。そこの草取りもしたようです。留学生のいた家の女性が猫のブリーダーでした、池波さんといいます。その家に行ったら、庭にいたので、ちょっと話をしました。ブリーダーといっても個人でやっていて、そんなにたくさんいるわけじゃなさそうです」
「そう、まあ、この件はあわてなくていいよ、薩摩と話したけど、いつまでに埋めた犯人を捜さなければならないということはないそうだ。まだ愛護団体には知られていないし、きちんと調査中だと言えればいいようだ、今年中に目星がつけばいいんじゃないのかな」
「そうですか、それじゃ、のんびりやります」
野霧と吉都は小手指でのことを詳しく詐貸に報告した。
「それじゃ、可也は明日、獣医大学に行ってくるんだ」
「ええ」
獣医大学は中央線の駅から歩いて数分のところにある。佐々木と駅の改札口で待ち合わせだ。吉都は少し前について待っていた。しばらくすると、客に混じって、佐々木がでてきた。
「よーしばらく」
佐々木には犬がほしいという依頼者に、甲斐犬を紹介してもらったことがある。
「俺なんかがついていっていいのかな」
「ゼミは午後だから、それまで大丈夫だよ」
「ちょっとこれを渡しとく」
吉都は池波さんのところにいたタイの学生の名前を書いた紙を渡した。
「サーマート・リー」だね。
だいたいのところは電話で話してある。
「一昨年、佐々木のでた大学に交換留学生でいたんだ、誰かにどんな子だったか聞いてほしいんだ」
「うん、その前にどの研究室にいたのか学生課に聞いてみるよ」
歩きながら話を聞くと、アジアからの留学生はほとんどが国立大学にいくという。私立の獣医大学は金がかかるのであまりこないらしい。
「その人、タイのどこの大学かわかるかな」
「いや、きいていないんだ」
獣医大学にはずいぶん高いビルが建っていた。前に来た時にはなかった。
「おおきいの建てたね」
「あれは、医学部の進学課程だよ」
「医学部って」
「うちの獣医大学は、私立医大の系列の大学だよ」
と、よく知られている医大の名前を言った。
「獣医大はこっちのほう」
彼は門から入ってすぐの石造りの古い建物に入った。歴史のある建物で、吉都はこっちの方がいいと思いながら彼について行った。
「あら、先生、ゼミは午後でしょう」
事務所の女性が彼に声をかけた。
「うん、ちょっと高校の同級生を連れてきたんだ、動物好きでね、都内の大学の生物の大学院をでた奴なんだ」
吉都は事務の女性におじぎをした。
佐々木がその女性に、「この人、一昨年タイからきた留学生なんだけど、どこの研究室にいたかわかるかな」と書いた紙を渡した。
「ええ、すぐわかりますよ、留学生の名簿をチェックしますから、ちょっとまってください」
彼女はPCにカタカナの名前のリストをよびだした。
「うーん、リー、さんという人は何人かいますけど、サーマートという人はいませんね、名字の違う人はいます、それにしても、一昨年にはいませんよ」
「スペルわかる」
佐々木聞かれた吉都は首を横に振った。
「先生、在学生も調べましたが、いませんね、それに短期間来た人や訪問した学生の名簿にもありませんね」
「あー、どうもありがとう」
彼は彼女にお礼を言うと、吉都をひっぱって外にでた。
「おかしいね、名前が間違っていないのかい」
「いや、そんなことはないと思うけど、もう少し調べてから、またお願いするかもしれない」
「うん、かまわないよ、その人なにしたの」
「いや、話したように、猫のブリーダーのところに一年いた人間で、ここの留学生だということだったんだ、別に何をしたということはないけど」
「そうか、研究室や動物舎をみせてあげるよ、そのあと、学食で、飯でも食べよう」
吉都は、動物小屋などを見せてもらって探偵事務所に戻った。
「サーマート・リーという人、あの獣医大学にいた形跡がありませんでしたよ」
吉都が野霧に報告した。
「おかしいわね、もう一度、池波さんのところに猫を見せてもらいに行って、彼のことをほじくりだしてみるわ」
「そうですね」
野霧が電話をかけた。笑顔でうなずいている。
終わると、人差し指と親指で丸をつくった。
「よろこんでいたわよ、ただ、買うかどうかわからないけど、みせてほしいといったのよ、私が話を聞いてくるわ」
野霧はすぐに事務所をでて、小手指の椿山団地に向かった。
「こんにちは、さっそくまいりました」
野霧は笑顔で玄関に入った。小手指の駅からバスで来たらとても近い。出迎えてくれた池波夫人も嬉しそうである。
「よくきてくださったわね、お友達が猫を飼いたいのですってね」
「ええ、でも、まだはっきりしないいのですけど、友人は北海道に住んでいて、これないので、様子を見てきてほしいと言われたんです」
「どうぞどうぞ、早速見てくださる」
婦人の家は木造の間数のある二階屋である。彼女は二階に野霧を案内した。
「二階に私の寝室と、猫ちゃんの部屋が二部屋、それに、猫用お風呂場とトイレがあるの、猫ちゃん用よ、一階に居間と客間、それに私用のお風呂があるのよ」
「ご家族は一階で生活なさっているのですね」
「この家は私一人で住んでいるの、二人の息子はもう家族を持ってますから、一人は新所沢にいるの、猫が病気になったときは息子が車で送ってくれるのよ」
「そうなんですか」
池波夫人が一つの部屋の戸を開けると、薄緑の絨毯の敷かれた床に丸まっていた一匹の猫が、ちょっと首を上げて野霧を見た。部屋の中には立体的な遊び場や、猫の遊び道具が入っている木製の棚がおいてあり、野霧が足を入れると、その猫が起き上がってそばに寄ってきた。大きな箱からももう一匹出てきた。コレットとシャムだ。
「よくなれているでしょう、これはコレットとシャムの雌」
隣の部屋にはシャムがいた。そこには少し大きくなった子猫たちが、遊び転げていた。
「かわいいですね」
「ちょっと触るの遠慮してちょうだいね、もう少し大きくなるまで、私も手を消毒してからだっこしてるの、ブリーダーは大変なのよ」
野霧が写真を撮っていいかと聞いたら、「パンフレットにのせてあるので、ごめんなさいそれをもっていって」と断られた。
「この子たちは七ヶ月だから、お譲りできるわよ」
彼女はアルコール消毒をもってきた。
「これを手に掛けてから、お触りになっていいですよ」
野霧の手に消毒用アルコールを噴霧し、タオルをわたしてくれた。
手を拭いた野霧は一匹を抱き上げようとした。だが猫がすーっと身を引いてしまった。
猫の管理はとても厳しくやっているようだ。
「シャム猫は飼い主にはよくなつくけど、ちょっと気も荒いところがあるのよ」
「ええ、知っています」
「お友達はシャムがいいのかしら」
「どちらかというと、おとなしい方がいいようです」
「とすると、コレットの方がいいわね、下でお話を聞かせてくださいな」
一階の応接間にいくと、コレットがソファーに寝ていた。
「一階にいるのは私が飼っている雄猫ちゃん、もちろん血統証つきよ、繁殖の時期になると、ブリーディングルームにいれて、子供を産ますの、この猫ちゃんたちはご自由にお触りください」
野霧が寝ているコレットの頭をさすると、首をあげて顔を手にこすりつけてきた。
「かわいいですね、よくなれている」
彼女は紅茶を入れてもってきた。
「あ、すみません」
「いただいたお饅頭食べましょう、日本茶のほうがよかったかしら」
「いえ、紅茶好きです」
「前にいただいた、地蔵最中も紅茶でいただいたわ、おいしかったわ」
「それならよかったです」
「猫ちゃんは飼いかたでかわるのよ、かわいがりすぎるのもだめ、嫌われるわよ、かわいがってほしいという顔の時にだっこするの、自分が好きなことをしたいと思っているときに引き留めると怒るわよ、その度合いね、子供と同じ、まず、猫ちゃんに、この人は自分の気持ちをよく知っていると信じてもらうこと」
なかなかよくわかっているようだ。
「長いんですか」
「そうでもないの、まだ五年ほどよ、主人が亡くなって十年、そのころはなにもする気がおきなかったけど、息子の嫁に勧められて、友達さそってタイに旅行に行ったの、五年前ね、タイで猫のブリーダーのところに行ったとき、猫を飼いたいと思っていたら、その主人がいろいろ話してくれて、シャムを送ってもらうことにしたの」
「サーマートさんのお父さんですか」
「そう、よくおわかりになったわね」
「前きたときに、教えてくださいました」
「そうだったかしら」
「それからなんですか、ブリーダーになったのは」
「ええ、息子たちも協力してくれているし、本当にかわいがってくれる人にだけ譲っているの」
「なぜ、猫目石なんですか」
「主人が貿易関係の会社やっていて、まだ若いとき、スリランカから買ってきてくれたのよ、大事にしているの」
池波夫人は茶色のビロード張りの宝石箱をもってきて見せてくれた。
「まだ、ぺーぺーのときだったから、こんな小さいのしか買えなかったといって言ってたけど、くっきりと目が光るでしょ、それなりにがんばって買ってくれたんだと思うのよ」
「すてきですね」
「お友達は、ご家族で猫を飼うのかしら」
「ええ」
「普通の愛玩用なら、ノラちゃんでも助けてあげるのがいいんですけどね」
ブリーダーらしからぬことを言ったので、野霧はちょっと、池波夫人を見直した。人がとても良さそうだ。
「そうですね」
「うちの猫ちゃんは、買うときは高くはないけど、血統証つきだと、毎月の維持費が相当かかるのよ、獣医さんが気にするからね、普通の猫ちゃんかわいがる方が気楽かもしれないわね」
猫を売る気がないのだろうか。野霧は話を変えた。
「サーマートさんはここから中央線でかよっていらしたんですか」
「最初はそうしてましたよ、所沢から、東村山で西武国分寺線に乗り換えられるでしょう、中央線の国分寺にでらるの、でも、すぐに中古車を買って、それでかよってました。
「ご自分で買ってきたのですか」
「ええ、国分寺の中古車屋だと言ってたわ、彼は国際免許を持っていたらしいわ、それに日本語がかなりできたのよ」
「駐車場を借りていたのですか」
あの空き地を借りていたことは知っていたが、わざと聞いてみた。
「ええ、そこの班長さんにお願いして、一時だからって、空き地にとめさせていただいたのよ」
「あの、草取りをしたというところですね」
「ええ、そうなの助かったわ、彼って買い物にもつれて行ってくれたのよ」
「サーマートさんのお父さんからは、まだ猫を買っているのですか」
「もううちで増やしているので、買ってはいないけど、どうしても本場からほしいという人には紹介しています」
「どのようなところなのか見てみたいわ」
「パンフレットをごらんになって」
彼女がバチェラ・リーの猫ショップのパンフレットをもってきた。猫が飼育箱に入れられている写真がならんでいた。
「すごいところですね、ホームページで見てみます」
野霧は書いてあったホームページを書き写した。
「息子さんがあとをついでいるのですか」
「いえいえ、まだ若いので、世界をとびまわっているようですよ、いずれ、そうなるのでしょうけど」
「会ってみたかったですね」
「お父さんとはあまり似ていなかったわね、きっと、お母さんになんでしょう」
パンフレットには父親の写真が載っていた、丸顔の人が良さそうなにこやかな顔をしている」
「息子さんは写っていませんね」
「彼ね、写真を撮るのはずかしいっていやがったけど、一枚あるのよ、タイに帰るとき、うちの猫ちゃんといっしょの写真を撮ったの、これよ」
彼女は一枚の写真をもってきて見せてくれた。確かに、細面の顔で、父親と似ていない。
「そうだ忘れてた、コレットとシャムの写真撮らせてもらっていいですか、池波さんがだっこしているところ、友達に送ります」
「はいはい、いいですよ、シャムは私の部屋だから連れてきますね」
池波さんが部屋をでたとき、パンフレットと、サーマートの写真をスマホで撮った。
「はいつれてきましたよ、コレットも一緒にとってね」
二匹の猫を膝のうえに載せて、婦人がほほえんだ。
「写真焼いて送りますね」
「あ、うれしいわね、お願いね」
「そういえば、池波さんはホームページを立ち上げていないのですね」
「私コンピューターだめなのよ」
「ネットで、キャッツアイっていう猫の美容室があって、輸入もやっているみたいでした。関係ありませんよね」
池波夫人がちょっと躊躇した。
「あら、そんな人がいるのね、知らないわ」
「池波さんのところの猫ちゃん、みんなお行儀がいいし、かわいいから買い手がつくんでしょうね」
「ええ、そうなの、売れ残ったことないのよ」
「サーマートさんからは連絡があるのですか」
「世界で勉強中で、忙しいのでしょう、帰ってからは、一度タイから礼状が来たけど、それ以来ないわね」
「そういえば車は帰るとき売っていったのですか」
「ああ、あのサニーは、買ったところに売ったといってましたね」
「すみません、長居して、友人には高級すぎて無理かもしれませんけど、ほしいという人がいたら、紹介しますので、そのときはよろしくお願いします」
「きてくださってうれしかったわ、またいらしてくださいな」
「ありがとうございます」
野霧はバスで小手指にもどり、その足で所沢から国分寺にでた。
スマホで国分寺の中古車会社を探すと、三軒あった。駅にいちばん近い店に行き、タイ人にサニーを売ったことがあるかきいた。店の主人は覚えていて、帳簿を調べてくれた。二年前、買っていった車をまた売りに来たので、買い取ったという。池波夫人の言っていたことと合致する。
「感じのいい人でしたよ、何か問題がありましたか」と聞かれたので、とっさに、無断で空き地に駐車していたようで、調べてほしいと頼まれた、と探偵事務所の名刺を出した。
「サーマート・リーという人ですね」
野霧はついさっき池波夫人宅で撮影した写真を見せた。
「確かにこの人だけど、名前は違ったな、トンチャン・ウオンとカタカナで書いてありますね、だけどもうタイに帰ると言ってましたけど」
「ああ、それじゃ違う人ですね、住所はどこになっていますか」
「国分寺市のマンションですね、住所からすると西国分寺駅に近いですね」
野霧はいそいで、手帳に名前と住所を書いた。
「そうでしたか、どうも情報が交錯しているようで、私の探している人とは違うようですね、この写真の出所もよくわからないのですよ、住んでいたところは小手指でした」
「そうですか、問題になると面倒だと思っていたのですけど助かりました」
「他を当たります、すみませんでした」
野霧は何かおかしいと感じていた。事務所に戻ったら、サーマート・リとトンチャン・ウオンを調べよう。もどる前に、西国分寺のトンチャン・ウオンの住んでいたマンションを見に行っておいたほうがいいだろう。
そのマンションは、西国分寺駅南口からちょっと歩いたところにあった、八階建てで比較的新しい。駐車場もある。
野霧は場所だけ確認して、事務所に戻った。
「ご苦労様、そのまま帰ってもよかったのに、なにかわかったの」
詐貸がデスクから顔を上げた。
「なにかありそうなんです、草刈りをしたというタイの留学生が、違う名前で車を買って、マンションも借りていました」
野霧は中古自動車屋でのことを話した。
「サーマート・リとトンチャン・ウオンか、大学ではトンチャン・ウオンだったのかな、きっとそれがパスポートの名前かもね、ちょっと怪しいな」
「獣医大学のタイ人の名前は控えてありますよ、二人いました、だけど、トンチャン・ウオンもありませんね」
「それじゃ、薩摩に連絡して、出入国管理の方に確認してもらおう」
「世久さんに、メイルで連絡しましょうか」
「可也、頼むよ」
吉都が世久希紅子、愛称、キックにメイルを送った。
「トンチャン・ウオンのいた西国分寺のマンションも見るだけ見てきました。ハチ公からの返事を待って、また行ってみようと思います」
「うん、二人で行ってみてよ、留学生ではないかもしれない。日本で何かをしていた可能性があるね、よくあるのは薬の密輸だな」
二人はうなずいて、その日の仕事はおわりにした。
あくる日、野霧と吉都は西国分寺のマンションに行った。管理人のいないマンションである。入り口にある機械の番号を押さないと、エレベーターのエントランスに入ることができない。新聞受の数から四十軒ほどあることがわかる。入り口に管理している不動産屋の名前と電話番号が書いてあった。
「国分寺の不動産屋ですね、電話をかけて行ってみますか」
「そうね」
そこにエレベーターから、子連れの母親が降りてきて、外に出てきた。野霧が声をかけた。
「すみません、ちょっとお聞きしたいことがあるのですが、お時間ありますか」
「なんでしょうか」
「こういう人を捜しています、行方不明なんです、一昨年このマンションにいたことがわかっているのですが、タイの人です」
野霧が池波夫人のところで写した写真を見せた。
「ああ、この人は見かけたことがあります、話したことはありませんけど、にこにこしてお辞儀をする人でした。よく猫ちゃんの籠もっていましたね、子供が興味をもってうちも飼いたいとだだをこねられました」
「このマンションは猫が飼えるのですか」
「ええ、結局うちも去年から飼いはじめました」
「彼はいつも一人でしたか」
「女の人と一緒のこともありました」
「すみません、お引き留めして、このマンション、この不動産屋さんが管理しているのですね」
「ええ、よくメンテナンスしてくれるいい不動産屋さんですよ、その方のことも行けばわかると思います」
「ありがとうございました」
二人は西国分寺駅に近いところにある不動産屋に行った。
吉都は探偵事務所の名刺をだし、トンチャン・ウオンの行方を探していることを言った。
「探偵さんですか、最近は個人情報ということで、なかなかお話しできないのですが」
六十ほどのまじめそうなおじさんだ。
「警視庁からの委託をうけています。警視庁の内線にかけて確認いただけますか」
吉都が、ハチ公の内線番号を教えた。本当におじさんは警視庁に電話をかけた。「今、庚申塚探偵事務所の吉都さんという方が、トンチャン・ウオンさんのことでみえているのですが、警視庁からの委託だそうで、確認の電話したんですが」
本当にまじめだ。
「その吉都可也さんです、はあ、協力いたします、すみませんです」
おじさんは受話器を置いた。顔がにこやかになっている。
「有名な探偵事務所さんだそうで、はい、なんでも聞いてください」
「ありがとうございます、二年ほど前、トンチャン・ウオンさんが、あそこのマンションを借りたと思いますが、そのときの様子を知りたいと思いまして」
「ウオンさんはおぼえていますよ、いい人で、一年間だけど借りたいと言ってきまして、なんでもタイで国際的な動物商をやっていて、日本にも本拠地を探したいのできたと言っていましたな、それで、犬猫を飼えるマンションを探していたということでした。一年間前払いでしたよ」
「月いくらですか、トンチャンさんの部屋は十三万で、月の管理費が一万二千ですよ、さらに一年しかいないので、できれば光熱費は月二万ということで、こちらに支払う形にしたいとおっしゃいましてな、そんなに電気を食わないでしょうし、水道代だってたいしたことはないので、いいですよということで、それも前払いでいただきました、あと駐車場の代金もいただきました」
「なにをしていたのでしょう」
「動物を輸入して、日本で売っていたようです、それをしながら、どこに支店を出そうか考えていると言っていました」
「特に、トラブルはなかったですか」
「え、私も気になっていたので、最初はメンテナンス会社に様子を聞いたりしましたが、ゴミは少ないし、きれいにしていたということです」
「やめるときには顔を出しましたか」
「ええ、タイに帰ると言うことでした」
「どこかに行くとはいっていませんでしたか」
「そういう話はしなかったですね、最後にお菓子などをもってきて、日本人みたいだなと思いましたよ」
「そうですか、パスポートは確認されましたか」
「はあ、まあ、外人さんに貸すときは、コピーをとらせていただいています」
不動産屋のおやじは帳簿を引き出すと、ページを開いて、貼り付けてあったトンチャン・ウオンのパスポートコピーをみせてくれた。
「きちんとされてますね」そう言いながらスマホで写真を撮った。
「いや、あたりまえなんですけど」
「あ、そうですね」
吉都はあわてて笑顔を作った。不動産屋とはいい加減なものだと思っていたからだ。
「また何かありましたらくるかもしれません、そのときにはよろしくお願いします」
野夢が巣鴨の饅頭を差し出した。
「これはどうも、探偵さんからお饅頭をいただくとは思いませんでしたな」
「それでは、失礼します、ありがとうございました」
二人は不動産屋をでた。
「ハチ公に、トンチャンがなにを輸入していたのか調べてもらいましょうよ」
うなずいた吉都がハチ公にスマホで電話をすると世久がでた。元気な声なので、野霧にも聞こえる。
「さっき、不動産屋から電話があったわよ、宙夜さんがでたんだけど、猫の骨のことだろうと思って、思いっきり探偵事務所をほめておいたと言ってたわ」
「うん、おかげで、話がスムースにいったんだ。調べてほしいことがあるんだ。サーマート・リーは偽名で、トンチャン・ウオンであることがはっきりした。不動産屋にあったパスポートのコピーでわかったんだ。ウオンは猫を輸入していたようなので、輸入管理局あたりで、調べてもらえるかな」
「できるわよ、こっちもトンチャン・ウオンについては調度調べがついたところ、メイルで送るわよ、猫の輸入についても調べてみるわ」
「うん、これから事務所に帰るところだから、またメイルする、たのむ」
「うん」
野霧が笑いながら、「世久さん元気ね、ここまで声が聞こえる」
「うん、元気すぎる」
「西国分寺のおみやげ買わないの」
「そんなもんないでしょ」
おちょくられた吉都がどぎまぎしている。
二人が事務所に戻ると、詐貸が、ハチ公からトンチャン・ウオンについて連絡がきているよと教えてくれた。
「先生、トンチャンは小手指の池波さんにはだまって西国分寺で動物商をしていたようです、猫を輸入していたようで、それもハチ公に調べをお願いしました」
「そう、ハチ公のメイルでは、ウオンは確かに二年前に来日して、一年いて、タイに帰っている。ただ、詳細にパスポートのコピーをみたところ、偽物の可能性があるそうだ。あとタイのバッチェラ・リーというのはそれなりの大きな猫のブリーダーだそうで実在する。息子はサーマート・リーだが、来日したことがない、そう書いてあるよ」
二人がPCをあけると、たしかにそうあった。ということは、トンチャン・ウオンは誰で、何のために日本にきて猫を輸入したのか。十八匹の猫の骨とどのような関係があるのか。
「ずいぶん高い猫を輸入したようだけど、もしあの猫の骨がそうだとすると、輸入してなにをしたかったのでしょう」
「マンションの親子がウオンはたまに女性を連れていたといっていましたね、誰なんでしょうね」
「池波さんではない猫目石かもしれない」
「猫のブリーダーということですか、骨とつながらないとはいいきれないけど」
「猫女か、なんかあるのかな」
「たちはだかるは猫女のお岩か」
「猫女石だな」
詐貸がぼそっといった。
その後、ハチ公から、西国分寺のマンションのトンチャン・ウオンに高級猫がいろいろな国から送られてきていたという報告と、その猫の種類が、骨になった猫たちの種類に一致するということだった。手続きはまともなものだったようだ。個人輸入で、それで商売をしていたのなら問題だが、輸入して、儲けなしで誰かに譲るとしたら、問題ないそうである。
ともかく、トンチャン・ウオンが十八匹の猫の骨を埋めたことはほぼ確かだ。
小手指の団地の空き地から見つかった猫の種類と一致したことは、譲り渡したのではなく死なせてしまった可能性がある。ずいぶん上等な猫ばかりで、猫の価値からすると、総額五百万はくだらないだろうという。死んだら大損である。
ハチ公と打ち合わせをして、世久が吉都と一緒に西国分寺のマンションに行った。警察官となら隣の家などに聞き込みができる。
隣の住人は、トンチャン・ウオンを覚えていた。
「ええ、感じのいいひとでしたよ、よく上等なバスケットに入れた猫をもっていましたね、女の人がたまにきていましたよ、帰るときにはバスケットをもっていたから、猫を受け取っていったのかもしれませんね」
「猫はどのような種類でした」
「私猫の種類は分からないのですけど、日本の猫ではないようでした」
ほかの住人からこんな話も聞いた。
「トンチャンさんがきたとき、家庭電器製品を運ぶのを見ましたが、大きな冷蔵庫が印象的でした。一人暮らしであんなに大きいのいるのかなと思いましたね」
「夜は出かけていて、部屋にはいないようでしたね、午前中に車で帰ってきて、昼間いて、夕方車ででかけるようでした、私看護婦をしているので、夜にでることが三日に一度はありましたけど、夜に車はありませんでしたね」
そんな話が聞けた。
「裏にかなり大きな、なんかの組織がありそうな気がするわ」
キックがいうと、吉都もうなずいて、
「うん、あの空き地に埋められた猫の骨は、トンチャン・オン、別名サマート・リーが、何らかの理由で、埋めたわけだ、売り物の大事な猫をどうしたのだろう、いったい彼はなにをしていたのだろうね、猫を取りに来ていた女とは誰なのか」
「すぐには解決しそうもないわね」
「我々の前に猫女が岩のように立ちはだかっていると言ったら、詐貸所長がそれは猫女石だって」
「その女を追いかける必要があるのかもね」
その後、輸入された猫は、管理局の方に、直接トンチャンが車で取りに行っていたこともわかった。
猫の交通事故
庚申塚探偵事務所の電話が鳴った。野霧がでた。
「はい、猫探しは得意です、しかし百パーセント見つかると思わないでください、雄ですか、雌ですか」
「雌です」
「つらい言い方ですが、雄は雌より遠くまで遊びに行くので、見つかっても、自動車にはねられたりして亡くなっていることもあれば、他の家の猫になっていて、そこの子供が離さないなんていうことがありますが、雌ではあまりそういたことはないので見つかる確率は高いとは思います、しかし確かなことはいえません」
野霧は経験からはっきり言う事にしている。
「いなくなってどのくらいになりますか」
相手が細かく話し始めた。
「とすると、昨日、夕方、買い物にでて、帰ってくるといなかったわけですね、昨夜探したわけですか」
「はい、朝になってもでてこないの、今日も今まで探したんですけどみつからなくて、近くにすんでいる娘が言うには、早く手をうったほうがいいというので、猫探しをネットで娘が調べたら、おたくがでてきたのですわ、お高いのですか」
「料金ですか、基本料金は一日、一人だと、八時間で一万五千円、二人だと三万になります。お客様の申し出で調査期間をのばします。元気な状態で探し出したときには成功報酬として、基本的に二万円いただきます。一日で見つかった場合には、成功報酬は三万、二日以上かかると基本の二万になります。誘い出すために使ったもの、たとえば餌などは実費、見つけた猫の運搬賃も実費です、トラックの荷台にのって、百キロ先で見つかったなんてこともあります、何処にいるかがわかったところまででよければ、成功報酬は一律一万円です、早い方が早く見つかる確率が高くなります、ちょっとまってください」
野霧が受話器を押さえて、詐貸に聞いた。
「目白で猫探し依頼です、すぐいっていいですか」
「いいよ、たのむよ」
野霧が相手に
「準備ができたらすぐ行きます、近いのですぐいけると思います。目白の駅から電話します」
野霧はそういうと受話器をおいた。
「猫探しとは久しぶりだね」
「ええ、目白台2丁目のマンションで一人暮らしの女性の人です、声からすると、六十すぎくらい」
「どんな猫」
「ペルシャの雌です、飼い始めてまだ二ヶ月で、近くの公園にだっこして連れて行ったことがあるだけで、外にはだしていないそうです、夕方買い物から帰るといなかったということなの」
「盗まれたんじゃないの」
吉都が言った。
「その可能性もあるわね」
「そうね、高い猫だしね、所長、それじゃでます」
「うん、吉都も暇だろ、一緒にいっといでよ、一人分の料金で、二人で探しますと言えば喜ぶよ」
「はい、いきます、所沢の猫の骨の件から外にでる機会がないから」
「野霧さんどういきましょうか、都電で雑司ヶ谷か、山の手で目白駅」
野霧が聞いた住所を地図で調べた。
「目白通りに近いようだから、目白にしましょう」
二人は書類をもち、庚申塚探偵事務所をあとにした。
巣鴨から目白までは近い。目白駅から歩き、不忍通りとの交差したところを過ぎると目白台になる。何本目かの路地を曲がり、二つ目の通りの角に瀟洒な十階建てのマンションがあった。そのマンションだ。住宅街の一角で、公園なども整備されている。
依頼人は柳井真智子といった。入り口の前に、迷子猫の紙がすでに貼ってあった。電話を入れると、入り口が開いた。エントランスが広い。エレベーターで二階に行き、ベルをおすと小柄な女性が顔を出した。
「庚申塚探偵事務所の者です、契約をする前に、いろいろお話をして可能性を考えたいのですが」
野霧が名刺を出した。
「動物に詳しい者もつれてきました。やはり庚申塚の探偵助手をしています。生物学の大学院をでた人ですので、猫のことはよく知っています、お手伝いします」
「お二人でお探しになるの」
料金を心配しているようだ。
「はい、一人の料金で結構です、今三時ですので、明日の三時まで、その間八時間ほど調査します。」
彼女はにこにこして、二人を部屋に招き入れた。ソファーに座ると、野霧が契約書の説明をした。
「ええ、それで結構です、すぐ探してくださるの」
「はい、その前に、猫の写真のあるビラを何枚かください、ほかにあったら写真もお借りしたいのですが、それと、いつも食べている餌をください」
「名前はペルちゃん」よといって、もってきた。目のくりっとした、真っ白でお嬢さんタイプの猫ちゃんだ。目の色は両方とも青、赤い首輪をしている。
「どうされたんですか」
「買いましたのよ、直接、純粋なペルシャをタイから輸入してもらいましたの」
「動物商が手配してくれたわけですね」
「ええ、、税関から直接うちにきたんですの」
「何処の動物しょうですか」
「娘の紹介で、猫のトリマーの人で輸入もやっている方がいて、その方に頼んだのです、動物商もやっているということでしょうね、すべてやってくれて、しかも、そのほうがずいぶん安い猫ちゃん、ちょっとわけ有って言ってたけど、とても元気だったしかわいいのよ」
「そうですか、それでは、これからあたりを歩いて調べてみます。夜中も我々は探しにきます。場合によっては夜の方が見つけやすいこともあります。まだこのあたりになれていない猫ちゃんだから、どこかの隅にうずくまっているのではないでしょうか。夜、お腹がすいて、いつもの餌の匂いに誘われて出てくることもあります」
「私も餌を持って探しました」
「一つ心配なのは、逃げ出した猫ちゃんを捕まえて、売りさばいてしまう悪い奴がいること、そうなると、探しようがないですね」
「怖いわね」
「それに、大きな道ももちろん怖いのですが、住宅地のいつも車が通らないようなところでも轢かれてしまうことがあります。自動車は猫を轢いても知らん顔で行ってしまう、ちょっと良心のある運転手でも、轢いた猫を道の端に寄せるだけのことが多いですね、動物病院に連れて行ってくれたなんて話は今まで聞いたことがないですね」
「それもいやね」
「あ、怖いことばかり言ってすみません、これから、マンションの敷地内を確認し、道沿いを探して、夕方またまいります、それまでに契約書を書いておいていただけますか」
「はいはい、お願いしましょう」
「外にでる前に、お部屋をみせてくれますか、どこからでたとお考えですか、トイレの窓だとか、風呂場だとか、どうですか」
「そうだわね、この居間の戸も外はベランダだから可能性はあるけど、昨日は寝室にいれてでかけたから、寝室の窓ですわね、時々鍵をかけるのを忘れることがあるのよ、ごらんになる、窓の下は居間につながるベランダですのよ」
寝室を見た。確かに窓の外はベランダであり、下はマンションの敷地である。落ちたとしても、土の庭で怪我をするようなことはない。その場で鳴いているだろう。他の住人が鳴き声を聞いている可能性もある。
「マンションの人は気がついていないのですね」
「聞いたた限りでは、猫の声などもきいていないようです」
鳴き声をあげなかったとすると、歩き回って、物陰や木の陰などに隠れるだろう。歩き回って、偶然庭から外に出てしまった可能性もないではないが、盗まれた可能性がかなり高い。
「外に出るとやはりこの窓ですね、鍵が開いていたとすると、ベランダからマタタビなどでおびき寄せて、盗んだということも考えられますね」
窓からは小さなマンションがちらほら見える。道を隔てて、大きな個人の家も集まっている。
「あちら方面に広がっている戸建てのほうは探してごらんになりましたか」
「はい、道の向こうにはちょっと行きました。公園にも」
「我々はこのマンションの周りからはじめて、いそうなところを探します。これから夜の十時頃までさがして、朝の四時からまた探します。このマンションは管理人は住んでいらっしゃらないようですね」
「ええ、通いの方がいます、朝のゴミ収集の準備と掃除で、午前中で帰るわね」
「私たちが、猫探しをしていることを、その方か、管理会社に言っておきたいのですが、どこに連絡をしたらいいでしょうか」
「管理人の人は猫がいなくなったことを知っています、それにマンションの管理組合の会長さんにも言いました」
「ありがとうございます、会長さんには今から挨拶にうかがいます、なん号室でしょうか」
野霧と可也は会長に挨拶してから、猫の捜索に当たることにした。会長さんに言っておかないと、我々の方が怪しまれてしまう。
「柳井さんも、時間のあるときにはマンションの中を探してみてください。飼い主の声が一番安心しますから」
「ええ、もう何度か回ったんですけど、また歩いてみます」
管理組合の会長さんも、笑顔で「とうとう、探偵さんがお出ましですな、うちにも猫がますから気持ちはわかりますよ、ぜひみつけてあげてください」
そう激励された。いい人である。
マンションの周りは、金網の柵が張り巡らされており、内側の庭にはつつじなどの低木が植えられている。二人は植木の間を一通り見ると、建物の周りを見て回ったが、隠れるような場所はなく、少なくともビルの庭にはいない。すでに飼い主が調べたわけだから、見ることもないが、万が一と確認をしたわけである。
猫が外にでやすいところは、やはり玄関前の道路の方向である。道路沿いも一通り見て、道路の反対側の個人住宅街にはいった。柳井さんの部屋から望めた場所である。人の気配が濃いところだからいる可能性はある。道の側溝には蓋がしてあるが、開いているところがあると、そこから中に入りやすい。どの家にも広い庭があり、高い塀で囲まれている家の庭にはいってしまうと、ちょっと大変だが、夕方お腹がすいて、家の周りをうろついて家人に見つけられていることもある。しかし、飼ってまだそんなに日数がたっていないことと、家猫であることを考えると、他人に対し恐怖心の方が勝っているかもしれない。
二人はチラシを、堅い透明のファイルに挟み首にかけ、背中に回した。こういうところは排他的で、変な目で見られる。警察にでも通報されると面倒だ。見かけた人には可能なかぎり話しかけ、チラシを渡し、自宅の庭をチェックしてもらったりした。路地を一時間ほど歩いたが、手がかりはなかった。
少し離れているが目白台運動公園や日本女子大などがある。そういう広いところに行ってしまうと大変だ。目撃者を捜す必要がある。
六時近くになり、柳井さんの家に一度戻った。
「住宅地をちょっと歩いただけですから、まだわかりませんが、見かけた人はいないようでした。夜になると、お腹も減り、寂しくなって、鳴くと思うのですが、鳴き声を聞いた人も居ませんでした。夜になってからまた探しにきます。ここにはよりませんが、何時頃お休みなりますか」
「十時ころですけど、でも眠れませんね、今日は」
「そのころ一度電話をします、猫ちゃんのことはお任せいただいて、ともかく体調を整えておいてください」
そう言って事務所に戻った。
「どうだった」
所長が待っていた。
「ちょっとやっかいかもしれません、マンションにはいないようで、前に広がる住宅地の中に行った可能性もあります」
「夜中にそのあたりを探します」
「うん、いそうなところだけをあたれよ、全部見るのは無理だから、それに盗まれていたりしたらどうしょうもないからな」
「ええ、その可能性はありますね、だけど、部屋を見た限りでは確証はえられませんでした」
「話が違うが、薩摩から電話があってね、所沢の猫の骨の件、トンチャン・ウオンの正体ははっきりしない、それに、今はどこにいるか全くわからないみたいだ。ウオンのマンションに行ったとされる女に関しても全く手がかりがないということらしい、その件はゆっくりと調べるので、とりあえず、うちへの委託は終了だってさ。雀の涙ほどの委託料が振り込まれるそうだよ」
詐貸が笑った。
「そうですか、我々は、八時頃もう一度目白に探しに行きます。十一時まで探して、見つからなかったら、明日の早朝出直します」
「俺は何時に行こうか」
「朝早いのは大変ですか」
「必要ならいくよ」
吉都が「でも、八時から十一時までに所長と野霧さんが行って、四時頃、僕が一人で行きます、九時あたりから、野霧さんが合流してくれますか、その方が効率がいいでしょう」
「所長と吉都君がいいならいいわよ」
詐貸と吉都がうなずいた。吉都は猫探索の道具をもつと、家に帰る準備をした。
「頼むな、ヘッドライトをつけて猫のチラシをからだにつるしておいたほうがいいからな」
「はい、4時頃から始めてます」
吉都が事務所をでた。
「我々は、腹ごしらえをしてから出かけようよ」
「はい、そうします」
「そば屋に行こうか」
「いいですね」
詐貸には行きつけのそば屋があった。都電荒川線の庚申塚駅からちょっと歩いたところにある「ひさご」である。探偵事務所は隣の駅の新庚申塚のほうが近い。そば屋まで四、五分歩かなければならない。
「お、詐貸さん、野霧さんも久しぶり」
「お久しぶりです、いつものください」
「おれも」
天ぷらそばである。四月初めだと主人が茨城まで行って、採ってきた山菜の天ぷらだが、今は野菜である。
「私は、ししとう、あすぱら、みょうが」
「どれも三本つづにするよ、サービス、それに大盛り、始めてきたときを思い出すね」
野霧は嬉しそうにうんうんとうなずいた。普通は二本ずつである。
ひさごは七人はいると一杯になるカウンターのそば屋である。
四年ほど前に、野霧は庚申塚探偵事務所の助手募集の公告を見てやってきた。庚申塚駅で降りてしまい、まごまごしているところに、通りかかった人に事務所の場所を尋ねた。それがたまたまそば屋に行く詐貸だったのである。
そばを食べながら、就職相談をしたのだが、そのとき、野霧はザルそばを二枚ぺろりと食べた。主人はそのことを言っているのだ。
野霧は事務所に入ってから、三つほど大きな事件に関わったが、吉都とともに大活躍をした。
「またなんか大きな事件あった」
「いや、今猫探しているところ、こないだね、土の中からたくさんの猫の骨が出てきてね、警視庁から委託されて、調べたんだけど、まだはっきりしない」
「猫の飼いすぎで、何とか屋敷になって処分しちゃったんじゃないの」
「うん、それがみんな高級な猫ばっかりでね、どうもわかんないんだ」
「伝染病だとやだね」
「それは考えなかったけど、調べた警視庁ではそれはいってなかったから、違うんだろう」
「薩摩警視元気かね」
「うん、元気で飲んでる」
主人も野霧も笑った
カウンターにはできあがった天ぷらが塩の小壷とともにだされた。
塩で天ぷらを食べ、そのあとそばをうでてくれる。
「去年は犬の骨の事件じゃなかったっけ」
「うん、いや、犬の骨もあったけど、卑弥呼の事件だったな、あれはちょっと大変だった」
「解決したの」
「うん、いや、半分解決した」
「そりゃ、解決とは言わないね」
ヒサゴの主人が笑った。
「確かにそうだね」
「いつもそうですよ」
野霧がいうと、詐貸が「それだけ難しい事件ということだよ」
と笑った。
「猫、どこで探してるの」
「目白」
「カテドラルか、アーメンだな」
「どういうこと」
「天に召されているかもしれないね」
主人の冗談だが、なんだか笑えないものがある。本当になりそう。
「目白台だから、アーメンからはちょっと離れているわ、おそばおねがい」
野霧が大きな声をあげた。
おいしくそばを食べた野霧は、「まだ時間が早いですね、どうします」と詐貸を見た。
「うん、どうしよう」
「詐貸さん酒のむ」
主人の誘惑の手が伸びたが、野霧が、「これから猫ちゃん探し、高級住宅地の夜中に、知らない酔っぱらいが歩いていたらお巡りさんにひっぱられちゃう」
「そうだね」
「酔うことはないけど、野霧君の言うとおりに酒はやめとこ、コーヒーでも飲む」
詐貸に喫茶店に誘われたのは初めてかもしれない。野霧は、行きます行きますと、喜んだ。
「それじゃ、事務所に行って、コーヒーわかすよ」
詐貸がそう言ったので、野霧はがっかりしたが、うんとうなずいた。
「マスターごちそうさま、またゆっくりくるよ」
詐貸と野霧が立ち上がった。
「ありがとうござい、またどうぞ」
主人に見送られて、二人は事務所に向かって歩いた。
黒い猫が横町からでてきた。
「夜になると、猫ちゃん元気になるわね、おいで」と野霧がてをだすと、あわてて逃げていった。
「そういえば、愛子さん最近訳しているのですか」
「どうだろう、ノールウェーにはよく行っているようだよ」
「富山の方には一緒に行かれないのですか」
詐貸は顧問弁護士を引き受けている、富山の会社に月に一度、最近は二月に一度ほどだが、でかける。野霧や吉都が暇なときには一緒に行くこともあるし、時には愛子と一緒に行くこともある。この会社は愛子の祖父が起こしたものだ。
「行っていないね、君たちとも行っていないよね、この猫騒動が終わったら行こうかな」
野霧は行きたいと、うなずいた。
事務所の近くにくると、
「私、お菓子かってきます」
そう言って、腕時計を見ながら野霧は和菓子屋にかけていった。もう閉まっているかもしれない。
「コーヒーに合うのを頼むよ」
「なにがいいですか」
「わからんな、まかせるよ」
だいたい所長は自分で決めないんだからと思いながら、いつもの和菓子屋に行くと、主人のおじいさんとばおばあさんが、シャッターを閉めようとしているところだった。
「あら、野霧さん遅いじゃない」
おばあさんが振り返った。
「らっしゃい、今閉めるところだったよ、残っているのは、ポテトモンブラン」
おじいさんが、半開きの店の中のガラス棚を指さした。
「え、モンブランつくったの、はじめてね」
ここは、素甘、最中、饅頭、カステラそのようなものしかない。アイルクリームもある。どれも野霧の好物だ。
「芋でこさえてみた」
「おじいちゃんがつくったの」
「わしゃ、若い頃、洋菓子の修行をしたんじゃ」
サツマイモをたくさんもらってね、作ってみた、だけど売れ残り、どう、一つ百円でみなもってかない」
「あら、三つもあるじゃない」
「一つ250円なんだよ」
おばあさんが横から口をだした。
おじいさんは箱に入れてわたしてくれた。
コーヒーにはこのほうがいいかもしれない。
「ありがとうね、まだ仕事なんだね」
「うん、これからね」
「探偵だもんね」
野霧は猫探しとは言わなかった。
事務所に戻ると、詐貸がコーヒーをいれていた。だいぶ前に買ったモカを引いてもらった粉だ。
「所長すいません、そのコーヒー古いから味はどうかな」
詐貸は粉の入ったフィルターの上に、新しく沸かしたらしい湯をゆっくりと注いでいた。
野霧が買ってきたものを見ておやっという顔をした。
「あの和菓子屋のおじいちゃん、若い頃、洋菓子の修行をしたことがあるんだって、お芋のモンブラン」
そこではじめて、詐貸が笑顔になった。
「きっとおいしいな」
珍しく一言言った。
「和菓子屋さんだからわからないけど」
「ずいぶんよく練っている、甘みを抑えて、芋の味を出そうとしたんじゃないかな、カステラはいつも作っているカステラより砂糖を減らして焼いたものだよ」
詐貸が見ただけで、そんなことを言った。野霧葉オヤッと思いながらモンブランを皿に載せた。
詐貸がコーヒーをテーブルにもってきた。
「飲んでみて」
詐貸にいわれて、野霧は一口飲んでびっくりした。
「これ、棚に置きっぱなしにしていたコーヒーですか」
「うんあったやつ」
事務所ではお茶をよく飲むので、八女茶を用意してあるが、コーヒーはもう半年もいれていない。
「こんなにおいしいくなるとは思いませんでした」
モカだから、香りもさほどないだろうなどと思っていたら、上等のキリマンジェロのように、コーヒーの香りもただよってきた。味も、しっとりと隠し味のように酸味の利いたモカだ。
「おいしい」
「きっと、モンブランもおいしいよ」
詐貸は先にモンブランにホークをいれ口にいれた。珍しい。
「うん」
ただ一言うなずいた。
野霧も食べた。詐貸が言ったとおり甘すぎない、お芋の香りと味が残っている。
「どうして、食べないうちから、おいしいとわかったんです」
詐貸の笑い顔は簡素な笑いでいい。正直な笑い顔だ。滅多に笑う訳じゃないが、野霧はいつもそう思った。
「色の具合、湿り気、全体のバランスかな」
そういうことをすぐに判断してしまうすごい能力を持っているのが所長なんだ。それにしてもあの古いコーヒーが、なんておいしいコーヒーになるんだろう。野霧がきく前に詐貸が言った。
「おれね、バーテンやってたろ、バーテンは酒の味や知識だけじゃなくて、飲んだ後の始末も勉強するべきなんだよ、飲んだあと、ラーメンを食べるやつもいるだろう。そうだったら、おいしいラーメンの味を知っておく必要があるよね、できたら作れなくちゃならないね、サンドイッチ、スパゲティーなどもね、同じように、コーヒーにたばこを飲むやつもいる。コーヒーもおいしく入れられなければだめだよね、今たばこはやめたが、そのころ、世界のたばこを試したよ。コーヒーも家では自分でいれるようにしていたんだ。
「いまでもですか」
「うん、昔ほどじゃないけどね、ラーメンもつくるよ、それに、ウイスキーのおつまみは用意してある。いろいろね」
「はじめて知りました、まさかおいしいコーヒーとおいしいケーキにありつけるとは思っていなかった」
「野霧君は口が肥えているよ、あの和菓子屋のじいさんは相当わかっている人だね、だからおいしい和菓子を作れるんだ。コーヒーも野霧君の口に合うようにおいしくいれてみたんだ」
詐貸に自分のことを言われたのは初めてである。ちょっと嬉しかった。
「一つじゃ、たりないだろ、モンブランもう一つ食べたら、コーヒーもっと飲むかい、二番だしだけど」
「はーい、食べます、飲みます」
いつもの野霧にもどっている。
八時近くになった。野霧はあわてて皿とカップを洗った。
「最初に目白の警察署に行くからね」
「なんかあったんですか」
「いや、今日二人が猫探しに行っているときに、薩摩から飲もうって電話があったんだよ、だけど、目白で猫探しと言ったら、目白警察に電話いれとくから挨拶しとけっていわれてね、いいよっていったんだけど、夜中に歩いているとあのへんじゃ交番に通報されるってさ」
「マンションの会長さんには挨拶したんですけど、確かにそうですね」
二人はザックに必要なものを詰め込んで事務所をでた。
「目白警察だと、JR巣鴨から目白駅ですね」
「タクシー使おう、夜だしね、必要経費だよ」
詐貸は一人だと電車を使う方が多い。きっと、野霧に気をつかったのだろう。
目白警察署について、受付にいくと、すぐに刑事課の警部が二階から降りてきた。
「詐貸さんですか、薩摩警視から連絡ありました。所沢の大量な猫の骨の件で、調査委託をした探偵さんで、弁護士さんでもあるということをお聞きしています。目白台で猫の調査だそうで、警視は裏に大きな事件があるかもしれないとおっしゃってました」
なんだ、薩摩のやつずいぶん大仰にいいやがって。
警部は名刺を詐貸にわたした。詐貸も名刺を出し、助手の野霧を紹介した。
「それで、何か聞かれたら、私の名刺を見せてくださってかまいませんし、目白の交番にも伝えておきます」
「ありがとうございます、今日明け方も捜索をしますし、見つからない場合にはもっとかかるかもしれません、よろしくお願いします」
「薩摩警視は柔道も強かったですね、警視がまだ警視庁に入り立ての時でしたね、警視庁の柔道大会で準優勝されましたな、私とほぼ同期ですよ」
「そうでしたか、それではよろしくお願いします」
詐貸が野霧と警察署をでようとすると、「ここから目白台まで歩くのですか」と、警部が声をかけた。
「ええ」
「だいぶありますよ、私はこれから家に帰るところです、目白通りを通りますから、私の車に乗っていってください」
「そんな、ご迷惑をおかけしては」と遠慮をしたのだが、家に帰る用意をして降りてきていた警部はどうぞどうぞと、彼の車に二人を連れていった。
車の中で警部は、
「大学生の時に法律の国家試験に合格していて、なぜ探偵さんになられたんです」
ときいた。薩摩がべらべらしゃべったようだ。
「いや、私の考えの至らなかったところです。だけど、今は満足しています」
「そうですか、薩摩警視は仙台の警察にいるときに大きな事件でたいそう助けられて、それで、警視庁にもどれたんだ、と言っていましたよ」
どうも薩摩の話はおおげさだ。
すぐに目的の場所についた。
「ありがとうございました、これから十二時くらいまで探します」
「いや、大変ですな、どうぞおきをつけて」
人のいい警部は車をだした。
「薩摩の奴、そうとうほらを吹いたな」
野霧は「そうでもないんじゃないですか、みんな本当のことですよ」と笑いをこらえた。
「あいつ、警視庁に戻りたいと思っていなかったんだよ」
「そうでもないかもしれませんよ」
野霧に言われて詐貸もちょっとうなずいた。
「このマンションです」
野霧と詐貸はヘッドライトをつけて、チラシの入ったファイルを首から吊し、玄関から、柳井さんに電話を入れた。
「これから、夜の調査をします」
「あ、今玄関にいらっしゃるの、ちょっと下におりますからまってて」
柳井さんがおりてくると、「これ、喉がかわいたときにどうぞ」とペットボトルのアセロラドリンクをもってきた。
「あら、吉都さんじゃないの」
「詐貸所長です、これから、十二時まで捜索し、吉都は朝四時から始めます、私も九時頃合流します」
「所長さん、みずからですの」
「詐貸です、みつかるといいのですが、数日かかるかもしれません」
「よろしくおねがいしますね、ペルちゃんとはやっと仲良くなり始めたところですのよ」
「これありがとうございます」
詐貸と野霧はアセロラドリンクをザックに入れて、もう一度マンションの周囲を見て廻ってから、道を渡って住宅地に行った
「うーん、ゆっくり歩いて、塀の陰や木の下などをみるしかないね、庭にいれば住人が気づくだろうしね、問題は隠れられるところだね、エアコンの室外機のわきだとかね」
「ええ」
野霧は小さな声で、「ペル、ペル」といいながら歩いた。ところどころにある、小さな空き地や公園を入念に調べた。いきなり懐中電灯で照らすと驚いてでてこないから、物陰があると、ちょっとあけた猫餌の缶詰をおき、声をかかける。それでも反応がないと、懐中電灯で照らしてみる。繰り返しいろいろなところで試みたが、猫は出てこない。それよりも、一匹の猫にも出会わない。
「あまり遠くに行かないと思うのだけどね」
「先生はずいぶん猫を探したのでしょう」
「うん、一人でこういうところを歩いたけど、マンションの場合にはだいたい、建物の周りでみつかったし、一戸建ての家からいなくなったのは、側溝や公園の藪の中、よその家のあいている物置だったかな。外に自由に出している猫がいなくなったときには、猫とりにつかまっていたり、車の荷台に載ってどこかにいってしまったり、やっぱり交通事故で、死体を清掃局で処理していたりだね」
「清掃局なんですか」
「死んじゃっているときは、最終的にそこに行くけど生きていればどこかの動物病院で、動物愛護団体によってマネージされている」
「ペルちゃんはどう思います」
「うーん、飼ってまだ一月、外にはほとんど出していないようだから、地理感覚は全くない、とすると、猫の本能で、安心できるところに身を隠している。あまり遠くには行かない。しかし、近くにはいない。とすると、高価な猫だから盗まれた可能性があるな」
「家に誰かはいった様子はないと言ってました」
「猫を盗みに入る奴はいないことは確かだろう、危険な割にはあまりもうけもないし、ペルの場合には柳井さんが飼っているということがまだあまり知られていない。もし盗まれたら、何か他の理由がある。、交通事故に遭うほど遠出しないと思うよ、マンションの前で事故にあえばすぐわかるだろうしね」
「今探しているところはどうですか」
「ここかい、マンションから数軒先だね、このあたりまでは、何らかの拍子にくるだろうけど、もう少し先にはあまり行かないだろうね、雌だったよね、その場所をよく知っている雄猫で、出歩ける自由猫ならいくだろうけどね、それでも野良雄の縄張りは直径1キロほどらしいよ、広い畑や山のある田舎と都会では違うし、個体の性格にもよるしね、家猫の縄張りは基本的には自分の家と、庭、歩き回っても100メートルほどではないかな」
「とすると、このあたりは、マンションから200メートルほどですか、ここまで来ている可能性は薄いですね」
「まあ、ペルだとここまでこないだろうな」
「どうしましょう」
「マンションを中心として、東西南北、だいたいこの距離まで歩いて探せば十分だね、それで終わりにしよう、十分すぎるかもしれないな、売っている猫の餌しか食べていないとすると、おなかが空いて、マンションのあたりをうろうろしているはずだから、ここまで調べていないなら、何らかの理由で、遠くに運ばれたということだろうね」
「まだ九時半ですけど」
「もう一度同じところを見回って、マンションの周りを回って終わりにしていいだろう」
「それでも見つからなかったら、どうしましょうか」
「吉都が朝見回ってでてこないようなら、ここにはいないということだよ、別の角度から考えないとね、上等な猫だから、人にはなれているだろうけど、道路や騒がしいところはなれていないだろうね、一日で終わりにした方がよいだろうね、依頼主さんにもそういって、別の方法で探すことを考えたほうがいいよ、だけど、あの飼い主さん、あんまりご執心のようじゃないようだね、むしろ娘さんに勧められて飼ったのじゃないかな」
「十時頃電話をいれることになってます」
「もう一回りして電話をしたら」
「はい」
二人はマンションに戻り、周りを歩くと、依頼者に電話を入れた。
「あ、まだ見つかりません、すみません、あと一時間ほど探して、次は4時から、吉都と交代します」
眠そうな柳井夫人の声が聞こえてきた。
「あら、残念ね、よろしくお願いしますね」
「はい」
電話が切れた。
「依頼人の声が聞こえたよ、あまり熱心でもないね」
「そう思いますか、あと一時間探しますか」
「無駄なようだな、やめて、事情を話して、捜索料を安くした方が喜びそうだな」
「それじゃ、戻りますか」
「うん、そうしようよ」
二人は目白にでて、詐貸は事務所に戻り、野霧は京王線笹塚の家に戻った。
次の朝九時、野霧は柳井さんのマンション入り口に行った。吉都がぼーっと立っている。
「あ、野霧さん、おはようございます」
「おはよう、ごくろうさま、どうだった」
「生きたペルちゃんは見つかりませんでした」
「どういうこと」
「まだ、柳井夫人には連絡していないのですけど、四時からこの周りを探していて、朝八時頃、ここに戻る途中で、集団登校する小学生とすれ違ったんです。その中の一人が僕のかけていた猫のチラシをみて、「あ、あの猫だ」と指差したんです、それで、「見たの」ときいたら、「おととい学校から帰るとき、あっちの道で轢かれてた、母さんが電話した」と教えてくれました。確認してから柳井さんに連絡しようと思って」
「そう、だとすると、清掃局かしらね、そこで確認してから、柳井夫人に連絡しましょう」
「それじゃ、目白だから文京区の区役所に聞いてみますけど、開くのは九時ですね」
「そうか、それじゃ、いったん事務所にもどろう」
二人は事務所に行き、野霧がお茶を入れる準備をした。
「なんだか、いいコーヒーの香りがしますね」
吉都が不思議そうな顔をしてソファに座った。
「うん、昨日、猫さがしの前に、所長がコーヒーを入れてくれたのよ、とても上手なの、おいしかったわ」
「へー、所長が、珍しいですね」
事務所のテレビをつけ、時間になるまで待った。
九時、吉都が電話番号をさがしだして清掃課に連絡した。
吉都がえっと、驚いている。吉都はスマホのスイッチを押して、相手の話が野霧にもきこえるようにした。
「死んだ猫ちゃんは、私道で見つけた場合には、東京都委託の文京区清掃事務所に連絡いただいています。2600円です。都道で見つけた場合には、引き取り手がなければ、無料で同じ事務所です。または自宅の猫ちゃんを引き取る場合も、同じ事務所でいいのですが、2600円いただきます。区道のときは、道路課維持係りに連絡ください。国道の場合には、国土交通万世橋出張所、公園だと、みどり公園課です、電話番号をお教えします」
「あ、はい、都道と区道の電話番号を教えてください、それに目白台2丁目担当の清掃事業所のものも」
野霧が手帳に素早く書き留めた。
「ありがとうございました」
「ばらばらでたいへんですね」
「ほんと、あそこは都道か区道ね、きっと区道でしょう、そこに電話してみるわ」
野霧が道路課維持係りに電話をした。昨日の夕方、目白台の2丁目で轢かれた猫のことを聞くと、清掃事業所の方にあるということで、そちらに電話したら、冷蔵室にあるという。場所を聞いて、すぐ取りに行くことを連絡した。
そのあと野霧が柳井さんに電話をした。
「今、探偵事務所から電話をしています、残念ですけど、自動車事故にあわれて、いま清掃事業所の方にご遺体があることがわかりました。これから行こうと思いますが、一緒に行きますか」
柳井さんも行きたいということで、タクシーでマンションにまわり、柳井さんをひろうことにした。
十時前なので詐貸はまだ事務所にでてきていない。後で連絡すればいいだろう。
タクシーがマンションの前につき、電話を入れると、柳井さんはおしろいを塗って、正装をしてでてきた。
「ペルちゃん、お気の毒です」
「ほんと、かわいそうね、痛かったでしょうね」
「このままタクシーでいきます」
「おねがいしますね」
目的の清掃事業所に着くと、係りの人が冷蔵庫から布にくるまれた猫の遺体をもってきた。
「ご確認ください」
からだがつぶれている。
柳井さんは「あ、ペルちゃんだわ、首輪もしている」
「首輪に住所を入れておくと、こちらから電話できたのですが」
係りの人は、申し訳なさそうに言った。
「ええ、次にはそうしますわ」
「ご遺体、もって帰られますか」
「どうしましょ」
「ここでもお引き取りできますが、2600円かかります」
「そうしてもらえますか」
野霧と吉都はちょっと驚いた。
「首輪はどうしましょう」
係りの人がきくと、「いらないわ、次のには新しいのを買いますから」と柳井さんはことわった。
「領収書をいただけますか」
係りの人はちょっと意味がわからなかったようだ。
「引き取りの2600円の領収書」
「あ、はい、その前に、書類をお書きいただきたいのですが」
係りの人がもってきた書類に柳井夫人が記入している間に、吉都が布を広げて遺体を詳細に観察をした。
吉都が何かを見つけたようで、野霧のところにいって、耳打ちをした。野霧は鞄からカメラを取り出すと、猫の遺体の写真をいろいろな角度からとった。ひっくり返しても撮った。特にお腹のところをズームして撮った。
「なにしてらっしゃるの」
書類を書き終わった柳井夫人がよってきた。
「すみません、我々、仕事の証拠を残しておかなければならないので、写真を撮らせていただきました。ファイルしておかなければなりませんので」
野霧がいうと、そうねと、お金を払いにいった。おわると、
「私、これから買い物に行きたいんだけど、そちらのお支払い後でいいかしら」
「はい、近々請求書を作って、おもちします、明日以降になりますが、お伺いします」
「いいですことよ、ありがとうね、それではここで失礼するわね」
柳井夫人は出ていってしまった。
野霧と吉都は顔を見合わせた。
「あのう、ちょっとうかがっていいですか」
野霧が係りの人にきいた。
「はい、どうぞ」
「ペルちゃんは一昨日、帰宅中の小学生が車に轢かれているのを見つけたと聞いてますが、何時ごろでしょうか」
「ちょっとお待ちください」
係りの人は帳簿を開いた。
「一昨日の四時頃ですね、子供の親という人から、電話があって、こちらの係りの者が取りに行ったとかいてあります」
我々が探し始めているころだろうか。
「現場の様子は書いてありますでしょうか」
「そうですね、道の端よりのところにあったようです」
「もう死んでいたのでしょうか」
「そうですね、見つけた子供の親は死んでいたと言っているようです」
「即死と言うことはよくあるのですか」
「頭などをやられると、即死ですね」
「この猫は頭に打ち傷はないようですね、上から轢かれたようようですが、それにしても内蔵がでていませんね」
「ええ、こちらで、からだのなかにいれたのかもしれません、通常は見た目をきれいにしてあげます」
「猫って体の上から轢かれるってあるのですか」
「ありますね、はね飛ばされて頭やからだを打って死ぬことが多いのですけどね」
「はじめから体を轢かれることありますか」
「ないとはいえませんが、多いのは、二台目の車に体を轢かれてしまうことですね」
「それで、ペルを見つけてくださった方にお礼をいいたいのですが、電話番号を教えていただけますでしょうか」
「あのう、今個人情報でうるさいので、無理ですが、これから飼い主が見つかったことを発見者に報告しますので、お礼を言いたいという人に電話を教えていいか聞きます。柳井さんの関係の方ですか」
「あ、猫の捜索を頼まれていた探偵事務所です」
野霧が名刺をだした。
「ああ、それじゃ、外にでてしまった猫ちゃんですか、よく事故に遭うんですよね、年間三十万もの猫ちゃんが事故に遭うというデーターもあります。野良猫などの殺処分が年間三万ほどですから、事故死は十倍にもなりますよ、特に雄が出歩く1月から3月に多いんですよ」
「そんなに」
「ええ、かわいそうなものです」
係りの人が、発見者に電話を入れてくれた。直接でてくれと言うことで、野霧が電話にでて、説明をしたら電話と住所を教えてくれた。
「おかげで、いろいろ片付きました。ありがとうございました」
係りの人もいい人でよかった。お礼を言ってそこをでると、野霧が吉都に言った。
「それで、何で、ペルの写真を撮れっていったの」
「事務所に戻ったら、写真をPCにいれてください、気がつきませんでしたか。おなかがきれいに真ん中から切れていましたよ」
「あ、そうね」
「ちょっと奇妙なので見てみたいんです」
「うん、先に、どこかでお菓子かって、発見者のところに行こう」
ちょっとしゃれた洋菓子屋で、クッキーの詰め合わせを買うと、通りでタクシーを止め、発見者の住所のところに行った。昔からの家が集まっているところだ。
柳井さんのマンションが見える。
呼び鈴を押すと、まだよちよち歩きの子供をつれて、若い奥さんが顔を出した。
「先ほど、清掃事務所から電話をした、庚申塚探偵事務所の者です、猫のことでお礼をと思いまして」
「あら、ご丁寧に、上の子が学校から帰ると、猫が死んでいるっていうんで、見に行ったら、白い猫が道の端で死んでいたんです、それで保健所に電話したら、清掃事務所に電話しろと言うことで、電話したんです」
「飼い主は、ちょっと用事でこれませんが、大変感謝しておりました、これは飼い主の方からです。ありがとうございました」
「あら、そんな、ありがとうございます、どちらの方ですか」
「あのマンションの方です、柳井さんといいます」
「猫ちゃんの名前は」
「ペルちゃんです」
「悲しんでいらっしゃるでしょうね」
「ええ、それで、お子さんは事故を目撃されたのではないのですね」
「ええ、その日は四時ごろ、学校から一人で帰ってきました」
「車の量はかなり多いのですか」
「いえ、あまりないところです、このあたりに住む人か、用事できた人ですね、大きな道のバイパスにもならない道です」
「そうですか」
「息子もみな動物が好きなんですよ、下の子がもう少し大きくなったら、猫を飼いたいと思うのですけど、自動車事故は怖いですね、家のなかで飼わなければなりませんね、なんかそれもかわいそう」
「そうですね、ありがとうございました」
二人はその家を後にした。
巣鴨の事務所に戻った。
「ごくろうさま、交通事故だったね」
詐貸がデスクで仕事をしていた。
「はい、清掃事務所にいってきました」
「柳井さんは泣き叫んだろ」
「いえ、それが、死体の処理を清掃事務所にまかせて買い物にいきました」
「ふーん」
「轢かれた死体の写真がありますので、野霧さんにPCにいれてもらいます」
みんなで見ることができる。
ペルの腹部が映し出されたときに、吉都が、
「皮膚がまっすぐに切れているのがわかりますか」
と二人に聞いた。
「うん、わかる、これは刃物で切ったようだな」
「それじゃあ、誘拐犯がペルを捕まえて、切って殺して、道に放り出したわけかしら」
「それも一つにはありえる、だけど、動物を殺すのを愉快に思う奴は、すぐに見つかるようなところで殺して、放り出すことをするかい、飼い主に恨みがあるようなときにはそうするだろうけどね、人影のないところで殺してそこに放置するのが普通じゃないかな、夕方ではなくて夜やることが多いよ、轢かれたように見せた可能性もあるね」
「裏に何かある可能性がありますね」
「そうだね、だけど、柳井さんには言わないほうがいいよ」
「明日、請求書を持っていくことにしてあります」
「一日の一人の料金で請求してよ、必要経費は別に計算して」
「はい、作っておきます」
野霧が書類作成をはじめた。
「この件、ハチ公に連絡してみようと思うんですけど」
吉都が詐貸にきいた。
「その、お腹の件かい」
「ええ、キックに情報送っとこうと思います」
「うん、動物虐待の可能性も残っているしね」
「私、明日、柳井さんに、ペルちゃんのこともう少し聞いてみますね」
「そうだね」
明くる日、野霧は柳井さんからちょっと驚くことをきいた。
「昨日はありがとうね、おいくらかしら」
「所長が、一日一人分の基本料金三万円でいいということです、あと、交通費、それに、ペルちゃんを見つけた人へのお礼で、端数をおまけして、合計三万五千円です。これが明細と請求書です」
「あら、三人もでてくださったのに、それでいいのかしら、わたしのほうはね、保険が下りるのよ」
お金を出した彼女に領収書を渡しながら野霧は怪訝な顔をした。
「動物にも死んだときの保険があるのですね」
「ええ、だけど、これは特別なの、輸入をとりもった方の、特別配慮なの、うちに猫がきて半年以内に病気になると治療代がでるし、病死や不慮の事故死の時には、買ったときの金額が戻るの、または新しい猫をくれるのよ」
「そのようなのがあるのですね」
「ええ、娘が私に猫をプレゼントしようと思って、デパートの動物売場に行ったら、声をかけてくれた女性がいて、猫のトリマーをやっているのだけど、猫の個人輸入もやっていて、そんなに手間賃を取らないで、安く純系の猫が手に入るし、保険付きということで、名刺をくれたそうなの、流産したり、帝王切開したり、ちょっとわけありの猫だけど健康でペットとしてはとてもいいと、娘がペルシャ猫をそこにたのんだわけなの」
「なんという、方なのですか」
「本名は知らないけど、キャッツアイ、という猫の美容室よ、猫の輸入もやっているのよ」
野霧はどきっとした、猫目石だ。
「住所はわかりますか」
「知らないけど、娘が知っているわ、私はコンピューターできないけど、ホームページがあるようよ」
「今度の猫ちゃんもペルシャですか」
「どうしようかしら、猫ちゃんもかわいいけど、わんちゃんもいいし、お金でも返してもらえるから、キャッツアイでも買おうかしらね」
野霧は笑っていいのか、ちょっと複雑な目で、無邪気にしゃべっている柳井夫人を見た。
「私も猫に興味持ちました。お嬢さんに連絡していいですか、キャッツアイのことお聞きしたい」
「いいわよ」
「電話番号教えていただいていいですか」
柳井夫人は娘さんの携帯を教えてくれた。家で子供の世話をしているだけだから、いつでも大丈夫だという。
事務所に帰った野霧は柳井夫人の様子を報告し、吉都に「キャッツアイ」のホームページをみてくれとたのんだ。
「前に猫の動画を見ているときに出てきたやつかな、あ、ホームページがでてきました」
ホームページにはいろいろな種類の猫の写真がはりつけてあり、キャッツアイの主人が猫のお面をかぶって、薄茶色のペルシャ猫をトリミングしている動画があった。料金表があり、純系猫の輸入代理もおこなうことがかかれていた。吉都は電話番号とメイルアドレスをひかえた。
「キャッツアイを調査しましょう」
「ちょっとあやしさがあるね」
詐貸も気になるようだ。
「あ、キックからメイルがきました。ハチ公には猫の異常な情報はいくつかあるけど、矢で猫をねらったり、水に投げ込んだり、みな鬱憤晴らしのようです。これから、猫の交通事故のこと調べてくれるそうです、所沢の大量に見つかった猫の骨が、いま、第八研究室に持ち込まれていて、古本さんと高胎さんが組み立てているそうです」
「なにそれ、骨どうするんだろう、もう遺伝子検査はすんでいるんでしょう」
「そうですね、なんだろう」
「あそこの人たちは凝り性だから、おおかたプラモデルのように、組み立てて遊んでいるんだろ」
詐貸の想像が当たっていることを後になって知ることになる。
「薩摩がみんなで、神無月で飲みたいとさかんにいってるよ」
「わたしはいつでもいいですよ」
「ぼくもいいですよ」
「今週の土曜日にでも集まるか」
「それじゃ、私予約取っておきます」
「うん、むこうが何人くるのかきいとくよ」
ともかく、猫探しの仕事はとりあえず一見落着である。だが、詐貸にはこれがとんでもないものとして発展していく予感があった。
猫の輸入
土曜日、久しぶりに警視庁の捜査支援分析センター第八研究室、通称ハチ公のスタッフと、庚申塚探偵事務所のめんめんが、巣鴨の飲み屋、神無月に集まった。昨年、奇妙な事件の解決に向け、協力をしたことからよく集まるようになった。
「おっさん、適当にたのまあ」
神無月の入り口をあけると、薩摩が大きな声を上げて入っていった。みんなもぞろぞろとあとをつく。
主人が「今日は貸し切りじゃないよ」と怒鳴り返した。
「うまいもん食いたきゃもっと丁寧にいえ」
「あなたの声も大きいのよ」
奥さんの姫子さんが、三十も離れている禿頭の店主をいさめている。といっても、薩摩も主人も姫ちゃんもみんな笑い顔だ。周りのみんなは、いつものことと、しれーっとしている。
みんなが勝手にテーブルを移動して、周りに椅子をおいて腰掛けた。
「詐貸さーん、オールドパーの古酒があるよ」
主人がうれしそうに言った。
「いつ頃」
「兼松江商だよ、輸入税の証紙が貼ってある」
「ということは、一九七三年より前のものか」
「まだ開けてねえよ」
「開けるつもりなら、あとでください」
「うん」
周りの者にはこの会話はわからない。昔バーテンをしていた詐貸はウイスキーのことをよく知っている。
「ウイスキーのボトルの上に、昔は輸入税の証紙を張ったんだ、1974年からその制度が廃止されたんだ」
「どうしてです」
野霧が聞いた。
「そのころ洋酒の輸入がとてつもなく多くなったんだよ、一本一本貼らなきゃならないからね、無理になったんだ」
「そういうミニボトルうちにも何本かあるな」
ハチ公の凝り性で古い物が好きな古本羊貴が言った。彼は日本の古文章を読み解くことができる、プロの中ではよく知られている男である。
「今日は宙夜さん来てないのね」
「出張」
野霧がきくと、世久希紅子、キックが答えた。
「どこいってるの」
「インドから、タイから、ミャンマーからいろいろ」
「個人的な旅行じゃ楽しいですね」
「警視、言っていもいですね」
警察官は、やってることをやたらと外に漏らすことはできない。
「かまわんよ」
「最近宝石の密輸入が増えたんです、その組織を調べるために出かけているの」
そこへ姫ちゃんがビールと突き出しをもってきた。
「今日は畳鰯」
「ほう、めずらしい」
薩摩がぐっとジョッキを持ち上げた。
「とりあえず乾杯」そういって、半分ほど飲み干した。
「暑くなってきたので、うまいね」
「宝石の買い取り業者が、ここのところ、ずいぶん質のいい宝石が持ち込まれると言ってきたの、いくつものそういった業者と関係があって、情報が入るのよ」
「でも、それがなぜ密輸入なの」
「鑑定書がついているけど、今までみたことのないものなの」
「それで、宝石は本物なの」
「それが、宝石はれっきとした一流品なのよ、だとすると、きちんと輸入されていれば、税関の帳簿には残っているはずだけど、それらしいものがないのよ」
「税金のがれと言うことは密輸か」
吉都が畳鰯を珍しそうに食べている。
「醤油つけてもうまいよ」
詐貸が醤油を吉都に渡した。
「高胎さんと古本さん、猫の骨、組み立てているんですってね」
「あら、もう知ってるの、古本さんがバラバラの骨をもってきて、ジグゾーパズルみたいだって並べ始めたのよ、それで、この骨どこの骨ってきくものだから、一緒になって、ならべたの、これは骨盤とかね」
高胎蓉子はフランス文学をでてから、看護学校に入って看護師の資格をとった。だから解剖に詳しい。
「動物の骨は何度かあつかったことがあったからわかったのよ」
「高胎さんのおかげで、出来上がりましたから、いつか見にきてください」
古本羊貴はなににでも熱中すると仕上がるまでがんばる。
「十八匹の猫を全部ならべたのですか」
吉都がびっくりしている。
「もっと驚くぞおー」
薩摩が大きな声をあげた。
「なんですかあ」
野霧がジョッキをもうからにしている。
「立体に組み立てちまった、第八研究室は科学博物館だって、警視庁のお偉いさんまで見に来たよ」
「誰です」
「警視総監」
「よかったですね、驚いたでしょ」
「あの警視総監のあほ、暇なんだなー、なんてぬかしやがる」
「そりゃそう思うよ」
詐貸まで笑った。
「暇そうでおもしろそうだね」
カウンターの中で手を動かしていた主人も笑っている。
「宙夜さんは、どういうところに行って調べているのかしら」
「一つには、宝石の原石のでる採掘現場、原石がどのように、売られているか、現地の警察とも連絡して調べているのよ、それに、どこでカットされて、売られているか」
「時間のかかる仕事でしょうね」
「そう、一月はかかるみたい、随時連絡はもらうことにしているの、それでも終わらないでしょ、向こうの警察にも調べてもらうことにしてるのよ」
キックが野霧と吉都に説明している。
「それで、偽のパスポートを使っていたトンチャン・ウオンはタイにもどっているんでしょ」
野霧がキックに尋ねた。
「うん、関西空港から帰っていることは確かだけど、今タイにいるかどうか全くわからないみたい。本名もわからないし」
「偽造のパスポートずいぶんでまわっているんでしょ」
「そのようね、宙夜さんが、タイに行ったときに調べると言ってたから、そのうち情報が入るでしょう、猫のブリーダーのバチェラ、リーさんのところにも行くって言ってたわ」
「宝石の密輸って、どこが一番多いのかしら」
「どこかしらね、分からないけど大きな組織があるみたいよ、宝石の産出国は開発途上国も多くて、掘り出されたいいものを、横から買い取って、他の国で研磨して、大きな組織に売り渡し、それを外国に密輸して、その組織が大儲けするわけ」
「その組織の解明に宙夜さんがいっているわけね」
「そう、彼は宝石にも強いからね、ミャンマーやインドあたりから、タイなどに流れ、そこから日本に密輸されている可能性を考えているのじゃないかな、それに、南米からのものもいったんアジアのどこかに行って、日本に来るというルートもあるようよ」
「ヨーロッパからの密輸は少ないの」
「ないわけじゃないわ、ヨーロッパからは偽のアンティーク物が多いのかな、ともかく、密輸業者はあの手この手でもってくるわね、宝石を飲み込んで運んだり、義足の中に入れたり」
「かなり儲かるのね」
「原石で五百万で買ったものを、きれいにカットして、裏の組織に一千万でうって、組織が日本に密輸し、正規輸入品なら一億のものを、五千万で売りさばいても、儲けはすごいわね」
それだから、密輸は絶えないのだろう。
「猫って密輸入されることがあるのかな」
吉都がきくと、キックが「どうかな、一匹持ってきて、高く売ったとしても、たいした儲けにならないでしょう、だいたい隠し持ってくることができるかしら」
「は虫類なんかはあるようだね、小さなカメレオンとか」
「鳴かない奴はできるかもしれないけど、猫は鳴くしね、子猫なんてもっと鳴くから無理だよ」
「所沢の骨の事件、いっぺんに殺しちゃうということは、飼えなくなったブリーダーかしら」
「そういうこともあるわね」
「だけど所沢の骨は、年齢がほぼみな1歳から2歳ほどで、専門家は栄養失調や病気の兆候はないということだった、と言うことは、死ぬときまではそれなりにケアーされていたと言うことだな」
古本がそういって、ビールくださいと声を上げた。
「今日は元気ね」
高胎が焼いたノドグロをきれいに食べ、骨だけを箸で挟んで、「あげようか」と古本をおちょくった。古本はいつもほとんど会話に加わらないほど静かだ。
古本羊貴は当然、やだよとか言うかと思いきや、「そうか、今度は魚の骨を組み立てよう」と自分の魚の骨についていた身を綺麗に箸でつまみ始めた。
そういうことに目を輝かせるところが古本だ。
「そういえばなあ、成田の空港に警備のチーフで再就職したのがいてね、へんなことをいっていたぞ」
薩摩が話はじめた。
「警視庁にいた人かい」詐貸が聞いた。
「うん、有能な人で、いろいろ教わったことがあるんだが、政治的な人じゃなくてね、部長止まりで、退職して、そのあと、警備会社にはいったんだ、空港の警備主任のほうがいい収入だってさ」
「薩摩も早くやめるなんていいだすんじゃないだろうな」
「まだまだ、子供も小さいし、宮城に帰ったってそういい仕事はないよ、せいぜいマーケットの警備員だ。空港警備会社の主任になった人はな、宝石泥棒を捕まえる名人だったんだ。おもしろい話があるよ、彼が捕まえた宝石泥棒のことだけどな、銀座の大きな宝石店から、きれいな宝石が一つだけ盗まれた。銀座だけじゃなくて、都内の名だたる宝石商から、たった一つ盗むんだ。しかも、プロが見て、とても質と、カットのいい赤い宝石だけだ。その店で一番高い宝石を盗むということじゃないんだ、犯人が気に入ったやつだけだ」
「そいつは趣味だな」
詐貸が言った。薩摩もうなずく。古本が目を輝かせて聞いている。
「宝石商に泥棒にはいるのは相当大変なんでしょ、いくつかそういった映画がありますよね」
野霧も興味をもったようだ。
「そう、それは何重にも防犯がなされているよ、だけど、プロの盗み人はそこをかいぐるんだな」
「なぜ赤い宝石だけだったのです」
「まあ、先を急がないで、それで、その刑事さん、俺にいろいろ教えてくれた、尊敬すべき人だよ、彼がその犯人を突き止めたんだ。犯人は、六十過ぎの男性で、自分自身は産地直送の天然の山菜、茸、などを、ネットで注文を受けて売っていた。自分で採りに行くこともあるが、だいたいが地方の七十、八十にもなろうとする老人に採ってこさせ、それを売っていたんだ。高級料亭からの注文がけっこうあって、いい商売をしていたようだ」
「宝石泥棒とは結びつかないわね」
「そうなんだ、それを、やっこさんはあることで見抜いたんだ」
「なんだったんです」
「それがな、刑事さんは秋田の山奥の出身、犯人は信州の山奥で育った男だった。犯人は子供の頃から、茸をとり、それを食べて育った。茸取りの名人だよ。刑事さんも茸はよく食べたようだ。犯人は無類の茸好きで、毎日、茸の料理をかかさなかったようだ。刑事は宝石が盗まれると、いの一番に駆けつけ、現場を検証した。赤い宝石を盗む奴の時は、必ずその場に昔かいだことのある匂いが残っていた」
「肥やしの匂いじゃない」
野霧がいった。
「いいや、他の人にはわからない臭いだった。茸の臭いなんだ、なんといったらいいか表現ができんが、ちょっとムレた汗となんかが混じった匂い。それで茸を扱う、茸の好きな奴が犯人だとめぼしをつけた。野菜を扱う奴、しかも茸だ。ということで、珍しい天然茸をネットで売っていた男に目をつけ、夜中に張り込んで、横浜の大きな宝石店に盗みに入ったところをお縄にしたんだ」
「すごい嗅覚ですね」
「そう、子供の頃に経験した臭いって忘れないものかもしれないな」
「それで犯人は宝石を売りさばいていたのですか」
「いや、刑事が犯人の家に捜索に入ったら、立派な黒柿でできた宝石棚に、いろいろな種類の赤い宝石、しかも超一流のカットが施された物が、きれいに並べられていたそうだ。宝石の美術館でもそれほどのものは見られないだろうということだった。写真を見せてもらったよ、そりゃすばらしいコレクションだ。総額は億を越えている。犯人は、いつか返すつもりだったといっていたそうだ。目のいい犯人だ。プロの宝石鑑定の資格ももっていたというんだ。宝石は元に戻ったが、プロの人がもう一度見てみたいというほどすごいものだったんだね、棚は犯人の寝室においてあった。毎日眺めて床についていたのだろう」
「やっぱり趣味か」詐貸がぼそっと言った。
古書が「うらやましい」とひとこといった。
そこへ姫ちゃんが料理を持ってきた。
「これ、カラカサタケのホイル蒸しです」
それぞれの前に皿をおいた。
「茸たあ、いいタイミングだ」薩摩が早速、箸でアルミホイルに穴をあけた。湯気が立ち上った。
「お、熱々か、カラカサタケって、どんなの」
「唐傘みたいで、結構大きい茸です、意外とどこにでも生えますよ」
姫ちゃんが説明する。
薩摩がホイルを箸で乱暴に破ると、中の茸をはさんで、口に入れた。
「お、うまいね、こんな茸売ってるの」
「いんや、茸の好きなお客さんが採ってきてくれたんだ、だから、サービス」
「おいしいわね」
女性たちも箸をいれた。薩摩が「あ、そうだった」と動かしていた箸をとめた。
「空港の警備会社のはなしだったな、その宝石泥棒を捕まえた刑事が、宝石を密輸入する手口を教えてくれたよ、体のいろいろなところに、隠すんだよな、飲み込んで、後で下剤で出すとかあるようだよ」
「そいつはよく聞くよな」
「その人がな、去年、羽田でちょっとおかしな数字がでたというのだ。羽田におりた外国からの観光客で、ペットで猫をつれてくるのがいるんだが、帰りは猫をつれていないのが目立ったそうだ。いつもの年は、日本で観光中に死んでしまったりして、単身で帰る人はほんの一人か二人だ、しかし昨年は二桁だったというんだ、ほら、帰国するときも、検疫のチェックをするからわかるんだ」
「つれていない場合もチェックするのか」
「一緒に帰ったのだけわかれば、残ったものは一緒に帰っていないということだろうな」
「その理由はわからないんだろ」
「ああ、どうってことはないかもしれないけど、猫の骨のことがあったので、彼の話が頭に残っていたんだ」
吉都がそれを聞いていて、首をかしげた。
「現場の方がそういう感じを持ったということは何かあるかもしれませんね」
薩摩と詐貸も、そう言った吉都を見た。
「人間が宝石を飲み込んで、密輸ができるのなら、動物に飲み込ませて、運ぶことができるのじゃないかと思って」
「それで、猫を密輸業者にわたして、一人で帰るってわけか、たしかにな、探偵事務所の助手さんたちの勘はすごいからな」
「薩摩室長、猫を残して帰った人の国や、猫の種類はわかるわけですね」
「おそらくな」
「それじゃ、税関に調べるようにいったらいいかもしれないですよ、宙夜さんの調べてきたことと、付け合わせるのもおもしろいし」
キックが大きな目を飛び出させていった。
「警備の方だからな、お宅の探偵事務所に頼もうか、金だせるかどうかわからんが、上の許可を取って、依頼するか」
「よせやい、うちは猫を探すので精一杯だ」
「なあ、その羽田の警備会社の主任に会って、話をきいてくれないか、なにかでてきそうなきがするがね」
詐貸は野霧と吉都をみた。二人ともおもしろそうという顔をしている。
「うん、まあ、暇みてやるか、マスター、ウイスキーちょうだい」
詐貸がカウンタの中を見ると、主人がロックを飲んでいる。
「そろそろだとおもって、味見してるよ、あまりほこりくさくねえよ、保存は良かったみてえだ、姫子、詐貸さんにロックで」
すぐに姫ちゃんが、詐貸の前にウイスキーをもってきた。
「あたしも飲んでみたい」
野霧が珍しく詐貸のグラスを指さした。
「俺も飲んでみよう」
薩摩まで言いだしたので、みんな飲んでみたいと言うことになった。
「少しづつだよ、貴重なんだから」
主人はみんなの分もつくった。
「くせないのね、甘めね、おいしい」
野霧がくーっと飲んでしまった。
野霧が「きょうは、五十嵐先生こなかったな」とつぶやいた。
著名なミステリー作家、五十嵐五十老は、必ずといっていいほど、神無月に飲み荷にきている。
朝、探偵事務所で野霧はハチ公との話を思いだしていた。猫を輸入するのは大変なんだろうか。
「可也ちゃん、猫の輸入の仕方しっている」
「知りません、たぶん、ペットをつれての海外旅行、どうするのだろう」
「税関でチェックされるのでしょうね」
「空港の検疫所でしょうね、海外から帰ってくると、熱のある人は申告してくださいっていってるところ、植物やサラミなんかのハムなんかを持っている人も申告してくださいっていわれますよね」
「そうね、肉の製品は持ち込めないわね、果物もだめね、ということは、生きている動物だって同じよね、ペットも許可をもらっているはずね」
「そうですね、調べてみますね」
吉都がPCを開いた。
動物の検疫で調べると、動物の輸入輸出の方法がでてきた。
「農林水産省の管轄ですね、動物検疫所というのがあります」
野霧もPCを開いている。
「人間の検疫は厚生省管轄ね、予防ワクチンを打っているかとか、熱がないかとか、そういえば税関そのものは税を取り上げるところだから財務省でしょうね」
「あ、そうですね、とすると、空港って国土交通省管理だけど、厚生労働省、農林水産省、財務省、もちろん環境省も関係して、我々が海外旅行するのに、色々な管理を受けているわけですね」
「うん」
「猫犬の輸出入のことがでていますよ、結構大変だな、もっとも長い場合には百八十日の観察期間が必要ですよ、もっとも輸出する国における観察期間と、日本にきてからの観察期間だから、輸出する前にしっかりとその国で観察期間を終えていれば、日本での観察期間は短くてすむ、どちらの国へも、かなりの書類を書かなければなりませんね、それに猫の場合は狂犬病の予防注射を打っておかなければならないみたいだ」
「猫なのに狂犬病?」
野霧が不思議そうな顔をしている。
「狂犬病はほ乳類はみなかかりますよ、だから人間だって、日本じゃほとんどなくなりましたけど、致死率が高い怖い病気です、水を怖がるようになるので、恐水病とも言いますね」
「何で水が怖いの」
「狂犬病はウイルスで、神経に入って、脳にはいりこむと、麻痺して死ぬんです、水を飲むときにノドがとても痛くなるので、水を飲むのが怖くなるからその名前があるといわれてるんです」
「さすが、吉都君よく知ってるわ、それで、海外から持ってこられた猫ちゃんは、どこかに泊まることになるのかしら」
「動物検疫所の係留所があって、そこに泊まることになるようです、検疫そのものは無料ですが、餌やその他すべて自前になりますね」
「観察期間が百八十日って半年じゃない」
「猫をペットとして旅行するのは大変ですね、ただ、前もって自分の国で長い観察をすませなきゃいけない、あ、それをしなくてもいい国がある」
「なにそれ」
「指定地域というのがあって、アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアムは、半年以上そこで飼われていて、マイクロチップがはいっていること、その国の証明書がいりますけど、それにかなり前に事前輸入届けをだしておけば、簡単につれてこれる」
「どうしてなんだろうな」
「狂犬病がなくなっている国のようです」
「それにしても、ペットと観光というのは大変ね」
「それでも、愛猫と一緒に来たい人がいるんですね」
それか数日後、詐貸と二人は羽田の警備会社の事務所にでかけた。羽田の警備はいろいろな警備会社が担当している。薩摩の知り合いがいるのは第二ターミナルにある会社だ。
警備の主任である津軽夏也元警部は、薩摩とは違って、細身の、というよりしまった、一見、学校の先生のような雰囲気の人である。もう六十をすぎているのに、五十前半に見える。
「詐貸さんは薩摩警視のお友達だそうですね、彼がべらぼうに優秀な探偵さんたちだと言っていましたよ、薩摩は一見大げさのようだけど、そうでもなくて言葉を意外と選んでいましてね、彼がそういうには相当の理由がありますよ」
ちょっと俳優の笠智衆のような雰囲気だ。
「ええ、薩摩と同じ大学で、サークルメートです、こちらは助手の逢手と吉都です、今日はよろしくお願いします」
野霧がきいた。
「海外からつれてきた猫が、持ち帰られないケースが多くなっていると言うことですが」
「そうです、薩摩と話したときちらっとそんなことを言いました。あいつもよく覚えていましたね、私もちょっと気になっていたんですが、宝石の密輸入とつなげて考えるなどとは恐れいりましたな、ご存じだと思いますけど、動物検疫所は管轄が全く違いまして、農林水産庁なんですよ、羽田に支所があるのですけど、そこの担当の男と飲んだりすることがよくあるので、そんな話を聞きました。それをあいつに言ったんです。
薩摩からは電話で書類を見たいということだったので、動物検疫所の男に頼みました。書類は整えてあります、羽田だけのですけどね、個人情報でもあり、本当はまずいかもしれませんが、とりあえず、名前を消した物をお渡しします、本当に事件と関係があることがわかったら、薩摩の方に正式にお渡しします」
「ありがとうございます、他の空港ではそういったことはお聞きになりませんでしたか」
「ええ、気になったんで、検疫所の男に他の空港のことも聞いてもらったら、そのようなことはなさそうだということでした」
「なぜ羽田だけなんでしょうね」
「それはわかりませんね、ただ、昔の習慣が抜けませんでね、もやもやしてついつい調べてしまったんですよ、すると、一つのことがわかりました。明確にわかったんです」
なぜか、そう言った津軽元警部は嬉しそうな顔になった。きっと犯人に目星がついたときの顔ではないかと詐貸は思った。
野霧と吉都は渡されたコピーを見ている。
「猫を持って帰らなかったのは、ハワイからきた客でした」
確かに重要な発見である。それを聞いた野霧がたずねた。
「今書類のところにかかれていた飛行機の便をみていたのですけど、記号が違いますね」
「よく気がつきましたね、ハワイから羽田に乗り入れている航空会社はたくさんありましてね、JAL,ANAばかりじゃなくて、アメリカやタイの飛行機もはいっていますよ」
「ああ、それでですか」
「旅行者の国籍はばらばらのようですね、アメリカ人もいれば、タイ人もいる、ただ、ヨーロッパ人はいないようですね」
吉都が指摘した。
「ああ、そうです、その通りなのです、まさかとは思いますが、薩摩さんが言っていた宝石の密輸入と関係あるかもしれませんね」
「そうか、ハワイは特別地域なんだ」
吉都が言うと、「それなに」と詐貸がきいた。詐貸には動物の輸入のことを説明していない。
津軽警備主任が笑いながら「助手さんはしっかりしている、よくご存知で、ハワイは狂犬病のないところで、ハワイの輸出書類が整っていれば、犬や猫を、タイなどのアジアやヨーロッパの一部の国からと違って、楽に日本に運べるのです」と言った。
「そうすると、旅行客のペットばかりじゃなくて、猫を輸入するときも、ハワイからの方が楽なわけですね」
「そうなりますね、オーストラリヤ、ニュージーランド、グアム、フィジーなんかもそうですね」
「薩摩に動物検疫所のほうに連絡してもらって、ペットだけじゃなくて、猫の輸入について調べてもらいます」
「それがいいですね、やっぱりいいところに気がつきましたね、私も元の職業に戻りたくなりましたよ、宝石と猫か、面白いミステリーですな、探偵もおもしろそうですね、いつか探偵術おそわろうかな」
詐貸も津軽元警部は探偵に向いているかもしれないと思った。
「いや、たくさんのヒントをいただきました、それにこの書類、ありがとうございました。結果がでたらお知らせします」
「楽しみですね、他に私にできることがあったら言ってください」
津軽元警部は本当にうらやましいという顔をしている。
「ありがとうございます、津軽さんはこの近くにお住まいですか」
「家は赤羽ですけど、ほとんどこの近くの宿舎にいます、休みの時に家に戻るくらいです、家内と長男家族がいます」
「だったら、巣鴨も近いですね、たまに薩摩と巣鴨で飲みます、お時間があったらいらしてください、薩摩も喜びます」
「ああ、それはうれしい、その機会には誘ってください」
詐貸たちは丁重にお礼を言って羽田をあとにした。
事務所に帰ると、すぐに詐貸が受話器を取り上げた。
「薩摩に動物検疫センターにそっちから手を回してもらおう。それこそ民間の探偵より、警視庁からの依頼の方がいいからな」
話が長引いている。
野霧は帰りがけにかった素甘をもうほうばっている。
「宙夜さんからはどんな連絡が入っているんでしょうね」
吉都も素甘を食べながら、ネットでキャッツアイを検索している。
「想像がつかないわね、きっと採掘しているところからは、宝石販売の正規のルートにのるもの以上の石がいろいろな筋に流れているんじゃないかな」
「いろいろな筋って」
「日本だと、ほらやくざの組織に流れて、資金になるように、世界のやくざ、麻薬と同じような組織があって、そこから世界中にいって、日本に密輸入されているのじゃないかしら」
「そうですね、野霧さんがいう通り、儲かるところにそういった組織が手をだすでしょうね」
「宙夜さんは、そういった国際的な組織の解明にいったわけでしょ、大変なことね」
「八公の仕事と言うより、警察そのものの仕事ですね」
「そうね、どうして宙夜さんが派遣されたのかな」
「宙夜さんは宝石に知識がありましたよね、それだけじゃないでしょうね、宝石の密輸入にエックスファイル的なところがあったからでしょ」
「彼が義眼の事件を解決したからかしら」
「博多の妣視杞事件ですね」
博多では亡くなった人の目が義眼に置き換わっている事件があった。宙夜が博多に行ってたった二日で重要なことを明らかにした。
「義眼って玉になっているのじゃなくて、表面の眼のところがそっくりに作られていて、眼球の部分は義眼台とかいって、樹脂でできた玉のようなものですよね」
「そうだったわね」
「そこに宝石隠せますね」
「あ、可也君すごいところに気がついたわね、そういう密輸もあるかもね、通関の時、そういったことは記載をしないわね」
「義眼台の中に宝石をいれておいて、日本にきて、眼科でそれを取り出す」
「妣視杞さんにきいてみようかしら」
前の事件に八人の女性が関わった、その中の一人は眼科医の妣視杞で、義眼のコレクターでもあり、ガラスの眼の作家でもある。遺体の眼を義眼に変えた犯人の可能性があるが、犯人を見つける前に解決してしまった事件である。この事件は、卑弥呼と関連してきて、まさに小説のような話で、野霧がノーベライズしているところである。もうすぐできるのではないだろうか。
「そうですね、野霧さんよく連絡しているのでしょう」
「うん、個展にもいくよ、みなさん元気」
「小説の方はどうなってるんです」
「だいたいできたのよ、今年中にはだしたいわね」
野霧が初めての小説として、探偵事務所の費用で自費出版することになっている。
詐貸の電話が終わった。
「なんだか大変なことになりそうだよ、かなり大がかりな、密輸組織が暴かれるかもしれないそうだ、彼ははっきり言わないけど、ハチ公のところが中心じゃなくて、国際犯罪の担当部署が中心のようだ。きっと外に言えないのだろう」
「それで、動物検疫所の件はどうでした」
「うん、世久さんと一緒に事務所に来るってさ、キックに動物検疫所に行ってもらうそうだ。都内にも支所があるんだって」
「それじゃ、我々の仕事は終わりですか」
「そうだな、きっと薩摩がきたときにそのことも話すんじゃないかな、宙夜さんの報告があるようだよ、メイルはもちろん、電話でも話せないような口振りだった」
羽田の警備主任、元警部の津軽夏也にもらった、動物検疫室の書類を整理し終わってみると、津軽の言うとおり、昨年はずいぶんペットを日本に残して帰った海外旅行客が多い。それが確かにハワイからの便から降りた客である。帰りはどこに帰ったかわからない。国籍は様々である。
一段落したところで、薩摩とキックがくるという連絡が入った。
十一時頃、「お久しぶりでーす」とキックがにこにこと入ってきた。
「こんちわ、薩摩警視は」野霧が訪ねると、キックは「和菓子屋さんによってまーす」と、ソファーに腰を下ろし、鞄から書類袋を出すとテーブルの上に置いた。
遅れて薩摩が入ってきた。
「おじゃまするよ、あの店にモンブランがあったよ」
「また作ったんだ」
野霧が顔を丸くして受け取った。嬉しいんだ。
「それうまいよ、そんじょそこらの洋菓子屋では食べられないよ」
詐貸もソファーに移動した。吉都はもうキックの隣に座っている。
野霧がお茶の用意をしに行くと、「手伝いなさいよ」と吉都がキックにしかられている。「あ、そうだ」と言いながら、吉都が野霧の後を追いかける。
「野霧さんお茶は俺入れる、ケーキお願い」と用意を始めた。
ソファーに座った三人は仕事の話を始めた。
「野霧さんたちにも聞いてもらったほうがよくないですか」
キックに言われて、薩摩がうんうんそうだ、と話し始めたのをやめた。
吉都がお茶だけ持ってきた。
「モンブランは」とキックがきくと「野霧さんが、仕事の話が終わってからの方がいいと言ってましたと、お茶をおいて吉都がキックの隣に座った。
「おまちどうさま、あとでだしますね」
野霧が詐貸の隣に腰掛けると、お茶を一口飲んだ薩摩が説明を始めた。
「まず、宙夜からの報告をしておこう」
持ってきた書類を広げた。
「まず、彼の使命をはっきりさせとく、もうだいぶ昔からだが、宝石の原石を簡単に研磨して、いろいろな形で日本に密輸している組織がある。というより、原石を横流しする組織、それを日本ばかりでなく、それぞれの国に精通していて工夫をして密輸を計画する組織があって、その全体を俯瞰してうまく動かす闇の国連があり、トップにはどんな奴がいるのかわからない。宙夜は密輸組織を調べている警視庁のグループに混じって、原石の横流しから、闇の加工組織、密輸出方法を中心に調べているところだ」
吉都が口を挟んだ。
「ハチ公、いや、第八研究室に役割がふられているということは、通常ではないことが行われているということですか」
「実はそうなんだ。今もあるけど、体の中に麻薬を隠したり、袋に入れて飲み込んだりして密輸しただろう、宝石も飲み込んで持ち込んだのがいたんだ、そこまでは、麻薬課や密輸課のしごとだが、数年前だから、俺が来る一年前だね、眼の落とし物があってね、羽田に着いた飛行機の乗客の降りた後の掃除で、清掃員が見つけて、落とし物として届けたわけだ。当然、落とした本人は大変だろうということで、空港事務所でも本人の特定をしようとしたんだな、眼の色が青かったんで、ヨーロッパ、アメリカ系の人間だろうとふんで調べたわけだ。ところが、見つからず、落とした本人も届けてこなかった」
「義眼の落とし物だけでハチ公ですか」
野霧も不思議そうだ。
「それがね、警視庁のおかしな落とし物については、ハチ公でも画像で見ることができるんだ。変な事件に関わることがあるからね、それでね、俺がきてからだけどね、宙夜がたまたまその義眼を画像で見てね、おかしいと言うんだ、一般に義眼ていうのは、表面だけのようだね、コンタクトレンズのようにはずして、毎日洗うんだって、眼の中に入っているのは義眼台と行って樹脂のようだ」
野霧と吉都がうなずいている。
「だから、義眼はそんなに厚いものじゃないわけだ。ところが、落とし物の義眼は中央、瞳のところがずいぶん厚い物だったんだ、それを宙夜がおかしい、自分で見てみようと保管しているところに行ったわけだ。彼は宝石にも詳しいだろう、そしたら、義眼の中央部はエメラルドを加工した物だった」
「義眼をはめていた人は趣味で宝石を義眼にしていたわけですか」
吉都の質問に薩摩は首を横に振った。
「宙夜はそうじゃないだろうと考えた、なれた人は義眼を落とすようなことはないし、大事にしていたならなおさらだというんだ、きっと、なれない者がつけていたのだろうというんだ、義眼を再加工して売ってもに三百万はするだろうと言ってた」
「でも、たった三百万という感じもするんですけど」
「それが、もしかすると、義眼台の方に大きなすごい石が入っていたんじゃないかというんだ、それから、宙夜は義眼に関して調べていてね、そんなとき、ほら、博多の妣視杞さんの義眼事件があっただろう、それで、あのとき彼が博多に飛んだんだ、だけど、それは密輸入とは関係なかったわけだけどね」
あのとき宙夜が二日で事件を解決した理由がよくわかった。
「それで、宙夜は宝石の密輸に眼科医が絡んでいる可能性を、原石のでる国に行いって調べているわけだ。この報告書によると、原石を磨く加工師は眼を使うので、目医者が大いに関係しているようだ。怪しそうな人物を捜し出しているようだよ」
「そうだったんですね、すると、義眼の中に宝石を隠して持ち込まれている可能性があるんですね、この間、吉都君がそんな推理をわたしにきかせてくれました」
「そりゃすごいね」
「いえ、タイのトンチャン・ウオンが下宿していたのは、猫のブリーダーで猫目石って言うものだから、そこから想像しただけです」
「あの、所沢の猫の骨がでたところか」
「ええ、トンチャン・ウオンは猫のからだに宝石を仕込んでいたかもしれませんね、人間の眼に入れるより楽でしょう」
「ほんとだな、それでね、東京の動物検疫所支所にキックが聞きに行くんだけど、かまわなければ、吉都君にも一緒に行ってくれないかな、こちらが気づかないこともあるからな、二人の方がいい」
吉都は詐貸をみた。
「いいよ、交通費はでないの」
「なんとかだすよ」
「吉都はいいの」
彼はうれしそうにうなずいた。野霧はそりゃそうよと、笑顔になった。
「羽田の津軽さんは明晰だな」
詐貸が言うと、薩摩もうなずいた。
「秋田の津軽さんだ、リンゴスターだ」
野霧は何でビートルズが出てくるのかと思って、そうか秋田も津軽もリンゴの産地かと気付いて、薩摩の平行思考もたいしたものだと思った。
「津軽さん、薩摩に会いたいと言っていたよ、そのうち巣鴨で飲むとき誘うと言っておいた」
「いいね、もうすぐ宙夜も帰ってくるし、帰国祝いでもするか」
「宙夜さんは今はどこにいるのです」
「タイだよ、そのトンチャン・ウオンを確認しているよ、猫のブリーダーで大金持ちって奴のところにもいくよ、バチェラ・リーだったな、本当に猫好きか、裏はないかってとこだね」
「もし、トンチャン・ウオンがリーさんの息子をかたっていたとすると、バチェラさんは関係ないかもしれませんね」
「バチェラが関係していたら、息子を名乗らせて、自分の名前がでるようなことはしないということだろ」
「そういう考え方もあるけど、日本人をだますのに便利なら、平気でやるだろう、それだけで足が着くような組織じゃないだろうからな、もしバチェラが裏の組織を持っていたとしたらな」
「室長、もう少し話てもいいんじゃないですか、探偵事務所の方たちにはこれからお世話になるんだから」
キックが薩摩を促した。
「うん、あの件だろ」
そういって彼が話したのはハワイが、猫の輸入の特別地区であることに関わることであった。
「宙夜からの連絡では、バチェラがハワイの猫のブリーディング会社に関係しているようだというんだ」
「それで、バチェラが宝石の密輸にも関係しそうなんですか」
「いや、まだそこまではわかっていない、むしろ、日本の密売組織を明らかにすることで、その辺がはっきりするのじゃないかと思う」
「所沢の猫の骨が、宝石の密売に関係するかもしれないわけか」
「うーん、そうかもな、そうなったら、庚申塚探偵事務所の方々にも大いに働いてもらおうと思っているんだ、どうだい」
薩摩が詐貸を見た。
「そりゃかまわんが」
「吉都さんの偉大な推理があったろう、猫に宝石を運ばせる、それが本当になるかもしれないんだ」
「義眼の件はどうなるのです」
「それはうちの方で調べるよ、本当に関係がありそうなら、密輸の連中も総動員だ」
「猫の骨が大きな事件になったな」
「まずは、吉都さんとキックに動物検疫所で、猫を持って帰らなかった人が、日本からどこに帰ったか、何処の国の人間かを明らかにしてもらおう」
「うん、それに、宙夜さんが帰ってきたら、神無月にいこう、津軽さんもさそって」
野霧が薩摩の買ってきたモンブランをテーブルに持ってきた。吉都がお茶の急須をとりにいった。
「うまいねー、このホンモンの芋のモンブラン、あのじいさんたいしたもんだな」
薩摩が一口で半分食っちまった。
「でも薩摩さんラッキーですよ、いい芋が手に入ったときだけしか作らないみたいだから」
野霧もモンブランをいっぺんに半分口に入れた。
見ていた詐貸が眼の脇にしわを寄せた。
キャッツアイ
キックから吉都のスマホに電話が入った。
「羽田空港貨物合同庁舎にいかなければならなくなった、薩摩警視の言った大田区の動物検疫所支所は、東京港湾貨物合同庁舎で海の防疫関係を扱うところだって」
「それじゃ、羽田にいかなければならないんだね」
「そうね、私明日いけるわよ」
その日、キックと吉都は羽田に行った。薩摩室長から羽田の動物検疫室長に、あらかじめ連絡をしてもらったので、資料も取りそろえてあり、質問に要領よく答えてもらうことができた。
キックと吉都が聞いてきたのは、猫を連れてきて、連れて帰らなかったのは、ハワイからの客が大多数であることが確認できた。国籍はアメリカかタイであった。さらに奇妙な一致があった。日本を出国するとき、羽田からではなく、成田からハワイかタイにいっている。キックは乗客の名簿やパスポートもすべての情報を得ることができた。
次の日、吉都は事務所で聞いたことを話した。
「やっぱり、タイの猫のブリーダーがおかしいわね、それとハワイ」
「そうですね、宙夜さんがどんな報告をもって帰るか期待したいところですね」
「薩摩の話だと、一週間後に戻るようだ、しばらくは忙しいだろうから、落ち着いたら飲もうということだった、その前に極秘以外のことはみな教えてくれるそうだ、タイの猫のブリーダーについては教えてもらえるよ」
「そうですか」
「ねえ、猫を連れて帰らなかった入国者の足取りを調べてみると何か出てくるかもしれないわね」
野霧が大事なところに気がついた。
「そうですね、名前もわかっているし、ただ、我々では動けないですね、個人情報は知らないことになっている」
「大っぴらに調べなきゃいいんだよ」
詐貸が方法を伝授した。
「その観光客が、どこのホテルに泊まったかぐらいは調べられる、だがホテルがわかっても、ホテルに聴くのはキックにでも頼むしかない、もし個人宅なら、どのような家か、我々でも調べることはできる、猫を日本で手放した連中に共通点がみつかれば、それからのことはハチ公と相談しよう」
「そうですね、やってみます、キックとも連絡を取って、一緒にいけるところには行きます」
「うん、本当の探偵になれるかもな」
詐貸に笑われた。
「俺は久しく富山に行っていないので、明日から行ってくる、猫トリマーのキャッツアイは気になるな、もし時間があったらちょっと調べといて」
「愛子さんも一緒にいくのですか」
「いや、彼女はまたノールウェーだよ」
「詐貸所長をほったらかしですね」
「おい、おい、もう関係ないよ、変に気を回すなよ、あいつの人生に俺はもういないよ」
「所長の人生には必要でしょう」
詐貸は珍しくまじめな顔をして言った。
「必要なわけはないよ、君たちの方がずーっと必要だよ」
野霧と吉都は顔を見合わせて、どう答えようか迷っていたが、野霧がいきなり、
「うっれしい、しばらく首にならない」
と大声で言ったので、詐貸も吉都も大笑いした。
「君たち首にしたら、俺も首だな、次に富山に行くときは一緒にいこう」
野霧と吉都はうなずいた。
「キャッツアイは私が調べときます」
野霧が言った。
詐貸は富山に出かけた。猫のトリマーで、猫の輸入を斡旋している「キャッツアイ」の住所と電話は控えてある。野霧がネットでホームページをあけて店を確認した。池袋なので、そんなに遠くない。池袋と言っても、西武池袋線で一駅目の椎名町駅でおりる。駅の近くだ。そんなに大きな店ではなさそうだ。
野霧はキャッツアイから猫を輸入した、柳井夫人の娘さんに電話をしてみることにした。
「もしもし、庚申塚探偵事務所の野霧と申します、初めまして、ベルちゃんの捜索を引き受けた者です。柳井さんから娘さんの電話を教えていただきました。実は私も個人的に猫をほしいと思っていましたので、キャッツアイさんのことをお聞きしたいと思いまして電話しました」
柳井夫人の娘さんはお母さんと違って、はっきりとした人だった。
「あ、はい、母がお世話になりました、お名前は聞いております、ベルは残念でしたが、早く見つかってよかったです、キャッツアイさんは池袋のトリマーの店で、個人的に猫の仲買をしています、保険までつけて安く売ってくれます」
柳井夫人から聞いたことだ。
「どんな人でしょう」
「担当した方は感じはよかったですね、背の高いきれいな人ですよ、母の性格を聞いて、猫を選んでくれました、よく人になれたかわいい猫でした、一度子供を産ませた猫で、帝王切開をしたからその跡が少し残っているので、とても安かったのです」
「なんという方でしょうか」
「名刺には、鈴木とありました」
「猫は店に行けば見ることができるのでしょうか」
「いえ、トリミングのお店で、猫はおいていませんでした。写真があって、それから選ぶのです、ただ、輸入に時間がかかるので、二ヶ月も待たなければなりません、だけど、とてもいい猫がふつうの半額以下ですから、三分の一ほどの値段の猫もいました」
「それじゃ、もうけにはなりませんね」
「キャッツアイでは、血統証はついていても、売りものにならなくて、処分されるような猫がかわいそうなので、儲けは考えていないといっていました」
「ありがとうございました、私も行ってみます」
野霧は電話をきった。吉都はなんだか腑に落ちない顔をしている。
「猫の帝王切開ってそんなにあるものなんでしょうか」
「そういえば聞いたことがないわね」
「佐々木に聞いてみますよ」
吉都は渋谷の佐々木動物病院に電話を入れた。
「やあ、久しぶり、あのときは世話になった、今大丈夫か」
「ああいいよ」
「猫って帝王切開が多いのかい」
「いや、ほとんどそういうことはないね」
「猫の手術はよくするの」
「もちろん、骨折などが多いけど、癌が結構あるね」
「手術をしたことのある猫を安く売っているところを知ってる」
「うーん、俺は知らないね」
「売るのはかまわないのかい」
「そうだな、はっきり病暦が書かれていれば違法じゃないね、ちょっと骨を折ったぐらいなら、寿命とあまり関係ないけど、癌で手術した猫などは売れないよね」
「池袋のキャッツアイっていう、トリマーなんだ、猫の輸入もしているみたい、急がないから、何か分かったら教えて」
「うん、でも帝王切開なんて書くの素人だな、他の手術をしたのをごまかしているのかもしれんね」
「手術の跡から、どんな手術したのか分かるかな」
「臓器の位置か何を手術したか推測はできるけど、何の病気かわからないな」
「そうか病気だと寿命は短くなるだろうな」
「そうだね、悪い病気だと当然短いね」
野霧が小さい声で吉都に言った。
「猫に宝石を飲み込ませたらどうなるか聞いて」
吉都はうなずきながら、佐々木に聞いた。
「変なことを聞くけど、猫に石を飲み込ませたりしたら、すぐ糞に出てくるのかな」
「胃や腸に傷つけない形で、あまり大きくないならね、時間がたてば糞にでるだろうな」
「飲ませてどのくらいででる」
「どうだろうな、物にもよるだろうし、よくわからないけど」
「数時間ということはないだろ」
「ああ、もっとかかるだろう、早くだそうと思うなら、下剤を飲ませればいい」
「いや、逆に出させなくするにはどうしたらいい」
「胃や腸の動きを悪くすればいい」
「そうか」
「下痢に効く薬などはそういうことになるな、水分を吸収させて便を固める、そのかわり猫の健康にはわるいよな」
「いや、ありがとう」
「また、探偵ごっこ、いや探偵だったな、事件に関係あるのか」
「まだわからないけどね、話せるようになったら話すよ」
吉都は電話をきった。
「ありがとう、話は全部聞こえたわ、帝王切開などで産ませることはほとんどないわけね」
「そうですね、何か匂いますね」
「うん」
吉都のスマホがなった。ハチ公からの連絡のようだ。
「今日、午後から、キックーと池袋のホテルに行ってきます」
「なにそれ」
吉都の言い方に野霧は大きな口を開けて笑った。吉都も気がついて、「いやだな、野霧さん、変な想像して」と苦笑いをした。
「猫をつれて帰らなかった入国者の何人かが、池袋のあるホテルを使っていました、それで、調べにいきます」
「そう」
「それと、日本国籍の人で、ハワイから猫をつれてきた人が何人かいます、その人についても調べます」
「その情報はどうしたの」
「やっぱり津軽さんからだそうです、津軽さんが、ハチ公にそういう人も調べた方がいいんじゃないかって、連絡くれたそうです」
「あの元刑事さんすごいわね、私は今日、キャッツアイの店をのぞいてみるわ、明日結果を教えるわよ」
「僕の方の情報も教えます」
「お昼はキックと食べるんでしょ」
吉都はちょっとまごまごしていたが、「うんそのつもり」と答えた。
「それじゃ、私は、一人でヒサゴにいってそばを食べてから池袋に行くわね」
野霧は出かける用意をした。
「はい、いってらっしゃい」
吉都も出かける用意をした。
「おや、今日は逢手さん一人」
そば屋、ヒサゴにはいると、主人が二人の客の天ぷらを揚げていた。
「うん、詐貸所長は富山に仕事、吉都君も都内で調査、私もこれから行くとこあるの」
「忙しくていいね」
「暇なときのほうが多いくらい」
「今日はなににする」
「ぶっかけの大盛りにして」
「はいよ、ちょっと時間かかるよ」
「いいわよ」
「これからどっちにいくの」
「椎名町」
「なんだ近いんだ、ゆっくり昼食べてってよ、そんでなにしにいくの」
「猫のトリマーさんのところにいくの」
「猫飼ってるの」
「飼ってないけど、見学」
「それも仕事」
「猫のこと教えてもらうの」
野霧は出てきたどんぶりそばを食べ始めた。
「俺の若い頃は、猫なんてほっとかれて、味噌汁ご飯、いいときゃ鰹節まぶしぐらいだったね、洗ったりドライヤーで乾かすなんてやらなかったもんだ」
「そうね、今は餌はキャッツフードが多いでしょうけど、トリマーに行って手入れするなんて、そんなに多くないでしょ」
「愛護団体が、猫は家から出すななんて、有名な奴に歌わせていたけど、猫がかわいそうだね、猫は家畜にならんぞとがんばってんだから」
野霧はぶっかけそばを口にほうばりながらうなずいた。
「ほんと、だけどマンション暮らしじゃ、飼うことができても外にだせないわね、この間、いなくなった猫探しをたのまれたんだけど、車に轢かれてた」
「たしかにな、東京の猫は人間と同じで自然を知らないから仕方ないのかね」
「人間は、自分自身も家畜化してきたのね」
「おもしろいこというね逢手さんは」
「さ、ごちそうさま、所長帰ってきたらまたくるから」
「まってますよ」
野霧は庚申塚から荒川線にのって池袋の東口にでた。西武池袋線に乗れば椎名町まではほんの数分でつく。
椎名町は初めて降りるが、道沿いに家が建ち並んでおり、飲み屋も結構ある。
キャッツアイは駅の北口からでて、首都高中央環状線の下を横切ると、ちょっと行った路地の角にあった。三階建ての小さなビルである。一階がキャッツアイの店だが、看板はでておらず、入り口のガラス戸に「猫のキャッツアイ」と書いてあるだけである。
野霧はスマホで写真を撮り、離れたところから、しばらく様子を見ていたが、誰も出入りする様子がない。
入ってみるか。野霧は戸にふれた。
入ると目の前がカウンターになっていて、作業は奥の部屋のようだ。カウンターには、料金表が立てかけられており、猫の輸入代行しますともある。それに猫ホテルもやっているようだ。
野霧が入ると、白いエプロンをつけた女性がでてきた。背の高い美人だ。柳井夫人の娘さんが言っていた鈴木というのはこの人かもしれない。
「いらっしゃいませ」
名札をつけている。キャッツアイ店長、猫トリマー長、ドロシーとなっている。言うなれば源氏名だ。女性は本名を書いておくと、悪用されることがあり、別の名前をつけていることが多い。トリーマー長とあるのは、従業員が何人かいるのだろう。
「猫ちゃんは連れてこられなかったのですか」
ドロシーが笑顔で野霧にたずねた。
「いえ、まだいないのですが、知り合いから猫の紹介をしてくれると聞いたので、仕事の途中でちょっと寄ってみました」
「そうですか、ちょっとお待ちください」と中に入った。かわって出てきたのは、おっとりとした、四十くらいの女性である。丸顔でふっくらとしていて、野霧的だ。
「いらっしゃいませ、猫ちゃんお探しですか」
「いえ、まだ、飼うと決めたわけではないのですが、デパートなんかのペット売場をみていると猫ちゃんがいいなと思うようになって」
「猫ちゃんは、癒してくれますよ、お嬢さんには柔らかな感じの猫ちゃんがお似合いですよ、そう日本猫もいいわね、だけど、よく仕込まれた洋猫は、マンションなどで飼うにはとてもよろしいのですよ、ゆったりした、ラグドール系がいいかもしれませんね」
その女性はカウンターのアルバムを開き、ちょっと毛の長いふっくら系の猫を示した。かなり大きな猫だ。
「ほんと、かわいいわ、でも、子猫かと思っていたのですけど」
「デパートの売場では子猫をおいているでしょ、確かに子猫から飼う楽しみもありますね、その方が気持的には育てたという満足感もありますしね、うちは、もう少し大きくなった、と言っても一歳から二歳ですけど、そういうのを紹介していますのよ、それはよく訓練されていて、面倒を起こすこともなくって、飼い主さんには喜ばれてますの」
「それもいいですね」
野霧は相手にほどほどに同調して話を引き出すのがうまい。
「そうお思いになるなら、うちの紹介する猫ちゃんは天下一品よ、値段は半額以下なの、正直いいますとね、だいたいの猫が帝王切開で子供を産んだ猫ちゃん、もう繁殖させることできないから、なかなか売れないの、処分されるのもいるのよ、かわいそうでしょう、それに、繁殖させようというほど、いい猫ちゃんなわけ、血統はすごくいいわけね、だから姿形は最高よ、それでもいいという人に輸入して差し上げているの、生活の伴侶としていいわよ、それに猫助け」
うまく説明するものである。
「ええ、かわいければ、どんな猫でもいいですよね、その猫ちゃんはどこにいるのですか」
「それがちょっと問題なのよ、ハワイの猫のブリーダーのところでのびのびと暮らしているのですけどね、輸入となると時間がかかりますのよ、輸入するには半年の観察期間が必要なのですけどね、ハワイからはもっと短くていいんです、それでも場合によっては二ー三ヶ月かかってしまうのですよ、それだけ待ってくださるのなら、最上の猫ちゃんが手に入ります、半額以下でね、このラグドールなら、日本に来るのは今からだと二才くらいになるわね、八万ほどでいいのよ」
ふと女性の服装をみた野霧は、この女性がエプロンもつけていないし、着ているものはおそらく高級ブランドだと思われ、店員らしくないことに違和感を持った。左手に石の入った指輪をしている。猫目石だ。首からかけているペンダントヘッドは、とても小さいが、きれいな黄緑金色に輝くやはり猫目石だ。
この人はだれだろう。もしかすると、この人が店のオーナーではないのだろうか。 「輸入するとなると高くなりませんか」
「輸入代金込みなのよ、半分猫だすけのつもりでやってるの、しかも一年間の保険付き、病気になったり、事故に遭ったりしたときおりるのよ、輸入された猫ちゃん、違う環境にきて、食欲がなくなったり、家を飛び出して車にはねられたりするでしょう、そういったときには購入代金がもどるか、新しい猫ちゃんが無料で提供できるのよ、ちょっと時間はかかりますけどね」
「いい制度ですね」
「猫ちゃんを飼ったことがおありになるの」
「いえ、マンション暮らしで」
「ご家族と」
「一人です」と嘘を言った。
「ごめんなさいね、よけいなことを聞いたかもしれません、一人なら、なおさら猫ちゃんがいると、家の中が前とは違うようになりますのよ、ちょっと身勝手なルームシェアーした友人かしらね、ぬいぐるみが好きな人は、このラグドールなどはむいていますわね、名前そのものがぬいぐるみですものね」
と説明しながら女性は楽しそうに笑った。話すのがうまい、引き込まれる。本心からそう思っているようだ。
「今日は、ちょっと通りがかりにのぞいただけですので、また改めてきたいと思います」
「ええ、ええ、いらしてください、店の名刺をおとりくださいな」
「はい、いただいていきます」
「どうぞ、またきてくださいな」
女性は立ち上がって野霧にお辞儀をした。胸にかけているペンダントの目が光った。
野霧はその足で、区役所に行った。猫トリマー「キャッツアイ」のビルは、株式会社「猫睛石」の所有になっている。なんと読むのだろう。社長は池波光子となっていた。動物貿易会社とあった。
あれ、所沢の個人猫ブリーダー、池波夫人と同じ苗字じゃない、しかも猫目石。、関係があるかもしれない。
野霧は事務所に戻ると所沢の池波夫人に電話をかけた。
「いつぞや猫をみせていただいた、野霧です、その際にはお世話になりました」
「あーら、お久しぶり」
「お元気ですか、あれからデパートなどの、ペットショップなどみたり、ネットで調べたりしたのですけど、池波さんの猫ちゃんが一番安いし最高です」
「そうでしょう、それでお友達、どうですって」
「実は猫を欲しがっていた友人に子供ができちゃったので、飼うのが無理になりました、せっかく色々説明いただいたのに申し訳ありません、それで電話しました」
悪いと思ったが、嘘をいった。
「そう、残念ね、でもわざわざ電話ありがとう」
「あの、話は違うのですけど、池波光子さんてご存じですか、関係ないかもしれないのですけど」
「あら、光子ちゃん、長男の嫁のことかしら、デパートの宝石売場かどこかでごらんになったのかしら、宝石の鑑定師の資格をもっているのよ」
「あ、そうなんですか、宝石のパンフレットに名前が載っていて、なんとなく、池波さんと雰囲気が似ていたものですから」
野霧は調子をあわせて話を進めていく。
「あら、そうね、光子ちゃんもふっくら系だものね、宝石にも興味がおありなのね」
池波夫人は笑った。
「ええ、宝石は好きです、息子さんも宝石屋さんですか」
「いえ息子は商事会社をやっているので、直接は関係ないわね、必要なときは助けてくれているみたいよ、宝石の輸入などのときにね」
「義理の娘さんの会社はどこですか」
「会社などに勤めていませんよ、フリーの宝石鑑定士よ、銀座の宝石商などにしょっちゅう出入りしていますけどね」
「やっぱり猫ちゃんお好きなんでしょうね」
「いえいえ、あの娘は残念ながら、猫はだめなの、息子は好きで飼いたいのですけどね、アレルギーだからしょうがないわね」
「あーそうなんですね」
「光ちゃんは、宝石に関してプロで、私が主人からもらった小さな猫目石、お見せしたでしょ、結構質のいい物なんですって、娘も猫目石が大好きで、集めているのよ、宝石鑑定のアルバイトで結構もうかるみたい、私にも買ってくれるっていうんですけど、亡くなった主人の一つで十分だからいいって言ってるの」
「うらやましいですね、池波さんの関係のある人であることがわかってよかったです、ご活躍でいいですね、猫のことはすみませんでした」
「いいえ、また猫ちゃんが欲しい人がいたら紹介してくださいね」
「はい、ぜひそうします、あ、そうだ、お嬢さんは所沢なんですか」
「いえ、長男は府中にいるのよ」
「そうでしたか、また、機会がありましたら、猫ちゃんに会わせてください」
「いつでもいらしてね」
そこで電話を切った。
なんだかおかしい、池波光子が猫のトリマーや、輸入に関わっていることを言わない。池袋のキャッツアイの会社の名前、猫睛石の読み方がわからない、野霧は電子辞書をひいた。
「なんだ、びょうせいせき、ってよむんだ、これも猫目石のことじゃない」
と独り言を言った。それにしても、池波光子は周りに黙って、動物貿易商や猫トリマーの店を経営しているのだろうか。それで、宝石鑑定士、なんだか変につながっていくような感じをもった。
吉都とキックは明日どのような報告を持ってくるか。家に帰る支度をした。
朝十時、野霧が事務所の戸を開けると、吉都がお茶を飲んでいる。
「おはよう、はやいわね」
「うん、昨日はおもしろかった」
「わたしもよ」
吉都がお茶をもってきてくれた。
「ありがとう、猫トリマーのキャッツアイは、池波夫人の義理の娘、長男の嫁が経営者よ、ビルも彼女のものだった、池波光子っていうんだけど、宝石の鑑定士なのよ」
「えー、あの小手指の池波さん」
「ええ、それで、池波夫人は義理の娘が動物商をしていることを知らないようよ」
「おかしいですね」
「それで、KKのほうはどうだった」
「なんですかKKって」
「キットとキック、何か音楽のデユオか、絵本のようね」
「なるほど」
吉都はまじめにうなずいている。野霧は笑い顔だ。
「池袋のホテルで、キックがマネージャーに説明をして、泊まった三人のことを調べてもらったんです、三人とも二泊しています。それがおかしいんですよ、動物は一緒ではなかったというんです、ペットが一緒の場合、申告してもらっているそうですが、それもなく、泊まった後の清掃の報告にも、動物の毛だとかそのような記載はありませんでした。すべてハワイからきた女性で、一人はアメリカ国籍、一人はタイ、もう一人はカンボジアでした」
「猫は空港で受け取らなかったのかしら」
「そうですね、十二時間の検疫隔離が必要だから、後で取りに行くつもりだったのかと思っていたのですけど、キックが高胎さんに連絡して、その三人の猫について検疫所に問い合わせてもらったら、代理の人が取りに来たことがわかりました。誰だかわかりません、今日、キックが調べてくれることになっています」
「それで、猫はどうしたのかしら、その客にもどったのかしら」
「猫は十二時間の検疫観察ですから、その日には本人の手に渡っていいはずです、そうなっていないのは、受け取った人がどこかにもっていったということです」
「そうね、それを追いかける必要があるわね」
「それから、ハワイから猫を持ってきた日本人の家に行きました、白井さんといいます」
「どこだったの」
「六本木のマンションでした。行く前にキックが電話を入れたんです、それで、ハワイから持ってきた猫のことを聞きたいといったら、交通事故で死んでしまったということで、ちょっと驚いたんです、キックは逆にそれをつかって、猫の交通事故について調べている警視庁の者だと言って、行くことの承諾を得ました」
「さすが世久さん、機転が利くわね」
「いつも驚いています」
「吉都君が驚くんじゃよほどね」
「それで、訪ねると、高級マンションの二階で、感じのいいご婦人でした。退職したご主人とよく外国旅行するそうです、ハワイで一月滞在した時に、街中のペットショップで紹介された、猫のブリーダー会社に行ったそうです、小さな島一つがその会社の物で、大きな建物やホテルもあり、そこで世界中の猫を繁殖させていたそうです。ハワイからだとつれて帰るのが容易だということで、しかも、お値段も安い、ちょうど飼っていた猫が老衰で死んでしまって欲しいと思っていたので、買って帰ることにしたそうです」
「どんな猫だったのかしら」
「ロシアンブルーだそうです」
「青っぽい毛の猫ちゃんね」
「検疫はその繁殖会社の日本での協定会社が、すべてすませてくれると言うことで、日本に戻った次の日に連れてきてくれたそうです、しかも一年の生命保険までつけてくれたそうです、ところが、一週間もたたないうちに、ベランダから出てしまったようで、近くの道路で車に撥ねられたようです。日本に帰ってから獣医に行って、マイクロチップを入れておいたので、うちの猫だとわかって連絡をもらったそうです、それで引き取りに行ったそうです」
「マイクロチップって、海外からの猫にはみんなはいっているんでしょ」
「そうでしたね」
「目白台の柳井さんはマイクロチップのこといっていなかったわね」
「あ、そういえばそうだ、輸入したときのマイクロチップで、いろいろわかるはずですね、なくなっていたのかな」
「それもおかしなところね」
「ええ、それで話を戻すと、白井さんは生命保険のところに電話したら、担当の人がきて、葬式からすべてやってくれたそうです、猫を購入した金額か、新しい猫ちゃんを送るかどちらにするかということだったのだけど、日本で買うことにして、お金をいただいたということでした」
「柳井さんと同じね」
「それで、僕がいい業者さんですねというと、キャットパラダイスというそうです、ハワイの会社です」
「あ、そう」
「代理店の方は猫と一緒に保証書と名詞をおいていったそうで、見せてもらいました。保証書はハワイのキャットパラダイスのものでした。名詞はキャットパラダイス日本代理店、猫なんとか石という会社で、女性の名前は鈴木美和でした。電話番号も控えました」
「もしかしたらこういう字」
野霧が紙に書いて見せた。
「あ、そうです」
「これせいびょうせき、と読むのよ、猫目石のこと、社長は池波光子、キャッツアイがキャットパラダイスの代理店やってるのね、鈴木はそこの店長かもしれない」
吉都もびっくりした。
「え、所沢の池波夫人の娘でしたね」
「ええ、それで、これからその人のこと調べようと思っていたのよ、府中に住んでるの」
「どうなってるんだろう」
「しかもね、池波光子は宝石鑑定士なのよ、輸入した猫の事故死、マイクロチップの消失、なんだか猫と宝石がつながりそう」
「たいへんだ」
「そうでしょ、だからキャッツアイの池波光子が、池波夫人の義理の娘か再確認することと、宝石鑑定士としてなにをしているのか、動物商としてなにをしているのか調べなければ、十八匹の猫の骨のこともわかってくるかもしれない、それにハワイのキャットパラダイスとの関係が分かると、宙夜さんが追いかけていることと繋がる可能性もある。」
「宝石なら、ヒミコさんの誰かに聞いてみるといいかもしれませんね」
ヒミコとは昨年引き受けた大事件で出会った不思議な八人のヒミコで、あの有名な卑弥呼と関わりがありそうなのである。八人のヒミコはみな医者か歯医者で、アーティストでもあり、コレクターでもある。
不思議な事件で、首謀者は、事務所に依頼してきた弁護士であることがわかり、稀覯本のコレクターで、卑弥呼が書いたと思われる日本最古の本を手に入れるために仕組んだことだった。あぶりだされてきたのは八人の美女たちであった。その物語を、今、野霧がミステリーとしてまとめているわけである。
吉都が言った「ヒミコ」は八人の中の一人、「翡海湖」で、鵠沼でアクセサリ制作工房を経営している。自分も骨の細工をする整形外科医である。本名は月足美目(つきたりみま。義眼を作る博多の「妣視杞」も宝石を扱うが、博多にいるのでちょっと遠い。
「そうね、工房の方に電話をいれてみよう」
野霧が本を書くにあたって、八人には協力してもらっており、仲よくしてもらっている。
「あ、野霧です、ちょっと教えてください、池波光子さんという宝石鑑定士をご存知ですか」
「ええ、直接はなしたことはないけど有名な方よ、とても目利きで、特にキャッツアイ効果の宝石や、スターのでる宝石については詳しいし、本人もキャッツアイのコレクターという話よ、彼女がどうしたの」
野霧は動物商のことに関してはだまっていた。
「ちょっと仕事で会ったご婦人の、義理のお嬢さんだということをうかがったので、翡海湖さんがご存じかもしれないかと思って、電話したのです」
「野霧さん、なにかあるんでしょ、内緒の仕事なのでしょうから聞かないわ、緋虎ジュエリーの人にきいてみますね、なにが知りたいかしら」
翡海湖さんはお見通しだ。緋虎ジュエリーとは銀座の宝石店である。
「どのような人か写真があれば見たいと思ったものですから、それにどこにお住まいなのかと思って」
「写真はわからないけど、住んでいるところはすぐわかるわよ、緋虎ジュエリーに名刺ぐらいはあると思うわよ、鑑定士は出入りしていますから」
「すみません、お願いします」
「ねえ、野霧さんの本いつできるのかしら、楽しみにしているのよ、われわれみんなで売りさばいちゃうから」
「そんな、大それた物ではないのですけど、もうすぐできると思います、よろしくお願いします」
野霧は電話をきった。
「緋虎ジュエリーにきいてくれるって」
「昨日はいろいろ収穫がありましたね、僕らも宝石のことを知らないといけなくなるかもしれませんね」
吉都はネットで宝石で検索をかけた。あまりにもありすぎて、何かに絞らなければなにもわからない。
猫目石で引いてみようと画面をみたとき、「国際宝石展」という字が目に留まった。
「国際宝石展というのがありますね、色々な宝石をみることができるのかなあ」
独り言を言いながら、吉都は「国際宝石展」のホームページをあけた。
「野霧さん、国際宝石展て、とても大きい展覧会のようですね、世界から宝石商が集まって、プロの人たちが買いにいくところですよ、お台場の展示場だ。ずいぶんたくさんの店がでてます。こういうところには必ず宝石鑑定士のような人は行くでしょうね」
「そうね、我々も行ってみる」
「会員制ですよ、宝飾関係の人か、推薦してもらわなければだめなようですね、名刺を提出とあるから、かなりむずかしそう」
「また、翡海湖さんにきいてみよう」
野霧が電話をかけると、宝石展には、翡海湖本人はいかないが、工房の人が行くということだった、翡海湖自身も会員なので推薦してくれるそうである、案内状は探偵事務所あてではまずいので、野霧の自宅に送ってもらうことにした。
それからまもなく翡海湖から野霧に電話があった。銀座の緋虎ジュエリーから、メイルで宝石鑑定士、池波光子の連絡先が送られてきたので転送するというものだった。
野霧がメイルをあけると、転送されてきたのは、スキャンされた名刺で、GG,AG 宝石鑑定士、池波光子、とあり、府中の住所と、携帯の電話番号がかいてあった。それに緋虎ジュエリーに来たときの写真が添付してあった。
「やっぱり、キャッツアイと猫睛石の社長は、池波夫人の義理の娘だったわよ」
「でも池波夫人は、息子の嫁さんが、動物輸入業や動物美容室してるの知らなかったのでしょ」
「そうね、知っていたら、そこから猫ちゃん買うでしょう、だけど、タイに観光に行くのは義理の娘さんが勧めたからだって言ってなかったっけ」
「あ、そうでした、ミステリーらしくなってきましたね」
次の日、詐貸が富山から帰ってきた。二人は今までのことを詳しく話した。
詐貸も「猫女石ミステリーになってきたか」と、富山からもってきたものを二人に渡した。
「水良(みずら)さんからの土産だよ、養殖した魚の薫製だって、今度は一緒にきてくださいって言ってたよ」
水良は詐貸が顧問弁護士をしている北京骨商の社長で、骨に効く薬を作っている。新たな薬の開発だけでなく、魚の養殖もこころみている。交配や遺伝子編集で、質の高い魚を作り出している最中である。水良は魚の発生の研究者でもあり、会社の敷地に世界中の魚の剥製博物館を開こうとしている。
「次にはついていきまーす」
野霧も吉都も富山の会社のゲストハウスに泊まるのが大好きである。夕食には新鮮でおいしい魚料理がふんだんにでる。
「それで、国際宝石展のことですが、翡海湖さんがたのんでくれて、招待券を送ってくれるそうです、行きたいのですが」
「うん、いいよ、いつまでやっているの」
「結構長いんです、五日間やってます、始まるまでまだ十日ほどあります」
「富山に行っているときに、薩摩からメイルがはいってね、宙夜が明日帰ってくるってさ、それで、話を聞きにこないか言われている、宝石の話が聞けていいかもしれないね」
「そうですね、ハチ公のところに行くのも久しぶりですね」
「うん、話の後、宙夜と神無月でどんちゃんしたいらしいよ」
「それはいいですね」
「ところで、野霧君の本の原稿はそろいそうかい」
「はい、だいたいできました」
「半田の一粒書房との交渉はすんでいるんだろ」
「ええ、それで、表紙の絵を誰に頼もうか考えているのですけど、いい人いますか」
「うーん、そっちの方は知らないな、ヒミコさんたちもちょっと違うしな、野霧君自分で描いたら」
「あの、私が絵の具つけて転がった絵がありますが」
詐貸と野霧がぎょっとした。つなぎ合わせた紙の上に野霧が体中に絵の具を塗って、転がった絵だ。
「冗談ですよ、私絵かけません、吉都君の方がうまい」
野霧が顔を膨らして笑っている。
「僕は生物のスケッチは得意だけど、図鑑の絵のようになってしまう」
詐貸が野霧を見た。
「野霧君のお姉さんにたのめ」
野霧は、あ、っと叫んで、こっくりとうなずいた。
「いいですか」
「絵描きさんだろ、書いた原稿を読んでもらったらいいじゃないか」
野霧は顔を丸くした。嬉しいときだ。
宙夜の報告
それから三日後、庚申塚探偵事務所の三人は、警視庁の研究支援センター第八研究室にでむいた。部屋に入った野霧が「わっと」と声を上げて立ち止まった。吉都と詐貸も驚いた。机の上や棚にいろいろなポーズの猫の骨が突っ立っている。はっと三人が気がつくと、ハチ公のスタッフが自分の机にすわって、笑いながら三人を見ている。
「おーよくきてくれた」
室長の薩摩が大きなデスクから立ち上がった。彼の机の上にも二体の猫の骨が置いてあった。
四人のスタッフも立ち上がった。
「宙夜さん、久しぶり」
野霧と吉都が声をかけると、
「久しぶりです」、
律儀な宙夜が腰を曲げてお辞儀をした。この中では宙夜とキックが一番若い。
「宙夜から聞いたところによるとな、かなり大がかりな宝石の密売組織があるようだ。密輸摘発のグループは世界に飛んでかなりの成果をあげたようだな、ところが、宙夜は思わぬことに、日本への宝石密輸組織があることを見つけてきたんだ。宝石密輸の世界の大きな組織の一端ではあるが、それが明らかになると、敵さんにはかなりの打撃となるはずだ」
皆が会議のテーブルにつくと、薩摩がそう口火をきった。
「宙夜は調査の連中と、まずタイの原石発掘の現場に行き、その町の石の売買市場を調べ、その後、何班かに分かれ、周りの国に行ったんだそうだ。宙夜の斑は、かなり大きな売買市場であるバンコクに行ったんだ。そんなことで、宙夜から最初に原石採掘のところの話から聞こうと思う、資料はコピーはまずいのでとっていない、机の真ん中においておく、見たいときには見てくれ」
結構大変な調査だったようだ。それにしても、このような機密情報を我々に見せていいのだろうか。詐貸は一言言おうと思ったが、当然薩摩の方でもそれはわかっていることだ。思いなおし何もいわず宙夜の話を聞くことにした。
「宙夜さん痩せたようね」
野霧が顔を三角にしている。ちょっと気になっているときだ。宙夜はどちらかといったら小柄である。目がちょっと窪んでいる。
「そうですね、結構ハードでした、神経使いましたからね、日本に帰った日は二十時間眠りました、スタッフには客観的なことしか話をしていないので、今日は探偵事務所の方たちに、主観も交えて説明します。何でも質問してください」
「向こうでなにを食べてました、おいしかったですか」
野霧は食べることにまず気をとられる。詐貸が全くもーという顔をしている。だがああそうかと思い直すところが詐貸である。野霧は緊張をほぐそうとしているのだ。
「辛い物が多いことはよく知ってますよね、だけど結構うまかったですよ、実は一般の旅行客や宝石に興味のある素人のなりをして、町にはいった捜査員は、町の人たちの食べる店や、土産物屋にいきました。何人かの調査員は、富裕層の格好をして、大きな宝石商の格好ですね、土地の案内人を従えて、潜り込みましたので、結構高級なものを食べていたでしょうね」
「それで、宙夜さんはまさか、富裕層に化けたんじゃないのでしょうね」
吉都が言ったので、野霧は、
「そんなことはないよ、御曹司の雰囲気もあるじゃん」
とやんわり否定した。
「野霧さんはずれ、吉都さん正解、ヒッピー風、学生風の格好をして、店屋をのぞきました。ただ、採掘現場には向こうの警察関係者といっしょに、技術屋の格好をして行ったり、向こうの会社のお偉いさんの説明を聞いたりもしましたよ」
「顔がわれちゃうんじゃないの」
「そういう会社は問題ありません、もちろん、会社の内部の社員などに関しては、地元の警察が内偵していて、怪しい動きのある人間はリストアップされています。そういう連中とは顔を合わせることはありません、実は許可を得て採掘しているところの何十倍、何百倍の個人採掘や裏組織の採掘地が山奥にあって、そういう物が密輸品になることが多いと思われます、もちろん、有名なところの物も、別のルートで密輸品になる場合もありますが」
「タイの宝石はなにがいいんですか」
「ルビー、サファイアーでしょうね、山にある玄武岩からでます。特にタイの西部地方に産地があって、ボ・ライ地区は宝石の町といわれ、宝石の市があって、カンボジャ、インドネシヤなどの宝石の産地から持ち込まれた石が安く売られています、バイヤーがうろうろしていますよ、調査員の何人かは日本からのバイヤーに化けていました」
「観光客でも買えるのですか」
「もちろん大丈夫です、ただ、偽物をつかまされることが多いので、目利きの人と一緒じゃなければ怖いですね」
「機械で掘り出して、石を探すのですか」
「大きな会社ではそうですが、山の奥では、まだ玄武岩を手作業で掘り出して、水で洗って、サファイヤながどはいっている石を拾い出すという、原始的な方法でもやっています、そういったところで大きな拾い物があるようで、それを裏組織がかなりの額で買い取って、密輸などに回すわけですよ、裏組織そのものが発掘を指揮していることが多い」
「そうか、それを、密輸でもちこんで、その国で加工するわけか」
「そうです、日本でもやってるでしょう」
「山梨あたりかしら」
「そうですね、甲府あたりは調べる必要があるでしょう、だけど逆に有名なところじゃなくてもいいわけです、腕のいい技術者が目立たないように地方で、宝石を加工しているかもしれない、東京だって言いわけ」
「タイにはそういった宝石の町は沢山あるのですか」
「ありますね、南東部のチャンタブリは世界の宝石が集まり、加工され輸出されるところで、そこもいきました。タイの加工技術はとてもすすんでいます。最近タイと山梨県が宝石の協定を結ぼうとしていますね、日本の技術はすごいのですが、宝石はあまりでません、甲府の水晶ですら少なくなって、あまり採ることができない状態です、ただ加工技術は世界で認められているところです」
「向こうに行って、怪しい組織がわかりましたか」
「密輸の捜査員たちはすでに、いろいろな情報を入手してから出かけています、向こうの警察でも調べは進んでいて、怪しい人物などはリストアップされています、そういった人物の動きを実際に見て、どのようなものか確認をするのが、まず一つの目的でした。それと、うまくいったら、そういった裏組織と、日本との関わりがどのようなものか、ヒントを見つけることが目的です。これが始めてではなく、担当官数人で潜入することはこれまでもやってきたし、今までの情報の積み重ねはあります。今回のように、ハチ公ややくざの担当官、輸入関係、それに交通関係の者など幅広い構成で調査に行くのは初めてです」
「どうして、交通警官が関係するのかしら」
「交通警官と言うより、車、飛行機など運搬について知識のある者といったらいいでしょうね、輸入された車の一部に石を隠すこともありますし、飛行機の荷物に紛れ込ませることもあります、心理学者も一緒でしたよ、錯視の専門家です、だまし絵の原理を調べている人でした」
「おもしろいわ、本物の宝石を逆にガラス玉と思わせて密輸出するのに、心理学が大事なんだ」
「そうなんです、当然ガラス玉だろう、または樹脂でできているだろうと思わせるんです、僕が日本で気がついた義眼が宝石だったということから、心理学者にも加わってもらったわけです」
「そうなんだ」
「こんなこともありました、心理学者と、宝石の市を歩いていてたとき、日本人の観光客が、宝石を売っている男と交渉していたのを見て、おかしいというんですよ、なにがおかしいのかこっちはわからなかったんですが、彼はあれは日本人観光客を装っているアジア人だというのです。離れたところにいたのに心理学者はそう言ったのです。それで、タイ語のできる刑事が近づいて様子を見ていたら、その日本人がルビーを買ったのです、日本語を交えて交渉をしているのを聞いて、その日本語がおかしいことにその刑事も気がつきました。それにその日本人のような振りをしていたアジア人は、明らかに偽物だとわかる石を買ったのです。刑事はそのことを伝えにきたので、ヒッピー風の僕ともう一人、観光客に化けた刑事が、その偽の日本人のあとをつけました。宝石市では、さらに二つサファイアの偽物を買いました。その後、オトコは町の一角の観光客むけの珈琲屋に入り、タイ語のできる刑事がはいりました。僕は外で見張っていました。少したつと刑事がでてきて、タイ人の男が、その日本人のふりをしている男から、買ったルビーとサファイアを受けったということでした、僕はその店の反対側の路上で、珈琲屋に出入りする人間の映像をわからないように撮影しました。その男が珈琲からでてきて、刑事がその男のあとをつけました。僕はその後出てきた日本人の偽者を映して、あとをつけました。
偽の男は貧民窟にはいっていったので、そこで追うのをやめました。一人でふらつくのは危ない場所です。タイの警察にもどったら、タイ語のできる刑事ももどっていて、向こうの警察の担当者に映像を見せ、話をしたわけです。偽の宝石を受け取った男と日本人に成りすましていた男の素性はすぐわかりました。どちらもタイのマフィアのグループでした。
なぜ観光客の振りをして偽の宝石を買ったか、それは偽物を売った宝石売りを恐喝して、買った値段の数十倍の価値のある本物の宝石をとりあげるということをしていたんです。きっとそういった石を密輸出するか、他で売るかして資金を得るのでしょう。話は長くなりましたが、心理学者はそういった人の動きも見破ることができます」
「なるほど、だいたい刑事さんは心理学者よね」
野霧が一人でうなずいている。
「探偵さんもね、小説家だってそうだ」
古本さんが珍しく口をはさんだ。
「でも、僕の知っている心理学者は、自分のこともわからないような人でしたよ」
吉都は心理学者がにがてのようだ。
「それは、基礎心理をやっている人じゃないかな、往々にして理論だけからしか、人がみえない」
高胎さんは、看護師の資格がある。しかも文学部出身でもあり、心理の先生とは長く接してきた経歴がある。そんな感想を言った。
「でも心理学者は離れたいたところから見ていて、よく偽の日本人だとわかったものですね」
「日本人の振る舞いは同じアジアの中でもちょっと違う、物を買うのに遠慮がちだし、それに自信がなさそうなのだが、その男は売り手とかなりてきぱきやり取りをしているのがわかったからだそうです」
「そうなんだな、買ったほうがありがとうとお礼を言うのは日本人だものな」
吉都もうなずいた。
「それで話を元に戻すと、ともかく、タイは宝石の産地でもあるし、国際マーケットの一つの中心地でもあるわけで、裏の組織が入り込んでいることは確かなわけです、国際的な宝石鑑定士の資格を出す組織がバンコクにある。AJGSAといって、そこで資格を取得すると、AGという称号がもらえる。世界に通用する資格です」
野霧が思い出した。
「今私たちが追いかけている宝石鑑定士がいるの、池波光子っていう人だけど、名刺にAGがついていたわ、それにGGもついていた、なんでしょう」
「GGはGIAというアメリカの宝石学会のだすもので、もっとも権威のある宝石鑑定士の資格ですよ、かなり歴史のあるものです、AGは1970年代からだから新しいけど。二つもっているということはすごいことですよ」
宙夜は宝石のことに詳しい。それにしても池波光子は二つもなぜ取得したのだろう。
「アメリカやタイに行かなければ取れない資格ですか」
吉都がきいた。
「いや、どちらも日本に委託された協会があって、日本でとれます。通信課程がありますが、それにしてもお金はかかります、英国の宝石学会の宝石鑑定士の資格はFGAといいますが、歴史的にはもっとも古いもので、それも日本でとれます」
「そうなのね」
「現場を見ると、いくらでも裏の道が考えられます、石をどのような方法で、それぞれの国の裏の組織にわたすのかというところを調べる必要があります、産地の調査は地元の警察に任せ、我々はタイから外に出す場所を調べました。、空か海なので、大きな空港や港があるところに裏の組織が発達するでしょう、もちろんタイの警察もそれは考えていて、いくつもの密輸出の組織をすでに見張っています。だがそれをかいくぐってうまくやっている、さらに裏の組織がいくつもあると思います。そういう組織は少人数でやっている可能性がある。石を見る眼のある人間と、外に持ち出す方法に詳しい人間がいれば密輸出できます。後は相手の国にいる裏の売人組織と関係つける力があるかどうかです」
「どうやったらその組織をみつけることができるのかしら」
野霧がたずねたら、宙夜じゃなくて、吉都が答えた。
「もし日本でタイからの密輸された石がみつかったら、隠す方法がタイでならどのような組織でできるか考えるわけですね。たとえば、宙夜さんが義眼に隠していたことを明らかにしたということは、タイで義眼作成技術を持つ組織の中でおかしな動きをする人間を捜し出す、ということですね」
「吉都さんの言うとおりです、それで、僕はバンコクに行く班にはいり、義眼からそういう組織を探そうと思いました、今回は怪しいと思われる人間が何人か浮かんだ程度で帰ってきました。
その間に、バッチェラ・リーの猫の会社を見てきました。メーオ・サワンという会社です。バッチェラ・リー本人とも会いました。彼はまっとうなブリーダーでした。ただ、野霧さんや吉都さんが言っていたような貴族、金持ちではなく、ふつうの市民でした。家族と何人かのアルバイトで猫を飼育していました。ただサポートをしてくれている人はいるようです、なんとか聞きだそうとしたのですけど、猫好きの人としかいいませんでしたね、アメリカ人のようです。産まれた子供をハワイに送っているようです。アメリカ人はキャットパラダイスという猫の店を経営していて、そこにおろしているので、安定した収入があるようです」
野霧と吉都が顔を見あわせた。
「でましたね」
「なんのことです」
野霧が言ったことに宙夜が不思議そうな顔をした。
「キャットパラダイスで猫を買った日本人が、帰国するとすぐ、猫が自動車事故で死にました。日本の代理店が保険をかけていて、払ってくれたそうです。その代理店は、動物輸入商「猫菁石」といいます、キャッツアイという猫の美容室もやっていて、社長が池波光子という宝石鑑定士です」
「へえ、そのGGとAFGをもっている人ですね」
「そうなんです、猫目石のコレクターでもあるようですし、所沢の猫の骨事件のときに、バチェラ・リーの息子だと言っていたサーマート・リー、すなわちトムチャン・ウオンが下宿していた、池波夫人の長男の奥さんです」
「そういえば、バチェラ・リーに子供はたくさんいましたけど、サーマート・リーというのはいませんでした。トンチャン・ウオンの足取りはまったくわかりませんでした」
「バチェラ・リーさんの猫の会社はメーオ・サワンというのでしたね、どんな意味があるのです」
「そういえば、タイ語で猫の楽園だ、キャットパラダイスだ、名前の由来はきかなかったな」
宙夜が「メイルで聞いておきましょう」と首を傾げた。
「池波光子はGGもとったのに、なぜAFGもとったのでしょうね」
吉都の質問に「タイとのコネを強くするためかもしれないですね」と言った。
「タイはキャッツアイがとれるのですか」
「キャッツアイはロシア、スリランカ、インドやブラジルでしょう、タイでは特産ではないですね、ただ、さっき話したように、世界の宝石が集まるところだから、手にいれやすいでしょうね」
「だからかしら」
「それから、キャッツアイとは宝石ことじゃないのですよ、まあ、同じこととして使われていますけどね、キャッツアイとはキャッツアイ効果のことで、宝石を磨いてでてきた真ん中の白い筋のことなんです、猫目石はクリソベリルという石、日本語で金緑石ですけど、その白い筋のでるものなんです。正式にはクリソベリルキャッツアイといいますね、蜂蜜色で、乳白色の白い筋が真ん中にでるのが最上の石と言われています」
「そうなんですね、いくらぐらいです」
「数百万でしょうね、他の石にもキャッツアイ効果がみられるものもあるのですよ」
「誰かそんな指輪くれないかな」
指輪コレクターのキックがつぶやいたが、みんな顔を背けた。
「宙夜さん、大変でしたね」
ずーっと黙って聞いていた詐貸が口を開いた。
「日本の受け皿はどう考えていますか」
宙夜は困ったなという顔をした。
「完成された宝石を密輸したなら、それを売ればいいわけだけど、完成されていないものだと、現地で磨かなければならない、甲府などにそういう組織があってもいいわけだ、もちろん、東京のどこかにある可能性も高い」
「そうなんです、日本の宝石協会からも情報をもらってはいます、だけど、そういうのをかいくぐって、個人でやっている人間もいるでしょうし、だが、磨く技術はおいそれと手につくものではないので、いい宝石をつくりだすとすると、かなりの加工技術を持つ、一時名を馳せたような人じゃないとできないでしょうね」
「宝石の研磨の技術を取得したのだけど、理由があって別の道に進んでいる奴だとか、こっそり副業でやっているとかですね」
「そうですね」
「猫屋が宝石屋をやっているなんていうのも、やっぱり気にしたほうがいいね」
「池波光子ですね、それは所沢の猫の骨のことを明らかにするためにも調べなければなりませんね」
「やることがはっきりしてきたな、どうだい、あとは巣鴨にいこうや」
薩摩が声をあげた。
「やーじいさん、久しぶり」
神無月の暖簾をくぐった薩摩が、カウンターの中にいた主人に片手をあげた。
「きやがった」
「いらっしゃいませ、お早いですね」
姫さんが奥から出てきた。客はまだだれもいない。ハチ公の連中は、四時にならないのに警視庁を出てきたのだ。もっとも、今日は早朝出勤したので早退あつかいにはならない。
「羽田の津軽さんは今日は無理だってよ、次の機会にきてもらうことにした」
薩摩が後ろにいた詐貸に言うと、
「こないだ来たばっかじゃないか」
主人が笑いながら薩摩を見た。薩摩はすでに津軽をつれてきたようだ。
「みなさんお揃いで、探偵さんたちも、こりゃ宴会だね、いつものコースでいいね」
「たのまー、宙夜が一月ぶりにご帰還でね」
「宇宙飛行士みてえだな」
皆はぞろぞろと入ってくると、勝手に机を動かし、くっつけて、席に着いた。
「どこにいってらしたの」
姫さんがおしぼりをみんなに配った。
「内緒ですよ、タイにいました」
「タイっていやあ、宝石泥棒追いかけたんだろう、それとも盗みにいったか」
じいさんの反応が早い。
「ご主人タイにいったことあるんですか」
野霧の質問に、「へへ、新婚旅行、こいつに宝石買っちまった」
神無月のじいさんが、どんな顔をして、姫子さんに宝石を渡したのか想像して、むーっと口をつぐんだ。
「なんでえ、じいさんが宝石を買うなんて、似あわねえ、おっと、姫子さんにはどんな宝石でも似合いますよ」
薩摩が口を滑らすと、主人が包丁を振り上げて、「サツマイモの天ぷらにしてやる」
とどなった。
そこにお通しとビールがでてきた。いつものように、野霧が、
「宙夜さん、おかえりなさい」と、ぐーっとビールのジョッキを半分まであけた。
「宙夜君、宝石の指輪かってきた?」
キックがきいた。宙夜は首を横に振った。
「買うなら細工されていないのを買ってきて、日本で指輪にしたほうがいいよ」
「それじゃ、宝石は買ったの」
しつっこくきく。
「いや、仕事でいったんで、現地で買うわけには行かなかったんだ、バンコックのデパートや免税店ならいいかもしれないけど、そうなると安くもない。原石の小さいのなら日本だって数百円で買えるから、俺、化石の方に興味があるんだ、ミャンマーで蟹の化石が見つかったようだけど、そういうのほしいなと思ってたんだけど、なかった」
「タイでも化石でるの」
「うん、恐竜もでるし、貝の化石が有名だよ、スーサン ホイっていう」
「タイのリーさんとこの猫は見たんですか」
「ええ、みんなきれいにしてましたよ、丁寧にあつかっていた」
「タイでも売れるのかしら」
「いや、タイのお金持ちも買ってくれるけど、かなりは輸出だって言ってましたよ」
「それじゃ、日本にも輸出しているわけ」
「ハワイに送る以外は、日本が一番いいお客のようですよ」
「ハワイや日本には直接輸出しているのかしら」
「いや、タイにエージェンシーがあるらしくて、輸出には時間がかかるでしょう、そちらにまかせているようですね、それがサポートしているアメリカ人だと思います、だからブリーディングだけに専念しているようです」
「そのエージェンシーはわかりますか」
「僕のファイルにはありますよ、猫の方は仕事じゃないので、今回の宝石密輸の調査ファイルには記録を残してありません」
「そうよね、バチェラさんとは連絡つきますか」
野霧が聞いた。
「もちろん、メイルアドレスも知っています」
「まえからバチェラさんのブリーディング会社はメーオ サワンといったのかしら」
「十年前はバチェラ猫産業といったらしいけど、輸出のエージェンシーと組むようになって、名前をそうしたといってました。そのほうが高級感があるとも笑って言ってましたね」
「名前にこだわるようだけど、取引先のハワイのキャットパラダイスから考えたのじゃないかしら」
「同じ猫の楽園ですからね、バチェラに聞いてみましょう」
「まあ、宙夜君ごくろうさま、しゃべってたら、ここのうまいもん食えないよ、まあ、飲んでくれ」
薩摩が宙夜のジョッキに自分の飲んでいるジョッキをかちんとあてた。
「あら、ごめんなさい、また質問ぜめにしてしまったわ」
野霧もジョッキをぐーっとあけた。
詐貸が薩摩に言った。
「俺たちも乗りかかった船だから、池波光子についてはもっと調べるよ」
「池波光子に宝石を依頼して、猫の輸入を監視するのはどうかしら」
「そりゃいいかもしれない、でも宝石を買う金がないよ」
詐貸がいうと、薩摩が「誘拐犯に札束を用意するように、こっちで何とする、宝石を買う役割は、高胎君がいいな、その女の心理を解析してもらおう」
「いいですよ、ほんとに宝石ほしいわ」
高胎蓉子は日本酒をのんでいる。
薩摩が「焼酎くれ、じいさん」と声を張り上げた。
「なんだ、じいさんとは、はいよ、探偵さんには、きょうはマルベリーね」
姫子さんが、マルベリというウイスキーの満たされたロックグラスと、チェーサーをもってきた。
もう一つ、百年の孤独がどんとでてきた、氷のはいったグラスも一緒に薩摩の前に置かれた。
「お、こんな高いの飲んだことないよ、じいさんありがとよ」
「じいさんじいさんゆうな、薩摩から札束をふんだくるんだ」
「うひゃあ」といいながら、薩摩はグラスに百年の孤独をついだ。
「こいつも薩摩切り子だ」と身震いした。「いくらとるつもりだ」小声でそういいながらぐいと飲んだ。「うめ」。
古書が野霧に声をかけた。
「もう、本がでるんでしょ」
「原稿はだいたいできあがってるんだけど、まだ校正を重ねなければいけないし、いま表紙の絵などの企画をたてているところ、もうすぐ出版社に渡します」
「なんというタイトルなんです」
「八人の卑弥呼」
「いいね、八人の美女の犯罪か」
薩摩が酔っぱらってきた。
「あんまり、ミステリーっぽくないんです、まあ殺人のない歴史探偵小説とでもいうのかな」
「おもしろそうですね、ハードカバーでしょ」
古書は本そのものに興味がある。
「ええ、A5のハードカバー」
「ケースも作りましょうよ」
「予算がわからない」
「だいじょうぶだよ」
詐貸がからになったグラスをふった。主人がうなずいている。
そこに客が入ってきた。
「らっしゃい、なんだ」
主人が入り口をみると言った。入ってきたのは五十嵐五十老だ。有名な推理小説作家。
「あ、五十嵐先生」
声を上げたのは野霧だ。野霧は五十嵐の本をたくさんもっていて、神無月で、サインをもらっている。ペンネームは黒川三郎というのだが、この店でその名前は言ってはいけないと、神無月の主人に言われている。知られると人が押し寄せてきて、五十嵐はこなくなるだろうと言うことだ。
「いつものたのむよ姫ちゃん」
作家がカウンターに腰掛けると、詐貸がいきなり立ち上がり、五十嵐の脇に行った。
「失礼します、詐貸と言います」と、名刺を差し出した。
野霧や吉都、それにハチ公の連中はきょとんとしている。もちろん五十嵐も驚いている。
五十嵐は名刺を見ると、「あ、ほんまものの探偵さんね、知ってますよ、逢手さんが自慢しているからねえ、何度かここでお見かけしましたな」
五十嵐はなんだろうという目で詐貸を見た。
詐貸がかしこまっている。
「じつは、今度、逢手が本を自費出版することになりまして、ミステリーというか、歴史物というか変格探偵小説でして、もし、できれば、先生に原稿を読んでいただいて、一言書いていただけると光栄に思うしだいです」
なんとも詐貸がかなり堅くなっている。いや演技だろうか。
「ほう、逢手さんが」
五十嵐が野霧を見た。野霧は詐貸の言ったことにびっくりしてあわてている。
「そりゃおもしろい、是非読ませてよ、楽しみだな、もし一言書かせてくれるなら、喜んで書きますよ」
五十嵐は満面の笑みを浮かべながら、カウンターに用意された熱燗を猪口にそそぎ飲んだ。
野霧があわてて、駆け寄って、徳利を空になった猪口に傾けた。
「いや、いや、逢手さんが注いでくれるとは、この一杯だけでいいよ、いつものように一人で飲みますからな」
五十嵐は一人でのんびり飲むのが好きなのだ。
「よろしくお願いします」
野霧が頭を下げた。
「原稿はいつ読ましてもらえるのかな」
「一応もうできています、送っていいですか」
「明日もくるから、ここでもらうよ」
「はーい」
やっと野霧も野霧らしくなった。
「みなさんはプロ、あたしゃ素人の嘘つきで、面白いねたがあったら教えてくださいよ」
老探偵小説家は、皆のほうにお猪口をさしあげた。
すると、いきなりみんながたちあがって、
「野霧さんをよろしくお願いします」
と頭を下げたのには、さすがの老練作家もびっくり。
店の主人が「おー、野霧さん人気だねー、そんじゃ、いっぱいずつおごりだー、と声を張り上げた。薩摩までしっかりと頭を下げていた。
野霧はじーんとなってハチ公のテーブルにもどった。
「楽しみだなー」
古書たちに言われて、野霧も笑顔に戻った。
野霧は詐貸を見た。ウイスキーグラスを手に持って、神妙に回しながら飲んでいる。あんなことに、あんなに緊張して、でも野霧はとても嬉しかった。
国際宝石展
詐貸が事務所に入ってきた。
「あ、おはようございます、昨日、五十嵐先生にたのんでくださってありがとうございました」
野霧が自分の席から立ち上がった。
「いや、余計なことしたかな、あの場で思いついたもんだから、つい」
「とんでもない、五十嵐先生に読んでもらえるなんて、すごいことですよ、私もほんとはそうしたかったんですけど、神無月で飲んでいる先生はのんびり飲んでいるようで、どこか人を寄せ付けないんですよ、以外と近づきがたいんですよ、有名だからじゃなくて、なんていうか、やっぱり人生の大御所ですね、私は詐貸先生に一言書いてもらうつもりでした」
「ええ、あーそう、五十嵐先生にたのんでよかった、俺書けないよ」
そう言いながら詐貸は自分のデスクに腰掛けた。
吉都がPCを見ながら言った。
「宙夜さんから、メイルが来てます、タイのバッチェラ・リーの猫の会社に投資して、輸出を受けもっているエージェンシーは、ハワイのキャッツパラダイスのタイの支社とあります、会社の名前もエージェンシーの意見があったそうです」
「つながってきったわね、それにしても宙夜さんやることがはやいわね」
「昨日の夜、メイルをいれておいたそうです、九時には返事もらったみたいです、タイとの時間差は二時間ですから、向こうは朝七時ですね、動物の世話をするところは早起きですよ」
「そうね、ハワイのキャッツパラダイスがあやしいとこね」
「ええ、もうホームページはみました。小さな島一つですが、ずいぶん広い敷地で、ホテルも経営していて、ビーチもあって観光もやっているようです、どのような人がやっているかわかりません、あの、キャッツパラダイスで買った猫ちゃんが車に轢かれてしまった人にもう一度会ってみようと思います」
キックと吉都が六本木に訪ねていった白井さんだ。
「あ、そうね、ハワイで買ったんだから、向こうの人に会っているわね」
「また、キックと行ってきます」
「たのむよ」、詐貸も二人の話を聞いていたようだ。
吉都はすぐに、その件に関してキックにメイルをいれた。
詐貸が二人にこれからの予定を話した。
「薩摩とも話したんだけどね、高胎さんが池波光子に宝石の相談をすることになった。もし、商談が成立したら、光子の動きを調べるのと、ハワイのキャッツパラダイスから送られてきた猫を税関の検疫所で詳しく調べる、古本さんも検疫所のチェックに加わる、それで、まず池波光子という女性を見てみたいそうだよ」
「宝石鑑定士としての電話番号はわかりますが、素人が直接購入の電話はおかしいでしょう、猫のトリマー店にいればいいのですけど、いつもいるわけじゃないようだし、店に電話をいれてみようかしら」
野霧が鞄から名刺をとりだし電話を入れた。
「もしもし、池波光子さんはいらっしゃるのかしら」
いたら猫の性格のことでも聞こうかと身構えたのだが、電話口にでた女性は、
「社長さんは、今日は見えません、しばらくはご用時でいらっしゃらないと思います。猫のことなら、他の者でも大丈夫ですが、なんでしょうか」
国際宝石展が始まるからその準備かもしれない。
「あの、年取った母親が猫に興味を持っているんですけど、どんな種類がいいでしょうか」
「ああ、そういうことですか、お年寄りなら、手の掛からない、ゆったりした猫がいいでしょうね、あまり重いのもよくないので、日本猫の雌がいいかもしれません」
「日本猫も売っていらっしゃるのかしら」
「いえ、うちは洋猫で、ちょっと訳のある猫をとても安く売っています、和猫はいませんが」
正直である。猫を売るのにあまり商売っ気が感じられない。
「洋猫を輸入しているわけですか」
「取り次ぎをしています」
「よくわかりました、和猫をあたってみます、ご丁寧にありがとうございました」
野霧は電話を切った。
「やっぱり、いませんね、いたにしてもあの店で宝石のことをいうのはまずいかもね、どうでしょう、翡海湖さんが国際宝石展の招待券を何枚か送ってくれるので、高胎さんをさそいます」
「でも、池波光子はいくのかな」
「GGとFGAを持っているんだから行くでしょう、いなくても、宝石を見ておくのもよいと思います」
「そうだな、おれも時間があったら一緒に行くよ」
珍しく詐貸もその気になっている。
「僕はどうしましょう」
吉都も行きたいという顔をしてる。
「吉都には頼みたいことがあったんだ、薩摩とも話したんだが、宙夜さんと一緒に、甲府の宝石関係の調査に行ってもらいたいんだ、吉都には池波光子と甲府の関係を調べて欲しい」
「あ、そのほうがいいです、日帰りですか」
「いや、一日じゃ終わらないよ、必要なだけ、三日か四日かもっとかかるかもしれない、薩摩のほうで甲府の警察に依頼しておくそうだ」
「わかりました、宙夜さんに宝石のことを教わってきます」
「うんたのむな」
吉都は明日キックと白井さんに会いに行く。宙夜と甲府に行くのは数日先になる。
野霧が家に帰ると翡海湖さんから国際宝石展の招待券がとどいていた。詐貸所長と高胎さんの名刺を作っておかなければいけない。所長は地学の大学准教授にしとこう、高原胎さんはジュエリーデザイナーが似合う。私はどうしよう、ケーブルテレビの記者とでもしとこう。名刺はコンピューターで簡単に作ることができる。とても助かるが、名刺は信用できないということだ。
野霧は次の朝、事務所で、みな違う紙を使い、三人それぞれの名刺を作った。国際宝石展は明後日から始まる。池波光子は少なくとも初日にはくるだろう。初日には芸能人のトークがある。人が集まることだろう。
吉都は午後からキックと白井さんに会いに行く予定だ。
夕方、吉都からメイルが入った。
「すごいことがわかりました、まず、ハワイのキャットパラダイスの実質経営者は日本人のようです。白井夫人がホノルルのペットショップをのぞいたときに、日本語のできる店員がいて、キャットパラダイスを勧められたということです、それで、ビーチもあることだし、キャットパラダイスのホテルに泊まったそうです。行ったら、ホテルのベルキャプテンが、ホテルの経営は、キャットパラダイスの持ち主でもあり、島の持ち主でもあることと、日本人の富豪だと言うことを教えてくれたそうです。アメリカ人じゃありませんでした。
キャットパラダイスにいくと、日本語のできる店員が案内してくれて、猫ちゃんをだっこさせてくれ、猫を選んだそうです。ただ、帝王切開をしたので、おなかにちょっと傷があるけど、避妊手術もそのとき施しており、ブリーダーには売れないので、愛玩猫として、安くてお得ですと言われたということでした。よくなれていてかわいい猫だったそうです」
詐貸も自分のPCで吉都の報告を読んでいた。
「日本の富豪って誰だろうね、土地もちかIT会社か」
「調べればすぐわかることでしょうね」
「薩摩にやってもらうよ」
吉都のメイルはまだ続いている。二つ目のメイルをあけた。
「これからが、すごいことです、白井夫人がいうには、キャットバラダイスを案内してくれた日本語がうまい外人はタイの人だというので、なんとなく、トンチャン・ウオンを思い出して、野霧さんが所沢の池波夫人のところで撮った写真をスマホで見せたんです。そうしたら、この人だと白井夫人が驚いていました。誰だと聞いたので、日本の獣医大学に留学していた知り合いだと言っておきました」
「すごい情報ですね、サマート・リー、またはトンチャン・ウオンは、ハワイのキャットパラダイスの中で働いていたんですね、つながってきましたね」
「ほんとだな、これは重要な手がかりだ、薩摩に伝えておかなきゃな」
「キックさんが一緒だから、薩摩さんには伝わりますよ」
「そうだな」
吉都の三番目の最後のメイルには「ホテルは海の料理がおいしかったし、ホテルの中の施設も充実していて、売店もタックスフリーで、ずいぶん大きな宝石ショップがはいっていたということでした、特にキャッツアイがいろいろあったということです、今日はこのまま帰ります」とあった。
「すごい情報だ、ご苦労様」
と、詐貸が返信した。
「あとは池波光子の正体と、トンチャン・ウオンを捕まえれば、所沢の十八匹の猫の骨のことがわかりますね」
「いや、それだけじゃないかもしれない、宝石の密輸もね」
「えーそんなに関係づけちゃうんですね」
詐貸の言うとおりになるかもしれない。
「それで、高胎さんと国際宝石展いくの明日だっけ、東京ビックサイトだよね」
「そうですね、十時に大崎で待ち合わせです、携帯番号きいてあります、先生の名刺作っておきました。地学の大学准教授、高胎さんはジュエリーデザイナー」
「うん、ありがとう、こういうときだけ大学の先生になれるね」
そういうことで、次の日、三人はビックサイトにいった。大崎から臨海線で十五分ほどである。
国際展示場に向かって人がぞろぞろ歩いている。
「結構いくんだな」
入り口には何人もの警備員が配置され、入ったところの受付では、招待券と名刺を渡した。もちろんバックの中も見られた。数年前の宝石展で強盗がはいったらしい。
招待状と一緒に送られてきた予定表にはイベント広場のもようしものの日時があり、会場の店の位置もかかれている。ずいぶんたくさんの店がでている。
詳しいパンフが会場にあり、相談コーナーがあることも書かれている。相談員は宝石鑑定士のようだ。
「相談のところに行けば、池波光子がいるかもしれませんね、もしいたら、私は一度会っているから、高胎さんと所長でお願いします」
「うん、そのコーナーの時間がかいてあるだろう、今からだと、十時から十二時まで、そのあとは二時から四時、2回だね」
「それまで、三人で見て回ろう」
「私いいのがあったら買っちゃう」
高胎蓉子は大いに興味があるようだ。
バイヤーらしき人たちは目的のところが決まっているようで、会場に入るとまずは目的のところに向かって、あまり店をのぞいたりしない。始めてきたような素人は、隣の店へ移動しながら、全部見ると行った様子で動いている。野霧たちもそうだ。きれいな宝石のおいてあるところで立ち止まって、あれこれ見回した。
「女性は自分の指輪の大きさというの知っているんだろ」
詐貸が野霧に聞いている。
「そうですよ、私は九」
「細いですね、私は十よ」
高胎はすらっとして背が高く手も大きいようだ。野霧はゆったりとしているわりには指は細い。
「俺なんか自分の指の太さなんて知らないな」
「ふつうそうですよね、でも今の若い男性は指輪もイヤリングもするから知っているんじゃないですか」
詐貸がそろそろ行こうと二人に声をかけ、東側の隅にもうけられている相談コーナーにいった。机が五つあって、すでに鑑定士が座っている。
三人は男性で二人が女性だ。
「いる」
野霧が二人に言った。黒い服に身を包んで、五人の真ん中の席にどっしりと腰掛けている。
「あら、野霧さんに似たとこあるわね」
高胎にいわれて、「そうかしら」と野霧はちょっとおもしろくない。だが、キャッツアイで会ったとき自分でもそう思ったくらいだから、そうなのだろう。
「それじゃ、俺たちはちょっと行ってくる、野霧君はそのあたり見ててくれる」
「ええ、宝石の勉強してきます」
高胎と詐貸は池波光子のデスクにいった。隣の男の鑑定士は、客が持ってきた宝石をルーペでみている。
「すみませーん」
高胎がいつもとはちがって、ちょっと軽い声で池波に声をかけた。
「はい、ご相談ですか」
「はーい」
高胎が椅子に腰掛けたので、詐貸は後ろに立った。
「なんでしょうか」
「前からほしいと思っていた宝石があるんですけど、どうやって選べばいいかわからないし、怪しいところでは買いたくないし、ジュエリーのお店に行っても、説明を受けると、必ずこれはいい石だって言うんで、どうも買えないんです」
高胎はさすがに捜査官で演技はうまい。池波光子はそれを聞いてやんわりと笑って言った。
「そうでしょうね、それで、どんな石を探していらっしゃるのかしら」
「猫が好きなので、キャッツアイがいいんだけど、値段もピンからきりで、わからないの」
「そうですね、なかなか素人にはわかりませんね、だけど、まずは気に入るきことがだいじね、安いものでも本物はありますから、好きになること」
池波の説明もなかなか上手だ。
「キャッツアイっていっているのは、ふつうはクリソベルキャツアイといって、クリソベルという宝石を磨いたものですのよ、真ん中に白いくっきりとした線がでているのがいいものね、他の宝石でもキャッツアイにはなるのよ、だからキャッツアイでも色のちがうものもありますわよ」
クリソベルのことは宙夜から聞いている。
「茶色っぽいのやら、緑っぽいのやらありました」
「蜂蜜色が一番いいとされているけど、好きなら緑っぽくってもいいでしょうし、虎目石、タイガーズアイってあるのご存じかしら」
「ええ、もっとずーっと安い人造石ですよね」
「いいえ、あれも天然なのよ、ただ、熱を加えて塩酸処理をすると、猫目石にそっくりになるの、それを猫目石と偽って売る人もいるから気をつけないと」
詐貸も聞いていてうなずいた。よく説明している。
「選ぶの難しいな」
「大きなお店なら偽物をつかまされることはないからだいじょうぶよ」
「そんなに高いの買えないから、逆にわからないの、だって高いのは五百万だとか一千万もするでしょう」
「なんかの記念にお買いになるの」
「兄が買ってくれるっていうから」
池波が詐貸を見た。高胎蓉子の演技には驚いたものである。
「いいお兄さんね」
「IТ会社やってるから」
詐貸は心の中で、こりゃすげえ、と思っている。
「私もキャッツアイの石は好きで集めてます、お見せしましょうか」
池波はバックから皮の箱を取り出し蓋を開けた。
二十個ほどのキャッツアイのリングがおさまっている。色は薄い茶色から緑がかったものまで、どれも真ん中に白い線が浮き出ている。大きさはだいたい同じ程度である
「きれい」
「この中に、偽物が一つ、一千万のものが二つはいっているのよ、みなだいたい五カラットほど、お好きなものを一つ選んでごらんになって」
高胎は少し緑かかかったものを指さした。
「いいものをえらびましたね、それだと百五十万ほどの本物よ、上の真ん中にベージュがかったものが二つならんでいるでしょう、どっちがいいかしら」
高胎は左側のものを指さした。
「それはにせもの、五万程度ね、その隣のそっくりなのが一千万よ」
「うわー、わからない」
「むずかしいわね、偽物でも本物と信じていれば、その人は幸せね、でも専門家に本物と確実に言われたものを持つのも幸せ、最初に指さされた百五十万の石はなかなかいいものですよ」
「この会場で探して見つかるかしら」
「ご自分のものを鑑定することはしますけど、買う前にこれ本物かと持ってこられても鑑定はできないのよ、もし探して、みつけることができなかったら、名刺を差し上げとくわ、ご相談にのりますよ」
池波光子が名刺をくれた。
高胎は名前を言った。
「ここでお買いにならなかったら、ぜひご相談の電話くださいね」
池波光子は笑顔で高胎と詐貸を見送った。離れたところで見ていた野霧は、うまく言ったようだなと思って、先回りをして二人を待った。
「お、野霧君、高胎さんの演技すごかったぞ、俺、高胎さんのお兄さんになっちゃったよ、IТ会社の社長」
詐貸がにこにこしている。よほどおもしろかったに違いない。
「名刺をもらいました、そのうち電話して、猫目石買います」
「捜査のお金で買った猫目石は、警視庁でどうなるのかしら」
「私もわからないけど、競売にかけて、損をした分は捜査費用ということになるのかしら、薩摩主任に聞いてみないと」
「競売だと私も参加できるのかしら」
野霧が言うと、詐貸が「密輸品だったら押収だね、全額捜査費用になっちゃうんだろうね、証拠品だから、競売にはならないよ」とがっかりさせることを言った。
「少し宝石を見て帰ろう」
「詐貸所長、お先にお帰りになっていいですよ、私たちゆっくりみたい。お母ちゃんとお姉ちゃんに買ってあげようかな」
「私も何か買おう」
「偽物をつかまされないようにね」
「偽物を買うくらいのお金しか持ってないから、心配いらないですよ」
「今日はそのままひけていいよ、それじゃ俺はささっと見てから帰るから」
詐貸はそういって二人と別れた。
詐貸はその後、警視庁に向かった。薩摩に会うためである。警視庁に行くと、薩摩が「たくさん話したいことがあってね、ちょうどよかったよ」と、テーブルに詐貸を座らせた。宙夜は吉都と甲府にでかけている。高胎は野霧と一緒だ。キックは最近の猫交通事故の現場を飛び回っている。古書だけ、この件とは関係ない殺人事件のことでほかの部署につめている。ある怪奇小説によく似た事件の手伝いである。だから、薩摩しか部屋にいなかった。
「宙夜君はタイでいい仕事してきたね、すごいね、優秀だよ」
「いや、お宅の二人の助手がすごいよ」
「おたがい、周りでもっているんだな」
「そうだな」
薩摩も苦笑いをしている。
「それでな、例の所沢の猫の骨の件、ずいぶん深い根っこがありそうだな、ちょっとまとめてみたんだよ、まずそこからでてきた、トンチャン・ウオン、日本ではサマート・リーといった男、野霧君が写真を撮っていたおかげで、ハワイのキャッツパラダイスで働いていることがわかった。少なくとも、その男は旅券偽造の罪がある。それで、ハワイの警察に調査を依頼した。返事がすぐかえってきたよ。アメリカ国籍をもっていて、モンクット・チェンといって、正式なパスポートをもっているが、一度も海外に行っていない、特に問題を起こしたこともないので、どんな人物かわからないようだ」
「三つ目の名前だな、それが本名か、アメリカ国籍」
「ああ、キャッツパラダイス社長室じきじきの補佐役をしており、国内の出張はしょっちゅうだそうだ、それと、トンチャン・ウオンが海外に入国していないか調べてもらった。そうしたら、かなり出入りがあることがわかった。タイと日本だそうだ」
「それでどうするの」
「アメリカ入国には指紋が必要だろう、それで、ウオンとチェンの指紋と照合をたのんでいる。もし、同じだったら、向こうの警察で逮捕するだろう、偽造旅券使用でね」
「次にハワイのキャッツパラダイスと、タイの出向会社のことだけど、持ち主はアメリカ人ではなくて、日本人だ、それも調べてもらったが、簡単にわかった、Mitsuko,Ikenamiと連絡があった。税金はアメリカにきちんと払っている。ものすごい富豪というわけではないようだよ、もちろん、我々庶民からすればすごいらしいが、ほらトランプとかそういうレベルではないようだ」
「え、池波光子なのか、すごいやりてだな、日本で財産の申告をしなくていいの」
「いや、しなければいけないな、それで裏からちょっと調べてもらったら、光子は宝石鑑定士と猫関係の会社の収入に関して、きちんと納税はしているけど、ハワイのほうのは申告していない」
「もしはっきりすれば、脱税になるな」
「そう、追徴金ということになる」
「それで、キャッツパラダイスから日本への猫の輸入は今もあるのかな」
「それは、検疫のほうから警察の方に連絡をもらうようにしてあるよ、ハワイの会社からくる猫に関しては詳しく調べてもらうことになっている。津軽さんにも簡単には話してあるから、いろいろ考えてくれていると思うよ」
「元刑事だけあって、勘のいい人だね」
「うん、それだけじゃなくて、いい人だ」
「宙夜が吉都君と甲府に行ってるだろう、裏のジュエリー加工職人はすぐわかると思うよ、どの世界にも、仲間からすこしはずれているのがね、自分のやり方を曲げないから、組合にはいらないで、気に入った仕事しかしない、山梨県に山梨水晶宝石共同組合っていうのがあるけど、そういうのに入っていなくて、個人的にしか引き受けない。裏の世界じゃそういうのを一本釣りして、仕事をやらせるわけだよ、宝石ならば、そういうものが世に出たとき、加工師の名前はでないが、宝石にニックネームまでつけられて、高額なものになっちまうんだ、甲府には原石を加工する職人、宝石デザイナーから、指輪にするための貴金属の職人まで、いい人材がそろっているということだ」
「隠れた頑固者か、池波光子なんかは当然甲府に、カットを頼んだりするのだろうな」
「きっとね、もし裏の何かをやっているのなら、表でも、それなりにジュエリー加工職人と知り合いになっているだろうし、そうしとくと、高度な技術を持っている人間を見つけだすことができて、こっそり頼めるるわけだ」
「宝石の原石を安く密輸入して、一流の加工をほどこして、それでも、市価の半値ならば、ほしがる客はたくさんいる。ぼろ儲けなんだろうな」
「高級な宝石を作らせてね」
「俺は猫を使った密輸入じゃないかと思うんだ、猫の業者は表の顔で、うまく密輸入をしているのじゃないか、タイとハワイをつなげて、組織とルートを作り上げたと思うんだが」
「そうだな、詐貸の推理どおりになるかどうかわからんが、もしそうなったら、すごいな、また野霧さんに本を書いてもらわなきゃ」
「そうだね、野霧の本もあと一月ほどででると思うよ」
「おまえが、神無月で後書きを頼んだ推理小説作家、俺も読んだことがあるほど有名な人だから、その人の後書きがあるとすると売れる」
「自費出版だからどうかわかんない、野霧君は文が書けるから、面白いとおもうよ」
「もう読んだの」
「少しはね、文章が上手だ」
「本がでたら大いに飲もうぜ」
「あの八人のヒミコが大騒ぎしてくれるだろうね、そうなったら、五百部じゃ足りないね」
「おいおい、ベストセラーになるぞ、十万部だ」
薩摩の言うことは大きい。結局、その日、薩摩と詐貸は高田馬場の店でしこたま飲んでしまうことになった。
山梨の宝石職人
詐貸たちが国際宝石展に行くために大崎に集まった頃、吉都と宙夜は新宿から特急あずさに乗っていた。
「宙夜さんは、地学を学んだのですか」
「まあそうです、子供の頃から化石が好きだったので、地学のある大学にはいって、古生物学をやろうとおもったんです、それでアンモナイトを卒研に選んだのですけど、アンモナイトを調べていくうちに、鉱物の結晶形成も面白くなって、大学院は鉱物結晶の先生につきました。そこで宝石のことも学びました」
「アンモライトですか」
吉都もアンモナイトには興味があった。
「よくご存知ですね、そうなんです、宝石化石、きらきら光るアンモナイトがあって、それを見てから、結晶に興味をもったんです」
アンモライトとは、アンモナイトなど生命体の化石が赤緑色に輝いて宝石化したものである。宝石の一種として認められるようになった
「僕は生命科学の出身なんです、遺伝子をいじりました」
「演劇じゃなかったのですか」
「おはずかしいんですが、趣味で劇団にはいっていたんですけど、全く芽がでなくて、詐貸所長に拾われたんです」
「野霧さんもですか」
「野霧さんは、図書館に勤めていて、探偵事務所の助手募集を見てきた人です、僕と同じときにはいりました、それまでは、所長一人の探偵事務所でした」
「彼女は本を出すくらいですから、文学部でしょうね」
「たぶん、文学部です、東大のミステリークラブだといっていました」
「東大出に見えませんね」
どういうことだろう。宙夜が、
「頭が柔らかい、ああいう人が本当に頭のいい人って言うんですね、東大じゃ少ない」
とつけくわえた。吉都も宙夜のいうことになんとなく納得がいった。
「かわいらしい人ですしね」
吉都がさらに付け加えた。宙夜もうなずいている。
「今日はまず甲府署にいって、そっち関係の刑事さんと話をしてから、町の中をみませんか」
宙夜の提案に吉都はうなずいた。
「僕は、宙夜さんのじゃまにならないように、お手伝いしながら、池波光子について調べます」
新宿から甲府までは一時間半だ。
「吉都さんは甲府、初めてですか」
「ええ、諏訪だとか松本の方には行ったのですけど、山梨は素通りです」
「僕はずいぶん来ています、山梨大学には水晶の結晶研究センターもあるので、鉱物の結晶化のセミナーに通ったことがあるんです」
「それじゃ、よく知ってますね」
「大昔は、水晶がごろごろととれたようですけど、今は地元のものは少なくなってしまって、だいたい輸入ですね、塩山に水晶山という、水晶がでる山があって、今でも人気ですけど、個人の山で、荒らす人が多くなって、入ることは禁止ですけどね」
そんな話をしていると、甲府についてしまった。
駅の大きな出口からでると、広い広場になる。大きな建物が取り囲む。甲府は県庁所在地だからあたりまえの風景だ。
「駅の反対の方は、まっすぐに歩いていくと武田信玄を祀る武田神社があって、その奥の方に山梨大学があるんですよ」
宙夜は駅の前のバス停に吉都を連れていった。
「歩ける距離だけど、バスで行きましょう」
バスは県庁前、市役所を通り、二人は警察署前でおりた。ちょっと歩くと甲府警察入り口である。
中に入って、宙夜が名のると、薩摩警視から連絡をもらいました、と会議室に通され、刑事とは思えない、タレント風の男性がはいってきた。
「宝石関係の三井です、薩摩警視から話はききました、密輸入の件は、我々もいつも注意しています。ここは水晶ですら外国産のものになってしまっていますから、それ以外の宝石のほとんどは輸入品です、この町の宝石商はすべてまっとうな店です、ただ、どこにでも裏があって、われわれは変な商品の動きがないか、いつもとは違った人物が宝石の取引をしていないか、目を光らせています」
「警視庁支援センターの宙夜です、この人は手伝っていただいている探偵事務所の吉都さんです」
「よろしくお願いします」
「いろいろな国から人が来るのでしょうね」
「ええ、インド、タイ、カンボジャ、スリランカ、ロシア、南米北米、至る所から宝石のバイヤーたちがきます、それと、日本の観光客も宝石を買いにたくさんきます。そういった中でおかしな動きをする人物をチェックします。店も協力してくれています、やくざが入り込むとまずいですからね」
「近頃何かおかしなことがありましたでしょうか」
「入荷した宝石の中に偽物が混じっているということはいつもあることで、それぞれの宝石商で対処しています、報告は受けるようにしていますけど、いつもと同じ程ですね」
「そんなことがあるのですね」
「輸出者がだまされていることの方が多いんですよ、だからだまそうと思って送ってきたわけじゃないので、それは業者間で問題を解決します」
「宝石の組合にはいっていない、加工業者や職人というのは多いのですか」
「そうですね、リタイアーした人はかなりいますよ、だけど、人手が足りないところでアルバイトしていますね」
「全くはじめから組合にはいっていないというような人はいるのでしょうか、自宅で個人でやっているという人など」
「我々すべて把握はしているわけではありませんが、そういうことは組合の人のほうが詳しいでしょう、紹介しますよ、一緒に話をききましょうか」
「お願いできますか」
三井刑事はすでに手はずを整えていたとみえて、どこかに電話を入れると、「すぐ来るということです」と言った。
「どういう方ですか」
「宝石の組合の理事で、本人も宝石の研磨に長い間携わってきた人です、田辺さんといいます、われわれとも長いつきあいです」
田辺という七十ほどの組合の理事は十分もするとあらわれた。
「田辺です」
警察にはなれているとみえて、気楽に宙夜たちの前に腰掛けた。
宙夜が三井刑事に話したことを聞かせると、
「そりゃあいますよ、宝石研磨やカットでは、とても若い職人ではまねできないような凄腕をもっているのが、そういう男はほかに仕事を持っていたりして、気が向かないとやらなかったり、本当にやりたいものしかやらない奴です」
「そういう人にカットなどを頼むのはどのようなつてで行われるのですか」
「結局は、我々のような宝石関係者が紹介することになりますな」
「直接たのむことはないのですか」
「宝石職人の看板を掲げている人ならば、外の人もわかりますけど、そうじゃない場合には、山梨の宝石業界のことをよく知っているプロじゃないと難しいでしょう」
「プロというのはどういう人のことです」
「たとえば、宝石鑑定士で、甲府の宝石のことをよく知っているとか、そういう人が直接たのむこともあるでしょう、我々としては組合にはいっている人に頼んでほしいのですが、それは個人の自由ですから」
吉都が初めて口を開いた。
「宝石鑑定士はいろいろなところから来るのでしょうね」
「それはもちろんです、外国から来るバイヤーは皆そのような資格をもっていますよ」
「知り合いに池波光子さんという鑑定士がいますが、ごぞんじですか」
「ああ、池波さんね、よく組合の方にも見えますよ、あの方はGGとAFG両方ともおもちで、猫目石のコレクターでもありますね、しかもGGは日本ではなくアメリカでおとりになっているし、AFGはタイでとっている、両方持っているのも珍しいけど、日本ではなくて、本校で資格をとっているというのは少ないでしょうね」
「そうなんですか、甲府には何か買いに見えるのですか」
「キャッツアイの珍しいのが入ったときなどには見に来ますね、何度か買われていますよ、元値を知っているから、たたかれますけどね」
田辺さんは苦笑いをした。
「組織だった裏の宝石加工などは今までありませんでしたよね」
刑事の三井さんがいうと、田辺さんもうなずいて
「甲府の宝石関係は、あぶないところはありませんよ」
と自信を示した。
吉都は池波光子が甲府の宝石組合と関係があることを知ったのは第一歩だと感じた。あとは原石の加工を頼まれた人を探すことだ。
宙夜が「若い人で、組合にはいっていない、研磨やカットのうまい人というのはいるものでしょうか」とたずねた。
「うーん、若くても上手な職人はいますけどね、みんな組合にはいっている工房で働いている人ですね」
「そんな人で、老練な職人に負けないような人もいるのでしょうね」
「そういっちゃなんですが、いますよ、新しい感覚でやっているのが」
「そういう人に直接頼むことはできるんですか」
「やっぱり親方に頼むのが筋ですね、ふつうじゃしないけど、親方にだれだれにやってもらってくれということはいえるでしょうね、さっき話にでた宝石鑑定士の池波さんなんかは、キャッツアイの線条をきれいに磨き出す若手の職人に頼んだりしていますよ」
「原石をもってきてやってもらうのですか」
「そうですね、しょっちゅうじゃないけど」
この情報はすごい。
「そんな人に会ってみたいものですね」
吉都が言った。
「その工房の親方ならよく知っているから見学できますよ」
「ありがとうございます」
その親方には明日会うことにして、街中を歩いてみることにした。宝石店リストと地図は三井さんがくれた。
「僕もだいたいわかりますよ、新しい店は知らないけど、古い店はよくいきました」
そういうことで、町中の食堂でほうとうを食べ、宙夜の案内で宝石の店をまわることにした。
「山梨でとれた水晶と輸入の水晶をみわけることができますか」
吉都が聞いても、宙夜は首を横に振った。
「うーん、むずかしいな、加工していない自然のままの水晶だと、わかりやすいんだろうけど、僕にはわかりませんね、店の人を信用するしかないかもしれない、結晶の様子などを機械にかけて詳しい解析をすればわかるのでしょうね、でもいちいちやっていないでしょうしね、それより、粉にして固めた人工水晶と本物をまずみわけられないと」
「水晶を固めたものなんかあるのですね」
「水晶の器などありますよ、特に化学実験のビーカーなどを水晶で作ります、ものをすりつぶすすり鉢を瑪瑙で作ったりもします」
「そんな高いガラス器具は使ったことがないな」
「おみやげに水晶を買いますか」
宙夜によまれたようだ。
「ええ、両親にお守りのようなものを、それに探偵事務所の人たちにも」
「明日会う職人に聞くといいですよ」
「いや、そんなんじゃなくて、おみやげ品でいいんです、どこかで買わしてください」
「それじゃ、いい店を教えますよ」
それから、何軒かの店により、宙夜は店の主人に、宝石の輸入先や、経路など、警察手帳をみせて、密輸に関しての調査をしていることをあかして聞いた。吉都はその間、店の中の宝石を見て回り、宝石鑑定士の、池波光子のことをさりげなく聞いたりしたが、付き合いはないようだ。
宙夜が一軒の、水晶専門店の前で言った。古い建物である。
「ここは大丈夫ですよ」
店にはいると大きな水晶玉が飾ってある。非売品で、明治の頃、甲府でとれた水晶とあった。陳列棚なには、小さく磨いたお守りのようなものもあったが、岩にくっついた小さな六角形の水晶が生えている自然のものもあった。地元でとれたものは地元産とかいてある。店の三代目だという若主人が、
「すべて天然物です、地元と書かれていないのは輸入です」とはっきりと言ってくれた。
吉都はまよったが、磨いていない六角柱の自然の石を五本ほど買った。
宙夜が「さすがに、生物が好きな人ですね、自然の形のままがいいですよね」と納得している。
それからも何軒か宝石店をまわって、予約しておいたホテルにはいった。
「どこかで、一杯飲んで、食事しませんか」
宙夜のさそいで、こじんまリした食事処にいった。つまみに煮貝でビールを飲んだ。
「煮貝は今輸入が多いんですよ、ここもそうだけど、つまみにはいいでしょ、この店、昔からあるんです」
宙夜のなじみの店のようだ。
「本物の煮貝はまだ食べたことありません」
吉都は土産に煮貝もいいなと思いながら口に運んだ。
「宙夜さん、地学はどこの大学で学ばれたのです」
「東大なんです」
恥ずかしそうに答えた。だから、東大のことをあんな風に言っていたんだ、と吉都は理解した。吉都は、野霧はもちろんだが、宙夜だってすごい、と前々から思っていた。やっぱり赤門だ。
飲んだ後、そこで食事をすませるとホテルに戻った。
明くる日、警察で話をした、水晶宝石組合理事の田辺さんを訪ねた。
「幸い、宝石の加工や装飾品を作りたいという若い人は結構いましてね、都内にも宝石デザインの専門学校がたくさんあるでしょう、そいうところをでてから、甲府の宝石会社に就職する者もいますけど、なかなか大変な職業でもあるので、途中で別の道に行ってしまう人も多いですな。あと個人でやっている加工職人のところに、直接弟子にしてもらうという場合もあります。まあ、それにしても、独り立ちは大変です、ほどほどにおぼえると、独立したくなって、田舎で農業をやりながら宝石を磨くとでていくのもいます」
「そういった人の中にも腕のいい人はいるのでしょうね」
「いないとはいいませんが、なかなか日本や世界で認めてもらうのは大変なことですね」
「甲府にもそういった一人狼のような人はいますか」
「ええ、組合にはいっていなくて若い人に人気な職人などはいますよ、ただ、新しいものを作り出そうとしている人たちですね、たとえば、昔からのブリリアンカットを、誰もが認めるようなものにしたり、クラシカルな装飾を、イギリスやフランスの専門家をうならせるようなものに作ることができる人はそういう人の中には見あたりませんね」
「全国にたくさんの宝石鑑定士がいると思うのですが、そういう人がカットをたのんでくるというようなことはありますか」
「もちろんありますよ、目利きだから、そういう人が頼む加工職人やカット職人、デザイナーは相当の人たちですね」
「昨日お話しした、池波さんなんかもそういう人に石の研磨やカットを頼んだりするわけだ」
「あの方はキャッツアイだから、光の線条の専門家だね、特に水晶の数野さんのところにいってましたな」
それはいいことをきいた。その工房にいく必要があるだろう。
田辺さんからは輸入や輸出、それに国内での販売組織について話を聞き、街にでた。
「数野さんの工房に行きたいけど、どうでしょう」
吉都が宙夜にきいた。
「ええ、行きましょう、その前にいくつかの工房をみましょう」
最初に著名な大きな工房に行った。多くの人が働いている。その後、数野水晶研磨所にいった。数野さんは息子さんと弟子一人とともに、水晶専門の研磨をやっている。三代目だということで、水晶に対する目もたしかである。息子さんと弟子もカット技術は相当なもののようだ。
「水晶だけでやっているのは少なくなりまして、地元の水晶も採れなくなったし、息子たちはいずれは他の石の加工もしなければ食っていけないでしょうね」
数野さんは現状を嘆いた。だがなぜ水晶だけの工房に池波光子は頼みにくるのだろう。
「鑑定士の池波光子さんがたのみに来ると言うことを、田辺さんが言っていましたが、水晶のカットなんですか」
「池波さんをごぞんじでしたか、あの方は、キャッツアイのコレクターで、何度かきて、水晶に光の線条は出せないかといいにきましたな、もう私の世界じゃないので、弟子の篠田に池波さんの相手をさせました、透明な水晶では無理だから、色つきの濁った水晶でやってみたんですけどね」
篠田良夫という弟子は一心不乱に研磨機に向かって水晶をあてている。
「僕も一つ水晶をカットしてもらおうかな」
吉都がいきなり言った。
「どのくらいの大きさのですかね」
「いや、今思いついたので、きめていませんが、興味があるので」
「やっぱり光の線条がほしいのかね」
「いや線条はいりません、カットってどんなのがあるのか知らないのでわからないのですが」
数野さんは息子さんを呼んだ。
「ダイヤのような丸いラウンドカットはあまりやらないね、ペンダント用の滴のような形のカットで、ローズカットというのはやるね、クラシカルなローズカットというの俺は好きだけど」
吉都にはイメージがわかない。
息子さんがカットの見本をもってきた。大きめのカットのローズカットはたしかに水晶でもいいかもしれない。
「あのキャッツアイにするような楕円の形のものはなんというのです」
「これ、カボションカットね、キャッツアイはカボションカットで真ん中に光の線条をだしたものですよ、水晶でカボションを頼まれたことはないね」
息子さんが見本の図を指さした。
「さっぱりしていていいかもしれない」
「カボションカットのできそこないはいくつかあるよ」
息子さんは吉都を作業している篠田良夫のところにつれていった。宙夜は親方と話をしている。
「あのカボションの試作みせてくれよ」
篠田は手を止めて、ゴーグルとマスクをはずした。
「うん、どうするの」
彼は隅にある自分の机に吉都をつれていき、引き出しから箱に入った楕円形の水晶をとりだした。
「これは、水晶をためしにカボションカットにしたものですよ」
透明な水晶が二つほどあった。
「この色のついた濁ったものは、線条を出そうとしたけどうまくいかなかったもの」
いくつかの濁った紫や黄色のカボションカットの水晶がしまってあった。
「皆山梨でとれたものですか」
「透明な二つは、山梨で取れた水晶ですが、色つきは輸入されたものです、線条はでてないでしょう、むずかしい」
「たのんだのは池波光子さんですか」
「ええ」と彼は答えた。
「他の石をたのまれませんでしたか」
そう聞くと、篠田はちょっと困った顔をした。
「親方には言いません」
そういうと、うなずいた。
「なんどもあったのですか」
またうなずいた。それだけで吉都は十分だった。
「カボションカットの透明な水晶を作ってもらえますか、僕個人で払いますので、親方にもいいますから」
急に吉都が話をかえたら、篠田はちょっと安心したように、
「ええ、価格は親方と相談してください」
とうなずいた。
吉都は親方のところに戻ると、水晶を一つほしいことを言った。
宙夜がちょっと驚いていた。
「そりゃもちろん、篠田に作らせましょう、もし、今見てもらった、ためしに作った石の削り直しでよければ、安くしておきますよ」
「あ、それでいいです、カボションカットで」
「え、それじゃあの形でいいのですか、それじゃもう一度磨き直します、それで台はいりますか」
「えーと、さっぱりしたのを、指輪にしてください、大きさは9で」
「なにで作りましょうかな」
「うーんと、プラチナ」
「夕方またきます、そのとき値段を教えてください」
宙夜には聞こえていたとは思うが、なにも詮索しなかった。
そこをでてから吉都が宙夜に、
「あそこの篠田に池波が石の研磨とカットを依頼してます、親方を通してないものがあるようです」と言った。
「それは特ダネですね、これから、大都市の怪しい宝石商や、関係者を追いかけて、甲府との関係を調べてみる必要があります、日本の密輸の裏組織を解明するには、、地元の警察に外の方から情報をいれてあげる必要がありますね」
宙夜の言う通りである。
「僕は、もう一度、原石の輸入元を確認しながら、他の工房も見て回ります、吉都さんは数野工房をもっと調べたいのではありませんか、別行動しましょうか、昼も適当に食べましょう」
十一時半だ。吉都はすぐにでも数野工房に戻りたい気持ちだったので、申し出はありがたかった。
「それでいいですか」
「もちろんですよ、僕は警察によってから、夕方にホテルに戻ります」
「それじゃ、そのころ僕もホテルに帰ります」
吉都は数野水晶工房のある通りにもどり、工房の近くの喫茶店にはいった。事件の時にはこうやって、人の出入りを見張ったものだ。
喫茶店でサンドイッチを食べ、コーヒーを飲みながら、数野工房の入り口を見ていると、十二時半ごろに、息子と篠田が二人して出てきた。息子はすぐに篠田と別れて喫茶店の前を通って歩いていった。篠田は反対方向に歩いている。
吉都は喫茶店から出ると篠田を追った。篠田は郵便局に入っていく。のぞくとATMの前にならんでいる。吉都は行き過ぎて、電信柱のところでスマホを出し、見ている振りをした。
篠田はすぐにでてきた。吉都は追いつくと「篠田さんじゃないですか」と声をかけた。篠田は振り向いて「さっきの」と笑顔になった。
「時間がとれたので、水晶のリングのことでまたお宅にいくところでした、今昼休みですか」
「ええ」
「お昼は食べましたか」
「ええ、いつも親方たちと、おかみさんの作った昼を食べます」
「僕も食べてきたところです、どうですかコーヒーでも、お願いした水晶のことも話したいし」
「いいですよ」
吉都はいま出てきた喫茶店にまたはいった。また来たといわれないように、ウエイトレスと目をあわせないようにしながらコーヒーを二つ頼んだ。
「篠田さんは長いのですか」
「まだ八年です」
「カットがお上手だと親方が言ってましたが」
「いや、まだまだです」
「池波さんはよく頼みに来るのですか」
「よくではないのですけど、二年ほど前から何度か頼まれます、それも大きな立派な、簡単に削ってある石を送ってきます、磨きがいがあります」
「数野工房にですか」
「いや、親方の家は広くないので、僕は近くのアパートで一人暮らしです。食事は親方のところでします。それで池波さんはアパートに石を送ってきます。水晶でキャッツアイ効果を頼みに来たときはいらっしゃいましたが、その後は一度来ました、後はメイルや手紙での依頼です」
「いつ磨いたりカットするのです」
「八時過ぎが多いですね、練習に夜中までやっていることがあります、親方は自由に使っていいと言ってます」
「いずれ独立されるのですか」
「資金もありません、今、わずかですが、給金の一部を実家に送ったところです、母親と体の不自由な妹が九州にいます」
まじめそうな人だ。
「リングの細工もするのですか」
「ええ、他のところの人に教わったりして作っています」
「それじゃ、それもお願いしますね、シンプルなのがいいな」
「はい」
吉都は腕時計を見た。
「そろそろ昼休みはおわりですね、工房のほうに行きましょうか」
吉都は紙をとると立ち上がった。
「僕の分です」と彼が財布をだしたので、
「いえ僕が誘ったので気にしないでください」と払った。
「ごちそうさまでした」
「いえいえ」
工房で、数野の親方に頼んだ指輪の値段をきいた。
「水晶は良いもんだけど、傷もんを焼き直すのだから、五万にします、ただリングの方は材料によって違ってくるけど、プラチナは高いけどいいですか、しかもカボションカットだと石の台が透けて見えるから、台の表面を工夫しないと綺麗に見えないから技術がいるんですよ」
「はい、一番シンプルに、これも縁ですから、リングも篠田さんにおねがいしましょうか」
「もちろんいいですよ、リングの方が高くなりますね、十万ほどかな、トータルで十五万でどうです」
「ええ、それじゃこれで」
と吉都がカードを出すと、親方が困った顔をした。
「カードはやってないんですが」
「あ、そうですね、じゃちょっと郵便局のATMにいってきます」
吉都はお金をおろして戻ってきた。
「ああ、すみませんね、篠田がコーヒーまでごちそうになったようで」
まじめな男だ。
「いや、お昼を食べてどこかでコーヒーを飲もうと、ここに向かってきたら、ちょうど篠田さんが歩いていて、おつきあいしていただいただけです」
吉都は名前と送り先を書類に書いた。
「ところで、朝一緒にきたのは警視庁の人ですよね」
「ええ」
「吉都さんもそうですか」
「いえ、ぼくは彼の友達で、彼の仕事にくっついてきただけです、だから、僕だけこうして観光です」
「そうなんですな、指輪は彼女にですか」
「あ、いえ、まあ」
そんな吉都を見て、親方は笑顔になった。
「篠田にきれいに磨かせます」
その後、吉都はまた町中をぶらぶらするとホテルに戻った。
その夕、吉都は宙夜から、甲府に原石がおくられてきた会社のリストをみせてもらった。この中に裏の組織が関わっているかもしれないので、ハチ公に戻ったら精査するということだった。
野霧の本
吉都が甲府から戻った。
「これ甲府のおみやげ」
朝、吉都は野霧と詐貸に、天然水晶の原石と煮貝をわたした。
「ありがとう、ネットで報告読んだわよ、すごい収穫ね、池波光子が裏で宝石の原石を磨きに出していたわね」
「まあ、そうですけど、原石が密輸されたものかどうかはわかりません」
「私たちも収穫ありよ、高胎さんが池波光子に宝石の相談をすることになったわ」
野霧が国際宝石展での出来事を話して聞かせ、高胎が電話で光子に会う算段をつけたことを説明した。
「百五十万のキャッツアイですか」
自分が買った水晶のリングの十倍だ。
「うん、でも一般に売っているものの半額ぐらいよ」
「すごい世界ですね」
「それでいつ会うんですか」
「明日だと思ったわ」
「俺の方も薩摩からすごいことを聞いてきたよ、野霧君には話したけど、ハワイのキャットパラダイスの持ち主は池波光子らしいぞ、向こうの警察から、Mitsuko,Ikenamiと連絡があったんだってさ、トンチャン・ウオンはアメリカ国籍で、モンクト・チェンといって、偽造旅券でタイや日本にきていたようだ」
「お、すごい、かなりはっきりしてきましたね、池波光子はやり手なんですね、それじゃ警察も本気で動くでしょう」
「そうだな、薩摩もそういっていたよ」
「これから、高胎さんたちは、ハワイのキャッツパラダイスから日本に輸入された猫のチェック、それに動物商の猫菁石の動きの監視をやると思うけど、我々も手伝うことになると思うわ」
「今ハワイからの猫の輸入はどうなんでしょうね」
「ここのところキャットパラダイスからの猫はないみたい、いままでの輸入も調べたら、一昨年は、かなりの数の猫が輸入されたらしいわ、といっても年間五十匹ぐらいなのかな」
「それはやっぱり、猫菁石が関係していましたか」
「みんなそうだったようよ」
「かなり煮詰まってきましたね」
「煮貝はうまそうだな」
詐貸がへんなタイミングで言うものだから、二人で顔を見合わせて笑った。
吉都がPCを見た。
「宙夜さんからメイルがはいりました、池波光子とは関係ないことですが、甲府の宝石加工店に原石研磨を依頼していた都内の業者で、怪しいのが二、三あるそうです」
「それは、どういうこと」
「そういう業者が正式に輸入をしているのかどうか調べて、輸入先がわからないような業者が、どのような組織と関係している調べ、密輸入のルートの解明をするということです」
「いいアイデアね」
吉都は自分が言い出したことであることは言わなかった。
「もし、池波光子が密輸に関わっていたりしたら、所沢の義理のお母さんは嘆くでしょうね」
「そうですね、どこまで広がるでしょうね、長男は関わっているかどうかもこれからですね」
それから二日後、高胎蓉子からメイルが入った。
「池波光子と新宿の喫茶店で会って、百二十万のキャッツアイを購入しました。これから磨きをかけるので、二十日後にできあがるそうです、手付け金として十万渡しました。対応はとても親切でした。
原石はどこのですかと聞いたところ、スリランカだそうです。原石も見せてくれました。簡単に磨かれています。ということは私が買ったものはこれから輸入する原石ではないようです」
「とすると、ハワイからこれから輸入される猫を調べてもしかたないかもしれないわね」
「いや、それはわかりませんよ、いっぺんに原石をいれて、ストックするというやり方だってありますから」
吉都の推理はよく当たる。
吉都は高胎に情報のお礼と、これからも様子を教えてくれるようにメイルで頼んだ。
そのとき、電話が鳴り、詐貸がとった。
「え、そんなにたくさん、それでいつ」
「一月後か、いやありがとう、いつ着くかわかった教えてよ、そのときは動くから」
詐貸が電話を切ると二人に言った。
「薩摩からだ、羽田の動物検疫所に古書さんが行った、ハワイのキャッツパラダイスから日本へ猫を輸送する申請がでているそうだ、申請は四十日前にださなければいけないんだって、だから、十日前すでにに申請はきていたようだ、書類は整っていたので、許可を送ったということだ、ということは一月後に、日本に到着ということになるんだって、ハワイでの検疫検査は十分クリアーしてる、日本に着いてからの、係留は数時間ですむだろうということだ、貨物で来るようだから、その便が明らかになったら考えよう、あ、そうだ、輸入業者は描菁石だそうだ」
「いよいよですか、僕がバイクで羽田に行って、描菁石の車がきたら、どこに行くか後を付けます」
「うん、薩摩の話では、当日、輸入業者は羽田の貨物合同庁舎にくるだろうから、古書さんもそちらに行って待機しているそうだ。というのも、輸入代行を大手の運輸会社や小さい会社でもやっているから、描菁石の車が来るとはかぎらないかもしれないようだ」
「そうですか、古書さんと連絡をとりあいます」
「猫はどんな種類です」
「薩摩が情報をメイルで送るといっていた、それに書いてあると思うよ」
薩摩のメイルはすぐはいった。
[ペルシャが五匹、ロシアンブルー三匹、シャム三匹、ラグドール三匹、チンチラが一匹、すべて避妊手術済]
「やっぱり上等の雌猫ばかりね、美容室のキャッツアイに電話してみようかな」
野霧がスマホで電話を入れた。
「もしもし、猫のことでお聞きしたいのですが」
「はい、なんでしょうか」
でたのは店長のようだ。
「知り合いから聞いたら、そちらで血統証付きの猫を安く売っていると聞いたものですから、今どんな猫がいるのでしょうか」
「うちは、頼まれてから輸入しますので、かなり時間がかかります、それに、訳ありの猫ですので、直接来ていただかないと、わからないかもしれません」
「ペルシャを考えていたのですが」
「ペルシャですと、避妊手術をしたばかりのが、今頼まれれば、比較的早く入ってくると思います、それでも一月半後になります」
「そうですか、それではそのうちうかがいます」
「どうぞいらしてください」
野霧は電話をきった。
「一月半後に猫がはいるといっているわ」
「一月後じゃないんだ」
吉都が不思議そうな顔をした。
詐貸がぼそっと言った。
「この事件、ずいぶん広がってきたけど、どこかで間違うと、違う方向に行ってしまう気がする。整理しながらいこう」
「どういうことです」
「いや、出てきた結果に疑問をもちながらやっていったほうがいいからな、今、首謀者を宝石の鑑定士であり、猫のトリマー経営者である池波光子を、宝石密輸の重要参考人にしている。それに、所沢で出てきた猫の骨とも関係していると考えている。だが、まだあのトンチャン・ウオンと池波光子の関係はわからない、トンチャン・ウオンが義理の母親のところに下宿していたという事実しかない、所沢の池波夫人はトンチャン・ウオンをバチェラ・リーの息子だと言っていただろ、光子から頼まれたとは言わなかった、ちょっと気になるな」
「そうですね、でも、ハワイのキャッツパラダイス経営は、Mitsuko,Ikenamiですから」
「うん、そこのところもう一度考え直しておいた方がいいな」
そこに電話がかかってきた。吉都が電話をとって、
「愛知県半田市の一粒書房からです」と電話の保留ボタンを押した。野霧が自分の机上の受話器をあげボタンを押した。
「はい、ちょっとまってくださいね」
野霧が受話器を押さえて詐貸に言った。
「本ができたそうです、支払いが探偵事務所になっているので、ここに本を送るのか聞いています」
「そりゃ、かまわないよ、段ボールで十箱ぐらいかなちょっと聞いてよ」
「結構ありますよ、二十五箱だそうです」
「どこかにおけるよね、送ってもらって」
野霧はそう返事をかえした。
「黒猫で明後日の午前中に着くようにたのみました」
「一箱に二十冊だろ、八人のヒミコには一箱づつ送ろう、残りは十二箱だから、部屋の窓のわきに積んでおいたらいい、野霧君は好きなだけ持って行きなよ、友達や知り合いにあげたらいいよ」
「ありがとうございます」
「ハチ公の連中にはできたって言えば取りに来るだろ」
「キックがきますよ」
吉都が答えた。
「みんな飲みに来るかもしれないな、そうだったら、また神無月だな」
「楽しみだな、野霧さんのお姉さんの表紙でしょう」
「さっぱりした絵なのよ」
本が届いた日、事務所の壁際には、二十五の段ボール箱が四段重ねでならんだ。
野霧が一つを開けると、まん丸な顔になって、できましたと、手に持って高くあげた。
詐貸が受け取ると、ケースから出して「きれいな本だな」とページをめくる。
詐貸が、「あ、ごめん、先に開いちまった、野霧君、机に座って、ゆっくりとみたらいいよ」
そう言って何冊か箱から取り出すと、野霧の机の上に置いた。
「僕も一冊もらいますよ」
吉都が段ボール箱から一冊拾い上げた。
「ペンネームは野霧なんですね、のむなんだか、やぎり、か」
「のむよ」
野霧は机の前に腰掛けて、ゆっくりとページを開けた。
初めての自分の本である。小説を書くのは大変だった。でもでそれを手にした瞬間、また書きたいという気持ちがわいてきた。
「いい本だね、お姉さんにも早く送ってあげなよ」
「はい」
吉都が「八人のヒミコさんに送る手はずは俺がしておきます、野霧さんヒミコさんたちの住所教えてください」
「やってくれるかい、野霧君は自分の友達、知り合いに送る用意をしたらいいや、送る費用はここのでいいよ、猫探し探偵のパンフレットをいれといてよ」
野霧は「すみませーん」とうなずいた。
「そうだ、野霧君は早引けしなよ、何冊か家に持って帰って、お母さんに見せたらいいよ、今猫と宝石の事件は時間待ちだし、しばらく本で楽しもう」
高胎さんが池波光子に頼んだ宝石ができるまで二十日あるし、描菁石宛のハワイからの猫は一月先になる。それにハワイのトンチャン・ウオンは、ハワイ警察と警視庁で話を煮詰めているところで、まだ動きはわからない。
吉都が一冊箱から取り出すと、
「これ事務所の入り口のところに飾っていいですか」と野霧に聞いた。野霧が答える前に詐貸が「そうしようそうしよう、吉都、本の前に立て札を考えてよ」そういいながら、丸いすを一つ、ドアの外に持ち出して脇に置いた。
「ここがいいよ」
「はい、本を立てるもの買ってきましょう」
そういって、外に飛び出した。
「あいつどこに行くんだ、近くに文房具屋あったっけ」
そういえば、この近くでみたことがない。
「野霧君、本当に早引けしていいよ」
「いえ、いつも通りに帰ります。私ちょっとお菓子屋にいってきます」
「本を持ってけよ」
野霧は笑いながら、一冊取ると、やっぱり飛び出していった。
誰もいなくなった事務所で、詐貸は改めて、野霧の書いた「八人の卑弥呼」を手に取った。
後書きから読んだ。
「猫探しの名人、探偵、詐貸美漬のいる庚申塚探偵事務所にいたからこそ、この話を書くことができた」と、詐貸と吉都に謝辞が書かれていた。それと、一文をよせた著名な推理小説作家に感謝の言葉が述べられ、作家と出会えたのも探偵事務所にいたからこそだと書いてある。詐貸は野霧らしいなと思いながら、後書きを読み終えた。
著名な推理小説家である、五十嵐五十老の「八人の卑弥呼を読んで」は次のような内容だった。。
『構成がしっかりした、目配りのきいた、メリハリのある文章で、登場人物の気持ちが良くかかれている。時を経て、卑弥呼が八人になって、この世界に戻ってくる、不思議な歴史推理物語である。言葉遣いが柔らかくとげがない。著者の作中人物への温かみのある眼差しが感じられる、極上の探偵物語である。長く読み継がれるに違いないし、次の作品が待ち遠しい』
とある。さすがにプロの作家の言葉である。
野霧が大きな袋を下げて戻ってきた。
「買ってきました。素甘にウグイス餅、それにシュークリーム」
「あの店シュークリームもつくるようになったの」
「生クリームと、芋クリーム半々のシュークリームつくってみたそうです、本をあげたら、これは試しに作ったので、あげるって、五つもくれました」
「よかったな」
「今、お茶入れます」
「俺が入れるよ、ほら、自分の本をゆっくり見たら」
野霧は珍しくのたのたと自分の机に向かった。ふーとため息をつくと、紙袋からお菓子を取り出した。ちょっと興奮している。
おやおや野霧らしくなく、心どこにあるのかだな、そう思いながら、詐貸はお茶じゃなくて、コーヒーの袋を取った。粉をフィルターにいれて、湯の温度を見ながらそそぎ、匙でかき回しながらカップに落とした。部屋にコーヒーのいい匂いがただよってきた。時間をかけて野霧を落ち着かせなくちゃ。
野霧が振り向いた。ちょっと赤い顔をしている。
「先生、またコーヒーいれてくださったんですか」
「新作のシュークリームを食べようよ、新作の本を見ながら」
「可也くん遅いですね」
「どこまでいっちまったんだろう」
詐貸が来客用のテーブルにコーヒーを二つおいた。
「こっちで飲もう、シュークリーム持ってきてよ、吉都には帰ってきたらいれるよ」
野霧は皿を三つ持ってくるとシュークリームをのせて、テーブルにもってきた。
「お菓子屋のじいさんばあさん、野霧君の本を見て喜んだろう」
「はい、私作家になっちゃいました、サインしろって、おじいさんがペンを持ってきて、書こうと思ったら、二人の名字も知らなかったことがわかりました」
「なんというの」
「白星(しらぼし)源之心さんと、ひみさんだった、おばあさん、あら私の本みたい、と喜んでいました」
「灯台下暗しか、こんな近くに卑弥呼の匂いのする人がいたんだ」
「おばあさん、糸島の生まれですって、驚いた」
詐貸がシュークリームを食べて「うまいよ」と、コーヒーを飲んだ。
野霧は詐貸の入れたコーヒーを飲むのは二度目だ。古いのになんでこんなに美味しくなるのだろう。
吉都が「遅くなりましたー」と飛び込んできた。ずいぶん大きなものをもってきた。
「巣鴨の駅の先まで探しにいっちゃいました、古道具屋があって、そこで、この電話台を見つけて、お皿を立てるものもあったので、両方とも買っちゃいました」
昭和の中頃の引き出しと飾り棚のついた、しゃれた木の電話台だ。上に野霧の本を載せるつもりだろう。
「一万円でした、入り口のところにおくとかっこういいと思って」
「ずいぶんいいもの見つけたな、野霧君の本がはえるよ、野霧君がシュークリームもらってきたんだ、今吉都のコーヒーをいれるよ、まあ座って」
「あ、はい、コーヒーのいい匂い」
「吉都君ありがとう」
野霧があらたまって頭を下げた。本当は涙がでそうなのだ。
「野霧さん、演劇の仲間だったのに、本の好きなのがいるんですけど、一冊もらえませんか」
「いいわよ、探偵事務所の本よ、読みたい人がいたらあげてよ、何冊でも、いいでしょ、先生」
「野霧君がいいならいいよ」
詐貸が吉都にコーヒーをもってきた。
吉都はシュークリームにぱくつくと、コーヒーを飲んだ。
「おいしいコーヒーですね、買ってきたんですか」
「違うわよ、昔からここにある古いコーヒー、詐貸先生はコーヒーを入れるのがプロなの」
「いれ方でずいぶん違いますね、前に野霧さんがいれたのは、ほこり臭いような味がした、あ、すみません」
「いや、本当よ」
「このシュークリームもおいしい」
「あそこのおじいさんが作ったの、名前を初めて知ったのよ、白星源之心、おばあさんはひみさんだった」
吉都もまた卑弥呼かと驚いた。食べ終わると、事務所の入り口に電話台をおき、野霧の本をかざった。その後、八人のヒミコに本を送るため黒猫に集荷をたのんだ。
詐貸はいずれ、野霧にテディーじいさんの話も本にしてもらおうと思った。
巣鴨の飲み屋、神無月にハチ公の連中が来るということになった。そこで野霧の本を受け取るという。まあ飲みたいのだろう。
野霧はすでに、神無月に本を持って行き、主人にも五十嵐五十老にもわたしている。五十嵐五十老はずいぶん喜んでくれたということだった。
その日、野霧と吉都は本を十冊ほど抱えて神無月に行った。余った分は常連さんで、本の好きな人にあげてもらおうと思ったからだ。詐貸は薩摩と落ち合ってからくるという。
神無月にいくとまだ誰も来ていない。
「らっしゃい、野霧先生、本読んだよ、おもしろいねえ、八人の卑弥呼に会ってみたいね」
「やだ、先生なんて、ヒミコさんたちと、まとまっては会うのは難しいですよ、九州から千葉までいろいろなところにいるんです、だけど銀座のジュエリー店で八艸草展開きますから、何人かには会えますよ、ともかくみんな美人」
「俺はそんなとこいけねえなあ、今度姫子をつれてってやってよ」
「あら、マスター姫子さんに何か買うつもり」
「へへ、どうするかな」
主人がはずかしがっている。姫子さんも、
「すごい人たちがいるものね、お医者さんやって、趣味のことも一流、それが卑弥呼の遺伝子なのね、私はどこかで遺伝子がずれちゃった」と笑った。
野霧は姫子の言っていることがわからなくて、きょとんとしているが、吉都は
「姫子さんすごい発想ですね、遺伝子の一部「み」が、ふたつずれて、「め」になったということでしょう」
姫ちゃんはそれを聞いてこっくりとうなずいた。ちょっと遅れて野霧が、
「あ、そうか、まみむめも」と声を出したら、主人も「ああ、そういうことかい」と、包丁を動かし始めた。
キックと宙夜と高胎と古書が入ってきた。
「野霧さんおめでとう」
みんなが口をそろえた。
「みなさんありがとう、はいこれです」、野霧はそれぞれに本を配った。
古書が「逢手さん、もし余裕があったら、もう一冊いただけますか」と遠慮がちに言った。本好きの古書のことである、きれいにとっとこうとでもいうのだろうか。
「いいですよ、枕にでもしてください」
野霧が言うと「冗談んでしょう」と、古書は持ってきた袋の中に本を大事そうに入れた。
「サインがはいってないじゃない、神無月にてとか書いてほしいな、それに私にももう一冊くださいな、奈良の野実に送りたい」
キックが言った。野実は野霧が奈良に行ったときに一緒にオートバイで五條に行った、奈良県警のキックの友達である。
「もちろん、あげて、それから野実さんのお兄さんにも、サインはずかしいわあ」
「みんなにちょうだい」
そういわれて、野霧はもう一度本をかえしてもらって、サインをいれた。
「下手な字でやだなあ」
「野霧さんの字はのびのびしていて動き出しそうで好きだなあ」
とは宙夜の感想である。
「それじゃ、料理並べるぞー」主人の一声で、「ビール」とみんな叫んだ。
「また、大将たちこないな」
「どっかで、ひそひそ話だよ、きっと部下たちの不満をぶっつけあってんだ、先にやってよう」
姫ちゃんがビールとお通しをもってきた。今日のお通しは、なんだこれは、とみんながみつめた。四角い小さな白い器の底に、得体の知れないものがぐずっと、すっ立っている。
「動き出しそう、虫かしら」
「食ってみなよ、うまいから」
大将がみんなの様子を見て言った。
「あたったら、今日の代金ちゃらにしてやる」
そう聞いたら、みんな一斉に箸をいれた。味噌の出汁が利いている。なまこよりは柔らかい感じだが、なんだろう。
「なまこ、ほや、クラゲ、みみず」それに「子宮」と叫んだ。
「あたんねえな、味はどうだった」
「おいしかったわ」
「そいつわな、味噌汁に入れることもあるんだ」
なんだろう。
「姫、教えてやんな」
「イソギンチャクよ」
「ありゃ、イソギンチャク食っちゃうんだ」
「九州の方では食べるところがあるのよ、私の実家では食べたわ」
「姫子さんどこなんです」
「九州の柳川よ」
ここにも卑弥呼に近い人がいる。
「ともかく、野霧さんの出版祝い」
キックがジョッキを持って立ち上がった。
「マスターたちもどうぞ」
吉都が声をかけた。
「おめでとう」の合唱で、またジョッキが空になった。
サイコロステーキが出てきた。
「おや肉とはめずらしいわね」
野霧が口に入れると「おいしい」とまるい顔になった。
「そりゃ、秋田皆瀬の牛でね、あまり知られてないが旨いんだ、今日は最後に稲庭うどんでしめるからな、キノコ料理もあるよ、魚は深海魚」
「深海魚って、ぬるっとしたのかしら」高胎が心配そうに言うと、吉都がああそうかという顔で、「キンメでしょう」と言った。
「キンメって深海魚なの」
「そうだよ、500メートルほど深いところにいるんだ。200すぎると深海だからね」
サイコロステーキがなくなるころになって、詐貸と薩摩が入ってきた。
「おう、おそくなった、おっさん頼むな」
「なにがおっさんだ、おまえのほうがずーっとおっさんじゃねえか」
いつもの掛け合いが終わると、
薩摩が「今日はまだ飲んでないんだ、ビールちょうだい」
と声をかけた。
ビールがくると、「ともかく、野霧先生おめでとう」とジョッキを半分からにした。
また先生か、と思いながら野霧は、「ありがとうございます」とお礼を言った。
野霧もジョッキをからにして、薩摩に本を渡した。
「こりゃ、イソギンチャクか」
お通しを口にした薩摩が言った。
「お、さすが薩摩だ、九州の人間は知ってらー」
主人が声を上げると、姫ちゃんが、
「警視は仙台ですよ、ホヤと間違えなかったのはすごいですね」
と言った。
「いや、ついこないだ、九州出身の警視庁の奴に連れて行かれたところで食った」と頭をかいた。
詐貸が「ちょっとまじめに、今までのことを二人で整理してたんだ」
「どこで」
野霧がつっこんだ。
「馬場」
飲まないわけはない。
「猫の骨事件、以外と大きなことに関わっているかもしれないよ」
詐貸がそう言った。
「じつはな、ハワイの警察から、日本の警察官をよこしてほしいということでな、密輸担当からも行くが、宙夜にもまたたのむよ」
「いつからですか」
「来週あたりから、いつまでになるかわからんが、あのモンクト・チェンてやつ、相当のやり手で、なかなかしっぽださないようだ」
「はーい」
宙夜はしばらくまた外国暮らしだ。
そのあと、みんなは「八人のひみこ」事件の思い出話になってしまった。庚申塚探偵事務所に依頼されて始まった事件で、ハチ公とも関係がでてきたのだが、刑事事件としては成立しなかった。今回の事件は、ハチ公から庚申塚探偵事務所が手伝いを依頼されたことから、どうやら、大きな刑事事件になりそうだ、というのが詐貸の思っていることである。
神無月の戸が開いた。
五十嵐五十老が顔を出した。
「あ、先生だ」野霧が気がつくと、五十老が「やー」と手を挙げた。
老推理小説作家は若い男性を連れていた。男性は五十嵐の前に行くと、カウンターの椅子を腰掛けやすいように整えた。
「姫ちゃんいつものね」
「はい、沢井さん久ぶりね」
沢井と呼ばれた若い男が五十嵐の隣に腰掛けた。
「沢井さんもお酒でいいのかしら」
姫ちゃんがきくと、沢井という男は「僕はいつものウイスキーください」と言った。
「あいよ、沢チャンのハイボールね」
主人が酒を暖め、角のハイボールをつくりはじめた。沢井と呼ばれた男はよく来ているようであるが、ハチ公と庚申塚事務所の面々とは初顔合わせだ。
酒が用意され一口飲んだ五十嵐五十老は、後ろを振り向いて、
「野霧さんの本、よかったよ」と野霧ではなく、詐貸の方を見て言った。
詐貸も気がついて、なぜ自分に言ったのだろうといぶかしげにお辞儀をした。
次に、五十嵐は野霧に向かって、
「この男、沢井一郎といってね、ワシのマネージャー」と言った。
そういわれた沢井は、椅子から降りると、直立不動の姿勢になって、
「いえ、マネージャーなんかじゃなくて、先生の書生をしております、今後ともよろしくお願いします」
皆に向かって頭を下げた。
みんな、なにが始まるのか、食べる手をとめて沢井を見た。
神無月の主人が、「このボケ老人は、沢井さんだけはここにつれてくるんだ」と言った。この超売れっ子の推理小説作家が沢井をいかに信用しているかということだ。
沢井がまた腰掛けると、五十嵐五十老は、
「野霧さんの本のことで話がありましてな、それと、第八研究室のみなさんにもお願いがありまして、かまわなければ、ここからみなさんにお話させていただいていいですかな」
カタツムリのようにゆっくりと話しはじめた。
みんなが静まりかえった。大きな声で聞いてくれてと叫ぶより、はるかに効果のある話し方だ。
「野霧さん、あの本は自費出版だけではもったいない、どうだろう、発行元は半田の一粒書房として、大手のミステリー出版社から発売をしたらいいんじゃないかと思うんだが」
五十嵐は野霧と詐貸を見た。
野霧はどう答えたらいいかわからないようだ。
詐貸が「そんなことできるのでしょうか」と訪ねた。
「お節介かもしれんが、わしが出版社に言いますよ」
これはすごいことだ。詐貸は、
「野霧君、君が良ければたのみなさいよ」と声をかけた。
「は、はい、もちろん嬉しいことです」
「そう、それはよかった、わしも嬉しいですよ、この沢井がすべて取りはからってくれます、そのうち探偵事務所の方にうかがわせます」
沢井は立ち上がって、またぺこりとお辞儀をした。
「沢井はもと、出版社の編集をやっていましてな、小説を書くのが好きで、わしのところに住み込むようになっちまったのだが、わしの方がいろいろ助けられていましてね、わしゃいいかげんな文章を書くもんだから、直してくれておるんですわ、校正はすごい腕ですぞ、それにな、内緒の話ですが、眞鍋星太郎といいまして、二冊ほど本をだしています」
野霧はその名前を聞くとまた驚いた。
「あの新進気鋭のSF作家」
「野霧さんはよく知ってますな」
五十嵐五十老は笑顔になった。
「それからですね、薩摩警視どの、第八研究室のことも、ちょっと調べさせていただきました、いや、面白い事件をたくさん扱っているようで、そんな部署が警視庁にあるとは思ってもいませんでしたな、それで、捜査中の事件のことを話してくれとはいいませんが、こんな事件があったなんてことは話してもらえるでしょうかな、探偵事務所の吉都さんと同じように、みなさん優秀な方がそろっていることもわかっています、たまに、我が家で飲みませんかな、いや、一人の頭の中から話をこしらえるのは容易ではないものです、いくら想像をめぐらしてと言っても個人の頭では限られる、いろいろなところから、質のいいヒントが重要なのですな、それがハチ公にはごろごろしている。野霧さんの本のような内容のことは、頭の中だけでは作り出せませんな、野霧さんは探偵事務所の事件を下敷きにこれからも本にするでしょうから、ハチ公のみなさんわしを助けてくれませんかな」
確かにそうだと、野霧も思った。いい探偵事務所にいるからこそ書けたのだ。この大先生でもやっぱりヒントは必要なのだ。
「どうですかな、警視どの、たまに我が家で酒宴などは、このじいさんも、たまに家に来て飲むんですわ、もちろん姫ちゃんも」
薩摩は「こりゃ、大変な仕事が増えましたな、警察は外に秘密を漏らさないように気を使っていますが、大それた作家の秘密を知ってしまうと、首になるかもしれませんな」
「サツマイモをおしつぶしゃ、スイートポテトだよ」
じいさんが変なしゃれをとばした。
「行きたい奴だけでいいなら、お話はうかがったことにします」
薩摩がそういうと、ハチ公たちは「いってみたーい」とみんな声を上げた。
「それは嬉しい、今日は野霧さんの本のお祝いをここでやると、この爺から聞き込んだので、沢井を連れて、おじゃましたしだいですわ、ありがたい、どうぞよろしく願います、じいさん、みなさんに美味しいものふるまってくれよ」
「もうふるまってるよ、じゃあ、きょうのはみなおまえさんにつけちまうからな」
「いいよ、そうしてくれ」
それをきいた、薩摩と詐貸が打ち合わせたように声を合わせた。
「酒は自分の金で飲むのがうまい」
五十嵐先生は、「おっと、その通り、失礼しましたな、どうでしょうな、このじいさんにすべてお任せで」
主人を指さした。
「おまかせ」
これまた、みんなの合唱がきこえた。
「あいよ、ともかく、逢手さんの本のお祝いだ、みんな忘れて、飲んじゃってくれ」
その日、神無月の主人は暖簾をはずしてしまい。貸し切りになった。
その後、五十嵐五十老の秘書、沢井一郎がやってきて、大手ミステリー出版社と話をつけたことを野霧に伝えた。出版社の編集者と会う手はずを決め、野霧はそれから忙しく出版社と話を煮詰めることになった。来年の発売ということで、装丁は野霧の姉の絵をつかい、新たな装いにするために装丁家に頼むことになった。印刷製本は一粒書房が行うことで合意された。野霧が作家として本格的にデビューする事になるわけである。
その週は忙しいことばかり続いた。八人のヒミコが東京に集まるので、探偵事務所のみなさんと食事がしたいと言ってきた。
東京ステーションホテルに泊まるので、中のレストランの一室をかりて、食事をしようということだった。八人のヒミコは医者としても忙しい。探偵事務所としては、時間のとれるときでよかった。
レストランに行くと、八艸会会場ですね、と案内された部屋には、真ん中に大きなテーブルがあり、コースのセットがされていた。
野霧先生出版祝賀会の札が立ててある。
「はずかしいわ」野霧は俯いて会場に入った。
八人のヒミコがすでにみなそろっている。
「すげえ、なんか怖いな」
吉都が身震いするほど、八人が集まると迫力がある。
「野霧さん、おめでとう」
野霧はみなに祝福されて、なんだか押しつけられたあんパンみたいにひしゃげた顔をしている。
「本の中でわたしたち、なんだか、輝きすぎていないかしら、あんなに神々しくないわよ」
翡海湖が野霧に言った。
吉都は、そんなことはない、もっと輝いて見えると思った。
フルコースの料理がふるまわれ、詐貸も吉都も小さくなっておとなしく食べた。野霧はいつものよう楽しく食べている。
「わたし、もしかまわなければ豆本にしたいのだけど、電子版で原稿かしていただけるかしら」
浜松の皮膚科の医師、匪実虚は豆本の収集家でもあり制作者でもある。
「いいですよ、たぶん大丈夫です」
「おや、たぶんなの、なにかあるのかしら」
「じつは、ミステリーの出版社からから本格的に発売するんです」
「わ、すごい、私たちもどんどん売っちゃうわね、自費出版したのを豆本にするなら、著者の許可があればいいのよ」
ひみこたちも大喜び。
「私たちの宣伝に使っちゃおう」と大変な盛り上がりだった。
詐貸と吉都は探偵しているより疲れたと音を上げて、野霧はぼーっとして、それぞれ家に帰った。
野霧の本の騒ぎは、それだけでは終わりではなかった。ノールウェーにいる愛子に本を送って、しばらくしてからだが探偵事務所に荷物が届いた。
何かとあけると、トロール人形と一緒に、袋に入った書類と、野霧宛の手紙があった。それには、とても面白かったという感想とともに、いつかノールウェー語に訳して出したいということがかかれていた。トロール人形はみんなでわけてくださいとあった。
「愛子さんからこんな手紙もらいました」
野霧が詐貸に見せると、「夢久家の事件の本は書いているのかな」とつぶやいた。
野霧が送られてきた箱の中から、三体のトロール人形を取り出すと、その下に、また大きな封筒がある。手紙とともに、タイプで打たれたものが束ねられていた。
「まだ何か書いたものがありますよ」
野霧がそれを取り出すと、こんなことが書いてあった。
「野霧さま、八人のヒミコをよんで、野霧さんが天性の文章家であることがよくわかりました。ここに同封したものは、夢久家の歴史と家系図をまとめたものです。私があの事件のことを本にするために調べました。詐貸君にも言われ、本にしようとはりきってはじめて三年になります。ところが、頭の中で構成がなかなかまとまりませんでした。そうこうしているうちに、これを書いて本にすると、当然私の素性を調べる人が出てきます。私も会社の経営陣の末尾に名があることから、北京原人の遺伝子をもつ人が、北京骨商にいると詮索を受けることになります。従業員の人たちや、水良の叔父の研究にも迷惑がかかります。私はこの話を本にするのはやめたいとだいぶ前から思っておりました」
だから、なかなか本にしなかったのか、と野霧は納得した。愛子さんはやることが早い。それなのになかなか本にならないと不思議に思っていたのだ。
「それで、野霧さんなら、あの事件の現場にいた人ですし、このようにすばらしい文章を書くことができるので、この話を小説にするのに適している方だと思いました。もし、野霧さんさえよければ、小説にしてみませんか、私がまとめた資料は差し上げます。
私はノールウェーの作家を日本に紹介する仕事が好きです。野霧さんがこれからも書く本をノールウェー語に訳してみたいとも思います。またいい日本の本があったら教えてください。訳してみたいと思います。ノールウェーの暮らしの方が私にはあっているみたいです。
詐貸君によろしくいってください」
野霧は複雑な気持ちになった。詐貸に彼女の手紙をみせた。
「愛子はよくわかっているみたいだね、僕もそう思うよ、野霧君がよければ、夢久家の事件だけじゃなくて、テディベアー事件も本になるよ」
それを聞いて、野霧はちょっとどきっとした。テディー爺さんの事件は、野霧にとってつらい事件だった。
「小栗老人の生き方をじっくり書いたらどうだろう、ミステリーじゃなくて、戦後の彼の生き様を」
詐貸が言ったことに、野霧の顔は四角になったままだ。頭の中で何か複雑な気持ちが渦巻いているんだろう。
「まあ、それはそれ、ゆっくり考えたら」
詐貸は一つ目のトロール人形のおじいさんを持って自分の机にいった。
そして、十一月をむかえることになった。野霧は一月の発売にむけ準備に追われていた。新たな装いの本になる。野霧は出版社にもよくでかける。
そんな中、久しぶりに、池波光子の情報がもたらされた。メイル連絡である。八公の高胎蓉子が池波光子と会って、できあがったキャッツアイの指輪を受け取ったということである。とても丁寧に説明してくれて、産地の証明書とカットの人のサインもあった。Y Shinodaだそうである。やっぱり、甲府の若い職人の彼に頼んだんだ。
さらに、ハチ公は警察にいつも協力してくれている有名な宝石鑑定家に、その石をみせたところ、よい出来で、全く問題なく。産地の証明書も本物であり、通常3ー400万で売っていて不思議がないということである。
ということは、池波光子がどこから安く原石を仕入れているかということになる。本人の宝石鑑定士としての事業「猫菁石」の納税はきちんとしているようで、原石を納めている輸入業者の書類があった。輸入業者はいくつもあって、本人がいいと思った原石を業者から買っていると判断できるという。池波光子の宝石の商売は書類上では全く健全なものであった。
振り出しに戻ったような感じだった。
「ハワイのキャッツパラダイスの経営の儲けは相当なものだと思うけど、お金は日本に動かしていないということなんですね」
吉都が言った。詐貸も首をひねった。
「うーん、そういうことなのか、少なくとも、キャッツパラダイスの経営に関しては、ハワイの税務署では全く問題にしていない、それは儲けがたいしたことはなく、もし貯蓄があったとしても、すくなくとも第三国の裏の銀行にあずけているということなのだろうかね」
パナマ、バージン諸島、モナコ、ルクセンブルクなどの、タックスヘブンである。そこでは貯金に課税がかからず、秘密が保持される。
「そうなるとわからないですね」
「宝石の密輸解明はハチ公たちが手段を考えるだろう、我々は池波光子の「キャッツアイ」をあらおうや」
「猫が届くのはあと十日ですね」
「久しぶりの大量の猫の輸入だけど、そんなに需要があったのかな」
「そうですね、ともかく大量の猫が必要となったわけですね」
「そのへんもあとでわかるだろ」
「ところで、高胎さんが買った百二十万の宝石はどうなるんですか、そっちは問題なかったので、無駄になりますね、警察が買ったことになりますね」
野霧の疑問に詐貸が答えた。
「おとり捜査に使うお金だから問題ないんだろ、宝石はしばらく保管され、買った値で売ると思うよ」
「競売しないのですか」
「そういうお金でもうけちゃいけないからね、きっと、鑑定してくれた宝石屋が買って、そのお金は何事もなかったように、警察にもどり、帳簿にものらないんじゃないかな、これは想像だけどね」
「そういうもんなんですね」
キャッツアイの正体
ハワイのキャットパラダイスから猫が羽田に届く。古書も貨物動物検査合同庁舎に出向く。猫の到着は夕方の飛行機だ。
その日、吉都は久しぶりに125ccのバイクにまたがった。巣鴨の探偵事務所に寄ると、野霧がガソリン代やいざというときに使うための現金を用意していてくれた。
「事故らんように行けよ」と詐貸に送りだされ、吉都はちょっと緊張して、首都高速に入った。高速にのると羽田は思ったより近かった。
身分証明書などをみせ、空港の敷地内にはいると、庁舎の動物輸入の窓口に行った。古書がすでに来ていて、特別な入構許可証をわたしてくれた。
「おはようございます、よろしくお願いします」
「こちらこそ」
「僕は駐車場に行っています、それらしい車がきたら、降りた人の後についてここにきます」
「いえ、ここで待っていれば大丈夫です、係りの人からハワイの荷物を取りに来た人がきたら教えてもらえることになっています」
しばらく待っていると、係りの人が、今窓口に来ている人だと伝えてきた。窓口で書類をだしているのは背の高い美人である。目白台の柳井さんや六本木の白井さんが言っていた猫を空港から連れてきた人だろう。キャッツアイ店長の鈴木さんにちがいない。
吉都と古書は受付から出ると、その女性を見守った。女性は書類の処理が終わると、駐車場に向かった。
駐車場に「猫美容室 キャッツアイ」と書かれたワゴン車があった。キャッツアイの店員が猫の輸入もやっているのだろう。女性は運転席に乗り込んだ。一人のようだ。
古書が、「西貨物ターミナルに向かうでしょう」と自分の車にのった。吉都もバイクにまたがった。
貨物ターミナルはすぐだった。駐車場にはいると女性は台車をおろし、押して建物の中に入っていった。十五匹の猫となると、二匹づついれたとしても七つか八つのケージはあるだろう。
古書が車から降りてきて吉都のところにきた。
「吉都さんこれ使ってみてくれますか」
「なんですか」
「盗聴器です、これが受信機、トランシーバーのようなものです、スイッチを入れておいてください自動録音されます」
吉都にも使い方はだいたいわかる。
「彼女の車の運転席のどこかに、盗聴器を吸い付かせておくと話が聞けます。これは違法です、我々はこれを使っても証拠にできません。逆に訴えられる。ただ、吉都さんが使ってくださるならかまわんでしょう、会話の中から情報を得ることはできる」
「わかりました、やってみます」
吉都は受け取るとキャッツアイの車の運転席に受信機をつけた。メーター類の下ならわからない。こういう行為をしたのは始めてである。ちょっとどきどきした。
古書は建物に入り、女性の向かった荷物の受け取りのところにいった。吉都はトランシーバーのイヤホーンを片耳につけ、スイッチを押すとバイクにまたがったままいつでもだせる態勢でいた。
しばらくすると、古書が出てきて、吉都に「今きます、彼女一人で全部やっています」と言った。
「僕がついて行きます、おそらく椎名町の猫の美容室に運ぶのだと思います」
「お願いします、何かあったら連絡ください、途中まで一緒に行って、僕は警視庁に戻ります。キャッツアイについてはもう少しあたってみます、何か分かったら連絡します」
「はい、僕の方も連絡します」
そこに女性が台車を押してきて、毛布のかぶされている猫のケージを車に積み始めた。
「それじゃ」
古書は車に乗った。二人はキャッツアイの車がでるのを待った。
女性は手際よく、ケージをしまい終えると車をだした。そのあとを吉都のバイクと、古書の車がついた。キャッツアイの車は動物を乗せているためだろう、あまりスピードを出さず、吉都にとってはゆっくり過ぎる感じがあった。首都高にはいり、途中で古書の車が隣の路線に入り追い越していった。
首都高から降りて、キャッツアイの車はますますゆっくりと走っていった。もう夕暮れで、あたりは薄暗くなっていた。運転中、トランシーバーには車の音しか伝わってこなかった。
車は椎名町の猫の美容室の前に着いた。吉都はバイクをちょっと離れたところに止めた。
いきなり、上着のうちポケットに入れておいたレシーバーの着信ボタンが赤く点滅し耳に女性の声が響いた。
「今ついたわよ、猫を置いたら一度もどるから」
キャッツアイのビルには明かりがついていない。誰もいないようだ。その会話のあと、女性が車から降りた。入り口の鍵を開け、明かりをつけると、部屋の中にケージを運びいれている。吉都はバイクから降りて、美容室の入り口のところまで行った。
4階の窓に明かりがつき、機械の音がした。リフトのようだ。
十分もすると4階の明かりは消えた。吉都はあわててバイクのところに戻った。
女性は店から出ると、再び車に乗った。トランシーバーが赤く光って録音状態になった。
「猫は無事いれたわ、これから帰る、夕食は外にでようよ、そのあとにしよう」
家の誰かに電話をしているようだ。電話が切られると、すぐにエンジンをかける音が聞こえた。
吉都は車の後をついた。車は五分も行かないところにある家の脇の駐車場にはいった。吉都は手前でバイクをとめ、女性が車から降りるのをまった。
女性が家に入り、吉都は家の前にいってみた。
「鈴木動物病院」とある。診療時間と、定休日、木曜日、祝祭日と書かれた看板が吊るされている。猫を運んできたのはやはり鈴木さんで動物病院の人なのだ。吉都は病院の写真をとり、しばらく物陰に隠れて監視していた。
運転していた女性が中背の男性と家から出てくると、繁華街の方に向かって歩いていく。食事に行くのであろう。
吉都はついていくことにした。二人は通りをしばらく歩くと、なれた様子で、洋食屋には入った。吉都も少し遅れて中に入った。二人は席について、メニューを見ているところだ。テーブルを真ん中に二人掛けのソファーが向かいあっている。大胆にも吉都は二人の隣のテーブルに、二人に背を向けて腰掛けた。
女性はオムレツを、男の方はステーキ定食を頼んだ。
通りかかった店員に吉都はハンバーグ定食を頼んだ。その後はスマホを見る振りをして、隣の会話に耳を集中させた。
女性が男に「猫はみな元気だったけど、いつやる」ときいている。
「定休日だね」
「だけどね、木曜日に社長がくることがあるのよ」
「一日中いるわけではないだろう」
「うん、だいたい午前中ね」
「定休日の午後にやろうか」
「そうしようか」
次の木曜日は三日後である。猫に何かするのだろうか。なにもされないうちにあの猫を調べることができないだろうか。社長って池波光子という宝石鑑定士のことだろう。彼女に知られないようなことを二人はやっている。どうしてだろう。
吉都は急いで食事をすませると、二人を残して店を出て、巣鴨の探偵事務所に戻った。詐貸所長と野霧産はすでに帰っている。
吉都はPCを開いて、古書に、猫が「キャッツアイ」の四階に納められたことと、鈴木という店長は、近くの鈴木動物病院の奥さんであること、それに定休日の木曜日に、何かたくらんでいることを書いておくった。
すると、すぐに電話がかかってきた。
「吉都さんご苦労さまです、なにかありそうですね、木曜日に見張る必要がありますね」
「ええ、だけど、中に入れないと、なにをしているのかわかりません、何とかその前に、猫を調べることができないでしょうか。傷つけられる前の猫を調べると、何かの証拠にもなります」
「そうですね」
「検疫所のほうから、再検査の必要があると言って、猫をつれだす方法がないではないのですが、猫を密輸入したわけではないし、よほど明確な理由がないと、警察としては動けませんね」
「ハワイの方の書類の不備とかいえませんか」
「むずかしいな、あした、薩摩さんに相談してみます、でも吉都さんのおかげで、なにかつかめそうですね」
「いいえ、盗聴器は役に立ちました、まだついたままですので、利用できそうです」
電話を切って一息つくと、吉都は家路についた。
次の日、探偵事務所で、吉都が羽田の出来事を報告していると、薩摩から詐貸に電話があった。
詐貸が吉都と野霧に薩摩からネット連絡があるので見るように言った。
詐貸が電話を受けている間に、二人は薩摩からのメイルを読んだ。
内容はハワイに行っている宙夜からの連絡だった。ハワイの警察が、本名モンクット・チェンを、偽造旅券使用の罪で調べていたのだが、その目的が明らかになった。宝石の密輸にかかわっている。猫にガラスの飾りのように装った本物の宝石をつけた首輪をつけ輸出したり、送る猫と一緒に入れた餌の中に宝石を混ぜたりしたことをやっていた。やり方を次々に変え、この数年は猫の体の中に隠して輸出していたようで、猫のブリーダーでもあるキャットパラダイスを調べることになったということだ。ハワイの警察から日本の密輸宝石の受け皿を日本警察の方で調べるよう要請されたとあった。
「やっぱり、どうしても池波光子とキャッツアイが関係していますね」
薩摩と電話をしていた詐貸が、受話器口を手でおさえた、
「昨日、吉都が古書さんに提案したことをやるので、吉都と古書さんとメイルで相談してくれと、薩摩が言っている」
そう言うと、詐貸はまた薩摩と話はじめた。
吉都は古書に「昨日の件どうでしょうか」とメイルを送った。古書からは次のようなメイルがきた。
「薩摩室長が、ハワイの状態を報告したと思います。室長からも日本の受け皿を洗うという目的で、吉都さんの提案のように、検疫所から、猫を一度検疫所に戻す手続きをとるということです。一緒に貨物として運ばれた猫に、猫白血病が確認され、検疫所の責任において、キャッツアイの十五匹も調べるというものです、そのあと、吉都さんとして、提案がありますか」
とあった。
吉都は「動物検疫の施設にレントゲンがあったら、レントゲンにかけてみてください」と、うちかえした。猫の胃の中に石が入っているかどうかチェックするのがいいと思ったわけである。
「我々もその可能性を考えています、検疫所に運んだあと、あらゆるチェックをします。レントゲンのある動物病院か大学に委託します、猫を受け取りに行くとき、僕も同乗しますが、吉都さんも行きますか」
「いきます、キャッツアイへの連絡は、トリマーの鈴木さんじゃなくて、社長の池波光子に直接連絡した方がよいのではないですか」
池波光子を引っ張り出した方が、明らかになるだろうと思ったからだ。
「そうします、検疫所の所長から池波光子に連絡をしてもらいます、猫を取りに行く車に警視庁によってもらって、僕も乗ります、おそらく今日中に受け取りに行けると思います」
「キャッツアイにいく時間がわかれば、僕もそちらに行っています」
「おねがいします、後で電話をかけます」
吉都は詐貸と野霧に古書の計画をはなし、自分もキャッツアイに行くことを報告した。
「たのむな、薩摩も宝石の密輸が絡んできたので、動けるといっていた、吉都には感謝していたぞ」
野霧が「もし、池波光子がそんなことをやっていたら、所沢の義理のお母さんどんな顔をするかしら、かわいそうね」
とつぶやいた。吉都も所沢のにこにこした池波婦人の顔を思い出していた。
詐貸がふっと思いついたように、
「池波光子の旦那は貿易会社に勤めているという話だったよな、旦那もあやしいな」と言った。
「そうですね、池波光子だけでこのような組織作れませんね」
野霧がうなずいた。
「僕もそう思います、まず、トリマーの鈴木さんと、旦那の獣医がどのように関わっているのか、木曜日に猫になにをしようとしていたのか調べましょう、みんなグルなのかもしれないけど、腑に落ちないのは、社長のいない間に何かをする予定みたいでしたね」
「そうだね、なんだろうね」
吉都の言ったことに、詐貸も引っかかっているようだ。
「長男までかかわっていたら、どうなるのかしら」
野霧は所沢の池波夫人が気になるようである。
午後になって、吉都のスマホがなった。
「はい、四時ですね、それじゃ、そのころ行っています。キャッツアイの4階から、猫を運ぶのを手伝います」
吉都が詐貸たちに言った。
「古書さんからです、すでに電話をいれてあって、四時頃、椎名町のキャッツアイに猫をとりにいくそうです、僕も行きます、池波光子はずいぶん驚いて、猫の美容院を臨時休業にして、本人もすぐに行くということです、いま預かっている猫はいないので、ちょうどよかったということでした」
「ハワイの警察からも、詳しい状況が送られてくることになっているらしい、キャッツアイが何かやっていることは間違いないだろう、もしその辺が明らかになると、宝石密輸の日本の組織が明らかになり、ハチ公のお手柄になるとさ」
「僕はキャッツアイに行ってます」
「うん、たのむ」
吉都が机の上にのせておいたトランシーバーが赤く点滅した。車の中で誰かが話をしているのだ。
トランシーバーのスピーカーをオンにすると、キャッツアイ店長の鈴木の声がながれてきた。
「あなた、いま車の中から電話してるの、誰かに聞かれるとまずいから、たいへんよ、あの猫、検疫所にもどされる、一緒に運ばれた猫に猫白血病がでたんだって、ばれないかしら、え、検査はキットで簡単にできるわけなのね、それにワクチンをうつだけなの、陰性ならすぐにもどしてもらえるわね、一日二日でね、そうか、よかった、四時頃くるみたい」
そのあと、車の戸が閉まる音がした。
「いよいよあやしいわね」
野霧がそれを聞いて言った。
「それじゃ、いってきます」
「はいこれ、四時までまだ時間があるからお腹すくわよ」
野霧が素甘を包んで吉都にわたした。
吉都は二時半にキャッツアイについた。店の前を通ると、臨時休業の張り紙が目に入った。駐車場には吉都が盗聴器をつけた車がとまっている。彼はそうっと近づくと、扉をあけ、盗聴器をはずした。もう必要ないだろう。
吉都は離れたところから、店への出入りを監視していた。駅の方から、せかせかと歩いてきた恰幅のいい女性がキャッツアイの中に入っていった。顔を見ることはできなかったが、池波光子のようだ。その後、人の動きは全く見られない。
電信柱の陰でもらった巣甘を食べていると、携帯電話がなった。古書からだ。警視庁をすでにでたので、三時半頃にはつくということである。吉都はキャッツアイに駐車場があることを伝え、その付近にいることを言った。三十分ほどでくることになる。
そのころになると、白いワゴン車がゆっくりとやってきた。車が駐車場にはいった。車に動物検疫所とある。
吉都は急いで駐車場にはいった。
「おまちどうさま」古書が車からでてきた。運転手もでてきて、「検疫所の者です、よろしくおねがいします」と吉都に挨拶した。吉都のことを古書からきいていたのであろう。
運転手は書類カバンを抱えると、「それではいきます」とキャッツアイの戸を開けて中に入った。
「失礼します、羽田の動物検疫所より参りました。このたびは大変ご迷惑をおかけしますが、連絡しましたように、万が一こちらの猫に病気がうつっているといけませんので、私どもで調べます。申し訳ありません、引き取らせていただきます。なんでもないようでしたら、すぐにお返しします」
丸顔のちょっと野霧に似た女性が奥から出てきた。
「池波です、どうもごくろうさまです、四階のデイサービスの場所においてあります。他に猫はいません」
運転手は書類を見せた。猫を引き渡したときの書類のコピーである。それに名刺をだした。
池波光子も名刺を出した。
「これが預かり証になります」
古書が別の書類をだした。
「ご案内します、こちらが店長の鈴木美和です」
池波が奥から出てきた白衣姿の背の高い女性を紹介した。
鈴木が「こちらです」とエレベーターを指差した。確かに羽田に猫を取りに来た女性だ。
古書がバックからビニールでできた割烹着のようなものと、手袋をだして、吉都にもわたしてくれた。防疫服のようだ。
鈴木について四階にあがった。広い場所に猫のケージがおいてある。壁際には二段の棚があり、空のケージが並んでいる。デイサービス用のものだろう。
檻の中で猫たちはのんびりと横になっている。元気そうだ。きちんと管理されている。
「どのくらいで戻していただけるのでしょうか」
「陰性なら、二日ほど後に戻します、おそらく大丈夫だとは思いますが、この病気は致死率が高いので、注意が必要です。人にはうつりませんから」
「はい、それは存じています」
「それでは運びます」
吉都が言うと、店長の鈴木が「猫用のリフトがあります」と言った。しかし、古書が「いえ、病気のこともありますので、我々手持ちでエレベーターに乗せます。リフトやこの部屋の消毒はお願いします、場合によっては補償費用がでます」とケージを持ち上げてエレベータにのった。
吉都たちも一つづつ抱えると下に降りた。数回繰り返し、車に乗せ終わると、吉都も車に乗り込んだ。
池波光子がきて「この猫ちゃんたちはどれも血統証つきですが、訳ありで処分されたかもしれなかった子たちです、かわいがってくれる人に安く譲っています。どうぞよろしくお願いします」と頭を下げた。
吉都にはなんだか犯罪などとはほど遠い人のような気がした。本当に猫から何かが見つかるのだろうか。自信がなくなる。
「それじゃ、お預かりします」
古書がそういって、運転手が車を出した。
「思っていたような人じゃありませんね」
古書が吉都に言った。同じように感じたようだ。
「これから、吉都さんが言ったように、獣医大学に行って内科の教授に猫を見てもらいます」
「どこにいくのです」
「武蔵境です」
サーマート・リーが留学したと言っていた獣医大学だ。高校の同級生でこの大学出身の佐々木に、リーのことで吉都もつれてきてもらったところだ。池袋からだとそんなに時間がかからない。古書が五時前にはつくことを獣医大の教授に電話を入れた。
キャンパスにはいり駐車場にとめると、内科のスタッフが、台車をもって猫を取りに来た。古書と吉都は助手の人に案内され、教授の待つ研究室にいった。
「よろしくお願いします」
「お話はきいています、猫白血病の検査をしたあと、レントゲンにかけます、異物があるかどうか、調らべればいいわけですね」
「はい、お願いします、費用は後で請求してください」
「いや、いりませんよ、学生の勉強にもなる、レントゲンを撮る間、どこかでお待ちになりますか」
「証拠になりますので、できたら我々も見ていたいのですが、レントゲン室に入れますか」
「ええ、問題ありません、個体識別のために、カルテを作ります、種類や年齢、それに体の傷のチェック、血液もとっておきましょう、結果は後になりますが報告します、白血病のチェックもそのときしておきましょう」
「私どもすべての猫、立ち会わせてください」
「いいですよ、レントゲンは猫を何人かで保定して撮りますが、猫が暴れなければ大して時間はかかりません、あの猫たちはよくなれているので問題ないでしょう」
古書と吉都はレントゲン室にはいった。何人かががスタンバイしている。
最初のペルシャ猫が血液を採られ、抱き抱えられてきた。
「おとなしいですよ」つれてきたスタッフが言った。スタッフが言ったとおりで、レントゲンの機械の下で、おとなしく二人に手足をもたれ、横にされて静かになった。
「ありゃ」
教授がレントゲンの画像を見て声を上げた。すぐPCに画像が映し出される。
「お腹のところ、これは腹腔の中ですね、ほら丸っぽいものがはいっている」
猫の腹に黒いものが映っている。
「大きさはどの程度でしょう」
「長さ三センチ厚みは二センチほどでしょうかな、カプセル状のものですな」
「なんでしょう」
「レントゲンを通さないもの、石などです」
吉都と古書は顔を見合わせた。
「人工的なものですか」
「からだでつくられたものではありません、挿入されたものです、身体のチェックでも手術の跡があります、避妊手術の跡に似ていましたが、避妊と同時に中に入れたとも考えられます」
「取り出すのは大変ですか」
「避妊手術と同じですね、大したことはない、麻酔をかけ行います」
「すべての猫のチェックが終わったら、上司と相談して、その件もお願いするかもしれませんがどうでしょうか」
「これからといわれると無理ですが、時間さえいただければ可能だと思います」
こうして、かなり時間がかかったが、十五匹の猫は、すべての体の中に楕円形の石がはいっていた」
「猫も、レントゲンの画像も大事な証拠品になりますから、警察の方で保管しなければなりません」
「ええ、USBなりに入れましょう、取り出すときにもご協力します。その程度のことなら、学生でもできる手術です。連絡をお待ちします」
教授は協力的だった。
その後、レントゲンの終わった猫は、動物検疫所の車で警視庁に運ばれ、結局、捜査支援分析センターの第八研究室、ハチ公に運び込まれた。まだ部屋にはみんなが残っていた。
「わー、猫ちゃんがきた、やっぱり生きているほうがかわいい」
キックが叫んだ。
薩摩もでてきて、「だっこはだめだよ、証拠品だからな」と言って、ケージに手を突っ込むと、ラグドールの頭をなでた。
そうか、抱っこはだめだが、頭をなでるのはいいんだ。みんなはしゃがんで、檻の中に手を突っ込んだ。面白い光景だ。
十八体の猫の骨の置いてある部屋の床には、生きた猫の檻がならんで、その周りに人間がしゃがんでいる。吉都はなんだか噴出しそうになった。
古書の報告に、薩摩が、
「猫のためにも早く腹からだしてやろう、なにが出てくるか」
「猫女石でしょう」
吉都が言った。
「猫ちゃん飼いたいな」
キックが吉都に言った。吉都はキックに「何匹」ときいた。
「吉都さんも猫好きなんだね」
薩摩がにこにこ顔になった。キックは「まず二匹」と答えた。
「この猫ちゃんたちどうなるのかな」
「まず、キャッツアイの連中に話を聞いて、それからすべて取り出すことになるだろうね」
「いや、そのあとは」
「うーんどうなるのだろう、最後は競売になるんじゃねえか、まずは証拠品だから、お客さん待遇で、しばらくどこかに預かってもらうことになるな」
「我々も買えるのかな」
「うーん、関係者は遠慮しなきゃなんねえ、競売で買った人からなら買えるかな、競売で買い手やもらいてがなければ、どこかに管理を委託のような形になるのかな、俺もわからんよ、生き物は」
薩摩がまた猫の頭をなでて、自分の席に戻った。
「池波光子にいつ連絡するのですか」
「とりあえず、もう猫白血病は陰性だったことは、係りの方から伝えてもらったよ、返却などに関して明日連絡することになっている」
「すぐ返しちゃうのですか」
「いや、君たちに行ってもらって、レントゲンの結果をはなし、そのことを知っているか聞くことにする、知らないと言うかもしれないが、そうしたら、腹のものを取り出す手術をしてから戻すということになるだろう、そこで、向こうも観念して、ゲロすれば、逮捕と同時に、猫はまたあの大学で手術をしてもらうことになる」
古書が「それじゃ、明日、僕がいきましょうか」
「うん、それにキックもいってくれるかな、吉都さんもできたらお願いできるかな」
「詐貸所長に話しておきます」
「それじゃ、明日、吉都さん十時にキャッツアイに行ってくれますか、我々も行きますので」
「はい、そうします」
「きょうはご苦労さまでした」
もう十時になる。
「私食事して帰ろ」
キックが帰る支度をした。吉都も「ぼくもそうする」とキックの机の上に置いておいた自分のバックをとった。吉都は思い出したようにバックから盗聴器を取り出して、古書に
「これはずしておきました」
とわたした。
「あ、さすが吉都さんだ、相手に見つかったら詮索されて面倒なことになるところだった」
古書が受け取りながら言った。
「それじゃ、明日よろしくお願いします」
吉都とキックは研究室をでていった。
「またあした」
なぜかみんなが二人に手を振った。
明くる朝、家をでる前に、吉都の携帯がなった。キックからだ。
「今日我々キャッツアイにはいかないことになったわ、薩摩室長が、池波光子と鈴木美和を警視庁によんだって、二人とも十時くらいに来るんですって、所長と古書さんが話を聞くそうなんだけど、可也がこれたら来てほしいらしいわ」
「わかった、いくよ、どうしてそうなの」
「ハワイにいる宙夜さんから情報がはいったようなの、日本に送った動物に石を埋め込んだことを、モンクット・チェンが白状し始めたらしい、それで、キャッツアイの二人を参考人として、呼ぶことができると判断したのね、任意できてもらうのかな」
吉都は警視庁にむかうことを、事務所のメイルにいれた。
九時半、警視庁の受付にいくと、高胎とキックがおりてきて、一緒に面接室の裏にある部屋で、キャッツアイの二人の話を聞くことを説明してくれた。
「隣の部屋が面接する部屋、二人の言っていることでおかしいと思ったら、おしえて」
キックが吉都に説明した。
「面接の様子を見ることはできないの」
「うん、そういった窓はここにはないの、尋問室じゃないのよ、ただの会議室、面接の声は、ここでも聞こえるわ、最初に鈴木美和が面接よ」
十時になった。鈴木美和が面接室にはいったようだ。薩摩の声がテーブルの上にあるスピーカーから流れた。
「おはようございます、おいでいただいてすみません、お話をうかがいたいのですが、我々の対応の問題もありますので、録音と映像の記録はとります。録音映像が必要がないと言うことがわかったときには消去します。よろしいですか」
「はい」
「猫白血病は陰性で問題がなかったのですが、念のためレントゲンをとったところ、猫のお腹に石のようなものがみられまして、猫に何をしてあるかご存知かと思いまして、来ていただきました、ご存知でしたでしょうか」
ちょっとの間があり、鈴木美和が答えた。声が震えている。
「い、いいえ、避妊手術をしている猫ときいていますが、それ以上のことは」
「変な病気じゃなければいいと思うんですが、お腹に石などできるのでしょうかな」
「腎臓や尿管に結石ができますが」
「石のあるところが違いましてな、これです」
レントゲンの写真を見せたようだ。間があった。
「さー、私にはわかりませんが」
「鈴木さんは、トリマーの仕事だけじゃなくて、いつも猫の輸入のお手伝いもするのですか、今回も猫の受け取りに行きましたね」
「はい、手伝っています」
「お給料はもらっているのですか」
「いえ」
「キャッツアイには他にもトリマーやデイサービスの猫を管理する人が働いていますね、そういう人も猫の輸入のお手伝いをするのですか」
「いえ、わたしだけです」
「店長だけということですね」
「ええ」
「猫の輸入のための書類は鈴木さんがみなやっているみたいですね、書類の字も鈴木さんのものですね」
古書がすでに調べたことである。
「そうです」
「輸入をするために、ハワイのキャットパラダイスに注文するのも鈴木さんですか」
間があいて、「はい」と小さな声が聞こえた。
「モンクット・チェンという人を知っていますか」
「はい、キャットパラダイスの輸出責任者です」
「そうですね、送り主であるキャットパラダイスの書類にあります、よく知っている人ですか」
「いいえ」
「猫の注文はこちらからするのですか」
「そういうときもあります」
「そうじゃないときはどういうときですか」
「売ってくれと頼まれます」
「売れないときはどうするのです」
「とても安く、他の業者に渡します」
「大変なんですね、鈴木さんはハワイには行ったことはないのですか」
「海外は結婚したときに、タイのプーケットに行っただけです」
「いや余計なことを聞きました。もう少し猫のことをお聞きしたいのですが、お疲れになったでしょう、ちょっと、向こうで一休みしてください、コーヒーでも用意させます、そのあと、もう一度話を聞きますのでちょっと待っていてくださいますか、すみません」
戸が開く音がして、少し経つと、今度は戸が閉まった。誰か入ってきたようだ。池波光子だと、高胎が吉都とキックに言った。会話がはじまった。最初に薩摩が、鈴木美和に説明したように、録音録画していることの了解を取った。
「猫ちゃんたちは元気なのでしょうか」
光子の声だ。古書が「元気ですよ」と答えている。
「猫白血病は大丈夫だったのですが、体の中に何かあることが、レントゲンでわかったのです」
「ガンですか」
「いえ、石のようなものが、十五匹すべての猫にありました」
「まあ、なんでしょう」
驚いている声だ。
「ハワイのキャットパラダイスの書類には何か書いてありましたか」
「いえ、私は書類を見ていません、避妊手術をしてあることは知っています。それだけじゃなくて、帝王切開をした猫などで、もうブリーディングに使えないので、処分されるような猫を私どもで安く譲っていただいて、高級な猫ちゃんですから、大事に飼ってくれる人に安くお譲りしているんです、猫にも猫の好きな人にも良いことだと思って」
「今まで羽田に猫を取りに行ったことは」
「いえ、鈴木が、輸入手続きも、ほしい方への搬送や、保険についてもやってくれてますから」
「鈴木さんはトリマーなのに、猫輸入を手伝っているんですね」
「ええ、とてもいい子で、ご主人が犬猫病院をやっているものですから、調子の悪い猫がいると、その病院でみてもらいます、よくやってくれます」
「別に給料をだしていないのですね」
「ええ、彼女の方から要らないっていうんです、鈴木動物病院を紹介してもらえればいいと言っています」
「鈴木さんのご主人はキャッツアイの店にはよくこられますか」
「デイケアーの猫ちゃんの調子などを見てもらうこともありますが、病院の方がありますからあまりみえないようです、避妊手術はとても上手だという評判です」
「ところで、池波さんは宝石鑑定士ですね」
「はい」
「十五匹すべての猫のお腹のものは石のようなのです」
「え」
という声のあと、時間があいた。
「なんでしょうか」
「宝石が入っている可能性があります、そのようなことはご存知ないですね」
「も、もちろんです」
「宝石鑑定士の資格をアメリカとタイでとっていらっしゃいますね、日本じゃなくて」
「はい、主人が貿易会社をやっているので、アメリカに数年いたことがあります、そのとき、主人に勧められてとりました。アメリカの鑑定士の元で働いたので、勉強になりました。主人がタイにも数年行ってたことがあって、やはり主人にすすめられました。タイはいろいろな国からの宝石が売買されていますので、とても勉強になりました」
「それが、なぜ猫の輸入業者や猫の美容室を開いたのですか」
「あ、それは私が猫が好きですし、義理の母も猫のブリーダーをやっています、主人は貿易に関して手広くやっていたことから、友人のやっていた猫の輸入業を引き受けたのです、その友人は病気でなくなりました。それで、理由はわからないのですが、ほとんど儲けのない個人会社なので、私が社長になっておいてくれということでした。給料はないようなものです、会社の名前は私がつけました。猫睛石としました、私の好きな猫目石のことです、主人はなんだか分からないと反対していましたけど、やっぱり誰も読めないので、みなキャッツアイって言ってました」
「猫の美容室も池波さんが開いたのですね」
「はい夫が、なくなった友人の猫の輸入会社を鈴木病院の院長先生がそのころから手伝っていらして、院長の奥さんがトリマーで、猫の美容室をやりたいということで、主人が最初お金を出して、猫の美容室をつくり、キャッツアイという名前でやることになりました。お金を出したことから、猫の美容室も猫睛石の経営ということになり、私が社長ということになりました」
「すると、美容室の方も鈴木さんがほとんどやっていたのですか」
「ええ、私はそっちのことはなにも知りませんから、ただ、猫のほしい人には相談にのっていました。猫は私も大好きですから」
「ハワイのキャットパラダイスも経営者ですよね」
「え、なんのことでしょう」
ちょっと時間があった。
「キャットパラダイスの経営者は、この書類にMitsuko Ikenamiとありますが」
「さあ」
「ご主人の名前はなんとおっしゃるのでしたっけ」
「池波静夫ですわ」
「キャットパラダイスには関係していませんね」
「はい」
「この人をみたことがありますか」
高胎が「モンクット・チェンの写真を見せたのだと思います」と吉都に説明した。
「いえ、ありません」
「ご主人の貿易会社はなにをあつかっているのです」
「主に民芸品やその地の昔からのものです、タイ、スリランカ、南米のいろいろな国ですわ」
「それじゃ、社員はたくさんいるんでしょうね」
「いえ、十人ほどです、コンピュータがあって、言葉に通じていれば、輸入は難しくないと、主人は言っています」
「オフィスはどこですか」
「月島の方です」
「いや、ありがとうございました、後でもう一度お話をきかせていただきたいので、あちらで待っていただけますか、なにせ、猫の身体に宝石がはいっているかもしれないものですから」
戸の開く音がした。光子が出て行ったのだろう。しばらくすると、足音が聞こえ、人が入ってきた。
「鈴木さん、面倒なことですみませんが、この人を知っていますか」
古書がやはり、モンクット・チェンの写真を見せたようだ。
「はい、タイのサーマート・リーさんです」
「どこであいましたか」
「日本に来ていた留学生で、獣医大の学生さんだと、主人に紹介されました、留学中に猫の輸入を手伝ったことがあります」
「ご主人との関係は」
「なんでも、主人のでた大学に留学していて、将来日本に輸入会社をつくりたいということで、東京でもマンションを借りて輸入をすでにはじめていました」
「ご主人はどこの大学をでられたのですか」
「相模原の獣医大学です」
サーマート・リーは中央線沿線の獣医大学に留学していたことになっていた。話がちがう。しかも、鈴木美和はハワイのモンクット・チェンの本名を知らないことがこれでわかった。吉都はこの組織に鈴木の主人もかなり関わっていると思った。
「ちょっとやっかいなことになっていましてね、先ほど言った、猫たちの身体に入っているのが、宝石の可能性が高いことがわかりましたので、摘出手術をします。そうすれば明らかになりますよ、もしあなたが何らかに関係しているのなら、はっきり言ってくだされば、その方が少しは罪が軽くなりますよ」
鈴木からの返事は帰ってこない。隣室の面接室がのぞけるなら、鈴木はうつむいて考えているのだろうなと、吉都は思った。
「本当のことを言ってくださいね」
薩摩の声がちょっと高くなる。
やっぱり、鈴木の声は聞こえない。
「やっぱり、知っていましたか」
という薩摩の声が聞こえる。鈴木がうなずいたようだ。
「それで、猫のお腹の中のものは何ですか、取り出せばわかるわけですよ、知っていたら言ったほうがいいですよ」
かなり間があって、
「宝石の原石です」と、鈴木の声が聞こえた。
裏の部屋で、高胎が「ゲロしちゃったわね、これから組織の解明ね」と二人に言った。
「それは宝石の密輸ということですね、誰の指示ですか」
「私は、言われたとおりにやっていて、ハワイから猫を送るから、売るようにと言う指令がきます。受け取って猫を売ります」
「池波社長の指令ですか」
「いいえ、ハワイから直接いってきます、社長には猫がきますと伝えます」
「すると、社長が猫を取りに行くように鈴木さんに指示するわけですか」
「いえ、私がすべてしています」
「猫のお腹の石をどうやって取り出すのですか、胃に入っているのではないので、手術をしなければなりませんね、誰がやりますか」
ちょっと躊躇したのだろう、答えるのに時間がかかった。
「いつもではないのですけど、主人です」
「それで、帝王切開をした猫といって安く売るわけですね」
「はい」
「帝王切開した猫と宣伝にはかいてありましたが、誰がキャッチコピーを考えたのですか」
「私です」
「猫の帝王切開というのはあまりないようですね、ご主人がしたことがあるのですか」
「あの、医院には事務と補助の方をお願いしてあるので、私は手伝ったことはありません」
聞いていた吉都は、だから、あんなコピーを書いたのだと納得した。
「ご主人には話を聞かなければなりませんが、電話をする時間を差し上げますよ、もし、自首するような形ですと、ご本人の為にもなります、今は司法取引という方法もあります、ご主人に電話しますか」
「はい」
「もしその気がありましたら、すぐに最寄りの交番、警察にいって、そのことを伝えれば、パトカーを迎えにやります、そうでなければすぐに警察官が逮捕しに行くでしょう」
鈴木美和の電話する声が聞こえてきた。
「あなた、みんな調べられているわ、自首した方がいいわ、猫に原石が入っていることも知られてしまっている」
相手の声は聞こえない。
「近くの交番に行くと言っています」
「電話をかわりましょう」
「はい」
「もしもし、警視庁の薩摩です、奥さんがすべて話してくれました。ご主人もこちらですべてはなしてください。司法取引をしてもいいですよ、そうすれば、刑は軽くなると思いますよ」
隣の部屋で、高胎蓉子が吉都たちに、
「薩摩警視は鈴木夫婦が末端の人間だとふんでいますね」と言った。
「池波光子をあぶり出そうとしてるのかしら」
キックが言うと、吉都は「なんだか違う気がするな、もっと違う人間が首謀者のような気がする」と否定した。
「鈴木さん、ご主人がきても会わせることはできません、一応、宝石密輸の件で重要参考人ということで、留置します。お二人とも今日は留置場の方にはいっていただきます。誰か弁護士をよびますか」
「いらっしゃらないようでしたら、こちらで弁護士をよびます」
そこで会話は終わった。
今度はまた池波光子の面接がはじまった。
「レントゲンでわかった原石の形は楕円形でしたが、どんな石でしょうか」
「さあ、全く想像ができません、どのような原石でも楕円に削ることができます。お腹の石は、猫ちゃんには負担ですね、はやくとってやらないと」
「明日には取り出してもらいます」
「猫はどうなりますでしょうか」
「こちらで、しっかり管理します」
「処分などしないでください」
「そんなことはしませんから安心してください、ところで、ご主人はキャッツアイの管理には関与していないのですか」
「ありませんわよ、家でも聞かれたことがありません」
「ということは、鈴木さんが一人で運営しているのですか」
「ええ、そういうことになります」
「鈴木美和さんのご主人は経営に参加されていますか」
「いえ、猫が調子の悪いときは見てもらいますが、経営に関係はないと思います、美和が相談くらいはしているかもしれませんが」
「あなたのご主人は、キャッツアイに顔をだされますか」
「ほんのたまに、私が行っているときなど来ることがあります」
「それだけですか」
「私の知っている限りではその程度です」
「池波さんのご主人はご自分で会社を興したのですか」
「いえ、主人の父親が立ち上げた会社で、亡くなってから引き継いだのです二代目です」
所沢の池波夫人のご主人も貿易会社をやっていたと言っていた。
「あの、いろいろありがとうございました、ただ、キャッツアイが輸入した猫が宝石の密輸入に使われたということで、あなたは重要参考人です、社長ですからね、今日はお帰りになってかまいませんが、明日にはもう一度来ていただいて、猫たちのお腹の中のものを取り出す立ち会いをしてください」
「わかりました」
「ちょっとはやいのですが、九時に警視庁にきてください」
「はい」
「ご主人は何時頃おかえりですか」
「今、タイにおります」
「このことは、おっしゃらないようにしてください」
「はい」
面接は終わったようだ。
吉都は池波光子を帰してしまっていいのか疑問に思った。ハワイのキャットパラダイスの経営者なら、そのことを追求しなくていいのだろうか。
薩摩が急いではいってきた。
「高胎さん、キックと一緒に池波光子を自宅まで送ってくれないか、覆面パトカーでたのむよ」
「はい、わかりました」
「それと、光子を明朝まで張ってほしいんだ、主人やハワイの方と連絡をするかもしれないし」
「はい」
二人ともすぐでられるようにしていたようだ。やっぱり光子には見張りをつけるわけだ。
「それじゃ、吉都さん、また、今日はごくろうさまでした」
高胎がそういって、二人が部屋をでると、薩摩が、
「吉都さん、聞いていただいたとおり、だんだん様子が分かってきたね、吉都さんたちのおかげだよ、詐貸には電話をかけとくけど、これから必要なことがあったら、またお願いしますよ」
「鈴木美和の方ははっきりしましたけど、池波光子がよくわからないですね」
「そうですな、周りを気をつけないと、主人だな問題は」
「ハワイのキャットパラダイスのことは追求しませんでしたね」
「直接に聞くと身構えちまうから、ちょっと泳がせておこうと思ってね、二人にはってもらうわけですよ、国際電話をかければ、ハワイの方で気がつくでしょう、だんなに連絡すれば、逃げるか、急いで日本にもどるかすると思うよ。タイの警察には連絡をしてあるよ」
やっぱり、プロはすきなく動いている。
「それじゃ僕はこれから事務所に帰ります」
吉都は警視庁をでた。
猫女石の正体
吉都がもどると、巣鴨の探偵事務所では、野霧と詐貸がPCにむかっていた。
「ごくろうさま、薩摩から電話があったよ、話はきいた。野霧君にも話したよ、薩摩はこれからだと言っていた、それで、薩摩の方で見落としていることがあるかもしれないから、気がついたら教えてほしいとさ」
「警察の面接の様子というのがよくわかりました。薩摩さん誘導尋問上手ですね」
「あいつは、見かけと違って、神経使う男だからね」
そういえば誰かもそう言ってたな、と吉都は思った。そうだ、羽田の津軽さんだ。
「薩摩さん、最後に池波光子の周りがあぶない、主人だなと言っていました」
「俺にも言ってたよ」
「あの、光子のまわりって、所沢の池波夫人もはいりますよね、ちょっと気になりました」
吉都が言った。
「十八匹の猫の骨か、そうだな、もう一度、小手指で、池波夫人のことを聞いてみるかい」
「吉都君行くなら、私も行きます、あのときは偶然、池波夫人に会って、サーマート・リーのことを知ったわけです。サーマート・リーが下宿していたということは、関係ないことはないでしょうね、池波夫人が利用されていたとか」
「それじゃ、明日小手指に行ってみてくれる、彼女に電話しないでね」
「どうしてですか」
「ウン、勘だけどね、もし池波夫人が関係あったとしたら、頻繁に野霧が連絡することを不思議に思うからね」
「あの夫人が関係あるとは思えないけど、わかりました、今度は芋シュークリームをもっていきます、猫の骨のことを調べに来たついでだと言います」
ということになった。
あくる日、二人はお菓子屋によってから池袋に向かった。
「野霧さん、池波さんのところにいく前に、シルバー会の畑山さんのところによってみませんか、池波さんのことをもう少し詳しく聞いてみませんか」
畑山さんは椿山団地のシルバー会の会長さんである。前にきたときは池波夫人やサーマート・リーのことを教えてもらった。
「そうね、あのときは詳しい話をきいたわけじゃないものね、確か池波さんはシルバー会に入っていないって言ってたわね」
「そうですね」
小手指につくと、タクシーで畑山さんの家にいった。
ベルをおすと、畑山夫人とおぼしき人がでてきた。
「四月に、警視庁から頼まれて、猫の骨のことでお世話になりました、探偵事務所の者ですが、ご主人はいらっしゃいますか」
「ああ、主人から話は聞いてますわよ、今日、主人出かけていますが」
「あのときはお世話になりました。猫の骨を誰が埋めたか、まだ明らかになっておりません、猫の愛護の点から言っても、はっきりさせたいと思ているところです、もう少しお話を聞かせていただこうと思って訪ねたのですが、奥様は池波さんのところに下宿していた、サーマート・リーという学生のことをご存知ですか」
「主人から話だけは聞いています、どうぞおはいりになって、主人ほど知りませんが」
野霧と吉都は畑山夫人の招きに応じ、家にあがった。
「あの学生さんが猫をどうにかしたのですか」
畑山夫人はお茶を持ってきた。
「いえ、そうではないのですが、あ、おかまいなく、そうだ、これ、探偵事務所の近くのお菓子屋のものですけど」
野霧がシュークリームの箱を渡した。
「え、いいんですか、主人いませんけど」
「どうぞ、どうぞ、結構おいしいシュークリームです」
「それじゃ、私もいただきながら」
畑山夫人は、シュークリームを皿にいれてもってきた。
「リーの下宿していた池波さんは、猫好きでいい人ですね」
野霧は話のはじめを作っていくのが上手だ。
「うーん、そうですね、あの辺じゃ一番大きなうちで、あまりおつきあいがない人なんです、ちょっと近づきにくいところがあるんですけどね、ご主人とは話したことがありますわよ、貿易会社を自分で起こした方で、いい方でした。早く亡くなってしまって残念でしたね、奥様はしょっちゅうハワイに行ったり、アジアの各国に行って、結構派手に遊んでいらっしゃいましたわね」
「タイにも行かれていたのでしょうね」
「池波さん、宝石もちで、タイに行くと必ず宝石を買ってきたということでしたよ、ご主人が亡くなってからは、長男の方が貿易会社のあとを継がれて、お母さんに宝石をずいぶん買ってくるようですよ、池波さんの近くに住んでいる私の友達がそう言っていました」
池波婦人からは小さなキャッツアイをみせてもらったが、たくさんの宝石を持っているとは言っていなかった。
「ご長男が跡を継がれたんですか、それで、サーマート・リーさんの下宿をお引き受けされたんでしょうかね」
吉都が言うと、
「どうでしょう、その辺は知りません」
「次男の方がいるということでしたが」
「そうらしいですわね、府中のご長男は、よくお母さんのところに見えているということですけど、所沢の次男の方は近いけれど、あまりみかけないと、友達が言っていましたわね」
「ご長男の奥さんもよくみえるのでしょうね、池波光子さん」
畑山夫人はえっという顔をした。
「長男の奥さんのことは知りませんね、光子さんというのですか、池波さんも美津子さんよ」
それをきいて、吉都は「あっ」と声をだしそうになり、野霧の顔を見た。野霧の顔が三角になっている。野霧が腕時計をみて、
「ずいぶん長くお時間とってしまったわ、申し訳ありせん」といって、吉都に出るように促した。
「いいえ、お役に立てなくてごめんなさいね、シュークリームおいしかったわ」
「とんでもない、色々お話助かりました、ありがとうございました、ご主人によろしくお伝えください」
二人は畑山夫人に礼を言って、早々に畑山家をでた。
「野霧さん、池波婦人もミツコ、イケナミですね」
「でもまさかね、どうしようか、池波夫人のところに行って、怪しまれてしまわないかな」
野霧の声のトーンが変わった。まだ信じられないようだ。
「詐貸所長に、所沢の池波夫人の名前がみつこであることを連絡しましょう」
「そうね、Mitsuko Ikenamiがどっちのみつこか、ハチ公のほうで調べてもらうように言ってよ」
吉都が詐貸に電話を入れた。
「所長が、池波夫人のところには行かないようにと言っています。動きを知られないほうがいいということのようです。すぐ帰ってくるようにとのことです」
「そうね、もどりましょう」
巣鴨の事務所では、詐貸が首を長くして二人を待っていた。
「ごくろうさん、薩摩に連絡したら、すぐ返事があった。宙夜に調べてもらった結果、キャットパラダイスのCEOのイケナミ ミツコの住所は所沢だと連絡があり、キャットパラダイスの収入の大部分はタックスヘブンにあずけてあるのだそうだ、所沢の池波夫人が、美津子という名だったとは迂闊だったな、ただ、実際の運営はヒロシ イケナミ、所沢の池波美津子の長男だ」
「所沢の池波夫人はただの猫のブリーダーだと思っていましたから、驚きましたね」
そう言って野霧を見ると、だまったままだ。裏切られたという顔だ。いや自分が信じられないという顔か。
「そうだな、それで、鈴木獣医師が逮捕されて、警察で尋問をうけているが、薩摩の話では司法取引をする予定だそうだ、それと、高胎さんとクッキーが府中の池波光子を張り込んでいたけど、動きはなかったそうだ。朝、そのまま光子を警察につれてきたんだって」
「鈴木静夫はどういう立場なのですか」
「池波寛が光子を社長にした動物商の、前から出入りの獣医だったことから、そのまま頼まれていたようだが、池波寛が宝石輸入の仲間に引きずり込んだようだ。元々はある動物病院に所属していたが、寛が金を出し、独立させて、キャッツアイの近くに開業をさせたということだな」
そのことは光子が言っていた。
「それで、司法取引をすると、鈴木静夫はどの程度の罪になるのでしょうね」
詐貸は法律家である。
「どうだろうな、宝石密輸に関しては問わないことにして、猫に間違った手術をしたかどで、動物虐待の罪ぐらいかな、それに奥さんの鈴木美和もその補助をしたことの罪ぐらいに落ち着くんじゃないか」
「宝石鑑定士の池波光子はどうでしょう」
「旦那のやっていることと、全く関係ないことがわかれば、罪はないことになるだろうな」
「所沢の池波美津子はどのくらい関係しているのでしょうね」
「薩摩の話では、密輸担当の部署で、総力を挙げて調べているのだから、そのうち池波美津子も参考人で呼ばれ、家宅捜索を受けるだろうとのことだよ、もうそろそろ、我々の出番はなくなるよ」
「あの十八匹の猫骨のことはどうなるでしょうね」
「君たちがだいぶ調べてくれたから、きっとモンクット・チェンがはくことだろうと思うよ」
「それじゃ、私、アイスクリーム買ってくる」
「寒くなってきたのにかい」
詐貸がおどろいていると、野霧は、
「なんだか、やっともとにもどれるようだから、アイスクリームがいちば暖かい」
と外に出て行った。
「所沢に持って行った芋シュークリームが一箱余っているから、我々はそれにしましょう」
吉都がお茶をいれにいった。
猫の腹部から原石を取り出したのは、次の日だった。獣医大学の先生の都合で一日遅れた。研究室の助手や講師総動員で、手術を行った結果、三時間で、すべての猫から石をとりだした。
池波光子にも立ち合わせたという。手術の様子を見て、気を失いそうになっていたということだ。
立ち会った古書の話では、でてきたものを見て、教授をはじめみんなびっくりしたということである。それは磨かれた石ではなく、硬度の高い透明な樹脂に包まれた原石だった。どれもほぼ同じ大きさで、つるつるしており、内臓を痛めることがないようになっているという。
取り出された石はその場で池波光子が鑑定したそうで、とても質のよいルビーやサファイア原石だそうだ。すべて証拠品として押収される。
猫はみな元気で、とりあえず獣医大学の動物飼育室に保護されている。
ちなみに、宝石鑑定士の池波光子は、逃亡や何かを隠蔽する心配なしと判断され、東京からでないということを条件に家に帰された。自宅にいることを言い渡され、夫への連絡も禁止された。夫のことに関してはいっさい知らされていないし、ましてや義理の母のことは全く知らない。
夫の池波寛はタイ警察からすぐ日本に戻すという連絡があったという。
それから一週間ほどたったとき、薩摩から詐貸に電話があった。大きな流れは解明されたということであった。それはタイとハワイ、それに日本の、猫を使った密輸のルートで、貿易会社をやっていた池波親子が主犯級であること、モンクット・チェンが、タイの密輸組織の一員で、池波寛に協力していたことが判明した。貿易商をやっていた池波寛が、世界のいろいろなところと関わっていたことから、宝石の大きな密輸組織に繋がっていて、世界の密輸組織を暴く糸口になることだとうということだった。
「所沢の池波美津子の家には、時価にすると、数十億の宝石の原石が隠してあったということだよ、あそこが倉庫だったわけだ、磨いて売ったらその数十倍の価格だそうだ」
「すごいものですね、それで十八匹の猫の骨や、猫睛石が輸入した猫が自動車事故にあった件などはこれからですか」
「自動車事故に関しては、鈴木静夫がみな説明したようだよ、柳井さんや白井さんなど個々の件はこれからだが、やっぱり石を身体に入れた猫を盗み、石を取り出した後に、車にひかせいたようだ、それは池波寛の指示で、やくざの連中にやらせていたようだ。池波寛はやくざを介しても宝石の原石を売りさばいていたようだな、猫の骨に関しては、サーマート・リーとして日本にきていたモンクット・チェンが、借りていた国立のビルにいっぺんに十八匹の猫を輸入し、麻酔死させ、自分で取り出したようだ、猫を羽田からつれてきたのは鈴木美和とモンクット・チェンの二人だ。鈴木美和がみなしゃべったんだ、チェンが日本にきていたので、池波親子の指示でやったらしい」
「死体を所沢に埋めたのも、池波美津子の指示だったのでしょうかね」
「その件は後回しにされている、そのうち池波美津子から聴取するだろう」
「人を見る目がまだまだ甘いと思いました」
野霧は今日は素甘を食べてる。
「すあまを食べてるからね」
「え」
詐貸の冗談はわけのわからないことがある。
野霧も吉都も横を向いて笑った。
十二月にはいってすぐ、宙夜が帰ってきた。ハワイから毎日のように連絡をもらっていたので、ハチ公のスタッフはだいたいのことは知っていた。
薩摩から探偵事務所の方にきて、今までのことを報告したいということだった。
それからしばらくしたある日の夕方、薩摩はキックを連れて探偵事務所にやってきた。
「や、久しぶり、吉都さんと野霧さんにはたいそうお世話になって、ありがとうございました」
「宝石の世界をのぞかせてもらって面白かったです」
野霧が言ったことに、吉都もうなずいた。
薩摩はこの事件を猫女石宝石密輸事件と呼ぶことにしたとを言った。
「猫目石じゃなくて、猫女石ですか」
「うん、吉都君がそんなこと言ってたじゃないか、キックがそう呼ぼうと主張してね、ブリーダーの猫目石、池波夫人が首謀者の一人だったわけで、本人が安く宝石を手に入れたいために、貿易会社をひきついだ長男の寛をたきつけて、宝石密輸もさせたんだ、寛もお金には執着がある人みたいで、今の組織に発展させたらしいよ、だから、猫の女の石事件としたわけ」
「最初は、詐貸所長が猫女石って言ったんです、僕は所長がそう言っていたのを覚えていたんで言ったんです」
吉都が訂正すると、薩摩は「ともかく、庚申塚探偵事務所が名づけたわけだよ」と笑った。
「池波親子はもうはいたのかい」
詐貸が聞いた。
「うん、みんなしゃべった、裏もとれたし、ハワイの警察もそれをもとに、さらにモンクット・チェンを追い詰めたらしい、もうこの事件は第八研究室からはなれたよ」
「それで、所沢の骨のこともわかったわけですか」
宙夜がそのことを詳しくききだしたようだよ、モンクット・チェンは、ボスのマザーが、そのへんに埋めたらと言ったので、車を止めていたところに埋めたということだよ、池波美津子もそう言ってたよ、あれは密輸に使われた猫の遺体だよ」
野霧も吉都もかわいそうにと思った。
「草取りのふりをしてか、池波夫人はあまり深く考えないでそんなことをさせたのですね」
吉都は、猫をだっこしている池波夫人を思い出していた。義理の娘である池波光子と似た風貌をしているが、生き物に対する思いは全然違う。
「義理の娘の方はどうなったんです」
「基本的には罪はないけど、なんらかのおとがめは受けるだろう」
「まさか、夫と義母がそんなことをしていたとは驚いたろうな」
詐貸が言った。
「それでだ、庚申塚探偵事務所のおかげが半分以上あるだろ、それは上にも言ってあったんだ、われわれ、第八研究室は、警視総監から褒められてね、実は警視総監が、ここに感謝状をだすっていうんだ」
薩摩が言うと、
「おいおい、そんなもんもらってもなあ」
詐貸がやめてほしいという顔をした。
「そう言うと思ったよ、ふつうの探偵事務所なら、大喜びで、立派な額に入れて、事務所にかざり、宣伝に使うぜ」
「猫探しの探偵事務所にはいらんねえ」
「だがな、おれの顔をたててくれよ、もらってくれよ、飾れとはいわないからさ」
薩摩がなきついた。詐貸は苦笑いをしながら、
「庚申塚探偵事務所宛の表彰状だと、所長、詐貸殿になるだろ、吉都と野霧君の名前が入るのならいいけどな」
「できるかな、やってみるよ」
「アイウエオ順にしてくれよ」
「わかった、それならもらってくれるな」
「うん」
というわけで警視総監から感謝状がくることになった。
「そのうち打ち上げをやろうか」
「そうだな、今日、神無月にいこうか、研究室にいる連中も呼ぶから、宙夜も来ると思うよ」
「そうしよう、津軽さんにも連絡してみるよ」
その日、神無月にみんな集まった。
これで終わった。
エピローグ
猫女石事件が、探偵事務所の手を放れ、打ち上げをしてから十日ほどたつ。十二月も半ばになる。今年もあと二週間。野霧の本は予定通り一月に発売される。
その日の朝、野霧と吉都が事務所に行くと詐貸がもう来ていた。
「昨日、薩摩と飲んだんだけど、これを渡されたよ」
紙筒から警視総監からの感謝状をとりだした。
「本当は俺が警視庁にもらいに行かなきゃならなかったんだが、仕事が忙しくて行けないということにして、薩摩に頼んだんだ」
詐貸が感謝状を広げた。
「俺が言ったとおりに書いてくれたけどね」
感謝状には宝石密輸事件の解決に多大な貢献をしたことが書かれており、庚申塚探偵事務所 所長 逢手野霧、吉都可也、詐貸美漬 殿、となっている。
野霧がそれを見て三角の顔になっている。
「何ですか、これ、あたし、所長になっている」
「ほら、アイウエオ順に書いてくれって言ったろ、薩摩がまじめにそう言ってくれたんだな、ところが、事務方が、事務所のあとに所長を書いちまったんだと思うよ、それでこうなったんだろう、所長逢手野霧だよ、面白いから、これ額に入れようか」
野霧は「いやだー」と、笑いながら首を振った。
「しまっときましょう」
吉都もそう言って突っ立っている。
「そうか、そんじゃしまっとくか、金一封でもでりゃいいのにね」
詐貸は感謝状をまた筒のなかに入れた。
吉都がなんだか、緊張した面持ちで言った。
「あの、これから、キックがきます」
詐貸も野霧はその声にびっくりした。うわずっていて、いつもより高音だ。
「なにしにくるの」
野霧がもしやという顔をしている。
「早引けしたいのかい」
詐貸も、もしやと、顔を上げた。
「それもあります」
「なあに」
「あの、結婚しようと思って、報告です」
吉都がどもりながらいうと、野霧が目を大きくして、顔をしわくちゃにして笑顔になった。
「あー、やっと、よかったわね、その報告にくるの」
「薩摩も前からそんなこといってたよ、俺より先にかよ」
詐貸がなんだか半分真面目に言うと、野霧が、
「所長もそろそろでしょう」と言った。
「愛子さん首ながくしてまっているんじゃないですか」
「それはないよ、愛子はこれから一年、いやずーっとかもしれないけど、ベルゲンに住むよ」
「え」
吉都も野霧も驚いた。
「それじゃ、庚申塚探偵事務所おしまいですか」
「まさか」
詐貸の答えに、野霧と吉都は顔を見合わせた。
「だって、愛子さんと一緒に行くんじゃないのですか」
野霧の言ったことに、詐貸は野霧を見て、首を横に振った。どういうことなのだろう。
「野霧君」
詐貸の声が改まった。野霧が詐貸を見た。
「結婚してくれないか」
野霧の顔が三角になった。きょとんとしているのだ。それから笑い出した。
「そんな冗談、よしましょうよ」
野霧は困った笑い顔だ。
吉都が「所長本気のようですよ」と野霧に言った。
野霧は吉都の方を向いて、なにがなんだかわからないと言う顔をした。
詐貸が話し始めた。
「俺はね、親も兄弟もいないんだよ、北海道の篤志家がね、修道院に預けられた、一歳の俺をね、支援してくれてね、修道院の院長が親代わりに中学まで育ててくれた。それからね東京の私立高校に受かっていたので、寮に入ってね、大学も東京だったから、それ以来東京で一人暮らしだったんだ。
本当の親はね心中して俺だけ助かったんだ。理由は教えてくれなかった。調べもしなかった。
修道院の院長が三月に亡くなってね、葬式に出てきたんだよ、その人はたくさんの親のない子供をを育てた人でね」
そういえば、詐貸所長の家族のことなど一度も聞いたことがない。
「夢久家の愛子の家族が、俺を愛子と引き離そうとしたのは、それも一つの理由なんだ。水良さんが話してくれたよ、彼は何もいわなかったらしいけどね、水良さんも孤児のようなもので、夢久家に育てられたのだからね、しかも自分の子供に、愛子を嫁にと言うことだったし、気持ちはよくわかるよ。複雑だったろうね、それよりも何よりも最後は、愛子の決断だよ、やっぱり夢久家だよ、親の意向に沿ったんだよ、前に言ったろ、愛子もそうだろうけど、俺ももうとっくに愛子にはその気はないよ、偶然あの事件で愛子と会うことになったけど、それがなければ、一生会うこともなかっただろう、野霧君、俺じゃだめかな」
野霧が大声で泣き出した。外にまで聞こえるのではないだろうか。大きな目から大粒な涙が止めどもなく落ちている。
机の上の書類が濡れちゃうじゃないか。吉都は変なことが心配になった。
テディーじいさんも北海道の修道院で育ったんだな。まさか同じ修道院じゃないよな。時代がちがうな。でも、プロポーズ、よりによって、俺の結婚報告のときじゃなくてもいいよな、いや、こういう機会じゃないと、所長、野霧さんに言えなかったのかもな、吉都も、そんなことを考えていると、
詐貸が「テディじいさんは札幌だったけど、俺は網走に近いところだよ、女満別」と言った。
野霧の泣き声がまた大きくなった。
事務所の戸が開いた。希紅子が入っきた。びっくりして、
「野霧さんなぜ泣いているの、誰なの泣かしたのは」
詐貸を見た。
「所長さんでしょ、なに言ったの」
希紅子が怒こったような顔をしたので、吉都が、
「大丈夫だよ」と希紅子の肩に手をおいた。
希紅子の指に、吉都が甲府で作らせた地元の水晶の指輪がはめられている。
「なんなの」
「所長が野霧さんに結婚してくれって言ったんだ」
「え」
希紅子もびっくりして野霧をみた。野霧は涙で顔をベチャベチャにしている。
「野霧さん、所長いやなの、そうならそういっていいのよ、パワハラだわよ」
希紅子がそう言ったら、野霧がちょっと泣きやんで、半笑いになった。
「そんなわけはないよ、急だったんだよ」
野霧じゃなくて吉都が言った。
「おれたち、でようよ、二人にしとこ」
「どこいくの」
「お岩さんの墓に報告にいこう、また戻ればいいよ」
お岩さんの墓のある妙行寺は吉都の散歩の場所だ。吉都が希紅子の手を引っ張った。
野霧が泣きやんで二人に、「おめでとう」と言った。
詐貸も気がついて「おめでとう」と言った。
詐貸が野霧のところに来て、赤いビロードに包まれた小さな箱を野霧の前におくと、蓋をあけた。中に小さいが濃い赤色のルビーの指輪が入っている。星の線条がきれいにでている。スタールビーだ。国際宝石展で買ったもののようだ。色の白い野霧の指に映えるだろう。
野霧が詐貸の方を向いて、
「うれしい」
と言ってまた泣き出した。
詐貸が野霧の肩に片手をおいた。
柔らかくてあったかい。
吉都と希紅子が階段を下りていく靴音が聞こえる。
「俺たちも行くか」
「はい」
野霧も立ち上がって、手を引っ張られ、二人の後を追った。
どうしてお岩さんのお墓なの。
野霧がそう思ったとき、詐貸がぼそっと、
「おいわ いだものな」と言った。
無理してる、野霧の顔が膨れて大きな笑顔になった。詐貸の腕にしがみついた。
腕が折れそう、詐貸は笑いそうになった。
作者は、庚申塚探偵事務の二組の仲人となり、めでたくこの探偵物語を終えることになりました。探偵小説は恋愛小説と変貌をとげたのです。作者にはどちらも苦手なジャンルです。ぎごちないことこの上ない。恋愛探偵小説、いや探偵恋愛小説か、そういう新しいジャンルをつくってしまいました。さようなら。
あ、この中の話はすべてフィクションです、信じないで下さい。
おわりに
2022年は新コロナウイルス(COVID-19)の新たな株、オミクロン株の急速な感染が、1月2日からはじまった。世界ではすでに蔓延しているとても感染力が強い株である。まさに新コロナウイルスは、新年おめでとうと、お互いに挨拶をかわしていることであろう。一方、日本国民は、またかと思いながらもマスクをし、第三回目のワクチンをおくればせながら、あせってうちはじめた。
最初の探偵小説は2019年1月にだした「洒落頭」で、目眩に襲われベッドに縛り付けられたまま書き上げたものである。体調が完治しないまま、新たな構想が浮かび上がり、同年9月に第二探偵小説「美衣羅」をだした。2020年コロナが流行り始め、体調ももとにもどらないなかで、第三探偵小説「秘魅古」を書きだし、2021年6月に本にした。どの本も、巣鴨の庚申塚探偵事務所の探偵と二人の助手の引き受けた事件の話だが、次第にその三人の人間に興味がわいてきた。感情移入というところか。今回の本を書く動機は、その三人にまつわるエピローグが頭に浮かんだからである。したがって、最後の顛末が頭にあり、それにむかって、事件をつくりあげたという、プロには信じられない方法で、書き上げたものである。これも、素人だからできたことだろう。
2021年の8月21日、新コロナのデルタ株が猛威を振るい始め、第五波といわれた感染者数上昇のさなか、第四探偵小説である本書の最初の章ができあがった。11月13日に最終章が書き終わり、2022年7月7日付けで本にすることにした。
この本の表紙装丁は、前三冊とは趣が異なる。その三冊はすでにできていた木版画を使ったのだが、体調を悪くしてからは筋力が衰え、板を彫る気にならず、今回はペン書きの絵に色彩を施したものを、表紙や中扉に用いた。
これを書き終えて、これで探偵小説を書くのは終りだ、と現在の筆者はほんわかとした幸せ感に浸っている。後は今年中にオミクロン株の終息と、新たな新コロナウイルスの株が出てこないことを願うだけである。
2022年3月
猫女石(ねこめいし)-第四探偵小説(最終)


