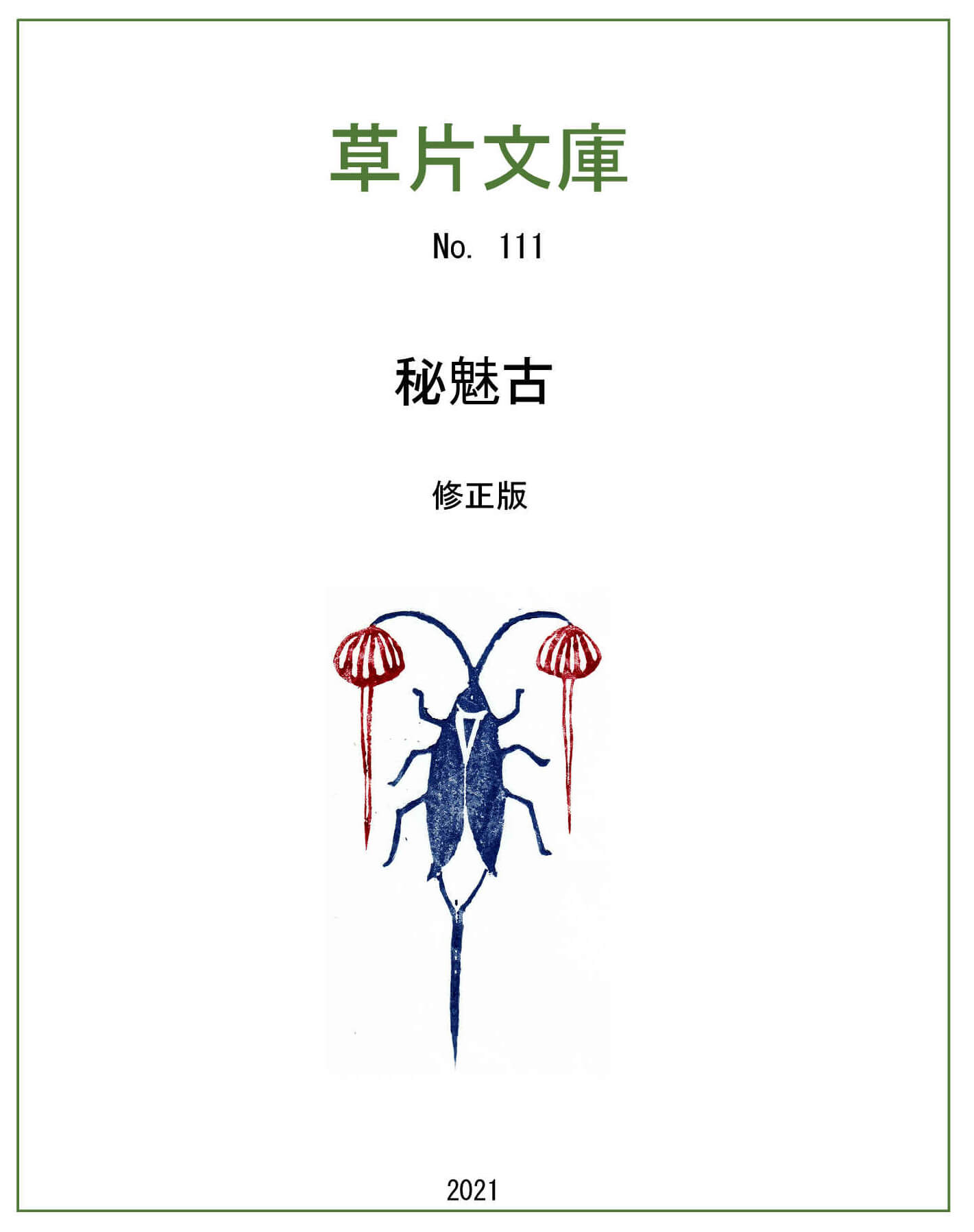
秘魅古(ひみこ)―第三探偵小説
殺人のない長編探偵小説です。
秘魅古 目次
秘魅古プロローグ
倭國神社
氷見己
火美胡
妣視杞
皮実沽
痺弭弧
緋巳壷
翡海湖
匪実虚
嵩丸弁護士の行方
八乳艸(やちぐさ)会
秘魅古エピローグ
おわりに
秘魅古 プロローグ
卑彌呼(卑弥呼)は日本でも一、二を争う誰でも知っている女性の名前である。顔の記録も残っていないのに、クレオパトラと同じように美女だと思ってしまっているのは、人間の脳の想像力の限界なのだろう。
卑彌呼は邪馬台国の長として、鬼道、すなわち妖術を用いて、民衆をまとめた女王である。民衆にどのように何を伝えたのであろう。卑彌呼の活躍した3世紀前半のころ、言葉はどのようなものだったか、専門の研究者が追求しているところで、素人にわかるわけもないが、意思疎通に話し言葉は必要であり、なんらかの形のものがあったことは確かだ。邪馬台国の話し言葉が、日本語の源流であるということも言われており、邪馬台国が台頭する以前より、すなわち弥生後期のころには話されていることばがあったと推測してもかまわないだろう。それをどのように表記していたか、漢字以前の文字を神代(かみよ)文字(もじ)というらしいが、神代文字とはなんとも想像力を刺激される魅力ある言葉である。
卑彌呼の話に戻ると、卑彌呼とは魏志倭人伝に見られるもので、邪馬台国のことば「ひみこ」を当時の中国人が漢字表記したものである。皇帝から「親魏倭國王」の称号をもらった「ひみこ」は自分の名前はこう書くのかと思って使ったことだろう。しかし、神代文字ですでに自分の名前を書いていたことも想像できる。どのように書いていたのか興味のあるところである。
日本最古の書物とされるのが、聖徳太子の三経義疏(さんけいぎしょ)(611-615年)とされる。その中の「法華義疏(ほっけぎしょ)は自筆ではないかという。それでは、神代文字で書かれた書物は残っていないのであろうか。日本で紙を作るようになったのは、610年高句麗より伝えられてからという。紙でなくとも書くものはある。皮でも、樹皮でもいい。紙も魏から持ってきているかもしれない。とすれば卑彌呼だって何かを書きたくなるだろう。
書物は伝えたいことを残す手段である。しかし、それだけではない。書物は文字と絵を、時空を超えて、包み込んでいる、途方もなく大きな空間である。マニアは魅力のある本を目の色変えて集める。この話しは、執念を燃やした収集家に翻弄される探偵物語である。
主要登場人物
庚申塚探偵事務所
詐貸美漬(さがしみつけ) :探偵 探偵事務所所長
逢手野霧(あいてのむ) :探偵助手
吉都可也(きっとかなり) :探偵助手
夢久愛子(むくあいこ) :詐貸の大学時代の彼女、サークル仲間
嵩丸司書(たかまるししょ ):依頼人 弁護士
警視庁刑事課 捜査支援分析センター分室(第八研究室)(通称八公)
薩摩冬児(さつまとうじ) :警視、室長 詐貸の大学時代サークル仲間
世久希紅子(よくきくこ) :分析官 化学博士
宙夜 央(ちゅうやおう) :分析官 宇宙、地学
高胎蓉子(たかはらようこ ):分析官 心理学 看護師
古書羊貴(ふるほんようき ):分析官 古文書
紅酒野実(あかきのみ) :奈良県警 白バイ警官 世久の友人
秘魅古
倭國神社
庚申塚(こうしんづか)探偵事務所で、探偵、詐(さ)貸(がし)美(み)漬(つけ)がデスクで電話の応対をしている。
「はい、確かに猫犬をさがします」
「いえいえ、犬などを買うお手伝いはできません、ペットショップでお聞きになった方がいいと思います」
かなりてこずっている。
「え、主人に従順で、警察犬のような犬ですか、獣医さんにお聞きになった方がいいのではないでしょうか、はあ、ちょっと待ちください」
詐貸が、助手の吉都に手招きをした。固定電話の話口を手で押さえている。
「可也君、犬のことは詳しいんだろ」
吉(きっ)都(と)可也(かなり)は生物の大学院をでている、演劇役者をやっていて、そこに見切りをつけて探偵事務所に勤めることになった。
「いや、今の生物学は遺伝子ですよ、犬のことなら農学部の畜産か獣医関係でしょうね、最近は動物の行動や福祉を扱っている大学も出てきています」
「そういったところに知り合いはないの」
「高校の時の同級生で獣医になったのがいます。渋谷で犬猫病院をしています」
「犬の紹介などもするのかな」
「すると思います」
「電話番号わかる」
「ちょっとまってください」吉都は自分のデスクにもどり、手帳をもってきた。
「佐々木動物病院と言います、これが電話番号です」
彼は紙に電話番号を書いた。
詐貸は「おまたせしました、いい獣医さんがあります、佐々木動物病院です」そう言って、電話番号を教えた。
「いえ、いえ、料金などいりません、犬が迷子になったら探しますので、ご連絡ください」
電話を切った。
「まったく、何で探偵事務所に飼いたい犬を探してくれなんて言ってくるんだろう、犬猫を探すのが上手な探偵事務所だとさ、勘違いしてる」
詐貸がむくれている。助手の逢手(あいて)野(の)霧(む)は笑うのをこらえている。逢手は図書館勤めをやめて、この探偵事務所に入った。
「誰だったのです」
「わからない、三角歯医とか言っていた」
詐貸はその後、急に二人に話し出した。
「おもしろい事件があるよ」
大正終わり頃に書かれた、江戸末期の奇妙な出来事をまとめた本に載っていたことのようだ。詐貸美漬がこのような話をするのは珍しい。自分のデスクに戻った吉都は三角の顔をびっくりしたように詐貸に向けた。野霧のふっくらとした顔が振り向いた。
「墓から骨が盗まれる事件が昔あったんだ」
「いつごろですか」
「昭和1年頃」
「それ、北原北明の明治大正綺譚珍問大集成じゃないですか」
「いやちがう、手書きのものを製本してあって、誰が書いたのかわからないやつ」
「どうしたのです」
「古本屋で見つけたって、知り合いが貸してくれた」
吉都可也は口をとんがらして三角の顔をPCの画面に向けながら、
「変なことが起きるのは、昔も今もかわらないのですね」とうなずいている。
「先生がそういう本を読むのは珍しいですね」
詐貸が読む本といったら探偵小説しかない。野霧の不思議そうな顔がああそうかと納得の顔にかわった。
「うん、知り合いが読んどけと言ったんだ」
「愛子さんでしょう」
「うん」
詐貸の大学時代につきあっていた夢久愛子は探偵小説の翻訳家になっている。数年前、この庚申塚探偵事務所に北京原人の頭骨を探す依頼がきた。結果は、骨がみつからず、収集家の集めた変わった頭骨の発見につながった。依頼人が夢久家の関係者で、詐貸は愛子と十何年ぶりに再会した。
野霧が「はっきり言えばいいのに」小声で言うと、可也が声を出さずに笑っている。
詐貸がにらんでいる。
「それでどんなことが書いてあるのです」
野霧の質問に、詐貸は書いてあることを二人に話した。
その老人は浅草の実生(みしょう)寺で子供たちに字や歴史を教えていた。実生寺の住職である草休和尚はその老人、不同(ふどう)の兄である。長男の草休が寺を継ぎ、次男の不同は書家となった。実生寺の隣にあるかなり広い家に住み、若い頃はそれなりに名の知れた書家で、城からの依頼で書を納めたりもしていた。
ある日、不同は紙屋で紙を頼んだ帰り道、足を引きづっている、生まれてまだ一才になっていない子犬に出会った。彼が五十半ばになろうとしているときのことである。犬は腹が減っているとみえて、右の後ろ足を持ち上げたまま、片足でよろよろと不同についてきた。不同は動物が好きで、猫が三匹ほど家にいる。犬は飼ったことがない。とうとう家までついてきたこともあり、残った飯に残った味噌汁をかけて犬の前に置いた。犬は嬉しそうに不同を見上げ、がつがつとあっという間に食ってしまった。おとなしそうな優しい目をした茶色の犬である。飼っていた猫の筆、墨、紙もでてきたが、犬に背を丸めるようなことはしなかった。動物同士、性格はよくわかるのだろう。飼ってやるか、と意を決めた不同は縁側の下にむしろを敷いてやった。
その頃、不同は屏風に字を入れる仕事を頼まれていた。そんなことから、その犬を屏風と名づけた。屏風と呼ぶと、尾っぽを振って嬉しそうな顔をする。
不同は娶ることをしなかった。決して女に興味を持たないわけではない。旅などに出れば女を買ったりもした。だが、と不同は犬を見て思った。女は尾っぽを振らないものな。ないものは振れないが。猫だって尾っぽをいつもパタンパタンさせて不同を楽しませてくれる。犬はちょっと振りすぎだが、かわいいものだ。木の上に止まっている鳥を見ていたって、ぴょこぴょこと尾っぽを上下させている。不同はかわいいものが好きなのだ。女に尻尾があったら、かわいい嫁をもらっていたことだろう。
不同は六十と長寿だった。不同が死んだのは犬の屏風が家に来て五年目のことでああった。屏風は猫とも仲が良く、不同にかわいがられていた。不同のいなくなった家には兄の草休の娘、栞が婿をとり住むことになった。婿は商家の出であったが、比叡山に修行に行き、僧となった。田休(でんきゅう)と名のり草休の跡を継いだ。
栞は子どものころから、不同に書を習い、学問に通じていたこともあり、女性でありながら、不同と同じように子供たちに書や歴史を教えていた。当時として珍しいことである。
犬の屏風や残った猫たちは、栞や田休にもかわいがられた。
不同の死から二年の歳月が流れた。長生きした草休が、年が明けると亡くなった。栞と田休は不同の家から住職の住まいに移った。不同の家は寺子屋として使うだけになった。屏風も猫たちも住職の住まいの方に移された。
犬の屏風もいい年になり、寺の墓の脇にある、住職の住まいの縁側の上で一日寝そべっているようになった。ただ、日のいいときには、一日に一度は不同の家の庭に散歩に行った。栞が教えている子供たちがくると、鼻の頭をなでられ、気持ちよさそうに縁側にねそべり、子ども達が勉強しているのを眺めていた。
その年の八月、不同のたち日だった。朝、住職の田休が寺男と墓地の掃除をしていたときである。不同の墓が掘りかえされていた。これは大変と墓守に調べさせたところ、崩れた棺桶から骨の一部が持ち去られていた。
これは野良犬か獣のたぐいがやったことだろうと、土をかぶせ丁重にもとにもどした。ところが、次の朝もまた不同の墓が掘られていた。獣は新しい墓があると、食べるために掘ったりはするが、二年もたった墓を暴いたりはしない。今まで、この寺ではそのようなことはおきたことがない。墓守に調べさせると、墓には不同の頭骨だけ残っているという。ともかく、もう一度埋め直し経をあげた。
そして次の朝、またもや不同の墓が荒らされ、残りの頭骨もなかった。
番所に届けたが、そのようなことにまで調べには来てくれない。田休も盆の用意に忙しいこともあり、不同の墓の件はそのままになってしまった。
それ以後、墓が荒らされることなく、何事もなく過ぎた。
秋の風が吹き始めたころ、犬の屏風がものを食べなくなった。もうそろそろお迎えがくるだろうと、栞も田休も柔らかいものを与え、大事にしていた。足下がおぼつかなくなったにも関わらず、毎日屏風の不同の家に入っていく姿が見られた。
月が煌々と輝く満月の前日、月見の用意をしていた栞が縁側にいつもいる屏風がいないことに気づいた。時々庭に出たりしているので、気にしなかったが、次の日、餌を用意したのに屏風はいなかった。
どこかで倒れているのではないかと、心配になった栞は寺男たちと境内を捜した。田休も一緒になって探したがみつからず、不同の家にまで捜しに行った。
庭や縁にはいない。戸は閉まっており、中に入ることはないと思い、家の周りをまわってみると、台所の引き戸が少し開いていた。鍵をかけるようなことをしていない。犬も戸を開けることがあると聞く。もしやとも思い、上に上がった、子供たちを教えている広間に行ったが屏風はいなかった。
広い家の中を探し回った。はずれにある不同が寝所として使っていた小さな部屋の戸が少し開いているのに気づいた。不同が亡くなってから、その部屋は物置にしている。
戸を開けた栞と田休は驚きのあまりその場にたちすくんだ。
荷物の隙間に、人の骨が人の形にならべられていた。その脇で屏風が寄り添うように息絶えている。
栞は涙が出てなにも言えなかった。
不同の骨だ。墓を掘り起こしたのは犬の屏風だったのだ。主人の骨を主人の寝室に運んで寝かせた。そしてその脇で自分も死んだ。
その後、不同の骨は改めて墓に埋められ、屏風も一緒の墓に入れて供養されたということであった。
聞き終わった野霧はしょんとしている。屏風の気持ちになってしまっている。詐貸がこんなに長く話をするのも珍しい。
「詐貸先生話すのうまいですね」
可也が驚いている。詐貸は口数が多いほうではない。いや無口である。
「先生は犬派ですか、猫派ですか」
詐貸が、黙って寝ている猫から、いきなりよくほえる犬になったみたいに感じたからだ。
「可也君はどうなんだ」
「猫です、好き勝手にしているから」
「俺は、生き物はにがてだ」
心配性で、動物を飼ったらべたべたになる人なんだ。だから飼えない。結婚もできない、動物も人間もほっとくのがいいのよ。野霧は詐貸を見た。
そこにまた電話がかかってきた。詐貸が受話器を取った。
電話に向かって「難しいですけど、お話はうかがいます、今日の午後一時ならかまいません」と言っている。
また捜し物の依頼だ。変な電話のようだ。声の調子で分かる。
詐貸の庚申塚探偵事務所は何でも探し出すことで有名だ。詐貸は愛子の実家の会社の顧問弁護士も引き受けており、小さな捜し物の依頼は受けるが、大きな事件はよほどでないと引き受けない。
「依頼ですか」
野霧がきいた。詐貸が椅子からたって野霧と可也の机のところにきた。
「先祖捜しの依頼だ、高名な弁護士と同じ名前の人からだ」
「どういうことなんですか」
「自分の先祖が関わっていた神社について調べ、どのようなことをしていたのか知りたいそうだ、神社の場所は知多の半田」
「知多半島ですか」
「そうらしい、神社はもうないそうだ、その神社の神主について知りたいそうだ」
「さほど難しい話ではないですね」
「わからんな、あの弁護士だとすると、自分でも調べたけどわからなかったから、頼んできたのだろう」
「出張できますね」
二人はその方が楽しみのようだ。
「依頼人は一時にくる、昼飯をくっておこう」
三人は事務所を出た。少し歩くが、庚申塚近くの蕎麦屋、ひさごに行った。一日七十食しか作らない手打ちそばが目当てだ。七人でいっぱいになるカウンターしかない店である。
「らっつしゃい、久しぶりだね、詐貸さん」
「ごぶさたしています」
「今日は山形、酒田の蕎麦だよ」
「山菜があるんですね」
山菜は店主が自分で茨城のほうに採りに行く。
「あるよ、昨日採りに行ってきた」
「あたし、それお願いします」
「僕も」
三人とも山菜蕎麦になった。
「マスター、犬飼ったことある」
野霧が聞いている。
「猫がいるけど、犬はないね、犬も猫も好きだけど、犬は主人の顔を見るから苦手だね、好き勝手にしている猫の方がいいよ、身勝手だって猫を嫌う人がいるけどな、あれが動物として正直なんだ」
野霧も可也もうなずいている。
「詐貸さんは動物飼っていないの」
「うん」
「そうか、一人もんだよね、探偵だと家に帰れないこともあるから無理だよね」
「それもあるし、動物はにがてなんだ」
「そう」
主人は蕨、タラの芽、ゼンマイを油からあげると、三人の前に置いた。塩をつけて食べる。その後にゆでたての蕎麦がでる。
三人は満足して事務所に戻った。
野霧はデザートに買ってきた雪見大福を食べている。可也はPCを開いて知多半島を見ている。
一時少し前に茶色の背広を着た、貫禄のある男性が事務所に入ってきた。新聞で見たことのある顔だ。
その男は「お電話した嵩丸です」と、入り口で直立不動になった。
「どうぞ」と野霧は立ち上がってソファーを指さした。こんな改まった依頼客は初めてである。どこか演技じみてはいるが。
詐貸がソファーに腰掛けると、客は笑顔になり、再びゆったりと立ち上がって、
「詐貸先生には前からお会いしたいと思っておりました」
名刺を差し出した。受け取った詐貸はちょっと緊張した。やっぱりあの有名な弁護士だ。また変な依頼のような予感がする。
弁護士、嵩(たか)丸司所(まるししょ)。今世間を賑わしている事件の担当弁護士だ。
「詐貸です」
詐貸も名刺を出した。客は腰を下ろすと話し始めた。
「詐貸先生の評判はいろいろなところで聞いております。若くして国家試験を通り、何でも解決するということで、私などと違って、広い世界に生きておられる」
大仰な言い方だ。
「弁護士で探偵という方は詐貸さんしかこの国にはおりませんで、お願いにあがりました」
むしろ詐貸の方が近づくこともできないような高名な弁護士だが、見かけよりづーっと腰の低い人だ。この人なら依頼を聞いてもいいかもしれない。
「先生ほどの世の中に知られた弁護士はいないと思います、私などに何ができるのですか」
「私の祖父は鎌倉に住んでおり、金貸しというどうしょうもない商売を営んでおりました。しかし決して高利で金を貸したりせず、漁民が船を必要なときには船を造って引き渡し、ほんの少しの利子をつけ、すこしずつ返済してもらう、言うなれば銀行のようなことをやっており、神社仏閣の修理の費用なども、立て替えたりしてもおりました。
父は市役所勤めでした。私は鎌倉で育ちましたが、弁護士になってから鎌倉から離れました。曽祖父や祖父はとっくに亡くなっておりますが、一年前父が死に、残された書類などを整理していましたところ、先祖が知多の土地持ちだったことがわかり、祖父の代からだと思いますが、鎌倉に移ったようです。どうして鎌倉に移ったかわかりません。祖父は先祖からある土地のすべてを売り払って、鎌倉に住んだようで、それ以外はよくわからないのです。
先祖は半田にある倭國神社の氏子代表をしていたこと、神社が燃えて消失し、そのこともあってかわかりませんが、鎌倉に出てきたようです。神社に関する書き物はないのですが、なぜか倭国神社のご神体というものが我が家にありました。よほど縁の深い神社だったのだと思います、それでこの神社と祖先の事が知りたくなったのです」
嵩丸はもっていた風呂敷をほどいた。今時風呂敷とは珍しい。
「嵩丸さん、二人を同席させていただいていいですか、三人で出来ないことでしたら、お断りしたいと思います」
二人に調査に行ってもらうことになる。聞いておいてもらわなければならない。
「どうぞどうぞ、この探偵事務所には優秀な助手の方たちがおいでのことも聞き及んでおります、どうぞよろしくお願いします」
嵩丸は野霧と吉都に向かってお辞儀をした。
二人が詐貸と並んでソファーに腰掛けると、嵩丸は風呂敷の中身をだした。
黄色くなった新聞紙に包まれた長方形のものがでてきた。嵩丸は新聞紙を破らないように丁寧に広げると、中から板を取り出した。
幅三十センチ、長さ四十センチ、厚さ一センチほどの木片である。よほど古いものであろう、色が飴色になっている。
「私も父が死んではじめて見たものです」
木片には日本のような地図が書かれている。
「このご神体はいつ頃のものかわかりません、包んであった新聞は倭國神社が燃えたときの地方紙で、そのことがのっています、一九三八年八月七日でした、木片はもっともっと古いものだと思います」
「それで、何を調べたらいいのでしょう」
「神社の歴史を調べて頂くと、うちの先祖の事もわかると思いまして」
「神社の神主さんや、他の氏子の方を調べればわかると思いますが」
「それが、氏子はもういないようで、それに、神主さん夫婦もいないのです」
「どういうことでしょう」
「この新聞に載っていますが、神社は隕石が落ちて燃えてしまい、神主さんと巫女の奥さんが亡くなったとあります。名前が出ていますから、市役所で調べればはっきりすると思います」
「それで、このご神体はどうされたのです」
「神棚の裏にあったのです、どうして、うちにあるのかわかりません」
「この木に書かれている地図の赤い印のあるところの意味は御存じなのですか」
炭のような黒でかかれた地図に、かすれた赤い丸が何カ所ある、おおよそ、九州の福岡か大分、山口と萩、奈良か三重、愛知の半島、島根、静岡、鎌倉 富山あたりだろうか。
「いえ、全く分かりません」
「遺跡なんかがありそうな場所ですね」
「そうです、いったいこれは何の場所を示しているのか、知りたいことの一つです」
「歴史学者にあたったほうがはやいですよ」
と、野霧が口をはさんだ。
「歴史学というのはなかなか決定的なことを示してくれることはありません、よほどはっきりした証拠がない限り、みな推測です、それでしたら、探偵さんの推測の方が正しいかもしれません」
ずいぶん飛躍した理論だと詐貸は思った。
「この赤い丸のある場所がどのような意味を持つかわかりませんが、倭國神社にかかわりのある場所かもしれません、とすると、我々嵩丸の家も関係するかもしれません」
「この地図の愛知あたりの赤丸は知多半島のどこかと考えていいのでしょうね」
「そのようですな、おそらく倭國神社のあるところだと思います」
またもやもやもやした頼みごとだ。
「我々ではなかなか解決できそうもありませんが」
「いえ、是非にお願いしたいのです、時間のあるときでけっこうですので、何も出てこなくても構いません、調べていただけないでしょうか」
「その神社の由来などが書かれたものはないのでしょうか」
「父のもっていたものの中にはありませんでした」
吉都が聞いた。
「この板は何年前のものか専門家に聞きましたか」
嵩丸は首を横に振った。
「まだ、なにも手つかずです、仕事の方もあるもので」
「知っております、あれは国選ですか」
「ええ、そうです、ご存知の殺人事件です、ちょっと複雑で、弁護も難しいところにありまして」
「そうですか、この板の年代を調べてもらっていいですか」
「ええ、お願いします」
炭素の同位体組成を調べることで年代はわかる。
「嵩丸さんの家系図はありますか」
「家系図はないのですが、父がとってあった本籍の謄本がここにあります」
彼は鎌倉市役所名の入った袋をとりだした。
「父の名は嵩丸祈(き)切(せつ)、祖父は嵩丸於(お)爾(いじ)です」
「おあづかりします」
「あと、神棚に古い紙がありました。鎌倉の家の神棚は祖父が作ったものですので、おそらく倭國神社の祭神を祀ったものだと思います」
「何が書いてあるのでしょう」
「氏子代表、嵩丸家としかありません、実は祖父も父も、鎌倉で神棚に灯明を上げるとか、拝むとかしていたのを見たことがありませんでした、おそらく知多から移ったときにはもう信仰心は薄れていたのではないでしょうか」
「嵩丸さんはその倭國神社の場所に行かれましたか」
「はい、一度行きました、神社は基礎が残っているだけです、小さなものです」
「わかりました、倭國神社のことは調べるのにそんなに時間はかからないと思います。ただその板の印に関してはどうなるかわかりません、それでよろしければお引き受けします」
「お願いします、費用として、このお金をお使いください」
嵩丸弁護士は分厚い封筒を詐貸に差し出した。
「いや、規定料金がありますから後で請求します」
「それでは、このお金をお預けします、それぞれの領収書はいりません」
「いくらはいっているのですか」
「二百万あります」
「そんなにですか、それでは預かり証をだします」
野霧が証書をもってきた。嵩丸は受け取ると、礼儀正しくお辞儀をして、「急ぐことではありませんので宜しく」と出て行った。
詐貸はまたかといった顔をしている。
「まいったな、まあ、二人に頼んでいいかな、半田には行かなければならないな、連休明けにでもに行ってちょっと調べてよ、神社と神主の戸籍をたのむよ、何度か行ってもらう事になるかもしれないな」
「はい、行ってきます」
二人とも飛び回るのは好きだ。
「この板と書き付けは、写真を撮ったら、金庫に入れておいてよ」
「はいやっときます」
吉都が立ち上がった。
「どのような神を祀った神社なのでしょうね」
野霧がつぶやくと、吉都は、「さっきネットで見たけど、でできませんでした」と答えた。
「さて、頼まれたご神体の年代測定はどうしようかな」
「僕が知り合いに頼みましょうか」
「可也にいるの」
「科学博物館に勤めた知り合いがいるんです、生物の進化に興味を持った奴で、本来は遺伝学をやってたんですけど、遺伝子の変化をダイナミックにとらえたいといって、古生物学を学びなおし、科学博物館で非正規助手を長くやってたやつです。最近ようやく正規の研究員になったんです。化石も扱っているので、炭素の同位体で年代測定ができる人を知っていると思います」
「そりゃあ、助かるな、解析たのめるかな、かかる費用はだすから」
「きいてみます」
次の日、科学博物館の知人のところに、ご神体の板をもっていった。
板は胡桃の木であることを聞いてきた。
次の週、野霧と吉都は半田に向かった。倭國神社は近鉄の知多半田駅から歩く。名古屋で近鉄に乗り換え、知多半田まで三十五分。二人は3泊ほど半田に滞在する予定だった。その間に詐貸は顧問弁護士を引き受けている富山の会社に行ったり、ご神体の板の写真を愛子に見てもらったりするつもりだ。
愛子はノールウェーの幻想推理作家の本を訳している翻訳家である。翻訳を続けながら、推理小説も書いていているようだ。もう二年も前になるが、詐貸が巻き込まれた愛子の一族の奇妙な物語である。大学時代二人ともミステリークラブにいて、分からないことがあると、意見をもらったりする。
野霧と可也が半田に行った次の日、詐貸は渋谷の喫茶店で愛子に板の写真を見せていた。
「これ何の木なのかしら」
「吉都に調べてもらった、樹木の専門家が胡桃じゃないかと言っていた」
「胡桃って寒いところの方が多いんじゃない」
「そうなのか、とすると、寒いところで作られたのかな」
「でも暖かいところにもないわけじゃないし、逆に暖かい地方では貴重だから、手に入れてご神体にしたということも考えられるわよ、それに昔は関西の方もかなり寒かったんじゃないかな」
「そうか」
「半田ってどんなとこ」
「愛知、名古屋の豊田の先の知多半島、国際空港に近いところ、歴史があるようだな、今じゃ自動車会社でもっているようなとこじゃないのかな」
「当時はどうだったのかしらね、海にしろ空にしろ、物を運ぶのにべんりなとこだったのかしらね」
「野霧と可也が行ってるから、何か見つけてくるよ」
「あなたは行かなかったの」
「うん、明日富山にもいかなければいけないし」
「彼女達だから、もう報告がきているでしょう」
「うん、彼らからの連絡では神社のあったところは、まだ神主の娘の土地になっているようだな」
「そこ掘ったらなにかでるかもね」
「そうだなあ」
二人がそんな話をしているときに、野霧と可也は半田の市役所や、昔から住んでいる人から、倭國神社の情報を集めていた。
野霧と可也が半田から明日帰ってくるという日、薩摩から会わないかという電話が詐貸にかかってきた。二週間前に東京の警察の官舎に入ったという。薩摩は詐貸の大学のミステリーサークル仲間で、宮城警察の刑事部長だった。宮城での事件を詐貸たちが解決に導いたこともあり、薩摩とはよく連絡をするようになった。今度、宮城県警から警視庁に異動すると連絡を受けていた。
その日の夕方、高田馬場の飲み屋で会うことにした。詐貸が駅に着くと、薩摩は大きな体を駅の柱にもたれかからせて改札口を睨んでいた。
「おーい」
詐貸が改札口をでると、薩摩が手を挙げた。手を挙げなくても十分いることがわかる。存在感まるだしだ。あれでは尾行などできないだろうな。刑事にも見えない。どこかのおっさんだ。
「馬場もずいぶんかわっちまった」
「うん、そうだな、人は多いしね、大学の正門にいく都バスはドル箱路線だってよ」
「ふーん、どこにいこうか」
「その辺にいくらでもあるよ、ちょっと裏にいこう」
「昔この近くに旨い餃子屋があったな」
「むろ、だろ、もうとっくにないよ」
詐貸は駅の前の道を右に折れて細い道に入り、一軒の飲み屋に案内した。
「ここの大根の煮込みは数が限られているんだ、うまいよ」
詐貸が適当に見繕ってくれるように店の人にたのんだ。
「ビールでいいかな」
薩摩がうなずいたので、大ジョッキをたのんだ。
「栄転おめでとう」
すぐに運ばれてきたビールを詐貸がもちあげた。
「よせやい、なんだかわからないところに来ちまったんだ」
「刑事部長の次はなんだい」
「警視ってやつだけどな」
「警察の組織はよく知らないんだ、薩摩は地元仙台の警察の試験を通って入ったんだろ」
「いや、違うんだ、公務員試験を通って、最初警視庁にはいったんだ、キャリア組さ、五年ほど品川の警察にいたんだよ」
「俺が、探偵を始める頃だな」
「それで、仙台の方に人が欲しいという話があって、地元だから志願したら行かせてくれたんだ、自分の家があるもんな、まさか戻ってくるとは思わなかった」
「なんか、警視というととても偉そうだ、キャリア組ってなんだい」
「公務員採用一種試験に通って、警視庁の警察官になったやつらのことさ」
「薩摩もそうなんだ」
「そういうことになるが、ノンキャリアの連中のほうが力があるよ、そう言う場面にずいぶんでくわした」
「そんなもんかな」
「俺の入ったのは、刑事課ではあるけど、表に出てこない部署の一つで、そこの室長てやつだ、奇妙なところだ」
「何という部署なんだい」
「名前がないんだ、科学捜査室の隣の捜査支援分析センターだ、そのまた分室と呼ばれるところでな、八号室なもんで第八研究室というところなんだ」
「それでなにをやるの」
「捜査支援分析センターは基本的には、画像解析や、コンピューター解析を行って、刑事や科学捜査室の連中にデーターを提供するところだけどな、俺の担当の分室はどうしても通常の考え方では解決できない事件を、分析官で解析し、必要に応じて専門家を呼んで、解決の糸口を探すわけだ。刑事課の連中にアドバイスしたり、地方の警察に情報を提供したりする頭脳集団のいる部屋だ」
「まだ、よくわからないな」
「簡単に言えば、エックスファイルだよ」
「あの宇宙人捜す奴か、モルダウとスカリーがいるんだな」
「スタッフは俺をいれて五人、超常現象を解析するところじゃないが、そういう場合もあるようだよけど、主におかしな事件をあつかっている。今までにかかわった事件を見ると、偏執狂によるものが多くて、事件としては大したものじゃない。殺人にまでいたるようなものは少ない。最近の例では、幼児の誘拐事件がある。何件かおきたんだが、幼児はなにごともなく戻った。誘拐犯人は捕まったが、男は幼児が涎を垂らすのを見て、性的な興奮を覚えるやつだった。涎を見て自慰をしていたということだ。刑事課では最初、性的な女児の誘拐とみて、今までの犯罪者やその線での聞き込みなどしたが埒があがらず、第八研究室に相談がきた。スタッフは、誘拐された中に男の幼児もいたし、ただの性的な問題じゃないだろうとにらみ、母親から聞き取りをして、その子供たちが普段からよだれをよく垂らすということを聞き込んできた。精神科や泌尿器科の医者の意見を聞いて、性的不能者によるものと考え、絞っていって、犯人に至ったということだ、よだれを見ると性的に興奮するやつの仕業だった」
「そんなやつもいるんだ」
「俺にはそんなの向いていないよ、前任者も他のところに移りたくてしょうがなかったようだ、長くいたので希望通り移動させ、空きを何とか埋めようと、仙台での三つ子死体紛失事件を解決したから移れということだったようだ」
詐貸たちが助力をした事件である。
「だけど、いつかまた仙台にもどるんだろ」
「そうしたいけどね」
「スタッフはどういう人」
「若くていいよ、それぞれ専門をもっている、みな科学的な思考をもっていてコンピューターのベテランだし、明るくてね、SF、ミステリー、歴史、アートそんなのが好きな奴が集まっていて、昔の変な事件のことなんかよく知っているんだ、出身は化学、地学、文学、医療などいろいろさ、キャリア組みの俺なんか何にも役に立たないよ」
「周りの人間がいいならいいじゃないか」
「そうだな、それで、刑事課や公安、生活安全課などから、今起きている事件のリストがメイルで回ってきているんだ、意見を言ってほしいわけだ。スタッフはそれの中から、これはと思うのを選んで、調べて意見を張り付けて返信する、それぞれのところでは、それを犯人探しなどに役立てるというわけだ」
「みんな頭のいい連中なわけだ」
「そうだな、男二人女二人だ、楽しそうだよ、それでね、変な事件がいくつかピックアップされててね」
「どんなの」
「女が誘拐されてね、だけど一晩で無事に戻るんだが、どうも何かをされているらしいということだ、性的なものではなく、着ていたものが一度脱がされているようだと言うんだ」
「持ち物はとられていないの」
「うん、それどころか、十万の札が自分の手提げに入れられているのだそうだ」
「どんなことが考えられるのだろうね」
「我々は今、鑑識でその女性たちの皮膚に何かついていないか調べている」
「女性たちって何人もいるの」
「いまのところ、五人かな」
「共通点はあるの」
「みんな美人といえるな、均整がとれている、職業はばらばら、芸能関係とは無関係な堅い職業に就いている女ばかりだ、年は三十近くから四十の間」
「若い子じゃないんだな」
「人生の脂がのってる」
「場所はどこなの」
「富山」
「都内じゃないんだね、それじゃ富山警察の管轄だろう」
「そうだけど、日本国中のそういうおかしな事件の相談が持ち込まれるんだ」
「大変だね、その女性の誘拐はまだ起きてるの」
「いや、最後は俺がここにくる一月前の事件で、それからはないね、誘拐された女性はまだ気味悪がっているそうだ」
「だろうね」
「そういったのがあってね、相談するようなことがあると思うけどよろしく頼むよ」
「なにもできないけど、話はいつでも聞くよ、そのうち事務所の方にも来いよ」
「うん、行ってみたいね、あの二人にも会いたいね」
野霧と可也のことである。
野霧と可也が九州からもどってきた。写真のデータや電子化できるデーターは、詐貸の手元に随時送られてきていたので、見やすいように項目別にフォルダーにいれてある。
「名古屋から近鉄で三十五分かかりました。以外と遠いですね」
「いいとこだった」
「ええ、半田は海に近いし大昔にはなにかあったのでしょうね、新見南吉がでたところですよ」
「誰それ」
「ゴン狐、を書いた人」
「あ、あの童話の、反省したいたずら子狐を殺しちゃう悲しい奴」
「所長よく知ってるじゃないですか」
「うん、子供の頃うちにあって読まされた」
野霧と吉都が顔を見合わせた。なんだか詐貸所長とゴン狐が重ならなかったからだ。
「倭國神社の跡は基礎石があるだけのようだね、いつ頃建てられたのかな」
詐貸は写真をすでに見ている。
「三、四百年ほど前かもしれません、江戸時代です。燃えた神社の基礎はそのままになっていて、境内にあったと思われる胡桃の木や椿の木が大きく茂っていました」
「そこを掘ることは可能なのかな」
「市役所で調べました。まだ神主の月足の名義になっていました、娘はどこにいるのかわかっていないようです、地主に連絡がつかないというよくあるやつです」
「神主さんの事も調べました、名前は月足陽司、奥さんの月足久遠は巫女をやっていました、神体を包んでいた新聞にあった通り、神社が燃えたとき亡くなっています」
娘はしばらく知多で関係者に保護されて暮らしていたようですが、関東の誰かのところに引き取られたようです、半田では大きな地主だったようですが、神社のところ以外はすべて売り払われ、その金と供に移ったようです。関東での居所はわかりません」
「大きな地主さんだったなら、地元の人と関わりがあってもいいのになぜだろう」
「氏子に守られていて、あまり周りと関わらなかったようです」
「半田の郷土史などにはでてないのかな」
「市役所や図書館で郷土史のことを聞きました。いくつもある郷土史に全く名前が出てきませんでした、祀っている対象が、知多の町の人の信仰となるものではなかったのだと思います、それも周りとあまり関わらなかった理由ではないでしょうか」
「かなり個人的な宗教の神社なんだな」
「そのようですね」
「氏子たちはどうなったのだろうね」
「神社の近くに氏子たちが集まって住んでいたところがあったそうですが、神社が燃えてからは、散りじりになったようです」
「神主の戸籍はみせてもらえたの」
「はい、市役所に行って、神社の歴史を知りたいと話をして、弁護士の嵩丸さんに話を聞いてきたと言ったら、古い戸籍簿を特別に見せてもらえることになりました、嵩丸家はその昔知多の名士で、半田にもいろいろ功績があった人のようです。嵩丸弁護士も氏子の代表と言っていましたよね、きっと嵩丸家が神主一家を守っていたのではないのでしょうか。月足の土地の処分や、一人娘を関東にやったのも嵩丸家の人だった可能性もあります、そんなことでご神体の板も嵩丸家にあったのではないでしょうか」
野霧が戸籍の写しを広げた。
「倭國神社の神主、月(つき)足(たり)陽司(ようし)は入り婿で、移籍前の住所が名古屋の千種区になっていました、両親の名前がわかりませんでした、陽司の前の神主は、妻である久遠の父、久(こう)爾(し)です、久遠は一人娘だったわけです。
久遠の母の名は永野(えの)、久爾も入り婿で、岐阜から来ています。やはり両親の名はわかりません。永野は半田のその神社で生まれ一人娘です。おばあさんは日魅(ひみ)といいます。八人姉妹の末っ子です。末娘が倭國神社をついで婿をとっています。姉妹のあとの七人はどこかに嫁に行ったのでしょう。おじいさんの名前は政司(せいし)、わかったのはそこまでです。ただ、戸籍簿の月足のところに、倭國神社と書いた古い紙が挟んであって、日魅の母は日女(ひめ)、その母は八女(やつめ)と名前だけわかりました。八女に初代とありました。おそらく、八女が神社の出来た時の最初の神主か巫女という事でしょう、代々娘が神社を受け継いでいることが推察できます。戸籍簿類はみなコピーしてありますので、嵩丸さんに見せることができます」
「それはいいね、だけど、どの代も父親の方の素性がはっきりしないわけだ、女系で神社を維持しなければならない理由があったのかもね」
「先生さすがですね、そう思って、倭国神社の由来を市役所をはじめ、図書館などで調べてきました。郷土史家の方ともお話をしてきました」
「少しはヒントがあったの」
「ええ、倭國神社の氏子たちは、日本国の歴史をよく議論していたということです」
「大昔のことなのかな」
「大昔は中国の魏の国から日本は倭の国と呼ばれていました、だから単純に考えれば倭国神社は日本の国の神社となります。日本の神話からすれば、日本を作ったのはイザナギ、イザナミの二人の神、イザナミが矛を海をかき回して日本をつくりました、いいかんげんですね」
野霧にそう言われても、吉都と詐貸は曖昧にうなずくしかない。
「それは古事記や日本書紀の神代の話しで、伊勢神宮や日本の神社はそこにでてくる、イザナギ、イザナミの子供たち、天照大神などが祀られているわけです。しかし、それより以前の日本のことは中国の書にあり、それでわかる程度です。そのころ神社というものはなかったのでしょう、しかし崇拝されていた、自然、または権力者は神のような存在で、地方それぞれにたくさんあったものと思います」
「古事記や日本書紀はいつごろの本なの」
吉都はそう言う本をまともに読んだことがない。
「古事記、日本書紀は七百年代、それにたいして、中国には三世紀に歴史の本が書かれています。三国志です。二百年代後半のころです、だから、日本は四百年もの間、倭と呼ばれていたことになるわ」
「日本には誰がいたの」
「代表的なのが卑弥呼よ、魏の国から親魏倭王、倭の国王という称号をもらったんだから」
「ああ、そうか、金印をもらったんだっけ、国宝だよね」
吉都が口を挟んだ。
「いや、違うの卑弥呼に送ったことが書かれているけど、まだ出土してないの、でれば邪馬台国もはっきりするでしょうけどね」
「あの国宝の金印はなんなの」
「漢委奴国王印、筑前の那珂で発見されたもの、紀元前200何年かのものだから、卑弥呼より前に、九州の国が漢の国と関係があったわけね」
「あの木の板にかかれていたものに、言葉は書いてなかったけど、倭国神社は古事記に由来する神さんじゃないとすれば卑弥呼あたりが妥当だね」
「先生、その通りです、古事記などに由来する神の神社が平安時代ころから作られるようになったとすると、それとは関係ないものを信仰していた人たちは、めだたないように、自分たちの神社をつくったのでしょうね」
「だけど、卑弥呼の時代から、日本に言葉があったの」
「卑弥呼は弥生時代後期にひっかかるほど古い時代の人なんです、そのころはいわゆる原始日本語で、朝鮮語などの系列の言葉だったのではでしょうか、文字があったかどうかわかりません」
吉都が野霧が訊いた。
「卑弥呼のころ宗教はあったの」
「宗教はどうなのかな、卑弥呼は巫女であり、呪術師だといわれています、鬼道といったらしいけど、卑弥呼は自分を民に崇拝させるように、うまく立ち回っていたのでしょうね、ということは政治を司るのに宗教的な要素が重要だった」
「なんで木の地図がご神体なのだろう」
「半田に倭國神社を開いた人たちが決めた物ですから、その時の理由があったのでしょうね、そうなると、卑弥呼のような昔のものではないですね」
「そうか、木が古くても、書かれたのは後かもしれない」
「そうですね」
「気になったのは、久遠のおばあさんの日魅が、八人姉妹の末娘なのに跡を継いでいるけど、あとの七人の姉妹はどうしたんだろうね」
「その辺も知る必要があるかもしれませんね」
「女系の神社なら、分家でもしたのだろうか」
「でも、末娘が本家を継ぎますか」
「そうだね、そこも気になるところかな、ともかく、久遠から五代目まではおえたわけだ、しかも女系の私的な神社ということが分かった」
「最後は宗教法人にはなっていました。倭國の復活を信じていた宗教なのでしょう、ただ、登録には三人の役員が必要ですが、神主さん、巫女さん、それに嵩丸羅刹と言う人でした、代表は巫女さんの久遠さんになっていました」
野霧の後を可也が引き継いだ。
「嵩丸羅刹を調べてみました、しかし半田市にはその名字はありませんでした、知多市にあるということでしたので行ってみました」
「知多市ってどんなこ」
「半田市の隣で、反対の海の方です、国際空港に行く線が走っているところ、古い町ですよ、半田からは車を使わないと、名古屋方面に一度戻ってから別の線に乗り換えて行くことになります」
野霧が補足した。
「それで、知多市にその人はいたの」
「市役所で調べたら、高丸羅刹という人が、子供を連れて、神奈川に越していました、子どもの名は於爾でした、嵩丸弁護士のおじいさんです」
「嵩丸さんはおじいさんが知多から移ったと言っていたが、曾おじいさんが、鎌倉に移したわけだ」
「そうですね、だけど、弁護士からはその名前がでてきませんでしたね」
「うーんそうだな、嵩丸家にその名前が残っていないわけはないよな、嵩丸弁護士が知らないのは不思議だな、薩摩に嵩丸さんのこと聞いてみるかな」
「そういえば薩摩さん東京に来たんですね」
「うん、警視庁の分析支援センターの第八研究室室長、警視だよ」
「偉そう、だけどなにするところです」
詐貸は薩摩に聞いたことを話した。二人とも「Xファイルですね」と言った。
「いや宇宙人じゃなくて、変質者を探すところと言ってたよ」
「秘密クラブですね」
「それいいわね、第八研究室なら、八公、しかもお国に忠実だから、忠犬八公」
野霧が言ったら二人とも大笑い。
「薩摩に言ったらしょげるぞ」
「また会いたいですね」
野霧たちは一年ほど前に宮城で会ったきりである。
「うん、あいつもそう言ってた、一緒に飲もうか」
野霧の顔が丸く膨らみ、吉都の顔の三角の角が丸くなった。どちらも嬉しいのだ。
「そういえば、あの板の年代はいつわかるの」
「そうだ、知多に行っているときに、デスクのPCに連絡してくれていると思います。
吉都がPCを開いた。やはり来ていた。
「炭素同位元素測定で、千年ほど昔の板だそうです、炭と朱で書かれたものだということです」
「卑弥呼よりだいぶ新しいな、やはり神社が作られたときにご神体にしたのだな」
「墨や朱の年代も調べないとわからないですね」
野霧の言うとおりである。
「まあ、板が古いものであることが分かっただけでもいいじゃないか、あとは嵩丸弁護士と話をしてみよう」
薩摩との飲み会はその二日後に行われた。高田馬場の店である。
「薩摩警視、おめでとうございます」
野霧と吉都が声をあわせたので、「よせやい」、薩摩が膨れた。
「久し振りですね、みな変わらずで、詐貸事務所はいいね」
「お話は聞きました、薩摩さんの忠犬ハチ公はとても面白そう」
薩摩はそれを聞いてなんだという顔をした。
「野霧たちが言ったんだ、第八研究室だから、忠犬八公だとよ」
「ひゃ、まいったね」
薩摩が笑った。
「その節はお世話になりました、今度のところは、もっと変な事件ばかりで、みなさんにまたやっかいになると思いますよ」
「食べるのならいつでもご一緒します」
野霧は食べることにかけては誰にもひけをとらない。
みんなで生ビールの乾杯。
「嵩丸弁護士ってどんなやつだった」
薩摩はうなずいて「有名人だからな、結構すごい人だよ」と言った。
「彼はね、今六十一、評判通りいい弁護をする人だ、基本的には殺人罪で死刑確実のような人の弁護を頼まれる人でね、犯人の人物像をうまくほじくりだして、裁判官までも納得させて、刑期を軽減させる名人だね、今やっているのは死刑が求刑されている、夫殺しの女性の弁護だよ、三人も夫を毒殺しているようだが、内容が複雑なようで、美貌に誘われた夫の悪癖が、毒殺を生み出したと、崇丸弁護士は、いま奮闘中らしい」
「相当口がたっしゃなんだな」詐貸がボソッと言った。
「ネットにでてました、薬剤師の資格を持つ奥さんが、主人を毒殺したという事件ですね、読むと死刑確実と思うような内容でした」
吉都が言うと、薩摩は「犯人の動機というのは、病的な場合をのぞいて、本当のところはわからないものでね、本人にはそうする訳があったんだろうな」と言った。
「どういうことです」
「最初の夫は医者で、外からは名医と言われていたが、夜は相当変質的だったようだ、いやがることをさせられたらしい、二人目の大きな不動産屋の旦那は、もう結婚したくないと言う彼女を、半分脅しのような形で結婚を迫り、結婚をしたとたん旦那は、遊びまくった末、離婚をしたいと言った彼女に暴力を振るったらしい、三人目は彼女も普通の主婦になれると思って結婚した大学の文学の先生だったのだが、相当嫉妬深くて、彼女は精神科医に安定剤をもらい、あげくは、精神科医との間まで疑われるようになって精神的な圧迫をうけたらしい、皆外からは見えない部分だ、といって、殺すのは犯罪だ、そこを今、崇丸弁護士は奮闘しているということなのだ」
「いろいろありますね」
「どこもかしこもいろいろでね」
「薩摩刑事さんの部署はおもしろい人がいるそうですね」
「うん、おもしろいだけじゃないよ、とても助かっている、ワトソン君が四人いるようなものだ、特に女化学者はすごいよ、いつか第八研究室に来てごらんよ」
「いいんですか」
「ああ、年はみんな逢手さんや吉都さんと同じくらいかな、きっと話は合うな」
「面白そう、いつか行きます」
「みなさん飲むんですか」
「今の若い人はしゃれたものしか飲まんけど、飲めないわけじゃないようだな」
「薩摩刑事ははじめての一人暮らしなんだ」
「そりゃ大変ですね」
「ところが、ほら、ごらんよ、ゆったりした顔してるだろう、とてもいいようだよ」
詐貸がちゃかした。
「その通り、ちょっと若返った」
「愛子も会いたいって言ってたよ」
「俺もあいたいな、おまえの彼女、どうなったんだい」
詐貸がちょっと照れた。
「変わりなくおきれいですよ」
野霧が言った。
「野霧さん知ってるんだ」
「ノールウェーのミステリーを訳しているんですよ、私もミステリー大好きで、話をしました」
「俺も読んでサインをもらおう、詐貸はもちろん読んだんだろう」
詐貸はちょっと困ったような顔をした。
「うーん、もってるけど、まだなんだ、飾ってある」
「なんだ、しょうがないな、明日にでも買おう、野霧さん本のタイトルわかる」
「メイルしますね」
「おねがいします」
馬場でのおしゃべりは、仙台での事件のことから、薩摩のところに来ている、変な事件のことにまでおよび、終電になった。
嵩丸弁護士にはとりあえずわかったことをまとめて郵送した。数日後会いたいと言う打診が来た。次の週の月曜日、嵩丸弁護士は事務所にきた。
「いろいろわかりました、ありがとうございます、これ」
と言ってさしだしたのは、トップスのチョコレートケーキだ。ビターの方だ。
野霧の目がすぐにそちらの方にいった。
「すみません、まだまだ、一度の捜査であまり詳しくわかったわけではありません、少しづつ調べます」
「いや、だいぶ分かりましたね、ありがたいことです、私は私の曽祖父の名が羅刹で、半田の倭国神社を支えていたことがわかっただけでも、とても満足しています。しかも羅刹が知田を引き払って、祖父の於爾と鎌倉に越したことがわかったのはよかったと思っています。私は祖父が越してきたと思っていました。曾おじいさんが土地を売り払って鎌倉にきたのですね、その頃、羅折はいい年だったろうと思います。祖父が色々取り計らったのでしょう、倭國神社が燃えたころのことですね」
「はい、そのようです、鎌倉に移られたのは昭和十三年より後になります。倭国神社の月足陽司宮司と奥さんの巫女だった久遠の娘は日美といいますが、崇丸さんより年上になります。両親がなくなって、日美さんは東京のどなたかにひきとられています。そこまでしかわかりません、一時知多にいたようですから、やっぱり羅刹さんが関係していたのではないでしょうか、月足の半田の土地もその時処分されていますが、子供の日美さんにできる事ではありませんから」
「そうですか、すると、日美さんに家族がいれば、みな関東にいる可能性があるのですね」
「そうですね、嵩丸羅折さんがキーパーソンですね、長く倭國神社の氏子代表だったのだと思います」
「ほとんど月足一族と崇丸一族は生活をともにしていたと言っていいほどですな」
「そうかもしれません、それと、ご神体お返しします、吉都が手配してくれて、年代測定をしました、板そのものは千年経っているそうです、ただ、地図に使われた墨の時代まではわかりませんでした」
「古い板に書いた可能性もありますな」
「はい、書かれたのが神社のできたときだとすると、三、四百年前、どこからで使われていたものか、出土したものをご神体にしたとすると、もっともっと、昔に書かれた地図かもしれません、赤丸は後につけた可能性もあります」
「そうですね、神社の基礎を掘ってみるとわかるかもしれませんな」
「我々も、それを考えました」
「ともかく調査を一年の契約で正式にお願いできますか」
「はい、あまりはっきりしたデーターがだせないかもしれませんが」
「ともかくお願いします」
「担当されている事件はいかがですか、大変だと思いますが」
「いえ、淡々とやるだけです、どんな人間も悪いことをしているものです、それはしょうがない、ただその悪いことを、できるだけ他人に害のないようにするのは教育で、教育するのは親や学校の先生だけではなくて、環境そのものです、罪を犯したとしたら、環境という先生が悪いのですな、それにはもちろん親や教育のシステムも大きく関わります、教育は判断力、決断力をつけてやることで、教科書の知識を増やすことではない、死刑の判決がでたら、その人間は教育が足りなかったということで、周りにも責任がある、その分さっぴけば、死刑制度はなくなるはずですな」
嵩丸は笑った。野霧と可也は神妙な顔をしている。
「さて、それでは失礼します」
野霧があわてた。「すみません、お茶の用意をしていて、お湯をいれていませんでした、すぐもってきます」
吉都も一緒に野霧についていった。
「そうでした、すみません、お茶をいっぱいだけでも」
詐貸もあやまっている。
「そうですか、それじゃ、お茶をいただいてから帰りますか」
嵩丸はソファに越しかけ直した。
「詐貸さんは一時、法曹界から離れていらっしゃいましたな、理由はあるのですか、学生時代に国家試験を通っていたのに、大学も辞めてしまわれた」
きっといろいろ調べたのだろう。
「全く若気の至りです、だけど、弁護士も、検事も、裁判官もむきません」
「犯罪の断罪は今のAIではできません、人間的な判断を求められます。詐貸さんならいい裁判官になると思いますよ」
「面倒だからみんな有罪か無罪にしてしまうくらいいい加減ですから」
「AIにはいい、かげんができないのですよ」
二人がお茶をもってきた。さらには近くの和菓子屋の素甘がのっている。
崇丸弁護士はピンク色の素甘をとった。
「甘すぎず、だけどちょっとねちょっとし、なんともいい、かげんな和菓子だとおもいますよ」
おいしそうに食べ、お茶を飲んだ。野霧は無性に嬉しくなったようだ、顔を丸くしている。
「おいしかった、ありがとうございました」
崇丸は二人におじぎをすると出ていった。
「もらった、チョコレートケーキだすんだった」
野霧があわてた。
「いいよ、ゆっくり食べたらいい」
詐貸に言われて、野霧は「へ、失敗」と顔をひしゃげた。
氷見己
朝出勤してきた吉都と野霧に、詐貸が「薩摩がくるって」と言った。「遊びに来るんですか」と言いながら吉都がPCを開けた。
「頼みたいことがあるんだって」
野霧が給湯室にお茶を沸かしに行った。ここのところ野霧は朝和菓子を買ってきて、お茶とともに一息入れる。
薩摩は十一時ちょうどに現れた。
「巣鴨は昔の東京だね」
「このあたりは特にね」
「こじんまりした事務所だね、もっとでんとしたところかと思ったよ」
「迷い猫探すのに広いところ入らないよ」
薩摩は野霧と吉都に向かって、「狭くないかい」とたずねた。
「探偵社はここが始めてなので、他のところは知らないし、いい事務所だと思ってます」
野霧がお茶と菓子を薩摩の前に置いた。
「僕も小さな劇団しか知らないから、自分の机がもらえるなんて、考えてもいませんでした」
「詐貸はいい助手をもっていていいね」
詐貸もうなずいた。
「素甘うまそうだ、もらうよ」
薩摩はお茶を飲むと素甘をほうばった。どうもここに来る客は素甘が好きなやつが多い。野霧の丸い顔に笑窪がよった。
「それで、用事って何だい」
「富山で女性の誘拐事件がまたあってね、すぐ富山に行けとお達しがあったので、部下を連れて行ってきた、富山の警察でもちょっと心配していてね、今までは女性に身体的被害が無かったが、これから何かあるといけないというんだ、それで、新しい被害者に詳しく聞いてほしいということでね、連れて行ったのは、うちの部屋の世(よ)久(く)希(き)紅子(くこ)(よくきくこ)というんだけど化学の博士さんでね、化学物質にめっぽう強いんだ。薬のこともよく知っている」
「何で、化学(ばけがく)屋を連れていったの」
「いや、出身がそうなだけあって、周りをよく見通せる女性でね、化学博士だから細かいところにもよく気がつくし」
「それで、被害者に会ったの」
「ああ、その前に、被害者の調書を見せてもらったよ、年齢二十八、丸顔で目が大きく、色はふつう、長めの髪」
薩摩が写真を見せてくれた。美人の部類に入るだろう。全身の写真がない。
「それで大きいのかい」
「身長百六十一センチ、手足は太めだけど均整はとれてる、はきはきとしゃべる、なにせ、小学校の先生だからな、独身」
「それでなにされたの」
「金曜日の夜、同僚数人と食事をして、夜八時頃だから遅くないし、自宅マンションも店から歩いて十分のところだ、みなと別れ、家に帰る途中に公園があるが、そこの道でいきなり口を押さえられ、意識がなくなって、あとはわからないそうだ。気がついたときは、次の日の朝で、ベンチに寝かされていた。警官に揺り動かされ、やっと目を開けることができたということだ。朝散歩に公園にきた老人が女の酔っぱらいが寝ていると警察に連絡したそうだ。警官はまず病院に運んで、医師の診察を受けさせた。これは賢明だった。酔って寝ているようには見えなかったのでそうしたそうだ」
「なにも盗られていなかった」
「うん、それどころか、バックに十万入っていたそうだ、前と同じだ。ただ着ていたものは変わりなかったんだが、何かしっくりしなかったそうだ」
「前の事件と全く同じだね」
「うん、それで、本人が会ってくれるということなので、食事をしながら、三人で話した」
「医者の調書があるんだろ」
「うん、血液中によく使われる麻酔薬がわずかだけど検出されたそうだ、素人が使うような麻酔薬ではなくて、病院で使うような専門的なものらしい。吸入によるものと飲む薬両方使われているということだ」
「連れ去るときかがされて、そのあと飲まされたのかな」
「麻酔がかかっているとき薬は飲めないね」
「とすると、注射と言うことだが、針のあとは見あたらなかったそうだ」
「本人とはどのような話をしたんだい」
「それで、会ったのは水曜の午後でね、事件の五日後ということになる、うまく誘導質問をしないと新しいことは出てこない、世久希紅子がその点上手でね、化学屋なのに文学少女だったようだよ」
薩摩はそのときの様子をまとめて話してくれた。イタリアンレストランで昼を食べながら話を聞いた。しゃれた店なんぞ警察がやることじゃないが、世久希紅子の提案だったそうだ。
希紅子は被害者に警官に起こされたときになにを思ったか聞いた。すると、頭がひっつれた感じで、寝不足のときのようだったとのことである。病院で検査され、警察で調べを受けて、家に帰って、それからどうしましたという質問に、被害者は、もう一度寝たと答えた。その後、昼前に起きて、風呂を沸かし入って体を洗ったということだった。風呂で何か体に感じたことは無かったかと希紅子が尋ねると、やけにお湯が熱く感じられたそうだ。お湯の温度はいつも四十一度にセットされているという。次の日も熱く感じたそうだが、四日目の晩はもう感じなかったということだ。
「それを聞いた希紅子は被害者にいつバスタブを洗いましたかときいたんだ、被害者は二日にいっぺんほど湯を変え、一人で使っているのでさほど汚れないので、浴槽を洗剤で洗ったのは一週間ほど前、事件より前ですと答えた。そうしたら世久が風呂場を見せて欲しいといってね、被害者も承諾したので、マンションに行ったんだ。それで、希久子が風呂の栓を抜いて、ゴミをトラップする網をはずして、ついている毛やゴミを採取したんだ」
「それで、そのゴミから何かでたの」
「それがね、でたんだよ、まず被害者の髪の毛、これからは特になにもなかった、ところが陰毛が数本あったが、その二本に絵具の赤と緑がついていた。目で見てもわからないけどな、しかもどの会社のものかまでわかった。油性のものだ。それと、ゴミに混じって、同じ絵具が検出された、色は青と赤だ」
「小学校の先生なら絵具を使うだろ」
「陰毛につけるかよ、それに学校じゃ油絵具なんて使わない、希久子が油絵を描くか聞いていたよ、描かないって言ってたな」
「手に着いていたのがゴミの中の毛についた可能性もあるだろう」
「たくさん落ちていた髪の毛からは検出されていないんだ」
「それでなんだ」
「世久が言うには、体に絵の具が塗られたのじゃないかって、それで油の絵の具を落とすために薬品を使ったから、皮膚が敏感になっていて、湯が熱く感じられたのじゃないかって」
「何のために」
「わからん、それでな、詐貸のことを思い出したんだ」
「なんで」
「富山の愛子の会社の顧問じゃないか」
詐貸は愛子の実家の会社、北京骨商の顧問弁護士である。ちょっとした秘密をかかえた会社であるが、なにごとも無く、順調に運営されている。
「たまにはいくのだろ」
「うん、この間も行った」
「愛子さんもか」
「一緒の時もあるけど、野霧と吉都と一緒に行くことが多い」
「行ったとき、富山の警察の担当の刑事と会ってよ」
「会っても何もできないよ」
「話聞くだけでいいからさ、また違ったことを発見するかもしれない、ただペイはないけどな、無理にとは言わないよ」
「近々いく予定ではあるけど」
「先生、私たちも行きたい」
野霧が顔を四角にした。期待の顔だ。
「そうだな、それじゃ行くときは連絡するよ、向こうの担当者の電話など教えてよ」
「わかった、資料は渡せないけど、向こうの刑事からきいてくれ、さて、またハチ公にもどろう、たのむな、みなさんもよろしく、この素甘どこの」
「道沿いにわる和菓子屋さん」
野霧が説明する。
「連中に買ってってやろう」
「若い人食べるかしら」
「あいつら若いけど、俺より年とっているところがある、草餅はどこのがいいなんて話をしてるぜ、それじゃ」
薩摩が出て行った。
「嵩丸弁護士の仕事もしなければならないけど、ゆっくりでいいようだから、今度の金曜あたりに、富山で二ー三泊するか」
「そうしましょう、ホテルとりますか」
「愛子も行くって言ってたから、一緒にいこう、北京商会のゲストハウスが借りられるかもしれないな」
「嬉しいな、あそこの料理、他じゃ食べられませんから」
野霧はもう富山の海の幸を思い浮かべている。
吉都が「嵩丸さんのご神体の地図にも富山あたりに赤丸がありましたよ」
可也はいいところに気がつく。
金曜日、しばらくぶりに野霧と吉都、それに愛子と四人一緒に富山の北京商会にむかった。愛子が、社長で、亡くなった愛子の亭主の父親でもある水(みず)良(ら)今(こん)に連絡をしてくれた。彼は魚の発生の研究者だが、寿命の遺伝子を追求してもいる。詐貸を顧問弁護士に引っ張り込んだのも彼である。
「詐貸さんやみなさんと一緒に食事するのは久し振りですね」
もう七十半ばなのに元気に研究に打ち込んでいる。
会社のゲストハウスの夕食は、会社で養殖したり、改良した新鮮な魚介類の料理で、野霧と吉都の大きな楽しみである。
「なにもお役に立てなくて」
「とんでもない、おかげで安心して仕事ができます」
「去年、探偵事務所がおかしな事件を解決したのよ」
愛子がテディじいさんのことを話した。あまり後味のいい事件ではなかった。
「いや、野霧と吉都ががんばってくれて」
「そう言う人間的な事件は詐貸さんじゃなきゃ解決できないですね」
「今度も事件で富山に来たのよ」
「ほう、そんな事件が起きているんですね」
「いや、表にはでていないと思います」
「まだ秘密の事件ですな」
「いえ、事件らしい事件じゃありません、それで新聞にものりません」
「聞いてはいけないのでしょうな」
「いえ、女性が一晩誘拐され、なにもなく次の朝もどされ、しかも十万円バックに入っているというものです、友人の刑事に頼まれて、富山警察の刑事と会うことになっています」
「なにもされていないのですか」
「ええ、しかしこれから何かあるといけないので対策を練っておこうということです、会社に関係ない仕事で、何日も泊めてていただくのは申し訳ないのですが」
「詐貸さん、気にしないでください、いつでも使ってください」
「ありがとうございます」
「詐貸君は仕事がんばってね、野霧さんと吉都さんは休暇、だから私と一緒に富山の町を遊ぶの」
野霧と吉都は愛子にそう言われてにこにこしている。仕方ないか。
次の日、詐貸は富山警察の刑事に会った。
「まだ事件になっていないんですが、小学校の若い美人の先生で、変質者の仕業だといけないと思いましてね、それで警視庁のほうに連絡していたのです。被害者たちはその後なにもなく無事に過ごしているのですが、そうしたら警視庁に新たに赴任された薩摩警視に、詐貸さんに相談した方がいいと言われまして、北京商会の顧問弁護士さんでいらっしゃると言うことで」
「ええ、いろいろ偶然が重なりまして、北京商会のお嬢さんと大学のサークルが一緒で、薩摩もいたものですから」
「そうなんですか」
「薩摩から今までの被害者のことも聞きました、なにかされているようだけど、そのへんがはっきりしないということでしたね、衣服に違和感があるということだったとすると、一度裸にされている可能性があります。変質者で、不能者、個人的な楽しみで一晩、眺めていた、などと言うことも考えられます、ただ、犯人が男だと衣服を元通りに戻すのに女性の気持ちになれない。今までの調書をみると、違和感程度で、はっきりわからない、衣服をいじって、自然の状態に戻せるのは女性じゃないとできないのではないですか。ただ誘拐したのは男であったかもしれない。まだ犯人像はしぼれませんね、医者や薬剤師が絡む可能性はありますが、麻酔薬だけじゃなく薬は以外と誰にでも手に入れられますしね」
「そうですね、富山は薬の国ですしね」
ちょっと筋違いの返事で、詐貸の顔が笑っていた。
「ただ、今度の被害者の調査で、絵具という新たな証拠がありますが、これも意味が分かりません」
「ええ、薩摩警視から連絡は受けています」
「毛、しかも下の方の毛についていたということは、裸にされ、絵の上にうつ伏せに寝かされた可能性があります」
「確かにそうですが、そうすると犯人は、女の背中や尻を見てなにをしたんでしょうね、男だったら、上向きにさせるでしょう」
この刑事は話が通じる。
「いや男によっては尻が好きだったり、足が好きだったりへんなのはいます。目的はわかりませんね」
「女が犯人ということもあり得ますね、しかし、男だと写真でもとって、自分のコレクションにするとか、考えられますが、女性が犯人だと何をしたいのでしょうね」
詐貸は答えに詰まった。
「確かに、わかりませんね、それで、すでに数人同じような目に遭っていて、その人たちは、その後問題ないのですか」
「ええ、幸いなにも起きていませんし、はじめは怖がっていましたが、もう普通の生活に戻っているようです」
「全く犯人像は浮かびません、申し訳ありません、ただ夜道の一人歩きの防犯ポスターを増やすなどしなければなりませんね」
「ええ、もう印刷はやっています、それに女性だけの職場にはそれとなく注意するように伝えています。詐貸さんのおかげで、少し何かが明るくなった気がします、犯人が女の可能性は全く考えていませんでした」
「また薩摩と話してみます」
「北京骨商さんからは、ずいぶん寄付をいただいているのですよ、交通遺児の基金や、市の文化的なもようしには必ず名前が載ります」
「私は弁護士といってもなにもしていなくて」
担当の刑事はなかなかよくわかっているようだ。詐貸は自分など必要ないと思いながら、警察署をあとにした。
携帯がなった。ショートメールだ。愛子からだ。時間があいたら電話ちょうだいとあった。
すぐに電話をすると、「野霧さんと可也さんと富山駅にいるのだけど仕事は終わったの」と愛子の声がした。
「終わった」
「市民の絵画展を見てきたの、みなたいしたものね、プロなみよ」
「それはどこ」
「富山警察に近いわよ、それで午後はみんなで一緒にどこかに行かない」
「うん」
「とりあえず富山の駅にいらっしゃいよ」
「いいよ」
ということで、富山駅で三人と落ち合うことにした。駅に行くと三人でなにやら熱心に、いや楽しそうに話している。
「待たしたかな」
三人が振り向いた。もう来ちゃったのという顔をしている。
「今見てきた市民の展示会すごかったのよ、私はガラスの細工がよかったけど、野霧さんは動物拓がよかったって」
愛子が言っていること理解できない。
「なに、その動物拓って」
「動物の拓本」
野霧はいつもの調子だ。
「猫や犬や鼠の拓本ですよ、猫に絵具塗って、紙の上に寝ころばせて、形を取って、それに色を入れて、ちょっと面白いんです」
「どうやるんだろうね、おとなしくしているのかな」
「無理でしょう、眠らすのでしょう」
生物学をやった吉都も興味がありそうだ。
「それ、自分の飼っている動物なんだろうか」
「そうみたいよ、タイトルは家族だったから、猫、犬、鼠、ハムスター、インコ」
「鳥もいたの」
「それだけじゃないんですよ、本人の拓本もあった」
「え、自分に絵の具塗って、紙にころがるのかな」
「そうでしょ、自分というタイトルだったから」
「女の人」
「ええ、氷見己て書いてあったわね」
「いろいろなことをやる人がいるんだね」
「ね、詐貸君、世界残酷物語って見た?」
「生まれるずーっと前の映画だよね、見てないな」
「私見たのよ」
「あれは父と一緒だったかな、まだ小学生の時、たまたま富山に来ていたとき、2番館で昔の怖い映画何本かやっていたの」
「何でお父さんとなんだろう」
「あの中に鳥葬なんかでてくるでしょう、骸骨に興味があった父は、そういった映画を見ていたのね、それで、私はまだ小さかったから寝ていたようなの、ところが、わたし一つ覚えていたことがあったのよ、女の人が裸になって青い絵具を塗って、大きな紙の上に転がって絵にするの、面白そうだなと思って、また寝ちゃったのね、大学生の時、ビデオでもう一度みたわよ」
「へー、昔からそういったのがあったんだ」
「でも、氷見己いう人の作品はほんとに拓本なの、人間の女性の裸体がそこにあるの、だけど、凹凸があるから絵の具が付かないところがあるわね、そこは絵にしているのよ」
「半分拓本で半分絵ってところか、髪の毛も拓本だった」
「顔だけで、髪の毛は書いたようだったわ
「その人いつもは魚拓をそういう形でやっているようなの」
「ところでこれからどこに行く」
「吉都君が魚津に行きたいって」
「いえ、どこでもいいんですけど、魚津の埋没林博物館が見たかったんで」
「へー、埋まっていた木の博物館てなにがあるの」
「昔の林が土の中に埋まっていたのでそのままの形で残っているんです、泥炭状態の場所には昆虫もそのままの形であったりするんです」
「古いものなの」
「二千五百年前の樹齢千年の木の樹根などが残ってます」
「古いんだな、倭國神社は三,四百年前だし、卑弥呼だって千八百年前ぐらいだろう」
「地球は四十六億年前」
と可也がつぶやいた。
「行ってみましょうよ、蜃気楼はみられないかもしれないけど」
「蜃気楼がみられるんだっけ」
「うん、三月から六月はじめ頃までね、運がよければね、私は子供の頃見たわ、父につれられてきた」
愛子が補足してくれた。
「見ることができなくてもいいや、行こう」
ということで、あいの風富山鉄道にのって一時間弱、新魚津についた。駅の近くで軽い昼食をとり、海岸に向かって歩いた。
「富山の名物ホタルイカ、蜃気楼、みな魚津ね」
「埋没林も天然記念物ですよ」
吉都がこだわる。海の近くの魚津埋没林博物館にはいると、「埋没林のはなし」という小冊子をさっそく買った。
中はさほど広くないが、水の中に大きな木の根がしずめられ、何か幻想的である。北京原人の死体が冷たい水の中に腐らずに見つかっていたことを知っていたこともあり、条件さえ整えば、水が生ものをそのままの形で残すことができるのには驚く。木の根の間から、生き物がにょうっと顔を出しそうな薄気味悪ささえある。
そこは吉都のペースで見学をして、漁港の蜃気楼観光スポット海岸に行った。晴れてはいたがそれらしいものは見えない。
「滅多にでないものだからしょうがないですね」
吉都が蜃気楼のできる原理をはなしてくれたがわかるわけはない。空気がレンズのようになって遠くのものを空気のスクリーンに映し出すんです、とまとめたところだけわかった。
しばらくぶらぶらして、あいの風富山鉄道で高槻にでて、氷見線で国分の北京骨商に戻った。
その夕も社長の水良と食時をともにした。
「おじさん、魚拓はしないの」
愛子は本来の専門は魚の発生である水良に尋ねた。
「釣りのための釣りはしないからね」
研究のための魚の剥製はたくさんある。いずれ博物館を作る予定だ。
「今日、富山の市民展覧会で動物の拓本を出していた人がいた、氷見己と言う人」
「氷見己って人、きっと氷見にすんでいるのね」
野霧が北京商会の改良した魚の寿司を訪張りながら言った。この会社では鰹の大きさのマグロを作ったりしている。
「そうかもしれない」
吉都がホタルイカの石焼きでビールを飲んでいる。
「あの展覧会はうちも協賛金を出しているよ、いいものがあると、買い上げてもいるよ」
「今回も買うのあるの」
「木彫りのホタルイカを出だしている人があっただろう、あれは博物館を作ったとき飾りたいので、改めて作ってもらうことにしているよ、お得意さんにも配るつもりだよ」
「おじさんもう見たの」
「いや、販売部の連中が見に行って頼んだそうだ、私はあまり展示会に行かないんだ、時間もないしね」
「そうでしょうね、でもいい展示会よ」
「動物の拓本じゃ、紙に毛がへばりつくだろうね」
それをきいた詐貸が顔を上げた。
「猫なんかでやったら毛だらけになりますね」
それをきいた詐貸は「ちょっと失礼」と、席を立ち、廊下で富山警察の刑事に電話した。電話にでた刑事に、市民展覧会の、動物の拓本に使われている絵具を調べてほしいと言った。
「どうしてでしょう」
「いや、見当はずれかもしれないのですが、その展示に、自分の拓本もあるのだそうです」
「自分というと、人間のですか」
「ええ」
「女性なのですか」
「氷見己という人の作品だそうです」
「その人が誘拐の犯人と思われましたか」
「いえ、人間の拓本にどのような絵具を使うものかと思ったので、ただの思いつきです、無理なら無視してください、もし絵具がわかったら、薩摩の方に連絡していただけますか」
「ええ、わかりました」
電話を終えて戻ると、「どうしたの」と愛子がきいた。
「その、人間の拓本の絵具を調べてほしいって、富山の刑事に頼んだんだ」
「事件に関係ありそうなんですか」
水良が聞いた。
「いえ、絵具の話を聞いて、電話をしたんです、何でも調べてみる必要があるので」
「さすがに、名探偵さんですね、思いついたらすぐ行動する」
「詐貸所長、あの事件に氷見己が犯人と思ったわけですか」
野霧がきいた。
「いや、もし人間の体に塗ったりするとしたら、どんな絵具を使うのかなと思っただけなんだ」
「氷見己っていう人に直接きいたらいいかもね」
「そうだな」
「先生、私明日また絵を見に行ってみましょうか、もう一度富山にでて、母と姉に何か送りたいし」
野霧がそういうので詐貸はうなずいた。
「明日、僕は氷見に行ってみたいけどいいですか」
「もちろん、好きなようにしていいよ」
「私久し振りだから、おじさんと八尾の倉庫に行くつもり」
八尾には魚の剥製を保存してある借りた別荘がある、いずれ会社の敷地内に博物館をつくり陳列するつもりである。
「詐貸君も来る」
「いや、僕は野霧君と一緒に拓本を見たいな、そのあと野霧君は買い物、僕は自由」
そう言ったが、その後どうしていいかわからなかった。
次の日、それぞれ目的のところに向かった。
「オートバイで来るといいですね」
野霧も大型オートバイの免許を持っている。
「そうだな、今度は三人してバイクで来るか」
富山駅の近くのデパートが展示場になっている。
確かに素人といってもそれなりに年季の入った人たちの作品だ、どれも秀作だ。
「これです、ほら猫ちゃん、わんちゃん、自分」
「身長が百六十あたりだな」
女性の拓本をみて詐貸が言った。詐貸はふと女の拓本の足の間を見た。
「ちょっと電話してくる」
詐貸は会場からでたところで電話をいれた。
「詐貸です、たびたびすみません、昨日話をした、市民の展覧会の女の拓本ですが、もし可能なら、足の間に毛がついているようなのでそれを採取してもらえませんか」
「はあ、まだ絵の具も調べてなくてすみません、何とかしてみましょう、作者のこともまだ」
「いやいいですよ、できたらで、よろしくお願いします」
そう言ってもどった。
「また刑事さんに電話ですか」
野霧は勘がいい。
「このことでしょう」
小さなビニール袋をひらひらさせた。
「なに」
「これよく見てください」
中に毛のようなものが入っている。
「どうしたの」
「つまんだの」
彼女は詐貸に親指と人差し指を見せた。色がしろく意外と細い。いや、ずいぶんきれいな爪だ。透明のマニュキアが塗られているが、程良く延びていて針でもつまめそうだ。
「どうして」
「だって、所長あそこばかりみているんだもの、それですぐ電話しにいったでしょ」
詐貸は「ちらっと見ただけだよ」と頭をかいた。
「いや、ありがとう、薩摩へいいみやげだ」
「所長、お土産買いに行きますが、一緒にいきません」
行くところがないことまでお見通しだ。
「そうだな、このお手柄にお昼をごちそうしよう」
「あーら、こんな毛一本でお昼ごちそうしてくださるんですね、三百六十本だったら毎日お昼ね」
野霧は何を言ってるんだ。
北京骨商のゲストハウスの夕食は今日も豪華だ。所長は用事があって一緒じゃないが、四人で海の料理をいやというほど食べた。
「氷見はどうだった」
吉都に聞くと「氷見の地ビールおいしいんです、黒がすごい、ギネスどころじゃないおいしさですよ」
「飲むためにいったんだ」
「それもあるけど、おやじが好きなんで、送ったんです」
みんなしっかりしている。
「それに、氷見己て気になったんで、何かわかるかと思って」
「それでなにかわかったの」
「それが、大きな総合病院の宣伝看板が駅にあって、丸林病院ってあったんです。それで、院長、丸林美神、とありました」
「その人がどうしたの」
「カラー魚拓作家、氷見己、と名前の脇に書いてありました、それで駅の売店の人にきいたら、若い麻酔科医で、最近お父さんの跡を継いで院長になった人だそうです、お父さんが釣ってきた魚の魚拓を作る手伝いをしているうちに、自分でカラー彩色をして、作品を作るようになったということだそうです、休みの日に、病院の隣にある、自宅でカラー魚拓を作る会を開いているそうです」
「よく調べたね、さすが吉都だ、それで病院に行ってみたの」
「はい、駅から歩いて十五分ほどでした。ずいぶん大きな病院ですが、丸林美神の家が隣にあって、魚拓師、氷見己と書いてありました。敷地内です。小さな神社というより、お稲荷さんまでありました」
「お医者さんの趣味だったのね」
愛子がそう言って感心していたが、詐貸は今度の事件とどう関係するかすでに頭の中でまとめていた。吉都や野霧も考えているだろう。
「愛子さん、八尾の剥製はどうでした」
野霧が聞いた。
「久し振りに見たら、魚の剥製がまた増えていたわ、おじさんはもう博物館の設計図もつくらせていて、このゲストハウスの隣に作ろうと考えているみたい。それに、食堂も作るみたい、来た人の為にですって」
「魚介類のレストラン」
「おそらくそうなるでしょう、でも食堂にしたいんだって、安くておいしいランチ、ここは離れているから、電車で来る人はあまりいないだろうから、駐車場も作りたいようよ」
「その話は、会議の時にもでていたな、水良さんはあまり目立つようなものにはしたくないようだ、ただ、博物館はしっかりしたものを作って、富山の小学生や中学生が来たくなるようなものにするそうだ。だけど、最先端の魚の博物館にしたいようだね」
「探偵事務所首になったら、雇ってください」
生物学出身の吉都が愛子に頼んだ。
「そうね、顧問にでもなってもらうようにしようか」
「冗談で言ったんですけど」
吉都は愛子のまじめな反応にちょっと驚いている。
「私はそれじゃ、もし事務所を首になったら、愛子さんの秘書にしてください、校正くらいできます」
「あら、それもいいわね」
「おい、みんなもってっちゃうなよ」
詐貸が言って、みんな大笑いした。
東京に戻り、詐貸は野霧が採取してくれた毛を持って、警視庁の薩摩のところに行った。鑑識の奥に彼の部屋があった。スタッフは富山に行った世久希紅子を除いて皆外に出ていた。彼らと富山でのことを話した。
希紅子は小柄で、くりくりした目を詐貸に向け、
「薩摩警視からよくお聞きしています、どんな事件も解決する探偵さんだって」
と穴があくほど見つめるので、詐貸はうつむいてしまった。
「あら、警視さんとおんなじ、はずかしがりやでいらっしゃる」
野霧といい勝負だ。好きなことを言う。
「おい、キック、だめだよいきなりいじめちゃ」
冬児が笑っている。
希紅子のことをキックと愛称で呼んでいる。薩摩も第八研究室、忠犬ハチ公にとけ込んでいるようだ。
詐貸もつい笑い顔になった。珍しい。
「いや、今までの事件は解決した訳じゃなくて、尻切れトンボなんです、解決した事件はそれまで百パーセントだったんだけど、逃げた猫を探したり、落とし物を捜したり、そんな事件ばかりだから」
「一つ目の猫なんか探せますか」
「キックなに言ってるんだ」
「片目の見えない猫なら探しやすいですね」
「ほら、玄人探偵はそう言う答えをするのよ主任」
薩摩はそう言われて頭をかいた。
「本題に入ろう、詐貸がもってきた毛は、解析の方に回すよ、富山の刑事から連絡があったよ、おもしろい探偵さんだってさ、人の拓本の毛と絵の具の採取を頼まれて、まだ何もしないううちに、採取できたからいいと連絡が来たと言っていた、それでもやっこさん、その作者のことを調べてくれたよ、氷見在住、丸林美神、二十九歳にして、丸林医院の院長、独身、麻酔科医、父親の跡を継いだ。趣味で拓本をやっている」
「吉都が氷見に言って聞き込んできたよ、同じことを言っていた」
「優秀な助手だな」
詐貸はうなずいた。
「地元では相当有名な女性らしい、住民から慕われている、刑事もまさか誘拐の犯人ではないだろうと言っていたよ」
「だけど、そう言う人が怪しいんです」
キックが口をはさんだ。
「麻酔医だと薬が手に入る」
「そうです」
「そうだな、ともかく、詐貸がもってきた毛の解析をするよ、それともう一つ、被害者はこれからなにもなければ訴えるつもりはないらしい、とすると、もし彼女が犯人であっても、犯罪にならない、警察としては今後を見守るしかない、詐貸には迷惑かけたよ、ビール一杯で勘弁してくれ」
薩摩はすまないという顔をしている。
「別にどうでもいいんだ、富山には仕事で行ったんだし、毛の解析結果がでたら、教えてくれよ」
「ああ、どうもこの部署の扱うものってそういうのが多いんだ、いくつか相談がきているから見てってよ」
「私が説明しましょうか」
キックがもっていたPCをあけた。
「俺が見てもいいのかな、民間人だけど」
キックが薩摩を見た。
「大丈夫だ、詐貸が誰かに言ったって、信じてもらえないよ、個人の名前は伏せたリストだから。箇条書きだよ」
「しゃべったりはしないよ」
「こんな事件だよ、最近墓から骨が盗まれた、遺体の髪の毛を盗まれた、義眼が盗まれた、歯がなくなっていた、背中の皮膚がなくなっていた」
「骨が盗まれた話は俺も捜査したことがあるけど、髪や爪や眼なんて何で盗んだんだ、一人の遺体からとったということは、その人特異体質で、研究者が欲しかったんじゃないのかい」
キックが笑って補足してくれた。
「全部別の事件なんです、しかも場所も、日にちも違います」
「変なことをする人間がいるもんだね」
「収集癖は一種の病気でもあるし、それが元で芸術や文化が発展することがあります」
キックはよくわかっている。
「俺はないから発展しないんだな」
薩摩がぼやいている。
「俺もないな」
「私は三つ婚約指輪を集めました」
「なにそれ」
薩摩がキックに尋ねた。
「婚約してくださいってもってきたから、受け取ったけど、ちょっと付き合ったら、逃げていきました」
「どうして」
「私怖いようです」
「なにそれで、婚約指輪返してないの」
「集めてます」
何だ、この子は。
「返してほしいと言いにこないから、もらっときます」
なに考えているんだろう、キックはまじめな顔をしている。
「増えるといいね」
「はい」
普通に答えている。
「毛の解析はすぐにわかるよ、事件として扱われることはないだろうけどな」
「それじゃ、みなさん事務所の方に遊びに来てください」
「あたし、巣鴨好き、警視つれてってください」
「それじゃ、そのうちいくから」
詐貸は警視庁をでた。
富山の誘拐の件は個人的に薩摩から頼まれたことである。結果がどうであれ、直接の関わりはない、今たのまれているのは嵩丸のご神体の解明だ。そちらの方が心配だ。
三日後、野霧が一時間ほど遅れて出てきた。朝は十時までに来ることになっているが、探偵家業は出勤時間にはうるさくない、徹夜で張り込みなど、仕事の時間は不安定である。
「遅くなってごめんなさーい」
野霧は自分の背丈よりかなり長いものを持っている。
「試してみました」
「なにを」
吉都も不思議そうな顔をしている。
野霧は持っているものを床に広げた。高さは二メートル、幅は四メートルほどある。絵が描かれている。
「模造紙を張り合わせて作ったんです」
模造紙の大きさは一メータあるかないかである。
「八枚紙を使いました」
「それで、この絵はどうしたの」
橙色の何かを転がしたような模様だ。
「あたしです」
それを聞いて、詐貸と可也はぎょっとした。眼を背けていいものかどうか。
「自分で拓本やったの」
野霧はにっこり笑うと、
「母が珍しく北海道の姉のところに行ってるんです、キッチンのテーブルをどかして、そこに張り付けた模造紙をしいて、お風呂場まで、青いシートを敷きました。お風呂場で、水溶性の絵具を溶かして、体に塗って、いそいでころがったらこうなったんです、前と後ろと横。ずいぶん絵の具がいりました」
そう言われると、部分がわかる。どうしようと、思ったのは、詐貸だけではなく、可也の目玉もせわしなく動いている。どう言ったいいかわからなかった。
「どうしてやってみたの」
「どのくらい時間がかかるのものかみたかたんですが、水溶性なら後が楽ですが、油性の絵の具だと後をきれいにするのが大変、一人でやるとすると、そう言った場所を作って、作った後はシャワーのようなもので、勢いよく落とさなければだめでしょうね、相当時間がかかります」
「薩摩のところの世久って言う分析官もそう言っていた、それで気分はどうだった」
「おほほほほ」
野霧は笑っただけである。
「でもわかったことがあるのよ、ほらみてください、ただ転がっただけでは、いい拓本にならないの、紙を第三者が押し付けなければ駄目みたい。ということは、氷見己さん一人じゃだめなわけ」
「第三者がいるってことかな」
「もし、氷見己さん一人で作りたいと思ったら、他の人を使うしかないのよ、紙をからだに押し付ける必要があるわ、何人も誘拐したのは、きれいなのができなくて、今度家族と言うタイトルで出品しようと思って、また誘拐したのじゃないかしら」
「もし彼女が犯人なら、野霧くんの言う通りかもしれない」
「これどうするのですか」
吉都が聞いた。
「欲しければあげるわよ」
そこに電話が鳴った。詐貸がでた。詐貸も吉都もどう答えたらいいかまよっていたので助かった。
「それでどうするんだい」
詐貸が聞いている。うんうんとうなずいて、電話を切った。
「誰からです」
「薩摩からだ、やっぱり、あの毛は誘拐された小学校の先生のものだった。ついていた絵具も同じ」
「じゃ、犯人はあの氷見己ということですね」
「きっとそうだろう、だけど、真実はまだわからない」
「マニアなんでしょう」
吉都が簡単に言い放った。
「それじゃ、氷見己さんは捕まるのですね」
「いや、薩摩が言うには、被害者たちは事を荒立てたくないようで、訴える気はないそうだ、もっとも裁判になったら、公の証拠がないからな、野霧がとった拓本についていた毛と、薩摩のところの監察官が被害者のところから見つけた毛だけだからな、薩摩が言うには、もっと困った事件に発展したら動くと言うことだったよ」
「そうですか、これどうしましょう、いりませんか」
野霧がまた聞いた。詐貸も吉都も困った顔をした。
大きな胸と、大きなお尻と、足と手と、鼻の顔と、それを見ると、野霧を想像してしまうじゃないか。詐貸が黙っていると、野霧はやっとわかったようだ。
「そうか、それもそうね」
詐貸が「あと四十年もたつと、若いときの記念になるから大事にしときなよ」と珍しく口を滑らせた。
こちらも珍しく、野霧の顔がぷくーっとふくれた。
火美胡
土曜日の午後、薩摩が世久希紅子をつれて庚申塚事務所に来た。
「やあ」
薩摩がソファーに腰を下ろした。
「おじゃまします」
希紅子が元気な声でおじぎをして、立ったまま薩摩を見た。デスクにいる詐貸のほうを見る、野霧に顔をむけた。なにか迷って、結局、つるしてきた紙袋を、可也の机に持って行った。あわてた可也は中腰になって、野霧を指さした。土産を誰にわたしたらいいかわからなかったようだ。
「すみません、これ警視からです」
野霧にわたした。
野霧がケラケラけらと笑った。希紅子がドキッとして、薩摩の方を振り向いた。どうしたらいいのと言う顔をしている。
「ほら、さすがのキックもこの探偵事務所の面々にはかなわんなあ、まあここに座れや」
「はい」
希紅子はおとなしく椅子に腰掛けた。
「あの姉さんは、詐貸探偵のワトソン君、逢手野霧さん、彼は変装させたら世界一の尾行男、吉都可也さん、詐貸探偵の長優秀な助手さんたち、この迷い娘は世久希紅子です、よろしく」
「あらいやだ、薩摩さん、一緒に飲んだとき、うちには優秀なワトソンが4人いる、中でも女化学者はすごいって言ってたじゃないですか、みんなワトソンにされちゃうんだ、よろしくお願いします」
野霧が希紅子に挨拶をした。
「俺だけ、尾行男」
「可也はひがみのワトソン」
野霧がそう言ってまた笑った。
「俺そんなこと言った」
薩摩が詐貸に助けを求めた。
「やっと俺のいることを思い出してくれたよな」
詐貸が笑い顔でソファーの方にやってきた。
「そう言ってたよ、みんな俺をけっとばすんだ、特に世久さんが蹴るんで、キックと呼ぶことにしたんだってさ」
「俺そんなこと言ってないよ、希紅子だからキックだよ」
薩摩が困った顔をしたところで、野霧が、
「これいただきましょうよ、お茶入れてきます」と立ち上がった。
「あたし手伝います」
希紅子が立ち上がって野霧のあとをついて行った。吉都が詐貸の隣に座った。
湯はいつも沸いているので、お茶の用意はすぐ終わるが、三人の男たちはなにもしゃべらずに待っていた。
「なんだか、おあずけをされた犬みたい」
お茶を運びながらキックがつぶやいた。
「ほんとね、お菓子の包みもまだ開いてないわ」
野霧に言われて、あわてて吉都が包みを開けると、五家宝がはいっていた。
「あら、私これ大好き」
野霧は米でできた菓子が好きだ。
「私、熊谷なんです」
五家宝は上野の国、五箇村の人が作ったものと言われている。
「通ってるのですか」
吉都が聞くと、大きな目で吉都を見てうなずいた。
「かなり時間かかるでしょ」
「いえ、それほどでもありません」
薩摩がなにを思ったのか、「キックは指輪集めてるんだよ」と言った。野霧はそれを聞いて、不思議そうな顔をした。
「でも、今日はしてないのですね」
やはり目が早い。
「できないので、しまってあるのです」
「それじゃ、安いのじゃだめですね」
吉都がいきなりそんな風に聞いた。高価な指輪でなくすといけないから、していないのだと思ったのだ。
「そんなことないですよ」
それを聞いて吉都が立ち上がると、自分の机の引き出しをあけて、中のものを取り出した。
「それじゃ僕もあげましょ」
ビニール袋に入ったものを、希紅子に差し出した。野霧も詐貸も吉都がなにを渡したのか、まず想像できなかった。
希紅子も面食らったようだ。
「テントウ虫」
笑顔になって袋から出すとみんなに見せた。
「あら、指輪じゃない」
「かわいいわ」
希紅子が指にはめた「ほらちょうどいい」
薩摩と詐貸は笑い出した。
「世久さんが集めているのは、婚約指輪」
詐貸が言うと、それを聞いて驚いたのは野霧である。
「どういうことなのかしら」
「キックは婚約指輪を贈られても、みんな逃げちゃって、指輪が三つたまっているんだよ」薩摩が真面目な顔でそう言った。
「え、どうして逃げるの」
ちょっと見にはかなりかわいらしい女の子だ。
吉都が不思議そうだ。希紅子が「私怖いそうよ」
と言ったのだが、吉都はまじめな顔で「幽霊には見えないし、妖怪や怪物にも見えない」と言ったものだから、キックもケラケラ笑った。みんなも同様である。
「それにしても、可也ちゃんその指輪どうしたの、世久さんが来るので用意したのかしら」
野霧が尋ねると、吉都は三角のカマキリのような顔の口をとんがらせて、「そんなわけないでしょ、がちゃでそれがでちゃった」
と言ったものだから、詐貸まで声を出して笑った。
「吉都君ガチャやってるんだ」
「いや、昨日、駅のホームの中にある千円床屋に行ったら、サービスでガチャを一度やらせてくれて、指輪がでた」
「あたしのために髪を切りに行ってくださったの、指輪コレクションしておきます」
希紅子が指にはめたテントウ虫を見た。吉都が頭をかいている。
「髪の毛を切る変質者がでてね」
それを聞いて、思いだしたように薩摩警視が話始めた。
いきなりなので、野霧や可也、それに詐貸は何事かと薩摩を見た。
「電車に乗っているときに、髪の毛を坊主にされた女の子がいてね、五年ほど伸ばしていた髪の毛を根元からばっさり」
野霧が顔を三角にしている。そんなことあり得ないと思っているときだ。
「ちょっと切られたというならわかるけど、眠らされていたのかしら」
薩摩は首を横に振った。
「それが、被害者は寝ていなかったと言っているし、薬を飲まされるようなことはなかったというんですよ」
「どこで被害にあったんだ」
詐貸が聞いた。
「萩行きの電車の中だよ」
「萩って、山口のですか、東京の話じゃないんですね」」
「そう、ただ被害にあったのは東京の女子大生、旅行で萩へ向かう電車の中、日本海側の景色を眺めているうちに、坊主になっていた、キックが詳しいよ」
「なんだか妖怪の仕業のようですね、髪切り婆みたいな」
吉都がいうと、野霧が「なにそれ、ゲゲゲにでてきたっけ」と聞いた。
吉都は首を横に振って、「いや、いそうな名前だと思って」
「おもしろい、吉都さん小説家か漫画家になれますよ、私は丸め事件と呼んでました」
希紅子が薩摩の代わりに話し始めた。
「萩と島根の警察から、警視庁に連絡が入り、話は八研究室に回ってきたんです、全部で三つあります、三つとも薩摩警視がうちにくるまえです。最初は一昨年の春、萩の警察からのもので、今警視が話しはじめたものです。東京の女子大生が博多から萩の旅行を計画し、博多で二泊、門司に一泊して、船で関門海峡を渡り、下関で一泊、そのあと電車で、萩に向かいました」
「門司から下関は船でどのくらい」
吉都が尋ねると、野霧が「可也ちゃん。五分よ」と答えた。なぜか知っているようだ。
「へーそんなに近いんだ」
「だけどその狭いところを大きな船が一日何百隻も通るのよ」
「その後、下関の駅までは近いけど、下関の駅から萩までは、連絡がよくても二時間半かかる」
「乗り換えるんですか」
「下関から厚狭まで山陽本線で三十分、そこから長門市まで美弥線で一時間、さらにそこから、山陰本線で萩へ三十分、髪きり事件は最後の山陰本線の中で起きたの」
「たった三十分の間にですか、髪がざっくり切られた状態でしたか」
「それが、綺麗に丸坊主にされていて、切られた髪の切れ端一つも落ちていなかったということよ、女性の見栄えは悪くなかったみたい」
「と言うことは、犯人は切った髪の毛、それに綺麗に刈って落ちた髪の毛もすべて持って行ったということ」
「そうなんです、ただ、一気に髪を切れば切れ端を落とさずできるかもしれません」
「携帯用のバリカンのようなものがあるのですか」
「今、探せばそういう高性能のものがあります、特に業務用で、充電式のものがあります、残る髪の長さも調節ができて、慣れた人なら、あっという間に切ることができるでしょう」
「それでその子はいつ気がついたのです」
「それが、改札口手前のトイレの鏡で気がついたということなんですよ」
「どうしてそれまで気がつかなかったのかな」
「警察では、下関の旅館や、駅でその子の髪が切られる前の写真を見せたりしたようだけど、坊主ではなかったと証言しているの」
「山陽線と美弥線で犯行が行われた可能性はないの」
「乗り換えは改札通らないから見た人は探せなかったけど、本人が言うには、最後の電車に乗り換えるとき、髪留めがゆるんで、頭の上に丸めておいた髪が膨らんできたので、立ち止まって直したそうです」
「やっぱり髪切りばばあだ」
吉都が言って皆笑った。
「何か変わったことを感じたと被害者が言っていましたか」
「警察の調べでは、特になかったようです、その車両には自分の前に座っていた女の人がいて、窓の景色を見ていたそうです」
引き継いで薩摩が説明した。
「女性の話だと、その車両に乗客は二人きりだったそうで、犯人は車掌か前の席の女性の可能性がでてくるが、車掌は問題ないし、電車から降りてきたのは被害者だけだったということを萩の駅員は証言している、ということは、本当に女が乗っていたか、逃げたかということになる、もっとも俺が調べた訳じゃなくて、そう記録に書いてあった」
「警視のいう通りで、被害者の言っていることも曖昧です」
「女の人は前にいたのではなく、隣にいた可能性もあるな、窓の方を見ていたということは、被害者の方を向いていたと言うことで、その女性が何らかのかたちで被害者を夢うつつの状態にして、被害者の顔を見ながら髪の毛をきったということではないかな、前に座って窓の方をむいていたと思わされた」
詐貸の推理力はすごい。
「そんな風に考えてみませんでした、確かにそうですね」
「それから同じような事件があったわけね」
野霧がなにやら考えている。
「はい、昨年の秋のことでした。萩の警察と津和野の管轄の警察から連絡がきました。新山口の駅からでる萩行きのバスで、乗客の女性が坊主にされました。長いきれいな髪だったそうです。一時間二十分の乗車時間のあいだの出来事です。その数日後、津和野の警察から、山口から津和野に行く電車の中で、髪の長い若い女性の頭を丸められたという報告がありました、こちらは一時間の間です」
「犯人は明らかに同じ人間ね」
「そうですね、しかも長い髪ばかりねらっている」
「それで、バスには何人も乗っていたのでしょう、まさか一人とか二人とかじゃないよね」
詐貸が聞くと、キックは、
「ええ、そんなに多くはなかったようですが、それでも十数人ほどだったそうです、ただ、被害者は後ろから二番目に腰掛けていて、ほとんどの人は前の方の席で、被害者の周りには、後ろの一人をのぞいて、誰もいなかったようです」
「それで、被害者はいつ気がついたの」
「降りるときだそうです、バスのサイドミラーに移った自分を見て、頭に触ったら髪の毛がないので、驚いて運転手に言ったそうです、それで営業所から、警察に連絡したようです」
「乗っていた人たちはどうしたの」
「皆すでに降りた後です、彼女が一番後で、訴えられた運転手はあまりにも突拍子のないことで、被害者の言っていることが信じられず、他の乗客のことまで考えなかったようです、そりゃそうだと思います」
「初めから坊主だったということはないのですね」
「萩のバスの営業所で、山口の方に問い合わせをしたところ、坊主頭の女性がそのバスに乗ったのは見ていないと言うところまでははっきりしたそうです。被害者がバスから降りて、営業所の中で待っていると、交番の巡査が駆けつけて、一緒に話を聞いたそうです、萩では前年に同じようなことがおきていたこともあり、すぐ本署の刑事が駆けつけたそうです。その女性は名古屋の会社員で、休暇を取って萩に遊びに来た人です」
「津和野に行った人も観光ですか」
「そうだそうです、その人はやはり東京から一人で行った人です、長い髪の女性で美容師だそうです、電車を降りる前に気がついて、降りてから驚いて駅員に説明したそうです。警察に連絡が行くまではだいぶ時間がかかり、萩の事件が島根の警察には伝わっていなかったので、信じてもらうまで時間がかかったようですね、それで警視庁の私たちのところに連絡が回ってきて、萩で同じような事件が起きたばかりのことを伝えました。そこから、萩と合同の調査が行われたのですが、らちがあきませんでした」
「津和野に行った人の車両はやっぱり空いていたのでしょうね」
「そうです、前に人が座っていて、端にもいたそうです、ただ降りるとき、自分の頭に気がついたので、あわてていて、何人乗っていたか正確にはわからないそうです」
「空いているにしても人がいるわけだし、寝てしまったわけではないのに毛が刈られるなんてあるのかしら」
「どこかに見落としがありますね、詐貸所長がいったように、みな催眠状態だ」
吉都が言った。
「目的もわからんな、被害者は誰かに恨みをかっていたということもないようだし」
薩摩がそうつぶやくと、吉都が、
「髪の毛は高く売れます、よくウイッグにしますね」
吉都はいくつか簡易のウイッグをもっている。変装用である。
「病気で頭の髪を刈らなければならなくなった人に、自分の髪を伸ばし寄付するというのもあるわね」
「だけど、そういう人はそんなことして髪の毛を取るようなことはしませんね、まだ趣味で人形を作る人が、髪の毛がほしくて気に入った髪をもっていくほうがあるんじゃないかな」
「等身大の人形作りならあり得るけど、お金を出せば買えないない訳じゃない」
「そうですね、目的がはっきりすると犯人の目星がつきますね、共通するのは、乗っている人数の少ない乗り物の中であることと、長い髪の女性が被害者、三十分から一時間少しの間に素早く行われていることかしら」
「萩、津和野のあたりに関係のある人間の仕業なのかな」
「私たちもそう思いました、それで、前の室長と、私ともう一人で、萩と津和野の警察に行って話を聞き、帰りに名古屋の被害者、帰ってきてから東京の二人の被害者と話をしました」
「犯人を相当恨んでいるのでしょうね」
「それがそうでもないのです、皆美人で、頭は短いままでもとてもきれいで、今はその髪型が気に入っていました、一人は丸坊主、二人は坊主に近い髪型で、もう伸ばさないと言っていました」
「犯人を訴える気はなさそうですか」
「それはわかりませんが、とられた空白が気持ちが悪いと言っていました」
「それでな、らちがあかずのときに、俺が赴任しちまったんだ、とりあえずらちを開けたいよね、庚申塚のみなさんの助けがほしいな、無報酬ですまんけど」
「おもしろそうな事件って言っちゃ悪いけど、詐貸先生お手伝いしましょうよ」
「推理の手伝いぐらいしかできないけどな」
「いや、それで助かるよ、ハチ公の連中もたいしたもんだが、庚申塚探偵事務所の三人が加わると、合計八人、これで本当の忠犬ハチ公だ」
「八公ってなんですか」
キックには伝わっていなかったようだ。
「ほら、このお姉さんが、第八研究室だから、ハチ公ってつけてくれたんだ」
「ひゃははは、いい、みんなにも言っとこ」
キックが喜んでいる。
「おいおい、冗談じゃないよ、忠犬にはならんぜ、ただのハチ公ならいいけどな」
詐貸が言ってみんながさらに笑った。
「ハチ公じゃなくて、八犬伝のワンコウの集まりだ」
吉都がつぶやいた。
「八匹の野良犬か、野良八クラブ」
野霧がつぶやいた。
「もっと格好いいのがいいな、エイティードッグ」
キックは若い。
「やっぱり、八公だよ、蕎麦食いに行こう」
詐貸が立ち上がった。
野霧が最後に言った。
「くりくり坊主にするのはなぜ」
詐貸がすでに電話をしていたと見えて、蕎麦屋、ひさごは誰もいなかった。空けておいてくれたのだ。
「らっしゃい、詐貸さんまってましたよ」
「久しぶりです」
「警察の旦那もごいっしょですな」
キックがはいると、主人が、「新しいお客さんはお一人、おや、奥さんか」
と想像力を働かせたすぎた。
「警察官だよ」
詐貸が言った。
「婦警さん」
「とはちょっと違って、特殊捜査官といったらいいのかな」
「かっこいいね、今日は山形の蕎麦、コースだからね、ゆっくり食べていってね」
おやじさんに見つめられて、キックもちょっと縮こまっている。
「ビールは恵比寿しかないよ、酒も決まってる、燗酒」
「私、燗いただく」
キックが顔を上げた。
おやじさんが、ほーっという顔をした。
「俺ビール」
他はみんなビールになった。
通しは茸の煮物。
「少しずつ天ぷら出すからね」
主人は野菜の天ぷらを始めた。
薩摩が話しの続きを始めた。
「犯人の像がつくれなくてね」
「最初の電車で萩に行った被害者は、前の席の女性の姿形は覚えていません、バスで萩に行った人は後ろの人が何かしゃべていたのを聞いていますが、内容は覚えていないし、姿は見ていないのですが、女性の声です。あれ、おかしいな、後ろの席には一人乗っていたとありましたね、二人いたのかもしれませんね、津和野は電車の前にいた女性を比較的よく覚えていて、青っぽい服装、髪は短め、被害者が美容師だっただからでしょう、いつもだったら、もっと覚えているのだが、そのときはそのくらいしか覚えていないと言っていました」
キックが手酌で飲みながら説明を加えた。
「最後の事件からほぼ半年ってところかしら」
「そうです、このしし唐のて天ぷらおいしい」
キックは塩をちょっと付けて二つ目を口に入れた。
「あとで出てくるだし巻きも旨いよ」
詐貸が椎茸の天ぷらを口にれた。
「俺はこっちに来てから知ったことで、あまりいい考えが浮かばなくてな、キックやほかの連中も行き詰ってんだ」
「犯人の目的はどう思いました」
野霧が天ぷらを食べ終わってしまって、箸をもったままビールを飲んでいる。
「野霧さんにおまけ」
主人が大きなかき揚げを野霧の器においた。野霧の顔が丸くなる。
「さっき吉都さんが言ったカツラのことなども考えたのですけど、わざわざ盗む必要がないし、綺麗な人ばかりが被害者なんで、嫉妬心が裏にあるのかとも思ったりしたんですけど」
「毛を使う仕事や趣味の人の同一犯、下関と山口から萩へ、それに津和野に移動した人を洗い出す必要あり」
吉都が言った。
「そうですね、乗客についても調べました、でも誰もそれらしい人はいません」
「下関で仕事かなにかを終えて萩に帰った女性、山口で用事があり萩に戻った女性、その女性は数日後も山口に用事がありそこで用事を済ませ、今度は津和野に行く必要があった。萩に住んでいて、髪に、いや毛を必要とする事をやっていて、下関に行ったり、山口や津和野に行ったりする人」
「可也ちゃんの言う通りかもしれないけど、丸坊主にする理由はなにかな」
野霧がだし巻き卵を半分食べた。
「嫉妬の逆もあるかなと思った」
「なにそれ」
「綺麗な人の髪をざっくり切っただけでは申し訳なくて、綺麗にかったわけ、綺麗な人って坊主にするとまた綺麗だから、後始末をつけたわけ、ということは、悪いことをしていると言うことを知っていて、だけどその毛が必要だった」
「可也ちゃん、よく考えているじゃん、私は似合わないわよ」
野霧が勝手に膨れている。
「そんなことないですよ、野霧さん似合いますよ、本当の尼さんに見えますよ」
「それ、ほめてんだか、なんだかわからないうまい答え方ですね」
キックが言って、野霧が笑った。
「口挟んじゃいけねえかもしれんが、髪の毛とられた人がいるんですかい」
主人が言った。
「いや、地元の新聞には載ったのでかまわないですよ、電車の中で髪をとられて、盗まれたんですよ」
「変なやろうがいるんですね、警察も大変だ、髪の毛っちゃあ、おもしろい商売があるね、娘に初孫が産まれましてね、珍しいんですね、自宅で産んだんで、産婆さんが来てくれましてね、もう九十近いおばあさんで、昔の人だから国家試験など受けた人じゃない、それで娘の助産婦さんと一緒にくるんですよ、だけどばあさんの方がうまくて、ほとんど自分でやるんですな、娘の方は事務的なことや、健康管理、市役所への手続き方法など説明するんです、ばあさんは赤ん坊を産湯からあげると、乳のやり方、げっぷの出し方なんぞ説明をする、それで、最後に臍の緒をガーゼに包んで箱に入れ、筆ペンで日にちを入れてくれる、それで帰り際に、最近は子供の産毛を集めて、記念の小筆にしてくれるところがあると言うんです、知り合いがやっているんだそうで、そうしとくと、子供は字がきれいに書けるようになるそうでね、娘夫婦が迷っていたので、俺が出してやるって、頼みました、柄にする竹の種類によって値段が違うそうでね、名前をいれてもらって、中くらいの頼みました、五万でしたよ」
「臍の緒より記念としてはいいわね」
野霧が言ったとき、吉都が「そうか、髪の毛は筆になる」と大きな声を上げた。
みんなもそうだったという顔をした。
「たしかにな、だが目的が一つ増えただけだな」と詐貸の冷静な声が聞こえた。
「蕎麦うでるよ」
「おねがい」野霧の切実な呟きがきこえた。
月曜日、詐貸が事務所に行くと、吉都が自分の机のPCを開いて、覗き込んでいる。よくある風景ではあるが。
「よう、早いな」
詐貸が席ににつくとやっと気がついて「あ、おはようございます」と顔を上げた。
土曜日は、ひさごのあとに、薩摩と詐貸が二人して高田の馬場にでたので、吉都と野霧とキックは巣鴨駅近くの居酒屋で飲んだのだ。
「なに調べてんだい」
「下関、山口、萩、津和野地方の新聞です」
「事件のこと載ってたかい」
「ええ、事件のことはそれなりに扱われていました、探していたのは、百貨店の催しものや画廊の宣伝です」
「なにを探したいの」
「四つの場所で事件の日の前後に、共通する書道展がないかと思いまして」
「書道に着目したの」
「ええ、ひさごの親父さんの言っていた筆が気になったので、昨日も自宅で調べたんですけど、もしかするとと思われるのがあります」
「なんだい」
「同じ展覧会ではないのですが、下関で一週間、現代の書という展覧会がデパートで催されていて、最初の事件はその催しの最後の翌日です、山口から萩へのバスの事件の日には、山口のデパートで新作書道展があり、津和野行き電車の事件の翌日からは、津和野の和風喫茶で「書の美」という個展がありました、その個展は火美胡という名になっています」
「火美胡っていう人は、下関や山口のデパートの催しにも参加してるのかな」
「まだわかりません、カタログを探さないと、ただ、萩の新聞の地方版には「火美胡展」の評価を美術史家が書いていました、第十二会とありましたから、だいぶ前から萩で活躍している人だと思います」
「なるほどね、よく調べたね、だけど直接の関連証拠を探さなければならないね、それでなんて書いてあった」
「生きている文字、紙から飛び出す文字というタイトルで、素人の書道展だけど、これだけ動きのある字を書く人も希だとありました」
「どんな人なんだろうね」
そこに野霧が事務所に出勤してきた。
「お二人とも早いですね」
「可也が萩の書道家をピックアップしたよ、火見胡って人」
可也が野霧に火美胡展の記事を見せた。野霧はチラッと見ると
「可也ちゃんの勘は当たるから」と自分のデスクにバックを置いた。
「僕、もう少し調べてみます」
「うん、わからなかったら、忠犬ハチ公に連絡して調べてもらいなよ、あそこは全国に連絡網があるから、すぐわかるよ」
「そうですね、キックに連絡したほうがはやいですね」
吉都は巣鴨の八公から忠犬ハチ公へと打ち込んでいた。もう連絡網を完備させたようだ。
結果は二日後に吉都宛のメイルが送られてきた。キックからのものだ。暗号文だ。吉都とキックはパスワードを作っていた。
「吉都さん、犯人かどうかはわかりませんが、吉都さんの推理は大当たりです。忠犬ハチ公一同、感謝しております。
1.萩に火美胡という雅号の素人書家がいます。本名は牛島美霧。
2.最初の犯行のあった日は下関の丸三デパートでの「現代の書展」中日でした。火美胡も参加しています。
3.第二の犯行のあった日は山口の湯田デパートで「新作書道展」が行われていました。火美胡も参加しています。
4.第三の犯行のあった日は「新作書道展」最終日の次の日で、火美胡は翌日に津和野の喫茶室「ふるび」で個展「書の美」を行っています。
5.萩では年に一度「火美胡」展を開催しています。
火美胡は三十五歳の女性で、趣味で書をしています。ダイナミッックで躍動感のある字を書く人で、精神科の医者です。県立病院勤めで、催眠療法の専門家です。
写真の貼付があった。細面の優しそうな顔をした女性で、長い髪を肩まで垂らしている。とても犯人には思えない。むしろ被害者になりそうな髪の毛をしている。書の写真もあったが、一字を一気に書いたものが多い。
吉都は「医者だとすると、個展を開くときには休暇を取っているのですか」とキックにメイルを送った。返事はすぐ来て「常勤の医師ではなく、週二回、月、火に県立病院で診察をしている、自宅で個人的に催眠療法を患者に施している。違法なものではなく、一般の人がピアノを教えたり、絵を教えたりしているようなものです、書道教室も同様です、安い月謝で教えているようですが、すべて確定申告されています。したがって、かなり自由な生活をしています。萩の警察では、なぜ美霧を調べるのかわからないと言ってきています、本当は犯行当日のアリバイがほしいところですが、萩の警察はあまり乗り気ではありません、我々も様子見です」とあった。
この結果を詐貸に報告すると。
「ご苦労さま、よくそこまで気がついたよ、我々もそれ以上首を突っ込むこともないだろう、嵩丸弁護士依頼のの調査にもどらなけれならないしな」
「そうですね、知多の神社跡も発掘しなければならないし」
次の日、嵩丸司書が事務所にやってきた。
「嵩丸さん、忙しいでしょう、事件の裁判のことは新聞にもよくでています」
「ええ、まあ、なるようにしかなりません、実は知多の倭國神社跡のことですが、知り合いの大学教授が、学生たちに発掘させてくれないかと言ってきました。日本歴史の教授で、縄文時代の専門家です。詐貸さんのことも話しました。結果は報告してくれることになっています。彼らの勉強のためにもなると言うことなので頼みました、勝手に事を運んでしまってすみませんが」
「それはよかったです、こちらで発掘の専門家を探さなければならないかと思っていたところです」
「ところで、お願いがあるのです、わかっている倭國神社の神主さんの一人娘、日女は八人の娘を産んでいますね、その末娘、日魅が倭國神社のあとを継いでいる。それ以外の七人はどうしたのでしょうね、どこかに倭国神社の支部など出しているかもしれません、ご神体の赤丸のところが関係していないか興味がありますね、
その辺をお調べくださいませんでしょうか、費用はだします」
「そうですね、ただ、あの地図ですと非常に漠然としていますから、捜し当てることができるかどうかわかりませんが、それでもよろしければ」
「もちろんです、嵩丸家が倭國神社にかなり関わっていたようなので、我々の遠縁も神社とともに散らばっていったのかもしれません、急ぎませんので、どうかよろしくお願いします」
お茶ともらいものの五家宝をもってきた野霧が「どうぞ」と、嵩丸の前に置いた。
「あ、こりゃ、ありがとうございます」
嵩丸弁護士は五家宝を口に入れた。
「神社の好きな人は多いので、いろいろな本がでています、名のある神社では物足りなくなった人のために、ちょっと奇妙なというか、その地方の人しか知らない、または朽ちた神社を集めたような本があると思います、それを探すといいかもしれません、倭國神社も名を変えて存在しているかもしれません」
「そうですね、是非、本もそろえてみてください、費用はだしますので」
「野霧君、頼むよ」
「はい探します」
野霧は本が好きである。
「この、五家宝、うまいですな」と嵩丸はいって茶を飲み終えると立ち上がった。
「よろしくお願いします」
嵩丸弁護士は帽子をかぶると帰っていった。発掘のことを言いに来ただけのようである。忙しい中何故だろうと、詐貸はちょっと不思議に思った。
吉都が「忠犬ハチ公の、髪の毛盗難事件も萩だし、赤丸もありました。萩に行きませんか、そのあとに、あのご神体の地図にあった、福岡あたりにも行くといいかもしれません」と提案した。
「だけど、ずいぶん漠然とした探し物ですね、お遊びですね」
野霧はちょっと嬉しそうではある。
「萩から九州じゃ大変ではないか」
「いえ、下関から門司まで船で五分、門司港駅から博多あたりなら、近いですよ」
詐貸はこれじゃ慰安旅行だと思ったが、まあいいか。大体、一回の旅行でおいそれと何かがわかるはずはない。倭國神社に関しては、あまりにも情報が少ない。吉都がネットをつかい、野霧が神社関係の本などで調べ始めて入るが、倭國神社の名前はどこにも出てきていない。本当に他のところにもあるのか疑問だが、一度くらい、赤丸のある地に行くのはいいだろう。
「それじゃ、嵩丸さんの依頼の件を調べると言うことで、萩と福岡に行くか」
吉都も野霧もこっくりしてうつむいた。
「八女も古墳が多く、卑弥呼の邪馬台国の候補地でもあるのですよ」
いつも八女茶を買っている野霧が言った。
「それじゃ、宇部まで飛行機、萩、福岡そのあと野霧君の八女までいって、新幹線でもどるか」
「長い調査旅行ですね」
「まあ、知多の発掘は嵩丸氏が手配してくれるし、その分、中国、九州の調査に回そう、あまり長いのは困るよ、もし何か手がかりがあったら、もう一度行けばいい」
「それじゃ、私、宿の手配しておきます、萩と博多は二泊、太宰府に一泊、そこから八女に行って帰る」
野霧の采配は早い。
「二人に任せたよ、切符と宿頼む、もし行っている時になにかみつかったら、二人にはいてもらって、俺だけ巣鴨に帰ってくるよ」
野霧と吉都は大きくうなずいた。
萩に向かう飛行機の中で、野霧が何冊かの本を二人に見せた。地方の小さな神社を紹介した本である。
「色々なところにあって、だけどほとんどが大きな神社、熊野神社や厳島神社の神さんを祭っているところですね、独特の宗教の神社をまとめたものはありません」
「そう簡単に探せないから、今回は神社の雰囲気を知るだけでもいい、それとちょっと邪馬台国を気にしよう、卑弥呼との関わりはありそうだからね」
詐貸はそんなに簡単に倭國神社が出てくるとは思っていない。
萩は天気に恵まれた。飛行機を下りるとリムジンで萩の駅に行き、タクシーでホテルに入った。
ホテルは海に近いところの見晴らしのいいところにあった。昨日吉都が忠犬ハチ公に萩に行くことを連絡をしたところ、薩摩から詐貸に電話があって、萩の警察の刑事に会ってくれと言ってきた。薩摩は手を引くようなことを行っていたのにと思いながら、結局萩でも詐貸は刑事と髪の毛事件について話を聞くことになってしまった。
三人とも萩には来たことがない、ホテルについたあとタクシーをチャーターして、神社や寺を回ってもらった。神社のあるところは、神社そのものもだが、なにかしらが人間を引きつけるものがある。それは山であったり、石であったり、池であったりする。実際に山そのものがご神体だったりする。そういうところに神社を建てることで、さらにその場所に、霊験あらたかな雰囲気がうまれ、多数の人の頭の中から生じた、不思議な能力のある闇が作りだされる。そこがまた新たなものを生み出し、他のところへ飛び火していく。
三人は三大神社の一つ、住吉神社を見て、椿八幡宮をまわった。萩は歴史のある町であると同時に、日本の歴史を作った町でもある。学問の生まれたところで、名だたる人たちが育っている。松田松蔭の松陰神社にも行ってもらった。こういった神社系のところをみたが、倭國神社は違う観点から探していかないと、みつからないことは、詐貸も二人も感じていた。
ホテルで食事をしながら彼らは自分の思いを話していた。
「今日みたのは文化がかなりはっきりした、系統立った神社だったね」
詐貸はこのような神社仏閣を好んで見て回るようなことをいつもはしない。
「神社の奥にある得体の知れない作り出された影のような精神は好きだけど、倭國神社はもっと原始に戻って探さなければだめですよね」
野霧は模造紙の上を、絵の具を塗って裸で転がった感触が、なんだか自分を生まれたときの気持ちに近づけた、というか解放された気持ちを持ったことを思い出していた。原始ってそういうことなのだろう。
「萩もそうですし、このあたりには、縄文、古墳時代の遺跡もたくさんあるし、あの秋芳洞も近いんですよね」
吉都は自然が作り出したものが好きである。
「倭國ということばからは古墳時代や弥生時代、卑弥呼の時代につながるような気がするわ、萩には毛筆家の火美胡もいますしね」
詐貸もそういったことは漠然と頭にあった。
「萩は魚もおいしいわね」
野霧はすぐ食べ物に話が行く。河豚の刺身を口に入れた。今回下関は素通りするので、夕飯に河豚刺しを別注文したのだ。
「俺は明日、こっちの刑事に会うんで、野霧君たちは、倭國神社を探しながら、ついでに、牛島美霧について評判など聞いてみてよ」
「はい、私たちは観光案内にあった穴観音古墳や見島ジーコンボ古墳をみてみます」
穴観音古墳は昔のむつみ村というところの古墳で、丘のような斜面の途中にある。一方、見島ジーコンボ古墳は萩の東南に位置する海岸にある、石を積んだ塚で、日本人の墓ではないだろうといわれている。そこを見ても倭國神社に繋がることはないだろうが、実際行って見ると何があるかわからない。
次の日、詐貸は萩警察の浦根警部に会った。
「薩摩警視から伺っています、なんですか全く予算もつけずにお願いしているということで、恐縮しております」
背のすらっとした、警察官には見えない男だ。
「いえ、依頼されていることがあって、こちらにきています、ついでですので、気になさらないでください」
「そうでしたか、毛の盗まれた事件は、私どもにとってもはじめての事件で、どうしたらいいのか、ある意味で途方にくれています、全く解決の糸口がないのです、しかも事件後、今になると被害者の方の関心が薄れていましてね、ほうってあると言うのが正直な話です」
「僕もはじめて聞く事件です、電車の中で、本人が知らない間に坊主にされるということは、本人が目覚めていると思わされていたのだが、実は寝ていたという状態だったと考えるしかありません」
「あ、催眠術ですか、そこまでは考えませんでした」
浦根警部はなるほどといった顔をしている。
「それと目的が全くわからない、髪の毛を何にするのか、鬘など毛を使うものなら、髪の毛を得る方法はいくらでもある、若い女性の長い毛をどうしても使わなければならない理由があるわけですね」
「よく言われる、どこの何々を使えば、出来上がったものに魂が入るとかいった、言い伝えとか、思い込みから、髪の綺麗な女をねらったのでしょうか」
その通りなのである。浦根刑事は結構推理力のある人だ。
「そうですね、かなり美意識の高い人間の犯罪のようですね、萩が中心の事件ということは、萩にそのような話などがあるのでしょうか」
「私は聞いたことはありません、郷土史を読んでいるわけではないので、詳しいことはわかりませんが」
「スリルを楽しんで悦にいっているのかもしれない」
「そういう男もいないことはないでしょうね、そうやって髪の毛をとって、性的興奮をするということもあるかもしれません、変態的な男も考えて、当たってみたのですが、犯人に結びつくような者はでてきませんでした」
「話は違うのですが、萩は書道が盛んなのですか」
「特にそうかはわかりませんが、ふつうに書道教室はあります、ただ、有名人が排出されていますから、いろいろな人の書が残っていることは確かです」
「火美胡という書道家はどうでした」
「薩摩警視から示唆されましたが、この当たりでは評判のいい方で、そのようなことをするはずはありません」
「県立病院の精神科の医者だそうですね」
「そうですね」
「萩にくる前に事務所の者がネットで見ていたら、火美胡展が毎年行われているということが載っていましたので、気になって薩摩に進言したのです」
「詐貸さんが薩摩警視に話されたのですか、火美胡の毛の盗難があったときのアリバイは調べていませんが、盗難時に火美胡の関わる展示会があったことは確かです、しかし、本人を直接調べるには、被害者から強い訴えがないとできませんし」
「いえ、調べて欲しいということではありません、わたしども、依頼人から卑弥呼に関わるかもしれない事柄の調査をするためにきたものですから、同じ名前だったので、つい余計なことを言ったようです」
「そうですか、卑弥呼に関わることで萩にいらしたのですか、萩焼をご存じだと思いますが、大きな窯元が三つあります、その中の一つに有名な陶芸家の三輪休雪という人がいますが、十二代目が型破りな陶器を作る人で卑弥呼の書という陶芸作品があります、博物館に展示されています」
「そうですか、何故卑弥呼の書を陶器にしたのでしょうね」
「個人的な崇拝かもしれません、私はそういった芸術系に弱くて」
刑事は頭をかいた。
「いや、私もわからない口です」
「書道家の火美胡のことで何かわかったら連絡しますよ」
「あ、いや、無理にではなくて結構です、何かあったら薩摩のほうにお願いします」
詐貸は警察をでた。
野霧と吉都はホテルでもらった町のガイドをたよりに歩いた。萩の町は町自体が博物館だと書いてある。その中心が萩博物館だ。中に入り歴史のところを見にいった。この一帯には縄文や古墳時代の遺跡がかなりある。
「ずいぶんある、観光案内にあった古墳に行ってもらちが明かないかもしれないわね」
「この町を歩いているほうが何かにぶつかりそうな感じがする」
「そうね、古墳まわりはやめようか、倭國神社に関してはなんの手がかりもないのだから、見つけようと思ってもだめね」
「地理的に面白そうなのは、笠山のようですよ」
二人は笠山のコーナーにいった。海に突き出た小さな火山で、112メーターほどしかない、説明には世界最小の火山とある。
「小さい火山ってかわいらしいわね、それと、この明神湖おもしろいわ、厳島神社にあるのね」
明神湖は笠山と本土の間にあって、厳島神社の境内の中になる。火山の噴火で海がせき止められ、薄められて汽水湖になっている。
「海跡湖っていうんだな、海の魚がいるんだっていうからおもしろい」
「行ってみたいな、笠山には椿の原生林もあるようだし」
「それじゃ、午後ここにしませんか、これから町の中を歩いて、陶器の博物館など見て、町の様子を見てから考えましょうよ」
二人は、博物館をでると、マップを見ながら町を歩いた。古い建物が続く歴史を感じさせるところで、かなりの観光客が歩いている。
「夏みかんが特産なのね、イメージが違うわね」
「たしかにそうですね、やっぱり焼き物の店が多いですね」
「高そうな店ばかりね」
「有名な萩焼きの窯元がたくさんあるから」
「ギャラリーもある」
「やはり萩焼きの個展が多いですね」
吉都がギャラリーの入口に貼ってあるポスターをみて「変な焼き物ですね」と立ち止まった。
「昔のポスターね、有名な人の作品のようね」
野霧も近くによった。
「これ、本の形をしている、陶器で作った現代ものですね、あれ、卑弥呼の書とある」
「十二代目の三輪休雪作とありますね」
ギャラリーだと思ったら、三輪という萩焼きの窯元の店だった。
中にはいってみると、その窯元の焼き物が並んでいた。ちょっと手がでるようなものではない。野霧が店員に近寄って、なぜ卑弥呼の書を作ったのか聞いている。
店から出て野霧が「十二代の休雪というひとは、エロスとタナトスをテーマに、伝統にとらわれない陶芸作品をつくった人のようだけど、卑弥呼にどんな女性を見ていたのかしらね、もうお亡くなりになっているから、本格的な休雪の伝記本でも読まないとわからない」と首を傾げている。
「やっぱり火美胡が気になりますね」
「書道家の精神科のお医者さんて、どんな女性なのかしらね」
それから、県立萩美術館にいったら、また休雪の作品をたくさん見せられた。
美術館からでたときに、吉都のスマホに詐貸から電話が入った。
「野霧さん、詐貸所長が一緒に昼食べようって、警察からでて、今博物館のところにいるって」
野霧と吉都は博物館のところに戻った。
「もう終わったんですか」
「警察もあまり関わりたくなさそうだ、なにもわかっていない、牛島美霧のことはもう一度調べてみるといっていたけど、乗り気じゃないね」
「おそばおいしそうですよ」
野霧はもう頭を切り替えている。歩いたときに店の目星をつけておいたようだ。
結局そこに行って、ざるそばを注文した。
「警察からこっちに向かう途中に立派な骨董屋があってね、入り口に火美胡師匠来店、実演という大きなチラシが張ってあった、ちっとのぞいたんだが、昔ながらの骨董屋で、中が広くて、茶碗と掛け軸がたくさん棚にあった、広い帳場があるんだ。そこで火美胡が字を書くようだよ」
「誰でも見ることができるのですか」
「そのようだけど」
「何時ですか」
「二時からだった」
「是非見ましょうよ」
野霧の提案で、笠山に行くのは明日にすることにした。
「おいしいおそばだわ、もう一枚頼んでいいですか」
野霧がそばをたのんだ。
「警察はどうでした」
「感じがよかったね、まじめそうな警部でね」
「萩焼きの有名な窯元の作者が卑弥呼の書というシュールな焼き物をつくっていました」
「休雪と言う人だろ、刑部もそんなこと言っていたよ」
「この辺は卑弥呼と関係があるところなの」
詐貸はそういうことをよく知らない。
「あまり聞いたことはないですね、九州のこれからいく福岡の方には邪馬台国だったという場所もあります、八女もそうですけど」
「そっちの方がおもしろそうだな」
野霧はもう一枚もあっという間に食べてしまった。
「あと、四十分あります、所長まだ町を歩いていないでしょ、ちょっと歩きますか」
三人は町中を歩き、吉都が親に萩焼きの湯飲み茶碗を買った。
詐貸の案内で骨董屋に十分前についた。すでに何人か店内にいる。店の中央にあった机をどかし、椅子が並べられていた。
野霧が予約もしていないけどいいのか聞いた。三十人の予約の人で満席だが、後ろの立ち見は自由ですということだった。三人は椅子の後ろに立った。
参観者が次から次へと入ってきた。小学生や中学生らしき子どももいる。美霧の書道教室に通っているのだろうか。若い女性もかなりいるが、みな真っ黒な髪を長く伸ばしている。書道家らしき和服に身を固めた老人も混じっている。
時間になると、茶色の背広をぴしっと着こなした眼鏡をかけた青年が帳場に現れた。
「店主の宝彩でございます、今日は火美胡師匠にお願いしまして、笠山に奉納する書をここでしたためていただきます。師匠はそのために、特別な筆をあつらえ、墨は天性を用意されております。火美胡師匠のご経歴などは、すでにみなさまにはお渡ししてありますので、省かせていただきます。十二代の三輪休雪に私淑し、自由奔放に筆を走らせる火美胡師匠の舞姿をご覧になるみなさまは、脳裏に笠山の字が浮かぶことに違いありません、
書かれたものは厳島神社に奉納され、御倉に所蔵され、神社の祭祀の時に公開されることと思いますが、それまでは見ることはできないもの、どうぞ火を噴く笠山をご覧いただきたいと存じます」
何とも大仰なせりふである。
二畳もあるほどの大きな和紙が帳場におかれた。墨が入ったおおきな壷が運ばれ、筆先が八十センチか九十センチもある大きな筆が、木の枠に吊るされてでてきた。
それを見た吉都が「あ」っといった。野霧も詐貸も目をこらした。
一緒に出てきたのは白い着物に赤い袴の色の白い背の高い女性である。帳場の前に立つと何もいわず皆に向かって腰から折り、頭を下げた。後ろには同じ衣装の助手を務める女性が二人いた。薩摩が送ってきた写真は短髪だったと思ったが。
狐だ、吉都は思った。
火美胡は助手が渡した赤いたすきで袖をからめ、大きな筆を手に抱えると、ゆっくりと墨壷の中に筆先を沈め、しばらくの沈黙があった後に、壷から筆先を持ち上げ、助手が筆先の下に大きな布をかざすと、二人して紙の上に移動し、火美胡は「ややあああ」という声をあげ、紙の上に一気に大きな筆を走らせ、笠の字を書いた。すぐにもう一人の助手が大きな布を筆の下にかざし、火美胡はもう一度、墨壷のところにいって筆をおろした。また先と同じように筆を運び、山、を書いた。
見ている人たちから拍手がわいた。
火美胡は筆をおき、たすきをはずすと、帳場の前にきて、一礼し何も言わず奥に入っていった。
五分ほどのイヴェントだった。
主人が出てきて、少し乾いたらみなさまにお見せするので、しばらく待つように言った。
五分ほどすると、火美胡は白いブラウスと紺のタイトスカートという、昭和の時代の雰囲気で髪をアップにして出てきた。ほんの少し下っぷくれの柔和な顔をしている。狐からお多福だ。三人はその変化におどろいた。きっと精神科医の顔なのだろう。
拍手がわき、係りの者が出てきて書かれた紙を吊るした。また拍手がわいた。
今まさに火を噴こうかという動きのある「笠山」である。竹冠が左右に開いて、下の立の字が空に向かって飛び出しそうな雰囲気である。
「先生、ありがとうございました。ご来場のみなさまもありがとうございました、この書と先生特製の大筆はしばらく、この場に飾らしていただきます」
司会の言葉で、火美胡は深くお辞儀をし、やはり言葉を発することなく、拍手に送られて奥に入った。
三人は外に出た。
「私ちょっと、話をしたい人を見つけたので、ここで分かれていいですか」
野霧が詐貸に言った。
「ああ、もちろん、我々もこれから好きにするから、夕食は一緒にするだろう」
「ええ」
野霧はそう言うと、店から出てきた若い女の子の後を追った。黄色いミニスカートをはいている髪の長い娘だ。
「誰でしょうね」
吉都がなんだろうという顔をしている。
「後で話してくれるさ、吉都はどうする」
「ぶらぶら歩きます」
「それじゃ一緒に行くか、どこかでビールでも飲むのもいいな」
詐貸と吉都は二人してまた、町を歩くことにした。
夕方、詐貸が野霧に電話をすると部屋に戻っていた。六時半にフロントに集まると、目星をつけておいた料理屋にはいった。萩の料理は、美味しい牛肉もあるが、やっぱり海のものである。
「あのお大きな筆の穂先、真っ黒でしたね」
吉都が太刀魚の刺身を摘まみながらつぶやいた。
「そうね、だけど人の髪の毛で作ったのかどうかはわからないわね」
ウニがおいしい。
「変わった女だな、顔つきが変化する、華奢な感じがしたけど、字は迫力がある」
詐貸は焼いたノドグロをつついている。
「だけど野霧君、追いかけていったあの女の子は誰」
「会場に若い女の子が何人かいたでしょう、その中の一人で、火美胡の書道教室に通う女の子だと思って、話を聞いたのです、ケーキをごちそうしました」
「それで何かわかったの」
「書道教室では一月ほど基本的なことを教わって、そのあとは、字をきちんと書くのではなくて、字に自分の気持ちを投影して書くことを教わるのだそうです、字に感情移入する心理訓練だといっていました。おもしろいのは、ときどき催眠教育をうけるそうです」
「なに、その催眠教育って」
「先生の部屋に呼ばれて、ソファーで隣同士にすわって、話をするそうです、先生がつぶやくように話すので、いつの間にか寝てしまうのだそうですが、その間に書こうと思っている字に書きたい意図を伝えるのだそうです」
「精神科の医者だから、催眠療法は心得ているのだろうな、上手な催眠術師なわけだ」
「催眠術って本当にかけることができるのですか」
「かかりやすい人とそうでない人がいるようだけど、上手な催眠術師だとできるのだそうだよ、催眠術にかかって、犬にされている自分が、猫に向かってほえている映像を見せられた人もいるらしい」
「それじゃ、なんでもできるじゃないですか」
吉都が声を上げた。
「あ、そうか、催眠術をかけ、髪の毛をとったわけね」
「その可能性もあるけど、彼女が犯人かどうかわからないよ」
「でも、かなり可能性ありますよ」
野霧が続けた。
「その女の子の話だと、火美胡は女の子に髪を染めないで、長く伸ばしなさいと指導するそうです、段をとると、お祝いに本人の髪で筆を作ってくれるそうです」
「人の髪で筆を作る人がいるんだ」
「本人が作るそうです、火美胡の持っている筆は多くが自分で作ったものだそうです」
「ふーん、だけどそれなら、わざわざ盗まなくても、依頼して髪を伸ばしてもらって、それを使えばいいけどな」
「宗教的なものがからむと、条件を満たした女性の髪じゃなければならないとかあるかもしれませんね」
野霧がまとめた。警部も言っていたことだ。
「明日は、嵩丸さんに依頼された神社を探してみよう、木簡ひとつから探そうっていうのだから無理かもしれないけどな」
「そうですよ、何年もかかると思います、明日は笠山にいきませんか、今日、火美胡が書いた「笠山」は笠山の麓の厳島神社に奉納されるのだし」
「うん、そうしよう」
次の日、朝早くから、三人は笠山にでかけた。笠山は山陰本線越ヶ浜駅から十分もかからない。萩湾のはずれにある砂州で陸続きの島の山である。
三人がまばらな観光客に混じって歩いていくと、北側に嫁泣港が見えた。わたしゃなきなき水くみに、と嫁泣節に歌われているように、砂州のため井戸を作っても塩水しかでないので、本土に水を汲みに行かなければならないところであったという。
先に進むと明神池にぶつかった。明神池は海がせき止められてできたのだが、溶岩には隙間があり、海の水が出入りしている。ということは海の満ち干が明神池の水面を上下させる。
脇を笠山のほう歩いていくと、厳島神社にきた。厳島神社は小さい。
「この神社はなにを祀っているのかな」
「広島のは三人の姫さんよ、田心姫命、市杵島姫命、瑞津姫命」
「なにやってくれるんだ」
「それぞれ役割があるのよ」
「この厳島神社は市杵島姫命で弁天さんのようだ」
吉都がスマホを見た。
「弁天さんて、仏教じゃないのかな」
詐貸はこの辺のことよく知らない。
「神仏習合で、神道の市杵島姫命は仏教の弁才天を吸収、まあ同じということ」
「なにそれ、同じって、神と仏が集まるのが神仏集合でしょ」
詐貸がそういったら、野霧が笑っていいのかどうかちょっとがまんしたようだ。
「集まったんじゃなくて、簡単に言うと、信仰が一つになって、信仰の対象が混じり合って融合してしまうの」
詐貸にはまだわからないようだ。日本人はいい加減だ。
「厳島神社って全国に五百もあるんだって」
吉都はまだスマホを見ている。
「どうやってブランチを作っていくのかな」
詐貸がつぶやくと、「きっと、信仰を広めにいく人がいるんでしょう」と野霧が答える。
「広島の厳島神社は600年に建てられ、萩の厳島神社はその千年後のようです、当時の大将が誘致したんです」
鳥居をくぐって中に入った。
小さな神社だが、なんだかすーっと涼しい。
「神様がいるみたい」
野霧がそういうと、「神社の後ろに風穴があるんだ、溶岩にたまった冬の冷たい空気が夏になると吹き出すんだ」と吉都が興ざめのことを言った。
「元々何かがあったところに新たに神社を建てたのかしら、どうやってこの場所を選んだのかな」
野霧がつぶやいた。
「人の気持ちを何か揺さぶるようなものがあるところだね」
詐貸が言うと、吉都は「要するにパワースポットのようなところですね、それは自然が作り出すのでしょうね、風穴もその一つ」そうまとめた。二人もうなずいた。
「ここに火美胡さんの書が収められるのね」
「何か意味があるのかな」
「火美胡さんには意味があるのでしょうね」
「そうだな、さて笠山の方にいこうか」
笠山入り口に向かった。といっても、とても低い山である。頂上まであっというまであった。ところが眺望がとてもいい。
「この火山は一万年前に噴火したそうだけど、このあたりには人がいたのかしら」
そういわれて吉都がスマホを出した。
「ホモサピエンスは二十万年前くらいにでてきて、世界に広がっていったのはその十五万年あと、日本では旧石器時代、三、四万年前には人がいたようだけど、このあたりではなさそうですよ、縄文は一万五千年前だから、この場所じゃないにしても萩の近くにはいたでしょうね、火吹いてびっくりしたんじゃないかな」
「そうか、そうね、縄文時代の始まりを忘れていた、人がいたわね」
「ともかく火があり水があり風がある、パワースポットだな、そろそろもどるか」
「柚子屋でみやげ買っていこう」
野霧は母親に萩の名物を買っていくつもりだ。
三人は笠山の食事処で海鮮を食べ萩の町に戻った。
「倭國神社のことは全くわからないな」
「あまりにも漠然としてますから」
三人はこれからどうするか、ホテルのロビーで話しあっていた。
「秋芳洞はどのくらいかかるんだろう」
吉都は行ってみたいようだ。スマホで調べて、首を横に振った。
「東萩駅からバスがでてるけど、一時間以上かかる、バスの本数も少ないな」
「嵩丸さんの費用で行っていいよ、タクシー使いなよ」
タクシーだと相当かかる。
「野霧君も行ったらどうだい」
「私、もう少し萩の中をみます」
詐貸の携帯がなった。
「詐貸です、はい、それじゃ伺います」
「萩警察の浦根警部からだ、牛島美霧のことを調べてくれたらしい、これから署の方に行ってくる、二人とも好きなようにしてくれ、夕飯も好きなようにしよう」
「私、萩焼きの窯元見てくる」
「僕はやはり秋吉洞に行ってきます」
詐貸は警察に向かった。
「詐貸さん、すみません、本腰を入れて調べました。牛島美霧医師はずいぶんかわった経歴がありますね、それよりまず隠れ名士のようです。私は萩生まれではないので知らなかったのですが、彼女は十何代も続く家柄の娘で、父親も医者でした。ただ開業医ではなく、勤務医ですね、父親は今でも萩の有名な病院に内科医として勤めています。彼女は県立病院の精神科で非常勤医師を週二回していますね。祖先は薬師のようです。厳島神社の氏子です」
だから、書を厳島神社に奉納したわけか。
「最初は私立大学の心理学に入学したのですが、途中から、医大に入り直し、精神科医になっています。
書道の方は小さい頃からやっていたようで、萩のある先生についていましたが、中学卒業後辞めています。大学時代に前衛の書家について学び、医者になる頃には書の方もかなり知られるようになっていました」
「昨日、陶器の店で、厳島神社に納める書の実演をみました」
「そうでしたか、それで、髪の毛が盗まれた時のアリバイは全くありません、むしろ、詐貸さんが指摘したように、事件の時に電車に乗り合わせていた可能性はかなりあります、といっても、証人はだれもいません、本人の個展や展示会が事件のあった頃、確かに行われていました、それと精神科でも催眠療法の専門家で、被害者が髪を盗まれたときの状態が催眠にかかっているのと同じような症状ではないかと、鑑識の医師が言っていました」
「しかし、盗む動機はありそうですか」
「わかりませんが、警察としては全くないと思っています、きれいな長い髪だけをねらって、しかもただ散切りにするのではなくて、きれいな坊主頭にしています、髪フェチの男で、美しい女性の髪を側に置きたい、しかも髪をもらった女を不幸にはしたくない、きれいに刈り込んで、前とは違った魅力を引き出すということを考えたのではないでしょうか、事実、東京の被害者は格好良いと、その後短いままでいると聞きました」
「私もそう聞きました、私が来てもなにも役に立ちそうにありません、すみませんでした」
「とんでもない、ありがとうございました、薩摩警視に、難しい事件を解決した探偵さんとお聞きしています、お会いできて光栄でした、何かわかりましたらよろしくお願いします」
浦根警部はよくできた人であった。詐貸はこれ以上自分にアドバイスすることなどできないと詐貸はホテルに戻った。
夜の八時、吉都が秋芳洞から帰っていると詐貸に連絡がきた。野霧ももう戻っているだろう。詐貸は二人にラウンジで会おうと呼び出した。
「吉都は夕食食べたのか」
「ええ、途中でタクシーの運転手と一緒に、食堂で食べました」
「野霧君は」
「町でまた海鮮食べました」
「秋芳洞はよかったです、ほかにも鍾乳洞があってそこも回りました」
秋吉洞近隣の美祢市には是清洞、中尾洞、大正洞などの鍾乳洞もある。
「秋芳町には別府厳島神社があって、弁才天が祀られていました」
「別府って」
「秋芳町に別府と言うところがあるのです、小さなひなびたいい神社でしたけど、そこで降りて社を見ていると、ちょうど神社の人がいて、話をしました、おもしろいことを聞きました。その神社にも、火美胡から、秋芳洞という書を奉納してもらったということでした。その人が言うには、火美胡が大きな人の毛で作ったありがたい筆で書いたものだということを言っていました。氏子の方だったようです」
「どうしてありがたいの」
「その昔、火を噴く山の神をなだめるのに、髪の長い女性を生贄に差し出したと言う伝説があり、やがて娘ではなく長い娘の髪をお供えするようになったそうです。神がながくながく静まっていてほしいと言うことで、長い髪だそうです、しかも神がうっとりとするような、美しい娘でなければならないそうです」
「まだ、髪を納める風習は残っているの」
「いえ、火見胡の髪の毛で書いた書が納められたので、今はやらないそうです」
「おもしろい情報だね、それにあの大きな筆、人の毛で作ったのかな」
野霧は詐貸がそう言うのを聞いて、顔を丸くしてビニール袋を差し出した。
「私はこれおみやげ、ハチ公の証拠」
「なにこれ」
「あの大きな筆の毛です」
「どうしたの」
「私萩焼きの窯元をいくつか回って、またあの実演のあった店に行ったのです、火美胡の書いた書がまだ掛けてあって、大きな筆も隣に吊るしてありました。
それで、私母親にそこで萩焼きの茶碗を買ったんです、ちょっと奮発して、それで、書をそばで見たいといったら、帳場にあげてくれて、一生懸命見ている振りをして、筆にもさわって、ちょっと毛の一本、先をいただいちゃった」
「えーさすが、野霧さんですね、遺伝子検査に回すんでしょ、被害者の毛と同じだったら大変だ」
吉都が顔をつきだした。詐貸も「そりゃすごい、いいみやげができた、薩摩にわたそう」と驚いた顔をした。
それからしばらく話をして部屋に戻った。あしたは博多に向かう。詐貸はフロントに行くと、野霧の採取した筆の毛を宅急便で薩摩に送った。
妣視杞
「下関に行くのには色々なルートがありますよ」
吉都がスマホを見ながら言った。
「バスと電車を乗り継いで早くても二時間五十分、電車だけだと、新幹線を交えて何回も乗り換えて三時間半、山陽本線だけだと一回乗り換えるのですが、4時間ちょっと、どうしましょう」
詐貸はめんどくさいのは嫌いである。
「山陽本線でグリーンにしよう」
そういうことで、長門駅で乗り換え下関に行くことにした。
朝八時に出たが、下関には十二時過ぎた。下関から唐戸桟橋までバスもあるが、三人なのでタクシーででた。大きな市場がある。そこで海鮮丼を食べ、野霧と吉都は瓶入りの煉ウニを買って船に乗った。煉ウニは冷蔵庫に入れるなというほどよく練れたいいものである。関門海峡を五分でわたり、門司港についた。門司港駅は港のすぐそばである。
JR門司港駅は古く一九一四年に建造され、駅舎として重要文化財第一号である。東京駅と同じ建築家によるものではないかと推測されているが、わかっていないようだ。五年ほどかけて、修復し復元される予定である。周りにも古い著名な建築物が立ち並ぶ。三人は船から上がると、そのまま駅に向かった。
門司港から門司にでて、新幹線で博多まで三十分ほどである。それでも乗り替えやなんやかやでついたのは四時近くになった。
博多は三人とも何度か来たことがある。駅の近くの予約しておいたホテルに入り、夕飯をどこかで一緒に食べようということで、ホテルロビーに七時に集まった。
「博多っていっても広くて、倭國神社を調べるのは大変ですね」
「うん無理だね、福岡あたりというだけだから、有名な神社はたくさんあるし、古墳や遺跡もあるし、どこに目を付けたらいいんだろう」
「駅の近くに櫛田神社があります、縁結び」
吉都がホテルでもらったパンフレットを見た。野霧が「三人とももうでないといけませんね」と言ったら、詐貸は「おれはもういい」とそっけない。
「厳島神社は西区の太郎丸に一つ、瑞梅寺川の河口にあります、もう一つは飯塚市鹿毛馬にあります、福岡県に広げれば春日市下白水、田川郡福智町、久留米市御井町、宮若市上大隈、みやま市高田町ーーー」
「もういいよ」詐貸がさえぎった。
「あ、これはおもしろい、博多西区の隣の糸島市に、志登神社というのがあります、その神社の中に弁財天がありますよ、それだけじゃないですよ、糸島市に、魏志倭人伝の伊都国があったということです」
「それはおもしろいわね、卑弥呼に関係あるところかも」
吉都のスマホがなった。
「あ、世久さんからメイルが入りました」
「なんだって」
「事件の相談です」
「萩のことは薩摩に連絡してあるよ、筆の毛をとても喜んでいたよ、犯人かどうかは別として、調べているはずだよ」
「いや、違います、別の事件のようです、先生のPCのメイルに薩摩さんが送るそうです」
「何で、急に、大変な事件なのかな」
「いや、博多の事件のようです」
「ちょっと、部屋に行こう、一緒に来てよ」
博多の町へのお出かけは少しばかりおあずけになった。詐貸は部屋のデスクにおいておいたPCを開いた。
「博多で起きている事件のようだよ、見たら電話くれとある」
「どんな事件ですか」
「ハチ公の事件だから、変な事件なことは確かだな、眼が盗まれている」
「なんですか、それ」
「遺体から目玉が盗まれているそうだ」
二人ともびっくりした。
「怪奇映画にはでてくるけど、本当にそんなことする人がいるんだ」
「だけど、眼をとってどうするんだろう、眼をかざっておくとすると、腐らないようにしなければならないけどな、医学部ではホルマリンにつけるのが一般でしょう」
吉都が首を傾げている。
「この一年だそうだ、昨日もあったらしい、俺たちが博多に行くと彼にメイルしたせいだ、薩摩のやつ都合がいいとおもって連絡してきたようだ」
「被害者というか、ご遺体はどういう人ですか」
「よくわからないな、ちょっと薩摩に電話するよ、その辺すわっていてよ」
狭いビジネスホテルだから、野霧と吉都はベッドにこしかけた。
詐貸は電話でしばらく話をしたあとに、
「俺、明日、博多の警察の人に会いに行かなきゃならなくなった。また話を聞いてくれと言うことだよ、ハチ公の事件はおかしいのばかりでやだね」
「世久さんのメイルだと、眼の宝石も盗まれているようですね」
「宝石」
野霧がひし形の驚いた顔になった。
「そうらしい、ダリの宝石でできた眼だ、薩摩のメイルにもある」
「あの有名な奴ですか」
吉都が世久の書いたメイルをもう一度開いた。
「ダリの宝石類は、昔、秋葉原の電気屋が有名なものをみんな買ったらしいですね、一時店舗にダリの宝石ミュージアムをつくり、その後鎌倉にミュージアムが移ったのだけど、資金難でつぶれて、宝石類はどこに行ったのか表にはでなくなった、個人が所蔵しているらしいが、そこから眼の宝石が盗まれたようですよ」
「それが博多」
「いや、それは違うようです、持ち主の住んでいるところは言えないそうです」
野霧が不思議そうな顔をした。
「おかしいですね、それはふつうの盗難事件ですね、ハチ公が担当するものじゃないですね」
「博多のは本当の人の眼だよ、ダリの宝石とは違う話だ」
詐貸が困ったような顔をしている。
「まさか髪の毛のように、催眠術で寝ている人の眼をとるのじゃないでしょうね」
「いや、民間の霊安室で死体から盗まれている、福岡でね」
「何にするのでしょうね」
「宝石じゃないけどね、福岡では義眼も盗まれているようだ」
「ガラスの義眼ですか」
「うん、アンティークだよ、今は純粋なガラスで作られているわけじゃないらしい、合成樹脂だよな、だから昔の義眼を集めている人もいるらしい、それに、人形の眼も盗まれているようだ」
「それが福岡で起きているのですか」
「うん、この一年、急に警察への訴えが多くなったらしい、義眼、死体の眼、人形の眼」
「おかしな事件ですね、警察から帰ったらお話聞かせてください」
「うん、今日はこれから三人で櫛田神社に行くか、ホテルから近いからな」
野霧さんはふふんとなんとなく笑顔になった。
大きな神社だった。櫛田神社にお参りをして、街中の食堂でカレーライスを食べた。詐貸が食べたいといったからだ。
次の朝、詐貸はタクシーを拾って警察に向かった。
「野霧さんどこにいくの」
吉都はどこに行っていいのかわからないようだ。
「倭國の神社って言ったって、こんな大都市に放り出されても探せっこないし、半分慰労旅行でしょ、吉都君好きなところに行けば」
「うん、だけどわかんないな」
「私について来ても、博多人形のお店を回るくらいよ、一つほしいんだ」
「それじゃ、僕もくっついていく」
野霧は笑った。
「いいわよ、甘いモンたくさん食べさせてもう少し太らせてあげる」
地下に地下鉄が走っている大きな通りを歩いて天神の方向に向かった。
天神の地下街にはいったが、ごちゃごちゃと広く、同じような店ばっかりで、どうしようもない。土産物屋に博多人形はいくらでも売っているが、のぞく気がしない。
吉都がスマホを出した。
「博多人形の制作者はたくさんいますね、県指定の無形文化財の人が何人もいます。若い人も多い。大きな店もありますよ、博多区中州の博多人形会館松月堂、川端の増屋」
「うーんどうしようか」
野霧も困った様子だ。
「まあ、歩きましょうよ、大壕公園の方に行きますか、店もあるしのぞきながら」
二人はまた地上にでた。
歩いていくと、人形を売っている店はちらほらあったが、大都市だ、東京とさほど変わらないブディックなどが軒並みある。
ふっと、野霧が足を止めた。近代的なギャラリーで、創作博多人形展開催とある。
「ちょっと見ていこう」
中はかなり広く、いろいろな博多人形がおいてあった。創作というから、かなり現代風のものかと思ったら、そうでもなく、確かに今の服を着たものなどがあるが、それなりに落ち着いていて、飾っておきたいようなものが多い。
ひときわ目についたのが、人とほぼ等身大の大きな博多人形である。一つは昔ながらの、巫女の格好をした女性である。紅い袴を着たその人形を見たとき、野霧も吉都も、萩で見た書道家の火美胡を思い出した。
しかし、顔を見た野霧は口元を引き締めた。ちょっと怖いと思ったのだろう。吉都ですらぎょっとなっている。目が描いたものではなく、ガラスだからだろう、眼球が人の目そっくりにはめ込まれていた。
「恐ろしいものを作るわね」
「そうですね、こんな大きなもの焼くのも大変だろうし」
女性の店員がそばによってきた。
「趣味で作っていらっしゃる方ですけど、このあたりでは有名な、眼のコレクターでもいらっしゃいます」
今日、詐貸から眼の話を聞かされたばかりである。二人ともちょっと身を乗り出した。
「どんな眼を集めていらっしゃるの」
野霧が聞くと、係りの女性は「あらゆる眼です、人形の眼や眼の彫刻、絵、義眼、コレクションの展示会などもたまになさいます、このギャラリーでも一昨年おこないました」
「それではこの人形はその方が作ったわけではないのですね」
「いえ、そうです、博多人形も作られます、それに集めた眼をはめ込むのです」
「こんなに大きな博多人形を焼くのは大変でしょうね」
係りの人は博多人形の作り方を丁寧に説明してくれた。博多人形の歴史は古く、1600年代に土人形として作られ、今の博多人形になったのは1800年代で、二百年以上前、江戸時代になる。粘土で型を焼き、型に粘土をいれ、とりだして焼き、貝殻の粉である胡粉をつける。岩彩などで彩色をするのが本当の博多人形だそうだ。今は型をつくるのに、石膏をつかい、おみやげ品などは、胡粉や岩彩ではなく、合成絵具のようだ。
「この大きな人形は、部分部分の型を作って、焼いたものを粘土でつなぐのですけど、つなぎの部分はバーナーで焼くとおっしゃっていました」
「売っているのですか」
「小さいものはお売りになることもありますが、この大きい人形はご自分のコレクションルームにおかれることと思います」
「公開しているのですか」
「残念ながらしておりません、個展をなさるときにお出しになります、小さいものは向こうの常設コーナーにあります」
店員に案内されて、一般の博多人形のならべてあるところに行った。創作ものだけではなく、古典的な作品も並べてある。
「これです」
店員が教えてくれたのは、動きのあるかわいらしい童の博多人形だった。ただ、眼はガラスがはめ込まれている。ちょっと異様ではあるが、新しい感覚だろう。
「私、ふつうのかわいいのほしい」
野霧がそういうと、中堅どころの作品だという、手鞠を持った童女の人形を示して、「この人は伝統工芸師ですが、何度か賞もとっている方です」
と店員が教えてくれた。
「それじゃ、それください」
野霧が頼むと店員は笑顔になって、「おみやげですか」とききながらレジに行った。
吉都が小さな声で「値段みたの」と耳打ちした。野霧はこっくりうなずいて「おかあちゃんに」と答えている。八万円もするものだ。
野霧が博多人形を包んでいる店員に聞いた。
「あの、硝子の眼の作家さんはなんとおっしゃるのですか」
「妣視杞さん」
野霧と吉都が顔を見合わせた。またひみこだ。
「妣視杞さんはガラス工芸もなさいますので、ご自分で眼を作ることもします、博多人形の工房もおもちです」
「今、どこかで妣視杞さんの眼の作品を見ることができるでしょうか」
「博多人形は私どもの店だけですが、ガラスの方は、大濠公園の脇のギャラリー「火眼、ひめ」にあります」
包んだものを手提げにいれ、野霧に渡しながら店員が言った。二人は店員からその場所を教わって外にでた。
「野霧さん高いもの買いましたね」
「こういうのって、やはりいいものを買わないと、結局、ちょっと置いておいて、すてることになるのよ、それなりのものだと、見ていても飽きないし、たとえ仕舞っておいても、いつか取り出したとき新鮮に感じて、また飾りたくなる」
そういうものかもしれない。
「野霧さん、あの妣視杞って作家、気になったのでしょう」
「うん」
野霧の顔が五角形になっている。かなり興味を持っているようだ。
「詐貸所長、警察からどんな話持ってくるのですかね」
「そうね、どう、目玉の勉強のために、火眼っていうギャラリーに行ってみる」
教わった通りに歩いていくと、火眼はすぐみつかった。小さなビルの一階にある、ガラス張りの近代的な店である。紅い目玉の看板がよく目立つ。
中に入ると、さほど広くはないが、いろいろな目玉が並んでいる。目玉だけというのはなんだか気味の悪いものである。若い人たちの作品のようだ。
「はじめてだわこういう眼の展示会は」
「僕もです」
「きれいなものね、身体の一部って、怖さもあるけど、きれいで魅力のあるものなのね、眼っていうのは心の中を映し出すわけだから、人によって違うだけじゃなくて、そのときのその人の心を写す目になるのね」
「動物だってそうですよ、猫だっていつも違う、そのときどきに変わりますよ、きょろんとした目をしてこちらを見ると、ああ遊びたいんだなとか、ネエっといった眼は餌がほしいんだなとか」
「生物学ってそんなこと習うの」
「今の生物学はそういうこと教えてくれません、化学物理になってしまっています」
「眼でも耳でも鼻でも、造形はそれだけで何かを訴えるでしょう、その役割とは違ったものを」
「そうですよね、動物の身体そのものが、誰が作ったかわからないけど、作品ですね」
「人間は神様の作品、神様は人間の想像物、どこまで考えてもメビウスの輪ね」
「宇宙の怪物の映画があるでしょう、誰かが空想して考え出した怪物なのに、深海や化石に同じようなものがいる。結局人間の想像力は神の想像力なんだ」
「いいこというわね、人間と神はイコールか、哲学のおもしろい命題」
硝子でできた眼は、作者の頭の中にあるものを映し出してもいる。それだけで、優しさ、怖さ、寂しさを感じさせる。
「富山の氷見己は身体全体、萩の火美胡は髪の毛、そして、ここの妣視杞は眼、なんだかつながりがありそう」
「奇妙なことですね、ハチ公の犯罪は卑弥呼が指図しているような」
「でも、ここの妣視杞が、眼の盗難と関係があるとまだわかっていないでしょ」
二人でもそもそ話していると、店員がよってきた。
「いかがですか、ブローチもありますし、イヤリングもあります、ヒトの眼だと気になる方は猫ちゃんの目もあります、猫の目を作る作家さんのものは結構売れますのよ、その方は、飼い猫の写真を持って行くとそっくりに作ってくれます」
「あの、妣視杞さんの硝子の眼はどこにあるのかしら」
たくさん並んでいて、見つけだすのは大変である。
「あ、あちらの棚すべてそうです」
アンティークの木の棚を指さした。一番目立つ、どっしりとしたイギリス製らしい棚だ。妣視杞の作った硝子の眼はそこに並んでいた。ヒトの眼そのもののような硝子の眼である。
「妣視杞さんのは特別扱いなのね」
「オーナーの作品ですから」
「え、このお店は妣視杞さんの店なの」
「はい、仁(に)田原(ったばる)美芽さんのお店です」
「妣視杞さんはにったばるていうの、珍しい名前」
「そうです、本当は目医者さんです、古くからの土地の方たです」
それを聞いた二人はまた顔を見合わせた。毛筆家と同じ境遇だ。
「妣視杞さんのは値段が付いていませんね」
吉都が聞いた。
「はい、眼は売りません、博多人形の小さいものはお売りになっていますが、このギャラリーにはおいてありません」
「猫の眼はどれがいいでしょうか」
吉都は買うつもりになっている。
「眼に興味があるのね」
野霧がちょっと笑っている。
「世久さんにおみやげ、こういうの好きそうだから」
「それじゃヒトの眼の方がいいんじゃない」
「猫が好きなようです」
そう言って、小さなガラスの猫の眼のついた指輪を買った。
「ガチャの指輪しかあげなかったから」
吉都が変ないいわけをしたので、「婚約指輪がいいんじゃない」と野霧は声を出して笑った。
夕方、三人で焼き肉屋にはいった。
「先生、どんな話でした」
「うん、刑事の話だと、遺体から眼が盗まれているということなんだ」
「女の人ですか」
「今回は女二人、男一人」
「両目ですか」
「うん」
「だけど、おいておいた遺体から眼を取り出すのは時間がかかるでしょ」
「三十分から四十分だそうだ」
「結構早いんですね、それにしても遺体のところでそんなことはなかなかできないでしょう」
「遺族が、病院から戻った遺体の眼がおかしいと気がついたんだ、それで義眼とわかって警察に電話したらしい」
「義眼がはいっていたのですか」
「そうみたい」
「病院では何と言ったんでしょう」
「病理解剖が終わった後、霊安室に運んだそうだ、病理解剖で眼はいじっていないということだった、しかし取り出す時間はどこかにあるね」
野霧が博多人形と硝子の目玉のギャラリーに吉都と行ったことを話した。
「それで、創作博多人形のギャラリーで、等身大の巫女さんの人形があって、眼は書いたのではなく、義眼でした。その作者は、妣視杞といって」
「ひみこだって」
詐貸が声を上げた。
「はい、富山、萩、そしてここもひみこです、だけど字が違いますけど、それで、その妣視杞さんは、硝子で眼を作る作家で、ギャラリーのオーナーでもあってそこに行きました。本名は仁田原美芽、眼科のお医者さんだそうです」
「また医者か、だがその人が犯人ということは言えないからな」
「調べてみる価値はありますね」
「うーん、我々の仕事じゃないから、薩摩に知ったことを伝えるだけにしよう、ここの警察にそのことを言うのはあまりにも関係する証拠がないからね」
「確かにそうですね、倭國神社の方が本当の仕事ですものね」
「それで、糸島市の志登神社にいくほうがいいかもしれません」
吉都が提案した。
「そうだな、明日、糸島市にいって、それから野霧君の八女に行こう」
ということになった。
神社はJR筑肥線の波多江にあるが、四十分ほどかかった。博多から地下鉄の姪浜でJFの筑肥線に乗り換える必要があるが、地下鉄空港線の直通電車があるので博多から一本でいけた。駅から志登神社までは歩いて二十分ほどかかった。
落ち着いたいい神社である。
「ここは海からはかなり離れているわね」
「でも、千年も経つ神社ですよ」
「豊玉姫をまつっている神社でしょ、豊玉姫は海の神様でしょう」
「そうですね、小さいけど見晴らしのいいところに、厳島神社もありますね、糸島は糸島市と博多西区から構成されていて、大昔の糸島は本当の島だったようですね、この神社のあるあたりは砂洲の麓のだったのかもしれない」
「この地区は福岡市西区と糸島市一部からなる旧いと地区だそうです」
「伊都国のあったというところね」
「いとの曽根や三雲には遺跡群があります、曽根のワレ塚古墳、銭瓶塚古墳、狐塚古墳は千五百から千六百年前の古墳時代のもので、いろいろ出土しています。三雲の密倭南小路古墳は二千年前で、弥生中期後半とでています」
吉都がスマホで調べあげた。
「今日は太宰府まで行くから、あまり時間がないし、タクシーでそのあたりまわってもらおうか、ただ見るだけになるけど、雰囲気は大事だからな」
詐貸の提案でそうすることにしたが、タクシーが通らない。結局駅まで戻って乗ることになった。
あわただしく遺跡群をみて、天神に戻るともう二時をまわっていた。西鉄の駅まで歩き、サンドイッチを買って電車に乗った。太宰府までは三十数分でつく。今日は太宰府で一泊して、八女に行くという算段である。
「日本は至る所に古墳や遺跡がありますね、それ以上に神社があるのはおもしろいでしよ」
野霧はサンドイッチを口に入れて話している。
「だいたい有名な神社の神様は日本書紀に書かれている神様ばっかりでしょ」
吉都はもう食べ終わっている。
「そうよ、ということは、ギリシャ神話の神様は世界創世のお話だけで、祀られていないようだけど、西欧の人たちは現存したキリストを神に祭り上げて、宗教ができて、教会がつくられたのだわね、まあなくなってからだけど現人神のようなもの、日本人はギリシャ神話に相当する日本書紀のお話を信じて、それを祀った神社を造ったのだから、どちらかというと、架空の話を信じて神社を造ったわけ、日本人はお話を信じたのよ」
「それが、日本の平和なところだな、政治をやる人たちが日本書紀の神を利用したんだな」
詐貸が珍しく口をはさんだ。
太宰府ではホテルに荷物をおいて、天満宮にお参りに行った。
ホテルに戻ると、詐貸に薩摩から電話があった。
「今、天満宮に行ってきたところなんだ」
「いいねえ、探偵さんはいろいろなところに行けて」
「神社で飽きちまったところだよ、なんだい」
「萩の筆の結果がでたよ、女性の毛だ、しかも被害者の一人の毛と一致した」
「萩の警察には連絡したのかい」
「ああ、連絡はした、だが、これも事件にはならないかもしれないな、被害者が動かないようだ、それに、萩の精神科の女医さんは人気がある人らしくて、おいそれと手が出せないような雰囲気だな」
「またかい、ハチ公の扱う事件は、事件もおかしいけど、犯人が分かっても決着が付かないのばかりじゃないか」
「そうなんだ」
「博多の方の目玉の事件を報告しようと思っていたこともあるんだ、刑事からあらましは聞いたよ、俺たちの目的は頼まれたことを調べに来たんで、目玉の盗難に関してはなにもわからないけど、野霧と吉都がおもしろい女をみつけた。眼科の医者でね、義眼や人形の目玉を作ってもいるし、集めてもいるようだ。その女性は等身大の博多人形をつくって、義眼をはめ込んでいる」
「そんなのがいるんだ」
「しかもね、妣視杞っていうんだ、本名新仁田原美芽、俺たちは明日八女に一泊して帰る、そうそう、博多の刑事に妣視杞のことは言っていない。そっちで言ってよ」
「ああ、わかった、誰か博多の方にやるよ」
「世久さんか」
「いや、地学に詳しいのがいるからね」
「何で地学」
「義眼や宝石類は石だろう、地学が役に立つさ、そいつはもちろんコンピューターも強いが、古生物、地球、宇宙に詳しくてね、目玉の化石なんかもよく知っている」
「目玉って」
「昆虫から恐竜、そいつ等の化石の眼だよ」
「変なのがいるんだな」
「宙(ちゅう)夜(や)央(おう)って男だ」
「犯人を見つけそうな名前だな」
「いやどうなるかな、その妣視杞って気になるな、ともかくありがたい、とっかかりになるよ」
「それじゃ、帰ったらまた連絡する」
そういった会話を、詐貸は太宰府の酒処で二人に話した。
八女までは西鉄で久留米駅まで行き、そこからバスで四十分ほどかかった。
「私来てみたかったんだ」
野霧は満足そうだ。母親が好んで飲んでいるお茶は八女から取り寄せている。ガイドブックでは、古くからの町で、昔の家並みが保存されているという。それも見たかったのだが、卑弥呼の邪馬台国があったという説もあるところである。五、六世紀の八女古墳群やいろいろな神社もあると書いてある。
吉都がスマホを見て、
「八女には二、三世紀に八女大国があって、日御子という支配者がいて、八女の人を全国に送りこんだとありますよ、八女古墳群は日御子の配下の豪族の墓のようです、三百もあるみたいです」
「そこが邪馬台国なのかしら」
「そうとは言えないようですが、そう信じている人もいるようです、さらに八女には八女津神社が森林に囲まれたところにあるようで、森林浴にはいいパワースポットとあります、八女津姫神が祀られていて、このあたりを支配していた女神のようです」
「女の支配者ばっかりね」
「松尾弁財天という神社もあります」
「卑弥呼臭いね」
詐貸が言った。
「でも、倭国神社とどうつながるのでしょうね」
「まあ、今回はらしい場所を楽しんで帰ればいいよ」
萩から福岡の旅は嵩丸にたのまれたことの下検分である。結論を持って帰る必要はない。
「岩戸山古墳が大きいようですね、八女津姫神社もいいところのようだし、松尾弁財天は厳島神社だし、全部行くのは無理だな」
「古墳の資料や、神社の資料を集めたら、後は好きなように回ってよ、俺はこのあたりをふらふらする」
「私、お茶買えばそれでいい」
野霧は八女に行けると張り切っていた割におとなしい。まあるい顔がちょっと小さくなっている。疲れているようだ。
「うーん、、八女津媛神社は岩穴の下にあって、その岩穴は、例の天照大神が隠れたという天の岩屋という説があるようだし、この女神さんは八女のあたりではかなりあがめられていた神のようだから、僕はそこに行ってみる、神仏混淆のようだし、松尾神社もおもしろそう、写真を見ると地衣類のついた鳥居を入り、石段を登って高いところにあって、いい神社ですよ、白蛇もまつっている、両方行けるかな」
そういいながら、吉都は八女津媛神社に行った。
詐貸と野霧は町をぶらぶらした。
「お茶を買いませんか」
野霧は詐貸を誘って、お茶屋にいった。野霧は決まっていたようで、すぐにお目当ての茶を買った。詐貸はうろうろしている。
「先生は買わないのですか」
「うーん、いや、うちではあまり飲まないので、一年前買ったのが残っている」
「あら、やだ、それ、事務所に持ってきてください飲んでしまいましょう、おいしいのを少し買ったらどうですか」
「うん」
あまり気乗りのしないような返事である。
「愛子さんに、お土産いいんですか」
「うん、今ノールウェーにいる」
「また行ってるんですか」
「そうみたいだ、著者に会いにいってる」
愛子が訳しているノールウェーの推理幻想作家は、写真を見る限り、ずいぶん格好いい男である。詐貸所長はちょっと複雑な気持ちでいるのかもしれない。
「事務所にうちの費用で少し多めに買っておいてよ、むしろそこから少しもらっていくよ」
詐貸はやっぱりおとなしい。萩でも博多でも何も買わなかった。
「ハチ公にはいりませんか」
「そうか、それは俺が買おう」
ちょっとその気になった。
次の日、博多にでて新幹線で東京に戻った。
二人には一日休暇を与えたが、詐貸は次の日に事務所にでた。郵便物もそんなにないし、PC持参の旅だから、デスクのPCを開いても新しいものはない。
詐貸は薩摩に電話を入れた。
「お、帰ってきたのか、萩の件では助かったよ、それに博多の件もわかってきたよ、ただ解決には至らないけどな、おまえさん方が太宰府と八女に行っているときに、うちの宙夜が博多に飛んでいな、聞き込んできたよ、向こうの刑事も協力してくれて、ほとんどわかった、やっぱり犯人というか、おまえさんたちが怪しいとふんだ、妣視杞が関係していたよ、どうだい、馬場にでもでないか、詳しく話すよ」
「うん、いいよ、八女の土産を渡そうと思ってたところだ」
その夕、馬場のいつもの飲み屋で薩摩と会った。
「長い旅だったな、なにを依頼されていたんだ、嵩丸弁護士だろう」
「うーん、依頼人の昔を探すように頼まれたというところだよ」
「そりゃなんだい、先祖探しか」
「そんなところだ、情報が少なくて、日本の何カ所かを当たらなければならないんだ」
「旅行ができるのはいいな」
「わからないならわからなくてもいいという楽な依頼でもあるけどな」
「おかしな依頼だな」
「今回は、あいつらの慰労もかねていてね」
「そんなところに、用事を頼んでしまって悪かったかな」
「いいや、ちょと刺激になって、あいつらも結構楽しんでいたよ」
「いい助手たちだよな、筆の毛をとったのは野霧さんなんだろう」
「うん、萩の火見胡は吉都の推理通りだったんだ、博多の方も妣視杞に気がついたのはあの二人なんだ、博多人形から眼のギャラリーでいろいろ聞いてきたんだよ」
「そうなのか、それでな、博多の妣視杞、仁田原美芽はな、ずいぶん古い家柄の目医者でな、相当腕が立つらしい、博多の大学病院では教授格でひっぱろうとしたこともあったらしいし、今でも大きな眼科ではなんとか来てもらおうとしているが、本人は非常勤でちょっと働いているだけなんだ、後は人形づくりや硝子細工だ。義眼や人形の眼を作っている。それだけじゃなくて、相当のコレクターのようだ」
「それで、死体から眼を盗んだのは彼女だとわかったのか」
「いや、なんといったらいいか、彼女が主犯という訳じゃないし、犯罪になるかならないか瀬戸際の仕事だ」
「なんだいそりゃあ、萩のほうもそうだったじゃないか」
「富山もそうだったな、目を盗まれた死体は三件、一件は若いきれいな娘、白血病でなくなった、もう一件はIT会社をおこし活躍していた男、かなりの金持ちだ、年は三十五、脳出血だ、最後の一人は画家だ、六十七の男だが、現代アートの旗手だった人だ、信奉者がたくさんいる、自動車事故だ」
「それで、なぜ妣視杞がその三人の眼を必要としたのだ」
「妣視杞は頼まれたのだよ」
「だれが頼んだのだ」
「若い娘は恋人が頼んだ、ITの男は奥さん、画家は信奉者のとある大会社の社長夫人」
「そいつ等は眼をどうしようとしたんだ」
「そこなんだ、仁田原は体の組織を特殊な透明な樹脂にいれ永久に保存できる方法を知っていた」
「そんな方法あるのか」
「ほら、昆虫や蟹なんかを透明の樹脂に埋め込んで、売っていたりするの知らないか」
詐貸はそういうことに疎い。
「生物学者、医学関係者はその方法はよく知っているんだ。動物の身体を顕微鏡で見ることができるようにするのに、なんミクロンという薄い切片にしなければならない、それは樹脂をからだの組織や細胞のなかに浸透させて堅くして、鋭い刃で薄く切るんだ、その技術を改良して、目玉を丸ごときれいに透明の樹脂にいれることが、彼女はできたんだ。それを知った眼を保存しておきたいと思ったその三人が仁田原美芽に依頼したわけだ」
「でもどうやって取り出したんだ」
「死んだ病院で取られたのだろうと思う、そのうち二人は仁田原美芽が非常勤で勤ていた病院でだ」
「仁田原がやったのか」
「それはわからない」
「宙夜が病院関係者から訊いたところ、亡くなって、病理解剖をするときとや、安置室に移されてからも、遺体に近づくことができる時間はあったようだ、さらに、自宅に遺体が帰ってからも時間はあったようだよ、今回はそれはなかったようだが、眼球を取り出して、義眼を入れるのはたやすいようだから短時間でできる」
「だけど、誰が警察に訴えたわけ」
「それが、訴えたのは娘の姉妹や、男の兄弟、それに画家の奥さん、義眼になっているのに気がついたんだ、それで、どうしてかと病院にたずねたようだが、病院からはそんなはずはないと言われ、警察に訴えたというわけだ。警察の方は義眼になっていたことを確認し、病院などにも問い合わせたが、自宅にもどった後ではないかと言っていたようだ」
「眼をとるように依頼した者は周りには内緒で、妣視杞に頼んだのだな、でもよく、そこまで調べたな」
「宙夜も勘が良くてね、それで、ほら、逢手さんと吉都君が行ったという「火眼」だっけかな、ギャラリーにいったら、猫の目玉が樹脂に入れられて置いてあったそうだ、ギャラリーの店員に話を聞くと、大事にしていた猫の眼だと言うことで、妣視杞がガラスの眼を作り、樹脂にいれたということだ。本物にそっくりでしょうと、店員は言ったが、宙夜はおかしいと思ったらしい、それならば眼だけでいいのに、なぜ樹脂にはいっているのだろうというわけだ。これは本物だと思ったんだ、きっと医者の妣視杞は同じように人間の眼も作っていると踏んだわけだ。妣視杞が犯人と確信し、その店が重要な手がかりだと思い、警察手帳をかざして、盗品を探しているので、迷惑をかけないからと、来店者や購入者の名簿を見せてもらったわけだ。すると白血病でなくなった娘の恋人の名前、IT社長の奥さん、画家の信奉者たちの名前が浮かんできたそうだ」
「それで、依頼者がわかった」
「うん、みな博多の人間だったので、その人たちと直接会ったそうだ、画家の信奉者はなにも知らないと言ったが、娘の恋人とIT社長の奥さんは、涙ながらに話をしてくれて、大事にしまってある眼をみせてくれたそうだ」
「それで、その人たちを捕まえるのかい」
「娘の恋人と、IT社長の奥さんは、自分から兄弟姉妹に説明しますと言うことだったのでまかせることにした、それに画家の信奉者というのは、画家の奥さんと懇意にしていた女性でね、彼女には奥さんに言うように説得するつもりだよ、きっと訴えは取り消されると思うよ」
「そうなんだ、それにしても宙夜君というのはすごいね、二日でそれだけのことをしてしまうなんて」
「うん、頭の中がおかしいんだ、話しているとすっ飛ぶよ、おもしろい知識もたくさんあるしね、特に宇宙ね」
「なに、宇宙って」
「隕石も好きで、宇宙の成り立ちを考えている」
「俺とはぜんぜん違うな」
「俺とも違う」
「また、結果をおしえてくれよ」
「ああ、お互い、若い連中にはかなわんね」
結局終電まで飲んで分かれた。
皮実沽
野霧が買ってきた八女茶をおいしく入れてくれた。詐貸が一口飲んだ。
「確かにうまいね、甘みがある」
「そうでしょ、親もそう言ってます、それに萩焼きの茶碗で飲むからますますいいですね」
結局、探偵事務所の三人の湯飲みは、萩から買ってきたものに変わった。客用にと手ごろなのを三つ野霧が買ったのだが、自分たち用にしたのだ。詐貸が余り客が来ないからみんなで使おうと言ったからだ。客に出す湯飲みよりずーっとよいものになってしまった。
「昨日薩摩と飲んでね、博多の眼が盗まれたのは妣視杞が関わっていたということだ、吉都と逢手君にはとても感謝していたよ」
詐貸は薩摩から聞かされた話を二人に語った。
「それにしても宙夜って人すごいわね」
野霧も可也も彼を賞賛した。
「そうだね、それはそうと、萩と福岡の報告を嵩丸さんにしなければならないね」
「神社や遺跡を回ったことなら、私たちでまとめておきます」
「やってくれるかな、ただの旅行記みたいになると困るけど」
「大丈夫です、二人でなんとかします、やっぱり厳島神社とのつながりは気になります、八女の八女津も何かありそうですし」
「うん、一週間ほどしたら、嵩丸さんに書いたものを送るよ、半田の発掘のことも聞きたいし、一度は嵩丸さんの事務所に行かなきゃならないけどな」
「この依頼からなにが出てくるのでしょうね」
「また霧中事件になるのかも」
北京原人の頭骨事件、ミイラ事件、皆解決したようで解決しない事件だった。吉都はそれを霧中事件と呼んだのだ。夢中になって追いかけたのに答えは霧の中で捕まえて、よく見えなかった。ようするにすっきりしなかったのである。
結局、萩と福岡の結果を持って、嵩丸司書の事務所に行くことにした。実際に調査書類を作ったのは逢手と吉都も連れていった。
嵩丸の事務所は世田谷の奥沢にあった。夢久愛子の家があるところである。しかし駅の反対側で、九品仏のある浄真寺の近くだった。二階建てのビルで「嵩丸法律事務所と看板がでている。隣は古くからの屋敷のようで、石塀に囲まれた広い庭には木がうっそうとしげり、大きな平屋の瓦屋根だけが見える。
「愛子さんの家とこんなに近いとは思っていませんでした」
野霧は書類を送っていたので、嵩丸の事務所が世田谷であることは知っていたが、愛子の家の住所は正確には聞いていなかった。
「寺もいいし、このあたりは古くからのいい住宅地ですね、愛子さんはまだノールウェーですか」
吉都の質問にも詐貸は黙ってうなずいた。
嵩丸の事務所はコンクリートではなく、石造りである。かなり古そうである。エントランスの床は大理石で、真ん中にスフインクスの彫刻がおいてある。
一階は会議室のようで、二階に事務所があった。昔ながらの大きな木の戸を開けて、中に入ると、広い部屋には木の机が並べられ、男性のスタッフが数人、書類に眼をとおしたり、PCを操作したりしている。受付の女性が立ち上がり「詐貸先生ですか」と聞いてきた。詐貸が名乗ると、「お待ちしておりました、嵩丸は奥の部屋におります」とガラスのはいった扉を開けた。部屋の中も立派だった。壁三方に作り付けの本棚があり、革製の本がずらりと並んでいる。それを見た野霧が、あまりの本の多さと、立派な本ばかりで、ぎょっと立ち止まった、
古い大きなデスクで仕事をしていた嵩丸が立ち上がった。
「おいでいただいてすみません、半田の発掘がだいぶ進みましたので、その報告にこちらから、そろそろ伺おうと思っていたのです」
秘書の人が来客用のソファーに座るようにすすめてくれた。
「今の弁護の仕事も、後すこしで片が付きそうです、それが終わればもっと先祖のことに集中できるのですけど」
崇丸はそういいながら、彼らの向かいに腰掛けた。
「萩や福岡はいかがでしたか、楽しめましたか」
三人とも何ともいえない笑い顔を作った。
「変な仕事を頼んだので、いけませんでしたな」
「いや、そうじゃないのです、すみません、倭國神社に関わることはなにもわかりませんでした、これが報告書です」
嵩丸はにこにこした。
「そりゃあ、そうでしょう、あの板切れの日本かどうかわからないような地図の赤い丸印しかヒントしかないのですから、当たり前ですよ」
嵩丸は報告書をちらとめくって、「ほう」と野霧と吉都を見た。
そこに秘書がお茶を持ってきた。
「厳島神社に注目されたのはさすがですな、だいたい古事記や日本書紀なるものがどのような背景でかかれたのか、完結したのが七百年代、卑弥呼が活躍したのは二百年代、古事記は古墳時代より前の世にその下地があったはずで、卑弥呼にしろ、豪族たちにしろ、古事記の成り立ちに何らかの影響を及ぼしたのではないかと思いますね、日本書紀に卑弥呼は出てこないと言う説が強いようですけど、出てくる神功皇后が卑弥呼だと言うことを言う人もいる、ヒミコと日本書記という、石原藤夫の著書もありますよ、倭國神社も当然でどこかで卑弥呼ともつながると思います、それどころか、卑弥呼を祀ったものかも知れませんな、あ、お茶どうぞ」
嵩丸もお茶を手に取った。野霧が「これ八女茶ですね」といった。
「はは、そうなんです、詐貸さんの事務所でごちそうになってから、うちも八女茶にしました、どうぞこれもつまんでください」
目の前には、木の器に石衣が積んである。緑がかったものがいくつか混じっている。鶯餡だろう。
野霧がそうっと一つとった。吉都は「骸骨みたい」といいながら口に入れた。
「たしかに」と嵩丸もまじめな顔で一つ食べた。
「こいつが好きでしてな、松露とも言いましてね、要するに茸ですな」
と笑った。
「そうだ、厳島でしたな、海と女神と、なにかありそうですな、それに八女の八女大国、八女津姫、引っかかりますな」
「やっぱり、そうですか」
「実は、半田の神社の跡から、こんなもんが出てきました」
彼はデスクに戻ると、机の下から袋を引き出してもってきた。
「あの小さな神社の跡を十メートルも掘ったのです、するとですな、麻のような布の袋が見つかりましてな、中からでてきたのですわ」
野霧が眼を見張った。
「まさか」
「まさかなんです、これは発掘した大学の連中も知りません」
「どういうことです」
「大学の教授も、あんな田舎の三、四百年ほどの神社の跡では、大したものはでないと思っていたのでしょう、学生の訓練のためにやったようなものです、一メートル掘ったところで土器がいくつも出てきました、かなり古いもので、面白いことに、縄文式のものと、弥生式のものが混じっていました、それに基礎石が並べられていたので、そこで彼らは終わりにして、倭國神社が建てられるずっと昔に、あの場所に何かまつる建物があって、土器はお供えするためものだったという仮説を作り、今解析をしているところです。彼らはそれらに満足してとても喜んでいます。
彼らはその後、二メートルまで彼ら自身で掘り進め、なにもでなかったので終了しました。
今度は私の方で、土建屋に頼み、小型重機を使っていいからもっと下まで掘ってくれと頼んだところ、土がしみこんだ布袋が引っかかってきたわけです」
嵩丸は袋の中のものを取り出し、テーブルの上に広げていく。
女性の長い髪の毛の束、小さな皮袋に入った爪や歯、骨のかけら、眼の形の水晶、それと皮に包まれたもの」
吉都はスマホで写真を撮っている。
「これを広げましょう」
嵩丸が太い指で、皮の包みをほどいた。
みんなえっと目を見張った。
中から出てきたのは金印である。嵩丸が金印の表を上に向けた。
野霧の目が倍の大きさになっている。
『親魏倭王之印』と読める。
「本物でしょうか」
「まだわかりません、表に出しませんから、ご内聞に」
「なんですか」
可也が野霧に聞いた。
「卑弥呼が魏の皇帝からもらったかもしれないものよ、少なくとも卑弥呼は親魏倭王という名はもらったのよ、だけど印はみつかっていない、すごい発見」
「そうですね、一緒に出てきたものの年代などがわかった上で、専門家に見せるかもしれませんが、そうしないかもしれません」
嵩丸は落ち着いたものである、慎重なのか、それとも何か意図があるのか。詐貸はちょっとひっかかった。
「萩で卑弥呼の書もみました」
野霧は萩の美術館の話を始めた。
「え、卑弥呼の書ですか」
嵩丸の目が見開かれた。なぜか驚いたようだ。
「ええ、萩焼きの著名人が作った本の形をした陶器で、卑弥呼の陰部が本の間にあるエロティックなものでした」
吉都が「それに、萩の火美胡という人が、人の毛で作った筆で書をしたため、厳島神社に奉納しました」
「ほう、それもヒミコですか」
「博多でも、妣視杞って人が硝子の眼を作ってました」
「そりゃまた、どうしてその人たちを知ったのです」
「それは」と野霧が言いおうとすると、詐貸が「町を歩いていたら、たまたま陶器屋やギャラリーで見かけたものですから」とちょっと嘘の説明をした。
詐貸が二人に目配せをした。薩摩から頼まれたことは口外できない。二人ともはっと気が付いた。
「あっちの方は卑弥呼の人気が高いから」
詐貸が矛を収めた。
嵩丸は「みんな同じ卑弥呼と書くのですか」と聞いた。
二人はどうしようという顔をしていたら、詐貸が「いや、萩の人は火山の火、美しいの美、楽器の胡弓のこでした、博多のヒミコは女偏に比較のひ、視覚の視、くこの杞でした」
「皆さん卑弥呼にあこがれたんでしょうね」
嵩丸はそう言いながら、手帳に詐貸が説明した卑弥呼の漢字を書いた。
「そうですね」
詐貸がうなずくと、野霧が、
「倭國神社の卑弥呼の金印が本物だったら、水晶の目は卑弥呼の目を形作ったのかもしれないし、髪の毛、爪、歯、骨、みんな卑弥呼のものかもしれないですね」と、掘り出したものに話をもどした。
「そうだとすると、今2011年、卑弥呼が死んだとされるのは250年くらいだから、千八百五十年ほども前のものになる」
吉都が計算した。
「すごいものになりますね」
嵩丸が金印を革に包み始めた。
「その皮なにかしら」
野霧が訊くと、嵩丸はつぶやくように言った。
「人間の皮のようなのです」
「え、まさか卑弥呼の皮じゃないですよね」
「そんなことはないでしょう」
野霧が指で触ってみている。
「どうしてわかったのです」
「皮について、趣味のこともあって、ちょっと詳しいのですよ」
「もしかすると、棚にある本ですか」
「そうです、みんな革装でしょう、革装の本はいいですよ」
「みんな、法律の本ですか」
「いや、聖書も、小説も、図鑑もあります、世界のきれいな革装の本が好きで、集めています」
「でも、人の皮というのはないのではないでしょう」
「いや、あるのですよ、稀ですけどね、イタリアのものを一冊だけ持っています、ところが最近、稀覯本を扱う本屋から、人の皮といわれている豆本が手に入ったのでいりませんかと言ってきましてね、買いました。日本の手作りのものです、外国の本と手触りが同じです」
「人の皮膚も革として使えるのですね」
「東大の医学の標本室に、入れ墨をした皮膚が、かざってありますよ、西洋には有名な人の皮の本があります、人皮装丁本といいますが、十七世紀には人の皮をなめす方法が確立していたようです、ヴェサリウスの人体構造の写本で人皮装丁本があります、どれも稀覯本です、とても手には入るものではありません」
「日本の豆本はここにあるのですか」
「ありますよ、見たいですか」
野霧がうなずいた。
嵩丸はデスクの後ろの棚から木箱を持ってくると、テーブルの上で開いた。箱の中は小さな棚になっていて、豆本が並んでいる。上下で十冊、嵩丸は中の一冊を取り出した。
「小説です、印刷所に活版印刷を頼み、特製の和紙を美濃に注文して、簡易製本し、それに専門家に頼んで、革製の表紙をつけたものです」
タイトルの下に赤い茸の絵が押されている。
「話もすべて自分で書いています、幻想的なもので、すべて茸にまつわる話です」
「だけど自分の皮膚で作ったわけではないでしょう」
高さ五センチ、幅三センチほどの本である。自分の皮膚を使うとなると、片方の腿のかなりの皮膚をとらなければならない。十冊分となると一人分のからだが必要だろう。
「稀覯本屋がいうには、一冊は作者自身の皮膚かもしれないということですよ」
「全部だと、その人は赤裸になっちゃう」
「でも皮膚は再生するよ」
吉都が言った。
「いやだわ、痛そう、ひりひりする」
野霧の感覚はよくわかる。
「高いんでしょう」
野霧が聞くと嵩丸がうなずいた。
「でも、全部で五百万でした」
いとも安そうに言うが、とんでもない値段だ。
「作者が若くしてなくなり、独り者で家族がなかったので、遺産相続した遠縁の者が売りにだしたようです、最初の一冊の本のあとがきに、本人が一週間入院して、自分の腿の後ろの皮膚をとって使ったことが書かれています。後の本は、装丁者に任せたようです」
「それじゃ、残りの九冊の皮膚は誰のかわからないのですね」
「そうですね、死体からもとれますからね」
「犯罪になる可能性もありますね」
「ええ、ただ、金のほしい遺族が承諾するかもしれませんしね」
なんだか怖い話になってきた。
「ああ、どうも、私の趣味の話になってしまいましたな、どうか急ぎませんから、ほかのところも調べてみてください、前も申しましたように、倭國神社の三代目、日魅には姉が7人いたので、ご神体の赤丸と関係があるかもしれません、どうぞ調査を継続してください」
「やってはみますが、難しい仕事です」
「詐貸先生方の暇なときで結構ですから、あのご神体の木に示された場所に行ってみてください、行ってみていただくだけでもかまいませんので」
「そうですか、今回の調査も半分慰安旅行でした、そういうこともあり、経費の半額をただいたものから引かせていただきます」
詐貸が計算書を差し出した。
「とんでもない、どうぞ、全額、調査費用としてください。実はこのような調査というのは、ちょっと余裕をもって見てもらった方が、なにかに気がつくものです、今回のひみこの話は面白かった。他のところも、ゆっくりと、旅行のつもりで行ってください。報告書は大変参考になります、こういう感じでお願いします」
ずいぶんありがたい申し出ではある。秘書がきて、封筒を嵩丸に渡した。それを詐貸に差し出すと、「追加の費用です、使ってください」
詐貸が躊躇していると、「ぜひ」と詐貸の手にのせた。
「あ、それじゃ、わかりました、なんだか、遊んでいるだけのようですみません」
「いや、今度は私の方から先生の事務所に出かけます、あそこの素甘は旨いですからな」
と笑った。
「あ、この娘は秘書の嵩丸夢霧です、姪っ子でして」
秘書は笑窪を寄せて軽くお辞儀をするともどっていった。しゃんとしたモデルのような女性だ。
「詐貸さんこのあたりは初めてですか」
詐貸が答えるのにちょっと遅れると、野霧が、
「駅の反対の方に、詐貸所長の大学の時の彼女がいます」
詐貸が野霧をにらみつけた。
「おお、それじゃ、よくご存じなのですな、なんとおっしゃる方で」
「夢久さんです」
「おや、夢久さんですか、よく存じていますよ、お父さんは、機械を作る会社の社長さんでしたな、お母さんはお茶の先生、お父さんの根付けのコレクションはすごいものでした、見せていただいたことがりますぞ、お父さんは早く亡くなられましたな、お嬢さんは今どうなさっているのです」
「推理小説の翻訳をなさっています」
「そうですか、それじゃ、詐貸さんはよく来られるのですな」
「あ、いや、あまり、さて、そろそろ失礼します」
詐貸があわてて立ち上がった。
野霧と吉都はちょっと笑いたいような気持ちだったのだろう、がまんをしている。
「こちらに来たときには寄ってください、私はいないことのほうが多いかもしれませんが、夢霧がお茶くらいなら差し上げられる」
嵩丸弁護士は包みを野霧に渡すと、愛想よく三人を送りだした。
道にでてから野霧が包みを開けてみると、石衣がごろごろ入っていた。吉都が覗き込んで笑っている。詐貸はぶすっとしている。
「所長、嵩丸さんは夢久さんをご存知だったのですね、これから何かとやりやすいですね」
野霧が言っても、ぶすっとしている。
「愛子さんノールウェーからいつ帰るのです」
吉都が聞くと「知らない」と一言答えが返ってきた。
「愛子さんの訳しているノールウェーの推理小説家のお嬢さん、愛子さんとずいぶん仲がいいみたいですね、二人でノールウェーのトロールの歴史を調べているみたいですよ」
それを聞いた詐貸の顔の緊張がちょっとほぐれた。
「俺はそんなこと聞いたことないよ」
「私、愛子さんと、メイルやりとりしているんですよ」
「ノールウェーの作家って、そんなに大きな娘がいるの、新進作家じゃないの」
「大学の教授をしていて、リタイヤーしてから書き始めたということです」
それをきいてから、詐貸の顔がすっとした。著作には作者の若いころの写真があったのだ。ちょっと妬いている。単純まじめなんだから、野霧は笑いたかったけど我慢した。
事務所に帰って、詐貸は薩摩に電話をした。ちょっと気になっていたことがあったからだが、ずいぶん長い電話である。
野霧と可也は来客用のテーブルのところで、もらった石衣を食べながら、何の話だろうと、ちらちら詐貸をみる。
小三十分ほどもしゃべっていただろう。詐貸がやってきた。
「薩摩にね、ちょっと、人の皮で作った豆本のことを聞いたんだよ、あいつが驚いてね、何で知ってるんだと、逆に聞かれたよ。ハチ公にも一年前から、情報が入っているらしい、ただ、犯罪としてではないらしいよ、皮膚を買う人がいるということだ、結構いい値でね、ただ、二十代から三十代の女性から買うらしい、二十五センチ四方で三十万円だそうだ」
「誰か売った人がいるのですか」
「いるらしいとしかわからないそうだ」
「何にしているのですか」
「ハチ公たちも、小さいものを作るのだろうと調べたそうだ、すると、革装の豆本作家が何人か浮かび上がっているそうだが、どの作家の作品も人の皮を使ったものはないようだ」
「とすると、嵩丸さんの本の作者を探すとわかるでしょうね」
「うん、それで、嵩丸さんの趣味は内緒でもないだろうし、薩摩も嵩丸弁護士のことは知っているので、彼が人の皮をつかった豆本を最近買ったことを伝えたよ」
「すると、薩摩警視は嵩丸さんに連絡するのでしょうね」
「彼じゃなくて、スタッフの誰かだろうね、犯罪じゃないし、参考のためということになるね」
それから一週間後だった。事務所に薩摩から電話があった。
「文学部心理学から看護学部にはいりなおして、看護婦の資格を取ってから、警察官の試験を受けて、科学捜査室にはいって、ハチ公のスタッフになった女性がいるんだ、高胎蓉子(たかはらようこ)といって、仲間の中では一番年上で、三十三歳、トリックアートの専門家だそうだ。その彼女が嵩丸さんからうまく豆本の出所を聞き出したようだ。ある本屋から聞いたので一冊売ってくれと連絡したそうだ。そうやって話をしていくうちに、稀覯本屋の名前を聞き出してしまった、その本屋に今度は、警察の顔をして行って、犯罪性がないかどうか調べるとして、作者の名前をききだしたそうだ」
「すごいですね、それでなんて言う名前です」
「驚くなよ、皮実沽、本名、國武美藻、皮膚科の医師、趣味で革装丁本を作っている。依頼されれば作るそうだ、自分用のものも作っているが、革装の豆本のコレクターでもあるようだよ」
「また、ひみこ、ですか、それに医者、コレクター」
「ああ、浜松にすんでいる」
「知多にもさほど遠くない、静岡はご神体の木にマークがありましたね」
みんなだまりこんでしまった。
「嵩丸弁護士もその装丁家のこと、知っていたんじゃないかな、皮装本のコレクターなら知りたいと思うことだろう」
詐貸がぽつっと言った。
痺弭弧
「八公の仕事はヒミコばっかりですね、それと嵩丸さんの依頼が重なりませんか」
吉都が野霧のくれた雪見大福を食べながら言った。詐貸は富山にいつもの会議に出かけている。愛子さんも一緒のようだ。二人も誘われたが、九州から帰ったばかりだし、事務所で今までの結果を整理しますと断った。
「偶然には思えないわね、嵩丸さんのご神体に指図されているようね」
最近雪見大福に種類が増えて、野霧はチョコレートのはいった新発売を食べている。
「ヒミコと言う人を追いかけると、嵩丸さんの倭國神社の歴史に関係するかもしれませんね」
「そうかもしれないわね」
「嵩丸さんの祖先もなんだか、ヒミコあたりにつながってきそうな気がするけど」
「そうね、倭國神社の最後の子どもは、月足日美っていったわね、知多からどこに行ったのかしらね、それを調べるのもいいわね」
「それと、嵩丸さんそのものの先祖をおってみるのもいいと思いますよ、そのへんやってみますよ」
「そっちは、私がやるわよ、吉都君、ハチ公の世久さんと連絡取って、他のヒミコの事件がないか探ってよ」
「そうですね、野霧さんの仕事も手伝うから言ってください」
「情報がまとまってきたら、お願いするわ」
吉都は世久希紅子に、ひみこ事件はどうなったかメイルをうった。
「萩と博多のヒミコ事件は、あれから蒸し返されることなく終わっています、それで、ヒミコが気になったので、似たたような事件がないかチェックしました」
世久の返事である。八公もすでにひみこを気にしている。
「事件そのものは見つかりませんが、奈良の友人が、ヒミコというネイルアート作家がいると、教えてくれました。奈良や熊野周辺で活動しています。ただ、これは我々のところに報告されてきたものではありませんので、事件ではありません。ヒトの爪を玉虫のように使って、箱に張ったり、そのまま飾ったりしています。マネキンの手に、本物のヒトの爪をつけたりもするようです。左手を事故で失った、とある女優さんの本人の爪をつけた、木でできた左手が、個展で飾られたりしたそうです」
博多の目玉の妣視杞に似てなくもない。
「どこに住んでいる人ですか」
「詳しいことは知らないみたいです、話をきいただけで、私は調べていません、吉都さん調べてくださいますか」
「はい、やります」
吉都は早速、奈良のネイルアート関係者を調べた。ネットではネイルアートと検索すると、爪に模様を書くファッションの方の作家がたくさん出てきてしまって大変だったが、その中にはヒミコらしきものはいなかった。
爪をキーワードにしたら、美容室やら、皮膚科、それに琴の店がでてきた。やはりヒミコにつながるものはなかった。琴が上がってきたのは、琴の爪によるものだ。琴の爪は合成樹脂系で作られているようだが、昔は象牙である。
どのようなキーワードがいいのか、考えあぐねた可也は、萩の時のようにギャラリーに着目した。爪、つめ、ネイル、nailで調べたが、そのような展示や、もうようしものはひっかかってこない。
奈良県にギャラリーはいくつくらいあるのか調べてみると意外と少ない。
「これじゃ、なかなか、みつからないな」
吉都が独り言を言っていると、野霧が「なに開いているの」と聞いたので、「奈良県のギャラリー」と答えると、「今までのひみこさん、有名になりたいという感じはなかったでしょう、ひっそりとやってるから、見つけにくいのよ、ギャラリーじゃなくて、もっと市民的なもようしをチェックしてみたら」
「そうですね」
「そういう文化的なもようしは、大きな町や市でおこなわれるものね、奈良県なら、奈良市や橿原市あたりね、奈良市には、その昔、平城京があったでしょう、それより前は平安京よ、藤原京ともいうわね、それは橿原市や明日香村あたり、倭國神社のご神体もその当たりを指しているのかも知れない」
「平安京や平城京はいつごろです」
「六百年終わりから、七百年はじめ」
「卑弥呼の四百年あとですね」
「うん、だけど日本書記は720年頃完成しているようだから、藤原京よりあと、平城京に移ってからね、日本書紀より少し前に、古事記もあるし、その前にもいくつか歴史を書いたものもあるようよ、現存していないみたいだけど」
「やっぱり、奈良市や橿原市は大事なところですね、そのあたりにしぼりましょう」
それでもギャラリーはあまりないようだ。
「えーい、厳島神社でいこう」とさすがの吉都も疲れてきたようだ。
「ありますね、厳島神社が、ちいさいけど、橿原線の畝傍(うねび)御陵前駅から歩くみたい、まだほかにもあるようだ」
「橿原は奈良県でも大きい都市だからたくさんあるかもね」
「そうですね、畝傍御陵前というのは神武天皇陵からきた名前ですね、畝傍山があり橿原神宮もある、あ、お琴のプログラムが載っている、発表会のようだ」
「なにに」
「橿原神宮の近くの、神社関係の施設のようです」
「どうして驚いたの」
「これどうようむのだろう」
野霧が椅子から立ち上がって、吉都のPCをのぞいた。お琴のプログラムの最後に、痺弭弧と言う演奏者の名前ある。
「これ最初の漢字は、麻痺の「ひ」でしょう、次のはわからないけど、三つ目は弓の「弧」でしょう、真ん中は耳や弓だと、み、と読めるかもね」
「ひみこですよ」
「ほんとね、世久さんの友達が言っていたヒミコかもしれないわね」
「その人はネイルアートでしたけど、ともかく世久さんに報告します」
次の日に吉都に希紅子からメイルが入った。
「奈良県警に問い合わせをしました。痺弭弧という人は、趣味でお琴を弾く人で、素人と言っても、町の演奏会にはときどき顔を出す玄人はだしの人です、私の友人が言っていた人のようで、古いお琴の爪を集めていますけど、自分でも爪を使って、象眼をやったり、石膏づくりの手首の指先に模様を書いた爪をつけて、アート作品を作っています。爪は樹脂でできているようですけど、前にも書きましたが、怪我や病気で腕や手首を切らなくてはならなくなった患者さんに依頼され、本人の手とそっくりなものを作って、本人の爪をはめ込むそうです。患者さんには喜ばれているようです。
本名、室園美弓、皮膚科のお医者さんです、五條にすんでいます」
「また、医者だ、五條に住んでいるんだって、五條ってどこだろう」
野霧に聞くと教えてくれた。
「五條は奈良から、電車で奥に行ったところで、吉野川が流れているところ、桜も有名ね、熊野に近くなるわ」
「古い町なんですね」
「倭國神社の情報もそのあたりにありそうね」
「世久さんのメイルにおもしろいことが書いてありますよ」
「それで、ヒミコをぬかして、医者、アート、蒐集と言ったキーワードで、過去五年の事件をもう一度あらってみたのだけど、参考と言うフォルダーに、カタツムリの収集家の女医のことがありました、なぜうちに情報がきたかというと、耳の奥に蝸牛管というのがあって、これが骨に囲まれているそうで、カタツムリのコレクションにそれも飾ってあったと言うことらしい、警察が気にしたようよ。頭蓋骨の耳のところを壊さないと、とりだせないんだって、甲木(かっき)美夜と言う、島根の耳鼻科医のお医者さん」
「蝸牛管って、平衡に必要なものでしょう」
そのへんは、生物学をやった吉都がよく知っている。
「そうです、取り出すのが大変だそうです、ご遺体から取りだしたんですね、お医者さんじゃなきゃできないですね、きっと、解剖学の教育用に取り出したものなんでしょう、耳鼻科なら必要かも」
「おもしろい名前、蝸牛管なんて」
野霧が興味を示した。
「音を感じるところなんですよ、蝸牛管には平衡感覚を司っている三半規管がつながっている」
「カタツムリのような形してるの」
吉都が、蝸牛をPC画面にだしてみせた。蝸牛は骨で、その中に蝸牛管が入っている。
「あ、思い出した、高校の生物の教科書でみた。なんでかたつむりの形してるの」
「音を伝えるのにはこれがよかったんでしょう、中にはリンパ液が入っているんですよ、音は空気の振動でしょう、外耳道から空気振動が入り、鼓膜をゆらすと、その奥、中耳の小さな三つの骨をゆらして、最後の骨が、蝸牛管の膜をゆらし、中のリンパ液を振動させる、そのゆれはカタツムリのような管の中を伝わって、カタツムリの先に行く。カタツムリ管にはそのゆれを感じる感覚細胞があって、その情報が神経細胞に伝わって、脳にいき、音として感じられる」
「よく知っているわね」
「生物学ではあまり教えてくれないけど、古本屋で医学部の教科書を買って調べたことがあるから、高い音はカタツムリ管の入り口、低い音は先っちょで感じるから、低い音を感じるときも、入り口の感覚細胞が働くわけ、だから高い音を感じる細胞が疲れやすいので、年をとると高い音が聞きにくくなる」
「すごい、すごい、勉強になるなあ、耳くそはその感覚細胞のカスかしら」
野霧がそう言ったので、吉都が大笑い。
「それおもしろい、でもただの皮膚のゴミ」
野霧がまじめな四角い顔になった。
「島根も赤丸のところ、倭國神社に関係ないとはいえないな、出雲大社があるものね、十月には神さまが集まるところよ」
「まさかヒミコじゃないでしょうね」
「詐貸所長が帰ってきたら、話してみましょうよ」
ハチ公の変な事件と、嵩丸弁護士の依頼、なんだか奇妙に共振している。
二日後に詐貸がもどってきた。
「北京骨商ではだいぶ研究が進んでいるようだよ、一つは魚の改良で、肉がたっぷりついたタイだとか、脂ののったサンマだとか」
北京骨商では魚の骨から漢方薬を作っているが、魚そのものの改良も試みている。
「長寿の遺伝子の方も進んでいるようだ」
その会社で働いている人は、北京原人の血が流れていて、問題は短命のことだった。そこで、寿命の遺伝子の特定をやっている。これは北京骨商の研究所の人と詐貸たちしか知らないことだ。
「先生の留守の間に、八公の世久さんから、奈良の五條に爪を集めている皮膚科のヒミコ、と、島根にカタツムリを集めている耳鼻科の女医がいるという話がきました」
吉都が報告したが、詐貸が「なに、それ」とぴんとこないようだ。
「嵩丸さんの依頼と、ハチ公のヒミコの事件とかぶるところがあるって、吉都君が調べたんです」
詐貸もうすうすは感じていたが、その可能性は頭の中では意識的に否定していた。
「一応離して考えておいたほうがいいよ、だけど、奈良も島根も行ってみなければならないところだよな、来月、それぞれ分担して、行ってみてもらおうか、どのような場所かみておいてもらうのもいいだろうから」
「はーい」
野霧の顔が丸くなった。うれしいのだ。
「吉都君どっちにいく、そうか、カタツムリだものね、島根でしょう」
「野霧さん、奈良に行きたいのでしょう、歴史ですものね」
野霧はうんうんと大きくうなずいた。
野霧が奈良に行った時の様子は次のようなものである。奈良に行くに当たって、忠犬ハチ公の世久希紅子の友達を紹介してもらった。爪のひみこと奈良の町のことを聞こうと思ったからである。
奈良に着いて、ホテルから希紅子の友達に連絡したら、次の日の昼休みに、ホテルに来ると言うことだった。
十二時の待ち合わせなので、少し前に、ロビーの椅子に腰掛けて出入りする人を見ていた。白バイの制服を着た警官が入って急いで入ってきた。フロントから従業員があわてて出てきて、話をしている。何かあったのだろうか。
警察官は手で違うという仕草をした。警官はヘルメットをはずし、サングラスをとると、ロビーの方を指さした。女性だ。その女性警察官はつかつかと、野霧の方に向かってくる。
背が高い、まるでモデルさんのようだ。
「逢手さんですか」
それを聞いた野霧はぎょっとした。
「希紅子より聞いています、紅(あか)酒(き)野実と申します」
世久の友達が警察官だとはきいていなかった。よく考えれば、希紅子も警察官なのだ。
「逢手野霧です、お仕事中すみませんでした」
「いや、今日の午後はフリーなのですが、この近くでの事故処理が長引いて、着替える暇がなかったので、とりあえずこのまま来てしまいました。すみませんが寮に戻って、着替えてきますので、三十分ほど待っていただけますか、お腹がお空きでしょうから、食事の後にお会いしてもいいのですが」
「あ、いえ、ご一緒に食事させてください。三十分でいいんですか、もっとゆっくりでもかまいません」
「大丈夫です、十二時四十分頃、もどってきますので」
そういうと、彼女はさっそうとホテルから出て行った。
かっこいい女性だ。野夢はちょっと気後れした。
三十分後に戻ってきた紅酒は、全く別人のようだ。赤いスーツをぴしっと着こなして、外資系会社社長秘書だ。
「どこか外に行きますか、それともホテルにしますか」
「ここで、ゆっくりお話しできればと思います」
逢手と紅酒はホテルのレストランにはいった。
紅酒はサンドイッチを頼んだのだが、逢手はオムレツとパンを頼んだ。
「希紅子とは警察に入ったのが一緒だったのです、彼女は大学院を出てから、科学捜査に興味を持って入ったのすけど、私は女子大を出て交通警察官になりたくて入ったんです、最初警視庁の新入生の集まりで知り合って、よく一緒に飲みました。逢手さんも警視庁ですか」
野霧はちょっとあわてた。
「あ、いえ、私は探偵助手をしてます、警察の人間ではありません」
「あ、そうですか、希紅子がすごい推理力のある人だと言っていたので、てっきり警察の方と思いました」
「いえ、うちの探偵事務所の所長が、世久さんの主任と大学のサークル仲間で、おつきあいがあるものですから、八公さんの人たちとも飲んだりします」
「ハチ公って、希紅子のいるところですか」
そう言って、ああと言う顔をした。納得したようで野実は笑った。
「確かに、第八科学捜査室ですね、それで、ネイル作家の痺弭弧さんのことをお知りになりたいということですね、だけど、希紅子がこなければいけないことなのではないですか」
「あ、説明しなければいけませんでした、私は別の依頼の調査に奈良の方にきたのですけど、ついでに痺弭弧のこともということだけなのです、ある依頼人の祖先のことで、神社など古い遺跡などを見て回るつもりです。五條にも行くつもりです」
「そうですか、痺弭弧が目的じゃなかったのですね、奈良は古い町で遺跡だらけでしょう、公共交通で行くのは大変ですよ、レンタカーが便利です」
「車の免許はないのですけど」
「明日は私の休みの日です、レンタカーでごいっしょしましょうか」
「あの、私オートバイなら免許持ってます」
「そうなんですか、バイクなら私のを使ってもらってもいいのですけど、大きいから」
「大型免許持ってます」
紅酒はちょっとびっくりしたようだ。
「それなら、私のを使ってください、700ですけど大丈夫ですか」
「ええ」
「私は彼のバイクでいきますから、明日は奈良の古いところをまわりましょう、今日はこれから、そのネイルアートのおいてあるところをご案内します」
「いいんですか」
「ええ、結構退屈なんです、古い都は」
そう言うと、紅酒はふっと立ち上がって、請求書をつかんだ。野霧はあわてて追いかけて、自分が払うと言ったのだが、彼女はもう財布からお金を渡してしまった。
「希紅子からもてなすように言われています」
「すみません、だけど私、出張費でてますので、どうぞ気にしないでください」
「それじゃ、夜ごちそうしてください、いい焼鳥屋があります」
「あ、もちろんです、私そんなに飲めませんけど」
本当はかなり飲める口だが、実野の振る舞いを見ていると、とてもかなわないと思った野霧が、あわてて口にしただけの事である。
紅酒野実はさっさとホテルから出ていく。
「遠いんですか」
「いえ、歩いて三十分ほどです」
驚いた野霧はちょうどきたタクシーに手を挙げた。
「みんな必要経費で落ちるので、これでいきましょう」
三十分歩くのは野霧にはつらい。紅酒は笑顔でタクシーに乗った。
痺弭弧の作品の展示は、美容室の一角だった。一般にいう、爪の手入れ、ネイルアートをしている店のようだ。雪実美容室とある。
野実がガラス戸を押し開けて、ずかずかとはいった。入り口にいろいろなものが飾ってあり、そこをすぎると、爪ケアーのカウンターがあり、さらに奥が美容室になっている。
店員が野実をみて「いらっしゃいませ」と声をかけている。
野霧は入り口に飾ってある、ネイルアートの見本を見た。隣にきれいに磨いた爪をびっしり張り付けた木箱がいくつかおいてあり、五万円の値札がつけてある。化粧道具を入れる箱だ。その隣には、手首が二つならべてあった。マネキンの手だけである。爪がきれいにつけてある。作者、痺弭弧、とある。
野実が店員をつれてきた。
「せっちゃん、説明してあげて」
店員に気軽に頼んでいる。
「逢手さん、ここのオーナー、日田(ひた)雪(せつ)美(み)」
紹介してくれた。店員じゃなくて店主だった。店に自分の名前を付けたのだ。若いチャーミングな小柄な人だ。
「この手は頼めば作っていただけます、型でつくるのは十万ですが、木で作ると片方で五十万します。爪は注文者の手の写真から、そっくりに樹脂で作ります」
「頼む人がいるのですか」
「多いのは、ディスプレーで使いたいという人で、指輪などを売っている店の方です、あとは、手首の先をなくした方ですが、その場合、本当の爪が使えれば使います。多いのはお子さんのかわいい紅葉のような手、七五三の記念に作ってもらって、記念にするおじいちゃんおばあちゃんもいます、その子がおとなになって、本人もなつかしいと思いますよ」
「ねえ、この作者、お医者さんだって」
野実が主人に気軽に声をかけている。
「うん、五條で皮膚科をしているのよ、大昔からのお医者さんの家なの」
「お琴もするんでしょ」
「それで爪を集めているのよ」
「どうして、このお店に作品があるのかしら」
野霧が聞いた。
「私どもネイルのケアーをしていて、あるとき、五條から観光に見えた方が、ここで爪を磨いたのですけど、爪が病気のようでしたので、皮膚科に行くようにおすすめしました。そのお客様が、ご自宅のある五條の皮膚科に行ったら、ちょっと怖い病気のはじめだったようで、治ってからお礼に見えて、室園皮膚科のことを教えてくださいました。その人から院長先生の作品のことをお聞きしたのです、一度ここで、爪に関わる展示をやったことがあって、お誘いしたら来てくださって、それ以来常設にしていただきました」
「そうなんだ」
「野実さん、興味があるのですか」
「いや、東京からきた逢手さんが爪の芸術見てみたいって、お連れしたのよ」
「紅酒さん、ここの常連さんなのね」
野霧が野実の指をみると、真っ黒のマニキュアをしていた。
「美容院にきているの、たまに爪もきれいにしてもらいます」
「黒が好きなんですか」
「白バイに乗っているので、白か黒に塗ります、これは自分でやっています」
彼女に捕まった暴走族の若者が、彼女の爪を見たらどう思うだろうか。おそらく尊敬の眼で彼女を見て、はいはいと言うことを聞くに違いないと、野霧は想像した。
「この人に会えませんか」
野霧はオーナーに聞いてみた。
「時間が合えば大丈夫だと思いますけど、お忙しいようですよ、病院は日曜日と木曜日が休診で、土曜日は午前までです。夜はよくお琴の会に出てらっしゃるようですし、休みは工房で爪の作品を作っていらっしゃるという話です」
「逢手さん、明日五條に行ってみましょう、ちょうど木曜日だけど工房は見せてもらえないのかな」
「オープンにはしてないみたいだけど、依頼人にはみせているようだから、私から電話してみましょうか」
日田雪美は電話をかけに奥にはいっていった。
「明日は、工房で制作しているそうです、午後、見に来てかまわないと言うことです、工房の地図がありますから差し上げます」
「ありがとうございます」
野霧は礼を言った。
「野実さんもいくのですか」
「うん、今日はこれから、兄貴のところに行くわよ」
「そうですか、ありがとうございます」
「雪美ちゃんありがとう」
ずいぶん親しそうだ。
「まだ三時半か、準備している最中だけどいいか」
野実は独り言を言いながらギャラリーからでて、通りを歩き始めた。
「町をぶらついて、焼鳥屋にいきましょう」
それから、結局三十分ほど町を歩き、名物の大きなどらやきの店や、鹿の角細工の店を教えてもらい、横道の小さな居酒屋の戸を開けた。まだ暖簾がでていない。
「二人よ」
大きな声を出した。小さなカウンターと、二人席が二つある狭い店だ。
カウンターの中から背の高い男がニョッキリ立ち上がった。
「はええなあ」
「うん、知ってる、煮込みはまだ途中よね」
「うん、あと三十分はおいとかなきゃ」
「焼き鳥はできるの」
「串には刺してあるよ」
「東京からのお客さんなの、なにかない」
「それじゃ、焼いてやるよ」
「頼むね、こちら逢手野霧さん」
「らっしゃい」
百九十はあろうと思われるがっしりした男だが、顔は柔和な奈良の鹿のようだ。
「日田雪(せつ)林(りん)、せっちゃんのお兄さん」
あの美容室のオーナーの兄貴か、妹は小柄だが、兄はずいぶん大きい。
「美容室に今お世話になってきました」
野霧が挨拶をすると、野実が「明日、奈良と橿原まわって、五條に行くの、バイクかして」
「いいよ、自分のはどうしたんだ」
「逢手さんに貸すの」
雪林がおっという顔で野霧を見た。
「何にのってるんです」
「トアイアンフの古いのです」
「いい奴だな、俺のを逢手さんに使ってもらったらいいや、川崎だけど」
「うん、そうしようか、それでいいですか」
野霧はもちろんとうなずいた。教習所では川崎の車で練習した。
席について、明日の計画を話していたら、焼き鳥が焼けた。頼まないのに生ビールもでてきた。
「やっぱり、白バイ」
雪林がビールをおきながら聞いた。野霧は首を横に振った。
「東京の有名な探偵社の方よ」
野実がいうと「かっこういいな」とカウンターにもどっていった。
彼のバイクを借りると言っていたから、雪林が野実の彼氏か。何となく納得した。
「食べましょう」
彼女はジョッキを片手にぐいと飲み、焼き鳥をほうばった。野霧も同じようにしてみたいが、彼女のように格好良く飲めない。
それにしても塩の焼き鳥はおいしかった。
「おいしい鳥ですね」
「ゆきりんが自分で飼ってる鶏だから」
自分で飼っている鳥を、絞め殺して肉にするのは、自分にはできないな、と野霧が思っていると、
「ゆきりん、自分じゃ手を下せないから、業者におろしているんだ、世話は行き届いているから、ほしい業者はたくさんいるんだけど、はし切れと臓物をただでくれる業者に売っているんだ。だから、焼き鳥の材料費はほとんどただ」と野実が笑った。
「養鶏場をやってるんですね」
「それが違うの、オートバイのレーサー」
ずいぶんいろいろやっている人だ。
「だけど、痺弭弧って人、お琴もやるというのは知らなかったな、希紅子から話を聞いたけど、変な事件ばかり調べているって、いやがっているようだけど、楽しそうだ」
「世久さんはエネルギッシュな方ですね、それに三度も求婚されて、指輪をもらったけど、結婚にいたらなくって、指輪集めているって言ってましたね」
それを聞いて、野実は大笑いした。初耳の様だ。
「爪を集めるよりいいかもね、それで、明日最初に五條に行きますか、それとも、先に奈良市や橿原市でどこかみたいところがありますか」
「五條に行ってみましょうか、痺弭弧という人と話してみたいし、五條の厳島神社に行ってみたい」
「厳島神社に何かあるのですか」
「いえ、そう言う訳じゃないんだけど、いつの間にか厳島神社が頭に巣くっちゃって」
「厳島神社の霊が乗り移ったわけですか、海の女神は何にでも化けるかもしれないから」
「なぜでしょう」
「女は化けるもの」
それを聞いていた、雪林がうなずいている。
「おれ、てっきり男かと思ったもんな」
「なにさ」
実野が怒った。
雪林ができあがった煮込みをもってきた。
「俺捕まったんだ、こいつに、スピード違反で、たった十キロしかオーバーしていなかったのに、てっきり男の警官かと思ったら、女だったんですよ、まいったな、すごいスピードで追いついてきて、止められちまった」
「一所懸命ぺこぺこあやまって、何とか見逃してくれって言うから、だめっていったら、罰金払う金がない、ってしょげてたから、お金貸してあげたのよ」
「あのとき、鳥インフルエンザで、飼っていた鳥はすべて処分、もうだいぶ前の話ですけどね、立て直すのに借金だらけ、この店も始めたばかり、そのとき、この店は休業しましてね、その二年後に再開して、そのあとはなんとかやってます」
「なかなか返しにこないからあきらめていたら、この店が再開したときに返しにきて、利息にと、焼き鳥をごちそうしてもらってからの付き合いですよ」
なれそめは納得した。
「どうして養鶏場をはじめたんですか」
「いや、おやじがやってたんで、兄貴と俺が手伝っていて、そのまま養鶏をしているだけですよ、ところが兄貴は畜産大学にいって、養鶏場を継がなくて、今大学の教授、俺はしかたなしにやってる、おふくろは美容室をやってて、妹がついだんですよ、オートバイは趣味」
「ねえ、雪ちゃんのところで、爪の箱の展示があるでしょう、作者に会ったことある」
「うん、寄ったときにたまたまいたことがある、日本風の顔をした女性だったな、雪女みたいだと思ったな」
「色が白いってわけ」
「うん」
「挨拶したの」
「ちょっと話したけど、感じがよかったな、四十にはなっていないだろうな」
「五條のお医者さんなのよ」
「へえ」
「明日、会いに行くの」
「何しに」
「爪の細工を見せてもらうんです」
雪林がそう言った野霧の手をみたので、あわてて隠した。
「それに、倭國神社のことを調べているんです」
「ゆきりん知ってる」
「聞いたことはないな」
その日は、焼鳥屋「ゆきりん」で、鳥茶漬けを食べて野実と分かれた。次の日は野実と雪林、本当はせつりと読ませるらしいが、バイクでホテルに九時に来てくれることになった。ヘルメットは野実が二つもっているので貸してくれる。
次の朝、ホテルのロビーで、ブルゾン、ジーパン姿で野霧がまっていると、野実がはいってきた。真っ赤なスラックスに真っ赤なジャンパーだ。
「おはようございます、駐車場に止めてあるから行きましょう」
野霧が駐車場にいくと、真っ赤なバイクの隣に、雪林が真っ黒なバイクにまたがっている。
野霧が挨拶をすると、雪林が彼のバイクにのってみてくれと言った。野霧はまたがると、オーケーのサインを出した。
「俺は、野実に店まで乗せてもらうので、そこまで付き合ってください」
彼は野実のバイクの後ろにまたがった。
「それじゃいきますよ」と、野実がエンジンをふかし、野霧も久しぶりにバイクのキーをまわした。
天気は悪くないし、お巡りさんと一緒だし、安心だ。
焼鳥屋、せつりんの前でいったん止まり、雪林はおりた。
「夜、よかったらまた食べにきてください」と雪林は店の中にはいった。
「逢手さん、京奈和自動車道路で行けば五條まですぐだけど、どうします、ゆっくりと、下の道に行きますか」
野実がたずねた。
「おまかせします」
「それじゃ下の道を橿原までいって、橿原の明日香村でもみて、ちょっともどって、普通の道路で五條までいきましょう」
そう言って、野実がエンジンをかけた。野霧もあとにつく。
24号線をかなりゆっくりとすすんでいく。きっと野霧に気を使ってだろうと思ったら、197号線にはいると急にスピードを上げた。80キロでている。30キロオーバーだ。だがすぐに50キロにもどした。緩急交えて野実はバイクを滑らせていく。
橿原の表示がみえてきた。橿原の町はかなり大きい。
交差点の手前で野実が停車の合図をして止まった。野霧があとにつけると、
「ここから、橿原神社にいけますが、よらずに明日香村にいってみますか」と聞いた。特に考えていなかった野霧が「明日香村に行ってみたいわ」と答えると、「それじゃ155号線をすすみますよ、山の中のようなところです」
「はい、橿原の見たいところを特に考えてこなかったので、様子だけ見ることができればと思います」
「それじゃ、ツーリングを楽しみましょうか」
左折して、155号にはいった。しばらく行くと、明日香村役場前で、野実がバイクを止めた。
「このあたりが、飛鳥時代の都のあったところですか」
「そう、大昔し栄えた場所です、もう少し先までいったら、15号にはいって、奥明日香の宇須多岐比売命(うすたきひめのみこと)神社にいってみましょう」
「何の神社ですか」
「私はよく知らないけど、一度行ったとき雰囲気のあるいい神社と思った、ただ190段の石段を登らなきゃならないから大変だけど、それと、15号線は桜井明日香吉野線といって、吉野川にでられるので、そのまま川沿いにいけば五條に行くわよ」
「それはいいですね」
二人は15号線に入った。ところがほんの五分もすすんだとき、カーブを曲がったところで野実がスピードを緩めた。道の先に砂煙が見える。
近づくと、車が二台ひっくりかえり、一台から白い煙がでていた。
実野はゆっくりとバイクを道の脇に止めた。
「事故だから、私ちょっと見てきます」
バイクを止めた野霧にそう言って、かけだしていった。手にもつ携帯を耳にあてている。
野霧もバイクから降りてあとについた。
軽乗用車が道の端で横転し、ワゴン車が脇につっこんでいる。川に落っこちそうだ。5号線は飛鳥川に沿っている。
はじめは気がつかなかったが、バイクが道の真ん中にひっくり返り、ヘルメット姿の男が、道の真ん中にころがっている。三重衝突のようだ。
実野は野霧に「そっちから車がきたら止めてください。上着かなにか降って合図お願いします」と手を振った
「警察にはもう知らせましたから、まもなく来ると思います」
そう言い終えると、軽乗用車の中をのぞき、失神していた野良着姿のおばさんをひっぱりだすと、道の脇に横たえた。
ワゴン車からは、運転していたと思われる男がよろけながら出てきた。
「大丈夫ですか」
野実が「道の端で、しゃがんでいてください」とどなった。そのままバイクの男のところに行き、道のわきにひきずっていった。意識はないようである。
まもなく、小型のパトカーがやってきた。年取った一人の警察官がおりてきて、実野に「あんただいじょうぶかね」と声をかけた。
「警察です」
実野は警察手帳をだした。
「あ、こりゃ」
「手伝いますから、反対から車がきたら止めてください」
年取った警察官はおろおろしている。
まもなく救急車と普通のパトカーがきて、けが人の収容と調査が始まった。
後からきたパトカーの警察官に、野実が現場の状態を説明している。
ふっと、野実が道の脇にたっている野霧にきがついた。あわててよってきた。
「ごめんなさい、現場手伝わないわけにはいかないから、逢手さん、一人でいってください、すみませんけど」
「あ、いいですよ、私も手伝いましょうか」
「いえ、大丈夫です、ここが終わっても、最後まで付き合わなければならないでしょうから、第一発見者ですからね、しょうがない、私は五條には行けないと思います、奈良に戻ってきたら、バイクはホテルの駐車場にいれておいてくれますか、連絡ください、すみません」
野霧は一人で五條に向かうことになってしまった。ちょっと心細いところもある。
パトカーの警察官がよってきた。
「この人も事故にあったのですか」
「いえ、私と一緒に五條に向かっていたところです、私非番ですよ」
「あ、こりゃ、すみません」
「私は手伝いますから、どうしましょうか」
「軽を追い越したワゴンが、前からきたバイクをはねたようですね、ブレーキをかけたワゴンに軽が接触と言うことのようです、ワゴンの男を逮捕しますが、ちょっと怪我をしているので、救急車にのせます」
「バイクは私がどかしましょう、道をあけましょう」
「非番のところすみません」
警察官は処理に走っていった。
「ごめんなさい、逢手さん行ってください」
「はい、大変ですね、それでは私は五條に行って、宮園先生に会ってから、ちょっと回って帰ります」
「15号線をいけば、その神社にも行き着くし、吉野川をいけば五條に行けます」
「はい、スマホ持ってますから、問題ないと思います、大変ですね」
「こんな商売だからしょうがないですよ、気をつけていってください、何かあったら電話ください」
野実は現場に戻って、野霧はバイクを始動した。
それから15号線を走り続けた。
飛鳥宇須多岐比売命神社の入り口らしき石段が見えた。石灯籠が二つおいてある。石に神社の名前が刻まれている。野霧はバイクを止め見上げた。野実が言ったようにすごい石段だ。スマホをとりだして神社を調べた。ご神体は後ろの南淵山とある。祭神は宇須多岐比売命、神功皇后、応神天皇だそうだ。水の女神の雨乞いの神社だ。神功皇后は卑弥呼に関わりがあったんじゃなかったのかしら。野霧はうろ覚えの知識を頭の中からさがしだした。
そんなに車が通る訳じゃないし、バイクを盗まれることもないだろう。キーを抜いて、階段を上がった。
よっこらのぼって、息切れして到着したとこは古びた社だ。意外と広い雰囲気のある神社だ。小さな社もある。これが神功皇后のものだろう。
あまり時間をかけられないので、神社を出るとまたバイクを走らせた。飛鳥川と山に挟まれた道だからとても気分はいい。
やがて吉野川にでた。169号線が沿って走っている。車や人も通る。それからは注意をしながら走った。
看板などに五條の名が出てくるようになり、まず駅に向かった。駅の近くにデパートがあった。駐車場にバイクを入れると、遅い昼を食べるためにデパートの食堂にはいった。久しぶりにバイクで遠乗りしたので、ちょっと緊張もしたし、お腹がすいた。もう一時近い。
カレーを食べながら、そばを通った食堂のおばさんに、室園皮膚科のことを聞いててみた。
「ああ、室園先生、知ってますよ、昔からの病院で、お父さんは内科の先生でしたね、吉野川の近くに大きな病院がありますよ、今の室園先生は皮膚科だから、使わない入院室を芸術工房にして、アトリエとしていろいろな人が借りていますね。先生も何とかアートをやっているそうだけど、あたしゃそっちの方はよくわからないんでね」
「遠いんですか」
「いや、すぐだよ、吉野川に突き当たったら、右の方にちょっと行くと、大きな病院があるから、すぐわかりますよ」
「ありがとうございました」
ここのカレー意外とおいしいと思いながら、野霧は返事をした。
大きな病院なら駐車場もあるだろう。
コーヒーを飲み終えた野霧ははたと思った。みやげも何も持ってきていない。なぜ爪に興味を持ったか聞かれたらどう言おうか。ハチ公のことは口に出すことはできない。よく考えたら野実と一緒でなかったのはよかったかもしれない。
食堂をでてバイクにまたがると、ほぼ頭にはいっていた道をすすんだ。一見、昔の小学校のような南京じたみの建物が見えた。大きく「室園医院」とある。駐車場はすぐわかった。
バイクをおいて、医院の敷地内にある昔の病棟らしき建物に向かった。小学校の建物ような雰囲気だ。室園アトリエとある。白く塗られた入り口を開けると、広いエントランスで、奥を見ると廊下を挟んで小部屋が連なっている。病室だったところだろう。それぞれが貸しアトリエのようだ。
エントランスの壁に、部屋番号と借りている人の名前が書かれている札がつるしてある。
野霧がそれを見ていると、作業着をきたおじいさんが手に何か持って、近くの部屋から出てきた。「どなたをおたずねかな」と野霧に声をかけた。
「室園先生にお会いする約束をした、逢手と申します」
野霧がいうと、「ああ、痺弭弧先生のアトリエなら二階の201ですよ、あがってすぐです、ちょうど今いくとこだったんで、行きましょう」
おじいさんは、しっかりした足取りで階段をのぼっていく。野霧もあとをついた。
201はすぐ角の部屋だった。戸を開けおじいさんが入ると、「あ、先生」と言う女性の声が聞こえた。
「これできましたよ、それにお客さんですよ」
野霧が部屋にはいると、痺弭弧と思われる女性がおじいさんから何か受け取っている。
「よくできていますね、ありがとうございます」
「それじゃ」
おじいさんは野霧にお辞儀をすると、部屋を出ていった。野霧はおじいさんに礼を言い、痺弭弧に向かって、「雪美さんに紹介していただいた逢手です」とお辞儀をした。
痺弭弧は瓜実顔の色の白いすらっとした女性だった。笑みを浮かべながら、「はい、雪美さんから連絡受けました、よくいらっしゃいました、想像していたような柔らかい方ですね、どうぞ、そちらのテーブルでお話し聞きましょう」
野霧が椅子に座って、もじもじしていると、
「今逢手さんを連れてきてくださった方は、よく知られている木彫の先生です、これをもってきてくださったのよ」
野霧の前に木で彫った手首を置いた。動き出しそうだ・
「すばらしいでしょう、私がこれに着色して爪をつけます」
野霧が驚いていると、
「右手を失った女性の手です、その人の爪を私がはずしました、まだ二十歳になったばかりの方で、事故でどうしても上腕を切らなければならなくなったのです、写真をさっきの先生にお渡しして、彫っていただいたのです、もう八十五にもなるのにお元気なのですよ」
と説明をしてくれた。七十くらいだと思っていた野霧は驚いた。
「私にご用というのは、爪のことではありませんね、痺弭弧という名前についてお知りになりたいのではありませんか」
そう言われた野霧はまた驚いた。まだ一言も話をしていない。
「もしやもすると、倭國のことではありませんか」
もっとびっくりした。野霧はやっと声をだした。
「その通りです、なぜそう思われたのです」
「私、なぜかどこか他の人と違うのです、変な勘をもっているようです、このようなこと他の人には言ったことはありません」
切れ長の目、鼻筋が通っていて、薄いけれど赤い唇から白い歯が、声を出すたびにちらりと見えて、野霧は夢の中に誘い込まれるような、気持ちのいいような、怖いような気持ちになっていた。
「その通りなのです、奈良にきた本当の目的は、依頼人の祖先をさがしにきたのです」
「それで、ヒミコなのですね、ずいぶん古いことを探っていらっしゃるのね、警察の方ではないようだし、依頼人がいるということは、相手さんは探偵さんか、歴史家でらっしゃるのでしょうか」
また当てられた。
「探偵の助手をしています、きいてよろしいでしょうか、なぜ倭國のことをご存じだったのです」
「ヒミコに興味をお持ちの方なら、倭國だと思ったのです、私の家に言い伝えられていた話だからです。宮園に嫁いだ娘の祖先は倭國と言う国を治めていたということでした。もう三百年ほど前に、月足と言う名字の女性が産んだ八人の女子の長女が、我が家の先祖と言うことが書かれたものがあります。どこの出なのかもよくわかりません、倭國の女の長を祖先とするようなことが書かれています」
知多の倭國神社の神主の名字だ。日女に八人の子供がいる。
「ヒミコが長だったのですか」
「いえ、ヒミコを敬っていたのではないかと思います」
「奈良も邪馬台国のあった場所として考えられていますが、そういうことでしょうか」
「邪馬台国のことはわかりません、逢手さんもいろいろな神社を見てこられたと思いますが、原始には、山、川、海、空、そこに神が存在していたわけで、神社はずいぶん後になってできたもの、ただ、自然の中にあった神が、実際にいたごとく、神話がつくられ、人の形になり、信仰の対象としてつくりだされ、その神の住処、宿泊所として、神社を造りだしたわけです。しかも、ご神体まであるわけです。偶像ですね。その地域の長が、神として敬われるようになったことは、人間の脳がよりどころをほしかったからでしょう。あるいは、その地域の指導者がそのようにふるまったのかもしれません」
医者らしい解析の仕方である。
「それでは、倭國はこのあたりにあったのでしょうか」
「それはわからないのです、系図は我が家の父方のところしか書いてありません、室園は大昔から、豪族で、薬師の家でした。今も続いているわけです、父は内科医でしたが、もう亡くなりました。私は皮膚科医になったので、入院棟はいらなくなり、このようにアトリエとして使っています」
「嵩丸という名を聞いたことがおありですか」
「嵩丸は新聞に出ている弁護士さんですか」
依頼人の名前は伏せなければならない。
「知多に倭國神社があったのですが、神主の名前は月足、先生がおっしゃった八人姉妹の末っ子が神社を継いだようです、嵩丸は氏子の代表の名前です」
「そうですか、やっぱり、その神社は卑弥呼を祀っていたのでしょうか」
「いえ、それはわかりませんが、その可能性はあります」
「でも、先祖のことがわかって嬉しかったです、もし詳細がわかったら教えてくださいますか
「もちろんです」
野霧は名刺をだした。痺弭弧も名刺を持ってきて渡してくれた。
「美弓先生はお琴もなさいますね」
「ええ、母から教わりました、指はきれいに手入れしなさい、と子供の頃から言われました、琴を弾くとき、近くで見る人は指先を見ます、動く指は優雅でなければならないといわれて育ったのです、それもあって皮膚科になりました」
野霧には皮膚科と爪の関係がわからなかった。そのような顔をしていたのであろう、痺弭弧は「爪は皮膚が変わったものですから」と言った。
「爪は皮膚だったのですか」
「二本足で動くようになったヒトは両手が使えるようになり、細かな作業をすることが出きるようになりました、動物の指に爪があるのは指先を強くするためです。ものを摘まむのに爪があった方がしっかり摘まめますし、動物によっては、木に登ったり、ひっかいたりする道具になります」
野霧は自分の指を見た。爪は綺麗に手入れしているつもりである。
「痺弭弧という名前になさったのは、倭國からつけたのですか」
「そうでしょうね、それだけではなく、ここで育ったので、このあたりの歴史の中で、卑弥呼がかならずでてきて、染み付いていたからでしょう、そう言ったことが信仰の対象にもなるし、私のように芸名にしてしまったりするのでしょうね」
と笑った。
「そのう、系図のようなものを見せていただけますでしょうか」
「いいですよ、古いものは一つの箱まとめてあります、家のほうにありますから、ちょっと待っていてください、とってきます、コピーの機械がここにありますから、撮っていかれていいですよ」
とてもありがたい申し出である。それにしても思っていたことと違う方向に進んでいる。野霧が工房の中の作品をみていると、痺弭弧は古そうな本と巻物をもってきた。
「系図の巻物と、古文書がありますけど、私は古い字は読めません、系図は宮園家が中心です」
野霧があけてみると、ミミズが縦にはったような字でかかれている。少しは古文書の読める野霧にも無理である。
「私も読めません、コピーさせていただいて、読める人さがします」
「わかったら教えてくださいね」
「はい」
痺弭弧が部屋の端にあるコピーの機械のところに野霧をつれていった。
「私はデスクで作業していますので、ご自由にお使いください」
「はい、壊さないように丁寧にあつかいますから」
「気になさらないでいいですよ」
彼女は笑いながら作業にむかった。
野霧が古文書や巻物をコピーしているあいだ、彼女は熱心に手を動かしていた。
三十分ほどでコピーが終わった。
「先生、できました」
「そちらのソファでちょっとお待ちになって、すぐいきます」
野霧がまっていると、プラスチックの小さな箱をもってきて、向かいに腰かけた。
「ちょっと手をだしてくださいな」
野霧は手を美弓のほうに差し出した。
「逢手さん、指が細いですね、爪が綺麗、手入れされていて細い毛などもつまめそう、皮膚がとてもきれい、程々に張りがあって、色も桜がかった白、体の調子はとてもよさそうですね」
「はい、太ってます」
そういったら、美弓は大笑いした。
「やせてはいらっしゃらないけど、でぶじゃありませんよ、指だって細いくらい、きれいな肌、なかなかそういう人はいません、男性の目を引くものです」
「引かれたことありません」
また、痺弭弧は笑った。
「親指と人差し指の、爪カバーを作ってみたので、ちょっと、つけてみてください、調整します」
痺弭弧は箱から、薄ピンクのきれいな爪をとりだして、野霧の左手の親指と人差指にあてた。右手の方も同じようにした。ほぼぴったりと合っている」
「脇と付け根のところちょっと調整しますね」
それをもって、痺弭弧は作業机でヤスリをかけると、もどってきた。もう一度つけると、ぴったりとあった。だけど動かすと落ちてしまう、なにするものだろう。
「爪に張るカラーの人工爪があるでしょう、それと同じですけど、これは作業用です、ちょっと張ってみますね」といって、作った爪の裏に、チューブの糊を付けて、野霧の親指と人差し指に貼り付けた。
自分の爪より先がほんの少し長い。一分ほどすると、「ちょっとこれ摘んでみてください」と一ミリに満たないビーズをもってきた。
野霧が人差し指と親指で摘まむと、なんなくひろえた。
今度はもっと小さなガラスの玉の入った箱を前においた。
いとも簡単に摘むことができた。
「どうです、作業用の爪を開発してみたんです、爪の角度、そり具合、工夫をしたのですよ、細かな作業をなさる方の爪です、まつげ一本でも簡単に摘めます、いずれ売り出すことになります、使ってみてくださらないかしら、一度張るとその日はおちません、マニュキアの徐光液で落ちます」
「え、いいんですか」
「どうぞ、どうぞ」
「ありがとうございます」
「今日はこれから直接奈良に帰るのですか」
「どうしようか迷っています、こちらにも厳島神社がありますから、そこに寄ってからにしようかと思っています」
「厳島神社が倭國やヒミコに関わりがあると思ってらっしゃるわけですね」
お見通しのようだ。
「ええ、海の女神」
「邪馬台国の卑弥呼は、すべての神社に関係しているのではないでしょうか、このあたりだと、飛鳥宇須多岐比売命神社など強く関わっていたかもしれませんね」
「あ、来る時、寄ってきました、途中まで雪美さんの、お兄さんの友達と一緒だったのですが、事故の場面にぶつかって、来れなくなったので、一人できました」
「雪美さんのお兄さんは焼鳥屋さんやってますね、恋人は警察官の人でしょう、会ったことはないけど、雪美さんに聞いたことがあります、きっと私の爪のコレクションが、法に触れてないか気になさっているでしょう、そう言うことはしていないから大丈夫だって言ってください」
彼女は笑いながらそう言った。みんな読んでいる。
「いえ、その人、野実さんは白バイのお姉さんで、そのようなことは考えていません、私、雪美さんのお兄さんのバイクを借りてきたんです」
「あらそうでしたの、まだその焼鳥屋さんいったことがないの、今度いってみます」
「喜ぶと思います、おいしい焼き鳥です、帰ったらそこで落ち合う予定です」
「逢手さんはオートバイなさるのね、いいわね、私も免許とろうかしら」
ずいぶん進歩的な人だ。
帰るときはオートバイのところまで見送ってくれた。
野霧は爪のみやげまでもらって、五條の街中を少しばかり走り、結局どこにも寄らずに奈良に戻った。帰ったときにはもう五時近くになっていた。ホテルの自分の部屋にコピーしたものなどをおいて、雪林に向かった。
暖簾はもう出してあった。入ると客はまだおらず、野実がカウンターの中で彼の手伝いをしていた。
「おや、逢手さん早かったですね」
野美が出てきた。
「ええ、先生のところで随分話をしましたので、五條そのものはちょっとバイクで回った程度です」
「行きは問題なかったですか」
「はい、スムースに行きました。神社にも寄りました、事故の処理は大変だったのではないですか」
「いや、そうでもありません、私は軽を運転していた農家のおばちゃんの付き添いで、いっしょに警察まで行って調書をとる手助けをしただけです」
「警察官はなかなか休むことができませんね」
「あんなもんです」
雪林が聞いた。
「今日は醤油で焼きましょうか、五條には小さいけどとてもうまい醤油の醸造の店があります、それつかってるんです」
野霧は「おねがいします」と返事をして席に着いた。
前に座った野実に指の爪を見せて、爪楊枝のとがった細い先をつまんだ。
「どうしたのです」
野霧は痺弭弧のところでの話を詳しく話した。
「不思議な人のようですね、会ってみたいな」
「野実さんのことも、ここの焼鳥屋さんのことも皆知っていました。一度来てきてみたいといっていましたよ、それにバイクにも興味示されていました」
それを聞いて、雪林が「そりゃうれしいな、バイクも教えてあげますよ」と昨日とは違う味付けの、焼き鳥をもってきた。醤油がとてもうまい。
「おいしいですね」
「その醤油の小瓶、みやげにどうです、うちで販売しているんですよ、ズックの小さな袋にはいってます」
「あ、ください、三つ」
「逢手さんどうして大型のバイク免許持っているのです」
野実がきいた。野霧はテェディーじいさんの事件のことを話した。どうもその話をすると、野霧は喉がつかえる。もっとあのおじいさんとは話したかった。
「生きたままミイラになったのですか」
「ええ」
最後に雪林が鳥の雑炊をもってきた。
そのときには、生ビールがそれぞれ五杯消えていた。
雪林が「よく野実、よく野霧お客さんだ」としゃれをいって、終わりになった。
ホテルで、野霧は詐貸と吉都に概略をメイルした。詐貸から、
「それはいい資料が手に入った、ごくろうさま、一日遊んでいらっしゃい」
と返事が来た。さらに「理由があって、また富山に来ている」とあった。
緋巳壷
野霧が奈良に行っている間、可也はカタツムリコレクターの耳鼻科医がいる島根の浜田にむかっていた。彼はこの医者もヒミコというのではないかと思っている。浜田には厳島神社もあるようだし、今までたずねたところと、どこか似ている。
浜田は以外と行きにくいところである。広島から高速バスで行けば、比較的近いことがわかったが、出雲大社を見てから、浜田に行く予定を立てた。そうすると、どうしても、出雲の飛行場におり、出雲で大社をみて、一泊してJRで浜田に行くことになる。
吉都は、「出雲縁結び空港」と書かれた空港をでた。なんだこれは、縁たって、いろいろな縁があるじゃないか、変な奴と縁ができたら大変だと思いながら、ザックを背負い、出雲市駅に行くバスに乗った。出雲大社は初めてである。
倭國神社が出雲大社とどのように関わりがあるかわからないが、出雲大社には神無月にすべての神が集まるというのだから、倭國神社に祀られている神もくるのだろうか。
倭國神社の祭神が、日本書紀や古事記に出てこない神であれば、出雲大社との関係はないだろう。おそらく地方地方に、個人や家族、または同族しか奉らない神もいるであろう。倭國神社は神社という形をとっていても、日本中にある厳島神社のように大きな組織を持っている神々とは縁がないかもしれない。むしろ、出雲に集まることなど興味がないかもしれない。吉都は自分がマイナーな劇団にいたころが、意外と楽しかったことを思い出すことが多い。食べてはいけないが、やりたいことをやっていた。テレビにも取り上げられている大きな劇団を羨ましいとその当時は思ったこともあるが、今考えると、小さな劇団の意味は違うところにあると思うようになった。倭國神社の氏子たちもこれに似た気持ちを持っていたのではないだろうか。
こんなことを思うのは神社巡りをしているせいだろう。組織の大きさに違いがあるが、出雲大社と倭國神社の神に大きさの違いはない。知られてようが、そうでなかろうが、その神の存在は信じる人にとっては同じだ。
もし、倭國神社が本当に卑弥呼をまつっているのであれば、その名前からすると、もう少し大きな組織になっていても不思議はないような気がする。ということは、何らかの理由で、飛鳥、平安時代の人に、特に権力者たちが、卑弥呼を知らなかったのではないであろうか。今こそ教科書に乗っているが、その当時はそう思われていなかったのか。
そんなことを考えてバスに乗っていると、あっという間に山陽本線の出雲市駅についてしまった。二十五分ほどである。
駅に近いところのホテルを予約している。まだお昼だ。ホテルに行って、荷物を預けると、出雲大社の地図をもらって駅に戻った。あらかじめ浜田に行く時刻表を見た。特急「おき」が一時間に一本ほどある。それだと浜田まで一時間三十五分、各駅停車だと、半額で二時間五十分。やっぱり特急で行くか。三千円ちょっとである。
出雲大社には一畑電鉄か一畑バスでいく。電車の方がおもしろそうだ。彼は出雲市駅舎内の蕎麦屋で出雲そばを食べ、一畑電鉄の電鉄出雲市駅にむかった。すぐ隣である。
一日券があった。それを買うとちょうどでるところの電車に乗り、野っ原を見ながら十分ほどで川跡駅につき、別のライン、大社線に乗り換えた。それも十一分ほどで出雲大社前についた。山が近くに見える。
ずいぶんしゃれたコンクリートづくりの駅だ。中には色ガラスの窓まである。駅から十分ほど歩いたところに、昔のJR大社駅の駅舎が残っているとある。とりあえず行ってみた。ずいぶん立派だ。考えていたのとは違い、社の形をした凝った建物である。なぜJRは乗り入れをやめたのだろう。
出雲大社入り口は、駅から歩いて七、八分のところである。駅をでて道沿いに行くとすぐ鳥居が見えてくる。まっすぐ突き当たりが大社になる。神前通りと言うらしい。松の生えている道をすすみ、四つの鳥居をくぐると大社になる。
これが重要文化財か。吉都は社を見上げた。
出雲大社には大國主の命が祀られている。元は千年以上前につくられた神社だ。そのころは杵築大社と呼ばれていたようだ。
大社の境内にはいくつもの小さな社があり、それぞれ命が祀られている。吉都はそう言ったことをよく知らないが、何処に行っても歴史のある場所というのは何かを感じる。自然でも人が作ったものでも、時が移っても変わらずに存在し、何百年もそのままの状態であったものには、時の垢がつく。それはデパートに売っているものにはない。時の垢がそのものに魅力をくっつけていく。いくらアンティークのような色合いのものを今作り上げても、新しいものは新しい。すぐわかる。
アメリカの魅力はどんどん新しくなっていくところで、なろうと思っても、歴史が積み重なったイギリスにはなれない。日本人は大陸から切り離された島で、大陸からわたってきたホモサピエンスが日本という海に囲まれて、周りからの影響をあまり受けないで作り上げられてきた人間である。日本には独自の時代の垢がついている。今、日本人はその垢をこすり落として、ヨーロッパやアメリカと同じになろうとしている。明治大正はヨーロッパやアメリカを取り入れて、日本の垢の中に刷り込もうとしていた。むしろ外人の方が日本のその垢のよさが見えるかもしれない。
神社仏閣の魅力はペンキではでてこない。意味あるなしはどうでもいい、古事記や日本書紀は本を作り出していこうとした人間たちの思考の集大成だろう。吉都は西洋にしろ東洋にしろ、必ず神がいるが、そんなものは文学の材料にしかすぎないと思っていた。しかし、出雲大社の社の前に立ったとき、その場所、その建物には、そこにきたことのある、関わったことのある人間の気持ち、魂がつくりだした空間があり、それが、社、場所に他と違った雰囲気を作り出し、訪れた人にそれを感じさせることにきがついた。人が作り出した神は、長い長い間日本社会を人々の間でさまよい、人々の思いをからだに身につけ、今生きている人間に何かを感じさせてくれている、やはり文学の登場人物だけの存在ではないことがわかった。神が作るパワースポットとはそういうものかもしれない。一方で、人々はそれを神々が作り出していると思っているわけだが、実は自分たちがそれを作り出しているにすぎない。人の脳が作り出しているのだし、感じているわけである。
本殿の屋根の切妻は尖っている。尖っているのは男神、平らなのは女神だそうだ。出雲大社は確かに男の神だ。神に何で男と女が必要なんだ。昔の人間は単純に動物には男と女がいて、それは子孫を残す仕組みであることを理解していた。神も増えなければならない。古事記、日本書紀には男の神と女の神はやたらと子供を作る。しかしそこは神で、人間を含む動物と必ずしも同じようには子孫を作らない。水滴一つ垂らせば新たな神が生まれる。にもかかわらず、やはり男の神、女の神が、いがいみあい、くっつきあい、なんとも忙しい。古事記や日本書紀を書き上げた人たちは、さぞ楽しかっただろう。小説家が書いた話が、国を作る元になったようなものである。いや、国を作る算段として神を作ったのか。昔の憲法のようなものか。
可也にしてはなんだか、珍しく科学から離れて回りを見てしまった。
本殿の脇の道に行った。両脇には東西の十九社(じゅうくしゃ)と呼ばれる、十月に神々が集まり、寝床にする社がある。神々の旅館である。男の神と女の神はここで出会って、また新しい神を作るのだろうか。近年新しい神は生まれていない。誰か作ってくれよ、吉都は小説でも書いてみようかなどと変な方向に気がいった。
そこを過ぎて、社の裏に回った。ひっそりとしているところに小さな社があった。何か惹かれるものがある。吉都は素直にその社の前に立った。素鵞社(そがのやしろ)というらしい。素戔鳴(すさのうの)尊(みこと)が祀られている。乱暴な神のようだったが、ヤマタノオロチ(八岐大蛇)を退治した勇者でもある。ヤマタノオロチは八つの首、八つの尾を持つ蛇で、八つの峰や谷をまたぐほど大きいそうだ。ヒトはオロチを沈めるために娘を差し出してきたが、スサノオはこのオロチにうまい酒を飲ませ、やっつけたということだ。そのへんはあまり勇者らしくない。
天照大神(あまてらすおおみのかみ)の弟、大國主命の父というから、出雲大社の神の父ということになる。
この小さな素鵞社の脇の岩は、出雲大社の裏にある四百数十メートルの山、八雲山に続く。八雲山はヒトが入ってはいけない山で、古くは出雲大社のご神体だそうである。古い神社のご神体が山そのものであったりすることはままある。自然のものがご神体なわけだが、それが鏡であったり木でできているものであったり、小さな神社は、ご神体として偶像を作ってそれを拝んだ。神を身近なものにしたかったのか。
それにしても八ばかりだと、日本人の八の好きなのにはあきれた。もっとも八という数字は吉都も好きな数字である。
そこをおまいりして、反対周りで、大社の表に戻り、また駅に帰った。途中に大昔の出雲大社の社の模型がおいてある資料館のようなところがあった。昔の建物の基礎から想像したもので、大社は三十メートルもある木の階段の上にあったそうである。八雲山を高いところから拝んだのだろうか。
出雲市駅にもどり、町を歩いていると瑪瑙の店が目に付く。出雲の産物を調べてみると、濃緑色の出雲石がでてくる。青い瑪瑙が出雲石といわれて特産らしい。しかも勾玉になったものが、パワーストーンとして人気があるのだ。一軒の立派な店にはいってみた。おいてある出雲石をみると、安いものでも数万する。びっくりして、ちょっと見ると出てしまった。だが勾玉がほしい。
吉都はみやげ店にはいった。小さな勾玉が千円ほどで箱に入ってごろごろおいてある。千二百円と千五百円の箱もある。きっと偽物かと、店のおばさんに、何の石か聞くと、出雲石だという。信じられないと言う顔をしていたのだろう、おばさんはにこやかに、濃い緑色の上等な石だと数千円はするけどね、色が薄いのや混じったものはね、この値段。でも本物ですよ、そう教えくれたので、なんだかほっとした。キーホルダーにいい、野霧さんと所長、それに世久さんと、俺、家族にも買うか、といい色のものを選っていると、おばさんが、いくつ買うのか聞いた。七つというと、それじゃ、こっちから選んでいいよ、七千円でかまわないから、と一つ千二百円の箱の中の勾玉を指した。そっちの方がもう少し色が濃く見栄えがいい。ありがたいことだとおもい七つ選んだ。おばさんは、それぞれ緑色の小さな巾着袋にいれてくれた。いいみやげになった。
明くる朝、JR出雲市駅から特急「おき」で浜田に向かった。
出雲から日本海を眺めて一時間半、浜田の駅におりた。駅前に恵比寿の社の乗っかった塔がお出迎えである。どんちっち神楽時計というからくりのようだ。
ホテルで荷物を預けるときに、どんちっちってなんだと聞いたら、郷土芸能に石見神楽というのがあり、お囃子の音がどんちっちと子どもには聞こえたので、どんちっちが浜田のブランド名となったという。浜田のとれる魚の名前の前にくっつけ、どんちっちカレイとか、どんちっちアジというそうだ。特にカレイの水上げは日本一で、カレイ、アジ、ノドグロを加えて、どんちっち三魚というらしい。
無駄かと思ったが、甲(かっ)木(き)耳鼻科について聞いてみた。
「甲木先生の病院は浜田高校の隣ですよ」と、教えてくれた。さらに「甲木先生のカタツムリのコレクションの展示が、しまね海洋館でおこなわれていますよ、病院にもコレクションルームがあって、誰でも見ることができます」と、水族館と甲木耳鼻科のパンフレットをくれた。
ロビーのソファーで、水族館のパンフレットを見ると、カタツムリの殻が並んだ標本箱の写真に緋巳壷コレクションとある。これはなんと読むのだそう。可也はひみこを想像して、もう一度フロントに行った。
「ひみこと読みます。甲木先生は、緋巳壷というペンネームでカタツムリのことについて、いろいろ書いていらっしゃいます。カタツムリの小説やら、詩、童話いろいろあります。ブログで発表されています。緋巳壷で調べると出てきますよ、世界のカタツムリのことも載せていらっしゃいます」
やっぱりヒミコだ。ちょっとおもしろくなってきた。可也は礼を言って、またロビーのソファーに腰掛けた。スマホで島根浜田の緋巳壷を調べた。あった。緋巳壷でんでん虫、というブログである。
緋巳壷のいわれが書かれていて、2000年、浜田の馬島の厳島神社跡で発見した、赤いキセル貝の仲間の写真があった。甲木美夜がみつけた新種の陸生巻き貝である。それで、赤い自分の壷ということで緋巳壷と言う名前を付け、ペンネームにもしたとある。
馬島は浜田の松原湾沖にある小さな島で、ある会社のものだという。古い灯台が有名だそうだ。
ブログは一週間に一度ほど更新していて、童話、小説、カタツムリの紹介など幅広い。いつでも病院の緋巳壷コレクションを見に来てくださいとある。行ってみるのがいいだろう。明日は木曜日、行こう。
浜田の地図を見た。甲木耳鼻科が隣の浜田高校は駅からみると、ホテルのある海側ではなく反対側である。今日は海側の方を歩いてみることにした。浜田は七つの漁港を持つ町である。その中でも浜田漁港は、日本で十三カ所しか指定を受けていない特定第3種漁港という政令で定められた水産振興の重要なところとある。当然近くに厳島神社があだろう。
調べてみる。やはりあった。浜田城跡のある公園の近くで松原港の脇だ。恵比寿さんも一緒に祀ってある。まだあった。公園の川を挟んで海側になんと高尾山という山がある。さらにその海の方に、瀬戸ヶ島と言う半島があって、そこにも厳島神社がある。その沖に馬島とや南箆(やな)島(しま)がある。
吉都は町をぶらぶら歩いて、浜田城趾のある公園に向かった。だんだん漁師町のような様相を呈してくる。公園の脇の道を通り、厳島神社に行った。そのあたりの人たちが頼りにしているといった時代色と、漁師たちの汗と笑顔が染み着いているような小さな神社だった。恵比寿様も祀られている。萩や九州、それに出雲大社と大きな神社を見てきたので、フレンドリーな神社で、脇に腰掛けて、海でも眺めていたい気持ちになった。
歩いて行くと、小さな食堂があった。昼を食べようと汚れたアルミサッシの戸を開けて入った。定食しかない。580円の定食を頼むと、焼いたあじ二匹と、味噌汁と、おしんこ、それに白いご飯がこんもりと盛られたどんぶり、それが長方形のアルミのお盆に乗せられて、可也の前におかれた。湯飲み茶碗と急須もいっしょである。
「ゆっくりな」
顔にしわを寄せたおばあさんが、笑顔で言うと、奥に入っていった。漁師らしい男が二人で向かい合って食べている。そのテーブルの下で、白黒の猫が見上げている。一人が食べ終わったアジの骨をしたに落とすと、猫はあわててかじりついた。
吉都はそれを見ながら、アジに醤油をかけて食べた。うまい。焼き魚をこんなにうまいと思ったのは今までないかもしれない。富山の北京商会のゲストハウスよりも旨い。東京では炉端焼きやチェーン店で食べると、必ずどこどこでとれた魚などと、魚の名前の前になにかがついている。この店は地元の「どんちっち」の名前も付けていない。こういう店が本物のどんちっちだ。
おいしかった。礼を言って出ると、城趾の公園の中を通って、城戸ヶ島のほうにでた。港である。潮の匂いに囲まれて半島にいき、もう一つの厳島神社を見た。鯨が獲れたのか、捕鯨の図が有名のようだ。
こうやって厳島神社をまわってみても、倭國神社の昔がわかるわけでもないが、神社に慣れたというか、神社の存在の意義みたいなものが体得できた。パワースポットの意味もわかってきた。神社の元の神々は日本の昔の人間が作り上げたにしても、そこに昔の人の何かが付着している。もちろん、ヒミコもそうだろうし、そのころ生活をしていた人々の気持ちだ。
演劇でシェークスピアの作品をやったとすれば、シェークスピアの作り出した人間になって演じなければならない。シェークスピアそのものの気持ちが、作中の人たちすべてにくっついている。さらに脚本家による気持ちがくっつき、演じる人の気持ちがくっつき、それを見ている人は、自分の気持ちをそれにくわえる。
同じように神はそれを作り出したすべての事象、自然、それに人々がくっついている。弁天は海の女神、それだけではないわけである。浜田にある厳島神社二つは、そこにいるのは同じ女神だが、違う神となっている。松原港と城戸ヶ島は、日本という国からみると隣どうしに見えても違う神がいる。一卵性双生子でも、育った環境で違った性格を帯びる。周りによって変わってくる。
吉都は何を考えているんだろうと自分に不思議に思った。島根というところは、そのものがパワースポットで、俺はその中にはまり込んでいる。そういえば、宍道湖という何となく地についておらず、他の世界の間に存在するような湖もある。
倭国神社は厳島神社からは見えてこないのではないのではないだろうか。ふとそう思った。
馬島の影が見える。馬島には江戸時代に二つの厳島神社があったという。なぜ二つなのだろう。馬島にいってみようか。行き方を調べても載っていない。馬島について書いたものもない。私有地で特に観光客を呼び入れているようではないようだ。ただ周りは釣り場のようである。ということは釣り船が行っているはずである。
吉都は城戸ヶ島のバス案内所で、釣り船屋を教えてもらった。
「あの島にはなあ、あまりかってにゃはいれねえな」
馬島にわたりたいことをはなすと、そう言って船の親方は首を横に振った。
「一時間ほどでいいんですけど」
「なにするんだい」
そう聞かれた吉都はちょっと戸惑ったが、「甲木先生の見つけたカタツムリの仲間を見てみたいんです、厳島神社のあったところだそうですが」と、口からすらっと嘘がでた。自分でもうまく答えたと思った。
「おお、美夜先生の奴か、あんたさん研究者かい」
「○○の生物の大学院をでました」
これは嘘じゃない。船長は「それじゃあ、ちょっとだけ行ってやるよ、見られるとまずいからな、帰りは一時間ほどで迎えにいくよ、携帯が通じるから、電話をくれるかね」。
吉都はうなずいた。かたつむりの研究者と思ったようだ。それは勝手である。釣りは朝か夕方で、今の時間は暇のようだ。
「船賃はいくらでしょう」
「釣りに行くのと同じでいいよ」と、小屋に張ってある料金表を見た。基本は一時間で二千円である。
「お願いします」と言うと、すぐ船を出してくれた。
港から十五分ほどである。こうして吉都は馬島に上陸できた。どのようなカタツムリでもいいから、殻を一つ拾って、甲木医師と話す機会を作ろうという魂胆である。
荒れた道を通って、厳島神社の跡というところに向かった。だいたいの位置を釣り船の親方が教えてくれたのだ。草の生えているところにカタツムリはそう見つかるわけではない。
神社跡にはなにもなく、基礎になっていたらしい石が重なっておかれてあった。石をどかしてみた。
あった、キセル貝の殻が二つほど転がっている。よくある普通のもののようだが、吉都は喜んで拾うと、今度は木々の間を歩き、どこかじめじめしたところがないか見て回ったが、以外と乾いている。時計を見ると四十分を経過していたので、船着き場にもどることにした。
林の中を下っていくと、カタツムリの殻がおちていた。これもラッキーと拾った。海岸にでて、いつでも迎えにきてほしいと電話を入れ、周りを見ていると、海岸の地層がはだけているところに、小さな普通の形をしたかたつむりがいた。生きているのは採らないでおこう、そう思ってスマホで写真だけ撮った。
そうこうしているうちに、迎えの船がきた。
「どうだったかね」
吉都は拾ったカタツムリの殻を見せた。
「珍しい奴かね」
「いえ、そうじゃないのですけど、集めているものですから」
「それじゃ、甲木先生と同じ研究者なんかね」
「はい、明日先生と会う予定です」
また嘘をいった。
こうして、吉都は城戸ヶ島にもどって、ホテルに帰った。その日は、どんちっち商店街の中の食堂で、夕食を食べた。そこのメニューの魚にはどんちっちとあった。どんちっちカレイのからあげにビールは旨かった。
次の日、木曜日である。この日は甲木耳鼻科の休みの日である。休日でも緋巳壷コレクションルームは開けてあるとあった。十時頃ホテルをでて、駅の反対側に行き、浜田高校を目指して歩いた。
地方の県立高校というと、先生方は名士である。浜田高校も多方面に活躍する生徒を排出する、よく知られた高校である。落ち着いた雰囲気のいい高校だ。隣に昔ながらの和風作りの大きな家がある。石塀に囲まれていて、入口の石の門柱に、甲木耳鼻科と書かれた陶板がはめ込まれている。時代を感じさせる。門の中にはいると、和風の自宅と病院が独立してある。病院は白いペンキ塗りの洋式の建物だった。病院の玄関の左に、甲木医院と木札が、右に緋巳壷でんでん虫ルームという板が付けてある。玄関は開いていたが、本日休診日の札が下がっている。
矢印の通りに診察室の手前を右に進むと、奥の方に戸の開いた部屋にはいった。緋巳壷でんでん虫コレクションの部屋である。
中はずいぶん広く二十畳もあるだろうか。一つの壁には大きな窓があり、庭が見える。残り三方の壁が木製の棚になっており、その前に机がおいてある。入り口の机には来場者記名簿、パンフレット、出版した小説や童話、などがおいてあった。
棚や机にはたくさんのカタツムリがはいった標本箱や標本瓶がおかれている。吉都は、緋巳壷が見つけたという赤いキセル貝をさがした。キセル貝ばかり集めたコーナーにおいてあった。用意されている丸椅子をそこに運んで腰かけた。丸い小さなシャーレにいれられていて、和名ヒミコとあり、学名が書かれている。産地は島根県浜田市城戸ヶ島、馬島とあった。
見ていると、背の高い、色の白い切れ長の目をした女性が入ってきた。吉都をみとめ「いらっしゃい」と声をかけてきた。
吉都は振り返ると、誰かに似ていると思った。萩の毛筆家の火美胡だ。吉都は椅子から立ち上がって「甲木先生ですか」とおじぎをした。
「はい、カタツムリがお好きですか」
吉都はちょっと間をおいて「はい」と返事をした。
「コレクターのようではありませんね」
緋巳壷はにこやかにそばによってきた。
なにやら、もう見透かされている。吉都はポケットから、ビニール袋に入れたキセル貝とマイマイの殻を見せた。
「これ馬島で拾ったのですけど、船長がカタツムリの研究家の先生のことを教えてくださったものですから」
緋巳壷はビニール袋を受け取って、中の貝を見ると、「ほんとうね、馬島のかたつむりのようね、でもよくあの島に入れましたね」
緋巳壷は椅子を持ってきて、吉都の脇に腰かけた。吉都も腰を下ろした。
「船長に頼みました」
「キセル貝はナミキセルね、カタツムリはイズモマイマイかもしれないわ、ちゃんと調べないとわからないけど、生物関係の方のようね」
「はい、○○大学の生物をでました」
「あそこは生化学が主流よね」
「はい、発生関係をやりました」
「ほかに見る所があるのに、朝早くからここに来られたのね、浜田には観光ではなさそうね」
なんだか、どんどん正体がはがされていくようだ。
「ええ、全く関係ない調べ物です、厳島神社です」
「確かに、馬島には江戸期には厳島神社があったし、海岸沿いには二つの厳島神社がありますね、でも海の町だから不思議じゃないわね、かたつむりの収集でいらしたわけではないのになぜカタツムリを馬島で拾ったのかしら、私のところに来るためかしら」
こうなったら正直に言うしかない。
「今は探偵事務所で働いていて、依頼人から、倭國神社のルーツを調べるようたのまれています」
それを聞いて、緋巳壷はびっくりした様子になった。
「倭というのは昔の日本人の倭人の倭でしょ、それに昔の國の字」
「はい、愛知の半田にあった神社です、卑弥呼に関係があるようです」
「それで、私のところにきたわけ」
「いいえ、甲木先生が緋巳壷と名乗っていらっしゃるのは、こちらに来てから知りました
「ということは、こちらに来る前から、私のこと知っていたわけ」
吉都は三角の顔をとんがらせた。どうも嘘はつけない。彼は正直にうなずいた。
「はい」
「昔一度警察に調べられたことがあるのよ、蝸牛をおいておいたら、どこでとったかとききにきたの。医学部の学生の時に解剖学教室で、実習の後取ってみたいといったら、先生が技術員の人に教わるようにと、準備室で三日かけてとりだしたものよ、取り出すの大変なんですよ、それがきっかけで、耳鼻科に行ったのですけどね、蝸牛をカタツムリ展でにもだしておいたら、見た人が気持ち悪いって言って、それが市議の奥さんだったから、警察が聞きに来たのですよ、自分の体にもあるものなのに、日本の人は自分の体のことを知らなさすぎるのね、もっとしっかり、義務教育で教えればいいのに」
「先生のおっしゃるとおりです、警察に友達がいて、浜田に行くといったら、カタツムリを集めている耳鼻科の美人の先生がいると教えてくれたものですから」
「嘘でしょ、私がいることはそうかもしれないけど、美人とは言わなかったでしょう」
これに吉都はちょっと困った、余計なことを言うものではない。
「えーと、お名前なんておっしゃるの」
あわてて、吉都可也と名乗って、名刺をだした。
「探偵さんおもしろそう、吉都さん、私の祖先が倭國に関係あるということをきいているのですけど、それを知っていらしたの」
「え」
今度は吉都が驚く番である。
「全く知りませんでした」
「倭國のことご存知なのね」
「いえ、分からないことが多くて調べています」
「知っていること教えてくださらないかしら、私の祖先のこともお教えできてよ」
それはこちらで聞きたいことであった。
「今日はこちらに泊まるのかしら」
「はい」
「それじゃ夕御飯食べながらお話聞かせてくださるかしら、倭國神社のことを知っている方ははじめて」
「はい、あの、あまり高いところだと、予算がないものですから」
吉都はちょっと恥ずかしいけどはっきりいった。
緋巳壷は笑って、「私の家でよ、ばあやの手料理、結構おいしいのよ、ご招待、五時頃に家の方に来てくださるでしょう、私、これから、しまね海洋館のカタツムリ展示会場に行かなければならないので」
「ありがとうございます」
彼女は部屋から出ていった。吉都はぼっとしながら、カタツムリの展示を見て、甲木耳鼻科を出た。ホテルにもどる途中、駅の売店によって、おにぎりとそばビールというのがあったので、それを買った。まさか緋巳壷が倭國に関わる人だとは、特ダネだが、そんなことがあっていいのかと狐に摘ままれたような気分で、おにぎりにかじりついた。そばビールは少し甘めだがうまかった。中途半端なアルコール量だったからか、緋巳壷との面会の緊張のせいかわからないが、ベッドにごろっと横になると眠ってしまった。
目を開けると四時である。三時間ほども昼寝してしまったことになる。滅多に昼寝などしないのに可也はやはり何かに執りつかれているのではないかと、ぼーっとしたままなかなか目がはっきりしなかった。
風呂に入った。
五時ちょうどに甲木耳鼻科についた。石の門を入ると、大きな和風の屋敷の呼び鈴を押した。
ハーイという声とともに、どうぞという声が聞こえ、吉都は玄関を開けた。広いたたきに、時代のある大きな木の下駄箱、その上には大きなアンモナイトの化石がおいてある。
「いらっしゃい、来てくださって有り難う」
緋巳壷が自らで迎えてくれた。こういう場所はなれていない。吉都は堅くなって「今日はありがとうございます、嘘も言ってすみませんでした」と深くお辞儀をした。
彼女はそれを聞いて笑った。
「木曜日の休みの日は、よくお友達を呼ぶの、どうぞ気にせずお入りください」
緋巳壷の笑顔に少しはほぐれたが、吉都はまだ三角の顔がつっぱっている。きれいな石畳の玄関に汚れた自分のズック靴がなんだかさみしい。
玄関口から廊下に案内され、奥の部屋の障子を開けてくれた。庭に面した十畳ほどの洋風の部屋に、どっしりとしたテーブルがおかれている。椅子が六客ある。緋巳壷がどうぞと、庭が見える方の椅子をひいてくれた。テレビで百年名家とか言う番組があり、有名な建築家が作った金持ちの古い家が紹介されている。それを小型にしたような家だ。
吉都はぎごちなく腰かけた。いつもの吉都なら、すげえ、と言っただろう。
「ビールでいいかしら」
「え、ははい」
返事からしてうわずっている。
「ばあや、ビールたのむわね」緋巳壷が開いている戸から廊下に向かって声を上げた。
すぐに恰幅のいい六十ちょいのおばあさんが、ピッチャーにビールを入れて、コップとつまみの皿を持って入ってきた。
「おじょうさん、いつものビールでよかったんですか」
「いいわよ」
おばあさんは、丸い顔でちょっと野霧に似ている。大きな目で吉都を見ると、眼尻にしわを寄せて、コップと小皿をおくと、ピッチャーからビールをついだ。
「ばあやのヒミさん、こちら探偵社の吉都さん、東京から来られたの、倭國のこと調べられているの、いっしょにどう」
「あれ、倭國のことですか、おじょうさんそれはよかったですね、何かわかるかもしれませんね、用意が終わったら来ていいですかね」
「お願するわ」
ヒミばあやはいったん戻ると、大きな皿にでんでん虫をたくさん載せてまた入ってきた。とり皿とホークにカタツムリを挟む金具を二人の前に置いた。
「ありがとう、あとで来てね」
「はい」
ヒミばあやはまた出ていった。
「これは地ビールなんです、飲んでみてください」
吉都はぐーっとのどに流し込んだ。柔らかなビールだ。これでちょっと緊張がほぐれた。
「どうです」
「なめらかで、さっぱりしていて好きです」
「よかったわ、このエスカルゴ、レストランの味付けとちょっと違うのよ、食べてみてくださいな」
吉都はまともに食べたことはない。緋巳壷がエスカルゴを挟んで、ホークでくるっとうまく中身を取り出すのを見て、同じようにやった。少し茶色っぽい身がするりとでてきた。
「あら、慣れてらっしゃるわね」
「いえ、はじめてです」
「器用なのね」
緋巳壷と同じように、取り出した身をナイフで、半分に切って口に入れた。え、っとおどろいた。醤油味だ。うまい。つぶ貝に似ている。
「おどろいたでしょう、ヒミばあやにエスカルゴ作っていったら、私にはできません、と言ってこうしたの、そうしたらお客さんみんな喜んで、うちのエスカルゴはどんちっちエスカルゴだって有名になったんですよ」
「おいしいですね、ビールと合います」
「ばあやの料理は自己流の和風料理、でも煮物もおいしいし、煮魚、焼き魚はすばらしいのです、材料も自分で調達してくるし、エスカルゴは違いますけど」
「昔から、耳鼻科なのですか」
「ええ父も祖父も、母は看護師で、父と母と二人でやっていたので、忙しくて、私のためにばあやをやとって、私はばあやに育てられたようなものですの」
「ご両親はもうお医者をやめたのですか」
「ええ、というより、亡くなりました、私、おそい子だったので、なくなったとき両親とも八十過ぎていました、今はばあやと二人暮らしですの、父は私がカタツムリを集めるの手伝ってくれたのですよ、結構蒐集癖がありましたね、私が似たようです、父は切手を集めてました世界中の海の魚の切手でした。浜田に育った人だったからですね、まだ大事にとってあります。貝の切手もありましたが、カタツムリはあまりないですね、私が集めています」
エスカルゴの身を殻から抜くのにスムーズにいくようになったとき、ばあやが、ノドグロを煮てもってきた。
「私もいただいていいですか」
「もちろん、これから昔のお話しするのよ、ばあやから話してもらった方がいいわ」
「はい、はい」
ヒミは自分の分を取りに行った。
「ビールでいいのかしら、お酒もありますけど」
「あ、ビールがいいです」
おいしいビールである。
「ばあや、ビールも持ってきて」
ヒミコは自分のノドグロと、ピッチャーにビールを満たしてもってきた。
「それじゃ、私もいただきます」
ノドグロはいい味に煮てあった。
「おいしいです」
吉都が言うと、ばあやは「もう四十年も料理してますからね」と吉都を見た。目が喜んでいる。
「ヒミばあやは私が生まれたときから、この家にきてもらったから、それで父はばあやに放送大学の学生にさせたの、日本の歴史を専攻して、放送大学卒業よ」
「ありがたかったです、わからないと先生や奥様が教えてくださいました」
「それで、父は自分の先祖が倭國の女性だと聞いていたと言っていました、私はあまり興味がなかったので、ばあやによく話をしたようなの、だから、ばあやの方がうちのことよく知っているのよ、ばあやは、本当はヒミじゃなくて、秋野さん、父がうちの先祖はヒミコだと勝手に思っていて、ばあやのことヒミコって呼ぶようになってしまったの、それで、だんだんヒミばあやになったわけ、私の作家名は見つけた貝に由来するところもあるけど、頭にヒミコがあったからですね」
「恐れ多いことです」
ばあやは顔を丸くして、ビールをぐぐぐと飲んだ。野霧とよく似ている。
「ご祖先は月足といったのではないですか」
美夜もばあやも食べる手を止めた。
「その名を知っているんですか」
ヒミばあやは驚いたようだ。グラスを机の上に置いた。
「はい、知多半島に倭國神社というのがあったのですが、その神主は皆婿取りで、名前を月足りといいます、調べていくと、わかる限りでは、二代目の神主には八人の娘がいて、その末娘がなぜか神社を継いで、巫女になり婿を迎えています。その神社は卑弥呼にかかわりがあるようなのです」
ばあやが身をのりだした。
「私が聞いていたのは、倭國の主がご先祖様で、ずーっと後に、主をまつった神社の神主の八人の娘の一人が、甲木の嫁としてきたと言うことでした、その主と言うのは卑弥呼だろうと、お父様は話しておられました」と言った。
一致した。これはすごい話だ。
「系図のようなものがあるのでしょうか」
「言い伝えだけですけと、お父様はおっしゃっていました」
「なにか、ご先祖様の残したようなものはあるのですか」
「書いたものはありませんけど、古い衣装みたいなものはありますわよ」
美夜がいうと、「食事が終わったら、お持ちしましょうか」と、ばあやが言った。
「ええ、お願するわ」
そのあと、焼いたカレイ、茶碗蒸し、酢の物、マグロの赤身の刺身、それにご飯がでた。刺身が普通は最初にくるのにおもしろい出し方だとおもっていると、緋巳壷が、
「お魚を楽しんで、最後に刺身でご飯を食べるの、ちょっと変わっているでしょう」
と言った。
吉都が出雲大社や厳島神社にいったときに、いつもとは違う思考方法になったことを話した。
緋巳壷がうなずいて、
「それぞれ地方で、日本の神様が人の垢にまみれて個性を持つというのはおもしろいですね、カタツムリは歩くのがのろいでしょう、だから、地域からあまり外にでないの、それで、同じ種類でも地方によって、変種が多いのよ、ローカルの味がついたのね」
吉都はそう言うことは大学で習ってよく知っていた。
「植物でも寒葵は成長が遅く、地方にいろいろな種類があります、熱狂的な寒葵ファンがいますね」
「寒葵ってどんな植物なのです」
ばあやがきいた。
「江戸時代では葉っぱを鑑賞する園芸植物で人気があったんです、徳川の葵の紋は、双葉葵だと言われていますね、寒葵の仲間です」
「あら、そうなの」
「花がおもしろいんです、原始的な花で、春は早くに咲くのですけど、半分土の中で気がつく人は少ないんじゃないかな、ラフレシアを小さくしたような形です」
「どうして生物学ををやった人が探偵になったのです」
緋巳壷が聞いた。吉都はちょっと嘘を交えて、「研究も一つのことを探り出すのですけど、探偵もそうです、うちの探偵事務所は百パーセント見つけだすと評判なところだったんです、迷子猫ですけどね」とお茶をにごした。
そういったら、緋巳壷ばあやも緋巳壷も大笑いした。
食後に見せてもらったのは、何百年か経った巫女の衣装だった。吉都は写真を撮らせてもらった。探偵事務所にある情報を知らせることを約束し、これからの協力をお願いして、おいとまをした。
ホテルに戻った吉都は、野霧からメイルが入っているのをみた。五條のヒミコは月足の子孫だとある。びっくりして、吉都も詐貸と野霧に今会ってきた緋巳壷のことを報告した。
詐貸から、「それはすごい話だね、ごくろうさま、一日休暇をあげるから遊んでいらっしゃい」と連絡があった。詐貸は理由があって、また富山にいるということだった。
吉都は明日宍道湖によって、土曜日に東京に戻ることにした。
月曜日、詐貸がいつも通り事務所に行くと、野霧と可也はもう来ていた。いい情報を得たときにはいつも早く出てくる。事務所には久しぶりに三人がそろった。
「おはようございます」
二人そろって、挨拶をした。
「ああ、ごくろうさん」
詐貸は自分のデスクに腰を下ろした。
「みんないい情報をとってきたね」
野霧がお茶を入れにいくと、吉都が自分がやりますとついていった。
二人でお茶の用意をして、客用のテーブルにおいた。
詐貸もソファーに腰掛けた。
野霧が「これおみやげです」ですと、地元の醤油を二人にわたした。
「へー地元の醤油とはいいですね」、吉都は、「これは僕のみやげです」と瑪瑙の勾玉を二人にわたした。
野霧は「いいわね、携帯のストラップにしよう」と携帯を取り出した。
「それじゃあ、俺の方から先にはなそうかな」詐貸が手帳を開いた。
「じつは、この間富山には行ったばかりだったのだけど、水良さんから電話があってね、遺伝子の編集で、大きな魚ができたそうだ、一メートルもの大きな鯛だ、マンボウみたいだった」
野霧が「北京骨商では、遺伝子の改変はやらないって言ってましたよね、交配によって変化させていくって」ときいた。
「それが今はやるようになったんだって」
吉都が補足をした。
「遺伝子の編集、ゲノム編集というのは、許されるようになったんです、これは、遺伝子の一部をきったりすると、抑えられていたものが抑えられなくなって、改良されるんです、きっと、成長を抑える物質を作る遺伝子を抑えたんでしょう、それは交配によって、遺伝子がそうなる可能性があるからです、遺伝子編集の方が早く結果が出る」
「俺はよくわからないけど、そのようなことをいっていた」
「だけど、許されないって何かに書いてあったような気がしたけど」
「それは遺伝子の組み替えでしょう、それをすると、単純な言い方をすると、マグロのあたまに鯛の頭を作ることができる、それは許されていません、どんな生き物ができるかわからないから」
「そうなんだ」
「それで、いちばん大きくなった鯛の魚拓を作ろうということになって、あの人間拓本の氷見己に頼んだら、引き受けてくれたということだ」
「それで、北京骨商の研究所にくることを知らせてくれた、それで行ったんだ、氷見己と話をすることができたよ、今回二人が調べてくれたことと重なったよ、氷見己も自分の祖先に月足という苗字だった女性がいることを知っていた。書いたものもあるそうだよ、倭國神社のことは知らなかった、卑弥呼に関わりがあると聞かされていたので、作家名もそうしたと言ってたよ」
「なんだか、ハチ公の事件と、嵩丸さんの依頼が完全に重なりましたね」
「うん、それで、野霧君のコピーした古文書の解読は難しいの」
「系図ははっきりしていますけど、古文書の方は全く歯が立ちません、八公の古書さんにでもお願いできませんか」
「薩摩にきいてみるよ、可也のカタツムリの先生も、月足にいきついたんだよね」
「はい、残っていた巫女装束は本当に古いものでした」
その写真はすでに送ってある。
「萩や博多のひみことも話せばよかったな。ハチ公の事件だと思っていたからな」
「そうですね」
「ともかく、今回の二人の結果をまとめてくれないか、嵩丸さんに報告しよう」
「あの、五條の痺弭弧さんに、こちらの資料を送りたいのですけど、何処までいいでしょうか」
「僕の方も、でんでんむしの緋巳壷さんに、わかったこと教えると言いました」
「倭國神社から出て来た物のことはまずいけど、わかった系図と月足日美が関東のどこかにいることくらいはいいだろう」
「はいわかりました」
野霧と可也は早速作業に取りかかった。詐貸は薩摩と嵩丸に電話をかけた。
翡海湖
久しぶりに、嵩丸が事務所にやってきた。
「いろいろわかりましたな、ありがとうございます」
「嵩丸先生も、そろそろ結審で、お忙しいですね」
嵩丸の数年越しの弁護の結果がもうすぐでる。
「ええ、どうでますかわかりませんがね」
「発掘された出土品の鑑定はどうでした」
「それが、どうも新しいもののようで、まあ、それでも四百年近く経っていますが、おそらく神社を造るときに形として作って埋めたのでしょう」
「そうでしたか」
野霧がお茶をもってきた。
「あ、すまんです、これ、つまらんものだけど」
嵩丸が紙袋を野霧に渡した。
「なんですか」
野霧がのぞき込む。
「草餅です、食べてください」
「すぐ、お皿に入れてもってきます」
「人皮の豆本のことではお騒がせしましてすみませんでした」
「いえ、あれも、ヒミコという人の作品でしたね、あれから、逢手が奈良に、吉都が島根にいきまして、そこでもヒミコがいて活躍しています、しかもみな医者、その上、その二人のヒミコの祖先が月足という家からでた家柄で、家系図や古文書まで、さらに大昔の巫女の装束までが存在しました。今その古文書は知り合いに解読してもらっています、それまでの報告書がこれです」
束ねた書類を嵩丸にわたした。吉都と野霧が数日かけてまとめたものである。
「それはすごい発見ですな、さすが、詐貸探偵事務所のみなさんはすごい、ありがとうございます」
そういいながらも、嵩丸はあまり驚いた様子がない。
「解読しているのは、警視庁の科学捜査室、第八研究室の人じゃないですかな、薩摩警視、詐貸さんの大学のサークルメート」
「お調べになったんですか」
「まあ、あそこの、古書さんは、古文書解明に関しては一人者でしてな、テレビの骨董の探偵団がありますな、あそこにでているプロでもわからないものは、彼に解読してもらっているという裏情報がありますな、若干三十二歳ですからな、すごいものです」
詐貸はハチ公の三人の名前は知っていたが、最後の一人を知らなかった。
「その人とは会ったことがありません」
詐貸は嵩丸の人皮本のときには、高胎という女性が嵩丸から聞き出した本屋から、豆本作家を探り当てたはずである。
「古書(ふるほん)羊(よう)貴(き)さんと言いましてな、古文書を読むのがすきな男で知られてますな、古文書の中から、その当時の奇妙な事件を集めてましてな」
「古書で、ふるほんですか、その人のことは薩摩からまだ聞いていませんでした」
野霧が嵩丸のもってきた草餅を皿にのせてもってきた。
「みなさんもこちらでどうです、これから私の方でわかったことをお話ししますから」
野霧も可也も加わって草餅を食べた。
「おいしい」
野霧の顔が丸くなっている。嵩丸が話し始めた。
「実は、倭國神社の最後の神主だった月足陽司と久遠の娘の居所がわかりました、鵠沼にすんでいて、本人はもう亡くなっていましたが、娘がいまして、月足美目(みま)といいますな、それが整形外科医でして、なんと、角などの細工をしております、その界隈ではかなり名が売れていて、銀座のジュエリー店に作品をおいたり、たまに個展をしたりしています、しかもですね、作家名が翡海湖ですわ、驚きますな、詐貸さんのところで調べていただいたことが、すべてつながってきそうです、月足さんにはお目にかかっておりませんが、いずれお会いしたいと思います。私の仕事が終わってからだと思っております、それでお願いがあります。今、銀座の緋(ひ)虎(こ)ジュエリー店で翡海湖展をやっています、私の秘書にも行ってみるように申してありますが、どのような女性か逢手さんあたりが行って、話してみてくれませんか」
野霧が身を乗り出した。
「そんなすごいところ行ったことがありません、作家さんをつかまえて話すなど大変ですね」
「ここに、調査費用をもってきました、これを使って、作品を一つ買ってくださらんか、それをきっかけに、話をしてくださればいいでしょうや」
「そういう仕事、秘書さんの方が向いているのじゃないですか」
嵩丸事務所にいる秘書は嵩丸の姪子だと言う、モデルのような女性だ。
「姪はそういうことは駄目ですは、調査のちょっとした手伝いぐらいしかできません、人と話すのは得意ではありません」
確かに、嵩丸事務所に行ったときに会ったが、あまり会話がなかった。
「私の兄弟、親戚連中には全くこのことを話しておりません、興味もなさそうだし、巻き込むのも問題なので、私一人の趣味のようなものです」
「そうですかそれなら、野霧に行かせます」
嵩丸は翡海湖展パンフレットを鞄から取り出し野霧にわたした。
野霧はそれを開くと、ぎょっとした。一番やすいブローチで、二十万円している。一角の角の細工である。
「それじゃ、よろしくお願いします、奈良と島根のひみこの報告読んでおきます、逢手さんと吉都さんには感謝しています、随分色々なことが分かってきましたな、今後もよろしくお願いします」
嵩丸は報告書を鞄に入れると立ち上がった。
「古文書の解読が終わったら報告します」
「はいお願いします、この事務所にきますと、落ち着きますな」
と笑顔で出ていった。
「明日にでも銀座にいってくれる、このお金持ってっていいから」
詐貸が袋ごと野霧に渡した。
野霧は中を覗くとぎょっとた。
「二束ありますよ」、
「それじゃ、一束おいてって」
「それでもこんなに使えない」
「気に入ったの買わないと翡海湖と話せないよ」
詐貸は百万を野霧に渡した。その時、彼の携帯が鳴った。
「あ、どうだった、うんうん」
野霧は薩摩からの電話だなと思った。案の定、長い電話が終わってから、詐貸は二人のデスクのところに来て、
「薩摩が、あの古文書の解読がおわったといってきたよ、まず二人にお礼を言ってくれと言っていた。爪の細工のことやでんでん虫のことが分かってよかったといっていた」
「誰が解読したのですか」
「うん、やっぱり古書っていう人がやってくれたらしい。内容は倭國神社のことだ、ヒミコをまつっていたことは確かだな、ヒミコが知多にきたということではなさそうだ、ヒミコは亡くなると盛大な葬儀が行われたことがいわれているそうだが、この古文書には違うことが書いてあるそうだ、薩摩がどこで手に入れたか聞いたが、依頼人のものなので言えないと言っておいた、高丸ということは知っているだろうけどな
探偵事務所にメイルで解読文を送るといっていたから、もうじき来ると思う。古書と言う人は結構寡黙な男らしい、歴史にはとても強いのだそうだ、彼は嵩丸の事は良く知っているそうだよ。
それから、また変な事件が起きたそうだよ、鎌倉だけど、古い墓が掘じくられたそうだ、骨がなくなっているかも知れないと言うことでね、事件のようなら、助けてくれってさ、ほら、うちが墓の頭蓋骨盗難の事件を扱ったことを知っているからな」
「特定の人の墓なのですか」
「わからない、残った骨が露出していたそうだ、犬かもしれないけどね、だけど最近、野良犬はいないからな」
「骨を持って行ったのでしょうか、何にするのでしょうね」
変な人間はたくさんいる。
吉都が「古書さんから事務所にメイルが着ています」と言った。
みんな自分のPCを開いた。事務所宛のアドレスは皆共通に読めるようになっている。
「警視庁、分析支援室、第八研究室の、古書羊貴です。薩摩警視よりご依頼の古文書の訳を送付するように指示されましたので添付します、簡単な封がしてあります、次のメイルで、暗号を送ります」とあり添付書類があった。添付書類をダウンロードし、次のメイルをあけた。
8himiko8 とあった。
野霧も吉都も開いてみると次の文がでてきた。詐貸が開けないと言っている。吉都が詐貸のデスクに行って「最初の8は全角文字です、後すべて半角」と教えた。
『これは、倭国神社に伝わる話である。そのむかし、我が神である卑弥呼さまは、伊都国(いとのくに)の邪馬台国を納めていたが、肥後の犬狼を敬う狗奴国(くぬのくに)とたびたび戦になり対立をしていた。そのさなか、いきなり卑弥呼さまは姿を消した。それは狗奴国の男、隼人と夫婦になるため、国を去ったのである。そのとき、密かに夫婦の一人の男と一人の女も共に連れていった。その男は卑弥呼さまの鬼道を助けていた腹心の家来であり、女も卑弥呼さまにつかえる女だったという。卑弥呼さまは死んだことにされ、一族の十三歳の女子、臺與(とよ)に政を押し付け、将来その娘が国を平定することになった。
隼人である男は狗奴国一の勇者であったが、卑弥呼さまを戦の場で相対してからはとりこになり、卑弥呼さまもその猛勇ぶりにみとれたという。卑弥呼さまは腹心の家来の女を通して、その隼人と連絡を取り、密かに、どちらも国から離れたということである。
行き着いたところは八女である。卑弥呼さまの腹心である男は、その地の者たちをまとめ、あらたな國をおこした。卑弥呼さまと隼人の間には姫ができ、その姫は八女津媛として、祀られるようになった。腹心だった男と女は子供をたくさん生み、その子供たちも鬼道をあやつり、その地の豪族となった。そうして富める町をつくりだした。
その地にいた人たちは、豪族の導くもとに、八女津姫をあがめたが、豪族の長たち、すなわち卑弥呼の腹心だった男と女の子供たちは、密かに卑弥呼さまを倭国の神として、あがめていた。豪族の子供たちには鬼道が伝えられ、やがて、時がたち、奈良に都ができ、時代が下り、戦国の世が終わる頃、八女の豪族のいくつかの家族は九州を離れ、海路、知多半島にきた。そこで、小さいながらも、卑弥呼さまを祭神とする倭国神社を建立し、お守りするようになった。そのときの長が月足の娘である。自ら神社の神主となり。神社の地の奥深くには、卑弥呼さまのものと、さらに下には魏より送られた財宝を埋めた。卑弥呼を祀る倭國神社の継承者は女子とがぎるものとする」
「おもしろいですね、後でただ作られた話かもしれませんけどね、とすると、月足は、卑弥呼の腹心だった夫婦の末裔とうことですね」
「そうだね、神社の跡からいろいろ出てきたし、話が一致するね、吉都君、それ打ち出してくれないかな、嵩丸さんに郵送するから」
「メイルに添付ではいけませんか」
「まあ、メイルだと守秘義務がはたせないかもしれないし、きちんとした書類として提出したいからね、これは個人でたのまれたことだからね」
「そうですね、可也ちゃん打ち出してくれたら、私が送っておきます」
野霧が草餅を飲み込んだ。
次の日、野霧はいっちょらを着て、銀座に出かけた。絵を画く姉が北海道でみつくろってくれたクリーム色のふわっとしたワンピースだ。
銀座は苦手、そう思いながら銀座線をおりた。地上にでて、パンフレットをたよりに、銀座通りを築地の方向に歩き、わき道にそれ、すぐのところに緋虎があった。間口はそれほど広くはないが、五階建てのビルである。ネットで調べると、ジュエリー緋虎が所有するものらしいことがわかった。ホームページの写真では、一階が比較的買いやすいブティックとジュエリー、二階から四階までが、高級なジュエリーや小物の販売と、個展会場である。
翡海湖の個展は三階で行われていた。店の前に立つと、扉が開き、入るとすぐに女性の店員が声をかけてきた。
野霧がパンフレットを見せると、なぜか少し丁寧な言葉遣いになって、しかもエスカレーターに一緒にのって三階まで案内してくれた。
小さな建物なのにエスカレーターがあるとはかなり贅沢である。まあ、高級店だから当たり前か。
三階フロアーにいくと、超高級な服を着たマネキンが出迎えてくれた。洋服はそれだけで、あとはジュエリー関係のようだ。
「ごゆっくりご覧ください」
翡海湖のコーナーがあった。
飾ってあるのはペンダントからイヤリングなど、細かな細工がされた角でできているものである。派手さはないが、相当腕の立つ人が作っていることは野霧でもわかった。小さな石が涙のような雫型に磨かれて、それぞれの作品にはめ込まれている。
案内の女性がよってきた。
「翡海湖さんは、少し前までは象牙で作っていらっしゃったのですが、もう手に入りません、今では鹿の角や、ほかの動物の角、海獣の歯などを使っています」
親指の先ほどの大きさの角の細工に、数ミリのダイヤがはめこまれていて、値段は百万をこしていた。とても私の世界じゃない、と野霧は思っていた。
「この石はダイヤモンドです、あのブリリアンカットにはせず、このような磨き型で作られるのは、もっとも贅沢なことです、こういうのを好まない方の方が多いのですが、本当に宝石の好きな方は選ばれます」
それらの細工物とはべつに「根付け」のコーナーがあった。案内の女性が「翡海湖社長は根付けを作っていらっしゃいます」とそこに並べてあった十個ほどの花の彫り物を指さした。おもしろい花である。翡海湖社長とはどういうことだろう。
「寒葵の花がお好きで、彫られているのです」
野霧は寒葵を知らなかった。みると世界で一番大きい花と言われているラフレシアに似ている。
「やはりお高いのでしょうね」
「お売りしておりません、社長が自分の趣味で作ってらっしゃいます」
そういえば、値札がない。角か何かの骨でできているようだ。着色もされている。地味だがおいておきたくなるような一品である。
そこへ背の高い、瓜実顔の、色の白い女性が瑠璃色のドレスに身を包んで歩んできた。
微笑みながら「よくいらっしゃいました」と声をかけてきた。
案内をしてくれていた女性が、「翡海湖社長です」と紹介してくれた。
彼女は名刺を野霧にわたした。翡海湖工房、社長翡海湖とある。翡海湖は工房の名前のようだ。野霧も名刺をだした。探偵事務所の名刺ではない、いくつかある一つで、社長秘書の肩書き担っている名刺だ。名前は鈴木啓子としてある。一番普通の名前だ。
「どのようなものをお探しでしょうか」
野霧は指輪もペンダントもイヤリングもしていない。だまっていると、
「ペンダントなどいかがですか、今何もつけていらしゃらないのは、何と決めずにお気に入りのものを探す方です。他の装身具に合わせたい方はそれを付けていらっしゃいます」
そういう考え方もあるのかと、大したものを持っていないので、つけてこなかった野霧は感心した。
「これは古い象牙を手に入れて作った、寒葵の花をデザインしたものです。鎖も鈍い光の金のものをつかいました。今のお洋服にお似合いかと思います」
楕円の象牙色の地味なペンダントである。値段はとみると、三十八万とある。三つの花が織りなすように彫られている。他のものは、安くて二十万円台、高いものは八十万円台である。
「根付けは売り物でないのですね」
「はい、私自身のコレクションです」
「象牙ではないようですね、何かの骨か角のようですけど、動物の骨ですか」
「いえ、人の骨です、亡くなった方の骨で、その方の好きだったものを彫ってほしいと、遺族の方から頼まれるのです、同じものを二つ作り、一つは私のコレクションにさせていただいています。たいがいの方は仏壇に入れていらっしゃいます。ここにはおいてありませんが、それこそペンダントにして、いつも首からかけていたいという方もいらっしゃいます」
「お売りになっている作品はすべてお一人で作られるのですか」
「いいえ、根付は私自身ですが,他のものは分業です。翡海湖工房には私のほかに三人います、私はデザインを考えますが、細工は職人達です。角細工、ダイヤを磨いたり、植え込んだりするデザイナーたちがいます。チェーンや金具の専門もいます」
「翡海湖さんていい名ですね、何から付けられたのですか」
「私の祖母が卑弥呼をを祀っていた神社の神主と巫女の娘だったからですわ」
野霧はどきっとした。
「そうなんですか」
「作者の方とお話ができると思っていませんでした、これすてきですね、このペンダント、いただきます」
「ありがとうございます」
「お似合いになりますよ、鏡持ってきて」
彼女が店員に声をかけた。鏡に映った自分の胸元に、地味だけどしっくりくるペンダントが映った。
「すてき、いつから作っていらっしゃるのですか」
「若い頃から趣味でやっております、今でも趣味ですの」
「でも、社長さんでいらっしゃる」
「儲けはありません」
「他にお仕事があるのですか」
野霧は翡海湖が医者なのを知っていて聞いた。
「勤務医ですのよ」
案内の店員が、「お包みしてよろしいですか」と、と翡海湖に聞いた。
野霧が「つけていきたいのですけど」と言うと、翡海湖がその場で、野霧の首にペンダントをかけた。
「色が白いからよく合いますね、きれいな肌、うらやましいです、お洋服にも合います」
野霧が財布をだそうとすると、「あちらで」と案内の店員と一緒にレジにいった。
三十八万ということは四十一万八千円になる。
野霧が四十二万出すと、「四十でけっこうよ」と翡海湖が店員にいった。「おみやげ忘れないでね」というと、店員が「はい」と小さな包みを取り出した。
「これはご招待の方に差し上げています、小さなものですけど、鹿の角でできています」。
緋虎の手提げ袋に、ペンダントの箱とともにいれてくれた。
野霧がきょとんとしていたのであろう、翡海湖は「このパンフレットは招待した方用のものです、緋虎の社長が配ってくださいました、おそらく鈴木さんの社長さんがお知り合いだと思います」と言ったので、野霧はあわててうなずいた。
「社長がこれ持って、見にいっておいでといったものですから」
と嘘をいった。翡海湖が、「向こうの隅に、体に飾るものではないのですけど、きれいな印章がいくつかおいてあります、私と同じように、趣味で作っている人です、ちょっとごらんになっていきません」
翡海湖のコーナーの反対側の机に並べてあるものを指さした。なんだろう。
翡海湖について行くと、おいてあったのは印章であった。
「これも角や象牙でできているのです、売り物ではないのですけど、歯で作った判子もあります、私と同じように、亡くなった方の歯を印にしてほしいという方がいて、彼女が作っています」
やっぱり女性だ。野霧は判子よりも、作者の名前を見ておどろいた。匪実虚とある。
「この方もみひことおっしゃるのですね」
「そうなの、実は、生まれてすぐ養子に出された双子の妹なのです、私が双子ということを知ったのは大きくなってからです、家は愛知だったのですけど、祖母が小さいとき神奈川の方に出てきたのです。とある作品展で彼女と一緒になり、自分でもそっくりとおもって、話をしていくうちに、彼女が私の双子の妹であることがわかりました。彼女の両親は月足ということで、私の父と母だったのです、父は入り婿でした。両親が養子に出すのに、親戚筋の家を選んだようです、妹は生まれたとき、役所にも届けていないのですよ、どのようにその家の養子になったかわからないけど、歯医者の家で、彼女も歯医者です」
「どこにお住まいなんですか」
「鎌倉です」
これで、神の板に付けられた赤丸の所すべてにひみこがいることが分かった。
「あの、私の知り合いで、探偵やっている人がいるのですけど、事務所の公印を作りたいと言っています、お願できるのでしょうか」
「喜ぶと思います、彼女のパンフレットがそこにあります、お持ちください」
三角美矢が本名で、注文先の電話番号も書いてあった。
「ありがとうございます」
野霧がパンフレットを受け取った。
「こちらこそありがとうございました、次の個展にもどうぞいらしてください」
翡海湖におくられて、案内の店員と一階の入り口まで降り、また店員のありがとうございましたという声を後ろに聞いて道にでた。
野霧はふっとため息をついた。結構緊張していたんだ。目を胸のところにやる。三十八万のペンダントが揺れている。こんなすごいのしたことがない。どこかでケーキを食べて帰ろう。
そう思って、ちょっと気が軽くなった。
匪実虚
事務所に戻ると詐貸がどうだったときいてきた。
「ずいぶん、控えめな感じのよい方でした。やっぱり巫女さんが似合いそうな人、よくいる芸術家や職人とは全く違う感じでした、趣味でやっているそうです」
「それで何か買ったの」
可也が聞いた。
「これ」
ペンダントを見せた。
「結構地味なんだ、前からつけているみたいですね、でもよく見ると細かな彫りだ」
吉都が野霧の胸元を見つめている。
「高いんでしょ」
「三十八万」
可也も詐貸もぎょっとした。
「これ、所長にお渡しします」
野霧がペンダントをはずそうとしたら、詐貸が、「使っててよ、嵩丸さんからのプレゼントだよ」
と笑った。
「いいんですか、そうだ、あのパンフレット、招待した方のもので、おみやげまでもらいました」
野霧は詐貸に包みをわたした。詐貸が開くと、小さなブローチが出てきた。
「野霧君、これも使わないか」
と差し出したので、「愛子さんにあげたらどうですか」と言うと、「あいつは自分で好きなものを買うからいらないよ」
「可也君、彼女にどう」
野霧が聞くと、可也はちょっと、ブローチに目をやると、「野霧先輩使ってくださいよ」とちょっと声がわずっている。
「遠慮しないで、いいでしょ所長」
詐貸もうなずいた。
「いいんですか」と可也は野霧を見た。
「いいじゃないの、わたし、こんなすごいのもらっちゃったんだから」
野霧が可也に渡した。
「可也、彼女いるんだ」
詐貸がひやかすと、「これから探します」と可也が答えたのだが、野霧はああ、やっぱり、と想像がついた。詐貸は難の話かわからないようだ。所長はだめねえ。
「後になりましたが、翡海湖さんのおばあさんが月足日女で、しかも彼女はは双子で、妹は生まれてすぐ、月足の籍にも入れずに、鎌倉の親戚筋に貰い子にされ、今は鎌倉で歯医者さんをやっています、三角美矢といって、角や象牙の印章を作っています。歯も判子にします。作家名は匪実虚といいます」
「ヒミコだって?」
「はいそうです」
「それはすごいことを聞いてきたね、嵩丸さんも知っていないようだったよな、知ってたらここに来たときに言っていただろうからね」
「それで、知り合いの探偵事務所が公印を作るのでと言って、紹介のパンフもらってきました」
「それはいい、すぐ頼もうよ、その前にその話をまとめて、嵩丸さんに送っておく、ちょっと驚くだろう」
詐貸は鎌倉の匪実虚のパンフをコピーすると、デスクで書類を作った。あっという間だ。
「嵩丸さんに送ってよ」と、野霧にわたした。
詐貸は文章にまとめるのがとても早い。
「さて、それじゃ、今度は、その匪実虚の方だ、吉都君、公印を作りに行って、その歯医者さんと会ってきてよ、お金はあるから高くてもいいよ」
「はい、電話して行ってきます、鎌倉ですね」
吉都は匪実虚のパンフレットを手にとって、住所を見ながら考えている。三角形の顔の口がとんがっている。何かを思い出そうとしている。
吉都の眼鏡の奥が緊張した。
「所長、だいぶ前ですけど、今年に入ってからすぐだったかに、犬を選んでほしいという依頼がありませんでしたか」
「そんなことあったね」
「私もよく覚えています、所長が、江戸時代の墓を掘る犬のことを話してくださいました、あのとき、私、わんちゃんの主人思いに目がうるっとしたこと覚えています」
野霧は書類を封筒に入れ終わり、ポストに行こうと立ち上がったところだが、また腰掛けた。
「あれ、鎌倉の歯医者さんじゃなかったですか」
「そうだったな」
「名前も三角歯科じゃなかったですか」
吉都は物覚えがいい。
詐貸は電話機を操作した。この電話機はかかってきた電話の番号を、日付とともに記録してくれる特別製だ。もちろん音声も記録されている。記録は付属のハードデスクにある。探偵事務所には必須のアイテムだ。記録装置からPCに情報が送れる。
新年度だから四月だ。着信電話番号の記録をPC上に出した。詐貸は吉都たちのPCでも読めるようにした。
「あ、あります、三角歯医の番号です」
「あのとき、吉都君の知り合いの獣医さんの電話を教えたんだよね」
「そうです」
「鎌倉に印を作りに行く前に、知り合いの獣医さんから、その時の話をきいてくれないかな」
吉都も、野霧も、もちろん詐貸も薩摩の電話のことを考えていた。
「ハチ公の墓の事件と関係がありそう」
野霧はそう言うと、また立ち上がって、嵩丸に送る書類を、ポストに出しにいった。
吉都は高校の同級生に電話を入れた。佐々木獣医である。
「明日、彼と会います」吉都は詐貸に言った。
次の日、朝刊に、嵩丸弁護士また勝訴と大きな見出しがあった。逮捕された三人殺しの女性は、執行猶予つきの判決になった。三人も殺したのに執行猶予がつくとはまずないことだ。
午後になり、探偵事務所では佐々木動物病院に行ってきた吉都が報告していた。
「三角さんには甲斐犬を世話したそうです、甲斐犬は純粋なのが少なくて貴重です、とても優れた性質があります。中型犬で飼い主だけにしか慣れない、狩猟犬です」
「どんな犬」
吉都はスマホを詐貸と野霧に見せた。黒っぽい虎毛な地味な犬である。大きさは柴犬ほどだろうか、だが柴犬より険しいような感じを受ける。
「難しそうな犬だな」
「三角さんは警察犬のように訓練したいということだったそうです、それで、トレーナーも紹介したそうです」
「警察犬って、どういうこと、警護のためかしら」
野霧が不思議そうだ。
「警察犬にするには、普通は訓練所に預けて4ヶ月から6ヶ月かかるそうです。そのためには、警察犬のトレーナーの資格を持っている人に訓練させなければならないけど、そういう資格を持っている人を紹介したということです」
「本格的なんだ」
「そうですね、だけど、三角さんはとても静かな人だったということです」
野霧が詐貸に聞いた。
「先生、動物飼っていたことがあるんですか」
「子供の頃ね、家に猫が三匹いた」
「飼いたいと思わないのですか」
「思わない、生き物は死ぬからね」
「泣いちゃうからいやなのですね」
詐貸は笑って答えなかった。歯を食いしばって我慢をするのがいやなんだ。
「甲斐犬っていいわね、私も欲しくなっちゃう」
「日本犬はどの犬もいいですよ、秋田犬だって、柴犬だって、外国でとても人気が高い」
「可也は犬飼ったことあるの」
「団地だからないけど、猫はいた」
「ともかく様子はわかった、三角さんが、薩摩の言う墓荒らしに関係があるとは限らないから、薩摩にはまだ言わないよ、判子作りに行って、様子を見てきてよ」
吉都は匪実虚の印章の工房に電話を入れた。病院の番号とは違う。匪実虚工房の開設日は木曜日、日曜日、および土曜日の午後です、お急ぎの方はこちらから電話をかけますので、留守番電話に連絡先をお話くださいと録音された音声が流れた。吉都は詐貸にその話をして、木曜日にいくことにした。ホームページは立ち上げていないようで、住所を調べると、北鎌倉の駅南口前の道を左に折れ、十五分ほど歩かなければならないようだ。道の反対側には大きなお寺がある。
道に面した小さな間口の。お店とはわからないような建物だった。匪実虚工房と札がかかっている。隣の石積みの塀の奥に見える洋館が歯医者のようだ。入り口にご自由にお入りくださいとある。昭和の家のガラスの引き戸だ。彼は戸を開けた。軽いガラスの鈴の音が響いた。
店の中の棚には印章の材料が並べてある。
「いらっしゃいませ」
作業机の前にいた女性が立ち上がった。色の白い瓜実顔の背の高い女性だ。やっぱり巫女さんだ。
「電話をくださった探偵社の方ですね」
「はい、庚申塚探偵事務所の助手をしております吉都と申します」
「匪実虚です、お座りください、探偵さんって、初めてお会いしますわ」
吉都は作業台の前に置いてあった丸椅子に腰掛けた。
「間接的ですけど、鵠沼の象牙細工の翡海湖さんの紹介でまいりました」
「あ、そうでしたか、美目ちゃん、がんばってますものね、それで公印がお作りになりたいということですね」
「はい、庚申塚探偵社、とお願いしたいのですが」
「角印ですね、なにでお作りしましょうか」
「歯で作るとお聞きしたのですが」
「翡海湖さんが言ったのですね、歯で公印はつくれませんし、あれは遺族の方が、たってと希望されたときだけお作りしておりますし、小さなものになります」
「それでは象牙だと、おいくらくらいになりますか」
「象牙は国内の登録してあるものしか使えないので、高くなりますし、実は今、実印のような小さなものならできるくらいの象牙はありますが、公印のような四角の大きなものを作るのは、新たに探さなければなりません、お急ぎだと無理だと思います。象牙の仕入れの値段によりますので、いくらになるかはわからない状態です。一般的に公印は木や石で作ります、ただマンモスや鯨の歯などでも作りますが、それは象牙よりも高くなる可能性があります」
「所長は珍しいもので作りたいようなのですが」
「マッコウ鯨の歯だと二十万しますが」
「あ、それでお願いします、歯医者さんですから歯がいいと思います」
匪実虚は笑った。
「歯医者であることもご存じなのですね」
「ええ、実は、覚えていらっしゃらないかもしれませんが、四月頃に、犬を探してほしいとうちの探偵社に連絡されませんでしたか、僕の高校の同級生の佐々木を紹介しました」
匪実虚はあっと言う顔をした。
「そうでしたか、犬や猫を探すのが上手な探偵社だと聞いて電話しました、後で私もおっちょこちょいだと思いましたけど、紹介していただいた佐々木動物病医から、とてもいい甲斐犬を探していただきました。吉都さんの同級生でしたか、ありがとうございました」
そう言うと、「おいでぽち」、と奥に声をかけた。ちょっと開いていた戸から、黒と茶のまだらの犬が、あくびをしながら入ってきた。匪実虚が鼻の先をなでると、うれしそうにくーんとすりよった。熊狩りにかり出される犬というイメージだったので、なんだか拍子抜けだ。
「警察犬のようにしたいと、おっしゃってたと、佐々木が言ってましたが」
匪実虚はまた笑った。
「ええ、防犯と思って、トレーナーの方にもいろいろ指導いただいたのですが、こういう有様で、猫みたいにかわいくなっちゃって」
作業場から店に出てくると、吉都にもよってきて、なでてくれと頭を低くした。
これじゃ墓ほりなどできるわけはない。
「かわいいですね、月足美目さんとは双子の妹さんとうかがいましたが」
「そうなのです、美目ちゃんが母親から双子だったということを聞かされていなかったそうで、偶然に作品展で会ったのですが驚きました。私の方は養父と養母から、親戚筋の家に養子に来たことは聞いていたのですが、事情は聞けなかったので、あえて探そうとしませんでした。養父から、大昔、三角の家のお嫁さんは、知多の月足の娘だったことを聞きました。その妹が倭國神社のあとを継ぎ、私の実のおばあさんがその娘だったそうです。倭國神社がなくり、両親もなくなり、おばあさんは後見人とともに、関東にでてきて婿を取り、その娘に双子が生まれ、一番下の娘が家を継ぐというしきたりのあった家だったので、私が三角に養女にだされたようです」
今までの話と一致する。これはすごい情報だ。
「それでは、月足の家の家系図みたいなものをおもちだったのですね」
「家系図はありませんが、私が養女になるとき、母が持たしてくれたものがありました、祖母から母がもらった倭國神社の古いお守りでした、中に地図が入っていました、知多の地図です、神社のあるところが描いてありました」
「僕はそういう古いものに興味があります、見せてはいただけないでしょうね」
「いいですよ、住まいの方にありますから、ちょっと取ってきます」
匪実虚は裏の戸を開けて出て行った。ぽちも後をついて行く。
すぐに相当古そうな布の小さな袋をもってもどってきた。
「きっと数百年前のものと思います、和紙に書かれた、知多の昔の地図です、社の描いてあるところが、倭國神社で、文字もはいっています」
「これは、美目さんもご存じですか」
「いえ、まだ美目ちゃんはここにきたことがないし、来たときに見せようと思っていました。私は美目ちゃんの双子の妹ということになっていますが、養父は長女と申していました、現在は双子の先に生まれたほうが上ということになっていますが、昔は先にお腹に入っていた方が後に生まれるので、後のほうが上と考えられていました。美目ちゃんの方が先に生まれたので、古いしきたりの祖母が、妹として手元に残し、後に生まれた長女の私を三角に幼女に出したのだと思います。しかし、母は今のひとですから、美目ちゃんを長女と言って育てたのだと思いますし、双子を手元におきたかったのだと思います、不憫に思った母がこのお守りを私に持たせたのだと思います」
「匪実虚の作家名は、倭國神社の神としてひみこが祀られていたからですか」
「そうですね、きっと頭の中にあったのだと思います」
「この赤い丸はなんでしょう」
倭國神社より東にちょっと行ったところに、赤い丸印がある。
「何でしょうね、私は知多にも行ったことがないし、全くわかりません、そういえば、今週の日曜日に、弁護士事務所の秘書さんが、印鑑を買いに見えましたわ、そのとき、吉都さんと同じように、美目ちゃんから話を聞いたと言っていました。古いお家のようだから、昔の地図のようなものを持ってないかお聞きになったので、この地図をお見せしました。スマホで写真を撮っていかれました。何か意味があるのでしょうか」
吉都はおやっと思った。
「なんとおっしゃる弁護士さんですか」
「今、有名な方ですわ、そういう方の印を作るのは私としても、光栄なので、喜んでお引き受けしました、嵩丸弁護士です、つい最近の新聞にも大きな事件の弁護をなさって、刑を軽くしたことが載っていましたね」
「ああ、そうですね」
なぜ嵩丸弁護士の秘書が頼みにきたのだろう。
「判子はもう取りにこられたのですか」
「いえ、お送りしました、吉都さんの事務所にもお送りしましょうか」
「はい、お願いします、僕もスマホで写真撮らせてもらっていいですか」
「もちろんどうぞ」
吉都は撮った写真をすぐに事務所のPCあてに送った。
事務所に戻った吉都は、匪実虚が実は双子の方の長女であったこと、それに養子先の三角家は、月足の八人の姉妹とつながっていることを話した。
「それで送ってくれた古地図はなに」
「匪実虚は養子にされたとき、大昔の倭國神社のお守り袋を渡されていて、その中に入っていた知多の地図です」
「倭國神社の場所から東に朱の印があったけどなんだろう」
「なにを意味するのでしょうね」
「それからおかしなことを聞きました。嵩丸弁護士の秘書が、匪実虚のもとを訪れ、嵩丸の判子をたのみ、やはりこの地図の写真をスマホで撮ったそうです」
「なんでえ」
野霧が声を上げた。詐貸も顔を上げた。
嵩丸はなにを考えているのだろう。事件が終わって、自分で調べる気になったのか、なにかありそうだ。
「あ、それから、甲斐犬は、もうでれでれで、ぽちと呼ばれていました。もう熊などおえません」
吉都は笑いながら犬の様子を報告した。詐貸も野霧も美矢の甲斐犬とハチ公の鎌倉の墓掘り事件を関連づけて想像していたのだ。関係なさそうだ。
「庚申塚探偵社の公印は、マッコウ鯨の歯でたのみました。二十万円」
「ごくろうさま、その赤丸の意味を考える必要があるね」
「嵩丸さんにはこのこと連絡しないのですか」
「うーん、奇妙だと思わないか、翡海湖の個展に野霧を行かせて、秘書も行っている、翡海湖から何かを聞き出したかった、とすれば秘書でも十分な気がするけどね、あの個展は一月くらい長い間のものだったよね」
「そうです、もう二週間よりもっと前からです」
「秘書がすでに行ったのだけど、話は聞き出せなかった、それでうちに話をもってきた、うちには逢手君という、有能な探偵がいるからね」
「やだ、私まだ探偵じゃないですよ」
「あの秘書さんだと、モデルさんのようで、世間話をするような感じがないですからね」
吉都がそういうと、野霧がぷすっとした。それに気がついた吉都が「あの、野霧さんをほめたのですが」と背を丸めた。
「それで、野霧君が聞き出した鎌倉の匪実虚に関する情報は、うちから書面で報告を受けて、すぐに秘書が鎌倉に行って、こんどはうまく双子の姉から昔のお守りを見せてもらうことができた」
野霧が気づいた。
「こんな大事なことなら、うちに知らせがきてもいいですね」
「そうなんだ、嵩丸弁護士は、仕事が終わったとはいえ、まだまだ、後かたづけに忙しいからかもしれないが、それにしても、秘書からそのことをこちらに伝えてくれてもいいだろうと思う、鵠沼の翡海湖のことはわざわざ出向いてでも知らせてくれたよね、まだ事件が終わっていない忙しいときにだよ」
「確かに不思議ですね」
「電話をかけてみようか」
詐貸は嵩丸の事務所に電話をかけた。誰もでない。
「おかしいな、誰かは必ずいるはずだが」
「ねえ、先生、愛子さんに連絡して、嵩丸弁護士事務所の様子みてもらいませんか」
野霧だけではなく、みんな何かありそうだと思った。詐貸はうなずいた。すぐ、携帯で愛子に連絡をとった。
その三十分ほどあとに詐貸に連絡があった。詐貸が神妙にうなずいている。
「愛子からだ、あの弁護士事務所は閉まっているそうだ。しかも嵩丸弁護士事務所という看板は消されている。それで愛子は知り合いに聞いてみたそうだ。その人が言うには、弁護士事務所の家は、昔地元の弁護士の持っていた家で、嵩丸弁護士は独立したときにそこを借りて事務所を開いたそうだよ、ずいぶん昔の話だね、なぜ嵩丸の名前が消されているかわからなかったそうだ、その家を管理している不動産屋がどこかわかれば聞いてくれると言っていた」
「大きな事件が終わったので、どこかほかに事務所をかまえるのでしょうか」
「だけど、結審したけどまだまだ忙しいと思うよ、薩摩にきいてみよう」
詐貸は薩摩に電話をした。
「調べてみると言っていたよ、それから、鎌倉の墓の事件は解決した。珍しいことだけど、野良犬の仕業らしい、引っ張り出された骨は、近くの池の畔に放り出されていたようだ」
「嵩丸弁護士の秘書が、匪実虚さんのところに行ったのは日曜日ですから、もし事務所を閉めたとすると、そのあとでしょうか」
「そうだよね、少なくとも、翡海湖の個展に行った野霧君のまとめた情報を送った以降だね、匪実虚の存在を知った後だ」
「嵩丸弁護士は、それで鎌倉に秘書を行かせたのですね」
「そうだろうな、今回の鎌倉の匪実虚さんのことに関して、まとめてくれるかな、書類ができたら嵩丸事務所に送ってみてよ」
吉都が鎌倉でのことをまとめて、すぐに野霧が投函した。
嵩丸弁護士の行方
月曜日の朝、事務所で朝刊を見て詐貸はぎょっとした。嵩丸弁護士行方不明の見出しがある。読んでいくと、いろいろなメディアが嵩丸弁護士と連絡を取ろうとしてもできず、弁護士事務所に雇われていた数人の弁護士の話だと、先週の月曜日に、突然解散宣言をうけ、退職金が支払われたという。今までの事件の書類は、担当していたそれぞれの弁護士のところに保存されているということだった。警察では、雇われていた人たちの話を総合すると、突然だったことは奇妙だが、事件性は低いと判断している。秘書で奥さんの嵩丸夢霧さんも連絡が付かないので、個人的なことで夫婦ともども姿をくらましているのではないかと、記事を結んでいた。
野霧と吉都が出勤してきた。
「嵩丸弁護士がいなくなりましたね、秘書じゃなくて奥さんだったのですね」
詐貸は無言だった。
吉都が「半田にいったのではないですか」と言った。詐貸もそれを考えていたようである。
「半田に行こう、倭國神社のあったところから東の方角に赤丸があった、あれを確認しよう、野霧君すぐ新幹線の指定とって、このまま行けるならみんなでいく」
「はい、大丈夫です、いつもバックに一泊くらいできる準備はしてあります」
野霧も返事をして、ネットでのぞみの予約をした。名古屋は近い。東京から一時間半でいく。東京駅にでて、十一時半ののぞみに乗り、二時には知多半田の駅に着いていた。詐貸は初めてのところである。ずいぶんのんびりとしたところだ。
駅から野霧たちの案内で倭國神社まで歩いた。神社の社のあったところは、木々に囲まれた公園のようになっている。ベンチがおいてあり、倭國神社跡と立て札があって、半田市の管理になっているようだ。
「あれ、ずいぶんきれいにしちゃいましたね」
野霧が驚いている。
吉都が通りがかったおばあさんを呼び止めた。おばあさんはにこにこして、吉都に話をしていた。
「なんだったの」
「この公園、土地の持ち主が、地ならしして、公園として市に寄付したそうです、ほんの最近のことだそうです、ゲートボールなどにも使えるので嬉しいと言ってました」
嵩丸がそうしたのだろうか。
「でも、この土地は月足のものなんだろう」
詐貸が首を傾げる。
「前に市役所で確認したときにはそうなっていました」
「そういえば、嵩丸さんは大学の先生に頼んで、掘ってもらったと言ってましたね、そうするのに持ち主の許可が要りますね、その時点で鵠沼の月足美目さんのことを知っていたということになりませんか」
「たしかにそうだね、月足さんに聞いてみなければならないな」
「美目さんの電話番号控えてあります、所長電話をかけてみたらどうですか、もしかすると病院に行っていて、工房にいないかもしれませんけど」
「やってみよう」」
詐貸は電話をかけた。うまく居たようだ。話し始めた。
「庚申塚探偵事務所の詐貸と申します、嵩丸弁護士の知り合いなのですが、嵩丸弁護士と連絡が取れないので、電話をさせていただきました、忙しいところすみません、嵩丸さんが、以前月足さんと知り合いと言っていたものですから、嵩丸弁護士とは最後いつお会いになりましたでしょうか」
詐貸はちょっとかました。
「実は私、嵩丸弁護士とはお会いしたことがないのです、秘書の嵩丸夢霧さんとはお会いしました。半田の私の祖母の所有となっている土地をすべて買いたいというお申し出でした。嵩丸弁護士は知多の方だったそうで、嵩丸弁護士のおじいさんが、倭国神社の理事だったそうです、倭國神社がなくなってからこちらに出てこられたそうで、世話になった市のために跡地に何か作りたいということでした。あの有名な嵩丸弁護士が買ってくださるならと、私もうちの弁護士にまかせてお売りしました。祖母から名義を私に移すのに面倒だったようですが、かなり高く買ってくださったのです」
「いつ頃です」
「今年の夏のころでした」
「それで、嵩丸さんは今半田にいらっしゃるのでしょうか」
「私は全く存じ上げなくてすみません」
「言え、こちらこそ急に電話を入れて申し訳ありませんでした、ありがとうございました」
「嵩丸弁護士はかなり前から、月足美目の事を知っていたんだ」
詐貸は今月足美目と話したことを二人に伝えた。
「どうして、知らないと言ったのでしょうね」
「なにかあるな」
「それで、社の跡を自由に掘り返したわけですね、だけど、美目さんのことをわかっていたとすると、倭國神社の何を知りたかったのでしょうね」
吉都が何かおかしいという目をしている。
「あの、赤い印の場所を探してみよう」
スマホに三角美矢のもっていた神社のの地図を表示した。
「ここからそんなに遠くありませんね」
倭國神社の前の道を東の方にいけばその場所にでそうである。雑木林の前を通って、畑が広がるところにでる。赤いしるしのある場所へ三人は向かった。小さな川に橋が架かっている。渡ったたもとにお地蔵さんがあった。顔が削れて鼻などはなくなっている。相当古そうだ。その脇には畑が広がって。地蔵の脇がかなり広く掘り返された跡がある。詐貸はそこを見つめている。
「赤丸はこのあたりですね」
「掘り返した跡ですね」
「誰かに聞いてみよう」
三人は道端で立っていたが、なかなか人が通らないね。
「駅に戻って、タクシーで市役所に行ってみましょう、前に親切にいろいろ調べてくださった方がまだいると思います」
三人は市役所に行き、野霧が戸籍係の戸部さんと話した。
「四月にはお世話になりました、おかげさまでいろいろわかりました、また知りたいことができて伺いました」
野霧はスマホを見せて、地蔵のある土地のことを尋ねた。
「あの土地は、個人のもので、今なにも作っていません、もう所有者がお年寄りで、畑もできないし、誰かに委託して、実の生る木でも植えて、農地としておいておくと言っていましたね」
「あそこのお地蔵さんは古いものですね」
「ええ、おそらく、倭國神社と同じくらいでしょう、市としても保存したいと思っています、土地はその人のものです」
「あそこの土地の持ち主の方はお地蔵さんのことをよく知っていらっしゃるのでしょうね」
「そうですね、もう何代も続く家です」
「話を聞かせてもらいに行って大丈夫でしょうか」
「ええ、年はめしてらっしゃいますが、しっかりしていて、昔のことを話すのは好きな方です、私のほうからみなさんが行くことを電話しておきますよ」
「ありがとうごいます、お手数かけてすみません」
「いや、半田をもっと知ってもらいたいと思っています」
三人はお礼を言って、紹介してもらった都筑家にタクシーで向かった。
都筑家の十代当主は八十九になる老人だった。しかし話はしっかりしている。
「倭國神社の信者たちはかなりまとまっておってな、われわれ元々半田にいた人間とはちっと違った人たちでしたな、人当たりはよかったので、問題なかったが、それをとりもってくれていたのが、知多市の嵩丸さんだったな、神社を支えておったな、嵩丸さんも昔は半田にいたらしいが、商売の方で、表の海に近い知多の方にいったらしいな、嵩丸さんの子孫が、あの有名な弁護士になっとんたんですね、倭國神社の土地も嵩丸さんが持ち主から買い上げて、市に寄付してくれましたな、えらいことですわ。
うちの畑のはずれの地蔵さんは、倭國神社ができたとき一緒にできていたようですな、あのあたりは信者の土地で、信者の家がいくつも建っておったということです、しかし、なんと神社に隕石が落ちて、燃えたことがあって、それ以来、信者も離散して、わしのうちが土地を買って、畑にしましたんで、まあ地蔵さんはそのままいい風景になっていますな」
「畑が掘り起こされたあとがありますが、何かにする予定ですか」
「いえ、最近嵩丸弁護士が来ましてな、倭國神社の歴史を調べておって、地蔵のあたりに、神社に落ちた隕石が埋めてあるかもしれないので、調べさせてほしいと言ってきました。今はなにも植えていないし、どうぞといいましてな、その日の夜中にブルドーザーを持ってきて掘り起こしたということです、結局なにも出てきませんでしたと、嵩丸弁護士からは連絡を受けました、畑をほじくり返して申し訳ないと、ずいぶんの商品券をくださいましたが、あそこは栗畑にでもしようかと思っていたので、逆に耕してもらってありがたいくらいでしたのにの」
「そうでしたか、嵩丸弁護士が今行方不明なのはご存じですか」
「ええ、知っております、新聞やテレビで報道していますからな」
「私たちは、嵩丸弁護士の知り合いなのですが、もしかすると、半田にいるのではないかと思って、来たのです」
「そうですか、わしらにはなにも知らせはありませんな」
「このあたりで、大きな工事を請け負うところはどこでしょうか」
詐貸が聞いた。
「そうですな、半田重機でしょう」
「嵩丸さんもそこに頼んだのでしょうね」
「ああ、そうだよ、わしが教えてやったから、社長は知り合いだしね」
「電話番号を教えていただけますか」
吉都が半田重機の電話番号をスマホにいれた。
「いや、ありがとうございました」
三人はタクシーを呼んだ。
野霧と吉都はそのまま駅に帰るのかと思ったら、詐貸が運転手に、半田重機に行ってほしいとたのんだ。
「どうして半田重機にいくのですか」
「聞いてみたいことがあるんだ」
半田重機は駅の反対側をかなりいったところにあった。
事務所にいくと、詐貸は「嵩丸弁護士の知り合いで、彼の行方をおっています、夏頃、ここでブルドーザーをお願いしていると思いまして、お話を伺いにきました」
と名刺をだした。
「あ、探偵社の方、それに弁護士さんですか、お仲間ですね、確かに嵩丸さんが最近、ブルドーザーを頼まれました。都筑さんのところの畑を掘ってほしいと言うことでした、都筑さんからも連絡もらっていましたので、夜中でしたけど、投光器を持たせて、行かせました」
「畑をすべて掘ったのですか」
「担当者の話では、あまり広く掘ったわけではないということです、地蔵の脇のほんの十メーター四方を五メートルほど掘ったところで終りでした。なんでも、何か大きなぼろぼろの布袋がいくつか出てきて、それでおしまいでした、むかしの土嚢のような感じだったと言ってました。一時間もかからなかったので、運転手は楽な仕事だったと言っています」
「出てきたものはどうしたのでしょう」
「そのまま、秘書さんが運転してきたワゴン車に積んで持って帰ったということです、担当者はブルドーザーでそこをもう一度ならして、社に戻りました」
「その後、嵩丸弁護士から連絡はあったでしょうか」
「いえ、費用を払っていただいてからそれっきりです」
「倭國神社後をならしたのもお宅ですか」
「ええ、そうです、その後、土地を市に寄付されました。たいした方です」
「そうですね、お忙しいところどうもありがとうございました」
詐貸たちは事務所をでると駅に戻った。
「嵩丸弁護士はなにを見つけたのでしょうね」
野霧がいうと、吉都が、「嵩丸さんの目的は、鎌倉の匪実虚さんの地図だったかもしれませんね、野霧さんが、五條の毘眉胡さんからもらった古文書のコピーを見て、倭國神社に卑弥呼のものが埋まっていることを知ったんです、古文書にさらに掘ると何かがあると書いてありましたね、それを知りたくて、鵠沼の翡海湖さんとコンタクトをとって、結局、双子だと言うことを野霧さんが聞き出して、それで、僕より先に鎌倉に行って、地蔵の場所を知ったのです、それで急いで都筑さんの畑を掘った」
「すごい推理ね、可也君、嵩丸弁護士はそのために我々に依頼したわけね」
「そういうことになる、倭國神社に埋まっていたものよりもっと価値のあるものを掘り出したんだな」
詐貸もうなずいた。
「だけど、八公の事件と、嵩丸さんの依頼がこんなに結びつくなど不思議ですね」
吉都はまだ考えている。
「嵩丸の目的は自分の先祖の系図を探ることでも、倭國神社のありかを探ることでもなかった。われわれに、ちらばった倭國神社の祖先を捜させて、なにかを捜したかっただけなのでかもしれんな」
詐貸が渋い顔をして言った。
「ともかく名古屋にもどる。今日は名古屋に一泊しよう」
三人は名古屋のドーミーインに泊まった。駅の近くなのに温泉があるホテルだ。
食事をしながら、今までのことを整理した。
「嵩丸弁護士から倭國神社の調査の依頼があった。薩摩から、富山で女性が誘拐される事件がおきていることを聞かされ、偶然にも、麻酔医、丸林美神、すなわち氷見己、が犯人であることがわかった。倭國神社のご神体の木切れの地図に八つの赤印があり、その中の二つ、萩と博多にいくと、薩摩の連絡で、人毛が盗まれる事件があり、犯人が、萩の毛筆家、火見胡、皮膚科医の牛島美霧であることを我々が突き止めた。博多では、亡くなった人から眼が盗まれる事件があり、その犯人は、眼のアーティストの妣視杞、眼科医の仁田原(にったばる)美芽が犯人であることをつきとめた。しかし、倭國神社につながるものは見つけていない。ただ、八女に関しては、かなり倭國神社に関わりのありそうな場所だということがわかった。
嵩丸弁護士の趣味である革装の豆本集めから、薩摩たちが探していた人の皮膚を買う人間が、浜松の皮実沽、皮膚科の國武美藻であることがわかった。彼女に関しては倭國神社との関係はわからない。
五條で野霧君が、薩摩の探っている事件の中の、爪のコレクターが、琴の名人、爪のアーティスト、室園美弓、本業、外科医であることをつきとめ、しかも倭國神社の子孫の一人であることを明らかにする。さらに、吉都が島根の浜田で、カタツムリのコレクター、執筆家、甲木美夜が耳鼻科医で、作家名を緋巳壷といって、倭國神社に関わりがあることをつきとめる。
嵩丸自信から、倭國神社の本家の孫娘、月足美目の居場所が鵠沼であることを知らされ、野霧が会って、双子であり、もう一人は倭國神社の末裔の家に養子に出されていることを突き止め、さらに吉都が鎌倉で歯医者をしていて、かつ歯を使った印刻家であること、本当は月足の長女で、お守りを持っており、そこに地図があったことを調べてくれた。
こうして薩摩の第八研究室で調査をしている事件と、嵩丸の依頼が重なった」
「そうですね、この八人は、倭國神社の、二代目の神主の八人の娘が子孫とわかったわけです」
そういいながら、吉都は系図をまとめて、詐貸と野霧のすマホに送ってくれた。
「警視庁の八公と嵩丸弁護士がどこかでつながていたのか」
詐貸が疑問を投げかけた。
「薩摩警視は赴任したばかりですから、嵩丸さんとつながっているとは思えませんが、嵩丸さんから見たら、薩摩警視が詐貸所長とつながっていることはわかっているのではないですか」
野霧が言った。
「たしかにそうだけど、おかしな事件は前から第八研究室に送られていた情報だよ」
「送るようにし向けることはできるわ」
「それは難しいだろう、一番可能性のあるのは、前からいたハチ公のだれかから情報をもらっていた。有名な嵩丸弁護士のことだから、うまく聞き出していたんじゃないか」
「そうですね、とすると、本でつながっていた古書さんですか」
「可能性の高いのはそうだろうな」
「巣鴨に帰ったら、一度、ハチ公のみなさんと、飲みますか」
野霧の提案に三人ともうなずいた。
「嵩丸弁護士がおいていった費用まだたくさん残っている、嵩丸弁護士を捜す会にして、つかっちまえ」
詐貸がやけっぱっちに言った。
「高級ホテルのディナー」
「ぼくやだ」
吉都は堅苦しいところが苦手だ。本当は野霧だって、詐貸だってだめだ。
「わたしが、巣鴨のどこか飲み屋を探し、ひさごそばじゃ狭いですものね」
野霧がおとなしくなって言った。
嵩丸の消息はつかめていないようだ。
巣鴨駅のあたりにはいろいろ飲みやがある。良さそうな居酒屋を野霧が探し出した。店名が、「神無月」と不思議な名前だ。土曜日の夜7時より貸し切った。鉢巻をしたじいさんと、若い女性の店員の二人でやっている小さな店だが、いかにも手作りの感じで良さそうだ。
焼き鳥からピザまである。お酒、ビール、ワインからウイスキーまである。ただ銘柄は一つだけ、どうもそのじいさん好みのものだけがおいてあるようだ。
七人ほど座れるカウンターと、四人席が二つつあった。貸しきりだと、テーブルをつなげて、無理すれば八人から十人座れる。
薩摩たちに声をかけたら、大喜びで来ることになった。ただ土曜日の夜にしてくれということだった。
野霧と吉都はホストとして少し早く店についた。
「いらっしゃいませ」
三十そこそこと思われる女の店員さんは、化粧もしていないのに、なぜか顔が輝いている。落ち着いたきれいな人だ。
「らっしゃい、今日はどうもありがとうございます」
頭に鉢巻をまいた、ごま塩の坊主頭をしたじいさんが、包丁を持って、腕を振るっている。よく見ると俳優の奥田瑛二に似てなくもない。年の割には背の高いじいさんだ。
「今日は全くのお任せで、腕をふるうから、飲み物は姫子にいって」
え、っと吉都が驚いた。野霧が「ヒミコじゃないわよ、ヒメコさん」と笑った。頭が卑弥呼漬けになっているのは吉都だけではない、野霧も最初そう聞こえた。
「こちらこそよろしくお願いします」
「何の集まりで」
「まーあ、仕事の打ち上げってところかしら、いや、中間報告会」
野霧が笑って答えた。
そこで、じいさんが改まって、野霧に言った。
「遅くなると、常連が入りたがるが、一応断る、だけど無理矢理入ってくるやつがいるかもしれない、じゃまさせんから、そのときはよろしく」
ちょっと耳を疑ったが、「はい」と二人は答えた。
七時になるとどやどやどやと四人入ってきた。ハチ公の若い人たちだ。
「こんちわ」
顔を知っている世久希紅子がとびこんできて、
「うちの連中でーす、宙夜さん、古書さーん、大先輩の高胎さーんです」と紹介した。みなニコニコしてお辞儀をした。
「なにさ、古書君とたった一つしか違わない」
高胎さんが文句をいいながら椅子に腰掛けた。
「でも、わたしより五つ上」
なんだか、ハチ公も賑やかそうだ。
「今晩わ、逢手です」「吉都です」
二人ともかしこまっておじぎをした。
「好きなところに座ってください、飲み放題です、料理はお任せでお願いしてあります。時間制限なし、半分貸しきりです」
みんなバラバラに座った。
「逢手さん、半分貸し切りってなに、入り口には貸し切りって書いてあったけど」
世久が聞いた。じいさんが笑いながら料理をしている。
「遅くになると、常連さんが、勝手に入ってくるんですって」
「おもしろ」
宙夜がぼそっといった。詐貸と薩摩がまだ来ていない。どうしようか逢手がまよっていると、「親分きてないけどはじめようよ」と世久が声を上げた。
「飲み物は、最初ビールでいいですか」
「はーい、なにビール」
すると、じいさんが大声を上げた。
「ビールはびーるしかないよ」
野霧が「お願いします」
とまけずに声を上げた。
店の女性が、大きめのグラスにビールをついでもってきた。野霧が小さい声で聞いた。
「姫子さん、なにビールです」
姫子さんはにこにこと、「うちのです」と答えた。
みんななんだという顔をしたら、カウンターの中から、じいさんが、「ビールと日本酒はうちが造らせているんだよ、ワインも樽で買ってうちのラベルだ。焼酎も鹿児島に頼んであってね、ただ泡盛は石垣島古酒、ウイスキーブレンドは角、シングルモルトはグレンロシスだよ、アイラは隠してあるから言ってくれ」
意味がわかったのはいないようだ。
「みんなおまかせですね」
「飲み方はオーダーしてね」
「それでは、よくいらっしゃいました」
野霧が音頭をとった。どうも一番年上かもしれない。ぐーっと飲んだ。
「うまいビールだな」
声を上げたのは静かにしていた古書である。
「古書さんは、本だけじゃなくて、なんでもうるさいからな」
宙夜ももうグラスの半分空けている。
はっと、乾杯の音頭の後、腰掛けた野霧を見てみんなが驚いた。グラスの中のビールはすべて胃の中に入っていた。
黙っていたのにもかかわらず、姫子がビールを運んできて、野霧の前においた。
「すぐにお通しをもってきます」
皆に小皿が配られた。
「えー」希紅子がびっくりしている。小皿の上に小さな蟹が一匹のっている。
「沢ガニの唐揚げ、おいしいよ」
吉都がバリバリ食べた。希紅子ははじめてのようだ。
「いろいろな事件を解決していただいてありがとうございました、逆にこちらがごちそうしなければいけないのに」
高胎が野霧と吉都に言うと、野霧が「いいえ、うちの依頼人の仕事とこんなに重なってくるとは思っていなかったんです、行く先々で第八研究室の事件と絡んできて、旅がおもしろかった」
「依頼人て、行方不明の嵩丸弁護士じゃないですか」
古書が言った。
「そうなんです、どうしてわかったんです」野霧がうなずくと、古書が説明を始めた。
「数年前から、嵩丸弁護士から、個人的に古い日本の本の解読をたのまれていました」
「豆本ですか」
「いえ、あの方は、豆本もたくさん持ってらっしゃるようですけど、稀覯本もかなりお持ちですよ、それで、何回かお目にかかって、話をしたのですけど、捜査支援分析センターの第八研究室であつかっていることに興味をおもちでしてね、変態的な事件が多いのですけど、嵩丸弁護士は、趣味的な変わった事件に興味をもっていました。具体的なことは言わなかったのですが、こう言ったことはあると、いろいろ話しました。おそらく、おもしろい本に関わることはないか考えていたのではないでしょうか」
「何か探していたのですか」
「うーん、よく話をしていたのは、邪馬台国の時代、まだ日本の言語はなかったんだが、中国では言語があって、紙に字を書いていたのだから、日本でまねをして、本のようなものを作っていたのではないかと、自分の考えをおっしゃってました」
「卑弥呼ですか」
「そうですね、魏とつながっていて、いろいろなものをもらっていて、当然、紙ももっていただろう、それで、本のようなもの、記録をつけたような冊子を作っていたのではないだろうかと、言うことです、魏から、卑弥呼は親魏倭王と呼ばれたくらいですから」
「年代的に、三国志の魏史倭人伝は卑弥呼が死んでから書かれていますね」
野霧が聞いた。魏志倭人伝は280年から297年にかけて書き上げられた三十巻にもなるものだ。
「そうですね」
「そのころ、日本では話し言葉しかなかったとすると、ヒミコという字は、魏の人がヒミコから派遣されてきた人間から聞いて、向こうの漢字に当てはめたわけですよね、逆に魏の皇帝から親書をもらったヒミコは自分はこう書くのだとわかったのですね」
「あ、そうですね、そういうことになりますね、そこで、嵩丸弁護士は、ヒミコが自分でも字を作りたいと考えたのではないかと思ったわけです。卑弥呼は呪術、鬼道といわれていますが、それをつかって民衆を率いていたわけで、おそらく、何かの印をつくって、それを民衆の前に見せ、敬わせていたとも考えられます、そこに、魏の文字で、自分の名前を書く、さらに、国の名前や、人の名前、そういったものを、漢字で表し、民衆を驚かせる。そのようなことをしていたとしても不思議はありませんね、ですから嵩丸弁護士は、最古の日本の本は、卑弥呼が作っているのではないかと思っていたと思います」
「それで、なぜ、ハチ公、いや、第八研究室の事件のなかで、趣味的な事件に興味を持たれたのでしょう」
ハチ公といったら、ハチ公の人たちが笑った。
野霧はまずいことを言ったと俯いたら、希紅子が「今では私たちも、自分の研究室をハチ公と呼んでますよ、薩摩室長が、庚申塚探偵事務所の連中が、忠犬ハチ公と呼んでたよ、と言ってました、それから我々の研究室は忠犬ハチ公です、でもあまり忠犬ではないけど」
今度はみんなが笑った。古書が続けた。
「趣味的なというのは、ヒミコの何かを知っていたからかもしれません、僕には理由がわかりませんが」
野霧が、もう言ってもいいだろうと思って言った。
「そうなんです、ヒミコをまつっていた神社の神主について、調べてほしいと嵩丸さんが言ってきたのです」
ハチ公の連中はほーっと言う顔をしている。
「そうか、博多の眼の事件は、眼のコレクターで、アート作家の妣視杞だった」
宙夜が言った。
「五條の事件も、爪のコレクター、アーティスト、痺弭弧だった」希紅子が言った。希紅子の友達である、奈良県警の紅酒野実に助けられてわかったことだ。
「浜松の人皮装丁者も皮実沽、富山の氷見己もいる、みんなアート関係、しかもヒミコ」
高胎がうなずいた。
「しかも、嵩丸弁護士は、薩摩警視がうちの詐貸所長の友人であることを知って、われわれをやとって探らせたわけね、我々は嵩丸弁護士の祖先と倭國神社のことを調べるのだと思っていたけど、嵩丸弁護士は卑弥呼の何かをみつけたかったということだわね」
野霧が四杯目のビールを半分飲んで言った。その間にいろいろな料理がだされている。みなおいしいものばかりだ。
と、ふと、吉都が時計をみて、「薩摩さんと、うちの所長まだこないな、八時ですよ、一時間過ぎている」
皆、ふーっと我に返った。確かに遅すぎる。とそこにがらがらと二人が入ってきた。
「よー、遅くなった、わりいな」
「へい、らっしゃい」
じいさんが声をかけた。
薩摩が空いている席にこしかけた。詐貸もこしかけた。
「警視、飲んできたでしょう」希紅子が叫んだ。
「いや、この探偵と、ちょっとした打ち合わせでな、おやじさん、うまい酒ちょうだい」
神無月の主人に声をかけた。
「あいよ、これで、八人の神さんがそろったね、うちの酒はどれも美味いよ、そちらの神さんなにするね」
詐貸にじいさんがきいた。
「おれは、ウイスキー」
「お、角かモルトか」
「モルト、ロック」
「あいよ」
姫子が二人に残してあった、お通しと料理を前に並べた。
「お、美人だねえ」
薩摩はだいぶ飲んでいるようだ。姫子がにこにこしている。ますますかわいらしい。
「あたりめえだ」
じいさんが返事している。
「警視、なにしていたんです」希紅子がきつい調子で詰め寄った。
「うん、俺たちがいない方が、いい結論をだしてくれるだろうと、このだちが言うもんでな、がまんして、馬場で二人で待ってたんだよ」
高田馬場のいつものところで二人で飲んできたのだ。
「ふぐの唐揚げ出すよ」
じいさんが言うと、姫子がカウンターに入り、揚げたてのふぐを大きな皿に盛って、とり皿とともに持ってきた。
薩摩がさっそく箸をとると、「うめえ、こんなにうまい店が、ド田舎にあるとはな」とわめいた。
じいさんが笑って言った。
「東京のアホにしちゃ、口が肥えてるじゃねえか」
「俺は、仙台だ、東京なんか知らねえ、こいつは東京だ」
薩摩が詐貸を指さした。詐貸がウイスキーにくちをつけ、ぼっそっと「ハイランドか、うまい」と言ったのを、じいさんがききつけた。
「東京人はウイスキーだきゃわかるね」
じいさんに言われて、詐貸が「ご主人もどうぞ」
と言った。
「おー、やっと言ってくれたね、だれもいってくれねえ、若いやつらはだめだね、やっぱりそういうとこは東京の男だね、渋いね、いただきますよ、アイラをね」
じいさんは足下からウイスキーの瓶を出すと、タンブラーにそそいで、口に含んだ」
「うめえ」
「飲み過ぎないでよ」
姫子がじいさんに言っている。
「ここまで、ラガブーリンが匂うよ」
詐貸が言うと、じいさんは「恐れいりやした、よかったら、どうぞ」とびっくりしたように詐貸に言った。銘柄を当てたようだ。
「後で、お願いするよ」
「この集まりはなんだね、警視だ探偵だと、ミステリークラブですかね」
じいさんがウイスキーを飲みながら、みんなを見渡した。
「あたりー」
野霧が大声を上げた。
また玄関が開いた。
「貸し切りとあったけどいいだろ」
白い髭を生やした老人が入ってきて、爺さんが何も言わないうちに、カウンターに陣取ってしまった。
「向こうのミステリークラブの人たちがいいと言えばいいよ」
じいさんが言っている。
老人が、「どうも」とみんなの方を向いてお辞儀をした。
「あ、五十嵐五十老」
野霧が叫んだ。髭の老人がにっこりと、野霧に向かってほほ笑んだ。
「だれ」
詐貸が聞いている。じいさんがたいしたもんだという顔をしている。
「ミステリーの通だね、本名を知っている人はあまりいないよ」
野霧が有名な探偵小説作家の名前を言った。詐貸が驚いた。
「今度、本を持ってきます、サインをください」。
野霧が老人に声をかけた。
「しょっちゅうきているよ、この先生」じいさんが言った。老人も野霧にうなずいた。
老人が、
「奥さん、いつもの出して」
と姫子に声をかけた。
野霧をはじめ、八公の連中も目を丸くした。
「奥さんって」
野霧が思わず声をあげた。
「姫ちゃんだよ、じいさんの奥さん、全く、この爺のどこがいいのだろうね」
推理作家がそう言った。
「へぼミステリー作家がなにいってやがる、そっちにいるのは本まもんの、警察官と探偵だ」
じいさんがやりかえした。わかっていたとみえる。
野霧は嵩丸弁護士の秘書が本当は奥さんだったことを思い出した。
なんだかすさまじい飲み会になった。
それからわあわあやって、十一時になったころ、解散ということになった。
可也がみやげを希紅子にわたしている。野霧はちらっとそれを見ながら会計をすませた。ずいぶん安い。お金がずいぶん余った。
野霧はまだ飲んでいる老人に「先生、本当にサインください」と言った。
老人は「おうおう、いつでも」とうなずいた。
「ごちそうさま」
みなが店の外にでると、主人と姫子がでてきた。
「ありがとうございました、またどうぞよろしくお願いします」
姫子が挨拶した。
「あの日本酒うまかった」
薩摩がじいさんに敬礼した。
「そりゃあそうだ、味はわかるんだな」
「へへ、そいじゃ」
「ありがとうさんで」
じいさんに送られて、駅の方に向かった。薩摩は詐貸とまたどこか行くようだ。みなばらばらのようで、いっしょのようで、とこもかく、駅でさようならを言って分かれた。野霧は一人で新宿に向かった。
月曜日、野霧と吉都が事務所に行くと、詐貸がデスクでPCを見ていた。
「おはよう、嵩丸はどこにいったのかな、薩摩がハチ公に捜索するように回ってくるかもしれないと言っていた。となると、うちにも助けてくれっていうことになるよ」
「そうですね、土曜日はだいぶ飲みましたね」
「うん、結論どうなった、やっぱり嵩丸はハチ公とつながっていたんだろ」
「つながっていたというか、情報はもってました。古書さんがいろいろ話してくれました」
「嵩丸の目的はなんだったんだろう」
「古書さんの推理では、日本で最古の本を探していたのではないかと言っていました、卑弥呼が作っているんじゃないかという推理です」
「だけど、姿を隠す必要があるのかな」
「なにかみつけたのじゃないですか」
「そうかもな、我々が調べたことはどうなるのかな、厳島神社なんて関係なさそうだしな」
「直接はなさそうですね、日本の歴史すべてを相手にしたような気持ちです」
野霧が言った。
「どうなんだろう、ひみこが八人あぶり出された。みんな倭國神社につながっている可能性が高い。話を聞いていない、萩、博多、浜松のひみこたちにその辺をきいてみたいね」
「そうですね、どうでしょう、可也君が行った鎌倉の歯医者の匪実虚さんに、今までのことを話して、ほかのひみこさんと連絡を取ってもらったらどうでしょう、ご自分の歴史で、もとをたどると、月足の八人の娘につながります、鎌倉の匪実虚さんがある意味では直系になります、みんな医者で、みんなアーティスト、なにかあります、倭國神社はともかく、その昔には興味を持たれるかもしれません」
「野霧君、いい考えだね、判子はまだきていないね、吉都、野霧君と一緒に取りにいって、今までのことを話してみないか、もし、興味を持って、こちらに調べてくれて言うことであれば、費用はなしでやってもいいよ、依頼人からと言えば、他のヒミコさんも考えてくれるだろうからね」
「はい、もう公印できてもいい頃ですね、電話してみましょう」
そういうことで、鎌倉の三角美矢を訪ねることにした。
野霧と吉都は予約した日に鎌倉に向かった。
「公印遅くなってすみません、いいマッコウ鯨の歯を手に入れるのに時間がかかりました」
「いえ、ありがとうございました」
野霧が費用を払った。
「電話でちょっと話したのですけど、倭國神社の二代目の神主さんに娘さんが八人いまして、末娘が神社の跡継ぎになり月足日女さんにつながります、三角さんのおばあさんです、七人のうち四人まで娘さんの嫁ぎ先がわかりました。一人は三角家です、あと奈良の五條と島根の浜田、それに富山にいることが分かり、倭國神社につながりがあることがはっきりしました。それが皆不思議なことに、その家の女性たちは医者で、ひみこという名で、美術活動をしています。さらに、倭國神社とどのような関係か分からないけど、同じようにひみこを名乗り、美術芸術関係の活動をしている女医さんが、萩、博多、それに浜松にいらっしゃいます、その三人の方が倭國神社に関係があるか調べてもよいかと思いますが、ある意味では月足の直系である先生が興味をお持ちならら、その方たちに連絡を取ってもよいと考えているのですが、いかがでしょうか」
「え、そんな方たちがいらっしゃるのですか」
三角美矢はかなり驚いたようだ。
「ご存じでしょうけど、嵩丸弁護士が行方しれずです、倭國神社件は嵩丸弁護士に頼まれたことで。弁護士の祖先も倭國神社に関係がありました。もう打ち切りになると思います、しかし、三角さんに興味があれば、われわれも続けます、他のヒミコさんに、この件を問い合わせてみます、費用は要りません、ご迷惑のようでしたら止めることにしています」
「あ、いえ、とても興味があります、美目ちゃんも興味を持つことと思います、一緒にお願いしたいと思います。もし月足の家と関係なくても、同じひみこの方たちと会ってみたいし、たくさんは出せませんが、少しなら調査費用はだせます」
「それは、ご心配なさらないでください、嵩丸弁護士の依頼費用がたくさんあまっています」
「是非お願いします」
この匪実虚さんも瓜実顔で、やっぱりひみこだ。野霧はそう思いながら、吉都と鎌倉をあとにした。
「ずいぶん立派な公印ができたわね、なにに使おうかしら、領収書ぐらいかな」
「そうですね」
二人は事務所にもどると、詐貸と相談をして、野霧が萩、博多、浜松の三人に、今までにわかった卑弥呼をまつる倭國神社の歴史、神社の二代目、月足日女の八人の娘が、祖先である可能性、最後の神社の神主の月足陽司と久遠の双子のひ孫娘が、みなさんと自分たちとのつながりがある可能性を考えていること、を書面で詳しく書き、三角美矢と月足美目の依頼によるもので、三角のほうに連絡をくれるように書いた文を作成した。さらに、富山、五條、浜田の三人にも、今までの経緯を書いて、三角と連絡してくれるように書いた。
そこで、初めて、匪実虚が造った庚申塚探偵事務所の公印を押した。
それをみた詐貸が、
「うちの事務所のイメージとは違ってすごいね、立派な嵩丸弁護士の事務所のようなところを想像させる判子だね」
と感想を言った。
明くる日、書類を整え、ポストに投函した野霧が、近くの和菓子屋から、ウグイス餅をかってきた。
「八女茶、僕がいれますから」
吉都がお茶をいれてきて、それぞれのデスクに配った。
「いったい、嵩丸弁護士はなにを見つけたのでしょう」
「あんなに有名になって、これからもますます依頼がいくと思うけどね、ただ、自分から消えただけならいいけど」
詐貸はちょっと心配もしているようだ。
「秘書さんが奥さんだったわ、親子ほど離れていましたもんね」
「神無月の亭主と奥さんもそうだし、テディーじいさんもそうだし、すごいわね」
「なにが」
吉都が聞いた。
「おじいちゃんたち」
「野霧さんもおじいちゃん好きでしょ」
「別におじいちゃんじゃなくてもいいわよ、世久さんになにわたしたのよ」
野霧が話題を変えたので、吉都はどきっとして、三角の顔をとがらせた。
「出雲の青翡翠のマガダマ、それに野霧さんにもらった翡海湖さんのペンダント、でも、あーら指輪じゃないのって言われた」
野霧がヒヒヒと笑った。
「まじめにやれ」
詐貸が口をとんがらかせた。
八乳艸(やちぐさ)会
それから一月が過ぎた。嵩丸弁護士の消息はいまもつかめていない。
鎌倉の匪実虚さんから詐貸に手紙がきた。
「萩の火見胡さんは、今、厳島神社の信者になっているそうだけど、家系を調べると、先祖は半田出身のようとありました。博多の妣視杞さんは、先祖に日女という名前の人がいるそうです、浜松の豆本の皮実沽は日女の娘が医者の國部家に嫁いだときのことが書かれている古文書があるそうです、看護師になって國部医院で活躍したとあります」ということがかかれていた。
「みな月足八女を先祖とする家であることがわかったようだよ」
「すごい偶然、こんなことがあるものでしょうか」
野霧はまだ信じられないように、空を見ている。
「嵩丸弁護士もこの結果を知ると驚くだろうな」
「そうですね、でも、嵩丸弁護士にはどうでもいいのかもしれない」
吉都は夢久家の頭骨の収集への執念を思い出していた。収集癖を持つ人間はなにを考えるかわからない。
詐貸は手紙の続きを読んだ。
「八人で近々会おうということになっています、だって」
「あの八人が集まったら見事でしょうね」
ひみこたちは皆背が高く、凛としている。
「医者であり、アーテイストであり、奇妙な感覚の持ち主たち」
「邪馬台国の卑弥呼の能力を受け継いでいるのかも」
野霧が言うと、吉都は、
「卑弥呼が八人に分裂したのでしょ」と言った。という事は、あのすごい八人を一緒にしたのが卑弥呼か。
「八人の性格の遺伝というものがわかれば、卑弥呼の考え方やどのように振舞ったか見えてきますね、性格と遺伝子はまだ解析されていない分野です」
吉都の言うとおりかもしれない。
詐貸もうなずく。
「週刊誌がかぎつけると大変だね、嵩丸弁護士も絡んでくるのが分かったら特にね」
「しかも倭國神社のことが知れると、隕石が落ちて燃えた神社の秘密とか、ミステリーを書く人が現れるかも知れませんよ、あのミステリー作家に教えちゃおうかな」
野霧は今有名な推理小説作家に、神無月でサインをもらったようだ。
「これは漏らしちゃだめだ、でも、野霧君、君が書いたらいい」
詐貸にそう言われて、野霧の顔が丸く膨らんだ。ちょっと嬉しいときの顔だ。
十一月にはいると、翡海湖から、銀座の緋虎で、八人のひみこの展示会をする案内がきた。招致券が数枚枚入っている。
八乳艸会となっていた。
「俺は行かないから、みんなで分けて」
詐貸は全部野霧わたした。
「所長行かないんですか」
「うん」
「愛子さんと行けばいいのに」
「野霧君から渡してよ」
「可也君は二枚ね」
「どうして」
「希紅子さんと行くんじゃないの」
「やだよ、ああゆうの、だめ」
「希紅子さんだめなの」
「違うよ、ああいう展示会、カタツムリはいいけどもう見たし」
「私も行きづらいな」
「どうして」
詐貸が不思議そうな顔をした。
「だって、私、翡海湖さんに、鈴木敬子の名刺だしたんだもん」
「謝ればいいじゃないか、探偵の仕事だったんだから、そのおかげで、彼女たちは八人集まれたんだから」
「所長が一緒に行ってくれれば行きます」
「それなら僕も行きます」
詐貸は苦笑いをした。「それじゃ顔を見に行くだけでも行くか」
野霧も吉都も笑顔になった。
「招待状まだたくさんあります、十枚ありましたから、あと七枚」
「それじゃ、愛子とハチ公におくっておいてよ」
「はい、そうします、一枚あまりますが、知り合いに送っていいですか」
「うん、いいよ」
「誰」
吉都が聞いた。
「奈良で世話になった警察の実野さん、来るかどうかわからないけど、世久さんの友達」
吉都はうなずいた。
「だけど、嵩丸弁護士はどこにいったのでしょうね、世間も騒がなくなってきたけど」
「うん、八人のことは、嵩丸弁護士の話がなければわからなかったんだよね、それにしても、我々の推理はすべて外れたな」
「ほんとう、いやになりますね」
「何だったんだこの事件、嵩丸弁護士の言っていたことが信用できないとすると、倭國神社の跡からみつけた袋の中のもの、弁護士は後世のものだと言っていたけど、本物だったのではないかな」
吉都はつぶやいて、スマホを開いた。嵩丸弁護士に見せてもらったとき、全部スマホで撮っておいた。
「嵩丸弁護士がもっているんだから調べようがないね」
その週の土曜日、銀座のジュエリー緋虎にみんなででかけた。入り口に、「八乳艸会」と書で書かれた看板が出ている。明らかに火美胡が書いたものだ。三人はエスカレータで三階にあがった。ここがメインの会場である。
エスカレーターを降りると、集まって話をしていた八人の女性が一斉に振り向いた。
「すご」
吉都がちょっと恐れをなした。なんだこの雰囲気は、ここ全体が、なんだか神社のパワースポットのようだ。
野霧も何かを感じているようだ。
「あ、いらっしゃいませ」
案内の店員さんがよってきた。
「庚申塚探偵事務所の詐貸です」
詐貸が店員に名刺をわたした。
店員がそれをひみこたちに見せると、ぞろぞろとそろってやってきた。皆ロングドレスを着て、モデルさんが襲ってくるような感じだ。吉都はちょっと身をひいている。
匪実虚が詐貸に「はじめまして、公印を作らせていただいた匪実虚です、八人そろうことができたのも探偵社のみなさんのおかげです、ありがとうございました」
と頭を下げた。ほかの七人も「ひみこです」と声をそろえた。
翡海湖が、「あ、あのときの」と野霧をみつけた。その日も野霧はクリーム色の服を着て、翡海湖の三十八万円もする翡海湖のペンダントを吊るしている。
「鈴木さんでしたわね、庚申塚探偵事務所と関係あったのですか」
「すみません」と野霧が頭を下げた。
詐貸が、
「いや、すみません、私が彼女に頼んだのです、というより、嵩丸弁護士から翡海湖さんの様子を見てくるように言われたものですから、本当はうちの探偵事務所の逢手野霧です」
「すみません」野霧はまた大きな体を小さくした。
「そうだったのですか、いえ、とてもきれいな肌の方で、うらやましいと思ったので覚えていました、探偵社の方でしたか」
「はい、翡海湖さんに、双子の妹さんのことを聞いて、鎌倉の匪実虚さんのことを知ることができました、それでこういうことになりました」
「それじゃ、逢手さんのおかげですね、ありがとうございました」
「とんでもありません、仕事でしたけど、嘘をついてしまった上に、こんなすてきなペンダント私のものになりました」
野霧と吉都にそれぞれ地元で会ったヒミコたちが話しかけ、だんだん打ち解けてきた。
そこに世久と奈良警察の実野が入ってきた。
野霧が「わー、野実さん」
とかけよった。
「あーら、野霧さん、会いたかった、バイクの運転、私より上手で驚いたのよ」
世久に説明している。
「え、逢手さんバイクやるの」
「私の彼氏の700cc、格好良く乗ってたわ」
希紅子が尊敬の眼で野霧を見た。
「ハチ公のほかのみなさんは来ないのですか」
「警視はこないけど、後の人たちは明日来るって言ってました、野美が今日東京にきたので、連れてきたんです」
詐貸だけが一人でぽつんと展示物を見ていたら、愛子が入ってきた。詐貸のところに来た。
「あ、来たの」
「うん、目玉見にいこ」
愛子は妣視杞のコーナーに詐貸を引っ張っていった。
ひみこたちは増えてきた客の相手を始めている。吉都も野霧の仲間に入って見て回った。
鎌倉の匪実虚が野霧のところに来て、
「ひみこ一同、感謝しています、われわれ、これから行き来することにしました、八乳艸会は少なくとも年一回、誰かのところで開催することにします、日本中に行けるのは嬉しいですね、案内出しますので遊びがてら来て下さい」と言った。さらに、
「みんなと会って、おもしろいことに気づいたのです、私たちの名前、月足、國武、丸林、牛島、室園、新田原、甲木、丸木は八女市に多いそうです、やはりつながりがありますね」
と言った。
「不思議ですね」
野霧は疑問が増えるばかりと思った。
あくる朝の新聞に、八人のヒミコと言うタイトルで、銀座の八乳艸会の紹介がしてあった。これでみなは有名になる事だろう。
我々のやったことはなんだったのか。探偵がやる事なのか。
詐貸は考える事をやめた。
エピローグ
とうとう今年も最後の月を迎えた。コートが必要である。
探偵事務所にしゃれた木製のガラス戸が来客用のソファーの後ろに置かれている。中にガラスの目玉や、木でできた手首、骨の細工、革装の本、綺麗な外国の蝸牛の殻、爪貼りの小箱、八人のひみこたちが、くれたものがはいっている。愛子が買えと言ったガラス戸である。ちゃっかり、愛子は事務所に来たときに、自分の訳した本も並べていった。
詐貸はうちの事務所に似合わない、というよりもったいない、と思う。
それだけではない、毛筆で書かれた「庚申塚探偵事務所」と言う板が入り口に釣る下げられている。火美胡の字だ。
野霧が新聞を脇に抱えて事務所に出てきた。
吉都はもうデスクでPCを開いている。
「これ見ましたか」
野霧が新聞を、客のテーブルに開いた。三面記事の前のページに、大きく「卑弥呼の印か」という見出しがあった。アンティークオークション、クリスティーに、落陽からみつかった、「親魏倭王」の金印がだされた。それ以外にも、水晶の眼球、たくさんの銅鏡、陶器類が五十数点、日本人の研究者も注目とある。歴史の研究者のコメントでは「魏の皇帝が卑弥呼に渡す予定のものだったか、卑弥呼まで届かなかったのか」とあった。写真もいくつか載っている。
「あの、有名なアンティークの競売だろう、今はスマホでも見ることできるんだな」
「買うこともできますよ、360度の画像で示されるので、買う方はすべてみることができて、判定しやすいと言うことです」
吉都がクリスティーオークションを開いて、びっくりした。
「これ、嵩丸弁護士が倭國神社から掘り出したのではないですか」
吉都は嵩丸のところで撮った写真をスマホの画面によび出した。
「全く同じだ」
詐貸と野霧ものぞき込んで、ほんとだ、と驚いた。
「もう買い手がついているの」
吉都はスグ、クリスティーの画面にもどした。
「この金印落札されていますよ、2500万からはじまって、1億8900万円だって、ほかのものも5000万以上ですよ」
「誰が落としたのだろう」
「それはのっていません、日本人ならいいんですが、これだけだすのは中国人じゃないでしょうか」
「オークションにでているものは、嵩丸弁護士のところで見せてもらったものだけではありませんね、もっとずーっとたくさんある」
「あの地蔵のある畑で掘り出したんじゃないの」
「そうですね、鏡や、剣もあるみたいだし」
「総額にしたら大変な額になりますね」
「でも、なんで落陽から出土ということにしたんだ」
「日本で見つけたっていったって、信用されないんじゃないですか、落陽は魏の中心地ですよ」
「そうか、でもなぜ売っちゃうんだ、やっぱり倭國神社のことなんかどうでもいいのか」
「古書さんが言っていたように、日本で最古の本があったのかも知れませんよ、後のものは興味がないので、お金に換えた」
「確かにそういう可能性もあるね」
「嵩丸弁護士はイギリス、いやヨーロッパのどこかに行るんじゃないですか、掘り出したものや、集めたものを全部もって」
吉都が言った。
「どうして」
「クリスティーもイギリスが本拠地でしょう」
「だけど、イギリスに行ったのならわかるだろう、飛行機にのりゃ、警察はすぐ察知できる」
「嵩丸さんて本名ですか」
吉都の一言で、詐貸がすぐ動いた。薩摩に電話をかけたのだ。
詐貸が神妙に聞いている。電話を切ったら、すぐに二人に言った。
「大変なことがわかっていたよ。ハチ公でも嵩丸を調べていてね、四十年ほど前、嵩丸司書は嵩丸家の養子になったことがわかったということだ」
「養子だったんですか、彼がまだ大学生のころですね」
「そう、前の名前を狗奴史郎といって、九州隼人出身らしい、苦学生だったようだよ」
「嵩丸家には子供がいなかったのですか」
「いや娘がいたが、結婚して家をでている、嵩丸弁護士の奥さん、嵩丸夢霧はその娘のようだ」
「確かに姪ということになりますね」
「そう、ところがこれからの話だよ、一年前、鎌倉のすべての土地を売っぱらい、もとの狗奴の名字に戻した。もちろん奥さんも苗字が変わった。しかし弁護士活動は嵩丸のままでおこなっていた」
「我々のところに依頼しに来るちょっと前ですね、どうして苗字を戻したんでしょうか」
「それはわからない、本名で航空券を買っているんだ、ロンドンに奥さんと一緒に飛んでいることが分かった」
「吉都君の勘が当たったわね、嵩丸弁護士はロンドンにいるのね」
「薩摩が言うには、全く事件にはならない事柄で、本人の意思によるものだから、警察はなにもできないし、この話は外には漏らさないと言うことだった、まあ、どこかの優秀な雑誌記者が調べるだろうね、でもなぜそうしたかというようなことはわからないだろう」
「私たちは少しわかりますね」
「だけど、なぜ卑弥呼の宝を日本から持ち去って、売ってしまったか、しかも落陽から発掘などといって、せっかく日本の大事な歴史の証拠物なのに」
「わからないわね、卑弥呼に恨みがあるのかな、狗奴国は邪馬台国と敵対していたから」
「卑弥呼は隼人とともに駆け落ちしたのでしょう」
「駆け落ちした隼人も狗奴國からは恨まれていたのかもしれないしな、もう千八百年も昔のことだから」
「そうですよ、とすると、嵩丸弁護士はただ、趣味のものを見つける為に依頼にきたのかも知れませんし」
「まったく、なんだ、この事件は」
詐貸はなんだか気持ちが悪かった。
十二月二十五日、一通の航空便が庚申塚探偵事務所にとどいた。
ロンドンからだ。差出人はS.Kunuiとなっていた。
『詐貸美漬 様、皆様
クリスマスおめでとうございます。
おそらく、私のせいで、皆様すっきりしないクリスマスをお過ごしではないかと心苦しく思っております。まずはおわび申し上げます。このように早く、私の探していたものが見つかるとは思いもよらぬことでした。存在していると期待はしていましたが、可能性の少ないものとを考えておりました。流石は詐貸弁護士の能力にあらためて驚き、感服しておるところです。野霧さん、吉都さん、素晴らしい助手の方々の存在も探偵事務所を超一流の物にしているのでしょう。
あのご神体は倭國神社の物に間違いは無く古いものです。私が養子にはいった嵩丸家にあったものです。この神社の祀神が卑弥呼だとわかり、神社に卑弥呼に関わる宝物がある事も知りました。私も仕事で国内を回るとき、ご神体の赤丸のところでは、それなりの調査もしましたが、何もわかりませんでした。今回の弁護の仕事が終わったら、、ゆっくりと探すつもりで、庚申塚探偵事務所にお願いしたわけですが、あっという間に解決の道が見えてきて、神社跡の発掘になり、大学の教授に頼んだのは本当ですが、その後は私共で発掘をして、卑弥呼の物を掘り出しました。しかし、私の思っていた物はありませんでした。ところが、さらに掘るべき場所を、探偵事務所の方で見つけて下さった。鎌倉の匪実虚のお守り袋の中の地図です。すぐに掘り出し、私は家内とロンドンに渡りました。
さて、私の経歴をお話します。私は八女で生まれ、八女で育ちました。高校を出て、東京の大学にはいったころ、嵩丸家の養子になりました。八女の両親は借金だけしかないような生活をしており、私はアルバイトで大学生活を維持しておりました。両親はなにもないのに、自分の家系を狗奴の直系だとそれだけを誇りに生きていたようなものです。私も狗奴については調べました。邪馬台国の卑弥呼とは敵対していたようです、それで卑弥呼にも興味を持ちました。
嵩丸家の養子になったのは、以前お話ししましたように、嵩丸家の祖父の於璽は篤志家で鎌倉で活躍していました。私が大学一年の夏に漁船のアルバイトに行きました。その親方が高丸於璽と懇意で、話す機会があり、苦学をしていた自分を気に入ってくださり、孫の相手にと市役所に勤めていた息子、祈切に会わせてくれたのです、しかし、孫娘はすでに心に決めた相手がいたようでその話はなくなったのですが、養子にどうだと言う申し出があり、私の両親の納得の上で受けることにしたのです。おかげで、大学は好きな勉強ができ、司法試験にも受かりました。妻の夢霧は義妹の娘です。
弁護士事務所は九品仏にかまえましたが、鎌倉の家にはたびたび帰りました。父親の祈切とはよく話しましたが、父は祖先のことも、倭國のこともあまり興味はなかったようです。鎌倉の佐助の名士として満足していました。私も祖先のことに興味を持っていたわけではありませんが、偶然、嵩丸家に卑弥呼とつながりがありそうな家の歴史がある事を知り、私も九州狗奴の人間であることから興味を抱きました。
嵩丸の父が死んで整理をしていると、倭國神社に何か残されているようなことが分かりました。あのご神体です。私は弁護士になった頃から、本に興味を持ち、初めは法律の本でしたが、幅広く皮装本を持ち始め集め始めました。日本では皮装本は明治になってからです、あるとき、和綴じ本にも興味がわきました。日本で最古の本を持つことを夢見るようになったのです、ちょっとばかり身近になった卑弥呼と考えをつなげてしまいました。卑弥呼は本を作っていたと信じ、嵩丸の祖先と月足の祖先を調べることをとっかかりにして、夢見るようになりました。稀覯本を扱う古書店とは深い付き合いになりました。しかし卑弥呼と本に関しては一つとして関係がありそうなことは出てきませんでした。なかなからちがあかず、詐貸先生ならなにか手がかりを見つけて頂けると、お願いに上がったという次第です。
八人ものひみこが浮かび上がってくるなど想像しておりませんでした。ただ、警視庁の分析支援センタ―には、思わぬような事件がストックされていることをあるところから聞き及び、古文書の解析をお願いすることで、分析官の古本さんと知己を得て、不思議な事件があることを知りました。古書さんには迷惑をおかけしたと思っています。だましたようなものでしたから。ただ古書さんは、決して重要なことは私に話してはいません。
卑弥呼の末裔ならば、なにかしでかすのではないかという、私の勘で動いたことです。詐貸先生が、薩摩警視が異動したことで、分析センターと関わるようになるとは思っていませんでした。偶然の事です。
先に話をすすめます。皆様の推理が当たっていることと思いますが、倭國神社の布袋のものは本物です。金印は卑弥呼が魏から送られたもの、後は神社を建てた際に、月足一族がそろえたものと思われます。それでもその当時の細工物は高価なものです。むしろもう一カ所、地蔵脇から掘り出したものは魏から卑弥呼への返礼品や、卑弥呼の周りが作ったもので、たくさんありました。それに私がほしかったものもありました。おわかりのことと思います、日本最古の本といっていいでしょう、卑弥呼の鬼道の書です。中国の古い紙で作られていて、和とじのような形ですが、表紙は皮です。ただし人の皮ではありません。おそらく山羊の皮ではないでしょうか、秘密めいたとても魅力のある古文書です。卑弥呼自筆のサインがあります。その頃の日本の文字で書かれています。神代文字と言うものでしょうか。カタカナ、ひらがなに通じるものがあります。最後に、魏からもらった、卑彌呼という漢字でもかいてあります。私はこの書に秘魅古と名付けました。誰も知らない、私だけが持っている、日本最古の本です。いずれ私が死んだときには、経緯など書きおいたものが表に出るでしょう。詐貸さんにはご迷惑はお掛けしません。
これから、世界一の稀覯本ミュウジアムを、どこかの国に作りたいと思います、本の管理のしやすい、ある程度乾燥していて、暑くない国がよいと考えています。まだどこの国とは決めていませんが、湿気の多い日本ではないことは確かです。皮装本の本場イタリアあたりもいいでしょうね。
掘り出したものはほしかったもの以外はすべてお金に換えます。稀覯本ミュウジアムのためです。といっても、私にも少しは良心の呵責があります。自分の勝手ではございますが、ここに、小切手をいれさせていただきます。探し出したものの価値と比べたら些少ですが、必要経費と考えていただいて、お受け取りいただきたいと思います。詐貸所長にお任せいたします。
さて、最後に、あの八人のヒミコたちですが、私も驚きました。みな優秀で、一癖も二癖も持っている女性たちです。日本の国際テレビ放送で、銀座の八人のひみこ展のことを知りました。おそらく、庚申塚探偵事務所の皆さんのおかげで、八人が出会えたのだろうと思っております。
犯罪すれすれの事までして、自分のやりたいことをやっていく、卑弥呼の能力を受け継いでいるのでしょう。弁護士をしていた人間として感じるのは、彼女たちはこれから有名になるでしょう、ただ、どこかで羽目を外すこともありうることです。誰かが見守る必要があります。大きな犯罪をさせないように、ぜひとも詐貸先生の監視をお願いしたいところです。彼女たちをいい方向に導くことのできるのは、詐貸先生しかいないと思います。よろしくお願いいたします。
お礼の言いようがありません。感謝しております。もう日本の土を踏むことはないと思います。
もう一度、庚申塚探偵事務所の皆様に厚く御礼申し上げます。
狗奴史郎」
それを読んだ詐貸はため息をついた。相当さっぱりしない。ヒミコたちを監視するなど、とんでもないことだ。手紙を野霧と吉都に渡した。
読んだ野霧は無言のままである。
吉都が「重要文化財級のものを持ち出すのは犯罪ですよね」と言った。
「でも証拠がないでしょう」
野霧が顔を膨らめた。
「僕のスマホに写真があります」
「我々しか見ていない、掘り出した人も見たのは袋だけだ。吉都の写真に写っているのはレプリカだと言われれば終わりだよ」
詐貸が言った。
「もう作ってあるかもしれませんね」
野霧がそう言ってうなずいた。吉都は、
「この手紙があります」と言った。
「確かに手紙は一つの証拠だが、誰が彼を訴えるんだい、これを知っているのは我々だけだ、と言うことは、訴えるのは我々しかいない、吉都やるかい」
吉都は首を横に振った。
「嵩丸弁護士は何も犯罪行為をしていないよ」
詐貸は突っぱねるように言った。
「今回の事件は、全て犯罪になりそうでならないものばかりでしたね」
野霧が机の上で頬杖をついた。
「だまされたのは、我々だけだ」
三人ともしばらく黙っていた。
吉都が、
「この二千万どうします」と聞いた。
詐貸はしばらく考えていた。
「きっと口止め料ということだろうな」
「それじゃ安すぎませんか」
「そうかもしれんな」
「返しますか」
また詐貸は考えた。
「いや、もらっとこう、千五百万はユニセフや国境のない医者団に寄付してくれないか」と言った。
「残りの五百万はどうします」
「野霧君、この話、前言ったようにフィクションとして書いてくれないか、君の初めての小説として出版する、その費用に使う」
詐貸はそう言って、自分のデスクに座ると、
「もちろん、取材協力者として、吉都と庚申塚探偵社も後書きにいれてくれよな、それに、八人のひみこたちにインタビューでもして、八人の遺伝子に潜んでいるものを探り出すといいかもな、会合費もそこからだすよ、早速、今日、神無月で打ち合わせとするか」言った。
野霧と吉都は顔を合わせて、ヒヒヒ、と笑った。
完
おわりに
2020年と2021年は新コロナウイルス(COVID-19)の年である。コロナウイルスと戦う年と書くものもたくさん出てくるだろう。コロナウイルスは人間と闘っているわけではない、動物の細胞を借りてただ子孫を残したいだけである。ウイルスはそういう生き物である。しかも環境を先取りして、自分を変える力が強い。一方で、人間は考えを変えることさえ大変で、さらにからだをおいそれと変えてしまうことはできない、次の代にいくのに15年かかる。15という数字は生殖可能な大まかな年である。しかし、一代でからだがそんなに変わるわけはない、今の人が作り出した環境では、むしろからだを弱くしていく方向にいっている。
人間はいつも戦っている、最もつまらない戦いは、生きるためではなく、主義主張、金儲け、領土拡張のためのもので、人が死に、ばかばかしい。コロナウイルスはじっくり我慢して、自分は滅んでも、新たに生まれてくる子孫を生きやすいように変化させる。がまん強い。何故こんな話になってしまったのか。この第三探偵小説である「秘魅古」は2020年の一月に書き始め、4月までに書いたものを、しばらくほうっておいたが、七月にプロットしなおし、翌年2021年1月18日に原案を作り上げたものである。まさにコロナの年に生まれた。
コロナが世界で最初に報告されたのは2019年12月8日、日本で始めて感染者が確認されたのが2021年1月16日とネットに書かれている。ということは日本で確認された2日後にこの小説を書き始めたことになる。コロナなど頭にないときである。2019年より目眩と強い眼精疲労、筋肉疲労に責められていたときで、筆者はむしろ自分のからだを休めるように努力していた。この小説も寝転びながら、ポメラで書いていた。はじめは犬が骨を盗む短編小説のつもりだったのだが、とうとう、六百枚近くになってしまった。
秘魅古は今までと同様、殺人や死体が出てこない探偵小説である。毎度の事ながら、地理歴史が苦手な筆者が書いたものである。間違いだらけだろう。こう言っておかないと、違うじゃないかといわれかねない。全てフィクション、いや嘘である。
2021年6月
秘魅古(ひみこ)―第三探偵小説


