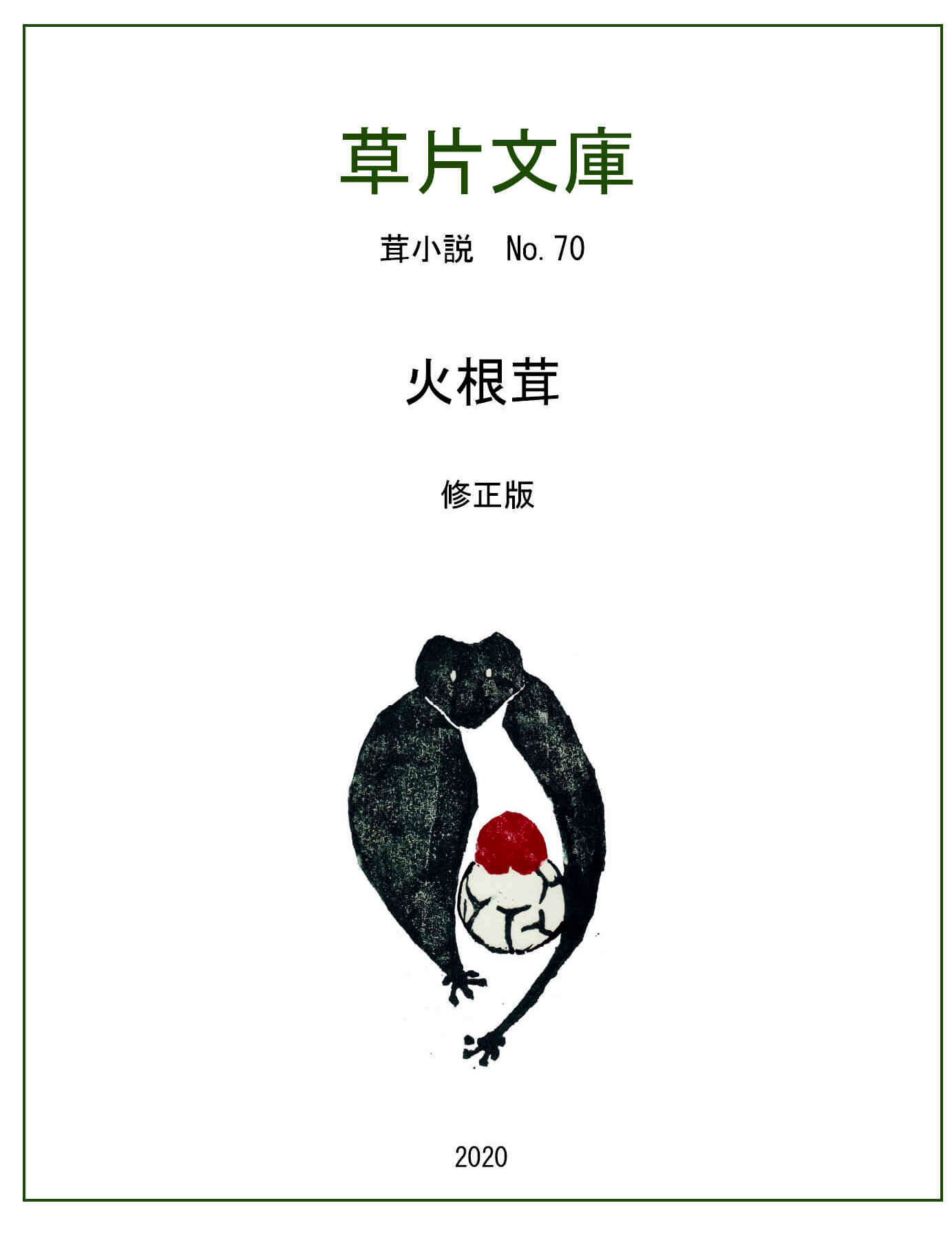
火根茸(ひねじ)
230枚ほどの茸小説です。縦書きでお読みください。星空文庫、茸小説200編になりました。ここで、茸小説掲載を一時、休ませていただきます)
序
新月である。星がきらめく宵、大きな緑色の蝙蝠が、山のてっぺんにある大きな杉の木の上から、片翼をひらひらさせて降りてきた。もう一方の手でなにやらくるんでいる。片翼で飛ぶなど器用なものである。
蝙蝠は木耳に覆われた大きなブナの木の前にある、これまた大きな切り株に降りた。
蝙蝠は、白い壷から真赤な顔をちょっとだしたばかりの卵茸の子どもを、翼からとり出すと、ひょいと切り株の上においた。
「どうじゃ、気分は直ったか」
「はい、よくなりました」
卵茸の娘は調子が悪かったようだ。
「何にあたったのであろうな」
「きっと、昼間の日の光が強すぎたのでございましょう」
「うむ、たしかに、今日は、十一月の終わりというに暑いものであった」
「なにやら起きそうな気がします」
「そなたもそう思うか」
「はい」卵茸の娘はうなずいた。
火(ひ)根山(ねやま)の森の中には静けさがただよっている。
「お嬢、このあたりの茸は一族か」
「みな、私の父の仲間でございます」
「火(ひ)根(ね)茸(じ)であるな」
「はい」
赤い茸は傘をふるわせた。それを合図にか、様々な形をしたな茸が切り株の周りに顔を出した。
「火根茸の皆さん、緑蝙蝠にございます」
蝙蝠が丁寧に頭を下げた。シルクハットに杖があればいっぱしのイギリス紳士である。
「私を助けてくださるお方です」
卵茸の娘は火根茸たちに緑の蝙蝠を紹介した。
集まった火根茸たちは声を出すこともなく、静に、ただ深く頭を垂れた。
この茸たちは話をしたくとも、しゃべることが許されておらず、ただただ、傘を揺らして気持を表すほかなかった。唯一、一族の長の娘である卵茸が話をすることを許されていた。火根茸たちは、いつか許され、自由に話が出来るようになることを待ち侘びているのである。
「これから、茸にされてしまった私たちの呪縛を解く鍵を探しにまいります。この緑蝙蝠さんの助けがなければできません、時が来ると、あなた方の力をおかし願うこともあるでしょう」
火根茸たちはふたたび深深とお辞儀をした。
「みなさんを元の人に戻す薬がみつかるまで、皆さんは茸としてこの森で静かに暮らしていてください」
緑色の蝙蝠は再び卵茸を片方の翼にくるみこむと、一つの翼で夜空に上手に舞い上がった。
火根茸たちは無言のまま二人を見送った。
師走ー出発
「師走だな」
緑蝙蝠がつぶやいた。
冷たい空気が辺りを包み、空には無数の星が凍りつくような冷たい輝きを放っている。
「今日は一段と空がにぎわっているな」
火根山の森の外れの杉の木の上で、緑蝙蝠が空をあおいだ。
卵茸の娘も空を見上げた。
「北の果てにいってください」
卵茸が頭を緑蝙蝠のほうに向けた。
緑蝙蝠が卵茸を片方の翼に包み込んだ。
蝙蝠らしからぬが、ふわりと宙に舞い、すーっと、空の上に昇っていく。
まばゆいほどの星屑の中に蝙蝠と卵茸は溶け込んでいった。
「風の流れに乗るとするか」
蝙蝠は北極星を頼りに北を目指した。
日本の国の空を、強い風に押されて、福島、秋田、青森と数日かけて飛んだ。明日になれば年が変わる。
「海の上は冷たい、暗いが海の底を通るとしよう」
緑の蝙蝠はつぶやくと、くるまれた翼の中で卵茸の娘がこっくりとうなずいた。
青函トンネルに入ると暗闇が蝙蝠たちを包んだ。
しかし、なんと、あっという間に、北海道の星明りの下に緑蝙蝠の姿が現れた。するすると、上空に舞いあがった蝙蝠は函館の上空を舞った。
函館の地は火根山と違い、緑蝙蝠と卵茸を冷たい空気が針のようにちくちくとつついた。
凍てつく空気が蝙蝠を通して、翼の中の卵茸を包み込む。
「お嬢、大丈夫か」
「はい、私は大丈夫です、蝙蝠さんこそ無理をなさらずに」
やがて、二人はそのまま、網走へとむかう。
網走の風と雪は函館どころではなかった。緑蝙蝠は流されるように飛んだ。
「お嬢、こんな寒いところに何があるのだ」
蝙蝠が尋ねた。翼にくるまれた卵茸は蝙蝠を見上げるように答えた。
「一角の角が必要です。我々の呪縛を解く為の薬の一つになるものでございます」
「一角はここにいるのだね」
「一角は北極に棲むもの、だが、北海道のこの地の海に密かに来るといわれております」
「おおそうか、だが、このような寒いところ、茸になったお嬢はだいじょうぶかね」
「はい、茸もほとんど生えないようなところでございますが、私は元々人間でございます。茸になっても流れる血、いや体の中の液は暖かく保たれております」
「ふむ、そして、どうして、ユニコーンの角がよいことがわかったのかな」
「父が教えてくれた歌にございます」
「ほう、それは」
「小さいときから覚えさせられたもので、いつもその歌を歌って遊んでおりました」
「ほーう」
「人が茸に、茸に人が、北の果て棲む一角獣、赤い飛沫の角の先、赤い実のなる曼珠沙(まんじゅしゃ)華(げ)、赤腹井守の真黒胎児、甲斐の洞窟赤水晶、赤に染まった竜宮使、箱根の赤岩硫黄粉、尾張名古屋の赤い栗、赤河豚心臓下関、泡踊りの赤平家、九州阿蘇の溶けた赤顔、そして最後があるのですがそこのところははっきりしません」
「難しい歌だな」
「はい、子供の頃は全く意味を知らずに歌っておりました。私どもの国では、悪いことが起こると、火根山の妖術師が人を茸に変えてしまうという言い伝えがありました。今、歌が元に戻す薬を造るためのものであることがわかりました」
「それをすべて集めて一緒にすれば薬になるのか」
「それはわかりません、必要な量も、その割合も全く分からないのでございます。まずそれらを集める事が肝要、その後、それを解く鍵を探さねばなりません」
「そうか」
ここで少し説明が必要であろう。そのむかし、甲斐の国に火根山と呼ばれる隠れ山があった。火根山の麓は富士の水脈から清い水の湧き出るとても住みやすいところである。そこに住んでいたのは、火根一族で、神代から、人の起源にまつわる大事な壷を守る役割を担っていた。いずれ、必要となったとき時、蓋を開けるというものである。誰が蓋を開けるのか、それは、そのお告げがあった時わかる。いつになるか、開けたらどうなるか、知るものは誰もいなかった。
一族はお告げを聞き分けるよう歌を覚え、耳を鍛えていたのである。
一族の食物は茸のみ、それ以外のものは口にしてはいけないことになっていた。理由などありはしない、何世紀にも続くことである。しかし、それは苦にならなかった。火根の一族は茸しか味を感じることができず、茸が唯一幸せをもたらす味であったからである。
当然のこと他所の人間がその一族の元を訪れることもない。一族の中で長老が夫婦になるものを指名し、今まで子供は無事産まれ、一族は多すぎもせず減ることもなかった。
そこにある日、大きな変事が起きた。錯乱を起こした女がいたのである。五十になったばかりの女である。火根の一族は寿命が百八十と長い。火根の娘は十五になると、長老が夫になる男を指名する。しかし、その女は行状から長老が夫になる男の指名をしなかった。その女は独り者であった。
錯乱女は壷の安置されていた火根神社に忍び込み、持ち出して森の中で壷の蓋を開けようとしたのである。そのとたん、その錯乱女はその場でブナ(ぶな)の木にかわり聳え立った。そのブナの木の幹には木耳(きくらげ)が鈴生りになった。
壷はいつの間にかブナの木の根の中に囲われてしまった。さらに、火根一族の生きている者すべてが茸にされてしまったのである。火根一族が姿を変えた茸は火(ひ)根(ね)茸(じ)と呼ばれた。それは妖術師ではなく、火根山の神によりなされたものだという。もう、百年も前のことである。
今、緑色の蝙蝠に抱かれているのは、卵茸になった一族の長の娘である。この蝙蝠は、長老の家の床の間に置かれていた緑色の万年茸である。火根山一族が茸に変わったとき、逆に、万年茸は緑色の蝙蝠に変わった。蝙蝠に変えられた万年茸は、まだ小さな壷だった卵茸を拾い上げ、空に舞い上がったのである。緑の蝙蝠は洞窟の奥深くで卵茸の壷から茸の顔がのぞくのを待ち続けた。
そして、百年近く経ち、卵茸の壷が割れた。その中から赤い小さな傘がのぞいたのは、ほんの半年前のことである。
こうして、緑蝙蝠は卵茸を火根山の林の中へ連れてきたのである。
睦月ーオホーツク
網走の海にでたとき、日の出の時刻を迎えた。新しい年になった。
オホーツク海である。沖に白いものが押し寄せてきている。
「流氷が来ています」
卵茸が言った。緑蝙蝠は、大きな氷の塊がひしめいているのを見てぞくっとした。
「冷たいのう」
今日は凪ぎいているが、荒れるととてつもなく激しい海のうねりが押し寄せる。
「一角の角はどこに行けばみつかるのかな」
蝙蝠が卵茸にたずねるともなくつぶやいた。
「この荒れた海辺に打ち上げられるのを待つしかないようです。それもただの角ではだめなのです。赤い角が必要なのです」
「じゃが、この広い海のどこから上がるのであろう」
「一角が現れる場所を探しましょう」
蝙蝠は最果ての地の情報を、岩に止まっていたエトピリカに聞いた。
「一角を探しておるのだが、教えてくれぬか」
エトピリカは橙色の嘴をあけた。
「一角は争いごとのきらいな生き物でな、人知れず海の底で子供を作り、世界を巡り、北極に暮らす。そして、年老いた一角は、この地にくると、海の底で死を迎える。人間はそのことを知らぬ。ほんのたまに、死したからだから離れた角はこの近くの岩場に流れ着くこともあるが、岩にたたきつけられ砕けてなくなってしまう」
「赤い角をもっている一角はおるのだろうか」
緑の蝙蝠がたずねた。
「それは聞いたことはない、わしらも一角に会ったことはないのだ、伝え聞いたことを教えたまでじゃ」
エトピリカは不思議そうな顔をした。
「お主、何者じゃ、一角の角を薬にするのか」
「一角の角は薬になるのかね」
「知らなかったのか、毒を解く、よく効く薬になる」
「それはいい」
「それで、そなたの抱えている茸はなんじゃ」
「わしの主人の娘でな、茸に変えられてしまったのだが、もとに戻す薬を作ろうとしているのだ」
「それは気の毒にな、時間がかかるが、その機会は必ずくる、気長に待つことじゃ」
エトピリカはそういい終えると、強い風の中を力強く羽ばたいて去っていった。
赤い角が手にはいるのはいつになるのだか、それが一年、二年になるかもしれない。しかし、待たなければならないのだ。
それから卵茸と緑蝙蝠は毎日のように海辺で過ごした。
岩の上から赤い茸が荒海を見ていた。寄せる大きな波は岩場に打ちつけられ、跳ね返った。時々、赤い茸もしぶきに濡れる。
「大丈夫か、姫さん」
空から見回りをしている緑蝙蝠が戻ってきた。
「あの三角岩の先に割れた角のようなものが打ち上げられました」
茸が言うと、緑蝙蝠は海のしぶきを浴びながらも、それらしいものを探した。白い骨のかけらのようなものである。
「あったぞ、しかし、これは赤くはない、それに一角のものかわからんな」
「そうですね」
そうやって、一月の末、雪の吹雪くある夜、荒れた海の中から大きな白い角が突き出たのである。
「あ、一角の角が」
茸の姫が叫ぶと、別のところからも角が突き出された。
「ウム、すごい、一角が二頭あらわれたか」
緑蝙蝠が目を見張っていると、二つの海の上に突き出された角が、つつっと近寄るなり、かちーんという大きな音と共にぶつかり合った。
一端離れたと見ると、巨大な二頭のユニコーンが白く渦巻く海の中からそそりたった。目は真っ赤に血走り、たがいに、うなりながら角を突合せている。
「何を争っているのでしょう」
「あの怒りはなんであろうな、一角は争わぬ生き物のはず、しかも、ここは死を迎える場所とエトピリカは言っておった」
二頭は何度も角をぶつけ合うと、白く渦巻く海の中に沈み、また顔を出す。太い角がお互いにぶつかり合う。角が当たると、がつーんと言う音とともに、光がでる。
「あれ稲妻が走る」
卵茸の姫は恐ろしさに赤い頭を壷の中に隠した。
「そうだな、だが、姫、よく見ておきなされ」
緑蝙蝠の声でまた卵茸は頭を出した。
光がでると、どちらの一角も苦しそうにもだえて、海に沈んでいく。
あたりは吹雪いている。エトピリカが飛んできて二人のいる岩におりた。
「なぜ争っているのでしょう」
「争っているのではない、助け合っているのだ、わしも初めて見る」とエトピリカは言った。
また、二頭が顔を出した。角が血で濡れている。一頭の左の頭から血が出ている。角が擦れて傷ついたようだ。その一角が、もう一頭の頭に角を突き立てた。角の先が血で赤く染まった。二頭は血で染まった角をつき合わせた。
ごつーん、きりーと金属音がして、二頭の角の先が折れ、宙に舞った。
「あ、あれ、赤い角」
茸の姫が叫ぶ。その声の前に、緑蝙蝠は卵茸を岩の上に置くと、すでに吹雪の中に飛び出し、空を舞っていた。
宙に上がった赤く染まった一角の角の先は緑蝙蝠の足によって捕らえられた。
緑蝙蝠はすぐさま岩に降り立つと、赤い茸に血染めの角を見せた。
「あ、きっとこれが一角の赤い角です」
「よかったな、姫」
角の折れた一角たちは、ふたたび海面に顔を出すことはなかった。
「これから、二頭は決めた死に場所に行って静かに死をまつのだ」
「どういうことですか」
「年老いた一角は死に場所を決めると、海の奥の岩に何度も何度も角を突き立てて、角を折るのだよ、そうしないと死が訪れない。二頭いる時にはお互いに角をぶつけあい、角を折って、死を迎えるのだよ」
そう言う言い終えるとエトピリカは雪の中を飛んでいった。
卵茸はその話を聞いて、それぞれの生きものに死に方があることを知った。
緑蝙蝠は岩の上で雪に埋もれそうになっている卵茸と角を抱えると、海岸から離れた空き家の屋根裏に戻った。
「思ったより早く見つかったものだ」
緑蝙蝠は血のこびりついた一角の角を板の上に置いた。
「火根山の森に運ぶには仲間が必要だな、あいつに聞いてみるか」
「どなたです」
「エトピリカだよ」
「それは無理でしょう、私が呼びます」
「姫に連絡できるのかね」
「はい、私どもは、空気ではなく、空気と空気の間の無の中を通して、茸になった、仲間に意思を伝えることができます」
「だが、火根茸は手助けに来ることはできまい」
「火根茸はしゃべることはできませんが、森のムササビ、梟、、夜鷹など火根山の動物と意を通じることができます。きっと、夜鷹が取りにくると思います」
「夜鷹なんぞ、俺を食っちまいそうだ」
「大丈夫です、夜鷹も、その昔、火根山一族でした、ちょっとした出来事で、夜鷹にされたのです、火根山にはそういう者たちがたくさん住んでいました。山そのものに妖術を使う意志が宿っているのです」
「ふーん、そういうものか」
それから五日後、夜鷹が一角の角を取りに来た。
月が変わった。
如月ー十三湖
二月に入った。
「さて、火根山の姫様、今度はどこかね」
「青森の十三湖に参ります。そこで赤い実の生る曼珠沙華を探します」
「あの死人花が実を付けるのかね、それに今はまだ土の中で居眠りだ」
「曼珠沙華の実は見たことがありません、実というのがどのような意味なのか、行かないと判らないことだと思います」
「そうだな、では行くかい」
「はい」
卵茸をくるんだ緑蝙蝠は網走の空に舞い上がった。
冷たい風に乗ると、北海道を横切り、今度は海の上を本州に向けて飛んだ。波しぶきの中を、海豚が群を成して泳いでいる。
卵茸が「あ、海豚(いるか)の中に一角がいる」と、叫んだ。
海豚の中を一角がなにやら話しながら泳いでいた。
「一角は海豚と仲がよいようじゃな」
「海豚と一角獣の話が聞こえてきます」
「お嬢は、そんなことができるのか」
「はい、あの一角はまだ若い雄、その一角が海豚に懸想をして、この地にやってきて、静に死のうとしていた一角の邪魔をしたようです、でも、若い一角は海豚に諭されて、北極に帰るところのようです、あのように海豚が送っていくところです。年老いた一角は海の底で海豚に守られて死んでいくのです」
「そうなのか」
緑蝙蝠は考え深げにうなずいた。
「海の中の生き物たちも様々な苦労があるようです」
「そうだな」
蝙蝠と卵茸は本州に渡ると、そのまま上空の風に乗り、青森の端に行った。
十三湖は土で濁って茶色だった。冬の土手には枯れた草がしおれ重なっている。
「春が来て、夏が来て、秋がこないと曼珠沙華は咲きません」
「そうだな、その間に、他の薬の材料を探すわけにはいかぬのか」
「私にはわからないのです、あの歌の順番でなければいけないのか、そうでなくてもよいのか、せっかく集めて、順が違うことで薬にならないとすると、それは無駄になります」
「そうだな、妖術を解く薬となると、そのようなしきたりというのを無視するわけにいかぬだろうな、じっくり待つしかない」
「私もそう思います、蝙蝠さんには大変なことで、申し訳なく思います」
「そんなことはない、火根山一族を守るために我々は生きてきて、その役目が私に回ってきたのだから、何の苦にもなりはしない、むしろ誇りなんだよ」
「それならばよいのですが」
それから、卵茸は十三湖のほとりの土手の一角で一日を過ごし、秋を待っていた。十三湖の水はいつも土の混じった茶色をしているが、一時、きれいに澄むときがある。そんなとき、卵茸は水の底にいる者たちの会話を聞いていた。
「今年の夏は暑くなりそうだな」
「ああ、水は濁ったままだろうな」
「そうかもしれん、だが、土の粒に旨いものがついて落ちてくる」
「そうだな、それは嬉しいことだ」
十三湖に棲む蜆(しじみ)たちの会話である。
「秋の林檎のできはどうだろう」
少し大きな声が聞こえた。鮒が蜆たちに声をかけているようである。
「今年もいいだろう」
「そういえば、黄作村の雀が遊びに来て、ここの雀と話していたが、黄作村の林檎畑にはまだ林檎がなっているそうだ」
「そりゃどうしてだ」
「その林檎の木は花を付けるのがずいぶん遅れたそうだ、そのおかげで実が今ごろついたそうだよ」
「どうして遅れたんだい」
「花をつける時期に雷がたくさん光り、怖くて花芽が膨らまなかったんだ」
鮒が蜆に言っている。
卵茸は冬の赤い林檎を思い浮かべて寒いだろうなと、一人で同情していた。
そこに、あたりを飛び回り、曼珠沙華の赤い実にまつわる話がないか、聞いていた緑蝙蝠が戻ってきた。
「お嬢、なかなか、曼珠沙華の話は聞くことができぬ」
「秋まで待つしかないかもしれません、今面白い話を聞きました。黄作村の林檎が今生っているそうです」
「ほお、誰の話なのだ」
「鮒が蜆に話していました。黄作村の雀から聞いたと申していました」
「そりゃどうしてそうなったのかね」
「雷のせいだそうです、怖くて花芽が出なかったといっていましたが、むしろ、そこだけ季節がかわったのかも知れません」
「そうか、その村の季節がおかしいとすると、彼岸花が咲いている可能性もあるかもしれぬな」
「あ、私はそこまで考えませんでした。さすがに蝙蝠さん、黄作村に行ってみませんか」
「そうしよう」
緑蝙蝠は近くにいた雀に黄作村の場所を聞くと、卵茸を翼にくるんで空に舞った。寒いけれども気持ちがいい。
緑蝙蝠の飛ぶ早さは日本一だろう。あっというまに黄作村に着いた。
小さな村のあちこちに林檎畑があったが、村の真ん中の畑の林檎の木に赤いものがちらほら見えた。なにやら少し暖かいような気もする。
「あそこではないでしょうか」
「そうらしいな」
緑蝙蝠たちが降り立った林檎畑には、たわわではないが、真っ赤な林檎が一本の木に数個なっていた。黒いような赤い色できれいだ。
「こりゃ秋映という種類だ」
「珍しいのですか」
「いや、信州でつくられたもので、甘酸っぱくて、実はしまっていてうまい林檎だが、青森の方でもとれるのだな」
「蝙蝠さん、果物も食べるのですか」
「俺は得意じゃないが、後でちょっといただいてみよう」
「私は匂いで十分です」
「では、彼岸花を探してみるか」
緑蝙蝠は茸を抱えて林檎畑を歩いた。蝙蝠が歩く様を見たことがあるだろうか。よたよたと体を右左に揺らして、ペンギン鳥のようにぎごちないというか、滑稽である。
「ないねえ」
小さな林檎畑を一周したが、曼珠沙華など生えてはいなかった。
緑蝙蝠が一本の古そうな太い林檎の木をみて、「おや」っと立ち止まった。
「なあに」
「あの林檎の木の途中に穴があいているだろう」
「ええ、中に赤いものが見える、林檎が落ちているのかしら」
緑蝙蝠はその木に近づいて穴の中をのぞいた。、
「あ」っと言った。
卵茸もその穴をのぞくと、なんと赤い曼珠沙華が咲いていた。
卵茸と蝙蝠はその木の上のほうを見上げた。
「あそこに、林檎がなっています」
真っ赤な熟れた林檎が一つ揺れている。
「まるで陶器のように奇麗じゃないか」
「蝙蝠さん、あれが、曼珠沙華の赤い実ではないでしょうか」
「おお、そうか、姫、きっとそうだ」
蝙蝠は赤い大きな林檎を口でもぎ取ろうとした。
「まって、曼珠沙華が咲いているのはなにか意味があるよう、聞いて見ます」
卵茸は曼珠沙華に声をかけた。
「林檎の木が亡くなりました、ありがとうございました」
卵茸と蝙蝠はしばらくそこにたたずんだ。
「なぜここに生えているのです」
しばらく話していた卵茸は蝙蝠に言った。
「この年取った林檎の木は、死ぬところだそうです、最後の実をつけたので、曼珠沙華は林檎の木を見送るため、花を咲かせたそうです、最後の実を落すと死ぬのです」
「お嬢は花とも話ができるようになったのだな、そのようなわけがあるとすると、簡単にはこの実を取るわけにはいかぬな」
「はい、しかし、火根茸のことを説明しました、曼珠沙華がこの年取った林檎の木に聞いてくれたのです。最後に役に立つのは嬉しいとのことでした」
「だが、この林檎の木は死ぬのじゃな」
「はい」
「それを下さるとは、ありがたいことじゃ」
蝙蝠はそれを聞いて、林檎の木に一礼すると、林檎を採った。
「ずい分重い林檎じゃ」
林檎の木からまだ青い葉がぱらぱらと散った。
曼珠沙華の花も洞からパーッと散った。
「ありがとう」
もう一度卵茸は梅の木に向かって礼を言った。卵茸を抱えた蝙蝠は空にまった。
二人は近くにあった農家の納屋まで飛んだ。
蝙蝠は林檎と卵茸を床の上に降ろした。
「貴重な林檎の最後の実をいただきました、死との引き換えにくださったのです」
「そうだのう、大事な彼岸花の赤い実だ、役立てねば」
緑蝙蝠は林檎を藁の上に置いた。
「この林檎は石のように硬い、なんでしょう」
「確かに重いし、てかてか光っている、おそらく何年も木についたままで、化石になったのかもしれぬな」
「きっとそうです、彼岸花もこの林檎を守って咲き続けていたのかもしれません」
「この大事な林檎、誰に運んでもらうかな」
「火根山のムササビに頼みます」
卵茸はムササビに連絡した。
「明後日に来ると言っています」
こうして、曼珠沙華の実は無事に甲斐の森にとどいた。
卵茸と蝙蝠はもう一度林檎畑に戻った。
林檎をくれた年取った木はまだどっしりと立っていた。
祠の中に二人は入った。
「温かい」秋映の実を目の前にして緑蝙蝠と卵茸はよりそっていた。
他の木になっていた秋映えを食べてみようと採ってきたのだ。
緑蝙蝠は口を伸ばすと季節はずれの秋映をかじった。
林檎の甘酸っぱい匂いが洞の中にうずまいた。
「果物も旨いものだな」
「林檎の良い匂い」
卵茸と緑蝙蝠は安寧の一時を過ごした。
弥生ー胎内
三月になった。
「次にはどこに行くことになるのかな、お嬢」
「新潟に飛んでください」
「新潟のどこに行くのかね」
「胎内です」
新潟に胎内という所があり、胎内川が流れている。その奥の地を奥胎内という。
「ほう、そこにはなにがあるのか」
「わかりません、ただ歌の三番目は赤腹井守の黒い胎児です、井守はほ乳類ではありません、胎内にいる赤腹井守のことではないでしょうか」
「うむ、そうだな、わからんが、行ってみるか」
「お願いします」
蝙蝠は卵茸を抱え、十三湖から日本海側に渡ると、海の上空を新潟へと旅をした。
胎内は新潟の中心の町よりほんの少し秋田寄りである。秋田の由利本荘で一休みして、胎内まで飛んだ。
胎内に来ると、卵茸と緑蝙蝠は胎内川の河原に降りたった。
「しばらくここにいて、井守のことを誰かに聞こうじゃないか」
「はい、まだ寒い時ですが、確か井守はしばらくすると産卵の季節かと思います」
河原の土手の石で囲まれた隙間をみつけた。いい住処になる。
青森より少しは暖かいのであろうが、風が吹きすさぶ日本海側の寒さは別である。
このあたりを飛んで情報を得なければならない。冷たい風の中、緑蝙蝠は卵茸を抱いて空を飛んだ。なだらかな山が遠くに見える。眼下には田や畑が点在している。
時に下に降り立って、田圃の脇でまだ穴の中にいるざりがにや泥鰌の話に耳を傾けた。彼らは季節の話やら、仲間内の噂話に花を咲かせていた。
井守たちも田んぼの脇や水底で冬眠をしている。少し気の早い井守が顔をのぞかせた。
「あ、井守さん、黒い胎児ってなんだか分かるかしら」
まだぼんやりしている井守はきょとんとしている。眼の焦点が合っていない。眠そうにしてすぐにもぐってしまった。
二人は毎日毎日、胎内川の両岸を飛び回った。疲れると河原の石の隙間にもどった。
そんなある日、石と石の隙間で河原の虫が寒さをしのいでいるのに気がついた。食物である虫について緑蝙蝠は熟知している。しかし、その河原の石の間にいる虫たちは今まで見たこともない連中であった。
「この冬も寒かったが、もうすぐ春だ」
虫が隣の虫に話かけている。
「だがな今年の春は短いな、暑い夏が早くくる」
「そうだな、でもな暑いのもいやだが、寒いのもいやだ、早く春になってほしいな」
「そういえば、川のカワゲラの子供が言ってたな、上流の井守がお産だそうだよ」
「はやいね、このあたりのやつらは卯月あたりだろ」
「なんでも、二十年も生きている妖怪井守で、卵を産むのは春先とは決まっていないんだそうだ」
「こんなに冷たい水だと卵がかえらないじゃないか」
「それで、その井守のばあさん胎内川をのぼっていって、どこか温泉に行くという話だ」
「温泉じゃ卵がうだっちまうじゃないか」
「いやさ、温泉そのものに入ろうっていうんじゃないらしい、温泉の湧くそばの清流にいくのだろうって、カワゲラのガキたちが言っていたよ」
「そうか、おれたちも移動して暖かい思いをしたいな」
「おれたち、無動虫だ、川の岸辺までしか動けない」
「そうだな、一生石の間だからな」
緑蝙蝠は無動虫という虫を知らなかった。緑蝙蝠は虫たちに話しかけた。
「おまえさんがた、その井守はいつお産だい」
緑蝙蝠は石の間をのぞいた。あれ、さっきまで見えていた虫たちが、全く見えない。みんないなくなってしまった。
「蝙蝠の旦那、我々にはわからないよ」
虫は見えないが、声だけかえってきた。
「おまえさん方、姿が見えないがどうした」
「はは、虫は蝙蝠の好物、うかつに姿を現したら食うだろう、わしらは透明になって、身を守るんだ。だから人間にも知られていない」
「そうか、いや、食うきはないが、ありがとよ」
緑蝙蝠は卵茸に言った。
「その井守を訪ねてみるかい、お嬢さん」
「はい、私も聞いていました」
「無動虫よ、ありがとうよ、今日の夜、胎内川をのぼってみるよ」
「ああ、そうしなよ」
石の間に虫たちが姿を現した。はじめみたときには茶色の汚れた虫だと思っていたところ、金色に輝くきれいな虫たちだった。
「おれたちはな、河原の砂金を食って生きているんだ、体は金でできている、こんなことを人間が知ったら、おれたちゃ、とっつかまって、飼育されて、砂金とりだ、最後にゃ火にくべられて金の延べ棒さ」
緑蝙蝠がうなずいた。
「そうだな、気をつけてな」
「ごめんなさい」
卵茸が謝った。
「おや、その茸なんなんだい」
無動虫が顔をだしたばかりの卵茸を見た。。
「人間だよ、茸にされちまったんだ」
「こりゃまずいことを聞かれちまった。人間に知られたらおしまいだ」
「大丈夫です、約束します、誰にも話しません」
「約束してくれよな、卵茸のお嬢ちゃん、もし、しゃべったら、また茸に戻っちまう呪文をかけておくからな」
無動虫はぴかっと光って茸を照らした。
「儂も保証する」
「そうかそれならいいよ、元気でな」
虫たちはまた透明になった。
夜になると、蝙蝠と卵茸は胎内川の上を上流に向かった。
星空のもと山奥にむかってしばらく行くと、川は小さくなり、川べりには大きな石がごろごろところがって、蒸気が漂い出ているのが見えた。
山奥の胎内川の源流である。
蒸気を追い求めていくと、温泉のわき出る小さな泉があった。泉の山際から冷たい水がそそぎ込み、反対側の泉の底から熱い湯が湧き出ていた。水面から蒸気があがっている。
「ここに違いない」
蝙蝠は卵茸を抱えて、泉のほとりに伸びていた大きな木の根の瘤の上に降りたった。
卵茸は泉を見ると、
「井守のおばあさん、どこにいるの」
と声をかけた。
すると、池の中ぽこっと、年取った井守が顔を出した。
「なんだい、茸の嬢ちゃん」
「これからお産するんですって」
「早耳だね、誰に聞いたんだい」
「無動虫」
「ああ、あいつらか、おしゃべり虫だね、そうだよ、これから卵を生むんだよ」
「いい赤ちゃんを産んでください」
「そりゃ、毎年たくさんの子供たちを送り出しているんだから、それも、みんないい子だから」
「そうでしょうね」
「隣にいる緑色はなんだい」
「お初にお目にかかります、蝙蝠でございます」
「何で、緑なんだい」
「へえ、緑の苔が生えまして」
「動かなかったのかい、ものぐさだったのだね」
「いえいえ、ほんとは万年茸だったんですが、蝙蝠にされやした」
「そうかい、元茸か、まあいいや」
そう言った井守の顔が真っ赤になった。
「卵がでそうだ」
井守はからだも真っ赤になって、卵茸と蝙蝠の立っているところにやってきた。
「ほれ、産むよ」
卵茸たちが泉をのぞいていると、井守は尾っぽを上に上げ、ぽとぽとと水草の中に卵を産み落としていった。最後に真っ黒な卵を一つぽとりと落とすと、
「ほーすーっとした」
そういいながら水底を見回し、最後の卵が落ちているのを見ると顔をしかめた。
「ありゃ、最後の卵が黒こげだ、こりゃ生まれないね」
「どうしたんです」
卵茸が聞くと、
「いやね、ちょっと焦って生んじまったら、あまりにも早く卵がでてね、最後の一つが摩擦熱で死んじまった。炭素になっちまった。真っ黒な玉だよ、石炭より黒くて堅い玉だよ」
「それ、ほしい」
卵茸が声を上げた。これが赤腹井守の黒い胎児に違いがない。緑蝙蝠も頷いた。
「こんなもんをかい、死んだ卵だよ、どうするんだい」
井守が水草に絡んでいた黒い卵を口にくわえて水面に顔を出すと、茸の前に放り出した。
「何かの記念かね、もっていきなよ」
「これは私たちの探していたもの、だいじなものです」
卵茸は火根山の出来事を話した。
「そうかい、大変なんだね、孵らずの卵は役に立つんだね、それは嬉しいよ」
緑蝙蝠はいつの間にか太ったミミズをつかまえて、井守のばあさんの前に落とした。
「お、うまそうだね、卵を生んで疲れた体にゃ、ミミズが一番だ、蝙蝠は気が利くね、この寒い時によくみつけたね」
「卵を生むのは大変なことを知ったんでな」
井守は大きなミミズをほうばった。
「この黒い胎児をいただいて帰ります」
「ああ、あたしゃ、このミミズを食べたら、温泉にゆっくりつかって、からだを回復させるんだ」
「温泉は気持ちがいいのでしょうね」
「ああ、それだけじゃない、力が湧いてくる」
「さ我々はそろそろ帰るか、お嬢」
緑蝙蝠が卵茸に促すと、茸はもじもじして、
「私も温泉につかりたい」
と言った。卵茸は人間のとき、野天湯に使って気持ちの良かったことを覚えていた。
「へえ、わしは温泉などに浸かったことがない」
万年茸だった緑蝙蝠には想像がつかないと見える。
「それじゃお嬢、はいってみるとするか」
緑蝙蝠はと卵茸をかかえると、暖かい湯の湧き出るところに浸かった。
それを見た井守は、
「あたしゃ、二十年も生きているが、蝙蝠が茸を抱えて温泉に入っているのは始めてみたよ、なかなか似合うねお二人さん」
とミミズを飲み込んだ。
「温泉てやっぱり気持がいい」
卵茸は赤い小さな頭をますます赤くした。
「茸のお嬢ちゃんも温泉始めてかい」
「茸になってから初めてです」
「いいもんだね、いつもは冷たく澄んだきれいな水にいるんだがね、年をとってからは、よくはいるよ」と二人の脇に泳いできた。
「たしかに気持のよいものだ」
緑蝙蝠の目もとろんとしている。
しばらく浸かった蝙蝠は、
「お嬢、今度は梟にでも黒い胎児を取りに来てもらうかい」
「いえ、一度、火根山にかえりましょう」
「そうか、明日まで浸かって、帰ることにしよう」
こうして、一晩、卵茸と緑蝙蝠と井守のばあさんはおしゃべりとお湯を楽しんだ。
朝日が昇った。
温泉からあがった蝙蝠は黒い玉と卵茸を抱えて、空中に舞い上がった。
井守のばあさんが手を振る。
「それじゃ、井守のおばあさん、ありがとう、さよなら」
「ああ、湯冷めしないようにね」
卵茸と蝙蝠は湯気を立てながら胎内を後にした。
卯月ー甲斐
卵茸と緑蝙蝠は、黒い玉を持って、甲斐火根山の森に戻った。
四月になった森は若葉に覆われ、柔らかな緑色になっている。日が差す林の中は暖かい空気に包まれていた。
「久しぶりに帰ってきました」
「そうだな、だが、一つを見つけるのに何年もかかるのではないかと思っていたが、お嬢の知恵で三つも見つかったな」
大きなブナの木の前の大きな切り株には一角の角、林檎が乗っている。緑蝙蝠がその上に卵茸を降ろし、黒い井守の卵を置いた。
あたりから火根茸が顔をだした。
「おー火根茸のみなの衆、もう、三つも集まりましたぞ、お姫さんは頑張っていらっしゃる、楽しみに待っていてくだされ」
火根茸たちが深くお辞儀をした。
卵茸は火根茸に今までの冒険の話を聞かせた。
「みな、緑蝙蝠さんのおかげです」
卵茸がしめくくった。
火根茸たちはうなずいて、また深くお辞儀をした。
「さて、お嬢、こんどはどこに」
「今度はこの近く、洞窟を探して赤い水晶を見つけるのです」
「おお、それなら、他の連中にも手伝ってもらえるな」
「しかし、茸になった者たちは動くことができません」
「いや、そうではない、我々の仲間がいる」
緑蝙蝠は甲斐に住む蝙蝠たちを呼んだ。
甲斐にはいろいろな洞窟がある。洞窟を一番よく知っているのはやはり蝙蝠たちである。いつも蝙蝠たちは自分の住んでいる穴を自慢しあっているのである。
「洞窟の中の赤い水晶を探してくれ」
緑蝙蝠は仲間たちに頼んだ
「赤い水晶は見たことがないな」
蝙蝠たちはささやきあった。
「ともかく探してみてくれ、まず、自分の住処、次には蝙蝠のいない洞窟だ」
「おいさ、わかった、やってみるよ」
蝙蝠たちはそれぞれの洞窟に戻っていった。
「お嬢、私も探しに行くが、ここに居るか、それとも、一緒に行くか」
「はい、ご一緒にまいります」
「では、いくとするか」
緑蝙蝠は卵茸を抱えて飛び立った。
「仲間の洞窟はまかせて、われわれは蝙蝠が住んでいない洞窟を探すとしよう」
緑蝙蝠はまず森の上に舞いあがり、目を凝らせ、音を発して穴のありかをさぐった。この音は人間には聞こえない超音波である。反射してきた音を解析し、虫だけではなく、山の様子を知ることができた。それは緑蝙蝠しかできないことである。
最初に目についたのは水の流れ出ている岩穴であった。しかし、緑蝙蝠はその穴を無視した。住んでいる蝙蝠がいるのである。
緑蝙蝠は、火根山の南側の杉林の麓に、小さな穴が開いているのに気がついて降り立った。
「これは入口は小さいが、中は大きな鍾乳洞だな」
「どうしてわかるのです」
卵茸が聞くと、「ほら」、と、茸を穴の入り口につれていった。
「あ、冷たい」
茸がびっくりした。しかも、ひゅーっと風を切る音が聞こえる。
「この音は、奥も深く、長く大きなものだといっている。おそらく古いものに違いがない」
「入ってみましょう」
「ああ、しかし水晶の洞窟かどうか分からんがな」
そういいながら、緑蝙蝠は卵茸を抱えると穴に入った。小さな穴からは強い風が吹き出してくる。緑蝙蝠は卵茸を飛ばされないようにきつく抱きしめた。
「つぶれそう」
卵茸が声を上げた。
「そりゃいかん、すまぬな、なれぬもので」
ちょっと翼をを緩くすると、ぽこっと、卵茸が飛び出してしまった。
卵茸は宙に舞った。
「あれー」
洞窟に卵茸の叫びが響く。
洞窟はとてつもなく大きく、底が見えない。どうも川が流れているようである。
卵茸は底に吸い込まれていく。緑蝙蝠はおおあわてで急降下し、途中で卵茸を捕まえた。
「おー怖い、つぶれてもいいからぎゅっと抱いていてください」
卵茸は震えている。
緑蝙蝠は卵茸を強く抱いて、流れの脇の岩の上に降りたった。
「すまぬ、怖い思いをさせてしまった」
「いえ、ありがとうございます」
卵茸と緑蝙蝠が下をのぞくと澄んだ水が流れている。しかし、水は浅く、水底で真っ白の海老が群をなしてゆっくりと歩いている。
一匹の白い海老が、
「お、とうとう、この洞窟にも蝙蝠が住むようになったようだ」
と仲間に言うのが聞こえた。
「あの蝙蝠、緑色だ」
「苔でも生えたのか」
「赤い茸を抱えているぞ、茸を食べる蝙蝠か」
卵茸はそれを聞いて笑ってしまった。
「茸が笑っている」
「あれが笑い茸なのか」
「いや、違いそうだ」
そこに、緑蝙蝠が口を挟んだ。
「卵茸のお嬢さんだ」
「そうか、おい、蝙蝠のおまえさん、この洞窟に棲もうっていうのかい」
「いや、そんな気はないが、なかなかいい洞窟だ」
「そりゃそうだ、人間に見つかっていないということは、本当にいいことだ。壊れていない洞窟だ、ところで、なぜ茸をもっている」
「訳あってお守りしているのだ」
「ふーん、訳ありの二人か、で、この洞窟に何のようだ」
「赤い水晶を探している」
「水晶なら、ごろごろしてら」
「おお、どこにだ」
「この奥の方だ、奥の奥の方で、火がメラメラと燃えている」
「火があるとな、だがそのわりには、ここはずい分寒いじゃないか」
「おおよ、火が燃えているのは奥だからな」
「奥はどのくらいあるんだ」
「わからん、奥に行くには何十日もかかる」
「そうか、行くのは大変か」
「俺たちの一生だ、行き着くところで死ぬんだ」
「そうか、ありがとよ」
蝙蝠は白海老に礼を言う。
「いや、久しぶりに違う生き物に会った、またどこかで会おうな」
「ああ、その時にはまた世話になる」
緑蝙蝠は、
「お嬢、一度、森に戻ってから考えるとしよう、仲間の誰かが赤い水晶を見つけているかもしれない」
そう言って、卵茸を抱きかかえ、洞窟の上に舞い上がった。
「はい、お願いします」
緑蝙蝠は穴の出口に向かった。
火根山の森に戻ると、すでにブナの木の前に蝙蝠たちが戻ってきていた。
「水晶はたくさんあったが、赤い水晶はなかったね」
どの蝙蝠も見つけることは出来なかった。
緑蝙蝠は他の蝙蝠たちに今見てきた洞窟のことを話した。
「奥の奥で、火が燃えているという水晶のある洞窟を見つけたが、火が燃えているところまで何日もかかるようで一端戻ってきた、我々はもう一度行くつもりだ」
「緑の兄さん、俺たちも手伝うよ」
三匹の赤い太った蝙蝠たちが前にでてきた。
「おれたちもいくよ」
他の蝙蝠たちも言った。
「ありがたい、だが、たくさん行ってもしょうがない、赤蝙蝠の助けを借りよう、後の者は、また、いつものように、洞窟を守っていてくれ」
蝙蝠たちの役目は洞窟の様子を知ることであった。洞窟の様子で天地異変の前兆を知ることができるのである。蝙蝠はそれを山の生きものたちに知らせる。
赤蝙蝠が三匹残って、後は自分の洞窟に帰っていった。
赤蝙蝠の一匹が「おいらたちが、そのお嬢さんを抱えていくから、緑の兄貴は、洞窟の中を先導しておくれ」
「そうか、そうしてくれると、超スピードで奥に行くことができる」
「火が燃えているところは危ないから気をつけてくださいよ」
もう一匹が言った。
「ああ、三匹で、卵茸のお嬢さんをたのむよ」
「おいきた、交代で抱えていくよ」
赤蝙蝠は卵茸のお嬢さんを翼につつんだ。
「あれ、緑蝙蝠さんとは違うわ。ふかふかしてる」
「ああ、おいらたちには柔らかい毛が生えているんだ、緑の兄貴は筋肉でできているから固く締まっているよ、強いんだよ」
「皆同じじゃないのね」
「ああ、おいらたちはお嬢さんの家の裏に置いてあった、ほだぎに生えていた椎茸さ、緑の兄貴と同じように、呪文で蝙蝠にされちまったんだ。だから、お嬢さんを守る役目もあるんだ」
「そうだったの、よろしくお願いします」
「まかしといて」
赤蝙蝠は宙に舞った。
緑蝙蝠の先導で洞窟の入り口についた。
「小さい入口だなあ」
赤蝙蝠が言った。
「さあ、中は風が強いから気を付けてな」
緑蝙蝠が中に入った。
赤蝙蝠たちも中にはいると、宙に浮いた。
「先にいくからな」
緑蝙蝠は洞窟の中を猛スピードで奥に向かった。 緑蝙蝠はあっという間に見えなくなった。
一方、茸を抱えた赤蝙蝠はふんわりふんわりと、底に降り、水の流れの上を、奥に向かってゆらゆらといく。水の中では先ほどの白海老が並んで行進していた。
「今度は赤い蝙蝠が赤い茸をかかえていらあ、緑の蝙蝠はどうした」
「緑の兄貴は一目散でおくにむかいやした」
「せっかちなこった」
赤い蝙蝠たちもスピードを上げた。真っ暗の洞窟でも蝙蝠たちには超音波で様子が目に見るようにわかる。鍾乳石や石筍が立ち並ぶ間をうまくすり抜けて飛んでいく。
半日ほどたったところで、洞窟の中が寒くなくなってきた。鍾乳石はみられなくなり、白い石の洞窟に変わった。石英である。石英は水晶と同じ成分である。もう少し進むと水晶に出会えるに違いない。
だが、なかなか水晶はあらわれなかった。緑の蝙蝠は丸一日飛んだ。石英の洞窟が続く。しかし、洞窟の空気が暖かくなってきた。遠くに明かりが見える。蝙蝠はスピード上げて進んだ。
やがて水晶でできた明るい洞窟になった。そこは洞窟の壁もすべて水晶だった。底には水の流れが続いていた。水底に真っ赤な海老が群れていた。
「おう、緑の蝙蝠、よくきたな、白海老から連絡が入った。赤い水晶を探しているのだとな」
「あんた方は離れていても話せるのか」
「ああ、長いひげを震わすと水が振動して伝わる、だが赤い水晶は見たことがない」
「この明かるさはどうしてだろう」
「マグマだ、地球の奥のマグマが、厚い水晶の底で動いているんだ、その光が水晶を貫いて洞窟まで達しているのよ」
「熱いのだろう」
「熱いは熱いが、何百メートルの厚さの水晶がそれを冷ましてしまう、もう少し先にいくと、その様子が見える」
緑蝙蝠は礼を言い、洞窟の明かりに向かって飛んだ。
洞窟の突き当たりには大きな池があった。その池からまばゆい光がでている。緑蝙蝠は池のほとりの水晶に降り立つと、水の中を見た。真っ赤なマグマが地底で動いている様が、ゆらゆらと水を通して見える。池の底は厚い水晶で出来ているようだ。
池の水に触れてみると、暖かい。
緑蝙蝠は池に入った。新潟で卵茸と一緒に入った温泉を思い出した蝙蝠は、温泉につかって、赤い蝙蝠と卵茸が到着するのを待つことにした。
それから一日半すると、ふわふわと、三匹の赤蝙蝠が飛んできた。
「緑の兄貴、明るくてきれいなところだな、温泉とはぜいたくな」
「緑蝙蝠さん、遅くなりました」
卵茸が言った。
「いや、みんな遠いところを大変だった。なかなかいい湯だ、暖まってくれ」
茸と赤蝙蝠も温泉に浸かった。
卵茸は池にプカプカ浮いて下をのぞいた。赤いマグマがうごめいている。
「きれい、水の底は水晶なのね」
「ああ、この洞窟は水晶でできている。しかも地下何百メートルもあるそうだ、ずいぶん厚い水晶だ。しかし、透明度が余りにも高いのでマグマが見えるのだ」
緑蝙蝠は池からあがった。
「ずいぶん長いこと浸かったので、ふやけたよ」
空中に舞うと、平らなところに降りた。
足下をのぞくと、池の底のように、真っ赤なマグマが動いているのが見えた。
卵茸を抱えた赤蝙蝠も池からあがると、緑蝙蝠の脇に着陸した。
「本当にきれい、真っ赤な水晶ね」
卵茸が赤く輝く水晶を見て言った。それを聞いた緑蝙蝠は言った。
「お嬢さん、赤い水晶ってこのことではないだろうか」
「そうですね」
「ここの水晶のことで、赤くなくてもいいのかもしれないぜ、兄貴」と赤蝙蝠が、とびあがった。
「でも、これをもって帰ることはできるのかしら」
赤蝙蝠たちは落ちている水晶をさがした。しかしなかなか見つからない。
一匹の赤蝙蝠が首を横に振った。
「水晶は固いから欠いてかけらもとれないね」
赤い海老たちが川の底をぞろぞろと、池に向かって歩いて来た。
「どうだ暖かいだろう」
赤海老たちは蝙蝠たちを見上げた。
「とてもいい湯だ」
海老たちは池に入ると泳ぎ回った。もっと赤くなった。
緑蝙蝠が尋ねた。
「この水晶を一かけら欲しいのだが、硬くて取れぬが、何とかできないものかな」
「水晶はかたいものだ、俺たちならとれるが」
「そうか、わしらは、どうしても赤い水晶を持って帰らねばならぬ、頼めるか」
「何にするのかい」
「火根山の一族が茸になっている。それを元に戻すには必要なのだ」
卵茸が今までのことを話した。
「だが、ここの水晶は赤くはない、透明できれいだ」
「マグマの色で真っ赤に染まっている」
「確かに、しかし、外にもって行けばただの透明の石にしか過ぎぬ」
「やはり、これは赤い水晶ではないのだな」
「そう思う、もっと探しなされ」
赤海老の長老が激励した。そしてこう言った。
「わしらは本当は白海老なのだ、この洞窟を長い時間かけて歩いてくると、だんだんと赤くなり、ついには真っ赤になる。、そうして、ここで、命が尽きるのだよ」
もう、何万年もそうやって、わしらはここで死んでいる。この温泉で、ゆったりして死ぬのだ」
「赤海老の爺様、いくつになるのかね」緑蝙蝠が尋ねると「そうよなあ、もう二百ぐらいになるかもしれんの」
わしらが死ぬと、この池の底にたまるのだよ、それが、水晶に取り込まれ、赤海老水晶になると信じられている。みんなそれを夢見てここで死を迎えるのだ」
「赤海老水晶とやらはどこで見られるのかな」
「わしらでも見たことがない、我々の死骸が池の底にたまり、何かの拍子に川に流れ出て、それが途中に引っかかり、長い年月の末、水晶に取り込まれる」
赤蝙蝠が池の隅を覗いた。そこには赤海老の死したる亡骸が積み重なっていた。
「このあたりをくまなく探すしかない、運が良ければ、あるだろう、わしらも加勢してしんぜよう」
「それじゃあ、みんなで探すぞ」
緑蝙蝠は号令を発した。
蝙蝠たちはおっちら、おっちら歩いて広い水晶洞窟の中を探しまわった。
赤海老入りの水晶はなかなか見つからない。
赤海老たちも池から上がるとみなでぞろぞろと、探すのを手伝った。
赤蝙蝠が歩くのが疲れたと、卵茸を水晶の上に置くと、あたりを飛び始めた。
洞窟には水晶の石柱がたくさん突き出ている。石柱の間を飛び回ったが、赤海老は入っていない。
一匹の赤蝙蝠が天井につる下がった。その赤蝙蝠が下を見ると、突き出た水晶の棒の先がなにやら赤く見える。
赤蝙蝠はそこに飛んだ。そして、あっという声を上げた。
「赤い海老が入っている」
蝙蝠たちは舞い上がった。
尖った水晶の柱の先に赤海老が腰を曲げたまま埋もれている。
赤海老たちもその水晶柱の根元に集まったが見ることができない。
緑蝙蝠が一匹の長老赤海老を抱えると、水晶柱の先に連れて行った。
「確かに、我々の祖先だ、何億年も前だろう。わしも赤海老の入った水晶を見るのははじめてだ、ありたがいことだ」
そして、海老は自分のはさみを水晶に突き刺した。それには緑蝙蝠もびっくりした。
「なんと、おぬしの鋏は水晶も切ることができるほど硬いのか」
「ああ、わしらは水晶を食しておる」
「驚いた生き物よ」
「このご先祖様は、死して池から流れ出ると、水晶岩の上に取り残され、そこで何千万年も経って水晶に包まれ、それは柱になって上に突き出たのだ」
赤海老の長老は、水晶柱の尖った先を切り落とした。
それを赤蝙蝠が受け取ると、緑蝙蝠は海老の長老と共に下で待っていた卵茸のところに舞い降りた。
「お嬢、これが正真正銘の赤い水晶だろう」
「ほんとうに、うれしいことです、でも、赤海老さんたちには先祖です、もっていっていいものでしょうか」
赤海老の長老は首を縦に振った。
「いや、かまわぬ、ただ、今日一日、我々一族に拝ませていただきたい」
「もちろんです、ありがとうございます、どうぞ、皆さんで、水晶の中の赤海老さんを弔っていただきましょう」
「いや、弔うのではなく、お役に立つことはうれしいこと、ここは火根山の一部、わし等もその仲間と思っておりまする」
「この何億年も前の赤海老の入った水晶、貴重なものありがとうございます、赤い水晶も死の水晶でした」
こうして、蝙蝠たちは洞窟を出ることにした。
「赤蝙蝠さんのお陰で赤い水晶をみつけることができました。ありがとうございます」
卵茸のお嬢さんは赤い頭をひょいと下に下げた。
「いえ、偶然だから、それよりなあ、緑の兄貴、おれたちゃ、ふわふわとしか舞えないから時間がかかる。卵茸のお嬢さんをだいて先に帰ってくれないかな」
「おう、いいよ、お嬢それでよいか、俺の翼は硬いが」
「お願いします」
「それじゃ、赤蝙蝠よ、先に戻らせてもらう」
緑の蝙蝠は赤海老の入った水晶のかけらを持つと、卵茸を抱えて飛び上がった。
「おいらたちは、ゆっくり温泉を楽しんで帰るよ、もう少し赤海老たちとも話したいしな」
「それがいい、なんなら、ここを住処にしたらだうだ」
「赤海老たちがいいって言ったらそうするよ」
こうして、緑蝙蝠と卵茸は森に戻った。
皐月ー魚津
火根山の森のブナの木の前にある切り株に、緑蝙蝠は赤海老の入った水晶をおいた。卵茸も脇に立った。
火根茸たちが顔を出した。
「ほれ、、これが赤い水晶だ、水晶の中の赤い海老は何億年も前に亡くなったものだ。貴重なものよ、火根茸の仲間たち、よかったな」
緑蝙蝠は火根山の洞窟の中のマグマの話をした。火根茸たちは、わさわさと、体を動かした。
「行ってみたいでしょうけれど、我慢をしてください、すべてのものを探し出せば皆さんも元に戻ります」
卵茸は茸たちに話しかけた。火根茸はまだまだ我慢をしなければならない。
青い空がきれいな日が続く。五月晴れである。人里では鯉幟が青い空にはためいているに違いない。
「次はどこに行くのかな、お嬢」
「今度は富山に行きます」
「富山か、さほど遠くはないが、お嬢、疲れたであろう、大丈夫か」
「はい、茸は疲れませんが、蝙蝠さんは疲れるでしょう」
「いや、万年茸は疲れることがない」
「それならばお願いします」
卵茸を抱えた緑蝙蝠は空高く舞い上がった。
「富山のどこかね」
「魚津に行きたいのです」
「そこで、こんどはなにを探すのだったかね」
「竜宮の使いです」
「わしは聞いたことがないが、それはなにかね」
「深い海にすんでいる魚です」
「正体が知れているなら、探すのは、容易いことだ」
「いえ、海の深いところにいるので、なかなかみつかりません、ほんのたまに海岸に打ち上げられます。それを待つしかありません」
「一角の角ようだな、そいつはさぞ珍しい魚なのだろう」
「はい、昔の人間はこの魚を人魚と間違えたりしたようです」
「時を過ごせばいつかは見つかるということだな」
「はい、しかし、わたしたちが必要とするのは、赤い竜宮の使いでなければなりません」
「うむ、一角獣のときのように、我慢をして待つしかない」
「はい、深海から偶然にも打ち上げられるのを待つしかないのです、それだけではありません、もう一つ問題があります。あの大きく長い竜宮の使いをどのようにこの森までもって帰るのか考えねばなりません」
「うむ、それはなんとでもなる、蝙蝠の仲間にも頼めるし、鷲や鷹たちと力を合わせればよい」
「また、蝙蝠さんにお世話になります」
「お嬢を助けるのがわしの役目、楽しくてしかたがないのだ」
卵茸は黙って赤い頭を下げた。そんな卵茸を緑蝙蝠は翼の中に包み込み、
「さあ、いくか」
と、五月晴れの青い空の上に舞いあがった。
火根茸たちも空を見上げ、卵茸と緑蝙蝠が点になるまで見送った。
甲斐の火根山から富山までは大きな山をいくつも越えなければならないが、青森や北海道と比べれば気楽な旅である。
緑蝙蝠は空高く高く上った。雪をかむった山々が眼下にみえる。このあたりは、日本のアルプスと言われる、険しいが優雅な山々が連なっている。今回は景色を楽しみながら飛ぶことができた。
「蝙蝠さん、ゆっくり飛ぶと、とっても気持ちがいい」
「五月の空はよいものじゃ、急ぐときは落としちゃいけないと思うから、ぎゅうっと締め付けちまうからな」
緑蝙蝠は水晶の洞窟で谷底に落ちていった卵茸を思い出していた。
「でも、そのほうが安心します」
卵茸は頭を赤らめた。
「魚津では竜宮の使いが打ち上げられそうな海岸を探しましょう」
「そうだな、今度は、どこか住処を決めて、毎朝早く海岸線を飛ぶことにしよう、気持が良さそうで楽しみだ」
「ええ、赤い竜宮の使いがいるとよいのですが」
富山湾が見えて来た。蝙蝠たちは魚津の港に降り立った。
「やや、ありゃなんだ」
緑蝙蝠が海の彼方を見て叫んだ。そこには、赤や緑の建物が浮かんでいた。
「あ、あれは有名な蜃気楼、きれい」
「ああ、あれが蜃気楼というものか、だが、何が映っているのだろう」
「ほんに、どこかよその国の建物ではないでしょうか」
「なんだか、話に聞いた竜宮城のようではないか」
卵茸もうなずいた。やがて、蜃気楼はもやもやと消えていった。
緑蝙蝠は海岸沿いに空を舞って、崖っぷちに建っている一軒の古い家屋をみつけた。誰も住んでいなかったが、庭も家もきれいに手入れが行き届いている。隙間から屋根裏に入ると、区切られた小さな空間があった。具合のいい広さの住まいである。
「これはいい家だな」
茸を隅におろし、蝙蝠は天井にぶらさがった。
「本当にいいところ、風も入らない」
卵茸は片隅で壁に寄りかかり居心地が良さそうだ。
「今日は休んで明日の朝早くこのあたりを飛ぶことにしよう」
蝙蝠は眠りについた。
真夜中のことである。なにやら歌声が聞こえてきた。屋根裏の隣の部屋である。
蝙蝠が目を覚ました。
天井伝いに隣をのぞくと、そこでは、小さな小さな鼠たちが集まって、歌っていた。二十日鼠の半分ほどの大きさである。
蝙蝠がいるのを一匹の小鼠が気がついたようである。
「あ、誰かいる」
「どこの鼠だ」
「こっちにおいでよ」
緑蝙蝠はそれを聞いて天井づたいに、隣の部屋に入った。
「あ、鼠じゃない、蝙蝠だ」
小鼠たちが騒いだ。
「食われちまう」
「いや、食わないから大丈夫だ、入り込んですまなかった」
「なにしにきたの」
小鼠は入ってきた蝙蝠から距離をおいている。怖いのだ。
「赤い竜宮の使いを探しにきたのだ」
「あの、深海にいるやつかい」
「そうだ、知っているか」
「会ったことはないが、蛸の奴が会ったと言っていたよ」
「どこでかな」
「それがなあ、じいさん蛸の奴、馬鹿な蛸がいるものだが、岩から落っこちて、深い深い、海の底に沈んじまったんだよ、そりゃ真っ暗で、重い水がのしかかって、つぶれてしまって動けなくなったのだそうだ。こんな寒いとこだが、深海には鮫もいて、蛸の奴、もう少しで食われるとこだったらしい。だが、大きな竜宮の使いが、『ほらつかまれ』と、尾鰭を出してくれたそうだ、ほんのりと光が届くところに来ると、蛸を岩の上に置いて、『もう大丈夫だ』、と戻っていったのだとよ」
「ずいぶん親切な魚じゃないか」
「蛸が言うには、あれは、海の神の召使いだということだよ」
「海にはどんな神がいるのだ」
「知らないが、蛸がその岩から海面向かって登っていくとき、海の奥から、人間のような顔をした白い頭ががすーっと出てきて、蛸が踏ん張っているところで、ぎょろりと睨むと、『小奴か、アホな蛸は、岩を滑り落ちるなど、蛸をやめて蟹にになっちまいな』と悪態をつくと、ふにゃふにゃ泳いでいったそうな。その後を、竜宮の使いが何匹もついて行ったんだと。最後の一匹が近寄ってくると、『まだいたのか、のろい奴だ、早く帰らないと食われちまうぞ』と注意してくれたそうな。どうもそいつは、自分を助けた奴らしい。蛸はその白い坊主が神様だと思ったそうだよ」
緑蝙蝠はそれを聞くと首をかしげた。
「神様は悪態などつかない、それは、海坊主だろう、悪さもたくさんする猛者だ」
しかし、小鼠は、
「海坊主は神様の一つの姿なんだ」
と首を横に振った。
「海の見回りをしている神様さ、蛸が岩を滑って深海に落ちたのを見ていて、竜宮の使いに助けるように言ったのだよ」
「ほーお、その神様に会うことができると助かるが、居場所を知ってるか」
「うーん、俺は知らないが、蛸に聞いてみたらどうだろう、たまに海岸に行って海のやつらと話をするんだ、ヤドカリなんざ、いつも愚痴ばかりだ、なかなか自分に合う貝殻がないんだそうだ、蟹のやつはいつも腹ペコで、なんでも鋏で挟んで口に入れるし、だが、海の世界は面白いね、話しを聞くだけでも楽しいよ」
「それはよいな、それでその蛸はどこに行けば会えるのかな」
「海岸に行くと、海の中に眼鏡岩という大きな岩が突き出ている。二つ穴があいている岩だからすぐわかる。その上にでてきて空を見上げてポカーンとしている蛸だよ」
「助かった、隣の部屋をしばらく借りるがいいか」
「いいよ、いつまでも」
蝙蝠が隣の部屋に戻ると小鼠たちはまた歌いだした。
「鼠の糞は、はまなっとう、
鼠のしっぽは大根おっぽ
鼠の耳は木耳さ
三つ併せて、なっとうご飯
ヒトに食わせて、腹くだせ
やっつけろ」
卵茸はそれを聞いて、笑っていた。
「緑蝙蝠さん、聞いていました、明日、蛸に会いに行きましょう」
緑蝙蝠はうなずいて天井に張り付いた。
朝日が昇ると同時に、緑蝙蝠と卵茸は眼鏡岩にやってきた。
卵茸を下ろすと、緑蝙蝠は眼鏡岩の周りを飛び回った。波打ち際に何匹かの蛸が顔を出している。その中のポカーンと空を見上げている蛸に緑蝙蝠が尋ねた。
「お主、海坊主をご存じないか」
そいつは空中に停止している緑蝙蝠を見た。
「蝙蝠が何で、アブみたいに空中で止まっているんだ、それで何のようだい」
緑蝙蝠はことの次第を話した。
「ふーむ、赤い竜宮の使いは見たことがない、それに、海坊主もそのときちらりと見ただけで、話しをしたわけでもなし、わからんな、おれも命の恩人だから礼の一つも言いたいが、あれから見かけたことはないね」
この蛸が小鼠が話をしてくれた岩から深海に落ちてしまった蛸のようである。
「もし、何かわかったら教えてくれないか」
「役に立てずにすまんねえ、分かったら教えるよ、たまに眼鏡岩にきてくれよ」
「それは助かる、よろしく頼む」
戻った緑蝙蝠は岩の上の卵茸に報告した。
「それでは、これから海坊主を捜すのですね」
「そうだが、海の中のことだし、蛸を当てにするしかないのはつらいの」
「私によい考えがあります」
「なにかな」
「私を海に落としてください。蛸のように深海に沈みます。きっと海坊主が助けてくれます。そのとき赤い竜宮の使いのことを聞いてみます」
「それは無理というもの、もし海坊主が気がつかないと姫は死んでしまう」
「茸は水の中でも死にはしません」
「だが、海坊主が助けてくれなきゃ、沈んだままだ」
「そうです、仕方がありません」
「それは危険だ、お嬢がなんと言おうとも許すことできぬ」
「大丈夫です、会えないときは何とか浮き上がる方法を考えます」
「お嬢に糸をつけて、浮きにつなげておけばよいが、深海とはどのくらいの深さなのであろうかな」
緑の蝙蝠は蛸に聞いてきた。
「なんと、二千メートルもある深い海の底があるそうだ、蛸はそこに落ちたと言っている、他にはもっと深いところもあるそうだ、ということは、それだけ長い糸を用意しなければならぬな」
「そんなに長い糸がありますか」
「うーん、蜘蛛の糸はそんなに強くない」
「糸はあきらめましょう、必ず助けてくれることを信じて、私をその深海の真上に落としてください」
「それはできぬ、お嬢をお守りするわしにはとても許すことはできない。深い海についてわしは何も知らない。海に住むものに知恵を授けてもらうしかないであろうな、やはり、また蛸にでも相談するしかあるまい」
緑蝙蝠はそう言うと、ふたたび眼鏡岩にむかった。
夕方になり戻ってきた緑蝙蝠は卵茸に蛸から聞いたことを教えた。
「お嬢、蛸はあまり深いところにはいけぬが、日の光があたるところまでは十分に案内ができると申しておる、それより深いところにいく方法を、蛸が考えてくれた、それより深く潜ることのできる水母(くらげ)たちに声をかけてくれるそうだ。水母もいろいろいて潜れる深さが決まっているそうだ。最初の水母が潜れるところまでいって、今度はそれより深いところに住んでいる水母がお嬢を包んで下に降りる、最後に、深海にすむ水母にお嬢を渡してくれるそうだ、その水母は深いところまでいけるそうだ」
「それは嬉しいこと、すぐにでも行きましょう」
「だが、深く行くと海の水が重くなり、からだがつぶれるということだが、お嬢がつぶれるのは困る」
「そこは茸です、どうにでもなります」
「それならいいが」
緑蝙蝠は次の朝、卵茸を抱えると、眼鏡岩に行った。蛸が岩の上で八本足をひろげ空を見て、だらしなくからだ干しをしている。
「おい、蛸のじいさん、お嬢さんを連れてきた」
蛸の脇に卵茸をおろすと、蛸の顔が嬉しそうにほころんだ。
「おお、かわいらしい茸の子供だ、わしは、不覚にも海の深みに落ちてしまったが、決して危ないところではない。ただ、海の水が重くのしかかってくる。それに耐えさえすれば問題がない。生き物は自分のからだにあった海の深さに住んでいる。水母たちは表面にも、海の中の途中にも、深海にも住んでいる。その連中にわたりはつけておいた。だから、心配ないよ、最初は水水母、その次は行灯水母、そして深海では櫛水母だ、櫛水母は光るときれいだぞ、いい連中ばっかりだ」
「ありがとうございます」
「大丈夫かね、蛸のじいさん」
緑蝙蝠は心配顔でたずねる。
「心配するな、茸の嬢ちゃんのほうがずーっと胆がすわってるじゃないか」
「儂はお嬢を守らねばならぬ、一緒に連れて行ってくれまいか」
「そりゃあだめだよ、蝙蝠なんざ海の水の重さで押しつぶされて、小鼠になっちまう。その前に、空気がないんだよ、水の中は、だからお前さんは海の中に入っただけで死んじまう」
いわれてみればその通りである。緑蝙蝠は言い返すこともできず顔をしかめた。
「緑蝙蝠のあんさん、大丈夫だよ、海の中の生きものたちは平和なやつらだよ」
みんなこの蛸のようなら安心なのだが、と緑蝙蝠はうなずいた。
蛸は八本の足を緑蝙蝠のほうに差し出して、握手をもとめた。
「蝙蝠のあんさん、あんたも偉いね、茸の少女を助けて苦労をしているんだろう」
緑蝙蝠はちょっとはにかんだ。
蛸は八本足を卵茸に巻きつけた。
「あれ、にゅるにゅると」
卵茸が声を上げた。
「嬢ちゃんきもちわりいかい」
蛸が気にして足をゆるめた。
「いえ、はい、大丈夫です」
緑蝙蝠は苦笑い。
蛸はからだの下に卵茸を包むと、海に入った。
「気をつけてな、お嬢」
「はい」
蛸は卵茸を抱えて、海の中の岩をそろりそろりと降りていく。卵茸は温泉には入ったことがあるが、それでも潜ったことはない。まして海の中は始めてである。回りを大小の魚たちが珍しそうに蛸に抱えられている茸を見る。
「可愛いだろう、ほら、茸のお嬢ちゃんだ」
蛸は近寄ってくる魚たちにいちいち説明をした。
子どもの魚が勢いよく近寄ってきて、赤い茸の頭をつっついた。
「こら、このがきゃあ」
蛸が腕を一本伸ばして、魚の子どもの頭をこずいた。
「いいのです、蛸の小父さん子どもの魚を怒らないで」
「卵茸のお嬢ちゃんはやさしいね」
少し日の光が弱くなってきた。透明な生きものが長い足を何本もたらして、ふわりふわりと漂って来た。傘の上にきれいな四つの輪が見える。
水水母である。卵茸は水母って茸に似ていると思った。
「蛸の大将、茸の子どもってその子なの、赤い頭でかわゆいねえ」
「そうなんだ、何でも、薬になるものを探しているそうだ」
「そりゃあなんだい」
「はい、赤い竜宮の使いです」
「竜宮の使いは赤くないねえ、それに、あんなでっかいの、どうやって薬にするのだい」
「海坊主さんが知っているかもしれません」
「どうかわかんないね、あの生臭坊主、だけど顔が広いから、知っている者を知っているかもしれないね、それじゃ蛸の大将、茸の娘さんをよこしてくださいよ」
「あいよ」
蛸は卵茸を水水母の傘の下にいれた。
「気をつけてな茸のお嬢ちゃん」
「はい、ありがとう、蛸の小父さん、、水水母さんよろしくお願いします」
「まかしときな、卵茸の嬢ちゃん、あたしゃ、茸ってえものを始めてみたが、わちきらとなんとなく似てるね」
水水母は微笑みながら卵茸を包み込んだ。
「そいじゃ、いくからね、蛸の大将、まかしとき」
「水水母の姉さんたのんだよ」
水水母は海のさらに底へと卵茸を運んでいった。
「ほら、だんだん沈んでいるんだよ、見ることができないだろうけどね」
水水母が卵茸に説明をしている。海の水が重く感じられるようになり、日の光は感じられなくなってきた。
「はい、私は茸ですが、すべてを見ることができます」
「おや、そうだったか」
「水水母さんの模様きれいです」
「おお、ありがとう、こりゃあ、子供を産むためのものなんだよ、おまえさん、だけど、どこで周りを見ているんだい」
「傘全部が目なのです」
「それだったら、私らと同じさ、体ですべてが見えるんだ」
「はい、周りに、お魚が泳いでいます。名前はわからないのですが」
「そうだね、今のは秋刀魚だよ」
「はい、お仲間の水母さんもたくさんいます」
「ああ」
赤い卵茸をくるんだ水水母に、周りの水母たちが興味を示している。
一匹のとてつもなく大きな水母がそばによって来た。
「珍しいのを連れてるね」
「ああ、卵茸の娘だよ、蛸のじいさんに頼まれてね、深海底まで送るのさ」
「こんにちわ」
卵茸が挨拶をした。
「おや、しゃべるじゃないか」
「そうだよ、周りもすべて見えるのだそうだ」
「そりゃいいや、海の中を楽しむといい、陸とは違う景色だよ」
「はい」
「おまえが深海につれて行くのかい」
「いや、行灯水母に渡すんだ」
「それがいいよ、水水母じゃつぶれるよ」
そういい残すと、大きな水母は深海に沈んでいった。
「あの水母さんはどなたなのです」
「あいつは、越前水母と言って、大物よ、人間にゃあ嫌われているけどね」
周りでは、ときどき、魚たちが珍しそうに近寄ってくる。やがて日の光がだいぶ届かなくなってくると、赤いきれいな水母が、ふわふわと寄ってきた。
「水水母の姉さん、かわいい茸じゃないか」
「おおや、茸とよくわかったね、おとなしいよ」
水水母は卵茸を行灯水母にわたした。行灯水母も触手の中に茸をかくまった。
「よろしくお願いします」
「こんだ、おいらが、下に運ぶからね」
「水水母さんありがとうございました」
「ああ、気をつけていきな、蝙蝠には無事行灯水母に渡したと言っておくよ」
「ありがとうございます」
行灯水母は水水母とは違って触手で卵茸を持つと、前に掲げて沈んでいった。
「どうだい、ほら、だんだん暗くなってくる、だが、まだまだ、少しだが日の光は入ってくるんだ」
「あ、ちいちゃな、ちいちゃな白いお魚」
沈んでいく茸の周りには白いつぶつぶが揺れている。
「プランクトンだ、プランクトンは海面にでたり、沈んだりしているんだ、おいらたちもプランクトンの仲間といってもいいのさ」
「なぜですか」
「プランクトンというのは、浮遊生物の総称で、そういう種類はいないのさ」
「それじゃ、あたしもプランクトン」
行灯水母はそれを聞いて卵茸を持っている触手をゆらゆらと揺らして笑った。
卵茸はふらふらと暮らすのは楽しいことだろうと気持では分かったが、まだ気を張っていた。火根山で待つ火根茸たちを思い浮かべ、やらなければならないことがたくさんある。
しばらくの間プランクトンに囲まれて沈んでいくと、暗い世界になってきた。かすかに、何かが動いているのが見えるだけだ。
「だいぶ生き物たちが少なくなってきた、そろそろ、深海にはいるよ」
「どこから深海なの」
「海面から二百メートルからだよ、おれはそこまでだよ。だが、海坊主は千メートルよりもっと深いところにいるんだ」
「私つぶれないかしら」
「茸が深海にいくのは始めてだろう、破裂しそうになったら言いなよ」
「はい」
行灯水母は卵茸を前に掲げて沈んでいく。やがて真っ暗になり、「そろそろ二百メートルだ、苦しくないかい」と聞く、卵茸は首をちょっと横に振った。
「まだ、大丈夫そうだけど、傘のところが縮まってしまったわ」
「それりゃ、危ないね」
茸が下の方を見ると、なにかが緑色に光ってふらふらしている。
「あれが、櫛水母さ」
「緑色に光るのねえ、きれい」
櫛水母は行灯水母を見つけるとあがってきた。
「ごくろうさん、おや、可愛いね、茸っていうのは、ちょっと水母に似ているね」
「そうだよ、でもね、茸は地の主なのだよ」
行灯水母が櫛水母に言った。
「何で知ってるんだい」
「竜宮の使いに聞いたのさ、あいつら、陸のことをよく知っているよ」
「でも、人間じゃないのかい、陸の主って言うのは」
「ところが違うんだよ、地上で生意気に歩き回っているのは人間だけどね、地面の下には、茸が、というより菌糸がしめているんだよ、だから、この星の主は菌類なのだよ、茸はその花だよ」
「よく知ってるね、兄ちゃん」
櫛水母がうなずいた。
「茸のお嬢さんそれじゃ、気をつけてな、海の水が重くなるからな」
行灯水母が卵茸を櫛水母に渡すと、触手をふって上がり始めた。
「はい、行灯水母さん、ありがとう」
櫛水母は卵茸を傘の中に包み込んだ。
「櫛くらげのおばさん、よろしくおねがいします」
「大丈夫、私の傘の中に入れていくからつぶされないよ」
「緑の光がとてもきれい」
「そうかい、ありがとよ、お前さんの真っ赤な頭もきれいだよ、海の底にはそんな色はないからね」
櫛水母は緑色に光りながら、ふらりふらりと落ちていく。真っ暗な海なのに、その光でまわりのものが見える。
「あ、大きな魚」
魚がよってきた。
「なに持ってるんだ」
「茸を案内するのよ、海坊主のところに行くさ」
「茸が何の用なんだ」
「赤い竜宮の使いをさがしているんだってさ」
「ふーん、俺は知らないな、がんばってお探し」
大きな魚は離れていった。
「あれは、深海鮫よ、好奇心が旺盛なの、食い意地も張ってるけどね」
今度は光が長く連なったものがよってきた。あたりがまた明るくなった。どうもこれも水母の仲間らしい。
「よう、櫛水母のおばさん、かわいいもの入れてるね、それが卵茸かい」
卵茸が深海に来ることが水母仲間には伝わっているようだ。
「そうだよ、私が連れていくことにした茸さ」
「用事がなかったら我々が案内したのにな」
「誰に聞いたんだ
「行灯水母に会ったんだ」
「お前さんたち、今日はどこにいくんだい」
「地底の温泉にな、仲間の一人が調子悪くてな、ほら、光っていないだろう」
確かに、数珠つなぎの前から三番目に明かりがない。
卵茸がつぶやいた。
「たくさんの釣鐘がつながっているみたい、きれい」
「そうだよ、このヒノオビ水母はつながって生きているんだ」
「ああ、我々一族は、こうやって身を守っているんだ」
「深海にも温泉があるのね、温泉はいいわ、私も大好き」
「温泉好きかい、仕事がうまくいったら連れてってあげるよ」
ヒノオビ水母は長い糸のようにくねりながら流れていった。
櫛水母と卵茸の周りは真っ暗、ちょっと怖いようだ。
「もうすぐだよ」
櫛水母が言った。
ほどなく、深海の砂の上に櫛水母に包まれて卵茸は降りたった。
真っ白な蟹がたくさんよってきた。
「よお、かわいい茸だね」
「海坊主のところに連れていくんだよ、今海坊主はどこにいるのかしら」
「おーい、誰か海坊主の居所知ってるか」
「あの妖怪は、今日は温泉だとよ」
「どこの温泉だい」
「知らんな」
そこへ、大きな竜宮の使いがゆらりゆうらりと泳いで来た。
卵茸は「あっ」と声を上げた。
「珍しいものを連れてるな」
竜宮の使いは大きな顔を櫛水母の抱える卵茸の娘に近づけた。
「これは茸の子どもじゃないか、何でこんなところにいるんだ」
「この卵茸の娘はあんたたちに会いたいんだとよ」
「俺にかい、それで、何のようなんだ」
「赤い竜宮の使いがほしいのです」
「どうするのだい」
「薬にするのです」
竜宮の使いは苦笑いをした。
「なんだい、殺しちまうのかい」
卵茸の娘は自分のしようとしていることに気がついて、あわてていった。
「すみません、私たち一族を助けるために、探しているのです」
そう言って、卵茸は一族の古い言い伝えの歌を歌い、一族が茸にされたこと、元に戻すために歌の中の物を集めていることを説明した。
「そうか、わかった、赤い竜宮の使いのヒゲの一本もあればいいのだな、だが、俺たちの仲間に赤いやつはいないな、背鰭のところは赤いけどな、それじゃあだめなのだな」
竜宮の使いは自分の赤い背鰭をひらひらさせた。
「はい、言い伝えでは赤い竜宮の使いになっています」
「ふーむ、もしかすると他の意味があるかも知れんな、海坊主のところに案内しよう」
「お願いします」
「どこの温泉だい」
蟹が聞いた。
「竜宮岩の温泉だ」
竜宮の使いが振り向いて答えると、
「おいらたちも行くぞ」
白い蟹たちもぞろぞろと後をついた。
櫛水母と卵茸は竜宮の使いの後に浮かんでついていった。
竜宮の使いは振り向いて笑った。
「深海では変わったことが起きないからな、茸がこの深い海を訪ねてくると言うことなど、今まで聞いたことのない大事件だ」
みると、蟹だけではなく深海の海老や魚が後をついくる。
どんどん生き物たちが増えて、海底の大行進がはじまった。
真っ赤な深海蛸もいた。
「あら、深い海にも蛸さんがいる」
深海蛸がよってきた。
「あんた、あの眼鏡岩のじいさん蛸知ってるかい」
卵茸はこっくりとうなずいた。
「そのおじいさんが水母さんに頼んでくださって、私がここにこれたのです」
「あのおっちょこじいさん、あたしが深海にいることを忘れているんだよ、連絡してくれればあたしが連れてってやったものを」
「ありがとうございます」
櫛水母の緑の光が強く輝いて赤い蛸に言った。
「よかった、強い見方が出来た、一緒に助けてやってくださいね」
「それにしても驚いたね、こんなに生き物が集まったのははじめてだよ」
「この深い海に、こんなにいろいろな生き物たちがいるのね」
卵茸は周りの生き物たちを見て驚いている。
「そうだね」
深海の海底はふかふかと、土のような砂のようなものがたまっている。蟹や海老たちはその上を上手に歩いて行く。
やがて山が見えてきた。
「あれが竜宮岩だよ」
竜宮の使いは竜宮岩の裏にまわった。
卵茸たちが後をついていくと、その岩山の麓には石で囲われた場所があり、その底から暖かい水が噴出していた。海底温泉だ。
「お、暖かい」
蟹たちがぞろぞろと温泉のわき出るところに入っていった。後についてきた生き物たちも、入った。海老も、水母も、魚たちも一緒くただ。
ずぼっと大きな音がして、温泉に入っている深海の生き物たちの真ん中に、坊主頭の真っ白な魚が飛び出してきた。
「なんだ、こいつらは、落ち着いて温泉にもつかれないじゃないか」
そいつは、竜宮の使いをを見つけると、どなった。
「おまえだな、こいつらを連れてきたのは」
「へえ、すみません、勝手についてきてしまったので、卵茸の娘が海坊主様に会いたいというので案内してきました」
「なに、茸がこの深海まで儂を訪ねてきたのか」
海坊主は海底温泉から飛び出ると、櫛水母の抱える卵茸に顔を寄せた。
「卵茸にございます、お願いがありまして参りました」
「珍しい客だ、よくきたな、そうか、それじ、儂の家で話を聞こう、竜宮の使いも参れ」
「かしこまりました」
竜宮の使いは海坊主の家来である。
真っ白な海坊主は長い尾をゆらゆらと揺らしながら、もっと深い深い海の底に向かって降りていった。
海坊主は深海のさらに深い海の底に開いている穴に入った。
櫛水母に包まれて中にはいると、明るい岩屋になっていた。
たくさんの光る水母が浮いている。
「珍しいお客さんだよ」
海坊主が中に声をかけると、真っ赤な海坊主が顔を出した。
「おや、真っ赤な茸の子供じゃないか、珍しいお客だね」
「こいつは、俺の女房、海女(あま)坊主というんだ」
「こんにちわ」卵茸は櫛水母の中から挨拶をした。
「おい、櫛水母、ご苦労だったな、卵茸のお嬢ちゃんや、この部屋の中では水の重さは感じないから大丈夫、水母からでておいで」
卵茸は水母からでると、水の中に浮かんだ、ふわふわと、水母たちの間をただよって、海女坊主に近づいていった。プランクトンだわ、と卵茸は喜んだ。
「ほほほ、かわいいね、茸が水の中を水母と一緒に泳いでいるのはいいもんだ、それで、なにしに来たのだい」
海女坊主が聞いた。
「はい、赤い竜宮の使いを探しに参りました」
「なにをするんだい」
「妖術を解く薬をつくります」
そのわけを話した。
「だがね、赤い竜宮の使いとはねえ、会ったことがないね、もしいたとしても、殺しちゃうのは問題だよ」
「いえ、私にはそんなことはできません、きっと、赤と言うところに別の意味があると考えています」
「ほう、そうかね」
その時、海坊主が何かを思い出したようだ。
「お、そうだ、おまえ、俺が拾ってきた珊瑚を見せてやってみな」
「どうして」
「まあ、もってきな」
海女坊主がそれをもってくると卵茸に見せた。
「これは、海坊主が探してきてくれたんだよ」
それは白い珊瑚だった。
「ほれ、これをみな、この形は竜宮の使いに似ているだろう」
「あれま、確かにそうだね」
その白い珊瑚は竜宮の形をしていた。
「この珊瑚はな古い妖怪のような珊瑚でな、わしゃ深海珊瑚と呼んでいる。他所にはいないんだ。赤と白があってな、珊瑚が成長して死んでいくと、それが生き物の形になって下に落ちるんだ、赤い色の竜宮の使いに似ているやつが落ちているかもしれないぞ」
「それってなんでしょう」卵茸が聞いた。
「珊瑚はぽつぽつのなかにからだが入っていて、磯巾着のような触手を出している、硬いところで護られているわけだ。海岸に打ち上げられる珊瑚は死んだ珊瑚の殻なのは知っているだろう、ところが、その深海珊瑚は先っちょが死ぬと、空になった珊瑚が、生きものの形になって千切れるのさ、遊んでいるんだ、そのあとにまた新しい珊瑚が生えてくる」
「お前さん、そこに案内しなさいよ」
海女坊主が言うと、海坊主がうなずいた。
「そうするか、俺しか知らんのだよ」
「こんな海の底にも珊瑚があるのね」
卵茸が不思議そうな顔をすると、海坊主が説明した。
「そこはな、やっぱり温泉がでていて、一面がちょうどいい暖かなところさ、さっきの温泉とは桁違いにいいところさ」
「あたしも行きたいね」
海女坊主が言った。
「だがな、他のものには教えるんじゃないぞ」
「はい、言いません」
卵茸と櫛水母と竜宮の使いもうなずいた。
海坊主は自分の家の孔を出ると、深海のさらに深い海の底を泳いで、珊瑚の岩場にでた。そこに開いていた横穴に入ると、奥から明るい光がさしてきた。そこにいくと、洞窟の床が明るくなっている。
「ここはな、床が水晶になっていて、下から光が出ている、しかも暖かだ。なんでも甲斐の洞窟につながっているという話しだ」
「え、甲斐の洞窟ですか、もしかすると私の知っている洞窟です、、水晶の洞窟です、行きました」
「お嬢ちゃんは甲斐の火根山だったな、さぞきれいな洞窟だったろうな」
「はい、その水晶の奥の奥はマグマがもえていました」
「そうなのか、ここの水晶の下にもマグマが燃えているから明るくて暖かいんだな、不思議なところがあるものだと思っておったわい」
「神様でもご存知なかったのですね」
卵茸がいうと、海女坊主が大笑いした。
「この人が神様かい、生臭坊主にすぎないよ、竜宮の使いが何か勘違いして、神様扱いにするからいけないのよ」
「その大昔、私らは浅い海に住んでおったのだが、ゆったりしか泳げないわしらを食う鯨や鮫がたくさんおって、死に絶えるところだった。それを海坊主様が深海に住むようにしてくださり、生き延びたのです、だから神様にはかわりがありません」
「海坊主は子分がほしかっただけよ」
海女坊主はてきびしい。
水晶の洞窟を進んでいくと穴の壁ににたくさんの珊瑚が生えていた。色とりどりの珊瑚がところせましと岩にくっついている。床から出る光でとてもきれいだ。
「ほら、そこの珊瑚をごらん」
洞窟の壁のくぼみに特に大きな赤と白の珊瑚が枝を繁らせている。よく見ると、珊瑚の先がいろいろな生きものたちによく似ていた。その下には色々な形の珊瑚が落ちている。
「これが深海珊瑚なのですね」
「そうだよ」
「きれいだね」
海女坊主も珊瑚の周りを泳ぎまわった。
櫛水母に抱かれて卵茸もおちている珊瑚を見て回った。
「あ、赤い竜宮の使い」
卵茸が竜宮の使いの形をした真っ赤な珊瑚をみつけた。
「とってあげますね」と櫛水母は触手でそれをとって卵茸に見せた。
「そっくりです、きっとそれが探していた赤い竜宮の使いです」
「あ、こっちに、あたしそっくりなものもある」
櫛くらげがそれを拾った。
「おみやげに持っていったらいいですね」
「そうしましょう、みんなに自慢できる」
櫛水母はうれしそうに、拾った自分に似ている珊瑚を傘のなかにいれた。
「儂もみつけたぞ」
海坊主は海坊主そっくりな白い珊瑚をとり、海女坊主も自分にそっくりな緋色の珊瑚を拾った。
「おや珍しい、緑色の珊瑚があるぞ、大きく育っている、この間は小さかったんだ」
緑色の珊瑚が壁から生えていた。下には緑色の珊瑚が落ちている。
海坊主が、「蝙蝠そっくりなのがある、こんな小さな鼠のようなのもある」と落ちている緑の珊瑚を拾った。
「友達の、みやげにしなさい」と卵茸を抱えている櫛水母に手渡した。
「ほら、これも」
海女坊主が緋色の卵茸そっくりな珊瑚を見つけて櫛水母に渡した。
「ありがとうございます、これで、火根山に帰れます」
「よかったな」
「蛸のおじいさんが、海坊主さんに会ってお礼を言いたいと言っていました」
「ああ、あのおっちょこちょいのじいさん蛸か」
「ほら、白い蛸の形の珊瑚がおちてる、これをもっていってやんなさい」
海坊主が拾った。
「この珊瑚は珊瑚の死んだ姿なのですね」
「そうだな、深海珊瑚の死んだからだだよ」
「大切なものですね、ありがたくいただいていきます」
「珊瑚も役に立ったと喜んでいるさ」
「蝙蝠さんたちきっと心配している、もっといたいけどそろそろ帰ります」
「ああ、また遊びにおいで、お前さん、上まで送ってやりなよ」
海女坊主は海坊主の尾ひれをたたいた。
「そうだな、俺が送っていくよ、ついでに眼鏡岩の蛸じいさんに会って、蛸の珊瑚をやろう」
「茸と土産はわたしめが上まで持ってまいります」
竜宮の使いが珊瑚を櫛水母から受け取るとくわえた。
「お願いします。海女坊主のおばさん、櫛水母の姉さんさんありがとうございました」
卵茸は海坊主と竜宮の使いとともに深海の底からゆらゆらとのぼっていった。途中で、行灯水母や水水母に挨拶をした。
海坊主は最後にはすごい勢いで、海面に飛び出した。
海面では緑蝙蝠が飛び回っていた。
海坊主が空を指差した。
「緑色の蝙蝠が舞っているが、あれがお嬢ちゃんの守り役か」
「はい、緑蝙蝠さん」
卵茸が大きな声をあげた。
すると蝙蝠があわてて降りてきて、勢い余って海の中に顔を突っ込んだ。
「助けてくれ」
「世話のやけるやつだな」
海坊主はばたばたしている緑蝙蝠を海から引っ張りあげた。
「助かった」
緑蝙蝠は卵茸をみて海坊主の頭の上にかじりあがった。
「おお、良かった、お嬢無事だったか」
「はい、この海坊主さんのお陰で、赤い竜宮の使いも手に入りました。しかもお土産まで。竜宮の使いさんにはずーっとまもっていただきました」
緑蝙蝠は海坊主の頭にいることに気がついてあわてて舞い上がった。
「すまぬことをしました、お嬢をありがとうございました」
「なになに、たいしたことをしておらんよ」
「それに、私も助けていただいて、なんともお礼を申してよいやら」
「おぬし、もっと落ちつかぬと卵茸の娘さんを守るどころか、自分が死んじまうぞ」
「へえ、面目次第もありません」
「まあ、でもよかった、わしは、眼鏡岩の蛸の爺さんに会って帰るよ」
竜宮の使いが拾った珊瑚を緑蝙蝠に渡した。
「これはこれは、大事なものを運んでいただいて、ありがとうございました」
緑蝙蝠は受け取ると堅苦しく挨拶をした。
「まじめな蝙蝠だ、おれみたい」
竜宮の使いがつぶやいた。
「海坊主のおじさん、竜宮の使いさんありがとうございました」
「こっちも楽しかったよ、深海に茸がきたのは初めてだしな」
「海女坊主さん、水母さんたちに、よろしく伝えてください」
「ああ、伝えとくよ」
海坊主と竜宮の使いはは眼鏡岩に向かって泳いで行った。
緑の蝙蝠は茸と珊瑚をかかえると、崖の上の家にもどった。
「無事でよかった、お嬢良くやったものよ」
「皆さんに助けられました」
「これが赤い珊瑚の竜宮の使いか、」
「はい、深海珊瑚の死んだからだです」
「ふむ、やはり死んで残ったものだなあ」
緑蝙蝠はなにやら思うところがあるようである。
「これは蝙蝠さんにおみやげ」
「おや、珍しい、緑の珊瑚でできた儂じゃないか」
「これは私」
卵茸はもらった緋色の茸の形をした珊瑚を見せた。
「確かにな、かわいらしい珊瑚だ」
そこへ隣の部屋から、鼠たちが顔を出した。
「みつけたのかい」
「おお、お蔭さまでな、この茸のお嬢さんが、深海に潜って、見つけてきたのさ」
と、小鼠の形をしている珊瑚をわたした。
「こりゃ、我々とそっくりだ、うれしいね」
鼠たちがそろって顔を出した。
「きれいな珊瑚だね」
「お祝いだね」
こうして卵茸と緑の蝙蝠は、隣の屋根裏部屋で、拾ってきた珊瑚を真ん中において、鼠たちと一晩中歌を歌った
水無月ー箱根
緑蝙蝠は赤に染まった竜宮の使い、すなわち赤い珊瑚でできた竜宮の使いをブナの木の前の切り株に置いた。
「お嬢、冒険だったな、少し大きくなったようだ」
「はい、でも、怖くありませんでした、深い海の中にもあのようにいろいろな生き物が生活しているのです。みな親切で楽しい旅でした。」
「わしは心臓がどきどきしておった」
「すみません、でも、なんとしてでも赤い竜宮の使いが欲しかったのです」
「よくやったものだな」
色とりどりの火根茸たちが切り株の周りに顔をだした。
今回は緑の蝙蝠が、いつものように卵茸の姫様が赤い竜宮の使いを見つけるまでの話をした。茸が海にもぐるなど、さすがの火根茸たちも驚きと賞賛に傘を震わした。
あれから一月、水無月になっていた。
「さて、今度はどこだね、お嬢」
緑蝙蝠は切り株の上で考えにふけっている卵茸に聞いた。卵茸は殻から少し頭を伸ばし、大きくなっている。
「今度は箱根にいくことになります」
「ほう、また温泉かね、温泉が好きだねお嬢」
緑蝙蝠が笑った。
「いや、歌にそうあるだけで、赤岩を探して、そこの硫黄を持ってくるのです」
「そりゃあ、難しい」
「赤岩を見つければいいだけなので、そんなに難しくはないと思います」
「いや、お嬢、わからぬぞ、日が当たっても赤岩になるし、マグマの明かりでも赤岩になる、どれを探すことになるやら、全く違うものかもしれぬしな」
「確かに、緑蝙蝠さんの言うとおり、容易なことではないかもしれません。赤が何を意味するのか、硫黄は黄色いものなのになぜなのか、なにを示すのかわかりません、考えが足りませんでした、赤い竜宮の使いは、赤い珊瑚でした」
「箱根に行ってみなければ分からぬな」
「箱根の温泉に浸かってゆっくり考えたいと思います」
「やはり、お嬢は温泉がすきだの」
緑蝙蝠が笑うと、卵茸は少しはにかんだ。
緑の蝙蝠は卵茸を片翼にくるむと空に舞った。
夏に向かって少しばかり汗ばむほどの気候になった。
木々の濃くなってきた緑色が日の光を反射させて地上が緑一色に見える。
「きれい」
「そうだなあ、これが秋だったら、紅葉した木に覆われた岩も赤い岩になる」
「ほんとう、そうです」
箱根の山も緑に囲まれて輝いている。上の方では所々から蒸気が昇っている。
「ここは温泉らしい温泉だな、だが、我々の入れるような温泉がどこにあるかわからんな、人間が占領しているからな」
「そうですね、箱根の生き物たちに聞いてみましょう」
「ああ、箱根にはな、主みたいな生き物がいる」
「それは誰ですか」
「山椒魚だ、箱根山椒魚に会えれば、いろいろ教えてくれるだろう」
「どこに行けばいいのでしょう」
「きれいな流れを探せばあの一族は必ずいる」
緑蝙蝠は茸を抱えて流れを探し、一筋の透きとおった清い流れを目にとめると、その上を上流に向かった。途中で沢蟹が顔を出していた。
「この辺りで、箱根山椒魚に会えないかね」
「上のほうに行けばいるよ、たまにここまで降りてくることがある、一度話したことがあるが、気のいい山椒魚で、捕まえた小魚を半分くれたよ」
「そりゃいい山椒魚だ」
「なにしに行くんだい」
「赤い岩を探しにきたのだが、山椒魚に聞こうと思ってね」
「赤い岩ってたくさんあるよ、ほらそこにも」
沢ガニが鋏で示した。そこには流れから顔をだしている赤い岩があった。
「確かに、だが、赤い岩の硫黄がほしいんだ」
「硫黄か、そりゃ分からないね、箱根山椒魚は詳しいよ、おいらの会ったのは若いやつだったが、物知りの長く生きている山椒魚が奥のほうにいるよ」
「ありがとよ」
緑蝙蝠たちはさらに上流に向かった。だんだんと流れの幅が狭くなり、石の間をチョロチョロと流れるだけになった。しばらく行くと、石の間から山椒魚が顔をだした。
「おお、緑色の蝙蝠が卵茸を抱えているとはな」
「分けあって、赤岩の硫黄が必要なのだが、知らぬかな」
「何にするのかね」
卵茸の姫が今までのことを話した。
「大変なことだな、赤岩は沢山あるが、さて、どこのものかわからない、それに硫黄のことは知らないな」
「誰か詳しいものを知らぬかな」
「うちのひい爺さんなら知っているかもしれないがな」
「会わせてくぬか」
「それはいいけど、遠いところにすんでいる、別の流れの上流にいる」
「教えてくれぬか」
「東側の谷間を探してごらん、緑色の水の流れている小さな川がある。その上流にすんでいる、もう百年も生きている爺さんだ」
「会ってくれるだろうか」
「それは大丈夫だよ、面倒見のいい爺さんだ、うちの親父なんかわからないことがあると、まだひい爺さんに教えてもらいに行く、世話好きさ」
「それはありがたい」
蝙蝠は空に舞いあがると東側に向かって飛んだ。
「山椒魚ってもっと大きいかと思っておりました」
卵茸が蝙蝠の翼の中でもそっと動いた。
「箱根山椒魚はそんなに大きくはない、イモリやヤモリの連中と同じくらいだ」
「なぜか大きいイメージがあるのです」
「それは、大山椒魚だろう、あいつはでかいからな」
「私が、子供の頃、読んだ本のせいですね、岩に閉じこめられた山椒魚のお話、かわいそうだった」
「ほー、やっぱり人間はいろいろなことを考えるのだな、儂は万年茸、ただ床の間に飾られただけ」
「でも、私よりよっぽどいろいろ知っています」
「あの座敷で聞きかじったことだけだよ」
「お父様がいつもお客様をもてなしていたところだから、いろいろなお話が聞こえたでしょうね」
「ああ、お嬢ちゃんが障子を破いたのも見たね」
「あら、いや、はずかしい」
卵茸が身をよじった。
「そんなことはないさ、かわいいものだった」
そんな話をしながら飛んでいくと、川の石が苔に覆われた緑色の流れがあった。
緑蝙蝠たちは流れに沿ってすすんだ。奥深くに進むと、大きな岩がごろごろしているところに行き着いた。さらに岩の間を上流に向かって飛んでいくと、黒っぽい岩の上で大の字になり、腹をお日様に当てている山椒魚がいた。若い山椒魚よりかなり大きい。
「きっとあいつだ」
緑蝙蝠は黒い岩の上に降りると、山椒魚の脇に歩いていった。
山椒魚は起きあがろうともせずに、目玉を動かして、
「ほいさ、誰ださ、歩く蝙蝠はみっともないね」
わかりにくい発音で蝙蝠に言った。
「お初にお目にかかります、火根山の緑蝙蝠でございます、いま曾孫(ひまご)さんに会いました」
緑蝙蝠は卵茸を石の上においた。
「ふぁ、かわいい茸じゃ」
山椒魚は茸を見た。
「こんにちわ、教えていただきたいことがあって参りました」
「茸が口を利きよる、はじめてじゃ」
「赤い岩の硫黄を探しています」
「赤い岩か、赤かね、朱かね、紅かね、茜かね」と、山椒魚は赤を並べた。
「私は赤と聞いておりました」
「ふむ、赤か、赤い岩は箱根にはいくつもある、硫黄はどれにもある、ただ、おまえさんのいったのが、赤い硫黄だとすると、一つしかない、しかもなかなか現れない。硫黄は黄色いもの、温泉やマグマの蒸気が吹き上げて岩にたまったものか、岩の間にできた硫黄か、結晶そのものか、いろいろあるが、時として、黄色ではなく赤くなることがある。それはな、硫黄竜が吐き出す硫黄でな、滅多にあるものではない」
「硫黄竜って何でしょうか」
「それは、神だ、マグマの神だ、マグマが暴れないように見張っている神だよ」
「なぜ赤い硫黄を吐き出すのです」
「マグマに毒素がたまってな、赤い硫黄になる、その毒素がマグマを暴れさせる、地底の奥の奥にすんでいる硫黄竜はマグマにそれができると、飲み込むんだ、だから、硫黄龍はあの熱いマグマの中を泳ぐことができる」
「そんな竜がいるのですね」
「硫黄竜は神だ、マグマの火も治めている、色々な竜がいて空や水を治めているのもいる」
「マグマに赤い硫黄ができるのはどういうときですか」
「茸のお嬢ちゃん、それはなマグマをいじめたときだ」
「誰がいじめるですか」
「人間が地下にいらぬものを捨てたりする、そうするとマグマは弱るのじゃ」
「人間はそんな悪さをするのですね、私どもも考えねば」
「ちかごろ、人間が地の下によからぬものを大量に埋めておる、だいぶ硫黄竜は忙しいようだ」
「箱根で赤い硫黄がとれたことがあるのでしょうか」
「あるよ、もう数百年も前のことだがな、マグマの毒素を飲み込んでは、箱根の山に顔を出して、赤い硫黄を吐き出すので、そのときは至る所で赤い硫黄がとれたそうだ」
「その赤い硫黄はどこかにあるのでしょうか」
「それがな、空の龍の好物でな、硫黄龍が赤い硫黄を吐き出すと、いち早く空から駆け下りて食ってしまうのだ、食った空の竜は、空の上の上のほうにのぼり、空の星に向かって吐き出して宇宙に捨てるんだ」
「硫黄竜に会いたい」
「それは無理だろうな、何せ、あの熱い地下の地下にいるのだから」
「私たちは甲斐の水晶洞窟で、マグマが地上に近いところで燃えているのを見ました、深海の洞窟の中にもありました」
「おお、そうか、箱根にはそのようなところはないな、いや、まてよ、箱根の噴火口を探すとあるかもしれんな、儂たちは熱いのは苦手で、行ったことはないが」
「それはいい、お嬢、わしが飛んでいこう」
緑蝙蝠は卵茸に言った。
「私も行きます、つれていってください」
「あぶないので、やめたほうがよいかもしれぬ」
「大丈夫です、注意します」
「焼き茸になっちまわないようにな」
山椒魚の爺さんも心配そうである。
「私は深い深い海の底にも行きました。今度はマグマです」
「元気な茸さんじゃ、気をつけて行くんだよ」
「箱根山椒魚のおじいさんありがとう」
緑蝙蝠は卵茸を包んで飛び上がった。
強羅に向かい、噴火口にやってきた。硫黄の匂いが充満している。
「すごい匂い、私は大丈夫だけど、動物の緑蝙蝠さんは苦しくない」
「はは、蝙蝠だけど万年茸、大丈夫だ」
緑蝙蝠たちは熱い蒸気の噴き出す火口を飛び回った。どこもすさまじい勢いで蒸気がでている。とてもそんな中に入っていけるものではない。
「むずかしいの」
飛び回っていると、蒸気の出ていない穴が一つあった。猫の頭がやっと入るほどのほどの穴である。その周りの岩が黄色になっている。硫黄が噴出している証拠だ。ということは、中の奥の奥のほうでマグマが煮えたぎっているに違いない。
「蒸気がでていないけど、いつでるかわからない危険な穴だな」
緑蝙蝠は中をのぞき込んだ。
「おや、何だろう」
底に赤いものがちらっりと見える。穴から出る空気は熱くない。
緑蝙蝠は穴に手を入れて岩肌に触ってみた。
「全く熱くない」
「この穴はなんだろう、マグマの穴ではないようだ」
緑蝙蝠は目を凝らして穴の底を覗いた。
緑蝙蝠はあわてて顔を上げた。
穴の底から真っ赤な大きな眼が見上げている。
卵茸に言った。
「穴の底には何かがおる、赤い眼がわしを見た」
「その者はだれでしょう、硫黄竜の目ではありませんか」
「わからぬ、穴の底にいるとすると、硫黄竜かもしれぬな」
「私が降りてみましょう」
「それは無茶だ」
「でも、蝙蝠さんにはこの穴は小さすぎるでしょう」
緑蝙蝠は羽を広げると穴より大きかった。
「いや、翼を折りたためば入れないことはない」
「蔓を探してきてください、私をつるして下におろしてください」
「また、危ないことを考える」
「大丈夫ですやらなければなりません」
緑蝙蝠は長い間考えた。
「いたしかたがない、探してこよう」
緑蝙蝠は茸を下において山の麓まで飛んだ、林の中にいろいろな蔓が、それこそ木に無尽蔵にからみついている。
緑蝙蝠は蔓をとり、結わえあわせて強く長い紐を作った、さらに、蔓の先を編んで小さな籠をつくった。
それを持って卵茸のもとに帰った。
「蝙蝠さん、器用ね」
「いや、なんのこともない、お嬢がこの籠に入れば下に降ろす」
「すごい、また、楽しいことが起こりそう」
卵茸の姫は大胆である。
「なにが起きるかわからん、なにかったあったら、必ず大声を出しなさい」
「はい」
卵茸は籠に入った。
緑蝙蝠は蔓の一方を岩にくくると、ゆっくりと茸を穴の中におろしていった。
「どのようかな」
「大丈夫です、もっと早く降ろしてくださいますか」
「元気なお嬢さんだ」
緑蝙蝠ははするすると蔓をおろした。
どの程度降ろしたのだろうか、途中で止めることもできず、姫に任せた緑蝙蝠は、額に汗の粒を光らせていた。
「どこまで行くつもりなのか」
深海に下ろしたときより、緑蝙蝠は不安にかられた。
蔓がたるんだ。
「お嬢ついたのか」
小さな穴の入口から声が聞こえた。
「はい、大丈夫です。」
ところがその返事を最後に全く何の音もしなくなってしまった。
緑蝙蝠はしばらくがまんをした。しかし中から声は聞こえてこない。何度も叫んでも返答がなかった。
あわてた蝙蝠は蔓をあげた。軽い、卵茸が籠に入っていない。蝙蝠はしばらく考えあぐねていたが、翼を畳むと穴の中にもぐりこんだ。両手を踏ん張って、少しずつ下に降りていった。
卵茸はこんな状態だったのだ。
卵茸の乗った籠は次第に速さを増して降りていった。やがてぐにゃっと何かにめり込んで止まった。
卵茸は周りを見た。すると、大きな声が聞こえた。
「痛いじゃないか、眼の上おちてくるとは」
卵茸は籠から摘み出された。
「何で茸がこんなところにいるんだ」
卵茸は目を回していたが、やがて気がついた。
「どなたです」
「わしは竜だ、お前こそ誰なんだ」と声が聞こえた。
「私は、甲斐の火根山の者、茸にされた者にございます」
「それは、大神のなされたことだろう」
「硫黄竜の神にお願いがあります」
「確かに、わしは硫黄竜だが、誰に聞いてきたのだ」
「箱根山椒魚のおじいさんに教えていただきました。」
「あの爺さんか、あいつは物知りだし、山椒魚の大事な指導者だ」
茸はぐっと持ち上げられた。自分が竜の指で摘まれている。卵茸はちょっと身震いした。そこは広い部屋になっており、竜はとぐろを巻いて外に通じる穴をのぞいていたようである。
「ここで、なにをなさっていらっしゃたのでしょう」茸が聞いた。
「わしか、空をのぞいていた。たまに地底よりでてきてこの部屋の穴から空を見る。空の様子を調べているのだ、時々、空に眼が浮かぶ、空の竜だ、そいつから地球の様子を教えてもらうのだ」
「私は硫黄竜さんの眼の上に降りてしまったのですね、ごめんなさい、痛かったでしょう」
「蚊に刺されたほどだが、外が見えなくなったのが問題である」
「なんとしたら許してもらえるでしょう」
「許すも許されるもない、もうお前は自由ではないか」
「はい確かに、私は自由です。でもしなければならないことがある。私は赤い硫黄を探しています」
「何でだね」
卵茸は火根山一族のことを話した。
「ほー、そんなことがあったのかね、火根山のことは儂もしらなかった、どんな神の世界なのかね」
「私はまだ若くてなにも聞いていないのです」
「人を茸に変えることのできる神だ、儂らの力は及ばない世界なのだろうな、空の竜と水の竜に聞いてみるか」
硫黄竜は穴に向かって大声でほえた。
すると「うわー」と、大きな声がした。
部屋に何かが落ちてきて、硫黄竜の目の前で、「ぎゅう」と伸びてしまった。
「なんだ、こいつは」
卵茸は落ちてきたものをみると大声で叫んだ。
「きゃあー、緑蝙蝠さん、死んじゃいや」
「私は茸で動けない、硫黄竜さん助けて」
硫黄竜はその叫び声のあまりの大きさにびっくりした。
硫黄竜は床にのびてしまている緑蝙蝠のほっぺたをひげで叩いた。
「ほれ、おきろ、緑の蝙蝠とは珍しい、何で穴なんかに入ったんだ、危ないことをする」
「私を助けにはいったのです」
「お前さんの知り合いか」
緑蝙蝠のことを硫黄竜にくまなく説明した。
「そうか、まじめなやつよのう、この穴は飛び交うことができるほど大きくはない、きっと手と足を踏ん張って降りてきたのだろう、儂の声に驚いて落ちちまったんだな、それは可愛そうなことをした」
硫黄竜は蝙蝠に熱い息を吹きかけた。
蝙蝠がぴくっと動いて、首をあげ卵茸を見た。
「お嬢、よかったご無事で」
「はい、大丈夫です、危ないことをしないでください」
「蔓が緩んで、こりゃあお嬢が落ちちまったと思ってね、降りてきたのだがね」
蝙蝠は顔を上げた。そこで大きな蛇のような竜に気がついた。
「あ、竜の神様」
「私を硫黄竜のおじさんが、助けてくれました」
卵茸の話を聞いて緑蝙蝠は二本足で立つと、硫黄竜にふかぶかとお辞儀をして、卵茸に近寄った。
「硫黄竜の神様、ありがとうございました、お嬢、この竜は神様のお仲間で、おじさんなどと言うでないぞ」
「はは、そんなことはない、おじさんでもじいさんでもよいよ、わしの声でびっくりさせて悪かったな、この茸の娘と話していてな、どんな神が人を茸に変えたか空の竜に聞いてみようと思って吠えたのだ」
そのとき、穴の先に見えていた青空が真っ暗になった。
「ほら、空の竜がのぞいている」
「なんかようか、土の竜」
「ああ、ここにいる卵茸と緑蝙蝠のすんでいる火根山にいる神とはなんだ、お前知っているか」
「甲斐の火根山か」
「そうだそうだ」
「あそこの世界は儂等の世界ではない、この地球の未来が温存されている場所だ、その神は未来を司る神だ」
「だから人間を茸に変えたり、茸を蝙蝠にすることができるわけか」
「そうだよ、もし地球が滅びたとしても、火根山の生き物たちが次の地球の種となる。火根山一族はそれを守る役割の人間たちである。それが茸に変えられてしまったということは、未来の神の怒りをかったのだ、神の怒りを解く薬がある、しかし、それが見つからないと、別の生き物が未来の地球の主人となる」
「なるほどよくわかった。空の竜よありがとう」
「いや、最近火根山に何かあったことを、水の竜に聞いて、ちょっと調べてみたからだ、それよりも硫黄竜よ、おぬし火根山の水晶洞窟のマグマのことを知らぬとは」
「ああ、思い出したしばらく行っておらぬ、火根山のマグマには汚れたものがない、それに深海にも水晶の洞窟がある、そこのマグマもきれいなものよ、人間がうようよいるところの奥にあるマグマがよごれていてのう」
「確かにな、硫黄竜も忙しいな、俺も忙しい、空気の中の塵が増えた」
「確かにな、おたがい忙しいの」
「それじゃ、俺はいくよ」
空の竜の目玉が消えた。
「聞いたとおりだ、火根山の森は大変な役目を持っているわけだ」
「ところで、硫黄竜の神様は土の神様でもあるのですか」
「ははは、硫黄竜はニックネームだ、本当は土の竜という」
「どうしてですか」
「赤い硫黄を食うからだよ」
「土の竜の神様、赤い硫黄をいつ吐き出すのですか」
赤い茸が聞くと、土の竜は口をとがらして、ひゅっと赤い硫黄を吐き出した。
「ほらあげよう、もっていきなさい、汚れて死んだマグマだよ」
「あ、赤い硫黄、ありがとうございます」
「最近マグマが弱っていてな、人間のやつ土の奥深くに危ないものを捨ておる、それで、未来の神が怒ったのかも知れぬな」
「はい、私どもが茸から戻ったときには、そのようなこと止めさせます」
緑蝙蝠は赤い硫黄を拾った。
「外に出してやろう」
土の竜は緑蝙蝠と茸を手の上に載せると強く息を吹きかけた。茸と蝙蝠は息に押し出され穴の外に飛び出した。
そこには、空の竜がとぐろを巻いて宙に浮かんでいた。
「目的を果たしたようだな、茸の娘、蝙蝠もご苦労」
「はいありがとうございます。空の竜の神様」
「なに、どうってことはない、これからもがんばって人間に戻る薬を探しなさい」
「はい、しかし、もし人間に戻れなくても、他の生き物が主となれるなら、あまり心配がいらないことがわかりました」
「そうだな、えらい考えだ、それでは儂は帰る」
「空の竜の神様、なぜ我々が出てくるのを待っていたのですか」
「ちょっと、かわいらしい茸のお姫さんを見てみたかっただけだよ」
空の竜は照れて空に消えていった。
「竜の神様はみんなかわいい」
卵茸はつぶやいた。
「緑の蝙蝠さん、ありがとう、また助けていただきました、でも危ないことはしないでください」
「お嬢こそ気をつけてもらわなくてはな、無茶をするでないよ」
緑蝙蝠は卵茸を優しくくるむと宙に浮かびあがった。
「火根山に帰って、未来の神に許しを請わねばな」
「はい、そうします」
文月ー尾張
箱根の山から火根山の森は近かった。
空の上から見る文月になった火根山の森は緑が濃くなり、甲斐といえども温かな風が林の中を通り過ぎていく。いろいろな草が花をつけはじめて、虫が舞っていた。
ブナの木の前の切り株に卵茸と緑蝙蝠が降りたった。
蝙蝠は切り株の上に赤い硫黄をおいた。
火根茸たちが顔をだした。卵茸の娘は空の竜の話を伝えた。茸たちは無言で未来の神に人間の行いを懺悔した。
すると、いきなり、林の中に大きな水色の竜が現れた。
「あ、水の竜の神様」
卵茸は頭を垂れた。火根茸も同じように竜に向かって頭をたれた。
「水の竜の神様が、なにようでございますか」
緑蝙蝠がたずねた。
「空と土の竜から聞いた、努力をしているそうな、努力をすればするだけお前たちの未来も明るい、ただ、火根山の神がどのような判断を下すかは儂らには分からぬ、次元の違う神である、じゃが、今のように努力すれば悪いようにはならぬであろう」
「ありがとうございます」
「確かに、空の竜が言うのも分る、卵茸の娘はかわゆいの」
そういい終えて水の竜は消えていった。
「お嬢、竜の神が現れたということは、お嬢の力が強くなってきたことだ、きっと元に戻ることができるだろう、火根茸の皆の衆ももう少しがまんしてくれ」
火根茸たちは深深と二人に向かってお辞儀をした。
「さて、次はどこか」
「尾張名古屋の赤い栗です」
「名古屋か、名古屋城だな」
「でもどこの栗なのでしょう、なぜまた赤なのでしょう」
「まずは、行ってみないとわからんな」
緑蝙蝠は卵茸をくるんで舞い上がった。
名古屋は遠くない、信州を越して駿河に出ると、ちょっと海の上を飛んでいけば尾張である。
名古屋城の本丸はかなり大きい。城内も広く多くの木がのびのびと枝を茂らせている。緑蝙蝠は一本の大きな木の枝に降りた。
「ここの蝙蝠たちに聞くことにしよう、夜まで一時休むとするか」
緑蝙蝠はしばらく寝ることにした。
卵茸は寝るということをしない、木の上から城の庭をながめていた。
ある時、卵茸に緑蝙蝠が言ったことがある。「万年茸だった自分は寝るということがなかった。動物の寝るという行為は実にすばらしい、寝ている間はなにも見ず聞かず静かだ、起きたときには気持ちがさっぱりとしている」
そのときはそんなものかと思っていたが、卵茸は今、寝てみたいという気になった。茸でも寝ることができるのであろうか。
卵茸は心をどのように閉じることができるのかわからなかったが、むかし禅の和尚さんに瞑想の仕方を教わったことがあった。座禅を組んで眼を閉じ、頭の中を無にするのである。今卵茸はそれをやってみた。
できそうである。眼を閉じることができないのは大変だが、入ってくるものの意味を考えないようにすることはできないことはない、それをやってみると、だんだん入ってくる光と音は遠ざかり、暗闇が迫ってくると、音も消えた。卵茸はその暗闇の中に入りこんでいった。
どのくらいたったかわからないが、緑蝙蝠が、
「逢魔が時だ」とつぶやいた。その声で、卵茸は瞑想からもどった。
「本当、寝るというのは気持ちがいい」
「お嬢は大したもんだ、茸なのによく寝ていたようだ」
「はい、座禅をしたときを思い出しました」
「万年茸に戻ったときには、座禅とやらを教えていただこう」
「はい、とても気持が落ち着くものです」
城の庭内には人影がなくなり、たくさんの蝙蝠が飛び始めた。
緑蝙蝠はそばを通りかかった蝙蝠に声をかけた。
「教えてほしいことがあるのだがね」
「おや、緑色の蝙蝠とはしゃれてるね」
黒い蝙蝠が緑蝙蝠の脇に止まった。
「何を知りたいっていうんだ」
「尾張の赤い栗ってなんだかわかるかね」
「いきなり言われてもね、天守閣に住んでいる白蝙蝠のじいさんに聞くといい、真っ白な蝙蝠で、もう何百年も生きている」
「いきなり行っても大丈夫かね」
「ああ、退屈してるからな」
どの生きものも年をとるとすることがなくなり、暇をもてあますのである。
「ありがとうございます」
卵茸が頭を下げた。
「緑色と、茸の嬢ちゃんの真っ赤な傘はよくマッチしているね、白蝙蝠の爺さんが喜ぶよ」
黒い蝙蝠は虫を求めて飛びたった。
緑蝙蝠は卵茸をくるんで天守閣にむかった。金の鯱が夕日に照らされてまぶしい。
天守閣を一回りして白蝙蝠の住んでいそうなところを探したが、それらしいものは見つけることができない。
「おかしいな、確かに天守閣にいると言っていたが」
「私もそう聞きました」
もう一度回ってみるか、緑の蝙蝠は茸を抱えてゆっくりと飛んだ、一周してもやはりいなかった。
とその時、頭の上から声がした。
「緑の御仁、なにをやっているのかな、その赤いものはなんじゃ」
飛びながら上を見ると、金の鯱の口のところに何かが蔓下がっている。
蝙蝠である。明らかに白い蝙蝠である。金色に溶け込んで分かりにくい。
「そちらに行ってもよいでしょうか」
「もちろん、この城は儂のものではない、自由じゃ」
緑蝙蝠と卵茸が金の鯱の脇に降りると、白蝙蝠は逆さのまま、
「なんだ、卵茸の子どもじゃないか」と目をしょぼしょぼさせる。
「はい」
「それに緑の蝙蝠とは珍しいの」
「初にお目にかかる、火根山よりまいりました」
「ご苦労じゃが、何をしに来たのかな」
「名古屋の赤い栗を探しにまいりました」
「してまた、どうして赤い栗がいるのかな」
そこで、卵茸はいきさつを話した。
「ふむ、名古屋と栗とはな、どのような謎が隠されているのか、ちと面白い、考えてみよう」
「尾張名古屋は城でもつと聞いたことがあります」
「人間が言っていたことだな、確かにこの城は大きく目立つ、立派でもある、だが、もっと落ち着いた尾張として誇る城があるのは知らぬかな」
「はい、名古屋の他の城のことは知りません」
「犬山城といってな、小さな城だが、木曽川の畔の高台に作られたよい城だよ、そこに、私の親父がいる。白蝙蝠一族は、全国の城に必ず一匹いるのだよ、だが、犬山城にいる蝙蝠はすべて真っ白な、白蝙蝠一族だ、城ができれば必ず誰か一匹がそこに行く、城がなくなれば、犬山城にもどるのだ、犬山城は白帝城という名でも呼ばれるが、それは我々がつけた名前じゃ」
「犬山城に赤い栗はあるのでしょうか」
「それはわからんがな、おやじに聞いてもらうとなにかヒントがあるかもれぬぞ」
「ありがとうございます」
「緑蝙蝠よ、緑は森のことであろう、とすればそなたは森を守る蝙蝠ではないかな」
「いえ、万年茸でございます」
「万年茸は森を守るものじゃ、万年茸が緑蝙蝠になったのか、それは何か重要な意味があるに違いない、先ほど、卵茸から事情は聞いたが、卵茸も大事な役割があるに違いない、茸は地の下を治めるものなのだ」
「はい、ゆっくりと考えてみます、ありとうございます」
緑蝙蝠と卵茸は暗くなった空に飛び上がった。
犬山城は名古屋城から北西の木曽川ぞいにある。小高いところに築かれた城で、眼下にゆったり流れる木曾川が楽しめる。
「すてきなお城」
蝙蝠の翼の中から卵茸が言った。。
「城の屋根に降りるとしよう」
名古屋城のように鯱があるわけではないが、古い瓦が蒼然と並んでみごとである。
降り立ってみると、屋根の瓦の上で白い蝙蝠がこっちを見ていた。
「来なすったな」
白い蝙蝠はよちよちと歩いて茸たちに近寄ってきた。
「お初にお目にかかります、緑蝙蝠にございます」
緑蝙蝠は腰を低くして挨拶をした。
「あ、いや、あんたがたが来ることは息子が知らせてきましたじゃ、探しているものも聞いたがな、尾張名古屋の赤い栗とな、栗はいたる所にあるが、赤い栗とは栗ではなく他のことを意味しているのだろうよ、火の中にくべた栗はぱちんとはじける、じゃが、赤くはならん、赤い石で作った栗や、日の光に透けて見える栗や、いろいろあるが、名古屋に結びつくものはないようじゃな、ただ、犬山には栗栖という地域がある。そこには栗栖神社があり、猿たちがたむろしておる。栗栖とは反対の方向になるが、本宮山というきれいな山があり、そこに住む猿たちが病にかからぬよう栗栖神社に三日にあげず参拝するのだよ。その神社は宇(う)麻(ま)志(し)麻(ま)知命(じのみこと)を祀っておるのじゃ。そこの猿に聞くとなにか知っておるかもしれん、行ってごじゃれ」
「はい、ありがとうございます、行きたいと思います」
「探すのも面倒であろう、わしも暇じゃ、あないしよう」
白い蝙蝠はよたよたと飛び上がった。
緑蝙蝠も卵茸を抱えて飛び上がった。
「よい景色じゃろう、犬山城はよいところに作ったものよの、ところで、かわいらしいそなたは緑蝙蝠のなんじゃな」
白蝙蝠は飛びながら卵茸に聞いた。
それに緑蝙蝠が答えた。
「卵茸は私の主人のお嬢さんで、私は守る役目を仰せつかっている」
「とんでもありません、緑蝙蝠さんは私の先生です、何でも知っています、今までもたくさん教えてもらって、助けていただいています」
「そうか、深い縁なのじゃな」
そういいながら、のんびりと白蝙蝠は飛んでいく。
「猿はどこじゃい、猿はどこじゃい」
白蝙蝠は栗栖神社の上にくると、境内に呼びかけた。
すると、神社の一本の木から、「ここにいるぞ、白蝙蝠のじいさん」と声がした。
「おーそこにいたか、今降りるからな」
神社の樫の木の枝にはたくさんの日本猿が顔をならべていた。
「久しぶりじゃな、皆元気そうだ」
「じいさんも元気そうで、それで、今日は何の用だい」
白蝙蝠と緑蝙蝠は猿たちが腰掛けている枝に降りたった。
「この御仁たちに話を聞かせてやりなさい、きっと何か知っておる」
「こんにちわ」
緑蝙蝠の翼から卵茸の赤い頭が現れた。
「おや、卵茸の子どもじゃないか」
猿たちが驚いた。
「わけがありまして、赤い栗を探しております」
「赤い栗をどうするのだ」
「私たちが元に戻る薬を作ります」
ここでも卵茸は今までのことを話して聞かせた。
「すると、あんたは人間で、そこの緑の蝙蝠は万年茸って言うわけか、面白いね、赤い栗はこの神社の宝物の中にあるかもしれん」
「宝物はどこにあるのですか」
「それはちょっと言うことができぬ、我々もその宝物が入っている箱は開けたことがない、本宮山の長老たちを集めて意見をきこう」
「たのみますだ」
白蝙蝠は言った。
「ちょっと時間をくれぬか、その間、この神社の中で寝泊りしてもかまわぬよ」
「それじゃ、わしも、しばらくこの御仁たちと、神社に住まわせてもらおう」
「そうしてくれ、我々は一端、本宮山に戻って、長老たちと相談して戻ってくる」
猿たちはそう言うと、本宮山に向かって走っていった。
「行ってしまった、猿たちの会議は長くかかるから、ゆっくりと羽を伸ばして、神社で休むことだ」
それから毎日そのあたりを散策し、木曽川の水の流れを楽しんだ。
白蝙蝠の言ったとおり、時間がかかり、八匹の年をとった猿が栗栖神社に現れたのは五日後であった。
一匹の年寄り猿が言った。
「本宮山の猿たち全員一致で協力することに決めた。まず宝物の入っている箱を開けることにする。もう何百年も開けていない、だから誰も何が入っているか知らないのだ、赤い栗があるかどうかもわからんが、それでよいな」
「はい、ありがとうございます、見せていただければ、それから考えたいと思います」
猿たちは、栗栖神社の縁の下から、板を持ち上げて本堂に入った。
大きな栗の形をした鏡がご神体であった。
「栖というのはな、巣と同じで、住処なのだ、だからこの神社は栗の住処ということになる」
ご神体に下に大きな葛(つ)籠(づら)があった。
猿たちはご神体をおろし、葛籠の蓋を持ち上げた。
「あやや、ここにあったのか」
猿の長老が目を見張って叫んだ。
葛籠の中には赤い紙に包まれた薬がぎっしりと詰まっている。
猿の長老が一つの包みを開けた。朱色の半透明の固まりが入っている。
「これはなにかな」
白蝙蝠が興味深そうに覗き込んだ。
猿の長老が喜びを隠しきれないように笑顔で説明をした。
「これは、本宮山に生えている一本の古い栗の木から浸みだした樹液が固まり、何百年もかかって熟したものだ。毎年その木の幹に樹液が吹き出て固まる、それは我々の薬になる貴重なものだ、それが時をかけ熟すと薬の効力が強まり、我々猿の活力をを強くする特効薬になる。我々の言い伝えでは、その昔、祖先が作ったものをどこぞへしまったとある。しかし、その場所を示した図が紛失して、どこなのかわからなかったのだ、本宮山にあるものと思っておった」
「きっとこれが、赤い栗です、一かけらいただけないでしょうか」
卵茸が頼んだ。
「もちろんじゃ、お前様たちが来なかったら、ここにあることが分からなかった、こちらこそお礼申そう」
「わしら蝙蝠にもよいのじゃろうか」
猿の長老は頷いて、一かけらずつ緑蝙蝠と白蝙蝠にわたした。
「その一かけらで、何千もの者たちの病気が治る」
長老の猿たちはそれぞれ一かけらずつ手に取ると、葛籠を元のように戻した。
「我々は本宮山の猿の八つの部族の長なのだ、これからこれをもって帰り、病人、老人に分け与える、もちろん我々もいただくのだ」
「元気な猿は飲む必要はないのだな」
緑蝙蝠が尋ねると、猿の長老は首を横に振った。
「いや、若い猿も、子猿も、ほんの小さなかけらだが分け与える」
「どうなるんだい」
白蝙蝠が聞いた。
「病人は狂った体調が元に戻る、病気でない年寄りは若返り、若いものは、もっと元気になる。元気になれば食べ物もうまい、水もうまい、子供も作りたくなる」
「ほー、それはいい」
「それにな、二日酔いが直る、だから若い猿たちは、栗の木のできたての樹液の固まりをみつけたその夜は、酒盛りをして、騒ぐのだ、次の日の朝、その樹脂をほんの少し水に浮かしてみんなで飲むと、二日酔いがなくなる」
「若い樹液でもそんな効果があるのだな」
「じゃが、やはり、すごいのはな、年を経て熟した樹液の固まりを火にあぶって、溶かし、硫黄とともに混ぜて固まらせた丸薬を飲むと、なくなった身体の一部が元に戻ることだ、妖薬じゃ」
「それはどういうことですの」
卵茸が聞いた。
「言い伝えであるが、片目を竹に突き刺して見えなくなった小猿に、その妖薬を飲ますとな、だめになった眼がぽろっと落ちて、新しい眼が生えてきたということだ。身体が元に戻るのじゃ」
「すごい薬、再生の薬ですね」
「そうなのだ、この妖薬が手に入ったからには、本宮山の猿は皆健康に暮らせる」
「すてき、そんな大事なものいただいてすみません」
卵茸がまたお礼をいった。
「大丈夫だ、見た通り、あんなに沢山ある、悪さをしない生き物たちにも分けてやろうと思う、人間にはやらんがね」
「はい、だまっています」
「おーそうだ、卵茸は人間だったな、黙っていておくれ、人間が知ったら大変だ」
「はい、言いません、一つお聞きしたいのは、なぜ大事な葛籠を開けてくださったのでしょうか」
卵茸は不思議に思っていた。
「それはな、お前さんの話に空、水、土の竜に助けられたことがあったからじゃ、あの神々は決して意味のない人助けはしない、きっと、そなたたちが、火根山の未来の神とやらと関係があるからじゃろう、お前さんがたに協力するのはきっと、この世この星に幸をもたらすことになると信じたからじゃ」
「ありがとうございます、私たちも自分たちのことを知りません、このご恩は無駄には致しません」
「よいよい、さて、白蝙蝠のじいさまにお二人さん、我々のすみかに来ないかね」
猿の長老たちは笑顔で白蝙蝠と緑蝙蝠、それに卵茸を誘った。
「おお、是非行きたいね、酒を飲むのかね」
白蝙蝠は嬉しそうである。
みんなして、猿の住処に行った。
それは本宮山の中腹にある林の中の泉の脇にあった。岩にいくつもの穴があいており、そこに住んでいるのである。
「猿酒はいつでもたっぷり用意してある」
若い猿たちがよってきた。猿の長老は宴会の準備をするように言いつけた。若い猿たちは穴の奥から酒の入った瓢箪を持ち出してきた。
猿の造る猿酒は動物の間では有名である。他の動物では造ることができない。
若い猿たちも泉の辺で車座になった。
「さて、今日は客人がいる、犬山城の白蝙蝠の長老と、甲斐火根山の卵茸の姫に緑蝙蝠だ、長い間探していた本宮山の栗の樹脂の妖薬を見つけてくれた恩人である。その薬が手に入ったからには、病はいえ、怪我は治る」
猿たちは瓢箪に入った酒の回し飲みを始めた。
白蝙蝠も緑蝙蝠も瓢箪を一つずつわたされた。
「こりゃうまい、噂に聞いた猿酒じゃ」
白蝙蝠はすぐに口をつけ、舌なめずりをした。
「甘いいい匂い」
卵茸は飲めないけれどに匂いを嗅ぐことができた。
「そうだ、茸のお姫さんは飲めないな、おい、若いの、器を持ってこい」
猿の長老が言った。
「へい」若い猿が穴から、お椀のような形の石をもってきた。
「ほら、酒をそそいで、茸を入れてやれ」
猿の長老が言った。
「ちょっと待ってくれ、姫は酒を飲むには若すぎる」
「なんと固い緑蝙蝠だ、悪いことは早いうちに経験させるほうがいいんだぞ」
白蝙蝠が笑っている。
「お嬢、ちょっとだけだぞ、気持ちが悪くなったら言うんだぞ」
緑の蝙蝠がしぶしぶ卵茸を抱えて中に入れると、猿の大将が猿酒を注いだ。
「あれ、気持ちがいい、暖かくなって、ふわふわしてきた」
卵茸はますます赤くなった。
「栗の新しい樹液をその中に少し入れてやれ、二日酔いにならん」
猿の長老の言葉で、若い猿がとってきた栗の樹液を木のへらで茸のはいっている器の中にいれた。
赤い樹液は酒の中に溶けて、酒が赤くなった。
「身体がどこかにいってしまいそう、あれー」と声を上げると、卵茸の笠がするすると伸びた。
「お、卵茸が壷から伸びた」
白い蝙蝠は仰天びっくり、猿たちもびっくり、大喜び。
「卵茸が大きくなった」
だが、卵茸は何にも言わない。
「お嬢、大丈夫か」
緑の蝙蝠が尋ねても何とも言わない。
緑の蝙蝠は大きくなった卵茸を器から出して、木の根本に置いた。
「きれいな茸だな」
猿たちも卵茸の周りによってきた。
白蝙蝠と緑蝙蝠は猿たちと一晩中酒を飲んで楽しんだ。
林の中に朝日が差し込み卵茸を照らし出した。
大きくなった卵茸の頭がふらふらとゆれて、
「あー、いい気持ち」
と声を発した。
「お嬢、酔ったのか」
「瞑想の世界にいました、何か背が高くなったよう」
「お嬢はずい分大きくなった、薬が効いていきなり大きくなったのだ」
「そういえば高いところからものを見ているよう、ほんとう、でもまだ傘は開いたていません」
「赤い栗は今まで集めたものの中で最も強い薬になりそうだ」
「茸って気持ちがいいものね、今までわからなったけれど、空気をこんなに感じることができるし、土の香りのすばらしいこと」
「茸は土の中と土の上のどちらも自分の世界だからな」
「茸はすてき」
「さて、お嬢、甲斐の火根山に帰るとしよう」
「はい、猿のみなさん、白い蝙蝠のおじいさん、ありがとう」
「達者でな、うまいことやりなよ」
猿と白い蝙蝠は明け方になってもまだ猿酒を飲んでいた。
緑蝙蝠は少し大きくなった卵茸を壊さないようにそうっと、翼でくるんだ。
ふわっと浮かぶと、すーっと、今までとは違った飛び方で,甲斐の火根山に向かって行った。
葉月ー下関
火根山に戻って、もう半月が経つ。
八月の熱い空気が火根山をつつみ、緑蝙蝠と卵茸は火根茸といっしょに、林の中で静かにしていた。切り株の上の集めたものの中には、赤い栗、すなわち栗の木の樹脂が熟したものが加わっている。再生に大事な薬になる。
赤い栗によって背の伸びた卵茸の傘はまだ饅頭型で、姿はひょろりとしている。
「お嬢、傘の下の柄が少し細くなったが、折れちまう心配はないのか」
「大きくなると傘が開いてもっと細くなります。、細いけれどとても強いのです」
そう言って、卵茸は、自分から傘を地面すれすれまで曲げて見せた。
「ほお、からだを曲げることができるようになったな」
「ええ」と、頭をぴょこっとあげると、その拍子に、卵茸のからだが、ぴょんと前に進んだ。
「あれ、前に進むことができた」
卵茸は頭を折り曲げて、ぴょこっと起すたびに前に進んだ。
「私、自分で動くことが出来るようになりました」
「確かだ、歩く茸になった」
緑蝙蝠が感心した。
「私も前より少しは役に立つかもしれません」
「いや、今までも大した働きだ、ここにある薬はみんなお嬢がみつけたのだよ」
「いえ、緑蝙蝠さんや神さま、それにいろいろな生きものたちに助けられてきました」
「それは、卵茸のお嬢が神がかってきたからだ」
火根山の夏は他のところより涼しいが、それでも太陽の光は茸たちを暑くほてらせる。
「どこも夏は暑いが、そろそろ出かけるのも良いかもしれん、お嬢はどうだ」
「はい、私もそう思っておりました」
「次はどこだったかな」
「下関に行きます」
「おう、そうだった、海ならば少し涼しいかもしれん、河豚の奴だな、河豚のなにを探すのかな」
「赤河豚の心臓です」
「きっと毒があるのだろう、毒は薬になる」
「私もそう思います」
緑の蝙蝠は少し成長した卵茸を抱えて飛び上がった。
富士の上に舞い上がった。
「富士山きれい」
「やっぱり日本一だなあ」
「あの歌は富士山も入っていたと思うけれど、どのようにはいっていたのか覚えていないの、きっと、最初か最後に、富士の山というのがあったと思うのだけど」
「大事なことじゃないのか」
「ええ、そうかもしれない、だけのあの歌を歌うとき必ず富士山がでてくるわけじゃなかったの」
「どんなときかな」
「それが、よく思い出せないのだけれど、お父様が今年は富士の山を入れて歌うようにって言ったときに、その年は必ず富士の山を入れたと思うの」
「どういうことかな」
「いつか思い出すのではないかと気にしています」
蝙蝠と卵茸は富士山を横切ると、太平洋側にでて、日本を縦断した。
赤い栗をもらった尾張名古屋を過ぎ、大阪、京都、広島、そして山口にでた。鍾乳洞のあるカルスト地形を下にみて、横切ると日本海側から下関にむかった。
下関の海岸に達した緑蝙蝠と卵茸は海の向こうの門司の陸地をながめた。
「向こうはもう、九州なのですね」
「この関門海峡にはいろいろな河豚がいるのだろう」
「河豚に聞いてみなければ、赤河豚の意味がわかりません」
「そうだな、また海の中だ」
緑蝙蝠は海沿いの漁師小屋に入った。捨てられ朽ちかけている小屋である。
「河豚にはすぐに会えるだろう、また赤い色であったな」
「はい、赤河豚の心臓です」
「今までの経験だと本当の心臓ではないかもしれぬし、赤河豚といっても、赤くないかもしれぬ」
「はい、その通りです」
「明日の朝早く、海に行くとしよう」
その日は漁師小屋の中で、ゆっくりと波の音を聞いていた。
夜になって、小屋の中に大きな鳥が入ってきた。
その鳥は緑蝙蝠と卵茸を見ると、首をかしげた。
「おや、お前さん、どうしてここにいるのだい」
部屋の中で緑蝙蝠に気がついた鳥は鳶であった。鳶は大きな翼を広げた。
「鳶の親分、甲斐火根山の緑蝙蝠にございます、勝手に小屋に入りまして、申し訳ございません」
「いや、むしろ、俺の方が後に来たので侵入者だ、だが、今日はよろしく頼む、あの雲行きだと、大風が吹く」
「そうですか、よろしくお願いします」
卵茸が挨拶をすると、鳶の親分は驚いた。
「茸の少女がいるとは思わなんだ、蝙蝠の連れか」
「私が使えるご主人でございます」
緑蝙蝠が卵茸を紹介した。
「甲斐というのは本州の中程だろう、遠いところから何しに来たのかね」
「赤い河豚を探しに来たのです」
「赤い河豚とは何のことだ、皮を剥かれた河豚のことか」
「いえ、わかりません」
建てつけの悪い小屋には隙間から風がひゅーっひゅーと入ってきた。
「暑い夏の風は湿り気が強い、特に大風の時にはそうだな、強い風になりそうだ、この小屋とてわからないぞ」
そこへ数匹の蟹が入ってきた。赤手蟹である。
「おお、先客さんがいますな、おや珍しい、茸もいるじゃないですか。あたしゃ、茸の種類にゃ疎いんだが、なんとおっしゃるのかい」
「卵茸と申します」
「そっちの緑の蝙蝠がご主人ですかな」
「滅相もない、わたしは卵茸のお嬢さんをお守りする家来ですよ」
緑蝙蝠が首を振った。
「いや、私の家来なぞではありません」
卵茸は頭を振った。
「まあ、どうでもいいが、蝙蝠と卵茸の取り合わせって言うのは、いわくがあってのことだろう、苦労してるって顔に出てるよ」
「わしもそう思うよ」
「おや、鳶の旦那もそう思いなさるかね、でも旦那はずいぶんしゃれてらっしゃる、トンビなのにワシとは」
「なにを言っているんだ、しゃれでいったんじゃないよ、この蟹のばあさんは」
赤手蟹は鋏を鳶に向けて振りあげた。
「婆さんではない、まだ八十年しか生きていない、ここにいるのはみんな女の姉妹だ」
「婆さん蟹の集団か」
「口の悪い鳶だ、だがな、かなり風が強くなりそうだ、一晩仲良くしよう」
「そうだな」
大きな鳶も小屋の隅にうずくまった。
「ところで、どうして茸がここにいるのかね」
蟹のばあさんたちは興味しんしんで卵茸を見た。
卵茸は今までの冒険の話を皆に聞かせた。
「そんなことがあるのだねえ、ということはお前さんは人間だね」
「はい、そうです」
「元に戻るためにがんばっているんだね、茸のままもいいよ人間より」
「私はかまいませんが、ほかの火根茸たちは、人間に戻してあげなければなりません、私の役目です」
「それで、赤い河豚の心臓を探しているのか」
「明日、海に行ってみるつもりです、深い海の中に行ったこともあります」
「大したものだね、茸なのに海の中に入ろうなんて勇気のいることさね」
「蛸、水母、魚の皆さんみな親切でした」
「海の中は大風がおさまってからだね、海の底はお手の物だ、関門海峡には平家蟹って親戚もいるしね、手伝えることがあればやってやるよ」
「蟹のばあさんたち退屈なんだろう、空の上からたまに見ているが、海岸の岩陰に集まって、いつもぐちゃぐちゃしゃべっているじゃないか」
鳶が笑って言った。
「婆でうまそうではないから食わないんだ」とも言った。
「やだよ、食べちゃ」
「食わんよ、それより、だいぶ風が強くなってきたが、この小屋はもつかね」
「今回の大風は大きそうだね、屋根が吹っ飛ぶかもしれないが、なんとかもつんじゃないかい」
「そうか、それじゃ、このままいるか」
「それがいいさ、あれこれしてもだめ、覚悟しなきゃ」
「ところで、蟹のばあさんは赤い河豚ってわかるのかい」
鳶が聞いた。
「赤い河豚なんて知らないよ、だけど、赤い心臓なら知ってるよ」
「ほーそりゃなんだい」
「突然変異だ」
「難しい言葉をしっているじゃないいか、ばあさん」
「ばあさんばあさんってうるさいね、せめて、おばあさんぐらい言えないのかい、このすっとことんび」
「ああ、悪かったばあさんじゃない、おばあさん」
「そういえばいいのさ、蟹の血は青い、だから心臓も青い、だけどね、中にゃ、赤い血の蟹がいてね、そいつの心臓は赤いんだ、なかにゃそんな風に生れるのもいるのさ」
「そんな蟹がいるんだ、じゃあ、河豚にもそういう奴がいるんだろうな」
「魚の血は赤い、だから心臓は赤い」
「それじゃ、河豚の心臓はみんな赤いんじゃないか」
「そうさね、ということは、赤い心臓のことじゃないね、やっぱり、赤い河豚を探すんだね」
そこに強い風が小屋の中に吹き込んできた。小屋がミシミシと音を立てた。
「こわいね、雨が降ってないだけいいけどね」蟹たちは角に固まった。
「心臓って本当に心臓のことしら」
卵茸が言った。
「そういやあ心臓っていうのは、真ん中の大事なもののことでもあるな」
緑蝙蝠は納得してうなずいた。
「そうだよ、河豚に聞いてみなきゃわからんな」
蟹がそういったとたん、大風がはいってきて、大きな音とともに屋根が吹っ飛んだ。
「あれえ」
卵茸が雲が深く垂れ込めた暗い夜空に舞い上がった。卵茸はどんどん上に巻き上げられていく。蝙蝠が飛び上がって追いかけたが、風がじゃまして追いつかない。
「よっしゃ、まかしとけ」と鳶が舞い上がった。
いつもの勢いで空に上ると、すごい勢いで追いかけていった。しかしなかなか追いつかない、茸はぐんぐん上に上っていった。風が急に止まった。
「あれー」
卵茸は真っ逆様に、関門海峡の海の上に落ちていった。
鳶もあわてて急降下した。それをみていた蝙蝠も卵茸の落ちた方に向かった。
しかし、二匹とも卵茸を見つけることができなかった。
海面に落ちた卵茸は海に浮かんで波に大きく揺れていたが、荒れた海はとうとう卵茸を飲み込んだ。卵茸は海底に向かって沈んでいく。
海底の岩の間に卵茸が挟まった。
海底は穏やかではあったが、いつものように、海の水は勢いよく流れていた。
卵茸は荒れた北の海や、日本海の深海にまで行ったことを思い出していた。それは寒い時期だったが今回は真夏、海の水は冷たくない。それだけは助かっていた。しかし、潮の流れの早い海の底である。どこに連れて行かれるか分からない。
卵茸は岩の間から吸い出され、転がりながら流されていくと、長い海草がたくさん生えているところに入り込んだ。海草にからまって、卵茸はやっと一息ついたのである。
どのように戻ったらいいか思案に暮れていると、
「なんだ、こんなところに、茸がからまってら」
という声が聞こえた。
何匹もの小さな河豚がよってきた。河豚の子供たちである。子どもたちは卵茸を口で突っついた。
「あれ、突っつかないでちょうだい」
卵茸が身をよじった。
「この茸話ができるぞ、どこから来たの」
一匹の子河豚が尋ねた。
「甲斐の国の火根山からきたのよ」
「なにしに」
「赤河豚さんを探しにきたの」
「赤河豚さんに会いたいの」
「赤河豚さんいるのね」
「うん、おい等たちの先生、おばあさん」
「会いたいな」
「会えるよ」
「そいじゃ、ついておいで」
河豚の子供たちは一列になって藻の中を泳ぎ始めた。
卵茸は身体を折ったり伸ばしたりしてみた。何とか海の中を動くことがでるようだ。懸命に子供たちの後を追った。
陸では大風が吹いているというのに、海の底の長い海草が茂っているところはなんと静かであろう。
やがて、海草の間から大人の河豚がたくさん顔を出した。
「坊主たち、なにしにきたのだ」
一匹の大きなじいさん河豚が聞いた。
「茸のお姉ちゃんが、赤河豚のおばあさんに会いたいんだって」
「茸なんぞ海の中にいないぞ」
「ほら」
じいさん河豚が振りみると一番後ろから、赤い茸が身体を前後に揺らしながら進んでくるのが見えた。
「おや、ほんとだあ、赤河豚のばあさん、茸がきたよ」
じいさん河豚が海草の中に声をかけると、真っ赤な河豚がユタユタと出でてきた。
「おーや、ほんとに茸がきた、卵茸じゃないか」
赤河豚のばあさんは喜んだ。物知りのばあさんは茸が卵茸であることを知っていた。
「海の中は殺風景、赤い色は貴重だよ、卵茸の姉さん」
「はい、河豚のおばあさんきれいですね」
「そうだろう、あたしゃこのあたりじゃ一番きれいな魚なんだ」
そう言うと、プーと膨れて大きくなった。赤い風船みたいでとてもきれいだ。
「わーきれいね」
卵茸がほめると、赤河豚のばあさんはますます膨れた。
じいさん河豚がそれをたしなめた。
「調子に乗ると、この間のように破れるよ」
「破れたことがあるのですか」
「あるある、何度もある、ほめられるとすぐ調子に乗って膨らむので、破れちまう、でも数日で治っちまうからすごいね」
赤河豚はほめられると喜ぶ癖があるようだ。
「もう止めな」
じいさん河豚が大きな声を出した。
「なんだいびっくりするじゃないか、これからがいいところなのに」
赤河豚はしゅーっとしぼまった。
「それで私に何のようなのだい、茸の姉さんは」
「赤河豚の心臓って何でしょう」
「え、私の心臓かい、そりゃ、心臓だから、赤い血をからだに送っているものさ」
「そうですね」
「どうしてそんなことを聞くのだい」
そこで、茸はことの顛末を話した。
「ありゃ、いやだ、お前さん、あたしの心臓をもっていこうっていうのかい」
「いや、そういうつもりはありません、きっと、別の意味があると思って、ここに来ました、赤い河豚さんなんていると思っていませんでした」
じいさん河豚が口をはさんだ。
「そういや、赤河豚のばあさん、お前さん、昔拾ったものがあったな」
「あの赤い得体の知れないものかい」
「ちょっと見せてやれよ、ばあさん」
赤河豚は海草の中に潜ると、赤い固まりを口にくわえてきた。それは、ハートの形をしたものであった。
「あ、心臓」
「どうしてこれが心臓だい」
「人間の心臓はこのような形をしているのです」
「でも、これは海の底で拾ったんだ」
じいさん河豚が言った。
「何百年も前にこのあたりに棲んでいた人魚の心臓じゃないかと、わしゃ思ってるんだ」
「人魚の心臓はこんなに堅いのかい」
「わしは、昔聞いたことがあるぞ、人魚が死ぬと、心臓が固まって、希望の石になるっていうことだぞ」
「それじゃ、これが、人魚の心臓なのかしら」
卵茸が聞くと、赤河豚のばあさんはちょっと首をかしげていたが、
「そうかも知れないね」
と言った。
「これなら、あたしが持っていても、役に立たないしお前さんにあげるよ」
「でも、こんな大事なものもらえない」
「気にしなくていいよ、拾ったものさ」
「嬉しい、ありがとう、河豚のみなさんありがとう、ぼおやたちもありがとう」
卵茸は目があったら涙を流したかった。と思ったらかさの下のほうから雫が出たようだが海の中ではわからない。
「赤河豚のおばあさん、お礼をしたい、欲しいものはありませんか」
「あたしゃ、子供たちに囲まれてほんとに幸せで、欲しいものなどありゃしない」
といいながら、赤河豚のばあさんちょっと考えた。
「欲しいもんなんてないけど、一度、空からあたしたちが棲んででいる海を上から見てみたいと思ったことがあったね」
「それじゃ、戻ったら、みんなに相談します」
「無理なことさね」
「私には空を飛ぶ友達がいます、きっと心配していることでしょう、でも、私一人では戻れません」
「心配要らないよ、みんなで送っていくから、だけどまだ上は大風だ。それが収まるまで、ぼおやたちと遊んでやってよ」
「喜んで、それじゃ遊びましょ」
子河豚たちがよって来た。
「はーい、それじゃ、ふくらましっこのコンテストをやるから、審査委員長をやって」
「なーに膨らましっこって」
「僕たちが、膨らむから、誰が一番膨らんだかきめてよ」
「いいわよ」
「一等賞は、茸を突っつくこと」
「くすぐったいけどいいわよ」
と、河豚の子供たちは思い切って膨らんだ。
さて、関門海峡の海の底でそんなことが起きているとはつゆも知らない蝙蝠と鳶は、強い風にあおられながら、海の上を探し回った。
一晩中探したが、茸は見つからない。
「どこに落ちたのだろう」
緑の蝙蝠はくたくたになりながら屋根が吹き飛んだ小屋に戻った。
蟹のばあさん達がすみっこで固まっていた。
「茸の娘はどうしたい」
「海に落ちていなくなっちまった」
緑蝙蝠はぐったりとして蟹の脇で横になった。だが心配で寝ることができない。
「流されちまわなければいいのだけどね」
鳶も疲れて横になった。
蟹のばあさんたちも心配して口から泡を吹いた。
「まあ、ともかくご苦労だったね、しばらくお休みよ、朝になったら探しに行こうじゃないか、あの茸の娘は強い力を持ってるから大丈夫だよ」
朝になると大風がぱたっとやんだ。日が海から昇った。嘘のように海はないで海面には細かな白波がたっていた。
緑蝙蝠は無言で飛び上がった。
「俺も手伝うよ」
鳶も飛び上がった。蟹のばあさんたちもぞろぞろと海岸に向かった。
空に舞った蝙蝠と鳶は海岸近くでになにやら動めいているものを見た。
「河豚が集まっているぞ、なにをしているのだろう」
目のいい鳶がそう言って近づいた。蝙蝠も後をついて降下すると、河豚がぞろぞろと海岸に向かって泳いでいる。その中に真っ赤な河豚がいて、背中に茸が乗っていた。
「お、茸の娘さん無事だ、河豚の上に乗ってるぜ」
鳶が叫んだ。
緑蝙蝠は大声を上げた。
「おーい卵茸のお嬢、ここだ」
卵茸が気がついた。手があれば振りたいところだ。
「緑蝙蝠さん、鳶さん、河豚さんたちに助けられたの、しかも、赤い河豚さんから心臓をもらいました」
「なんと、そりゃ、よかった」
「それで、赤河豚さんが、空の上から海を見たいそうです」
「そりゃ、たやすいこと、少しの間なら水からでても大丈夫だろう、連れていってやるよ」
「大丈夫だよ、死んでもいいよ」
赤河豚のおばあさんが大声を出した。
「元気がいいね」
「あったりまえよ」
河豚たちは海岸線に来ると、茸をぽーんと放り投げた。蟹のばあさんたちが、茸を受け止めた。
「よかったね」
「はい、ありがとうございます」
「オーい、蟹さん、これももってってくれ」
じいさん河豚が人魚の心臓を砂浜に放り投げた。
「おーや、珍しい、これが、赤河豚の心臓か」
「赤いふぐのおばあさんが拾った人魚の心臓なんです」
卵茸はそういって海に向かって声を上げた。
「赤河豚さん、みなさん、坊やたち、本当にありがとう」
「がんばんなさいよ」
河豚たちが大きな声で言った。
茸は蟹につれられて、屋根のとれた小屋にもどった。
海の上では、空中旅行が始まった。
鳶が海の水面まで降りてきて、「空に連れてってやろう」
と、赤河豚ばあさんの尾っぽをくわえた。
「ひょう、空中旅行なんて生きているうちにできると思わなかったよ」
赤河豚はつるされながら嬉しそうに背鰭を揺らして膨らんだ。空飛ぶ風船だ。
鳶が空の上のほうに昇ると、海面がきらきらと光った。
「海はきれいなものだねえ」
「ああ、だいじょうぶかい」
「まだ大丈夫、もうちょっとだね」
かなり上まで上って、河豚が「もうだめだ」と目を回した。
あわてて鳶が海面に向かって急降下した。
ボチャンと音がして赤河豚が海に落とされた。
そのとたん、赤河豚のばあさんは正気に戻って空に向かって言った。
「あー、きれいだった、ありがとさん、子供たちにも見せたいね」
「よっしゃ、わしにまかせろ」
緑の蝙蝠が一匹の子供の河豚をくわえて空に上った。
「わー、すごい」
蝙蝠は代わる代わる、子供たちを空の上に運んだ。
鳶はじいさん河豚を空に運んだ。
こうして、関門海峡の河豚は空から自分の棲む海を見ることができたのである。
しばらくして鳶と蝙蝠が小屋に戻ってきた。蟹のばあさんたちと卵茸が、赤い心臓を真ん中にして輪になっていた。
「鳶さん、緑蝙蝠さん、ありがとうございました」
「いや、お嬢、心配した、元気に戻ってきてよかった」
緑蝙蝠は疲れた様子で壁に寄りかかった。鳶も壁に寄りかかり言った。
「ああ、わしも面白かった、あの河豚たち大喜びだった、河豚の子供たちにとってとてもいい経験だったろうよ」
「ほんとに、ありがとう」
「あの赤河豚のばあさん元気だったな」
「すてきな河豚さんたちでした」
緑蝙蝠が赤い心臓を見て言った。
「あの赤河豚のばあさんの心臓ではないな」
鳶が、「まさか、二つある一つをくれたってわけじゃないだろう」とまんざら間違っていないだろうと思いながら言った。
「ほんと、と言いたいところだけど、そうではありません」
茸はみんなに、赤河豚が拾った人魚の心臓であることを説明した。
「そりゃあ、珍しいものをくれたね、人魚の死んだ心臓か、希望の心臓なんだね」
「はい、人間に戻る希望の大事な心臓です」
「大事な薬だね」
「みなさんに助けていただいたおかげです、ありがとうございました」
「動物は助け合わなきゃ、大風の縁だよ」
「蟹のおばあさんいいこというね、これから蟹のばばさまと呼ぶか」
「もっと悪いじゃないか、口の悪い鳶だね、どっかにおとんび」
「ダジャレがにばあさん」
茸と緑蝙蝠は笑いながら鳶と蟹と別れ甲斐に戻った。
長月ー阿波
火根山の森も秋の風情が色濃くなってきた。火根茸たちは土に潜ることなく、いつも顔を出していた。いろいろな茸に混じって、火根茸たちも気を使うことなく、秋の風を受けている。虫たちの歌声も一日中森の中にこだましている。
ブナの前の切り株の上には集まったものがならべられている。
緑蝙蝠が切り株に止まって、集まった物ををながめていた。
「ずい分集まったものだ、次は何だったかね」
「はい、赤い平家蟹です、本当は下関から戻らないでそのまま行くつもりでした。しかし、長月は茸の月、顔をだしているみなに会いたくて戻りました。やっかいをかけてすみません」
「なに、大したことはない、姫はそんなに気を使わなくてよいぞ」
「泡踊りの平家蟹だから、きっと、関門海峡の反対側、下関からすぐの、門司の平家蟹なのだと思います、またあちらに行かなければなりませんがよろしくお願いします」
「だがな、土佐の阿波踊りじゃないのかね、平家蟹はそちらにもいるだろう」
「そうですね、蝙蝠さんの言う方通りかと思います。薬は全国から集めたものから作ります。四国にはまだ行っていません、阿波に行きましょう」
緑の蝙蝠は卵茸をつれて徳島に向かった。
富士山の上を通り、海沿いに西に向かうと、懐かしい名古屋をこし、京都を通り、大阪を通り、岡山にきて、海にでた。鳴門の渦をみながら四国に渡り、徳島の海岸に降りた。
ここでも漁師の漁具がしまってある小屋を宿とすることにした。
「さて、まずここいらの海岸にいきませんか」
二人は小石の海岸に降り立つと、歩き回っている船虫に赤平家について聞いてみた。
「知らんな、平家蟹はかなり深いところにいるんだよ」
船虫は忙しそうに首を横に振った。
小石の間から蟹だましが大きい方のはさみを振りかざして出てきた。
「きいていたぞ、おりゃあ知ってる、酒の好きな平家蟹がいてな、そいつは酒を飲むと真っ赤になる。今は土佐の海にいる」
「阿波の国ではないのですか」
「昔の話だが、阿波の国の一部は土佐になったことがある、今は徳島だがな、そのころ土佐にいた平家蟹だよ」
「それじゃ、土佐に行けばあえますか」
「約束はできないが、もう何百年も生きている蟹だから、どうなったかわからんよ」
「ありがとうございました」
蟹だましはもそもそと、ふたたび小石の下にもぐっていった。
「緑蝙蝠さん、土佐に飛びましょう」
「ああ、そうしよう」
緑蝙蝠は少し成長した茸を包み込んだ。
土佐に飛んだ蝙蝠たちは高知城に降りた。
高知城は大きくはないが、素朴な、昔の生きものたちの匂いのする城であった。
ここでは猿が造ったものではないが、人間が大量の酒を作って楽しんでいた。城の持ち主が酒を理解する無類の酒好きであった。。
高知城の一番てっぺんの軒に降りた緑蝙蝠と茸は、とても落ち着いた気分になって、町の中を眺めていた。
「赤平家というのは平家蟹のことなのかどうかもわからぬな」
「ではなにでしょう」
「難しい、平家にまつわる何かかもしれないが」
「でも平家にまつわるものなら、下関か門司でしょう」
「うむ、そうか、ここではやはり平家蟹か」
「まず海にいかなければならないでしょう」
うなずいた緑蝙蝠は卵茸を翼でくるんだ。
高知城を飛び立った卵茸と蝙蝠は瀬戸内海の海岸についた。
「さて、どのように探したらいいか」
卵茸はからだをくねらせて蝙蝠の翼から石の上に飛び降りた。
「いつものように、ここにすんでいる鳥や虫たちに聞きましょう」
緑蝙蝠はちょんちょんとはねると海岸の岩の上を進んだ。
卵茸もからだを弓なりにしてぴょんぴょんと跳ねながら後をついていった。緑蝙蝠が振り返った。
「お嬢、歩くのが上手くなった」
「でも、疲れます」
「そうであろうな、からだをくねらせるのは大変だ、わしなにはできぬ」
緑蝙蝠が磯だまりの中を覗きこんだ。
緑色の筋の入ったきれいな磯巾着が半透明の触手を長く伸ばしくねらせている。 「磯巾着のお嬢さん、ちょっとものを尋たいがいいだろうか」
磯巾着はいきなり触手を縮め怒鳴った。
「わしゃ、じいさんじゃ」
「そりゃ、失礼を、あまりにも綺麗で、優雅なものだから、てっきり、お嬢さんかと思っちまいまして」
「そういう一族なんじゃ、、それで何のようだ」
磯巾着は機嫌を直したようで、また長い触手を伸ばしてくねらせた。
卵茸が磯たまりを覗き込んだ。
「赤平家をさがしております」
磯巾着がびっくりした。
「なんと、茸が口を利いておる」
「はい、未来の神によって、このような姿に変えられました」
「未来の神がなぜそのようなことをしたのだ」
「我々火根山一族にお怒りになったのです」
「未来の神はなんと言ったのだ」
じいさん磯巾着は触手を縮めた。
「私にはわかりませんが、未来の壷の蓋を開けようとした者がいたために、人間から茸にされてしまいました」
「ふむ、ようするに、お役目に逆らったわけだ」
「はい、お怒りになりました。これも試練です、元にもどす方法が言い伝えにあります、それに従って、必要なものを集めております」
「その中に、赤平家があるわけじゃな」
「はい、それで平家蟹かと思いまして、この海岸にやってきました」
「知り合いの蟹を呼んでやるから聞いてみるといい」
磯巾着は触手を伸ばして踊るように動かした。
すると、小さな貝たちがぞろぞろと、潮だまりからはいでると、海の中に飛び込みはじめた。
「御化(おばけ)貝たちじゃ」
「おばけ貝って、はじめて」
卵茸が小さな貝に近寄った。
「あ、やどかりさんたち」
磯巾着が言った。
「そうも呼ばれているな、御化貝たちは、海の中で、蟹の元締めを捜してくれるじゃろう、元締めはちょっと深いところにおってな、時間がかかる、明日の今頃、ここに来れば元締めの居場所が分かるだろう」
磯巾着は触手を振った。
「明日まいります」
緑蝙蝠は卵茸を抱えて飛び立った。
「お嬢、時間もあるし、土佐の町を見てみるかい」
「はい、四国の景色はどうでしょう」
目の下には高知城を中心に町が広がっている。
「何か、ゆったりとしていていいですね」
「酒の香りが強い町だ、飲兵衛が多いとみえる」
「ほら、あの川の脇で何かしている」
男たちがそれぞれに柄杓を手にして車座になっている。
「見物とするか」
緑蝙蝠は川岸に生えている大きな桜の木の枝に止まった。
卵茸も枝の上に乗って男たちのしていることをながめた。
男たちは、じゃんけんを始めた。何度かじゃんけんをすると、一人が、柄杓をもって、真ん中においてある大きな樽の中の酒をすくって、ぐーっと飲んだ。
「うまい」
その男は声を上げた。
また、じゃんけんをし、今度は別の男が柄杓でしゃくってぐーっと飲んだ。
「あれは何をやっておるのだろう」
緑蝙蝠は不思議そうにつぶやいた。
「私にはわかります」
卵茸が説明をした。
「じゃんけんと言って、みんなで同時に、手を前にだします。そのとき、指をすべて丸めたのが、ぐー、石です、すべて広げたのが、ぱー、紙です、指を二本だけ出したのがチョキ、はさみです。グーはチョキに勝ち、チョキはパーに勝ち、パーはグーに勝ちます。それで勝つものを決めるです」
「なるほど、勝ちを決める面白い方法だな、さすが人間だ、だったら、戦などじゃんけんにしまえばよいのに」
「蝙蝠さんは平和主義者なのですね」
「主義などはないが、どのような男でも、じゃんけんに勝てばが酒が飲めるというのは公平に思えるが」
「男の人たちが、遊びながら飲んでいるのです、でもじゃんけんに負け続けると飲めない」
最初に飲んだ男が、また柄杓もって樽からすくった。
「ついている男よのう」
他の男たちが言っている。
「ああ、あのように、得する者もいるのだな」
「得すると言うより、運がいいというのです、偶然ですから、誰でも納得するわけです」
「確かにな、力が強いとか、頭が回るとか、そう言う個人の能力が関係なくなるわけだな、我々動物は、それが生き死にに関係してくるが、人間はそのようなことがらを排除してものを決める能力を持っているわけだな」
「確かにそうですね」
「茸や植物は、その環境に適した者が強い者になる、ところが環境が変われば弱者だった植物が繁ることもある」
「そうですね」
「それにしても、酒をよく飲むことよ」
「土佐の男はそうなのですね」
その後、蝙蝠と茸は土佐の町の中を飛び回って見て回った。かなりにぎやかな町であったが、酒の匂いがいろいろなところから漂ってきた。
蝙蝠たちが、再び川辺にもどってくると、じゃんけんをしていた男たちがむしろの上で大いびきをかいている。
「幸せよのう」
「ほんとうに」
「お嬢、樽の中にはいってみよう」
空になった大きな酒樽が空に向かって口を開けている。底に掬い取ることのできなかった酒が少したまっている」
「飲みたくなりましたか」
卵茸が緑蝙蝠の顔を見た。
「犬山城の猿と白蝙蝠のじいさんたちを思いだすのう」
「あの猿酒はおいしかった」
「お嬢には初めての酒だったな」
二人は酒樽の底におりた。たまっていた酒が蝙蝠の足をぬらした。茸も酒に浸かった。
「お、美味い酒だ」
蝙蝠が口をつけて酒を吸った。
「気持ちがよくなってきました」
酒が浸み込んでいった橙色の卵茸は、子供の頃のように真っ赤になった。
「いい気分だ、土佐の男たちはこんな美味いものをいつも飲んでいるのか」
その時、一人の男がが樽の上から中をのぞいた。
「蝙蝠と茸が酒をくらっておる」
大きな声を上げ、仲間の方を向いた。
その隙に、緑蝙蝠は茸を包み込むと、大急ぎで樽から空中に舞い上がった。
下を見ると、目が覚めた男たちが樽をのぞき込んでいる。
「お主、酔っぱらっておるなあ、何もおらんじゃないか」
男たちが笑っている。
緑蝙蝠と卵茸もその様子をみて、笑いながら高知城に戻った。
「おお、うまい酒だった」
緑蝙蝠は天守の軒下で横になった。
眠ることのないはずの卵茸も緑蝙蝠によりかかって寝てしまった。
明くる朝、二人は気持ちよく目が覚めた。
「よく寝ました」
「ほんとだ、気持ちのよい日だ」
朝日の輝きにに高知城が包まれている。
蝙蝠と茸は海岸に飛んだ。
潮溜まりでは緑色の磯巾着がのんびりと触手を伸ばしていた。
「おー、来たな、蟹の元締めと連絡がついたぞ、もうすぐ、来るといっておる」
御化貝たちも顔を出した。
「宿借りさんたちありがとうございました」
卵茸がお礼をいうと、一匹の御化け貝が貝から身を乗り出した。
「初めて茸にあいました、かわいい植物ですね」
「植物ではないのです。動物でもないのです。茸の世界の住人です」
「動物でも植物でもないのですか」
「ええ、動物は動物界に生き、植物は植物界に生きて、そして、茸は菌界に生きているのです」
そんな話をしていると、沖の方から、赤い大きな生き物がのしのしと歩いてきた。
「蟹の元締めが来なすった」
緑色の磯巾着が言った。
近づくにつれ、それがとてつもなく大きな蟹であることがわかった。
「高足蟹の親分だ、世界で一番大きな蟹なんだよ」
磯巾着が言った。
高足蟹は三メートルもあろうかと思われる長い足を岩場にかけた。「よいこらしょ」と掛け声を上げて、潮溜まりの脇にのぼってきた。青空に見上げるように立ち上がった。
「磯巾着のじいさんが呼んでいるというのできたよ」
高足蟹はそう言うと、脇にいる緑蝙蝠と卵茸に気がついた。
「こんなところに茸と蝙蝠とは珍しい」
「いや、この二人が、赤平家に会いたいというのでな、呼んだのじゃ」
「赤平家とな、どうしてあやつに用があるかな」
高足蟹は卵茸に聞いた。卵茸は今までのいきさつを話して聞かせた。
「なるほどな、赤平家蟹は自堕落蟹だ、こまったことに、土佐の雰囲気に飲まれて、酒がないと生きていけないようになってしまった、そこで酒を断つように、深い海の底で、おとなしく生きるようにいいつけてあるのだ。ただ満月の日にだけ飲んでも良いと言ってある。たまたま今日は中秋の名月、この機会に酒を飲ましてやろうと思う、どうだ、酒は手に入るか」
「はい、何とか探してまいります」
「それでは、夜になったら、ここに参れ、わしも赤平家を連れてこよう、わしも一緒に楽しませてもらう」
「分かりました、いい酒を探してまいります」
緑蝙蝠は高足蟹に約束をした。
高足蟹は「たのんだぞ」と言い残し、海の中に沈んでいった。
「それでは、お嬢、酒を探してこよう、磯巾着の爺様、感謝しておる、おぬしの酒も用意する」
「楽しみにしておるぞ」
磯巾着は触手を広く伸ばした。
蝙蝠と茸は空中に舞い、土佐の町中にでた。人間たちが朝の食事を用意する煙があがっている。一軒の家をのぞいていみると、夫婦が朝食を食べていた。
脇に徳利がおいてあり、口にひもが付いていた。
食事が終わった夫は席を立って別の部屋に行った。嫁の方は食器を持って台所に向かった。蝙蝠はその隙をねらって、ひもをくわえると、徳利を持ち上げた。そのまま、窓から家の外にでて、海岸に向かった。
潮だまりの磯巾着が「もう、酒をみつけたのか、たいしたものじゃ」と触手を動かした。
「もっと持ってまいる」
「わかった、たくさんもってきて儂にも飲ましてくれ」
「お嬢、ここにいてれ、わしが探してまいる」
「そうですね、私がいると、徳利をもってくるのが大変です、私はしばらく磯で遊んでいます」
緑蝙蝠は卵茸を磯巾着のいる潮溜まりの脇に置くと再び飛び上がった。
緑蝙蝠の姿が見えなくなると、卵茸はぼちゃんと、潮溜まりに飛び込んだ。
驚いたのは磯巾着である。
「あ、大丈夫か、茸が海に落っこちた」
ところが、、卵茸は潮溜りの中で体をくねらせて泳いでいる。
「れれ、茸が泳いでおる」
「泳げるのよ」
大きいのや小さいのや、たくさんの御化貝がよってきた。
潮溜まりの海の水の中で、卵茸はくにゃくにゃとからだを動かして、泳いだ。海栗や海星も驚いた。
御化貝が、「卵茸に貝を持ってきてやろうよ」と、海の中に入っていった。
やがて、空の白い芋貝を持ち上げて、もどってきた。
「卵茸のお嬢さん、この貝はどうだろうね」
岩の上におかれた芋貝に卵茸がもぐりこんだ。
「素敵、いいおうち、ありがとう」
「お椀のような貝はないかしら」
「あるよ、なにするの」
「お酒を入れるの」
「よし、見つけてこよう」
御化貝たちは、さすが専門家である、お椀のような貝殻をたくさん拾ってきた。
茸は御化貝に言った。
「どなたか、貝のお椀に、お酒をいれることができるかしら」
「海の中の大将にたのもう」
一匹の小さな御化貝が海の中にはいっていくと、すぐに、大きなサザエの殻をしょった御化貝が何匹も現れ、磯の上に上がってきて徳利の酒を貝のお椀に注いだ。
「いい香だがまんできないね」
ヤドカリが、はさみを酒の中につっこみ、ちょいとなめた。
「旨いね」
「後でみんなで飲みましょう、たくさん入れ物を探してください」
ヤドカリたちはいろいろな貝殻を拾ってきて、岩礁の上に並べ酒を注いだ。。
「ワシも飲みたい」
緑磯巾着が触手を思い切り伸ばして海面の上にだした。だけどお椀に届かない。
「よしきた」
それを見ていた大きな御化貝が、潮溜まりにはいって、磯巾着をはさみで岩からはがした。
「ほら、緑磯巾着の爺様を持ち上げるから誰か受け取ってくれ」
そう言って、海面に磯巾着を持ち上げた。磯の上にいた御化貝が受け取ると、酒が入った貝のお椀にポチャンと落とした。磯巾着は酒の中に沈んだ。
「おー、しみる、旨いねええ」
磯巾着は酒に囲まれ上機嫌になり、触手をうごめかし、とうとう真っ赤にかわった。
「なんだ、磯巾着のじいさんもう飲んでるのか、梅干磯巾着になっちまったな、酒は美味いか」
蝙蝠が徳利を抱えてもっておりてきた。なぜかよろよろとしている。
磯巾着は上機嫌で「もっともってまいれ」などと酔っ払っている。
「緑蝙蝠さん、お疲れの様子、ありがとうございます」
卵茸がお礼をいうと、緑蝙蝠はお椀に入った磯巾着に気がついた。
「磯巾着のじいさん、もういい気分だな」
「はは、そうじゃよ、おかげでな」
蝙蝠は徳利から空いている貝のお椀に酒を注ぐと、また、空に舞い上がった。
「どんどんもってくるからな」
「どこからもってきたのです」
「土佐の人間はどこの家に行っても酒徳利がおいてある、いい町だ」
そういいながら飛んでいった。
その後、蝙蝠は何度も往復して酒を運んだ。
夕方になり、よろよろと降りてくると、緑蝙蝠は徳利の酒を貝殻に移した。たくさんの貝殻がお酒でいっぱいになった。
緑蝙蝠の目が赤い。
「緑蝙蝠さん酔っ払ってる」
卵茸が気がついて笑った。
「すまん、片手でお嬢を抱えているときには出来なかったが、片手が空いていたのでつい、飛びながら徳利を傾け、なめちまった」
「おいしいお酒なのですね」
「みんな違う酒だけど、どれもうまい、さすがに土佐だ」
蝙蝠は磯巾着の入った貝殻に寄りかかるといびきをかきだした。
「赤平家を待つとします、その大きな貝のお椀を一つとっておいてください。後はみなさんで飲んでください」
「そりゃあ、ありがてえ」
御化け貝たちはみんなして、酒の中にどっぷりとつかった。
夕焼けがきれいに空を染め、やがて、雲の合間に大きな月が輝きだした。
高足蟹が長いはさみを振りかざして、海からあがってきた。
「なんだ、もう酒盛りか」
「みなさん待ちきれなかったようで」
「ほら、赤平家蟹だ、年は何百歳だかわからんが」
高足蟹は長いはさみに真っ赤な蟹を挟んで持ち上げ、岩礁の上におろした。
真っ赤な平家蟹は卵茸の前に進み出た。
「御用がおありとのこと、なんでござんしょう、謹慎の身上、大したお手伝いはできないが」
卵茸も挨拶の後、今までのいきさつを話した。
「なるほど、そりゃあよくわかりやした。私をさしあげやしょう」
「赤平家蟹さんをいただけるのですか」
「高足蟹の親分さんに、今日は酒をいただけるといわれ、嬉しくここにまいりやした、酒を飲めるとあれば、もう思い残すことはござんせん」
「そんな、赤平家蟹さんを薬にしてしまうようなことはできません」
「おい、平家蟹、何を気取って言っているんだ、卵茸のおじょうさん、心配いりませんよ、酒を飲ませばわかります、この赤平家蟹のやつ、深海で一人芝居にこっちまって、そんな言い方しか出来なくなっちまった」
「すまんこってす」
「ともかく、今日は、存分酒を飲んでいいぞ、一年に一度のことだ」
「おおせのとおり、おありがとうござんす」
目を覚ました緑蝙蝠が貝のお椀を指さして、
「土佐の一番いい酒にござる、どうか赤平家蟹殿、お召し上がりのほどを」
と芝居調子で言ったものだから、赤平家蟹は大喜び。
「おお、かたじけなや、それでは」と、貝のお椀に足をかけ、ざぶんと入った。
「おお、これはこれは、言う言葉もない」とごくごく飲んだ。
「わしもいただけるかな」
高足蟹がはさみを持ち上げた。
「高足蟹のだんなには、これをどうぞ」
緑蝙蝠が、徳利を渡した。
高足蟹は「おお、それが一番」そういうと、徳利をを持ち上げて、酒を口に注いだ。
「うむ、うまい」
赤平家蟹は、貝のお椀の中で顔を沈めたり出したりしながら卵茸に声をかけた。
「茸のお嬢さん、そういいなさるが、元は人間」
「はい、そうです」
「あっしの背中にゃ、怒った人の顔、いざごらんあれ」
卵茸が赤平家蟹の背中を見る。
「おじいさんの背中の顔はあまり怒った顔には見えません」
「どうでござんしょう、人の顔にみえますか」
「はい、似ています」と、卵茸が言ったそのすぐに、赤平家蟹の甲良の模様がくちゅっと動いて、笑った。笑い顔が変わって猫の顔になった。
「あら、猫ちゃん、私の飼ってた猫にそっくり」
「黒ちゃんでござんす」
「ええ、そんな顔をしていまいした」
「黒ちゃんの運命は」
「わたしがこうなって、その後はわかりまぜん」
「だが、心配めさるな、背中に出るのは吉兆、生きてる証拠」
「そうですか、それはよかった、私はその黒ちゃんと一緒に大きくなったようなものです。母親が黒い猫を拾ってきて、育て始めたのです。私が一歳のことでした」
「今でも元気で、ご主人様を待ちわびていなさるのでござる」
赤平家蟹は普通の話し方にもどった。
「うれしい」
「ああ、この酒の旨さ、かわいい卵茸、なんと今宵はいい夜だ」
赤平家蟹の甲良に微笑んでいる女性の顔が現れた。
「あ、わたし」
卵茸が言った。
「残念ながら、見ることできず」
平家蟹は目玉をのばそうとしたが、そうはいかない。
高足蟹が言った。
「そりゃあ残念だね、とってもかわいい女の子だよ」
周りの者たちは平家蟹の入っているお椀をのぞき込んだ。
「ほんとに、かわいい」
御化け貝たちが騒いだ。
「俺にも見せてくれ」
お椀酒に長い間酒に漬かって、よれよれになっていた磯巾着が触手をわやわやさせた。
高足蟹が、お椀から緑磯巾着の爺さんを掬うと、持ち上げて、赤平家蟹の背中を見せた。
「おお、こりゃ、美少女だ、大人になりゃあ絶世の美女だ」
「磯巾着のおじいさん、酔ってる」
卵茸が言うと、みんな大爆笑。平家蟹の背中に浮き出ていたのは卵茸その物だったのである。
その時、満月の光が卵茸にあたった。卵茸はするすると背が伸び、朱色の傘が開いた。
「お、お嬢、傘が開いた」
緑蝙蝠が叫んだ。
卵茸は大人の茸になった。
満月の光は貝のお椀の酒に浸っている赤平家蟹の背中にもあたった。
赤平家蟹が、燃えるように真っ赤になった。
体を上下させるやいなや、卵茸の顔を持った真っ赤な殻が、酒の上に浮いた。脱皮をしたのである。
「おお、これは、なんと、確かに赤平家」
緑蝙蝠が殻をすくい上げた。
「柔らかいかと思ったが、ずいぶんかたいものだ」
「柔らかいのだが、土佐の酒で硬くなったのだろう。蟹は殻を脱いで大きく成長する、脱皮が続けば永遠の命、良い薬になるであろうよ」
高足蟹が説明した。
「それはすごいことです、赤い平家蟹さん、ありがたくいただきます」
「役に立てば嬉しいことでござる」
「赤い平家蟹、長く生きていてはじめて役に立ったのではないか」
「高足蟹の大将、その通りでござんす、もう思い残すことはありやせん」
「おおげさな、まあいい、これからも、役に立つことを考えろ」
「はい、肝に銘じて、茸のお嬢さん、ありがとうござんした」
こうして、中秋の名月の、輝くような金色の光の中で、土佐の海の仲間たちの酒宴は終りを告げた。
緑蝙蝠が赤平家の赤い抜け殻をみなに広げて見せた。背中にはきれいな女の子の顔が浮きでていた。
「おお、卵茸のお嬢さんだ」
みな祝杯をあげた。
月が煌々と高知の磯を照らし出した。
「お嬢、そろそろ甲斐に帰るとしよう」
「緑蝙蝠さん大丈夫ですか」
「蟹の抜け殻のお嬢の顔を見たら、酔いはさめた、お嬢も火根茸に帰って皆に見せたいだろう」
卵茸は頷いた。
緑蝙蝠が、背が伸びて、傘の開いた卵茸を翼でそうっと包み込んだ。
「皆さんありがとう」
「お、ご両人、月の光に導かれ、未来の国へお旅たち」
赤い平家蟹が芝居の幕を閉じた。
磯巾着が触手を持ち上げた。蟹も御化け貝もみな鋏をもちあげた。
緑蝙蝠は卵茸と赤平家蟹の殻をたずさえて、夜の空にに舞いあがった。満月が二人を照らし出した。
潮が満ちてきた。土佐の荒い海の波がそこにいた生き物たちを覆い隠した。高足蟹の甲羅も海の中に消えていった。
神無月ー阿蘇
土佐から甲斐に戻るには少しばかり時間がかかった。
「お嬢、土佐の生き物たちの気持はよかったの」
「本当に、土佐の空気、土、みな、豪快で気持ちのよいものでした」
切り株の上に、赤平家蟹の脱皮をおいた。
火根茸たちが大きくなった卵茸を眩しいように見上げている。
切り株の上に、大きく傘を広げた朱色の玉子茸が土佐の出来事を茸たちに話した。
緑蝙蝠が土佐からもらってきた赤平家蟹の抜け殻を広げて見せた。その背中には卵茸が人間の時のかわいらしい少女の顔が浮き出ていた。火根茸たちは身を捩じらせて見上げていた。声が出したい、みな茸たちはそう思っていたに違いない。
「あと一つです、溶けた赤顔」
「早いものだな、次はどこに飛ばなければならぬのか」
「阿蘇山です」
「九州だな」
「はい、行ったり来たりになりますが、緑蝙蝠さんはお疲れになっていませんか」
「なんの、あと一つ、こんなに早く集まるとは、お嬢の幸運を吸い寄せる力の強さに感服しておるところ、楽しいくらいだ」
「そう言っていただくのは嬉しいことです」
「お嬢、いくか」
緑蝙蝠は柔らかく、傘の開いた卵茸を包み込んだ。
また二人は空に舞った。
緑蝙蝠は速さをあげ、神風のような勢いで火の国、熊本まで飛んだ。
阿蘇山の上は黒い煙で渦巻いていた。
「大変なことだ、山を見ることができない」
緑蝙蝠はそう言いながらもゆっくりと下降し、岩場に降りた。
「少し山から離れたところにいきましょう」
「そうだな」
緑の蝙蝠はもう一度舞い上がると、煙の薄い方に向かって飛んだ。
山が見えてきた。
「はじめからこちらに来ればよかったな」
緑の蝙蝠は外輪山の林の中に降り立った。
林の中には、茶色の茸がたくさん生えている。
「お嬢、お仲間がたくさんいる」
「そうですね、何か教えてくれるでしょうか、茶色の茸さんたちはなにやら話しているようです、どのように話しかけましょうか」
「私が、言おう、万年茸だ、茸らの気質はお嬢よりわかる」
緑蝙蝠は口を閉ざして、体をふるわせた。茸は体全体ですべてを感じ取る。植物もそうである。
「教えてほしいことがある」
緑蝙蝠は体を揺すった。
「何かね」
「赤顔はどこかにあるかね」
「何をいっているのかわからんね、茸に顔はない、頭だけだ」
「あ、いや、失礼、我々は溶けた赤顔を探しているのだが」
「そりゃ、なぞなぞだな、顔だったものが、溶けたのかね、それとも溶けたものが顔になったのか」
「うーむ」
蝙蝠は卵茸に聞かざるを得ない。
「お嬢さん、今のは聞こえましたかな」
「はい、どちらかわかりません、まずは顔が浮き出た、溶岩でできた石を探すことがよいのではないでしょうか」
「確かに、私もそう思う」
緑蝙蝠はそのことを茶色の茸に伝えた。
「だがな、溶岩が固まった石は五万とある。高く吹きあがった火山弾は広く散りばって、それをみな捜すとなると一生かかっても難しい」
「でもやらなければならないのです」
卵茸も全身を使って、茶色の茸に訴えた。
「なぜ、そのような石を探しておるのだ」
「はい、私は甲斐の火根山の者、未来の神の怒りをかい、茸にされております。この緑の蝙蝠さんは、私を助けるため、万年茸から蝙蝠にされました」
「それは難儀なこと、だが、未来の神の気持を静めるのは難しい、しかし、お二人とも茸に関わる者たち、力にならないでもない」
「ありがとうございます」
「阿蘇の山は、中岳という火を噴いている真ん中の山と、周りを取り囲む外輪山、阿蘇の山は鋸山といっているが、それらの山すべてを捜さなければならないのだよ」
「確かに大変だ、ここは鋸山なわけか」
「そう、その中の根子岳というのだよ、中心は中岳だ」
「中岳を探すべきかも知れぬな」
「危ないところだが、それがまずだろう、我々の仲間が助けてくれるだろう、林も他の植物もみんな手伝ってくれる、茸や植物は動けないが、自分の周りにある地の石を見ることはできる」
「それは助かります、茸や植物の生えているところはわかるということですね」
「そうだ、見える範囲は大丈夫だ」
「ということは、我々は茸や植物の生えていない、中岳を中心に探せばいいことになる」
「それも、猫たちに手伝わせよう、この根子岳は九州に住む黒猫が、生きている間に一度は来るところだ、名前の通り、根子岳は黒猫の神聖な地である、黒猫は大人になると、ここにきて、他の猫にはない能力を身につけて帰るところだ」
「うむ、黒猫は他の猫とどこかが違うと思っておったが、それはどのような力なのか教えてくれぬか」
緑蝙蝠は尋ねる。
「違う世界と通信する能力だ、だから、黒猫は地球とは異なった世界を知っておる」
「それは、九州の黒猫だけなのか」
「いや、北海道も、四国も、本州も、そういった、猫の神聖な地がある」
「本州はどこ」
「あんたらの住む、甲斐の国さ、しかも火根山村だ、昔は火根子山と言ったのだ、火で焦がされた黒猫、それは、日本国の最も力のある猫たちなのだ」
「確かに、火根山の家家には必ず黒い猫がいました、私のところにも黒ちゃんがいたのです」
「そうだろう」
「茶色の茸のみなさん、これから、しばらく、助けてください」
「もう、植物や茸ははじめている、黒猫たちにはこれらから伝える。我々茸が動物に話をするには、まず虫に話をして、それが、鳥に話をする、すると、獣たちに伝わる、伝えることのできないのは人間だけだ」
「感謝する、我々は、中岳に行ってみる」
「気をつけなよ、熱い石が飛んでくる」
「ああ、それではまた、連絡をして欲しい」
緑蝙蝠は卵茸を抱えて舞い上がった。
中岳の上に飛ぶと、さっきとはうって変わって、山全体が良く見えるようになっている。煙がない。
「噴煙が止んでいるようです」
「そうだな、溶けた顔を捜すのにはいい機会だ」
中岳の噴火口につくと、熱い風がおそってきた。
「煙がなくなったといっても、ずい分熱い」
「でも不思議です、煙が全くなくなったのはなぜでしょう」
「たしかに気味が悪いほどだ」
卵茸と緑蝙蝠が空中から下を見ていると、岩を黒い生き物がぞろぞろと、登ってくる。
「お、黒い猫たちではないか」
「そのようですね」
緑蝙蝠たちは黒猫たちの中に降りていった。
ばあさんの黒猫が蝙蝠と茸を見た。
「あんたたちだね、溶けた赤顔を捜しているのは」
「はい」
「茶化(ちゃけ)茸(じ)から様子は聞いている」
「あの茸さんは茶化茸というのですね」
「そうだ、阿蘇山を昔から見ている茸だ、阿蘇の山を管理している」
「溶けた顔とはなにのことをいうのでしょう」
「わからないね、顔の形を持った溶岩石を探すが、違うものかもしれない」
「ありがとうございます」
年をとった黒い猫は金色の目を卵茸にむけた。
「あんたが人間から茸にされた娘だな、火根山の黒猫から聞いている」
「私の黒ちゃんは元気なのでしょうか」
「ああ、あんたが、人に戻るのを楽しみに、火根山に住んでいる」
「嬉しい、黒ちゃんは生きている、土佐でも言われました」
ばあさんの黒猫の後には、いろいろな目の色をした黒猫が従っている。
「黒猫のおばあさん、お仲間は何匹いるのです」
「ざっと八千匹かね、それでも、この広い阿蘇の岩場でその溶岩石を探すのは難しいね、約束はできないよ」
「わかっています、でも最後のものです、何年かけても探すつもりです」
「えらい心がけだ、根子岳で洗礼をうけた賢い猫ばかりじゃ、見つかることと思うよ、猫たちゃあ退屈しているからね、いい仕事だよ」
「黒猫のおばあさんはいつからここにいるのでしょう」
「わたしゃ、もう百八十八歳、化け猫の域に入ってしまってから、死ぬことができない、本当は死に場所を探しているのさ」
猫たちは中岳の岩場に散っていった。
「お嬢、我々もぽちぽち探すこととしよう」
「たいへんなこと、この広さを考えると、何年かかるか」
「大丈夫だ、黒猫と茶化茸がついている」
卵茸はうなずいた。
岩場に立った卵茸は、細いからだを折り曲げて、ぴょんぴょんと前に進んだ。
硫黄の臭いが立ち込めている。熱い空気が二人の周りを取り囲む。
汗をかきながら緑蝙蝠は岩場の石をつぶさに見ていく。
石だらけである。その中から溶けた顔の石を捜すとは大変なことである。
「緑蝙蝠さん、疲れたでしょう」
「確かに、一休みするとしよう」
緑蝙蝠は卵茸とともに岩場に腰をおろした。
「飛ぶのは得意だが、歩くのはにがてだ」
「大変なことお願いしてすみません」
「そのようなことはない、時間がかかってすまぬ」
そこに黒猫のばあさんが現れた。
「根子岳の茶化茸から連絡がきた、椿がそれらしき石を見つけそうだ、飛んでいってみてくれるか、私らはここで探している」
「はい、ありがとうございます」
緑蝙蝠と卵茸を包んで飛び立ち、根子岳の林の中におりた。
茶化茸が待ちかねたように言った。
「おー、来ましたな、向こうに、人間の住む家がある。その屋敷の庭に赤い花の咲く肥後椿の木があるが、その手元に、溶岩石が並べてあり、その一つに顔が浮き出ているそうだ、正しいかどうか分からんが行ってみるといい」
緑蝙蝠と卵茸はその家に飛んだ。庭の南端に肥後椿の木があった。その根本に降りてみると、椿の木が緑蝙蝠に話しかけた。緑蝙蝠は体ふるわせて、茸の言葉で返事をした。
「礼を申します」
卵茸も庭に降りて、飛び跳ねながら溶岩石の表面を見た。確かに、一つ、顔の浮き出ている石があった。顔は女性のものであった。「おや、ここにもある」蝙蝠がもう一つ見つけた。
蝙蝠は茅葺き屋根の家をのぞいた。土間では白髪の老人が石を刻んでいた。
蝙蝠は椿のところに戻った。
「人間が石を彫っている」
「そうなのか、俺はここの老人が何をしているのか見ることができないが」
「石屋のようだ」
「すると、この石はその石屋が彫ったものなのか」
「そうであろう、うまく彫れなかったものを、ここに並べたのだろう」
「それでは、あなた方が探しているものとは違うのだな」
と椿がいった。
「そんなことはありません、とても感謝しています」
「お嬢、人が作ったものとはいえ、この石のことかも知れぬ」
「そうですね、考えが浅かったと思います。肥後椿さん、ありがたくいただいていきます」
蝙蝠は二度にわたって石を運ぶと、中岳にもどった。
中岳の岩場で金色の目の黒猫が待っていた。
黒猫のそろえた前足の先には硫黄で黄色になった石がおいてあった。
「どうだったかな、顔のある石はあったかい」
「あったが、人間の石工が溶岩に彫った顔であった」
緑蝙蝠が説明をした。
「そうかえ、うちらも一つみつけた、硫黄のかぶった石に顔があったよ」
その石には黄色い男の顔が浮き出ていた。
「自然にできたようですね」
卵茸はそれを見ていった。
「これは、溶岩石に硫黄が吹き付けられてできたものだろう」
「そうですね、この石も一つの候補ですね、ただ、気になっているのは、今まで、赤いものばかりでした、赤い顔でないといけないのかもしれません」
「確かに、お嬢の言うとおりだ」
緑蝙蝠はうなずいた。
「もう少し探すかね」
黒いばあさん猫は「いくよー」と皆に声をかけた
そのとき、中岳の真ん中から火の柱が空に向かってあがった。
黒猫のばあさんが叫んだ
「噴火だよ、みんな逃げるんだ」
黒猫は一斉に下に駆け降りた。火の固まりが降ってくる。
緑蝙蝠も卵茸を抱えて宙に舞って、下に飛んだ。
猫たちは目も留まらぬ速さで降りていく。やがて下の方の林の中に逃げ込んだ黒猫たちはほっと一息ついた。
緑蝙蝠と卵茸も猫たちのそばに降り立った。空は黒煙が渦巻いている。
「やれやれ、ともかく助かった、だがまだ油断できないぞ」
黒猫のおばあさんがそう言ったときである。
火の玉が黒猫のばあさんを直撃した。
「阿蘇の火で焼かれるのだね」
ばあさんはそういうと、ばーっと、燃えてしまった。
ばあさんの後には真っ赤に火を噴いた石が落ちていた。
「黒猫のおばあさん」
卵茸は燃えた黒猫のいたところに行こうとした。
「やめな、熱い」
大きな雄の黒猫が止めた。
「熱いよ、あのばあさんは自分でも言っていたが、百八十八歳、もう死ぬしかなかったのさ、燃えて死ぬなんて本望だったと思うよ」
「でも、あたしが、こんなことをお願いしたために」
「いや、あのばあさん手伝いができて本当に幸せだったのだ」
「涙が流せないのは悲しい」
卵茸は涙を流したかった。
「茸には涙はないのだ、しかたないじゃないか」
卵茸の傘の下から、滴がぽたりぽたりと落ち始めた。
「お嬢は涙を流している」
「はい」
「未来の茸になったのだな」
「はい、涙がでて、気持ちが落ち着きました」
「人間は悲しいとき涙を流す動物なのだ、人間のような茸になりなすったな」
卵茸はこっくりとうなずいた。
「そろそろ近寄ってみよう」
雄の大きな黒猫がばあさんが燃えたところに近寄った。みんなも後に付いた。
黒猫のばあさんが燃えた跡は黒く影になり、その真ん中に落ちてきた石が冷えて真っ赤な溶岩石になっていた。
「ほら、みてごらん」
黒い雄猫が赤い溶岩石の表面を指した。
その表面には黒猫の顔が浮きでていた。
「あのばあさん、ほら、赤い石の顔になった」
「きっと、この赤石が、溶けた赤顔だ」
「そうです、黒猫のおばあさん、ありがとう」
「よかったな」黒猫たちが空を見上げた。阿蘇はまだ黒い煙を上げている。
茶化茸が集まってきた。
「黒猫のばあさんが溶けた赤顔になったって」
「ああ、黒猫のばあさんが死んで赤顔になった、阿蘇の黒猫の頭領が死んだ」
黒猫たちが石の周りに集まった。
「だが、黒猫のばあさん喜んだことだろう。黒猫の未来を見ていたばあさんだった。黒猫も火根山の未来の神に役割を仰せつかったということだ。卵茸の姫殿、火根山の黒猫に伝えておく、火根茸の皆さんには未来があるとな、さあ、持って帰っておくれ」
百八十になる雄の黒猫がばあさんの石を拾って緑蝙蝠に渡した。
「大事な石いただいていきます」
緑蝙蝠は溶けた赤顔と卵茸を抱えた。
「黒猫のみなさん、茶化茸のみなさん、お礼申し上げます、ありがとうございました」
二つはふわりと宙に舞い、黒い煙をよけて火根茸に向かった。
霜月ー琉球
二人は甲斐に戻った。
大きなブナの前の切り株に、黒猫の顔のある赤い溶岩石をおいた。
「これで、一角獣の赤い角、曼珠沙華の赤林檎、、赤腹井守の黒い玉、赤水晶、赤い珊瑚の竜宮使、赤い硫黄、赤い栗、赤河豚の赤い心臓、赤平家、顔の赤い石がそろったな、お嬢」
「ええ、でも何か足りないような気がします、歌の最後をはっきり覚えていないのです、人間だったときは確かに覚えていて歌っていました、しかし、茸に変わってから、その部分がわからなくなっているのです、もう一つ何かがありました、それと、富士も関係あるようです」
「そう言っておったな、それも未来の神による仕置きであろうかも知れぬな」
「はい、だけど、この一年の間に、なんとなく思い出してきています、何かの赤い実です」
「どのように致せば、思い出すかな」
「分かりませんが、訪れたことのないところから考えましょう」
「なるほど、お嬢の勘は鋭いから、それがいいのだろう、それでどこにいっていないのだろうかな」
「北のはて北海道、本州は北から南まで、四国も九州もいきました、そういえば南の果ては、そう南の島、阿児奈波、琉球の島々、今の沖縄の国にいっていません、日本の大事な国を忘れていました」
「お嬢、そうだ、琉球だ」
「そうです思い出しました、歌の最後は、竜が落とした赤い鉄の実、それは琉球の蘇鉄の実に違いありません」
蘇鉄の実はいろいろな病気に効く、人間が偽物の刀で腕に傷を付けた振りをし、腕の偽の赤い血の上に蘇鉄の実の軟膏を塗ると、跡形もなくなるという、大道の薬売りを見たことがある。それにしても蘇鉄の赤い実は薬効が強いという。
「薬にもなるが、毒でもあるようだ、使い方によっては怖いぞ」
緑蝙蝠はちょっと心配顔である。
「行って見れば分かるのではないでしょうか、蘇鉄の実を採りにまいりましょう」
緑蝙蝠と卵茸は琉球の島に飛んだ。
霜月にもかかわらず、沖縄は暖かく、赤い花がいたるところで咲いている。
「ずいぶん明るいところですね」
「そうだなあ、それにきれいな海に囲まれている」
「あ、蘇鉄」
海岸には蘇鉄が至る所に生えていた。赤い実がたくさんなっている。
「真っ赤な実、きれいな実です」
「確かに、ちょうどいい時期のようだ」
「私たちが作ろうとしている薬の大元になるような気がします」
「すると、たくさん必要になるのだな」
「そうだと思います。これを磨り潰して、それに今まで集めたものを加えるのではないでしょうか」
「我々だけで運ぶとすると、何度も往復しなければならぬな」
「火根山の夜鷹、むささび、梟にも頼みます」
「元は火根一族だった連中だな、それだけでは足りまい」
「はい、私はあの者たちしか知りません」
そこに、赤い蜻蛉が飛んできた。
「おや、珍しい客だな、緑の蝙蝠が卵茸を抱えている」
赤い蜻蛉が話しかけてきた。
「甲斐、火根山の者でございます、私らは、赤蜻蛉しかしりませんが、お姉さんのような桃赤色の蜻蛉に会ったのは初めてでございます」
「俺は雄だよ、紅蜻蛉だ」
「それは失礼しました、あまりにも綺麗だったので女子かと思いました」
「それで、何をしてるのだ」
卵茸が今までのいきさつを説明した。
「蘇鉄の実を火根山にもって行きたいのだが、助けてもらえないだろうか」
緑蝙蝠が尋ねると紅蜻蛉は、
「なににするのかね」と尋ねた。
卵茸は今までのことを話して、「その薬の大本の粉にするのです」と言った。
「蘇鉄の実はそのまま粉にすると毒になる、気をつけなければな、本当にただの蘇鉄の実か」
「はい、竜が落とした赤い実です」
「それは、この辺の蘇鉄の実ではないな、俺が聞いた話しでは、その大昔、石垣島の海で大きな竜が空に上り、石垣島に赤い実を降らしたという話がある。石垣島に行けば、もっと詳しい話しが聞けるかも知れんぞ、きれいな島で、森も広がっている」
「はい、行ってみます、紅蜻蛉さんありがとうございました」
卵茸を抱えた緑蝙蝠は石垣島に飛んだ。降りたところはきれいな砂浜だった。
「さて、竜のことを誰に聞いたらいいだろう」
緑蝙蝠は砂浜に卵茸を置いて、上空に舞った。
「星の形をした砂がいっぱいある、すてき」
卵茸は壷の部分を砂にめり込ませた。
「気持がいいわ」
そこに、大きな動物がのしのしとやって来た。
「きゃー」
その声で緑蝙蝠が砂浜をみると、大きな角を持った牛が卵茸に鼻をくっつけている。
あわてて緑蝙蝠は急降下すると牛の背中に降りたった。
「お嬢さんに何をする」
牛が振り向くと、
「なんだ、緑色の蝙蝠じゃないか、今卵茸の少女と話をしてるんだ」
「いじめたんじゃないのか」
「そんなことしないよ」
「悲鳴が聞こえた」
「ごめんなさい、ちょっと驚いただけなの」
緑蝙蝠は卵茸は抱え上げた。
「いや、俺がいきなり、匂いをかいだからびっくりしたのさ、竜の落とした赤い実を捜しているんだってな、きっと、あっちの森に落ちているやつだ」
「それはなんだい」
「昔の話しだが、竜巻がおきてな、なぜか蘇鉄の実だけを巻き上げてしまってな、しばらくすると空からそれが落ちてきたんだ、不思議なことに、百年も経つのにその森におちた蘇鉄の実は赤いままで、なっている時と同じだそうだ」
「その実がほしい」
「もってってかまわないよ」
「でもどうやって探したらいいかしら」
「あの森には大蝙蝠が住んでいる、おしえてくれるさ」
「ありがとう」
「いや、こんなところに卵茸の娘がいるとは驚いたよ、かわいいね」
「だが、大蝙蝠とは面識がないが、どうしたら連絡がつくのだろうか」
緑蝙蝠が聞いた。
「大丈夫だ、森の入り口まで一緒に行って呼んでやるよ」
牛のお兄さんは森までついてきてくれて、
「うもももーう」
と鳴いた。すると、大きな蝙蝠がわさわさと森からでてきた。緑蝙蝠の何倍も大きい。
「なんだい」
「緑蝙蝠が、竜巻の落とした蘇鉄の実がほしいんだと、助けてやってくれな、俺はこれから一仕事だ」
牛のお兄さんはそう説明すると家にもどっていった。これから荷物を引っ張るのだ。
「よう、緑の蝙蝠とはめずらしいな、蘇鉄の実ならいくらでももっていけばいい」 「お初にお目にかかります、緑蝙蝠にございます」
緑蝙蝠が挨拶をした。
「ついてこい」大蝙蝠は森の中に飛び立った。。緑蝙蝠たちも大蝙蝠の後についた。
ちょっと行くと、下草のなかに赤い実がいたるところに転がっていた。
「たくさんある、でもどうやって運んだらいいかしら」
卵茸が言うと、大蝙蝠が緑の蝙蝠から顔を出した卵茸にびっくりした。
「茸じゃないか」
「はい、卵茸と申します」
「それで、緑の蝙蝠との関係はなんなのだ」
緑蝙蝠が頭をかきながら言った。
「大蝙蝠どの、卵茸の姫は俺のご主人様だ」
「卵茸が主人とな」
「これを拾って運ぶのかい」
そこで卵茸は今までのことを話し、火根山まで運ばなければいけないことを説明した。
「たくさんの蘇鉄の実が入用だが、運ぶのを手伝っていただきたい」
緑蝙蝠も頼んだ。
「それはかまんよ、この機会に本州の森を見てこようと思う」
「ありがとうございます、火根の森には果実がなる木もございます、どうぞいらしてください」
大蝙蝠は果物が大好きである。
「それは楽しみな、みんなでてこい」
その声で、森の中から、ばさばさと大蝙蝠が飛んできた。
「なんだい」
「蘇鉄の実を拾って、本州甲斐の火根山に運ぶぞ、うまい木の実があるそうな」
それを聞いた。沖縄大蝙蝠たちは蘇鉄の実を拾い集めた。。
大蝙蝠のリーダーが、
「それじゃいくぞ」と一声。
大蝙蝠はばさばさと大きな音を立てて、空に舞いあがった。空一面に蝙蝠が群がった。
そのまま、沖縄本島、鹿児島を経て、太平洋岸を静岡まで来ると、横切って火根山に到着した。
空一面の大きな蝙蝠の群れに、顔を出していた茸たちはびっくり仰天地下にもぐった。動物たちも何が起こったのかと、木の陰に隠れた。
大蝙蝠は降りてくると、ブナの木の前の切り株に蘇鉄の実を積み上げた。
緑蝙蝠が降りてくると、切り株の上に卵茸を載せた。
卵茸が叫んだ。
「最後の赤い鉄の実を、沖縄から大蝙蝠さんたちが運んでくださいました、これで元に戻る薬ができるのです」
地にもぐっていた火根茸たちが顔を出し、大蝙蝠たちに傘をたれた。
ブナの木の前の大きな切り株の脇には蘇鉄の実が山盛りになっている。
「火根山の恵の実を集めてください大蝙蝠さんたちに食べていただきます」
卵茸の一声で、火根山の森の生き物たちは、卵茸の声であけび、柿、林檎、いろいろな果物を集めてきた。
そこで、大蝙蝠と火根山動物たちとの宴会になった。
火根茸も一晩中その様子を楽しそうに見ていたのである。
あくる朝、大蝙蝠たちは火根山を後にした。
「富士を眺めながら帰るとするか」
「沖縄大蝙蝠さんたち、また、遊びに来てください」
「そうよの、だが、あんたたちがまた人間に戻っていたら、話は出来ないかもしれないな」
「そうですね、でも、美味しい果物を用意しておきます」
「それはありがとう、また来ますよ」
「世話になった、お礼申します」
緑蝙蝠も頭を下げた。
「それでは、うまくいくように祈っている」
大蝙蝠の集団は空を埋め尽くすように、石垣島に飛んで帰ったのである。
晩冬ー火根山
再び師走の火根山に、卵茸と緑蝙蝠がたたずむ。
「おかげさまで、すべてのものがそろいました」
「お嬢の力はすごいものだ」
「いえ、緑蝙蝠さんや、みんなに助けられてここまでこられました」
火根茸たちも寒いさなか土の中から頭をだして、卵茸と緑蝙蝠の話を聞いている。、
切り株の上には集められたものが乗っている。
卵茸が歌いだした。
「人が茸に、茸に人が、北の果て棲む一角獣、赤い飛沫の角の先、赤い実のなる曼珠沙(まんじゅしゃ)華(げ)、赤腹井守の真黒胎児、甲斐の洞窟赤水晶、赤に染まった竜宮使、箱根の赤岩硫黄粉、尾張名古屋の赤い栗、赤河豚心臓下関、泡踊りの赤平家、九州阿蘇の溶けた赤顔、竜が落とした赤い鉄の実、その跡が分かりません、冨士がでてきます」
火根茸がもどかしそうに傘を揺らしている。
緑蝙蝠が言いなおした。
「北の果て棲む一角獣、赤い飛沫の角の先、北海道で一角が角を折って死を向かえるその血のついた角だ、
赤い実のなる曼珠沙(まんじゅしゃ)華(げ)、青森の最後の実をつけた年老いた林檎の洞に咲く曼珠沙華、その死を迎えた林檎の実だ。
赤腹井守の真黒胎児、越後胎内の年取った井守のばあさんの生んだ死んだ卵だ、
甲斐の洞窟赤水晶、火根山の水晶洞窟で死んだ赤い海老がはいった、何億年もかかってできたい水晶、
赤に染まった竜宮使、富山の魚津の沖合いで、深海にできた珊瑚が作った竜宮の使い、
箱根の赤岩硫黄粉、箱根の火の山の奥の奥の死んだマグマを食べたマグマ竜の神が吐き出した赤い硫黄、
尾張名古屋の赤い栗、犬山城の近くの栗栖に住む猿達の大昔からの栗の木の樹液からとった薬、
赤河豚心臓下関、下関の海の下で河豚が拾ったその昔死んだ人魚の心臓がかたまったもの、
泡踊りの赤平家、土佐に棲む赤い平家蟹の脱皮した甲羅、甲羅の背中には卵茸の姫の顔が浮き出している、脱皮は再生、
九州阿蘇の溶けた赤顔、阿蘇山で噴火の石に当たり、やっと死ぬことのできた百八十八歳の黒猫の顔の浮いた赤い溶岩石、そして、琉球石垣島でその昔竜巻で巻き上げられ林に降ってきた赤い蘇鉄の実、死と再生と希望で作られる薬だ、お嬢、これをどうしたらよいかな、まずは磨り潰すのだろうか」
「つぶさなくても良いのかもしれません、むしろ、これらを水の中に入れて煮るのではないでしょうか」
「どこの水がよいのか」
「なぜ、火根山村が未来を背負うことになったのでしょうか」
「うーむ、なぜだろう」
「美しい水が湧き出ています、からだによい温泉もあります、名前の通り、火の根っこがあります」
「マグマのことか」
「はい、この地の力の元です」
「綺麗な水を汲んでこなければならぬな」
「そうでした」
卵茸は緑蝙蝠の言葉ですべての歌を思い出した。
「富士の山が歌に出てきました、雨が少ない年に、お父上が富士の山におたのみ申そう、清き流れを、と歌の最後につけるように言いました、富士からわき出る神聖な水が、火根山神社の脇にあります」
それを聞いていた火根茸が嬉しそうに身をよじった。
火根山神社は火根山の麓にある、火と水をまつる神社である。信心深い火根山の住民たちは、毎月八日に神社を訪れお供えをした。
「富士の水ならばよい薬をつくれるであろう」
「二人だけではとても無理だと思います」
「火根山の鼠たちに助けを乞おう、ここの鼠たちはとても器用だ」
その話はすぐに火根山の鼠たちに伝わった。
いつからか火根山にはたくさんの鼠が棲むようになっていた。その鼠の額には必ず濃い赤茶色の丸い模様があった。火鼠とよばれ、山に棲んでいたことから火根一族の住居に入り込むことがなく、お互いに干渉をすることなく生きていた。
話が伝わり、鼠たちが集まり、切り株の回りに顔を出している火根茸の脇で、切り株を見上げている。
「よく来てくれました、火根茸を元に戻す薬を作ります、手伝っていただきたいのです」
切り株の上から卵茸の姫が挨拶をした。
火鼠の長老がすすみでた。
「我々の使命はいざというとき火根一族を助けること、今がその時と存じます」
「ありがたいことです」
卵茸が、鍋に富士の水を汲み、蘇鉄の実を砕いて入れ、、そこに切り株の上のものを順に入れ、煮詰めることを説明した。
「お任せいただきたい」
火鼠たちは万事心得ていると働き出した。
火根山一族の家から大きな鍋を担ぎ出した火鼠たちは、火根山神社に向かった。
火根山神社の脇にはきれいな水をたたえた泉があった。
緑蝙蝠が神社の扉を開け、中に卵茸をつれてきた。
火鼠が大鍋を運んでくると、大きな茸のご神体の前に置いた。
その中へ、動物達が器を使って泉の水を運び、一杯にした。
林の切り株の脇に積まれていた赤い蘇鉄の実は、火鼠が運び、歯で砕くと鍋の中に放り込んだ。
「緑蝙蝠さん、集めたものをお願いします」
緑蝙蝠が全国から集めたものをブナの木の前から、社の中に運んできた。
卵茸が見守る中、緑蝙蝠が一角獣の赤い角、赤い林檎、、赤腹井守の黒い玉、赤水晶、赤い珊瑚の竜宮使、赤い硫黄、赤い栗、人魚の赤い心臓、平家蟹の赤い抜け殻、顔の赤い石を順に鍋の中に入れた。
周りに頭を出している火根茸たちはその間、からだを震わせて祈った。
「さて、お嬢、どのように煮たらよいか」
「火根山神社のお祭では、大人たちが、松明を持って、歌いながら神社の前で踊ります。その歌の中に、神に火をつけ泉をわかし、この地の未来をいつまでもとあります」
「とすると、神社に火をつけるのか」
緑蝙蝠が驚いた。
「そうしたいと思います」
緑蝙蝠、卵茸、それに鼠たちは社の外に出た。
「火はどのようにつけたらよいだろう」
「水晶洞窟の赤蝙蝠さんに水晶をもってきてもらうようにお願いできませんでしょうか」
「ああ、あの椎茸だった連中だな」
緑蝙蝠は喉を震わせ、超音波で連絡をとった。三匹の赤蝙蝠は赤い海老に削り取ってもらった水晶の欠片を咥えふわふわと飛んできた。
「お嬢さん、久しぶりです」
「はい、赤蝙蝠さんもお元気そう」
赤蝙蝠は水晶を差し出した。
「ありがとう、これで火をつけます」
「お嬢、どのように使うのか」
「日のほうにかざして、光を神社に当ててください」
「どこでそのような知恵をおもちになったのか」
緑蝙蝠は卵茸の姫の賢さにおどろいた。
「これは、人間が火を起す一つの方法です」
「やはり、人間は進んだ生きものであったのだな」
「火をつけるのはおいらたちがやろう」
椎茸だった三匹の赤蝙蝠が水晶を持ち空中に浮かんだ。
水晶を日の方にかざした。
光が神社の柱に集まって、煙が上がりはじめた。
しばらくすると、柱の一部がじゅぶじゅぶと燃え始め、赤い煙があがった。その時はすでに夕暮れになっていた。しかし間に合った。火根山神社の柱に炎が上がった。
やがて日が沈みあたりが暗くなったとき、勢いよく火の手が上がったと見るや、瞬く間に真っ赤な炎が火根山神社をつつんだ。
あまりにも炎の力が強く、中におかれた鍋がどうなったか見ることもできない。
卵茸を抱えた緑蝙蝠も火鼠たちも遠巻きに燃えている火根山神社を見ていた。
火根山神社が真っ赤ななマグマになりそそりたった。
緑蝙蝠と卵茸、それに何百といる火鼠たちは、マグマと化した火根山神社が、真っ赤な竜になり、身をくねらせて天に昇ろうとするのを見た。
真っ赤なマグマ竜は地上を離れると、星がきらめく夜空の中にゆっくりと上っていく。赤竜は火の粉を散らしながら上へ上へと昇り、やがて星の間に赤い点となって、消えていった。
あたりが暗くなった。
卵茸が神社のあったところを見ると、真っ赤に焼けた鍋があった。鍋から熱い風が吹いてくる。
緑蝙蝠がその上を飛んだ
鍋の中には真っ赤になった液体がぐつぐつと煮えたぎっていた。
緑蝙蝠が卵茸に言った。
「よく煮えておる」
「鍋が冷めたらそのお薬を皆に配りましょう」
「明日の朝にならなぬと冷めぬな」
「長い旅でした、緑蝙蝠さんありがとう、赤蝙蝠さんたちもありがとう、火鼠さんたちもありがとう、我々は明日になれば元にもどれます」
赤蝙蝠たちは言った。
「水晶洞窟はとても住みやすいので、おいらたちは、蝙蝠のままでいることにしたよ」
「椎茸にはもどりませんか」
「水晶洞窟を守る役目をいただきたいと思います」
「わかりました、明日の朝は、できた薬を皆に配るのを手伝ってくださいね」
「もちろん、明日の朝にまた来ます」
「私たちも来ますよ」
火鼠もそう言うとねぐらに帰っていった。
卵茸は緑蝙蝠の翼にくるまって目を瞑り瞑想の世界に入った。
朝日が火根山神社の跡を照らし出した。
鍋が緑色に変わっている。中を見ると、真っ赤などろどろの薬が渦巻いていた。だがもう熱は冷めているようである。
卵茸と緑蝙蝠がのぞいた。
「やっとできました」
「効けばよいがのう」
火鼠たちが顔をだした。
「おはよう」
「おお、もう来てくれたか、薬ができた、これを林の火根茸たちに配らねばならぬ」
そこへ、三匹の赤蝙蝠も来た。
「お安いごよう」
火鼠と赤蝙蝠たちは、火根山から瓢箪をかき集め、薬をつめた。薬の入った瓢箪を、鼠と蝙蝠たちは火根茸に配るために火根山の林の中に散っていった。
緑蝙蝠も卵茸を抱きかかえて、火根茸の待つブナの木の切り株に飛んだ。
卵茸は体中をふるわせて火根山一族に顔を出すように連絡をした。
いたるところから火根茸が頭を出した。
「元に戻ることのできる薬ができました、今、火鼠さんと赤蝙蝠さんが薬を林の中にいる火根茸のみなさんにもっていきました、ここにいる皆さんの薬はここにあります、緑蝙蝠さんが配ってくださいます」
緑蝙蝠が言った。
「お嬢、まず最初に薬を飲まねば」
火根茸たちも身を震わせてそう願った。
「いえ、私は最後にします」
「さあ、緑蝙蝠さんお願いします」
火鼠も手伝って、薬を茸たちの頭に振りかけた。
だが、なかなか効果は現れなかった。火鼠と赤蝙蝠は何度も林の中に薬を運んだ。緑蝙蝠もブナの木の前にいる火根茸にかけた。
それでも火根茸たちは茸のままであった。
とうとう、鍋の中の薬は少なくなった。
「まだ足りないものがあったのでしょうか」
卵茸がか弱い声で言った。
「いや、時間が必要なのだろう、私が蝙蝠に変わったとき、まず顔ができて、胴ができて、手足ができてそして翼ができた、何日かかかった」
「わたしは一晩で頭が茸になって、手足が体に吸い込まれ、壷ができて、卵茸の子どもになりました」
「ということは、今日の夕方にはみな戻ることが出来るだろう」
「それでは、緑蝙蝠さん、薬を飲んでください」
「いや、お嬢が先に」
「緑蝙蝠さんが万年茸に戻ったら、私はこのまま卵茸のままでおそばにいます」
「え、なんと申した」
緑の蝙蝠は驚いた。
「だけど、火根一族の将来がお嬢にかかっているのだよ」
「いえ、皆が元に戻れば、それでいいのです、皆が将来を守るでしょう、さあ、緑蝙蝠さん、お願いだから薬を飲んでください」
緑蝙蝠は、それを聞くと、瓢箪の底に残っている赤い薬に口をつけた。
すると、驚いたことに、緑蝙蝠はすぐに大きな万年茸にもどった。
「お嬢、私はあっと言う間に万年茸にもどった、お嬢も早く」
「いえ、私はこのまま、緑蝙蝠さんのおそばにいます」
卵茸は切り株の上の万年茸の隣に立った。それから、卵茸はもう自分では動くことができなくなった。
その時、卵茸と万年茸にまわりの茸たちの声が聞こえてきた。今まで話すことができなかった茸たちが、しゃべり始めたのである。元に戻っている証拠に違いがない。
卵茸に懐かしい父親の声が聞こえた。
「あ、お父様」
「よくやってくれた、これで私たちもまた、使命を果たすことが出来るようになる」
父親の茸は林のはずれの木の下に生えていた。母親も一緒だった。
「また会えますね」
母親の声であった。
木耳に覆われた大きなブナの木がみしみしと音を立てて後ろに倒れた。根元から真っ赤になった壷が転がり出ると、蓋が開いた。
そのとたん、火根茸たちが一斉に生き物に変わった。
だが、人間ではなかった。
現れたのは白い鼠だった。人間には戻らなかったのである。
「みんなが、鼠になってしまった」
卵茸は声をあげた。
火根一族の長であった父親が言った。
「将来のこの地は、いや地球は、鼠になって我々が担えということだろ、未来の神のお気持ちなのだ」
火根山一族だった者はみな鼠にかわった。その真っ白な鼠はおでこのところに真っ赤な丸い模様があった。
白い鼠たちは人間であったときと同じように会話をした。日本足で立ち、手の指は発達して物を作り出すことができた。
残っていた赤い薬はそこに昔からすんでいた火鼠たちに飲ませた。火鼠は赤い鼠になり火根一族に加わった。おでこのところには白い丸い模様があった。
こうして、火根山一体は新しく生まれた鼠たちの世界になった。
火根鼠の長は一族に言った。
「我々の未来を築いた二つの茸に社を建てようではないか」
「お父様、ありがとうございます」
卵茸は喜んだ。
「万年茸の緑蝙蝠殿、人間の時から床の間で我々を見守ってくださっていたのですな、娘を、いや、卵茸をよろしくお願いします」
「お嬢と一緒にいられるとは思っておらなかった」
「いつまでも」
そう言って卵茸は万年茸にますます寄り添った。
火根鼠は器用に木を切り出し、木材を作り、社を造り始めた。鼠たちは人間の時のことをすべて覚えており、人間にできること以上にいろいろなことができた。
鼠たちの町は次第に出来あがってきた。新たな火根山神社も創られた。それに、万年茸と卵茸の神社もできた。小さなきれいな神社だった。火根山鼠たちは二つの茸を社の中に運び込んだ。
日の光がかすかにはいる、一段と高くなった白木の床に、卵茸と万年茸はおかれた。
鼠たちは社の中に、桧でできた風呂を用意した。そこに温泉をひいた。鼠たちは八の日になると必ず茸たちを温泉に浸した。
卵茸と万年茸は湯に浸かりながら、昔行ったところを思いだして、話をしているのであった。
その小さな神社は火根茸神社と呼ばれ、真っ黒な大きな猫が、茸たちを守るように棲みついていた。
「緑の蝙蝠さん、鼠の世界になりました」
「そうだな、人間が滅びた後のために、未来の神が準備された生き物たちだ」
「私たち茸も未来の生き物になれるのでしょうね」
「もちろんだ、お嬢、茸や植物はこの地球に必要だからな、動物も必要だが、どの動物が中心になるか、それは未来の神のお眼鏡にかなった動物なのだろうな」
いつの間にか、新しい火根山神社の社の奥に真っ白な壷が置かれていた。次の世が入っている壷である。これからは鼠たちがその壷を守る。
今でも、誰にも知られることのない、未来を生み出す火根山が甲斐にある。
完
火根茸(ひねじ)


