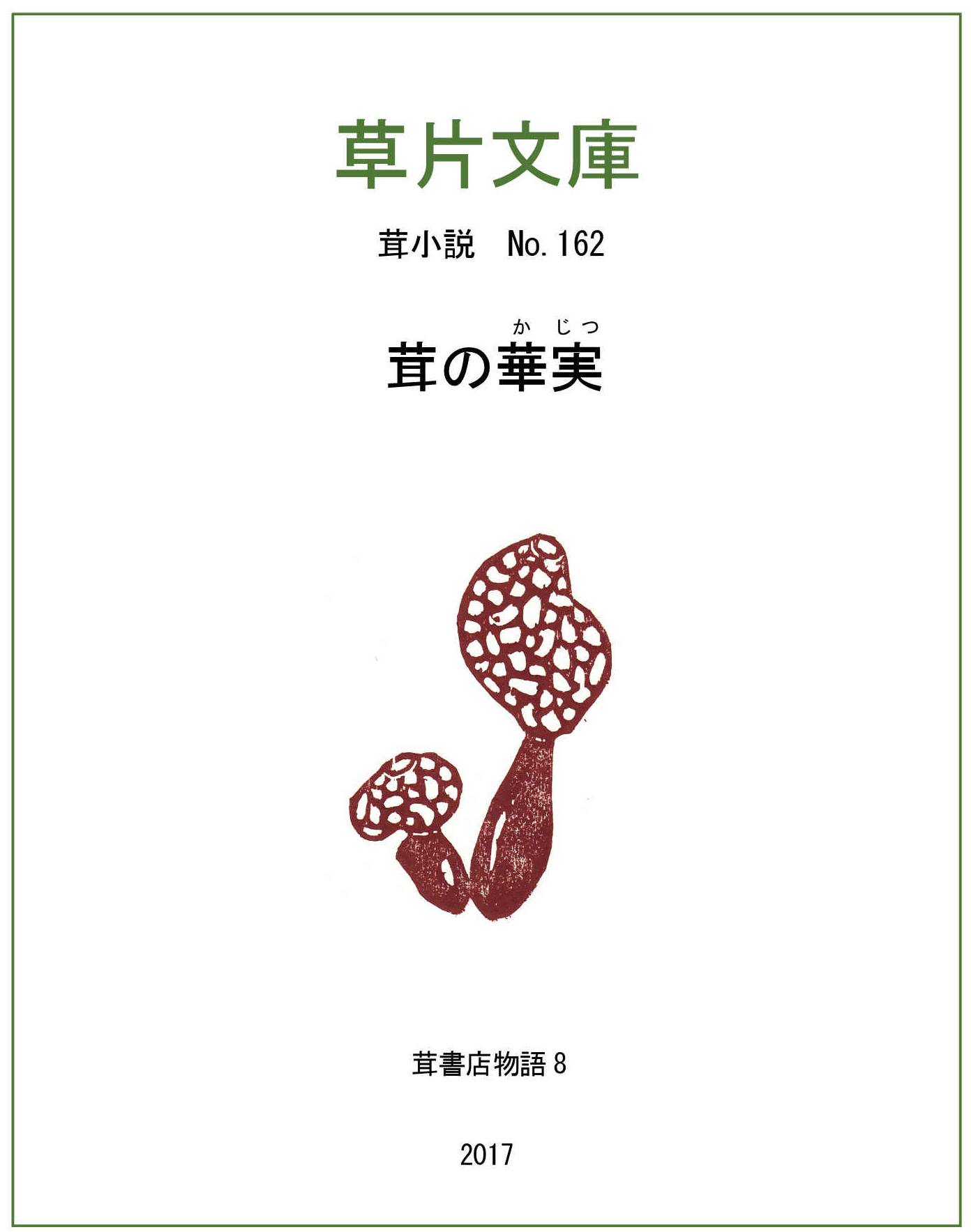
茸の華実(かじつ)-茸書店物語8
芦花公園の住んでいるマンションの近くに、市の世田谷文学館がある。面白い企画が多くて、必ず見に行くようにしている。常設のムットーニの幻想的な現代からくりも魅力で何度見ても飽きない。
今、奇妙な植物の文学展をやっている。色や形の面白い植物は身近にもかなりある。荒俣宏氏の著書、花の王国4、珍奇植物(平凡社)をもっている。それには、西欧の著名な図鑑から採録した華麗な絵とともに、六十八のおもしろい植物が紹介されている。すべてカタカナの名前になっているが、日本でも見ることができるものがかなり含まれている。たとえば、天南星の仲間はとても花の形が面白く、私自身も好きなものである。天南星の中の浦島草や蝮草という名はかなり知られているだろう。それらは里芋科の植物で、ザゼンソウもそこに含まれている。
ページをめくっていくと、ラフレシアは寄生性の植物、最も大きな花としでなじみが深いし、寄生性のナンバンギセルは里を歩けば出会うこともあり、見るのは難しくはない。馬の鈴草の種類が掲載されているが、寒葵の花はラフレシアを小さくしたようで、いろいろな形があり、よく見られる珍奇な花だが、土に埋もれたように咲くので、葉っぱは知っていても花に気がつく人は少ないかもしれない。
ページをめくっていくと、土栗、鬼フスベや籠茸がのっている。茸である。昔の教科書では、茸は植物に含まれていた、それが今では、植物でも動物でもない、菌類として、第三の世界に独立した。そういう意味でも面白い生きものだ。千葉の中央博物館に行った時に知ったのだが、茸類は恐竜より後に生まれた可能性があるという。ということは、動物や植物よりかなり新しい生物ということになる。
これらの植物や菌類は文学と切り離すことは出来ない。文学館では、植物の写真と、その植物に関する文学作品が陳列されていた。浦島草はそのものの名前で大庭みな子の作品がある。寒葵は徳川の紋となるほど身近なものであり、かつ、ちょっと他の植物とは違った気品のあるもので、万葉にも歌に読まれたようである。
座禅草は萩原朔太郎の生誕の地、群馬の沼沢で見事な花が見られるようだが、朔太郎は取り上げていないようだ。座禅草というタイトルでミステリーを書いている素人の人もいるという。面白いのは、怪奇小説家のラブクラフトが短編の中で扱っているらしい。英語でスカンクキャベツというそうで、臭いのだろうか。
茸の小説もいくつか紹介されていたが、茸だけで文学展ができるほど、小説の中には登場するという。茸の個々の名前そのもののタイトルの本もかなりあるようだ。茸小説や茸漫画のアンソロジーも出ていることが書かれていたが、本そのものは置いていなかった。今回の文学展では、茸に力は入れられていない。
その展覧会を見てから神田に出た。京王線の芦花公園駅は各駅停車しか止まらない。しかし、各駅で終点の新宿まで行ってもさほどかからないので、いつもそのまま乗って都心に行く。神田神保町に行くには、笹塚で都営新宿線直通の電車に乗り換える。そのほうが新宿にでるより早い。神保町は笹塚から八つ目である。
もうすぐ一時なので、駅を出るとそのままランチョンに行った。今日のランチはサーモンフライにトンカツである。トンカツのタレがなかなか美味しい。食べるとすぐに草片書房に行った。
木のドアを開けると、今日は姉妹とも店にいた。入っていった私を見て「いらっしゃいませ」「いらっしゃい」と、二人から声がかかった。
私が地方出版のところに行くと、姉の笑子さんが「はいっていますよ」と笑顔になった。
棚を見ると、草片叢書第八集「茸の華実」があった。華実とはどういう意味でつけたのだろうか。手にとって見ていると、妹の泣子さんが「それ、そのままの意味なんですよ、花と実ということ、華は昔の字を使ってますけど、作者の趣味でしょう」とそばによって来た。茸に種はできないから、何か他の意味があるのかもしれない。
「対馬島の人が書いたのですけど、古い伝承的なお話らしいです、あのあたりには民話はいろいろ残っているみたいです」
「あの、長崎の対馬山猫のいる島ですか」
「ええ、椎茸栽培が盛んですね」
姉の笑子さんが話しに加わった。
「原木で採れる椎茸がとても立派で、大きな傘に花の模様のような割れ目があって、華茸とよばれるのですよ、それを書いた人も、島に古くから住んでいる人です、それで華という字を使ったのじゃないですか」
対馬島で茸栽培が盛んだとは知らなかった。長崎にはずい分行ったし、たくさんの島があるが、島巡りをしたのは本土に近いところの小さな島だけである。小さな島でも教会が建てられている。その建物を見るだけでも価値があり、そのあたりを旅の雑誌にのせたことがある。なぜか対馬には行かなかった。動物学者にツシマヤマネコのことを書いてもらったことはある。
「笑子さんのレストランでも華茸を使っているのですか」
笑子さんは茸のレストランの経営もやっている。行こうと思うのだが、予約しないといけないような高価な店で、ちょっと躊躇している。
「シェフに任せていますけど、使っていますね」
「だけど、対馬の自然の茸はどうなのですか」
「あそこには原始林が残っていて、いろいろな茸が生えるとのことです、その作者の方にも会いましたが、本気で研究すると新しい茸がたくさん見つかるのではないかとおっしゃていました。なにしろ、大昔は大陸とつながっていて、大陸の人が日本にやってくる中継所のようなところだったのですから」
知識としては知っていたが、行って見なかったのが悔やまれる。
第八集の表紙の茸の絵は椎茸ではない。薄黄茶色の可愛らしい茸が書かれている。今にも動き出しそうな茸である。
「その茸、ショウゲンジ、というんですよ、美味しい茸です」
「食べたことはありません」
「地元では食べる茸ですけど、培養ものがないから、都会にはあまり出回らないでしょうね」。黒皮と同じようだ。都会の人間は知らない。
お願いしますと脇に来ていた泣子さんにその本を渡した。
「今日、世田谷文学館で、奇妙な植物の文学展をやっていて、見てきたのだけど、茸がちょっとありました、だけど茸の小説の本は紹介だけで、置いてなかったです」
「茸の文学はずい分ありますから、それだけで展覧会ができるでしょうね、日本の小説家もずい分茸をあつかっています。アンソロジーが出ていますけど、ちょっと本のつくりは小説や詩を読む雰囲気ではありません、お勧めできません。読みづらいと思います。むしろ個々の作家の本を読まれたほうがいいと思います。有名なのは泉鏡花の茸の舞姫でしょうか。幻想小説では中井英夫の短編集にあります。最近では泉鏡花賞を受賞した、中島京子の妻が椎茸だったころ、というのがあります。お勧めしたいのは、加賀乙彦のくさびら譚です。加賀乙彦全集の1です。いい本です。それらの本はその棚に入っています、ご覧ください」
笑子さんが指差した棚のところに行ってみると、茸小説コーナーと書いてある。確かにたくさんある。翻訳されたものもあり、レイ、ブラットベリーなど知っている作家の名前もあった。
加賀乙彦は精神科医で小説家ということは知っていたので、笑子さんが教えてくれたくさびら譚を手にとって見た。地味な装丁だが、表紙の茸の絵にしてもとても感じのいい本である。値札は二千円になっている。値が上がっているようだ。しかし欲しくなり、デスクに持っていった。「これ、お願いします」と差し出すと、「いい本を選ばれましたね、ほら」と笑子さんが、本の見返しを開いて見せてくれた。そこには野上彌生子宛の献辞があった。サイン本である。貴重なものだ。
「限定版もあるのですけど」
泣子さんが棚からもって来た。茶色の布張りの帖に入った綺麗な本だ。113部限定。欲しくなる。
「おいくらなんです」
「二万円です」
装丁から考えると、決して高くないが、今持ち合わせがないし、内容もまだ知らない。それを察したように、笑子さんが「読んでみてからよ、泣ちゃん」と言った。
「そりゃそうね、すみません」
泣子さんはその本を棚に戻した。笑子さんが「くさびら譚は加賀乙彦が東大の脳研究所にいたときの、脳の解剖の教授をモデルにして書いたものらしいのよ、その教授は有名な茸好きで、加賀さんはずい分尊敬していたらしいの」、笑子さんはよく知っている。
「なんと言う人ですか」
「小川鼎三先生という方だそうですよ」
どこかで聞いたような名前である。
「それじゃ、読んで、欲しくなったら、次の機会に」
「はい、またいらしてください」
こうして、帰りの電車に乗った。くさびら譚を開いた。六つの短編が入っていて、くさびら譚は五つ目である。家に帰ってからも、ベッドに寝っころがって読み続けた。若い頃は周りのことをすべて忘れて小説を読みふけったものだが、年をとってからはずい分久しぶりである。もう七時になっている。茸の華実は明日にしよう。
次の日、三時に目が覚めた。たまに車の通る音が聞こえるが、まだ外は寝静まっている。
朝風呂に入り、トーストと紅茶、それにヨーグルトと簡単な朝食を済ませた。昨日、活字に集中したせいか、ちょっと本を読む気にはなれなかった。ボーっとしていた時、突如として、笑子さんの言ったことを思い出した。くさびら譚のモデルは小川鼎三先生である。その人の本をもっている。といきなり思い出したのである。自分の書棚を眺めていくと、あった。小川鼎三氏の「医学用語のおこり、東京書籍」という本である。箱に入った立派な本だ。小川鼎三という人は叔父の友人であり、叔父の娘、従姉妹が面白い本だと教えてくれて買ったものである。もう五十年も前の話で、自分にとっては領域外のものなので、ざっと目を通し、医学用語の起源が面白く書かれていたと思った記憶がある。改めて目次を見てみると、確かに茸の話がいくつものっている。
その朝は、その本を読み始めてしまった。医学用語のなりたちも面白いものである。ヒステリーは子宮からきているということだ。発音はわからないが、ギリシャ語で子宮はヒステラというらしい。
そういったことで、語草片叢書「茸の華実」を読むのはその夜、ベッドに入ってからになった。
著者は長崎、対馬の商工会議所の理事の一人のようだ。
「茸の華実」
対馬島はたくさんある島々の中で最も大きく、しかも長崎本土からかなりはなれ、ユーラシア大陸に近いところにある。その昔は大陸と地続きだったという。縄文時代には島となっていたと考えられているが、大陸からの様々な影響があったであろう。そのようなことから、日本にとって、大陸諸々からの攻撃を防ぐために重要な場所でもあった。
気候的には暖かいところで、五百メートル前後の山がいくつかあり、原生林が覆っている、自然の宝庫である。一つの例が、あの有名なツシマヤマネコである。山猫は日本には二種類しかいない。あとの一種は西表島のイリオモテヤマネコである。それ以外にも、対馬島でしか見られない昆虫がいる。植物も特有なものがあるが、茸に関しては、調査が十分でないこともあり、この地特有なものの報告がない。しかし、椎茸の栽培に適したところで、華茸と呼ばれる大きく、味の濃い立派な椎茸が生える環境にあり、未発見の茸も多いに違いない。
古い家が多く、蔵には昔の書物がたくさんしまわれている。その中に対馬のことを個人的に書き残したものもあり、これから紹介するのは、その一で、茸が面白おかしく書かれた民話的なものである。
この地に生える茸の一つ、ショウゲンジにまつわる話だ。正源寺と書くが、信州では虚無僧、名古屋あたりでは坊主、などとも呼ばれ、よく食べられている。だが対馬ではこの茸を食べることはなかった。その昔は、食毒不明の、しかし、よく見かける茸程度に認識されていたものだった。名前のとおり,坊さんのような風貌である。
これは津島の霊峰、白嶽(しらたけ)に名前がつけられていないころの話である。
真夜中、林の中の落ち葉の間から茸が顔を出した。周りにも仲間の茸が頭を出している。
「今日はええ具合の暖かさじゃ、ショウゲンジにはいいのう、みんなも顔をだすことができたのー」
はじめに頭を出した茸が、すこしばかり背がのびて、まわりを見回した。まだ頭だけのものもいる。何故関西弁をしゃべったが、理由はまったくない。何しろ、土の中ではみんなつながっていて、海の底の土の中を菌糸がのびて、日本列島すみずみまでいきわったっているので、どの地方のことばを話すか、茸は生えてみないと分からないのである。
「早く出てこんかい」
そう言って急かすものだから、周りのショウゲンジも面倒臭そうに伸びてきた。
「そんなこと言ってるから、虫に食われちまうんだ」
「へえ、ショウゲンジはうまい茸ですからな、しょうがおまへんな」
「人間に知られたら、みんな食われちまう」
「対馬の人間はショウゲンジのことを知りませんから、大丈夫でっせ」
「それはそうだ、ここの人間はみんな椎茸ばかり食っている」
「椎茸の連中に人間は任せておきましょうや、大将」
「そうだな」
ショウゲンジがあたり一面に育ってきた時、ばさばさと鳥が舞い降りて来た。ショウゲンジたちは喰われちまうと戦々恐々となったが、茸は動けない。
「こんな時動けたら逃げることができるのに」
ショウゲンジの大将がこらえきれずに、身をよじったのだが、どうしようもない。
大きな鳥は下草の中に降りたつと、すでに鼠をとらえていた。それを見たショウゲンジはすこしばかりほっとした。
大きな鳥が鼠をくわえて木の上に飛んでいった。
「あの鳥は肉食だった、よかったな」
ショウゲンジの大将はほっとして、ちょっとふにゃっとなった。
「あの鳥はなんだったのですかい、大将」
「知らねえな、夜に飯食うなんて、なんてやつだ」
そこに、大きな猫が顔を出した。
ショウゲンジはまたおどろいた。と、猫が言った。
「あいつはオオコノハヅクだ、俺が狙っていた鼠をかっさらっちまいやがった」
「大きな猫さんよ、おいら達のことばがわかるんかい」
「ああ、対馬の生きものは、茸がしゃべろうが、草っぱや木がしゃべろうが対馬同士ならみんなわかる」
「へえ、対馬にしかいねえ生きものっていうと、お猫さまはそうなんで」
「そうだ、ツシマヤマネコだ」
「わっちらはショウゲンジという茸でやんすが、すると我々も対馬の茸でしょうか」
関西弁が関東弁になったようだ。わっちは吉原ことばから、やんすは江戸も上方も使う。茸の話しことばはいい加減だ。
「きっとそうだ、大陸にも日本本土にもいない茸だ、対馬で生まれたのだろう」
「へえ、それじゃ、ツシマショウゲンジってことですか」
「そうだろう」
ツシマヤマネコはそう言うと鼠を探しに行ってしまった。
林の中が明るくなって来た。日の出だ。
「おい、みんな、俺たちは、大陸にも日本にもいねえ茸だそうだ」
「大将、だけど茸だよな、何とか他の茸より立派になりたいねえ」
「さっきから聞いてりゃ、いい気なもんだ、花も咲けねえのによ」
そう言ったのは虫だった。
「お前さん、話ができると言うことは、この島の住民だね」
「ツシマカブリモドキだ」
「マイマイかぶりかね」
「そんなもんだ」
マイマイカブリはカタツムリに頭を突っ込んで喰っちまう虫だ。
「おたくさん、茸は華だってことを知らないのかい」
「花ってのは、ぱっと咲いて、実をつけるんだ、あんたら茸に実がなるかい」
そう言われたツシマショウゲンジたちは考え込んでしまった。確かに、胞子をパーッと撒き散らしておしまいだ。シツマショウゲンジの心が読めるのか、ツシマカブリモドキが言った。
「いいかい、動物ってのは、男と女がいて、子どもが出来るんだ、雄の魚はパーッと水に精子を出して、雌の魚は卵を産んで、精子と卵子がくっついて子供になるんだ、植物だって、雌しべに雄しべからの花粉が付いて、実ができて、中の種が子供になるんだ」
茸には雌雄がない。ショウゲンジは虫に雄と雌があることが羨ましい。
本当は茸が動物と植物の後から進化してきたのだから、動物植物よりもっと高度な生きもののはずなのだ、きっと、対馬の外のことを知らない茸だったからそう思ってしまったのだろう。ツシマショウゲンジは実というものにあこがれてしまったのだ。
ツシマカブリモドキが遠くにいる餌の蝸牛を見つけると、すっ飛んで行ってしまった。腹が減っていたようだ。
「大将、胞子じゃなくて、花を咲かせ実をならしてみたいものだな」
「そうだな」
「どうしたら胞子から実になるんだろう」
お昼近くになって、林の中はお日様の光で満ちていた。
ツシマショウゲンジたちが生えているところに、花のような花ではないような、橙色のものが生えてきた。
ツシマショウゲンジの大将がおどろいて、みんなに「気をつけろ」
と声をかけた。ショウゲンジたちが、何が出てくるのか見ていると、花のようなものが伸びてきて大きくなった。
「危なくはなさそうだ、だが我々の仲間なのだろうか」
形は花に似ているが、葉っぱはない。
「絶滅種だ」
その花のようなものは話す事ができた。ということは、対馬の生きものだ。
「お前さん、茸か」
「いや、花だ、ツシマラン」
「蘭は植物だ、それじゃ実がなるのか」
「残念ながら、まっとうな実はつけないが、植物だ」
「我々も花を咲かせ、実をつけてみたい」
「茸は植物より後からこの世に出てきた生き物、花を咲かせたいということは、進化ではなく退化することになるぞ」
この答えに、ツシマショウゲンジはなるほどとは思った。しかし、林を見上げると、アケビがたくさんなっている。ああいう、立派な実を成らしてみたいものだ。ツシマショウゲンジはアケビに声をかけてみたのだが、返事は無かった。どうもツシマだけの生きものではないようだ。
「ツシマショウゲンジのみなさん、我々ツシマランも実はできないが種は出来る」
「ほう、種は出来るのか」
「花粉が雌しべにつけば種ができる、種は粉のように細かいので風に乗って遠くに飛ぶ」
「そこは胞子と似ているな、だが、大きな種がつくりたい、それに種を包む実もならしてみたい」
「茸は雄と雌がないであろう、まず、雄雌をはっきりさせるべきだ」
というツシママランの忠告があった。
ツシマショウゲンジの大将は、
「まず、雄の胞子と雌の胞子をつくらねばならんな」と仲間に言った。
「どうやって」
そこに声がした。
「俺なんか、いや、あたいなんか、卵子と精子を両方持ってるのよ」
ツシマショウゲンジは誰が言ったのか周りを見た。
いた。萎れた羊歯の葉っぱによじ登っているオレンジ色のナメクジだ。言葉が分かるということは対馬にしかいないやつだ。そう思って、ショウゲンジの大将は「そこの、橙のナメクジ君、ツシマの生まれかい」ときいた。
「あたい、女よ」
「失礼、ナメクジさん」
「男でもあるよ、ツシマナメクジだ」
「まあ、どっちでもいいが、どうやったら両方もつようになれるんだ」
「生きものはその気になりゃあ、何でもできるのよ」
「そういうもんかね」
そこに、ツシマアマガエルがきた。食われては大変とナメクジはかなりの速さで逃げ出した。ツシマガエルが追いかけると、今度はツシママムシがやってきてツシマガエルを喰おうと追いかけた。ツシマナメクジはツシママムシに助けてもらおうと、追いかけ始めた。ところが、蝮は蛞蝓が大の苦手、蛙は蛇に食われちまう、対馬の三匹は、ショウゲンジの生えている周りを逃げ回った。
ツシマショウゲンジの大将は目が回り、「対馬から出て行けえー」とどなった。三匹はそれを聞くと、驚いて、三方に逃げていった。対馬にいれなくなったら大変だと思ったようだ。
一方、目が回ったツシマショウゲンジは、傘のひだの間がジーンと熱くなった。なにやら熱を持っている。胞子が熟してきたらしい。
「おい、お前ら、胞子が熟しちまったぞ」
「ええ、そのようよ」
「大将、だいぶ胞子が大きくなってきやした」
「そのとおりでござんす」
ツシマショウゲンイたちの様子が何かおかしい。男言葉と女言葉を話すやつが出てきた。
「何でえ、お前ら、雄と雌になったのか」
「そんなことはねえです」
「そのようなこと、ありませんわ」
さっきは女言葉のツシマショウゲンジが男言葉を話し、男言葉を話していたツシマショウゲンジが女言葉になった。
「あら、いやだ、かわっちまって」とショウゲンジの大将が女言葉になった。
傘の襞の中の胞子は、真っ白いものと真っ黒のものがある。
「おい、胞子がどうも雌と雄になったようだ」
ツシマショウゲンジの傘の中で、白い胞子の中に黒い胞子が入り込んだ。
「こそばゆい」
男言葉のツシマショウゲンジが身をよじった。女言葉のツシマショウゲンジも
「なんだか、傘の中がはれぼったいわ」と身をよじった。
ツシマショウゲンジの大将も「なんだか傘の下が痒いような、ちょっと変な気持ちだ」とぐっと我慢をした。
傘の襞の中では、緑色の小さな蕾ができはじめ、それが次第に大きくなって来た。
しばらくすると、大きくなった緑色の蕾が傘の下で開いた。中から真っ青な花が垂れ下がった。
ツシマショウゲンジの傘の下に花が咲いた。
大喜びだ。
茸は菌糸から出た花のようなものだ。それに本当の花が咲いた。花が花を咲かせたのだ。豪華なことだ。大将はしみじみと思っていた。
やがて、花はしおれ、青い実ができた。青い実はどんどんと大きくなった。
「なんだか、傘が重いなあ」大将をはじめツシマショウゲンジは柄を踏ん張った。
傘からつる下がった青い実は傘の半分もの大きさになったので、ツシマショウゲンジがしなった。
「立派な実がなったようだぞ」
ツシマショウゲンジの大将が周りのショウゲンジを見回した。
どいつもこいつも実がたわわに垂れ下がっている。
「嬉しいじゃないか、俺たちも実を作った」
ショウゲンジたちは実が重くなり、傘をのせている柄が膨らんできた。
「頑張ろうじゃないか」大将が周りのショウゲンジを励ました。
そしてとうとう、青い実が熟して真っ赤になった。中には大きな種が入っているはずである。
赤い実はツシマショウゲンジの襞から、土の上にぽたぽたと落ちた。
実は土に落ちるとぱかっと割れ、中から黄色い種がはじきでた。黄色い種は林の中の土の中にもぐりこんだ。
親のツシマショウゲンジたちは萎びてきた。
夕日が当たり始めた。一日が終わる、明日も晴れるようだ。夕焼けが綺麗だ。
夕日が海に落ちた。
薄暗い林の中の土の中から、種が芽を出した。小さなツシマショウゲンジの傘が現われた。種から茸が生えてきたのだ。
花が咲いて実をつけ、種をまいてしまった萎びたショウゲンジは、種から子供ができたことを喜んだ。明日の朝には立派なツシマショウゲンジになるだろう。
夜の間に、すくすくと大きくなった子供のツシマショウゲンジは立派だった。
親のツシマショウゲンジはもうすぐとろけてしまう。とろけながら大満足だった。実をつけることのできる植物茸が生まれたのだ。
ところが、土の上ですっくと立った若いツシマショウゲンジは言った。
「父上、母上、ありがとうございました」
言い終わると、ぴょこんと土の上に飛び上がった。
朝日が林の中に差し込んできた。
育った若いツシマショウゲンジの傘が黒くなった。傘の下から黒い衣が垂れ下がった。一部のショウゲンジの傘は白いままだ。そいつらの傘の下から白い衣が垂れ下がった。
黒いショウゲンジと白いショウゲンジは一列になって歩き出した。雄と雌のショウゲンジのようだ。
「我々はコムソウ茸になり、この山の頂で修行を続け、子孫を残しまする、父君母君、おいとまいたしまする」
口上を述べると、列をなし、林の中を頂上に向かって登っていった。
ぐずぐずに溶けた大将だったツシマショウゲンジは、
「植物茸ではなくて、動物茸になりおった」と独り言を言った。
こうして、ツシマショウゲンジは退行進化をとげて動物になった。まだ人間にはみつかっていない。今でも実をつけ、種から動物が生まれる動(どう)茸(じ)という生きものとして、対馬の霊峰、白嶽の険しい石灰岩の中で修行をしているそうである。
しかも、本土の霊峰と呼ばれる山々にも、まだ数は少ないが住み始めているということだ。
読み終わった。
眠くなってきた。ツシマショウゲンジたちが寺に入っていくのが見えた。虚無僧のようだ。大広間に入ると祭壇ができていた。お棺の前に遺影が立てかけてある。見ると私の写真だ。ツシマショウゲンジたちの読経が聞こえてくる。そのまま眠りにおちていった。
あくる朝、気持ちよく目覚めると同時に話を思い出した。
面白い話しであった。
これは、対馬に行ってみるしかないであろう。著者に会って、話が聞きたい。春ならばいい気候だあろう。連絡をして一週間後に行くことになった。
長崎まで新幹線と九州新幹線を乗り継ぎ、長崎空港にたどりついた。かなりの旅行である。そこから四十五分、対馬空港に下り立った。待ち時間をいれたら、家から五時間半かかった。もちろん、笑子さんを介して、対馬の筆者には連絡してある。乙成(おとなり)さんという方である。
私が行くととても喜んでくれた。住所は津島市三津島町洲藻である。白嶽神社があるところである。
おそらく同じ年くらいだろう。洲藻白嶽神社の檀家さんでもある。
「よくこられましたな、対馬は韓国とも近いし、日本の領土でもある。経済的には日本に維持されてますが、韓国などの外国からのお金も馬鹿にならない。祖先は確かに、縄文時代の人間から始まるかもしれませんが、やっぱり、大陸からの影響は強いものであったわけです。特に弥生時代からは。残っていた古文書の意味というのは、ある分野では大変な価値があるでしょうけど、語草片に紹介したものは、この町からも、県からも、国からも相手にされるようなものではありません。酔狂な男が書いたものの可能性があるからです」
背の低いずんぐりした、茸のような風貌の乙成さんは、大きな自宅の蔵に案内してくれた。蔵にはたくさんの古文書が積んであった。
「これらはにはそのような話がたくさん書かれています。すべて同じ男が書いたものです。紹介した茸の話だけではなく、話の中にも出てきたツシマヤマネコや虫、蛙、蛇、植物など、対馬の生きものの滑稽話が書かれています。伝承ではなくて、その男の作り話なのだと思っています。古い時代によくあんな素っ頓狂な話を考え出したものです」
確かにその通りである。
その原本を見ると、確かに古いもので、乙成さん自身の創作ではない。彼はそれを現代訳にしているという。いずれ、一冊の面白い本になるだろう。
その後、椎茸を食べさせてくれる店に連れて行ってくれた。
「猪も良く獲れるのですよ」
彼は、椎茸がたっぷり入った猪鍋を注文した。
「それで、あれを読んで、私も動茸に興味を持ちましてね、一時、白嶽には毎日のように登りました、捜し歩いたのです」
彼はそんな話をした。
「今は登らないのですか」
彼は頷いた。どうして登らなくなったのだろう。
「あれは創作ではないのですか」
そう聞くと、私を見て首を縦に振った。
「まさか、動茸に会われたのではないでしょうね」
彼はちょっと目じりに皺を寄せて、軽く頷いた。その後、動茸についていろいろ聞いた。身軽な茸で、石灰岩の穴の中で暮らしているという。頭がいい連中で、決して人には見つからないだろうという。
「話が出来るのですか」
「私も対馬の人間ですから」
乙成さんは笑った。
「かわいいやつらですよ」
そう言った。どこまで本当なのか、私にはわからない。
「ししの肉も柔らかいし、美味しい椎茸ですね」
「そうでしょう」そう言った乙成さんは、猪肉や野菜を食べてはいるのだが、椎茸を食べようとしない。不思議に思って聞いた。
「椎茸はお嫌いなのですか」
「共食いになっちまう」
彼は小さい声で言った、そして私を見て笑った。ふっと椎茸の香りがした。
茸の華実(かじつ)-茸書店物語8
私家版 第十茸小説集「語い草片、2021、246p 一粒書房」所収
版画:著者


