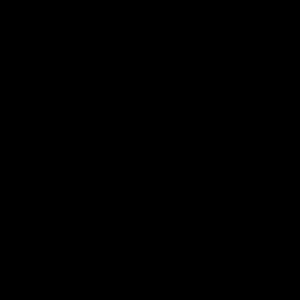赤
人物紹介
◆佐島(さとう)
桜城学園1年D組。
ふとした時に鼻血が出てしまう謎の体質を持ち合わせた少年。
その体質が仇となり、長年学校生活でも家庭内でも馴染めずにいる。
静かで、冷静沈着。人に心を開かず、空虚な生活を過ごしてきた。
◆須々木(すずき)
桜城学園3年A組。
天真爛漫な性格の持ち主で、いわゆる陽キャというポジションで学園生活を謳歌していた。
ある日、後輩にちょっかいを掛けるという罰ゲームという名目で佐島と接する。
◆桜城学園
とある離島にある島唯一の高校。
島特有の閉塞感のある文化を持っており、過ごしやすい人間にとっては温床となっている。
第1話
暑さもだいぶ薄らいで、金木犀の香りを辿る時期になってきた。島唯一の高校「桜城学園」の3年の俺――須々木は今日も学園生活を謳歌している。
「はい須々木の負けー!」
「えー!嘘だろ!」
確か、しょうもないゲームだったと思う。俺は負けた悔しさ半分、ゲームの面白さでテンションが上がっていた。小突かれる頭が多少痛んでも、何とも思わない。俺は両手を挙げて降参のポーズを取った。
「で?罰ゲームって何?」
「それは~…」
俺は目隠しをされ、友達に押されるがまま歩いた。友達がニヤニヤと湧き立っているのが雰囲気で取れて分かる。「ジャン!」とパッと目隠しを取られ、飛び込んできた突然の明るい景色に目を細めた。
「…ここって…生物学部の部室…?」
友達みんな揃って何度も頷いている。ここが何だと言うのだろうか。俺は話が分からず、生物学部の名前と友達の顔を交互に見た。その中のひとりが教室を指さし、声を潜めてこう言った。
「ここにいる奴にちょっかい掛けて来い」
「はあ⁉ それは度が過ぎてるだろ!俺達だけなら良いけど、知らん他人を巻き込むのは…」
「いーって、いーって!どうせここにいるのは1年坊だけだしさ」
「後輩だからって、そりゃ…」
言い出したら止まらない友達の勢いに気圧されてしまう。頼まれたら断れない性格がここで裏目に出てしまった。俺は何も言い返せず、あたふたしてしまう。
すると突然、言い出した奴の隣の奴が教室の扉を開けて、俺をドン!と突き入れた。うわ、とアホな声と一緒に入り込んだ俺は、後ろを振り返ると既に扉は閉ざされ、友達が行け行けと言わんばかりの好奇心に満ちた目で俺を見ている。その中のひとりが奥を指さしていたので視線を向けると、目を丸くした1年の少年がこちらを見ていた。姿を見られてしまい、ましてはバックには友達が見ている手前は「間違えました」なんて言って出て行く度胸も無い。
「…あ、あのー……」
そもそも、ちょっかいって何だよ。失礼過ぎるだろ。俺は友達のそういう所が苦手なんだよな、なんて脳の片隅で思いながら、何を言って出て行こうかと思いあぐねていた。1年の少年は未だこちらを、目を丸くして見ている。
「…き、キミさ、1年?」
問うても、返答がない。それもそうかもしれない。突然やってきた先輩に驚いて、何を言われたのか、というか俺の声が小さ過ぎて聞こえたのかすら怪しい。俺はもう一度言おうと口を開くと、同時に目の前の1年は突然顔を手で覆った。
えっ、と俺は慌てて駆け寄ろうとする。どこか具合が悪いのなら、どうにかしなければ、という気持ちの衝動だった。しかし1年は押さえていない方の手で俺を制し、首を横に振る。どうしたのだろう、と俺はひとり慌てていると、指の隙間から赤い、真っ赤なそれが、滴る。
真っ赤なそれは、紛れもない鼻血だった。それと同時に少年の顔が赤らんでいく。
同時に俺は、何ていけない事をしてしまったんだ、と頭の中が真っ白になっていくのを、引いていく血の気と共に感じていた。
続
第2話
「マジうけるわー。普通ビックリしただけで出る?鼻血とか」
「俺、ガキの時にぶつけて以来出した事ねえよ」
俺の机を囲んでゲラゲラ笑っている友達の声が、思考の片隅で嫌にこだまする。正直、うるさいな、と思っていたのだが、俺は窓から外を見て苛立ちを紛らわせていた。今日も海がきれいだ、なんて思っても、友達の嫌な笑い声は教室内を響かせている。そのうち、女子も「なになに?」なんて言って群がって来て、たちまち教室内はあの1年の少年の話題に持ち切りになった。
「あ、うちその子知ってるよ。いつもひとりでいる子でしょ?」
「顔きれいだからさ、良いよねって話してたんだけど。この前いきなり走り出してさ、先生たちもビックリしてんの。何?って」
「そしたらさ、顔覆ってて。よく見たら鼻血出てたんだよ」
「急に興奮する変態なの?って。めちゃくちゃ気持ち悪ってなってさー。超萎えたの」
「萎えたとかかっこいいとか、お前ら主観の話はどーでも良いけど、やっぱ急に鼻血ってめちゃくちゃおもしれえな」
ゲラゲラと笑う友達を横目に、何が面白いんだ、と俺は罪悪感と戦っていた。ムスッとしている俺を見た友達が、肩に腕を回して寄り掛かってくる。
「何不機嫌な顔してんだよ。海そんな好きだっけ?」
「…まあ」
「いいなー海。今年も行けて良かったよな!来年も行きてーなー」
「来年って俺ら、島にいるかも分かんねえよな。卒業だし」
卒業とか寂しい事言うなよ、と反応する友達の声と同時に先生が教室に入ってくる。授業だぞ、の一言で机に戻る俺達は、比較的良い子なのかもしれないけど。昨日の事で頭がいっぱいになって、正直授業とかどうでもよくて。
先生も、あいつの事、変って思ったのかな。
海見に行こうぜと言う友達の誘いを適当にあしらって、俺は昨日と同時刻にとある教室の前に立っていた。
「生物学部…」
思えば、この部活って普段何してるんだろう。昨日は頭がいっぱいで何も考えられなかったな。ノックをするが返答がない為、恐る恐る中を覗き込む。中には誰もいないようだ。
「失礼します…」
何となく悪い事をしているようで、声も潜まる。辺りを見渡すと、水槽やら試験管やら、生物というか、化学っぽいものばかりが溢れているが、きれいにきちんと整頓されていた。これもあいつがきれいにしているのだろうか。
金魚をこんなに近くで見たのは、ガキの時に母ちゃんに連れてって貰った本土の水族館以来だ。こんなに大きくなるんだな。そういえば、金魚って仲間も食べて大きくなったりするんだっけ。何だか、無慈悲っていうか、弱肉強食っていうのはこういう事なのかなというか。
何でも恰好の餌にしたがるのは、俺達人間と同じだな。
「あの」
突然背後から掛かった声に俺は驚いて、背筋をピーン!と伸ばす。声が出なかっただけ褒めて欲しい。声の方を振り向くと、昨日の1年の少年が袋を抱えて俺を怪訝そうな目で見ていた。
「…また、いたずらでしょ?」
その言い草にカチンときた俺は1年の前に立ちはだかり、距離を詰める。こうして見ると1年は結構、背が低かった。真っ黒で細い毛質の猫毛はすとんとまっすぐ眉の少し下あたりまで下りていて、形の良いきのこみたいなシルエットだ。
「いたずらじゃねえ」
「じゃあ、何ですか」
「何…、何…と、言えば…その……」
1年は溜息をついて、袋を開けて水槽の前に立ち、スプーンで袋の中の物を掬い、水槽の中にそうっと入れていく。成程、それは金魚の餌だったのか。
「どうせ、からかいに来たんでしょ。変態って」
聞いた事のあるフレーズにギク、となる。同時にゲラゲラ笑っていた友達と女子の顔が次々に浮かんだ。手に汗を握り、俺は1年に身体を向けた。
「違う。からかいに来てなんかない」
「じゃあ何ですか?また罰ゲームですか?」
「罰ゲーム、でもない」
何だ、この少年には何もかもお見通しだったのだ。俺は急に恥ずかしくなって顔を背けた。改めて、なんて失礼な事をしていたんだ、と昨日の自分が恥ずかしくなった。
「いいですよ、別に」
そう言う少年の声は無機質だ。歳相応とは、とても思えない。
「慣れてるんで、そういうの。今更どうこう思わないですよ」
そう言って少年は机に腰を掛け、俺を見据えた。真っ黒な瞳は、何も宿していない。こちらの出方を伺う訳でもなく、ただ、どうぞお好きに、という感情だけは読み取れた。
俺はそれにまたカチンときて、少年に再び詰め寄った。
「嘘つけ。お前、昨日顔赤らめてたじゃねえか」
「別に。生理現象じゃないんですか。誰しも、見られて気持ち良いもんじゃないでしょ」
そう言われて、ぐっと言葉に詰まる。人の身体の事をネタにするなんて、改めて、残酷だと思った。女子も、友達も、俺も。
「用が無いなら出て行って貰えますか?いつまでも笑いものにされるの、慣れてるとは言えど、良い気持ちはしないんで」
「違う。俺は謝りに…」
少年は手で制し、目を細めた。首を傾げて、心底だるそうに、俺を突き放す。
「情けとか同情とか要らないです。悪いっていう言葉も要らない。言われても何も響きませんよ。現に教室とかで笑ってるんでしょ?」
「そんな、俺は…」
「噂、回ってきてますから。ボクの教室まで。同学年の次は、3年の先輩に笑いものにされてるってね」
カッと顔が熱くなるのを感じた。見られて、同時に俺は顔を俯かせる。それと同じですよ、と諭され、少年は水槽の前に屈む。金魚を見て、何か手帳を付けているようだった。少年の視界に俺はもう、入っていなかった。俺は黙って教室を後にする。
俺はあいつらと違うと、胸を張って言えなかった。
続
第3話
「佐島!」
1年の廊下で大勢の視線を集めているのは俺――須々木だ。佐島、と呼ばれた見慣れた黒いきのこ頭は、パッとこちらを振り返った。同時に目がみるみる、丸くなっていく。
佐島ってあの子?あの鼻血の…。ノイズが次々に飛び交い、それはざわめきと化していく。俺は構わず黒いきのこ頭に近寄り、腕を組んで見下ろした。
一瞬、少年の――佐島の目に恐怖の色が浮かんだ。
「授業終わった?」
「…え、…はい。終わりました、けど…」
俺は佐島の手を掴んで引っ張り、ずかずかと人を押し退けて歩いた。佐島の手からファイルやら教科書やらがバラ撒かれたが、それすらも無視した。後ろから聞こえる佐島の声がみるみる震えて、小さく萎んでいく。
クソ、こういう時に限って、元来色素が薄くて明るい髪色に見える俺の髪が悩ましい。まるでいじめの対象を攫っていくヤンキーみたいな絵面だ。終いには佐藤は何も言わなくなっていた。
掴んだ佐島の手がじんわりと汗ばんでいくのを感じていた。
「ようし、邪魔者はいなくなった」
「…って、ここって…屋上…?立ち入り禁止じゃ…」
「良いんだよ。他の所いたら邪魔が入るだろ」
佐島はさっと顔を俯かせる。身体が小さく震えているのをしっかりと見た。昨日の言い草は、所詮強がりに過ぎない。俺はそれを見通していた。
「佐島」
俺は佐島の前に立ち、腕を再び組んで見下ろした。一向に目を合わせてくれようとしない佐島に、俺はだんだん胸が限界を迎えつつあった。そして、俺は衝動のまま、頭を下げた。
「すまんかった‼」
暫しの静寂。そして、佐島の、えっ、という声に俺は更に頭を下げた。
「昨日、謝ろうとして、お前の強がりに気付けずに!そのまま帰ってしまった!」
俺は佐島の目を見て、緊張で震える声で、情けない姿だなと客観的に思いながら、ひたすら謝った。
「…甘えていたんだ、俺は。それに…酷い事をした。謝っても謝りきれないくらい、酷い事を。それなのに気圧されたとか、何とか、言い訳ばかりして…友達には良い顔して。そんなの…許される訳がない。だから」
佐島が息を飲んで、細い喉仏が上下するのを見た。
「赦してくれなくて良い。俺を罵倒しようが、軽蔑しようが、佐島、お前の思うままにしたら良い。でも、これだけは言わせてくれ」
俺は深々と頭を下げて、額が膝につくくらい身体を丸めた。
「本当に、ごめん」
次の授業のチャイムが鳴り響いて、長い時間そうしていたんだと改めて体感した。佐島は溜息をついて、顔を上げて下さい、と言ってから、顔を背けて、口を開いては閉じて、と繰り返していた。そうしてやっと、佐島の声が聴けた。
「…変人って、言われません?先輩」
「…何も考えてない馬鹿とは言われる。けど、良し悪しはきちんと、分かってるつもりだ。だけど…あんな事をしてしまって、俺…佐島にも、佐島の母ちゃんたちにも悪くて……」
「…ふふ」
佐島は口を押さえて、肩を震わせている。きょとん、俺は膝に手をついて佐島を見上げていた。佐島は首を傾げて、目を細めた。
そして、
「あのね。罰ゲームに付き合わされる方の身にもなって下さいよ」
俺を、予想もしない俺を、予想もしない角度から、突き落とした。
暫く、何を言われたのか分からず、言葉尻が頭に降りてきてから、えっ、とだけ声を上げた。
「違、罰ゲームなんかじゃ…本当の…」
「授業、遅れたの初めてだな。何言われるんだろ…鬱陶しいな」
「佐島…!」
佐島は背を向け、屋上の扉に手を掛けて、顔だけこちらに向けて、歪に笑んだ。
「遊ぶつもりなら、勝手にどうぞ。さようなら」
錆びた扉が閉ざす音が、非情に俺と佐島を隔てた。
馬鹿野郎、と、行き場のない利己的な罪悪感が、胸を渦巻く。自己陶酔だけの謝罪、だったのかもしれない。俺は、心の底から申し訳ない、と思っていた。しかし、佐島には届かなかった。それは、もしかすると、やはり、少しだけエゴが入り混じっていたのを、佐島の黒い瞳が見通していたのかもしれない。
かもめの声が、俺の心の底を笑うように、頭上を通り過ぎて行った
続
第4話
悲しいかな、もう見慣れてしまった1年の廊下の風景に、俺は溜息をついて腕を組む。1年にこそこそと噂話をされるのも慣れた。同級生の友達に変な目で見られるのも、慣れた。
「…先輩」
「佐島!」
後ろから声を掛けられて、パッと振り返ると、見慣れた黒いきのこ頭がこちらを見上げていた。佐島は俺よりも深い溜息をついて、呆れたように首を横に振る。
「もう良いですって。これだけでも噂になってますから」
「俺が噂になるのは良いけど、お前を巻き込んでしまっているのは申し訳ないな。ごめん」
ふい、と顔を背けて、俺の言葉を無視した佐島は、教科書を胸に抱えて俺の前を通り過ぎていく。俺はそれを慌てて追い掛け、後ろから必死に声を掛けた。
「つ、次の授業は何なんだ?」
「別に。関係ないです」
「得意教科か?と、得意なら、生物とか…」
「1年は生物は必須科目じゃあありません」
1年の時から適当に授業を受けていたのが仇になった。周りが不真面目な友達が多いというか、この島特有の文化というか。
そもそもこの島では、残る者と出て行く者の二択に分かれる。その際、歴然としてくるのは、残る者と出て行く者の、学力であるとか、社会能力であるとか、そういった一般的な、いわゆる「常識」というものの差が表れてくる。俺は勿論前者で、出来ればこの島で、ぬくぬくと生きていきたいなんて、ぼんやりとしか考えていなかったから、学校生活なんて適当だし、何とかなる精神でこれまでやってきた。何せ俺は、特段この島内で変な噂も立っていないし、嫌われていない。
出て行く者の特徴として、主に転勤族であるか、もしくは本土に興味があるか、それか変な噂が立ち、嫌われ、出て行かざるを得ない状況に陥るかのどれかである。佐島の場合、どうなのだろうか。やはり、島を出て行きたいのだろうか。多分、そうだろう。ここまで、というと失礼な物言いになるかもしれないが、現実問題、ここまできてしまうと、出て行かざるを得ない気もする。
俺がもしその立場だったら、佐島のように気丈に振舞えるのだろうか。
「先輩。チャイム鳴ってますけど」
「あー…そうだな。遅刻だ」
佐島は教室に入ろうとして、少し立ち止まり、ふいに俺の方を振り返った。さらりと流れる黒髪が女子みたいで、まるでこの島の潮風なんて気にもしていない気強いその髪に、どきりとした。
「先輩って、馬鹿ですよね」
「ばか?」
ターン!と目の前で扉が閉まる。あれ、これ、デジャブじゃね?
須々木、職員室に来い、と先生に肩を掴まれても尚、佐島の「馬鹿」が頭の中をこだましていた。
佐島、お前。気が強いのか、弱いのか、俺はだんだん分かんなくなってきたぞ。
職員室の中で先生に説教をされながら、俺は佐島の事だけを考えていた。
続
第5話
「あれ、鼻血くんじゃん」
「…!」
購買でパンを買いに出ようと言ってきた友達の付き添いをしに来ると、ばったりと佐島と出会ってしまった。思いがけない偶然に驚いているのは俺だけではなく、佐島もらしいが、どちらかと言えば友達が言った「鼻血くん」と言う言葉にぎくりとしたらしい。俺は友達を小突いた。
「馬鹿。変な事言うな」
「は?だって、こいつそうじゃん。お前の顔見て鼻血出してさァ」
「声でかいって…!」
佐島は俯いて、パッと踵を返し、その場を去って行った。あ、と言う俺を変な目で見てきた友達が俺をじっと睨み、パンを買いながらふと言った。
「あのさー須々木。お前何考えてっか知らねえけど。変な事言ったらお前もあいつみてぇになるんだぜ」
「どういう、…」
友達の目は、いつもみたいなふざけた表情をしていなかった。冷たく、凪いだ色をしていて、小学からの付き合いだが、初めてそんな目を向けられた。
「そのまんまの意味だよ。島に残りたかったら余計な事すんなよ」
てめぇも、てめぇの家族の為にもな、と友達は俺の肩をぽん、と叩いて教室へ足を向ける。島から、出て行かなければならない。俺はさっと血の気が引いていくのを感じた。
俺がやっている事は、いけない事なのだろうか。
「あげる」
何となく屋上にいる気がしたので向かってみると、案の定佐島は屋上のダクトの上に座り、ぼんやりと空を見上げていた。佐島の膝にいちごジャムパンを乗せると、佐島は目を丸くして俺に視線を移していた。
「何で」
「何で、って…俺達のせいで買えなかっただろ」
佐島は、違う、と首を横に振る。
「あれだけ言われてたじゃあないですか。脅されてもいた。ボクみたいになるかもしれないって、言われてたのに…」
「ああ、その事か」
座って良い?と一応断りを入れて、よいしょ、と佐島の隣に座る。気温が心地良い気候だ。俺は空を見上げて、雲を指さした。
「あれさ、いつまであの形でいられると思う?」
「…あの雲ですか?」
「そう。いつまであの形でいられるか」
佐島は、考えた事ないです、とパンを両手で持ち、視線をそちらへすぐ移した。
「俺もさ、分かんないんだよね」
「…答えのない問いをしないで下さい」
「ごめん。でも、いつまでもあの形じゃあないって事は分かるんだ」
「そんな事、ボクにだって分かります」
だよなー、と俺はパンの袋を開けて、ひとくち齧った。お前も食べたら?と促すと、ようやっとパンの袋を開けて、佐島もひとくち含む。リス食いなんだな、と脳の片隅で思った。
「俺達だって、いつまでも同じ形じゃあないんだよな」
雲が流れていく。そうして次第に、雲の形が徐々に変わっていく。丸みを帯びていた大きな雲が、散れ散れになっていった。
「いつまでも、一緒じゃあないんだよな。だからって、無理に変えようとも思わない。あいつらと一緒にいるのだって、何らかの縁だし。だから、あいつら、酷い事言うけどさ、嫌いになれないし。あんな脅され方したって、あいつらが俺の事嫌いって言うまでは、何も出来ないっていうか。何もしたくないっていうかさ。うーん…難しいけど」
「…それ、悪口言われてるボクに言います?」
「そうだな。でも、こうしてお前と話してるのも、何かの縁なんだよ」
「ちょっと無理矢理な気もしますけど」
しつこいっていうか、馬鹿だからなー俺、と笑うと、佐島は空になったパンの袋を綺麗に畳んで、立ち上がり背伸びをした。
「でも、何だか不思議です」
「何が?」
「貴方みたいな人、初めて会ったから」
個性的、と言われて褒められているんだろうか。俺は、いやあ、と頭を掻くと、褒めてません、ときっぱり切り捨てられてしまった。
「探しちゃうんですよ、無意識に。先輩、今日来てるかなって。ボクの日常に割り込んできて、本当にしつこい人です」
「俺を?探す?」
マジで?と聞き返すと、佐島は顔を真っ赤にした。咄嗟に手で顔を覆うと、次第に指の隙間から鼻血が溢れ出す。うわあ、と驚いた俺は慌ててハンカチを佐島の顔に押し当てた。
「だ、大丈夫か」
「だ、だ、だいじょうぶ、っていうか、ハンカチ…っ」
「ハンカチ?母ちゃんが持って行けって毎日うるさいから持ってるんだよ」
「ちがう、そういう事じゃなくて…」
いいから、と俺は佐島にハンカチを渡す。佐島は、ぺこり、と律義に頭を下げて、ハンカチを鼻に押し当てながら、視線を泳がせた。
「…汚しちゃって、…」
「あー気にすんな、気にすんな。たまに俺も血まみれで帰るし」
「血まみれ…⁉ 何で…?」
「喧嘩。この髪色だからさ、目付けられやすくて。それでボッコボコ」
けらけら笑う俺を、不思議そうに見上げる佐島の顔は赤らんでいる。やはり、鼻血が出ると血色が良くなるのだろうか。
「…よく、無事でいられますね」
「空手やってたから。逆にやっつけるんだぜ」
ヒーローのパンチみたいな構えをすると、佐島は目を細めた。その瞬間が陽に照らされて、きらめいて見えた。俺はまたどきり、として、佐島を見つめてしまう。多分、相当なアホ面だったと、思う。
「先輩って馬鹿強いんですね」
「…お?お、おお…そうだな…」
佐島は時計を見ると、もうすぐだ、と少し焦りの色を見せる。ハンカチを離した鼻に少し血がついていたから、咄嗟に指で拭った。
「…え」
「…あ」
しまった、と思ったら、佐島は咄嗟に顔を背ける。機嫌を損ねてしまったのだろうか、と慌てたが、耳から顔まで真っ赤になっていた為、また具合が悪くなったのだろうか、と心配になる。しかし差し伸べようとする俺の手を、佐島は拒んだ。
「ハンカチ、ありがとうございます。きれいにして返しますから」
「え、あ、ちょっ、」
佐島は踵を返し、屋上の扉に手を掛ける。声が飛び出したのは、咄嗟の事だった。
「明日も!ここで、待ってるから!」
風に乗って、佐島が振り返る。やっぱり、陽に照らされても真っ黒なその髪は、いつ見てもどきりとする。佐島は目を丸くして、ふんわりと笑みを表情に乗せた。
屋上の扉が閉ざされる。あれ程心地良いと思っていた気温が、今度はシャツの下の肌を蒸すような温度まで上がっていた。いや、これは、俺の体温か。
呆然と立ち尽くす俺に、先生の怒号など聞こえやしない。俺は、初めて見たあいつの笑みで、胸がいっぱいになっていた。
「…笑えば、すっげぇ良いじゃん」
続
第6話
「いたいた~」
クールに登場してやろうと思っても、やはり顔を見るとニヤけてしまう。俺は屋上にひょいっと足を踏み入れると、むすりとした顔の佐島の隣に座った。
「何で佐島が先に来たの?」
「それはこちらのセリフですよ。何でボクが先に…」
「来てくれたんだ」
目をじっと見つめて笑むと、佐島は唇をへの字に結んで、顔を逸らした。
俺はすっごく嬉しかった。佐島が約束を覚えてくれていたという事も嬉しかったが、来て、いなかったけど、俺を待ってくれていた事。しかも律義に、パンをふたつ持って。こんなに心が躍るのは久々だな、と足をぶらつかせると、佐島はぶっきらぼうにパンを押し付けてきた。
「昨日のお返しです」
気にしなくて良かったのに、と言おうとすると、佐島が同じ文句を被せて言った。
「貴方はそう言うでしょうけど、借りたままは嫌なので。あ、あとハンカチはクリーニングに出してますから。少し待ってください」
「ありがとー。律義なのね。優しいんだから」
しかも、きちんといちごジャムパン、ひとつだけ。どこまで几帳面なんだろうと俺はにんまり笑うと、佐島は怪訝そうな顔でじとりと見つめる。そしてすぐにパンを開けて、いつものリス食いでぱくぱくと食べていく。
「それだけで足りる?」
「それもこちらのセリフです。すみません、パンひとつしかあげられなくて」
「俺、もう早弁したから、結構良い感じのボリューム。食細いんだな、佐島。もっと食べて太れよ」
おなかを突こうとすると「ふもっ」と不思議な声を上げて佐島は避ける。口にパンが入ってるのか。面白い反応をする奴だ。
「気安く触ります?普通。知り合って間もないのに」
「まー男子だし。そういうノリって、あるじゃん?」
「知らないです。少なくとも、ボクはお断りです」
ケチ言うなよ、と俺もパンを食べる。いちごジャムの甘酸っぱさが、くすぐったいというか。今日は一段と身体をすっと逆撫でするような感覚が走った。
「いちごジャムって、もっと甘くて良いと思わねえ?」
「十分甘いと思うんですけど」
「いやあ、酸っぱいよ。このジャムだけかな?本土のジャムって、もっと甘かったりするのかな」
「同じですよ。どこでも、大抵は」
そういえば、佐島と本土の話をするのは初めてだった。今更言うが、本土というのは島内の人間が言う「日本列島」の事で、大まかに言えば大阪とか、北海道とか、いわゆる一般的な日本の事を言う。島特有というか、何となく「うち」と「本土」で文化を分けたがる癖があるというか。何かにつけて「本土は」なんて話をするのが、我々島民の考え方だったりする。
「佐島ってどこ出身?」
「東京です」
「と、東京⁉ そんな都会っ子だったのか!」
「実家はまだ東京にあります。ほら、ボクって垢抜けてるでしょう?」
「垢抜けてるっていうか、こまっしゃくれてるっていうか。へー、良いなあ東京。何でもあるし、不自由しないってイメージ」
「まあ、そうでしょうね。普通は多分、そうだと思います」
含みのある言い方をする佐島に言及をしようとしたが、佐島の真っ黒な瞳に何か、凪いだ海のような色が乗っていたから、言葉は喉を通って胃の中へ帰って行った。
「そういえば、佐島ってちょっと離れた所から来てるんだっけ」
「そうですね。車で来てます」
「大変だよなあ。高校、ここしか無いもんな」
そうですね、と顔を真っすぐに向けて、一向にこちらへ表情を見せようとしない佐島に、どうしてここに来たのか、いつからここにいるのか、家族の事とか、色々聞きたいが、なかなか言葉が出てこない。しん、と空気が静まった。
「あ、初めてだ」
「何が?」
「先輩と居て、こんなに静かになったの」
「誰がお喋りマシンだ」
「本当、尽きないですよね。感心します。同時に、羨ましい、かも」
ボクってほら、上手に喋れないから、と、佐島は制服から出てきた糸の端を弄りながら、声を細くして、ぽつりと零す。
「話せてるじゃん。こうして」
「それは先輩とだからですよ。普通のボクを知らない癖に」
「物静かでミステリアスって、ちょっと憧れるけどな」
「でもそれは、一緒に居たい理由にならない」
佐島はやっと初めて、俺の目をじっと見る。俺の目の中の湖を覗き込まれているような感覚がして、むず痒くなった。
「罪滅ぼしですよね、結局。ボクとこうして居るのって」
「し、失礼な奴だな!」
佐島はすぐに、でも、と言葉を繋ぐ。
「でも。楽しいです」
静かに、面を叩く水滴のように、呟く。
「罪滅ぼしだとしても。同情だとしても。ボクは、嬉しい」
あまりにも繊細な、声音だった。
さようなら、と去って行った佐島の、少し残る体温に触れる。
あの子は、どうして泣けないんだろう。どうして、涙を知らないんだろう。
寂しいと、素直になれないのだろう。
「…馬鹿だなー、俺」
髪をわしわしと乱暴に掻いて、頭を抱える。自分のこの不器用さが、昔から嫌いだった。もっと、きちんと、言葉を見つけられたら、佐島はもっと笑ってくれるに違いないから。
「……そうだ」
俺は顔をバッと上げ、咄嗟の思い付きに、思わずニヤリとした。
馬鹿は馬鹿なりに考えがあるんだぜ、佐島。
良い事思いついた。
続
第7話
「…大きい」
呆然と呟く佐島の背中を押して、中へ入るように促す。
「どうぞ~わが家へ、いらっしゃいませ」
「寒くなって来たからね、あったくして。ほらこっちあったかいから、おいで。ここは結構潮風が入り込むから冷えるんだよ。もうすぐごはんが出来るからね。ごはん、食べられないのってあるの?あったら言ってね。多かったら残しても良いから。ほら、うちって身体大きいでしょ?よく食べるから、加減が分からなくてね。しかし不思議だね。うちの子みたいなのが、こんなきれいなお友達を連れてくるなんて。来る子みんないい子なんだよ、島の子って感じで。でも、ほら、えっと…佐島くんだっけ。貴方みたいな華奢な子は珍しくてね。あら、あらあら、鍋が噴き零れそう!ちょっと待っててね。寝転んでも良いから、ゆっくりしてて」
嵐のような早口の捲し立てに、佐島は完全にフリーズしている。俺は苦笑いして、ごはんが出来るまで自分の部屋に、と案内した。
「うちの母ちゃん、やばいだろ。あれ普通だから」
「…カエルの子はカエル」
「言えてる。母ちゃんずっとひとりで喋ってやんの。毎日だぜ?」
キシシ、と笑い、お茶を勧めると、佐島は大人しく啜る。瞬間、目がパッと丸く開いた。
「おいしい」
「だろ?うち、茶園営んでるんだよ。もう何代目だっけかな。昔からあるらしくて」
「ほんとうに、おいしい」
佐島の素直な反応が嬉しくて、何だか照れくさくなってくる。作ってるのは父ちゃん。摘むのは母ちゃん。たまに手伝うのが俺。そう言うと、佐島は「へえ」と頷いて、じっと湯飲みを覗き込む。
「目で見ても旨い、がうちのモットー。お茶って飲むとほっとするだろ?呼ばれた先で出されたら、嬉しいのもお茶。コミュニケーションの入り口にもなるし。そういう面でもお茶ってスゲーんだぜ」
「確かに。お茶を出されると、嬉しいです。今も、そうです」
「まあまあ呼ばれなって、出されるとついつい飲んじゃうよな。俺もこの歳だけどさ、うちのお茶が一番うめえし、一番心がこもってるって思ってる。その形になるまでの過程を1から全部見てるからっていうのも、勿論あるけど」
「何だか、先輩らしくないですね」
夢があるって良いな、と佐島は呟く。俺は、佐島がそれ以上を言わない事を十二分に知っているから、言葉尻までしっかり噛み砕いて、飲み込んで、なあ、と声を掛けた。
「うち、手伝いに来ない?」
「…え、」
「うちの営業って島内だけじゃなくてさ、本土の人の手土産でも有名なの。戸数が多いから、商品にするのが大変で。な、お給料もちゃんと渡すし」
佐島は、はた、と目を瞬かせ、湯飲みを置いて、しっかりこちらを見て。そうして、頭を下げた。
「ボクで良ければ、是非」
「マジ⁉」
がたん、と机に膝をぶつけながら立ち上がる。思ってもいなかった展開に、俺は素直に胸を躍らせた。俺の言葉を、佐島が素直に受け取ってくれるなんて!
「母ちゃんも喜ぶよ!ありがとう、佐島!」
「い、いや…まだ手伝っていないし、実際やると、迷惑を掛けるかもしれないし…」
「そんなの1個も気にしねえよ!やったー!楽しみが増えたぞ!」
俺は佐島の両手を掴んで、同時に上に振り上げた。呆然と俺を見上げながら、ぶらりと万歳をする佐島があまりにも間抜けで、俺はゲラゲラ笑った。
「佐島、やったー!って言え!」
「え、えっ?」
「いいから!やったー!」
「や、やったー…」
俺は佐島を引っ張り上げ、ぐるぐると回りながら踊った。佐島は目をまんまるにしていたが、次第に柔くなっていって、すぐに吊り上がった。
「痛いです。離してください」
「へっへっへ、離すかこのやろ」
脇腹をガッと掴むと、佐島は「ひっ」と声を上げて、身を竦める。パッと赤らむ顔に俺はまずい、と慌てて手を離し、次にくる鼻血に身構えた。ティッシュ何処にやったか、なんて視線だけで探していると、佐島は顔を両手で覆い、来るか、とじりじり近寄ると、蚊の鳴くような声がぽつりと聞こえた。
「…先輩って、本当に馬鹿」
ばか。ばか?
ばかって、また言われた。というか、泣かせた?
俺は焦りを通り越して呆然としてしまい、重たい沈黙がふたりの間に流れる。母ちゃんの「ごはんよー」という声だけが、変に誇張されて流れて来た。
続
第8話
器用貧乏って、本当にこの世にいたりするのだろうか。俺は絶対にその言葉に当てはまらない人間だから、何となく、そういう新しい世界に惹かれたりもする。けれど、器用貧乏って言われる人たちは、きっと、虚しさであるとか、理想と現実の差にもがいたりするんだろうと、ふんわりとではあるけれど、察している。
対する、猪突猛進型の俺にだって悩みはある。馬鹿だな、とか、もっと言葉をたくさん知っていたら目の前の状況が良くなっていくのかもしれないのにとか。馬鹿は馬鹿なりの悩みがある。それを口にしても、そういう場面に遭遇しても、決まって周りは「馬鹿だな」と一蹴するだけなのだけれど。その度、お前が言うな、という気持ちと、そうだよな、という素直な俺が見え隠れする。そういう時にも、上手い回避方法の引き出しをたくさん持っていれば、なんて、無いものねだりをしたりして。自己嫌悪だって、勿論、ある。
「佐島、今日のメニューは何だと思う?」
「卵焼きは確定です」
「おー正解」
「激熱ですね」
パチンコのおっさんか、と隣に座りながら吐いて、小さな弁当箱を佐島に渡す。
佐島が俺の家に来て以来、佐島があまりにも母ちゃんの料理を旨いと食べるものだから、気を良くした母ちゃんが佐島の分まで弁当を作ると張り切りだしたのだ。本当に良いのか、迷惑なら遠慮しないで言ってくれ、と一応佐島に断りは入れたのだが、佐島はほくほくした顔で、何だかつい嬉しくて、と零し、母ちゃんと俺に深々と頭を下げたのだ。その様子に、新聞に穴が開くほど読んでいた父ちゃんすら、目を丸くして佐島を見ていた。本当に佐島は、希少な人間なのかもしれない。
「母ちゃん、明日からフルーツも添えるって」
「え、そんな、頂けるだけで十分なのに」
「良いって、良いって。その代わり、お手伝いしてくれたら、母ちゃんも父ちゃんも喜ぶからさ」
そこの所だけよろしくな、と俺は笑むと、佐島はこくりと頷いて、目をはた、と瞬かせて、また頷いた。
何となく、何となくだが、佐島はきっと、家庭の愛情というものに疎いのかもしれない、と失礼な物言いかもしれないが、推測をしていた。作ってくれた手料理を食べるのは久々だ、とも言っていたし、母ちゃんの会話に、うんうんと頷きながら相槌を打っていた姿は、まるで小さな子供さながらであった。
それでも、何故か佐島に家族の事を切り出せないでいた。何となく今っていう時期は、男子って家族を恥ずかしがる時なんだと思うから。俺は隠そうとしても、母ちゃんがあんな感じだから、学校でもちょっとした有名人だ。それに、島内唯一の茶園を営んでいるというステータスだけで、既に俺の家とは、というトピックが持ち切りになるのは、一時期の波ではあれど、1度や2度、それ以上の頻度で質問責めにあうのだから、もうすっかり慣れっこになってしまった。
「トマトがある」
「これ、島のブランド品なの知ってる?」
首を横に振る佐島に、俺はしたり顔で胸を張って言った。
「俺の同級生がやってる農園でさ、結構有名なトマトなんだよ。ブランドだから高いけど、お友達価格って事でこっそりお手軽値段で頂いてる。旨いんだよ。全国から注文きてさ、うちが落ち着いてたらたまに手伝いに行くくらい」
「この島は、本当に色んな有名なものに溢れてるんですね」
「そうだな。観光的な収入が大半かもしんない。魚も旨いし、釣りスポットとしても有名なんだぜ。今度、釣り行く?」
「さ、魚は、顔が怖いので」
「変な奴」
魚の顔真似をすると、佐島に冷たい目で見られた。辛い。
「…いいなあ。友達が多いと、色んな情報が得られて、得した気分になりますよね」
「そうだな。でも友達って数が多ければ良いってもんじゃないと思う。現にさ、ほら、俺とこうして話してるじゃん。俺っていうひとつの媒体だけで、色んな情報も、思い出も出来るだろ?得してるんだよ、お前」
「…そうかなあ」
佐島は首を傾げて弁当を畳む。ごちそうさまでした、と手を合わせる姿がきれいで、育ちが良いんだな、とその度に思う。佐島は、言葉遣いもきれいだから、家庭環境がどうであれ、育ちや教育が、少なくとも俺とは全く違う方向でされていたんだろうな、と思っていた。
今日も天気良いな、とふと零した独り言に、ずっと晴れていて欲しいですね、と思ってもいないレスポンスが返って来た事に、俺はニヤリとした。
続
第9話
「佐島が、いない?」
1年の教室を訪ねると、俺の風貌を見て「ひっ」と声を上げ、ビクビクした様子で俺の問いに答えてくれた1年坊は、もう堪忍してくれ、という目で俺を見上げている。教室内もすっかり静まって、視線は横目で俺を伺う、という、めちゃくちゃ申し訳ない空気になってしまっていた。
「何でいないんだ」
「し、知らない、です。早引きとか、何とか…。先生に呼び出されてて、何か聞こえたのは、」
おばあちゃんが、事故に遭ったそうだ。
俺は先生に託された連絡事項の書類をぐしゃぐしゃに握って、佐島の元へと走っていた。
おばあちゃんは大丈夫なのだろうか。事故って、どんな事故だ。詳しい事を教えてくれなかった先生は、行くならついでに、と書類を突き付けてきた。
お前、自分の生徒がしんどいのにそんなに飄々として、他人事みたいな態度とりやがって。我関せずでいれば、年度内本土に転勤出来るんだもんな。このくそったれ。お前みたいな大人が大っ嫌いだ。
そんな事を早口で、大声で捲し立てた、気がする。職員室は静まり返って、言われた先生は顔を真っ赤にして、怒っていた。教頭やらを呼び出されそうになったタイミングで、俺は学校を飛び出した。もしかしたら、連絡がもう家にいっているかもしれない。それでも俺は構わなかった。先生すら、佐島の味方じゃなかったという現実が、信じられなかった。信じたく、なかった。
大人は、子供に寄り添わなきゃ、大人じゃないだろう。
俺は行き場のない怒りで、感情が昂ぶり過ぎて、何故か涙が溢れていた。
佐島が一体、お前たちに何をしたって言うんだよ。
「佐島!」
横開きの扉を力任せに開くと、目を腫らした佐島がパッと振り返り、目を丸くしていた。
「おばあちゃんの、容体は」
「…散歩していたら、後ろから来た車に追突されたみたいで。他県ナンバーだったから、多分、観光客だろうって。打撲だけだけど、頭打っちゃったから、一応検査で今日と明日、念のために入院するらしい。今は、寝てるだけ」
落ち着いた佐島の声は、所々霞んでいた。頬が濡れ、乾いて、引き攣っている。佐島はいつもの無表情を通していたが、口の端や、目の端が時折痙攣していた。
この子ひとりで、どんなに怖い思いをしただろうか。
「佐島」
俺は先生に貰った書類を投げ捨て、佐島をぎゅっと抱きしめた。佐島はフリーズしているが、俺は構わず、ぎゅうっと抱きしめる。佐島の心臓が、バクバクと早まっていた。
先輩、と慌てて身を捩っているが、俺は、佐島、ともう一度名前を呼んで、佐島の髪をくしゃっと撫でた。
「頑張ったな、佐島。怖かったろ」
こんなに細っこい子供が、ひとりで抱えきる荷物じゃない。俺は胸がいっぱいで、佐島の髪をわしわしと何度も撫でた。
すると、肩がじんわりと濡れていくのを感じる。
次第に佐島は俺の背中に手を回して、子供のように声を上げて泣き出した。
「すみません、さっきは…あの、取り乱してしまって…」
「落ち着いた?」
俺は自販機で買ってきたあったかいココアを佐島に渡す。ちょっと熱いかも、と言って渡すと、佐島は少し顔をしかめて、ほんとだ、と両手で遊ばせる。
「あー……安心した」
深い溜息をついて、俺は項垂れた。佐島に見つめられている気配がする。どんな顔をしているんだろう。
「佐島、お前おばあちゃんと暮らしてたんだな」
「…はい。二人暮らしです。おばあちゃんはこの島にずっと住んでいて。両親が、というか、母親が海外に転勤になったので、こっちに来たんです。おばあちゃん、ひとりで心配だったし。それに…」
佐島は言いあぐねて、目を逸らして、手元のココアに視線を落とした。
「それに、ボクは、母親の邪魔になるだろうと思ったから」
温かいココアを持っているのに、佐島の指が、嫌に白く見えた。俺は黙って佐島の声に耳を傾ける。
「おばあちゃんは元々足腰が弱くて。すっかり畑もやめちゃったんです。集落の人たちもすっかり本土に移っちゃって、集落にはもうおばあちゃんとボクしかいないんです。観光地化っていって、一帯を整備するから、退去願いが出ていて。おばあちゃんの故郷を潰したくない。けど、ボクたちの声って小さいから。家一軒と、今後の利益を天秤に掛けたら、どっちが大事か分かるでしょうって、言われたんです。確かに、そうかもしれない。歴史って、そうして動いていくから。ボクたちは受け入れなきゃいけないのかもしれないって思ったんです。けれど」
佐島は俺の目を見て、ふ、と何も宿さない笑みを浮かべた。
「おばあちゃんは、もういいよ、って」
もう、たくさん頑張ってくれたから、私が退けば事が丸く収まるなら、それがこの島の運命なら、従うしかないね。
そう言う、佐島のおばあちゃんの気持ちを、島の人間が一番分かってあげなければいけないのに。俺は、丸ばかりだと思っていた今の島の在り方に、とある角度の現実をぶつけられて、愕然とした。
「だから、ボクが大学に出るこの2年後を期限に、おばあちゃんのお家は、故郷はなくなっちゃうんです」
佐島はそう言うと、ココアの缶を開けて、ひとくち飲んだ。
「…良いわけが、ない」
俺の咄嗟の声に佐島は顔を上げる。
「良いわけが、ねえよ。そんな事。佐島、お前は、どれだけ自分を殺し続けてきたんだ」
俺は立ち上がり、佐島の肩を掴む。いた、と顔をしかめるのも、気にしてられない程、俺は今、怒っていた。
俺自身に、非情に、怒っていた。
「決めた。俺はお前とおばあちゃんの手伝いをする」
「手伝い…?畑なら、もうとっくにやめて…」
「違う。俺は、おばあちゃんの故郷を守る手伝いをするって言っているんだ」
佐島は目を丸くして、へら、と笑った。
「どうやって?もう、手遅れですよ。先輩は知らないでしょうけど、おばあちゃんの家の前に、これ見よがしに既に「工事予定」の看板が立ててあるんです。おばあちゃんも、これで良いって」
「良くない」
「うちはもう決めたんです。ボクがこの島に来た、5年も前の時に。それで話はもう収まったんです。おばあちゃんも、もう身の回りの整理を始めてる。新しい家に移れるっていう、利点もあるからって、前を向いてるんです。だから、良いんです」
「良くない!」
「先輩がボクたちの何を知ってるんですか!」
「知らねえよ!知らねえけど、俺はおばあちゃんの事も、お前の事も、島の事だって思って、声を上げてるんだ!」
佐島は、ぐっと詰まる。俺は病院で声を荒げてしまい、焦って声を潜めようとするが、感情的になった衝動は抑えられず、拳を握って熱を逃がしていた。
「俺はお前の事も、おばあちゃんの事も、ちっとも分かってない。お前がどんな生活を過ごしてきて、おばあちゃんがどんな気持ちでいるかなんて、これっぽちも分かっちゃいない。けどな、おばあちゃんの人生を、思い出を、目先の利益だ、観光だなんだっていう理由で全部掃いちまうのは、絶対に間違ってる」
「……そんな事言ったって、でも、」
「お前がこうして俺に話してくれた。それで何か変えられる事があるかもしれない。お前が非力だって、自分を責める必要なんか、ちっともない。お前は、お前なりにおばあちゃんに寄り添っていると思う。俺はおばあちゃんじゃないから分かんねえけど、絶対感謝してると思うから。だから、今度はこっちが、おばあちゃんをあっと驚かすサプライズを用意してあげるんだ」
「…だって、もう、…話は、ついてるから、」
「そんなのくそくらえだ。全部白紙にしてやる。やれる事をやってやろう。おばあちゃんの為にも、お前の為にも」
俺は勢いに任せて佐島の手を取って、立ち上がらせた。ココアが床に落ちて、カン、と軽い音を立てて、中身をぶちまける。
「佐島、お前は現実、本土の人間だ。本土の人間が島の事を言うのは、相当な勇気が要ると思う。けど、俺がついてる。何なら、俺の母ちゃんも、父ちゃんもついてる。大丈夫だ。お前は勇気を持って、声を上げて良い。自分を主張して良いんだ」
佐島の真っ黒な瞳から、ぽろりと涙が落ちる。また、顔をくしゃりとさせて、俺の手を掴んだ。
「…いいんでしょうか。ボクなんかが」
「お前だから、良いんだ」
俺は佐島の手を握り返して、目を覗き込んだ。
「やってやろうぜ。若人がせいぜいあがいて、ひっくり返してやろうじゃねえか」
そう言うと、同時に尻のポケットに入っていたスマホが震え「母ちゃん」と表示した。俺は、さっと顔が青ざめるのを感じ、恐る恐るスマホを取り出した。
「…ま、まずはうちの母ちゃんの怒りを収める事から、だな…」
佐島は口に手を当てて、肩を震わせていた。
続
第10話
あんな豪語を謳ってしまった以上、もう引く事は出来ない。しかしその日の夜、確かに俺は布団に包まって「何てことを言ってしまったんだ」と目を強く瞑ったのも事実だ。俺たちで、大人に勝つことは出来るのだろうか。でも、佐島のあの顔、佐島のおばあちゃんの気持ちを聞いて、黙ってそうですか、と素通り出来る事は出来ない、良く言えばお人好し、悪く言えば出しゃばりの性格をした俺は、決めた事なんだから、やるしかねえとひとり決心を固めていた。
しかし具体的に何をしたら良いのか。うちは歴史ある茶園とはいえど、島の政治に関しては声が弱い。これまで、良ければ好きなように、というスタンスでやってきたものだから、今更反対の声を上げたら、それこそ島内の一部の人間たちから干される事態になり兼ねない。ここは慎重にいかないと、俺も、俺の家族も、佐島の家族も大変な事になってしまう。閉塞感のある島の文化が築かれている以上、これは避けて通れない生理的な現実なのだ。
あれ、そういえば。
「お前の家って、確か市議会の役員だったよな、父ちゃん」
授業の休み時間。俺は隣に座る、いつも絡んでいる友達こと、五嶋に声を掛けた。五嶋はそれがどうした、と顔をしかめて、腕を組んだ。
「父ちゃんの話はあんまりすんなって言ったろ」
「ごめん。ちょっと気になる事があってさ。聞きたい事あるんだけど」
「何だよ。島の事なら俺知らねえし。聞くだけ聞いてやるけど」
島内で進められている事業。佐島の住んでいる地域が観光地化される事。佐島の名前は出さず聞いてみると、五嶋は首を傾げた。
「うん、確か言ってた気がする。ていうか、その事、この前先生も言ってたじゃん。近々工事が始まるから、近寄るなって。それがどうした?」
「いや、どうしたって…その…」
ダメだ、佐島の名前を出そうとしてしまいそうで、喉がつっかえる。俺は言葉を濁して、何とか上手く五嶋の父ちゃんと話せないか、と頭を悩ませた。そして、それは突然舞い降りて来た。
「そうだ、五嶋。お前の父ちゃん、うちのお茶好きだったよな」
「うん、好き。俺も好きだけど。それが、何?」
「うちで新茶がとれてさ、良かったら味見して欲しいなって。もしかしたら新商品の開発するかもしれなくて。それじゃあ、味を良く知っている人たちの見分を聞いた方が一番参考になる、かな、なんて……」
何という適当。何という嘘っぱち。ごめん、母ちゃん、父ちゃん。帰ったらきちんと話すから、今だけは許してくれ、頼む。
「あ、そういう事か。良いけど。うちも結構忙しくてさ、お茶って疲れも取ってくれるから最近よく減るの。助かるわ、正直」
五嶋は、よろしく頼んだぜ、と笑う。咄嗟の嘘っぱちだったが、何とか上手くいった、らしい。俺はインスピレーションをくれた神様に心の中で感謝して、帰宅してから母ちゃんたちにする言い訳を考えるように、脳をシフトチェンジした。
「馬鹿!嘘をつく子に育てた覚えはないよ、この馬鹿たれ!」
帰宅して、母ちゃんに相談と言う名の謝罪をしたら、一言目がこれだった。こんな歳になっても、母ちゃんの怒号には慣れない。心臓がきゅっと縮まるのを感じた。
「ごめん、母ちゃん。嘘ついてしまったのは、五嶋にも、母ちゃんたちにも悪いと思ってて。その…でも、俺、佐島を救いたくて…」
「アンタね、父ちゃんがどんな苦労をして毎日お茶と向き合ってるか、想像した事あるんか!一言で「新商品」って言って、父ちゃんがどんだけ大変な思いをしてるか、アンタも目で見た事があるだろう!」
「ごめん、その通りだと思う。俺の、言葉がいかに浅はかで…父ちゃんたちの苦労を一言で片づけてしまったっていう、そういう申し訳なさは感じてる。でも聞いて欲しい。佐島が…」
「佐島くんの話は別。アンタの気持ちはよく分かってる。佐島くんの力になりたいって、そりゃ立派な事だよ。でもね、母ちゃんは、そこに怒ってるわけじゃない」
「…ごめん」
正座をして項垂れていると、早千代、と父ちゃんの声が居間から聞こえた。父ちゃんは新聞から目を離さずに、言葉だけをこちらへくれた。
「感情的になったら、話したい事も話せないだろう」
父ちゃんはそう言うと、新聞を捲る。母ちゃんは、父ちゃんに怒鳴ろうとして、言葉を飲み込み、深呼吸をした。
「…そうだね、その通りだ、父ちゃん。熱くなりすぎちゃったね」
「馬鹿息子の話はもう良い。佐島くんの為にやれる事を考えてやろう。大人として」
父ちゃん、と母ちゃんの声と俺の声が重なった。
「島の事に口を出したら干されるなんて、そもそもおかしいだろう。良くする為の一案を声に挙げているだけなんだから」
「でも、父ちゃん。もしかしたら嫌がらせとかも、出てくるかもしれない」
「その時は、その時だ。また別の場所で茶をやればいい」
父ちゃんは新聞から顔を上げ、茶を啜り、俺をしっかりと見据えた。その剣幕に、思わず生唾を飲み込む。
「お前は俺の息子だ。親が力になれなくて、どうする」
その言葉に、母ちゃんは何か納得したらしい。俺は、父ちゃんの息子だ、とただ言われただけ、と思っていたが、長く寄り添っていると、否、子を持つ親になると、分かる事があるのだろうか。
「父ちゃん、お茶出たから淹れようか」
母ちゃんは腰を上げて、居間へ父ちゃんの湯飲みを取りに行く。もう怒ってないか、ドキドキしてつい母ちゃんを視線で追ってしまうが、母ちゃんは急須を置いた土間へ消えた。母ちゃんの気配が遠ざかって、父ちゃんは溜息をつく。
「…ごめん、父ちゃん」
「お前の馬鹿さは今更何も怒らん。けどな」
新聞を畳み、テレビをつける。バラエティ番組からすぐにニュースへ変えて、父ちゃんはこちらに視線を向ける事なく、まるでテレビに話しかけるように、ぽつりと言った。
「人への優しさだけは、きちんと持て。良いな」
母ちゃんが土間からお盆に湯飲みを乗せてやって来る。代々大切に使われている居間の一枚板の机に、3つの湯飲みが置かれた。
「おいで。お茶飲もう」
母ちゃんの声が柔くなっていて、俺は大きな安堵の溜息を殺しつつ、ありがとう、と一言言って、居間に座った。
続
第11話
「大人になりたくない」
いつもの昼下がりの屋上で、開口一番、突いて出たのはその言葉だった。佐島は気にした様子もなく、母ちゃんの弁当をつついている。今日の卵焼きは甘い味だ。
「大人になったら色んな事考えなきゃいけない」
「それは子供だってそうです」
「そうだけど。俺達ってまだ守られてるから、そこに甘えられるじゃん」
「確かに、ボクもおばあちゃんにまだ甘えてばかりです」
「だろ?それが大人になると、全部自分で背負わなきゃいけない。大変だろ」
「でも、自由の身にもなれます」
「自由と責任は何とやら、じゃねえか。俺はそんな自由、いらねえなあ」
俺は空を見上げて、溜息をひとつ。佐島はこちらに一度も目を向ける事はなく、黙々と弁当をつついている。
「少なくとも、ボクは早く自由になりたい」
「何で」
「その方が、おばあちゃんを助けられるから」
佐島はそう言うと、やっと顔を上げて俺の目を覗き込んできた。相変わらず、何も宿していない、真っ黒な瞳だ。
「ボクは非力です。子供だから。それは仕方ない。けれど、大人になって、お金を稼いで、それなりの言葉を持つ大人になれば、おばあちゃんを助ける事が出来る」
「確かに、俺達があれこれ言っても、子供の言う事って片付けられる事多いしなあ」
「それは、とても悔しいじゃないですか。いち人間として、きちんと意見を持っているのに」
佐島は食べ終わった弁当を畳み、ごちそうさまでした、と手を合わせた。いちいち綺麗で、いちいち律義で、俺と佐島の環境の差というのをたまに感じる時が時たまある。
佐島は小さく溜息をつき、足をぶらつかせた。
「ボクは、もっと力のある大人になりたい」
「力のある大人、って?」
「政治家とか」
「政治家!?」
思わず大きい声が突いて出てしまった。佐島は、しっ、と指を唇にあて、誰にも聞かれていないか、辺りをきょろきょろ見回した。ごめん、と言うと、佐島は俺をキッと睨む。
「政治家って…すげえ頭良くないとダメじゃん。コネもいるし」
「先輩、ボクの印象だけで話してません?それ。ボクがどんな人物で、どんな環境で育ってきたか、ちっとも分かってないじゃないですか」
「そりゃあ…」
「…そういう話、あまりしてこなかったから、当たり前ですけど」
だろ、と言おうとすると、佐島は手で髪を撫でる。今日は北風が少し強く吹き込む日だった。
「ボク、実家が単身赴任で、母が海外出張って話したじゃないですか」
「うん。それで、東京育ち」
「それはどうでも良いです。…ボクの両親、政治関係の家系なんですよね」
「…それは……、」
めちゃくちゃ住む世界が違う訳だ。
俺は昼飯で膨れた腹、先生のお経のような授業に、眠気と戦いながらぼんやりと考えていた。
佐島は、確かにどこか品があって、育ってきた環境が違うんだなと思う事が多々あった。それは礼儀であったり、言葉遣いであったり、雰囲気であったり、様々な面で、だ。うちで佐島をおもてなしした時も、あの母ちゃんのマシンガントークを上手く打ち返す話術であったり、とにかく、佐島には驚かされる事がよくある。
親が政治家ならば、自分もそうなりたい、と思うのが普通なのだろうか。俺だったら、どうだろう。母ちゃんたちが政治家で、小さい頃からその背中を見てきて、母ちゃんが突然海外に行くから、と言って、離れた小島に住まわされて。おばあちゃんがそこにいると分かってはいるものの、やはり親は変えられない存在だ。寂しさとか、感じないのだろうか。
引っ越した先で苛められて。俺だったら――。
「須々木―この問いの答えは何だー」
「俺ですか?俺だったら…非行に走ります」
「は?馬鹿かお前」
バシン、と教科書の束で頭を叩かれる。いってえ、と声を上げると、周りが一気に笑い声で湧いた。
「そういう事は先生から隠れてやるもんだ。けど、暴力と酒とたばこだけは、絶対だめだぞ」
「そういうの、かなあ。俺、非行に走った事なくて分かんねえや」
「少なくともお前のその身なりの第一印象は、優等生とかけ離れた印象だけどな」
また、笑いが湧く。俺は自分の髪の毛先を指でつまんで見る。そんなに俺って、ヤンキーっぽいんだろうか。体格は良いし、喧嘩をふっ掛けられる事も多いし。俺は一度も思った事はないけど、傍から見るとそうなのかもしれない。
そんな事をしたらお前のお母さんは黙ってないだろうけどな、と先生にまた教科書でぽんぽん、と頭を叩かれ、授業に戻る。
佐島ってやっぱり精神力が凄い人間なんだ。普通、あそこまで苛められたら、学校に来なくなるのも不思議じゃないし。それでも必死に耐えて、自分の夢の為に足を踏ん張らせているなんて、俺だったらきっと、折れているかもしれない。
「…ていうか、俺…結構無神経な事、佐島に話したな」
ぼそ、と言う俺の言葉を、たまたま拾っていた隣の五嶋が「また佐島か」と突っ込んでくる。俺はそれに構う事なく、自分のやってしまった事への少しの後悔と、改めて、佐島という人物とは何ぞや、という疑問で、頭がいっぱいになっていた。
続
赤