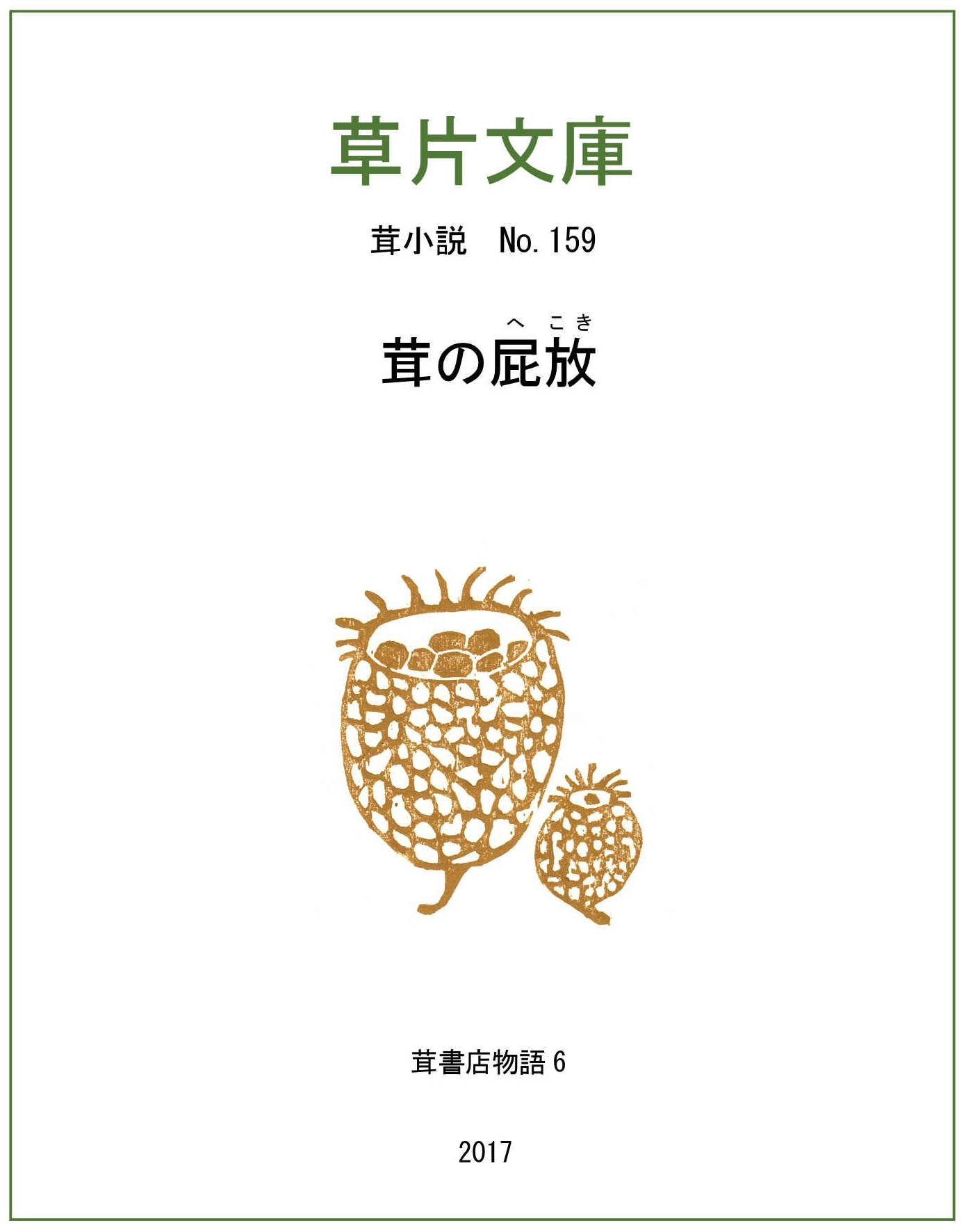
茸の放屁(へこき)―茸書店物語6
御茶ノ水の聖橋口を出ると、斜め前に中古のCD屋がある。時々覗いて、紙ジャケットのジャズを買う事がある。本と同じで、カバーのデザインがいいとほしくなる。
もちろん、なんの楽器のジャズか見るが、アーティストの名前は知らないことのほうが多い。本と同じで、結構当たるもので、好きなジャケットのCDには気に入った音が入っていることが多い。自分はスローテンポのジャズを好む。せっかちな性格だから、ゆったりするにはそうでなくてはならない。
今回、店をみたが、特に手をとりたいようなものはなく、神保町に向かった、このあたりは楽器店が多い。靖国通りにでると、信号を渡り、鈴蘭通りをちょっと行くと三省堂の脇の入口がある。そのほぼ隣のビルの3階に豆本でよく知られる吾八書房がある。豆本そのものには関心が薄いが、美術関係でいい本があるので覗くことにしている。
その後、鈴蘭通りを進み、すぐのところを右折して靖国通りに面した田村書店に行った。田村書店では今までずい分いい本を安く手に入れた。最近は本を買うこともないのだが、入ることが神田の古本屋に来た証拠のような気持ちになる。結構、爺さんがふらりと入っていくのを見かける。同じような仲間だろう。
お昼である。今日は何を食べようか。ランチョンにはいったが、選ぶのに時間がかかった。いつもは食べたいものが頭に浮かんでランチョンにはいるのに、今日はなぜか頭の中の様子が違う。
メニューを見た。何にしよう。なかなか決まらなかったが、昼間のメニューじゃなく、正式メニューのメンチカツをたのんだ。ここの有名な料理でもある。ライスもつけて、ビールまでたのんでしまった。ちょっと頭のねじが狂っている。なぜか珍しくコーヒーまで飲んだ。ともかく美味しくお昼を済ませ、ゆったりとした気分になった。
草片書房に行くと、ウエザーリポートがかかっていた。あまり茸とはマッチしない。
今日は妹の泣子さんがデスクにいる。金髪に染めた髪が照明に反射して、音楽とはちょっとあっている。ウエザーリポートは彼女の好みなのだろう。
ウエザーリポートは私が学生のころだから五十年以上前に結成され、そのころは新しい音として一世を風靡したジャズグループである。ロックのほうでは、シンセサイザーが登場し、ピンクフロイドやちょっと後発のタンジュリンドリームなどのプログレシブロックである。クラシック畑ではシュトックハウゼンの電子音楽など、そういった時代だった。彼女は古いものがすきなのかもしれない。
いつものように、地方紙の棚に行くと、第六集の語草片叢書がでていた。タイトルを見ると、茸の屁放である。面白いタイトルだ。絵はよく知っている埃茸や、土栗、それに脳茸が描かれている。蹴っ飛ばすと煙が上がる茸ばかりだ。茸の語源・方言辞典(奥沢、山と渓谷社)をみると、「玉っころ」と呼ばれている連中だ。
デスクに持っていくと、泣子さんが「面白い題名ですね、書いた人は東京の音楽家で、字頭さんですよ」とニコニコしている
「字頭って、あの現代音楽の巨匠のですか」
驚いた。字頭希は映画音楽、テレビ番組の音楽、さらに、オーケストラのための音楽を作曲している、今一番注目されているシンセサイザーの大御所である。
「そうなんです、青梅のほうに家をお持ちで、そこで作曲活動なさっているのだそうですよ、生まれは福島で、子供のころは茸が身近にあったそうです。青梅に移られたら、やはり茸がたくさん生えるので、子供のころ、お爺さまに聞いた話しを思い出されて、書かれたとのことです」
冊子の作者名をみた。宇土時汎とある。
「ペンネームになってますね」
泣子さんはうなずいて、
「宇土時はじとうのさかさま、汎は希の反対の意味ですって、本名で書くのは嫌だとおっしゃって、これを書くために名前をつけたようですよ」
「この語草片叢書は誰が編集しているのですか」
「おねえちゃん、姉は字頭さんの知り合いなんです」
「すごい人と知り合いなんですね」
「姉はやりてなのよ、この本屋も、編集も、それに、茸のレストランも経営しているんですよ、夜はそっちにいます、茸のシェフをやとっているの、字頭さんもよく見えているのでご挨拶をしたらしいけど、そこで意気投合したみたい」
初耳である。
「どこにあるのです」
「国立ですけど、行く時には紹介します、完全予約制なので」
とても私がいけるような値段のところではなさそうだ。
「その時はお願いします」といって、第六集を受け取った。
現代音楽の巨匠が書いた茸の本というのは面白そうだ。今日は寝る前に楽しめる。
泣子さんがなにやら棚から小さな本を取り出した。
「これ、もう最後の本なのですが、とても人気がありました。増刷はしないかもしれませんが、綺麗で、お客様にあいそうです」
手に持っていたのは文庫版よりちょっと大きいハードカバーの本で、厚さは二センチもあるだろうか、三方金が塗ってある。贅沢な本である。「ちいさな手のひら図鑑、茸とあり、赤い綺麗な絵が書かれている。中を開くと、西欧の本やカードから取った絵と、それに、それぞれの種の説明が書かれている可愛らしい翻訳図鑑である。ミリアム・ブラウンとい人が書いたもので、グラフィック社発行である。
当全欲しくなる。値段を見ると千五百円、ずいぶん安い。それをみて、泣子さんは商売が上手だと思ったのは間違いで親切なだけなのだろう。
帰りの地下鉄の電車の中で、その図鑑の茸の絵と説明をみていると、あっというまに、芦花公園についた。
その夜、ベッドに入って語草片を開いた。
「茸の屁放」
私は仙台の農家に生まれた。赤子のころ、両親や祖父が働いている田のあぜ道に置かれた、籠の中に寝かされていたようである。少し大きくなると、田んぼの周りを駆け回り、山裾の道まで遊びに行った記憶がある。特に危ないところはなかったので、両親たちは私にかまうことなく仕事をしていた。秋になると山裾の道には茸がちらほらと生えていて、玉のような茸、玉っころを蹴っ飛ばして遊んだものである。埃茸である。
我家では、九十の曽祖父が、田にはもうでることはなかったが、家で縄をなったり、籠を編んだりしていた。そのころになると、夜に曽祖父が寝床で私や私の兄弟に昔話を聞かせてくれたものである。曽祖父は九十にもなるのに、頭がはっきりしていて、話がとても面白かった。
これは曽祖父が話してくれた茸の話だが、すべてを覚えていないので、私の想像を交えて、というより創作したことが入っていると思って読んでいただきたい。
その森の中にはいろいろな茸が生えていた。昔昔のことだが、その森の茸には身分に違いがあったという。
泉鏡花先生の茸の舞姫の中には紅茸の姫と腰元がでてくる。ということは同じ茸で身分の違いがあったことが書かれているが、この森の中では同じ茸の中でそれはなかった。茸の種類の間に身分の違いがあった。
まずは地面から生えている茸が、木の幹に付いている茸より位が上だった。例えば、猿の腰掛けよりも、小さいが土から生える落ち葉茸のほうが上だった。それじゃヒトの世界で高価といわれる松茸はどうだったかというと、松の木を頼りに生えているので、落ち葉茸より下に見られていたのだよ。虫から生える虫茸は、それこそ地位の低い茸として、下賎茸と馬鹿にされていたそうだ。
この茸の身分制度は、毒をもつ背の高い天狗茸たちがつくった。その仲でも赤く目立つ紅天狗茸や、逆に真っ白な毒鶴茸が中心になった。
それはこういうことがあったからだ。
あるとき、林に入ってきた腹の減った鹿が猪口や滑子を喰った。まだ足りないといって、真っ赤な紅天狗茸も食べた。そうしたら、鹿のやつ、へろへろになって、木の幹に体当たりはするわ、すべって転んで、片方の角を欠いちまうわで大変だった。それから鹿は紅天狗茸を怖がった。
まだある、奥山から遊びにきた猿の家族が、たくさんの猪口を食い満足をした。そのとき父猿だけ食い足りなかった。そこで近くにはえていた毒鶴茸を食べちまった。すると、熱をだし、腹痛がひどくなり動けなくなった。母猿や子どもたちは死にそうな父親を林から引きずり出し、川へ投げ込んだ。熱を冷まそうと思ったのだ。父猿は嫌というほど水を飲んで吐き出した。そうしたら何とか助かって奥山に帰ることができた。それ以来、猿たちは毒鶴茸に近寄らなくなった。
こういうことがあってから、天狗茸の仲間は、動物も怖がるほど強いんだ、と威張るようになったわけだ。
こうして、紅天狗茸や毒鶴茸などの天狗茸の仲間が一番偉いという、身分制度がこの森にできてしまったというわけだ。
茸の中で、土の上に生えているが、身分が低いとじゃけんにされていた「玉っころ」という、柄のない丸いフォルム茸たちがいる。土の上にコロンと生えているやつらだ。
玉っころの丸い頭の上には穴があいている。普通の茸は傘の裏にひだがあってそこで胞子をつくるが、玉っころは体の中で作って、頭の上の穴からふーっと吐き出す。
こいつらは腹菌類という一族で、埃茸、土栗(土柿とも呼ばれる)、脳茸、海辺の松林にいる松露など、茸茸していない連中で、ちょいと変わり者だ。
そいつらは、体の中の胞子が熟すと、頭の穴から煙のように噴出するので「煙出し」と呼ばれたりもする。
ところが、その昔は、玉っころは煙をはくことはなかった。玉っころの胞子は頭の穴からぱらぱらと土に落ちるだけだった。傘のある茸が胞子を傘の裏の襞からぱらぱらと落とすのと同じだったわけだ。
ともかく、玉っころは天狗茸たちからじゃけんにされ、森のなかにいれてもらうことができなくて、森の入口や、周りの道に集まっていた。
森には猪口の仲間が一番多い。猪口は柄もある傘の広いいい形のきのこだったのだが、天狗茸よりかなり背は低かった。それで、天狗茸にいわれ、森の入口に近いところに集まってくらしていた。猪口の仲間は茸仲間からとても好かれていて、信望が厚い。面倒見がいい茸たちで、玉っころとも仲がよかったわけである。
森の泉の近くの一等地には紅天狗茸や毒鶴茸が占拠しているわけである。
花猪口がぬめり猪口に言っている。
「泉の近くは住みやすいところだったのにな」
「たしかにな、みんなそう思ってるよ」
「身分制度なんて、何で神様がゆるしたんだろう」
「神様はかんけいないさ、天狗茸たちがかってにつくったものだよ」
「どうして、みんなあんなやつらのいうことを聞いているんだ」
「あいつらの毒はつよいからな」
「だけど、動物たちには毒でも俺たちにどくってわけじゃないだろう」
「そうだな、茸はみんなおとなしいから、言うこと聞いちまったんだ、日本人みたいにおとなしんだ」
「日本人は茸がかわったのかい」
「そんなことはあるまいがな、日本人は茸好きで、よく食べる、もともと茸だったら食ったりしないだろう」
「それで、天狗茸をおとなしくさせるにはどうしたらいいだろう」
「あいつら毒があることで、自信満々で、えばっているわけだよ」
「ということは、毒を抜いちえばいいわけだ」
「どうやってだ」
「ふーむ、むずかしいな」
猪口たちがそんな話が玉っころに聞こえてきた。
「身分制度はもともとあるものじゃないんだな」
土栗が埃茸に言った。
「そのようだな」
「森の中で仲良く暮らしたいよな」
「猪口たちが言っていたように、あいつらから毒をぬくのがいいのかな」
「他にいい手があるんじゃないか」
そう思った玉っころたちは考えたのだが、なかなかいい案がおもいつかない。
また猪口の話し声が聞こえてきた。
林の泉のそばで、茸虫がたくさん生まれたそうだ、しばらく経つと、大きくなって、我々茸を食べに来るぞ」
「そりゃ困った、何かよい方策はないかね」
「ふーむ、どうしたらいいもんかね」
「紅天狗たちが何とかしてくれないのかね、身分の高い連中は茸の国を守るのが役割だろう」
「そうだが、茸虫は毒茸だろうがまずかろうが、みんな食っちまうからな」
「逃げるしかないな」
「と言っても、我々は虫のように早くは動けんからな」
それを聞いた玉っころたちもこまった。
「茸虫がきたらどうしよう」
土栗が言うと、埃茸は
「風で転がってにげるしかないな」といった。
「俺はなかなかころがらないんだ」
そう言ったのは、玉っころの中でも大きな脳茸だった。
「俺たちは、森のまわりにいるんだから、茸虫が泉の近くの茸だけで満足してくればやってこないかもしれないな」
「たしかにそうだが、森の茸たちがいなくなるのは悲しいな、何とか茸虫を退治できないものかな」
「そうだな、天狗茸から毒を抜くよりた安いかもしれんが、それでも、どうしたらいいかわからんな」
「ともかく、この丸いからだではなにもできないないよ、ただ土の上で、コロンと転がって、胞子をふわっとそとにだすだけだからな」
「からだを変えなきゃしょうがないよ」
「茸虫は何が嫌いだろうか」
「虫は匂いに敏感だけど、嫌いな匂いは知らんなあ」
「好きな匂いは分かるよ、茸だろう」
「そりゃあたりまえ」
「ということは、茸の匂いを強くすれば、そっちに茸虫はよってくるな」
「それでどうするんだ」
「茸虫を集めて、そこで、いやな匂いをかがせて、一網打尽だ」
「やっぱり嫌いな匂いが分からなければできないだろう」
そう言われて玉っころたちはだまってしまった。
そんなある日、猪が林の中に入っていった。入口に生えていた埃茸が蹴っ飛ばされて転がった。
「痛え、乱暴なやつだ」
埃茸は頭の口を尖がらせて怒ったものだから、胞子がシューっと勢いよく空に向かってでてしまった。
それを見ていた土栗は「お、すごいね」と自分達も口を尖がらせてみた。すると、胞子が勢いよく飛び出した。
「これはいい、これに茸虫の嫌いな匂いがついていればいいんだがな」
そういっているところに、鼬がやってきた。鼬は林の中にのこのこと入って行った。
「林の中には猪がいるのに、入って行っちまいやがった、いじめられるぞ」
脳茸がそう言って鼬を見送った。
鼬は泉のそばまでやってきた。そのあたりには紅天狗茸がたくさん生えている。
猪も泉のそばにいた。腹が減っていた猪が紅天狗茸は食えるかどうか考えていた。
猪が鼬に気がついた。
猪は紅天狗茸が旨い茸で、鼬が横取りに来たのだと勘違いした。
猪は走り出して、鼬を牙で突っつこうとした。鼬は驚いて逃げた。森の入口に向かって、かけていくと、猪も猛スピードで追いかけてきた。
玉っころたちが生えているところに来ると猪が鼬に追いつた。
玉っころたちは鼬が突っつかれる、と目をつぶった。怖いところを見ることができないほど玉っころは気弱な茸だった。
鼬の尻に牙がちょっとばかり突き刺さった。
そのとき、ぽーんと大きな音がした。
玉っころたちは、驚いて眼を開けた。
すると、鼬が逆立ちをして、尾っぽを高く上げると、ポーンという音とともに屁をひったところだった。
その臭いの何のって、猪は鼻に匂いをかけられ、あまりにも臭いので、逃げていってしまった。
目を開けた玉っころたちは、逃げていくのは猪だけではなく、あたりにいた虫たちも、右往左往して、穴の中に隠れるやつや、草の葉っぱに頭をこすり付けるやつや、どの虫も、鼬の屁の臭いには大変な思いをした。
「鼬の屁は虫たちも嫌がっているぞ」
脳茸が
「体の中に鼬の屁が入っちまった、臭いな、こいつを噴出したら、虫がにげるかもしれんな」
そういいながら、脳茸は頭の穴をとんがらせて、思い切り、体の中にたまっていた鼬の屁を吐き出した。
そうしたら、やっぱり、虫たちがくさいくさい、ここにはいたくない、とどんどん走ってにげていった。
そこに、冬の間、ヒトの家にいく亀虫たちが通りかかった。
「臭いね、でも、おいらたちの屁のほうがもっと臭いぞ」
亀虫が虫っころに言った。
虫の中で亀虫ほど臭い屁をする虫はいなかったんだ。
それを聞いた埃茸は、これだ、と思った。
「亀虫の旦那、その匂いを我々に向かってひってはくれまいか」
「そりゃお安い御用、冬寝をするためにヒトの家にいくが、臭いと嫌われる、ここでひっていけばにおわないから好都合だ」
埃茸は玉っころたちにむかって、
「みんな、亀虫の旦那やかみさんたちに屁をひってもらって、それを吸い込もう、それで、転がって、森の中にいって、茸虫をやっつけるんだ」
そうさけんだ。
森の入口いた玉っころたちは、亀虫の屁を吸い込んで、体の中に溜めた。
屁を吸い込んだ埃茸が、ためしに頭の穴をすぼめ勢い良く胞子をへりだした。それがぶつかった蝮草の赤い実が、あまりの臭さに萎れてしまった。
「大した威力だ」
玉っころたちは自信をもった。亀虫に屁をたくさんかけてもらい、どんどん吸い込んだ。そうして、玉っころたちは、ころがって林の中に向かったのである。
屁を吸い込んだ玉っころ、埃茸、土栗、脳茸は泉のところにやってきた。
そこにはもう茸虫がいた。茸たちはみんなたべられていた。たくさんの紅天狗茸たちもぼろぼろになってみすぼらしくなっていた。
茸虫に這い上がられた紅天狗茸が、恥ずかしげもなく「助けてー」と声を上げ、逃げようともがいている。
「たすけてやるぞ」
玉っころたちがぞろぞろと、紅天狗茸や毒鶴茸の下にあつまった。
紅天狗茸が下を見ると、玉っころたちが見上げている。
紅天狗茸は、
「なんでお前達がここにいるんだ、森の入口に帰れ」
と言った。
「へえ、茸虫を追っ払らったら、かえりやす、紅天狗茸の大将に加勢をしようと思ってきたんで」
それを聞いた紅天狗茸、
「できるなら、やってみな、うまく行ったら、泉のところに入ってきてもいいことにしてる」と叫んだんだ。茸虫がかじり始めていたわけだ。
玉っころたちは紅天狗茸にたかっている茸虫に向かって、頭の穴をすぼめて、しゅーっと勢いよく胞子をぶちあてた。臭いにおいが紅天狗茸を包んだ。
臭いを吹きかけられた茸虫は鼻を掻きながら、紅天狗茸からおっこち、すたこら退散し始めた。玉っころたちは茸虫をおいかけ、匂いをかけた。とうとう、茸虫は林からでて行ってしまった。
生き残った紅天狗茸も毒鶴茸もやっと改心した。
これでこの森の身分制度はなくなったのである。
だが土栗、埃茸や脳茸はもといた森の入口にもどった。
「森の中より、このあたりのほうがあかるくていいね」
土栗も埃茸は、お日様が好きのだ。道端のほうが気持良かったのだ。
こうして、玉っころは蹴っ飛ばされると、怒って、胞子をシューっと飛ばすようになったそうである。そうなった彼らは「煙出し」たちとも呼ばれたんだ。もう亀虫の臭い匂いはしなくなったけど屁放茸とも言われるようになった。
とっぴんぱらりのぷー。
面白い昔話である。
字頭氏のひい爺さんはこの話をして、みんなのためになることをしなさい、自分のやりたいことをみつけなさい、と子供のころの字頭氏に教えたのではないだろうか。字頭氏が世界でも指折りの作曲家になれたのはこの話が背中を押したのだろう。彼が苦労してやりたかった音楽の道に入ったということをどこかで読んだ気がする。彼の生まれたころはもうなかった士農工商の身分制度だが、ひい爺さんの若いころにはまだその名残があったのだろう。彼のひい爺さんも何かがやりたかったのかもしれない。私は読み終わってそんなことを感じた。
そのような感慨にふけっていると、なんだか臭い匂いが漂ってきた。天井を見ると、たくさんのカメムシが張り付いている。壁を伝わって、数匹のゴキブリがカメムシたちの中にはいっていく。カメムシが一斉にケツをあげ屁を放った。ゴキブリが目を回して、私の顔に落ちてきた。私も目を回し意識がなくなった。いや眠ってしまった。
茸の放屁(へこき)―茸書店物語6
私家版 第十茸小説集「語い草片、2021、246p 一粒書房」所収
版画:著者


