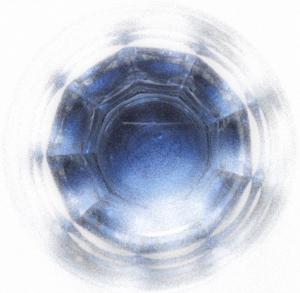「敬」
七百二十席のホールは大方埋まっていて、席を探しながら中ほどの通路を上ってゆくと通路側の一席を空けて彼が座っていた。
「隣、よろしいですか」
とよそよそしく笑いかける私に、
「どうぞ」
と笑い返す彼。そんなに久しぶりでもない。彼と会うことは度々あって、今日ここに来ていることにも別段驚きはなかった。聴衆はみんなスーツや改まった服装で、彼もきちんとしている。シンポジウムが始まるまでの少しの間、今手がけている研究の話をした。
今度、一緒にやろうよ。
どちらからともなくそういう話になって、私は、
「じゃあ連絡先を教えといてよ」
と、手帳を開いて差し出した。
彼は「そうだね」と言って快く書いてくれた。私の愛用の、レモンの手帳に。昔よりもずっときれいな、大きさの揃った字で名前と住所と番号を書いてくれた。
彼と仕事ができると思った。私の胸に恋い焦がれた子どもの頃のような昂りはなく、私たちは互いに一人の社会人として、手を携える関係になったのだと思った。
でも、途中休憩で席を外して戻ってきてみると、彼はいなかった。彼の黒いコートも。荷物ごと、消えてしまっていた。
胸騒ぎがしたが、手帳を開くと彼の文字はちゃんとそこにあったから、私は閉会まで会場に残った。シンポジウムの内容は素晴らしかった――。
どうして、私はそこから目を覚ましてしまった。
学会になど、出かけていなかった。
だから、今しがた彼に会ったことも、彼が手帳に書いてくれたことも、全部、全部……。
カーテン越しに射し入る残酷な朝日が一つ一つ、パラパラとめくり返すようにあったことを夢へと変えてしまう。抵抗しようとして、私は彼の文字を瞼の裏にくっきりと浮かび上がらせた。そして、気がついてしまった。
夢の中で、私は彼の名を間違えていた。
あれほど慕った彼の名前。彼自身誇りにしていた、二音一文字の美しい名前。
忘れるはずはないのに置き換わっていた、その文字は――。
「敬」