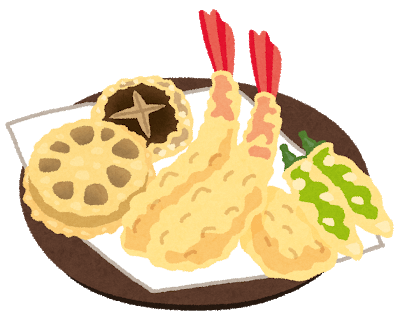
てんぷら
あるところに米寿を迎えたお爺さんがいた。腰は曲がりくの時になろうかというほどで、体の方は老いを見出す他ないが、頭の方は存外しっかりしていた。この間近所の高橋さんが様子見ついでに世間話をしに訪れた時などは、最近どこそこの誰々が鬼籍に入ったとか、田んぼの水が今年は少ないなど、身の回りのことに関しては話題が尽きぬほどであった。そのくらい生気を失っていなかった。
お爺さんは山の上に住んでいた。麓というと語弊があるが、山を下りて少しした場所にあるスーパーに車で行くまで半時はかかるといった具合に田舎であった。お爺さんは週に一回山から下りてそこに食料を買いに行くことにしていた。年のせいで歯は碌に残っていなかったため、固いものは食べられなかった。お爺さんは柔らかい天ぷらをよく買っていた。
お爺さんはその日もいつもと同じように冷蔵庫に入れていた天ぷらを温めていた。電子レンジに入れて一分すれば、どんな冷たいものでも作りたてのように温かくなる。冷やすために家の傍の川に浸けておき、常温に戻すために火を炊くか放置しておくという労力の多い遠回りな手段しかなかった昔を忘れたわけではなかったが、そのくらいお爺さんが電化製品を使う姿はほとんど日常ど同化していた。一分経ち、温めた天ぷらを電子レンジから出す。蒸気のせいで容器を包むラップが膨らんでいる。それを剥そうとしたが中々剥がれなかったため、お爺さんはわざわざ鋏を使ってラップを破った。切れ間から中の蒸気が漏れていく。漏れた蒸気は天井に吊られた蛍光灯の明かりを散乱させて、部屋に白いもやが広がっていった。そのもやは切れ目から尽きることなく流れ続け、ついには部屋中が白いもやで満たされてしまった。お爺さんはただ天ぷらを見続けることしかできなかった。重い腰が石のようにさらに重く感じる。
その内、とうとう目の前の天ぷらすら見えなくなった。見えるのは自分の着ている上着と左手に持つ箸のみであった。お爺さんは恐る恐るてんぷらがあるはずの位置に右手を伸ばしてみた。するとなんらの感触を得ることなくテーブルにぶつかった。どうやらてんぷらは消えたか移動したらしかった。おじいさんは消えてほしい腰の痛みが消えず、消えてほしくないてんぷらが目の前で消えてしまったことに驚き、混乱してなにがなんだか分からなくなった。その内寝て目覚めたら、先ほど無くなったはずのてんぷらが湯気をたたえて机の上でおじいさんが食べるのを待っていた。お爺さんは嬉しくなり、その日は岩塩をつけて意識高めに食べたとさ。めでたしめでたし。
てんぷら


