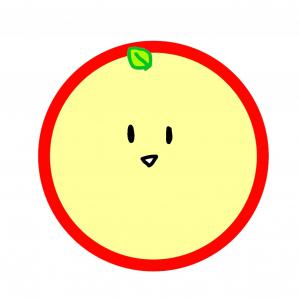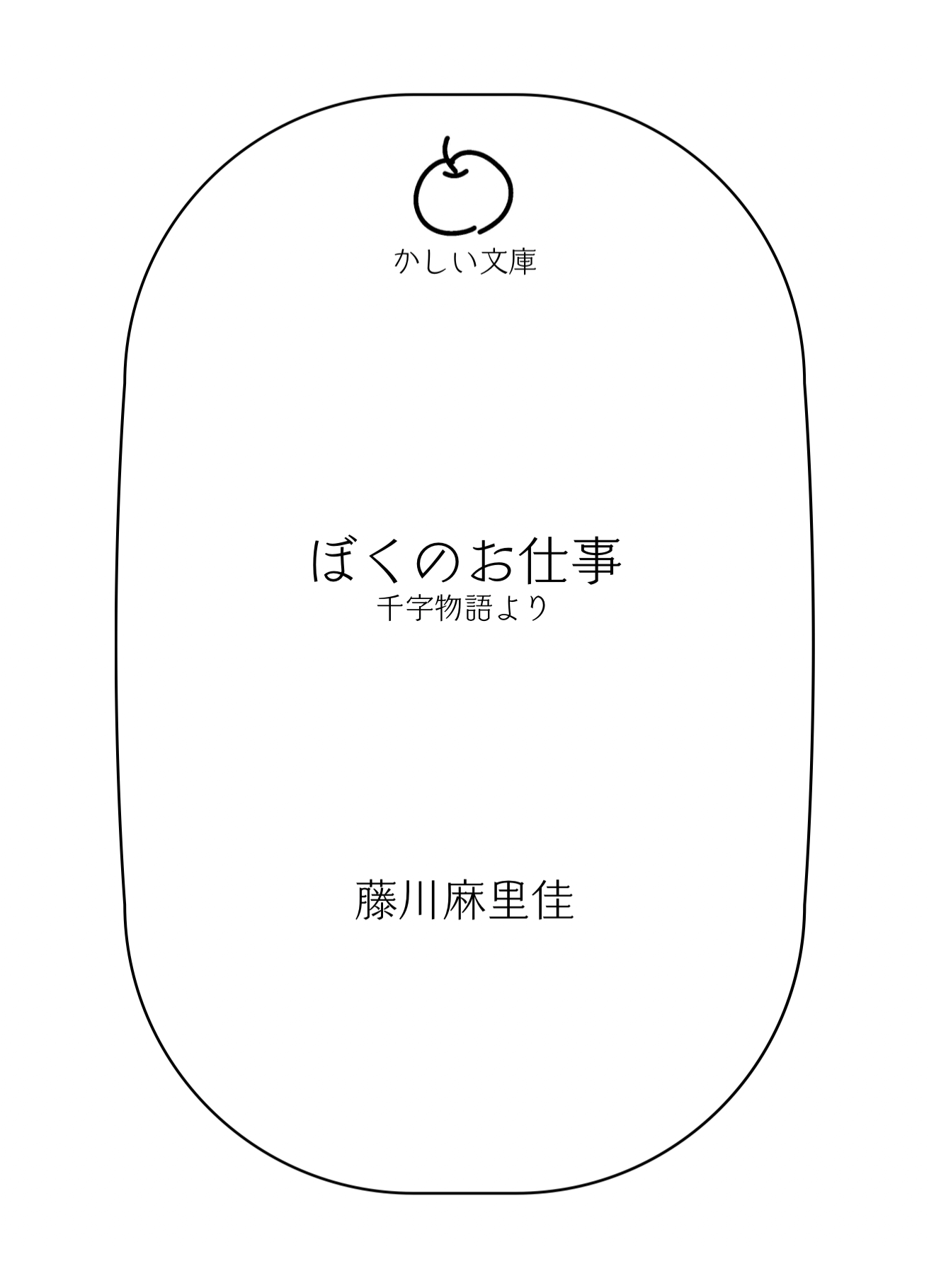
ぼくのお仕事
祖母の家には縁側がある。昔ながら、懐かしの、と言えば聞こえはいいが、遊びに来ると必ず雑巾掛けを任されて、祖母が良しとしないと夕飯までやらされることになる。やりたくないと母に言っても、祖母は歳でお掃除ができないのだからと意に介さない。子供の頃は家族みんなでやっていたけど、中学生に上がった頃からこれは僕一人の仕事になった。
僕は部活には入らなかった。月に二、三度祖母の家に行き、雑巾掛けをする。楽しいわけではないが、元々腰が曲がり気味だった祖母の代わりに掃除をして、お礼を言われたりお菓子を買ってもらったり、美味しいコロッケが夕飯に出てきたりするのが嬉しかった。
祖母は畑で作物や花を植える。雑巾はかけられないが土いじりは出来るという。お風呂椅子みたいな低い箱に座り、プランターの中の雑草を抜いたり、この花はどこに植えようなんて一緒に話す。無理しないで、と僕が言っても全然聞かなくて、日避け帽をかぶってしゃがみ込んでいる。
僕が大学二回生になって彼女ができた頃、祖母の家に行く機会が減って、母から、ばあちゃん寂しがってたよ、なんて聞いて、ゴールデンウィークになったら行こうと思っていた。
早朝、電話が鳴った。祖母のかかりつけの病院からだった。危ないから来てくれとだけ伝えられ、着の身着のまま車に飛び乗る。
つつじが明明と咲いていて、その隣では薄紫の芝桜が鳴いていた。日の出が早くなって、だけどうすくフィルターかかった春の空、僕が祖母の顔を見る頃には、こときれたあとだった。
「おばあちゃん」
去年家に行った頃と全く変わらないのに、呼んでもこちらを見ない祖母の、目尻がすこし光っていた。母は雪崩れ込むように祖母に向かって倒れ、父はその様子を悔しそうに見つめている。しばらくして先生が病室に来てくれて、経緯やこれからのことを話していった。僕は祖母の遺体から目を逸らせずにいて、両親が質問したり納得したりするのを黙って聞いていた。
祖母の手にそっと触れた。血管の形がありありとわかる日焼けした手は、昨日まで好きな畑仕事をして過ごしていたことがよくわかる。冷たい、ただそれだけが昨日と違った。
祖母は生前、母の勧めでエンディングノートや遺書を残していたらしい。それによると、法的に相続できるものは母に、僕には好きなものを持っていっていいとの記載がある。未払いの税金や借金はなかった。母は家も土地も全て相続し、僕はその家の掃除係になった。
縁側に赴くと、芝桜とあやめが咲いている。ほかにはよもぎが生えて、その陣地を増やしている。
雑巾掛けは晴れた日にかぎる。生垣の隅で猫が寝ている。
ぼくのお仕事